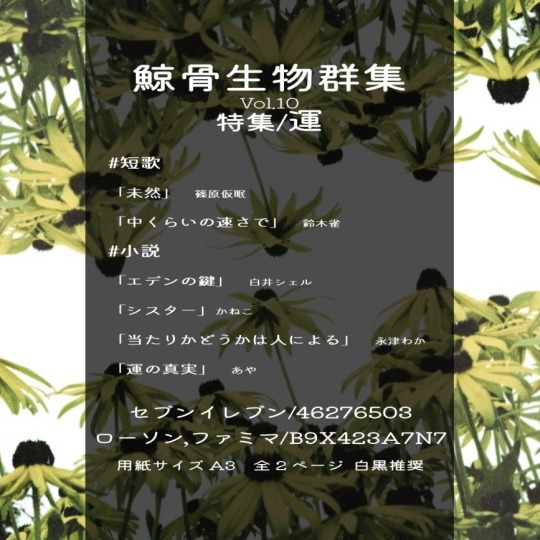#短��小説
Explore tagged Tumblr posts
Quote
短編小説「じゅたろう」 ① 9回裏 1-3 ワンアウト一、二塁 地区予選大会決勝。相手チーム南園学園は140kmの速球と125kmのスライダーを誇るサウスポーのエースピッチャー野村。 俺たち大友商業の3番セカンド北川は手堅くまずは得点圏に同点ランナーを進めて4番安藤、5番のオレ久富に回そうと送りバントの構え、そこに野村の高速スライダーが右バッター内角に食い込む。ガッと鈍い音がして、バントの打球は転がらず三塁側に変な回転の飛球が少しだけ上がる。野村がノーバンで拾おうと、マウンドを猛ダッシュで駆け下りて来る。 二塁ランナーは三塁に猛ダッシュする。一塁ランナーはノーバンで捕られたらゲッツーで試合終了になると考え迷ったが「捕られたら二塁ランナーは飛び出してるし、どっちにしてもゲッツー」と思い遅れて二塁に走る。ピッチャー野村は打球に走るが寸前でノーバン捕球は間に合わず、瞬間、迷ったが何とフォースアウトを狙い三塁に豪速球を送球。間一髪アウト!ツーアウトだ。 三塁手はすかさず、アウトに出来れば試合終了と、走塁が遅れている一塁ランナーが向かう二塁に猛然と送球。アウトのタイミング!一塁ランナーは二塁にヘッドスライディング。土煙りが上がる。 「終わったか、、、」とその時、ボールが二塁に入ったセカンドのグラブから溢れた。 「セーフ!」と大きな声が響く。 送りバントは失敗したが、辛うじて試合は続く。 9回裏 1-3 ツーアウト 一、二塁 バッターは4番こちらもサウスポーの安藤が左打席に入る。地区大会首位打者の安藤はこの試合まで4割を超える打率だったが、相手エース左投手の野村に押さえ込まれてノーヒット、三打席とも詰まった内野ゴロ。普段は明るく人気者の安藤の表情は野村の前にやや硬く見える。 一方、左ピッチャーが好きなオレは野村からセンター前ヒット、レフト前ヒット、そして、7回に今日の大友商業、唯一の得点をソロホームランで叩き出してる。 「フォアボールでもデッドボールでもいいから、オレに回してくれ」満塁になれば、ツーアウトだから、ランナーは全員思い切り走れる。 ヒットでも同点に出来るだろう。 1球目 内角速球を引っ張った安藤の打球は又、詰まって一塁側に転がる!観客席から悲鳴と歓声が同時に響く。 「ファール!」主審の声。 2球目 サウスポー野村の切れ味鋭いスライダーが外角を襲う。安藤、空振り! ノーボール、ツーストライク。 あと、一球で試合終了か。 3球目 更に外に少しはずしたボール球のスライダーに泳いだ安藤が手を出す!ポップフライが三塁側に上がる。さっき猛然と二塁に投げた相手サードがファールグラウンドに走る、走る、レフトも走って来る。再び耳をつんざく歓声と悲鳴。 「落としてくれ、、、、」 ファールグラウンドから観客席ギリギリ打球が飛ぶ。 入った。 観客席に入った。 「ファール!」 「タイミングが全く合ってない。」オレは呟いた。 「安藤!最後だ!悔いなく思い切って振り切れ!」オレは叫んだ。 安藤はこっちを向いて、日焼けした顔、切れ長の目で少し、はにかむように微笑んだ。 あれ?こいつ硬くなって無いのか? 4球目 またタイミングが合わない高速スライダーだ!安藤が右足をグッと踏み込んだ。泳いで無い。 すくい上げた。 パキーン!と甲高い打球音が球場に響いて左中間の深いところににボールが飛ぶ。飛ぶ。飛ぶ。 観客もピッチャー野村も安藤もオレもベンチの選手も審判も白球の飛ぶ夏空を見上げる。 一塁ランナーも二塁ランナーも見上げながらも走る、走る、走る。 「行っけ〜!!!」とオレは叫んだ。 と、センターが手をあげた。 打球が青空から落ちて来る。 悲鳴と歓声がこだまする。 安藤は一塁に走りながら、また、微笑んだ気がした。 安藤が右腕を突き上げている。 入った。 観客席に入った。 ホームランだ。 アレ?スリーランホームランだ? あれ?という事は? 4-3の サヨナラだ!!! 時が止まったような球場のベースを安藤がゆっくりと回っていく。 ピッチャー野村は膝を折った。 ニコニコ笑った安藤がホームベースに着く頃、オレたちはみんな安藤の笑顔を揉みくちゃにすべく、ホームベース上に集まり、抱き合って、待っていた。 「ゲームセット!」 「いいとこ、取りやがって!」とオレは叫んだが、果たして、ツーアウト満塁になってオレなら本当に結果が出せたのか??? そんな事は今は良い。 とにかくサイコーだ。 この日、オレと北川や安藤や野球部の仲間はサイコーに喜んでいた。 (②定食屋「イカ天」に続く) https://x.com/takigawa_w/status/1787822221651845444?s=46&t=8Vf8aUwk_B-ZbQ5UAGv05w #短編小説 「#じゅたろう」 #野球 https://x.com/takigawa_w/status/1787822805494739318?s=46&t=8Vf8aUwk_B-ZbQ5UAGv05w
https://x.com/takigawa_w/status/1787822805494739318?s=46&t=8Vf8aUwk_B-ZbQ5UAGv05w
19 notes
·
View notes
Text
今夜の夢は
ルネは夢棚にある沢山の夢の中から一つの夢を選ぶとベッドに横たわる。
今夜の夢は小人になって、ヒョウタンボクの木の上で暮らす夢にした。
何時ぞやの夢は猫に喰われて、お腹の中の不思議な町を旅するものだったりと、ルネの夢棚には色んな夢がある。
──夢を貸してください。
ある夜、ルネの元に少年がやって来た。
ルネは夢棚から選ぶように伝えた。
──僕は一度も夢を見たことがありません。どれも楽しそうだけれど少し怖い。一緒に夢を見てくれませんか。
そう言われてルネは、夢の中でもいつも一人きりだったことに気がついた。
月下、二人は一つの夢を選ぶと手を繋ぎ夢の中へと潜り込んだ。
.
3 notes
·
View notes
Text
わたしを監獄に連れて行って(掌編)
「何をしているの?」
「あなたさえいれば十分さ」
会話が始まった。二人が暮らす部屋はもうずっと手狭だった。
腰に手を伸ばした。女のような柔肌に、あなたは相変わらず興奮していた。女ではだめなのだ。女のように、美しくないといけなかった。そう、あなたは、どこまでも偽物のわたしにほんとうを見出して、愛していた。
「監獄には何があると思う?」
昔は小麦のパンが並んでいた食卓も、少しずつその色合いにライ麦の黒が混ざっていって、最後にはそれすらも少しずつ小さくなっていった。ぼくらの憂鬱や絶望も、その暗闇に吸い込まれて小さく消え入ってくれればよかったのに。
あなたのどこまでも広い胸にもたれ掛かると、罪の象徴がちくちくとして痛かった。神はぼくらの睫毛の一本一本さえも咎として象ったという。ぼくらは裏切り者で、ずっと前にエデンを放逐されていた。そして、監獄での断罪からさえも、怯えて逃げ回っていた。
「監獄には何もないさ。ドラマツルギーな、最後の審判だってありはしない。ぼくらは引き裂かれて、感慨もなく死んでいくまでだ。」
そうしたらぼくらの罪は贖われるのだろうか?
疑問は室内に霧散した。愛のことばは埃となって、ベッドの上に降ってきた。階下ではどたどたと、何や��物騒な物音がし始めていた。
「ねえ」
「ん?」
「後悔は、していないかい?」
「していないさと言えば、嘘になる。けれど、けれど……」
「ねえ」
唐突に会話が断ち切れた。数瞬の沈黙のあと、
『わたしを監獄に連れて行ってはくれないか?』
二人の声が重なった。あとは言葉など要らなかった。ただ愛の為だけに唇を使った。だんだん階下の音は大きくなっていく。汚れることのない歌を歌おう。どこまでも綺麗な牢獄で、まじりあって、二人はほんとうになっていった。
◯
ゲシュタポが突入すると、部屋の真ん中で、熊男と女男が頸動脈を刺しあって血を流しているばかりだった。「移送」対象者が自ら事切れているのは普通なら好都合だが、いまは戦況も劣勢で、いくらユダヤのゲイ二匹だとは言え、栄光の轍への貴重な労働資源になるはずだったろう。上官は不機嫌そうな顔で部屋を立ち去り、腹いせに大家をぶん殴ったのだった。
5 notes
·
View notes
Text
置き去り
大人になるなんて死ぬまで死ねないだけだ

小学校の卒業式をひかえて、将来の夢なんて作文を書かされたのを憶えている。
違和感はそのときから感じていた。何で、もう未来のことを決めなきゃいけないんだろう。僕の未来なんて、きっと大して輝くものでもないのに。
働いて、食べて、眠って、また働いて──そんなもんだろ。
教室が暗くなってもできあ��らなくて、結局宿題になった作文は、家のPCで“将来の夢”“作文テンプレ”を検索にかけて、ヒットしたもので埋めた。そんなズルをした日から、僕の感覚は周囲から外れていった気がする。
中学生になったら、あれがしたいとか。高校生になったら、これがしたいとか。同級生たちのそんなきらきらした話に、混じることができなかった。
大人になるなんて、死ぬまで死なないのが憂鬱なだけじゃないか。人生なんか、早送りで終わってしまえばいい。
志望。進路。就職。歳を重ねるほど、将来を枠にはめて決めつけようとする周囲が鬱陶しい。
「やりたい仕事はないのか?」
「したいことはあるだろ?」
「大学には進んでおかないと──
やりたいことなんてない。何もしたくない。モラトリアムに大学に進むなんて妥協には、吐き気がする。
いずれにしろ僕は、機械のような、ろくでもない大人になるだけだ。
だから、叶うのならば、早く死にたい。
気づけば、高校を卒業していた。結局医療系の専門学校に進むことになった。頭がおかしいぐらいに、死にたい、と一日じゅう願っている僕なのに、人の健康をサポートする勉強をするなんて、いよいよお先が暗い。
大学生になって、ケータイをガラケーからスマホにした。機種変のとき、連絡先は転送したけど、連絡が減ってやがて途切れた奴から、容赦なく削除していった。
どうせ、愛想咲いで何とか合わせていただけの友達だ。向こうにだって、僕はそんなものだろう。僕から何も連絡しなかったら、問い合わせてくる奴もいなかった。
大学でもなるべく深いつきあいはせず、連絡先交換もかわした。教えろなんて、わざわざ食い下がる奴もいなかった。
僕のスマホは、SNSの鍵アカウントで脈絡なく吐くか、それなりに世界を知っておくために、ハイライトニュースを見るためだけのものだった。
そして留年もなく、二年生になった。
じわりと覚醒してきた頭の上で、鳥がさえずっている。平日の朝は、五時半に起きる。そして、一時間以上かけて市内にある例の専門学校に通う。
スマホのアラームを止め、腕を伸ばしてカーテンをめくった。初夏の青空が薄目に射しこむ。身を起こして、窓に透けて映る、光のない腐った目つきを見た。老けて見えて、吐き気がする。
頭が少し痛い。だるい動作でベッドを降りると、黒のジャージのまま部屋を出てダイニングに向かった。
「おはよう」
共働きの両親が、すでにいそがしそうに身支度を整えていて、ばたばたしながら僕にそう声をかける。���は同じ言葉を返しながら、テーブルにあったふくろから食パンを取り出して、トースターにかける。
待つあいだにインスタントコーヒーを淹れてすすっていると、ベルが鳴ってトーストが焼き上がった。それにマーガリンを塗って、甘い匂いの蜂蜜を少し垂らす。リビングに移動し、さく、とトーストをかじりながらテレビをつける。
朝のワイドショーではなく、報道が映った。どうでもいい政治の話題の次に、女子中学生が踏切から線路に飛びこんだというニュースが流れた。部屋から遺書も見つかり、自殺とみられているということだ。
ダイヤの乱れが出ているとまくしたてるキャスターを無機質に眺め、マーガリンの塩みと蜂蜜の甘みが溶けこんだトーストをかじっていく。半分ぐらいで食べる気がなくなったけど、安い苦みのコーヒーで無理やり胃に押しこんだ。
中学生の弟がかったるそうに起きてきて、すでに三十分経っていて六時が近いのを知る。僕は部屋でジャージからシャツとジーンズに着替え、歯を磨いたりトイレに行ったり、身支度を整える。
僕より先に両親は出勤してしまう。だから、いつも僕が弟に戸締まりをしていく確認をして、いい加減に返事されると、さっきレースカーテン越しに見たときより光が強くなっている空の下に出て、駅に急ぐ。
五月になって、連休も終わったところだ。もう真夏日もある。熱中症とか、水分補給とか、そんな言葉を早くも見かける。
雨の日は、服や靴が濡れるから鬱陶しい。でも、こうして晴れた空の下を歩くのも息苦しい。
まるで罪の意識があるみたいだ。実際、僕は白日に晒されたら、心が自殺願望で腐りきっていて、とても醜いけれど。いい天気の日は、リストカットに依存する子が、長袖しか着れないみたいな気分になる。
駅はラッシュが始まって騒がしく、たくさんの人がホームで電車を待っている。学校まで乗り換えは一度だけど、この人たちを全部詰めこむ満員電車だから、座れるわけもなく、長く揺られることになる。
乗りこんだ車内は蒸し暑く、誰かがちょっと汗臭い。ヘッドホンで曲をシャッフルで聴きながら、僕は倒れないように地味に踏ん張りながら、スマホをいじる。
SNSのハイライトに、朝テレビで見た中学生の飛びこみ自殺のニュースが上がっていた。タップしてコメントを目でたどる。
『まだ電車止まってるんだけど。いつ復旧するの?』
『イジメかなあ?』
『朝のラッシュ止めて、金払うのは残った親だろ』
『まだ中学生? 可哀想……』
『イジメだろう���~加害者が死ねよ』
『樹海で首吊ればいいのに。飛びこみって一番迷惑』
僕はこめかみのあたりにゆがみを感じ、眉を顰めて、スマホの画面を落とした。
別に、それくらいいいじゃないか。そう思った。死ぬときぐらい、こんなに生きていたくなかったのだと、気づいてもらえていいじゃないか。そうでもしなきゃ、この子はどんなに傷ついていても、みんなに見て見ぬふりをされていたのだろう。
「死にたい」とひと言吐ける相手がいたら、この子もこんな悲鳴は上げなかった。誰もいない、誰も見てくれない、誰も聞いてくれない、きっとひとりぼっちで突っ立っていたのだ。
だったら、迷惑であったとしても、軆を飛び散らせた一瞬くらい、人に振り向いてもらえないと浮かばれない。
顔を伏せて、またスマホを起こしながら、無意識にちょっと嗤ってしまった。そんなふうに考える僕は、だから生きているのがこんなに苦しいのだろうか。
世界と感覚がかけはなれている。普通の思考でものを見れない。すごく冷めていて、とても虚しくて、やたら刺々しい。
裾のほころびのようにいつのまにか生まれて、歳を重ねるほどふくれあがっていく、「死にたい」という想い。イジメも虐待も、何にもない人生を送っているけど、家族も友達もそれなりの僕だけど、その虚しいほどの日常に滅入る。
このまま、僕の人生は安全��過ぎて、達成感のない死を迎えるのだろうか。子供の頃、大人になりたくないと思っていた。今、社会人になるのが嫌だ。そして社会人になったら老後が怖いのだろう。
平坦に過ぎていくだけの未来を思うと、ひどくぞっとする。そんな植物人間みたいな将来しかないなら、いっそとっとと死んだほうがマシだ。
死にたい。せりあげてくるその想いを、僕も誰にも打ち明けられずにいる。
家族に? 分かってくれない。
友達に? ヒカれるに決まってる。
心を、喉を、頭を支配していく黒い霧のような希死念慮で、僕は朦朧としている。ああ、もう、はなから生まれなきゃよかったな。どうせくだらない未来しか待っていないし、そんなのただ死にたいだけだ。
僕も今朝命を絶ったその女の子みたいに死にたい。こんな人生は願い下げだと訴え、その絶叫で喉をはちきれさせて死にたい。
かたん、かたん、と電車が小さく揺れている。汗ばむ温度。煙草、あるいは香水が染みついた服の臭い。曲と曲の三秒間に聞こえる物音。
電車の中にいると、とりわけいろんなものが神経に障って、黒い想いが強くなる。背広のサラリーマン。スーツのОL。学生は眠そうだったり、ゲームをしていたり。
そんな中に混じっていて、自分もまた見分けのつかない大人になろうとしていることに愕然とする。僕がダメになっていく。このままじゃ、腐った世界を見るこの目から全身が腐っていく。
早く死ななきゃ。限界だ。毎日この想いに耐えて、生きていくなんてつらすぎる。自殺願望が背骨に食いこむほどのしかかってきて、もはやまっすぐ立つこともできない。
重い。痛い。死にたい。逃げたい。今日こそ終わらせたい。
そう、こんな毎日はたたき折るのだ。どこにだってつながっているあの駅から、僕も旅立つ。
乗り換えの駅でいったん電車を降りて、路線を変える。早歩きの人たちが放射状にうごめく、大きな駅の構内の気持ち悪い光景の中を縫っていく。
この駅からは、いろんな路線が出ている。さまざまな場所へと連れ去ってくれる駅だ。なのに、誰もが毎日決まったホームに向かう。
そんなふうにせわしなく生きて、ひとりも疑問はないのだろうか。どうして、こんな行き先が決められた朝が、当たり前みたいに生きていられるのだろう。消費するだけの日々に無抵抗で、平然と改札を抜けている。
みんな死にたくならないのだろうか。なぜ、こんな昨日と同じ朝が普通だと納得できるのだろうか。
僕は嫌だ。こんな朝に溶けこみたくない。ホームへの階段を降りている。目的地への列に並んでいる。そんな自分に、本当は悲鳴を上げたい。
前方を薙ぎ倒し、線路に飛び降り、ばらばらに轢き殺されたい。怖いという感情は日に日に薄れていく。ただ、それがこのホームにいる人全員のトラウマになると思うと、荷が重い。
でも、分かっている。いつかそんな気遣いも壊れていって、僕は電車につぶされて上半身と下半身がちぎれるのだ。
頭の中が、ゆらゆらしている。毒を受けたように隈のついた暗い目が、無数の人の中を泳ぐ。甲高い女子高生の笑い声がして、舌打ちを殺して、音楽のボリュームを上げた。それでも、いらいらはまとわりついて、今にも発狂しそうな自分を必死に抑える。
死にたい。いや、ダメだ。何で? 死にたい。電車が来たとき、あの線路に飛び降りれば楽になれる。
楽になりたいだけなんだ。人並みに息抜きをしたいだけなんだ。死ねば、僕はやっと生まれてよかったと思えるんだよ。
なのに、どうして死んではいけない?
一歩、踏み出しそうになる。それを必死にこらえる。こらえる理由は分からない。
いや、たぶん、勇気が足りないのだ。死ぬ勇気。消える勇気。それは僕のこの上ない望みなのに、結局、僕は怖い。この意識が、感情が、思考が蒸発するのが怖い。その矛盾が歯がゆくて、いっそう僕はいらいらしてくる。
僕は意気地なしだ。ひと思いに死ねば、少しは自分を見直すのに。躊躇う自分が、うざったい。
もし僕が死んだら、ここで電車に飛びこんで死んだら、今このホームにいる人たちは僕を憎むのだろう。
ばらばら死体なんか見せやがって。電車を遅らせやがって。何でひっそり死なないんだよ。そんなに可哀想だと��ってほしいのか? お前がどれだけ苦しいかなんて知るかよ。ただ迷惑なんだよ。お前は最後の最後まで迷惑だったんだよ!
息が引き攣って、まばたきをした。幻聴と思えないほど、僕の死体への罵声が聞こえた気がした。
迷惑、か。僕がここで死んだら迷惑がかかる? じゃあもう、お前らが死ねよ。みんな死ぬなら、僕の死なんてそれこそ些末なものだろう?
世界なんか滅亡してしまえ。何だっていい、みんな死んでくれ。そして僕のことも殺してくれ。神の裁きみたいに、こんな世界のほうから終わってくれ。
そんなことを考えている自分を、ぼんやり観察する外側の僕がいる。外側の僕が、僕を正気みたいに見せて整える。
死にたいとか。殺してくれとか。すべて終わってくれよとか。そんなイカれた思考回路を、もうひとりの僕が黒子みたいに立ちまわって偽る。
奇声を上げて線路に飛びこむのを我慢しているあいだに、そいつによって、僕の本当の心は、自傷痕を隠す包帯を巻いたように包み隠される。
ホームの中の人たちは、みんな生きている。みんな動いている。笑って、話して。スマホをやって、文庫本を読んで。何気ない朝がそこにあって、その景色の中で、僕の気持ちだけ取り残されている。
今日もまあ頑張ろうと思っている人たちの中で、僕はその線路に飛びこんで死のうと思っている。
そんなの、誰も理解してくれないよな。このホームで僕だけ違う。僕だけみんなに染まれない。僕だけ醜く浮いている。
……無様だな。本当はそれが寂しいんだろ? みんなに溶けこみたくないとか思って、僕は誰よりもみんなと咲えたらいいのにと思ってるんだろ? でも、それがきっと一生できないから、死にたいんだろ?
鋭利なナイフをぐさぐさと突き立てるように、自分に対して思って、泣きそうになった。
いつも通り、目的の駅に止まる電車が入ってくるアナウンスが流れる。ああ、死ぬのが電車に乗るだけだったら楽なのにな。今日だけ、天国行きって言ってくれないかな。いや、僕は地獄行きかな。どっちだっていいや。
混ざれないいつもの場所に行きたくない。僕はただどこかに溶けこみたいだけなのに。受け入れてほしい、認めてほしい、分かってほしいだけなのに。
電車が迫ってきて、僕は小さく口を開く。
「……死にたいな」
電車が起こした風の轟音で、それは誰にも聞こえない。
こんなふうに毎朝、やってきた電車で僕は心を押し殺す。このホームに心の死骸を何度も何度も捨てて、それで何とか自分を取り繕って、今日を始める。
扉が開き、列が動いて、人は電車に乗りこんでいく。それに従って、電車に踏みこんで、僕の心はいつもこのホームに置き去りにされる。
そして、今日という日も、何の爪痕も残らない日になるのだ。
FIN
2 notes
·
View notes
Text
🟧各ストアにて販売中🟧
⭐Amazonロマンスカテゴリー(Kindle)ベストセラー(ランキング1位)[2019]⭐ 龍を待ち続けた娘、娘を愛し続けた龍の弟。仙界を舞台にした切ない中��ファンタジーラブロマンス
📕火龍の花嫁 (BLIC-Novels)📕
【電子書籍版】 Amazon:https://amzn.to/491YvI3 ※Amazon以外での電子書籍ストア配信はこちらをご覧ください https://sites.google.com/view/ayanetanizaki/books/
🩷恋した相手は、決して好きになってはいけない相手だった🩷 幼い頃に炎を司る龍王・火龍から花嫁と定められた三娘(さんじょう)。しかし年頃を過ぎてもその相手は迎えに来ず、彼女は国王からの求婚に応じることを決めた。 婚礼当日、いざ輿に乗ろうとしたそのときとっさに逃げ出してしまった彼女は、亡き母の私室でかつて結納の品として受け取ったものを放り投げた。そうすることで火龍のもとへ行けると聞いていたからだが、床に落ちた赤い宝玉が粉々に砕けた直後に立ち上がった炎に包まれ三娘は気を失った。 意識を取り戻したところ、見知らぬ場所で見知らぬ男に抱きしめられていた。三娘がいたのは、神々や仙人たちが住まう仙界。そこで彼女を待っていたものは驚くべき真実と自分を愛し続けた男の一途な思いだった。
💡海外からのご利用は【楽天kobo】がおすすめ https://sites.google.com/view/ayanetanizaki/ 💡日本のAmazonを海外から利用するには? https://sites.google.com/view/ayanetanizaki/
💡投稿を目にしたくない方は【アカウントをブロック】してください
#電子書籍#単行本#新刊#楽天kobo#短編#ラブストーリー#ヒューマンドラマ#純文学#ライトノベル#ティーンズラブ#おすすめ小説#40代#日本の本#東日本大震災復興支援#被災地#募金#japanese#Japan#フランス#ドバイ
2 notes
·
View notes
Text
我是今天早上起床后决定去死的。
收拾了昨夜吃剩下的泡面,汤水倒进了马桶,认真做好了垃圾分类。挑选了最喜欢的那身切尔西的帽衫,这是我妈在我20岁生日那天送我的。
收拾好一切,蹲坐在鞋架边,数着墙上时钟上的分针,因为六点半才能丢垃圾。
其实去死这个念头也仅是今天才有的,我开始回想起事到如今的原因。因为工作,家人,伴侣,生活。想了许久,想要挖出那一根被引燃的导火线。
那场面,大概就是燃烧着的蜘蛛网,火势从六边形的每个角落涌向中心点的我,而我还只是黏在网上的一只待宰的昆虫而已,没有这火,也只是等着被织网的蜘蛛蚕食罢了。
思绪截至在时钟指向六点半的那一刻,蹲了太久,站起来一瞬间两眼发黑,我扶着鞋架,待大脑重新回来,拎着几袋垃圾出��了。
两分钟后我折了回来,想死的心太急,马桶忘记冲了。
元旦假期前,同事涨薪失败,看着他双眼发红发朋友圈的样子,我满是羡慕。那种还对世界充满希望的泪水与愤怒,早就被我丢在人生道路上的哪个有害垃圾的垃圾桶了。我能猜到她的朋友圈内容,大抵是被老板数落能力不行,配上发红的眼眶自拍。嘴是一定会捂上的,毕竟这时候的表情要么就不太合适,要么就不太好看。
没多久,那条朋友圈就会有着数十个点赞,朋友会关心,家人会安慰,同事会帮着骂上几句,男朋友会扬言揍老板一顿。这一切会激烈的讨论整个下午,而话题中心的老板此刻正淡定的躺在自己办公室的按摩椅上,准备好好睡上一觉。
没多久,我就在那天屏蔽了不知多少人的朋友圈里点了一个赞。
爱埋怨是件好事,这是一个人知道一件事何为正确的象征。
我家人也爱埋怨,因为他们觉得我应该去厂里上班,应该去乡下讨个媳妇。不懂事的时候我还会愿意同他们争论。如何在厂里上班的同事,照顾好乡下的媳妇。
于是他们会埋怨我花了他们的钱读了书,却只知道和他们顶嘴。
这时候我就没法回,因为我也没读好书。
我大概是应该去厂里上班的。
听说那里有着定期发放的工资,每日的餐食,干净的宿舍,不用动脑的工作。
那是值得向往的工作,只可惜不是那个刚毕业热血的我向往的工作罢了。
当年的我烧着热血,离开父母,在这个外卖商家刷不到底的城市里,决定两年买车,三年买房,十年达到财富自由。
想到这,我坐上了公交车,临死前再看看吧,这个曾经我热爱的城市。
离财富自由的期限还有两年,房价已经比刚来时翻了几倍,公交车都从汽油换成了电车。
很怀念那些年,我还做着设计师的梦,即使身无分文,至少不像现在到处欠钱。
我前女友当年也很支持我做设计师的。
那时候她会夸我有才华,也因此,我有时还真的会相信我可能真的是个天才。睡前我总会翻着朋友圈,向她吐槽同行的垃圾图纸,客��带来的破烂样图。
其实我不也并非真的看不上,只是我很喜欢她对我说对对对的样子。
所以,当有一天,她说我不对的时候,我们分手了。
车正路过之前我们一起等车的站台时,一个老头坐在了我旁边,想必上车前才掐断最后一口烟,身上的味道像湿垃圾分类的垃圾桶。
我向里挪了挪,看着远去的站台忍不住笑了,这种吊人怎么好意思坐公交车,这种吊人怎么好意思有过女朋友。
后来我就习惯说对对对了。
我对老板说,对同事说,对客户说,对家人说。
对对对,您骂的是。对对对,问题在我。对对对,你的想法非常超前。对对对,厂里确实不错。
反正我是错的,那和我意见相反,应该都是对的。
后来我就决定去死了。
我难以得知正确的样子,让我在这个世界上没有了存在的意义。
这个世界是留给那些对的人的。
我一直坐在公交车上,一遍遍的看着这个熟悉的城市,我在这找过工作,在这见过客户,在这吃过火锅,在这遇到过老头。
“爷爷,你怎么一直不下车啊?”我问了问,这老头和我在这车上拉回好几遍了。
“逛逛。”老头盯着正前方,双手环抱着,看着不太愿意搭理我。
我又向里挪了挪,也环抱着,眯眼睡了过去。
被司机拍醒时天已经黑了,司机说他下班了,麻烦我把路费补一下。
我微信转了他一百四,倒不是我大方,手机里就这么多。
我一个人下了车,老头不知何时走的,大概是老年卡才可以这么肆无忌惮吧。
一年的最后一天,这个偏僻的末站倒挺热闹,大家裹着衣服猫着腰,即使躲避着初冬的寒风,依然要在这一天找一个地方,等待庆祝新一年的来临。
我走到一个老旧的小区,就这吧,看这附近应该砸不死人。
看了三遍招聘平台的广告,电梯上了顶楼。再爬了一层没有夜灯的台阶,终于来到了天台。
我抬头看了看天,不像夏天,冬天的天空总是灰蒙蒙,看不到一点星光。
真好啊,夏天,一切都很美好,阳光,白云,最老套的词却描绘着最具希望的样子。
只可惜我是等不到下一个夏天了。
更可惜的是,天台有人了。
“爷爷,你咋也在这呢...”
“看看。”老头回头看了我一眼,他正盘坐在围墙上,十七层楼的下面,车子还不时传来不耐烦的汽笛声。
“爷爷,你这样不安全,要不你先下来吧。”我被风吹着忍不住打了个寒颤,声音都在发抖。
“我等着死呢。”老头的声音平稳有力,我甚至能在冷气中闻到他嘴里的那股烟臭味。
我哆哆嗦嗦挪到老头的身边,手掌隔空扶在他的背后,至少他要是往后倒下来,不至于摔伤。
往前倒,也不是伤不伤的问题了。
离的近些,我也才真的好好看了看这个老头。没有中年人的地中海,头发已经仅剩些白色的绒毛吸附在发皱的脑门上,眉毛的尾部已经飞出眉形,紧皱着望向楼下堵住的车流。
公交车上的那烟味还未散去,只是现在我是一点不敢离开。
“有烟吗?”老头回头上下扫了我一两眼,“跟着我这么久干嘛?”
“没跟着你啊,我...”
我不知道该如何解释此刻的天台相遇,憋了半分钟,假装掏了掏口袋,回了句没有。
“罢了,临死了连根烟都抽不得。”老头头又转了回去,双手始终环抱着。
看似取暖的动作,却在寒风中有着不惧的威严。
我又瞧了眼楼下,车已经纹丝不动,但停下的人们并未发现楼顶的这出闹剧。我一个寻死的人,此刻害怕另一个寻死的人去寻死。
我踩着地上散落的烟头,腿控制不住的发抖,脚趾已经冻得没了知觉,手仍悬在空中搂着老头身后的空气。
“有啥想不开的爷爷,先下...下来再说啊。”
“活着没意思,早该死了,死完了。”老头再次回了头,这次他身子也转了过来,利索的从围墙上跳了下来。搓了几下双手,从中山装的的上口袋里掏出一个塑料打火机,蹲了下来,利用着火光,寻找着残余的烟头。
“爷爷您这...,要不我给你子女打个电话来接您成不?”
老头没理我,翻了一会儿,找到一个还算长的烟头,靠着墙边,躲着风。点燃后,他猛吸了一口,收起了火机。
城市的灯光未被收起,还能看见那眉头终于松了下来。
老头在地上坐下,伸了伸双腿,一吞一吐,瞄了瞄弯着腰跺脚的我,“小伙子,做什么的啊?”
“我,看看风景...”
“我是问你做什么工作的。”
“设计,额,大概是设计。”我补充了一句。
老头又猛吸了口烟,残根的烟头立马就烧到了底,散着刺鼻的焦味。
“我和你差不多,我年轻的时候是个画家。”
“哦哦,蛮好的。”
“也就两年功夫,画了两年你知道吧,后来不画了,没人搭理,我们那不兴这个,家里人不让。”
“哦,那,那个挺惋惜的。”
“不可惜,不让的人后来死的都比我早,就我活着,没人管了。”
“哈哈....”我不知该回什么。
“那时候想死,不想活了,一家人拉着我,我在那喊啊,我去死了,不活啦。我妈就在那拉着我哭,在那念阿弥陀佛。”老头挥舞着双手,演着曾经的自己,“他们觉得我疯了,觉得我入了邪道了。”
我也坐在冰冷的地上,看着他眼神反着光。
“他们越是觉得我疯了,我越想死。可惜了,那时候该死。”
“活着不好吗,爷爷你看你现在活着多精神是不...”我说。
“那时候死了,兴许他们会觉得自己错了。死的晚了,他们都死了,他们都觉得自己都是对的才死的,可惜了,弄得现在我觉得我是错的。”
“您是对的,哦哦...您是错的,那个,我...”不知怎么的,我的眼泪就大颗大颗的往下掉,突然感觉极度的痛苦,还有害怕。不知痛什么,也不知怕什么,只有撑在地上的手能感受到冰冷,还有泪水滴在上面,烫的发疼。
“该死的,应该死的,白活了这么久,现在死了也没人问了。”
“我...大爷你干嘛和我说这个,你能别说死不死的吗,我害怕,我不想死,我,我不想死啊!”
“我又没让你死,你哭个屁。”
“我,我就是怕啊,我怕啊!”
风一阵阵的刮着,远方传来了阵阵烟花声,天空是不是闪着光,我的脸烫的发麻,感觉声带正在做着抵抗。
对啊,我在怕什么呢。
明明垃圾都分好类了,马桶也冲了下去。
在怕什么呢?
不知道自己在嚎什么,只感觉浑身的痛。
老头半天没说话,我也总算冷静了下来,抽了抽鼻子,抬头看着烟花。
老头也在看烟花,一阵黄,一阵红。在眼前,在远方。
“对不起,我,我可能有点紧张,我陪您下楼吧。”
“下去给我买包烟成不,一包红南京,十二快的,楼下有个超市。”
“啊?”
“我看你���神不太好,动动,完了陪大爷唠唠。”
我缓慢的爬起来,膝盖僵硬的不像话。
“没钱了。”我想了起来,最后那点存款给了公交司机。
老头又翻了翻衣服的上口袋,只掏出一个火机。随后起身,手揣进裤子口袋里掏了掏,摸出一些钱。
“再买瓶酒,十五的随便,白酒,别买别的,喝不惯。”
我伸出手接过那一沓皱巴巴的纸币,擦了擦眼泪。
“那你等我会儿。”
“好,别买错了,十二的红南京。”
我借着烟花的光走向楼梯,摸索着扶手下了楼。
楼下的灯光让我回过神,完全不知刚刚什么情况,身体突然的不受控制。
看着电梯门的镜面,发现自己的头发都吹的服服帖帖,蓝色的帽衫上沾满了白灰,眼睛通红。我按了电梯,狠狠地揉了揉自己的脸。
电梯从一楼到���楼到三楼,突然听见电梯边的人家传来了一声声倒数。
“十,九,八,七...”
电梯边的广告窗还在播着那个招聘平台的广告,里面的人穿着统一的绿色紧身衣,不知为何的聚在一起跳着舞。
“五,四,三,二,一!”
“彭!”
而后,周围的房间内传来了一阵阵欢呼。
烟花吗,我问着自己,随后走进电梯,捏着纸币的手按下了一楼的按钮。
新年了啊。
8 notes
·
View notes
Text
「我想請教一下,您那邊以前有沒有一爿叫『天涯海角』的館子?」
聽筒那頭沉默了兩秒,『你是說「天之涯,地之角」的「天涯海角」嗎?』
「是。」
『你們怎麼會想問這爿館子?』
連結:https://www.penana.com/article/1164829
2 notes
·
View notes
Text
見ることも知ることもない
宇宙から地球を見たら、いま自分が悩んでることなんてちっぽけに思えるという言葉があるけれど、それよりももっと有効な例えがある。
君が生きている世界を一つのゲームと仮定する。そのソフトは生きている人間の数だけ、あるいは命ある生物の数だけ存在する。君は君としてそのゲームをプレイしている。スタートもエンディングもソフトによって、プレイヤーによって異なる。そのゲームはある一人の製作者の脳内で構成されている。その製作者とは誰か。それは君自身である。
仮に、君が死ぬまでに一度も耳にすることも目にすることもなかった音楽が存在するとする。つまり存在を認知できない音楽だ。仮にその曲の作曲者をアレックスとしよう。彼はカリフォルニアに住む大学生だとしよう。アレックスは得意のピアノでその曲を作曲する。仮にその曲のタイトルを「青い象」としよう。君は生きている間にアレックスがカリフォルニアに実在していたことも、「青い象」という曲が作られたことも知ることはない。だから君は君の脳内でこの「青い象」のメロディを演奏することはできない。すると君はこの存在を認知できない音楽、「青い象」は存在しないと同義だと考えるかもしれない。しかしそれは違う。それは同義なんかではなく、ハナから存在しないんだよ。なぜなら世界や宇宙、あらゆる事物は君の脳内で生まれるんだから。
あそこの水槽の中にサカナがいるだろ。仮にあのサカナはあの水槽の中で生まれて、水槽の中から出ることなく死ぬとしよう。その場合どうだろう、あのサカナは自分のルーツが海であるということを知ることはないだろうね。なぜなら海というものが存在するなんて想像もできないんだから。つまりあのサカナにとって海なんて存在しないと同義だ。でも君は海というものを知っている。ではあのサカナは海の存在を認知できないまま生涯を終えることを悔やむだろうか。悔やまないだろうね。だってあのサカナにとってのルーツはあの水槽でしかないんだから。
6 notes
·
View notes
Text
バラ色の連帯と称する奇妙でみだらな疑似家族を営む母娘と俺との、エロティックな関わりの始まりと終わり。
2 notes
·
View notes
Text
秘密の夜会
未散は今宵も星空を眺めながら美酒を飲む。
水瓶座から滴るその美酒は例えようがないほどに甘くて美味い。
あ々おいしい──。
未散は次々と美酒を飲み干した。
そのうち未散の体温はどんどん上昇しだした。
熱い、熱いわ。
それでも水瓶座の美酒はやめられない。
そうしてとうとう未散は蒸発した。
蒸気になって夜空に登ると、星座たちが未散を待っていた。
乙女座の手酌で未散はまた美酒を飲み始めた。
一夜の宴は始まったばかり。
未散は蕩ける美酒に酔い痴れた。
.
3 notes
·
View notes
Text
職員室に入ったとき、コーヒーの匂いがした。私はその匂いが大嫌いだ。大人が大嫌いだから。大人になりたくないから。苦い味に麻痺しているみたいで。苦いと知りながら麻痺しているみたいで。それはコーヒーだけでなく。
私は大人の言うことを聞いた。小さな頃から素直に従っていた。大人たちからしたら、言うことを聞く都合のいい子供だったのだろう。それは中学生になっても変わらず、大人と子供に挟まれた何者でもない、人間なのかも分からない、道具のような機会のような誰かの者になっていた。
あれから何年が経っただろうか。思い出したくもないが、私は、今、コーヒーが好きだ。これは麻痺なのかも知れない。けれど知らないふりを続けるのだ。
「コーヒー」
2 notes
·
View notes
Text
祈りが届く夜
純粋にお祭りを楽しみ、幸せを願う人の中で

残暑の夜、この町では無数に心願成就の赤い提燈を灯し、にぎやかなお祭りが行なわれる。
子供の頃からこの町に住む私は、いつもこの日は浴衣を着てお祭りをまわる。昔は両親と、そのうち友人と、今は彼氏と。
遠方からの人も混じるお祭りはかなり混雑するので、はぐれないように必死になる。駅前から神社までの道にも警備員が入るほど、今夜の町はざわめいていた。
隣町の高校で知り合った、初めての彼氏である智行は、私と駅で合流して、「浴衣エロいな」とか言って私をむすっとさせる。笑って「かわいいよ」と言い直したシャツとジーンズの智行を私は見上げて、「智行は甚平着ないの?」と首をかたむけた。
「持ってないし」
「来年着てよ」
「それは、来年も別れてないということでいいんですかね」
「え……わ、別れてると思うの?」
私が不安をあらわにして智行の服をつかむと、智行は笑って、「俺が振られてなきゃ続いてるだろ」とアップにかんざしをさした頭を、丁重にぽんぽんしてくれる。私は智行を見て、その手を取るときゅっとつかんだ。
「智行とはずっと一緒にいたい」
「じゃ、大丈夫だろ。告ったのは俺だぞ」
「でも、私も二年になって同じクラスになってから、智行がずっと好きだったし。落とせそうだったから、告白し──」
智行がつないだ手に力をこめたから、立ち止まった。その隙に、唇にキスをされた。
びっくりしてまばたくと、「千波はその卑屈な��こを直しなさい」と言われた。私は智行の瞳を見つめて、何とも返せずに素直にうなずく。
「よし」と智行は私の手を引いて再び歩き出した。
「智行」
「んー」
「私、小学生のときに、このお祭りで両親とはぐれたことがあるの」
「マジか。大丈夫だったのか」
「知らないおにいさんとお祭りまわった」
「は⁉ 何だよそれ、警察沙汰?」
「ううん。普通におとうさんとおかあさんに保護されたけど、家でめちゃくちゃしかられた」
「おにいさんをしかれよ」
「悪かったのは、ついていった私だからって。何か、その頃から、悪いことが起きたら原因は私じゃないかって思うくせがあるの」
智行は私を見下ろして、「千波はいい子だよ」と言った。私はこくんとして、智行の肩にもたれた。夜風は涼しいけど、伝わりあう体温はまだ熱い。
前方に目をやると、あふれそうに提燈がつるされた上り階段があって、その先にもたくさん赤提燈が並んでいる。「すげえ」と智行は子供みたいな笑顔を向けてきて、でも駆け出す前に私に引っ張られて足を止める。
「ちゃんとここで神様に挨拶したら、お願いが叶うんだよ」
神社への階段、提燈の光が届かない入口のかたわらに、子供の図工の作品のような案山子が静かに何人か立っている。この案山子には、ライトアップも何もなく、たいていの人は見向きもせずに階段をのぼって、喧騒に混じっていく。
「これ、神様なのか?」
「そう。ほんとに叶うから」
「ふうん。じゃあ、千波と結婚できますように!」
「ここでそれを、大きな声で言わなくてもいいんだけど」
「もう言っちゃってから言うなよ」
「普通に、『今日はお邪魔します』って挨拶するの」
私はそう言って、その案山子を見つめた。
そう、このお祭りに来たら、この神様に「お邪魔します」と挨拶して。帰るときは、「ありがとうございました」とお辞儀する。そうして、きちんと神社で託した願いを預けると、神様はそれを叶えてくれる。
あの人もそうだった。あの人が私に教えてくれた。
私は七歳で、小学校に上がって一年も経っていなかった。右手にいちごのかき氷、左手に大きな綿飴、両手がふさがって「はぐれちゃダメだよ」と両親に何度もお祭りの人混みの中で言われていたのに、ちょっと立ち止まって顔を埋めるように綿飴を食べた隙に、おとうさんとおかあさんの背中を見失ってしまった。
焦ってきょろきょろして、駆け出そうとしたけど、慣れない浴衣と下駄でつまずきそうになった。「わっ」と声を上げて地面に崩れかけて、誰かが肩をつかんでそれを止めてくれた。
私は慌てて振り返り、そこにいた高校生ぐらいのおにいさんに、急いで頭を下げた。
「あ、えと、すみません。ありがとう」
たどたどしい口調で言うと、おにいさんはたくさんの赤提燈の明かりの中で微笑んで、首を横に振った。
「おとうさんとおかあさんは?」
「あっ、い、い���くなっちゃって。探してて」
「はぐれたの?」
私はうなずいて、転びかけてこぼれそうになっていたかき氷を少し食べる。
「ひとりで探せる?」
私は暖色に彩られたあたりを見まわして、首を横に振った。振ってから、どうしよう、と瞳が滲んできた。このまま、おとうさんとおかあさんが見つからなくてひとりになってしまったら。
おにいさんは腰をかがめて、私の手から綿飴を取ると代わりに手をつないだ。
「一緒に探してあげるよ。ひとりだと危ないからね」
「いいの?」
「うん。おとうさんとおかあさん、どっちに行ったかは分かる?」
「たぶん、まっすぐ」
「境内のほうかな。足元、気をつけて」
私はうなずいて、おにいさんの手をつかみ、たまに甘いかき氷を食べながら、人混みの中を歩きはじめた。
赤い光が高く、永遠のようにいくつもいくつも並び、それで楽しげな夜店が浮かび上がっている。金魚すくいや水風船、おいしそうな匂いがあふれてくるベビーカステラや、宝石のようないちご飴やりんご飴。笑い声や叫び声がはじけて、みんなはしゃいで、お祭りを楽しんでいる。
「今日は、何か願い事はあるの?」
ふとおにいさんが問いかけてきて、「え」と私は顔を仰がせて、まばたきをする。
「お願い」
「このお祭りは、神様に願い事を伝えるお祭りなんだよ。たくさん、提燈あるでしょ」
「うん」
「そのひとつひとつに、願いが込められてるんだ」
「そうなんだ。知らなかった」
「ふふ。神様も大変だよね。こんなにお願いされて」
おにいさんは、まばゆく灯っている提燈を見やった。その横顔がどこか哀しそうに見えて、私は口を開いた。
「おにいさんは?」
「え、僕?」
「おにいさんも、お願いがあるから来たの?」
「ああ、……うん。そうだね」
「どんなお願い?」
「うーん……いろいろあるけど、子供が欲しいかなあ」
「赤ちゃん? 結婚してるの?」
おにいさんは微笑んでそれ以上言わず、「ひと口もらっていい?」と綿飴をしめした。私がうなずくと、おにいさんは綿飴を食べる。「甘い」とおにいさんは咲ってから、不意にうつむいた。
「僕のお願いは、醜いのかもしれない」
「えっ」
「こんなに提燈があって、それだけ人の願い事があって。綺麗なお願いもあるよね。でも、醜い願いもあると思うんだ」
「……みにくい」
「純粋にお祭りを楽しんで、幸せを願ってる人たちの中で、僕はたぶんすごく汚い」
「おにいさん、優しいよ? 一緒に、私のおとうさんとおかあさん探してくれてるよ」
私がそう言って、つないだ手を引っ張ると、おにいさんは泣きそうな顔をして、それでもうなずいた。私は考えて、「かき氷も食べていいよ」とさしだした。「ありがとう」とおにいさんは涙が混じった声で言って、懸命に私に微笑した。
騒がしい混雑の中で、おとうさんとおかあさんはなかなか見つからなかった。私がつまらない想いをしないよう、おにいさんは少しお金を出してくれて、食べ物を買ってくれたり遊びに混じらせたりしてくれた。
私が下駄の鼻緒がちょっと痛いのを言うと、おにいさんは腕時計を見て、「僕も帰る時間だし、出口で座って待ってたほうがいいかな」とにぎやかな露店の通りを抜け、ゴミを捨てて階段を降りていった。
提燈が途切れた暗がりで、来るときには両親とはしゃいで���て気づかなかった案山子が、階段のかたわらに立っているのに気づいた。暗闇の中で不気味に見えて、おにいさんの手をぎゅっとつかむと、「この案山子には、神様が宿ってるんだよ」とおにいさんは私の頭を安んじてくれた。
「かみさま」
「このお祭りに来たときには、この案山子に『お邪魔します』って挨拶するんだ。そして、帰るときは『楽しかったです、ありがとうございました』ってお礼を言う。そしたら、願い事を叶えてもらえるんだ」
「私、来るとき挨拶しなかった」
「ふふ、来年からね」
おにいさんが咲ったときだった。みんなお祭りに吸いこまれて、今は人がまばらの道の中から、「橋元っ」と声を上げながらこちらに駆け寄ってくる人がいた。おにいさんははっと振り返って、「湯原」とつぶやいた。
おにいさんが私の手を離したのと同時に、その人がおにいさんにぶつかってそのまま抱きしめた。
「ごめん、家抜け出せなくて」
「ううん。来ないかと思ったけど」
「二十一時には帰るって言ってたから、焦って来た」
「そっか。来てくれて嬉しい」
「もう、一緒に見てまわれないよな」
「そう、だね。……いや、湯原が来てくれたなら」
「無理すんなって。また来年──」
「湯原と一緒に、願掛けたいから。来年にはもうこんな町出てて、一緒に暮らしてて、家族になるって」
「……橋元」
「ほんとに……ごめん。僕が、女じゃなくてごめん。もし湯原の子供とか作ってあげられるなら、こんな──」
「バカ。いいんだ、そんなもう気にしないって決めただろ」
私は、ふたりのおにいさんが抱きしめあうのを見つめた。
そのとき、「千波っ」と呼ばれてはたと階段をかえりみた。おかあさんが階段を駆け降りてきていた。おにいさんたちも私を見て、私は一緒にお祭りを見てくれたおにいさんに何か言おうとした。でも、すぐさまおかあさんに乱暴に手首をつかまれ、引きずるように階段をのぼる。
私は、なおもおにいさんを見た。好きな人の腕の中から、おにいさんも私を見上げてきた。
子供が欲しい。女じゃなくてごめん。子供を作ってあげられるなら。
ああ、と思った。だから、おにいさんは自分の願いを「醜い」なんて言ったのか。
でも、私はそう思わないよ。せめてそう言いたかった。おにいさんがその人を好きなのは、すごく分かったから。そして、好きな人と子供を持ちたいというのは、ぜんぜん普通で、とても綺麗な願い事だよ。
「ほんとに、あんたは何してるのっ」
階段をのぼって、また赤提燈がふわふわ浮かぶ中に戻されると、おかあさんは軽く私の頬をはたい��。
「よりによって、あんな気持ち悪いうわさのある子たちといるなんて」
その言い草に私は驚いて、おかあさんを見上げたけど、提燈の逆光でその顔は見えなかった。
「ほんとに嫌、うわさ通りなのね。男の子同士で抱きあってたわ」
「まったく……千波、何でおとうさんから離れたんだ。はぐれるなって言っただろう」
��もう何も買ってあげませんからね。おとうさんの手をちゃんとつかんでなさい」
「千波、その男に何もされてないよな?」
「う、うん──」
すごく優しかったよ、と続けたかったのに、それは聞かずにおとうさんは息をつく。やっぱり、提燈の逆光で顔は見えない。
「ああいう輩には、いい加減この町を出ていってほしいな。気分が悪い」
「ほんとだわ。見かけるだけで嫌になるわね」
何で。何で何で何で。
��にいさん、優しかったのに。私のこと、心配してくれたのに。あの男の人が、大好きなだけなのに。
どうして、おとうさんもおかあさんもひどいことを言うの? うわさってことは、みんなおとうさんたちみたいに、おにいさんたちをひどく言ってるの? あのふたりは、ただの恋人同士なんじゃないの? 一緒にいたいだけなのに、そんなふうに悪く言われているの?
次の春、おにいさんと男の人は、一緒に高校を卒業して一緒に町を出ていった。ふたりはお盆もお正月も里帰りなんてしなかったけど、私が中学生になった夏、一度帰ってきたとうわさになった。
孤児の子を養子として迎えた報告だったそうだ。でもふたりの家族は誰もそれを喜ばないどころか、受け入れることもしなかったらしい。ふたりとその子は、町に泊まることなく、平穏に暮らせているのだろう場所へ帰っていった。
……よかった。子供持てたんだね、おにいさん。お願い、叶ったんだね。
それを言いたかったけど、結局伝えられなかった。
「──おっ、射的だぜ。やろうぜ、射的」
「いや、小学生しかやってないよ?」
「景品的には、さっき通った輪投げやりたいんだよ。まだこらえてるんだよ」
「輪投げ……」
「何か欲しい景品あるか? 狙ってやるぞ」
智行は財布から出した三百円をおじさんに渡して、代わりに射的銃を受け取っている。
本当に、小学生の男の子しかいないのだけど。その保護者の人に、何だか智行は生温かく見られているのだけど。
恥ずかしい、と思いつつも、私は並ぶ景品を覗きこむ。一応見渡してから、私は智行に耳打ちした。
「智行」
「おう」
「私も、結婚がいいな」
「えっ」
「今夜、ここでのお願い」
智行は私を見た。私は照れながら咲った。「よし」と智行も笑顔になる。
「じゃあ、あの指輪でも撃ち落とすか」
私たちは思わず咲いあって、「もっと上か」とか「少し右」とか一緒に照準を狙い、それが小学生より真剣なので、店番のおじさんにちょっと苦笑される。
「もっとこう持ったほうがいいよ」と小学生たちにアドバイスまでされはじめて、智行はそれで銃を持ち直したりして、授業中よりまじめなその顔に私は微笑んでしまう。
境内まで続く提燈が、暖かい光を灯して無数に並んでいる。その提燈のひとつひとつに、願いが込められている。
それはどこまでも綺麗な祈りしかないようで。
あまりにも貪るように願って醜い気もして。
幻想的に揺れるあの赤い光は、どんな願いを聞き届けているのだろう。
家族になりたい。階段の下の陰にたたずむ神様は、おにいさんのあの願いを叶えてくれた。そして今夜も、明るくにぎやかなお祭りから聴こえてくる願い事に静かに耳を澄ましている。だから私も、このお祭りで神様に祈りたい。
この人と、いつまでも一緒にいられますように。
それが私の祈り。両親に縛られ、自分の気持ちを言えない私が、初めて強く持った望み。
どうか届いて、私にその光のような未来を。好きな人と家族になれる幸せを。
提燈の光が、瞳の中に煌々と降りしきる。昔から変わらないその優しい明かりの��にいると、願い事は確かに神様に届いた気がした。
FIN
4 notes
·
View notes
Text
猫と夢
短歌連作 猫と夢
音楽も甘いおかしも取らないでひそかな季節の体脂肪がある
かわいい夢を昼猫が見る窓辺には三百六十五日の舟が行く
悪戯ときみが結んだ怠惰とか砂漠に浮かぶ月を眺めている
車椅子のぎこぎこを押させてはゆっくりでいいと私は言うだろか
もし男だったら航空パスポート手に持ち日がな君を忘れる
1 note
·
View note
Text
9/22開催の文学フリマ札幌9に硯水堂分室として青海波がソロ参加します!
お久しぶりです! 今回のイベント参加は9/22(日)開催の文学フリマ札幌9です~! 青海波のみのソロ参加、あららぎさんはいません&あららぎさんの本『鉱物異装』『天然石異装』はありませんのでご注意ください🙏




スペースを詩歌で取ったのに、色々、ほんと色々ありまして新刊はなぜか短編小説になりました!計画性がない!!


既刊2冊とグッズも持っていきます! お品書きにないですが、しおりとステッカーもあるよ💪

【文学フリマ札幌9 開催概要】 🕙9/22(日) 11:00〜16:00開催 📍札幌コンベンションセンター 大ホール ✅入場無料✨ 📘文学フリマとは?→ https://bunfree.net/attend/ 📕イベント詳細→ https://bunfree.net/event/sapporo09/
青海波はじめてのソロ参加、基本びびってぷるぷるしてると思う🥺 ご都合良ければぜひ来てくださいましね~!
1 note
·
View note