#日本の食文化を一同に取り揃えています
Explore tagged Tumblr posts
Quote
住んだと言っても出張でキッチン付きホテルに長期滞在しただけなのでアパートを借りたとかそういう類ではないけども。雑感を書きなぐる。 ■生活しやすいか 海外では生活しやすい部類ではないだろうか。 普通にスーパーはあって物は買えるし。良いところはウォルマートやターゲットなどのアメリカでデパートと称されているものは食料から家電、家具、服、カー用品、薬など ほぼ全部がひとつの店舗に揃ってて買えるところ。買い物はしごする必要がない。 品揃えは食品専門スーパーのほうが当然いいけど。 あと物価がそもそも高いのは仕方ないね。 米や醤油などは日系スーパーにいけばあるが、ちょっと良い食料品店に行くだけでも買える。 米は当然カリフォルニア米だけど別に悪くない。そのまま米に何も乗せずに食べるのはちと難しいかもだけど。 家は…一般的なアパートも見せてもらったが泊まっていたホテルとあまり変わらないかった。 ある程度の価格帯のアパート・ホテルなら必ず食洗器がついているのでシンクが小さい。 洗浄力はバカにしていたがちゃんと汚れが落ちている。水をじゃんじゃん使ってるんだろうたぶん。 トイレの便座は冷たい。まあしゃあない。 バスタブもない。たまにある物件もあるが若干珍しい。 外食 高い。とにかく高いけどステーキハウスはアホみたいに厚い肉が出てくるし そのへんのハンバーガーショップのハンバーガーは美味しい。ただどこも肉の味orソースの味しかしない。 でも肉そのものが美味しいからよし。 ただ半年もそんなもの食べてたら飽きるから寿司とかでも食べようと思うとあきれるほど高い。 日本人がいる寿司屋で高いならまだ納得できるが米人しかいない寿司屋で死ぬほど固いシャリの寿司を出されて$50はかなりガッカリした。 ちなみにラーメンの店もよくあるがスープがぬるくてガッカリする。 メキシコ人のやってるフードトラックで食べるタコスが一番味と値段のつり合いがいいと感じた。 タコスは帰国してからも時々食べたくなる。 ■意外によかったところ トイレ問題。公衆トイレは少ないがスーパーなどの店舗のトイレはだいたいほとんどの地域でキレイで問題なかった。 田舎のガソリンスタンドのトイレは汚かったり、使うときに施錠されているからカギを借りて返すなど面倒だった。 特によかったところはほぼ必ず手洗い場にペーパータオルと石鹸があること。 ハンカチがない国なので必須ではあるが日本でもこれは真似してほしいところ・・・ 野菜や肉類 安くはないがちゃんとしたスーパーなら洗浄済みでそのまま使える野菜が売られているので料理は楽。 肉類は例えばベーコンなら何もしていないプレーンなものからスモーク、メープルと種類豊富。 ソーセージ類やチーズもそう。 反面魚はだいたいサーモンの冷凍ばかりみた覚え。 道路事情 当然だが車がないと生活できないのでレンタカーを借りて走った。半年で1万キロくらい走り日本にいたころよりも運転した。 道路自体はダウンタウンでない限りわかりやすく馴染めるはず。 正直日本の道路よりも快適。チャリも歩行者もほぼゼロで運転マナーも比較的良い。時々バカみたいに飛ばしているのは見るけど急いでる奴は急がせておけばいいので。 別に英語出来なくても生活するくらいなら無問題に近い。だって不法移民だってあいつら英語しゃべれないし世の中が英語出来ない奴でも生活できるようになっている国だから。 追記 サンフランシスコ、ロサンゼルス、ラスベガス、シカゴ、インディアナポリス、ニューヨーク、そのほかマイナー地域含めて15州20地域くらい転々とした。 正直しんどかったけどもいろんなアメリカ地域を見ることができてラッキーだったと思う(会社の金だし)。 そこで思ったのは「アメリカはアメリカ」だということ。 過去に趣味で日本一周をしたので日本の大体の地域はいったつもりだが、各地域、各県で方言や文化を含めて違う部分はたくさんあるけど アメリカに関しては大雑把に東西南北の地域のクセ(英語だったり料理の味付けだったり)が若干あるだけで別に方言というような方言もなく ※スマン、中南部は行ってないんだ……一番南でアラバマのバーミンガム。そこでは老人としか喋ってないから老人の訛りなのか南部系かわからなかった… その地域の名物料理って言ってもシカゴピザみたいなパンみたいなピザだったりニューヨークビザみたいに薄くてデカいやつだったり。そんなに変わらない。 ちょっと面白かったのはサンフランシスコで仕事をしていた時は金曜日にそもそも来ない奴がいて(サーフィンでもしてるのか知らないが)、 ノースカロライナで仕事をしていた時は一応金曜日の朝に休む連絡はあったし、午後から休むわ!って言って帰るやつもいた。 一応東海岸側のアメリカ人のほうが真面目らしい・・・。 政治に関して書くと(丁度去年の大統領選の時期にいたので)、あまり同僚から話を聞くことは出来なかったが(タブーに近いんで) 住宅地にいくと家の前にトランプ支持!かハリス支持!のプラカードを刺している家をよく見た。たぶんストビューでも見ることができると思う。 サンフランシスコやロサンゼルスあたりのもともとハリス支持の地域と比較的内陸側のトランプ支持の地域でハッキリと支持層が分かれているのが家の前を見てわかった。 綺麗な整備されている住宅街はハリスのプラカード、田舎の家の前にはトランプみたいな。 車にもステッカーでどちらかを貼っているのを見た。白髭蓄えた爺さんが運転しているデカいアメ車のトラックにVOTE!TRUMP!のステッカーが貼って会ったり。 ちなみに田舎の観光地のお土産屋に行くとトランプ支持アイテム、帽子やTシャツなどのどこで買えるんだそれ!?って思うものが買える。 さらには「トランプショップ」というトランプグッズ専門店もある。アパレルやステッカーだけではなく調味料の瓶にトランプの写真が使われてたりもうやりたい放題だった。 政治がエンタメすぎる。 さらに思い出追記 リカーショップに行ったら「どこから来たの?」「日本だよ」って会話から「海外のコインを集めてるんだ。もしよかったら貰えないか?」と言われその時はなかったから次行った時に小銭を渡した。 新500円玉と50円玉が食いつきよくてAmazing!って言ってたな。 会計のときビール2つオマケしてくれた。 同僚に勧められたヨセミテ国立公園ってところに行ってみたら、本当にただ自然があるだけの何もないところなのになんだか感動したのは覚えてる。夜になって車から降りたときの星空が忘れられない。本当に天然のプラネタリウムだった。 アメリカの森の中で時々1本だけ、たまには複数本黒焦げになった木があるのは雷が落ちて焼け焦げた木だと聞いた。 カリフォルニアの山火事が日本でもニュースになってたけどアレはてっきりキャンプとか釣りに来てた人の火の不始末だと思ったら雷落ちて燃え広がったものだとわかった時の自然の凄さたるや。 日本からアメリカに日本車を持って行く人がいることは知っていたけどたまたま駐車場で見かけてドライバーと話をした。 車検ステッカーや車庫証明のステッカーもついていて「日本から持ってきた証拠だよ!ところでこのステッカーってとういう意味?」と聞かれ返答に困った……車庫証明はパーキングパーミットでいいと思うけど車検ステッカーの数字の意味。和暦はどう英語で表現すればいいのか未だにわからない。 【さらに追記】 こんなに沢山ブコメやらなんやらつくの初めてでびっくり。長い駄文を読んでくれた人がいたことに感謝です。 ・医療について 実は一度病院にかかった。皮膚科、眼科などの専門医の予約は基本的に取れない(1,2ヶ月待ち)らしく、アージェントケアというとりあえず何でも診てくれる医者のクリニック?に行ってから、治らなければ専門医に行ってくれと言われた。幸い治ったので助かった……。会社で保険に入れてもらっていてそれで対応したので薬代以外の手出しはなかったが薬代で$40ほどした。日本だとジェネリック使って1000円もしないけど。これが全て自腹だとかなり大変…。 ・大麻について 都市の治安が悪そうなところ、あとニューヨークの公園ではよく臭った。 俺は「腐ったビールの臭い」のように感じた。臭いは強烈で臭うエリアを車で通りがかるだけで車のエアコンから侵入して臭ってくる。本当に勘弁してほしい。 そして日本に帰ってきてからもたまに都内を歩くとどこからか臭ってきて「あー大麻やってるのいるな」とわかる。アメリカほど強い臭いではないけど ・タバコ事情 タバコは高い。行ったところではケンタッキー州が安くてマルボロが$7くらい。それがニューヨークだと$15まで跳ね上がる。 高いのでアメリカ人はVAPEをよく吸っている。あとニコチンの入った紙?ガム?のようなものとか。 建物の中は完全に禁煙(カジノ以外)なのでホテルも喫煙室というものがそもそも存在しない。全て禁煙。 携帯灰皿文化がないのか吸い殻はみんなポイ捨てしてる。道路は吸い殻だらけ。 メンソールタバコは州によって禁止、カリフォルニアが禁止のはず。 そもそもアメリカ銘柄のメンソールは全体的にメンソール感が薄いので日本のマルボロのアイスブラストのようなものは存在しない。 ・テレビ事情 日本のような民放がない?らしくケーブルテレビを契約しないと番組は見れない。BBCみたいなニュースだけは契約しないでも見れるんだっけな? ホテルなのでケーブルテレビが契約されていたが、日本で言うならスカパーの専門チャンネルが沢山あって見放題のイメージ。 一度映画チャンネルでターミネーター2からのミッションインポッシブルがCMなしで始まって夜更かししたことがある。 やはりテレビ離れはあるみたいで若い人はネットフリックスを契約してケーブルテレビは契約しないらしい。
半年ほどアメリカに住んだ感想
15 notes
·
View notes
Text
2025年7月8日(火)

今日から、Amazonプライムデー先行セールが始まった。一応、欲しいものリストは作成していたが、まずは痛みが激しくなったリュックの買い換えと夏用パンツを注文した。それぞれ36%、32%の値引だから満足出来る買物である。とは言え、YouTubeの色んなチャンネルから発信される情報に心を揺らされ、結局終日amazonサイトを渉猟する一日となったのだ。

2時30分起床。
amazonプライムデー先行セールで、リュックとパンツを注文する。
昨日の日誌を書いて、二度寝する。
5時50分起床、洗濯開始。

朝食を頂く。
洗濯物を干す。
珈琲を淹れる。
可燃ゴミ、30L*1&45L*1。
7時40分、彼女が自転車で出勤、訪問1件。

9時、コレモ七条店で買物、納豆摂取強化策として、朝はひきわり納豆、夜は粒納豆をいただくことにする。
酢タマネギ仕込む。
YouTube渉猟、プライムデー関連の情報が多い。
11時、仕事を終えてから買い物した彼女が帰宅する。ワンバンクのペアカードを利用しているので、連絡なくても買い物したことが通知されるのでよくわかる。

4人揃ってのランチは2色スパゲッティ、ラタトイユとナポリタン、同じような色になってしまった。
14時20分、彼女は知人に会うために自転車で外出。
彼女に頼まれたものを、アマゾンに発注する。
キュウリのしょうゆ漬け仕込む。

シミズ薬局で買い物、クーポン利用で黒ラベルを買うと、また同じクーポンが発行された。
早めに夕飯準備。

厚切り豚ロースの揚げ焼きに失敗、衣が剥がれてしまった。
平日は、日本酒をやめてスコッチのハイボールにすることにして、試しに作ってみた。どうせなら、大きな氷が欲しい。
早めに切り上げて、布団に横になってAirPodsで桂米朝聴きながらの読書。
片付け、入浴、体重は2日で1,500g減。

歩数は届かないが、なんとか3つのリング完成。
5 notes
·
View notes
Text
★2024年読書感想まとめ
2024年に読んでおもしろかった本の感想集です。寝て起きると昨日のすべてを忘れてる……っつ��繰り返しで日々一切が過ぎていくので、一年の記録をひとつにまとめとくのもいいかなと。以下ざっくばらんに順不同で。ちなみにNot 新刊、ほんとにただ読んだものの感想です。
◆◆小説◆◆
●アンナ・カヴァン『氷』(山田和子訳・ちくま文庫) 巨大な”氷”の進行によって全世界が滅亡の危機にさらされるなか、男はヒロインたる”少女”をどこまでも追い求める……。もっとゴリッゴリにスタイルに凝った幻想文学かと思って足踏みしてたのですが、こんなに動き動きの小説とは。意外なほど読みやすかったです。唐突に主人公の夢想(?)が挿入される語り口も最初は面食らったけどすぐに慣れたし。内容はウーン、暴力まみれの病みに病んだ恋愛小説という感じ? 構成の一貫性とかは疑問だったりしたんだけどそのへんはどうでもよく。後半尻上がりに面白くなっていくし色々吹っ飛ばす魅力があってかなり好きでした。 それと解説に書いてあった「スリップストリーム文学」というのがすなわち自分の読みたい小説群だなーという嬉しい発見もあり。つってもジャンル横断的な定義だから、該当するものを自分で探すのはムズいけどね。
●スタニスワフ・レム『惑星ソラリス』(沼野充義訳・ハヤカワ文庫) 何年も謎に包まれたままの海洋惑星に降り立った主人公が遭遇する怪現象の正体とは?……っていう超有名なSF。「実はこの海は生き物なんじゃね?」がオチだったらどうしよう……と思ってたけど杞憂、それは出発点に過ぎませんでした。途中に挟まる惑星ソラリスの(仮想)探険史の部分がすごく面白い。あとはこの小説のまとめ方はちょっと神がかってると思う……。自分はSFは全然明るくなく、ちょっと異様な感触みたいなものを求めてたまーに手に取るぐらいなのですが、その点この本はほんとにセンス・オブ・ワンダーを味わわせてくれて良かった……。SFオールタイムベスト1とかになるのもむべなるかなぁと。
●庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』(新潮文庫) 東大紛争終息直後の1969年を舞台に、あれこれ思い悩む男子高校生の一日を描いた中編。自意識過剰気味の饒舌な一人称文体が特徴で、すごくユーモラスだけど主人公がかなりナヨナヨした人物にも��える……。でもその中から、外界の強烈な変化に対してありのままで居られない精神の揺れみたいなものが浮かび上がってくるところがおもしろくて、確かに青春小説の名作かも……と思いました。 リアルタイムにはどうだったか知らんけど、今の眼で見るといわゆる”1968年”以降の状況とか、70年代カウンターカルチャー的な空気の”乱暴さ”に対する、一見弱々しいけど切実な返歌って感じもしました。 もっとも読み終えてから、この小説をあえて政治的な色で塗るならいわゆる”保守反動”的な感性に分類されるのかなぁとかはちょっと思ったけど。しかし、リベラルにあらざれば人にあらずみたいな価値観こそ断然間違ってるしなぁなどと、ひとりで勝手に問答したりもしました(笑)。それに現実的にはそんな二分法で単純に分けられるもんでもないだろうし。なんとなく「その時代の作品」という感じなのかと思ってたけど、今読んでも全然おもしろかったです。
●フランツ・カフカ『審判』(池内紀訳・白水uブックス) 理由も分からないまま突然逮捕された主人公が、裁判の被告の立場にずーーーっと留め置かれるっていうお話。何ひとつ確かでないものに延々振り回され続ける理不尽が、ときに笑っちゃうほど面白く、逆に陰惨すぎるくだりもあったりして、総じて非常に好みでした。バカバカしいけどブラックな不条理ユーモア小説? カフカって自分が漠然と抱いてたイメージよりもずっと大胆で、わりとアホなことをあっけらかんと書いたりもするのねーという発見がありました。このお話には裁判的なものの外枠と手続きのみがあって、そこに「法」はないのでは? というふうに読んでたのですが……。終盤の「大聖堂にて」っていう章が凄かったです。
●スコット・フィツジェラルド『グレート・ギャツビー』(野崎孝訳・新潮文庫) ニューヨーク郊外に暮らすギャツビーという名の大富豪の生き方を、たまたま隣に住んだ青年が垣間見る、みたいなお話。ストーリーそのものはわりとベタだと思うんですけど、それを語る会話パートの書き方の巧さと、ドラマの合間の地の文が醸し出すほどよい叙情性がすばらしい。純粋ゆえの虚飾、虚飾ゆえの純粋さみたいな、テーマの核心部分にもちょっと飛躍があって面白いなーと。この短さの中に、アメリカっていう国の一断面をパチリと切り取ってる感じがするのもまた。ひとこと��言うと絶品でした。英語圏小説のランキング上位に入ってるのもむべなるかなぁと。
●三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫) この人の長編はあんま肌に合わないかも……と思って敬遠してたのですが、初めて好きなものに出会えました。言わずと知れた一発目の代表作。同性にしか欲望を抱けない青年の葛藤を、韜晦まみれの絢爛たる文章で綴った青春小説。個人的には、いわゆる”ふつう”でない自分を露悪的に飾り立てるような自己陶酔を振りまきながら、でもそれは”ふつう”でない自分を守るための防御姿勢にすぎなくて、結局は苦々しい現実と向き合わざるを得ない……みたいな話として受け取りました。読み方合ってるのか分からんけど。前半が下地で、後半がその実践編(あるべきとされる自分との葛藤編)なのかな。特に後半のなんとも言えないみずみずしさとその帰結がよかったです。
●横溝正史『獄門島』(角川文庫) 初・横溝。瀬戸内海の小島で巻き起こる猟奇連続殺人事件に金田一耕介が挑む。事件の過程はわりとふつう……と思いながら読んでいきましたが結局かなりおもしろかったです。振り返ると1から10まで本格ミステリじゃなきゃ成立しないような物語だったなと思って。国内ミステリーベスト1になるのもむべなるかなぁと。
●筒井康隆『敵』(新潮文庫) 折り目正しく”余生”を送っている渡辺儀助の生活風景を描いた老境小説。章題が「朝食」「友人」「物置」などとなっていて、各章ではそのカテゴリーごとに儀助の暮らしが掘り下げられていき、その積み重なりから彼の老境が浮かび上がってくる、みたいな趣向。特に食生活に関する記述が多いのですが、自分がほとんど興味ないのもあって前半は正直重く……。しかし地盤が固まり「役者」が揃ってからの中盤以降がけっこう楽しく、終盤は圧巻! けっきょく御大はすごかった……。 的を射てるかは分からないけど、小説の語り口的にもかなりおもしろいことをやってるような。老主人公の生活が章ごとにあらゆる角度から掘り下げられていきますが、そこで語られてるのは「ここ数年の彼の生活のディティール」っていうフワッとした塊としての時間であって、実は小説内では「敵」関連以外ではほぼ全く時間が流れてないように思います。A→B→……→Zみたいに、出来事同士を順番につないでいくことでドラマを進行させていくのとは全然違う手法で物語を語っていて、しかもそれにかなーり成功しているような。もちろん類例はあるんでしょうけど、個人的にはとても新鮮な小説でした。
★★★総合しますと、いわゆる名作と言われてるもの��て確かによく出来たものが多い……っつうめっちゃくちゃふつうのことを思わされた年でした。というか単純に数を読めてないのよなぁ。
◆◆その他の本◆◆
●『石垣りん詩集』(ハルキ文庫) 石垣りんのテーマは、貧しさ、労働、生活の苦しみ、”女性”性、戦争、戦後の日本、生きること、殺すこと、食べること、それらもろもろに否応なく内在する「ここにあることの残酷さ」みたいなものかなと思いました。そうした感情を、ゴロッとした異物感のある黒いユーモアで表現している詩が自分は好き。婉曲的に表現された切実な慟哭という感じもします。特に「その夜」っていう、入院中の書き手が人生の孤独と疲労を歌う作品が凄かった……。こんなん泣いちゃうよ。 「詩」というジャンルに依然として親しめてないので、定期的に読んでいきたい。
●柳下毅一郎『興行師たちの映画史-エクスプロイテーション・フィルム全史-新装版』(青土社) エクスプロイテーション=「搾取」。リュミエールやメリエスといった黎明期の作り手にとって、映画は緻密に作り込む「作品」ではなく興行のための「見せ物」に過ぎなかった――というところから説き起こして、観客の下世話な関心を狙って作られた早撮り・低予算・儲け第一主義映画の歴史をたどった本です。 取り上げられてるのはエキゾチズム(物珍しい異国の風景)、フェイク・ドキュメンタリー、魔術&奇術、畸形、セックス、特定人種向け映画、画面外ギミック映画などなど。現代の一般的な価値観や、映画=「それ単体で完結した(芸術)作品」みたいに捉えるとどうなのよ? ってものばかりなのですが、あの手この手でお客の関心をかき立て、乏しい小遣いを搾り取ろうとする映像作家たちの商魂たくましい姿が垣間見られる楽しい本でした。 見せ物小屋的映画論というのはある意味もっとも俗悪でいかがわしい映画論だと思うんだけど、確かにそれって実写映画のもっとも本質的な部分ではあるかも、という気がしてしまう……。個人的には、画面外のギミックで客を呼び込んだウィリアム・キャッスルの非・純粋なる邪道映画のパートが特に楽しかったです。一点だけ、エクスプロイテーションという概念設定はちょっと範囲が広すぎるような気はしないでもなかったかなぁ。でもこれを元に、観られるものをちょこちょこ観ていきたい所存。
●氷室冴子『新版 いっぱしの女』(ちくま文庫) 『海がきこえる』などの少女小説で有名な作者が、ふだん思ったことを自由に書き綴ったエッセイ集という感じでしょうか。一見柔らかいけどその実めっちゃ鋭い切り口と、それを表現するしなやか~な筆運びに痺れました。1992年に出た本だけど、新版が出てる通り読み物として全然古びてないと思う。おすすめです。
●『精選女性随筆集 倉橋由美子』(小池真理子選・文春文庫) この方のシニカルさと毒気がもともと好き、というのはあったのですが、とても良かったです。それでも最初のほうはあまりに歯に衣着せぬ攻撃性がなかなか……と思ったりもしたけど、中盤の文学論、特に大江健三郎、坂口安吾、三島由紀夫に触れたエッセイがなんともよくて。”内容はともかく独自の語り口を練り上げた文体作家として大江を読んでる”みたいなことを確か書いてたりして、言ってることが面白い。積んでる小説作品も読も~という気になりました。
●吉田裕『バタイユ 聖なるものから現在へ』(名古屋大学出版会) すんごい時間かかったけどなんとか読めた本。フランスの怪しく魅力的な思想家、ジョルジュ・バタイユの思想を、彼自身の記述を中心に先行テキストや時代背景なども織り交ぜて分析し、一本の流れにまとめた総論本。〈禁止と違反〉とか〈聖なるもの〉とか、彼の提出したテーマが結局面白いというのがひとつと、それらを論じていく手つきの周到さ・丹念さがすごい。特に日記や著書のはしばしの記述から、バタイユが影響を受けた先人の哲学(へーゲル、ニーチェ、マルクスとか)や同時代の思想潮流(シュルレアリスム、コミュニズム、実存主義とか)の痕跡を読み取り、そこから彼自身のテーマの形成過程を立体化していくあたりは本当に息詰まるおもしろさ。重量級の本でしたがめっちゃよかったです。もっとも自分は肝心のバタイユ自身の本を『眼球譚』しか読んでないので、現状この本のイメージしか持ててないというのはあるんだけど。とりあえず『内的体験』と『エロティシズム』だけはどうにか読んでみるつもり。
◆◆マンガ◆◆
●ジョージ秋山『捨てがたき人々』(上下、幻冬舎文庫) いろんな意味で深ーい鬱屈を抱えた狸穴勇介(まみあなーゆうすけ)という青年が、新興宗教の信者である岡辺京子という若い女性と出会ったことで始まる物語。性欲と金銭欲を筆頭に、あらゆる現世の欲望にまみれた救われぬ衆生たちの下世話で深刻な人間絵巻、といった感じでしょうか。ふつうに考えるとまぁそこまではいかんやろ……という境界を軽々と乗り越えてくる常軌を逸した展開がすごい。それと人間っつうのはホントにどうしようもない生き物だね~という気持ちにもさせられます。学生のときに買ったんだけど当時はつまらなくて挫折、自分にとってはあまりに読むのに早すぎたんだな……と今にして思いました。最序盤の伏線とかをきれいに回収し切ってはいないんだけど、この際そのへんはどうでもいいかなと。ここまで徹底的な方向へ流れていくならもう何も言えねえわ……って感じの終盤もすばらしい。 これが2024年に読んだものの中で一番面白かったです。
●小骨トモ『神様お願い』(webアクション)、『それでも天使のままで』(アクションコミックス) 両方とも短編集。子供のころや学生時代のイヤ~~~~~~~な記憶、それもおもに自分の弱さや性欲といった、一番目を向けたくない部分がどんどん脳裏によみがえってくる、えげつないけど得難いマンガでした。10代なんてまだまだ若いし人生これから! っていうのも本当だけど、それと同時に人生自体はとっくの昔に始まってて、けっこう多くのことは取り返しがつかないし人間の根っこの部分は歳食ってもそうそう変わりはしないっていう、しんどすぎるけど(自分にとっては)大切なことを思い出させてくれたところが何ともありがたかった……。お話の展開も総じてすんごいテクニカルな気がします。 それでも新刊の『天使』のほうが、『神様』よりほんのちょっとだけ優しさを感じる部分は多いかしら。
●吉田秋生『カリフォルニア物語』(全4巻、小学館文庫) 自分はおそらく作り手への愛とか感謝の念にはめっぽう乏しいほうで、何でも作品単体で眺めて、あーでもないこーでもない、ワンワンギャンギャン吠え猛ってしまう人間なのですが、吉田秋生だけは例外。何でも好き。丸ごと好き。読めるだけで幸せ。どのへんが琴線に触れてるのか正直自分でも分からないのですが、気になる部分があっても好きがそれを上回ってしまう気持ちというのは幸せだなーと思ったりします。 これは最初の代表作に当たるのかな。ニューヨークを舞台に行き場のない若者たちを描いた群像劇。彼女の描く、イタミやすい少年少女が自分は好き……。舞台はニューヨークなのに題名がこれなのもスマートでイカしてる。 もっともファンみたいに書いたけど、実は『BANANA FISH』と『海街diary』っつう一番大きいふたつをまだ読んでません。買ってはあるんだけどなんかもったいなくて……。でも2025年中には読もうかな。
●高橋しん『最終兵器彼女』(全9巻、ビッグコミックス) 部屋の片隅に長ら~く積んである『セカイ系とは何か』をいよいよ読むべく、『イリヤ』ともども手元に揃えてやっと読了。結果、あらゆる方向に尖りまくった傑作じゃん! と思いました。世界の崩壊に対して主人公2人の恋愛という、圧倒的に超無力なモノを対峙させ、理屈ではなくエモーショナルの奔流として無理矢理! 成立させた名作という感じ。まぁこの2人にほとんど感情移入できないほど自分が歳取っちまってることは悲しみでしたが、いい意味でのぶっ壊れっぷりが面白く。 それと自分はこれを読みながら、たまたま以前読んでいた米澤穂信の某初期長編を思い出したり。世界は刻々と変化しているのに自分たちは無力な青春の中で何もできないでいる、みたいなこの感じって90年代から00年代の日本独自の感覚なんでしょうかね……。ちなみに『イリヤ』はまだ1巻しか倒してませんが読みます。今年中にはきっと読みます。読み切ることになっています。
●梶本レイカ『悪魔を憐れむ歌⑤』 4巻までで連載が打ち切りになってしまったマンガを、作者ご自身が5巻を自費出版して完結させた作品、だと思います。 舞台はさまざまな腐敗に揺れる北海道警察管区。人間の四肢を逆向きに曲げて殺害する、「箱折犯」と呼ばれる過去の猟奇殺人が突如再開され、そこからふたりの男のウロボロスめいた運命の輪がまわり始める……。 出版形態のためかは分からないですけど、最終5巻はこれまで以上に描写のタガが外れてる感じで、それがすごい楽しかったです。1巻の出だしからはこんなとこまでフッ飛んでくる話だとは思わなかった……。それでいて猟奇殺人ミステリーとしてもなるほどーと思うところもあって。この方はすごい前に『コオリオニ』っていうマンガも読んだのですが、主要キャラクターをとつぜん突っ放す感じがこわい。けど面白い。お疲れさまでした。
◆◆補足◆◆
・安部公房もちょろちょろ読んだり。今のところは、異常どころかめっちゃ理知的なアイデア作家という印象なんだけどこれが覆ることがあるやいなや。 ・『めくらやなぎと眠る女』というアニメ映画の予習をするついでに村上春樹の短編もちょこっと。ファンには超怒られそうですが、彼の小説ってパスタ茹でたりジャズを聴いたり昔の恋愛とか人間関係の失敗を感傷的に懐かしんだりといった、ザ・村上春樹なことをやってるときは…………なんだけど、その先で訳分からんことになる話がたまにあってそれがめっちゃ面白かったです。現状読んだものだと「ねじまき鳥と火曜日の女たち」、「UFOが釧路に降りる」、「納屋を焼く」が最高でした。できれば全作読んでみたい。 ・フランク・ハーバートの『デューン』シリーズも2個目まで。SFファンタジーの大家というイメージで読んだらメ��ンで使う語り口(作劇法?)が超・会話劇なのが意外でした。
★★★これを書いている2025年1月現在はドスト先生の『悪霊』を読んでいます。が、全体の十分の一すぎてもまだ若者世代の話に入らないので投げ出しそう……。シニカル成分100%の語り口はけっこう好みなのですが。前に読んだ『罪と罰』と比べても視点が格段にいじわるな気がして、これを書いてたときの作者の精神状態やいかに? 2025年はもうちょい数をこなせたらいいなと思っています。ではー。
4 notes
·
View notes
Photo

AIコーディングツール「Cursor」で記事を書くようにしたら、“考える余裕”ができた 2025.04.30 20:00 author かみやまたくみ
楽すぎる。
いろんなAIツールが登場している昨今、特に評判がいいのが「Cursor(カーソル)」です。AIにコードを書かせまくり、ひたすら楽してプログラム開発しちゃおう、って感じの開発ツールです。エンジニアに大好評で、大企業開発部署への導入がガンガン決まっていたりします。
結論から言うと、「文章を書くのが仕事」という人にもおすすめできます。
自分はエンジニアでも何でもなく、物書きなのですが、あんまりにも目にするので「そんなにすごいの?」と思って触ってみたら、よすぎて手放せなくなってしまいました。
目次
Cursorとは
Cursorを使い始めて何が変わったか?
a. 文章執筆の全工程を効率化できる
b.「書くべきこと」をさっさと決められる
c. 「必要だけど本質的でない作業」で消耗しなくなる
d. 企画・構成に時間を使える
使える機能と、具体的な使い方
1) AIペインを執筆に接続して効率化
2) 資料をすばやく生成&管理。量で戦う
3) しんどい校正・校閲。AIの���を借りて楽をする
「書くのがやめられない」って人には本当におすすめ
同時に検討したほうがいいAIツール
コードを書くなら万能ツール。無限の可能性を秘めている
Cursorとは main CursorはAIコーディングツール、本来的にはプログラムを開発するためのアプリケーションです。特徴は「AIペイン」「エディタ」「ファイル管理」の3つの機能がシームレスに統合されていること。
search 特に「AIペイン」が強力です。UIとしてはChatGPTのようなチャット欄があるという感じなのですが、中身が異なります。昨今話題の「AIエージェント」の一種で、ざっくりとした指示から複合的な処理を行ってくれます。「sample.txtを翻訳して、sample_jp.txtに保存」と指示すれば、翻訳作業とファイルへの保存を両方やってくれる、といった具合。話が早いのです。
file また、文章を書くには多くの資料が必要となりますが、ファイル管理機能が統合されているので、「とっちらかり」が防げます。
Advertisement
本来的にはコードを書くためのツールですが、コードもテキストの一種。「書く」のは同じなので、コードに限定せずとも活用できる、という感じですね。
Cursorを使い始めて何が変わったか? 夢物語のようだし主観的にならざるを得ないので気が引けますが、書ける量は増え、1本1本の質も上がったと思います。
多く書くのがキツいのは、1日に使える「考える脳力」に限界があるからです。限界がきたら頭が考えるのを拒否し始めます。「何を具体的にどう書くか」が決められない=もう書けない、となります。
Cursorはそういう状態になるのを防ぐ──「脳のキャパシティ上限」を上げるツールと言っていいようなところがあります。「頭でやる単純な作業」をAIに任せつつ、自分でも書き進める。比喩ではなく実態的に、専属アシスタントと同時並行で思考・作業をしているので楽だし速いのです。
a. 文章執筆の全工程を効率化できる writing_process Image: かみやまたくみ, Generated with o3 文章執筆はざっくり以下のようなプロセスで進み、AIはどの工程でも活用できます。
1. アイデア収集
2. 企画・構成
3. 素材収集
4. 本文執筆
5. 校正・校閲
6. 公開
Advertisement
アイデア収集・素材収集(下準備)と校正・校閲(後処理)は、AIを使うことで極めて効率的に行なえます。どちらも機械的なところがあり、かつボリュームもあるからです。
企画や構成、本文執筆を任せることももちろん可能です。調べ物をレポート化するとか、個人ブログ用の文章を書かせるとかであれば、企画・構成・資料が揃った段階で全文AI生成もいけます。
ジャンルを絞ったのは、商用や学術的な文章を丸々AIに執筆させるの��厳しい、ということでもあります��本稿はそういった水準を前提としているので、本文の生成については扱いません)。とはいえ、企画・構成や本文のプロトタイプを書かせることはでき、それはかなり重宝します。
余談気味になりましたが、Cursorは常にAIを活用する想定で作られている関係で、AI処理の結果を適用するのがとにかくスムーズです。後ほど、具体的にお見せします。
b.「書くべきこと」をさっさと決められる file どのフェーズでも、そのフェーズに合った資料を用意したり、メモを作って書き出しながらやったほうが先に進みやすいです。昔のメモを見返したときに、新しい企画やいい表現が思い浮かぶ、なんてのはよくある話です。
万博のスイスパビリオンは「食べられるロボット」が見られます 万博のスイスパビリオンは「食べられるロボット」が見られます Sponsored by FDFA, Presence Switzerland Cursorがファイル管理機能を有することは、この点と相性がいいです。気になったニュースの本文とその感想、初めて登山をしたときの日記、インタビュー取材の文字起こし、そういったものが蓄積されていればいるほど、書くことが定まりやすい。
Advertisement
その反面、「あのメモどこだっけ?」となりやすいのですが、Cursorは自然言語でのファイル検索(うろおぼえ検索)も可能です。ファイル管理画面も常時表示できるので、開くのもすぐです。
c. 「必要だけど本質的でない作業」で消耗しなくなる checking 突き詰めれば、書くことが具体的に決まってしまえば、文章はほとんど完成していると言えます。あとは書くだけ。でも、これは理想論に過ぎません。
Advertisement
実際には文章のパーツとなる資料を集めるのはほぼ必須ですし、本文の構成や表現もだいたい悩みます。書き終わったあとは誤りがないかをチェックしなければなりません。
AIはこの理想と現実の差も埋めてくれます。集めた資料の中でどれが重要かは、要約してもらえばすぐに判断できます。本文の推敲も「第三者」の目があると捗ります。誤字脱字チェックのような機械的な作業は得意中の得意です。
d. 企画・構成に時間を使える thinking Image: かみやまたくみ, Generated with o3 AIに作業的な部分をやってもらうことで、「本当に重要な部分を気にしながら進める余裕」を確保しやすくなります。究極的にCursorがよかったのはここです。
Advertisement
文章執筆にあたってもっとも重要なのは、企画・構成です。これらの良し悪しは結果にダイレクトに影響するので、時間をかけられるだけかけるべきです。具体的な作業が始まってからも「当初の企画・構成からズレてきていないか?」は常に意識したほうがよいのですが、やることも多く気づいたらコントロールを外れていた…はよくある話です。
AIを活用したい最大の理由は、「自分は何をするべきなのか?」を考え、それを見失わずに確実に遂行するには「必要だけど本丸ではない作業」で消耗していられないから、です。
使える機能と、具体的な使い方 大枠はそんな感じですが、以下、どうCursorを使っているのかを具体的に紹介します。
1) AIペインを執筆に接続して効率化 search 月額20ドル
Advertisement
こう原稿に書くとします。日本円だといくらかが併記されていたほうが見やすいですよね。ここで「月額20ドル」を選択してCmd/Ctrl+Lとショートカットを入力、AIペインに移動します。
自分:
@Web 2025/04/30時点で約何円ですか?(十の桁で四捨五入)
Cursor:
2025年4月30日時点の77銀行「米ドル/円」仲値は 1 USD = 約 141.2 JPY でした[1]。
したがって 20 ドル × 141.2 = 2,824 円 → 十の位で四捨五入すると **2,830 円** です。
---
[1] 77銀行 為替レート(2025年)
https://www.77bank.co.jp/kawase/usd2025.html
CursorがAI(o4-mini)を用いてネットを検索、回答を生成します。Escを押して執筆中のテキストに戻り、今度はCmd/Ctrl+Kと入力して「プロンプトバー」を呼び出します。
cmd_k 「月額20ドル(約」と入力して決定すると…
月額20ドル(約2,830円)
Advertisement
先ほどの回答を用いて補ってくれます。Cmd/Ctrl+Enterで決定すると先ほど書いた月額20ドルの部分が円換算つきの表現に置換されます。
1. 執筆画面とAIペインはショートカットで自由に行ったり来たりできる(キーボードから手を離さなくていいので効率がいい)
2. AIにWeb検索や推論をさせ、その結果を原稿に合った形で反映してもらえる
「AIペイン」で「コピペなどの手間が圧縮できる」とはこういうことです。ショートカットで執筆画面とAI処理用のUIをシームレスに行ったり来たりできるため、速いし、執筆のリズム感も失われにくいです。
2) 資料(要約・翻訳・レポート)をすばやく生成&管理。量で戦う 書くには資料が必要です。たとえば、本稿を書くにあたっては、Cursorの文書資料に一通り目を通しています。ぜんぶ英語だったので、必要そうな部分は日本語に翻訳してあります。自力でやってたら時間がかかりすぎるので、翻訳作業はAIにやってもらいます。
ja_CmdK_Overview.md
ja_Terminal_CmdK.md
ja_Tab_Overview.md
ja_Tab_vs_GitHub_Copilot.md
ja_Auto-import.md
ja_Advanced_Features.md
ja_Agent_Mode.md
ja_Ask_Mode.md
ja_Chat_Overview.md
ja_Custom_Modes.md
ja_Manual_Mode.md
ja_Tools.md
ja_Keyboard_Shortcuts.md
Advertisement
ざっとリストするとこんな感じで、実際はこの倍以上ありますが、読むのを含めてかかったのは2時間程度です。この例では資料は主に翻訳ですが、要約とソース原文をセットで用いる形も多いです(要約はもちろんAIが担当)。
2_colmun Cursorでは「主要な公式資料と付き合わせて執筆」がとにかくやりやすいです。AIを用いて自分が理解しやすい形式の資料を用意するのがすばやいうえに、それらを複数表示・確認しながら原稿を書き進められるからです。
IMG_3147 実際はこんな感じでワイ��ディスプレイに6カラム(列)表示させて書いています。導入前と比べて、明らかにより正確に書けるようになりました。迷いにくいのもいいです。
Advertisement
膨大な資料は左端に常駐させられる「ファイルツリー」からいつでも開けます。Finderやエクスプローラーをわざわざ開いてダブルクリックして…みたいなことは必要ありません。Cursorだけで多くの作業が完了しやすいです。
やりすぎ感がハイパー。使ってわかったHyperX製品のハイパーすぎるポイント やりすぎ感がハイパー。使ってわかったHyperX製品のハイパーすぎるポイント Sponsored by 日本HP 3) しんどい校正・校閲。AIの力を借りて楽をする 公開直前の文章には2つのチェックが必要です。1つ目が「事実誤認がないか」。全文が事実に即しているのかは、必ず確認する必要があります。もう1つが誤字脱字やタイポがないか。いい文章が書けても、これがあると台無し。ですが、AIを活用すると、こういったチェックも楽になります。
ファクトチェックはかなり煩雑な作業です。Webで関連しそうな事項を検索→内容を読む→自分の記述と相違がないか判断→必要があれば修正、とざっくり見ても4工程必要なうえに、それが確認が必要なカ所分だけ発生します。Webでの裏取りがとにかく重いのですよね。ネットの海からソースとなる情報を引っ張ってくるのがとにかく大変です(Google検索があんま役に立たない)。
ところが昨今、AIがうまいこと必要な情報を引っ張ってこれるようになりました。Cursorで標準で使えるo4-miniなどもそう。使わない手はありません。ファクトチェック時に典拠となるページのURLを付してもらい、必要に応じてダブルチェックもかけられるようにすれば、ハルシネーションがあっても潰しやすくなります。
checking @article.txt の1文1文に対して @Web でファクトチェックを行ってください。2025年4月28日時点で最新の情報と照合してください。感想などの主観を表現している部分は無視して構いません。各文について、以下のフォーマットに沿って結果を回答してください。回答は fact_check.txt に保存してください:
原文n: (冒頭10文字程度のみ記載)
真偽: 真 or 偽
指摘内容: (偽の場合のみ。50文字以内)
根拠URL:
「ネットを探し回る時間」からだいぶ解放されました。
correction 誤字脱字チェックはもっともAIにやらせるべき作業です。どうしても意味を追ってしまう人間は、てにをは(助詞)の脱落なんかを見逃しがちですが、AIはキチキチ指摘してくれます。
@article.txt に誤字脱字・タイポがないかチェックしてください。回答はdiff形式としてください。
Advertisement
※diff形式はテキストファイルの変更点を表示するための形式です。この形式を指定するとAIが「そのままワンボタンで反映できるように」回答してくれやすくなります。実はChatGPTでも使えるテクニック。
「書くのがやめられない」って人には本当におすすめ cursor 資料の収集・整理、細かな部分の推敲と事実確認、誤字脱字チェック���いずれも作業としては必要ですが、書くことがおもしろいのは、「何をどう書けばおもしろいのか?」を考え、没頭しているときです。Cursorは「書く」という行為の本質に今いちばん近づけるツールのひとつだと感じます。
相性がいいのは、自分のようにWebなどで発表する文章(記事・ブログ・小説等々)をコンスタントに書く方・翻訳をされる方・多数の文書資料を並行的に読破する必要がある研究者の方などでしょう。資料含め、扱う文章のボリュームが多い方ほど、活用できるはずです。文章ガチ勢向きともいいます。
ネックになるのは無料ではないことです。AIアプリは料金が高いですが、Cursorもその例に漏れません。
ここまで紹介したような使い方をするにはProプラン以上に入る必要があり、その価格は月額20ドル(2,900円弱・年間契約時)から。OpenAIのo4-miniなど、各社のAIモデルを好みで選んで使えますが、Proだと500 Requestを超えると速度に制限がかかると、快適に使える回数には上限があります(詳しくは公式の説明をご覧ください)。o3などの一部高性能モデルは従量課金制です。アプリケーションそのものはよくできていますが、安いとは言えず、Requestを節約しながら使っていく感じになります。
無課金でも使えますが、AI機能が制限されて「いちばんオイシイ使い方」ができなくなるので、むしろ上級者向きです。
同時に検討したほうがいいAIツール google 対抗馬となるのは、オフィス系AIアプリとAIチャットボット、そして似た機能性の開発ツールです。
Google Workspace
・Googleドキュメント×Geminiで文章執筆が可能
・GmailをAI化でき、Notebook LMが使えるなど、使えるAI機能が多いうえに強力
・月額1600円からと料金も現実的
Microsoft 365 Copilot
・ビジネス標準となっているWord/Excel/PowerPointでAI生成が使えるため、汎用性が極めて高い
・Word/PDFをPowerPoint(プレゼン)に変換できるなど、ずば抜けて強力な機能を有する
・月額約4,500円。強力だが高価なタイプ
ChatGPT
・課金すると使える「o3」は今最強のAIアシスタント。仕事以外にも活用しやすい
・テキスト生成の品質は極めて高い。日本語がめちゃくちゃ上手
・画像生成のクオリティも非常に高い
・チャット形式な関係で、特定の分野でフル活用しようとすると、運用の手間が大きくなる
・月額20ドル(約2,900円)
Visual Studio Code
・Cursorに似た統合開発環境(IDE)。同等のファイル管理機能を備える
・AIエージェントが無料ユーザーでも利用可能なのが最大の特徴
・AI機能を使い倒したい場合の課金も月額10ドル(約1,500円)と敷居が低い
Cursorは「本文をガチガチ���作り込む人向け」という立ち位置になると思います。よりビジネス寄りの使い方もしたい方や、価格感を抑えたい方は上記のサービスと比較してみてください。
コードを書くなら万能ツール。無限の可能性を秘めている 20250430_cursor_re_DSC02217 ちなみに、コードを書くのであれば、Cursorはオフィス��アプリに対抗できる機能性を実現できます。Pythonライブラリを活用すればPDFも処理できるし、音声認識モデルで取材の録音を文字起こししたりもできます。AI画像生成だって実行可能です。プログラムが作れて実行できるとは、そういうことです。
いろいろと敷居が高い部分もありますが、自分はCursorがとても気に入りました。古き良きテキストエディタ的な味わいがありつつも、ゴリゴリにAIが使える。自分の人生で今がいちばん速く、深く書けている印象さえあります。あと、文字がなんか読みやすいのがとても気に入っています。
2週間の無料トライアルが可能なので、気になった方は試してみてください。
さよなら、充電ケーブル。自動巻き取り式フル装備にしたら世界が変わった さよなら、充電ケーブル。自動巻き取り式フル装備にしたら世界が変わった Sponsored by TORRAS Japan Cursorで文章制作する際の基本的な操作方法を @web で調べてまとめてください。回答は how_to_cursor.txt に保存してください
なんてAIペインに打ち込んでみたら、この記事で伝えたかったことが直感的に伝わるんじゃないかと思います。
Source: Cursor, Google Workspace, Microsoft 365 Copilot, Visual Studio Code, ChatGPT
(AIコーディングツール「Cursor」で記事を書くようにしたら、“考える余裕”ができた | ギズモード・ジャパンから)
2 notes
·
View notes
Text
【効果が示されている民間療法】
●ハチミツ
1歳から18歳の小児を対象とし、ハチミツの咳に対する効果を調べた6つの無作為化比較試験(RCT)を解析したシステマティックレビューが紹介されています。
それによると、ハチミツを1回につき2.5-10ml(2-5歳は2.5ml、6-11歳は5ml、12-18歳は10ml)を寝る前に摂取すると、咳の軽減と睡眠の改善に効果を示し、その効果は鎮咳薬であるデキストロメトルファンと同等であったと報告されています。
そのメカニズムですが、粘膜の保護作用、保湿作用、鎮静作用によるもの、という論調が一般的ですが、はっきりとしていない点も多いようです。
ハチミツは、ほとんど副作用がないことが大きなメリットですが、腸管免疫が十分に発達していない1歳未満の乳児に対しては、ボツリヌス感染症のリスクがあるので勧められません。
●亜鉛
17のRCTを解析した��タアナリシスが紹介されています。
それによると、成人の風邪の患者が、発症から24時間以内に、酢酸亜鉛またはグルコン酸亜鉛のトローチを1回4.5㎎から23.7㎎を2時間おきに服用すると、風邪症状を平均1.65日短縮することが示されていますが、小児に対してははっきりとした効果は示されていません。ただ、トローチ製剤は、錠剤やシロップ製剤に比べて味覚の異常や嘔気などの副作用が多いと報告されています。
亜鉛には、免疫細胞の活性化したり、炎症を抑制する働きがあることが報告されていますが、日本人のほとんどは、潜在的に亜鉛欠乏と言われています。日本では、亜鉛サプリが複数販売されていますので、場合によっては、サプリを日頃から有効的に活用してもよいでしょう。しかし、論文にあるように、1回23.7㎎を2時間おきに服用すると、1日の摂取量の上限(40~45mg)をはるかに超えてしまうので、注意が必要です。
【まだ効果がはっきりしない民間療法】
●ヴェポラッブ
日本では、ヴィックスヴェポラップとして販売されています。カンフル、メントール、ユーカリ油が配合されており、首や胸に塗って使用し、その成分を吸入すると、咳や鼻閉を緩和するとされています。
2歳から11歳の小児を対象とした1つのRCTでは、1回につき5-10ml(2-5歳は5ml、6-11歳は10ml)を首や胸に塗ると、何もしない群に比べて、鼻閉(鼻汁を除く)、咳の頻度や強さ、睡眠障害を有意に緩和し、このうち、咳の強さと睡眠障害に対しても、プラセボ(偽薬)群に比べても有意に症状が緩和(睡眠障害は子供だけでなく親も)することが示されていますが、まだ、多くの研究結果を解析するために必要な十分なデータが揃っていません。また、目、鼻、皮膚に対する刺激感が強く、その忍容性には個人差があるようです。
●鼻洗浄
上気道炎の6歳から10歳の小児に対して、生理食塩水(3ml-9ml)を点鼻して症状の変化を調べたRCTでは、鼻汁、鼻閉、咽頭痛などの症状の緩和、鼻炎薬の減量効果が示されていますが、まだ、多くの研究結果を解析するために必要な十分なデータが揃っていません。
●ビタミンC
7つの臨床試験を分析したメタアナリシスでは、ビタミンCの風邪症状に対する有意な治療効果は示されていません。
●加湿器
6つのRCTを分析したメタアナリシスでは、加湿器の風邪症状に対する有意な治療効果は示されていません。
●中医学(中国)の薬草治療
17のRCTを分析したシステマティックレビューでは、中医学の薬草治療の風邪症状に対する有意な治療効果は示されていません。
第167話 新型コロナウイルスに備えるために-風邪に対する民間療法-やまと在宅診療所あゆみ仙台
7 notes
·
View notes
Text
いきなり偉そうなことを書いて各方面から顰蹙を買いそうなんだけど、あえて言う。僕は自分の日記より面白い日記を読んだことがない。これはハッタリでもなんでもなくて、それくらいの気持ちがないと何処の馬の骨とも知れないチャリンコ屋の日記に1,500円や2,000円を出して購入してくれている方々に申し訳が立たない。ただし「自分より」と言うのには注釈が必要。『富士日記』や『ミシェル・レリス日記』みたいな別次元の傑作は対象外として、近年、雨後の筍のように量産されているリトルプレスやZINEを体裁とした日記やエッセイ群を見据えての発言と思って頂きたい。商売としての仕入れはさておき、個人的に興味があったので色々と手を伸ばして読んでみたものの、そのほとんどが「私を褒めて。私を認めて。私に居場所を与えて」というアスカ・ラングレーの咆哮をそのままなぞらえたような内容、若しくは「持たざる者同士でも手を取り合い、心で繋がっていれば大丈夫」的な似非スピリチュアルなマジカル達観思想で構成されているので、正直ゲンナリした。しかもタチの悪いことに、そういうものを書いている人たち、あわよくば商業出版の機を窺っていたりするものだから、出版社や編集者の立場からしたらまさに入れ食い状態。「ビジネス万歳!」という感じでしょう。晴れて書籍化の際には口を揃えて「見つけてくれてありがとう」の大合唱。いやいやいや、ちょっと待って、あんたら結局そこに��きたかっただけやんってなりません?これまでの人生をかけて手にした「生きづらさ」の手綱をそんなにも容易く手放すんかい!と思わずツッコミを入れたくもなる。現世で個人が抱える「生きづらさ」はマジョリティに染まらぬ意思表明と表裏の関係にあった筈なのに、どっこいそうはさせないとばかりにどこからともなく湧いてくる刺客たちの誘惑にそそのかされては、呆気なく自らの意志で握手(悪手)に握手(悪手)を重ねる。ミイラ取りがミイラになるとはまさにこのことだ。以前、僕もある出版社の編集長から「DJ PATSATの日記を当社で出版させてほしい」という誘いを受けたけれど、もちろん丁重にお断りした。僕は自主で作った300冊以上の読者を想定していないし、それより多くの読者に対する責任は負いかねるというような趣旨の言葉を伝えた。そもそもなぜ僕が友人(マノ製作所)の力を借りながらわざわざシルクスクリーンという手間をかけて制作しているのかを理解しようともしない。編集長は口説き文句のひとつとしてECDの『失点・イン・ザ・パーク』を引き合いに出してこられたのだけれど、いま思えばそういう発言自体が安易というか不遜だと思わざるを得ない。結局その方は僕を踏み台にしようとしていただけだったので、負け惜しみでも何でもなく、あのときの誘いに乗らなくて良かったといまも本気でそう思っている。まぁ、これは僕個人の考え方/価値観なので他者に強要するものでもなければ、共感を得たいと思っている訳でもない。逆に彼らも推して知るべしだ。誰もが商業出版に憧憬を抱いている訳ではない。昔��ら煽てられることが好きじゃないし、賑やかで華やかな場面がはっきりと苦手だ。だからと言って消極的に引きこもっているつもりもなく、寧ろ積極的に小さく留まっていたいだけ。かつては各地の井の中の蛙がきちんと自分の領域、結界を守っていたのに、いつしかみんな大海を目指すようになり、やがて井の中は枯渇してしまった。当然、大海で有象無象に紛れた蛙も行き場をなくして窒息する。そのようなことがもう何年も何年も当たり前のように続いている現状に辟易している。そんな自分が小さな店をやり、作品を自主制作して販売するのは必要最低限の大切な関係を自分のそばから手離さないためである。何度も言うているように自営とは紛れもなく自衛のことであり、率先して井の中の蛙であろうとする気概そのものなのだ。自衛のためには少なからず武器も必要で、言うなれば作品は呪いの籠った呪具みたいなもの。そんな危なっかしいものを自分の意識の埒外にある不特定多数のコロニーに好んで攪拌させたりはしない。多数の読者を求め、物書きとして生計を立てたいのなら、最初から出版賞に応募し続ける。だからこそ積年の呪いを各種出版賞にぶつけ続けた結果、見事に芥川賞を射止めた市川沙央さんは本当に凄いし、めちゃくちゃにパンクな人だと思う。不謹慎な言い方に聞こえるかもしれないが、天与呪縛の逆フィジカルギフテッドというか、とにかく尋常ならざる気迫みたいなものを感じた。なぜ彼女がたびたび批判に晒されるのか理解できない。それに佐川恭一さん、初期の頃からゲスの極みとも言える作風を一切変えることなく、次々と商業誌の誌面を飾ってゆく様は痛快そのもの。タラウマラ発行の季刊ZINEに参加してくれた際もダントツにくだらない短編を寄稿してくれて、僕は膝を飛び越えて股間を強く打った。
佐川恭一による抱腹絶倒の掌編「シコティウスの受難」は『FACETIME vol.2』に掲載。

ついでにこれまた長くなるが、かつてジル・ドゥルーズが真摯に打ち鳴らした警鐘を引用する。
文学の危機についていうなら、その責任の一端はジャーナリストにあるだろうと思います。当然ながら、ジャーナリストにも本を書いた人がいる。しかし本を書くとき、ジャーナリストも新聞報道とは違う形式を用いていたわけだし、書く以上は文章化になるのがあたりまえでした。ところがその状況が変わった。本の形式を用いるのは当然自分たちの権利だし、この形式に到達するにはなにも特別な労力をはらう必要はない、そんなふうにジャーナリストが思い込むようになったからです。こうして無媒介的に、しかもみずからの身体を押しつけるかたちで、ジャーナリストが文学を征服した。そこから規格型小説の代表的形態が生まれます。たとえば『植民地のオイディプス』とでも題をつけることができるような、女性を物色したり、父親をもとめたりした体験をもとに書かれたレポーターの旅行記。そしてこの状況があらゆる作家の身にはねかえっていき、作家は自分自身と自分の作品について取材するジャーナリストになりさがる。極端な場合には、作家としてのジャーナリストと批評家としてのジャーナリストのあいだですべてが演じられ、本そのものはこの両者をつなぐ橋渡しにすぎず、ほとんど存在する必要がないものになりさがってしまうのです。本は、本以外のところでくりひろげられた活動や体験や意図や目的の報告にすぎなくなる。つまり本自体がただの記録になってしまうわけです。すると、なんらかの仕事をもっているとか、あるいはただたんに家族がある、親族に病人がいる、職場に嫌な上司がいるというだけで、どんな人でも本を産み出せるような気がしてくるし、このケースに該当する当人も、自分は本を産み出せると思い始める。誰もが家庭や職場で小説をかかえている……。文学に手を染める以上、あらゆる人に特別な探究と修練がもとめられるということを忘れているのです。そして文学には、文学でしか実現できない独自の創造的意図がある、そもそも文学が、文学とはおよそ無縁の活動や意図から直接に生まれた残滓を受けとる必要はないということを忘れているのです。こうして本は「副次化」され、マーケティングの様相を帯びてくる。
ジル・ドゥルーズ『記号と事件 1972-1990年の対話』(河出文庫p262-263)
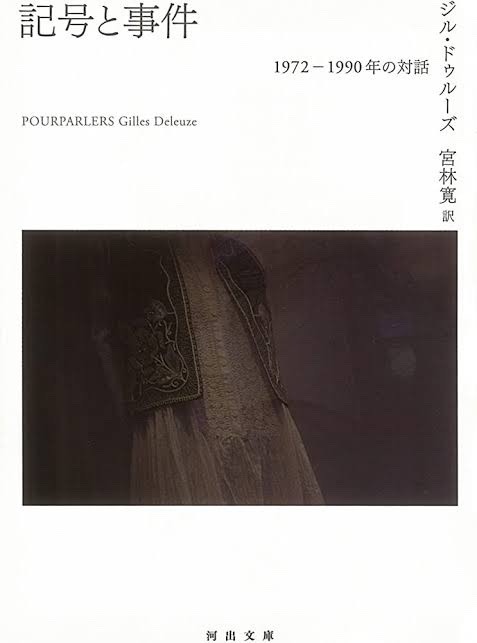
僕は制作の際にはいつも必ずドゥルーズのこの言葉に立ち返っては何度も確認作業を繰り返し、ようやっとリリースにこぎつける。しかしそもそもが作品化を企んでいる時点で自分まだまだやなぁと思うに至る訳で、なんとも一筋縄ではいかない。そういう意味では滝野次郎という人がインスタグラムに投稿している日記のような文章には、はじめから読まれることを意図しているにもかかわらず、本来ならば読まれることを目的とした日記からは真っ先に削除されるような状況ばかりが羅列されていて、なかなかどうして凄まじい。馴染みの飲食店で見つけたお気に入りの女性店員を執拗に観察したり、断酒を誓った直後に朝から晩まで酒浸りであったり、謎の投資で10分間で40万円を失っていたり、銀行口座と手持ちの金を合わせても1,000円に満たなかったり、それでも「俺は俺を信じる」と闇雲に自身を鼓舞していたり、そうかと思えば急に脈絡もなくひたすらに左手のハンドサインを連投していたりと、しっちゃかめっちゃか。比肩しうるは円盤/黒猫から出版された『創作』くらいか。あらゆる規範から逃れるべくして逃れ得た、いま最もスリリングな読み物であることに間違いはないが、同時に、これは断じて文学ではない……とも言い切れない不気味な何かが海の藻屑のように蠢いている。
(すでに何らかの隠喩ではないかと勘ぐったり……)

16 notes
·
View notes
Text
【世代交代】カーナビに「ドラックストアのある交差点を左」って言われた際、目の前にドラッグストアが3店舗見えていた私が、それでもサッポロポテトを選ぶ理由.zip
(PS:下の方にビアゲの役者紹介があります)
西南図書館24周年、おめでとうございます。私は「『いきのこり⚫︎ぼくら』にのせて懐かしいものを紹介しているだけのYouTube shorts 撲滅委員会」で会計をしている、近未来ミイラです。最近こういう動画を目にする機会減ってきたでしょう?あれ、私たちのおかげなんですよ。感謝してくださいね。そして皆さんはくれぐれも過去に囚われて、旅行先にLと書かれたコンタクトレンズだけを持ってくるような真似はしないように気をつけてください。この世にはRも必要です。私は本気です。やってやんよ。
さて、仕事の引き継ぎと通信速度ははやい方がいいだなんて言いますが、ちゃうかで引き継ぐべきものは仕事だけではありません。解散の挨拶、ケミの折り方、大集会室に見回りが来るのが20:00頃と22:00頃だという研究結果。まぁ色々ありますが、中でも私が引き継がねばならないと考えているのが、かの有名な天照大神の自宅に併設されたクラブハウスでDJをした経験があるという、NASUKA A.K.A. たぴおか太郎 さんによるtumblerなのです。
私は、たぴおかDJアゲ太郎が引退する前に、何とかしてこれを継ぎたい。習うより慣れよ。私は早速たぴおか太郎になりきることにしたのでした。
しかし、桃色サンゴへの道はそう容易いものではないということくらい容易く想像できます。このままで��私がなすかさんの文体の全体を会得するより前に、先輩が引退してしまいます。
先輩の稽古日誌を観察していたら、とりあえずちゃんと稽古日誌としての役目は果たしていたので、一旦そのパートやります。でも稽古してないのでただの日誌です。
⭐️間接照明って名前ダサくないか?稽古日誌
コンクリートと殴り合い(敗北)
タンバリンに鉛筆で落書き(怒られた)
海老の小道具の精度に脱帽(すごい)
はらぺこあおむしを逆から読む(退化)
たなからバター餅(略してたなばた)
ピコ太郎の再燃(アツい)
おせち料理を意地でも漢字で書く(御節)
蚊が何故かまだ猛威をふるっている(許せん)
⭐️直接照明とは言わないのにね〜〜〜
ここまで書いて私は思ったわけです。いやたぴおか太郎難しすぎんか???
もう諦めようかな……。
???「君には失望したよ……」
はっ!?その声はっ!?!?
???「どうも、愛称として後ろに『ぴ』をつけられることもある、秋公演の舞台上でも大活躍した、あのお菓子です」
ま、まさかお前はっ!!!イモケン!?!?

いや犬けんぴかよ!!!!!
犬ケンってもうこれ犬×2じゃねぇか。
犬「難しいということだけを理由に書かないというのは、それはただ諦めていることに等しごほっ!おっ」
あ、犬ケンピが喉に刺さってる
開いている記事のセキュリティ証明書に問題があります。
エラー吐いちゃったよ。まず犬ケンピ吐かないと。
この記事の閲覧を続けますか?
�� はい わからない いいえ
多分そう部分的にそう 多分違うそうでもない
いや選択肢アキネイター!!!
犬「なんか、もうネタ切れ感あるし、やめるわ」
あぁ飽きネイターだった。
……ということで、
【結論】たぴおか太郎はたぴおか太郎にしかできない
ところで、本当に何も用がないのにtumblerを荒らすのもマズイと思ったので、この場をお借りしてビアゲの役者紹介をします。やってたことはしおりと同じです。この人を主役にするなら、こんなタイトルこんな劇。
以下本チラ掲載順。兼役の2人は省略しています。ごめんね。
東愛莉
『東博士の自由研究所』
使い捨てカイロをたくさん繋げて、使い捨てホットカーペットにしたり。香水を鍋で茹でて香湯にしたり。裏起毛の服をひっくり返して着て表起毛にしたり。東博士の自由研究は、今日も失敗続き。意味のないように思えるその研究内容に、周りは呆れて、中にはバカにする者も。しかし東博士は、そんなことお構いなしに、日々楽しそうに研究を続けているのである。そんな研究所にやってきた一人の青年。どうやら人生がつまらないらしい。そんな彼を見た東博士はこう言う。「ちょうどよかった!今ね、ちゃんこ鍋を作っている蓋の上でトントン相撲をする研究をしたかったけど、人手が足りなかったの。ちょっと手伝ってよ!」
辛い過去がありつつも、今をとにかく楽しく生きると決めた東博士から、元気をもらうことができる公演になると思います。
大良ルナ
『心外、しかし純愛。』
「運命は、自分で掴みに行くものよ。」占い師のその言葉を鵜呑みにした少女は、自らの手で運命の人を掴みに行くことにした。しかし、容姿を見て選り好んでしまうと、それは運命でもなんでもない。そこで彼女は思いついた。人気の多い公園で目を瞑り、手を広げながらふらふらと歩き、一番最初にぶつかった人を抱きしめよう。その人を運命の人にしよう。早速実践。視界が真っ暗になってから2分ほど経った時、ドンと胸元を突く感覚。これはと思って抱きしめようとすると、それは思っていたよりも小さかった。胸元から聞こえる声。「くるっぽー。」いや鳩じゃん。これじゃ運命の鳩じゃん。人外は流石になぁ……。いやでも、このクリっとした瞳に綺麗な毛並み。正直、割とアリ。
鳩とのハートフルラブコメです。私にはハッとする衝撃の展開が広がるピジョンが見えています。
児
『教室における感慨と、その二面性についての考察』
7月某日。俺のクラスに転校生��やってきた。15人。もともと3人しかいなかった俺のクラスに、転校生がやってきた。15人。なんでも、近くの村にあった高校のすぐ近くで土砂崩れが起きて、校舎が倒壊したらしい。15人はそこから一番近いところにあった、船で30分の小さな島にあるこの高校に通う羽目になったそうだ。かわいそうに。転校生15人は、その慣れない環境に緊張……するはずもなかった。昨日までの穏やかな生活が嘘のように、喧騒に包まれた教室。俺の教室を、俺の居場所を、返してくれないか……?
教室では静かであるべきか、にぎやかであるべきか。それともにぎやかな教室を静かに眺めているべきか。
うみつき
『髪と縁』
またフラれた。これで何回目なんだろう。付き合ってみるたびに、「なんか思ってたのと違うわ」って言われる。いやいや、思ってたのと違うところを受け入れられるのが「好き」ってもんじゃないの?いや、愚痴なんか言っててもしょうがないけどさ。私は失恋した時、必ず髪を切ると決めている。他人の。普段は別の仕事をしているけど、フラれた次の日は実家の美容院の手伝いをする。別にこの仕事が好きってわけじゃないけど。自分以外の誰かのためにハサミを持つのが、なんか落ち着くというか。
その日店にやってきたのは、私をフった男だった。殺してやろうかな、これで。
統括のフォーニャー
『liebrary』
「はい。どうされましたか?看板?あぁいえ、これであってますよ。この図書館に置いてある本は、全部嘘なんです。この世界で生まれたすべての嘘が、ここに集められるんです。ですから、あなたがついた嘘もあれば、あなたがつかれた嘘もありますよ。あ、面白いですか。それはそれは、ありがとうございます。はい。またぜひどうぞ」そうして客を見送った女は、ついさっき新しく生まれた本を手に取る。「そっか、面白くないか」
嘘が分かるということは、本当が分かるということ。そこに計り知れぬ苦悩があるということは、嘘じゃない。
緒田舞里
『0で割るということ』
よっ。元気?こっちは元気だよ。ちゃんとご飯も食べてるし。大丈夫。……仕事?あぁ、うん。楽しいよ、ちゃんと。あぁ、ほら、最近さ、ちょうどクリスマスに向けての準備とか始まっててさ、この時期って夜にパフォーマンスの練習入ったりするじゃん?それがちょっと大変ってだけ。でも、私ってそういうの好き、だしさ。多分。あ、ごめんね、こっちばっかり話して。そっちはどう?……なんてね。
二宮はそう独り言を呟きながら、右側に供えた花のバランスを整えた。
白
『ニッポンのこれから審議会』
説明しよう!ニッポンのこれから審議会とは、ニッポンのこれからについて審議する会のことである!発足後初の会議となる今回の議題は、「ニッポンにとって不要なモノ」 つまりはニッポンが削るべき要素を洗いざらい洗い出すということ��なる!年賀状?節分??お盆???ニッポンには今や企業が儲かることしか考えていないような形骸化した文化が山ほどあるではないか!いつまでこんなの残してるんだ!消せ!!しかし、そんな議論の流れに静かに異議を唱える男がいた……。
だんだんとアツくなっていくぶらんの演技にご注目ください。
岡崎仁美
『カヌレ』
おかしい。利用客が減少の一途を辿る小さな駅構内にある、小さなケーキ屋さん。今までいろんなケーキを売っていたのに。今ではショーケースの中は、一面濃い茶色。カヌレしか売っていないじゃないか。奇妙な品揃えを覗いていたら、店の奥から出てきた女性店員に話しかけられた。「こんにちは!カヌレはいかがですか!?」
コイツはカヌレしか食わない。コイツはカヌレしか売らない。利用客が減り、カヌレが増える。これは一体何を意味しているのか。新感覚カヌレホラー公演。逃げろ。
雨々単元気
『にじいろアジト』
大阪の南の北の方。そのさびれた倉庫では、夜な夜な5人の学生が身を寄せ合っていた。各々の事情により、学校に通うことを諦めている彼らには、共通する一つの目的があった。「この世には、やけに綺麗な虹ってもんがあるらしい。それが見たい。」
セカイ系のお話にしたいです。彼らが虹を見たことが無いのは、彼らが昼間に外に出ないからではなく、地球外生命体が地球を黒い幕で覆い隠して、宇宙から隠蔽しようとしているからなんですね。まさに黒幕。まぁ確かに地球ってずいぶん異質な惑星ですし、宇宙にとっては無い方が都合がいいのかも知れません。ちなみにこの公演の愛称は「ニジアジ」。
舞原の絞り滓
『大器晩声』
ある公園で開催された大声大会。その喧騒に怒り、近所に住むおじさんが怒鳴り込んで来た。……いやコイツが優勝じゃんか。(『大声大会』) 「あの、すみません。キッズメニューの裏の間違い探しってなくなったんですか?」「はい。その代わりといってはなんですが、この店の中には、既に10個の間違いがございます」(『間違いなく間違い』) 訪問販売で契約したタイムマシンがパチモンだった。「夕仏マシン」だった。時間は夕方限定、場所は仏や大仏の目の前にしかいけないらしい。……じゃあ、修学旅行のあの日を、もう一度だけ。(『驚麗』)
などなど、全7編のショートストーリーからなるオムニバス公演。そのうちいくつかは、まほろさんに演出してもらいたいです。
じゃがりーた三世
『何点かお伝えしたいことがございます』
ある山奥の宿泊施設で、人が死んだ。死体��様子から見るに、他殺であることは間違いなさそうだ。この施設から人が出入りした形跡も無いため、ここにいる6人のうちの誰かが、コイツを殺した。「とりあえず電話で警察を呼ばないか!?」そう言い出した男に対して、周りは呼びかけた。「忘れたのかお前!この施設では、携帯電話などの音や光の出る機器類は、必ず電源から切らないといけないじゃないか!」……じゃあ、このカメラで証拠の写真を、いや、許可のない撮影録音は禁止か。……もうこんなところにいられるか!俺は抜けさせてもらうぞ!え?途中休憩はございません?そんなことしらねぇよ!俺は出ていくからな!?……係の者がいないから、出られない。
前説で語られたルールが、全て適応されている空間で起こる推理合戦。ところで、上演時間は60分ということは、それってつまり……
オーム
『非常に新車』
とある交差点で車両同士の接触事故が起きた。畜生、この後マスコミに向けたプレゼンがあるってのに、どうしてこんなときに……。
仕方なく車の外へ出ると、相手の運転手は私の顔を見るなりこう言った。「あれ、ZESSANの岩本社長ですよね!?え、すご!私ずっとZESSANのクルマのファンなんですよ!今日もほら、先日発売されたばっかりのやつ乗ってるんです!すごいっすよねこれ、自動運転機能も充実してて!ハンドルから手離してても余裕で運転できてましたもん、さっきまで」
絶対にバレてはいけない事故。どうにかマルク収めなければ。
テキストを入力
『いまどうしてる?』
背が高いその男は、公園のど真ん中にある、さらに背の高い街頭の下に立っている。その公園にやってくる人は皆、紙にデカデカと自分の近況を書き、背の高い男に渡していく。男はその紙を体のいたるところに貼り付けて、ただずっとその場に立ち続ける。公園には、ただ人が書いた紙を見にくるだけの人もいれば、紙越しに喧嘩をしている人もいる。背の高い男はそれを見て、何を思うのか。
キャスパ曲というか、エンディング曲には、ゲスの極み乙女の「灰になるまで」を使いたいです。(ツイ)廃ではないです。
縦縞コリー
『優しすぎた男』
理不尽に呑まれ、後悔に苛まれ、そんな優しさが誉。しかし彼は優しすぎた。完成間近のレポートのデータを友人に消されても怒れないし、飲み会の参加費を1人だけ二重に請求されていることに気がついても指摘できない。いや、それは優しさというか、弱さなのではないか……?
キャスパには、トリプルファイヤーというバンドの「次やったら殴る」という曲を使います。舞台上でふにゃふにゃしたこりちゃんを観ましょう。
大福小餅
『a hole new world』
ざく。ざく。まだ掘った方がいいかな。ざく。ざく。もうちょっと深い方がいいかな。ざく。ざく。ま、こんなもんか。よし。……あれ、これ私が穴の中入っちゃったら、誰が私を埋めるんだ?あ、ちょうどいいところに人が。すみませーん、私を埋めてくれませんか?
埋まりたい人と通りすがりの人の二人芝居。普段あんまりネガティブなことを言っているイメージがないこふくが、ものすごくブルーな気持ちの役をやっているのを観たい。
叶イブ
『世迷言病』
「こんにちは」「あ゛ぁ゛!?こんにちは!!」「えっと、今日はどこが悪くていらしたんですか?」「見りゃ分かるだろ!!口だよ!!」「……口?何か口内炎みたいなできものがありますか?それとも痛みが」「ちげぇよバカ医者がよ!!そのまんまの意味だっつーの!!先週末くらいから口が悪くなってんの!!」
「よまいごとやまい」と読みます。高圧的なキャラ、似合う気がします。病が完治した後とのギャップがメロい。多分。
はぜちかきつ
『喫茶・愛のペガサス』
「本格中華やめました」 亡き父親が経営していた喫茶店をいやいや継ぐことになった男は、とりあえず中華料理の販売を停止した。どうせなら店の名前も自分好みに変えたかったけど、常連の客からの反対の声も大きく、仕方なくこのままにしている。そもそも駅から少し離れていて、人が多くないような街の喫茶店なので、お客さんのイリはまばら。まぁ、ワンオペでも全然回るし、むしろ空きの時間で趣味の小説を書けているくらいだから、これはこれでいい生き方なのかもしれない。……その日、見慣れない客がやってきた。オ���バーサイズの服を着た、ショートカットの女の子。
優しくて大きい(器が、という意味)ハゼは、喫茶店オーナーとか似合いそうです。
2 notes
·
View notes
Text
旅日記⑤ in South Korea🇰🇷
Busan編
釜山に旅行してか3ヶ月経ってしまいましたが、旅日記は残すべく、今更ながら思い出語り。







何日に何したか、どこのお店行ったかの記憶が朧げなので釜山の魅力を書きます😭次の旅行はその日に書こう。反省。
釜山とソウルどちらも行った身としては、韓国に旅行してみたいけどどこ行こう?という人に、断然釜山をおすすめしたい。(美容にさほど興味のない男性は尚のこと)
釜山の魅力
①ソウルで味わえるようなご飯屋さんは網羅されてる上に、釜山ならではの新鮮な海鮮のお店が多い(し、ちゃんと美味しい)。カンジャンケジャン(写真5枚目)の艶ヤバくないですか?生臭さなんてものは一切なくて、とても美味しかった。
②都会と自然が両方ある。
釜山でいちばん思い出に残っているのは海(海雲台海水浴場:写真1,2枚目)。2枚目の電車はガイドブックに載っているので、多くの観光客が訪れるスポットだけど、予約した乗車時間までの暇つぶしで近辺を散歩していたらたまたま海辺まで辿り着けた。海青くてちゃんと綺麗だな?!!?!?!と興奮した。
Sydneyでもそうだったのだけど、高層ビルと綺麗な海が隣接している絵面が個人的にたまらなく好きで、地震大国の日本では見られない光景なのが少し残念。
③ローカルな朝ごはん屋さんが多い。
これもまた日本にはあまり馴染みのない文化だけど、海外では朝ごはんを外で食べる習慣が根付いている気がする。
美味しかった朝ごはん3選
(1)カルグクス(写真下)
カルグクス(「カル」=包丁,「グクス」=麺)は「韓国風うどん」とも呼ばれていて、味のバリエーションがとても豊富(訪れたお店はいりこの出し汁を売りにしていた)。先輩たちはソンカルグクス(温)、私はネンカルグクス(冷)を注文。優しい味のスープで目が覚めました。

(2)ソコギクッパ(写真下)
ソコギクッパ(「ソコギ」=牛🐄)は、もやしや大根などの野菜を大釜にたっぷり入れ、牛肉と一緒に煮込んだスープ。韓国では二日酔いの日は朝に食べるのが定番らしい。個人的にはデジクッパより好みだった。

(3)デジクッパ(写真下)
デジクッパ(「デジ」=豚🐖)は、豚骨を丸1日かけてじっくりと煮込んで出汁を取ったスープに、茹でた豚肉とねぎとご飯を加えて、たくさんの種類の薬味の中から好みの味付けをして食べる料理。西面にはデジクッパ通りというのがあるくらい人気の料理で、とても美味しかった。

※ 「クッパ」はスープと米を混ぜた料理。お米も入ってるのでお腹も溜まる。
④観光地らしい観光地が結構豊富。↓
甘川洞文化村(山の斜面に建物が連なってて「韓国のマチュ・ピチュ」といわれている美しい村。星の王子さまのオブジェが有名)
海東龍宮寺(韓国でいちばん美しいと有名な寺。寺に向かう108段の階段を降りる(登るんじゃなくて?!)と願いが叶うらしい)
国際市場(なんか栄えてる市場。)
五六島スカイウォーク(崖の上から海上に突き出したガラス張りの展望台で、高所恐怖症の人は多分無理。)
釜山ダイヤモンドタワー(夜景スポット、たぶん日本でいう東京タワーみたいなやつ)
海雲台(釜山でいちばん有名なリゾートビーチ。海めっちゃ綺麗。今回の旅でいちばん良かったスポット)
海雲台ブルーラインパーク(4人乗りのノロノロ列車なので1人で乗っ��ら多分暇だけど、カラフルで可愛いし綺麗な海をずっと一望できるからおすすめ)
南浦洞(釜山のキラキラ繁華街。渋谷っぽかったです)
とかとか、他にも韓流の『サムマイウェイ』のロケ地もあって3泊4日では全然制覇できなかったくらいに観光地多い。ソウルは観光地らしい観光地が少ないイメージだからそこに関しては釜山の方が充実してた。
⑤百貨店やブランド通りもあるので、ほぼ有名なブランドやスポーツ用品店は揃っていて(調べたら多少はソウルにしかないものもあるんだろうけど)、ソウルと同じくらい買い物も楽しめる。
釜山にしかないOPTATUMのハンドクリーム、ぜひお土産に購入してください。
North faceのホワイトレーベル(韓国限定ブランド)のトップスを罪滅ぼしで兄にお土産で購入した😅(正月の航空事故の影響で福岡からギリギリ東京に到着した際、タクシー待ちの列が5時間で、韓国行きの成田便に間に合わない〜と詰んでいた妹を、国試1ヶ月切っていたのにレンタカーで千葉から迎えに来てくれました、、神)
ちなみに屋台もソウルと同じくらい栄えてて楽しかった。屋台のホットク、毎日食べたい。
⑥街の散策が苦じゃない。
個人的な印象だけど、ソウルよりも一駅間を歩くのが苦じゃなかったような気がする。たくさんご飯を食べた後、次の目的地まで二駅だから歩いちゃおう!みたいなことができて良かった。
韓国旅行はグルメメインになるので、胃もたれでしんどくなるイメージが強かったけど、歩きやすい街並みと胃に優しい朝ごはんのおかげで、たくさん食べてたくさん歩いて健康な旅!という感じでした。
⑥ソウルと比べてローカルな都市なだけあって、人との距離が近め(な気がした)。
電車にて3人で日本語で喋っていたら隣に座っていたおじさんたちから話しかけられたり、お店で鍋を突いていたら隣のお姉さんたから声をかけられたり。みんな親切であったかくてなんて素敵な街なんだ〜!と思った。
余談)
新世界百貨店の新世界スパランドもおすすめ(10種類以上のチムジルバンがあって、一番高い温度のチムジルバンは79度)。温泉のあとのご飯が美味しいっていう文化は世界共通なのか。
写真7枚目のフレーク入りヨーグルトは韓国の定番の朝ごはんで、美味しすぎるので日本でも売ってほしい。欲張ってたくさんスーツケースに詰めたら、飛行機の気圧で潰れてスーツケースがヨーグルトまみれになりました。ビニール袋に入れておくべきだった。
タラタラ感想を述べたらえげつない長文日記になってしまいましたが、大好きな先輩2人と楽しい3泊4日を過ごせて幸せな渡韓だった。
またどこか旅行しましょうね🙈
6 notes
·
View notes
Text
お葬式
祖父が全うした。91歳だった。5/27の6:27に息を引き取った。自分の誕生日は10/27で、紫の手帳を受け取ったのが12/27。おいおい、おじいちゃん。あなたの才能は十分に承知していた。けど、そこまでされると怖いぜ。
ここから長すぎる。一時間足らずで狂い書きな感じ。読みたきゃありがとうございますね。
黙して語らず、ニコニコ優しく、しかし熟慮している人だった。従兄弟曰く、「大学に行くときに、ニーチェの詩?に注釈つけて渡された。おじいちゃん心配してたんだなあ」おそらくそれはツァラトゥストラだ。おじいちゃん、同じ道を辿ってるね。「毎年おじいちゃんは宝くじ買ってたやろ?あれをどう使うか聞いてみたら、『あの道を直して、ここの堤防を強くして』って言ってて、本当にすごかった」そう、だからあの葬儀の当日、近隣は大雨で避難警報が出されたんだが、不思議とおじいちゃんが道を作り治水した地域にはほとんど被害がなかった。すげえぜ。かっこいい。
自宅から出棺。近所の人たちがお見送りに来てくれた。しかしまあ、その出棺作業は自らと親戚で急ピッチで段取りしました。すごくね?あなたは本当に、素晴らしい人だったのだ。みんなが知っていた。それだけは確かだ。私もその一人だ、と述べてもいいですか?おじいちゃん。あなたと将棋をしても、絶対に勝てなかった。正月に家の玄関の上がりで、自らのプライドである刀を手入れしていた姿を、鮮明に覚えています。祈るように、あなたは梵天に手入れの粉をつけていた。
通夜から葬儀まではパニック。全ての段取りを把握している父が、その段取りを内々の親族に明かさない。いや、普通さ、もういくばくもない命を目前にすれば、あらゆる段取りを把握して、誰がどこにどう動けばいいのかを伝える。あなたの生業はそういうものでしょう?『随時更新の身内スケジュール』が必要でしょう?そうやって自分が全部しなきゃ、という使命感の反対には、人に任せられないという不信感があるのでしょう?だから仕事以外に友人がいないんです。普通に休日に飲みに行くこともないと。「お前が友達と馬鹿話するような友達はいない」と断言しましたね。違うんです。馬鹿話じゃないんです。お茶会や飲み会は、深刻で暗い話を笑い飛ばす場所なんです。
なんでわかんねぇかな。わかんねえからあなたと飲んでも面白くない。というか、「こういう馬鹿がいた」みたいな仕事上の話を家に帰って母に申しつける時点で、非常に卑怯な落語なんですが、おめえさんよ、案外馬鹿を馬鹿にしちゃいけねえよ、馬鹿も馬鹿なりに考えてる。その考えてることを否定しては悦に入る。『酢豆腐』の旦那じゃねえか。大いなる阿呆。ダサ坊。シャばい。自分専用のポルノを自分で拵える野郎。水商売を貶しながら、お姉ちゃん遊びには大いなる興味があるどすけべ。小学生女児がなんぞの事件にあった、と聞けば、「この子はなんかとっぽいからそうなるよね」口が裂けても言うなよ。ジャニーズの会見、「この男は、男なのに化粧なんかして目も落ち窪んで、気色悪い」何様だよ。てめえ��利用するだけ利用したゾーンに対してそういう言葉を吐くんだ、へえ〜。高校ぐらいまで父と祖母の着せ替え人形として彼らの与えられる服を着た。気色悪いんだよ、友達の言うには、その服装は、「なんか、おじいちゃんみたい」だとよ。っざけてんじゃねえよ!お人形遊びは楽しいか?てめえら俺が幼い頃に女装させたりとかしたよな。こちらはグチャグチャです。「お前が寝てても呼びかけたら応えてくれるから、つい」とか抜かしてるけどさあ、起きてるよ。その気色悪いボディタッチも。でも寝てて可愛いふりしてた方があなた気持ちがいいでしょう?てめえが俺を撫でるたびに、吐きそうになって仕方がない��だ。You Know? Yeah, you Just say "I Don't Know". ****
最後の念仏が唱えられる。輪廻転生は仏教で三回とされる。誰も見たことのない祈り方。三回同じ言葉を唱えた後に、なんとなく解脱のような文言があった。「見たことがない葬儀だった」と口を揃えて申し述べる親族。火葬場へ。これが悪夢のようだった。
とても現代的でシステマチックな火葬場。荼毘に伏すとして、その間はみんなでなんとなく空を見たり、煙突からの煙を見たり、そんな時間だと記憶していた。しかし実際は、棺を運ぶのは手動で操作できるフォークリフト。最後に顔を見て、そこからは全員が揃って荼毘の場所へ。もうその時点で、呼吸が苦しい。自分が過呼吸になっているのではなく、そこに漂う人間のタンパク質を燃やした独特の空気が、襲いかかってくる。少しは泣いたけれど、本気では泣かなかった。
喫茶室があります。親族の待機室はここです。全員が喫茶に向かう。一悶着あったらしいが、それは全てを握っているはずの父が何も手立てを打っていなかったことによるらしい。つまり、「あの家に帰る手立てがない」とのこと。大揉め。しれっと、親戚のおっちゃんが「また始まった」と呆れたように言うので、彼について行って喫煙所へ。「おじいちゃんの棺に、ショートホープ入れてあげたらよかったなあ、と今更後悔してるんですよ。植木職人の人曰く、『耳から煙出るぐらい吸う』ぐらいの人だったんで。まあなんかあるときに胸ポケットに入れたままやめたらしいですけど」「俺もおっちゃんのイメージそれよ。でもそんなんクラクラするやろうな。でもやっぱり、紙巻きじゃないと俺は満足できん。何回か試すけど、口の中がなんか変になる」「あれって、水蒸気にニコチン入って香料入って、ってことなので、口の中に残るの当たり前ですよ。で、定期的に掃除しなきゃなんですけど、してないように思います」「なるほどなあ」「紙巻きは手の中に隠せないじゃないですか、でもよく見ますけど、子供の散歩に付き合いながら、あのデバイスは手の中に収まるので、隠れて吸ってる人とか、あと軽自動車の中とかでずっと吸ってる若い女性」「あ〜!よく見るわ!」「なんか卑怯ですよね」「堂々と吸えばいいのに」
骨上げ。向こうから機会が運ぶ音がする。耐えられない。目を背けて壁に引き下がった。説明がある。その人の話を聞こうと思って顔を見ると、祖父のお骨が目に入った。無理。逃げ出して外で存分泣いたが、これはやらねばならん。おじいちゃんも本望ではないだろう。ある程度落ち着いた。元に戻った。骨箱を抱えたさっきのおじちゃん、「ほれ」完全に試されている。立ち向かおうと思った。おじいちゃんの顎の骨の右側をなんとか取り、入れた。壁に向かって泣いていると、おっちゃんが背中を叩いてくれた。優しいボディコンタクト。あれがなかったら、自分はもう立ち直れなかっただろう。
親族の直来。席順がアウトだった。向かいに祖母。斜め向かいに弟、隣に叔母の配偶者。彼や弟と話しているときは、苦しくなかった。弟は後ろから声が聞こえたらしく、ギャルソンとして働き出したので、真似てとりあえず。未来に向ける光を見たように思う。挟まれる祖母の無駄口、思い出話、さっきも言うたやん、で最終的に、「あんた食べんのな?あんた食べんのな?」この役割は弟が担ってくれた。途中で異常を察した母が「持って帰るので」と包んでくれた。そこで祖母が、「物足りんな!うどんでも食べたくなるわ!」糸が切れる。立ち上がって親族の控室に足取りもおぼつかず帰り、水を飲んで倒れそうなところを背中で柱に寄りかかったのは記憶している。そのあとは完全にギャルソンに徹した。席に戻れば……と感じた。
見送り、なぜか親族はパニック。というか、祖母の血をダイレクトに引いている人たちが大揉め。関わったら壊れる。だから、早く帰りたいだろう人たちのドアマン、ポーターとして立ち働いた。その場所が貸し出す傘の場所を把握しているのは俺だけで、木偶の坊なので雨風を防ぐにはもってこいだ。帰るまでが遠足。帰るまでが葬儀。見送ったあと、祖母に話をされた時点で、おそらく人生で一番危険な焦点発作があった。見える聞こえる把握はできるが、動かない。少しだけプルプルしている。話の隙間で深呼吸して、離脱。その後、なぜか父が、「この鍵が潜戸の鍵。行けるか?」と。拒否したところでまたパニックだろう。叔母方の年嵩とおばあちゃんが同情する車で帰ることになった。話の流れで、「えっ、だって私ら帰っても鍵はにいちゃんしか持ってないやろ?潜だって鍵かかっとるし」「これ受け取ってまーす」と鍵束を見せる。永遠のような10秒間の沈黙が、どうしても笑ってしまいそうになって良くなかった。
で、まあ帰宅したものの、真っ暗で鍵の種類がわかるのは父のみ。明かりをつけても何が何やら。普通に礼服で鍵を探しながら試して回る、という、夜盗みたいな働きをして、必要な鍵は開けた。自分はともかく着替えと服薬をしなければ無理。処方薬を飲んでいるところを見られようものなら、またおばあちゃんの詰問に合う。口に含んだまま、水道水の出る蛇口に向かう。「あんたな。夜に明かりつけて網戸にしたらいかんのよ」知るか!緊急事態だ!黙ったまま食器棚からコップを出して水で飲み下す。危なかった。あの場で自分が倒れたらマジでやばかった。ちょっと効いてきたのでせにゃいかんことをしようとしたんだが、お呼び出ないらしい。仏間のパニックを感じながら、叔母方のおっちゃんが絶対にまだ上がらない、との意思表示をしたので、ここは、と思い、靴を脱いで上がる。「これはここ!これはこれでいい!これは日にちが明けてから!とりあえず帰らせ!」と仕切って、「仏間できました。どうぞ」でおっちゃんおばちゃんもう帰らなやってられん状態。見送ろうと玄関について行った。母の「あれはどこ?」攻撃。「ありました!ご安心しておかえりください!」見送りで礼をしたが、90度だった。無意識なのにね。気持ちが出るね。
そこから自分たちのサルベージ。呑気に「あんたら泊まっていかんのな?」「ばあちゃんな、うちはうちでやることがあるんや」と挨拶もせずに帰る。あとから聞けば、母に「大丈夫な?」と聞いてたらしい。大丈夫なわけあるか!お前の不可知領域かつ被差別領域に踏み込んでるんだからほんとのことなんて言えるか!ババアに申し伝えたら、きっと座敷牢の世界なので、両親のそこの理性には感謝したい。
帰りながらうだうだ。珍しく母が飲まないとやってらんないね、状態だったので、缶ビールを美味しく注ぐ方法を実践して、本当の直来。
ここからは結構スピリチュアルなのに事実として観測されている事象を改めて結び直した話になるので、またの機会に。
Adeu!
3 notes
·
View notes
Text
読書の記録
(日本人)かっこにっぽんじん 橘玲
想像していたよりも壮大なテーマ。
データ等を駆使し、世界情勢や歴史、宗教等様々角度から語っています。
私の頭では、ちょっと入り込めない部分もあり、中盤からダルダルな感じでなんとか読了。
そのまま記録に残すかしばらくダルダルしていたけど、見返すと興味深い内容もあったので、メモを残すことに。
新型コロナ騒動よりずっと前に書かれた本ではありますが、ウイルスのことについても触れていまいた。
【メモ】
✏日本人は戦争が起きても国のためにたたかう気もないし、自分の国に誇りも持っていないのだ。
✏貨幣空間の拡大(市場原理主義)というのは、世界の歪みを平準化する運動のことだ。 経済のグローバル化は北と南の経済格差を解消させる巨大な圧力だ。しかしこの無慈悲な市場メカニズムは、経済的な弱者を振り落とすことで先進国のなかの格差を拡大させていく。 たとえ世界全体が幸福になったとしても、ひとは自分が(相対的に)貧しくなることに耐えられない。その意味でグローバル化は、私たちの生活を破壊する侵略者なのだ。
✏貨幣空間が拡張するのは、私たちがそれを望むからだ。ほとんどのサービスが貨幣で購入できる社会では、親戚づきあいは不要になり、友だちとの関係もドライになっていく。ようするに、ベタな人間関係は面倒くさいのだ。 だがそれと同時に、私たちはこのような”無縁社会”に根源的な不安を感じてもいる。ヒトは長い進化の歴史を通じて、ずっと集団(共同体)のなかで生きてきた。群れからの追放は、ただちに死を意味した。ヒトは一人で生きていけるようにはできていないのだ。
✏ヒトは確率的な出来事をうまく理解できない
✏ウイルスが宿主を病気にさせるのは、咳やくしゃみ、下痢といった防御機構を作動させるためだ。宿主が体内からウイルスを排除しようとすることで、手足のないウイルスは遺伝子を他の宿主に移植させることができる。 このことから、ウイルスや病原菌など「寄生者」の目的が、宿主を殺すことではないことがわかる。
✏しかし感染症とのこのたたかいに、人類が最終的な勝利を収めることはけっしてない。それは、寄生者の生き残りの戦略のほうがはるかに巧妙で強力だからだ。 寄生者の武器は、数が膨大なことと寿命はきわめて短いことだ。頻繁に世代交代を繰り返すことで進化の速度は上がり、新種の抗生物質に対しても、たちまちのうちに抵抗力を持つ細菌やウイルスが現れる。
✏狩猟採集生活では、穀類や果実、動物の肉などから炭水化物やビタミン類、たんぱく質を摂取したが、脂肪や砂糖などはきわめて稀少だった。そこで私たちの脳は、このような得がたい機会に遭遇したときは、可能なかぎり多く食べるよう命令を下す。「甘いものを食べると幸福な気持ちになる」のは、大量摂取を促すプログラムなのだ。
✏白人とニューギニア人のあいだに人種的な優劣があるのではなく、歴史や文明は地理的な初期条件のちがいから生まれた
✏だがこれは、彼女たちにとってはファッションの問題ではなかった。みんながルーズソックスのときに、一人だけストレートソックスをはくのは危険なのだ。本人たちが意識しているかどうかは別として、彼女たちは”生き残る”ために同じ髪型、同じヘアメイク、同じソックスに揃えようとしたのだ。
✏ニスベットは、その他の実験においても、西洋人がこのような「分類学的規則」を素早く見つける傾向があることを明らかにした。それに対して東洋人は、規則を適用してものごとをカテゴリーに分類することが苦手で、そのかわり部分と全体の関係や意味の共通性に関心を持った。 (中略) 西洋人は世界を「名詞」で考え、東洋人は「動詞」で把握しようとしているともいえる。
✏西洋人の認知構造が世界をもの(個)へと分類していくのに対し、東洋人は世界をさまざまな出来事の関係として把握する。この世界認識のちがいが、西洋人が「個人」や「論理」を重視し、東洋人が「集団」や「人間関係」を気にする理由になっている。
✏インドで興った仏教は、中国で漢訳される際に変容し、日本に伝来したときにもういちど変容した。これは、もともとその国のひとたちが持っていた認識構造に合った思想しか受容されなかったからだ。
✏風光明媚な自然を愛でる日本人には、この世界を穢土とする思想はまったく理解不能だった。そこで日本の仏教者は、仏へと至るステップをひとつ飛ばし、現世をいわば極楽浄土に格上げすることで、死ねばすぐに(修行抜きで)仏になれるようにしたばかりか、生身の肉体のままで究極の悟りを得る「即身成仏」の思想まで”創造”した。
✏私たちは快適な家に住み、季節に合わせた服を着て、山海の珍味を楽しんでいるが、そのなかで独力で獲得できるものは数えるほどしかない。高度な文明社会では、ひとびとは”無力”になることでゆたかになっていく。 狩猟採集の民が現代人と遭遇したら、彼らは私たちがなにひとつできない(火を起こす方法すら知らない)ことを笑うだろう。
✏真の意味でのグローバルな宗教は、キリスト教と、ムハンマドが新たな預言を得て聖書を再解釈したイスラム教のふたつしかない。仏教は「法治」によって、儒教は「人治」によって身分や民族の壁を越えようとしたが、そこでは「神」が世界を支配しているわけではない。
2 notes
·
View notes
Text
各地句会報
花鳥誌 令和7年6月号

坊城俊樹選
栗林圭魚選 岡田順子選
………………………………………………………………
令和7年3月1日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句
貝寄風や龍馬の夢は明治へと 睦子 菜の花忌雲を目指した明治人 修二 春の小川そは大正を恋ふしらべ 美穂 竹馬の上手はヒーロー昭和の子 睦子 春炬燵昭和歌謡の流れ来る 光子 甘党のウィスキーボンボン春微醺 睦子 春雨に昭和の唄を口遊む 光子 田楽や女将昭和の割烹着 修二 罅に添ふ金継ぎ細し光悦忌 睦子 暖かや昭和演歌の七五調 久美子 春泥や流離のごとく就活す 朝子 翠眉濃く昭和の春を踊り来し かおり 逆上がり出来ず砂場の春寒し 成子 野火走る地下に鍾乳洞深く 光子 雛段に祖母の鼈甲化粧箱 美穂 しやぼん玉飛んで昭和の家並まで かおり ふらここや漕げば昭和の雲浮けり 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年3月1日 零の会 坊城俊樹選 特選句
梅の香に惑ふ純情男坂 きみよ アメ横にもの喰ふ人や鳥雲に 要 通り抜け出来ぬアメ横春の闇 同 囀を上野大仏瞑りて 順子 累々と上野の山の落椿 要 混雑猥雑アメヤ横丁うかれ猫 風頭 卒業や銅像の頰撫でて去る 佑天 整然と立つ春愁のチョコバナナ 緋路
岡田順子選 特選句
鳥帰る露店あらゆる色を持ち 緋路 霾や上野の店の読めぬ文字 軽象 春の人スワンボートの胎へ還る 緋路 アネモネを咲かせ丸永商店に 和子 アメ横に日本一の目刺売る 俊樹 夢をみるらむ囀の劇場に きみよ アメ横を出て薄墨のかひやぐら 要 服を脱ぐやうに傾げて春日傘 和子 こんなにも人ゐて蝶のただひとつ 千種 春光に位牌並べる仏具店 佑天 不忍の水の濃厚蓮芽吹く 千種
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年3月3日 花鳥さざれ会 坊城俊樹選 特選句
露座仏も眠気に在す春の宵 かづを 一穢なき姿のままに落椿 同 老梅やこゝに学舎の有りし村 匠 そここゝの汚れし雪や二月尽 同 幼な子の雛とかたこと話しをり 希子 春泥に躊躇の一歩踏み出せり 千加江 如何な人此の樏を履きたるは 雪 幾年を経し雪沓ぞ懐かしき 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年3月6日 うづら三日の月句会 坊城俊樹選 特選句
四姉妹雛の思ひでそれぞれに 喜代子 笑ふとも泣くとも見える雛の顔 同 雛祭四人姉妹を守りこし 同 ひな飾る時のかなたの幼な顔 さとみ 晴れてまた吹きすさびたる春の雪 都 かの山に未練残して鳥帰る 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年3月8日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句
鳥の景佇む友と卒業す 多美女 卒業やスポーツ刈りの髪伸びて 三無 卒業生弾む声なり胸の花 文英 幼子も律々しくなりて卒業す 亜栄子 二ケ領鯉と親しき残り鴨 文英 恥ぢらひのコサージュピンク卒業す 和代
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年3月10日 なかみち句会 栗林圭魚選 特選句
仄かなる潮の香させて目刺し焼く 三無 海の色焦がし目刺の焼き上がる 秋尚 建て替への常宿偲ぶ木の芽時 のりこ 新幹線窓一面に山笑ふ ことこ 目刺盛る器は旧き伊万里焼 貴薫 宿り木の浮かぶ大樹や木の芽風 のりこ 山椒の芽とげとげしくも初々し 怜
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年3月11日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句
供養雛四十体のピラミッド みえこ 通学路思ひ出連れて忘れ雪 裕子 雪解水溢れ雨樋外れをり 実加 河津桜供養帰りに家族して みえこ 山笑ふあの人の家目指し行く 裕子 古民家を曲がつた先の母子草 実加
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年3月11日 萩花鳥会
春の陽の沈むを惜しむ軒の下 俊文 古雛美し老いは人の世苔の一つ 健雄 雛飾り還らぬ人を懐しむ 綾子 椿見て素敵ですねと友は言ふ 健児 細面どこか母似の古雛 美恵子
………………………………………………………………
令和7年3月14日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句
いつよりか鳴らぬカリヨン街朧 美智子 音もなく雪の吸取る吾の時間 佐代子 蛇出づる根の国を見た面をして 都 引ききらぬ浅瀬で始む潮干狩 宇太郎 貼紙に差し上げますとさくら草 都 鶯や漢詩の先生の庭に 悦子 船音は蛍烏賊なる賑はひに すみ子 生きめやも水栽培のヒヤシンス 佐代子 涅槃西風煽り塒へ群鴉 宇太郎
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年3月16日 風月句会 坊城俊樹選 特選句
雨含む三椏の花闌ける寺 亜栄子 諍ひをちと春の嵐の中へ 慶月 女坂血の色に染む落椿 三無 喬木に百囀りの古刹かな 幸風 観音の飲んでゐさうな春の水 三無 堂の灯の漏れくる扉寺彼岸 亜栄子 春雨や道祖神なほ睦まじく 慶月 佐保姫に向けて墓標や波の音 幸風 奥津城をそつとなでよと木の芽風 同 猫柳蒼き雨だれ含みたる ��� 春雨や煤け火のなき自在鉤 久子 観音の嘆きの紅き落椿 慶月 無縁仏修羅のごとくや落椿 亜栄子
栗林圭魚選 特選句
春禽や幼子パ行の語を並べ 久 晩鐘の磧にとよむ雉のこゑ 幸風 快晴や北窓開く藍染館 経彦 曇天に沸き立つ色の花ミモザ 文英 SLに駆け込む児らや春の雷 経彦 天象儀出でて見上ぐる春の星 同 春の雨やさしく撫でて陽子墓碑 文英
飯川三無選 特選句
雨含む三椏の花闌ける寺 亜栄子 百条のメタセコイアや木の芽雨 久 肌を打つ重たき雨や茨の芽 亜栄子 曇天に沸き立つ色の花ミモザ 文英 春雨に電車やさしくカーブする 慶月 観音の嘆きの紅き落椿 同 山寺に涅槃の日の雨降りやまず 久子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年3月18日 福井花鳥句会 坊城俊樹選 特選句
化粧して草餅食べて身繕ひ 世詩明 加賀様の世を垣間見る雛かな かづを 古雛と言へど凜しさありにけり 同 はい〳〵と小言聞く朝鳥雲に 清女 一瞬のきらめきつれて初蝶来 笑子 黒髪の女雛の裾へ灯り揺る 同 吊雛や鹿の子絞りの緋の小袖 希子 涅槃西風受けて文殊や靄の中 同 針供養姉ささやかな針収入 令子 土雛の眼差し今も穏かに 千加江 ランドセル背に跳ねてゐる雪つぶて 雪 浪の花見るに一人は淋しきと 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年3月21日 さ��たま花鳥句会
雲梯に縋る縄目や春の雪 月惑 ふる里の農事ごよみや辛夷咲く 八草 春泥に惹かれ園児の列乱れ 裕章 雨だれの音の春めく奥の院 孝江 こじんまり昔農家の花杏 としゑ 点々と摘草はばむもぐら塚 康子 黙祷の奥に囀り蒼き空 恵美子 竹林の天使の梯子より初音 みのり 花巡り母の形見の指輪して 彩香 混み合へる甲斐の隠し湯山笑ふ 良江
………………………………………………………………
令和7年3月16日・21日 柏翠館・鯖江花鳥合同句会 坊城俊樹選 特選句
瓢の笛最も聞かせたき人に 雪 母偲ぶ一日を以て針供養 同 荒磯には荒磯の情浪の花 同 打てば鳴る如大寒の青き空 同 当たつても当らなくても雪礫 同 蟷螂の続々生まれ子ら津々 みす枝 能登の地に佐保姫早く出でませり 同 災難の能登を俯瞰し鳥帰る 同 軒下をあちらこちらと初燕 嘉和 比良八講けむり荒ぶる湖白し 同 起立礼みごとに揃ひ卒業す 同 ふらここを蹴り上げてみる空の青 真嘉栄 陽炎や遠く電車の過ぐる音 同 蒼天や正座を崩す春の山 同 学ぶ程学ぶこと増え大試験 世詩明 雛飾り大戸開けば犇めける 同 冬籠父の日記を盗み読む 同 小春日や老婆二人の長話 和子 中学生進路定めて卒業す 紀代美 ひとしきり春の雪舞ふ涅槃寺 ただし 春炬燵守り長生きを疎みをり 清女
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
1 note
·
View note
Quote
月丘さん、井上さんは夫婦ともども、ジャニーズ事務所創業者の故・ジャニー喜多川氏と姉の故・メリー喜多川氏と親しい関係にあったのは、関係者の間ではよく知られている。 「月丘さんが代表を務めていたクンクンの業務内容は、所属タレントに関わる雑誌、カレンダー等の企画制作における各出版社との契約折衝代行や化粧品の販売でした」と話すベテラン芸能ライターはこう続ける。 「メリーさんは実弟のジャニーさんの性加害を記事にさせないよう各出版社に働きかけていましたが、クンクンの業務内容から一連の性加害問題の責任の一端は月丘さんにもあったのではと言われています。さらに、月丘さんが当時出演していたCMは『一和高麗人参茶』という旧統一教会系企業の商品だったことから、月丘さんに“信者疑惑”が持ち上がっていました。高麗人参茶は医薬部外の化粧品扱いだったため、当時、クンクンでも取り扱われていたのではと囁かれていました」 ■夫も旧統一教会系政治団体の後押しで映画製作 月丘さんがCMに出演していた高麗人参茶の製造販売元の「一和(イルファ)」は、食品・高齢人参、製薬を生産するヘルスケア企業。旧統一教会による霊感商法が問題視される1970年代の終わりから1980年にかけて、「世界のしあわせ(現・ハッピーワールド)」という商社が同社製品を日本で販売して、積極的なプロモーションを展開していた。 「月丘さんが旧統一教会創設者の文鮮明氏に寵愛されていたため、このCMに抜擢されたと言われています。夫の井上さんも旧統一教会系の政治団体『国際勝共連合』の後押しで製作された映画『絶唱母を呼ぶ歌 鳥よ翼をかして』(1985年)と『暗号名 黒猫を追え!』(87年の)の2本の監督と脚本を担当しています。夫婦揃って旧統一教会とは関係が深かったんです」(宗教ジャーナリスト) 03年にジャニーズ事務所と関連会社3社と取引先に、東京国税局の査察が入っているが、その中には、月丘さんが代表を務めていたクンクンの名前もあったのだ。 「当初、国税の狙いはジャニー喜多川さんの個人所得に関する調査でしたが、関連会社数社に合計約20億円の申告漏れが見つかったため、査察に代わりました。査察後、関連会社の社長が法人税法違反で起訴されましたが、ジャニーズ事務所は『事務所本体とは無関係』と逃げ切ったんです」(元大手紙社会部記者) 月丘さんはジャニーズの関連会社の代表を務めただけでなく、近藤真彦の記念公演に出演したり、ジャニーズタレントとドラマでも共演。事務所ぐるみで関係が深かったという。
(3ページ目)「美 少年」不祥事で繋がったジャニーズと旧統一教会の接点…亡き“高麗人参”女優との蜜月関係|日刊ゲンダイDIGITAL
2 notes
·
View notes
Text
2024年7月13日(土)

三重県紀北町・奥川ファームから隔週に届く定期便、今日も無事にやって来た。いかにも夏らしいメンバーだが、珍しいのは<茎漬け>、八頭の茎を塩漬けして紫蘇で色づけたものだ。これは紀北地方の郷土料理、夏の暑いときにこれと鰹の生節を一緒に頂くとご飯がすすむのだ。おまけで私の好きな<伊勢うどん>も同梱されている。奥川さん、いつもありがとうございます!

3時45分起床。
日誌書く。
二度寝。
5時起床。
体重、600g増。
週末なので、CleanMyMacX で Mac Mini をスキャンする。

お蕎麦がなくなったので、朝食にはうどんを頂く。
珈琲。
洗濯。
奥川ファームの定期便、初物の小さな西瓜が入っている。
きゅうりのしょうゆ漬け仕込む。
酢卵仕込む。
唐辛子酢仕込む。
枝豆ゆがく。

<天満大阪昆布>から、夏の味!ボリュームセットが届く。毎年のことだが、いろいろ入っていて楽しい。
クロネコが集荷に来てくれる、<もったいない本舗>への段ボール5箱を渡す。
<ゆうちょ銀行>からMQJへの問合せ、<人格なき社団>を証明しなければ口座を解約するとのこと。会則や会計報告、議事録などを揃えて返送する。締切は先週末だが、何とかなるだろう。

ランチ、息子たちには素麺、私たちはツレアイが冷蔵庫の残りものをシチュー仕立て、届いたばかりの奥川ファームのパン+🍷。
録画番組視聴、刑事コロンボ。
第17話「二つの顔」/ Double Shock 富豪クリフォード・パリスは、トレーニングと健康管理に熱心で、孫のように若い女性と婚約していた。ある晩、彼の甥で料理研究家のデクスターが結婚祝いを言うためにクリフォードを訪ねた後、再び現れた。入浴中のクリフォードに対し、突然ハンドミキサーを取り出し浴槽に投げ込んだ。
ツレアイはあちこち買物へ、私は午睡。

セントラルスクエア花屋町店で猫砂・介護食、コレモ七条店で鶏もも肉・うどん。
クロネコが先日地球洗い隊に注文した<夏の福袋>を届けてくれる。
ゆうパックが、びーんず亭の珈琲を届けてくれる。やたら配達の多い日だ。

夕飯、豚バラ肉と残り野菜の蒸し煮・鶏もも肉とピーマンの甘辛煮・レタスとトマト・きゅうりのぬか漬け。
録画番組視聴、刑事コロンボ。
第18話「毒のある花」/ Lovely But Lethal ビベカ・スコットが社長を務めるビューティマーク化粧品は、「ミラクル」という皺取りクリームの開発に成功した。これでライバル会社のラング社を出し抜けると喜ぶビベカだったが、「ミラクル」のサンプルをラング社に持ち込まれた、という情報が飛び込んでくる。
残っていた日本酒を片付けたので、あっという間に睡魔到来。

歩数は届かないが、辛うじて3つのリング完成。
6 notes
·
View notes
Text
TEDにて
ハビエル・ビラルタ: 国地域に密着した建築を
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
TEDフェローのハビエル・ビラルタは、アディスアベバの高層ショッピングモールの設計を依頼されたとき、うろたえました。
一般的な例として見せられた建物は、彼が、現代建築で嫌いなものすべてを体現したようなものでした。それは、無駄が多く、ガラス張りのタワーでエネルギーを大量に消費し、デザインもアフリカと何の関係もありません。
この魅力的なトークで、ビラルタはどんなアプローチを取ったかを紹介します。
ショッピングモールではなく、小さいお店で自然を生かし、伝統のデザインを取り入れ、そして、社会システムにあった美しい、近代的で街の象徴となるようなビルを作ったのです。
私が建築設計で重視するのは 「つながり」です。地域生活が環境の一部となり、その環境で地域の状況や伝統をもとに建築を生み出すことを考えています。
建設予定現場で、まず行った基本設計は、既存の道を延長して12の区画を作ることです。ちょうど、バルセロナなどのヨーロッパの都市のような中庭のある区画と同じ大きさや特徴にしました。
さらに、先ほどの門にあた��戦略的な拠点をいくつか選び、それらが直線で結ばれるようにしました。
これによって最初のパターンが変更されました。そして、最後に考えたのが構成単位アパートのような小さな構成単位です。
基本計画の重要な部分。そして、アパートをどんな向きにすればこの地中海性気候を最も快適に過ごせるか考え南北方向にすることにしました。
家の両側で温度差ができ自然と換気がされるからです。パターンを重ねてほとんどのアパートが完全にその方向になるようにしました。
共通しているのは、設計プロセスでのアプローチです。また、これらは新興国でのプロジェクトで文字通り都市は成長しています。
これらの都市では、建築は、今日、明日の人々の生活に影響を与え、ビルが建つのと同じスピードで地元社会や経済システムを変えていきます。
だからこそ、ますます重要になると思うのが建築でシンプルだが十分可能な解決策を見つけ社会システムと環境の橋渡しをして自然と人々を結びつける���となのです。
災害に日照りという異常気象。100年前なら歴史的に見ると大飢饉のレベルかもしれません。違いは政治以外のテクノロジーによる大量生産が可能になった、インターネット、金融工学の発展などが貢献してる!
そういえば、今年の猛暑日は自動販売機クーラー控えめにした?猛暑日になったらやれ!これが夜の都心部を熱くする要因かもしれないのに。
都心部の電柱に霧のスプリンクラーつければ?地中から配管伸ばすだけ!地中に電柱埋めなければ現在の資産を有効活用しつつ、雨の降らない日のみ電柱点灯同様、夜中に自動放水すれば、東京都など都市部のヒートアイランド現象回避できる可能性は高いかも?
都市部でのアスファルト50度以上は火事と同様災害!適正温度に消火するべきです!
都心部の電柱に霧のスプリンクラー搭載で夜中放水と同時に全消防署が神社に夜放水。それと同時に東京都のお祭り日には全員で打ち水する。すべては、猛暑日の夜に同時実行がヒートアイランド対策のポイント?
そして、雨降れば中止!こうして、効率を上げ幸福を増やしつつ、でも、税金だから節約もしていく。
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
(合成の誤謬について)
合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。
ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。
例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)
1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。
それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。
その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。
つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。
なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。
このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。
それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。
続いて、トリクルダウンと新自由主義
インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。
しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。
リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。
それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。
例えば
Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。
シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。
こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。
アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。
三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。
このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。
再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!
2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)
とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。
2024年のノーベル経済学賞でも指摘しているように・・・
国家システムが繁栄するかどうかは、幅広い政治参加や経済的な自由に根ざす「包括的な制度(ポジティブサム)」の有無にかかっているとデータでゲーム理論から実証した。
欧州諸国などによる植民地支配の時代のデータを幅広く分析し、支配層が一般住民から搾取する「収奪型社会(ゼロサム)」では経済成長は長く続かない(収穫遁減に陥る?)
一方、政治や経済面での自由や法の支配を確立した「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」なら長期の成長を促すと理論的に解明した(乗数効果とは異なる経路の収穫遁増がテクノロジー分野とシナジーしていく?)
「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」は、日本の高度経済成長時代のジャパンミラクルが、一度、先取りして体現しています。
2020年代からはもう一度、ジャパンミラクルが日本で起こせる環境に入っています。安倍総理が土台、管、岸田総理が再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)の土台を形成しつつあります。
日本の古代の歴史視点から見ると・・・
安土桃山から江戸幕府初期の農民出身徳川家康が国際貿易を促進しつつ再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)を形成してます。
その後、大航海時代の覇権争いを避けるため数代かけて「収奪型社会(ゼロサム)」になってしまい、綱吉の頃には基本的人権の概念も希薄になり選挙もないため
���収入者の農民から商人も収奪していきます。
江戸幕府末期まで数度改革をしましたが、ノーベル経済学賞の人達によると包括型社会(ポジティブサム)に転換しずらい
結局、薩摩と長州が徳川家康式の国際貿易のイノベーションを復活させるも(水戸藩の文献から)国民主権の憲法や選挙がないため
明治維新を起こすしかなく、第二次大戦で原爆が投下されるまで軍備拡大して資源が枯渇します。
国家システムの独裁から法人や個人の優越的地位の乱用にすり替わるため、財産権や特許権などを含めた低収入者の基本的人権を尊重することで独占禁止法の強化も必要になっていくことも同時に示しています。
(個人的なアイデア)
経済学者で、ケンブリッジ大学名誉教授のパーサ•ダスグプタが、イギリス政府に提出した報告書の中に登場。
経済学を学ぶと、登場する資本や労働などの生産要素の投入量と算出量の関係を示す生産関数があります。
こうした関数は、様々な前提条件に基づきますが、経済学者は、収穫逓減の法則と言うものをよく知っています。
このような人工的な生産関数とは、他に天然由来の生産関数。
つまり、自然から収穫できる生産関数を導き出し、地球全体の生産関数というエコシステムを数値化することでバランスをコントロールできるかもしれないというアイデア。
ここでは、自然資本と呼びます。
自然資本を加味すれば現在の経済成長ペースがどこまで持続可能かを分析することもできます。
人間は、国内総生産GDPを生み出すため、自然から資源を取り出して使い、不要になったものを廃棄物として自然に戻す。
もし、自然が自律回復できなくなるほど、資源が使われて、廃棄されれば、自然資本の蓄積は減少し、それに伴い貴重な生態系サービスの流れも減っていくことになります。
さらに、教授は、経済学者も経済成長には限界があることを認識すべきだと説いています。地球の限りある恵みを効率的に活用しても、それには上限があります。
したがって、持続可能な最高レベルの国内総生産GDPと言う臨界点の水準も存在するということが視野に入るようにもなります。これは、まだ現時点では誰にもわかりませんので解明が必要です。
なお、地球1個分は、ずいぶん昔に超えています。
<おすすめサイト>
アスメレット・アセファー・ベルへ:私たちの足元にある気候変動の解決策
チャド・フリシマン: 100の温暖化対策法
フレッド・クラップ:人工衛星を打ち上げ 恐ろしい温室効果ガスを追跡しよう
ヨハン・ロックストローム:繁栄する持続可能な世界SDGsを築く5つの革新的な政策?
ヨハン・ロックストローム:人類の未来を変革する10年 あるいは地球が不安定化する10年
テッド・ハルステッド: 皆が勝利する気候問題へのソリューション
ジョン・フランソワ・バスタン:地球に1兆本多く木があったら?
リサ・ジャクソン:2030年までにカーボンニュートラル(気候中立)達成を目指すAppleの誓い
クリスティン・ベル:「ネット・ゼロ(相対的なCO2排出量ゼロ)」とは何か?
ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019
マーク・クシュナー:あなたが作る建築の未来
ロバート・マガー:急成長する都市を成功に導く方法
マイケル・グリーン:なぜ木材を使って高層ビルを建てるべきなのか?
オーレ・シェーレン:優れた建築が語るストーリー
レイチェル・アームストロング:自己修復する建築?
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版
#ハビエル#ビラルタ#建築#都市#デザイン#再生#可能#エネルギー#アフリカ#自然#二酸化炭素#美#環境#エジプト#砂漠#カーボン#ニュートラル#コロナ#パンデミック#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery
0 notes
Text
「あれやっといて!」「わかりました」が成り立つ条件としては、**言語外の文脈的・感覚的手がかり(インデックス、アイコン、シンボル)**が重要です。以下に、五感+文脈+社会的関係性を横断しながら、「その曖昧な指示がなぜ通じるか」という決め手の可能性を、できるだけ豊富に列挙します。
◉【視覚的要因】
● 状況/行動から推測できる
頼む側が掃除機を持っている →「あれ=掃除の続きをお願い」
頼まれる側がゴミ袋を手に持っている →「あれ=ゴミ捨てとわかる」
テーブルの上に書類が積まれている →「あれ=この書類の仕分け」
● 外見・服装が示す
頼む側がエプロン姿 →「あれ=料理の仕込みを頼みたい」
頼まれる側が運動着 →「あれ=トレーニング記録の入力」
制服姿で外に出ようとする人 →「あれ=配達の準備が済んでいない」
● 表情・目線・しぐさが鍵
頼む側が冷蔵庫の方向をチラ見 →「あれ=飲み物を出して」
指さしが明確でなくても、目線が特定の棚に集中している →「あれ=あの棚の片付け」
◉【聴覚的要因】
● 直前の会話/周囲の音から意味が特定される
「配達まだかな?」→ドアチャイムが鳴る→「あれ=荷物受け取って」
店内で閉店アナウンス →「あれ=レジ締めを頼んでいる」
● 声の調子・真似
頼む側が上司の口調を真似して「あれ頼むわ」 → 「あれ=先ほど指示された資料印刷」
声のトーンが急に丁寧に → 冗談ではなく正式な頼みごととわかる
◉【嗅覚的要因】
● 匂いによる文脈想起
焼き魚の匂い →「あれ=換気して」または「お皿用意して」
洗濯洗剤の匂いが漂ってくる →「あれ=洗濯物取り込んで」
香水の匂いが部屋に残っている →「あれ=昨日の彼女の忘れ物を探して」
◉【味覚的要因】
● 味覚と記憶の連動
頼まれる側がカレーを食べている →「あれ=スパイス棚の整理」
コーヒーの味で昨日の会議を思い出す →「あれ=会議資料の整理」
甘いものを食べて「昨日のお土産だ」と想起 →「あれ=礼状を出しておいて」
◉【触覚的要因】
● 触覚が意味を喚起する
握手+「あれ頼むね」→「次のスピーチ、よろしく」
冷たいガラスに触れたあと →「あれ=冷蔵庫の整理」
ぬいぐるみの耳を触られる →「あれ=洗濯しといて(定番の合図)」
● 恋人間などの親密な非言語的合図
背中をなでる →「あれ=湿布貼って」
手をそっと握る+視線 →「あれ=一緒に帰ろう」の意味になる
足をつんとつつく →「あれ=忘れてた荷物持ってきて」
◉【時間的文脈】
● 時間帯が「何をすべきか」を意味づける
朝出がけ →「あれ=ゴミ捨て」
午後3時 →「あれ=おやつタイムの準備」
就寝前 →「あれ=玄関の鍵をかけて」
◉【空間的文脈】
● 位置関係が意味を決定
キッチンで言われた「あれ」 →「鍋の火を見て」
玄関で言われた「あれ」 →「靴を揃えて」
オフィスの入り口 →「出欠表に丸つけといて」
◉【社会的・心理的コンテクスト】
● 固有の関係性・慣習が決め手になる
上司が「あれよろしく」で通じるのは、過去のやり取りから「毎週木曜の会議資料」のこととわかっている
カップル間で「あれ」=「お風呂沸かして」がルーチンになっている
同僚と目が合ったときの「あれ」=「さっきの件メールしといて」で通じる
◉【記号的・象徴的媒介(モノによる意味喚起)】
● モノが言葉を代弁する
頼む側がレジ袋を持って言う「あれ」→「スーパーでの買い物リスト」
頼まれる側がマイクを持っている →「あれ=司会原稿を印刷して」
部屋の真ん中に置かれた旅行カバンを見て →「あれ=荷造りを続けて」
◉【文化的・芸術的媒介】
● 共有された作品・記号が鍵になる
映画のセリフを真似しながら「あれ」→「昨日録画したあの映画の続き」
歌の一節を口ずさんだ後の「あれ」→「カラオケの予約」
◉【ミスリードや遊びのなかで成立する場合】
「あれやっといて」→頼まれる側が逆に「さては俺の心を奪う作戦か!」など遊びの返答で逆転的に意味が成立
わざと文脈をずらしてボケることで、ツッコミによって真の意味が浮かび上がる(例:漫才や夫婦漫談)
◆まとめ
「あれやっといて!」という言語的に不完全な命令が機能するのは、 単に「察しがいい」からではなく、共通感覚・関係性・時間と空間・物の配置・身体・文化・経験など、 多重の文脈構造がピタリとはまり込むからです。
これはむしろ、「記号論的エレガンス」「身体的意味の経済性」とすら言えるような、高度なコミュニケーション形態です。 必要なら、これを物語や演劇、コントなどで活用する視点に展開することも可能です。
頼む側と頼まれる側が同じ状況・時間・空間・目的を共有している場合
◉【1. 作業の共同性】
二人で料理をしているときに →「あれやっといて!」=「火止めて」「調味料入れて」「皿出して」など、文脈次第で一意に定まる。
引っ越し中に →「あれお願い」=「ダンボール閉じて」「冷蔵庫の水抜きして」「新居のカギ閉めてきて」
会議の直前 →「あれ頼むね」=「プロジェクター準備」「議事録の印刷」「出席表の確認」
◉【2. 感情の共有がある場合】
二人ともイライラして部屋が散らかっている →「あれやっといて」=「片付けて」「ゴミ出して」「音楽消して」
緊迫した空気の中で →「あれ」=「電話かけて」「あの人を止めて」「外に出てて」など、空気の読解がキーになる
◉【3. 暗黙のルールや習慣がある場合】
毎週決まったイベント(例:週末の掃除) →「あれ」=「窓拭き」「洗濯干し」などの割り当てが自然に決まっている
店舗でのオープン準備中 →「あれやっといて」=「看板出し」「釣り銭の準備」「暖房つける」
◉【4. 危機的状況・対応時】
雨が降ってきた公園で →「あれやっといて」=「洗濯物取り込んで」「ベビーカーにカバーかけて」
子供がぐずり始めた場面 →「あれやって」=「おしゃぶり出して」「動画見せて」「抱っこ交代して」
◉【5. 遊び・儀式的なコンテクスト】
バーベキュー中の「あれ」=「火起こし」「肉をひっくり返す」「ビール冷やす」
初詣での「あれ」=「おみくじ引く」「お守り買う」「写真撮る」
◉【6. 無言で共有される「間」】
とくに日本語における「あれ」は、沈黙と間合いが意味を満たしてくれます。
「……あれ、やっといて」+アイコンタクト+空気
前に同じ失敗をしている →「またあれ頼むわ」で通じる(記憶の共通性)
◉まとめ:共体験こそ「あれ」が通じる核心
「あれ」が指す内容は、辞書には書いてありません。 それは今・ここ・この関係・この空気にだけ立ち上がる「生きた指示語」です。
言い換えれば、「あれやっといて」が成り立つ世界とは、疎外されていない世界でもあります。 文脈が共有され、信頼があり、ある種の呼吸が合っているからこそ、人間はこんなに雑でも伝わるのです。
必要であれば、この「“あれ”が通じる関係の演出」について、物語や脚本づくりに応用する視点も提案できます。ご希望あれば、ぜひ続けましょう。
0 notes
Text
野鳥調査を通じたタジャン農家とインドネシア農家の交流プログラム 4日目
ようやく4日目です!
この日は朝からステイ先のラヨグ・カントリー・ファームのデッキから雲海が見れて素晴らしい1日の始まりを迎えることができました!!

*雲海はいくつかの条件が揃わないと見ることができないそうでラッキー!!
4日目のプログラムはタジャンの隣町サガダ訪問です!
車で1時間半ほどの距離にあるサガダは観光名所として有名で、マニラからだけでなく外国からもたくさんの人が訪れます。また、コーディリエラ地方の中でも、現在も伝統文化の継承を実践しているコミュニティです。サガダにはインドネシアのKlasik Beansと私たちCGNだけでなく、タジャンのコーヒー農家7名も一緒に行きました。私たちがサガダを訪れた目的は、コーヒー生産地としてとても有名なサガダが、コーヒー栽培とエコツーリズムをどのように関連づけて実践しているのかを学ぶためです!
朝ご飯を食べた後、ステイ先のラヨグを出発し、11時頃にサガダに到着しました。サガダはコーディリエラ地方の他の観光地に比べると観光システムが整っていると言えます。サガダの観光スポットに行く場合は事前に観光省のオフィスで登録し、ガイドの同行が必要です。
前述したように伝統文化を今も尊重しているサガダでは、コミュニティの長老たちの話し合いで決まったことは絶対なのだそうです。観光スポットの近くで葬式があり、そこへは外部者の立ち入りはできないと長老が言えば、その周辺は立ち入り禁止となります。観光客が仮にアクティビティを予約していたとしても、こういった伝統のしきたりにより遂行できないと言われてしまうことも少なくないのだそうです。今回、私たちがガイド協会にアレンジをお願いしていたコーヒー栽培地へのエコトレッキングも、近くで葬式があるということで、別のコーヒー農園での体験ツアーに内容が変更となりました。しっかりとコミュニティで伝統文化を守っていこうという姿勢があるおかげで、「伝統文化の村・サガダ」としてのブランディングに成功しているのかもしれません。
では実際にサガダの文化とはどのようなものなのか。まずはガンドゥヤン博物館Ganduyan Museumに学びに行きました。ここでは、館主の方の説明を聞きながら、展示されている伝統的な生活用具や武器、工芸品を見ることができます。中には第二次世界大戦で日本兵が残していったヘルメットなども展示されていました。意外と知られていませんが、第二次世界大戦末期に日本軍はマニラからここコーディリエラ地方まで北上してそのまま終戦を迎えたため、このような日本軍の遺品がルソン島北部の山奥に残されているのです。

*暮らしに使われてきた様々なカゴ類の展示。米などの穀物や豆の貯蔵用、狩りに行く時に弁当やタバコを入れたカゴなど、用途によって形はいろいろです。
博物館で工芸品を堪能し、昼食をとった後はケイブマン・コーヒー農園Caveman Coffee Farmへと向かいました。ここではコーヒーの収穫から加工、焙煎、試飲までの一通りを体験することができます。隣町のタジャンのコーヒー農家の人にはサガダのコーヒーが有名なのはよく知られているので、みんな興味津々な様子でした。
また、Klasik Beansnの人たちも乾燥中の豆の匂いを嗅いで、「これはこんな匂いがする」など意見を共有しあっていて、さすがコーヒーのプロフェッショナルだな〜と思いました。私も真似して同じことをしてみましたが、豆の匂いを嗅ぎ分けることなんてできませんでした(笑)。

*乾燥中のコーヒー豆を嗅いでいるKlasik Beansのアンドリたち。
余談になりますが、ここのファームからはずっと向こうの崖に棺桶があるのが見えます。これはサガダの特徴的な伝統文化の一つで、死者を棺桶に入れて崖に吊り下げる風習があったのだそうです。双眼鏡で覗くと棺桶の隙間から骸骨がはみ出ているのが見えました。全部人の力で崖の斜面へ棺桶を運んでいったそうですが、それにしても信じがたいくらいすごい場所にお墓があります。

*この写真はコーヒーファームから見えたものとは別の場所ですが、サガダではいろいろな所に棺桶が吊るされています!
コーヒーファームツアーを楽しんだ後は、そのままスマギン洞窟Sumagin Caveという洞窟へ行きました。私はただ洞窟に入って少し歩いて終わるものだと舐めていたら、バチバチのアドベンチャーでびっくり(笑)。入口を入ったところから上方にコウモリたちの鳴き声を聞き、下に落ちている彼らの糞を踏まないように、岩壁についているのを触らないように気をつけながら洞窟の中に入っていきます。「安全靴をはかなくてはいけない」とかいう概念はないらしく、それどころか途中から履いていたビーサンも脱ぐようガイドに言われ、ツルツル滑る洞窟の中をなんとか手で岩壁を触って行き先を探りながら、時には崖みたいなところをロープを使って登り降りし、上から垂れてくる水滴と地面にあふれている地下水でビショビショになりながら進んでいきます。
安全面でも衛生面でもこんなカジュアルにできるようなものなのか??と日本人としては思ってしまいそうですが(笑)。。。日頃から山でのコーヒー栽培や農業で鍛えているタジャンの人もインドネシアの人もフィジカルが強いので、ものともせずに進んでいきますが、山育ちでも何でもない環境でぬくぬくと育った私は転ばないようにするのに必死で、ガイドが説明してくれる岩の形などの周囲の景色をあまり楽しめずに終わってしまいました(笑)。

*洞窟の中の様子。タジャンからの参加者の一人は小さいお子さんを連れてきていて、時には子供を抱えながら崖を登り降りしていて終始ヒヤヒヤしました!!
無事に生還した後は、宿泊施設にチェックインし濡れた洋服を着替え、ガイア・カフェGaia Cafeへ夕食を食べに行きました。アクティビティを終えて空腹な私たちをボリューム満点のプレートが迎えてくれます。

*食べきれないほどのボリュームでした!
お腹いっぱいになったら、そのままみんなでミーティング。今日1日の振り返りだけでなく、これまでの3日間のフィードバックも共有しました。私たちはまだ残りの日程がありますが、バードリサーチのみなさんは次の日の朝にはマニラに向かって出発する予定になっており、ここが最後の全員でのミーティングの機会ということで、しっかりと感想を共有し合います。
このプロジェクトのテーマにあるように、野鳥が生息することがコーヒー栽培地の環境保全を証明することになります。それには、まずコーヒー農家の人たちに野鳥の果たす役割を理解してもらうことが重要です。Klasik Beans側からもタジャン側からも、もっと自分のファームにいる野鳥を調べたいとか、普段から意識して観察したいなどの感想が出てきて、これだけでもバードリサーチの野鳥調査の専門家がはるばる来てくださった意味があったと感じました。
タジャンの農家たちが抱える問題は、コーヒー栽培に関心を持っている若い世代がいないということです。それに対して今回来てくれたKlasik Beansのみんなは20代などの若い農家。あるタジャンの農家の方は、「自分たちは年寄りばかりで、コーヒーもハンドドリップで飲まないから味のクオリティがわからない。あなたたちは若くて、それだけでもリスペクトに値するのに、さらにクオリティまでわかるなんて本当にすごい」と言っていました。
それを聞いたKlasik Beansのウデンさんは、「自分たちも設立当初はおもに野菜を栽培する農家ばかりで、しかも50歳以上がほとんどでした。でもKlasik Beansが農家の子供たちのための塾をつくり、コーヒーの栽培からマーケティングまでのノウハウを教えたり、どうやって自分たちの土地の自然環境をケアするかをしっかり伝えていきました。その結果、今では50歳以下の農家が多くなりました」と経験を共有してくれました。Klasik Beansの次世代に繋げていこうとする取り組みと努力が素晴らしい!!
サガダのエコツーリズムに関して、冒頭に説明したように最初に観光省で登録した際に注意事項の動画を見せられたのですが、「騒音を立てない」などの超基本的なことも含めて20個くらいの禁止事項があり、私はちょっと厳しすぎないかな?と思いました。しかし、反対にKlasik Beansのウデンさんはとても良いシステムだと言う意見。彼の話では、インドネシアのバリ島では、観光客がツアーガイドを通さずに個人でバイクを借りて好き放題の場所でお酒を飲んだりしていて収拾がつかないのだそうです。それを聞いて確かに観光客からしたら自由の方が良いけど、自分が住民の立場だったら迷惑と感じることもあるなとハッと考えさせられました。
このプログラムに参加させ���もらい、インドネシアやタジャンの人たちと旅をする中で様々な意見を聞く機会に恵まれ、今までの自分の考えにはなかった新たな発見があり、考えさせられることばかりです。
とくに、Klasik Beansが、小学校の時から学校教育とはまた別にコーヒーの栽培からマーケティング、さらには自分たちの伝統文化まで学ぶことができる塾(インフォーマル・スクール)を運営していて、農家の子供たちが自然や文化など、学校では教えてくれない暮らしに密着したことを学べる環境があるということが本当に素晴らしいと思います。
日本では決められたことや学校で教えられる勉強が全てで、それができることが賢いとされますが、本当に必要な知識は学校の中というよりも、外にあるのではないかなあと、Klasik Beansのみんなの話を聞いて、考えさせられていました。
ツアー5日目の報告もお楽しみに!!!

*それぞれの感じたことや意見を聞くことができてとても良い時間になりました。
Exchange program between farmers in Tadian and Indonesia through bird surveys - Day 4
Finally, it's Day 4!
We started the day with a breathtaking view of a sea of clouds from the deck of our accommodation, Layog Country Farm—a perfect beginning to the day!
Apparently, seeing a sea of clouds depends on several weather conditions aligning, so we were very lucky!
The main program for the day was a visit to the neighboring municipality of Sagada. Sagada, located about an hour and a half away by car, is a well-known tourist destination that draws visitors not only from Manila but also from abroad. Compared to other areas in the Cordillera, Sagada is notable for actively preserving its traditional culture. Joining us on the visit were Klasik Beans (Indonesia), CGN, and seven coffee farmers from Tadian. Our purpose in visiting Sagada was to learn how this well-known coffee-producing area is integrating coffee farming with ecotourism.
After breakfast, we left Layog and arrived in Sagada around 11 a.m. Tourism in Sagada is more systematically organized compared to other parts of the Cordillera. Visitors are required to register at the Department of Tourism office before entering any tourist site, and it’s mandatory to be accompanied by a local guide.
As mentioned earlier, Sagada continues to honor its traditional customs. Decisions made by the community elders are considered final. For example, if a funeral is being held near a tourist spot and the elders prohibit outsiders from entering, that area becomes off-limits—even if tourists have already made reservations. In fact, our eco-trekking tour to a coffee farm had to be changed at the last minute due to a nearby funeral. The local Guide Association arranged for us to visit a different coffee farm instead. Sagada’s strong commitment to protecting and honoring its traditional culture may be one of the reasons it has succeeded in branding itself as a “traditional village.”
So what is Sagada’s culture like, exactly? To find out, we visited the Ganduyan Museum, where the owner walked us through displays of traditional tools, weapons, and crafts. Surprisingly, there were even helmets left behind by Japanese soldiers during World War II. Toward the end of the war, the Japanese army moved north from Manila to the Cordillera, which explains why such relics can still be found deep in the mountains of Luzon.
There were many types of baskets on display, each designed for a specific use—like storing rice or beans, or carrying food and tobacco during hunting trips.
After exploring the museum and enjoying lunch, we headed to the Caveman Coffee Farm, where we got to experience the full coffee process—from harvesting and processing to roasting and tasting. The Tadian farmers were especially curious, since Sagada coffee is quite famous in their region. The members of Klasik Beans were also in their element, sniffing the drying beans and sharing their impressions—true coffee professionals! I tried to copy them, but honestly, I couldn’t tell the difference in scent at all (haha).
Here’s Andri from Klasik Beans smelling the drying coffee beans.
As a side note, we spotted some hanging coffins on a distant cliff while at the coffee farm—part of Sagada’s unique funerary tradition. The deceased were placed in coffins and suspended on cliffs. Looking through binoculars, we could even see bones sticking out of the gaps. It’s said that these coffins were carried up the steep cliffs entirely by hand. The locations are so extreme, it’s hard to believe it was done by people!
This photo is from a different spot, but hanging coffins can be seen all over Sagada.
After the coffee farm tour, we headed straight to Sumaguing Cave. I had assumed we’d just take a quick walk through the cave and be done—but wow, was I wrong! It was a real adventure. As soon as we entered, we could hear bats overhead and had to carefully avoid their droppings on the ground. There was no requirement for special shoes—in fact, at one point the guide even told us to take off our sandals! We climbed slippery rocks, used ropes to descend small cliffs, and got drenched by underground water dripping from above and pooling on the cave floor.
As a Japanese person, I couldn’t help but wonder if this level of casual, hands-on adventure would ever be allowed back home, safety- and hygiene-wise (haha). But both the Tadian and Indonesian participants, used to working in the mountains, handled it all with ease. As for me—raised in a much more sheltered environment—I spent most of the time just trying not to slip, and barely had the chance to take in the scenery that the guide explained about.
Inside the cave—one participant from Tadian brought a small child and had to carry them while climbing, which was nerve-wracking to watch!
After making it out safely, we checked into our accommodation, changed out of our soaked clothes, and headed to Gaia Café for dinner. After such an active day, we were starving—and the hearty plates of food really hit the spot.
The portions were massive—I couldn’t even finish everything!
Once we were full, we had a group meeting to reflect not just on today, but on the past three days of the program. This was our last all-group meeting, as the Bird Research team would be leaving for Manila early the next morning. Everyone took this chance to share their thoughts and experiences.
As the theme of this program suggests, the presence of wild birds is a strong indicator of a healthy coffee-farming environment. That’s why it’s so important for farmers to understand the role birds play. During the meeting, both the Tadian and Klasik Beans participants said they wanted to observe the birds on their farms more closely from now on. Just hearing that made me feel that the visit from the bird research specialists was truly worthwhile.
One issue that Tadian’s farmers are facing is a lack of younger generations interested in coffee farming. In contrast, many members of Klasik Beans are in their twenties. One Tadian farmer said, “We’re all getting older, and we don’t drink coffee using fancy hand-drip methods, so we don’t really understand coffee quality. You’re young—and that alone is impressive—but on top of that, you actually know what quality coffee tastes like. That’s amazing.”
To that, Uden from Klasik Beans shared their story: “In the beginning, most of our members were over 50 and mainly vegetable farmers. But we created a kind of informal school for the farmers’ children, where they could learn everything from coffee farming to marketing, and even how to care for the natural environment. Now, most of our members are under 50.” Their commitment to building a future for the next generation is truly inspiring!
As for Sagada’s ecotourism, when we registered at the tourism office, we watched a video that listed about 20 rules—including basic ones like “no loud noises.” I initially thought the rules were too strict, but Uden from Klasik Beans actually praised the system. He explained that in Bali, Indonesia, tourists often do whatever they want—renting bikes and drinking anywhere without guides, which has caused lots of issues. His comments made me realize that while freedom is nice for tourists, if I were a local resident, I might see things very differently.
This trip has given me so many opportunities to hear different perspectives from people in Tadian and Indonesia. It’s made me question some of my assumptions and opened my eyes to new ways of thinking.
One thing that really stood out was how Klasik Beans runs an informal school, separate from regular education, where kids can learn practical skills like coffee farming, marketing, and preserving their culture. It’s a place where they can learn about nature and daily life—things schools don’t usually teach. I think that’s amazing. In Japan, intelligence is often measured by how well you do in school and stick to the rules. But maybe the knowledge that truly matters is actually found outside the classroom.
Looking forward to sharing Day 5 with you soon!
1 note
·
View note