#恋愛ドキュメント
Explore tagged Tumblr posts
Text

【まさにロックスター✨】最高の宝石ドレスで大満足💕/ マイ・ドリーム・ウエディングドレス シーズン15





#ドレスデザイン研究室#アメリカ人#アメリカ文化#アメリカ生活#ウエディング#ウェディングドレス#カップル#ドレス#ブーケ#リアリティショー#リアリティ番組#��ーホリ#国際恋愛#外国人#婚活#恋愛ドキュメント#文化の違い#海外#海外ドラマ#海外生活#海外留学#留学#結婚#結婚式#英語#英語勉強
0 notes
Quote
園 子温(その しおん、 1961年〈昭和36年〉12月18日 - )は、日本の映画監督・脚本家。愛知県豊川市出身[3][4]。 来歴 出生から高校 1961年(昭和36年)、愛知県豊川市生まれ[3][4]。父である園音巳は英語を教えていた愛知大学の教授であった[1]。豊川小学校、豊川東部中学校を卒業[4]。とても厳格な家庭で育った反動で17歳の時に実家を飛び出し、上京したとされるが[1]、豊橋東高校は卒業している[4]。17歳で詩人デビューし、『ユリイカ』と『現代詩手帖』に詩が掲載された。 大学入学以降 映画監督として活動する以前は漫画家志望でもあり、法政大学入学後、20歳の時に出版社に漫画の持ち込みを行うも「まだ他人の気持ちがよく判らないんじゃないかな」と言われボツを喰らう[5]。 その後、リベンジのため本を読み漁り、映画を年間何百本と鑑賞したことがきっかけで8mm映画を撮り始める。 1986年、8mm映画『俺は園子温だ!』がぴあフィルムフェスティバル(PFF)入選。翌年、8mm映画『男の花道』でグランプリを受賞[4]。 1990年、ぴあフィルムフェスティバルスカラシップ作品として制作された16mm映画『自転車吐息』は、第41回ベルリン映画祭正式招待された[4]。 1993年、『部屋』を制作。翌年、サンダンス映画祭審査員特別賞を受賞。 『桂子ですけど』(1996年)、『風』(1998年、通産省制作)など、映画制作を続ける。 一方、街頭詩パフォーマンス「東京ガガガ」を主宰する。4000人のパフォーマーが渋谷のストリートで展開。このドキュメントを収めたジャン=ジャック・ベネックスのテレビ番組はフランスで視聴率40パーセントを超える。 ファッションデザイナー荒川真一郎とのプロデュース、短編『0cm4』(1999年)を上映した。 1994年3月10日〜17日、吉祥寺バウスシアター全館を貸し切り「園子温��臨祭」を開催。 1995年、100時間に及ぶ素材からなる大長編映画『BAD FILM』制作に取りかかる(2012年完成)。 2000年、『うつしみ』を制作、劇場公開。 2001年、『自殺サークル』を公開。新宿武蔵野館における過去最高の観客動員数となった。カナダファンタ映画祭(ファンタジア2003)にて“観客賞”を獲得。同時に“今年、最も優れた映画に贈る賞”も獲得。2002年度日本映画プロフェッショナル大賞第10位 。 2002年、『HAZARD』という ニューヨークを舞台にオダギリジョー扮する不良青年の青春映画を制作した。 2003年、前作に続けてオダギリ、田中哲司、村上淳、市川実和子等が出演した『夢の中へ』を制作。さらに同年、宮崎ますみ主演でR18指定の家族劇『奇妙なサーカス』を制作。 2006年『紀子の食卓』を公開。第40回カルロヴィヴァリ映画祭・コンペティション部門の“特別表彰賞”と、国際シネマクラブ連盟による“ドン・キホーテ賞”を受賞。また韓国で開催された第10回プチョン国際ファンタスティック映画祭コンペティション部門の観客賞と主演女優賞受賞した。 2007年、テレビ朝日系ドラマ『時効警察』に監督として参加した。 2008年、『愛のむきだし』を公開。第9回(2008年)東京フィルメックスにおいて観客の投票によって選出される「アニエスベー・アワード」を受賞。第59回(2009年)ベルリン映画祭に出品され、「カリガリ賞」「国際批評家連盟賞」を受賞した[4]。続く『ちゃんと伝える』では故郷・豊川を舞台にした。 2011年、『冷たい熱帯魚』を公開。第67回ヴェネツィア国際映画祭オリゾンティ・コンペティション部門に正式出品した[4]。さらに同年『恋の罪』を公開。 結婚以後 2011年10月23日、監督した映画『冷たい熱帯魚』『恋の罪』に出演した神楽坂恵と婚約した旨が報じられた。結婚以降も妻の神楽坂を多くの自身の作品に出演させている。 2012年、『ヒミズ』を公開。古谷実の同名漫画を映画化で映画監督と脚本を担当した。園にとって、初の漫画原作物の映画化担当であった。第68回ヴェネチア国際映画祭コンペティションに出品され、主演の染谷将太、二階堂ふみが「最優秀新人俳優賞(マルチェロ・マストロヤンニ賞)」を受賞した[4]。 10月、原発事故を描いた『希望の国』を公開。 第37回トロント国際映画祭にて「NETPAC アジア最優秀映画賞」を受賞。主演の夏八木勲は第63回芸術選奨・文部科学大臣賞並��に第67回毎日映画コンクール男優主演賞を受賞した。 2013年4月、テレビ東京系ドラマ『みんな!エスパーだよ!』にて総合監督を務めた。同月、「芸人」宣言をし舞台デビュー。9月、『地獄でなぜ悪い』を公開。 第70回ヴェネツィア国際映画祭オリゾンティ部門に正式出品された[4]。第38回トロント国際映画祭では、ミッドナイト・マッドネス部門観客賞を受賞[4]。 2014年6月、小説「毛深い闇」を河出書房新社より出版。8月、井上三太原作の『TOKYO TRIBE』を公開。11月、雑誌「GQ JAPAN」が「GQ MEN OF THE YEAR 2014」を受賞した。 2015年5月、和久井健原作、綾野剛主演で『新宿スワン』を公開。園作品最大のヒットを記録。同年6月、「魂の集大成」と謳ったSFファンタジー怪獣映画『ラブ&ピース』を公開。第5回北京国際映画祭にて日本映画として初の出品作になった。カナダ・モントリオールの第19回ファンタジア国際映画祭では観客賞を受賞したものの[4]、翌2016年公開されて81億円の興収を出した『シン・ゴジラ』と同じ長谷川博己主演の映画であるが興収は5300万円であった[6]。 2015年7月、山田悠介の原作にオリジナル要素を加えた『リアル鬼ごっこ』を公開。第19回ファンタジア国際映画祭にて最優秀作品賞(シュバル・ノワール賞)、審査員特別賞を受賞した[4]。スペイン・マラガ・ファンタスティック映画祭では最優秀作品賞と特殊効果賞を受賞[4]。 同年9月、テレビドラマシリーズも監督(3人)と脚本(4人)の一人として担当した『みんな!エスパーだよ!』の映画化時には、脚本を田中眞一と共に[7]、監督は一人で務め、全面愛知県の東三河でロケしている[4][7]。 2015年7月、初の個展「ひそひそ星」展を開催。同時期にワタリウム美術館オン・サンデーズにて絵本「ラブ&ピース」の原画展も開催。9月、Chim↑Pom発案の「Don’t Follow the Wind」展(ワタリウム美術館)にて映像インスタレーションを発表した。 2015年に地元の「とよかわ広報大使」に就任する[4]。 2016年4月、美術館では初の個展、園子温展「ひそひそ星」をワタリウム美術館にて開催。5月、第40回トロント国際映画祭にてNETPAC賞(最優秀アジア映画賞)を受賞した『ひそひそ星』を劇場公開する。大島新監督のドキュメンタリー映画「園子温という生きもの」が公開される。 心筋梗塞による入院以後 2019年2月7日、心筋梗塞を発症し、病院に救急搬送され手術を受ける[8]。同月21日、退院[9]。6月25日、「Netflixオリジナル作品祭」に出席し、病後初めて公の場に姿を見せた[10]。 2021年10月8日、ハリウッド初挑戦となる映画である、『プリズナーズ・オブ・ゴーストランド』が公開された[11]。ニコラス・ケイジを主演として起用し、2019年に撮影を終えていた『エッシャー通りの赤いポスト』のワークショップ参加者も多数参加した作品である。 2021年12月25日、原点回帰のインディーズ作品として2019年に撮影が完了していた『エッシャー通りの赤いポスト』が公開された[12]。51名の無名役者が参加するワークショップで制作された映画作品であり、出演者が店舗や路上で宣伝活動やチケットの手売りを行ったり、関東の複数のミニシアターで多数回の舞台挨拶も行った。 性加害報道以後 詳細は「#不祥事」を参照 2022年3月、セクハラ・性行為強要を告発される。(#不祥事参照) 2022年11月7日、SmartFLASHが報じたところによると、12月20日から上映される『もしかして、ヒューヒュー』にて、偽名を用いて脚本を担当したと、妻であり事務所社長でもある神楽坂が取材に応じている[13]。 人物 洋画好き 著書によれば幼少期・少年期から映画好きであり、それも洋画ばかり見ていた。少年期から好きな作品にアメリカンニューシネマのアーサー・ペン『俺たちに明日はない』『左利きの拳銃』やフランス映画のジャン・ギャバン主演『望郷』や『ジャンヌ・ダルク裁判』にフランソワ・トリュフォー作品、1960年代までのアメリカ映画はかなり見ていたと述べている。好きな監督にウィリアム・ワイラーやイタリアのヴィットリオ・デ・シーカ、好きな役者・スターにジョン・ウェイン、リチャード・ウィドマークやジャン・ギャバン、アラン・ドロン、ソフィア・ローレン、リリアン・ギッシュ、ポール・ニューマン、イングリッド・バーグマンなどを挙げ、とりわけイングリッド・バーグマンとは本気で結婚したいほど好きな思いを抱いていたという[14]。 出演したラジオ『スカパー! 日曜シネマテーク』でルネ・クレマン監督のフランスの反戦映画の名作『禁じられた遊び』を好きな映画に挙げ、「この映画は小学生の時にテレビで見ました。当時はほぼ毎日、地上波で夜9時から映画番組があって、ゴダールやトリュフォーすらも放送していたんです。家族で『ウルトラマン』を見た後にゴダールを見るなんて、今ではちょっと信じられないですよね(笑)」と述べている[15]。 深作作品・格好良いヤクザ好き また別の回のラジオ『スカパー!日曜シネマテーク』では深作欣二監督の『仁義なき戦い』を選んでおり「深作監督とお話する機会はなかったんですが、僕にとっては心の師匠。映画を作る時は常に深作監督のことが頭にあり、『地獄でなぜ悪い』でも「深作警察署」が登場したり、『仁義なき戦い』の音楽が流れたりします。それくらいずっと憧れてきた、影響を受けてきた監督です。」「ヤクザ映画なんですが、実は深作監督も菅原文太さんもすごく真面目���タイプで、ヤクザに対して距離感を持っている人です。でも実はそれがヤクザが格好良く描ける秘訣。コッポラが『ゴッドファーザー』を撮った時も同じで、ヤクザやマフィアをまったくリスペクトしてない人が撮ると、客観的に描けるので格好良くなるんです。」と評している[16]。 主張 ジャパニーズアニメ嫌悪 2016年は「近年稀に見る邦画の当たり年と言われた本年」と呼ばれたが、そのなかでも話題を一手に集めたのは、新海誠監督のアニメ映画『君の名は。』と、庵野秀明監督の『シン・ゴジラ』の二作品であり、『君の名は。』は年間興行収入ランキング1位の251.7億円、『シン・ゴジラ』は3位であるが、例年なら邦画興行収入で首位となるレベルの81億円を記録する大ヒットとなった。しかし、園子温は2016年12月9日に、「糞ジャパアニメ、すべて死ね。」「あとよ、怪獣映画のリメイクで儲けたクズどもも。」「二度と怪獣映画のリメイクごときで現代の311を語るな、クズども」、と下記の島国辺境ツイートと共に四時間にわたって連続で罵倒のツイートをした[17]。後に上記のツイートは削除された。ネット上では『シン・ゴジラ』と同じ長谷川博己を主演で前年に撮られた自身の怪獣映画『ラブ&ピース』が興収5300万円だったことから、「園が嫉妬のあまり中2病を発症させた」と園を批判するツイートが殺到した[6]。 ただし、インターネットメディアリテラは園による『君の名は。』『シン・ゴジラ』批判について、「まさに正論だと思うが、しかし、こうした意見はしょせん異端に過ぎない。」と賛意的な報道をした[6]。 護憲・SEALDS支持 自民党が2016年の参院選で改憲を現実のモノにしようとしているとして、2015年9月11日に安倍晋三内閣における特定秘密保護法・集団的自衛権行使容認への反対や護憲、「従来の政治的枠組みを越えたリベラル勢力の結集」を訴える『TAKE BACK DEMOCRACY(民主主義を取り戻せ)#本当に止める SEALDs 5時間SPECIAL!!!!!』に、磯部涼(司会)、SEALDs、中野晃一上智大学教授、日本学術会議の廣渡清吾前会長らと共に出演した[18]。 2016年12月に上記のジャパニーズアニメーションへの批判の際に、「評論家のための評論しやすい映画ばかり。狙ってんのかお互い癒着して。革命家も産めない肉体のない言葉、、乾いた言葉を。」「去年見たSEALDSの何倍も何倍も薄めた小さなセカイ系とやら。セカイ系の正体は地球上の規模じゃねえ。このセカイの小さな島国辺境の、空想されたせ・・か・・い・・やめろ。」とツイートしている[6]。 批判 宇野維正はキネマ旬報にて、2021年12月に園が映画監督を務めた「エッシャー通りの赤いポスト」について、「現実から浮遊したスモールワールドで若い女優が暴れ回り、反体制的なイメージと戯れる」という園子温自身のシグネチャー・モデルに回帰した作品で5段階中星1という完全否定的な評価をしている。園の帰属する「日本のサブカル村」についても演者も含んだ村内で互いに誉め合っている2010年以前と変わっておらず、園の作品は客観性の徹底的な欠如はずっとそのままであるとし、「ここまでの作家的増長の責任は、本人よりもそれを看過してきた業界にあるのではないか」と業界を含めた批判をした[19]。 園子温作品の著名なファン・友人 ファンであり友人である著名な者として、水道橋博士[20]や『映画秘宝』を創刊した映画評論家・コラムニストの町山智浩が知られる。町山は2009年のベスト10を選んだ際に、園の『愛のむきだし』を一位に選んだ。同年に日本で公開されたクリント・イーストウッド監督・主演『グラン・トリノ』を二位にして「『グラン・トリノ』は『愛のむき出し』を見るまで一位の作品」「どちらも(『グラン・トリノ』と『愛のむきだし』)「不在の聖母」を描いた作品。」と評した[21]。水道橋博士とは親交が深く[22]、お笑いライブを二人で開催したりしている[23]。水道橋博士は園子温を「映画監督として圧倒的に天才」と絶賛している[24]。他に園と親交が深い友人として、茂木健一郎、会田誠[25]、宮台真司がいる。宮台はあいちトリエンナーレの「表現の不自由展」に対する批判意見への反論に友人・園子温の作品を例にあげ、「そもそもアートは心に傷を付ける。心を回復させる娯楽とは違う」「こうした基本的なことでさえ、行政、政治家、そして市民までもが分かっていないことに驚きました」と開催を擁護している[26]。 2009年のキネマ旬報のオールタイムベストの日本映画編のアンケートにおいて、熊切和嘉は自身のベスト10に園の『紀子の食卓』を選んでいる。熊切は『紀子の食卓』を鑑賞した日の夜に興奮のあまり園に電話をし、「あの妹役(吉高由里子)って誰ですか!?」と直接聞いたと述べている[27]。 不祥事 2022年3月、『週刊文春』による性加害告発の流れが起きている中、日本人ハリウッド俳優で映画『硫黄島からの手紙』等に出演した松崎悠希が、Twitterにてアクターズヴィジョンのワークショップにおける園のセクハラ・性行為強要を告発。被害者は何十人もいるとしている[28]。告発後、アクターズヴィジョンは園のワークショップ映画第二弾に向けて行われる予定だったオーディションの中止を発表した[28]。 4月1日、園の制作プロダクション「シオンプロダクション」のホームページで謝罪コメントを掲載。「事実関係を整理して、改めて発表いたします」としている[29]。 4月4日、「週刊女性PRIME」が園の性加害を出演女優らが告発した記事を掲載。[30]。週刊女性PRIMEが園に電話取材を行ったところ性加害疑惑について否認。電話口を代わった女性から文書での質問を要求されたため対応したものの、期限までの回答はなかった[30]。 4月6日、「週刊女性PRIME」の報道を受けて園が謝罪文を発表。関係者や作品の視聴者にお騒がせしたことを謝罪し、監督として今後の在り方を見直したいと記した。一方で性加害の報道内容については事実と異なる点が多く、自分以外の関係者にも迷惑が掛かっていることを考慮し、法的措置をとる姿勢を示した[31]。その後、5月18日付で『週刊女性』を発行する主婦と生活社を相手取り、損害賠償や謝罪広告、ネット上の記事の削除を求める訴訟を東京地方裁判所に起こした[32]。 12月27日、主婦と生活社が『週刊女性』2022年4月5日発売号および4月12日発売号の記事と同一内容の「週刊女性PRIME」のインターネット上の記事を全文削除することを受け入れ、裁判上の和解により解決した[33][34]。 作品 映画監督作品 LOVE SONG(1984年、劇場未公開) 俺は園子温だ!(1985年、劇場未公開) 愛(1986年、劇場未公開) 男の花道(1986年、劇場未公開) 決戦!女子寮対男子寮(1988年、劇場未公開) 自転車吐息(1990年5月12日) 部屋 THE ROOM(1993年10月23日) BAD FILM(1995年当時未完、2012年完成。Hi-8撮影によるオリジナルビデオ。2015年1月6日DVD発売) 桂子ですけど(1997年2月8日) 男痕 -THE MAN-(1998年10月31日) 0cm4(パリコレクションバージョン)(1999年7月14日) うつしみ(1999年12月18日)[35] ある秘かなる壺たち(2000年2月7日)- 公開時のタイトルは「性戯の達人 女体壺さぐり」 風(2001年1月27日。製作は1998年。16mmフィルム作品) 父の日(2001年、劇場未公開) 自殺サークル(2002年3月9日) プロムナイト(2002年、未完) ノーパンツ・ガールズ 大人になったら(2005年11月12日。製作は2004年) 夢の中へ(2005年6月11日) Strange Circus 奇妙なサーカス(2005年12月24日) 紀子の食卓(2006年9月23日) HAZARD(2006年11月11日。製作は2002年) 気球クラブ、その後(2006年12月23日) エクステ(2007年2月17日) 愛のむきだし(2009年1月31日) Make the last wish(2008年、未完) ちゃんと伝える(2009年8月22日) 冷たい熱帯魚(2011年1月29日) 恋の罪(2011年11月12日) ヒミズ(2012年1月14日) 希望の国(2012年10月20日) 地獄でなぜ悪い(2013年9月28日) TOKYO TRIBE(2014年8月30日) 新宿スワン(2015年5月30日) ラブ&ピース(2015年6月27日) リアル鬼ごっこ(2015年7月11日) 映画 みんな! エスパーだよ!(2015年9月4日) MADLY(2016年4月14日) ひそひそ星(2016年5月14日) 新宿スワンII(2017年1月21日) アンチポルノ(2017年1月28日) クソ野郎と美しき世界「ピアニストを撃つな!」(2018年4月6日) 愛なき森で叫べ(2019年10月11日、Netflix) 緊急事態宣言「孤独な19時」(2020年8月28日、Amazon Prime Video) プリズナーズ・オブ・ゴーストランド(2021年10月8日、ハリウッドデビュー作品) エッシャー通りの赤いポスト(2021年12月25日) テレビドラマ 時効警察 第4話 (2006年2月3日) 「犯人の575は崖の上」 第6話 (2006年2月17日)「恋の時効は2月14日であるか否かはあなた次第」 帰ってきた時効警察 第3話 (2007年4月27日)「えっ!? 真犯人は霧山くん!?」 第6話 (2007年5月18日) 「青春に時効があるか否かは熊本さん次第!」 みんな!エスパーだよ! - 総合監督 第7話・番外編では自らもカメオ出演 第1話 (2013年4月12日) 「なんで僕に超能力だん?バス停の風、大作戦!」 第6話 (2013年5月24日) 「エスパー抗争勃発?縛られたあの娘を救え、大作戦!」 第7話 (2013年5月31日) 「禁断のコーヒー!?"セクシー女"大量生産を止めろ、大作戦!」 第10話 (2013年6月21日) 「(最終章・序)恋の罪!?モーニングコーヒーはあなたと!」 第11話 (2013年6月28日) 「(最終章・破)時は来た!善と悪の最終決戦…チームエスパー解散!?」 第12話 (2013年7月5日) 「(最終回・青春の夢)僕が世界を救うんだ!ワンワンワン大作戦!?」 番外編〜エスパー、都へ行く〜(2015年4月3日) ビデオ・オン・デマンド 東京ヴァンパイアホテル(2017年6月16日配信開始、Amazonプライム・ビデオ) 愛なき森で叫べ:Deep Cut(2020年、NetFlix) ミュージックビデオ Mail Me / 桃井はるこ (2000年) 書籍 『自殺サークル 完全版』(2002年4月 河出書房新社 / 2013年9月 河出文庫) 『夢の中へ』(2005年 幻冬舎) 『愛のむきだし』(2008年12月 小学館 / 2012年1月 小学館文庫) 『希望の国』(2012年9月 リトルモア) 『非道に生きる』(2012年10月 朝日出版社) 『けもの道を笑って歩け』(2013年9月 ぱる出版) 『毛深い闇』(2014年6月 河出書房新社) 『受け入れない』(2015年6月 中経出版) 受賞歴 映画賞 俺は園子温だ! ぴあフィルムフェスティバル入選 男の花道 ぴあフィルムフェスティバル入選 自転車吐息 第4回PFF(ぴあフィルムフェスティバル)スカラシップ作品 第41回ベルリン映画祭フォーラム部門正式出品 部屋 THE ROOM サンダンス映画祭 in Tokyo 審査員特別賞 自殺サークル 第7回ファンタジア国際映画祭(カナダ) 画期的映画部門観客賞・画期的映画賞審査員賞 StrangeCircus奇妙なサーカス 第56回ベルリン国際映画祭フォーラム部門 ベルリナー・ツァイトゥング紙・新聞読者審査賞 第10回ファンタジア国際映画祭(カナダ) グランプリ・最優秀主演女優賞(宮崎ますみ) 紀子の食卓 第40回カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭 特別表彰 国際シネクラブ連盟(FICC)ドン・キホーテ賞 第10回プチョン国際ファンタスティック映画祭 観客賞・主演女優賞(吹石一恵) 第28回ヨコハマ映画祭 最優秀新人賞(吉高由里子) 気球クラブ、その後 第16回日本映画批評家大賞審査員特別監督賞 エクステ 第3回��ースティン・ファンタスティック映画祭 ホラー審査員賞 愛のむきだし 第59回ベルリン国際映画祭フォーラム部門 カリガリ賞・国際批評家連盟賞 第11回バルセロナ・アジア映画祭 観客賞 第13回ファンタジア国際映画祭(カナダ) 審査員特別賞・最優秀主演女優賞(満島ひかり)・観客賞(アジア映画部門金賞・革新的映画部門金賞) 第8回ニューヨーク・アジアンフィルムフェスティバル グランプリ 第13回プチョン国際ファンタスティック映画祭 NETPAC賞特別賞(満島ひかり、安藤サクラ) 第9回東京フィルメックス アニエスベー・アワード(観客賞) 第34回報知映画賞 最優秀新人女優賞(満島ひかり) 第64回毎日映画コンクール 監督賞・スポニチグランプリ新人賞(西島隆弘、満島ひかり) 第83回キネマ旬報ベスト・テン 助演女優賞(満島ひかり)・新人男優賞(西島隆弘) 第31回ヨコハマ映画祭 助演女優賞(安藤サクラ)・最優秀新人賞(満島ひかり) 第14回日本インターネット映画大賞 新人賞(満島ひかり) 冷たい熱帯魚 第67回ヴェネチア国際映画祭オリゾンティ・コンペティション部門正式出品 第43回シッチェス・カタロニア国際映画祭 カーサ・アジア最優秀作品賞 ファンタスティック・フェスト2010 ファンタスティック部門 長編部門脚本賞 第13回ドーヴィル・アジア映画祭 批評家賞 第15回ファンタジア国際映画祭(カナダ) 観客賞(アジア映画部門金賞) 第35回日本アカデミー賞 最優秀助演男優賞(でんでん) 第54回ブルーリボン賞 作品賞 第66回毎日映画コンクール 男優助演賞(でんでん) 第36回報知映画賞 作品賞・助演男優賞(でんでん) 第21回東京スポーツ大賞 作品賞・監督賞・助演男優賞(でんでん) 第85回キネマ旬報ベスト・テン 監督賞・助演男優賞(でんでん) 第33回ヨコハマ映画祭 監督賞・助演男優賞(でんでん) 第16回日本インターネット映画大賞 作品賞・監督賞・助演男優賞(でんでん) 恋の罪 第64回カンヌ国際映画祭監督週間正式出品 第44回シッチェス・カタロニア国際映画祭 カーサ・アジア最優秀作品賞 第85回キネマ旬報ベスト・テン 監督賞 第16回日本インターネット映画大賞 監督賞 ヒミズ 第68回ヴェネチア国際映画祭 マルチェロ・マストロヤンニ賞(染谷将太、二階堂ふみ) 第14回ドーヴィル・アジア映画祭 批評家賞 第30回ブリ��ッセル国際ファンタスティック映画祭オービットコンペティション部門 グランプリ 2012年映画芸術日本映画ワーストテン2位 希望の国 第37回トロント国際映画祭 NETPACアジア最優秀映画賞 第86回キネマ旬報ベスト・テン日本映画9位[36] 2012年映画芸術日本映画ワーストテン1位 地獄でなぜ悪い 第38回トロント国際映画祭ミッドナイト・マッドネス部門 観客賞 ファンタスティック・フェスト2013 ガットバスターコメディー部門 作品賞・監督賞 リアル鬼ごっこ 第19回ファンタジア国際映画祭 最優秀作品賞(シュバル・ノワール賞)/審査員特別賞/最優秀女優賞(トリンドル玲奈)[37] ひそひそ星 第40回トロント国際映画祭 NETPACアジア最優秀映画賞[38] 映画賞以外 GQ MEN OF THE YEAR 2014(2014年)[39] 出演 テレビ スタジオパークからこんにちは(2011年12月20日、NHK総合) 園子温ケーブルテレビ実験室(2013年4月 - 2013年9月、ケーブルテレビJCN) アウトデラックス(2013年8月22日、フジテレビ) 有吉ジャポン(2013年11月8日、TBS) 100秒博士アカデミー(2013年12月3日・10日、TBS) ブラマヨとゆかいな仲間たち アツアツっ!(2013年12月21日、テレビ朝日) さんまのまんま(2014年3月8日、関西テレビ) 言いにくいことをハッキリ言うTV(2014年3月31日、テレビ朝日系列) 踊る!さんま御殿!!(2014年4月15日、日本テレビ) 竹山ロックンロール(2014年5月10日・17日・24日、テレビ埼玉・千葉テレビ・tvk・サンテレビ) たかじんNOマネー(2014年5月17日、読売テレビ) 情熱大陸(2014年6月15日、TBS) ダウンタウンDX(2014年6月26日、読売テレビ) ゴロウ・デラックス(2014年7月17日、TBS) ニノさん(2014年8月3日・10日、日本テレビ) - 「だって男の子だもん」回 ゲスト キン肉マン THE LOST LEGEND(2021年10月8日 - 12月10日、WOWOW) - 本人 役 ラジオ 園子温のズバリ!ラジオ(2013年1月25日、ニッポン放送) スカパー!日曜シネマテーク 特別版(2014年5月5日、TOKYO FM) ドキュメンタリー映画 園子温という生きもの(大島新監督 2016年) 伝記 速水由紀子『悪魔のDNA 園子温』祥伝社、2013年 参考文献 東方出版『KAMINOGE』vol.64 家賃3部作 園子温監督による実際の事件をベースとした3シリーズ 冷たい熱帯魚 - 1993年に埼玉県熊谷市で発生した埼玉愛犬家連続殺人事件がベースとなっている映画である。 恋の罪 - 1997年に東京都で発生した東電OL殺人事件がベースとなっている映画である。 愛なき森で叫べ - 2002年から福岡県北九州市で発生した北九州監禁殺人事件がベースとなっている映画である。 関連項目 サブカル[19] Category:園子温の監督映画 日本の映画監督一覧 脚注 [脚注の使い方] ^ a b c “厳しいを通り越して異常!? 園子温の「犬神家の一族」みたいな実家とは”. AERA dot.. (2016年5月16日) 2020年7月29日閲覧。 ^ 園子温 12月公開映画に「脚本・山本孝之」でステルス復帰!妻・神楽坂恵も“偽名”は「事実」と認める FLASH ^ a b c “愛知)園子温監督の復帰作品、豊橋市でロケ”. 朝日新聞DIGITAL. (2019年8月12日) 2020年7月29日閲覧。 ^ a b c d e f g h i j k l m n o p とよかわ広報大使 - 園子温氏の紹介 - 豊川市公式HP ^ 『月刊漫画ガロ』(青林堂)1996年4月号 ^ a b c d “園子温が『シン・ゴジラ』『君の名は。』を罵倒!「金儲け映画ごときで3.11を安易に暗喩にしたてるな」 (2016年12月18日)”. エキサイトニュース. 2022年4月4日閲覧。 ^ a b https://sgttx-sp.mobile.tv-tokyo.co.jp/static/html/bangumi/esper/introduction.php テレビ東京 ^ “園子温監督、心筋梗塞で入院し手術、命に別条なし”. スポーツ報知 (報知新聞社). (2019年2月7日) 2019年2月7日閲覧。 ^ “園子温監督が退院「これからも作品をつくり続けます」 事務所通じコメント”. スポーツ報知 (報知新聞社). (2019年2月21日) 2019年2月21日閲覧。 ^ “園子温監督 心筋梗塞後、初の公の場で「1回死んでよみがえって来ました」”. デイリースポーツ online (株式会社デイリースポーツ). (2019年6月25日) 2019年6月25日閲覧。 ^ “映画『プリズナーズ・オブ・ゴーストランド』”. bitters.co.jp. 2022年2月7日閲覧。 ^ “映画『エッシャー通りの赤いポスト』オフィシャルサイト”. 映画『エッシャー通りの赤いポスト』オフィシャルサイト. 2022年2月7日閲覧。 ^ bw.asuka (2022年11月7日). “園子温の “ステルス復帰” に「セコすぎる」の声声声…神楽坂恵の言い分にも苦言”. Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]. 2022年11月8日閲覧。 ^ 『非道に生きる』(2012年10月 朝日出版社)13p-16p ^ http://www.tfm.co.jp/movie/index.php?itemid=79809&catid=1737 ^ https://web.archive.org/web/20140222062821/http://www.tfm.co.jp/movie/index.php?itemid=69985 ^ “園子温監督、過去には「糞ジャパアニメ、すべて死ね」ツイッターで暴言事件も | リアルライブ”. archive.ph (2022年4月9日). 2022年4月10日閲覧。 ^ “DOMMUNE PROGRAM INFORMATION 2015/09/01 (火)”. DOMMUNE. 2022年4月4日閲覧。 ^ a b “映画鑑賞記録サービス KINENOTE|キネマ旬報社”. www.kinenote.com. 2022年4月4日閲覧。 ^ “水道橋博士が語る、天才・園子温監督の生き様 | CINRA”. www.cinra.net. 2022年4月4日閲覧。 ^ 『映画秘宝』2010年3月号 ^ “水道橋博士、園子温監督のモノマネで「地獄」を体験”. ORICON NEWS. 2022年4月4日閲覧。 ^ Inc, Natasha. “園子温が芸人デビュー、水道橋博士とお笑いライブ開催”. お笑いナタリー. 2022年4月4日閲覧。 ^ “水道橋博士が語る、天才・園子温監督の生き様 | CINRA”. www.cinra.net. 2022年4月4日閲覧。 ^ “1億円突破!園子温監督『地獄でなぜ悪い』を茂木健一郎、会田誠、水道橋博士がヒットの秘密を分析!”. シネマトゥデイ. 2022年4月4日閲覧。 “大ヒットを記念するトークショーに園子温監督が登場。日ごろから親交の深い脳科学者・茂木健一郎氏、現代美術家・会田誠氏、お笑いタレントの水道橋博士とともに、ジョークと毒舌、ときには会場を煙に巻くような過激なトークを繰り広げた。” ^ “そもそもアートは誰かの心を傷つける。宮台真司さん 「生半可な覚悟で見に行けば不快になって当然です」”. ハフポスト (2019年12月30日). 2022年4月4日閲覧。 ^ 「キネマ旬報オールタイムベスト 映画遺産200」。2009。同書57pの熊切のアンケートより ^ a b “日本人ハリウッド俳優、園子温監督のセクハラ告発「知り合いは身体を要求された」被害者は何十人も?”. リアルライブ (リアルライブ). (2022年3月31日) 2022年3月31日閲覧。 ^ “性加害報道の園子温監督 制作プロが謝罪【全文】 11年に20歳下出演女優と結婚”. デイリースポーツ (デイリースポーツ). (2022年4月5日) 2022年4月5日閲覧。 ^ a b “園子温の性加害を出演女優らが告発!「主演にはだいたい手を出した」と豪語する大物監督の“卑劣な要求””. 週刊女性PRIME (主婦と生活社). (2022年4月4日) 2022年4月4日閲覧。 ^ “園子温監督、性加害疑惑報道を受け直筆謝罪文を発表「今後のあり方を見直したい」「事実と異なる点が多く…」法的措置とる姿勢も”. 中日スポーツ (中日新聞社). (2022年4月6日) 2022年4月6日閲覧。 ^ “園子温監督、週刊女性側を提訴 「性行為強要」の記事「事実異なる」”. 朝日新聞デジタル (2022年5月19日). 2022年8月9日閲覧。 ^ “園子温監督が「週刊女性」記事巡り出版社と和解 性行為強要の記事を削除”. 産経ニュース. 産経デジタル (2024年2月1日). 2024年2月1日閲覧。 ^ “園子温氏、“性加害疑惑”週刊誌訴訟で和解を報告「記事は全文削除されております」【コメント全文】”. ORICON NEWS. oricon ME (2024年2月1日). 2024年2月1日閲覧。 ^ “公式ホームページ” 2022年9月6日閲覧。 ^ “2012年・第86回キネマ旬報 ベスト・テン”. キネマ旬報社. 2018-08-07m閲覧。 ^ “トリンドル玲奈に最優秀女優賞!初主演『リアル鬼ごっこ』が作品賞含む3部門受賞の快挙!”. シネマトゥデイ (2015年8月6日). 2015年9月22日閲覧。 ^ “園子温監督が夫婦で作った『ひそひそ星』がトロントでNETPAC賞受賞!【第40回トロント国際映画祭】”. シアターガイド (2015年9月21日). 2015年9月24日閲覧。 ^ “GQ MEN OF THE YEAR 2014”. GQ JAPAN (2014年11月20日). 2014年11月21日閲覧。
園子温 - Wikipedia
2 notes
·
View notes
Text
2024年8月30日に発売予定の翻訳書
8月30日(火)には34点の翻訳書が発売予定です。そのうち14点がハーパーコリンズ・ジャパンからです。 なお、夏目漱石『それから』の英訳版を含みます。
テッド・ヒューズ詩集 カラス

テッド・ヒューズ/著 木村慧子/翻訳 山中章子/翻訳
小鳥遊書房
「カウボーイビバップ」のサウンドトラック

ローズ・ブリッジス/著 長尾莉紗/翻訳 小室敬幸/解説
DU BOOKS
アメリカを変えた夏 1927年

ビル・ブライソン/著 伊藤真/翻訳
白水社
禁書目録の歴史 : カトリック教会四百年の闘い

ロビン・ヴォウズ/著 標珠実/翻訳
白水社
脱成長と食と幸福

セルジュ・ラトゥーシュ/著 中野佳裕/翻訳
白水社
黄金の獅子は天使を望む

アマンダ・チネッリ/著 児玉みずうみ/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
裏切りのゆくえ

サラ・モーガン/著 木内重子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
大富豪と遅すぎた奇跡

レベッカ・ウインターズ/著 宇丹貴代実/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
声なき王の秘密の世継ぎ

エイミー・ラッタン/著 松島なお子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
カサノヴァの素顔

��ランダ・リー/著 片山真紀/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
十二カ月の恋人

ケイト・ウォーカー/著 織田みどり/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
愛を宿したウエイトレス

シャロン・ケンドリック/著 中村美穂/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
伯爵夫人の条件

ペニー・ジョーダン/著 井上京子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
公爵の花嫁になれない家庭教師

エレノア・ウェブスター/著 深山ちひろ/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
ギリシア富豪と路上の白薔薇

リン・グレアム/著 漆原麗/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
嵐の夜が授けた愛し子

ナタリー・アンダーソン/著 飯塚あい/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
忘れられた婚約者

アニー・バロウズ/著 佐野晶/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
追いつめられて

シャーロット・ラム/著 堀田碧/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
禁じられた結婚

スーザン・フォックス/著 飯田冊子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
桜の花のかがやき 上巻
稲見春男/翻訳
リフレ出版/東京図書出版
桜の花のかがやき 下巻
稲見春男/翻訳
リフレ出版/東京図書出版
疫禍動乱 世界トップクラスのワクチン学者が語る、Covid-19の陰謀・真実・未来
ポール・A・オフィット/著 ナショナル ジオグラフィック/編集 関谷冬華/翻訳
日経ナショナルジオグラフィック社
And Then
Soseki Natsume/著 Norma Moore Field/翻訳
チャールズ・イー・タトル出版
地球のためになる365のこと : 1日1つ持続可能(サステナブル)な暮らしへの ステップ
ジョージーナウィルソン=パウエル/著 吉田綾/監修・翻訳 上川典子/翻訳
東京書籍
エクスペリエンス・マインドセット
ティファニー・ボバ/著 高橋佳奈子/翻訳
日本能率協会マネジメントセンター
水文学〔原著第2版〕
Wilfried Brutsaert/著 杉田倫明/翻訳 筑波大学水文科学研究室/監修・翻訳
共立出版
マーシャの日記 その後 : 旧ソ連のユダヤ人差別
マーシャ・ロリニカイテ/著 清水陽子/翻訳
新日本出版社
肥満の科学 : ヒトはなぜ太るのか
リチャード・J・ジョンソン/著 中里京子/翻訳
NHK出版
サラゴサ手稿 下
ヤン・ポトツキ/著 工藤幸雄/翻訳
東京創元社
雪山書店と嘘つきな死体
アン・クレア/著 谷泰子/翻訳
東京創元社
ほん��うの名前は教えない
アシュリィ・エルストン/著 法村里絵/翻訳
東京創元社
ドキュメント民営刑務所 : 潜入記者の見た知られざる刑務所ビジネス
シェーン・バウアー/著 満園真木/翻訳
東京創元社
かぼちゃスープ
ヘレン・クーパー/著 せなあいこ/翻訳
好学社
皮はぐ者
ミシェル・ペイヴァー/著 さくまゆみこ/翻訳
評論社
0 notes
Text








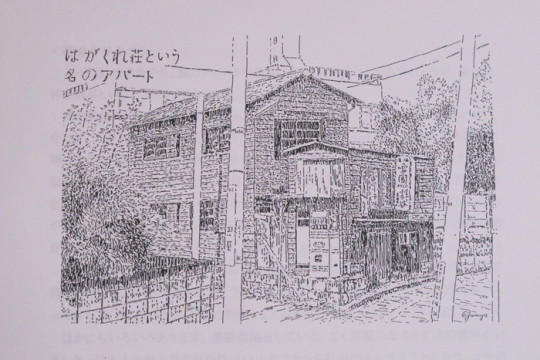



思い出を振り返る
編集 | 削除
Tuesday 11 February 2014
2014年1月9日(木)夜10時4分、おかあさんが92歳で亡くなった。おかあさんは、自分の母のことではない。ハルオは、26歳の時人生のターニングポイントを迎えた。それはカメラマンになる修行を始める時だった。キーパーソンは、カナダ人のジョン。ジョンとの出会いは、ハルオが当時勤めていたカメラ量販店(24〜26歳)でのことで販売員(ハルオ)とお客(ジョン)の関係から始まった。そのジョンにカメラマンになりたいと伝えるとジョンはある女性を紹介してくれた。その女性は、ハルオが師事する事になったカメラマンGが手掛けていた雑誌の編集者をしていた。ハルオは、ジョンを介してその女性と会いまもなくカメラマンGを紹介してもらい彼の元で働きながら写真を学ぶことになった。
ハルオは、当時国分寺に住んでいた。カメラマンGの仕事場は中目黒にあった。一方ジョンは中目黒に近い下北沢のアパート「葉隠荘」に住んでいた。そのアパートは、いわゆる外人ハウスで管理人がいなくある意味無法地帯のアパートだった。そのアパートがあった敷地内におかあさんが営む一杯飲み屋「小料理 小千谷」があった。ハルオは、国分寺のアパートをキープしながら葉隠荘(3畳部屋)に移り住んだ。そしておかあさんと出会った。おかあさんは、当時70歳だった。1991年のことだ。「小千谷」とはおかあさんの生まれ故郷新潟県小千谷のことだ。「小千谷」カウンターに5席ほどの小さい飲み屋でおかあさんが一人で切り盛りしていた。メニューは、300円と600円のみ。瓶ビール(大瓶)500円。おかあさんは、自分のことを『昔はあばずれ、今は聖母マリア』と言った。そして『おかあさん』と呼んでと言われる。おかあさんは、外国人しかいない葉隠荘に日本人がやって来たことが嬉しかったのだろうかハルオとおかあさんはすぐに打ち解けて仲良くなった。「小千谷」は夕方から12時まで営業していたので仕事が遅くなった時でもお店は開いていてよくハルオはおかあさんに会いにお店に寄った。おかあさんは昔の下宿屋のおばちゃんみたいな存在だった。おかあさんは世田谷区に住まいがあり旦那さんと暮らしていたが葉隠荘にも1室部屋を持っていた。その部屋はジョンの部屋(6畳部屋)の隣りだった。ジョンもハルオも20代後半の血気盛んな時期で週末となればどこからともなく外国人たちがジョンの部屋に集まりテクノミュージック(後にトランス)を聞いて騒いだ。ボロアパートの葉隠荘だから音は筒抜けでおかあさんは最年長でテクノを聞いていたことになるだろうか。聞くだけならともかくその音はおかあさんには不快でよくジョンの部屋に来て『うるさいよ〜』と注意に来た。
「小千谷」には、常連のお客さんがたくさんいて当然おかあさんのファンでもあった。おかあさんが道で拾った鶏をカゴに入れて飼っていた時があった。そのカゴは「小千谷」の店先に置いてあってある日おかあさんはそのコメコと名付けた鶏を写真に撮っている女の子Aと出会う。そして「うちにも写真を勉強しているハルオ君という子がいるよ』と伝えハルオはその女の子と「小千谷」で会った。ハルオは、その女の子を気に入りやがて2人は付き合う様になった。おかあさんは愛のキューピッドをし他にもおかあさんがお客さんとお客さんの縁を取り持ち結婚までしたカップルがいた。ハルオには、18歳で上京して以来2番目に仲良くなったTという友人がいるがそのTも「小千谷」が気に入り常連になった。そのTもやはり常連だった女性と恋に落ちその縁は今でも続いている。
ハルオが葉隠荘にいた期間は3年間だったがその間に「小千谷」が30周年を迎えた。近くの北沢八幡宮の宴会場を借りて大勢の人が集まり盛大に開催された。おかあさんは、得意のかっぽれを踊った。おかあさんはハルオに葉隠荘の外観写真を撮ること依頼しその写真を使い記念テレフォンカードを作った。おかあさんが何かの病気になり病院に入院した。それは大したことではなかったが退院の日ハルオはおかあさんに頼まれて迎えに行った。当時ハルオは400ccのバイクに乗っていておかあさんをシートの後ろに乗せて葉隠荘まで連れ帰った。そのことは後々までもおかあさんの記憶に残っていて時折そのことを懐かしんでハルオに話した。
「小千谷」には焼き飯というメニューがあってとても美味しく量がありハルオはよく好んで食べた。他には、刺身や漬け物、焼き魚等のメニューがあった。時折ハルオが朝仕事に出掛けると葉隠荘の入り���におかあさんからハルオに宛てたメモがありお店で残ったメニューの焼き飯やおにぎり、惣菜、を詰めてハルオに弁当を持たせてくれた。おかあさんは"お母さん"だった。ハルオは、バイクで交通事故に遭い肩甲骨と鎖骨を折って入院したことがあった。その際にはハルオの母も看病にやって来たのでハルオの母とおかあさんは顔を合わせている。その後年賀状のやり取りも続く。
ハルオが葉隠荘に住んで約3年後葉隠荘が取り壊しになる話が進められていた。丁度ハルオはカメラマン修行も終えた頃で立退料を大家の代理から30万円貰って早々に羽根木公園の近くのアパートに引っ越しをした。その後も暫く葉隠荘も「小千谷」もそのまま健在だったが遂に取り壊しをする時がやって来た。おかあさんが75歳前後のことだろうと思う。ハルオは、葉隠荘が取り壊される日、ドキュメント写真を撮った。その後まだ元気だったおかあさんは世田谷区上町駅近くの商店街に「小千谷パート2」を開店させた。ハルオは、定期的におかあさんに会いに行った。さてその店が何年続いたか?2〜3年?ハルオには記憶にない。下北沢という好条件にあった時に比べ上町ではお客さんが少なくなっていた。それでもおかあさんはお店を続けたかったんだと思う。
おかあさんは、水泳を好んで良くプールに出掛けていた。『ハルオ君、今度私が泳いでいるところを撮って』とおかあさんに言われたことがあったが実現には至らなかった。『小千谷パート2』が終りかけた頃、おかあさんは、自分史を書いた。その文章を常連のお客さんたちが小冊子に纏めた。その中にハルオについての話を書いてくれた。
2006年、ハルオは、写真展「十人十ゑろ」を開催した。しばらくおかあさんとは会っていなかったがおかあさんに写真展の話をすると行きたいと言ってくれた。しかしおかあさんは足が悪くなっていて自力では来れない。ハルオは、タクシーをチャーターしておかあさんの送迎をした。「十人十ゑろ」は10人の女性の素肌(殆どがヌード)をキャンピングテントの中で撮影した作品だった。その後おかあさんとのやり取りは年賀状や時折の電話で続いて行った。
2008年、ハルオは25年間住み慣れた東京から静岡に引っ越しをした。この年の前後(記憶が乏しい)におかあさんに会いに行った。場所は下北沢から近い世田谷区の淡島通り付近の喫茶店。おかあさんの住まいは一戸建だったがとても小さく人を迎い入れるには難があった。おかあさんの足は更に悪くなっていた。その時は、ハルオはおかあさんがキューピッドをして付き合うことになった女の子Aと行った。Aとのお付き合いは半年も続かなかった。しかし元々Aはカメラマンになりたかった女の子でハルオに触発されてか付き合っている頃から写真学校の夜間部に通い晴れてカメラマンになっていた。ハルオとAは、友達として連絡を取り合っていたのでいい機会と一緒におかあさんに会いに行ったのだった。ハルオは、写真を撮って後でおかあさんにその写真を額に入れて贈った。おかあさんはその後世田谷の住まいをそのままにして小千谷に近い新潟県長岡市に身を寄せた。始めはおかあさんだけ��その後旦那さんも。
2011年、おかあさんからハルオに手紙が届いた。その日は偶然にもハルオの誕生日だった。手紙が入った封筒には、現金2万円と写真も入っていた。その時何故現金が入っていたのか分らずハルオは、誕生日プレゼントだと勝手に思った。(しかしそれは後で気付いたが新潟までの往復の交通費だった。)そして写真だがそれが驚いたことにおかあさんのヌード写真だった。おかあさんが50〜60歳位の頃の温泉の露天風呂に入っている写真で下半身はタオルで隠れていて上半身は裸で乳首は見えそうで見えてはいなかった。手紙に『ハルオ君の個展か何かに出せるんじゃないかと勝手に考えました。自分のうぬぼれかも知れないけどそんな風に役立てて下さい。お願いします』とあった。随分大胆だなとハルオは驚いた。ハルオは、この時以前プールの写真を撮ってとリクエストされたことを思い出した。
手紙を貰った後中々新潟までおかあさんに会いには行けなかった。 ハルオは、それがはがくゆく気になっていたのでおかあさんに会いに行く決意をする。 おかあさんに貰った交通費2万円を使い時がやって来たのだ。
2013年春、 その旨をおかあさんに伝えようと身を寄せていた新潟県長岡市のお宅に電話すると旦那さんが危ないからまたの機会にして欲しいと言われ延期した。おかあさんには2人のお子さんがいて長女さんは大阪に住んでいて息子さんはすでに亡くなっていた。その息子さんの奥さんがおかあさんと旦那さんの世話をしていたのだ。間もなく旦那さんは亡くなられた。そして10月の始め、おかあさんに会いに静岡から車で出掛けた。久しぶりに会ったおかあさんは、すでにガンに侵されていた。部屋の中で2時間ほど話した。写真も撮った。しかしおかあさんの笑顔は撮れなかった。おかあさんは、長年の伴侶だった旦那さんが亡くなり生きることよりも死ぬことを願っている様に見えた。ハルオは、おかあさんと別れた後おかあさんの勧めで小千谷にも寄って来た。おかあさんの実家は小千谷駅近くにあった。甥っ子さんが寿司屋を経営し、その同じ通りにおかあさんの幼馴染みが住む金物屋があって両方訪ねた。幼馴染みの方はご健在で写真も撮ることが出来た。
『おかあさん、これから手紙を定期的に送っていい?』そうハルオはおかあさんに尋ねると承知してくれたのでその後迷惑にならない様に気を使いながら手紙(葉書)を送った。しかしおかあさんはそれから3ヶ月後に帰らぬ人になってしまった。
おかあさんのご冥福を心からお祈り致します。 長い間本当にありがとうございました。 安らかにお眠り下さいね。
2014年2月21日(金) ハルオ
0 notes
Text
2023年11月25日の記事一覧
2023年11月25日の記事一覧 http://dailyfeed.jp/feed/23663/2023-11-25 (全 23 件) 1. Sonar Pocket - あなたのうた 2. Sonar Pocket - 100年先まで愛します。 3. Sonar Pocket - 365日のラブストーリー。 4. Sonar Pocket - 好きだよ。〜100回の後��〜 5. Sonar Pocket - GIRIGIRI 6. 尾崎裕哉 - Glory Days 7. Eripiyo (CV:Fairouz Ai) - ♡桃色片想い♡ - Special ED ver. 8. Kotori - 秘密 9. 千住明 - 新・ドキュメント 太平洋戦争 - Main Theme Ver. A 10. 千住明 - Family Love 11. 千住明 - VIVANT 12. 千住明 - 日曜美術館 2009 13. 千住明 - Father's Land 14. 上妻宏光 - 風林火山 ~月冴ゆ夜~ 15. 千住明 - 「人生の隙間」 - 恋する気持ち 16. 千住明 - Crime and Punishment 17. 千住明 - Lullaby of Resembool 18. エドヴァルド・グリーグ - Grieg: Old Norwegian Romance with Variations, Op. 51: XIX. Andante molto tranquillo (Orchestral Version) 19. HimeHina - ヒビカセ 20. T-Pistonz+KMC - マジで感謝! 21. CHERRYBLOSSOM - DIVE TO WORLD 22. Tayori - 風のたより 23. 河野マリナ - たからもの via 複数のRSSをまとめるのデイリーフィード - DailyFeed http://dailyfeed.jp/feed/23663 November 26, 2023 at 05:00AM
0 notes
Text
「これ見た?」
って仲の良い友人からなんでもない日に連絡が来た真っ昼間。「アイナに見て欲しい」その思いの吐露になんだか嬉しくなって、なんだろうと覗いた吹き出しの文章に送付されてたタイトルはもう既に見覚えのある作品で。単純に好みが似てるんだよなあ。そんな小さな幸せも一緒に咀嚼しながら舌で転がして味を噛み締めつつ、目に入るその作品名「モアザンワーズ」私は原作のファンで、その後に映像化されるのを知って。正直、よくある話で原作漫画が好きなあまり実写化を観るつもりはなかったんだけど、その可愛い友人からのゴリ押しということもあり。いざ観たら2日、3日で全部一気見のコンプリートするっていうね。食わず嫌いはほんとダメだな、って思った。まず、ドラマの魅せ方がめちゃくちゃに憎い。全くの素人が言えることじゃないのは分かってますが、ワンカットで撮影されてるシーンが多くて実際に登場人物の日常をリアルタイムで観察してるような、そんな感覚。言わばドキュメントを観ているようで。胸が苦しくなるようなシーンや、どこにもぶつけようがない痛いくらいの感情がストレートに心に突き刺さって。ただただ圧巻。もう観て、としか言いようがないんだけど。観た人にしか分かんないよこの気持ちは。で、何より衝撃的だったのは作品にEXITの兼近さんが出てるんですが、それがまた。あんな声色出せるんだってかなり意表を突かれた。最初の登場シーン、本当に誰だか分かんなかったくらいに。結構内容的には重くて、だから好みは別れるかも知れないけど、近い作品で言うと大倉さんの「窮鼠はチーズの夢をみる」かな。あれも凄く、凄くすき。海辺のシーンでの成田さんのセリフは圧巻だった。"好きってその人だけが例外になる"。もうまさにそれだ、っていう好きとは、の模範解答。恋愛における"人を好きになるということ"に対しての多幸感と惰性が入り交じった正解みたいな言葉なのに、別れを決意した最後の台詞なのがもう、ギュッとなるよ。愛しくて狂おしい。
ぜひ、興味のある方は二作品見てみて下さい。アイナの推しです。


0 notes
Text
2019年4月5月6月7月読んだ本
「新潮日本文学1森鴎外集」 「新潮日本文学6谷崎潤一郎集」 「新潮日本文学8志賀直哉集」 「新潮日本文学10芥川龍之介集」 「新潮日本文学15川端康成集」 「新潮日本文学35太宰治集」 「新潮日本文学44井上靖集」 「新潮日本文学45三島由紀夫集」 「新潮日本文学46阿部公房集」 「新潮日本文学56遠藤周作集」 「新潮日本文学60司馬遼太郎集」 「新潮日本文学62石原慎太郎集」 「新潮日本文学64大江健三郎集」 「精神分析入門」フロイト 角川文庫 「ボォヴァリー夫人」フロベール 角川文庫 「笑いと忘却の書」ミラン・クンデラ 集英社 「プラトン的恋愛」金井美恵子 講談社 「モモ」ミヒャエル・エンデ 岩波少年文庫 「美徳の不幸」マルキ・ド・サド 角川文庫 「砂漠の惑星」スタニスワフ・レム ハヤカワ文庫SF 「金星応答なし」スタニスワフ・レム ハヤカワ部個SF 「エデン」スタニスワフ・レム ハヤカワ文庫SF 「声で読む日本の詩歌166おーいぽぽんた」編集委員 茨木のり子、大岡信、川崎洋、岸田衿子、谷川俊太郎 福音書店 「別冊ライトニングVol.185 デニムコンプリート」枻出版 「ユリイカ2017年2月臨時増刊号 総特集 矢野顕子」青土社 「みすず6月号」 「ちくま7月号」 「ミュージックマガジン7月号」 「ルーカス・クラナッハの飼い主のメキシコ旅行」山本容子 徳間書店」 「ルーカス・クラナッハの飼い主は旅行が好き」山本容子 徳間書店 「英語の壁」マーク・ピーターセン 文春新書 「常識の世界地図」21世紀研究会 文春新書 「ナショナリズムの克服」姜尚中、森巣博 集英社新書 「物語ラテンアメリカの歴史」増田義郎 中公新書 「自然再生」鷲谷いづみ 中公新書 「森と文明の物語」安田喜憲 ちくま新書 「おしごと年鑑2019」朝日新聞社 「おしごと年鑑2018」朝日新聞社 「おしごと年鑑2017」朝日新聞社 「第5回言の葉大賞言葉の力を感じるとき」京都柿書房 「言の葉大賞2018春号」言の葉協会 「言の葉大賞2017春号」言の葉協会 「クルアーンやさしい和訳」監訳者水谷周 国書刊行会 「イエス・キリスト」遠藤周作
��� 追記 「新潮日本文学3夏目漱石集」 「新潮日本文学6志賀直哉集」 「言の葉大賞2019春号」言の葉協会 「ドキュメント検察官」読売新聞社会部 中公新書 「ナノテクノロジーの世紀」餌取章男、菅沼定憲 ちくま新書 「二十歳の原点」高野悦子 新潮文庫 「花のノートルダム」ジャン・ジュネ 新潮文庫
4月から他の施設に移送になり中学の勉強を教えてもらってます。ここではあまり本が借りられませんが、勉強に専念します。
15 notes
·
View notes
Text
2019年8月18日(日)

立秋・末候は「蒙霧升降(ふかききりまとう)」
森や水辺に白く深い霧がたちこめる頃。朝夕のひんやりとした心地よい空気の中、深い霧が幻想的な風景をつくりだします。(暦生活)
前任校のセミナーハウスが信州・蓼科にあったので、子どもたちの小さい頃は毎年家族の夏休みを過ごしていた。高原の朝は確かに幻想的であったなぁ・・・と、近頃はやたら遠い目をすることが増えてしまった。

今朝の朝ご飯、昨晩の残りの「笹寿し」をかき玉汁と一緒にいただく。

尾瀬あきら「どうらく息子 18 (ビッグコミックス)」がやっと届く、これで全巻完結。いやぁ、なかなかの力作・佳作、すっかり予定が狂ったとは言え、今年の盆休みがとても充実したものとなった。
ツレアイは正真正銘の休日、アフリカン太鼓の練習に出かける。

息子たちのランチは素麺、私は牛飯@松屋。32個も届いたときはどうなることかと思ったが、昨晩長男に10個持たせたのでずいぶんと冷凍庫に余裕が出���た。葱と紅ショウガをトッピング、少し甘めなので七味で調整。

午後1時にホンダ五条店、定期点検。店内は冷房が効いているが、外は37度を超える猛暑。半年間洗車していないので、車もタイヤも見違えるほどにピッカピカ。
帰宅して録画番組視聴。
「京都人の密かな愉しみ Blue 修業中 祇園さんの来はる夏」
待望の第3弾!祇園祭の夏は恋の季節! さらに目が離せない、せつない京都青春群像!
陶芸家見習いの釉子役にあたらしく吉岡里帆を迎え、庭師見習いの幸太郎(林遣都)、板前見習いの甚(矢本悠馬)、パン職人見習いの葉菜(趣里)、農家見習いでワケありな影を持つ鋭二(毎熊克哉)、それぞれのひと夏を描く。幻想的な宵山(よいやま)、荘厳な山鉾(やまほこ)巡行でクライマックスを迎える祇園祭は、熱き青春の恋の舞台。番組では今年1150年の節目を迎える祭を完全ドキュメント。ドラマとドキュメンタリー、虚と実を行き来しながら、若者たちの愛と涙が祇園祭の熱気の中で交錯する。
昨晩はライブで観たが、改めて録画を観直す。祇園祭の説明が大変うまくできており、教材としても使用できる(全部は長いが)。おしむらくは、粽(ちまき)の説明の中に、「庶民将来子孫也」の解説が欲しかった。

今夜も家族揃って早めの夕飯、昨晩の料理の残りをアレンジ。
長男にいただいた「八潮杜氏」は鳥取県倉吉市の酒、本当に綺麗な仕上がりで平気で一気飲みできそうなほど。
録画番組視聴。
日本の話芸 桂吉弥 落語「くしゃみ講釈」
第398回NHK上方落語の会から桂吉弥さんの口演で落語「くしゃみ講釈」をお送りします(2019年7月4日(木)NHK大阪ホールで収録)。【あらすじ】後藤一山という講釈師に小町娘との仲を邪魔された男。なんとか仕返しをと考えていると、友だちが「後藤一山が講釈をやってる最中に、火鉢に胡椒の粉をくすべたら、くしゃみが出て講釈がやれなくなる」と教えた。件の男、八百屋へ胡椒(こしょう)の粉を買いに行くのだが…
同じNHKの収録ではあっても、「上方落語の会」ではなく「日本の話芸」枠で放送されるのは「全国区扱い」の証拠。結構なことである。

今週は完全休養日、明日からは普段のリズムに戻さなくては。
1 note
·
View note
Text
レッドホットジャム Vol.304 女優と飲み・・・そして泊まりSEX : 美咲恋 - 無料動画付き(サンプル動画)
レッドホットジャム Vol.304 女優と飲み・・・そして泊まりSEX : 美咲恋 - 無料動画付き(サンプル動画) スタジオ: レッドホットジャム,女優と飲み・・・そして泊まりSEX 時間: 120分 女優: 美咲恋 「最後なので思いっきり飲んでイキまくりたいです!」と語るのはちっちゃなボディに巨乳を持つ美咲恋ちゃん!なんと引退宣言ですっ!!最後の一本になってしまうかものこの作品ありのままの恋ちゃんが見れると~っておきの見逃せない一本ですっ!!! チャプター1ではデビュー当時の話、本音トークやプライベートの話。そして台本無し、演技無しでねっとりじっくり愛撫で始まる本気のイキまくりハメ撮りSEX! チャプター2では、美咲恋ちゃん!今まで本当にありがとう!恋ちゃんファンへの感謝を込めて最後に最高のアクメ!本気で求め合う男と女の本能のSEX。女優最後にふさわしい涙の引退ドキュメント!素直でま DVD・DVD販売サイト【DVD村】 DVD正規販売のDVD村です。動画ダウンロード$1.49!サンプル動画あり、ブルーレイ、DVDあり。
0 notes
Photo



「ムラカミロキ」映像上映
2/21(火)
東京 高円寺 Fourth Floor Ⅱ
超未来映像!VOL.10
open. 19:00 / start. 19:30 Adv. / Door. ¥2,000+1drink
●上映作品
監督:ムラカミロキ
「症例A -映画characterから見る殺人者への考察-」 6min 「character」35min
「人は言葉でしか現実を語れない、けれども言葉で現実は語れない」 別の所へ行ってしまった女。それを追い続け、自分なりの偏愛と恋愛を続ける男。
監督:野上亨介
「デ・クーニングは許せない!」20min
かつて描いた中途半端な絵画がずっと気になっていた‥‥途中放棄されたアクリル絵画を再開させ、完成させるプロセスを細かく追いながらも、さまざまな「リフレクション=反省」によって中断させながら描写をつづける様子を追った美学的ドキュメント。2023最新作品。
高円寺フォースセカンドにて拙作『character』とその関連作品『症例A』が約10年ぶりに同時上映されます。よろしくお願いします。
Fourth Floor Ⅱ second 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-6-7 第5日東ビル B1 Twitter: @kouenji4th https://twitter.com/kouenji4th
https://fourthfloor.jp/
https://murafake.hatenablog.com/entry/2023/02/20/163126
0 notes
Text

【VS激ヤバママ】主役の座を奪わないで!非常識ママに困惑花嫁🧖♀️ / マイ・ドリーム・ウエディングドレス シーズン15





#ドレスデザイン研究室#アメリカ人#アメリカ文化#アメリカ生活#カップル#リアリティショー#リアリティ番組#ワーホリ#国際恋愛#外国人#恋愛ドキュメント#文化の違い#海外#海外ドラマ#海外生活#海外留学#留学#英語#英語勉強
0 notes
Text
#文芸賞 に関するニュース 全36件
文芸賞に沢大知さん - 佐賀新聞
文芸賞に沢大知さん 「眼球達磨式」 - 中日新聞
中公文芸賞に山本文緒さん - 日本経済新聞
山本文緒さんの『自転しながら公転する』が、第16回中央公論文芸賞を受賞しました! - PR TIMES
芥川・直木賞贈呈式 澤田瞳子さんら4氏が感慨と抱負 - 産経ニュース
第4回徳島新聞 阿波しらさぎ文学賞・審査評 - 徳島新聞
<今週の激推シネマ>「仮面ライダーバルカン&バルキリー」 「ゼロワン Others」シリーズ完結編 刃唯阿に仮面ライダー滅亡迅雷の破壊指令(MANTANWEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
「内向の世代」代表する作家の一人、坂上弘さんが死去…「優しい碇泊地」で読売文学賞 - 読売新聞
芦田愛菜「大きな幸せも大切だけど…」日常の小さな幸せに共感(シネマトゥデイ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
第20回(2021年度)小林秀雄賞・新潮ドキュメント賞、受賞作品が決定しました - PR TIMES
島本理生が描く、コロナ禍で迎えたひと夏の物語。(ananweb) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
傑作。見逃さないで。「本屋大賞」翻訳部門No.1作家の新刊 - ニフティニュース
島本理生が描く、コロナ禍で迎えたひと夏の物語。 - ananweb
【文芸時評】9月号 資本主義の矛盾と芸術 早稲田大学教授・石原千秋 - 産経ニュース
千葉雅也さんが語る「小説を書く人生」 2冊目は「オーバーヒート」 - 毎日新聞 - 毎日新聞
【書評】『貝に続く場所にて』石沢麻依著 大震災と現在つなぐ時空 - 産経ニュース
『岬のマヨイガ』新キャストに江原正士、桑島法子ら 公開前予告&場面写真公開も公開(クランクイン!) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
『岬のマヨイガ』大竹しのぶ絶賛 超絶作画の本編映像“昔話シーン”解禁(クランクイン!) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
全国高校生読書体験記コンクール作品募集 - 愛媛新聞
第3回「日本おいしい小説大賞」受賞作を、村崎なぎこ『百年厨房』に決定しました! - PR TIMES
第165回直木賞受賞の佐藤究さん、書くことで気づかされた「物語とは、敗れた者たちのためにあるんだ」(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
小林秀雄賞に「音楽の危機」(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
『ONE DAY, 2050 / Sci-Fi Prototyping』 を『Sony Park展』にて8/31(火)から開催 - PR TIMES
一つの物語から生まれた、文楽と落語と直木賞。3つの芸が生み出す新しいコラボイベント - PR TIMES
【ユーザー投票で決める新しい賞】「次にくるライトノベル大賞」始動! 10月1日(金)13時から作品エントリー開始!:時事ドットコム - 時事通信
朝刊小説「かたばみ」連載を前に 木内昇 - 東京新聞
[レビュー]嫌韓と嫌日の二分法を超えて(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
インパクトのある強いタイトルで時流をうまく捉えた「文庫化」作品(レビュー)(Book Bang) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
ロングセラーを読む 無言の棋士と豊穣な観戦記 川端康成著「名人」 - ライブドアニュース - livedoor
「殺人」がキーワード? 文芸書ランキングで存在感を示す、“どんでん返し”づくめの極上ミステリ(リアルサウンド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
村上春樹の小説『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』、貴重な執筆秘話と自作朗読をラジオで披露!(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
坊っちゃんって実は“コミュ障”!? 現代を生きるヒントが満載の“書店仕込み”の名著ガイド - auone.jp
長身イケメン…!13歳のエリザベス王女が恋したフィリップ王子との出会い(婦人画報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
各界の読み巧者が唸った『謎ときサリンジャー ――「自殺」したのは誰なのか』 新潮選書からついに刊行!:時事ドットコム - 時事通信
ファンタジーならではの謎解きに注目!『聖女ヴィクトリアの考察』刊行記念 春間タツキインタビュー - カドブン
『かぐや様は告らせたい』続編が初登場首位!『孤狼の血』続編は4位スタート - シネマトゥデイ
文芸賞:受賞作ドットジェイピー
0 notes
Text
☆円盤、その他
※未取り込みの物は(未)記載あり
★7ORDER
・UNORDER
★Kis-My-Ft2 ※未取り込み多数の為お問い合わせください
LIVE
・Kis-My-Ftに逢えるde Show vol.3(本編)
・Everybody Go at 横浜アリーナ(本編)
・Kis-My-MiNT(本編、初���特典)
・SNOW DOMEの約束(本編、オフショット、Goodツアー)
・Kis-My-Journey(本編、初回特典、通常特典)
・KIS-MY-WORLD(本編、各WORLD、ドキュメント、ユニットドキュメント、アンコール、新春)
・ISECREAM(本編、密着、ソロドキュメンタリー、アンコール、ハプニング&名珍場面)
・MUSIC COLOSSEUM(本編、メイキング〜打上げ)
・Yummy(本編、アンコール、密着、7Yummy)
・FREE HUGS!(本編、ソロ密着、密着、ハプニング&名場面)
・To-y2(本編、ドキュメント、KIS-MY-TV)
シングル
・PICK IT UP
初回A(MV、MV字幕、メイキング、キスマイスポーツ、裏キスマツ荘、マルチアングル)
初回B(KIS-MY-TV)
・赤い果実
初回A(MV、MV字幕、MVダンス、MVダンス字幕、メイキング)
初回B(ゆるスポ、裏スナック)
・You&Me (HOMEレコーディング、ZERO)
・LOVE
初回A(MV、MV字幕、メイキング、ゆるスポ)
初回B(MV、MV字幕、メイキング、裏Yummy)
・君、僕。
初回A(MV、MV字幕、メイキング)
初回B(KIS-MY-PARTY)
・君を大好きだ
初回A(MV、MV字幕、メイキング、もしもシリーズ)
EXTRA盤(Extra Yummy!!)
・HANDS UP
初回B(永遠結び、永遠結び字幕、ルラルララ、インタビュー)
・Edge of Days
初回A(MV、MV字幕、メイキング)
初回B(MV、MV字幕、ゆるスポ、騙しているのは誰?)
・ENDLESS SUMMER
初回A(MV~メイキング)
初回B(KIS-MY-TV)
・Luv Bias
初回A(MV、メイキング)
初回B(KIS-MY-TV)
・Fear/SO BLUE(初回A、初回B、通常)
・Two as One(初回A、初回B、特別版)
アルバム
・Kis-My-1st
SHOP(あしあと)
・KIS-MY-WORLD
初回A(MV、ミッション、振付け、ユニットレコーディング)
SHOP(北山)
・ISECREAM
初回4(各Re:、ソロMV、6movies、Re:制作密着)
初回2(MV、メイキング、シェアハウス)
・MUSIC COLOSSEUM
初回A(MV、MV字幕、メイキング、KIS-MY-TV)
・Yummy!!
初回A(キスマイ語録、キスマツ荘後篇)
・FREE HUGS!
初回A(MV、MV字幕、MV Lip、MV Lip字幕、メイキング)
初回B(KIS-MY-TV)
・To-y2
初回A(MV、MV字幕、AFA、BNA)
初回B(KIS-MY-TV)
・BEST of Kis-My-Ft2 2011-2021(Blu-Ray)
★舞祭組
LIVE
・舞祭組村のわっと! 驚く! 第1笑(密着、SP企画)
シングル
・棚からぼたもち(MV、メイキング)
・てぃーてぃーてぃーてれって(MV、メイキング)
・やっちゃった(MV、メイキング)
・道しるべ
初回A(MV、メイキング)
初回B(合宿)
アルバム
・舞祭組の、わっ!
初回A(シングルMV、メドレーMV、メイキング)
初回B(100日ドキュメント)
★King & Prince
・1stコンサート(本編)
・2ndコンサート(本編)
★素顔
・8.8祭(本編、ドキュメント、ISLAND FES)
・ぷれぜんと(本編、メイキング)
・雪Man in the Show(本編、メイキング)
・関西Jr(本編、メイキング)
・CHANGE THE ERA -201ix-(本編、メイキング)
★JUMP
・1st(本編、メイキング)
・I/O(本編、メイキング)
★SixTONES
LIVE
・TrackONE-IMPACT(本編、ドキュメント、コメンタリー、Rough xxxxxxダイジェスト)
・OneST(本編、ドキュメント、コメンタリー)
・Feel da CITY(全Blu-Ray)
シングル
・Imitation Rain(初回、With)
・NAVIGATOR
・NEW ERA(初回、限定)
・僕が僕じゃないみたいだ(初回A、B)
・マスカラ(初回A、B)
・共鳴(初回A、B)
・わたし(初回A、B、マルチアングル)
アルバム
・1ST(初回A、B)
・CITY(初回A、B)
★関ジャニ∞
・十祭(本編)
・十五祭(本編)
・8UPPERS FEATURE MUSIC FILM / DIRECTOR’S GIFT(未)
★Sexy Zone
・2019PAGES(本編)
・サマパラ2016(佐藤、菊池)
・サマパラ2017(佐藤、菊池、中島)
★KAT-TUN
LIVE
・お客様は神サマー(未)
・海賊帆(DISC1、DISC2)
・UNION(本編)
・CAST(本編)
・IGNITE(本編、MC集)
シングル
・Roar(初回、FC限定)
・We Just Go Hard feat.AK-69/EUPHORIA(全形態)
★多数出演
・One!(本編)
・滝沢歌舞伎
2010(第一幕)
2012(第一幕、第二幕、特典ファミリー公演)
2014(第一幕、第二幕、ドキュメント)
2015(第一幕、第二幕、ドキュメント、シンガポールドキュメント)
2016(第一幕、第二幕、ドキュメント)
2018(第一幕、第二幕、ドキュメント、カンパニー、BBQ、千秋楽)
ZERO(第一幕、第二幕、ドキュメント)
・滝沢革命
2009(第一幕)
・滝沢演舞場(第一幕)
・銀河英雄伝説
撃墜王(未)
輝く星、闇を裂いて(本編、特典)
第三章 内乱(本編、特典、カーテンコール)
第四章 後篇 激突(本編、特典)
・○○な人の末路(月、海 ※特典含む)
・Twenty★Twenty
・SUMMARY2004(本編)
・PLAYZONE
2005(本編)
太陽からの手紙(本編、特典)
・キフシャム国の冒険
・DREAM BOY(DISC1、DISC2-1〜3)
・DREAM BOYS
2006 KAT-TUNVS関ジャニ∞(未)
2008 亀梨田中屋良(未)
2017 玉森宮田千賀(本編)
★ドラマ・映画
・BAD BOYS(ドラマ本編、ドラマメイキング、 劇場版)
・お兄ちゃんガチャ(本編)
・ごくせん3(本編)
・ごめんね青春(本編)
・メンズ高校(事前番組)
・スプラウト(本編)
・ゼロ一攫千金ゲーム(本編)
・バカレア(ドラマ本編、ドラマメイキング、劇場版本編、劇場版メイキング)
・一億円のさようなら(本編1-3話)
・少年たち劇場版(本編、メイキング、舞台挨拶)
・未満警察(本編)
・節約ロック(本編)
・簡単なお仕事(本編)
・花晴れ(本編)
・野郎組(本編)
・荒ぶる荒野(本編)
・HIGH and LAW(THEMOVIE、2ENDOFSKY、FINALMISSION、REDRAIN)
・グラスホッパー(本編)
・最後の約束(本編)
・午前0時、キスしに来てよ(本編)
・京都大奏行進曲
・foney(本編)
・忍ジャ二(本編、メイキング)
・俺スカ(本編、メイキング)
・仮面ティチャー(ドラマ)
・SHARK
・SHARK2(本編、特典)
・フリーター、家を買う(本編、特典 ※高比率)
・美男子ですね(本編、特典)
・黒崎くんのいいなり
・花より男子
・近キョリ恋愛
・DIVER(1〜5話)
・映画ごくせん(本編、特典)
0 notes
Text
『シチューションズ 「以後」をめぐって』
シチュエーションズ
1。百年の失語
「新潮」の四月号に、「震災はあなたの〈何〉を変えましたか? 震災後、あなたは〈何〉を読みましたか?」という特集が載っていた。総勢二十八名の作家が、編集部が投げ掛けた先の二つのアンケートに答えている。中でも印象的だったのは、「ワイルドサイドを歩け」というタイトルの付いた、町田康による回答の一節だ。
いま小説を書ける奴は小説家じゃないですよねぇ、と死んだ父に語りかけて小説を書いている。四月号と言いながらその実、三月に出て、そこに載る文章を一月に書いていること。その矛盾がいま露になってなにも言えない。
ここでは二つの問題提起がされている。「いま小説を書ける/書く」とは如何なることなのか、という、端的かつ直截な問い。それから「月刊」である文芸誌の制度的な慣習への違和感の表明。「いま露になってなにも言えない」と言うのだから、二つ目の問題は一つ目と実は繋がっている。読者の側からみれば、この三月に、四月号と記された誌面で、一月には書かれていた言葉を読んでいるという「矛盾」は、もちろん今に始まったことではないし、文芸誌だけのことでもない。だが、このささやかなタイム・パラドックスは、この企画が「100年保存大特集」と銘打たれていることによって、一挙に加速拡大することになるだろう。「100年」という数字は、或る途方も無さとリアリティとを併せ持っている。百年後の未来は、それほど遠くはなく、それほど近くもない。 なぜ「100年」なのか、という時間についての説明は、なぜか「新潮」には無いのだが、たとえば、アンケートに回答を寄せてもいる古川日出男が、十七人の作家・詩人の「3・11」をめぐるアンソロジー『それでも三���は、また』のために書き下ろした短篇「十六年後に泊まる」の中に、ひとつの答えを見つけることが出来るかもしれない。二〇一一年の五月、十六年目の結婚記念日に、作家は妻を伴って、約一年ぶりに福島の実家へと帰郷する。その経緯を綴ったエッセイ風の小品だが、小説の最後にふたりは東京に戻るべく、ホテルを出てタクシーに乗る。
僕はどんなタイミングで思い出してもよかったのだが、実際にはこのタイミングで、イギリスの科学誌『ネイチャー』になる論文が掲載されたとの報道を思い出した。福島第一原発の廃炉には数十年から一〇〇年かかる、と、その論文��指摘していた。たとえば三十年後か四十年後ならば、僕にも廃炉を見届けられるチャンスはあるだろう。妻にもあるだろう。しかし、一〇〇年後には? 僕は、自分はこの地上にはいないし、妻もいないし、この運転手もいないな、と感じた。いや、理解した。われわれは誰もいない。
この後一行で、小説は終わる。つまり「一〇〇年後」とは、ひとつには、たとえば「福島第一原発の廃炉」が完了するまでに要するかもしれない時間のことである。 私たちは、今から百年前に書かれた小説を、そこに書かれた言葉を読むことが出来る。もっとずっと昔に書かれた言葉だって読むことが出来る。だが、百年前に何かを書いていた人々は、百年後か、それ以上先の未来に、自分の言葉が誰かに読まれていることを、たとえそう望んでいたとしても、確信することは出来なかった。それは百年後には廃炉が成されているのかどうかを、そう願う人々の誰ひとりとして確かめることが出来ないのと同じである。 保坂和志は、新しいエッセイ集『魚は海の中で眠れるが鳥は空の中では眠れない』の中で、こんなことを書いている。
私は自分の本が一〇〇年後にも読まれているとは思っていない。一〇〇年後に読まれていると想像することができたら、幸福感か満足感を味わうことができるかもしれないが、私はそういう風には楽天家ではない。
いかにも保坂氏らしい、率直な発言だが、「しかしそれでは何故、なぜ自分は小説を書くのか?」と、すぐさま氏は続ける。
小説家が小説を書くのは、小説を書くという行為を通じて何かを考えたいからだ。そして、できるなら人間の考えるという営みに関わりたい。 ここで注意してほしいのだが、私は作品という形で残りたいと思っているのではなく、考えたり感じたり記憶したりするプロセスに小説を書くことで関わりたいと思っているのだ。
保坂氏が言っているのは、特に「いま」には限らない普遍的なことだろうが、作家たち、言葉の使い手たち、あるいは、言葉に限らない諸芸術表現の作り手たちの多くが、あれからの一年間を、一種の失語症に直面しつつ過ごし、今もなお、そこから完全には出てこられていない者もいる、という事実を鑑みると、「いま」こそ「考えたり感じたり記憶したりするプロセス」に立ち戻ってみること、そこからふたたび始めるしかないのではないか、とも思う。それは未来の他者に向けて、タイムカプセルに「保存」される言葉を、後悔抜きに紡ぎ出すためにも必要とされている。百年後の読者は、ことによると、いま以上に、失語への動揺と絶望を乗り越える術を求めているのかもしれないのだから。 ところで、もうひとつ押さえておかなくてはならないのは、町田康が韜晦まじりに記した「いま小説を書ける奴は小説家じゃないですよねぇ」に対して、それでも書いてしまった者はどうなのか、という問題である。それは、鈍感にも難なく書けてしまえた、ということなのか。失語症への共感が強化される場では、ともすればそれは短慮による仕業と解されかねない。ならば、失語の強迫と誘惑に抗い、勇気を奮ってようやく言葉を発した、ということならば赦されるのか。失った言葉を取り戻した者と、言葉を失わなかった者の差異は、何処にあるのか。あるいは、こう言ってしまってもいい。短慮で何が悪いのか? 高橋源一郎の『恋する原発』は、二〇一一年に書かれ出版された「純文学」のなかでも、もっとも倫理的な作品のひとつだった。無論、「3・11」のチャリティーAVを作ろうとする話だなんて、不謹慎という物議=ウケを狙った火事場泥棒的な無恥の所業であるという非難もあっただろう。各章が全部途中から日本語吹き替えミュージカル仕立てになるだなんて、幾らなんでも悪ノリが過ぎるという批判もあり得るだろう。軽挙妄動、正に短慮そのもの、あんなのは不誠実のフリをした誠実さのフリをした不誠実だよ、と。だが私はそうは思わない。あれは不誠実のフリをした誠実さのフリをした不誠実のフリをした(…)やはり紛れもない誠実さなのだ。言い換えればそれは、自分の紛れもない不誠実さを隠さない、ということでもある。重要なことは、高橋氏が「短慮」を怖れず、そこから逃げもしなかったということだ。私が感銘を受けたのは、演技でもいいから真面目にやってないと誰もまともに受け取らないだろう状況において、演技ではない不真面目を丸出しにすることでしか表現され得ない何かがあるのだということに、たぶんあの時点では『恋する原発』だけが意識的だったからである。 二〇一一年に高橋氏がツイッターに投稿した「つぶやき」に、同時期に書かれたエッセイや評論、小説などの断片を挟み込んだ本『「あの日」からぼくが考えている「正しさ」について』の「おわりに」に、高橋氏はこう書いている。
いつもの年より、ずっとたくさんの「ことば」を、ぼくは書いた(発した)。いつもなら書かないだろう、そんな「ことば」も、ずいぶんあった。 中には、いいものも、たいしてよくないものも、つまらないものもあるだろう。繰り返しや、混乱もあるだろう。でも、ぼくは、その「ことば」たちと一緒に、真剣に、なにかを探ろうとしたのだった。
若干いい子ぶってるように読めなくもない。だが、それでもやはり、ここには「失語」に抗する「ことば」の遣い手であるひとりの作家の姿がある。「ひとりの人間が、なんの準備もなく、ある事件に巻き込まれる。その様子を、正確に再現してみたかった」と高橋氏は記している。そしてそれは、書くこと、書き始めること、書いてしまうことによってしか試行されないのではないか。 失語が抱える問題は、わたしは言葉を失った、とは言えてしまうということである。これはいわゆる「表象不可能性」のパラドックスに似ている。「表象不可能なもの」は「表象不可能」として、実質的には表象されている。真正の「表象不可能」とは、けっしてそう呼ばれてはならないし、呼べもしないものなのだ。同様に、くだんの「震災」と「原発」によって惹き起こされた失語症もまた、そう表明し告白されることによってパラドキシカルな発話として機能し、発語を選んだ者を無意識に断罪する。そして、それはそれで無理もないことだとも思うのだ。だが、忘れられてはならないのは、わたしは言葉を失った、とさえ口に出来ない者たちへの想像力と、短慮の謗りを恐れず発語を選んだ者たちへの真っ当な理解である。そうではないか?
2。「後ろめたさ」と「みっともなさ」
映画『311』には、ドキュメンタリー作品としては些か例外的なことだが、監督として四人の名前がクレジットされている。森達也、綿井健陽、松林要樹、安岡卓治。森にかんしては説明は不要だろう。綿井は、アフガン、イラク、東ティモール、(津波被害の)パプアニューギニア等々を現地取材してきた国際派の映像ジャーナリスト。四名の中で最も若い松林は気鋭のドキュメンタリー映画作家。そして森の『A』『A2』、綿井の『Little Birdsーイラク戦火の家族たち』、松林の『花と兵隊』のプロデュースを務めたのが安井である。 二〇一一年三月二六日から三一日にかけて、彼らは一台の車に同乗し、東北へと向かった。岩手県陸前高田、大船渡、遠野市、宮城県仙台、石巻、東松島市、福島県三春、浪江、大熊町と廻り、四名が各々ビデオカメラでその一部始終を記録した。そうして残った五〇時間強の素材を、追って安井が編集し、一本の長篇ドキュメンタリー映画として完成したのが『311』である。だが四人とも、それぞれの動機によって、とにもかくにも「現認」するために行ってみよう、というだけで、当初は作品にするつもりなどなかったという。映画化へと至る顛末については、公開に合わせて刊行された四人の共著『311を撮る』に詳しい。 『311を撮る』の中でも、ロードショー公開に先んじて山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映された際の観客からの激しい反応について触れられているが、確かにこの映画の評価は賛否両論が真っ二つに分かれるだろう。「震災」と「原発」をめぐっては、すでに夥しい数の映像作品が撮られているが、その中でも『311』は極めつけの問題作だと言える。その理由を安岡卓治は一言でこう述べる。「この映画は、被災地を取材しているが、主人公は取材した我々自身だ」。 作品にするつもりがなかったのだから当然と言えば当然かもしれないが、映画の冒頭、被災地へ出発してまもない頃の四人の言動は、まだどこか緊張感を欠いている。確かに『311』の「主人公」は、四人の監督自身である。だが、それとは別に、実はこの映画には前半と後半で、それぞれ「主役」が居る。前半の主役は「線量計」である。福島第一原発から約150kmに位置する東北自動車道で計ってみると、見る見るうちに数値は上昇していく。東京とは比較にならない、その上がりっぷりに驚きと戸惑いを隠せない彼らだが、それでもその言葉の端々には、びびりながらも面白がっているような雰囲気が窺える。「健康への影響は?」「直ちに?」「直ちに、ある��思います」という、当時何度も繰り返されていた枝野官房長官の言い草をもじったやりとりは、まだ軽口の次元を出ていない。しかし道中が進むにつれて、線量は飛躍的に上がっていく。線量計が発するピコピコという電子音がずっと聞こえている。防護服を買い、マスクとゴーグルで顔を覆った彼らは、福島第一原発を目指すが、8kmのあたりでタイヤがパンクしてしまい、敢えなく引き返すことになる。その修理の間も、ビニール袋に包まれた線量計は、ピコピコを発している。すでに数値は東京の百倍を超えている。 作戦(?)を練り直した彼らは、今度は津波被害に遭った地域を目指す。陸前高田で、あまりにも圧倒的な被害の甚大さに茫然とする四人。まだ地震から二週間ほどしか経っておらず、あちこちで行方不明者の懸命な捜索が続けられている。仙台で共同通信の多比良孝司記者と合流して、石巻の赤十字病院や避難所となった高等学校などを取材し、石巻市立大川小学校に辿り着く。まるで爆撃に遭った跡のような壊滅的な光景がひろがっている。ふと気づくと、四人の中でも森達也が画面に映し出されることが増えている。森が被災者に話しかけ、インタビューする様子を、別の者が撮影し、そのカメラのファインダーを、もうひとりが撮影していたりもする。だが、映画の後半の「主役」は、この過程で唐突に映し出される「豚の死骸」である。いつしか四人の暗黙の目標は、遺体を撮ることへと収斂していっている。なぜならば、どこに行っても、すでに遺体はすべて運び出された後であり、その不可解といえば不可解な事実への微妙な違和感が募っていったからだ。人間の遺体が撮れなかったので代わりに豚の映像を置いたのだと言えば、不謹慎と思われても仕方がないが、それでもおそらく間違いなく、確実に、しかも大量に存在していた筈であるのに、イメージとしては徹底して不在の「人間の死」を代補するものとして、無造作に土の上に横たわる「豚の死」は、編集段階で残されたのだと思われる。 『311』の賛否両論を二分する重大な出来事が起きるのは、この後である。青いビニールシートで覆われた、おそらくは遺体を運んでいる様子を、やや後方から撮影していた彼らは、その場に居た男性から突然、木片を投げつけられる。なぜ撮ろうとするのか、撮らないでくれ、どういうつもりなのだと詰め寄る男性に、森が抗弁する姿を、ドキュメンタリストとしてのあるべき態度だと捉えるか、何もそこまでやらなくても、流石にみっともないのではないかと思うかで、この作品への評価は真逆になる。実際、あまりにも後味の悪いラストであるという感想も、映画を観た者から多々寄せられたという。その中には、森たちと同じ、取材する立場の人間も居た。 ひとつ確実に言えることは、しかしこの後味の悪さは、安岡卓治が編集作業を通して発見し、四人の合意の上で、意図的に刻印されたものだということである。『311を撮る』は、四名が一章ずつを書き下ろした共著であり、内容的な擦り合わせや統一は敢て行なわなかったという。結果として、それぞれの考えや受け取り方の違いが鮮明に出ている。綿井健陽は、百戦錬磨のジャーナリストらしく冷静な熱意をもって取材に当たりながらも、過去に経巡ってきた戦場をも超える被災地の惨状に茫然とする。彼は遺体を撮ることに強く執着し、後になって自らの執着について省察を続ける。彼はその後も何度か別のチームで福島へと向かうことになるだろう。松林要樹は、映画祭や試写で浴びた批判について「褒められるよりけなされたほうが、どこか納得のゆく気持ちが起きる」と記している。「消化不良の感情はいまだにある。この生煮えの感覚をどう乗り越えていくのか」。彼は『311』の取材から東京に戻った四月一日の翌日、南相馬市に支援物資を届ける旧友の車に同乗し、ふたたび被災地に向かった。彼はそれから幾度も南相馬を訪ね、そこに生きる人々と触れ合いながら撮影を続け、やがて『相馬看花ーー第一部 奪われた土地の記憶』という一本の映画として完成させ、『311』と同じく山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映するに至る(私はこの作品を未見だが、必ず観るつもりでいる)。プロデューサーであり編集者でもあるという、他の三人とは異なる立場を背負った安岡卓治は、何よりもまず、これを作品として完成させること、そして完成した映画を公開することにかんして、その是非について悩み続ける。その時、彼の頭を過ったのは、ジョナス・メカスの「われわれの欲しいのは血の色をした映画なのだ」という言葉だったという。彼は書いている。
映画『311』は、何もなしえなかった我々の無力さを描いている。ネガティブなスタートラインだと思う。それは、二〇一一年三月時点の我々の姿をはっきりと刻み込むことだ。この無念さを消したり、何かキレイごとで覆い隠したりはしない。
森達也は、あの日のあの時間、「ドキュメンタリー番組企画コンペティション」の審査会のため、六本木の高層ビルに居た。仕事は中止され、交通機関も動かないので、地震と津波が東北に齎した、今まさに齎しつつある悲劇を知らぬまま、居酒屋で泥酔した森は、夜になってから被害の規模を知って愕然とする。彼はそれから二週間近く、自宅に閉じこもってひたすらテレビを見続けた。他には何もせず、時には泣いたりしていた。だから綿井健陽から被災地への同行を求められた時も、最初は「無理だよ」と答えている。だが、森はその直後、自分から綿井に電話して「行く」と告げたのだった。
心変わりした理由は、自分でもよくわからない。このま家でテレビを観続けながらメソメソしていても仕方がないと思ったことは確かだ。(略)被災したわけではないし家族が津波で流されたわけではない。食べるものに困っているわけでもないし、寒さに凍える夜を過ごしているわけでもない。 つまり僕は非当事者なのだ。 ところが気分的には当事者になりかけている。最も悪いパターンだ。ならば現地に行くべきだと考えた。もちろん現地に行ったとしても、当事者になれるはずはない。でも非当事者には非当事者の役割がある。自分にも自分の役割がある。
森は完成した映画を「被災者たちを後景にしてセルフ・ドキュメントを撮るようなもの」と認めている。それは安岡がいう「我々の無力さを描く」ということでもある。無力な非当時者であるしかない自分は、そのままの存在として、被災地にカメラを向け、カメラを「反転」させて、無様でみっともない自らの姿を映し出す。善意の取材者を装い(と敢て書くが)、何とかして被災地に在る者たちから「悲劇」を聞き出そうと、それを無理にでもカメラに記録させようとする森の物腰は、ともすればトゥーマッチな露悪趣味のように見えなくもない。映画の中盤から、水を得た魚のように活躍し出す、このような森の態度は、大川小学校のシーンで、いわば負のクライマックスを迎えることになる。だが、森は自分の非道ぶりを、誰よりもよくわかった上で、そうしているのだ。彼はただ「自分の役割」に忠実たろうとしているだけだ。
自覚すること。自分は残酷な存在なんだと思い知ること。撮ったり取材することは鬼畜の所業なのだと認めること。後ろめたさを引きずること。
森は、英語で「Survivor's Guilt」と呼ばれる感情について書いている。それは、生き残った者、死ななかった者の罪の意識、後ろめたさのことだ。彼はアウシュヴィッツを生き延びた作家プリーモ・レーヴィの死に触れ、Survivor's Guiltを特権意識とパレスチナへの憎悪に転化させたイスラエルについて述べる。そして、大切なのは、「sens of guilt」を引きずること、引きずりながら前に進むことだ、と書く。 四人の監督の認識は、少しずつ、部分的にはかなり異なっている。だが、全員が認めているのは、『311』という映画が、「後ろめたさ」についての映画であるということだ。それは「非当事者」であるがゆえの感情である。だが、何をどうしたとしても「当事者」にはなれない事態というものが、この世界には存在している。だから出来ることと言えば、背負ってしまっ��「後ろめたさ」をけっして手放さず、それと向き合い、むしろ凝視するようにして、そしてそれでも何ごとかをやるつもりがあるのなら、ただやればいいだけだ。それはしかし、当事者ではありえないからこそ出来ることがある、などといった、やはり綺麗事というしかないような言い訳とは違う。そうではなく、それはあたかも鈍感であるかのような表情で、他人に晒け出されるのはもちろんのこと、自分自身にも翻って突き刺さってくるだろう、ある歴然とした、みっともなさに耐えることなのだ。 『311』は、どうしようもなくみっともないドキュメンタリー映画である。だが私は、こう言ってよければ、ある爽やかさを感じた。それは「後ろめたさ」が乗り越えられているからではなくて、まったく反対に、そこに「後ろめたさ」がくっきりと映っているから、四人の監督が、それぞれの「後ろめたさ」を大事に抱え持っていることが、正にその後味の良くない「みっともなさ」ゆえに、よくわかるからである。
3。「俺だって考えてる」
『魚は海の中で眠れるが鳥は空の中では眠れない』の「��えがき」で、保坂和志はこんなことを書いている。
この連載が終わりに近づいたところで三月十一日の地震と津波があった。福島第一原発の事故もあった。私は当然それについて書くことになるのだが、それはそんなに“当然”だったのだろうか? 私はあの地震のことも津波のことも原発のことも本当に書かないではいられなかったんだろうか、そのとき私の関心は他のほとんどの人と同じくそのことにしかなかったんだからそういう意味では当然なのだが、それでもやっぱりそのことが私の心のすべてを占めていたわけではないことを考えると、結局私はまわりの人というよりもむしろ私自身に向かって、 「俺だって考えてる」と、言い訳したりポーズを取ったりしていただけなんじゃないか。
「俺だって考えてる」と言いたいがためにだけ書かれたと思しき「ことば」は、間違いなく数多ある。むしろそれを言いたい相手が「まわりの人」ではなく「私自身」であるだけましではないかと思う。私はかなり早い時点から、多少とも社会的な発言を求められていると自認しているらしき連中による「俺だって考えてる」に辟易させられていた。何かを思うこと、何ごとかを考えるということと、それを他者に伝えること、公に発言することは、まったく別の次元にある。無論、外に出さなければ誰にもわからないわけだが、ひとは考えてもいない/思ってもいないことだって口に出せるし、書けてしまう。それに「俺だって考えてる」と誰かに思われたくて書かれるようなことは、保坂氏も言うように、大概は退屈である。だが時として、とりわけ非常時には、ひとは「退屈」を真摯さと取り違える。それで益を得る者も居る。 だから私は、長らく「震災」と「原発」にかんする発言に、たぶん人一倍警戒的であったし、シニカルでもあった。その種の求めは、ほぼ全て断った。私の目と耳には、多くのそうしたものは「俺だって考えてる」に翻訳されたし、だから自分がそうしても結局は「俺だって考えてる」になってしまうのではないか、と思っていたからである。この自分でも幾分神経過敏ではないかとも思える感覚は、いまも基本的には変わっていない。だが、多少の変化はある。 スガ秀実の『反原発の思想史』は、戦後の「反核=反原子力=反原発」の歴史を専らニッポンの左翼運動/思想史の視点から読み直すことで、従来の了解に野太い楔を打ち込む刺激的な一冊だが、全体の論旨からするとやや傍系に属する部分に、ごく短い和合亮一への言及がある。一九五四年に編まれた『死の灰詩集』に鮎川信夫が浴びせた痛烈な批判にかんして触れた箇所で、スガはいささか唐突に、こう書く。「在住地福島からツイッターによって発信され、詩集として刊行されている和合亮一の詩(『詩ノ黙礼』、『詩の礫』、『詩の邂逅』、いずれも二〇一一年)は、震災・原発事故以後の「国民感情」におもねっただけのものではないのか、どうか」。 「国民感情」というのは、鮎川信夫が、詩人の代表的団体である現代詩人会による「反核」の表明である筈の『死の灰詩集』が、執筆者の顔ぶれとしても、また本質的にも、大東亜戦争総力戦体制下における愛国的/戦争賛美的な「文学報告会編『辻詩集』の戦後版」だと喝破したこと、両者に共通するのは、その時々の「国民感情」におもねってみせる姿勢だとしたことに因っている。そしてスガはこう続ける。
和合の詩は、たとえば、宮沢賢治という東北出身の「国民的」詩人を頻繁に参照することで適当にソフィスティケートされており、適当に「つぶやき」であり適当に「叫び」である。「南相馬市を見捨てないで下さい」と言うことは、実際にそうであるか否かは問わず、「見捨てる」と言うはずもない、「国民感情」におもねっているのではないのか。そのソフィスティケーションは、震災直後から公共広告機構のCMでいやというほど流された、金子みすゞ程度のゆるいものである。そのゆるさが、おもねりの証明なのだ。
スガは和合の「ツイッター詩」を、あくまでも「詩」として、あるいは「詩集」として、つまり「作品」として評価し審判しているが、それは現実には、余震と放射線量に脅えながら毎日毎晩、携帯からきれぎれに発された「つぶやき」の集積である。もちろんそれらは和合自身によって明確に「詩」であると宣言された上で、ネット上に送り届けられたものではある。詩の言葉として客観的に読めば、そこに「ゆるさ」があることは確かだが、現代詩の中でもアバンギャルドな作風であった和合が、あのようなナイーブでストレートなフレーズの数々を書き付けざるを得なかったという事実が意味するものを、和合の「詩」の「以前」と「以後」の落差をこそ読むべきではないか。「南相馬市を見捨てないで下さい」という台詞に、「国民感情」は「見捨てる」と言うわけがない、と返すのは、あまりにも和合に酷ではないだろうか。絶対に見捨てられる可能性などないと、あの時点で和合に確信出来た筈がないのだから。 たとえば「以前」の和合亮一の「詩」とは、次のようなものである。
(「GO NO GO」、冒頭より「ゲームオーバー/リセット」まで) (「爆笑悶絶反転大龍」、冒頭より「驚天動地の現実に取り残される一行としての龍」まで)
二〇〇五年に刊行された和合の第四詩集『地球頭脳詩篇』の二篇から抜粋した。すこぶる「現代詩」らしい書法と言っていいだろう。和合はもともと、ヴァラエティに富んだ主題を、先行世代のさまざまな達成を踏まえた華麗なテクニックを駆使して作品化してきた。彼は「現代詩」の「現代詩らしさ」に、極めて敏感な詩人である。そんな彼が、二〇一一年三月十八日深夜の「ツイッター詩」では、こう書きつける。
あなたの街の駅は、壊れていませんか。時計はきちんと、今を指していますか。おやすみなさい。明けない夜は無いのです。旅立つ人、見送る人、迎える人、帰ってくつ人。行ってらっしゃい、おかえりなさい。おやすみなさい。僕の街に、駅を、返してください。(『詩の礫』)
これを前掲の諸作と同じ次元にある「詩」として読むならば、むろん明らかに弛緩している。それは間違いない。それに和合の振る舞いの内に、スガをして先の批判を綴らせるような部分がまったく無いとは、私も思わない。けれども、もっと重要なことは、かくのごとき「ツイッター詩」が、自分が過去に書いてきた「現代詩」とは較べるべくもない水準にあることを誰よりもよく知っている筈の和合自身が、それを敢て「詩」と呼んだ、ということなのではないか。それは「現代詩」としての純然たる価値判断とは別の、だが切実極まりない理由によって為されたことだ。「失語」に必死で抗するために、どうしても発さざるを得なかった言葉なのだ。これもまた「短慮」かもしれない。だが、和合は「これは詩ではない」と述べることだって出来たのだ。しかし彼はそうしなかった。このことの意味を考えなくてはならない。 ところで、スガ秀実は、こんなことも書いている。
アドルノは、「アウシュヴィッツ以降、詩を書くことは野蛮である」(『プリズメン』)という有名な言葉を残した。しかし、「福島」以降の「詩」の問題とは、おもねることのない野蛮な���を書くことなのである。そのような詩を書ける詩人は、今の日本において皆無に近いだろう。
「野蛮な詩」が必要とされているという指摘は、あまりにも正しい。「詩」に限らずとも、今こそ「野蛮」さが必要とされている。だが、その「野蛮」さとは、単純な意味で「国民感情」と逆立すれば、そう見えればいいわけではないだろう。「短慮」や「後ろめたさ」や「みっともなさ」だけではないのはもちろんのことだが、「俺だって考えてる」に陥らず、「失語」をも回避するためには、一見「野蛮」とは思えないような、新しい「野蛮」が要請されているのではないか。このことは今後、時間を掛けて考えていきたい。
4。「三月一一日」と「三分一一秒」
『反原発の思想史』の和合亮一への言及に続けて、スガ秀実は、「映画においても、似たような事態が発生している」と書き添えている。
『殯の森』で二〇〇七年のカンヌ国際映画祭グランプリを獲得したことで知られる映画監督の河瀬直美は、三月一一日の「福島」に際し、世界の著名な映画監督に三分一一秒の短篇を作ってもらい、それを集めてオムニバスの六〇分にして、被災地を巡回上映すると呼びかけた。この試みが愚劣なのは、まず何よりも、「三分一一秒」という言葉の無意味な美学化にある。
ここでもスガの言っていることは正しい。だが同時に、やはりどこか不十分であるとも感じる。私は河瀬直美企画のオムニバスは観ていないが、同じく「三分一一秒」の短篇映画四十二本から成る、仙台短篇映画祭映画制作プロジェクト作品『明日』を観ることが出来た。「ショートピース!仙台短篇映画祭」は、従来は短編映画の一般公募をメイン・プログラムとする映画祭だが、震災によって昨年度の開催が危ぶまれる中、発足十一年目にして、はじめてとなる映画制作に踏み切った。映画祭実行委員の菅原睦子が『明日』のパンフレットに寄せた文章は、「映画祭をやりたい。ただ、その思いだけだった」という一行から始まる。
そのとき久しぶりにスタッフが顔を合わせ、みんなで寄り添いながら確認したことは、「予算も会場もなくなったけれど、今年も映画祭をやりたい」、「できることなら、上映する映画を新たにつくってもらおう」ということだった。 映画をつくってもらうなんてことが、本当に頼めるのか。つくってもらうなら、どんな内容がいいのか。躊躇していた私を、4月7日、2度目の���きな地震が襲った。春の訪れとともにやっと回復の兆しを見せ始めた街から、再び電気が消えていく。そんな光景を目の当たりにし、私はどこか壊れてしまったのかもしれない。「つくってもらうぞ!」という勢いで、本当に勢いだけで、監督や制作に携わっている70人近い方々にメールを出した。 けれども、勢いでメールを出した元気は、翌日にはあっけなくしぼんでいた。映画をつくるなんてことを、こんな時に言っていいのか。能天気な発想ではなかったか。沿岸部の大変さや福島のことを考えると、あまりに考えなしの行動と映るのではないだろうか。やってしまったことに不安が跳ね返ってきて、一気に気持ちが悪くなってしまった。 そんなとき、ひとつ、ふたつと返信が届き始めた。「やりましょう」。何度も何度もメールを見た。小さなノートパソコンのモニターが、闇を照らす光のように思えた。
こうして四十一人の監督による四十二本の短編映画が完成した(ひとりだけ二本制作した者がいるのだ)。決まり事は二つだけ、テーマは「明日」、そして「三分一一秒」であること。当然のことながら内容は非常にヴァラエティに富んでいる。参加した監督も、塩田明彦、山下敦弘、篠原哲雄、鈴木卓爾、入江悠、瀬田なつき、真利子哲也、甲斐田祐輔、佐藤央、濱口竜介、堀江慶、内藤瑛亮、田中羊一、等々、若手から中堅まで注目の才能が揃っている。河瀬直美もいる。だが私がもっとも印象深かったのは、唯一、二本を監督している冨永昌敬の作品だった。 二つの「三分一一秒」は連作になっており、どちらも冨永監督が手を変え品を変えつつ継続しているシリーズ「シャーリー・テンプル・ジャポン」で主人公シャーリーを演じている俳優(福津屋兼蔵)が映画監督に扮している。最初の『妻、一瞬の帰還』は、監督が病院から退院してきた妻を迎えに行くと、どうやら嫉妬心のあまり精神に異常を来していたらしい彼女はすぐさま自分が入院中の夫に疑いの目を向けて錯乱し、そのまま自ら「病院」へと引き返す。『武闘派野郎』は、その翌日の話である。前日の妻の台詞の中で語られていた若い女性(妻の前夫の妹)が男友達を連れて監督の家を訪ねてくる。単細胞丸出しの男友達は映画に出たいと言って初対面の監督に不躾な質問を浴びせ続けたあげく、腕相撲で勝負しようと挑みかかる。 何しろ「三分一一秒」しかないので、どうしてもコントみたいになってしまうし、実際かなり笑えるのだが、しかしよく考えてみると、かなり巧妙に出来ていることがわかる。二本立てなのは、一本目の翌日が二本目ということで、これによって「明日」というテーマをクリアしたということだろう。人を食っているといえばそれはそうだが、企画を逆手に取った、冨永昌敬らしい発想だと思う。また映画のラストは二本とも、家に居候している友人の「何かあったの?」という問いかけに対して、監督が「何でもない」とぶっきらぼうに答えるというものである。ではこの友人はどこから来たのか? ひょっとすると被災地かもしれない。そう考えられる証拠は映画のどこにもないのだが、しかしこの二本が『明日』というオムニバス映画の一部であるということが、観客にそのような想像力を働かせることを許している。 じつは先ほどの菅原氏の文章の中で、彼女に『明日』の製作を決意させたのは、冨永昌敬であったことが明かされている。冨永監督の映画『パンドラの匣』のロケ地は南三陸町であり、彼は二〇一一年四月一日に同地を見舞った帰りに仙台へも立ち寄り、かねてより親交のあった映画祭のメンバーと再開した。引用部分冒頭の「そのとき」とは、冨永監督の来訪時のことを指している。『明日』のパンフに彼は「映画制作のこと」という文章を寄せているのだが、そのとき、彼は「企画上映やりましょう。みんなで短い映画を持ち寄れば大きなプログラムになりますよ」「どんなに忙しい監督だって5分や3分の短編だったら撮ってくれるでしょ」などと叫んだのだという。そこから、いつしか「三分一一秒」の短篇オムニバスという企画が立ち上がっていったということらしい。
だからこの企画は、不特定多数の被災者や被災地に向けて発案されたものではないと僕は思っている。ましてやこの未曾有の国難下の日本に救いをもたらすような殊勝な意志でも決してない。何よりも願うべくは仙台短篇映画祭の健全な開催なのであって、そのためならばと、多くの作り手たちが手製の小品を持ち寄ったというのが正確なところではないだろうか。(中略) その中身がどんな「3分11秒」であろうと、積み重ねれば「6分22秒」にも「9分33秒」にも「12分44秒」にもなる。いや、いずれ「3日11時間」くらいの大作にまで膨張するかもしれない(いったい何年後だろう?)。まあともかく、うずたかく積まれた小さな固い石の集まりが、やがて強固な防波堤となり、映画を愛するこの美しい町を人知れず囲んでしまうことを僕は夢想する。
真に感動的な文章だと思う。なぜ冨永作品だけ二本あるのか、という素朴な疑問への答えも、これで明らかだろう。もちろんそれは「三分一一秒」を「六分二二秒」に、そしてそれ以上に「膨張」させていき、遂には「強固な防波堤」を築くという「夢想」を実践的に示唆するために行なわれたことなのだ。ほとんど巫山戯ているとしか思えない内容の二本の「三分一一秒」によって、冨永昌敬は仙台の映画の友人たちの想いに応えようとしたのである。明日には「明日」が存在しているということ。無数の「三分一一秒」が「防波堤」にだって成り得ること。このふたつの事実を示すことによって。そう考えれば、監督と友人による「何かあったの?」「何でもない」の反復も、また別の意味を帯びてくるのではないか。 ここでようやっとスガの指摘に戻るが、ひとつ確実に言えるだろうことは、もしも「三分一一秒」という言葉の「無意味な美学化」と言える作業が為されているのだとしたら、それは「三月一一日」を「三分一一秒」に短絡的に変換することだけではなく、そうして現れることになった「三分一一秒」を殊更に問題化してみせることによって完遂されるのだということである。菅原睦子の文章には「三分一一秒」にかんする言及は一切ない。冨永昌敬が書いているように、それはいわば単なる思いつきでしかない。「三」と「一一」という数字=言葉には、何の意味もありはしない。もちろん「三月一一日」についての「三分一一秒」の映画というと、すぐに思い出されるのは、「九月一一日」をめぐって世界十一カ国の監督たちがそれぞれ「11分9秒1フレーム」の短篇を撮ったオムニバス映画『セプテンバー11』である。おそらく河瀬直美には、あの作品のことが頭にあっただろう。だが『明日』は違う。それはただ「どんなに忙しい監督だって5分や3分の短編だったら撮ってくれる」ということなのだ。四十二本の「三分一一秒」は、無意味ではあるが美学化されてはいない。そこには「三」と「一一」という数字=言葉によって悲劇をシンボライズするという意図は存在していない。それはただ、誰かに撮ってもらえたらと願う、未だ見ぬ映画へのささやかなきっかけとして差し出されているだけなのだ。 スガ秀実の言う「「三分一一秒」という言葉の無意味な美学化」は、その批判としての正当性、有効性を十分に認めた上で尚、それ自体も「美学的」であると私には思える。それは「三月一一日」から「三分一一秒」を抽出するという行為に対する趣味的価値判断であるからだ(「無意味」というのは言い換えれば、美しくない、醜い、ということだろう)。だが『明日』における「三分一一秒」は、要するに只の口実に過ぎない。四十一人の監督の誰ひとりとして「三分一一秒」に「意味」を感じてはいなかっただろう。けれども、この無意味で美しくはない「口実」がなければ、仙台短篇映画祭の菅原睦子は、依頼のメールを送ることは出来なかったのだ。
5。切り返しとオーバーラップ
『なみのおと』は、「仙台短篇映画祭」と同じく、せんだいメディアテークを拠点とする「3がつ11にちをわすれないためにセンター」の活動の一環として、東京藝術大学大学院映像研究科によって製作された長篇ドキュメンタリー映画である。ともに同大学院を修了した濱口竜介と酒井耕の二人は、二〇一一年七月から幾度か三陸沿岸部を訪ね、六つのインタビューを撮影した。この映画では(『311』とは対照的に)被災地の光景は、まったく映されない。津波の跡も瓦礫も原発も登場しない。二時間半近い上映時間のほとんどは、自らの被災体験を話す人々を捉えた映像である。昭和八年の三陸大津波を体験した老姉妹、気仙沼の消防団員たち、かけがえのない親友を喪った初老の女性、石巻市議会議員の男性、津波で家ごと流されたが九死に一生を得た夫婦、相馬市で働く若い姉妹。それぞれ数十分の長さを持った各シーンの間に車での移動のショットが挟み込まれる以外は、他の要素は一切ない、シンプルな佇まいの作品である。 この映画は「オーラル・ヒストリー(口述による歴史)」の試みであるとされている。「この“語り”は、実際は過去や未来のためという以上に、今まさに起こっている「復興」の活動そのものなのではないだろうか、という気がしています。それは、瓦礫をただの瓦礫にしないための、個人と共同体の歴史を取り返す作業であるからなのです」(「作者のことば」山形国際ドキュメンタリー映画祭・東日本大震災復興支援上映���ロジェクト「ともにあるCinema with Us」カタログ)。実際、全体としては淡々とした雰囲気を保ちながらも、だがしばしば抑えようとする感情が否応無しに溢れ出すこともあるインタビューイたちの話は、いずれも実感と今だ生々しい記憶によって語られているだけに、現在形の歴史性とでも呼ぶべき強度を備えている。 だが、それと同時に、この映画を観る誰もを少なからず戸惑わせることになるのは、インタビューの撮られ方である。通常のドキュメンタリー映画において、インタビュー場面は、基本的に長廻しで撮影するか、一連の語りを複数のカメラで撮影しておいて編集するという形が取られることが多い。だが、この映画では、まるで劇映画のように、いや、もっと精確に言うなら、まるで小津安二郎の映画のように、いわゆる「切り返し」が多用されているのである。 最初の老姉妹のシーンを例に説明しよう。インタビューイが複数居る場合、別々に撮影するか、横に並んでもらって話を聞くのが普通である。だが『なみのおと』では、二人は互いに向かい合って坐っている。つまり対話をしているように見えるのだが、にもかかわらず、二人をそれぞれ真正面から撮ったショットが細か��挟まるのである。だが二人の話は切れ目なしに続いている。対面する二者を正面から捉えた画面が交互に編集されることを「切り返し」という。これは劇映画においては特に珍しいことではないが、ドキュメンタリーでは奇妙な印象を与える。明らかにインタビューである筈なのに、あたかも緻密なカット割りが施されているように見えるからである。この奇妙さは、インタビューイが更に多い消防団員のシーンでは、より強調されることになる。また、インタビューイが一人しかいないシーンでは、聞き手を務めているらしき監督が対面して「切り返し」が行なわれている。 一体どのようにして、このような場面が撮られたのだろうか。推測の域を出ないが、おそらく各々のインタビューは二度(もしくはそれ以上)行なわれている。監督たちはまず普通にインタビューイに話を聞いて(二名以上の場合は個別にインタビューして)、その上で各シーンの構成をカット割りまで含めて或る程度準備してから、本番(?)の撮影に臨んだのだ。その際、インタビューイは、同じ体験談を二度以上することになるが、それゆえに個々の話は反芻され、整理されて、却ってリアリティを増しているのである。二名が対面するシーンでは、各々の真向かいからややずれた位置にカメラを据えて撮影したと思しきショットもあるが、しかし「切り返し」が引き絵になった時にはカメラは消えている。これは相当に計算して撮影していないと不可能なことである。 濱口竜介と酒井耕は、いずれも元々はフィクション映画を撮ってきた監督であり、『なみのおと』が初めてのドキュメンタリー作品である。「切り返し」という劇映画的手法の導入が意図的なものであることは明白だが、ではなぜ彼らはこのような(おそらくはかなり面倒な)方法をわざわざ取り入れたのだろうか。もちろん、まず第一に、人の顔を真正面から撮ることによって得られる美学的側面ということがあるだろう。この映画の感想をネットで幾つか読んでみたが、この点にかんする言及はやはり多かった。だが、表情をつぶさに映し出すということのみならば、ドキュメンタリーであれば「切り返し」を用いなくても出来ることである。だからむしろ、より重要なことは、カメラに、ではなく、生身の誰かに語りかける、誰かと語り合う、ということだったのではないか。インタビューはその本性上、問いと答えの応酬という形式を取る。だが問われる前から、インタビューイの内には、誰かに向けて語られるべき記憶の物語が潜在している。如何にしてそれを、出来る限りそれそのものに近い姿で掴み出すか。逆説的なようだが、劇映画的「切り返し」は、そのためにこそ召喚されたのだ。「ドキュメンタリーは嘘をつく」と言ったのは森達也だが、その反対側には「フィクションは現実を晒す」という真理が存在している。『なみのおと』における「切り返し」は、いうなればフィクションとドキュメンタリーとハイブリッドである。先ほど、インタビューは二度以上行なわれたのではないかという仮説を述べたが、だからといって一度目が本物であり、二度目以降は演技ということではない。そうではなく、一度目から多少は演技であり、二度目以降にも真実は宿っている。『なみのおと』では撮る側も撮られる側も、そのことに意識的にならざるを得ない。ただカメラを回して質問を口にするだけでは、或いはカメラの前で自由に会話してくださいと求めただけでは、どうしても露わにならないことがある。それは「切り返し」のようなあからさまな作為の介入、フィクション性の導入によってこそ、画面に現れてくるのである。 これと似た感覚を、『311』の監督のひとりである松林要樹の単独作品『相馬看花ーー第一部 奪われた土地の記憶』でも味わった。前回も触れておいたように、『311』のロケから東京の下宿に戻って間もない四月三日、松林は支援物資を届けるという友人の車に同伴して、ふたたび被災地に向かい、福島県南相馬市原町区を訪ねた。彼はそこで偶然に南相馬市議会議員の田中京子と知り合う。地震と津波による被害のみならず、福島第一原発から20キロ圏内に自宅がある為に避難所生活を余儀なくされている田中夫妻と南相馬市原町区江井地区の人々との交流は、思いがけない継続的な撮影へと松林監督を誘っていった。そうして一本の映画として出来上がったのが『相馬看花』である。 成立の経緯だけではなく、これはまさしく『311』の「続編」と呼ばれるべき作品である。『311』への「消化不良の感情」を隠そうとしていなかった松林監督が、自分なりの落とし前をつけようとした映画であると言っていい。田中氏の導きによって、震災と原発事故によって生活を根こそぎ損なわれた人たちとの幾つもの出会いがあり、彼は只管それをカメラに記録していく。それはやがて、この土地に深く刻印された、原子力発電所との、必ずしも望まれたわけではない共生の歴史=記憶を遡っていくことになる。「第一部」と題されているということは、当然「第二部」以降も予定されているのだろうし、事態は今現在も刻々と変化しているのだから、文字通りのドキュメントとしての役割を、この映画が担っていることは間違いない。だが私は、そればかりではなく、一編の「映画」として、『相馬看花』は紛れもない傑作であると思う。それは何よりもまず、この映画における「映像=イメージ」の複雑かつ繊細な用いられ方による。 『相馬看花』には、松林要樹が撮影したもの以外にも、複数の「映像=イメージ」が登場する。田中夫妻と親しくなった彼は、警戒区域への一時帰宅が認められた際に、居住者ではない自分は同行が許されないため、ビデオカメラを貸して撮ってきてもらうことにする。映画には田中氏の撮影による一時帰宅の一部始終が、ほぼそのまま取り入れられている。また、そのとき松林監督は、田中夫妻に自宅から一枚の写真を持ってきてくれるように頼む。それは原発から約15キロにある小高神社であげた夫妻の結婚式の記念写真である。まだ立ち入りが可能だった或る日、田中久治氏に桜を撮ってくれと言われて、その神社を訪れた折に想い出話を聞いたことがあったのだ。数十年も昔のモノクロ写真には、若かりし頃の田中夫妻と一緒に、すでに松林もよく知っている人達の姿が映っている。小高神社は、東京電力が原発の安全祈願を行なう所でもある。 結婚式の写真だけではなく、この映画には数枚の写真が画面に現れる。興味深いのは、それら写真の幾つかが、まず説明抜きにカットインやオーバーラップで提示されるということである。たとえば若き田中京子氏と子どもたちが写った写真は、最初に出てきた時には何であるかわからない。彼女の回想がその写真に記録された過去へと差し掛かると、ふたたび画面に写真がオーバーラップしてきて、ようやく観客はあれはこれだったのか、と納得することになるのだ。このようなカットバックならぬカットフォワードとでも呼ぶべき手法が、この映画では何度か使用されている。 もっとも印象的なのは、粂という老夫婦のエピソードである。足の不自由な妻のため、避難勧告が出てからも自宅に留まっていた二人を、田中氏と共に松林は訪ねる。水道も電気も止まった屋敷で、夫妻は炭で暖を取って生活していた。酒が足りないと話す粂氏に、次に来る時は一升瓶を持ってくると約束した松林は、ふたたび友人の写真家を伴って被災地を取材した折に、酒を土産に粂家を再訪する。粂氏は引退してから既に二十数年が経っているが、かつては福島第一原発の安全専任者として働いていた。帰りがけに写真家は夫妻を屋敷の軒先で撮影する。レンズに向かって穏やかに微笑む二人の背後に原発の鉄塔が見えている。それからまた暫く経って、粂夫妻は避難所に移っている。松林は写真を渡しに二人に逢いに行く。粂氏はとても喜んで、お返しだと言って自分のカメラで松林を撮る。だが現像されたその写真が画面に映し出されることはない。 このように『相馬看花』は、直截的なテーマとはまた別に、「映像=イメージ」と「見ること」をめぐる映画という側面を持っている。複数の古い写真や、作者とは異なる者による映像の意図的な挿入が、この映画に豊かな時空間的膨らみを与えている。それらはいずれも、いつかどこかで誰かが見た光景である。更には、素性がすぐにはわからないイメージのオーバーラップ/カットフォワードが、観客の「見ること」への意識を刺激する。そもそも題名からして「相馬で花を看る」という意味である。看ること。見ること。テーマとは別だと言ったが、しかし松林要樹にとっては、あの『311』の「続編」として、自分はいったい何を撮れるのか、撮るべきなのか、という現在進行形の内省と、南相馬の人々との親密なかかわりの中で、原発に蝕まれた土地の記憶=歴史への問題意識の深まりと共に、自然と導き出されてきたものであることも、また確かだろう。 『なみのおと』と『相馬看花』、二本の映画に共通しているのは、ドキュメントするためにこそフィクション��必要なのだ、という意識もしくは無意識である。「映画」に記録されているのは、常に既に嘗て「現在」であった「過去」であり、そうでしかない。だがそれが見られるのは常に「現在」である。だから「過去」を「現在」へと呼び戻すためには、その回帰に真の意味での切実さを与えるためには、何らかの仕掛けが要るのだ。それをフィクションと、ここでは呼んでいる。それは冨永昌敬の、一見したところ何とも不真面目な二本の「三分一一秒」に宿っていた誠実さとも響き合っている。そして私は、このあたりに「野蛮」へのヒントがあるような気がしているのだ。
6。算数・距離・測定
「群像」の五月号に掲載されていた大澤信亮の評論「出日本記」を読んで、あれこれ考えた。「言葉が出てこない。問いが定められない。何を考えても嘘になる。そういう状態が九ヶ月間続いた」という驚くほどに率直な「失語」の告白から、この文章は始まっている。
何が自分を立ち止まらせているのか、わかっている。未曾有の大災害という事件ではない。一人の他者だ。二〇一一年三月二十四日。福島の農家の方が自殺した。六十四歳の男性だった。三十年以上も有機農業を続けてきた人だった。そんな人が「もうだめだ」と自ら命を絶った。もう生きることが出来ないと。ここが出発点だと思った。 (中略)何かを書こうとすると、いつも男性のことが頭をよぎった。津波や地震で亡くなった方たちには、自然な同情も共感も抱けない私が、どうしてこの出来事にこうも囚われるのか。自殺と背中合わせの働くということ。そこに届く言葉が自分に言えるのか。そう考えてしまう。
このような述懐をナイーヴと取るか真摯と取るかは読み手によるだろうが、ここで自問されている「どうしてこの出来事にこうも囚われるのか」への答えは明らかだと思う。地震や津波は基本的には自然災害だが、農家の男性の自殺には間接的ではあれ下手人が居るからだ。撃つべき敵が特定されているからだ。だからここで言われているのは数万人の死者たちと一人の自殺者の対立ではない。ひとりの背後に無数の人々を見ているのである。だが敢てこのような、受け取り方によっては如何にも不謹慎な言い方を挑発的にしてみせることで、大澤氏は百二十枚に及ぶ自身の論考の発進力としている。だが同時にこういうことも言える。たとえば「東日本大震災の犠牲者は二万五千人。だが日本の毎年の自殺者は三万人」というような言表がある。この数字は正しいのだろう。しかし、このデータによって提示されているのは、数が多い方が相対的に深刻だということではもちろんない。当然のことである筈だが、私たちはしばしば、この点を見誤る。数が問題なのではない。数万人だろうが、たった一人だろうが、望まれざる死であったことには変わりない。二万五千よりも三万の方が多いという算数は、たとえ生真面目な心性に基づくものであったとしても、してはならない。世の中には、数えてはいけないことがあるのだ。 今回の地震は千年に一度の大地震だった。そういう出来事に対して普通の感覚だけで考えてはいけないと思った。千年に一度の出来事には、千年を超える思想だ。
こんなことを真っ直ぐに書き付けられるのが大澤信亮という批評家の個性であり、才能だとも思う。千年は「100年保存」の十倍、「あれから一年」の千倍である。無論こんな算数もしてはならない。ここで言われていることは、俺は「千年を超える思想」のつもりで書いてみせる、という個的な決意表明であって、それ以外ではない。だから私はひとりの読者として、その意気やよし、と思いつつ、この論考を読んだ。だが、その感想を述べるのは、ここでの目的ではない。千年と書いてあったから読む気になったわけでも、千年とあったのに読む気をなくさなかったのでもない。ただひとつ言っておきたいのは、次のようなことである。 震災後、百年後であれ、千年後であれ、自分が綺麗さっぱり居なくなってしまった後の「この世界」に向けて何事かを語るという仕草が、以前にも増して散見されるようになった。そしてそれらは多くの場合、或る種の「責任」の意識とワンセットで語られているよう���思う。しかし私は、こうなる以前から、そういった言説には微妙な違和感を禁じ得なかったのだ。それはまず第一に、百年後に向けて何かをすることと、「百年後に向けて何かをするべきだ」と語ることの間に横たわる断層が、どうしても気になってしまうからである。そこには欺瞞の萌芽がある。「自分が存在しなくなった未来」を云々したがる者ほど、実のところは「今」に強く拘泥し、責任感の披瀝の陰で、目先の利得に汲々としていることがあるのではないか。そして今度の出来事が、そのような者に都合の良い言質を与えたということなのではないか。私にはそう思える。断っておくが、大澤信亮がそうだというのではない。むしろ逆だ。「出日本記」を通読すれば誰にだってわかるように、大澤氏にはパフォーマティヴな戦略性がほとんどない。いや、戦略の有効性と限界を十二分に知悉した上で、敢て潔く毅然として勇ましくそれを捨ててみせている、というのが、彼の唯一のパフォーマンスと言うべきかもしれない。 先の引用のもう少し先で、大澤氏は平野啓一郎による「被災地への距離」と題された「被災地見学記」を取り上げ、批判している。自身の体験に照らして、平野氏の文章には、臭い、すなわち「潮の強烈な臭気と、瓦礫の下の死体の腐臭」の描写が存在していないことに触れ、「それは、主体に否応なく侵入してくる外部の経験を、氏の「書くこと」自体が遠ざけているからではないか」と大澤氏は述べる。
もし、書くということが「距離」を作るだけだとしたら、恐ろしいことだ。
「その距離は被災地と東京の距離以前に、作家と現実との距離のように思えた」。私は平野氏の文章を読んでいないので、この批判がどの程度当たっているのか、或いはまったくの言いがかりであったりするのかどうかは知らない。それよりも目に飛び込んできたのは「距離」の二文字である。 『震災とフィクションの“距離”』は、「2011年3月から9月の期間に15人の小説家が執筆し、期間限定で著作権を解除、転送自由のチャリティ作品として「早稲田文学」サイトで発表された16作品を一挙収録。並行して公開された英中韓3カ国語のバージョンと、執筆者たちによる対談・座談も同時収録(オビ文より)」された単行本である。参加している作家は、古川日出男(二編)、阿部和重、円城塔、福永信、芳川泰久、青木淳悟、松田青子、村田沙耶香、中村文則、木下古栗、中森明夫、牧田真有子、川上未映子、鹿島田真希、重松清の十六名。震災にかかわる小説アンソロジーとしては、古川、阿部、川上、重松の四人の執筆者が重なっている『それでも三月は、また』と並ぶものである。 個々の作品については、また後で触れることがあるかもしれないが、さしあたり私は、書名にもなっている座談会「震災と「フィクション」との「距離」」を、色々な意味で興味深く読んだ。「フィクション」には「言葉・日常・物語…」とルビが振られている。出席者は阿部和重、川上未映子、斎藤環、辛島デイヴィッド、市川真人。かなり長い鼎談で、さまざまな事が語られているのだが、たとえば「百年後」ということに対して、川上氏はこんな風に問うている。「たかだか三百キロ離れた福島のことを想像できなかったわけでしょう? 百年後のことを想像できる人がいると思う?」。
市川 それこそが、作家の責任なんじゃないのかな。百年後について、想像力を駆使して書けるじゃないですか、作家たちは。 川上 でも、想像力を駆使して書いたことは、結局、解決にはならないんじゃないですか。フィクションが寄り添うものだったり耐え難い現実の緩衝剤だったり、そういう役割はできても、そういう存在をつくることと、百年後の未来を想定していま現実的にどう振る舞うかを考えることは、似ていて違うことだと思うんです。
この座談会は二〇一一年六月三日に収録されたものなので、その後、意見が多少変わったことだってあり得るが、右のやりとりを経て、市川氏は、文芸評論家であり編集者の「読む者」としての立場から、関東大震災後の坪内逍遥の発言に批判的に言及し、今こそ「癒し」としての矮小な「私」性への逃避を是とすることのない「大きな作品」を読みたいのだと述べ、川上氏は「大きな話には大きな話にしか達成できないものがあって、小さいものには小さいものの役割がある」と躱しつつ、では「書く者」である自分は、小説によって何を成せるのか、という心境を具体的に語ってゆく。 大小はともかく、ここで「書くこと」と「読むこと」の両極から交叉的に測られているものが「距離」である。それは「作家と現実との距離」であり、出来事と「フィクション」を隔てる「距離」である。では、この「距離」は、果たして測定可能なのだろうか? 頑張れば踏破出来るのだろうか? もしも、書くということが「距離」を作るのだとしたら?
7。ベルリン・レクチャー
佐々木敦です。日本の、東京の、渋谷という街から参りました。 僕は三年前にも、ここでレクチャーをしたことがあります。そのときは日本の九〇年代以降のポップ・ミュージックについて、実際に音楽を掛けながら色々とお話しました。僕は複数の芸術・文化について文章を書いているのですが、しかし今日は、このイベントでただひとりの日本人スピーカーとして、やはり昨年の三月十一日以降の出来事にかんして語らないわけにはいかないだろうと思います。これから皆さんに幾つかの映像をお見せします。��ずれもおそらく海外ではまだあまり知られていない、日本の新しいクリエイターによる作品です。まず最初は、ドキュメンタリー映画作家松江哲明による長篇映画『トーキョードリフター』の予告編です。
(『トーキョードリフター』予告編、YouTubeによる上映)
この映画は、どういう作品かと言いますと、前野健太というシンガーソングライターが、昨年の五月の或る日の夕方から翌日の早朝にかけて、東京のあちこちを移動しながら、ギターで弾き語りをする、その模様をひたすら記録した、ただそれだけの、たった一晩のドキュメンタリー映画です。 実はこの作品は、以前に同じ組み合わせで作られた映画の続編ともいうべきものです。二〇〇九年の一月一日に、松江監督は、東京の吉祥寺という街を、前野健太がギターで弾き語りをしながら歩き続ける様子を、八〇分間ワンカットで撮影し、一本の映画として発表しました。『ライブテープ』という作品です。『トーキョードリフター』は、それと同じように、やはり前野さんが歌うだけの映画です。 松江監督は、日本で「セルフ・ドキュメンタリー」と呼ばれている、従来のドキュメンタリー映画が題材としてきた社会的、あるいは政治的な主題というよりも、自分や自分の周囲のささやかな事象にフォーカスして映画を撮る、ここ数年の新しいドキュメンタリー作家たちの潮流の中心人物といわれている人です。予告編の中で松江さんが話していたのは、こんなことです。ドキュメンタリーを撮る者ならば、なぜ福島に行かないのか、行くべきではないのかと、たくさんの人から何度も言われてきた。だが、福島を撮ることだけが、ドキュメンタリー作家としての使命を果たすことなのだろうか。自分はむしろ、この暗い東京を、映画に記録しておきたいと思ったのだ。 ご存知の方もおられるかもしれませんが、福島第一原発の事故によって、電力供給が不足するとのことで、東京では、かなり大がかりな節電を行なわなければならない状況が生じました。その結果、たとえば渋谷という街の駅前、ハチ公前というのですが、そこはもともと交叉点に位置するビルに設置された複数の屋外大型ビジョンに絶えず映像が映し出されており、色とりどりのイルミネーションに彩られた、大変に明るく賑やかな場所なのですけれども、節電によってほとんどの照明が落とされて、非常に暗くなっていました。渋谷に限らず、東京の繁華街は、この頃はどこも暗かった。 そもそもヨーロッパに較べると、東京の夜は明る過ぎるので、多少明るさが減ってもいいような気もしますが、ともあれ以前に較べると、異常と呼んでもいいほどの暗さであったわけです。この映画は、そんな暗い東京の姿を捉えています。節電対策がほぼ解除されて、以前の明るさが戻ってきたのは、九月半ばのことでした。つまり半年間くらい、東京は暗かった。この映画が撮影された五月の段階では、まだ人々は暗さに慣れていなかったのではないかと思います。しかもこの日は雨も降っていて、全体として、うら寂しい感じを受けます。松江監督は、この暗い東京を撮っておきたいと考えたのです。 この映画は昨年の十二月に劇場公開されましたが、僕もそのときに見て、大変に驚きました。なぜなら、東京がこんなに暗かったということを、僕自身、いつのまにか忘れかかっていたからです。明かりが戻って来てから、まだ三ヶ月しか経っていないにもかかわらず、暗い東京の記憶は早くも薄れかかっていた。いや、もちろん覚えていたのですが、映像で見ることによって、あらためて強い衝撃を受けたのです。僕は渋谷に事務所を構えているので、日々の変化は目の当たりにしていた筈なのですが、それでも非常に驚いた。このことだけでも、この映画には存在意義があると思います。 予告編の最後で、松江監督はこんなことを言っています。「映画って、どんなにネガティヴな状況でも、もう撮った時点で、絶対ポジティヴになるんですよ」。この作品は、夜が明けて、雨が上がって、朝を迎えたところで終わります。そこには、明日は必ずやって来る、というメッセージが込められているようにも思えます。これを単なる楽観主義と言ってしまえば、それはそうかもしれません。実際、この作品は松江監督の以前からの支持者の間でも賛否両論があるようです。でも僕は、この試みは、とても貴重なものだと思います。 去年の三月十一日以後、日本のアーティスト、芸術家たちは、それぞれにショックを受けて、自分が属しているジャンルにおいて、さまざまな形で、このかつて体験したことのない事態に応接しようとしてきました。それは、僕がかかわっている分野だけでも、音楽、映画、美術、演劇、小説など多岐にわたっています。僕は、そうした沢山の表現を、必ずしも自分から進んで、ということではありませんが、結果として数多く体験、鑑賞してきて、色々なことを考えるようになりました。 当然、よいと思えるものもあれば、これはどうかなと思うものもあります。中には、あの日以前の自分の問題意識の欠落に対して、誰に向けてということなのかはわかりませんが、一種の言い訳をしているかのように思える表現もありました。僕はそれは欺瞞だと考えざるを得ない。その中で、僕が自分として好ましいと思えたものは、あの一連の出来事、地震、津波、原発事故というものを、必ずしも直截的に扱ったものではない、ことによると、一見する限り、ほとんど無関係にさえ見えるようなものが多かったのです。それは、どういうことなのでしょうか? ここで、次の映像を見ていただきます。
(『福島でゴドーを待ちながら』、YouTubeによる上映)
いまご覧になったのは、かもめマシーンという、まだとても若い劇団による公演『福島でゴドーを待ちながら』の抜粋です。チェーホフの『かもめ』と、この国の偉大な劇作家ハイナー・ミュラーの『ハムレットマシーン』を合体させたユニークなネーミングですが、まだ日本でも知名度が高いとは言えません。出演者一名、観客一名、たった五回の公演ですとか、オーストリアのノーベル賞作家エルフリーデ・イェリネクの『雲。家。』をビルの屋上でひとり芝居で上演するとか、実験的なアプローチを取ることが多いカンパニーです。 ビデオにもあったように、彼らは去年の八月に、サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』を、福島第一原発から20.5キロの路上で上演しました。現在も半径20キロ圏内は警戒区域となっており、法律で立ち入りを禁じられ、自宅のある住人たちも戻ることが出来ません。彼らはそのぎりぎりの場所で、演劇の公演を行なったのです。 彼らはのちに、この公演のドキュメント・ブックを制作しています。それによると『ゴドー』という選択には、二〇〇三年にスーザン・ソンタグが、サラエヴォで『ゴドー』を上演したということが、ひとつのインスパイアになっていたようです。また、それだけでなく、この戯曲の内容、ゴドーという男をずっと待っているのだが、いつまで経っても現れない、という設定が重要であったのだろうとも思います。 しかしドキュメント・ブックによれば、この公演はいわば思いつきのノリで実行されたようです。『ゴドー』は割と長い戯曲で、そのまま上演したら二時間を優に超えてしまうだろうと思いますが、かもめマシーンの主宰で演出家の萩原雄太は、登場人物の数を三人に減らして(もとは五人)、更に台詞を極端に削って、約三十分の作品に切り詰めました。上演場所は、とにかく福島まで一台の車に同乗して行って、それからロケハンをして決めたそうです。 公演といっても、このようなものですから、とにかくやる���と自体に意義があるのだと考え、観客ゼロであっても上演はするつもりで、ほとんど告知もしなかったらしいのですが、当日になると、なんと東京からたったひとりだけ観客がやってきたそうです。台詞を削ったと言いましたが、それどころか実際には、これはこの戯曲でもっとも有名なくだりであるとは思いますが、ウラジーミルとエストラゴンの「もう行こう」「ダメだよ」「なぜさ?」「ゴドーを待つんだ」「ああ、そうか」というやりとり、これが何度か繰り返される以外は、ほぼ完全に無言劇にしてしまったそうです。そうして一度きり上演された様子が、先ほどの映像です。三人の若い役者は、ただぼんやりと突っ立っているように見えますね。 20.5キロというのは、放射線量的には、おそらくはかなり高い地域です。そんな危険な場所まで東京からわざわざ行って、まだ二十代の役者たちが、ひとりしか観客の居ない、もしかしたら誰も観なかったかもしれない芝居を演じる、この明らかに無謀と言ってよいだろう試みは、ひとりよがりで自己満足的な行為かもしれません。いえ、それは確かにそうなのです。松江哲明は、敢て福島には行かずに、震災以後の問題を描くことを選んだ。反対に、かもめマシーンは、福島に行かなければならないと考えた。それは彼らが演劇という営みによって、この出来事に応答しようとするためには、どうしても必要なことだったのです。両者のアプローチは対照的ですが、しかし動機の部分、なぜ映画を、演劇をやるのか、という根っこのところに存在しているものは、実はかなり近いのではないかと思うのです。 先ほども述べたように、僕はあの日以来、数多くの「震災以後の表現」に接してきました。思うに、それらの表現に潜在している問いは、次のようなものだと思います。今、あの日以後である今、わたしたちに「何が出来るのか?」「何をすべきなのか?」「何がしたいのか?」。これらの問いへの答えは、それぞれに誠実であったり、真摯なものであったりします。だが、中には僕の目には欺瞞に映るものもあります。それは、これらの問いが、自らの内側から発されているというよりも、その者と外界との関係というか、社会とか公とか呼ばれているようなものから暗に強いられている、この出来事にダイレクトに応じる責任感の披瀝を求められている、そう思うがゆえに提示されていると思える場合です。 常々思うことですが、芸術というものは、本来的には、究極的には、あってもなくてもいいものです。そしてしかし芸術は、それでも存在し、作り出され、生まれてくるものであり、それによって、ある人の生そのものが救われたり、大きく変わったりすることだってある、そういうものだと思うのです。ただ単純に、震災以後の状況に対して、意味のあることをしたいと考えるのであれば、募金やボランティアをすればいいのです。その方が有意義だし実利的です。だが、それはそれとして行なったりもしつつ、それでも芸術の名において何かをするというのであれば、それは自分だってこの問題について真面目に考えているのだというアリバイ工作のようなものでなくてもいい筈です。あってもなくてもいいものであるからこそ、それでも芸術を為そうとするからには、「何が出来るのか?」「何をすべきなのか?」「何がしたいのか?」という問いよりも、むしろ「何をしないではいられないのか?」という問いの方が重要なのではないかと僕は思います。松江哲明は暗い東京を撮らずにはいられなかった。かもめマシーンは福島の路上でベケットを上演せずにはいられなかった。どちらも、誰に求められたのでも強いられたのでもなく、しかも結果として自分にとって益や誉れにはならないかもしれないような危うい試みであるのに、彼らはどうしてもそうせざるを得なかったのです。そのことに僕はむしろ本当の意味での誠実さを感じます。しなくてもいいのにしないではいられない、ということ。これこそが僕は信用に足るものだと思っています。 それでは三つ目、先の二つとはまた趣きの異なる作品を見ていただこうと思います。東京デスロックという劇団の『再/生(RE/BIRTH)』という作品です。東京デスロックは、多田淳之介が主宰、演出を務めるカンパニーです。『再/生』は、スラッシュのない『再生(REBIRTH)』として二〇〇六年に初演された作品の改訂版です。しかし、このふたつの作品は、結果として大きく違ったものになっています。ではまず、最初のヴァージョンの『再生』から御覧ください。
(DVDを再生しながら)照明が暗めの部屋に若者たちが集って、食べ物をつまんだり飲み物を呑んだりしながら、他愛のない話をしています。一見すると、ホームパーティ、いわゆる呑み会の光景です。やがて彼ら彼女らは音楽に乗ってダンスをし始めます。ドイツでも知っている方が多いと思いますが、日本を代表するテクノ・ユニット電気グルーヴのヒット曲「Shangri-La」が爆音で流され、若者たちは激しく踊り狂います。そして、こういう展開になります。 (早送りして)踊っていた若者たちが突然、一人ずつぶっ倒れていって、遂に全員が床に倒れ伏します。そう、実は、これは集団自殺の場面だったのです。これだけでもショッキングですが、この作品の凄いところはこの先です。 (更に早送りして)ふたたび音楽が流れ出すと、死んでいた筈の若者たちはむくりと起き出して、劇のいちばん最初から、まったく同じ芝居を繰り返します。『再生』というタイトルは、ここからきています。そしてやがてまた踊り出し、音楽が最高潮に達したところで、床に突っ伏して皆、死ぬ。そしてまた音楽が始まると共に最初のシーンに戻ります。この作品は、この一連のプロセスを、精確に三度、反復する、というものです。
『再生』は、舞台上での死は常に虚構の死でしかないという、演劇という表現が持っている絶対的な条件を逆手に取った作品だと、まずは言えます。また、こちらの方がより重要だと思いますが、繰り返しも三度目になると、毎回、全力で踊っていた役者たちはさすがに疲れてきて、死んでいる演技をしなくてはならないのに息があがってしまい、虚構の死がより強調されてしまう。ここには、演劇という一種の反復表現に潜むアポリアが垣間見えています。僕は以前、或る本で、この作品について分析したことがあります(『即興の解体/懐胎』)。多田淳之介は、このように、演劇を根本から凝視め直し、批判しようとするユニークな作風で知られています。では、昨年の七月に初演され、今年の三月に早くも再演された『再/生』では、どのように変わったのでしょうか?
(DVDを再生しながら)最初に女優がひとり舞台に出てきて、観客にこう語りかけます。「今は、幸せについて考えています。そもそもなんでそんなこと考えて、考え始めたのかというと、ずっと前から考えていたような気もするんですが、考え始めたきっかけといえば、あるとき、といってもいつだったかもうわからないんですが、過去のあるときのわたしは、幸せではなかった、と思ったんですね。過去のあるときのわたしは、幸せじゃなかった、と思って、じゃあそれじゃあ今、わたしは幸せなのか、という逆説?、がふっと湧いて来たのが、そもそものきっかけといえば、そうです」。この台詞はリアルタイムで録音されていて、すぐに再生されます。女優はアルカイックな微笑みを浮かべながら、今しがた発したばかりの自分の声を黙って聞いている。そしてそれもまた録音されていて、再生される。そうしているうちに、他の役者たちが現れて、音楽が流れ出し、彼ら彼女らは踊り始めます。しかしそのダンスは『再生』とは違って、きわめてアブストラクトというか、なんとも奇妙な踊りなのです。こんな風に。 (早送りして)いま流れているのは、日本で非常に人気のあるバンド、サザンオールスターズの「TSUNAMI」という曲です。これは昔の曲ですが、昨年の三月十一日以降、日本ではよくあることなのですが、一時的にテレビやラジオ等でのオンエアが自主規制されました。見ていてわかると思いますが、役者たちは奇妙なダンスを踊りつつ、唐突に床に倒れ、また起き上がるという仕草を繰り返しています。全員バラバラに踊っていますが、そこだけ共通している。そして何曲かを経て、Perfumeの「GLITTER」が始まります。Perfumeは中田ヤスタカという天才肌のプロデューサーが手掛けている三人組の人気女性ユニットで、三年前のレクチャーでも紹介しました。アップテンポのエレクトロ・ポップが大音量で流れる中、ダンスもヒートアップしていきます。 (早送りして)曲のラストで、役者たちは全員、床に倒れて動かなくなります。しかし暫くすると、曲が最初から再生され出して、彼ら彼女らは起き出して、また奇妙なダンスを踊り始める。やがて音楽は盛り上がって、全員が倒れる。これが何度も繰り返されます。つまり『再/生』は『再生』とはほとんど別の作品と言ってもいいと思いますが、ここだけは同じなのです。音楽も違うしダンスも全然変わっていますが、この反復という方法だけは、前作を踏襲している。僕は『再/生』を実際に劇場で観ましたが、一曲丸ごとフルに踊って、死んで、すぐにまた踊り出すという反復は、『再生』以上にハードなもので、何度目かになると、役者たちは息も絶え絶えになっていて、ほんとうにこの場で死んでしまうのではないかと心配になるほどでした。しかし、また曲が流れ出すと、彼ら彼女らは必ずまた起き上がり、奇妙なダンスを始めるのです。上演が終わったとき、役者たちは汗だくでした。僕を含む観客は、彼ら彼女らに惜しみない拍手を送りました。実際、僕は、涙が出るほど感動していたのです。しかし、この作品のどこが、それほど感動的だったのでしょうか? 僕は『再生』から『再/生』へのアップデートは、二〇一一年三月十一日に起こった幾つかの出来事と、その後に生じ、今なお続いているさまざまな出来事と、無関係ではないと思います。倒れて死んで生き返る、その機械的でやみくもな反復という要素において、二作は繋がっている。二〇〇六年のヴァージョンでは、それは集団自殺を示唆したものであり、また演劇へのラディカルな批判を含むものだった。 しかし去年の夏に上演された『再/生』になると、描かれていることは更に抽象化され、ほとんど演劇というよりもパフォーマンスのようなものになっている。でも、僕はこれはやはり演劇だと思うのです。単なるナンセンスで巫山戯た作品のように思われる方も居るかもしれませんが、ここには間違いなく、あの日以後のわれわれの生と、そしてわれわれ以外の人たちの数多の死に対する、演劇という芸術からの応答が存在していると僕は思います。倒れて死んで生き返る、倒れて死んで生き返る、というひたすらな、ひたむきな反復が、役者たちの酷使される身体によって演じられることによって、多田淳之介という人が、いったい何を表現しようとしたのか、そのことをよくよく考えてみなくてはならない。 東京デスロックの『再/生』は、僕が出会ってきた「震災以後の表現」の中でも、際立って印象的な作品でした。もっとも感動した作品と言ってもいいと思います。確かに、ここには明確な問題提起や、わかりやすい主張はありません。しかし、真顔でストレートに語ってみせている者が真にシリアスであるとは限らないのと同様に、一見すると迂遠だったり無関係とも思えるような表現の内に、切実なメッセージが隠されていることもあると思うのです。 以上、駆け足で、三つの作品を見てきました。僕の考えは、おそらく日本人の中でも、また芸術や文化に携わる者の中でも、かなりマイナーなものかもしれません。しかし、僕は敢て、このドイツという特殊な場所で、こういう話をしたいと思いました。ご清聴を感謝します。ありがとうございました。
8。ベルリン・レクチャー補記
前節は、五月五日にベルリンの劇場HEBBEL AM UFER(HAU)で催されたフェスティバル「APOCALYPSE NOW (AND THEN) ーTHE END OF THE WORLD IN POP CULTURE」で行なった講演の採録である。いささか大仰なタイトルだが、フェス全体のコンセプトやプログラムの内容にかんして、私はほとんど知らないままだった。正直に言っておくなら、聴衆はけっして多くはなかった。一時間足らずのごく短いレクチャーであったし、やや舌足らずなところもあると思うので、以下に幾つかの事柄を補足的に記しておきたい。 私のレクチャーはこの日の二つ目のプログラムで、その前に話したのはドイツ人アーティスト、ニナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニだった。二人は長年、チームで活動を続けており、札幌市立大学准教授として日本に長期滞在したこともある。私は以前、東京・初台のインターコミュニケーション・センター(ICC)等、幾つかの機会に、二人の展示を観たことがあった。ICCでの《ニーチェが洗礼を受けた教会》というインスタレーションは、かなりミスティックな作風だったが、二人は一方で、きわめてアクチュアルな問題意識に沿った映像作品も手掛けている。長崎県の端島=軍艦島を題材とする《サヨナラ・ハシマ》や、成田空港拡張反対運動を描いた《成田フィールド・トリップ》など、日本で制作された作品も多い��� ���二人は昨年の九月から年末にかけて京都に滞在し、原発事故にかんする一連の取材を行なった。レクチャーは、そのインタビュー映像の一部や、福島から一時避難してきた若い主婦が京都の街頭でマイクを握って脱原発を訴える様子、渋谷の駅前に貼られた東北地方への観光キャンペーン・ポスターの映像(私が自分のレクチャーの始めにわざわざ「渋谷から来た」と言ったのは、先に渋谷の光景が映されていたからである)、あるいは黒澤明監督のオムニバス映画『夢』に一篇で、富士山の噴火と原発の爆発が描かれるカタストロフィックな「赤冨士」というエピソードなどを上映しながら行なわれた。二人の明確にアクティヴィスト的なスタンスからすると、私が用意した三つの作品は、ややもすればなまくらなものだと感じられたかもしれない。 二つのレクチャーの後、これまたごく短い時間ではあったが、ニナとマロアン、男性の評論家と女性のモデレータ(いずれも名前は忘れた)、私の五名でパネル・ディスカッションも行なわれた。こうした場のパネルにありがちなことだが、やはり議論は特に深まることなく散漫なまま終わってしまった、という印象だったが、ニナとマロアのどちらかが話していたことで(パネルは録音しなかったので記憶を頼りに書いているのだ)、日本の若いアーティストたちは、ダイレクトにこの問題を扱うことを避けているのではないか、という感想があった。それはそうかもしれない。だが、そうとばかりも言えないし、私が紹介した『トーキョードリフター』『福島でゴドーを待ちながら』『再/生』は、いずれもけっして避けているのではない。むしろ、かくのごときあり方こそが、事態に真正面から全力で向き合おうとした結果なのだ。だが、日本の現状に深い知識と理解を持ち、初対面の私に対しても終始すこぶる感じの良かったニナとマロアンにさえ、私が言いたかったことが、どの程度ちゃんと伝わったのかはわからない。何しろ日本人相手にだって、しばしば、あまりわかられてはいないのではないかとも思っているからだ。 それは、詰まるところ、こういうことだ。どうせ言いたいことは変わらないので、以前に書いた文章の一部を、そのまま引用する。「あれだけの出来事があったのだから、ニッポンのありとあらゆる表現は、否応無しに、意識するとしないとにかかわらず、大なり小なり、何らかの影響を受けることになるのは間違いない。一見まるで無関係無関心に思えるものであったとしても、けっして「あの日以後」であることから逃れられてはいない。むしろ、あからさまにそのことを問題にしているものよりも、もしかしたら影響は深刻かもしれないのだ。「あの日以後」を自分なりに受け止めて、内面化し、これから自分がやっていくことに繋げてゆこうとすることと、そのことを他者に対して公的に宣言することのあいだには、やはり大きな違いがある。どうして、わざわざ問いを口にしなければならないのか。それは問いに答えようとする以前に、すでに一種のパフォーマンスなのではないか。そう思うと僕はそこに微かな欺瞞の芽を感じ取ってしまう。しかもそれは、いまや或る絶対的な正しさによって保証されているパフォーマンスであり、真っ向から批判することが、どうにも許されないような欺瞞なのだ」(「「音楽に何ができるか」と問う必要などまったくない」、季刊アルテス1号)。 ことによると、いや、間違いなく私は、この「欺瞞」ということに、おそらく必要以上にこだわっているのだろう。それは認める。だが、私が批評を生業とする者の端くれとして、自分の役目というと大袈裟なようだが、実際そう思っているのは、「以後」であることに、はっきりと自覚的な表現よりも、ほとんどそのようには見えなかったり、真面目にやっているとは思えなかったり、表現者自身でさえ、その意味をよくわかっていなかったりするような試みや営みの中に、他ならぬ「以後」の徴を、その刻印を、その傷を読み取っていくことこそが、いまや必要なのではないか、ということなのだ。なぜなら、いずれにしろ、すべては「以後」なのだし、そうであるしかないのだから。避けるも避けないも、逃げるも逃げないも、望むと望まざるとにかかわらず、われわれはあまねく「以後」を生きているのである。省みるまでもなく、これが端的な事実なのだ。だとすれば、殊更にそのように標榜することはなくても、しかし実は「以後」を全身で受け止めてしまっている、そう思える表現を、繊細かつ大胆に、時には無理にでも見出してゆくことの方を、私はやりたい。それは「以後」の無意識を探ることにもなるだろう。 毎年、秋から冬にかけて、池袋近辺を中心に催されている舞台芸術のフェスティバル「フェスティバル/トーキョー」の昨年度「F/T11」のドキュメント・ブックが送られてきた(私も寄稿している)。F/Tでは会期中に何度かシンポジウムが行なわれるのだが、その内の一つ、宮台真司、黒瀬陽平、鴻英良(司会)とのパネルにおいて、宮沢章夫が、次のような発言をしているのを読んだ。
われわれが目にしている表層に演劇があるわけではない。その向こう側に描くべき対象があるから、目の前に黙っている人がいても、僕たちはそこに何か別の言語が出現していると考えます。ですから僕は「語らなくてはいけないことのためにこの方法がある」とは考えません。僕は、そこに立つ人の内面より、その表層的なシルエットがどんな劇言語を発するか、それによって空間がどう変化するかを知りたいし、それが、僕が舞台上で、何かを表現することなんだと思います。 (「日本・現代・アート〜「終わりなき日常」の断絶から」)
これは「演劇」にかんしてだけのことではないだろう。別の芸術、別のジャンルをここに嵌め込んだとしても、宮沢氏の言っていることは正しい。むろん「語らなくてはいけないことのためにこの方法がある」がすべてよくないということではない。ただ、それはあやまちも生むこともあれば利用されることもあるということは知っておかなくてはならない。そういうことだ。 或る芸術、或る表現が、私たちの前に示されるとき、それはいずれにしろ「表層」として現れる。だがしかし「表層」が只の表層に留まり切ることは、人間に想像力と思考力がある限り、あり得ない(だからこそ、かつて「表層批評」なるものは力を持ったのだった)。ひとは必ずそこから意味を引き出す。それがどんな意味であれ。しかし、ならば「表層」の向こう側に鎮座する「意味」から、その表現、その芸術が生まれてきたのかというと、そうとは限らない。まず、どこからかどうしてか、ふと、或る「表層」が出現し、しかし如何なる理由でそれが出現したのか、それが何なのか、誰にも理解できず、それがどのような「意味」を持っているのか、次第にわかってくるのは、誰か他者へと送り届けられてから、ということだってある。こんなことはわざわざ言うまでもない大前提である筈だが、いつのまにか周りを見渡すと、創造や表現をコミュニケーション・ツールとしてのみ考え、そうであるからには誤解抜きに十全に伝わらなくてはならないとする、一種の神経症めいた感覚が蔓延しているようにも思えるのだ。「表層」に、ありうべき「意味」すなわち「語らなくてはいけないこと」を何もかも染み込ませずにはいられない作り手の心性には、生真面目さとともに、弱さと疾しさが仄見えている。それは強さと責任感を装うこともある。 「震災以後の無意識」は、あらゆるところにある。それはわれわれ全員を覆っている。ありとあらゆる芸術表現は、まるでそうは見えなかったとしても、その影響下にある。たとえ「以前」と少しも変わっていなかったとしても、そこには変わらなさという論じられるべき問題があるのだ。そう考えるならば、「以後」にかかわる批評の対象は、視界と同じだけのひろがりを持ってゆくことになるだろう。 ベルリンのレクチャーで、私が「何をしないではいられないのか?」が重要だと述べてみたのは、あってもなくてもいいのだが、しかし不断に生み出されている芸術と呼ばれる営みは、つまりは別にしてもしなくてもいいものなのだが、だからこそ、やるからには何らかの強い動機づけがあって欲しい、パブリックな視点からしたら、取るに足らないような個人的な動機であったとしても、それが切実なものとして迫ってくれば、そこには必然性が生じる。そのような必然性こそが試されているのだ、ということを言いたかったのである。それはささやかなものであるかもしれないが、しかし当人にとっては、けっして譲ることのできないものでもある。自分でもよくわからないが、どうしてもそうしないではいられない、ということ。必ずしも結果を見越して為されるわけではないそれは、いわば実験である。そんな「以後」の「実験」の数々を、私は見届けたい。 ところで、このように論を繋いでくると、お前はそうやって「以後」というタームをやたらと述べ立てることで、何かを語ったつもりになっているようだが、そのような「以後」の強調こそが一種のフレームアップであり、お前が忌み嫌う「欺瞞」を招き寄せることにもなっているのではないか、という物言いがつけられるかもしれない。さんざん「以後」的な振る舞いをした者からそう言われるのだとしたら噴飯ものだが、しかし「以後」という問題設定について、その有効性をはかるところから、より踏み込んだ精査が必要であることは確かだろう。「以後」というからには「以前」があるのである。いや、むしろ「以後」によって「以前」は形成される。次回、私はこのことを、何篇かの小説を取り上げて論じてみたいと思う。
9。「以後」との遭遇
今、あなたが目にしている「文學界」には「二〇一二年八月号」と記されている筈である。だが、この号が出るのは八月にはまだ一ヶ月近くある七月七日であり、私がこれを書いているのは六月の二十日過ぎのことだ。前に町田康の「四月号と言いながらその実、三月に出て、そこに載る文章を一月に書いている」という文を引用したが、どういうわけかは省くとして、雑誌にはこのような慣習があり、したがって「一月号」とあるならば、それはおおよそ前年の十一月下旬に入稿されていることになる。 ということは、単行本の奥付に「初出「群像」2011年1月号〜2012年1月号(2011年8月号を除く)」とある多和田葉子の『雲をつかむ話』は、実際には二〇一〇年十一月から二〇一一年十一月にかけて入稿されており、「文學界」の「二〇一〇年一月号〜二〇一一年十二月号」に連載された保坂和志の『カフカ式練習帳』は、二〇〇九年十一月から二〇一一年十月にかけて書き継がれていたわけである。もちろん連載小説だからといって、毎月の入稿時に合わせて書かれたとは限らない。何回分か纏めて執筆されていたり、実は連載開始前に全て完成していたということだってありえる。けれども、執筆期間のある日以前には絶対に書かれ得なかっただろう言葉がそこに読まれる場合、ひとつづきの小説の内に、時間の切れ目のようなものが挿し込まれているさまを、われわれ読者は目撃することになる。 『雲をつかむ話』は、近年の多和田葉子の長編小説の例に漏れず、先の展開の予測がまったく不可能な、奇怪にして優美なロマネスクであるが、全十二章の最後から二番目のチャプターの終わりがけ、やや唐突に、次のような記述が現れる。
地球の一部ではあっても、ある国の一部としてすぐに受け入れられるとは限らない。仙台からわざわざバンコクに飛んで、用もないのにしばらく滞在してからロンドンに飛んだのも、疑われないようにと用心を重ねた結果だった。わたしは欧州連合のパスポートを持っているわけだから、すっとパスポート審査をパスできるかと思えば、向こうはわたしの顔をじっと見てパスポートの出生地の欄に「東京」と書かれているのを発見して眉をひそめ、「アジアですね」と注意深く言う。これが第一の罠だ。出生地が東京ですね、と言うのでもなく、今バンコクから来たんですね、と言うのでもない。アジアという場所があるわけではないのに、わざと曖昧な言葉を使って泳がせて尻尾を出させて捕まえようとしているのだ。
語り手の「わたし」は、飛行機から降りて入国手続きをしようとしている。この章は、『雲をつかむ話』という極めて謎めかした小説が、一種の種明かしへと急速に収斂していくパートであり(尤も種が明かされるからといって謎が解けるとは限らない)、さながら探偵小説のような、或いは訝しい夢のような暗合に満ちている。しかし、このパスポートをめぐる挿話には、それらとはまた違った、妙に生々しい不穏さが纏わり付いている。「パスポート審査官の目が成田のスタンプにとまったのが分かった。眉が寄せられ、わたしを見る目が豹変した」。ああ、そういうことか。やはりそうなのか。
案の定、制服の女性が二人すぐにあらわれた。身体が触れないように左右からわたしを連行する二人の緊張した表情には、哀れみのようなものも混ざっていた。Rと書かれたドアの前まで来ると、英語で書かれた説明書を持たされ、部屋には一人で入るように言われた。中には機械があって、どのようにその機械を使えばいいのかは説明書に書いてある、と言うのだ。読まなくても分かる。身体に放射性物質がついていないか調べる機械なのだろう。一人その部屋に入れば、外から鍵をかけられてしまうかもしれない。しかも調べた数値は外からしか読めないようになっているかもしれない。そしてもしも数値が高かった場合は監禁されて、その後いったいどうなるのか。
『雲をつかむ話』の「わたし」は、長年ドイツに住む日本人の小説家で、日本語とドイツ語の両方で作品を発表している。数年前にハンブルグからベルリンに転居した。最近は学会や講演でアメリカに行くことも多い。つまりは、限りなく「多和田葉子」に近い人物なのだが、しかしこの小説が、いわゆる「私小説」とは似て非なる、いや、似ても似つかぬものであることは、読めばわかる。だが、虚実というより虚に虚を織り重ねてゆくかのごとき幻惑的な語り/騙りのなかで、この箇所だけが、陳腐な表現を許していただけるなら、無闇とリアルなのだ。無論、作者である「多和田葉子」が現実に同様の体験をしたのでは、などと言いたいわけではない。そうであろうがなかろうが、読者には関係のないことである。しかし、このシーンが「二〇一一年三月十一日」以前に書かれていなかったことだけは間違いない。そしてこの端的な事実は、「人は一生のうち何度くらい犯人と出逢うのだろう」という魅力的な一文によって開始され、「わたし」が思い出すままに時間と空間を自在に経巡ってゆくこの小説の、フィクションとしての臨界点を露わにしているように思えるのだ。 ところで、これと酷似した場面を、多和田はアンソロジー『それでも三月は、また』に書き下ろした短篇「不死の島」でも書いている。
パスポートを受け取ろうとして差し出した手が一瞬とまった。若い金髪の旅券調べの顔がひきつり、唇がかすかに震えている。声を出すのは、わたしの方が早かった。「これは確かに日本のパスポートですけれどね、わたしはもう三十年前からドイツに住んでいて、今アメリカ旅行から帰ってきたとこです。あれ以来、日本へは行っていませんよ。」そこまで言って言葉を切り、それから先、考えたことは口にはしなかった。「まさか旅券に放射性物質がついているわけないでしょう。ケガレ扱いしないでください。」受け取ってもらえないパスポートを一度手元に引き戻して、今度は永住権のシールを貼ってあるページを開いて改めて差し出すと、相手はふるえる指先でそれを受け取った。
言葉遣いは更にリアルで、ますます実際の体験談のような気がしてしまうが、しかし実はこの小説の舞台は二〇二三年なのだ。掌編というべき「不死の島」が描く「日本の未来」は、おそろしくグロテスクなものである。二〇一三年に天皇主義者による脱原発クーデターが起こり、それがきっかけで勃発した政変の果てに日本政府自体が民営化され、すべてが経済合理性と隠蔽体質に覆われる。放射能汚染に対する疑惑と忌避もあって、日本国は世界から孤立してゆく。二〇一七年に「太平洋大地震」が起こったが、すでに日本への渡航は途絶えていたため、それでどうなったのかはわからない。二〇二三年、日本に密航してきたポルトガル人の旅行記が出版される。それによると、二〇一一年に福島で被爆したとき百歳を越えていた老人たちは「死ぬ能力を放射性物質によって奪われて」、全員がまだ生きている。その代わり、当時子供だった者たちは重篤な障害を発症した。「若いという形容詞に若さがあった時代は終わり、若いと言えば、立てない、歩けない、眼が見えない、ものが食べられない、しゃべれない、という意味になってしまった」。老人が若者を介護する社会が訪れる。そんな中、ふたたび巨大地震が起こったのだった。「わたし」は二〇二三年の今になって思う。「福島で事故があった年にすべての原子力発電所のスイッチを切るべきだったのだ。すぐまた大きな地震が来ると分かっていたのに、どうしてぐずぐずしていたのだろう」。 「不死の島」は「震災以後」を主題とする数多の小説の中でも、際立った問題作である。だが「日本国のパスポート」をめぐる挿話にかんしては、連載が「震災以前」に始まっていた『雲をつかむ話』の最終回直前に語られたものの方に、むしろ不意撃ちのようなインパクトがあった。それは、小説家が書くつもりではなかった、小説が書き始められたときには書かれる筈ではなかったことが、現にここに書かれてある、という静かな衝撃だった。 保坂和志の『カフカ式練習帳』は、フランツ・カフカが遺した膨大なノート、そこに記された創作メモや随想、身辺雑記、日常の観察、小説の一部、等々のような種々雑多な断片を、連載小説という枠組みの中で意識的に書いてみるという、特異な方法意識に支えられた「長編小説」である。「思いついたらいつでも書けるように家の中のあちこちにノートを置いておいてその場で書き出す」。そうして数冊のノートに徒然に書かれた断片群が、毎月編集者によって回収されてランダムに並べられることで、連載の各回が構成されたのだという。したがって長短さまざまな断片と断片のあいだには基本的に連続性や一貫性は存在していない。それでも一冊となった際に、れっきとした「長編小説」としての佇まいを持っているのは、保坂和志の「小説家」としての技量と才覚、そしておそらくそれ以上に「小説」という営みに隠された神秘というべきだろうが、しかし同時に、このことは、ずっと昔から長い時間をかけて書き貯められていたのではなく、あくまでも連載期間の責務(?)として日々書かれていったものであるということも深く関係していると思われる。つまり『カフカ式練習帳』の断片群は、すべてが、ある具体的な時間のフレームの内に収まっているのだ。 『カフカ式練習帳』に「地震」という単語がはじめて登場するのは、連載も三分の二を過ぎようとしたあたりである。 二月五日午前十時五十六分に起きた地震は、震源が千葉県南島沖で、マグニチュード5・2。震源の深さは六十四キロ。東京二十三区は震度3だった。ちょうどそのとき私は外にいた。震度3とはとても思えない強い揺れを瞬間感じ、揺れと同時に、私の右のスガスガから左のスガスガにピアノ線がピンッと張られたような、右から左に弾丸よりずっと小さな粒子が貫通したような、感覚があった。痛みというよりも電気にちかいか、右のスガスガから左のスガスガは方角としてはほぼ南から北だった。私はやや上体を屈めて、外の猫たちに餌を出していた。
この断片を含む回は「文學界」の「二〇一一年五月号」に掲載されている。したがって、それは二〇一一年の三月下旬に入稿された筈だ。おそらくは「三月十一日」以後のことである。だが、ここに書かれているのは「二月五日」にあった千葉県沖を震源とする震度3の地震のことである。「三月十一日」の「地震」に言及した断片は、この回にはない。 『カフカ式練習帳』が、日記やエッセイのようにも読める断片が多くを占めているにもかかわらず、れっきとした「長篇小説」であるということは、たとえばこうした点にも現れている。ここには書くこと、書かれること(読まれること)の選択と操作がある。しかしそれでも、これ以降の連載��は、「三月十一日以後」を、さまざまな形で刻印された言葉が紛れ込んでゆく。たとえば、こんな断片がある。
津波が迫ってきたが、もう逃げられないので娘と二人で二階に駆け上がるしかなかった。駆け上がっている途中で、津波が足許から膝までどんどん上がってきて、二階に上がったときには津波が背より高くなり、二人とも完全に津波にのみ込まれた。いったんは観念したが体を沈めると足が床についた。床を思いきり蹴ると顔が天井と水の隙間に出た。窓が開いているのが見えた。そこから出られると思い、娘と窓からでて屋根に這い上がった。這い上がると今度は引き波で屋根が沖に流された。二人で屋根に載ったまま沖を漂ううちにあたりは夜になった。娘が携帯を出すと、通話はできないが機械は壊れていなかった。携帯のライトは何も明かりのない海の上ではすごく明るい。娘と二人でそれぞれの携帯を手に持って必死に振っていると、津波を逃れて沖に行っていた漁船がもどってきたところに発見された。
保坂氏に娘はいない筈である。勿論いたとしても変わりはないが。私は、この断片が、ノートに手書きの文字で書かれてある光景を想像する。保坂和志が、こんな断片を、ノートに書きつけている姿を想像する。 「大地震の日にもうジジは生きていなかった」と始まる比較的長めの断片は、「三月十一日以後」を刻印された断片群の中でも、最も重要なものだ。ジジとは猫の名前である。言うまでもないことだが、保坂作品において、猫たちとは、生と死、そして時間という不可思議なるものの象徴でもある。
あの大地震のときにジジは生きていないで良かった。スマトラの大地震と津波にあれだけ反応したジジの反応が、今回どれだけ激しかったことか。しかし、生きていないで良かったということが本当にありうるのか。いくつもの苦痛を抱えて生きていることと死ぬことのどっちがより望ましくないことなのか。 生きていないで良かったと思うのはジジがもう生きていないからだ。
誤解を畏れずに述べよう。前言を覆すようであるが、これは「小説」ではない。精確に言うと、この断片のみを読むのなら、それは「小説」と呼ばれる必要は、おそらくない。そして、そんなことは重々わかった上で、保坂氏は、これを書いている。そう思える。
震度3程度で「余震におびえる」というのは言葉の綾にすぎず、気持ちの連続が中断したり、やっていたことが中断したり、気持ちが平静になりきれなかったりしていた日々、私と妻で何度も口にし合った「ジジが生きてなくて良かった」という言葉は、誰のために何のために言われていたのか。被災者の中に血縁も友人もいないのに一日一度は涙ぐむような、今もこれからも楽観的になることが難しいときに、せめてもの良かったことが、ジジがもう地震や津波と呼応して具合が悪くならずにすんだことだと、悪いことばかりじゃなく、いいことだってあるじゃないかと二人で確認し合っていたのか。 それとも、 「今はジジが生きていなくて良かった。でもジジが生きていたときはもっとずっと良かった」 と、ジジが生きていた日々は巨大地震が起きる以前の世界だったと一緒にしているのか。
ここに書かれているのは、最早どうしたって「以前」には戻れない、という酷薄な真理である。巨大地震が起きる以前、ジジが生きていた日々には、もうけっして戻れない。猫の死と大災禍は、到底受け入れ難いが受け入れるしかない事実という意味では同じことなのである。つまり保坂氏は、ほんとうは単にこう言いたいのだ。ジジが死んでいなければよかったのに。巨大地震が起きていなければよかったのに。両方とも起こっていなければよかったのに!……この反実仮想の無意味さをやり過ごすためには、彼は「今はジジが生きていなくて良かった」と言うくらいしか出来ないのだ。 『カフカ式練習帳』には、「不死の島」の「わたし」と同じ怒りを抱え持つ、こんな直截な断片さえある。
『日本人はなぜ戦争を止められなかったのか』という番組名を見て、 『日本人はなぜ原発を止められなかったのか』という番組が、三十年後、五十年後に作られる恥を感じた。
10。「徹底的に推敲しろ」
こんな時に思い出すのはプーラのことだ。 言葉づかいは少し間違っているかもしれない。こんな時に思い出せるのは、と訂正したほうが真っ当なのかもしれない。しかし、真っ当とは何だろう? あらゆるイメージがあらゆる人たちに〝その日〟の以前と以後とで異なる感情を与えている。だとしたら、この瞬間、この今に忠実に回顧するしかない。ふり返るしかないのだ。
古川日出男の「プーラが戻る」の冒頭部分である。この短篇小説は、二〇一一年三月二十五日に「早稲田文学」のウェブサイトに掲載され、のちに単行本『震災とフィクションの“距離”』に収録された。中学校のプールの底に棲み、冬になって水が抜かれるとともにどこへともなく消えてしまった怪獣プーラの想い出を語るこの愛すべき小品は、おそらく古川が「三月十一日以後」に書いた最初の小説である。周知のように、その後、古川は中編小説『馬たちよ、それでも光は無垢で』を「新潮」二〇一一年七月号に発表する。すなわち入稿されたのは五月下旬ということになるが、では書き出された日時はというと、他ならぬ小説の中で告げられている。
この文章を起筆したのは二〇一一年の四月十一日だ。十枚ほど書き進めて、すると、福島県の浜通り地方で余震があった。最大震度は6弱。 巨きな余震があるたびに、私は推敲する。 余震が、私に何かを許さない。「徹底的に推敲しろ」との声がする。
『馬たちよ、それでも光は無垢で』は、『雲をつかむ��』の「わたし」とは異なり、作者の「古川日出男」自身であることを至ってストレートに明示してみせる「私」が、まだほとんど福島第一原発の事故の状況がわかっていなかった四月のある日(だが、それが「四月十一日」以前の何日であったのかは記されていない)、新潮社の編集者数名とともに出身地である福島へと向かう、一種のドキュメント小説の体裁を採っている。だが、興味深いことは、出来事の時系列が、今まさに書かれつつある小説の時間の内にバラバラにされて溶かし込まれ、前後の脈絡を脱臼されているばかりか、余震のたびにどこからか聞こえてくる「徹底的に推敲しろ」という何ものかの命令に従って、書かれた筈の言葉が度々廃棄され、幾度となく書き直されて、しかもそれを逐一、小説の中で告白してゆくという、独特なスタイルが選ばれていることである。「推敲」とは、確定されかかった過去=小説を絶えず未了へと追いやっていく、原理的には終わりのない作業のことである。結果として、この小説にはきわめて重層的な時間が畳み込まれており、それはほとんど混乱の一歩手前に到っているようにさえ見える。ところが、そのような錯綜した語りによって、現実の記録であった筈のこの小説に、あのメガノベル『聖家族』の虚構の登場人物である「狗塚牛一郎」が忽然と立ち現れるという離れ業が成されるのだ。つまり「牛一郎」は「推敲」の渦中から召喚されてくるのである。それは古川にとっては『聖家族』の舞台となったフィクショナルな世界を、どうしようもなくリアルな「以後の世界」と、強引にも接続させる、というミッションを意味してもいただろう。 やはり『震災とフィクションの“距離”』に収録されている重松清との対談「牛のように、馬のように」において、古川は「以後」に自分を襲った恐慌について、驚くほど率直に語っている。
古川 (…)震災前から書いてる作品が三つあったけれど、ひとつはもう駄目になりました。もう書けない、だから最終回にする。しかも最後に、ぜんぜん関係ないのに福島の話をして終わろうとしている。もう一個は、書けなくなると思わなかった作品だけれど、それすら突っかかってしまった。でも、本になるのは二年後になるかもしれない長いものだから、震災から二年経った人々が読みたいものに変えられるんじゃないか、そこに必死に縋っています。もう一作は現代を舞台にしていて、そのぶんもしかしたら逆にこのままいけるかもしれないけれど…… 重松 震災も取り込んじゃって。 古川 そう、消化していけるかもしれない。でも、いまもう通じない作品があり、二年後に出しても通じない部分が見えたとき、「お前がやっていたことは、地震が来たら崩れる程度のことだったんだよ」と認めざるを得なかった。単純に、エゴのために書いていたものがあるとわかったんです。「自分はすごいんだ」と人に言わせたかった、そういうものを書いていたんじゃないか。そのことにガッカリしました。 重松 そこまで言うのは、自分に厳しすぎる感じもしますけれど……あれらの作品はぜんぶエゴですか? 古川 わからないです、ほんとうのところは。ただ、そのことについてはいまも考えます。周囲では、だんだん震災や被災の空気がなくなって、復旧に向かっていると思うんです。でも、自分のなかでは進行形のまま、小説家として小説に対して内部被爆している。これを認めていくしかないと思っています。
ここで語られている三つの作品とは、駄目になったひとつ目が『黒いアジアたち』、二つ目が『ロックンロール十四部作』、そして「このままいけるかもしれない」という三つ目が『ドッグマザー』のことだと思われる。三部から成る長篇小説『ドッグマザー』は、第一部「冬」が二〇一〇年七月号、第二部「疾風怒濤」が二〇一一年二月号、第三部「二度目の夏に至る」が二〇一二年二月号、いずれも「新潮」に発表された。近年、驚異的な速度で次々と新作を世に問うてきた古川日出男としては、かなりじっくりとしたペースと言えるが、当初の予定では、第三部は二〇一一年の夏には発表されることになっていたらしい。だがそれは右の発言にある理由により遅延することになった。「冬」と「疾風怒濤」は、明確に「以前」に書かれたものである。だが「二度目の夏に至る」は「以後」であるしかない。物語の時間は連続している。この小説は、更に以前に書かれた『ゴッドスター』で登場した少年が、同志のような偽の母親の庇護を離れて、東京の埋め立て地から京都へと移動し(同じく京都を舞台とする『MUSIC』ともシンクロする)、前世を売る謎の「教団」と出会うことで、奇怪にして神聖な成長を遂げてゆく、というものである。畝るよう��息の長い文体といい、液体的とも言うべき濃密な描写といい、それ「以前」の作風とは大きく変化しており(それは『ゴッドスター』と比較してみるだけでもわかる)、デビュー以来、絶えざるヴァージョンアップを重ねてきた古川日出男が、これまで以上のアップデートに挑んだ、紛うかたなき野心作である。古川はたびたび村上春樹への畏敬の念を語っているが、ここで彼がターゲットにしているのは「日本・現代・文学」を造り上げたもうひとりの人物、中上健次だと思われる。古川は中上が直視しようとした「天皇」を自分なりの仕方で生け捕ろうとしている。『ドッグマザー』は、その第一歩である。 「二度目の夏に至る」は、二〇一一年四月に始まり、六月で終えられる(ただし「母親」からの手紙という形で、あれから「二週間とか三週間」の時期のことも語られる)。「三月十一日以後」に起こった、起こりつつある出来事は、小説の世界に必然的に取り込まれている。だが、この「必然」は、当然のことながら、これに先立つ「冬」と「疾風怒濤」の時点では、欠片さえ存在していなかった。したがって、たとえば次の文章は、書かれていなかった筈なのに、書かれたのだ。
平等な慈悲とは何か。 これは日輪子の考えか。日輪子が僕の分身とするなら、これは僕の考えか。僕の? 因果の法則をすっかり受け入れてしまって、その夥しすぎる死が、前世の報いなのだと仮定してみる。これらを天罰なのだと仮定してみる。いま現在の被災死亡者は一万四千人か。行方不明者はやはり一万と数千人か。詳細なデータ、人数は日輪子ならば日々把握しているのかもしれないが僕はそうではない。変動も激しい。けれども、それでもわかる。ここには無辜のものが混じっている、この一万、二万という数は罪のなさをも偶然的(アクシデンタル)に内包するからこそ夥多だと感じられる、直観される、数には数の生理があるのだ、ならば。そうであるならば、その無辜の人々はいったい何に(「何に」ダッシュ)生まれ変わる? 前世はある、と受容したのならば来世はどうだ? この応報は、どうなる?
『馬たちよ、それでも光は無垢で』において「私」の耳に何度となく鳴り響いていた「徹底的に推敲しろ」という「声=命令」は、すでに「以後」となった世界で発されていたものである。だが『ドッグマザー』で、古川日出男は、いわばあらかじめの「推敲」を求められることになったのだ。われわれが読む、読むことの出来る「二度目の夏に至る」は、もしも世界が「以前」のままであったなら、確実に違う姿をしていた筈である。これは『聖家族』の「牛一郎」が、福島へと向かう車内にいつのまにか坐っているという離れ業の、いわば裏返しの所業である。古川は「以前」に胚胎されていた世界を「以後」へと「推敲」することによって、『ドッグマザー』という物語を、こう言ってよければ、なんとか書き終えることが出来たのだ。それはほとんど、生きるか死ぬかの綱渡りのようなものだったのではないか。連載も回数を重ねており、すでに大作となっていた『黒いアジアたち』が、にもかかわらず放棄されることになったのは、このあらかじめの「推敲」が、どうにも不可能だと判断されたからだろう。 「推敲」ということで思い出されるのは、言うまでもなく、川上弘美の『神様2011』である。あの誠実にして真摯な、そして切実きわまる試みが、同時に、ある途方もない痛ましさを放っているのは、あの書き直しによって、川上にとってデビュー作であった『神様』が、決定的に「以前」のものになってしまったから、そして、そうなることがわかっていながら、川上自身が、そうすることを選んだからに他ならない。小説が、小説家が、想像力が、書くことが、「以後」に向き合おうとするとは、なんと過酷なことなのだろうか。
11。「以前」の「以後」
阿部和重は、新潮社のPR誌「波」の二〇一〇年十二月号から二〇一二年二月号まで、『幼少の帝国ーー成熟を拒否する日本人』という評論を連載していた。この論考は、戦後日本社会の特徴を「こどもっぽさ」すなわち「大人になること(=成熟)への拒否」に見出すという口実=フィクションを戦略的に引き受けてみせることにより、それ自体すでにクリシェと化している「日本=成熟拒否」論の耐久力をはかり直そうという、如何にも阿部和重らしい捻れまくったコンセプトを持っており、しかも最初からそのように宣言した上で開始されたものである。小型化や軽量化によって世界を席巻した日本の「ものづくり」を評価するのはまだわかるとしても、やがて「成熟拒否」を「アンチエイジング」と無理矢理読み替えて、あの高須クリニックの院長へのインタビューを行なうなど、論旨は(明らかに意図的に)暴走してゆく。ところが、連載開始前には予想もしなかった事態が起こったことで、この評論は当初の計画から大きく逸れていった。そのあたりのことについて、阿部は単行本の「あとがき」で、次のように書いている。
東日本大震災が発生したのは、連載なかばの頃だった。わたしたちの企画にとっても、ここが大きなターニングポイントになった。 テーマ自体が借り物だったこともあり、それまではどこか他人事のように「現代日本」に目を向けていたところがあった。戦後史というフィクションを、一定の距離を起きながら振りかえるつもりで、例によってわたしたちはひとつの偽史的なストーリーを組立てようとしていた。 ところが3・11を経たことにより、この国で今なにが起きているのかをだれもが否応なく直視せざるを得ない状況が生まれてしまった。先端的な文化や産業の現状を通じて「現代日本」の粗描を試みていたわたしたちも、例外ではなかった。連載の途上にあったわたしたちにとり、選択肢はふたつしかなかった。二〇一一年三月一一日金曜日になにごともなかったかのように振る舞うか、あるいはそうではないかのどちらかだ。わたしたちはただちに後者を選んだ。
私の知る限り、阿部和重という小説家は、ひとつの作品を書き出す前に、あらかじめ緻密な設計図を引いておき、実際の執筆作業では、ひたすらそれをリアライズすることに務めるという、完璧主義者というべきタイプである。それは『幼少の帝国』でも基本的には同じだったろう。だがしかし、不測の出来事により、設計図は破棄されることはないまでも書き換えられることになった。「二〇一一年三月一一日金曜日になにごともなかったかのように振る舞うか、あるいはそうではないか」という二つの選択肢は、多和田葉子が、保坂和志が、古川日出男が直面したものと同じである。そして阿部もまた、三人と同じ選択をしたのだった。 高橋源一郎は、選考委員を務めた第48回文藝賞の選評の中で、受賞作となった今村友紀の『クリスタル・ヴァリーに降りそそぐ灰』について、こんなことを述べている。
『クリスタル・ヴァリーに降りそそぐ灰』を、ぼくは、3月11日以降に書かれた小説であろうと思って読んだ。それは、ぼくの勘違いだったのだが、そのことがわかった後も、やはり、「以後」の小説である、という感想に揺るぎはなかった。この小説は、「以後」を描いている。主人公の「私」は、突然、ある大きな事件(「戦争」?)に巻き込まれる。そして、その事件について、この小説の最後まで知ることはないのである。それにもかかわらず、「私」は、前へ進む。たとえば「私」はいくつものパラレルワールドと関わる。そこでは、既成のどんな論理や倫理も役に立たない。だから、「私」は全く新しい論理や倫理を作り出さねばならない。「以後」の小説の課題は、そこにしかないのである。
実をいえば、高橋氏と同じ誤解を、私は北野勇作の『きつねのつき』という小説にかんしてしていた。「以後」に書かれたものだとばかり思っていたら、二〇一〇年には脱稿されていたのである。しかしそれでも私は、高橋氏が『クリスタル・ヴァリーに降りそそぐ灰』に感じたのと同様に、『きつねのつき』を、すこぶる優れた「「以後」の小説」だと思っている。時間的に「以後」に書かれたものだけが「以後」であるわけではない。「以前」から「以後」を語っていた言葉がある。つまり「以前」にも「以後」はあったのだ。 「以前」の「以後」。これには、もうひとつの意味がある。「二〇一一年三月十一日」より「以前」を描いた、しかし歴然と「以後」の小説という��のがあるのだ。次回、私は二人の小説家の最新作を取り上げる。阿部和重の『クエーサーと13番目の柱』と柴崎友香の『わたしがいなかった街で』。二作とも、舞台は二〇一〇年である。
12。「廃棄物最終処分作戦」
『クエーサーと13番目の柱』は、奇妙な小説である。それはつまり、いかにも阿部和重らしい小説ということだ。この物語で描かれるのは、タレントへの監視行為、いわゆるパパラッチである。だがそれは芸能マスコミによるものではない。主人公と呼んでいいだろう、元写真週刊誌記者のタカツキリクオと、彼が属する様々な出自の人間から成るパパラッチ・チームは、カキオカサトシという資産家のアイドルオタクに雇われて、カキオカが「Q」というコードネームで呼ぶアイドルを二十四時間モニタリングしている。「Q」とは、KINGを自認するカキオカ=KAKIOKA=「K」にとっての永遠に結ばれることのない精神的伴侶=執着の対象としてのQUEENの頭文字であると同時に、「地球から観測できるぎりぎりの、物凄く遠いところにあって、凄まじいエネルギーを放ちながら宇宙一明るく輝いている天体」である「準恒星状天体(Quasi-steller-object)」=クエーサーの頭文字でもある。カキオカは、けっして成就されない、それゆえにこそ絶対的な強度を持ち得る「天体観測者の愛」を「Q」に注ぐための道具として、タカツキたちを使っている。だが(というべきか、だから、というべきかわからないが)そのパパラッチは、盗聴、盗撮、張り込み、侵入行為等、スパイさながらのチームプレイと種々の最新テクノロジーを駆使した、ほとんど荒唐無稽とさえ思える大仰さであり、映画シナリオ或いはノベライゼーションを想起させる、いつにも増してドライで無機質でぶっきらぼうな文体で綴られてゆくタカツキたちの過剰なミッション・インポシブルぶりが、この作品の前半の読みどころであると���ってよい。 また、それと同時に、この小説は、かねてよりタカラヅカ、ジャニーズ、モーニング娘。(特にゴマキ)等への偏愛を表明してきた阿部和重が著した、一種の「アイドル論」でもある。いや、精確には「アイドルオタク論」だろうか。カキオカのクイーン=クエーサーへの倒錯した愛情は、にもかかわらず彼が「Q」をあっけなく別のアイドルに変更してしまえるということによって、その倒錯ぶりをより際立たせることになる。当然、パパラッチ・チームの監視対象も更新されるのだが、その新しい「Q」は、人間、ボーカロイド、アンドロイドの三人組新人アイドル・ユニット、エクストラ・ディメンションズ(ED)の、唯一の生身の人間のメンバーであるミカである。ところがミカは、EDの中でもっとも「アンチ(特定のアイドルに敵対し、ネット上などで「叩き」をするファンのこと)」が多いメンバーなのだ。このあたりの設定の実に捻くれた考え抜かれ方は、まさしくいかにも阿部和重である。二〇一二年のニッポンは、誰もが数年前には予想だにしなかったような形で、史上何度目かの「アイドル黄金(戦国)時代」を迎えているわけだが、阿部はこの作品において、彼が長年推してきたモー娘。以後に登場したPerfumeと初音ミク(後者は実際には音声合成ソフトウェア=VOCALOIDの商品名であるが、私は彼女も「アイドル」の一人であると考えている。何故って実体の無い、ユーザー各自が勝手に脳内でイメージを醸成できるキャラクターとしてしか存在していない声=ソフトウェアこそ、究極の執着の対象、あの「天体観測者の愛」が差し向けられるアイドルではないだろうか?。ちなみにほぼ同時期に登場したPerfumeとミクは明らかに相補的な存在である)、そして現在のマーケットにおける圧倒的な覇者であり、ことによると日本の「アイドル史」の最後の輝き(或いはとどめの一撃)になってしまうかもしれぬAKB48までを射程に収めつつ、それらの固有名詞を出すことなく、その「アイドル」としての人気の構造を解き明かそうとしている。阿部の「アイドルオタク論」は極めて批評的であり、それゆえ辛辣かつアイロニカルなものだが、既に別の場所でも述べておいたように(*)、だからといって単に高みの見物を決め込んだ意地の悪いお遊びというわけではない。そこには阿部和重の「フィクション」という得体の知れないものに対する独特の明察が潜んでいるのだ。 だが、われわれの論議にとって重要だと思われるのは、一見すると本筋とはあまり関係のない、オープニング・シーンともいうべき次の場面である。「二〇〇九年一二月一七日木曜日、午後一一時三八分」、タカツキリクオと相棒のサワザキコウタは、路駐したSUVの車内に居る。サワザキが「今まで見つかったなかでいちばん地球に似てるスーパーアースが発見された」というネットで拾った話題を振る。張り込み中の無駄話といったところだ。二人はスーパーアースの生き物の有無について意見を戦わす。地球上の常識に照らすとそれは無理っぽいのだが、別の天体にはまったく異なる生命の可能性だってあるかもしれない。ひょっとすると「ウルトラマンの怪獣みたいにバカデカいの」だっているかもしれない。
「しかしいくらスーパーアースつっても、ウルトラ怪獣はいないんじゃないのか。だいいち、ウルトラ怪獣がいるのならウルトラマンもいなくちゃ釣り合いがとれない。宇宙の真実はそこまで器デカくない気がするけどな」 「そうすかね」 「おそらくな」 「でも、気がするってのも、結局は常識的判断にすぎない。それだって真実を見落とすきっかけになっちゃいますよ」 「まあ、それもそうだな」 「でもやっぱり、ウルトラマンはいないだろうな」 「いやいるさ」 「あんなのいるわけないじゃないですか。所詮は絵空事ですよ」 眼鏡の男は依然外を見ながら笑っている。 「しかし人間の科学の常識が、間に合わせの真理じゃなくなる日ってくるのかな」 「どうだろうな。そもそも神の視点に立てない以上、人間には真理を真理と判定する術がないからな」 「どういうことですか?」 「模範解答集がなければ、テストの答え合わせはできないだろ。人間は真理の模範解答をしらないんだから、答え合わせも不可能だ」 「なるほど。答えが出せても自己採点はできないから、試験にパスしたかどうかは永遠に分からないわけか。しかしそいつは切ない話だな。布きれ一枚しか身につけてなかった時代から、人間は必死こいて真理の追究に明け暮れてきたってのに……あれ今、地震あったのか。伊豆で震度五弱て、かなりデカいな」 丸刈りの男は、いつの間にか画像検索をやめていて、ニュースサイトの閲覧に戻っている。地震情報を眺めながら、中身が半分になったペットボトルを彼は上下に振っている。 「そんなに揺れたのか。こっちはいくつだ?」 スマートフォンからいったん目をそらし、ペットボトルのなかで弾けまくる炭酸のあぶくを凝視しながら、丸刈りの男が答える。 「いや、東京はちっとも揺れてませんね。せいぜいイチとか、そんなもんです」
『クエーサーと13番目の柱』は、「二〇〇九年一二月一七日木曜日、午後一一時三八分」に始まり、「二〇一〇年八月三一日火曜日、午前零時二三分」に終わる(阿部和重の小説の例に漏れず、この作品においても日付は重要な、だが秘密めかした意味を担わされている)。この小説は「群像」の二〇一二年二月号から四月号まで三回にわたり分載された。したがって引用部分を含む第一回は二〇一一年十二月中旬に入稿された筈だが(年末進行を考慮するともっと早かったかもしれない)、実はこの作品は、そこから一年半以上遡った時期に、すでに執筆開始されていたか、少なくとも構想されていたことがわかっている。というのも、私は『ピストルズ』の刊行の際、阿部和重と公開インタビューを行なったのだが、その対話の最後で、次回作の予告として、この作品のことが語られていたのだ。
阿部 (前略)ここだけの話でチラッと言いますと、講談社の百周年の記念の作品なので、講談社の社員が主人公なんです。「フライデー」の元記者が主人公になって、色々とダメな感じの出来事が起こります! 佐々木 (爆笑) 阿部 という企画になっておりますんで、そういう問題に関心のある方は是非。僕の二〇〇〇年代のフィールドワークが全てそこに投入される予定になっておりますので。 (『小説家の饒舌』)
このインタビューが行なわれたのは二〇一〇の四月一六日である。理由はともあれ、結果として発表が遅れた『クエーサーと13番目の柱』には「講談社百周年記念」という銘記は見当たらず、タカツキリクオの前職も「フライデー」とは書かれていない。だが、これが同じ作品のことであるのは間違いないだろう。となると、次のような推測が成り立つ。阿部和重は、のちに『クエーサーと13番目の柱』と題されることになる小説を、二〇一〇四月一六日の時点で「ちょうどまさに今書き始めてるところ」だった。だが同作が入稿されたのは、二〇一一年末のことだった。もちろん脱稿がいつだったのかはわからない。ことによると、先の発言から程なく二〇一〇年中には書き終わっていて、何らかの理由で一年ものあいだ寝かせられていたということだってあり得ないことではない。だが、もしも先に引用した場面を阿部が「以前」に書いていたのだとしても、二人の登場人物の雑談の最中に取ってつけたように起こる地震が、二〇一一年三月一一日の「以後」を生きる読者に、なんらか特別な意味合いとともに受け取られるだろうことを、彼が意識していなかった筈はない。そう考えるなら、サワザキコウタがふとした思いつきのようにタカツキリクオに言う「しかし人間の科学の常識が、間に合わせの真理じゃなくなる日ってくるのかな」という台詞も、明らかに「以後」の色彩を帯びた問いかけとして聞こえてくるのではないか。 同様のことが考えられる箇所が、『クエーサーと13番目の柱』には少なくとももう一つある。物語の後半、タカツキたちは、インターネット上の電子掲示板でカキオカサトシとその下請け一味を敵視するオタたちと物理的な闘争を繰り広げるのだが、オタたちは自分たちの妨害工作と攻撃をこう呼ぶのだ。「廃棄物最終処分作戦」。ご丁寧にもこの九文字はゴチック体で強調されている。この語が当然のごとく喚起する連想は述べるまでもないだろう。私はこの九文字だけは、二〇一一年三月一一日以後に書かれたことを確信している。もちろん、このネーミングは小説全体の中では、さして重要な意味を持ってはいない。けれども、物語の時間が二〇一〇年の夏に設定されていることを考え合わせるなら、これは「以後」に書かれた「以前」を舞台とする小説に「以後」をあからさまに投げ入れる、という作業であったことになるのではないか。しかも、驚くほど単純明快な手口によって!
*「DAYDREAM BELIEVER」ー「群像」八月号
13。「引き寄せ」の法則(の捏造)について
『クエーサーと13番目の柱』の奇妙さを担う重大な要素として、物語全体を貫く「引き寄せの法則(ロー・オブ・アトラクション)」というものがある。パパラッチ・チームの最年長だったミドリカワユウゾウは、外為取引=FXで儲けたからと仕事を抜ける。株のことなど無知だったというミドリカワをFXの勝者に導いたものこそ「引き寄せの法則」だった。ミドリカワはタカツキにも勧めてくるのだが、そういうのってやたらと情報量が膨大で初心者は尻込みしてしまうとタカツキが言うと、ミドリカワはこう答える。
「ところがそういうのはまったく問題ないんだわ。なぜかっていうとさ、引き寄せの法則ってことでは、根本の部分はみんな一緒だからね。つまりさ、たとえ話でもなんでもなく、本当に『思考は現実化する』ってことなのよこれは。願えばなんだってかなうっていうのが、この法則の大原則。要はね、その大原則が絵空事じゃない当たり前の物事なんだって、自分の頭んなかにしっかりと根づかせること。それさえできれば、効果はおのずと出てきちゃうわけ。そうすればさ、好きなだけ儲けられるしなんでも手に入れられるし病気だって治せちゃうのよ。なにしろ思ったことがどれも実際に起こるんだもん。不思議だよねえ。でもこれは、神秘現象なんかじゃなくてさ、いわゆる自然の摂理なんだよタカツキちゃん」
思考は現実化する。この俄には信じ難い(し最終的にも信じられない?)法則、大原則、摂理が『クエーサーと13番目の柱』の世界を統べている。ミドリカワと交代でチームに加入し、EDに詳しいことから重宝されるが、次第にその悪魔的(?)な正体を露にするニナイケントも、偶然にも「引き寄せの法則」を口にする。彼はこう説明する。
「(前略)要するに、宇宙にはデータベースみたいなものがあって、そこにはこの世界で生じる、あらゆる出来事や物事の可能性がデータとして記録されていて、時々刻々と更新されているわけです。そしてその可能性のデータというのは、だれでも常に取りだして使うことができる。というよりも、だれもかれもが例外なく、常にそれを使って人生を組み立てている。なぜなら願望を抱���ということは、その後に起こり得る出来事に直結する、なんらかの可能性を引き寄せるということだからです。人は皆、こうなりたいとかああなりたいと念じることで可能性のデータを宇宙からたぐり寄せ、現実の形にする。そのときに、正しく願いさえすれば、その願望にいちばん近い可能性のデータがこの世界に引き寄せられて、実現するという運びです」
このようにニナイの話は一挙にオカルトじみてくるのだが、彼の理屈は、素朴に言い直せば「強く信じれば夢はかなう」ということであって、とりたてて特別な考え方ではない。というよりも、大方の自己啓発本の類いは、ほぼこんなものである。ニナイは嬉々として続ける。
「でも願い方が間違ってると、本来の願望とはズレた形で現実化してしまう。たとえば念願の成就にわずかでも疑いや否定的な印象を持っていたり、思念の中身にどっちつかずなところがあったりすると、宇宙はそれを忠実にトレースしてしまう。宇宙のデータベースには、文字通りあらゆる出来事や物事のデータが収納されているわけです。だから細かい点までぴったり一致してる可能性のデータが見事にそろってて、願う者の思いを鏡のようにそのまま反映してしまう。したがって、たとえ毎日願ってても、いやそれだからこそ、あなたの借金はいっこうになくならない。なぜならあなたの思念には、そんなバカなことあるわけねえという否定の先入観が絶えず混ざり込んでいるから。そのために、本当に望んでいる出来事の可能性をいつまで経っても引き寄せられない。そもそもそれは、あなた自身が、そのことを自分が本当に望んでいるのだと思い込んでいるだけのことであって、結局はちゃんとした願望にすらなっていないんですよ。どうです? 心当たりありませんか?」
しかしこうなると、誰もが思うことだろうが、何だってありにも出来れば、なしにも出来る、何事であれ、起こすことも起こさないことも可能だ、そういうことにならないか。しかしニナイは、引き寄せ的には、出来事を起こさないことは起こすことよりもずっと困難なのだ、と言う。
「事情に暗い人はそんなふうに考えたがるものです。しかしそれは現実的な方法とは言えない。実際にはまだ起こってもいないことを想定して、それが起こらない可能性を引き寄せるというのは、当てはまるシチュエーションが無限にありすぎてイメージをまとめにくいんです。宇宙のデータベースは、構文ではなくイメージによる抽出データの指定を好みます。そのためこちらが思い描くイメージがぼんやりとしたものになっていると、可能性を引き寄せる力はそれだけ弱まってしまう。だったらより具体的に、起こるとわかっていることを想定して、そのなかのひとつの可能性を引き寄せるほうが間違いがないんです」
こうしてニナイは或る陰謀(?)に着手し、タカツキはそれに巻き込まれる。そしてそれは物語のクライマックスを惹き起こすことになるのだが、未読の方に配慮して、これ以上は述べない。ともあれ、いささか唖然とさせられるのは、繰り返すが、この突拍子もない理屈が、この小説を駆動する内的な論理でもあるということなのだ。こうして前代未聞のパパラッチ小説であり、卓抜な「アイドルオタク(論)小説」でもあった『クエーサーと13番目の柱』は、きわめて奇妙な「可能世界(論)小説」としての顔を晒け出すことになる。それは「思考は現実化する」「信じればかなう」という狂った論理が本当に現実化する異常な世界の物語である。 阿部和重は、すでに何度か名前を挙げたアンソロジー『それでも三月は、また』と「早稲田文学ウェブサイト(→『震災とフィクションの“距離”』)」の両方に、同じ一本の短篇小説を提供している。「RIDE ON TIME」と題されたその短篇は、或る金曜日、十年ぶりの巨大な波=グランド・スウェルがやってくるのを待ち望むサーファーの「ぼく」を語り手としている。「一〇年前のライディングでは、ぼくらは総じて撃沈されはしたものの、皆どうにか陸に戻ってこられた」。さあ、だが今回は、果たしてどうだろうか?
そろそろぼくも、あの大いなるうねりの頂点に立つべく舟を漕ぎ出してみようかと思う。 たとえまたもやライディングに失敗したとしても、そのありさまが、三〇〇人もの人たちの目に留まれば、ひとつの意味がどこかに浮かびあがりはするだろう。 ひとつの意味がどこかに浮かびあがれば、それも突破口をこじ開ける、力の一部に生まれ変わるにちがいない。 そうすれば、いつもとはまったく異なる金曜日を、いつも通りの金曜日に変えることができるかもしれない。
この後一行で、小説は終わる。二〇一一年三月一一日が金曜日だったことを覚えていない者は居まい。だからビッグ・ウェンズデイならぬビッグ・フライデイを描いたこの掌編は、大津波でサーフィンをするという、ある紛れもない不謹慎さを身に纏ってみせているのだが、そんなことより読み取るべきなのは、この「ぼく」のやみくもな想い=願いが『クエーサーと13番目の柱』の「引き寄せの法則」と、まったく同じものであるということだ。「いつもとはまったく異なる金曜日を、いつも通りの金曜日に変えること」。それが「できるかもしれない」という無根拠な希望は、ニナイケントが言っていた「正しく願いさえすれば、その願望にいちばん近い可能性のデータがこの世界に引き寄せられて、実現する」というのと、そっくりなのだ。それは保坂和志が『カフカ式練習帳』の断片に記していた「今はジジが生きていなくて良かった。でもジジが生きていたときはもっとずっと良かった」という言葉、そしてその裏に隠された「ジジが死んでいなければよかったのに。巨大地震が起きていなければよかったのに。両方とも起こっていなければよかったのに!」という反実仮想を思い出させる。「引き寄せの法則」に貫かれた『クエーサーと13番目の柱』は、一編のファンタジー、フェアリー・テールである。何故ならば、信じれば叶う、可能性を引き寄せる、などというのは幼稚な絵空事であることを、私たちはよく知っているからだ。だが、そんな狂った論理が通用する狂った世界の提示は、望んだわけでもない酷薄な現実の世界で生きるしかないわれわれに、次こそはうまくやってみせる、巨大な波にだって乗ってみせる、必ず生き延びてみせる、という想い、そんな「ひとつの意味」を浮かび上がらせるのだ。 『クエーサーと13番目の柱』が「震災以前」の物語であることにこそ「以後の小説」としての意味が込められている。つまり、奇跡はすでに一度は起こった、ということなのだ。「無数に分岐して展開してゆく可能性が折り重なる、ホログラムのような像」から「とうに決めてあったひとつの可能性」を引き寄せ/選び取ることが、ひとたびは出来たのだから、それはもう一度、いや、何度だって出来るかもしれない。そういうことなのだ。『クエーサーと13番目の柱』は、希望と奇跡と再生の物語である。ほとんどそのようには見えなくても、これはすぐれて切実な「以後の小説」なのである。
14。「距離」のパラドックス
柴崎友香の『わたしがいなかった街で』は、「新潮」の二〇一二年四月号に掲載された。物語の舞台は二〇一〇年の初めから夏にかけて、である(偶然にも『クエーサーと13番目の柱』と、ほぼ重なっている)。三十六歳のOLである「わたし」は、離婚してひとりで住むためのアパートに引っ越してきた。この小説は、「わたし」の日々を淡々と記録していきながら、中途から別の登場人物、三人称で綴られる「葛井夏」の存在が迫り上がってきて、遂には「わたし」と入れ替わる、という特異な構造を持っている。ほとんど異様なものと言っていいこの仕掛けにかんして謎解きめいたことを書くのはさしあたり慎んでおく。柴崎友香の小説のヒロインはいつもそうだが、この「わたし」も普通のようで普通ではない。それは小説の中で彼女が耽溺する二つの習慣(?)に如実に現れている。まずひとつ、「わたし」はiPhoneで六十五年前に書かれた『海野十三敗戦日記』を読んでいる。それは彼女が越してきたのが東京の世田谷区若林であり、戦時中、海野十三がそこに住んでいた、という事実がきっかけと記されているのだが、それにしても些か奇異ではある。彼女はiPhoneで海野日記の空襲の記述を読みながら近所を歩いたりもする。 もうひとつは「わたし」のささやかな趣味であるドキュメンタリー映像鑑賞である。やや長くなるが、最初に突然それが登場する場面を引用する。それはこの小説の叙述の風景を、それまでとは一変させるインパクトを有している。
三十二インチの液晶画面を、装甲車のタイヤが横切った。タイヤが踏んで行ったアスファルトには、真っ赤な血だまりができている。銃声が何度も響き渡った。サラエヴォの中心市街の大通りに伏せていた民衆たちが、建物のほうへと逃げ惑う。撃ち合いが始まり、警察の装甲車が出動し、人々は手を叩き拳を突き上げて口々になにかを叫んでいた。 ユーゴスラヴィアの内戦の過程を追った全六回のドキュメンタリーの四回目だった。各勢力の指導者たちの証言が差し挟まれてから、国境近くの山間の小さな町が映し出された。既に戦車に包囲され、並木の新緑が芽吹く川沿いの道から、砲撃を受けていた。春の花が咲く茂みで、普段着の民兵たちは、ベルト状につながれた尖った弾丸を機関銃に装填して応戦の準備をしている。検問では、怯えた顔の人々が兵士たちになんとか身分を証明しようとしていた。村では、車から降りた迷彩服の男たちが、それぞれ片手に自動小銃を持って、これから殺す人を探し出すため、脅し文句を叫びながら、白い家の敷地に入っていった。ベージュのトレンチコートを着た白髪の男が、迷彩服たちに連れられて出てきた。迷彩服たちは、片手の自動小銃を体の一部になったように一瞬も離すことはなく、もう片方の手で男のトレンチコートを引っ張り、小突いて、連れ出した。トレンチコートの白髪の男は、不安げに、ちらっとカメラを見た。映像はそこで途切れ、次の映像に切り替わると、別の男たちが死体を片付けていた。中年の女の死体を、一人が右肩、一人が左肩、一人が足を持ち、道路脇に停められたトラックへ向かって、庭の小道を下っていった。肉付きのよい中年の女の死体は、地面に伏せた姿勢のまま、完全に固まっていた。男たちが服を引っ張って持ち上げても、死後硬直した両方の肘は外に突き出されたまま宙に浮いていた。手の上に顔を伏せ、腰から不自然な方向に曲がった、殺される直前のその形のまま空間に浮かび、運ばれ、トラックの荷台に放り投げられた。荷台にはすでに、同じような形で固まった男の死体があった。また別の場所が映る。草地の上に、さっき運ばれた女とよく似た体型の老女が、さっきの女とよく似た体勢で倒れていた。セーターの背中の真ん中には、銃弾の跡が丸く開いていた。しかし血は見えない。横向きになった顔と、通常の関節とは逆方向にまがった腕の先のては、灰色に変わっていた。誰かの持ち物だった鞄やノートが、道に散らばっていた。ところどころ、インタビューを受ける国連職員の証言が差し挟まれる。わたしのジープは曲がり角にあった血だまりで横滑りしました。死体を積んだトラックを何台も何台も見ました。
「なにかきっかけがあって急に見続けるようになったわけではない。しかし、見る時間は確実に少しずつ増えている。減ることはなく、増えていく一方だった。一人になってから。この数ヶ月のあいだ」。このあと「わたし」は幾度もこの種のDVDを再生するだろう。そこには、ここから遠く離れた場所での悲惨と災厄が映っている。あらゆる映画=映像は必然的/不可避的/運命的に「過去」の記録であるが、ドキュメンタリーはその中でも一際、歴史=時間に穿たれた出来事の目撃者としての使命を帯びている。「わたし」が凝視めるのは「過去」の内でも、とりわけその取り返しのつかなさが悲劇的である出来事の記録である。それが何故なのかは彼女自身にもわからない。ただ、ひとつのことは言える。ここには時空間の断絶と連続のアンヴィヴァレンスが働いている。つまり、いま目の前で展開しているサラエヴォの光景は、わたしが居合わせたわけでも赴いたことがあるわけでもない、こことは完全に断絶した土地で、こうしてDVDの映像に刻まれている以上は、すでに遥かに過ぎ去った、けっして巻き戻すことの出来ない或る時において生じていた出来事である。だがそれは同時に、疑いもなく、わたしが今いるここ、ここにある今と、繋がっている。それは別の世界の出来事ではないのだから。それは虚構ではないのだから。 時間と空間の断絶と連続、その両義性、言い換えればそれは「距離」のパラドックスである。「わたし」は、今ここ、と、或る時或る場所で、の間に横たわる、踏破不能な、だがけっして計測不可能というわけではない「距離」に囚われている。このような感覚は、彼女が読み続ける『海野十三敗戦日記』との「距離」にも現われている。「わたし」は終戦の年の海野の記述を追いながら、その時彼が���際に居た同じ土地を歩く。「日記」という形態の特殊なところは、後から手を加えたりしていない限り、日々の記録は、当然ながらその時々のものでしかないので、それ以後に起こるだろう出来事にかんしては、多少は予想出来ることもあったりはするとしても、それがそのまま現実化するとは限らないし、突発的に生じる事件だって無論ある、だから結局、日記はいわば不連続な連続性の中で書き継がれるしかなく、それを後から読む者にとっては、時としてそれはパラドキシカルに思えもする(何故なら読者はその先のことを既に知っている場合があるから)ということだ。日記はフィクションではないのだから、それを書いている誰かは、未来を知っているわけはない。だからこのとき、日記の書き手よりも読み手の方が「作者」と呼ばれる存在に近い、と言ってもいいのかもしれない。 『わたしがいなかった街で』は、次の一文で始まる。「一九四五年の六月まで祖父が広島のあの橋のたもとにあったホテルでコックをしていたことをわたしが知ったときには、祖父はもう死んでいた」。だからもうその頃のことを祖父に尋ねることは出来ない。「わたし」は祖父が料理をするところさえ見たことがなかったのだ。一九四五年八月六日午前八時一五分、周知のように、広島は米軍による原爆投下を受け、十四万人ものひとびとが瞬時に死亡した。もしもあと二ヶ月、祖父が広島で働いていたら、彼は原爆で命を落としていたかもしれない。だが、そうはならなかった。そのようなことは、けっして起こらなかった。 一九四五年八月十四日の昼、京橋駅周辺は空襲を受けた。爆弾は現在の環状線の線路を貫通し、その下を交差して走る片町線のホームに避難していた大勢の乗客を直撃した。死者の数は六百人以上とも言われているが、その後の混乱もあってほとんどが行方不明のままだ。 八月十四日? 明日、戦争が終わるのに。 三月の大阪大空襲のことは知っていたが、八月のそんな時期にまで大規模な空襲があったとは知らなかった。 八月十四日、明日戦争が終わることを、その日の人たちは知らなかった。 八月十四日に京橋で空襲があったことと、祖父が八月六日に広島にいたかもしれなかったことは、たぶんわたしの中で一対になっている。そこにいたのにその日はいなかった祖父と、たまたまその日にそこにいた人たち。あとから考えれば、生死を、その後の人生を左右した決定的な偶然は、実際に爆弾が投下されたそのときまでは、生活の一部として特別重大なこととは意識されないできごとだったと思う。 祖父がいた場所で起こったこと、何度も自分自身が乗り降りした駅で起こったこと。そこにいて死んだ人、いなくて助かった人。そうしてたまたま、私は生きている。存在しなかったかもしれないわたしが、京橋駅のホームに立っている。 八月十四日に空襲があったのは、大阪の京橋だけではなかった。山口県岩国と光、そして十四日夜から十五日未明にかけて、群馬県伊勢崎と太田、埼玉県熊谷、神奈川県小田原、東京都青梅、秋田県土崎……。 戦争が終わることはすでに決まっていて、しかし多くの人がまだそのことを知らなかった時間に。 そう思うのは、戦争が終わったことをわたしが知っているから。終わったあとで、その前の日のことを考えるから。
ここには、複数の、きわめて複雑な「距離」のパラドックスが、畳み込まれるようにして記されている。そして次第にこのパラドックス群は、否応なしに「わたし」を覆い尽くしてゆくだろう。それは最初から『わたしがいなかった街で』という題名によって予告されている。「存在しなかったかもしれないわたし」は、しかし存在している。今ここに、存在してしまっている。この当たり前の、そして残酷な事実認定は、阿部和重の『クエーサーと13番目の柱』における「無数に分岐して展開してゆく可能性」から引き寄せられる「ひとつの可能性」と、明らかに共鳴し合っている。
15。「わたしがいなかった」ということ
阿部和重は『クエーサーと13番目の柱』で、オカルトまがいの自己啓発と思われかねない「引き寄せの法則」を闇雲に肯定してみせることで、いったい何をしようとしていたのか。 「無数の可能性」から、ありうべき「ひとつの選択肢」を掴み取る、ということは、あくまでも未来へと向かう問題である。どれだけ強力な「引き寄せの法則」を駆使しようとも、確定された過去を改変することだけは出来ない。残念なことに、タイムマシンは未だ発明されてはいないのだから。むしろこの残酷な事実認定こそが「引き寄せ」を引き寄せているのだと考えるべきなのだと思う。変えられる可能性があるのは、これから起こる出来事だけであり、起こってしまった出来事に対しては、ただそれをどう過ぎ越してゆくか、どう受け止められるか、どう解釈するか、ということにしかならない。過去が過去であるがゆえのこの無情さを、如何にして未来の希望へと反転させるか、阿部和重の目的は、この一点に集中していると言ってもいい。それゆえにこそ『クエーサーと13番目の柱』は、表面的な荒唐無稽さや不謹慎さを超えて、ひどく切実なのである。 「わたしがいなかった街で」の柴崎友香もまた、過去の改変不可能性と、けっして変えられない過去が、他ならぬ現在とひと続きであるというもうひとつの残酷さに、真摯に向き合おうとしている。ベトナム戦争のドキュメンタリー映像を観ながら「わたし」は考える。
何度も何度も、別のヘリコプター、別の飛行機から撮影された映像が、繋ぎ合わされ、光の塊が空中を進む時間が、重ねられていく。また別の村、別の橋、別の道路、森、田畑が、銃撃され、爆撃され続けた。 新しい場所が現れては破壊されていくのを見ているうちに、もしかしたら、人間は、この時間のことを考えることしかできないのかもしれない、という思いが湧き上がってきた。 発射された弾丸や爆弾が空中を進んでいき、地上を爆破するまでの、そのあいだのわずかな時間。破壊は決定されているにもかかわらず、まだその破壊が訪れない、その何秒かの、しかし最後に向かっていく限りなく永遠に近く感じられるその時間。 爆弾がおちてくることがわかっているのに、そのときはすでに爆弾は投下されていて、誰も止めることができない。時間はあるのに取り消すことはできない。少しでも遠くへ逃げるか、なんとか物陰に隠れて、すでに決められた破壊を見ることしかできない。 目撃した人は、考え続ける。もし、あれが発射されていなければ、もし、あの場所にいなければ、もし、戦争が起こらなければ。 起こらなかったことについて考えるのは、難しい。 それでも、思い続ける。 もう少し早く、ほんの少しでも早く、気づくことができたら。 そうしていつかは、引き金が引かれるより一瞬でも早く、爆弾投下のスイッチが押されるよりほんのわずかな時間だけでも早く、伝えられるようになれば。撃たないで! 落とさないで! と叫���ことができたら、叫び声が向こう側まで聞こえたら、と願い続けている。 変えることのできない過去、取り戻すことのできない時間、絶対に行けない場所。それらを、思い続けること。繰り返し、何度も、触れることができないと知っているから、なお、そこに手を伸ばし続ける。
起こらなかったことについて考えるのは、とても難しいし、おそらくは無意味なことでもある。だが、それでもわれわれには、考えてみることは出来る。しかし悲惨の只中にある者には、今起こっている出来事を顧みることさえ出来ない。その結果、この世界から消えてしまった人々には、それを過去として思い出すことも、忘れてしまうことも叶わない。われわれはしばしば、その時その場にたまたま居合わせてしまったがゆえに、取り返しのつかない事件や事故の犠牲となった者に対して、偶然や意思の働きがほんの僅か違っていたら、自分がそこに居合わせていたかもしれない、悲劇と遭遇していたかもしれない、という可能性に思い当たり、震える。そのとき、それは私であったのかもしれないという想像は、しかしそれは私ではなかったのだという事実と、裏腹になっている。だが、それは私だったかもしれないが私ではなかった、とは、ほんとうは、どういう意味なのか。そのような認識が齎す、紛れもない自責の念とは、結局のところ、安心の別名ではないのか。 「わたし」の祖父は、一九四五年八月六日の広島に居たかもしれなかった。もしもそうであったなら、「わたし」は存在していなかったかもしれない。だが事実としては、祖父は「そこにいたのにその日はいなかった」のだし、そのかわりに「たまたまその日にそこにいた人たち」が消えてしまったのだ。ここには交換可能性は無い。無いからこそ「居たかもしれない」が生まれてくるのだから。だが、だからといって、この「かわりに」という錯覚の強迫を、真っ向から引き受けてしまったなら、われわれは到底生きてゆけないだろう。 あらゆる過去は必ず、現在から遡行していった時間の系の内に属している。起こらなかった過去は、そのどこにも存在してはいない。それはただ現在という時点から、かりそめに想像されているだけである。だが、それを言うなら、現実に起こったことにしたって、実はほとんど同じことではないのか。忘却がそうさせるということだけではなく、そもそも記憶されなかったこと、自分が体験しなかったことは、思い出すことも忘れることも出来ない。それはせいぜいが、ただ知ることが出来るだけである。 「わたしがいなかった街で」で柴崎友香は、明らかに意識的に、以前の彼女だったら敢て書かなかっただろう、たとえ行間には存在していたとしても進んで言葉にしようとはしなかっただろう事柄を、たくさん書いている。思うにそれは、かなり勇気が必要な行為だったに違いない。「新潮」の二〇一二年九月号に掲載された岡田利規との対談「〈わたし〉がいない過去と未来へ」の中で、彼女は次のように言っている。
柴崎(前略)これまで私が書いてきた小説は「何気ない日常を描いてる」と言われることが多くて、私自身はずっと「そんなつもりじゃないのにな」と思っていて……。 岡田 「日常」という言葉を当てはめられることに、違和感を持ってたんですね? 柴崎 「当てはめられることに」というよりは、おそらく人が「日常」と呼ぶものが、たとえば「普通の、変わらない毎日」とか「何でもない毎日」だとしたら、私のそれとは多分、違うものなんじゃないかと疑問に思っていました。 岡田 ああ、既にそこからずれてるってことですね。 柴崎 だから私の作品がそう受け取られてしまうのはどうしてなのか、そして私は何故それを違うと思うのかを考えて、作品の中で形にしないといけないのではないか、という思いがここ何年かのうちに、強まっていたんです。
岡田利規の演劇ユニット、チェルフィッチュの公演『ゾウガメのソニックライフ』を観劇した際、英語字幕の「日常」の訳が「day-to-day」になっていたことに触れ、柴崎は「自分が思う「日常」と近い」と述べている。一日また一日。その連鎖を「日常」と呼んでいる。それは端的に「時間」のことでもある。明日が今日になり、昨日となり、過去になってゆくという、不可逆的なプロセス。同じ一日などなく(必ず何かは違っている)、何も起こらない日もありえない(必ず何事かは起こっている)。そのような「day-to-day」が蓄えてゆく「過去」は、常に二重のものとしてある。「わたし」の中にある「時間」と、「時間」の中にある「わたし」。言い換えるなら、記憶と歴史。この二重の「過去」は並走しつつも完全には重なり合うことはない。ミクロとマクロ。「わたしがいなかった街で」の「わたし」は、彼女の「日常」の中で、記憶に穿たれた歴史と、歴史と共振する記憶を、幾度となく喚び起こし、反芻する。
どんな大きな事件も悲惨な戦争も、最初の衝撃は薄れ、慣れて、忘れられていく。また事件や戦争が起こったら、忘れていたことを忘れて、こんなことは経験したことがない衝撃だ、世界は変わってしまったと騒ぐけれど、いつのまにか戻っている。戻ったみたいに、なっている。 世界貿易センタービルに飛行機が突っ込んだときの映像を見たり、それを思い出したりすると、あのときは父が生きていた、と必ず思う。わたしは勤め先を辞めた直後で東京に引っ越す荷造りのために、実家にいた。自分の部屋にいた父が駆け下りてきて、すごい事故が起きてる、と言ってテレビのスイッチを入れた。ラジオでニュースを聞いたらしかった。食卓に母が座っていた角度も、床に転がっていた自分がそのときめくっていたファッション誌のページも覚えている。 「事故」ではない、とわかったのはその数分後に二機目がもう片方のビルに突入する映像が映ったときだった。そこで日付が変わるくらいまで見て、あとは自分の部屋のテレビで一晩中見ていた。大きな戦争が始まるのではないかと、怖くて眠れなかった。戦争が始まったことを自分はテレビで知らされるだろう、と子供のころから明確なイメージがあった。何か起きて、テレビをつけるともう世界は元に戻れなくなっ���いて、わたしは二度と家から出られない。翌日から、アメリカのニュースチャンネルには「UNDER THE WAR」の文字が並んでいた。 父が死んだのはそれから一年以上あとで、そのあいだに父と話したり病院に通った記憶もいくつもあるのだが、あの瞬間にまだ生きていた、はっきりと実感するのは二〇〇一年九月十一日、日本では夜の、父が階段をどたどたと下りてきて「すごい事故が起きてる」と言ってテレビをつけた、その一連の動作と時間だった。だから二つの高層ビルが煙を上げる映像を見ても、その日の話題が出ても、わたしにとっては必ず「父がまだ生きていた時間」として蘇る。「事故」ではない、とわかるまでの時間、北棟が崩れ落ちるまでの時間、南棟も崩れ落ちてそこにタワーがなくなってしまうまでの時間、そのあと一人でテレビを見続けていた時間。
ここには、極めて繊細な、それと同時に驚くほどにざっくりとした印象もある、独特の時間感覚が働いている。「わたし」は「二〇〇一年九月十一日」の他にも「一九八九年一月七日」のことや「一九九五年一月十七日の朝」のことを思い出す。今日のこの日から「day-to-day」を巻き戻してゆけば、その日は必ず、そこにある。「わたし」には、その日の記憶が、確かにある。そこでは記憶と歴史は、歴史と記憶は、かろうじてとはいえ、繋がっている。けれども海野十三の日記を繙くとき、海の向こうの戦場の映像を見るとき、「一九四五年八月十四日の昼」や「一九四五年八月六日の広島」を思うとき、そこに刻み付けられた時間と空間に「わたし」は見当たらない。だが、それは確実にあったのだし、あるのだ。ということは、今ここにいる「わたし」と、いつかどこかの「わたしがいなかった街」は、やはり繋がっている。この断絶と連続のパラドックスが「わたしがいなかった街で」という小説を駆動している。そうして「わたし」は、やがて「日常」にかんする次のような省察へと至る。
日常という言葉が指す何かがあるとしたら、あのときも、現在も、遠い場所でも、ここでも、同じ速さの時間で動き続けている街の中に、ほんのわずかのあいだだけ、触れたように感じられる。だが、その次の瞬間には、もうそれがどんな感じだったか伝えられなくなってしまうような、そういう感じ方のことだと、思い始めている。 見たり忘れたり現れたり消えたりしたあとで、わたしの中に残っている数少ない確かなことは、自分が今、この世界で生きていると思うこと。わたしは生きているし、映画のセットや張りぼてみたいに思えても、今この網膜に映っているものは、そこにあって、近くまで行けば触れる。そして、しばらく見ていてもなくならなかった。
「わたしは、かつて誰かが生きた場所を、生きていた」。だがしかし、この作品がおそろしいのは、すでに述べておいたように、「わたしがいるここ」から「わたしがいなかったそこ」を、「わたしが生きている今」から「わたしがかつて生きていたその時」と「わたしがまだいなかったその時」を透かし見る、この小説の進みゆきの果てに、他でもない「今ここ」から「わたし」が消滅してしまう、ということなのだ。「わたし」の一人称に、物語の中途から彼女の旧い友人の妹である「葛井夏」を視点とする三人称が紛れ込み始める。この三人称はどこか奇妙なものであり、一見ごく変哲のない文章であるようでいて、まるでそのすべてが「わたし」の主観の内部に閉じ込められているようにも思えてくるのだが、しかし東京に居る「わたし」と大阪に住む「夏」は一度も出会うことなく(二人は共通の知人である「中井」を介してのみ互いのことを知る)小説は終わってしまうのだ。全二四章から成る「わたしがいなかった街で」は第二三章の途中から三人称に変わり、最終章には「夏」しか出てこない。だが、そこで語られるエピソードを読めばすぐに気づくことだが、そのとき「夏」には「わたし」が溶け込んでいるのだ。 岡田利規との対談の中で、柴崎友香は『わたしがいなかった街で』について、「自分がいない場所のことを考える」ことが一番大きなテーマだった、と語っている。「別の時間が同時に存在するように、読む人の中で混ざり合うように」書こうとした、とも。
柴崎(前略)場所にしても時間にしても、人間は二箇所に同時にいることはできない、というのが、たぶん自分のいちばんのテーマです。「今」「ここ」からは、時間的にも空間的にも、どこかとの距離が必ずある。絶対に越えられないその距離と、距離を越えようとすることの、両方を書きたいです。
二〇一〇年の初めから夏の終わりにかけての出来事が綴られた「わたしがいなかった街で」を読む私たちは、ちょうど「わたし」が『海野十三敗戦日記』を読んでいたのと同じように、それから数ヶ月後に何があったのか、二〇一一年の三月一一日に何が起こったのかを知っている。意識していなくとも、常に頭のどこかにはある。そして柴崎友香は、そのことをよくよくわかった上で、この小説を書き上げたのだと私は思う。物語の末尾から「day-to-day」を繋いでゆけば、やがてその日になり、そして今日になる。だが、このときはまだ、それは起こっていないし、起こることを誰も知らない。この作品に幾重にも畳み込まれた「時間」をめぐる断絶と連続のパラドックスは、こうして未来に、この現在にまで延びている。「わたしがいなかった街で」が、「以後」に書かれた、しかし「以前」を舞台とする、すぐれた「以後の小説」であるというのは、ざっと以上のような理由による。 書いておくべきことは、まだある。単行本『わたしがいなかった街で』には「群像」二〇一一年十月号掲載の短篇「ここで、ここで」が併録されている。このごく短い小説は、阿部和重の「RIDE ON TIME」が『クエーサーと13番目の柱』に対して持っていたような位置を、本篇(?)に対して持っている。舞台は「わたしがいなかった街で」から約一年後の二〇一一年の夏、今度ははっきりと「以後」である。大阪出身だが今は東京住まいの「わたし」は、神戸の三宮で催されるトークイベントに出演するついでに里帰りをする。彼女がこの仕事を受けたのは、「三月の地震以来、わたしは何度も神戸のことを思い出していた」からだ。この「わたし」は「柴崎友香」に限りなく近い人物と思われ、そのせいかややエッセイ的な雰囲気を感じさせもする(のだが、もちろん書かれてあることが事実とは限らない)。「わたしがいなかった街で」と最も強くシンクロしているのは、幼い姪のエピソードである(タイトルもここから採られている)。「わたし」が与えた動くぬいぐるみに吃驚して床にひっくり返って頭を打った姪は、しかし泣き出しはせず、むくっと起き上がってテーブルの縁を指差し「ここでここで」と言い、続いて椅子の脚を指差して「ここでここで」と言う。
「ここで? 頭打った?」 指をくわえたまま、姪は三回頷いた。 「前に?」 さらに二度頷いた。それから頭を打ったことは忘れたように、台所へ歩いて行った。そのあとについて行きながら、わたしは動揺していた。一歳八ヶ月の姪に、すでに過去の時間があって、彼女がそれを理解していることに。彼女が、過去のできごとをわたしに向かって説明しようとしていることに。自分は前にこことここで同じようなことを経験した、と。 わたしはそれを聞いてしまった。
もうひとつ、姪は母親に言われて、仏壇に向かって正座をして、会ったことのない「じいちゃんにちーん」をする。
自分が生まれる前に祖父が死んだということを、姪が理解するのはいつごろだろう、と小さな背中を見ながら思った。もしかしたら、もう知っているのかもしれない、 それでも変わらないのは、父が、彼女が生まれたのを知らないこと。
「過去」の存在と「時間」の不可逆性。越えられない「距離」と、それでも「距離」を越えようとすること。ここには紛れもなく「わたしがいなかった街で」のエッセンスがある。だがそれと同時に、この短篇は「わたしがいなかった街で」よりも半年早く発表されており、舞台は一年後なのだ。二篇が一冊の単行本に収められることで、更なるパラドックスを形成している。それは、小説の内側だけでなく、今ここで読んでいるこちら側にも働きかけてくるのだ。
16。「現在地」から遠く離れて
さて、そろそろ話を変えていかねばならない。どこに向かうべきか暫し思案したが、ちょうど接続もいいので、岡田利規のチェルフィッチュが二〇一二年の四月下旬に初演した舞台『現在地』のことを書こうと思う。先の柴崎友香との対談で、岡田は「わたしがいなかった街で」が「戦争」という題材に思い切って踏み込んでみせた蛮勇(?)を讃えつつ、自分自身が経験していない出来事を書くことの難しさを語っている。
岡田 経験してる人は、書けるじゃないですか、経験してる、というごく単純だけれど強力な理由から。でも、戦争を経験もしていなければ、それにまつわる歴史についてだって大した教養があるわけでもない僕なんかが、作り手としていったいどういうことができるのか? そういうことは割としょっちゅう考えていて、それでよく落ち込むんですけど(笑)、でも結局行き着く答えって、そんな自分の考え方がどうやって変化していったかを示すこととか、そういうところにしか僕は自分の可能性とか価値とかを見いだせない、ってことなんですよ、いつも。というか、そこには可能性があると無理矢理思い込むことでなんとか首の皮一枚つながってることにしようとしてるんだと思いますけど。
だから「僕にやれることがあるとしたら、僕らがどうやって現代を生きてて、そしてそこにどうやって歴史に対する想像力を挿入させていくか、その試行錯誤のプロセスを晒すこと、それにはかろうじて、ある種のドキュメントとしての意味があるかも」と岡田は述べている。確かに岡田利規とチェルフィッチュは、一貫してそのようなことをやってきた。ほぼ無名と呼んでよかった彼らが一躍注目を浴びた、岸田國士戯曲賞受賞作『三月の5日間』は、二〇〇三年の三月、米軍のイラク爆撃の真っ最中に渋谷のラブホテルで四連泊するゆきずりの男女を描いたものだったし、二〇〇六年末の『エンジョイ』では、急速に社会問題化していた非正規雇用者=フリーターたちの生態を、当時勃興していたフランスの学生デモと絡めて作品化し、二〇〇八年の『フリータイム』では、引き続き雇用と労働を主題にしつつ、より抽象化された舞台で岡田独自の演劇的方法論を更新し、二〇一〇年の『わたしたちは無傷な別人である』では二〇〇九年八月末の衆議院選挙の前日を舞台に、持てる者と持たざる者の相克、すなわち格差問題へと踏み込み、二〇一一年二月に上演された『ゾウガメのソニックライフ』は、それまでの作品群で描いてきたリアルな現状認識を持ったまま、現在のニッポンで生きること、生きてゆくことを肯定するためには、果たしてどうすればいいのかと問うたものだった。『現在地』は、前作以来一年二ヶ月ぶりに発表された、チェルフィッチュの長篇最新作である。公演にあたって、岡田利規は次のように書いている。 『現在地』は変化をめぐる架空の物語です。SFみたいな。 わたしたちは、状況を変化させたいと強く望んだり、変化させなければと焦ったり、怒ったり、実際に変化に身を投じたり、それはできずにためらったり、常に冷静で穏やかであろうと努めたり、変化するしないを勇敢さ臆病さの問題として考えたり、考えなかったり、開き直ったり、自分の考えていることが正しいのかどうかの確信をどうしても欲しいと思ったり、正しい人間でいたい過ちを犯したくないと思ったり、たとえばその気持ちを過去に人類が起こした取り返しの付かない過失に準えようとしたりします。 『現在地』というフィクションの中の人物たちも、そうやって生きます。
多くの点で『現在地』は、それ以前のチェルフィッチュの作品とは明確に違っている。まず、七人の出演者は全員女優であり、それ以前の全作品に出演してきた看板俳優の山縣太一をはじめ、男性はひとりも出てこない。また、岡田利規の得意技である役柄の非固定化や移動/交換、時空間のあからさまな操作/変形、或いはチェルフィッチュのトレードマークだった異様にきょどった発話や動きも、ほぼ皆無となっている(これらの点については拙著『即興の解体/懐胎』を参照)。もちろんそれらは『三月の5日間』以降の作品群において次第に変化してきていたのだが、『現在地』には、それまでの方法を敢て封印してでも新たな作風に向かおうとする、はっきりとした意志が感じられる。そこで鍵となるのは、右の文章の最後にも出てくる「フィクション」の一語である。 「新潮」の本年四月号のアンケート特集「震災はあなたの〈何〉を変えましたか? 震災後、あなたは〈何〉を読みましたか?」には、岡田利規も回答を寄せている。「僕はかなり変わったと思う」と題された文章は「フィクションを作る想像力を欲しいと思うようになった」と��う一言から始まっている。「こう書くと驚かれるかもしれない。(略)お前は持ってないの? はい。持っていません。それでも小説を書いている。それでも書けるから。現実を自分なりの仕方で見るブラウザみたいなのを用いることで、僕は小説を書いている」。文芸誌なのでもっぱら小説が話題にされているが、もちろん事は演劇でも同じである。そして「以前」は、それでも別によかったのだ。だが、心境の変化が訪れた。
想像力は、現実とたとえ無関係でもかまわない。現実と拮抗する何かを作るということ。現実のオルタナティブを作るということ。僕はそんなふうに書いたことがこれまでない。少なくともそのように書こうという意志の在り方が僕にはなかった。けれども今の僕が興味があるのは、そういうことだ。この興味に従うとしたら、僕は変容することになる。その変容を成功させる自信は今のところないけれども、変容してしまうことへの恐怖はほとんどまったく持ってない。どうにでも変わってしまえばよい、と思っている。想像力、という問題に自分自身をできるだけ強く押しつけていき、その界面で自分をこすり続けていったらどうなるか? そんなことを考えるようになったのが最大の変化です。
現実の対抗物足り得るフィクションと、それを作り出すための想像力。時期的にいって、この回答を書いている頃、岡田利規はまさに『現在地』の準備中であった筈である。「ドキュメント」から「フィクション」へ。ならば『現在地』は、どのような演劇作品だったのか? すでに述べたように、この作品の登場人物は七人の女性である。そしてこれも述べておいたが、チェルフィッチュには極めて珍しく、七人の女優がそれぞれひとりずつ、名前のある(こともチェルフィッチュでは非常に珍しい)、固定された役柄を演じている。つまり、ごく普通の演劇と同じ形態になっているわけだが、しかし実際の舞台から受ける印象は、ごく普通のドラマとは、かなり異なっている。これは岡田作品の例に漏れず、幕間や舞台転換などは一切無く、役者は全員が最初から最後まで舞台上に居るのだが、全体は登場人物の数と同じ七つのチャプターに分かれており、章が変わるごとにメインの語り手となる人物が変わる(台本では各チャプターに、その章で中心となる役柄の名前が記されている)。章ごとに数人が入れ替わり立ち替わり、それぞれの場面を演じ、その間、台詞のない他の女優たちは、黙ってその様子を見守ったり、退屈そうにしたり、ぼんやりしたりしている。これが奇妙というか、どこか不気味なのだが、しかしこの極度に形式化された構成と、メ��演劇的な趣向は、過去のチェルフィッチュと相通ずるものだとも言える。この作品の新機軸は、やはりあくまでも「SFみたいな架空の物語=フィクション」としての佇まいにこそある。それはほとんど寓話と呼んでもいいようなものである。 どことも特定されていない「村」。ある土曜日の夜、ナホコは恋人と湖にドライブに行った際、青く光る巨大な雲を目撃する。ナホコはそれを村で噂になっている怪しげな占い師の予言、とつぜん何かが起こり、それが原因となって村が滅び、それどころか世界がまるごと破滅してしまうかもしれない、そしてそれには予兆となる現象がある、という恐ろしい予言の兆しではないかと疑い、そのことをカスミに話す。カスミはそんな予言は信じるに値しないと言う。だがナオコは、あの雲はひょっとしたら兆しではなく、村を、世界を破滅させる「何か」そのものではないかとも思い、それがきっかけで恋人とも別れてしまう……これが物語の発端である。ナホコとカスミと同じように、予言をめぐって村は二分されているようだ。ところで、どうやらこの「村」は、おじいちゃんおばあちゃんの世代が、荒廃して内戦が続いていた「日本」という国から脱出してきて作ったものらしい。もっともそれも「これからする話は、おとぎ話みたいにして話すわ」と宣言されてから語られるので、真偽のほどは定かでないのだが。カスミは、あるときハナを連れてきて姉のアユミに紹介する。だが二人はすでに顔見知りだった。道端でハナはアユミに声を掛けていたのだ。ハナは少し変わっている。彼女は噂をひどく怖がっている。だが同時に「たぶん私が今怖がってるのは、そんなものを怖がる必要はほんとうはないものを怖がってるんじゃないか」とも言う。「自分がそれを怖がらなくなるのも、やっぱり怖い」とも。カスミはハナに、不安に捉まえられないように忠告していたかと思うと、とつぜん首を絞めて殺してしまう。カスミはハナの死体に「私たちは、今みたいに世の中がそわそわしているときは特に、不安に陥らないように心がけなければいけないのよ。不安は、人から正気を失なわせるからよ」と言う。やがて、湖の水位が下がり始める。原因不明の出来事に、村人たちは恐怖する。カスミはハナの死体を湖に沈めていたので、別の意味で不安になるが、事故として片付けられる。湖が完全に干上がると、その地中から大きな乗り物が現れる。村人たちはそれを「船」と呼ぶが、どうやら宇宙船のようなものらしい。間近に迫っているやもしれぬ破滅を前にして、人々は選択を迫られる。「船」に乗って「村」を脱出し、遠い場所に行くか、それとも一か八か、この場に留まるか。「船」に村人全員は乗れない。それにそもそも予言が真実であるのかどうかも、まだわからない……実に複雑な余韻を残すラストシーンは記さないでおこう。『現在地』は、ざっとこのような物語である。 『現在地』の戯曲には、役名指定のない「声」とだけ書かれたパートの台詞が何度か出て来る。たとえば「声」は、こんなことを語る。「ときどき世の中に噂が流れると、私たちはそのたびに、選択をせまられるの、その噂を信じるか、信じないのか?」「でも、それよりもっと大事な選択もせまられるの。それは、自分が決めたその噂との付き合いかたと違う付き合いかたを選択した人と、どう向き合うのか?」。或いは、こんなことも言う。「村にこれから悲惨な出来事が起こると言ってる人もいるし、いやもう悲惨なことは日曜に起こってしまってもう取り返しが付かないと言っている人もいるし、それが起こったのは日曜じゃなくて土曜だという人もいるし、何ひとつ起こってないしこれからも起こらないという人もいる。本当はどうなのか、というのは誰にも分からないの。本当はどうなのかは誰にも分からないから、それを尋ねることには意味がないの」。「寓話」と呼んでおいた理由がわかっただろうか? あまりにもあからさまではないか? 誰もが気づくように、『現在地』の物語は、福島第一原発の事故以降、被災地のみならず関東在住の人々のあいだにも巻き起こった、さまざまな紛糾や��動を、ほとんどダイレクトに思い出させる。このことは、岡田利規自身が、震災後に妻子と共に横浜から熊本に転居した事実を考え合わせるなら、より切迫した問題提起として受け取られるかもしれない。だが、彼はけっして作品の中で結論を出そうとはしていない。現実の行動はどうであれ、あくまでも「変化をめぐる架空の物語」であり「現実と拮抗する何か」でもある「フィクション」として、観客に問いを差し出してみせているだけである。あなたは「予言=噂」に対して、どう振る舞うのか? あなたは迫りくる「破滅」を前にして、何が出来るのか? あなたは「村」を出ていくべきなのだろうか? それともここに居るべきなのか? この作品で岡田利規は、これらの問いを問うこと、このような問いを観客と共有すること、それしかしていない。これは極論ではないと思う。私はむしろ、彼が『現在地』という「フィクション」を使って、ただそれだけしかしようとしなかったということに、少なからぬ衝撃を受けたのだった。もしかするとここには、問い自体よりも重要な何かが顔を覗かせているのではないか、そう思えるのだ。
17。せんだいメディアテークで交わされた言葉、その1
仙台に行ってきた。せんだいメディアテークで毎年九月に開催されている「仙台短篇映画祭」のプログラムのひとつとして行なわれた「シネマてつがくカフェ『震災と映画』」に参加するためである。本連載の第二回で、私は同映画祭の映画制作プロジェクトによる、四十一人の映画作家が撮った四十二本の「三分一一秒」の短篇映画から成るオムニバス作品『311明日』について、やや詳しく述べた。このことがきっかけとなって、同作にたった一人だけ二作を出品していた冨永昌敬監督ともども、トークのゲストとして招かれたのである。驚かれるかもしれないが、私にとって初の仙台だった。 「シネマてつがくカフェ『震災と映画』」は、仙台短篇映画祭とは別に、有志によって継続的に運営されている「てつがくカフェ@せんだい」との共同企画によるもので、九〇年代にフランスで生まれた、専門家とアマチュア、学者と一般人との垣根を取り払った、ジャーゴンを使用しない哲学的な語らいの場である「てつがくカフェ」の特別編だった。いわゆるパネルディスカッションの形式とは違い、一応ファシリテーターが交通整理はするものの、基本的にはその場に集った全員が同じ立場で自由に発言し、対話を交わし、議論を深めてゆくというものである。当然、冨永監督と私も、その中の一員として話した。これはとても貴重な経験だったと思う。 当日配布されたチラシに、「てつがくカフェ@せんだい」の西村高宏氏は次のように書いている。
震災以降、被災地の〈リアル〉を伝えようと数多くのドキュメンタリー映画が制作されつつあります。しかしながら、作り手の意図によって世界が切り取られ編集されていく以上、映画という表現手法にはどこまでも〈フィクション〉の要素が付き纏っているとも言えます。 『311明日』ーー今回のシネマてつがくカフェで取り上げるこの映画は、そういった震災のドキュメンタリー映像ですらありません。41人の映画監督1人ひとりが「3分11秒」という条件、そして「明日」というキーワードをもとに多様な切り口で震災を描いた、まさに〈フィクション〉としての映画です。それは、震災を敢えて〈フィクション〉として描くことで、ドキュメンタリーやニュース映像では捉え切れない震災が持つ問題性をあらためて私たちの前に焙り出そうとする、〈映画表現による震災理解の試み〉とも言えます。
「震災から1年半を迎えた今、あなたは、この映画をどのように受け止めるでしょうか?」。トークが開始される直前に上映が終わるように『311明日』がプログラムに組まれていた。この作品は昨年の映画祭でも上映されているが、一年という時を経て、どのように見え方が変わったか、或いは変わっていないのか、を問い直そうということである。その際に、映画における「リアル(ドキュメンタリー)」と「フィクション」の関係性という問題意識が踏まえられていることも、あらかじめ告げられている。 ここでひとつ付言しておかなくてはならない。冨永昌敬監督の二本の「三分一一秒」ーー『妻、一瞬の帰還』『武闘派野郎』ーーは、前にも述べておいたように連作になっているのだが(そしてこの「連作」ということ自体に深い意味が込められているのだということも前に書いた)、今回の上映にあたって冨永監督は、彼が教えている映画専門学校の卒業生六名にメガホンを握らせ(彼自身は全作品でカメラマンを担当している)、なんと「三分一一秒」×六本もの新作を引っさげて、映画祭に乗り込んできたのである。それも誰に求められたわけでもなく、完全に自発的に。そしてこの六本は当然のごとく冨永監督の二作の続編になっていたのだ。以下に作品名と監督名を挙げておく。『ライバル』堀切基和/『居候』市来聖史/『野郎釣り』鈴木薫/『行くも千里、戻るも千里』岡部徹/『背水』松尾圭太/『捲れる』増田和由。ストーリーは、この順番で続いている。冨永監督は、この内の三名を伴って仙台にやってきた。こうして、出来立てほやほやの新作六本に最初の二本を加えた「三分一一秒」×八本による「武闘派野郎サーガ」(と勝手に命名しておく)を『311明日』とは別に一挙上映してから、この日の「シネマてつがくカフェ」は開始されたのだった。 「武闘派野郎サーガ」の第三話以降では、第二話で登場した「武闘派野郎」こと単細胞な俳優志望のミュージシャンが、第一話、第二話の映画監督に代わって主役(?)となっている(映画監督も出て来るが)。彼はどう見てもカラオケボックスにしか思えない映画のオーディション会場で沢田研二を熱唱したり、そこでライバルと出会ったり、釣った小物の魚をめぐって謎の青年と喧嘩したり、俳優をめざすべくバンドを脱退しようとしたら後釜が例のライバルだったり、悪夢になぜか第一話に登場した映画監督の妻が出てきたりするのだが、総じて言えることは、もともと『311明日』の中でも特に「震災」と関係がなさそうに見えた最初の二本にも増して、「311」と「明日」から遠ざかっていってしまっているように思える、ということである。もちろん、この連作には、冨永昌敬の「仙台短篇映画祭」に対する想いが込められている。以前にも引用した彼の言葉を、ふたたび引いておく��
その中身がどんな「3分11秒」であろうと、積み重ねれば「6分22秒」にも「9分33秒」にも「12分44秒」にもなる。いや、いずれ「3日11時間」くらいの大作にまで膨張するかもしれない(いったい何年後だろう?)。まあともかく、うずたかく積まれた小さな固い石の集まりが、やがて強固な防波堤となり、映画を愛するこの美しい町を人知れず囲んでしまうことを僕は夢想する。 (「映画制作のこと」、『311明日』パンフレット)
冨永監督とその弟子たちは、この「夢想」を実現するべく新作を撮ったのだ。それは間違いない。八本だから「25分28秒」まで来たわけである。だがそれにしても、前二作以上に、一見しても何度見ても、ほとんど巫山戯ているとしか思われないだろう「武闘派野郎サーガ」の後で、仙台のひとびとによって、いったいどんな「震災と映画」にかんする言葉が交わされるのか。私は正直、いささか緊張して「シネマてつがくカフェ」に臨んだのだった。 せんだいメディアテークの一階、オープンスクエアと呼ばれている吹き抜けのスペースで「シネマてつがくカフェ」は始まった。エントランスにはカフェやショップが併設されており、マイクで話す声はフロアに丸聞こえだから、興味を感じた人はいつでも加わることが出来る。約三十分の「武闘派野郎サーガ」上映後、やはりというべきか、会場は当惑まじりの奇妙な静寂に覆われていたように思う。てつがくカフェ@せんだいのファシリテーターの方が、まず今観終えたばかりの映画への率直な感想を求める。暫しの沈黙の後、ひとりの中年の女性がおずおずと手を上げた。彼女は言葉を絞り出すようにして、ここ仙台から、被災地から遠く離れた、いわば無関係で安全な土地に住む、冨永監督をはじめとする映画作家たちが、このような機会にこうして映画を撮ったということ自体について、率直な感謝の意を述べた。しかしそれにしても、今の映画は何だったのだろう?。そんな戸惑いの空気がいまだ会場に流れていたのは事実だ。その空気を取り払おうとするかのように、冨永監督が比較的長い発言を行なった。語り口調を残しつつ、以下に再構成してみる。
「これは若干説明が必要な作品だなと、僕自身さっき観ながらしみじみ思ったので、ちょっと説明させていただいてもよろしいでしょうか。「震災と映画」というテーマの中で、こういった作品、内容的には震災とまったく関係のない作品を観ていただいたわけですが、なんでこんな作品が出来たのかということをお話させていただければと思います。 遡れば、震災以前になるんですけれども、去年の仙台短篇映画祭で、映画祭にゆかりのある監督何人かに、宮城県内で短篇映画を撮らせるという企画があって、僕も声を掛けられていたんです。それで、どういう映画を作ろうかアイデアを練っていたのですが、主人公を映画監督にして、まあ僕自身がモデルになっているとまではいいませんが、とにかく監督が主人公で、彼が映画を撮るのに些細な日常に邪魔されるといいますか、映画作りをする上で、日々のあれこれに色々と揺さぶられながらやっているんだということを描こうと考えたんです。映画を作っている人間の生活を描くということですね。そこで、その監督のところに俳優志望の男、しかも物凄く自己主張の強い男がやってきたら、一体どうなるか、というストーリーを思いついた。というのは普段、僕なんかがオーディションや俳優学校の教師をやる際にも、そういう人はよく現れるわけです。かなり誇張はしてますけれども、あの「武闘派野郎」は、われわれにとってはかなりリアルな人物で、よくいる厄介な男という奴なんですね。自分が如何に映画俳優として優れているかをアピールするのならまだしも、どういうわけか、自分が如何に優れた男であるか、演技とは無関係な一芸に秀でた男であるか、あまつさえ強い男であるか、といったことをアピールしてしまう人ってのが実際にいるわけです。どこの世界にもいるかもしれませんけど、一言でいうと、これは馬鹿な人であるわけです。それで、いつかこれを映画にしてやろうと思ってたんですね。 その機が遂に来た、と思ったわけなんですが、そんな時に震災があった。震災後一ヶ月くらいの頃ですか、まだ今年の映画祭が開けるかどうかわからない時期があったんです。当然、僕が依頼されていた企画も断念さぜるを得なくなった。それでスタッフの方達が相談している場に僕がたまたま居合わせた際に、ごく短い映画であれば、みんな何かしら撮ってくれるのではないか、それを集めて上映したらどうか、と提案させていただいて、それはあくまできっかけに過ぎませんけれども、それが最終的に『311明日』になった。 「三分一一秒」の映画を、と依頼されて、それぞれの監督たちが考えたのは、震災と映画ということだけではなくて、震災と映画祭と自分、ということだったと思うんです。あのまま映画祭が中止になってしまっていたら、ある意味で、自分たちも被災することになってしまう。それだけは食い止めなくてはならない。そういう思いで、皆さん映画を撮った。だからまず参加すること、とにかく間に合わせることが何よりも重要なことだった。結果として、皆さん好き勝手な映画を作っているようにも見える。まったく別の理由で撮りつつあった映画を「三分一一秒」に編集して提出した方もいただろうと思います。だから内容的に震災とまったく関係のない作品も沢山ありましたし、僕の作品もそうだと思います。 僕自身が意識していたのは、先ほどお話した、そもそも東日本大震災があろうとなかろうと撮るつもりだった映画を、そのまま撮ろうということでした。これはひとつの考え方でしかありませんが、そうしないと震災に負けたような気持ちになってしまうと思ったんです。震災の前からやると決めていたことをやる。だから作品の内容自体は、震災などなかったかのようになっていると思います。去年、僕だけ二本、フライングみたいに出したわけですが、ほんとうは、もしも作品の集まりが悪かったら、僕ひとりで十本でも撮りますよ、とか言ってたんです。なのにたった二本だったということに僕自身、しこりを感じていまして、ずっと反省としてあったんです。だからこれは翌年、翌年と繋げてゆくしかない、そう思った。三作目からは、最初の計画の映画監督ではなく、俳優志望の愛すべき馬鹿を描いてゆこう。だから今年、新たに六本持ってきたのは、映画祭から求められたわけでは全然なくて、これはもう自分で決めて勝手にやったんです。だからこそ、この場では、まず続編を観てもらわないと、僕としては話を始められない。なぜなら、これが僕にとっての、震災と映画と自分、震災と映画祭と自分のかかわり方であるからです。震災が起こってから、僕もいろんなことを考えながら生きてきました。けれども、生活人としての自分と、映画人としての自分は混同しないようにしたいのです。 もうひとつだけ言っておきますと、これで完結ではありません。来年もきっと新作を持ってくると思います。僕はさっき、もしも映画祭が中止になっていたなら、東京に住んでいる自分も被災していた、と言いました。映画祭スタッフの皆さんが大変な努力をしてくれたおかげで、僕らは被災しなくてすんだわけです。でもそれは去年で終わりではない。去年の開催は、震災が起こる前から当然決まっていたわけです。しかし今年は明確に震災後です。むしろ今年の方が中止される可能性があったのではないか。今こうして正常に開催されているという事実を、僕は嬉しく思います。だからこそ続編を作って持ってくるべきだと思ったのです。だから来年も再来年も撮ります。どれだけ撮ればいいのか、考えてみたんですけれども、少なくとも最初に集まった本数と同じだけ、四十二本までは撮り続けなくてはならないのではないか、そう思っています。そして四十二本に辿り着く頃には、ようやくこの連作は震災と関係してくるのではないか、そうも思っています。だから来年、再来年もここに来ますので、末永くお付き合いをお願い致します……」
冨永監督の長いスピーチを聞きながら、私は彼が言っていること、彼の話しぶりに、ある紛れもないパフォーマティヴな含意が隠されていることに気づき、静かな感銘を受けた。彼は昨年の仙台短篇映画祭を中止にしないために「三分一一秒の映画」に至る提案をした。それは自分自身が「被災」しないためだと言った。そして彼だけが「三分一一秒」を二本撮った。今年、彼は弟子たちと六本もの「三分一一秒」を自発的に撮って仙台にやってきた。そして彼は来年も再来年も新作と共にここに来ると宣言した。つまり、彼は来年以降も映画祭が中止されることがないように「三分一一秒」を連ねていこうとしているのだ。彼の発言は、弁明でも韜晦でもない。彼はただ、これからも「三分一一秒」は延々と繋げられてゆくので、上映の場であるこの映画祭はちゃんと開催されて欲しい、と祈願しているのだ。なぜならば、そうでないと、たとえ時間が経っていっても、やがて「被災」してしまうから、震災に負けてしまうから。冨永昌敬は本気で「防波堤」を築くために「小石」を積んでいくつもりなのである。 私も発言した。だがそれは、ほとんどが本連載でこれまで書いてきたことの繰り返しなので、ここでは再現しない。私は「震災と映画」というよりも「震災と芸術(表現)」全般についての自分の考えとして、いや「震災」とのかかわり以前に「芸術(表現)」について常々思うこととして、内的な必然性、切実さ、の話をした。「せねばならない」ではなく「しないではいられない」ということ。「こうあるべき」ではなく「こうしかできない(こうしかならない)」ということ。やらなくてもよい、そうしなくてもよい、という当然さを乗り越えて現れるもの。否定(やらない/ではない)の否定としての能動性。責務として引き受けられる(押し付けられる)ものではなく、無為の権利を無根拠に逆転して露出する行為。私には『311明日』という映画の試みが、そしてその中でも冨永昌敬がやろうとしたこと、やったこと、これからやろうとしていることが、そのような意味での切実さ、内的必然性を強く帯びていると思った。誤解を畏れずに言ってしまえば、それは内容やテーマとは別個に存在しているのだ。 今年の仙台短篇映画祭のサブタイトルは「継続ーー物語を続けよう」である。私はパンフレットにテクストを寄稿した。会場でしか配布されなかったものなので、以下に再掲しておきたい。
「明日の映画と映画の明日」
震災以後、誰であれ自分は何も変わっていないとうそぶくのなら、それはもちろん嘘だ。だが、すべてが変わってしまったとか、変わらざるを得ないとか変わるべきであるとか、変わろう変えよう、変えろ変われ、などと言われると、それもどこか間違っているような気がしてしまう。われわれは皆、多かれ少なかれ、否応無しに、すでに変わっており、変わり続けている。認めると認めざるとにかかわらず、われわれ全員が、あの日の「以後」を生きているのだから。何をするにしたって、それはなんらか影響してこざるを得ないだろう。むしろだからこそ、殊更に変化を強調するわけではない、ごく淡々とした営みの中にこそ、不可逆的な変化が滲んでおり、本人自身も気づいていないかもしれない、そんなありさまを見て取ることこそが、たとえば自分のような仕事にやれることなのかもしれないと考えたりしている。 こんにち映画を撮るということは、昔よりもずっとお手軽で簡単なことになっていると同時に、ますますむつかしさを極めていっているようにも思える。デジタル機材の充実は、間違いなく映画制作の現場を変えたし、それは日進月歩を続けてもいる。だが、映画監督として身を立てるとか、自分の映画を不特定多数の観客=他者へと向けて差し出し、後世へと残してゆく、といった事となると、以前より困難になっているのかもしれない。作り手だけでは作品は完結しない。スクリーンを介してカメラと瞳が出会わなくては、映画はほんとうの意味で、この世界に生まれ落ちたことにはならない。だが、メジャーな映画の業界を見回してみると、ゼロ年代を通じて完全に覇権を握った製作委員会の名のもとに、テレビ局やら大手芸能事務所やら広告代理店やら巨大出版社やらの利権と思惑に突き動かされるメディア・ミックスしか、映画が生まれる方法はなくなってきているとさえ思えてくる。そういう、たかだか「商品」でしかないもの(もちろん、それにも良し悪しはあるにせよ)と、われわれが本当に観たい映画とは、同じ「映画」と呼ばれてはいても、もしかすると全然違うものになってきているのではないか。そんな疑いさえ頭をもたげてくる。そろそろ違う名前を用意するべきなのかもしれない。 僕が観たいのは、ある紛れもない必然性をもって生まれてくる映画だ。この必然性は、切実さを伴っていなくてはならない。撮らずにはいられなかった映画、生まれてこないわけにいかなかった映画。切実さは、個人的なもので構わない。それは使命感とか責任感とは違う。もっとある意味では取るに足らない、他人にすぐには伝わらないような、こだわり���ようなものでもいい。作られる価値がある映画というよりも、出来はともかく兎に角作りたいという動機だけは煌煌と輝いている映画。役に立つとか立たないとか、ウケるとかウレるとか、そういうことはもうどうでもいい。ただひたすら、ああ映画が撮りたかったのだな、ああこの映画が撮りたかったんだな、と納得してしまうような、強い動機と必然性を帯びた映画が観たいのだ。この気持ちは、前からそうだったけれど、去年の三月一一日以後、ますます増してきている。 仙台短篇映画祭は、そんな動機と必然性を持った映画たちを送り出す、ささやかなプラットホームのごとき映画祭だと思う。誰かのカメラと誰かの瞳が出会う場所としての映画祭。 他のあらゆる芸術と同じく、今のこの状況下で「映画」に何が出来るのか、なんて問い直す必要はない。ただ撮られ、観られるだけでいい。いちばん大切なことは、明日に映画が生まれること、明日も映画が生まれること、明日の映画が生まれることなのだから。大きくなくていい、小さな映画でもいい。小さくてもとても強い映画はあるのだから。そしてそんな映画たちには、われわれ全員が今もその渦中を生きている、あの日からの不可逆的な変化が刻印されていることだろう。僕はそれを、けっして見逃さないつもりだ。
18。せんだいメディアテークで交わされた言葉、その2
ファシリテーターの方から、彼女自身が昨年『311明日』をはじめて観た時の感想として、ついていけない、と思ってしまった、という発言があった。「三分一一秒」はあまりにも短すぎて、次から次へと矢継ぎ早にスクリーンを駆け去ってゆく小さな映画たちが、忙しなさや焦燥のような感覚を抱かせたということだろうか。これに対して冨永監督は、「三分一一秒の映画」は、実はとてもむつかしいのだ、と応じた。確かにそれは手早く作ることが出来る短さではある。けれどもその短さで一本の映画=物語をまがりなりにも完結させるためには、やはり相応の技術が要る。たぶん自分はまだ「三分一一秒」の正しい使い方を学んでいる途中なのであり、それが次第にわかってくるのと、「震災と映画」についての当事者としての感覚が芽生えてくるのは、同じ時期であるかもしれない、と。これに対して、てつがくカフェ@せんだいの西村氏が発言し、ついていけない、という感覚の意味は、長い短いの問題という客観的な時間よりも、まだ震災から半年しか経っていない時期に、被災した仙台という場所で、フィクションが大量に眼前を通過してゆくのを、何よりもまずからだ自体が受け付けなかったということなのではないか、と述べた。何しろわれわれは、はっきりとフィクションを凌駕してしまったと思える現実の映像を、のべつまくなしに見させられていたのだ。冨永監督はもっぱら映画の作り手の側から話してくれたが、われわれ観客にとって映画とは当然ながら見るものなのだから、そこには身体的なタイミングとマッチングが、やはりあるのだ、と。そしてそれを受けて、ふたたびファシリテーターの方が、あれから一年が経って、今回は少し観た感じが変わった。思えば一年前は、映画だけではなく、他のジャンル、書かれたものも含めて、作品としての良し悪し以前に、すべてがフラットになってしまったような感じがあった。あの頃に較べると、今は中身を咀嚼する余裕が出来てきたように思う、と語った。興味深い応酬である。 このあたりで、やっと場も熟れてきたのか、来場者からもぽつぽつと発言が出て来るようになった。それらは私にとっていずれも、さまざまな意味で示唆的なものだった。幾つかランダムに、仙台の人たちの声を拾ってみたいと思う。 「昨年の映画祭でこの作品を観ました。たくさん映画があって、いろんな感情が次々とわき起こったんですが、もちろん作り手の方々はそれぞれに勇気の要ることだったと思います。でも、観ているこちら側も、感情を揺り動かされること自体が、後ろめたい、という気持ちを感じながら観ていたという印象があります。観ているものに対して、なにかしら自分の感情が変化してゆく,そのこと自体が後ろめたい。その繰り返しの中から、先ほど言われていた「追いつけない」という感覚が生じてゆく感じが、自分にもあったと思います」(女性)
「わたしはずっと映画とか必要じゃないと思っていて、ほとんど観ないで育ったんです。それがたまたま、震災よりずっと前のことなんですけど、冨永監督の短篇映画を観て、そのとき、何かすごい理由があったわけではないんですけれども、親にも悪いし、震災で亡くなった方たちにも申し訳ないのですが、ただわけもなく死にたくてしょうがないと思っていたときに、その映画が、何も考えなくてもいいんだよって言ってくれている気がしたんです。監督がそう思っているということではないと思うんですけど、死にたい死にたいと思っていた頃に、何も考えなくても過ごせる時間があるということを、教えてくれたっていうか。 震災でいろいろあって、大切なひとが亡くなってしまったりした人が、たとえ一時でも、何も考えないで過ごせる時間があって、その時間を楽しめたりするということは、それだけでも映画って必要だな、と思ったんです。だから映画祭が開かれたことが嬉しいし、冨永監督にも来年も来てほしいし、新しい映画を作ってほしいです。短篇映画でも長い映画でも、震災と関係があってもなくても、いろんな映画が撮られて、ここで観ることが出来ること、いろんなものが存在していることが、幸せなんだと思います」(女性)
「ピカソに『ゲルニカ』という絵がありますけども、ピカソの郷里が空爆にあって、その哀しみを描いた絵と言われています。完成した絵は人物が手を広げていて、叫びや哀しみを表しているとされていますが、下書きでは握り拳をしていて、元は怒りの絵だったと言われているんです。わたしは映画ってメッセージだと思うんです。メッセージの伝え方にはいろいろあると思う。いま、震災の哀しみが怒りに変わってきた気がしています。それが次は諦めに変わっていってしまうのが怖いんです。だから怒りを維持させてくれるような映画が観たい。映画は観れなかったのですけれども、わたしは、そう思っています」(男性)
「震災があろうとなかろうと、自分が作りたい作品を撮るしかないという冨永監督の気持ちには賛成しますし、それと同時に、震災の記録を残して欲しいという気持ちもよくわかります。でも、いつか必ず、わたしたちは震災を忘れる必要もあるのではないか。そのための時間が必要なんじゃないか。かなしみや怒りにばかり時間を使っていると、気持ちが過去にばかり向かってしまって、未来をクリエイトできないと思うんです。だから、いずれ忘れるということも大事なのではないか、そう思います」(男性)
「『三月一一日』について、ここ仙台では、被災した東北では、もはやひとつのイメージが出来上がってしまっていると思うんです。わたしたちの誰もが、震災についてのイメージを共有している。そして何を見ても、ついついそのイメージを探してしまって、それを確認しようとしてしまう。でもこの映画を見ても、そんなイメージは見当たらない。探せど探せど、そんなものはどこにもない。それに監督自身が、映画と震災は関係ないって仰っている。でもそれが逆に、わたしたち当事者だけでは打ち破ることのできないイメージの展開を生んでいると思ったんです。映画というものが持っている可能性として、ずいぶんと固くなってしまった構造を壊すような出来事として「三分一一秒」があった、今はそんな気がしています」(男性)
発言された方々は比較的年配の方が多かった。震災を忘れる必要もあると話した男性は、まだ若く見えたし、そう思って発言を読むと、字面だけとはまた異なる印象があるのかもしれない。皆さんそれぞれの立場で、『311明日』について、「武闘派野郎サーガ」について、そして「震災と映画」について、意見を述べられた。ふと気づくと、予定時間をかなり超過していた。最後に手を挙げて発言されたのは、初老の男性だった。同心円状に配置されたベンチの一番外周のあたりに坐っておられた方である。
「一言でも喋って帰らないと、なんだか具合が悪くなりそうなので、ひとに語ることでもないのかもしれませんが、少しだけ話してみたいと思います。映画は去年の九月に観ました。ほんとうは今日の二度目も観たかったんです。一年間が過ぎて、同じ映画をどう見る自分がいるのか確かめたかったんですが、仕事のために来られませんでした。とても残念です。 一年前に見た時のことを思い出すと、作り手たちと似通った感情を持っていたのだという気がします。戸惑いとか迷いとか、もしかしたら照れのようなものとか、あるいは妙な力みとか、そのような感情を、映像を見ながら作り手と共有していた、そんな気がします。ある意味、作る側も見る側も、すごく無理をしている、ある種の無理をしている、それを映画というものを通して共有していた。先ほど、ついていけない、追いつけない感覚、ということを仰った方がいましたが、そういう感覚を私も持ちました。けれども、こういうものを観ようとしている自分って何なんだろう、というのが、ずっと自分の中で引っかかっていて、それはどこかで、震災というものと向き合う自分を確認したい、それを言葉にしていきたい、いろんな感情を通して、真面目腐っていえば、自分を見つめていきたい、みたいなところがあったのだと思います。 先ほど、作り手としての内的な必然性、切実さ���いう話がありました。それだけではなくて、私たち観る側、オーディエンスにも、観る側の必然性ってものがあると思うんです。それは自分にとって何なのだろう、とずっと問いかけながら、『なみのおと』とか『測量技師たち』とか、色んな映画を震災後、観てきました。どうして観るんだろうかと自分に問うてみると、それはやっぱり、震災と自分との距離感を推し量りかねてるんですよね、ずっと。あれから一年半も経っても、一年半しか経ってないっていう言い方もあるかもしれませんが、そこに答えを見つけかねている。たまたま被災地にいるということで、何かを清算できない自分を抱えたままでいる。 冨永さんの今日の映画も、正直いって全然理解できないんです。でも、理解できないから投げ出してしまうのではなくて、わからない自分も大切にしたいな、というか。何かを清算できない、震災との距離感をはかりかねている、ずっと戸惑ったままの自分っていうものを、そのままちょっと抱えていきたいというか。変にわかりたくない、わかったつもりになりたくない、という気持ち。だからきっとこの先もずっと、自分は冨永さんの作る映画を観ていくのだろうと思います」
こうして「シネマてつがくカフェ『震災と映画』」は終了した。最後の男性の言葉に、私は深く感じ入っていた。彼は答えを必死で探しているのだが、それは見つからない。答えはなかなか得られない。そしてどうやらそんなものはないのだろうということにも、彼は薄々(最初から?)感づいていることだろう。それでも彼は探すことを止めることはないし、止められない。東京から来た若造の映画監督たちがこしらえた映画を見たって、さっぱりわからない。だがこのわからなさは、単純な理解や了解の問題や、世代や時代の差異に還元出来るようなこととは、どこか違っている。どうしてこいつらは、よりにもよって、この機会に、こんな折に、こんな映画を、誰かに頼まれたわけでもないのにわざわざ自力で撮って、ここ仙台まで持ってきたのか。何の責任も関係もありはしないのに、どうしてギリギリまで編集や音声の調整を行ない、一台のクルマに同乗して、ボスである冨永昌敬が自ら運転して、東京から数時間を費やして、せんだいメディアテークにやってきたのか。ほんとうにさっぱりわからない。だが確かに、そういうことがあったからこそ、自分は今、ここでこうやって喋っているのだ。正直言って全然わからない。だが、わかったつもりにもなりたくない、そう語っているのだ。 19。「フタバ」から遠く離れて
『フタバから遠く離れて』は、『Big River』『谷中暮色』など、これまではもっぱら劇映画を撮ってきた舩橋淳監督が、はじめて発表した長篇ドキュメンタリー映画である(もっとも彼はニューヨークを拠点として主にテレビ用のドキュメンタリー作品は数多く作っている)。フタバとは福島県双葉町のこと。同町には東京電力福島第一原子力発電所の5号機と6号機があり、更に7号機と8号機の招致も進んでいた。二〇一一年三月一一日、1号機の水素爆発によって、双葉町は全面立ち入り禁止の警戒区域に指定され、一四二三人の町民全員が、埼玉県の旧騎西高校へと避難し、現在も同地での生活を余儀なくされている。原発事故によって、ひとつの町が丸ごと移転したのは、被災地でたった一件、フタバだけである。この映画は双葉町民たちの「以後」の生活を、舩橋監督が九ヶ月間にわたって記録したものである。 この映画の題名には複数の意味が込められていると私は思う。ま��空間的な側面から述べると、ここには少なくとも三つの「遠く離れて」がある。まず第一に無論のこと、それは福島県双葉町と埼玉県旧騎西町(現在の加須市)を隔てる約250kmもの物理的な距離のことである。否応無しに故郷から引き離され、途方も無い距離を抱え込まされた双葉町のひとびとの境遇を、この言葉は表している。だがそれだけではない。映画で「から遠く離れて」と聞いて、すぐに思い出されるのは、言うまでもなく『ベトナムから遠く離れて』である。ジャン=リュック・ゴダール、アラン・レネ、クロード・ルルーシュ、ウィリアム・クライン、ヨリス・イヴェンス、アニエス・ヴァルダの六名の監督がベトナム戦争をテーマに撮り上げた一九六七年のオムニバス作品。“Loin du Vietnam”という原題には、不毛で悲惨な戦いの続くベトナムと映画作家たちとのあいだに横たわる或る絶対的/絶望的な距離(それは具体的なものだけではなく、非=当事者性とでも呼ぶべき認識ともかかわっている)と、その距離を越えて発言しようとする意志とが共に表現されている。舩橋監督もまた、フタバから遠く離れてある、そうあらざるを得ない自分を絶えず確認しつつ、それでも/それゆえにカメラを構えて撮り続けたのに違いない。彼は広島の被爆二世であると映画の資料には記されているが、そのことがこの作品の動機と関係あるのかないのかは、実のところ本質的な問題ではない。そうではなく、長くNYに住み、現在は東京で暮らす彼が、フタバとの距離をしかと自覚しつつも、距離を何らかの仕方で縮めようとするのではなく(それは結局、どこまでいっても不可能なことだ)、むしろ距離を丸ごと受け止めることによって、この映画を完成させた、ということが重要なのだ。それは報道や記録という行為にかかわる責務の意識というよりも、こう言ってよければ、本能や衝動といったものに属している。何者としての本能や衝動なのかと問われたら、ドキュメンタリー作家としての、映画監督としての、表現者としての、ひととしての、と答えよう。したがって「遠く離れて」の第二の意味とは、舩橋淳の立つ場所を指している。そして第三に、それはこの映画の観客が意識する距離のことでもある。この作品は、東京・渋谷のミニシアターでロードショー公開された。ある場所を定点観測したドキュメンタリー映画が、そこから遠く離れた場所で赤の他人たちによって観られるということ。観客に、彼ら彼女らがスクリーンを見据えている渋谷の映画館と、そこに映っている埼玉の廃校となった高校と、そこに映っているひとびとが引き剥がされてある福島県双葉町、その二重となった途方もない距離をどうにかして実感させること。それは安易な共感や憐憫の発動によっては果たされない(むしろそれは真逆に振れるだけだろう)。フタバから遠く離れて映画を観ている、言ってしまえばただそれだけの者たちに、如何にしてその距離を受け止めさせられるのか。 遠く離れてあるのは空間だけではない。時間的な距離もまた、そこには複層となって横たわっている。映画とは常に過去の缶詰であり、昔にしか行けない、しかも傍観することしか出来ない、いわば一種の欠陥タイムマシンの機能を有している。映画を観るたびに、そこではあの日ある場所で現実にあったこと(それはドキュメンタリーでもフィクションでも同じことである)が何度でも繰り返される。そして必然的に、撮影されることで反復再生可能とされた過去の時間と現在との時間的距離は、刻々と開いてゆくことになる。この映画が「二〇一一年三月一一日以後」の約九ヶ月を描いていることは既に触れたが、それだけの期間にわたり撮影され記録されたフッテージが、編集作業を経て一本の映画として完成し渋谷の映画館で公開されたのは「二〇一二年十月十三日」のことである。ここにある十九ヶ月余という時間。『フタバから遠く離れて』に記録された時間は、永遠にこの内にある。そしてそれは、常にその時々の現在において再生されることによって撮られた過去の時間から、しかしそこにいつまでも同じ時間が佇んでいることでその都度の現在からも、どんどん遠く離れてゆく。今後幾度となく上映されることになるだろう未来の時間の中で、この映画に留められた過去の或る時間は、そのままであり続けることによってこそ、その意味を変えてゆくのだ。 実際のところ、現時点でも、双葉町のひとびとが故郷に戻れる時期はおろか、それがいつかは可能であるのかどうかさえわかっていない。埼玉県への町ごとの避難を決定し主導した双葉町の井戸川克隆町長は、映画の中で名前と肩書きのテロップと共に登場する最初の人物であり、国と東電に極めて 厳しい態度で臨む首長として報道メディアにもたびたび取り上げられている方だが、彼が旧騎西高校内に移転している町役場の仮の町長室(そこはおそらく校長室だったのだろう)で、地図や資料を示しつつ淡々と語る双葉町の歴史は、日本の原子力行政が抱える問題の縮図である(この映画の英語題名は“Nuclear Nation”)。七〇年代、福島第一原子力発電所の5号機6号機を迎え入れることによって巨額の「原発マネー」が入り込み、「福島のチベット」とも呼ばれた農業の脆弱と過疎による税収の低下に伴う困窮から一時救われ、ハコ物やインフラ整備などを次々と行なうなど繁栄したが、その後は原発を抱え続けることで得られる固定資産税も年々減少し、二〇〇七年には財政破綻目前となってしまう。新たに町長となった井戸川氏は、国からの交付金と新たな固定資産税以外に町を救う手立てはないと決意し、二〇〇二年の東電によるトラブル隠しがきっかけで長年棚上げされていた7号機8号機の誘致を決定、それは事故が起こる一ヶ月後には着工されることになっていた。つまり明確な原発推進派だった井戸川町長は、しかし今では、それはすべて間違いだったのだと、原発の功と罪を較べてみるならば、罪の方が圧倒的に多かったのだと語る。 映画の後半には、全国原子力発電所所在市町村協議会の事故後初の会合の模様も描かれる。当時経済産業大臣だった海江田万里が挨拶に立ち、すぐに公務のためだと言って退席、次いでマイクを握った細野豪志内閣府特命担当大臣(当時)も発言を終えるやいなや退席という光景には唖然とするしかない。関係省庁の席の前列がほとんど空席となった異様な状態で発言に立った井戸川町長が「なぜこのような思いをしなくてはならないのか、はっきり言って悔しい」と語り出し、被爆検査さえ遅々として進まない現状を訴え、やがて静かに怒りを爆発させる場面は、ネットやテレビでも伝えられた。なぜ自分らの家に住めなくなってしまったのか、悔しい。映画のラスト近く、次の字幕が映し出される。「2011年12月、日本政府は、福島第一原子力発電所が冷温停止状態に達し、事故は収束したと発表」「さらに放射性廃棄物の中間貯蔵施設を双葉郡内に設置する計画を打ち出した。除染が進まないかぎり、町へは5年以上帰還できないといわれている」。 二〇一二年十月十五日、井戸川町長は、いわき市東田町の福島地方法務局勿来出張所跡地に双葉町の役場機能を移す方針を町議会臨時会で明らかにした。年内にも仮庁舎建設に着工し、二〇一三年三月までには移転する計画だという。だが、関東地方に避難している町民も多いことから、旧騎西高校の避難所は当面継続するとのことである。十月十八日には、旧騎西高校の双葉町役場を長浜博行環境大臣と園田康博副大臣が訪問し、井戸川町長に就任の挨拶と意見交換を行なった。町からは十一項目に及ぶ要望書が手渡されたが、長浜環境相は「持ち帰って検討させて下さい」とだけ述べて、具体的な内容については言及しなかったという。かくのごとく状況は推移している。『フタバから遠く離れて』と「今日」との距離は、一日一日広がってゆく。その距離を測定し続けること。 舩橋監督は、映画のプレスシートに寄せた文章にこう書いている。
この映画は、避難民の時間を描いている。1日や1週間のことではない、延々とつづく原発避難。今回の原発事故で失われたのは、土地、不動産、仕事…金で賠償できる物ばかりではない。人の繋がり、風土、郷土と歴史、という無形の財産も吹き飛んでしまった。それに対する償いは、あいにく誰も用意していない。用意できるものでもない。 そして、僕たちはその福島で作られた電気を使いつづけてきた。無意識に、加害者の側に立ってしまっていた。いや我々は東電じゃないんだから、加害者じゃない、というかもしれない。本当にそうなのか。地方に危険な原発を背負わせる政府を支えてきたのは、誰なのか。そんな犠牲のシステムに依存して、電気を使ってきたのは誰なのか。 いま僕たちの当事者意識が問われている。
避難民の時間。フタバから遠く離れて生きるひとびとの姿は、当然ながら一通りではない。それぞれの家庭が抱える事情や問題、補償の現状、将来への展望などによって、双葉町民の「距離」の認識は異なるし、それはまさに時間とともに変化してゆく。映画はそうした違いもつぶさに描いている。校舎の入口に飾られた七夕の短冊に幼い手書きの文字で「ふたばに帰りたいです」などとあるのを見ると胸が詰まるが、後半では、避難所生活からマンション暮らしとなった老夫婦が、もう双葉に戻るつもりはない。戻れないだろうし、たとえ戻れたとしても、今より生活が良くなるとは思えない。それに、もうこちらの生活に慣れてしまったのだ、と語ったりもする。二〇一一年七月中旬に東京・日比谷公園で行なわれた抗議デモのシーンでは、数十人の避難民たちが「双葉を返せ!」「俺たちは双葉に帰るぞ!」などと叫びながら路上を練り歩き、最後は自民党本部前でのほとんど戯画的というしかない陳情の場面となる。デモ隊の人たちが必死で訴えているのに、通り一遍の笑顔と握手、空疎な言葉によってしか応じようとしない自民党代議士たちの不気味さ。映画の製作日誌を基にした書籍『フタバから遠く離れてーー避難所からみた原発と日本社会』の中で、舩橋監督はこのデモの直後、抗議に参加した知り合いの女性に「事故がまだ収束しない中で、政府にどうやって双葉を返して欲しい、と思うのですか?」と率直な質問をぶつけてみたと書いている。それに対する女性の答えはこういうものだ。
「あたしらだって、知ってるわよ、帰れないって。今度一時帰宅があるけど、行っても家の中ぐちゃぐちゃで何か持ってこようって気にもならないと思う。あそこに行ったら、もう戻れないだろうなって思う。それはわかっててやってるのよ……無駄だってわかってやってるのよ」
もちろん双葉に帰る願いが永久にかなわないと決まっているわけではないし、その望みを諦めてしまったわけでもないだろう。だがおそらくはもう「帰れない」と、だからデモをしても「無駄」だとわかっていながら、頭の中ではそう認識していながら、故郷を返せ、故郷に帰りたいと、声を上げずにはいられない、そうせずにはどうにもやり切れないという気持ち。この叫びと、もう帰らない、帰らなくてもいい、という発言は、正反対のようだが、どちらも或るひとつの出来事、誰一人として望んだわけではない出来事を端緒としている。「遠く離れて」を自ら選んだのではないという点で、双葉のひとびとは全員が同じ条件に属している。そこから先が異なるのは当たり前である。そこから先しか彼らは選択の余地がないのだから。だからむしろそのような個々の選択を強いられるという事に悲劇があるのである。フタバから遠く離れて、あなたはどうしますか? この問いこそが悲劇なのだ。 『フタバから遠く離れて』は、森達也他の『311』とも、松林要樹の『相馬看花ーー第一部 奪われた土地の記憶』とも、まったく違う感触を持ったドキュメンタリー映画である。『311』の賛否両論をものともせぬ突撃精神も、『相馬看花』の詩的とも思える叙述も、この映画にはない。あるのは対象に対する適切な、きわめて適切な「距離」感である。この「距離」は先に述べておいたように複層的なものである。舩橋監督は『フタバから遠く離れてーー避難所からみた原発と日本社会』で、次のように書いている。
震災後、多くの映像ディレクターが東北に向かった。何かを撮らなければいけないという使命感、もしくは義務感に駆られてキャメラを手にした人がほとんどではないだろうか。告白すると、私も同じように感じ、気仙沼や南三陸町へ訪れもした。何かを撮らなければいけないという衝動ばかりだったのだが何をどう撮ってよいのか、正直わからなかった。地震で無惨に崩壊した家々を写す者、津波に呑まれた死体を写す者、ガイガーカウンターをカメラの前にかざし、どれだけの高い値か興奮して話す者など、さまざまな震災映像があった。しかし、私のケースでいうと、「未曾有の大災害のものすごい映像」を見せることに抵抗があった。車からレンズを突きだして、トラッキングショットで荒野をなめてゆくのは、何も知らない部外者による物見遊山以外の何ものでもないと思った。「見せたもん勝ち」という感性にいかに抗うかが、震災ドキュメンタリーの肝だろうと考えたのだ。
作品名は書かれていないが、これはおそらく『311』への批判でもあるだろう。これに続く記述で、舩橋淳は故・佐藤真監督のドキュメンタリー論に触れ、佐藤による「ジャーナリズム=言語情報として要約できる映像」と「ドキュメンタリー=言語情報でまとめられないもの」という定義と分類を自分も踏襲したいと述べたのち、だが実際にはジャーナリズム的なドキュメンタリーやドキュメンタリー的なジャーナリズムも数多く存在するし、実のところは前者が大勢を占めているのが現状である、しかし自分はジャーナリズム的ではないドキュメンタリー映画を志向すると書いている。映像の力に頼り切るのでもなく、言語化の誘惑になびくのでもない、映画であるがゆえの剰余や冗長性を武器とすること。だが同時に映画であるからこその制約や有限性も大切にすること。その結果『フタバから遠く離れて』は、けっして怒りを露わにすることなく「怒り」を表現し得た、すぐれた「ドキュメンタリー映画」となった。 十月十四日、日曜日の夜、私はオーディトリウム渋谷における『フタバから遠く離れて』上映後トークショーのゲストに招かれて、舩橋淳監督と話した。初対面だった。公開翌日である。観客は十数名だった。トークの前に帰った観客もいただろう。この日の昼間は井戸川克隆町長と双葉町の方々がゲストだったので、そちらは盛況だったのかもしれない。私の人気がないだけかもしれない。六月二十四日、日曜日の午後、私は同じ映画館で『相馬看花』の松林要樹監督とも話した。このときも観客の数は少なかった。やはり私のせいなのかもしれない。だが私は、舩橋淳の文章にあった「当事者」という言葉を、そして「遠く離れて」ということ、「距離」ということを、考えざるを得ない。考え込まざるを得ない。
20。『希望の国』のエクソダス
『希望の国』は、古谷実の十年前の原作を「震災以後」に設定し直して撮り上げた傑作『ヒミズ』に続く、園子温監督による「以後の映画」第二弾である。福島第一原発の事故が未だ真の収束には至っていない今から数年後、架空の「長島県」(長崎+広島+福島)で、ふたたび大規模な原発事故が起こる、という設定の下、或る家族の物語が描かれる。 『ヒミズ』は震災以前からの企画だったが、舞台を被災地にすることによって、紛れもないアクチュアリティと切実さを獲得すると共に、物議を醸しもした。物議は園監督の専売特許とも言えるが、これまでの監督人生を回想した書物『非道に生きる』の中で、彼は「震災直後に被災地を映像に収めること」の是非を多くの人から問われたこと、罪悪感は感じないのかという反応があったと述べてから、こう書いている。
しかし僕が感じていたのは罪悪感ではなく、緊張感に近いものでした。目の前に広がるあまりにも悲惨な情景に、現実的な既視感が生まれ始めた今となっては、それを自分と無関係な場所として見ることはできない。
この「現実的な既視感」は、舩橋淳のいう「当事者意識」と一続きのものだろう。『ヒミズ』の冒頭は瓦礫の山が延々と続く長回し、文字通りの荒野をなめてゆくトラッキングショットである。それはけっして確信や自信をもってやれたことではなかっただろう。だが、園監督は被災したスタッフの実家や親戚の家を撮らせてもらった際、意外な声を聞く。
そこで僕が聞いたのは想像していたのとまったく違う言葉でした。「片付けられてしまう前に記録を残してもらってよかった」。さらに1年後に同じ場所で聞いたのは「『いまだに津波の映像を流したりすると、思い出す��らやめてほしい』と言う人たちは、忘れても大丈夫な人たちなんだ」という意見でした。
空間的な距離は他人事という感覚をどうしたって強めるし、時間的な距離は忘却のツールとして作用する。この二重の距離を埋めるためのひとつの道具として、たとえば映画というものはある。距離はどこまでも開いていくだろうが、それでもそれを測ることが出来るということには、なにがしかの意味がある筈だ。そう思わなければ、そこにカメラを向けることは出来なかったに違いない。
大事な人を亡くし、直後に大きな被害を受けた人たちは、その現実を忘れたくても忘れようがないと思います。かつて家があった場所は更地になり、やがて国が買い取ってセメントが入り、永遠に住めない土地になるかもしれない。自分が住んでいた愛する土地を記録に残しておきたいし、人々の記憶にも留めてもらいたい。被災された方がそう思うのは自然ではないでしょうか。 「思い出すからやめてくれ」というのは、被災の映像を見なければ思い出さないということでもある。被災地ではなく、たとえば東京で報道を見て、そう言う人もいる。しかし本当に被災者は、自分は被災者だと声高に叫ぶ人ではないのではないか。僕はそう思いました。10年後、20年後と歳月が経った後に『ヒミズ』を見た人が「やっぱり、あのとき撮ってくれてよかった」と言ってくれることを願っています。
こうして『ヒミズ』を完成させた園監督は、しかしこれでは終われない、と思ったのだという。前作では「震災」を間接的にしか描き得なかった。次はそこでは語れなかった「原発事故」を、正面切って取り上げる。『希望の国』は、このような強い動機によって生み出されることになった。それはしかし、相当な難産であったという。この問題を扱うということだけで、映画への出資を尻込みする者が多く、なかなか製作資金が集まらなかったのだ。しかしなんとか映画は出来上がった。そして『希望の国』は『ヒミズ』と、いや、過去の園子温の映画のどれとも似ていない新たな作品となった。映画のシナリオと製作日誌と後日譚とを合体させた、かなりユニークな書物『希望の国』に、園監督はこう書き付ける。
映画は、ゆっくりと撮れば良いものが撮れるわけではない。一瞬の内に気持ちのまま撮る時もある。 被災地の感情を撮りたいと思っていた。 報道が記録なら映画は記憶。 報道やドキュメンタリーが「真実の記録」なら、「情感を記録する」装置が映画。情感をカメラに記憶させたいと思った。
佐藤真=舩橋淳が示した「ジャーナリズム」と「ドキュメンタリー」に加えて、園子温による「フィクション」としての映画の定義が、ここには端的に述べられている。だが「情感を記録する」とは、間違っても(時に園監督が誤解されがちなように)いたずらにエモーショナルでスキャンダラスなだけの、いわゆるセンセーショナリズムを意味してはいない。『非道に生きる』で彼は「震災直後に被災の当事者が何度も思ったのは「寒い」だったろうし、その最中は寒すぎて「この寒さの原因は東電のせいだ、けしからん」なんて論理的なことを考えている暇はなかったと思うのです。出来事の追想ではなく、出来事の真っただ中にいるときの気持ちや情感を、貧弱な言葉でもいいからそれで綴ること、それがドラマ映画にあるべきスタンスだと思います」と述べている。 では『希望の国』は、どんな物語なのか。長島県大原町で酪農を営む小野泰彦と、認知症を患うその妻・智恵子、父親の仕事を手伝う息子の洋一と妻のいずみの四人が主人公である。ある日、マグニチュード8.3の巨大地震がとつぜん襲い、大原町内にあった原発が事故を起こす。この経緯はすべてが現実に福島で起きたことの再現である。原発から半径20キロ圏内が避難区域に指定され、小野家はギリギリでその範囲には入らなかったが、道を一本隔てた隣家は避難を強いられる。かねてから原発の安全性に疑念を抱いていた泰彦はガイガーカウンターを出し、洋一夫妻にここから遠くに逃げろと命令する。父親を愛する洋一は最初は嫌がるが、いずみが妊娠していることがわかり、息子夫婦はオオハラから遠く離れた町で暮らし始める。いずみは泰彦から貰った原発関連の本を読み、医者からも恐ろしい真実を聞かされることで放射能への不安を募らせ、宇宙服で外出するノイローゼ状態に陥る。一方、泰彦と智恵子は静かな生活を続けようとするが、強制退避命令と牛の殺処分命令が届き、遂に泰彦は或る決意をする。 こんな物語のどこが『希望の国』なのかと思うことだろう。誰もが引っかかる「希望」という言葉の含意を、なぜこの題名を付けたのかを、園監督はさまざまな機会に繰り返し説明している。きっかけはやはり『ヒミズ』だった。
(『ヒミズ』の取材で)「絶望に勝ったのではなく、希望に負けた」と僕は何度も言いました。絶望的な状況で「参りました」と白旗を上げる、敗北宣言です。普段は「希望なんてクソくらえ」と思って生きていても、水も食べ物も酸素もなくなって、落ちるところまで落ちたときに、「仕方がないんだ。希望が欲しくなっちゃったんだよ」と言ってしまうようなもの。
だが「それは、やさしい面をした希望ではなく、とても残酷な希望です」とも園監督は言う。「それは「負けた」というネガティヴな表現でしか言えないのです」。『希望の国』は、最初は『大地のうた』という仮タイトルを持っていたという。言うまでもなくサタジット・レイの名作と同じ題名である。園監督はまず、被災地に何度も長期間赴き、現地のひとびとへの取材を行なった。無論、希望などという言葉を被せられるような話はまったくと言っていいほどなかった。当初は現実と地続きの話にするつもりだったが、複数の土地で何人もの被災者から聞いたエピソードをバラバラのまま提示するのは不可能と判断し、架空の町を設定することにした。だがシナリオはなかなか進まなかった。自分が撮ろうとしている映画に確信が持てなかった。そんな折、二〇一二年元旦の早朝、南相馬に居た園子温は、ふと思い立って、20キロ圏内の柵を乗り越えて、海へと向かった。初日の出を見ようと思ったのだ。そして啓示の瞬間が訪れた。
真っ赤な、真っ赤な初日の出でした。こんなに美しい太陽を見たことがない。そう思うくらい感動しました。昨年、人々を襲った津波を生み出した「張本人」のあの海から静かに立ちのぼる朝日。その真っ赤な美しさを息を殺して見つめているうちに、放射性物質をいっぱいに含んだこの大地に到来した新しい息吹を感じ取るようになり、力一杯呼吸をしました。その瞬間、そうだ、『希望の国』というタイトルの映画が作れるぞ!と思ったのです。このタイトルにしたのは、たくさんの論理的な理由を超えて、これが一番です。 『希望の国』と言いながらも、僕は「これが希望だ」と提示するつもりはありません。この映画に描かれたものを希望だと思えるならそう捉えてもらっていいし、希望じゃないと思うのであればそれでいい。こちらから一方的に何かを「希望」だと言うのは強引です。僕は映画が「答え」を出してはダメだと思っています。映画は巨大な質問状です。「こうですよ」という回答を与えるものではないと思うのです。
この映画のタイトルにひとが否応なく抱くだろう疑問は、だから園監督によって敢て選び取られたものなのだ。「あの日の出こそ、僕に突きつけられた巨大な質問状でした。そして心の底で自分は答えを出した。その答えをあえて映画の中では口に出したりはしません」。園子温という映画作家には、とかく「確信犯」という評語が付きまとってきた。だが彼にかんしては、それは自分の正解を持っている者のことではない。彼は「僕は基本的に「想像力を羽ばたかせる」というのが嫌いなんです。なぜなら、想像する自分があてにならないから。「想像力」と言えば聞こえはいいけれど、それは断定とか独りよがりといった言葉にも置き換えられるものだと思います」とも言っている。或いはこうも。「僕の映画は主張しすぎだと言う人がよくいますがーーたしかに僕は映画の中でたくさんのことを「しゃべり」ますがーーそういう人は、僕がそもそも「答え」を用意していないことに気づいていないのです」。巨大な質問状としての映画。『希望の国』という作品が、なぜこのような物語なのか。こんな物語の映画が、なぜ『希望の国』という題名なのか。その答えはすべて観客に委ねられているのだ。 『トーキョードリフター』の監督、松江哲明は、園子温の『奇妙なサーカス』のメイキング映像や『夢の中へ』『紀子の食卓』の予告編を手掛けており、園監督とは公私ともに親しい人物である。彼は最近、映画評論家のモルモット吉田氏と共著で出した『園子温映画全研究1985ー2012』において、『ヒミズ』と『希望の国』について語っている。
松江 園さんが『ヒミズ』で「希望に負けた」という言い方をしましたが、すごく誠実だと思ったんですね。それで『希望の国』を観たときに、これは否定的な意味で捉えてほしくないんですけど、初めて園さんがフィクションに負けた映画だと思ったんです。あんなにノンフィクション至上主義を嫌って、「実在の事件は結末がわかっているからつまらない」と言っていた人が、今回の震災と原発事故に触れて、初めて自分のフィクションを捨てたと思いました。過剰なフィクションを入れ込むことでものを作ってきた人たちが、そんなことさえでき��いくらいに、現実に圧倒されてしまった。でもその態度は、とても誠実だと思いました。
いかにも松江哲明らしい、それ自体とても誠実な発言だと思う。もちろん園監督は「自分のフィクションを捨てた」とまでは思っていないだろうが、しかしノンフィクション(ドキュメンタリー)であれフィクションであれ、その厳格な定義にてらして、自分は常に完璧な整合性をもって対応していると断言する映画作家が居たとしたら、そんな者の方がずっと信頼に足らない。そうではなくて、迷いながら悩みながら、圧倒されたり負けたりしながら、それでも撮る、それでも作る、ということの中にしか、映画が現実と切り結ぶ術はないのだ。そしてこれは映画以外の芸術にかんしても同じである。 書物『希望の国』の末尾には、詩人でもある園監督が「クランクインの直前に書いた、二〇一一年最後の詩」が据え���れている。題名は「数」。この詩は、次のように始まる。
まずは何かを正確に数えなくてはならなかった。草が何本あったかでもいい。全部、数えろ。 花が、例えば花が、桜の花びらが何枚あったか。それが徒労に終わるわけない。まずは一センチメートルとか距離を決める。一つの距離の中の何かを数えなくてはならない。例えば一つの小学校とか、その中の一つの運動場とか、そこに咲いている桜が何本とか、その桜に何枚の花びらがあったとか、距離と数を確かめて、匂いに近づける。その距離の中の正確な数を調べれば匂いと同調する。たぶん俺達の嗅覚は、数を知っている。匂いには必ず数がある。 その町の人口が何人だとか、その小学校に何人いたか、とか、例えばその日のその時間に何匹の虫が、何匹の蝶が、何匹の芋虫が、いたか、をきっかり、調べるべきだ。俺の嗅ぐ匂いは詩だ。政府は詩を数字にきちんとしろ。
詩はまだ続く。私は強く揺さぶられている。園子温という表現者の凄みに、今更ながら瞠目せざるを得ない。「今度またきっとここに来るよという小学校の張り紙の、その今度とは、今から何日目かを数えねばならない」。数。数えること。計測の意志。そこに流れる紛れもない叙情。叙情を喰い破る強さ。ただの抵抗の身ぶりとは根本的に異なる勇気。「数値に出せないと政治家に言わせるな、数値で出せ、と訴えろ。全てを数えろと言え、数値で出せと言え」。そして園子温は、よく読め、彼は最後に、こう書いているのだ。
「膨大な数」という大雑把な死とか涙、苦しみを数値に表せないとしたら、何のための「文学」だろう。季節の中に埋もれてゆくものは数え上げることが出来ないと、政治が泣き言を言うのなら、芸術がやれ。一つでも正確な「一つ」を数えてみろ。
21。『言葉』
村川拓也は、毎秋都内で催されている舞台芸術祭「フェスティバル/トーキョー(F/T)」の二〇一一年公募プログラム(主催演目とは別に新進カンパニー向けにエントリー形式で行なわれている)として『ツァイトゲーバー』という作品を発表した。実際に介護の現場で働く男性が全身不随の障害者と過ごす一日を普段通りに淡々と再現する、基本的にはそれだけの内容なのだが、障害者の「フジイさん」を公演毎に観客席の女性から募って演じてもらうという特殊な趣向の一点によって(やらせは一切ないという)、意想外の卓抜にして深遠な劇的効果を上げることに成功していた。この作品はかなりの評判を呼び、まだ無名と言ってよかった村川拓也は一挙に注目されることになった。『ツァイトゲーバー』は二〇一二年九月にも東京都近代美術館で再演されている。 『言葉』は、今年の「F/T」の正式プログラムとして上演された、村川拓也の新作である。この夏、彼は出演者の前田愛美と工藤修三(彼は『ツァイトゲーバー』の「介護士」だった人物である)と一緒に被災地を一週間ほど廻った。各地ではバラバラに別れて行動し、各々が毎日平均六時間もあちこちを歩き続けながら、見たもの聞いたもの感じたこと考えたことなどをメモしていった。台本は、出演者二人のメモに記された膨大な「言葉」を村川が再構成することによって作られている。舞台にはマイクスタンドとスピーカー以外には何もない。工藤と前田はほぼ交互に、過去に自分自身が記した「言葉」を台詞として発話する。連続しているように思えるところもあるが、基本、二人の発話は断絶しており、対話を構成しない。ほとんど何も無い舞台上に「言葉」が響いてゆく。『言葉』は、言ってしまえばこれだけの作品である。前作と同じく、極めてシンプルな作りと言えるだろう。村川は、公演パンフに附されたインタビューの中で、「被災地に限ったことではないと思いますが、現地を訪ね、目の前の様々な印象を捕まえて言葉にしようと突き詰めて考えていくと、どんどん深みにはまっていく感じがあり、それを回避するために“歩き倒す”というような過酷な行程を敢て組みました。歩き疲れてヘトヘトになった身体と頭からは、シンプルで正直な言葉しか出て来ませんから」と語っている。実際、工藤と前田の「言葉」は、文字で書かれたものというよりも、その時その場で二人の脳裡に浮かんだとりとめの無い心象そのままであるかのように思える。青森から福島まで移動しながら、毎日毎日ただ只管歩き続ける中で書き留められた、被災地の今なお残る傷跡への素朴な驚きであるとか、ふと出くわした風景に突き動かされた想像、それだけでは何を意味しているのかよくわからない呟き、単なるぼやきとした思えないような一言、などなど。いったい何故、村川拓也は、このような方法を選んだのだろうか。同じインタビューで彼は、宮本常一からの影響について述べている(私は観ていないが、村川には『移動演劇 宮本常一への旅 地球4周分の歌』という作品もある)。宮本の著作に記録された「過去」の言葉を、現代に生きる人間が語ろうとする際、まず出て来るのは「喋れなさのリアリティー」ではないかと村川は言う。それは「過去」と「現在」のギャップそのものを提示するということである。
僕が以前創った作品はそこまで止まりだったかもしれません。でも、本当はもう少し違うことをやりたいと思っていました。それは、「過去」に書かれた言葉の、その時の情景をそのままダイレクトに舞台上で再生できないか、ということです。それは単に役者が役にのめり込んで喋れば達成されるものでは絶対にないと思いますし、ひょっとするとその言葉を使わない方が、その時の情景に迫れるのかもしれませんが、とにかくその「過去」に書かれた言葉の、その時の「現在」をどうやったら今の「現在」で再生できるかといったことを探究したい。(略)過去を現在との距離から語るのではなく、過去の現在性を再生させるという、演劇ではほとんど不可能な領域に向かっているのかもしれません。
実は『言葉』には、対になる作品が存在している。映像作家でもある村川が今年完成した中編映画『沖へ』。甚大な被害を受けた宮城県本吉郡南三陸町で、江戸時代から続く互助会「伊里前契約会」の会長を務める千葉正海氏の日々を追ったドキュメンタリーである。村川はカメラを携えて千葉氏とその家族の生活に寄り添い、畏まったインタビューというよりも単なる会話のようにして被写体に話し掛け、千葉氏も気さくに村川の問いに答えてゆく。取り戻しようのない災禍を経て日常を維持しようとする被災地の人々の姿を等身大で捉えた、魅力的なドキュメンタリー映画である。船で沖へ出ていき、当のこの海が襲われた津波について語る千葉氏。クルマに乗って帰り際、不意に村川を呼び止め、カーステで曲を聴かせながら「これ何かわかる?」などと尋ね、まったく唐突にCAROLの想い出を語り出す千葉氏。東京新橋での講演会の帰りにカラオケで熱唱する千葉氏。そんな何でもない場面の数々が不思議な感動を催させる。それは間違いなく、監督である村川拓也と被写体である千葉正海との距離感の適度な縮まりに由るものだと思える。しかしこの映画を制作しながら、村川は一種のジレンマに苦しんでいたという。
『沖へ』の撮影のためのインタビュー中、僕は「全然会話ができていない」という感覚にずっと囚われていた。被災地では色んな方と喋り、また基本的には皆さんよく喋るのですが、その言葉に行き先がない感じがしたんですね。切れ切れでどこにも届かない、行き場のない言葉が、津波で更地になった所にビッシリ生い茂る夏草のように充満し、溜まっていく。そんなイメージを再現できるような対話や言葉を抽出し、舞台上に乗せることで、観客の中にも無数の言葉が生まれ、むさ苦しいほど充満していくような作品を創りたいと思っています。
やはりインタビューから引いた。こうして村川拓也は『言葉』を創ったわけである。ところで、先には触れなかったが、この舞台には工藤修三と前田愛美以外にも出演者が居る。それはいずれも黒服に身を包んだ(工藤と前田は限りなく普段着に近い服装である)手話通訳の女性たちである。女性たち、と書いたが、彼女たちは三名居り、交替で現れて工藤と前田の「言葉」を翻訳する。最初は舞台脇で控え目に立っているのだが、最後に登場した通訳の女性は、出演者二名が上手と下手の端に座って語っているのに、ただひとり真ん中に立って手話で語り出す。ここに至って観客は、彼女たちが単に公演の為に用意された通訳ではなく、紛れもない「出演者」としてそこに居るのだということに気づかされる。だから『言葉』のキャストは、二名ではなく五名なのだ。手話を解さない私には、彼女たちの身ぶりは(もちろん多少は推察できるところはあるとしても)文字通りの「身ぶり」でしかない。だがそれは「言葉」なのだ。その言葉が私たちにはわからないが、それが言葉であることは知っている。むろん通訳なのだから、今しがた彼か彼女が話した言葉が手話に翻訳されているのだろう。それは知っている。だがそれは「発話」ではない。そこには音がない。私を含む観客のほとんどにとって、それはただ見ることしか許されない「言葉」なのである。 『ツァイトゲーバー』でも、全身麻痺の「フジイさん」役の観客に最初に願い事を尋ね、本番中に三度、任意のタイミングで、その願い事を「台詞」として呟かせる、という「演出」が、驚くべき効果を発揮していた。「介護士」はその言葉に一切反応しない。それは彼が普段からそうしているのか、何を言っているのか聞き取れなかったのか、それともそもそも「フジイさん」の心中で呟かれただけだったのか、観客には判別出来ない。しかし「介護士」役である工藤修三にも、「フジイさん」がいつ、どのタイミングで「台詞」を発するのかは予期出来ないのだから、その「言葉」はいつも不意撃ちのように舞台と客席に響くことになるのだ。 聞こえる/聞かれるべき音として発される言葉と、聞こえない/聞かれない言葉との、矛盾と照応。この意味で、『言葉』は明確に『ツァイトゲーバー』の問題意識を引き継いでいる。手話通訳の「出演者」化によって浮き上がってくるのは、確かに発された言葉が聞かれておらず、発されていないかもしれない言葉が聞こえる、という前作が炙り出した事態に対して、聞こえていえないかもしれないが確かに発されている言葉の実在、である。このことは、この舞台のもうひとつの仕掛け、舞台前に客席に向けてマイクが数本立てられており、無言の場面になると観客の立てる咳や身じろぎが集音され、増幅されてスピーカーから返されるという、やはりシンプルだが秀抜な趣向にも込められている。 被災地に生きる者の「行き場のない言葉」を、そこから遠く離れた舞台上で、当事者ではない「出演者」の声によって響かせる、ということは、結局のところ、不可能なことである。これは「演劇」の限界なのかもしれない。だが、だからこそ「過去の現在性を再生させる」ために、村川拓也は『言葉』の、一見すると迂遠とも思える手法を選択したのだ。彼と工藤、前田の旅は、どこまでいっても(言葉は悪いが)物見遊山の謗りを免れないものではある。『言葉』上演後、映画監督の想田和弘を迎えて行なわれたアフタートークの冒頭、村川自身が「作品を作るために被災地に行った」と語っていた。どれだけ真摯な想いが彼の内にあり、どれほどの震撼がそこに待っていたのだとしても、それはやはり、そうなのだ。だからむしろ問題は、そのことに背を向けない、ということだったのだろう。二人の「出演者」によってメモに書き付けられた「言葉」は、被災地の、被災者の「言葉」ではない。そうではない、そうではありえない、そうなりえないという歴然たる事実を上演すること、それが『言葉』がしていることであると思われる。その「言葉」たちにはーーこう言ってしまってよければーー然程の深い意味も価値もない。ただしかし、そこでは「「過去」に書かれた言葉の、その時の「現在」をどうやったら今の「現在」で再生できるか」が、無骨なまでに真正直に問われている。そしてそれは、けっして完全なる「非当事者」ではあり得ない筈なのに(それは舩橋淳も言っていたことだ)、しかし「当事者」を自ら標榜することはけっして許され���しない者が、如何にして「当事者」の「言葉」を通訳出来るのか、という取り組みでもあるのだ。 だからこそ、一個の作品としての『言葉』には不満がないわけではない。中盤に、突然スクリーンが降りてきて、ランディ・ニューマンのペーソス溢れる軽やかな歌声をバックに、旅行時のスナップショットがスライドショーで映写される場面があるのだが、旅のドキュメントとしての要素を残しておきたいという意図は汲めるとしても、全体の中では小休止というか、緊張感を緩める結果になっていることは否めない。また、先に述べたように「言葉」は殆どランダムに並べられているのだが、ラストに至って、現地で催される花火大会で離散していた一行が落ち合おうとする展開となる。事情あってそれは果たせないのだが、前田の「言葉」は花火の模様を描写する。そしてラストの一言は「あれ、今揺れた?」。この「言葉」によって『言葉』という一編の芝居が終われたということはあるだろうし、絶妙な余韻が残されたことも確かだ。それにこれらは全てがもともとメモにあった「言葉」である。そこには作為も虚構もない。だが私には、少々上手に終わり過ぎてしまっているように思えた。村川拓也が排したいと思っている(と私が思う)ドラマツルギー的な感覚が入り込んでいるように思ってしまったのだ。もっといつ終わったのかわからないような「言葉」でもよかったのではないか。極論かもしれないが、『言葉』の「言葉」それ自体は、含蓄や情動を持たない、いや、持てない、ということにこそ意味があるのだと思われるからである。
22。「言葉」
『言葉』を含む本年度の「フェスティバル/トーキョー」のテーマは「ことばの彼方へ」である。舞台芸術において言葉=言語は特異な位置を占めている。戯曲やテクストは重要だし、しばしば最初に書かれるものだが、読めば済むのなら上演の必然はなくなってしまう。だが、かといって「言葉」が二義的な要素というわけではない。内外含めて十数本から成るプログラムは、総体として「言葉」と「舞台」をめぐるアクチュアルな問題系を形成していた。その中でも呼び物は、劇作家としても名高いオーストリアのノーベル賞作家エルフリーデ・イェリネクが東日本大震災と原発事故をテーマに書き下ろした『光のない。』と『光のない II〜エピローグ?』の上演である。今年のF/Tは、他にイェリネク解釈の第一人者といわれるドイツのヨッシ・ヴィーラー演出による『レヒニッツ(皆殺しの天使)』、公募プログラムで重力/Noteによる『雲。家。』と、さながらイェリネク祭の様相を呈していた。 村川拓也は「行き場のない言葉が、津波で更地になった所にビッシリ生い茂る夏草のように充満し、溜まっていく」と述べていたが、この表現はそのままイェリネクにも当て嵌まる。だがそのあり方は正反対かもしれない。『ピアニスト』『したい気分』『死者の子供たち』といった小説では、引用と参照に満ちた高度に知的な企みの内に遊び心溢れる闊達さやポストモダン文学的なサービス精神(?)も披露するイェリネクだが、とりわけ戯曲は難解さをもって知られている。彼女の劇言語は(やはりオーストリアの小説家、劇作家トーマス・ベルンハルトと同じく)たとえ複数の登場人物が配されていたとしても本質的にはモノローグ的であり、断言と韜晦が奇妙に共存する台詞は強固に閉じた印象を与えつつ、同時に異様な、バロック的と呼んでもいいような過剰な意味性へと開かれてもいる。たとえばそれは、こんな具合である。
ああ、わたしにはあなたの声がほとんど聞こえない、どうにかしてほしい。あなたの声を響かせてほしい。わたしはわたしを聞きたくない、あなたにわたしをかき消してほしい。ただ、少し前から思っている、わたしはわたしも聞こえない、耳を制御盤にあて、つかもうとしているのに、音を。あなたもそのくらいはできるはず! もっと強く弾いてほしい、難しいはずはない。ここは喚き声ばかり、わたしにはわからない。畜舎? 設備の停止? 設備が停止したならどうして叫ぶのだろう。力づくで押さえているのか。自動停止? だがそれはすべて静まることを意味しない。力は消えることができない。なにかが消えることなど決してない、まだ叫んでいる、怪物の腹の中で、蝉のように、喰われても猫の腹で叫びつづける蝉のように。 (「光のない。」、林立騎訳)
イェリネクはこの度の上演に当たって日本の観客に向けて書かれたテクストにおいて、自分の生活は「ほとんど日本に囲まれているようなもの」だと述べる。なにしろ庭も日本風に竹を植えているのだ。彼女は竹を「地下茎=リゾーム」と言い換え、自らの言葉の様態を重ね合わせてみせる。そして歌舞伎については詳しくないと断わりつつ、たとえば「長いモノローグや技巧的に歪めた声」という点で自分の作風は歌舞伎と似ていなくもないのだと述べる。歌舞伎には「様式化された人工美の規則」がある。「観客は作品を見て読み解き、なにがなにを意味するか知るのでしょう。わたしの作品にそれは不要です。言わばわたしの作品は、過剰に規定されています、わたしは開かれた余地を残しません、竹が隙間を残さず、土があればどこまでも広がるように。竹は必ず防根シートで囲まれます、しかしそれを越え出ることさえあります。なんらかの感覚が、なんらかの意味が、わたしの地下茎を越え出ることはあるでしょうか。あってほしいと思います」。実際のところ、何が主題の芯に据えられているのか、どこから作品が書き出されているのか、という意味では、イェリネクの戯曲は常におそろしく具体的である。即物的とさえ言ってもよい。『光のない。』の「光」とは、福島第一原子力発電所の事故によって施行された計画停電のせいで一時的に関東地方から失われた、松江哲明監督の『トーキョー・ドリフター』に不在の形で映し出されていた光=明かりのことであり、と同時に原発の発電システムそれ自体のことでもあり、ピカドンのピカのことでもある。イェリネクはケルンの劇場から、より抽象的なテーマ(「デモクラシーの黄昏」)で委嘱されたものだったというが、彼女は敢てこの題材を選び、追ってホームページで全文を公開した。そして震災ー事故から一年と一日が経った二〇一二年三月十二日に、「エピローグ?」と題された続編を、やはりHPで発表した。 イェリネクは自分の「言葉」は「過剰に規定されて」いると言う。それは「規則」に従った読解や意味の抽出を必要としていない。言い換えるなら、それは完膚なきまでの誤解/誤読の余地の無さ、ということだろう。だがしかし、だからといってそれは明解であるわけではない。むしろ逆である。竹。夏草。繁茂。どこまでも即物的で直截的足ろうとする意志こそが、見る間に視界のすべてを覆い尽くしてしまうほどに「言葉」を生い茂らせてゆく。イェリネクの文学の全てに言えることだが、膨大な文学的/歴史的引用や参照が多重露光のごとく入り込み、即物性と斥き合うように、テクストを濃密に、息苦しいほどに濃密にしてゆく。二本の戯曲はこうして書かれた。では、日本の演出家たちは、そのようなイェリネクの「言葉」を、どう受け止めたのか? 『光のないII〜エピローグ?』から語ろう。何故なら私が鑑賞したのが、こちらが先だったからである。構成、演出はPort Bの高山明。ここ数年のF/Tの常連アーティストである彼は、劇場という固定されたトポスから脱して、インターネットや移動手段を駆使したさまざまな方法論で、「日本」というコンテクストにおける「ポストドラマ演劇」を試行している。今回の公演は、このようなものだった。事前にエントリを済ませた観客は、一人ずつ新橋の駅前にある「ニュー新橋ビル」から街へと送り出される。持たされるのは十数枚のポストカードが入ったビニールケースと短波ラジオ。ポストカードには次に向かう場所への経路と地図が印刷されている。観客はそれをガイドに新橋駅周辺に設置された「舞台」を経巡る。指定されたポイントに着いたら、観客はカードに記載された周波数に短波ラジオを合わせる。すると、その都度異なる若い女性の声が(それらは被災地の高校生たちの声である)「エピローグ?』のテクストを朗読している声が聞こえてくるのである。ポイントは雑居ビルの一室であったり、小公園だったり、路上だったり、パチンコ屋の店先であったり、空き地であったりする。ポストカードを裏返すと、土屋伸一による被災地の人々や原発作業員たちの写真があしらわれている。一時間ほどの「観劇」を終えて、ふたたび出発点に戻ってくると、一階上でラストシーンを体験してくださいと言われる。そこはビルの最上階である。同じポストカードが大量にある。雲間から光が射し込む青空の写真。一枚お取りくださいとある。裏返すと、そこにはこう記されている。「ニュー新橋ビルから135km、福島第一原子力発電所から91km」。距離。計測。そこにある光。そのイメージ。
真実の言葉は一つとして、言われないままにはしなかった、と彼らは言う、彼らが見たはずはない。目撃証言としてわたしは言う、真実の言葉はどれも、言われないままになっている。容器の水は足りてない、もういい! わたしたちの運命は他の誰でもないわたしたちだけのもの、だが容器の中のあの水が、そう、鉄琴は溶け落ちた、多くの人間が焼け出されたように、だが活発な活動は止まない、ひどく加熱され燃えている、わたしたちの都市の近く、わたしたちは一見無傷な家畜、あの水がわたしたちの運命をもたらすだろう。わたしたちはそれをつかめない。わたしたちのまわりには水しかない、だがそれはまた別の水。さまざまな水! (「エピローグ?[光のない II]、林立騎訳)
延々と続くモノローグ。短波ラジオから聞こえるイェリネクを読む音声は、それぞれのポイントから離れると次第に遠ざかっていき、やがてホワイトノイズに呑み込まれてしまう。私は移動中もイヤホンを耳から外さずにいたので、聴覚は視覚をあっけなく凌駕して、新橋の雑然とした町並みは鈍いノイズに塗れ、そのままの姿で刻々と変容していった。ポイントの幾つかには被災地を如実に想起させるセットもあったのだが、私にはむしろ何でもない新橋の夜(夜だったのだが)の風景の方が「舞台」のように見えたし、誤解を恐れずに言えば、短波ラジオが発するホワイトノイズも、イェリネクのテクストの一部であるかのように思えた。それはとても不思議な体験だった。公演パンフに掲載された土屋伸一との対談の中で、高山明はこう述べている。「福島のある風景を東京のなんの文脈も共有していない空間に再構成した結果は変に決まってます。でも、その不協和音の中にこそ、自分が福島にいないこと、今東京にいるということ、その距離がはっきり見えて来るんじゃないか。演劇を作る時にも観る時にも、感情移入はつきものですが、でも今は、それよりも、僕らの前に現実にある距離を測り、感じることの方が重要なんじゃないのかな」。 「エピローグ?」の末尾には参考文献(?)として、ソポクレース「アンティゴネー」と共に、次の一文が添えられている。「多くの、多くの報道を読んだ」。引きこもり的な生活を続けているというイェリネクは、インターネット経由でそれらを読んでから(読んだから)書き始めた。そうして書かれたドイツ語は、林立騎によって極めてマシーナリーに日本語へと翻訳され、いわき総合高校演劇部の女子部員たちによって朗読され録音された。ここにも複数の距離と複数の翻訳が介在している。高山は対談で、こんなことも言っている。
ウィーンの郊外にツベンテンドルフ原発という、一度も使われないまま、国民投票で廃炉になった発電所があるんです。そこに行くと、「未来のエネルギー」と書かれた垂れ幕がかかったままで、時間が止まっちゃって、未来もフリーズしたような奇妙な感覚に捕らわれる。あの感じはもしかしたら、福島の避難区域の、蒲団がはがれたままの、突然誰もいなくなってしまった部屋と似ているんじゃないかと想像します。僕が『光のないII』を読んで、いちばん表現したい、掴みたいと思ったのは、そういう、時間が失調してしまうような感覚です。それは、原発が欲しいと思って、それが実現して、でも津波で壊れてしまって、今度は原発を止めたいっていう別の願いを持つことになって……と、時間が錯綜して振り出しに戻ったかと思えば、全く別の場所に出ていたりするような感覚でもあります。
「それは〈福島/フクシマ〉が、もはや言葉だけのものとして、終結させられつつあることへの批判でもありますが、それ以後全く違う時間が始まったという意味でもあるんじゃないか」。フクシマから遠く離れて。その時間的空間的距離の自覚。『光のない II〜エピローグ?』の舞台が新橋であったことは恣意的な選択だったかもしれないが(そういえば村川拓也の『言葉』で千葉正海氏が赴いたのも新橋だった)、それは福島や被災地であってはならなかった。そこから絶対的絶望的に遠隔された場所でなくてはならなかった。それはエルフリーデ・イェリネクが、ウィーンの自宅のコンピュータがアクセスするインターネットやテレビ、報道媒体などから得た映像と文字の情報のみを頼りにテクストを書いた、という事実と対応している。しかし同時に、絶対的で絶望的な距離が、安全で無責任な傍観者であることを保証するわけではない、ということも高山は勿論わかっている。これはフィクションではない。別の世界の出来事ではない。われわれは、残念なことに、同じひとつの世界にしか居ない、イェリネクに筆を執らせたのも、遠く離れたアジアの島国で起こったことが、自分の生きる同じ現実の内にある、という実感によるものだったのではないか。「距離」の測定は、連続性の把握でもあるのだから。 観劇を終えて、ニュー新橋ビルの屋上に出てみた。ちょうど歓楽街が賑やかになってくる時間だ。ポストカードを夜空にかざして、私はこう考えた。ここから135km離れた場所の、或る日の空に、この雲と光があった。そして、そこから91km離れた場所に、福島第一原子力発電所がある。
『光のない。』は、京都に拠点を置く劇団、地点を率いる三浦基が演出を担当した。彼は自ら劇作は行なわず、チェーホフの四大戯曲を始め、既存の劇作品を極めて独創的な解釈で上演することによって国際的な注目を集めてきた。また近年は、太田省吾、ジャン・ジュネ、アントナン・アルトー、太宰治などのテクストを再構成した野心的な舞台を次々と発表している。今回も同様で、イェリネクのテクストは役柄にかんする指定のないAとBが交互に語るというものだが、三浦はその全部は採用せず、彼自身の取捨選択によって六割ほどに編集している。そして戯曲では二つの声となっている台詞を、地点の五人の俳優に分散して演じさせている。このことについて、三浦は二→五という処理に意味があるわけではないと語っている。単に彼が信頼を寄せる役者の数が目下のところ五名なのだ(つまり現在の地点は基本いかなる人数の戯曲であっても五人で演じられる)。 地点の演劇をはじめて観る者は、何よりもまず、役者たちの異様な発話にしたたか驚かされることになる。時に「地点語」などと評されるそれは、戯曲に書かれた台詞を、いわゆる自然な口調とは完全に真逆の、シラブルの切断や語の強調、イントネーションの付け方などによって、徹底的に異化してしまう。それは確かに日本語である筈なのに、まるで外国語のように聞こえる。意味性を解体/変容し、異なる次元へと絶えずパラフレーズしてゆくこの手法こそ、演出家三浦基の最大の発明であり、武器でもある。その手腕は今回も遺憾なく発揮されており、私がこれまでに観た地点の公演の中でも、圧倒的な高みに至っていた。それは戯曲に書かれた「言葉」を舞台上に響く「音声」へとメタモルフォーズする。イェリネクの、それ自体過剰なまでに濃密なテクストを、役者の身体によって加圧し、彼らの声を通して煮詰め、何か更に奇怪な、だがおそるべき生々しさを放つものに仕立て上げている。 だが、これだけならば、言ってしまえばいつもの地点である。今回は、そこに厄介な前提が纏わりついている。言うまでもなくそれはエルフリーデ・イェリネクに『光のない。』というテクストを書かせた具体的現実的な出来事のことである。この作品を演出することは、なかば必然的にこの出来事に対する何らかの意見表明を意味してしまう。幸いなことに、この点にも鋭敏な三浦は、公演パンフに附された「演出ノート」において、まず政治と政治性を分割して、自分が問題にしているのは「政治性という普段からちりちりとくすぶっているよくわからない人間の性」の方だと述べる。
政治性とは関係性と言ってもよい。劇は関係性によって成り立つ。誰との? ロミオとジュリエットとのではない。イェリネクは、わたしとあなたとのでもないと言っている。わたしはあなたであり、わたしたちでありあなたたちだと一見、ふざけたことを言っている。イェリネク作品での主語に「わたしたち」が頻出するのは、政治性を問うた結果である。つまりイェリネクが書くのは、物語ではなくわたしたちに起こった「出来事」についてなのだ。残念ながら、震災があった。それに伴う原発事故があった。
そしてこうも述べる。「この劇が、みなさんに反原発を訴えるはずはないし、そんなつもりは毛頭ない」。誤解のないよう言い添えておくが、三浦が言っているのは、悪しき芸術至上主義の標榜ではないし、日和見主義でもない。「政治」は行動とメッセージだが、「政治性」は思考と内省である。そして芸術は、演劇は、後者を追求すべき営み/試みなのだ。 ところで『光のない。』の達成に貢献しているのは、演出家三浦基と地点の俳優たちばかりではない。今回はそこに新たな才能が加わっている。音楽監督を務めた作曲家の三輪眞弘である。私は個人的に、この起用には感嘆を禁じ得なかった。なんと見事な人選だろうと舌を巻いたものである。ひとつには、三輪はコンピュータを駆使した、いわゆるアルゴリズミック・コンポジ���ョンの研鑽を経て、演算もしくはその遂行が生身の身体(それはプロフェッショナルな楽器演奏者であることもあれば、ただの素人であることもある)によって行なわれる「逆シミュレーション音楽」という独自のアイデアに辿り着き、近年めざましい作曲活動を継続しているのだが、そのユニーク極まるアプローチは、そういえば確かに地点と相通じるものがある、と思えたからだが、もうひとつは他でもない、三輪眞弘が「中部電力芸術宣言」の起草者であったからである。
いついかなる時でも電気が必ず供給され続けることを前提として、人類が未来を考えるようになってから、ほぼ半世紀が経った。この前提は、近現代の、テクノロジーによって生み出された数々の地球的規模の危機はテクノロジーによってでしか解決できないと考える思想、すなわちひとつの「信仰」の全面化を意味すると同時に、人々が自らの責任と子供達の未来を考えることが、そのまま「今よりもさらにテクノロジーを進歩させること」へと回収される、まったく新しい時代を産み出した。我々はこの状況を、厳然たる事実として認めつつも、この事実に対して自覚的かつ批判的であるために、人類史におけるこのような発展段階を「電気文明」と名付け、そこから生まれる様々な視聴覚及び演算装置による創作一般を「装置を伴う/による表現」と呼ぶことにする。
と始まり、「確認しよう。なぜ電気なのか?・・それは、電気エネルギーがすでに我々の社会の、思考の、そして身体の一部であるからに他ならない」と結ばれるこの「宣言」は、二〇〇九年八月二十五日には一旦脱稿されていたが、一年半のあいだ公表されることはなく、二〇一一年三月十三日に突然、三輪のホームページ上にアップされた。東日本大震災と原発事故を受けての公開であったことは疑いない。「電気文明」の時代における「芸術」と「音楽」について、一読する限りでは突拍子もない主張が述べられているようにも思われるこの宣言文は、しかしながら検討すべき内容を多々有している。そしてここにこそ、三輪眞弘がエルフリーデ・イェリネクと、三浦基と、『光のない。』というテクストと切り結ぶ最大のクリティカル・ポイントが示されていると思われる。
23。「電力芸術宣言」のジレンマ
三輪眞弘が「中部電力芸術宣言」によって俎上にあげようとしたもの、それは「テクノロジー」と「音楽/芸術」の関係性をめぐる本質的な問題、そしてその前提を成す「テクノロジー」と「(人類の)生」の問題である。三輪はこの「宣言」において、至って即物的に、今日の「テクノロジー」を、その駆動力たる「電力」がなくては維持も進歩も最早あり得ないものと定義する。そして「人類史におけるこのような発展段階を「電気文明」と名付け、そこから生まれる様々な視聴覚及び演算装置による創作一般を「装置を伴う/による表現」と呼ぶ」。この呼称は、つまり「芸術」の別名である。
その際、活動の、いや、そもそも人間生存の大前提となった電力供給に我々は常に意識的であらねばならない。一体、電気がどのような物理的特性において、どこから、どのようにして提供されているのか? その実態を把握せずに我々はもはやこの世界を決して語り得ないにもかかわらず、人々はそのことの持つ意味についてあまりに無自覚である。例えば、日本では現在10の電力会社によって(家庭用は)100V/200VAC電力が供給されており、その電力網は県境を越えた「地方」という単位に対応している。つまり地方文化と電力会社はほぼ1対1の対応関係にあるという事実、さらに、東日本と西日本というふたつの領域が50Hzと60Hzの二種類の交流周波数によって峻別されているという事実は、「地方文化の差異」を、それとは本来まったく無関係なはずの、電力各社の電力網区分が代表していることでもある。さらに、それら各地方電力会社が供給する電力の起源に我々は注目する。すなわち、それが太陽由来の電気なのか、そうではないのか?
そして三輪は「太陽エネルギーに由来しない電気はすべて、人間が「資源」という名の下に自然環境に対して行う地球規模の略奪行為として今後断固拒否する」と述べる。過激な主張と言っていいだろう。だが無論「水力、風力、太陽光発電等の太陽由来の電力は容認せざるを得ない」し、現実として「太陽由来の電力」とそれ以外の「電力」を峻別することはわれわれには困難である。そこで差し当たり次のような立場が表明されることになる。「以上のような自覚に基づき、我々はまず、発起人の在住する中部電力が供給する電気によって電力芸術活動を開始し、「装置を伴う/による表現」を電力会社名として名付けられた各地方文化において運動を展開させていくことを目標とする」。こうして「中部電力芸術」が「宣言」されることになったわけである。
言うまでもなく、電気の地域性によって作品が変わることはない。しかし、西洋音楽において、たとえば現代の管弦楽作品が、世界中の都市に遍在するオーケストラという、地域文化の固有性を越えたグローバル・スタンダードを前提として作曲家独自の表現を可能にしていることと同様、グローバル化社会における究極の前提であるユニバーサルな電気を我々がどのように捉える/扱いうるかこそが今、我々に問われているのである。それは地域文化の固有性や作家の独自性を、現在考え得るもっともニュートラルな条件の下に映し出す、ひとつの鏡となるに違いない。
自分の「音楽」が何によって生かされているのか、自分が何によって生かされているのか、そのことにもっと意識的にならなくてはならない。「宣言」の末尾に、三輪は「中部電力芸術家の目標、条件、他」として、以下のような要項を挙げている。
- 電気文明における電気を利用した「装置を伴う/による表現」を電力芸術と呼ぶ。 - 中部電力芸術家は電力芸術を実践する。 - 中部電力芸術家は、浜岡原子力発電所を含む火力、水力発電によって中部電力から供給される60Hz/100VAC電力によって活動を行う。 - ただし、中部電力芸術家は、非太陽由来の電力、すなわち火力発電及び、物質それ自体からエネルギーを収奪する究極の技術としての原子力発電に対して常に批判的である。 - 中部電力芸術の趣旨に賛同する限り、他の電力文化圏(50Hz地方を含む)在住芸術家の、電力会社の壁を越えた積極的な参加を歓迎する。 - 中部電力芸術宣言は作曲家、松平頼暁氏の立ち会いのもと、湯浅譲二氏八十歳の誕生日に構想された後、坂本龍一氏の批判を受けて改訂された。
繰り返しておくが、この「中部電力芸術宣言」は、二〇〇九年八月二十五日には第一稿が書かれていた。従って三輪眞弘が、この特異と言っていい「宣言」を起草するにあたっての動機には、彼自身の生活や信念といった個人的な条件がかかわっていたのかもしれない(三輪は以前から、CD等のメディアに記録され流通することを本願とする「録音芸術」としての音楽ーー「録楽」と名付けられているーーの様態には鋭い疑問を呈していた)。だがそれはいったん開示されることなく封印され、二〇一一年三月十三日にはじめて公表された。どうしてこのタイミングだったのかを問う必要はないだろう。重要なことは、これが「以前」に書かれた「以後の言説」であったという事実である。そして私たちは、いまだに「東京電力芸術宣言」を持ってはいない。 では『光のない。』の音楽監督として三輪眞弘は何をしたのか? 「電気文明」に拘束された「装置を伴う/による表現」=「芸術」=「音楽」。この等号を射抜くために、三輪は二つの戦略を採った。ひとつ目は、舞台中盤に役者全員がやおら互いの両腕に電極を装着したかと思うと、それぞれ鈴を持つ、そして電気ショックで不随意に手が動くことによって間歇的な音楽が奏でられる、というものである。それはつまり「電力芸術」としての「音楽」が暴力的な直截さによって表現された場面だった。もうひとつ、より重要であったのは、この作品に召喚された異様な「合唱隊」の存在である。舞台前方、左右にしつらえられた陥没に客���を背にして仰向けに横たわり、全員が両足の先しか見えない総勢十数人による混声コーラスは、意味のわかる歌詞=言葉をうたうことは一度としてなく、囁きや呟き、かすれた叫びやかそけき呻きのような声=音を発する。それら複数の音=声はランダムに聴こえるが、実は三輪眞弘の「逆シミュレーション音楽」の代表的な作品である「またりさま」の応用によって、合唱隊のメンバー自身が一種の演算装置となってリアルタイムで作曲=演奏されているのだ。作曲ー演奏ー出音に至るまで「電力」は一切関与していない。それは「電力」が途絶えても、「光のない」世界でも、生まれ/生きることの出来る音楽なのである。合唱隊の「声=音」は、地点の五人の俳優の、エルフリーデ・イェリネクによって書かれ林立騎によって日本語に翻訳され三浦基によって演出された「台詞=言葉」の発話と混在しながら、舞台空間を音響的に埋め尽くしていった。 三輪眞弘は「フェスティバル/トーキョー」のフリーペーパー「TOKYO/SCENE」No.1に「魔法の鏡 または、三浦基氏に宛てた『光のない。』の私的パラフレーズ」と題した長めのテクストを寄せている(「「中部電力芸術宣言」の続きとして」 という註釈が添えられている)。そこではイェリネクにも『光のない。』にも地点にも直接言及されることはないが、先にも触れた「音楽」と「録楽」の異なりについて、より詳しい思弁が述べられている。「魔法の鏡」とは、「この世」の営みを複製する「あの世」を可能にする「テクノロジー」のことを指している。
わたしは本当に音楽を聴きたいのか? わたしに音楽は必要なのか?……そうだ。「録楽」ではなく、「音楽」は決して「魔法の鏡」によって分身し、再現され、反復されることはない。 音楽は常に記号から逸脱するからだ。
私には、その奇妙と呼ぶしかない「合唱隊」の、意味性を欠いた、しかし同時に意味生成性が充満してもいる摩訶不思議なサウンドは、Port B『エピローグ?』の、あのFMラジオのホワイトノイズと似た機能を担わされていると思えた。ただし、ラジオは電池が切れたら、音はしなくなってしまう。ただし、ヒトは生命を失ったら、音がしなくなってしまう。「装置」と「人間」は、何によって生かされているか、の違いはあれど、何かによって生かされている、という点は同じである。そして結局のところ��電力」は、双方に深くコミットしている。『光のない。』にしても、光のない、電力のない空間での上演は、無論のこと不可能である。だから「電力芸術宣言」は、自ずからひどくアイロニカルなものにならざるを得ない。ここには明らかに、声を上げつつ口ごもっているような晦渋さがある。それは起草者の三輪眞弘自身、百も承知のことだろう。もしかすると、それが公開されなかった理由のひとつであったのかもしれない。だが、それでも敢て「宣言」する必要が、新たに生じたのである。とはいえ、アイロニーが解消されたわけではない。むしろそれはより深刻度を増し、強力な難問として我々の目の前に立ちはだかっている。「浜岡原子力発電所」という単語があるからといって、この「宣言」はストレートな「反原発/脱原発」を謳っているわけではない。そうであったらむしろ話は簡単だったろうが、そうであればここで検討するには値していない。何故ならば、ここにある紛れもないジレンマこそ「電力芸術宣言」の真の問題提起だと思われるからだ。 ところで、先の「魔法の鏡」は、こう結ばれている。
Lux aeterna luceat eis, Machina(機械よ、永遠の光を彼らの上に照らし給え)。しかし、わたしは祈れるのか? 光はどこから来るのか? 「彼ら」とは誰か? 被災地に置き去りにされた家畜たちのために。
「Lux aeterna luceat eis, Machina」とは、三輪眞弘が二〇一一年十月にサントリー芸術財団の委嘱作品として発表した『永遠の光…オーケストラとCDプレーヤーのための』のラテン語題名であり、本来はMachinaではなくDomine、すなわち「Lux aeterna luceat eis, Domine(主よ、永遠の光を彼らの上に照らし給え)」。グレゴリオ聖歌のレクイエムの一節である。
24。「アクチュアリティ」と「わたしたち」
オーストリアのウィーン在住で、日本には一度も来たことのない作家エルフリーデ・イェリネクが、東日本大震災と福島の原発事故にかんする「多くの、多くの報道を読んだ」ことによって、何ものかに突き動かされるようにして書いてしまった二つのテクスト。それらをそれぞれの方法で現実の舞台へとリアライズした高山明と三浦基という二人の演出家と、三浦に随伴した三輪眞弘という作曲家。彼らはいったい、何をしていたのか?……いや、こんな問い方はいかにも理由ありげでいささかみっともないが、しかしそろそろ、これまでここで私が書いてきたことの全部とかかわって、要するに彼ら(というのは彼ら彼女ら全員のことだ)は何をしているのか、何をしようとしているのか、あらためてじっくりと考えてみる必要があるように思う。たとえば三浦基は、前にも引用した『光のない。』の公演パンフレットの「演出ノート」に、次のように書いている。
リアリティという言葉は、いつの間にかアクチュアリティにすり替わってしまった。私のリアリティとみんなのリアリティなんてかわいい感覚ではもう駄目で、もっと大きな文脈を背負うべきという強制的な響きをもって私には聞こえる。「君にはアクチュアリティがないなぁ」と言われたらちょっと困る。「君にはリアリティがないなぁ」と言われたら、相手を睨むことができるだろう。つまり対話が始まる。が、どうもそんな対話は古いので人々は敬遠する。誰だがわからない立場で、アクチュアリティを武器に個をいち早く捨てる術を持った。
「私は、だからアクチュアリティと闘うつもりだ。口が裂けてもこの言葉を簡単には使わないようにしたいと思う」と続けておきながら、すぐさま三浦はこう述べる。「『光のない。』は、東日本大震災と福島の原発事故がテーマになっているアクチュアリティ満載の作品です。嘘です。イェリネクがこうしたテーマを選んだことがアクチュアリティなのではなく、この出来事に彼女が「わたしたち」の一員だと宣言したことが、アクチュアルなのである」。 確かに「アクチュアリティ」の一語は現在、以前の「リアリティ」に成り代わって、特権的な地位を占めているかに思える。それはほとんど一種のマジック・ワードと化していると言ってもよい。わたしたちはアクチュアリティに真摯に対峙し得ているか? わたしたちは如何にしてアクチュアルであり得るのか? この自問に「芸術」に携わる者たちはひとしなみに晒されている、そのように映る。だがそれがマジック・ワードであるということは、あたかもそれが口に出される/書き付けられるだけで魔法が成立してしまうかのような誤解と錯覚がまかり通っているということでもある。三浦が辛辣な語調で違和感を表明しているのはそのことだ。彼の言う「アクチュアリティを武器に個をいち早く捨てる術」の問題、つまり「アクチュアリティ」と「わたしたち」との相関が、ことによると事態をより不分明に、悪しき曖昧さに追いやっているということもあるのではないか。 「アクチュアリティを武器に個をいち早く捨てる術」とは、「わたし」が「わたしたち」に変換される回路のことである。イェリネクの戯曲には「わたしたち」という主語が頻出する。それは『雲。家。』に最も顕著だが(この作品には「わたしたち」しか登場しない)、『光のない。』『エピローグ?』でも多くの言葉が「わたしたち」によって語られる。それはたとえば、こんな具合である。
わたしたちはどうして沈黙するのか。わたしたちは正しくなかったのか。それはわたしたちの役に立ったのか。まったく、わたしたちは何も決められない、わたしたちは残らないから。別のなにかが残る。別のなにか! わたしたちが決めていたらわたしたちはわたしたちが今もつものをもたなかった。わたしたちはなにももたかなった、だがなにものでもないものをもつこともなかった。呼びかけに応えわたしたちはなにかを手に入れた。それがわたしたちみなを今ここから引き離す。どうすればわたしたちはわたしたちのあとに来る者たちのことを決められるだろう。だがもう誰も来ないのか。あれほど時間があったのに! (「光のない。」、林立騎訳)
『光のない。』には、ソポクレース「イクネウタイ」とルネ・ジラール「現実的なものの埋もれた声」からの引用がある。『エピローグ?』にも同じくソポクレースの「アンティゴネー」が参照されている。つまりイェリネクは彼女の他のテクストと同様、単一の「アクチュアリティ」へと還元され得るような「言葉」として二本の戯曲を書いているわけではない。それらは常に過剰なまでに多層である。従って、ここでの「わたしたち」もまた無数のレイヤーを成しているに違いないが、それでもやはり、これが他でもないわたしたちのことで(も)あると思わないわけにはいくまい。そして疑いなくイェリネクだって、そのつもりで書いているのである。とはいえ、ここにはおそらく或る種のギャップがある。それはイェリネク的な「わたしたち」とわたしたちの「わたしたち」の間に横たわる懸隔である。たとえば『雲。家。』であれば、そこでの「わたしたち」は第一義的には「ドイツ人」のことであると思われる。だが、それ自体が既に実は単数ではない。それは「ドイツ人」というカテゴリー以外の者を指していることもあるし、そもそも「わたしたちドイツ人」の内にレイヤーがあるのだ。つまり、さまざまな「ドイツ人」が居り、それらが入れ替わり立ち替わり「わたしたち」として語ってみせるのである。こうしてイェリネクの戯曲は、モノローグにしてポリローグという独特の様態を獲得することになる(それゆえ彼女の戯曲は「声」の数がキャストの数を規定しない)。『光のない。』『エピローグ?』でもそれは同じことで、たとえ「東日本大震災と福島の原発事故」がなければ書かれることはなかったのだとしても、二本はいずれもそのことだけに収斂/拘泥しているわけではない。そこで行なわれているのは、こう言ってよければ、もっと複雑且つ豊かな営みなのである。もちろん三浦基の言うように「この出来事に彼女が「わたしたち」の一員だと宣言したこと」は重要なことではある。けれども「わたしたち」を名乗ること、「わたしたち」の一員となるということは、常に「わたしたち」以外を措定すること、「わたしたち」ではない誰かを弾き出すことでもある。 たとえば私も批評文を書きながら、時として「私」を「私たち」「我々」などと書いてしまうことがある。これは私に限らず、フィクション以外の文章では散見される現象だろう。ここにはたぶん、素朴な心理学的考察が妥当する機制が働いているのだとも思われるが(独善的になることへの抵抗心と自信のなさ、その反転としての共感や同意の強要…)、それと共に無視することが出来ないのは、日本的と言ってよいかもしれぬ、同胞(無)意識というか、自ら進んで陥る同調圧力というか、複数形一人称で語ることに潜在する奇妙な安心感である。ここには明らかに「個をいち早く捨てる術」の効用のようなものがある。しかし、こうして選ばれた主語としての「わたしたち」には、イェリネク的な多数性が欠けている。それは幾つもの「わたし」が代入し得る可能態としての「わたしたち」ではなく、いわばただひとりの特権的主体を志向する「わたしたち」なのである。ここには罠がある。もちろん三浦基も高山明も、その演出において「わたしたち」をポリローグへと開くことを果敢に実践しているし、それは高いレヴェルで成功してもいる。だが「わたしたち」が「アクチュアリティ」という語のもとに彼らの試みを語ろうとする際、知らず知らずの内に、いつのまにか「罠」に嵌まってしまっていることがあるのではないだろうか? 三浦基が書いていたのは、このことだと思われる。 只の「わたし」が「わたしたち」を標榜することによって、或いは「わたしたち」から承認されることによって、やっとのことで獲得されるような「アクチュアリティ」とは、今ここにある「問題」から目を背けない覚悟や認識や勇気から、甘えた協調の構造や危険な他者排除へとたやすく転じかねないものである。「わたしたち」という呪文が「アクチュアリティ」というマジック・ワードを呼び寄せるだけだとしたら、誰にでも出来る簡単な魔法を使って、もうひとつの魔法を可能にしているだけのことではないのか。このような「わたしたち」は別の言葉にも言い換えられる。それは「当事者」という言葉である。
25。いわゆる「当事者性」について
「フェスティバル/トーキョー」の関連企画として行なわれた「F/Tシンポジウム」のパネルの第一部は「演劇における「当事者の時代」 」と題されていた。登壇者は高山明、村川拓也、『アンティゴネーの旅の記録とその上演』で参加したマレビトの会の松田正隆、写真家の畠山直哉、司会はパフォーミングアーツ・ジャーナリス���の岩城京子だった。二時間のあいだにさまざまな話題が出たが、私を含む聴衆の多くがもっとも感銘を受けたのは、ゲスト・スピーカーとして招かれた畠山直哉の発言だったのではないかと思う。 畠山氏は、岩手県陸前高田市気仙町の生まれである。二〇一一年三月十一日のあの時、彼は東京のスタジオに居た。その数日後、氏はオートバイを駆って郷里への旅を敢行する。実家に程近い気仙川周辺を長年にわたり撮影していた未発表の写真と、震災後の写真、「気仙川へ」と題された旅の道程を綴った文章を一冊に収めた『気仙川』は、個人的な感慨を極力排した無機質で形式的な写真作品によって国際的な評価を受けてきた畠山直哉の従来のイメージを大きく塗り替える、きわめて「私写真」的な作品集である。 「気仙川へ」は、このように書き出される。
何かが起こっている。いまここではない遠いところ、ほら懐かしいあの場所で、何かとてつもないことが起こっている。その様子がいま僕のいるところからでは、よく見えない。誰かが教えてくれるかもしれないと思って、少し期待して待っていたが、誰も何もしてくれなさそうだ。だから僕は自分で、それが見えるところまで動いて行くしかない。でも動きとは時間だ。あの場所にたどり着くまでには時間がかかる。おそらく数日。でも数日後、僕は見ているだろう。そしてすべてを理解しているだろう。僕の町が、家が、家族がどうなったのかを、僕は残らず理解しているだろう。だがそこへたどり着くまでの数日間、僕には何も見えないままだ。僕は何も知らないまま、進まなければならない。
道中、姉からの電話によって、行方の知れなかった母親が津波によって命を落としていたことを知らされた畠山氏は、二〇一一年三月十九日、亡き母と対面することになる。だが「気仙川へ」という文章は、その前日、彼がほんとうの意味で故郷へと辿り着く直前で終わっている。『気仙川』に刻まれた悲嘆は、アーティスト畠山直哉が長い年月をかけて培ってきた美学と倫理によって抑制されながらも、むしろそのことによってこそ、透明な痛ましさを放っている。 「F/Tシンポ」の「演劇における「当事者の時代」 」に畠山直哉が招かれた理由は、あまりにも明らかだろう。パネルの冒頭で、登壇者はそれぞれに「当事者(性)」にかんする立場表明をしたのだが、畠山氏は「この中では自分がいちばん「当事者」に近い存在ということになるのだろう」と語った。関西で生まれ育ち、自分の映画と演劇の取材で被災地を幾度か訪ねただけの村川拓也、同じく被災地出身でも在住でもない高山明、松田正隆と、当然ながら彼の意識/認識は根本的に異なっている。そしてこの座談会は終始、この差異に引き裂かれたままであったように私には思われた。 誤解なきように言い添えておくが、もちろん畠山氏自身は彼の「当事者性」に対して、ほぼ一貫して客観的足ろうと努めているように見えた。彼はけっして個人的な体験のみを軸に語ろうとはせず、著書『話す写真』で詳しく述べられている原理的な「写真」論に依って立ちつつ、率直な物言いで他の登壇者や「演劇」へのコメントを行なっていた。 問題は、にもかかわらず、つまり畠山直哉自身の意志と或る意味では無関係に、その発言の数々が、そこでの最も「当事者」と言える者によるものであることを、私たちの方が勝手に強調的に受け取ってしまうということである。たとえば畠山氏は「フェスティバル/トーキョー」のここ数年の傾向にも明確に現れている「ポストドラマ演劇」「ドキュメンタリー演劇」について、何故それほどまでにイリュージョンやスペクタクルを拒否しようとするのか、自分にはよくわからないと疑問を呈した。それは拒否というより断念ではないのか。旧来の良く出来た「劇」をこしらえられない才能や努力に乏しい者たちが、これ幸いと取りすがった方便ではないのか。どうしてよりによってわざわざ「震災」や「原発」を主題にして、フィクションとも呼べないような奇妙な「演劇」を作ろうとするのか。この指摘は非常に鋭い。実際、会場は一瞬、いっそう静まった気さえしたものである。畠山氏は疑いなく、アクチュアルな演劇に対するこのような批判意識を以前から抱いていたのだと思う。つまり彼が表明した疑念は「震災」とも「原発」とも関係はない。だがしかし、それでも彼の問いかけは、その場で「当事者」の濃度が一番高い者による言葉として響いてしまう。いうなれば「アクチュアリティ」による審判の声として聞かれてしまうのだ。繰り返すが、これは畠山氏の意志とはまったく別個の問題である。だが、ここには「当事者性」をめぐる厄介なパラドックスが露わになっていると私は思う。 「当事者」というマジック・ワードの困った所は、同じひとつのイシューについてでさえ、その線引きがまるっきり一様ではない、ということにある。「F/Tシンポ」の第二部は「演劇の言葉はどこにあるのか?」と題して、三浦基、三輪眞弘、林立騎、大澤真幸の四名を登壇者に迎え、私の司会で行なったが、その中でも「当事者性」は暫し話題となった。そこで大澤氏が「究極の当事者とは死者を置いて他には居ない」という意味の発言をしていた。その通りだと私も思う。しかし、だからこそ問題は「究極の当事者」である「死者たち」を除いた「当事者性」のグラデーションになってしまうのではないか。つまり、わたしとあなたの、彼と彼女の、どちらが、より「当事者」と呼べるのか、という問題である。『311』の森達也は、こう書いていた。
被災したわけではないし家族が津波で流されたわけではない。食べるものに困っているわけでもないし、寒さに凍える夜を過ごしているわけでもない。 つまり僕は非当事者なのだ。 ところが気分的には当事者になりかけている。最も悪いパターンだ。ならば現地に行くべきだと考えた。もちろん現地に行ったとしても、当事者になれるはずはない。でも非当事者には非当事者の役割がある。
冨永昌敬は「仙台短篇映画祭が中止になってしまっていたら、自分たちも被災することになってしまう」と語っていた。『フタバから遠く離れて』の舩橋淳は「いま僕たちの当事者意識が問われている」と書きつけた。園子温は「目の前に広がるあまりにも悲惨な情景に、現実的な既視感が生まれ始めた今となっては、それを自分と無関係な場所として見ることはできない」と書いていた。それぞれの、さまざまな、幾つもの「当事者性」が、ある。「わたし」は「当事者」なのか「非当事者」なのか? どの程度まで「当事者」であり、どのくらいそうではないのか? おそらくこんなことが言える。「わたしは当事者である」と述べても「わたしは当事者ではない」と述べても、やがて必ず「わたし」には違和感や不足感、そして森達也の言っていた、あの「後ろめたさ」が生じる。「当事者性」の相対比較に晒されるか、それとも他人事を決め込んだ謗りを受けるか。「わたしは当事者である(のではない)」と「わたしは当事者ではない(のではない)」。このまるで正反対のカッコ付きの否定辞が、語るや否や、必ずやってくる。それは具体的な何者かによって齎されるとは限らない。そうであることもあるが、たとえ誰からも何も言われなかったとしても、他ならぬ「わたし」自身が、すぐさま自問を開始し、否定辞を付け加え始めるのだ。 それは避けられない。避けようがない。「究極の当事者」が「死者」であるとしたら、もう一方で、この出来事とは完全に無関係な他人、すなわち「究極の非当事者」もまた、この世界にはひとりも存在していない。エルフリーデ・イェリネクに筆を執らせたのは、そんな遠く離れた、だがヒリヒリと肌を刺すような「当事者意識」であった筈だ。我々は皆、程度は違えど幾らかは「当事者」であり、と同時に、常に中途半端な「当事者」でしかあり得ない。要するに、これが真実である。だがそれでも、私たちはどうしても「当事者性」を問うことを止められない。誠実である者ほど、そうあろうとする者ほど、そうなってしまうのだ。そして自ら問うておきながら、そこに宿る「後ろめたさ」や疾しさ、やるせなさに堪え切れなくなり、「わたし」を「わたしたち」へと昇格させ、あの魔法、あの「個をいち早く捨てる術」によって、「アクチュアリティ」を獲得したと思い込もうとするのではあるまいか。 だが、私が「わたしは当事者なのか?」と問うた時、この問いを自らに向けて発してしまった時、ほんの僅かでもいい、踏み止まって考えてみなくてはならない。この問いは、本当はいったい誰が口にしているのか、と。それは確かに「わたし」であるには違いない。だが、では「わたし」の中の何者がそれを問うているのか。「究極の当事者」である「死者」か、延々と続くグラデーションのどこかに位置する相対的な「当事者」たちか、それとも「社会」とか「世間」などと呼ばれている何かか。それとも「あなた」、つまり自分自身なのか? 畠山直哉は、『気仙川』の「あとがきにかえて」の終わり近くに、こんなことを書いている。
今でも心ある人たちが発している「忘れるな」という呼びかけは、「震災という出来事を忘れるな」「被災者のことを忘れるな」「死者のことを忘れるな」という意味だけで発せられているのではない。あの時僕らの多くは、真剣におののいたり悩んだり反省したり、義憤に駆られたり他人を気遣ったりしたではないか。「忘れるな」とは、あの時の自分の心を、自分が「真実である」と理解したさまざまを「忘れるな」ということなのだ。
素朴な意見と断じる人もいるかもしれない。しかし私は、このくだりに二度出て来る「自分」という二文字こそが、何よりも大切なものであると、あらためて思う。それは「忘れるな」よりも、或る意味では重要だ。だがそれは「わたしたち」を拒絶して、単なる「わたし」に留まれ、などというエゴイズムの奨励では無論ない。私が「わたし」であることに堪えられないがゆえに「わたしたち」を目指したとしても、そこに待ち構えているのは「わたしたち」という名の単数でしかない。エルフリーデ・イェリネクのように、真の複数形で「わたしたち」と語り出すか、さもなくば「わたし」へと、ありうる限りの勇気を奮って、ふたたび立ち戻ること。「わたし」が「当事者」であり得るのは、究極的には「わたしであること」の他にはないのだから。これは詭弁ではない。私たちは、自分の心を、自分が「真実である」と理解したさまざまを、自分が自分であり自分でしかないという明白にして厳然たる事実を、もう一度、何度でも、思い出してみなくてはならない。
26。「わからなさ」を撮るということ
ひと月ほど間が開いてしまったが、年の初めに仙台に行ってきた。せんだいメディアテークで一月半ばまで催されていた志賀理江子の個展『螺旋海岸』を観るために、約四ヶ月ぶりに東北新幹線に乗った。昨年九月に「仙台短篇映画祭」に呼んでいただいた時、まだ開催前だったが既にチラシが置いてあり、そこにあしらわれた漆黒の中に浮かび上がる艶やかで謎めいたイメージに、強い興味をそそられた。これは時間をやりくりしてでも絶対に来ようと思った。そして予感した通り、展示はおそるべきものだった。 私は志賀理江子という写真家のことをほとんど知らなかった。まとまった数の作品を見たのはこれが初めてである。だからこそ、出会い頭の衝撃は過激なものだった。せんだいメディアテークの六階にある「ギャラリー4200」には、宮城県名取市北釜在住の志賀が、同地でこれまでに制作した243点もの写真が展示されていた。それほど広い空間ではないのだが、エレベーターを降りてまず驚いたのは、ディスプレイのされ方である。スペース中央の柱を軸に、文字通り螺旋状に膨大な写真が配されているのだが、それらは大半が大きく引き延ばされており、通常の写真展のようにシールドされてもおらず、まるで立て看板のように鬱蒼と切り立っている。キャプションは全く無い。確かに一番から九番まで、一応のゾーニングはされてあり、受付で写真家自身による説明文が附された場内配置図のような紙片を渡されるのだが、それ自体があまりにも謎めいていて、マップに振られた番号もあちこちに散らばっているので、順番通りに見て廻ることは難しく、またそれが真に望まれているのかどうかもわからない。いきなり気圧された私は結局、何度も場内をぐるぐると経巡��ながら、見落としている作品がまだ何処かに隠れているのではないかという奇妙な不安と緊張に絶えず支配されながら、小一時間ほどを掛けて、とりあえず(おそらくは)全ての写真を見終えたのだった。 志賀理江子は東北の出身ではない。彼女は一九八〇年に愛知県岡崎市で生まれた。ロンドン大学チェルシーカレッジ・オブ・アート卒業後、写真家として活動を始め、最初の作品集『Lilly』で第三三回木村伊兵衛写真賞を受賞した。以来、国内外を頻繁に移動しながら作品を創ってきた。彼女が北釜に居を構えたのは二〇〇八年のことである。その経緯については後で触れるが、まず端的に事実を記せば、彼女は二〇一一年三月十一日の地���と津波を北釜の地で体験した。津波によって、それまでに撮った写真の大半は失われてしまった。このことについても後述する。従って『螺旋海岸』の写真群は、実際には志賀理江子が「震災以後」に北釜で撮り上げた作品から成っている。しかしかといって、直截的にあの出来事が描かれてはいるわけではない。そこに写っているのは、『Lilly』や、その後に発表された写真集『CANARY』と共通する、志賀理江子独特の、徹底的に作り込まれた、こう言ってよければ、きわめてシアトリカルな写真である。たとえば、そこにあるのは、幾つもの正体不明の手が中空に横たわる子供を持ち上げて運びつつある様子であり、夜に映える草木とともに正装をしてこちらを見据える男性の姿であり、地面に横たわる銀色の宇宙服に包まれた何者かであり、砂浜に巨大な渦巻きが幾つも描かれている無人の光景であり、仲睦まじく腕を絡めて闇に立つ老夫婦の、男性の胸を切り株が貫いてるとしか見えない映像である。それらはいずれも奇異と呼んでいい幻想的なイメージであり、少なくとも日常的/現実的なものではまったくない。一言でいうなら『螺旋海岸』の写真群は、いわゆるドキュメント的な作品ではない。 写真家は、先のマップに附されたテキストに、次のように書いている。
写真のなかにいる人々はカメラを意識し、なにかを演じ続けています。 演じることは枠のなかからまったく違うところへ飛躍する行為です。 その姿は、日々の生活の様子を切り取ったものではなく、北釜の土地と一体化し、あらゆる物語を表象します。 つまり、写真のなかの身体には「土地」と「物語」が混在しており、後にこれらの写真を見た人に無意識に読み解かれていきます。
この文章には志賀理江子独自の写真観が凝縮されている。個展に合わせて出版された、彼女がせんだいメディアテークの(私も別の企画に参加した)「考えるテーブル」の一環として、個展の準備期間中に七回に分けて行なわれた連続レクチャーの採録を元にした『螺旋海岸|notebook』と、その他幾つかの資料やインタビュー記事などによれば、志賀は写真家としての出発点から、ドキュメント的要素にはほぼ関心がなかったようである。いや、精確に言うと、通常思われているようなスナップショット的アプローチや、場所や出来事を客観的/主観的な視座から「記録」するといったやり方では、「現実」や「世界」に対峙したことにはならない、と彼女は最初からわかっていた。『螺旋海岸/notebook』を繙くと、たぶんに身体的・生理的な感覚から生じたものであったろう違和感や確信を、彼女が多くの経験と学習によって深く煮詰めてきたことがわかる。私の考えでは、ここにはフィクションとドキュメンタリーの二項対立、或いは相互浸透という従来的な思考法を乗り越えるポテンシャルが隠されている。だが今は北釜のことに戻ろう。 志賀は二〇〇五年から機会を得て、仙台、オーストラリア、シンガポールの三箇所でアーティスト・イン・レジデンスとして制作を行ない、その成果を『CANARY』として刊行した。だが彼女自身、「一つひとつの写真を見ても、そこでなにが起こっているのかまったくわからなかった」。その「わからなさ」とは、彼女が十代を捧げたバレエを諦めてカメラを手にした瞬間から始まった「自分(私)」と「イメージ」との間に穿たれる「わからなさ」である。志賀はこの「わからなさ」ゆえに写真を撮るのだと言ってもいいのだが、だからといって彼女は、それをそのままにしておくことは出来ない。彼女は「イメージ」が抱える「わからなさ」と格闘し、それを咀嚼し、我有化しようとして、さまざまな試行錯誤をする過程で、すこぶる興味深いことだが、「言葉」を発見する。そこで彼女は『CANARY』の写真群を自ら見直し、問い直し、それらに「言葉」を付与した一種の姉妹篇『カナリア門』を発表する。それから志賀は、もう一度、東北に、宮城に赴き、そこに長く住んで、作品を制作しようと決意する。だが、なかなか適切な場所が見つからなかった。そこでふと、以前の滞在制作ではあまり立ち寄らなかった海岸の方に行ってみた。そして彼女は、北釜と呼ばれる土地に辿り着いた。
本当になんとなくという感じで、三陸のリアス式海岸、松島や塩龜、七ヶ浜、そして仙台港を抜けて、ひたすらに長い海岸に着いた。誰もいないんです。海と並行するように松林がだーっと広がり「ああ、いい場所だなぁ」って最初はぼんやり思った。そしてどんどん南に行くうちに、いままで訪れたことがない土地(「いままで訪れたことがない土地」に強調濁点)に私は来ているという確信めいた、胸が高鳴るような気持ちになったんです。探検するように周囲を歩き回っていたら、松林は夕日に照らされてむちゃくちゃ幻想的になっていった。とにかくこの場所にずっといたくなるような、やっとここに来られたような、私はここを探していたような……
北釜の海岸の松林に魅せられた志賀は、その足で突撃的に同地のひとびとに当たっていき、さまざまなハードルと手続きを経て、この場所に住まいとアトリエを構えることとなった。どうせ住むなら土地の行事や祭りを公式に撮影する「専属カメラマン」にならないかと言われ、よろこんで引き受けた。こうして彼女は北釜の人間となった。あらためて記すと、それは二〇〇八年の冬のことである。それから彼女は北釜のひとびとと触れ合いながら、少しずつ新たな創造へと歩み始める。だが、一足飛びに記せば、それから二年としばらくして、彼女は同地で地震に遭遇した。やってきた津波は、たくさんの物と人を押し流していった。『notebook』には、震災後まもなくして彼女が知人友人たちに送ったメールの文面が掲載されている。「四月五日 心配してくださったみなさまへ」と表題のついた文章の、前半部分を引用する。
私の住む集落(約三七〇名)では五三名が亡くなりました、現段階で七名はまだ見つかっていません。津波は自然のありのままの姿だったと思います。恐怖の限界を遥かに超えていました。だからあの恐怖の絶頂で息絶えて流されたたくさんの人のことを思うとなにも考えられなくなる。どんな苦しい思いで水にのまれて意識を失っていったのか、一人ひとりのことをどれだけ想っても届くことがないです。 * ただあの日一瞬だけ、時間、生、死、感情、物の価値などが崩壊して、そこにあったすべてが見渡す限り真っ平らになった。そして大雪が降って真っ暗な夜になりました。ラジオで沿岸部では数百人の遺体が見つかったと知り、ここから約八〇キロしか離れていない福島第一原発の事故の状況が繰り返し流れるなか、揺れつづける地面の上でいろいろなことを覚悟した。私は体がはち切れたようで、あらゆることに違和感を感じなかった。けっこうどうでもいいことが次々頭に浮かんできて、体とはこういうものかと思った。 * そしていま、あの均一な暗い夜を取り戻すことばかり考えて、二度と絶対に嫌だけど、でも同時にあの時間が体から消えてしまうのが怖いのです。
志賀は自宅とアトリエにあったハードディスクを津波に持ち去られてしまったが、北釜の集会場に行事を撮った二冊のアルバムが保管されていたことを思い出し、瓦礫の山となった集会場に赴き、それらを必死で探した。運良くアルバムは、「一冊は集会場付近から見つかり、後に北釜の人が見当もつかなかった場所からもう一冊を見つけてくれ」た。それから、瓦礫が撤去された集会場には、志賀の撮ったものだけではない、誰のものとも知れない、拾われた写真が、膨大に集められてくるようになった。「瓦礫に混じって落ちている写真に、なにか無視できない、拾わせてしまう力があるんだなと思いました。そう思わせるぐらい写真というのは風景のなかで目立つのです。いろいろなものが刷り込まれたあの小さな紙というのはぐーっと現実世界に異様に抗っている」。彼女のものらしい大きな写真があったよと言われて行ってみたら、展示で使ったプリントの塩水や泥と写真の薬剤が溶けて混じり、異様な臭いを発していたこともあった。やがて彼女は、写真の洗浄を始める。「おおよそ三万枚強の写真が集会場には集められていました。北釜は一〇七世帯で、一軒に約一〇〇〇枚ほどの写真があったと仮定したら、その約三割が発見され集会場に集められたと認識しています」。『notebook』には集会場を撮った写真も載っている。それはまるで部屋全体が祭壇のように見える。
津波で娘さんを亡くされたあるお母さんは、娘さんの写真を毎日集会場に探しに来ていました。家も流されてしまったから写真が一枚もない。私はその方と肩を並べて写真を探すうちに「彼女が探しているのは写真ではない、娘さんそのものなんだ」と猛烈に身に沁みた。彼女のなかで「娘の写真」が「写真」ではない次元にまで振り切れていたんです。写真はそこになにが写っていようがいまいが、写真であるだけで拾われましたが、その価値は「ただの紙切れ」から「自分の娘そのもの」にまで激しく変化する。その。触れ幅によって写真の価値のあり方を身をもって知らされた気がしました。
こうした体験は、志賀の写真観、彼女の「イメージ」論に、当然のことながら甚大な影響を与えた。それ以前から彼女は、北釜の老女から「遺影」を撮影してくれと請われ、躊躇いながらも初めてそれを行なった経験から、新たに「作品」を撮り始めるための手がかりを得ていた。そして今や、亡くなった「娘の写真」を「娘そのもの」と考えるひとがいる。彼女はかねてより自分の中にあった「無鉄砲な仮定」に或る確信を得る。すなわち写真の撮影は「過去現在未来の時間から解き放たれる空間のための儀式」なのだと。そして彼女は、のちに『螺旋海岸』と題されることになる個展のため、ふたたび撮影を始めた。写っているのは北釜の海岸、砂浜、松林。被写体となっているのは北釜の土地のひとびとである。だが、既に述べておいたように、それらはいずれも著しく非日常的、非現実的な風景となっている。志賀は北釜のひとびとにさまざまな、しばしばかなり奇妙と言ってよい依頼を行ない、ひとびとはよくはわからないまま、だがけっして不審がることはなく、それに快く応じていった。たとえば先に触れた「切り株」の作品の志賀による説明は、次のようなものである。
最近まで松くい虫の害に遭った松は被害の拡散を防ぐために切られていたので、松林には切り株がたくさんあるんです。土地の持ち主の方に「切り株を掘り起こしてみてもいいですか?」と聞いたら承諾してくれたので掘ってみた。砂地だから想像していたよりも簡単に掘れたのだけども、小さめの切り株だと思っていたら根がびっしり生えていた。まだ水分が含まれていたし、ひたすら長くいろいろなところにつながっていて、私にはその木の根が古い写真の中のお父さんのように思えた。それで「掘ってみたんですが、私、お父さんに会ったような気がしました。この松の根と一緒に写真を撮らせてもらえませんか?」と伝えたんです。 木の根が血管にも思えて、おじいさんの体とつながっているようにしたかった。そこで半分に切って身体の前後で挟み込むようにして。大きな根の塊はおじいさんのお孫さんがクレーン車で引き上げてくれて、おじいさんはもう片方の根の断面で体を支えていたから「楽に立ててるよ」と言った。この方の奥さんはこの根を見上げながら「旅行に来たみたいだね」と、おじいさんの隣にそっと寄り添って背中をぎゅっとつかんで背筋を伸ばして立っていてくれた。 (竹内万里子との対話より抜粋)
これに限らず志賀の写真は、いずれも一種のシアトリカルな、フィクショナルな体裁を持っている。しかしそれはよくあるような、芸術家が自分の内なるイマジネーションやヴィジョンに耽溺し、他者や外界を覆い尽くそうとする独善とはやはり違っている。「まずは写真のなかのわからないものをわからないままにしておきたいのです。発酵させるように寝かせておきたいんです」と彼女は言う。「わからなさ」との格闘は続いている。それは志賀理江子という個体と身体の内側にも外側にも、内外をめぐる回路にもある。二〇一一年三月十一日の出来事は、そんな「わからなさ」を丸ごとキャンセルするようなものであったとも言えるし、或いは「わからなさ」の極点だったと言うことも出来る。志賀は「あの日」以後、決定的に変わったとも言えるし、何も変わっていないとも言える。そうした解釈や分析が、いずれも届かないところに(それゆえに、それらの全てが可能になってしまうだろうところに)彼女が相手取る「わからなさ」はある。ただひとつ確かなことは、彼女は撮ることを辞めるつもりはない、ということである。「写真のなかにいる人々はカメラを意識し、なにかを演じ続けて」おり、そして「演じること」とは「枠のなかからまったく違うところへ飛躍する行為」である。ここでいう意識や演技とは、カメラを向けられた者から決して消えることのないものだ。志賀はそれらを無視したり隠蔽したりする欺瞞を拒絶し、むしろそれらを増幅し、変調しようとする。そうして、撮る者と撮られる者、見る者と見られる者が一緒になって「まったく違うところ」へとワープすることを希う。 写真に定着された「イメージ」とは、いわば「現実」に織り重なった「虚構」である。それは「虚構」に織り重ねられた「現実」と言っても同じことだ。『螺旋海岸』には、ストレートに震災と関連付けられるような写真は一枚もない(先の集会場の写真も展示はされていない)。にもかかわらず、それは凡百の「震災写真」を凌駕する力を備えている。それは「出来事」の強度に立ち向かおうとする「虚構」としての自覚と信念に依っている。志賀の言う「土地」と「物語」が混じり合うさまとは、正しくこのことである。そして無論のことだが、それは彼女が「現実」を生きていない、という意味ではない。
このあいだ久しぶりに、北釜でお世話になったあるおばあさんと話す機会がありました。彼女は、「わたしね、ここが好きだから、またね、石を拾って、それを積むことから始めたいの、だからそれができるようにいまは草取りしてる」と言って更地になった家の周りの草取りに通っていました。彼女はあらゆる復興計画から自立して自分がどうしたいか自分の頭で考え、それを軸にしてその手で石を拾い、草をむしって、野菜を植えている。もうここには住めないことを十分理解したうえで本気でやっている。社会と欲望の矛先ばかりを考えてしまって、そのことにがんじがらめになってしまった私にとって、社会の一部でどう生かされるかを考える前に、生きることの根底にある生活の小さなことを淡々と実行する彼女に目を覚まされるような気持ちになって、私も彼女のようになりたいと思った。そういう長い時間を生きてきた人、自然に寄り添った人が目の前にたくさんいることはすばらしいことで、教わることが日々あるんです。食べものがないときは芋の蔓を食べたこと、堆肥をつくり背負って売りにいったこと、暗くなったら寝て日が射したら起きること、道ばたに花が咲いているのを見るとうれしくて疲れが吹き飛ぶこと……。彼女が昔のことを話してくれたことを必死に思い出すんです。
「おばあさん」が積もうとしている石は、「仙台短篇映画祭」の映画『明日』のパンフレットに冨永昌敬が書きつけていた「うずたかく積まれた小さな固い石の集まり」と、確かに響き合っているように、私には思える。もちろん疑いなく志賀理江子は、たとえ北釜に住まなかったとしても、震災を自ら体験しなかったとしても、非凡な作品を作り続けていただろう。彼女が北釜に住むことになったのは、いわば偶然と成り行きの産物である。けれども、それを運命と呼ぶのだ。彼女は、彼女にしか可能でないやり方で「あの日以後」を生きている。それはとても複雑な内実を持った行為、営みである。だが同時に、それはとても素朴で単純なことでもある。
北釜の人が遠くから私を見つけては手を振ってくれて話しかけてくれること。「なにやってんの〜。今度なにつくるの〜」って目を見つめてにっこり笑ってくれること。なによりもまずここにいさせていくれること。失敗しても許してくれること。その途方もない優しさみたいなものを彼らから受けるたびに、そのことがあまりにも尊すぎて体が破裂しそうになります。いろいろなところからたくさんの救いの手が私たちの生活に差し伸べられたことによって、この世にはその手が差し伸べられない領域がたくさんあることを実感します。どこかの国で助けられもせず死ぬ人がたくさんいるということ。そしてそれはどうしようもなくそういうこととしてあること。生きていることはあまりに強い。
こう述べてから彼女は、まるで今ふと思ったことのように、次の言葉を言い添える。「だから、これらのことがどのように「芸術」とつながりをもつかなどは全然わかりません」。
27。「0円ハウス」から遠く離れて
『ZERO COST HOUSE』は、岡田利規がアメリカのPIG IRON THEATRE COMPANYに書き下ろした戯曲である。オガワアヤによる英訳台本を用いて、岡田の立ち会いの下、リハーサルが重ねられ、二〇一二年の九月に同劇団が拠点とするフィラデルフィアで初演された。戯曲の日本語オリジナルは「群像」の二月号に掲載されている。そこに添えられた覚書によると、岡田は「この日本語テキストを用いた上演を、私は想定していませんし、望んでもおりません」とのこと。日本公演は二〇一三年二月、神奈川芸術劇場(KAAT)で、PIG IRONによって行なわれた。この作品は多くの点で、同じくKAATで上演された(本連載でも以前取り上げた)岡田率いるチェルフィッチュの現時点での最新作『現在地』の続編もしくは姉妹篇と看做しうるものとなっている。 事前に戯曲を読んでいたものの、あくまでもアメリカ人の俳優によって英語で演じられることを前提に書かれたこの作品は、実際に舞台で観てみると、日本語で読んだ際には感じなかった、じつに複雑きわまりないニュアンスが込められていることがわかる。まず、この作品には原作が二つある。ひとつ目は、ヘンリー・デイヴィッド・ソローの『ウォールデン(森の生活)』。そしてもうひとつはタイトルからも明らかなように、坂口恭平の一連の著作(言動)である。そしてこの舞台には、「ヘンリー・デイヴィッド・ソロー」と「坂口恭平」、そして「岡田利規」と「過去の岡田」と呼ばれる人物が登場する。 全三部から成る『ZERO COST HOUSE』は、要約することがなかなか難しい作品である。いや、それはもちろん可能だが、そうすると重要なニュアンスが失われてしまうおそれがある。しかし無理を承知でかいつまんで内容を記すと、第一部「二〇一〇年」の冒頭では、「岡田利規」が『ウォールデン』を読みふける「過去の岡田」を眺めつつ、自らの過去に思いを馳せる。いわく自分は劇作家であり、現在は「気鋭の」とか「十年に一度の逸材」などと呼ばれるような評価を得ている。だが今から十五年前、まだ大学を出たばかりだった頃は、既に芝居はやっていたものの、単純なデータ入力のパートタイムをしていて、そのことに不満は持ってもいなかった。むしろ下手にやりがいのある仕事に就くよりも、余った時間を好きに使えるだけましだと思っていた。そんな「過去の岡田」は、ソローの『ウォールデン』を愛読していて、そこに書かれたライフスタイル、人生哲学に私淑していた。「現在の岡田」は、アメリカの劇団からコラボレーションを依頼されて(それがこの作品なのだが)彼自身の「自伝」を作品化しようと思い立ち、それには『ウォールデン』が不可欠だと考えた。と、そこに突然、見知らぬ男が現れて「ヘンリー・デイヴィッド・ソロー」と名乗る。「現在の岡田」と「ソロー」は会話をかわす。いちおう「現在の岡田」は感激してみせるのだが、どこかいまいちノリが悪い。「ソロー」と別れてから、どうせなら十五年前の「過去の岡田」に会わせたかった、正直今は『ウォールデン』を読んでも昔ほど(というか実はちっとも)感動しないのだ、という自分の気持ちを彼の「マネージャー」に述べる。そこに更に男が登場する。名乗るのは第三部になってからだが、男は「坂口恭平」である。「坂口」は「過去の岡田」と対話し、『ウォールデン』は理想主義的な本じゃなく「マジで現実的な本」だと言い放つ。ここまでが第一部。第二部「「ベイカー農場」より」では、「ソロー」が、『ウォールデン』の重要な章である「ベイカー農場」を書いているところに「現在の岡田」がやってくる。ところで第一部から、舞台上には、ここまで述べていない登場人物が何度か出て来ている。それは「ウサギ」の「夫妻」で、どうやら「過去の岡田」「現在の岡田」そして「ソロー」が書いている人物であるらしい。「ウサギ夫」と「ウサギ妻」が「ヘンリー」(「ソロー」が書いている「ベイカー農場」に出て来るソローのこと)とのやりとりを語ると「現在の岡田」は違和感を表明する。それはarrogant(傲慢)という言葉で表現される。『ウォールデン』で示される哲学は、やはり一種の傲慢ではないのか。だが、ここで「過去の岡田」が、しかし「現在の岡田」にとっても、『ウォールデン』はふたたび大事なものになりかけている、と言う。ここで第二部は終わり、第三部「二〇一一年」が始まる。「坂口恭平」が現われて、延々と「岡田利規」との馴れ初めを語る。最初は二〇〇六年、東京で彼の芝居を観たのがきっかけだった。その時からずっと機を伺っていた。「彼と俺が知り合いになるべきときかいつか?」と。それは二〇一〇年にやってきた。やはり「岡田」の芝居を観た後、「坂口」はロビーで「岡田」に握手を求め、「岡田さんの作る芝居くらいヤバい本です」と言って、自著を手渡した。それは「都市の中でゼロ円で家を作って、ゼロ円で暮らしていくための本」、抽象的に言うと「この世界に存在する別のレイヤーをとらえることを読む人にそそのかす本」である。その時の「岡田」の態度は当然ながら微妙だったが、そういう反応には慣れているので大丈夫。そこで「マネージャー」が話し出す。「二〇一一年三月十一日」の「午後二時四十六分」に地震があって、そのとき自分は「岡田」とたまたま山口に居たのだが、それから二週間後、とつぜん「岡田」が九州に引っ越すと言い出したのだ。もちろん「放射能の影響」が心配だから、である。というか「岡田」は実際に転居し、かつては真っ向からは語らなかったような社会的な発言をするようになる。「マネージャー」は、それはちょっと危険なことではないかと意見を述べるが、「岡田」は「自分がarrogantになってるかもしれないってことを恐れちゃだめだよね」と妙に毅然とした様子である。この「変化」に合わせて、「岡田」が書いているらしき「ウサギ夫妻」も「震災以後」に生活していることにされる。そこでは放射能汚染への恐怖が非常に直截に語られる(ここでの「ウサギ夫婦」のやりとりは、園子温監督の『希望の国』の息子夫婦を思い出させる)。そこで「坂口」がふたたび登場し、彼自身の「自伝」を語りながら、このような「岡田」の「変化」を促したのは、他ならぬ自分なのだと述べる。地震の五日後、福島第一原発事故の推移を見守ってきた「坂口」は、事の深刻さに気づいて家族を伴い東京から避難し、三月中には出身地である熊本に戻って、ツイッターで放射能の危険性をエネルギッシュに訴え続けるとともに、西への避難を呼びかけた。それに応じて妻子を連れて熊本に移住したのが「岡田」だったというわけである。「坂口」は『ウォールデン』を題材に、「思考の解像度」を高めることで世界の「別のレイヤー」を見出す意義を語り、そうして見出された「ゼロ円ハウス」「ゼロ円生活」の可能性を、そしてそのような考え方が「震災以後」に明らかに重要度を増すことになった事実を語り、自分は「新しい政府」を樹立し、自ら「初代内閣総理大臣」に就任することにした、と宣言する。「マネージャー」は、「坂口」のカリスマティックな行動と理念にも、それに過敏に反応した「岡田」にも百パーセント同意することは出来ない。だがどうも「岡田」は本気で「坂口」に共感しているらしい。なにしろ「岡田」は「坂口総理大臣」のスピーチライターまで買って出たのだから。この舞台は「ウサギ夫妻」が「新政府首相」の「坂口恭平」のもとにやってきて「亡命申請」をする場面で終わる。 いちおう付言しておけば、劇中で語られる「坂口恭平」の哲学は、坂口恭平の一連の著作、とりわけ『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』『独立国家のつくりかた』に書かれているものと同じであり、現実の「震災後」の坂口恭平と岡田利規の行動も、ほぼ同じである。チェルフィッチュの『現在地』との連続性は明白だろう。ここではまたもや、あの作品で問われていた「村を出ていくべきか否か」というアンヴイヴァレンスが、重要な主題のひとつとして掲げられている。だがSF的と言ってもよい抽象的な物語だった『現在地』に対して、『ZERO COST HOUSE』は「岡田利規」の「自伝」だとされ、いわばセミ・ドキュメンタリー的な作品として、あからさまに現実との共通項をもって描かれている。けれども、もちろん事はそれほど単純ではない。劇のほんとうのラストは、「マネージャー」の次の台詞で締めくくられる。
マネージャー みなさん、これで岡田利規の自伝的内容の、このお芝居は終わりです。でもみなさん、ここでお話ししたことの全部が実際に起こったことではなくてですね、たとえば実際の岡田さんは坂口さんのスピーチライターなんてやってないですから。岡田さんは劇作家です。
この作品でもっとも重要なのは、この「岡田さんは劇作家です」という、言わずもがなの断言である。この一言によって、この芝居の中で語られたあらゆる事どもが、一挙に虚構化されて、宙吊りにされてしまうのだ。もちろん、繰り返すが劇中で語られる多くの事がらは、現実にほぼそのままの参照点を持っている。だが、かといって『ZERO COST HOUSE』は、岡田利規による何らかの立場表明や自己肯定を企図した作品ではない。たとえそのように見える部分があったとしても、それらは全て「岡田さんは��作家です」という断わりによって相対化されることになる。しかしそれは当然、虚構に安住していられるわけでもない。それはすぐさまふたたび相対化され、現実へと投げ返されることになるだろう。そして間違いなく、この絶えざる相対化という運動こそ、岡田利規がこの作品をこのようなものとして提示した理由なのだ。 ひとはなんらかの選択を迫られた時、それもAor Not Aというような決定的な二者択一を強いられた場合、自らが選んだ選択肢の正しさを、まず誰よりも先に自分に対して強弁しようとするし、選ばなかった方の選ばれなくてもよさを妥当なレベルよりついつい強調してしまいがちである。そのようなケースにおいて、フィクションという装置が出来るのは、両論併記、それも単なる「どちらも正しい(=どちらも正しいわけではない)」とは異なる、それぞれの選択の不可逆性を踏まえて、双方の決断の不可避性を共に示してみせることだと思う。岡田利規は、彼ならではの非常にユーモラスかつアイロニカルな方法によって、それをやってのけたのだ。しかもここでは、それらが英語でアメリカ人によって演じられるという巧妙な仕掛けが加わっている。いや、というよりも、その条件があったからこそ、このような特異な作品が構想されたのだ。日本の外で、日本語以外で、これが物語られること自体が、相対化の極端な徹底ということだったのである。だからこそ、それを日本で観るという体験は、私に或る居心地の悪さを催させたのは事実である。それはなんというか、相対化のリミットから、もう一度こちらに想定外に巻き戻ってきてしまったかのような感覚だった。なぜなら私は、われわれは「劇作家」ではないからである。
28。そこに残る者たち
「大地のゲーム」は「新潮」の二〇一三年三月号に一挙掲載された、綿矢りさの長編小説である。舞台はおそらく今から数十年後の近未来の大学キャンパス。女子大生である語り手の「私」は、すでに働いている兄と同居する集合住宅に戻ることなく、他の大勢の学生たちとともに、大学構内に住んでいる。それは夏休みに入る二日前のことだった。「未曾有の大地震が私たちを襲った。そして、また年内に巨大な地震が来ると政府は警告している。夏の大地震よりひどいか、同程度の揺れが私たちを襲うと断言し、対象地域一帯に避難勧告を出した。この大学ももちろん対象地域に含まれている」。帰る家がないわけではない。キャンパスの方が安全ということでもない。だが、それにもかかわらず「私」も、地震で両親を亡くした「私の男」も、他の多くの学生たちも、そのまま大学に居残り続けている。 巨大地震の被害はあまりにも甚大なものだった。「わずか二分の間にこの国の半分が破壊されて五万人が命を失った。その後に亡くなった人間が二万人追加されて、震源地で生活していた私たちのなかに、親族や知り合いを一人も亡くしていない人間など一人もいない」。それは「有史以来最悪の自然災害」として世界中に報道されたほどの規模であった。そしてもう一度必ず、巨大な揺れはやって来る。政府はその時のために特例警戒ベルを設置したが、まだ一度も鳴らされたことはない。避難シェルターがあちこちに作られているが、余程の揺れでもない限り、最早いちいち逃げ込んだりはしなくなっている。大学生たちは無責任な政府や自分たちを見捨てた教授たちをもう信用しようとはせず、キャンパス内で緩やかな自治を行ないながら、それなりに平和に生活している。もちろんトラブルはあるし危険もあるが、それは外の世界でも同じことである。 その中で、俄に頭角を顕わした男子学生がいる。彼はリーダーと呼ばれている。大地震の後の混乱の中で図抜けた行動力とカリスマ性を発揮したリーダーは、学生理事という役職を得て、「私」や「私の男」を含むグループを率いて学内のさまざまな事案にコミットしてゆく。彼は自らの組織を「反宇宙派」と名付ける。「実体のない大きな世界をなんとなく信用する時代は終わったのです。国家を疑い地球を疑い、宇宙をも疑う」というのが命名の理由である。彼はまもなく開催される大学���で演説をして、外から来た一般の人々にも反宇宙派としての理念をアピールしようとしている。「私」はリーダーの弱点や欺瞞にうすうす気づきながらも、彼に否応のない魅力を感じてしまっている。やはりリーダーとは因縁のある「私の男」も彼女の気持ちの揺れをわかっているが、時おり揶揄するだけで、強く咎め立ては出来ないでいる。 この小説の舞台は、いうなれば「以後の以後」の世界である。「不死の島」の多和田葉子や、『希望の国』の園子温と同じように、綿矢りさは、東日本大震災を直接的に描くのではなく、その後(これから)どうなるのか、そして災禍がもう一度起こったとしたら、果たしてどうなるのか、という想像力を駆使して、物語を構築している。したがって「大地のゲーム」は、一種のディストピア小説の様相を呈することになる。原子力エネルギーを諦めた日本は、全土的に自然エネルギーに転換することで、低エネルギー社会を実現させたが、その代償として、都会から明かりは消え、ひとびとから活気は失われた。リーダーは演説でこう言う。「相次ぐ急激な気象の変化、それに伴う衣食住の変化、また不安定な国内情勢により、私たち国民の平均寿命は年々短くなり、去年、ついに女性は七十代後半、男性は六十代後半となりました。しかし思い出してください、もともと我々は百年を軽々と生きられる民族だったのです。男女とも平均寿命が百年近くまで上がる、確かにそんな時代も過去にはあったのです」。更には巨大地震が、この国を襲った。そして次の揺れも、遠からずやってくる。この状況を生き抜き、かつて日本人が持っていた、百年も生きられたような生命力を取り戻すためには、大きな仕組みや力にすがるのを止め、「頼れるのは自分と周りの人間だけ」という「超個人主義」に目覚め、何事にも「勇気」をもって臨むことが必要だ、とリーダーは訴える。「私たちに足りないのは勇気です。ほかのなにものでもありません。外に出て行く勇気、殻を破る勇気。大きなものを疑う勇気から始めましょう!」。 「私」と見知らぬ女子学生が校舎の屋上で会話をする場面がある。災害案内板にアクセスし、連絡の取れなかった父親とメール出来たという。彼女は言う。「でも、父親が〝おれたちの昔経験した地震災害も同じくらい規模が大きかった。地震のあとに津波が襲ってきた分、もっと悲惨だったといってもいい。でもあのときからも立ち直れたから、今回も絶対に大丈夫だ〟って書いて送ってきたの。私、それに腹が立って」。「分かる。すごくよく分かる」と「私」は応える。そんな遥か昔の知りもしない出来事と、いま自分たちが直面していることを、どうして比較出来ようか。「いっしょにしないでほしい。どんな昔の体験とも、どんな痛みとも」。 ここで述べておかなくてはならないことは、綿矢りさは京都出身であり、十一歳の時に阪神淡路大震災を体験しているということである(このことは何度かインタビューでも語っている)。つまり「私」と女子学生の会話には、東日本大震災と阪神淡路大震災の関係が重ねられている。災害の規模が問題なのではない。それはあくまでも客観的な視座からの、往々にして無関係な第三者(非当事者)による認識でしかない。重要なことは、それが「私」の体験であるかどうか、なのだ。このような感覚をエゴイズムと断じることは出来ない。むしろ正反対である。なぜならば、柴崎友香の『わたしがいなかった街で』の「わたし」と同じく、ここでの「私」とは「生き残った=死ななかった私」のことであり、その裏側には「死んでいたかもしれない私」が、そして更にその背後には無数の「(私以外の)死んでしまった人たち」が控えているのだから。私は思う。「私より偉い人も、できる人も、美しい人も、みんな死んだ。大地に強い根を張るのはいま生き残った、これからの私たちだ」。煎じ詰めれば偶然と確率の結果でしかない寄る辺なき生存を、「私(たち)」は権利として、また義務として、未来に向けて行使していかなくてはならない。 リーダーはその言動において何よりも「勇気」を強調し、「私」もそれに突き動かされる。しかしこの言葉はけっして単純なものではない。象徴的と言えるのが、前半に置かれたバンジージャンプの挿話である。リーダーに言われるまま、「私」は屋上から飛び降りる。リーダーがすぐさま続く。それはまさしく純粋に「勇気」を試す遊びなのだが、そこには別の意味もある。「あの日のあと、近親者を亡くしたショックや激変した環境になじめずに自殺する人間が、後を立たない。死んだ親族、死んだ仲間たち、考えれば考えるほど引きずり込まれそうになる。大人たちは人の心の傷つきに麻痺して、さらに麻痺させようとしてる。頭をスリルで痺れさせないと、私たちだって危ない。死なないために、飛び降りている」。このように、やみくもな勇気とギリギリの保身は、じつは裏腹になっている。そもそも「外に出て行く勇気」と言いながら、彼らは大学から出ていこうとはせず、巨大地震が来るとわかっているのに、そこから離れようとはしない。物語の最後に、当然のごとく、ふたたび大地震はやってくる。その後、またもや生き残った「私」は、自らに問いかける。
(……)なぜ私たちは、わざわざ危険な土地に、危険と知りながら残ったのだろうか。土地に愛着があったから、土地に執念があったから、大切な人がいたから。土地を踏みしめているときには、そのような理由だと自分で信じ込んでいたが、実は違ったのではないか。 私たちは、何度でも大地の賭けに乗る。 Bet. 地球全体に広大な敷地を持ちながらも、大地はあの土地にばかり執拗にコインを積み重ね、賭け金の倍率をつり上げる。ディーラーのよく手入れされた細くなめらかな指先、からからと回るルーレットを凝視する賭博者たち、視線の先には今後活発に動くと予想される、大注目の活断層。 天上知らずに集まるパワーとテンションが一等賞の賞金の額を膨大に増し、四方八方からぎゅうぎゅうに押されて耐えきれなくなった地面が口を開き、私たちはその裂け目から暗闇へと飲み込まれる。 でも私たちは、この地から動きたくない。動けない。どれだけ大穴の危険地帯となっても、ここで自分の人生を紡ぎたい。
「大地のゲーム」という題名の意味が、ここでは述べられている。それはどこかバンジージャンプに挑む感覚と似ている。もちろんバンジーは「死なないために、飛び降りて」いたのでもあった。だがバンジーだって事故が起こる可能性はゼロではない。「死なないために」と言いながら、そこには「死ぬかもしれない」が、僅かではあれ常に含まれている。スリルを味わうなどといった皮相な話をしているのではない。ここには、なぜここから逃げないのか、なぜここに留まっているのか、という、おそらく誰もが「あの日以後」に意識的無意識的に問うたことのあるに違いない、あのパラドキシカルな問いへの、答えとは言わないが、ひとつの切実な思弁が存在していると思う。彼女たちは、「私たち」は、私たちは、なぜ、まだ、ここに居るのか? 『現在地』と『ZERO COST HOUSE』の岡田利規が抱えていた問題が、ここでは反対側から問われているのである。 だが惜しむらくは、最後の最後で、綿矢りさは、この思弁を、「私」と「私の男」の、まさに私的な物語に回収してしまっているように、私には思えた。いや、或る意味でそれこそが綿矢の作家としての武器なのだが。とはいえ「勇気」がそうであったように、そこで示されるポジティヴさや希望も、作者自身の考えはどうであれ、やはり一筋縄ではいかない。この小説の末尾は「私は私が抱えられるだけの命を、一つも落とさずにこの道を歩もう」という一文である。この宣言には、いわば毅然とした諦念のようなものが感じられる。その外側には、私が抱え切れない、抱えることの出来ない命たちが、明らかに沢山、存在しているのだからだ。
29。そこに向かう者たち
「In A Large Room With No Light」(最近の阿部小説の例に漏れず、これは曲名で、元ネタはプリンスである)は、「文學界」の二〇一三年三月号に掲載された、阿部和重の短編小説である。二〇一一年の四月、福島の警戒区域内のどこかに秘匿された、埼玉の運送会社の金庫から強奪された五億円を探しに、「日山昭伸」「美里剛洋」「崔哲生」の三人の小悪党が、被災地へと出張ってゆく。映画的と言ってもいいスピーディーな展開と、抜群のリーダビリティを誇る、阿部和重ならではのピカレスクの佳品である。そしてまた、あの「RIDE ON TIME」とはまた別の意味で、確信犯的に不謹慎な小説でもある。震災と原発事故から間もなく、津波によって居住者が亡くなったり、避難したりして無人となった家々や、使用する者の居なくなったATMなどに残されたままの金を盗みに、少なからぬ犯罪者たちが被災地を訪れたこと��、その後の報道でも知られることになった。彼らは文字通りのハイエナだが、それもまた震災後の現実である。火事場泥棒の景気のいい話を耳にしながら、その恩恵に浴すチ���ンスになかなか出会えなかった「日山昭伸」に、小生意気だが頭のキレる舎弟の「美里剛洋」から、奪われ隠された五億円の話が齎される。話を立ち聞きされたせいで仲間に加えざるを得なくなった在日韓国人の「崔哲生」とともに、彼らはミニバンで福島に向かう。おそらくは『幼少の帝国』執筆時の取材に基づくものだろう、具体的な土地勘に彩られた描写は、きわめてリアルなものである。三人のチームは、当然のごとくまるで一枚岩ではない。嘘と策謀と裏切りが連続し、あれよあれよという間に、読者は思いも寄らないラストシーンに辿り着くことになる。大きな余震が起こる。何しろ地震から一ヶ月足らずのことである。「美里剛洋」に裏切られた「日山昭伸」は、致命傷に近い傷を負った「崔哲生」とともにミニバンの車内に居る。そこに大津波がやってくる。それからどうなるかは書かないが、やはりすこぶる映画的な、じつに印象的な幕切れであるとだけ言っておくことにする。 小説的な仕上がりとしては、百戦錬磨の阿部和重にすれば、手慰みの範疇と言っていいのかもしれない(実際、彼はこのような作品なら幾らでも量産出来るだろう)「In A Large Room With No Light」が、書かれた動機とは何だろうか? それは「RIDE ON TIME」の傍らに、この小説を置いてみることで明らかになる。この二編はいずれも、間違いなく他の小説家には絶対に思いつきもしないだろう、きわめて独創的な「津波小説」なのである。阿部和重は、小説によって「津波」を、それが持つ意味を、徹底的に解体しようとしているのだ。 物語の最後に「日山昭伸」は、或る決断をする。それはやむにやまれぬものではあるが、それでも以前の彼であれば、およそありえない選択である。それは「悪党」であればけっしてしないであろう選択である。しかし彼がそれをすることによって、この小説は終わる。そして見事というしかないのは、このエンディングが、そのまま一種の「メッセージ」になっているということなのだ。それは「以後の世界」へと向けた、ほんとうに大切なものとは何なのか、という、ほとんど素朴とさえ呼んでいいようなメッセージである。「RIDE ON TIME」と同じく、阿部和重は言葉にすれば余りにも単純過ぎる、それゆえに賢しい者ほど表立って言おうとはしない、だが紛れもなく重要な真理を、じつに彼らしいヒネクレたやり方で、語ってみせているのである。
30。そこに留め置かれた者
こんばんは。 あるいはおはよう。 もしくはこんにちは。 想像ラジオです。
いとうせいこうの『想像ラジオ』は、こんな呼びかけから始まる。この小説は「文藝」の二〇一三年春季号に掲載され、その後、単行本として刊行された。いとうは震災後、哲学者/小説家の佐々木中と、東日本大震災へのチャリティとして、ヒップホップの流儀で交互に即興的に小説を書き継ぐという試みを行ない、のちに『Back 2 Back』として刊行した。また「今井さん」(「すばる」二〇一二年三月号)、「私が描いた人は」(「文藝」二〇一二年夏季号)という二編のごく短い小説を発表しているが、本格的な作品としては『去勢訓練』(一九九七年)以来、十六年ぶりである。 喋っているのは、DJアークと名乗る人物である。彼はひたすら喋っている。どこか素人ぽくはあるが、それなりに軽妙なトークが、小説ののっけから始まる。だが、すぐさま読者は疑問にとらわれることだろう。「想一像一ラジオ一」というジングルも高らかに、DJアークはノリノリで喋り続けているが、この「ラジオ」とは一体何なのか? その答えはすぐに与えられる。「この想像ラジオ、スポンサーはないし、それどころかラジオ局もスタジオもない。僕はマイクの前にいるわけでもないし、実のところしゃべってもいない。なのになんであなたの耳にこの僕の声が聴こえてるかっていえば、冒頭にお伝えした通り想像力なんですよ。あなたの想像力が電波であり、マイクであり、スタジオであり、つまり僕の声そのものなんです」。だから「想像ラジオ」。なるほどそれはわかったけれど、でもだからそれは何なのか? そもそもDJアークとは誰で、彼は一体どこから放送しているのか? だが、この疑問にもすぐに答えが与えられる。彼は三十八歳、「三流大学に入って東京に出ると仕送りでエレキギター買って、アフリカのビートを取り入れたちょっとひねくれたバンドに加入して、けっこう評判はよかったもののメジャーデビュー出来ずに裏方として小さい音楽事務所入りましてね」、「そこそこインディーズで売れたメートルズとかマイティ・フラワーとかアトム&ウランとか新人アーティストを色々マネージメントしてるうちに、なんか嫌になっちゃって、といっても十数年やった上でですよ。まあ、そこで見切りをつけて昨日実家に帰ってきたんです。年上の奥さん連れて。川も山も海のあるこの町に」。妻の名前はミサト=美里。彼にはアメリカのジュニア・ハイスクールに通うソウスケ=草助という中二の息子もいる。つまりいわゆるUターン組というわけである。だが、昨日郷里に戻ってきたばかりの彼が、なぜいま「想像ラジオ」の「DJアーク」として喋りまくっているのか? しかも「高い杉の木の上に引っかかって、そこからラジオ放始めるはめになった」とは、どういうことなのか? そして、この当然の疑問に、痛みと悲哀と慈愛に満ちた答えが与えられるのが、要するに『想像ラジオ』という小説なのである。 この小説が載った「文藝」のいとうせいこう特集の一環として行なわれた星野智幸との対談の中で、いとうは震災後の自分の行動について、こんな風に述べている。
(……)世界観が崩壊しましたからね。震災後は映像ばかり見てしまってどうしていいか分からないし言葉なんて一つも役に立たないと思ってたんですよ。でも震災の二日後というタイミングで、ラリー・ハードがDommuneでDJをやったんですよ。ット・ット・ット・ットって四つ打ちで全部インストだったんだけど、四次元に脳が連れて行かれて、そこで何かのエネルギーが補填されていくのを感じた。自分は四つ打ちの音楽は作れない、だけど同じことを言葉でやらなければいけないなと思って、文字DJというツイッターのアカウントを作って、YouTubeもラジオも聴けない状況だったけどツイッターだけは機能してたから、その中でありもしない曲から実際の曲までつぶやいていたんですね。想像すれば絶対に聴こえるはずだ、想像力まで押し潰されてしまったら俺達にはあと何が残るんだと思っていた。
この「文字DJ」の延長線上に「想像ラジオ」という発想が生まれたのだろう。「まず僕は被災したわけじゃないから、絶対的な断絶がありますが、でも世界を自分が出来る限り真正面から引き受けて、そのかわり全部想像しますからね、という姿勢でした」。佐々木中との『Back 2 Back』は即効性を何よりも第一とする試みだった。ツイッターによる「文字DJ」もまたリアルタイム性を最優先させるものだった。だが一編の小説、それも或る纏まりと長さを持った小説は、それらとは異なる。小説は遅い。小説は遅くなる。小説は遅れる。遅れてくる。遅れざるを得ない。だから「遅さ」こそを武器にしなくてはならない。そこでいとうが選んだのが、一言でいえば、死者の声を聴くことを想像する、それも徹底的に、出来うる限りの技を用いて、必死で想像する、ということだった。そして彼はそのことだけを書いたのである。 DJアークは、高い杉の木の上に引っかかったまま、彼の「想像ラジオ」を続ける。ラジオであるからには、リスナーからの電話もあれば、メールだって届く。音楽だってかかる。番組はなかなか賑やかである。しかし読み進むほどに、否応無しに読者は、それらが、あの地震と津波にかかわっているということ、いや、すべてがその話なのだ、ということに気づかされることになる。作者はもちろん、そのことをいつまでも隠したりはしない。DJアークに何が起こり、彼が語りかけている「想像ラジオ」のリスナーたちとは誰なのか、読者には程なく分かる。だから私はそれを書かない。この小説は五章立てであり、第二章と第四章にはDJアークとは別のSという作家が登場する。彼はどこか(というかあからさまに)作者いとうせいこうを思わせる人物である。Sはボランティアに行った宮城と福島で、非常によく似た「樹上の人」の噂を耳にした。大津波が何もかもを押し流していった後、しばらく杉の木の上に引っかかっていた人がいた、という話。それぞれの「樹上にいたのが同じ人であるはずもないが、私にはふたつの体が同一のように思えて仕方なくなったし、それどころかありとあらゆる場所にその体があって我々を見下ろしているように感じられた」。彼は「樹上の人」の声を聴きたいと思うが、しかし「その声が私には聴こえない」。だから「私はもっと集中するべきだと思う」。 第二章で、福島からの帰路、車中でボランティアたちが交わす議論がある。リーダー格の若者が「樹上の人の声」にこだわるSに対して、こう言う。「あのですね、俺らは生きている人のことを第一に考えなくちゃいけないと思うんです。亡くなった人への慰めの気持ちが大事なのはよくわかるんですけど、それは本当の家族や地域の人たちが毎日やってるってことは体育館でも仮設住宅でもいくらでも見てきたじゃないですか。(中略)その心の領域っつうんですか、そういう場所に俺ら無関係な者が土足で入り込むべきじゃないし、直接何も失ってない俺らは何か語ったりするよりもただ黙って今生きてる人の手伝いが出来ればいいんだと思います」。これを聞いて、Sは自分を軽々しい人間だと思って恥じ入るが、それでも事態に無関係な者は、他人の死にかかわる「心の領域」に入り込むこと、すなわち「想像」などするべきでない、という考えに完全には納得出来ない。そると別のボランティアの青年が、バイト先の植木職人の親方から又聞きした東京大空襲の話を始める。
……亡くなった人が無言であの世に行ったと思うなよ、とおやじさんが仕事帰りに植木道具を置きに行くと奥の座敷から廊下に出てきて茶碗酒片手で俺によく言うんだよ。叫び声が町中に響き渡ったはずだし、悔しくてどうしようもなくて自分を呪うみたいに文句を垂れ続けたろうし、熱くて泣いて怒って息を引きとるまで喉の奥から呻き声あげたんだぞって。先代の親方は、自分が知らないその夜のことをおやじから聞いて、しょっちゅう夢見て飛び起きたんだって言ってたけど、先代は話を聞いて公開したことねえぞって言うんだ。 俺は亡くなるまでのその声を考えるのと、亡くなったあとを想像するのにそれほど差があんのかって思う。恨みはあるし、誰かに伝えたかったこともあるし、それが何だったか考える人がいてもいいし、いやいなくちゃいけないし、それがSさんだったりするんじゃないかって……
しかしボランティアのリーダーは反論する。「それは遠い過去になったから語る人が色々でもむしろ事実を忘れないためにいい」のだが、しかし直近の震災で「自分一人だけ生き残った人に対して、あなたのご家族は今あの世でこんなことをつぶやいてるんじゃないかなんてことを、いくらな���でも口に出来ない」のではないか。その上で彼はSにこう告げる。
これは失礼な言い方でほんとに申し訳ないんだけど、Sさんは元は博多の人で長く東京に住んでて、親戚の誰一人東北にいないし、友達が亡くなったわけでもないと聞いています。そういう人が死者への想像を語る時期でも、そもそも語る問題でもないと俺は思うんです。まして亡くなった人のコトバが聴こえるかどうかなんて、俺からすれば甘すぎるし、死者を侮辱してる。
ボランティアという行為自体が、「甘い想像で相手に接してる限り何度でも、お前に何がわかるんだとつっぱねられるんですよ」と彼は厳しく言う。そこに、更にもう一人のボランティアが話に加わってくる。確かにその通りだ。生半可な同情や想像など、被災地の人たちからしたら、単なるこちらの自己満足、自己欺瞞以外の何でもない。「問題は役に立つか立たないかで、あとは全部考えをやめる」という態度は正しい。だが、それでも「亡くなった人の声を自分の心の中で聴き続けることを禁止にしていいのか」とも思う。「行動と同時にひそかに心の底の方で、亡くなった人の悔しさや恐ろしさや心残りやらに耳を傾けようとしないならば、ウチらの行動はうすっぺらいもんになってしまうんじゃないか」。
作家っていうのは、俺よくわかんないけど、心の中で聴いた声が文になって漏れてくるような人なんじゃないのかと思うんですよ。その場で霊媒師みたいに話すんじゃなくて、時間かけてあとから文で。しかも確かにそれが亡くなった人の一番言いたいことかもしれないと、生きている人が思うようなコトバをSさんは、なんていうか耳を澄まして聴こうとしていて、でもまったく聴けないでいるってことじゃないか。
これこそ「遅さ」の効用というべきものである。だがリーダーは「禁止してるんじゃない」と応じつつも、それでもやはり、こう���べる。「いくら耳を傾けようとしたって、溺れて水に巻かれて胸をかきむしって海水を飲んで亡くなった人の苦しみは絶対に絶対に、生きている僕らに理解出来ない。聴こえるなんて考えるのはとんでもない思い上がりだし、何か聴こえたところで生きる望みを失う瞬間の本当の恐ろしさ、悲しさなんか絶対にわかるわけがない」。 このように第二章は、当事者性と想像という行為にかんするディスカッションと言えるものになっている。無論それは作者自身の自問自答でもあるだろう。ところで、第一章の終わりで、DJアークは一曲かけていた。アントニオ・カルロス・ジョビンの「三月の水」。ボランティアたちの車内に沈黙が降りたとき、それまでずっと黙っていた運転席の、中一の時に阪神淡路大震災を体験し、それから何年か言葉を喋らなかったという青年が、カーラジオのスイッチは切ってある筈なのに、なぜか音楽が聴こえてくる、と言う。それはジョビンの「三月の水」だ。繰り返しかかっている。誰か男の声も聴こえたと言う。だが、Sには何も聴こえない。 『想像ラジオ』は、痛ましさとやり切れなさに覆われた小説である。十六年ぶりの本格的な小説の題材として、このようなものを選んだ、選ばざるを得なかった、いとうせいこうという作家の勇気に、私は静かに戦慄する。ここでは想像すること、書くことへの、強い動機と強い疑いとが、同時に存在し、激しく鬩ぎあっている。「震災小説」を、「以後の小説」を、ただタイミング良く、小器用に書いてみせるのとは、わけが違うのだ。作者には、この小説が必然的に帯びてしまうだろう、隠しようもない欺瞞が、最初から見えていた。たとえ感涙する読者が居るとしても、その感涙の内にこそ、当事者でないがゆえの、安全地帯から見守っているがゆえの、無傷な憐憫というしかないものが仄見えていることを、書き出す前からよくよくわかっていた。それでも、どうしてもこれは書かれなくてはならなかったのだ。書けない/書かないことへの、ギリギリの否定/逆転としての、書くこと。 先の星野智幸との対談で、いとうせいこうはこんなことを述べている。 死者の声を聴くっていうことが、やっぱり歴史なんだと思うんです。批評家がよくこの小説には歴史がないとか言いますけど、その歴史って小説で考えたら、死者の声でしかないんですよ。相手が大勢であっても、たった一人であっても、死者の声にじっと耳を傾けることにしか歴史はない。もちちん死者っていうのは今生きていないっていうことでいえば、未来の人の声でもある。だからリアルな今の状況を写せば小説家といったら決してそうではなくて、小説が作れる現実というのは死者の声を過去からも未来からも聴いて、その時間が渾然一体となって同じ平面に出ることなんだと思うんです。同じ平面ということでいえばそれが小説のきわめて不自由な側面でもあり、しかし同時に多声的に読める自由さでもあるんですよね。
死者の声を聴く小説。いや、小説とは死者の声を聴くことなのだ。けれどもこの発言は、他でもない『想像ラジオ』を書き終えたからこそ出来たものでもある。いとうせいこうは、あの紋切り型の問い、けっして安易に問われるべきではないのに誰彼無しに何度となく問われてしまった問い、すなわち「〜に何が出来るのか?」という問い、つまり、小説には何が出来るのか、という問いを、真っ向から引き受けるために、ほとんどただそれだけのために、長いブランクを経て、ふたたび小説を書いたのだ。このことは強調しておかなくてはならない。小説は遅くて不自由なものだが、それでもやれることはある。小説にしかやれないこと、小説だけが切り拓く自由が、確かにある。だったらば、やってみる価値はあるのではあるまいか。誰もそれをやっていないようであれば尚更。 しかしもちろん、それは同時に、小説という形式に耽溺すること,小説という行為に安住することを意味しているのではない。いとうはこんなことも言っている。「特に純文学をやっていらっしゃる方々は、間接性しか取らないんですね。直接的にものを言うことを避ける。3・11の後、「とにかく募金を集めよう」って普通に各々のサイトとかにデカデカと書けばよかったように思う。それをやらずに間接的なやり方が目立った。エンターテインメント畑は違ったと思う。ストレートであることを恐れなかった」。『想像ラジオ』の作者は、アクティヴィストでもある。だからこそ彼は、こんな小説を書いた/書けたのだ。「文学者が直接的に言葉を使わなかったということは、逆に言うと作品が間接的に書けていないからじゃないですか? 間接的に書けてこそ、直接性が怖くなくなるんじゃないでしょうか?」。この問い、いや挑発に、一体どれだけの「文学者」が抗弁出来るのだろうか? 小説の終わり、DJアークの「想像ラジオ」は、遂に放送終了の時を迎える。彼はおもむろに「この機会にしゃべっておきたいこと」を語り出す。 今日も明日も想像を求める新しいDJが次々と世界にあらわれる。何人も何人も、日々あらわれる。それどころか、あらわれない日がないんです。いや、今この時もすでに無数のDJたちがやかましいくらいに自分の番組をオンエアしてる。彼らはゴキゲンな放送を続けるでしょう。僕だっていつでも戻ってくる。語りかけるし、話を聴く。その声に必ず耳を澄まして欲しい、リスナーたちよ。また新たに生まれるリスナーたちよ。
この後どうなるのか、もちろん私はそれを書かない。
31。「午後二時四十六分十八秒」
山下澄人の「水の音しかしない」は「文學界」の二〇一一年十二月号に発表され、現在は作品集『ギッちょん』に収録されている。他の山下作品と同様、小説による/小説における「野性の思考」をまざまざと体現したかのような、自由奔放かつ繊細精緻な書法によって、或る出来事が描かれる。 「出勤途中によく駅で会う男がいた。土日をのぞいてほぼ毎日、その男に会った。だからお互い、顔をあわすといつの頃からか、軽く会釈をかわすようになっていたのだけれど、わたしはそれが実は鬱陶しくて面倒くさくて、だから今朝、電車の時間をひとつ早いのに変えた」。それにもかかわらず、彼はその男と今朝もやはり会ってしまい、仕方なく初めて挨拶を交わし、車内で話をする羽目になる。「わたし」は「斉藤」、男は「中嶋」と名乗る。ふたりの家族構成は子どもの年齢も含めて、まったく同じだった。「わたし」は、明日は電車を更に一本早めようと考えつつ、「中嶋」と別れ、会社に着くと、何故か自分の机が移動されている。そればかりか、隣席の「真島」をはじめ、同僚たちの姿がひとりも見えない。課長の「溝口」だけが、昨日と変わらずに居る。怪訝に思って「わたし」が尋ねると、おもむろに「溝口」は答える。
「昨日だよ。すべてが変わったのは。斉藤はいなかったっけ? 昨日の午後、何時だ? 二時過ぎか?」 知らない女が来た。髪が金髪だ。溝口はその金髪の女に 「昨日のあれは、何時だったかな」 と聞いた。女は 「二時四十六分です」 といった。 「だって」 と溝口は私にいった。わたしは話がまったく見えなかったので、それは何ですか、と溝口に聞いた。 「それが何だ、といわれても、それはそれだ、だから何だ、としかいいようがないよ斉藤ちゃん。昨日の午後二時、ええと」 「四十六分」 とわたしはいった。 「そう。四十六分。その時、すべては変わったんだよ。すべてというのは、すべて。全部。全部というのは何もかも。一切合切。外も中も全部。ただ」 溝口はのっそりと立ち上がって、ホワイトボードに黒いペンで「ただ」と書いて、ふたつの字の上に傍点をつけた。
ああ、これはそういう話なのか、と読む者はここでいきなり気づかされることになるのだが、当然のごとく、山下澄人は、この作品をあからさまな「震災小説」として書こうとはしていない。 翌日の朝、電車をもう一本早めたのに、「わたし」はやはり「中嶋」と会ってしまう。ふたりは一昨日の帰宅困難について語り合う。職場に行くと、「溝口」と金髪の女「森林サリー」に加えて、新しい人間が居る。「わたし」と同じ名前の巨漢の男「ビッグ斉藤」と、「わたし」の妻の「ナオミ」によく似た若い男。山下澄人の小説は、通常われわれがリアリズムだと思い込んでいる常識を、あちこちであっさりと逸脱しているが(そして同時に、こっちの方が真の意味でのリアリズムなのではないか、と強く思わせもするのだが)、このあたりからこの作品も、視点や時制や描写が、ゆるゆると解けてゆく。あの日の「二時四十六分」に起こったことを、「わたし」は忘れてしまったのか思い出せないのか、それとも覚えているのだが自分で留め金を架けているのか。あの日のあの時間、一体「わたし」はどうしていたのか。それからどうなったのか。「わたし」以外の連中はどうなったのか。そして「わたし」は今、ほんとうはどうしているのか。何もかもが曖昧にされており、どうにもよくわからない。 それでもどうやら読み進むにつれて、事の次第らしきものが少しずつ推察可能になってくる。「水の音しかしない」が、他の山下澄人の小説と一線を画していると思えるのは、誰もがどうしたって明確な事実性と結びつけざるを得ない、他ならぬ「二時四十六分」に因っている。それゆえに、ここは評価の分かれるところかもしれない。事実は虚構の支えになるが、同時に重石でもあるから。そして確かに『緑のさる』や「ギッちょん」や「トゥンブクトゥ」のような過激な跳躍ぶりを、この小説は必ずしも見せてはいないようにも思える。しかし、それでもこれは山下澄人にとって、どうしても書かなくてはならなかった、書かれなくてはならなかった作品なのだと私は思う。 後半には、次のような場面が現れる。 溝口はタクシーの中にいた。現場に向かうつもりが、そこでの作業は早々と終わったことをタクシーに乗る前に溝口は真島から聞いて、そのまま帰っても良かったのだけれど。せっかくここまで来たのだからと、浜へ向かっていた。運転手にはなまりがあった。午後二時四十六分ちょうどだった。 その十八秒後、突然、広大な土地にいる人間、猫、犬、うさぎ、ネズミ、いたち、ゴキブリ、等々のからだ、建物、電信柱、木、草、地面が、山が、海が、揺れた。 同時に香山が声をあげたから、からだが揺れたのはわたしだけではなかったのだとわたしは思った。揺れる中わたしはカモメが何羽も飛ぶのを見た。揺れがおさまり、興奮した真島が十年以上前に経験した遠い土地での大きな地震の話をはじめた。真島にいわせると、そこでの地震のほうがずっと激しいものだったらしい。 「縦に揺れてから、横に揺れたからな」 わたしたちは浜からあがって、溝口を待った。溝口はタクシーの運転手とさっきの地震の話をしていた。運転手がつけたラジオはどこも地震のニュースだった。「津波」とアナウンサーがいうのが確かに聞こえた。しかしほとんど溝口も運転手も聞いていなかった。わたしはそんなニュースが流れていることすら知らなかった。香山が携帯電話を見ながら原口と何か話していたけれど、その時も確かに「津波」と聞こえた気がするけれど、わたしは飛び交うカモメを見ていたので、ちゃんと聞いてはいなかった。頭の禿げた男が寝グセのついたきれいな女の肩を抱いて浜を上がって来た。女は泣いていた。どこかでサイレンが鳴った。しかしわたしには、というかわたしたちには何のサイレンかわからなかった。
この部分だけを読んだら、紛れもないリアリズム小説の一節だと思われるかもしれない。そしてこのあと、阿部和重の「In A Large Room With No Light」の「日山昭伸」が、いとうせいこうの『想像ラジオ』の「樹上の人=DJアーク」が見舞われたのと同じ事態が、「わたし(たち)」を襲う。 だがしかし、かといってこの小説は、あの日の「午後二時四十六分十八秒」へと遡行してゆき、取り返しのつかない出来事へと収斂していって、悲劇が露わになって、それで終わるわけではない。むしろそこで、むやみと混乱した、だが同時にすこぶる透明な筆致で描かれているのは、あの『想像ラジオ』とはまた別のかたちで、そこにいつまでもいつまでも留められて、繋がれてあるさま、である。そして、そうあるしかないのは、他でもない「わたし」というものが存在しているからである。山下澄人の場合、それは「存在していた」と、過去形で言ってもまったく同じことだし、「わたし」ではない誰か/何か、と言ってしまっても、おそらく同じである。さしあたり「わたし」は「斉藤」という名前を持っているのだが、それは誰もがとりあえず名前を持たされているからに過ぎず、何よりも重要なことは、この体験をした者が現に居た(かもしれない)ということなのだ。「現に」というのも一通りの意味ではないのだが。 結末に向かって、この小説はふたたびしどけなく解け始める。時間が弛み、記憶が変調し、「わたし」の意識が、意識と呼ばれる何かを表す言葉たちが、段々と溶け始める。ふと気づくと「わたし」はまた「中嶋」と、電車内で話している。
「あれからど���してた?」 あれからというのは、どれからかわたしにはわからなかったけれど、適当に見当をつけて話し始めた。いつも会う男と話すようになった事、会社から真島たちがいなくなっていた事、かわりに森林サリーとビッグ斉藤とナオミに似た若い男がいた事、溝口までいなくなった事、そして結局、会社からいなくなった溝口や真島たちの行方はわからずじまいであり、その事を気にしていても仕方がないと、それ以上考えないようにした事。 「うん」 あとは、ナオミに似た若い男が倒れて、ビッグ斉藤と食事をして、終電に乗り、記憶喪失の夢を見て、終点まで寝過ごしてしまい、公園でそこに住む事を妄想して、そこに住む男を妄想して、妄想した男と会話して、港へ出て、その前に商店街で若い女と子供を見て、港で海に浮かぶ木材を拾い上げて、そこに真島たちがあらわれて、みんなで行った焼き鳥屋でさっき別れたビッグ斉藤が働いていて、ホテルでは森林サリーが働いていて、隣にいた男の顔が思い出せなくて、明くる日みんなと海に行って、原口が何度もはねる魚を見て、地震が来て、揺れて、その後、津波が来て、そしてその津波にのまれた事などを話した。
これはそのまま、この小説の簡潔なあらすじになっている。だが、では、そしてそれからどうなった? どうなったのかを「わたし」は言うことが出来ない。それを言えるのは一人称の話者である「わたし」しかいないにもかかわらず、それからどうなったのかを適当に見当をつけて話すことが「わたし」には出来ない。そうすることがどうにも出来なくなってしまっている、ということが、この小説に書かれていることだと言ってもいいかもしれない。かろうじて可能なのは、解け切った「わたし」の、たとえば次のような混乱した述懐だ。 空は曇っていた。わたしから見える限りの空はねずみ色だった。雨が降っていた気がわたしはしていたが、わたしのからだはたえず濡れていたから雨をあまり意識出来ていなかった。というか、わたしはわたしのからだが濡れているのかどうかさえ、ほんとうはよくわかっていなかった。しかしまだ、濡れるのはよくない、という意識だけはかすかにあったから、わたしは水につかっていた足をわたしのからだが乗っている、わたしが、何か、としか認識していない青い屋根の上に面倒くさいと思いつつ、さっき上げた、と思っていたが、しかし実際はそれは昨日の事だった。わたしは水に飛びかかられた事はおぼえていた。その轟音も。何度も「ごうおん」という音が、なのか、言葉が、なのか、轟音の中、わたしの頭に点滅した。どれくらいの時間、わたしはこうしているのか、わたしはわかってはいなかった。何度か暗くなった事はおぼえていたが、その記憶もわたしからは消えかけていた。それでもわたしは生きていた。息を吸い、吐いていた。心臓は休みなく鼓動し、他の臓器もそれぞれの役目をまだきちんと果たしていた。わたしはまだ生きていた。
「わたしはまだ生きていた」。だから、今、こうして過去形で語っているのである。だが「今」とはいったい何時のことなのか? そもそも「過去形」とは何なのか? 「中嶋」が「あんたとは駅で話すようになんなきゃいけないんだから、元気出してよ」「まだほんとうは俺はあんたに名乗ってもいないんだからさあ」と「わたし」に話し掛けてくる。「この事、思い出せるかな」と「わたし」はふと口に出す。「電車で会った時にさ」。男はもういない。水の音しかしない。 32。良いニュースと悪いニュース
二〇一三年四月十二日、村上春樹は書き下ろしの長編小説『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』を発表した。発売当日まで、題名以外の一切の情報は明らかにされていなかった。小説としては前作に当たる『1Q84 BOOK 3」が出たのが二〇一〇年四月十六日だったので、ほぼ三年ぶりの新作ということになる。それは、次のような物語である。 タイトルにある通り、主人公の名前は多崎つくる。三十六歳の独身男性で、西関東の鉄道会社の駅舎設計管理部門に勤めている。彼はどういうわけか、幼い頃から「駅」が大好きだったので、夢をかなえたのだと言ってもいい。実際には関東地方に新たに駅を作ることは稀であり、ほとんどの仕事は改修工事絡みなのだが。実家のある名古屋での高校時代、つくるには四人の親友が居た。頭脳明晰な優等生のアカこと赤松慶、熱血漢のラグビー部キャプテン、アオこと青海悦夫、誰もが認める美人で、ピアノを流麗に弾きこなすシロこと白根柚木、熱心な読書家だが、さっぱりとした性格のクロこと黒埜恵理。五人は高校のクラスのボランティア活動を通じて仲良くなり、あっという間にどんな時にも行動を共にするほど親密になった。まったくと言っていいほど性格やキャラクターは異なっていたが、むしろそれゆえにこそ彼らは他の四人に魅力を感じ、必要とし、惹かれ合ったのだ。ただ、つくる以外の四人は、姓に色を示す字が入っていた。だから互いに色のあだ名で呼び合うようになったのだが、色彩を持たないつくるだけは「つくる」だった。そのことにつくるは少しだけ疎外感のようなものを感じていたが、だからといって五人の関係に歪みはまったくなかった。それはまるで正五角形のように完璧な友情だった。 つくるは「駅」を造るという将来の夢のために東京の大学に進学した。他の四人はそのまま名古屋に留まった。それでも五人の仲に変わりはなかったが、大学二年の夏、二十歳を目前に帰省した折、つくるは何の前触れもなく、四人から絶交を告げられた。理由は説明されず、彼にも思い当たることは皆無だった。つくるは甚大なショックを受け、絶望し、放心して、引きこもり、一時は死を強く願うほどの状況に陥る。そしてギリギリの窮地から現実に引き返して来た時には、彼は激痩せして別人に見えるほどの変貌を遂げていた。それからの十六年間、彼は五人の元親友たちと一度も再会していない。そしてこの経験は、つくるの他者へ��かかわり方に、当然のことながら多大な影響を及ぼした。その後の大学時代に、たまたまプールで知り合った年下の大学生、灰田文紹(言うまでもなく、ここにも色が含まれている)と親しくなったが、灰田もまた唐突に、つくるの前から姿を消す。それからつくるは、けっしてそう決めたわけではないものの、男女を問わず、誰かと一定以上に距離を詰めることなく生きてきた。だがつくるは最近、仕事の関係で知り合った旅行会社に勤める二歳年上の女性、木元沙羅から、十六年前の五人組からの追放の真相を、今こそ確かめるべきだと言われる。彼女はつくるに「あなたはたぶん心の問題のようなものを抱えている」と指摘し、それを解決しなくては二人の関係は先に進めないと告げる。こうしてつくるは、長い時間封印していたパンドラの匣を開けるべく、彼の「巡礼」の旅に赴くことになる。 多崎つくるの「巡礼」は、故郷名古屋へ、そしてフィンランドの町ハメーンリンナへと、彼を誘う。そこで俄に明らかにされる遠い過去の思いがけない秘密と、そこから掘り出されてくる幾つもの新たな謎、それらに宿る途方もないやりきれなさと不条理、そしてつくると沙羅の関係の展開にかんしては、これ以上は述べない。それよりも、なぜこの『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』が、ここで取り上げられているのか、ということについて語らなくてはならない。全十九章から成るこの小説の第三章、つくるが死の間際から何とか生還し、だが体重が七キロも落ちていたという記述に続いて、次のような文章が置かれている。
死にかけているように見えたとしても、それは仕方ないかもしれない。彼は鏡の前で自らにそう言い聞かせた。ある意味では、おれは実際に死に瀕していたのだから。木の枝に張りついた虫の抜け殻のように、少し強い風が吹いたらどこかに永遠に飛ばされてしまいそうな状態で、辛うじてこの世界にしがみついて生きてきたのだから。しかしそのことがーー自分がまさに死にかけている人のように見えることがーーつくるの心をあらためて強く打った。そして彼は鏡に写った自分の裸身を、いつまでも飽きることなく凝視していた。巨大な地震か、すさまじい洪水に襲われた遠い地域の、悲惨な有様を伝えるテレビのニュース画像から目を離せなくなってしまった人のように。
この小説において、「二〇一一年三月十一日」に多少ともかかわっていると読める言及は、ただこの一箇所のみである。そしてこれは読んでの通り、喩えに過ぎない。周知のように村上春樹は、現代作家としては例外的なほどに比喩を多用する作家だが、ここでの「のように」は、この小説にも膨大に投じられている他の無数の「のように」とは、どこか性質が異なっているように思える。それは言うなれば、いささか唐突に、取ってつけたように見えるのだ。だがそれゆえにこそ、妙に気になってしまう。 もちろん、この点を取り上げて、村上春樹が自身のフィクションを無理矢理「震災」に結びつけようとしているとして批判することは可能かもしれない。ほんとうは全くの無意味な、単なる仄めかしでしかない、真摯さを欠いたはしたない行為であると。だが私は、それとは正反対のことを、これから主張したいと思うのだ。 物語がまだ始まったばかりの第二章で、つくるは沙羅に十六年前の出来事、これまで誰にも話したことのなかった辛い想い出を告白する(それはそのまま読者に対する過去の説明にもなっている)。彼女は当然のごとく、どうしてその時にちゃんと理由を問いたださなかったのか、と尋ねる。
「なにも真実を知りたくないというんじゃない。でも今となっては、そんなことは忘れ去ってしまった方がいいような気がするんだ。ずっと昔に起こったことだし、既に深いところに沈めてしまったものだし」 沙羅は薄い唇をいったんまっすぐ結び、それから言った。「それはきっと危険なことよ」 「危険なこと」とつくるは言った。「どんな風に?」 「記憶をどこかにうまく隠せたとしても、深いところにしっかり沈めたとしても、それがもたらした歴史を変えることはできない」。沙羅は彼の目をまっすぐ見て言った。「それだけは覚えておいた方がいいわ。歴史は消すことも、作りかえることもできないの。それはあなたという存在を消すのと同じだから」
「記憶を隠すことはできても、歴史を変えることはできない」。沙羅の言葉は、この『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』という小説の通奏低音として、物語の深い所に潜行しつつ、静かに鳴り響いてゆくことになる。タイトルにもある、かつてシロがよく弾いており、灰田がつくるにレコードをくれたフランツ・リストのピアノ曲集『巡礼の年』のように。それはつまり、一度起こったことは二度と消えない、ということである。あったことはなかったことにはならない。これはいわば当たり前のことだ。だがひとはしばしば、さまざまな理由から、時にはやむにやまれぬ事情によって、歴史=過去から目を背けようとするし、忘却どころか記憶や記録からの抹消を試みさえする。そしてそれに成功することもある。しかし、ほんとうは過去は消えてはいない。それはずっとそこにあり、あり続けるのだ。 だがしかし、それはそうであるとしても、なぜわざわざ、忘れた筈の、思い出すことをやめた筈の、ほとんどなかったことになりつつあった筈の過去への「巡礼」に向かわなくてはならないのか。それは、しなくてもいいのではないか。しなくていいのなら、しないままの方が幸せな場合だってあるのではないか。むしろそうすることによって、過去と現在が一直線で繋げられてしまうことによって、過去が現在に襲いかかり、すべてを台無しにしてしまうことが起こり得るのではないか。過去の中には、そっとしておくべきことが、誰にだってあるのではないか。そうも思える。そして実際、つくるの「巡礼」の旅は、世界そのものの悪意と呼んでもいいような、あまりにも酷薄きわまりない事実を明らかにする(登場人物のひとりは「それは悪霊だった。あるいは悪霊に近い何かだった」と表現する)。それでも、それを知らぬままに済ますことは「あなたという存在を消すのと同じ」だというのだろうか。最後まで知らずにいた方がいいことだって、人生には確実に存在しているのではあるまいか。 つくるは名古屋でアオ、アカと十六年ぶりに再会する。アオはレクサスの販売代理店でディーラーとして働いていた。つくるは彼から十六年前の絶縁の理由を聞かされる。それは想像もしていなかったものだった。アオはつくるに謝罪する。十六年経っても、彼は真っ直ぐな人間のままだ。東京の有名大学に十分受かるだけの優秀な成績でありながら、敢て名古屋大学に進学し、大手銀行に就職したものの二年でサラ金へと転職し、更にそこも辞めて自己啓発セミナーまがいのビジネスを始め、大成功をおさめているアカは、表面的には高校時代とはずいぶん人間が変わっていたが、それはむしろ時間と共に彼の芯の部分が露出してきたということかもしれない。アオはアカの商売を快く思っていないようだったが、つくるはアカの率直な話しぶりから、優等生の顔の裏に反骨精神を隠した昔の���人の姿を感じ取る。別れ際に、アカはつくるにふと、こんな話を披露する。 「おれがいつも新入社員研修のセミナーで最初にする話だ。おれはまず部屋全体をぐるりと見回し、一人の受講生を適当に選んで立たせる。そしてこう言う。『さて、君にとって良いニュースと悪いニュースがひとつずつある。まず悪いニュース。今から君の手の指の爪を、あるいは足の指の爪を、ペンチで剥がすことになった。気の毒だが、それはもう決まっていることだ。変更はきかない』。おれは鞄の中からでかくておっかないペンチを取りだして、みんなに見せる。ゆっくり時間をかけて、そいつを見せる。そして言う。『次に良い方のニュースだ。良いニュースは、剥がされるのが手の爪か足の爪か、それを選ぶ自由が君に与えられているということだ。さあ、どちらにする? 十秒のうちに決めてもらいたい。もし自分でどちらか決められなければ、手と足、両方の爪を剥ぐことにする』。そしておれはペンチを手にしたまま、十秒カウントする。『足にします』とだいたい八秒目でそいつは言う。『いいよ。足で決まりだ。今からこいつで君の足の爪を剥ぐことにする。でもその前に、ひとつ教えてほしい。なぜ手じゃなくて足にしたんだろう?』、おれはそう尋ねる。相手はこう言う。『わかりません。どっちもたぶん同じくらい痛いと思います。でもどちらか選ばなくちゃならないから、しかたなく足を選んだだけです』。おれはそいつに向かって温かく拍手をし、そして言う、『本物の人生にようこそ』ってな。ウェルカム・トゥー・リアル・ライフ」
いかにも自己啓発セミナー的に思えるこのエピソードは、先の沙羅の言葉と組み合わされることにより、この小説の核心を成す、重要なテーマを示すものだと、私には思える。この話が表している世界観/人生観のようなものは、読んでのごとくきわめてペシミスティックである。だが、ポイントは話される順番にある。まず「悪いニュース」が提示される。それはおそろしく惨い仕打ちである。出来ることなら回避したい。逃げ出したい。だが「それはもう決まっていることだ。変更はきかない」。この宣言は、明らかに沙羅の言葉と対になっている。彼女が「過去=歴史」について述べていたことを、アカは「未来」について語っているのだ。とにかく途方もなく惨いことが、これから行なわれるのである。それから「良いニュース」が提示される。だがしかし、そこには選択の余地がある。確かにそれはどちらを選ぼうと惨事には変わりなく、だから選択自体が虚しい行為と呼ぶべきかもしれない。だが選ばなければ、自分で選択しなければ、事態はもっと確実に悪くなるのだ。この場合、選択肢の決定それ自体には、実のところほとんど意味はない。そうではなくて、それでも選択する意志を持てるかどうか、悲惨の渦中にありながら、欠片ほどの自由を行使することが出来るかどうかが問題なのだ。どっちもたぶん同じくらい痛い。でもどちらか選ばなくちゃならない。だからしかたなく選んだだけ。そんなおおよそ積極的とは言い難い選択に対して、ウェルカム・トゥー・リアル・ライフという言葉が与えられることの意味、そこにこそ、どうして村上春樹が、突然この小説を書いたのか、という謎へのヒントがある。 最終章、つくるはフィンランドへの「巡礼」から戻ってきたが、沙羅にはまだ会えていない。彼女に報告することが、そして彼女にどうしても問わなくてはならないことが、彼にはある。物語は終わりに向かっている。だが、まるで終着駅の手前で急に電車が点検に入ったかのように、この小説は奇妙な停滞を見せる。つくるはJR新宿駅に来ている。彼はこの駅を眺めるのが好きだ。彼は朝のラッシュアワーの雑踏のことを考えている。「よく暴動が起きないものだ。事故による流血の惨事がもたらされないものだと、つくるはいつも感心する」。そこで、次のような記述が現れる。 もしそんな極端に混雑した駅や列車が、狂信的な組織的テロリストたちの攻撃の的にされたら、致命的な事態がもたらされることに疑いの余地はない。その被害はすさまじいものになるだろう。鉄道会社で働く人々にとっても、警察にとっても、もちろん乗客たちにとっても、それは想像を絶する悪夢だ。にもかかわらず、そのような惨事を防ぐ手だては今のところほとんどない。そしてその悪夢は一九九五年の春に東京で実際に起こったことなのだ。
村上春樹が、オウム真理教による地下鉄サリン事件の被害者たちに取材して著したノンフィクション『アンダーグラウンド』は、一九九七年三月に書き下ろしという形で刊行された。地下鉄サリン事件が起きたのは一九九五年三月二十日だから、ちょうど二年後のことだった。先にも述べておいたが、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』は、二〇一三年四月十二日に書き下ろしで刊行された。二〇一一年三月十一日の東日本大震災から二年と一ヶ月が経っていた。二つの出来事と二冊の本は、ほぼ同様の時間的な関係を持っている。このことは何を示唆しているのだろうか。何かを示唆しているのだろうか。『アンダーグラウンド』が地下鉄サリン事件に対して有していた位置と意味を、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』は東日本大震災に対して有している、たとえほとんどそうは読めなくても、ほんとうのところは、そうなのではないか。いや、むしろすぐにはそうと思えないからこそ、それはやはり、そうなのではないのか。そう考えてみると、この小説の物語、この物語のあらゆる挿話、それらの挿話の細部の何もかもが、実はすべて、あのことを語っている、語ろうとしているのではないかと思われてくる。 私はこれを穿ち過ぎだとは思わないし、殊更に好意的に解釈してみせているのでもない(何度も繰り返し述べてきたように、小説であれ何であれ、私は「震災」を取り上げること自体に意義があるとは全然思っていない)。村上春樹という作家の最大の特長は、彼の書く小説が、リアリズムからも私小説からも限りなく遠い、という点にある。村上春樹の作品には、現実がそうであるように意味性を欠いた要素はひとつとして存在していない。その意味が明らかにされないことはあっても、そこには必ず、それがそこにあり、それがそうであるということの理由が存在している。この意味で、村上春樹の小説は、基本的に現実世界との接点を持っていない。それは最初から最後まで作家の脳内にあるのだ。村上春樹の小説はリアリズムとは関係がない。それは常に一種のファンタジーなのである。そしてまた、彼の小説における主人公、一人称ならば「僕」と称し、三人称なら固有名詞で呼ばれる人物は、その物語を語り、この小説を書いている「村上春樹」自身と、他の作家とはかなり異なる形で、曖昧に混じり合っている。それは初期の「僕」たちよりも、近年の作品群、この『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』のような三人称小説において、その特異性を露わにする。たとえば先ほどの引用の最後の「その悪夢は一九九五年の春に東京で実際に起こったことなのだ」の「実際に」には強調を示すダッシュが振られているが、それは誰がしているのか? むろん、村上春樹がしているのである。この小説は、多崎つくるという主人公の視点と主観によって綴られていくわけだが、結局のところ、彼はいわゆる物語の主体とは、かなり違っている。つくるは自分を「色彩を持たない」空っぽの存在と感じているが、それを言うなら一色ずつを配された他の登場人物たちは、それぞれの役割と機能を作者から割り振られた、いわば叙述上の要素であるに過ぎない。色を持っていないつくるは、空だからこそ、彼にかかわる人物=要素たちが齎す、さまざまな真実や秘密や嘘や謎を、丸ごと包含することが出来る。そうして、多くの線路が交叉する「駅」をつくるのである。 「巡礼」の最後には、こんな場面が置かれている。
そのとき彼はようやくすべてを受け入れることができた。魂のいちばん底の部分で多崎つくるは理解した。人の心と人の心は調和だけで結びついているのではない。それはむしろ傷と傷によって深く結びついているのだ。痛みと痛みによって、脆さと脆さによって繋がっているのだ。悲痛な叫びを含まない静けさはなく、血を地面に流さない赦しはなく、痛切な喪失を通り抜けない受容はない。それが真の調和の根底にあるものなのだ。
私小説とは、作者が自分自身と同一か、でなくとも限りなく自分に近い存在を小説の中心に据えることにより、むしろ逆に「私」を虚構化してゆくプロセスのことだ。村上春樹がしているのはこれとは真逆である。彼は「多崎つくる」というあからさまな虚構の存在を拵え、その周囲にやはりあからさまに虚構の何人かを拵えて、その関係性の内側に幾つかの虚構の事件を配して、そうすることで、そうすることによってしか可能ではないやり方で、紛れもない現実に起こった、けっして忘却も消去も出来ない過去に起こった、二年前のあの出来事に対して、小説家として、言葉を差し伸べようとしている。彼には言いたいことがあったのだ。『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』は「以後の小説」である。
33。「言葉たち」、イントロダクション
あれから二年と数ヶ月が過ぎた。あの日に起こったこと、あの日から起こったこと、今もまだ続いており、いつまで続くのか、いつ終わるのか、いつか終わるのか、いつか区切りが付けられるのかどうか、そもそも何をもって区切りと呼んだらいいのかもわからない、ひと繋がりの、だがけっしてひとつではない、無数の出来事にかんして、たくさんの言葉が、対話が、鼎談が、議論が、さまざまな機会に交わされてきたし、今も交わされている。私は、そうした「あの日」と/の「以後」にかかわる「言葉」の応酬を、幾つも読んできたし、時には直接耳にしたこともあれば、時には(ごく限られた機会にではあるが)自分自身が語ったこともあった。 それらの「言葉たち」の中から、幾つかの断片を拾い出して、以下に並べてみたいと思う。配列はランダムだが、読み進む内に、前後の文脈から抜き出された「言葉たち」が、本論がこれまで辿ってきた道程と、さまざまに響き合ってゆくさまに気づかれることだろう。尚、引用はひとつのまとまりごとに行なっており、基本的に省略はしていない(一箇所だけ中略した部分は「*」で示しておいた)。
34。「言葉たち」その1、ノイズ
高橋源一郎 このあいだ、千宗屋さんていうお茶の武者小路千家の次代の宗主になる人の茶室に招かれたんですけど、その茶室は麻布にあって、東京タワ−向きに窓が作ってあって、反対側には六本木ヒルズが見えるんですけど、茶室って行ったことあります? いい茶室。 大友良英 お寺とかにあるのを見学させてもらったことくらいしかないですね。 高橋 茶室って、千利休が基本形を作ったんだけど、まず狭い、そして暗い。入る時に狭いにじり口から入って、暗いのに窓もない。そしてこれがおかしいんだけど、茶室には掛軸がかけてあって、お茶の作法では、最初にそれを見なくちゃいけない。見て何かを言うわけです。だったら、合理的に考えたら、「明るくしろよ!」ってなる(笑)。鑑賞するっていうのが作法に入ってるのに、わざわざ暗く、ほとんど見えない状況にしている。「なんでこんなことしてるのかね?」って訊いたら、「感覚を鋭くするためです」と。 つまり普段の僕たちは、実は何も見てないんです。明るい中で目に入ってくるものを受け止めているだけ。見るっていうのはお茶で言う「拝見の型」みたいに意識を働かせて、対象に前身して、全神経を込めて見るっていうのが、本当の「見る」。だから普段の「見る」は、見ているうちに入らないっていうのが茶室の思想なんですね。音についても、茶室は真っ暗だから目の次に頼るのは聴覚です。茶室ではお湯を沸かしてるでしょ? 茶を立てる時に何をしてるのかと言うと、お湯がどういう状態かをずっと聴いてるんだって。ずっとシーンとしてるので、聞こえてくるのは自分の鼓動とお湯の音だけ。それではじめてものを考える、と。ここにはある種の合理性がありますよね。一瞬ノイズと反対のような感じがするけど、でも、これは暗くしてノイズを増やして、そして見る、ということ。 なんでこんな話をしたかというと、これを社会にあてはめると、社会のノイズっていうのは弱者なんです。障害を持っている人とか老人とか病気の人とかっていうのはノイズで、そういう人がいないほうがいいって考える。でも、それだと殺さないといけないので、どうするかと言うと、施設に入れちゃう。つまり遠ざける。昔はみんな家にいたでしょ。だから、ノイズが周りにあった。これは実は全部同じ問題で、近代というのは、すべてのノイズをなくそうとする時代です。するとどうなるかと言うと、わかりやすくなって、強い人だけが残る。意味があるものだけ。そうしたかたちが続いてきて、それが今の社会を作っている。だからね、音楽のノイズが一番正当的なんですよ、大友さん!(笑) 大友 いやいや(笑)。でも、ノイズの世界にいる人たちってやっぱ���どこか感覚的にそれがわかっているところがあると思うんです。そうやって社会が不要としてたものの中に、自分にとっての大切なもんが実はいっぱいあって、そのことを感覚的に、もしかしたら身体感覚のような感じで知ってるんですね。どうもみんな、強いものとか権威のあるものに対して牙をむくクセがついちゃってるのは、そのためだと思うんです。それは反体制とか、政治的なポジショニングとは明らかに違う。もっと生きてくことの原始的な感覚として、そうなってるような気がします。 (大友良英×高橋源一郎「世界のノイズに耳をすませて」、『シャッター商店街と線量計−ー大友良英のノイズ言論』)
35。「言葉たち」その2、花火
中沢新一 日本のデモの様式は、本当に「様式」です。型がもう決まってしまってるんですね(笑)。僕が学生のときにデモというと、もう「序破急」みたいな……。何か、そういう独特のスタイルがあった。 國分功一郎 (笑) 中沢 でも、外国のデモを見ていると、あまり様式がないでしょう。道端までいっぱいに拡がって、みんな勝手にシュプレヒコールを叫んでいる。そういうのを見ていると「やっぱり日本は様式の国なんだな」と感じますよね。安保闘争のときのデモにもはっきりした様式があって、これに対する機動隊も様式的に振る舞っていた。しかも、そういうデモってだんだん組合主導になってくるじゃないですか。組合主導のデモの様式というのが、また気に入らなかったなあ。 國分 たぶん、みんなそれが嫌で、だんだんやらなくなったんでしょうね。 中沢 センスが悪いから(笑)。それでセンスのある人たちはデモに行くのが嫌になっちゃった。でも、この間の首相官邸前デモではずいぶん風景が違いましたね、半分くらいが「ファミリー・エリア」にいて、「どこが一番よく見えるの?」とか会話していて、これはもしかして花火大会なのかなと(笑)。近年のデモの様式の変化には、高円寺の「素人の乱」のサウンド・デモの影響も大きかったとは思います。 國分 流れている音のリズムや雰囲気もお祭りに近いものでしたね。 中沢 花火大会とデモが接近しているんです。花火大会だと、みんな動かなくていいじゃないですか。デモにおいては「動く」ということは重要な要素ですが、同時に動くと危険性も発生します。歩いていると、押されて警官にぶつかったりして、場合によっては公務執行妨害で逮捕されますからね。でも、花火大会の場合は動かない。動いてくれるのは花火ですから(笑)。集まっているだけで動かなくてよかったというのが、官邸前デモが拡がった大きな要因の一つじゃないかな。 (『哲学の自然』中沢新一、國分功一郎)
36。「言葉たち」その3、アクチュアル
相馬千秋 今回の『光のない。』『光のない II 』の上演は、震災へのいち早い、演劇からの応答でした。しかし、それを持ってアクチュアリティがある、だからよいというふうに受け取られるのは本意ではないんです。では、単なる内容主義や時事ネタではない形で、社会に演劇が必要とされるためにはどうすればいいか。演劇はどのように他のメディアと拮抗し、その特性を発揮できるか。そういった演劇の「政治性」について皆さんはどう考えられていますか。 高山明 僕は結構、『国民投票プロジェクト』なんて名前のせいもあって、政治的なものをモロに扱う作家だと勘違いされるんですよね(笑)。でもあれだって実際は中学生のインタビューを見せているだけで、内容として政治的なところはないし、そもそも政治運動に興味があるわけでもない。それよりは、さっきの「迷子」の話みたいに(註:これに先立つ部分で高山は、迷子になった外国人が道を尋ねているのを見て、奇妙な感覚に襲われたと語っている。「そこで感じたのが、この失調感覚は、震災後、僕が一時パニックになった時の感覚と似ているなということでした。秩序の崩壊を目の当たりにして、何かがおかしいけれど、それが何かは分からないまま過ごしていた頃の、放射能を体に感じられるくらいのビリビリとした感覚が、その時蘇ってきたんです」)、作品を通じてその人の置かれた環境や思考に亀裂を入れたり、溝を作ったりするようなことができれば、その方が政治的なんじゃないかなと思います。ですから「アクチュアリティ」という言葉は、僕の中では「距離」という言葉と結びつきます。三浦さんも以前発言されていましたが、みんなが共有している時事ネタを扱って、「これがアクチュアルだ」というような舞台は僕も勘弁です。むしろ、そういう距離のない状態になってしまったものに、いかに距離を入れられるかを考えていった方がいい。たとえば、新橋を歩いていても、一九七一年という年を思い出すことはない。でも、『光のない II 』の出発地であるニュー新橋ビルと、福島第一原発が、同じ年に作られたというふうに並べられることで、一九七一年が呼び起こされてくる。そうやって「いま」という時間に中断や亀裂が入ることをアクチュアルと呼びたいし、政治的と呼びたいなと思っています。 三浦基 僕が批判したのはマスメディアで「絆」とかいってお金を集め、思潮社を動員するような、安いモラルのことなんです。もちろん演劇だって政治に利用されることはあるし、いろんな宣伝文句を使って動員したりもします。特に日本人はみんなで集まってワーッと盛り上がりたいってのがあるし。でもそういうことに歯止めをかける効果は必要だし、意義のあることです。それも税金を使って、経済としては絶対に無理なことをすることに意味がある。ダメな芸術家は「経済効果にはならないけどやる価値があるんです」って言う。もっとダメな人は「少しでも興行収入を増やして、半官半民でやります」って言っちゃう。でも、そういう経済の論理に呑み込まれること、その議論に参加すること自体、絶対にしては行けないと僕は思います。基本的には、現代演劇は無駄。でもしょうがなくて、やるしかない(笑)。それが豊かなことなんだと、私たちは言っていかなくてはいけない。イェリネクの上演にしても、原発の問題を扱うのは辛い。でもそれは日々、われわれが問われていることだし、うすうす抱いているマスメディアへの違和感を提示するきっかけにもなる。それがまず必要なことなんです。 (高山明×三浦基×林立騎×相馬千秋「ことばの彼方へーーイェリネクの演劇言語をめぐって」、『フェスティバル/トーキョー12ドキュメント』)
37。「言葉たち」その4、儀式
磯部涼 小熊さんが言う官邸前デモの達成とは、著書『社会を変えるには』のあとがきで柄谷行人氏の言葉を引いて書かれているように、「デモをやって何が変わるのか」と問われれば「デモができる社会が作れる」ということですよね。そこをどう評価するのか、という問題にようにも思えるのです。 東浩紀 僕は、「デモをやることによってデモができる社会が作れた」というのはトートロジーなので、意味はないと思う。たとえば、「ゲンロンカフェを作ることによって、こういうスペースができる東京になりました」などと言っても仕方がないわけで、スペースを作ったらその次のステップを駆動するために別の目標を決めなくてはいけない。 小熊英二 それについての私の意見は『社会を変えるには』でもっと詳しく書きましたから、ここではくりかえしません。東 言い替えれば、僕はある種の「儀式」を求めている。形式主義者なんだと思います。僕は脱原発というのは「メッセージ」でいいと思っている。「何年までに全廃」とか具体的な行程の話になると、必ずいろいろなところから異議が出て潰れてしまう。そうではなくて、「福島という悲惨な事故があった以上、われわれは基本的に原子力をなくす方向でいきます」という、極めて抽象的なメッセージを掲げて、それを国是としていくというのが大事なんです。 いま政治というとすぐ実現性を求められる。実際にスケジュールを切って、「何年までに脱原発できるの?」と問われれば、いくらでも反論が出てくる。でも僕は原発の問題に関しては、「基本なくす」ということをきちんと宣言し、抽象論として共有するということこそ、政治の役割だと思うんですね。 * 東 民主主義は、そもそもそういう儀式がなくては成立しないものだと思います。 小熊 私の言い方に翻案すれば、「原発が止まることだけが目的なのではなくて、『自分たちの力で止めた』と思える事が大切だ」ということですね。それは冒頭に私が言った運動の二つの評価基準(註:「ひとつは、政策的な運動の目的を設定して、それに即して手段を考えるということ。もうひとつは、目的達成のために人々が参加して、それを通じて成長していくということ」)で言えば、政策的な目的を実現できればいいだけではなくて、みんなが力をつけて政治決定に参加できた自覚を持てることが大切だということです。儀式が必要だというのは、ある意味ではロマンティシズムかもしれないけれど、それがないがために、政治や運動に対する無力感を現実以上に広げてしまったことの影響は大きいですから。 東 日本では99までは成果が積み上がるんだけど、最後の1個のピースがいつもない。僕がこの5、6年ずっと思っているのは、ある種のビジョンを立ち上げることが必要だということです。ビジョンと言うと「大きな物語」のようで悪い印象がありますが、それは「最後の一歩」のことなんですよ。実質をずっと積み上げていった時に、最後にそれをどう名付けるか。そういう儀式が必要なんです。この名付けるという行為がないと駄目なことってあるんです。 (小熊英二×東浩紀「どう“社会を変える”のか」、『踊ってはいけない国で、踊り続けるためにーー風営法問題と社会の変え方』磯部涼編著)
38。「言葉たち」その5、パノラマ
伊東豊雄 2012年の初めに東京都写真美術館で畠山さんが展覧会をされて、最後の部屋で被災前の陸前高田と被災後の陸前高田の写真を同時に展示しておられましたね。ヴェネチアでも同じように被災前と被災後の展示をされて、さらに、会場全体を取り巻くパノラマ写真で被災後1年以上経った陸前高田の写真を展示されました。 畠山さんの写真は、僕が今まで見た畠山さんの写真の中で最も感動的というか、こんなに沈黙してる写真はないと思ったのです。カタストロフィの悲惨な風景でもなく、かといって日常的でもない、あの写真が沈黙すれば沈黙するほど、逆に何かそこに込められている思いみたいなものがすごく伝わってくる。 畠山さんは、昨年お願いした時点では「僕はまだ写真を撮る期になれないんですよ。とてもそんな前向きな気持ちにはなれません」と言われました。決して前向きにとらえた写真ではないのですが、でもあの会場(註:第13回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展。伊東豊雄のディレクションの下、乾久美子、藤本壮介、平田晃久の三人の若い建築家と、写真家の畠山直哉が参加した。この展示は彼らが陸前高田で取り組んできた「みんなの家をつくろう」プロジェクトのドキュメントとなっている)を覆っていた写真1枚によって、畠山さんはきっとまたひとつ新しい境地に到達したんだなということを実感したのですが、ご本人がいかがですか。 畠山直哉 写真家はとても不思議な立場に置かれている人種です。自分の行為をよく理解できないんですね。 私は今回、4人のアーティストのひとりとしてクレジットされていますが、同時に国際交流基金のカメラマンを奉仕で兼ねました。それで会場設営作業なども撮っていたのですが、展示が完成して「じゃあ、みんな並んで撮りましょう」というときに、僕はカメラの後ろにいるでしょう。そうすると、参加アーティストとしての僕がフレームの中にいないことになる。伊東さんたちがあわてて「畠山さんも入ってくださいよ。こっち、こっち」と呼ぶんですが、もし僕がそっちに行ったら、シャッターを切る人がいなくなる。 まぁ、そのときは、僕もにこにこ笑いながらみんなの間に入って、誰かにシャッターを切ってもらったのですが、そういうときに、カメラマンというのは、やっぱり出来事の外に出なくちゃ仕事にならないんだな、ということを深く感じます。 僕は常に出来事の外に出るという癖がからだにしみついています。だから、大変な出来事を前にしても、自分で意識しないままに、ついそこから外に出ちゃうという態度で振る舞っていることがあまりに多くて、自分でもちょっと精神的にこれは危機ではないのかと思える瞬間がたくさんあります。 日常そういうふうにして写真を撮っていますから、実際に写真を褒められても、ピンとこないわけですね。たぶん時間が経つと、あのときの自分の行為はこういうことだったんだなとわかる瞬間がくるかもしれませんが、今、伊東先生がおっしゃったパノラマ写真で新しい境地に達したかどうかは、今のところ、あまり自分では分析できていないです。 伊東 畠山さんが、写真家はそうやって外側に立たなくてはならないと。そのことをさっきナレーターという言い方で言われたのだと思いますが、あのパノラマ写真は、写真技術の問題としてどうか、あるいはカメラの使い方がどうかという���題を抜きにして、今年の初めに写真美術館で見た畠山さんの被災後の写真は、外側に立てていないという感じがすごくしましたが、今回派もう一度外側から見ることができるようになったのかな、という気がしています。それと畠山さんには陸前高田とほかの場所を撮るのではまったく違う想いがあって、やはりそこがビエンナーレの写真の感動に繋がっているのではないでしょうか。 畠山 そのパノラマ写真について補足しておきますと、あれは今年の6月24日にもと陸前高田駅があった場所のそばにある瓦礫の丘から撮ったものです。撮影をしながら気がついたのですが、カメラをパノラマ雲台に載せてパンニングしていたら、県立高田病院の建物がファインダーに入ってきて、その4階の破れた窓にファインダーの中心線がピタッと合った。そのときに僕は、「あっ、そういえば、あそこまで津波が来たんだっけ!」と思い出したんですよ。カメラは完全に水平が出ているわけですから、僕がそのとき立っているところ、僕のカメラのレンズから下も、水だったんだ!と、その瞬間想像できました。 そう想像しながら、360度のパノラマ写真を24カットに分けて撮影しました。ですから日本館の壁に写真を展示したときは、そのことを英文で入れました。「この写真は津波が来た高さと同じ高さから撮られています。ここから下はすべて水没していたのです」と。目の高さにその文章がありますから、読み終えた瞬間に、自分の目から下が水没しているという想像を観客に与える。そういう効果もあの写真にはあります。 (『ここに、建築は,可能か』伊東豊雄、乾久美子、藤本壮介、平田晃久、畠山直哉)
39。「言葉たち」その6、消失/喪失
和合亮一 自分が消滅するということをどうして求めるのかなってずっと考えてきたんですが、今回の震災で少しわかった気がするんです。消滅する、消えていく、消失する、言葉を失う、家族を失う、平穏な日常を失う、……いろんなものを失ってきたし、あるいは失ったひとをたくさん見てきた……。だからこそ、よりはっきりしてくる「生」といったらいいのかな。一回、一回、そういうものを求めたい、はっきりとした存在を求めたい、確然とした世界を求めたいから、自らの手で消滅させるんだなって思った。言葉を失って、写真を撮ってもう一度、言葉を取り戻した感覚を持ったとき、震災前までは自分の言葉にしがみついてたんだなってわかったんです。やってきたことにしがみついていて視界を狭くしていた。でもすべて消し去って、ぜんぶ投げ出したときに、すごく拙い何かが自分のなかに現れてきた。そういうことを能楽師のかたはおっしゃっていたのかもれないって(註:この直前に、和合は能楽師の津村禮次郎と会話に言及している。「能楽でいちばん自分がうまくいっているときってどんなときですかってお聞きした。そうすると即座に、自分がこの世界にいないって思えたときだっておっしゃった」)。 吉増剛造 言葉を変えると、本当に巨大な喪失、底知れない喪失、あるいは巨大な虚無みたいなもの、……それが世界の次の光を見せるんだよね。……その声を聞かせるんだよね。だからそれは作品、とくに詩をつくっていると必ずぶつかります。いろんな雑音が出てくるし、いろんな言説が出てきますよ。だけどね、それを突破するようなときと、生きかたを与えられたんだよね、……。歌声とシャッターから、何かが詩の傍に出てきた、……ヴィジョンが出てきた、……だから今度の詩集がたいへんな評価を受けるとかさ、芸術家ってそういうことを考えるし、そういうことも大事ではあるけれども、本当はそれだけじゃない、……もっともっと大きな洞穴の眼みたいなものを見たからさ、……だから、これからダンテの『神曲』みたいなものを書かなくちゃいけないのかもしれないし、……だね(笑)。 (吉増剛造×和合亮一「四辻の棒杭、つぶやきの洞穴」、現代詩手帖二〇一三年五月号)
40。「言葉たち」その7、アート
宇川直宏 デモの話なのですが、まず3・11に関するデモはエクストリームである必要性がないのではないか? と。今回の場合は、別に社会的に威圧された少数派の主張を公の場に唱えているわけではないですから。「反原発!」「NO NUKES!」これは八〇年代のハードコアパンクのクリシェでもありましたが、放射性物質によって生活環境が汚染されてしまって、健康が脅かされ、内部被爆の危険に晒されている現状、脱/反原発は大衆の生の声であり、すでに全体意志である訳だから、別にここでエクストリームな主張はむしろ必要ないとさえ思います。マイノリティを含め様々な立場に存在する日本国民が連帯して、法で定められたルールにのっとったうえで、原発問題と対峙して、広く大衆にその主張を知らしめることが目的ですから、逆にマジョリティとしてのアピールが必要なんですよ。つまり暴走しないほうが国民の声として拡散されて行くし、賛同者も増える。DOMMUNEではデモの番組をたくさんやっていますけど、表現のスタイルとしてのエクストリームはけっこうありますよ。このまえ「怒りのドラムデモ」というのがあったんですが、とりあえず打楽器を持っている人たちだけがただ叩いているだけ(笑)。もちろんスネアでもジャンベでも和太鼓でも、自転車のベルでも、フライパンでも、クッキーの缶でもなんでもいい、利権を守っているやつらの鼓膜をぶち破るように、抗議の感情でドラムを叩き続ける!(笑)これは表現として、ある意味エクストリームですよね。 東浩紀 うーん。しかしそれははたしてデモなんでしょうかね。 宇川 デモです。つまりデモは社会の注目を集めて、公共の側に主張を拡散していく、それを世論に変えて行くことが目的なので、怒りや悲しみが、大衆に伝わるのであれば、どんな表現方法をとってもいいわけですよ。しかも現代のデモは、ゴミ拾いも同時に行なわれているので、デモ隊が通ったあとの路上は綺麗になっています。これって巨大な掃除機ですよ。デモ隊はダイソン以上の吸引力(笑)。これって現代アートの世界では赤瀬川原平さんたちハイレッド・センターが、メンバー全員白装束で、とにかく掃除して街並みを綺麗にしてみせた「首都圏清掃整理促進運動」という直接行動と同じで、暴力的なパフォーマンス以上にむしろ異質、ゆえにアピールとして成功しているのだと捉えることもできます。 東 ちょっと意見が違うかな。 僕は、むしろそういう行動は、逆に世の中で許されている感じがするんですよね。居場所が確保されたうえで変なことをやっている。そもそもいまでは、「アート」という言葉自体、本来はエクストリームだったものに社会的な承認を与え、馴致するために使われるものになっているでしょう。要は、「アート」と名づけられた瞬間、攻撃性を失ってしまうわけです。デモにも同じことが言えないですか。だから僕としては、『思想地図β』で震災特集号を作ることを選んだのだけど。 たとえば柄谷行人さんが、反原発デモで「デモをすることによって、日本の社会は変わる。なぜならば人がデモをする社会に変わるからだ」と演説をしていました。僕はちょっと待てと思うわけです。いま柄谷行人に求められるのは、そんな自己肯定的な演説をして聴衆に拍手されること��のか。むしろ柄谷行人は本を書くべきではないのか。デモに一〇回行くよりも本を書くほうがずっと大変なはずではないのか。これはいま、言論人やアーティストがなにをやるべきなのか、一般的な問題と関わっています。政治運動、イコール、デモみたいな発想は疑問です。 宇川 仰るとおり、3・11以降、東さんのような言論人、そして僕のようなアーティストは、どんなアクションを起こすのか? 社会示唆的な価値を問われているのは確かです。とくに自然災害のような人知の及ばない強大な力を見せつけられたあと、作家の本質は炙り出されますからね。でも僕らはそんなステージに本来立っていたのだし、それは作家の宿命だとも言えます。なので、柄谷行人さんは、本を書きながらデモに参加すればいいのだと思います。 (宇川直宏×東浩紀「「ばらばら」から始まるエクストリーム」、東浩紀対談集『震災ニッポンはどこへいく』)
41。「言葉たち」その8、言語
山田亮太 3月11日の後に、詩人の中でもいま詩人は何をすればいいのかと多くの人が考えました。沈黙する人もいれば、いまこそ詩の力をと積極的に行動する人もいました。外からも詩の言葉が求められることが多かったと思います。そんな状況を谷川さんはどう考えられていたのでしょうか。 谷川俊太郎 僕は被災者じゃないから書かないという立場ですね。出来る限り平常心を保った方がいいと考えているから、津波とか震災のことを気にしないようにしてるんだけど、意識下にはあるから、書くと自然にそういうものが出てきてるとは友人に言われましたね。詩ってそういう多義的なところがあるから、流行ったんじゃないかと思うね。 山田 書きたいという衝動はなかったですか? 谷川 ないですね、ぜんぜん。僕は自分から書くとかないんだもん。「どういう気持ちで書いてますか」ってよく聞かれるけど、「原稿料いくらかなと思って書いています」って言うと凄いしらけるのね(笑)。僕はあまり言語を信じていないんですよ。だから書けたところがあって、ああいう災害があった場合に自分の詩が役に立つっていう意識では書けないんです。和合(亮一)さんは自分も被災者として何か言いたくて仕方がなかったし対話したかったというのは凄く理解できるんですが、僕は災害について詩を書くことには後ろめたさがあります。いくつかは書きましたけどね。詩を書くくらいならお金を出した方がいいという立場です。 (現代詩手帖特集版『はじまりの対話 Port B「国民投票プロジェクト」』)
42。「言葉たち」その9、日本語
高橋源一郎 震災の直後、作家たちはみんな「書きにくい」という話をしていました。なぜ書きにくいのかというと、自分の書いたものが読めないんです。日常生活の底に潜む危機とか夫婦の不安とか、存在の不安とか、バカバカしくて書けないし、読めない。つまり、いままでの書き方では危機に対応できない。ただ、これは震災に始まったことでもないという気がします。どういうことかと言うと、ちょうど一週間前に、同じ会場で古井由吉さんの作品集の刊行を記念してトークイベントがありました。僕も登壇したのですが、そこでおもしろいなと思ったのは、古井さんはいま七五歳で、震災以降も書き続けていて、日本文学の王道を行くような人にもかかわらず、自分では全然そう思っていないと言ったんです。僕はその理由を聞いてびっくりしたんですが、自分より若い作家たちは文章がきれいすぎると。彼はいわゆる「内向の世代」に属する作家ですが、彼ら以前の作家たちは、そもそも文法的に誤りがあったり、てのをはが間違っていたりと、文章がめちゃくちゃだった。それに比べて若い作家たちはなぜ、みんなきちんとした日本語を書いているのだろう、と疑問に思ったと言うんです。すごく繊細に、細かな違いを描き出そうとしているのだけれど、その前にもっと考えるべきことがあるだろうと。たしかに古井さんの小説は、いま読んでも日本語が変なところがある。 なにを言いたいのかというと、僕はやはり三月以降、ほとんどの小説が読めなくなりました。自分のなかで言葉に対する感覚がものすごく鋭くなっていて、まさに危機対応の状態なので、ほとんどの小説が読めなかった。たとえば和合亮一さんの詩も、すごくまじめに書かれているのだけれど、だからこそ読めない。一方で、古井さんの文章は読めたんですよ。なぜかと言えば、いろいろなものが間違っているから。つまりどういうことかと言うと、きちんと書けるということは、文章のことしか見ていないということでもあるのではないでしょうか。この世界についてもっと知りたい、それを書きたいと思うと、言葉がおかしくなるはずです、もちろん、小説家は技術によって言葉を整えるのだけれど、そういう、言葉しか見ていない作家の文章は読めなくなってしまった。僕は3・11以降とくに顕著になったのだけれど、本当はいつでもそうでなきゃいけないのかもしれない。 (高橋源一郎×市川真人×東浩紀「3・11から文学へ」、『震災ニッポンはどこへいく』)
43。「哲学」に何が出来るか?
最初からそのつもりだったわけでは必ずしもないのだが、結果として本連載は、二〇一一年三月十一日に起きた東日本大震災と、それに続く福島第一原発事故、ふたつの固く結びついた出来事によって分割されたとされる時間軸をめぐって、より精確に言うなら、あの日「以後」ということ(「問題」という語は敢て使わないでおく)へのかかわり合い、コミットメントのありようをめぐって、とりわけ広義の「芸術」や「表現」或いは「言論」と呼ばれる領域において、私なりに思考を巡らせてみる、というものになっていた。それはもとより何らかの答えなり結論なりを目指してきたわけではない。私はただその時々に出会った/見知った「芸術」や「表現」や「言論」か���対象を選び、言葉を書き連ねてきただけである。そしてその道程も、まもなく終わろうとしている。 デイヴィッド・ヒューム研究を出発点とする一連の因果論(『原因と結果の迷宮』『原因と理由の迷宮』『確率と曖昧性の哲学』など)で知られる哲学者の一ノ瀬正樹は、茨城県南部の自宅二階の書斎で、あの日あの時を迎えた。「最初はいつものこととたかをくくっていた。しかし、揺れが激しさを増す。ドアの敷居のところに行って身を守ろうとする。まもなく、生まれて初めて経験する大きな揺れが襲ってきた」。
ここから新しい世界が始まった。まもなく水道が止まり、電気もストップした。私はラジオを持っていなかったので、その日の晩遅くに車載のワンセグでテレビが見られることに思い至るまで、一体何が起こったのか分からずにいた。ようやく情報を得て、東北地方でとてつもないことが起こったことを知る。巨大地震と大津波、東日本大震災である。下半身から力が抜けていくような感覚を覚える。数日間、ロウソクともらい水の生活をした後、ようやくライフラインが復旧するかと思った頃、津波震災の結果として、福島第一原子力発電所一号機から四号機までが次々と爆発した映像を目の当たりにすることになる。三月十二日から十五日にかけてのことである。
それから約二年の時を経て、一ノ瀬正樹は『放射能問題に立ち向かう哲学』という書物を上梓した。右はその「はじめに」から引いた。このように(誰もがそうするように)自身の体験と実感の記述から始めながら、この本の著者の姿勢は、他の数多の「以後の論者たち」とは、かなり異なっている。この本は「東日本大震災と原発事故に起因する放射性物質拡散の問題について、原発それ自体の是非をめぐる政治的問題性やイデオロギー性から一旦切り離して、あくまで放射線被爆の健康影響にまつわる事実認識・事実評価を論じるというスタンスから、哲学専攻の著者が少しずつ書きためてきた哲学ノート」なのである。 『放射能問題に立ち向かう哲学』で展開/吟味される主張は主として四つ、それらはあらかじめ「はじめに」に提示されている。以下に掻い摘んで記すと、(1)「たとえかりに被災地からやや離れた地域に住む人が、放射線被爆によって二〇年後に病死するという事態が発生したとしても、二〇一一年三月十一日に津波によって溺死や打撲死したという人々の方が、圧倒的に余命が短かった」のだし、また「避難生活や仮設住宅暮らしを余儀なくされている方々の、そうした生活に起因する苦悩も、現在進行形の物理的な苦しみであり、晩発的な苦しみよりずっと実在的である」。従って「放射能問題」ばかりクローズアップすることは、却ってマイナスになりかねない。(2)「放射能が原発から漏れ出してしまったという事実はすでに起こってしまったのであり、キャンセルできない」。ゆえに「日本に暮らす限りは、以前よりなにがしか多い不必要な放射線被爆をする蓋然性がやや高いという事態(現存被爆状況)に向き合うしかない」。だからこそ「現存被爆状況」を「程度の問題(a matter of degree)」として冷静に認識しつつ、「この環境の中で私たちはどのように生き抜いていくか、どのように社会を構築し、復興していくか、ひいてはどのように生きる目標や喜びを見いだしていくか」を課題にするべきである。(3)だが「少なくとも放射線被爆という生体的影響に関わる点では、外部と内部の両方の被爆に関して、最初に懸念されていたほどには深刻にならずにすんだという事実も確認するべきである」。「被爆線量の情報からして、余計な被曝はせいぜい胸部CTスキャン一回の医療被曝と同程度」か、それ以下である。そしてこれは国や電力会社の責任や原発の是非とは別個の問題である。 (4)しかしながら「津波震災そして原発事故が人々の心に及ぼした影響は、大変に甚大である」ことは言うまでもない。それゆえに不安や不快や不信、不当な差別や不毛な論争などといった「不の感覚」が、今も大量に社会全体を覆っている。「もしかしたら、この事態こそが放射能問題がもたらした困難の核心、最大の有害性かもしれない」。このような事態の克服をこそ目指さなくてはならない。そのためには「一つの発言、一つの行動には、良い面と悪い面の両方が伴う」という「道徳のディレンマ」に敏感であることが必要である。 これら四つの論点を、一ノ瀬氏は本文で「専門家や有識者の見解に学び、それに沿って考えていく」。『放射能問題に立ち向かう哲学』に先立ち、伊東乾(音楽)、影浦峡(情報論)、児玉龍彦(分子生物学)、島薗進(宗教学)、中川恵一(放射線医学)の諸氏と交わした討議と論考を纏めた『低線量被曝のモラル』も出版されている。各論点の詳細には立ち入らないが、かくのごとき一ノ瀬氏の主張が、少なからぬ反論や疑問に晒されるであろうことは想像に難くない。とりわけ「反原発」をエモーショナルに信奉しているような者には、おそらく大いに不満だと思われる。『放射能問題に立ち向かう哲学』の「おわりに」で、一ノ瀬氏は、現在の状況下では「安全性の度合いを高めること」と「度合いが高められないことが判明したものは少しずつなくしていくこと」、すなわち「度合い」と「少しずつ」という二つの概念が必須であると述べ、だがこのことがなかなかわかられていないと書く。「しかし、どうも私とは異なる捉え方をする方々がおられた。「度合い」と「少しずつ」という論点などは関係なしに、「いかなる被曝も危険」とか「不安を抱くのは当然」といった言説が流通し、そういう捉え方がむしろ社会正義を体現するかのような報道が多々なされたのであった」。
放射線を徹底的に避けること、そういう行動が容易に実行可能であり、しかもそうすることで別の害を発生させないのであるならば、そういう行動を取ることはまったく個人の自由だし、むしろ推奨されるだろう。けれども、残念ながら、私たちの世の中の多くのことは、もっと複雑なのである。一つの害を避けるという行為はそれ自体としてはの労力を必要とするのであり、そのことによって、別の害を産み出してしまうことがあるのである。(略) 放射線被曝を避けようとする「避難」という行為に、まさしくこのことが当てはまる。正直なところ、(中略)いかなる被曝も危険だと主張する方々が何を述べたいのかが私には本当の意味では理解できないのだが、もしそれが、福島原発周辺の広範な地域に住む人々に「避難」を勧めているということだとするならば、それは、現状に関するこれまでのデータからして、有害な勧奨であることはほぼ間違いない。人々を救うどころか、かえって人々を苦しめ、場合によっては死に至らしめてしまいかねない、迷惑な、そして危険な勧めである。(略)ネットなどを通じて、子どもを守るのは親の当然の務めだとして、避難したり、福島産の産物を忌避することなどを宣言している人がいるが、それは、長い目で見るならば、結果として、自分自身に、そして他人にも、害を及ぼす恐れのある危険な行為であることに気づくべきである。せめて、人に語ることなく、自分だけで実行するところでとどめてほしい。他人を巻き込まない行為は、自身が受ける害益はどうあれ、基本的に自由だからである。
この、ほとんど静かな憤怒ともいうべき文章の意味するところを、どう受け止めるかも、読む者によってかなり異なるだろう。私自身はといえば、一ノ瀬氏の主張に概ね同意すると同時に、極私的な「不の感覚」の膨張に突き動かされて、「度合い」と「少しずつ」を頭で理解はしても採用することが出来ず、やみくもに「避難」や「忌避」を表明したがる心性を、やはり否定することは出来ない。私自身はまったくそうは思わないが、そうなってしまう人が存在することを前提にしないで、「以後」を考えることは不可能だと思うからである(一ノ瀬氏の立場も実際にはこれに近い)。ともあれしかし、繰り返しておくが、『放射能問題に立ち向かう哲学』という本の主題はあくまでも「放射線被曝の健康への影響」であり、著者はその中で「原発」にかんして肯定/否定いずれのステイトメントも述べてはいない。そして「放射線」にかんして、科学的なデータや資料、専門家による多数の研究を援用しつつ、論述の構えとしては、一ノ瀬氏が「あの日以前」から長年継続してきた「因果」や「パラドックス」についての思考、すなわち「哲学」を駆使している点が、この本の最大の特長である。つまり一ノ瀬正樹は、こう言ってよければ、単に自分にやれることをやったのである。それはしかし、哲学者としての責務でもなければ、もちろん権利でもありはしない。書名に選ばれた「立ち向かう」という言葉の意味を、私たちは、よくよく考えてみなくてはならない。
44。「私小説」に何が出来るか?
佐伯一麦の『光の闇』と『還れぬ家』は、これまで幾度か取り上げてきた「以後の小説」の風景に、また新たな光を投げかける。どちらも「二〇一一年三月十一日」を挟んで書き継がれたものである。『光の闇』は「欠損感覚」をテーマとする連作として雑誌「en-taxi」に数年がかりで発表された七編の短編に、やはり「欠損」が描かれているが「私小説」ではない「二十六夜待ち」を加えて一冊としたものである。「鏡の話」では聴覚、「水色の天井」では左足、「髭の声」では視覚、「香魚」では嗅覚、「……奥新川。面白山高原。山寺」では声の欠損が、それぞれ主題とされている。佐伯一麦の多くの作品と同様に、それらは作者自身の実人生に想を得ていると思しく、各編に登場するさまざまな欠損を負った人物たちも、おそらくは実在している。健常者であれば、ごく普通に身体に備わっている筈の感覚を何らかの理由によって失った人たちが、しかし「欠損」を殊更に否定的にも肯定的にも捉えることなく、いわば人生のありのままの現実として静かに受け止めている姿が、いつもながらの淡々としつつも鮮やかな筆致で描かれている。 連作が五作目まで発表された後、あの日が訪れた。その後に書かれた「空に刻む」は、一作目の「鏡の話」の後日談である。仙台在住の作家である「僕(「茂崎皓二」という名前を持っている)」は、市民センターの文学講座で知り合ったろうの老人の「堀井さん」が、やはりろうの夫人と二人で住む海に近い自宅を「鏡の話」で訪問していた。「堀井さん」は講座に熱心に通ってきて、「僕」と筆談で会話を交わすようになり、やがてFAXでの個人的なやりとりも始まった。「ろうの人が自分で書き記した体験の話は少ないんです。それを、私は書き残してから死にたいんです。ですから文章の指導をお願いします」と、ある時のFAXにはあった。「鏡の話」では、堀井宅でのひととき、「僕」がロンドン土産に買ってきた万華鏡を夫妻に手渡しつつ、染めた糸を編んで服やアクセサリーを作るアーティストである妻が工芸展に出店するのに同行したロンドンで、急に入り用になった大きな鏡を探して町中を奔走した際の苦労話を筆談で物語る。言葉がちゃんと通じない外国での体験と、耳の聞こえないろうの人々の日常感覚が、穏やかに、やんわりと織り重ねられる。 それから三年近い月日が過ぎた「空に刻む」は、震災後、「僕」が宮城県立美術館で、聴覚障害者でもある画家の松本竣介が一九三七年に描いたとされる『郊外』を見た時のことから語り起こされる。「何層もの深いみどりの森の中にある白い建物は小学校だろうか。その校庭で子供たちが遊んでいる。犬もいる。瀟酒な家々も緑の中に見え隠れして点在している」。それは「メルヘンチックとさえも感じられ、正直のところこれまでは、その絵の前に立つと僕は、多少の気恥ずかしさを覚えないでもなかった」。ところが、あらためて見た『郊外』は、印象がまるで変わっていた。
そこには、震災以後、何度となく想像させられることになってしまった光景が描かれているように、僕には感じられた。 左右に黒っぽい青と深い緑の海藻がゆらめく海の底に、小学校らしい白い建物が沈んでおり、その校庭では子供たちが遊んでいる。犬もいる。そして、背後の“みどりの波間”に、津波に浚われた白い瀟酒な家々が見え隠れしている……、というふうに、同じ画面が、震災前に目にしていたときとは、一変して見えた。 もちろんその風景は、絵を描いた当時に住んでいた東京の落合とも、幼少年期を過ごした岩手県の花巻や盛岡とも言われているが(現実を自由に再構築する名手だった松本竣介だけに、そのどちらでもあったのだと僕には思えるが)、ともかく地上の郊外を描いたことは確かだ。だが、そのときの僕には、地震の後に津波に襲われて流され、海の底に存在しているもう一つの世界の光景と思われてならなかったのだった。
その絵の前で立ちつくしながら「僕」は「堀井さん」のことを考える。海沿いの土地に住んでいた「堀井さん」と奥さんは「家から一キロほどの距離の中学校に逃げ込んだものの、奥さんのほうが津波に呑み込まれて行方不明となっている」。そして「堀井さんは、娘さんの所に身を預けることになったが、いまは誰とも会いたくない、と固く心を閉ざして���る」。震災から十日ほど経った頃、「僕」は「鏡の話」と同じように、以前に「堀井さん」の自宅があった場所に行ってみようとする。だが、津波の被害はあまりにも惨く、そこまで辿り着くことさえ出来なかった。 「空に刻む」は、震災から四ヶ月後(それはつまりこの小説が書かれた時のことだ)に「僕」が「堀井さん」に宛てた手紙で終わる。「堀井さんはいま、どこでいかがお過ごしでしょうか」と書き出される文面は、やがて美術館で松本竣介を見たことを語る。『郊外』と一緒に『白い建物』という作品も見た。「絵の中の建物の上には青空が描かれていました。その受苦の色の青を目にして、以前堀井さんから教わった空文字のことを思い出していました」。「空文字」とは、筆談用の紙がない際に、宙に文字を書くことをいう。この言葉を「鏡の話」で「僕」は「堀井さん」から教わったのだった。
堀井さんが、樹々の緑や草花、そして青空に目を留めるようになるのはいつのことになるでしょうか。そのとき、青空に空文字を一文字書くとしたら、どんな文字となるでしょうか。
言うまでもあるまいが、この短編の幕切れがこの上なく感動的なのは、筆談で会話を交わしてきた「堀井さん」に向けて、小説の中の手紙という形で、「僕」が、いや、佐伯一麦自身が、声を投げ掛けているからに他ならない。誰とも会おうとしない、どこに居るとも知れない「堀井さん」は、だがしかし、もしかしたら、これを読むかもしれない。たとえ返事はなかったとしても、この小説の姿を纏った手紙を(それは「手紙の姿を纏った小説」と言っても同じことだ)読んだかもしれない。そんな微かな希いが、この「空に刻む」という小説が書かれた動機であり、存在理由となっている。つまり、この「手紙=小説」も、一種の「空文字」なのである。 連作の末尾となる表題作「光の闇」では、「髭の声」に登場した「僕」の旧友である盲学校教師の「棚橋」が、東北地区の盲学校の弁論大会の審査員を「僕」に依頼してくる。あいにく「棚橋」自身は異動となり、大会には不参加だったが、「僕」は引き受け、盲学校の生徒たちの弁論に耳を傾ける。震災時の体験が聞けるかと思っていたのだが、実際には「すべてが自分の障害に関するエピソードを語ったものだった。自分がいつ、どこで失明したのか。そこからどう立ち直ったのか」。震災から一年後、「僕」は「棚橋」、そしてやはり「髭の声」に登場していた盲学校の「吉岡先生」と「中山先生」、そして初対面の「太田先生」と居酒屋で語り合う。三人の先生いずれも全盲者である。「僕」は気づかなかったが、じつは三人とも、あの弁論大会に出席していたのだった。彼らは「僕」が聞きたかった震災体験を、それぞれに語る。七つの短編小説から成る連作は、こうして幕を閉じる。 長編小説『還れぬ家』は「新潮」の「二〇〇九年四月号」から連載が始まり、約三年半にわたり書き継がれて「二〇一二年九月号」で終了した。途中何度か休載が挟まるが、「二〇一一年四月号」から「二〇一一年七月号」まで二ヶ月のブランクがある。もちろん震災によって中断したのである。連載が再開されたのは第八十章からだと思われる。その間の事情について、やはり佐伯一麦とほぼイコールである「私」は、作中に登場する「二〇一一年三月十五日火曜日」という日付の付いた「震災以後の出来事のメモ」に、こう記す。
電話がようやく繋がるようになり、S編集部より見舞いの電話あり。「還れぬ家」、今月は取りあえず休載とさせてもらうことにしたが、これから先を書き継ぐことが出来るのか、大いに不安となる。連載の今の時点では、作中の「私」は、二〇〇八年八月を生きているところ。そして、父は、連載を始めた翌月の二〇〇九年三月十日に死んだ。あと数回を費やして、その父の死までの半年余りを、現在進行中の出来事として再現させるつもりだった。だが、三月十一日の大震災によって、小説の中の時間も押し流されてしまったのを痛切に感じる。もはや、前に続けて書き進めることは無理かもしれない。父のことが、急に遠景に退いたように感じられる。その実感に就き従って、小説に段差が生まれるのを恐れずに、現在進行中の出来事から回想へと表現を変えるべきか。
そして実際、重度の認知症に陥った父親と、息子の「私」、「私」の妻、母親という四人の家族(他に兄と姉も居るのだが、実家の近隣には住んでいない)の数年間を克明に描いてきたこの小説は、第八十章以降、いきなり父親の死後に記述が跳び、それからは当初の予定であった「父親の死へと至る時間」と、執筆時の現在である「震災以後の時間」が、並行して語られてゆくことになる。それは当然、唐突さを拭えないし、いささか混乱した印象も与えている。それでもやはり、作者はそうすることを選んだ。そうせざるを得なかったのだ。 右の「メモ」とほとんど同じ心境を、佐伯一麦は二〇一二年二月三日に東京大学本郷キャンパスで行なわれた公開講義『震災と言葉』(岩波ブックレットで冊子化されている)の中で語っている。この講義の時、まだ連載は継続中だった。「僕が主に書いている小説は「私小説」と言われるジャンルです。(略)その時に思ったのは、自分の実感を裏切りたくない。ということでした。それを裏切らないことが、自分の小説表現の一つの立場であろう、と。そうすると、その前に書いていたやり方では書けなくなってきたという実感が、やはりどうしようもなくあるわけです」。
もう少し具体的に言いますと、例えば小説を書いている時には、時間の流れというものがある。明日とかあさってとか、三ヶ月後とか、あるいは三年前に父はこうだったとか、時間の流れみたいなものがあるわけです。すると、着々と時間の経緯というものがある場合は、それで通用するのだけれども、明日、といってもまだ余震がずいぶん続いているような状況で、明日どうなるか分からない。二週間後とか三週間後とか書いても、自分自身が二週間後や三週間後を信じられない、そういう言い方を、肉体の方が信用していないわけですね。自分自身が、三週間後はこの状態のまま続くとはとうてい思えないという場合に、その三週間後とはどういう意味合いを持つのか。一年後、二年後というのも同様です。
「時間の流れみたいなものを書こうとするだけで、手がこわばるといいますか……」。「メモ」にあった「段差」という言葉が、講義では「断層」とも言い換えられる。「時間の断層」によって「小説」が塞き止められてしまっているのだ。「小説の言葉というのはあくまでも時間の推移というものが信じられるぐらいの日常性がないと、そもそも出てこないということです。それがないと、言葉による表現は成り立たないのではないか」。だが「日常性」は失われてしまった。
さすがに今回の震災みたいなものだけは、事前に考えようにも考えられなかった。いくら仙台では三十年以内に九十九%の確率で大きな地震が起こると言われても、こんなふうになるとはやはり考えられなかった。しかし、それについて僕自身は、書き手としても何となく敗北感のようなものをいまだに持っているのです。ただし、そういう状態の中で、この作品を最後まで書き切るということでしか、これは自分としても乗り越えられないのではないかと思っています。
そして佐伯一麦は、こう語ってから残り数回の連載を経て、『還れぬ家』を完結させた。小説は第百八章まで続いたのち、「早瀬光二の手記」と題されたエピローグで終わる(「早瀬光二」とは作中の「私」の名前である)。「平成二十年三月十一日に、アルツハイマー型の認知症である、と診断された父は、それからきっかり一年の余命を送り、翌年の三月十日に亡くなりました。父の存命中に筆を起こしたときには、これほど早く父が逝くことになってしまうとは思っていませんでした」という述懐から始まる。前に述べたように「新潮」で連載が開始されたのは「二〇〇九年四月号」だった。同誌が発売されたのは三月初旬、雑誌に入稿されたのは二月、ということはつまり、ほんとうに「これほど早く」父親は亡くなったのだ。『還れぬ家』は、その出発時から間もなく、既に一度、或る「断層」を超えていたのである。 この小説自体が「私=早瀬光二(=佐伯一麦)」による一種の「手記」と言えるのかもしれないが、その最後にあらためて「早瀬光二の手記」として置かれた文章には、それまで描かれていなかった父親の葬式、そして震災後に重篤な被害に遭った地域に赴いた時のことが語られている。そこに「聴覚障害者のMさん」の話が出てくる。「ご主人が運転する車で避難所に指定された中学校の建物へ辿り着いたものの、車を駐車場に入れようとした夫が、突然襲ってきた津波に目の前で流されてしまい行方不明となってしまった」という「Mさん」は「震災以降、誰とも会いたくない、と娘のところに身を寄せている」という。「Mさん夫妻」の家には「大きな鏡」があったというのだから、いやがうえにも「鏡の話」と「空に刻む」の「堀井さん」を思い出してしまう。だが、頭文字は異なるし、津波で行方不明になったのが夫なのか妻なのかも違う。しかしそれは、何らかの配慮によるというよりも、「私小説」とは、「小説」とは、そういうことをするものなのだ、ということなのではないか。「堀井さん」や「Mさん」が、実はまったくの虚構の人物であったのだとしても、その事実によって、これらの作品の意味が根こそぎ損ねられてしまうわけではない。なぜならば、そのようなひとは、間違いなく現実に居たに違いないからだ。
45。「世界」が君に救われるように
稲川方人の『詩と、人間の同意』は、『彼方へのサボタージュ』と『反感装置』(いずれも一九八七年刊行)以来、およそ四半世紀ぶりとなる詩人の随想集である。『彼方』は詩論、『反感』は映画を中心とした評論の集成だったが、この本は、ちょうどその中間の表情をしている。 もともとは、もっと前に出る筈だったのが、著者自身の意向によって、この二〇一三年の五月まで、刊行が遅らせられた。更に、当初の予定から書名を変更し、内容や構成も一部改められている。稲川方人は、その理由を、冒頭に据えられた「はじめに」で明確に述べている。
本書の初校ゲラが二〇一一年三月以前に組まれてあったからである。一年ほどゲラを手にすることも避けていて、二〇一二年六月になってようやく目を通した。この「まえがき」も改めている。書名を変えたからといって何が変わるわけでもない。初校に組まれてあったいくつかの文章を割愛したりもしたが、変えようとすること、そして、だが変わらないことーー二〇一一年三月から一定の時間を経たいまの苦い心象だ。ただ、私個人を吐露すれば、変わらないことと「詩」の終わりとはもはや同義にしか思えなくなった。
稲川方人という詩人は、登場した時から「詩の終焉」と共にあった。それは「文学の終焉」と言い換えてもよい。だがその「終焉」は、いつまでも真の幕引きを迎えることはなく、「終わり」の儀式を限りなく引き延ばしながら上演してきた。稲川の言葉は「詩=文学」を終わらせる決意を漲らせながら、しかしその終わらなさから目を背けることもなく、数十年の時間を過ぎ越してきた。そして「二〇一一年三月」があった。そこで何かが決定的に変わったのではなく、それでも変わらなかったということが、終焉が竟にやってきたのではなく、それでも終わらなかったことが、言葉が失われたのではなく、それでも言葉が今なお延命していることが悲劇なのだ。「私の個人的な任意でしかないことだが、「人間の同意」を希求しながら「同意」自体が詩から(文学から)奪われていく過程がこの二十数年だった。二〇一一年三月の出来事がそれを明らかにしたのではなく、以後の時間がそれをあからさまに象徴したのである。そして、その被剥奪の象徴はまだ完了してはいない。この認識をできるだけ直線的に了解したいと私は思う。詩的な(文学的な)当為が無意味かどうかを問うことにたしかにいまは消耗しているが、それが「震災以後」という言説の特権であろうはずはない。また「震災以後」という言辞をめぐる理性的かつ知的な議論も消耗である」。そして詩人は、一切の勿体抜きに、おもむろにこう告げる。
私は福島県南部の区域に生まれ、ある年齢までそこで暮らした。そこが私の「郷里」であり(無意味なことを言うが)それゆえ、自分の生に唯一、同一性を持つ場所である。個人的で超越的なその場所とそこでの経験に即して私は二篇だけ随想を書いたことがある。当初はそれも収めてあったが、削除した。国家/資本の余りにも脆弱な根拠による、余りにも無造作と言うよりほかない「殺戮」と「暴力」から、自分のなけなしの同一性を避けておきたいからだ。また、何ら特異でもなく、なんら特殊でもない「福島」という地名の、この間の異様な顕現にもいっさい与したくない。
この本の最後には、書き下ろしの文章が収められている。「郷里が避難区域にな���たら、俺はそこに戻って被曝しながら抵抗するよと、オーストラリアン・リトルホースに耳打ちした」という長いタイトルの付けられたその文章は、それ自体かなり長いものだが、読点は一つきり、つまりひと続きの一文である。「国家・共同体そして生命領域に決定的なことが起こっているし、いまこの時刻にもさらに決定的なことが起こりつつあり、またこれ以後も次々に決定的なことが起こるというのがいまわれわれが経験している震災からの予断のない日々であり、その決定的ななにものかは、「以後」とか「以前」とかの理性的なチャートが無意味だと拒んでいるようにも思えるので……」という書き出しを読みながら、私は背筋が伸びるような気がする。そして「私は、ただ私が見るべきものを見て、知るべきものを知るということにしか自分の態度はないと思うようになり、その狭い意志の範囲でも、見るべきもの、知るべきものは多くあって、そのひとつ、ほんとうなら断じて見たくはないし、断じて知りたくはない事象なのだが」、福島第一原発の近くで、罪なき生きものたちの殺戮が起きていることを、詩人は見て、知ってしまった。それから詩人は、かなしみと怒りに打ち震えながら、二十数年ぶりに編まれつつあった本の作業を中断したのだった。
福島第一原発から七十数キロの地に位置する、福島県中通りにある小さな町に生まれ育ち、いまは無産者のひとりでしかない私は、何をするべきかではなく、何を考えるべきなのかと、それを自分の重責とするよりほかないそんな折りふと思い出すのは、子供のころ、と言っても十代の終わりのころは自分には二十一世紀は関係ないと思っていたことであり、一九四九年に生まれている私の年齢が五十歳を越えるのと二十世紀が終わるのとはほぼ同じで、五十歳を越えるころに自分はこの世からいなくなるのが妥当だと子供のころは確信していたので、余分な二十一世紀が始まって間もなく、たとえば二〇〇一年の九月には、ほらやっぱり無用に生きているから見る必要のないものを見てしまうことになるんだと昔の自分のいかにも文学的な感性が正しかったかを痛感したが、それから十年経って、しかし今度は、見るべきものを見る必要に直面している自分を、やはり無用な生を生きてしまったのかと思いながら、
読み続けながら私は、このような文章を、詩人が何を思いつつ書いているのだろうかと考える。ここにあるのは諦念でも断念でもない。それは限りなく絶望に似ているが、しかし彼は、それでも書くことを選んでいる。いったい何のためになのか。そんな問いには、何の意味もありはしない。ただ彼は書いたのであり、だから私はそれを読んでいるのだ。 私は、この連載を、『詩と、人間の同意』の終わりの、長い長いひと続きの文章の終わりで終えたいと思う。
子供や猫や小さな生き物には暮らし難い私の住む借家のある住宅地から多摩川上流へ、いつものように自転車を走らせていると、黒と茶のなんとも優しい顔をした柴犬に出会い、声をかけると、名前はチャミオだと教えてくれたその飼い主の訛りのイントネーションが間違いなく私の郷里の近くだと分かり、「棚倉ですが」と言うと「須賀川だよ」と答えたその声に涙を堪えるのが精一杯で、苦難にある互いの田舎のことを話す気にはまるでならず、行儀よく足下に座ってふたりを見上げていたチャミオに、世界が君に救われるようにと言うしかなかったが、須賀川にいる兄弟たちに見舞金を出すのに苦労したよと言う飼い主のおじさんはもちろん理解してはくれなかったし、「世界」という言葉がいかにも虚しく響いて苦笑いもできなかった。
(了)
13 notes
·
View notes
Photo

一年前日記20(2020年5月13日~19日)
5月13日 こないだ車で前を通った公園に歩いて行く。途中コンビニでおにぎりとお茶を買った。公園にはなぜかプーさんのぬいぐるみがいた。和菓子屋さんで豆大福を買ったらお店の人に「まだ冷たいです」と言われる。冷凍してるらしい。そっかあと思いながら、まあいいかなと買って帰った。今日は、土用明け恒例の温泉、には行けないので、「行ったつもりで過ごす日」にしていたのだが、お昼からお風呂に入っていると、宅配便の人が来たり、電話がかかってきたり。やっぱり本当に温泉に行かないとダメだな。電話は近所の人だったのだが、「給付金もマスクも上から順番に配られる。私らみたいな下々の者は最後や。」って言っていた。上ってなんなんだ。冗談なのか本気なのか分からないが、まあいつもの調子で元気そうでよかった。夜ご飯は焼き空豆、鮭とじゃがいものグラタン、ほうれん草のスープ。豆大福はあんまり美味しくなかった。そんな気はしていたが。姉より母の病院の報告。とりあえず今は本人が困っていないし治す意志もないので何もできないですって感じ。でも自分ではきっぱりやめると言っていたそうだ。介護認定はまだ出ないので見送りとのこと。そうなのか。結構頼りない感じだと思うんだけど、なかなか難しいもんだな。
5月14日 朝、もう一度お風呂に入った。昼はどん兵衛を食べて、本を読んでるうちに眠くなってがっつり寝てしまう。夜はニラ入り卵焼き、ポテト、味噌汁。ヨーロッパ企画の生配信を聞く。今日はスタンバイズの日。懐かしいな。ファンダンゴ行ったなあ。恋愛の話とか、毎日何してるかとか、ゆるくて楽しかった。
5月15日 仕事の日。週に一度だとたいしたことはできないよなあと思いながら淡々とする。電話もだんだん増えてきた。本屋さんと銀行と酒屋さん(お持ち帰りの肴を買った)と八百屋さんとスーパーに寄って疲れる。9000歩ぐらい。やっぱり日常生活の運動量ってすごい。晩ご飯は、買ってきた肴たちを。鶏もつ煮、鯵の南蛮漬け、貝のレモン味のもの。水菜と油揚げの煮浸しを作った。肌寒かったので、お酒をお燗して飲んだ。
5月16日 雨の土曜日。読書、ご飯、読書、ご飯、パズル、ご飯、おやつ、買い物、ご飯、読書、お風呂、寝る。日記書くまでもない毎日だなあ。それでも前はもっといろいろ感じていたと思うのだけど。俳句を日常的に作るようになってから、書きたい欲がなくなってしまった。この現象は何なんだろう。精神的には安定しているっぽい。夜ご飯は夫が作ってくれた。タリアテッレタリアテッレと張り切っていたが、業務スーパーにタリアテッレは売ってなかったのですぐに茹でられる冷凍パスタを買った。美味しくない乾麺よりは美味しいぐらいの美味しさ。ラグーソースのパスタでした。でもあまり煮込んでないからボロネーゼなのかな。パセリをたっぷり入れてもらった。パセリ大好き。
5月17日 日曜日。朝、録画していた兵庫区の駄菓子屋さんのドキュメント72時間を見ながら泣く。お昼は豆腐丼。夕方、二人で散歩に。もう近くの道という道は歩きつくしたと思っていたが、まだ知らない公園や神社があった。お腹が空いたのでコンビニでおからと焼豚を買って、つまみながら鯛のカルパッチョを作って食べた。
5月18日 ウクレレを弾いてみた。先週はピッチが狂いやすくなってるかなと思ったが、今日はそんなこともなかった。やっぱり楽器は弾いてあげるのが大切なのかな。何年も放置していたけど、いい音。いい楽器だ。大事にしなきゃ。夜は豚しゃぶ。片付けも少し進める。
5月19日 読書の合間にパズルにはまってしまう。夕方散歩へ。夜ご飯は牛肉とセロリのオイスターソース炒め、ミネストローネ。やはり自分の中で何かが変化している感じがする。きっかけは俳句かなと思ってたけど、多分あのハナミズキの下で多幸感を感じた日からだ。今までも何度か「もう満たされた」と思ったことはあったけど、しばらくするとまた違うレベルの「満たされた」がやってくる。それは実際には満たされていなかったのか、その分だけ器が大きくなったのかどちらなんだろう。どちらにしても、何者でもない感じを存分に味わえた今の期間は自分にとってとてもありがたいものだったことは間違いない。
0 notes
Text
☆円盤、その他 ※取り込み済みのもののみ記載
★7ORDER
・UNORDER
★Kis-My-Ft2 ※未取り込み多数の為お問い合わせください
LIVE
・Kis-My-Ftに逢えるde Show vol.3(本編)
・Everybody Go at 横浜アリーナ(本編)
・Kis-My-MiNT(本編、初回特典)
・SNOW DOMEの約束(本編、オフショット、Goodツアー)
・Kis-My-Journey(本編、初回特典、通常特典)
・KIS-MY-WORLD(本編、各WORLD、ドキュメント、ユニットドキュメント、アンコール、新春)
・ISECREAM(本編、密着、ソロドキュメンタリー、アンコール、ハプニング&名珍場面)
・MUSIC COLOSSEUM(本編、メイキング〜打上げ)
・Yummy(本編、アンコール、密着、7Yummy)
・FREE HUGS!(本編、ソロ密着、密着、ハプニング&名場面)
・To-y2(本編、ドキュメント、KIS-MY-TV)
シングル
・PICK IT UP
初回A(MV、MV字幕、メイキング、キスマイスポーツ、裏キスマツ荘、マルチアングル)
初回B(KIS-MY-TV)
・赤い果実
初回A(MV、MV字幕、MVダンス、MVダンス字幕、メイキング)
初回B(ゆるスポ、裏スナック)
・You&Me (HOMEレコーディング、ZERO)
・LOVE
初回A(MV、MV字幕、メイキング、ゆるスポ)
初回B(MV、MV字幕、メイキング、裏Yummy)
・君、僕。
初回A(MV、MV字幕、メイキング)
初回B(KIS-MY-PARTY)
・君を大好きだ
初回A(MV、MV字幕、メイキング、もしもシリーズ)
EXTRA盤(Extra Yummy!!)
・HANDS UP
初回B(永遠結び、永遠結び字幕、ルラルララ、インタビュー)
・Edge of Days
初回A(MV、MV字幕、メイキング)
初回B(MV、MV字幕、ゆるスポ、騙しているのは誰?)
・ENDLESS SUMMER
初回A(MV~メイキング)
初回B(KIS-MY-TV)
・Luv Bias
初回A(MV、メイキング)
初回B(KIS-MY-TV)
アルバム
・Kis-My-1st
SHOP(あしあと)
・KIS-MY-WORLD
初回A(MV、ミッション、振付け、ユニットレコーディング)
SHOP(北山)
・ISECREAM
初回4(各Re:、ソロMV、6movies、Re:制作密着)
初回2(MV、メイキング、シェアハウス)
・MUSIC COLOSSEUM
初回A(MV、MV字幕、メイキング、KIS-MY-TV)
・Yummy!!
初回A(キスマイ語録、キスマツ荘後篇)
・FREE HUGS!
初回A(MV、MV字幕、MV Lip、MV Lip字幕、メイキング)
初回B(KIS-MY-TV)
・To-y2
初回A(MV、MV字幕、AFA、BNA)
初回B(KIS-MY-TV)
★舞祭組
LIVE
・舞祭組村のわっと! 驚く! 第1笑(密着、SP企画)
シングル
・棚からぼたもち(MV、メイキング)
・てぃーてぃーてぃーてれって(MV、メイキング)
・やっちゃった(MV、メイキング)
・道しるべ
初回A(MV、メイキング)
初回B(合宿)
アルバム
・舞祭組の、わっ!
初回A(シングルMV、メドレーMV、メイキング)
初回B(100日ドキュメント)
★King & Prince
・1stコンサート(本編)
・2ndコンサート(本編)
★素顔
・8.8祭(本編、ドキュメント、ISLAND FES)
・ぷれぜんと(本編、メイキング)
・雪Man in the Show(本編、メイキング)
・関西Jr(本編、メイキング)
・CHANGE THE ERA -201ix-(本編、メイキング)
★JUMP
・1st(本編、メイキング)
・I/O(本編、メイキング)
★SixTONES
LIVE
・TrackONE-IMPACT(本編、ドキュメント、コメンタリー、Rough xxxxxxダイジェスト)
シングル
・Imitation Rain(未)
・NAVIGATOR(未)
・NEW ERA(初回、限定)
・僕が僕じゃないみたいだ(初回A、B)
アルバム
・1ST(初回A、B)
★関ジャニ∞
・十祭(本編)
・十五祭(本編)
・8UPPERS FEATURE MUSIC FILM / DIRECTOR'S GIFT(未)
★Sexy Zone
・2019PAGES(本編)
・サマパラ2016(佐藤、菊池)
・サマパラ2017(佐藤、菊池、中島)
★KAT-TUN
LIVE
・お客様は神サマー(未)
・海賊帆(DISC1、DISC2)
・UNION(本編)
・CAST(本編)
・IGNITE(本編、MC集)
シングル
・Roar(初回、FC限定)
★多数出演
・One!(本編)
・滝沢歌舞伎
2010(第一幕)
2012(第一幕、第二幕、特典ファミリー公演)
2014(第一幕、第二幕、ドキュメント)
2015(第一幕、第二幕、ドキュメント、シンガポールドキュメント)
2016(第一幕、第二幕、ドキュメント)
2018(第一幕、第二幕、ドキュメント、カンパニー、BBQ、千秋楽)
ZERO(第一幕、第二幕、ドキュメント)
・滝沢革命
2009(第一幕)
・滝沢演舞場(第一幕)
・銀河英雄伝説
撃墜王(未)
輝く星、闇を裂いて(本編、特典)
第三章 内乱(本編、特典、カーテンコール)
第四章 後篇 激突(本編、特典)
・○○な人の末路(月、海 ※特典含む)
・Twenty★Twenty
・SUMMARY2004(本編)
・PLAYZONE
2005(本編)
太陽からの手紙(本編、特典)
・キフシャム国の冒険
・DREAM BOY(DISC1、DISC2-1〜3)
・DREAM BOYS
2006 KAT-TUNVS関ジャニ∞(未)
2008 亀梨田中屋良(未)
2017 玉森宮田千賀(本編)
★ドラマ・映画
・BAD BOYS(ドラマ本編、ドラマメイキング、 劇場版)
・お兄ちゃんガチャ(本編)
・ごくせん3(本編)
・ごめんね青春(本編)
・メンズ高校(事前番組)
・スプラウト(本編)
・ゼロ一攫千金ゲーム(本編)
・バカレア(ドラマ本編、ドラマメイキング、劇場版本編、劇場版メイキング)
・一億円のさようなら(本編1-3話)
・少年たち劇場版(本編、メイキング、舞台挨拶)
・未満警察(本編)
・節約ロック(本編)
・簡単なお仕事(本編)
・花晴れ(本編)
・野郎組(本編)
・荒ぶる荒野(本編)
・HIGH and LAW(THEMOVIE、2ENDOFSKY、FINALMISSION、REDRAIN)
・グラスホッパー(本編)
・最後の約束(本編)
・午前0時、キスしに来てよ(本編)
・京都大奏行進曲
・foney(本編)
・忍ジャ二(本編、メイキング)
・俺スカ(本編、メイキング)
・仮面ティチャー(ドラマ)
・SHARK
・SHARK2(本編、特典)
・フリーター、家を買う(本編、特典 ※高比率)
・美男子ですね(本編、特典)
・黒崎くんのいいなり
・花より男子
・近キョリ恋愛
・DIVER(1〜5話)
・映画ごくせん(本編、特典)
0 notes