#哲学の道
Explore tagged Tumblr posts
Photo

Kyoto, Japan
721 notes
·
View notes
Text


京都・哲学の道
何年かぶりに訪れてみましたが、
川の流れの音を聞き、
美しい景色を見ることができ、
心地よい一日が過ごせました。
39 notes
·
View notes
Text

母と一緒に西田幾多郎記念哲学館を訪れました。哲学の道は緑豊かで秋の訪れを感じながら一歩一歩歩きました。
I had the opportunity to visit the Museum of Philosophy dedicated to Japanese philosopher Kitaro Nishida in Ishikawa with my family. Inspired by a Shogakukan children's manga my daughter read about his life, she expressed a keen interest in exploring his philosophy further. Together with her grandmother, we engaged in thoughtful discussions and discovered the intriguing concepts that shaped Nishida's ideas. It was a meaningful experience that brought us closer as a family while deepening our understanding of philosophy.
日本語はこちら
#Kitaro Nishida#Philosophy#Philosophy Museum#Ishikawa#Japanese philosophy#Museum of Philosophy#西田哲学#山田なつみ#西田幾多郎#哲学の道#original photographers#photography#photographers on tumblr#photodiary#ordinaryphoto but a special moment
1 note
·
View note
Text
なぜ世界は存在しないのか?
youtube
【宇宙は幻なのか?】京大教授「ホログラフィック原理」・橋本幸士/タイムトラベルは可能なのか?/シン・エヴァンゲリオン物理学監修/学習物
0 notes
Text

暴力の哲学 酒井隆史 シリーズ・道徳の系譜 河出書房新社 カバーイラスト=前田晃伸
5 notes
·
View notes
Text
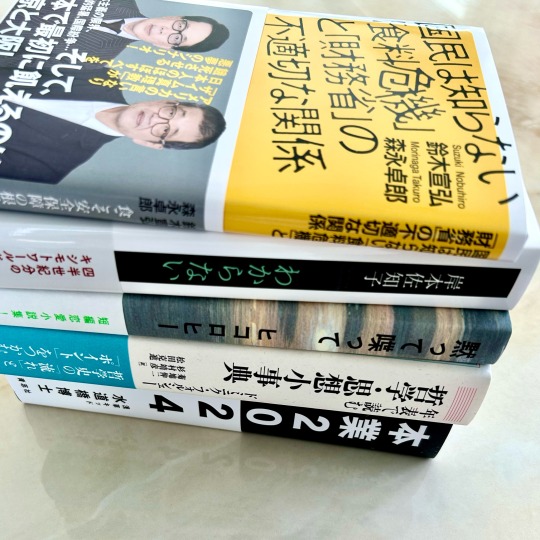
#積読#国民は知らない「食料危機」と「財務省」の不適切な関係#わからない#黙って喋って#年表で読む哲学・思想小事典#本業2024#鈴木宣弘#森永卓郎#岸本佐知子#ドミニク・フォルシェー#水道橋博士#乱読#積ん読
0 notes
Text
#子の道 ー #キリストの道、#宇宙の子の道 ー。
魔法使いー。癒してあげたいー。助けてあげたいー。
痛いの痛いの飛んで行けー!
#イエスの奇跡
世界のイニシエートのリスト(Ⅲ)より
ー光線構造と進化の段階ー
ナザレのイエス(4.0) 6-1-1-2-1 霊的教師 (紀元前24-後9) パレスチナ

0 notes
Photo

人は自己家畜化で優しく従順に進化した 人工環境と社会に適応
テクノロジーと人類(48)長内洋介
2025/3/29 10:00
人類が今日の繁栄を築いた根本的な理由は何か。その謎を解く鍵として注目されているのが「自己家畜化」という概念だ。人は優しく進化して飛躍を遂げたのだという。
家畜と共通点
人類は約1万年前、ヤギやヒツジ、ウシなどの野生動物を飼育して家畜化した。奇妙なことに、人はこうした家畜とよく似た性質を持っている。この事実は古代ギリシャ時代から知られ、19世紀にダーウィンも注目して研究したが、理由は突き止められなかった。
家畜化された動物は、どの種でも共通の性質が表れる。人を攻撃せず従順で、ストレスに対して鈍感、頭や顎は小型化し、体は白くなり、顔は平面的で幼くなるといった変化だ。
これは「家畜化症候群」と呼ばれ、その多くは人でもみられる。人はチンパンジーと比べて温和で、反射的に攻撃することは少ない。数百万年に及ぶ進化の過程で顎や歯は小型化し、顔は平面的になった。
人はなぜ家畜と似ているのか。その理由を説明するのが自己家畜化だ。人は誰かに家畜化されたのではなく、自ら家畜のような性質に進化したというものだ。
動物を家畜化するときは人に従順な個体が選ばれる。人類も攻撃的な人は排除され、仲良く協力できる人が自然淘汰(とうた)で生き残ってきたと考えられる。自己家畜化が始まった時期は不明だが、われわれホモ・サピエンスが誕生した頃に大きく進展したらしい。
東京大の外谷(とや)弦太特任助教(複雑系科学)は「人類は道具を使い、協力して狩りをすることで多くの食料を得られるようになった。人口が増えて社会が複雑化すると役割分担が始まり、より仲良くすることが有利になって自己家畜化が加速した」と指摘する。
愛知県立大名誉教授で野外民族博物館リトルワールド館長の稲村哲也氏(文化人類学)は「他者と協力し、相手を思いやる人間の特性は自己家畜化の過程で残ってきたのだろう。人は自ら作った高ストレス社会に適応して、より優しくなった」と話す。
仲良くなると情報や物資の交換が活発になり、新たなアイデアが生まれイノベーション(技術革新)が起きる。自己家畜化が人類の繁栄と文明の進歩に重要な役割を果たしたことは間違いないだろう。
人は大人になってもよく遊ぶ。旺盛な好奇心の表れであり、遊びによる探索や試行錯誤が新たなひらめきの源泉になる。イヌは進化の過程で自ら人に近づいたともいわれ、人と同じようによく遊ぶ。
人類は道具や社会制度を作り、農耕や都市化によって人工的な環境を生み出してきた。人が作った環境の中で家畜が飼育されるように、人間も自ら作った社会や環境の中でしか生きられない存在だ。こうした視点からも人は自己家畜化したと指摘されている。
言語にも関係
自己家畜化は人間らしさの根源である言語の誕生にも関係しているという。小鳥のジュウシマツは野生種を品種改良した家畜で、野生種より複雑なさえずりができる。人も自己家畜化によって言語の進化が起きた可能性がある。
京都大の藤田耕司名誉教授(進化言語学)によると、野生動物は生きていくため常に天敵や餌の心配をしているが、家畜はその必要がないため余裕が生じ、多くのことに注意を払い考えられるようになる。
「これが複雑な構造を持つ人間の言語が生まれた一つの要因ではないか。言語による複雑な思考やコミュニケーションが可能になった背景には自己家畜化がある」と藤田氏は指摘する。
家畜化の研究は、���シアで20世紀半ばに行われたキツネの家畜化実験で大きく前進した。人に従順な雄と雌を交配させ、生まれた子から従順な個体を選び交配させることを繰り返した結果、わずか数世代でイヌのように尾を振る人懐っこいキツネが生まれたのだ。
しかもこのキツネは耳が垂れ、色が白いなどの家畜化症候群も呈していた。数千年は要したであろうオオカミからイヌへの進化を人工的に再現したようなものだ。
この実験によって、従順さを求めると家畜化することが実証されたが、なぜ体の変化も同時に起きたのか。これを説明する画期的な仮説が約10年前に登場し、注目されている。
鍵となるのは神経堤細胞という特殊な細胞だ。胎児のときに脊髄付近から全身に散らばり、ホルモンを分泌する副腎や骨などさまざまな場所の形成を促す。
この働きが低下すると、攻撃性を高めるホルモンの分泌が減るなどして穏やかで従順になる。骨や軟骨の形成も阻害されるため、頭が小型化したり、耳が垂れたりする変化が同時に起きることも説明できるのだ。
この仮説が正しければ、動物の家畜化は神経堤細胞の働きが低い個体を選別する行為といえる。人の自己家畜化も、そういうタイプの人が仲間や結婚相手として多く選ばれ、進行した可能性がある。
京都大ヒト行動進化研究センターでは、チンパンジーと、近縁種で自己家畜化した性質を持つボノボの人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使って、それぞれの神経堤細胞を作り、その働きを比べることで自己家畜化��決め手となる遺伝子を探す研究が進んでいる。
権力への依存
現代人も自己家畜化が進んでいるという。山口大の高橋征仁教授(社会心理学)によると、日本での代表的な美男子コンテストの候補者は、時代を追うごとにひ弱で優しく幼い印象の顔になっている。家畜化で生じる特徴的な変化だ���
分析の結果、女性は男性の優しい顔に恋愛や結婚の相手としての魅力を感じることが分かった。女性が穏やかで従順な男性を選ぶことで人の自己家畜化が進んでいる可能性がある。
自己家畜化の進行は人類の将来に何をもたらすのか。高橋氏は「幼くなるのは若々しくなることで良い面だが、課題は巨大な権力への甘えと依存が強まることだ」と話す。
インターネットが普及した今日、現代人は巨大IT企業が支配する情報インフラを従順に受け入れ、すっかり依存している。人はネット空間という見えない柵の中で飼育され、情報という餌を与えられて生きる家畜への道を自ら選んだと言ってもいいだろう。
一方、外谷氏は「人が協力して行ってきたことの多くは生成AI(人工知能)に置き換わる。人は協力することに価値を見いださず、他者や社会に無関心になっていく」と予想する。
家畜は人間に興味を示す半面、自分と同じ種への関心は低い。人間同士が無関心になることは自己家畜化の帰結ともいえそうだ。
稲村氏は「人は自己家畜化によって社会性や共感を強めてきたが、集団を超えた協力はできていない。集団内の結び付きが強いほど、外部の集団と戦争を起こしてしまう。この矛盾をどう解決するか問われている」と警鐘を鳴らす。
自己家畜化論は人種差別や優生思想と結び付いて政治的に利用された過去があり、現在でも誤解されやすい。だが人間の本質を探る上で重要な論点であり、人類史を俯瞰(ふかん)して理解する新たな視座になるだろう。(科学報道室編集委員)
(人は自己家畜化で優しく従順に進化した 人工環境と社会に適応 テクノロジーと人類(48)長内洋介 - 産経ニュースから)
193 notes
·
View notes
Text


【京都 桜 Kyoto】哲学の道 桜と花筏
638 notes
·
View notes
Quote
「お前は見られている」が宗教。「見られていなくても」が道徳。「どう見ているか」が哲学。「見えているものは何か」が科学。「見えるようにする」のが数学。「見ることが出来たら」が文学。「見えている事にする」のが統計学。「見られると興奮する」のが変態
「お前は見られている」が宗教。「見られていなくても」が道徳。 : ぁゃιぃ(*゚ー゚)NEWS 2nd
304 notes
·
View notes
Text

[Image above: D. T. Suzuki (11 November 1870 - 12 July 1966) was a Japanese Buddhist scholar and doctor of literature. ]
A message from 23 nights temple Q&A: Part 2 [Part 1]
Next question was, want to know more about Tendai Buddhism and how to do face-to-face learning outside of Japan:
More than 1,400 years after its introduction, Buddhism in Japan was born from the founders of sects in Japanese history and culture. Today, about 13 major sects exist, including the Tendai sect. Of these, three are Zen sects: the Soto, Rinzai and Obaku.
Among them the most representative are, Saicho, founder of the Tendai sect, whose head temple is Enryaku-ji on Mt. Hiei; Kukai, founder of the Shingon sect, who brought esoteric Buddhism to Japan, whose head temple is Kongobu-ji on Mt. Koya; and Dogen, author of the Shobogenzo, a philosophy book said to be a manual for Zen meditation practice and originator of mindfulness. Founder of the Soto sect, whose main temple is Eiheiji Temple.
Buddhism means 'Buddha's teachings'. In the beginning, everything was transmitted orally and it was only after Buddha's death that documents and scriptures were created. All of the Buddhist scriptures that remain today were described by the memory of Buddha's disciples. In the meantime, it underwent various transformations through the views of translators and other factors, and representative gurus from different countries established and divided into sects. The Tendai sect is one of these sects, founded by Master Saicho. Incidentally, my trusted teacher is a Zen monk of the Soto sect, and he says that one should not be confined to a sect. It is because Dogen, the founder of the Soto sect, taught that the Buddha's teaching is one and that we should not be obsessed with sects.
Those wishing to study face-to-face or Buddhist thought outside Japan should visit your local Buddhist temple or Zen centre. You can easily find one by hitting the usual keywords. However, not all are good teachers. It is recommended to search patiently for a teacher or centre that suits you. For international learners, books by Japanese Buddhist scholar D.T. Suzuki are relatively accessible. He wrote on Zen in English and introduced Japanese Zen culture to the rest of the world. He was also a prolific translator of Chinese, Korean, Japanese, Vietnamese and Sanskrit literature.
In fact, the teachings of Zen that we are learning are not like there is a holy scripture that says this is the absolute truth, nor is there a founder who says that this is the absolute truth.
And it is best not to decide on a teacher based on sect or culture, but to knock on the door of a person you can identify with. More importantly, he or she may not only be in the temple.

二十三夜堂からのメッセージ Q&A: その2 [その1]
次の質問は、天台宗についてもっと知りたい、日本国外で対面で学ぶ方法を知りたいというものでした:
伝来から1400年余りの年月を経て、日本の歴史文化のなかで、宗派の開祖たちから生まれたのが「日本の仏教。 現在、大きな宗派として存在しているのは、天台宗を含め約13宗派。その中で禅宗は、曹洞宗、臨済宗と黄檗宗の3宗。
中でも代表的なのは、天台宗の開祖の最澄、総本山は比叡山延暦寺、日本に密教をもたらした、真言宗の開祖の空海、総本山は高野山金剛峯寺、そして、坐禅修行のマニュアルとも言われている哲学書「正法眼蔵 (しょうぼうげんぞう)」の著者でマインドフルネスの元祖、曹洞宗の開祖の道元、大本山は永平寺など、が挙げられる。
仏教とは「ブッダの教え」という意味である。当初、全ては口頭で伝えられており文書·経典ができたのはブッダ没後のこと��。今日残っている仏教経典はすべて、ブッダの弟子たちの記憶によって記述されたもの。その間訳者の見解などを通して様々な変形を繰り返し、各国の代表的な教祖が宗派を立ち上げ分かれていった。天台宗はその一つで、最澄が立ち上げた宗派である。因みに私の信頼できる先生は曹洞宗の禅僧だが、彼は宗派に囚われるべきではないと言っている。というのも曹洞宗の開祖である道元禅師が「ブッダの教えは一つであり、宗派に執われるな」と教えていたからだ。
国外で対面学習や仏教思想を学びたいとご希望の方々は、ローカルの仏教寺院、または禅センターを訪ねてみると良いと思います。お決まりのキーワードを叩けば、すぐに見つかります。但し、全てが良い先生とは限りません。自分に合った先生やセンターを根気よく探すことをお勧めします。海外の方々は、日本の仏教学者、鈴木大拙氏の本が比較的手に入りやすいと思います。彼は英語で禅に関する著作を発表し、日本の禅文化を世界に紹介し、また中国語、韓国語、日本語、ベトナム語、サンスクリット語などの多作な翻訳者でした。
実際、私たちが学んでいる「禅」の教えは、これが絶対の真理だという聖典があるわけでも、これが絶対の真理だという教祖がいるわけでもありません。
宗派や文化で師を決めるのではなく、ご自分が共感できる門を叩くのが最良かと思います。もっと言えば、その人はお寺にのみいらっしゃるとも限りません。
107 notes
·
View notes
Text



銀閣寺近く、哲学の道は圧巻の花筏。
#sourced#my gif#あひる#duck#nature#naturecore#animals#scenery#sakura#cherry blossom#さくら#japan#日本#kyoto#京都#kawaii#kawaiicore#cute#cutecore#flowers#flowercore
128 notes
·
View notes
Text
京都でよかったデートの記録 0412 6歳下の学生起業家と梅田でランチデート。なんでわたしと会おうと思ったんだろう?と思っていたら前の彼女が10歳以上年上だったとのことで合点、そしてとても好感度があがった。目が切れ長で歯並びが綺麗なところがとても好みだった。若いのに色気あるね、と言おうかと思ったけどわたしが言うと褒めているというより恫喝めく気がしないでもなくてやめた。起業してる人って頭よくてほれぼれするし、わたしの奇天烈な行動にも笑顔で聞き流してくれて、話が早くて助かる。 梅田から西梅田まで送ってもらった。 0414 清水五条の工房に行き、清水焼の器を買った。本当はマグカップだけでよかったのだけれど、どうしてもパスタ皿にひとめぼれして、すこし思い切った価格だったけれどこれも出会いだからと思って2つセットで買った。そしたら職人さんにとても感動されて「工房まで買いに来てくれたひと初めてなんです。嬉しいので一つなにかプレゼントします、なんでも」と言われ、恐縮して、追加で2つ茶碗をえらんで一つプレゼントにしてもらった。不恰好に膨らんだ厚い手が、さまざまな色に灼けていてとてもセクシーだった。蕎麦屋さんをいろいろ紹介してくれたが(一緒に行ってくれたらいいのに)と思っていた。 日が空いたけどやっぱり焼き物の職人さんかつ同世代の方と知り合う機会ないと思うから、蕎麦屋に誘ってみよう。蕎麦食べたらすぐ帰るから、って。 0418 「アンゼルム・キーファー:ソラリス展」を高橋君にとても勧められたので、絵を描く趣味があるという起業家を誘って2回目のデートをした。 わずかな隙間の窓から漏れる昼間の陽射しの力だけで照らされてぎしぎし鳴る木の廊下を歩く。暗く翳った部屋の中で、彫刻や巨大なアクリル画をゆっくり見て回った。 暑い日だったのでそのあとジェラートを食べた。地下鉄の階段を下りながら彼が振り返って「楽しかったです」と恥ずかしそうに告げてきたのが印象的だった。 0418夜 吉田寮のKG+の展示を見に行った際、別なイベントが食堂でやっており、たまたま話しかけられて親しくなった人が哲学専攻の博士5年生だった。東京が地元で、高校時代から生粋のドラマーらしい。小説の話をしたら「仕事しながらものつくりも並行してる人って本当にすごい」と言ってくれた。 ���に進んだ時点で自分の人生は王道の、まっとうな人生からはずれている、と零していて、わずかに劣等感と矜持の両方を感じた。「自転車のサドル高すぎたから、今度直してあげるよ また寮来て」とLINEが来て、なんてかわいいデートの誘い方なんだろう、とそれだけでめろめろになった。 0421 シェアハウスを介して2度会った26歳の学部3年生から「もっと話してみたかったのでお茶しませんか」と直球のデートの誘いがあったのでよろこんで承諾してコーヒーショップヤマモトへ行った。 わたしのこと好きってコト⁉と思ったけどそういうことではなくて、単純に人間としてわたしに好奇心を寄せてくれたみたいでそっちの方がうれしいかもしれない。 とても綺麗な顔をしていて、わたしは好きじゃないけどめちゃ女の子からモテそうだなあと思ったらやはりそうだった。モテの弊害の話聞いて面白がる。波長があって、サンドイッチと1杯だけで3時間粘った。 3カ月後から東京へ引っ越すらしいので次は東京で会おうね、と言って別れた。 0421夜 桂離宮へ予約を取っていたのだが同行者飛んじゃったんだよねと熊野寮で船橋さんに愚痴った。「俺建築好きだし行きたいな」と言われたが、食堂で、本を読みながらごはんを食べているめがねの男の人がとてもセクシーで、どうしても目がいってしまい、彼が読んでいた本は「辞書で読むドイツ語」(何それ)で、好ましくてどうしようもなかった。 「彼は建築の学生だよ。学年は知らないな」と船橋さんが教えてくれた。「わたしあの人と桂離宮行こうと思う。ごはん食べながら本読むなんて、ありえないくらい貪欲だからわたしと気が合うよ」と宣言して、食べ終わった後彼の部屋に案内してもらった。「24日の16時に桂離宮に同行してくれませんか」とドアから出てきた途端いきなり要求した。とても緊張した。彼は突然の闖入者に戸惑いながらも面白がってくれて、「ゼミあるけど行きましょう」と言ってくれた。M1で、博士はヨーロッパで取る予定だそうだ。 「きみのコミュニケーションは気さくなんじゃなくてごり押しだよ」と高橋君に指摘されたが、本当にその通りだと思う。
29 notes
·
View notes
Text
youtube
アントニオ・ダマシオ:意識の理解はどこまで進んだか
オートポイエーシスはソマティック・マーカー仮説によって、すなわち、身体によって基礎づけられなければならない。
本書は感性または悟性(理性とは区別された経験に関する知性)に関する書籍である。より分かりやすく説明すると、マインドフルネスを哲学的に論じた書籍であるといえるだろう。さて、私たちが今生きているこの世界において二つの大きな力が私たちに作用しているのは言うまでもないだろう。それはリビドー(性的欲求)とライフ・オブ・ラインズ(線としての生)である。(その作用の様相に関しては添付した資料の図1を参照されたい。)

そして、この二つの力のうちライフ・オブ・ラインズ(線としての生)に焦点を当てているのが本書である。
第一部―結び目をつくることーでは、社会的な生命の紐帯の中の個々の存在の生命線の絡み合い(相互浸透)について論じている。(ex;私たちの精神が交わるとき、つまり自らの意識を相手の意識とつなぐとき、相互浸透しているゾーンはたちまちどちらかに属するのをやめて、両者が責任を有する異質な存在、すなわち「社会」に組み込まれる。)人々にしても、他の生物にしても、あるいは生物による加工を経た事物にしても、こうしたすべてが関わっている出来事にしても、すべては様々な線のかたまりとして、絡み合いとして出来上がっている。つまり、線の生態人類学とはまさに「すべてはすべてと関係している」ことを見極めようとする関係の学であり精神的態度だが、我々の世界を構成するすべての存在=事件(出来事)のエコロジー(生態学)をティム・インゴルドは企てているのである。もちろん、そのドン・キホーテ的企画に完成などありえないのだ。すべては「うろつき」の中で見出され、また見捨てられてゆく線の集合離散のダイナミクスとその履歴の問題となるのだ。そして、成長と運動というプロセスを経て諸々の物が絶えず生じ続ける世界においてーつまり生命の世界においてー生命の線を(関係としてのライフ・オブ・ラインズを)結ぶことが可干渉性の基本原則であることを示すことがティム・インゴルドの目指すものである。この結ぶことは思考や実践の様々な領域の中に現れることになる。そして、結ぶことによって諸々の文化、パターンは維持され、人間の生活のすき間に結び付けられているのである。そうしたものは以下のようなものが含まれる。空気や水、コード類や木といった物質の流れや成長のパターン、編むことや縫うことに見られる身体的な動きや身振り、おそらく見ることよりも特に触れたり聞いたりするといった感覚的な知覚、そして人間関係とそうした関係をもたらす感情などである。すなわち、結びつくことは人々が互いに活動し語ることのリアリティの中に、人々が自分の関心を見つける間のものの中に、そして人間関係の網目を織り込んだものの中にあるのである。続く、第二部ではたくさんの人々や数多くの力がその環境���感情の中で揺れ動く様子を論じている。
第二部―天候にさらされることーでは大気=雰囲気について論じている。具体例としてティム・インゴルドは植物の成長と運動を挙げている。ティム・インゴルドによると、植物は大地的であると同時に天体的であるという。そうであるのは空と大地の混じり合いそれ自体が生命と成長のための条件だからである。植物が「大地に属するものである」から(大地の上にあるのではなく)、植物は「空に属するものでもある」のだ。また、もう一つの具体例として人の知覚を挙げている。私たちは空気を呼吸し、空気の中で知覚する。それゆえ、空気がないと窒息してしまうだけでなく、感覚も失ってしまうだろう。通常私たちは空気を見ることができない。けれども時折霧の中で、炎や煙突から煙が昇る中で、空気の流れの繊細な模様を見ることができる。しかし、正確には空気を見ることができないのは、私たちが見ることができる生を維持させる媒体の透明性が故である。さらに言えば、空気が振動して音の波動を伝えてくれるので私たちは音を聞くことができるし、空気が与えてくれる運動の自由の中で私たちは触れることができるのである。このようにすべての知覚は空気に依存しているといえるだろう。逆に言えば、空気のない固まった世界の中では知覚することは出来ないだろう。それゆえ、まさに感情を持つものとしての私たちの存在は天候(世界)に浸っていることを前提としているのだ。そして、このような大気=雰囲気をより感じ取るために必要な態度が「・・・とともに、・・・とともに、・・・とともに」という態度である。例えば、あなたがチェロを演奏している時チェロとともに奏でているならば、あなたのチェロから流れ出すラインは音のラインであり、それはあなたが聴いている時に聞こえる、あるいは一緒に聞こえるものなのである。その音はあなたの生命にライン吹き込むことであなたはチェロと大気=雰囲気と調和し、マインドフルネスへと至るだろう。このような現象が大気=雰囲気現象なのである。そして最終章である第三部では、このマインドフルネスな状態がいかに私たちをより人間らしい調和の取れた生き方へと導くかを論じている。
最終章である第三部―人間になることーでは生に導かれることがいかにして私たちを人間化するということを生じさせるのかを論じている。長らく西洋的伝統において、私たちが行うことは立案者として頭の中に構想を持った動作主(エージェンシー)のよって行われると考えられてきた。しかし、ティム・インゴルドはこれを否定しており、生は立案者として頭の中に構想を持った動作主(エージェンシー)に従属的ではなく、エージェンシーが生に従属的であることを主張しているのだ。すなわち、この導かれた生によって(「C・オットー・シャーマー」が主張する「出現する未来から導く」ことによって)、いかなる瞬間にあっても人間は自らがそれであるものではなく、自らがそれになりつつあるものたらんと決心していなければならないのである。すなわち、いかなる点でもその過程が最終的な結末に到達することはあり得ないのだ。達成は常に延期され常に「未だない(未完成である)」。人間はどこで生きているのであれ、そしてどのようにして生きているのであれ、常に人間��なりつつあるのであり、つまりその進展とともに自らを創造しているのである。すなわち、人間はこの意味において自分自身の生の脚本家あるいは小説家なのである。
総括したい。ティム・インゴルドは私たちが独立し、自立して存在しているというより環境や他者と相互依存しそれらと調和生きていたいと切望する存在であり、またシステム思考のような態度で生きていくことの大切さを教えてくれるだろう。
youtube
1 note
·
View note
Text
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和七年(2025年)3月22日(土曜日)
通巻第8706号
アメリカで研究費をふんだんに使わせて貰った恩義を忘れ
中国へ陸続と帰還する著名学者にはノーベル省受賞者も
*************************
米国で最新の科学、医学、化学などを学び、マスターし(なかにはノーベル賞受賞者も三人)、さんざんアメリカの資金で研究を極めた中国人学者が、中国へ還る。アメリの巨額投資の成果はみすみす中国へわたる。
典型例は楊振寧の場合だろう。
父親も世界的な数学者だった楊は安徽省に生まれ(そのときは中華民国だった)、アメリカへ渡って素粒子の研究にはげみ、同じく中国人の李政道と一緒にノーベル賞に輝いた。
台湾からの李遠哲もノーベル賞を最初に貰った台湾人。最終的に楊振寧は中国へ帰った。
逆に中国の高給とふんだんな研究費、助成金に釣られたアメリカ人学者が中国と協力する「科学スパイ」がいる。典型はハーバード大学化学部長だたチャール・ズリーバーで、米国予算からもふんだんの助成金を受けながら同時に中国から2億円の研究補助を受けていた。
これは「千人計画」の一環だった。政治的判断の出来ない日本人研究者も多数が中国の高給と研究環境、待遇などの条件に惹かれ中国へ渡った。
半導体や電池技術に関しても、アメリカで研究し米国企業でノウハウを学んだ台湾人がTSMCやエヌビデイアを設立し、世界を席巻した。そのTSMCからごっそりと数百のエンジニアが中国へ渡りSMICを設立した。SMICはいつのまにか7ナノ半導体を生産出来るまでに『成長』していた。
中国人とみたらスパイと思えが米国で合い言葉となった、いずらくなった中国人の中国��国が目立ち始めたのは、この五年ほどで、博士クラスが束になって中国へ帰国し、学部学生の留学生となると、卒業後80%が中国へ帰る(海亀派)。
ボストン大学でロボット工学をマスターしたイエ・ヤンジン(音訳不明)は中国人民解放軍の幹部だった
ブラウン大学でバイオ研究30年の曹浩乃は精華大学教授として帰国した。在米20年のホー・イクイエンは北京大学教授になった。
英国留学でも同じ現象が起きた。
ケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所で博士研究員として在英中国人学者のパン・リンフェン(音訳不明)は権威ある『ネイチャー』誌に30本以上の論文を発表し 花形とされた。英国の大學に特有な伝統的人事に嫌気したパンは英国を去り、中国が用意した顕職につく(『サウスチャイナ・モーニングポスト』、2025年3月22日)
日本の大學は中国人留学生を歓迎し、授業料免除ばかりか月20万円ほどの生活費まで支給している。しかも彼らは帰国すると反日になるのである。
──忘恩の徒、倫理? それはなんのこっちゃ。
17 notes
·
View notes
