#坂口建設
Explore tagged Tumblr posts
Photo




「もう日本の町じゃない」成長続ける”世界のニセコ”―時給高騰し人集められず…閉鎖する介護事業所も 2/16(日) 17:01配信
パウダースノーを武器に、世界的リゾートに成長した北海道のニセコ地域。投資熱は冷めず、円安を追い風にインバウンド(訪日外国人)の流入も止まらない。食品スーパーには、外国人向けの1折3万円を超える生ウニが並び、飛ぶように売れている。
【写真で見る】北海道各地でトラブル…“迷惑外国人”も出現―雪まつり会場スタッフに“雪玉攻撃”する様子配信
バブルのような好景気に沸く一方で、労働力が枯渇し、時給水準が東京より高い2000円を超えるまでに高騰している。人を集められず、閉鎖する介護事業所も出てきた。
外国人の交通事故も一冬500件を超し、住民とのトラブルも増えている。拡大を続けるニセコの現状に迫った。
スーパーに並ぶ3万円のウニ 地元民は「手が出ない」 倶知安町のスーパーで販売されている1パック3万円を超える生ウニ
ここは本当に食品スーパーなのか――。ニセコ地域の一角、倶知安町の「マックスバリュ倶知安店」には、世界的なリゾート地にふさわしい高級食材が並んでいた。
「外国人客が多い冬期間は観光客に満足してもらう商品を豊富に取り揃えている。やはり味にこだわらないと需要はない」(店長の田村誠さん)
北海道産生ウニが1折で3万2184円。急速冷凍したタラバガニのボイルには2万7864円の値札がついていた。霜降りの和牛もきれいに陳列されている。地元住民が目を丸くするような金額だ。
ウニを前に大興奮の外国人観光客
店内を見わたすと6割が外国人。高級食材をためらいなく、買い物かごに放る。アメリカの男性は「どの商品もアメリカより安いし、この品質なら全然高くない。せっかく日本に来ているから、おいしいものを食べないとね」と満面の笑み。かごをのぞくと総額11万5000円の食材が入っていた。
「私には縁がないかな。品ぞろえが良く安く買えるので、ほっとしている」。地元住民の買い物客はうらやましそうに外国人を見つめていた。
外国人ばかり 住民「私たちの町じゃない」とため息 外国人観光客らが歩くニセコのひらふ地区
ニセコ地域は倶知安、ニセコ、蘭越の3町を指す。2023年度の外国人宿泊数は、統計の残る2006年以降最多の延べ73万8800人。12月から3月のハイシーズンは関係者の間で「ニセコ100日戦争」とも言われている。
スキー場のふもとにあり、最もにぎわう倶知安町の「ひらふ坂」は目の前には雄大な羊蹄山が広がる絶好のロケーション。1戸10億円を超えるコンドミニアムや別荘、高級ホテルが並ぶ。
1平方メートルで70万円以上する土地もあり、価格は10年前の倍。札幌の高級住宅地よりも高いところがあり、投資熱は一向に冷めない。 行き交う人の大半は外国人。バス停の行列も外国人だ。「活気があるのはいいが、ひらふはいまや私たちのマチではなくなった」。地元住民の女性が本音を漏らした。
時給2000円超も 開発で上昇する賃金水準 店頭に出されているすき家5号倶知安店の求人
外国人の開発は賃金の高騰をもたらした。人材サービス大手の「ディップ」によると、去年12月のニセコエリアの平均時給は3年前を555円上回る1585円。これは札幌より445円、東京都より117円高い。
地元関係者によると、ひらふ地区の相場が時給2000円、英語を話せるなら2500円。市街地の大手牛丼チェーンでは時給1650円、深夜なら1900円でスタッフを募集していた。
あるホテルのスタッフは「飛び抜けてよい条件は出せないので早めに求人を出して目立つようにしている。たくさんの応募があるので面接するのが大変」と笑う。
別の関係者は「うちを含めて飲食店や宿泊施設は常に人が足りていない」と打ち明ける。
賃金格差大 人材争奪戦に敗れ撤退した法人も 地域内で賃金の格差が生じているニセコ地域
人手不足は地元民の生活を支える施設でも深刻だ。ニセコ地域を管轄する岩内公共職業安定所によると、介護や接客などのサービス業の有効求人倍率(去年11月)は4.52。人手が足りず、壮絶な争奪戦となっている。
倶知安町では、訪問介護事業所と認知症対応型の共同生活介護施設の2つの事業所が去年10月までに���次ぎ閉鎖した。
運営する社会福祉法人によると、理由は「働く人が集まらない」。他の地区よりニセコ地区の単価を上げて求人を出していたが、5年間応募はゼロだった。
物価高や最低賃金の上昇が追い打ちをかけ、廃止を決めた。利用者約20人は町内2か所の事業所に引き継がれた。
閉鎖する介護事業所もあり、高齢者にしわよせが
ある町内の事業所には8人が移った。そもそも人手不足でヘルパーを増やせないので、以前からいた利用者にしわ寄せが及んだ。 「週3から週1に減った方もいる。お金を払うからもっと利用したいと言われても対応できない」(利用者を引き受けた事業所の職員)
この法人が運営する別の事業所で働いていた従業員が内情を明かす。
「介護は大変なわりに時給が1000円ちょっと。ひらふはベッドメイキングでも時給2000円。あまりにも賃金の格差がある。ひらふ辺りはもう日本の町じゃない」(元従業員)
介護事業所の閉鎖はすぐに町内を駆けめぐった。倶知安町で暮らしてきた70代女性は不安を口にする。
「いまは人手不足の時代なので、介護する人も少ないのは仕方ないが、年齢が年齢なので不安。やはり最期は倶知安で過ごしたい」 交通事故の4割外国人 日々の生活に不安 夜も外国人でにぎわうひらふ地区
北海道警倶知安署によると、ニセコ地域で昨冬に起きた交通事故は前年同月比133件増の1024件。そのうち45%を外国人が占めた。大半は冬道に不慣れな人の操作ミスが原因だが、地元住民にとっては不安の種だ。
「交差点で一時停止しない。スピードを出して走っている」「気を付けないと。対向車線を走っている外国人がいるので」(いずれも地元住民)
日本の法律を確認せず、自国のルールや価値観で車を運転することもある。
1月13日未明、ひらふ地区で、オーストラリア国籍の男(31)が酒気帯び運転の現行犯で逮捕された。
警察の調べに男は「自国のルールでは少しアルコールが残っていても大丈夫なので、日本でもいいと思った」などと供述した。
スキーヤーの連絡手段? 不法電波で飛び交う外国語 パウダースノーを求めてやってきたスキーヤーら
法令違反は道交法にとどまらない。違法な周波数で無線を使用するケースも多い。総務省の出先機関、北海道総合通信局によると、1月の調査で確認された121回の不法電波の交信のうち、114回は外国語だった。
バックカントリーが盛んなニセコでは、外国人のスキーヤーらが仲間と連絡を取るために無線を使っているという。
「パトカーや消防、航空機の通信が���害され、人命に危険を及ぼす可能性がある」(北海道総合通信局)
悪意はないとみられるが、明らかな違法行為だ。
物価高で「普通の生活」さらに困難に 識者の懸念 倶知安町駅で行われている北海道新幹線の延伸に向けた工事
倶知安町の人口は1万7000人。外国人が20%以上を占める。
ニセコ人気の先行きは――。北海道の不動産に詳しいアナリスト、志田真郷さんは今後も投資が進むと分析。物価の上振れで、家賃の高騰し新たな施設が建設しづらくなる。地域住民が生活しづらい状態は加速するとみている。
新幹線の開業を知らせる看板
「ニセコは海外の所得水準に合わせて上振れしている。住宅地の価格も上がっていて、通常の住宅地や商業施設、介護施設が成立する水準ではなくなってきている。生活の利便性も下がっていくだろう」
夜も外国人観光客でにぎわう
オーストラリア人がニセコに投資し始めてから20年がたつ。ニセコはアイヌ語で「切り立った崖」の意。隔絶された豪雪地帯から世界の富裕層を魅了する高級リゾートとなった。
北海道新幹線が延伸されると、札幌との移動は2時間超から25分に短縮される。インバウンドの流入や投資は止まる気配はない。 パウダースノーを武器に、世界的リゾートへと成長したニセコ。最もにぎわう「ひらふ坂」は見渡すかぎり外国人で、まるで異国のようだ。
スキー場のふもとにある倶知安町は人口2万人弱の町。平均時給は東京を上回り、ひらふでは、時給2000円超えはめずらしくない。「ひらふ辺りはもう日本のマチではない」。地元住民が嘆くのも無理はない。
深刻なのは、介護事業所の相次ぐ閉鎖だ。撤退をよぎなくされた事業所によると。他の地域より単価を上げて求人を出しても応募は5年間ゼロだった。「あまりに賃金の差が大きい」(介護事業所の職員)。たしかに介護職の時給はひらふの半分ほど。格差が生まれ、従来の地域コミュニティーをゆるがしかねない事態になってしまった。
北海道新幹線の延伸が予定され、ニセコへのインバウンドの流入や投資は止まる気配はない。「最後は倶知安で過ごしたい」。取材中に何度も聞いた高齢者の言葉が脳裏に浮かぶ。地元住民の思いは届くのだろうか。
※この記事は北海道ニュースUHBとYahoo!ニュースとの共同連携企画です。コロナ禍からのインバンドのV回復に追いつかず、オーバーツーリズムの危機に直面する北海道観光の現状を追いました。
(「もう日本の町じゃない」成長続ける”世界のニセコ”―時給高騰し人集められず…閉鎖する介護事業所も(北海道ニュースUHB) - Yahoo!ニュースから)
10 notes
·
View notes
Photo

『 貨物列車で行こう!』長田 昭二 緒 (文藝春秋)
わたしも乗りたい。
第一章 ついに貨物列車に乗る! 貨物線を歩く/乗れないから乗りたい――そこにロマンがある/人��れず日本の物流を支える駅/極限までのスリム化/「拳一つ分」の隙間/動力車の拠点「機関区」/ついに貨物列車に乗る!/突然の鉄道無線/いよいよ「貨物専用線」に進入/東京で貨物列車を見ない理由 第二章 ルポ・東京貨物ターミナル 鉄道貨物の全容を見るべく「東京タ」へ/貨物列車に乗って貨物駅に向かう/「新鶴見信号場」とは/梯子段を上る「垂直乗車」/「ブレーキ、ゆるめーゆるめー!」/心躍る〝短絡線〟/「いよいよ来たか……」貨物列車は地下へ/羽田空港の下を通る点線=東京港トンネルへの憧れ/昭和で見た夢が令和に実現/添乗区間が延長した!/「東京タ」の構内をほぼ二往復/輸送量は毎年��一〇三%の伸び/高まる大型コンテナのニーズ/変わりゆく物流の仕組み/日本最大の貨物駅にある「中央研修センター」に潜入/異常生時の対応を学ぶシミュレーター/ここに座った以上は定時運行遂行の義務がある/「輸送指令」は〝二度呼び〟が基本/懐中電灯一つで長大な列車を点検 第三章 経営再建と未来の貨物輸送――JR貨物トップインタビュー 「変えるをよし」の企業風土が自信をもたらした/さらなる被害が予想される南海トラフ地震への対策/経営が厳しいJR旅客会社が増えた現状/貨物輸送の新提案・新幹線による鉄道輸送は?/総合的な輸送体系「モーダルコンビネーション」という概念/「安全」のための人材確保と労働環境の整備が不可欠/あらゆる物流の集積地点「東京レールゲートWEST」/銀行員、ハウステンボス……様々な経験から生まれた経営軸/「企業として安全はすべての基盤である」/原風景は「貨物列車のある情景」/「ベテランから若手へ」鉄道を支える、技術を受け継ぐ仕組み/運転士によるリレー方式――確立された輸送体系が強み/鉄道貨物が抱える問題をテクノロジーで解決できるか/従来の設備を有効活用「積替ステーション」/「空荷」を解消した「ビール列車」 第四章 広島車両所探訪記 重要拠点・広島/迂回運転を実現した「匠の技」/歴史を刻む広島車両所/「日本一」の車両所/全般検査と重要部検査奈々枝歴史ゆえの「使いにくさ」/「走って磨かれて輝く」車輪/時に親子、時に兄弟/機関車にはトイレがない/憧れの〝車掌車〟の現実/ベテランから若手へ「技の伝承」/車両所は「大きな家族」 第五章 「セノハチ」貨物列車添乗ルポ――広島貨物ターミナル駅‐西条駅 フィーダー輸送の拠点/数字に出てこない忙しさ/日本一のフォークリフトドライバー/営業面の司令塔/もし列車が遅れたら……信号扱い所の修羅場/〝途中下車〟できない貨物は……/鉄道マンにとっての〝難所〟はマニアにとっての〝名所〟/九州と首都圏を結ぶ物流の大動脈/居住性に優れた運転室/無線の通信に沸き上がる感動/普段乗れない貨物線を走行/本格的な上り坂へ――補機本来の業務開始/上り線に���架線が二本/「ノッチオフお願いします。どうぞ」/登りきって連結を外す/「ポウッ!」遠ざかる本務機/待ち時間も切らさない集中力/「発車!」「進行!」一人ぽっちで走り始める/視界も広く、軽快に走る/帰りのほうが忙しい/シカ、イノシシ……夜に遭遇する動物たち/登りと同じ十三分で「瀬野八」を下り終える/列車は貨物専用線へ。時速八十キロで快走/廃車を待つ〝もみじ色〟の機関車/物流を支えるプロの技と知恵 第六章 「文藝春秋」を北に追え!――青函トンネル貨物列車添乗ルポ 大きなミッションを持って貨物列車に乗り込む/「文藝春秋」十月号の積み込みを見学/貨物の積み下ろしや旅客の乗降は行わない「青森信号所」へ/貨物列車でなければ通れない区間に感じるロマン/中村さんが席を譲ってくれた理由が判明/トンボが乱舞する田園地帯を疾走/青函トンネル五十三キロを貨物列車はひた走る/世界第四位、長大トンネルの入口/しばらくすると飽きてくる……運転士の眠気対策は/地上に出たと思ったら次々とトンネルが……/津軽海峡と函館山を望む〝絶景路線〟/急に無数の線路と並走するようになり……/三〇五九列車は定刻より二分遅れで到着/「北斗9号」で三〇五九列車を追跡/コンテナ貨物取扱量全国二位の「札幌タ」/十七時間五十分の鉄路の旅/「盛りだくさん」にもほどがある一日の終わり/一日半ぶりの対面/「イクラ丼」か「混載丼」か/「あとがき」に代えて
18 notes
·
View notes
Text
旅荘野毛?
数か月前、横浜への出張が決まり、わくわくしまくって、マッサージしてくださるお店を探してみる。
アーユルヴェーダ?いいかも^^なんて思い、予約してみる。
その後、期日が近まるにつれて、テンションが上がっていたけれど、結構、何か月かごとに、コースも値段も変更されてるみたい。電話番号書いてある人が優先です、とも書かれ始めたり。その度ごとに、前に予約をお願いしているものなんですけど、って、確認がてらメールをしていたら、
「何回とご連絡いただいておりますが、予約については検討させてください。
当サロンは普通のアーユルヴェーダ施術サロンです。
性的サービスを売りにした様なゲイマッサージ店でもなく、また、極端な感情を持ち込まれても施術に支障を来たすだけになります。
これまでにも、同じような方がお見えになられましたが、全員トラブルを起こしています。原因は一方的な病的なまでの感情移入です。
大変申し訳ございませんが、そちらも今一度ご検討くださいます様、お願い申し上げます。」(原文ママです)
あ、そんなふうに思われてたんだ、僕、、
ごめんなさい、そういうつもりではありませんでした、、今回はキャンセルでお願いしても大丈夫ですか?ってメールしたけど、返事は来ず。
ま、いっか。しゃあない。多分、ちゃんとキャンセルで��てるでしょ、って、自分に言い聞かせて。
次、次、ってな感じで(切り替え早いんです僕^^)、気になってたお店にメールしてみる。
空いてません、とか、時間が遅いので難しいです、とか、、うーん、なんとも、、
そんな中、おひとりの方と、予約を完了^^
おっしゃ、と思っていたら、当日、新幹線に乗る前のバスに乗る前にメールが来て、コロナになってしまいました、って、、
そっか、それは仕方ないですよね、、お大事になさってください^^って、返事をしたものの、、
いやいやそうは言うけどさ、淋しいじゃん今晩、、
って、必死になって、バスに乗ったあと、再度検索。よさげなマッサージやさんをゲット^^
当日、飲み会のあとで、ちょっと待ち合わせに遅くなってしまったら、帰ります、ってメールが来てしまって、、
あ、すいません、今戻りました、って、待ち合わせの10分後くらいに送ったら、戻ってきてくださいました^^優しいマッサージ屋さんで、よかったです^^若いごつむちさんを、がっつりと、堪能^^
飲んでたのもあり、僕は完了できず、、
解散後、どうしようかな、って思ったけど、以前爆サイで検索してて見つけた、旅荘野毛ってところに、行ってみることに。(えびす温泉ってとこもあったんですけど、やっぱり、ごろんとできそうなとこがいいかなーって^^)
(あと、まあまあ近くに、みんながまぐわるとこもあったみたいなんですけど、すでに50代やし、49歳までに見えるでしょ?っていうルックスでもないし、、
入られへんやん、ってなわけで、早々にあきらめました^^)
2月の半ばの木曜日、小雨降ってましたけど、そんなに寒くなくて、小走りで、10分くらいで到着。
動物園に近づく坂のあたり?とか覚えていたので、そのあたりでごそごそしてたら、赤い看板を発見。(えらいえらい、この野生の勘^^って、言うほどでもないですけど^^)
お、いいじゃん、この感触^^このこっそり感が、素敵です^^
入ってみる。ひっそりな感じ。ご年配の方が対応してくださる。設備は古いみたいやけど、小綺麗にされてるのがすごく伝わってくるし、親切。
ちょっと、昔あった浜松喜楽や、ビジネスイン久松(遠いんですけど、行ったことあるんです、2回も^^)みたいな雰囲気なのかな。コンクリートの丈夫な建物で、床は赤いじゅうたんが敷いてあって、レトロな雰囲気。
こちらはね、暖房ついてないですけど、つけてくださっていいですよ、って。テレビの下に並んでるのは、雑誌サムソン。
わー、見たいなー、マンガ結構えろいやつあるし、、とか思ったけど、上に部屋がありますので、って教えてくださったので、上に。
おひとりいらっしゃいますよ、って言われたので、どうかなーなんて思いながら、上の部屋に行ってみると、あたたかい空間が。布団が敷き詰めてあって、シーツも清潔。
そこに、いらっしゃいました、おひとり。うーん、どうなん?
寝息をたててみえる。歳は一緒くらいなのかな。普通な感じ。
横を向いてみえるから、首筋あたりに鼻を近づけてみる。あ、少し、野郎の匂い。
もう、むらむらしてるんで、嗅ぎまくりながら、すぐさま舐めてしまう。
くうんくうん言ってる。受けなのかな?
まあいいや、浴衣の胸元あたりをまさぐる。あ、胸毛を剃ったあとの、ちくちくの感触。
あ、すっげ、この胸毛剃ったあとのちくちくたまんないです、とか、口走ってみる。
乳首は少し大きめで、感じやすそうな予感。もう、好き勝手してしまえ。
むしゃぶりついてみる。乳首にも、玉にも、竿にも。
この、ふかふかな感触がたまらない。やっぱ、歳が近い(勝手にそう思ってますけど^^)人の肌って、ぶにっていう感じがあって、好きだなあ。
あ、穴あたり、やわらかいんですね。いいかも。
まわりをねぶって、指なんか入れてみたりして。
このあたりの匂いって、なんてこんなにいい匂いがするんだろ。好き放題ねぶらせていただく。
そのうち、覆いかぶさってくださり、僕のも心地よくしてくださる。
あ、溶けそう、ほんと気持ちいい。あ、ほんとたまんないです、ちんぽ気持ちいいです、とか、口走ってしまう。
最近、まぐわってるときに、さわさわ亀頭責めされたり、じゅぼじゅぼねぶられたりすると、頭の中がものすごく気持ちよくなって、こんなこと、つい言ってしまう。
乳首もれろんれろんしてくださる。この人の舌、ものすごくエッチだ。
あ、乳首きもちいいです、たまんないです、溶けちゃいそうです、あーすげ、とか、つい言ってしまう。(でもたいした単語言ってないです���^^)
たまらなくなって、いってもいいですか?って聞いて、自ら暴発。
相手の方も、僕が下から見上げるような位置に半立ちになって、暴発してくださる。
もう、へろへろ。すんごい気持ちよかった。
書き込みでは、人がいませんとか書いてあったけど、偶然にも、まぐわってくださる方が1人おられて、僕は大満足でした。
また横浜に来られるかな。また会えるといいな。
20 notes
·
View notes
Photo








(建築設計事務所 可児公一植美雪から)
KUGENUMA-Y 敷地は湘南の海の近く、5層高さ15mのRCラーメンフレームが6層長さ150mの鉄骨スロープを纏った、単純な構成の住宅。 最初に施主から求められたのは高さが15mである事、そして何があって���その高さまで登れる事という2点だけだった。これには施主の大らかな生き方と、海の近くで生きてきた覚悟のようなものを感じた。この施主にとっての生きる事を具現化したような力強く、かつ軽やかで大らかな建築がふさわしいと考えた。同時に海に近いこの場所で、建築自身にも生き残っていける強かさが必要だとも感じた。 15mのラーメンフレームには溶融亜鉛メッキの施された鉄骨のスロープが巻きつく。エレベーターでもなく、階段でもない単純な坂道であるこのスロープは、どんな時でも必ず各層を経て15mの高さまで届けてくれる。また、この単純な坂道は様々な別の意味でも捉えられる。 外部に生み出す拡張空間は上層階でありながら、全ての開口部で掃き出し窓を可能とし、上層での複雑な内外の繋がりを生み出す。それは拡張する床であり、日射を遮る庇であり、安全のための手すりであり、地上からの視線を遮る目隠しとなる。 また、天井高の高い1,2層、壁のない3層、トンネルのような4層、東屋のような5層、均質な5層のフレームの中の質の異なる空間に対して、均質な6層のスロープが少しずつずれながら絡みついてくる事で均質なルールの中に小さな歪みを生み出す。同時に、このスロープは住人が建物の隅々までを自分の目で見る事を可能としている。 通常、高さ15mの建物の外壁は近くで見る事が出来ず、知らず知らず劣化し建物の寿命を縮めていくが、ここでは常に目線の高さにあり、日常的な確認ができる。メンテナンス工事の際には、高さのある建物は足場も高くなり大きなコストとなるが、ここではスロープが足場となる。住人の生きる事が同時に建築を生かす、そんな単純で複雑な建築を目指している。
建築敷地 : 神奈川県 竣工年月 : 2018年3月 工事種別 : 新築 主要用途 : 専用住宅 主要構造 : 鉄筋コンクリート造 地上4階 敷地面積 : 185.67m2 建築面積 : 69.04m2 延床面積 : 102.89m2 構造設計 : 鈴木啓/ASA 担当 : 木村洋介 長谷川理男 施工会社 : 大同工業 担当 : 川上冬樹 写真撮影 : 藤井浩司/ナカサアンドパートナーズ
- - - - - - - - - - - - - - - -
via
増井 俊之 - 江ノ島のマクドの隣にあるこの建物がすごく不思議なのだが...... | Facebook
14 notes
·
View notes
Quote
元日の1面記事は新聞各社が力を入れるのが恒例だ。この数十年で見たとき、とりわけ大きな衝撃を与えた元日報道が30年前、1995年の読売新聞だ。大見出しは<サリン残留物を検出 山梨の山ろく「松本事件」直後 関連解明急ぐ>。地下鉄サリン事件前のこの一報は、その後のオウム真理教への本格的な捜査や報道につながる第一歩となった。また、この記事が出たことで、数十万人の被害を防いだ可能性もある。あの報道はどのように出されたのか。取材していた元読売新聞記者、三沢明彦さんに話を聞いた。(文・写真:ジャーナリスト・森健/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部) 松本サリン事件に結びつく“異臭騒ぎ” 「1994年夏、(警察庁刑事局)捜査一課の人たちにあたると、第一通報者である河野義行さんが怪しいとみんな言う。ただ、具体的に河野さんのどこが怪しいのかというと、たいした根拠がない。彼の家の庭に農薬が複数あったとか、息子に『警察に話すなよ』と言ったとか、その程度。一方、その有毒ガスの中身は青酸カリの数百倍の毒性をもつ化学兵器のサリンだった。そんなもの河野さんがつくれるんだろうかと……。とは思うものの、当初は報道も警察もみんな、河野さん以外に疑いをもつことができなかったのです」 三沢明彦さん(68)はそう振り返る。当時、三沢さんは読売新聞東京本社社会部の所属。警察庁の担当で記者クラブではキャップ(担当記者のまとめ役)を務めていた。このとき、警察庁で高い関心が置かれていたのが「松本サリン事件」だった。 1994年6月27日、長野県松本市の住宅街で起きた松本サリン事件(写真:毎日新聞社/アフロ) 事件は1994年6月27日夜、松本城(長野県松本市)に近い住宅地で起きた。有毒ガス発生という通報で警察がかけつけると、現場では池のザリガニが浮き、ハトが地面で羽を広げて死んでいた。7人が死亡(のちに8人)、重軽症者は600人以上に及んだ。当初は有毒ガスの実体が何か、誰が撒いたのかもわからなかった。被疑者不詳のまま、第一通報者の河野義行さんが重要参考人として疑われた。 有毒ガスの正体がサリンと発表されたのは6日後の7月3日。ナチス・ドイツがつくった有機リン系神経毒物質の化学兵器だった。そんな高度な化学兵器がなぜ住宅街で使われたのか。捜査も報道も混迷する��か、時間だけが過ぎた。 事態が膠着していた同年10月、三沢さんは警察庁関係者から意外な情報を相次いで耳にした。一つは松本サリン事件に新興宗教のオウム真理教が関係しているという話。もう一つは、山梨県上九一色村(現・甲府市、富士河口湖町)にあるオウムの施設周辺の土砂を警察庁の科学警察研究所が鑑定しているという情報。どちらも信じがたいものだったと三沢さんは言う。 「取材を進めると、当時、長野県警がひそかに捜査を進めていたのがわかった。7月、上九一色村で異臭騒ぎがあった。犬が泡を吹いて死に、草木が薬品で焼かれていたという。松本サリン事件と似ている。そこで長野県警はそこに捜査員を派遣、捜査員が山菜採りの格好に変装して、教団施設の土砂を採取したんです。すると、そこからサリン生成時にできる有機リン系の残留物、つまり松本サリン事件と同じものが検出された。また、130人体制の薬品捜査班もつくり、サリンの合成に使う原材料の化学薬品をどこが入手したのかも調べていた。その結果、東京などで4つの怪しい会社が浮かび上がった。そこで長野県警の警部らはその会社に向かったのです」 東京・世田谷区にあるその「会社」は古いアパートの一室だった。警部が階段で2階に上ってみると、玄関ののぞき窓から見張られていることに気づいた。異様な雰囲気に驚き、その場を離れた。ところが別の場所でも、カメラをもった若い男が警部らを尾行し、撮影していた。長野に戻ってから警部らが警視庁に問い合わせた結果、その「会社」は「オウム真理教の信者が集団生活している」という拠点だとわかった──。そうした捜査状況を取材で得るなか、三沢さんは報じる側も注意が必要だと気を引き締めたという。 「その数年前、統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の問題を報じたことがありました。そうしたら、統一教会の関係者が会社に押しかけてきて、大変なことになった。もともと宗教を扱うのはなかなか難しい。と同時に、オウムについて言えば、1989年に起きた坂本弁護士一家失踪事件(のちに殺害事件)でも、オウムのバッジが現場に落とされていて、一家の失踪は教団の関与が疑われていた。これは大変だな……というのは、取材を始めながら考えていたことでした」 サティアンのヘッドギア姿の若者たち 1994年当時、オウム真理教は異様な宗教団体という理解は世間にあったものの、犯罪組織と捉えられていたわけではなかった。同教団は教祖・麻原彰晃のもと、前身団体を経て1987年に設立。ヒンドゥー教やチベット仏教的な要素をにおわせながら、空中浮揚ができる、悟りを開くなど超常能力や神秘体験を謳い、若者を勧誘していった。テレビや雑誌などにも積極的に登場し、宗教学者や著名タレントなどと語り、信用を得ていった。 そうした裏で、教団は異常な活動に及んでいた。強制的な信者勧誘、薬物による修行、異常なルールでの集団生活。こうした活動のなか、坂本堤弁護士によって「オウム真理教被害者の会」が1989年に発足。同年、「サンデー毎日」によるオウム問題の連載報道が始まり、坂本弁護士も登場した。すると、麻原は坂本弁護士を敵と認識。麻原の指示によって、坂本家の3人(坂本弁護士、妻、子)は殺害された。だが、事件当時、坂本家の3人は「失踪」とみなされ、教団の捜査までは至らなかった。 教団はその後、ハルマゲドン(世界の終末)などを掲げ、日本の国家中枢を破壊することを計画。ロシアから軍用ヘリコプターを購入し、サリンやVXガスといった化学兵器などの開発に乗り出した。1994年にそれらの試作品がつくられだし、ジャーナリストの江川紹子氏や弁護士の滝本太郎氏などが殺害対象として化学兵器で襲われた。松本サリン事件は当時教団による土地売買で訴訟が行われていた長野地裁松本支部の官舎を狙ったものだったが、大量殺害計画の最初の試みだった。 ただ、そうしたことが明らかになったのは、すべての事件が終わった後のことだった。 11月11日、科学警察研究所の鑑定の結果で、上九一色村で採取された土壌からメチルホスホン酸が検出された(正式な鑑定書は16日)。それはサリンを合成する際にできる副生成物だった。 12月初旬、三沢さんは上九一色村の現地まで車で出向いた。粉雪が舞う寒い日。牧草地の向こうに異様な建物群が現れた。その日のことは、後年、自著でこう記している。 <教団のサティアンは広い敷地に点在していた。そして、その周辺には不気味なヘッドギア姿の若者たちが突っ立っている。見張りなのだろうか。途中ですれ違う白い修行服姿の女性の顔は青白く、表情がない。ダクトやパイプが複雑に交錯する目の前の白い建物が、サリン工場の第七サティアンとはその時、わかるはずもなかった>(『捜査一課秘録』) 1995年、山梨県上九一色村(当時)にあった化学プラント・第7サティアン(写真:ロイター/アフロ) まもなく教団の関連会社が大量のサリン原料物質を購入していることも判明。オウムを扱っていた長野県警、神奈川県警、山梨県警、宮崎県警、静岡県警などの県警が警察庁に集められた。静岡県警は教団がロシアから購入したヘリのプロペラを回している様子を上空から撮影していた。サリンを空から撒く可能性があるのではないか──。そんな指摘がされ、いよいよ緊張が増してきた。 だが、この段階でもまだ警察庁はどう教団と対峙するかを考えあぐね��いたと三沢さんは言う。 「いくつか理由がありました。一つは、どの県警も一斉捜索のための人員が十分ではなかった。その体制で踏み込んで中途半端な結果となると、『宗教弾圧』と批判されかねない。そして、もう一つ恐れていたのは教団側の暴発です」 1993年、米国であるカルト集団がFBIと銃撃戦を行い、1994年秋は別のカルト団体がスイスやカナダで集団焼身自殺をしていた。そんなケースが頭にあり、もし下手に踏み込んで教団側がサリンを撒き散らしたらどうなるか。信者や警察官はもちろん、住民にも被害が出たら……。警察も恐れていた。そして、そんなリスクに対する恐れは、記者である三沢さんにもあったという。 「特ダネです。でも、書くのか書かないのかといえば、私もまた迷っていました。彼らがもっていた薬品の量から、数十トンという大量のサリンがつくれることが推察された。もし記事を出したことで、反発してサリンを撒かれたら……? 一方で、出さないことで、国民が事実を知らないままでいいのか。そのせめぎ合いの中にいました」 記事を出すときは「ガサ(家宅捜索)に入るときだろう」とぼんやり考えていたが、出すタイミングは思わぬときにやってきた。 オウムとは書かなかった元日報道 12月20日過ぎ、会社にいると社会部の先輩デスクに声をかけられた。アレの件、正月どうだ? 「そうか、正月報道という手があるかと。じゃあ、どこまで書くか。オウム真理教であることはほぼ間違いないが、この時点でどの程度関わっているかがわからず、名指しまではできない。でも、上九一色村の施設で異臭騒ぎはあり、検出された物質が松本サリン事件と同じくサリンの副生成物であることも確定している。それも同事件の直後だったと。だから、オウムの名前を出さず、その事実だけでいこうと決まったわけです」 この頃、脱会した信者から内部資料も入手していた。そこには「小銃製造、生物・化学兵器、細菌兵器、神経ガス、レーザー開発」といった教団の計画が4枚のレポートに記されていた。国家を破壊するテロ計画。三塩化リンなどサリンの原材料が4つの会社からトン単位で大量に購入されていたのもそのせいだった。だが、この時点ではまだその大量購入を非難できない悩ましさもあった。それら大量の化学薬品の購入自体は違法ではなかったためだ。それでも、三沢さんが最終的に記事を出すと決めたのには別の理由があった。 1995年3月20日、地下鉄車内でサリンが撒かれ、現場に向かう化学防護服を着た東京消防庁化学機動中隊の隊員(写真:毎日新聞社/アフロ) 「それまで松本サリン事件といえば、河野さんが犯人という見方が強かった。でも、この記事が出れば、みんな河野さんへの認識を変えるだろう。それだけで意味はあると思いましたね」 原稿を書きあげたあとの大みそか、三沢さんは警察幹部の自宅を訪ねた。翌日の朝刊で発表することを通告するためだった。怒られることも覚悟した��、幹部は意外な言葉を返してきた。 「わかった。一緒に戦おう」 そして1995年の元日、新聞が配られた。 元日、メディア関係者には衝撃が走った。少なからぬ報道関係者がすぐに集められ、正月休みを返上してオウム取材に動かされることになった。当の読売でも三沢さんのもとに十数人の記者が集められ、本格的な取材が始められることになった。 ただ、順調には進まなかった。1月17日、阪神・淡路大震災が発生。多くの記者が震災報道にとられた。同様に、各県の県警によるオウム捜査もはかばかしく進んだわけでもなかった。 そうし��状況を見透かしたかのように、オウム側は大胆な行動に出た。 2月28日、東京・品川区で目黒公証役場の事務長、仮谷清志氏を拉致して殺害。そして3月20日には地下鉄サリン事件を引き起こした。朝の丸ノ内線、日比谷線、千代田線でサリンの袋に穴を開け、中から気体が拡散。14人が死亡、6300人以上が負傷した。化学兵器による無差別テロだった。 警視庁は機敏に動いた。事件2日後の3月22日、目黒公証役場事務長拉致事件の逮捕監禁容疑で3都県の25カ所に一斉に家宅捜索に入った。上九一色村には、機動隊を含む捜査員2500人という大所帯で乗り込んだ。ガスマスクを装着し、カナリアのカゴをもってサティアンに入っていく中継映像は日本に衝撃を与えた。 この事態に三沢さんも驚きつつ、ついに本格的な捜査に入ったことにホッとしたという。その後、三沢さんは1年近くありとあらゆるオウムの取材に関わっていった。 最初に報じた元日の一報に大きな意味があったことがわかったのは半年ほどしてからだった。 1日2トン、計70トン製造のサリン計画を防いだ 1995年10月から始まった各種オウム裁判で、さまざまなことが明らかになった。たとえば、読売の元日報道直前の1994年12月下旬、上九一色村ではサリンの5つめの工程(最終工程)のプラントが完成目前だったと公判で明かされた。 「サリン合成には5つの製造工程があるのですが、化学工場である第7サティアンでは第4工程まで進んでいた。その最後となる第5工程を麻原は『マホウプラント』と呼んでいた。それができれば、1日に2トンという大量のサリンがつくれる。それだけの量があれば、100万人単位で“ポア(殺害)”できる。そんな状況だったんです」 ところが、1995年1月1日、読売新聞が上九一色村の施設でサリン残留物が検出されたと報じた。 裁判での検察側の冒頭陳述によると、麻原はこの報道に驚き、強制捜査を恐れたという。そして「証拠を消せ」と早川紀代秀(オウム内の建設省大臣)や村井秀夫(オウム内の科学技術省大臣)に命じた。のちの捜査で、第7サティアンでは1月3日付で除染用シャワー室に「使用禁止」という通達が貼られたこともわかった。 麻原の命令のもと、廃棄を担当したのは土谷���実や中川智正だった。その際、中川は第4工程でできた中間生成物のメチルホスホン酸ジフロライド1.4キロは捨てずに隠したという。この廃棄されなかった物質が、後に地下鉄サリン事件に使われることになったと三沢さんは言う。 「あそこで使われたのは純度の低いものだった。もし純度が高ければ、もっと多くの人の命が奪われていたでしょう」 だが、元日の読売報道が出ていなかったら、サリンは1日2トン、計70トンが製造される体制にあった。もし第5工程が実施されていれば、おびただしい数の人たちが犠牲になった可能性があった。読売報道から事態が変わったことは、裁判での検察側の冒頭陳述でも読み上げられていた。 あれから30年、三沢さんは特ダネばかり追ってきただけと照れるが、元日報道ができたことはよかったと振り返る。 「地下鉄サリン事件から半年くらいして、ある検事が『読売報道がなければ、100万人死んでいた可能性がある』と発言していました。地下鉄サリン事件は起きてしまったので、すべて防げたわけではありません。でも、100万人、少なくとも数十万人という無差別テロを止めることはできたのではないか。それに貢献できたことはよかったと思いますね」 三沢明彦 1956年生まれ。1979年読売新聞社入社、横浜支局を経て、東京本社社会部で警視庁、警察庁キャップ、宮内庁を担当。編集局次長など歴任し、福岡放送、静岡第一テレビ常務取締役など。著書に『捜査一課秘録』『刑事眼』など。 森健(もり・けん) ジャーナリスト、専修大学非常勤講師。1968年、東京都生まれ。『「つなみ」の子どもたち』で2012年に第43回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『小倉昌男 祈りと経営』で2015年に第22回小学館ノンフィクション大賞、2017年に第48回大宅壮一ノンフィクション賞、ビジネス書大賞2017審査員特別賞受賞。2023年、「安倍元首相暗殺と統一教会」で第84回文藝春秋読者賞受賞。
「数十万人の被害を防げた」1995年元日報道「サリン」一報を出すまでの記者の葛藤 #災害に備える(Yahoo!ニュース オリジナル 特集)
2 notes
·
View notes
Text
無題
義兄の命日で、事故現場に同行させてもらった。彼女はあらかじめ1週間の休みを取って、丈母と2人で西日本を漫遊していた。坐禅体験とかしたらしい。俺は当日日帰りで、早朝の新幹線で日本列島を下って合流した。350mlの缶ビールを2つだけ空けた。やはり日帰りの岳父もそこへ合流して、4人揃って在来線に乗り換えてさらに小一時間、徐々に口数が減っていく中、緑豊かな山間にある郊外の駅に降りたった。
駅中のファミマでお供物の水や菓子や缶ビールを買い込んで、乗ってきた線路にまっすぐ沿っている坂道を上っていった。ガードレールのない歩道はひび割れて、わずかに陰になっているところに苔類がむしていた。陰湿な6月の陽射しがじりじり蒸し暑かった。あそこだよ、と彼女がいうので目を上げると、すぐ向こうが見通せる短いトンネルがあった。その手前が現場だった。片側二車線の国道で、中央分離帯の縁石にわずかな白い跡が残っている。事故の痕跡だという。
そばの街灯に岳父の設置した花立があって、そこに買ってきた供花を生けるのだが、近づいてみると、配電盤の筐体が大きくひしゃげて、黄色い規制線みたいなテープが何周も巻きつけられていた。新しい事故の跡らしかった。歩道にも削り取られたようなタイヤ痕が残っていた。単車だろうか。義��親は特段そのことには触れず、慣れた手つきで花立を洗浄し、水を入れ替え、供物を並べていく。短い蝋燭と線香を一本焚く。甘い匂いがする。そうしている間にも、すぐそばを猛スピードで車が駆け抜けていく。
道路はトンネル手前の緩やかなカーブを抜けたらほぼまっすぐに伸びて駅の方まで続く急な下り坂で、現場のすぐそばに傾斜8%という標識があった。あとで航空写真を見ると、トンネルの入り口手前からのっぺりした白い文字で速度落せという標示が繰り返されていた。街灯にはスリップ注意という標識があった。去年はなかったよね、と彼女が岳父にいっていた。
義兄の車は何らかのきっかけで短いトンネルの入口でバランスを崩し、最終的に数十メートル先で電柱の支線に後方から乗り上げる形で停止した。致命的だったのは、運転席に横から直撃した街灯だった。午前3時だった。街灯は捥ぎ取られていた。今あるものは事故後に新しく建て直されたもので、その費用は義両親が補償したらしい。
茫然としていると、岳父が淡々と顛末を語ってくれた。直前に義兄の追い抜いたバイクが事故を目撃して、通報してくれたのだと。
*
駅でタクシーを拾って、昼食をとるためにもう少し大きな駅まで移動した。ロータリーの横断歩道で若い男が飛び出してきて、運転手が急ブレーキ踏んで悪態をついた。岳父が、自殺行為ですね、といって笑った。土地の名物を食べた。生ビール2杯飲んだ。
*
現地で義両親とは別れた。来てくれてありがとう、と丈母がいうので、来られて良かったです、と俺は素直にいった。新横浜に帰り着いて、ビアホールで彼女と献杯して、色々話した。
あの場所に行っていつも考えるのはね、と彼女がいった。あの場所に行っていつも考えるのはね、兄が最期に見た景色はこれだったのかっていうこと。
*
今もああやって生々しい事故の跡が新しく増えていたわけで、車もビュンビュン飛ばしてた、事故現場そのものというか、標識ばかり増やして何も対策しない行政とかに対する義憤みたいなものはないの? と俺は思ったことを訊いてみた。
道路のせいとは思わない、あくまで兄がばかをやらかした、と私たちは考えている。と彼女は答えた。私たち、と彼女はいった。
*
兄の声が思い出せないのが嫌なんだよね、といって彼女は目を潤ませた。この日初めて見る彼女の涙だった。忘れていることが年々増えている。バイクの人が通報してくれたことも、岳父の話を聞くまで忘れていた、と。
*
忘れることは、悲しみやトラウマから人間が立ち直っていくために必要な機能だから、と俺はありきたりなことをいった。しかしまた、思い出すことが供養になる、ということも話した。祖父の十三回忌の時に、坊さんの説法で聞いた話だった。俺はこの考え方を信仰している。リメンバーミーみたいな話だけど。あの場に行って、俺がここにいる意味は何だろう、とずっと考えていた。丈母が立ち尽くして泣いている横顔を見て、俺にできることはマジで何にもないな、とさえ思った。この考えが既に傲慢なんだけど、けど。
*
義兄に会ったことはない。思い浮かべることしかできない。岳父と、丈母と、彼女と、そこへ俺がもう一人加わった。マイナスではないはずだと思いたい。悼む、偲ぶ、思う、祈る、なんでもいいけれど、そうする人間が一人増えた。それだけで良いことだと思いたかった。
50 notes
·
View notes
Text
Recommended Books 【京都・Kyoto】
&Premium特別編集 まだまだ知らない京都、街歩きガイド。 (MAGAZINE HOUSE MOOK) 雑誌 – 2024/8/6
マガジンハウス (編集)
雑誌「&Premium」発、人気の京都ガイド第5弾! 混雑する観光地から離れて、暮らす人だからこそ薦めたい15のエリアと8つのテーマ、全316軒を紹介します。 ■大和まこの京都さんぽ部 暮らすように歩く、京の街
【紹介エリア・テーマ】 静かに過ごす時間/七条通/四条南/御所南再訪/自分みやげ/叡電/現地系中華/老舗の味/賀茂川/河原町松原/栗の菓子/鹿ヶ谷通/アペロの時間/二条城南/東大路通/冷泉通/吉田&聖護院/壬生/整える/北野天満宮界隈/栗の菓子2/御所西再訪/京丹後
女人京都 ペーパーバック – 2022/9/28
酒井 順子 (著)
京都に通い続けるエッセイスト・酒井順子による、全く新しい視点から切り取った京都エッセイ&ガイド。 女性の生き方、古典、旅、文学など幅広く執筆活動を行う著者が、小野小町、紫式部、清少納言、日野富子、淀君、大田垣蓮月、上村松園など歴史上の女性たち43人の足跡をたどる旅に出た。
「京都の中でも、京都らしさを最も濃厚に抱いている存在は、名所旧跡でも食べ物でもなく、京都の『人』なのではないかと私は思います。(中略)京都の都会人の中には、今も、平安以来続く都会人らしさのしずくが、滴り続けているのです。」(「はじめに」より)
京都に暮らした女性たちの生き様を知ることは、現代の京都の人々、そして京都の街を知ること。 この本を片手に歩いてみると、平安時代の遺構がそのまま残っているところもあれば、貴族の屋敷が今は児童公園になっていたりすることにも気づく。京都の通りを上ル下ルし、西へ東へと歩き回り、時代を行ったり来たりして、新たな旅の提案を教えてくれる。 この本を読むと京都の歴史や文学がぐっと身近になること間違いなし。
京都散策に便利な地図付きです。
お茶の味 京都寺町 一保堂茶舖 (新潮文庫) 文庫 – 2020/5/28
渡辺 都 (著)
ゆったりと流れる時間、その時々で変化する風味、茶葉が持つ本来の美味しさ──お湯を沸かし、急須で淹れてこそ感じられるお茶の味わいがあります。江戸時代半ばから京都に店を構える老舗茶舗「一保堂」に嫁いで知った、代々が受け継ぎ伝えてきた知恵と経験、家族のこと、お店のいまと未来、出会いと発見に満ちた京都生活。お茶とともにある豊かな暮らしを綴った、心あたたまるエッセイ。
京都、パリ ―この美しくもイケズな街 単行本 – 2018/9/27
鹿島 茂 (著), 井上 章一 (著)
◎26万部『京都ぎらい』の井上章一氏、フランス文学界の重鎮である鹿島茂氏が、知られざる京都とパリの「表と裏の顔」を語り尽くす。たとえば、 ・日本には「怨霊」がいるが、フランスにはいない ・日本のお茶屋とパリの娼館は、管理システムが似ている ・パリの娼館は、スパイの温床だった ・日仏では、女性のどこに魅力を感じるか ・洛中の人にとっての「京都」はどこ? ・パリの人にとっての「パリ」はどこ? ・パリと京都の「汚れ」に対する意識の違い など、知っているようで知らなかった「京都とパリ」の秘密がわかる。
京都のおねだん (講談社現代新書 2419) 新書 – 2017/3/15
大野 裕之 (著)
お地蔵さんの貸出料は3000円、発売第一号の抹茶パフェは1080円、では舞妓さんとのお茶屋遊びは? 京都では値段が前もって知らされないことも多く、往々にして不思議な「おねだん」設定に出くわす。京都を京都たらしめているゆえんともいえる、京都の 「おねだん」。それを知ることは、京都人の思考や人生観を知ることにつながるはず。京都歴二十余年、サントリー学芸賞受賞の気鋭の研究者が解読する、京都の秘密。
なぜこれがこんな高いのか、あんな安いのか、なんで無料なのか、そもそもあんなものになんでおねだんがつくのか―― 大学進学以来、京都住まい二十余年。往々にしてそんな局面に出くわした著者が、そんな「京都のおねだん」の秘密に迫る。 そもそも「おねだん」の表示がされていない料理屋さん、おねだん「上限なし」という貸しビデオ屋、お地蔵さんに生ずる「借用料」。 そして究極の謎、花街遊びにはいくらかかる?
京都人が何にどれだけ支払うのかという価値基準は、もしかしたら京都を京都たらしめているゆえんかもしれない。 京都の「おねだん」を知ることは、京都人の思考や人生観を知ることにつながるはず。 2015年サントリー学芸賞芸術・文学部門を受賞、気鋭のチャップリン研究者にして「京都人見習い」を自称する著者による、初エッセイ。
京都 ものがたりの道 単行本 – 2016/10/28
彬子女王 (著)
「京都という街は、タイムカプセルのようだ」と著者は言う。オフィス街の真ん中に聖徳太子創建と伝えられるお寺があったり、京都きっての繁華街に、坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺された地の石碑がひっそりと立っていたり。そこには人々の日常があり、みなが変わりない暮らしを続けている。そんな石碑になど目を留めない人もたくさんいるはずだ。 それでも著者は、そんな場所に出会う度に、タイムカプセルを開けたような気持ちになるのだという。幕末の争乱期の京都へ、平安遷都する以前の京都へ、近代化が急速に進んだ明治・大正時代の京都へ……。さまざまな時代の“時"のカケラが、街のそこかしこに埋まっている。この場所で徳川慶喜は何を思ったのだろう。平家全盛のころの六波羅は、どんな景色だったのだろう。安倍晴明はここで何を見たのだろう。その“時"のカケラは、一瞬の時間旅行へと誘ってくれる。 日本美術研究者として活動する著者が、京都の通り界隈にまつわる逸話から、神社仏閣の歴史、地元の人々の季節折々の暮らし、街歩きでの目のつけどころや楽しみどころ、京都人の気質までを生活者の視点から紹介する。さらに、自身のご家族のこと、京都府警と側衛の方たちとのやり取りなどの日常生活の一端を、親しみやすい文体でつづる。6年以上、著者が京都に暮らす中で感じ、経験した京都の魅力が存分に語られており、「京都」という街の奥深さと、「京都」の楽しみ方を知る手がかりとなる。 新聞連載の24作品に、書き下ろし3作品を加えて刊行。京都の街歩きに役立つ「ちょっと寄り道」情報や地図も掲載。
京都はんなり暮し〈新装版〉 (徳間文庫) 文庫 – 2015/9/4
澤田瞳子 (著)
京都の和菓子と一口で言っても、お餅屋・お菓子屋の違い、ご存知ですか? 京都生まれ京都育ち、気鋭の歴史時代作家がこっそり教える京都の姿。『枕草子』『平家物語』などの著名な書や、『鈴鹿家記』『古今名物御前菓子秘伝抄』などの貴重な資料を繙き、過去から現代における京都の奥深さを教えます。誰もが知る名所や祭事の他、地元に馴染む商店に根付く歴史は読んで愉しく、ためになる!
京の花街「輪違屋」物語 (PHP新書 477) 新書 – 2007/8/11
高橋 利樹 (著)
京都・島原といえば、かつて興隆をきわめた、日本でいちばん古い廓(ルビ:くるわ)。幕末の時代、新選組が闊歩したことでも��名である。その地でたった一軒、現在でも営業を続けるお茶屋が、輪違屋(ルビ:わちがいや)である。芸・教養・容姿のすべてにおいて極上の妓女(ルビ:ぎじよ)、太夫(ルビ:たゆう)を抱え、室町の公家文化に始まる三百年の伝統を脈々と受け継いできた。 古色なたたずまいを残す輪違屋の暖簾をくぐれば、古(ルビ:いにしえ)の美しい女たちの息づかいが聞こえてくる。太夫のくりひろげる絢爛な宴は、多くの客人たちを魅了し続けている。 本書では、輪違屋十代目当主が、幼き日々の思い出、太夫の歴史と文化、お座敷の話、跡継ぎとしての日常と想いを、京ことばを交えてつづる。あでやかでみやびな粋と艶の世界----これまでは語られることのなかった古都の姿が、ここにある。
2 notes
·
View notes
Text
左翼的市民運動のアイコンとして重要な坂本龍一氏の考えを否定することは、左翼界隈ではタブーとなっている。そしてこの坂本龍一氏の遺志を継げとの対応は、その界隈の強い支持を集めるには、極めて重要だ。だから蓮舫はこれを争点化すると、ぶちあげざるをえなかったのだろう。
ユネスコの諮問機関であるイコモスも計画撤回を求めているなどということが報じられているが、単に声の大きな主張にしか耳を傾けないイコモスのあり方が改めて浮き彫りになっただけだと見ればよいだろう。
神宮外苑の再開発について、現実的に考えれば、国や都、都民がその再開発のあり方について余計な口出しをすべき事案ですらないことを理解してもらいたい。
2 notes
·
View notes
Text
初日舞台挨拶レポート
昨年9月に行われた第80回ベネチア国際映画祭で初上映されて以来、世界各国の映画祭、劇場での上映が行われてきた本作。この日は待望の日本公開初日ということで、初日舞台あいさつの会場となったBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下は超満員。そして映画上映後、スクリーンで繰り広げられる圧倒的な物語の余波に浸っていた様子の観客の間からは自然と拍手がわき起こった。
そんな熱気あふれる会場内にやってきた大美賀は緊張の面持ちで、「今日までものすごく緊張していたんですけど、(映画上映直後に)皆さまが手をたたいてくださっていたのを聞いて。良かったなと思っております」と安どの表情。濱口監督も「完成してから9カ月くらいですが、ようやく日本で公開できまして。本当にうれしく思っております。今日はよろしくお願いします」と感激した様子を見せた。
本作主演の大美賀は、もともと濱口監督の『偶然と想像』にスタッフとして参加しており���イベントではその時のメイキング写真が紹介されるひと幕も。だがその後、自分が映画の出演者となり、ベネチア国際映画祭のレッドカーペットを歩き、そして日本での映画初日を迎える。その当時からすると予想もつかなかった人生に「これを超えるハイライトが今後、自分に訪れるのかどうか」と笑顔を見せた大美賀。

濱口監督も「フランスでは2週間早く公開されることになったので、わたしもパリに行ってお客さまと一緒に映画を観たんですけど、結局この人(大美賀)はずぶといなと思ったんですよね。今日も戦隊もので言ったらレッドの位置、どセンターに立っているわけですが(笑)」と冗談めかして会場を笑わせつつも、「究極そういうのができちゃう人だというのは、頼む前は知りませんでした。でもこの映画をつくる前、脚本を書く前にロケ場所などのリサーチをしていたんですが、その時はドライバーとして入ってもらっていました。しかしカメラの前に彼に立ってもらったりしているうちに『あれ、いいかも』という気持ちになって、ここまで来たので。見る目があったなと思っております」と自負してみせた。さらに、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、香港で公開中の本作(今後もアフリカを除くほぼ全ての地域で公開予定)が、フランスでは1週間で7万人の観客が訪れたことも明かされ、会場からは驚きの声が上がった。

グランピング場建設計画の説明会のシーンの話になると、「あのシーンは本当に緊張しました。2日間かけて撮ったわけですが、最初の方は本当に頭が真っ白になりましたね」と振り返った大美賀。『偶然と想像』にはエキストラ的な感じで少しだけ出演したことはあったものの、本格的な芝居をしたのは初ということで「これ以上ない景色を見ています」と語る大美賀に対して、会場からは大きな拍手が鳴り響くなど、俳優・大美賀均が観客に受け入れられている様子がうかがえた。
そしてこの日はもうひとり。小坂も、もともとは濱口監督の『ドライブ・マイ・カー』に車両部として参加していたスタッフ出身の俳優であった。濱口監督が「彼はもともと俳優なんですが、その時は車両部として入っていて。その時に『僕もチェーホフが好きなんです』と言われて。トラックを運転している人からチェーホフが好きと言われたんで、ギャップ萌えをしてしまいました」と笑いながら語ると、その言葉に補足するように小坂が「あの映画では、車両部と監督だったので、なかなか話せる機会がなかったんですけど、最後に話す機会があって。僕も(同作に重要なモチーフとして登場する)『ワーニャ伯父さん』が大好きで、(『ドライブ・マイ・カー』の)台本に感動したので。そのことを伝えたのがはじめて会話をした時でした」と振り返った。
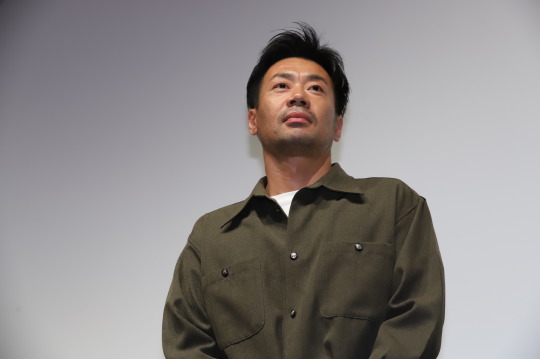
それゆえ本作で濱口監督の演出を受けることとなり「しあわせでしたね」と笑顔を見せた小坂。「それこそ『ドライブ・マイ・カー』の時に、こういうところでお芝居をしたいなと感じていたので。濱口監督は、お芝居をする、という環境づくりにこだわってる方なので、そういう場所でやってみたいなと思っていたんですが、僕もそれが急に実現したので。それが幸せでしたね」としみじみ付け加えた。
主人公・巧の娘、花を演じた西川も本作で忘れられない印象を残すが、彼女はオーディションで選ばれたという。「短い台本にちょっとアドリブを入れてやったりとか。そんなに難しいことは言われなかった」と振り返った西川。濱口監督も「実のところ大美賀さんと一緒にしゃべってもらうというところがメインだったんですけど、西川さんはいい感じで距離があったというか。他の子でも、大美賀さんと本当に親子のように話せる子もいたんですが、西川さんは大人として喋っているような感じがあって。それが良かった」と大美賀との相性が決め手だったことを明かす。大美賀との芝居も「家で自分のお父さんと話すみたいに緊張せずに、普段通りに話しました」という西川に対して、「すばらしいと思います。普段、お父さんと話すようにできないと思うんですが。助けられました。ありがとうございます」と頭を下げる大美賀。そんなほのぼのとしたやりとりに会場も笑いに包まれた。

一方、2015年の映画『ハッピーアワー』に出演していた渋谷。本作は久々の濱口組となったが、「わたしも濱口さんも大きくは変わっていない気がしましたが、ふたりともちょっとずつは大人になっているかなと思いました」と笑うと、「実際に撮影が始まって本読みに入っていくと、『ハッピーアワー』の時にみんなとやっていたことが、さらにどんどんブラッシュア��プされていて。また一緒にできてうれしかったです」と感慨深い様子。濱口監督も「『ハッピーアワー』の時がはじめてだったと思うんですが、その後も彼女の舞台を観に行ったりもしていて。渋谷さんは『ハッピーアワー』の頃もいいと思っていたんですけど、その良さを失わないまま、俳優として成長しているものがあった。だから今回、この役は渋谷さんでいけるかも、というインスピレーションがあった時にお願いしたら受けてくれたので。一緒に仕事ができて良かったです」と晴れやかな顔をみせた。

本作が生まれたきっかけとなったのは音楽家・石橋英子から濱口監督への映像制作のオファーだった。そこからふたりは試行錯誤のやり取りを重ね、「従来の制作手法でまずはひとつの映画を完成させ、そこから依頼されたライブパフォーマンス用映像を生み出す」ことから生まれたのが石橋のライブ用サイレント映像『GIFT』と、本作『悪は存在しない』である。残念ながらこの日は石橋は不在だったが、石橋からは手紙が寄せられ、その手紙を渋谷が代読することになった。
「ちょうど昨年の今ごろ、この映画のために音楽をつくりはじめました。それが昨日のことのような、まるで遠い過去のことのような。時間の感覚が分からなくなるくらい、この作品はわたしの人生にとって大切に作品になりました。わたしがライブのための映像を濱口さんに依頼したのが発端ではありますが、心の大きな濱口さんやプロデューサー、参加してくださったスタッフの皆さま、キャストの皆さま、お一人お一人のこれまでの人生、すばらしいお仕事によって、このようなすばらしい作品になったと思いますし、そのことを心からうれしく思います。感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝の思いがしたためられたその手紙は、さらに「そのような大事な映画の、大事な初日に伺えないことは本当に残念で、悲しくて、悔しいです。本当はこの映画の舞台あいさつの後に、夜中の便でイタリアの映画祭に『GIFT』の上映のために向かうつもりでしたが、25日と26日では、飛行機代がありえないくらいの差があり、ゴールデンウィークを本当に恨む次第でございます。いいことばかりでもつまらないと自分を言い聞かせながら、今はイタリアに到着したばかりのボンヤリとした頭で、迎えの車を待っているのでしょう。ただただゆったりと映像と一緒に身を委ねて、楽しんでいただけたらと思っております。自分が関わっていても、本当に何回観ても飽きない作品だと思います。末永くよろしくお願いします」とつづられていた。
そんな大盛り上がりの舞台あいさつもいよいよフィナーレ。最後に濱口監督が「初日に来ていただいてありがとうございます。皆さまがどう思われたか分かりませんが、皆さまの感想をどこかで目にすることができたら、それがどのようなものでも本当にうれしく思います」と呼びかけると、「フランスでこの映画を観ていた時に、この映画を支えているのは映ってる人たちだなと。本当にすごいなと思いながら観ていました。それは撮影現場でもそう思っていたんですが、ひとりひとりが存在として輝いている。わたし自身そういう印象を持ち、感動したので、ぜひ多くの観客に観ていただきたいなと思います。ひとりひとりのありようとか、仕事を観ていだけいたらと思います。この映画、末永く、よろしくお願いします」と会場に呼びかけると、観客からは万雷の拍手が鳴り響いた。

2 notes
·
View notes
Text
最近って言うと笑われるかもしれませんが、
YouTubeというものがどういうものかと やっとわかってきた。
見てたんですが、あんまりチャンネル登録とか、
未だに概要欄に貼ってますという、概要欄の意味も分からず、
いつもどこ?どこ?と探してる程度。
前までは寝れない時は、子犬の動画見て寝落ちする程度w
なので最近いろんなジャンルの動画を観てると 、いろんなお勧め動画がでてきますよね。
そのなかには、
「今日の何時までに観てください」
とか
「ここにたどり着いたあなたは導かれたのです」
とか
「削除覚悟です、消される前にご覧ください」
とそれはそれは 皆さん再生回数を上げるために凄いですね、
そんな事も知らずに、
「えっ、マジ!!」
とYouTubeに抗体のないチェリー坂口、
毎晩毎夜 寝不足にされてしまい疲労蓄積。
ということで、
先日仕事も大きく一段落したので、
湯治に出かけてきました。
そこで、良く見てるYouTubeじゃありませんが、
「良くぞそこのあなたっ!ここに導かれました」
「削除覚悟です、消される前にお読みください 」
と4月から情報流通プラットフォーム対処法なんて法律もできたので、BANされる前にお読みください、。
さて、皆様!
先進国であるにもかかわらず、また世界では最先端の医療大国日本がなぜがん患者が減らないのでしょうか?
わかりません(^_^;)
いかにもYouTubeで都市伝説を聞いて感化されたっぽいでしょw
にわか知識やからやめときます。
(^_^;)
2年前にコロナがあけて、はじめて言った場所が
鳥取県の三朝温泉。
鳥取と言うと砂丘くらいのイメージですが、
しかし知る人ぞ知る、
県内に10カ所も温泉がある温泉県なんですね、
はわい温泉、皆生温泉 岩井温泉などなど
そして今回2度目となる三朝温泉。
三朝温泉は癌になったお医者さんが化学療法が嫌でここに湯治に来たり、有名人がお忍びで湯治に来たりと言った噂がある温泉。
というのも三朝温泉のお湯は
ラドン含有量温泉でラジウムは世界有数のラドンの含有量を誇り、世界的にもトップクラス。
て書いてます。
なんか放射線やらなんちゃらで体に悪いんちゃうかと思うけど、
これがほんま体の奥まで熱を通して温めてくれため、
かなり前から温熱療法といって化学療法に頼らない癌治療法もあり、それは身体を温め癌細胞を死滅させると同時に免疫力を上げていくというもの。
それにしても昔の人は凄いね、知ってか知らずか、化学が発達するまえから、自然治癒力を高めるために湯治をしてたんですね。
とにかく そんな目で見てるからかしらんけど、三朝のおじいちゃんおばあちゃんみんな元気。
その元気の源が
この「株湯」
といわれる温泉の湧き出ている場所にある浴場!
入浴料400円てまた安い。

そしてヤバいくらいお湯が熱い、
私なんか 最初はつま先、次はくるぶし、次はふくらはぎと
浴槽に入っては出て水をかけてと10回くらい繰り返してはじめて肩までつかれるくらいの暑さ。
そんなことしてると、地元のじいちゃんがやってきて、
かけ湯を3回ほどしたら、躊躇なく肩まで
ドボンっ!
慣れは怖いね(^_^;)
そんなチキン坂口を見ながら笑ってる地元のおじちゃんが話しかけてきた、
先日小学2年の子が1人で浴場に入ってきて、かけ湯したらそのまま入ろうとしてるから、僕 気つけなお湯熱いでって言うまえに、湯船に入って肩までつかって なんと言ったかというと、
「すこしぬるい」
って言ったらしい。
その子はなんと群馬県の草津温泉から来たらしく、毎日暑いお湯に入ってるらしい。
慣れは怖いな(^_^;)
外に出ると お湯も飲めます。

温泉宿は全てと言っていいほど源泉掛け流し。
川の横には無料の露天風呂もあり、橋からおっちゃんのフリチン姿も拝める特典が!
今回の宿は橋津屋さん、小さい可愛いお宿、もちろん宿の浴場でもラジウム三昧。
ほんと優しいいいお湯でした。
サービスも最高!

そんなこんなで、
ちょっと皆さんも一度機会があれば、身体の疲れを取りに行ってみてください。
今から歳とって具合悪なった時のシュミレーションしとかなねw
また話長なったわ。
今回の旅行の目的は、
湯治もそうですが、二日目がメイン。
その目的地は、
岡山県津山市に祀られている、
「サムハラ神社」
これまた、知る人ぞ知る神社、
大阪にも分社がありますが、
とにかくネットでは、
呼ばれた人しかいけないと言う神社。
そう、呼ばれてないのに、
欲の塊 、煩悩坂口の2日目の話は近々またブログに書きます。
今週書きますので、是非読んでくださいませ。
1日目出発は朝7時出発!
途中 中国道で1時間の事故通行止めにあい、
昼食は 11:30鳥取では有名な
回転寿司「北海道」にて
ここ、えげつないくらい並んでるけど、めちゃくちゃ美味しかったです。
何店舗かあります。

そして三朝温泉温泉までの途中に
名探偵コナンの作者 青山剛昌の出身地でコナン君に会い。

あがさ博士とすれ違い

倉吉白壁土蔵群を見学して

三朝温泉到着の行程です。
それでは今日は失礼します。
貝塚市 岸和田市 泉佐野市 泉大津市 和泉市 泉南市 阪南市 熊取町 忠岡町 田尻町
貝塚市水間町 新築 リフォーム坂口建設
天然素材スイス漆喰カルクオウォール
リボス自然塗料取扱店
貝塚市水間リフォーム工事
鳥取県三朝温泉
鳥取県三朝温泉橋津屋
ラドン温泉
名探偵コナン
青山剛昌出身地
回転寿司北海道
倉吉白壁土蔵群
あがさ博士
アンティーク雑貨古材OneBee
#リフォーム#新築 家を建てる#貝塚市水間町 新築 リフォーム坂口建設#リボス自然塗料取扱店#天然素材スイス漆喰カルクオウォール#坂口建設#貝塚市塗装工事#貝塚市水間寺前古民家リフォーム工事#鳥取県三朝温泉#鳥取県倉吉白壁土蔵群#青山剛昌記念館#名探偵コナン#アンティーク雑貨 古材 onebee
0 notes
Text
風景的螢幕實踐 第2回 中平卓馬與西澤諭志的權力=風景論【後篇】
風景的螢幕實踐|佐佐木友輔
第2回 中平卓馬與西澤諭志的權力=風景論【後篇】
西澤諭志——對短暫性權力的發現
大阪・關西萬博──濾鏡文化的建築,以及數位自然的建構
2022年4月18日,大阪・關西萬博的主題項目「生命的閃耀計畫」發表了基本規劃。在由媒體藝術家、研究者與創業家落合陽一擔任總策劃的代表性展館「null²」中,其概念之一,是「透過變形結構建築所創造出的全新風景之鏡」。該展館的外觀由一種名為「鏡面膜」的新材料所包覆,這種材料是由金屬與樹脂混合製成的。展館內部裝設了機械手臂,能夠從內側推動、拉動或扭轉這層膜。因此,投映在鏡面膜上的周圍景物會呈現出如軟體般扭曲變形的效果,使人們能夠即時欣賞不斷變化的未知風景。
50多年前,中平卓馬持續透過攝影,試圖將「風景」這層面紗具體化,並將其撕裂。但如今的做法則是試圖發明、實用化一種新的面紗,進而創造出一層覆蓋現實、再造風景的新形式。「null²」的鏡面膜,明顯可被視Instagram、TikTok等社群媒體中濾鏡文化的延伸。一旦萬博開幕,勢必會有大量照片與影片在這座建築物周圍被拍攝,並上傳至各種社群平台。而在這些平台上,套用濾鏡的行為並不會被視為逃避現實、或試圖遮掩權力不想被看見的面貌,反而會被理解為是一種對平庸現實加以修飾,並創造出更具吸引力現實的正面手段。因為捕捉「原原本本的現實」本身就是不可能的事——換句話說,這樣的提問本來就是錯的——想要分辨「什麼是真實,什麼是虛構」,從根本上就是徒勞的嘗試。既然如此,與其過度恐懼人為的詮釋、操作與演出所帶來的風險,倒不如思考:我們該如何善用、巧妙運用當前可用的技術,這樣反而更具建設性。落合陽一曾提出「魔法的世紀」與「數位自然」等概念,並多次強調未來將是虛實界線模糊的時代,實體與虛擬、類比與數位、自然物與人工物之間的界線將逐漸變得模糊、難以區分。隨著數位技術的發展,我們獲得了一種幾乎能「直接觸碰資訊」的感知,逐步進入一個使用者不再意識到媒介存在的環境——也就是所謂「非媒體意識」狀態。這正是一種「新自然」,幾乎成為每個人都無法避免、理所當然的存在條件。當人與媒體的關係不再是對立,而是協作與共生時,中平式的風景批判與媒體批判——那種認為「權力遮蔽了原本的現實」的疏離論批判——就會在這樣的情境下失去作用,變得不再有效。
被甲烷氣體撕裂的風景
截至2024年8月,位於大阪灣的夢洲地區,正加緊進行即將於翌年舉辦的大阪・關西萬博會場建設工程。夢洲是一座人工島,於1970年代後半開始進行填海與土地開發,目的是作為廢棄物的最終處理場。這座島嶼原本是為了承擔日本社會發展與維持日常生活所排放的大量垃圾而存在,而今則被鋪上瀝青與混凝土等「面紗」,試圖改造為反映國家與地方政府所描繪之理想未來景象的風景。
然而,將這些新風景的面紗撕裂的,既不是如永山則夫那樣的殺人犯或恐怖分子所發出的子彈,也不是如中平卓馬那樣的藝術家或新聞攝影師所拍攝的照片,而是從地底垃圾中釋出的甲烷氣體。2024年3月28日,會場西側工區正在建設中的一棟廁所建築發生爆炸事故,起因是焊接作業所產生的火花點燃了積聚在管道坑中的氣體。根據日本國際博覽會協會的說法,事故雖未造成人員傷亡,但在事發現場之外的多處地點也檢測到甲烷氣體,引發社會對於萬博期間潛在事故風險的強烈關注。
從日本國際博覽會協會所公開的事故現場照片來看,可以看到混凝土地面嚴重損毀,嵌入其中的鋼筋裸露出來,混凝土碎片散落四周,雖然爆炸規模不大,卻足以揭示其破壞力已將堅硬地表撕裂,現場狀���令人震撼。

我之所以被這張照片深深吸引,是因為它正象徵了當下的風景。在這張照片中,一方面,它記錄了風景的殘骸。源自這塊地被強行填埋、作為最終處理場之歷史的甲烷氣體,將試圖覆蓋其上的風景面紗撕開,赤裸地暴露出原本權力欲加隱蔽的事物——例如建設過程中的內部結構,以及事故風險等真實面貌。但另一方面,這張照片也帶有一種宛如廢墟攝影般的靜謐感。與其說它帶來了看到「不該見之物」的衝擊與醜聞式感受,不如說更強烈的是一種似曾相識的既視感——一種「我曾在其他地方也看過這種場景」的熟悉感。像是那些鄉間荒廢的公路,或是災後遲遲無法復原的受災地街景,在財政短缺、基礎設施難以維持的情況下,被半公開地遺棄的地區,這些景象與這次事故現場照片重疊在一起,顯得毫無違和。
簡言之,今日由權力所構築的風景,原本就並非意圖完全「隱藏」某些事物。權力早已放棄遮蔽不利內容的努力,而僅僅將資源投注於打造它想讓人們看到的部分。到了2025年的萬博會場,極有可能會同時並存著兩種極端風景:一種是由最新技術所建構的未來感十足、華麗耀眼的風景;另一種則是令人體會到日本衰退實況的貧窮、破敗且難堪的風景。觀眾將無言地被詢問——你想持續觀看哪一種風景?你希望活在哪一種「現實」之中?並被迫做出選擇。
西澤諭志的風景論
身為一個長期生活於數位技術已滲透至日常生活每個角落的現代人,我無論有意或無意,都在享受其所帶來的便利。因此,我並不認為有必要現在才去撕裂所有的「面紗」,回到那種未經數位技術與媒體介入的「原始自然」或「純粹現實」這種虛構的起點。可是,將這種「新自然」的維護與管理全盤委託給少數技術者或權力者,自己只顧著沉浸在無媒介意識的生活中,我也無法認同。即便如落合陽一所說,我們選擇與數位技術及媒體共生的道路,那也並不表示我們必須永遠順從。在這樣的環境裡,我們依然可以選擇偏離既定路徑、走出曲線行走的方式,甚至為原本被規定好用途的物品開創新的使用方式。換句話說,在這片「新自然」中,我們也可以透過竊取或偷獵其恩惠,試著「設法活下去」。這也是一種對抗壓迫體制與權力,同時又不放棄從中獲得可取之物的「共生技術」。
如果如此,那麼中平卓馬與松田政男所發展出的風景論——其試圖揭露無意識間滲透進日常生活的權力樣貌——至今依然具有當代的意義。因為,唯有了解我們的生命是被什麼樣的權力與技術所制約,我們才有可能進行抵抗或逃逸。不過,如前所述,當代所需的風景論,必須擺脫「現實/虛構」「自然/人工」「個人/國家」等二元對立的思維框架,並以符合當下時代的方式加以更新。而在面對這項課題並進行實踐的藝術家之中,西澤諭志無疑是一位值得關注的攝影師。
西澤諭志1983年生於長野縣,就讀於東北藝術工科大學資訊設計學科的影像課程,至今持續透過攝影展覽與影像作品的方式進行創作活動。其早期作品多半聚焦於學校校園、自宅房間或個人物品等自身生活周遭的事物,透過攝影凝視並重新思考這些熟悉對象,同時結合多種方法——如收集、排列、文字書寫、施力等手法——深入分析這些物件。而在2018年時,他舉辦了睽違七年的個展《[普通]交流・復興・振興》(TAP藝廊),攝影範圍也延伸至日本全國各地。此展之後的延伸發展,則為2022年於水戶藝術館當代美術畫廊第九展間舉辦的個展《CRITERIUM 98 西澤諭志》(策展人為該館當代美術中心策展人後藤櫻子)。
在該次展覽中,四面牆上共展示了14件裝框的攝影作品,其中有些作品是在一張紙上排印多張照片。其拍攝對象主要可分為兩大類,一類是與戰爭災難、人為災難或自然災難相關的紀念性設施(追悼空間),如長崎原爆資料館、水俁生態公園(Eco Park Minamata)、東日本大震災與核災傳承館、雲仙岳災害紀念館;另一類則是國家政策性活動或宗教儀式所用之設施,如東京奧運與帕運選手村、建於皇居前廣場的令和大嘗宮。不過也有些作品難以歸入這兩類之中。例如福島縣雙葉郡富岡町的災害廢棄物處理設施,該設施於2014���至2019年間運作,主要用於東日本大震災後的災害廢棄物與除污物處理,它雖與災害有關,但性質上並非紀念性空間。又如東京23區內的某座公園中設置的告示板(張貼著由兒童繪製的洗手與漱口宣導海報)以及樹木間所圍起的警示封鎖線,也很難說是紀念物或國家設施,但透過「防災」與「健康」這類關鍵詞,與其他照片之間產生了某種鬆散的關聯。

正如上述,西澤在其展覽中展示的照片群,彼此之間構築起了錯綜複雜的連結,形成了一張意味的網絡,進而促使觀者去解讀每張照片之間的共通點、差異與關聯。尤其值得注意的是,作品中反覆出現一種「包覆」「纏繞」「遮掩」的意象,例如廢棄物處理設施與大嘗宮那種臨時���的、仿如搭建而成的外觀、公園內搭設的小型帳篷、穿著日本國家足球代表隊球衣的坂本龍馬雕像、展示於雲仙岳災害紀念館中的防護衣,甚至還有北方領土宣傳吉祥物「愛莉卡醬(エリカちゃん)」的立體看板人像。這些元素都共同構成了一種「遮蔽」的形象。
對此,後藤櫻子在該展覽的說明手冊中撰文指出,一般而言,紀念性建築的功能之一,就是用所謂的「無害化」方式來掩蓋戰爭與災難的慘痛經歷,藉此讓現場的實況、個別當事人的經驗與情感變得不可見。這種對紀念性建築雙重功能的問題意識——既可呈現新的風景,又同時具備隱蔽現實經驗的能力——與中平卓馬與松田政男的風景論互相呼應。中平與松田的觀點指出,權力所製造的風景面紗會遮蔽「原本應該被看見的現實」,而西澤則透過攝影與剪接的方式,試圖揭示「圍繞我們生命的權力機制」。
短暫性權力=風景──從「美麗的日本」到「加油吧日本」
不過,值得注意的是,西澤並不是試圖撕開風景的面紗,以可視化其背後應該存在的某種真實。正如前述,那種基於「現實/虛構」二元對立所展開的疏離論式風景批判,在面對「既然無法掌握所謂『原原本本的現實』,那不如透過人工操作創造更好現實」這種務實主義立場時,很容易失效。為了從這種思維困境中掙脫,西澤選擇嘗試對象化(即「風景化」)的,不是被面紗遮蔽的現實,而是那片「面紗」本身,以及「面紗」實際被應用於現實後所產生的新的樣貌。他透過攝影的拍攝與展覽的排列,詳細分析紀念性建築、政策設施與祭祀設施等在設計上的目的、象徵意圖與實際功能,並進一步揭示這些設施到底遮蔽了什麼,又強調了什麼。
事實上,若僅是要探究個別面紗所遮蔽之物的真實樣貌,那並不是一件困難的事。在《CRITERIUM 98 西澤諭志》展場中,有提供一份展出作品的清單,簡明列出每張照片所對應的設施、其功能與背景,作為「資料」供參考(編寫者為後藤櫻子)。清單右下附有QR碼,觀者掃描後即可連結至展覽資料所參考的網站等出處。換言之,西澤與後藤所選擇的方式,並非以揭發或衝擊性的手法暴露被遮蔽之物,而是以任何人都能自行查找的公開資訊,靜靜地將其呈現出來——彷彿是在說:「這並非藝術的任務」。
對一場攝影展而言,更為重要的,是這些各自的照片/風景經過並置與關聯之後,所共同浮現出的那個關於「權力機制」的整體樣貌。
重新觀看此次展覽中所展示的照片,不難察覺那些基於不同目的而設置的「面紗」,其共通點在於皆擁有一種短暫性(ephemeral)的物質性。無論是廢棄物處理設施、大嘗宮,抑或是穿著球衣的坂本龍馬像所呈現的臨時性裝飾,這些設施本質上都並非為了長期設置而建構,而是在某個特定期間過後,必定會被剝除、拆卸,命運終將歸於撤除。至於像是皇居前廣場上的交通錐、或是貼在公園樹木上的封鎖膠帶,它們同樣不具任何防止外敵入侵的實質堅固性,僅能作為「此處請勿越界」的象徵性警示而已。
而最具象徵性的,莫過於那些由孩童繪製的宣導海報與吉祥物(例如愛莉卡醬)所展現的姿態。這些「面紗」自我定位為脆弱的(vulnerable)存在——脆弱、易傷,甚至可能激起他人攻擊慾望的存在——並以這種姿態行動。換句話說,它們所進行的遮蔽,不是出於惡意或愧疚,而是基於善意與謙遜。

西澤所記錄並蒐集的這些風景面紗,透過針對兒童、復興補強、宗教禁忌等領域所鋪展出的無數互文性意義網絡,使得這些風景無法輕易地被一刀切開,而展現出一種柔韌卻頑強的強度。這些風景並非以壯麗宏偉的姿態高舉自我、彰顯權威,而是以短暫而脆弱的外觀毫無保留地呈現於眾人面前,進而激起人們的同情與憐憫,讓原本銳利的權力批判語調變得柔和,甚至轉而成為「讓我們一起度過這場困境吧」、「讓我們攜手合作吧」、「讓我們共生吧」這類溫和的呼喚。
如此一來,也就不難理解,為何西澤會在過去的展覽中選擇「普通」「交流」「復興」「振興」等關鍵字作為命題與串聯的核心。現今包圍著我們的風景,已不再是1970年代「探索日本(Discover Japan)」觀光宣傳所召喚出的「美麗的日本」風景,而是源自於二戰期間國威宣傳的語彙、延續至東日本大震災等重大災害復興話語所構成的語脈傳統,也就是那個「加油吧日本」的風景。
5 notes
·
View notes
Text
2023/12/11〜

12月11日 昨日つけ置き洗いをした加湿器の給水タンクのキャップを捻り開ける力がなくて水を捨てられず、朝そのままで出かけた。浴室乾燥していた洗濯物も気温が下がって乾きが悪くなり3時間では乾かなくなってしまい干したまま出かけた。
この調子で毎晩毎晩掃除や片付けや、やらなくてもいいのに儀式的にやってしまうことを減らしたい。その日の感じに合わせて必要ならばやる、程度にしたい。
お昼休みに歩いていたら、向かいから坂を降りて来た自転車の方がすっころんでズボンの膝が破れてしまった。私含め近くにいた人たちは遠巻きに心配そうに、でも声をかけたりもできずにいる様子で見守っていて、本人はやっと少しずつ起き上がって、そんな時に後ろから悲観するばかりでない明るい声で「あら〜大丈夫かしら?」と声をかけてくれた年配の女性がとても救いの存在だった。 心配そうに「大丈夫ですか?!」と言われたら「大丈夫です」しか言えなそうだけれど、余裕を持った明るさで声をかけてくれたら「ズボンの膝が破けちゃった…」と、少し泣き言を答えることも許してくれそうだな、と思った。
お休みに入った上司の代わりを務めてくださる方と、まだ様子見あってお仕事をしている感じがなんだか煮え切らなくてぎくしゃくして話す度に泣きそうになっている。

12月12日 向かいのデスクの方が自分で設計した自邸が1月末に完成するお話を聞かせてもらう。写真も見せてもらって白と木が良い塩梅の素敵なお宅だった。 すごい!うらやましいとか尊敬するとか目標としたいとかそうゆう次元でなくて、なんかこれはとても嬉しいだろうな!?と率直に思ってしまい、他人のことだけれど「嬉しくないですかこれ!」と少しテンションが上がってしまった。 年が近い彼女よりお仕事でできないことが多い(と勝手に思っている)私は、時々それに落ち込んだりしていたけれど、彼女は本当に建築が好きなんだ!と嬉しくなる発見ができた。 私は建築はお仕事でしかなくて、作家さんの作品や考え方を観るのは好きだけれど自分で作りたい分野ではない切り分けはできているので、全く別の類の方としてやっと彼女を捉えることができた気がする。 お家ができたら遊びに行かせてもらうお願いもできた。

昨晩、教えていただいた大阪のギャラリー情報を確認し、ちょっと違うかな〜となっている。 今日から京都のギャラリーも少しずつみてみよう。
友人へ次会った時に渡そうとしていた京都限定のルルルンのパックと光線さんのガチャガチャをレターパックライトに詰めて送ろうとしたらポストに入らなかった。また3センチ(今回はプラスの5センチも)をオーバーしてしまった。
マスクが苦し過ぎてくらくらするのと、日中の噛み締めがひどくて顔が痛くなるので、2日間外す生活をしてみたけれど、なんとなく人と喋る時の飛沫恐怖が発生してしまい、唾が飲み込めないことがたくさんあった。また良くない症状を発症させてしまったかもしれない。

12月13日 ガスの点検の立ち会いのため午前中はお仕事をお休みをした。 そのため昨晩は出来る限りの掃除をしたり日記を更新したりとても忙しく過ごし、22時からの一食目のご飯は栄養補給でしかなくて味がしなかった。
でも朝起きて、まだ薄暗い中で大島さんの新しい読み切りの漫画を読んで二度寝をしたら、夏に展示をしたギャラリーの白濱さんと大学時代の好きな友人が夢に出てきてとても幸せだった。alt_mediumで小規模のブックフェア的なイベントを開催していて、私はそれに参加して写真集を販売したり自分の作品についてトークをしたりして、出版関係のお仕事をしている友人はたまたま仕事でこのイベントに来ていて、写真を通してお仕事でこうやって好きな方々と再会できた幸せな夢。

朝起きても、半日仕事を終えても、まだどことなく今日良かったことがあった、と思う気持ちはこの夢のおかげだと思う。 こうなると今の仕事を続けることを少し悩んでしまう。
フィルムカメラで写真を続けるためにNikonF100の修理をするべきだと、もう一度修理店を探して、インター���ットで見つけた2店舗に連絡をとってみた。修理するより中古機材を買った方が安いのかな。
午後から出勤する道中、イルミネーションの準備が進められていて、夜帰宅するときちゃんと光っていた。
いつも行くスーパーの品揃えについて、私がお決まりで毎日買い続ける商品が、ある時から私が買うごとに一つずつ減ってき、最後の一つを購入した次の日からその商品の取り扱いが終わってしまうことが何回か続いていて悲しい。その中の需要と合わないものを嗜好してしまっているの?
無事でいたすぎて、年明けの有給の予定を立て始めている。

12月14日 ティカ・αが作曲、最果タヒが作詞した曲が、1月24日にリリースされる情報を知る。え?!と、なってしまう。え?!ティカ・αと最果タヒが作品を作ってしまったのですか。嬉しさや楽しみな気持ちより、もうこれまでの空虚な気持ちに近い感覚。
ティカ・αエピソードのひとつ、“愛・テキサス”のMステ動画のコメント欄が意外と愛が溢れていて(山Pファンでない人達の山Pへの評価について)、なんかよかったことをたまに思い出します。
ポストに入らなかったレターパックライトを郵便窓口でプラスに変えてもらう。差額と手数料だけ払って、使用済みだけれどライトを返却して完了した!
有言ジーザスなので朝デスクについてから始業まで年賀状の宛名を書くようにしている。でも裏面のデザインが定まりきらずにいて今年は出すのがギリギリになってしまいそう。
昨日の日記にスーパーの品揃えについて書いた矢先、いつも買っていた商品がまた取り扱い終了となってしまった様子。これまでの取り扱い終了商品履歴。ナチュラル豆腐ビヨンド、揚げなすとトマトのフリーズドライスープ、豆のサラダ、雑穀のサラダ、殻が剥いてあるゆで卵、畑生まれのまろやかソイ、サラダ豆。これ以上私に食の不自由を与えないでください。
来週もどこかでお休みを取れないか探してしまう。

3 notes
·
View notes
Text
我が国の未来を見通す(85)
『強靭な国家』を造る(22)
「強靭な国家」を目指して何をすべきか(その12)
宗像久男(元陸将)
────────────────────
□はじめに
前回も書きましたが、私は、1978年から2年間、
アメリカに留学し、航空宇宙工学という工学部では
当時、最先端を走る分野を学ばせて頂く機会があり
ました。
これもすでに触れましたが、当時はアメリカ経済が
停滞し、その反動で円高が進み、毎月の円建て給料
がベースアップするなどお陰で助かりました(今は
その逆で、留学生は日々の生活も大変だと聞いてい
ます)。また、アメリカ国内にはベトナム戦争の
“後遺症”が残っていて大学構内でも反戦集会が開
かれるなど、アメリカ全体の“士気”が落ちている
ような時期でもありました。
この間、アメリカ人の他、留学生仲間で親しくなっ
たのは台湾人、韓国人、ベトナム人、フランス人、
エジプト人、アルジェリア人、イラン人、コロンビ
ア人などで、当時は中国大陸からの留学生はおりま
せんでした。
滞在間に、イラン革命が発生し、イラン人留学生が
帰国するかどうか悩んでいたこと、そして台湾が国
連から脱退し、台湾人留学生を慰めたことなどが昨
日のことのように思い出されます。
留学先のコロラド大学はコロラド州立ですが、アメ
リカでは規模もレベルも中堅クラスの大学でした。
大学が所在するボルダー市は標高(約1マイル〔1
600m〕)が高いという立地条件も手伝って、航空
宇宙工学などは割と有名でしたが、ほかの学部にも
日本からの留学生がたくさんおりました。
また、大学には、夏季を利用した留学生のための英
語の集中講義があり、秋に全米のビジネススクール
などに入学する日本人も夏季期間中だけキャンパス
に滞在していました。当時は、数多くの名立たる企
業が優秀な社員をアメリカのビジネススクールに留
学させていたのです。前回、“日本にも誇らしい時
代があった”と書きましたが、現在はどうなってい
るかについては本論で触れましょう。
もう一つの思い出が、大学の研究費のほとんどが政
府や州、それに軍などの公共セクターや企業から援
助を受け、割と潤沢だったことです。ほとんどの教
授たちがそれを当たり前のように活用していました
が、大学では「基礎研究のための資金を集められる
教授が優秀な教授」というレッテルが貼られていた
ことをおぼろげながら覚えています。
わが国では、いわゆる「産軍学複合体」を悪いこと
の象徴のような観点からの解説が多いですが、アメ
リカのみならず、中国やロシアを含む先進国はすべ
て、政府も産・軍・学も共同して、必死になって
「国益」を追求しているような現実を、私は40数
年前に(その一端ではありますが)を自分の経験と
して触れることになりました。
もう一つの思い出が「よく勉強した」ことです。私
の人生の中で、まさに“寝食を惜しんで”あれほど
勉強したのは後にも先にも経験がありません。英語
のハンディもあったとはいえ、「アメリカの大学は
入るのは簡単だが、出るのは難しい」と言われるよ
うに、授業では毎回、課題(宿題)が出ますし、半
年の学期の間に中間試験が3回もあったります。そ
れらはすべて成績に反映され、及第点をとれなけれ
ば容赦なく「F」(Failure:不合格)と判定されま
すので、学生はみな、必死でした。
さて現在、わが国の「教育」はどうなっているので
しょうか。本論で日本の「教育」に関する諸問題を
取り上げ、いかに「国力」に影響を与えているかな
どについて考えてみましょう。
▼「教育」が「国力」に与える影響
わが国の「教育」の現状についての“切り口”はた
くさんありますが、いつものように国際比較からス
タートしましょう。最初の出典は、「大学教育が普
及し、教育水準が高い。そんなニッポン像はもはや
幻想」として教育の構造的な問題をあぶり出してい
る『「低学歴国」ニッポン』(日本経済新聞社編)
です。書籍のタイトルのように、「教育もここまで
落ちたか」というのが正直な読後感です。
目についた所を少し紹介します。まずは次の数字で
す。日本人120人、米国人281人、韓国人28
4人、ドイツ人336人、英国人374人……読者
の皆様は、これが何を意味する数字かわかるでしょ
うか。
答えは、「人口100万人あたりの博士号取得数」
の2018年のデータです。(前回も少し触れまし
たが)10年前の2008年より減少しているのは
日本だけだそうで、修士課程を経て博士課程まで進
んだ学生は、2003年度の1万1637人をピー
クに減少し続け、2018年度は約半分の6022
人まで落ち込んだようです。その原因として、博士
号をとっても正規雇用で安定した研究ポストが減り、
その先の展望を描きにくいことが背景にあるといわ
れます。
実際に、2019年度のデータによると、米国の博
士は、企業で21万5千人、大学で24万1千人働
くなどその差はほとんどありませんが、日本の場合、
企業ではわずかに2万4千人余りしか働いておらず、
博士号保持者の75%に相当する13万6千人が大
学で働いています。企業の研究者に占める博士の割
合も、フランスの12%、米国の10%を大きく下
回り、韓国(7%)、台湾(6%)にも後れをとる
4.4%に留まっています。
その結果として、前回紹介しましたように、注目度
の高い科学論文数の順位が落ちつつあること、そし
て鉄鋼や造船のような重厚長大型産業のみならず、
ハイテク分野などの産業競争力の低下が進む要因に
もなっているのです。
経営者の学歴も違いは鮮明です。日本の時価総額上
位100社のうち、84%の経営者が大卒ですが、
米国の経営者の67%が大学院卒で博士課程修了者
も約1割おります。つまり、経営者の「低学歴」も
日本企業の競争力向上を妨げているとの見方も出来
るのです。
個人的な体験に戻れば、コロラド大学の修士課程に
は、陸海空軍の将校たちもたくさんおりました。時
々、校内で軍事訓練をしている光景も目にしました
が、当時、アメリカの将校の約30%は修士以上の
学歴を保有していました(陸上自衛隊では、約30
0名の同期のうち、米留と国内留学合わせて5名ほ
ど、防大の研究科を加えても10数名でしたので、
その差は歴然です。今も変わらないと思います)。
話は変わりますが、だいぶ前に“リケジョ”という
言葉が話題になりました。理工系の学部に進む女性
の割合に関するOECDの2019年の調査結果で
は、工学・製造・建築分野における女性割合は16
%、自然科学・数学・統計学では27%でした。い
ずれも36カ国中、日本は最下位の36位です。そ
の要因として、工学部の就職先は多様で、進学した
後の将来像が見えにくいことがあるようですが、時
代が変わり、工学部卒の女性は産業界から引く手あ
またで、“女性の発想が不可欠になっている”と言
われているにもかかわらず、女性の割合は増えてい
ないようです。“リケジョ”が少ない原因に、その
ような「産業界の実態を高校の教員がほとんど知ら
ない」ことにもあるようで、今後の普及が望まれて
います。
さて、歴史をさかのぼれば、明治期には、近代国家
の国づくりの担い手となる官僚の養成機関として東
京大学などの帝国大学が創設されました。しかし、
近年は、東京大学卒でキャリア官僚を目指す若者が
減り続け、2020年合格者は349人と1999
年以来最少となっています。
法学部卒の優秀な学生は官僚よりも外資系コンサル
タントを選ぶことが珍しくなくなっているとのこと
です。外資系のコンサルでは20代から高給が得ら
れ、各省庁などからの委託を受けて政策立案にも携
われるなど、官僚より“うま味”があることにその
理由があるようです。
かつては、「立志」と「立国」が同時に実現できた
のが、現在は、日本の「国力」が落ち、国際社会の
地位が相対的に低下しているなど、国の将来像が不
透明なうえ、人々の価値観も多様化して、“志と倫
理意識が希薄化している”との分析があります。な
かでも、「今の受験エリートは、勉強するのは自分
のためと教えられて育つため、ノブレス・オブリー
ジェ(高貴さに伴う義務感)や社会に恩返しする感
覚がない」(昭和女子大総長・坂東真理子氏)のよ
うな危機意識を持つ見方もあります。
これらから、「教育」の分野も「鶏が先か卵が先か」
の議論が当てはまるようです。つまり、「このよう
な若者の価値観の変化が『国力』が低下する要因と
なっている」と考えるか、「『国力』の低下が若者
の価値観を変化させている」と考えるか、悩むとこ
ろではありますが、将来の解決に向けて、一つのヒ
ントを与えてくれていることは間違いないでしょう。
本書には、「ゆとり教育」をはじめ、その他の「教
育」に関して山積している問題や課題がほぼ網羅さ
れていますが、良し悪しは別として「Z世代」とい
われるような若者の資質が育まれる、その要因の一
つも「教育」があると考えられます。紙面の都合で
細部は省略します。
本書以外の「教育」に絡む国際比較を少し追ってみ
ましょう。はじめにアメリカに留学している最新
(2021/22年度)の国別ランキングを見てお
きましょう。第1位はダントツで中国(29万人)
であり、2位インド(20万人)、3��韓国(4万
人)、4位カナダ(2.7万人)、5位ベトナム
(2万人)と続きます。1990年代から中国とイ
ンドの留学生が急増し、全体の約半数を占めている
ようです。
中国人がアメリカに留学する理由はさまざまあると
は思いますが、逆に中国に留学しているアメリカ人
は、2020/21年度には382人まで減り、全
体でも1.1万人ほどにしかいないことからすると、
両国の“教育格差は歴然”と言って過言でないと考
えます。
さて日本です。日本からアメリカへの留学は、19
50年ごろから1990年代前半までは増加の一途
をたどります。特に1980年代中頃から急速に増
加し、90年代前半には約4万7千人に及びます。
しかし、2000年代に入った頃から急速に減り続
け、最新のデータで1.3万人余り(11位)まで
減っています。その原因の筆頭に挙げられるのが日
本経済の長期停滞にあると言われています。
経済の長期停滞は国内の教育支出にも影響があった
と推測されます。OECDによると、2019年時
点の「GDPに占める教育機関への公的支出の割合」
は、日本は2.8%であり、37か国中36位でし
た。前年の同率最下位からは改善しましたが、依然
として低い状況が続いています。ちなみに上位3か
国はノルウェー(6.4%)、コスタリカ(5.6
%)、アイスランド(5.5%)で、主要な先進国
は3%半ばのようです。
これに関しては、わが国は、2008年、福田内閣
の頃、文部科学省がGDPの3.5%(当時)の教
育支出を10年間で5%に引き上げる数値目標を盛
り込むことをも目指し、教育会や自民党の文教関係
議員の賛同を得るところまで漕ぎつけましたが、財
務省の反発にあって“頓挫”したという経験がある
ようです。
「国家100年の計は教育にあり」のように、人材
育成こそが国家の要であり、長期的視点に立って人
を育てることが即、「国力」に影響を及ぼすことは、
時代の変化や洋の東西を問わず、普遍の真理である
はずなのですが、財務省の抵抗とそれを跳ね返す力
が当時の政府になかったことが、結果として、「低
学歴国」の“現状”を招いているとすれば由々しき
問題であるのです。
それだけではありません。その結果として、大学な
どの高等教育を受ける学生の「私費負担」の割合は、
日本は67%と、OECD平均の31%を大きく上
回っています。つまり、“子育てには金がかかる”、
よって“子供をあまり作らない”との少子化の要因
にもなっているのです。今頃になって、慌てて育児
手当などを引き上げようとしていますが、当時の
「国家100年」の大義など全く頭になかった罪は
大きいと言わねばならないでしょう。
まだまだあります。2020年時点の高等教育を受
ける学生の私立教育機関に在籍する割合も79%と、
OECD平均(17%)の4倍以上になっています。
再び上記『「低学歴国」ニッポン』によれば、「東
大生の世帯年収は950万円超が5割を超す」との
結果も明らかになっています。つまり、「所得格差」
による教育機会の差異が生じているのです。さらに
は、「東京と沖縄の大学進学率は26.9ポイント
の差」があるなど、「地域格差」による教育機会の
差異も明らかになっています。
面白いデータもあります。の東京都の合計特殊出生
率(2020年)は1.08で47都道府県中ワー
ストですが、沖縄県は1.86で、1974年以降
47年連続で全国1位を維持しています。当然、
「教育」以外の要因があるとはいえ、ここにも将来
のヒントがあるような気がしてならないのです。
▼「教育」は、「未来の国力」維持増強の“一丁目
一番地”
改めて、戦後GHQの占領政策以降の我が国の教育
体制を振り返ってみましょう。GHQの教育改革は、
戦前の教育の抜本的に改革を狙いとして5本の柱を
建てて断行しました。つまり、(1)軍国主義や国家神
道を排除するための「教育関係者の追放」、(2)思想
の自由化を推進するための「教育勅語の廃止」、
(3)性別による教育差別をなくす「男女共学の導入」、
(4)地域ごとに教育内容を決定する「教育の地方分権
化」、(5)「6・3・3・4制度」の確立と小・中学
校を義務教育化、でした。この改革にはさまざまな
意見がありますが、現在のわが国の教育体制の基礎
となりました。
戦後のわが国の「教育」を抜本的に見直そうとした
のも安倍元首相でした。首相着任前から、イギリス
のサッチャー首相の教育改革を参考に、「教育再生」
を推進しようと決意されたようです。安部氏の『美
しい国へ』から抜粋しますと、サッチャー教育改革
の柱は、(1)自虐的な偏向教育の是正、(2)教育水準
の向上にありました。あまり知られていませんが、
当時のイギリスも、歴史教育において、長い間の植
民地政策の「負」の側面を重視するあまり、わが国
と同じような“自虐的な自国の歴史観”が生まれて
いたそうです。
サッチャーは、歴史の否定的な部分と肯定的な部分
のバランスのとる方向で教科書を書き直すとともに、
教育水準の向上のために、教育省から独立した「学
校査察機関」をつくり5千人以上の査察官を全国に派
遣して徹底的にチェックし、水準に達していない学
校は容赦なく廃校にしたようです。当然ながら、学
校現場からはデモやストライキなどの猛反発を受け
ましたが、サッチャーは一切妥協せず、ついに改革
をやり遂げました。
安倍元首相は、幹事長時代にイギリスに調査団を派
遣し、その実態を研究するともに、首相に就任する
や「戦後レジームからの脱却」を掲げ、「教育再生」
にも取り組みました。
そのために、「教育再生実行会議」を設置し、「教
育の質の向上」「教育機会の均等化」「生涯学習の
推進」「国際理解教育の強化」「道徳教育の位置づ
けの明確化」などの改革の方向を定め、GHQによ
る教育改革の結果として、“国に対して誇りを持っ
ている若者が少ない”現状を改善するために、「日
本の伝統や愛国心を育むことを教育の目標」に掲げ、
「我が国の郷土を愛する」という文言を条文に追加
するなどの「基本教育法」の改正を実行しました。
案の定、「戦前の価値観に回帰する可能性がある」
とか「行政がゆがめられた」など論理矛盾している
ような批判が文部科学省内部からも噴出しました。
さて、その成果が現在の若者教育にどのように反映
されているのでしょうか。聞くところによると、小
中学校では、「道徳」の時間がいじめ防止を目的に
「特別の教科」に格上げされたり、大学では返済不
要の給付付奨学金が導入され、授業料減免も拡充さ
れるなど「所得格差」による教育機会も改善されつ
つ、現在に至っているのでしょう。
岸田政権は、これらの教育改革を継承して「教育未
来創造会議」を立ち上げ、昨今のさまざまな環境の
変化を受けて、「オンライン教育体制の推進」「リ
カレント教育の強化」「拠点大学を指定して再編を
先導する大学改革」などに取り組んでいるようです
が、それらを含め、近年の「教育改革」の成果が見
えるのはもっと先なのかも知れません。
一方、わが国の「少子高齢化」は待ったなしです。
現在大学進学率は50%を超えていますが、私立大
学の定員全体に占める入学者数は100%を切り、
大学の50%超が定員割れを起こし、定員50%に
満たない大学も約5%あるようです。しかも首都圏
など都会地の大学と地方の大学の定員充足率も広が
りつつあり、将来、少子化と過疎化が加速すること
によって、この現象がますます顕著になることでし
ょう。
すでに、「東京工業大学」と「東京医科歯科大学」
が統合するとか、「早稲田大学」と「慶応大学」ま
でも近い将来、統合するとの話も出ているようです
が、遅かれ早かれ大学の統廃合は避けられないので
す。
政府は、2022年に「国際卓越研究大学法」を制
定し、この大学に認定されれば600億円規模の予
算が投入されることを担保しているようです。学生
や研究者から「選ばれる大学」を政府が支援をする
のは当然としても、前述したような過疎化を助長す
るようなものであってはならず、ほかの政策との連
携は必須でしょう。
将来の「教育改革」は、純粋に「国家100年���計」
に基づくものであるべきで、予算投入の条件として
“無用な縛り”を加えたり、文科省役人の天下り先
の確保のようなものにならないことを国民は注視し
なければならないでしょう。
バイデン大統領は、今後10年間、幼児教育や子育
て支援などに4000億ドル(約45兆円)を投じ
る計画を打ち出し、同様に、中国は、2035年の
「教育強国」実現に向かって高等教育の機会拡大を
目論んでいるなど、「国家100年の計」はどの国
も同じです。改革する側が、大義を忘れて姑息な思
惑で目先の結果だけを追い求めていると、現時点は
おろか、50年先、100年先の世代も「戦わずし
て負ける」ことになりはしないかと懸念します。
改めて、「教育」は、「未来の国力」を維持増強の
ための“一丁目一番地”であることを肝に銘じる必
要があるのです。
次回は、「国力」を構成する「ハード・パワー」の
最後である「文化」を取り上げ、その後、「ソフト・
パワー」を取り上げて読者の皆様とともに、わが
国はいったいぜんたいどうすればよいのか、考えて
みたいと思います。長くなりました。
(つづく)
(むなかた・ひさお)
6 notes
·
View notes
Text
阪神大震災の混乱がまだ収まらない平成7年3月20日朝。東京・霞ケ関駅を通る地下鉄車両に猛毒のサリンが散布された。13人が死亡し、負傷者は6千人以上に。大都市で生物・化学兵器が用いられるという未曽有のテロは、世界に衝撃を与えた。
実行したのはオウム真理教。自前でサリンを製造し、これに先立つ松本サリン事件(6年)でも多数を死亡させていた。教団の被害者から相談を受けていた坂本堤弁護士一家殺害事件(元年)の関与も疑われ、警察の強制捜査を牽制(けんせい)するため、中央省庁が集まる霞が関を狙ったのだ。
一連の犯行を担ったのは、「グル(尊師)」と呼ばれた教祖、麻原彰晃(しょうこう)=死刑執行時(63)、本名・松本智津夫(ちづお)=に服従する一部の幹部メンバーたちだった。
「絶対的」な帰依の素地
はじめは、ヨガの先生に過ぎなかった-。大手ゼネコン出身で、教団独自の省庁制では建設省大臣に任ぜられた早川紀代秀(きよひで)=同(68)=は入信からわずか4年で、弁護士一家殺害の実行犯の一人となった。
神戸大農学部に進学し、その後景観工学などの修士課程に学んだインテリの早川。安易に「心」を持ち出す宗教はむしろ嫌いだったという。ノストラダムスの人類滅亡論などオカルトがブームだった社会人当時、本屋で「超能力」の文字が躍る麻原の著書をたまたま手にし、まだヨガサークルだった「オウム神仙の会」に興味本位で電話をかけた。
参加したセミナーで、麻原の「シャクティーパット」を受けた。麻原が参加者の額に手を当てるイニシエーション(秘儀伝授)の一種。「神秘体験」とまではいかないが身体が熱くなりエネルギーが入ってくるのが分かったという(『私にとってオウムとは何だったのか』早川、川村邦光、ポプラ社)。
ヨガの修行は宗教団体としてのオウムの特徴の一つだ。抽象的な説法だけでなく肉体を動かすため、なにがしかの変化を実感できる。早川はたばこをやめられるようになった。こんな小さなエピソードが後に「絶対的」となる帰依(きえ)の素地をなしていく。
「オウム真理教は基本的に二十四時間フル稼働の空間である。睡眠するための時間というものが基本的に設定されていない」。6年に出家した当時のことを、元信者の高橋英利はこうつづる(『オウムからの帰還』草思社)。過酷な修行に加え、「ワーク」なる作業奉仕が何時間もあった。
サティアンと呼ばれた教団施設は不潔極まりなく、ネズミやゴキブリが走り回る。「掃除はしないのか」と不平を漏らすと、清潔さや衛生を求めるのは「煩悩」と、別の信者にたしなめられた。
信者同士の私語は原則禁じられ、連帯はない。あるのは麻原とそれ以外。高橋は出家生活について「それぞれの個人のなかに閉じ込められている」と表現した。
善人ほど取り込まれ先兵に
出家信者はときに幻覚が現れるような苛烈な集中修行を課され、疲労により判断能力が減退した脳に、麻原の説法を流し込まれた。合成麻薬のLSDを服用させ、意識変革を迫るイニシエーションも行われていた。
「人は死ぬ。必ず死ぬ。絶対死ぬ。死は避けられない」。麻原はこのフレーズを何度も繰り返し、輪廻転生(りんねてんせい)を説くことで信者に死後の魂の行方を強く意識させた。生きていても悪業を重ねる人の殺生は「ポア」である-。より良い転生に導くための「善行」と教え込み、教団批判者の殺人を正当化した。
弁護士一家のポアを命じられた際、早川にもためらいはあった。だが、救済者たる「偉大なグル」の弟子というおごりがその迷いをかき消した。早川はこれを「慈悲殺人」と称した。
「自分ははまらないと思っている人がほとんどだが、大半がはまる」
信者のオウム脱会を支援していた弁護士の滝本太郎(66)はそう話す。オウムによ��サリン攻撃を受けても教団と対峙(たいじ)し続けた滝本だが、個々の信者は「純粋ないい人ばかり」と振り返る。善人ほどカルトのマインドコントロールに取り込まれる。そして残虐行為もいとわないテロの先兵と化してしまう。
ハルマゲドン(最終戦争)による終末論を唱えていた麻原は、自らも立候補した2年の衆院選で惨敗して以降、国家転覆を妄想し、自動小銃調達やサリン製造など教団武装化の道をひた走った。今や陰謀論の定番となった「公安」「フリーメーソン」からの攻撃も盛んに口にした。両サリン事件というテロはこの延長線上にあったといえる。
逮捕後、妄信から覚めた早川は「権威が示す正義」の恐ろしさに言及した。自らのエゴを捨て絶対的権威に従う形を取っているが、実はそれは、形を変えた自分のエゴだったのだ、と。(呼称・敬称略)
2 notes
·
View notes
Text
9月8日
図書館で借りていた坂口恭平『思考都市』を返却し、近くのカフェで昼食を食べた。 落ち着いたところで軽食とコーヒーを飲めたらいいなという気持ちで入ったが、思いのほか広く賑やかな店内と思ったより多い量の食事が出てきて、カフェというよりはレストランだった。
坂口恭平は高校時代に村上春樹の『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』を読んで、これは自分が書きたかったやつだと思い、書くことを始めたという。 彼は人に会うとその人の中のだれにも侵されていない街が見えるらしい。それを思考都市と呼んでいると言っていたので、そういうものが見える人が世界の終わりを読んだらこれは自分が書きたかった話だという気持ちになるだろうなと思った。 その意味での思考都市の話をしているのかと思って本を借りたが、そこでは自分年表的な樹形図を思考都市と呼んでいた。 自分が好きなことだったり関心があることとその派生を細かく記録していて、その綿密さは彼の幼少期の記憶も鮮明に思い出せる能力にある。(なにせ胎児の頃の記憶があるというのだから) マラニ―は『リサーチのはじめかた』で他人のためではない自分の欲望を探せと言うが、子供の頃の欲望というのはまさにそれだろう。 自分の外にいる審判者のことなどよそ目に、純粋に内的な欲望だけに従ってやっていたことが思い出せれば、それはそのまま自分証拠になる。
はじめて建築ということを意識したのは高校3年の進路決定の時期だった。 文理選択は2年のときで、そのときは理系のほうが友達が多いという理由で理系にした。 進学先を考えるのに、自分の興味がある職業を書き出し、そのなかに建築家があった。 この頃もゲームが好きで、ゲームのプレイ自体が好きというより、この世界とは違う別の世界を動き回れるのが楽しくてやっていた。 そのなかでも、たとえば『ダークソウル』のような荘厳な教会や城が出てくる世界観が特に好きで、こういうものを現実の世界でつくれるのは建築家だと思った。 「世界の美しい街」とか「世界の美しい城」みたいな写真集を眺めるのも好きだったし、逆にそういうものが全くない地元やこの世界に不満を持ってもいた。 今思えばフィクショナルな空間体験に根差して建築学科にすすむというのは、ややねじれがあるように思うが、そういうものに空間体験を見出していたというのは大事にしてもいいのかもしれない。
この日記を書き始めたときは、建築というのが自分の内的な欲望に基づいているのか怪しく、なぜなら建築を意識したのは高校3年の進路決定の時期で、自分の外にいる審判者の目を意識してしまっていたのではないかという着地になると思っていたが、当時を思い出しながら書いてみると自分の好きなことでちゃんと選んでいたような気がしてきた。
建築を目指したルーツがフィクショナルな空間体験に根差しているというのは重要そうだ。 それだけ城や教会が好きなのに在学中に一度も海外旅行をしていないし(同級生はみな一度くらいはどこかの国へ出かけている)、国内で有名な建築を見に行ったこともあまりない。 そもそも設計の授業が苦手で最後の設計の判定はCかD(一応提出はしたから単位をあげるというレベル)だったし、卒業論文もゲームの建築について書いた。
建築の表象を見ながら、何かフィクショナルな別のものを見ているのかもしれない。
2 notes
·
View notes
Quote
自由が丘駅前にある「不二屋書店」(目黒区自由が丘2、TEL 03-3718-5311)が2月20日で閉店する。 自由が丘駅北口(正面口)の女神広場前に立つ「不二屋書店」外観 同店の創業は1923(大正12)年。現店���・門坂直美さんの祖父・吟一郎さんが、自由が丘の隣にある世田谷区奥沢で商いを始めたのが始まり。門坂さんによれば、吟一郎さんは商人の家に生まれたが、本当は作家になりたかったという。 奥沢での商売が軌道に乗ってきた頃、「自由が丘の駅前に店を出してみないか」という誘いが舞い込んだ。当時の自由が丘は、1927(昭和2)年に東京横浜電鉄東横線「九品仏駅」が開設されたが、1929(昭和4)年の目黒蒲田電鉄二子玉川線(現・大井町線)の開業で現・九品仏駅が開設されることになったため、「自由ヶ丘駅」(旧表記)と改称することになった。そのタイミングで鉄道関係者から出店の誘いを受けた吟一郎さんは同年、自由が丘に店舗を移転した。 当時は「駅改札口の真ん前」に立つ木造造りの店だったそうだが、1945(昭和20)年の東京大空襲で消失。戦後、現在の場所に店舗を再建し、やがて門坂さんの母で女学校の教員だったという郁さんが店を継いだ。 書店を営む家庭に生まれ、小さい頃は「好きなだけ本を読んでいいよ」と言われて本に親しんだという門坂さん。しかし、「書店だけは継ぎたくない」と学校卒業後は自立を目指し、航空会社の国際線客室乗務員として勤務。家業とは無縁の生活を送っていたが、年老いた母が商売を続けることが難しくなってきたのを目の当たりにし、40歳で店を継ぐことを決心した。 自分の代になり、「駅前の書店」として住民や来街者向けに幅広い品ぞろえを心がけてきた。中でも文芸書や新書、文庫本を豊富に取り扱い、「最初に仕入れを担当した」という思い入れのある児童書にもこだわってきた。また、文芸・学術系の岩波書店やみすず書房の在庫も多いことから、コアなファンにも愛されてきた。 その同店の店頭に1月8日、「閉店のお知らせ」が貼り出された。「これまで102年にわたりお客様方にかわいがっていただいたこと、只々(ただただ)感謝申し上げます。そして頼りにしてくださっているお客様方を心ならずも裏切ってしまい、ご不便をおかけすることを心よりお詫び申し上げます」(原文のまま)とつづられていた。 店を継いで約30年、親子3代にわたって102年間営んできた。「ここ数年、全国で書店の閉店が相次ぎ、『街の書店』の経営に明るい要素がないと感じる。おいやめいも経営に携わっているが、私の代での閉店を数年前から覚悟していた」と悔しさをにじませる。同店のある地区の再開発事業が延期になったことも、閉店を早める決断に至った理由の一つだという。 「街の書店経営が難しいことは皆さまもご存じなので、『ここまでよく頑張ったね』『お疲れさま』の声を頂いている」と言い、「書店がなくなってしまった街も多いが、自由が丘は古書店も含めると数軒残っている。だから安心して託したい」とほほ笑む。 営業時間は10時~20時。
自由が丘駅前「不二屋書店」が102年の歴史に幕 幅広い品ぞろえ貫く - 自由が丘経済新聞
2 notes
·
View notes