#タカ目タカ科
Explore tagged Tumblr posts
Text
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和六年(2024年)11月15日(金曜日)
通巻第8504号 <前日発行>
トランプのディープステート殲滅作戦が始動
今度は司法長官、国家情報省にもっとも戦闘的な議員らを配置
*************************
ドナルド・トランプ次期大統領は司法長官に「議会の暴れん坊」といわれるマット・ゲーツ下院議員(共和党・フロリダ州)を指名した。
国務、国防、CIA、国土安全省と、ずらり対中タカ派を勢揃いさせたから、次の人事でディープステートとの戦いを宣言したも同然である。財務長官の指名は後回しになった。
「フロリダ州選出のマット・ゲーツ下院議員が米国司法長官に指名されたことを発表できることは大変光栄です」とトランプ大統領は声明し、「マットはウィリアム・アンド・メアリー法科大学で学び、才能に恵まれ粘り強い弁護士であり、司法省で切実に必要とされている改革の実現に力を発揮してきた」
指名を受けたゲーツ下院議員はXで「トランプ大統領の司法長官を務めることは名誉なことだ」とした。
ゲーツは暗号通貨の推進派でもあり、トランプ支持の動きで注目を集めてきた。
とくにゲーツ下院議員は「国会議事堂の騒乱においてトランプ氏はいわゆる『反乱』に関与していない」とする決議案を提出し、また理不尽なトランプ裁判を捉えて、司法省検察官のジャック・スミスを選挙介入で告発した。くわえてゲーツ下院議員は、連邦所得税をビットコインで支払うことを許可する法案を提出、また国土安全保障省はトランプ大統領を狙う5つの「暗殺チーム」を知っているなどと発言してきた。すなわち司法省にメスを入れる爆弾男になり得るとトランプが判断したことになる。
ついでトランプはトゥルシー・ギャバード(元下院議員、退役中佐)を国家情報長官(DNI)に指名した。DNIはCIA、FBIなど18の情報機関を統括し情報を総合的に収集し、管理する部署。
上院指名公聴会で、一番揉めそうなのは人事だろう。
上院は共和党53vs民主党47となったが、共和党院内総務にトランプ派のトム・スコットではなく、トゥーンが選ばれたことによってRINO(名前だけ共和党)の抵抗があると予測されるからだ。
トランプ次期大統領はトゥルシー指名理由を次のように言った。
「彼女は長きに亘ってすべてのアメリカ国民の自由のために戦ってきました。彼女はかつて民主党の予備選に出馬して、ヒラリー候補と競った。両党から幅広い支持を得ている。トゥルシーは、輝かしい経歴を特徴づけ、恐れを知らない精神を国家諜報機関にもたらし、憲法上の権利を擁護し、強さを通じて平和を確保してくれると確信しています。トゥルシーは私たち全員を誇りに思わせてくれるでしょう」
▼女性だが退役中佐、その軍歴も光る
トゥルシーは七月の共和党大会でも雛壇にのぼり演説をしており、その直前までは、あるいは副大統領候補としてトランプとチケット組むかとまで言われた。
筆者は拙著『トランプ劇場2・0 世界は大激変』(ビジネス社)ならびに『アメリカは新南北戦争に突入する』(ワック)でトゥルシーを特筆し、閣僚入りは確実だろうと書いている。
たぶんホワイトハウスのスポークスウーマンかとも予測したが、トランプの彼女への評価はうんと高かったのだ。
彼女はサモア生まれで、母親はインド系。したがってヒンズー教徒とも言われる。
ハワイ選出で4期連続連邦下院議員をつとめた。軍人としても、中東とアフリカの戦場に3回派遣された陸軍予備役中佐。911テロ後、陸軍州兵に入隊。第29旅団戦闘団の一員としてイラク派遣に志願し、医療部隊に配属された。
2006年に帰国後、トゥルシーは上院退役軍人問題委員会の���ダニー・アカカ上院議員の立法補佐官として活躍、また小隊長として2度目の中東派遣に志願した。
31歳で米国議会に立候補し、軍人仲間の命と犠牲を称えることを誓った。彼女は厳しい選挙に勝利し、四期連続でハワイ選出の連邦下院議員。軍事委員会、国土安全保障委員会、外交委員会に貢献した。2022年10月、トゥルシーは民主党エスタブリッシュメントの腐敗、堕落とその全体主義的な体質に愛想をつかして離党、トランプ陣営に駆けつけた。
9 notes
·
View notes
Quote
今年1月に書いたブログ記事 『松本人志さんの罪についての考察と提案』はネットメディアに転載されて大きな反響を呼びました。その後、 『松本さんについての記事への反響など』 『被害者の存在を消すな』 この2本の追加記事を出してから、私は松本さんの件には言及してません。なぜかと聞かれたこともあったんですが、いまに至るまで自分の考えにまったく変化はないので、言及する必要がなかったというだけのことです。 寄せられた多くのご意見にはすべて目を通しました。ご意見といっても、批判の99.9%はまともな日本語の文章にすらなってない誹謗中傷、悪口雑言、泣きごと、負け惜しみ、呪詛、邪言の類。こういった、膿のような人間の悪意博覧会に目を通すのはもちろん不快です。ただ、私は長年物書きをやってきたのでもう慣れてます。権力者や人気者に媚びを売らず、正しいことを正直に書くと、必ずゴミくずのような批判を投げつけられるのです。 比較的長文の批判も少しありましたけど、論点ずらしの詭弁に終始しているか、無関係の事例をあげて反論したつもりになってるだけでした。女性蔑視イデオロギーに取り憑かれて論旨の破綻した妄言を述べてる人もいましたけど、経験上、この手の人たちは相手にしないほうがいいです。論理的思考が出来ない人とは議論が成立しませんから。 いずれにせよ、私の考えを変えさせるようなまともな反論はひとつもありませんでした。 私が松本さんの人間性を軽蔑する気持ちにも、まったく変化はありません。それどころか、先日の訴訟取り下げ後に公表した声明文を読んで完全に見放しました。この人が救われる道はもう、出家して���間と隔絶した山奥の寺にこもり、リアル松本坊主として余生を送るしかないんじゃないかと。 あれほど人をバカにした声明文も珍しい。しぶしぶ謝罪する体を装ってるだけで、本心では反省も後悔もしてないことが透けて見える、ダメすぎる謝罪文です。こんなのダメだ書き直せ、と松本さんを諫めることができる人が周囲に誰もいないってのが、やはり問題なんです。それが松本さんを腐らせたんです。政治でも会社でも同じことがいえますが、権力者を批判できない体制のもとでは、必ず組織と人間が腐っていき、周辺の人々にまで悪影響を及ぼします。 事実無根だ、裁判で戦う、とあれだけ気炎を揚げていた松本さんが急に訴訟を取り下げたのは意外ではあったけど、想定内だったとの見かたもできます。 というのは7月に、被害を訴えていた女性の身辺を探偵に探らせて弱みを握り、裁判での証言をやめさせようと画策してたことが発覚したからです。 結局、その弱みというのはガセネタだったことが、関係者の実名証言であきらかになったのですが、脅迫まがいの姑息な手段を弄さねばならないほど追い詰められてた時点で、裁判で勝てる材料がなく焦ってる様子が見え見えだったし、そんな裏工作は裁判官の心証を悪くする可能性もあるのだから、松本さんの失点でした。もはや万策尽きた松本さんが白旗を揚げるのは時間の問題だったともいえます。 * 先日の声明では、まだ懲りずに物的証拠の有無にこだわって自分を正当化してるところにも呆れました。そもそも性行為に同意してたかどうかなんてのは内面、心理的なことなのだから、物的証拠を出せと要求すること自体にムリがあります。両者の力関係によっては、強制されてイヤなのに拒めないこともありえます。社長や上司や芸能界の大御所みたいな人を訴えることで自分のキャリアが終わってしまうリスクと天秤にかけて、泣き寝入りを選ぶ人が多いことにもうなずけます。なので物的証拠にこだわらず、状況証拠と双方の主張内容を比べて、どちらの信憑性が高いかを判断するしかないんです。 で、今回の場合はじつは非常に単純なケースだったのです。女性側は文春の記事で、詳細かつ具体的な証言をしてます。だから女性の主張内容に決定的な矛盾がいくつもあることを指摘できれば、松本さんは裁判で勝てたはずです。しかも松本さん側は具体的な証言を一切してないから女性側は松本さんの矛盾を指摘できません。これは松本さん側のワンサイドゲームになっていてもおかしくないケースでした。 ところが松本さん側は絶対的に有利な立場にありながら、女性の証言内容���まったく切り崩せなかったわけです。唯一の切り札とされたLINEのお礼メッセージも、被害者が恐怖のあまり加害者にへつらうことは普通にあると、性犯罪の事例に詳しい専門家たちから一蹴されてしまいました。 文春側は、次の弁論に向けて大量の証拠を提出する用意があったそうですが、松本さん側にはもう手持ちの札がない。裁判を続けてさらに悪行が暴露され、恥の上塗りを重ねるか、それとも訴訟を取り下げてしっぽ巻いて逃げるか。プライドお化けの松本さんにとってはどちらに転んでも敗北の屈辱にまみれるのだから、苦渋の選択だったに違いありません。 * これによって文春は記事内容の訂正も謝罪もしなくてよいことになりました。週刊誌がいいかげんな記事を載せることはたしかにありますが、この件では、文春が長期間裏取り取材を重ねた上で掲載に踏み切った様子が読み取れます。裁判でも証言するといってたA子さんの告発はとりわけしっかりとスジが通っており、あれがもし全部作り話だったら、逆に驚きます。もしそんな才能があるのなら、テレビ局はすぐ彼女を脚本家として登用したほうがいい。 松本擁護派のみなさんは、先に自分が信じたい結論を正解と決めてしまって、その結論に合うようにすべての言説を読みかえてしまいます(これは陰謀論やエセ科学の信奉者に共通する思考法ですし、私の記事を批判してる人たちもこれをやってます)。 彼らは訴訟取り下げという事実上の敗北宣言を認めたくないものだから、「真相は闇の中だ」などと負け惜しみをいってますけど、全然違います。 記事は事実無根とする訴えが取り下げられたのだから、記事内容と女性たちの主張は大筋で事実であると松本さんが認めたことになります。今後はテレビなどのメディアが女性側の主張をそのまま報道しても、名誉毀損にはあたらないわけです(松本さんはそれに対して新たに訴訟を起こすこともできますが、依頼を受ける弁護士がいますかね)。 そもそも事実無根であるかどうかの議論は、全否定か全肯定かをめぐる議論ではありません。報道は人間がやるものですから、100パーセントの正しさを求めるのは非現実的です。記事が漢字を一文字間違えてたことだけを理由に、記事は事実無根だ! と主張するのはバカげてます。 細部に一つ二つ誤情報が含まれてたとしても、全体として大筋で事実を伝えていれば、それは事実無根とはなりません。細部の間違いは訂正すれば済む話であり、記事のすべてを撤回する必要もないのです。 女性側の詳細かつ具体的な多くの証言に対し、松本さん側は細部の間違いを立証する証拠すら出せなかったのだから、彼女たちの主張は大筋で正しいものとみなされて当然です。 ネットなどでさんざん、ウソつきだ、カネ目当てだ、売名だなどと根拠もなく叩かれてきた女性たちの名誉は、とりあえず回���したことになりますが、あくまで形式上のものにすぎません。彼女たちが被ったさまざまな被害や苦しみを考えれば、報われたとは到底いいがたい。 ネットで大量の誹謗中傷や侮辱を受けたことに対しては、なんの補償もありません。実名や勤務先を晒されて被害を受けた人もいると聞きましたが、もしかしたら無関係の他人が誤情報で被害に遭ってる可能性もあります。いずれにせよ、女性たちを中傷してた連中はなんの罰も受けず野放しのままです。 このあと女性たちへ松本さんから正式に謝罪する場が設けられるのかも不明です。松本さんの身勝手さからすると、先日の声明文で、あれで謝罪は済んだからもうええやろ、くらいにタカをくくってることもじゅうぶんありえます。 * これまでテレビのワイドショーなどは、文春の記事内容や女性の証言を詳しく紹介するのを避けていたように私は感じてました。おそらく、裁判で松本さんが勝って記事が撤回される可能性に配慮してのことだったのでしょう。 でも訴訟が取り下げられたのだから、もう具体的な記事内容を放送してもかまわないのです。なんなら、仰天ニュースみたいな実録もの番組で女性側の告発内容を再現VTRにして放送すれば、視聴者に分かりやすく説明できます。 私は決してふざけてるわけじゃないですよ。松本さんのテレビ復帰がウワサされるいまだからこそ、あらためて女性たちの具体的な証言を詳しく報じて、視聴者に問うのがスジだと申し上げてるのです。一連の文春記事に書かれた女性たちの告発内容を知れば、松本さんらの行為が常習的かつ計画的で、一般人の常識的倫理からかけ離れたものであるとわかるはずです。それを知ってもなお、視聴者のみなさんは松本さんのテレビ復帰を許しますか、と問いかけるべきです。 これまでテレビでも詳細が報じられなかったし、週刊文春のバックナンバーをわざわざ読んだ人も少ないだろうから、たぶんほとんどの人たちは、女性たちの具体的な証言内容を知らずに、不確かな伝聞と想像だけで判断してるんです。 みんなが具体的な詳細を知らないのをいいことに、松本擁護派は、芸人が女性をお持ち帰りしただけだ、些細なスキャンダルにすぎない、などと事実を曲げる印象操作を執拗に繰り返し、事件の矮小化を狙ってました。 * これまでさんざんコンプラ、コンプラとうるさくいってきたテレビ局の本気度が試されるときがやってきました。性加害こそ立証されずうやむやにされたとはいえ、松本さんが結婚後も不倫を繰り返していたのは事実です。それも過去に例を見ないほどゲスなやりかたで。 不倫が発覚したことで何年もテレビから干されてるタレントが大勢います。松本さんだけを特別扱いするのは不公正です。少なくともこの先2、3年はテレビ出演を見合わせなければ、他の件との整合性が取れなくなってしまいます。 松本さんが絶対的な地位を利用して後輩に性行為要員としての女性を用意させてたのも事実無根ではなかったわけで、これはパワハラとしてコンプラ違反の審査対��になります。 もしかしたら、一番わりを食ったのは後輩たちかもしれません。松本さんの勝訴にすべてを託していたのに、あっさり見捨てられたのですから。 松本さんの訴訟取り下げによって、松本さんに協力していた小沢一敬さんらの行為も事実無根ではないとみなされます。小沢さんが自分の名誉を回復したいなら、今度は自分で文春を訴えねばなりません。 なんというか、こういうところにも松本さんの、自分さえ良ければいいという器の小ささがあらわれてます。本当に男らしさやアニキぶりを誇示したいのなら、自分が全責任を取って芸能界を引退するから、自分の命令に背けず従っていただけの後輩たちは復帰させてやってくれ、くらいのことをいったらどうですかね。そうすれば世間の風向きも変わるかもしれないのに。 それと、松本さんは文春に5億越えの破格の賠償金を要求して大物ぶってましたけど、今度は賠償金をもらうことより払うことを心配する番です。 女性たちに対する賠償金などはないといってますけども、松本さんがテレビ各局とCMスポンサー各社に対して払わねばならない莫大な賠償金、違約金は依然として存在するはずです。 賠償金などに関する契約内容は非公開なのであくまでウワサですが、松本さんよりかなり格下のタレントでも、過去に数十億の賠償金を払うことになったケースがあると囁かれてます。松本さんクラスのギャラをもらってたタレントなら、テレビ各局とスポンサー各社、すべて合わせて数百億になってもおかしくありません。まあ、それくらい払うのは屁でもないほどのお金持ちだろうから同情はしませんが。 * 私がキビシい意見を書いて松本さんと支持者を批判してるのは、彼らが社会に向けてひどく間違ったメッセージを(意図的であれ無意識であれ)発信しているからです。 それは、権力者は何をしても許される、あるいは、何をしても権力者になれば許されるというメッセージです。それを容認したら、権力者は何をしても許されるのだから、逆らってもムダだ。権力者には黙って服従せよという脅しを正当化することになります。私はそんなことを到底容認できません。権力を自由に批判できることは、民主主義の基本だからです。 松本さんらがやってたことは、人としてやってはいけないこと、すべきでないことでした。多くの常識的な人たちはその点を批判したのです。他の不倫やパワハラで処分されたタレントと同じ処分をするべきだ、特別扱いはするなと主張してるのです。 しかし松本さんを擁護したい人たちは、才能ある芸人だからなどと、あの手この手の論点ずらしによる反論を試みました。そのひとつが法律論。常識や倫理なんてのは個人の価値判断でしかない。裁判で法に反していることが確定しなければ批判も処罰もできない、それが法の論理だと牽制してきます。 それに対して、人としてやってはいけないことは、たとえ法的に問題なくても、すべきではない、などと反論したら、きっと松本擁護派の人たちは、何もわかってないなと嘲笑するのでしょう。 はたして本当にそうなのかな。もっともらしい法律論を振りかざす彼らの考えは法哲学的な観点からも正しいといえるのでしょうか。 私の認識��異なります。じつは、倫理的に正しいことは論理的にも正しいことが多いし、倫理的に間違ってることは論理的にも間違いであることが多いんです。 法に反しなければ何をしてもいいって考えは理論的には成立しますが、現実には実行不能な絵空事にすぎません。 法に反しなければ何をしてもいいという宣言には、法に反することを絶対にしないという縛りが含まれるからです。それを厳守しなければ矛盾が生じてしまいます。法に反しなければ何をしてもいいと主張する人が法に反することをしていたらそれはあきらかに矛盾ですから。 それ、現実の世界で実行できますか。不可能ですよね。厳密にすべての法律を適用すれば、誰もがなにかしらの法律違反をしているはずです。でも警察や国家権力が全国民の一挙手一投足まで監視することはできないから、社会通念上問題ない些細な法律違反は見逃されてるというだけのこと。 それを悪用する人がいるんです。バレなければ法に反することをしてもいいという考えかた。犯罪者の行動原理です。 法に反しなければ何をしてもいいという、合理性を装った考えと、バレなければ何をしてもいいという堕落した考えは、表裏一体といってもいいほど近い考えかたです。なので自制心、自律心の薄い人ほどその境界を容易に踏み越えて犯罪に走ってしまいます。 人としてやってはいけないことは、やっぱり、すべきではありません。これは道徳的なお説教ではなくて、論理的に正しい結論なので、堂々と主張してもかまいません。 松本さんは、人としてやってはいけないことをやっていたと、私はみなしてますし、多くのみなさんが同調してくれるでしょう。 法的に罪が問われなくても、倫理的な問題が多々あったのは事実なのだから、すぐにテレビに復帰させるという考えは甘すぎます。 以前松本さんは、テレビのコンプラがうるさくなって、自由にお笑いができなくなったとこぼしてましたけど、皮肉なことに、松本さんみたいな人がいるからコンプラが必要なのだと証明されてしまいました。 * 私は、吉本興業の社員と芸人にも問いたいのです。彼らのなかにも、松本さんに批判的な人はたくさんいるんじゃないですか。でも権力に逆らって発言するのをためらっているのではありませんか。 吉本の内部から、松本さんをテレビに復帰させるべきではないと毅然と主張する声が自主的に上がることを、私は期待しています。 以前、新潮社の『新潮45』という雑誌に政治家が書いた差別的な記事が掲載され、世間から批判を浴びました。会社の上層部はあまり問題視しない方向で動いてましたが、新潮社の社員の間から記事を批判する声明がSNSなどに続々と上がってきたことで会社も無視できなくなり、結局雑誌は休刊になりました。 ひとりで権力に逆らうことは危険ですが、常識的な倫理観と少しの覚悟がある人たちが何人も集まることで、吉本の社員・芸人も松本さんのテレビ復帰に反対することは可能ですよ、とお伝えしておきます。
松本さんの件に関する現在の私の考えをお話しします反社会学講座ブログ
3 notes
·
View notes
Text
本田宗一郎・ざっくばらん
【真理に徹す】
今度うちは三重県の鈴鹿に新工場をつくることになった。
僕は、この工場も浜松や和光の工場と同じように、エア・コンディション付の無窓工場にするつもりだ。
これなら外気の温度や湿度に影響されずにすむからだ。
日本にはずい分のん気な人がいる。
無窓工場なんてトランジスター・ラジオやカメラみたいな精密工業には必要だが、自動車なんてものにはゼイ沢だと思っている。
自動車はそんなにヤ��なものではないということらしいが、精度を問題にしないその神経の図太さには恐れ入るほかはない。 それだけではない。
海辺に工場を建てようと考えている人がいる。潮風は、製品に悪影響があるだけでなく、機械そのものを傷める。
日本は島国だから、どこへ行ったって潮風はくるさとタカをくくるのはよくない。
あるピアノ会社が、社長の出身地だからという理由で、海岸のそばにピアノ工場を建てて失敗したことがあるが、これこそ音痴的なものの考え方である。
製鉄所みたいに、精密度はあまり要求されず、運送費の多寡がそのまま利潤の大きな部分を占めるというのなら話も分かるが、自動車みたいに高度な加工をやる工場を、単に運賃が安いとか、土地が安いということだけで海辺に建てるのはどうかと思う。
話を戻すが、エア・コンディションは、機械や製品にいいだけでなく、なによりも工場で働く人たちが気持ちよく働けるという利点がある。
最近は、冷暖房をする会社が多くなったが、それは本社だけ、あるいは重役室だけの話であって、工場の方は旧態依然たる有様である。夏は汗をかき、冬は吹きっさらしの中で仕事をしているところが多い。
これでは自由にして平等だとはいえない。第一、工場で働く人間を大事にしないような企業は長持ちしない。僕は自分が大事にされたいから、みんなを大事にする。
愉快に働いてもらって能率をよくしてもらった方が、どれほどいいか分からない。
設備は一度やれば一生なんだから、充分にしてもたいしたことではないと思う。
日本のように温帯にある国では、夏と冬の温度差が激しいから、余計働く人たちに気をつかう義務がある。
ドイツみたいなところなら、冬はべらぼうに寒くても、夏は窓を開けなくても仕事ができる程度だから、暖房だけあれば事足りる。
外国の工場も暖房しかないとそのままウのみにしては困る。
それから従業員に休息を与えるということを、何かマイナスになるというか、罪悪視する人がいる。
仕事というものは、何か目をつり上げて息もつかせずにやらなければいけないという固定観念にとらわれている人がいる。
TTレースに行ったうちの河島監督が帰って来ていうことには、うちのチームは、日曜も夜遅くまで仕事をやるし、風呂に入るにも順番を決めて、廊下にプラン表をぶら下げていた。
それをみたイギリス人が、日本人は何て能率の悪い国民だろうといったそうだ。
二宮尊徳流に薪を背負って本を読まなければならない国民にとって、団体生活をするときに、入浴の順番を決めることなんて普通のことだが、個人主義が徹底しているイギリス人からみれば���リタリズムの変形にみえるのは当然かも知れない。
TTレースの期日は何年も前から分かっているのに、夜明かししなければならないというのでは、非能率にみえるのは無理もない。外国人の考える能率とは、働くべき時間にいかにたくさん働くかということで、休み時間に働くのは能率ではないわけだ。
この間、楠トシ江と対談したときにも話したが、僕が床屋に行って十五分でやってくれと頼んだら、やっと四十分でできた。いつもなら一時間もかかる。
そこで床屋のおやじ曰く
「あんたは遊ぶひまがあるんだから、その時間に床屋に来てくれれば、こうせかせないでゆっくりキレイになる」
そこで僕は 「冗談いうな、遊ぶために働いているんだから、床屋にきて一時間もかかってたまるかい。こんな能率の悪い床屋なら一生来ない」 と言ってやった。
本当のことをいって、人間は八〇%ぐらいは遊びたいという欲望があって、それがあるために一生懸命働いているのでないだろうか。それを働け働けといってヤミクモに尻を叩いても能率が上るわけはない。
よくイミテーション・パーツが問題になるが、イミテーション・パーツが出るのはメーカーの純正部品が高いか、高い割に性能がよくないか、潤沢に出回っていないかの三つの条件が満たされていない場合である。
この点は、うちも大いに反省しなければならない。しかしそのためにかくしナンバーを打つようなことはやらない。
そんなことをすれば、手間が多くなって能率が悪くなる。ならばその分だけ安くする方が先決である。
人間は疑り始めたらキリがない。
コップ一杯の水を飲むのにいちいち毒が入っていないかどうか疑い出したら、自分で井戸を掘って、毎朝水質を調べなければならない。
これはいささか極端な例だが、人は信用した方が得である。
うちは、クレーム部品の判定権をディーラーに任してしまった。
代理店といっても数が多いから、いい人ばかりではないかも知れない。
中には悪い人もいるかも知れない。
しかしそれはあくまでもごく少数である。そのごく少数の人のレベルに合わせて、何かいかめしく、人を頭から疑ってかかるような検査制度をつくっては、大多数のいい代理店は気分を害してしまう。
検査制度なんてものは、警察や検察局がそこら中やたらにあるのと同じことで、気持ちよく仕事はできない。
こういうものは非生産的なものだから、生産の中にたくさんあればあるだけ、モノが高くなるのは当然である。
また人間というものは信用してまかせられれば、悪い人も悪いことができなくなるものである。
逆に四六時中疑われれば、反感からいい人も悪いことをしたくなるものである。
そういう意味から、うちはディーラーに判定権をまかせてしまったわけである。
もちろん統計は一��とってあるから、ある一店だけ特定のクレーム部品がべらぼうに多く出るということになれば、チェックできるようにはしてある。
近ごろ、わが社は厳重な検査をやっています、といった広告が新聞によく出る。
しかし厳重に検査をやっているから、品物がいいというのはおかしい。
初めからつくる目的はわかっているのだから、つくってしまってから検査するのを、オニの首でもとったように宣伝するのはうなずけない。
つくってしまったものはあとに戻らないのだから、つくる前に、検査しなくてもいいようにすることがいちばんいいわけだ。
本当は検査なんかやらなくてもミスがないというのが理想である。その理想に近づくために検査員がいるというのならいいが、検査しなければいけないような品物をつくっていて、それを検査しているからといって自慢しているのではスジが通らない。
うちでも検査設備は、もちろん完璧なものにするよう努力しているが、それに頼ってはいない。検査員だってよそよりは相当少ないはずだ。
それに僕は、ミスを出すたびに検査員を一名ずつ減らすといっている。
人間が多すぎると検査はミスが多くなる。シビアな感覚がうすれてくる。
自動車というものは、人命を預かる機械だから、つくる側に徹底した慎重さが欲しい。
科学技術というものは、権力にも経済的な圧力にも屈してはいけないものである。
ガリレオが「それでも地球は回っている」とつぶやいたように、権力をもった者が、どんなに真理を否定しても、真理は真理として残る。
真理は一見冷たい。しかしその真理を押し通すところに、熱い人間の面目がある。
工場には、その冷たい真理だけがある。
真理だけが充満していなければならぬ。 こういう体制を押し通していけば、少なくとも機構上の欠陥からくる事故はほとんどなくなるはずだ。
悪いところに気がついても、いま変更したら金がかかるとか、混乱するとか、発表したばかりのものを改造するのはみっともないとか、変な面子がからんで、ズルズルと見て見ぬ振りをするところがある。
うちは面子がないから、悪いところを見つけ次第改造してゆく。ラインに乗せてからも一日に数回変更することもある。
そのために、工作機械の位置を大幅に移動させるようなことも少なくない。工場の連中も、初めは面喰らったようだが、いまでは、いつでも変更に対処できるような準備ができている。
とにかくお客さんには、うちで考える最良の品を提供しなければならないのだから、無理はあくまでも通すつもりだ。
いささか古い話だが、昭和二十八年に、うちの新車につけたキャブレターの性能が思わしくなかった。そこで売ってしまった一万台の車のキャブレターをすぐ取り替えた。
そのときの僕の考え方は頭をペコペコ下げたって、悪いものは悪いのだから取り替えるより仕方がない。
たとえそのお客さんと親戚になったって、夫���になっても、キャブレターの悪いのが直るわけではない。
このとき、うちが取った処置が実に早かったし立派だったといってくれる人がいるが、僕はまだ遅かったと思っている。
よそとの比較でいえば早いかも知れないが、お客さんにとってはまだ早くない。
比較対照でいえば、カラスが白いのと同じである。いまだに僕はクレームの処理が遅いとどなることがある。
お客さんにとっては、取り替えるのに一分しかかからなくても、壊れれば遅いわけである。待っている時間は永久に帰ってはこない。壊れることは、壊れないことよりも絶対に悪い。
それからもう一つ考えなければいけないことがある。
それは、この工場の製品は九九%の合格率だからすばらしいと賞める人がいるし、賞められて鼻を高くする人がいるということである。
ところがお客さんは、自動車にしてもオートバイにしても、百台も買いはしない。
買ってもせいぜい一台か二台である。
もしその一台の車に、残りの一%の悪い車が当ったとしたら、そのお客さんにとってその車は一〇〇%悪いことになる。
だから工場というのは最低一〇〇%、理想的にいえば一二〇%くらい合格しないと話にならない。
お客さんというのは、金を払って自分が目的地に行くために走っている。
もしエンコすれば、ほかに直す人がいないから自分でいじらなければならない。
それが人里離れた山の中ででもあれば、分らないなりに全知全能を費やしてひねくるわけである。それだけにエンコしたという意識は痛切である。
うちがいちばん最初の五〇ccのバイクエンジンを売っていたころ、お客さんから電話がかかってきてエンコして動かない、こんなものを売りやがってとガンガンどなられた。
慌てて飛んで行ったら、ガソリンがなくなっていた。しかしそのお客さんは、二度とガソリンがないのをエンコと間違う失敗はやらなくなる。そこでそのお客さんは一段進歩したわけだ。したがって、売ったりつくったりする僕らが、お客を馬鹿にしていると反対に遅れてしまう。
ところが工場の連中は、案外こういった感覚が抜けている。
どうしてかといえば、その道の専門家が、その辺にいっぱい控えているからだ。
この故障は電気部品だと思えば、電気屋を引っ張ってきて、自分は知らん顔をしている。みんな技術屋でありながら、依頼心が強い。
そして実際のレベルは低くても、俺たちがつくっているのだということで、いかにも自分たちが専門家であると錯覚を起こしやすい。
お客さんから苦情が出ても、やれ使い方を知らないからだとか、それは一部であって全部ではないとか、勝手な屈理屈をつけて、真剣にその苦情の内容に取り組もうという気を起こさない。
このうぬぼれが技術屋をいちばん危うくする。
会社そのものを危うくする。
1 note
·
View note
Text
「鳥 ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統」展

国立科学博物館で特別展「鳥 ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統」を見る。充実の内容だったが、出かけたのが会期末になってしまったため会場内は大混雑で、鳥より人間の後ろ姿ばかり見る形になり、じっくり見学できなかったことが悔やまれる。せっかく撮影可だったのに写真もあまり撮れなかったので、ここに載せられるものも限定的である。
展示室入口ではクジャクとシマエナガがお出迎え。人が多くて、遠くから隠し撮りするかのような撮り方しかできず。

展示は全8章で構成されている。

第1章では恐竜まで遡って鳥の進化の過程を辿っている。恐竜の段階ですでに鳥の鳥たる特徴が備わっていたのだそう。可愛らしい小鳥も恐竜時代からある特徴を受け継いでいるわけだ。
脊椎動物の飛行のしかたを解説するコーナーでは、鳥類でない脊椎動物も宙に浮いていた。

展示会場ではときどき上を見なければならない。たとえば下の写真のように、ペラゴルニス・サンデルシ(空を飛ぶ史上最大の鳥といわれる。約2600万年前に生きていた。翼開長は7m)の復元を試みた成果が上から吊るされていたりするからである。

第2章では最新のゲノム解析で分類された鳥類の多様性を取り上げている。たとえば��従来タカ目と分類されてきたハヤブサが、ゲノム解析によりインコやスズメに近いことが判明したため、ハヤブサ目が新設された。他にも目レベルでさまざまな再編がなされたという。
第3章からは鳥の種類ごとの紹介で、まずはダチョウなどの走鳥類が登場。第4章はカモやキジの仲間、第5章は陸鳥や水鳥、第6章は猛禽、第7章はいわゆる小鳥。
卵の大きさの比較。走鳥類の卵は大きい!

この展覧会で展示されているのはまるで生きているかのような姿の剥製(本剥製)がメインだが、死んだような姿の仮剥製が紹介されている展示ケースもあった。

ツルの仲間。

チドリ目の皆さん。チドリ目はスズメ目の次に科の数が多く多様であるとのこと。

狙われにくいように進化したらしい卵のいろいろ。

次の写真はペンギンの仲間大集合コーナーの一部。見学する人間も大集合していたのでこの程度にしか撮れず……

アホウドリの仲間。

ヒマラヤを越えて飛ぶことのできる、インドガンとアネハヅル。インドガンはひたすら羽ばたくパワー型、アネハヅルは気流や風を利用する省力型で、タイプは異なるが、どちらもすごいことには変わりない。

渡り鳥の主要な経路、フライウェイを示した展示パネル。世界地図とともに示されるとそのダイナミックさが際立つ。

蜂の巣を再利用した、アカショウビンの巣。

猛禽の仲間の皆さん。

最後の第8章は「鳥たちとともに」と題して鳥と人との関係を紹介している。自分ではバードウォッチングとか環境保全活動ぐらいしか思い浮かばなかったのだが、下の写真の模型などを見て、鳥の名を冠した人工物も確かにいろいろあるなと唸った。

要所要所にある「鳥のひみつ」というコラムが楽しくおもしろくわかりやすくてためになった。ぬまがさワタリさんのイラストがしばしば笑える内容で、展示に華を添えている。







なお、適応放散のコーナーに展示されている鳥は、ガラパゴス諸島に棲むダーウィンフィンチ類で、剥製でなくバードカービング(彫刻)。剥製にしろ彫刻にしろ、人間の手の技にも恐れ入る展示だった。

1 note
·
View note
Photo





鳥とは何か? ゲノム解析から知ることができる特別展「鳥」が科博で開幕 2024/11/01 21:16
著者:小林行雄
恐竜の子孫である「鳥」 世界中に哺乳類の6000種よりも多い約1万1000種が存在し、人の次にゲノム解析が進んでいるとされる「鳥」。このゲノム解析の進展により、鳥の分類にも変化が生じるようになってきた。そんな最新のゲノム解析を踏まえて“鳥”とは何か? を知ることができる特別展「鳥 ~ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統~」が東京・上野の国立科学博物館(科博)にて2024年11月2日より開催される。
特別展「鳥」の会場 特別展「鳥」の会場は科博地球館地下の特別展示室
同展最大の特徴は、国立科学博物館が持つ3000点の標本含め、国内のほかの博物館などの協力も得て展示される600点以上の貴重な標本群。世界中の大小さまざまな鳥たちの標本が一堂に会するこれまでになかった規模の“鳥”に関する展示会で、科博の特別展のテーマとしても初めてのものとなるという。構成は序章「鳥を知ろう」から始まり、第2会場の第8章まで全部で9つの章立てとなっている。序章では、鳥という生き物が環境の影響を受けやすく、たやすく絶滅してしまう存在であることを日本から姿を消した大型のキツツキである「キタタキ」や「トキ」、「コウノトリ」などを交えて紹介している。
シマエナガ 会場に入った瞬間出迎えてくれる「インドクジャク」と「エナガ(シマエナガ)」。インドクジャクの大きさに見逃しがちだが、その右手に頭が白いエナガ、いわゆるシマエナガが待っていてくれる
日本国内で絶滅した鳥たち 日本国内で絶滅した、もしくは絶滅が危惧される鳥たち。鳥は種類も多いが、それゆえに絶滅した種も多く、現在進行形で絶滅しかかっている種も多い
音声ガイド 会場入り口では音声ガイド(有料)もレンタル可能。ナビゲーターは日本野鳥の会の会員でもある芸人のレイザーラモンRGさん(男子への同展おすすめは猛禽類たち)と、子供のころから鳥が好きだという女優でタレントの高柳明音さん(おすすめはシマエナガ)。解説件数22件と、かなり内容が詰まった音声ガイドになって��た
恐竜の子孫である「鳥」 続く第1章「鳥類の起源と初期進化」では、獣脚類恐竜の子孫である存在として、現生鳥類の基本形態を見た後に化石記録を基に鳥類の起源と初期進化について見ることができる。
鳥たちの翼の形状の違い 鳥たちの翼の形状の違い。鳥たちの特徴によって、違っていることが一目でわかる
鳥たちの羽毛も特徴によって異なってくる 鳥たちの羽毛も特徴によって異なってくる
かつて鳥は恐竜であった かつて鳥は恐竜であったということで、恐竜の化石も待ち構えている
「ペラゴルニス・サンデルシ」の生体復元モデル 翼開長7mの史上最大の飛べる鳥「ペラゴルニス・サンデルシ」の生体復元モデル。ワタリアホウドリなどを参考に復元に挑んだという
第2章「多様性サークル」は、ゲノム解析によって変更が加えられた日本鳥学会による「日本鳥類目録」の改訂第8版に基づいて44目に増えた鳥たちの関わり合いをそれぞれの目に何種存在するのか、といった形で見ることができるほか、ハヤブサがタカ類よりもインコ類に近いといった意外な鳥の進化系統を知ることもできるようになっている。また、現在、人類が確認できており、約2600万年前に生きていた翼開長7mの史上最大の飛べる鳥「ペラゴルニス・サンデルシ」の生体復元モデルも展示されており、その大きさを間近で感じることができる。
この記事は Members+会員の方のみ御覧いただけます
ログイン/無料会員登録 会員サービスの詳細はこちら
AIが勧める、あなたのための会員限定記事 初手は人とデータの分類から - ゼロトラスト導入に向けたポイントを専門家が解説 セキュリティ 鍵アイコン 初手は人とデータの分類から - ゼロトラスト導入に向けたポイントを専門家が解説 防災DXでまちの安全を守るNECのシステムとは ‐ CEATEC 2024 ITインフラ 鍵アイコン 防災DXでまちの安全を守るNECのシステムとは ‐ CEATEC 2024 ルネサス、Armコア搭載マイコン「RA8シリーズ」のエントリーラインマイコン2製品を発表 半導体 鍵アイコン ルネサス、Armコア搭載マイコン「RA8シリーズ」のエントリーラインマイコン2製品を発表 ノートPCにキーボードを載せて疲労軽減×作業効率向上、選び方と使い方 開発/エンジニア 鍵アイコン ノートPCにキーボードを載せて疲労軽減×作業効率向上、選び方と使い方 ソフトバンク、自動運転車へ遠隔指示するマルチモーダルAIを開発 開発/エンジニア 鍵アイコン ソフトバンク、自動運転車へ遠隔指示するマルチモーダルAIを開発 横浜銀行がフィッシング対策にDMARCとBIMI導入、乗り越えた課題とは セキュリティ 鍵アイコン 横浜銀行がフィッシング対策にDMARCとBIMI導入、乗り越えた課題とは
アクセスランキング
鍵アイコン 京大など、「キタエフ量子スピン液体」の有力候補物質から未知の量子干渉模様を発見
2024/10/30 16:20
鍵アイコン 鳥とは何か? ゲノム解析から知ることができる特別展「鳥」が科博で開幕
2024/11/01 21:16 レポート
鍵アイコン 理研など、大型放射光施設の大改修計画「SPring-8-II」の設計指針を発表
2024/10/25 21:55
鍵アイコン 東大など、光合成活性を持った葉緑体の動物の細胞への移植に成���
2024/11/01 17:32
H3ロケット、3機連続打ち上げ成功 防衛通信衛星を搭載
15時間前 ランキングをもっと見る
ピックアップ 周辺環境モデルと車両1台分のシステムを結合した検証環境を構築 周辺環境モデルと車両1台分のシステムを結合した検証環境を構築 メインフレームにこそ生成AIを活用すべき理由 メインフレームにこそ生成AIを活用すべき理由 NECが掲げる「ファクトドリブンマネジメント」 NECが掲げる「ファクトドリブンマネジメント」 Amazon Bedrockは企業の生成AI活用をどう変えるのか Amazon Bedrockは企業の生成AI活用をどう変えるのか リリース作業を効率化したい! 最適なツールって? リリース作業を効率化したい! 最適なツールって? ヤマハが実現した、データによる意思決定の推進に迫る ヤマハが実現した、データによる意思決定の推進に迫る もっと見る 編集部が選ぶ関連記事 東大、鳥類にもジェスチャーが存在することをシジュウカラの観察から確認 サイエンス 東大、鳥類にもジェスチャーが存在することをシジュウカラの観察から確認 東大、鳥類の翼は恐竜「マニラプトル類」で進化して受け継がれたと解明 サイエンス 東大、鳥類の翼は恐竜「マニラプトル類」で進化して受け継がれたと解明 恐竜から鳥類への進化の過程での羽ばたき飛翔の起源の高精度推定に前進、名大 サイエンス 恐竜から鳥類への進化の過程での羽ばたき飛翔の起源の高精度推定に前進、名大 徳島大など、ニワトリ胚の雌雄を卵の外から早期に判別可能な方法を開発 サイエンス 徳島大など、ニワトリ胚の雌雄を卵の外から早期に判別可能な方法を開発 ヤマハが実現した、データによる意思決定の推進に迫る ヤマハが実現した、データによる意思決定の推進に迫る 医療現場の業務効率を向上させた、デジタル化の事例 医療現場の業務効率を向上させた、デジタル化の事例 国立科学博物館 生物 ゲノム解析 関連リンク
特別展「鳥 ~ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統~」 国立科学博物館
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
(鳥とは何か? ゲノム解析から知ることができる特別展「鳥」が科博で開幕 | TECH+(テックプラス)から)
0 notes
Text
ハイデルベルクは完全に大学の街。ドイツ最古の大学だから当然かな。ルプレヒト・カール大学が正式名称で、1386年に神聖ローマ帝国のもと設立された3つの大学の内の一つ。後の2つは、プラハのシャルル大学、ウィーンのウィーン大学。ワシは、これでエウロッパ滞在中に神聖ローマ帝国設立大学、全コンプリートしたザマス。
なお、ドイツで一番難関は、ミュンヘン大学、工学ではミュンヘン工科大学。両大学とも、世界ランキングでは東大より上。ちなみにハイデルベルクは東大より格下。やはりドイツは、南部に行かないと、寒いしひもじいしで、勉学なんてできっこないのだ。衣食足りて礼節を知るである。ハイデルベルクは、全ドイツではミュンヘンに次ぐレベル。学生も比較的落ち着いていて、賢そうな奴もいる。ハンブルグの、金持ちがクソ頭悪いけれど社会的地位維持のために無理矢理大学頑張って行ってみます系と大違い。

ボートに乗った後、旧市街のハイデルベルク大学図書館に潜入し、学生達を観察。ハイデルベルクは、学生を眺めていると、やっぱり、ナチュラルに賢い感じが滲み出ている。Yaleより低いけれど、Yaleと互角な感じがチラホラ見受けられる。日本なんて、東大でさえハンブルグ大学レベルなので、幻滅する。そう。図書館で勉強しなくちゃいけない層というのが、どの大学にもいて。。。その層の相対比較だから、まぁ間違いない。ちなみにワシは生涯、図書館で調べ物はしても、勉強なんてした事ない。ちなみに上の写真が、図書館の入口にいるおタカさん。
教えるようになって思うのだが、大学なんて行かなくて良いから、畑耕せっていう奴は、しかし、日本の場合、どのレベルの大学にも相当数いるのが面白い。学内多様性の担保ができているのだ。そうした事が、Yaleでは体育会系と軍隊関係者が、その位置を占めているように思うが、完全に住み分けされている。次期天ちゃんの東大推薦入試が話題になっているが、多分、志願したら入れるだろうね。今の東大って、実にそんなところ。プライドもクソもあったもんじゃない。
っという訳で、ワシはハイデルベルクの民度の高さに感動。これならラーメンもうまいはず。ハイデルベルクは京大、東北大と連携しているので、日本人学生も多いはず。ホテルの近所で見つけたラーメン屋が気に入り、二日間、毎日通った。ハンブルグではありえない。一日目は、ボートの出発時間があるので急いでおり、日本で食べそこねた冷やし中華を食す。ゴマダレだった。トマトとコーン多めで、薄焼き卵も少しだけあった。うまい。ユズとライムのジュースをschore、炭酸割りにする。


二日目は、日本人に絶大人気らしい、辛味噌ラーメンのチャーシュー乗っけ。それにパッションフルーツジュースのショーレ。締めて17ユーロでした。うまい。悶絶。ちぢれ麺に絡む辛味噌。うまい。日本でもここまでうまいラーメンは、なかなか無いザマス。そしてチャーシューが素晴らしい。暑さ1.5センチはある分厚いチャーシューが二枚も乗っているザマス。悶える。そして、大量のコーンが沈んでいる。なんで、コーンやねん。。。と思うが、まぁ、サッポロラーメンからヒントを得たんやろうと思う事にする。





ラーメンを食べた後は、お城まで坂を歩いて登り、急いで降りて、途中からトラムに乗ってホテルに戻り、預けた荷物をゲットして、ホテルの目の前のトラムから中央駅へ。ICに乗って、乗り換え無しでハンブルグまでの6���間半の旅ざます。ワシも、ハイデルベルクに住んでいたらドイツのイメージが変わっていただろう。大学街なので、大らかさが漂う。ハンブルグのお高く止まった冷たさと反対である。
クロアチア人の心理学者のお兄ちゃんと、ドイツ人の分子生物学と計算機工学のお兄ちゃんと、仲良くなって、会議後もずーっと立ち話。気付いたら、昼も食べずに2時前だった。喋りすぎたので、予定よりも観光時間が駆け足だったが、超満足でしゅ。分子生物学のお兄ちゃんとは、zoomしようねと約束。これからの交流が楽しみざます。どこでもモテモテのワシ。ぶはは。
1 note
·
View note
Text
2024年5月5日
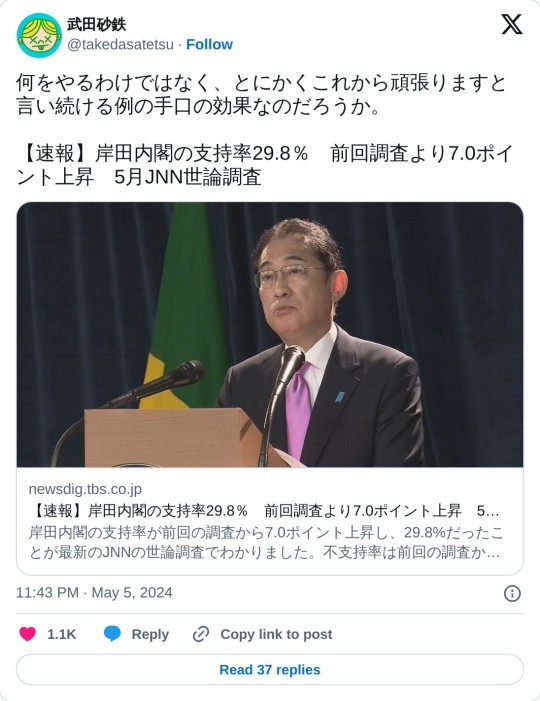
【速報】岸田内閣の支持率29.8% 前回調査より7.0ポイント上昇 5月JNN世論調査(TBS NEWS DIG)2024年5月5日
岸田内閣の支持率が前回の調査から7.0ポイント上昇し、29.8%だったことが最新のJNNの世論調査でわかりました。
不支持率は前回の調査から7.1ポイント下落し、67.9%でした。
また、政党支持率では、▼自民党の支持が前回の調査から1.6ポイント下落し、23.4%、▼立憲民主党は4.1ポイント上昇し、10.2%、▼日本維新の会は0.3ポイント上昇し、4.6%でした。
【調査方法】 JNNではコンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。
5月4日(土)、5日(日)に全国18歳以上の男女2143人〔固定850人、携帯1293人〕に調査を行い、そのうち47.3%にあたる1013人から有効な回答を得ました。その内訳は固定電話508人、携帯505人でした。
インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにもJNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。
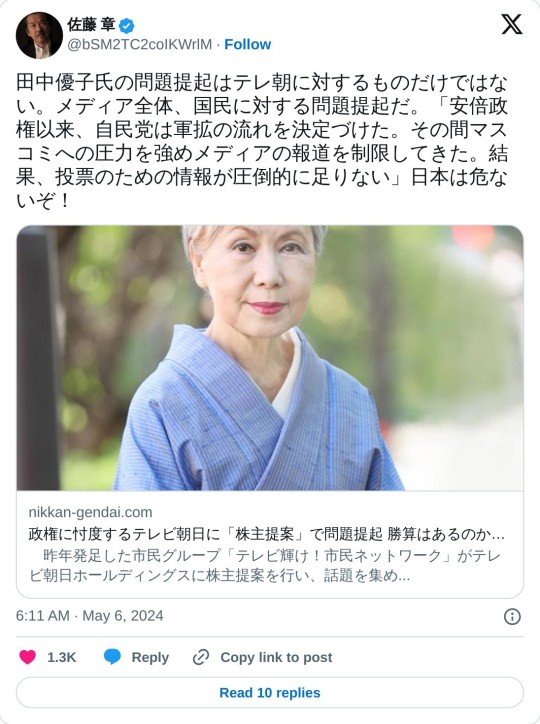
政権に忖度するテレビ朝日に「株主提案」で問題提起 勝算はあるのか…田中優子さんに聞いた(日刊ゲンダイ 5月6日)
【注目の人 直撃インタビュー】 田中優子さん(法政大前総長)
昨年発足した市民グループ「テレビ輝け!市民ネットワーク」がテレビ朝日ホールディングスに株主提案を行い、話題を集めている。権力による報道介入を防ぐため、定款変更を求めるというもの。過去10年間に圧力を受けたり、放送番組審議会が機能不全に陥っている場合などには、独立した第三者委員会を設立して調査・公表する▽番組審議会委員らの任期に上限を設ける▽共同代表を務める元文科次官の前川喜平氏を社外取締役に就ける──とする議案を出した。なぜ今、こうした手法で問題提起をしたのか。勝算はあるのか。前川氏と共に共同代表を担う法政大前総長に聞いた。
──在京キー局を抱える持ち株会社は5社あります。どうしてテレ朝なのですか。
テレビ朝日の報道姿勢は、ある時を境に大きく変わってしまった。政権に対する忖度が露骨になった。そうした認識を私たちが共有しているからです。
──「ある時」というのは?
「報道ステーション」のコメンテーターだった(元経産官僚の)古賀茂明さんが降板した2015年です。(過激派組織)イスラム国による日本人人質事件をめぐり、古賀さんは政府の対応を「I am not ABE」という言葉で批判したため、2カ月後に番組から降ろされてしまった。チーフプロデューサーも異動を命じられた。官邸がテレビ朝日側に圧力をかけたと古賀さんらからも聞き、とんでもないことが起きていると危機感を抱き始めました。
──安倍首相が中東歴訪中に「ISIL(イスラム国)と戦う周辺各国に総額2億ドル程度、支援をお約束します」と発言。反発したイスラム国が人質殺害を警告する事態となり、古賀発言につながっていきました。
■耐えがたかった卒業生殺害
拉致された末に殺害されたフリージャーナリストの後藤健二さんは、法政大学の卒業生なんですね。私は総長として、悲しく耐えがたい出来事を特に卒業生たちに報告しなければならな��った。とても、とてもつらいことでした。ですから、古賀さんの発言の真意はよく分かりましたし、深く共感していた。後藤さんを救出したい一心のご家族は、水面下で必死の交渉を続けていたんです。にもかかわらず、安倍政権が待ったをかけた。なぜあんな結末を招いてしまったのか。政府の対応は疑問だらけだし、テレ朝の動きもおかしい。そうした疑念を裏付けたのが、(昨年明るみに出た)総務省の内部文書でした。
──総務省文書には、放送法が定める「政治的公平性」の解釈変更をめぐり、2014年から15年にかけて官邸が総務省側に圧力を強めていった記録が克明に記されています。
やり玉に挙げられていたのが、テレビ朝日とTBSでした。(TBSの)「サンデーモーニング」には私自身が出演していましたが、特に変化はなかった。関口宏さんが3月末にお辞めになったのは、世代交代が理由でした。それはそうなのでしょう。だけれども、テレビ朝日で明らかに大問題が起きた以上、番組の質を注視していく必要はあると思っています。
大手ほどやらない調査報道
──テレビ朝日HDの株主総会は6月。市民ネットワークは昨年9月末までに48人で計4万株(400単元=約6000万円分)を購入し、会社法に基づく議題提案権行使に必要な「300単元以上の議決権を6カ月継続保有」をクリア。他の株主に提案を開示させる道筋をつけたほか、株主名簿の閲覧謄写も請求できるそうですね。
提案できる態勢を整えたのは、すごく大事なこと。テレビの影響力はまだまだ強い。信頼しているがゆえにしっかりしてほしい。資金もマンパワーもある大手メディアこそ調査報道に力を入れるべきなのに、大手ほどやらない。おかしいでしょう。私たちは批判するのではなく、励ますための提案をしているんです。
──前川氏は官僚時代、安倍官邸から強い圧力を受けました。社外取締役への推薦は、テレビ朝日に果たし状を突きつけたように見えます。
前川さんはふさわしい人物だと思います。社外取締役は取締役会などを通じて経営に助言したり、監督する立場。テレビ朝日HDの大株主である朝日新聞を含む報道機関としての経営のあり方、政権との関係をちゃんと見ておくことが必要なのであって、「公正にやってください」と言っているに等しい。番組制作の現場に直接口を挟めるわけではありません。取締役会の決定を覆すこともまずできないので、果たし状でも何でもない。それでも、テレビ朝日は私たちの提案にはなかなか応じないでしょうね。
──議決権比率の問題ですか。
そのあたりは事務局の阪口徳雄弁護士が詳しいのですが、米国では株主の10%以上が賛成した提案について、会社は何らかの対応をしなければならない。相当な発言力を得られるんです���ね。私たちもそこを目指したいのですが、とても遠い。さらに200倍を超える資金を投じなければならなくて。
──200倍! テレビ朝日HDの時価総額は2190億円超に上ります。いかに賛同を広げるかが今後の展開を左右しますね。
この運動は今年限りのものではありません。これを機に「そういう方法があったのか」と知っていただき、来年に向けて多くの方が「一緒に株を買いましょう」となれば、大きなうねりになる可能性はあります。政府は22年末、閣議決定で安全保障関連3文書を改定しましたよね。安保政策を大転換し、大軍拡に舵を切った。それを受けて23年1月に「平和を求め軍拡を許さない女たちの会」を立ち上げ、一連の動きを俯瞰したいと思って年表を作ったんです。自民党は野党時代の12年4月に改憲草案を発表し、12月に政権復帰。13年に特定秘密保護法、15年に安保法制、17年にいわゆる共謀罪法が成立した。第2次安倍政権以降の10年あまりで軍拡の流れは確固としたものになり、その間にマスコミに対する圧力を次第に強めていったのではないか。そうした思いを強めました。
■「◯◯政権」と呼ぶ意味がない
──確かに、深掘り報道がグッと減りました。
沖縄に関する情報は本土では全然報じられない。自衛隊の南西シフトに対し、沖縄の人々はどう反応しているのか。メディアが伝えなければ、一般市民は正確な情報を知る術がないでしょう。それともうひとつ、企業の存在も大きい。提供(広告)を通じてテレビ局に影響を及ぼしています。軍拡に関与している企業は少なくありません。一方で、企業は消費者の声やプレッシャーを無視することはできない。そうした関係を踏まえながら、報道を望ましい方向へ持っていくアプローチを始めたということなのです。
──タカ派の安倍政権、菅政権の9年。当初はハト派と目された岸田政権は、3年を待たずに馬脚を現しました。
状況はどんどんひどくなっている。首相の名前を取って「◯◯政権」と呼びますけれど、私は全く意味がないと思っているんです。自民党政権は首相が誰であっても中身は同じですから。米国の傀儡であり、抱き込まれるままなのが既定路線。訪米した岸田首相は米軍と自衛隊の指揮統制の連携強化で合意しました。その先に主権制限があるのは明白ですが、それも自民党政権は織り込み済みなのでしょう。
──主権の一部を切り離す方針は米軍の公式文書に明記されています。
民主主義を担保するのは選挙です。それなのに、投票行動の前提となる情報が圧倒的に足りない。政府が、自民党が何をしようとしているのかが判然としない。だから、私たちはちゃんとした報道を求めているんです。(聞き手=��本千晶/日刊ゲンダイ)
▽田中優子(たなか・ゆうこ) 1952年、横浜市生まれ。江戸文化研究者。法政大文学部日本文学科卒、法大大学院人文科学研究科博士課程満期退学。法大社会学部教授、社会学部長、第19代総長を歴任し、現在は名誉教授。著書「江戸の想像力」で芸術選奨文部大臣新人賞、「江戸百夢」で芸術選奨文部科学大臣賞とサントリー学芸賞を受賞。2005年に紫綬褒章受章。
0 notes
Text
マステの整理をしてたら、顔真卿展の時に買った自叙帖のマステが出てきた これ祭姪文稿と並んで特別展限定グッズだったんだよねー でもきっと台北故宮博に似たようなグッズあるじゃろとタカくくって1個ずつしか買わなかったら、後日ないことを知ってちょっと泣いた
もっと買っておけばよかったーーー
ところで台北故宮博から出てる「書法の美」だと、懐素は玄奘から教えを受けたってなってたので一時真に受けてたのだけど、天来書院の自叙帖解説ではこちらは同名異人の経歴で、誤りとあった。 あぶねーなーもーーー 顔真卿と知己、かつ自叙帖の作者の方の懐素は現湖南省出身で姓は銭氏、一方玄奘弟子の懐素は唐のはじめの人で、現河南省出身で姓は范氏
なお、自叙帖は長期にわたり真贋論争が絶えず、2000年代はじめに台北故宮博と日本の機関による合同分析で一応の決着(双鉤塡墨ではなく、直書きであり、補筆、後筆がある等)が出たそう(同・天来書院)
五馬図巻と言い、この手の論争って科学分析が可能になった今でこそある程度の目度がつくものの、その辺に頼れなかった時代は大変だよね…となる
あと自叙帖だけ(ほかもあるかもしれんけど)台北故宮博でも特殊にガードが硬い印象がある いつものルートでは画像データにたどり着けなかった
0 notes
Text

昼夜の寒暖差が激しくて最近まで昼間は夏日が続いてたのに 今日は突風が吹き荒れて底冷えがするほど寒い。 夏から秋を素っ飛ばして急に冬になったような感じだ。 暖冬だとタカをくくって厚物衣料を買わなかった人達が ショッピングモールに押し寄せているらしい。 先程冬物衣料を買いに行った家族がそう言っていた。 海外の文化であるBLACK FRIDAYがいよいよ日本にも上陸したが 本来の日を完全無視して1週間早く始まっている。 セール期間になった頃にはお目当ての色やサイズは無いだろうに。 俺は激混みの店に行くのは嫌なので早々とZOZOTOWNで仕入れ済。 前回の母親の救急搬入騒動から約1ヶ月が経った。 定期的に診断を受けている循環器科で主治医から 「大変でしたね~、色々訊きましたよ?」 と言われたらしい。 俺が宿直医をゴルァした件はどうやら院内で知れ渡ってる様子。 まぁでも泌尿器科の主治医が言うには腎盂腎炎の中では重いやつで あのまま入院せず家に帰ってたら今頃死んでたらしいので。 あの時強気な行動に出て本当に良かったと思ってる。 前職の会社が全国的に派遣社員大量解雇したせいで不本意な転職をしたのが今年の4月。 最初は天国みたいな職場だと思っていたが大きな勘違いだった。 夏頃より育成担当から連日パワハラ・モラハラを受け続けている。 何気に俺はこの業界歴20年で育成担当よりもキャリアが長い。 俺のキャリアを否定するような発言がやたらと多いので どうやら嫉妬を受けてしまったと思われる。(知らんがな… とりあえず派遣元に相談したら「派遣先に改善要望を出して猛抗議する」と言い始めた。 「いやいや…ソレだと俺の立場微妙になるし面倒なんで…」 どっちにしろ派遣だしその会社に長居するワケじゃないんだから 見切り付けて他探せば良いと思ってる。 派遣営業は納得いかない顔をしていたが…。 このままやり過ごして水面下で転職活動すれば良いと思ってたが派遣先上司に 「調子はどうかね?」 と根掘り葉掘り近況訊かれて結局話さざるを得なかったという。 「お願いだから辞めないで!!すぐに改善対策を立てるから!」 と全力で引き留められた。 席割りを離したので接触する機会が減った為ハラスメントは劇的に減ったが 今度は新しい仕事を俺にだけ研修させない問題が勃発。 冷静に考えてみて最早ここに留まってメリットは無いのではないか?と思い 水面下で転職活動を決行することにした。 タイムリミットは2ヶ月しか無いので気合入れてやるつもりだ。 次の職種はコルセン以外も視野に入れて幅広く探す予定。 キャリアの長さで嫉妬されるの今回だけじゃないんだよなぁ。 東京にいた時も同僚に嫉妬されてモラハラ受けたことあるしなぁ。 経験者として入社したら即戦力にならないといけないので 猛烈に頑張ってた俺は職場の人から重宝がられた。 だが同僚は経験値が少なかったので仕事がうまくいかなかったらしく 『あなた私のことずっと馬鹿にして上から見下しているでしょ!! いい加減にしてよね!!いつもいつも!!人のこと馬鹿にして!! いくら私が仕事出来ないからってふざけないで!! いつも涼しい顔して何でもソツなくこなして!! どうせ影で私のこと馬鹿にしているんでしょう!! お願いだからこの会社辞めてよ!! あなたのキャリアならあんな仕事しなくても良いでしょう?! さっさと私に居場所譲って他の会社へ行ってよ!!』 なんて言われたことがあったなぁ…(遠い目 それこそ被害妄想もイイとこでとんだとばっちり。 俺は自分の仕事に一生懸命で他人のこと考えてる余裕無いし。 人をバカにして俺に何かメリットでもあるのだろうか? 損にも徳にもならない行為をする意味を見出せない。 自分が仕事出来ないのを他人のせいにするなんて愚の骨頂。 モラルが欠如してるとしか思えないね全く…。 お前の承認欲求満たす為に俺がいるわけじゃねぇっつの。 正直嫉妬されるのは疲れるんだよなぁ。 勝手に敵対視されて悪者扱いされるのはまっぴらごめんだ。 まぁ本来なら俺のキャリアと年齢なら指導者側になっててもおかしくない立場だからなぁ。 キャリアが少ない人からしたら正直やりにくいのかもしれない。 でも指導者は拘束時間長いしシフトが不自由で面倒くせぇ…。 通勤するのに朝5時起床で2時間かけて通ってるから残業とか絶対にしたくないもんな。 ここらでキャリアを投げ捨てて別の業界の扉を開くのもアリかもな。 コルセン業もAI化されたら仕事無くなるらしいしなぁ。 AI社会が主流になってもやっていけるような業界探してみるかぁ! 今日はしばらくインベの肥やしにしていたアイテムを掘り起こしてみた。 個性的すぎてコーデしにくそうなもの同士を合わせたらどうなるか実験。 うんうん…意外とシックリ合っててイケるんじゃねぇ? ■HAIR Dura-Anime11
■TOPS [Deadwool] Morgan jacket
■BOTTOMS Legal Insanity - Opie leather pants
■SHOES [Deadwool] LDN boots
■BACKDROP .PALETO.Backdrop:. MIDNIGHT
0 notes
Text
AIに聞いてみた
キッシンジャー、ブレジンスキー、ヌーランドの生い立ち、思想、宗教観、哲学、外交官としの実績、地政学的、人物を教えて下さい
以下に、ヘンリー・キッシンジャー、ズビグネフ・ブレジンスキー、ビクトリア・ヌーランドの生い立ち、思想、宗教観、哲学、外交官としての実績、地政学的な視点、そして人物像について詳しく説明します。それぞれの人物が国際政治に与えた影響を考慮しつつ、客観的かつ包括的にまとめます。
---
### **ヘンリー・キッシンジャー (Henry Kissinger)**
#### **生い立ち**
- **出生**: 1923年5月27日、ドイツのバイエルン州フュルト生まれ。ユダヤ系の家庭に育つ。
- **幼少期**: ナチス政権の台頭(1933年)により迫害を逃れ、1938年に家族と共に米国へ移住。ニューヨーク市で暮らし、工場労働者として働きながら夜学に通う。
- **教育**: ハーバード大学で政治学を学び、博士号を取得。国際関係論の研究者としてキャリアをスタート。
#### **思想**
- **現実主義 (リアリズム)**: キッシンジャーは「力の均衡」を重視する現実主義者。国家間のパワーバランスが国際秩序の安定に不可欠と考え、理想主義よりも国益を優先。
- **冷戦観**: 米ソ間の緊張緩和(デタント)を推進しつつ、共産主義の拡大を抑える戦略を重視。
#### **宗教観**
- ユダヤ系の出自を持つが、公的な場で宗教的信念を強く打ち出すことは少なく、外交においては世俗的なアプローチを取った。宗教よりも地政学や歴史的文脈を重視。
#### **哲学**
- 歴史から学ぶ重要性を説き、19世紀の欧州外交(特にメッテルニヒやビスマルク)に影響を受けた。外交を「芸術」と捉え、長期的な視点での戦略的交渉を重視。
#### **外交官としての実績**
- **職歴**: ニクソン政権およびフォード政権で国家安全保障担当補佐官(1969-1975)、国務長官(1973-1977)を歴任。
- **米中関係正常化**: 1971年の極秘訪中と1972年のニクソン訪中を主導し、冷戦下で中国をソ連牽制に利用する三角外交を展開。
- **ベトナム戦争**: 1973年のパリ和平協定をまとめ、米国撤退を実現。ノーベル平和賞を受賞するも、協定後の混乱で議論を呼ぶ。
- **デタント**: ソ連との緊張緩和を進め、軍縮交渉(SALT I)を成功させた。
- **批判**: チリでのピノチェト政権支援や東ティモール侵攻の容認など、人権侵害への関与で非難も。
#### **地政学**
- ユーラシア大陸の支配が世界覇権の鍵とみなし、「ザ・グランド・チェスボード」的な視点を持つブレ��ンスキーとは異なり、複数の大国間の均衡を重視。米中ソの三角関係を活用した。
#### **人物像**
- 知性と冷徹さを併せ持ち、「外交の魔術師」と称される。ユーモアと鋭い洞察力で各国首脳と信頼関係を築く一方、強引な政策で敵も多い。晩年もAIや地政学に関する発言で影響力を維持。
---
### **ズビグネフ・ブレジンスキー (Zbigniew Brzezinski)**
#### **生い立ち**
- **出生**: 1928年3月28日、ポーランドのワルシャワ生まれ。貴族階級の出自。
- **幼少期**: 外交官の父に伴い、ドイツでヒトラーの台頭、ソ連でスターリンの大粛清を目撃。1938年にカナダへ移住し、第二次大戦後は米国へ。1958年に米国籍取得。
- **教育**: マギル大学とハーバード大学で学び、政治学博士号を取得。
#### **思想**
- **反共主義**: ソ連への強い敵意を持ち、その崩壊を戦略目標とした。ポーランド出身ゆえの歴史的背景が影響。
- **地政学的覇権論**: ユーラシアの支配が世界覇権に直結すると主張(著書『ブレジンスキーの世界はこう動く』)。
- **親中派**: 米中関係の強化をソ連封じ込めの手段と位置づけた。
#### **宗教観**
- カトリック系のポーランド文化に根ざすが、宗教的言及は控えめ。思想や政策は地政学と現実的な戦略に基づく。
#### **哲学**
- 全体主義を批判しつつ、民主主義の拡大を支持。ただし、現実的な力の行使も厭わない戦略家。長期的なビジョンを重視し、「ゲーム・プラン」を描く。
#### **外交官としての実績**
- **職歴**: カーター政権で国家安全保障担当補佐官(1977-1981)を務める。
- **米中国交正常化**: 1978-79年に中国との正式な外交関係樹立を推進。
- **アフガニスタン戦略**: ソ連のアフガン侵攻(1979年)を誘発し、CIAを通じたムジャヒディーン支援でソ連を疲弊させ、冷戦終結に寄与。
- **イラン革命対応**: 1979年のホメイニ政権成立で米国が影響力を失う中、対応に苦慮。
- **三極委員会**: 日米欧の協力を提唱し、設立に貢献。
#### **地政学**
- ユーラシアを「世界のチェス盤」と呼び、その中心である「ハートランド」を支配する国が世界を制すると主張。ロシアの封じ込めと中国の活用を重視。
#### **人物像**
- 情熱的で戦略的思考の持ち主。ソ連への憎悪からくる強硬姿勢と、知的な分析力が特徴。日本を「ひよわな花」と評し、議論を呼んだ。晩年まで地政学の重鎮として発言。
---
### **ビクトリア・ヌーランド (Victoria Nuland)**
#### **生い立ち**
- **出生**: 1961年、ニューヨーク生まれ。外科医で歴史学者の父を持つ。
- **幼少期**: 米国で育ち、ロシア語を学び、ソ連への関心を深める。
- **教育**: ブラウン大学で歴史と政治学を専攻。
#### **思想**
- **ネオコン寄り**: 民主主義の推進とロシアへの強硬姿勢を支持。ブレジンスキーの反共思想に影響を受けた可能性。
- **介入主義**: 米国が積極的に国際秩序を形成すべきと考える。
#### **宗教観**
- ユダヤ系の出自を持つが、公的な宗教観は明言せず、政策は世俗的アプローチに基づく。
#### **哲学**
- 民主主義と人権を重視するが、現実的な力の行使も容認。歴史的教訓からロシアの拡張主義を警戒。
#### **外交官としての実績**
- **職歴**: クリントン、ブッシュ、オバマ、バイデン政権で要職を歴任。国務次官補(欧州・ユーラシア担当、2013-2017)、国務次官(政治担当、2021-2024)。
- **ウクライナ危機**: 2014年のクリミア併合時、ウクライナ支援と対露制裁を主導。「ファック・ザ・EU」発言で物議。
- **ロシア政策**: NATO拡大とロシア封じ込めを推進。プーチン政権への強硬姿勢を維持。
- **実績と批判**: 民主化支援に尽力する一方、介入主義が紛争をエスカレートさせたと批判される。
#### **地政学**
- 東欧とユーラシアでのロシア影響力削減を目指し、NATOとEUの拡大を支持。ブレジンスキーの地政学を引き継ぐ側面も。
#### **人物像**
- 直言居士でタフな交渉者。ロシアへの強硬さから「対露タカ派」と評される。外交現場での実践派として知られる。
---
### **比較と総括**
- **共通点**: 三者とも冷戦やポスト冷戦の地政学に深く関与し、現実主義と戦略的思考を共有。米国覇権の維持を目指した。
- **相違点**: キッシンジャーは均衡外交、ブレジンスキーはユーラシア覇権論、ヌーランドはロシア封じ込めと民主化推進に焦点。
- **影響**: キッシンジャーとブレジンスキーは冷戦終結に寄与し、ヌーランドは現代のロシア-西側対立を象徴する存在。
これらの人物は、異なる時代背景で米国の外交戦略を形作った巨人と実践者です。質問があれば、さらに深掘りします!
2 notes
·
View notes
Photo

🎏 トリ店員巡廻中🦅 🎏 : : #錦鯉 #真鯉 #錦鯉飼育 #各種器具 #錦鯉飼料 #全国発送 #微生物濾過 #高性能 #高機能 #高耐久 #ろ過材 #バイオメッシュ #BIOMESH #発売元 #篠田山養鯉場 #鳶 #トビ #タカ目タカ科 #sonyalpha #鳥店員 (錦鯉(Koi) 篠田山養鯉場) https://www.instagram.com/p/CYLgNWXpkYm/?utm_medium=tumblr
#錦鯉#真鯉#錦鯉飼育#各種器具#錦鯉飼料#全国発送#微生物濾過#高性能#高機能#高耐久#ろ過材#バイオメッシュ#biomesh#発売元#篠田山養鯉場#鳶#トビ#タカ目タカ科#sonyalpha#鳥店員
0 notes
Photo


桜の枝を折るオオタカ
13 notes
·
View notes
Quote
7月14日に喉に違和感、その日のうちに微熱で検査。 翌午前に陽性が確認されてから10日間の自宅療養を選択して無事ミッション完遂するも 「確率は低いらしいし大丈夫では」とタカを括っていた後遺症が出てしまった。 25日の待機終了から本日(8月5日)で12日が経過しているが、依然として37度を割り込むのは 1日に1度あるかないかといったところで、少しの運動や入浴でも倦怠感が出てしまう生活を送っている。 後遺症の出る確率が年齢や性別でどの程度異なるのか正確なデータは不明だが オミクロン株に置き換わってからは大半の方が1日、2日の発熱で軽快するため 世間では「コロナ恐るるに足らず」という認識が広まっているように思う。 しかし、ワクチン接種3回済みの私ですら7日間は38度を切ることのない生活が続き やっと37度台になったかと思えば今度はそれ以上下がり切らず 発熱時のようなダルさが抜け切らないまま現在に至る。 それでも現在の判断基準では「軽症」に振り分けられるのだ。 このことの怖さを、どうかまだ感染したことのない幸運な方は頭の片隅にでも置いておいて欲しい。 ひとりでも多くの方の参考になればと思い、以下に待機明けからの日記を一部抜粋して再掲する。 行動制限のない久しぶりの夏休みを安全に楽しく過ごすために、目を通していただければ。 <感染から12日目> 37度前後の微熱がなかなか下がらず、少し動くと動悸がする状態が続いている。 今日の大阪は37度と全国一暑かったことも一因かも知れないし 連日の猛暑による夏バテが重なっている可能性もなくはないか。 老いをヒシヒシと感じつつ、もうしばらくは様子を見ながらの生活になりそう。 <感染から13日目> 東京も大阪も連日2万3万と感覚の麻痺する人数が続いているところに さらなる新株のケンタウロス(BA.2.75)の感染報告が出始めた。 このままいけば7波が収まる前に8波に突入する可能性もあると感染症の専門医が言っているが だからといってもう皆社会生活を回す方向に舵を切ってしまった以上、 今度はそう簡単に緊急事態宣言も出さないであろうし、一体どれだけの人が感染することになるのだろう。 私は14日の発症、15日からの自宅待機で今日が13日目。 倦怠感と微熱がまだ続いていてどうもすっきりしない。 喉の腫れ・痛みが治ったので食事が取れているのが幸い。 ただ、まだ通常量を取るほどには至らず、エネルギー系のゼリーなどを追加して なるべくカロリーを摂取しているのだが、それでも体重が減る一方でさてどうしたものか。 <感染から15日目> 依然として倦怠感が続き、熱も37度からすっきりとは下がらないまま。 同様の症状が続いている知り合いが複数いるのだが、 皆もう気にしても仕方がないので測らなくなったと言っている。 本来の決まりである「平熱まで戻ってから72時間経過」を守っていたら、 一体いつ行動制限が解除して良いのかもわからない。 発症から6日目以降は人に感染させる量のウィルスは放出されていないと何かで読んだので ��場の買い出し程度には動いているのだが、発熱期間が長いせいなのか帯状疱疹からの疲労蓄積なのか、 すぐに疲れてしまって困っている。 <感染から15日目> 潰瘍性大腸炎の治療でお世話になっている胃腸科の通院日なのだが 病院が少し遠方にあり、まだそこまで行くだけの体力に自信がないため初めてオンライン診療を試してみた。 「CLINICS」というアプリを使い病院名検索をかけて予約時間を登録すれば 前日と当日の2回、「間も無くですよ」という通知が届く。 あとは診察時間に接続するだけで、いつもの先生がスマホの中に現れた。 診察後は処方箋を徒歩圏内の薬局まで飛ばしてもらい受け取るだけ。 支払いは診察料はアプリ登録時のクレカで決済、薬局はいつもと同じ。 難点は、オンライン診療の場合は薬が最長でも1ヶ月分しか出せないこと。 私はいつも2ヶ月分をまとめて出していただいているので、また来月同じ形で診察をうけなければならない。 とはいえこれは便利だ。便利な世の中でよかった。
新型コロナウィルス感染の後遺症は想像以上に厄介です - 忍之閻魔帳
4 notes
·
View notes
Text
§º所謂「殺人鬼」に対する過大評価
特にフィクションの世界で、所謂「殺人鬼」を「神聖視/特別扱い」する傾向がある。だから、死んだあとに最凶の悪霊となって人々を苦しめ続ける「敵役」として造形されがち。しかし、「殺人鬼」は、知性現象としては所謂「フツウの人」よりも未熟な、即ち完成度の低い、デキソコナイに過ぎない。つまり、真にポンコツ人間なのだ。こういうポンコツ人間に対する評価を誤らせる元凶が生命教信仰。生命教信者は、[生命を、蔑ろにして自らの快楽のためだけにモテアソブ存在]を[人間を超越したナニモノカ]であるかのように、つい、思ってしまうのだ。
更に云えば、だから、その手の「殺人鬼」が現われると、世間や、特に精神科医界隈が「アリガタ」がって、「殺人鬼」の死刑に反対し、その言動の研究や、刑務所内での対話や、[告白本の執筆/出版]を望んだりする。しかし、「殺人鬼」なんぞは大量生産に付き物の「不良品」にすぎない。一定の割合で出てくる、極アリフレタ存在。そのアタマの中にあるものもタカが知れてる。
もちろん、「殺人鬼」を或る種の「病気」と捉えて、たとえば、脳のどの部分がどのようになれば「殺人鬼」が出来上がるのかの研究をする、ということはあるだろう。そして、もし、その研究が成功すれば、「殺人鬼」を「治療」することもできるだろう。そうなれば、元々は「殺人鬼」ではなかった人間が、あるときから急に「殺人鬼」になってしまった場合などに、原因を突き止めて、その人を元の「フツウの人」に戻すこともできるようになるかもしれない。
が、思い出して欲しいのは「殺人鬼」は現に凶悪な殺人をおそらく複数回繰り返したから「殺人鬼」と認識されるわけで、そんな存在をわざわざ治療したり生かし続けたりすることで、当該社会は一体どんな利益を得るのだろう? 一種の人体実験として「殺人鬼」を治療して「フツウ」に戻し、その上で、懲役刑あるいは極刑を科すとか? しかしそうではなく、たとえば、十五人殺した「殺人鬼」が「治療」によって「フツウ」なったら、社会に復帰させるとなったとき、被害者たちの遺族は、あるいはそれ以外の人々も、冗談じゃねえや、と思うに違いない。
「殺人鬼」と「フツウの人」とで一番に異なると考えられるのは、やはり「共感力」だろう。「他人の気持ちになる」という能力。「殺人鬼」にはこの「共感力」がないので、被害者の苦しみが自分の苦しみとはならず、だから、「平気」で殺し続けられる。あるいは、「共感力」はあるが、それがねじれてしまっている場合もあるだろう。「殺人鬼」は、他人の恐怖や苦しみに「共感」して「快感」を覚える、というパターン。いずれにせよ、ただの障害。「ただの障害」というのは、耳が聞こえないとか目が見えないとかの障害の一つに過ぎない、という意味。しかし、目が見えない、耳が聞こえないなどの障害と違い、連続殺人にまでつながるような「共感力のなさ」は、数多ある障害の中でも、社会にとって、絶対に看過できないシロモノなのもその通り。
だが敢えて言いたい。「殺人鬼」も所詮は障害の産物である。「殺人鬼」は「超人」ではなく「障害者」である。しかも、目や耳の障害と違って、知性に関わる部分の障害である。だから、知性現象としては、フツウの人よりも、一段も二段も「低級」な存在なのだ。その点を忘れないことが大切(「だから、その罪を許せ」と言っているのではない)。
もちろん、知性として「低級」でも侮ることはできない。地全災害・天変地異は知性現象としては「低級」どころか「完全な無」だが、それよりもずっと高級な知性現象である「フツウの人々」を簡単に殺す。「殺人鬼」が人を殺せるのも、一番は、この理屈。
1 note
·
View note
Link

以下引用
https://ja.wikipedia.org/wiki/ヘビクイワシ
ヘビクイワシ
ヘビクイワシは、タカ目ヘビクイワシ科ヘビクイワシ属に分類される鳥類。本種のみでヘビクイワシ属を構成する。
和名の「蛇食い鷲」は、蛇を蹴り弱らせて食べる姿に由来している。
全長:100-150cm。翼開張:200cm。体重:2-4kg。メスよりもオスの方が大型になる。
サバンナに生息する。単独もしくはペアで生活するが、野火が起こると、火から逃れて草むらから飛び出す獲物目当てに集まり、集団で観察されることもある。地上を徘徊して獲物を捕らえるが、翼が退化して飛べないタカヘやダチョウなどとは異なり、飛翔能力はある。
パフアダーなどの蛇を捕食する際、その頭部に連続で蹴りを入れ、弱らせてから食べる習性が知られているが、蛇を専門的に狙うわけではなく、昆虫、爬虫類、鳥類とその卵、ネズミやウサギなど幅広い動物性の餌を食べる。獲物を蹴飛ばす際には翼を左右に広げてバランスをとり、ソウゲンワシなどと獲物を取り合いになった時は、飛び上がって蹴り、追い払う。獲物を掴んで上空から落としてから食べることもある。
繁殖形態は卵生。ペアは一生解消されない。樹上に木の枝を組み合わせた巣を作る。巣は同じ物を使い続けるため、時に巨大な巣を形成することもある。
5 notes
·
View notes
Photo






Unknown Image Series no.8 #1 山元彩香「organ」 Ayaka Yamamoto "organ" 2019. 11. 1 (fri) - 11.30 (sat)
void+ではUnknown Image Series no.8 #1 山元彩香「organ」を11月1日より開催いたします。Unknown は、インディペンデント・キュレーターのカトウチカが企画するシリーズの展覧会で、2011年より開催。シリーズ8回目となる本展は、Unknown Imageというタイトルで、5名の作家による連続個展形式のグループ展としてHIGURE 17-15 casとvoid+にて開催する予定です。
初回の山元彩香は、京都精華大学芸術学部で絵画を専攻しましたが、米国への交換留学を機に写真の制作を始めました。近年は、自身の持つ知識、経験、言葉の通じない外国へ赴き、現地で知り合った少女たちのポートレート写真を撮り続けています。訪問先は、エストニア、ラトビア、ロシア、ウクライナ、ブルガリア、ルーマニア、ベラルーシなど東欧各国、今年は初のアフリカ大陸、マラウイを訪問し、精力的に制作活動をしています。
本展では新作となる映像作品と、その他旧作と新作で構成した写真作品を展示いたします。会期中にはDIC川村記念美術館学芸員の光田由里、愛知県美術館学芸員の中村史子をゲストに迎え、トークイベントを開催いたします。
-------------------------------------------------------------------------------------------
<展覧会概要>
■タイトル:Unknown Image Series no.8 #1 山元彩香「organ」 ■会期:2019 年11月1日(金)— 11月30(土)14:00-19:00 ・レセプション:11月1日(金)19:00-21:00 ・トークイベント:11月29日(金)19:00-20:30 山元彩香+ 光田由里(DIC川村記念美術館学芸員)+ 中村史子(愛知県美術館学芸員) ■会場:void+ 東京都港区南青山3-16-14, 1F ■定休日:日、月、祝日 ■入場無料 ■お問合せ:Tel: 03-5411-0080/メール: [email protected]
[主催]void+委員会/Unknown実行委員会 [企画]カトウチカ [助成]令和元年度港区文化芸術活動サポート事業助成 [協力]Taka Ishii Gallery Photography / Film、YN Associates [機材協力]ソニーマーケティング株式会社
・未就学児の入場可能 / 車椅子ご利用の方は事前にお申し出ください。
Starting on November 1, void+ will present Unknown Image Series no.8 #1 YAMAMOTO Ayaka “organ.”
The Unknown series of exhibitions, launched in 2011, are planned and coordinated by independent curator Kato Chika. This eighth exhibition takes the title “Unknown Image,” and will be staged as a group show by five artists in the format of consecutive solo exhibitions at HIGURE 17-15 cas and void+.
Featured in the first show is Yamamoto Ayaka, who majored in painting at Kyoto Seika University’s Faculty of Arts, but began producing photographs during a student exchange in the United States. Recent years have seen Yamamoto traveling to parts of the world where her own knowledge, experience and language do not apply, and shooting portraits of girls she meets there. She has thrown herself enthusiastically into the project, visiting Eastern European nations including Estonia, Latvia, Russia, Ukraine, Bulgaria, Romania, and Belarus, and this year traveling to Africa for the first time, to take photos in Malawi.
Unknown Image Series no.8 #1 YAMAMOTO Ayaka “organ” will present a new work on video by Yamamoto, along with a selection of photographic works. In conjunction with the exhibition, a talk event will also be held, featuring, in addition to the artist, guests Mitsuda Yuri, curator at Kawamura Memorial DIC Museum of Art, and Nakamura Fumiko, curator at Aichi Prefectural Museum of Art.
<Exhibition data>
■Title: Unknown Image Series no. 8 #1 YAMAMOTO Ayaka ”organ” ■Dates/Hours: Friday, November 1 – Saturday, November 30, 2019 14:00–19:00 • Opening reception: Friday, November 1 19:00–21:00 •Talk event: Friday, November 29 19:00–20:30 YAMAMOTO Ayaka + MITSUDA Yuri (Curator, Kawamura Memorial DIC Museum of Art)+ NAKAMURA Fumiko (Curator, Aichi Prefectural Museum of Art) ■Venue: void+ 3-16-14, 1F Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo ■Closed: Sundays, Mondays, holidays ■Admission: free ■Inquires: Tel: 03-5411-0080 Email: [email protected]
Organized by: Unknown executive committee / void+ committee Conceived and planned by: KATO Chika Supported by: Minato City Cultural Arts Support Project With cooperation from: Taka Ishii Gallery Photography/Film, YN Associates Equipment provided by: Sony Marketing Inc.
*Preschoolers welcome. Wheelchair users please let us know in advance.
------------------------
「organ」について
2011年に初めてラトビアを訪れたとき、毎朝友人の鼻歌で目覚めた。
それは、言葉になる前の声の連続で、彼女の内部に無意識的に蓄積されている記憶が音のイメージとなって発せられているようにも思えた。
会話とはまた別のレベルで、彼女が辿ってきた時間そのものに触れているような感覚があった。
放たれた声は私の身体の一部となり、自らの声で再び発することで他者へと循環、連鎖してゆく。
organとは、容れ物としての器という意味を持ちながら、臓器や楽器の意味を成す。
遥か昔、儀式に使われていた鈴や鐸はその空洞に響く音によって、それを身につけた人間に見えざるものを憑依/循環させていたそうだ。
空の器としての身体に宿る音により、その奥底にかすかに在る未だ見ぬものに触れたいと願う。
(2019年10月 山元彩香)
About “organ”
When I first visited Latvia in 2011, I was woken every morning by my friend, humming. To me this felt like the continuation of a pre-verbal voice, the emission of memories unconsciously accumulating within her, in the form of sound images. The sensation was one of experiencing the very time she had traveled, at a different level from conversation. Her voice, released, become part of my body, and emitting it again in my own voice causes it to circulate and connect to others. An organ may be a body organ or a musical instrument; in Japanese the character (器) read as ki or utsuwa has these meanings, while also referring to a vessel. Back in the mists of time, the sound of a bell used in rituals, reverberating in the cavity of that bell, would apparently cause the wearer to be possessed by some invisible presence, or have such a presence circulating within them. Hopefully the sounds harbored by the body as empty vessel will put us in touch with glimmers of yet unseen things found in its depths.
(YAMAMOTO Ayaka, October 2019)
--------
organ
一見、古典的な絵画のように見えるその写真には、非現実なまでに美しい「いきもの」が写っている。彼女たちの表情は虚ろでどこか遠くを見つめているか、死者のごとく目を閉ざしている。あるいは仮面やベールをつけて、その表情すら見えないのだが、仮面をつけた身体やベールの奥にかすかに残っているものがある。果たしてそれはなんなのだろうか?
山元は、あえて言葉が通じない国に出かけ撮影する。言葉に頼らないコミュニケーションに よって被写体と共同作業でイメージをつくり上げる。個人を形成している様々なレイヤーを剥ぎ取って新たな衣を纏わせていく過程において、最後には被写体の自意識が消えてしまう瞬間が生まれるのだという。 今まで纏っていた衣服、名前、記憶、自意識、文字通りすべてを剥ぎ取り新たな姿を与える撮影は、写真が持つ本質的な暴力性を孕んでいる。しかし、作家が被写体の属性をいくら奪おうとしても奥底に残るものがあるのだという。彼女はそこに何を見出したのだろうか。異国の他者を撮影することで何を問い続けているのだろうか。その静謐なポートレートは、作家の問いであると同時に、イメージの謎そのものなのである。
今回の個展で、山元は映像作品(撮影地ラトビア、2019年制作)を展示する。organ=空の器としての身体は、言葉ではない歌を歌う。映像=時間の中に置かれた空の器は、いかなる音を宿すのか、さらなる問いを生じさせる。
カトウチカ(Unknown Series キュレーター)
organ
Yamamoto’s photographs, at first glance reminiscent of classical paintings, show “creatures” of almost unreal beauty. The girls appear either to be vacantly staring at some point in the distance, or have their eyes closed as if dead. Or they wear a mask or veil, making it impossible to even see their expression, although something remains in the body wearing the mask, or visible faintly behind the veil. What is it? Yamamoto deliberately sets out to take photographs in countries where she does not speak the language, constructing images in collaboration with her subjects via non-verbal communication. The process of peeling away the layers that go to make up an individual and clothing them in new garb apparently, in the end, creates a moment in which the subject sheds her self-consciousness. Photo shoots that strip away literally everything previous—the clothes the person was wearing, their name, memories, self-consciousness—to give them a totally new appearance, are filled with the intrinsic violence of photography. Yet the artist says that no matter how much she endeavors to denude her subjects of their attributes, deep down, something remains. What has Yamamoto identified there? By photographing strangers from other countries, what question does she continually ask? These tranquil portraits serve at once as inquiries on the part of the artist, and the very riddle of images. In this solo outing, Yamamoto will present a video work, shot in Latvia in 2019. The organ/body as empty vessel, sings a song without words. This generates further questions about what kind of sounds are harbored by the empty vessel placed in a video/time.
KATO Chika (Unknown Series curator)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<作家プロフィール>
山元彩香| YAMAMOTO Ayaka
1983年 兵庫県生まれ。2006年 京都精華大学 芸術学部 造形学科洋画コース卒業。言語による意思疎通が難しい状況下での撮影は、写真というメディアが本質的に抱える性質以上に他者との様々な接点を作家にもたらし、以降、暴力的でありながらも魅力的なイメージ生成の場とも言えるポートレートの撮影を続ける。主な個展に「We are Made of Grass, Soil, and Trees」(タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルム、2018)、「Nous n'irons plus au bois」(同、2014)など。主に東欧各地で撮影を行い、国内外で写真展やレジデンスに参加。2019年に写真集『We are Made of Grass, Soil, and Trees』(T&M Projects、2018)が「さがみはら写真新人奨励賞」を受賞。
YAMAMOTO Ayaka Born 1983 in Hyogo, Japan. BFA in painting, Kyoto Seika University, Faculty of Fine Art. In a situation in which communication through words was difficult, photography took on a value beyond its intrinsic nature, serving as a point of contact with others. Since then, Yamamoto has continued to take in a certain sense violent, yet alluring portraits. Solo exhibitions include ”We are Made of Grass, Soil, and Trees” (Taka Ishii Gallery Photography/Film, 2018) and “Nous n’irons plus au bois” (Taka Ishii Gallery Photography/Film, 2014). She photographs mainly in Eastern Europe, and has participated in photo exhibitions and residencies in Japan and overseas. She won the 19th Sagamihara Prize for Newcomer Professionals in 2019 for her photobook We are Made of Grass, Soil, and Trees(T&M Projects, 2018).
<ゲストプロフィール>
光田由里|MITSUDA Yuri
DIC川村記念美術館学芸員。専門は近現代美術史と写真史。近年の主な企画に、「描く、そして現れる―画家が彫刻を作るとき」(DIC川村記念美術館、2019)、「美術は語られる―評論家・中原佑介の眼―」(同、2016)、「鏡と穴-彫刻と写真の界面」(ギャラリーαM、2017)、「ハイレッド・センター直接行動の軌跡」(松濤美術館、2008)など。主な著書に、『高松次郎 言葉ともの』(水声社、2011)、『写真、「芸術」との界面に』(青弓社、2006、日本写真協会学芸賞)、『安井仲治写真集』(共同通信社、2004、倫雅賞)など。
MITSUDA Yuri Curator, Kawamura Memorial DIC Museum of Art, specializing in modern/contemporary art history and history of photography. Recent exhibitions include ”Painting into Sculpture – Embodiment in Form” (Kawamura Memorial DIC Museum of Art, 2019), “Talking about Art – The Viewpoint of Yusuke Nakahara” (also at KMDMA, 2016), “Mirror Behind Hole: Photography into Sculpture“ (gallery αM, 2017), and “Hi-Red Center: "The Documents of ‘Direct Action’” (Shoto Museum of Art, 2008). Among her published writings are Words and Things: Jiro Takamatsu’s issue(Suiseisha, 2011),Shashin, “geijutsu” to no kaimen ni[Photography, in its interface with “art”] (Seikyusha, 2006; winner of the Photographic Society of Japan AwardsScholastic Achievement Award), and Nakaji Yasui photographer 1903–1942(Kyodo News, 2014, Ringa Prize).
中村史子|NAKAMURA Fumiko
愛知県美術館学芸員。専門は視覚文化、写真、コンテンポラリーアート。担当した主な展覧会に「これからの写真」(2014)、「魔術/美術」(2012)、「放課後のはらっぱ」(2009)など。また、若手作家を個展形式で紹介する「APMoA Project, ARCH」を企画し、伊東宣明(2015)、飯山由貴(2015)、梅津庸一(2017)、万代洋輔(2017)を紹介。2017年にはタイでグループ展「Play in the Flow」を企画、実施。
NAKAMURA Fumiko Curator, Aichi Prefectural Museum of Art, specializing in visual culture, photography and contemporary art. Responsible for exhibitions including “Photography Will Be” (2014), “Art as Magic” (2012) and “In the Little Playground” (2009), as well as for planning “APMoA Project, ARCH” presenting young artists in a solo show format, which to date has featuredItohNobuaki (2015), Iiyama Yuki (2015), Umetsu Yoichi (2017) and Bandai Yosuke (2017). In 2017, she planned and implemented the group show “Play in the Flow” in Thailand.
-----------------
<Unknown Image Series no.8 展覧会>
未知のイメージを創出する
イメージが持つ力と本質を探り、未知のイメージを創出する。
この世界においては、日々膨大なイメージが生まれては消えていくが、ときに稀有なイメージが出現する。今回の参加アーティストは、三田村光土里、横山奈美、鈴木のぞみ、山元彩香、庄司朝美の5名。連続する個展の形式をとる。各回のトークイベントとテキストのゲストには、光田由里、梅津元、飯田志保子、中村史子、中尾拓哉らを招く。 シリーズの終了後にはバイリンガルの記録集を制作し、本というメディアにおいても新たな表現の展開をはかっていく。
女性たちがつくるイメージ
Unknown Imageのシリーズは、イメージをテーマに、今、注目すべきアーティスト一人一人の作品とその世界を深く掘り下げ、その可能性をさらに見出していく場でもある。今回は、はからずも全員が女性アーティストとなった。
初回の山元彩香は、言葉の通じない国で神秘的なまでの美しさと暴力性をもつポートレートを撮影する。被写体の名前や意識すら剥ぎ取り、空の器にしようとしても残るものとはなんなのか。鈴木のぞみは、写真や時間の原理の静かな探求者である。生命なき事物に「視線」と「記憶」を出現させ、写真に身体のようなものを与える。横山奈美は、絵画の大きな歴史と私的な小さな歴史を交錯させ、日常の取るに足らないものたちの美しさや、明るく輝くものの背後にある存在を描き出す。庄司朝美の描線は、舞台のように見る人を引き込む物語性と、生命と死のエネルギーに満ちた身体的絵画空間をつくり出す。三田村光土里は、このシリーズではもっともキャリアの長いアーティストである。ごく私的なイメージや言葉の数々は、写真、映像、オブジェ、ドローイング、インスタレーションとなるが、それらは個人の物語やアートの枠組みを越えて普遍性を帯び、見る人の心を捉えて離さない。そして、ゲストは性別や年代は幅広いが、いずれも芸術の発生の現場において、極めて優れた批評の言葉を紡いできた方々である。
美術史において、かつて周縁の存在であった女性アーティストたちは、今、最先端にいる。彼女たちがつくるイメージはどのようなものなのか。なぜそれを生み出さねばならなかったのか。参加者の出自やキャリア、テーマ、歴史や現在の状況との向き合い方、その目指すところも様々である。だが、彼女たちの存在と彼女たちがつくるイメージは、それぞれに強く鮮やかだ。その未知のイメージは見る人を深く静かに揺るがし、世界に多様な変化を生み出す力ともなっていくだろう。
<Unknown Image Series no.8 exhibitions>
Creating unknown images
Exploring the power and essence possessed by images, to create unknown images.
A vast number of images are generated every day in this world, only to vanish, but just occasionally, some extraordinary images do emerge. The artists in this eighth Unknown exhibition are Mitamura Midori, Yokoyama Nami, Suzuki Nozomi, Yamamoto Ayaka, and Shoji Asami, who will stage consecutive solo shows. Those serving as guests for the talk events for each of these shows, and providing the texts, will include Mitsuda Yuri, Umezu Gen, Iida Shihoko, Nakamura Fumiko, and Nakao Takuya. After the series is finished a bilingual document will be produced, thus extending the exhibition into another form of expression, that of the book.
Images made by women
The Unknown Image series is also an opportunity to delve deeply into the individual work of some of today’s most noteworthy artists and their worlds, identifying further possibilities for each. This time, albeit not by design, all the artists are female.
Yamamoto Ayaka, featured in the first of the exhibitions, travels to countries where she does not speak the language, and takes portrait photographs suffused with a beauty and violence verging on the mystical. What is it that remains even when everything is stripped from her subjects, down to their names and consciousness, in an attempt to turn them into empty vessels? Suzuki Nozomi is a quiet explorer of the principles of photography and time. Endowing non-living things with a “gaze” and “memory” she gives her photos something like a physical body. Yokoyama Nami blends the vast history of painting and small personal histories to depict the beauty of everyday, insignificant things and what lies behind the bright and shiny. Shoji Asami’s lines create a narrative quality that draws the viewer in like a stage, and a corporeal painterly space suffused with the energy of life and death. Mitamura Midori is the artist in this series with the longest career. Her many very personal images and words are presented in photographs, videos, objects, drawings and installations, that go beyond individual stories or the confines of art, taking on a universal quality that irrevocably captures the heart of the viewer. The guests, meanwhile, are a varied lineup in terms of age and gender, but all individuals on the frontlines of art creation, of superb critical talent.
Once a marginal presence in art history, female artists are now at its cutting edge. What kind of images do these artists make? Why have they felt the need to produce them? The artists participating in these exhibitions have different origins and career trajectories, different ways of engaging with their themes, with history and current circumstances, and different aims. Yet their presence, and the images they create, are without exception strong and vibrant. Their unknown images will quietly shake the viewer to the core, and likely serve as a force for many types of change in the world.
----------------
<Unknown Image Seriesno.8個展スケジュール>
#1|山元彩香 [会場]void+ 2019年11月1日(金)―30日(土) トークイベント:11月29日(金)19:00-20:30 山元彩香+光田由里(DIC川村記念美術館学芸員)+中村史子(愛知県美術館学芸員)
YAMAMOTO Ayaka @void+ Friday, November 1 – Saturday, November 30, 2019 Talk event: Friday, November 29 19:00–20:30 YAMAMOTO Aya + MITSUDA Yuri (Curator, Kawamura Memorial DIC Museum of Art)+ NAKAMURA Fumiko (Curator, Aichi Prefectural Museum of Art)
#2|鈴木のぞみ [会場]void+ 2020年夏(予定) トークイベント: 鈴木のぞみ+梅津元(埼玉県立近代美術館学芸主幹/芸術学)参加予定 テキスト執筆:梅津元
SUZUKI Nozomi @ void+ Summer 2020 (TBD) Talk event:SUZUKI Nozomi + UMEZU Gen (Curator, The Museum of Modern Art, Saitama / Art Studies) TBC Text: UMEZU Gen

鈴木のぞみ《光の独白》2015ミクストメディア ©️SUZUKI Nozomi
#3|庄司朝美 [会場]HIGURE 17-15 cas 2020年9月(予定) トークイベント:庄司朝美+光田由里(DIC川村記念美術館学芸員)
SHOJI Asami @ HIGURE 17-15 cas September 2020 (TBD) Talk event:SHOJI Asami + MITSUDA Yuri (Curator, Kawamura Memorial DIC Museum of Art)

庄司朝美《18.10.23》2018 アクリル板に油彩 画像提供:損保ジャパン日本興亜美術館
#4|横山奈美 [会場]void+ 2021年5月(予定) トークイベント:横山奈美+飯田志保子(キュレーター)
YOKOYAMA Nami @ void+ May 2021 (TBD) Talk event:YOKOYAMA Nami + IIDA Shihoko (Curator)

横山奈美《Cross》2019 麻布に油彩 Photo by WAKABAYASHI Hayato
#5|三田村光土里 [会場]HIGURE 17-15 cas 2021年(予定) トークイベント:三田村光土里+中尾拓哉(美術評論家)
MITAMURA Midori @ HIGURE 17-15 cas 2021 (TBD) Talk event:MITAMURA Midori + NAKAO Takuya (Art critic)
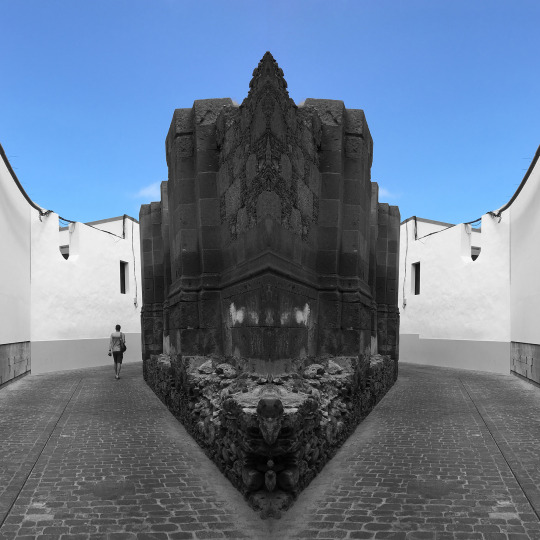
三田村光土里《ここにいなければどこかにいる》2018 ピグメントプリント ©︎ MITAMURA Midor
<その他参加作家プロフィール>
鈴木のぞみ| SUZUKI Nozomi
1983年 埼玉県生まれ。東京藝術大学大学院 美術研究科 博士後期課程在学中。何気ない日常の事物に潜む潜像のような記憶の可視化を、写真の原理を通して試みている。現前しているが不在であるという性質を持つ写真を事物に直接定着することで、写真に触覚的な身体のようなものが付与され、過ぎ去りゆく時をいまここに宙づりにする。近年の主な展示に「あした と きのう の まんなかで」(はじまりの美術館、2019)、「MOTサテライト2018 秋 うごきだす物語」(清澄白河、2018)、「無垢と経験の写真 日本の新進作家vol.14」(東京都写真美術館、2017)、「NEW VISION SAITAMA 5 迫り出す身体」(埼玉県立近代美術館、2016)など。受賞歴多数。現在、ポーラ美術振興財団在外研修員としてイギリスにて研修中。
SUZUKI Nozomi Born 1983 in Saitama, Japan.Currently in the doctorate course of Intermedia Art at Tokyo University of the Arts.Attempts to visualize, through the principles of photography, the memories resembling latent images submerged in innocuous everyday objects. Fixing photographs, which have the characteristic of being present yet absent, directly to objects, assigns photographs something like a tactile body, suspending passing time in the now. Recent group exhibitions include “In the middle of tomorrow and yesterday” (Hajimari Art Center, 2019), “MOT Satellite 2018 Fall: To Become a Narrative” (Kiyosumi-Shirakawa, 2018), “Photographs of Innocence and of Experience: Contemporary Japanese Photography vol.14” (Tokyo Photographic Art Museum, 2017), and “New Vision Saitama 5: The Emerging Body” (The Museum of Modern Art, Saitama, 2016). Among her many awards, she was recipient of the POLA Art Foundation Grant for Overseas Research in 2018, under which she is currently studying in the UK.
庄司朝美| SHOJI Asami
1988年 福島県生まれ。2012年 多摩美術大学大学院 美術研究科 絵画専攻版画領域修了。「線が引かれる。それは必ずしも天と地を分割するような境界線ではなくて、地を這う生き物が砂/泥へ残した痕跡のような、動くことで開かれていく空間がある。私たちは誰かの想像した世界を連綿と引き継いで生きている。」庄司の絵画には特定の物語がないにも関わらず、見る人はそこに様々な物語を見出す。また、絵画の空間的体験によって、自由な身体感覚が循環する生きた絵画空間が誕生する。主な個展に「明日のまみえない神話」 (gallery21yo-j、2019)、「泥のダイアグラム」(Cale、2018)、「劇場の画家」(gallery21yo-j、2017)、「夜のうちに」(トーキョーワンダーサイト渋谷、2017)などがある。「FACE2019」損保ジャパン日本興亜美術賞で大賞受賞。
SHOJI Asami Born 1988 in Fukushima, Japan. Earned her MFA in printmaking in 2012 from Tama Art University (Tokyo). ”A line is drawn. It is not necessarily a borderline of the kind dividing heaven and earth, but perhaps a space that opens up through movement, like that of a creature that crawls along the ground, leaving a track in sand or mud. In our lives we are continuously inheriting a world imagined by someone.” Despite not having a specific narrative, Shoji’s paintings reveal various stories to the viewer. They also spawn a living painterly space of circulating free physical sensation, through the spatial experience of painting. Solo shows include”Tomorrow’s Unseen Mythologies” (gallery21yo-j, 2019), “Diagram of the Mud”(Cale, 2018), “A Painter in the Theater” (gallery21yo-j, 2017), and “During the Night” (Tokyo Wonder Site, Shibuya,2017). Grand Prix winner at the “FACE 2019” Sompo Japan Nipponkoa Art Awards.
横山奈美 | YOKOYAMA Nami
1986年 岐阜県生まれ。2012年 愛知県立芸術大学大学院 美術研究科 油画版画領域修了。捨てられる寸前の身の回りの物や、ネオン管の裏側に隠された器具や配線といった主役にはならないものに光を当てることで、そのものが持つ役割の枠を取り払い、すべてのものに備わる根源的な美しさと存在意義を表現する。近年は、「LOVE」の意味を問いかける油画とドローイングを続けて発表している。主な展示に、アペルト10「LOVEと私のメモリーズ」(金沢21世紀美術館、2019)、「日産アートアワード2017」(BankART Studio NYK)、「手探りのリアリズム」(豊田市美術館、2014)、「Draw the World-世界を描く」(アートラボあいち、2013)など。 主な受賞に「日産アートアワード2017オーディエンス賞」などがある。
YOKOYAMA Nami Born 1986 in Gifu, Japan. Earned her MFA in painting in 2012 from Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music. By shining a light on things that never take center stage, such as familiar objects in the moment before their discarding, and the fittings and wiring hidden behind neon signs, Yokoyama does away with the parameters of the roles played by these things to express the fundamental beauty and raison d’etre possessed by all things. Her recent drawings and paintings continue to question the meaning of love. Solo and group exhibitions include “Aperto 10: Memories of Love and Me” (21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, 2019), “Nissan Art Award 2017” (BankART Studio NYK), “Reaching for the Real” (Toyota Municipal Museum of Art, 2014),and “Draw the World” (Art Lab Aichi, 2013). Recipient of the Nissan Art Award 2017 Audience Award.
三田村光土里| MITAMURA Midori
1964年 愛知県生まれ。1994年 現代写真研究所 基礎科修了。「人が足を踏み入れられるドラマ」をテーマに、日常の記憶や追憶のモチーフを、写真や映像、日用品、言語など様々なメディアと組み合わせ、私小説の挿話のような空間作品を国内外で発表。近年の主な個展に、グラン・カナリア(スペイン)での「If not here, then I'm somewhere else」(Galeria Manuel Ojeda、2018)、「Art & Breakfast」(CAAM – Atlantic Center of Modern Art、2017)がある。展覧会ではイギリスの「フォークストン・トリエンナーレ2017」関連企画「Leaving Language」、国内では、「あいちトリエンナーレ 2016」(愛知芸術文化センター)など。2019年にはウィーンで、日本−オーストリア国交150周年記念展「Japan Unlimited」に参加。
MITAMURA Midori Born 1964 in Aichi, Japan. Completed the fundamentals course at The Institute of Contemporary Photographyin 1994. Taking as her theme “dramas that people can step into,” Mitamura combines motifs of everyday memories and reminiscences with various media such as photography and video, household goods and language, presenting in Japan and further afield spatial works that resemble an episode of an autobiographical novel. Recent solo exhibitions include ”If not here, then I'm somewhere else.” (Galeria Manuel Ojeda, 2018) and “Art & Breakfast” (CAAM – Atlantic Center of Modern Art, 2017)both in Gran Canaria, Spain. Among her group show participations are “Leaving Language,” a collateral program of the Folkestone Triennial 2017in the UK, and Aichi Triennale 2016 (Aichi Arts Center) in Japan. In 2019, she will participate in “Japan Unlimited,” an exhibition staged in Vienna commemorating 150 years of friendship between Austria and Japan.
<その他ゲストプロフィール>
梅津元|UMEZU Gen
埼玉県立近代美術館学芸主幹。専門は芸術学。同館での主な企画(共同企画を含む)に「DECODE/出来事と記録ーポスト工業化社会の美術」(2019)、「版画の景色 現代版画センターの軌跡」(2018)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相ー大地》が生まれるまで」(2005)、「ドナルド・ジャッド1960-1991」(1999)、「<うつすこと>と<見ること>ー意識拡大装置」(1994)など。ギャラリーαMでの企画に「トランス/リアルー非実体的美術の可能性」(2016-17)がある。美術手帖や展覧会カタログなどに寄稿多数。
UMEZU Gen Curator, The Museum of Modern Art, Saitama, specializing in art studies. Exhibitions he has organized/co-organized at MOMAS include ”DECODE / Events & Materials: The Work of Art in the Age of Post-Industrial Society” (2019), “A View of Prints: Trajectory of the Gendai Hanga Center” (2018), “100th Birth Anniversary, Q Ei” (2011), “Artist Project: Toward the Emergence of Sekine Nobuo’s Phase – Mother Earth” (2005), “Donald Judd 1960–1991” (1999), and “Visualization in the End of the 20th Century” (1994), as well as “Trans / Real: The Potential of Intangible Art” (2016-17,Gallery αM). He has contributed a great number of essays to the art magazine Bijutsu Techo, as well as to art catalogues and books.
飯田志保子|IIDA Shihoko
キュレーター。1998年の開館準備期から2009年まで東京オペラシティアートギャラリーに務める。主な企画に「ヴォルフガング・ティルマンス―Freischwimmer」(2004)、「トレース・エレメンツ―日豪の写真メディアにおける精神と記憶」(東京オペラシティアートギャラリー、2008/パフォーマンス・スペース、シドニー、2009)など。2009-2011年クイーンズランド州立美術館/現代美術館で客員キュレーター。その後、国際展のキュレーターを歴任。2014年度から17年度まで、東京藝術大学美術学部准教授。「あいちトリエンナーレ2019」ではチーフ・キュレーターを務める。
IIDA Shihoko Curator. Worked at Tokyo Opera City Art Gallery from 1998, when it was preparing for inauguration, until 2009, where her major exhibitions included “Wolfgang Tillmans: Freischwimmer” (2004) and “Trace Elements: Spirit and Memory in Japanese and Australian Photomedia” (2008/Performance Space, Sydney, 2009). She was a visiting curator at Queensland Art Gallery/Gallery of Modern Art in Brisbane from 2009 through 2011, and has since co-curated successive international art exhibitions. Associate professor at Tokyo University of the Arts for the academic years 2014–2017. She was Chief Curator (Head of Curatorial Team) of Aichi Triennale 2019.
中尾拓哉|NAKAO Takuya
美術評論家。博士(芸術)。近現代芸術に関する評論を執筆。特に、マルセル・デュシャンが没頭したチェスをテーマに、生活(あるいは非芸術)と制作の結びつきについて探求している。2014年に論考「造形、その消失においてーマルセル・デュシャンのチェスをたよりに」で『美術手帖』通巻1000号記念第15回芸術評論募集佳作入選。2017年に単著『マルセル・デュシャンとチェス』を平凡社より出版。主な論考に「50年あるいは100年後の鑑賞者ー日本・マルセル・デュシャン論再考」(��美術手帖』2019年2月号)など。
NAKAO Takuya Art critic. PhD in art. Writes criticism on modern and contemporary art. In particular, has been exploring the connections between living (or non-art) and creative practice from the perspective of chess, in which Marcel Duchamp was also engrossed. His 2014 essay, “The Plastic, in Disappearance: From Marcel Duchamp’s Chess” received honorable mention in the 15th (1000th Issue Commermorative) Bijutsu TechoArt Writing Competition. His book Marcel Duchamp and Chesswas published by Heibonsha in 2017. Recent published writings include “One’s Public, Fifty or One Hundred Years Later: Reconsidering Marcel Duchamp Studies in Japan”(Bijutsu Techo, February 2019).
--------
photo: Ayaka Yamamoto, “organ”, 2019
1 note
·
View note