#胸元に白い毛の模様
Explore tagged Tumblr posts
Text
"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消���神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦��替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍
“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
193K notes
·
View notes
Text
【小説】非・登校 (上)
目覚まし時計が鳴る前に起きることができた朝の、清々しさったらない。
階段を降りて行くと、ママが僕を見てにっこりと微笑んだ。
「あら、今日は早いのね。朝ご飯、すぐに用意するわね」
自分でできるから大丈夫だよ、と返事をしたが、ママは忙しそうに白いエプロンを揺らして奥のキッチンへと消えてしまう。僕の頭上では、三階の天井から吊り下げられたシャンデリアが、東向きの窓から射し込む日光にきらきらと輝いている。完璧な一日が始まる予感がした。そんな朝だった。
ダイニングではパパがコーヒーを飲みながら朝刊を読んでいた。
「おはよう。今日は早いんだな」
そう言うパパも、いつものようにパジャマ姿ではない。背広を着て、もうネクタイまで締めている。
「パパも早いね」
「うん。今日は、大事な商談があるんだ」
ショウダンというのがなんなのか、僕にはよくわからないけれど、それがある日はパパが気合いを入れていることはわかる。パパの気合いというのはその前髪の形に表れているのだと、いつだったか、ママがこっそり教えてくれた。今日のパパは前髪をオールバックにしていたから、これは気合いマックスってことだ。初めてママに出会った日も、パパはこの髪型をしていたと聞いた。
「そう言うケイタは? 今日は何か大事な予定があるのか?」
「まぁね」
僕はそう言いながらコーンフレークの袋を手に取ろうとしたが、そこにママが颯爽と現れて、「ほらほらケイちゃん、用意できたわよ」と言いながら、トーストと、ハムエッグの皿をテーブルに並べた。
「自分で用意できるって言ったのに」と、僕は肩をすくめてコーンフレークを棚に戻し、それから「もう、ケイちゃんって呼ぶの、やめてよ」と言うべきか、一瞬悩んだ。しかし、そうしている間にも、ママは「オレンジジュース持って来るわね」と、再びキッチンへと消えてしまった。
トーストにバターを塗り、ハムエッグを頬張っている間にオレンジジュースが運ばれてきて、最後に残り物のポテトサラダがちょこんと皿に盛られて��かれた。それらを順番に咀嚼して、「ごちそうさまでした」と手を合わせた僕は、歯を磨くために洗面所へと向かう。
歯ブラシに赤と青と白の三色歯磨き粉を捻り出していると、階段を降りて来る緩慢な足音が聞こえた。
「リスコ、起きたのか? おはよう」
階段に向かってそう声をかけると、僕の妹はまだ眠たそうな声で返事をする。
「ケイタにいちゃん、おはよー」
リスコは寝起きがあまり良くないが、この時間に一階へ降りて来たということは、今日はまぁまぁ、上出来な方だった。僕は歯ブラシを小刻みに動かしながら、廊下の柱時計を見やる。今日は僕も、良いペースだ。口をゆすぎ、洗面所を出る。
ランドセルは昨日のうちに、玄関先に用意してあった。お気に入りのマッドシューターのスニーカーもばっちりだ。ランドセルを背負い、靴を履いて爪先をとんとんしていると、ママが出て来て僕を見送ってくれた。
「気を付けて行ってらっしゃい」
僕がもっと小さかった頃は、出掛ける前にいつもハグしてキスしてくれたママだけど、さすがに最近はするのをやめてくれるようになった。僕はそれが、自分がたくましくなったような気がして、少し誇らしい。
行ってきます、と手を振って家を出た。
今日はいつもより時間が早いから、まだハカセもボーロも通学路に出て来ていない。いつもならそのふたりと一緒に登校しているが、今日は僕ひとりで学校へ向かうつもりだ。ふたりを早い時間に付き合わせるのは申し訳ないような気がしていたし、そしてそれ以上に、他の誰にも知られたくない、僕だけの秘密でもあったからだ。
どんなに仲の良い友達にだって、秘密にしておきたいことがあるのは、別におかしなことではないはずだ。
今はすっかり葉桜となった桜並木を黙々と歩く。ひとりで歩く通学路は退屈なはずだったが、今の僕はこの後に待つ出来事が楽しみで仕方なかった。ハカセやボーロと昨日観たテレビの話をしたり、僕たちが異様なほどに熱中しているテレビゲーム、スターストレイザーの進捗を確認したりすることができなくても、胸の奥がわくわくして、羽でも生えたかのように足取りは軽い。
小学校の校門をくぐると、登校してきた児童の姿はまだまばらだった。僕は早足で広い校庭を横切り、昇降口で靴を脱いだ。上履きに履き替えながら、もう完璧に位置を把握している、ナルミヤの下駄箱を横目で確認するのも忘れない。
僕の予想通り、ナルミヤの黒いエナメルのスニーカー、ブラックキュートの最新モデル(らしい。妹��リスコがそう言っていた)は、すでに下駄箱に納まっていた。やはり、もう登校しているのだ。五年二組の靴箱をざっと見渡してみたが、他に登校してきたクラスメイトはまだいないようだった。僕は心の中でガッツポーズをする。
三階の教室まで向かう。急いで来たようには感じさせず、眠たそうにも見せず、クールに、自然に。シャツの襟が折れていないか、袖口が汚れていないか確認しながら、階段を一段一段、登って行く。
三階の廊下にずらりと並ぶ教室は、灯かりが点いているクラスが半分くらいだった。まだ登校してきた児童が少ないのだ。僕が目指す五年二組の教室は、廊下から電気が点いているのが見えた。閉まっているドアを引く。大きな音を立てないように、かと言って、あまりにもそろそろと開けるのでは不自然だ。
「あれ? おはよう、ケイタくん」
僕の予想通り、ナルミヤはすでに教室にいて、水を交換してきたばかりらしい、ロッカーの後ろに花瓶を置いているところだった。
「おはよう。日直の時、ナルミヤはいつも早いね」
「そう言うケイタくんこそ、どうしたの。もしかして、日直の当番の日、間違えちゃったの?」
「あはは、そうじゃないよ。一時間目の国語、今日は漢字のテストでしょ? でも、うっかり漢字ドリルを持って帰るの忘れちゃってさ」
自分の机にランドセルを置きながら僕がそう言うと、ナルミヤは目を丸くして、それから小さく、ふふっと笑った。
「ケイタくん、いつも置き勉してるんだ、いけない子だね」
そう言う彼女の口調には、僕を蔑むでもなく咎めるでもなく、不思議とどこか楽しそうな、嬉しそうな、そんな響きがあった。僕にはきょうだいが妹しかいないが、もしも姉がいたらこんな感じだったのかもしれない、なんて思う。同級生のナルミヤを姉のように思うのは、少しおかしいのかもしれないが。
しかしナルミヤは、このクラスで一番、大人びている。透き通るような白い肌も、まっすぐに伸びた毛先の揃った長い髪も、誰かの冗談に口元を緩めるようにして笑う様も、その時の見守るような優しい眼差しも、とても僕らと同じ年に生まれたのだとは思えない。
彼女の細い指先は、教室のオルガンを優美に奏で、花の絵に繊細な色を塗り、習字の時間には力強くも整った字を書き、授業の板書を美しくノートに写していく。僕はナルミヤと同じクラスになって、すぐに彼女の魅力に気が付いた。そしてこのことは、僕だけの秘密にしておこうと決めた。
僕は自分の席で漢字ドリルを取り出し、漢字を覚えようとしている振りをしつつ、ナルミヤのことを眺めた。彼女は僕に背を向けて、黒板に新しいチョークを並べていた。今日もいつものように、水色の水玉模様のパッチンヘアピンが、彼女の左耳の上、艶やかな黒い髪に留まっている。
日直になると、朝と帰りに��番の仕事をこなさなくてはいけない。朝は教室の花瓶の水を取り替えたり、植木鉢に水をやったり、生き物を飼っているクラスでは餌をあげたりする。それから、黒板に新しいチョークを並べて、黒板消しを綺麗にする。どれも時間のかかる仕事ではないから、普通に登校してきてからでも十分に間に合う。でもナルミヤは、日直の当番が回って来た日、いつもより早く登校して来て、その仕事をする。
そのことに気付いたのは、ナルミヤが前回、日直の当番になった時だった。学校に宿題を忘れて帰ってしまった僕は、翌日に早く登校して、そうして偶然にも、その事実を知った。だから今回は、僕も早く登校して、彼女が日直の仕事をこなすところを、こうして眺めることにしたのだ。
教室にいるのは、僕とナルミヤ、ただふたりだけ。
少しすれば、クラスメイトたちが登校してきて、教室はいつも通りのにぎやかな空間になる。ふたりだけでいられるのも、ほんの短い時間だ。何か今のうちに言っておくべき言葉を、僕は探そうとしたけれど、でもこの静けさを大切にしたいような気もする。
僕はパパの今日の前髪を思い出しながら、僕も気合いを入れた前髪にすべきだっただろうか、と思った。猛烈なアタックをしてママと結婚したパパは、ナルミヤとふたりきりでいるこの状況で何も話しかけない僕を見たら、「そんなんじゃ駄目だぞ」と怒るだろうか。でもママなら、僕の気持ちをわかってくれるかもしれない。おしゃべりが必要な訳じゃない。ただそこに居てくれるなら、それを見つめることが許されるなら、それだけで僕は満足した気持ちになる。それは、やるべきことがすべて終わって、家族におやすみを言って布団の中に潜り込む時のような、そんな気持ちに似ていると思う。
黒板消しを手に取ったナルミヤがこちらを振り向きそうな気がしたので、僕は目線を彼女から外して、手元の漢字ドリルへと向けた。
「ねぇケイタくん、こないだ聞いちゃったんだけど」
ナルミヤは黒板消しクリーナーのスイッチを入れながら、そう話しかけてきた。ナルミヤから話しかけてくるとは思っていなかった僕はびっくりして、思わず彼女の顔を見る。彼女は黒板消しにこびり付いているチョークの粉をクリーナーに吸い込ませている最中だった。ぶいいいいいいんという間抜けな音が、教室に響いている。
「ヒトシくんとキョウイチロウくんと、スタストの話、してたよね」
僕はその言葉に、再度びっくりさせられた。まさかナルミヤの口から、ヒトシやキョウイチロウやスタストの名前が出て来るとは、まったく思っていなかった。ヒトシというのはボーロの本名で、キョウイチロウはハカセの本名だ。スタストは僕たちがハマっているテレビゲーム、スターストレイザーの略称。
「う、うん。そうだけど……」
僕たちは教室でも廊下でも、スターストレイザーの話をよくしているから、どこかで会話を聞かれたのかもしれない。彼女が僕たちの話している内容を覚えていたということが、なぜか少し嬉しかった。
「ケイタくんもやってるの? スタスト」
「やってるけど……」
「ケイタくんは、強い?」
ナルミヤが黒板消しクリーナーを止めた。教室は再び静かになる。
ナルミヤが僕を見ていた。彼女の大きな瞳。ふたつのそれが僕を見ていた。その目に、もっと見つめてほしいと思う気持ちと、お願いだからこれ以上見つめないでほしいと思う気持ち、その両方が湧き上がった。
「ねぇ、ケイタくんは強いの?」
「えっと……弱くはないと思うけど、僕よりもキョウイチロウの方が強いよ。キョウイチロウが考えてきた攻略方法を、僕たち三人で検証してるんだ」
「トチコロガラドンが倒せないの」
トチコロガラドンは、スターストレイザーに出て来る敵モンスターの名前だ。その名前を知っているということは、「倒せない」ってことは、まさか。
「もしかして、ナルミヤもスタストやってるの?」
僕の問いかけに、彼女は小さく頷いた。意外だった。ナルミヤがテレビゲームをしているところを、僕はまるで想像できていなかった。彼女がクラスメイトとテレビゲームの話をしているところを、少なくとも僕は聞いたことがない。
「……私がゲームするなんて、変かな?」
僕は慌てて首を横に振った。
「変じゃないよ。ただ、少しびっくりしたものだから」
スターストレイザーは、いかにも女子が好きそうな、洋服を集めて着せ替えするゲームでも、畑で作物を育てて収穫するゲームでも、家を建てて家具を並べるゲームでもなく、宇宙から飛来する巨大で不可思議な敵を殺していくゲームだ。このクラスでスタストを遊んでいるという話を聞いたことがある女子はいないし、男子だって、全員がプレイしている訳じゃない。いや、女子だとヒナカワがプレイしているらしいけれど、あいつは筋金入りのオタクだから、特殊なケースだろう。
僕とボーロだって、ハカセから、「このゲーム面白いよ、皆でやろうよ」と言われるまで、そんなゲームが発売になったことすら知らなかった。テレビでコマーシャルが流れることもなかったし、電器屋さんにソフトを買いに行った時も、ゲームコーナーの新発売の棚の隅っこに、ぽつんと置いてあっただけだ。そんなマニアックなゲームを、ナルミヤが遊んでいただなんて。
スターストレイザーは、発売から半年以上経った今も、攻略本という物が発売されていない。十二人の操作キャラクターと十二種類の使用武器をプレイするたびに自由に選択することができ、どれを選択するかによって戦略が変わってくる。ひとりでもプレイすることができるが、インターネットを介したマルチプレイにすれば、戦略の幅が大きく広がり、同じ敵でも倒し方は数十通りあり、どのように倒したかによってストーリーが細かく分岐していく。だから僕とハカセとボーロは、いつも「どの敵をどう倒したらストーリーがどうなったのか」を報告し合って検証し、ゲームクリアに向けて最適解の近道を模索している。
「トチコロガラドンが、いつも第八都市を壊滅させちゃって、そこでゲームオーバーになっちゃうんだよ」
「第八都市は、壊滅させるしかないんだ」
「え……?」
僕の答えに、ナルミヤは大きな瞳を真ん丸にした。
「あれって、都市を壊滅させるのが正解なの?」
「そう。僕と、ハカセ……キョウイチロウとヒトシと、三人で何度も調べたけれど、どう隊列を組んで戦略を練っても、最終的に第八都市は壊滅する。だから、トチコロガラドンを倒すための本拠地を第八都市ではなくて隣の第七都市に置いて、そこから出撃するしかない。第八都市は、見捨てるしかないんだ」
これは僕たち三人だけで辿り着いた結論ではなく、ハカセの家のパソコンでインターネットの掲示板を見た時も、同じ結論が導き出されていた。世界じゅうの、顔も知らないプレイヤーたちもまた、同じように見つけ出した答えなのだ。「絶対に何か他の戦略があるはずだ」と検証しているプレイヤーは今もいるが、第八都市を陥落させずにトチコロガラドンを倒したという声は、確認した限り、まだない。
「そうだったんだ……。私、てっきり都市を守り抜くのがあのゲームのルールなのかと思ってた……。そうなんだ、見捨てるしかないんだね」
驚きつつも、小さく頷きながらナルミヤはそう言って、それから微笑んだ。
「全然知らなかった、すごいね、ケイタくん。教えてもらって良かった。今日家に帰ったら、早速やってみるね」
そう言うナルミヤの笑顔があまりにも嬉しそうで、僕もなんだかとても嬉しくなって、そして同じくらい、胸が苦しい感じがした。でもその苦しさが、本当はちっとも嫌じゃなくて、むしろ心地良くて、僕はそんな風に、嬉しくなるような苦しさを感じたことが初めてで、一体どうしたら良いのか、ナルミヤになんて言えば良いのか、わからなくなった。
そこで教室のドアががらりと開いて、クラスメイトたちが数人、教室にぞろぞろと入って来た。登校してきたクラスメイトと「おはよー」の挨拶を交わしたところで、ナルミヤはくるりと僕に背を向けて、綺麗になった黒板消しを置き、新しいチョークをてきぱきと並べてから、廊下に出て行った。日直の仕事を終えて、廊下の水道に手を洗いに行ったのだろう。
その後も続々とクラスメイトたちが登校して来て、教室の中はいつも通りのにぎやかさになった。ハンカチで手を拭きながら帰って来たナルミヤは、僕の席の方に来ることはなく、自分の席に戻ってしまった。僕は彼女との会話が終わってしまったことを名残惜しく思った。
でも今日の短い会話で、ナルミヤと共通の話題ができたことは大きな収穫だった。今度一緒にスタストをやろうよ、と声をかけてみようか。僕がナルミヤの家を訪ねるのと、彼女にうちへ来てもらうの、どっちの方が良いんだろう。
本当は、トチコロガラドンの攻略方法だって、あんなあっさり教え���のではなく、「今度、僕が一緒に倒してあげる」とでも言えば良かったのかもしれない。僕のパパだったら、きっとそうしただろう。僕たちが何度も挑戦して掴み取った倒し方を、簡単に教えてしまうのではなくて、ナルミヤと一緒に検証しても良かったはずだ。僕はそのことを少し、今になって後悔した。
「あ、ケイタ! やっぱり、先に学校に来てたんだな!」
そう言いながら教室に飛び込んで来たのはボーロで、その後ろから、
「ひどいよケイタくん、ひとりで先に行っちゃうなんて!」
と、文句を言ってきたのはハカセだった。
「ごめんごめん、漢字ドリル、学校に置いてきちゃってさ」
僕はそう謝ってみたけれど、ボーロの目は吊り上がっているし、ハカセの顔は泣き出しそうだった。親友ふたりの僕への非難は、先生が教室に入って来て、「さぁ皆、自分の席に着いて」と言うまで続いた。僕はふたりの話を聞いているふりをしながら、途中何度か、ナルミヤを見つめていたのだけれど、彼女は僕には気付いていないようで、一度もこちらを見る���とはなかった。
「朝の会を始めましょう。今日の日直はナルミヤさんね、お願いします」
先生にそう促され、ナルミヤの凛とした声が、朝の教室に響き渡る。
「起立」
椅子をがたがたと鳴らしてクラスメイトたちは起立する。僕も立ち上がりながら、「今度、一緒にゲームをしよう」と、放課後にナルミヤを誘ってみよう、と決めた。
ナルミヤとふたりで秘密の攻略方法を発見することができたら、どんなに幸せだろうか。もしかしたら誰も発見することができなかった、第八都市を壊滅させないでトチコロガラドンを倒す方法が、ナルミヤとだったら見つかるかもしれない。彼女を見ているとそんな風に、僕はなんでもできるような気分になってしまうのだ。
と、いうのはすべて、僕の妄想だ。
現実の僕は、廊下の床に片頬をつけたまま、中途半端に閉められたカーテンの隙間から射し込んで来る、冷たい光を見ていた。光を見てそれを冷たいと感じるのは、光がカーテンの青色を透過して部屋じゅうが青っぽく見えるからなのかもしれないし、もしくは僕が布団どころかカーペットさえ敷かれていない、冷え切った廊下に横になっているからかもしれない。
眩しさに目を細めながら、寝ぼけたままの僕はその光が朝陽だと理解して、室内の壁にかかっている時計へと目を向けた。時計の示す時刻と部屋の中の明るさは、午前中だとしたらあまりにも暗く、午後だとしたらあまりにも明るく、それを妙に思うよりも早く、秒針が動いていないことに気が付いた。昨日の夜に止まったままになっているのであろう時計から目線を逸らし、「電池を交換しなきゃ」と思ったものの、電池がどこにあるのかわからない。そこで、この家に時計は壁のそれひとつだけだと思い出す。運良く新品の電池を見つけたところで、時計がそれしかないのだから、正しい時刻に合わせることもできない。
今は何時なんだろう。
せめて母親の携帯電話があれば、時刻を知ることができる。部屋の中をもう一度見渡してみたが、母親の姿もなければ、部屋の隅のローテーブルの上にいつも置かれている携帯電話も見当たらない。母親も携帯電話も、外出したまま、戻って来ていないようだ。
母親が不在であることに安堵と落胆が入り混じったような気持ちになりながら、僕は床から起き上がり、まずはトイレへ、それから洗面所へ向かった。トイレにも洗面所にも、その隣の脱衣所にも、浴室にも、家族は誰もいなかった。用を足して手を洗ってから顔を洗う。
洗面所の鏡には、皮脂にまみれた髪が額にべったりと貼り付いている僕の顔が映って、顔を洗うついでに蛇口の下にまで頭を突き出し、髪を濡らしてごしごし擦ってみたけれど、物事が好転したようにはまったく思えなかった。どこかにあるらしい傷に、水がしみて痛かった。
何日も着替えていない服からは饐えたような臭いがしていたし、手も足も少し擦るだけですぐに垢が剥がれ落ちた。もう何日間、風呂に入っていないんだろう。この部屋のガスが止められてからどれくらい経ったのか、思い出せない。今はこうしてトイレも使えるし顔も洗えているけれど、水道が止められる日も近いのかもしれない。
いつ洗濯したのかもわからない、黄ばんだタオルで濡れた髪を拭きながら洗面所を出た。さっきまで横になっていた廊下を踏みしめて部屋に入り、ローテーブルの下に転がっていた煙草の箱とライターを拾って、ベランダへ続く窓を開ける。
窓の鍵は開いたままになっていた。素足のままベランダに出て窓を閉めてから、箱から煙草を一本引き抜いて、口に咥えて火を点ける。息を大きく吸って鼻から煙を細く吐きながら、外が思っていたよりもずっと明るいことに気が付いて、もしかしたら、もうとっくに学校へ向かわなくてはいけない時刻になっているのかもしれない、と思った。
室外機の上に置かれた灰皿に灰を落としていると、アパートの下の通りをふたりの小学生男子がおしゃべりしながら歩いて来るのが見えたので、僕は咄嗟に、ベランダに置かれた目隠しパネルの陰に隠れるようにしゃがみ込んだ。そうすることで彼らから僕の姿は見えなくなり、僕からも彼らの姿が見えなくなったのだけれど、わざわざ顔を確認しなくても、僕はそのふたりが誰なのかを知っていた。同じクラスのハカセとボーロだ。
ハカセというのもボーロというのも、本名ではなく、あだ名だ。ハカセと呼ばれている、分厚いレンズの眼鏡を掛けた背が小さい男の子は、確かキョウイチロウというのが本名で、もうひとりの、ボーロと呼ばれている体格の良い坊主頭の男の子は、ヒトシというのが本名だ。ヒトシというよりフトシという感じだけれど、そう呼ぶと泣くまで殴られるので、誰も間違ってもそうは呼ばない。クラスメイトのほぼ全員が、ふたりのことをハカセ、ボーロを呼ぶので、僕はそのふたりの名字を思い出すことはもうできなかった。
ふたりは近所に住んでいるのか、仲が良いのか、登校の時間になるといつも決まって、おしゃべりしながらこのアパートの前の通りを南から北へと歩いて行く。朝から元気が良いことに、ふたりの会話はベランダにいる僕にまでよく聞こえてくる。
話の内容は、昨日観たテレビのことか、スタストとかいうゲームのことがほとんどで、ときどき、マッドシューターの最新モデルがかっこいいだなんて、スニーカーの話をしていたりする。今日はなんの話をしているのだろうと思いながら、目隠しパネルの陰で煙草を吸っていると、僕がそこにいることなんて知りもしない彼らが、いつも通りおしゃべりをしながら歩いて行く。
「なぁ、聞いたか? 昨日皆がしてた噂話」
「ナルミヤさんの話でしょ? あんなの信じられないよ。何か証拠があるのかなぁ」
「でもほら、火のないところにナントカって言葉もあるだろ。何にもないのに、ナルミヤがエンジョコーサイしてるなんて噂、出回る訳ない」
「あれって、ヒナカワが言い出した話だよね。ヒナカワってほら、ナルミヤさんと仲良くないじゃない。なんでヒナカワが、仲良くもないクラスメイトの秘密を知ってるのか、不思議に思わない?」
「なんだ? ハカセはナルミヤの噂が嘘だって疑ってるのか? 信じたくないって? なんだハカセ、お前、もしかしてナルミヤが好きなのか?」
「ち、違うよ! ただ僕は、ヒナカワがナルミヤさんを嫌いだから、あんな噂を広めたんじゃないかって思ってるだけで……」
「なんでヒナカワがナルミヤを嫌ってるってわかるんだよ?」
「だってほら……ナルミヤさんは美人だけど、ヒナカワはブスじゃ���……」
僕は短くなった煙草を灰皿に押し付けて、火を消してから立ち上がる。部屋に戻る頃には、ハカセとボーロの会話は聞き取れないくらい、ふたりはもう遠くへ行ってしまっていた。
一本抜き取ったことが判明しないことを願いながら、煙草とライターを元通りローテーブルの下に置き、それが不自然に見えないよう、あたかもずっとそこに転がっていたことを装うようにその角度を微調整してから、台所の方へと目を向けた。
電気を点けないといつも薄暗い台所は、窓の近くからでは中の様子がよく見えない。僕は意を決して、台所へと近付いた。食べられる物がほとんどなくなってしまって久しい台所は冷え切っていて、とても静かだ。冷蔵庫のコンセントはとっくの昔に引き抜かれているし、蛇口も長いこと捻られていない。
時計の秒針さえも止まってしまった今、家の中は恐ろしいほどに静かだった。ただじっとしているだけでは、この空気に取り込まれて、僕まで透明になってしまいそうな、そんな錯覚に陥りそうになる。僕は台所の入り口に立って、その薄暗がりの中を覗き込んでみた。
台所の床の上にはどす黒い色をした水溜まりが広がっていて、その中心には、僕の父親が倒れている。
たいした深さもないはずの水溜まりの真ん中で、溺れてもがいているかのように、こちらへ右手を伸ばしたまま、どこか遠くをじっと見つめたまま動かない父親は、もうかれこれ二日はこのままの状態で、脈を確かめるまでもなく、完全に絶命していた。心臓を刺し抜いているのであろう包丁の切っ先が、父親の背中から突き出していて、その汚れた銀色だけが、暗闇の中で妙にはっきりと見える。それはひどく恐ろしい光景だった。
怖いからなるべく見ないようにと過ごしてきたけれど、一度目を向けてしまうと、まるで縛り付けられたかのように身体が固まり、目線すら動かせなくなってしまう。ずっと見つめ続けたところで何も変化など起きないのに、僕は間違い探しでもしているかのように、目の前の光景を食い入るように見つめている。
ふと、父親の身体の下に広がっている水溜まりの中に、何かが転がっているのを見つけた。今まで何度か台所を覗き込んでいたけれど、それに気が付いたのは初めてだった。
あれはなんだろう。恐る恐る、水溜まりへと近付いた。その時、突然父親の右手が動いて僕の足首を掴んでくるところを想像してしまい、思わず悲鳴を上げそうになった。けれどそれは僕のただの妄想で、実物の父親はやはりぴくりとも動かない。明らかにこちらを見ている様子のない両目が、それでも僕を見つめている気がして、何度も父の顔を見てしまう。家にいる時はいつも父の機嫌を窺って過ごしていたけれど、死んでからも顔色を窺わなくちゃいけないことが急に馬鹿馬鹿しく思えてきた。それでも、一度想像してしまった恐怖から逃れることはできない。僕は怯えながら水溜まりに落ちている小さなそれを拾い上げる。
ねちょ、という感触がして、指に赤と黒の中間色のような色が付着する。「それ」も僕の指を汚したのと同じ液体がべったりとこびり付いていて、摘まみ上げた「それ」がなんなのか、最初はわからなかった。「それ」は小さくて、金属でできていて、何かを挟むような形状をしていた。
しばらく見つめているうちに、僕の目は「それ」にまだ汚れが付いていない部分があることを発見し、そしてそこに描かれているのが水色の水玉模様だと認識した時、僕はナルミヤのことを思い出した。
透き通るような白い肌、まっすぐ伸びた長い髪、大きな黒い瞳。ナルミヤは僕のクラスの一番美人な女の子で、いや、きっと、学校で一番の美人だ。けれど誰も、彼女が笑ったところを見たことがない。というのが、もっぱらの噂だった。
ナルミヤは笑わない。そして、人前で口を開くことはほとんどなく、開いたところでつっけんどんな、素っ気ない言葉が棘にまみれたような声音で吐き捨てられるだけなのだった。彼女がクラスメイトを見つめる時、それは眉をひそめるように細められた冷ややかな眼差しで、ぱっちりとした瞳が台無しに思える。ナルミヤの美しさは、男女問わず誰でも彼女と仲良くなりたくなるような、ずば抜けた輝きがあったけれど、当の本人がそういう具合でしか他人と関わろうとしないから、誰も彼女には近付かない。しかし誰ともつるもうとしないその姿勢が、彼女の美しさをより一層引き立てているように見えなくもない。
ナルミヤは孤高だ。クラスメイトの誰にも似ていない魅力が、彼女にはある。
僕は指先で摘まんだ金属片を見つめたまま、どうして今、彼女のことを思い出しているのか不思議であったが、やがてその水色の水玉模様が、ナ��ミヤの左耳の上、髪に留められているパッチンヘアピンの模様だと気付き、そしてこの金属片が、彼女のヘアピンなのだとわかった。
これはナルミヤの物だ。だから、彼女に返さなくてはいけない。
そう思った僕は洗面所に引き返し、ヘアピンを洗った。赤黒い粘着質な汚れは、執念深く擦り続けているうちに流れ落ち、それから、自分の手もよく洗った。もう何日も風呂に入っていない僕の頭を拭いたタオルでナルミヤの私物を拭くことをなんとなく躊躇して、軽く水を切ってから、僕はそれをズボンのポケットへと入れる。
学校へ行ってみよう。ナルミヤはきっと、登校しているだろう。
汚れがマシな靴下があったら履こうかと思ったが、そんな物はどこにも見つけられず、僕は裸足のまま玄関へ向かった。
玄関の土間には、僕のスニーカーと父親のくたびれた革靴と、妹のリスコが落ちていた。リスコは手足を縮めるようにして土間にうずくまり、まるで芋虫のようだった。うつ伏せの姿勢のまま、そこにじっとしているので、顔は見えない。ぐっすり眠っているのか、僕がすぐ側でスニーカーを履いても、ぴくりとも動かなかった。
僕と同じようにずっと入浴していないリスコの髪には、ところどころ綿埃が付着している。その髪は明るい茶色をしていて、これはリスコが母親にねだって市販の薬剤で染めてもらったからだった。茶髪になったことが嬉しくて、はしゃいでいた妹の様子をまるで昨日のように思い出す。でも今は、その髪も汚れきっている。
妹はいつから、ここで寝ているんだっけ。
リスコは昔から寝起きの機嫌が良くない。起こそうとして噛みつかれたことも一度や二度ではないし、あの父親でさえ、眠っているリスコを起こそうとはしない。だから僕は、妹には触れることなくスニーカーを履き、その横を黙ってすり抜けた。
玄関のドアを開けて、外へと出る。家の鍵は持っていないので、ドアを閉めても鍵は閉められない。僕が不在の間に誰かが訪ねて来て、うっかり妹を起こしてしまうなんてことが、なければいいのだけれど。
家から一歩外に出ると、不思議と気持ちが楽になった。僕が家の中にいるとどことなく居心地が悪い理由は、そこに両親がいるからだと今まで思っていたけれど、母親が帰って来なくなり父親が呼吸をしなくなっても、やっぱり家の中にはいたくないというのが、僕の本心らしかった。比較的軽い足取りでアパートの階段を降り、学校へ向かうための通学路を歩き出す。スニーカーの中に溜まった砂が、たちまち足の裏にまとわり付くのが気持ち悪かった。
どうやら小学生が登校する時間はとっくに過ぎているようで、もうどこにも黄色い帽子やランドセルを身に着けた子供の姿を見つけることはできなかった。ひとりでとぼとぼと学校へ続く道を歩きながら、そういえば僕のランドセルはどうしたんだっけ、と考えた。
学校へ行くのであれば、ランドセルくらいは持って行っても良かったかもしれない。でもどうせ、教科書もノートもないし、鉛筆は皆折れているし、ランドセルだけあってもどうしようもない。
葉桜になった桜並木を歩いて行くと、途中、一本の桜の木の陰に、思わぬ人物の姿を見つけた。ナルミヤだった。
彼女は桜の木にもたれかかるようにして立っていた。しかし、登校の時に被るように言われている黄色い帽子も、真っ赤なランドセルもない。足元はいつもと同じ、エナメルの黒いスニーカーだったが、黒と白のワンピースは、学校の制服ではなかった。ナルミヤは僕に気が付くと、まるで汚物でも見るような目をして、顔をしかめた。
「……ケイタくん」
「おはよう、ナルミヤ」
「……おはよ」
「ここで、何してるの?」
「別に」
「学校、行かなきゃいけない時間じゃないの?」
ナルミヤは僕から顔を背けるように真横を向きながら、それでいてその目は、突き刺すように僕を見ていた。
「そう言うあんただって、学校は?」
「今、行くところ」
「……その格好で?」
「うん」
「あっそ」
僕はポケットの中からパッチンヘアピンを取り出して、ナルミヤへ差し出す。
「これ」
「……何それ」
「これ、ナルミヤのでしょ」
「なんであんたがそれを持ってるの?」
「僕の家に、落ちてた」
「…………」
「これをナルミヤに返そうと思って、それで学校へ行くところだったんだ」
「…………」
ナルミヤはまるで引ったくるように、僕の手からヘアピンを取ると、すぐさまそれをワンピースのポケットへと仕舞った。横を向いたまま目だけで僕を睨んでいるのは、変わらなかった。
「そのために、来たの?」
「うん」
学校に辿り着くずっと手前で、ナルミヤに会えたことは予想外だったけれど。
「それだけ?」
「うん」
「…………」
彼女は僕を睨みつけていたが、やがて、その目線さえもそっぽを向いた。
「ケイタくんさ、わかってんの?」
「何を?」
「あんたのお父さん殺したの、私なんだよ」
「うん」
僕は頷いた。
「私のヘアピン、証拠じゃん。私が殺したっていう証拠」
「そうかな」
「だって殺人現場に落ちてるんだよ。犯人が落としたんだって、思うでしょフツー」
「そうかも」
「ケーサツ呼んでないの?」
「呼んでない」
「なんで呼ばない訳?」
「うち、電話ないし」
ナルミヤの目がさらに細くなる。細くなればなるほど、僕を貫くように視線��研ぎ澄まされていくように感じる。しかし今、彼女の目は僕の方をまったく見ようとしていなかった。
「はぁ? 電話なんかなくたって、ケーサツくらい呼べるでしょ。近所の人とか、お店の人とか」
周囲の大人に助けを求めれば良い、と言いたいのだろうか。しかしナルミヤは、それより先の言葉を口にはしなかった。
「あんたのお父さん、どうなってんの?」
「どうもなってないよ」
「どうもなってないって?」
「そのまま」
「あれから、ずっと?」
「そう」
「…………」
ナルミヤは最大級に嫌そうな顔をした。
「…………きもちわる」
ぺっ、とナルミヤは僕に向かって唾を吐いた。彼女の唾液は、放物線を描いて僕の足下へと落ちる。僕がその唾液の、白いあぶくを見つめていると、ナルミヤは心底不機嫌そうな声で、怒鳴るように言う。
「用が済んだらさっさと失せろ。二度とその面を見せるな」
それはまるで、僕の母親が言いそうな言葉だった。けれど彼女が僕の母親に似ているとは、ちっとも思わなかった。ナルミヤの方がずっと綺麗だ、と思った。
学校へ向かおうと思ったけれど、目的はすでに達成してしまったし、もう何もすることはないので、僕は家に戻ることにした。さっき出て来たばかりなのに、もう引き返すのかと思うと、それだけで足が重くなる。結局、僕はあの家から逃れられないのだろうか。のろのろと歩きながら、一度だけ後ろを振り返ってみたけれど、もうナルミヤの姿はなかった。
ナルミヤはどこへ行ったのだろう。あの格好だと、学校へ向かった訳ではないような気がする。彼女も家へ帰ったのだろうか。それとも、僕の予想もつかないような場所へ向かったのだろうか。
帰っている途中、どこからかサイレンの音が聞こえてきた。パトカーのサイレンだ。家が近付くにつれて、その音はどんどん大きくなっているような気がした。
寝ていたリスコは、この音で起きてしまうかもしれない。寝起きの妹の相手をするのは、考えるだけで嫌な気持ちになる。妹なんて、一生あのまま、目覚めなければ良いのに。もしくは、リスコはもうとっくに、死んでいるんじゃないだろうか。起こしたくないから触りたくなくて、ずっと土間に転がしたままにしていたけれど、本当は、もう二度と目覚めないのかもしれない。
アパートの前まで来ると、そこには三台のパトカーが停まっていた。近所迷惑を考えてか、さすがにサイレンは鳴らしていなかったけれど、赤色灯がくるくるくるくる、風車みたいに回っている。目の前の光景に呆然としていると、二部屋隣に住んでいるおばさんが駆け寄って来る。僕の家のドアは開いていて、中から出て来た警察官が階段下にいる僕を黙って見下ろした。
やっぱり、家の鍵をもらっておけば良かったな、と僕は少なからず後悔して、今度母親に会ったら、ちゃんとそれを伝えようと思った。でもそれと同時に僕は、もうこの家に二度と母親が戻って来ないような気もした。
と、いうのはすべて、僕の妄想だ。
現実の僕は、きちんと制服を着て、黄色い通学帽を被り、ランドセルを背負って、玄関で靴を履こうとしている。ママは僕の後方、廊下の奥の部屋の入口で、中にいる妹のリスコに熱心に声をかけている。
「リスちゃん、もう出掛ける時間よ。いつまでもぐずぐずしているなら、ママは先にケイちゃん���学校へ送りに行くけど。ねぇ、本当にいいの?」
リスコは部屋の中から何か返事をしたらしかったが、なんて言ったのかまでは聞き取れなかった。
「そう、じゃあ先に行くからね。ケイちゃんを送って帰って来たら、ママと一緒に学校へ行きましょうね」
ママはそう言うと、廊下を早足で歩いて来た。
「ケイちゃん、先に行こう。リスコは後で送るから」
僕は黙って頷いた。ママは仕事に行く時の洋服を着ているのに、靴はいつもの黒いヒールではなく、コンビニに行く時のピンク色のサンダルを履いた。僕を小学校へ送ってからそのまま会社へ向かうのではなく、どうやら本当に、また家へと戻って来るつもりらしかった。でも、ときどきママは間違って、そのサンダルで会社へ行ってしまうことがあって、だから僕は、ママがサンダルを履いたことを指摘するかどうか悩んだ。
けれどママの言葉の端々が、妙に尖っているように聞こえることに気が付いたので、そのことを口にするのはやめた。決して表情に出さないように努めているようだったけれど、ママが今までになく緊張しているのがなんとなくわかった。 僕はアパートの階段を先に降りて駐車場の車のドアの前に立ちながら、玄関を施錠したママが後から階段を降りて来るのを待った。車の鍵を操作したのか、唐突にピッと車の鍵が開いたので、僕は後部座席に乗り込んで、さっき背負ったばかりのランドセルを隣の座席へと置く。運転席に乗り込んだママが何も言わないままシートベルトを締めて車のエンジンをかける。ルームミラーで後部座席の僕をちらりと見て、いつもだったらそこで、「ほら、シートベルトしなさい」と言うはずだったけれど、今日のママは「じゃ、行くわよ」と言っただけだった。
※『非・登校』(中) (https://kurihara-yumeko.tumblr.com/post/766015430742736896/) へと続く
0 notes
Text
ある画家の手記if.60 告白
知られたくない、そんな時間は終わった。
強烈に頭が痛くて目が覚めた。水分不足だ、泣いたまま寝ちゃったせいか…
ベッドからろくに体を起こせないまま、手を伸ばしてサイドテーブルの引き出しの中の非常用のペットボトルから水を飲んで、一つ上の引き出しから頭痛薬を取り出して飲んだ。
もう一度ベッドに横になって薬が効くのを待ちながら、考える。
香澄に伝えたいこと、本当に知っていてほしいと思うことだけを、もっと冷静な状態で話すべきだったのに、
昨夜の僕はめちゃくちゃだった。知られたくないことをよりによって香澄に知られて、…怯えて。
言葉がぼたぼた溢れるみたいに喉から出て、思ったことそのまま、なんの説明もない、ただの暗い内面を中途半端に香澄に晒しただけだった。
香澄にあんな話をするきっかけになったのはーーー絢…
親戚だけど、僕と直接会ったのは数えるほどの回数しかない。名廊の本家に行かなきゃいけないタイミングで偶然会ったことが数回あるだけで。
まだ絢は小学生だったかな。親戚が集まったときに、絢が夏休みの宿題の読書感想文をフランス文学を読み解いて感想を書いたのが大きな賞をもらって、掲載したがる出版社が出てきていちいち断るのが面倒だって親戚が愚痴をこぼしていたのを聞いた。どんな些細なことでも絢の名前が知れるのは避けたかったんだろう。当時、僕は絢の書いたその感想文を読んだ。次に絢に会ったとき、「美しい訳文だと思った」っていうようなことを言った、気がする。絢と接触して会話したのはその時くらい…
でも会わなくても僕たちの関係がずっと緊張感を孕んだ繊細なものだったことも確かだ 理人さん…
香澄にちゃんと落ち着いて話したいと思う、香澄がもし聞いてくれるなら。そのために話を頭で整理する。どこまで… どのことを…
絢が…香澄に近づいて何をしようとしてるのかまでは分からない、でも、絢にほとんど生涯を通じて僕のことを気にかけさせてしまっているのは…知ってる。僕を憎んだっていいのに、絢はそんな風には育たなかった、優しい子。
香澄を傷つけたり危害を加えるなら、そのことについてだけはたとえ絢でも許さない
でも…今回の絢の行動は…もとを辿れば僕のせいだ
絢がどこまでどう話したかは知らないけど、結果香澄を混乱させた
香澄と絢が会ってるなら 香澄を通して僕を絢に会わせてもらえれば… でも香澄から聞いたところ絢は、僕には「内緒」、僕とは、会いたくないのか…
まだ纏まらない頭でも頭痛薬は効いてきてくれた。ようやく体を起こしてベッドから出る。
リビングに行くともう食事が用意されてて、キッチンにいた香澄は僕が起きてきたのに気づいて駆け寄ってきてくれた。
「おはよう直人、朝ごはん食べられそう?…あれから眠れた?」
香澄はもう着替えてる、髪の毛、寝癖ついてる…こんなタイミングでも「かわいいな」なんて思っちゃう自分も大概だと思って小さなため息で肩を落とす。そんなこと思ってる場合じゃないんだってば…。
「…うん。話の途中だったのに…寝ちゃってごめん…」
テーブルの上を見る。香澄が作ってくれた食事はどれも柔らかくされた食べやすいもので、きっと昨日の話から心配、してくれてる…
テーブルの席に着こうとした香澄に後ろから腕を回してぎゅっと抱きついた。
香澄の後頭部に額をコツンと合わせてちゃんと謝る。
「昨日はごめんね。自分勝手に…中途半端な話しして…そのまま香澄を置いて一人で眠って…」
「……俺も…ごめんなさい…。直人に苦しいこと、無理に話させて…」
「…僕は…」
香澄が首をそらして後ろにいる僕の顔を見ようとした。その時、襟が高めの香澄の服の隙間から赤い筋がのぞいた「……っ!」香澄の体を急いで振り向かせて首元を確認する、爪で引っ掻いたみたいな痕がいくつも残ってた。急いで香澄のシャツのボタンを外して長く伸びた痕の先を見る。胸元あたりまで続いていた。
「……、」香澄の両腕を掴んだまま、その場にガクンと膝をついた。香澄の体に頭を当てる、そのままうつむいたら床に目から涙がぽたっと落ちた。僕が泣いてどうするんだ、怪我をしてるのは香澄なのに、怪我をさせたのは誰だ、そんな負荷を香澄の心にかけたのは
「…………… ごめん…」
そのあと、まだ出勤まで時間があったから香澄の服をソファの上で全部脱がせて、他にも怪我をしてないか全身を確認した。首ほど密集してないけど他にも体のところどころに引っかき傷があった。
それら一つ一つを濡らした布でそっと拭いてから消毒して、絆創膏を貼る。ひどい出血じゃないけど、服と擦れるときっと痛む。手当てしながら何度も謝って、そのたびに目から勝手にぽたぽた涙が落ちた。
「直人…。ごめん、俺… 眠ってた間で気づかなくて…油断してた…」
手当てが終わってから香澄は眉を下げて謝った。手を伸ばして僕の眦に残った涙を指先で優しく拭ってくれる。
こんなのは…僕がやったようなものだ。香澄が謝ることじゃない。香澄の頭を胸に抱き寄せて、髪の毛を優しく梳いて撫でた。
精神的にも肉体的にも、負荷をかけてしまってる。
香澄の頭を撫でながら、提案した。
「昨日半端に話したことを、ちゃんと、話したい。絢から聞いてばかりじゃ、香澄も信じていいのか混乱するだろうし、意味が…分からないことばっかりだったと思うから。…落ち着いて、話したい」
香澄は僕の胸元に頰を擦りよせながらそっと目を閉じて言った。
「俺は、直人が話したくないことは無理に聞き出したくない。昨日の直人、話してるだけですごく、…苦しそうだった……俺は…そんなの嫌だよ…。絢人くんが俺に話そうとしても、今後は彼から直人の話は勝手に聞かない。直人の話は直人から聞きたい。それも直人が俺に話したいって思うことだけで、俺はいい」
香澄の顎をとって顔を僕のほうに上げさせて、しっかり香澄の目を見つめて言った。
「…僕は…話したいよ。楽しくない話でごめんね…。それでも僕は、…今みたいな形で…香澄の中に香澄を傷つけるような形で、昨日の話を残したままにはしたくない。…それに香澄には、……知っててほしいと…思う。知って何をしてほしいわけでもない…全部もう昔の…過去の話だから。香澄も聞いたって…今さら困るかもしれない。…それでも」
一緒に、背負ってくれる…?
知られたくない、なんて時間はもう絢が終わらせてしまった。
それなら二人で一緒に抱えさせてほしい。どこまでも僕のわがままだけど。
香澄はしばらく考えるようにした後、それならと言って、次の香澄と僕の仕事の休みが重なる日を丸一日空けておいてくれることになった。
その日まであと二日ある。
僕も一度気持ちを切り替えて、仕事に行く支度を始めた。とりあえず裸の香澄の体にもう一度きちんと服を着せ直す。
ブラシで自分の髪を梳かす前に思い出して、香澄を鏡台の前に座らせて、さっき見つけた寝癖をブラシで丁寧に梳いて綺麗に整えた。
僕の髪がずいぶん伸びたから職場で不清潔じゃないように、これまで適当な安いシャンプーで洗って濡れたまま自然乾燥で放置してたのを改めて、ちょっとお高めのシャンプーとトリートメントコンディショナーを買ってドライヤーでちゃんと乾かすようになった。自然と香澄も同じものをお風呂に入る時は使ってるみたいだ。僕が香澄の髪の毛洗うことも多いけど。だから今は僕が香澄の髪に顔を寄せたら僕と同じ匂いがする。そのたびにくすぐったいような、あったかい気持ちになる。
終わったら鏡台の前でうつった香澄を見る、伸びてきた髪の毛を綺麗に梳かしてまっすぐ整えた香澄は、同じ色の長い睫毛や眉が白い肌に映えて、とても綺麗。図書館勤務になってから屋内で過ごすようになったせいか、生来の肌の白さが前より際立ってまるで絹のように美しくなった。色素が薄めで睫毛とぼさぼさの髪の毛に隠れがちだった瞳は、肌が白くなったからコントラストで存在感を増して、いくつもの色が複雑に重なって混じり合う、宝石の原石を割ったときにのぞくような不思議な放射状の模様を宿して輝いている。それが僕には眩しい太陽みたいで、強烈に憧れるような気持ちでいつもじっと見つめてしまう。
…こうして見つめているとあちこちで狙われるのも仕方ないような気になってきてしまう、いくら香澄が美しくても何も仕方なくなんてないし電車でのことも思い出すたびに僕はいまだに内心でキレてるしれっきとした犯罪なんだけど。
二人で香澄の作ってくれた朝食を食べる。どれも柔らかくて喉を通りやすくて、作ってくれた香澄の気持ちを考えただけで少し泣きそうになった。
食べる途中で香澄が「俺と食事するとき、無理してる…?」って小さな声で聞いてきた。…絢に事実以外にもなにか言われたかな。
「まさか。香澄といて無理したことなんてないよ。僕は香澄と一緒に食事できるのが嬉しい」にっこり笑ってそう答えた。実際いつも香澄の帰りが少し遅くなりそうな時でも、僕は一緒に食べようと思って食事を作ったあとも香澄の帰りをしばらく待ってることが多い。
出勤のために二人で車に乗り込んだ後で、駐車場で周りから誰も見てないことを確認してから、運転席から体を伸ばして助手席の香澄の体を引き寄せて、香澄の唇をあっためるように優しいキスをした。
続き
0 notes
Text
[ハロウィンの夕暮れ、ヒナイチは幼い頃に迷い込んだ森に再び足を踏み入れた。森を抜けて、薄紫色の夕暮れに咲くひまわり畑の遊園地でヒナイチは男の子に出会う。でもなんだか初対面とは思えなくて、彼女はつい遅い時間まで一緒に遊んでしまった]
という264死の数年後設定
※
「わあ、どうしたんだ急に?」
彼のひらひらの白い胸元のフリル、紅いベストの上で紫に煌めくアメジストのブローチ、くるぶしまで届く長い黒いマント。そのマントの裾が土埃で汚れるのも厭わずに跪く姿は、吸血鬼というよりもまるで王子様みたいだ。
「…………また会える?」
そっとヒナイチの目を覗き込んで薄く笑む黒の王子様の口元に、小さな牙が白く見え隠れする。
「ああ、良いぞ?」
この子はどうしてそんな簡単な事を、難しい宿題を解けない時みたいな顔して聞くのだろう。
彼が浮かべている笑みは、『やれやれ、これは到底叶わない』と初めから諦めてかかっている気がする。そんな事あるものか、明日の夕方にでも、学校帰りに会う約束をすれば良いだけじゃないか。待ち合わせ場所はどこがいいだろう。
(うん?この男の子は、この辺りの小学校に通っているのだろうか?)
おじいさんがこの子を喜ばす為だけにこんな、びっくり箱をひっくり返したみたいな大掛かりなハロウィンパーティーを開くくらいだから、きっと凄いお金持ちのおうちの子には違いない。そしてお金持ちの子ばかり通う、遠い学校に電車で通っているのかも知れない。そういう難しい学校に通う子はさらに塾なんかにも通って、物凄く難しい宿題が毎日たくさん出るのかも知れない。
もしほんとにそんな生活なら、すぐに遊ぶ約束をするのは難しいだろう。新しい友達とまた会えるか、不安になるのも仕方ないだろうけど。
「……ほんとうに?」
ヒナイチの答えを聞いた男の子は口の端の笑みをぎゅううっと大きく吊り上げて、それでもまだヒナイチの前から立ち上がりはしなかった。そして、今までより低めの静かな声で、ゆっくりと話し出した。
「…………ヒナイチくん、君にお願いがあります。」
それはもう真剣な、夏休み最後の日に友達に宿題を写させて欲しいと頼むような声だったので、ヒナイチも思わずお菓子の袋の上で居住まいを正した。
「……うん。」
男の子はかしずくように煉瓦の道に片膝をついて、黒いお城のシルエットを背に、真摯な眼差しで自分を見上げている。
(なんだろう、こういうのを、どこかで見たことがあるな)
ヒナイチはふわふわ広がる自分のチュールスカートに目を落とした。
「どうか私の……」
(あっそうだ、これはこの間テレビで見たディズニーの映画の、結婚の申し込みの場面に似ている)
映画の中では青空の下、お城を背景にした白いフロックコートの王子様が、金髪のお姫様にプロポーズをしていた。
それならハロウィンの今夜、オレンジ色のランプに浮かぶ黒いお城の城下町。私はお菓子の玉座に座る赤毛の魔女で、彼は青い顔の吸血鬼の王子様だ。
「城で……」
(……あっしまった、今、何と言っていた??)
空想に浸っていた所為で、ヒナイチは彼の台詞を聞き逃した。男の子は言葉を続けた。
「来月の、私の誕生パーティに出席して欲しいのだけど、いかがでしょうか?」
「誕生パーティ?……それは、ええっと。うーん、どうなんだろう?」
ヒナイチはぐるりと周りを見渡して、夜を煌々と照らす遊園地の景色を眺めてみた。
初対面の男の子のうちに、いきなり遊びに行ってしまっても良いのだろうか?礼儀正しくしないといけないと道場で言われているし、まずはお母さんに相談してみないといけない。
あっ!
遊ぶのに夢中ですっかり忘れていたが、ここは一体どこなのだろう!?
森を抜けて、薄紫色の夕暮れに咲くひまわり畑の遊園地で初めて会った男の子。でもなんだか初対面とは思えなくて、ついこんな遅い時間まで一緒に遊んでしまったけど。今何時なんだろう、兄さんはきっと心配している。
「…………もう帰らないと。」
「えっ!?」
ぽそりとこぼしたヒナイチの呟きに、男の子が素っ頓狂な声をあげた。ヒナイチがどきっとしてまた彼に目を戻すと、男の子はしょんぼりと耳を萎れさせて俯いていた。
「帰っちゃうんだね……招待客はみんな、暫くうちに滞在すると聞いていたんだけど、君は違うんだね……」
眉までもへの字型に項垂れた男の子に、ヒナイチはとても気の毒な気分になった。
「うわっ!な、泣かないでくれ!」
「……あっそうだ!お父様にお願いして、君の家まで送ってあげよう!」
パッと顔を上げた男の子の表情は早替わり、今度は泣き出しそうだった目を輝かせて、とびきり悪戯っぽい笑顔を浮かべた。
「お父様に乗せて貰えれば、おうちまでひとっ飛びで帰れるからね!」
「えっ!?乗せてとは車の事だろうか?それはご迷惑だろう、ありがたいが遠慮させて……」
お菓子袋から立ち上がりかけたヒナイチの肩を男の子は両手で押し戻して、小さな牙をちらっと光らせて笑った。
「ここで待ってて、お父様を呼んでくるから!」
言った瞬間、背を向けた小さな身体は思いがけず俊敏な動きで走り出した。そしてヒナイチが呼び止める間も無く、彼はきらきら廻るメリーゴーランドとティーカップの間をマントをたなびかせて走り抜け、夜の中にすっかり見えなくなってしまった。
……ううむ、出来れば家に電話をかけさせて欲しかったんだが、頼み損ねてしまった。しかし、あの男の子がお父さんに頼んでみてくれたところで、初対面の女の子を家に送ってくれだなんて聞いてもらえるはずがない。すぐ戻って来るだろうから、頼んで兄さんに電話をさせてもらおう。遊園地の所在地をはっきり教えてもらえれば、多分兄さんの方が車で迎えに来てくれる。
ヒナイチは袋の上に大人しく座って、男の子の帰りを待つことにした。
◉
「ヘロー、楽しんでる?」
しばらく待っていると、遥か頭上から太い声が落ちてきて、ヒナイチは肩越しに振り向いた。菓子袋の後ろにはいつの間にか、それはそれは高い背の、吸血鬼マントの外国人のおじいさんが立ってヒナイチを見下ろしていた。
「あっおじいさん!」
ヒナイチは腰掛けていたお菓子袋から降りて、おじいさんの前できちんと頭を下げて挨拶した。うんと見上げた男の人の後ろには既に夜の帳が下りて、ちらちら星が瞬いていた。
「もちろん楽しんでいる!こんな楽しい遊園地��初めてだ。自分のうちの、こんな近くに遊園地があったなんて、どうして知らなかったんだろう。」
お母さんもお父さんも兄さんも、誰もここを知らないんだろうか?今まで、学校の友達も道場でも、この遊園地の噂を誰かが話すのを聞いた事がない。
「ここ、今日出来上がったばっかり。」
このおじいさんの返答は、ヒナイチの想定外だった。
「え?そうなのか!?そうか、それなら誰も行ったことが無いのは当たり前だな!……だけど、こんな大きな遊園地なら、出来上がる前にちょっとくらい噂になっていてもおかしく無いのだが……?今日みたいな1番初めの日なんか、もっと沢山の人がいっぱい集まるのではないだろうか?どうしてこんなに遊びに来る人が少ないんだろう?どの乗り物も凄く面白いのに、並ばなくても何回もすぐに乗れるから不思議だ!」
ぐるりと遊園地を見渡して、ヒナイチは改めて広さと明るさ、その見た目も奇想天外なアトラクションに感嘆した。前にお母さんに連れられて行った新装開店のスーパーは広くて、あまりの人だかりに呑まれてうっかりお母さんの手を離してしまった。はぐれて店内をウロウロするうちに、店員から渡された開店記念の風船がペンギン顔のプリントだったのを、ヒナイチは決して忘れはしない。(その後気をうしなって倒れるまで叫んで走り続け、お店の人に迷惑をかけたから、お母さんに物凄く怒られたのだ)
「ここは、私の一族のハロウィンパーティー会場。今日の招待客は、一族の者だけ。」
片言気味の日本語でおじいさんが話す内容を、ヒナイチはゆっくり頭の中で噛み砕いた。
「うん?んん??それは、おじいさんの家族でこの遊園地を貸し切っているという事なのか?ハロウィンパーティーの為に!?」
な、なんて凄いお金持ちなんだ。園内ですれ違う大人が全員吸血鬼マントだったのは、親戚みんなでお揃いの衣装を着ていたからなんだな。
おじいさんは近くの観覧車から遠くジェットコースターと、順に指差していきながら話した。
「あれ全部、皆を喜ばせようと思って、急いで一日がかりで作った。」
おじいさんの示す遊具には“HAPPY HALLOWEEN”や
“TRICK OR TREAT” とか緑や紫に光る絵の具で描かれたノボリが垂れていたり、園内の至る所にカボチャのランタンやガイコツが吊り下がっていたから、その飾りつけに一日中かかったという意味なのだろう。
規模こそこじんまりした遊園地だが、たった一日でこれだけ華やかなパーティーの用意が出来るのは凄いと思う。
「作るのは面白かったろうな!」
「オブコース。みんな喜んで遊んでいた。あの子が大喜びではしゃぐのを見たお父さんなんか、お母さんが泣いて喜ぶと言って、写真を撮りながらえんえん泣いていた!」
ここ一番の真剣な声色のおじいさんの問いかけに、ヒナイチが屈託ない笑顔で応じると、おじいさんは目を瞑って静かにこくりこくり頷いた。
「グレイト。ところで、一人?」
「うん、あの子はお父さんを探すと言って、走って行った。そうだ、おじいさん……あの子に、今度開く誕生日パーティーに来ないかと誘われたんだが、私は行っても構わないのだろうか?」
おじいさんは、じっと私を見てから首を横に振った。
「ウーン、城に呼ぶには、まだチョット早い。」
「あっ、うん……!そ、それはそうだろう、初対面の子をおうちに呼ぶのは、流石に早すぎるな!」
ヒナイチは視線をずらして、どもりながら答えた。こんな質問をして、礼儀知らずと思われただろう。恥ずかしくて顔が火照る。でも男の子の家をちょっと見てみたかったのはヒミツにしておく。
「ええと、おじいさん。あの子はお父さんに、私をうちまで送ってくれるよう頼みに行ってくれたんだ。でも初対面の私を送ってくれるはずはないし、家族に迎えを頼みたいから電話をかけさせて貰えないだろうか。それから……。」
景品で当たった、とてつもなく馬鹿でかいお菓子袋をヒナイチは未練たっぷりに眺めた。
「残念だけど、うちの車にはこれだけの量のお菓子は載せられないから、少しだけ貰って残りは置いて帰らなければならない。申し訳ないのだがおじいさん、この袋はここに残していく……」
あまり洋菓子は得意でないヒナイチも、おせんべい派のうちではまず出てこない珍しいお菓子の味が気になった。ハロウィンカラーの派手な包紙の下には、どんなお菓子が隠されているのだろう。何よりあの子が作るのを手伝ったお菓子って、どれの事だろう。
ヒナイチはぱんぱんにはち切れたお菓子袋の口元にしゃがんで、緩んでいた紐を全部解いた。袋からお菓子がぽろぽろとこぼれるのを拾い、被っている魔女のとんがり帽子を脱いで、袋がわりに詰め始めた。しかし、楽しげな色のキャンディーや可愛いラッピングのマドレーヌなど、帽子に全部詰めるにはあまりに種類が豊富で、ヒナイチは大変な誘惑と戦うことになった。
「ううむ、どうしよう、どれも美味しそうで気になってしまう……うわっ何だこの変な形のクッキーは?ネコなのか?シマウマ?」
吸血鬼マントのおじいさんは暫くの間、帽子に入れたお菓子を袋に戻したりまた選り出したり悩み続けるヒナイチを見下ろしていた。やがて、彼はぽそりとたずねた。
「全部ほしくない?」
一つ一つお菓子を手にとって吟味を繰り返すヒナイチは、おじいさんが自分のぴったり真後ろに回ってきたのに気が付いていなかった。
「実を言えば欲しいけれど、うちの車には載せ切らないし、そうだ、考えたら他所の人にこんなにお菓子を貰ったらお母さんに怒られてしまう!あれっ?」
「ぜんぶ持って帰りなさい。私が送る。」
0 notes
Text
知らないうちにtumblerがアップデートされ、若干使いにくくなっていた。このほかにも、Instagramやtwitterといった個人的にヘビーユーズしているsnsが軒並み改悪されていっている。
いかがなものか。
つらつらと文字を並べたくなったので、久しぶりにタンブラーを更新する。先に断っておくが、この文章にはまとまりもなければオチもない。ただ書き連ねたいことを、文字に直すだけである。
______________________________________________________
フランスに行っている友人が毎日パリの写真を送ってくれる。人、犬、街並み、食べ物、アート、パリを成す小さな要素を切り取った写真はどれも本当に美しい。
彼女の出国前に 「出来るだけパリの日常を切り取った写真を送って欲しい」というなんとも身勝手な約束を焚きつけたにも関わらず、嫌な顔せず丁寧な.pngを日々共有してくれる彼女には感謝しかない。
______________________________________________________
互いにファッションが好きということも相まり、件の友人が現地でのファッション模様を送ってくれる。
程よくキマっていて、肩張らないファッションをそつなく楽しむパリの人たち。いいな!と思うのは全て homme modeである。わたしも髪を伸ばそうかな


最近は、緩やかな服装を好んで着ている。体型の隠れるオーバー気味のシルエットに、短い髪の毛をピタッと固めるのがマイブーム。たまにタイトな服やスカートを選ぶけれど、なんとなくソワソワして落ち着かない。
胸が邪魔だなと思うことが増えた。低身長の割に主張のある自分の胸元がずっと気に食わない。服を着る度に邪魔すんなよ〜と胸にキレている。
______________________________________________________
ピカソとその時代展に行ってきた。
ドイツを代表する大コレクター、ベルクグリューン氏が蒐集したコレクションの展覧会。もとより狙いを定めていた ピカソの描いたドラ・マール、マティスの油絵や切り絵、ジャコメッティのブロンズを観れたので大満足でした。
また 例に漏れず、今回もミュージアムショップで大金を叩いた。
帰宅し、母に戦利品である 「緑色のマニュキュアをつけたドラ・マール」 のクリアファイルを自慢すると、「あんたそっくり」 とのコメントをいただいた。褒められてはねえな。

ここ最近、月一ペースで美術館に行っているので、自室の壁がどんどんポストカードで埋められていきとんでもないことになっている。
______________________________________________________
あなたに似ている、と言われた作品がもう一つある。
それがこちら。
Bronzino
-Portrait de jeune homme tenant une statuette, dit autrefois Portrait de Baccio Bandinelli
(和訳 : ブロンズィーノ 「彫像を持つ青年の肖像画」 )

わたしは己の顔つき云々に興味がないので、誰かから報告を受けるたびに周りからこう見えてんのか〜と面白がってしまう。
それはさておき、この彫像、なんとなく姉に似ている。
とまあこんな感じで、指も疲れてきたしオチもないので唐突に終わります。
とりあえず、わたしは元気です。
追伸.
ラブリーな写真を送ってくれるスーパーラブリーな友人へ、とびきりの愛と感謝を込めて
0 notes
Text
(短評)映画『イニシェリン島の精霊』

(引用元)
『イニシェリン島の精霊』(2022年、英国、原題:The Banshees of Inisherin)
突然絶縁されて困惑する男&絶縁したのに付きまとわれて困惑する男の小競り合いが次第に島の人間模様を浮き彫りにし、悲劇を加速する💨
教養や創造性のない人は無価値? 優しく良い人であること自体は無価値?
そんな二項対立の間のグレーな部分の揺らぎを描いた良作‼️

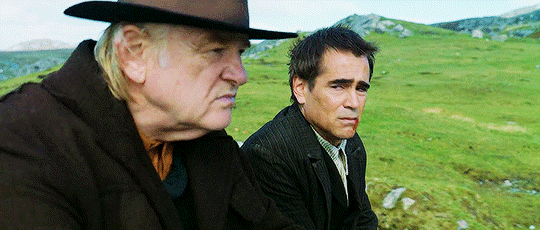

個人的な争いと戦争の地続きを意識させる映画でしたが、それよりもっと人間関係の価値についての根源的な部分を考えてしまいました😮💨
優しさは残らない≒価値がないと言い放つコルムに対して、パードリックが自分の妹が優しいことを一生忘れないと言い返す場面は、この物語の核心に触れる場面でした💨
だんだん自分の存在意義について迷い始めるパードリック、人の優しさの価値を否定しきれないコルム、この2人の困惑した表情と、こちらも困惑するような行動の連鎖は、胸を痛めつつも面白い‼️
動物達を絡めた演出も見事だったと思いますし、脇を固める登場人物たちも���力的でした👍
流石です🌟
主人公2人の眉毛力が凄い‼️
眉毛の形状はもちろんのこと。困惑したり話込んでる時の眉毛の動きの豊かさよ‼️
とくにコリン・ファレルの眉毛が素晴らしく、劇中の7〜8割はハの字型で上下したり、軽く旋回したり😅
#movie#movie review#映画#映画レビュー#イニシェリン島の精霊#the banshees of inisherin#inisherin#マーティン・マクドナー#martin mcdonagh#コリン・ファレル#colin farrell#ブレンダン・グリーソン#brendan gleeson#ケリー・コンドン#kerry condon#バリー・コーガン#barry keoghan
0 notes
Photo

リポスト:@fast8ener (勝手に失礼します) 【緊急募集‼️】【拡散希望】【捜索ボランティアの方募集❗️】 12月20日11時頃、トリミングサロンに預けていた際に迷子になりました。捜索から11日が経ちました。未だ目撃情報がほとんどない状態です。 そこで範囲を広げて捜索したいと考えているので下記の日時に一緒に捜索にご協力いただける方を募集しています。 *訂正事項:場所→大日町、鹿放ヶ丘、み春野、上志津原のみの2日間、同じ方面で捜索を行います。 2022年1月2日(日)、3日(月)の2日間、時間はともに13時~ 場所は、 千葉県四街道市大日町、鹿放ヶ丘、み春野、上志津原方面(目撃情報から北側) 集合場所→ローソン四街道市大日富士見ヶ丘店前 〒284-0001 千葉県四街道市大日2081−1 ご参加いただける方、この投稿に返信、もしくはDMをお願いします。 *もしくは明日、そのまま現地に来ていただいても、構いません。 ※この時世なので、参加時はマスク着用でお願いします。 #迷子犬 #迷い犬 #黒トイプードル #黒プー #胸元に白い毛の模様 #千葉県四街道市 #四街道市大日町 #四街道市鹿放ヶ丘 #四街道市美しが丘 #四街道市和良比 #四街道市みのり町 #千葉市 (千葉県四街道市のどこか) https://www.instagram.com/p/CYOQESgvc8c/?utm_medium=tumblr
1 note
·
View note
Text
日本はドラッグ無法地帯!? ドラッグの世界潮流と日本ドラッグ事情
2009/07/25 18:00
ohno_gendai.jpg
『週刊現代』8月9日号(講談社)
「犯罪者である彼あるいは彼女にも我々同様に人生があり、そして罪を犯した理由が必ずある。その理由を解明することはまた、被害者のためにもなるのでは?」こんな考えを胸に、犯罪学者で元警視庁刑事・北芝健が、現代日本の犯罪と、それを取り巻く社会の関係を鋭く考察!
昨今の日本では、ドラッグ関連の報道はもはや珍しいものでもなんでもない。芸能界からスポーツ界、有名大学の学内、そのほかありとあらゆるところにドラッグが蔓延しているのが現実である。ドラッグは日本の闇の文化の一つとして成り立ってしまったといっても過言ではない。そしてそれは、世界的なドラッグの流通ルートに、日本が組み込まれていることをも意味する。今や世界のドラッグ業界において、日本は無視することのできないほど大きな市場の一つなのである。
日本におけるドラッグ全体のシェアは、大麻がトップ、次いで覚せい剤とMDMA(合成麻薬)が肩を並べる。そして、この三種類が日本に出回るドラッグのほぼすべてを占めている。これらのドラッグは、大麻が『ダウナー系ドラッグ』、ほかの2つが『アウェイキング・ドラッグ(またはアッパー系ドラッグ)』と呼ばれ、程度の差はあるがどれも自身の感覚が鋭敏になり、セックスの快楽を増す作用がある。ダウナー系は他者に対しての警戒心が鈍くなり、羞恥心が薄らぎ、多幸感、および大麻であればマッタリ感、アッパー系なら極度の強迫観念や攻撃性が増すようになる。これらのドラッグの売値は、クラブに出入りするプロのディーラー(卸元)やプッシャー(密売人)など取り扱う者にもよるが、平均してMDMAは1錠2,000~4,000円(末端価格。以下同)。大麻はタバコ状になっているもので1本2,000~3,000円。覚せい剤は1g4~7万円前後。これは近年値上がりした価格で、それまでは長い間耳かき一杯で7,000円前後の相場であった。これらのドラッグの流通には当然、闇社会が関わっている場合がほとんどで、相場価格はコントロールされているため大きな値崩れはない。
日本に入ってくる覚せい剤は、北朝鮮で製造され海を渡ってくるものが有名だが、中国の香港や大連からも密輸される。ヘロ��ンやアヘンはミャンマーとタイ、ラオスの三国境が交わる山岳地帯、業界では『ゴールデン・トライアングル』とも呼ばれる一大麻薬密造地帯から日本に来るルートがある。これは、まずバンコクを通り、グアム経由で成田や関空に入ってくる。また、バンコクからシーチャン島~台湾~沖縄を通る、台湾マフィア”チクレンパン”が仕切っているルートもある。なお、余談だが、実はチクレンパンが仕切るこのルートはオウム真理教の手配犯、高橋克也、平田信(菊地直子は偽造パスポートで関西空港からバンコクへ出国)が国外に逃亡したルートでもある。オウムと麻薬組織とのつながりは、オウムが覚せい剤を密造していた関係からできたものであり、現在、彼らはミャンマーの山村で”麻薬将軍”ことウェイ・シューカンに保護されている。3人がかつて潜伏していたというミャンマー北部の一軒屋には、昨年私の友人や捜査官も実際に足を運び、その痕跡を確認したので間違いないはずだと思っている。
大麻は世界中のいたるところで密造されている。世界的に有名なのはインドのガンジャや中東、東南アジアのタイ、南アフリ���、アメリカならばカルフォルニアのビッグ・サーあたりであろう。世界中というのには当然日本も含まれており、福島や栃木の山間部や北海道に違法な大麻畑があるという情報もある。欧州発のドラッグであるMDMAは、主にオランダ、ポーランド、チェコで密造され世界各国に流れる。ドラッグ市場の規模で言えば日本以上である欧州は、ドラッグの種類に関わらずその多くがヨーロッパドラッグカルチャーの中心であるオランダ・アムステルダムに一度集められて欧州全土に広まるが、日本にはオランダ経由で航空貨物やシベリア鉄道などを通じ流入する。日本に入ると、まず六本木に集められ新幹線を使って全国のクラブにばらまかれる。
三大ドラッグと比べれば数は少ないが、アヘンやヘロインも少しずつだが日本に入ってきている。アヘンに関しては1988年にイラン・イラク戦争が終わり、イラン人が日本に大量に入国した際、『テリヤキ』と呼ばれるアヘンスティックを持ってきたことで流行した。当時それらは1本6,000円くらいで取引されていたが、これが現在でもイランからのルートで国内に入ってきている。また、昨今は01年のアフガン戦争以降、アフガニスタンでは厳しく取り締まられていたケシ畑がタリバンによって復活し、アヘンや精製されたヘロインが国内にも流れてきている。ただ、アヘンは日本ではさほど需要がなくアメリカや欧州、中東、アフリカにおいて多くが取引されている。
以上が、日本に流入するドラッグの主だったルートである��、このようなルートが各国に存在し、それこそドラッグの世界潮流とも言うべきものを為している。これだけわかっていて、なぜドラッグの流入を防げないのか? そう考える人もおられるかと思うが、実際に国内へのドラッグ流入を阻止するのは非常に難しいのが現実だ。まず、空港に入ってくるドラッグの場合だが、家具や家電に巧妙に隠され税関をスルーしていく。個人では身体に巻きつけたり、防水加工したりして体内に隠す場合もある。国内に来る人、荷物の数に比して空港警察や税関職員、厚生省麻薬取締官、麻薬犬の数は圧倒的に不足している現状では、一定の成果を上げているとは言っても、残念ながらその何倍ものドラッグが空港を通過していると考えられる。そして、船を使った場合は漁船でやられたらほぼ100%スルーになってしまうのが現状だ。数は減ったとはいえ、依然として北朝鮮製覚せい剤がドラッグ市場からなくならないのも、海からの流入を防げないからである。北朝鮮から積み出された覚せい剤は、日本海沿岸において防水加工され海に流される。それを、広域暴力団に雇われた漁船が吊り上げ、日本に持ち帰るのだ。つまり、いくら港の税関の取締りを厳しくしてもドラッグの流入は防げないのが日本の現実なのだ。
日本はこのように、島国といえども関係なくドラッグに入り込まれやすい地帯なのだ。ドラッグから身を守るためには、そんな現実を認めて個人各々が「ドラッグには手を出さない」という強い意志を持っていくしかないのである。
(談・北芝健/構成・テルイコウスケ)
shibakenprf.jpg●きたしば・けん
犯罪学者として教壇に立つ傍ら、「学術社団日本安全保障・危機管理学会」顧問として活動。1990年に得度し、密教僧侶の資格を獲得。資格のある僧侶として、葬式を仕切った経験もある。早稲田大学卒。元警視庁刑事。伝統空手六段。近著に、『続・警察裏物語』(バジリコ)などがある。
アヘン王国潜入記
ケシ畑で農業体験?
amazon_associate_logo.jpg
【関連記事】 止まらない芸能界のドラッグ汚染──”薬”を手放せない悲しき業界
【関連記事】 相次ぐ大学生の大麻摘発 裏にはお役人の点数稼ぎ
【関連記事】 闇社会の勢力図と今後の展開 そしてそのキーパーソンとは!?
「硬くなりすぎよ…」1980円の●●で妻が泣くほどフル勃◯!マカより凄い3大…
株式会社クロコス
「夫がビンビン過ぎて…」1980円の●●で妻が泣くほどフル勃◯!マカより凄い…
株式会社クロコス
伊東家の裏技「更年期女性の50㎏以上は絶対痩せる」9割が知らない3日激やせ方法
ハハハラボ
「勃◯し過ぎ���…」1980円の●●で妻が泣くほどバキバキ!マカより凄い3大…
株式会社クロコス
最終更新:2009/07/25 18:00
-ADVERTISEMENT-
Twitterでシェア
[PR]「お腹の脂肪は菌で減ると判明」NHKが特集した菌で脂肪減少
[PR]「NHKが放送」体重落とす菌が爆売れ
こちらもおすすめ
伊東家の裏ワザ「顔が垂れ下がったら絶対やって」女性の9割知らないと驚愕
PR (FABIUS)
“パクリ”批判の声も…1月期ドラマは吉高由里子『星降る夜に』と井上真央『100万回言えばよかった』の一騎打ち?
「歯磨きに〇〇混ぜるとセラミック級の白い歯に」簡単すぎて大炎上
PR (ソーシャルテック)
コーヒーで黄ばんた歯が真っ白に!ドラッグストアで売り切れ続出中
PR (マーキュリー)
インプラントはあなたが思うより安くなるかもしれません
PR (Red Gobo)
医師の夫「痩せすぎるから1日1錠ね」更年期主婦の9割が3日で66kg→44kg
PR (ピュレアス)
更年期の薄毛女性の9割が成功!ドラッグストアで即売り切れ続出中
PR (RAVIPA)
「吸いごたえヤバイ」ヘビースモーカー救済タバコがメガヒット
PR (北の達人コーポレーション)
キムタク「テレビに出づらい奴」発言、平野紫耀と黒島結菜…2022年7月の人気芸能記事
「バカ売れの育毛剤ニューモ」使いすぎた男の末路とは
PR (ニューモ)
“目の下だるん”に刺すヒアルロン酸が凄い!貼って寝るだけでハリが…
PR (北の達人コーポレーション)
「女性の薄毛は簡単だと判明」ドラッグストアで即完売
PR (ヴィワンアークス)
実は女性薄毛の原因は「あるモノが足りないから」と判明!専門家の妻が暴露!
PR (ヴィワンアークス)
「タバコ吸うならこっち吸う」たばこ税ゼロの新型タバコなら1日264円
PR (ロックビル)
「脱毛行くよりコレ塗って」アソコの毛もツルツルにできる裏ワザ大公開
PR (グロリアス製薬)
伊東家の裏ワザ「だるシワ顔の45歳が25歳に若返り」9割知らないと驚愕
PR (リタマインド・ジャパン)
NHK紅白、いまさら「工藤静香に篠原涼子」の崖っぷち度
爪の中まで殺菌!4度完売、絶賛の声続出の爪周り薬用ジェルの秘密に迫る
PR (北の達人コーポレーション)
「右脳を使えば記憶力は鍛える必要ない」9割が知らない記憶力を5倍にする裏ワザとは
PR (Art of Memory)
乃木坂46与田祐希の『格付けチェック』発言がカット? ネット上ではあだ名が定着
【歯が白くなる10秒習慣】黄ばみっ歯の人が知らない魔法のアイテムとは
PR (株式会社VC)
ちゃんぴおんずは優勝でブレイク?『ぐるナイおもしろ荘』出演芸人のネタを全検証
登録不要!自分の家じゃなくても実家の価値を調べられるサイト
PR (HOME4U)
キンプリの不仲説が飛び交う中で… テレビマンが見た笑顔のメンバーたち
キンプリ分裂劇の謎、キスマイ“テレ東スルー”の不可解…2022年11月の人気芸能記事
Recommended by
仮想ライブ空間SHOWROOMで人気アイドルの配信を無料視聴
PR(PR)
イチオシ企画
「クリティカル・クリティーク 」気鋭の文筆家によるカルチャー時評
写真
特集
宇多田ヒカル「First Love」とアジアの“青春”
写真
人気連載
『どうする家康』は大河の伝統を覆す?
写真
インタビュー
クリエイティブな次世代モデル・MONICA
写真
配給映画
サイゾー人気記事ランキング
05:20更新
連載・コラム
総合
『すずめの戸締り』大ヒットの裏で…
大ヒット作の失敗大失敗続編たち
『どうする家康』は大河の伝統を覆す?
『芸能人格付けチェック』高視聴率の裏事情
賛否両論必至の「ラ王」新商品実食
ハーヴェイ・ワインスタイン事件描く映画
『THE FIRST SLAM DUNK』に感じた違和感
『笑点』亡き円楽の後継争いが熾烈!
「独立」と「性加害」の芸能界
星野源、だし巻き卵の作り方から人生を熱弁
関連キーワード
カルチャー 警察 戦争 暴力団 犯罪 鉄道 北朝鮮 早稲田大学 航空 沖縄 アメリカ 講談社 農業 闇社会 月9 家電 オウム真理教 インド 六本木 M 関西 コント 芸能界 日本 北海道
日本はドラッグ無法地帯!? ドラッグの世界潮流と日本ドラッグ事情のページです。日刊サイゾーは芸能最新情報のほか、ジャニーズ/AKB48/アイドル/タレント/お笑い芸人のゴシップや芸能界の裏話・噂��お届けします。その他スポーツニュース、サブカルチャーネタ、連載コラム、ドラマレビューやインタビュー、中韓など社会系の話題も充実。芸能人のニュースまとめなら日刊サイゾーへ!
日刊サイゾーとは
会社概要
お問い合わせ(情報提供/記事)
広告に関するお問い合わせ
プレスリリース掲載について
個人情報保護方針
Cookieポリシー
月別アーカイブ & キーワード索引
株式会社サイゾー運営サイト
copyright © cyzo inc. all right reserved.
3 notes
·
View notes
Text
Doc Martin(ドクターマーティン)1-4
マーティンが断り余ってしまったダンスパーティーのチケットを、ルイーザは駐在マークにあげてしまい、頭の痛い勘違いを引き起こす。一方マーティンは、ポートウェンから離れて住む森林保護官のもとへ出張診療するが。。。
気になる語���・ノート
医療
- bacterial strain:細菌株
- nitrazepam:ニトラゼパム - ベンゾジアゼピンの一種で睡眠薬などとして処方される - 依存性が強く、長期服用の場合などは忌避される
- insomnia:不眠症
- benzodiazepine:ベンゾジアゼピン
- CPN:地域精神専門看護師 - イギリスの地域精神医療制度のもよう。自宅へ行ったり、GPの診療所へ出張して診療し、より高度な医局へreferしたりする - GPも含めて、イギリスの地域医療はナカナカ面白い仕組みの模様
- sprain:捻挫
- ligament:靭帯
- ascorbic acid:アスコルビン酸 - ビタミンCとして作用する
- de-alpha tocopherol:D-α-トコフェロール - ビタミンEとして作用する
- pyridoxine:ピリドキシン - ビタミンB6として作用する
一般
- mug:強請る、たかる - ほかにもマグカップ、バカ、変顔する、(知識を)詰め込むなど幅広い意味がある - The drug is a mug’s game:ヤクなんてのは愚か者のやることさ
- auspicious:素晴らしい、吉兆の、成功を見込む
- nab:取り押さえる、捕まえる、とっ捕まえる - We’ve got to gather 4 people to play Mahjong and still one to go. Why don’t we nab the guy over there? Hey Stewart, come over!:麻雀するには4人必要だが、あと一人たりない。あそこのヤツをとっつかまえるとするか。おいスチュワート、こっちこいよ!
- pass up:(良い機会を)のがす
- appal:ぞっとさせる、嫌悪感をもよおさせる
- blimey:冗談じゃない、おいおい、まじか - イギリスではよくつかわれる表現 - ハリーポッターの親友ロンが連発する傾向にあり、邦訳で「おったまげー」などと訳されているのは”blimey”
- blackbird:クロウタドリ
- blackcap:スグロムシクイ
- bluetit:アオガラ
- brambling:アトリ属の一種
- bullfinch:ウソ
- chaffinch:ズアオアトリ
- thistle:アザミ
- groundsel:キオン属の総称、主にノボロギク
- whinger:泣き言野郎、不平屋
- perky:はつらつな、活発な、生意気な
- the showers:勃起時と通常時で男性器の大きさが変わらないこと - the growersが対義語 - 劇中では、この「シャワーズ」のことなのか、シャワーで見る限りではということなのか少し判別つかない。面白いから「シャワーズ」の意味でとっている笑
- arm and a leg:(コストが)莫大な
- afar:遠く - from afarなどとするが、少し古風な用法
- jamboree:お祭り騒ぎ、パーティー、ボーイスカウトのキャンプ大会
- bloke:lad、chapに同じ - この手の言葉のニュアンスの違いをだれか教えてほしい。。。おそらく地域や年代によって差異があるのだろうが
- lynch:私刑、リンチ - 古典的な”lynch”は”get tar and feathers”。。。タールと羽を体中にくっつけて市中引き回しというマジで意味不明な儀式 - 宗教もしくはケルトの伝統か?
- neurotic:神経質な、神経症の
- audacity:豪胆さ、厚顔さ、ずうずうしさ
- conceive:妊娠する、はらませる - 劇中の表現にならえば、こうなるか - Christmas Eve. It’s the night most of Japanese children are conceived. - 言い過ぎは承知笑
- fussy:小うるさい、こだわり屋
- delusion:妄想、錯覚、間違った信念
- every now and then:しばしば、時折、折に触れて
- over the top:やりすぎる、いきすぎる - You’d better apologize to her for the last night drink. You’ve gone over the top.:昨日飲んだ時のこと、彼女に誤っておいたほうがいい。あれはやりすぎ。
- gang up on:寄ってたかって攻撃する、徒党を組む
ストーリー・感想(※ネタばれ注意)
第3話のラストで一緒にパブに出かけるなど、少し距離が近くなったルイーザとマーティン。バートからダンスパーティーのチケットを二枚買ったルイーザは、マーティンを誘う。本話もルイーザが積極的に動くものの、マーティンのような人間に「パーティー」なんて持ち出すのは論外だろう。案の定、断られてしまう。 やむを得ずパーティーに参加することがあっても壁に寄りかかって静かに時間をやり過ごし、頃合いを見て早退するのが 、私も含めたこういう手合いの生態だ笑
行き場を失ったチケットは、たまたま通りがかった駐在マークの手に入る。これが要らぬ誤解を生んでしまう。 マークはアホとまで言わないが、そこら辺にいる「ちょっと挙動が人とズレた」感じの人だ。例にもれず異性関係も得意でない。そんな人だから、実は恋焦がれていたルイーザからパーティーのチケットをもらったとき、即座に「デートに誘われた」と解釈してしまったのだった。 まあ世の大半の男性であれば、少しソワソワしてしまうシチュエーションだし、私もするだろう笑 そして同じような文脈で本当にデートのパターンだって少なくないだろうことを思えば、ルイーザの言動も軽率だったはずだ。女性の意見を聞きたい笑
さて、彼のウキウキもつかの間である。マークは以前付き合った女性に”too gentle”と言われてフラれたことを曲解?してか、アレの大きさが不安でしょうがない。不安のあまり、ネットで見つけたサプリを常用しているほど。 ルイーザの「誘い」をきっかけに、彼は診療所を訪ねる。ここのやり取りがナカナカ秀逸だ。
Netflixの邦訳はかなり飛ばしたり暈したりしているので、拙訳を下記に。
Doc「つまり、あー、君はアレの大きさに問題があると?」 PC「わからない。”The showers”であることも一つだけど、わからない」 Doc「専門医を紹介しよう」 PC 「いや、普通のサイズを知りたいだけなんだ」 Doc「普通にも範囲があって……」 PC 「そうじゃなくて、僕も測ったわけじゃないけど……そう、6インチ、6インチは普通だと思うか?」 Doc 「6インチなら普通だろう、うん、うん……よし、問題は解決だな」 PC「そうか……」
一度席をたつが、振り返るマーク
PC 「……つまり、5インチあたりは少し……」 Doc 「そうとも限らないさ」 PC 「さらに言えば、5インチよりも小さいのは良くない…と?」 Doc 「いや、あー、問い合わせてみないことには」 PC 「7-8インチであれば、と、と、問い合わせる必要すらないだろう?」
ちなみに、イギリスの公的保険機関である”National Health Service”は男性器のサイズについて大学との共同研究結果を公表している。 こちらの大本の研究やKCLの研究によれば、通常時は約9.2cm、勃起時は約13.1cmつまり5.1-2インチ程度ということらしい。らしいぞ、男性諸君。 そしてこの話題が男にとって如何に興味惹かれるテーマかは、マークの言動や、私がどれだけ字数を割いているかからもお察しいただけよう笑 くれぐれも言動には注意し給へ、女性諸君。
閑話休題、ここからは2つ目のサブストーリーも展開されていく。 エレインが現れ、町はずれに住むレンジャー(森林保護官)の電話が繋がらないから出張診療が必要であるという。 マークがルイーザからデートに誘われたとその直前に聞いたマーティンは明らかに動揺しており、レンジャーについての大事な情報を聞き逃す。
レンジャーのスチュアートを訪れるマーティン。Portwenn住民の悪口で意気投合するが、依存性の強い向精神薬を寄こせといい、さらにその薬はスチュアート本人ではなく友人アンソニーのためのものだという。
Ranger「アンソニーは今とても心細いんだ。ハイイロどもがそこら中にいやがるし」 Doc「ハイイロ?」 Ranger「ああ、やつらは何処にでも出てくる。しかもかなり攻撃的だ。お陰でアカはほとんど残っていない……おいおい、アカがいつもおびえて暮らしてるのはみんな知って…」
いきなり散弾銃をかますスチュアート
Ranger「見たか?あのクソいまいましいやつめ!ただ違う色だとか、触り心地がよさそうだとか言う輩もいるが、奴らはリス版のナチスだ!」 Doc「あー……君の友人アンソニーはリスなのか?」 Ranger「そうさ、この国には昔300万ものアカがいたものさ。いいか、300万だ。アンソニーはただのリスなんかじゃない。生残者だ」
いきなり妄想に向かって散弾銃をぶっぱなすイカレ野郎であった。さらに言えば、このアンソニーは人間大の赤毛のリスだという。怖いわ! スチュアートが引き留める中、マーティンはなんとかPortwennに帰り着く。彼をしかるべき保護監視下におくため、ダンスパーティー会場にいる駐在マークを探しにいく。
折しもダンスパーティーはピークだった。ルイーザはなんとか誤解を解こうと話をもちかけるが、マークはお気に入りのナンバーにノリノリで、とても話ができる状態ではない。音響もうるさいからと彼の耳元へ口を寄せた瞬間、間の悪いことにマーティンが到着し、二人の目が合う。ルイーザは言葉を失い、マーティンはそのまま会場を後にする。
会場を出ると、外は外で人だかりがある。スチュアートが激情して、他人の家で鳥の餌やりなどを壊して回っていたのだ。 翌朝、マーティンはマークとともにスチュアートを再訪し、薬を手渡す。前任者がニトラゼパムと偽って処方していたのがただのビタミン錠だと知り、しばらくはマーティンも同じやり方で様子見することにしたらしい。
帰りの車内で、ルイーザとの関係が進展しなかったこと、「これが運命の人」だと思えなかったことをマークから聞くマーティン。それで表情を緩めてしまうマーティンが可愛い。マーティンは逆に、マークが購入した「増大化サプリ」の真の姿はマルチビタミン錠、つまりプラシーボであることを明かす。もちろん動転するマークだが、ルイーザの件で振り回されたマーティンとしては多少胸のすく想いだろう笑
ちなみに本話には、小さいが大事な3つめのサブストーリーがある。小学生ピーターは学業的には極めて優秀。しかし社交性がなく、思ったことをずけずけと言い放ち、むだな教育には関心を示さない、教師としては扱いづらい生徒だろう。さながらミニマーティンだ。 ピーターは、本話の途中、スチュアートが破壊した鳥の餌場を持っているところを発見され、状況証拠から犯人に仕立てあげられてしまっていた。パーティーの夜の騒ぎで真犯人が判明すると、ルイーザからは「勘違いで咎められて、なぜ弁明しないのか」と問われ肩をすくめる。
これは盛大なブーメランではないか。ルイーザにあっても、誤解を与えたと思ったなら、マークやマーティンにすぐ説明すればよかったのだ。大人が子供を詰問するとき、冷静に考えるとブーメラン発言ということは少なくない。本話の視聴者に向けたメタ的メッセージと捉えるのがよさそうだ。
3 notes
·
View notes
Text
09072014
「読了、と。」
相変わらず小説を一本読み終えたような疲労感だ、と思いながらも、胸に巣食う不快感は抜けない。それは下手な話を読んでしまったからでもなく、内容が気持ち悪いからでもない。彼の書く小説は大体どれも悍しく、内臓を指で掻き回され、神経を指で直接嬲られているような感覚になるからもう慣れてしまった。
原因は、ただ一つ。
「...彼は、本当に皮膚が好きだな。」
筆者のフェティシズム。いわゆる性的嗜好の中に、皮膚愛好が時折含まれているということだった。大概のフェティシズムは容認出来る。魅せ方によってはむしろ魅力に気付かされ、此方が嵌ってしまう可能性すらある。事実僕は彼の小説に出会ってから、街ゆく人の眼球や、喉元や手先をよく見るようになった。彼の小説にあったような、口の中で転がすと鈴の音がなりそうな綺麗な眼球だ、犬歯を立てて噛めば齧りやすそうな白い喉だ。彼の小説で犠牲になった人のような、細く折れやすそうな指だ。頭の中で妄想していた曖昧な景色が現実と重なることで輪郭を得て、実写映画のように動いていく様に興奮したことは一度や二度ではない。
つまりは、少なくとも彼の小説において、フェティシズム自体に対する拒否反応は起きないということだ。ならばなぜ、この鳩尾から這い上がってくるような不快感と戦う羽目になったのか。
僕は、人の皮膚が苦手だ。
すれ違う人間と触れ合っただけでもぞわぞわと毛が逆立って、その部分の皮膚を削ぎ落としてしまわないと気が済まないような気分になってくる。勿論、低いながらも社会的地位がある僕は実際に行動には移さない。後に残らない程度にそこを擦り、掻いて、心を沈める。大丈夫、触れただけ、綺麗になった、もう大丈夫。そう言い聞かせて、1人になった瞬間声を出し発散する。ああぁぁあぁぁああぁあああぁぁぁあああ。何度かそうして頭を掻き回して部屋を歩き回ってはちゃめちゃに動いて、呼吸を出し切って、僕は僕に戻れる。皮膚、ならどこでもダメだった。手も、腕も、足も、爪の先ですら、人の皮膚らしい産毛の生えた柔らかな肉に触れた瞬間、気が狂いそうになる。正常でいたいと叫ぶ僕の脳が暴れ回る。
ひふ。皮膚。肌。上皮。ああ、その響きは僕にとって全て黒板を引っ掻く音。銀歯でアルミを噛む味。生理的嫌悪。精神病の一種なのだろうか。分からない。
自分の異常さを何度直そうと思ったか分からない。高級ソープから安い場末のデリヘルまで、数多の女を試した。さすがに男に走る気にはならなかった、というか、男であれば、道でぶつかる程度の接触には耐えられた。不思議だった。だから、色んな女に触れて、その度に敗北して帰ってきた。今日もダメ、美人も、可愛い子も、不細工も、平等に、生物学上女に分類される生き物の皮膚は全てダメ、というのが自身で出した結論だった。カタワ、その言葉が頭の中をぐるぐると回る。崇高な母親のもとで育てられ、様々な主義主張に触れ、結果ナチズムを崇拝する立派なレイシストとなった僕にとって、己が動物以下の生き物に成り下がることは到底耐えられなかった。今この世でT4作戦が始まったら、僕が対象になるのではない���。そう思うだけでもう、脊髄から神経をずるずると引きずり出されるような、じっとしていられない耐え難い苦痛に襲われた。
慣れることは出来なかった。無視して生きることは、もっと出来なかった。そんな僕にある日突然、受胎告知の如く正解が舞い降りた。僕が今までたどり着かなかった境地を、神は僕に与えてくれた。僕が優れているからか、選ばれたからか、それは天国へ行ったとき聞かなければわからないが。
目の前に転がる身体を、ゴム手袋越しに触ってみる。やはり、二の腕がぞわぞわりと粟立つ。鳥肌だ。ああ、寒い。掻き毟りたい。叫びたい。耐えろ、我慢だ。滅菌済パックを破りメスを取り出した。鋒を二の腕の内側に突き刺し、一本線を引いてみた。どうやら、骨と皮との間、皮下脂肪ごとひっぱり剥がせば上手く剥がれるらしい。まだ温かい肉の中に手を差し入れてみれば指の腹に硬い触感を感じる。これが骨か。ならば。隙間に合わせて指を這わせる。体内の、筋肉の緩やかな曲線と弾力を感じる。手の甲にぬらぬらと纏わり付く黄色い皮下脂肪。この調子でいけば、いけるかもしれない。身体をひっくり返し、背中にも真っ直ぐ一本、メスを入れる。綺麗に剥がなければ、僕の目的は達成されない。一度しかないチャンスを逃してしまえば、僕は一生カタワのままだ。落ち着け、落ち着け。ああ、そういえば、最初よりも幾分か、皮膚に触れられている気がする。ゴム越しだが、感じる皮膚の触感に、少しだけ、慣れたような気がする。柔らかな、産毛の感覚や手に吸い付くような質感はまだ味わえてはいないけど、でも、味わいたいと思い始めている。
所々萎びた背中の皮膚。一本通った赤い道から指を差し入れ、背骨から肋骨へ、骨を目指して、背中を抱きしめるようになぞり、指をめり込ませていく。
「良かった、何度皮膚を無くそうと思ったか。その度に立ち止まって、衝動を抑えた。彼らのようにバールで、コンクリートのブロックで、踊るような彼らを、何度羨ましく、憎らしく思ったか。ああ。」
首、手首、足首は切り落とし、それぞれから皮膚を剥ぎ取って並べておいた。体の部分、マネキンのようになったそれは床でべしゃり、轢き殺された蝦蟇のようにうつ伏せで這っている。背中の皮膚は大方剥がれた。身体をひっくり返し、同じように筋肉と骨の隙間、僕が還るべき場所へ還るように、手を馴染ませ、撫でて、愛していく。意を決して、ゴム手袋を外してみた。
「僕はこの光景を何度夢想したか分からない。己が正常に戻る日を、何度夢に見、そして泣き、心を折られてなお夢に見たか、分からない。」
素肌で、筋肉繊維に触れてみる。脈動も燃えるような熱さも感じない。緩く硬い感触。だが、ただ、人に、触れられている、その幸せだけが胸を満たして、じわり、視界がぼやけて滲んでいく。僕は、人に、触れた。素手で、人に触れられることができた。こんなもの、進歩でも何でもないと嗤う人はいるだろう。でも、僕の中では立派な進歩、成長、進化だ。
事前に、彼と僕とのつながりは全て絶っておいた。と言っても、閲覧履歴を消し、ブックマークを解除し、印刷しておいた彼の作品をシュレッダーに泣く泣く掛け水に溶かしてトイレに捨てただけ、だが。それで証拠の隠滅が出来るのか、知識のない僕には分からない。
ただ、彼に迷惑をかけるようなことがあってはいけないと思う気持ちが半分、彼の作品に触発されて行動した模倣犯扱いされたくない気持ちが半分だった。
模倣犯。何と嫌な言葉の響きだろう。僕は別に彼になりたいわけでもなく、彼の書く話の主人公達になりたいわけでもない。他人に感化されて人生を曲げるほど愚かな人間ではないし、自分の頭で自分の人生について考えられる程度の知能は持って生まれてきたはずだ。だから、あくまでも僕は、彼の小説は趣味として好んでいただけで、何も影響なんてされていない。
第一彼だって、自分の話を読んだからといって軽率に真似されるのは不快だろう。彼には彼の矜持がある。高尚な、僕の脳では追いつかないグロテクスでナンセンスでノーモラルな彼の世界がある。僕はそれを下から見上げながら、目の前に続く僕の人生を歩む。ただそれだけ。
「よし、だいぶ進んだな。」
上半身はすっかり、ダイビングスーツのような有様で萎んだ皮と剥き出しになった血液塗れのピンク味を帯びた肉になった。綺麗にできているはずだ。比較対象がないから、何とも言えないが。下半身。と視線を移して、はて、どうしよう。と首を傾げた。
局部の処理はどうしよう。周りを見渡す。ああ、包丁があった。丸く切り込みを入れて、そこは残しておこう。大切な場所だから。無闇に傷付けるわけにはいかない。ああ、これで、ちょっととちった部分もあったけど、綺麗に皮膚が全て剥がれた。幸せだ。どうしよう。ああ。達成感。
いや、そんなことはどうでもいいんだよ。忘れてた。そばに落ちてた服で手を拭いて、懐に置いておいた、中学の頃からずっと大切に使ってる裁縫セットを開けた。1番太い糸、黒しかないがまあいいか。針に糸を通すのは昔から得意だった。並べていた手足を指先で摘んで、ちまちま、恐る恐る、裏返していく。あれ、やっぱり、触っても大丈夫みたい。一度、してみたかったことが、出来るかもしれない。僕は一度針を針山に刺して、恐る恐る、左手を、左手の中に入れた。僕より小さい手。無理矢理ねじ込んで、血と脂でぬかるむから案外奥までちゃんと入った。軍手みたい。左手を、そっと持ち上げて、そして、僕の頭へと、それをポン、と置いた。
「あああ、ああああ、あああああああああああ、」
嬉しい、嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい!!!!!!背筋が全部鳥肌になったみたい、ぞわぞわぞくぞくして、ああ、何だか失禁しそう。僕、僕、ずっと頭を撫でられたかったんだ、でも、人の皮膚が頭に乗るって考えただけで、その皮膚から、得体の知れない毒素がじわりじわりと滲み出て、頭皮を覆い、その生温い液体がこめかみを伝って耳を流れ、しまいには頭蓋骨から僕の脳へ染み込んで侵食してくるような、悍しい、ただただ悍しい感覚がした。正気じゃいられない。
それが今はどうだ。こうも、当たり前のように、人の手に優しく頭を撫でられる多幸感を享受して、当たり前の人間のように、僕は、ああ。
ずるり、手を抜いて少しだけふやけたように膨らんだ皮膚をひっくり返す。ひっくり返す。ひっくり返す。ひっくり返す。ひっくり返す。ひっくり返す。ちくちくと地味な作業は案外得意だと手首と手、足首と足、首と首をつなぎ合わせて、縫っていく。そういえば僕が昔見たアニメ映画に、こんな感じのヒロインが出てきたような気がする。可愛かったなあ。よし、出来た。
「よし。」
身につけていたものを全て取っ払い、僕は、目の前に出来上がった、裏返しになった皮膚の背中に手を入れて、ぞわぞわと、肌を擽る産毛の感覚に脳内物質をどぱどぱ溢れさせながら、ゆっくり、じっくり、着ていった。手、手首、指先が指先へ到達し、ふわりぺちゃりと密着する。汗ばんでいるのは僕の素肌か。別人のようだと、どこか客観視している冷静な自分が感心する。ぱつぱつなはずなのに伸縮性のある皮膚は僕の太ももも二の腕もお腹も全て包み込んで、背中はさすがに開いているけど僕は頭まですっぽり、人の皮膚に覆われた。髪がごわごわがさがさと擦れあってくすぐったい。ああ、凄い、僕はやっぱりカタワじゃなかった、正常だった。理解し難いフェティシズムにも打ち勝てた。
視線を落とす。肋骨、乳房のすぐ下に、1センチ四方の規則正しい穴があった。動く度に、内側にあるカサついた唇と僕の唇が触れ合って何だか少し恥ずかしい。ちょこん、お皿に乗ったそれをぐちゃぐちゃした指でつまみ上げて、そして、真皮側を舌に、そっと、乗せた。
あぁ...彼はやはり、本当に皮膚片を食べたんじゃないだろうか。あんな的確な食レポ、とても想像だけでは書けないはずだ。きっと彼も僕と同じように舌にこの塩っけとヌルヌルした脂の匂いを感じて、そしてそこにほのかな甘みも感じたはずだ。ミルクのような、蜜のような、ほのかに微かに香る甘味を、僕は感じている。ころころ、転がす前に、舌を駆使してその皮膚片をひっくり返す。と、思わず娼婦のような悦に浸った声が出てしまった。あぁっ。それは産毛が僕の味蕾で遊ぶ感覚によるもので、あぁっ。もうダメ。イっちゃいそう。いやむしろ漏れちゃいそう。あっ、失禁、本当だ。彼は凄い、天才だ。
出し終わってスッキリした僕は床に座り込んで、体育座りをしてみた。全身の肌という肌に皮膚がまとわりついて、包まれて、脳がゆらゆらと湯煎されて溶けていくチョコレートのように、耳から流れて出ていきそう。目の前に転がったズル剥けの身体。綺麗に残った陰部。
粘膜の接触。それは僕が想像すらし得ない境地。彼の小説においても、粘膜の触れ合いが細かく書かれたものはない。恐らく彼は女性が苦手なホモセクシュアルか、もしくは無性愛者か、インポテンツだろうと予想していた。すっきりしたせいか、僕はすっかり興奮してしまっていた。今なら、こうして皮膚を纏えた今なら、何も怖いものはないのかも知れない。よし、いける、出来る。僕はぬるぬると滑る太ももに指を立てて何とか固定し、そして、テレビで見たセックスをした。ズン、と奥まで入り込む僕の陰茎が中で喜びに震えている。子供の素を、奥に奥に送り込もうと腰が揺れる。届け、届け。
「ママッ!!」
思えば、最初に嫌悪を覚えたのは、母に手を繋がれた時だった。買い物の帰り、まだ子供ながらに、そのかさついた手に触れられることがどうにも気持ちが悪く、振り払って手が血塗れになってもアスファルトに擦り付けていた。
「ママッ!!」
さすがに照れ隠しだとは思わなかったんだろう、そこから母は、僕に触れるのをやめ、腫れ物にでも触るかのように僕と接した。諦めが悪いのが女の特性なのか、それでも時折僕と接触を図っては、傷付いた顔を見せた。手を繋ぐ、頭を撫でられる、肩を叩かれる、手の大きさ比べをする、どれもこれも、僕は自分の手を切り落として見せつけてやりたいほど嫌だった。病気になって膝枕された時も、あれは気分が悪くて吐いたんじゃない。耳に当たる母の太ももの生暖かい体温に耐えかねたからだ。
「ママッ!」
何故なのか、分からなかった。最初はこの女が何かしらの毒素かオーラを出しているんだと思った。次は、宇宙から放たれた電磁波が脳に悪影響を及ぼしているんだと思った。アルミを巻いてもお題目を唱えても、治らなかった。そしてそれは、母以外の女へも波及していった。カタワにさせられたんだ。
「ママッ!」
何もかもが嫌だった。別に普通の母親だ。父が事故で亡くなってから、女手一つで僕を育てた立派な母だ。何が嫌だったのか、今となってはもう確かめようもない。少なくとも、僕は母がいなければまともなまま悩むこともなく、彼の小説を楽しみ、生きられたということだけは分かる。汗が皮膚と肌の間を伝って、いつかソープで塗りたくられた潤滑油のような感覚を覚えさせた。ああ、考えてるうちにまた射精しそうだ。赤ちゃんの部屋まで競争だ。届け、届け。
「届けッ!届けッ!」
2 notes
·
View notes
Photo

劇評など critic
作品をめぐるこれまでのテキス�� ※敬称略 ※所属や肩書きは執筆当時のもの
カトリヒデトシ(2010) 平山富康(2010) 亀田恵子(2010) Marianne Bevand(2011) 間瀬幸江(2011) 唐津絵理(2011) 金山古都美(2012) 島貴之(2012)
/
カトリヒデトシ(エム・マッティーナ 主宰 舞台芸術批評)
「なぜ日本人がチェホフをやるのか?」と問うのは、かなりダサい。
今までの蓄積に付け加える、新しい文脈・意味を発見し提示するのだという優等生的な答えは間違っていると思っている。それでは、ヨーロッパ文化をきちんと学んだという模範解答になり、単なるレポートになってしまうだろう。
古典を何度でも取り上げることは、芸術の目指す「絶対的有」への敬虔な奉仕である。「有りて在るもの」への畏怖の気持ちは洋の東西といったものは関係ない。芸術へひざまづき、頭をたれることは、芸術家の基本的な資質であるし、それこそが歴史や文化的差異を超えようとする意思の現れにつながっていく。現代から古典を読み直し、古典から現在を照らすことにこそ、古典に取り組む大きな意味がある。
また、孔子は論語で「子は怪力乱神を語らず」といった。これは軽々しくそれについて語ってはならないと理解するべきで、超常現象にインテリは関わらないということではない。芸術は人間を超えた存在、「不可知な存在」を認知することが第一歩であろうから。
第七の演劇には、不可知が全体を包みこもうとする力。またそれに触れた人間の、根源的な「生」への畏怖がよく現れている。
それらの二点で第七劇場は大切な存在だとおもっている。 たとえば、今回の「かもめ」はチェホフの本質に迫ろうとする試みである。
ダメな人間がダメなことしかしないで、どんどんダメになっていってしまうのがチェホフ世界の典型である。そこには没落していく帝政時代の裕福な階級を描き続けた、彼の本質が現れている。
それはチェホフには、たれもが時代に「とり残されていく」、乗り遅れていく存在であるという認識があるからである。つまり、「いつも間に合わないこと」こそが人の本質なのだという考えである。
取り残されていくことは悲しい。何も変わらなければ既得権を維持できるものを、時代の変化によって、何もかもが「今まで通り」ではいかなくなる。チェホフはそれを、「われわれは絶えず間に合わず、遅れていく存在なのだ」と確信にみちて描く。苦い認識である。
人間はいつでも誰でも、既にできあがった世界の中に生み落とされる。誰もがすべてのものが現前している中にやってくる。個々人は、養育や教育によって適応をうながされるだけである。人は限りない可塑性をもって生まれるが、時代や地域や環境によって、むしろ何にでも成り得たはずの可能性をどんどん削ぎ落とされていく。
現在ではすたれてしまったが、日本には古代から連綿と続いた信仰に「御霊」というものがある。人は死んだ際に、現世に怨みを残して死ぬと、祟るものだという信仰である。「御霊」は、残った人たちに、天災を起こしたり、疫病を流行らせたりする。やがて人々は天災疫病が起こった時に、誰の「祟り」であろう��考えるようになる。それを畏れるために死んだものの魂が荒ぶらないように崇め拝めるようになっていく。人々に拝まれ、畏怖されるうちに、荒ぶった魂は落ち着いていき、「神」として今度は人々を護る存在へと変わっていく。だから「御霊」はおそろしいものであるだけではない。
「荒ぶる魂」を、第七は「かもめ」の登場人物たちの「遅れ」「取り残されていく」姿の絶望の結果に見る。舞台はその絶望からの荒ぶりに共振し、増幅し、畏怖を現す。
チェホフの持っていた、人に対する「諦観」を大きな包容力で抱え込んこんだ上に、零落していくことへの激しい動揺を、魂の「荒ぶり」として表現する。それは現在の私たちでは到底もち得ない、激しい「生」の身悶えである。
その方法として舞台に遠近法が援用される。 奥行き作り出すことによって、「位相=層=レイヤー」が作りだされる。 後景の美しいオブジェは遥かに遠い「自然」の層で、あたかも人の世を見つめ続ける「永遠」や「普遍」を感じさせる。そして中景は「六号室」のドールンのいる老練の世界、経験に基づいて生きる老人の世界である。患者たちは遊戯する体を持ち、永遠の世界を希求する。その三層を背負って、最前景で「かもめ」の世界が現れる。かれらは都会と田舎、人と人の現世の距離によって引き裂かれていき、苦しみ世界を生きるものとして描かれるのだ。
そう、日本人「にも」チェホフが描けるのではない。 日本人「にしか」描けないチェホフがあるのである。
/
平山富康(財団法人 名古屋市文化振興事業団 名古屋市千種文化小劇場 館長)
遡って2010年2月、名古屋市の千種文化小劇場で企画実施した演劇事業『千種セレクション』(同劇場の特徴的な“円形舞台”を充分に活用できそうな演出家・団体を集めた演劇祭)で、第七劇場の『かもめ』は上演されました。企画の立ち上がった頃には、第七劇場は『新装 四谷怪談』の名古屋公演を既に果たしていて、その空間演出力が注目されていた事から企画の趣旨に最適でした。参加団体は4つ、持ち時間は各60分。それぞれ会話劇・現代劇の再構成・半私小説的創作劇とラインナップが決まる中、第七劇場のプレゼンは“チェーホフの『かもめ』を始めとする幾つかの作品”との事…たったの60分で。一体、どんな手法で時間と空間の制約に収めるつもりなのか。当惑をよそに第七劇場が舞台に作ったのは、さしずめ「白い画布」でした。舞台は一面、真っ白なリノリウムが敷かれ、無骨な机や椅子との対照が、銅版画のように鋭利な空間を立ち上げていました。舞台と同じく白い衣装をまとった俳優(彼女らは『六号室』の患者たち)は静謐な余白のようです。が、幕が開いて、彼女らが見せる不安な彷徨と激した叫びが「鋭利な銅版画」の印象をより強めていきます。この画布が変化を見せるのは、チェーホフの他作品の人物たちが続々と舞台に位置を占めていく時でした。彼らは暗い色の衣装をまとって、これまでの描線とは異なる雰囲気です。こうして、既にある版画の上から幾人もの画家が新たな絵画を描くように芝居は進みました。幾つもの物語の人物が、互いの世界を触れあわせていく現場。彼らが発する言葉と声、静と動が入り混じる身体の動きは、新たな画材でした。時に水墨画、木炭、無機質なフェルトペン。余白を塗り込めたと思えば余白にはねのけられる「常に固定されない描画」のようにスリリングな作劇が、観客の前でリアルタイムに展開されたのです。終演後のアンケートでは“視覚的に美しい贅沢な構成” “話を追いそこねても目が離せなかった” “世界がつくられていく感覚” “難しい様で実はわかりやすい”と、中には観劇の枠に留まらない感想も多々あり、第七劇場が『千種セレクション』で残したのは、限られた空間で無限に絵画を描く様な演劇の可能性だった…というのが当時の記憶です。名古屋市の小劇場で室内実験のように生まれたその作品が、再び三重県で展開され、これから皆さまはどのように記憶されるか。非常に楽しみです。
/
亀田恵子(Arts&Theatre Literacy)
第七劇場の『かもめ』を見終わったあと、どうしようもなく胸高鳴る自分がいた。新しい表現の領域を見つけてしまったという心密かな喜びと、その現場に居合わせることの出来た幸運に震えた。彼らの『かもめ』は演劇作品に違いなかったが、別の何かだとも感じた。「ライブ・インスタレーション」という言葉がピタリと腹に落ちた。「インスタレーション」とは、主に現代美術の領域で用いられる言葉で、作家の意図によって空間を構成・変化させながら場所や空間全体を作品として観客に体験させる方法だ。元々パフォーミング・アーツの演出方法を巡る試行錯誤の中から独立した経緯があるというから、演劇との親和性は高いのだろう。しかし、すべての演劇作品が「インスタレーション」を感じさえるかといえばそうではない。
舞台を四方から客席が取り囲む独自な構造を持つ千種文化小劇場・通称“ちくさ座”(名古屋市)。この舞台に置かれていたのは白い天板の長テーブルが1つに、黒いイスが数客。天井からは白いブランコが1つと、羽を広げた“かもめ”のオブジェが吊られており、床は八角形状に白いパネルが敷き詰められていた。役者たちの衣装もモノトーンやベージュといった大人っぽい配色でまとめられ、全体としてスタイリッシュな印象だ。舞台セットの影響なのか、作品中のセリフでは、チェーホフの『六号室』や『ともしび』といった他の作品の一部も引用され、人間の生々しい欲望や絶望を色濃く孕むセリフが続くが、不思議と重苦しさに傾くことがない。むしろチェーホフの描く狂気や人生における悲しいズレが、役者の身体と現実の時間を手に入れ、終末に向かって疾走する快感へと変容していく。役者たちの独自の強い身体性が、無機質な空間の中で描く軌跡は、従来の演劇の魅力だけでは説明が難しい絶妙なバランスを生み出しているのだ。
第七劇場の『かもめ』は、演劇の枠だけで完結しなければ「インスタレーション」作品として押し黙っている存在でもない。戯曲に閉じ込められた時間を劇場という空間に新たにインストールし、生きた役者の身体によって再生する。それは観客との間に「今、この瞬間」を共有する「ライブ・インスタレーション」として新たな領域を創造する行為に他ならない。
「インスタレーション」は、観客の体験(見たり、聞いたり、感じたり、考えたり)する方法をどう変化させるかが肝らしい。この作品は優れた演劇作品であると同時に「インスタレーションの肝」そのものではないかと思うのである。
/
Marianne Bevand(フランス・舞台芸術プロデューサー)
2011年3月、パリで第七劇場の『かもめ』を観たとき、このよく知られたチェーホフの戯曲において何が問題となっているかを、はじめてよく理解できた機会だった。『かもめ』は昨年にあまり成功していないと感じるいくつかの演出版しか観ていなかったが、私の心を奪ったこのロシア演劇の日本人演出を私はたまたま観る機会を得た。
私は演出・鳴海康平の力量に感動した。深く人間性を表現できる俳優への的確な演出があり、とても美しいシーンを舞台上に構成していた。このすばらしいパフォーマンスの中で、私はある種の普遍性を感じた。私の演劇に関する感覚的な願いが実現するためには、この日本の第七劇場を待たなければならなかった。チェーホフ戯曲の人物を演じながら、偉大なる悲劇だけに可能な想像空間のひとつへと、私を連れ去ることに俳優たちは成功していた。この芝居の最初から私は現実の世界から引き離され、登場人物が衝動や欲求や悲しみによってつき動かされることに目を見張った。それは『かもめ』の中心となる感情である。
素晴らしい身体的なパフォーマンスを通して、俳優たちはコンテンポラリーダンスを想起させる一連のムーヴメントを創り、ときに印象的な間の中で静止する。手をあげる彼女たちは、まるで空を飛びその状況から逃げ出したしたいかのようである。しかし、閉じこめられているかのように最終的には彼女たちは地上に留まる。自由への抵抗の中で、もしくは自由が欠けた結果として、白い服を着た3人の女性の登場人物(訳者注:患者2人とニーナの3人)は、狂気の中へ落ちていくように見える。彼女たちは動きが速く、それは視覚的には、黒い服を着た他の人物たちの緩慢な動きと対照的である。舞台の中央から端へとぐるぐると回る彼女たちを見て、彼女たちは自分たちが生きている規定された世界を象徴するある種の領域を爆破したいかのようなイメージが私の心に浮かんだ。黒い服を着た人物たちは、外部の者に自分の居場所を思い出させる支配社会の象徴を思わせる。
このことは私に、チェーホフがこの作品でいかにアーティストが社会の外側に位置し、つらい時代を生きていたかを明らかにすることで当時のアーティスト状況の描写を試みたことを思い出させる。かもめにおいて、3人の女性の人物たちは、ある異なる精神状態の中で、そして目まぐるしい時空の中で彼らがいかに必死に生きるか、また彼女たちがいつもいかに社会の爪に捕えられているかを現している。
この芝居の終わりに私は自問した。「もしあなたが他の誰かとは異なるふるまいをするなら、あなたは気が狂っているとみなされるのだろうか?」いずれにせよ、第七劇場のパフォーマンスが国境を越えて、いくつかの問いを私に起こしたことは確かである。
この美しく芸術的な作品とともに第七劇場が受けるにふさわしい大きな成功を果たすことを、そしてあらゆる世界を横断し、さらに多くの観客の目と心を開くことを、私は願っている。
/
間瀬幸江(早稲田大学 文学学術院 助教)
チェーホフは世界を面や立体としてとらえていた。人物という点や、人間関係という線は、それじたい基幹的ではあるにせよ、作品世界全体の構成要素のひとつでしかない。作品世界のこの広がりから何を「切り出す」のかが、舞台づくりの鍵を握る。
今回、第七劇場の「かもめ」(シアタートラム、9月8日~11日 構成・演出・美術:鳴海康平)で中心的主題として切り出されたのは、トレープレフがニーナに演じさせる劇中劇「人も、動物も…」の部分である。母親のアルカージナに「デカダン」と嘲笑され、当の演者であるニーナにも「よく分からない」と距離を置かれてしまうこの一人芝居の内容は、人間がいかに「やさしく」接しようともいずれ寿命を迎えて消滅することが決まっている地球という惑星の命の時間から考えれば、まったき現実である。その「現実」が、舞台奥中央の老木のオブジェによって密やかに具象される。活人画を思わせるこのオブジェは、開場とともに舞台に姿を見せる、ニーナを思わせる4人の女たちの狂気を孕む無造作な動きはもちろんのこと、見やすい席の確保を願うささやかな「姑息さ」を抱えつつ舞台上の彼女たちを横目で眺める観客たちの動きも、暗がりから見つめ続けている。そして本編が始まり、いつからかそこに照明があてられ、雪のようなものがしんしんと降りだすころ、前景では「かもめ」のいくつかのシークエンスが狂乱的リズムで反復運動を始める。母親にも恋人にも振り向いてもらえずに絶望する青年の物語にせよ、成功という幻想にからめとられたまま一歩も進めない女の物語にせよ、息子を愛しながらその愛を届けることに不器用な母親の物語にせよ、ツルゲーネフには勝てないと感じる自意識の牢獄から逃れることのできない小説家の物語にせよ、個別の物語が抱え込む不毛な反復のエネルギーから発せられる絶叫は、しんしんと降り積もる雪の世界に消えていくしかない。トレープレフは、チェーホフの作った物語のとおり、最後にはピストルの引き金を引く。発射音は聞こえない。しかしそれは、弾丸が発せられなかったからではない。観客は、朽木に降り積もる雪の世界から、トレープレフの自殺や、ニーナの破滅を眺めている。人も動物もヒトデも消えうせた孤独な世界に、ピストル音が届くのは、何万光年も先なのだ。
2011年の日本で、「終わり」というブラックホールを概念としてではなく実体としてほんの一瞬でも覗き見てしまった私たちにとって、朽木の住まう冷えきった世界は、もはや象徴主義の産物ではなくなってしまった。しかし、この終末感を100年前にこの世を去ったチェーホフがすでに言いきっていたことにこそ、私たちはかすかな希望をみるのである。「三人姉妹」を演出したマチアス・ランゴフは、「私たちはチェーホフのずっと後ろを歩いているのです」と言った。それから20年が経過した今なお、チェーホフは私たちの少し前を歩いていて、たまにふと振り返りいささか悲しげに微笑んでみせるのである。鳴海康平は、劇中劇を「切り出す」ことで、無数の点と線とが錯綜して作られる立体的な時空間の表出に成功した。その数多の点や線を大事に拾い出しながらもう一度観てみたかったとの感慨を抱きつつ、9月11日のシアタートラムを後にした。演技者たちの凛とした佇まいも素晴らしかった。
/
唐津絵理(愛知芸術文化センター シニアディレクター)
私たちの深層心理に迫りくる懐かしさの気配、演劇を超えて広がる舞台芸術への希求、それが第七劇場『かもめ』初見の印象だった。
白のリノリウムが敷かれ、白紗幕が下がった劇場は、ブラックボックスでありながらも、ホワイトキューブ的展示室をも想像させる洗練された空間。そこにあるのは、白い長テーブルと幾つかの黒い椅子、天井から吊られた真っ白のブランコやかもめのオブジェ、そして座ったり蹲ったりしている俳優たちの身体だ。白い空間にじっと佇む身体は、彫刻作品のようでもある。上演中も俳優たちは役柄を演じるというより、配役のないコロス的身体性を表出させている。身体の匿名性は、観客自身が自らの身体の記憶と結び付けるための回路を作り出す。それは抽象度の高いダンスパフォーマンスと通ずる身体。前半は僅かに歩いたり、ゆすったりしていた身体が、後半になるにつれて、走ったり、体を払ったり、震わせたりと、より激しく痙攣的になっていく。演劇的マイム性とは一線を画したこれらの身振りが、絶望的に重苦しく表現主義的になりがちなロシアの物語を今日の日本に切り開いていると言ってもよいかもしれない。
怒涛のラストシーンまで、作品全編を演出家・鳴海の真摯さが貫いていく。しんしんと静かに降り積もる雪のように、一見穏やかに見える身体の佇まいの内には、静かな情熱の灯がいつまでも熱く燃え続けている。それがこの作品の確かな強度となっているのだと思う。
/
金山古都美(金沢市民芸術村ドラマ工房ディレクター)
2010年2月千種文化小劇場、12月三重県文化会館で第七劇場の「かもめ」を観劇。時の交錯を感じた千種、閉塞と決壊を感じた三重。どちらについてもその『観後感』は、まったく違っていて。鳴海氏の構築する世界は、その“場所”で変化し、その“人”で変化するようです。“人”とは、役者はもとより、スタッフ、劇場の人々、そして当日来られる観客、すべての“人”を包んでいます。実際観に行った私自身の変化も少なからず影響しあいながら「劇場」という空間が形成されていくのでは。そしてそれは建物の中だろうが、外だろうが、1人だろうが1万人だろうが変わらないのでは・・・違うな。変わらないのではなく、変わることも含めての「作品」なのです。白い床も、テーブルも椅子も、ブランコも「かもめ」のオブジェも、何一つ変わっていないようなのに・・・。そんな演劇のもつ『その場でしか出会えない幸せ』に皆さんで会いに行きましょう。
/
島貴之(aji 演出家)
金沢21世紀美術館にあるジェームズ・タレル作「ブルー・プラネット・スカイ」という作品を見た事がありますか?
四角い白色の天井の中央が四角くくり抜かれ、そこから空が見える。故郷へ帰る度に見上げる空。移ろいやすい金沢の空。晴天、夕刻、曇り空、雨。冬はそのグレイの穴から雪が舞い落ちるのです。
曇り空の四角いグレイのグラデーション。無彩色に見えるグレイに、私は何度もさまざまな色を見た事があります。それを見上げる人の心情がそこに色を齎すのです。天井の枠に囲われた今の自分が、その遠く向こうにあるものを見通す瞬間に—。
この作品では登場人物が纏う衣装を見渡すと白から黒へのグラデーションとなっています。そして劇中では、登場人物の性格や事象に伴う心情があらゆる要素により明確に描かれています。個としての居場所、表情、身体、言葉_そしてそれらが合わさりバランスを変化させる事で、その瞬間にしかない色が次々と生まれては消えて行くのです。
それは、移ろいやすい金沢の空のようであり、また、あなたの心情を映すあのグレイのグラデーションであってほしいと願うのです。
2011年の9月に私は第七劇場の「かもめ」を拝見しました。大胆に再構成されたこの舞台に流れる時間は、キリスト教的な時間感覚の、すでに始まったが未だ終わっていない「時のあいだ」を意識させるものでした。時間は、何分・何秒という座標を流れているとされる概念だけでなく、事件・タイミングによって認識される感覚との2つに分けて考えることができます。あのハイコントラストな世界は、ニーナの事件史のある時点なのだろうと納得して観ました。クロノスでなくケイロス、あるいはゲシヒテによって物語を紡ぐ方法は個に依った場合は有効で、むしろ本質的な問いは、なぜそのように構成したかにあると思われました。それが私には「かもめ」の本体をよく知るために境界線を明らかにしようとしているというだけではなく、ほんのりと漂うロマンチックな印象に隠されているような気がしています。舞台を構成するあらゆる要素は一見、清貧とも言えるほど禁欲的に佇み、それがある種の理想として観客に迫っていましたが、私達は同時にその内側にあるもっと柔らかで繊細なモノも見ていました。その存在��、内側からも外側からもこの作品の再演を促しているのではないかと思っています。
1 note
·
View note
Text
iFontMaker - Supported Glyphs
Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker
#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language
8 notes
·
View notes
Text
月兎 01
雨の中華街は、まるで小さな映画館で観る古いキネマのようだ。燻んだ灰に烟る極彩色。濡れた地面に反射する赤、黄、青。中華角灯の連なる汚れた路地裏。公園の東屋。媽祖廟に関帝廟。映画のセットに一人取り残されたような気持ちで左馬刻は夜道を歩いていた。傘はない。霧雨は、肩にかけたスカジャンの下までは染み込んではこない。こんな日は人も静かだ。観光客の少ない街は必然、客引きの声が消える。商売をしても仕方がないと皆知っているから。脇に下げたホルスターの拳銃が、重い。自然丸くなる背をポケットに突っ込んだ手で支える。息をすることすら怠い。
沈んだ景色の中、不意に頭上に明かりを感じた。まるで、雲の隙間から気まぐれに顔を出す日の光のような。顔を上げると、眼鏡の男が居た。正確には、陳列窓の中に。男は、うたた寝をしているように見えた。アンティークのソファにゆったりと体を預けている。優美な曲線を描くマホガニーの肘置きに柔らかく添う指先。鈍い光沢のジャガード生地で作られたロングのチャイナ服。細い体。柔らかな質感の濃茶の髪。完璧な形をした耳には、赤い房飾り。シノワズリ趣味。それは男の装いだけではない。透かし彫の衝立も、天井から下がる黒の角灯とクリスタルのシャンデリアも、大胆なピオニー柄の淡碧の壁紙も。現代日本とは思えぬ、杳々とした空間。その中で眠る男に興味が湧いた。硝子に顔を近づける。繊細な装飾が施された眼鏡の、黒のフレームの奥。レンズ越しの瞼をまじまじと見つめる。放射状に広がる長い睫毛。丸みを帯びたまぶた。瞳の色は何色だろうか。白い頬に落ちる影。
「なぁ、目、開けろよ」
聞こえるはずはない。だが、話しかけずにいられない。明かりの消された店で、唯一明るい陳列窓の中で、眠る男が生身のはずはないのに。それでも、あまりに男が生々しくて。
「なぁ、なぁ」
気狂いのようにぽつ、ぽつと何度も語りかける。
どれ位の時間、そこに居ただろうか。縋るように硝子に手を突いて。ようやく諦めて、立ち去ろうとした。その時に。ふぅ、と男のまつ毛が持ち上がった。最初に見えたのは、明るい緑。晴れた夏の木漏れ日のような。それに見とれていると、ゆっくりとマゼンタが現れる。不思議な瞳の色だった。
「きれぇだな、お前の目」
こちらを見ない男に、話しかける。
「あっ?おい!」
男は無反応のまま、スゥと瞼を下ろした。何事もなかったように、上下のまつ毛が重なる。
「………くそ」
悪態をついた瞬間、店内がパッと明るくなった。
「何か、用か」
デカイ男が、にゅっと建物の脇から顔を出す。どうやら店の人間のようだ。裏口から回ってきたのだろう。
「あ、いや、こいつ」
左馬刻が、陳列窓の中の男を指差す。
「ああ……今店を開けよう。待っていてくれ」
そう言って、大柄の男が戻っていく。日の光を集めたような明るいオレンジ色の髪、晴れた海面のような明るい青の目。白色人種の特徴を持つ、彫りの深い顔立ちに、飾り窓の男と同じようなロングのチャイナ服。シノワズリを体現したかのような男と、店の佇まいが重なった。すぐに透かし彫の施された硝子扉が内側に開く。
「どうぞ」
背の高い男に招かれて、左馬刻は店内に足を踏み入れた。エキゾチックな花の香り。外からは見えなかった場所には、壺や茶器、置物などが並んでいる。
「茶を淹れよう。座っていてくれ」
縁にカーヴィングの施された、エボニーのティーテーブル。揃いの獣脚のアームチェアにドカリと座り、左馬刻は陳列窓の男の茶色い後ろ頭を、ぼんやりと見つめた。
「気になるか?」
オレンジの髪の男が、茶盤に並んだ茶器に湯を注ぐ。流れるような手つきで茶葉を洗い、再度鉄瓶から湯を注ぎ、蓋を閉めた小ぶりな急須に上からも湯をかける。コトリ、と目の前に置かれた透かし模様の白い湯のみに浮かぶ、黄金の輪。ず、と一口すすると、茉莉花の香りが広がった。
「銃兎も連れてこよう。起きるかどうかはわからないが」
そう言って、オレンジの髪の男が陳列窓に近づく。あの男は『銃兎』と言うのか、と左馬刻は思った。オレンジの髪の男に抱き上げられた銃兎が、左馬刻の向かいのアームチェアにゆっくりと降ろされた。
「銃兎、茶はどうだ?貴殿の好きな碧潭飄雪(スノージャスミン)を淹れたのだが」
スゥと、銃兎の瞳が開く。けれどまたすぐに閉じてしまって、オレンジの髪の男が苦笑した。
「どうやら、今日は��が乗らないようだ。部屋に戻せと言っている。すまないが、待っていてくれ」
そう言って、オレンジの髪の男は銃兎を抱き、カーテンに覆われた店の奥へと消えていく。それを、なぜだかひどく腹立たしい気持ちで左馬刻は見つめていた。いや、腹立たしいというのは少し違う。左馬刻は、羨ましかったのだ。オレンジの髪の男が。
「さて、待たせたな。小官は理鶯という。元軍人だ。船に乗るのが好きで、各国で買い付けをしては、こうして商いをしている。貴殿の名は?」
「左馬刻」
左馬刻は簡潔に答えた。
「銃兎、は一体なんだ?人間か?」
左馬刻の率直な問いに、理鶯が微笑む。
「あれは観用少年(プランツドール)だ」
「は?プランツ?嘘だろ?」
『プランツドール(観用少年・観用少女)』とは、その名の通り、観用の少年・少女だ。人工の。左馬刻の属する火貂組の組長・火貂退紅も一体、少女型を所持している。左馬刻は職業柄、派手な集まりに参加することが多いが、今まで目にした観用少女たちはみな、成人男性の胸元にも満たない姿だった。何年、何十年物でも。手入れを怠らなければ、同じ姿のまま二百年の時を越える個体もいると聞いている。
「稀に、育ってしまう物もいる。稀に、だが」
そう言って、理鶯は茉莉花茶に口をつけた。
「左馬刻、銃兎は名人の手による傑作だった。銘は『月兎(げっと)』」
銘がつくほどの観用少年の価値を、左馬刻は知っている。退紅のオヤジのプランツも、銘を持つ逸品だった。その値段は、億を超える。しかし、理鶯は『傑作だった』と過去形を使った。
「育ってしまったプランツの価値は、ほぼ無い。それでも、銘を持つプランツなら、ワンルームマンションを買えるくらいの価値を持つ」
語りながら、理鶯が茶を左馬刻の湯のみに注ぐ。一煎目より柔らかく重い香りが立ち上った。
「へぇ」
左馬刻が相槌を打つ。つまりあのウサギちゃんは、高級品っていうわけだ。
「一千万でどうだ?」
理鶯の言葉に、左馬刻が顔を上げる。
「は?」
訝しげな左馬刻に、理鶯が微笑みかけた。
「銃兎は、左馬刻を気に入ったようだ。興味がなければ、一瞬でも、瞳を開いたりはしない」
「アイツ、動けんの?」
ずっと、寝っぱなしなのかと勝手に思い込んでいたが、そういえば今まで見てきた観用少年・少女たちはみな、歩き、笑い、主人と何か会話をしていた。
「食べもんも食えんのか?」
理鶯が茶を勧めていた事も思い出した。
「ああ、風呂もトイレも、一人でこなせる。食事は日に3度、人肌に温めたミルク。週に一度金平糖を与えると肌ツヤが良くなるぞ。全体的に疲れが見えてきたら専用の栄養剤もある。銃兎は育っているから、人間と同じ食事も摂れるが、嗜好品だ。ミルクさえ与えていれば、ことは足りる」
左馬刻は頭を抱える。自分の家に銃兎がいる事を想像して、胸がぎゅっと熱くなった。コンクリ打ちっ放しの無機質な部屋だ。家具も最低限しかない。そんな空間に、あの、美しいものが存在する。それはなんと魅力的なことか。
「そいやさ、銃兎って名前は誰がつけたんだよ」
銃なんて物騒な名前が付いている。けれどその名は、あのお綺麗な顔に不思議と良く似合っていた。
「前の主人が、な」
含むように呟いた理鶯は、それきり理由を語ろうとはしなかった。
「返事は直ぐでなくていい。銃兎は気難しい。迷ったら顔を見に来るといい。眠っていても、銃兎は気づく」
流石に、高級車が買える値段を即決することはできなかった。
「馳走になった」そう言い残して、左馬刻は店を出た。
*
「いいのか銃兎?左馬刻は帰ってしまった」 天蓋付きの中華風の寝台の上、銃兎は絹のシーツに包まって眠っていた。理鶯の言葉に、パチリと緑の瞳が開く。理鶯が差し伸べた手をとって、銃兎はゆっくりと起き上がった。
「理鶯、余計な事はしないで頂けます?」
手厳しい一言に、理鶯が苦笑する。
「大体、一千万だなんて、安すぎます。私を何だと思っているんです」
ぷぅと頬を膨らませて、銃兎が涙を滲ませる。元は、数億で取引されていた個体だ。自尊心が大いに傷つけられたのだろう。
「だが、銃兎。貴殿の日々のミルク代や服、装飾品など、一体いくらの持ち出しになっていると思う?」
優しい声で理鶯が問う。責めているのではないことは、銃兎にはちゃんと伝わっている。けれど。
「……だから、嫌ですけど、ものすごく嫌ですけど、硝子窓で客引きしているじゃないですか」
「うん、それはとても助かっている」
言いながら、理鶯は銃兎の頭を柔らかく撫でた。現実、銃兎を目当てに店に飛び込んで来る客は多い。しかし、銃兎はそんな客たちには決して目を開かなかった。銃兎を目当てに入って来た客の中には、店の常連になる者も多い。もともと銃兎を欲しがる客というのは、美術品の好事家が多いのだ。
「だが、銃兎、小官は貴殿をこのようなところで飼い殺しにしたくない」
理鶯の言葉に、銃兎が泣きそうな顔をした。
「わたしは、ここに居たいんです。ずっとここに。ねえ、駄目ですか?お願い、理鶯」
理鶯の幅の広いチャイナ服の袖を掴んで、銃兎が懇願する。理鶯は銃兎を大切に扱っているが、それはあくまで商品としてだ。出来る事なら、商品としてではなく、銃兎を愛してくれる人間に届けたかった。
「もう、人間を愛するのは嫌なんです。もう、あんな思い、二度としたくない」
理鶯にすがり付く銃兎の背を撫でて、理鶯は物思いに耽る。通常、観用少年というのは、愛に絶望すると枯れるものだ。しかし、銃兎は、一度枯れかけはしたが、こうして未だ美しく咲いている。それは、銃兎も気が付かない心の奥底で、人の愛を望んでいるからではないのか。
「左馬刻は、きっとまた来る。ゆっくり考えたらいい」
そう言って、理鶯は銃兎を寝台に横たえた。椅子の背に脱ぎ捨てられたチャイナ服を、ハンガーにかける。
「おやすみ、銃兎。また明日」
暗闇の部屋から、明るい四角に足を踏み出す理鶯を、銃兎は寝台の上から静かに見送った。
1 note
·
View note
Text
オラデア日記 その弐

8月13日
オラデア観光2日目にして最終日。明日の朝の便でオラデアを発ち、ブカレスト経由でロンドンに戻る。今日もまた刺すような強い日差しの中を出かける。
12月1日公園(Parcul 1 Decembrie)で、オラデアに着いて初めて「これぞ旧共産圏!」という建物に出会った。嬉しくて小躍りする。モニュメンタルなファサードの大きな建造物だが、一体なんの施設なのか見当もつかないところもコミュニスト建築らしくて良い。北米資本主義の申し子Googleで調べてみたところ、「市民のための多目的娯楽施設」らしい。ますます嬉しくなる。

そして、同じく12月1日公園で、幼児を抱いた10歳ぐらいの少女にお金を乞われた。返答ひとつできずにベンチに座ったままの私に、眉を寄せルーマニア語で訴え続けた彼女の足は、裸足だった。
Cetatea Oradea (オラデア要塞)は不思議な場所だった。11世紀ごろに初めて建物が築��れ、その後次々と拡張、増築、改築、取り壊し、建て替えられてきた歴史を見せてくれる考古学的展示は大変面白かったが、そのまま館内を進んでいくと、様々な「特別展」が脈絡もなく次々と現れて驚いた。どうも部屋ごとに「貸し出す」ような形を取っているのではないかと思う。個人の写真関連のコレクション(現像トレイや印画紙まで!)を展示した部屋があったりした。説明文はルーマニア語とハンガリー語で、英語はあったりなかったりする。うまくこなれた英語のものもあれば、機械翻訳に毛が生えたような文章にも出くわす。手作り感溢れる展示が散見される。
要塞全体は、アートコンプレックスとなっているようで、博物館の他に文化センターやクリエイティブ産業向けのコワーキングスペースなどが併設されていた。小さな野外劇場もあった。観光のオフシーズンであるからか、カフェと食堂は閉まっていた。ここもやはりひっそりとしてあまり人影がない。行政の意欲に地元のキャパシティーが追いついていないような雰囲気がここにも漂っていた。

オラデア要塞の近辺には近代的な集合住宅がたくさん立っていた。団地育ちの私は懐かしさでいっぱい。もしオラデアに引っ越さなあかん日が来たら、このあたりに住むな、絶対、と勝手に胸に誓う。

ランチに入った川沿いのレストランでは、メニューの前菜の項に握り寿司があった。前の席の家族づれの小さな女の子(2歳くらいか)が手づかみで握り寿司を食べていた。母親はフォークで刺して食べていた。私が頼んだサラダのハニー&マスタードドレッシングはほぼ「ただの(極上の)蜂蜜」だったが、それはそれでなかなかの美味であった。
ランチのあと、川向こうを歩く。川沿いは木々が鬱蒼と茂る公園になっていて、ストリートレベルの遊歩道から川岸まで降りられるようになっている。ゆっくりと散歩する人々、木陰のベンチやカフェで休息する人々。岸には水着姿の若者たち、釣り糸を垂れるおじさんたち。川に沿って長く伸びた公園の中ほどの歩道橋を渡って、シナゴグへと向かう。川と橋のある街は良い。

Neolog Synagogue Sionは美しい場所だった。19世紀に建てられたムーア風のシナゴグは数年前に修復され、現在は地域のユダヤ教徒のためのシナゴグとしての機能は果たしてないためか、小額の料金を払えば中を自由に見学できる。そういえば、シナゴグの中に足を踏み入れるのは初めてだ。美しい幾何学模様が、すべて手書きで施された壁という壁、天井という天井。ため息をつきながら降りてきた階段の横に、金色の文字が書かれた黒い板がいくつも並んでいた。立ち止まって眺めて、アウシュビッツで殺された人々の名前が書かれたものだと気がつく。たった今あとにしたばかりの、座る人のいないベンチが並んだギャラリーを思う。かつてあそこに腰をかけていた人々の名前なのだ。


ハンガリー国境に近いオラデアは1940年にドイツとイタリアの仲介したウィーン裁定により、「北部トランシルヴァニア」としてルーマニア王国からハンガリー王国へ譲渡され、第2次世界大戦中はハンガリー領だったオラデアに住んでいたハンガリー系ユダヤ人は全員アウシュビッツへ強制収容された。中心部を少し外れた公園は、かつてアウシュビッツへ向けた列車が出発した場所で、そこに記念の少女像がある。おさげを垂らしたエヴァ・ヘイマンは静かにベンチに腰を下ろして死へと向かう列車を待っているようにみえる。隣に座ると、列車を/死を待つ彼女の目に映った景色が私にも見えるだろうか。

道端の小さなパン屋でCovrigなるパンを買う。「コヴリグをひとつ」というと「コヴリッヒだ」と訂正された。ひとつ2.5レイ、約50ペンス、65円。ホテルに戻って調べると、トルコ/アラブのベーグルとある。��もありなんといった形だが、手に持った感じはベーグルより軽い。割ってみると中からばら色のジャムが出てきた。酸味の爽やかなモレロチェリーのジャムだ。

Piata Unirii(統一広場)のカフェで夕食。広場に広げたパラソルの下の席に座ると、8時から予約が入っているが良いかと確認された。時計を見るとまだ6時半。大丈夫と頷く。オラデアの飲食店のサービスはどこもややのんびりしているが、観光客にはそれがちょうど良い。まだ日は高く、強く、パラソルからは時々涼を取るためのミストが撒かれる。頼んだのはラズベリーフローズンレモネード。ルーマニアについて以来すっかりレモネードファンになってしまった。
8時近くなってやっと日が陰って、統一広場に人の姿が増えてきた。日中あれほど閑散としていたのが嘘のように、ベンチに腰掛けて話しこむ老人たち、立ち話に興じる若い母親たち、乳母車で眠る赤ん坊、フットボールを蹴り合う少年たち、自転車やスクーターに乗った子供たち、家族連れ、手をつないで寄り添う恋人たち。観光客ではない、地元の人々だ。ははあ、暑い最中はみんな隠れていたんだなと思う。フォーマルなスクエアが村の広場に変身したかのようだ。オラデア最後の夜に、この広場で、この光景に出会えて本当に良かった。なんて素敵な旅の締めくくりだろう。

オラデアの写真はこちら オラデア日記 その壱
ブカレスト日記 その壱 その弐 その参
3 notes
·
View notes
Text
絞りすぎちゃってごめんなさい
爆乳、超乳、母乳、女子高生、人妻(未亡人)。女子高生の母乳が飲みたくて書いた
「うちの子が絞りすぎちゃったので、よかったらもらってくださいな」
ピンポーン、と呼び鈴が鳴ったので、何事かと思って出てみると、隣に住んでいるとある夫人が、一本の牛乳瓶を差し出して来ていた。
「牛乳、……ですか? ありがとうございます、ぜひもらっておきましょう。搾乳体験にでも行かれたんで?」
「ふふ、……まあ、そんなところ。あの子ったら張り切ってたくさん絞るものですから、もう飲みきれなくって、――はい、どうぞ」
と、貰い受けた牛乳瓶は、まだほんのりとあたたかい。
「おお、搾りたて」
「もちろん、さっき絞ったばかりですもの。あたたかいうちに召し上がれ」
「いやあ、美味しそうです。すみません、お返しもなくて、大切に味わいながらいただきます」
「お返しだなんて、……やっぱりいい子ね、あなた。ふふっ、ではごきげんよう」
と、夫人は堪えきれない笑みを浮かべながら手を振ると、
「ぜひ感想をちょうだいね」
と一言云ってから隣の玄関へ入って行った。
さて、僕の腕の中にはおよそ1リットルの牛乳瓶に、なみなみと注がれた牛乳があるわけだが、とてつもなく卑猥なことを考えてしまうのは何故だろうか。
決まっている。あの夫人から「絞りすぎちゃったので」と云われて手渡されたものだ、卑猥なことを考え無いほうがおかしい。
順を追って説明しよう。まず、先程僕が出会った夫人と云う女性は、ものすごく美人なのである。それはもう、立っているだけでも目がくらみ、歩くだけでも見とれてしまうほどに美人なのである。おっとりとした目元に、日本人らしい長い黒髪に、ぷるんとした弾力のある唇。……あゝ、思い出すだけでも鼻の下が伸びてしまう。
次に、現在の境遇。これは何ともかわいそうな話なのであるが、すでに夫を失っているらしく、今は実家の援助を受けなが���、高校二年生になる娘と二人きりで暮らしていると云う。要は未亡人である。未だに再婚をしないのは、一途な夫への思いからだろうか、それとも別な理由からなのだろうか。何にせよ、美人な未亡人というものには、何か惹かれるものがある。
そして3つ目、彼女の体つきがものすごいのである。最初見た時には我が目を疑ってしまった。ほっそりとした腕に、いかにも健康そうな足元に、女性らしいしなやかな腰回りを持つ彼女の胸元には、冗談のような大きさのおっぱい、おっぱい、おっぱい。……顔よりも遥かに大きなそれは、30センチは胸から飛び出しているだろうか、彼女が歩く度にゆさゆさ、ゆさゆさと揺れ、背中側からでもその膨らみが確認できる。綺麗な丸みは首の下からいきなり始まったかと思いきや、彼女のおヘソの辺りでいきなりキュッと引き締まって終わる。階段を上り下りする時には、たぷんたぷんと波打ち、エレベーターで一緒になった時などには、どこまでも続いて行きそうな谷間の入り口が姿を覗か��る。
一体何カップだろう? U カップ? V カップ? いやいや、Z カップだと云われても不思議ではない。昔、スイカをおすそ分けされた時、かなりの大玉であったのにも関わらず、おっぱいの方がずっと大きかったのだから、カップ数にすると普通でなはないことは確かである。
なればその血を受け継いだ娘がどうなっているのか、――それが最後の理由である。
夫人のおっぱいは冗談のような大きさだと云った。が、娘のおっぱいはそんな言葉では形容し得ない。非現実である。現実ではありえないのである。高校二年生にして母親を遥かに超えてしまったそのおっぱいは、直径にして約50センチ、方房だけでも米俵のように大きく、立てば腰よりもさらに下、太ももの辺りまでを膨らまし、振り返ろうものならブウン! と風切り音を発生させ、廊下などで行き違おうものなら、もはや相手を包むようにして通り過ぎなければならない。
まさに超乳。世の中の女性はおろか、母親のおっぱいですら、あの子のおっぱいからすれば小さく感じてしまう。しかも、未だに成長を続けているのである。一ヶ月前にはゆとりのあった特注の制服が、今ではおっぱいに耐えきれず、巨大でゴツゴツとしたブラジャーの模様が、薄っすらと浮かび上がっているのである。以前、親子二人と一緒にエレベーターに乗った時、
「こら、擦るとまた制服が破れるから気をつけなさい。高いんだから、……」
と母親に云われていたので、もうその瞬間が訪れるのも時間の問題かと思われる。
ここまで述べれば、僕がただの牛乳瓶を持つだけで、とてつもなく卑猥なことを考えてしまう理由がお分かりになろう。
――うちの子が絞りすぎちゃったので、……
――ふふ、まあ、そんなところ、……
――さっき絞ったばかりですもの、……
夫人のこの言葉には、あのおっぱいのように、とてつもない膨らみが隠れているような気がしてならない。特に、「搾乳体験に行かれたんで?」と聞いてぼやかされたこと、そしてこの、未だに人肌程度のあたたかさを保つ、牛乳のやうな白い液体。……
云っておくが、この近くには牧場なんて無い。こんな瓶に入れて持って帰れば必ず冷えてしまう。
――いったいどちらのなんだ。
僕の疑問はもはやそちらにあった。子供が高校生にもなって未だに出続けることも、その子供が妊娠もしていないのに出ることも、常識では考えられないが、あの親子のことである。母親の巨大なおっぱいから未だに母乳が出てもおかしくないし、娘の非現実的なおっぱいから母乳が大量に溢れ出しても、もはや不思議ではない。
僕は早速牛乳瓶の蓋を取った。二人の顔を思い浮かべながらコップに注ぎ、「いただきます」と呟いてから口に運ぶ。飲んだ感想としては、ものすごく美味しかった。芳醇な匂いも、濃厚な味も、喉を伝うコクも、どれも市販の牛乳を遥かに凌駕していた。明らかに、牛から出てくるようなものでは無かった。まあ、あの親子のことを牛のような、と、形容しようと思えば出来るのだが。……
明くる日、ゴミ捨て場から帰る際に呼び止められたので、振り返ってみると、夫人がにこやかな笑みを浮かべながら、小さく手を振っていた。彼女もまたゴミを捨てに来ていたのであろう、カットソー一枚に、ひらひらとした長めのスカートを合わせたラフな出で立ちで、腕やら腰回りやらはひどくゆとりがあるが、胸元はもうパンパンでパンパンである。なんだかいつもよりもゆったりとした服のせいか、巨大なおっぱいが、さらに巨大に見える。……
「美味しかったかしら?」
「ええ、とっても美味しかったです。一気に飲んじゃいました。いったいどこの牛乳だったんですか? ぜひ僕もこの手で絞ってみたいんですが。……」
と、少々意地悪く聞くと、夫人は少女のような可愛らしい顔を浮かべて、人差し指を口元へ持っていく。
「――ふふ、内緒。美味しかったのなら、それでいいわ」
「ええー」
「そんな顔しないの。今日も絞りすぎちゃって、まだたくさんあるから、……ね?」
「やった!」
「ふふふ、また後でいらっしゃい。搾りたてを用意しておきましょう」
それから世間話をしつつ、僕たちはアパートのエントランスに戻り、エレベーターに乗り、少しばかり陽に照らされた町並みを眺めてから、お互いの玄関の中へ入って行った。
まだ日も高くなっていないような早朝である。「もう一時間か、二時間くらいお待ちいただける? ベストなのはお昼前ね」と云われた僕は、非常にソワソワと、いや、正確には悶々とした時間を過ごしている。もう楽しみで仕方がない。「搾りたてを用意しておく」――この一言だけでご飯が何杯でもいただけそうである。
昨日の牛乳瓶を眺めては、底の方に残る白い液体に思いを馳せ、11時を少し回ったところで耐えきれなくなった僕は、とうとう隣室へ向かうことにした。呼び鈴を押すと、すぐさま、
「いらっしゃい。用意できてるわよ」
と、夫人が出迎えてくれ、そのまま中へと入ることになった。
「おー、……」
「うん? どうかしたの?」
「いやあ、初めてだったからつい。……ところで、娘さんは?」
もちろん、僕と彼女の娘は顔見知りである。僕がこのアパートへと越してきた時にはすでに、隣の部屋に住んでいたのだが、僕が独身であることも手伝って、かなり良くしてくれている。母親と同様に、器量よしのいい子で、会えば必ず挨拶してくれたり、こちらの詰まらない話に付き合ってくれたり、たまにプリンとかケーキを作っては僕の部屋まで持ってきてくれたりする。これがまた非常に美味しくて、殊にケーキに乗っているクリームなぞは、どんな店のものよりも絶品である。
「さっき塾に行っちゃったわ。――ふふ、会いたかった?」
「それはもう、この間のケーキも美味しかったですから」
「あら、それは直接伝えないとね。あの子、すっごく喜ぶと思うわ。――あゝ、それで約束の品はあの子の部屋にあるから、こっちにいらっしゃい」
「ほら、どうぞ。お好きなだけお取りなさいな。ベストなのは箱ごとね」
と、案内された可愛らしい女の子の部屋の中には、牛乳瓶で満たされたケースが一箱あった。どの瓶も娘さんの母乳と思われる液体がなみなみと注がれている。数えてみると12本あり、彼女は僕が自室で待っていた間に、おおよそ12リットルの母乳を搾って、塾へ向かったと云うのか。一本だけ手に持ってみると、まだあたたかく、なんとなく優しい匂いが僕の鼻に漂ってきた。と、同時に頭がぼんやりとしてきて、僕は牛乳瓶を見つめたまま、つい固まってしまっていた。
「うん? どうかした? もしもし? ○○くん?」
と夫人が顔を覗き込んでくる。が、動けない。ここにはあの子の母乳が、まだ高校二年生なのに非現実的なおっぱいを持つ娘さんの母乳が、そして目の前には、そのお母さんの巨大なおっぱいが、……おっぱいが、……
「おーい」
と今度は顔の前で手を振られる。が、それでも僕は動けなかった。ようやく口を開いたのは、
「うーん、……どうしましょう。……」
と夫人がすっかり考え込んだときだった。
「あ、あの、……」
「おっ、やっと動いた」
「あ、いえ、やっぱり何でもないです。すみません。……」
「んー? 言ってご覧なさい。怒らないから」
部屋に漂う優しい香りと、手の中でまだあたたかさを伝えてくる母乳と、そして何にも増して、目の前でカットソーを破ってしまいそうな途方もないおっぱいに、僕は魔が差してしまっていた。要は、夫人のおっぱいに触りたくて触りたくて、仕方がなかったのである。
「触っても、……いいですか?」
と云った時、僕はこの親子との関係が終わったと思った。けれども、夫人は吹き出したようにくすりと笑って、
「なんだ、そんなことだったの。いいわよ、ほら、――」
と、胸を突き出してくるのみ。僕の動きはまたもや止まってしまった。
「早くしないと、怒るわよ?」
あまりの光景に圧倒されていると、そう云ってきたので、僕は牛乳瓶を床に置くと、そっと両手を突き出して、彼女のおっぱいに触れた。ふにふにと柔らかく、力を入れればどこまでも沈み込む。……一度谷間に手を入れるとあっという間に飲み込まれ、左右から押し込んでやると、山のように盛り上がる。……
「す、すごい。おっきい、……それに重たい。……」
「気持ちいい?」
「とっても、――うわあ、すごい、柔らかい。……」
「ふふ、聞くまでもないようね。でも、もっと力を入れてもらってもよろしいかしら? こそばゆくって仕方がないわ」
「いえ、僕はこれでも、……おお、……うあ、……」
もはや言葉すら頭の中に浮かばないほどの気持ちよさ。感嘆の声を漏らしていると、彼女もまた、気持ちよさそうな声を手の間から漏らす。
「んっ、ふっ、……あなた意外とお上手ね。……あぁん、もう、二人共揃ってえっちなんだから。……」
しばらく揉みに揉んだ。手が疲れても、貪るように揉みしだいた。最高の体験だった。何と云っても、彼女のぬくもりがたまらなかった。
すると、とうとう耐えられなくなったのか、夫人は誤魔化すように、自身の胸について語り始めていた。
「昔はもっともっと小さかったのよ? こら、お聞きなさい。――お聞きなさいってば。……よろしい、いい子ね。頭を撫でて差し上げましょう」
と、優しく頭を撫でてくる。
「それでね、小さかったと云っても、普通の人からすればだいぶ大きくてね、高校生の時にはT カップはあったわ」
「てぃ、てぃカップ。……」
「んふ、すごいでしょ? でも、あの子を生んでからまたズドンと大きくなっちゃって、……」
「今は何カップなんですか?」
「うーん、……分からないわ。だって、もうずっと昔にZ カップを超えちゃったし、今は10箇所くらい細かくサイズを測ってからブラジャーを作ってるから、アルファベットでは表しようがないの」
「ぜ、Z カップを超えてるんですか?!」
「もう、驚きすぎよ。Z カップってあなたが思ってる以上に、意外と小さいのよ? それにね、――」
と手を取って、無理やり引き込む。ずぶずぶ、ずぶずぶと埋まる手は、どこまでも、どこまでも。
「あの子はもっとすごいわ。はい、もうおしまい。続きはいつか、……準備が出来たら、かしら?」
「え、ええ?」
「あんまり私がちょっかいを出すと、怒られちゃうからね。ほらほら、私はこれから出かけなきゃいけないから、この子たちが冷めないうちにケースごと持ってお行き」
「えええ? ど、ど、どういう、――」
「ふふ、それは次までの宿題にしておきましょうか。私の恥ずかしいところを見たんだから、このくらいの意地悪は許してちょうだい。――」
と、追い出されるようにして隣室を後にした僕の手元には、12本の牛乳瓶と、おまけでくれた一塊のチーズがあり、体に染み付いたほのかな匂いに、そ���日はとうとう風呂に入るまで、悶々とした時を過ごしてしまった。
次の日から僕には一つの日課が増えていた。それは朝、モーニングコールのついでに夫人が持ってきてくれる、母乳の入った牛乳瓶をもらうというもの。最初の方は何十本と用意して来てくれたが、さすがに飲みきれずに捨ててしまうので、最近では二本だけもらうことにしている。
毎回、
「絞りすぎちゃった」
と云って手渡される母乳は、日によって味のバラツキがあるようだ。夫人自身も、
「今日は少しサラサラしてるかもしれないわ」
だとか、
「今日はとびっきり濃いから、暇があればチーズを作るといいわ。作り方はね、……」
だとか、
「今日は味が薄かったわ。昨日の夜は、お腹が空いてたみたいね。ふふ、ダイエットでもしてるのかしら」
だとか云う。しかし、どんなに味が悪い日であっても、これまで飲んだどの牛乳よりも美味しく、香りも豊かで、1リットルや2リットル程度は飲みきるまでに10分とかからない。飲んだ後はふわふわと酔ったような気分になって、ふらふらと寝床に向かうことになるが、目が覚めた時の心地よさは、飲むのと飲まないのとでは全く違う。心なしか肌もきれいになり、日中の集中力も増したような気がする。
休日の今日も、何時も通り持ってきてくれた母乳を、朝食と共にいただいた僕は今、日中にあった野暮用から帰っている途中なのだが、ふと立ち寄った公園で見知った人影が、ベンチに座って本を読んでいるのが見えた。
「――沙羅ちゃん?」
と、声をかけても集中しているのか、本に釘付けである。塾の帰りなのだろうか、彼女は制服に身を包み、大きな大きな胸の膨らみを膝の上、ベンチの上に柔らかく乗せている。
「沙羅ちゃん、こんばんは」
と、もう少し近寄って、声をかけてみる。すると、
「ん、……?あっ、こんばんは、○○さん。一週間ぶり、……でしょうか」
「そうだね。あの時はケーキありがとう。相変わらずめちゃくちゃ美味しかったです」
「いえいえ、自信作だったので、そう言って頂けると嬉しいです」
と、心底嬉しそうな笑顔を見せる沙羅ちゃん、――とはあの夫人の娘であり、恐らく僕が毎日飲んでいる母乳の主。……こうやって時たま会うことはあるけれども、そのふるまいはごく自然で、とてもではないが、あれだけの量の母乳を出している女の子とは思えない。もしかして、夫人の母乳だったのだろうか。いや、別に残念という訳ではなく、あの夫人の母乳を飲んでいるのなら、それはそれで本望である。
「今日は塾の帰り?」
「そうです。来年受験なので、今のうちから頑張っておこうかと、……」
「おお、賢い。僕なんて怠けに怠けてから受験期に入ったから、それはもう大変だったよ」
「ふふっ、○○さんらしい」
「らしい、ってどういうことやねん」
クスクスと、口に手を当てて上品に笑う沙羅ちゃんは、やっぱりめちゃくちゃ可愛い。さすがあの夫人の娘である。だからといっていいのか良くわからないが、鼻の下が伸びて来た僕は、彼女に何か甘いものをご馳走したくなってきて、近くにある喫茶店へと向かうことにした。
その時の揺れるおっぱいのものすごさ! 一体何十キロあるのか分からない塊は、一歩一歩足を踏み出す毎に、たゆんたゆん、たぽんたぽん、ゆっさゆっさ、だゆんだゆん、……と揺れ、彼女の細い体では支えきれていないのか、歩き始める時や停まる時に危なっかしくバランスを崩していた。それに、横にも縦にも奥にも何十センチと広がっているために、道路上の何もかも、――標識だったり、ポストだったり、ガードレールだったりが、障害物となり得ていた。道行く人は云わずもがなである。段差がありそうな場所では、下を大きく覗いてから歩みを進める。曲がり角などでは、ちゃんと後ろまで確認してから体を傾ける。
「その、……当たっちゃうので、……」
と恥ずかしそうに云ってゐたけれども、合わせて成人男性の体重ほどもあるおっぱいにビンタされるなんて、笑い話では済まないだろう。そう云えば夫人も、振り返る時は周りのものに当たらないように気をつけていると、云っていた。
「暑くなってきたねー」
喫茶店に入ると、僕はそんなことを云いながら一息ついた。時間が時間だけに中は店主以外誰もおらず、ガランとしている。沙羅ちゃんは椅子に座るのも一苦労なようで、テーブルの上にあの非現実的なおっぱいを乗り上げさせながら、ゆっくりと、目一杯引いた椅子に腰掛けていた。今もテーブルの上におっぱいが乗っているのは変わらず、眼の前に居る僕からすれば、大変に魅惑的な光景が広がっている。
「ええ、ほんとですよ。蒸れちゃ、――」
「ん?」
「い、いえ、なんでもないです」
「そう? じゃ、何か注文しよう」
と、僕たちは同じパフェを注文して、夫人のことだったり、学校のことだったり、しばらくありきたりなことを話しながら舌鼓を打った。
パフェは美味しかった。でもやっぱり、クリームだけは彼女の作ってくれるやつの方が遥かに美味しい。絶妙な甘さと、コクと香りと、それに舌触り、……どの点を取っても沙羅ちゃんのクリームの方が上である。云うなれば、素材の元となった生乳が生きていると云うか、……あ、そういうこと。……
「いやあ、それにしてもお母さんには感謝しかないよ。ほんとに」
と、再び夫人の話に戻ってきた時、僕は毎朝もらっている母乳の事をふと思い出して云った。
「へっ? どうしてですか?」
「毎朝、牛乳を持ってきてくれてるんだよ。その牛乳がめちゃくちゃ美味しくて、――」
と、その時、沙羅ちゃんの顔色が急に変わる。
「ちょ、ちょっと待ってください。それって、もしかして、……えっ、もしかして、このくらいの大きさの瓶に入ったやつですか?」
ちょうどいつもの同じ形をジェスチャーしてくれたので頷く。
「えっ、うそ、……」
「沙羅ちゃん?」
「うわ、うわうわうわ、……もしかしてもしかしてもしかして、そんな、……まさか、最近寝起きにやれって云われるのって、……うわああああああああ、………」
と、頭を抱えて俯く。
「ど、どうしたの沙羅ちゃん」
「嘘でしょ? 嘘だと、――あっ、えっ、や、やだ、……なんでこんな時に、……」
と、何やら自分の胸元に手を当てると、今度はガバっと立ち上がる。
「すみません、ちょっとトイレに行ってきます!」
沙羅ちゃんはそう云うと、バックごと店内の奥にあるトイレへ駆け込んで行ってしまった。突き刺さる店主の目線がかなり痛い、……
正直に云うと、悪いことしたような感じがして心も痛かった。母乳の件を云った時、意地悪な気持ちが無かったことは無かったけれども、まさかここまで取り乱すとは思っていなかった。完全に自分の落ち度である。彼女が傷つけていなければいいのだけど、……
それから10分か、15分ほどして沙羅ちゃんは、思いの外明るい顔をしてトイレから出てきた。心なしか毎日嗅いでいるあの匂いが、ほのかに漂ってくる。
「ふぅ、……すみません、ちょっと取り乱してしまいました。お母さんには後で私からきつく云っておきます」
「いったい、どうしちゃったの?」
「ふふ、……ふふふ、なんでもありません。それよりも、そろそろ帰りましょう、暗くなるまでに帰らないと、お母さんうるさいですから」
「う、うん。沙羅ちゃんがいいなら、いいんだけど、……」
と、僕たちは立ち上がって、一見何事も無かったかのように帰路についた。
「沙羅に言っちゃったみたいね」
明くる日の朝、いつものようにやってきた夫人にそんな事を言われた。
「すみません、つい出来心で。……怒っていましたか? というか、怒られましたか?」
「ん? いえ、全然だったわ。そのかわりね、……」
一瞬、夫人の顔つきが真剣なものになったので、ゴクリと喉を鳴らした。
「ふふ、……ここから先は自分で確かめなさい。あと、今日はすごいことが起こりそうだから、いつものアレは無しね」
絞ってくれなかったし、……と夫人は呟いて、僕を部屋にまで招き入れた。
何が何だか分からない。沙羅ちゃんは「きつく云っておきますから」と云ったのに、夫人はそんなことは無かったと云う。あと、「今日はすごいことが起こりそう」とは何だろう。しかも「すごいことが起こりそう」だから、いつも欠かせない母乳を手渡してくれなかった。いったい、どういうことなんだろう。あの後、家に帰ってから親子に何が起こっていたのだろう。これから何が起きるのだろう。僕はドキドキから足がすくんで、沙羅ちゃんの部屋の前まで来ると、思わず日和ってしまった。
「ふふ、そんなに身構えなくても大丈夫よ。ほら、おいで」
と、夫人が腕を開いて待ち構えるので、僕は吸い込まれるようにし彼女の抱擁へ向かっていった。夫人の巨大なおっぱいが体に当たり、背に回ってきた腕に抱きしめられ、ギュウっと力を込められる。胸元で潰れたおっぱいは、背中の方にまで広がって、僕の体を丸ごと包んできそうだった。柔らかい、あたたかい、……
「気持ちいい?」
「と、とっても」
「でもね、――」
と、夫人は僕の体を引き剥がす。
「あの子のハグはもっと気持ちいいわよ? ――ふふふふふ、お楽しみに」
「沙羅? ○○来たよー。入れるねー」
と、僕を扉の前に立たせた時に、夫人は云った。
「へっ? ちょ、ちょ、ちょっとまって!!」
「待たない! じゃ、○○くん、またあとでね」
ドン! と背中を押されて部屋に入ると、沙羅ちゃんは今の今まで寝ていたのか、ベッドの上で上半身を起こしたばかりだった。着ているものは真っ白なワンピース、……だろうか、意外にも大胆に露出された素肌は、カーテンの隙間から漏れる陽の光に、まばゆく照らされている。そしてその胸元、――と、云うよりは体の前には、一見して何��のか分からないほど大きなおっぱいがあり、ワンピースの中で柔らかく膝の上に乗っているのが見える。が、すぐに毛布をかけられて、見えなくなってしまった。まだ開きそうにない目をグシグシと擦って、あくびを一回すると、沙羅ちゃんはこちらを向いて、
「もー、……」
と拗ねた声を出した。
「おはよう、意外とねぼすけなんだね」
「休みの日はいつもこんなですよ。おはようございます」
と、ふわあ、……ともう一回あくびをして、くー、……と伸びをする。その一つ一つの仕草がなんともお上品で、僕は天使が眼の前に居るのかとさえ思った。いや、実際に天使なんだろう。そう思わなければ、非現実的なおっぱいと同じくらい非現実的に可愛い沙羅ちゃんの姿に、頭が追いつかない。
「見過ぎですよ、もー、……」
「ごめんごめん」
「もー、○○さんって、えっちなんだから」
もー、……と云うのが、素の彼女の口癖なのだろう。はにかんで云うものだから、それもまた、可愛くって仕方がない。
「沙羅ちゃん、僕はね、ここには無理やり連れて来られただけだから、……」
「何言い訳してるんです、分かってるくせに、……お母さんも、○○さんもいじわるです、……」
と、拗ねたように云って、おっぱいを隠す毛布を取り去った後、するするとワンピースをめくり始める。飾り気のないナイトブラに覆われたおっぱいが、徐々に露わになる。
「うぅ、……恥ずかしい、……」
とは云うけれども、その手は止まらない。どんどんめくって行き、ついには谷間が現れる。ブラのカップから溢れそうになっているおっぱいは、痛いくらいにハリがあるようで、パンパンに張り詰めていた。
「ちょっと、沙羅ちゃん?!」
「なんですか、私はここ何ヶ月か続けてきた日課��しようとしてるだけですよ? ええ、そうです。これが日課だったんですよ」
「まさか、本当に、……」
拗ねに拗ねた沙羅ちゃんは、次に、
「ん~~、……」
と渾身の力を込めて、ブラジャーを下からぐいっと持ち上げた。するとある程度のところで、――ドタン! ドタン! と、二つのおっぱいが重々しく膝の上に落ち、柔らかくベッドの上に広がっていく。
――呆気にとられるしかなかった。眼の前では非現実的な本物のおっぱいが、持ち主の足を潰しながら、ふるふると揺れている。これが彼女のおっぱい、沙羅ちゃんのおっぱい、高校二年生にして他のどんな女性よりも、――自身の母親よりも大きくなってしまったおっぱい。……
紛れもなく、本物だった。本物のおっぱいだった。舐め回すようにじっくりと見てみると、先っぽについている乳首は意外と可愛らしく、大きさは親指の第一関節から上くらい、色はおしとやかな赤色をしているのが分かった。また、ところどころ血管が浮き出ているのも分かった。
生きている、血の通ったおっぱい、……僕はいつしか乳首の前に跪いていた。
「吸ってください。……たぶん、たくさん出てくると思います。……」
拗ねた声色は、いつの間にか泣きそうな声になっていた。そして、その言葉通り、つー、……と、白い液体が乳輪を伝って行く。
僕はまず、その漏れ出た彼女のおっぱいをぺろりと舐めた。――あゝ、これだ。いつも夫人が持ってきてくれる牛乳瓶に入った母乳の味。今日はこってりとコクがあり、それに砂糖を入れたように甘い。「絞りすぎちゃった」とは、本当に沙羅ちゃんが自分の母乳を絞りすぎたことだったのか。
「美味しい、……」
僕は自然にそんな声を出していた。
「ふふ、そうでしょうとも。昨日も○○さんに会いましたから、……ね。――」
と云いながら、沙羅ちゃんは自分のおっぱいを揉むようにして、マッサージをする。その様子を黙って見ているのもなんだか、と思い、僕も動きを真似してマッサージをしてみる。――これがまた、最高だった。
「んっ、ふっ、……なんでそんなにお上手なんですか。……あんっ、……」
そんな色っぽい声を出す沙羅ちゃんのおっぱいの感触、……それはもはやこの世で体験していいものではない。あまりの気持ちよさに、僕は手の感覚を無くしてしまっていた。一体指が何本あるのか、どこにあるのか、何を触っているのか、もう何も分からなくなってしまった。
このおっぱいは、ただ大きいだけじゃない。母乳が出てくるだけじゃない。人間ならば誰しもが心を奪われてしまう、そんな天使のような、――いや、悪魔のようなおっぱいだ。一度触れば終わり、後はゆっくりと溶かされて、ついには跡形も無くなってしまう。
僕は我慢できなくなって、顔をおっぱいに押し付けながら、乳首を口に含んだ。――途端、びゅーびゅーと母乳が染み出し、あっという間に口の中は満杯になる。
吸う必要なんてなかった。吸わずともどんどん出てくる。僕は必死で飲んだ。必死で飲まなければ、口の中から溢れ出してしまうほどに、出てくるのだ。
コロコロと乳首を下で転がしてみると、どんどん母乳が出てきているのが分かる。それはまるで、口に蛇口を突っ込まれたような気分である。だが、出てくるのは水ではない、母乳である。天使のように可愛い顔からは想像も出来ないほど、濃くて美味しい母乳である。
「あんっ、んっ、ちょっと○○さん! 落ち着いて! おねがい!!」
ぼんやりとした僕の頭にそんな声が響いてきた。――が、止まらない。止められない。いつしか声の主の口を塞ごうと、乳首から口を離して、キスをしていた。と、同時にこっそりと含ませていた母乳を流し込んでやる。
「んん!! んんん~~~!!!」
ぷはっと口を離すと、天使はとろんとした目で、不満そうにこちらを睨んでいた。――だが、それすらも可愛い。
僕は再び乳首を口に含み、母乳を飲むのを再開した。が、そろそろ腹が一杯になり始めていたので、今度はおっぱいを揉む手を激しくしてみる。もはやマッサージをしてあげるなどということは頭にはない。揉む。とにかく、天使のおっぱいを全力で揉む。揉みしだく。
「や、やめて! いっちゃう! いっちゃうから!!」
だが、やめてあげない。乳首を舌でいじくりつつ、男の全力でもっておっぱいを揉む。
するとその時は意外と早く訪れた。
「いやっ、あんっ! んん~~~~!!!」
と、一層甲高い声を出しながら、天使の体がビクリと跳ねる。そして、止まる。それは、あまりにも蠱惑的で、あまりにも美しいオーガズムであった。
同時にお腹の中も限界を迎えてしまっていたので、僕は一旦口を離した。眼の前では天使が、浅い息を吐きながら、顔を赤くしてくったりと横たわっていた。
「もー、ばか、……○○さんのばか、えっち、へんたい、ろりこん、じゅくじょずき」
「そ、そんなに云わなくても、……」
「もー、うるさいへんたい。私の初めてをうばってきておいて、文句いうな。もっともっと吸え。まだかたっぽしか吸ってない」
「ごめんって」
「早く」
もうお腹はいっぱいだったけれども、沙羅ちゃんにこう命令されては仕方がなかった。まだ手のつけていない房の乳首を口に含んで、母乳を飲み始める。先程のオーガズムを体験している最中に、かなりの量が出ていたような気がするが、それでもびゅーびゅーと大量に吹き出してきた。
それから僕は口から母乳を溢れさせながらひたすら飲んだ。だが、飲んでも飲んでも一向に終わる気配がない。まさにミルクタンク。一体どれだけの母乳が、この巨大なおっぱいに貯められているのか。赤ちゃんどころか、人を一人や二人は軽く養える気がする。
「沙羅ちゃん」
「んー?」
彼女はいつしか僕の頭を撫でながら、慈しみに溢れた目でこちらを見てきていた。
「全然無くならないんだけど、……」
「うるさい。乙女の恥ずかしいところを見たんだから、もっともっと飲め」
と、言葉はきついけれども、声音は舌っ足らずでとろけるように優しい。だからなのか、僕は彼女の命令に抗えず、再び乳首を口に含む。
「ふふっ、赤ちゃんみたい。よしよし、いい子いい子。美味しいでしゅかー?」
こくこくと頷く。実際、味の方は落ちるどころか、出れば出るほど、どんどん美味しくなっていっていた。
「そうそう、これはねぇ、あなたが昔からケーキやらなんやらで、毎日口にしてきたおっぱいなの。味はそのへんの牛乳なんかよりもずっと美味しいし、チーズだって簡単に作れちゃう。ライバルはお母さんだけ。――もー、こら、ちゃんと飲みなさい」
だが結局、腹の痛みに耐えられなかった僕は、乳首から口を離して、後は沙羅ちゃんの文句を聞きながら、おっぱいの感触を楽しむだけになってしまった。
「うぅ、……もうお腹いっぱい、……」
「あら、もう終わったの?」
一旦トイレに向かった僕をそう呼び止めた夫人は、エプロンを着て、昼食の準備をしているようだった。
「お楽しみになった?」
「え、……あ、はい。それは、……」
「あの子、すっごく不機嫌だったでしょう。――ふふ、こっちにいらっしゃい、顔を拭いてあげる」
と、母乳でドロドロになった僕の顔を、首を、手を、丁寧に拭いてくれる。その姿は夫人と云うよりは、まさに妻。――あゝ、こういう女性と結婚したいな。……
「後でお風呂に入りなさいね。私たちの母乳って、すっごくベトベトして気持ち悪いから」
「ありがとうございます。やっぱり、お母さんもおっぱいが出ちゃうんですか?」
「――もちろん。あとお母さんはやめて。雪って呼んでくださいな」
「ゆ、ゆ、……」
「ん?」
「雪さん。……」
「ふふ、よろしい。――ところで、沙羅にはしてもら、……ってないようね」
と、雪さんはしゅるりとエプロンを取り外して、椅子にかけた。
「おいで。まだあの子にしてもらってないのなら、私がやってあげる。さあ、こちらにおかけなさい」
と云われるがままに、椅子に座ると、雪さんは満足そうな目を見せた後、するすると、上に着ていたものを脱いでいく。徐々に見えてきたのは、くびれた腰に、腹筋のうっすらと見えるお腹に、娘と同じ真っ白なブラジャーに包まれた巨大なおっぱいに、光沢の出来るほど瑞々しい肌をしたおっぱい。その体つきは、高校生の娘が居るとは思えないほど若々しく、まだ二十歳だと云われても、何も疑問には思わない。むしろもう少し若いと云われても不思議ではない。雪さんは手を後ろに回して、ぷち、ぷち、……とホックを外してブラジャーを取り去った。
――ものすごく均整の取れた、美しい肢体だった。
見惚れて惚けた顔をする僕に、雪さんは取り外したブラジャーを突きつける。
「どう? 顔よりもおっきいブラジャーは初めて?」
と、云いながらパサリと頭から被せてくる。僕の目は真っ白なブラジャーに覆い隠され、見ると、口も、顎も、いやいや、首の下にある恥骨までもが全てブラジャーに包まれている。もはや帽子をかぶるどころではない。体積としては片方だけで、僕の頭二つ分はあるだろう。
そして何よりとてつもなく良い匂いがするのが、もうたまらない。甘くて、優しくて、とろけるような匂い。……それは先程まで嗅いでいた甘い匂いに近いような気がするが、このブラジャーに染み付いたそれはもっと蠱惑的である。
と、ブラジャーの匂いを嗅いでいる間に、僕の男性器はすっかり空気に曝されていた。
「あら、顔に似合わず立派なのをお持ちなのね。――いいわぁ、これ。久しぶりだから張り切っちゃうかしら」
ぴゅー、……と何かが僕のモノにかかる。それは雪さんの母乳、……見なくとも分かる。沙羅ちゃんのもそうなのだが、二人の母乳はとろとろとあたたかく、どこか優しい匂いでこちらを包んでくるのである。
「自分のおちんちんが食べられちゃうところは、ちゃんと見なきゃね」
と、ブラジャーを取っ払ってくる。
「準備はいいかしら?」
「ゆ、ゆ、雪さん。……」
「んーん?」
「あ、えと、お願いします。……」
「ふふ、――りょうかい」
――瞬間、僕の下半身は砕け散った。いや、現実には砕けてなどいないけれども、あまりの気持ちよさに一瞬、腰から下の感覚が全て無くなったのである。
「うあああ、……す、すげ、……」
「どーお? 気持ちいい?」
「うっ、くっ、……き、きもち、うぐぁ、……」
「んー?」
「おああああああ、……ひっ、そんな、……ゆきさ、――」
雪さんの問いかけに答えようにも、息が詰まって声が出ない。足がガクガクと震え、腰は浮き、口からはガチガチと歯の当たる音がする。
その快楽はもはや命の危機すら感じるほどだった。僕はもう死ぬのだと思った。今この瞬間、このなんでもないアパートの一室は、地獄と化していた。――天国ではない。地獄である。
「そんなに気持ちいいのかしら。体験できないから、よくわからないわ」
「ひっ、……や、やめ、おぐぉ!――」
「んふ、いい顔、……あなたほんとうに可愛いわぁ、――」
ぐっちょ、ぐっちょ、ぐっちょ、……と下品な音を立てながら、僕を殺す気で責め立てる雪さんの大きすぎるおっぱいが食べたものは、僕のおちんちんだけではなかった。薄目を開けて見ると、僕の腰回りをすべて飲み込んでいる。もう何にも見えない。僕の男性器も、おヘソも、足も、腰も、全部おっぱいに食べられてしまった。
「ほらほら、これはどう?」
と、雪さんがおっぱいを交互に動かす。
「そ、それは! それは、………!!!」
「んふ、それともこっちのほうがいいかしら?」
と、今度はギュウゥゥゥゥっ、………と締め付けを強くしてくる。―――また下半身が消えた。
「ひっ、―――ちょ、ちょっとこれ以上は、……ちょっと雪さん! 雪さん! 雪さん!!! し、死ぬっ!!!」
「まだ喋れるなら大丈夫よ。ほら、どんどんいくわよ。――」
それからありとあらゆるパイズリテクニックをかけられた気がする。が、肝心なところでずるりと引き抜かれるので、まだイかされてはいない。
「ひひ、……ふへへ、……もう死ぬ、……いや、死んだ? 僕は死んじゃった?」
「生きてる生きてる。でも、ほんとうに死んじゃいそうだから、そろそろ仕上げといきましょうか」
と云って、だっぽんだっぽんだっぽん、……と雪さんがおっぱいを動かすペースを早くする。――もうだめだった。一瞬で快感が頭にまで駆け上り、
「うおおおおおおおおおおお!!!!!!!!」
と、僕は雄たけびをあげながら、オーガズムを迎えた。ギュウっと搾り取るように締め付けてくるおっぱいが、あまりにも気持ちよくて、僕は全ての精子を雪さんの谷間の中に出したように思う。
しばらく目を見開いて放心してしまっていたようだった。
「気持ちよかったかしら?」
我に返った時、雪さんはうっとりとした表情で僕の顔を覗き込みながら、そう問うてきた。
「は、はい。……死んじゃうかと思いました」
「ふふ、それはよかった。私がこれをすると、昔から男の人はみんなこうなっちゃうのよ。悪くは思わないでちょうだい」
「ふぇ、……」
「あ、そうだ、――」
と、僕のモノと、自分のおっぱいを綺麗に拭った雪さんは、意地悪っぽく微笑んで、人差し指をくちびるに当てた。
「あの子には内緒、……ね?」
「も、もうバレてるんじゃ、……?」
「ふふ、かもしれないわね。はい、じゃあ、ご飯にしましょう。立てる?」
――立てなかった。雪さんの殺人パイズリですっかり腰を抜かしてしまったらしく、立とうとした僕は逆に椅子から転げ落ちてしまい、そのまま気を失ってしまった。本当に恐ろしいパイズリであった。―――
目が覚めた時にはすっかり夜になっていた。どうやらあの後ベッドに寝かしつけてくれたらしく、僕はふかふかとしたベッドの感触を背中に感じながら、そして、ふわふわとした途方もない柔らかさを、両方の腕と、腹と胸と腰とに感じながら、天井を仰ぎ見ていた。
「ふぅ、……」
とにかく疲れた。沙羅ちゃんのおっぱいをこれでもかと云うほど揉みしだき、腹が裂けるほど母乳を飲み、そして雪さんの地獄のようなパイズリを受ける。たった2時間にも及ばなかったが、それでもここ数年間で一番疲れた日だった。
「あれ?」
と僕は声を漏らした。
「ここは?」
ぼんやりと見ていた天井は、自分の部屋の天井ではなかった。そもそもベッドの置き場所が違う。
ハッとなって、右を見てみると、思わずため息が出てくるほどの美女が、左を見てみると、思わず天使かと思うほどの美少女が、それぞれ僕の方を向きながら、すやすやと気持ちよさそうに眠っている。
あ、と気がついてみると、途端に、体の上に乗っているとてつもなく柔らかいそれが重みを帯びて、僕の体にのしかかってきた。ものすごく重い。
「し、死ぬ。……」
僕は手を伸ばして、上からのしかかってきている何かをひとしきり揉むと、もう一眠りしようと目を瞑った。が、その時、良い匂いが辺りに漂っていることにも気がついてしまい、結局、左右に居る美女と美少女の目が覚めるまで、悶々とした時間を過ごすしか無かった。
(おわり)
10 notes
·
View notes
Photo

品川心中 2/3
金蔵のほうは、かねての約束通り、日の暮れがたになると、品川へやってまいりました。女のほうも、もうくるかと、首を長くして待っているところへ金蔵がきましたから、たいへんな喜びようで…… 「まあ、金ちゃん、よくきてくれたね。さあ金ちゃん、こっちへはいっておくれよ。金ちゃん、まあ、坐っておくれよ。金ちゃん、うれしいねえ。金ちゃん……」 てんで、金ちゃんの国から金ちゃんをひろめにきたようなさわぎで…… 「うれしいよ。あたしはね、おまえさんがきてくれなかったら、どうしようとおもってたんだから……もう今夜は、この世のおわかれだから、うんと飲んでさわごうよ」 「ああ、どうせ死んじまうんだ。勘定の心配はいりゃあしねえや」 ひどいやつがあったもんで、ふだんはしみったれなくせに、今夜にかぎって飲むわ、食うわ…… 「さあ、なんでも持ってこい。勘定��ほしけりゃあ、三途《さんず》の川までとりにこい。地獄へいっしょにつれてってやるから……」 「なにをいうんだよ」 「なんでもかまわねえ。どうせいきがけの駄賃《だちん》だ」 おそめは気をもみました。もし、こいつの口からあらわれてはたいへんだとおもいますから、 「さあ、金さん、いいかげんにお酒をよして、寝ておしまいよ」 と、へべれけに酔っぱらっている金蔵を寝かしてしまいました。とたんに、二、三の客があがってきましたので、そのまわしをすまして、真夜なかごろにきてみると、金蔵は高いびきで鼻からちょうちんをだして寝ております。 「まあ、なんて寝ざまだろう。あきれたもんだねえ。いま死のうてえのに、よくこんなにグーグー寝られたもんだ。この人のは度胸があるんじゃあない。のんきで、からばかなんだよ……あらあら、鼻からまたちょうちんがでてきたよ。あれっ、ひっこんだ。またでてきた。こりゃあ、きっとお祭りで夕立に逢った夢かなんかみているんだね……あれっ、ちょうちんがつぶれたよ。きたないねえ……あーあ、こんなやつといっしょに死ぬのかとおもうとつくづく情けないねえ……いつまでこうしちゃあいられない。ちょいと金ちゃんお起きよ。ちょいと金ちゃん、金ちゃん……」 「あーあ、もう食えねえよ」 「まだ食べる気でいるんだよ。なんて人だろう。ねえ、起きとくれよ」 「もう夜があけたのか?」 「夜があけてどうするんだい?」 「夜があけてどうする? ふざけるなよ。夜なかに追いだされてたまるもんか。高輪《たかなわ》のところにわるい犬がいて、このあいだ、朝早く帰ったら、犬にとりまかれてひどい目に会っちまった。おらあ、もう、犬は大《でえ》きれえなんだから……」 「なにをいうんだね。しっかりしておくれ。おまえ、わすれたのかい?」 「なにを?」 「今夜死ぬんじゃあないか」 「なるほど、ちげえねえ……そうそう、すっかりわすれてた。ひと寝入りして起きたら、すこしめんどうくさくなっちまった。どうだい、二、三日死ぬのを延《の》ばすわけにはいかねえか?」 「おふざけでないよ。心中の日延べなんてあるもんかねえ。さあ、早くしたくにかかるんだよ」 「よしきた。そのつつみの中をみねえ」 「おや、りっぱな白無垢《しろむく》があるね」 「これがおめえので、こっちがおれのだ」 「金さん、おまえのは、腰から下がないじゃあないか」 「ああ、倹約につきお取り払いだ……このほうがさばさばしてていいやな」 「なにか、死ぬ道具を持ってきたかい?」 「そのふろしきのなかに短刀《あいくち》がへえってるだろう?」 「短刀が? ……なにもありゃあしないよ」 「そんなはずはねえんだが……よくふるってみなよ……え? ねえかい? おかしいなあ……あっ、たいへんだ。たしかに短刀を買ってきたんだが、昼間、親分のうちへ暇乞《いとまご》いにいって、水がめの上へのせたままわすれてきちまった」 「まあ、そそっかしいねえ、この人は……あたしも、こういうことがあるかと虫が知らしたか、昼間のうちに、かみそりを研《と》がしておいたから……金さん、死ぬのはかみそりにかぎるよ」 「おい、待ちなよ……かみそりはいけねえ。刃のうすいので切ったやつは、療治がしにくいというから……」 「なにいってるんだよ……ああ、そうかい、おまえ、死ぬつもりがないんだね。あたしをだましたんだね……いいよ、おぼえておいでよ。あたしはこれでのどをかき切って死んだら、三日たたないうちにおまえさんをとり殺してやるから……」 「おい、待ちなよ。おいおい、あぶねえからはなしなよ……おいっ、あぶねえじゃあねえか。こんなものをふりまわして……」 「なにするのさ? 人のかみそりをとっちまって……」 「だからよ、なにも荒っぽいことをしなくったって、死ねりゃあいいんだろ?」 「どうするのさ?」 「もめん針を二十本ばかり持ってきねえ」 「もめん針を? ……どうするのさ?」 「ふたりの脈どこを、つっつきあっていたら、夜のあけるまでにはかたがつくだろう」 「おふざけでないよ。しもやけの血をとるんじゃああるまいし……じゃあ、裏へいっしょにおいでよ」 「なに? 裏へ? そりゃあだめだ、だめだ……松の木かなんかへぶらさがろうってんだろ? はなを二本たらして……ありゃあ、あんまり気のきいたもんじゃあねえ……」 「なにをぐずぐずいってるんだよ。なんでもいいからいっしょにおいで!」 「とほほ……いくよ、いきますよ……」 金蔵のやつ、すっかりべそをかいております。おそめにせきたてられて、うらばしごをおりてきました。庭にでまして、飛び石をつたわってくると、垣根があって、木戸には錠《じよう》がおりておりますが、これへ手ぬぐいを巻いてぐっとねじると、潮風のためにくさっていたものか、ぽきりととれましたので、これさいわいと、木戸をあけてでると、前はもう海でございます。折りしも空は雨模様で、ときどき大粒のやつがぽつりぽつりおちてくるというありさま……あげ潮どきとみえて、ドブーン、ドブーンと打ちよせる波は、岸を洗ってものすごうございます。 「さあさあ、金さん、なにしてるんだよ。ずんずん前へいくんだよ。桟橋《さんばし》は長いよ」 「とほほほ、桟橋は長くったって寿命はみじけえや……おいおい、あぶないよ。押しちゃあいけねえよ」 「なにいってるんだい、早くとびこむんだよ」 「そりゃあいけねえ。おらあ、風邪ひいてるから……えっ、だめかい? おどろいたなあ。このあいだ、占《うらな》い者がそういったよ……おまえさんは水難の相があるって……」 「いまさら、そんなことをいったって、しようがないよ」 「じゃあ、水へへえる前によくかきまわして……」 「お風呂へはいるんじゃあないよ。いせいよくとびこむんだよ」 「いせいよくったって、茶わんのかけらでもおちてたら、足を切っちまわあ」 「潮干狩じゃあないよ。じれったいねえ」 「どうもつめたそうだなあ」 度胸のないやつですから、泣き声をだしております。とたんに座敷のほうで、 「おそめさんえ、おそめさんえ」 二声、三声呼ぶ声が聞こえましたので、みつけられちゃあたいへんだと、金蔵のうしろにまわって、すかしてみると、がたがたと爪さきがふるえておりますから、腰のところに手をかけておいて、 「金さん、おまえばかり殺しゃあしない……かんべんしておくれ」 ドーンと、もろにつかれたから、金蔵のやつ、もんどりうって、ドボーンととびこみました。おそめもつづいてとびこもうとすると、店《みせ》の若い衆が、 「おっ、待った、待った。おそめさん、お待ちなさい」 「どうか、恥をかかしておくれでない。みのがしておくんなさい……どうぞ殺して!」 「まあまあ、お待ちなさい。つまらねえことをするじゃあありませんか。おまえさん、紋日《もの》前に金ができねえで、こんな無分別なことをするんでしょう? 金ならできた。できたんだから、死ぬのはおよしなさい」 「えっ、ほんとうに?」 「だれがうそなんぞつくもんですか。番町の旦那が持ってきました。『どうか当人に手わたしして、よろこぶ顔がみたい』って……おまえさん、四十両無心してやったそうだが、十両よけいで五十両、旦那がふところへいれて、さっきから待っていますよ」 「おや、そう、できたの? お金が! ……しかし、とんでもないことをしてしまったよ。もうひと足早ければ、こんなことをするんじゃあなかったのに……」 「どうしたんで?」 「ひとりとびこんじゃったんだよ」 「だれが?」 「金さん」 「金さんてえと、あの貸本屋の金公? あのばか金ですかい? あんなものようがすよ。流されて、鮫《さめ》かなんかに食われちゃうから……あいつは鮫好きのする顔だ」 「だって、おまえさん……」 「なあに、よござんすよ。知っているのは、おまえさんとあっしばかりだ。だまっていれば知れる気づかいはありません」 「それでもね、長年の馴染《なじみ》だもの……」 「勘定ができないで、居残りをしていたが、とうとうとびこんで死んだといえば、なんてえこたあありゃあしません」 「でもねえ、あたしがつきとばしたんだからねえ、その辺にいるもんなら、ひきあげてやりたいから、ちょいと待っとくれよ……ねえ、金ちゃん、もう死ななくてもいいようになったから、もう一ぺんあがっておくれな。ねえ、金ちゃん、あがって頂戴よ。おあがんなさいよ。ちょいと、ちょいと、ねえ、金ちゃん、世話を焼かせないでおあがりよ」 「店さきで客をよんでるわけじゃあねえから、そんなこといったってあがるもんですか。もうどっかへ流れちまったんだから……」 「そうかねえ。じゃあ、しかたがないねえ……じつはねえ、金ちゃん、あたしも死ぬつもりだったけど、お金ができてみると、死ぬのはむだだわ。あたしだっていつかは死ぬから、そうしたら、あの世でお目にかかりましょう。ただいままではながながと失礼……」 世の中にこんな失礼なはなしはありません。 金蔵は、アワをくらい……潮をくらい、面くらい、四苦八苦の苦しみをいたしましたが、ご案内の通り、品川は遠浅《とおあさ》でございますから、水は腰までしかございません。 「なーんだ。浅《あせ》えんだよ。こりゃあ、横になって水飲んだんだ。どうもあきれけえったもんだ……ハー、ハックション! ちくしょうめ、やっぱり風邪ひいちまった。あーあ、鼻がむずむずしゃがる。あれっ、鼻からダボハゼがでてきやがった……ちくしょうめ、人をつきとばしておいて、てめえは金ができたから死なねえとは……よくも人をだましゃがったな。どうするかみやがれ、おぼえてろ!」 金蔵は、元結《もつとい》が切れてざんばら髪、額《ひたい》のところをな��かで切ったとみえて、白い着物には泥と血がついてものすごいありさま……くやしいけれど、おそめのところへこのままあばれこめば恥の上塗りですから、やむをえず、海の中をガバガバと歩いて高輪の崖《がけ》へはいあがりました。すると、駕籠屋が、ちょうちんを前にして、ふたりでいねむりの競争をしておりますから、 「もし、駕籠屋さん」 と、呼んだんですが、駕籠屋がねぼけまなこをあいてみると、腰から下はまっ黒で、上のほうが白い。まして、さんばら髪で、額のところへ血が流れておりますから、駕籠屋はおどろいて、 「わっ」というと逃げてしまいました。金蔵は、駕籠がそこにあっても、かつぎ手がないので、駕籠のまわりをぐるぐるまわっているうちに、 「ワンワンワンワンワン!」 犬もあやしい姿をみてほえかかりますから、金蔵がむやみに逃げだしますと、犬もつづいて追いかけてまいります。芝までくると、犬のほうも係《かか》りがちがってまいります。ここからまた、ほかの犬にとり巻かれ、とうとう犬の町内送りになるようなしまつですが、自分のうちは空き家同様ですから帰るわけにはまいりません。しかたがないから親分のうちへまいりました。 こっちは、若い者をあつめて、さいころでがらっぽんと勝負ごとの最中でございます。とたんに、「ワンワンワンワン……」とほえる犬の声で、 「おい、みんなしずかにしなよ。ひどく犬がほえるから……」 というときに、表の戸をわれるように、ドンドンドンドンとたたきましたから、あわてたやつが、 「手がへえった!」 と、どなったからたまりません。ろうそくをひっくりかえす、行燈をけとばす、これをさいわいに場銭《ばせん》をさらうやつなぞがあって、もうたいへんなさわぎ。 「しずかにしねえかよ。大家《おおや》さんにちげえねえ……へえ、ただいまあけます。ひどくたたいちゃあいけません。大家さんがだしぬけにたたいたので、うちのやつらがねぼけやがって、あのさわぎでございます……おい、しずかにしねえ。だれだい? 金だらいをはいてかけだすのは……なにしろ、まっくらじゃあしょうがねえ……あっ、いてえ! だれか、おれのあたまをふみつけやがったな。人のあたまをふみ台にするやつもねえもんだ……とにかくあかりをつけなくっちゃあしかたがねえ。あの……ちょいと、なにを貸しねえ」 「え?」 「なにを貸せよ」 「なんです?」 「さっきから手まねをしてるじゃあねえか」 「くらやみで手まねをしたってわからねえ」 「ああ、あったよ。火打ち箱はここにあった……あれっ、しょうがねえな、なぜまたこう火打ち石が欠《か》けるんだろう? こんなに欠けるということはねえんだが……おや、ばかにしやがって、こんな中へ餅なんぞいれときゃあがって……だれだい? こんな中へ餅なんぞほうりこんどくのは……おい、ろうそくをだしねえ。しょうがねえなあ。夜がふけたから大きな声をだすなといったのに、ちっともかんげえなしでいやあがるから、こんなことができるんだ……へえ、大家さん、ただいまあけますから……」 ろうそくをつけて、がらりと戸をあけてみると、金蔵が、たいへんな姿で立っておりますから、親分は肝《きも》をつぶして、 「だれかきてくれ。ここに、へ、へ、変なやつが立ってらあ」 「へえ、親分、こんばんは……」 「あっ、びっくりした。てめえ、金蔵じゃあねえか。なんだって、そんなざまをしていやがるんだ?」 「へえ、品川で心中のしそこないで……」 「それみやがれ! だからいわねえこっちゃあねえ。あれほど意見したのを聞かずにでていきゃあがって……女を殺���て、てめえばかり助かってきてどうするんだ?」 「いえ、あっしだけが死にそこなって、女はまるっきりとびこまねえんで……」 「ばかだな、こんちきしょうは……どこまでまぬけにできてるんだか……こっちへへえれよ。へえったら、あとをしめろ。ほんとうにしょうがねえ野郎だなあ。待てよ、待ちなよ。そのまま上へあがられてたまるもんか。いま水をとってやるから、よく洗ってからあがるんだ。おーい、だれか水を持ってこい。金蔵がまちげえをしてきやがったんだ。ちょいと、たらいに水をくんで……あれっ、たいそうすすがおちてくるが……だれだい、梁《はり》にあがってるのは?」 「あっしです」 「虎公だな。ははあ、てめえか、さっき、おれのあたまをふみ台にしてそこへあがったのは?」 「へえ、いっしょうけんめいあがりはあがりましたが、安心したらおりられねえ」 「しょうがねえ野郎だな。きたねえ尻《けつ》だなあ。もうすこしふんどしをかたくしめろよ。だらしのねえざまをして……だれか、はしごを持ってきてやれ……あれっ、だれだい、ねずみいらずへ首をつっこんでるのは? 民の野郎じゃあねえか。なにしてるんだ? あれっ、てめえ、つくだ煮をみんな食っちまったな」 「逃げるんで腹ごしらえをしようとおもって……」 「あきれた野郎だ」 「ついでに、酒を飲もうとおもったが、ばかに塩っかれえんで……」 「それは酒じゃあねえ。醤油《したじ》だ」 「そうか。しょうゆうこととは気がつかなかった」 「ふざけるな、この野郎……この最中《さなか》にしゃれをいってやがらあ……おい、だれだ? へっついの中へ首をつっこんでるのは? あっ、でこ亀か……うーん、こりゃあ、わりいやつがへえっちまったなあ……ああ、だめだ、だめだ。ひっぱったってぬけないよ。あたまの鉢がひらいてるんだから……茶釜をとってだしてやれ。いいか、無理しちゃあいけねえよ。あたまがこわれるのはかまわねえが、へっついがこわれちゃあこまるからな……だれだ? いま時分ぬかみそをかきまわしてるのは? なんだ、留《とめ》じゃあねえか」 「へえ、親分、もうあっしは助かりません。親不孝をしたバチです。おふくろを呼んできてください」 「どうしたんだ?」 「縁の下へ逃げるつもりで、ぬかみそ桶の中へとびこんじまったんですが……」 「大丈夫か? あがれるか?」 「それがあがれねえんで……おっこったとたんに、きんたまをぶつけてとびだしちゃったんです。とても助かりません」 「しょうがねえなあ。おい、だれか医者をよんできてやれ。医者を……すぐにだぞ……どうした? で、きんの在所《ありか》はわかったか?」 「しっかり持ってます」 「そうかい。そいつあ気丈《きじよう》(気がつよい)だ。どんなものかみせてみろ」 「ばかっ、こりゃあ、なすの古漬けだ」 「なんだい、なすかい……あはははは、なるほどちげえねえ。きんはここにくっついていました」 「あれっ、いやにくせえな。こりゃあ、ぬかみそのにおいじゃあねえぞ。え? どうした? なに? 与太が便所《ちようずば》へおっこった? さあ、こりゃあたいへんだ。待ちねえ、いまあげてやるから……」 「へっへっへ、親分、もうあがってきた」 「ばかっ、あがってきちゃあいけねえ。さあ、洗ってこい! ……しょうがねえやつらじゃあねえか。どいつもこいつも意気地がねえ……みんな、伝兵衛さんをみろよ。さすがはもとはお武家さまだ。このさわぎにびくともせず、ちゃんと坐っておいでなさるぜ」 「いや、おほめくださるな。とうに腰がぬけております」
「おい、金蔵、まあ、こっちへきて坐れ」 「へえ、へえ」 「どうしたんだ?」 聞かれて金蔵が、「じつは、これこれ、こういうしだいで……」と事情を説明しますと、 「……うーん、じつにどうもまぬけなはなしじゃあねえか。しかし、その女もひでえやつだなあ。てめえ、くやしいだろう?」 「ええ、そりゃあもう……女は、たぶん、あっしが死んだとおもってますよ」 「うーん、どうもいめえましいはなしだなあ。こいつあ、ひとつ狂言を書いて仕返しをしてみねえか?」 「え? 狂言を書いて仕返しを?」 「そうよ。そのおそめてえ女を坊主にしてやろうじゃあねえか。あんまりしゃくにさわるから……」 「へえ、どうするんで?」 「うん……てめえ、大食いだったな?」 「へえ、おまんまと借金の多いことじゃあだれにもひけはとりません」 「つまらねえじまんをするなよ……じゃあ、てめえ、一ぺんめしをぬいたらすぐに顔にでるな」 「ええ、そりゃあもう……あっしゃあ一ぺんでもめしを食わねえと、すぐにやせて、眼なんぞくぼんじまいます」 「だらしのねえ野郎だなあ……しかし、まあ、それがこの狂言にはもってこいだ。一日ばかり食わずにがまんしろ」 「そんなことをしたら、ひょろひょろになっちまいます」 「だからいいんだよ。まっ青で、眼をくぼませて、ひょろひょろになったてめえが、大引け(午前二時)ちょいと前に白木屋へいって、すーっと登楼《あが》るんだ。むこうでも死んだとおもってるところだから、びっくりして、『どうした?』と聞かあ。そしたら、てめえいってやれ。『死んで十万億土という暗いところをすたすたいくと、金蔵、金蔵とよばれるんで、ひょいとふりかえるとたんに生きかえった。まだ生きかえりのほやほやだ』とかなんとか、縁起のわりいことをいろいろいうんだ。ものをあんまりむしゃむしゃ食うんじゃあねえぞ。わずかのあいだだからがまんするんだ」 「へえ、なるほど……」 「たいがいのところで、おめえが『心持ちがわりいから、寝てしまおう』といって寝るんだ。それがおめえの役だ。いいか。そうして戒名《かいみよう》を一枚書いてふところへいれとくんだ。そこでだ……おい、民公、ちょいとこっちへきねえ。おめえ、ご苦労だが、さっきから聞いててようすは飲みこんだろう? おめえは、金公の弟てえ役どころだ。そのおそめてえ女に会って、兄貴が死んだとこういうんだ」 「へえ?」 「おめえは、女の顔をみたら、ただめそめそ泣いてりゃあいい。それから、おれが、『金公がこの人ととりかわした起請《きしよう》(客と遊女ととりかわした愛情の誓いの文書)をだしねえ』というから、ふところからそいつをだすんだ。こんどは『戒名をだしねえ』っていうから、おめえがわざとふところをさがしてみて、『あっ、いけねえ。戒名をなくしちまった。おとしたのかな?』とまごまごするんだ。いいなあ、民公、これが、おめえの役だ。そこで、なあ、金公、おれが女に会って、『金公は死んだぜ』というと、女が、『死にゃあしないよ。金さんは今夜きているもの……死んだ者がくるわけがない』『なあに、死んだにちげえねえ』『そんなら証拠をみせてあげよう』ってんで、きっとおめえの寝てるところへつれていくだろう。そのごたごたしてるひまに、おめえはふとんからぬけだして、戒名だけそこへおいて、どっかへかくれるんだ。女はおめえが寝ているとおもうから、おれたちにみせようとおもって、部屋へつれてって、屏風《びようぶ》をあけてみると、寝ていたおめえがいなくなって、戒名だけがある。こいつあきっとおどろくぜ」 「うん、そりゃあおどろかあ」 「そいつをまたおどかすのが、民公、おめえの役だ」 「いない、いない、バーってやるか?」 「ばかっ、赤ん坊あやしてるんじゃあねえや……女だって身におぼえがある���ら、『どうしたらよかろう?』というやつをつかめえて、『てめえは兄貴をだまして、惚れたふりをして心中をしかけて、てめえは死なねえで兄貴だけを殺して、こうしてすまして商売している。兄貴はくやしくって、いくとこへいかれねえで、おめえのところへ化けてきたにちげえねえ。いまにとり殺されるぜ。兄貴はあれでなかなか執念深えんだから……』とかなんとか、かまわねえからうんとおどかしてやるんだ。こういやあ、女もびっくりして、『どうしたらよかろう?』というにちげえねえから、『それじゃあ、まあしょうがねえから、髪の毛を切って、それを寺におさめたら、兄貴も浮かばれるだろうよ』と、そういやあ、きっと女が髪を切る。切ったら、おれがポンポンと手を打つから、金公、おめえがそれへでるんだ」 「ははあ、こいつあおもしれえ趣向ですねえ……じゃあ、親分、よろしくおねげえ申します」 てんで、それからしたくをして、金公は夜食をぬきにして腹ぺこで、頃合いをはかって、ぼんやりと白木屋の店さきまでまいりますと、ちょうど清どんという若い衆が、二階からトントンとおりてきて、下駄をはいて外へでようというところへ金公がぬーっと顔をだしましたから、 「ああびっくりした……あれっ、おまえは金蔵さん?」 「清どん、しばらく……」 「あなた……どうなさいました? ずいぶんおやつれになりましたが、よくまあご無事で……」 「ええ、まあ、無事っていえば無事で……おそめはいますか?」 「ええ、おります」 「会って、はなしがしてえんだが、今夜は、ひとつ、ご厄介になりますよ」 「へえ、ありがとう存じます。どうぞおあがんなすって、さあどうぞ……おそめさん、おそめさーん、ちょいと、お顔を……」 「はい、なに?」 「あのう……きましたよ、青い顔をして……」 「だれがさ?」 「だれがって……貸本屋の金蔵が……」 「なにいってるんだよ。人をかつぐんじゃあないよ」 「いえ、べつにかついでるわけじゃあねえんですよ」 「だって、あの人は死んだんじゃあないか」 「それがきたんですよ」 「ほんとう?」 「うそなんぞつくもんですか。いまたばこを買おうとおもって、店をでようとしたとたんに、ぬーっ……」 「あら、いやだよ。幽霊かい?」 「そうですねえ。それがはっきりわからねえんで……なんだかまっ青な顔をして、『おそめはいますか?』というから、『ええ、おります』というと、『いるなら会ってはなしがしてえんだが、今夜は、ひとつ、ご厄介になりますよ』って、いまおあがりになりました」 「いやだよ、いやだよ。足があったかえ?」 「それがつい気がつきませんで……」 「いやだねえ。後生だから、おまえ、ついてきておくれ」 「ええ、ついてまいりましょう。さあ、おいでなさい」 「いくから、そうお押しでないよ」 「押しゃあしません。おまえさんがあとへさがるんで……」 「清どん、うしろを押さえながらおふるえでないよ」 「わたしゃあふるえやあしません」 「しっかりと、いいかい……あら、まあ、金さん? たしかに金さんだねえ……ほんとうにまあかんべんしとくれ。それでもまあよく無事でいてくれたねえ。あたしゃあ、ほんとうにおまえさんが、あれっきりになって、もう死んじまったとおもうから、朝晩|香花《こうはな》を手《た》むけてお題目《だいもく》をとなえていたよ。生きてるなら、早くきてくれればいいのにさあ……」 「まあ、こっちへおはいりよ」 「はい……」 「おそめさん、あたしはいっぺん死んだんだよ」 「ええっ、死んだ?」 「うん、十万億土という暗いところをすたすたいくと、金蔵、金蔵とよばれるんで、ひょいとふりかえるとたんに生きかえった。まだ生きかえりのほやほやだ」 「まあ、よかったねえ。じゃあ、こうしよう。今夜はいろいろはなすことや聞くこともあるから、あたしが台のものをとってあげよう」 「それが、もう、一たん死ぬと、人間は意気地のねえもんだから、なまぐさものはちっとも食べられない」 「あらそう……じゃあ、精進《しようじん》ものならいいだろう?」 「うん、そんならまことにすまないけれども、おだんごをすこし……」 「いやだよ。で、おだんごは、餡《あん》かい? それとも焼いたのかい?」 「白だんごがいい」 「いやなことをおいいでないよ」 「ここにある花なんぞよしちまって、樒《しきみ》(別名仏前草)を一本……」 「おふざけでないよ。縁起でもない。なにか甘いものをとろう。きんとんでも食べないかい?」 「もう、なにも食べたくないよ。なんだか心持ちがわるいから、寝かしておくれ」 「ああ、そう。それじゃあ、おやすみなさい」 金蔵を寝かしてしまうと、いれかわってきたのは、親分と民公という男でございます。 「おう民公、白木屋はここだな」 「若え衆に聞いてみましょう……おう、若え衆さん、白木屋というなあどこだい?」 「へえ、てまえどもで……」 「ここにおそめさんという女郎衆はいるかい?」 「へえ、おります」 「そうかい。じつは、その人にすこうしはなしがあるんだが、逢わしてもらいてえ」 「へえ……ええ、おそめさーん」 「はーい」 「ええ、ちょいと……」 「なんだい?」 「ええ、なんですか、初会《しよかい》のお客さまがおふたりで、あなたにちょっと逢いたいってんですが……」 「ああそう……おや、いらっしゃいまし。あたしがおそめですが……」 「そうかい。まあ、こっちへへえっとくれ」 「はい……」 「いいから、こっちへおはいり。すこうしばかりはなしがあるんだ。あとをしめてくんねえ」 「なんでございます?」 「まあ、はじめて逢ってこんなことをいうのもいやだが……おう、民公、縁あって、おめえの兄貴のかみさんになったのは、この人だよ」 「そうでございますか。はじめてお目にかかります。このたびは、兄貴がとんだことになりまして……」 「おいおい、泣きなさんな。みっともねえ。泣��たところで、死んだ者が生きかえるわけでもねえ……ねえ、おそめさん、この男がおまえさんの顔をみて、めそめそ泣いてるから、ばかか、気ちげえかとおもうか知らねえが、じつはなあ、こういうわけだ……あっしが、夜釣りに品川へきた。あいにくと雑魚《ざこ》一ぴきかからねえから、こんな夜は早くきりあげて帰ろうとおもって網を打つと、ずっしりと手ごたえがある。あげてみると、仏《ほとけ》さまよ。びっくりするじゃあねえか。それが金蔵の野郎だ。それからね、死骸をひきあげてみると、ふしぎなことに、からだについてるものはのこらず流れてしまった中に、おまえさんが書いた起請だけが、ぴったりと肌についているんだ」 「へえー」 「どうもおどろいたね。みんなふしぎがっているんだが、こりゃあきっと死ぬときに、野郎がおまえさんのことをおもって死んだんだろう。そんなこたあ、おまえさんも知るまいから、その起請と戒名をおまえさんのところへ持ってきてはなしをしたら、おまえさんもかわいそうだとおもって、題目なり念仏なりとなえてくれるだろう。そうすりゃあ、金蔵もきっと浮かぶだろうとおもって、今夜やってきたんだ……おう、民公、あの……なにをだしねえ、起請を……おそめさん、この起請は、おまえさんが書いて金蔵にやったもんだな?」 「ああ、そう……」 「うん、民公、こんどは、戒名をだしねえ」 「へえ……おや? ありませんぜ」 「おいおい、なにをいってるんだ。ありませんというなあおかしいじゃあねえか。戒名と起請をこの人のところへ持っていこうと、おめえはたしかにふところへいれたじゃあねえか……途中ではなでもかんじまやあしねえか?」 「とんでもねえ。ほかのものとちがって戒名ではなをかむなんて……」 「だって、起請があって、戒名がねえというなあおかしいじゃあねえか。早くさがせ!」 「ふふふふふ、およしなさいよ。おまえさんたちはなにをくだらないことをいってるんですよ。ばかばかしいじゃあありませんか」 「ばかばかしい? ばかばかしいたあなんだ?」 「つまらないいたずらをするもんじゃありませんよ」 「なんだ? いたずらというなあ?」 「なんだもないもんですよ。そんなことは、金さんがこない晩にきていえば、あたしだってすこしはおばえがあるからおどろきますが、お気の毒さま、今夜は金さんがひさしぶりできていますよ」 「えっ、金公がきた? だって、おそめさん、死んだ者がおめえさんのところへくるわけがねえ」 「わけがあってもなくっても、ちゃんともう寝てますよ」 「ほんとうかい?」 「ほんとうかいって、いやですよ。いつまでもくだらないしゃれをしていちゃあ……」 「しゃれであるもんか……ほんとうに金公がきてるのかい?」 「ええ」 「じゃあ、いってみよう」 「さあ、きてごらんなさい……ここですよ。ちょっと金さんあけますよ……あらっ、金さん、金さん……」 「どうした? いるかい?」 「おかしいねえ。たしかにいたんだけど……あらっ!」 「どうした? おやっ……おい、民公、おめえがおとしたてえのは、この戒名じゃあねえか?」 「えっ……養空食傷信士《ようくうしよくしようしんじ》……うん、こりゃあ、兄貴の戒名だ」 「あら、まあ、どうしたんでしょう?」 「じゃあ、戒名が途中でなくなったのは、おめえのところへ幽霊になって迷ってきたんだ」 「まあ、気味がわるいねえ……そのせいかしら? 白だんごが食べたいとか、樒を一本とか、縁起のわるいことばかりいってたのは……」 「おいおい、おそめさん、なにもふるえて泣くこたあねえ。はじめっから、おめえが、金公のために泣くような了見《りようけん》なら、こんなことになりゃしねえ。おめえが借金のために金公と心中しようといって、そうしてあいつをさきへ殺して、金ができたからといって死ぬのをよしてよ、おまけにずうずうしくここで商売をしている。これじゃあ、金公もいくところへいくこともできめえ。どんなばか野郎だって、こりゃあくやしいにちげえねえ。この調子じゃあ、これから幽霊が毎晩でて、おめえをじりじり責め殺すぜ」 「あら、たいへんなことになっちまった。どうしたらよかろうね?」 「じゃあ、こうしねえ。金蔵へのわびのしるしに、髪の毛を切って、回向料《えこうりよう》のいくらかでもつけて、寺へおさめて経をあげてもらいねえ。それよりほかにしょうがねえ」 「そうすりゃあ、あの人が浮かんでくれますかねえ?」 「ああ、きっと浮かぶにちげえねえ」 「そんなら、すこし待っておくんなさい」 と、かみそりを持ってきて、髪の毛をプツリ! 「さあ、これでよろしゅうございますか?」 「うん、大丈夫だ」 「浮かんでくれますかねえ?」 「ああ、いますぐ浮かばせるから……おい、金公、もういいから、でてこい!」 「おう」 「あら、いやだよ、いやだよ。じょうだんじゃあない。金さんは生きてるじゃあないか。ちくしょうめ!」 「ざまあみやがれ! てめえがな、あんまりあこぎなことをしゃあがるから、みんなでこうやって仕返しをしてやったんだ」 「ほんとうにまあ……みんなでよってたかって人を坊主にして、どうするんだい?」 「どうするって、おめえがあんまり客を釣るから、比丘《びく》(魚籃《びく》)にしたんだ」
3 notes
·
View notes