#心に���かぶ感情や感覚を動物に喩えて描く
Explore tagged Tumblr posts
Text
P3 Club Book Persona 2 Eternal Punishment pages scan and transcription.
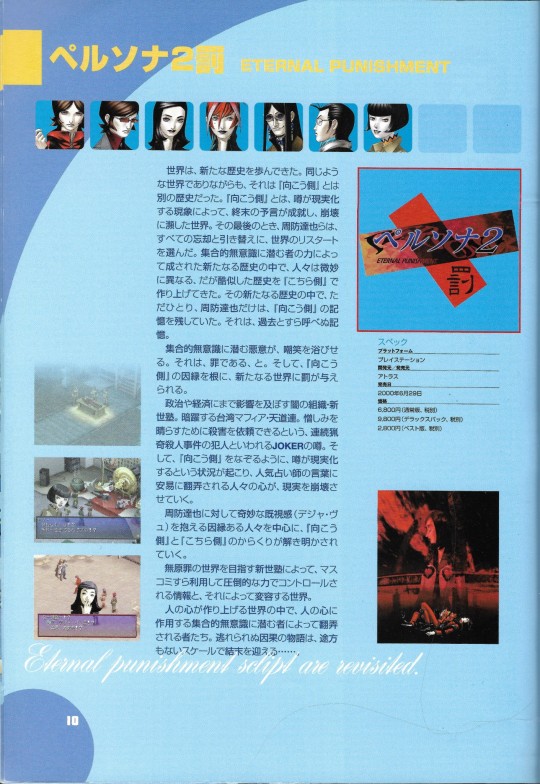
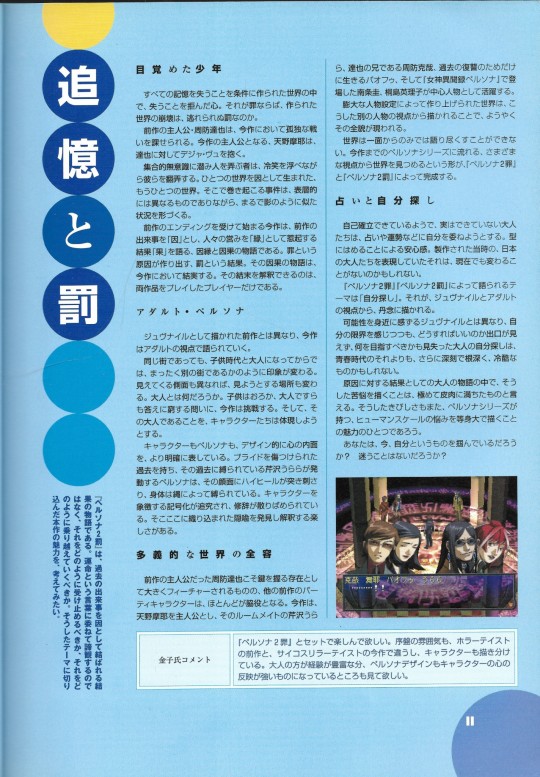
ペルソナ2罰 ETERNAL PUNISHMENT
世界は、新たな歴史を歩んできた。同じような世界でありながらも、それは『向こう側』とは別の歴史だった。『向こう側』とは、噂が現実化する現象によって、終末の予言が成就し、崩壊に瀕した世界。その最後のとき、周防達也らは、すべての忘却と引き替えに、世界のリスタートを選んだ。集合的無意識に潜む者の力によって成された新たなる歴史の中で、人々は微妙に異なる、だが酷似した歴史を『こちら側』で作り上げてきた。その新たなる歴史の中で、ただひとり、周防達也だけは、『向こう側』の記憶を残していた。それは、過去とすら呼べぬ記憶。
集合的無意識に潜む悪意が、嘲笑を浴びせる。それは、罪である、と。そして、『向こう側』の因縁を根に、新たなる世界に罰が与えられる。
政治や経済にまで影響を及ぼす闇の組織・新世塾。暗躍する台湾マフィア・天道連。憎しみを晴らすために殺害を依頼できるという、連続猟奇殺人事件の犯人といわれるJOKERの噂。そして、『向こう側』をなぞるように、噂が現実化するという状況が起こり、人気占い師の言葉に安易に翻弄される人々の心が、現実を崩壊させていく。
周防達也に対して奇妙な既視感 (デジャ・ヴユ) を抱える因縁ある人々を中心に、『向こう側』と『こちら側』のからくりが解き明かされていく。
無原罪の世界を目指す新世塾によって、マスコミすら利用して圧倒的な力でコントロールされる情報と、それによって変容する世界。
人の心が作り上げる世界の中で、人の心に作用する集合的無意識に潜む者によって翻弄される者たち。逃れられぬ因果の物語は、途方 もないスケールで結末を迎える······
スペック
プラットフォーム
プレイステーション
開発元/発売元
アトラス
発売日
2000年6月29日
価格
6,800円 (通常版、税別)
9,800円 (デラックスパック、税別)
2,800円 (ベスト版、税別)
Eternal punishment script are revisited
追憶と罰
『ペルソナ2罰』は、過去の出来事を因として結ばれる結果の物語である。運命という言葉に委ねて諦観するのではなく、それをどのように受け止めるべきか、それをどのように乗り越えていくべきか。そうしたテーマに切り込んだ本作の魅力を、考えてみたい。
目覚め��少年
すべての記憶を失うことを条件に作られた世界の中で、失うことを拒んだ心。それが罪ならば、作られた世界の崩壊は、逃れられぬ罰なのか。
前作の主人公・周防達也は、今作において孤独な戦いを課せられる。今作の主人公となる、天野摩耶は、達也に対してデジャ・ヴュを抱く。
集合的無意識に潜み人を弄ぶ者は、冷笑を浮べながら彼らを翻弄する。ひとつの世界を因として生まれた、もうひとつの世界。そこで巻き起こる事件は、表層的には異なるものでありながら、まるで影のように似た状況を形づくる。
前作のエンディングを受けて始まる今作は、前作の出来事を「因」とし、人々の営みを「縁」として惹起する結果「果」を語る、因縁と因果の物語である。罪という原因が作り出す、罰という結果。その因果の物語は、今作において結実する。その結末を解釈できるのは、両作品をプレイしたプレイヤーだけである。
アダルト・ペルソナ
ジュヴナイルとして描かれた前作とは異なり、今作はアダルトの視点で語られていく。
同じ街であっても、子供時代と大人になってからでは、まったく別の街であるかのように印象が変わる。見えてくる側面も異なれば、見ようとする場所も変わる。大人とは何だろうか。子供はおろか、大人ですらも答えに窮する問いに、今作は挑戦する。そして、その大人であることを、キャラクターたちは体現しようとする。
キャラクターもペルソナも、デザイン的に心の内面を、より明確に表している。プライドを傷つけられた過去を持ち、その過去に縛られている芹沢うららが発動するペルソナは、その顔面にハイヒールが突き刺さり、身体は縄によって縛られている。キャラクターを象徴する記号化が追究され、修辞が散りばめられている。そこここに織り込まれた隠喩を発見し解釈する楽しさがある。
多義的な世界の全容
前作の主人公だった周防達也こそ鍵を握る存在として大きくフィーチャーされるものの、他の前作のパーティキャラクターは、ほとんどが脇役となる。今作は、天野摩耶を主人公とし、そのルームメイトの芹沢うらら、達也の兄である周防克哉、過去の復讐のためだけに生きるパオフゥ、そして『女神異聞録ペルソナ』で登場した南条圭、桐島英理子が中心人物として活躍する。
膨大な人物設定によって作り上げられた世界は、こうした別の人物の視点から描かれることで、ようやくその全貌が現われる。
世界は一面からのみでは語り尽く��ことができない。今作までのペルソナシリーズに流れる、さまざまな視点から世界を見つめるという形が、『ペルソナ2罪』と『ペルソナ2罰』によって完成する。
占いと自分探し
自己確立できているようで、実はできていない大人たちは、占いや運勢などに自分を委ねようとする。型にはめることによる安心感。製作された当時の、日本の大人たちを表現していたそれは、現在でも変わることがないのかもしれない。
『ペルソナ2罪』『ペルソナ2罰』によって語られるテーマは「自分探し」。それが、 ジュヴナイルとアダルトの視点から、丹念に描かれる。
可能性を身近に感ずるジュヴナイルとは異なり、自分の限界を感じつつも、どうすればいいのか出口が見えず、何を目指すべきかも見失った大人の自分探しは、青春時代のそれよりも、さらに深刻で根深く、冷酷なものかもしれない。
原因に対する結果としての大人の物語の中で、そうした苦悩を描くことは、極めて皮肉に満ちたものと言える。そうしたきびしさもまた、ペルソナシリーズが 持つ、ヒューマンスケールの悩みを等身大で描くことの魅力のひとつであろう。
あ���たは、今、自分というものを掴んでいるだろうか?迷うことはないだろうか?
金子氏コメント
『ベルソナ2罪』とセットで楽しんで欲しい。序盤の雰囲気も、ホラーテイストの前作と、サイコスリラーテイストの今作で違うし、キャラクターも描き分けている。大人の方が経験が豊富な分、ペルソナデザインもキャラクターの心の反映が強いものになっているところも見て欲しい。
16 notes
·
View notes
Text
好きな詞を語らせておくれ/作詞について実しやかに思っていること
度々テレビのフレーム補完について議論が上がることがある。
FPSが上がっているようにヌルヌル見えるアレだ。それが映像の良さを消してチープに見えるので気持ちが良く無いと言う。自分もそう思う。古い考えかも。
理由の一つはシャッタースピード。24コマや30コマを想定して作られているものがフレーム補完をされるとブレたりヒュンと動く物の軌道がゆっくり見えてしまいもっさり感が増してまる��蛇に足が生えたよう。高フレームレートで撮影された映像は、よほど速くなければモーションブラーはかからない。
アニメーションではプロが考え抜いたコマ割りや中割りに野暮なことをしないで欲しいと思う。ズェッタイキル
ちなみに、海外ではこのテレビのヌルヌルをソープオペラ効果と言うらしい(ヘェ~ヌルヌ
作詞についても同じことを思っており、最初から最後まで蛇足にアリアリと説明するのはアリーヴェデルチ(さよならだ)
以下、とにかく好きな歌詞と曲を書かせておくれ。
※あくまで個人の解釈です
♪くるり「琥珀色の街、上海蟹の朝」
詞の中に愛の告白も好きの一説も無いのに、愛情の深さが伝わるくるりの名曲。
上海の堅物なワルが小さい子猫を拾ったら情が湧いたような石壁に咲いた花🌺トカレフやヒビ、クーデターなど物騒な言葉が出るので安全な生活はしていないと思います。
心配であれこれ言ったり不安で仕方ない中、束の間の休息に上海蟹を食べている様子を方杖をついて見ているようなサビ。上海蟹はとても食べにくいので集中して一生懸命食べているなあと眺めているのでしょうか。岸田さんの優しい歌い方も相まって慈愛に満ちている気がします。
溢してもいいという一説が食べ物だけではなく涙や感情の比喩のようにも読み取れます。上手に割れるとありますが、もしかしたらこの子を逃すために決別を意識しているのかもしれない。というか多分、外輪船に乗せて別れていると思う。
���っとサビで食べていた上海蟹が二人で食べる最後の晩餐だったのかもしれないと思うとエモい。説明不要。最高。
♪人マニア - 重音テト 原口沙輔さん
昨年、5万再生ぐらいの時にYoutubeで拝見して、歌詞の小気味良さとサビのキャッチーさに驚いた。コードが無いようで非常におしゃれでアングラなベースが印象的。
歌詞も度々聴いていくと、やるせねぇなあでも仕方ねぇなあでもやるせねぇなあと延々回っている自分に笑えてきたような虚しさを感じているのか
今日もどっかで誰かが炎上して、ツイ消しして、子供に夢を見せるほど素晴らしい大人になるはずだったのに、こんな大人になってしまった。もしくは、こんな大人で溢れてしまった。
やるせねぇなぁでも仕方ないなぁと最後には開き直って嘘を言う、その嘘を背負って生きていくんだなぁと完結しているようでなんというか安心しました。
学生の頃、高学年の人がカッコ良く視える現象があったかと思うのですが、いざ自分が高学年になった時にこんな感じかと思う感覚に似ている気がします。
全然本題と関係ないのですが、昨今落ち着いていた音圧競争に新たな刺客が現れたと一人感じています。音選びも秀逸で学ぶところが多くかってに拝ませて頂いています🙏
♪メランコリーキッチン 米津玄師
米津さんのこの曲がとにかく好きです。ただ、自分の解釈はハッピーエンドとは違いこの詞の人はどうしようもない人��なと思っています。
イントロお通夜のような夕暮れの雰囲気から始まるのですが、おそらく「あなた」が家出をしてしまったのだと思います。
自炊をするけど下手な料理しか作れない、「あなた」がいないと夜も塞ぎ込んでしまう。タイマーの電池も切れてる。あなたという存在に生活や精神面を強く依存していたことが分かります。
喧嘩をした後や自分が不機嫌な時も優しく懐柔してくれる、それにどれだけ救われてきたか感動的に言っているのですが、感謝の気持ちを言葉にするだけでは「あなた」は本当に救われるのだろうか。少々勝手過ぎるのではないだろうか。
「あなた」という存在は立派な人で恐らくこの人が居なくても生きていける気がします。帰ってくるのかどうか。それでもまた会えるまた元に戻れると信じている人。
そんなことを感じないほど良いメロディと詞が輝いていて本当に良い。そして虚しい。
イメージを崩してしまったら申し訳ないのですが、ハッピー以外もいいと思っています。(病気や死別の可能性もありますがナンセンスなのでスルーしています)
ーーーーーまとめ
自分はどうするのか。
こうやって整理をして思い浮かんだのですが、デッサンをするように陰影を描いて物事の形を浮き出すと良いのではと思った。
自分デッサンは下手なのですが、あれは物の重さや厚さや硬さなど正面や視覚から見えないところも理解して、キャンバスに書き起こす能力が必要だと思っています。それを陰影と呼ぶのですが、見えない裏側が見えるデッサンが自分は好きです。
具体的には、メロディの語呂と曲調にも寄るだろうけど、テーマに基づいて関連する言葉を選んであげると良いのではと思います。そりゃそうだよって感じですね。
例えば、愛はどうあがいても一つで完結することができないものです。仮に自己愛だとしても「我思う、ゆえに我あり」とこれはデカルトの言葉の引用なのですが、簡単に言うと自我と自分は同じものではなく、自分が自分と認識することで存在しているということです。あるいは、神様にそう認識させられているという説もあったと思います。
なので、愛の表現に対比は有効だと思います。故にユーエンミーのやつですね。君の〇〇が大好き!より、拒否と懐柔を行ったりきたりする方が愛っぽい気がします。
陰影を表現する方法で、情景を伝えるのも良いと思います。
しんと静かな空気は重たい物を。松尾芭蕉の有名な俳句で「閑さや岩にしみ入る蝉の声」という素晴らしい句があるのですが、煩いはずの蝉の音が岩という密度の高くて重いものを通すことで心に閑散とした静けさをもたらしているように感じますみたいなアレです(言葉にするのが難しい)
また、放って置いてはいけないものを表現すると淋しいや後悔、愚かな��覚になって良いですよね、どこかで聴いた冷たくなったコーヒーなどはそれに近いのではないでしょうか。
ただ、ここまで言ってあれなのですが、最近のショート動画の流行によりサビにキャッチーで分かりやすいありふれた表現を用いることも重要だと思います。ぶっちゃけ気持ちよく踊れたら良いのかもしれない。テレビのヌルヌルも見慣れた人は何も思わないかもしれない。
血迷ったわけではなく、質は適切に磨けば磨くほど良くなると考えています。油の乗った魚は捌かなくても(マグロはしっぽ切る)ヒレや身の厚さに表れ、達人のデッサンはたった一筆でもその人が達者だと分かる。
思考を止めないように精進し、論理的に考えた結果その言葉が最適解だったというふうにしていきたいです。出来るか分からないのであくまでふう。
という自論、長々と失礼しました。
2024年も宜しくお願い致します。
とりあえず、無色に出した曲早くしようか。
4o

5 notes
·
View notes
Text
インタビュー:ロビン・カイザー
僕たちはみんな、同じチケットを予約している:
“人間を経験すること”
インタビューア:プリスカ=マリア・ブリョーゼ

オリジナル動画:https://youtu.be/tXpOrZiMDZA
【和訳:ALAE PHOENICIS】 最新情報は Telegram へ:https://t.me/alaephoenicis
プリスカ:あなたにとって新地球とは?
ロビン: 最終的には意識の状態、時空間に定着されたものではないんだ。
我々は記憶を取り戻した時 自分たちの内部に 創り上げる意識の状態。
記憶というのは自分たちがどこから来たのか、 霊的精神的に自分たちがどのような存在なのか、ということ。
心の奥底でそれが確信として自己の中で目を覚ました感覚、忘れることのない感覚が起きる。すると、この肉体としての自己認識には陥らない。
その時、自分はこの地球の源であると言う自覚が起きる。
プリスカ:あなたの本には「新しい私たち」というのがあるけど、これはどのようなもの?
ロビン: 君が引用したのは「宇宙的観点からの私たち」で、これは新地球を改めて構築していく時の、互いのあり方とはあまり関係はない。
「新時代の私たち」には、新しいコミュニケーション文化、交信のための新しい言語を学ぶことなどが挙げられる。
我々の言語は、人類の分断が根底要素となっていて、主語・目的語といった区別は、如何なる文章でも相手(対象物)は自分以外の存在だと宣言している。新言語で新しい互いのあり方を表現することで、何が開かれるのか見えてくるだろう。
「愛を以て行動せよ」これを掲げたい。何にせよこの“材料”さえ入っていれば、何をしようと「ことは丸く片付く」。人生のどの分野であろうと、この“材料”が欠けていれば、いつの日か歪みとなって自己破壊に繋がるだろう。
プリスカ:新しいコミュニケーションの形態とは、どのようなものになるのか、イメージ、直感はある?
ロビン: 学校教育では合理的・論理的思考、と主に左脳が鍛えられる。
基本のコミュニケーションはしかし、芸術的なもの、例えば踊り(舞)はイメージとして隠喩的・芸術的な音響言語となり、自分の中の全く違った層で表現・伝達し合うことになる。
多くの人は自己表現ができないという感覚に陥っており、従って自分の存在は気付いてもらえないと感じている。なぜかというと、こうした“言語”という道具を使っても、人は自分の奥底にある内面を表現することが出来ないから。
そこで「僕たちはもっとクリエイティブにならねば」と思うわけ。
言語というものだけでなく、思考にも結び付けられているアイデンティティというものに、自分たちがどれほど奴隷化されているのか、そのことを芯から自覚すること。
つまり、「自分」と「自分が想っている自分」とを同一化してしまっていて、ここから分離化された存在への道を進んでしまうんです。
プリスカ:私には先日、イメージが浮かんで、その中では我々の精神がどんどん…この何千年の間なのかわからないけど、「自分・私(エゴ)」にばかりフォーカスするようになって行った。
今のあなたの話で思い出しました。
私たちは再び、自らの精神を宇宙というか創造的な方向へ向けていくとどうなるのかしら?
ロビン: (笑) この「自分・私」という“島”はまるで、広い大海に浮かぶナッツの殻のようなもので… 僕らの存在がそんなものだったためしなんかないのに。これがパラドックスで、僕らは「自分は自分が思ってるような自分」だと信じている… ひとつの意識層だけに存在感が与えられてしまっているけど、その横でパラレルに存在する多くの他の層で全く違った自覚の中にある。
一方では、“body-mind-identity(肉体=精神=同一性)”が肉体に繋げられた意識としてここにあって、僕らは「これが境界線(この線で終わる)」だと思っている。つまり、時空間を経験していると思い込んでいる。
しかしこれを超越して、認識を改めて見ると、「自分の意識は永遠」だということ、「“自分”には生まれ出た瞬間がない」ことに気づく。
これは…言葉では表現できない。ここには直接的な経験が必要になる。
その経験は、自分たちが行動を起こしている現実世界で疑問を掲げるようになって、そのうち行き着いた底を引っ掻くことになる日が来るまで、出来ない。
プリスカ:そうしたら、どうなるの?
その“底”を引っ掻けば、すべてが解ける?(笑)
ロビン: 実際には、切り離された現実からは、新しい我が家へ��何も持って帰れないんだよ。
僕らは多くの妥協を決意して、古い世界にある手段を使って新しい何かを創造しようするのだけれど、それは当然うまく行かない。
切り離された世界において、自分の精神や思考や想像で構築してきたものを完全に“洗い流す”ことを、本当に徹底して学ばねばならないと思う。するといつの日か、“新たなるもの”に出会える。
でも、これは単なるプロセスであって、プレッシャーを掛けても効果はない。つまり、成長を先取って歩むことは出来なくて、新時代の成長に向けた選択の手段とは力を込めたり圧力をかけるのではなくて、手放して委ねていくこと。全く違った進み方なんだ。
プリスカ:…その「手放して委ねること」というところに、自然な磁力の影響が実現されるのかしら?
ロビン: その通り。切り離されたアイデンティティからは常に、「私はAからBに移動して、目的に至る」ことが「常に自分の意思で起こる」ことになる。
新しい現実では、自分の意思というものは丸ごと手放して、宇宙の磁力に自分の運命・宿命が自分を引き寄せる現実へと導いてもらうんだ。
プリスカ:あなたがセミナーなどで寄り添っている多くの人たちには、その新しい意識に心を開くために、どんなことを勧めていますか?
ロビン: (笑)…つまり君には君の道があって、他の人にもそれぞれ、その人に道がある。これは何か「本質的」と言えるもの。非常に個人的なもの。
そして、いつの日か、僕らがその道を歩んでいった時に、どんどん互いに近づき合うように導かれる。切り離された現実では、僕らは「自分のバブル(泡)の中にいて、他人と互換性がない。僕らはある言語を話し、互いにすれ違い、それぞれの道は交わることがない。
しかし、徹底して内面の方向性従うようになっていけば、個々の人が歩む道は集まっていき、それは力強い大きな流れとなる。
そして、エネルギー的に地球上でそれが起これば、もう何もそれを止めることが出来ない(にっこり)。
プリスカ:果てしなく大きく広がっていくような感じね。
私たちが、もしくは一定の人数の人々が、そのような意識状態に至れば、この地球上で顕現される世界に、大きい変化が起きるのかしら?
ロビン: (笑) 類比論法で描写してみると、そこにはあるバッタの種族がいて、皆が後ろ足を抱え込みあえば、一定の数を超えるとひとつの生物体へと変容する。そのように、僕らも皆で手を取り合えば、個人の意識は「我々」という意識へと変化し始める。実はそういう場所、つまり部族文化がある場所から来て、氏族意識をもっていた。個人の意識というのはそれほど無かった。これは遅かれ早かれ、我々に開かれていかざるを得なくなる。なんでかって、個人にとって分離という道には先がもう無いからだ。僕達はもう最終点まで味わい尽くした。この一本道にはもう、自己破壊しか残っていない。
そして、僕達が人間���しての集団社会にあって、この道を選ばないならば、路線変更をしないといけなくなる。
ある程度は、誰もが責任をもって自分なりの貢献をするんだけど、上部に位置する創造レベルには…謂わば「シナリオ」が存在していて、それは人類の運命のようなもの。この話は別の文脈で話したことがあるけれど。
人々が、そのより大きい年代記というか、人類の運命的な流れに繋がった時、おそらく僕らは人として改めて自己破壊へ向かうような運命にはないだろう。
僕らはこれを経験してきた。この惑星で、僕らがいにしえのトラウマを再演出したことで、何度もそういうことがあった。最後にそういうことがあったのがアトランティス。この記憶を持っている人たちは、今この時代に沢山いる。なぜかというと、今日の時間質(タイムクウォリティ)が当時と同じだからだ。今、全く同じ状態が示されているんだけど、どうやら今回は上手くカーブを越せるようだ。それには異なった要素が関わってきている。集団意識性のクリティカルマス(急激に何かが激昂する分岐点)というものもある。これに達する時、高い意識を持った少数派が、普通の意識状態だった大衆を一緒に引き上げる。歴史上、大衆が世界の成り行きを統御したことはない。それはいつも少数派だった。…しかし、今までは分離の方向へと進んできた。
しかし、本当に「高い振動を保ちながら地球上で貢献している」と僕が呼んでいる人々の割合が一定のパーセンテージを超えたなら − 裏ではそれを起こすために多くの力が働いているんだけど − そのとき、新しい意識というのはまるで、地球を包む格子網のように張り巡らされ、そして… 無意識でも分離のアジェンダに従ってた者は、非常にそ~っと、そしてどの程度の抵抗があるかによってはちょっと辿々しく、その新しい意識に吸入されていく。
プリスカ:数年前にも聞いたことのある、その張り巡らされた金色の格子網のお話、好きです。
私が繰り返し体験しているのは、人々は意識発展の道にあって、反省とかしているんだけど、そこでも分離というのが、ジャッジによってあまりにも多く起こっていて…「ああ、この人はまだそういう意識状態じゃないのね」みたいなジャッジ。
(二人して笑う)
あなたはそういうのにどう反応するの?
ロビン: まぁね…『この人についてなんと言おう』ってやつだけど。
もし、僕が君について何かを陳述すれば、その時僕は「君について」だけでなく「自分について」も陳述していることになる。
だって、それは「君について」思っている僕の考え、ジャッジなわけだから。それをジャッジしている僕の精神について語っていることになるので、陳述したのは君のことではなくて、僕について、ということになる。だから、「誰もが鏡の間の中にいる」ということを、人は至るところで見かけることになる。
もし、誰かが「分離(別れ)」を口にしたならば、その人は「分離の意識」の中にあることになる。
それで、それとどう付き合っていけば良いのか、僕を助けてくれた大切な鍵となったのは、あらゆる総てに存在する権利がある、という認識。つまり、ちっぽけな虫から、この惑星上の最も偉大な意識体に至るまで、総てが己の存在の層で、大切な貢献をしており、そのちっぽけな砂粒がもし、掛けていたとすれば、大きな全体というのは完全ではなくなる、ということ。
この、存在の権利というのは、最も暗い闇の存在にも与えられている。消去しなければいけないものなど、何もない。そうではなくて、そこにあるのは我々が包容すべきもの、統合させてもらえるもの、自己の中にあるものに気付かせてくれるもの。それが出来れば溶かすことができるので。
プリスカ:ひとつになる、ということね? 素敵。
ロビン: ひとつになる、というのはもちろん素敵なこと。それは意識であって、そこにハマってしまえば、誰が何を言うのかなんて、もうどうでも良くなる。
僕らは皆、自分のフィルターを使って自分なりのベストを尽くし、それをやろうと思って着任したことを成し遂げようとしているんだけど、僕らがみんな「同じこと」のために着任したことは、明らかでしょ?
上部の位置から眺めた方向性、ミッションというのは、ねえ、みんな同じことを望んでいるんでしょ?
そう、これを…もう一度思い起こすことだよね。
そうした道の上を歩いていない者、無意識の道に変えてしまった者でさえ、望んでいるのは僕達が望むものと同じなんだ。ただ、彼らはそれを知らないだけ、別の層に納められてしまっているだけ、隠されているだけなんだ。
プリスカ:これまでも何度か聞かせてもらってきたけれど、私たちがワンネスの状態に在るようになれば、そこにはもう死はないわけで…私のマイクロビオーム(微生物叢・細菌フローラ)でさえ消滅したりはしない。つまり死ぬことはなく、そこらにある植物と一体化するのよね? (笑)
ロビン: 当然。
プリスカ:そうしたイメージだけでも、すごく美しいし、人々にとっても世界は広がると思う。だって、分離という精神・思考世界では、常に死への恐怖があるから。死、この世を去ることについて、あなたの考えを改めて聞かせて。
ロビン: 文明というものがどのような意識状態に在るのかを測るためには、実際には2つの基準があって、ひとつは「誕生」をどう扱うのか。もうひとつは「死」をどう扱うのか。
僕らはこの2つを非常に歪めてしまい、そこから酷く遠ざかっている。「死」は社会から排除しようとし、できるだけ意識しないようにしている。もうひとつの方はここでは深く述べないけれど、このことについて素晴らしい考察を書いている人が居る。
「死」というのは信じがたいほどの師匠・マスターなんだ。
「無常(全てがいつかは過ぎ去ること)」というものは、三つの大きな原理のひとつで、神の「三位一体」には、構築する原理、維持する原理、破壊する原理が存在する。この「破壊する原理」とは死、つまり「無常であること」。手放すことなんだ。
そして僕らの居るこの社会では、完全に、あらゆるものが「構築する原理」の中にある。
多くの人が、「維持する原理」と「破壊する原理」を文明から除外しようとしている。それは全てを「構築中」にしておくため。拡張、成長の加速。成長、成長、成長。だから、こんなに沢山の癌疾患が出てきている。だって、「構築の原理」のみに定着しているから。文化として、意識の中で。
対極となる原理が欠けている。僕に言わせると「破壊の原理・溶解の原理」だ。
インドでは調和というものがもっと強く存在していて、破壊の原理の象徴としてのシヴァ神がいる。
そう、「死」というのは意識の原理からいうと、実際には僕らが「移行」する時にまさに必要となるものなんだ。なぜなら、僕らは今この意識というものに、随分と長い間留まっていたわけで、その間ずっと「死」を排除しようとしてきた。
そして…分離されていたものを、どうやってひとつのものに戻して統合させるのだろうか?統合は常に溶解によって起こる。
僕らは謂わば「死ぬことのない(溶解せず、統合することがない)」ものとして凍結してしまっている。
「死」を排除しようとすることで、僕らはデジタル的なものに変容してしまった。保存したい、手放したくない、そういった意識から、今自分たちがはまり込んでいる時間のループがリピートされてしまう。
神の「三位一体」の基本的な側面を排除しようとしたことで、僕らはいつまでも同じループの中を繰り返しているんだ。
プリスカ:それは今、人類に反映されていますよね。
人類が自己破壊へと進んでいるのは、最終的に自分自身の肉体の組織を破壊することに顕れている。
以前もあなたが述べていたのは、この道から飛び出して統合…というより、この道へ踏み込んで統合へ向かえといいうことで…そうやって自己破壊へ進む人に、あなたはどう助言するのかしら?もちろん、その人によって違うし、ただ、その人が選んだ道が本人にとって本当に意義深いものになるように?
ロビン: 僕は…以前、もっと心理学的な世界観から実行者や変革者を軸に考えていたときは、「よし、さあこれに働きかけよう」って感じだった。しかし、僕は慎重になった。まずは、本当に高次の層から自分の内面に問いかけるんだ。「自分に変化をもたらすべき所に、そもそも至っているのか?それとも、変化することで、僕は何らかの運命的な経緯に介入してしまうだろうか?」と。だって、君の運命を信じないなんて、僕は何者なんだろうか?そして、君の運命を信じる方が難しいときがある。その時僕が、君が自己破壊の方向へ行こうとするのを目にしたならばね。大抵の人は、誰かが苦しんでいたら走り寄って支え、ヒントや助言を与えて状況を変えようと努めるだろう。しかしこの人たちは何を問題に感じているのだろう?この人たちは当人が自己破壊へ走って苦しむのに耐えられない。なぜかというと、それを見過ごして苦しむ自分に耐えられないからだ。しかし、自己の苦しみを受け入れていれば、目の前の人々が自分の運命を生きることに任せることが出来るはず。
ここで問いかけるべきことは、「愛に満ちた行為」とは何なんだろう、ということ。
誰かがやってきて、心底助けを求めたとする。これは別の問題だ。こういうときは、高次の層と申し合わせながら様子をみて、その人に「いいかい、君がその道を進んでいけば何が待っているのか前もって見せてあげる」と言える。
「自分は現時点で、どのどの���イムラインにいるのか」ということと、「このタイムラインを5年・10年と拡張させていくと、自分の人生はどのようになっているだろうか」、この2つの自問はどんなときでも役に立つ。
なぜかというと、小さなミクロの動きを起こす「時間」を今この場所で吹き込んだことで10年後がでっかく変化する。
小さなレーザーポインターをちょっと左にずらせば、10メートル向こうは大きく動いてしまう。これを聞けば、自分の人生において決断を下すということは、この光線を拡張させることであり、それがどういうことなのか明らかになるだろうし、自分の道のどの辺りで、いわゆる微調整をすべきなのかもわかると思う。
プリスカ:その話であなたが以前、「僕らは神の手の平よりも深く堕ちることはない」と言ったのを思い出したわ。私はこのイメージが大好きで。真実味というか、率直で…自然なことだと感じるの。
ロビン: そうだよ、僕らは認識し直さないといけない。僕らは一体何処に居るんだ?このゲームは何のゲームなんだ?
僕らは「人間という経験」ってのをブッキングしたんだ。宇宙の旅行代理店へ行ってね、「僕はこの惑星で“人間”という経験がしたいんですけど」って頼んだんだ。この旅行を自分でブッキングして、旅を始めた。みんな、ブッキングしたんだよ。いいかい?この宇宙のゲームはある特定の意識層で開催されて、その他の君の意識層は、僕らがここで何を体験しようがほんの少しも変化はしない。僕らが何者であるのか、という真実は変わったりしない。
どんな体験をしようとも、最も酷く暗い経験から最高の有頂天まで、僕らがこの意識層というスペクトル全体で味わう体験は、何一つとして本来の自分を変化させたりしない。
これを繰り返し認識し直すんだ。単に頭で理解するんじゃない、内面的な確信として識る。
僕らは深みに堕ちることは無いわけで、だったら何でそんなに必死になっているんだ?となる。
プリスカ:それが、先程あなたが言っていた「手放すこと」と「委ねること」に繋がっていくのね。
献身、手放し、統合、神の三位一体にある「破壊の原理」、これらをあなたとの話のまとめとして持ち帰りたいのだけど… 私たちは新地球でどのように「愛する」のかしら、あなたはどう感じている?
ロビン: (笑って暫く沈黙)…うん…愛するために特別に何かをしたりはしない。僕達は愛そのものなので、それ以外にどうしようもなくなる...自分が何者であるのか、というのを表現する以外のことはできないんだ。あらゆる言葉、あらゆる仕草、どんなかかわり合いにおいても、異なった層で愛を交わし合う。これは頑張ったりすることではなくて、単に愛の交換とは自由に流れる自然なんだ。僕らの道から僕らを隔てていたものが一掃されれば、ごく自然に、自ずとそうなっていく。だって、僕らの存在自体は依然として変わっていない。つまり、これまで条件付けによって学習させられていた層の下に、真に愛する心の鼓動があった。神的現実、つまり神によるマトリックスは今でも完全に健在だ。我々はそれを、イメージ・思考、想像など、条件付けによって構築した現実で��って閉まっていただけで。
でも、僕らが内省し、意識に集中し、溶解へと努力していくことで、ここを通り抜けることになり、「永遠の存在」は僕らの中、そしてありとあらゆるものの中に簡単に顕れてくる。
プリスカ:あなたが先程言ったように、私の中でも「これはただのゲームだ」って感じるの。私の子どもたちはとても良い先生なのよ。彼らは重く考えない「おや、そうなの?ではそうなのね」って感じ。遊び感覚で気楽なのよ。何時でもそんなに深刻にならなくてもいいわよね。
ロビン:僕らはこのゲームの中で、何かを失うんじゃないかって思っているんだ。なぜかというと、このゲームの中で何か特別のものを勝ち取れるんじゃないかって思っているからなんだ。でも、結局は僕らは僕らでしか無い。いつもそうだったし、これからもそうだ。このゲームで勝ち取るものなんかない。これがパラドクスなんだ。このゲームで勝ち取るものがあるっていうのは、とある層では何かを更に学ぶという点で、確かに正しい。それは相対的な面。でも絶対的な面では僕らは単に、自分に戻るだけなんだ。これまでも、これからもそうであることに変わりはない。
つまり、ここで達成出来るものなんかない。達成すべき目標がないんだから。「これが最終ゴール」ってところへ走りきったら人生トロフィーがもらえるなんてことしているわけじゃない。「ゴール」だと思う所に行き着くたびに、君は気づくんだ。「これじゃなかった」って。それがずっと続く。いつの日か、「おや、始めたところからまた始めるのか」となる。全ての存在の源でね。
(二人して高笑い)
プリスカ:あなたにとって、新地球での子供の役割は?
ロビン: その質問をありがとう。
子どもたちは、新地球にとって絶対的に本質的な鍵となる。
なぜなら、僕達が歩んできた道では、特定の条件付けが否応なしになされてきたからね。でも、次の世代がもっと自由に自分の人生を歩めるようになれば、つまり、常に煽られて条件付けられる、ということに触れることなくやってこれたなら... 僕達は自分たちの偉大さをよく識らないので、ソースをその目で見てきたばかりの今の子どもたちが、そうした認識を持って来てくれれば、僕達も少しはそれを思い出せるかもしれない、と僕は思うんだ。
実際、まさにこの移行期には宇宙の至るところから重要な役割を担っている多くの魂がサポートのためにこのに来ているんだけど、それは単純に、人類の目の前に「鏡」を突きつけるためなんだ。
僕らは過去何世紀かの長い間、強烈に「分離」の種を蒔き続けてきた。僕らがまだ理解出来ていないのは、それによってどんな収穫を得ることになるのかということ。「膨大な収穫」について語っているチャンネルもる。
この意識の意識化(そういう意識だと気づくこと)は、もしもずっと人為的・デジタル化された構築プロセスの中にあって、神の三位一体の3つ目である「破壊の原理」を意識に含めないならば、それなりの結果をもたらすだろう、それ以外はあり得ない、と僕は思ってる。それは恐れるべきものではなくて、単純に宇宙はバランスを取り戻すという、起こるべくして起こることなんだ。
これは、根底からして価値のあること、神聖なこと。
プリスカ:最後に、振動・周波数についてひと言、何か見つかります?
ロビン: うん…何が出てくるかな。
(目を閉じて、深く呼吸し、集中)
これについて出回っている情報は沢山あるよね。多くは矛盾しあっていたりして、「一体何が真実なんだ?」と不安を巻き起こしていたりもする。その意味で“理解”とは、という話になる。この「整理プロセス」を辿っても、僕らは先には進めない。必要なのは「直感の明確さ」なんだ。
変容プロセスはメンタリティから来るものではなく、父権制から女性的な能力とパワーへと引っ張られていく革命・進化という形で、バランスが取り戻されていくことにある。
これは、革命(Revolution “再展開”)か、進化(Evolution "伸展開")なのか…本当はInvolution"内展開"なんだけどね。だって内側へ展開していくことになるんだから。
これはどういうことか…避けられない、と僕は思ってる。
人類として我々は本当に、余りにもある極端さを極め切ってしまったような感じで、そこから戻る道のり(ラテン語で religio 、巻き戻すために統御する、というような意味。『宗教(religion)』の語源となる)を、僕たちは自ら進んで歩むのか、それとも否応なく歩まされるのか。否応なく、というのは溶解のプロセスが起こることでそうなる。
プリスカ:それは「神の三位一体(トリニティ)」を取り戻すためなのね?
ロビン: まさにその通り。
プリスカ:親愛なるロビン。あなたの言葉、それと共にあなたが運んできてくれる振動に、深く感銘を受けています。
私たちの活動やイニシアチブにおいて、意識というのは我々にとって土壌である地球…私達を養うものであり、これらが決定的なのだということ。私達を新世界に導いてくれるものなのよね…
6 notes
·
View notes
Text
2024年6月23日の読書、24日の読書
撮りすぎる写真 椿の葉を磨くものが時間と知りながらなお
新生児並べるようにタッパーへ夜のしじまへご飯を分ける
/穴根蛇にひき「雪と雪の鵺」(『短歌研究』2024年7月号)
日に照るのは確かに花より葉の部分と思うから磨くにすごく納得感があった 〈すぎる〉とか〈なお〉があると、長くてゆるやかな時間の流れ/短くて急に加速する時間の流れの対比が見えて、加速の危うさというか緊迫感がほんの少し出てくる気がする
タッパーを手元に見るときの日常の感覚から〈夜のしじま��で生活空間を外側から見る把握に移るときに新生児や日常のにぎやかさが���ぎ落とされるのがかっこいい 無音は揺るぎなく詩情だと思う それまでは音とかが聞こえてるけど〈ご飯を分ける〉動作は無音でモノクロの映画っぽく再生される気がする
いつかのホームページにあったドット絵の桜吹雪が流れるしかけ
スタンドバイミーがきこえてスタンドバイミーのストーリーを思い出す
/梨とうろう「8週目の天気」(『短歌研究』2024年7月号)
〈いつかの〉がおもしろい ドット絵とかのレトロな感じは共有できる全員のためのいつかにも思えるし〈ドット絵の桜吹雪が流れるしかけ〉は容易に想像がつく分かなり自分史的な、個人のいつかにも思える スタンドバイミーの歌もそういう側面があって並んである状態で読んでうれしかった
思い出を取り出してきたはずなのにとても似ている油絵だった
また一つ歩いていない道を消し四半世紀にさらに奥行き
/橙田千尋「パッチワーク」(『短歌研究』2024年7月号)
〈取り出してきた〉に対しての〈油絵〉、質感があることによって物体っぽく見えるのが本当に良い 映像や絵というか景の話は平面っぽいけど、この歌は厚みのある立体としてそれらを扱うから思い出がその人の身体に基づく実感のあるものに思える 歌を読んで、この他者の実感を信じきれると思った
〈また一つ〉でその人の暮らしの四半世紀を思い浮かべるんだけど、〈さらに奥行き〉でこれから消す/残るだろう暮らしを想像するときにそこにはその人以外の(私を含む)他者の暮らしも含まれている気がする 巨大な見せ消ちっぽい
からだは街へ柳のやうにしなだれてわたしはわたしの祭司をさがす
ガムを買つたレシートにガムを吐き捨てる立体駐車場の機能美
/佐原キオ「なにかある街」(『短歌研究』2024年7月号)
しなだれることの喩として柳は全然使われると思うけど、この歌ではわたしにとっての祭司が未だに不在である状態の街を想定したときに、風に吹かれる様とか、そういった動きを伴う柳として再度喩が立ち上がる 心底かっこいい
立体駐車場の内部には多分吐き捨てられたガムとかあるだろうな、とか、レシートから立体駐車場が商業施設に付随するものだったりすることを思うときに、内部にいる人まで含んで機能は機能たらしめられると思った 機能美に説得力がある
海のことざっと調べてぼくたちに還る資格はないと思った
がらがらの弱冷房車でいろはすをすこしこぼして靴でのばした
/遠藤健人「猫の形の」(『短歌研究』2024年7月号)
昨日ともだちと読んでていちばん笑った おもしろすぎる 〈ぼくたちに〉で謎の連帯をしようとしているところとか、〈がらがらの〉〈すこし〉でなにかから免れようとしつつ〈弱冷房車〉でその免れの手付きを描写にすり替えようとしている感じとか 丁寧なおもしろさがあると思う
行かなかった社員旅行のおみやげのパインケーキをデスクに飾る
デザインを依頼しながら渡してる栃の実せんべいは飛騨の銘菓
/城下シロソウスキー「トランジション・ピリオド」(『短歌研究』2024年7月号)
〈行かなかった〉の選択を踏まえたときに、パインケーキは食べるでもなく飾っているわけだし、つくづくこの社員旅行に魅力を感じていないように見えて通底した温度感のなさや結果として発生した動作がおもしろく感じる 栃の実せんべいについての説明や〈ながら〉の動作も同様で、歌における心身の捩れのなさやその空気感がしみじみ良い
引いた歌はもちろんすべて好きな歌だが、表題の記載があるものの中だと「雪と雪の鵺」「パッチワーク」「なにかある街」が良かった 好きな歌が多い
変じゃなく面白いって言いなさい、という指導が入っているな
/岩倉曰(『短歌研究』2024年7月号)
おもしろくてみんなに見せたかった
この冬のため手に入れたマフラーに描かれている冬の生き物
色々な指の曲げ方をしていると知らない鳥が来て調べたい
/奥村鼓太郎(『短歌研究』2024年7月号)
〈冬の生き物〉とか〈色々な指の曲げ方をしている〉手がバリエーションのある感じで平面的に立ち上がるのが良い
食べきればおのおの骨を返しゆくKFCが滲んだ箱に
/景川神威(『短歌研究』2024年7月号)
〈おのおの〉や〈滲んだ〉でファーストフードの感じが残りつつ、受け取れるところは余韻のような空気感なのが良い 箱のシンプルそうな感じもうれしい
てのひらの上で形を見いだした餃子に蓋をして焼いている
屋根裏を見たことがないひとのためシルバニアファミリー駆けつける
/新上達也(『短歌研究』2024年7月号)
私に常識がなければぜんぶの歌引きたいくらい良い
〈形を見いだした〉でまず 餃子の完成形のイメージがあって/そこに沿わせて成形し/てのひらに餃子が乗っていること がわかること、〈蓋をして焼いている〉ことからなんとなくてのうえにあったときと同じ姿勢の餃子がフライパンの上に並ぶことがわかる気がする 言い回しから受け取れるものが多い
〈シルバニアファミリー駆けつける〉ときの動機として〈屋根裏を見たことがないひとのため〉が挙げられたときに、家っぽさで言えば屋根裏とシルバニアファミリーの取り合わせは納得ができるのに、状況としては具体的にはわからないから〈シルバニアファミリー駆けつける〉の空想的な感じを損ねない 取り合わせのバランスが抜群に良いと思う
それに〈シルバニアファミリー駆けつける〉様はコマ送りで撮られた映像のようだと思うと可愛らしくて人形にもともとのコンテンツが与えるキャラクター性も改めて付与される気がする、そうなると〈ひとのため〉のための部分にも説得力が生じてきて読んでいてすごくうれしかった
〈見いだした〉も〈駆けつける〉も、動詞の選択が抜群に良い
新上達也さんの短歌、とんでもなく良い...... しみじみ......
むんむんとシャンプー提げて下ってく坂がなんだか友達みたい
考えていると時間が経っている花梨もこれでふくらむんだな
/橋本牧人(『短歌研究』2024年7月号)
むんむん............?
割と2首とも膨張の感じがあって、その膨張は長めの時間の経過が前提になっている気がする そこに対して坂の実際の距離や考えている時間が沿うように置かれると長い時間のほうは過程も含めて一枚絵みたいに景として置かれているように思えてきて、なんか、たぶん主体はめちゃ長生きしようとしていると思った
初恋を描くとしたら足癖の悪さをできるだけ美しく
/宇田川美実(『短歌研究』2024年7月号)
〈できるだけ〉がよかったと思う 〈足癖の悪さ〉自体は美しくなくて、美しいのはその足捌きだと思うけれど、そこも含めて〈できるだけ美しく〉描こうとするときに自分の体験から離れた/もしくは語に引っ張られ���イメージとして〈初恋〉が独立して存在するのがおもしろい 自分の経験をもって概念のすりあわせをしようとしている感じ
撫でているとふわふわになるカーペットそのうちうんちしてくれないかな
/太田垣百合子(『短歌研究』2024年7月号)
怖いと思った
許しあうことに慣れたら本棚の日なたにちかい本がきいろい
/髙田皓輔(『短歌研究』2024年7月号)
〈きいろい〉理由として〈日なたにちかい〉が挙げられているけれど別にちかいだけで日なたにあるわけではないから確定しようと思うと変な感じ、日焼けでも装丁の色でも〈ちかい〉だと説明しきれない この歌では〈日なた〉と〈きいろい〉のイメージの近さだけ受け取ってなんとなくわかった気がする一瞬があって、歌の中ではそれが物理的な近さとして置かれているのがおもしろいと思う 〈許しあうことに慣れたら〉、一応解決っぽいことにはなっているけどよく考えたらちょっと変なことばっかり起きている可能性が高い
純粋に数とレイアウトで目がすべる 読書ってむずかしいかも
気をつかうと気を遣わせてしまうから多めに肉団子を皿に取る
/松下誠一(『短歌研究』2024年7月号)
解説が先に来る実況が内包するのは〈気をつかうと気を遣わせてしまう〉の展開の実況と実際に行動に移すまでの考えごとをしている人の姿の実況で、この歌では後者の部分、あるいは元気そう/明るそうに見せようとする感じを肉団子が担保している気がする メインっぽい料理、肉料理として 〈多めに〉もその結果......みたいな感じで読んだのでこの歌は結構精緻な描写がなされているのではないか、と思った 〈から〉の接続でもしみじみと主体の善良な人柄や丁寧な気遣いの様を受け取れる気がして読んでいて好感度があるなとうれしくなる
鮭を焼くにおいのなかで実感は塩のかたちになって指から
/豆川はつみ(『短歌研究』2024年7月号)
塩を振るのであれば〈実感〉は既に焼いているときの〈におい〉の部分がそうなのではないかと思いつつ、焼かれている鮭に対しての能動的な動作は塩を振ることくらいかも......となった ひとつの動作の - 一連の動作の中の - 手順 だけ剥ぎ取ってラグを強引に生じさせる手つきがある気がする 指から離れた塩が鮭に届くまでの時差もこの歌は含んでいて、全体的に切れ切れの、階段状の放物線を思わせるフォルムの歌だと思う
0 notes
Text
先月、事実上史上最も著名なジャーナリストの2人が話題になった。プーチン露大統領にインタビューを行い、日本時間2月9日にSNSで公開したタッカー カールソンと、2月20日と21日に英高等法院で米国への身柄引き渡しを巡る審理が開かれた、英国で収監中のジュリアン アサンジである。 事実上史上最も著名なジャーナリストというのは、タッカー カールソンについては現在のアメリカで最も視聴者数が多いからで、例えば中国やインドなどにもっと多い視聴者数を抱えるニュース番組などがあるのかもしれないが、なんといってもアメリカは情報覇権国であって、今回のプーチン大統領へのインタビューについても、視聴者数の多さ自体が語るものというのがある。 内部告発サイト「ウィキリークス」の創設者であるジュリアン アサンジは対照的に今回の審理には体調不良により出席しなかった。アサンジが現在のインターネット上のメディアに与えた影響の大きさもそうだが、今回の審理をめぐっても、「ジャーナリズム」という概念そのものに対する影響というのが話題の焦点の一つになった。
こうした話題への関心は、実際のところは、主流メディアのみならずネット上のほとんどのメディアやジャーナリストとか、ジャーナリズムそのものへの懐疑とか厭世観の表れなんじゃないかとも思う。情報覇権国と言ってもその内部秩序は崩壊しまくってるようにしか見えないし、正しい情報が何かを救うとか言ってる人のこともバカだと思っている。そう言いながらもやたら情報を探し回ってぶん投げ合ってる自分たちはまるで、砂漠のような崩壊後の空間をモヒカン肩パッド姿で奇声をあげながら疾走してるようにしか見えない。
芥川龍之介は『西方の人』と『続西方の人』というエッセイで、イエス キリストをジャーナリストだと表現した。 『西方の人』の最初の章で「わたしは唯わたしの感じた通りに「わたしのクリスト」を記すのである。厳しい日本のクリスト教徒も売文の徒の書いたクリストだけは恐らくは大目に見てくれるであらう。」と断わったうえで、「ジヤアナリスト」と題した章で「我々は唯我々自身に近いものの外は見ることは出来ない。少くとも我々に迫つて来るものは我々自身に近いものだけである。クリストはあらゆるジヤアナリストのやうにこの事実を直覚してゐた。花嫁、葡萄園、驢馬、工人――彼の教へは目のあたりにあるものを一度も利用せずにすましたことはない。「善いサマリア人」や「放蕩息子の帰宅」はかう云ふ彼の詩の傑作である。抽象的な言葉ばかり使つてゐる後代のクリスト教的ジヤアナリスト――牧師たちは一度もこ��クリストのジヤアナリズムの効果を考へなかつたのであらう。彼は彼等に比べれば勿論、後代のクリストたちに比べても、決して遜色のあるジヤアナリストではない。彼のジヤアナリズムはその為に西方の古典と肩を並べてゐる。彼は実に古い炎に新しい薪を加へるジヤアナリストだつた。」と書いている。 『続西方の人』でも「ジヤアナリズム至上主義者」と題した章で「クリストの最も愛したのは目ざましい彼のジャアナリズムである。若し他のものを愛したとすれば、彼は大きい無花果のかげに年とつた予言者になつてゐたであらう。平和はその時にはクリストの上にも下つて来たのに相違ない。彼はもうその時には丁度古代の賢人のやうにあらゆる妥協のもとに微笑してゐたであらう。しかし運命は幸か不幸か彼にかう云ふ安らかな晩年を与へてくれなかつた。それは受難の名を与へられてゐても、正に彼の悲劇だつたであらう。けれどもクリストはこの悲劇の為に永久に若々しい顔をしてゐるのである。」と書き、「クリストの言葉」という章では「クリストは彼の弟子たちに「わたしは誰か?」と問ひかけてゐる。この問に答へることは困難ではない。彼はジヤアナリストであると共にジヤアナリズムの中の人物――或は「譬喩」と呼ばれてゐる短篇小説の作者だつたと共に、「新約全書」と呼ばれてゐる小説的伝記の主人公だつたのである。我々は大勢のクリストたちの中にもかう云ふ事実を発見するであらう。クリストも彼の一生を彼の作品の索引につけずにはゐられない一人だつた。」と書き、「貧しい人たちに」と題した最後の章でも、「クリストのジヤアナリズムは貧しい人たちや奴隷を慰めることになつた。それは勿論天国などに行かうと思はない貴族や金持ちに都合の善かつた為もあるであらう。しかし彼の天才は彼等を動かさずにはゐなかつたのである。いや、彼等ばかりではない。我々も彼のジヤアナリズムの中に何か美しいものを見出してゐる。何度叩いても開かれない門のあることは我々も亦知らないわけではない。狭い門からはひることもやはり我々には必しも幸福ではないことを示してゐる。しかし彼のジヤアナリズムはいつも無花果のやうに甘みを持つてゐる。彼は実にイスラエルの民の生んだ、古今に珍らしいジヤアナリストだつた。同時に又我々人間の生んだ、古今に珍らしい天才だつた。「予言者」は彼以後には流行してゐない。しかし彼の一生はいつも我々を動かすであらう。彼は十字架にかかる為に、――ジヤアナリズム至上主義を推し立てる為にあらゆるものを犠牲にした。ゲエテは婉曲にクリストに対する彼の軽蔑を示してゐる。丁度後代のクリストたちの多少はゲエテを嫉妬してゐるやうに。――我々はエマヲの旅びとたちのやうに我々の心を燃え上らせるクリストを求めずにはゐられないのであらう。」と書いている。 キリストについて書いたエッセイで、中心テーマに「ジャーナリズム」を置いている。しかし、「ジャーナリズム」という語について特に定義付けを行ってはおらず、つまりは当時の一般的な意味で使っており、それは現在ともそれほど大きくは変わっていないと思われる。
『西方の人』の初出は1927(昭和2)年の雑誌『改造』8月号で、『続西方の人』は翌月の���改造』9月号に掲載された。7月24日未明、『続西方の人』を書き上げたあと芥川は、致死量の睡眠薬を飲んで服毒自殺した。そのため『西方の人』『続西方の人』は必然的に作者の死と深く関連するものとして語られ、あるいは読者への遺書としても解釈されるが、死後に見つかった久米正雄に宛てたとされる遺書「或旧友へ送る手記」で芥川は自身の自殺の動機を「ぼんやりした不安」とした上で、それを解剖したものを『或阿呆の一生』に書いたとしている。『或阿呆の一生』は、『改造』1927年10月号に掲載された。それらを読み比べると、『西方の人』『続西方の人』はむしろ最期だからこそ自身の「不安」や、あるいは信仰などとは切り離して、唯感じた通りを書くことができたものだとも解釈できる。そして「クリストのジヤアナリズム」というのは、唯感じた通りを伝えることであり、それを聞いた人が見たまま聞いたままのことを感じられることであり、またそれぞれが感じた通りのことを表現できるようになることであって、それが「我々の心を燃え上らせるクリスト」だとも解釈できる。 「エマヲの旅びとたち」というのは、『ルカによる福音書』24章13節から32節に書かれているエピソードである。エルサレムから七マイルばかり離れたエマオという村へ歩いていたクレオパとルカとされるもう一人の弟子のところへ、復活したイエスが近づいてきて、その二人の弟子と語りながら一緒に歩いた。彼らの目はさえぎられて、それがイエスだと認めることができなかった。彼らが行こうとしていた村に近づき、夕暮になっていたため、なお先へ進み行く様子のイエスを引きとめ、一緒に食卓についた。イエスがパンを取り、祝福してさき、彼らに渡してるうちに、彼らの目が開けて、それがイエスであることがわかった。するとその時イエスの姿は見えなくなった。二人の弟子は互に言った、「道々お話しになったとき、また聖書を説き明してくださったとき、お互の心が内に燃えたではないか」。 この場面は多くの画家が描いた場面でもあり、なかでもカラヴァッジョが描いたや絵画『エマオの晩餐』(1601)が有名である。カラヴァッジョは、日常の中に訪れる日常を超越させるもの、日常生活を中断させる崇高な存在、自分自身の感情に自分自身が気づく瞬間といった、二面性や二重性を持つテーマを繰り返し描いた。カラヴァッジョはそれらのテーマを、一瞬を切り取る鋭い観察眼と見たままを描写できる卓越した技巧で超越すると同時に、その技巧をテーマで超越するという二重の超越で、二面性や二重性の中に、矛盾や逆説とは別の、それらを超える「超越性」そのものというような概念があることを提示し、西洋美術史に新たな美意識を加えた。 芥川もこの超越性のような概念に触れていて、『西方の人』の「復活」と題された章で、「我々は唯茫々とした人生の中に佇んでゐる。我々に平和を与へるものは眠りの外にある訣はない。あらゆる自然主義者は外科医のやうに残酷にこの事実を解剖してゐる。しかし聖霊の子供たちはいつもかう云ふ人生の��に何か美しいものを残して行つた。何か「永遠に超えようとするもの」を。」と書いている。 これらは作者自身の不安などとは切り離して唯感じた通りを書いたものだとも解釈できると言ったものの、「ぼんやりした不安」にあたるとも思われるものを、『西方の人』の「クリスト教」という章に書いている。この章は「クリスト教はクリスト自身も実行することの出来なかつた、逆説の多い詩的宗教である。」という文で始まり、「クリストは兎に角我々に現世の向うにあるものを指し示した。我々はいつもクリストの中に我々の求めてゐるものを、――我々を無限の道へ駆りやる喇叭の声を感じるであらう。同時に又いつもクリストの中に我々を虐んでやまないものを、――近代のやつと表現した世界苦を感じずにはゐられないであらう。」という文章で締められている。 この「世界苦」というのは、ドイツ語の「ヴェルトシュメルツ」をほぼ直訳したもので、「感傷的厭世観」「世の中の邪悪を思って悲しむこと」「悲観的世界観」というような意味を言い表す文学的概念だと説明される。もともとは、この「ヴェルトシュメルツ」という言葉は、ゲーテと同時代の作家のジャン パウルが遺稿となる小説『セリーナ』(1827)で造語したものとされる。小説の翻訳では「苦痛」や「苦悩」などと訳されている。「世界苦」という言葉は19世紀後半のドイツ哲学などで使われるようになり、19世紀のロマン主義の底流に流れていた文明に対するペシミスティックな懐疑主義のことを言い表す言葉になっていった。こうした文明に対する懐疑や厭世観が顕著に表れたのが19世紀末のデカダンス(退廃、世紀末芸術)である。この中からアールヌーヴォー(新しい芸術)やモダンスタイル(近代様式)などと言われる新しい潮流の可能性を見つけ、終末的な気分も終わった頃には、「世界苦」という言葉は、自己憐憫を「世界の苦悩」だとはき違えただけだとして一蹴され、そうした傾向を揶揄あるいは自嘲するための言葉としても使われるようになる。 悩みの多くは何かをはき違えただけというのも確かにそうかもしれないが、世の中に問題がないわけでもない。大雑把に分けると、18世紀後半の古典派は、教養と技術の習得によってこれを乗り越えようとしたのに対し、ロマン派は、問題の所在を明確にするための主題(テーマ)探しへと向かった。あらゆる問題を解決する教養は存在しないし、必要なすべての技術の習得も不可能で、テーマやスローガンなどに踊らされた群集心理は暴徒化する。1世紀近い混乱の時代の後で、これを乗り越えたのが大衆文化の成立で、すなわち近代ジャーナリズムの成立だった。
芥川個人の不安というのが何だったのかは結局はわからないし、関東大震災(1923年9月1日)後のCPTSDだとか、それっぽい理屈を当てはめるのも何か違う気がするが、後に解釈されるように、1920年代はどことなく不穏な空気が世界を漂い、ジャーナリズムも危機を迎えていた。検閲もそうだが、後にナチスが政権獲得(1933年)後に本格的に行うエンタルテテクンスト(退廃芸術)の排斥運動の理論的な基礎が組み上げられていた。 退廃芸術の排斥というのは、理屈としてはイコノクラスム(聖像破壊運動)にあたる。イコノクラスムに長けていたとされる宗派や集団というのが古くから存在していたとされ、アリストテレス学派やユグノーがそうだとも言われるが、議論も多く実際のところはわからないと言われている。イコノクラスムの目的の一つは経済的な支配権の獲得だと考えられていて、経済的な支配と思想的な支配はいわば車の両輪の関係にある。 近代ジャーナリズムの成立と、アメリカの南北戦争(1861年-1865年)によって奴隷貿易による利権が崩れたことは、間接的かもしれないが、少なくとも時期が同じという以上の関係があり、1930年代の世界恐慌とナチスの台頭は、間接的かもしれないが、少なくとも時期が同じという以上の関係がある。
2024年3月 リハイドレーション
0 notes
Text
おかぐの現パロ話を読んで今日になってもしんどかったから掃き溜め投げる
これを読む人が存在したと仮定して一応断っておくけど別にこれはdisじゃないと思う
気に入らないものを叩きたいだけなのに自分の善人ムーブをキープしたいヒステリックインターネットババアがよく使う保険だけどわたしが本当にdisりたいときは枕詞に「これは悪口だけど」ってちゃんと申告してから叩く
何がキツかったか要約すると「社会の縮図を感じてキツかった」って話なんで 作品自体面白かったしわたしが個人的にウーッってなったシーンも物語上必要な描写だったと作者の意図も理解できるので作品作者両方叩く意図はない
作者が、センシティブな議題を扱っているのにも関わらず作者がマジで何も考えてないんだろうなこの人…としか思えない描写をしていて、かつそれならキャラを凌辱するのが好きなんです!って堂々としてればいいのに自分は真っ当なカプ者です!ムーブをしている場合において殺意を抱くだけで、それが必要かつ考えられた描写だった場合には思想の合致はどうあれそういうものとして享受するので この作者はわたしにとっての地雷に該当しない
クリスマスにアリアスターの卒業制作らしい息子から父親への近親相姦DV映画をみせられて、面白くはあったけどDV加害者が被害者を詰めるときの被害者ムーブの解像度が高すぎてウッってなったんだけど、「キツかった」の種類としてはそんな感じ これはアリアスターと作品本編への嫌悪感を意味しない ここに書くことはそれと同じ
本題
作品の概要:剣道部沖田が部活の帰り道彼女の神楽がレイプされてるところを勢い余って犯人を撲殺、自首を主張するけど神楽の提案で逃亡、指名手配犯の二人でハネムーンみたいな逃避行するが行き場がなくなり捕まる前に逃げ出して一番幸せな瞬間に二人で心中して終わり
概要だけではキツいところとか特にないんですけど
わたしがウッてなったのは冒頭で、沖田が剣道部の部活中に大会目指す部のムーブに則って後輩指導という名の後輩いじめ(延長練における先輩陣における相手が泣くまで何時間もの不当な暴言・恫喝)に加担してるのね
それを見かねた神楽がお前は優しい人間なのにそんなことしてたら本当にひどい人間になってしまうよって言うんだけど沖田は嫌なら帰りゃいい、俺もそうしてたしって返す
苦言を呈していた神楽も結局ラブラブムードに流されてラブラブなままその場で別れる
いやしんどくね?
この沖田はその後神楽がレイプされてるのを見て犯人を殺し、神楽の言うままに一緒に逃げ、旅先でも神楽を守りつつ最後神楽に言われるがまま一緒に死んでやる、っていう好きな女の子を最後まで守る行為ができる人間なんだけど
そうやって他人のために心から奉仕できる「優しい」「善人」が、相手が特に自分にとって大事な人間ではない場合平然と加害者側に回れるという事実が、世の縮図を感じて本当に怖かった
これも所属組織の風潮に逆らえず渋々やってるんですって強制・抑圧されて心を殺しながら加害してるって話ならまだ理解できるんだけど(コンサル勤務の友達の上司がこのタイプらしい)、この場合沖田は先輩がダルいから帰るという選択ができるレベルの迎合せずにいられるハートの強さを持ち合わせてるわけで 沖田なんかは勇気を出さずともそれにノーを突きつけられる側の人間ではあるんだよね それにもかかわらず、内心ダルいと思いながらもその対象が自分にとって大事な人間ではない場合は「何となく」レベルの動機で不当に加害することができている その裏では、心の底から惚れた相手に身を挺して愛を捧げることもできる
社会的には善人として扱われている、誰かにとっての最愛である人間であるのに、自分にとってはどうでもいい誰かを自覚ありきで不当に加害できる人間、世の中の1/5くらいはこれで構成されてるんじゃないかと思う それでも善人として、正しさとして扱われ、誰かには真っ当に愛される 社会のリアルすぎる
作中の神楽だって沖田の加担している恫喝行為に関して指摘するもラブラブムードに流されて、結局その後は何も言わない
仮に自分の彼氏が自分に尽くしてくれて人間的にも尊敬できる人であったとして、会社ではパワハラに自覚的に加担してることが発覚したら軽蔑してしまうので別れを切り出す自信があるけど、作中の神楽含めて世の女の子たちは周囲のそういう加害に目をつぶってスルーできる それがリアルすぎて勝ち組同士の恋愛ってこんな感じなんだろうなー…って���えて鬱になった
結局「ひどい人間(鬼)になってしまう」=神楽を守った殺人を全く後悔してない、人を殺したのに神楽のようにろくに食べ���れなくなったりすることなく惚れた女の子との逃亡劇を純粋に楽しむことができている、という後々の沖田の自分が神楽とは根本的に異なる悪人と思う自己認識につながってくるし、最後神楽が一緒に死んでくれる沖田を「優しい」と言って終わることからも物語の構成としては必要なシーンではあるんだけど
まあ彼女を救うための衝動的な殺人もそれを後悔しないことも人間として優しいとか優しくないとかのベクトルからは逸れる話だと思うから、一連の流れにおける比較対象として羅列するのはちょっと違うと思うけど…
別に沖田・神楽はこんなことしないor沖田・神楽にこんなことさせるなんて!とかと思っているわけでは全くない そういった作品に対して怒りを覚えることが多いけどこれに関してはそれには該当しなかった レイプを魂の殺人として真っ当に描いているし作者の倫理観を疑っているとかも特にない 世の縮図を感じるレベルで普遍的な人間における善悪の曖昧さの解像度が高くて話としてはとても面白かったので何度も読んでる
これはifだけど仮に沖田からの加害を受けた名前も顔も出てこない後輩が自分がその後どうなろうと沖田を殺す決意をするくらいの強い憎しみを抱いたとして、相手に最大限の苦痛を与えることを目的に報復するのであれば本人よりも彼の最愛の神楽を狙うと思うから、そういう文脈でも直後被害に遭ったのが神楽だったという点において(本編における両者の因果関係は皆無だが)解像度高いなと思って読んだ
わたしの反応ポイントがおかしい自覚はある 昔から常人に比べて怒りのボルテージがデカすぎて一晩中毛布の中で「殺してやる」と永遠に唱え続けて朝になってることがザラにある人間だから、不当かつ故意的な加害行為に対して誰もが強い憎しみを抱く前提で考えてしまっている節は大いにある
そういう時は加害してきた相手に報復する権利はあるかもしれないが相手がこの世で一人で生きているわけではない以上は相手の家族や周囲を加害する権利は自分にないな、と自分に言い聞かせ続けて一晩かけて殺意を落ち着かせる
残念ながらわたしみたいに生まれつき怒りのメーターがぶっ壊れてる人間も一定数いるんだろうし、実際に客観的証拠からもそういった生まれながらの性質のみを理由に殺人を犯してしまった人間が友達の同級生にいることを聞かされているので、法や社会の抑止力も効かないレベルの憎しみを抱いてしまった時点で人は物理的に人を殺せるのだから、赤の他人をいたずらに加害するなら殺される覚悟を持った上で加害しろよ、人間殺そうという意志があれば今この場で簡単に殺せるのに相手に何をしようが自分は何ら報復を受けないという自負があるのすごいな、という思想がベースにあるが故に読んでウッってなったんだと思う
加害行為に対して敏感であるが故に他人に対してヒスる・詰めるという行為ができない人間だから、���面で対話もできないレベルの状況に陥ったときそういう世間で揶揄される嫌な発散の仕方ができない代わりに本気で頭に血が昇って視界の色が変わった時(比喩ではない)の対処法が、いまだに「辛うじて理性が応答するうちに相手に危害を加える前に一刻も早く相手を自分の視界から消す」くらいしかない 前に家族に対しての許容し難い侮辱を浴びせてきた親戚のジジイに部屋のストーブの灯油を引っこぬいてぶちまけた挙句チャッカマンで火をつけようとして羽交いじめされて止められたことがある キチガイだから怒りに飲み込まれすぎて本当にヤバくなった時、辛うじて動けるうちに相手から離れないととにかくその場における一番有効な手段を用いて相手を消すことしか考えられなくなる
父親もキレるとノータイムで出ていって一週間くらい帰ってこない人間だったんだけど、今思えば「気に食わないから出ていく」とかいうレベルのかまってちゃんの域ではないキレ方だったから加害しないためだったんだと思うし、遺伝ってあるんだなと思った
ただ世の縮図を感じたが故にウッってなったという掃き溜め 作品への所感を分析していたら自分自身の怒りという感情についての話になった I LOVE ハンムラビ法典
0 notes
Text
岡田斗司夫との付き合いは、「コロナ(covid-19)禍」の期間と同じになった。『コナン』の解説動画きっかけで観始めて、「最悪な平和とまだマシな戦争」発言で実質的に見限り、その後少しして、完全に「卒業」した。それ以降、全く視聴してない。その代わり、というわけでもないが、今は『山田玲司のヤングサンデー』を有料視聴している。
――もう少し詳しく
パンデミックで『キングダム』のアニメ制作がにっちもさっちも行かなくなったNHKが、倉庫の奥から『未来少年コナン』を引っ張り出してきて穴埋め放送したお陰で、数十年ぶりに『コナン』を目にすることになり、(いかにも今どきなことだが)それで、岡田斗司夫の解説動画に引っかかったという流れ。
最初に動画を見たときには、「この人が、数年前に『アオイホノオ』で濱田岳が演じていた『岡田斗司夫です〜♪』本人かあ」というくらいにしか、「全く知らない人」だったのだが、その後の約3年間の有料視聴で「だいたい分かったから、もういいや」となった。
――更に詳しく
岡田斗司夫が面白がる作品を「弁当」に喩えると、「確かにおかずはいろいろで美味いけど、とにかくどれも米が美味くない」というのが、一番ぴったりな表現になると思う。岡田斗司夫は不味い「米」が好きなのではなく、「米」の美味い不味いがよく分からない(気にならない)のだ。
ここでの「おかず」は、「新しい知識」や「物語の世界設定・SF設定」や「表現技法」や「時代背景」や「創作秘話」など。「米」は、「文章の美しさや気持ちよさ」とか「登場人物たちの心の描かれ方の深さや複雑さ」、要するにもっとずっと普遍的な要素。
岡田斗司夫が高く評価する「作品」にいくつか接してみれば、とにかく「米」に相当するものに対する評価が、「素通り」か「凡庸と言っていいほど甘くて幼稚」なことに気づく。だから、例えば、彼が強く推すSF小説などを試しに読んでみても、「設定は面白いが、物語は退屈」という感想になる。「わざわざ拙い小説に仕立てなくても、直に設定資料集で読ませてくれればいいよ」という感想になる。
――「卒業」の決め手になったこと
去年かそこらに岡田斗司夫が「激賞」していた『コーダ あいのうた』を自分でも観たとき、岡田斗司夫のサイコパスがただの「自称」ではなく「本物」であることを確信した。
岡田斗司夫は「安い感動」にしか感動できない人のことをよくバカにしているけど、あの映画を観て、「最後の2分間に訳の分からない感動を覚え」、「今年一番」「歴代二位の高得点」と褒めちぎるような60過ぎのおっさんが、「24時間テレビで安い感動をしている人」をバカにしちゃいけない。
ただし、もしかしたら、岡田斗司夫が体験した「訳の分からない感動」は、本当の感動というより、もう少し「手の込んだ」、或る種の「メタ感動」だった可能性もある。
つまりこうだ。
『コーダ あいのうた』の劇中で、娘(主人公)の歌の発表会に出席した父親(耳が聞こえない)が、自分は娘の歌は全く聞こえないのだけれど、周囲の観客が涙を流したり喜んだりしているのを目にして、自分の娘の歌の価値(娘が歌を歌うことの価値)に気付く場面がある。その場面と、感情移入が得意ではない(輒ちサイコパスな)岡田斗司夫が、映画館で、周りの観客が映画の観て泣いているのを目にして、この映画の価値に気づく状況とが、岡田斗司夫の中で「同じ」になったんじゃないかな? つまり、「劇中で父親に起きたことが、現実の自分の身にも今起きている!」と。それがあって「訳の分からない感動」を覚えたんじゃないのか?
しらんけど。
――岡田斗司夫ゼミの面白さについて
岡田斗司夫ゼミを視聴する面白さは2つあって、一つは、いわゆるオタク的な情報を聴く面白さ。要するに、今はなき「タモリ倶楽部」で、様々な分野のオタクが出てきて、愚にもつかない知識を喜々として披露しているときのアレ。もう一つは、サイコパス(感情移入が苦手)な岡田斗司夫の「人の心の機微の分からなさ」の面白さ。知能は高いのに、人の心の機微がわからないばっかりに、キャラクター分析や物語展開の理解が「大暴投」になる面白さ。それは、耳の聞こえない人の音楽解説のような面白さ。
例えば、「サイコパスの人生相談」の「独自性=キモ」はまさにこれで、要は、相談者と岡田斗司夫の「スレ違い」。弁当の喩えを使うなら、弁当の米が不味くて困っている相談者に対して、米は食わずにおかずだけ食べればいいでしょと答えてしまうのが岡田斗司夫。米なしでおかずだけを食べる味気なさや物足りなさに全く気づけない人間だけが「じゃあ、おかずだけ食べとけばいいでしょ」と平気で言える。でも、これでは、相談者の相談を答えたことにはなってない。岡田斗司夫当人にそのつもりはなくても、実際には「逸して」いるだけ。つまりは、一休さんの「とんち」と変わらない(だから、サイコパスの人生相談は面白いとも言える)。
――最後に
岡田斗司夫は『ガンダム』で何を学んだのだろう? 何を観ていたのか? サイコパスの「物語(映画・アニメ・小説)鑑賞者」は、耳の聞こえない音楽鑑賞者のようなものなのだということを、岡田斗司夫との3年間で学ばせてもらった。それで言えば、『コーダ・あいのうた』に対する、岡田斗司夫の頓珍漢な高評価が、岡田斗司夫卒業の決定打になったことは、なにやら意味深い。
ありがとう��岡田斗司夫。そして、さようなら。
0 notes
Text
どこかの汽水域 あとがき

この文章は、自作短編小説集『どこかの汽水域』が刊行から二年が経過したことをふまえて書きました、あとがき、とも、解説、ともいえる蛇足的文章です。
『どこかの汽水域』他、創作小説などの本は自家通販で常時販売しております。よろしければこちらからどうぞ。
『墨夏』
『どこかの汽水域』を書くよりも五年くらい前に、川に辿り着いて昴に会うまでの描写をずっとメモアプリに残したままにしていて、その先は点々と風景は浮かぶものの霞に隠れたまま。小説の本を作ると決めて先に『いつか声は波を渡る』が出来上がってから、他に何作かあわせたいと考えた時に、かつて残したままにした冒頭が甦り、徐々に続きを繋げていきました。現在もひそかに続けられている日記『朝の記録』の中で書いていて、日記と並行した小説を書くというのは別でやったけれども、日記の文中で小説を書いていく(実質連載)行為はたぶん今後もうやらないだろうなあと思います。そんなわけで実際に書いた時間以上に途中のまま漬けた時間が長かったので、完結まで至った時は独特の感慨深さと疲労感がありました。
途中、ひなこが、昴に憧れて自分の名前を星につけたいと考える文がありますが、ひなこは、漢字表記だと日向子という設定があります。字のごとく、太陽を重ねています。彼女自身は、誰もをまばゆく照らす、典型的な太陽らしい人間像ではないのですが、昴をはじめとして夜にちりばめられる星たちとはすれちがう存在としてのイメージをもたせています。
川辺で出会う青年とどんな交流をしていくかを考えていった時に思い出されたのが、小学校の時、夏休みの終盤に話題になった火星の大接近でした。さすがに火星で被らせるとなんだか記憶に近すぎたので金星に変えましたが、明けの明星である金星は、最後、太陽が昇って見えなくなっていくけれども消えるわけではない星たち、そしてひなこと昴の関係性を表現するには、想像の広がるモチーフだった、と思います。
ひなこと昴の重なる場として川が舞台となっており、彼らはそこで出会い、交流を深めています。川は、彼岸と湖岸の間を流れます。川岸に手向けられ、何度がふれられている小菊は、川に流されていった人たちへの供花でもあります。川に近づいてはいけないとお父さんの言葉がひなこの心では繰り返されていて、そうした事故が起こってきた過去を浮かばせています。お盆という時期もあって、物語の随所でお盆にまつわる描写がちりばめられています。
ひなこと昴の会話に対して家族との会話場面は地の文の中に埋め込まれながら、最後のお父さんからの「帰ろう、ひなこ」だけが鉤括弧で書いているのは、そのままおばあちゃんの家への帰宅を促す言葉であるし、彼岸より戻ってくる暗喩をこめています。
あとこの『墨夏』のすんごいのは、真島こころさんという即興ピアノ音楽をされている方が、冒頭のシーンをイメージして曲を弾いてくださったことです。いやすごい、とんでもないことです。どうぞ聴いてください。ツイートはこちらから。
『魚たちの呼吸』
耳の後ろには髪の毛が生えていない、と小中学生の時に漫画雑誌で知って、実際にさわってみると確かにそこには髪の毛がなくまっさらな肌があるだけ。驚きました。実際に自分の瞳でその密かな場所を見ることはない、この場所には一体なんの意味があるのか、いや、髪の毛が生えていてほしいわけではないのだけれど。もしかして、人間の尻尾の名残である尾てい骨のように、ここには何かあるべきものがかつて存在していて、今は閉じてしまったすべらかな跡なのかもしれません。
書いていてずっと不思議な浮遊感を抱いていた小説でした。
この小説は、他の二作を書いてから、短編集を作るにあたって最低限もう一作あると収まりがいいと、締め切りに追い立てられるようにして書き始めました。書きだす前は、前後二作が偶然夜明けで終わったので、それに合わせて夜明けで揃えるとか、逆に日没で終わらせるとか、時間的な統一感をもたせることを想定していたのですが、書きおわれば夜明けとは言いづらい薄くちぎれていくようなものになり、本としてどうまとめたものだろうと三作並べて考えていくと、そういえば水がこれらの作品に共通していると後追いで気付き、そこからは、水に由来するような自由自在にゆれるあわいの質感を大事にして全体を整えていき、のちに書く「汽水域」に繋がりました。
他作に比べるとちょっと空気感が違うので悪い意味で浮いてしまわないか心配だったのですが、川を舞台の中心に据えた『墨夏』と、東北の海を主題としている『いつか声は波を渡る』のあわい、橋渡しのような作品になったように思っています。河野という苗字。エラをもつ人間。水中を泳ぐ魚のモチーフ。そして最後、海へと向かっていく。
気に入っている文章は、62ページの、頑固として守ってきた河野の耳の裏に、一青の指が寄せられていく場面です。“髪の毛で出来た珊瑚や藻の森を抜けて魚がなめらかに泳いでくる。”という部分が好きです。それから、象徴的ではありますが、一青の、“だからちょっと息がしづらいんだ”も。
『いつか声は波を渡る』
『どこかの汽水域』の三作品の中では、一番初めに完成した小説です。書き始めた当時、インターネットで拾ったお題をもとに三題噺での即興小説をほとんど毎日noteに更新していて、そのお題のうちの一つ���不治の感情』と名づけられた「冷たい、昨日見た悪夢、殺したい」の言葉をもとにして浮かんだのが、冷え込んだ濁流の描写、『いつか声は波を渡る』でした。元々は二次創作での活動が主体ながら、いつか東日本大震災についての話を書こうという思いが燻り続けながら、きっかけをいただいたように思いました。書いていくうちに、これは一日だとかごく短期間で公開までもって���くような容易な物語にはしたくないなと気付き、一連の即興小説とは別で、中期的に丁寧に書いていくことにしました。出来上がってもしばらくは『不治の感情』というタイトルで、流石にお題の題を拝借し続けるのは気が引けたので、他作品『墨夏』『魚たちの呼吸』と並べた印象などもふまえて考えていった結果、『いつか声は波を渡る』に決定されました。ただ『不治の感情』という言葉自体は地の文中に残したままにしています。
3.11に関してはいつか小説なりなんなりの形にしたかった、それは自分にとってのエゴであったのは否めないと思っています。当事者とそうでない人の間には溝があって、それを越えることは難しいし、だからこそ経験していない自分が一体何を語れるのだろうとずっと思っていたし、今も思っています。だから今でもためらいがあります。それでも忘れたくはないし忘れることはない。また、書籍等を読むうちに、現地でもさまざまな考えの方がおられて、つらい震災の記憶を掘り起こさずに、復興していく・更新していく現状に注目してほしい、という方も多くおられることを知りました。ならば、当時は遠くにいてテレビで呆然と見ているしかなかった外側の自分にも、記憶を穿つように物語ることを許されるのではないかと思いました。作品は震災の日から六年後、実際に足を運んだ時に自分が抱いた印象が地盤となっています。現状にそぐわない部分もあるのだけれど、願うならば、許されたい。
喪失を受けとめる・向き合っていく過程は人によってまったく異なっていて、どんなかたちが正しいとも間違っているともいえないとは思うものの、長い年月、親友であるあーちゃんが突如として死んでしまった状況から立ち直れずにいる春香が、物語の中ではどんな結末を迎えるのか、手探りのままで書き進んでいった記憶がありますし、実際のところ終盤は決め切らなくてなかなか筆が進みませんでした。あーちゃんの生きていた証を探してもいた春香を突き動かすとすれば、あーちゃんそのものに値するなにか。
たとえば骨はどうだろうか、死んだ生き物を燃やして残った骨、あるいは灰、そうした肉体のかけらを密かにもって生活する・旅をする、といったアイデアは、生々しいけれども普遍的なものでもあって、どこかぴんとこない。そんな中でふと、まったく違う本を読んでいる時に、自然と抜ける乳歯に関する場面に出会った時に、歯だ、と繋がりました。あーちゃんとの思い出には笑顔がたくさん溢れていて、だから春香はあーちゃんの笑った顔の歯をよく見ていたはずで、あーちゃんの特徴として八重歯をちらつかせ、最後に春香が堤防で発見したかけらを「あーちゃんの歯だ」と断言する場面が浮かびました。
あーちゃんの歯だと信じる春香ですが、実際のところは歯を彷彿させる乳白色の小石や貝殻のかけら、かもしれません。夏希にとっては後者でした。もともと春香の危うさを察知していた経緯もあり、春香が妄想を吐いているとしか思えない夏希は、友人の体の一部と信じ込む姿に恐怖を覚えて引き戻そうとします。かけらが現実的にはなんなのか、というのは一つしか答えがなくても、どちらの言い分も本当、と思います。
最後の一文は、あーちゃんの歯を常に懐にしまっている、という状態を書きたくて当初は財布の中にしまっている、といった描写にしていたのですが、締めの文としてはあまりにも現実的だったので抽象化させました。
余談ですが、今、書きながら、でも、ここ数年のコロナ禍ではマスク着用が当たり前になって、会話して笑っている、「歯を見せる」といった状況は、マスクのない世界の常識なんだなあ、と今更ながら気付きました。
ここからは、刊行から二年が経過しての思いなど。
この小説が震災を扱ううえで適切な表現を突き通せたのかは、少々危ういと感じています。
フィクションという形態に甘えて安易に扱いたくないのは当然と思っていても、終盤の夏希との掛け合いや、あえて愛という言葉に収束させたこと、そして出産というかたちで、時の流れを意識した春夏秋冬の一角を二人の赤ん坊に担わせていく構成は、作り手の偏った決定権が行使されてそこに登場人物が操られていってはいないか、それはある種の偏見や思い込みをもたせてはいないか、そんなことを、ずっと考え続けています。ある程度の「わかりやすくきれいな終わり方」で装飾を施そうとしたのではないか。逃げてはいなかったか。さらっと書いたわけでもなくて、この海岸へ至ってからの終盤は模索が終わらなくて、書き直しの傷跡が無数に重なっています。それでも。震災という、傷の癒えていない現実的事象を中心に据えている以上、そしてそこで喪われた人について語る以上、簡単に逃げないと決めて書いていたものの、本当に過不足なく遂行できていたのか。でも、小説で書かれていることがすべてであることもまた確かで、読み返してみると、数多の分岐がありえた中で、この物語にはこの表現、この展開しかなかったようにも思います。けれど、それでも迷い続けている状態は忘れないようにしていたい、というよりおそらく忘れられずに続いていく。だから震災をめぐっての応答は終わってはいません。
そんなネガティブ気味に書くと、まるでこの物語を否定しているように受け止められるかもしれないのですが、決してそんなつもりではなくて、物語で春香があーちゃんを愛していたのは確かであり、その喪失と向き合う行程も、そして夏希が春香を繋ぎとめながらあーちゃんを探して海のすぐそばまで歩いていった暗い夜明けも、彼らが物語で必死に生きていた証は、何にも代えられません。いつか声は波を渡る、死んだあーちゃんの声は波となり、六年の時を経て春香の耳に届いて、筆舌しがたい情は、確かに春香の中に溢れました。必死ゆえに書いていくには迷いの渦巻く難しい物語を書き切って、世に出して良かったと思えるのは、この物語に呼応してくださった読み手の言葉に支えられているからでもあります。

『どこかの汽水域』
どこかの汽水域というタイトルの、「汽水域」は、三作品の初稿が揃ってさあタイトルどうしようという段階に、本を読んでいる際に目についた言葉です。辞書を引けば「海水と淡水とが混じり合っている塩分濃度の低い水」とある。また「汽」は湯気や水蒸気といった意味の漢字であり、そのどこか霧のようなニュアンスが今回の三作品になにか通ずるものがあるのではないかと思っています。どの作品もどこかに水が関連する場面があるということもありますし、彼岸と此岸、人と人、空と地、生と死など、どこまでいっても本当の意味では平行線のまま決して混じり合わないものが、けれどどこか混ざる瞬間があるような気がしていて、そうした瞬間が三作品には宿っているのではないかというタイトルを、私は気に入っています。
どの作品も、人によってさまざまな受け取り方があります。ここに書いたことは蛇足です。人それぞれの彩りがあってくれたら嬉しいです。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
1 note
·
View note
Text
『Q.E.D. iff』が10巻まで無料公開されていた。以下、メモ(含ネタバラシ)
「量子力学の年に」 -量子力学がミステリの題材にされるとき、大抵の場合「最先端」や「近未来」、「新しさ」が前面に出され、シュレディンガーの猫やコペンハーゲン解釈が比喩的に扱われるにすぎないが、本作はそもそも量子力学って歴史ある分野だよね、と云う観点からそのはじまりに遡って、古典物理学に揺さぶりがかけられた時代そのものを題材とし、科学と人間の関係を描いているところが秀逸。 -その着眼点だけで、傑作と云って良い。 -現代物理学の基礎でありながら直観に反する議論の数々――こちらのリテラシーを試すかのような揺さぶりを、一見すると直観に従っているが矛盾している新興宗教の教義と対置することで科学と宗教の相剋を捉え、しかし一方を安易に断罪することなく、むしろ底知れない教祖のヴィジョンを印象に刻む。その奥行き��� -賽は斜めに立ったのではないか? -事件の発端となる「教義の矛盾」と云う発想もユニークで、現実に「ルール」が敷かれてしまうことそれ自体の危うさがここに見出せる。 -特殊設定ミステリを念頭に置いて書いています。
「自転車泥棒」 -「巡礼」が巡礼者の物語と云うより彼を語ろうとする巡礼者たちの物語であったように、人間心理の深いところへ潜ることは、むしろ潜水者たちを見返してくる。燈馬には違うものが見えていたし、可奈もまた違うものを見ている。 -「美しい絵」しかり「不完全な密室」しかり、絵的なインパクトを活かしたアナロジーが抜群に巧い。 -自転車泥棒のトリックは拙いものの(そんなことは普通、起こらないのではないだろうか)、このトリックの眼目は実行――ファックスに施した仕掛けや犯罪の具体的な手際・手順ではなく、トリックがバレてもなお犯罪が露見しないそのシステムではないかと思う。人間心理の弱さを巧妙に衝いた発想。
「陰火」 -人間心理の暗闇、と云ういつもの魅力は本作では若干滑り気味。情報を詰め込みすぎて、決めどころで分散した感がある -それよりも感心したのは密室トリックだ。カメラの入れ替えと云うシンプルな発想で強固な密室があっさりと破られてしまう。幽霊は文字通り、映像の隙間へと消えるのだ。 -過去の事件も見逃せない。凶器がどこから来たのか、と云う設問から、事件当夜何が起きたのか浮かび上がる。確かにそれはそう使えるなあ、と膝を打った。
「アウトローズ」 -『Q.E.D.』シリーズはしばしば人間心理の巧みな観察を描くけれど、根本にあるのはむしろ「合理」。つまり、このシチュエーションならこうしますよね、と云う推理。あるいは、あなたがここでこんな行動を取るのは奇妙だ、と云う指摘。 -しかしそれは視点を変えるだけで容易にわからなくなる。 -もっとも、それこそ坂口安吾が云う「心理の足跡」だろう。 -「アウトローズ」は全篇が、云われてみれば、と云う指摘で成立していると云っても過言ではないコン・ゲームもの。読むのは人間の心理ではなく合理であり、作者はシチュエーションを呑みこませることでその合理を隠してしまう。
「ダイイングメッセージ」 -別解含めた密室トリックが面白い。ベニヤ板を歪ませる発想は、待ってました、と手を拍ちたくなる十八番芸だし、ベッドを置くだけでリネン室を客室に見せかける発想は、心理的な錯覚と物理的な抜け穴を巧みに組み合わせている。
0 notes
Photo

こころの動物たち 「和」 A Journey to Invisible Animals [Peace] #個展 #光明院 #波心庭 #禅 #京都 #イマココ #ART #水墨画 #日本画 #奏墨 #浦正 #tadashiura #soumoku #桑原茂一 #freedom_dictionary #水墨画展 #sumie #kyoto #zen #buddhism #象 #鶺鴒 #elephant #bird #exhibition #japan #平和 #peace #telepathy #心に浮かぶ感情や感覚を動物に喩えて描く https://www.instagram.com/p/CU3lvS8hQKc/?utm_medium=tumblr
#個展#光明院#波心庭#禅#京都#イマココ#art#水墨画#日本画#奏墨#浦正#tadashiura#soumoku#桑原茂一#freedom_dictionary#水墨画展#sumie#kyoto#zen#buddhism#象#鶺鴒#elephant#bird#exhibition#japan#平和#peace#telepathy#心に浮かぶ感情や感覚を動物に喩えて描く
2 notes
·
View notes
Photo




来たぞリヴァイアちゃん
誓約(うけい)がいつもウコッケイに聞こえるのは気のせいだと思います。罰当たり過ぎてゲンティアナさんに平手打ちされそう。(されたい)
ようやく来ましたリヴァイアちゃん。気位の高い水神様すごい好きです。あの性格で女性ってのがなお良い。船乗りが海を女性に喩えるところからそうしたのでしょうか。続きで本編EDについて触れてるのでネタバレ注意です。
*
帝国軍こんな面白い乗り物あるんですねー。欲しい。プロンプト編でこれいじりたかった気もします。帝国との戦いはなんだかんだプロンプトが良いシーンかっさらっていく。

水神の祭壇が月を象っているのは、最初から「神凪がここで誓約を結ぶ」と分かっていたのかなあと不思議に思いました。まあ六神なら知ってそうかも。でも六神(剣神)は未来が分かっている、というより、自分の決めたルート通りに人間が動いて欲しいということなので、「未来予知にてこれから起こることを知っている」のではなく「あるべき未来通りに動かしているから未来を知っているように見える」のかもしれません。
またリヴァイアサンを目覚めさせるこのシーン、サントラに入ってる曲「Song of the Stars」はルナフレーナ様が歌っているのでしょうか。なんとなくムービー見てると彼女が歌っていたように見えて感動。歌って目覚めさせるの良いなあ。海だけにセイレーンみたいですね。

しかし水神様の口調もあれだけど、神凪も神様にそういう口調なんですね。いいのか…いや、いいのか……。約束を破ろうとしているのが水神のほうだから強気でいかねばいかん、そういう感じなんでしょうか。


水神様のヒレを一つずつもいでいく所業。弱体化させて勝たなきゃいけないけど、逆に帝国軍にもやられやすくなるのでは、と思ったり。いいのかな…と震えながらプレイしていました。でもヒレもがれていく水神様かわいい。


誓約を済ませると巨神や水神が各地から消えるのは「星の中で眠っていた神々が、誓約済ませた後は王様に宿るから」と考えて良いのでしょうか。そのへんちょっと分からない。帝国にやられた訳じゃないですよね? そういう描写なかったし。弱らせたの確実にノクトだし。
気になるのは11章で、夜が長くなった話題に差し掛かった時にグラディオが「六神も半数がやられちまったしな」と答えていること。やられちまった、って表現するってことは、普通は誓約したら必ず消える訳じゃなくて弱ったところを殺されたっていう表現なんでしょうか?(でもノクトが呼んだら来るからやっぱり誓約したから消えたのでは??)

そして現れるタイタン。「あっこのシーン知ってる、イグニス編開始シーンだ!」と思いました。なるほど??? ここで出てきてたんですね。自分で出て来たのか、ルーナが出したのか…どちらだろう。DLCやる頃は完全に本編ストーリーの流れを忘れていたので何で巨神が出てるの?って思いながらプレイしていました。


最高に美しい死に際の演出……。血みどろのゲームばかりプレイしてたのでこんなに綺麗に亡くなってくシーンあんまり見たことなくてプレイ二回目なのに改めて感動しました。小耳に挟んだお話ではFF7エアリス?ちゃんと似た雰囲気の死に様だそうですが、そちらは知らないので、自分の中ではルナフレーナ様が最高に美しい死亡シーンだと思っています…。フリルのお洋服も髪降ろしルーナもとてもかわいい。
ところで演説の時、ルナフレーナ様が調印式に触れた時にコル将軍がなんとも言い難い表情を浮かべていてちょっと切なくなりました。ノーマルエンドを迎えた場合、一番辛いの将軍なのでは……守るべき主を三人も失い、弟子も失い、主の妻になるはずだった神凪も失い。
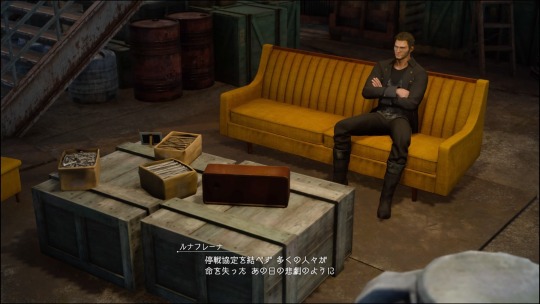
レギス世代とノクト世代のことを語り継いでいく使命を課されているのかもしれないけれど。うーん。うーーーん。将軍の心境を考えるとすごいつらい。ウィスカムさんとシドと仲良く幸せに暮らしてほしい……。
原作ED好きなんですが諸々考えたら救いと呼べる救いは、あんまりないんですよねえ。。
2 notes
·
View notes
Text
2021.7.24
今日は、はじめてちゃんと解説書を読んだので(あることを知らなかった)、Tree of Lifeのかたちで手順にのっとって引いてみた。カードの上下が必要だった気がするが間違えちゃった……… とりあえず結果から。
4. Hot Seat [HEAD] (Intellect)
54. Asylum [THROAT] (Dream)
30. Castles in the Clouds [HEART] (Emotions)
female side: 18. Soma & 3. Scarlet Woman
male side: 10. Wheel of Great Time & 45. Like a Bubble
58. Chameleon [NAVEL] (Vitality)
24. Solar Return [SPLEEN] (Health)
15. Ally [BASE] (Sexual)

まずはBASEから。
15. Ally
ここのbase centerにぴったりすぎてびっくり&笑ってしまった。色も赤だし。raw power of unconscious、まさに!base centerのパワー自体がrawのこういうパワーなんよね。そしてbase centerもそうだし、このAllyもsexual, eroticなsenseです。わたしは前々から思っていて最近確信したのだが、性のエネルギーとの関わりが深い。太陽牡牛座で月が蠍座、どちらもかなりセクシーな星座のエネルギーだし、興味のある道教や密教もかなり性を重要視している。だからこそ地に足がついていない(赤が足りない)とすぐふらつくのでは…… やっぱTao practiceやってみたくなったな。
ふつふつするマグマの湖の岸にいるAllyは、ギザギザの歯の間から炎を出している。これはAllyの、「破壊」と「むさぼり食う」の象徴。両手に二股の鎌を持っていて、それはAllyが「魂の捕獲者であり支配者」である(彼がcontrolする)ことを示す。彼の身体は、下位の存在の姿をした鎧で覆われている。彼の頭には、6つのグロテスクな獣の頭が飾られており、肩の飾りは動物の頭、そして下半身にはもう一つ悪魔のような顔がある。彼のここ��の機能は「敵の撲滅者」である。敵とは、隠し事がある者や恐れを持つ者を捕らえるものである。 下位である顕在意識を乗り越えるための助けを与えられている。Allyは、根源的な生のクンダリーニの炎のかたちであり、Tree of Lifeにおける根本となる蛇(クンダリーニ)のエネルギー。状況が好ましくないとき、それを打ち破るために、身体を通じて使われるエネルギーだと理解すると良い。自己の退行や破壊の側面が強く出てきているときには、もうすぐで助けがやってくることを暗示する。Allyを恐れる必要は決してない。彼は守護者である。このカードがbase centerにあるときには、無意識を示す。
次、SPLEENは。
24. Solar Return
大宇宙と小宇宙の関係をあらわす数字。時間の参照点。バランスをとって両極を統合する。 日食。黒い太陽と、中心に寄せては返すコロナの光。これは、星・惑星・月のサイクル(公転)による運命の満ち引きという、天空、宇宙のちからを象徴する。永遠の循環、長い時をかけて伝わる光。黒い太陽、またはブラックホールを連想させる。これはGreat Timeの抽象的表現であり、すべての経験の根本原理を滅ぼしかつ創造するというMahakaliのもう一つの面である。 個性や性格の根本への回帰。現在の状況の中でいちばん楽な方法へ至る道を見つけるために、生まれたときの星たち(占星術的な)の影響を考えてみなさい。未来を予言するためには、過去を解読しようと試みなさい。未来を現在に連れてきなさい。個人と集合的無意識との関係を考える必要がある。障害は、self-natureの認識によって出現する。それは、ある人間の進化の方向(ある人がどうやって成長していくのが望ましいか)を計算するような、外側の影響力による打算である。夢や前兆といった、吉兆のサインに注意深く気づく能力を身につけ、洗練しなさい。ポジティブなカードで、戦士としての路をだいぶ進んできている。対立や対決によって何かを得るチャンス。カルマを燃やし、根源に帰る。永遠への道。
これがわたしを構成する、あるいはわたしの気質である。そうかも……… Tree of Lifeを維持するための活力が、このエネルギー。根源への回帰とか、永遠への道を、自然と求めてしまうのかも。自然な生命のリズムのcenterなので、それが宇宙と共鳴する(大宇宙と小宇宙)ことを身体が、そして霊的身体が求めている。太陽、そして宇宙って根源的なエネルギーだから、それが身体と密接に関わってるのは素敵かも。
次はNAVEL。
58. Chameleon
ここは、自己変容のcenter。わお、それでカメレオンが出るの?シンクロしすぎでは。カメレオンって、状況や環境に自分を適応させていくエネルギーかな?「質問者の周りの状況」をあらわす。このcenterは、すべてのエネルギーが精錬される場所である。質問者が何を消費してどのように活力を凝集させるか、変容と作用にどのくらい気づいているか。質問者の態度。
今の状況でいちばん楽なのは、周りに適応することだよ、したほうがいいよってことなのか?というか自己変容なのだとしたら確かに、周りに適応したことないからしてみなよ、なのかも。
カメレオンは、「適応」への道をあらわすカード。カメレオンの顔が、蝶の翅の上にある。これは、置かれた環境に身体の色を合わせることによって、精神が発展する可能性を示す。カメレオンはどんな色にもなることができる。蝶の翅は、美と無常をあらわし、かんたんにひらひら飛び回りながら生命から出たり入ったりする(現世と夢を行き来する)。カメレオンが一時的に決定した色は、決して長い期間価値を持つものではない。諸行無常、盛者必衰。カメレオンは、制限された知能(動物?)のなかで最も完成しており、常に脅威に注意を払い、捕食者から身を守るためにその適応性を使うのである。 すべての周囲の状況を見ることはできるが、リスクを取りたくない人物のことを伝えているカード。質問者が簡単に周囲に影響されることは、世界の圧力から身を守るためである。これがNAVELにあれば、「心理的に適応できる姿勢」を伝える。精神状況(感情の状態)にどうやって適応するかを理解するために、気まぐれで移り気な自然のような心と、心に生起する影響の流れを併合させる必要がある、ということ。
最近感情揺れてたしなあ。本当に。周囲の状況によって。どうしたらいいかわかんなかった。心は移り変わって当たり前なんだから、その流れに身を任せるというか素直になるというか、それをやってみよってことかも。抑えようとしちゃうから。
お次はHEART、5枚。
30. Castles in the Clouds
HEARTは、感情。感情の部分で何を解決すべきか。また、質問者の将来の人生に何が影響してくるかを示す。それでこのカードなの、アツいね!空想、理想よ。それが心の真ん中にあるんよ。
意思のちからによる、より高い達成、発展。心の空に浮かぶ雲の中、高いところに、おとぎ話の城が浮かんでいる。雲は、こうありたいという自分を映し出すスクリーン、城は質問者の望みと吉兆のしるしそのもの。この城は、空想からパワーを引き出して得るという性質を持つ、空を渡る人の家である。このカードは、平凡な俗世に代わる新しい現実をあらわし、城は想像、イマジネーション、精神からできている。 あなたのいちばん深い望みに、意思のちからをもって従いなさい。現実になりつつある内なる欲望を妨げる身体的な怠惰に、決して屈してはならない。あざやかな想像力を示す。heart centerにあるときは、質問の結果として引っ越しがあることが暗示される。空想や想像のちからとともに、行為がなければ達成はないということも覚えておきなさい。今すでにある一つの目標に向かってひたむきに進みなさい。
周りの4枚は、心や感情への影響と捉えることもできるし、3の場所(今回は3. Scarlet Woman)が「意識的な考え」、4の場所(45. Like a Bubble)が「無意識の思考」、9の場所(18. Soma)が「望み」、7の場所(10. Wheel of Great Time)が「自己」をあらわすとしてもよい。
一つ目のペアは、徐々に自我を無くしていく過程において、永遠の、時代を超越するような美を守る、ということに対するバランスの取れた態度。
3. Scarlet Woman 「意識的な考え」
トリニティを司る。活動・不動・柔軟、過去・現在・未来、運命の三つのサイクル。 小さな赤い花たちの向こうから、真紅の女神の大きな黒い目が二つこちらを見ている。地球の豊かさ、肥沃さ、豊穣と、彼女が大きな赤い芥子の花によって結びつけられている。彼女はその姿を通して、女神の性的な側面をあらわす。もうためらう必要はない、実用的な行為によって準備が整い、結果を操縦することができる、ということを強調する。 赤は、自己実現のプロセスにおける、女性的な生のエネルギー(熱と湿気)を象徴する。芥子の花は、女神の子宮が神秘的な招待へと開かれていること。眉間のルビーは、彼女の炎のような超自然的な性質、そして彼女が権威を持っていることを示す。 わたしにとってのシャクティもしくは女性エネルギーの重要性をあらわす。そして、彼女は、世界の神秘的な片割れであるとともに、自己へ帰属しているという、両方を示すしるしである。隠れているにせよ表現されているにせよ、わたしの心にある、感覚からスピリチュアルの領域へと立ちのぼる、強い情熱という性質。これは多分にHeartのカードである。精神的なものと物質的なものの間の不和の解決を象徴し、素晴らしい創造的な成果が、彼女の原型と折り合うことによって得られる。創造的な女性原理。
マジでハートのカード!
これとペアになるのは、斜め上、お向かいの「自己」。
10. Wheel of Great Time 「自己」
ペアとして考えると、「過去・現在・未来」というところが共通しているな。
剣を持つ手は、過去・現在・未来を立ち切り、分けるちからを象徴する。そのほかの二本の手は、血で満たされた頭蓋骨を持っており、同情・自制の統合をあらわしている。炎は、行為の完遂によって過去のカルマが燃え、運命そのものがその姿を変容させることを示す。時計の周りの目や頭骸骨は、死を超えた生の輪廻をあらわす。真ん中の目は全てを見通す目であり、「全て移り変わる」という常に変わらぬ中心があることを思い出させる。火の玉のような二つの目は、宿命と運の世界の流動性と無常を示している。
すべては常に移り変わる。周辺ではなく、中心に集中しなさい。正しい行動によって過去のカルマを燃やし、現在と未来の支配者となりなさい。運命を自分の手の中に取り戻す。
そして次のペア。神秘的な啓蒙に対する魂の傾向と、欲望と対になる知恵を示す。
45. Like a Bubble 「無意識の思考」
自己が世界のものと結びついているという認識への道。女性の頭と胸は、色のついた水から現れ出て見えている。水は世界の物事のさまざまな側面をあらわし、女性は、純粋な意識が上がってくる(あらわれる)ためにはリラックスした態度でいることが必要であることを伝える。蜻蛉の透明な翅は、全ての経験の薄弱な性質、生と死をあらわす。紗のベールは、プールの表面を色づいたように(右の赤)、あるいは泡の表面をチラチラと揺らめかせる(左)幻想である。泡は、壊れやすいが、確かに存在し、そのあ��は無に帰す。「泡のように、夢のように、それが現実だ」。 予断や偏見を手放そう。その自然でオリジナルな性質に、みずからの心を開こう。どんな形にも固着させずに、浮かび流れる喜びと絶頂の瞬間瞬間を大事にしよう。世界に、あるいは色とりどりの現象に執着しないように。これがHeartにある場合、感情を我慢しようと思ってしまう傾向と、ロマンティックな性質が一緒になっているから、信念が必要だ。
18. Soma 「望み」
心の隠された領域からのパワーの認識、それらのパワーを達成のために融合すること。聖なるきのこは、宇宙の明かりの家として描かれており、蒸留した個性のエッセンスの容器である。きのこは、鏡像もしくは影として描かれており、白い氷河のなかで明滅している。この魔法のきのこは、地球圏外のちから、スピリチュアルな悟り、そして隠された知識の領域への通路を開くが、それらは決してその中にはない。このきのこは、ただ通路となるだけ。きのこは触れることのできない、実体がないものの象徴であり、この氷河は、底知れないほど大きな氷山のような集合的無意識、普遍的な心性の、ほんの一角であるように見える。きのこは月の直喩であり、光の反射と知恵の蒸留という性質を示す。きのこは万能薬であり、悟りの味がし、月の知恵の雫。Head centerに位置付けられ、三日月の下の先端から滲み出てぽつりと頭に落ちる雫である。 直観、想像力。知恵は、全ての経験の蒸留物を通して獲得できるということを伝える。夢の世界、幻影や夢のような経験の領域に説得力を持たせる。女性的な直観の知恵(月)を象徴する。チャクラを通るエネルギーの上昇の完了である(上昇したエネルギーが月で冷やされ、それが知恵の雫として頭に落ちてくる、という仕組みなので、もう身体にエネルギーは十分通ってますよの意味なのかも)。
わたしはまさにこういう状態を望んでいるな。ぴんとくる、みたいなのに憧れがある、いいなと思う。チャクラをいい感じに全部通したいからいまどうなってるか知りたいし。
ペアで考えると、感じられないような深いところから、何かが浮かび上がってくる、または落ちてくる、みたいな共通項が感じられる。
次は、THROATです。
54. Asylum
これぱっと見て笑っちゃった。休息のカード。休んでたいのかしら。というかわたしの夢はまさにこういう、のんびりした生活を送ることだからなあ。魔女になって、本を読んだり手紙を書いたり、花を摘んで活けたり庭でお茶会をしたり、草原でピクニックをしたり…… それをやっていきたい。ということで見てみよう解説!
speechのパワーのセンター。創造的な想像力、夢と空想の世界をあらわす。(わお!上で書いたことまんま。いまはまだ空想で夢だもん。)すべての物質が持つ振動というちからと関連している(喉、声も振動でつくられるもんね)。このcenterに置かれたカードは、質問者が好んで居る(精神もしくは身体的な)環境をあらわす。シンボルカラーの明るい青は、すべてに充満する、想像という性質の象徴。そして、このcenterは、知恵と方法の統合という側面を教えてくれる先生あるいはガイドの、平和的なしるし。経験から引き出される知恵と行動を象徴し、特に、「理想」の例、先生、あるいはガイドに関する神秘的な感覚の理解を示す。
イニシエーションの特徴としてのバランス。ユニコーンが木の上に休んで、美しい草原を見渡している。そこは牧歌的かつ神秘的な場所、想像のおとぎ話の地(それはユニコーンが象徴している)。休息し、世界のいたわり、ケアを受け取る。ユニコーンは真実と洞察をあらわし、母なる自然の庭でくつろぎ、完全な平和を感じている。 療養できる安全な場所を見つけ、あまねく心配や懸念から自由になる。想像のパワーを信じて、どんな問題や疑問に関しても、熟考するという立場を取りなさい。直観の純粋なパワーを信頼すれば、迷うことはない。あまねく問題から遠く離れて、ひとりでいるときのウェルビーイングな感じを示している。ポジティヴな状態の神秘的な前兆である。これがThroatにある場合、強い想像の傾向、空想の世界に生きることができる能力、神秘的な経験への導きを示す。
わーーー!うれしい!!!!!ファンシーで生きます。
長かった、最後はHEAD!
4. Hot Seat
かっこいいカード。自分の人生の主人公は自分。自分の椅子に堂々と座りなさいのカード。これが知恵として出ているの、なんだかすごいなあ。
質問に対する最終的な結果、生起したエネルギーの解答、それまでのカードを通して明らかになったことをあらわすcenter。抽出されたエッセンスであり、霊的な達成の錬金薬、神の美酒である冷たい「月の雫」。捜す者、求める者の最も高い望み、結果として生じる成就、実現。二元性の領域を超越した知恵と方法の双方をともに用いることによってもたらされる、精神的、霊的な変容。月、知恵の雫のcenter。
しっかりした基盤と信念に根ざしたより深い自己をあらわす。 この玉座は宇宙にあり、太陽の炎と火の玉に取り囲まれている。玉座の脚にはライオンの顔が彫られており、この位の高い高貴な場所に座る人の、莫大なパワーあるいは大きな権力を象徴する。重大な責任のある立場。玉座から出ている炎は、そこに内在する、とてつもない男性的な変容のパワー。このパワーは、霊的・俗的な権威と関連している。この席は、宇宙の支配者のものである。この地位につく準備ができている者は、十分に仕事を達成していること、そして責任を負う覚悟ができていることが確かでなければならない。 権威ある立場にいること、もしくは、質問者に押し付けられた責任があることをあらわす。緊急に決定がなされなければいけない立場にあり、リーダーシップを取るパワーと内なる信念を要求する。大志の実現の活路、とりわけ権威と権力を示す。より高次の意思のエネルギーで、精神を変容させなさい。
それがあなた自身であり、あなたの道だよ、と言われているみたい。
うわーん長かった。とりあえず終わりました。うおー。後で見返したりしちゃお!
1 note
·
View note
Text
11180143
愛読者が、死んだ。
いや、本当に死んだのかどうかは分からない。が、死んだ、と思うしか、ないのだろう。
そもそも私が小説で脚光を浴びたきっかけは、ある男のルポルタージュを書いたからだった。数多の取材を全て断っていた彼は、なぜか私にだけは心を開いて、全てを話してくれた。だからこそ書けた、そして注目された。
彼は、モラルの欠落した人間だった。善と悪を、その概念から全て捨て去ってしまっていた。人が良いと思うことも、不快に思うことも、彼は理解が出来ず、ただ彼の中のルールを元に生きている、パーソナリティ障害の一種だろうと私は初めて彼に会った時に直感した。
彼は、胸に大きな穴を抱えて、生きていた。無論、それは本当に穴が空いていたわけではないが、彼にとっては本当に穴が空いていて、穴の向こうから人が行き交う景色が見え、空虚、虚無を抱いて生きていた。不思議だ。幻覚、にしては突拍子が無さすぎる。幼い頃にスコンと空いたその穴は成長するごとに広がっていき、穴を埋める為、彼は試行し、画策した。
私が初めて彼に会ったのは、まだ裁判が始まる前のことだった。弁護士すらも遠ざけている、という彼に、私はただ、簡単な挨拶と自己紹介と、そして、「理解しない人間に理解させるため、言葉を紡ぎませんか。」と書き添えて、名刺と共に送付した。
その頃の私は書き殴った小説未満をコンテストに送り付けては、音沙汰のない携帯を握り締め、虚無感溢れる日々をなんとか食い繋いでいた。いわゆる底辺、だ。夢もなく、希望もなく、ただ、人並みの能がこれしかない、と、藁よりも脆い小説に、私は縋っていた。
そんな追い込まれた状況で手を伸ばした先が、極刑は免れないだろう男だったのは、今考えてもなぜなのか、よくわからない。ただ、他の囚人に興味があったわけでもなく、ルポルタージュが書きたかったわけでもなく、ただ、話したい。そう思った。
夏の暑い日のことだった。私の家に届いた茶封筒の中には白無地の紙が一枚入っており、筆圧の無い薄い鉛筆の字で「8月24日に、お待ちしています。」と、ただ一文だけが書き記されていた。
こちらから申し込むのに囚人側から日付を指定してくるなんて、風変わりな男だ。と、私は概要程度しか知らない彼の事件について、一通り知っておこうとパソコンを開いた。
『事件の被疑者、高山一途の家は貧しく、母親は風俗で日銭を稼ぎ、父親は勤めていた会社でトラブルを起こしクビになってからずっと、家で酒を飲んでは暴れる日々だった。怒鳴り声、金切声、過去に高山一家の近所に住んでいた住人は、幾度となく喧嘩の声を聞いていたという。高山は友人のない青春時代を送り、高校を卒業し就職した会社でも活躍することは出来ず、社会から孤立しその精神を捻じ曲げていった。高山は己の不出来を己以外の全てのせいだと責任転嫁し、世間を憎み、全てを恨み、そして凶行に至った。
被害者Aは20xx年8月24日午後11時過ぎ、高山の自宅において後頭部をバールで殴打され殺害。その後、高山により身体をバラバラに解体された後ミンチ状に叩き潰された。発見された段階では、人間だったものとは到底思えず修復不可能なほどだったという。
きっかけは近隣住民からの異臭がするという通報だった。高山は殺害から2週間後、Aさんだった腐肉と室内で戯れている所を発見、逮捕に至る。現場はひどい有り様で、近隣住民の中には体調を崩し救急搬送される者もいた。身体に、腐肉とそこから滲み出る汁を塗りたくっていた高山は抵抗することもなく素直に同行し、Aさん殺害及び死体損壊等の罪を認めた。初公判は※月※日予定。』
いくつも情報を拾っていく中で、私は唐突に、彼の名前の意味について気が付き、���の腕にぞわりと鳥肌が立った。
一途。イット。それ。
あぁ、彼は、ずっと忌み嫌われ、居場所もなくただ産み落とされたという理由で必死に生きてきたんだと、何も知らない私ですら胸が締め付けられる思いがした。私は頭に入れた情報から憶測を全て消し、残った彼の人生のカケラを持って、刑務所へと赴いた。
「こんにちは。」
「こんにちは。」
「失礼します。」
「どうぞ。」
手錠と腰縄を付けて出てきた青年は、私と大して歳の変わらない、人畜無害、悪く言えば何の印象にも残らない、黒髪と、黒曜石のような真っ黒な瞳の持ち主だった。奥深い、どこまでも底のない瞳をつい値踏みするように見てしまって、慌てて促されるままパイプ椅子へと腰掛けた。彼は開口一番、私の書いている小説のことを聞いた。
「何か一つ、話してくれませんか。」
「え、あ、はい、どんな話がお好きですか。」
「貴方が一番好きな話を。」
「分かりました。では、...世界から言葉が消えたなら。」
私の一番気に入っている話、それは、10万字話すと死んでしまう奇病にかかった、愛し合う二人の話。彼は朗読などしたこともない、世に出てすらいない私の拙い小説を、目を細めて静かに聞いていた。最後まで一度も口を挟むことなく聞いているから、読み上げる私も自然と力が入ってしまう。読み終え、余韻と共に顔を上げると、彼はほろほろ、と、目から雫を溢していた。人が泣く姿を、こんなにまじまじと見たのは初めてだった。
「だ、大丈夫ですか、」
「えぇ。ありがとうございます。」
「あの、すみません、どうして私と、会っていただけることになったんでしょうか。」
ふるふる、と犬のように首を振った彼はにこり、と機械的にはにかんで、机に手を置き私を見つめた。かしゃり、と決して軽くない鉄の音が、無機質な部屋に響く。
「僕に大してアクションを起こしてくる人達は皆、同情や好奇心、粗探しと金儲けの匂いがしました。送られてくる手紙は全て下手に出ているようで、僕を品定めするように舐め回してくる文章ばかり。」
「...それは、お察しします。」
「でも、貴方の手紙には、「理解しない人間に理解させるため、言葉を紡ぎませんか。」と書かれていた。面白いな、って思いませんか。」
「何故?」
「だって、貴方、「理解させる」って、僕と同じ目線に立って、物を言ってるでしょう。」
「.........意識、していませんでした。私はただ、憶測が嫌いで、貴方のことを理解したいと、そう思っただけです。」
「また、来てくれますか。」
「勿論。貴方のことを、少しずつでいいので、教えてくれますか。」
「一つ、条件があります。」
「何でしょう。」
「もし本にするなら、僕の言葉じゃなく、貴方の言葉で書いて欲しい。」
そして私は、彼の元へ通うことになった。話を聞けば聞くほど、彼の気持ちが痛いほど分かって、いや、分かっていたのかどうかは分からない。共鳴していただけかもしれない、同情心もあったかもしれない、でも私はただただあくる日も、そのあくる日も、私の言葉で彼を表し続けた。私の記した言葉を聞いて、楽しそうに微笑む彼は、私の言葉を最後まで一度も訂正しなかった。
「貴方はどう思う?僕の、したことについて。」
「...私なら、諦めてしまって、きっと得物を手に取って終わってしまうと思います。最後の最後まで、私が満たされることよりも、世間を気にしてしまう。不幸だと己を憐れんで、見えている答えからは目を背けて、後悔し続けて死ぬことは、きっと貴方の目から見れば不思議に映る、と思います。」
「理性的だけど、道徳的な答えではないね。普通はきっと、「己を満たす為に人を殺すのは躊躇う」って、そう答えるんじゃないかな。」
「でも、乾き続ける己のままで生きることは耐え難い苦痛だった時、己を満たす選択をしたことを、誰が責められるんでしょうか。」
「...貴方に、もう少し早く、出逢いたかった。」
ぽつり、零された言葉と、アクリル板越しに翳された掌。温度が重なることはない。触れ合って、痛みを分かち合うこともない。来園者の真似をする猿のように、彼の手に私の手を合わせて、ただ、じっとその目を見つめた。相変わらず何の感情もない目は、いつもより少しだけ暖かいような、そんな気がした。
彼も、私も、孤独だったのだと、その時初めて気が付いた。世間から隔離され、もしくは自ら距離を置き、人間が信じられず、理解不能な数億もの生き物に囲まれて秩序を保ちながら日々歩かされることに抗えず、翻弄され。きっと彼の胸に空いていた穴は、彼が被害者を殺害し、埋めようと必死に肉塊を塗りたくっていた穴は、彼以外の人間が、もしくは彼が、無意識のうちに彼から抉り取っていった、彼そのものだったのだろう。理解した瞬間止まらなくなった涙を、彼は拭えない。そうだった、最初に私の話で涙した彼の頬を撫でることだって、私には出来なかった。私と彼は、分かり合えたはずなのに、分かり合えない。私の言葉で作り上げた彼は、世間が言う狂人でも可哀想な子でもない、ただ一人の、人間だった。
その数日後、彼が獄中で首を吊ったという報道が流れた時、何となく、そうなるような気がしていて、それでも私は、彼が味わったような、胸に穴が開くような喪失感を抱いた。彼はただ、理解されたかっただけだ。理解のない人間の言葉が、行動が、彼の歩く道を少しずつ曲げていった。
私は書き溜めていた彼の全てを、一冊の本にした。本のタイトルは、「今日も、皮肉なほど空は青い。」。逮捕された彼が手錠をかけられた時、部屋のカーテンの隙間から空が見えた、と言っていた。ぴっちり閉じていたはずなのに、その時だけひらりと翻った暗赤色のカーテンの間から顔を覗かせた青は、目に刺さって痛いほど、青かった、と。
出版社は皆、猟奇的殺人犯のノンフィクションを出版したい、と食い付いた。帯に著名人の寒気がする言葉も書かれた。私の名前も大々的に張り出され、重版が決定し、至る所で賛否両論が巻き起こった。被害者の遺族は怒りを露わにし、会見で私と、彼に対しての呪詛をぶちまけた。
インタビュー、取材、関わってくる人間の全てを私は拒否して、来る日も来る日も、読者から届く手紙、メール、SNS上に散乱する、本の感想を読み漁り続けた。
そこに、私の望むものは何もなかった。
『あなたは犯罪者に対して同情を誘いたいんですか?』
私がいつ、どこに、彼を可哀想だと記したのだろう。
『犯罪者を擁護したいのですか?理解出来ません。彼は人を殺したんですよ。』
彼は許されるべきだとも、悪くない、とも私は書いていない。彼は素直に逮捕され、正式な処罰ではないが、命をもって罪へ対応した。これ以上、何をしろ、と言うのだろう。彼が跪き頭を地面に擦り付け、涙ながらに謝罪する所を見たかったのだろうか。
『とても面白かったです。狂人の世界が何となく理解出来ました。』
何をどう理解したら、この感想が浮かぶのだろう。そもそもこの人は、私の本を読んだのだろうか。
『作者はもしかしたら接していくうちに、高山を愛してしまったのではないか?贔屓目の文章は公平ではなく気持ちが悪い。』
『全てを人のせいにして自分が悪くないと喚く子供に殺された方が哀れでならない。』
『結局人殺しの自己正当化本。それに手を貸した筆者も同罪。裁かれろ。』
『ただただ不快。皆寂しかったり、一人になる瞬間はある。自分だけが苦しい、と言わんばかりの態度に腹が立つ。』
『いくら貰えるんだろうなぁ筆者。羨ましいぜ、人殺しのキチガイの本書いて金貰えるなんて。』
私は、とても愚かだったのだと気付かされた。
皆に理解させよう、などと宣って、彼を、私の言葉で形作ったこと。裏を返せば、その行為は、言葉を尽くせば理解される、と、人間に期待をしていたに他ならない。
私は、彼によって得たわずかな幸福よりも、その後に押し寄せてくる大きな悲しみ、不幸がどうしようもなく耐え難く、心底、己が哀れだった。
胸に穴が空いている、と言う幻覚を見続けた彼は、穴が塞がりそうになるたび、そしてまた無機質な空虚に戻るたび、こんな痛みを感じていたのだろうか。
私は毎日、感想を読み続けた。貰った手紙は、読んだものから燃やしていった。他者に理解される、ということが、どれほど難しいのかを、思い知った。言葉を紡ぐことが怖くなり、彼を理解した私ですら、疑わしく、かといって己と論争するほどの気力はなく、ただ、この世に私以外の、彼の理解者は現れず、唯一の彼の理解者はここにいても、もう彼の話に相槌を打つことは叶わず、陰鬱とする思考の暗闇の中を、堂々巡りしていた。
思考を持つ植物になりたい、と、ずっと思っていた。人間は考える葦である、という言葉が皮肉に聞こえるほど、私はただ、一人で、誰の脳にも引っ掛からず、狭間を生きていた。
孤独、などという言葉で表すのは烏滸がましいほど、私、彼が抱えるソレは哀しく、決して治らない不治の病のようなものだった。私は彼であり、彼は私だった。同じ境遇、というわけではない。赤の他人。彼には守るべき己の秩序があり、私にはそんな誇り高いものすらなく、能動的、怠惰に流されて生きていた。
彼は、目の前にいた人間の頭にバールを振り下ろす瞬間も、身体をミンチにする工程も、全て正気だった。ただ心の中に一つだけ、それをしなければ、生きているのが恐ろしい、今しなければずっと後悔し続ける、胸を掻きむしり大声を上げて暴れたくなるような焦燥感、漠然とした不安感、それらをごちゃ混ぜにした感情、抗えない欲求のようなものが湧き上がってきた、と話していた。上手く呼吸が出来なくなる感覚、と言われて、思わず己の胸を抑えた記憶が懐かしい。
出版から3ヶ月、私は感想を読むのをやめた。人間がもっと憎らしく、恐ろしく、嫌いになった。彼が褒めてくれた、利己的な幸せの話を追い求めよう。そう決めた。私の秩序は、小説を書き続けること。嗚呼と叫ぶ声を、流れた血を、光のない部屋を、全てを飲み込む黒を文字に乗せて、上手く呼吸すること。
出版社は、どこも私の名前を見た瞬間、原稿を送り返し、もしくは廃棄した。『君も人殺したんでしょ?なんだか噂で聞いたよ。』『よくうちで本出せると思ったね、君、自分がしたこと忘れたの?』『無理ですね。会社潰したくないので。』『女ならまだ赤裸々なセックスエッセイでも書かせてやれるけど、男じゃ使えないよ、いらない。』数多の断り文句は見事に各社で違うもので、私は感嘆すると共に、人間がまた嫌いになった。彼が乗せてくれたから、私の言葉が輝いていたのだと痛感した。きっとあの本は、ノンフィクション、ルポルタージュじゃなくても、きっと人の心に突き刺さったはずだと、そう思わずにはいられなかった。
以前に働いていた会社は、ルポの出版の直前に辞表を出した。私がいなくても、普段通り世界は回る。著者の実物を狂ったように探し回っていた人間も、見つからないと分かるや否や他の叩く対象を見つけ、そちらで楽しんでいるようだった。私の書いた彼の本は、悪趣味な三流ルポ、と呼ばれた。貯金は底を尽きた。手当たり次第応募して見つけた仕事で、小銭を稼いだ。家賃と、食事に使えばもう残りは硬貨しか残らない、そんな生活になった。元より、彼の本によって得た利益は、全て燃やしてしまっていた。それが、正しい末路だと思ったからだったが、何故と言われれば説明は出来ない。ただ燃えて、真っ赤になった札が灰白色に色褪せ、風に脆く崩れていく姿を見て、幸せそうだと、そう思った。
名前を伏せ、webサイトで小説を投稿し始めた。アクセス数も、いいね!も、どうでも良かった。私はただ秩序を保つために書き、顎を上げて、夜店の金魚のように、浅い水槽の中で居場所なく肩を縮めながら、ただ、遥か遠くにある空を眺めては、届くはずもない鰭を伸ばした。
ある日、web上のダイレクトメールに一件のメッセージが入った。非難か、批評か、スパムか。開いた画面には文字がつらつらと記されていた。
『貴方の本を、販売当時に読みました。明記はされていませんが、某殺人事件のルポを書かれていた方ですか?文体が、似ていたのでもし勘違いであれば、すみません。』
断言するように言い当てられたのは初めてだったが、画面をスクロールする指はもう今更震えない。
『最新作、読みました。とても...哀しい話でした。ゾンビ、なんてコミカルなテーマなのに、貴方はコメをトラにしてしまう才能があるんでしょうね。悲劇。ただ、二人が次の世界で、二人の望む幸せを得られることを祈りたくなる、そんな話でした。過去作も、全て読みました。目を覆いたくなるリアルな描写も、抽象的なのに五感のどこかに優しく触れるような比喩も、とても素敵です。これからも、書いてください。』
コメとトラ。私が太宰の「人間失格」を好きな事は当然知らないだろうに、不思議と親近感が湧いた。単純だ。と少し笑ってから、私はその奇特な人間に一言、返信した。
『私のルポルタージュを読んで、どう思われましたか。』
無名の人間、それも、ファンタジーやラブコメがランキング上位を占めるwebにおいて、埋もれに埋もれていた私を見つけた人。だからこそ聞きたかった。例えどんな答えが返ってきても構わなかった。もう、罵詈雑言には慣れていた。
数日後、通知音に誘われて開いたDMには、前回よりも短い感想が送られてきていた。
『人を殺めた事実を別にすれば、私は少しだけ、彼の気持ちを理解出来る気がしました。。彼の抱いていた底なしの虚無感が見せた胸の穴も、それを埋めようと無意識のうちに焦がれていたものがやっと現れた時の衝動。共感は微塵も出来ないが、全く理解が出来ない化け物でも狂人でもない、赤色を見て赤色だと思う一人の人間だと思いました。』
何度も読み返していると、もう1通、メッセージが来た。惜しみながらも画面をスクロールする。
『もう一度読み直して、感想を考えました。外野からどうこう言えるほど、彼を軽んじることが出来ませんでした。良い悪いは、彼の起こした行動に対してであれば悪で、それを彼は自死という形で償った。彼の思考について善悪を語れるのは、本人だけ。』
私は、画面の向こうに現れた人間に、頭を下げた。見えるはずもない。自己満足だ。そう知りながらも、下げずにはいられなかった。彼を、私を、理解してくれてありがとう。それが、私が愛読者と出会った瞬間だった。
愛読者は、どうやら私の作風をいたく気に入ったらしかった。あれやこれや、私の言葉で色んな世界を見てみたい、と強請った。その様子はどこか彼にも似ている気がして、私は愛読者の望むまま、数多の世界を創造した。いっそう創作は捗った。愛読者以外の人間は、ろくに寄り付かずたまに冷やかす輩が現れる程度で、私の言葉は、世間には刺さらない。
まるで神にでもなった気分だった。初めて小説を書いた時、私の指先一つで、人が自由に動き、話し、歩き、生きて、死ぬ。理想の愛を作り上げることも、到底現実世界では幸せになれない人を幸せにすることも、なんでも出来た。幸福のシロップが私の脳のタンパク質にじゅわじゅわと染みていって、甘ったるいスポンジになって、溢れ出すのは快楽物質。
そう、私は神になった。上から下界を見下ろし、手に持った無数の糸を引いて切って繋いでダンス。鼻歌まじりに踊るはワルツ。喜悲劇とも呼べるその一人芝居を、私はただ、演じた。
世の偉いベストセラー作家も、私の敬愛する文豪も、ポエムを垂れ流す病んだSNSの住人も、暗闇の中で自慰じみた創作をして死んでいく私も、きっと書く理由なんて、ただ楽しくて気持ちいいから。それに尽きるような気がする。
愛読者は私の思考をよく理解し、ただモラルのない行為にはノーを突きつけ、感想を欠かさずくれた。楽しかった。アクリルの向こうで私の話を聞いていた彼は、感想を口にすることはなかった。核心を突き、時に厳しい指摘をし、それでも全ての登場人物に対して寄り添い、「理解」してくれた。行動の理由を、言動の意味を、目線の行く先を、彼らの見る世界を。
一人で歩いていた暗い世界に、ぽつり、ぽつりと街灯が灯っていく、そんな感覚。じわりじわり暖かくなる肌触りのいい空気が私を包んで、私は初めて、人と共有することの幸せを味わった。不変を自分以外に見出し、脳内を共鳴させることの価値を知った。
幸せは麻薬だ、とかの人が説く。0の状態から1の幸せを得た人間は、気付いた頃にはその1を見失う。10の幸せがないと、幸せを感じなくなる。人間は1の幸せを持っていても、0の時よりも、不幸に感じる。幸福感という魔物に侵され支配されてしまった哀れな脳が見せる、もっと大きな、訪れるはずと信じて疑わない幻影の幸せ。
私はさしずめ、来るはずのプレゼントを玄関先でそわそわと待つ少女のように無垢で、そして、馬鹿だった。無知ゆえの、無垢の信頼ゆえの、馬鹿。救えない。
愛読者は姿を消した。ある日話を更新した私のDMは、いつまで経っても鳴らなかった。震える手で押した愛読者のアカウントは消えていた。私はその時初めて、愛読者の名前も顔も性別も、何もかもを知らないことに気が付いた。遅すぎた、否、知っていたところで何が出来たのだろう。私はただ、愛読者から感想という自己顕示欲を満たせる砂糖を注がれ続けて、その甘さに耽溺していた白痴の蟻だったのに。並ぶ言葉がざらざらと、砂時計の砂の如く崩れて床に散らばっていく幻覚が見えて、私は端末を放り投げ、野良猫を落ち着かせるように布団を被り、何がいけなかったのかをひとしきり考え、そして、やめた。
人間は、皆、勝手だ。何故か。皆、自分が大事だからだ。誰も守ってくれない己を守るため、生きるため、人は必死に崖を這い上がって、その途中で崖にしがみつく他者の手を足場にしていたとしても、気付く術はない。
愛読者は何も悪くない。これは、人間に期待し、信用という目に見えない清らかな物を崇拝し、焦がれ、浅はかにも己の手の中に得られると勘違いし小躍りした、道化師の喜劇だ。
愛読者は今日も、どこかで息をして、空を見上げているのだろうか。彼が亡くなった時と同じ感覚を抱いていた。彼が最後に見た澄んだ空。私が、諦観し絶望しながらも、明日も見るであろう狭い空。人生には不幸も幸せもなく、ただいっさいがすぎていく、そう言った27歳の太宰の言葉が、彼の年に近付いてからやっと分かるようになった。そう、人が生きる、ということに、最初から大して意味はない。今、人間がヒエラルキーの頂点に君臨し、80億弱もひしめき合って睨み合って生きていることにも、意味はない。ただ、そうあったから。
愛読者が消えた意味も、彼が自ら命を絶った理由も、考えるのをやめよう。と思った。呼吸代わりに、ある種の強迫観念に基づいて狂ったように綴っていた世界も、閉じたところで私は死なないし、私は死ぬ。最早私が今こうして生きているのも、植物状態で眠る私の見ている長い長い夢かもしれない。
私は思考を捨て、人でいることをやめた。
途端に、世界が輝きだした。全てが美しく見える。私が今ここにあることが、何よりも楽しく、笑いが止まらない。鉄線入りの窓ガラスが、かの大聖堂のステンドグラスよりも耽美に見える。
太宰先生、貴方はきっと思考を続けたから、あんな話を書いたのよ。私、今、そこかしこに檸檬を置いて回りたいほど愉快。
これがきっと、幸せ。って呼ぶのね。
愛読者は死んだ。もう戻らない。私の世界と共に死んだ、と思っていたが、元から生きても死んでもいなかった。否、生きていて、死んでいた。シュレディンガーの猫だ。
「嗚呼、私、やっぱり、
7 notes
·
View notes
Text
『心射方位図の赤道で待ってる』読書会レジュメ
この記事について
この記事は、文芸同人・ねじれ双角錐群が、2019年の第二十九回文学フリマ東京にて発表した第四小説誌『心射方位図の赤道で待ってる』について、文学フリマでの発表を前に同人メンバーにて実施した読書会のレジュメを公開するものである。メンバーは、事前に共有編集状態のレジュメに��由に感想や意見を書き込み合った上で読書会を実施した。読書会当日の熱気は残念ながらお伝えできないものの、レジュメには各作品を楽しむための観点がちりばめられているように思われる。『心射方位図の赤道で待ってる』読者の方に少しでもお楽しみいただけたならば幸いである。

『心射方位図の赤道で待ってる』についてはこちら
神の裁きと訣別するため
一言感想
実質まちカドまぞく
岸部露伴とジャンケン小僧的な
サウダージを感じる
むらしっと文体はミクロとマクロをシームレスに語るのに向いている、というか何を書いても神話っぽい感じがする。神待ちという地獄に誘う詩人ウェルギリウス的なポジとして冒頭に置かれているのがとてもいい。読者は思わず一切の望みを捨ててしまうだろう
いつもよりむずかしくなくて(?)そのぶんむらしっと文体の魅力に意識を割いて読めた
一読した印象として、古川日出男っぽいなというのがあった
完全なグー まったき真球〜チョキまでのくだり、かっこよさの最大瞬間風速
細部
箇条書きって進むポイントというか切れ目が明確? みたいな感じはあって、ノベルゲー(いや別にノベルゲーでなくても良い。ゲームで)で次のテキストに進むために決定ボタンを押すじゃないですか。なんかそういう感覚がある。箇条書きが一つ一つ切れていることが。
連打していく感じになる
それが後半で長いのがでてきたときに効いてくる
あとなんか連打のだるさみたいなのがあるじゃないですか? 別に箇条書きじゃなくてつながってるのと負荷変わってないはずなのに。ゲームもつながった文章を読むのと変わらんはずだが決定ボタンを押すリズムがこう負荷を作ってるよな。
上記は箇条書きがあげている効果について書いたんだけれども、そもそもどうしてこの作品は箇条書きなんだろうか? その意図というか、狙ったことがあるんだろうか? そこまでないにしてもなぜ箇条書きにしようと思ったんだろうか?
●のシーン。ナツキ(本田圭佑)が導入されてじゃんけんの話をしてこの時点でギミックと言うか、じゃんけん強いというのが、すでに引き込む力がある。じゃんけんからの視点の飛躍、特に蝉が木から落ちる下りで「次の年」っていきなりなるのは良いなと思った。
池袋西口、昔のおとぎ話、宇宙、キムチチャーハン、みたいな、遠近が入り乱れている世界観に特色がある気がする
★の家族のところが印象強くて、いたりいなかったりする兄とか、石を食べて予言をする姉っていうのが、マジックリアリズムな感じもありつつ、グラース家的なイメージも感じたりした。
▲のところで、つまり地の文のまなざしは父性だったということになるんだけど(実質)、それが変質していくというか、悪夢が変形する感じがちょっとあって。おとぎ話はグイグイ来て良い。
じゃんけんに関する要素が入れ子みたいになっている
完全なグー、外界を寄せ付けない孤独の象徴
P16「完全なグーについて」「ナツキの孤独について」で、ナツキがじゃんけんに絶対に勝ってしまい疎まれることが語られる。孤独。
●の部分がグーということなんだろうけど、ここでナンパの男にじゃんけんで勝ち続けて気味悪がられるナツキの孤独が語られている
完全なパー、記録すなわち過去の象徴
P18「完全なパーについて」「ナツキの記憶について」で、ナツキ(というより、「ぼく」)のナツキのはじめてのじゃんけんの記憶が語られる。
★の部分が(この完全なグーチョキパーを語っているところを含めて)ナツキの過去を語っており全体が記録、過去になっている
完全なチョキ、繋がりを切断する、他者との関係の象徴
P21「完全なチョキについて」ここはグーとパーと異なり「ナツキの●●について」という言葉は続かないんだけど、他者との関係、そしてそのつながりの切断についてということになるんだろう。家族のことが語られる
▲の部分が、逆に★の部分で語られなかった相手である「ぼく」、父親との関係とその断絶になっている
P21ではじめてのじゃんけんでナツキに無意識に出された手が、完全なチョキであったことの意味を噛みしめてる感
我が子に関係を「切断」されたということを否定したくて(その完全性を壊したくて)、躍起になったのかな
ところどころナツキが負けたがっていることを知っている描写があり、自分がナツキの完全性を否定することが彼女の救いになることもわかっているはずだ
でもなんか挑発的だし、やっぱり負けたのがすごく悔しかったのかもしれない
官吏(仮)も天体望遠鏡の順番決めでじゃんけんをしていた。むしろじゃんけんのほうをたのしみにしているようにも読める(P14)。
父もナツキに負けたことで、宇宙をいくつかまわって再び勝負をしかけるくらい入れ込んでいた。
父も実はじゃんけん自信ニキだった?
本田圭佑vs本田圭佑
全然関係ないが、じゃんけんする人の国民的ポジションを一瞬で本田圭佑がサザエさんから奪い去ったのすごいな
自信ニキにしてはパー(過去)を出すのにも「失敗したキムチチャーハン」で負けるあたり、舐めていたのか、地力が低かったのか、ナツキが強すぎたのか。
父は抱きしめてやるべきだったんだよこれ。
おとぎ話、これなんなんだ?
最強の手「グーチョキパー」と、官吏が囚人とのじゃんけんで出した手が官吏にしか分からない(グーとチョキとパーいずれかを事後報告できる)ということは、似ている
並行宇宙の話をしてたから、つまり重ね合わせの状態の手を出しているということか(???)
どの宇宙でも勝つように収束する
やけに星がよく見える池袋でナツキたちのちょうど反対側にいた男の故郷(この国でいっとう星がよく見える土地)と、官吏の故郷(星がいっとうよく見える土地というのがこの世界にはある。おれの故郷はそんな場所の一つだ)の類似
わからん。もう少し考えたい
それはちょっと意識してるのかなーとおもったけど、おもったけど、その先がわからなかったな
よく側を通り過ぎている女二人は官吏の妻と、彼女と密会していた女っぽい(P33)?
あの二人はなんか意味はありそうなんだけど、そうなんですかね? なんか手がかりある?
そもそも官吏の妻が密会していた女っていうのがよくわからん。p33「隣の独り身の女と、三日にいっぺんは会っていた」も最初は読み方がわからないというか、男の誤記か、会っていたの主語は官吏の方かとか考えてしまったから、でもここでその目立つ書き方をしているってことは、通り過ぎている女二人なのかもしれないな、必然性があるはずだと考えるならば。
「~しあわせな結末が待っている/そのまえにすこしだけの試練~(P12)」「おれの女房が、じつはおれのことを好いていない~(P33)」
同性愛で、片方には少なくとも家庭があり云々っていう話で素朴に読んでました。おとぎ話と「現実」が地続きなことを示唆する描写っぽいけど、地続きだとしてどういうことになるのかはまだよくわかりません。
反対側に官吏(仮)がいるので、当然彼女たちのことも見かけているはずだけど、そういうところには踏み込んでいない。
「塔のまわりをぐるぐる回るわたしにまとわりついて、しゃべりはじめた(P30, L9)」
ナツキの父の一人称は「わたし」じゃなくて「ぼく」
ここの「わたし」が「ぼく」の誤りだったら、「実は父の回想でした」筋が通る気がするんだけど
だとしたら反対側にいる男がおとぎ話の官吏で、囚人がナツキの父親なら、ふたりともここにいる/そこにいないのはどういうことかってなるし
おとぎ話パートに一人称が出てきてもなんらおかしくないという当たり前の結論に達した
これがただのおとぎ話だとしたらやっぱり、上記の類似はなに?ってなるな
「官吏のいかさま/それを覆す方法」のどちらかが、ナツキに「勝てる方法(P30, L2)」と対応する?
「つまらない方法」でも「教訓がない」と強調されている
P16で完全なグーチョキパーと「昨日見た夢」が並列に扱われている
おとぎ話との関係ありそうか?
最後のじゃんけんのところ
「親指をひろげて」「人差し指をひろげて」「中指をひろげて」「薬指をとじて」「小指をとじて」なんかじゃんけんの最強の裏の手みたいなやつか?
『ラッキーマン』で勝利マンがじゃんけんで出す最強の手「グーチョキパー」の印象が強かったので読みながらウフフとなった
指を家族にたとえる歌「おはなしゆびさん」
「中指をひろげて おにいさんゆび」って言ってるけどこの宇宙には、もうおにいさんは「すでにいない(P22)」はず
ナツキはおにいさんが「すでにいない」ことを知らないのか
「だからおおむね、いるのだといっていいのだろう(P22)」で解決か
小指=あかちゃんゆび=ナツキ自身
「わたしはもういなくなるから」の意味とは?
めっちゃかっこいいんだが、なんで勝つと神の不在を証明できるんだ?
自分を負かす存在を待っている→やってきた男に勝つ、という構図で、テーマが神待ちだから?
(1)完全性の自覚を打ち砕いてくれるくらい完全なもの(神)に出会いたい→満を持して史上最も期待できそうなやつ(父)が現れるが、勝ってしまう→神の不在に感じ入る
(2)「勝てる方法」を使用してくる父に勝つには「最強の手」を使うしかない→勝つために「最強の手」を使った自分は完全ではなくなった→「じゃんけんの神」であるナツキはいなくなった。(※「最強の手」には完全性が宿らないという前提)
後者だと「わたしはもういなくなるから」に若干繋がりそうな気配があるが……。
「気に入らない男だけれど、負けるのはほんとうらしい(P30)」
���は勝ってないけど負けることによって勝利しているとかそういう話の可能性は、ないか。
なにもわからなくなってきた。
最後のビュレットがないことの意図
ここまでの文が全部、ナツキが最後に出した「最強の手」の動線ってことなのか。
山の神さん
一言感想
広瀬の(声 - 小野大輔)感
笹さんは本当にエッチな男だなあ
広瀬の絶妙なすけべ感がすごいいいんだよな
舞台が大正時代なのもあって、なんとなく森見登美彦風味も感じた
実質ヤマノススメ
過去と未来、機械と人が「重なって」ゆき止揚される様がいい。
私は毎回打倒笹さんを目指してカワイイ女の子を描こうと四苦八苦しているのだが、そんな私の苦闘を尻目に笹さんは毎回さらりと可憐な少女を書いてしまう。私がシャミ子なら笹さんはさながらちよももといえるのではないか? この観点からね群とまちカドまぞくの類似点について指摘したい。
ね群とまちカドまぞくの類似点について指摘するのはやめろ
おもしろい小説を書くのってむずかしい(今回なぜかとくに思った)んだけど(隙自語)笹さんはすごいよ
時代は姉SF
対比的な文体芸が楽しい
ちゃんとそれぞれの文体の思考法でおのおのの結論に至るという意味での必然性もあり
短文が素打ちされていき、隙間にとぼけた感じが挟まれるこの手の文章が自分は好きなんだよなと思った。というか、思えるくらいに自然でうまいというのがある
p58で一瞬ネタにして明示してくれるの親切というか、やっぱりそうなんだ!っていううれしさがあり、かといってそれ以上しつこくネタにしない慎み深さがある
「機械の身体」にたいする各々の対照的な考えが、登山という身体性をともなう行為によって止揚される云々!テーマの消化のしかたがきれい
おれは登山をしたことはほとんどないが……
とまれ、こういう短いキャッチフレーズにまとめられるくらいの主題があるのは大事だよなあといつも思うんですよね……
会話が四コマ漫画を連想させてまんがタイムきららだろ、これ。
意識して読んだらマジでまんがタイムきららが脳内展開された。
ドキドキビジュアルコミックス
SF的な設定について
ものすごく複雑なことをしてるわけでもないと思うんだけど、人間と機械のきょうだいってのはちょっといろいろ考えがいがありそうなんだよな
血縁がないにもかかわらず姉妹を擬制するというのはひとつの伝統なので……
義姉妹の約を結んだのか……
単純にスペア的な存在のような気が(名前が神籬だし)
医王山登りたいな
プロットで動機や結末などを「重すぎず、軽すぎず」っていう思案してたっぽいけど、それがちゃんと活かされててよいな。
細部
大正15年、大正デモクラシーの流れで前年に男子普通選挙法、昭和が目前、世界恐慌前だしそんな世情はギスギスしてない感じだろうか。張作霖爆殺が昭和3年とかなので徐々に種が撒かれてた感もあるか
舞台は金沢らしい。旧制高校のエリートである
転移時の文章のくずれのかっこよさ、これなにか書くコツとかあるのかな……
実質パプリカ(映画)なんだよな
今敏監督で映画化だ
p52で先を歩かせてるときにスカートがちらちらするのぜったい気にしとるやろがそれを明らかにせず別の理由をつけるあたりのむっつり感
「まったく許しがたいことだ」じゃあないんだよ
p.72「広瀬は次に登る山のことを考え始めた」の爽快感がすごくよかった。
でもじつは神籬のことをめっちゃ考えてたんだけど、私小説的な照れ隠しでこの書きっぷりだった可能性もあるな
エピローグ(p.72の※以降)で広瀬たちと神籬の後日談があることが最高の読後感を提供してくるんだよな
囚獄啓き
一言感想
夜ごと街を走って体力を高めるの草
え、なんで妻は罪を犯したの?
愛だ。小林さんは愛の輪郭線をたどることで愛を浮かびあがらせるのが巧い。直江兼続の兜を想起させる。そして銀河犬が気になる。
いつもよりギュッとしてる
ぼくも同じ印象を持って、最初は漢字のとじひらきがかなり過剰に閉じ寄りになってるからかなと思ったんだけど、むしろいつもより地の文が多く、強めの短文を連打してるからなのかな
どこかに魚が出てくるかなと思ったけど、なかった
ところどころに小林さんの昏い性癖が出てる気がします
冒頭にある「地獄とは心の在り方ではないか」がポイントなんすかね
平等な地獄を作ったはずの主人公が、また別の、その人固有でしかありえない、妻の不在という地獄に……という、やっぱ愛か……
刑罰ってのがそもそも歴史がありその意義などいろいろな話があり現代に照らし返せるものの多い、したがって近未来の世界の「当たり前」がどうなっているかを描くまっとうなSFに向くテーマで、そのへんを上記の愛の話のもう片手として簡潔にまとめてるので、SF!って感じがするのだよな
理屈づけのおもしろさで魅せてく鴻上さんのとか、未来ならではの思索で魅せてく笹さんやばななさんのとあわせて、SFらしさのバリエーションがでてると思う
初読時には時系列というかエピソード間の間隔のことあんま意識して読んでなかったんだけど、妻が事件を起こしてから刑を執行されるまでにけっこう時間が経ってるのがわかって、なかなか大変やなというきもちになった
と言いつつ実はちょっとわかってないんですが、二人称で語られる断章は(多少その前な箇所もあるとして、おおむね)妻が捕まって以降の話ということでいいのかな?p85の妻への言及とかも相まって自信がないんですが
そもそもそのへんの語り全体が妻の見ている地獄という解釈もあるんだろうけど……(でないとなんで語り手がこんな詳らかに知ってるのかが説明できないというのもあり)
「牛乳を含んだ雑巾」みたいな独特の比喩から小林節を感じる。
SFってガジェット自体の新規性や利便性から話の筋を作るというのもあるんだけど、そういう未来を描くことで(かえってその迂回が)現在に通用する倫理とか問題意識を切実にさせる側面もあるんじゃないか、みたいなこと考えることがあり、これはすごくそれよりな感じがします(感の想)。時代によらず共感しうるものだったり、いま揺れている倫理に地続きの問いだったりが中心に据えられている。んじゃなかろうか。
「あなた」の作る地獄(への道)を「無関心」で舗装していたのは、むしろ妻のほうか(P79の後ろからL5、あるいは全体に漂うフラットな語り口から)? 舗装、とは言い得て妙かもしれない。その下に押しつぶされているもののほうをこそ俺はなんとなく想像してしまう。
妻の犯した過ちには子供の死と、ひょっとしたら、球獄とそれを取り巻く感情が関係している。いる?
平等であるというのは、ある意味残酷なことだ。だからこそふさわしいのだろう。意思が介入せず、全くぶれない罰を与える球獄だからこそ、罪の清算(救済)が可能である。それがどんなに償い難い罪だろうと、いやむしろ償い難いものであるほどそう感じられるのかもしれない。「あなた」による偏執的な研究の日々の傍で失われていったものがあるならば、それらの重さは球獄という完全性への期待に加担する。その信仰は、妻の中にも「あなた」の中にも、いつからかあるはずだ。
「神待ち」に関して
これから堕ちる地獄(世界)の創造主(=神)に「そこで待っている」という発言をしたことが、テーマに沿っている気がしたんだけど、どうなんだろう。
こういう発言にも妻の「あなた」への共犯意識が垣間見れるし、なんかやっぱり妻の罪の動機と球獄の製作って関わってるよね。そこをあえてすっぽり省いてる気がして。
脳波の逆位相を……という発想がよく考えたみたらどういうことだってところではあるんだけど、とくに瑕疵にらなないのはいいなというのがある
性的快感の逆位相=性的快感以外のすべてがある
妻がいない世界に生きる「あなた」=妻以外のすべてがある世界に生きる「あなた」
ということで、妻の地獄と、それ以降の「あなた」の生活は相似しており、このことがp.90「僕たちは二人並んで閻魔様に裁かれて、それから長い長い地獄に落ちるんだ」に繋がるところがうまいと思った。
細部
終盤で語り手が妻だとわかるみたいな仕掛けはやっぱりグッときちゃうんだよな
p80 パパ活やってて喫茶店のスティックシュガーパクる?と思って笑ってしまった
p81 京文線、なぜか印象に残る。急に架空の(だよな?)固有名詞が差し込まれるのが異質っぽいのかな?(ワイン、とか、省、とか、固有名詞が割と排除されている空気の中で)
「顔が見えていても私はいいんだけどね」「また来ても良い?」普通は、三倍払うと言われてそれに釣られてやってきた女は、こんな好意的な反応を返さない���ろうから、そこに都合の良さという��、あるいは記録者による逆のバイアスがあるのかなとか思ったりする
p82「再び端末のキーを押下」エンジニアしぐさ
p84「君の身勝手な自棄で何人の未来を奪ったんだ」なにやらかしたの?
p.86「銀河犬」「(おばあちゃん)その辺で見ませんでしたか?」の台詞がすごく好き。小林さんは一作目からこの手のシュールさを志向している印象がある
記録の語り手が妻っていうのはなるほどねと思った
p.85「それから数年にわたって女はあなたの研究室に通い続けた」以降は、妻が罪を犯した後?
p.88「語りが過ぎた。ここで記録は結ばれ、以降は記録ではなく〜」記録3の後の最後の断章は、妻が地獄執行される場面であり、妻はその場面の記録を執筆できないということを意味している
p.89「私の心は現在どのレイヤーにあるのだろうか。」レイヤー?わからなかった
杞憂
一言感想
中盤からの加速感
これ絶対あれだろと思って読んでたのにやられた
デジタルタトゥーとかそういう意味じゃないけどわかる単語がずるいよな
インディアンのネーミングについて調べてしまった(おもしろい)
この手の一般名詞(?)をそのまま訳して名前として表すやつがなんか知らんが妙に好きなんだよな
ナツメもライチも中国原産っぽい?
原産というか縁がありそう
両方とも滋養強壮できるらしい
ちゃんと資料にあたり、ネイティブアメリカンの習俗とかJKリフレの店内の様子とかそういう細かいところをしっかりさせてて、小説の足腰ができている、見習いたいんだ……おれは……神は細部に……
SF的な理屈をいかに飽きさせずに読ませるかってところで、JKリフレとの強引な対応関係をつくる手つきがすげえ上手いんだよな
馴染みのある語彙に変な言葉を紛れさせて地の文で展開する、みたいな
オーバーロードが中年男性に……(さらにはそれがエルクに……)っていう絵面的なおもしろさと設定的な必然性を両立してるのとか、漫才っぽいプレイの流れのなかでちゃんと話進めるところとか
文化盗用とかアーミッシュへの皮肉っぽい視線みたいなのは前回の感動ポルノに通じるところあるよな
バトルシーンの手の込みようとおっぱいで窒息するくだらなさの融合だけで“勝ち”なんだよな……
もしかしてこれをやりたいがためにここまでの全部を作り込んできてないか!?!?!?
古事成語オチをつけてなんかやっぱネイティブアメリカンの伝承の話だった?みたいにするふざけかたも好き
あ、ここから怒涛のあれが来るんだって予感でわくわくしてやはり来て、凄かった。
SF的な設定、未来の世界での娯楽・趣味的的な観点がけっこうよくて
意図されたであろう魅力が初読で存分に伝わるつくりで、かつ細部に注目する部分がたくさん残されているのがめちゃくちゃつよい。
人物やガジェットのネーミング、その他取り扱われている文化へのリスペクトなど。
細部
p97「俺たちの世界の理にして〜」、読み返してみると、焼き脛は序盤からちゃんとわかって言ってんだな……
侍ミーて
「ひょっとするとお忍びで欲望を満たしにきた元老院議員の可能性さえある。」ここクソ笑うんだよな。千と千尋のあれかよ。
「あれこれ無駄な心配をする痴れ者をさして杞憂と呼ぶ習慣」これ文脈的に杞憂じゃなくてマウンティングベアって呼ばれるんじゃないの??
なんか笑った
略されて使用されていくうちに逸れていく、みたいな、なんかそういう言葉いくつかある気がする。いまは思いつかないけど
用語について調べて/考えてみる
赫の終端(レッドコーダ):ハンドラ族の長
赫は赤いこと、勢いが盛んであること。コーダは音楽で終わるあれ。なので日本語とルビは直訳的に対応しているっぽい。レッドコーダーだと、競技プログラミングのあれになる。プログラミング力が高いから長なのか?
ポアソンの分霊獣
ポアソン:名前。有名どころだと数学者? ポアソン分布の。
分霊獣:分霊は分け御霊。獣?
分霊という言葉のもともとの意味は、分け御霊ということで、コピーして増えるという意味の分けるなんだけど、作中でこの獣の動きとしては、流れを分ける、分配するという意味の様子。
っていうかロードバランサだよな? だからポアソン分布なのか! 待ち行列だから神待ちなんだ!(今更気づいたの俺だけか?)
待ち行列SFらしいということは垣間みえていたんですけど、まさかこんなん出てくると思わんやろ
杞憂(キユー)
杞憂は空が落ちてくることを心配した故事成語。カタカナでキユウではなくキユーなのはなにか意味あるのかな。待ち行列のキュー?
あー!なんで杞憂なのかと思ってたら、そうか、queueか!気づかなかった……
キューとかレッドコーダーみたいな二重の意味、他のやつにもそういうのあるんじゃないかと思ったけどわからんな
キノコジュース
一言感想
光――
初手「ふざけるなよ」と感想を書こうとしていたんですが、本人がふざけているつもりないとしたらめちゃくちゃ失礼になってしまうな、と口をつぐんでいました。やはりふざけるなよでよさそうです。
そういう意味では、我々としてはかなり楽しく読めるんですが、どこまで本気でやってるのか測れない距離の読者からすれば、読んでいて不安になる可能性もあるのかもですね
購入者の感想がたのしみです(なんなら自分の作品よりも)
ふざけどころの緩急がすき
ナンセンス漫画ってやっぱ絵があるからこそギリギリ成り立つもんなのかなあと思っていたところ、それを小説で成り立たせてる腕力がすごい
理路のつながらなさをゲーム的な世界観と苦しむ顔がかわいい女を好きな思い込みの激しい男とでギリギリもたせている感じというか、一般のナンセンス文学の退屈さを補う怒涛のクリシェというか
ほかの人のはそれぞれに「自分もこういうのできるようになりたい」という部分があり、その一方で「だけど本当にそれが書けるようになることを自分は求めてるのか?」という立ち止まりもあるなかで、国戸さんのは心情的に共感みがすごいんだよな。「これをやりたいし、これをやればおれのやりたいことができるのか!」みたいな
好き。酒呑みながらブコウスキー読んだときとおんなじ仕合わせな気持ちになる作品。
実際完敗した感じはあるんだよな。旋風こよりを前にした上矢あがりみたいな。
国戸さんの料理好きな部分が出てるのか。登場する食べ物飲み物が気になる。苔とか。
笑えすぎて本当にずるい
細部
すべてが細部なので読みながら挙げていきます(正直一文一文挙げてきたいところはあるんだが……)
そもそも冒頭の大剣のくだりからしていきなりバカにしてて、そこから「エロい体」の「悪魔系の魔物」が出てきて(系ってなんだよ)、ハートがパチン、そして光——の畳み掛けで完全に引き込まれちゃうんだよな
本当に最初の3行ですごいじわじわきたところに「セクシーで人間と同じ形状をしたエロい体の悪魔系の魔物」でトドメ刺されるんだよな。笑えすぎる。
くっそお、俺はこいつが好きだ
「大型魔物」、「の」を入れないのが良い
最強の二人のもう片方、だれだっけて
双剣を捨てる言い訳から店主を攻撃して半殺しってところまで一文一文笑いどころしかない
全体的にそうだという気もするんだけど、とくに「ルシエは用心棒で〜」からのくだり、なんか妙にサガフロ2を思い出したんだよな
キノコジュースのくだり正直まったく不要で、リアリティを増すための習俗の描写を馬鹿にしまくってる感がある
そういう意味ではその前の鴻上さんの緻密さと対比的でおもしろいな
「戦闘で、全力でしゃべってるんだと感じた」突然詩的になるな+ペンダントのくだりの思い込みの激しさ
いきなり世界が壊れだしてから第三世界の長井みがこれまでにも増して、ちゃんとゲームの世界なんですよという無用の目配せに笑ってしまうんだよな
素直に強く反省する主人公
p136の唐突な暴力描写の投げやりっぷり
「まさか点滅して消えるだなんて」ほんと好き
「その勢いは凄まじく、まるで矢のような勢いで飛び込んで来たのだ。」ここも好き
ひかりごけをいきなり食って、しかも飢えた人間へと連想をつなげるのをやめろ
もうこのあたり完全にゾーン入ってるんだよな、一文一文が常に笑える
「強い恐怖は、それまで持っていた弱い恐怖を克服する」の決め台詞感に至るまでの思考回路がくだらなすぎる
玉ねぎの連想から無理やり涙につなげて、象徴にもなってない象徴を引っ張り出したうえで「確かに」と結論づけさせるのすごすぎる
「過去の出来事が現在の状況を暗示している」みたいなありがちなアレをばかにしてる
いきなり寝ている、いきなり寝るな
「すると〜」からの段落の描写の雑さが主人公の現実認識の雑さを象徴しててめちゃくちゃいいんだよな
ダグラスの登場あたりからやにわに話が盛り上がるのだが(そもそもこれで盛り上がってる感がちゃんと出てるのがまずすごい)、インベントリがいっぱいなことを心配したり���い虫の話をしたりさらには親の回想がはじまったりしてこいつ集中力がなさすぎないか?
とても速いなにかしらの虫ってなんなんだよ、ほんとに。何回読んでも笑ってしまう
でもなんかちょっとかっこいいんだよな
p140からのなんかいいこと言ってる感の空虚さがすごいし、そもそもなんでダグラス現出してんだよだし、それらすべてが学校の机でガタンの恥ずかしさとなんかしらんが��にリンクしてる感じがして凄みがすごい
「あれ、これだいぶ前にもやらなかったか?」で突然我に返って、読んでる方も一瞬我に返り、ページをめくると最終ページの登場である
「苦しそうな顔が〜」で最後までふざけて、ロケットが開くのもなんか勢いで、それから光——ではないんだよ
まさしく腕力
リュシー (Lucie)は、フランス語の女性名。 ラテン語の男性名ルキウス(Lucius)に対応した女性名ルキア(Lucia)に由来し、『光』を意味する。
蟹と待ち合わせ
一言感想
マァンドリン
わりと文章が硬質なんだけど擬音語擬態語とか、こういう音声的な話を印象的に使ってくる印象がばななさんにあったけど今回それが強まっている気がする
いつもより書いてて楽しそうな印象をうけた
どこかでも書いたがばななさんの導入いつもよいと思う(導入以外が、という話ではなく)
今作はわりとエキゾチックなんだよな。キャノンビーチの鳥居を蟹がくぐる光景がエモい。
全体的にアルカイックなのは意識の誕生以前の世界への回帰だからか。
おなじ文献に着想を得てるのに杞憂との落差よ。
御神体フェチ
毎回SFギミックがハードコアではあるのだけど今回もそうで、そのうえ↓の書き手の感想にあるとおり、実際書き方がより挑戦的になってる
んだけど、それなのに!夏の島のバカンスの雰囲気に包まれててめちゃくちゃさわやかなんだよな、なんなんだよ
そう、すごくさわやかなんだよな……本当に
ずっと空と海を描いていて、そのうつくしさは質感としては憧憬に近いんだけど、ラストで急にその突き抜ける青さが手元に戻ってきて調和するのがすきなんだ
人類補完でなにが起こるかのところにこの回答持ってきたのは(↓で書いた情報の出し方のおかげもきっとあるんだけど、個人的な考えとしても)個人的にはめちゃくちゃ納得感がある
収録作のなかでもアジテーション的で、わりと全体通してゆっくりアジってくるので「たしかにそうだよな……」みたいな納得感がある。あるよな?
「鯨」で強めの主張をしてからの「石球」での転調、そこからラストの「蟹」で落とす流れがきれい
というか、全体的に情報の出し方のコントロールという基本ががうまいんだよな。我慢できなくて設定語りしちゃわない?おれは我慢汁出ちゃう!
細部
ちょっと入り組んでいるので整理を試みます(みなさん適宜修正してくれ):
人類
全体と言語野を共有している
読む限り電脳である以外、形としては「普通の人間」でよさそう?
現代から100年後が舞台であること(そう遠くなく、まだ最後の電脳化が終わって間もない)、人間の肉体として考えて不自然な描写が出てこないこと
もし「異形」であるなら、相応の描写があっていいはず
自然な人間の形であるからこそ「四本足」や「七つの目」という描写が活きているんじゃないかと思って
しかし、なんでもいいというのも、この話の主題のひとつだ
「アラスカやシベリアの軍事拠点と並び、地球上で全住民の接続を完了した最後の地のうちの一つだった(P152)」
語り手たちはまだ完全に統合しておらず「人間らしい」雑念に溢れている(ように語っている、が)
笠木
御神体「ヘイスタック・ロック」
「キャノンビーチ」
笠木グループ:腕が各2本、脚が各2本の3体か
彼らの姿を想像することにあまり意味はなさそうだがいちおう
肉体(?)の数と一人称複数形のバリエーションの数は一致しない
p146で「三つの肉体」とあるから上記の解釈をしたんだと思うけど、最初読んだときそう読み取っていなかったのでなるほどと思った。何故かはよくわからないが、6本腕(兼ねる、脚)がある物理的には1つの塊を最初イメージした。p145で「七つの瞳」(3では割り切れない)とか、「三つの声、四つの声」とか書いてあるのを読んで、あまり整合的にわかりやすい体の形をしたものが何体かいるみたいな状況じゃないんだろうなと思ってしまったので。
でも油圧ショベルを操縦してるから、人間みたいな形をしているのだろうか(人間向けの油圧ショベルなのかどうかは定かではないが)
瞳のひとつは「対流圏から熱圏にいたる範囲を巡航する種々の飛行撮影機と衛星によって構成された視線(P163)」とのこと
なるほど!!
どうも彼らは記録をしているらしいことがわかる
マンドリングループ(たぶん)とは異なる一人称複数的な主体を維持しており、(一方的であれ)独立性を保てるらしいことがわかる
性交は非対称的な行為であること
「私たちは背中が三つある獣(P147)」すごいな
マンドリン
御神体「鯨→海自体へのイメージ」(仮)
マンドリングループ:腕が計6本、脚は計4本
……とあるけれど、海岸を歩んでいない2本があったりするかもしれないか
人類全体の意識(というべきではないかもしれないが)が共有されており、各々の肉体は物理的な入出力器官として位置付けられている、入れ替わることもあるていど自由っぽいことがわかる
「四本の足(P150)」という表現、ひとりはかならず共用スペースで開発をこなしているという描写(ここすき)
「肉体と精神の求めに応じて」とあるので海岸を散策する肉体も実際に交代してそうな雰囲気がある
「巨大な一つの意思たる海、それを身に纏う美しい惑星(P154)」(『ソラリス』だ)に自分たちの集合知としての存在を重ねる
パレイドリアがそれなり大事そうな概念として導入される
大戦があったこと、舞台が太平洋の群島であることなど、若干の歴史や場所の情報
環礁・核実験・地形などの情報からビキニ環礁だと思われる
鯨
鯨グループ:7つの眼
あとの「蟹」を読むかぎりでは笠木グループと同一であると思われるが……
パレイドリアの話の続きとして:自他の境界がない(このへんが神々の沈黙っぽい)→パターンを形作ることができず、生の感覚(?)としてしか受容できないみたいな話になってくる(現代的に見れば統合の失調ではある)
人間の意識(?)が完全に同一化するまでの過渡期らしいことがわかる
石球
御神体「石球」
「2121年9月のアラスカ」と明確に述べられている
時系列的にはちょっと前のように見えるが、正直よくわかってない
夢:イリアスっぽい描写
このへんも神々の沈黙で、ゆうたら「自他の境界がない、昔バージョン」の話
「開いた」球
視覚的な描写ができない、よね?
蟹
笠木グループっぽい
7つのうちのひとつの瞳が別の夢を見たらしい
俯瞰することの話ふただび
ここまでときどき出てくる語りのアップロードなどなどの話から徐々に彼らの生態の全体像が見えてくる形になってる
小さなボートのなかに女
「人類すべての言語野がつながったのが、いまからちょうど半年前(P152)」で七つ目の瞳は「一年以上にわたって(P160)」漂流していた女を見ていた(という夢を見ていた?)
P158で大地が揺れたことと関係がありそうなんだけど
鳥居をくぐる。今まで、あえて鳥居をくぐることはしなかった(P161)
純粋な観測者であるはずの7つ目の瞳が女をとらえて震える
「間近で見た御神体の岩肌は、海鳥の糞にまみれて白く汚れていた(P164)」は単純に美醜の描写を行ったり来たりすることで対象の存在感が強まるという効果もあるんだけど、もしかしたら「岩→女」への神性の移行ともとれる
女は一人称単数でしゃべる
濃い日焼け、脇毛ぼうぼう、乳に蟹
その前の段落の「あたしはようやく目を覚ます」の主体がちょっとあいまいで、おそらくこの女なのだけど、どうもここまでの一人称複数であった人間たちのうちの一個体のようにも読める……読めない?
むずかしい……最後の台詞の読解にかかっている気がする
ここで個としての人間が復活しているらしく、たしかにしているっぽいのだが
システムの「手足」に回収されつつある在りかたを、独立した「動物」のほうに引き戻してくれたらということなんだろうけど、この言いかただとそういう流れは止まらないと展望している
しかし七つ目の瞳のほうは、純粋な観測者としてあるまじき挙動をしていて……
もはや個を剥奪された端末になりつつある人間から全体への、人間性の逆流? といえばいいのか?
鳥居(文脈から切り離された木一般の意味が異邦で再構築される)というのが、いや鳥居に限らず漂着物の再構築などが(マンドリンもそうだ)、女の登場と構造的に対応しているように思う
単純な近似ではなく、その異質さを強調するための
イリアスパートの「怒り」は、システムに回収されつつある生の叫び(全体的な語りから読み取れる)に沿っている気がする(捕らわれたクリューセーイスの奪還と、漂着した「女」の物語的な関係やいかに。未読なので詳しくはわかりません)
鯨も同様、またソラリスの話も寓意に富む
女、オフラインなのかな(最後の台詞からははっきりと推測できない)
書こうか迷ったが、もしかしたら「正体」があるんじゃないか
P150の環礁・核実験・軍艦というワード(七つ目の瞳では観測できない海底)
ビキニ環礁のクロスロード作戦
鳥居への祈りから、日本の軍艦を連想
クロスロード作戦で沈没した日本艦は長門・酒匂
軍艦の擬人化と言えば艦これ・アズレン
双方のキャラクターの特性に照らす
「あたし」という一人称と「ささやかな乳房」という情報
「酒匂」ちゃん??
艦これの話か?
なんかこうもっとロジカルに導きたいんだけど、まだひらめきに近い
でもこう読むとすっと入ってくる描写とかある気がするんだよ
海への柔らかい執着とか、肉体の話とか
深海棲艦説としか思えなくなってきた
あー、なんかそっちっぽい!
最後の台詞がわかった気がする
元の肉体(艦)が(七つ目の瞳以外に)憧憬?をもって観測されつづけたことによって顕現できた、みたいなことか?
どうなんや
元あたし(傍点)じゃん?
いくつもあった「すれ違う」描写、しかし最後に「越境」して交わり、岐路に立つ!
つまり女の漂着は人類にとっての“クロスロード”だったんだよ!!!(キバヤシ)
ブロックバスター
一言感想
コインを振る。裏。←かっこいい
まったくわからないんだけど、いつもよりわかるよな
Cの盛り上がりがBとDのクライマックスと呼応していく感じが好き
読後感すごくいいからやっぱりこれ最後配置で正解なんだよな
津浦さんの作品一番難解なんだけど、なんか童話的な柔らかさがあるんだよな
ポリフォニック(ね群メンバーの作品は全体的にそうかもだけど)
こーしーもう一杯
王の祈る姿が比例して増えた←感謝の正拳突きしそう
細かな表現のかっこよさはもはや言うに及ばずなんだよな
Aの語りに出てくるモチーフの並置の伸縮自在さとか
あと「その大きさはもはや比喩の範疇を超えて唯一だった」がめっちゃ好き
挙げてくとキリがないのでやめます
細部
こっちもまずは整理してみる(修正求む)構成:4幕。
(1) p.168「「世界」という言葉がきらいだった」
(2) p.171「「世界」という言葉は、ずっと昔のあいまいな約束だった」
(3) p.174「「世界」という言葉は、その実なにも説明できていない」
(4) p.177「「世界」という言葉が薄い殻から芽吹くとき、その平熱の期待を逃してはならない」
語りの種類:5種類。
A:ほかと同じ明朝体のやつ
各挿話の最初に置かれ、「「世界」という言葉」からはじまる
p.168は病院に行く(お見舞い?)シーン?
p173「恋人の手」と「犬のクソ」は素晴らしいものと価値のないものを表しておりそれらを混同しないとみんな言いはるんだけど実際には紙一重だ、みたいなことを言っているように読み取れる、一方でp174では「生きている私たち」の強調によって、両者はいずれも生命を示しているというふうにも止揚されてくる
p.177「意味のある対象が〜
B:丸ゴシックのやつ
母を知らず、物語を作るハルと、魚から這い出したところを見つかった、八つ目の毛玉のキャット
八つ目!魚から!Cの「ものども」あるいは王だ!
母を知らないっていう宣言的な言い方がDとの関係というか、そういうものを感じる
p171「私は無垢を演じているのではないかと~」からも、直截的にはそういう読み方が誘発されると思った。Dの母との問題を無視した空想の世界。p171の描写は作り物感を補強している。p172「自身のスペアを要請」
世界の果てでコインを投げる
世界の果てが出てきて殻を破るって実質ウテナじゃん
p.180「あるいは誰かのその前駆が私と私の世界を作ったのだとしたら〜」エフェメラルな雰囲気がする
最後に揺れて、そのあと魚、でもって「彼」は(世界の)棘を持つ、(Cの)大亀だわな…
C:教科書体(?)のやつ←例のクレー
彷徨し、「世界の棘」を持つ大亀、王とものども
p.183より、ものども(たぶん王も)八つ目である
最後、魚がめっちゃとんできて世界の殻が壊れる
p.183Bによれば、Bにおける「物語」が世界と同一視できそうではある
D:薄めの丸ゴシックのやつ
現代劇っぽさのあるわたし(空想が好き、大学は文学部、就職に困る)と母。二人は折り合いが悪い
p178「世界に目を向けて」という母親の言葉とそれに従わずに目を閉じる私。「世界」という言葉への反発はAにつながっているように思う。
目を閉じて以降、空に魚が出現し母が消えるので、ここで世界に背を向けたように感じられる。というかp182のBにシーン的には合流しているように読める。丸ゴシック繋がりもあり。
ふと思ったがここの「わたし」が神待ち行為を行なっていた可能性があるぞ!!!!(ないです)
最後、やっぱ空に魚(バラクーダ!)が出現する。母はいなくな
E:薄めの明朝体のやつ
わたしと「彼女」(母性を感じはする)、あやとり
p.174「わたしは彼女の暇潰しの相手に過ぎない」が、その前のp.173B「気晴らし」につながらなくはなくて、そうなると物語自体ってことになるのか?
p.183「名づけたのは他でもない、わたしだ」。「世界」を?「世界の棘」を?
「ふだん浮遊している〜彼の棘はもたらす」らしいぞ!(だいじそう)
ストーリー性は希薄で、間投される語り
p.183、やっぱ魚は大亀の斥候なんだよな
あ、ここに寝室(Dの末尾の舞台)出てくんじゃん
あえて階層構造を仮定するなら、基底から順にD→B(Dのわたしの空想あるいは物語)→C(Bのハルの物語)で、大亀による崩壊がC→B→Dと還流してるように読めなくはない気はするんだけども……(BとDは……つーか、いうたら全部上下がなく並列でもいけるか)。で、それで世界がつながるのはわかる。じゃあ「その外に残された」の外って?(火じたいは王の演説にも出てくる)
レイヤーを想定しちゃうのは悪い癖だな。読み返してたらあんま上下関係ない説の方が強まってきた
自分だったらレイヤーを想定して書くのだろうが、多分作風的にはレイヤーとかじゃないんだと思う。しかし相互の関係性とかが変奏していく感じがあって良いんだよな
テーマについて
神待ち
神の裁きと訣別するため:自分を負かす誰かを待っている→勝って神の不在を証明
山の神さん:神待ちアプリ
囚獄啓き: 「地獄とは神の不在なり」なので、不在なんじゃないかな
杞憂:中年男性(世界を維持するための計算資源→神?)待ち、待ち行列理論
キノコジュース:ルシエが宮殿で完全性を持つであろう存在を待っていたこと
蟹と待ち合わせ:蟹待ち
ブロックバスター:亀待ち
むりやりまとめると、神待ちの「神」を、原義側に寄せた、圧倒的なものとか完全なものとかでとって書いたのが多数派、という感じだろうか
とどのつまりは祈りだ。
4 notes
·
View notes
Photo

スパイク・リー監督・主演『ドゥ・ザ・ライト・シング』 (その2:事件の背景と本作に込めらたメッセージ) 原題:Do The Right Thing 制作:アメリカ, 1989年. ベッドスタイの夏の日の朝、ラヒームの死を思う者は誰もいなかった。しかし、ラヒームは誰かの手で計画的に殺されたわけではない。かといって、「太陽が眩しかった」から殺されたわけでもない。 ラヒームはなぜ警官の犠牲になり、スパイク・リー監督はこの映画に何を込めたのだろうか。本稿では、(その1)の現場風景を手がかりに、映画『ドゥ・ザ・ライト・シング』の背景と本作に込められたメッセージを探ってみたい。 なお、以下の記述のうち現場に関連する多くは、(その1:物語の現場はどうなっていたか)に状況を記し、文中に登場する会話は太字で示した。
CONTENTS ・日常の均衡を象徴するラヒーム ・黒人と白人双方の憎しみが黒人の犠牲者を生む ・なぜ、ムーキーはゴミ缶を投げたのか? ・黒人殺害事件の背景:(1) 格差の実態 ・黒人殺害事件の背景:(2) 格差を生む教育システム ・黒人殺害事件の背景:(3) 恐るべき警察の収監システム
日常の均衡を象徴するラヒーム 本作はベッドスタイの街を、愛と憎しみが拮抗する日常風景から描きはじめている。全体として怒りと憎しみの描写が目立つが、愛と寛容も描かれている。 DJダディは愛と尊敬を込めて、60人もの黒人ミュージシャンの名前を読み上げる。酔っ払いの老人ダー・メイヤーは、諍いに出会うたびに仲裁し、18年ものあいだ愚痴を欠かさない未亡人に、なけなしの金をはたいてバラの花束を贈ったりもする。 ときには警官も寛容さを発揮する。街の若者が消火栓で水を撒き散らして遊ぶなか、通りかかった白人のクルマに水を浴びせる場面では、告訴すると怒る白人を警官がとりなし、黒人の若者を無罪放免にしたりする。 反対に、生活の苦しさや家族の軋轢を描いた場面は数多くある。ムーキーには恋人のティナとの間にできた男の子がいる。しかし、ティナと同居している母親との折り合いが悪く、寝泊りするのは妹のジェイドのアパートだ。ティナは子守をしてくれない母親と言い争い、面倒見の悪いムーキーに「くたばればいい」と罵声を浴びせる。だが、その母親が子守をするアパートの別室で、ティナはムーキーと愛し合ったりもする。 ラジオ・ラヒームはこの相反する感情のバランスを体現するかのようだ。彼はいつも手に下げたラジオで大音量の "Fight The Power" を鳴らしている。しかしラヒームは、そのことで「戦い」をしているわけではない。「愛が勝つんだ」と言い、子どもと手をつなぎ楽しげに街を歩く姿も見える。ラヒームにとって "Fight The Power" は、日常を彩るラップ曲に他ならない。だがラヒームは、憎しみを忘れたお調子者ではない。 両手にはめた "LOVE" と "HATE" の指輪は、そうした日常の象徴だ。ラヒームはムーキーに、「憎しみで人は殺しあう、愛が人の魂に触れる。最後は愛が勝つ」と話す。このときムーキーは「じゃ、後でな。平和を」といって別れている。ラヒームもムーキーも、憎しみを抱えながら愛の力で日常をやり過ごしている。 街のあちこちで、愛と憎しみのバランスを取りながら生きる人々の姿が伝わってくる。これが真夏のベッドスタイの日常風景なのだろう。スパイク・リー監督が本作の前半でこうした日常を描いて見せたのは、それがひとつの「正しいこと」だからだろう。だがその正しさは、穏健な牧師の説教のようなものではない。 黒人と白人双方の憎しみが黒人の犠牲者を生む 『ドゥ・ザ・ライト・シング』の前半で描かれる日常風景は、事件への伏線に他ならない。 サルのピザ屋にバギンがやってくる。ひと切れのピザに文句をいい、支払いを渋るバギン。それをサルが、「月賦で支払うか?」とからかったそのひと言で、保たれていたはずの均衡が崩れはじめる。このときバギンは壁の写真に黒人が一人もいないと文句を言い、これが高じて店のボイコットへと発展する。 そして、サルがラヒームのラジオをバットで叩き割ったことで、事件はさらに深刻になる。互いの暴力行為が警察の介入をもたらし、警官の過剰対応がラヒームを死に追いやる。過剰対応を招いた警官の心情はほとんど描かれていないが、街をパトロールする警官が黒人に目線を定め「クソったれ」と漏らす場面が描かれている。 このときパトカーにいた二人の警官が、ラヒームを警棒で締め上げ殺害した当事者だ。しかし、同時にこの警官はサルの店でピザを買い、黒人の水遊びに腹を立て告訴するという白人をなだめ、黒人少年を逃したりもしていた。白人警官の黒人に対する憎しみがわずかしか描かれていないのも本作の特徴だろう。 白人もまた黒人に憎しみの心情を抱きながら、なんとか愛と憎しみのバランスに折り合いをつけながらベッドスタイの日常を過ごしている。しかし、このバランスは黒人にとっても白人にとっても、少しの不注意や不寛容で崩れてしまう脆弱なものだ。その上でスパイク・リー監督はアメリカ系アメリカ人の登場と彼らへの悪口を控えているように見える。これは、白人が黒人を貶めるほどには白人を責めてこなかった、黒人の姿の反映かもしれない。 ラヒームが言うように、愛と憎しみのせめぎ合いのなかで人は殺し合う。だが、この日ベッドスタイでKO勝ちしたのは憎しみの方だった。店のボイコットを切っ掛けにラヒームは自らの憎しみをサルに向け、白人警官の憎しみは黒人のラヒームに向けられた。二重の憎悪が愛と憎しみのバランスを狂わせ、ラヒームがその犠牲になった。 黒人と白人の双方が憎みあい、黒人に多くの死をもたらす構造は、過去に起きた同種の事件に共通している。スパイク・リー監督は本作を「エレノア・バンパーズ銃撃事件」他5名の犠牲者に捧げているが、その6人はすべて黒人だ。直近では今年5月25日にミネアポリスで起きた「黒人男性拘束死事件」でも犠牲者は黒人だった。これだけを見ても、映画に描かれた状況は30年以上も変わっていないことがわかる。 なぜ、ムーキーはゴミ缶を投げたのか? 『ドゥ・ザ・ライト・シング』で最も興味深い場面は、ラヒームが死亡したあとの顛末である。パトカーが動かなくなったラヒームを運び去ったあと、ムーキーが思わぬ行動に出る。大型のゴミ缶をサルの店のウインドウに投げつける場面だ。これがきっかけで街の住人は暴徒化し、店の什器は破壊し尽くされ、現金が盗まれたあげく店に火が放たれる。 なぜ、ムーキーは店を破壊する行動に出たのか? それはムーキーが、サル一家を暴徒から助けようとしたから、というのがわたしの見方だ。本作が描く現場には、そう思わせるさまざまな状況証拠がある。 ムーキーがゴミ缶を投げる前、群衆の怒りがサル親子に向けられる場面がある。ムーキーもサルらの側に立ち、詰め寄る人々の怒りに囲まれる。このときのムーキーの表情が印象的だ。彼はサルの家族に視線を向け、祈るような仕草をする。ムーキーは「このままではマズイことになる」と思ったのだろう。 店で妹と食事を楽しみ、サルから給料をもらい、ピノと話が通じるムーキーの心情が、サルたちへの憎しみ一色だとは思えない。「家に帰れ」という警官にムーキーが「ここが家だ」叫んだように、彼らは日常をともに過ごす「家」の住人なのだ。彼はその生活の絆が徹底的に破壊されるのを避けたかった。だからこそムーキーは、群衆の気を引くように「憎しみだ!」と叫びながらゴミ缶をサルの店に投げてみせた。人々の怒りをサルたちにではなく、店に向けさせるために。 ムーキーの心情に憎しみのカケラもなかったかと言えば、そうでもないだろう。彼は何度も仕事ぶりをサルにけなされている。ピノとの折り合いも悪かった。その鬱憤を晴らす気持ちもあったかもしれない。それでもムーキーは、人々を暴動に誘おうとしてゴミ缶を投げたわけではない。彼の行動の本質は、サル一家に決定的な危害が及ぶのを阻止しようとことにある。別な見方はあるかも知れないが、わたしはムーキーの行動をそのように受け止めた。 このことは、群衆の怒りの矛先がコリアン雑貨店に向かう場面と辻褄が合う。サルたちはこのとき、雑貨店が餌食になる様子を息を飲むような表情で見つめていた。そこに、犠牲になりかねなかった自分たちの姿を重ねたからだろう。サルたちは、無関係の彼らが自分たちの身代わりになることを案じたのではなかっただろうか。 他にも証拠がある。翌朝、ムーキーは未払いだった250ドルの給料をもらいに焼け落ちたサルの店に行く。その際のやり取りで、激昂しながらもサルはムーキーがゴミ缶を投げたことを責めていない。普通に考えて、自分の店にゴミ缶を投げつけて壊し放火を招いた相手を目の前に、責めないことがあるだろうか。なぜ、サルはそのことを口にしなかったのだろうか? それはサルがゴミ缶を投げたムーキーの心情を知っていたからだ。また、ムーキーはサルが投げてよこした500ドルのうち、残りの250ドルもポケットに入れている。このやりとりでムーキーはサルに、「借りておく」と言っている。サルとの関係はこれからも続くということだろう。 店への破壊行為、友人の死、さらには店への放火といった暴力行為を描きながら、この作品を通じてスパイク・リーは、愛と憎しみの平衡を何とか取り戻そうとする主人公の姿を演じている。"Fight The Power" が "Black Lives Matter(黒人も大切にしてくれ)" の叫びに聞こえる。これは本作で彼が監督として示した一貫した姿勢だと思う。穏健な改革派のキング牧師と、暴力を否定しなかったマルコムXを同時に登場させたのもその現れだろう。 スパイク・リー監督が『ドゥ・ザ・ライト・シング』で行って見せたのは、時には暴力に訴えることもあるがやり過ぎてはいけない。ともかく黒人も大切にしてほしいという、ごく当たり前の訴えなのだと思う。 黒人殺害事件の背景:(1) 格差の実態 それにしても、本作に描かれた事件と同種の事件が後を絶たない。本作は制作年の1989年までに起きた同種の6つの事件に捧げられているが、本稿を書いている現在も先月5月25日にミネアポリスで起きた「黒人男性拘束死事件」の余波は世界的な広がりをみせている。 そして、またあらたな事件が起こった。数日前の6月12日、ドライブスルーで警官に撃たれた黒人男性が死亡した。こうした事件は、アメリカで1964年に公民権法が制定された後も絶えることがない。 ミネアポリスの「黒人男性拘束死事件」は、その後 "Black Lives Matter" として世界的な抗議活動に発展し、1) 現在も収まる気配がない。そうしたなか、この種の事件が起こる背景についてさまざまな報道が行われている。その多くは経済格差とその背後にある政治や司法の問題を指摘し、さらにトランプ大統領の政策が影響しているとする意見も多い。 例えば、6月11日付けの日本経済新聞は「黒人暴行死事件の背景を探る」として、黒人の置かれた状況をデータで示すとともに、人種差別の歴史を振り返る特集記事を掲載している。前者の要点は次のようなものだ。個々の詳細は、元記事2) を参照いただきたい。
白人の世帯年収平均金額の中央値は黒人の1.7倍 黒人の無保険者は白人の1.8倍 コロナによる黒人の死者数は白人の約2.5倍 各人口あたりの警官による殺害は黒人が白人の約2.8倍 マリファナ使用による逮捕者数は黒人が白人の約3.7倍 警察の呼び止めを正当と思う人は黒人より白人が多い 黒人有権者のトランプ氏支持率は9% 黒人はバイデン氏の支持率が圧倒的に高い
一見して白人と黒人の間の格差は大きく、記事がいう国家的な仕組みが関係しているとしか考えられないものだ。そうであれば、その制度を擁護し、声高に「アメリカ・ファースト」を主張し、「白人至上主義者にも良い人はいる」といった発言を繰り返すトランプ氏が黒人から嫌われるのは当然のことだろう。 トランプ氏のトレードマークにもなっている「アメリカ・ファースト」については、その差別的な背景について、2018年公開の『ブラック・クランズマン』のなかでスパイク・リー監督が鋭く切り込んでいる。同作品よれば「アメリカ・ファースト」には、明らかに白人の黒人に対する差別が込められている。 こうした差別や格差に関するデータについては、例えばソキウス101の「アメリカの貧困と格差の凄まじさがわかる30のデータ」などにより詳しく取り上げられている。3) 子どもの貧困、寿命格差、食糧支給、ホームレスなど、より広範な視点で世界中に広がる格差の状況を概観することができる。 黒人殺害事件の背景:(2) 格差を生む教育システム だが、こうした記事やデータを読むだけでは不公平な制度の中身はわからない。このため、日経記事が掲げるような問題、例えば黒人が白人よりも大幅に低所得なのは、彼らが働かないからだと思い勝ちだ。 本作でもムーキーがピザ屋に顔を出して最初の会話は、ピノからの「遅刻だ」の一言だ。通りを掃除しろと言われても、「オレの仕事はピザの出前だ」と聞こうとはしない。さらにムーキーは、配達中に道草をしてサルに叱られ「出前にはビトを(見張りに)付けよう」といわれたりする。そもそも、映画に登場するベッドスタイの住人のほとんどは働いていないように見える。 こうした描写を見ると、アメリカの保守派が口にする自己責任論がもっともらしく思えてくる。保守派にしてみれば保険も自己責任で費用を負担し加入しているのであって、働こうとしない人々に自分らが負担してまで保険制度を適用するのは反対だという考え方になる。これはオバマケアでさんざん議論されたことだ。 しかし、雇用、保険、教育など、人間が生きる上での基本的人権にかかわる制度自体に歪みがあり、黒人の雇用が狭められているとすれば、働かないのは働けない仕組みのせいになる。この点について、本田創造氏の『アメリカ黒人の歴史 新版』に次の記述がある。4)
「黒人問題」は、すでに詳しく述べた公民権運動の数々の輝かしい差別撤廃の成果にもかかわらず、依然として解決されていないということである。(…)しかし、黒人大衆の経済状態は、最近では、むしろ悪化さえしている。それは、かれらの存在そのものが、最高度に発達したアメリカ資本主義の重要な存立基盤のひとつとして、この国の社会経済機構の中に差別されたかたちで構造的に組み込まれているからである。 (Kindle の位置No.2903-2908).
同書は1964年に旧版が出たあと、公民権運動の中心となった黒人解放運動などを書き加え、1991年に新版として出版された。引用にある「最近」は、映画の舞台となったベッドスタイの時代と重なる。そしてその当時から現在まで、白人と黒人の経済格差はいっこうに縮まっていない。本田氏の言う「社会経済構造のなかの差別」は当時からおよそ30年を経過した現在も続いていることになる。 この制度問題に関する記事は必ずしも多くないようだが、ニューヨーク在住のライター堂本かおる氏が制度的人種差別について、「白人警官はなぜ黒人を殺害するのか 日本人が知らない差別の仕組み」のなかで次の指摘をしている。5)
米国の公立学校の財源はほとんどが固定資産税で賄われており、貧困地区と裕福な地区の極端な税収格差が、子供たちが受ける教育格差に直結している。こうした要素が重なり、貧しい黒人の子供たちが学力格差を克服するのはほぼ不可能に近いとさえ言われている。
また、同記事を補足する形で、ショーンKY氏が「アメリカの格差と分断の背景にある自治体内での福祉予算循環」と題する記事のなかで、アメリカに現存する制度的な差別の実態と構造を詳しく論じている。6) 格差社会アメリカの構造を知る上で有用な内容で、わたしは次の一節に至る理由を読んで、アメリカの格差問題は本当に根が深いと思った。
アメリカにおける自治体別の格差は、本質的には所得格差に由来するものである。これがなぜ人種格差と結びつくかと言えば、(…)それが学校・警察を経由した格差の相続装置であり、一度生じた格差を時間が経つごとに拡大させるエンジンになっているからである。
格差の発生源を「時間とともに格差を拡大させるエンジン」と形容したのは秀逸だと思う。この喩えを広げれば、税収は燃料、教育システムはエンジンと燃料で動く内燃機関になるだろう。 エンジンは富裕層が住むゲートの内側と外側にあり、それぞれの燃料(税収)の多寡に応じて働く。燃料が豊かなゲートの内側では教育設備や環境が整い効率的に富の生産が行われる。一方、燃料が乏しいゲートの外では設備の不足や老朽化が進み、教師も満足とは言えず価値の生産が滞りその質も低下する。 さらに言えば、ゲートの内側では学力の向上が高学歴を促し、生徒が社会に出て政治の世界に手が届くと、豊かな教育を受けた本人は自身の育ちを肯定的に捉え、内燃機関(教育システム)を信奉するようになる。反対にゲートの外側では劣悪な教育が犯罪の温床となり、そこでは機能しないエンジンを直そうとする者も育たない。エンジンの例えが秀逸だと思ったのは、ここで説明されている教育システムが、白人中心に営まれるアメリカ社会の原動力をうまく表現していると思ったからだ。 教育制度が抱えるこうした差別的な構造は、黒人の賃金を抑え白人社会に利益を移転する搾取の問題以上に、学習意欲や労働意欲を阻害する点で、人生により根本的で深刻な危害をもたらす。学校の設備は貧相で古いものばかり、そのうえ教師の能力も劣る。家に帰れば、貧しい家計が食事や医療を圧迫する。そうした環境で多くの黒人が育つとすれば、彼らが白人と同等の学ぶ意欲を持つのは容易ではないだろう。白人が同じ環境に置かれれば、同様に意欲を削がれはずだ。意欲なしには十分な知識や給与は得られない。生きる意欲なしに、一体どうすれば生活が良くなるのだろう。格差は拡大する一方だ。 ムーキーらが暮らす1989年のベッドスタイは、ゲートの外にある文字通り"DO-OR-DIE"の世界である。映画のなかで本の話題が二度出るが、どちらも「お前���本を読むか?」とからかうネタにされている。少なくてもムーキーとティナの子ヘクターがゲートの外にいる限り、彼を働き者に育てるのは容易ではないだろう。社会のシステムが、両親が得た以上の教育を受けることを困難にしているからだ。 映画のなかでムーキーは25歳だ。彼はちょうど公民権法が制定された年に生まれたことになる。本田氏の指摘によれば、その後「黒人大衆の経済状態はむしろ悪化」した。ムーキーの労働意欲の欠如と低い収入は、アメリカ社会の制度的な歪みが大きく関係していると思われる。ベッドスタイの人々の多くは、働かない生活を自己責任で選び取ったのではないだろう。黒人のすべてがそうだとは言えないが、その多くは働く意欲を削ぐ社会的な仕組みの犠牲者だというしかない。 黒人殺害事件の背景:(3) 恐るべき警察の収監システム 教育システムとともに、もうひとつ制度上の大きな問題がある。警察の収監システムである。『ドゥ・ザ・ライト・シング』のなかで収監そのものが描かれているわけではないが、これも当時の黒人の生活や、ラヒームが犠牲になった背景に関係している。 先日の「黒人男性拘束死事件」に端を発したデモの映像で、何度か警察予算の削減を訴えるプラカード "DEFUND THE POLICE" を目にした。7) この標語は "BLACK LIVES MATTER" とともに、この種の事件が発生するたびに何度も使われてきたスローガンである。 英語版のWikipediaによれば、"DEFUND THE POLICE" は警察からの資金を分離し、社会サービス、青少年サービス、住宅、教育、その他の地域社会の資源など、公共の安全と地域社会の支援といった非警察的な形態に向けて再配分しようと訴えるものだ。8) さらに解説を読み進むと、こうしたスローガンが生まれた背景に、凶悪犯罪を取り締まるはずの警察が軽犯罪ばかりを取り締まり、人種的偏見にもとづく、貧困層を狙い撃ちにした逮捕が横行する実態があることがわかる。 映画で描かれたラヒームとサルの喧嘩も、殴り合いだけなら軽犯罪で済んだことだろう。顔見知りで同じ街で生活を共にしてきた二人が、もつれあいのなか相手を殺害するとは考えにくい。もし、そうなりそうなら周りが止めただろう。サルはバットでラジオを壊しはしたが、バットでラヒームに殴りかかりはしなかった。また、ラヒームも凶器を持っていない。それが警察の介入で殺害へと変貌するのは、日常的に繰り返される逮捕の多さと、安易に過剰に走る取り締まりに問題の一端があると思わせる。 軽犯罪を理由に大量の人々を逮捕するには、警官の人件費や装備費に多額の予算が必要になる。こうした実状から、弱いものを狩る部隊と化した警察予算を分離し、弱いものを救うためのサービスに予算を振り替えようといのが "DEFUND THE POLICE" の主旨だが、そうなる理由を掘り下げて考えるには、Netflixが独自に制作した動画『13th -憲法修正第13条-』(以下、『13th』と略記)がひとつの手掛かりになる。9) 動画は奴隷解放がいかにして収監システムに姿を変えたかを、歴史を振り返りながら伝えている。奴隷解放宣言(1863年)のあと公民権法が制定(1964年)され黒人への人種差別はなくなったはずだが、奴隷だった黒人の多くは受刑者として、新たな制度に引き継がれたという。 動画の題名になっているアメリカ合衆国憲法修正第13条は、公式に奴隷制を廃止し、奴隷制の禁止を定めたものだが、「犯罪者を除外する」という主旨の例外規定がある。この例外規定が犯罪者を奴隷扱いすることを可能にしたというのが『13th』の本質を成す主張である。動画は概ね次のように述べている。
公民権法が制定されて、400万人の奴隷をどうするかが問題になった。彼らは南部の経済や生産に欠かせない存在だったからだ。では、奴隷だった者をどうするか? 奴隷の恩恵を得て伸びてきた経済をどうするか? この二つの問題解決に修正13条の抜け穴が利用された。
この抜け穴が大量の受刑者を生み出す原点となった。 いうまでもなく受刑者は刑務所に収監され、社会や家族との接触を断たれる。動画によればその数は、2014年の時点で230万6,200人を数える。国別ではアメリカが世界最多、米国内の人種別では黒人が受刑者の40.2%を占めるという。しかも、1980年から2000年までの20年間で、受刑者の数はおよそ3.5倍という増加ぶりだ。下図にアメリカ国内の受刑者数の推移を示す。10)
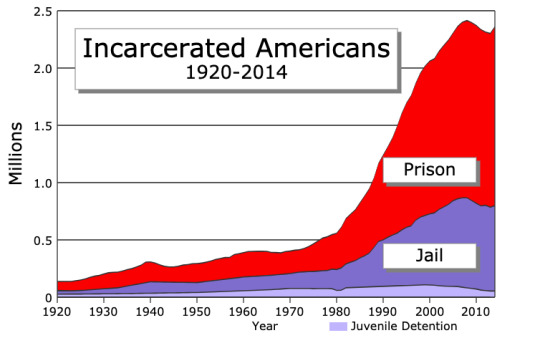
なぜ、これほどの数の受刑者がいて、しかも急激に増えたのだろうか? 動画はこの背景に、刑事司法制度と産獄共同体が抱える問題があると指摘している。前者の司法制度については、そもそも「容疑者に対する裁判そのものが行われていない」として次のように述べている。
保釈金を払って保釈されようと思えば1万ドルが必要だが、貧しい家庭ではできない。そこで、検事から司法取引が持ちかけられる。「司法取り引きするなら3年、裁判をするなら30年の刑だ。それでも裁判をするか?」貧乏人は裁判をしない。拘留された人のうち97%は裁判を断念し、司法取引に応じている。これは考えうる限り、アメリカにおける最悪の人権問題のひとつだ。
有罪か無罪かの真実ではなく、富が結果を決める現実がある。しかも、司法取引に応じて身に覚えのない罪を認め有罪になれば、その後生涯にわたって社会的な制限を受けることになる。 『13th』によればそうした社会的な罰は、学生ローン、���業免許、食糧配給券、家の賃借、生命保険など全部で「4万にもおよび」、「アラバマ州の黒人男性の約30%が、前歴のせいで投票権を永久に失っていることを誰も知らない。」という。掛けられた嫌疑の真実がどうであろうと、いったん有罪の烙印が押されれば、その印は一生ついてまわる。お金の多寡で罪が決められ、社会の仕組みによって罰が与えられるとは、何という悲惨、何という不幸だろうか。 こうした現実が長きにわたって続いているのは、司法制度と産獄共同体(産獄複合体とも呼ばれる)が一体となり、収監システムとして機能しているからだという。上述のWikipediaによれば複合体は、企業、政治家、メディア、看守組合などの利権集団で構成される。このうち『13th』で具体的に言及されるのは、CCA(Corrections Corporation of America)と呼ばれる民間刑務所会社、ロビー団体の米国立法交流協議会ALEC(American Legislative Exchange Council)とその会員企業である。動画はかなりの時間を、産獄複合体の実態についての説明に充てている。 それによれば、CCAはアメリカ初の民間刑務所会社として1983年に発足した。発足当時は小さな会社だったが、現在では全米60ヵ所以上で施設を運営している。Wikipediaによれば、直近の売り上げは約20億ドル、純利益1.9億ドル、従業員14,075人とある。売上高純利益率からいえば、すばらしい成績の優良企業だ。11) CCAがこれだけの好成績を上げていられるのは、刑務所が常に満杯で、しかも年々収容者数を増やしてきたからだ。『13th』はそれがどのように成し遂げられたかを次のように描いている(主旨)。
CCAは州と契約して投資を行うため、州は刑務所を満杯にする必要があった。CCAの働きかけででALECは、受刑者数を増やすための法案を提出した。クリントン政権の時代、「スリーストライク法」「必要的最低量刑法」「刑期の85%を下限にする」といった法律が次々と制定された。全て彼らが作った自分都合の法律だ。受刑者の安定供給によって生み出された利益は株主の懐に入る。80年代後半から90年台前半にかけて、刑務所運営は成長産業になった。成功が確実に保証された事業モデルだった。こうしてCCAは民間刑務所のトップになり、人を罰することで巨万の富を得ている。
「スリーストライク法」は、重刑を三回犯した者を一生刑務所に閉じ込めることを可能にした。「必要的最低量刑法」は比較的軽微な薬物犯などであっても、強制的に一定期間の拘禁刑を科す法律である。「刑期の85%を下限に」も含め、すべてクリントン政権の時代(1993年1月〜2001年1月)に法制化されたようだ。 収容者を増やすための法律という批判に対し、メリーランド州の上院議員がインタビューに「質問の意味がわからない」と答え、クリントン氏が「受刑者の増加率は減った」と反論する場面もあるが、前掲の図のように1993年から2001年のクリントン政権の時代、収容者は大幅に増えている。一方で、凶悪犯の検挙率が極めて低いことを考えると、収容者を増やすための法律といわれても仕方がないだろう。このような背景のもとで、収監システムは民間の刑務所のビジネスを急拡大させ、社会的な存在感を増していった。 『ドゥ・ザ・ライト・シング』が作られた1989年は、こうした時代の真っ只中にあった。司法と刑務所が収監システムへと姿を変え、貧困層の黒人をまるで利益のための餌のように狩る時代の嵐のなかでこの映画は作られたことになる。『13th』は動画の終盤で次のように訴えている。
理解してほしい、黒人の命だけが大切なのではない、全ての人々の命が大切なのだ。例外は存在しない。刑事司法制度の関係者も、産獄共同体の関係者もそうだ。黒人だけの問題ではない。人間の尊厳について、この国の意識を変える必要がる。
これは、スパイク・リー監督にとっても同じ思いではないだろうか。ムーキーは働かないのではない、働くための途方もなく高い壁を乗り越えられないのだ。その一方で、警官はシステムのなかで働く白人の一人としてラヒームを殺害した。その現場でムーキーはひとりの人間として、イタリア系アメリカ人のサル一家を暴徒から守ろうとゴミ缶を投げたのである。 スパイク・リー監督は本作を制作した29年後の2018年に『ブラック・クランズマン』を作った。その映像に彼は、ラヒームと同様に犠牲になった白人女性ヘザー・ハイヤー氏の、「憎しみのうちには、何人の居場所もない」という言葉を添えている。繰り返すが、ハイヤー氏は黒人女性ではない。生前ラヒームが拳を掲げて言ったように「最後は愛が勝つ」。スパイク・リー氏とともに、わたしもその言葉を信じていたい。
(その1:物語の現場はどうなっていたか)
1)BLMの訴え自体は、2013年2月にフロリダ州で黒人少年のトレイボン・マーティンが白人警官のジョージ・ジマーマンに射殺された事件に端を発すると言われている。 Wikipedia「ブラック・ライブズ・マター」 https://bit.ly/2Y5oGfW 2)日本経済新聞「黒人暴行死事件の背景を探る(上)(下)」2020.06.11. https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60150710Z00C20A6I00000/ 3)ソキウス101「アメリカの貧困と格差の凄まじさがわかる30のデータ」2020.4.30. http://socius101.com/poverty-and-inequality-of-the-us/ 4)本田創造『アメリカ黒人の歴史 新版』岩波書店, 1991. 5)堂本かおる「白人警官はなぜ黒人を殺害するのか 日本人が知らない差別の仕組み」文���オンライン, 2020.6.8. https://bunshun.jp/articles/-/38288?page=2 6)ショーンKY「アメリカの格差と分断の背景にある自治体内での福祉予算循環」note, 2020.6.9. https://note.com/kyslog/n/n5b8601ac8905 7)時事ドットコムニュース「「警察に予算回すな」 デモ継続、改革要求強まる―米」2020.6.8. https://www.jiji.com/jc/article?k=2020060800088&g=int 8)Wikipedia “DEFUND THE POLICE” https://en.wikipedia.org/wiki/Defund_the_police 9)Netflix『13th -憲法修正第13条-』2020.4.17. https://youtu.be/krfcq5pF8u8 10)Wikipedia “Incarceration in the United States” https://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States 11)Wikipedia「コレクションズ・コーポレイション・オブ・アメリカ」 https://bit.ly/2CjUJA5
7 notes
·
View notes
Text
返信
(返信のところって、文字数制限があるんだねえ)
『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』に限らず、Dickの作品��モチーフとしてちょいちょい出てくるのが、「人間が人間であるための一番の能力は他者に対する共感力ではないのか?」(そもそも『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』って、そういう意味だろうし。つまり「人間が羊を飼いたがるように、アンドロイドは電気羊を飼いたがるだろうか?」と)。で、この「他者」は、別に、生きた本物の人間である必要はない。人形でもいいし(『パーキーパットの日々』)、動物でもいいし、俳優が演じてるだけのキャラクターでもいい。実際、『電気羊』には、テレビで人気の「時々石をぶつけられながら荒野の坂を登っていく男」みたいなのが出てくる。昔の文庫本のカバーイラストで、羊の後ろに描かれているくらい重要な存在(実際、イラストの中心は、羊ではなく、その男だし)。
うろ覚えだが、主人公デッカードも、その「荒野の坂道を登る男」に激しく共感しているのだが、アンドロイドたち(たしかレイチェルとかも)はそれをすごく馬鹿にする。おそらくたぶん俳優が演じてるだけなのにバカみたい、というわけ(うろ覚えだけど)。
まあ、細かいところはどうでもよくて、つまり、人間なら、架空の登場人物に感情移入して泣いたり怒ったりすることを、実感として「さもありなん」と簡単に理解できるし、それを馬鹿みたいとも思わないのだが、アンドロイドたちには、それがまったく理解できないというふうに描かれているところがポイント。
共感力が[人間性の最も重要な能力の一つ]だと考えているDickにとって、共感力を持たないアンドロイドは非人間性の象徴。作中、嫌がらせでデッカードのヤギを屋上から落として殺したり、暇つぶしに蜘蛛の足をちぎってバラバラにしたり、テレビの登場人物に感情移入している人間をバカにしたりするアンドロイドには、どう考えても共感力が欠如している。
一方、映画『ブレードランナー』版のアンドロイドであるレプリカントの意味付けは「出自の違う人間」。ただこれだけ。そして、共感力の代わりに、もっと抽象的な「人間らしい心」のある無しが、モチーフになっている。レイチェルにも、ロイ・バティにも、そしてデッカード(映画版ではレプリカントらしいから)にも「人間らしい心」がある。「人間らしい心」のアルナシは、天然の人間(自然淘汰が生み出した我々人間)であるか、人工の人間(レプリカント)であるかに拠らない。「人間らしい心」を持たない非人間的な存在は、天然の人間の中にも、人工の人間の中にもいる。つまり、人間らしい人間かどうかは、「出自」では決まらないというのが映画版の主張。だから、映画では、(レプリカントへの差別意識全開の、天然の人間である)ブライアン(デッカードの「上司」)の方が、死んだプリスにキスしたり、最後の最後にデッカードの命を救うロイ・バティよりも、「人間らしい心」を持たない、いかにも卑しい存在として描かれている。
『電気羊』では、アンドロイドはあくまでも「非人間性を具現化した存在」。だから、自分たちが「非人間的」であることに悩んだり、共感力のある「人間らしい人間」になりたいと望んだり、自分が「本物の人間」ではなかったことを知ってショックを受けたりはしない。そういうコトに全く頓着しない(あるいは気づかない)存在を、Dickは「アンドロイド」としたのだから。だから、Dickにとっても、「出自」は関係がないとも言える。しかし、その意味は逆だ。つまり、現に共感力が欠如した非人間的存在なら、たとえ女の股から普通に生まれていても「アンドロイド」だと言いたいのが、Dickなのだ。人間にそっくりだが、人間にあるべきはずのものが欠けている存在としての「アンドロイド」という定義からして、絶対にありえないのが、共感力や「人間らしい心」を持ったアンドロイドも存在するかもしれないというほのめかしや、設定や、物語展開。「アンドロイドを無慈悲に殺す俺(デッカード)たちの方が、本当はアンドロイドで、アンドロイドだと言われて殺されているアイツらのほうが人間なんじゃないか?」的な、Dickお得意の「世界体験の確かさがあやふやになる、スキャナーダークリーな展開」が可能なのも、「アンドロイド即ち非人間的な人間」設定が動かないから。Dickは、「アンドロイドの中にも、いいやつは要るんじゃないか?」という話をしたいわけじゃない。
一方、『ブレードランナー』の「レプリカント」は、本当は人間と「同じ」なのに(ひどいやつもいれば、心優しいやつもいる)、生まれ方や体の仕組みが違うばっかりに、それだけの理由で、よく確認もされないまま、人権も与えられず、差別され、蔑まされている存在。まあ、だから、人種差別やら障害者差別やらの暗喩だよね。
だから、なんかもう、原作と映画は、まるで違うものだと分かる。別にお互いに議論しているわけではないけど、「論点がずれている」という言い回しがぴったりの「違い方」。前に、映画と原作は正反対って言ったような気もするけど、「正反対」ですらない。原作の方は、人間とアンドロイドを徹底的に対比させることで、「人間にとって最も大事なのは共感力なんじゃねーの?」と問いかけているのに対し、映画の方は、「人間とレプリカント(人工人間)、どちらも同じように心をもった存在かもしれないのに、無批判に境界線を引いて、人間がレプリカントを道具のように使い捨てにするのは、間違ってやしませんか? よく見てください。レプリカントも、人間と中身は同じじゃないですか」と言っている。つまり、原作と映画は、同じ学部の対立学派ではなく、そもそもの学部から違ってしまっている。
あと、フォークト=カンプフ検査がどんな感じで原作に登場したか全く覚えてないんだけど、やっぱりアンドロイドの共感力の不自然さを暴くものだろうから、それは映画と同じな気がする。つまり、[共感力を持った人間]のフリをしているアンドロイド(レプリカント)は、質問者(バウンティハンター/ブレードランナー)の言葉の意味は分かるが、それに対してどういう感情表現をすれば「正解」なのかが分からない(つまり、自然なリアクションが出てこない)ので、妙な発汗があったり、瞳孔に変な動きが現れる、的な。フォークト=カンプフ検査は、どれだけ共感できているかを調べるのではなくて、共感できずに困っている状態を暴き出す検査のはずだから、例えば、映画版の[検査を受けているレイチェル]の「動揺」は、質問によって描き出された場面や情景に感情移入(共感)して、不快になったり、恥ずかしがったり、怒りを覚えたりしている「動揺」ではなく、適切な感情反応ができずに困っている「動揺」のハズ。
あと、例の種本に拠ると、Dickは映画の完成品は観てないんだよね。死んじゃったから。撮影現場に来て、未来のロスの街の風景セットを観て、「すげえ、これだよこれ、イメージ通り」って感動したらしいけど。
2 notes
·
View notes