#ヒンズー
Explore tagged Tumblr posts
Text
TEDにて
アンジャリ・クマール: 失敗に終わった一神教での神の探求 - その代わり見つけたこと
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
多神教を知るアンジャリ・クマールは、一神教での神を探すつもりで始めた探求で、予期せぬ全く違う発見をしました。
人類共通の人間性を語る希望とユーモアいっぱいのトークの中で、彼女が出会ったニューヨークの魔女、ペルーの祈祷師や、ブラジルの悪名高き信仰治療者等を紹介しながら。
私達をスピリチャルな巡礼の旅に連れて行き、ある重要な教訓も共有します。
私たちを結びつける力は、分断する力よりもはるかに強いこと、そして私たちの間にある違いは克服不能なものではないという教訓です。
何年か前、私は神を探しに出かけました。最初から言いますが、この使命は失敗に終わったと弁護士の私が、そう認めるのは実に辛いことです。
ところが、その失敗に終わった旅で、その代わりに見つけた多くのことは非常に啓発的でした。
中でも特に、ある一つのことが、私に多大な希望を与えました。それは人間それぞれの違いの大きさと重要性に関係しています。
私はアメリカで、インド人の両親の元で育ちました。文化的にはヒンズーですが、宗教的には、インドの外ではあまり知られていない厳格な宗教のジャイナ教を実践していました。
それだけでいかに私が、少数派であるかを説明するとインド人はアメリカの人口の約1パーセントを占めてます。ヒンズー教徒が0.7パーセント。ジャイナ教徒はせいぜい0.00046パーセントです。
違う言い方をするとバーモント州のテディベア工場の年間来場者数は、アメリカのジャイナ教徒の数を上回ります。
それだけでも少数派の私なのに加えて両親はある決断をしました「いいことを思いついた!、カトリック系の学校に通わせよう」その学校では、私と姉だけが非白人系で非カトリック教徒の生徒でした。
イリノイ州フロスムーアのその学校「Infant、Jesus、of、Prague、School」ではそうなんです。本当にそういう名前の学校でした。
私達は、唯一の神という教えを信じ、神は創られたもの全ての源、世の中の全てです。天地開闢から道徳の導き永遠の命まで。ところが家に帰ると全く違うことを教えられました。
ジャイナ教の信奉者は、唯一神を信じておらず複数の神という考えすら受け入れません。その代わりに教えられるのは、個人が完全になることで神が表れる��いうことです。
信者は生涯をかけて神のような完全な人間になるのを妨害するような悪のカルマを取り除く努力をします。
更に、ジャイナ教の思想の柱の一つが「非絶対主義」と言われるものです。非絶対主義者らは、一人の人間が絶対的な真理を得たり知ったりすることはできないと信じています。たとえそれが信仰であってもカトリックの学校の神父様や尼僧にこの概念を試すつもりなら頑張ってくださいね。
私が混乱し、いかに自分が周りと違うと感じても無理ありません。場面は変わって二十数年後、私は深いスピリチュアルな人間になっていましたが、もがいてもいました。精神面で「ホームレス」だったからです。
私は「None、(無し)」の部類に属すことがわかったからです。これは決して頭字語でも器用な言葉のシャレでもなく「Nun(尼僧)」のことでもありません。それはただ単に、ピュー研究所の意識調査で、宗教の項目で「無し」をチェックする人に与えられる辛いほどつまらない名称です。
「無し」に属する人達に関して興味深い点を挙げてみると数では多数いること。若い人に偏っていること。アメリカでは2014年の時点で5600万人を超える人々が、宗教では無所属の「無し」でした。
「無し」は、18歳から33歳の大人の三分の一以上を占めています。ところが私にとって「無し」の人の一番興味深い点は、スピリチュアルな人が多いこと。実は私達の68%が、ある程度の確信を持って神の存在を信じています。
定義によってですが、ただ、その神が誰なのかに、迷っているのです。
自分が「無し」に属すことに気付き、それについて分かって最初に感じたことは、私一人ではないということでした。アメリカに存在する多数のメンバーを誇るグループの一員にやっとなれたことに安堵を感じました、ところが次に、少し不安を覚えました。
私達が多数いるってことは、いいはずはありません。だって深いスピリチュアルな精神を持つ私達が神を見出していないなら神を見つけるのは当初の予想より難しそうだからです。
そこで私は、自分のスピリチュアルな旅を続ける上でありふれたところは避けることを決めメジャーな宗教には一切目もくれず、その代わりあえてスピリチュアルな世界の非主流に属する霊媒師や祈祷師やグルを探すことにしました。
ただ、思い出してください。
私は絶対主義者ではないので何にでも心を開いて接することができそれが良い結果につながりました。ニューヨーク市で開催された魔女の持ち寄りディナー集会に出かけて行って2人の魔女と友達になりました。
20リットル容器に入った火山水をペルーから来たシャーマンと一緒に飲みました。会場��聖人に抱擁してもらいました。
メキシコの海岸の煙が充満した高温の儀式小屋で何時間も呪文を唱えました。テキーラ飲みの霊媒師と一緒になって霊を呼び出しましたが、その体験で変だったのが霊のなかには亡くなった姑とヒップホップグループ「ザ・ルーツ」の元マネージャーがいたこと。
そうなんです。姑は息子が私を嫁に選んだことをすごく幸せだったと言ってくれたの当然でしょ!そう、ところが、ザ・ルーツのマネージャーからは、食べ過ぎのパスタの量を減らすべきだと忠告されました。ここでみんな同意できるのは、夫がラッキーだったのは炭水化物を控えるよう忠告したのが彼の亡くなった母親ではなかったこと。
ネバダ州の砂漠でバーニングマンのイベントの公衆電話ボックスからレオタードを着てスキーゴーグルをかけて神に電話をしたりとか
探求を始めて間もなくブラジル人の信仰治療師ジョン・オブ・ゴッドを訪ねてブラジルの彼の居留地にも行きました。ジョン・オブ・ゴッドは、フルトランス・ミディアムと言われます。
要するに、死者と話せるのです。ただ彼は聖人と医師だけの特定の霊だけとチャネリングをすると主張し、そうすることでどんな病いも治せるそうです。ジョン・オブ・ゴッドは、医学の学位を持っているわけでもなく、ましては高校の卒業証書さえないのに実際に手術を行います。
メスを使った正真正銘の手術ですが、麻酔は無しです。そう、やや疑問です。彼は身体を切らずにすむ見えない手術や代理手術もします。患者の愛しい人を代理として手術をし、何千キロも離れたところにいる患者を治すことができるそうです。
ジョン・オブ・ゴッドに会うには、たくさんの規則と規定があります。すごく複雑な手続きですが、結果的には、ジョン・オブ・ゴッドに会ってなおして欲しいことを3点提出すると彼は聖人や医師の霊にあなたの願いが叶うよう働きかけて務めをさせるのです。
呆れて笑う前に、まずは検討してみてください。少なくとも彼のウェブサイトによると彼の手で800万人以上の人が昼間のテレビ番組の女神、オプラも含みます。ジョン・オブ・ゴッドと会っているので私も先入観にはとらわれませんでした。
ところが正直言って、この体験はちょっと変で結論には至りませんでした。最後にはそのまま飛行機に乗り、帰ってきてしまい出発前よりも混乱していました。だからと言って何も得なかったわけではありません。
ブラジルへ発つ数週間前から私の探求の計画を数人の友人や当時、弁護士として働いていたGoogle社の数人の同僚に打ち明けていました。もしかしたら他の人にも話していたか��わかりません。
私はおしゃべりなので近所の人や毎朝立ち寄るコーヒーショップの店員やスーパーの「ホールフーズ」のレジ係のおばさんや地下鉄で隣り合わせになった見知らぬ人に、皆それぞれに私の行く先を伝え行く目的も説明し、彼らの3つの願いも一緒にブラジルに持っていくことを申し出ました。
ジョン・オブ・ゴッドに会いに行く人は、誰でも代理人になることが可能で旅の手間を省くことができると説明しました。びっくりしたことに受信箱にメールが溢れるように届きました。
話が友達からその友達、更にその友達へと伝わり、その友達らももっと多くの友達や知らない人やコーヒーショップの店員へ伝え、私がブラジルに発つ日までの間に私のメールアドレスを知らない人はいないような状況になりました。
その時結論付けたことが、あまりにも異常な数の人に約束し過ぎたということだけ。ところが数年経ってみてメールを読み直してみると全く違うことに気付きました。
メールには3つの共通点がありました。最初の点はやや奇妙なことでした。
ほとんどの人が連絡方法を細かく指示してきたのです。私が彼らに伝えたこと。また、その友達が彼らに伝えたことは、3つの願いを書いたリストと共に写真、名前と生年月日が必要だということ。
ところが細かい住所、それもアパート番号や郵便番号まで送ってきました。ジョン・オブ・ゴッドが、家に立ち寄って会ってくれるか小包でも送ってくれるとでも思ったかのようです。
ありそうもないことですが、ジョン・オブ・ゴッドに願いをかなえてもらった場合を考え間違った人や住所に誤って届けられる可能性がないようにしたかったようです。可能性がないことがわかっていても万が一の失敗を防ぎたかったのです。
2つ目の共通点も同じように、奇妙でしたがもっとずっと控え目でした。
ほとんどの人、地下鉄で会った知らない人、コーヒーショップの店員、廊下先のオフィスの弁護士、ユダヤ人、無神論者、イスラム人、敬虔なカトリック教徒、全ての人がほとんど同じ3つのことを願っていました。
もちろん、全くはずれたことや現金が欲しいと言う人が何人かいました。でも、そのような少数の例外を除けば、残った人の共通点は驚くほどでした。ほとんどの人が、まずは自分の健康と家族の健康を願っていました。
ほとんどの場合、次に幸福を願っていました。そして最後に愛情をその順番に、健康、幸福、愛情、特定の健康問題が治ることを望む人もいましたが、ほとんどの場合ただ単に健全な体を願っていました。
幸福となると、皆それぞれやや違う言い方で表現していてもほとんどの場合が、幸福のサブタイプは同じで深く実感できるような魂の中に根付くような幸福、私たちを支えてくれるような幸福、たとえ他の全てを失った時でもです。
そして愛情に関しては、全ての人がロマンチックな愛情や長編ロマンス本に出てくるような魂で繋がれた相手を求め人生の最後まで伴にするような愛を。
ごめんなさい、夫のこと思って胸���いっぱいになっちゃった。困ったわ!どこまで話したか忘れてしまった。
という事でほとんどの場合、友達だろうと知らない人だろうと育った環境や人種や宗教に関係なく皆同じことを求めていて私が求めていたこととも同じでした。
社会科学者のアブラハム・マズローやマンフレッド・マックス=ニーフが確認した人間の基本的欲求を簡素化したものです。
誰も重要な実存的な疑問の答えを聞いてきたわけでもなく、私が探求していた神の存在の証や生きる意味でもなく、戦争や世界規模の飢餓を無くすことさえ求めていませんでした。
どんなことでも頼めたはずなのに、求めたことは、健康と幸福と愛だけ。
メールには、3つ目の共通点もありました。
どれも同じように締めくくっていました。遠いブラジルまで彼らの願いを運ぶ私にお礼を言う代わりにみんなこう書いたんです「誰にも言わないで欲しい」だから私は、みんなに言うことにしました。
それも今、この壇上で。それは、私が信用できない人間だからではなく、私達には実はたくさんの共通点があるという事実を。特に今、みんなが知る必要性を感じるからです。世界の様々な問題の原因は、私達がお互いの違いばかりに注目していて共通点に目を向けないことだと思うからです。
そう、自分で一番よくわかっているのは、私は統計学者ではないので提供できるデータは、メールの受信箱にたまったものだけ。
科学的というより逸話的で定量的というより定性的です。データを使った仕事をしている人なら誰でも言うように決して統計学的に有意でもなく、人口統計的に妥当なサンプルでもありません。
それでも、私は受け取ったメールのことを考えずにいられません。
自分の人生で直面した偏見や嫌悪を思い起こすたびに。あるいは憎悪犯罪や無意味な悲劇が起こって私達の間にある違いは克服できないかもという残念な気持ちが強まるたびに自分に言い聞かせるのは、私には証拠があること。
私達の人間性には謙虚で一体となる共通点があり、それは何でも叶えてもらえる機会を与えられた時でさえもほとんどの人が同じことを望み、それは自分がどんな人間であれ、どの神を信じていようとどの宗教を拠り所にしようと同じなのです。
もう1つ注目したいことが。人によっては願いがあまりに強いため「無し」の人にメールさえ、送ってしまうこと。精神面で混乱した他の面も混乱しているかもしれませんが、私のような「無し」にまでメールするのです。
見ず知らずの人を探し出し、最も深遠な願いをメールを送ります。もしかするとわずかでも可能性が残されていて神などではなく、ましてや自分が信じる神でもない人、自分と同じ宗教ですらない人、経歴を見ても期待に応えられるとは到底思えない人が願いを叶えてくれることがありやしないかと。
そこで今、私のスピリチュアルな探求を思い返してみて、私は神を見つけることはできなかったけれど、この事実を発見したことで自分の居場所を見つけました。
こんにちのような、宗教や民��、政治、思想、人種によって分断されてしまった世の中で私達には明白な違いが多くあっても結局のところ、人間の最も基本的な部分においては私達は皆同じということです。
ありがとうございました。
(個人的なアイデア)
古代エジプトは、紀元前30000年に集団が形成され、その後、紀元前3000年に人類最初の王朝が誕生。エジプトの主神であったアメン神は多神教で世界最初の中央集権国家として現在では知られています。
その後、「アクエンアテン」が推進したアテン神を中心とする一神教が、人類史上初の一神教として誕生。
合議制の多神教である神官と言われる人々が政治に口を出すために、破壊的イノベーションにより誕生したかもしれません。一部。大統領制や政教分離です。
しかし、一神教はエジプトでは破壊されてしまい。モーゼの出エジプト記になり、古代ユダヤ教になったと知られています。参考までに、一般的には古代中国は、紀元前2000年。古代ローマは紀元前500年です。
「出エジプト記」「創世記」「レビ記」「民数記」「申命記」の旧約聖書モーゼ五書も登場する「トーラ」と呼ばれるものの中にも記述されています。
毎年のナイル川の氾濫を正確に予測する必要から、天文観測が行われ、太陽暦が創造されています。
また、氾濫が収まった後に、農地を元通り配分するため、測量術、幾何学、天文学が構築されて発展しています。
世界のほとんどのアルファベットの起源も古代エジプト文明から始まっています。
古代エジプト時代の主食は、小麦から作るパン。現代と変わらないと言われている。サワードウによる発酵パンが誕生したのもエジプト。
古代ローマよりも早く、紀元前3800年頃に大麦から作るビールの生産が始まり、紀元前3500年頃にワインの生産が始まった。
<おすすめサイト>
ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019
サラ・パーカック:宇宙から見た考古学
ユバル・ノア・ハラーリ:人類の台頭はいかにして起こったか?
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版
#アンジャリ#クマール#宗教#イスラム#キリスト#ユダヤ#人類#エジプト#古代#アテン#インド#テーラ#ワーダ#ヒンズー#チャクラ#エネルギー#統計#瞑想#マズロー#宇宙#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery
0 notes
Text
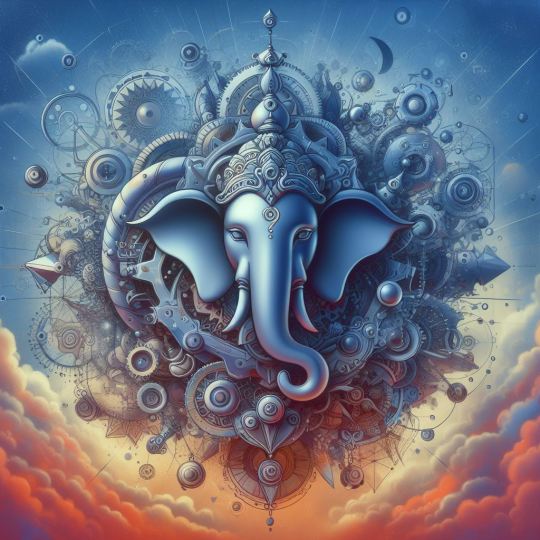
「富や知」をつかさどっているそうです。 その名の発祥はサンスクリッド語だったりして・・ 群衆 という意味も含んでいるらしい(くわしくはウィキみて)
#AI#生成AI#AIart#AIイラスト#bingimagecreator#DALLE#AIArtworks#illust#AI画像#illustration#dalle3#aiart#openai#ガネーシャ#ganesha#ヒンズー教#hinduism#गणेश
1 note
·
View note
Text
722名無しステーション 2025/05/10(土) 23:44:23.64ID:UihtLh8h0(7) 現実でも宗教が熱心な国って治安が悪いよね
888名無しステーション 2025/05/10(土) 23:46:17.23ID:T059A0cQ0 >>.722 治安が悪いから宗教にすがるんや
754名無しステーション 2025/05/10(土) 23:56:37.91ID:CzdUaaDl0(4) インドとパキスタンの戦争も ヒンズーとイスラムの宗教戦争だしな
870名無しステーション 2025/05/11(日) 00:00:23.76ID:UOmyIQgD0 >>.754 戦争の大義名分に宗教を利用することはあっても、宗教が原因で戦争になることはない 必ず領土や金といった俗な利益が原因になっている
6 notes
·
View notes
Text
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和六年(2024年)11月15日(金曜日)
通巻第8504号 <前日発行>
トランプのディープステート殲滅作戦が始動
今度は司法長官、国家情報省にもっとも戦闘的な議員らを配置
*************************
ドナルド・トランプ次期大統領は司法長官に「議会の暴れん坊」といわれるマット・ゲーツ下院議員(共和党・フロリダ州)を指名した。
国務、国防、CIA、国土安全省と、ずらり対中タカ派を勢揃いさせたから、次の人事でディープステートとの戦いを宣言したも同然である。財務長官の指名は後回しになった。
「フロリダ州選出のマット・ゲーツ下院議員が米国司法長官に指名されたことを発表できることは大変光栄です」とトランプ大統領は声明し、「マットはウィリアム・アンド・メアリー法科大学で学び、才能に恵まれ粘り強い弁護士であり、司法省で切実に必要とされている改革の実現に力を発揮してきた」
指名を受けたゲーツ下院議員はXで「トランプ大統領の司法長官を務めることは名誉なことだ」とした。
ゲーツは暗号通貨の推進派でもあり、トランプ支持の動きで注目を集めてきた。
とくにゲーツ下院議員は「国会議事堂の騒乱においてトランプ氏はいわゆる『反乱』に関与していない」とする決議案を提出し、また理不尽なトランプ裁判を捉えて、司法省検察官のジャック・スミスを選挙介入で告発した。くわえてゲーツ下院議員は、連邦所得税をビットコインで支払うことを許可する法案を提出、また国土安全保障省はトランプ大統領を狙う5つの「暗殺チーム」を知っているなどと発言してきた。すなわち司法省にメスを入れる爆弾男になり得るとトランプが判断したことになる。
ついでトランプはトゥルシー・ギャバード(元下院議員、退役中佐)を国家情報長官(DNI)に指名した。DNIはCIA、FBIなど18の情報機関を統括し情報を総合的に収集し、管理する部署。
上院指名公聴会で、一番揉めそうなのは人事だろう。
上院は共和党53vs民主党47となったが、共和党院内総務にトランプ派のトム・スコットではなく、トゥー��が選ばれた���とによってRINO(名前だけ共和党)の抵抗があると予測されるからだ。
トランプ次期大統領はトゥルシー指名理由を次のように言った。
「彼女は長きに亘ってすべてのアメリカ国民の自由のために戦ってきました。彼女はかつて民主党の予備選に出馬して、ヒラリー候補と競った。両党から幅広い支持を得ている。トゥルシーは、輝かしい経歴を特徴づけ、恐れを知らない精神を国家諜報機関にもたらし、憲法上の権利を擁護し、強さを通じて平和を確保してくれると確信しています。トゥルシーは私たち全員を誇りに思わせてくれるでしょう」
▼女性だが退役中佐、その軍歴も光る
トゥルシーは七月の共和党大会でも雛壇にのぼり演説をしており、その直前までは、あるいは副大統領候補としてトランプとチケット組むかとまで言われた。
筆者は拙著『トランプ劇場2・0 世界は大激変』(ビジネス社)ならびに『アメリカは新南北戦争に突入する』(ワック)でトゥルシーを特筆し、閣僚入りは確実だろうと書いている。
たぶんホワイトハウスのスポークスウーマンかとも予測したが、トランプの彼女への評価はうんと高かったのだ。
彼女はサモア生まれで、母親はインド系。したがってヒンズー教徒とも言われる。
ハワイ選出で4期連続連邦下院議員をつとめた。軍人としても、中東とアフリカの戦場に3回派遣された陸軍予備役中佐。911テロ後、陸軍州兵に入隊。第29旅団戦闘団の一員としてイラク派遣に志願し、医療部隊に配属された。
2006年に帰国後、トゥルシーは上院退役軍人問題委員会の故ダニー・アカカ上院議員の立法補佐官として活躍、また小隊長として2度目の中東派遣に志願した。
31歳で米国議会に立候補し、軍人仲間の命と犠牲を称えることを誓った。彼女は厳しい選挙に勝利し、四期連続でハワイ選出の連邦下院議員。軍事委員会、国土安全保障委員会、外交委員会に貢献した。2022年10月、トゥルシーは民主党エスタブリッシュメントの腐敗、堕落とその全体主義的な体質に愛想をつかして離党、トランプ陣営に駆けつけた。
9 notes
·
View notes
Text
「他者」の起源──ノーベル賞作家のハーバード連続講演録
著者 トニ・モリスン(Toni Morrison)
解説 森本あんり(Morimoto Anri)
訳者 荒このみ(Ara Konomi)
集英社新書2019年7月22日第一刷発行
原著 THE ORIGIN OF OTHERS by Toni Morrison. Harvard UP. 2017.
帯宣伝文 「人はなぜ 「差別」 をやめられないのか」
日本語版読者に向けて 森本あんり(巻頭特別寄稿)
人は、差別主義者に生まれるのではなく、差別主義者になるのである。──トニ・モリスンのこの言葉を読んで、ボーヴォワールの「第二の性」を思い起こす人は少なくないだろう。人は、女に生まれるのではなく、女になるのだ。これを、身体的・生物学的な性(セ��クス)から社会的・文化的な性(ジェンダー)への発展、と言い換えてもよいかもしれない。
だが、この類比には並行的でないところもある。女に生まれることと女になることとの間にはかなり強い繋がりがあるが、生まれたばかりの子どもには、差別主義者になるような身体的・生物学的な根拠はどこにもない。白人や黒人に生まれることと、人種差別主義者になることとの間には、実は何の関連性もないのである。
とすると、人はいったいどこでどうやって人種差別主義者になってゆくのだろうか。それを問うたのが本書である。モリスンは、その問いに「他者化」というプロセスを示して答える。人がもって生まれた「種」としての自然な共感は、成長の過程でどこかに線を引かれて分化を始める。その線の向こう側に集められたのが「他者」で、その他者を合わせ鏡にして見えてくるものが「自己」である。このプロセスは、本書で取り上げられた作品が物語るように、明白な教化的意図をもって進められることもあれば、誰の意図ともつかぬしかたで狡猾に社会の制度や文化の秩序に組み込まれて進むこともある。
やっかいなことに、人がこのプロセスと無関係に社会生活を営むことは困難である。「他者化は怪しからぬことだからみんなでやめようではないか」と論じたところで、実際に何かが成し遂げられるわけではない。ある時代のある文化に生まれ育つ者は、まずはその文化の規範をみずからのうちに取り込むことで成長する。つまり、われわれはみな、人としての自我をもつ存在となった時点で、すでにその文化がもつ特定の常識や価値観の産物となっている。だから人が他者化の問題を意識するときには、かならず自分の常識や価値観の問い返しとなり、それまで自分が学んできたことの「学び捨て」(unlearning)にならざるを得ないのである。モリスンの作品がしばしば読者の心に鋭い問いを突きつけるように感じられるのは、このためである。
個人だけではない。他者化の力学は、国家や民族といった大きな集団にも同じように交錯して作用する。近現代の歴史はその典型例をいくつも示してきた。第二次世界大戦が終結すると、植民地であった地域から旧宗主国のプレゼンスが消え、次々に独立国家が誕生した。ところが、宗主国という共通の「他者」がいなくなると、今度は自分たちの内部に新たな「他者」が見えるようになる。インドでは、独立を求めて共に闘ってきたはずのヒンズー教徒とイスラム教徒がお互いを「他者」と認識するようになり、印パ戦争を経て1947年にはパキスタンが独立する。さらにパキスタン内部でも、言語や民族の違いから東西がお互いを「他者」と認識するようになり、1971年にはバングラデシュが独立する。
1991年にソビエト連邦が崩壊したときにも、同じことが起こった。ソ連の崩壊は、連邦下に置かれていた各国の独立や、共産主義という理念全体の失墜をもたらしたばかりではない。東西冷戦というわかりやすい対立構造のなかで彼らを見ていた自由主義世界もまた、共通の「他者」を見失った結果、みずからの内部に新たな「他者」を見いだして立ち竦むようになる。西側諸国が誇ってきたリベラルな民主主義は、共産主義という外部の敵がいなくなった途端に暴走を始め、ポピュリズムや不寛容な民族主義という内部からの脅威に侵食されるようになった。今日われわれが世界の各地で目にしている民主主義の機能不全は、すでにこのときからゆっくりと進行してきた病態の表面化にすぎない。
だが、ここでも問題は単純ではない。こうした分断や暴走による不安定化は、たしかに歓迎されざる結果であるかもしれないが、かといってそれ以前の植民地時代や冷戦時代がよかったかと言えば、そういうわけでもないだろう。「以前はみんな仲良く暮らしていたのに」という台詞は、しばしばその背後に抑圧され封殺された多くの声があったことを覆い隠して語られる。モリスンの語り口に同調させて言えば、それは南部の善良で心やさしい白人たちが公民権運動前の時代を想い出して懐かしげに語るときの台詞に近い。
このように、本書が照らし出す「他者化」の概念は、通りいっぺんの批評を許さない多義性を帯びている。他者化とは、他者をその総体において、つまり自分の認識能力を凌駕する何らかの名付けがたい他者であるままにその存在を承認する、ということではない。われわれはしばしば、他者の一部を切り取って自分の理解に囲い込み、それに餌を与えて飼い続ける。やがてそのイメージは手に負えないほど肥大化し、われわれを圧倒して脅かすようになる。
それでも、人は知ることを求める。知って相手を支配したいと願うからてある。それは、相手を処理されるべき受け身の対象物となし、かたや処理する側の自分を正統で普遍的な全能の動作主体として確立することである。この批判は、かつてエドワード・サイードが論じた「オリエンタリズム」批判にも重なってくる。西洋人が非西洋を解釈するときには、非西洋の本人も自覚していないらしいオリエント的な本質が特定され代弁される。まさにその表象行為によって、そういう認識をする西洋人こそが真の人間であり、対象である非西洋を管理し支配すべき正統性をもった存在であることが宣言され根拠づけられるのである。
それゆえ本書の主題となっているのは、単にアメリカ国内に限定された人権や差別のことではない。それは、西洋と東洋、白人と有色人、キリスト教と他宗教、権力をもつ者ともたざる者といった多くのパターンに繰り返しあらわれる人間に共通の認識様式である。この認識様式は、合理的な思考や明晰な意識にのぼらない領野で神話的な構造��と転化し、他のすべての神話がそうであるように、われわれの見方や考え方を背後から支配する力をもつ。
このような隠然たる神話的支配を意識の明るみへともたらしてくれるのが本書である。物語の名手モリスンは、この普遍的は認識様式のからくりをごく小さな個人的で特異な出発点から展開してゆく。彼女によると、「黒人」はアメリカだけに存在する。彼らは「アフリカ系アメリカ人」とも呼ばれるが、アフリカに住むアフリカ人は、それぞれガーナ人でありナイジェリア人でありケニア人である。唯一の例外は南アフリカ共和国に住む人だが、こうした事実からしても、「黒人」が科学的な概念ではなく文化的な概念であり、人種という価値軸の中で序列化された概念であることが理解できるだろう。アメリカにおける黒人と白人は、お互いが自己を定位するために相手を必要とするという意味で、ほとんど心理学的な「共依存」の関係にある。
アメリカの奴隷制度にはキリスト教も少なからず加担しているが、これもアメリカ史に固有のことである。聖書には、古代世界の通念として、ある人びとは自由人で、ある人びとは奴隷である、という事実が前提されている。だが、それはもっぱら戦争捕虜か債務によるもので、肌の色とは無関係である。というより、キリスト教は肌の色に関して本来まったく無関心である。聖書には、エチオピア出身の人びとも登場するし、そのなかには伝説の美女や高位の官僚もいるが、彼らの肌がどのような色であったかについては、いっさい記述がない。中東人であったイエスや弟子たちの肌の色にも何ら言及がない。
ところが、アメリカのキリスト教は肌の色と人間の価値の間に、きわめて特異な緊張関係を構築していった。18世紀以降の奴隷解放運動を担���たのは多くのキリスト教指導者たちであったが、彼らに反対する頑固な奴隷制擁護論者もまた教会の牧師たちであった。前者が頭を悩ませ、後者がしたり顔に論じたのは、聖書が「神の前での平等」を語るものの、社会的現実としての奴隷制そのものを断罪していない、という事実である。やがて19世紀のアメリカでは、長い巻き毛で白人のイエスを強調した聖画が複製頒布され、広く流通していった。20世紀後半に始まった「解放の神学」が黒人のイエス像を前面に押し出すようになったのも、こうしたカラーコードへの反動である。
モリスンは、いくつかの特徴的な文学作品から、そしてさらに強烈な彼女自身の体験から、他者化の際に作用する「ロマンス化」の実例を描き出している。アメリカ史によく知られたハリエット・ビーチャー・ストウの小説『アンクル・トムの小屋』(1852)もその一つである。この小説が当時の白人想定読者層にどのようなメッセージとして受け取られたのか。そこに、奴隷制度の野蛮で残酷な現実を覆い隠し、あたかも非人間的なことは何も起こっていないかのような安心感を与えるロマンス化の作用がある。
しかし同時に、読者はこの読み直しが他ならぬモリスンの語りによって薄暗がりの中から明るみへと引き出されてきた、ということに気づかされるであろう。他者の存在は、自分が「他者の他者」であるという立場の交換により、はじめて鮮明に意識される。われわれは、自分という存在の限定性から自由になることはできない。だが、文学の虚構を通して擬似的に他者の視線をもつことができ、その他者の視線を通して自分を見つめ直すことができる。本書は、アメリカの黒人という特異点を設定することにより、それぞれの読者に自分では開くことのできない窓を開けるはたらきをしてくれる。その窓を通して、読者は自分を取り巻く現実とは違う世界に目を向けることができるようになるのである。
モリスンは本書末尾で、「自分たちの故郷にいながら故郷にいるとは言えない人びと」についても語っている。おそらくそれは、肌の色の如何にかかわらず、アメリカ国内の各地で人びとが感じ始めていることだろう。ここにも、われわれの想像力を呼び覚ます別の声が響いている。トランプ大統領の登場は、自分の国で自分の土地に暮らしていながら、いつの間にか「よそ者」のように扱われていると感じる人びとがいかに多いかを明らかにした。グローバル化の見えざる圧力は、大都市で世界を股にかけて活躍する国際派のエリートたちよりも、小さな田舎町で穀物の値段を気にかけつつ生きるほかない人びとに重くのしかかるだろう。そのひとりひとりに、自分が本来帰属すべき場所があり、心に感じながら生きるべきディープ・ストーリーがあったはずである。
人は誰も、自分ひとりでは幸せになれない。どこかに属し、誰かと繋がっていなければ、自分の存在意義を確認することもできないのである。もしそういう居場所が現実世界で見つけられなければ、ネットという仮想空間にそれを求めることがあっても不思議ではない。他者化の力学は、そこにも作用することだろう。人はそこで、生暖かい温もりに包まれたり、凶暴な正義感に酔い痴れたりして、日常と祝祭の間を行き来する。
他者の眼差しは、ときに人を不安にさせ、居心地を悪くする。日本人はこれまで、自分から海外へ出かけて行かない限り、こうした視線を向けることも向けられることも少なかった。しかし今や、日本を訪れる外国からの旅行者は爆発的に増え、外国人の労働力なしには日常生活すら回らないほどになっている。毎日の買い物で釣り銭を受け取るとき、あるいは地方の鄙びた温泉にゆっくりと浸かる安らぎを破られたとき、われわれの他者認識と自己認識には、どのような他者化の作用がはたらくことだろうか。
ターネハシ・コーツによる序文
2016年春、トニ・モリスンは、「帰属の文学」についてハーヴァード大学で連続講演を行った。これまでになされてきた数々の非凡な仕事を思い起こせば、モリスンが人種という課題に目を向けたのも驚くにあたらない。その講演はまさに時宣を得ていた。バラク・オバマ大統領は、二���目の最後の年を迎えていた。支持率は上向きだった。「ブラック・ライヴズ・マター(黒人の命も大事)」というスローガンを掲げた活動が盛んになり、黒人への「警察暴力」が全米的な話題として社会の前面に押し出されていた。これまでの「人種問題をちょっとかすめるだけの話題」とは違って、今回は結果を伴っており、効果も出ていた。オバマ政権時に、ふたりのアフリカン・アメリカン、司法長官エリック・ホルダー(在任2009〜15)とロレッタ・リンチ(在任2015〜17)は、全米の警察署の調査を開始させた。ファーガソン、シカゴ、ボルティモアでの騒乱が報告され、これまで長い間、瑣末な出来事として処理されていた、いわば組織的人種主義が現実のものであることを明らかにした。この積極的な問題解明の姿勢は、アメリカ合衆国の最初の女性大統領になるはずだった、ヒラリー・クリントンによって継続されていくものと期待されていた。じっさいトニ・モリスンが連続講演を始めたときには、政治家としてはライト級と見なされる、つまらぬ男に比べて、ヒラリーの好感度はきわめて高かった。これらのことはすべて、さまざまな歴史的規則に果敢に挑戦している国が、今、道徳の領域において長く伸びるアーチの、正義の先端へついに近づいているという動かしがたい証拠だった。
ところが、アーチの先端はさらに先へと伸びて行き遠ざかってしまった。
ドナルド・トランプが勝利すると、それに対する最初の反応は、アメリカの人種主義などたいしたことではないと矮小化することだった。零細企業の人びとが立ち上がり、2016年の大統領選挙は、ニューエコノミーに見捨てられた人びとが推進する、反ウォール・ストリートのポピュリスト的反乱であると決めつけられたのだった。クリントンは、「アイデンティティ政治」にこだわりすぎたために命運がつきてしまった、と批判された。
こういった議論は、しばしばかれら自身の破滅の種を産むことになる。ニューエコノミーに見捨てられやすい人びと──黒人やヒスパニックの労働者──がなぜトランプ陣営に入らなかったのか、その理由はまだ説明されていない。そのうえ、クリントンの「アイデンティティ政治」を批判する、まさにその人びとのなかに、「アイデンティティ政治」を利用するのにやぶさかではない者がいた。バーニー・サンダーズ上院議員は、クリントンの対立候補の筆頭だったが、あるときは自分のルーツが白人労働者階級にあると誇らしげに語り、またすぐその翌週には「アイデンティティ政治」を「乗り越えよう」と、民主党員に発破を掛けた。「アイデンティティ政治」とは、どうも等しく同じことを意味しておらず、かならずしも「生まれながらにして平等」を意味するのではないようである。
『「他者」の起源』(2017。The Origin of Others)──モリスンの新しい本は、ハーヴァード大学で行われた連続講演から生まれたが──ドナルド・トランプの台頭の背景とじかに関連しているのではない。だがモリスンの「帰属」の思考や、社会の保護下にだれが置かれ、だれが外されているのか、などを読み解くために、わたしたちは今日の状況を考慮しなければならないだろう。『「他者」の起源』は、アメリカの歴史を精査し、アメリカ史上最古の、しかももっとも影響力のある「アイデンティティ政治」について語っている──すなわち人種主義という「アイデンティティ政治」である。本書は、「よそ者(外国人)」の創出、「壁」の建設、文学理論・歴史・回想録について書かれているのだが、すべてはいかにして、いかなる理由によって、わたしたちはこれらの種々の「壁」を肌の色と結びつけてしまったのか、それを理解するためである。
本書は、20世紀の、消しがたい白人至上主義の本質に巧みに迫った一群の研究書と軌を一にしている。モリスンが同志と見なすのは、スヴェン・ベッカート(ハーヴァード大学教授。歴史学者。『コットン帝国──グローバル・ヒストリー』(2014)でバンクロフト賞を受賞)やエドワード・バプティスト(コーネル大学教授。歴史学者。『語られない半分──奴隷制度とアメリカ資本主義の生成』(2014))などで、かれらは白人至上主義の暴力的な性質や、そこから生み出される資本主義的利益の実態を暴露した。ジェイムズ・マクファーソン(プリンストン大学名誉教授。歴史学者。『自由への叫び──南北戦争の時代』(1988)でピューリッツア賞を受賞)やエリック・フォーナー(コロンビア大学名誉教授。歴史学者。『業火の試練──エイブラハム・リンカンとアメリカ奴隷制』(2010)でピュリッツア賞・バンクロフト賞などを受賞)は、人種主義が南北戦争勃発の契機を育み、その後、いかに再建の国家的努力をむしばんだかを明らかにした。ベリル・サッター(ラトガース大学教授。歴史学者。『家族の所有地──人種・不動産・都市の黒人搾取』(2009))やアイラ・カッツネルスン(コロンビア大学教授。政治学および歴史学者。『恐怖──ニューディールとわれわれの時代の源』(2013)でバンクロフト賞を受賞)は、人種主義がニューディール政策を腐敗させたことを解明する。カリル・ギブラン・ムハマド(ハーヴァード大学教授。歴史学者。『ブラックネスの糾弾──人種・犯罪・今日のアメリカの都会の創生』(2011))やブルース・ウエスターン(コロンビア大学教授。社会学者。『アメリカの刑罰と不平等』(2006))は、人種主義がわたしたちの時代において大量投獄への道を開いたことを明らかにした。
その中でもモリスンの仕事にもっとも近いのは、『レイスクラフト(人種狩り)』(2012)だろう。この本はバーバラ・フィールズ(コロンビア大学教授。歴史学者。『レイスクラフト(人種狩り)』(2012)の共著者)とキャレン・フィールズ(歴史研究者。『レイスクラフト(人種狩り)』(2012)の共著者)の共著で、アメリカ人は、能動的に作用する「人種主義(レイシズム)」の罪を、本来そのような作用を起こさないはずの「人種(レイス)」という言葉にすり替え、消し去ろうとしてきたという。一般にわたしたちが「人種主義」に対して「人種」と言うとき、「人種」とは自然界の特質を指し、「人種主義」はその当然の結果であると認識している。だがそれはまったく逆である。すなわち「人種主義」が「人種」という概念より先にあり、「人種」を証明しようと研究を積み重ねているのである。それにも��かわらず、アメリカ人は、いまだに論点を正確に把握していない。そのためわたしたちは、「人種差別」「人種的溝」「人種の分離」「人種的プロファイリング」「人種的多様性」といった言葉を平気で口にする──あたかもこれらの考えが、わたしたちが作り出したものではなく、別のところに根拠があるかのように。このことが及ぼす影響は些細なものとはとても言えない。「人種」が遺伝子とか神々、あるいは両者による作用の結果というなら、この問題を根本から打ち壊してこなかったとしてもしかたがない。
モリスンの問いは、「人種」と遺伝子の接点はわずかしかない、といういささか説得力に欠ける考えから始まっている。そこからモリスンは、何の根拠もないと思われる浅はかな考えが、なぜ何百万人もの心をつかんでしまったのか、わたしたちにヒントを与えてくれる。非人間的行為を通して、自分の人間性(ヒューマニティ)を確認したいという欲求が鍵だ、とモリスンは論じている。そこでジャマイカの大農園主トマス・シスルウッド(1721〜86)の記述を取り上げる。シスルウッドは、まるで羊毛刈りを記録する気やすさで、奴隷女たちを相手にした連続レイプの記録を日記に残している。性行動の合間に、農業・雑務・客の訪問・病気などについて記している、モリスンはぞっとしながら述べている。レイプに対してこんなにも無感覚になれるとは、シスルウッドの心の中でいったいどのような心理作用が起きていたのか。「他者化」の心理作用──奴隷王と奴隷との間には、自然で、ある種の神性を帯びた線引きが存在するのだと、自分自身を納得させること。さらにモリスンは奴隷のメアリ・プリンスが女主人からひどく叩かれたことを分析して、以下のように述べている。
奴隷が「異なる種」であることは、奴隷所有者が自分は正常だと確認するためにどうしても必要だった。人間に属する者と絶対的に「非・人間」である者とを区別せねばならぬ、という緊急の要請があまりにも強く、そのため権利を剝奪された者にではなく、かれらを創り出した者へ注意は向けられ、そこに光が当てられる。たとえ奴隷たちが大げさに語っていると仮定しても、奴隷所有者の感覚は奇怪きわまりない。まるで、「俺はけだものじゃないぞ! 俺はけだものじゃないぞ! 無力なやつらをいじめるのは、俺さまが弱くないってことを証明するためさ」と吠えているようだ。
「よそ者」に共感するのが危険なのは、それによって自分自身が「よそ者」になりうるからである。自分の「人種化」した位置を失うことは、神聖で価値ある差異を失うことを意味する。
モリスンは、奴隷を創り出す者と創り出された奴隷とについて語っているのだが、その社会的位置に関する指摘は今日でも正しいだろう。とくに過去数年間ずっと、アメリカの警官が黒人を比較的軽い条例違反で、あるいはまったく違反していないというのに、殴ったり、テーザー銃(スタンガン)を発射したり、首を絞めたり、���殺している映像が次々と流されてきた。そのためアフリカン・アメリカンのみならず、多くのアメリカ人が恐怖に陥っている。にもかかわらず、このような行為を正当化する言説がはびこっている。警官のダーレン・ウィルソンがマイケル・ブラウン(1996〜2014)を射殺したとき(2014)、「銃弾の雨あられの中を大きな塊が走り抜けた」ようだったと報道記者に語っている。まるでブラウンが人間とはかけ離れた大きな生き物に見えたようだが、じっさい人間以下と見なしているのだ。遺体を真夏の焼けつくアスファルトの路上に放置したことがその証拠で、人間以下の扱いが強く印象づけられた。ブラウンを怪物のように描いて殺人を正当化したウィルソンは、──司法省の報告によれば──まさにギャングと大差ないような警察官たちの職権濫用もまた許し、自分たちは非の打ち所のない人間だと主張させているのである。
人種差別主義者の対象を非人間化する行為は、象徴の領域の話ではない──現実上の権力の領域に及んでいる。歴史学者のネル・ペインター(プリンストン大学名誉教授。歴史学者。『白人の歴史』(2010))は、「人種とは考えかたであり事実ではない」と主張している。アメリカにおける人種に関する考えかたのもとでは、肌の色が白い場合は、マイケル・ブラウンやウォルター・スコット(1965〜2015)、エリック・ガーナー(1970〜2014)のように警察暴力による死を遂げる確率の低いことは明白である。しかもこのような死は、「他者」として生きるということの意味、偉大な「帰属」の枠外にいることの意味を示す最適の例である。いわゆる「経済不安」がドナルド・トランプ陣営へ投票社を引き寄せたと言われるが、かれらは大多数の黒人から見れば、明らかにより豊かな人々であった。共和党の予備選挙で、トランプに票を入れた者の世帯収入の平均値は、アメリカの平均的黒人世帯収入の約二倍だった。現在、多くは白人の(とはいえ全員ではない)間に見られる、合成麻薬の流行への危機感は、1980年代のコカイン危機に見られた非難の嵐とは違っている。特定の白人男性の死亡率には敏感に反応する今日の関心のありかたは、この国でこれまでずっと黒人の生命を脅かしてきた、黒人の高い死亡率の原因からは目を背ける、あの冷淡さと様相を異にしている。
人種主義は問題である(レイシズム・マターズ)。この国で他者でいることには重大な結果が伴う。──悲しいことにこれからその先も解決策は見つからず、問題でありつづけるだろう。人間社会は、素朴な利他主義のために、これまで持っていた特権を簡単にあきらめたりはしない。かくして白さを信奉する者がその信仰を捨てる社会は、これまでの特権が入手困難なぜいたく品になった社会しかない。アメリカの歴史上、そのような瞬間を何度も見てきた。長引いた南北戦争の結果、黒人もそれなりの人生をまっとうするにふさわしい��、白人は結論づけるにいたった。ソ連との冷戦は、黒人差別法であるいわゆる「ジム・クロウ法」が支配する南部を世界中の物笑いの種にし、敵側諸国に格好の宣伝工作の材料を与えてしまった。ジョージ・W・ブッシュ政権では、二度にわたる泥沼戦争(2001年のアフガニスタンおよび2003年のイラク攻撃を指す)、経済の急降下、ハリケーン・カトリーナ(2005年にアメリカ南部を襲ったアメリカ観測史上最大級の超大型ハリケーン)における連邦政府の組織的初動ミスが、アメリカ初の黒人大統領誕生の道を拓いた。このような出来事が起きるたびに、アメリカは歴史上の慣例を打ち破ったぞ、というひとかけらの希望が湧いたものだ。ところがそのたびに、希望は最終的には泡となって消えてしまう。
わたしたちが、なぜふたたびこのような状態にいるのかを理解するために、アメリカが生んだ最高の作家・思想家であるトニ・モリスンがいることは、なんと幸運であるか。モリスンの仕事は歴史にその根があり、ひどくグロテスクな歴史的事象からも美しさを引き出してくる。その美は幻想ではない。歴史がわたしたちを支配していると考える人びとのひとりに、モリスンが数えられているのも驚くにあたらない。『「他者」の起源』は、この理解を詳細に説いている。過去の呪縛からただちに解放される道が提示されなくとも、その呪縛がどうして起きたのかを把握するための、ありがたい手引きになっている。
✲ ターネハシ・コーツは1975年ボルティモア生まれ。作家・ジャーナリスト・漫画家。アトランティック、ヴィレッジ・ヴォイス、ニューヨーカーなどに寄稿。2015年、『世界と僕のあいだに(Between the World and Me)』で全米図書賞受賞。アフリカン・アメリカンについて、また白人優先主義に関する記事でよく知られる。2015年、「天才」に与えられるマッカーサー財団の助成金を授与される。父親は、ヴェトナム帰還兵で、小さな出版社を営む。
著者 トニ・モリスン(Toni Morrison)
1931年、米国オハイオ州生まれ。コーネル大学大学院で英文学修士号取得後、ランダムハウスで編集者として活躍しながら、70年に『青い眼がほしい』で作家デビュー。77年の『ソロモンの歌』で全米批評家協会賞、アメリカ芸術院賞、87年の『ビラヴド』でピューリッツァー賞受賞。89年から2006年までプリンストン大学の教授を務め、93年にはアフリカ系アフリカ人として初めてノーベル文学賞を授与される。他の代表作に『スーラ』『ジャズ』『パラダイス』『白さと想像力』など。
解説 森本あんり(Morimoto Anri)
1956年、神奈川県生まれ。国際基督教大学(ICU)教授・学務副学長。著書に『反知性主義』『異端の時代』など多数。
訳者 荒このみ(Ara Konomi)
1946年、埼玉県生まれ。米文学者。東京外国語大学名誉教授。
2 notes
·
View notes
Quote
読み終わったので自分的ハイライト集。 小学館含む原作者側がどれだけ振り回され、心労を負ったか、という点にフォーカスしているのか日テレ版で言うところのラリーの詳細が多い。 漫画家の芦原妃名子先生がご逝去されたことについて、改めて、先生の多大な功績に敬意と感謝の意を表するとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 重箱隅つつきなのはわかりつつ。報告書冒頭にはまずこれがあるべきですよね。 (日テレ版は報告書本体のリンク元であるプレスリリースには同様の記載があるが、肝心の報告書冒頭には記載していない) 社員 B は、日本テレビ社員 Y 氏とその上司の日本テレビ社員 X 氏とやり取りして 日テレの2人目の対応者って上司やったんかよ!!!いやそんな気はしてたけどさ!!! そもそも小学館側はきちんと担当部署だけでなく、各社員と上司を明示していてこの時点で日テレ版より分かりやすさが違う。 特に問題はないという意見を示しつつ、気になる点として、第 2 話脚本中に若い男女のメッセージのやり取りをメールでさせていることについて、今どきは LINE が普通ではないかと指摘したり 「今時のJKは短大よりも専門学校だ」という議論をできるドラマスタッフが、今時の男女のメッセージやり取り事情に精通していないなんて…。 また併せて飼っていたハムスターの逃走範囲に関するセリフについて、原作漫画の 100M 以内との吹き出しの記載を 200M 以内に変更した点にも疑問が呈された (略) ヒンズー教徒が多いインドでベリーダンスをするという点に疑問を呈した (略) またダンスの動画についても、初心者に過ぎない田中さんのダンスが動画で評判になるほどのものではあり得ないこと等の理由を詳細に説明して、日本テレビの補足説明中の提案を認めなかった。 日テレ版では省略されていた「ツッコミどころの多い辻褄の合わない改変」の具体的な例をきちんと書いてくれてますね。 「めっちゃ打ち合わせして議論してより面白くなるよう頑張ったんすよ」アピールしてた日テレさん、これも全て改変の意図がきちんと伝わらなかったの一言で済ますの? 社員 A は、上記の 10 月 2 日の日本テレビ社員 Y 氏あてメールで、本件脚本家に関して次のように問いかけている。 「確認なのですが、芦原さんが描き下ろした 8~10 話は基本的に変更無しで使用してほしい、という話は●●さん(本件脚本家。原文は実名)に伝わっていますか?●●(社員 B。原文は実名)から●●さん(日本テレビ社員 X 氏。原文は実名)にもお電話差し上げたのですが、そのお話しは●●さん(日本テレビ社員 Y 氏。原文は実名)に伝わっていますでしょうか?」 以後のメールで日本テレビ社員 Y 氏がこの点について回答した形跡はない。また本件脚本家によると、同氏は一切聞かされていないとのことである(本委員会質問に対する回答) 都合の悪いメールは読まなかったことにして��視、切羽詰まるとよくあるよね~(あるなよ) 10 月 5 日 16 時 45 分、芦原氏は社員 A に第 3 話脚本のシーン 50 で演じられるダンスが「ハリージ衣装でドラムソロを踊る」ことになっているが、これを「普通のドラムソロ」に変更するように日本テレビ社員 Y 氏に急ぎ伝えるよう要請した。 芦原氏が問題としてい���のは、同シーンでベリーダンスを田中さんがステージで踊る際、演出では「ハリージ衣装でドラムソロを踊る」こととされていた点であり、芦原氏は、社員 A に対して、ハリージ衣装でドラムソロを踊ることは、ベリーダンスの歴史的、文化的背景としてあり得ないので日本テレビ社員 Y 氏に確認してほしいと求めたのである。芦原氏の求めを受けた社員 A が同日 19 時 50 分ショートメールで、日本テレビ社員 Y 氏に対し、芦原氏からの依頼として、「ハリージ+ドラムソロ」はダンスの監修者が OK しているとは思えないので確認してほしいとの依頼があったことを伝えた。 これに対して日本テレビ社員 Y 氏は社員 A に対して直ちに、ダンス監修者には「OK 頂いている」という認識であるが、改めて確認すると返し、同日 23 時 35 分にダンス監修者から OK の確認が取れたと連絡してきた。 しかしこの時、実際にダンス監修者が OK と言っていたかという点には疑問が残る。 (略) ところが、後日、芦原氏は、「ハリージ衣装でドラムソロ」はあり得ないことを認識した。芦原氏は、日本テレビ社員 Y 氏(なお、撮影は 10 月 10日を予定していたが、日本テレビ社員 Y 氏は社員 A からの 10 月 5 日の問い合わせに撮影済みであると虚偽の発言をしていた。このことでも芦原氏は不信感を募らせていた)の対応に不信を募らせ、間違った有りようのダンスが公に放映されることを看過できず、ダンスの監修者の名誉のためにも撮り直しをするか、それができないなら番組 HP や DVD への釈明文掲載等を日本テレビに要求するように社員 A に依頼した。 3話リテイクの経緯詳細。 日テレ版では、 2023 年 10 月上旬、ドラマ撮影時に撮影シーンを巡って本件原作者が A 氏に対して不信感を抱く事案があった。A 氏は、C 氏より送付された本件原作者の意向に従って当該撮影内容としたつもりであったが、本件原作者はそのような趣旨では依頼していない認識であったため、C 氏に確認を依頼した。 C 氏を通じた本件原作者の撮影シーンに関する問い合わせに対し、A 氏は既に当該シーンは撮影済みである旨回答を行ったが、実際の撮影は 5 日後に予定されており、そのまま予定通り撮影が行われた。 その後、これらの経緯を本件原作者が知ることになった。A 氏によると、まだ撮影していない旨を回答すると本件原作者から撮影変更を求められるのは確実であると思ったが、A 氏は当該撮影シーンは客観的にも問題ないものだと思っていたこと、及び当該シーンの撮影のために 2 か月にわたってキャスト・スタッフが入念に準備を重ねていたため、撮影変更はキャストを含め撮影現場に多大な迷惑をかけるので避けたいと思って咄嗟に事実と異なる回答をしてしまった。このことは反省しているということであった。 と、「撮影前を撮影済みと嘘ついちゃいました、てへぺろ☆」なことしか書かれてないけど、その前に「ダンス監修者の了承が本当にあったのか?」という日テレ担当者の信頼度をさらに下げる一幕があったんじゃねーか!!!! まさか「今から変更したらみんなに迷惑かけちゃう…」という我が身可愛さで嘘付く人でも「ダンス監修者の了承はきちんと取っていたに違いない」と信じてるの? そしてどういうつもりで削ったの?(一応、読み落としたかと思って日テレ版を「ダンス監修」で検索してみたが見当たらない) この間、社員 J が 7 月 27 日に日本テレビに送信した契約書案に対して同社から 9 月 26 日に修正案が戻された。 その中では、改変についての原作者の承諾に関し、小学館提示の原案では小学館と原作者双方の同意が必要としたものを、日本テレビは、日本テレビとして合意を得るべき相手を小学館に限定する修正依頼があった。 原作者の承諾は不可欠であるため、小学館を介して原作者の承諾を得ることに修正し、社員 J は部内の承諾を得たうえ、10 月 23 日に日本テレビに送った。 うーんこの。日テレが原作者をどう思ってるか本音ダダ漏れなの草でしょ。 社員 A のメールは貴重な記録であるが、社員 B は大抵、日本テレビ社員 X 氏と電話で交渉したようであり、文章になった資料の提出はなかった。 本委員会において認定根拠としえたのは、社員 A への LINE メッセージである。日本テレビ社員 X 氏との電話交渉についてもより詳細な記録があれば事実経過の理解に役立ったと思われる。また、膨大な業務をこなしながら、日常行うのは大変かもしれない。 しかし交渉過程の記録はビジネスの鉄則である。記録がなければ、万一担当者に事故があればその成果は継承されない恐れがある。 多くの会社では、日報・日誌等で経過を報告し、上司・同僚と共有するのが普通である。そこから問題点の指摘を受けることもある。 ほんこれな。日テレ版もそうだったが電話で交渉しましたが多すぎる。 証拠を残さないために電話を使うのはあるあるだが、トラブる前の段階やネゴるところも全部電話で済ませるとか怖すぎるわ。
小学館版 田中さん報告書の見所
4 notes
·
View notes
Quote
●オッペンハイマー 「原子物理学の発見によって示された人間の理解力は、 必ずしもこれまで知られていなかったわけではない。 また、別段新しいというわけでもない。我々の文化にも先例があり、 仏教やヒンズー教では中心的な位置を占めていた。 原子物理学は、いにしえの智慧の正しさを例証し、強調し、純化するものだ」 ●アインシュタイン 「現代科学に欠けているものを埋め合わせてくれる宗教があるとすれば、 それは『仏教』です」 「仏教は、近代科学と両立可能な唯一の宗教です」 ●ニーチェ 「仏教はキリスト教に比べれば、100倍くらい現実的です」 「仏教は、歴史的に見て、ただ一つの きちんと論理的にものを考える宗教と言っていいでしょう」 ●ショーペンハウアー 「私は他のすべてのものより仏教に卓越性を認めざるをえない」 ●バートランド・ラッセル 「今日の宗教では、仏教がベストだ。 その教えは深遠で、おおよそ合理的である」 ●ユング 「仏教はこれまで世界の見た最も完璧な宗教であると確信する」 ●H・G・ウェルズ 「現在では原典の研究で明らかになったように、 釈迦の根本的な教えは、明晰かつシンプル、 そして現代の思想に最も密接な調和を示す。 仏教は世界史上知られる最も透徹した知性の偉業である ということに議論の余地はない」
【兵庫】「神様はアラーしかいない」「ここで祈るな」 ガンビア人の男、神社で暴れ賽銭箱など次々破壊…日本ムスリム協会が非難声明 ★5 [樽悶★]
24 notes
·
View notes
Text

本日は(2月14日)、ネパールのこよみの上で季節が冬と春とにわかれる日「節分」です。ヒンズー教では「バサンターパンチャミ」という特別な日です。「バサンターパンチャミ」は「立春」で、春の始まるを感じさせる日です。これから気温が上がってきて「シャクナゲ」や「ジャカランダ」など、春の様々な花が咲き始め、暖かい空気の中、花の香りが漂います。
「バサンターパンチャミ」は「サラショティ・プジャ」という特別な行事もあります。学問「知識、音楽、芸術、文化など」の女神様「サラショティ」のお祈りする特別な日です。ネパールではヒンズー教の人々は教育機関に集まって女神様のお祈りをします。子供たちに字を教えたり、入学させたり、文房具をプレゼントしたりする特別な日です。「サラショティ・プジャ」の日「サラショティ神」のお寺の壁は子供たちが自分の名前や字を書いて文字だらけになります。
6 notes
·
View notes
Text
インド

2023.11.20
・
9万人のインドの教会の映像は
やはりインパクトがあって
その日子どもたちと大いに盛り上がりました。
その中で
・
インドはヒンズー教が多く占めているけど
クリスチャンであることは
大変だったりしないのかな🤔
・
と子どもたちと話していたのですが
今日の礼拝の中で
特に北インドに住むクリスチャンの方々は
厳しい状況下にいて
とりなしの祈りが必要であることを
聞くことができました。
これから��っていきたいと思います。
・
(写真:今日はとてもいいお天気でしたが、
風が冷たかったです。)
6 notes
·
View notes
Text
ダーラムの問題は、彼が決して正しい仕事とは言えない間違った人間だったということかもしれない。彼はFBI や司法省の他の人々の助けを借りて名声を確立していました。 彼らは、彼がマフィアの捜査に使用した多くの証拠、つまり潜入捜査員、情報へのアクセス、盗聴、分析と監視のための人員の追加人員を彼に提供していた。彼は何年にもわたって友情を築き、維持し続けてきました。しかし、ワシントンの同僚を捜査する場合、��を寄せる必要はない。
彼と一緒に仕事をしていた人の中には、FBI が FISA の手続きを巧みに操り、特別法廷で思い通りに事を進めることが容易にできることをダーラム氏が理解しているかどうかは明らかではなかった。また、諜報機関の真面目な活動家たちが自分たちを法を超越しているとどの程度考えているかも理解していなかった。CIA本部から高速道路を下ったところにある中華レストランで、中東から来た秘密工作員たちと一緒に食べたランチは決して忘れられない。彼らは彼らがFBIのドジっ子だと描いていることをからかっていた――これは9/11直後のことだった――そして私はそのうちの一人に、犯罪を解決するために全員で協力しなければならないのに、どうしてFBIを嘲笑できるのかと怒って尋ねた。彼の答えはこうだった。「ねえ、FBI?FBI?彼らは銀行強盗を捕まえます。そして私たちは銀行強盗をします。そしてNSAは?シャツのポケットに分度器を入れていて、いつも茶色の靴を見下ろしているような男たちと私が仕事をすることを期待しているのですか?」
結局、ダーラムの名誉のために言っておきますが、彼は自分の信念を貫き、この脚注でクリントン陣営の行動についてさらに深く調査を拡大することを望んでいた人たちについてどう思うかを述べました。
「明確にしておきますが、当庁は、ある陣営による、敵対者に対する否定的な主張を広めるという政治的計画の存在の可能性を、いかなる点においても違法または犯罪であるとは考えていませんし、またそのような考えもしていません。」しかし、「政府に故意に虚偽の情報を提供する」キャンペーンは別問題になるだろうと同氏は付け加えた。
この 2 つをどのように区別するかが問題の核心です。ダーラムは、この言葉が適切であれば、物語全体を理解することができなかった点で、象を検査する盲人のグループについての古代ヒンズー教の寓話に登場する盲人の一人に似ています。各検査官は小さな部分について説明します。象とは、トランプ大統領とロシアを結びつけようとするキャンペーンのことだ。主流マスコミは、後に信用を失ったロシアゲートの物語を報道し、トランプをプーチンの傀儡として、あるいはソ連時代に遡るモスクワの二重スパイとしてさえ描いている。そしてダーラムは自分自身を単にFBIの管理上の欠陥を調査するよう命じられた弁護士だと考えている。一般の人は写真の一部しか見ることができません。
知るべきことはまだあります。
ロシアゲートに欠けている部分
ダーラム報告書では何が語られなかったのでしょうか?
シーモア・ハーシュ
3 notes
·
View notes
Text
ヒンズーのダキニ天信仰を輸入したが日本にはジャッカルは居ないので似た姿の狐を祭神とすることで発生したのが稲荷神社信仰という説もある
“稲作には、穀物を食するネズミや、田の土手に穴を開けて水を抜くハタネズミが与える被害がつきまとう。稲作が始まってから江戸時代までの間に、日本人はキツネがネズミの天敵であることに注目し、キツネの尿のついた石にネズミに対する忌避効果がある事に気づき、田の付近に祠を設置して、油揚げ等で餌付けすることで、忌避効果を持続させる摂理があることを経験から学んで、信仰と共にキツネを大切にする文化を獲得した”
— キツネ - Wikipedia (via mug-g)
4K notes
·
View notes
Text

x.com/GozukaraFurkan/status/1920398038423457960/video/1 記者「パキスタンよ永遠なれ?」 少年「永遠なれ」 記者「恥ずかしくないのか?」 少年「なぜ恥ずかしがる必要が?」 記者「パキスタンは滅ぼされるべきではない?」 少年「は?もちろん滅ぼされるべきではないよ」 記者「インドよ永遠なれ。イエスかノーか?」 少年「イエス」 記者「パキスタンよ永遠なれ。イエスかノーか?」 少年「イエス。どの国もその国のスペースで永遠なればいい。あなたも自分のスペースで暮らしているんだろう?」 記者「名前は?」 少年「ケイフだ」 記者「フルネームは?」 少年「ムハマド・ケイフだ」 記者「出身は?」 少年「ビハールから」 記者「インドに住みながらも、パキスタンを支持しているってことを少しも恥ずかしいとは思わないのか?なぜパキスタンを滅ぼしてはいけない?」 少年「あなたはそんなことを大事として報じていて、恥ずかしくないのか?そんなことをニュースにしていて、恥ずかしくないのか?ヒンズーとムスリムの問題にして、そこらじゅうに言いふらして。なぜインドを支持するかって?そ���前にまず答えて。あちらにも人びとがいる。こちらにも。向こうにもムスリムがいる。ヒンズーがいる。みな人間だ。なぜ“皆殺し“にする必要がある?教えてくれよ?なぜ皆滅ぼす必要がある?教えてくれよ?誰にも生きる権利がある。誰にでもだ。ならなぜ彼らを滅ぼす必要が?」 記者「君はパキスタンを支持するのか?」 少年「向こうに行ってあなたが誰かに殺されたとする。それで全ておしまいか?」 記者「君はパキスタンを支持するのか?」 少年「支持するよ」 記者「君はインド人ではないのか?」 少年「インド人だよ。あなたはあの国を滅ぼせという。滅ぼせと。けど、どこも人が住んでいるんだよ。」 記者「これだけ訊かせてくれ。誰がそんな考え方を教えた?」 少年「自分の頭だよ。決まってるだろ!」
0 notes
Text

ちょっと力強過ぎたかな。
「創造をつかさどる神」なんですよね・・
#AI#生成AI#AIart#AIイラスト#bingimagecreator#DALLE#AIArtworks#illust#AI画像#illustration#dalle3#aiart#openai#ブラフマー#Brahma#ヒンズー教#hinduism
0 notes
Text

【トランプテクニック】カードをバレずに簡単に選ばせるフォース ヒンズー・シャッフルver. 解説付き マジック 手品












0 notes
Text
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和六年(2024年)8月7日(水曜日)
通巻第8359号
バングラデシュは暴動から政権転覆。「黒幕はパキスタンと中国」とインド
インド紙は「イスラム過激派のテロリストが政変を計画していた」と報道
*************************
8月5日、ハシナ首相はヘリコプターにとりあえずの財宝(スーツケース数個)を積んでパキスタン空軍基地からインドへ脱出した。嘗て「民主主義のイコン」といわれた彼女も15年間、権力の座にいるうちに“腐った”林檎になったのか。
他方、自宅監禁になっていたジア前首相は自由の身になった。ジアは大統領未亡人で1991年に夫が暗殺されると首相となり五年間、バングラ国政を担った。BNP(バングラ・ナショナル党)党首でもあり、反ハシナ路線を唱え、2014年と2024年の総選挙をBNPはボイコットしてきた。
学生による暴動で死者は430名以上、負傷者数千。幕切れは呆気なくハシナ逃亡とともに軍が暫定的に権力を掌握し、新政府顧問にムハメド・ユヌス(2006年度ノーベル平和賞、84歳)を迎える。ユヌスは”亡命先“のフランスからダッカへ戻る。
当面は陸軍司令官のウエイカー・ウズ・ザマンが暫定政府を舵取りし「早い時期に総選挙を実施する」としている。
学生たちの最初の要求は公務員枠の撤廃だった。これは建国の英雄(アブドラ・ラーマン)が主導した独立戦争で犠牲となった遺族の子供達が公務員の枠で優遇され、これが不公平というものだった。ハシナはラーマンのむすめである。なにしろバングラでは1800万人の若者に職がなく、数少ない輸出産業の繊維産業もコロナ禍以後、ZARAなどが工場を縮小したため不況に陥っていた。若い女性の500万人が繊維産業に従事しているが、中国資本の人使いの荒さにも不満が昂じていた。
暴動は公務員枠の不公平が原因とされるが、これは口実でしかなく(すでに数年前にハシナ政権が撤廃を声明)、実際の狙いは政権転覆にあった。
中核となったのは「ジャマート・エ・イスラミ」というテロリスト集団だ。現在の指導者は不明。だが、インド情報部によればアフガニスタンで軍事訓練を受けた形跡があるという
「ジャマート・エ・イスラミ」は1975年に結成され、一時期はBNPと連携していたが、ヒンズー撲滅などを唱えて過激化し、非合法とされて地下に潜った。
「ジャマート・エ・イスラミ」の過激学生セクトが「シャハトラ・シビル」と呼ばれ、イスラム同胞団、イスラムジハードならびにハマスと連携している。この「シャハトラ・シビル」が暴動を煽ったプロ活動家である。
▼習近平は「貸したカネを取り戻せるのか」と心配
インドのメディアは政変の黒幕はパキスタンと中国とした。しかし中国は、むしろハシナ政権との癒着、巨額の汚職が問題であり、政権転覆でメリットはない。
中国のBRI(一帯一路)は、合計1兆3400億ドルを世界165ヶ国に投じて、合計20000件のプロジェクトを展開している。
ハシナ首相が訪中はつい先日、24年7月10日のことである。
北京の人民大会堂でバングラデシュのハシナ首相と会談し、両国関係を「包括的戦略協力パートナーシップ」に格上げしたばかり。中国はバングラデシュに50億ドルを投じ、さらにハシナ政権は追加50億ドルを訪中時に要請した。習近平は、とりあえず10億ドルでどうかと打診していた。
またハシナは23年4月に訪日しており、独立以来バングラへの支援は巨額に登る。バングラ進出の日本企業はすでに340社、在留邦人は千名を超えており、安全確保が急務とされている。
バングラデシュは世界銀行から195億ドルを借りており、年間の利払いだけでも2・5億ドル。日本のバングラデシュ援助は
バングラデシュのテロ組織は、ほかにJMB(ジャマトゥル・ムジャヒデン・バングラ)がISILの影響下にあって、その分派が2016年に日本人7名を殺害したテロ事件を起こした。他にAAI(アンサール・アル・イスラム)がアルカイーデの流れを組むとされる。
11 notes
·
View notes
