#いまマルクスが面白い
Explore tagged Tumblr posts
Text

いまマルクスが面白い-現代を読み解く事典 いいだもも・伊藤誠・平田清明=編 有斐閣新書 有斐閣 カバーイラスト=与儀勝美
#いまマルクスが面白い-現代を読み解く事典#いまマルクスが面白い#いいだもも#伊藤誠#平田清明#有斐閣新書#karl marx#カール・マルクス#マルクス#与儀勝美#anamon#古本屋あなもん#あなもん#book cover
22 notes
·
View notes
Quote
(...)自己責任の感情をもって仕事に取り組む労働者は、無理やり働かされている奴隷よりもよく働くし、いい仕事をします。そして、ミスをしたら自分を責める。理不尽な命令さえも受け入れて、自分を追い詰めてしまうのです。これは資本家にとって、願ってもないことでしょう。“資本家にとって都合のいい”メンタリティを、労働者が自ら内面化することで、資本の論理に取り込まれていく。政治学者の白井聡は、これを「魂の包摂」と呼んでいます。
なぜ死ぬまで働いてしまうのか…マルクスの資本論が150年前に警告していた「過労死の根本原因」とは
26 notes
·
View notes
Quote
射撃場には鼻をつく臭いが立ち込めていた。すでに実弾が何発も発射されていたからだ。 私は「黒い森」と呼ばれるドイツの森林地帯の静かな町、カルフの郊外にある射撃場にいた。2020年の初めに、ドイツ国内で最も厳重に警備されている陸軍精鋭部隊「KSK」の基地の内部を訪問する珍しい機会に恵まれたのだ。 壊れたドアの枠に沿って、G36自動小銃を持った迷彩服姿の兵士がしゃがみ込んでいる。2つの影が飛び出すと、兵士は頭、胴体、頭、胴体の順で4回撃った。その後、彼は2ダースの「敵」を片っ端から撃ったが、一度も的を外すことはなかった。 私はKSKの司令官でボスニア、コソボ、アフガニスタンに従軍した歴戦の勇者マルクス・クレイツマイヤー将軍に取材するために、基地を訪れていた。クレイツマイヤーは隊員に、あるパーティーについて4時間も尋問していたという理由で、取材に遅れてきた。 問題のパーティーでは、6人のKSK隊員が、国内で違法行為とされているナチス・ドイツ式の敬礼を繰り返しおこなっていたという報告があがっていたのだ。クレイツマイヤーは、部隊に対する忠誠心と、双肩にかかる深刻な問題のどちらを選ぶべきかで悩んでいた。 「軍内部でこれほどまでに極右過激主義が台頭している理由はわかりませんが、KSKが他の部隊よりも思想的な影響を受けているのは、明白な事実です」と彼は述べた。 戦後のドイツで兵士として働くということは、決して容易ではない。ナチスの歴史と第2次世界大戦による破壊が、軍を矛盾した存在に追い込んだからだ。 何十年もの間、ドイツは民主主義とその価値観を代表する軍隊を作ろうとしてきた。だが、2011年に徴兵制を廃止して志願制になると、ドイツ軍はますます閉鎖的になっていく。 クレイツマイヤーは、彼の部隊の兵士の大半が極右政党「ドイツのための選択肢(AfD���)」の拠点である東ドイツの出身だと語った。彼は「KSKは創���以来、最も困難な局面に直面している」と認めたが、極右グループが同隊に潜入することを阻止するのは難しいと述べた。 ドイツ当局は、新兵の「価値観」が変化していると指摘する。ある兵士は自身の転機として、2015年の欧州難民危機をあげた。 シリアやアフガニスタンから何十万人もの移民・難民がドイツに殺到すると、兵士たちの間に不穏な空気が漂ったと彼は振り返る。 「私たち兵士はこの国を守る義務を負っているのに、国境では何の制御もできませんでした。そのとき、自分たちの限界を感じたんです……」
ドイツのネオナチが激白「軍内部などに同志2000人、隠れ家は国内数十ヵ所」 | 台頭する過激派に政府は打つ手なし… | クーリエ・ジャポン
15 notes
·
View notes
Text
2025.1.26 27:01 日
マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝の『自省録』を少しだけ読みました。立ち読みで。
最近、哲学者の名言とか、固有名詞をバシバシ出して会話する人が何となく多い気がします。なんかかっこいいんですよね、そういう人たちって。かっこよくて憎い!
それについて行きたいと必死になってしまいそうなのですが、そういう人たちと一緒の土俵に立つとか無理なので、無理の立場なりに思ったことを書いておこうと思います。
この本は、格言が載ってる系のビジネス書みたいな構成です。何百年、何千年も昔の人の言葉なのにすごく読みやすいですし、その格言たちを読むとわかるのが、今も昔も悩みってそんなに変わらないんだなぁ、ということ。笑
千年くらいじゃあ、人の思考は進化しないのでしょうか。普通の時間感覚で考えるとそれが不思議です。環境も立場も言語も、全くもって違う人の言葉が沁みる不思議。
意訳ですが、刺さってしまった言葉がありました。※ここからはうろ覚えなので正確な文言は本で確認してください。
「苦痛について
耐えられない苦痛は、消え失せるものである。
長く続く苦痛というのは、自分にとって耐えうる苦痛なのである。」
耐えられない苦痛からは自然と逃れる/逃れざるを得ない、もしくはもっと厳しくきつい言い方をすれば、それによって自分自身さえ消えてしまうかもしれない。
でも、その苦痛が長く続くとなると、それは「自分が向き合って生きていかなくてはならない事柄」なのかもしれない。
最近って、「辛かったら逃げていい」 「苦痛に思うことから解放されよう」 的な励ましの言葉が世の中に溢れていると感じます。
もちろん、それこそ苦痛によって何かが 「消えてしまう」 ならば、そんなことになる前に逃げるべきだし、すぐさまやめられることは、やめた方が絶対に良いと思います。
でも、この言葉通りに考えるとすれば、
長年「辛い」と思いつつ、それからずっと「逃げたい」「やめたい」「解放されたい」と感じ続けて囚われていた(いる)ことは、それは逃げるべき苦痛ではなく、それと共に生きるべきことなのかもしれません。
そう思うと一瞬辛く感じます���、でもちょっと諦めもつきます。そうか、逃げたい逃げたいとばかり思っていたけど、それと共に生きるしかないのかって。しかも、そういえば私はそれに「耐えうる」から今も生きてるんじゃないかって。そうすると、「辛いけど、やるしかない!」みたいに前向きになれるような気がしました。
難しそうな本も、読んでみるものです。面白いから。
0 notes
Text
三宅香帆 (2024)『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』
「アニメ好き」を自称する会社の同僚と話していて驚いたことがある。私がいくつかアニメ作品を挙げると「いや、そういう少しでも頭を使うのは見れない」と言うのだ。あ、じゃあ日常系アニメが好きなんだね、と言うと、それもスマホ片手に「ながら見」をするのであるらしい。え、「アニメ好き」とは……??
ここで想起されるのは『花束みたいな恋をした』におけるパズドラ問題である。もともとサブカル好きだった主人公の男は、ブラック企業に勤め始めてから映画や文学を嗜めなくなってしまうのだが、それは「時間がない」ことが原因ではない。現に、パズドラをする時間はあるのだ。パズドラはできても、本は読めなくなってしまうのだ。
結論から言えば、働いていると本が読めなくなるのは、それが「ノイズ」だからである。哲学者の千葉雅也は『勉強の哲学』において、勉強とは「ノリが悪い人」になることであると説いている。例えばフェミニズムを学べば、「男同士の絆」的コミュニケーションには乗れなくなってしまうし、マルクスを読めば、現行の経済システムには乗れなくなってしまう。今まで自明視してきた世界観を崩壊させ、同じようには生きられなくなってしまうノイズを提供することこそが、読書の機能なのである。これは「仕事で自己実現!」と思っている者や、仕事のことしか考える余裕がない者にとっては、とんでもないことだ。せっかく市場に適合しようと頑張っているのに、読書はそれを不可能にしてしまうのだから。
読書が「ノイズ」とされる転機となったのは、バブル崩壊に端を発する「行動と経済の時代」への移行である。それまでは、社会は良くなっていくものだという期待があり、立身出世に必要なのは教養や勉強であるとされた。だが、バブル崩壊と就職氷河期の到来により、社会は変革不可能なものとして個人から切断される。頑張ったところで社会は変わらないのであれば、如何にして経済という大波に乗れるかだけを考えたほうが「利巧」である。そこで登場するのが自己啓発本だ。コントロール不可能な社会や他者などの「ノイズ」など考えるだけ無駄だ。コントロール可能な自己の変革に注力し、行動によってビジネスで成功を掴め!
このような状況に対する処方箋として、筆者は「半身」の生き方を提唱する。「全身全霊」で何かに打ち込むことは素晴らしいこととされるが、実はこれは楽な生き方なのだ。タスクの遂行に必要のないノイズを除去し、思考を停止してただ没頭すればよいのだから。おまけに、インチキな達成感もついてくる。これはキェルケゴールが言うところの「自己忘却」であろう。また「推し���」に人生のすべてを賭けてしまう者がいるように、趣味の領域さえ「全身全霊」の経済活動へと変容してしまっている。だからこそ「半身」で生きることが必要となる。新自由主義に心まで毒されてはならない。
さて、「働いていると本が読めなくなる」の対偶は「本が読めるなら働いていない」である。ところで、私は年間百冊くらい本を読んでいる。つまり、私は働いていないという結論が導かれる。これは本書になぞらえて言えば、私は「半身」でしか仕事をしていないということだ。だって、ノイズによって自己を揺さぶられることほど、この世に面白いものはないのだから。
0 notes
Text
「フリードリヒ・エンゲルス」にまつわる面白いエピソードと心に残る名言
### フリードリヒ・エンゲルスの豆知識と逸話 フリードリヒ・エンゲルス(1820年 – 1895年)は、ドイツの哲学者であり、カール・マルクスと共にマルクス主義の基礎を築いた重要な思想家です。エンゲルスの人生には、彼の思想や活動を彩る興味深いエピソードがいくつかあります。 #### エピソード: 友情と共同作業 エンゲルスとマルクスの友情は、非常に特別なものでした。彼らはしばしば手紙で意見を交換し、互いの理論を発展させました。特に、エンゲルスはマルクスが経済的に困窮していた時期に、彼を支援するために自らのビジネスを運営していました。エンゲルスは製綿工場を持っており、その利益をマルクスの生活費に充てていたのです。この友情は、彼らの思想だけでなく、互いの人生にも大きな影響を与えました。 ###…
0 notes
Text
weekly momentum 2024.09.09~
なんだか鬱々としている。結婚パーティーと、マガジン入稿、トークイベント、それと見積もりだしが重なったりでわたわたしている!!!!!こんなにたくさんのジャグリングを回せない。焦ると余裕なくなるし、ストレスで食生活が狂って浮腫んで気持ちが沈む。最悪や
離島経済新聞のいさもとさんへのインタビューをさせてもらう!おもしろい。継続したからこそ、島出身でなくても語れるようになったという話が面白かった。シマの人は語ってくれるし愛着もあるというのは、私の沖縄での少しの仕事経験からも本当にそう。私はそこで「私は島出身でもないし…」と引け目をすごく感じていたのだけど、継続したからこそ見えてくる世界があるんだよなあ。離島経済新聞の”経済”はカールポランニー『人間の経済』という話もとても面白かった。
どうして島というテーマを自分で持ち続けられたのか、という質問に対して、違和感だらけの世の中で、島に触れた仕事をしていると、人の魅力や産業構造に対してアプローチできるというような話をしてくれて。
あと途中で出てきた「知恵が詰まっている文化を大事にしなくちゃと思う」という言葉にも大きく頷く。ほんと面白い。この辺りの話をマガジンとしてまとめているので、詳細はぜひそちらを読んでもらえたら嬉しい。
村上隆の芸術論、Rehaqを見る。マルクス主義に純粋な斉��氏と、芸術作品を作ることに純粋な村上氏の観点の違いが面白い。左翼っていうのは、物事を悲観的、極端に捉えるふしは確かにあるのかもしれないな、とは思う。知識はさすが斉藤さんもすごかったけれど。資本主義と大きく言ったときに、その中でも人間の機微はあるし、作る喜びもある。
一時期私も「資本主義」という言葉を嫌悪の対象みたいに思っていたが、今はもうそういう言葉は恥ずかしくて口に出せないという感じがする。言葉が一人歩きしている時代性なのか、私のなかで一つの章が終わったのか。
日本人性において価値判断することを必要?とするのか?というのは最近うっすら私が考えていることでもある。民族主義ってここ数年のうちに出てきた概念だし、別にそこで括りきれないものがあるのは、当たり前だよね、という感覚。
「ナラティブに接続する」「誰のナラティブに阿るか」「敗戦国の悲哀、日本のこの風土に生まれ育ってしまった人間たちのリアリティがどう表現したら日本国以外の人たちに伝わるのか」「パンデミックでアマプラとネットフリックスづけになって、日本の価値観が直感的にわかるようになってる」ここら辺の言葉が面白かった。
kinkeeping
なぜこんなことを書いているかと言うと、Lobsterr Letter vol.127で紹介した『ニューヨーク・タイムズ』の 記事 で紹介されていた、家族の繋がりを育むキンキーピング(Kinkeeping)という行為やキンキーパー(Kinkeeper)という役割の話がとても印象に残っているからだ(Lobsterr FMでもこのテーマで話している回を最近配信した)。 キンキーピングとは、家族や親族関係という意味のキンシップ(Kinship) を保つ(Keep)ための様々な行為や行動のことを意味する。前述したようなこどもの誕生日などのお祝い行事を企画することから、家族の伝統や慣習を継承すること、あるいは日常生活における通院や定期検診などの医療ケアを調整したり、時には家族メンバーの悩み事や相談に乗るなどの感情ケアをすることまで含まれる。 キンキーピングは家族の繋がりやアイデンティティ、幸福感を育むやりがいのある仕事である一方で、とても時間がかかり、時には感情的な負担が重く、感謝されない見えない仕事になってしまっているケースが多い。そして、様々な研究からは、キンキーパーのほとんどが女性であることもわかっている。これは多くの人の肌感覚とも合致するのではないだろうか。ジェンダー研究を専門とする心理学者のベレン・アルフォンソは、家族の繋がりの���は、家族メンバーの健康、幸福、そして長寿にさえ大きな影響を与えるという研究結果があることにを紹介しつつ、「ここにおける不平等さは、多くの人が享受している恩恵が、女性によって生み出されていることです。人間関係を健全に保つため女性が担ってきた感情労働は長年見過ごされてきたんです」と『エル・パイス』の 取材に対して語っている
Lobstarr letter: vol.278
今週のRobsterr letterにて、kinkeepingのことが書いてあった。すごい大事な仕事よね、これ。後続に別のトピックとしてアメリカの孤独化の複雑な事情、というタイトルで、友人と繋がりを保つことができる個人が減っていて、偶発的なコミュニティ保持のアクティビティの必要性がみなおされている、みたいな記事も紹介されていたけど、これも友人と家族、別の話のようで、どこか繋がっているような気がする。
人間関係、ただぼーっとしていたら保たれないことに私も最近自覚しつつある。孤独感から繋がろうとしても面倒で逃げてしまったり、損得勘定でしかものごとを図れない呪いの産物なのか。。。 そういう感情を「え、誰でも面倒くさいでしょ、だけど超えていくでしょ」って言ってのける人が一定数いることも知っている(たとえば私の夫とか)。尊敬する。 自分がそうでなくなった理由を、時系列ごとにトピックを並べて説明もできるけど、そんなこと野暮だな、でいい気もする。
私のような本の買い方(それはそう珍しいことじゃない、特にamazon がすぐに届けてくれるようになってから。要は、気になったもの、こと、人の本をすぐに入手するという買い方)は、その世界に興味を持って動くという在り方の現れでしかない。資料としてたくさん積み上げるという。それは偶発的に、あるいは自らがもぐっていって出会う本や言葉ではない。情報としての本たち。むなしさは…ないけれど、資料としての本の多さに時々辟易とするかも。でもどの文豪も、どの思想家も、床が抜けそうなほど本は持っているはず。その世界をそれだけ私は知りたいんだ。
0 notes
Text
TEDにて
マーク・フォーサイス: 政治における言葉について
(詳しくご覧になりたい��合は上記リンクからどうぞ)
政治家は、言葉を選んで使い、その言葉で現実を、形作り支配しようとします。これは、有効な手法なのでしょうか?
語源の研究家マーク・フォーサイスは、ジョージ・ワシントンの称号を「大統領」にした背景等イギリスとアメリカの政治史から、いくつかの面白い政治用語の語源について語ります。
権力の乱用、権威付けを防止するため?時限立法の弊害?そして、驚くべき結論に至ります!(ロンドンで行われたTEDxHousesofParliamentから)
議院内閣制は、大統領制と並ぶ、議会と行政府との関係から議会と行政府(内閣)とが分立することで存在する政治制度
立法権を有する議会と行政権を有する行政府(内閣)が一応分立している18世紀から19世紀にかけてイギリスで王権と民権との拮抗関係の中で自然発生的に誕生。その後、慣習として確立されるに至った制度で日本も採用している。
スウェーデンやドイツも同様だが日本独自の問題点はいまだに解消されていない。ドイツは共和国型。イギリス、スウェーデンと日本は立憲君主型。
日本での法律案は議員からでるものを議員提出法案。行政府(内閣)から出てくるものを行政府(内閣)案。主に官僚がすべてを司っている。
国会に上がる前には、各部会を通過して、委員会という場所で承認を得ないといけないが、過半数であるか?全会一致ルールか?は不明。本来は、全会一致ルールを原則にした方が良いかもしれない。
内閣総理大臣、大臣で構成される閣議などは全会一致ルールを原則としている。
この根本は、先駆的なスウェーデンの経済学者ヴィクセル、ブキャナン、タロックの「公共選択の理論」です。
ヴィクセルは、全員一致ルールが経済学の「パレート最適化」という効率的な状態を実現させることを見出したとされている。
ノーベル賞を受賞したロナルド・コースの「コースの定理」にも通じます。
さらに、国家によっても異なりますが、日本の国家システムを簡単に説明はできないが、あえて簡単に説明してみると・・・
世の中は不公平が当たり前?ここから出発しないと自由資本主義が成り立たない?お金は当然、強い法人に資本が集まり、弱い法人は傘下に入るか、合併して対抗するような欲に目のくらんだ弱肉強食な最低の世の中になっていく。
新自由主義と呼ばれます。
マルクスも資本論で論じています。現代では、「21世紀の資本論」を書いてるピケティかな?
マイケル・サンデル:なぜ、株式市場に市民生活を託すべきではない��か?
すると、ほんとうの弱いお店、市民生活にまで弱肉強食となり、世の中がおかしくなるので、行政府をつくり法律をつくり税金でとり、セーフティーネット。みんなに再分配する。
人間の限界を超えるような大規模な共同作業を行うために、マクロ経済学に沿った地道な毎年の世界経済の成長のため、ある程度は法人として貨幣の集中を行う方がいいのかもしれません。しかし、独占禁止法を軽視しているわけではありません。
法律は行政府、政治家が創るので、弱いものはされるがままなのか?というとそうでもなくて、選挙の一票がその分強い権利をもつようになる。これは誰もが平等に持てる権利。
日本国憲法で保障されている国民主権。インターネットのようにみんなの票が集まるとみんなのチカラが弱者に結集します。ジャンジャックルソー、カント、自由民主主義です。
ほんとうの弱いお店に役に立つ法律を作ってくれる一大政党をみんなの一票でクリエイティブにクリエイトしてかないと日本はヤバいな〜親亀が転んでも平気な国になるよう祈ります。たぶん、こんなことは現実的には不可能でしょ。
実際は、国会という場で戦ってもらう議員を選ぶだけしか私たちにはできません。それは、議員でしか、法律を開発、変更、削除できない議院内閣制という法が運用されてるから!
つまり、議員は法律を創ることが仕事だからです。だから、きちんと法を開発→法案可決できる議員を選んだ方が良いです。善と悪は時代によって変わるもの!
選挙に通過したいだけの法案可決能力のない口先だけの議員は庶民が選挙で投票せずに間引びいていけば自動的に議員は良くなります。(個人別法案可決実績の履歴を公表してくれば可能かも!)
ですから、みんなで見極める目を養いましょう。それが結局自分のためになるのだから!権力に固執する人種が議員になる人だと前もって覚悟してればそんなに政治には失望しませんよ。
その前提で全住民がチェックすればいいのだから!
また、それには、競馬のパドックを見るように一頭一頭の法案可決能力を見極める必要があります。誰が一番、法案可決させたか?を!
でも、その多数のグループのきめた方向が、太平洋戦争の東條総理のようにドイツのヒットラーのように、間違っていたら?おそろしい未来がまってます。
過去の歴史では、ポピュリズムという、モデルのオンリーは失敗している現実があります。ハンナアーレントの書籍「全体主義の起源(The Origins of Totalitarianism)」「イエルサレムのアイヒマン- 悪の陳腐さについての報告」にもあります。
昔は、マスメディアが情報を独占して弱者はされるがままでしたが、現代では、分散システムであるインターネットがあるので、みんなの票が集まるとみんなのチカラが弱者に結集します。
今は法案可決能力のない少数のグループでも良い法案を出してる所は将来を見込んで投票し議員を当選させて育ててみるということもおもしろいかもしれませんよ。
さらに良い議員がまったくいなければ、無名の人に投票することもおもしろいかもしれません一人一人よく考えて今、選択して投票しないと未来は・・・
政治家を見極める目が必要です。
(合成の誤謬について)
合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。
ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。
例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)
1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。
それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。
その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。
つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。
なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の��に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。
このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。
それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。
続いて、トリクルダウンと新自由主義
インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。
しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。
リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。
それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。
例えば
Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。
シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。
こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。
アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。
三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。
このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。
ジャロン・ラニアーも言うように、再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!
2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)
とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ
<おすすめサイト>
毎年4 月 2 日は、国際ファクトチェックデー。
エピソード9 Episode9 - 各宗教と政治のチェックと指標について「パワーか、フォースか 改訂版―人間のレベルを測る科学 - デヴィッド・R・ホーキンズ Amazon」
エピソード4Episode4 - 政治の善性について(パワーか、フォースか―人間のレベルを測る科学 - Amazon)
この世のシステム一覧イメージ図2012
セザー・ヒダルゴ:政治家をあるものに置き換える大胆な構想
ヘイリー・ヴァン・ダイク:政府支出を年に何百万ドルも節約している技術者集団
ジェニファー・パルカ:コーディングでより良いスマートな賢い政府を創造する!
日本経済と世界経済(KindleBook)現代貨幣理論(MMT)の欠点も克服しています!- 東京都北区神谷高橋クリーニング
強い経済、子育て支援、社会保障のアイデア
ダニエル・カーネマン: 経験と記憶の謎(所得政策も)
個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)
世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷の高橋クリーニング店Facebook版
#マーク#フォーサイス#言葉#政治#ジョージ#ワシントン#大統領#イギリス#アメリカ#england#english#金融#システム#ノーベル#経済学#法律#政府#ハンナ#アーレント#人権#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery
0 notes
Text
2023年11月30日に発売予定の翻訳書
11月30日(木)には17冊の翻訳書が発売予定です。 "No Longer Human" は太宰治『人間失格』の英訳版ですね。
応報 組み替え人形の家

王蒙/著 林芳/翻訳
尚斯国際出版社
「戦争ごっこ」の近現代史
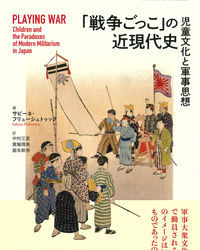
サビーネ・フリューシュトゥック/著 中村江里/訳 箕輪理美/訳 嶽本新奈/訳
人文書院
ソ連の歴史
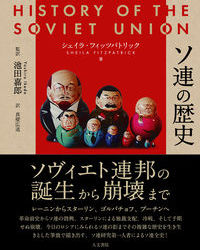
シェイラ・フィッツパトリック/著 池田嘉郎/監訳 真壁広道/訳
人文書院
マルクス研究会年誌2022[第6号]
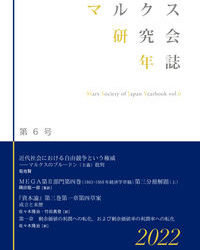
菊地賢/著 隅田聡一郎/監訳 佐々木隆治/翻訳 竹田真登/翻訳
堀之内出版
カリコ博士のノーベル賞物語
メーガン・ホイト/著 ヴィヴィアン・ミルデンバーガー/イラスト 坪子理美/翻訳
中央公論新社
ゴジラ:ギャングスター&ゴライアス
ジョン・レイマン/著 アルベルト・ポンティチェッリ/イラスト ルビー翔馬ジェームス/翻訳
フェーズシックス
家を失う人々 : 最貧困地区で生活した社会学者、1年余の記録
マシュー・デスモンド/著 栗木さつき/翻訳
海と月社
No Longer Human
Osamu Dazai/著 Juliet W. Carpenter/翻訳
チャールズ・イー・タトル出版
認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで 第3版 : ジュディス・ベックの認知行動療法テキスト
ジュディス・S・ベック/著 伊藤絵美/翻訳 藤澤大介/翻訳
星和書店
カラーモンスター きもちの きゅうきゅうばこ
アナ・レナス/著 おおともたけし/翻訳
永岡書店
真っ白いスカンクたちの館
レイナルド・アレナス/著 安藤哲行/翻訳
インスクリプト
呪いを解く者
フランシス・ハーディング/著 児玉敦子/翻訳
東京創元社
孔雀屋敷 : フィルポッツ傑作短編集
イーデン・フィルポッツ/著 ���藤崇恵/翻訳
東京創元社
シェフ
ゴーティエ・バティステッラ/著 田中裕子/翻訳
東京創元社
印
アーナルデュル・インドリダソン/著 柳沢由実子/翻訳
東京創元社
光の少年 : チベット・ボン教の聖者たち
サムテン・ギェンツェン・カルメイ/著 津曲真一/翻訳
ナチュラルスピリット
父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書
スコット・ハーショヴィッツ/著 御立英史/翻訳
ダイヤモンド社
1 note
·
View note
Text
美は存在すると信じているし、精霊とか妖精のように存在する美もあると思っている。 古代から美は感性の領域に属する概念であり、人は感性によって世界を認識する。認識という行為は、人間のあらゆる日常的、あるいは知的な活動の根源にある。 認識論という哲学分野では、人はどのようにして物事を正しく知ることができるのか、人はなぜ誤った考えを抱くのか、ある考え方が正しいかどうかを確かめる方法はあるのか、人間にとって不可知の領域はあるか、あるとしたらどのような形で存在するのか、などの問いが扱われた。19世紀末ごろまでに、認識論の一部が哲学の外に出て心理学という学問を成立させる。認識論で問われた問題を科学的方法論によって研究しようと試み、実験心理学も登場し、仮説を立て実験データとの照合を論じてはいたものの、その仮説自体はやはり思弁に過ぎなかった。人間の認識についての問いは「哲学的な問い」だった。
近代的な意味での認識論を成立させたのはデカルトである。 デカルトは、人間の感性を、霊肉二元論の立場をとって、肉体的な「感覚」と霊的(精神的)な「理性」に分け、認識の起源は理性であるとした。デカルトは理性を、人間が生得的に持った「内なる自然の光」と呼んだ。デカルトを引き継ぐ立場は「合理主義 (理性主義、大陸合理主義)」と呼ばれる。 認識の起源は経験であるとしたジョン ロックを引き継ぐ立場は「経験主義 (イギリス経験主義)」と呼ばれ、経験に先立って何らかの観念が存在することはなく、人間は「白紙状態 (タブラ ラサ)」として生まれてくると考え、生得説に反対する立場をとった。 これらの思想の相違点は、たとえば「大陸的-イギリス的」という区別で呼ばれるものの、どちらの思想も、1648年の八十年戦争の終結と、それによるネーデルラント連邦共和国(ほぼ現在のオランダ)の独立が非常に大きく影響した。オランダは1648年から17世紀終わり頃まで「黄金時代」と呼ばれる時代に入る。オランダ黄金時代は、レンブラントやフェルメールなどの画家が活躍した時代としても知られる。オランダの歴史においても、貿易、産業、科学、軍事、芸術が世界中で最も賞賛された期間でもある。 オランダにとっての八十年戦争の一部でもある三十年戦争(1618年-1648年)は、ドイツ(神聖ローマ帝国)でカトリック対プロテスタントの構図で始まったが、ヨーロッパ全体の戦争へと拡大し、宗教戦争とは言えない国際的戦争となった。結果として、神聖ローマ帝国は弱体化した。これにより、教皇や皇帝といった普遍的、超国家的な権力がヨーロッパを単一のものとして統べる試みは事実上断念された。 イギリス(イングランド王国)は三十年戦争に参加しなかったが、清教徒革命の内戦下(1642年-1649年、広義には1639年の主教戦争から1660年の王政復古まで)にあった。 宗派対立激化の結果、民衆にはヘルメス主義などの神秘思想が流行し、自分の目も感覚も明らかな証拠も信用せず、自分の経験すら偽りとしてまで、自らの教義に一致しないものを認めようとしない独断主義的な風潮が蔓延するというような社会情勢にあった。 オランダは、信仰の自由と、経済的、政治的な独立のために八十年もの間戦って勝利したという誇りと、他国で思想信条を理由として迫害された人々を受け入れることで繁栄したという自負があり、寛容の精神を重視した。この寛容な風土により、書籍の出版も栄えた。国外では論争の的になるような宗教、哲学、科学に関する多くの本がオランダで出版され、秘かに他国へ輸出された。17世紀のネーデルラント共和国は、ヨーロッパの出版社のようになった。 バートランド ラッセルは『西洋哲学の歴史』(1945)で次のように述べた。「デカルトは、ビジネスでフランスに数回、イングランドに一度行った以外は、オランダに20年間(1629-49)住んだ。17世紀における思索の自由のあった国としてのオランダの重要性は、強調しても強調しすぎることはない。トマス ホッブズは、彼の著作物をここで印刷する必要があり、ジョン ロックは、1688年以前のイングランドにおける最悪の5年間の反動期間、ここに避難していた。」 デカルトの「我思う、ゆえに我あり」という命題は、当時の保守的な思想である「信仰による真理の獲得」ではなく、人間の持つ「自然の光」を用いて真理を探求していこうとする姿勢を表現していると受け止められ、これが近代哲学の出発点となった。これは、「信仰の時代」から「科学の時代」への転換点でもあった。
18世紀末に、合理主義と経験主義の両方の限界を示す形で二派の対立を統合したとされるのがイマヌエル カントであり、19世紀は、カントを受けつつその反動として、カントを批判し乗り越えようとする潮流が生まれる。19世紀のこの流れは、19世紀後半にはドイツ観念論と呼ばれるようになる。19世紀後半から20世紀頭にかけて、ドイツ観念論を批判し「カントに帰れ」という標語を掲げたカント的認識論の復興運動が起こり、これは新カント主義と呼ばれる。 日本に認識論が入ってきたのはこの頃で、日本語の「認識論」もドイツ語からの訳語であり、新カント主義の影響が大きいとされる。新カント主義者は「真善美」という言葉を好んで使い、この真善美の調和を人間の理想��する考えは、近代思想として日本にも受け入れられた。 カントによれば人間の認識には限界があり、神の存在証明や絶対的真理などの超越的で形而上学的な問題は原理的に答えを出せない問題であり、科学化もできないし、哲学として議論すべきものでもないと斥けられたが、ドイツ観念論の思索家たちはこれには不満で、カントが否定した神の認識可能性を再び主張する。またドイツ観念論は、カントへの反動として、あらゆるものを科学的方法により解明できるという信念を強めていく。 新カント主義は、当時西欧を席巻しつつあった無規範な科学的思惟に対抗した。特にドイツ観念論のヘーゲル派の流れを汲むマルクス主義は、精神や文化を物質の因果律により支配されるものとしていたため、人間もまた因果律に支配された機械とみなそうとしていると危惧し、彼らを批判して、カントに習い先験的道徳律の樹立と、精神と文化の価値の復権を試みた。
19世紀後半の心霊主義ブームも、ドイツ観念論の潮流と同様に、精神や霊魂あるいは宗教などを科学的に解明しようという試みとしての側面があった。宗教の科学的解明というのは、特に心霊主義の初期においては、生活を縛り付ける教条主義的な権威からの解放や、腐敗の糾弾としての期待があった。あくまで科学だと主張を続けた団体も、科学化には至らず、ブームも去り、団体維持のためにオカルト(神秘主義)を取り入れた結果、当初の意味での心霊主義でもなくオカルトでもない疑似宗教となっていく。 心霊主義は自動筆記などの形で文学や美術にも影響を与え、また、文化的創作における精神面の科学的解明という期待があった。しかしこれも、インスピレーションやアイディアの作り方、根源的な創作動機などは、科学的あるいは論理的には説明することができないということを浮き彫りにした。 「芸術の社会理論」や「文化の科学的理論」などと呼ばれる、文化や芸術などを社会構造や時代的文脈などから読み解く考え方は、心霊主義やマルクス主義などと結びつく形で、特に評論においては現在においても影響を与えている。
確かに、あらゆるものは社会や時代の産物であるという側面はあるのかもしれない。回帰運動や復古運動も時代を逆流させるわけではない。 20世紀が始まってから第一次世界大戦(1914年-1918年)までの期間、特にヨーロッパにおいては、見るからにこれまでと全く違う表現が現れる。歴史的に見ても特異な変化だが、1930年代の世界恐慌から第二次世界大戦(1939年-1945年)の間に世界もこれに続くことになる。大きな時代の変化により、まるで人の認識自体が劇的に変化したかのように、新しく現れた美術表現などは難解でわけがわからない。というか、これ自体が矛盾であり、現在においても一見わけがわからないってことは、人の認識自体は変化していない。 キュビズムや抽象主義、シュルレアリスムなどを読み解くキーワードとして使えるものに、20世紀頭に登場した「表現主義」の他に、「プラスチック」と「ディメン��ョニズム」というのがある。「表現主義(エクスプレッショニズム)」というのは、いわば「印象主義(インプレッショニズム)」の対義語であり、どちらも主観的リアリズムを描こうとしているが、印象主義は、目で見たものが、自分の内面でどのようなイメージ(認識。イデー。カントの用語では「表象」)になったのかを描こうとしているのに対し、表現主義は、もともと自分の内面にあるイメージをそのまま描こうとする。自己の内面にあるイメージを描くために、どのような形を与えるかというのが主要なテーマになり、これが「プラスチック(可塑性。形作ること)」であり、ニュアンスとしては「これまでにない自由な形を与えること」を意図している。そのため現実に既にある形(具象)ではなく抽象や非具象へと向かう。ピエト モンドリアンは自身の美術理論を「ネオプラスティシズム(新造形主義)」と名付けた。 そして20世紀頭に多くの人が世界認識の大きな変化だと捉えたのが、「この宇宙は四次元時空である」という概念の登場だった。H G ウェルズの小説『タイムマシン』(1895)でも「時間が第4の次元」だとされていたが、1907年ごろにドイツの数学者ヘルマン ミンコフスキーがアインシュタインの特殊相対性理論を四次元の空間として数学的に表したこと(ミンコフスキー時空)が多くの人にインスピレーションを与え、これをどのように表現するかという挑戦が始まった。1936年に美術理論化のチャールズ シラトが「ディメンショニズム(次元主義)」という語を作った。 またこれにより、これまでのヨーロッパの絵画表現は、三次元空間の中に、第4の要素として「光」を描くことを目的としていたということを再認識する。 相対性理論を始めとして、量子力学などの理論物理学が飛躍的に発展し、デカルトやカントが前提としていたニュートン力学に対する疑義が出され、認識論は改めて学問の基礎付けへと向かった。
1960年代から1970年代にかけてアメリカを中心に世界的に行われた前衛芸術運動である「コンセプチュアルアート」は、マルセル デュシャンの、特に1910年代の作品や美術理論を、理論的支柱とした。デュシャンが、特に写実主義以降の19世紀の絵画を指して、美術が「網膜的になりすぎている」と批判していたことなどに影響され、「作品の具体化の否定」などにより、コンセプト(概念)を表現することを目指し、作品制作よりも芸術について論じることのほうを重要視した。 アンディ ウォーホルも、「コンセプチュアルな」実験映画を制作しており、コンセプチュアルアートの位置づけで見られてもいたが、「作品の表面だけを見てください。裏側には何もありません」と言い続けていた。 1950年代からのアメリカの抽象表現主義、ミニマルアート、そしてコンセプチュアルアートには、CIAの支援があったことが、1960年代末から70年代にかけて、暴露と情報公開のかたちで明らかになる。直接的な思想介入や市場操作があったわけではなく、冷戦下においてアメリカの文化的優位を世界に示すという目的で、海外での美術批評活動への支援が主な内容で、アーティストたちも支援があることを知らなかったが、情報公開は多くの人々が一挙に文化的な運動から退却していくきっかけにもなった。 なんなのかわからないものをなぜか解説したり批評したり論じたりしていたが、一体なにを認識していたのかわからなくなる。
網膜的ではない光もあると思う。
2023年10月 ターニング アンド ターニング イン ザ ワイドニング ジャイア
0 notes
Text
以下引用
「創造的であれ、さもなくば死だ」
安田:ルーティンワークと非ルーティンワークの区別について、もう少し、話を続けさせてください。これはカール・マルクスの「疎外」に関係していると思います。ルーティンワークか非ルーティンワークかを区別する考え方は、マルクスのもともとの考えに近いのではないでしょうか。
コーエン:そう思います。現代のパラドックスの一つです。ルーティンワークは疎外です。機械やロボットのように同じことを繰り返す労働者は「奪われた」状態にあります。もともとマルクスが考えていたように生産した商品を奪われるだけではなく、スキルも奪われるのです。工場でライン作業をする時は、いわば人間としての側面は忘れるように要求されます。
コーエン:例えば、1968年の五月革命[パリの学生運動を端緒にフランス全土、さらに多くの国々に拡大した大衆運動。ド・ゴール大統領退陣の契機となった]で、資本主義社会が最も批判されたのはそこでした。学生や労働者たちは、労働者に反復作業をさせて人間をロボット化していると批判しました。
現在では皮肉なことに、その声が聞き届けられたのか(笑)、テクノロジーによってそうした反復作業は消えつつあります。しかし、それでも1968年5月にベビーブーマーが思い描いていたような、平和で創造的な世界は訪れないというパラドックスが生じています。
今度は、創造力の追求が新たな義務になったのです。人々は創造的でなくてはならなくなりました。「ロボットになりたくない。ありのままの自分でいたい」と願うことと、「創造的であれ、さもなくば死だ」と迫られることは別のことです。
ベーシックインカムがあれば、ちょっと待ったと言える
安田さんに倣ってマルクスの用語を使うならば、今度は創造性の剰余価値を「搾取」されることになるからです。一つの搾取が別の搾取へ移行するだけです。
けれども、もし、ベーシックインカムのような社会保障制度が用意されるのであれば、私はこの移行は好ましいことだと思います。私たちは疎外の世界から搾取の世界へ移りました。グローバルなシステムに創造性を投入するという要求に応えることで、本当に搾取されるようになるのです。そこにはストレスがあります。
剰余労働は、工業の時代にそうだったように、またしても最大限まで押し上げられています。しかし、そこにベーシックインカムがあれば、人々は「ちょっと待った、その要求まではのめません」と言えるのです。
安田:基本的には利潤最大化という面では同じだということですね。利潤の源泉は変わったとしても。
コーエン:そうです。ルーティンワークの世界では、搾取されるのは体力でした。今ではそれは創造力です。ある意味で進歩したと言えますが、同じ矛盾を抱え、同じように極端な状況になっています。
コーエン:今の状況は後からでないと完全には理解できないでしょう。1968年5月や、その前後には、工業社会は限界に来ていると考えられていました。その認識は正しかった。しかし、工業社会から抜け出しさえすれば、その後には永遠の平和が待っているとの予測は外れました。当時の人々は、消費社会は存続しないと考えていたのです。
経済のルールに支配された世界
ケインズが1930年代に示唆していたように、働く必要がどんどんなくなり、別の世界に変わっていくと信じていました。
実際、���ビーブーマーは、日本でも、フランスでも、アメリカでも60年代に大きな声をあげていました。自分たちの使命はポスト物質主義の世界を構築することだと考えていました。当時の人々はそう信じていましたが、それは実現しませんでした。
実際には今でも、経済の問題は変わらず存在しています。そして、今日、ポスト物質主義の世界に入るために求められているのは、生産性を向上させ、創造力を高め、仕事がルーティン化した途端に職を奪ってしまう機械に勝つことです。私たちは、物質主義のレースから抜け出した途端、別のレースに参加させられ、同じ緊張感に晒されているのです。
私たちは経済の世界からポスト経済の世界に移ったわけではありません。それどころか、かつてないほどに経済のルールに支配された世界に生きていると言えます。
ただし、その性質は変わりました。工場制度が終わり、ポスト工業化の世界に移行し始め、やっと少しずつ見えてきた実態は、私たちに大きな幻滅と失望しか与えていません。
引用ここまで
現代の若者を見ていると、コーエンの指摘は正鵠を射ていることを痛感する。
起業する才覚のある人間は起業するだろうが、そんな才覚を持った人間はごく一部だ。才覚のない人間は、20世紀ならば普通に会社員として働いていた。
しかし今は、一般の起業に正社員として就職すること自体がいまや狭き門だ。正社員になれてもブラック企業なら自分をすり減らしていくだけである。非正規雇用にしかつけない場合、その多くは低賃金に喘ぐことになる。奨学金の返済で首が回らない人間も多い。
旧来の就労パターンが難しくなる以上、他に活路を見出すしかない。
Youtuberに憧れる人間はYoutuberに。ゲームが上手いやつ、魅せるプレイや笑わせるプレイができるやつはゲーム実況を始め、時にはTwitchでストリーマーをやる人間もいる。顔出しに抵抗があればVtuberを目指す。かつては声優崩れがVtuberになるパターンがみられたが、今ははじめからVtuberを目指す人間も多い。目端の利く人間はYoutuberやVtuberのプロデュース側に回り、大量にいるYoutuberやVtuberのタマゴを使い捨てる。普通のVtuberでは売れないと思ったらエロ系のASMRを出す。自分の声やトークスキルに自信がない人間はボイロ実況を始め���。ボイロ動画で人気が出たらグッズを作ってBoothで売る。中には怪しげな陰謀論や切り貼り動画やナショナリズム煽動系の動画で稼いでいる人間もいる。
あるいは、初音ミクに憧れて自分の声を音声・歌声合成エンジンに提供し、そこから声の仕事にありつこうとする人間もいる。音声・歌声合成エンジンの新規開発に躍起になる人間もいる。Youtubeやニコニコ動画の動画編集の代行を仕事にしている人間もいる。動画の素材となる音声や画像を売ったり、無料配布して広告収入を得る人間もいる。VtuberのガワにあたるLive2Dモデルや3Dモデルの製作や原画で稼ぐ人間もいる。
漫画が描ける人間はX(旧Twitter)でバズったら出版社から声がかかるが、今ははじめからFANZAやDLsiteで長編のオリジナル同人誌を出す人間も少なくなくなった。FANZA同人で発売した人気の同人誌シリーズをまとめて一般流通扱いでFANZA電子書籍として売るという流れもすでに定着している。
漫画は無理でも絵が描ける人間ならばX(旧Twitter)で名を売り、Pixivでいいねを集め、FANBOXやFantiaやPatreonやFantasticで支援を集め、コミッションで稼ぐという流れもすでに定着しているが、生成AIにおびやかされつつある。画像生成AIに不満が高まっているのは、それら絵師支援サイトでかろうじて糊口をしのぐ絵師たちと競合するから、という理由も潜在的にあるだろう。実際、AIで合成した絵を大量に公開してPatreonその他の支援サイトで稼いでいる人間は山ほどいる。さらに、noteで画像生成AIの使い方を有料記事にして稼ぐ人間もいる。
怖ろしいことに、Vtuberもnoteもfanboxも、始まって10年も経っていないのに、これらを利用したビジネスが完全に定着してしまった。過去20年ほどネットにへばりついてきた自分でも、変化が速すぎて恐怖を感じるレベルである。だが当然ながら、こうした副業で稼げるのはやはりごく一部の人間だけである。クリエイティビティを仕事にしたい人が、後ろ盾がなくとも活躍できるようになったことは掛け値なしに素晴らしいし、かつて自分も期待していた時代が来たことを喜んでもいる。
しかし、クリエイティブ系の職種を望んでいない人までクリエイティビティを求められるのは社会として歪んでいる。コーエンの議論に沿ってわかりやすく言えば、たとえば農業はなくてはならない職種のはずだが、農業だけでやっていけない農家が出てくるだろう。それに対して『農業系Youtuberやればいいじゃん、売れなきゃ自己責任だけど』などと発言する人間が今なら出てきそうである。だがそんな社会は歪んでいる。農業系Youtuberは面白いし存在してほしいが、Youtuberやらなくても生きていけるくらいの収入はあるべきだろう。
コーエンが語ったように、今は常に何か目新しいことをしなければ、生活していくだけの金を稼ぐことすら難しくなってきている。すなわち、創造性を強制されているわけだ。まさ��マルクスが言った「人間阻害」の真逆である。あのときから見れば、社会は極端から極端に飛んでしまったようだ。ベーシック・インカムを導入すべきか否かについては白黒で判断すべき問題ではないのでここでは保留するが(BIによる行政の経費節減を訴える向きもあるが、これは高い確率で失敗する。ただし格差の是正を目的とするBIであれば効果を発揮する可能性はある)、コーエンの指摘は概ね正しい。
0 notes
Text
こんなに青空の日もたまにある。昨日は一日、雨とアラレの寒い日だったが、今日は青空。最高気温20度。肌寒い位で快適。



ロンドン、ヒースローの管制塔が機能不全に陥り、一昨日はヨーロッパの空港は大変。特にシャトル便を飛ばしていたり、ロンドンを含めた周遊便の飛行機の都合で延着遅延だらけ。それでも、午後2時頃には帰宅できた。
お買い物に行って、機内食とラウンジ食には出てこない野菜を買い求める。ジンバブエ産の絹さやの花椒炒めと、ロメインレタスサラダ、凍らせて保存してあった豆腐と買い求めたシイタケで春雨の煮込みを作る。
昨日は寒いし、家にこもってお仕事。昼食はスエーデンのクラッカーにイタリアのブルーチーズを載せて、ロメインレタスサラダを食べる。その後、Springer社からやっと出版される事になった情についての論文の最終校正をする。意外に時間がかかる地味な作業。今どき、ケンブリッジ出版もSpringerも校正はインドに外注。インド人のいい加減さには呆れるし、やれやれという感じ。中国がピークアウトしていく先にはインドがありますよ。手強いインドの知識層は面倒臭いなぁと、改めて思う。仕事しないで偉そうにしていたいだけなんだけど、それがインド国内では、カースト制度で補償されている国ですからなぁ。まだ階級制度のある、中世、近世を引きずっているんですよね、あの国は。
外が明るいので気付かなかったのもあるが、仕事を終えて時計を見ると夜の8時前。先学期の授業を履修してくれた学生からのアンケート結果に対する所感を書かなくてはならないのだが、私の授業は実に楽しかったらしい、と安堵しつつ、どおりで所感書きながら、お腹空いてたわと、慌てて食事を作る。凍らせて保存してあった豆腐、トマトやネギ、ニンニクにショウガで炒り豆腐。それに絹さやの残りを、やはり炒めものにして、御飯を炊いて、人参の糠漬けを添える。悶絶するほどの美味しさ。
今日は朝から、未来哲学研のシンポジウムに参加。シンポジウムを聞きながら、なんとなく思ったことを下に記す。ちなみにシンポジウムでは、AIは悟れるかとか、統合学問の可能性とか、人間と自然の二項対立構造の限界とか、哲学とは概念変化を促す学問とかいうことが話題になっていた。私は彼らの話しに耳を貸しながら、全く違う事を考えていた。
宗教と国家だった前近代から、科学と国家だった近代社会と全体主義。日本がドイツみたいになれなかったのは、ある意味で天皇性のお陰でもある。つまり、神道は白も黒も並列的価値と見る。キリスト教は白のために黒を排斥する。それがダーウィンの進化論をベースにしたヘーゲル的な進歩史観と弁証法で合理化された時、ナチがとったような極端な優生思想になってしまう。科学的なという言葉の危険性は、マルクス主義にも当てはまる。マルクスはヘーゲル史観を受け継いでいるし、科学的であることを根拠にマルクスレーニン主義は台頭していく。ソビエト連邦の科学とは軍事産業でもあったし、それはパワーに直結する。
日本は、科学立国だったかもしれないが、そこに理念や思想は無く、ただ楽しいから追求するというゆるゆるな感じが、救いとして働いていることを思う。何事も、良い意味に働くことも、悪い意味に働くこともある。中庸でバランスを取り、極論に陥らない事。極論は疑うことが重要だが、今どきは、無教養な人々が多く、何が極論かを見極める能力が、そもそも論として欠落しているようにも見える。だから、誰にでも分かるように、数値という記号が多様され、数値化できれば科学的であるとしてしまうのが現代教育産物。数値もバイアスが入っていることが見逃され、数値化された時点で色が無いように思われる。何故なら記号だからだ。
日本では少子化は止まらないし、子供や親に金をばらまいても無意味。もっと教育に力を入れるべきと思うが、教員とは日本の未来に夢を託せない人間が就くべき職業ではない事も周知すべきと思う。アホが先生と呼ばれたいだけなのか、手の届く範囲の安定した職業が教員だったのか。。。教員らしい教員があまり見当たらない中、塾高野球部の監督、森林さんが幼稚舎の先生であることに、少しだけ救いを感じた。やはり教育は金をかけないとダメかな。Yaleのサルヴォイ学長が来年退任したいと宣言したらしい。私は教育者に戻りたいと。教育とは未来に触れる事。それはなんて素敵な事だろう。
などと、シンポジウムが終わった後、つらつら思いつつ、窓外の雲がゆったりと流れ行くのをぼんやり見ていた午後でした。今晩はカレーにしよっかな。寒いしね。
1 note
·
View note
Text
映画『オペラの夜』と『マルクス一番乗り』
U-Nextでマルクス兄弟の映画を2本続けてみました。
『オペラの夜』(1935)と『マルクス一番乗り』(1937)です。
どちらもパターンは全く同じーー年配の富裕な夫人に取り入る詐欺師まがいの男(グルーチョ)がいて、恵まれない境遇にある若いカップルがいて、そのカップルを応援する二人の男(チコとハーポ)がいて、若いカップルの歌と踊りがあって、チコのピアノの演奏とハーポのハープの演奏があって、マルクス3兄弟がカップルのためにオペラの公演や競馬のレースをめちゃくちゃにして、ハーポが体を張ったアクションをみせて、最後はカップルが結ばれてめでたしめでたしという展開です。
面白いかと聞かれたら「うーん、どうでしょう」としか答えられません。
私は笑いに新しいも古いもない、面白いギャグと面白くないギャグがあるだけだと思っていますが、この2本の映画を見ると「古いなあ」と思わずにはいられませんでした。
マルクス兄弟のギャグは結局他人を酷い目に遭わせるだけで、自分は全く痛い目に遭わないーーつまり他者を踏みつけにして笑いをとるギャグだからかもしれません(私は別に「他人に迷惑をかけてはいけない」などと偏狭な道徳を振りかざすつもりはありません。でも、他人を下げて笑いをとるより、自分を下げて笑いをとる方が好きです)。
ハーポがスタントを使わず自分で劇場の幕を割きながら下に降りたり競馬馬に乗ったりするアクションもすごいと言えばすごいのでしょうが、「スタントを使わず自分でやるのはすごい」というのはあくまで作り手側が言うことーー観客にとってはシーンそのものが面白ければそれでいいのであって、本人がやっていようがスタントマンがやっていようがどうでもいいことです(暴論ですか。でも私はそう思っています)。
聞くところによれば、ドリフターズは多くの点でマルクス兄弟の影響を受けているとか(志村けんと加藤茶のヒゲダンスはグルーチョ・マルクスの風貌を意識しているそうです)。
私はドリフターズがそれほど好きではない(我が家では土曜8時は『素浪人・月影兵庫』、『素浪人・花山大吉』をみていました。私は『8時だよ! 全員集合』を見ない数少ない小学生でした)ので、その源流となったマルクス兄弟も好きになれないということなのでしょうか。
これまた聞くところによれば、『オペラの夜』と『マルクス一番乗り』はマルクス兄弟がパラマウント社からMGM社に移籍して作った映画で、「アドリブや破天荒なギャグが減らされ、ストーリー性を重視した大衆的な作風に変化した」とか。
もしそうならば、パラマウント社時代の方がナンセンスでアナーキーで私好みだった可能性もありますが、どうなんでしょうね。
0 notes
Text
橋爪大三郎・大澤真幸 (2011)『ふしぎなキリスト教』
キリスト教について知りたいなら、最初の一冊はこれでいいと思います。オススメです。
我々の社会は近代社会です。近代社会とは西洋的な社会のことであり、西洋のベースにはキリスト教があります。つまり我々の社会は、キリスト教に由来する様々なアイデア・制度・思想がベースとなって設計されています。なので、信仰には興味がなくてもキリスト教のことは教養として知っておく必要があります。
信仰には意識レベルのものと、意識しない態度レベルのものがあります。例えばマルクス主義は宗教を否定しますが、その理論はキリスト教の理論と酷似しています。ドーキンスという生物学者は無神論者で、神の創造を否定し進化論を肯定する本を書きましたが、彼を駆り立てた「創造か進化か」という一貫性を求める情熱自体が、実はキリスト教に由来する態度なのです。
面白い話があります。『空気の研究』で有名な山本七平が太平洋戦争で捕虜となったとき、アメリカ兵に「日本人は進化論を知っているか?」と尋ねられました。もちろんみんな知っていると答えたところ、アメリカ兵は大変驚きました。「え、日本人って天皇を現人神として狂信的に崇めてるんじゃないの? それなのに同時に進化論も信じてんの? 矛盾していて平気なの?」というわけです。矛盾律などというものに関心を持たない日本人の態度が如実に表れたエピソードです。
このような西洋的な態度を基にして、民主主義という制度は誕生しました。よって、単に制度が民主的なだけでは社会は機能せず、国民の一人一人が西洋的な態度を持っていることが、民主制が機能する条件となります。さて、そんな民主制を矛盾や一貫性などに関心のない民族が運営すればどうなるか?みなまでは言いません。
別に西洋的な精神が偉いわけではないですし、日本的な精神にも美徳があるとは思いますが、西洋の精神に由来する制度を採用してしまっている以上、この点には自覚的になる必要があります。
0 notes
Text
■ 「越境する文化」 とは何か 02 「越境する文化 (transculturalité)」 という現象についてお話ししたいと思います。 異なる文化間にはさまざまなコミュニケーションがあるものですが、 それは 「文化」 対 「文化」の影響関係にとどまるものではありません。 文化は交流、 合体、影響を繰り返し、 新しいものを創出したり、 すでにある文化をより豊かにしてきました。 たとえば、 「絹の道」 を介した東アジアとヨーロッパとの文化的交流は、ギリシャ風の仏教芸術というギリシャ美術とも伝統的な仏教美術とも異なるまったく新しい文化を生み出したのでした。
03
ヨーロッパの文明や文化において、 「越境する文化」 という現象は新しいもの ではありません。 18世紀のパリに生まれた啓蒙思想や19世紀のイエナに誕生���たロマン主義はヨーロッパ全域に広まりました。 シュールレアリスムはヨーロッパの枠を超えて世界に広まっていきました。 今日、「越境する文化」 という現象は「地球の文化」というものを生み出そうともしています。
04
西洋の帝国主義を批判的に分析したカール・マルクスは、文学について 「国や 04地方に属する固有な文学がやがて普遍的な世界文学を生み出す」と予見しました。普遍性のある文学とはどういうことでしょうか。 世界中の人々が同じ文学を読むということではありません。 それは、西洋人が日本や中国の小説、アフリカや中南米の小説を読み、 中南米の人々も自分の属する地域以外の文学を読む、このような相互の交流によって、 ある 「地方」 に生まれた文学が 「普遍性のある世界の 文学」となっていくということを意味します。
05 音楽においてもグローバル化の現象は存在しています。 まず、西洋音楽が世界 に広まりました。 日本人の指揮者やニューカレドニア出身の歌手が活躍するように、西洋音楽は世界中で演奏されています。 一方、最近の傾向として、ヨーロッパは、アラブ、インド、 日本、 中南米、アフリカなど、世界中の音楽に門戸を開き、受け入れるようになってきました。
06
映画について、アメリカ映画が世界の映画市場を支配していることを指摘するだけでは充分とは言えません。 たとえば、フランスをはじめとしてヨーロッパでは、インドや日本、中国などの映画が配給されるようになってきています。 こうした 「トランスカルチュラル」な市場の成立は、それぞれの国や地域から生まれた固有の文化として映画を守るだけでなく、あらたな映画製作の可能性を広げることにも貢献しています。 黒澤明の映画はフランスや他の西欧諸国の映画文化に受け入れられ、新しい市場を見出したことにより、黒澤はさらに映画を撮り続けることができたわけです。 また、アンダルシア地方の固有な文化であるフラメンコをはじめとして、世界に無数に存在する地方に根付いた芸術表現や芸術様式の多くが、そのオリジナルのスタイルは遠く離れた異国のアマチュア愛好家によって守られているという現象もあります。
07
思想や学問、文明などの動きはきわめてゆっくりしたものです。 ヨーロッパで『易経』や『バガヴァッド・ギーター』 (インドの古典『マハーバーラタ』の一章) などアジアの古典文献が翻訳され、非西洋地域の文明についての研究が始まったのは19世紀になってからのことです。 20世紀に入ると文明史の研究が進み文学作品も紹介されるようになり、20世紀末には東洋の思想や宗教のいくつかの要素が欧米に入り込んで影響を与えるようにもなってきました。 たとえば、 仏教はアメリカやヨーロッパにも信者を得て、 その思想がよりよく理解されるようになりました。 東洋医学も認知され、 鍼治療はヨーロッパの大学の医学部や病院に導入されています。 西洋哲学は非西洋の哲学よりもすぐれており、支配的な立場にあって当然である、 というような考えはたしかにまだ残っています。 しかしながら、「越境する文化」の時代をむかえ、ヨーロッパは世界の中心ではなく、理性や真理を独占的に所有しているわけでもないことが理解されてきています。 要するに、ヨーロッパもこの地球上の一つの地方にすぎないと認識するようになってきたわけで、これは重大な転換と言わなければなりません。
8 産業化される文化— 「生産」 と 「創造」 の葛藤
09 今度は「越境する文化」という現象について、 メディア文化や大衆文化の視点から考えてみたいと思います。 この分野でも普遍化への大きな流れが認められますが、それは標準化、あるいは画一化、単純化が勝利したことを意味するのでしょうか。たしかにそういう面はありますが、それだけではありません。映画を例に説明しましょう。実に多くの要素で構成される映画は、俳優、音楽家、装飾家、衣装係など、さまざまなアーティストが参加する共同作業で作品ができあがるもので、芸術製作の方法という点で大きな革命を引き起こしました。 一方、ハリウッドでは、最大利益の追求という論理のうえに映画産業なるものが発展しましたが、その過程で作品を画一的にそして凡庸なものにしてしまうことも少なくありません。そして、ここにもパラドクスが生じています。つまり、文化産業というものは独創性や個性、あるいは才能と呼ばれるものを排除することはできない、むしろ必要としているということです。映画を作ることと自動車や洗濯機を作るこは同じではありません。 何らかの標準的な製作方法によって構想された映画であっても、やはり個性、独創性、独自性というものがあるはずです。 文化産業に属するものはすべて映画がその典型例と言えますがその中核部分に絶えざる対立があり、しかもその対立は相互補完的でもあります。 すなわち、 「創造(création)」 という個別的で芸術的なものと、 「生産 (production)」という産業的で商業的なものが対立すると同時に互いに補い合う関係にあるのです。 この対立は時として 「生産」 が 「創造」 を抑圧したり、押しつぶしたりする事態を招き、その結果、エーリッヒ・フォン・シュトロハイムやオーソン・ウェルズのようにハリウッドから立ち去ることを余儀なくされた映画人もいます。 しかしながら、一方では芸術的創造性ゆたかな作品が絶えることなく作られてきました。 もちろん、 ステレオタイプで画一的な作品も存在しますが、 それでもステレオタイプをほとんど神話のようなアーキタイプ (原型となる作品) に変えてしまうような力のある作品があることもやはり事実です。 たとえば、ジョン・フォードによる西部劇の名作はそのような神話性をもったアーキタイプと考えられると思います。
10 文化産業は、 創造性や芸術の可能性を破壊すると同時に呼びさますという矛盾 を抱え、しかもこの内なる矛盾によって活力を与えられています。 この矛盾は一方で集中型で官僚的、 資本主義的な組織体制で文化を 「生産」 し、 また一方で 「生産」される作品には独創性や創造性が要求されるという対立に進展します。 この意味において、 「生産」 は 「創造」を必要としているわけです。 同じような対立は文化を受容し、 消費する一般の人々にも見出すことができます。 標準化された作品に満足する人��が多いことは事実ですが、 文化を受容する方法や形態の個別化も進んでいます。これはメディア文化に顕著である「トランスカルチュラル」な現象と考えてよいでしょう。 このようにグローバル化や普遍化のプロセスは画一化や均質化だけでなく、創造性や多様性や個別化をともなうものです。 そして、この対立と葛藤がある限り、文化的な活力は保たれるのだと思います。
●地球のフォークロア
12 文化が普遍化していく過程で地球規模のフォークロアが成立します。 地球の フォークロアというのはアメリカ映画の神話性のある作品だけではなく、フランスで言えば 『三銃士』 のような冒険活劇小説、ローマ帝国の伝説や神話、あるいはその他の地域の冒険譚などを土台に、つまりある地域の文化を基盤に作品や文化の無数の出会いによって形成されていくものです。世界各地に広まった地球のフォークロアの例として、ニューオリンズを基点としながら、さまざまなスタイルに枝分かれしたジャズがまず挙げられます。 他にも、ブエノスアイレスの港湾地区で生まれたタンゴ、キューバ発祥のマンボ、ウィーンのワルツ、アメリカ生まれのロックなども地球のフォークロアと言えるでしょう。 とくにロックは、インドのラヴィシャンカールのシタール、ウム・カルスームのアラブ歌謡、アンデス地方のワイノなどを取り込み、地球のフォークロアとして一層豊かなものになりました。
13 このフォークロアのより深いところで何が起こっているかというと、それは文化の「混淆・異種交配 (métissage) 」 と 「共生 (symbiose) 」 です。 たとえば、 ジャズはアフリカ系アメリカ人のハイブリッドな音楽としてニューオリンズに誕生しました。 その後、 さまざまに変容を繰り返しながらアメリカ全土に広まりますが、新しいスタイルのジャズがそれ以前のスタイルを消去してしまうことはありませんでした。 やがて、 黒人だけでなく白人もジャズに耳を傾け、踊り、そして演奏するようになり、 黒人と白人とが共有する音楽となったのです。 こうして次々と新しいスタイルのジャズが世界中に広まり、 演奏される一方で、 発祥の地で忘れられていたニューオリンズの古いスタイルが外国から里帰りをするということもありました。 ジャズにみられるような現象は数多く、 世界中に広まっているロックはまさに 「越境する文化」 を実現してきたと言えます。 一例を挙げれば、 ロックと北アフリカの音楽とが出会い、両者の混淆を経てライという新しいジャンルが生まれました。 さらに、 ワールドミュージックと呼ばれるジャンルになると、単に複数の音が混ざり合うだけでなく、世界各地のリズム、 主題、 音楽性が出会い、予期せぬ結びつきから新しい芸術が生まれます。 こうした結びつきは好ましくない結果を生じることもありますが、多くは素晴らしい結果を生み出して、世界の音楽文化は地球時代の申し子であることには気が付かぬままに互いに豊かになっていくのです。
●文化の独自性を守りながら、 雑種性・混淆を促すこと
15 これまで述べてきたグローバル化のさまざまな現象が進行すると同時に、自らの根源、ルーツに回帰しようという動きも生じています。 その現象は音楽の分野でとりわけ顕著に認められるものです。 フラメンコについてお話ししましょう私はジャズだけではなく、フラメンコの大ファンでもあるので個人的な思い入れがたいへん強いのです。一時期フラメンコはその発祥の地であるアンダルシア地方で消滅しかけていましたが、自分たちのアイデンティティを守ろうとする若い世代によって復活することになりました。 さらに、CDや公演の国際マーケットがこの「復活」を後押しして、世界中でフラメンコ愛好家が倍増し��した。 パリには倉庫を改造したフラメンコ・クラブがあり、スペインからフラメンコ舞踊団がやって来て上演しますが、その後彼らはヨーロッパ各地を巡業して回ります。こうした経験がフラメンコ自体にあらたな活力を与え、フラメンコは本来の芸術として活性化され、 復活する一方で、 異なる音楽形式とも結びつき、 源泉への 「回帰」と「混淆」という対立しているかにみえるけれども、 実は相互補完的なプロセスを体現しています。 ヨーロッパではバスクやケルトなど、そしてアフリカやアジアにおいても、 若い世代が伝統的な音楽を、 楽器を、 歌を守ろうと必死になっています。 ここでも 「トランスカルチュラル」な市場はそれぞれの音楽の伝統を守る運動を支えながらも、 同時に音楽的な多様性を育んでいるのです。
16 固有の文化を守らなくてはならないが、同時に文化は世界に向かって開かれな ければならないこのように、 私たちが直面する文化の問題はきわめて複雑なものです。 この問題を考えるにあたって、いかなる文化もその起源においては純粋なものではないということをまず理解しなくてはなりません。 いかなる文化も、その起源においては接触や結合や融合や混淆があり、純粋なものではありません。また文化というものは異質な要素を自らのうちに取り込み、同化させることができますが、これは充分な活力を持った文化であればの話です。 活力が充分でない文化は、より強い文化に同化し、支配され、 そして自らは解体してしまうこともあるでしょう。 文化というものはすべからく豊かなものですが、 不完全なものでもあります。 ちょうど人間と同じで、よいところもあれば欠点も欠陥もあり、常に突然の死を迎えるかもしれない危険とともに生きているのです。
17
私たちには二つの相矛盾する複雑な至上命令が下されています。 その矛盾を解消することはできませんが、この矛盾こそが諸文化の生命には必要だとも思います。 その二重の命令にしたがって、 私たちは諸文化の独自性を守ると同時に混淆や雑種性を促していかなくてはなりません。 文化的アイデンティティを守ること、雑種的でコスモポリタンな普遍性を押し進めること雑種性が個々の文化のアイデンティティを破壊する可能性があったとしても、この二つを結びつけなくてはならないのです。
18 どうすれば、 「解体」することなく 「統合」 することが可能なのでしょうか。この問題はアマゾン・インディアンやイヌイットのような少数民族にとっては深刻な問題を投げかけています。 というのは、彼らにとって 「統合」 はポジティブなものではなく、むしろ文化あるいは社会そのものの解体を意味することにもなるからです。 技術や医学など、 現代文明から有益なものを取り入れてもらうことは望ましいと思いますが、同時に彼らが代々伝えてきた民間療法、シャマニズム、狩猟の技術、 自然についての知恵などを守っていけるように支援しなくてはなりません。 伝統と近代、 文化と文化の架け橋が必要になるわけですが、人種的混血だけではなく、むしろ文化的に混血の人々がその架け橋の役割を果たすことができるではないかと私は考えています。
19 今日の文化のグローバル化の進展はメディアネットワークや再生技術 (DVDやCD)の世界的普及と分かちがたい関係にあり、インターネットとマルチメディアがすでに述べたような多様性や、競合 対立するプロセスすべてを加速し、 増幅させていくことは間違いありません。 しかしながら、 私は書物が消滅してしまうとは思いませんし、映画がテレビに圧倒されて消滅するとも思っていません。書物は思索と孤独と再読の友として、映画は映画館の暗がりのなかで共感をもたらすものとして、つまりは文化として生き残り、それぞれへの回帰現象すら起こるように思います。
20 画一化や利益追求のプロセスは急激に進展していますが、にもかかわらず多様化のプロセスと個人化・個別化への要求によって逆向きの運動も起こっています。
0 notes
Text
興味深々,是非訪ねたい展覧会です(๑˃̵ᴗ˂̵)
古代ローマには昔からとても興味がありました。カエサルやアウグストゥス(オクタヴィアヌス)やマルクス・アントニウスといった人々の名前は早いうちから知っていたし,何か格好良いという憧れのようなものを感じていたものです。考えてみれば僕はキリスト教の幼稚園で学びイエス・キリストの生涯についての紙芝居などを先生から見せられていましたから,幼稚園時代から古代ローマにはご縁があったともいえるわけです。 大人になってからもそういった古代ローマへの関心は衰えることはありませんでした。幾つかの新書も読みましたが,僕が読んだ古代ローマに関する書籍といえば何と言っても塩野七生氏の名著「ローマ人の物語」です。専門家からは史実との相違点を幾つか指摘されることもあり,また僕のような素人でも新書や大学の講義で習った事柄との違いに「ん(・・?)」と感じさせられる点はあるにせよ,古代ローマの歴史や当時の社会情勢についての概要を知るという意味においても,また何よりも知的な喜びを感じさせてくれるという意味においても,これ以上の本を僕は未だに知りません。仮に無理を承知で挙げるとすれば,同氏がヴェネツィアの歴史を追った「海の都の物語」がある程度でしょうか。ヤマザキマリ氏の人気漫画「テルマエ・ロマエ」を読むに際しても「ローマ人の物語」の知識が有るか無いかでその面白さは段違いでしょう。もし皆様の中で「何か面白い本を読みたいが,何が良いかな」とお探しの方がいらしたら,僕は何を擱いても「『ローマ人の物語』を読むと良いよ」とオススメしたい思いです。
そんな古代ローマに関する展覧会「永遠の都ローマ展」が,2023(令和5)年9月16日から12月10日まで,東京都美術館で開催されることを知りました。古代ローマといえば2022(令和4)年にも東京国立博物館で「特別展ポンペイ」が開催され,僕も勿論鑑賞にお邪魔致しましたが,2年続けて古代ローマに関する展覧会に触れられることになりそうです。但し「特別展ポンペイ」が博物館で開催されたのに対し,今回の「永遠の都ローマ展」が美術館で開催されるということによるのでしょうか,両者の方向性はやや異なって���るようです。西暦79年のヴェスヴィウス火山噴火で埋もれた遺跡からの出土品を中心に展示��れた「特別展ポンペイ」に対し,今回の「永遠の都ローマ展」では当時の美術工芸品とともに「古代やそれ以降のローマを描いた作品・所縁のある作品」も多数展示されるのですね。前者に属する「カピトリーノの牝狼」といったローマ建国神話に取材した有名な作品の他,後者に属するものとしてドメニコ・ティントレットの「鞭打ち」やカラヴァッジョ派の無名画家による「メロンを持つ若者」などといった絵画作品も展示されると聞き,これは美術鑑賞と美術史の勉強とを兼ねた良い機会にもなりそうだと感じています。
夏の暑さも収まった頃,上野で心行くまで歴史や美術に浸れると聞き,今から胸の高鳴る思いを禁じ得ない思いです(ლ˘╰╯˘).。.:*♡
0 notes