#斜めにかぶったキャップ
Explore tagged Tumblr posts
Text
【コスチューム】斜めにかぶったキャップ
目次 ▼【グラクロ】【コスチューム】斜めにかぶったキャップの基本情報 ▼【グラクロ】【コスチューム】斜めにかぶったキャップのステータス ▼【グラクロ】【コスチューム】斜めにかぶったキャップの着用可能キャラ ▼【グラクロ】【コスチューム】斜めにかぶったキャップの評価 【コスチューム】斜めにかぶったキャップの基本情報 部位 ビューティー レアリティ SSR 入手方法 イベント 価格 ― 【コスチューム】斜めにかぶったキャップのステータス HP+930 回復率+1% HP吸収率+2% 【コスチューム】斜めにかぶったキャップの着用可能キャラ 【異世界転生者】ルーデウス・グレイラット 【コスチューム】斜めにかぶったキャップの評価 イベントでゲットできる 無職転生コラボイベントのルーレットにてゲットできるコスチュームのひとつ。ルーデウス・グレイラットを入手していてないと持…
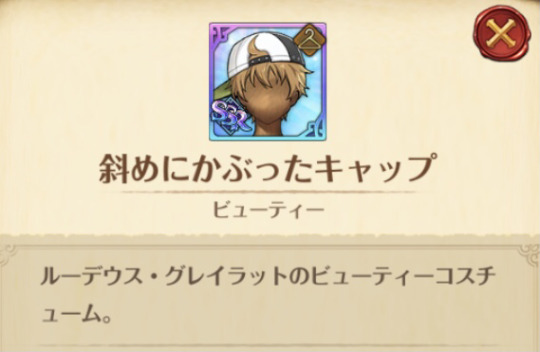
View On WordPress
0 notes
Text
BLACK POST JUNK / 2025.01.01 Part 3
それでは続きです。
90’s JANET JACKSON “RHYTHM NATION 1814” Embroidered Snapback Cap

90’s JANET JACKSON “janet.” Embroidered Snapback Cap

ジャネットのキャップが2個同時に手に入って嬉しかった思い出。 とあるフリーマーケットにて。 どちらもコンディション良好です。
90’s TRUMPETTE / GOT MILK? Sweatshirt [About XL]

プリント良しボディ良し。 既成ボディ(たぶんFRUIT)のタグカットして、TRUMPETTEなるタグが付いてる。 なにソレ?
90’s~ DETROIT SYMPHONY ORCHESTRA Sweatshirt [About XL]

ずらっと並んだクラシックの巨人達。 ビンテージの音楽家スウェットを一人ずつ集めるより、まとめて一つのこっちで良くない? コスパもタイパも高くて。
00’s LED ZEPPELIN / GRATEFUL DEAD / METALLICA Large Quilt

4パネルが連結する大判キルト。 裏面は一枚布のインヤンドラゴン。 ちょっと情報量多いて。 ファンメイドなのか何なのか、ただそれぞれコピーライトが入るので各パネルはオフィシャルだと思います。 にしても、作り的に素人の技には見えないんだよなぁ…。 機械的なキルティングステッチが一番最後に施されているから。 とにかく、ただパネルを繋げただけの品ではないです。
90’s~ PUNK Lightweight Slub T-Shirt [About XL]

ストレートなPUNKロゴ。 スラブ状に痩せた生地が大変マッチしていて気に入りました。 偶にはこれ見よがしに主張してみるのもアリです。
00’s DICKIES RED Zip Pocket Corduroy Pants [W33]

あまり馴染みの無いスタイルのDICKIESコーズパンツ。 ネーミングからしてLEVI'S REDの対抗馬でしょうか? にしては革新性は薄いけど…。笑 ただ見ていて、なんか良いなコレとジワジワくるものがあったので今回出すことに。 そんな気持ちを大事にしながら2025年も頑張る。
80’s~ SNAKE SKIN ILLUSIONS “BLACK CAMO” BDU Style Jacket With Boa Handwarmer Attachment Made In U.S.A. [XL]

これ中々に興味深いスネークスキンカモ。 なんか両ハンドポケットがモッコリしてるなと思ったら、筒形のボアが。 これはボタンで取り外し可能、まさに可変式のハンドウォーマーポケットです。 背中には大きなゲームポケットも配置。 面白いですねぇ…。 そもそもモノトーンタイプのBDU型ってだけでポイントは高いので、だいぶ満足度の高い一枚だと思います。
70’s~ UNKNOWN Padded Leather Riders Jacket [48]

昔から方々でサンプリングされるライダースの名デザイン。 中でもセリーヌがこのまんま作っててホッコリしたのも数年前。 モードスタイルにも耐える完成されたデザインなんだろうと思います。 こちらレザーは肉厚で柔らかい質感、ファッション性の高さは群を抜いて高いライダースです。
80’s BOUWITT “BLACK” All Leather Award Jacket [About M]

オールレザーのアワードジャケット。 ブラック。 こんなのカッコイイに決まってらぁ。
70’s~ UNKNOWN Patched Leather Riders Jacket [About L]

ラモーンズにU.K.サブスにスライムのパッチ。 ��縁部分のみレッドの配色切替。 きっと初期パン好きが着ていたんでしょう。 これならくっきーも良いねと言ってくれると思います。 ところで丁度一年前のBLACK POST JUNKで販売した鋲ジャン。 元気にしておりますでしょうか? ぶっちゃけ手放した事の後悔の念で一杯です!!
00’s MARITHE FRANCOIS GIRBAUD “BLACK” Twin Zip Cropped Pants [W31]

狂気じみているパターンワーク。 特に、膝下から裾までの間。 つまんで折って畳んでのオンパレード。 立体裁断の面白さと言うより、折り紙を折っているような楽しさを感じます。 はぇぇ~なんつって感動した後、穿いてみてまた悶絶。 着用写真を見たら、あぁPOST JUNKは好きだろうねって思うはず。
00’s DKNY Gunmetalic Silk Padded Shirt [XL]

滑らかなガンメタシルクにまさかのパデッド仕様。 オープンカラーの前比翼。 サイドアクセスの3D胸ポケット。 はぁぁ。 自分が欲しいなと思う服はこんな��じです。
00’s NIKE ACG “BLACK” Softshell Hooded Jacket [L]

00's ACGの傑作ソフトシェル。 良いの出来たわ、って絶対思ったでしょデザインした人。 ディテールは凄く強いんですけど、流線形の美しい切替線に全て溶け込んでる。 見事ですよ本当。 ブラックのLということで、お探しだった方は是非この機会に。
50’s~ SEARS / OAKBROOK Iridescent Black Gabardine Reversible Jacket [40]

玉虫もしくはグラデーション状に見える独特なギャバジン。 生地を観察すると経糸にブラック、緯糸にオレンジの糸で織られています。 見る角度によってオレンジと黒が異なるトーンで混ざり合い、本当に綺麗。 年代特有の妙なオラオラ感はなく、むしろ上品。 非常に良い���ャケットです。
90’s WILD THINGS SympaTex / Primaloft Denali Jacket Black Made In U.S.A. [L]

90's WILD THINGSの名品。 足し引きが一切不要のモデルですね。 私がよくやる、この服をより良くアップデートして下さいと言われたらどうする?という脳内遊び。 これはだいぶ苦行。
00’s PATAGONIA “BLACK” Winds-Day Jacket [XXL]

PATA界のはぐれメタルキャラ。 その特徴の無さから物陰に隠れまくっている迷作。 中でもブラックは激アツということで。 加えてXXLサイズとなると、この先ずっと隠れて出てこないんじゃないかと思うくらい尊い存在。
’01 PATAGONIA “BLACK” Integral Pants Early Model [XL]

最初期インテグラルジャケットの、下。 マニアックな品ではあるものの、これが滅茶苦茶格好良い。 濃いブラック部分はストレッチパネル、スミ黒部分は風合いの良いポリエステルシェル。 両サイドにベンチレーションジップ。 ブロードの白シャツを普通に合わせられちゃうくらい、スタイルレンジの広いパンツ。 大推薦。
00’s J.CREW Slant Stitched Nylon Pullover Down Hoodie [Women’s M]

基本的に大好きなプルオーバー型のダウン。 そこにこんな斜めステッチは反則だろうと。 加えてコンパクトに着用できる被りダウンというのも非常に新鮮。 ウィメンズモデルですが、男性の方にもおすすめしたいです。 超お洒落ですコレ。
90’s EURO LEVI’S White Stitched Hard Nylon Jacket [L]

バリバリとしたハリの強いブラックナイロンシェルに、ホワイトステッチ。 もうギャルソンじゃんこんなの。 ベーシックの中に一癖与えるこの感覚。 まさにユーロリーバイス節です。
80’s CRASS T-Shirt [About S]

オールドユーロボディのCRASS T。 表立って着るのも良し、体の一番内側に仕込むのも良し。 お好きな方に是非。
90’s PRIMAL SCREAM “SCREAMADELICA” Embroidered Snapback Cap

あんまり出ないプライマルスクリームのキャップ。 額には一番のアイコン。 そしてミントコンディション。
以上です。
当記事内でご紹介した全アイテムは 明日2025年1月1日(水) 21:00 から POST JUNK オンラインストア にて販売開始となります。
※商品の発送は1月6日(水)から順次開始となります。
よろし��お願いいたします。
POST JUNK Online Store
INSTAGRAM
FACEBOOK
TWITTER
山梨県甲府市相生2-4-24 モナークアイオイ1F
0 notes
Text
結婚したら…
厳しい注意をし、それを直すように言ったあと、勇利は確かによくなかった点を修正し、さらに、ヴィクトルが期待したり想像したりした以上の出来映えですべって見せた。ひとみをきらきらと輝かせ、はしゃいだように戻ってきた彼は、「どうだった!?」と声をはずませて尋ねた。 「よかったよ、勇利! すばらしかった! おまえは最高だ!」 ヴィクトルは勇利を抱き��め、感嘆の吐息をついた。 「いまの感覚を忘れないようにね。誰もを惹きつける、魅惑的な演技だったよ」 「ほんとに? ヴィクトルのことも?」 「もちろんさ。俺がいちばんとりこになるんだよ」 ヴィクトルは勇利の額にキスし、それからつややかな黒髪をいいこいいこと撫でてやった。勇利は頬を紅潮させ、うれしそうににこにこした。 「もう一回すべってきていい? いまのを身体にしみこませるから」 「いいとも。すてきな勇利をたくさん見せてくれ」 勇利は注意されたこともそれで上手くいった演技も忘れることなく、練習時間が終わるまで充実したすべりを見せた。ヴィクトルは更衣室で着替えるときも勇利を褒め、引き寄せて髪に頬を寄せた。 「どんどんよくなってきてるね、勇利。俺は鼻が高いよ」 「試合のときもそう言われるようがんばるよ」 勇利が更衣室から出ようとしたので、ヴィクトルは引き止めて彼と向かいあった。 「ちゃんとしなくちゃだめだ」 ヴィクトルは適当にぐるっと巻いただけだった勇利のマフラーをぐるぐる巻き直して、隙間ができないように工夫した。ヴィクトルにはなんともないけれど、ロシアは寒いので、勇利にはつらいだろうと思ったのだ。ニット帽も耳がきちんと隠れるようにひっぱってやり、眼鏡が曇らないために気遣ってマスクの位置も変えた。 「勇利のかわいい顔が見えなくなるのはさびしいけど、仕方ないね」 「なに言ってるの?」 勇利は本気にしていないようで、楽しそうに笑うばかりだった。勇利に夢中のヴィクトルは本気で言っているのだった。 「それから手袋も……、勇利、なんてことだ、手がつめたいじゃないか」 「えっ、そう? 感覚としてはあったかいんだよ。たくさん動いたから」 「でもふれるとつめたい」 ヴィクトルは大きな手で勇利の手を包みこみ、丁寧にあたためてやった。 「いいよ、そこまでしなくて」 「俺がしたいんだ。おとなしくしておいで」 「ヴィクトルは過保護なんだよ」 「こんな手をしておいて何を言ってるんだ?」 「だから、ぼくとしてはつめたくないんだってば……」 「油断はいけない」 「油断じゃないよ。事実」 「すこしは俺の言うことも聞いてくれ」 「聞いてるよ。いつも」 「いつも……?」 「いつもじゃん」 拗ねて頬をふくらませる勇利が、たまらなくいとおしかった。ヴィクトルは自分の満足がゆくまで勇利の手をあたため、それからふたりでクラブを出た。 「夕食の材料を買って帰ろう」 「ぼくあれ食べたい。ビーツが入った……」 「いいとも」 ヴィクトルは勇利が希望したスープの材料をたっぷりと買いこみ、勇利と連れだって帰宅した。こうして勇利と買い物をして歩くのは、ヴィクトルのもっとも好きな勇利との行動のうちのひとつだ。ヴィクトルは勇利とすることはなんでも好きなので、「もっとも」も何もないのだけれど。 「着替えたら居間でのんびりしているといい」 「ぼくもつくるよ」 「いいんだ。勇利はマッカチンと遊んでてくれ。さびしかっただろうからね」 「うん……」 ヴィクトルが忙しい時期は勇利が毎日食事をつくっていた。それ以外にも家のことをすべてこなして、ヴィクトルの生活がとどこおりないようにしてくれていた。だからヴィクトルは、自分に時間があるときは、できるだけのことをしたいのだった。勇利が来るまで料理なんてしたいと思ったことはなかったし、そうしようという発想すら持っていなかったけれど、いまはちがう。勇利との暮らしをいとなむためならどんなことでも楽しい。 「さあできたよ。こっちへおいで」 「お皿並べる」 「いいよ。席について」 「並べる!」 そう言い張って手伝う勇利があまりにもかわゆく、ヴィクトルはきゅんとして胸を押さえた。かわいい俺の勇利……。 ヴィクトルのスープを、勇利は「フクースナだよ」と言って食べてくれた。そう言うときの笑顔の可憐なことといったら……。 「それはよかった」 「でも、ここのところずっとヴィクトルにつくってもらってる。明日はぼくがやるよ」 「いいんだ。好きでやってるんだ」 「ヴィクトルって料理好きだったの?」 新しいことを知った、と勇利はにこにこした。ヴィクトルにあこがれているあいだに彼が得た情報では、料理好きなんていう項目はなかったらしい。当然だろう。 「好きだよ。日夜研究に励んでいる」 ヴィクトルは胸を張った。そっかー、と勇利は笑った。「そっかー」という発音がかわいいといったらなかった。 入浴はふたりでするようにしている。「温泉とはちがう」と勇利も最初は抵抗したけれど、度重なると慣れたらしく、何も言わなくなった。 「今日も一緒に入るの?」 「入るよ。当たり前だろう」 「はいはい」 初め、身体を洗ってあげるということを提案したのだけれど、それだけはいやだと勇利は激しく反対し、結局、ヴィクトルが彼の髪を洗うということで落ち着いた。ヴィクトルはなぜだめなのかわからなかった。 「そんなに気にすることじゃないだろう」 「気にすることだよ……どういう考え方してるの……」 「俺は洗ってあげたいけどな」 「けっこうです」 ずいぶん前、そんな会話をしたのをおぼえている。 今夜も勇利は身体は自分で洗い、そのあとちいさな椅子に座ってヴィクトルに背を向け、ヴィクトルのしたいようにさせていた。勇利の髪を洗っていると、ヴィクトルは、これがあのさらりとしたつややかな髪か、とときめかしさで胸がいっぱいになる。使うのはもちろんヴィクトルの選んだシャンプーだ。勇利の髪質を考え、いろいろなものをためした結果、これにきまった。勇利はヴィクトルがたくさんのシャンプーの中から選んだことを知らない。一度、シャンプーが切れそうだと言ったとき、彼が「じゃあこれ」と自分で買おうとしたことがある。ヴィクトルからするとそれを使うなんてとんでもないという代物だった。急いで大反対し、俺が買うと主張してシャンプー選びから手を引かせた。勇利は、どれでも同じなのに、という顔つきだった。 「勇利、もうすこし頭を上げてくれ」 「んー……」 ヴィクトルが丁寧に撫でるようにしながら頭皮を指先でこすっていると、勇利が眠そうな声を上げた。ヴィクトルはふわふわした泡を勇利の髪からすくい上げた。 「眠いかい?」 「ヴィクトルのシャンプー眠くなるんだよね……気持ちよすぎて……」 「それは光栄だね」 「ん、口が半開き……」 ヴィクトルは笑いながら、勇利の耳の後ろをそっと掻き上げた。そのついでに、耳のかたちもなぞって綺麗にしておく。 「あ、それ好き」 「そうかい?」 「うん。ヴィクトルに耳さわられるの好き」 「どきっとするせりふだね」 「どうして?」 ヴィクトルはちょうどよい温度でシャワーを使い、「洗い流すから目を閉じて」と注意した。 「はーい」 「口も閉じて」 「よだれは出してないんだよ」 ふくれて言う勇利を抱きしめて髪に頬ずりしたい。泡だらけでもかまうものか。 しかしヴィクトルはその誘惑に耐え、勇利の髪を綺麗に洗い流した。 「さあ、終わりだよ。あとはゆっくりつかってあたたまろう」 浴槽に入るときは、ヴィクトルが後ろから勇利を抱く姿勢だ。勇利はヴィクトルの胸にもたれかかってよい気持ちそうにする。これもヴィクトルがしあわせを感じる瞬間だった。 「もっと脚を伸ばして。身体をこっちへ」 「あんまりもたれると重いかと思って。こ���ただからね」 勇利はヴィクトルが「こぶたちゃん」と言うことをいつまでも恨みに思っているのだった。こころのこもった愛称なのだけれど、彼にはわかってもらえない。 「俺は勇利をリフトできる男だよ。勇利は羽のようにかるい。いや、勇利には羽が生えているのかもしれない。なにしろ天使だからね」 「何を言ってるのかわからない」 「いや……、天使以上にかわいいから天使ではないな……そんなものではない。もっと……」 「何を言ってるのかわからない」 ヴィクトルが引き寄せると勇利は素直にもたれかかり、完全に身体をあずけた。ヴィクトルは彼のすらっとした痩身を抱き、ちいさな顔に頬を寄せてまぶたを閉じた。なんてしあわせなんだ……。ヴィクトルは、勇利といつか結婚するということを考えた。 風呂から上がると、勇利は寝巻を着、簡単に髪を拭いただけで部屋へ引き取ろうとした。 「勇利!」 ヴィクトルは呼び止めて居間へ連れていった。勇利はいつもそうなのだ。こんなことをして平然としている。 「ちゃんと乾かさないとだめだ」 「大丈夫だよ。ほうっておけばすぐ乾くから。ロシアはいつだって部屋の中はあたたかいじゃない」 「それでもだめだ。風邪をひくかもしれないし、髪だって傷むんだよ」 「傷まないよ。そうだとしても気になるほどじゃない」 「だめだ! きみはいつもそうだ。俺の言うことを聞くんだ」 「わかったよ……」 ヴィクトルが叱りつけるようにとがめると、勇利はしおらしくうなずいた。しかし内心ではめんどうだと思っているにきまっている。ヴィクトルがいろいろ言うので反省したふりをしているだけだ。 「おいで。俺がやってあげる」 「自分でするよ」 「勇利は信用できない」 「ヴィクトルがぼくを信じないなんて」 「勇利のこういうことに関してはすべて疑ってかかるよ俺は」 ヴィクトルは勇利をソファに座らせ、ドライヤーで丁寧に髪を乾かした。勇利はヴィクトルの手がふれるあいだ、よい気持ちそうに目を閉じてじっとしていた。きっと髪を洗ってやっているときもこんな顔をしているのにちがいない。言うことを聞かない大変な子だけれど、このあどけない表情を見ているだけでヴィクトルは幸福を感じるのだった。 「かわいいな……」 「んー……? なに……?」 「なんでもないよ。すこし髪が伸びたね」 「へん?」 「いや、綺麗だ。勇利はいつも魅力的だよ」 勇利が笑いだした。どうやら冗談だと思っているらしい。 「さあ、これでいい」 ヴィクトルは納得してうなずくと、ついでに自分の髪もさっと乾かした。勇利はそのあいだぼんやりとテレビを眺めていたけれど、ヴィクトルがドライヤーを止めたところで立ち上がって、「じゃあ寝ようかな……」とつぶやいた。 「何を言ってる。まだすることがあるだろう」 「なんだっけ」 「毎日やってるのに勇利はおぼえていない」 「眠いんだよ」 確かに、あれほど練習しているのだから、疲れて眠りたくもなるだろう。しかし、だからといってじゃあおやすみと譲れるものではない。 「こっちへおいで。ここへ座るんだ」 ヴィクトルはソファの上であぐらをかき、膝を叩いた。 「やだよ、もう、そんなの……」 「何を恥ずかしがってる? 毎日裸だって見てるのに」 「変な言い方しないでよ。お風呂に一緒に入ってるだけじゃん」 「それでも裸を見てる」 「いちいち言い方が誤解を招くんだよ、もう……」 勇利はぶつぶつ言いながらヴィクトル��あぐらの上に横向きに座った。ヴィクトルは彼を自分に寄りかからせ、ほっそりした手を取って引き寄せた。この手が演技のときしなやかに動くのが、どれほど可憐でうつくしいことか。 「ほら、もっと手を出して……」 「くすぐったいよ」 「勇利が抵抗するからくすぐったいんだ」 ヴィクトルはききめのあるハンドクリームをすくい、それを勇利の手に伸ばして両手で包みこんだ。優しく、静かに揉むようにすると、くすぐったがっていた勇利がぴたりと黙った。 「痛くないかい」 「うん……」 「指先まで綺麗に……」 「こんなことしなくてもいいよ」 「だめだ。勇利は自分に無頓着すぎる」 「ヴィクトルがこだわりすぎなんだと思う」 「おまえはほうっておいたら何もしない」 勇利は溜息をつき、どうでもいいというようにヴィクトルにもたれかかって無抵抗だった。もっと自分のうつくしさについて考えればよいのにとヴィクトルは思った。もっとも、何も考えていなくても勇利は綺麗でかわいい。それに、こうしてなにくれとなく彼の面倒を見るのがヴィクトルは好きだった。可憐な勇利を、さらにうつくしくするのだ。 「もういい?」 「まだだ。片手しか終わってないだろう」 「ぼく、左手は何もしなくても大丈夫なんだ」 「何をわけのわからないことを言ってるんだ」 「ヴィクトルにわけわからないって言われたらおしまいだね……」 「俺こそ勇利にそう言われたらおしまいだ」 ヴィクトルは眠いとぐずる勇利をなだめすかして保湿をした。彼が黒髪やこめかみにキスすると、勇利は「そういうので騙されないから」などとかわゆいことを言った。 「勇利は俺をなんだと思ってるんだ」 「少なくとも、こんなにいろいろ言ってくるひとだとは思ってなかった」 勇利にだから言うのだし、世話を焼くのだけれど、この妙な子はそれをわかっているのだろうか。ヴィクトルは甚だ疑問だった。 「さあできた。勇利、もういいよ」 満足してヴィクトルがクリームのふたを閉じたとき、勇利はヴィクトルにもたれかかったまま動きもしなかった。 「勇利?」 顔をのぞきこむと、彼はすうすうと子どものような寝息をたてて眠っていた。ヴィクトルはほほえんだ。 「おいで、マッカチン」 ヴィクトルはあかりを消し、勇利を抱き上げて寝室へ行った。そして彼を慎重にベッドに横たえ、自分も隣に落ち着くと、優しく抱き寄せて髪を撫でた。 「んー……終わったの……?」 「ああ、終わったよ。もうベッドだ。寝ていいよ」 「そっか……おやすみ……」 勇利は深い眠りに落ちたようだった。ヴィクトルは彼を守るように抱きしめ、鼻先に接吻して目を閉じた。 「ジャージで行くの?」 「ううん、今回はスーツ」 勇利の全日本選手権に付き添ったヴィクトルは、滑走順抽選に向かう勇利がスーツの覆いを取るのを見て溜息をついた。 「俺が贈ったやつにしなさいと言っただろう」 「あんな高価なの、普段遣いにできないよ」 「普段遣いにするために買ったんだ」 勇利は何もわかっていない。しかも彼は、自分で以前から持っている、ヴィクトルには信じられない型のスーツを手に取って気楽そうだ。 「勇利、だめだ」 ヴィクトルは注意をうながした。 「だめだっていっても、これしか持ってきてないんだから」 「そうじゃない。スーツはもう仕方ない。俺はゆるせないけど、いまから買いに行くわけにもいかないしね」 「当たり前じゃん」 「バンケットの前に考えよう」 「バンケットのスーツもこれだよ!」 「とんでもないしろものだ」 「失礼なんだよ」 「ネクタイはちゃんと結ぶんだ」 「結んでる」 「勇利はいつもすこし斜めになる」 「だってこうなるんだよ」 「きちんと丁寧に結べばそうならない。来てごらん」 「ヴィクトル、ぼく時間ないから」 「まだ三十分ある。予定表を見てちゃんと知ってるぞ」 勇利は頬をふくらませた。彼は、いつも予定なんて考えないヴィクトルなのに、とぶつぶつ言った。 「勇利のことではこまやかになる」 「無理しないほうがいいよ」 「好きでやってるんだ」 ヴィクトルは後ろから勇利を抱きこみ、彼のネクタイをゆっくりと結んでやった。勇利はうつむいておとなしくしていた。 「あの、抱きしめないとできないの?」 「勇利、前からネクタイを結べるかい?」 勇利はしばらく思案し、「できないね」と素直に答えた。 「そうだろう」 ヴィクトルはきちんとしたかたちをつくって結び終えると、優しく上着を着せかけ、すぐ前の鏡を示した。 「ほら、見てごらん。うつくしいだろう」 勇利はよくよく自分の姿を観察し、「確かに、ネクタイはいつもより綺麗だね」と同意した。 「俺が言ってるのは勇利自身もふくめてだ。さあ、もういいよ。そんなに時間が気になるなら行っておいで。迷子になりそうならついていこうか?」 勇利は何か言いたげな表情でヴィクトルをじっと見た。 「なんだい?」 「……ヴィクトルってさ……」 「うん?」 勇利は彼独特のうつくしい澄んだ目でヴィクトルをしばらく眺めたあと、「なんでもない」とつぶやいて部屋を出ていった。おかしな子だ。もっとも、勇利はいつでもおかしいけれど。 試合当日も、ヴィクトルは勇利の支度をいろいろと気にした。 「そろそろ着替えるかい?」 「うん。更衣室へ行ってくるよ」 「俺も行こう」 「ひとりで大丈夫だよ。迷子にもならない」 「そういうことを心配してるんじゃない。いつだってそうしているだろう?」 ヴィクトルは更衣室で勇利の着替えを手伝った。彼の後ろから衣装のファスナーを上げてやるとき、つややかな肩がキスしたいくらい綺麗だといつも思うのだ。しかしそうはしなかった。それは演技のあとにとっておこう。 「どこも窮屈じゃないかい」 「うん」 「じゃあこっちへおいで。髪をやってあげよう」 勇利はもう何も言わず、ヴィクトルの言うとおりにした。ヴィクトルは鏡の前に座る彼の背後に立ち、勇利の朱塗りの櫛で髪を梳き上げた。これはまるでおごそかな儀式のようで、ヴィクトルはこうすることをたいへん気に入っていた。勇利もこのときこころを研ぎ澄まし、演技のためにととのえているようだ。ヴィクトルは満足すると、勇利の頬を両手で包んで前を向かせ、彼と一緒に鏡をのぞきこんだ。 「うつくしいよ、勇利」 「そう……」 衣装を身にまとい、こうして戦うための姿になった勇利は、本当に凛々しく綺麗なのだ。 「これからおまえはすてきな演技をするよ。俺を魅了し、勇利自身もどきどきする演技をね。俺にはわかってる。勇利は俺の生徒だ。そして俺の誇りだ。俺のかわいい子だ。愛してるよ、勇利」 ヴィクトルはそう言って勇利を氷の上へ送り出した。 ヴィクトルの予言どおり、勇利はすばらしいプログラムを演じ、ショートプログラムもフリースケーティングも終えた。ヴィクトルは自分のもとへ戻ってきた彼を抱きしめ、頬ずりをしてささやいた。 「すばらしかった。アメージングだよ、勇利。おまえは最高だ! 勇利、俺の勇利。俺はおまえに夢中なんだ……」 勇利が汗にひかるちいさなおもてを上げたので、ヴィクトルは彼の顔じゅうにせわしな��接吻した。勇利が笑いだした。 「みんなが見てるのに……」 「かまうものか」 「カメラもいるよ」 「知ってるよ」 ヴィクトルは勇利にジャージを紳士的に着せかけ、ひざまずいてエッジカバーを左右ひとつずつつけてやった。それからキスアンドクライで膝にマッカチンのティッシュボックスを置いてやり、ファンから贈られたぬいぐるみをまわりに丁寧に並べた。さらに、勇利が飲み物を飲みたそうにしたので、キャップを外して渡した。彼が飲み終えるのを待って、ひとつまだ持っていたおむすびのぬいぐるみを腕に抱かせた。 「大丈夫だったかな。点数悪くない?」 「あんな演技をしておいて何を言ってる?」 「ちゃんとできたつもりだけど不安で。自分でわかってない失敗があったかも」 「何もおそれることはない」 ヴィクトルは勇利を引き寄せ、髪にキスして優しく撫でた。勇利は笑い、それから輝くひとみでヴィクトルをみつめた。 「なんだい?」 「ヴィクトルってさ……」 ヴィクトルは勇利の言葉を聞き逃さないよう、彼の口元に耳を寄せた。そのとき、得点が出、歓声が上がって、勇利がうれしそうに白い歯を見せた。 あのひどいスーツにもかかわらず、バンケットのために着飾った勇利はひどくうつくしかった。ヴィクトルはこのときも勇利のために髪を梳いてやり、すらっとした彼の姿勢と装いに陶酔したように見蕩れた。 「綺麗だよ、勇利」 「ありがとう」 「さあ行こう」 ヴィクトルは会場で勇利をエスコートし、影のように寄り添って離れなかった。勇利はヴィクトルの腕に指をかけ、ほかの選手に話しかけられるとひかえめに返事をした。 「みんな、勇利に声をかけてもらいたいんだね。何か自分から言ってあげればいいのに」 「人が寄ってくるのはヴィクトルがいるからだよ」 「勇利……おまえは何もわかっていない」 「なんのこと?」 「何か食べるかい? 取ってあげよう」 勇利はすこし緊張しているようだ。食べさせないと、自分では何も取ろうとしないだろう。立食形式なので、自分で好きに食べ物を選んでよい。ヴィクトルは勇利が気にしたものをひとつひとつ皿に取り、甲斐甲斐しく彼に差し出した。 「美味しいかい?」 「うん」 勇利は口をもぐもぐさせながらこくっとうなずいた。そのいとけなく愛らしいしぐさにヴィクトルはたまらない気持ちになった。早くこのかわいい子と結婚したいものだ。今回は日本の大会だったけれど、いずれ世界大会で彼が金メダルを獲れたなら……。 「食べてばかりじゃ喉が渇くだろう」 ヴィクトルは水のグラスを取り、勇利に差し出した。勇利は礼を述べてそれを受け取ると、大きな目をぱちりと瞬いてヴィクトルに向けた。 「ヴィクトルってさ……」 「なんだい?」 そのとき、「勇利くん!」とやってきた後輩があったので、勇利はふしぎそうにそちらを向いた。声をかけられてふしぎそうにするのは勇利くらいのものだとヴィクトルは思った。 時間が経つと、勇利がふうと息をついてつぶやいた。 「なんか酔ってきた」 「勇利、飲んだのかい?」 「水だけだよ。でも人いきれで……」 「もう引き上げよう。じゅうぶんだろう。帰ってる人もいるみたいだ」 「うん……」 勇利の頬がほてっている。ヴィクトルは彼を外へ連れ出し、庭をすこし散策することにした。 「風が気持ちいい」 月明かりを浴びた勇利はうつくしかった。ヴィクトルは彼に見蕩れていたけれど、どこからか話し声が聞こえてきたので、ほっそりした腰を抱いて奥の道へと導いた。こんなとき勇利は人に会いたがらない。 「こっちへおいで。静かだよ」 「うん……、ヴィクトルってさ」 勇利はぱちぱちと瞬いて言った。 「優しいよね」 「突然なんだい?」 「すごく親切だなあって……。もともとファンに優しい人だから当たり前なのかもしれないけど、それだけじゃなくて……。生徒にこんなに優しいなら……ヴィクトル……」 勇利はくすっといたずらっぽく笑った。 「結婚したらどうなっちゃうの?」 ヴィクトルはほほえんだ。もちろん、ずっと、もっともっと勇利に優しくするのさ。そう答えようとした彼に勇利は言った。 「相手の人、びっくりするだろうね」 「……え?」 「ヴィクトルにこんなに優しくされたら舞い上がっちゃうだろうな。生徒にこうなんだから、結婚相手にはもっとでしょ? どんなふうにするの? 想像もつかない……。いったいどうなるんだろ?」 ヴィクトルはぽかんとした。勇利の言う意味がわからなかった。もしかして彼は、生徒だからヴィクトルがこんなに優しくしていると思っているのだろうか? 結婚相手にはそれ以上のことをすると? まさか──。 冗談じゃない! 「結婚相手はおまえだよ!」 ヴィクトルは叫んだ。突然大きな声を出した彼に、勇利は驚いたように目をまるくした。 「え?」 「俺はおまえと婚約してるつもりだし、愛してるからそんなふうに接してるんだ!」 「え……えっ……?」 「結婚したら優しくするよ! もっと別のことでもね!」 「うそ……えっ……ほ、ほんとに……?」 勇利は口元を押さえ、信じられないというように瞬いた。つめたい風でおさまりかけていた彼の頬が、また赤く紅潮した。まったく……自覚のない子だと思ってはいたけれど、まさかこんなことさえわかっていなかったとは……。 「え……うそ……やだ……そうなの……?」 「いや!? 俺と結婚するのがいやなのか!?」 「これ以上優しくされたら……」 勇利はひとみを大きくみひらき、ほのかにきらめかせてつぶやいた。 「ぼく堕落しちゃうじゃない……どうしたらいいの?」 ヴィクトルは驚いた。こんなことを言われるとは思わなかった。さっきから勇利はびっくりさせることばかり言う。 ヴィクトルは笑いだした。 「ヴィクトル、ぼくのこと好きなの?」 「言葉でも態度でもあらわしてたつもりなんだけどね」 「やだ……もう……」 「何がいやなんだ」 勇利はまっかになって両手で口元を覆った。 「そんなの……、照れるよ!」 世界選手権でクリストフに会ったとき、「ヴィクトルは勇利をうつくしくするのに余念がないね」とからかわれた。ヴィクトルは笑い、勇利は頬をうすあかくして答えた。 「このひと、ぼくのこと愛してるんだって……だからこんなふうなんだって。結婚したら別のことでも優しくしてくれるつもりらしいよ」
3 notes
·
View notes
Text
『大冒険はボタンから/1:Starting from a button of the mistake.』 1:ボタン
カツン、コツン、コロコロロ。
彼が、部屋の掃除を7割方終えた頃、|ソレ《・・》は、室内に転がり出た。
書類の束が|堆《うずたか》く積まれた上。壁面の高い所に取り付けられている大きくて丸い時計は、11時5分を指している。
コロロロロォ……カツン、ココンッ、ガキンッ―――! 机の上から、フローリングの床へダイブしたモノは、室内を縦横無尽に|跳ね回り続けている《・・・・・・・・・》。
「これは、いけませんねえ。面倒なモノを……見つけてしまったかもしれません」 額に|滲《にじ》む冷たい��を、手の甲で拭う、年の頃は20代半ばと思われる青年。
ボソン! ……コッーン! コカカカカカカーン! 紙束などに当たったときは、一瞬勢いが弱まるが、堅いフローリングに落ちたところで、勢いが復活してしまう。
コココッ、カキン! コロコロロロッ!
ゴロロロロロロロロッ……ゴチン! ソレは、部屋の隅、冷蔵庫が有るあたりへ転がっていった。
「やっと止まってくれましたか。あまり|煩《うるさ》くすると、また怒鳴り込まれてしまうトコでした……」 彼は、溜息を付き、手にしていたファイルと、ミストパイプを作業机の上に放り出した。高級そうなオフィスチェアごと、部屋の対角線へ振り返る。 彼の服装は、仕立ての良さそうなスラックスに、ノータイの薄ピンク色のYシャツ。年齢からすると、やや、堅い部屋着と言える。
ゆったりとした広さの、書斎のような空間。長い足を延ばして、ダンサーの|如《ごと》き跳躍をみせ、書斎の床の中央付近を華麗に飛び越えた。
すとん。その細身ながらも筋肉質な長身を、最大限に縮めて、着地の衝撃を吸収する。 ぺたり。着地した姿勢から、そのまま床にへたり込んだ青年は、1ドア、レトロな冷蔵庫の下へ手を伸ばした。
「んぎぎぎぎっ……」 顔面を冷蔵庫に押しつけるほど、伸ばした指先がコツリ。冷蔵庫の脚に踏ませてあった、耐震シートにくっついてた|ソレ《・・》に触れた。
コッコッガツン! コロコロコローーーーーーーッ! 再び、転がり逃げる小さくて丸いもの。
彼は慌てて立ち上がるが、振り向いたときには、既に遅かった。 コンッ、コココココココココンッ! サイドチェストと床壁面で囲まれたコーナースペースへ飛び込んだ丸くて平たいモノが、乱反射する度に加速していく。
ゴガカカカッ―――! それは既に、危険な速度に達していた。 「くっ!」 |飛翔物体《・・・・》は、青年に向かって、一直線に飛来する。
「―――それで、その跳ね回る物体を、どうやって捕まえたの?」
「それがですね、ちょうど冷蔵庫の方に向かって飛んできてくれたので、冷蔵庫のドアを開けて、―――」
「冷蔵庫に閉じ込めたというわけか」 鈴の音のような、聴き心地の良いソプラノ。
「はい。そのまま放置して……3時間は経過したので、流石にもう大人しくなってくれているとは思うのですが……」 彼が確認した店内の時計は、2時30分を指し示している。 24時間営業のファミレスの窓の外は、真っ暗で、何も見えない。
「あれ? 君、愛用の時計はどうした?」
「それが、……なにぶんアンティークなもので、とうとう壊れてしまいました」
「ふーん。良く似合��ていたのに……残念だな」 見方によっては愛嬌のある大げさな仕草で、ナイフとフォークをガシャンと放り出す。
「まあ、本当に古いモノだったから、仕方がないですよ。ただ、時間が判らないと不便ですけどね」 彼は手首を指し示す。
「ふむ。相変わらず、デジタル嫌いは直らないのか?」
「僕的には、デジタル時計も、スマホもノートPCも嫌いではないのですけどね……」
「そうだったね、デジタル機器の方が、君を嫌っているんだったね……初めて聞いたときは、とても信じられなかったけど」
「……はははは」 力なく笑う青年の横へ立つ、年の頃は17、8歳の少女。ヨレヨレの白衣、大きな洗濯クリップで|纏《まと》めただけの、ボサボサの髪。赤みがかった金髪が揺れている。
「どうしました? もう研究所へお戻りですか?」 青年は、仕立ての良さそうなスラックスに、薄手のパーカーを合わせている。 パーカーの首元から覗いているのは、薄ピンク色の|部屋着《シャツ》と思われる。
「何を言っている? 君の家に行くよ」 そう言って、置かれた伝票をひったくって、走り出した少女。 目の下の真っ青な隈、草地を蹴飛ばして歩いていることが伺える緑色に汚れたハイカットスニーカー。あまり見目良いとはいえない印象。
「え!? ウチ来るんですか? 待ってください!」 慌ててストライプのジャケットを羽織り、荷物を抱え、後を追う青年。 磨き込まれた革靴に、ジキトーチカ社製の高級メッセンジャーバッグ。
「僕が誘ったんですから僕が……」 「いーえ、上司が部下に奢るのは当然でしょう?」 そう言って、レジへ提示したのは、首から下げていた、顔写真入りの所員IDパス。『Kanon,Riina Lucie』と書かれている。
「部下といっても、僕は研究所出入りの、ただの文書屋ですから~」
「ふむ。私としては君を|ただの文書屋だなんて《・・・・・・・・・・》思ったことは一度もないが、そう言うなら|なおさらだ《・・・・・》、素直に奢られなさいよ」 ニタリとした笑みを浮かべ、青年を振り返る少女。 やや、不気味だったが、白衣の下のブラウンのワンピースだけは、ちゃんとしてくれていたため、辛うじて、ティーンエイジャーとしての|面目《めんもく》が保てている。
「あんた達、いちゃつくなら外でやっとくれ。ほかのお客に迷惑だろ」 レジに立つ、オールドスタイルなメイド装束の美女が、憮然とした顔で少女の首ごと引っ張って、IDパスをレジスタに通す。
ジージジジジッ、ガチーン♪
「アタシたちのほかに、お客なんて居ないじゃないさ」 フンッ! と首を持ち上げ、ネックストラップに取り付けられたIDパスを取り返す少女。
とっとと出ていってしまう少女を、眼で追いか��る青年。 レシートを受け取り、少女の非礼をウエイトレスに会釈して詫びる。 少女のモノであるらしい、小さなジュラルミンケースを小脇に抱えるその姿は、まるで付き人である。
長身で引き締まった身体。柔らかい物腰。彫りが深く高い鼻、どこの映画スターかと問いただしたくなるほどの、眉目秀麗さ。 「まったく、あんなにイイ男なのに、勿体ないったらありゃしない」 ウエイトレスは、青年と少女の座っていたテーブルに向かい、食器を片づけ始めた。
「待ってくだっ―――さい?」 |ファミレス《ダイナー》を飛び出し、家路へ向かうルートへダッシュした青年は、10歩も進まないウチに、少女を追い越した。
「ふー、今度一緒にジョギングでもしませんか? 運動不足では研究に差し障りますよ?」 歩道へヘタリ込んでいた彼女へ、手を差し伸べる彼。
「う、うるさいわね。ちょっと食べ過ぎで苦しくなっただけよ」 年相応な、|辿々《たどたど》しい返事が返ってくる。 普段の老人のような落ち着いた物言いは、彼女の地では無いらしい。
カカカッ。
「何よ、この音?」 と不意に顔を上げた少女と、眼が合う青年。 「何か聞こえましたか?」 青年には聞こえなかったようだ、あたりを見回している。
少女が向いている方向は、青年の住まいが佇む方角だった。 彼は振り向いたが、そこには暗闇と歩道しか無い。
ヴォムン! 爆発音と共に、小さな炎が飛び上がった。 漆黒の空を見上げる2人。
カカッ―――――――――!
突如、あたりは|眩《まばゆ》い光で包まれた。 白昼のように、いや、それよりも鮮明にあらゆるモノを照らし出した。 抱えていた荷物を放り出した青年は、光から顔を背けながらも、少女を|庇《かば》う様に覆い被さる。
眼をキツく閉じた少女の|瞼《まぶた》の裏には、上空へ飛び上がった物体の姿が焼き付いたようだった。
「あれ、|君ん家の冷蔵庫《・・・・・・・》じゃなかった!?」
凄まじい強さの光はやがて収まり、闇夜は一瞬にして漆黒を取り戻した。 ゴチャッ! 遠くの方で何か(おそらくは冷蔵庫)が、地面へ落ちた衝撃音。
「まあ、|我が家《ウチ》なら、……周りに|人家《じんか》も有りませんし、……だ、大丈夫ですよ、よ」 僅かに眼が泳いではいるが、気丈に振る舞う青年。
ヒュルルルルッーーーーカァーーン! 上空を見上げていた2人の目の前。 歩道へ落ちてきた赤く光るもの。 その尾を引く赤光は地を跳ね、2人を大きく飛び越した。
歩道脇の芝生へ飛び込んだ、燃えるような、……実際に燃えているソレは、プスプスと芝生を焦がし始める。
「|砥~述~《ト~ノベ~》!��―――水ーっ!」 少女は振り向きざまに、良く通る声で号令を出した。
「つぁーーー!」 彼、―――|砥述《トノベ》と呼ばれた青年は、さっきまでの物静かな口調とはまるで違う、奇声を発する。 腰を落とした直後、その姿が夜闇にかき消えるが如く、彼は姿を隠す。 袈裟懸けにされていたメッセンジャーバッグが、空中に取り残される。 ビキッ! 歩道に亀裂が入り、その上にメッセンジャーバッグが落ちた。
バッグの横に、取り付けられていたはずのミネラルウォーターは、煙を立てる芝生の直上にあった。 ボトルのキャップと底を、手のひらで押さえる|青年も一緒に《・・・・・・》だ。 空中に出現した彼は、上下逆の上に、斜めになっていたが、その――リムジンで言ったら約2台分の――距離を一瞬で跳躍した事になる。
「っつぁあ゛ーーーーっ!!」 そして再び、空気を一気に、吐き出すような|呼吸法《奇声》。 その気合いと共に、ペットボトルが両の手のひらに収まり、パコンと閉じられた。 スプリンクラーみたいに水が|満遍《まんべん》なく掛けられ、|燻《くすぶ》っていた芝生が|鎮火《ちんか》する。
ジュウウウウウウウッ! 赤く燃えて発光していた、コイン程度の大きさの|モノ《・・》は、冷却され水蒸気を発生させた。
ドタン! 身体をクルリと半回転ひねって、ギリギリで、芝生の上へ着地した|砥述《トノベ》青年。
「|砥述《トノベ》ー! 大丈夫かっ―――!?」 慌てて駆け寄って来た白衣の少女が、芝生に足を取られて、―――転んだ。 下は芝生だから、少しくらい転んでも安全だが、さっきまで燃えていた物体に、触れれば|火傷《やけど》をしてしまうだろう。
青年は、一瞬の|躊躇《ちゅうちょ》もなく、目の前の、まだ水蒸気を発している|物体《モノ》を、素手で掴んだ。
「あっち、あっちちっ!」 鎮火したとは言え、まだ、熱かったようで、手のひらの上をポンポンと、飛び跳ねさせている。赤く焼けていた金属に水を掛けた所で、直後に触れれば火傷するに決まっている。だが、彼は手の上で跳ねさせている。その様子から、特殊な材質で出来ていることが|窺《うかが》える。
「君は、そんなにも熱いモノを素手で掴んだりして、バカだなあっ、……あははははっ!」 そう笑う彼女は、焦げた芝生や|撒《ま》かれた水で、全身ぐっしょりだ。|頬《ほほ》も|煤《すす》だらけと、散々な状態だが、瞳をきらきらと輝かせている。青年をあざ笑うことに、全身全霊を|捧《ささ》げているのだ。
「……|佳音《カノン》さん、笑ってる場合じゃありませんよ。これがさっきお話しした、例の”|跳ね続ける物体《・・・・・・・》”ですよ」
彼の手のひらを、飛び跳ねている|煤《すす》だらけの���色の物体は、大きさは5セント硬貨くらい(直径2センチ、厚さ2ミリ程度)。直径沿いに2個の小さな丸穴が開いている。
「……確かに、飛び跳ねているな」 彼女、―――|佳音《カノン》と呼ばれた少女は、跳ねる動きに合わせて顔を上下させている。 「これは、|火傷《やけど》しないように、|手で跳ねさせてるだけ《・・・・・・・・・・》ですよ。硬い物じゃなければ反発は起きないようです、あちちっ!」 やはり、熱かったのか、|砥述《トノベ》はソレを放り出した。 ぼそり。 再び芝生の上に落ちたソレを、|佳音《カノン》がハンカチで、つかみ上げる。
「君、コレ、|シャツのボタン《・・・・・・・》にしか見えないのだが?」
1 note
·
View note
Text
2019.08 白馬三山 (1日目)

↑まるで絵画のような、夕暮れのモヤに浮かぶ剱岳
北海道の百名山3座を登ってから1週間後、今度は憧れの白馬岳へ。間隔狭すぎてなかなかにハードだけど、北海道でのテント泊の練習を実践に移すのもなるべく早いほうが良い。
2300新宿都庁駐車場発の毎日アルペン号に乗車。猿倉への道は大型バスが通行できない箇所があるらしく、長さが2/3くらいの中型バス。長さが短いだけで車内の広さ的には普通と変わらない。満席には少しだけ余裕あり。
しかし、関東は夜でも歩いているだけで汗が吹きでてくるな!これだけで水分補給が必要だ。茂原からの距離としては竹橋の方が近いんだけど、乗り換えの面倒臭さとか考えて新宿発の座席を購入した。てか、てっきり新宿→竹橋→猿倉と行くものだと思っていたけど、猿倉への直行だった。
バス会社のHPでは0550到着予定と書かれていたが、あれは途中にいくつも停車する場合の時刻で、今回使用した直行便は0430~0500が到着予定と車内でアナウンスがあった。まぁ早いぶんには問題ないな。実際に猿倉に到着したのは0440で夜明け前。北海道のときよりも明らかに涼しい~!猿倉荘ではトイレとか休憩スペースが設置さ���ているのでここで朝食をとるひとが多いが、自分は約1時間ほど歩いた白馬尻小屋で朝食を取ることに。ちょっとここは人が多い。
【コースタイム】猿倉荘(0440)→準備→出発(0510)→白馬尻小屋 (0600)→朝食→出発 (0630)→大雪渓入口 (0640)→大雪渓出口 (0745)→石室跡 (0805)→避難小屋 (0835)→白馬岳頂上宿舎 (0915)→テント設営・休憩 →出発 (1035)→丸山 (1045)→巻道分岐 (1115)→杓子岳 (1130)→ 巻道分岐(1140)→小鑓 (1205)→白馬鑓ヶ岳 (1225)→休憩→出発 (1300)→巻道分岐 (1330)→巻道分岐 (1335)→丸山 (1415)→テン場 (1420)

猿倉荘では装備を整えるだけで朝食はとらず、白馬尻小屋へ向かう。はじめのうちは景色が無いが、30~40分ほど歩くと視界が開けてくる。いきなり素晴らしい光景が目の前に!天気は晴れ、とても気持ちの良い青空!夏の日差しに映える緑がまぶしい。荷は重く(約10kg)歩を進める足はいつもより鈍いが、気持ちはかなり軽い。これから見える景色にはやる気持ちが抑えられない。ペースを上げすぎないように注意!
写真で見えているのはおそらく明日帰りに踏む小蓮華山とかだと思われる。
先週の北海道と比べて断然涼しい。基本的に風が通るし、気温も5℃くらい低い。歩けばさすがに汗は出てくるが、全然サウナではない。
約50分林道を歩き、白馬尻小屋に到着。「おつかれさん!ようこそ大雪渓へ」のデカイ看板がお出迎え。こちらのベンチをお借りして朝食タイム。今回も北海道のときと同じく菓子パン。結構カロリーあるし種類があるから好きなの選べるし、ゴミはかさばらない。ここ以降は山頂の小屋までトイレが無いので済ませておいたほうがいい。

いざ、準備を済ませ白馬岳名物の大雪渓へ!大雪渓の入口は小屋から10分ほど歩いたところにある。小屋のベンチからもちょっと見えているけど、目の前にすると、天へと繋がる長大な白い道と緑と岩肌のなんと美しいことか・・・。思わずため息が出てくる。この光景だけでも十分に百名山としてカウントされる価値がある。
雪渓では軽アイゼンの装着が推奨されている。自分はアマゾンで購入した2000円くらいの18本歯チェーンスパイクを装着。普通のアイゼンならあるけど軽はもってないし、チェーンスパイクのほうが脱着がラク(ゴムで靴にはめるタイプ)。実際に使用した感想は、(個人にもよるだろうが)チェーンスパイクの方が登りやすいと思う。軽アイゼン使ってる人の様子を見てみると、歯が靴の中央にしかついてい��いのでたまに爪先で滑っていた。チェーンスパイクは全体に歯がついているので”しっかり踏み込めば”足のどの部分で踏んでも安定する(チェーンスパイクの方が歯が短いからそこだけは注意)。 ストックの先はキャップとらな いと雪に刺さらない。みんなゴムキャップつけて登っていたけどね、雪山だと常識(夏山で雪山の知識が役に立つとは)。

雪渓は意外と汚い。もっと早い時期だと綺麗とのこと。また、表面が溶けて無数の凹凸ができているが、これは自分の好きな段に足を置くことができるので自由度が高く登りやすい。あと、50cmくらいの落石がそこらじゅうに落ちている。今回登っている最中にも「ガラガラ」と遠くで落石の発生する音が聞こえたので、なるべく早く通過するべし。
吹き降ろす風が雪渓で冷やされて気持ちいい!大雪渓は東斜面なので、朝のうちは真後ろから太陽の直射を受ける。そして前方からは雪による照り返し。サングラスと日焼け止めは必須。
上の写真で見えているのは白馬岳か?ちょっとよくわからなかった。

見下ろすと下から雲が迫ってくる。あの中は日差しがなくて涼しいんだろうなーと思いつつ、あれに追いつかれたら一気に景色がなくなる。別に競争するわけではないけど、できれば山頂から景色を眺めるまでは優位でありたい。
雪渓自体はかなり上までつづいているが、途中からは道を外れ登山道となる。今までは緩やかな林道か雪渓だったので、ここへきて初の本格的な登山道である。 ここからはかなりキツイ道。1歩が大きくないと登れないような ゴーロ帯で、いきなり北アルプスの様相を呈してきた。そして白馬名物その2、お花畑もここら辺から始まる。
雪解け水が流れるところを何ヶ所か通過する。この水は普通に飲めると思うので、水にはあまり困らないか(たぶんね)。

はぁー!!綺麗!!何が綺麗って、急峻な北アルプスの斜面を登っているはずのに、まるで草原の中を歩いているような風景。

おまけに両側はお花畑が広がり花々が応援をしてくれる。

草原の中に現れる先鋒と荒々しい山肌。たしかにここは北アルプス・・・なのか?異国のような不思議な感じ。白馬は見渡す限りすべてが美しい。

白馬尻小屋から約2時間でようやく頂上宿舎が現れる(実はもう少し前から見えてたけど)。宿舎のすぐ近くに雪解け水の水場あり、すごく冷たい。
猿倉から実動約4時間で白馬岳頂上宿舎に到着。長いようで、景色と道に夢中になっていれば案外あっという間であった。

まずはテント泊の受付。光栄なことに、本日1番目の受付だと!!そしてテン場に行ってみると・・・なんだこの光景は!!だ、誰もいない・・・。選び放題過ぎて、逆に場所を選べない。整地具合を入念にチェックしたり、どの場所が一番静かそうか考えた結果、テン場の最奥に決定!(入口近くだと便利かもしれないが足音とかうるさそう、あと水場も近いが同時にトイレも近くなんかヤダ)

こちらがテン場最奥に位置する我が城。緑のロープが張られており、これ以上先は行けない。山でのテント泊は今回が初の実践となるが、わりと綺麗に張れたと思います。
張り終わる間に2組の方がテントを張り始めていた。

設営を終えて支度がすんだら後半戦スタート、白馬鑓ヶ岳への往復へ。まずはテン場を上がって稜線に出ると北方には白馬岳。本記事初登場ではあるが、実際の行程でもちゃんと姿を眺めたのはこれが初めて。「北アルプスの女王 白馬岳」その佇まいたるや、まさしく!たしかに、「北アルプスの王」ではないんだよなぁ。

こちらは丸山より眺める杓子岳(左)と白馬鑓ヶ岳(右)。距離はあるのだが、それに加えてアップダウンが大きい。それにしても、ガスる前に写真撮れてよかったー。これからのルートが一望できる。白馬鑓ヶ岳までは、地図上ではざっと3-4kmの距離。

杓子岳直下、まずはここまでで大きなアップダウンが一回。ご覧の通りガレ場だが、これは白馬鑓までずっと続く。鑓までのピストンは軽装だったが、不要だと思って置いてきたストックはもってくればよかった。その方がバランス取りやすく、このような道には適している。

テン場から杓子岳までは約1時間。この間、とうとう雲が湧き上がってきてしまった。まぁずっと夏の日差しを浴び続けて暑かったから、クールダウンは必要。

振り向いてこちらは歩いてきた白馬岳方面。雲で隠されてしまった。

杓子岳ではしばらく勾配のない稜線を歩く。いっきにガスったが、いっきに晴れることも。基本的には晴れだった。

杓子岳下山中から白馬鑓方面。大きく下って、また大きく登る。2つ目のアップダウン。

大きな登りの途中から。あれが山頂だ!と思っていたのだが、登ってみたらこの先にもうひとつピークがあった(と記憶している)。あれはおそらく小鑓。もう一度だけ中くらいのアップダウンがあった気がする。

先程のピークを超えたら、ようやくあそこが目的地の白馬鑓ヶ岳。

山頂手前、なんか登山道を動く茶色いのがいると思ったら、アルプスのアイドル雷鳥の親子だった!こちらに気がついているものの、人間は無視して足やくちばしで穴を掘り、体をグルングルンさせて砂でこする。いわゆる「砂浴び」である。最初は親の姿だけだったが、じーっと観察しているうちに草むらから続々と子供が出てきて、最終的には6羽くらいで砂浴びしてた。親が子供に教えているのかな?なかなか貴重なものをみせてもらった。

山頂直下にある分岐より、唐松岳方面を臨む。どれが唐松岳かわ��らなかったが、おそらくここには写っていない。ここに写っているのはせいぜい天狗の頭くらいまでか?唐松岳はまだまだ先。
もうちょっと雲が少なければしっかりと立山連峰が見えたのだが、上の写真では剱岳のさきっぽだけがちょろっと頭を出している。行動中はたまに見えたり見えなかったり。

テン場から約2時間。大きなアップダウンをいくつか超えて、ようやく白馬鑓ヶ岳に到着。山頂には自分のほか3人ほど。 猿倉から大雪渓を登り、その後もかなりキツイ傾斜が続いたあとの足には、荷物が軽くなったといえども結構大変だった。ここでしばらく休憩。まぁよく1日のうちにここまで来たものだ。
北アルプス南方を眺める場合、白馬岳からよりもここ白馬鑓ヶ岳からの方が景観がいいかもしれない。翌日の記事の写真を見ればわかるが、白馬岳からだと白馬鑓ヶ岳の存在感がかなりデカく、北アルプスを結構隠してしまっている。今回は雲で覆われていたので残念ながら写真はなし。

鑓より白馬岳を臨む。雲が湧いたり晴れたりを繰り返す。

帰りは杓子岳の山頂は踏まず、巻道を通ってショートカット。横に2本道が走っているのが見えるが、このうち下の薄い方は通ってはいけない道(誰かが勝手に通り、後の人が続いたか)。本当の巻道は上の濃い方。ちゃんと分岐の看板が立っているから安心してよい。

最後の辛いところ。大きなアップダウン。

これを登りきれば・・・。

まだもうひとつピーク!

ようやくテン場が見えた!自分のテント、最奥すぎて誰も近くにいない、めちゃくちゃ浮いているんですけど笑、隔離されてるのかな?
白馬鑓ヶ岳からテン場までは約1時間半。到着したころはテントの数が40~50くらいになっていた。最終的には自分の周りにもテント張る人が何人かおり、自分で場所決めたのになんか安心した。
ここまでかなーり疲れたのだが、まさかとは思ったが夕食は棒ラーメンのみという・・・。これしか用意してこなかったっけ!?さすがに疲れた体にラーメンだけはきついので小屋に寄る。生ビール、コロッケ詰め合わせ、ポテチを購入して1700円。うまいなー!!!小屋の中では甲子園やっていて、結構皆で盛り上がっていた。
その後はテントに戻って一休み。北海道と比べて虫が全然いないので、テント全開にしても問題なし。おかげで日差しがあっても中は全然暑く無い。結構気持ちいいので、寝転んでいたらいつの間にか1時間くらい昼寝していた。起きたら天気は完全に曇り、風も涼しく過ごしやすいが夜は冷えそうだ。
今日はいろいろ見てきたが、昼は気温上がるとどうしても雲湧いちゃうから、景色は明日の早朝に白馬に立った時に期待だな~。
お湯沸かしてラーメンを食す。さっきいろいろ食べたからそんなにひもじくない。水はテン場のすぐ近くにあるけど、小屋を1分だけ下ったところの雪解け水を採取したほうが(気分的に)好み。テン場の水場はトイレの真隣なのでなんかちょっと・・・。ちなみに雪解け水の方は少し土が混じっていることがあるので注意。

18時頃、夕日を見に丸山へ。15℃くらいしかなくレインウェアを羽織ってもちょっと寒い。テント泊の他の人達も丸山に集合し、合わせて20人くらいで眺めていたか。

夕日によるブロッケン現象。自分が右手を挙げているのと、自分以外の山頂にいる人達も薄っすらと。

1830、モヤがかかる白馬鑓と、遠くには剱岳。どこかの雑誌の男性カメラマンと女性記者っぽい人(景色見ながらメモとってた)もいた。

1840、夕日に照らされ赤く燃える杓子岳と白馬鑓。

白馬は一体どこまで美しいのか。山だけでなく空までも・・・。
日の入りは1855。電波入らないし、特にすることも無いので1930くらいに就寝。すぐに寝付けた。
2日目に続く
1 note
·
View note
Text
「おかえり」
開かれた扉の向こうで待ち構えた最愛の彼の表情に、肩の力が抜けた。
『ただいま』
インターホンを鳴らしたほんの一、二秒後。玄関のドアが開いた瞬間に、美味しくて懐かしい匂いが漂った。その心当たりはすぐに見つけられた。夕方五時のチャイムを合図に友達にまたねと手を振って、駆けて帰る道中、あの子の家から流れるあの香り。そして、ドアを開ける前にもう半分靴を脱ぎながら玄関に飛び込んだ時、その言葉とほとんど同時に届くあの香り、だ。 彼が一瞬、俺の両の瞳をじっと見つめて、それから眦を下げて微笑む。
『飯作ってくれたの』
「うん、簡単なやつだけど。食べるでしょ?」
スリッパをぱたぱた鳴らしながら彼が先を歩く。キャップを脱ぎながらその背中を追いかけた。
『食べる。何?』
「味噌煮込みうどん」
「ちゃんとしてくれてんな」
IHコンロの前に戻った彼の背中に張り付き首筋に口許を寄せると、「危ないでしょ」と小言を言われたが聞こえなかったことにした。ほんの少しだけ高い肩口に顎を乗せて覗くと、柔らかく食欲を唆る香りが立ち上って来た。
「いや、適当飯だよ。冷凍うどんぶち込んだだけだし」
『いやいや、実に丁寧過ぎる暮らしだわ』
「エ、なんか馬鹿にされてる気がするんだけど」
『なわけないじゃん。俺、御前が作る飯ならなんでも好き』
わざとらしく怒った風の声を作った彼に、肩をすくめてわざとらしく芝居がかった声を作って返せば、彼はけらけら笑った。
『あー、腹減った』
「俺も。もうできるから手洗いうがいしてきて」
『はあい。ね、たまご落として』
「お、いいね」
軽やかな口笛を吹くその唇の先へもついでにキスのひとつでも落としてやろうかと思ったけれど、そんな一瞬の魔でこの大事な男に何処の馬の骨とも知らないウイルスが付き纏ってしまったら堪らないので、大人しく洗面所へ向かった。
きっちり指の根元や爪の間まで洗い上げ、泡を水で流した。清潔な白いタオルで水分を拭っていると、ふと見遣った鏡越しに疲れた顔をした男と目が合って、つい、溜息がこぼれ落ちた。閉じ切らなかった洗面所の扉の向こうから乳白色の明かりが漏れていた。食器の音が聞こえる。人の気配とは温かいものなのだな、なんてことは、彼と過ごすようになってから気が付いた。
『ごちそうさまでした』
「ごちそうさまでした」
揃って手を合わせてから、二人分の器を持って立ち上がった。「ありがとう」と言いながら、箸休め用にと出していた浅漬けの皿に彼がラップをかける。作る方と片付ける方、特段取り決めを交わしたわけでは無いのに、気が付けば役割分担がなされている。ときどき逆にもなるけれど、お互いが自然とそのように動く事実が俺はなんとなく好きだった。自然な流れの中にも毎回きちんと感謝の言葉を紛れ込ませる彼のことも、それに紛れて『ありがと、おいしかった』と素直に言える自分のことも。シンクで洗い物を片していると、彼が隣でケトルのスイッチを入れた。
『なに?』
「コーヒー。照も飲むでしょ」
『御前の愛情がたっぷり込められたヤツなら飲む』
「ドリップバッグだけどスタバの社員さんの愛情なら存分に込められてると思うよ」
『まあ、及第点』
「いや及第点貰えちゃうの。嘘だよ、込めとくよ愛情」
『ふは、ありがとう』
シンクの底を打つ水を止めて濡れた指先を拭いた。仕事の早い電気ケトルさんを手にしたその肩に顎を乗せて後ろから腰に腕を回すと、彼はくすぐったそうな声で「なあに」と甘く言った。
「照、ブラックでいい?」
『んー、牛乳あったよね。うんと甘いやつがいい』
「了解」
じゃあおれもそうしよー、と努めて朗らかな声で彼が言った。腰に回した手に、彼の手のぬるい温度が重なる。慣れた手つきで、彼はドリップバッグの備え付けられた二人分のマグにお湯を注いだ。刹那、ほろにがく豊かな香りが空間に広がる。それを鼻腔に吸い込んでから、彼のグレーのスウェットの肩口に顔を埋めて、長く吐き出した。コーヒーのそれと混じり合う君の匂い。ケトルを戻した右手は俺の頭に伸びて、さらりと髪を梳く。ぽたり、焦茶色の雫が水面に落ちる音が聞こえた気がした。
『聞かないんだ?』
「何が?」
とぼけたように彼が言う。あちち、とドリップバッグを指先で摘み上げると三角コーナーに放り、小洒落た白いシュガーポットに手を伸ばす。それぞれのマグに角砂糖をふたつずつ、甘党の俺好み。
『分かってて甘やかしてくれてんだろ?』
「今日の照さんはお疲れなのかな、って思ってただけよ」
背中にひっついた俺ことはそのままに、彼は数歩先の冷蔵庫にえっちらおっちら辿り着き、そこから牛乳のパックを取り出した。並べて湯気を燻らせているマグに注げば、どちらも等しく白が溶けて混ざり合っていく。
今日の仕事は、ずいぶん長引いた。同棲し始めて以降、将来の為と大幅に増えた仕事には、もうとっくに慣れたつもりだったけれど、今日はなんだか、ひどく空回った、気がする。接待の場での上司からの手酷いイジりにうまく笑えなかった。自分や友達、彼のことを馬鹿にされるのは、本当はすごく嫌いだった。それでもいつもなら適当に聞き流せていた程度の言葉だったのに、何故だか今日は喉の奥に刺さった魚の小骨みたいに引っかかって、飲み込めなかった。求められている返答を返せなかった。それでもなんとか体裁を取り繕ってかわしたつもりだったけど、接待も終わり帰ろうとした時、先方が薄く笑いながら俺の肩に手を置いた。
「大人になんなよ。もういい歳でしょ」
かっと頬が熱くなるのを感じた。すみません、と小さく答えるのがやっとで、今思えばその態度すらも社会人らしからぬそれだ。自分が迷惑をかけたのだから、もっときちんと頭を下げるべきだっただろう。長く同じ会社に身を置いていて、こういう類いの笑いに乗っかり相手方との親睦を深める事が新人の俺の役目で、いちいちそれをまっすぐ受け止めていたらキリがないことくらい、それこそ大人になる前から知っている。そういう世界で生きてきた。でも何故だか、今日はうまくいかなかった。思えば今日は、昨夜仕事が終わるのが遅く睡眠時間があまり取れないまま臨ん���昼間の会議から思うようにいかず、それもあって気分が落ちていたのだろう。すなわち、俺の問題だ。自分のモチベーションの問題。何の反論もなく、大人なら、こなせないといけない仕事だった。自分の大事なものを馬鹿にされても、大人なら、作り笑顔を貼り付けて求められる言葉を発しなければいけなかった。いつもはもっと鈍感に、それができるのに。
その腰に回した腕に、つい、力を込め過ぎた。彼が「ウ、照くん、流石に苦しいかも」と音を上げて初めて気付く。
『ごめん』
ぱっと拘束をほどくと、彼が振り返り、俺と同じ香りのする髪が鼻先を掠める。黒い瞳が覗いた。
「照が話したいなら聞くよ。だけど、そうじゃないんでしょ?」
そう言った彼の声があんまり優しいから、ぐっと胸の奥が詰まって、何も答えられなかった。シンクの縁に軽く腰掛けた彼は、うんともすんとも言わない俺の腕を引いて、 己の腕の中に導いた。斜め下に位置した彼の胸に収まる。
「いいよ、言わないで。照が今それを口にすることで、もう一度傷付く必要なんかない」
彼の無骨な手が、俺の後頭部をぽんぽんと軽く叩く。肩口に額を押し付けながら、はあ、と吐き切った息は湿っていた。同じ部屋に居る人間に隠し通せないほど気持ちが落ちていることくらいは、さすがに自覚があった。タクシーの窓の外を流れる見慣れた光の街にさえいやに感傷をかき立てられてしまって、あ、なんか無理かも、と思った。だけど、そうか。俺は傷付いていたのか。言い当てられて気が付くなんてまぬけだなあと思うし、気が付いてしまえばそれはじんじん痛かった。
「良いよ。俺のことハンカチにしても」
『泣いてねえよ』
「んは、はいはい」
泣いていなかった。本当に、そのときまでは。けれど、それを許されるとやっぱりちょっと涙が出た。彼のスウェットはグレーの生地だから、水分を含むと痕跡がよく目立った。確かに痛みを伴って存在を主張する傷が体の奥の方にあって、だけど同時に、それを癒そうと甘やかな何かが沁みていた。
『なあ、』
「うん?」
『俺、平気だから』
「うん」
『本当だよ』
頭の後ろに添えられていた手は背中に滑って、子どもを寝かしつけるときのそれみたいに、静かに一定のリズムを打った。
「うん。たぶんね、大丈夫なんだと思う。照が大丈夫って言うなら」
『うん』
「だけど、もし本当にやんなっちゃったときの逃げ場くらいになら、俺、なるからね。覚えておいて」
『うん』
ふっと息が抜けた。明けない夜はないとか、また朝日は登るよとか、そんなことは言わない奴だ。だから好きになったし、守りたいと思った。不確かで曖昧で無責任な言葉に呼吸が楽になって、そして、体を離して顔を上げて、驚いた。
————御前、なんて顔してんの。まるで、自分が傷付いたみたいな。その表情を目にした途端、ぎゅっと胸が締まった。痛かった。そして、ああ————なるほど、理解した。俺たち二人の痛みは、厄介なことに、どうやら伝染するらしい。
「ということで今日は、あったかいもん飲んで甘いもん食って、ふかふかの布団で、寝ろ!」
俺の鼻先にまだ湯気が揺れるカフェオレを突きつけて、彼はくるりと表情を作り替えて笑った。甘くて優しくて温かい香りが面前でふわり流れる。彼のもう一方の手には、きちんと俺の分もある。 こつん、と控えめな音を立ててマグの上部を合わせた。なんだかちょっとくすぐったくて、小声で『お疲れ』と言うと、「お疲れ様!」と彼はやたら楽しげな声で応える。
『てか、甘いもんもあんの?』
「えっとね、アイスと、あとなんか貰い物のロールケーキが一本ある」
『うは、男と同棲してる男にロールケーキまるまる一本贈るの何者? それ俺のことバレてんじゃないの?』
「バカ言わないで怖い怖い、深く考えないようにしよう。照くんの恋人である俺がロールケーキ切りますよー」
『んは、お願いします』
一口だけ含んだカフェオレのマグをケトルの隣に置いて、冷蔵庫の扉に手を掛けようと後ろを向いた彼の背中が視界に映った。見慣れた背中。綺麗な首筋。だけど、その瞬間だけは何故だか少し小さく見えて、思わず飛び付いた。
「オワッびっくりした、何?ていうかカフェオレこぼれるよ?」
『なあ、』
「なによ」
『有難う、大好きだよ』
痛みは、伝染して、そして分散するのだ。何も言わなくても勝手に一緒に背負ってしまって、そして軽くしてくれてしまう君は、骨格から逞しく見られがちだけど存外華奢なその背中に、きっとひとよりちょっぴり多めの荷物を載せている。そして、どうやら俺にも彼とお揃いのその痛覚共有機能が備わっているようなので、今度ぴぴーんとセンサーが察知した暁には、そうだな、俺はキムチ鍋でも作ってやるか。
友達と喧嘩をして帰った日。何も言っていないのに、なぜだか母はいつも自分が怪我をしたみたいに痛そうな顔をして、その日の晩ご飯は俺の分のおかずだけ兄弟より一切れ多かったことを、思い出していた。本当はあの頃から、何にも変わっていないのかもしれない。大人になったなんてとんだ思い上がりだ。だけど、もらったものにちゃんと気付けるくらいには、もう子どもじゃないから。
「ふは、なんか照いつもと違うね?」
『今日は素直な日だからさ』
振り返った彼と小鳥が啄むみたいな短いキスをすると、口の中に含んだ息を転がすようにして嬉しそうに笑った。
彼の言ったとおりにあったかいもん飲んで甘いもん食って、あとついでに一本ずつ缶ビールも飲んで、ふかふかの布団に包まれて抱き合ってたくさん寝たら、翌朝は二人揃って顔がすこぶる浮腫んだ。指を差し合って大笑いしていたら、あ、大丈夫だ、と気が付いた。
もう大丈夫、今日からはまた御前のこと俺が守ってくから。
0 notes
Text

2022 summer makeup
最近毎日毎日ずーっとやってるメイク方法。なんか初めてメイクが定番化した。メモとして残しておきます。
今使ってるのはANNA SUIだらけ。こんなにANNA SUIで揃えたの高校生ぶりぐらいかも。
化粧水と日焼け止めを塗り終えた後、ANNA SUIのフェイスパウダーで全体をマットにする。

こんな感じでパウダー部分とミラー部分が解体できるので、ミラー部分を丸洗いして清潔に保てるのが嬉しい。パウダーの上には透明のシート付きだからパフも清潔に保てるし。
次に眉毛。essenceのアイブロウペンシル(ブロンド)で眉尻〜中央あたりまで。眉頭は描かない。

キャップについてるブラシで眉の中央〜眉頭の部分を撫でてぼかす。
次はチーク。essenceパックマンのチークのブラウンパール(左上)〜コーラルピンク(右上)〜オレンジ(右下)を混ぜて、ブラシで思いっきり乗せる。めちゃくちゃ薄づきなので大げさなほどの広範囲に乗せても自然。

今まではブラウンパールだけ愛用してたから、めちゃくちゃ減っててもうすぐ無くなりそうな勢いだけども、この左下のオレンジも夏っぽくて可愛くてめっちゃ好きやわ。紙パケだから綺麗に保てないのがネックやな。
次はアイメイク。まずANNA SUIのビューラーでまつ毛を小刻みに3段階ぐらいに分けて上げる。最後に根本をグッと上げる。ビューラーの掃除がめんどうなのでアイメイク前にしか使わなくなった。

眉下にANNA SUIのP800(左)を乗せる。アイホールと下まぶた全体にはS801(中央)を乗せる。ブラシで乗せたり、指で乗せたり。丁寧にやるときはブラシですが急いでるときは指。丁寧にやるときは下まぶたはチップで乗せるけども、急いでるときは指で適当に乗せちゃう。切れ長っぽく見せるため、目尻はアイホールからはみ出すほど塗る。仕上げに目頭にP800をハイライトとして乗せる。粘膜の下、鼻の横(メガネのパットが当たる部位)って感じで。

このアイシャドウはマグネット式だから中身を全部取り出して丸洗いできるので清潔に保てて良い。中身をマグネット式の単色シャドウやチークを入れ替たりすれば、このケースも一生愛用できるしな。
目尻にdolly winkのブラウンのアイライナーでキャットラインを描く。

斜め上!って感じで。
キャットラインは太めに描くほど盛れる気がする。ちなみに私は目尻だけにしないと盛れないから目尻しかアイライナー引かない。

ANNA SUIのマスカラを塗る。下まつ毛はしっかり目に。
最後にTOOFACEDのラメラメグロスを乗せて完成。夏らしくオレンジ系のキラッキラメイクの完成。

ちなみにコンシーラーは出来るだけ塗らないです。そばかす気になる嫌だ!みたいなときは塗るけども、夏メイクなのでそばかすあるほうが可愛いかなーって思ってる、
0 notes
Text
焼きそばハロウィンはいかにして無敵のアイドルになったのか(1)
糸のように少しだけ開いたカーテンの隙間から朝陽が差していた。三角形に切り取られたやわらかな光の中を、田園を飛ぶ数匹の蛍のようにきれぎれの曲線を描いて埃が舞っていた。深い紫陽花色をしたチェック柄のミニスカートが、まっすぐにアイロンを当てられたシャツ、左右が完全に揃えられた赤いリボンとともに壁にかけられていて、部屋の主である女子高校生の内面を強いメッセージが込められた絵画のように表していた。 最も速い蒸気機関車が、そのペースをまったく乱されることなく東海道を走り続けていたように、その子どもがアスファルトを踏みしめるスニーカーのちいさな足音は正確に一分間当たり百六十回をキープしていた。それは彼女が小さなころから訓練に訓練を重ねてきた人間であることを示していた。太陽が地面に落とす影はすでに硬くなり、朝に鳴く鳥の歓びがその住宅地の道路には満ちていた。はっはっ、という歯切れ良い呼気が少女の胸から二酸化炭素と暖かさを奪っていった。 白いジャージに包まれたしなやかな身体は、湖面の近くを水平に飛ぶ巨大な鳥のそれに似ていた。ベースボールキャップからちらちらと見え隠れする桃色の髪がたった今自由になれば、相当に人目を引くほど美しくたなびいただろう。 ちら、とベビージーを見た視線が「ヤバイ」と言う言葉を引き出して、BPMが百七十に上がった。冷えた秋の空気が肺胞をちくちくと刺すようになったにもかかわらず、彼女の足取りは軽やかなままだった。そのままペースを落とさずに簡素な作りの階段をタンタンタンとリズム良く駆け上がりながら、背負っていた黄色のリュックサックからきらびやかなキーチェーンに取り付けられた部屋の鍵を取り出した。 かちゃり、と軽い音でドアが開いた。 「ヤバイってえ……」 靴が脱ぎ捨てられ、廊下を兼ねたキッチンの冷蔵庫が開かれると同時に、がっちゃんと重々しくドアは閉まった。その家の冷蔵庫は独身者向けの小さなサイズのそれで、天板に溜まった微かな埃が家主の忙しさを示していた。リュックから取り出された小さなタッパーを二つ、彼女は大事そうに冷蔵庫の中段に入れた。若干乱暴にそれが閉められた後、その場には一息に服が下着ごと脱ぎ捨てられた。浴室に荒々しく躍り込むと、曇りガラスの裏側でごろ、と音が響いて、洗い場の椅子が乱雑に蹴り退けられたようだった。 水が身体に跳ね返って飛び散り続ける音は短かった。男子高校生並のスピードでシャワーを終えて素早く黄色のトレーニングウェアに着替えると、彼女は強力なドライヤーで頭を乾かしながら鏡を睨みつけた。凄まじい早さで顔を直し、部屋の隅に立てかけてあったドラムバッグを一度だけひょいっと跳んで深くかけ直すと、小上がりに鎮座していたゴミ袋を掴んで「いってきます!」と誰もいない部屋に叫んだ。 キャップから出された、揺れるポニーテール。土曜日の早朝を走り抜けてゆく足音をゴミ収集車のビープ音だけが追っていた。 少女の部屋には静けさが戻る。
地下鉄の駅を出ると、人混みをすいすいとくぐってきつい坂を下っていった。途中にある寺の横を小さく一礼して通り過ぎ、降りきった先の人通りの少ない路地を抜けていくと、やがてダンススタジオのちいさな立て看板が見えた。軽い足取りで一番下までたどり着き、ふう、と軽く息を吐く。耳から完全ワイヤレスのイヤホンを引き抜いてポケットに突っ込み、「ごめん!」と、笑顔を浮かべたまま身体全体で重い扉を勢いよく開いた。 小さな子どもたちが彼女の頭上を通り過ぎる笑い声と一緒に、白い光が斜めに入り込んで、暗い床を小さく照らしていた。彼女の瞳は、誰の姿も捉えない。 「……あれ?」 「あれ、じゃない」 ばこん、と、現れた女性に横からファイルで強く頭を叩かれ、彼女は悶絶して頭を抱え座り込んだ。 「城ヶ崎……集合時間は何時だ?」 く〜、と唸り声を上げた美嘉は、しばらくしてから「九時」と涙声で言った。 「今は何時?」 「八時五十八分、に、なったところです」 「正解だ。じゃあな、私はデートに行ってくる」 「ちょ、っと。トレーナー!」 美嘉はトレーナーの服を掴んで、「え」と言ったあと「……冗談、ですよね」と半笑いの顔を作って聞いた。上から下までトレーナーの服装を見て、それがいつもの緑色のウェアとは似ても似つかぬ、落ち着いた色合いの秋物であることに気づく。 「失礼だな、私にも急なデートの相手ぐらいいるよ。年収五百五十万、二十九歳、私にはよくわからないのだがシステム系の会社でマネージャーをしている――」 美嘉はうんざりとした顔を浮かべて、 「相手の年収なんて聞いてませんよ。ていうかそうじゃなくて、私たちのレッスンはどうなっちゃうんです?」 「まず第一に、私はいつも五分前行動を君たちに要請している」 「……それは、すみません。朝、用事で家を出るのが遅れてしまって」 「第二に、彼は笑うとえくぼがとてもかわいいんだ。好きな力士は豪栄道」 「彼氏情報はもういいですから……」 豪栄道とトレーナーの共通点を美嘉がまじまじと探していると、「第三に」と言って、トレーナーは指を振った。 「次は三人揃わないとレッスンはしないと、前回宣言したはずだ。案の定だったな」 美嘉は、うわっ、と呻いて「志希のやつ……」とつぶやきながらスマホを取り出して乱暴に操作した。 「先に鷺沢に連絡しろー」と、ヒールを履いたトレーナーは外に出ながら言った。 「あいつ、いつも三十分前に来て長々ストレッチしてるんだ。本番前最後の確認でいきなり無断欠席となると、少し心配したほうがいいかもしれないぞ」 ドアの隙間から微笑んで、「じゃあな」と、一言言うとトレーナーは去った。ぽかんと美嘉は小窓から彼女を見送る。かつ、かつという高い音は、軽やかに去っていった。 おかけになった電話番号は、電源が入っていないか――。 美嘉は携帯から小さく流れる音声を一回りそのままにしてから消し、スタジオの照明をつけないまま日の当たるところへと歩いていった。『い』から『さ』へ大きくスクロールして、窓際であぐらをかく。『鷺沢文香』を押し、耳に当てる。短いスパンで赤いボタンを押す。『鷺沢』赤ボタン。『鷺沢』赤ボタン。『た』にスクロール。 『高垣楓個人事務所』 耳元の小さな呼び出し音を聴きながら「なんで……」と美嘉は呟いた。短いやり取りで、事務員に文香への連絡を頼んだ。 「プロデューサーにも連絡お願いします……いえ、アタシは……はい、残って自主練やります。」 電話を切った後、ふうう、と美嘉は長いため息をついた。一息に立ち上がり、バッグから底の摩耗したダンスシューズを取り出して履くと、イヤホンを耳に押し込んで入念なストレッチを行った。同い年くらいの少女たちが数人、スタジオの横を笑い声を立てながら通り過ぎ、その影が床をすうっと舐めていったが、彼女はそれに目もくれなかった。 床に丁字に貼られたガムテープの、一番左の印に立った。トリオで踊るときのセンターとライト、残りふたつのポジションに一瞬の視線が走り、美嘉は目尻に浮かんだ悔し涙を一瞬親指の背で拭った。 「くそ」 いきなり殴りつけられた人がそうするように、美嘉はしばらく下を向いていた。闘争心を激しく煽る力強いギャングスタ・ラップが彼女の耳の中で終わりを告げ、長い無音のあと、簡素な、少し間抜けと言ってもいい打楽器が正確なリズムで四回音を立てた瞬間、美嘉は満面の笑みを浮かべてさっと顔を上げ、ミラーに映った自分を見つめながら大きく踏み出した。だんっ、と力強くフローリングを踏みしめた一歩の響きは、長い間その部屋に残っていた。
「おはようございます……」と挨拶をしながら、美嘉がその部屋に入っていくと、「あら、めずらしい」とパイプ椅子に座っていた和装の麗人が彼女を見て笑った。その人が白い煙草を咥えているのを見て、美嘉は「火、つけます」と近寄りながら言った。 「プロデューサー、煙草吸うんですね」 「いやですねえ、二人きりのときは楓と呼んでくださいと、このあいだ申し上げたじゃないですか」 「……楓さん、ライター貸してください。アタシ流石に持ってないんで……」 こりこりこり。 煙草が軽い音を立てながら楓の口の中に吸い込まれると、こてん、と緑のボブカットが揺れ、「はい?」と返事が返った。煙草と思っていたそれが菓子だったことが分かって、美嘉はがくりと頭を垂れた。 「ええと、ライターですか……あったかしら……」 「……からかってるんですか?」 「まさかまさか」 楓がココアシガレットの箱を差し出すと、美嘉は「いらないですって……」と顔をしかめて言った。 「今日は、打ち合わせ?」 「はい、次のクールで始まる教育バラエティの……楓さん、ちひろさんから連絡行きましたか」 「はいはい、来ましたよ。文香ちゃん、大丈夫かしら」 「……軽いですね」 「軽くなんか無いですよ」 ついつい、と手の中のスマホが操作され、「私の初プロデュース、かわいい後輩ユニットなんですから、応援ゴーゴー。各所からアイドルを引き抜きまくって、非難ゴーゴー!」と、画面を見せた。『高垣楓プロデュースユニット第一弾! コンビニコラボでデビューミニライブ』と大きく書かれたニュースサイトの画面には、『メンバーは一ノ瀬志希、城ヶ崎美嘉、鷺沢文香』と小見出しがついていた。びきっ、と美嘉の額に音を立てて青筋が現れ、「だったら」と美嘉は言った。 「ほんっと、真面目に仕事してくださいよ! なんなの、『焼きそばハロウィン』っていうユニット名!」 「ええ〜かわいくないですか、焼きハロ」 「ユニット名は頭に残ったら成功なの! ニュース見たら一発で分かるでしょ、記者さんも訳わかんなくなっちゃって、タイトルにも小見出しにも使われてないじゃん! ていうか百歩譲ってハロウィンは分かるとして、焼きそばってどっからきたの!!」 「以前、焼きそばが好きだっておっしゃっていたから……」 「え、そんなこと言ってましたっけ」 「沖縄の撮影に三人で行ったとき、一緒に食べておいしかったーって」 「……あれ、たしかに……はっ、いやいやいや、丸め込まれるところだった。好物をユニット名にしてどうすんの」 「美嘉ちゃんには対案があるんですか?」 「た、対案?」 いきなりプロデューサー業を完全に放棄して頬杖をしながらがさがさとお菓子かごを漁る楓に、美嘉は「対案……」と呟いて顎を触った。は、と思いついて「たとえば、志希がセンターだから、匂いをモチーフに『パフュー(ピー)』とか、あと……秋葉原でイベントやるし、そうだ、三人の年齢とかを合わせちゃって『エーケービー(ピイィー!)』とか、あーもうさっきからピィピィうるさい! なんなんですかそれ!」 「フエラムネですよ。あっ、今の若い子はご存じないですか」 「アッタッシッがっ、しゃべってるときにはちゃんと聞いてよ、アンタが考えろって言ったんでしょ! ていうか文香さんのこと、早く何とかしなさいよ!」 「ははあ」 ごり、と、ラムネを噛み砕くにしては大きい音が楓の口内から立てられた。美嘉は激昂から一瞬で冷めて、口元に小さな怯えを浮かばせた。月と太陽とを両眼に持ったひとはそれらをわずかに細め、もう一つラムネを口の中に放り込んだ。 「焼きハロ、私はリーダーを誰かに頼みましたよね。誰でしたっけ」 「……アタシ、です」 ごり。 「トレーナーさんからも話を聴きましたよ。なんでも志希ちゃんは、初回以来一度もレッスンに現れていないとか」 「あれは! その……志希は、前の事務所のときからずっとそうで……」 ごり。 「ふうん、美嘉ちゃんはそれでいいと思ってるんですね」 楓がゆらりと立ち上がり、美嘉に近寄った。彼女が反射的に一歩大きく下がると、壁が背後に現れて逃げ場が無くなった。フエラムネをひとつ掴み、楓は美嘉の少し薄い唇にそれを触れさせた。真っ赤に染まった耳元にほとんど触れるような位置から、楓の華やかな口元が「開けて」と動いて、美嘉がわずかに開けたそこにはラムネがおしこめられた。ひゅ、と一瞬鳴ったそれに、楓は満足そうに微笑むとテーブルに寄りかかった。「口に含んでもいいですよ」と楓が言った。美嘉は少し涙の浮かんだ目で楓を睨むと、指を使ってそれを口に入れた。 「私は高垣楓ですから」 テーブルを掴んでいる指で、楓はとんとんと天板を裏側から叩いていた。「傷つかないんですよね、残念なことに。何が起きても」とほんとうに少し残念そうに言った。 「だから、あなた方が失敗しても、私は特に何も思わない。たとえばコンビニのコラボレーションが潰れても、私は特に怖くない。少しだけ偉い人に、少しだけ頭を下げて、ああ、だめだったのかあ、と少しだけ感慨に浸るんです。でもあなた方はきっと、違いますよね」 美嘉の口の中で、こり、と音が鳴って、 「……何が言いたいんですか?」 「自信がないの? 美嘉ちゃん」 質問に質問を返されて、しかし美嘉はもうたじろがなかった。「���高のユニットにしてやる」と自分に言い聞かせるように呟くと、「なんです?」と楓は聞き返した。 「何も、問題は、ない。って言ったんですよ」 パン、と楓は手を叩いて、「ああ、よかったあ」と、言った。 「今日はもうてっぺん超えるまでぎっちり収録ですし、困ったなあ、と思ってたんですよね。明日の店頭イベント、よろしくお願いします」と、微塵も困っていない顔で言った。 「文香さんち、いってきます」と宣言し、美嘉はトートを抱え直した。行きかけた彼女は楓に呼び止められて、投げつけられたココアシガレットの箱を片手で受け取った。 「さっきはちょっといじめちゃいましたけれど……」と楓が言葉を区切ると、美嘉は心底嫌そうな顔をして「はあ」と言った。 「ほんとうにどうしようもなくなったら、もうアイドルを続けていられないかもしれないと思ったら、そのときはちゃんと私に声をかけてくださいね。す〜ぱ〜シンデレラぱわ〜でなんとかして差し上げます」 「もう行っていいですか。時間無いので」 恒星のように微笑んで、楓は「どうぞ」と言った。美嘉がドアを開けて出ていくと。入れ替わりにスタッフがやってきて「高垣さん、出番です」と声をかけた。 立ち上がりながら、ふふ、と笑うと、「楽しみだなあ、焼きハロ♫」と楓は呟いた。 だん、だん、と荒々しいワークブーツの足音が廊下に響いていた。「いらないっつってるのに……ていうか、一本しか残ってないじゃん。アタシはゴミ箱かっつうの」と独り言を言いながら、美嘉は箱から煙草を抜いて口に咥えた。空き箱はクシャリと潰されて、バッグへと押し込められた。 「あーっ、くそ!」 叫んで、ココアシガレットを一息に口の中へと含む。ばり、ばり、ばり、という甲高い音を立て、ひどく顔をしかめた美嘉の口の中で、それは粉々に砕けていった。
「すみませーん」 美嘉は三度目の声をかけ、ドアベルをもう一度押した。鷺沢古書店の裏庭にある勝手口は苔むした石畳の先にあり、彼女はそこに至るまでに二度ほど転びかけていた。右手に持っていたドラッグストアの袋を揺らしながら側頭部をぽりぽりとかいて「……やっぱり寝込んでるのかなー」と心配そうに小さな声で呟いたとき、奥から人の気配がして、美嘉の顔はぱっと輝いた。 簡素な鍵を開けたあと、老いた猫が弱々しく鳴くときのような蝶番の音を響かせて、顔をあらわしたのは果たして鷺沢文香だった。「文香さん」と美嘉は喜びを露わにして言った。 「無事でよかったー! なんだ、元気そうじゃん」 美嘉は鷺沢のようすを上から下まで確かめた。ふわりとしたロングスカートに、肌を見せない濃紺のトップス。事務所でも何度か見たことのあるチェックのストールは、青い石のあしらわれた銀色のピンで留められていた。普段と変わらぬ格好とは裏腹に、前髪の奥の表情がいつになく固い事に気づいて、美嘉は「……文香さん?」と聞いた。 「ご迷惑をおかけして、申し訳ありません」と、文香は頭を深々と下げた。 どこか寒々しい予感に襲われ、美嘉は「あ……」と、不安の滲む声を漏らした。はっとすべてを消し去り、いつもの調子に戻して、 「今日のレッスン? もういいっていいって。連絡が無かったのはだーいぶあれだったけど、ま、志希のせいで無断欠席には慣れちゃったっていうか、慣れさせられたっていうか――」 「そうでは、なくて……」 文香は言葉に詰まった。合わない視線はゆらりと揺れて、隣家で咲き誇るケイトウの花を差していた。燃え盛る炎のように艶やかなそれを見ながら「アイドルを、やめようと思います」と彼女はゆっくりと言った。がっと両腕を掴まれて、文香は目の前で自らの内側を激しく覗き込もうとする黄金の瞳に眼差しを向けた。 「なんで!!」 美嘉が叫ぶと、文香はふら、と揺れた。陽が陰り、そこからはあらゆる光が消えた。産まれた冷気を避けるかのように、ち、ち、と小鳥が悲鳴を上げながら庭から去っていった。 「向いて、いないと、思いました」と、苦しそうに彼女は言った。 「突然で、ほんとうに、申し訳ありません……楓さんには、後ほど、きちんとお詫びをしようと――」 「嘘」 「……嘘では、ありません。自分が、古めかしい本にでもしがみついているのがふさわしい、惨めな人間――けだもの、虫の一匹だと、あらためて思い知ったのです」 「何があったの、だって」 美嘉は文香から一歩離れると、心の底から悲しそうな表情を浮かべた。 「あんなに……嬉しい、嬉しいって、新しいことを発見したって、何度も何度も言ってたのに!」 「間違いでした」 「何があったんだってアタシは聞いてるの!」 「もともと何も無かったんです!」 文香がこれまで聞いたこともないような大声を出したので、美嘉は呆然と立ちすくんだ。「すべてがまぼろしだったのです! ステージの上の、押し寄せる波のように偉大なあの輝きも!」と文香は一息に言って、興奮を抑えるようにしばらく肩で息をしながら美嘉を見つめていた。やがて、「まぼろしだったのです、あの胸の、高鳴りも……」と、悄然として言った。 「……なぜ」と美嘉は言った。その反転がなぜ起きたのか理解できないようすで、美嘉はただ文香を睨みつけて質問を繰り返した。 長い沈黙のあとに、「家に、呼び戻されました」と文香は言った。美嘉は唖然として「どういうこと」と聞いた。 「親の同意がないままアイドルをやってたから、やめろって言われたって、そういうことなの?」 文香はうなずいた。 「未成年者は保護者の同意書提出があるはずじゃん」 「あれは、東京の叔父に書いてもらいました」 「……だって、大学だってあるし、文香さんトーダイでしょ。そういうの、全部捨てて、帰ってこいって言う……そういうことなの?」 「そうです」 「そんなの、家族じゃない」 美嘉が断固とした調子で言うと、文香は口を一文字に結んだ。そのようすを見ながら「家族じゃない、おかしいよ」と美嘉は言った。 「だって、アイドルも、学校も、全部夢じゃん。自分が将来こうなりたいっていうのを、文香さん自分の全部を賭けて頑張ってたじゃん。アタシずっと見てたよ。すごいな、ほんとうにすごいなって、思ってたよ。ねえ」 文香の瞳をまっすぐに見つめて、美嘉は手を差し伸べた。 「全部捨てる必要なんてない、大丈夫だから」 青い海のようなそれに吸い込まれそうになりながら、美嘉は一瞬の煌めきをそこに見つけて、笑いかけた。文香が恐る恐るといった様子で、ゆっくりとその手を取ったとき、微笑みを浮かべた彼女の口元は「そう……分からず屋の家族なんて、捨ててしまえば――」と囁いた。「う」と小さな悲鳴を上げて、文香は手を振りほどくと、どん、と彼女の肩を両手で押し、庭土へと倒した。あっ、と倒れ込んだ美嘉は、文香を見上げ、「美嘉さんは、鷺沢の家を知らないんです!」と、文香が絶叫するのを聞いた。美嘉の眉はみるみるうちにへの字に曲がって、 「知らないよそんなの! アタシに分かるわけないじゃん!!」 ぐ、と文香の喉は、嗚咽するような音を立てて、やがて、ふううと長い息が吐かれた。 「……さようなら」と、短い別れの言葉で、ドアは閉められようとした。「待って!」と美嘉が呼びかけたときにその隙間から見えた、雨をたたえた空のようにまっしろな文香の顔色が、美嘉の目には消えゆく寸前のろうそくのようにしばらく残っていた。
どさ、と重い音を立てて、その白い袋は金網で作られたゴミ箱へと捨てられた。美嘉はよろめく足取りですぐ横のベンチに向い、腰を下ろした。眼の前には公園に併設された区営のテニスコートがあり、中年の男女が笑いあいながら黄緑色のボールを叩いていた。 美嘉はイヤホンを耳に押し込むと、ボールの動きを目で追うのをやめてうつむいた。両手を祈りの形に組み、親指のつけ根を皺の寄った眉間に押し当てた。受難曲の調べが柔らかく彼女の鼓膜を触り終わったあと、シャッフルされた再生が奇跡のようにあの四回の簡素なリズムを呼び出して、今朝何度もひとりで練習したあの曲が鳴り始めた。美嘉は口をとがらせ、ふ、と微かに息を吐きながら顔を上げた。そしてテニスコートの男女が消え、自分の周りにひとりも人がいなくなったことを見つけた。 空はまっ青に晴れ、柔らかな光が木々の間から美嘉に差していた。そのやさしさをぼうっと受け止めながら、美嘉は立ち上がってゴミ箱から先ほど投げ捨てた袋を拾った。冷えピタやいくつかの薬、体温計を自分のバッグに移し、二つのフルーツゼリーをこと、こと、と静かにベンチの横に置いた。 曲はサビに差し掛かり、いつの間にか美嘉は鼻歌でそれを小さく歌っていた。てんてんと指で指してみかんとぶどうからぶどうを選びとると、蓋を開けてプラスチックのスプーンを突き立てた。 口に入るかどうかわからないくらいの大きさでそれをすくい上げて、飢えた肉食動物のような激しさでがぶりと食いついた。 歌い始めたときにはもうこぼれていた大粒の涙が、収め切れなかったゼリーの汁と一緒におとがいへと伝って、ぽとぽとと太ももに落ちた。 泣くときに必ず漏れるはずの音を、美嘉は少しも立てなかった。涙を拭いすらしなかった。たまに「あぐ」という、ゼリーを口に入れるときに限界まで開いた顎の出す音だけが、緑の葉が擦れるそれと共にそっとあたりに響いていた。食べ終わると同時に曲が終わり、美嘉はイヤホンを引き抜いた。ほうっと息を吐いて、ぐすっと鼻を啜った。涙のあとが消えるまで頬のあたりをハンカチでごしごし擦��、そのまま太ももを拭くと、鏡を出して顔を軽く確認した。 そして、は、と後ろを向く。 ベンチの背越しに伸ばされた腕がゼリーを取って、「これ食べていいやつー?」と聞きながら蓋を開け、返事を待たずにスプーンですくい取った。 「志希」と、呆然と美嘉は言った。 「ん?」と、ゼリーを口いっぱいに頬張りながら志希は言った。
4 notes
·
View notes
Text
突然おっ始まる探検隊。

チャス!屋根に穴空いてるガイドです!世の中思い通りにいかない事っていっぱいありますよね!そんな時、思い切って違う方向に舵を切るってのも悪くないんじゃないでしょうか。

朝一、いつもいい位置に陣取るジョニー君。おはようござんす〜。急遽中止にした明日のお客さんはジョニー君とこいくみてーす。かたじけねえっす。

今日からおっ始まったロープウェイ。大変混雑しておりました。あ、メリケンジャップだ。

本日のお客様方。結構経験ある方が集まりました。こいつはちょっと攻めたツアーも可能では!?

朝は結構カチカチです。春コンディションになりましたねえ〜。

上部はなかなかなお風。当初の予定では上を目指していましたが、この風はなかなかなもんだぜって事で作戦会議。
協議の結果、俺も初めて行くニューラインを攻めに行く事に。
突如、長澤探検隊、おっ始まりました!!押忍!

とりあえず風が辛抱たまらんて事でさっさとドロップ。

板も走るし、面も綺麗でゴキゲンなコンディション!

右はちょいパウ、左は走るザラメ。楽しいです。

お、青空バックのいいの撮れたと思ったらピンボケ。我ながら流石だぜ。

北向きはいい雪、ギリギリ継続中!

いや〜いい地形でした!ほんじゃ登りますか〜。

本日はキングオブ行動食、小野塾塾長にお越しいただいております。まずは挨拶がわりのお稲荷さん。

ん?なんスカその手拭い?なに!松本しょうじ君の手拭いスカ!?アツい!

更にみかん。流石、他の追随を許すもなにも別にいなかった初代えんでかしブログチャレンジの王者。頭のオリジナル塾長キャップが静かに存在感を放っております。

いつもと違うラインでハイクしてると先日の雪崩の走路区がよく見えました。

バキバキに木をなぎ倒してます。

こんなぶってえ木も折れてました。くわばらくわばら。

いつもと違う場所は新鮮だぜ!

お、塾長、次はなんスカ?マカロニサラダ!?

更に納豆!!固定観念にとらわれない自由な行動食ですね。

なせ(なだらか)な尾根はシール無しのスキーモードで移動。初めての体験にきゃっきゃするゲスト達。塾長は慣れたもんですが。

さて、いよいよ初めてのラインにドロップしますよー!

出だしはなせな斜面。景色も良く雪も良く気持ちも良いです。

いいですぞー!
問題はこの先。地形図を見ると、この先急に斜度が増す地形になっているのですが、別に崖とかはなさそう。しかし、俺は知っている、地形図には載っていない崖がいくらでもある事を。案の定、どないなってんねんな地形だらけの中、なんとか入れそうなドロップポイントを見つけました。

出だしは急なシュートになっているのですがそこを抜けると
ヒューー!!
な広い地形が待っていました!

雪もいい!!

斜度もあり楽しー!!

綺麗なターンしますねえ〜!

「きゃ!」「おお!」「おわ!」ワンターンごとに声が出るゲスト。最後に放った言葉は「ひろ〜い!」いや、八方滑ってんじゃねえのかよ!

ものすげえ地形の谷です。

流石に下の方は北向きでもデロデロになってきました。

初めて来た沢底。南向きの斜面はいつでもどっかなんか落石や湿雪雪崩が起きてるような忙しい場所です。そして我々はその南斜面を登り返さなきゃいけないって訳なんですよ!

ま、お汁粉でもキメてから行きますか!

信用ならねえ地形図を見てなんとかここからなら取り付けるんじゃねえかって場所から登ってみる。

常に上からデロデロな湿雪が雪崩て来ないか注意が必要です。更にちょっと斜度のキツイとこを横切ろうなんてしようもんなら、たちまち湿雪雪崩で落ちてしまいます。

なんとかゆるいラインで���れました!いや〜緊張した〜。

酷え目に合わせた後のりんごサービス。

更にそれに加えての塾長のいちごの砂糖漬けサービス。疲弊しきった隊員達の体を癒してくれました。

もーちょい登りましょう。林の中でもデロデロな湿雪雪崩がいつ落ちてくるかわからないので注意です。

標高が低い林でも沢割れ、クラックなどで緊張な瞬間が続きました。

滑っては脱いで歩いたりを繰り返しなんとか本流の沢の下部へ出てきました。

いつ落ちるかわからないスノーブリッジを渡り

ダイナミックな全層雪崩を拝んだりしながら

後ちょっとのとこまできました。みんな疲れながらもやりきったいい顔してます。

すっかり遅くなっちゃいました。

最後の林は汚れた雪面で滑らなそうだったので出でよ!Magic wax!!

板、走って快適〜!

最後まで気を抜けないのが雪の少ない里山。

突如の行き先変更で車をデポってなかったのでタクシーに来てもらい無事下山!!
いや〜久々の探検。ドキドキしましたね〜!いい斜面に会えましたね〜!やべえ景色見れましたね〜!やっぱやめられませんね〜!!
皆様、お疲れ山でした!&おしょっ様でしたー!!
1 note
·
View note
Quote
それでも復帰を決意するまでには2カ月半かかった。相方の西野に「謝りに行ってええか」とメールし、自宅を訪れたところ、西野は上半身裸でキャップを斜めにかぶり、ギターを持っていたという。「すまん!申し訳なかった!殴ってもええぞ」と土下座すると、西野はギターをジャ~ンとかき鳴らし、「ええで」と返答。殴られることも怒鳴られることもなく、あっさり迎えてくれた。梶原は「こいつ���まそうとしてくれてんねや」と相方の優しさに感謝したという。
キンコン梶原 失踪騒動の一部始終語る/芸能/デイリースポーツ online
2 notes
·
View notes
Text
(b[land)mark]
近所の中学校指定のセーラー服を着たその少女はきっと思春期真只中で、だから大人の女性のような背伸びをしてみたくて、けれどそれを正しく手に入れるためのお金がなかった――どうせそんなところだろう。どこか怯えた様子で少女がポケットに一本の口紅をしまい込むのを見ながら、私はそんなことを考えていた。 少女が店を後にしてから、彼女が盗んだ口紅のテスターを自らの手の甲にこすりつけてみる。安物の不透明絵の具のように赤くちっとも品のないその色が、地味で貧相で頼りなげなあの少女に似合うはずはない。
*
「ねー。大畑さんさあ、金曜日ヒマ?」 「え?」 「だあから。金曜日、あさって。ヒマですかーって訊いてんだけど」 「え……ええと、なぜですか?」 「んー? ふふふ。だって、合コンするからさ。合コン」 ネイル用品コーナー、優香さんは【新商品!】と書かれたポップがつけられたマニキュアのピンク色だけをピックアップし、繰り返し瓶を光に翳してはその色味をじっくり確かめていた。合コン、と聞き、一瞬彼女が私をそういった場に連れていこうとしているのかと思い、けれどすぐさまそんなはずがないだろうと自ら思考を切り替える。地味で、貧相で、頼りなげで、どこをとってもつまらない私のことを、彼女のような派手な女性が合コンに誘うわけがなかった。どうせ優香さんの狙いなんて休日の交換に決まっている。 「ああ、合コン……それでマニキュアを?」 「そうそう! 爪ってさあ、結構見られてるもんじゃん? 普段はサロンでジェルやってもらってるんだけど、こないだ行ったら“ちょっと爪薄くなっちゃってるから、しばらくお休みしないとだめですよー!”とか言われちゃって。もうめっちゃショックー、すっぴん状態の爪とかさ、恥ずかしすぎて死ぬ、耐えらんない! こう、パンツ穿いてないみたいっていうかね、おかげでここしばらくずっと具合悪いもん」 「はあ」 どっちの色がいいかなー、などと言いながら優香さんは極めて自然な流れで二つの商品を開封した。思わず「ええ……」と呟いてしまうが優香さんは気にする様子もなく、左手の人差し指と中指にそれぞれの色を塗り、 「ねえ、大畑さんはどっちがかわいいと思う?」 私へ反転したピースサインを向ける。 「…………人差し指のほう、ですかね」 「え、ほんとに? 大畑さんセンスなくない? あたしはこの色、地味でダサいなーって思ったあ」 優香さんが無許可で開封した商品のキャップに油性ペンで【テスター】と書く。このドラッグストアでは、マニキュアにはテスターではなくメーカーから渡される色見本を設置することになっていた。彼女は三本目のマニキュアを手に取り、それをエプロンのポケットにしまうと、 「店長には万引きされたってことにしといてね」 そう言い残し、ひとり休憩室へと行ってしまう。 安物のマニキュア独特のつんとした臭いがあまりにも不快だ。私は優香さんの姿が見えなくなったことを確認したのち近くにあった消臭スプレーのテスターを辺りに振り撒いた。甘ったるく、べたべたと鬱陶しい「いかにも」な合成香料の花の香りは私の澱みを悪化させる。
帰りしな、私よりも先に優香さんへ声をかけたのは店長だった。猫なで声で返事をした彼女へ店長は淡々と、 「帰る前にさ、お金だけ、払ってもらっていい? 三本分。千三百二十円」 右手を差し出しながら言う。優香さんの目は泳ぎ、「え、なに、どういうことですか?」と明らかな動揺を見せていた。 「兎にも角にもうちは人手不足だし……ちょっとくらいならって目をつむってたんだけどね。さすがに多いわー。君、今までのバイトの子でも断トツでひどかったよ。誤魔化し方も雑だしさあ……何? テスターって。誰が許可した? そんなん」 優香さんが舌打ちをする。水色の長財布から二千円を取り出し店長へ抛ると、何も言わずに置きっぱなしの荷物を全て鞄の中へ強引に詰め込み始める。 「ああそうだ、ポイントカード。出してくれればつけるけど? きょう三倍デーだし」 優香さんは店長の言葉を無視し、香水の瓶を鞄に押し込む。 「あ、それもうちの商品だよねー。あのう、お会計前ですよねえ?」 優香さんが再び財布を開く。五千円を放り投げる。店長が笑いながら「へえ、今までのぶんあわせて七千円で足りると思ってるんだ? ホント面白いねー君! 最高だよ。さすがさすが!」と、優香さんを指さし大袈裟に手を叩く。優香さんが店長を睨む。 「んー? 何、その顔。警察呼ぼうか? 防犯カメラの映像、うちは長めに保存しておくルールだから結構面白いことになると思うけど」 優香さんが財布の中の札を一枚残らず店長に投げつける。店長は「これでも足りないんだからすごいよねー、俺には理解できないわー」などと言いながらそれを自身のエプロンのポケットへしまい込む。優香さんが裏口から出ていく。彼女はすれ違いざま私へ、 「チクってんじゃねえよ。死ね」 と吐き捨てた。こういう子は合コンで男性からどのような扱いを受けているのだろうか。私には何の想像もできなかった。
優香さんの足音が全く聞こえなくなったころ、再び店長は口を開き、 「さてと……」 鍵穴のついた引き出しから一冊のファイルを取り出す。どうやらそれは従業員の契約書類などをまとめたもののようで、中には優香さんの履歴書もしっかり収められていた。店長は優香さんの保護者欄を確認し、電話番号と彼女の父親らしき男の名前を適当な紙に書き写す。やけに画数の多いその名前は、結局一文字目以外片仮名で書かれた。 「子の不始末は親が責任とらないとねえ。それが世の道理だから。採用時はまだ未成年だったから親に連絡もつくし、それだけが救いだわ」 メモ用紙を乱暴にポケットにしまい、店長が出ていこうとする。私も退店してしまおうと「お疲れさまでした」と言いながら頭を下げると、そのタイミングで店長が、 「しかし大畑さんもさあ……なんで止めてあげなかったの? あの子と違って私は悪いことしてないしー、とかって思ってるのかもしれないけど、俺それは違うと思うんだよね。目の前に万引き犯がいて、しかもその子はバイト仲間でさあ。犯罪は犯罪なんだって、せめて俺まで情報あげてくれないと困るよ。大畑さんの、なんかそういう……事なかれ主義? みたいなところ、マジでよくないと思うわ。それって結局無関心なだけ、我関せずなだけじゃん。今回だけはまあ許してあげるけど、そういう在り方ってさあ……なんていうか人として、下劣だよね。正直ないわ」 私だけを部屋に残し、ドアが閉まる。 人手不足だし。 ちょっとくらいならって目をつむってたんだけどね。 先ほどの店長の台詞が当てもなく宙に浮いている。
*
優香さんが辞め、できた穴は全て私が埋めることになった。このまま八日連続勤務、一日休みを挟んでその後はまた八連勤、さらに一日休みを挟んで十連勤。 「働ける場所があるだけありがたいと思わなくちゃね!」 と笑った店長はきょうと明日二連休だという。
入り口近く、先ほど女子高生グループに荒らされたリップクリームのコーナーを整えていると、再びあのセーラー服の万引き少女がやってきた。彼女は店員である私に気がつくとわかりやすく身を縮め、薄く口を開いて、しかしそのまま踵を返そうとする。 「ねえ」 私は彼女の背に声をかける。彼女が、はい、と返事をする。 「さっきの口紅のことなんだけど」 「…………はい」 「まだ持ってる?」 少女がスカートのポケットに手を入れる。ゆっくりと引き抜かれたその手には先ほどの口紅が握られていた。少女はその手を私に近づける。私は無言でそれを受け取り、口紅が置かれていた棚のほうへと歩き出す。少女も大人しく私の後ろをついてくる。 「ねえ、なんでこの色にしたの?」 陳列された口紅を指さしながら、私は少女へ問う。少女が盗んだ口紅は他にも十種類以上の色味があった。少女はしばらく黙っていたが、観念したの��小さな声で、 「お母さんが……」 と言った。 「ああ、そう」 おそらくは母親が引く真っ赤な口紅を見てあのような衝動に駆られたのだろう。私は彼女の顔をちらりと見、それから、 「あなた、肌白いし黒髪だし、確かに赤い口紅も悪くはないと思うよ。でも、もし私の見た目があなたみたいだったらこっちを選んだと思う」 少女へ薄いサーモンピンクの口紅を手渡す。 「あの……」 「レジはうまく誤魔化しておくから。でももうこんなことはやめた方がいいよ。特にこの店では。私も、次は見逃してあげられない」 少女は私に何かを言いたげな様子でパクパクと口を開いては閉じ、けれど年老いた女が入店し「店員さあん、ちょっとお願いしてもいいかしらあ」と私へ向かって声をかけた瞬間、少女は私へ深く頭を下げ、そのまま店を後にした。
私は老婆の元へと駆け寄り、彼女に言われるがままケースの缶コーヒーを担いでレジを通し、車まで運び入れる。 老婆に執拗なまでの礼と興味のない世間話を伝えられる最中、ふと斜向かいのコンビニエンスストアの駐車場に先ほどの少女の姿を見つけた。少女は三十代後半ほどの女から大声で詰られていて、女は「へたくそ」「馬鹿」「出来損ない」などというわかりやすい暴言と「色が違う」「これじゃない」「何度も間違いやがって」という台詞を交互に発していた。 少女が俯いたままじっとしていると、女は少女の後頭部を力任せに叩き、思わずよろけた少女の顔面に何かを投げつけた。コンビニの中には店員が、近くのバス停にも複数人の大人が立っていたが、誰も二人を止めようとはしなかった。 その後少女は髪を鷲掴みにされ、近くの車の後部座席へ押し込まれる。女は乱暴にドアを閉めながら「死ね」と少女に向かって叫び、苛立ちを隠そうともせず運転席に乗り込むと、周囲を確認することもなく勢いよく走り去っていく。
バイト終わり、私は少女が詰られていたコンビニの駐車場へと立ち寄った。彼女が立っていた場所には私が手渡したあの口紅が落ちていて、しかしそれは車に轢かれてしまったのだろう、砕けたケースからはあの綺麗なサーモンピンクが吐き出されていた。
0 notes
Text
人間、捨てたもんじゃない…知らない人から受けた「親切」に心あたたまる
集計期間:2020年3月4日~3月6日 回答数:14138

人間関係の希薄化が叫ばれる現代社会では、人の嫌な面ばかりが見えてしまいがちです。ニュースでも、毎日のように残酷で陰湿な事件が報じられ、思わず人間に絶望してしまいそうになるという人も多いのではないでしょうか。
しかし、他者を信用できない世の中ほど寂しいものはありません。そして、そんな世の中だからこそ、人の親切に触れた時に受ける感動もひとしお。
そこで今回は「知らない人から受けた親切」にまつわるアンケート調査を行いました!
Q1.知らない人から親切にされたことはありますか?

回答者14138名のうち、全体の約4分の3にあたる人々が「見知らぬ誰かから親切にされたことがある」という結果に。なんとも希望を持てる数字ですね!
ここからは、具体的なエピソードを見ていきましょう。
<具体的な親切エピソード>

【赤ちゃん・子供・妊婦のエピソード】
・小さい子供が二人いるので、電車に乗る時や電車を待っている時、道を歩いているだけでたくさんのひとから話しかけられ、譲っていただいています。
・子供が電車のドアに腕を引き込まれてしまった時に見知らぬ男性が助けてくれた。お礼をしようとしたらその電車に乗って去ってしまった。
・年子の赤ちゃん連れて買い物へ行った際に、スーパーや薬局などのレジでお会計しながら袋入れしてもらうことが結構あり助かりました!
・5カ月の子供と電車に乗ったとき、泣き出してベビーカーを嫌がる息子。その時若い10代のカップルが、『ベビーカー僕たちが見てるので、ここ座ってください』と席を譲ってくれた。都会も捨てたもんじゃないな
・妊娠中、電車で席を譲ってもらった。
・妊婦の私が電車に乗った時、腰が痛かったので座りたかったけど席が空いてなくて、優先席の人も見て見ぬ振りをされてしょうがないなと窓際に立っていたら、離れた場所に座っていた女性が、自分が座っていた席に荷物を置いてキープしたまま席を立って私のところまで座ってくださいと言いにきてくれました。とてもありがたくて、こういう事��できる女性になりたいなと思いました。
・レジに並んでる時、子供がぐずってたらあやしてくれたり、順番変わってくれたりしてくれた
・子供の頃、自転車のチェーンが外れて困ってたら助けてくれた
・子連れでいると、年配の方に「頑張ってるね」「いま大変かもしれないけど、頑張ってね!」と温かい言葉をかけてもらうことが多いです。妊娠中は電車の中で20-30代の男性がよく声をかけてくださり、席を譲ってくださいました。
・息子がまだベビーカーに乗っているとき、駅で乗り換え方がわからずそこにいた学生さんに聞いたら『私、時間あるのでその駅まで一緒に行きますよ(^-^)』と言ってくれて、更にマザーズバッグを持ってくれて一緒に電車に乗って私が行きたい駅まで同行してくれた!帰り際に名前聞いたけど教えてくれなかったー!どこかの学生さんに間違いないけど本当に感謝しています。世の中イイ人もたくさんいる(((*≧艸≦)
・子供が小さいときに席を譲っていただき、「何年か経って大変そうな子供連れの方がいたら、代わってあげてね。私もそうしていただきながら、子供を育てたのよ。」と言ってもらいました。今、親切はそうやって世の中を巡っていくのだと思っています。
・妊娠中に会社から帰宅中に、上の子を迎えに行き電車に乗ってすぐに気を失って倒れてしまいました。子供に後で聞いたところ、車掌さんに連絡をしてくれた方、上の子の手をずっと繫いでいてくれた方、ホームから担架でおろしている間もまわりの方々が親切にしてもらったようです。ありがとうございました。
・抱っこ紐を忘れて赤ちゃんを抱っこしたまま買い物した物を袋詰めしてたら、やってあげるわよと言って袋詰めしてくれ、車まで荷物を運んでくださった親切なおば様。
・電車で泣き止まない息子に焦っていたら、声をかけていただいて、あついのかなー?おなかすいたのかなー?ママも大変ねって笑ってくれて、本当に嬉しかった。人の目があったので、怒られたら、と心配になってましたが、おかげで注意や非難されることなく無事に目的地に着きました。
・このコロナ騒ぎの最中、買い物にでかけた先で大量の鼻血を出した息子回りは白い目で見てた中、おばちゃんがポケットティッシュをポンとくれたちょうどティッシュなどの紙類がなくなる中、気にしなくていいからと去っていった姿にジーンとした
【雨のときに…】
・野外ライブで雨が降り、傘しか持ってなかったのに使用禁止で困っていたら、隣りの人がゴミ袋をくれた。
・急な豪雨で雨宿りしていたら、傘をくれた方がいた。
・バス停でバスを待ってたら突然の雨、知らないおばさんに傘いれてもらった。
・子供と散歩中、急に雨が降ってきて傘を持ってなかったので濡れて帰ろうと遊びながら帰っていると、車で通りかかった男性がわざわざ降りてきてくれて『傘使ってください!もういらないので!』とビニール傘を差し出してくれました。結構な雨の量だったのですごく助かりました。
・足の骨折で片松葉づえ状態の時、腎臓病の猫の通院日が雨だった。右手杖、左手猫のかごなので、傘させず雨の中帽子だけかぶって濡れながら駅に向かっていたら、知らない方が傘をずっとさしかけてくれた
・雨の日、子供を抱っこして予防接種に向かう途中あと少しで病院というところで、さしていた傘が崩れ壊れた。通りかかった年配のご婦人が赤ちゃん濡らしちゃったら大変と、折り畳み傘をくれた。その後病院にいる間に雨が強くなってきたようで、ご婦人が折り畳み傘じゃ濡れると病院まで普通の傘をわざわざ持ってきてくれた。ご近所にお住まいだったようだが、わざわざそこまで気にかけて頂き親切にしていただいて、本当に助かりとても感謝しています。
【電車内で】
・電車に乗っていたら知らないおばちゃんからみかんもらいました。
・特に人が多い日に満員電車に乗った際、押しつぶされ倒れてしまいました。その時に男子中学生が手を差し伸べて大丈夫ですか?と聞いてくれました。毎朝イライラしてる人が多い電車の中で心優しい子もいるんだなと嬉しかったです。
・色々な方に親切にしていただいた事があります。中でも20年前くらいのことですが、仕事で現場に向かう途中の朝の通勤ラッシュの電車内で貧血と過呼吸に見舞われ、意識が遠のいてしまった事がありました。意識が薄れる中、微かに「大丈夫?」と女性の声が聞こえたのを覚えているのですが、気づいた時は降りる予定の駅で、ドアが開くと同時に駅員の方が二人で私を抱えてくださっていました。その時は駅員さんに御礼を言うのがやっとでしたが、きっとあの時の声の方が、駅に連絡をしてくださったりしたのではないかと思います。どれくらい意識を失っていたのかも分からないので、誰かに引き継いでくださっての到着だったかもしれないので、もしかしたらその方だけではなかったのかもしれません。どんな方だったのか、何人だったのか、なぜ降りる予定の駅で救護して貰えたのか、など分からない事がばかりですが、ただ一つはっきりとした事実は、その時その場所には人の善意しかなかったという事です。恥ずかしながら今の私は辛い状況の中にいるので、その時の事を思い出すと、もう少し踏ん張って見ようと思えます。
【海外で困ったときに…】
・海外旅行中、ケネディ空港で迷子になり、搭乗口がわからなかった時、たまたま日本人おばちゃんが前を通りかかったので声をかけた時、自分と同じ飛行機に乗るとの事で搭乗口まで一緒に行ってくれた。1人旅で心細かったのでとても助かった。
・学生時代、海外でテイクアウトのコーヒーを買った。飲み始めて現金があと1ドル足りないことに気付いた。もう飲み始めている上に後ろにも列が出来ていた。カードも何も無くて半泣きになっている私に見知らぬ男性が黙って1ドル置いて立ち去った。追いかけてお礼を言うのが精一杯でお金を返せなかった。あれから30年以上経つが未だに忘れられない思い出です。
・オーストラリアのシドニーでお店を探していたら男性が話し掛けてくれた。店の行き方を教えてくれた、すぐ近くの銀行員だったが本当にありがたかった。
・パリで乗る電車が分からないとき声をかけてもらいました。
・バスに乗り間違えてロサンゼルスの郊外で迷子になった時、その場にいたメキシコ出身と思われる男性が親切に正しい戻り方を教えてくれた。無事に帰れたお礼を伝えることができず、今でも連絡先を聞かなかった後悔と、見ず知らずの若い日本人を助けてくれた恩に感謝しています。
・子供の頃バンコクに家族旅行に行った際、つば付きのキャップが風に飛ばされ水上ボートだったのですが船頭の少年が川に飛び込んで取ってきてくれた。
・アメリカでガソリンが無くなって困っていた所ガソリンスタンドまで乗せて行ってくれて携行缶を借りてくれようとしたが借りられず、自分の家のガソリンを取りに行ってお金も受け取らず助けてくれました。
・韓国に行った時、行きたい場所にたどり着けず困っていたらその場所まで一緒に歩いて連れて行ってくれたり行きたい店が見つからずHPを見せたら携帯で電話して聞いてくれたりとにかくとても親切でした日本でいるとイメージが真逆でびっくりしました
・台湾で夜に道がわからなくなってコンビニに入って店員さんに聞いたら、店内にいる他の人達もそれに気づいて一緒に探してくれて、最後には「女の子1人で夜道は危ないから」ってタクシーも呼んでくれて、到着後支払おうとしたら「友達だから!」ってタクシー代まで支払ってくれていた。海外で言葉もなかなか通じないのに、こんなに親切にしてくれて、本当に感謝と感動が止まらなかった。連絡先を聞き忘れた事を未だに後悔している。また出会えないかなぁ、と台湾に行くたびに思う。
【お金がらみのエピソード】
・小さい頃、スーパーのレジで金が足りないとき、レジの人が足りない部分の金を払ってくれた。
・子供のころ、買い物で10円足りなかったところ、知らない高校生の男の子が10円くださり、買い物ができました。自分も、大人になって、困っている子供に同じ事をしたことがあります。
・所持金が5000円しかない状態で深夜にタクシーに乗った時、その旨と予算内ギリギリの所までの走行をお願いしたのですが、500円ほど予算オーバーにも関わらず、5000円で自宅前まできちんと届けて頂いたことがあります。
・高校生のとき友達とスーパーの惣菜コーナーをみていたら知らないおばあさんにお金をもらって好きなものを買いなさいって言ってもらった
・終電で寝過ごして、同じ状況の人とタクシーで相乗りして帰った。その人は先に降りられ、私が家に着いたら全額払っていてくれた。
・他人から何故か駅でSuicaチャージする時にどうぞって1000円渡されたことある、全く知らない男
・高校生の時に定期を忘れて、遅刻したくない勢いで駅員さんに相談したら、しょうがないなぁ、と個人的にお金を貸してくれた
【迷子になったとき…】
・学生時代、道に迷って困ってたら道案内してくれた
・知らない土地で迷っていると声をかけられて、車で道案内してもらった上に食事まで奢ってもらえた。
・道を聞いたら、言葉だけでなく、わかりにくい道なのでと、分かり易くなるところまで連れていってくれたこの人はお年寄りでした
【ケガ・体調不良のときに…】
・体調を崩している所に、お水を渡してくれた
・山でバイクで怪我をしたとき、車で通りかかった夫婦に麓の病院まで乗せて行っていただいた時
・銭湯でのぼせたときに冷たいタオルを首に巻いて、水を飲ませてくれた
・駅で派手に転んでしまったら、若い男性が大丈夫ですか?と手を差し伸べてくれて、余計恥ずかしかった。
・体調が優れずに駅のホームにうずくまっていたら、周りの人が駅員さんをよんでくれた。苦しい間励ましてくれた。
・花粉症で鼻水ズルズルのとき知らない人からティッシュもらった
・骨折して松葉杖で歩いていたら雨が降ってきて知らない大人が車で家まで送ってくれた中学生の時
・ 脚を手術し、しばらく松葉杖で歩いていたら駅の階段で荷物を上まで運んでくれたひとがいた。
・風邪を引いてる時に寄ったコンビニで店員の女性がのど飴をくれた
・酔っぱらって道端で苦しんでいたら、知らない人がお手拭きをくれて、私の背中をさすって、「がんばれー!」って介抱してくれた。
・泥酔して気持ち悪くなって駅のホームで休んでいたら 見ず知らずの方にお水を自販機で買っていただいて 大丈夫ですか?と声を掛けて頂いたことがありますとてもありがたかったです
・高校生の時、学校に登校する途中で派手に転んで膝から血が出た。でも一旦家に帰ると遅刻してしまうためそのまま電車に乗った。膝から出る血をティッシュで押さえながら電車に乗っていたら、知らないおばさんが声をかけてくれて絆創膏をたくさんくれた。
・貧血でふらついてて転んで怪我をした時、手当てをしてもらった。自分が持っていたハンドタオルを濡らして血を拭いてくれて、バンドエイドを貼ってくれました。ありがとうございますとしか言えなかった。その節は本当にありがとうございました。
・出勤のため雪道を自転車で走っていたら見事なくらい派手にすっ転んだ。歩行者の女性と、車からわざわざ男性が降りてきて自転車を起こしてくれたり助けてくれた。恥ずかしいやら申し訳ないやらで、ひたすらすみません!有難うございます!大丈夫です!を繰り返しながら全身ビッショビショで仕事場に向かったけど、嬉しかった。
・バイクで自損事故をした時に119番して救護をしてくれた人が居た。知らん顔して遠巻きに見てる人が集まる中、その方の車の中からバスタオルを数枚持って来てくれて頭の下に敷いてくれたり会社にまで連絡をしてくれたらしいけど、救急車が来て立ち去った。聞けば祖母の病院へ着替えやバスタオルを持って行く途中だったとのこと。助けられました。
・足に釘が貫通した時、病院へ看護師さんを呼びに行って車椅子を持って戻ってきてくれた。
【色んな意味であたたかい】
・寒いなか外で仕事してたら、ホッカイロもらった。ありがたかったです
・飛行機に乗っていて寒いのを我慢していたら、隣の紳士なおじさまがブランケットをCAさんに頼んで「良かったらどうぞ」と笑顔で渡してくれた
・子供と某テーマパークのアトラクションに並んで100分が経過した頃あまりの寒さに泣き出して帰る!と言われ半泣きしていると、後ろに並んでいたカップルがホッカイロをくれた。
・フェリーのざこ寝の大部屋で、有料で毛布を借りるのをケチってそのまま眠った。目が覚めたら毛布であたたかい。途中の港で早朝下船した隣のおじさんがそっと毛布をかけてくれたらしい。
【遺失物・忘れ物がらみのエピソード】
・財布落としたら交番に届けてくれた方、本当にありがとうございました!
・落とし物を拾ってもらい、さらに速達で自宅に送ってくれた。無記名で手紙付きで。感謝しかないです。
・先日買い物の際財布を入れた鞄をショッピングカートにかけていたのを取り忘れたまま帰宅‼️途中気づいて慌てて戻ったらサービスコーナーに届けられてました。届けて頂いた方は名前も言われず行かれたとか。入ってた財布は諦めてたけどホント届けていただいた方には感謝‼️
・財布を落としたら後ろを歩いてた人に声かけてもらって財布を拾ってもらいました。今の嫁です。
・北海道で一人旅をしていて、バスに乗るって時に少し前に立ち寄った所に手荷物を忘れたので取りに行こうとバスの運転手さんに忘れ物を取りに行くので先に行って下さいと伝えたら、『 わかりました』と言ってたんですが、約1時間後再びバス停に戻ると同じバスが待っていて不思議だなと思い乗り込むと、運転手さん初め乗客の皆さんから拍手喝采。『 荷物が見付かって良かったね』と。私の事が心配で待っていてくれていたのです。その場に居た皆さんには感謝しかなかったです。初めての場所で初めて会う方々なのにとても優しさを感じました。
・私が学生の頃、電車に飛び乗ったとき、電車のホームに定期券を忘れてしまいました。しかし、私は定期券に気がつかず電車の扉が閉まってしまいました。そこに見知らぬ男性が私の定期券を持ちながら「車掌さんにこれ(定期)わたすよ」という身振りをしてくれました。後からその駅に戻ると私の定期を車掌さんが持っていてくれ無事に手元に戻りました。あのときは、ほんとうにありがとうございます。
【何かをもらった】
・ライブの当日券売り場に並んでいたら見知らぬ男性が良い席のチケットが余っているとただでチケットをくれました。
・イベントの入り口で入場券を買おうとしたら、余っている無料券を貰えた!
・スーパーで1000円毎に応募券もらえるっていうキャンペーンやってて、1000円いかなくてもらえなかった時に、おじさんが応募券いらないからあげるよって渡してくれた!すっごく嬉しかったです!
・牛丼屋でバカ食いしてたら、しらないオバサマから割り引き券を貰った。
・部品がなくなったときに、ホームセンターの人に、無料で譲ってもらったこと
・先日ドラックストアで、買いそびれたマスクを見ず知らずのご婦人に、譲っていただいた。ただ、自分も多少ストックが家にあったので、更に必要に迫られている知人に譲りました。
・ウォーキングしてる時、向こうから歩いて来たおばあちゃんから���タケノコあげると言って呼び止められ、結構な量のタケノコ頂きました。
・潮干狩りでちっとも獲れなかったんだけど、幼かった子供にたくさん貝をくれた。美味しくいただきました。
・何年も前の話です。出先でレジ袋を置いていないスーパーで買い物をし、会計時にそのことに気づきました。段ボールは置かれていたので、それに詰めて持って帰ろうかと夫と話をしていたら、知らない女性が手持ちのビニール袋を渡してくれました。とても有り難かったです。日頃から人に親切にすれば、困ったときに返ってくると信じて私も親切にしようと心がけています。
【行列で】
・イベントの並ぶ列がわからず困ってたら教えてくれた
・飛行機の搭乗手続きで 間違えた列に並んでいたのに気づかずにいたところ、後ろに並んでいた方が気づいてくれて 正しい列の場所を教えてくれました。
【災害時に】
・311の大震災の時、仙台駅から地元まで歩いて帰りました。高いヒールで、立ち止まったりしながら寒い中歩いていた時に、渋滞している車に追い越し追い越されをしていました。その時に親切な方に乗りなよ!って声をかけてもらったのですが、人見知りだし好意に甘えることに抵抗があり断りました。が、また歩いていると先ほど声をかけてくれた奥様の車が追いつきやっぱり乗りな!高校生の息子とその友達しか乗ってないから!と、断った私にまた声をかけてくれました。私に気遣い安心させてくれる声がけ。また、再度声をかけてくれたのを断るのは違うと思い乗せていただきました。さらに、乗車後にこんなのしかないけど、とバナナとチョコを、くれました。きちんとお礼ができていないのが悔やまれます。が、本当に人の暖かさに触れた瞬間でした。
【何か手伝ってもらった】
・スーパーで箱入りブドウを買うつもりで持ち歩き他の買い物してる時にブドウを落としてバラまいた時に一緒に拾ってくれた一人の方がいたこと
・買い物で自転車からちゃんと縛ったつもりの買い物した物が沢山入った段ボールが落ちて道路に散乱。知らないおばあちゃんが転がった玉ねぎやキャベツ大根など拾ってくれて段ボールに入れてくれた。
・駅の駐輪場で自転車がずらーっと倒れていてその間に自分の自転車があり、ひとつひとつ立てていってたら知らないおじさんがスマートに手伝ってくれた
・病院の駐車場で父を車から車イスに乗せかえる時に、それを見て知らない男性が車からサッとおりて来て「お手伝いします!」と言われて大変感動しました!以来私も知らない人が困っているのを見かけたら迷わず親切にしています!
・小学1年生の頃、終業式の日に学校に置いていた教材などを全て家に持ち帰らなければならず、それらを入れた重い袋を引きずりながら歩いていた学校の帰り道。知らないおばさんが「重そうね〜ちょっと持ってあげようか」と声をかけてくれて、しばらく持って歩いてくれた。
・20年位前、大きなスーツケースを持って、通勤ラッシュの浜松町駅の階段を登っていたら、ふっと軽くなり、あれ?と思ったら後ろからきたサラリーマンの人が私のスーツケースを持って階段の一番上に。そのまま颯爽と行ってしまいました。振り返る事もなく、あっという間の事で後ろから「ありがとうございます」と言うのが精一杯。スマートでありがたかったです。
【事件に巻き込まれたとき】
・車で信号待ち中に当て逃げされた時 逃げた車の後を走ってたというカップルの方が前の車の様子がおかしかったからってナンバーも覚えてくれてて慌ててる私に直ぐに警察へ行き!とナンバーと車種を教えてくださったこと。おかげで直ぐに相手が判り認知症のお爺さんでした。
【車にまつわるエピソード】
・豪雪の夜中に車のチェーン着けるの手伝ってもらった!しかもご飯までご馳走になってしまった!トラック運転手さんありがとうございました!
・何年か前の母娘旅行で、船の時間間に合わない時、駅にいてた��館送迎の運転手さん(宿泊してないです)が船着場まで送ってくれました!その旅館のお客さん乗ってたのに、その場のお客さんも文句言わず、無事間に合いました!
・早番の出勤で駅までのバス待ちをしていたら、大型トラックのドライバーさんが止まって「途中事故があって当分バス来ないから駅まで乗せてあげるよ」と親切に乗せて下さった。最初は知らない人の車で怖かったけど、とても良い方だった。
・免許取り立ての時 コンビニにいったら隣にトラック 後ろに街頭で 斜めに出る技術がなく 四苦八苦してたら知らない人が車を出してくれた。
・自分の車が脱輪したときに、周りの人が大勢助けてくれた。
・車で走行中にマフラーが外れてしまい、知らずに走っていたら、すぐ後ろの車の人がわざわざ教えに来てくれた。その後、とりあえず応急処置をしようとしていたら、知らないお兄さんが声をかけてくれて、やり方を教えてくれたけど、あまり機械に詳しくないと言ったら、全部そのお兄さんがやってくれた。神!
・冬、国道から路肩の雪山に車が落ちて埋まった時、見ず知らずの方達が何台かとまってくれ、交通整理をしたり車を引き上げてくれた。
・田舎で一日数本のバスを乗りすごし歩いていた時に通りがかりのタクシーの運転手さんに駅まで料金を取らずに送ってもらえたことがあります。お金を払うって言っても回送中なので受け取れませんということでした。
・昔、友達にバイクを借りて家に向かう途中、カーブを曲がりきれずガードレールに突っ込んでしまい、借りたバイクは一発廃車私は血だらけ、、周りにたくさん人もいて恥ずかしさの余りその場から早く立ち去りたかったので、逃げる様にその場から急いで去ろうとした時に声をかけてくれた障害者のお兄さん、私がパンツ丸出しで倒れてるのを見てハンカチで隠してくれてました。あの時はお礼も言えなかったけど感謝です。
・仲間とドライブして山で迷子になり挙げ句ダブルでパンク、冬場で雪も降り始めガソリンも底をつき途方に暮れてたと頃、麓のおばあちゃんが通り掛かり自宅に招待してくれ食事から宿泊まで面倒をみてもらって修理費まで建て替えてくれた。その後何年間か交流してくれたけど、暫くぶりに伺ったら亡くなれて家もなかった。
・職場から自家用車で帰宅途中、ふと気づくとワイパーに小さなメモが挟まっていた。気になったので高速道路に乗る前に車を停めて確認すると、「恐らく右の後輪がパンクしてると思います。JAFを呼んだ方がいいです。」と。朝、確かに変な形の石に乗り上げていたのと、運転中右にハンドルが取られる気がしていたので即納得、JAFを呼びました。メモは、近所に住む車に詳しい警備員の方からでした。通りがかりに気になって教えてくれたそうです。あのまま高速に乗っていたらと思うとゾッとします。
【喫煙者同士の絆】
・何年も前の事ファーストフード店でタバコを吸おうとしたらライターを忘れていた恐縮しながら近くの人にライターを借り、一服していたら、『1つ余分にありますから』と借りた方がライターをくれました
【トイレを我慢しているとき…】
・子供のトイレが漏れそうな時、順番を譲ってもらった
・子供の頃、トイレに行きたくて我慢出来ず、近くの家に飛び込んだとき、見ず知らずの私を快く家に入れてくれた。もちろん、トイレも借りました。
【そっと教えてくれる人】
・電車でチャック開いてたのをそっとおばあちゃんがおしえてくれた
・スカートの後ろチャックが開いていたのを、こっそり教えてくれて、サッと去って行った紳士
・出先でトイレ後、トイレットペーパー引きずって歩いてたのをそっと教えてくれたご婦人。
・カーディガンを裏表着てた時に教えて頂きました、今の旦那のご両親に会う時だったので本当に感謝してます!
【その他】
・徳島県で遍路道を歩いていた時、様々な人に励まされ、親切にされた。ご年配の方からも小学生からも親身になっていただき、無事に歩き通しました。
・社員旅行で、まだ入社したてだったからか、休憩のサービスエリアに置き去りにされ、携帯で連絡はできたが移動手段がなく困ったので、駐車場の車に声を掛けて、次のサービスエリアまで乗せていってもらった。
・花火大会で普段着慣れない浴衣の帯が取れて困っていたとき、通りすがりの女性に締め直してもらった。
・幼少期にプールで溺れて知らない人に助けて貰った。その人がいなければ今生きてない。
・ケンカの仲裁をされました。他人なので冷静になりましたね。
・人ではないがネコ、喧嘩の仲裁をしたその後 お礼なのか仕留めた鳩を加えて玄関へお土産として置いった。複雑な気持ちになった。
・バスの中で変な人にからまれ、外国人の方に守って頂いた。
・初めて甲子園に行ったとき、席探してると、阪神応援団の方が席案内してくれて、初めてだと言うと、選手応援歌の歌詞が書かれた紙をくれたこと。阪神ファンは怖いとか言う人いるけど、いい人ですよ。
・買い物中に顔面蒼白だったらしく、見知らぬご婦人から鏡を貸して頂いた事がある
・MonsterHunterWorldというゲーム内で慣れないことをやっている時、オンラインで他のプレイヤーがサポートしてくれたおかげで簡単に終わりました。そんプレイヤーは報酬を受け取らず、途中で離脱していったのが、またシブイです。
・昔、銭湯で知らない人に背中を洗ってもらいました
・子供が家出をしたが、知らない人が心配して連絡をくれた
・観光地でカップルでもじもじしてたら「撮りましょうか?」と。いい記念写真とれました。
・ジム行って機械の操作がわからなく色々なぶっていたら、このジムにいつも通っている人が近くに来てくれて操作を教えてくれた。
・蜂に刺された時、その場の近くの家の人がアロエを持ってきてくれて、刺されたところに塗ってくれた
・近所のスーパーで、お婆ちゃんが袋詰めの極意を教えてくれた
<まとめ>

以上が、皆さんの「見知らぬ他人から受けた親切エピソード」でした。どれもこれも、読んでいるだけで心あたたまる話ばかりでしたね。
寄せられたエピソードの中でも印象的だったのは、親切にしてくれた人から「私も以前、人に助けてもらったことがある」と明かされ「次は自分も困ってる人を助けてあげたい」と決意する人が多かったことです。一人の親切心が��大きな輪を広げていくのがわかりますね。
アンケートにご協力いただきありがとうございました。
グノシーの「アンケート」タブにて、毎日新しいアンケートを更新しています。ポイントが手に入るものもあるので奮ってご参加ください。

こちらの記事に関するお問い合わせは [email protected] までお願いします。
0 notes
Text
【キャプトニ】フィランソロピスト

ピクシブに投稿済みのキャプトニ小説です。
MCU設定に夢と希望と自設定を上書きした慈善家トニー。WS前だけどキャップがタワーに住んでます。付き合ってます。
ピクシブからのコピペなので誤字脱字ご容赦ください。気づいたら直します。
誤字脱字の指摘・コメントは大歓迎です。( Ask me anything!からどうぞ)
チャリティーパーティーから帰ってきたトニーの機嫌は悪かった。スティーブは彼のために、知っている中で最も高価なスコッチウイスキーを、以前彼に見せられたyou tubeの動画通りのやり方で水割りにして手渡してやったが、受け取ってすぐに上品にあおられたグラスは大理石のバーカウンターに叩きつけられ、目玉の飛び出るくらい高価な琥珀色のアルコール飲料は、グラスの中で波打って無残にこぼれた。 「あのちんけな自称軍事評論家め!」 スティーブは、トニーが何に対して怒っているのか見極めるまで口を出さないでおこうと決めた。彼が摩天楼を見下ろす窓ガラスの前でイライラと足を踏み鳴らすのを、その後ろから黙って見つめる。 トニーは一通り怪し気なコラムニストの素性に文句を言い立て、同時に手元の情報端末で何かをハッキングしているようだった。「ほーらやっぱり。ベトナム従軍経験があるなんて嘘っぱちじゃないか。傭兵だと? 笑わせてくれる。それで僕の地雷除去システムを批判するなんて――」 左手で強化ガラスにホログラムのような画面を出現させ、右手ではものすごい勢いで親指をタップさせながら、おそらく人ひとりの人生を破滅させようとしているわりには楽しそうな笑みを浮かべてトニーは言った。「これで全世界に捏造コラムニストの正体が明かされたぞ! まあ、誰かがこいつに興味があった���ニュースになるだろう」 「穏やかじゃないチャリティーだったようだな」 少しトニーの気が晴れたのを見計らって、スティーブはようやく彼の肩に触れた。 「キャプテン、穏やかなチャリティパーティーなんてないんだ。カメラの回ってないところじゃ慈善家たちは仮面を被ろうともしない。同類ばかりだからね」 トニーは振り返ってスティーブの頬にキスをすると、つくづくそういった人種と関わるのが嫌になったとため息をついた。「何が嫌だって、自分もそういう一人だと実感することがさ」 「それは違うだろう」 「そうか?」 トニーはスティーブの青い目を見上げてにやりと笑った。「僕が人格者として有名じゃないってことは君もご指摘のとおりだろ?」 「第一印象が最悪だったのは、僕のせいかい」 これくらいの当てこすりにはだいぶ慣れてきたので、スティーブは涼しい顔で返した。恋人がもっと悪びれると思っていたのか、トニーはつまらなそうに口をとがらせる。「そりゃそうさ。君が悪い。君は僕に興味なさそうだったし、趣味も好きな食べ物も年齢も聞かなかったじゃないか。友人の息子に会ったらまずは”いくつになった?”と聞くのがお決まりだろ。なのに君ときたらジェットに乗るなりむっつり黙り込んで」 「ごめん」 トニーの長ったらしい皮肉を止めるには、素直に謝るか、少々強引にキスしてしまうか、の二通りくらいしか選択肢がなかった。キスは時に仲直り以上の素晴らしい効果を与えてくれるが、誤魔化されたとトニーが怒る可能性もあったので、ここは素直に謝っておくことにした。 それに、”それは違う”と言ったのは本心だ。「君は自分が慈善家だと、まるで偽善者のようにいうけれど、僕はそうは思わない――君が人を助けたいと思うのは、君が優しいからだ」 「僕が優しい?」 「そうだ」 「うーん」 トニーは自分でもうまく表情を見つけられないようだった。スティーブにはそれが照れているのだとわかった。よく回る口で自分自身の美徳すら煙に巻いてしまう前に、今度こそスティーブは彼の唇をふさいでしまうことにした。
◇
結局、昨夜トニーが何に怒っていたのか、聞かずじまいだった。トニーには――彼の感情の表現には独特の癖があって、態度で示していることと、内心で葛藤していることがかけ離れていることさえある。彼が怒っているように見えても、その実、怒りの対象とは全く別の事がらについて心配していたり、計算高く謀略を巡らせていたりするのだ。 彼が何かを計画しているのなら、それを理解するのは自分には不可能だ。スティーブはとっくに、トニーが天才であって、自分はそうではないことを認めていた。もちろん軍事的なこと――宇宙からの敵に対する防備であるとか、敵地に奇襲するさいの作戦、武器や兵の配置、それらは自分の専門であるからトニーを相手に遅れをとることはない。それに、一夜にして熱核反応物理学者にはなれないだろうが、本腰を入れて学べばどんな分野だって”それなりに”モノにすることは出来る。超人血清によって強化されたのは肉体だけではない。しかし、そういうことがあってもなお、トニーの考えることは次元が違っていて、スティーブは早々に理解を諦めてしまうのだ。 べつにネガティブなことではないと思う。トニーが何をしようとも、結果は共に受け入れる。その覚悟があるだけだ。 とはいえ、昨夜のようにわざとらしく怒るトニーは珍しい。八つ当たりのように”自称軍事評論家”とやらの評判をめちゃめちゃにしたようだが、パーティーでちょっと嫌味を言われただけであそこまでの報復はしないだろう(断言はできないが)。彼への反感を隠れ蓑に複雑な計算式を脳内で展開していたのかもしれないし、酔っていたようだから、本当にただの”大げさな怒り”だったのかもしれない――スティーブは気になったが、翌日になってまで追及しようとは思わなかった。特に、隣にトニーが寝ていて、ジャービスによって完璧に計算された角度で開かれたブラインドカーテンから、清々しい秋の陽光が差し込み、その日差しがトニーの丸みを帯びた肩と長い睫毛の先を撫でるように照らしているのを何の遠慮も邪魔もなく見つめていられる、今日みたいな朝は。 こんな朝は、キスから始まるべきだ。甘ったるく、無駄に時間を消費する、意味だとか難しい理由なんかこれっぽっちもないただのキス。 果たし��スティーブの唇がやわらかな口ひげに触れたとき、トニーのはしばみ色の瞳が開かれた。 ……ああ、美しいな。 キスをしたときにはもうトニーの目は閉じられていたが、スティーブはもっとその瞳を見ていたかった。 トニー・スタークの瞳はブラウンだということになっている。強い日差しがあるとき、ごく近くにいるとわかる、彼の瞳はブラウンに緑かかった、透明水彩で描かれたグラスのように澄んだはしばみ色に見える。 彼のこの瞳を見たことのある人間は、スティーブ一人というわけではないだろう――ペッパー・ポッツ、有名無名のモデルや俳優たち、美貌の記者に才気ある同業者――きっと彼の過去に通り過ぎていった何人もの男女が見てきたことだろう。マリブにあった彼の自宅の寝室は、それはそれは大きな窓があり、気持ちの良い朝日が差し込んだときく。 けれど彼らのうち誰も、自分ほどこの瞳に魅入られ、囚われて、溺れた者はいないだろう。でなければどうして彼らは、今、トニーの側にいないのだ? どうして彼から離れて生きていられるのだ。 「……おはよう、キャップ」 「おはようトニー」 最後に鼻の先に口付けてからおたがいにぎこちない挨拶をする。この瞬間、トニーが少し緊張するように感じられるのは、スティーブの勘違いではないと思うのだが、その理由も未だ聞けずにいる。 スティーブは、こと仕事となれば作戦や戦略のささいな矛盾や装備の不備に気がつくし、気がついたものには偏執的なほど徹底して改善を要求するのだが、なぜか私生活ではそんな気になれないのだった。目の前に愛しい恋人がいる。ただそれだけで、心の空腹が満たされ、他はすべて有象無象に感じられる。”恋に浮わついた”典型的な症状といえるが、自覚していて治す気もない。むしろ、欠けていた部分が充実し、より完全な状態になったような気さえする。ならば他に何を案じることがある? 快楽主義者のようでいてじつは悲観的なほどリアリストであるトニーとは真逆の性質といえた。 トニーが先にシャワーを浴びているあいだ、スティーブはキッチンで湯を沸かし、コーヒーを淹れる。スティーブと付き合うようになってから、いくつかのトニーの不摂生については改善されたが、起床後にコーヒーをまるで燃料のようにがぶ飲みする癖は変わらなかった。彼の天災のような頭脳には必要不可欠のものと思って今では諦めている。甘党のくせに砂糖もミルクも入れないのが、好みなのか、ただものぐさなだけかもスティーブは知らない。いつからかスティーブがティースプーンに一杯ハチミツを垂らすようになっても、彼は何も言わずにそれを飲んでいるので、実はカフェインが入っていれば味はどうでもいいのかもしれない。 シャワーから上がってきたトニーがちゃんと服を着ているのを確認して(彼はたまにごく自然に裸でキッチンやタワーの共有スペースにご登場することがある、たいていは無人か、スティーブやバナーなど親しい同性の人間しか居ないときに限ってだが)、スティーブもバスルームに向かった。着替えを済ませてキッチンに戻ると、トニーは何杯目かわからないブラック・コーヒーを飲んでいたが、スティーブが用意したバナナマフィンにも手をつけた形跡があったのでほっとする。ほうっておくとまともな固形食をとらない癖もなかなか直らない。スティーブはエプロンをつけてカウンターの中に入り、改めて朝食の用意を始める。十二インチのフライパンに卵を六つ割り入れてふたをし、買い置きのバゲットとクロワッサンを電子オーブンに適当に放り込んでセットする。卵をひっくり返すのは危険だということを第二次世界大戦前から知っていたので、片面焼きのまま一枚はトニーの皿に、残りは自分の皿に乗せる。半分に割ったりんご(もちろんナイフを使う。手で割ってみせたときのトニーの表情が微妙だったため)を添えてトニーの前に差し出すと、彼は背筋を伸ばして素直にそれを食べ始めた。バゲットはただ皿に置いただけでは食べないので手渡してやる。朝食時のふるまいについては今までに散々口論してきたからか、諦めの境地に達したらしいトニーはもはや無抵抗だ。 特に料理が好きだとか得意だとかいうわけでもないのだが、スティーブはこの時間を愛していた。トニーが健康的な朝の生活を実行していると目の前で確認することが出来るし、おとなしく従順なトニーというのはこの時間にしかお目にかかれない(夜だって、彼はとても”従順”とはいえない)。秘匿情報ファイルであろうとマグカップだろうと他人からの手渡しを嫌う彼が、自分の手から受け取ったクロワッサンを黙って食べる姿は、人になつかない猫を慣れさせたような甘美な達成感をスティーブに与えた。 「今日の予定は?」 スティーブが自分の分の皿を持ってカウンターの内側に座る。斜め向かいのトニーは電脳執事に問い合わせることなく、カウンターに置いたスマートフォンを自分で操作してスケジュールを確認した。口にものが入っているから音声操作をしないようだった。ときどき妙にマナーに正しいから面食らうことがある。朝の短時間できれいに整えられたトニーの髭が、彼が咀嚼するたびにくにくに動くのを見て、スティーブは唐突にたまらない気分になった。 「僕は――S.H.I.E.L.D.の午前会議に呼ばれてるんだ。食べ終わったら出発するよ。それから午後は空いてるけど、君がもし良かったら……」 トニーの口が開くのを待つあいだ、彼の口元を凝視していては”健全な朝の活動”に支障を来しそうだったので、スティーブは自分の予定を先に話し始めた。「……良かったら、美術館にでも行かないか。グッケンハイムで面白そうな写真展がやってるんだ。東アジアの市場のストリートチルドレンたちを主題にした企画で――」 トニーはスマートフォンの上に出現した青白いホログラムから、ちらっとスティーブに視線を寄越して”呆れた”顔をした。よっぽど硬いバゲットだったのか、ようやく口の中のものを飲み込んだ彼は、今度は行儀悪く手に持ったフォークをスティーブに向けて揺らしながら言った。「デートはいいが、そんな辛気臭い企画展なんかごめんだ」 「辛気臭いって、君、いつだったか、そういう子供たちの救済のためのチャリティーを主催したこともあったろ」 「ああ、僕は慈善家だからね。現地視察にも行ったし、NPOのボランティアどもとお茶もしたし、写真展だって行ったことがある、カメラが回ってるところでな」 フォークをくるりと回してバナナマフィンの残りに刺す。「何が悲しくて恋人と路上生活者の写真を見に行かなくちゃならない? ”世界の今”を考えるのか? わざわざ自分の無力さを痛感しに行くなんていやだね。君と腕を組んでスロープをぶらぶら下るのは、まあそそられるけど」 「まったく、君ってやつは……」 スティーブは苦笑いするしかなかった。「じゃあ、ただスロープをぶらぶら下るだけでいいよ。ピカソが入れ替えられたみたいだ。デ・キリコのコレクションも増えたっていうし、展示されてるなら見てみたい。噂じゃどこかの富豪が画家の恋人のために、イタリアのコレクターから買い付けて美術館に寄付したって」 「きみもすっかり情報機関の人間だな」 「まあね。絵が好きな富豪は君以外にもいるんだなって思った」 「君は間違ってる。僕は”超・大”富豪だし、べつに絵は好きで集めてるんじゃない。税金対策だよ。あと、火事になったとき、三億ドルを抱えるより、丸めた布を持って逃げるほうが効率いいだろ?」 「呆れた」 「絵なんて紙幣の代わりさ。高値がつくのは悪い連中が多い証拠だな」 ところで、とトニーはスマートフォンを操作し、ホログラムを解除した。「せっかくのお誘いはありがたいが、残念ながら僕は今日忙しいんだ。社の開発部のやつらが放り投げた……洋上風力発電の……あれやこれやを解析しなきゃならないんでね。美術館デートはまた今度にしてくれ。その辛気臭い企画展が終わった頃に」 「そうか、残念だよ」 もちろんスティーブは落胆なんてしなかった。トニーが忙しいのは分かっているし、それはスティーブが口を出せる範囲の事ではない。ふたりのスケジュールが完全に一致するのは、地球の危機が訪れた時くらいだ。それでもこうして一緒の屋根の下で暮らしているのだから、たかが一緒に美術館に行けないくらいで残念がったりはしない。ごくふつうの恋人たちのように、夕暮れのマンハッタンを、流行りのコーヒーショップのタンブラーを片手に、隣り合って歩けないからといって、大企業のオーナーにしてヒーローである恋人を前に落胆した顔を見せるなんてことはしない。 「スティーブ、すねるなよ」 しかしこの(肉体的年齢では)年上の恋人は、敏い上にデリカシーがない。多忙な恋人の負担になるまいと奮闘するスティーブの内心などお見通しとばかりに、ニヤニヤといやらしい笑みを浮かべてからかうのだ。「君だってこの前、僕の誘いを断ったろ? しかも他の男と会うとかで」 「あれはフューリーに呼び出されて……」 「ニック・フューリーは男だ! S.H.I.E.L.D.の戦術訓練なんて急に予定に入るか? あいつ���僕が気に入らないんだ、君に悪影響を与えるとかで」 「君に良い影響を与えてるとは思えないのかな」 スティーブはマフィンに刺さったフォークでそれを一口大に切り分け、トニーの口元に運んでやった。呆気にとられたような顔をするトニーに、首をかしげてにっこりと微笑む。 トニーはしてやられたとばかりに、さっと頬を赤くした。 「この、自信家め」 「黙って全部食べるんだ、元プレイボーイ」 朝のこの時間、トニーはとても従順な恋人だ。
◇
トニーに借りたヘリでS.H.I.E.L.D.本部に到着すると(それはもはやキャプテン・アメリカ仕様にトニーによってカスタムされ、「なんなら塗装し直そうか? アイアンパトリオットとお揃いの柄に?」と提言されたが、スティーブは操縦システム以外の改装を丁重に断った)、屋内に入るやいなや盛大な警戒音がスティーブを迎えた。技術スタッフとおぼしき制服を来た人間が、地下に向かって駆けていく。どうやら物理的な攻撃を受けているわけではなさそうだったので、スティーブは足を速めながらも冷静に長官室へと向かった。 長官室の続きのモニタールームにフューリーはいた。スティーブには携帯電話よりもよほど”まとも”な通信機器に思える、設置型の受話器を耳に当て、モニター越しに会話をしている。というか、怒鳴っている。 「いつからS.H.I.E.L.D.のネットワークは穴の開いた網になったんだ? 通販サイトのほうがまだ上手にセキュリティ対策してるぞ!! あ!? 言い訳は聞きたくない、すべてのネットワーク機器をシャットダウンしろ、お前らの出身大学がどこだろうと関係ない。頼むから仕事をしてくれ、おい、聞いてるか? ああ、ん? 知るか、そんなの。あと二時間以内に復旧しなけりゃ、今後は機密情報はamazonのクラウドに保存するからな!!」 「ハッキングされたのか?」 長官の後ろに影のように控えていたナターシャ・ロマノフにスティーブは尋ねた。 「そのようね。今のところ、情報の漏洩はないみたいだけど、レベル6相当の機密ファイルに不正アクセスされたのは確定みたい」 「よくあるのか?」 「こんなことがよくあっては困るんだ」 受話器を置いたフューリーが言った。「午前会議は延期だ、午後になるか、夕方になるか、夜中になるかわからん」 「現在進行中の任務に影響は?」 「独立したオペシステムがあるから取りあえずは問題ない。だがもしかしたら君にも出動してもらうかもしれない。待機していてくれるか」 スティーブは頷いた。そのまま復旧までモニタリングするというフューリーを置いて、ナターシャと長官室を出る。 「S.H.I.E.L.D.のセキュリティはどうなってる? 僕は専門外だが、情報の漏洩は致命的だ。兵士の命に関わる」 「我々は諜報員よ、基本的には。だから情報の扱いは慎重だわ」 吹き抜けのロビーに出て、慌しく行きかう職員の様子を見下ろす。「でもクラッキングされるのは日常茶飯事なのよ、こういう機関である故にね。ペンタゴンなんてS.H.I.E.L.D.以上に世界中のクラッカーたちのパーティ会場化されてるわ。それでも機密は守ってる。長官があの調子なのはいつものことでしょ」 「じゃあ心配ない?」 「さあね。本当に緊急なら情報工学の専門家を呼ぶんじゃない。あなたのとこの」 すべてお見通しとばかりに鮮やかに微笑まれ、スティーブは口ごもった。 トニーとの関係は隠しているわけではないが、会う人間全てに言って回っているわけでもない。アベンジャーズのメンバーにも特に知らせているわけではなかった(知らせるって、一体どういえばいいっていうんだ? ”やあ、ナターシャ。僕とトニーは恋人になったんだ。よろしく”とでも? 高校生じゃあるまいし)。だからこの美しい女スパイは彼らの関係を自力で読み解いたのだ。そんなに難しいことではなかっただろうとは、スティーブ自身も認めるところだ。 ナターシャは自分がトニーを倦厭していた頃を知っている。そんな相手に今は夢中になっていることを知られるのは居た堪れなかった。断じてトニーとの関係を恥じているわけではないのだが……ナターシャは批判したりしないし、クリントのように差別すれすれの表現でからかったりもしない。ひょっとすると、彼女は自分たちを祝福しているのではないかとさえ思う時が���る。だからこそ、こそばゆいのかもしれなかった。 「ところで……戦闘スタイルだな。出動予定があったのか」 身体にぴったりとフィットした黒い戦闘スーツを身にまとったナターシャは肩をすくめて否定した。「私も会議に呼ばれて来たの。武装は解除してる」 スティーブが見たところ、銃こそ携帯していないが、S.H.I.E.L.D.の技術が結集したリストバンドとベルトをしっかりと装着していて、四肢が健康なブラック・ウィドウは未武装といえない。だかこのスタイル以外の彼女を見ることが稀なので、そうかと聞き流した。 「僕は復旧の邪魔にならないようにトレーニングルームにいるよ。稽古に付き合ってくれる奇特な職員がいるかもしれない」 「私は長官の伝令だからこの辺にいるわ。復旧したらインカムで知らせるから、とりあえず長官室に来て」 踵を返して、歩きながらナターシャは振り向きざまに言った。「残念だけど電話は使えないわよ。ダーリンに”今夜は遅くなる”って伝えるのは、もうちょっと後にして」 「勘弁してくれ、ナターシャ」 聞いたこともない可愛らしい笑い声を響かせて、スーパースパイはぎょっとする職員たちに見向きもせず、長官室に戻っていった。
◇
トニーの様子がおかしいのは今更だが、ここのところちょっと度が過ぎていた。ラボに篭りきりなのも、食事を取らなかったり、眠らなかったり、シャワーを浴びなかったりして不摂生なのも、いつものことといえばいつものことで、それが同時に起こって、しかも自分を避けている様子がなければスティーブも一週間くらいは目をつぶっただろう。
S.H.I.E.L.D.がハッキングされた件は、その日のうちに収拾がついた。犯人は捕まえられなかったが、システムの脆弱性が露見したので今後それを強化していくという。 スティーブがタワーに帰宅したのは深夜になろうかという頃だったが、トニーはラボにいて出てこなかった。これは珍しいことだが、研究に没頭した日には無いこともない。彼の研究が伊達ではないことはもうスティーブも知っているから、著しく不健康な状態でなければ邪魔はしない。結局、その日は別々に就寝についた。と、スティーブは思っていた。 次の日の朝、隣にトニーはいなかった。きっと自分の寝室で寝ているのだと思い、先に身支度と朝食の用意を済ませてから彼の居室を訪れると、空の部屋にジャービスの声が降ってきた。 『トニー様は外出されました。ロジャース様がお尋ねになれば、おおよその帰宅時間をお伝えするようにとのことですが』 「どこへ行ったんだ? 急な仕事が入ったのか?」 『訪問先は聞いておりません』 そんなわけがあるか、とスティーブは思ったが、ジャービスを相手に否定したり説得したりしても無駄なことだった。乱れのないベッドシーツを横目で見下ろす。「彼は寝なかったんだ。車なら君がアシストできるだろうけど、もし飛行機を使ったなら操縦が心配だ」 『私は飛行機の操縦も可能です』 「そうか、飛行機で出かけたんだな。なら市外に行ったのか」 電脳執事が沈黙する。スティーブの一勝。ため息をついて寝室を出た。 ジャービスはいい奴だが(このような表現が適切かどうか、スティーブには確信が持てないでいる)、たまにスティーブを試すようなことをする。今朝だって、”彼”はキッチンで二人分の食事を支度するスティーブを見ていたわけだから、その時にトニーが外出していることを教えてくれてよかったはずだ。トニーの作った人工知能が壊れているわけがないから、これは”彼”の、主人の恋人に対する”いじわる”なのだとスティーブは解釈している。トニーはよくジャービスを「僕の息子」と表現するが――さしずめ、父親の恋人に嫉妬する子供といったところか。そう思うと、自分に決して忠実でないこの電脳執事に強く出られないでいる。 「それで……彼は何時ごろに帰るって?」 『早くても明朝になるとのことです』 「えっ……本当に、どこに行ったんだ」 『通信は可能ですが、お繋ぎしますか』 「ああ、いや、自分の電話でかけるよ。ありがとう。彼のほうは、僕の予定は知ってるかな」 『はい』 「そう……」 スティーブはそれきり黙って、二人分の食事をさっさと片付けてしまうと、朝のランニングに出掛けた。 エレベータの中で電話をかけたが、トニーは出なかった。
それが四日前のことだ。予告した日の真夜中に帰ってきたトニーは、パーティ帰りのような着崩したタキシードでなく、紺色にストライプの入ったしゃれたビジネススーツをかっちりと着込んでふらりとキッチンに現れた。スティーブの強化された嗅覚が確かなら、少なくとも前八時間のあいだ、一滴も酒を飲んでいないのは明らかだった。――これは大変珍しいことだ。今までにないことだと言ってもいい。 彼は相変わらず饒舌で、出来の悪い社員のぐちや、言い訳ばかりの役員とお小言口調の政府高官への皮肉たっぷりの批判を、舞台でスピーチするみたいに大仰にスティーブに話して聞かせ、その間にも何かとボディタッチをしてきた。どれもいつものトニー、平常運転だ。しかしスティーブは、そんな彼の様子に違和感を覚えた。 彼が饒舌なのはよくあるが、生産性のないぐちを延々と口上するときはたいてい酔っている。しらふでここまで滔々としゃべり続けることはないと、スティーブには思われた。べたべたと身体に触ってくるのに、後から思え��意図されていたと思わずにはいられないくらい、不自然に目を合わせなかった。スティーブが秘密工作員と関係のない職種についていたとしても、自分の恋人が何かを隠していると気付いただろう。 極め付けはこれだ。スティーブはトニーの話を遮って、「君の風力発電は順調?」とたずねた。記憶が確かなら、この二日間、彼が忙しかったのはそのためであるはずだ。 「石器時代のテクノロジーがどうしたって?」 スティーブはぐっと拳を握りたいのを我慢して続けた。「だって、君――その話をしてただろ?」 「ああ……」 トニーは一瞬だけ、せわしなく何くれと動かしていた手足を止めた。「おもい出した。言ったっけ? ロングアイランド沖に発電所を建設するんだ。もう何年も構想してるんだけど、思ったよりうちの営業は優秀で――何しろほら、うちにはもっと”すごいやつ”があるんだし――そう簡単に量産は出来ないけど――それで僕は気が進まないんだが、州知事がGOサインを出してしまってね、ところが開発の連中が怖気づいてしまったんだ、というか、一人失踪してしまって……すぐに見つけ出して再洗脳完了したけど――冗談だよ、キャップ――でも無理はない事だとも思うんだ、だって考えてみろ……今時、いつなんどき宇宙から未知の敵対エネルギーが降ってくるかもしれないのに、無防備に海の上に風車なんて建ててる場合か? 奴らも責任あるエンジニアとして、ブレードの強度を高めようと努力してくれてるんだが、エイリアンの武器にどうやったら対抗出来るってんだ? 塩害や紫外線から守って次元じゃないんだろ? いっそバリアでも張るか? いっそそのほうが……うーん、バリアか。バリアってのはなかなか面白そうなアイデアだ、しかしそうすると僕は……いやコストがかかりすぎると、今度は失踪者じゃすまなくなるかも……」 スティーブは確信した。 トニーは自分に何か隠している。忙しいとウソまでついて。しかもそれは――彼がしらふでこんなに饒舌になるくらい、”後ろめたい”ことだ。
翌朝から今度はラボに閉じこもったトニーは、通信にも顔を出さなかった。忙しいといってキッチンにもリビングにも降りてこないので、サンドイッチやら果物をラボに届けてやると、その時に限ってトニーは別の階に移動していたり、”瞑想のために羊水カプセルに入った”とジャービスに知らされたり(冗談だろうが、指摘してもさらなる馬鹿らしい言い訳で煙に巻かれるので否定しない。羊水カプセル? 冗談だよな?)して本人に会えない。つまりトニーはジャービスにタワー内のカメラを監視させて、スティーブがラボに近付くと逃げているのだ。 恋人に避けられる理由がわからない。しかし嫌な予感だけはじゅうぶんにする。トニーが子供っぽい行動に走るときは、後ろめたいことがあるとき――つまり、”彼自身に”問題があると自覚しているときだ。 トニーの抱える問題? トニー・スターク、世紀の天才。現代のダ・ヴィンチと称された機械工学の神。アフガニスタンの洞窟に幽閉されてもなお、がらくたからアーク・リアクターを作り上げた優れた発明家にしてアイアンマン――億万長者という言葉では言い表せないほどの富と権力を持ち、さらには眉目秀麗で頭脳明晰、世間は彼には何の悩みも問題もないと思いがちだが――そのじつ、いや、彼のことを三日もよく見ていればわかることだ。彼は問題ばかりだ。問題の塊だといってもいい。 一番の問題は、彼が自分自身の問題を自覚していて、直そうとするどことか、わざとそれを誇張しているということだ。スティーブにはそれが歪んだ自傷行為にしか見えない。酒に強いわけでもないのに人前で浴びるように飲んでみたり、愛してもいない人間と婚約寸前までいったり(ポッツ嬢のことではない)、パーソナルスペースが広いわりに見知らぬファンの肩を親し気に抱いてみたり、それに――平和を求めているのに、兵器の開発をしたり――していたのは、すべて彼の”弱さ”であるはずだが、トニーはもうずいぶんと長いあいだ、世間に向けてそれが”強さ”だと信じさせてきた。大酒のみのパーティクラッシャー、破天荒なプレイボーイ、気取らないスーパーヒーロー、そして真の愛国者。アルコール依存症、堕落したセックスマニア、八方美人のヒーロー、死の商人というよりもよっぽど印象がいい。メディアを使った印象操作は彼の得意分野だ。トニーは自分がどう見られているか、常に把握している。 そういう男だから、性格の矯正はきかないし、付き合うのには苦労する。だからといって離れられるわけがないのだから、これはもう生まれ持ってのトラブル・メーカーだと割り切るしかない。 考えるべきことはひとつ。彼の抱える問題のうち、今回はどれが表面化したのか?
◇
トニーに避けられて四日目の朝、スティーブは再びD.C.のS.H.I.E.L.D.本部に出発しようとしていた。先日詰められなかった会議の再開と、クラッキング事件の詳細報告を受けるためだ。ジャービスによるとトニーはスティーブの予定を知っているようだが、ヘリの準備を終えても彼がラボ(あるいは羊水カプセルか、タワー内のいずれかの場所)から出てくることはなかった。見送りなんて大げさなことを期待しているわけではないが、今までは顔くらい見せていたはずだ。 (これじゃ、避けられてるどころか、無視されているみたいだ) そう思った瞬間、スティーブの中でトニーの抱える問題の一つに焦点が合った。
◇
ナターシャはいつもの戦闘用スーツに、儀礼的な黒いジャケットを着てS.H.I.E.L.D.の小さな応接室のひとつにいた。彼女が忙しい諜報活動の他に、S.H.I.E.L.D.本部で何の役についているのか、スティーブは知らされていなかった――だから彼女が応接室のチェストを執拗に漁っているのが何のためなのかわからなかったし、聞くこともしなかった。ナターシャも特に自分の任務に対して説明したりしない。スティーブはチェストの一番下の引き出しから順々に中を改めていくナターシャの後ろで、戦中のトロフィーなどを飾った保管棚のガラス戸に背をもたれ、組んだ腕を入れ替えたりした。 非常に言いにくいし、情けない質問だし、聞かされた彼女が良い気分になるはずがない。だがスティーブには相談できる相手が彼女しかいなかった。 「ナターシャ、その――邪魔してすまない」 「あら構わないのよ、キャップ。そこで私のお尻を見ていたいのなら、好きなだけどうぞ」 からかわれているとわかっていても赤面してしまうのは、スティーブの純潔さを表すチャームポイントだ、と、彼の恋人などはそう言うのだが――いい年をした男がみっともないと彼自身は思っていた。貧しい家庭で育ち、戦争を経験して、むしろ現代の一般人よりそういった表現には慣れているのに――おそらくこれが同年代の男からのからかいなら、いくら性的なニュアンスが含まれていようが、スティーブは眉ひとつ動かさないに違いない。ナターシャのそれはまるで姉が弟に仕掛けるいたずらのように温かみがあり、スティーブを無力な少年のような気持ちにさせた。 「違う、君は……今、任務中か? 僕がここにいても大丈夫?」 「構わないって言ったでしょ。用があるなら言って」 確かにナターシャの尻は魅力的だが、トニーの尻ほどではない――と自分の考えに、スティーブは目を閉じて首を振った。「聞きたいことがあるんだけど」 スティーブは出来るだけ、何でもないふうに装った。「僕はその、少し前からスタークのタワーに住んでいて――……」 「付き合ってるんでしょ。なあに、トニーに浮気でもされたの?」 スティーブはガラス戸から背中を離して、がくんと顎を落とした。「オー・マイ……ナット、なんでわかったんだ」 「それは、こっちの……台詞だけど」 いささか呆気にとられた表情をして、ナターシャは目的のものを見つけたのか、手のひらに収まるくらいの何かをジャケットの内ポケットに入れると、優雅に背筋を伸ばした。「トニーが浮気? ほんとに?」 「ああ、いや……多分そうなんじゃないかと……」 「この前会ったときは、あなたにでろでろのどろどろに惚れてるようにしか見えなかったけど、ああいう男は体の浮気は浮気だと思ってない節があるから、あとはキャップ、あなたの度量しだいね」 数日分の悩みを一刀両断されてしまい、スティーブは一瞬、自分の耳を疑った。音もなくソファセットの前を通り過ぎ、部屋を出て行こうとしたナターシャを慌てて呼び止める。「そ、そうじゃないんだ。浮気したと決まったわけじゃない。ただトニーの様子がこのところおかしいから、もしかしたらと思って――それで君に相談ができればと……僕はそういうのに疎いから」 「おかしいって? トニー・スタークが?」 まるでスティーブが、空を飛んでいる鳥を見て”飛べるなんておかしい”と言ったかのように、ナターシャは彼の正気を疑うような目をした。「そうだよな」 スティーブは認めた。「トニーはいつもおかしいよ。おかしいのが彼だ。何でも好きなものを食べられるのに、有機豆腐ミートなんて代物しか食べなかったり――それでいて狂ったようにチーズバーガーしか食べなかったり――それでも、何か変なんだ。僕を避けてるんだよ。通信でも顔を見せない。まる一日、どこかに行ったきりだと思ったら、今度はラボにずっとこもってる。ジャービスに彼の様子を聞こうにも、彼はトニー以外のいうことなんてきかないし、もうお手上げだ」 ナターシャはすがめたまぶたの間からスティーブを見上げると、一人掛けのソファに座った。スティーブも正面のソファに座る。彼女が長い足を組んで顎に手を当て考え込むのを、占い師の診断を仰ぐ信者のように待つ。 「ふーん……それって、いつから?」 「六日前だ。ハッキング事件の当日はまだ普通だったけど、その翌日はやたらと饒舌で……きみも付き合いが長いから、トニーが隠し事をしているときにしゃべりまくる癖、知ってるだろ」 「それを聞いたら、キャプテン、私には別の仮説が立てられるわ」 「え?」 「来て。会議の前に長官に報告しなきゃ」 ナターシャの後を追いながら、スティーブは彼女が何を考えているか、じわじわと確信した。「君はもしかして、S.H.I.E.L.D.をハッキングしたのが彼だと――」 「最初から疑ってたのよ。S.H.I.E.L.D.のネットワークに侵入できるハッカーはそう多くない。世界でも数千人ってとこ。しかもトニーには前歴がある。でもだからこそ、長官も私も今回は彼じゃないと思ってた」 「どういうことだ」 「ハッカーにはそれぞれの癖みたいなのがあるのよ。自己顕示欲の強いやつは特に。登頂成功のしるしに旗を立てるみたいに、コードにサインを入れるやつもいる。トニーのは最高に派手なサインが入ってた。今回のはまるで足跡がないの。S.H.I.E.L.D.のセキュリティでも追いきれなかった」 「トニーじゃないってことだろう?」 「前回、彼は自分でハッキングしたわけじゃなかった。あの何か、変な小さい装置を使って人工知能にやらせてたんでしょ。今回は自分でやったとしたら? 彼がMIT在学中に正体不明のハッカーがありとあらゆる国の情報機関をハッキングした事件があった。今も誰がやったかわかってないけど――」 そこまで言われてしまえば、スティーブもむやみに否定することはできなかった。 「……ハッキングされたのは一瞬なんだろう。トニーがやったのなら、どうしてずっとラボにこもってる」 「データを盗めたとしても暗号化されてるからすぐに読めるわけじゃない。じつのところ、まだ攻撃され続けてる。これはレベル5以上の職員にしか知らされていないことだけど、現在進行形でサイバー攻撃されてるわ。たぶん、復号キーを解析されてるんだと思う。非常に高度なことよ、通信に多少のラグがあるだけで、他のシステムには全く影響していない。悪意あるクラッカーやサイバーテロ集団がS.H.I.E.L.D.の運営に配慮しながらサイバー攻撃するなんて、考えられなかったけど――もしやってるのがアイアンマンなら、うなずける。理由は全く分からないけど」 ナターシャはすでに確信しているようだった。長官室の扉を叩く前に、スティーブを振り返り、にやりと笑った。 「ねえ、よかったじゃない――浮気じゃなさそう」 「それより悪いかもしれない」 スティーブはほっとしたのとうんざりしたのと、どっちの気持ちを面に出したらいいか迷いながら返した。恋人が浮気したなら、まあ結局は許すか許さないかの話で、なんやかんやでスティーブは許してしまったことだろう(ああ、簡単じゃないか、本当に)。しかし、恋人が内緒で国際平和維持組織をハッキングしていたのなら、まるで話の規模が変わってくる。 ああ、トニー、君はいったい、何をやってるんだ。 説明されても理解できないかもしれないが、僕から隠そうとするのはなぜだなんだ。 「失礼します、長官。報告しておきたいことが――」 四回目のノックと同時に扉を開け、ナターシャは緊急時にそうするように話しながら室内に入った。「現行のサイバー攻撃についてですが、スタークが関わっている可能性が――」 「報告が遅いぞ」 むっつりと不機嫌なニック・フューリーの声が響く。部屋には二人の人物が居た――長官室の物々しいデスクに座るフューリーと、その向かいに立つトニー・スタークが。 「ところで、コーヒーはまだかな?」 チャコールグレイの三つ揃えのスーツを着たトニーは、居ずまいを正すように乱れてもいないタイに触れながら言った。ちらりと一瞬だけスティーブに目をくれ、あとはわざとらしく自分の手元を注視する。「囚人にはコーヒーも出ないのか? おい、まさか、ロキにも出してやらなかった?」 「トニー、君……」 スティーブが一歩踏み出すと、ナターシャが腕を伸ばして止めた。険の強い声音でフューリーを問いただす。「どういうことです? 我々はサイバーセキュリティの訓練を受けさせられていたとでも?」 「いや、彼は今朝、自首しにきたんだ、愚かにも、自分がハッキング犯だと。目的は果たしたから理由を説明するとふざけたことを言っている。ここで君たちが来るまで拘束していた」 ナターシャの冷たい視線を、トニーは肩をすくめて受け流した。 「本当か? トニー、どうしてそんなことをしたんだ」 「ここだけの話にしてくれ」 トニーはスティーブというより、フューリーに向かって言った。「僕がこれから言うことはここにいる人間だけの耳に留めてくれ」 全く頷かない長官に向かって、トニーはため息をついて両手を落とした。「あとは、そうだな。当然、僕は無罪放免だ。だってそうだろ? わざわざバグを指摘してやったんだ。表彰されてもいいくらいだろう! タダでやってやったんだぞ!」 「タダかどうかは、私が決める」 地を這うように低い声でフューリーは言った。「放免してやるかどうかも、その話とやらを聞いてから決める。さっさと犯罪行為の理由を釈明しないなら、この場で”本当”に拘束するぞ。ウィドウ、手錠は持ってるか」 「電撃つきのやつを」 「ああ、わかった、わかった。電撃はいやだ。ナターシャ、それをしまえ。話すとも、もちろん。そのためにD.C.まで来たんだ。座っていい?」 誰も頷かなかったので、トニーは再びため息をついて、革張りのソファの背を両手でつかんだ。 「それで、ええと――僕が慈善家だってことは、皆さんご承知のことだとは思うんだが――」 「トニー」 自分でもぎょっとするくらい冷たい声で名前を呼んで、スティーブは即座に後悔したが――この場に至っても自分を無視しようとするトニーに、怒りが抑えられなかった。 トニーは大きな目を見開いて、やっとまともにスティーブを視界に入れた。こんな距離で会うのも数日ぶりだ。スティーブは早く彼の背中に両手を回したくて仕方なかったが、その後に一本背負いしない自信がなかったので、ナターシャよりも一歩後ろの位置を保った。 「……べつに話を誤魔化そうってわけじゃない。僕が慈善家だってことは、この一連の僕の”活動”に関係のあることなんだ。というより、それが理由だ」 ゆらゆら揺れるブラウンの瞳をスティーブからそらせて、トニーは話し始めた。
七日前にもトニーはS.H.I.E.L.D.に滞在していた。フューリーに頼まれていた技術提供の現状視察のためもあったが、出席予定のチャリティー・オークションのパーティがD.C.で行われるため、長官には言わないが、時間調整のために本部内をぶらぶらしていたのだ。たまに声をかけてくる職員たちに愛想よく返事をしてやったりしながら、迎えの車が来るのを待っていた。 予定が狂ったのは、たまたま見学に入ったモニタールームEに鳴り響いた警報のせいだった――アムステルダムで任務中の諜報員からのSOSだったのだが、担当の職員が遅いランチ休憩に出ていて(まったくたるんでいる!)オペレーション席に座っていたのはアカデミーを卒業したばかりの新人だった。ヘルプの職員まで警報を聞いたのは訓練以外で初めてという状態だったので、トニーは仕方なく、本当に仕方なく、子ウサギみたいに震える新人職員からヘッドマイクを譲り受け(もぎ取ったわけじゃないぞ! 絶対!)、モニターを見ながらエージェントの逃走経路を指示するという、”ジャービスごっこ”を――訂正――”人命と世界平和に関する極めて責任重大な任務”を成り代わって行ったのだ。もちろんそれは成功し、潜入先で正体がばれたまぬけなエージェントたちは無事にセーフハウスにたどり着き、新人職員たちと、ランチから戻って状況の飲み込めないまぬけな椅子の男に対し、長官への口止めをするのにも成功した。ちょっとしたシステムの変更(ほら、僕がモニターの前に座って契約外の仕事をしているところが監視カメラに映っていたら、S.H.I.E.L.D.は僕に時間給を払わなくちゃいけなくなるだろ? その手間を省いてやるために、録画映像をいじったんだ――もしかしたら。怖い顔するな。そんなような気がしてたんだ、今まで)もスムーズに成立した。問題は、そのすべてが完了するのに長編映画一本分の時間がかかったということだ。トニーの忠実な運転手は居眠りもしないで待っていたが、チャリティーに到着したのは予定時刻から一時間以上は経ったころだった。パーティが始まってからだと二時間は経過していた。それ自体は大して珍しいことではない。トニーはとにかく、パーティには遅れて到着するタイプだった(だって早く着くほうが失礼だろ?)。 しかし、その日に限って問題が発生する。セキュリティ上の都合とやらで(最近はこんなのばっかりだな)、予定開始時刻よりも大幅にチャリティー・オークションが早まったのだ。トニーが到着したのは、もうあらかたの出品が終わったあとだった。 トニーにはオークションに参加したい理由があった。今回のオークションに限ったことではない。トニーの能力のもと把握することが出来る、すべてのオークションについて、彼は常に目を光らせていた。もちろん優秀な人工知能の手も借りてだが――つまり、この世のすべてのオークションというオークションについて、トニーはある理由から気にかけていた。好事家たちの間でだけもてはやされる、貴重な珍品を集めるためではない――彼が、略奪された美術品を持ち主に返還するためのグループ、「エルピス」を支援しているからだ。 第二次世界大戦前や戦中、ヨーロッパでは多くの美術品がナチスによって略奪され、焼失を逃れたものも、いまだ多くは、ナチスと親交のあった収集家や子孫、その由来を知らないコレクターのもとで所有されている。トニーが二十代の頃に美術商から買い付けた一枚の絵画が、とあるユダヤ人女性からナチ党員が二束三文で買い取った物だと「エルピス」から連絡があったのが、彼らを支援するきっかけとなった。それ以来、トニーが独自に編み上げた捜索ネットワークを使って、「エルピス」は美術品を正当な持ち主に戻すための活動を続けている(��化財の保護は強者の義務だろ。知らなかった? いや、驚かないよ)。数年前にドイツの古アパートから千点を超す美術品が発見されたのも、「エルピス」が地元警察と協力して捜査を続けていた”おかげ”だ。時間も、根気もいる事業だが、順調だった。そして最近、「エルピス」が特に網を張っている絵画があった。東欧にナチスの古い基地が発見され、そこには宝物庫があったというのだ――トニーが調べた記録によれば、基地が建設されたと思わしき時期、運び込まれた数百点の美術品は、戦後も運び出された形跡がなかった――つまり宝物庫が無事なら、そこにあった美術品も無事だったということだ。 数百点の美術品のうち、持ち主が明確な絵画が一点あった。ユダヤ人投資家の男で、彼の祖父が所有していたが、略奪の目にあい彼自身は収容所で殺された。トニーは彼と個人的な親交もあり、特に気にかけていた。 その投資家の男がD.C.の会場にも来ていて、遅れてやってきたトニーに青い顔で詰���寄った。「”あれ”が出品されたんだ――」 興奮しすぎて呼吸困難になり、トニー美しいベルベッドのショール・カラーを掴む手にも、ろくな力が入っていなかった。「スターク、”あれ”だ――本当だ。祖父の絵画だ。ナチの秘宝だと紹介されていた。匿名の人物が競り落とした――あっという間だった――頼む、あれを取り戻してくれ――」 (なんて間の悪いことだ!) 正直なところ、トニーは今回のオークションにそれほど期待していたわけではなかった。長年隠されていた品物が出品されるとなれば、出品リストが極秘であろうと噂になる。会場に来てみてサプライズがあることなど滅多にない。それがまさかの大当たりだったとは! こんなことなら、時間つぶしにS.H.I.E.L.D.なんかを使うんじゃなかった。トニーは投資家に「落札者を探し出し、説得する」と約束し、その後の立食パーティで無礼なコラムニストを相手にさんざん子供っぽい言い合いをして、帰宅の途についた――そして、ジャービスに操縦を任せた自家用機の中で、匿名の落札者について調べたが、思うように捗らなかった。もちろん、トニーが本気になればすぐにわかることだ――しかし、ちょっとばかり酔っていたし、別に調べることもあった。そちらのほうは、タイプミスをしてジャービスに嫌味を言われるまでもなく、調べがついた。 網を張っていた絵画と同じ基地にあった美術品のうち、数点がすでに別の地域のオークションや美術商のもとに売り出されていた。
「これがどういうことか、わかるだろう」 トニーは許可をとることをやめて、二人掛けのソファの真ん中にどさりと腰かけた。デスクに両肘をついて、組んだ手の中からトニーを見下ろすS.H.I.E.L.D.の長官に、皮肉っぽく言い立てる。「公表していないが、ナチスの基地を発見、発掘したのはS.H.I.E.L.D.だろ。ナチスというより、ヒドラの元基地だったらしいな。そこにあった美術品が横流しされてるんだ。すぐに足がつくような有名なものは避けて、小品ばかり全国にばらけて売っている。素人のやり方じゃないし、僕はこれと似たようなことをやる人種を知っている。スパイだよ。スパイが物を隠すときにやる方法だ」 「自分が何を言ってるかわかってるのか」 いよいよ地獄の底から悪魔が這い出てきそうな不機嫌さで、フューリーの声はしゃがれていた。「S.H.I.E.L.D.の職員が汚職に手を染めていると、S.H.I.E.L.D.の長官に告発しているんだぞ」 「それどころの話じゃない」 トニーは鋭く言い放った。「頂いたデータを復号して、全職員の来歴を洗い直した。非常に臭い。ものすごい臭いがするぞ、ニック。二度洗いして天日干しにしても取れない臭いだ――」 懐から取り出したスマートフォンを操作する。「今、横流しに直接関わった職員の名簿をあんたのサーバーに送った。安心しろ、暗号化してある。解読はできるだろ?」 それからゆっくり立ち上がって、デスクの正面に立ち、微動だにしないフューリーを見下ろす。「……あんた自身でもう一度確認したほうがいい。今送った連中だけの話じゃないぞ。……S.H.I.E.L.D.は多くの命を救う。僕ほど有能じゃなくても、ないよりあったほうが地球にとっては良い」 「言われるまでもない」 「そうか」 勢いよく両手を合わせて乾いた音を響かせると、トニーは振り返ってスティーブを見つめた。ぐっと顎に力の入ったスティーブに、詫びるようにわずかに微笑んで、歩きながらまたフューリーを見る。「で、僕は無罪放免かな? それとも感謝状くれる?」 「帰っていいぞ。スターク。ひとりでな」 「そりゃ、寂しいね。キャプテンを借りるよ、長官。五分くらいいいだろう」 言うやいなや、トニーはナターシャの前を素通りすると、スティーブの二の腕を掴んで部屋を出ようとした。 「おい――トニー――……」 「キャップ」 ナターシャに視線で促され、スティーブはトニーの動きに逆らうのをやめた。うろんな顔つきで二人を見ているフューリーに目礼して、スティーブは長官室を後にした。
「トニー……おい、トニー!」 トニーの指紋認証で開くサーバールームがS.H.I.E.L.D.にあったとは驚きだった。もしかしたらこれも”システム変更”された一つかもしれない――トニーは内部からタッチパネルでキーを操作して、ガラス壁を不透明化させた。そのまま壁に背をもたれると、上を向いてふーっと長い息を吐く。 スティーブは壁と同様にスモークされた扉に肩で寄りかかり、無言でトニーを見つめた。 「……えっと、怒ってるよな?」 スティーブが答えないでいると、手のひらを上げたり下ろしたりしながらトニーはその場をぐるぐると歩き出した。 「きっと君は怒ってると思ってた。暗号の解析なんか一日もかからないと思ってたんだが、絵画の落札者探しも難航して――まあ見つかるのはすぐに見つかったんだが、西ヨーロッパの貴族で、これがまた、筋金入りの”スターク嫌い”でね、文字通り門前払いをくらった。最初からエルピスの奴らに接触してもらえばもうちょっと話はスムーズについたな。それでも最終的には僕の説得に応じて、返還してくれることになった――焼きたてのパンもごちそうになったしね。タワーに帰るころには解析も済んでるはずだったのに、それから数日も時間がかかって――」 「何に時間がかかっていようが、僕にはどうだっていい」 狭い池で周遊する魚のように落ち着きのない彼の肩を掴んで止める。身長差のぶんだけ見上げる瞳の大きさが恋しかった。「僕が怒ってるのは、君が何をしていたかとは関係ない。それを僕に隠していたからだ。どうして、僕に何も言わない。S.H.I.E.L.D.に関わりのあることなのに――」 「だからだよ! スティーブ……君には言えなかった。確証を掴むまで、何も」 「何をそんなに……」 「わからないのか? フューリーも気付いたかどうか」 不透明化された壁をにらみ、トニーはスティーブの太い首筋をぐっと引き寄せて顔を近づけた。「わからないのか――ヒドラの元基地から押収した品が、S.H.I.E.L.D.職員によって不正に取引された――一人の犯行じゃない。よく計画されている。それに、関わった職員の口座を調べたが、どの口座にも大金が入金された痕跡がない。……クイズ、美術品の売り上げは、誰がどこに流してるんでしょう」 「……組織としての口座があるはずだ」 「そうだ。じゃあもう一つ、クイズだ。その組織の正体は? キャップ……腐臭がしないか」 「……ヒドラがよみがえったと言いたいのか」 「いいや、そのセリフを言いたいと思ったことは、一度もない」 トニーは疲れたように額を落とし、スティーブの肩にもたれかかった。「だから黙ってたんだ」 やわらかなトニーの髪と、力なくすがってくる彼の手の感触が、スティーブの怒りといら立ちを急速に沈めていった。つまるところ、トニーはここ数日間、極めて難しい任務に単独で挑んでいた状況で――しかもそれは、本来ならばS.H.I.E.L.D.の自浄作用でもって対処しなければならない事案だった。 体調も万全とはいえないトニーが、自分を追い込んでいたのは、彼の博愛主義的な義務感と、優しさゆえだった――その事実はスティーブを切なくさせた。そしてそれを自分に隠していたのは、彼の数多く抱える問題のひとつ、彼が”リアリスト”であるせいだった。彼は常に最悪を考えてしまう。優れた頭脳が、悲観的な未来から目を逸らさせてくれないのだ。 「もしヒドラがまだこの世界に息づいているとしても」 トニーの髪に手を差し入れると、そのなめらかな冷たさに心が満たされていく。「何度でも戦って倒す。僕はただ、それだけだ」 「頼もしいな、キャプテン。前回戦ったとき、どうなったか忘れた?」 「忘れるものか。そのおかげで、今こうして、君と”こうなってる”んだ」 彼が悲観的なリアリストなら、自分は常に楽観的なリアリストでいよう。共に現実を生きればいい。たとえ一緒の未来を見ることは出来なくとも、平和を目指す心は同じなのだから。 「はは……」 かすれた吐息が頬をかすめる。これ以上のタイミングはなかった。スティーブはトニーの腰を抱き寄せてキスをした。トニーはとっくに目を閉じていた。スティーブは長い睫毛が震えているのを肌で感じながら、トニーを抱きつぶさないように自分が壁に背をつけて力を抑えた――抱き上げると怒られるので(トニーは自分の足が宙をかく感覚が好きじゃないようだ、アーマーを未装着のときは)、感情の高ぶりを表せるのは唇と、あまり器用とはいい難い舌しかなかった。 幸いにして、彼の恋人の舌は非常に器用だった。スティーブはやわらかく、温かで、自分を歓迎してくれる舌に夢中になり、恋人が夢中になると、トニーはその状態にうっとりする。うっとりして力の抜けたトニーが腕の中にいると、スティーブはまるで自分が、世界を包めるくらいに大きく、完全な存在になったように感じる。なんという幸福。なんという奇跡。 「きみが他に――見つけたのかと思った」 「何を?」 上気した頬と涙できらめく瞳がスティーブをとらえる。 「新しい恋人。それで、僕を避けているのかと……」 トニーはぴったりと抱き着いていた上体をはがして、まじまじとスティーブを見つめた。 「ファーック!? それ本気か? 僕が何だって? 新しい……」 「恋人だ。僕が間違ってた。でも口が悪いぞ、トニー」 「君が変なこと言うから――それに、それも僕の愛嬌だ」 「君の……そういうところが、心配で、憎らしくて、とても好きだ」 もう一度キスをしながら、トニーの上着を脱がそうとしているうちに、扉の外からナターシャの声が聞こえた。 「あのね、お二人さん。いくら不透明化してるからって、そんな壁にべったりくっついてちゃ、丸見えよ」 スティーブの首に腕を回し、ますます体を密着させて、トニーは言った。「キャプテン・アメリカをあと五分借りるのに、いくらかかる?」 唐突にガラスが透明になり、帯電させたリストバンドを胸の前にかかげたナターシャが、扉の前に立っているのが見えた。 「あなた、最低よ、スターク」 「なんで? 五分じゃ短すぎたか? 心配しなくても最後までしないよ、キスと軽いペッティングだけだ、五分しかもたないなんてキャップを侮辱したわけじゃな……」 「あなた、最低よ、スターク!」 「キーをショートさせるな! 僕にそれを向けるな! 頼む!」 スティーブはトニーを自分の後ろに逃がしてやって、ナターシャの白い頬にキスをした。「なんだか、いろいろとすまない。ナターシャ……」 「いいわ、彼には後で何か役に立ってもらう」 トニーがぶつぶつと文句をつぶやきながらサーバーの間を歩き、上着のシワを伸ばすさまを横目で見て、ナターシャに視線を戻すと、彼女もまた同じ視線の動きをしていたことがわかった。 「……トニーを巻き込みたくない。元気にみえるけど、リアクターの除去手術がすんだばかりで――」 「わかってるわ。S.H.I.E.L.D.の問題は、S.H.I.E.L.D.の人間が片をつける」 ナターシャの静かな湖面のような緑の目を見て、自分も同じくらい冷静に見えたらいいと思った。トニーにもナターシャにも見えないところで、握った拳の爪が掌に食い込む。怖いのは、戦いではなく、それによって失われるかもしれない現在のすべてだ。 「……もし、ヒドラが壊滅せずにいたとしたら――」 「何度だって戦って、倒せばいい」 くっと片方の唇を上げた笑い方をして、ナターシャはマニッシュに肩をすくめた。「そうなんでしょ」 「まったく、君……敵わないな。いつから聞いてたんだ」 「私は凄腕のスパイよ。重要なことは聞き逃さない」 「いちゃつくのは終わったか?」 二人のあいだにトニーが割り入った。「よし。ではこれで失礼する。不本意なタイミングではあるが――ところでナターシャ、クリントはどこにいるんだ?」 「全職員の動向をさらったばかりでしょ?」 「クリントの情報だけは奇妙に少なかったのが、不思議に思ってね。まあいい。休暇中は地球を離れて、アスガルドに招待でもされてるんだろう。キャップ……無理はするなよ。家で待ってる」 「トニー、君も」 スティーブが肩に触れると、トニーは目を細めて自分の手を重ねた。 「僕はいつでも大丈夫だ。アイアンマンだからな」 ウインクをして手を振りながら去っていくトニーに、ナターシャがうんざりした表情を向けた。「ねえ、もしかしてこの先ずっと、目の前で惚気を聞かされなきゃいけないの?」 そう言って、今度はスティーブをにらみつける。「次の恋愛相談はクリントに頼んでよ!」
◇終◇
0 notes
Text
パターソンについての考察ーFriday
頬に何かが擦れる感覚がする。羽のような、でも温かくて、もっとと頬を寄せてしまうような。心地よい感触に目を開くことができず、ふわふわと眠りの淵をさまよう。そうしているうちに、今度はまばらに生えたバッキーの髭をなぞり始めた。無精髭の上をさりさりと掠めていく何か。微睡から引き上げられたバッキーは僅かに眉間にシワを寄せて呻く。流石にそれは、
「……くすぐったい……」
もごもごと呻いて目を開けると、暗がりの中で自分を見つめるスティーブの顔があった。
「……ごめん、起こした」
「いい……もう、行く?」
まだ起き切らない頭で問いかける。確か、任務への出発は早朝だったはずだ。今が何時だか知らないが、部屋の中にまだ朝の気配はない。
「いや、まだ大丈夫。何か食べてから行こうと思って。バッキーはもう少し寝るか?」
「や、起きる……。お前、準備とかあるだろ、朝メシ、作るよ……」
なんとかそう返すと、頭に血を回すために寝転がったまま大きく伸びをした。口からんーという声が漏れて、身体中に酸素が行き渡る。起こされたのは確かだが、寝過ごすくらいなら早起きすぎるほうがマシだ。スティーブは眠気を追い払おうと格闘するバッキーを眺めて微笑んでいた。そういえば、寝起きのバッキーは言葉が幼くて可愛いと言われたことがある。そんなのお互い様、というか誰だってそんなもんだろうと思うけど。
バッキーはもう一度伸びをして身体を起こした。1人だけふにゃふにゃしているのが許せない時もあるのだ。今度はしっかりと目を開けたバッキーを見て、スティーブは小さく頷いた。
「……ありがとう、じゃあシャワーを浴びてくる」
そう言ってするりとベッドから抜け出す。ボクサーパンツだけを履いた後ろ姿には綺麗な背筋が見て取れる。その辺に散らばったTシャツを集めて寝室から出ていく時のしなやかな筋肉の動きをバッキーは眺めた。どうしてかスティーブのそれは誰よりも美しいと思う。もちろん自分の引き攣れた皮膚なんかとはそもそも比べるべくもないのだが。
(そういえばあいつ、ゆっくりしたいって言ってたか……)
夕べの言葉を思い出し、そして先ほどのバッキーが起きるまでのスティーブの行動を思い出し、その結果バッキーは朝から胸の内がむずつくような恥ずかしさに口元を押さえることになったのだった。なんて取るにたらない、ささやかな「ゆっくり」なんだろうと。
「やっぱアイツ……たまに恥ずかしいよな……」
もう少ししたらベッドから降りて顔を洗わないと。任務に発つスティーブの為にも、彼の望む朝――というにはまだ暗すぎるが――に答えてやらなくちゃいけない。
ミルクをたっぷりと使ったオムレツとトーストを食べ、結局バッキーもスティーブと連れ立って家を出ることにした。外はようやく木々の向こうが白み始めた程度で、町も人もほとんどが眠りについている。ただその中でも、ぽつぽつと窓から明かりの漏れる家たちがある。夜を迎える時と朝を迎える時、どちらにも同じ景色があるのに、夕方のそれが温かみを持つなら、早朝の空気の中に点在するそれらは清澄だ。
住民たちを起こさないような控えめなエンジン音が街を抜けていく。アベンジャーズ基地には既に調整の終わったクインジェットが待機しており、スティーブは小さなブリーフィングを終えるとナターシャと共に空へと飛び立っていった。
「……アンタも来たのか。アイツらが到着するまでは暇だぜ?」
小さくなっていく機体をラウンジの窓越しに眺めていると、後ろからサムの声がした。
「起きちまったんだよ……それを言うならお前だってそうだろ」
「オレは今から朝飯とか食う」
その言葉にふうんと返してサムの方を見ると、既に彼は振り向いてキッチンへと向かおうとしていた。朝の挨拶にしては随分だが、そういうところが彼らしい。サムもバッキーもスティーブたちが任務に当たっている間は基地で待機することになっている。基地内の居住スペースに滞在しているサムこそ、もう少しゆっくり起きてきても問題ないだろうに。
バッキーは軽く息を吐き、自身もコーヒーを淹れようとキッチンスペースに足を向ける。するとちょうど良くサムが顔を上げ、あまりにぶっきらぼうな顔でコーヒー飲むかと聞いてくるのだった。
「そういえばさ」
サムの朝食を見守り、管制室のモニターを眺めたりラウンジで過ごしたりしているうちに時刻はランチの時間になっていた。スティーブたちの作戦は進行中だが、かといって自分たちがモニターにひっついてできることなどそう多くはない。新たな暗号やデータが発見されればバッキーの出番であり、彼らに何かあった場合はサムがすぐサポートに向かうが、つまり今回の任務における待機なんてものはそんなレベルだ。大人しく昼食を取ることにした2人はソファにかけてサンドイッチを頬張っていた。
バッキーが斜め前のサムに声をかけると、彼はベーコンを噛みちぎっていた顔を上げる。咀嚼を急ぐ様子もない相手に、バッキーもまた気にせずに会話を続けた。
「この前スティーブと映画の話をしたんだろ」
「……あー、ああ、オレが勧めたやつか」
「それ」
それがさ、と続けようとしてバッキーはつと口を閉じた。そのまま窓の向こうへと視線を投げる。何となくサムに会ったら話そうとしていた気がするのに、話し出してみるとそうでもなかったことに気づいたような。口に出した途端、見切り発車のような浮遊感がバッキーを襲った。
「……それが?」
瞬きを繰り返すバッキーに向け、サムが続きを促した。
「ああ、うん……。スティーブは何て言ってた?」
「は? 面白かったって言ってたぞ。古き良きアメリカだなとか。……なんだよ、一緒に見たんじゃないのか」
サムが眉を潜める。
「いや、一緒に見たよ。面白かった、教えてくれてありがとうな」
そうは言うものの、バッキーの表情は今ひとつ煮え切らない。
「……あんまり面白かったって顔じゃないけどな」
「うるさい、顔は元からこんなだ……いや、面白かったよマジで」
言い淀んでいるのは、決して言いにくいことがあるからじゃない。なんとなく正しく言える気がしないだけだ。バッキーは両手に収めたマグをことんことんと傾けては中のコーヒーを揺らした。
「スティーブがさ、素直には信じきれないって言ってて」
「……スティーブが?」
「その、この映画が大事にされてるのは良いことだとも言ってた。けど……多分、あいつが言ってるのは、良い奴は報われるっていう、そういうとこなんだと思う」
「……へえ」
「もちろんファンタジーだってわかってるけど……。でさ、スティーブはそう言ってて。でもオレは、あの終わりを見ててさ……スティーブもこうなるべきだなって思ったんだ」
その言葉に、サムが首を傾げる。バッキーは続けて補う。
「自分の人生とか、幸せとか犠牲にして人助けしてさ、いろいろあったけど結局は報われるんだ。オレはすごく嬉しかったし、スティーブみたいだって思った。こいつがこんなに幸せになるなら、スティーブにだってきっとこれくらいの幸せが似合うって」
「……今のスティーブは幸せに見えないって?」
「そういう言い方はずるい」
バッキーが眉間に皺を寄せると、相手もそれをわかっていたのか意地悪げに釣り上げた眉をすっと下ろした。
今のスティーブが幸せじゃないなんて、自分は決して言えない。ワカンダにいた頃から、そしてアメリカに戻ってきてからも、バッキーが平穏に暮らせるように内に外にと奔走し、一軒家まで見つけてきた男のことを。2人で初めてソファに腰かけた時に、心の底から漏れ出たような安堵の息を。それだけの想いをかけて作り上げた今の生活のなかで、スティーブがどんな風に笑うのかを。それらを間近で見てきたバッキーは、たとえ胸の内がどうあろうとスティーブが幸せじゃないなんて言えるはずがないのだ。それでもそんなことを思うのは、おそらくバッキーがスティーブの幸せの形を知ってしまっているから。かつてスティーブが望んだであろう、ハッピーエンドに似合う光景を想像できてしまうから。だからなんとなく、彼にはゴールがあると、そう感じてしまうのだ。
しかしそれを上手く言葉にできるはずもなく、バッキーはマグカップを手の中で遊ばせてから呟いた。
「……まあ、そこそこ楽しくやってる。今のは映画を見て、なんとなくそう思ったってだけだよ」
そう言ってコーヒーを啜る。冷め始めたそれは少し酸味が強い。
サムはしばらくバッキーの顔を眺めてからふうんと呟いた。
「まあ、誰だってキャップには幸せになって欲しいって思うよ」
「ああ」
「オレには、今でも十分幸せそうに見えるけどな」
「……うん」
そう言ったきり、サムはサンドイッチの残りに意識を戻したようだった。
変な方向に話を振った挙句、言葉を呑み込んだ自分に合わせてくれる。バッキーの浮遊感は消えてはいないが、言葉にしただけでほんの少し気持ちが軽くなったような気がした。こいつも大概なお人好しだ。
情報は入手したが気になることがあるから別拠点によっていく。帰投は日曜になるだろうとスティーブから連絡があったのはその日の夕方のことだった。
家に戻り、夕食のチキンを焼き始める。1人だから適当にパスタでいいかと思った矢先、昨日も同じものを食べたことを思い出したのだ。同じメニューで構わないという妥協と、なんとなく気が乗らない自分とを天秤にかけた結果、冷蔵庫を覗いたバッキーはワカンダで覚えた一番簡単な料理を作ることにした。
フライパンで両面を焼き、残った油にニンニクとアンチョビをいれ、乾燥バジルの瓶を大きく一振り。塊で落ちてきたバジルが細かく泡立つ油の上に絨毯のように広がった。誰かをもてなしたり、考え事をしたりするときのものではなく、ただ単に胃を満たすだけの料理。10分で完成した食事を終えても、時刻はまだ20時にすらなっていなかった。
(……シャワーして、本読んで、22時か……寝るか)
バッキーはその通りに行動し、22時にはペーパーバックを置いて灯りを消した。明日はもうちょっと手間をかけたものをつくろう。そして習慣で横たわってしまったスティーブの部屋のベッドについても。キングサイズのベッドに1人なんて、2日もやるもんじゃない。明日は自分の部屋で眠ろう。
目を覆うようにカバーを引き上げバッキーは目を閉じた。彼の金曜日は雪の夜のようにひっそりと幕を下ろした。
0 notes
Text
【発売前レビュー】GLOW(グロー)2019年10月号《特別付録》大人の洒落眉メイク4点セット

2019年8月28日(水)発売のGLOW(グロー)2019年10月号《特別付録》大人の洒落眉メイク4点セットを、出版社様のご厚意でお譲りいただきましたので、いち早く「ふろく.life」でご紹介します。 ※発売前の見本品のため、発売後の商品と違いが出る場合がありますのでご了承ください

大人の洒落眉メイク4点セットはどんな付録?
秋冬の洒落眉&アイメイクのマストハブが勢揃い! 1.ミラー付き 10色パレット 容量(約)各1.1g 2.Wエンドアイブロウブラシ 長さ 13.8cm 3.アイブロウリキッド 容量(約)0.8g 4.アイブロウマスカラ 容量(約)3g 宝島社オフィシャルより

原産国は?成分は?

<製造国> 中国 MADE IN CHINA <10色パレット成分>

<アイブロウリキッド成分>

<アイブロウマスカラ成分>

付録ではどれくらいの容量入り? <容量> 1.アイブロウリキッド 0.8g 2.アイブロウマスカラ 3g 3.ミラー付き 10色パレット 各1.1g

<サイズ感> 10色カラーパレット・・A6横向きぴったりの長さ アイブロウリキッド・・B7サイズ横向きよりやや短めの長さ アイブロウマスカラ・・A7サイズ縦向きぴったりの長さ

付録を試してみた感想は? ☆10色パレット 開封するとミラー・アイシャドウパレットに保護フィルムがついていました。 中に一緒に入っているブラシはキャップなし。 パレットは全部で10色、手前のベージュカラーから奥に向けて カラーが「薄め→濃いめ」に配置されています。

カラー詳細の記述がなかったので、大体の伝わりそうな色味を筆者目線で。 ①・・マットなホワイトベージュ ②・・ラメ入りベージュゴールド ③・・ラメ入りシルバーゴールド ④・・マットなブラウン ⑤・・マットなオレンジブラウン

⑥・・マットなオレンジ ⑦・・ラメ入りブラウンゴールド ⑧・・マットな濃いブラウン ⑨・・マットなピンクブラウン ⑩・・マットな赤みブラウン

指でカラーを取り、腕に2度塗りしてみました。 薄めかな?と思った①のベージュカラーでさえも ハッキリと色がわかるほど発色が良く、1度塗りでも十分だと思いました。 上から下に、指先にて一筆で塗りましたが、下までキレイにカラーがつくほど なめらかな伸び具合でした。

そのあとすぐに、ウエットティッシュ(水99%タイプ)で ギュッと拭き取ってみたところ、①と②のカラーはほぼ消えましたが 他のカラーはしっかりと残っていました。

パレットについているミラーはアクリル製で、はめ込まれているタイプ。 (軽い力で爪を使って剥がそうとしてみましたが、取れませんでした。でも無理やりやれば取れそうな雰囲気)

ミラーとケースの隙間にアクリル独特のチープさが垣間見えました。 歪み、割れ、傷はありません。 横長なので、両眉・両目をバランスよく見ることができました。

☆Wエンドアイブロウブラシ アイシャドウチップと同じ作りの方と 斜めにカットされたブラシが1本になっています。 チップの方は100円ショップのチップに比べると やや厚みがあり、柔らかさ・指で引っ張った際の伸び方は一般的なチップと遜色なし。

ブラシは、毛束の厚さが3mmで、まつげほどの細くて柔らかな毛がフサフサと密集しています。 適度なコシもあり、試しにまぶたに当てて動かすとサラサラと流れるような感触で気持ちよかったです。

☆アイブロウリキッド リキッドアイライナーと同じ見た目。 まずはウェットティッシュに伸ばしたら意外と濃くリキッドが発色したので驚き。 これを眉に描くとゴルゴ状態になるのでは・・と不安に。

しかし腕に描いてみると肌となじんで薄くなったので安心。 力加減で濃淡は調整できます。線の細さも自由自在。 手持ちの3mm極細リキッドアイライナーと同じ細さの筆先で扱いやすかったです。

☆アイブロウマスカラ 筆者手持ちのケイト・アイブロウマスカラと比べると、 ブラシ部分が短くて太いです。

ツヤ眉とはどんなものか?とドキドキしながら 手にのせてみて、まず感じたのが「あれ?透明?」でした。 しかし、よ~く見ると小さなラメがちりばめられていて、光が当たるとホロラメのように キラキラと輝いている!!これが“ツヤ眉”の正体か・・!と驚きました。

手の上だと少し分かりにくかったので、 髪の毛に塗ってみました。(眉毛は生えそろってないため諦めました) 塗ったところ全体に潤い感とオーロラのごとくキラキラと輝くラメ! 眉毛を完璧に生やして塗りたい、と思いました。

この付録、アリ?ナシ?
あり! 「大人の」というネーミングだけあって、使い勝手の良いメジャーで無難なカラーパレット! 秋冬っぽいブラウンオレンジ系がたくさん、おそらく隣同士で塗ればグラデーションも簡単にできるのではないかなぁと思いました。 ツヤ眉は絶対キラキラしておしゃれそう!眉毛に早く塗りたい! リキッドアイブロウは使用したことがないので少し不安ですが、筆が細く自由自在に描けるので不器用な筆者もキレイな縁取りができそうです。 10色パレットの発色の良さはアイシャドウやアイブロウだけで��く、チークやアイライン使いもできるので優秀パレットだと思いました!
購入した付録つき雑誌/ムック

GLOW 2019年10月号 発売日:2019年8月28日(水) 宝島社 Read the full article
0 notes
Text
余市岳ビバーク登山
みなさん、こんにちは。
前回ブログの赤井川滞在記の翌日、余市岳登山の様子をご紹介します。

出発地点は、キロロスキー場駐車場横の林道からスタートです。

キャップはNotch Classic Adjustable Operator。
バイザーに切り込みがデザインされ、
サングラスなどのアイウェアをかけた状態でも帽子を深くかぶれます。
実際に使ってみますと、感心するほどフィット感が良いです。
OAKLEYのサングラスやスポーツアイウエアなど、
横にボリュームがあるデザインのサングラスと相性が良いです。

Notch Classic Adjustable Operator Black Color Free Size ¥3,672
*こちらの商品はFLHQ店頭かキャプテントムのウエブショップにて販売中。

コットン100%素材は快適な通気性と、
雨天時には糸が水分を含んで膨張することで
生地の耐水性能が上がるために雨にも強いです。

ピリングを起こしにくいベルクロでサイズ調整ができます。

フロントのベルクロベースにお好みのパッチを貼り付けられます。

SAPPOROワッペン ¥864
キャプテントムオリジナルのワッペン。
キャプテントムとFLHQでしか売っていませんので実は、レアなワッペン。
札幌のお土産にもオススメです。(^^)

林道を歩いていくと、連絡用の新しいゴンドラが建設中でした。

余市岳登山口方面に向かいます。

林道ではトレイルランニングの方とすれ違いました。

今回のシューズもARC’TERYXのテクニカルアプローチシューズ、
Konseal FL Gore-Tex Black/Pilot Color ¥23,760

林道から樹林の合間に余市岳が見えます。
1時間ほど歩くと、林道の先にあるスキー場に出ます。
標高1,000以上は雲に包まれています。

登山道入り口にはクマ出没注意の看板。

登山道へ進みます。

沢を渡る箇所があります。

ここで小休止しました。
携帯防虫器の”パワー森林香”を着火します。
キャンプサイド以外でも、バックパックに吊り下げておきます。
休憩時にも虫害を防ぎます。

この地図の赤井川村表記の”村”部分が現在地。
ZERO MILLITARY PROTRACTOR は使ってみると、
距離や方向の確認が簡単なので重宝しました。
この地図は2万5千分の1の縮尺なので、
この三角形内の定規の一辺は1,000m。

現在地や地図上のポイントに分度器を充てると、
行きたい方向の方位が瞬時に判ります。
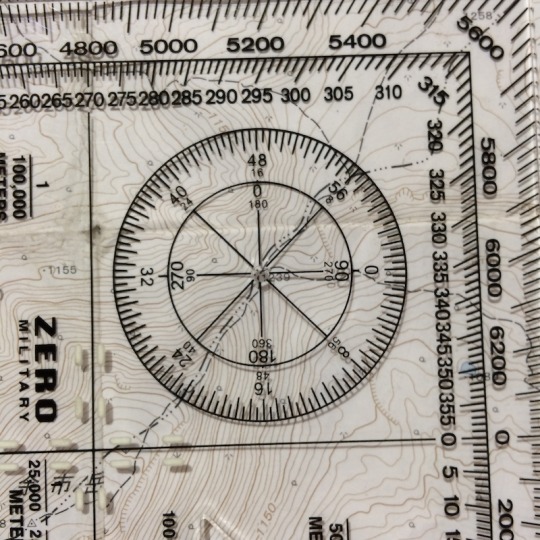
クリアなので、等高線による地形の把握も判りやすいです。
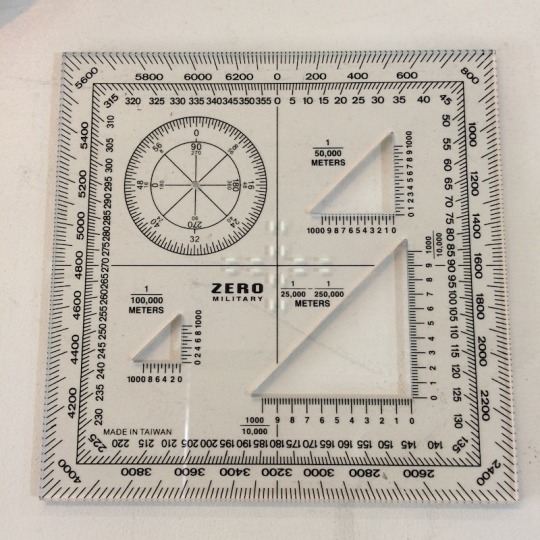
ZERO ミリタリープロトラクター ¥864
中心部に蓄光塗料のN夜光(ルミノーバ)が塗布されています。
経度、緯度や距離(マイル)が図れる製図作成器具です。
外周にはミル目盛り
※1周(360度)を6400に分割した値がミル目盛です。

ウインターシーズンには、この斜面の裏側辺りをよく滑っているエリア。

こんな登山道を登っていきます。

雲が湧いたり、抜��たり、風もあります。

振り返ると、キロロスキー場のセンターベースが見えます。

分岐点に到着。

ハイマツ越しに余市岳が見えてきます。

少し下りながら進みます。

こんな古い看板もあります。

毎年滑っている余市岳の南東面に広がる大斜面。

余市岳コルの分岐点。
定山渓方面の登山道は荒廃、通行不能ですって。
通行禁止ではないようですが、
笹ヤブに覆われて道が不明瞭なのと道の崩壊は問題ではなく、
クマとの遭遇が考えられるので、複数名での突破が妥当と判断。
*道が無い地形を踏破するスキルが無い人は行くべきではないです。

コルからは、249mの登りです。
山頂付近の登山道は前日降った雨による水が流れていました。

偽山頂に設置されている看板。

遭難碑のケルンが建てられていました。
遭難した年に私が生まれてます。

キロロ駐車場より3時間で余市岳山頂に到着。
この標識は倒れていましたが、石を組んで建てました。

山頂からの眺めは視界悪し。

昼飯はフリーズドライの、柔麺。

柚子風味の塩味が美味しい。

よく見てみると、バックパックには
赤く小さくて素早く動くダニが数匹うごめいていました。
クリーンなボディのバックパックはブッシュや岩に引っかからず
ダニが隠れることもできず、
完全防水なので内部にも侵入させず、安心です。
私が、バリエーションで使うARC’TERYX ALPHA FL 45バックパックは
それが理由だったりします。
ALPHA FL 45は、今月末には再入荷します。

登山道を少し離れた辺りには、一面のエゾオヤマリンドウの群落。
youtube
余市岳山頂のハイマツ樹林の中を歩いてみました。

ソフトシェルジャケット Tilak Noshaq Mig Jacketは、
踏み跡のない藪こぎに大活躍でした。
肘は耐久性の高いエルボーパッチで補強され、
全てのポケット内部はメッシュ構造となっていますので、
全て開放した高い排気性能を発揮して温度、湿度の調整ができ、
ベンチレーションから虫の侵入を許しません。
↑これが一番重要。

山頂から少し高度を佐方樹林帯に入ったところで雨が降り出します。
素早くシェルターのタープを設営して雨宿り。

登山道を流れる水を汲みます。

泥水なので、水の色は黄色。
水分確保できました。

雨が強く降り出してきましたが、
Noshaq Mig Jacket の高い撥水性能は水分を弾いてくれます。

近くでビバークポイントを探します。
今回はハンモックシェルターを装備してきましたので、
ハンモックを吊るせる丁度よい木が生えているか?
クマの痕跡が無いか?
しっかりとクマの食痕がありました。
地面を掘った跡です。
前日に降った雨で崩れた土の状態なので2日くらい前。

もうひとつ、クマの新しい食痕があります。
ここは、クマの餌場だ!
余市岳山頂付近はクマの行動範囲でした。

シェルターと汲んだ水をパッキングして、移動開始です。
キロロスキー場のゴンドラ山頂駅の手前にある
東屋へ避難することにしました。

辺り一面の笹ヤブの中に登山道が開拓されています。
youtube
余市岳からキロロスキースキー場へと向かう登山道の様子。

東屋へ到着。
浄水器で汲んできた水を濾過しますが、
浄水した水の色も泥の色。(^^)
水を得られただけでも良い環境。

晴れることはありませんでした。

もらったじゃがいもをカットします。

夕食はフリーズドライの「畑のカレー」とレトルトご飯、
牛すじ煮込み、じゃがいも。

コーヒーを淹れます。
VARGO 1,3L TITANIUM POTは蓋を外さずに細く湯を注げます。

濡れたシューズと靴下を脱いでZ SEATに足を置きます。

小分けタイプのレトルトご飯はこのようにク��カーに収めやすく、
150gx2で、300gのご飯が作れます。
その隙間にカットしたじゃがいも。

じゃがいもが茹で上がりました。

骨折用のサムスプリメントは風除けにもなりました。

ご飯の湯煎が完了したので、フリーズドライのカレーに湯を注ぎます。

カレーの完成。

小分けパックのご飯は全部投入。

カレーライスのカレーとご飯の分量配合も良いですね。

カレーライス食べたらレトルトパックの牛すじ煮込みを温めます。

ハンモック内部で食べます。
外は寒くて居られません。

じゃがいもも、ひとかけらを煮込みにトッピングして食べました。

ハンモックシェルター内はLEDライトの照明。
youtube
時刻は20時30分頃の様子です。
ハンモックは上部がメッシュなので、外気温そのままで風の侵入もあり、
過酷な寒さを一晩耐えなければなりませんでした。
youtube
時刻は24時30分。
8月後半の北海道余市岳付近の標高1,200m地点で
強風に晒されているハンモック内部は寒い!
経験値から、死ぬ環境では無いと判断していますが、
���まに震えが止まらない時があるくらいの、
低体温症ギリギリの状態で一晩過ごしました。
youtube
朝、5時13分のハンモックシェルター内の様子。
風はますます強くなってきました。
この後、5時30分に撤収して下山開始します。
バッテリーの残量が殆どなくなってきましたので、
画像は撮れませんでした。

7時27分、スキー場の林道に戻ってきました。
振り返ると、標高1,000mより上は雲の中。
下山に用した時間は2時間弱です。
林道歩き約1時間で8時30分頃、キロロスキー場センターへ到着。
9時30分発の小樽築港雪の無料シャトルバスに乗車して、
小樽築港駅からJRで札幌駅へ。
FLHQには11時20分頃帰着しました。
0 notes