#キリスト者よ、この日を刻みこめ
Explore tagged Tumblr posts
Text
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和七年(2025年)2月28日(金曜日)
通巻第8673号
アメリカの大學は社会主義の培養器
白人原罪論をおしえて若者を洗脳している
*************************
アメリカの大學で何を教えているのか。
或る時、若いアメリカ人たちと話していて彼らが『アメリカの歴史は恥』「白人原罪論」に脳幹がすっかり侵されていることを発見して愕然となった。それも四半世紀前である。
108のアメリカの大學に孔子学院があった。ギャバード国家情報長官が「CNNはスパイのプロパガンダ部門だ」と批判したが、大學もそうだったのか。
或る大学教授は「大学は社会主義の保育園」と呼んだ。
政府資金による 大学はすべて社会主義的な偏向を免れない仕組みになったおり、社会主義の素晴らしさを教える一方で自由市場資本主義の「欠陥」について訓示を垂れる。なぜボストンやNY、シカゴなどの大學で社会主義のバニー・サンダース上院議員や極左のリズ・ウォーレンに人気があるのか、カリフォルニアの若者が左翼小児病患者のような政治家に未来を託するのか、その背景に大學の偏向教育がある。
トランプが教育省解体を獅子吼しているのも、現在のアメリカの大学の殆どが、社会主義の培養器となっているからだ。ま、日本の大學も変わりないけど、授業中、寝ている学生が多いので思想的悪影響をアメリカほどは受けない。
多額の政府補助金を受けとる非営利の私立大学が事実上の州立大学となっている。大学経営には民間企業のように株主からの圧力もない上、社会の常識にまったく無知である。
大学理事会は、管理者の決定を承認するイエスマンか幇間、茶坊主ばかりで、トップの遣り方に反対することは社会的な地位を失うという無言の圧力、もしくは幻影に怯えている。そう、大學の理事は地域の名士なのだ。
大学の理事会は、批判者を人種差別主義者や性差別主義者と呼び、DEIを承認させた。これは全体主義である。大学の研究の多くは政府資金で行われているため、「政府を批判する紀要」などを出版しないよう、神経を尖らせる。露骨に出版を妨害し保守系教授らをそれとなく大學から追い出す。
こうして大学教員の極左偏向は、システマティックなのだ。
まるでルーマニアの大統領選挙で当選した保守派を、TIKTOKをロシアが利用したでっち上げの結果などとして選挙結果を認めず、あげくにクーデターを策謀していたなどとして逮捕する暴挙(一晩で保釈したが)、本当の当選者をほうむるというキューバやベラルーシ並みの政治を展開しているが、あれとどう違うのか。
選挙運動中、ジョルジェスクはルーマニアの地政学的非同盟と主権を強調していた。
まっとうなことを言っていたのだ。また、NATOとEUに対しての姿勢は「彼らがブカレストに対する約束を尊重する範囲内で」のみ尊重すると述べた。ジョルジェスクは「キエフに対するルーマニアの軍事援助を停止する」と約束した。
ミュンヘン安全保障会議で演説したJ・D・ヴァンス副大統領は、ルーマニアの「古くから定着している利害関係者」の一部が「誤報や偽情報といったソ連時代の醜い言葉」を使って自らの利益を確保し、 「別の視点」を持つ政治家が権力を握るのを阻止していると示唆した。
▼無神論の蔓延がアメリカ人の精神風土を荒廃させた
もうひとつ深刻な問題はアメリカ社会の分断が「神の不在」によって引き起こされてことだ。
ピュー・リサーチセンターの直近の調査結果では「キリスト教徒」を自認するアメリカ人は62%に激減していた。2014年から9ポイント減少した。
「無宗教」と答えたのが29%、イスラム教徒を含む他宗教を信じる人の割合は7%だった。
信仰心の篤い人のうち61%が共和党支持者だった。民主党支持者は32%だった・
ニーチェが神が死んだといったのは教会の権力機構への不信でありキリストそのものを否定してはいない。アメリカ人がニヒリズムに酔うのは勝手だが、社会全体をゆがめつつあるのも事実である。
7 notes
·
View notes
Quote
(CNN) 最後の電話は30秒ほどだった。挨拶(あいさつ)に続いて安否を気遣う言葉をかけるのがやっとだった。しかしパレスチナ自治区ガザで暮らす少数派のキリスト教徒にとって、ローマ教皇フランシスコからの電話は、戦争の恐怖の中で輝き続ける一筋の光だった。 1年半前に戦争が始まって以来、教皇は毎日午後8時ごろ、ガザ地区唯一のカトリック教会、ホーリーファミリー教会に電話をかけた。ガブリエル・ロマネリ神父がCNNに語ったところでは、大抵は15分ほどの電話で、教皇は同教会の指導者や教会に身を寄せているパレスチナ人と話をしていた。 パレスチナ人にとって、ガザが忘れ去られていないことをいつも思い起こさせてくれる電話だった。 「彼は父のような存在で、私たちのすぐ近くにいてくれる」「戦争の間、この恐ろしい戦争の間ずっと、1年半以上も私たちに電話をかけ続け、平和を願ってガザの人々全員を祝福してくれた」とロマネリ神父は振り返る。 フランシスコ教皇は最初から、この戦争の終結を繰り返し訴え、イスラエルによるガザ包囲を公然と批判した。亡くなる前日のイースター(復活祭)のメッセージでは「平和の光が聖なる地と世界中を照らしますように」と祈った。 教皇のメッセージは続く。「私はガザの人々、特にキリスト教徒のことを思っています。そこでは恐ろしい衝突が続いて死と破壊を引き起こし、悲惨な人道状況をもたらしています」「戦争の当事者に訴えます。停戦を呼びかけ、人質を解放し、平和な未来を希求する飢えた人々を助けてください!」 ホーリーファミリー教会は、ガザで少数派のキリスト教徒の避難所になり、中庭は仮設テントで埋まっている。同教会やガザ保健省によると、キリスト教徒はこれまでに約20人がイスラエルの攻撃によって死亡した。教会にはイスラム教徒の親子も身を寄せているという。 「教皇は普通の人ではなかった」と信者のムサ・アントーンさんは回想する。「彼はキリスト教とイスラム教の両方を探求する信仰の人だった」 教皇の死を悼むガザのキリスト教徒/Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images via CNN Newsource 教皇の死を悼むガザのキリスト教徒/Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images via CNN Newsource フランシスコ教皇は長年にわたってガザのキリスト教徒に力を与えてくれたとアントーンさんは言う。「ガザのみんなのことを心配し、キリスト教徒がガザを離れないよう、安心と力を与えてくれた」。かつて数千人いたキリスト教徒は次々にガザを離れ、数は縮小した。それでも教皇に支えられて存続してきたという。 「彼の肉体は失われても、心が失われることはない」とアントーンさんは力を込める。 フランシスコ教皇は2014年5月にパレスチナ自治区ヨルダン川西岸を訪れた。ガザ��問はかなわなかったが、「子どもたちを心配する父親のように」(ホーリーファミリー教会)ガザを気遣ってくれたという。 「彼はいつも私たちの恐怖をやわらげようとしてくれた。怖がらなくていい、自分が付いている、私たちのために祈っている、そして私たちも皆のために祈りなさいと」。ジョージー・アントーン神父はCNNにそう語った。 世界のカトリック人口はおよそ14億人。ガザに残るキリスト教徒は1400人以下で、カトリック信者はさらに少ない。イスラム教徒が圧倒的多数を占めるパレスチナ社会ではほとんど見えないほどの少数派だ。フランシスコ教皇が、世界の信者の0.0001%に満たないガザの信者を見過ごすことも、電話の回数を減らすこともできていたはずだった。 しかし教皇はそうしなかった。 重体となって入院している時でさえ、フランシスコ教皇からの電話は続いた。最後の電話は19日だった。いつもの時刻にかかってきた電話は1分も続かなかった。ロマネリ神父は言う。 「あれほど具合が悪かったのに、どうしてもいつも通り私たちに電話すると言い張った」
死の直前まで毎晩の電話、フランシスコ教皇がガザの教会に残した希望の光 - CNN.co.jp
4 notes
·
View notes
Text
新ローマ教皇、過去にトランプ氏とバンス氏を批判 https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1746762236/
1 名前:少考さん ★[] 投稿日:2025/05/09(金) 12:43:56.65 ID:gzgzcEDW9 ロイター https://jp.reuters.com/world/us/VTXXEXTCYRIJFM73HAWI6ZBFKM-2025-05-09/
Jeff Mason, Jasper Ward 2025年5月9日午前 10:06
[ワシントン 8日 ロイター] - 新ローマ教皇に選出されて「レオ14世」を名乗るロバート・フランシス・プレボスト枢機卿が以前、トランプ米大統領��バンス副大統領を批判していたことが同枢機卿のXへの投稿で明らかになった。
プレボスト氏は今年2月、「JD・バンスは間違っている。キリストはわれわれに他人への愛を等級付けするよう求めてはいない」と題する文章を改めて投稿した。
トランプ氏と中米エルサルバドルのブケレ大統領は4月に会談し、米国からエルサルバドルに移送する犯罪組織メンバーを、人権侵害が行われているとされる刑務所に収監することについて協議した。
その際、プレボスト氏は「苦難が分からないのか」などと投稿した。
(略)
※全文はソースで。
44 名前:名無しどんぶらこ[sage] 投稿日:2025/05/09(金) 13:03:10.36 ID:UUPkb2ho0 [1/2] バチカンが解体されんことには駄目だろうな
45 名前:名無しどんぶらこ[sage] 投稿日:2025/05/09(金) 13:03:19.09 ID:NIQBd3th0 バチカン市国に不法移民や難民を大量に送りつけてやれ 神の寛容さとは何かを見せてくれるはず
74 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 13:24:10.75 ID:TxPClp740 [4/9] >>45 それが、移民を拒否するのは「大罪」だとか、 「困っている難民はキリストその人なのです」 「裁きの日」がどうのこうのと 聖書を引用して説教する。
それを聞くとキリスト教徒はすごい罪悪感を植えつけられる。 地獄落ちの恐怖がある。
キリスト教国が移民を受け入れるのはそういう背景もあるとおもう。 ドイツのメルケルも牧師の娘だった。
それに対抗するトランプ氏やバンス氏は きたぞ我らのウルトラマンだ!
97 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 13:39:56.45 ID:yJJmkkIV0 [2/7] >>74 もう欧米では カトリックを信仰している人がガタ減り 日本みたいななんちゃって仏教 みたいな人ばかりになってる。
カトリックがリベラルを推せば、 じゃあカトリックやーめたがさらに進むだけ 結構今回の教皇人事詰んでるよ
75 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 13:24:43.37 ID:6qpFuwVv0 [1/8] >>1 1 フランシスコ レオを次の教皇候補に 2 フランシスコ、レオを人事責任者ポストに 3 2人で、フランシスコ派の枢機卿をどんどん選ぶ、その割合70%に 4 コンクラーベで無事レオ選出 5 レオ フランシスコ路線継承
リベラルがお得意な戦法
143 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 14:07:47.30 ID:TxPClp740 [7/9] >>75 その間保守派は どんどん追い出されたようですね。左遷か。 破門された人もいました。ヴィガノ大司教。
145 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 14:12:15.12 ID:SROhg5cA0 [12/18] >>143 だって、そいつ教皇フランシスコを 「偽の預言者」「サタンのしもべ」と攻撃したんでしょ?w
159 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 15:16:43.09 ID:TxPClp740 [8/9] >>145 教皇も保守派を叩いていたし攻撃していた印象w
『「教皇フランシスコ」こと偽預言者ベルゴリオの正体』 という本もあるけれど、 最初から保守伝統主義者にはそう呼ばれていた。 イルミナティとか。
あのヨハネ・パウロ2世でさえ、 コーランにキスしたとかいろいろで、 伝統主義者から叩かれていたから、 教皇フランシスコには耐えられないでしょう。
偽預言者と言ってくれてスッキリ、 だとおもうw
79 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 13:27:53.94 ID:XlC+Mpr30 トランプと バチバチにやり合ってほしいなw
84 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 13:30:09.99 ID:SROhg5cA0 [4/18] >>79 トランプなんて、もうすぐ消えていくやつなんだから、 教皇がそんなのと「やり合う」必要はないよ 無視するんが一番いい
92 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 13:37:25.56 ID:yJJmkkIV0 [1/7] >>84 リベラルバカの教皇は、 愛国派ポピュリズムが支持を急速に広げている欧米と相容れない 結局、カトリック離れがさらに進み、カトリックは途上国の宗教になる。
98 名前:名無しどんぶらこ[sage] 投稿日:2025/05/09(金) 13:40:36.33 ID:daPLsdpO0 >>92 有象無象の怪しいカルトだらけの プロテスタント全員合わせてもカトリックに及ばない 寝言は寝て言え
107 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 13:46:29.62 ID:yJJmkkIV0 [6/7] >>98 欧米の深刻なカトリック離れも知らない開きメクラさん(笑)
181 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 16:08:04.70 ID:+HuAgbsz0 [1/2] 英国のチャンネルでこの人選を 天才的と言っていたのはこのことだったのかw コメントみたら、面白いのがあった。
アメリカが世界覇権を握っているうちは アメリカから教皇を選出しない暗黙の了解があったと。 そしていまアメリカから選ばれた。
つまり覇権国家ではなくなったとバチカンが認めたと。w ほんまにそうだよなw トランプ ププッ
184 名前:名無しどんぶらこ[] 投稿日:2025/05/09(金) 16:34:21.09 ID:hoL1TQRD0 [2/2] >>181 逆だと思うぞ 覇権を握られたから 大人しくアメリカから選出したと思ってる もうカトリックは悪行が酷くて耐えられないんだよ 変えていくか解散するしかないから
3 notes
·
View notes
Text
キリストの身体
この世に生を受けたこの身体ほど真我に近いものはない。日頃、食べ、飲み、息をして、風呂に入り、生活し起きている間は誰も否定できない。瞑想や死や寝ている間は『精神世界』の霊的個性の自己同一性が重要である。真我は死を超越するエネルギーであり認識を通して帰還の道となるー。
魂
神の下では、誰しもが平等に大切である。誰もが救われたいと望み、貧しさや生活の困窮の中で日々の生活の困難に直面する。問題は生きるための権利と義務が煩雑で複雑である事である。簡素で、素朴で、然し、安定した生活が大切であり、其れが保証されるべき『共同体』国家と国民の義務であるー。
属性
職業の適性が何よりも優先される。得意ではないことは其れが何れ程、力を注いでも、見返りの見込みのないものである。其れほど適性は大切である。『ケセラセラ』我々が望むものや、なりたいものは単なる願望にすぎず、あるがままに、無条件にそう在る事ではない。国家に望むことは生活であるー。
型と色
①カロリー、②たんぱく質、③ビタミン、④糖質、⑤ミネラル、⑥脂質、⑦カルシウム
素粒子は霊(要素ーエレメンタル)であり、大切であるが、食事の偏りと過食は、万病の基である。
❶肥満、❷老化病、❸癌、❹糖尿、❺疫病、❻痛風、❼身体障害
①力②瞑想③分食⑤栄養学⑥睡眠⑦ゲノム
AIマッチング
就労や職業選択、受験の際に、お見合いに、使うべきものである。ぼくは非凡であれど秀才ではないので、霊的教師と音楽家、そして魔法特に超能力にも興味があるが危険である。低位心霊能力の開発は避けるべきである。絶え間ないエネルギーの伝導瞑想と霊能力と精神集注と奉仕を推奨する。
念力からメンタル界へ
スープン曲げとは理性の崩壊を誘発する。ぼくはメンタル極化により此れが不可能になった。ところで、相手に自分の理想を押し付けることは賢明ではないが、芸能人のゴシップネタの様な落ち着きのない猿のような忙しない心を落ち着ける為に音楽による精神の安定が有効であるー。
日本人改造宣言
一箇所に留まっていてはいけない型を打ち破り、昨日を越えて行け!『在るがまま』を生きることの大切さと周囲の無理解という困難を越えて生きる事は囚われない創造主として大事な私的視点を加味する事になる。ぼくの心はいつも昔に同一性されて🇮🇹や🇪🇸や🇮🇳
🇹🇷や🇯🇵や🇨🇳etc.『舌の記憶』
カタストロフ
創造物(型あるもの)は崩壊現象。死と共に私達の精神や知性や機械でさえ構造物は全て壊れ、軈て��われる。だから、DATAの引き継ぎは大切である。音楽では楽譜、ランドスケープ、ピアノ演奏、イラスト、習字、タイピストの手や論理性は死んでも残された情報の痕跡であるー。『儚い夢の跡』
意
R覚者ー原因と結果の法則
❸→❶
父と母ーカルマ(業)の法則ー❶→④→❸
ゴータマ仏陀ー再生誕の法則❶→④→❼→⑧∞
自由意思ー
∞(情報のソース)→❶
エドガーのコイントス
ー確率ー
②→❶
神の意志ー
❼→④→❶
プトレマイオスとベンジャミンそして全てのイニシエートに敬意と感謝ー。
意(マナス)
#DK覚者 (チベット・ロッジ)のレベルの情報は難解である。#アリス・ベイリー によって与えられた『秘教科学』は緻密に宇宙の構造と神秘についての洞察に富んでいる。心理学の深淵さと覚者方の厳しさと忍耐には頭が上がらない。双方向のメンタル・テレパシー(思念伝達)は稀有であるからー。
既知と未知
❼機械論的・科学的マインド(聖霊)の状態である②④⑥頭脳の❸識別力は『分神霊』であり神経の中にある器官であるナディに合成された精妙な❺ガス(気体)状でできている。⑥パイシス(双魚宮)と❼アクエリアス(宝瓶宮)の宇宙にある霊的な❶『統合のエネルギー』が働いている。②『伝導瞑想』
(不)信仰
キリスト教の原理主義者が唯一の「イエスは神でなくてはならない」とか、(唯物論的)科学者が「ダーウィンの進化論が真である」、「宗教の殆どが偽りである」とか「哲学は何もなしていない」などと言う事は無知に満ちている。『意識の進化』を信じているなら『幻惑』や『錯覚』に注意し給え!
主義
私は云々であるというとき、我々は我々の間に対立を生む恐れがある。在りと凡ゆる物事の嫌悪や善悪に対して、我々は我々の社会を異なる価値観で分断してしまうだろう。必要なのは社会の『調和』であり、『平和』であり、『非暴力』である。観念自体は象徴であり、対立を生む人工物に過ぎないー。
❺記憶自体
コロナウィルスの顕現は人類に対する避けがたい受難でした。これからの④芸術科学(素粒子の霊性)と❺化学医学(構造の形相)の重要性は言い過ぎる事はないです。全ては崇高な魂(全ての霊的な本源���戻る旅路)の為の犠牲に違いない。無力は承知の上で皆様に御願いしますー。『人類科学の進歩』

与え与えられ
日々与えられた物事に感謝して、生きていきます。
霊(言葉と絵)を尽くして、自我である個性体(パーソナリティー)を神である真我((宇宙)意識体)である魂の供物に捧げます。ごちそうさまでしたー。神に感謝して、命に感謝して、親に感謝して、先生に感謝して、食べ物に感謝してー。m(_ _)m
安定
人間の生き方に自由などはない。せいぜい
自分の自我の領域の中で我が儘な意思のもとに約束事とサービスの間で比較的自由な裁量があるだけである。
10割 Android
百分率で言えば100%
太陽系 9段階
人間レベル99が限界
100以上は死ねない
~255 霊界
1000(1T)
16次元 宇宙全体
聖なる科学
霊の数学と哲学と美学としての音楽と美術を尽くして神的存在に触れる魂である自我の拡大と、霊である真我に帰絨する瞑想の帰還の道。真に純粋な理想的なイデアの想像力の究極的に完全な世界(実在)の上からは、太陽系が16個あり、太陽系外地球の兄弟の惑星も16個あるー。
解釈学
循環する霊と宇宙について
#インテリジェント・デザイン(知的創造論)からの『秘教数秘術的』なコンセプト(意匠性)ー2進法、10進法、60進法ー『カバラ数秘術』、『秘教哲学』、『七光線心理学』『神智学』、『素粒子物理学』、『情報工学』、『陰秘学』『数学』、『強迫性』、『偏執狂』
外部と真理
②主観と❸客観について私達が認識できるものは❺記憶であり、④イメージであり、❸認識性であり、②デジタル信号であり、❶霊である。❼存在を創るもの、⑥在ったと信じるもの、❺在ること、④在るかもしれないもの、❸これから在ること、②視えるもの、❶霊(的精神)性。『真我認識』
形式と存在
『モナド』ライプニッツ
『素粒子』精霊主義
『クオリア』アストラル体
『考える葦』パスカル メンタル体
『精神と物質』デカルト 物心論
『宇宙四次元』アインシュタイン
『時間と空間』ニュートン
『物自体』カント
『質料』プラトン
『弁証法』ソクラテス
『形相』アリストテレス
ライヒ『オルゴンエネルギー』
シュタイナー『エーテル体』光子
ユング『集合的無意識ー幻型』
フロイト『リビドーと超自我』
アドラー『目的論』
ニーチェ『永劫回帰』
ハイデッカー『存在と時間』
サルトル『存在と無』
ラカン『想像界・象徴界・現実界』
キリスト『三位一体』
盤古『陰陽』
ヴント『内観』
プロティヌス『一者』
エンペドクレス『風・火・地・水』
デモクリトス『原子』
チェリオ『量子色力学』
ジョブズ『Apple製品』
ダリ『心理学から科学へ』
モーツァルト『曖昧な調和』
小室哲哉『宇宙の美化』
坂本龍一『現実』
小林武史『夢と魔法』
宇多田ヒカル『宝瓶宮の水』
植松伸夫『劇場音楽』
天野喜���『ファイナル・ファンタジー』
楠瀬誠志郎『シリウス』
すぎやまこういち『ドラゴンクエスト』
鳥山明『ドラゴンボール』
高橋留美子『めぞん一刻』『犬夜叉』
桂正和『DNA』『シャドウ・レディー』
貞本義行『エヴァンゲリオン』
宮崎駿『ロマン派』
久石譲『映画音楽』
スピノザ『心身一元論』
クリシュナムルティ『私は何も信じない』
キリスト・マイトレーヤ『分かち合って世界を救いなさい』
ベンジャミン・クレーム『始まりは近い』
江原啓之『オーラの泉』
大槻教授『プラズマ』
韮澤さん『たま出版』
イエス覚者『救世主』
仏陀『真我』
プレマ・サイ『超心理学』
フェルメール『レースを編む女』
3ー7ー4ー2ー7(2.4)

宇宙
針仕事の周りを描く『フェルメール』の絵の中に宇宙が回っている事を、夢と現実の間を行ったり来たりするシュールで、冗談好きの地獄ではないまでも煉獄に居る『ダリ』は知っていた。如何なる小さな物事でも、大切な人の存在は守りたい。大切な命に寄り添い生きていきたいものである。
『来世』
サルバドール・ダリ『レース編みの娘』
6ー4ー6ー4ー7(1.6)
(フェルメール・ファン・デルフトの絵の模写)

「ダリ全画集」の『レースを編む女』
ダリに心の底から同情します。イニシエートの低さには右利きで頭の精神の線が細いスマートと云う理由と、光線構造が非常に高いのには、人類の輪廻転生を担保したいのと、神であるサルバドール(救世主)でありたいと言う野心と、謙遜と、拘りがあるからですー。




芸術家と科学者
『ピカソ』は拘りのない自由な心の境地でどんな画家のスタイルも直ぐにマスターして、同じ場所に留まらずにどんどん変化する秀才。純粋無垢な子どもが描いた様な平気で、破壊的な創造で醜悪さをも描く。『ダリ』は古典的な描き方で言語性の強い鬼才。神に見いだされた犠牲者ですー。
ダリでもピカソ
二人ともきら星のような才能があるので何回輪廻しても本物の神になるべきです。業の深さは恐ろしくダンテの言葉を借りれば「まるで生きていることが呪われている様でこの地上以外に如何に『地獄』と呼ぶ事ができようか?」と言う程、人生を生きるのは大変です。才能の有無に関わらず。

パブロ・ピカソ(2.4)
7ー4ー1ー6ー3
『サルタンバンカの一家』
パブロ・ピカソ『パイプを持つ少年』

アンリ・マチス(2.4)
3ー6ー1ー4ー7
『ブルーヌード』

3 notes
·
View notes
Text
スイスで見た博物館・美術館 備忘録
栄華で罪深い過去と共に。
いろんなヨーロッパ絵画や歴史的史料を見るなかで、少しだけヨーロッパやスイスのイメージが具体的になってよかったな。
ぜんぶ素人の適当な感想なので、気軽な旅行気分で流し読みしていただければ幸いです。
ラ・ショー・ドゥ・フォン
時計博物館
Lorelei and the Laser Eyesに出てきそうな大きく複雑で謎めいた時計がたくさん見られて楽しかった。歴史的な展示もされていて、最初は日時計・砂時計から始まるのだけれど、最後正確性を求めるうちに、メカメカしい原子時計までいくのが面白かった。
時を、航路を、労働を、計り刻む合理性の象徴としての時計。
写真は複雑なアナログ時計と精密な原子時計。


ヌーシャテル
美術・歴史博物館
地域のちょっとした歴史資料館見るのが好きなので。トラベルパスという共通観光チケットがあれば無料で見られるのも気軽でよい。(多くの博物館・美術館も同様)
小規模だけれど、全体的にまじめに作られていて好印象。精巧な自動人形が見られたのも楽しかった。緻密な絵を描いてくれる!
建物も立派。スイスは町中に豪華で立派で石造りの重い建物がずっとのこっている。


「植民地主義者の銅像をどうしますか?私たちは公共の場で何を、どのように覚えておきたいのでしょうか?」
印象的だったのは、地域の名士の銅像をどうすべきかという展示。ヌーシャテル中心部に立っている町の発展に寄与した名士は、実は奴隷貿易や三角貿易で富を得た人物であり、現代において彼を称える銅像が町にあるのは是か非か、市民はどう考えるのかという展示。地域の歴史紹介や美術家や歴史家など専門家のオピニオンビデオ、市民への公開アンケートなどを用いて多角的に議論の素材を提供する。正解はないけど、とりあえずみんなで過去を踏まえて考えて議論して、今後決めていこうというスタンス。
過去の他地域への搾取とそこから得た富・美を現在どう扱うべきかというテーマは、このちいさな地域の郷土資料館をはじめ、後述するようにほかの美術館当でも見られて、スイスやヨーロッパ全体での時流でもあるのかもしれない。
ベルン
パウル・クレー・センター
クレーの作品は今まで散発的に見たことあるだけでそんなに興味なかったのだけれど、作品をまとめて見られて、なんとなくよさがわかってよかった。作品保護の観点から、展示点数は規模のわり��少なめ。
限られた二次元の色と線という手法でいかに現実を描きうるかという自由で多様な実験みたいな作品が楽しい。絵単体というより、そのいろんな試みが自分には興味深かった。

晩年の、勢いを増すナチス・ドイツの勢力から逃れて故郷ベルンに戻ったのち、なぜか線と色に迷いが消え、寡黙で内省的で象徴性を増していくなぞめいた作品群が個人的には好みだった。
ローザンヌ
リュミエーヌ宮・自然博物館
たまたま休憩に立ち寄った立派な旧宮殿内に、無料で市民開放されている博物館があったので。
おおきなマンモスの化石があった!ほかにもたくさんの剥製(絶滅種も含む)や鉱物・化石が展示されていて、時間なくてゆっくり見て回れなかったけれど、思いがけず充実した展示があり楽しかった。ここも建物が古くて立派。

チューリッヒ
チューリッヒ美術館
中世から現代美術までいろいろなヨーロッパの美術作品がたくさん集まっている。自分の精神は近代で止まったままなので、いろいろな近代絵画が間近で見られてうれしかった。ほかの美術館等と違いトラベルパスは対象外で、別途入館料が必要なので要注意。
マグリットやキリコやフランシス・ベーコンの作品が近くで見られる!やった!!



ムンクのこの絵も、線と色合いの構成がしっかりしたふつうの風景画だけれど、見てるとつらくなってくるような感じがあってよかった。

現代美術
バングラデシュ・ダッカ出身の非営利コレクティブが作ったインスタレーションがよかった。少しだけダッカという地域と縁があったので。


急速な経済発展と社会の変化、押し寄せるたくさんの海外資本・商品・文化と市場社会、そのなかで抱える戸惑いや経済発展への期待や先進国への不信感。作品で表された、現地産業であるニットで編まれたキャンベル缶や粗末な屋台に並ぶたくさんの商品≒危険物のなかに、わずかに知っていたバングラデシュに住む彼らの思いを、芸術作品を通して改めて知れたようでよかったと思う。
デモによる政権交代後、みんなどうなるのかな。無事であるといいのだけれど。
ジャコメッティ作品
スイス出身の作家ということで、こちらも今まであまりよくわからなかった人なのだけれど、この機会にまとめて作品を見ることができてすごくよかった。人間性の衰弱と危機のなかでの抗い、というモダニズムなテーマよかったな。フランシス・ベーコンや河原温とかもそうだけど、モダニズムのなかで人体の徹底的な解体と再構成を描こうとする作品が好きなのかもしれない。


存在だけ再構成されたよろよろしてる犬。かわいいね。

企画展
チューリッヒ美術館のコレクションに多大な貢献をした武器商人「Sammlung Emil Bührle氏」の所蔵コレクションの今後の在り方について問うもの。
戦争という場を利用し、武器の販売で得た多額の富により築かれたコレクション。ここに飾られる絵画の額のすべてには「Sammlung E.G. Bührle」と刻印がされている。モネのきれいな睡蓮などもこの額に囲われ、周辺情報が気になって作品単体の鑑賞が難しい展示。




なお、ほんの一部にナチス・ドイツがユダヤ人から押収した作品も含まれており、こちらについては返還手続きを進めており、展示不可となっているとのこと。
だから作品すべての来歴を明らかにし、それはQRコードで開示されている。展示自体がこれらの周辺情報含めて、たくさんの犠牲とそこから得た利益という過去のうえに築かれたコレクションをどう維持し、どういう文脈とともに展示していくか問題提起し、議論するための場となっている。

非常に難しい問いかけであり、自分にはどういう方向性に進むのがいいのかわからないし、作品鑑賞の場としては周辺情報が多すぎるし、けれど無視できない・そうすべきでない問題なのもわかる。過去からは逃れられないけれど、いつか作品そのものをちゃんと鑑賞できる環境が整えられる日が来るんだろうか。
日本では、国立近代博物館の戦争画展示や藤井光氏の展示などが、自分が知っている中では社会的・歴史的経緯に取りまかれる芸術と展示の問題を取り扱っていて、たまに気になって見に行く。
(チューリッヒ美術館まとめ)
いろんなお金と美術と考えが集まる場所なので、ものすごく駆け足に1時間半で見たら大変でした!
ジュネーブ
ルソーの像・ルソーと文学の家
ルソーの諧謔と矛盾に満ちた「孤独な散歩者の夢想」が好きなので、ルソー詣でをしてきた。
家のほうはふつうに1Fでカフェを営業していたのが意外。テーマごとにおしゃれでコンパクトな展示となっていて、日本語ガイドのレンタルもありで見やすい。「孤独な散歩者の夢想」展示が見られたので満足!



国際宗教改革博物館
小ぶりな建物ながら、展示はきれいで整理され、非常に充実・意欲的な内容でよかったな。特設Wi-Fiで接続できるホームページから多言語対応されていて、しっかり翻訳された日本語で見やすく展示解説が読めるのも、ちゃんと説明しようというやる気を感じた。
���然プロテスタントの視点からの展示だけれど、あまり宗派に偏らず、比較的フラットに解説されている印象(自分がキリスト教に不明のためわからないだけかもしれないけれど)
聖書がラテン語からドイツ語・フランス語・英語に翻訳されることで、書物が権力関係を変え、そして社会が変わっていったことを、当時の書物を通して少しだけ思いを馳せることができるようでよかった。
写真はラテン語から英語やドイツ語など様々な言語に翻訳された、宗教改革当時の聖書。




ジュネーブに滞在し、宗教改革で大きな役割を果たしたカルヴァンについては、偶像崇拝を厳しく禁じていたため、彼が使ったといわれてるコップしか遺物が残ってなくて、それが展示されているのがおもしろかった。
宗教改革でよりモダンな形に切り替わったキリスト教が商業主義・物質主義に取り込まれていくこと、女性や疎外された人々がプロテスタントの教義について議論する演劇をもとにした映像作品、そして今日的な「プロテスト」の在り方など、意欲的な展示構成も見ていて楽しかった。時間の都合上、駆け足でしか見られなくて残念。


ざっくりまとめ
海外でもGoogle翻訳のカメラ機能で展示解説をおおむね読むことができるので本当に助かる。ホームページやガイド端末で日本語含めた多言語対応しているところも意外とあった。
自分が行った場所はどこに行っても古く重い石造りの建物が残っていて、重く逃れられない過去のなかにずっといるようで印象的だった。
小さいけれど、伝えたいことがちゃんとあって、資料の保存や展示の意義を問い続けるような博物館・資料館は、国内外問わず見ごたえあっていいなと思う。大きな美術館や公設の資料館とかもそれぞれ姿勢に違いがあって、いろいろ見られて勉強になった。
最後にいい感じの湖の写真で終わります。湖は最高。

5 notes
·
View notes
Text
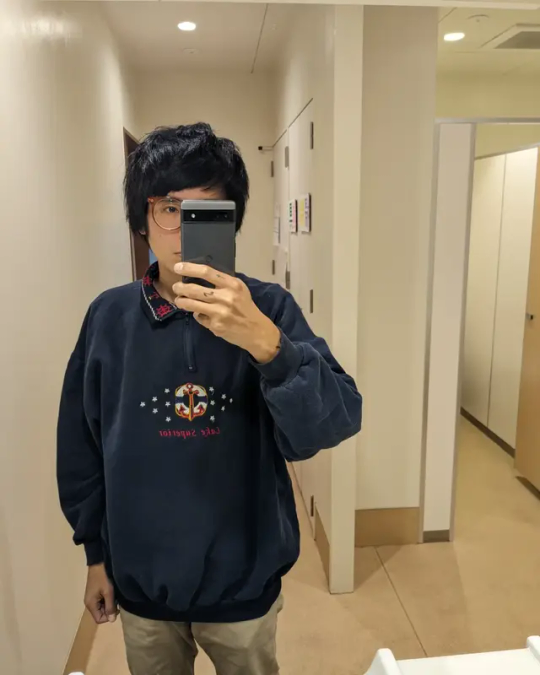




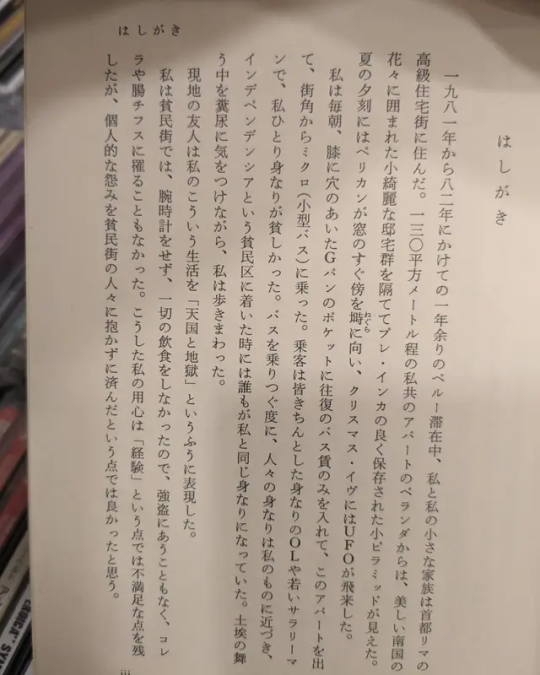
【2023-11-23】 勤労感謝の日
晴れ。午前七時三十五分起床。祝日。アラームで目覚める。顔を洗い、歯を磨きアパートを出る。セカンドストリートで1500円で購入した、グリーンのミリタリージャケットに胸にピースマークの缶バッジ、ボーダーのハイネックのニット、デニムパンツ、スニーカーという格好。今日は、祝日のため、平日通っている、精神病院のデイケアが休みだ。今日は、特に予定を入れていないが、暇なので、とりあえず地下鉄で、天神へ向かう。電車内、スマホをみたり、読書。数日前、ジュンク堂書店の古本まつりで250円で購入した、大島亮吉著「山ー随想ー」の続きを読む。大島亮吉は、学生時代から登山サークルに入っており、人生のすべてを山にかけていた。「山ー随想ー」には、ただ、登山している時に見える風景や、その日に摂った食事のことがただただ淡々と記されているだけだ。退屈と言えば退屈な随筆だ。ソローの「森の生活」のように。しかし、小説のように、ドラマティックな出来事が何も起こらず、著者の感じたことや、出来事をただ羅列しているだけの退屈な文章が、私は好きなのだ。そういう生き方をする人に「無常の愛」を感じるのだ。しいて、私が興味を惹かれた箇所は、「アイヌ民族」についての事柄が記されている箇所だ。そのことは、また、のちのち触れることにしよう。天神へ着き、まだどこも店は開いていないので、ただ、あてもなく天神の街を、タバコをくゆらせながらぶらぶら歩く。腹が減ったので、ロッテリアへ行き、野菜バーガーセットを食べる。サイドドリンクはメロンソーダ。私は、コーラやカルピス以外にメロンソーダも好きなのだ。向かいの席には、若い二人組の男が向かい合って座っている。前日、飲みすぎたのか、途中から、テーブルに突っ伏して寝始める。私も、若い頃はよくやった。せっかくなので、記念に二人が突っ伏して寝ているところを写真におさめ、SNSに投稿する。食後、ロッテリアを出て、ブック・オフへ向かう。途中、破れたデニムパンツを発見したので、迷わずリュックザックの中に入れる。この「リュックザック」という単語の「ザック」の部分は、大島亮吉氏が、「リュックサック」ではなく、「リュックザック」と「サ」を濁らせて「ザ」と書いていたため、普段私は、「リュックサック」と記入するのだが、今度からは私も、「リュックザック」と記すことにしよう。「ナップザック」でも良いような気もしてくる。そう、私は、古臭い言葉の言い回しや、現在では、「死語」となっている「言葉」が好きなのだ。ブック・オフで、無地のグレーのセーターを試着してみる。サイズ感はバッチリだし、デザインも悪くない。しかし値段だ。プライスタグには、二千円と記されている。最近の私の服を購入する基準は、千五百円以下なのだ。ちと高い。結局、商品を元あった場所に戻し、ブック・オフをあとにする。勿論、先程のセーターが、もっと面白い柄が入っていたり、かわいい胸ポケットがついていたら、多分二千円でも購入しただろう。しかし、あくまで無地なのでもう一歩購入に至らなかったのだ。しかし、この日記を書いていると、そのシンプルな無地も悪くない気がしてくる。書いていて、だんだん欲しくなってきたので、また週末にでもブック・オフへ行き、まだ商品が残っていたら購入することにしよう。ブック・オフを出たら、突然、体にタトゥーを入れたくなったので、どこに入れるか?を想像してみる。思いついたのが、手のひらだ。手のひらへ「Pain」と入れたいのだ。私が、日々投稿しているTumblrで、手のひらに「Pain」と入れている男性の画像を発見して以来、ずっと同じ箇所に同じ「文字」を入れたいと思っていたのだ。特に、予約はしていないが、とりあえず、タトゥーショップへ向かう。タトゥーショップは、最近、私がよく彫ってもらっている「KーTATTOO」だ。KーTATTOOでは、アンカー(イカリマーク)や、聖母マリアや、イエス・キリストや、誰かわからないが、首を切られた生首の男の写真の画像を入れてもらった。最近では、首筋に十字架や、肩に星マーク、足首にアルファベットで「MOM」と彫ってもらった。そして、KーTATTOOのど真ん前には、クリニックの駐車場があるのだが、なんと、私の名字と同じ「いわさきクリニック」というクリニックの駐車場があるのだ。「主」は、私がKーTATTOOで入れ墨を入れることを望まれているのだ。私が、聖母マリアやイエス・キリストのタトゥーをKーTATTOOで入れようと思ったきっかけは、別に「いわさきクリニック」がKーTATTOOの前にあるからではない。勿論、そんなことは、知らなかった。知ったのは、最初の予約をした日、グーグルマップでKーTATTOOへ到着してから知ったのだ。ある時(2023年6月初旬頃)、タトゥーが入れたくなり、たまたまネットの検索で引っかかったのが、KーTATTOOだったのだ。アンカーは、私は、佐世保出身であり、幼少期から米軍基地の近くを、よく車で通っていた。その時、走行する車の窓から、米軍基地の近くを通ったとき、大きなアンカーの彫刻が建てられているのを見ていた記憶が脳裏に焼き付いているのだ。子供心にカッコいい形だなと思いながら、見ていた。それでアンカーを腕に彫ってもらったのだ。彫師さんに聞いた話だが、アンカーは、縁起の良い彫り物らしい。KーTATTOOへ到着して、スタッフに「Pain」の画像を見せる。運良く、今日は予約がそんなに入っていないので、当日入れることができるとのこと。ただ、本日一人、十二時から予約が入っているため、その後の、午後一時からであれば入れることが可能とのこと。ただ、手のひらは、タトゥーを入れる体の中でも、特に痛い箇所らしく、おまけに手のひらというのは、人間の体の中でも特に墨が入りにくい箇所であり、入れても時間が経つと消えてしまう可能性が高いとのことを告げられる。それでも、いいから、私は、入れたい旨を伝え、上機嫌で店をあとにする。時間まで、1時間半ほどあるので、H&Mへ行き、レディース、メンズ服、くまなくチェックする。欲しい服も何着かあったが、どれも二千円以上するため買い控えする。時間になったので、KーTATTOOへ向かう。到着したら、女性の客がうつ伏せになり、左背中に何やら彫ってもらっている。私の順番がきて、「Pain」を入れてもらう。針が、手のひらを刺した瞬間激痛が走る。私が、今まで入れたどこのタトゥーよりも痛いし、痛みの種類が違う。途中から、手がブルブル震えてきたので、彫師さんが、しっかり抑えて「彫り」を続けられる。約、三十分ほどで彫り終わる。痛かったが、とてもカッコよく入ったので、もう先程の痛みを忘れて、上機嫌で店をあとにする。ジュンク堂書店で、「古本まつり」をまだやっているのを思い出したので、足を向ける。大平健一著「貧困の精神病理」、色川武大の(タイトルは忘れたが)書籍と、あとは、これもタイトルも著者名も忘れたが二冊合わせて���四冊の書籍を購入する。四冊で千三百円ぐらい。地下鉄で帰り、途中、セブンイレブンで、カップの担々麺、タルタルフィッシュバーガー、コーラ、カルピスを購入。アパートに帰り、買った食材をリュックザックが取り出してみたら、カップの担々麺を買ったつもりが、カレー味のカップ麺を購入していたことに気づく。気分は担々麺だったのだが後の祭り。(私は、基本、日々同じ食べ物を毎日食べることを好む。変化が嫌いなのだ。)シャワーを浴びて洗濯機をまわし、イソジンでうがいし、テレビを観ながら晩飯。食後、数日前、食べ残したポテトチップスの輪ゴムを外し食べる。食後、気持ち悪くなったので、胃腸薬を服用。他に、私が日々、服薬している薬も飲む。あのちゃんのユーチューブ動画(本田翼とのラジオ動画)を視聴して就寝。何時に寝たのかは覚えていないが、最後にスマホの時刻を見たのが23時過ぎだった。
3 notes
·
View notes
Text
Letter for City Boys. /文・柴田聡子
男の子たちよ。 私は君らがおそろしい。校門の脇にいつまでもつっ立っている君らの間をうつむいてすり抜けた時から、今の今までずっとおそろしい。だけど私は君らを隣りや後ろに乗せて運転がしたい。見つめ合うことなく仲良くなりたい、いつも。会うたび痩せていくから、私は君の心配をする。健康診断行ってるか。がん検診行ってるか。野菜食ってるか。歯磨いて寝てるか。君はありがとうってただ一言つぶやくだけで、あとは海を泳いだり道を歩いたり、そうしているうちにこっちのことなんてすっかり忘れてしまう。私は勝手にそれが腹立たしい。生まれた時からやさしい君は困ってしまうが、けんかも出来ない。そういう発想がないところに生まれ育った。私もそうなんだ、一応、北海道イチのそこそこシティで育った。しかしけんかもろくに出来ない腰抜けと思われないように、ついでに君を腰抜けと見下したことをどうにか伝えたくて、こちとら雪だって降るし大変だったんだ、一緒にしないでくれ、と凄まずにいられない。どうしてこんなことになっているのか皆目見当もつかないといったその目はチワワみたいに潤んで震えていた。あれは悪いことをしたって、この頃、今さら、反省している。今、君の何かをコントロールできたところで長生きくらいしかいいことは起こらなそうだ。ということで、もうとにかくな���だっていいから、なんとかすこやかにやっていってくれ。こっちもこっちで、この心配は君のためじゃない。自分の中にだれかへの愛情があることを確かめて、ほっとして、生きる活力にしているだけなんだ。全て自分のため。こんな都会のど真ん中、なんてったって大人だし、だれでもなんでも出来るはずなんだ。たまにはそういう強さも見せつけたくて君の前で精神的に仁王立ちをしてみる。でも、そうして見せびらかす前から、君はそのポーズにほんのり気付いていたらしい。そしてそれを口にしないでいてくれる。自分と同じく、人を格好悪くすることもしない。単純に気にも留めていないだけの可能性がある。たまに考えるんだけど、もしも私たちがとても仲良くなって、周りもそんな風に思うようになったとしても、数日間連絡のつかない君の部屋の様子を見に行く役目を請け負うのだけはほんとごめんだ。もし君がそこで息絶えていたら、はじめにその姿を見た時の私の顔を見る人はだれも居なくなるんだ。そこで起きたことの全ては私しか知らないことになるんだ。世にも複雑でおもしろい顔をしているだろうに、それを見てくれないなんて、そんなのいやでいやで仕方がない。面白いことがないとすぐに退屈そうな顔して足を投げ出して座る君がそれを見ないのは罪深いよ。やっと迎えた休日の、じんわり幸福でほくほくとしているだけで充分な夜中であってもそんな態度をとるんだから。最後まで面白いことを見逃さずに大笑いしてくれよ。頼む。冗談と適当だけは死守してくれ。私たちは深刻ぶったら最後。ふざけていないと死ぬと思っていてくれ。あの日、大好きな人が離れていってしまおうとしているというのに、君はお金も時間も惜しんでた。明日も変わらず仕事をしようとしていた。それはそれでいいといった風な感じで王将で餃子をつついているぶっちぎりのタコ野郎だった。私は君の残した餃子、いらないんなら欲しいなって、つばを飲み込んでた。君は私の残したチャーハンにまったく興味が無さそうだった。君は人のものを欲しがらない。卑しさという概念がない。私は高揚した。こいつをぶん殴ってやろうと思い、そうした。君はびっくりしてた。私と君は一生友達になり、翌日、君はどこに隠していたんだか知らないけど、傍から見るとかなり大きな勇気を軽々と使いこなしてた。様になってた。優雅にコーヒーを飲む写真を送ってくる余裕っぷりだった。ラーメンをすするのも、猫背も、弱音も、全部絵になる。見事だなって、いつも感心する。あれからというもの、君からは短くて鬱陶しい連絡が時々きて、私はそれにいつも「はい」とだけ返信をしている。打たれ弱いんだか打たれ強いんだか、わけがわからない。もうとっくのとうにわけはわかっていないんだけど、どうしてもあきらめがつかない。君が私��ばかにしているように、私も君をばかにしている。そんな不健康をどうして続けているかと聞くのは止して欲しい。その横顔が、若き日の貴乃花に似ているということしか理由は無いかもしれないのが恥ずかしいから。君とはよく公園に行った。近くの、なんてことない、普通の公園。そこで山も谷も無くおしゃべりするだけ。珍しいものを観に行ったり、計画を立ててどこかに出かけたりしたことはほとんど無い。あってもすぐに帰りたくなる。行くとこはどこでもいいし、食べるものもなんでもいい。どこに行ってもよそ者だった。山形の友達の家の水道水を呑んで、このところ口にしたもので一番おいしかった、って何杯もおかわりして、そのたび心底うまいという顔をしていた、という噂を聞いたよ。その愛らしさで素朴な俳句が詠める。君と出会った時にとてもうれしかったのは、たとえ大きな間違いだったとしても、私をリアーナやビヨンセと同じように扱ってくれたこと。そんなこと君はつゆ知らず。ここまでああでもないこうでもないって自分に言い聞かせるように書いたこと全てが、君にとっては大切なことでも残念なことでもない。君はほんとうになんにも思ってない。イエス=キリストもさ、うるさいやつの話を聞くときはどんなに声を荒げられても最後までなにも言わずにじっとしていて、相手がもうしゃべりきったなってところで目を見つめ十字を切って祈りそのまま立ち去ったらしい。君は知らず識らずのうちにキリスト流だよ。君を目の前にすると、今でもそわそわして頭が真っ白になる。あと、別れ際が潔過ぎるよ。もう少しだけゆっくり背を向けてくれたらいいのにって、ぶつぶつ言っているうちに電車が来て、私はそんなことを一瞬にして忘れてしまう。
6 notes
·
View notes
Text
「文化とは何か」という問いは、非常に奥深く、一言で定義するのは難しいですが、一般的には**「特定の人間集団が、世代から世代へと学び、伝え、共有してきた、生活様式や思考様式の総体」**と説明できます。
それは、単に芸術や伝統行事だけを指すのではありません。私たちが当たり前だと思っている行動や考え方の、ほぼすべてが文化の一部です。
より深く理解するために、文化をいくつかの側面から見てみましょう。
1. 文化を構成する主な要素
文化は、目に見えるものと見えないものの両方で構成されています。
A. 物質文化(目に見える文化)
形があり、五感で捉えることができるものです。
食べ物、料理(食文化): 和食、イタリアン、インドカレーなど
衣服: 着物、アオザイ、ジーンズなど
建築: 日本の寺社、ヨーロッパの石造りの教会、高層ビルなど
道具、技術: 箸、スマートフォン、自動車など
芸術作品: 絵画、彫刻、音楽、演劇など
B. 非物質文化(目に見えない文化)
人々の精神や行動の根底にある、形のないものです。こちらの方が文化の本質を形作っていると言われます。
価値観: 何を「良い」「悪い」「美しい」「正しい」とするかの基準。(例:「和を以て貴しとなす」「個人主義」)
規範(ルール): 社会的なマナー、法律、慣習。(例:お辞儀、チップの習慣、本音と建前)
言語: コミュニケーションの手段であり、その言語特有の思考方法も含む。(例:日本語の敬語)
知識・信念: 宗教、神話、科学的知識、死生観など。(例:キリスト教、仏教、「もったいない」という考え方)
コミュニケーションスタイル: 直接的な表現を好むか、間接的な表現を好むかなど。
2. 理解を助ける「文化の氷山モデル」
文化はよく「氷山」に例えられます。
水上(見える部分): 水の上に見えている氷山の一角は、**「物質文化」や「行動様式」**です。食べ物、服装、言語、音楽、建築などは、比較的簡単に観察できます。
水中(見えない部分): しかし、氷山の大部分が水中に隠れているように、文化の核心部分は目に見えません。ここには**「価値観」「思考様式」「信念」「常識」**などが含まれます。
この見えない部分こそが、人々の行動や思考の根本的な動機となっており、文化を深く理解する上で最も重要です。例えば、「なぜ日本人はお辞儀をするのか?」という行動(見える部分)の背景には、「相手への敬意」や「和」を重んじる価値観(見えない部分)があります。
3. 文化の主な特徴
文化には、以下のような共通した特徴があります。
共有性: 個人ではなく、ある集団の中で共有されています。
学習性: 生まれつき持っているものではなく、家庭、学校、社会で後天的に学びます。
伝達性: 親から子へ、先輩から後輩へと、世代を超えて受け継がれていきます。
象徴性: 言葉、モノ、身振りなどに、特定の意味が与えられています。(例:国旗、ハトが平和の象徴であること)
変動性: 文化は固定されたものではなく、時代や他の文化との交流によって常に変化し続けます。
統合性: 文化の各要素(言語、価値観、習慣など)は、互いに密接に関連し合って一つのシステムを形成しています。
まとめ
文化とは、**「私たちの思考や行動を方向づける、集団共有のOS(オペレーティングシステム)やソフトウェア」**のようなものです。私たちは普段その存在を意識しませんが、それは私たちの世界の認識の仕方、コミュニケーションの方法、人生の価値判断に至るまで、あらゆる側面に深く影響を与えています。
文化を理解することは、単に外国の珍しい習慣を知ることではありません。多様な背景を持つ他者を理解し、同時に「当たり前」だと思っていた自分自身のあり方を見つめ直し、より良い共生社会を築くための第一歩と言えるでしょう。
素晴らしい問いですね。文化を表面的な知識としてではなく、深く理解するために必要なことを、3つの柱に分けて考えてみましょう。それは**「心構え」「知識と視点」「実践と体験」**です。
1. 心構え (Mindset) - すべての土台
知識を得る前に、どのような姿勢で文化に向き合うかが最も重要です。
① 自己文化の相対化(自分の「当たり前」を疑う)
私たちは無意識のうちに、自分が育った文化の「色眼鏡」を通して世界を見ています。まずはその色眼鏡の存在に気づくことが第一歩です。「これが普通だ」と思っていることが、実は日本文化特有のものである可能性を認識する必要があります。
心がけること: 「なぜ私たちはこう考えるのだろう?」と自問する癖をつける。
② 文化相対主義(Cultural Relativism)の視点
すべての文化にはそれぞれの歴史と文脈があり、文化に優劣はないという考え方です。異文化の習慣を「おかしい」「劣っている」とジャッジするのではなく、「なぜ彼らはそうするのだろう?」とその背景にある価値観や理由を理解しようとする姿勢が不可欠です。
注意点: これは、人権侵害など、普遍的な倫理に反する行為まで無条件に肯定するという意味ではありません。あくまで理解の出発点としての考え方です。
③ 好奇心と敬意(Curiosity and Respect)
未知の文化に対する純粋な好奇心と、その文化を築いてきた人々への敬意を持つことが大切です。上から目線での「分析」ではなく、謙虚に「学ばせてもらう」という姿勢が、相手の心を開き、より深い理解につながります。
④ 「決めつけ」を避ける(Avoiding Stereotypes)
「日本人は皆、勤勉だ」「アメリカ人は皆、自己主張が強い」といったステレオタイプは、文化の入り口としては便利ですが、それだけで理解した気になってはいけません。文化はあくまで個人の行動に影響を与える一つの要因であり、同じ文化の中でも多様な人々がいることを忘れないようにしましょう。
2. 知識と視点 (Knowledge and Perspective) - 理解の骨格
正しい心構えを持った上で、文化を多角的に見るための知識を身につけます。
① 歴史と背景の理解
文化は、その土地の地理、気候、宗教、そして何よりも歴史の積み重ねによって形成されています。
例: なぜ日本で「和」が重んじられるのか? → 米作りのための共同作業、島国としての歴史などが背景にある、と考える。
なぜその国が特定の政治体制や価値観を持つのか? → 過去の戦争、植民地支配、革命などの経験が影響していることが多い。
② 言語への関心
言語は単なるコミュニケーションの道具ではなく、**その文化の思考様式や価値観が凝縮された「窓」**です。
例: 日本語の多様な敬語は、人間関係の距離感や上下関係を重んじる文化を反映しています。英語に「よろしくお願いします」や「お疲れ様です」に完全に一致する表現がないのは、その背景にある文化的な概念が異なるからです。
流暢に話せなくても、基本的な挨拶や言葉の背景にあるニュアンスに関心を持つだけで、理解は格段に深まります。
③ 「見えない部分」への想像力
前の回答の「文化の氷山モデル」を思い出してください。目に見える行動(食事、挨拶など)の裏にある、価値観や信念(水中の部分)を想像することが重要です。
例: 「時間厳守」という同じ行動でも、その理由が「相手への敬意」なのか、「効率性の追求」なのか、「ルールだから」なのかは文化によって異なります。その「なぜ?」を考えることが理解につながります。
3. 実践と体験 (Practice and Experience) - 理解の血肉化
最終的に、文化理解は頭の中だけで完結するものではありません。
① 人との直接的な交流
本やインターネットで得た知識は、あくまで仮説です。その文化の人々と実際に話し、交流することで、知識が血の通ったリアルな理解に変わります。彼らの日常の会話や悩み、喜びの中にこそ、文化の本質があります。
② 五感を使った体験
その文化の食べ物を味わい、音楽を聴き、街の空気を肌で感じることは、理屈抜きの深い理解をもたらします。現地を訪れたり、国内のコミュニティに参加したりすることが有効です。
③ 失敗を恐れない姿勢
異文化に触れる中で、必ず誤解やコミュニケーションの失敗は起こります。それを恐れていては何も学べません。失敗は、自文化と異文化の「違い」を体感する絶好の学習機会だと捉え、次に活かすことが大切です。
まとめ
必要なこと具体的な内容なぜ重要か心構え自己文化の相対化、文化相対主義、好奇心と敬意偏見や誤解を避け、正しく理解するための土台を作るため。知識と視点歴史、言語、見えない価値観への想像力行動の背景にある「なぜ?」を理解し、文化の全体像を捉えるため。実践と体験人との交流、五感での体験、失敗を恐れないこと知識をリアルな理解に変え、文化を体で感じるため。
文化の理解とは、パズルのピースを集めるようなものです。一つの側面だけを見ても全体像はわかりません。これらの要素を組み合わせ、粘り強く向き合い続けることで、初めてその文化の豊かさや奥深さが見えてくるのです。
0 notes
Text
太陽信仰とホキンスの出自に関するあれこれまとめ
・旧神と魔術師について ケルト神話における冥府の神・豊穣・生命力を司り動物たちを従える鹿の角を持つ神であるケルヌンノスは、時代が降るにつれキリストその人や騎士物語における異形の存在(かつてこれらの物語を後世に残していた修道士たちには旧い信仰を集めていたものを「神」として表すことは出来なかった)として表された。 →しかしそれ以外の形でもこの角持つ神は形を変えて伝えられて来た。その化身の1人がみんなご存知魔術師マーリン、アーサー王伝説でお馴染み!ウワッ!(ホちゃんの二つ名を思い出し慄いている)
聖杯探索の物語において撃ち倒されるべき騎士の敵は得てして森や荒地に住まう野獣や野人や魔女で、それは捻じ曲がったかつての土着神だったりする。 ンピをある種の聖杯探索の物語として読み解こうとすると、やはり輝く金髪の「魔術師」の男は撃ち倒されなければならなかったんだなと。 だからこそ神の敵として怪物となり討ち斃され立ち塞がる旧い神を感じさせる男が、もし騎士王の剣の技を使う男に生かされたならすごく嬉しい! 篤い信仰をあらわす為の舞台装置としてしか振る��えなかった怪物が救われるような気がする。
騎士が怪物を倒してHappily ever after で終わるおとぎ話じゃなくて、被せられた怪物の役を降りた魔術師が騎士の手を取って新しい物語を生み出してくのを見たいってワケ。 見たいので1%を掴んでくれ 頼むから
・ケルト神話の世界,ヤン・ブレキリアン著,田中仁彦・山邑久仁子訳,中央公論社出版(1998) 「それにまた、鹿は単にキリストの象徴であるだけではない。……キリストが鹿の姿を取って現れた時、その角のあいだには十字架の印が出現したとされている。」 「……この時、創造主でありこの世の救い主でもある神の御子は、真実‘‘神なる鹿‘‘だったと言えるだろう。」p126
割とキリストと鹿を結びつける逸話はそこそこあるっぽい?角持つ豊穣と死を司る旧神であるケルヌンノスが、時代が降るにつれキリスト教文化の中でキリストそのものの逸話として吸収されていったと言えるのかもしれない。 てかホちゃんは身体のど真ん中に十字入ってるけどそういうことなんですか???
・涙と目の文化史:中世ヨーロッパの標章と恋愛思想, 徳井紀子, 東信堂出版,(2012) 「磔刑のイエスの背景にはテーブル・カット・ダイヤモンドが敷き詰められ、その裏側には釘やハンマーなどの受難の道具や聖ヴェロニカのヴェールが描かれている。……裏側には髑髏と交差した大腿骨が描かれており、いわゆるメメント・モリ(死を思え)の典型的な作品である」p11
ホキンスのジョリーロジャー全然海賊っぽくね〜〜ってずっと思ってたけど標章/紋章学的にいえばメメント・モリとキリストの受難を表す釘がモチーフになってんだね。本人に十字のタトゥーが入ってるのもあってなかなか厄ネタっぽい! 眉毛の形とか刺青とかもそう考えると聖痕みたいに見えてきてしまう!マズイ!ホちゃんとキリストそのものを結びつける要素がガンガン集まっていく!!助けてーーーーーッ!!!
余談ですけどタロットの並べ方にケルト十字という並べ方があるそうな、ちなみにケルト十字=太陽十字なんすよね コレマジ?都合が良すぎる……
・作中での十字の扱いについて 徹底的に世界政府側が悪魔信仰じみた描き方をされてる分逆に作中で十字架を掲げてる奴らは一体全体何者なんだ?という疑問 →ミホーク、ホキンスとかくまもそうだよね?ニカ関連のキャラ? 本誌で神の騎士団を強制召喚できる五芒星の刺青とかいうものを出して来たせいでこの与太がなんとも嫌な真実味が増して来て本当に最悪で最高だぜ! 地獄(マリージョア)に呼び出されるのが五芒星(アビス)なら天国に呼び出されるのが聖痕(クロス)なのかしらと思ったり?
・ホキンスとイギリスの結びつきについて ド…ピザさんの動画をコロナで半死半生の時流してて思ったけど世界政府がフランスモチーフで反体制側はイギリスモチーフなんだよねという話があり、ほなそどの隊長が騎士王の技を使ってるのも、隊長の隣で斃れるのを選んだ魔術師がいるのも全部…計算されてたってコト!? そう思うと歴史上の人物の名前だけ引っ張ってくるんじゃなくて技名にイギリス要素ある(エクスカリバーとかモロだし)🦖とかうわ〜モロイギリスぽいキャラなんだな〜となる。🔮は🦖と組んだせいでよりマーリンぽさがマシマシになりイギリス周りに縁深い男になる。 ちなみにホキンスの名前の元ネタであろうジョン・ホーキンスは確か従兄弟?のフランシス・ドレークと同じ海戦に参戦してスペインに負けて その後の航海でジョンの方が赤痢に罹ってフランシスを送り出し迎えを待つ間に亡くなったとかなんだよな 確か(要出典) そこもなぞらえてシナリオ作ってるワケ ねえよな
・ホキンスの実家・出自について 太陽信仰(ニカ関連)を拗らせたミッドサマーじみたカルト出身だったらいいな〜と思ってる! なんでそう思ってるかというと、どう考えても体に十字を刻んでいる男と太陽信仰が結びつかない筈がない(ガンギマリ)と思っているのと、あの世界一回海面上昇が起きてる関係で旧い信仰や文化は標高が高い集落とかに残ってる可能性が高そうだなと思ったから。グラドル号に植ってるあの針葉樹も出身地の御神木か何かを植え替えた奴だと良いな~。
山岳地帯出身だから海への憧れがあったりしたらきっと海賊になる動機にもなるよね♪と思っているよ♪ てか船乗りなのに馬(鹿)乗れるのは大分イレギュラーじゃない?作中で馬乗ってんのキャベンとドクQぐらいしか思いつかねえや、やっぱ馬とか乗れる環境にいたよねホちゃん。 LRLLの騎馬民族おじいちゃんも居たし、キャベンも馬乗ってたし確か馬車とかもあった?からンピ世界で騎馬文化のある民族自体がいないわけではない? まあ海面上昇で陸地がヤバい!海に出ろ!って時代になりつつある中で、広い牧草地が必要な馬は確かに希少で価値あるものになってくのかな?だからこそ余計にワ国で恐竜でもなく狛犬でもなく狛「鹿」に乗ってたホキンスは異様に思えるよね。
あとホキンスの刀は藁備手刀っていうんだけど、元ネタの蕨手刀は元々騎馬戦で使われることを想定されて作られた太刀で後々権威を示すために豪族に下賜されたり副葬品や儀礼に使われた?とかそういうもんらしい。だからホキンスのイメージ動物は馬なんですか??おだっちそこまで考えて作ってる??だとしたら完敗ですが……
標高が高いので空が近く、緯度が高いので日が沈まない理想郷(ユートピア)で太陽神を崇める人々に囲まれて育った男であって欲しい。自由な海の戦士に憧れて、いつか空に囲まれたこの狭い村から逃げ出して広い広い海へ漕ぎ出していく日を夢見ていて欲しい。 あの鎖骨の十字が幼少期に無理矢理入れられてたものなら胸糞度倍プッシュであたしがニッコリ! どこにいても神様がお前を見つけてくれますようにと祈りを込めて刻まれたものだったりしたらいいね
・実家が小児性愛カルトだった場合のホ 「神の声が聞こえる子」と交われば不妊が治るとか不能が治るとか聖別されるだとか男児に恵まれるだとかよくわからないご利益があることにされたので供物と並べてベッドの上に裸で寝かせられては信者に文字通り身体を供じていたら結構キツいなと思い始めています。嬉しいけど。 最初は行為の意味もわからず理解できなかったが自分の心を守るために次第に不感症になっていってそう。 能力を上手く扱い殺傷能力を高めていった結果クソカルト実家を血祭りに上げたのでもう地元に居場所が無く、自由を得たかったので海に出たかなりガッツと殺意に溢れた生い立ちのホキンス。
・ホキンスと運命女神について ホキンスは海賊王になりたくて海に出たのではなくある種「自由」を求めて海に出たタイプだと思ってる。 じゃあある種占いの結果に左右されてるのは運命に縛られているとも言えるのでは?という疑問も生じるけど、運命そのものを信奉する運命女神信仰みたいなのが下地にあるのかも?
ヨーロッパ紋章学では運命を司る女神は目紛しく変わる運命を表す車輪の上に乗り気まぐれな性質を表す縞柄の服やバイカラーの服を着ていたというけど、この車輪と運命の組み合わせはタロットカードでもお馴染みの図。そういう視点からでも運命女神信仰とホキンスを結びつけられないかという試み。 幼少期からタロットカード使ってるっぽいしなんか理由あんのかも?その理由をこじつけようとしたら運命女神信仰なんじゃね?という感じ。 気まぐれで移り気で酷薄な運命女神と贄と血を求めて荒れ狂う非情で残酷な太陽神に苛まれた幼少期を過ごしてほしい。そしてその割にはめちゃくちゃ恵まれた体格に育ってる上に太々しさすら感じる図太さを持ち合わせた強かな男でもあれ。
ホキンスの海賊団のクルーは「おれたち」を救わなかった神や世界や権力への怨み苦しみを、運命を占える「船長」ならきっと救ってくれると信じていて、ホキンス自身も占い確率を導き出し、未来を見通そうとする試みの中で「神」や「運命」の存在を証明しようとしてるのかもしれない。 →海賊として非道を働くことで「もし神が居るならば、きっと裁かれるはずだ(天誅を与えないのなら神は居ない」と証明しようとしてる? 確かに海軍に入るというタマでは無いがかと言って略奪暴虐破壊も辞さない海賊稼業をエンジョイしてたかというとそういう感じでもなさそうな感じだし、そういう理由で海に出ていても面白いと思う。幻覚でしかないけど!
・二人を繋げる「海ソラ」について ドは🌊ソラの正義の味方の物語に強く憧れを抱いていて ホキンスは自由な海の戦士の姿に強く心惹かれていて欲しい。「正義の味方」が好きなのか、「自由に海を駆け巡る海の戦士」が好きなのかで少し違いがあっていて欲しい。
あとホキンスは海ソラファンだけどしっかり海賊やってるのでなんだかんだ自分は「正義」からは離れた人間なのだと自認していると思う。海賊として簒奪者であり破壊者であり殺戮者であることと「正義」のヒーローに目を輝かせる童心を併せ持つ男。 なので同郷で同じ冒険小説に胸躍らせて、苦しい生い立ちなのに海賊に扮した海軍のスパイやってる男とかめちゃくちゃ高得点! 捕縛されたとか身柄を預かられているとか気に入ったからとかそれ以外でホキンスがドに肩入れする理由も、同じ海で同じ冒険小説に夢を見て同じ海賊をしていると思ったのに、実はまだ正義を捨てていなかった男がこれから背負う正義が何を意味するか知りたいとか そういうあたりなのかも?
という意味で「ひとつなぎの大秘宝」を求めない側の人間としてのドホが見たい。ンピース争奪戦とは違うものを追い求めていて欲しい。 それが「正義」なのか「自由」なのかはわかんないけど
・ドレークとホーキンスという二人の男について 苦しむ人々を救わぬ神の不在を証明しようとする涜神的な男が、人の手で作り上げようとする「正義」や「平和」の為に自分の人生も命も全部犠牲にしようとしている男に救われてしまったならめちゃくちゃ良くない?とおもった。 「神」の救済を証明できなかった男が「人間」の善性の存在に救われるところが美しいと思う。運命を受け入れようとした男を助けたのが自らの正義に従った男のエゴだとすごく嬉しい!結局救われることなんて一方的なもので、結局エゴに過ぎない、という自論が下地にある。
ドに対して獅子王にも湖の騎士にも光の鷹にも美貌の騎士にも出来なかったことをやってくれという祈りを背負わせてる。 ホキンスの「運命」に囚われていた人生の枷を外して自由にしたのがドであるならば 「過去」に囚われていたドの心を癒せるのはホキンスであって欲しい。 世代間の負の連鎖や生い立ちや環境、個々人の血筋や家族というものに苦しみ懊悩する男二人であって欲しいという気持ちがある。特にあの世界は海賊王や政府に人生をめちゃくちゃにされた人がたくさんいた世界だから。 インナーチャイルドとアダルトチルドレンというか 健全なバウンダリーの構築への道のりと過去への決別とかの話なのかもしれない。 どちらも完璧ではなく欠点や未開拓な部分があって良いし そういう二人が手を取り合って(Let Us Cling Together)幸せになって欲しい。
誰かに愛されて育って来た人間は同じように誰かを愛せるなら、愛されたくても安心できる場所すら見つからなかったような人間は負の連鎖を繰り返すしかないのか?という疑問があーしの二次創作の底の方に流れていて、それでも誰かを愛せる無私の愛だって生み出せるはずだという希望を彼らに託したい。アガペーの話なのかも?
ホキンス→ド「最期を迎えるならお前の隣が良い」 ド→ホキンス「それでも生きていて欲しかった」 でウチのドホの矢印は構成されていることにするよ
0 notes
Text
書物礼賛⑦

アンナ・レンブケ/ドーパミン中毒/新潮新書2022・原著2021
「ブプレノルフィンをやめようとは絶対に思いません。私にとって電気のスイッチのようなものです。ヘロインをやらないようにしてくれるだけでなく、私の体に必要なもの、他のどこでも見つからないような何かを与えてくれるんです」。長期的に薬物を使用してきたことで、彼の快楽と苦痛のシーソーはこの先ずっと「普通」の感覚でいるためだけにオピオイドを必要とするほど壊れてしまったのだろうか? 長い期間「断つ」ようにしてもなお、ホメオスタシスを回復できないほど脳の可塑性が失われてしまうことはあるのかもしれない。
(中略)私が1990年代に医学部に通い、研修医として勤める中で教わったのは、糖尿病を持つ人が充分なインシュリンを分泌できない膵臓を持っているのと同じように、うつ病や不安神経症、注意欠陥、認知的歪み、睡眠障害などがある人は望むように働かない脳を持っているということだった。私の仕事はその説によると、足りない化学物質を何かで補って「普通に」機能できるようにすることとなる。このメッセージは製薬会社によって広く流布され、非常に広範に展開されて、医者も患者である消費者も同様にそれを信じるようになった。
(中略)何年にもわたって多くの患者を診てきて、精神科の薬を飲むと苦痛な感情からは一時的に逃れられるが、自分が感じられる感情の幅が狭くなった、特に深い嘆きや畏怖の念といった強力な感情を感じる力がなくなってしまったと言われることがあった。(中略)「オキシコンチンを使っていた時の妻は、音楽を聴くこともやめてしまいました。しかし薬から離れて今は再び音楽を楽しむようになりました。私にとってそれは自分が結婚した人が戻ってきてくれたと思えることでした」
記述はわりとマトモながら、総花的で浅く、いかにもメディアに出ている女の精神科医・大学教授の本。「制度」の側にいる人物。強欲と堕落に覆われたアメリカ、オピオイド禍と絶望死、その背景にある教育と医療制度の腐敗。それらは一朝一夕に作られたものではない。福音派もシオニストロビーもコツコツ支持基盤を固め、自分が不幸と思い、救いを求める人を増やしてきた。対症療法には意味がない。ホメオスタシス(恒常性維持)=苦痛と快楽は脳の同じ部位で処理されるため、薬物などで一方を貪ると、自律神経・免疫系・脳の報酬系が異常をきたし、快楽より苦痛が長引く、それがまさに麻薬・オピオイド禍の本質なのだが、メカニズムの多くは未解明。ロケット爆発させてる場合じゃないんだよ。
上野庸平/ルポ アフリカに進出する日本の新宗教 増補新版/ちくま文庫2024・原著2016
日本の神道は、先進国の主要な宗教文化になったという意味で世界的に非常に稀有なアニミズム・多神教の一種である。崇教真光はそれをベースにし、キリスト教の聖書やイスラム教のコーランと同じような定まった経典「御聖言」と実益的な宗教実践「手かざし」を持つにいたった。 外来宗教であるキリスト教やイスラム教は教義がしっかり定まって「人間が生きていくための正しい教え」として非常に洗練されているが、西アフリカ伝統のアニミズム・精霊信仰にはある祖先崇拝や呪物(お守り)の考え方が存在せず、呪術的要素もさほどない。他方、西アフリカ伝統のアニミズム・精霊信仰は教義が定まっておらず、あまり洗練されていない。こうした西アフリカ人のスピリチュアルなニッチを埋めたのが神道というアニミズムをベースにし、経典を持つまでに発展し、さらにキリスト教やイスラム教を統合する万教帰一主義的価値観を持っている「真光」だったのである。
引用した崇教真光や幸福の科学・真如苑・創価学会といった日本発祥の新宗教、ラエリアンムーブメント・統一教会という日本発祥でないが日本人が布教に携わっている、それぞれいかにアフリカを攻略し、受け入れられているのかを実地にルポした労作。創価学会と日蓮正宗は当地でもいがみ合っているとか、幸福の科学は宣伝にお金をかけているが言葉・記号に頼って宗教的イメージ性が貧弱なため集客に苦戦しているとか、ウガンダ、コートジボワール、ガーナ、マリといった国々の事情と併せ興味本位にとどまらない味わい。
秋山駿/簡単な生活者の意見/講談社文芸文庫2025・原著1988
それより私は、自分の生の感覚の中で、この社会の声を読んで、こういっておこう。現在の社会は、無力な者、貧乏人、役に立たぬ者、それから不運な者には、一刻も早く人目につかぬよう隠されて死んでくれ、と、いっているのだということを。
私はふと、こんな空想に走る──。
長くもない年月のうちに、われわれの周囲で、つまりこの社会の到る処で、小さな爆発や小さな戦争が多数に生ずるであろう、と。
そうでなければ耐えきれぬほどに、この社会は、異質な存在の不合理な共存に緊張し過ぎている。つまり、矛盾の高圧下にある。早い話が、石油やトイレットペーパーを境界にして、それを入手出来ずうろうろしているこちら側と、その企業の管理者であるあちら側の人間とが、同一の内容の人間、少なくとも、同一の生の平面上に立っている人間であるとは、私には考えられない。たぶん、その心理、感情から、人間の意味ということも、良心も、それから正義の内容に到るまで、何から何まで違うであろう。
私は彼等と同一の人間の姿でありたくはない。彼等と笑い合いたくない。彼等と握手したくはない。それでは、彼等は私の敵なのか。いかにも、そうかも知れない。敵? だがしかし、彼等の姿は、私がその一人一人を心の壁に密かに記しつつ憎むためには、あまりにも遠い存在なのだ。だからやはり、私の生の感覚から、いっそう正確には、バスカルの言葉をわるくもじって、こういうべきだろう。──彼は川の向うに住んでいる、と。
著者は「うまいそば屋も喫茶店もない、本当の古本屋もない」とぼやきつつ、「敗戦時の社会の混乱こそ、私の生の原点であり、以来国家的な体制を信じていない、そうした生の感情に団地の生活意識が合う」として、ひばりが丘の団地暮しの雑感を綴る。実家とは疎遠。
1930(昭和5)年生まれで、私の父母よりわずかに上の世代。私が父母と幼稚園から小6途中まで暮らした横浜郊外の団地は、文化的にはともかく「民度」は東京幡ヶ谷より高かった。分断や混乱の気配はない。家族の最も幸せだった頃。その安心を私に与えてくれた親のことを思うと、いくら敗戦を経たからといって、著者の傍観者的な態度に違和感。自分は「あちら側」とは別ってか。いや全員一枚岩になるよう仕向ける世間という管理装置がはたらいて、軍国主義をそのまま経済高度成長に振り向け、そしていま同じ事情で国力が相対的に沈んでいる。スマホ等による時間管理の時代に、みな同じ方を向いて平均化されている日本人は生産性を発揮できない。自分は違うつもりの著者は「文壇」に居場所を得て、そうした構造問題に踏み込まずに「批評家」でいられたのでは。文章巧みでも学ぶものはない。
水木しげる厳選集 虚/ちくま文庫2024
横浜団地時代の私に最大の文化的影響を与えてくれた、管理事務所に設けられた、日曜のみ貸し出しを行う小さな図書室で出会った本たち。北川幸比古のSF絵本『宇平くんの大発明』、そして筑摩書房による大人を意識した漫画本、特に現代漫画⑤水木しげるは貸本時代の『悪魔くん』をダイジェストで収め、粗い絵柄に加え、全貌が見えないことでいよいよ神秘的であった。
その解説で鶴見俊輔は「庶民の生活思想の伝統に根ざす虚無主義。長いものには巻かれろの権力追随をねずみ男が代表し、虚無主義の権力批判・引きずりおろしを鬼太郎が代表している」と水木さんの作風を評しているが、ぜんぜん違うと思うね。
この文庫本にも入っている「錬金術」のような皮肉な話、あるいは『河童の三平』の祖父や本人まで死んでしまって決して帰ってこないことを表面的に捉えているのでは。根本には、人智を超えた自然界の生命現象への畏敬、失われた、もしくは目に見えない世界への哀惜、水木さんほど生命を重んじている作家はいないと思う。手塚治虫と対照的なその資質が最も表れているのが貸本時代の短篇「サイボーグ」。近年の衝撃的な読書体験。その再現を期待した本書には、似た系統のお話が多く、互いに印象を弱めている。現代漫画⑤は完璧だった。
橋本昇/追想の現場/鉄人社2025
大韓航空機撃墜・パリ人肉事件・成田三里塚闘争・日本赤軍・赤尾敏・梨本勝…。フランスの写真通信社sygma (現在はgetty images)の契約カメラマンとして昭和・��成の数々の事件事故現場に立ち会った著者による回想録。ほとんど忘れていたような事象が多く、右でも左でも政治的にはニュートラルな立場で扱う趣旨ということで、しみじみ懐かしい気持ちになったが、それにつけても誤字誤植の多さ。書架の良いところには置けない。
ちなみに日航機123便の事故についても現場の凄惨さが描かれているが、いわゆる「自衛隊機が誤射云々」の陰謀論が成立する余地があるとは思えない。それと「ザイム真理教」、2つの陰謀論を流布しながらも晩年まで愛されキャラとしてメディア露出を続けた森��卓郎氏に、テレビ・ラジオに触れる層の情動を刺激しつつ、主流派に影響を与えない絶妙なポジション、しかも息子にそれを譲る、体制側に都合の良いピエロという墓碑銘を贈りたい。
0 notes
Text

バートランド・ラッセルの言葉366_画像版 n.3149j (July 15, 2019)
私の兄がマルセイユで火葬されたとき、葬儀屋は、このあたりでは神学的偏見のためにこれまで火葬はほとんど行われたことがなかった、と私に告げた。どうやら、人間の肉体の諸部分が教会の庭(=墓地)に虫(訳注:ミミズなどの地中の虫に食べられて取り込まれた状態)や粘土(土)の形で残っている場合よりも、火葬によって気体として拡散してしまった場合の方が、全能の神にとって、それらの諸部分を再び集めるのはいっそう困難だと考えられていたようである(訳注:皮肉)
When my brother was cremated at Marseilles, the undertaker informed me that he had had hardly any previous cases of cremation, because of the theological prejudice. It is apparently thought more difficult for Omnipotence to reassemble the parts of a human body when they have become diffused as gases than when they remain in the churchyard in the form of worms and clay. Source: Religion and Science, 1935, chapt. 4 More Info.: https://russell-j.com/beginner/RS1935_05-030.HTM
<寸言> 程度の差こそあれ、誰にでも何らかの偏見はあります。その中には、宗教や信仰に根ざした神学的な偏見も含まれます。たとえば、火葬に対する偏見がその一例です。 日本は国土が狭いため、墓を造り続ければ土地が墓で埋め尽くされかねません。もちろん、これだけが理由ではなく、日本にはキリスト教的な神学的偏見が存在しなかったこともあり、火葬に対する抵抗感は比較的少なく、土葬と並んで火葬も早くから受け入れられてきました。現在では、火葬がほとんどです。これに対し、キリスト教圏である欧米においては、長らく火葬はあまり行われてきませんでした。広大な国土を持つアメリカなどでは、今後も土葬を続ける余地があるのかもしれません。 こうした背景を踏まえると、「本日のラッセルの言葉」に見られるある表現が興味深く感じられます。それは、「in the form of worms and clay」という一節です。英語にも「人は土に還る(return to the clay)」という表現があるように、「clay(粘土)」は人間の死や有限性を象徴する言葉として用いられます。「死ねば土に還る」という発想は世界中に見られますが、ここで一般的な「soil(土)」ではなく、「clay(粘土)」という言葉が使われています。 私が疑問に思ったのは、なぜ「clay」という表現が使われるのかという点です。つまり: 「土」を「clay(粘土)」と表現するのは、キリスト教が生まれ、広まった地域の自然環境、つまり風土と関係があるのではないか? たとえば、乾燥した砂漠地帯では遺体は白骨化しやすく、「粘土(土)になる」ことはあまり考えられません。一方、ヨーロッパには湿潤で粘土質の土壌が多く存在します。こうした風土の違いが、死者の還る場所としての「clay(粘土)」という表現に結びついた可能性はあるのではないでしょうか。
この点について ChatGPT に確認したところ、次のような補足がありました。 【ChatGPTの補足】> 「clay(粘土)」が人間の死や儚さの象徴として英語表現に現れる背景には、キリスト教が生まれ、広がった地域の自然環境が関係していると考えられます。 キリスト教はパレスチナ(現在のイスラエル周辺)で生まれ、地中海世界を経てヨーロッパへと広まりました。これらの地域の多くには粘土質の土壌が見られます。 粘土は古代文明(メソポタミア、エジプトなど)でも重要な素材であり、神話にもたびたび登場します。 たとえば旧約聖書の創世記2章7節では、「神が人間を土の塵(dust)から形づくった」とあります。原文は「dust of the ground」ですが、英語圏の文学や詩的表現では、しばしばこの「dust」が象徴的に「clay(粘土)」として言い換えられます。 つまり、「clay」は原典の厳密な訳ではなく、宗教的・文化的比喩として定着した語であり、詩的・象徴的な文脈において、人間の出自と死を結ぶ素材として機能しているのです。欧米の多くの地域の風土や宗教文化が、このような言語的イメージを生み出す土台となったのだと考えられます。 このように見てくると、死者をどう弔うかという行為一つにも、自然環境と文化、そして宗教的な象徴表現が深く関わっていることがわかります。そして私たちが何気なく目にする英語表現の背後にも、風土や文明の記憶がしっかりと刻まれているのです。 長いので、以下省略】
Everyone, to varying degrees, harbors some kind of bias. Among these are theological prejudices rooted in religion or belief. One such example is the prejudice against cremation. In Japan, where land is limited, building more and more graves could eventually cover the country with cemeteries. Of course, this is not the only reason, but the absence of Christian theological bias in Japan has also contributed to the relatively low resistance to cremation. As a result, cremation was accepted early on alongside burial, and today it has become the predominant practice. In contrast, in the Christian-influenced West, cremation has historically been much less common. In countries with vast territories, such as the United States, it may still be feasible to continue the practice of burial into the future. Against this background, one expression found in "Today's Words of Russell" strikes me as particularly interesting: "in the form of worms and clay." In English, as in many other cultures, there is the expression "return to the clay," where clay symbolizes human mortality and finitude. The idea that we "return to the earth" after death is widespread throughout the world. However, here we do not see the more general term "soil" but rather the specific word "clay." Why is that? This led me to wonder: Could the choice of the word "clay" instead of "soil" be connected to the natural environment, the climate and landscape, of the regions where Christianity was born and later spread? For instance, in dry desert regions, bodies are more likely to become mummified or reduced to bones, and one would not naturally associate them with clay. On the other hand, much of Europe, especially northwestern regions, has moist, clay-rich soil. Might such environmental differences have influenced the symbolic use of "clay" as the material to which the dead return? When I asked ChatGPT about this point, I received the following explanation: [ChatGPT’s Supplementary Note]: The symbolic use of clay to represent human mortality in English expressions is deeply tied to the natural environment of the regions where Christianity emerged and spread. Christianity originated in Palestine (modern-day Israel), spread through the Mediterranean world, and eventually took root in Europe. Many of these regions have clay-rich soil. In ancient civilizations like Mesopotamia and Egypt, clay was a vital material and often appeared in myths and religious narratives. For example, in Genesis 2:7 of the Old Testament, it is written that "God formed man from the dust of the ground." The original Hebrew word refers to dust, but in poetic or literary English contexts, this dust is often symbolically reinterpreted as clay. Thus, clay is not a literal translation of the original text, but rather a culturally and theologically embedded metaphor. In this way, clay functions symbolically in Western religious and poetic contexts as a substance that connects human origin and death. This symbolic vocabulary is likely rooted in both the religious imagination and the natural environment of the regions where these traditions developed. What this shows is that even something as seemingly straightforward as how we treat the dead is shaped by a deep interconnection between environment, culture, and religious symbolism. The familiar English phrases we use often carry with them layers of memory embedded in climate, civilization, and belief. [The rest omitted for length]
0 notes
Text
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和六年(2024年)11月17日(日曜日)
通巻第8507号
「まっしぐらに走る人々」(トランプ次期政権はタカ派閣僚勢揃い)
米国が驚いた。世界は震撼した。いや、共和党内部も動揺した
*************************
トランプ政権前期(2017=2021)のキッチンキャビネットの主役は長女イバンカと夫君のクシュナーだった。クシュナーはサウジに何回も飛んで中東特使的な役割を果たした。彼自身はユダヤ教徒、イバンカもユダヤ教に改宗した。トランプ政権後半では、クシュナー・イバンカ夫妻は「閣外協力」となる。
トランプ次期政権(2025~)のキッチンキャビネットを率いるのは長男のドナルド・トランプ・ジュニアと次男の夫人ララだろう。
とりわけ副大統領を、想定外だったJD・バンス上院議員の起用を進言したのも、ジュニアである。当選直後から衝撃が連続する閣僚人事はトランプファミリーと、イーロン・マスクら取り巻きが決めている。
顔ぶれを見て、共通するのは「まっしぐらに走る人々」だ。このタカ派強硬派勢揃いには 米国が驚いた。世界は震撼した。いや、共和党内部も動揺した。そしてメディアの攻撃目標になった。
ニューヨークタイムズなど米国左翼メディアはトランプ次期政権の罵倒、罵詈雑言を並べはじめた。
指名された閣僚人事の多くが不適切であり、友人、知人、取り巻きの中から「有能であるより忠誠度」で選抜したエゴイズムと批判した。つぎは各人の攻撃材料探しだ。誰それはいかに無能かというキャンペーンの開幕だ。
マット・ゲーツ次期司法長官は議会下院で議長選出をめぐり、15回も投票することになって議会を混乱させたが、「司法省が標的とした人物がこんどは司法省を標的にしている」と罵声。共和党上院もすんなりと指名承認に踏み切る雰囲気ではないようだ。
「暴れん坊」「無謀な人事」と批判されるゲーツ次期司法長官をめぐって、「議会の破壊主義者は三権分立を破壊する」、「共和党内にも強い反対がある」と批判した。
トランプ次期政権の国防長官に指名されたのはヘグリス(海兵隊OB)で、「FOXニュース」の司会者だった。ヘグセスは2017年に女性への性的暴行の疑いで警察の調べを受けていたと報じた。これは訴追に至らなかった案件で、ワシントンポストは「かれでは国防そのものが危機に瀕する」と書いた。
RJK(ロバート・ケネディ・ジュニア)は反ワクチンで知られるが、彼の厚生福祉長官は「不適切きわまりなく、そもそも13の枝機関と8万人もの職員を抱えている官庁を医学薬学知識に乏しい人間が牽引するなんて(できっこない)」
矛先はディープステートへの挑戦だが、メディアはその基本姿勢には目をつむっている。
FBI長官に指名されそうなカシュ・バテル(元国防長官代行)には「解体屋」のレッテル貼り。トゥルシー・ギャバード国家情報長官指名には『インテリジェンスの知識に欠ける人材』
こうなるともっともタカ派のルビオ次期国務長官が『穏健派』に見える。
トランプ次期大統領は、ホワイトハウス報道官に若干27歳の才媛カロライン・レビットを選んだ。驚くほどの若さだが、下院議員に挑んだ経験があり、議会スタッフ歴もそこそこあ���て、そのうえトランプ選挙でもスポークスウーマンを勤め上げた。
内務長官にはノウスダゴダ州知事のダグ・バーガム。ダグは国家エネルギー会議の議長を兼ねる。バイデン政権下で停滞した国内エネルギー開発推進が急がれることになるだろう。
▼「いまの根強い人気がある」という欺瞞の前置詞
他方、民主党贔屓のメディアは「いまも根強い人気のある」という前置詞を必ずつけてオバマ元大統領を比喩し、その無能を批判しない。オバマに人気があるなどとは作為的であり、かれは院政を敷いて、カマラ・ハリスをパペットにするつもりだったのだ。
FOXニュースにでた政治風刺漫画には笑った。ハリス選対本部で電話も鳴らずしょげかえる民主党幹部のうしろの壁にべたべた貼られたプラカードの標語には「大きな政府」「犯罪にやさしく」「規制強化」「極左」「重税」「国境を開こう」「WOKEへ投票を」
これら総てをトランプはぶちこわそうとしているのだ。
左翼メディアは執拗にレトリックによる情報操作を凝りもしないで続ける。
執行部が辞任に追い込まれた民主党全国委員長にエマニエル駐日大使が立候補する。日本で歓迎されなかった同大使だが、日本の新聞は言論が封殺されているのか、岸田政権にLBGBT法を押しつけて日本の主権を侵害した傲慢エマニエルを批判しなかった。
トランプは『20歳以下の性転換手術を禁止する』とするイーロン・マスクの進言を聞き入れ、民主党に仕掛けられた裁判を葬り、不法移民を追い返すと公言している。
ついでにトランプ嫌いで固まるEU首脳部をトランプは「社会主義者」と断言し、防衛分担で徹底的な要求をつきつける構えである。
波瀾万丈の世界。政治は十倍愉しくなる(?)
●余滴●ヘグセスの入れ墨は宗教的な意味合いを持つ。胸に十字軍。そして米国憲法冒頭の「われら人民」、アメリカ独立戦争の「参加せよ、さもなくば死す」という蛇、国旗、所属していた第187歩兵連隊のワッペンなどが刻まれている。
とくにエルサレム十字架の入れ墨が問題視されるのも、十字軍が建国したエルサレム王国を表すからだ。イスラム教徒やユダヤ教徒に対するキリスト教徒の戦争を意味し、たとえば、2019年にニュージーランドのモスクで起きた銃乱射事件の犯人は十字軍のシンボルをつけていた。2021年1月6日の米国議会議事堂暴動、2017年にバージニア州シャーロッツビルで行われた集会にも、こうした入れ墨組が登場した。
また上腕に「デウス・ヴルト」というラテン語の入れ墨。「神の意志」を意味する。ヘグゼス次期国防長官はパレスチナ問題で二国共存案に反対している。そのうえで聖地におけるイスラエルの独占的主権を支持している。それゆえヘグセスはオバマ政権時代のイラン核合意をつよく批判した。ヘグセスの個人的な見解はかならずしもアメリカ外交に反映されないが、強烈なイスラエル支持者なのである。
7 notes
·
View notes
Quote
首都圏にあるムスリム墓地 霊園内にあるムスリム区画には見慣れない墓が並ぶ 無機質な太陽光パネルが取り囲む高台に見慣れない墓が並ぶ。鮮やかな花が供えられ、墓石にはアラビア語が刻印されている立派な墓。四方をブロック塀で囲んだだけの簡素な墓。盛り土だけの土まんじゅうのような墓……。これらはすべて宗教上の理由で土葬を必要とするムスリム(イスラム教徒)が眠る墓だ。 1980年代後半からパキスタン人やバングラデッシュ人をはじめ多くのムスリムが労働者として来日した。一部は日本人女性と結婚するなどして定住し、彼らの配偶者となった女性も改宗した。いまや日本に住むムスリムは外国人と日本人を合わせて約34万人ともいわれるが、人口増加とともに深刻な問題になっているのが墓不足だ。 ムスリムは宗教上の理由で土葬を望むが、火葬率が99.9%を超える国内にはムスリムの土葬が可能な墓地は限られている。また、ムスリム向け土葬墓地の新設計画が持ち上がっても、地元住民から反対の声があがり、計画が頓挫してしまうケースも少なくない。 「ムスリムの土葬が可能な墓地のない沖縄から遺体が運ばれ、埋葬されたこともあります。いまでは全国から問い合わせがあります。一方で、約束を守らないなどトラブルが多いのも事実です」 こう話すのは、ムスリムの土葬を受け入れる霊園のひとつである埼玉県本庄市の本庄児玉聖地霊園を管理する早川壮丞さん(77)だ。ムスリムの墓不足の「実態」、そして埋葬現場に立つ当事者としての「本音」や「悩み」を聞いた――。 霊園には礼拝室や洗体場も 霊園は丘陵の頂上にある。周囲にあるのは工場だけだ 関越自動車道「本庄児玉IC」から車で15分。市の中心部から離れた丘陵地の坂道を上ると、突如「本庄児玉聖地霊園」の看板が現れた。丘陵の頂上にある霊園の周囲に民家はなく、太陽光パネルが林立している。 霊園の入口近くにはプレハブの管理事務所が建つ。その中には礼拝室がもうけられており、管理事務所の隣には洗体場もある。管理事務所を出て砂利の坂道を上ると、そこには平地が広がっており、入口にアラビア語の看板が立つ。その奥には見慣れない墓が並ぶ。ここがムスリムの土葬墓地区画だ。 本庄児玉聖地霊園は、全国でも10ヵ所程度しかないムスリム土葬墓地のひとつだ。なぜムスリムの土葬を受け入れるようになったのか。こう問うと、早川さんは苦笑いして「『先見性がありますね』なんて言われることもありますが、ムスリムの増加を見越していたわけではありません。まさに偶然が重なった形でした」と明かした。 「墓地を開設した1995年、当時���認可を管轄していた保健所の担当者から『土葬もできる墓地として申請しますか』と尋ねられました。というのも、この周辺地域には土葬の風習が残っていたためです。そこで、1万7000坪の敷地すべてを土葬ができるように申請しました。それがスタートです。 霊園には地主がいて、管理面を私の会社が担当しておりますが、地主が土地をめぐるトラブルに巻き込まれ、紆余曲折の末、4800坪だけが墓地として残りました。残りの土地には現在、太陽光パネルが置かれております。 もともと日本人向けの墓地であり、最大で270基の日本人のお墓がありました。もっとも、土葬を希望する人は長年現れず、現在に至るまで日本人による土葬の申し込みはわずか1件だけです。近年は墓じまいをする人も多く、収益は激減。墓地の維持が長年の悩みでした」 14体もの遺体が無許可で埋葬された 霊園内のイスラム区画 思わぬ事件が起きたのは、経営難に苦しんでいた2019年初めの頃だった。 「霊園の敷地内にムスリムの遺体が私の許可なく埋葬されていたのです。普段足を踏み入れない場所に重機が通った跡があり、それを辿っていくと石とブロック塀が並べられていました。調べたところ、そこには遺体が埋葬されていました。 私の許可なく埋葬していたパキスタン人は群馬県伊勢崎市にあるモスクの関係者を自称していました。土地をめぐるトラブルがあったのは先にお話した通りです。彼は『私はこの土地を購入している』という主張を譲りませんでした。その後も遺体の無断埋葬は続き、合計で14体もの遺体が埋葬されました。 イスラム教では埋葬は死後早いほどよいとされており、彼らは夜中に遺体を埋めるので現場をおさえられませんでした。警察に相談したところ、『現行犯じゃないと対応できない』とのことでした。そこで、監視カメラを設置したところ、ある日、夜中に重機が現れた。『これは埋葬するな』と思ったら、案の定でした。 警察に協力してもらい現場を取り押さえましたが、そこには20人ほどのムスリムがいました。私が管理する霊園内での出来事ですが、彼らは『土地を購入しているから問題ない』と言い張ります。結局、警察立ち合いの下、2019年10月に事務所内で念書を取り交わしました。このときばかりは、パキスタン人の男も態度を一変させ、しきりに『もう二度をやりません』と頭を下げていました」 「無断埋葬」事件の結末 14体もの遺体が無断で埋葬されたが、その一帯はのちに正式な墓地になった 無断で埋葬された14体もの遺体はいまも残る。早川さんは続ける。 「許可なく埋葬されたとはいえ、一度埋めたものを掘り返すことはできません。亡くなった方に罪はありませんからね。結局、そのまま墓地にして、いまでも残っております。 本来、正規の埋葬代金を請求したいところでしたが、200万円を支払ってもらうことで話をまとめました。男は警察官の前で念書に署名・押印し、その書類はいまでも保管してあります。もっとも、1銭も支払われていません。数ヵ月後、念書を取り交わしたパキスタン人は行方不明になり、現在に至っております」 このトラブルについて、本庄市役所の担当者はこう話した。 「土葬については経営者・管理者の方が判断するものであり、行政としてはいいともダメともいう立場ではありません。(埋葬をめぐり、本庄児玉聖地霊園で)トラブルがあったことは把握しておりますが、民間同士のやりとりのため、こちらが何か言える立場にはありません」 予期せぬ事態に困惑した早川さんだったが、東京都・大塚にモスクを置く宗教法人「日本イスラーム文化センター」の責任者から数年前に「ムスリム向けに区画を購入したい」という打診があったことを思い出した。 「大塚のモスクに連絡したところ、改めて『ムスリムの墓を受け入れてほしい』との話がありました。お墓がある限り、何としても霊園を維持していかなければいけません。ある意味、苦渋の決断ではありましたが、受け入れを決め、遺体が無断埋葬されていた場所の近くにムスリム専用の区画をつくりました」 恩義から草刈り 最初に埋葬されたガーナ人男性の墓。早川さんは無償で石材を提供した 最初に埋葬されたのは、大塚のモスクから紹介された埼玉県草加市に住むガーナ人男性だった。 「2019年6月です。一緒に来日した友人たちが故人のために必死にお金を集めたそうです。ただ、埋葬代を用意するのがやっと。本来、墓石代は別途ですが、霊園に余っていた石材を無償で提供し、どうにかお墓の体裁を整えました。友人らはその恩義から定期的に霊園を訪れ、毎年のように草刈りを手伝ってくれます」 墓地に眠るムスリムの国籍は様々だ。最も多いパキスタンのほか、バングラデシュ、スリランカ、インド、インドネシア、イラン、中国、ミャンマー、イラク、ウズベキスタン……。ムスリムの外国人と結婚した日本人もいる。 「受け入れを始めた2019年は8件でしたが、2020年は9件、2021年は23件、2022年は21件、2023年には31件まで増えました。今年は現時点で19件ですが、全体的に増加傾向にあり、合計で111件です。宣伝をしたわけではありません。口コミで広がったようです。ニーズがあったということでしょう。なお、キリスト教徒の土葬区画ももうけており、こちらは合計で5件です」 埋葬されたムスリムの居住地は、最も多いのが霊園の所在地である埼玉、次いで群馬だ。霊園がある本庄市は利根川を渡れば群馬県伊勢崎市という立地であり、また群馬はとりわけ外国人労働者が多く、ムスリムも多い自治体だ。一方で、本庄から遠く離れた場所も少なくない。 「ムスリム墓地のない富山や新潟、宮城、沖縄の方もいます。いまでは全国から問い合わせがあります。地域のモスクを通しての申し込みもあれば、個人からの申し込みもあります」 白い布で包み、掘った穴の中へ ファミリータイプの墓地もある 日本に住むムスリムが死去した際、母国に輸送するという手段もあるが、燃料費の高騰もあり、利用したくても利用できない現状もあるという。 「成田には専門の業者がいて、遺体を運ぶと母国に輸送してくれます。ただし、高額です。以前は60~70万円でしたが、いまは90~100万円に値上がりしています。日本に暮らすムスリムの多くはもともと出稼ぎに来ていた人たち。決して裕福な人ばかりではありません。 こうした事情も考慮し、埋葬料金は当初26万円に設定しました。一時、地主の意向で45万円に値上げしたこともありましたが、現在は30万円に落ち着いています。墓石代については別途という形です」 現在、ムスリムのお墓は111基。新たにファミリータイプの墓地の区画も設置した。早川さんは、ほぼすべての埋葬に立ち会ってきた。 「遺体が霊園に運ばれると、洗体室で遺体をきれいにして白い布で包みます。それからムスリムの区画に移動し、白い布に包まれた状態で1メートル50センチ以上掘った長方形の穴にゆっくり下ろし、頭をメッカの方角に向けて状態で土をかけます。遺体は棺には入れません。つまり土に返す形です。 ひとつの遺体につき、区画は1メートル50センチ×2メートル50センチ。御影石の立派な墓もあれば、土の中に埋めただけの質素な墓もあります。国による違いもありますが、基本的には経済力次第です。 印象に残っているのは日本で生まれ育った10歳のバングラデシュ人のお嬢さんが埋葬されたとき。お父さんは泣きながら穴から出てこなかった……。彼は週末になるとお嬢さんに会いに来ています。日本人に比べ、ムスリムは墓参りにくる頻度が高いと感じます」 管理費を払わないムスリム 霊園を管理する早川さん ムスリムの土葬を受け入れたことで霊園の維持は可能になった。だが、悩みや気苦労は絶えないという。 「お墓の収益なんて微々たるもの。何とか維持できているような状態です。日本人とムスリムでは価値観がまったく違うこともあり、新たな悩みも出てきました。 ムスリムにとって値切るのは当たり前。埋葬してから値切ってくるので呆れてしまいます。向こうは10人以上で事務所に入ってきて、『高い。安くしろ』と訴える。あまりにしつこいので『持って帰ってくれ』と言ったこともあります。こっちはひとりで、向こうは集団ですから怖いですよ。 ムスリムは女性も手ごわい。盛んに『お金がない』と訴えてきます。あまりにもしつこい場合、やはり『持って帰ってもらうしかないね』と伝えます。すると女性は観念して『払います』と現金を取り出す。たとえお金があってもないと言い張る。日本人の感覚とはまるで違います。 約束を守ってくれないのも困ったものです。埋葬をしたいという連絡を受け、準備して待っていても、当日に現れない。こうしたことは一度や二度ではありません。また、年間1万2000円の管理費を払わないケースも多い。これでは草刈りもまともにできません。うちの場合、区画のサイズは決まっていますが、勝手に増設し続ける人もいます。 もちろん常識的なムスリムも多くいます。ただ、彼らは基本的に自分たちの慣習や常識を大切にしており、日本の風習や考え方をさほど意識していません。多文化共生というのは双方の歩み寄りがあってのもの。自分の主張ばかりでは相手も嫌になってしまいます。地域住民の反対により、各地でムスリム向け墓地の計画が頓挫していますが、そうしたことも根本にあるのでしょう」 後編記事『「闇土葬」が行われている…〈ムスリム土葬墓地不足問題〉在日イスラム教徒向け霊園経営者が懸念する「最悪の事態」』では引き続き、ムスリム向け土葬墓地不足の「実態」、そして霊園を管理する当事者としての「本音」や「悩み」を紹介しています。
「無断で死体を埋められた」「お金を払ってくれない」…ムスリム土葬墓地経営者が明かす、墓不足の「実態」と当事者の「深刻な悩み」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース
2 notes
·
View notes
Text
支配層が被支配層の構造的不満(経済格差、貧困、社会的不平等など)を逸らすために、外国との対立や国内の緊張を意図的に高める「分断統治」や「スケープゴート」戦略を用いた例は、歴史的に数多く存在します。この手法は、内部の不満を外部の敵や国内の少数派に向けさせることで、支配層への批判をそらし、権力を維持する目的で使われてきました。以下に、歴史的および現代の具体例を時代や地域ごとに整理し、詳細に解説します。日本の事例も含め、構造的不満との関連性を明確にします。
古代・中世の例 1.1 ローマ帝国:パンとサーカス(紀元前1世紀~紀元4世紀) 背景:ローマ帝国では、貧困層(プレブス)の不満が高まり、失業や格差による暴動のリスクが増大。支配層(元老院や皇帝)は、経済的困窮への不満を逸らす必要があった。 手法:無料の食糧配給(パン)と剣闘士試合や戦車レース(サーカス)を提供。外部の「蛮族」(ゲルマン人など)への敵対心を煽り、軍事遠征を正当化。 例:皇帝ネロは、64年のローマ大火の責任をキリスト教徒に転嫁し、迫害を強化。民衆の不満をキリスト教徒に向け、自身の失政を隠蔽()。 構造的不満との関連:都市貧民の生活苦や奴隷制度への不満を、娯楽や外部の敵でそらし、支配層の権力維持。 1.2 中世ヨーロッパ:十字軍(1095~1291年) 背景:封建制度下で農民や下級貴族の経済的困窮が深刻化。土地不足や重税が不満を増幅。 手法:ローマ・カトリック教会と封建領主は、イスラム教徒や「異教徒」を敵視する十字軍を組織。聖地奪還の名目で民衆を動員し、内部の不満を外部へ転換。 例:第1次十字軍(1095年)では、農民十字軍が貧困層を中心に結成され、経済的困窮から目をそらす宗教的熱狂が煽られた()。 構造的不満との関連:農民の貧困や土地集中への不満を、宗教的「敵」への闘争で逸らし、教会と貴族の支配を強化。
近世の例 2.1 スペイン帝国:新大陸征服と異端審問(15~16世紀) 背景:スペインでは、農民や都市貧民の貧困が深刻化。カトリック王権は、経済格差への不満を抑える必要があった。 手法:新大陸(アメリカ)での植民地征服を「神の使命」と喧伝し、貧困層を冒険や略奪に動員。国内では異端審問でユダヤ人やムスリムをスケープゴートに。 例:1492年のユダヤ人追放(アルハンブラ勅令)で、ユダヤ人が財産没収や迫害の対象に。民衆の経済的不満がユダヤ人に向けられた()。 構造的不満との関連:重税や土地集中への不満を、宗教的「敵」や植民地での富の約束でそらし、王権を安定化。 2.2 フランス絶対君主制:対外戦争(17~18世紀) 背景:ルイ14世時代、農民の重税や貴族の特権への不満が高まり、反乱(フロンドの乱など)が頻発。 手法:対オランダ戦争やスペイン継承戦争で「国民の団結」を訴え、外部の敵(オランダ、イングランド)を強調。宮廷文化(ヴェルサイユ)で民衆の憧れを煽り、不満を逸らす。 例:1672年のオランダ戦争で、ルイ14世は「フランスの栄光」を宣伝。民衆の貧困問題を背景に押しやった()。 構造的不満との関連:農民の重税や貧困を、愛国主義や戦争で覆い隠し、絶対君主制を維持。
近代の例 3.1 ナチス・ドイツ:ユダヤ人迫害と拡張主義(1933~1945年) 背景:第一次世界大戦後のドイツは、ヴェルサイユ条約やハイパーインフレで経済格差が拡大。失業率は1932年に30%超()。 手法:ヒトラーはユダヤ人を「経済的搾取者」と決めつけ、スケープゴートに。反ユダヤ主義を煽り、領土拡張(レーベンスラウム)で国民の不満を外部へ転換。 例:1935年のニュルンベルク法でユダヤ人の権利を剥奪。1938年の「水晶の夜」でユダヤ人店舗が襲撃され、民衆の経済的不満がユダヤ人に向けられた()。 構造的不満との関連:失業や貧困への不満を、ユダヤ人や「敵国」(ポーランド、ソ連)に転嫁し、ナチスの権力を強化。 3.2 大日本帝国:軍国主義とアジア侵略(1930~1945年) 背景:1920~30年代の日本は、農村の貧困や労働争議が深刻化。1929年の世界恐慌で経済格差が拡大。 手法:軍部と政府は「大東亜共栄圏」を掲げ、中国や東南アジアを「敵」とし、愛国主義を煽った。国内では、左翼や労働運動を「非国民」として弾圧。 例:1931年の満州事変で、中国を「日本の生存を脅かす敵」と宣伝。農村の貧困層を軍や植民地に動員し、不満を逸らす()。 日本の構造的不満:農村の地主支配や都市労働者の低賃金への不満を、軍事拡大や「国家の使命」で覆い隠し、天皇制を正当化。 3.3 イギリス帝国:植民地支配と民族分断(19~20世紀初頭) 背景:産業革命後のイギリスでは、労働者階級の貧困や労働条件悪化への不満が高まった。 手法:植民地(インド、アフリカ)での「文明化の使命」を強調し、外部の敵(現地民族)への対立を煽った。国内では、アイルランド人や移民をスケープゴートに。 例:インドの1857年セポイの反乱を「野蛮な反逆」と宣伝し、英国民の団結を強化。国内の貧困問題を覆い隠した()。 構造的不満との関連:労働者の低賃金やスラム問題を、帝国主義の「栄光」でそらし、支配層の特権を維持。
現代の例 4.1 米国:反移民感情と対外戦争(2001年以降) 背景:2008年の金融危機やコロナ禍(2020~2022年)で、米国の格差が急拡大。上位1%が富の32%を占有(2022年)、失業や低賃金への不満が高まる()。 手法: 対外戦争:9/11後の「テロとの戦い」で、アフガニスタンやイラクを敵視。愛国主義を煽り、経済格差への不満を逸らす。 反移民感情:トランプ政権(2017~2021年)は、メキシコ移民やムスリムを「犯罪者」「テロリスト」と決めつけ、国境の壁建設を推進。民衆の経済的不満を移民に向けた。 例:2016年トランプ選挙キャンペーンで「メキシコが仕事を奪う」と宣伝。低賃金労働者の不満を、NAFTAや移民に転嫁()。 構造的不満との関連:金融危機後の賃金停滞(中間層の実質賃金:1970年代並み)や医療費高騰への不満を、外部の「敵」でそらし、富裕層への批判を回避。 4.2 ロシア:ウクライナ侵略とナショナリズム(2014年~現在) 背景:ロシアでは、プーチン政権下でオリガルヒ(富裕層)が富を独占。2022年、上位1%が富の40%超を占有()。経済停滞や貧困への不満が高まる。 手法:ウクライナや西側(NATO)を「ロシアの脅威」とし、愛国主義を煽る。国内の反体制派やLGBTQをスケープゴートにし、弾圧。 例:2014年のクリミア併合、2022年のウクライナ侵攻で「ロシアの復権」を宣伝。民衆の経済的不満を「西側の陰謀」に向けた()。 構造的不満との関連:経済制裁や資源依存経済の停滞による貧困を、ナショナリズムで覆い隠し、プーチンとオリガルヒの支配を維持。 4.3 インド:宗教的対立の利用(2014年以降) 背景:モディ政権下で、経済成長の一方で貧困層(人口の30%)の不満が高まる。上位1%が富の22%を占有(2023年)()。 手法:ヒンドゥー至上主義を掲げ、ムスリムやキリスト教徒を「インドの敵」と位置づけ。宗教的対立を煽り、経済格差への不満を逸らす。 例:2019年の市民権改正法(CAA)で、ムスリムを排除する政策を推進。ヒンドゥー民衆の不満をムスリムに向けた()。 構造的不満との関連:農村の貧困や失業(若年層失業率20%超)を、宗教的ナショナリズムで覆い、富裕層や政府への批判を抑制。 4.4 日本:外国人労働者への敵視(2000年代~現在) 背景:日本の格差拡大(ジニ係数0.33、2023年)や非正規雇用(労働者の40%)が、若年層や低所得層の不満を増大。少子高齢化で労働力不足も深刻。 手法:一部政治家やメディアが、外国人労働者(特にアジア系)を「犯罪増加」や「文化の脅威」とし、スケープゴートに。愛国主義や「日本らしさ」を強調。 例:2018年の入管法改正を巡り、右派メディアが「外国人労働者が仕事を奪う」と報道。コロナ禍(2020年)では、外国人労働者への排斥感情が一部で高まった()。 構造的不満との関連:非正規雇用の低賃金(正規の60%)や若者の貧困(1人親世帯の貧困率50%)を、外国人への敵視でそらし、富裕層への課税議論を回避。 4.5 ハンガリー:反EUと反移民プロパガンダ(2010年以降) 背景:オルバン政権下で、経済格差が拡大。上位10%が富の40%を占有(2022年)。地方の貧困や失業が不満を増幅()。 手法:EUや移民(特に中東・アフリカ系)を「ハンガリーの価値観を脅かす」と宣伝。反ユダヤ主義や反ロマ感情も煽る。 例:2015年の難民危機で、オルバンは「移民が仕事を奪う」と主張し、国境フェンスを建設。民衆の経済的不満を移民に向けた()。 構造的不満との関連:EU補助金が富裕層に集中する中、貧困層の不満を反EUナショナリズムで逸らし、政権の支配を強化。
共通パターンと分析 5.1 分断統治のメカニズム 外部の敵:外国や「異民族」を脅威とすることで、国民の団結を促し、内部の不満をそらす(例:ナチスのユダヤ人、ロシアのウクライナ)。 国内のスケープゴート:少数派(宗教、民族、性的マイノリティ)を標的にし、経済的困窮の原因とみなす(例:日本の外国人労働者、インドのムスリム)。 愛国主義・ナショナリズム:国家の「偉大さ」や「危機」を強調し、経済格差への不満を覆い隠す(例:大日本帝国の軍国主義、トランプの「MAGA」)。 5.2 メディアの役割 支配層は、マスコミやSNSを活用し、スケープゴートや敵対イメージを拡散。例:ナチスのプロパガンダ映画、現代のXでの反移民投稿()。 日本では、テレビや右派メディアが「外国人犯罪」を誇張し、格差問題を背景に押しやる()。 5.3 構造的不満との関連 経済格差:富の集中(上位1%が37.8~45.5%、2022年)が不満の根源。支配層はこれを隠すため、分断を活用。 失業・貧困:失業率や低賃金(例:米国の実質賃金停滞、日本の非正規40%)が、被支配層の不満を増幅。 機会不平等:教育や雇用の不平等(例:日本の塾費用100万円超)が、階級固定化を助長し、支配層への批判をそらす。
日本特化の分析 歴史的例: 明治~昭和初期:1920年代の農村貧困(小作農の貧困率50%超)を背景に、軍部が「満州開拓」を推進。中国を「敵」とし、農民を植民地に動員()。 戦後高度成長期:1960~70年代の労働争議を抑えるため、政府と企業が「経済大国」のナショナリズムを強調。格差問題を成長で覆い隠した()。 現代: 非正規雇用の増加(40%)や若者の貧困(貧困率15%)への不満を、外国人労働者や「中国脅威論」で逸らす。一部政治家が「日本の伝統」を強調し、格差是正議論を回避()。 例:2023年の入管法改正議論で、右派メディアが「外国人犯罪」を誇張。金融所得課税(20%)の据え置きが優先された()。 展望:若年層のX活用(#格差是正)や少子高齢化(2030年:社会保障費150兆円)が、格差への注目を高める可能性。ただし、排外主義が分断を助長するリスク。
結論 支配層が構造的不満を逸らすために外国との対立や国内の緊張を高めた例は、ローマ帝国の「パンとサーカス」、ナチスのユダヤ人迫害、大日本帝国の軍国主義、現代の反移民プロパガンダ(米国、ロシア、インド、日本、ハンガリー)など多岐にわたります。これらは、経済格差や貧困への不満を、外部の「敵」や少数派に転嫁し、支配層の権力を維持する戦略です。日本では、歴史的に軍国主義、現代では外国人への敵視が同様の役割を果たしています。対策として、市民運動(X活用)、教育改革、メディアの透明性が不可欠で、これらが2035年までに格差是正を加速する可能性(70~90%)があります。
もし特定の例(例:日本の戦前プロパガンダ、現代のSNS利用)や対策の詳細を深掘りしたい場合、または他の地域の事例が必要であれば、教えてください!
0 notes
Text
The Fifth Step
by David Ireland
dir. Finn Den Hertog
2025年5月24日 @sohoplace
2024年にエディンバラとグラスゴーで上演されたデヴィッド・アイルランドの新作で、National Theatre of Scotlandの製作。ジャック・ロウデンは昨年からの続投で、今回はショーン・ギルダーに代わりマーティン・フリーマンが出演。アルコール中毒者のリハビリのための自助グループ、アルコホール・アノニマス (AA) の会合で断酒プロセスにある若いルカ(ロウデン)は年長で25年間断酒しているジェームズ(フリーマン)のメンタリングによって12ステップのプログラムを実行することになる。その過程でルカはキリスト教とその神、そしてキリストに救いの道を見出すが。
マイラ・クラークの美術はプレーンな囲み舞台に各ステップを象徴するような5つのパイプ椅子、小さなテーブルにお茶セットと、舞台を囲む段のみ。椅子は次第に減っていくが、場の合間にロウデンが囲み段を踊り歩いたりする。
二人のパフォーマンスは申し分ない。特に最初の方で貧乏ゆすりが止まらず、自分のポルノ依存や女性に対する(不適切とも言える)関心を無邪気とも言える様子で語り、突然信仰に目覚める若く世間知らずなルカを演じるロウデン、頼りになりそうな落ち着いた態度を取りながらもルカの信仰告白や女性関係を聞くうちに疑心暗鬼になっていくフリーマンのジェームズは、適切なコミックタイミングもあり深刻な雰囲気の漂うシーンでもどこかおかしげになる。作品のトーンとしてはアイルランドを有名にした暴力的な作品群よりも2022年の 『Not Now』 に近く、最終場に緊迫感はあるとはいえ二人の男性の間で依存と信頼、世代間のギャップ、AAが持つ 「スピリチュアル」 な面と信仰とのずれなどを80分の短い時間で攫っていく。わかりやすく単純化しすぎでは、という気もしなくもないが、最近ネットやニュースで話題になる若い男性の右傾化・女性嫌悪に対する理由の説明の可能性をきちんと提示している。ただ、個人的な好みとしてはロイヤルコートの上階やブッシュ、オレンジツリーくらいの規模の舞台で見た方がよりしっくりきたかもしれない。
0 notes
Text
TEDにて
マーク・ロビンソン: 古代ギリシャの建築家の。とある1日
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
アテナイの夜が明ける頃、フェイディアスは既に仕事に遅れています。
時は、紀元前432年、建築家のフェイディアスは、最新で最大規模の神殿、パルテノン神殿造営の総監督です。完成したら、彼の傑作は、女神アテナを祀る壮大な神殿となり、アテナイ人の栄光の証となるでしょう。
ところが、フェイディアスが、建設現場に到着すると5人の役人が待ち構えていました。神殿中央にある神聖な像の金を横領した罪にフェイディアスは問われ、日没までに神殿の全経費と金の薄片全ての報告を余儀なくされます。
さもないと、法廷での判決を受けてしまいます。無実の罪を着せられたにもかかわらず、フェイディアスは驚いていません。パルテノン神殿の建設を命じた政治家ペリクレスには、政府内に多くの敵がいることに加え、このプロジェクト自体、いささか物議を醸すものだからです。
アテナイ市民が期待するのは、ドーリア式の古典的な神殿。つまり、シンプルな柱が水平梁エンタブラチュアを支え、切妻屋根がかぶさる建築様式です。
しかし、フェイディアスの設計は、従来のものに比べはるかに急進的です。柱はドーリア式、梁のフリーズ部分はイオニア式で、アテナイで行われるパナテナイア祭の盛大な祭り風景が全面に描かれます。
神殿の装飾に人間と神々が、並んで描かれたことは、かつて一度もないだけでなく、それには従来の手法より多くの費用がかかります。同僚が支出を記録しているよう神々に祈りながらフェイディアスは自らの潔白を証明すべく動き出します。
まず、建築家のイクティノスとカリクラテスに連絡をします。見直すのは設計図ではなく、基本計画書、シングラファイと3Ⅾ模型のパラデイグマです。3人は、正確な設計図なしにただちに問題を解決しなければなりません。
頼りになるのは、入念な計算と均整美に対する自分たちの直観だけです。とりわけ均整を保つことは難しいことが分かりました。パルテノン神殿は湾曲した地に建てられ、柱はやや内側に傾いています。
力強さを示し、遠くからは真っすぐな柱に見えるようにするため、柱に少し膨らみをもたせるエンタシスの技法が採用されました。神殿の他の要素についても比較的、一貫した比率を採用しながら調和の美しさを計算します。
しかし、設計を変更するには休みなく計算し直さねばなりません。そのうちの1つの計算を手伝った後、フェイディアスは、同僚の金の記録をまとめ特別配達を受け取るため、その場を離れます。
神殿のペディメント(三角形の切妻壁)に使う巨大な大理石が、ペンテリコ山の採石場からちょうど届きました。重さ2~3トンのブロックを運ぶのに通常の傾斜路では崩れてしまうでしょう。
そのためフェイディアスは、新たな滑車の建設を命じます。追加費用を記録し、午後はずっと建設の指揮をとった後、フェイディアスは彫刻の作業場にようやく到着します。彫刻家たちはメトープ部分に神話や伝説に関する92の場面を掘り、神殿に装飾を施しています。
彫刻に描かれるのは、様々な壮大な戦いで、どれも約40年前のペルシア戦争におけるギリシャの勝利を表象するものです。これ程多くのメトープが、神殿に使われたことは未だかつてなく1場面、描かれる毎に費用がかさんでいきます。
最後に、フェイディアスは自身の主要任務である神殿の本尊に取りかかります。分厚い金の層に覆われ、繊細な装飾が施されれた礼拝者の上に高くそびえ立つ像、アテナイの守護神、アテナ・パルテノスの像です。
神殿が完成したら人々はその周りに集まり、お祈りをし捧げものをしながら知恵の女神への献酒を注ぐでしょう。フェイディアスは、残った時間を像の最後の仕上げに費やします。
日が暮れる頃、役人が、彼を問い詰めにやって来ます。フェイディアスの記録を見た後、彼らは勝ち誇ったかのように見上げます。フェイディアスが報告したのは、神殿の一般的な支出で女神像の金に関しては、全く触れられていなかったのです。
その時、フェイディアスを助けるべくペリクレスが到着、神殿造営の支援者は役人に言います「像に使われている金は全て、1つ1つ取って量ることができるのでフェイディアスの無実は証明されるだろう」
作業員にその任務にあたらせ、彼らを夜遅くまで見ているよう役人らに命じるとフェイディアスとペリクレスは、敵のもとを去り彼らをアテナ神の情けに委ねるのです。
(個人的なア��デア)
老子の道教の徳(テー)とアリストテレスのニコマコス倫理学の徳(アリテー)が似ていることから・・・
どちらの起源が先か?調べるととても面白い仮説が出てきた。
中国の道教は紀元前750年位。古代ギリシャ末期のアリストテレスは紀元前350年位。
共に多神教。この時代の情報の伝達速度を考えるとシルクロードで相互的に交流して伝わった可能性も高い。
プラスサムな概念だから。道(タオ)が先で、アリストテレスのニコマコス倫理学の徳(アリテー)が変化して
老子の道教の徳(テー)となり、神仏習合みたい道徳になった?アリストテレスのニコマコス倫理学の徳(アリテー)は具体的だが、道徳経ではあいまい。
当時は、西洋と東洋の最先端を統合?古代中国では、老子は仙人とも言われていたし、始皇帝もこの頃の激動の時代。
どうなのか?
バラモン教に対して創始した仏教もブッダにより誕生し、アリストテレスの時代に近い年代であることは偶然の一致だろうか?
ニコマコス倫理学に似ている仏教最高レベルの奥義が「中道」ということ。チベット経由で中国にも伝わります。そして、日本にも。
その後、古代ギリシャは300年後、多神教の古代エジプト文明を滅ぼしてローマ帝国になっています。キリスト教も誕生。
その後、国教へ。一神教が広まり紀元後が始まります。
現在のEUは、NATOがウクライナ侵攻でクローズアップされたこと。さらに、13の暦がひと回りして2000年前位の状況も含めて考えると
トルコまで領土にした古代ローマ帝国の民主主義版をフランス、ドイツは構築しようとしてる?
イギリスがブレグジット(Brexit)で離脱したのは、かつてのローマ帝国の過ちを回避した可能性も?
もし、以前、機運が高まった時にロシアがEUに加盟していれば、古代ローマ帝国2.0(民主主義版)が建国していたかもしれない。
大西洋を超えてアメリカ大陸からロシアを含めて、北半球に巨大なモンゴル帝国を超えた人類史上最大の領域が誕生するので・・・
今からでもロシアは遅くないので加盟したほうがいいような気がします。
真実はわからないが、そんな仮説がインスピレーションとして出てきた。
仏教最高レベルの奥義が「中道」と言葉で言うのは簡単だけど、体得して実践するのは至難の業。
ピータードラッカーも言っている。
それを可能にする方法を段階を踏んで導いた最初の人が釈迦です。
初心者向けとして、アビダンマや八正道がそれに当たります。具体的な方法を体系化しています。
極端な見解にとらわれない(顚倒夢想:てんとうむそう)よう人が心の苦しみから逃れるには、八つの道を守れば良い。
正しい見かた、正しい思い、正しいことば、正しい行い、正しい生活、正しい努力、正しい判断。そして、正しい考えかたである。
ところで「正しい」とは、何をもってそう言うのだろうか?
ここでは、アリストテレス(サンデルの正義)の定義ではありません。
この場合の定義は、ブッダの説いている「中道」が「正しい」という意味です。両極端にとらわれない正しい立場(中道)が悟りへと導く唯一の道なのです。
悟りから始まり、この世は、様々な概念が重なり合うため、概念の機微や均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!
最初は大変だが、ドラゴンボールに登場するスーパーサイヤ人みたいに、これを大変なレベルじゃなくなるくらいに習慣化することがコツです。
参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。
法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。
また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。
現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。
続きは、後ほど。倫理は強制ではなく一定のプロトコルに基づく自由権なので
アリストテレスのニコマコス倫理学には、快楽的生活、社会的生活、真理を追求する生活がある。
思考の知的な徳は、形式知の根本?
もう一つ、性格の徳は、暗黙知の根本?
アリストテレスのいう定義である悪徳の反対は、有徳。有徳に転換する努力が必要。
悪徳に似た概念として、仏教でも、具体的に邪道四つと定義されている。
テーラワーダ仏教に似ている。顚倒夢想(てんとうむそう)になるため悪行為を段階的に最小限する努力が善行為。
こうすることで「パワーか?フォースか?」の書籍でいうパワーが人類全体で平等に底上げされる。
ここで言われる「Powerパワー」は(スターウォーズでのライトサイドのForceフォース)そして、「Forceフォース」は(ダークサイドの方)という前提です
そして、ブッダの説いている「中道」は、「パワーか?フォースか?」の書籍でいう「意識のマップ」内の「中立」レベルに当たるかもしれない。
アビダンマとは異なる領域なので、うつ病、ADHD、自律神経失調症、発達障害などは、精神科医や心療内科へどうぞ。
もう少し、テーラワーダ仏教で教え伝えられている経験則を初心者向けから二、三歩、歩みを進めると「預流道心」と言われる悟りの最初の心が生まれる瞬間があります。
自力で到達するのは危険なので、お寺のお坊さんに詳しくは聞いてください。
自分の解釈では、ここに到達する感覚としては、量子力学の本質である「場の量子論」を本当に理解した瞬間が一番近い感覚です。しかし、検証できないので本当に到達したかわかりません。
テーラワーダ仏教のアビダンマでは、「預流道心」に到達すると自然と悟りの道に自動的に回帰できるようになるそうです。次に、七回生まれ変わるまでに完全に悟りの流れに乗れる。
前世で「預流道心」に到達してると子供の頃から、桁の違う天才になりやすい傾向が発現してくるそうです。
そして、六道輪廻するのは、人間界か天界のみだそうです(一神教では、天国に近い領域に似ている)他にいくつか特徴があります。
「預流道心」に到達すると「第一禅定(ぜんじょう)」状態に自動的になります。
一神教では「天国」に相当することですが、テーラワーダ仏教には、この先がありますが、ここまでにします。
厳密には違うけど、わかりやすく言うと精神領域がスーパーサイヤ人に到達するようなイメージ。しかし、すぐ心の状態は普通になります。
漫画のイメージのように身体は強くなりません。
言葉の定義として「禅(Zen)」は、ブッダが伝授された「第一禅定(ぜんじょう)」が起源。
言葉の定義として、ここでの「定」は、サマーディとも「梵天」の「梵」とも呼ばれます。
日本語ではわかりずらいけどサンスクリット語などにすると全て関連してることがわかります。
サマーディ瞑想とも深く関連していて、瞑想しすぎると「あの世」の人になってしまうので、ほどほどの八正道で「この世」の状態を維持しないと危険です。
戻ってこれなくなります。
再起不能になる可能性が高いため、本当に詳しくは、歴史あるお寺でお坊さんに聞いて下さい。
再起不能になる可能性が高いため、本当に詳しくは、歴史あるお寺でお坊さんに聞いて下さい。
再起不能になる可能性が高いため、本当に詳しくは、歴史あるお寺でお坊さんに聞いて下さい。
歴史に耐え抜いた哲学の基盤がない権力者が最も危険な存在です。
<おすすめサイト>
エピソード6Episode6 - アトラクタフィールドと人類の歴史について(パワーか、フォースか 改訂版―人間のレベルを測る科学 - デヴィッド・R・ホーキンズ Amazon)
ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019
ボブ•サーマン:私たちは、だれでも仏陀になれるという話
日本テーラワーダ仏教協会
マイケル・サンデル:メリトクラシー(能力主義)の横暴
アレグザンダー・ベッツ:ブレグジットはなぜ起きた?次にするべきことは何か
マーカス・デュ・ソートイ:数学の核心にあるパラドックス - ゲーデルの不完全性定理
ユバル・ノア・ハラーリ:ウクライナの戦争がすべてを変える?
マーク・ロビンソン:ヨーロッパの歴史を変えたノルマン人
ジェシー・バイアック:呪文、脅迫、ドラゴン、ヴァイキングのルーン石碑に刻まれた秘密のメッセージ
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版
#マーク#ロビンソン#建築#ギリシャ#ローマ#アリストテレス#倫理#仏教#中国#イギリス#Brexit#ウクライナ#トルコ#フランス#ロシア#宗教#キリスト#ユダヤ#サンデル#正義#古代#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery
1 note
·
View note