#骨董の似合う街
Explore tagged Tumblr posts
Text
〈お元気ですか?今日は、何の日?〉
https://sunnyhomewor.thebase.in/
ドライりんご 発売中です。
おはようございます。
「我々が いつも互いに助け合っていれば
誰も運など 必要としないだろう」
晴れのち曇り 最高気温22℃の予報です。
今日は たすけあいの日です。1965年に
全国社会福祉協議会が 制定します。
たすけあい、大切です。
If were the last day of my life,
I want to do what I am about
to do today?
今日もいろいろ頑張ります。
よろしくお願い申し上げます。
http://www.sunny-deli-secco.com/
#ドライりんご #ドライアップル
#乾きリンゴ #driedapple
#granola #driedfruits
#小樽市 #otaru #ワインのおとも
#北海道 #子どものおやつ
#サニーホームワークス
#おやつの時間 #小樽お土産
#苹果干 #apelkering #タルシェ
#말린사과 #オタルエ #otarue
#pommesséchées




0 notes
Text
各地句会報
花鳥誌 令和5年5月号
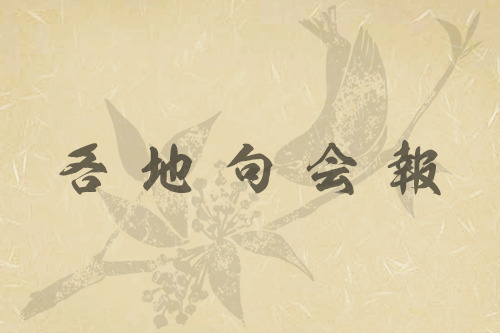
坊城俊樹選
栗林圭魚選 岡田順子選
………………………………………………………………
令和5年2月2日 うづら三日の月花鳥句会 坊城俊樹選 特選句
厨女も慣れたる手付き雪掻す 由季子 闇夜中裏声しきり猫の恋 喜代子 節分や内なる鬼にひそむ角 さとみ 如月の雨に煙りし寺の塔 都 風花やこの晴天の何処より 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月4日 零の会 坊城俊樹選 特選句
暗闇坂のチャペルの春は明日あたり きみよ 長すぎるエスカレーター早春へ 久 立春の市の算盤振つてみる 要 冬帝と暗闇坂にすれ違ふ きみよ 伊達者のくさめ名残りや南部坂 眞理子 慶應の先生眠る山笑ふ いづみ 豆源の窓より立春の煙 和子 供華白く女優へ二月礼者かな 小鳥 古雛の見てゐる骨董市の空 順子 古雛のあの子の部屋へ貰はれし 久
岡田順子選 特選句
暗闇坂のチャペルの春は明日あたり きみよ 冬帝と暗闇坂にすれ違ふ 同 大銀杏八百回の立春へ 俊樹 豆源の春の売子が忽と消え 同 コート脱ぐ八咫鏡に参る美女 きみよ おはん来よ暗闇坂の春を舞ひ 俊樹 雲逝くや芽ばり柳を繰りながら 光子 立春の蓬髪となる大銀杏 俊樹 立春の皺の手に売るくわりんたう 同 公孫樹寒まだ去らずとのたまへり 軽象
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月4日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句
敬な信徒にあらず寒椿 美穂 梅ふふむ野面積む端に摩天楼 睦子 黄泉比良坂毬唄とほく谺して 同 下萌や大志ふくらむ黒鞄 朝子 觔斗雲睦月の空に呼ばれたる 美穂 鼻歌に二つ目を割り寒卵 かおり 三路のマネキン春を手招きて 同 黄金の国ジパングの寒卵 愛 潮流の狂ひや鯨吼ゆる夜は 睦子 お多福の上目づかひや春の空 成子 心底の鬼知りつつの追儺かな 勝利
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月6日・7日 花鳥さざれ会 坊城俊樹選 特選句
潮騒を春呼ぶ音と聞いてをり かづを 水仙の香り背負うて海女帰る 同 海荒るるとも水仙の香の高し 同 ���庭の十尺灯篭日脚伸ぶ 清女 春光の中神���も丹の橋も 同 待春の心深雪に埋もりて 和子 扁額の文字読めずして春の宿 同 砂浜に貝を拾ふや雪のひま 千加江 村の春小舟ふはりと揺れてをり 同 白息に朝の公園横切れり 匠 風花や何を告げんと頰に触る 笑子 枝川やさざ波に陽の冴返る 啓子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月8日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句
雪を踏む音を友とし道一人 あけみ 蠟梅の咲き鈍色の雲去りぬ みえこ 除雪車を見守る警備真夜の笛 同 雪掻きの我にエールや鳥の声 紀子 握り飯ぱりりと海苔の香を立て 裕子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月10日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句
東風に振る竿は灯台より高く 美智子 月冴ゆる其処此処軋む母の家 都 幽やかな烏鷺の石音冴ゆる夜 宇太郎 老いの手に音立て笑ふ浅蜊かな 悦子 鎧着る母のコートを着る度に 佐代子 老いし身や明日なき如く雪を掻く すみ子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月11日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句
朝光や寺苑に生るる蕗の薹 幸風 大屋根の雪解雫のリズム良き 秋尚 春菊の箱で積まれて旬となる 恭子 今朝晴れて丹沢颪の雪解風 亜栄子 眩しさを散らし公魚宙を舞ふ 幸子 流れゆくおもひで重く雪解川 ゆう子 年尾句碑句帳に挟む雪解音 三無 クロッカス影を短く咲き揃ふ 秋尚 あちらにも野焼く漢の影法師 白陶 公魚や釣り糸細く夜蒼し ゆう子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月13日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句
犬ふぐり大地に笑みをこぼしけり 三無 春浅しワンマン列車軋む音 のりこ 蝋梅の香りに溺れ車椅子 三無 寒の海夕赤々漁終る ことこ 陽が風を連れ耀ける春の宮 貴薫 青空へ枝混み合へる濃紅梅 秋尚 土塊に春日からめて庭手入 三無 夕東風や友の消息届きけり 迪子 ひと雨のひと粒ごとに余寒あり 貴薫
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月13日 武生花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句
浅春の眠りのうつつ出湯泊り 時江 老いたれば屈託もあり毛糸編む 昭子 落としたる画鋲を探す寒灯下 ミチ子 春の雪相聞歌碑の黙続く 時江 顔剃りて少し別嬪初詣 さよ子 日脚伸ぶ下校チャイムののんびりと みす枝 雪解急竹���ね返る音響く 同 寒さにも噂にも耐へこれ衆生 さよ子 蕗の薹刻めば厨野の香り みす枝
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月14日 萩花鳥会
水甕の薄氷やぶり野草の芽 祐子 わが身共老いたる鬼をなほ追儺 健雄 嗚呼自由冬晴れ青く空広く 俊文 春の園散り散り走る孫四人 ゆかり 集まりて薄氷つつき子ら遊ぶ 恒雄 山々の眠り起こせし野焼きかな 明子 鬼やらひじやんけんで勝つ福の面 美惠子
………………………………………………………………
令和5年2月15日 福井花鳥会 坊城俊樹選 特選句
吹雪く日の杣道隠す道標 世詩明 恋猫の闇もろともに戦かな 千加江 鷺一羽曲線残し飛び立てり 同 はたと止む今日の吹雪の潔し 昭子 アルバムに中子師の笑み冬の蝶 淳子 寒鯉の橋下にゆらり緋を流す 笑子 雪景色途切れて暗し三国線 和子 はよしねまがつこにおくれる冬の朝 隆司 耳目塗り潰せし如く冬籠 雪 卍字ケ辻に迷ひはせぬか雪女 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月16日 伊藤柏翠記念館句会 坊城俊樹選 特選句
指先に一つ剥ぎたる蜜柑の香 雪 大寒に入りたる水を諾ひぬ 同 金色の南無観世音大冬木 同 産土に響くかしは手春寒し かづを 春の雷森羅万象𠮟咤して 同 玻璃越しに九頭竜よりの隙間風 同 気まぐれな風花降つてすぐ止みて やす香 寒紅や見目安らかに不帰の人 嘉和 波音が好きで飛沫好き崖水仙 みす枝 音待てるポストに寒の戻りかな 清女 女正月昔藪入り嫁の里 世詩明
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月17日 さきたま花鳥会 坊城俊樹選 特選句
奥つ城に冬の遺書めく斑雪 月惑 顔隠す一夜限りの雪女郎 八草 民衆の叫びに似たる辛夷の芽 ふじほ 猫の恋昼は静かに睨み合ひ みのり 薄氷に餓鬼大将の指の穴 月惑 無人駅青女の俘虜とされしまま 良江 怒号上げ村に討ち入る雪解川 とし江 凍土を突く走り根の筋張りて 紀花 焼藷屋鎮守の森の定位置に 八草 爺の膝捨てて疾駆の恋の猫 良江
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月19日 風月句会 坊城俊樹選 特選句
古玻璃の奥に設ふ古雛 久 笏も扇も失せし雛の澄まし顔 眞理子 日矢さして金縷梅の縒りほどけさう 芙佐子 梅東風やあやつり人形眠る箱 千種 春風に槻は空へ細くほそく ます江 山茱萸の花透く雲の疾さかな 要 貝殻の��の片目閉ぢてをり 久 古雛髪のほつれも雅なる 三無 ぽつねんと裸電球雛調度 要
栗林圭魚選 特選句
紅梅の枝垂れ白髪乱さるる 炳子 梅園の幹玄々と下萌ゆる 要 濃紅梅妖しきばかりかの子の忌 眞理子 貝殻の雛の片目閉ぢてをり 久 古雛髪のほつれも雅なる 三無 老梅忌枝ぶり確と臥龍梅 眞理子 山茱萸の空の広さにほどけゆく 月惑 八橋に水恋うてをり猫柳 芙佐子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月21日 鯖江花鳥句会 坊城俊樹選 特選句
師を背負ひ走りし人も雪籠 雪 裏庭開く枝折戸冬桜 同 天帝の性こもごもの二月かな 同 適当に返事してゐる日向ぼこ 一涓 継体の慈愛の御ん目雪の果 同 風花のはげしく風に遊ぶ日よ 洋子 薄氷を踏めば大空割れにけり みす枝 春一番古色の帽子飛ばしけり 昭上嶋子 鉤穴の古墳の型の凍てゆるむ 世詩明 人の来て障子の内に隠しけり 同 春炬燵素足の人に触れざりし 同 女正月集ふ妻らを嫁と呼ぶ 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月26日 月例会 坊城俊樹選 特選句
能舞台昏きに満ちて花を待つ 光子 バス停にシスターとゐてあたたかし 要 空に雲なくて白梅すきとほる 和子 忘れられさうな径の梅紅し 順子 靖国の残る寒さを踏む長靴 和子 孕み猫ゆつくり進む憲兵碑 幸風 石鹸玉ゆく靖国の青き空 緋路 蒼天へ春のぼりゆく大鳥居 はるか
岡田順子選 特選句
能舞台昏きに満ちて春を待つ 光子 直立の衛士へ梅が香及びけり 同 さへづりや鉄のひかりの十字架へ 同 春の日を溜め人を待つベンチかな 秋尚 春風や鳥居の中の鳥居へと 月惑 料峭や薄刃も入らぬ城の門 昌文 梅香る昼三日月のあえかなり 眞理子 春陽とは街の色して乙女らへ 俊樹
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和5年2月 九州花鳥会 坊城俊樹選 特選句
ポケットの余寒に指を揉んでをり 勝利 黒真珠肌にふれたる余寒かな 美穂 角のなき石にかくれて猫の恋 朝子 恋仲を知らん顔して猫柳 勝利 杖の手に地球の鼓動下萌ゆる 朝子 シャラシャラとタンバリン佐保姫の衣ずれ ひとみ 蛇穴を出て今生の闇を知る 喜和 鷗外のラテン語冴ゆる自伝かな 睦古賀子 砲二門転がる砦凍返る 勝利 小突かれて鳥と屋や に採りし日寒卵 志津子 春一番歳時記の序を捲らしむ 愛
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
4 notes
·
View notes
Text

日記2
もういいかいのまあだだよ。
布団を干して、座布団も洗って。とりこんで。
コンビニで配達をだして、買い食いするの我慢して。
おかっぱのおねいさんの回だった。大学生で混んでいた。
今日もごはんのお口がしないのでそうめんでごまかす。
ぼくも特に揖保乃糸と決めてなくて安いのは安いのでいい。
そいでも家にあるのはいつも揖保乃糸です。
でも、肉うどんもちょっと食べられそう。
骨董グラスけっこう集めているけどいつもは三ツ矢サイダーグラス。
近年にノベルティーでもらったロゴだけで使いやすいかたち。
朝日のビールジョッキもいっぱいあるんだよ。
ひまとも言うけど何かはまってギター弾いて暮れていきそう。
きっとハナミズキも散り際をむかえるのかな、
上からベランダで眺めるのが好きでたのしみだった、
そんな実家時代に母が「今の曲いい曲ね」というのは、
聴いているものよりか届きやすいぼくのコピーした、
bert janschの「one for jo」っていう曲でした。
今も好きかなぁ。たびたびだけど思い出す。
あとbaden powell版の「宇宙飛行士」も好きだって。
ギター試奏のとき必ずそれかフィッシュマンズの「ずっと前」。
びよーんってならないかなって。たったそれだけわかればいい。
パンクっ子だったぼくは帰郷して英国フォークの森へ爪弾きだした。
その先にかえって日本のふるいフォークロックがあったりしました。
ムーンライダースはずっと好き���参加作関連作も追って聴いて。
べただけどモダーンミュージックとカメラ=万年筆が好きです。
はちみつぱいと関連をあまり聴かずに通り過ぎてしまいました。
けど「ぼくの倖せ」も「酔いどれダンスミュージック」も大好き。
なんていうかうぬぼれか自分に似合いすぎてこわくなったのと、
火の玉ボーイ共々、誰かがいつだって持っていて、
また聴かせてもらえばいっかって小僧時代。
あがたさんは林静一さん鈴木翁二さんも好きで切っても切り離せぬ。
が「夢見るように眠りたい」のサントラが特に好きなのです。
友だちもいなくなってベイビーブルー。
センチメンタル通りいつか聞かせて。
街の君、”君がほしい、君がほしい”のところ、
がんばって目め見て歌ってみる。それかふたり鼻歌。激笑。
目まっ茶色なのでおもしろいですよきっと。歌うのはめちゃ苦手。
ド何なのですか?
そういえばうまれてはじめてのレコードは義兄のシティポップ群と、
川べりの骨董やさんで買った友部正人「もう春だね」10円でした。
次にあがたさんの「永遠のマドンナK」10円でしたっけね。
幻のようなお店で「あそこに骨董屋さんあったよね」って、
近所に住む高山くんに話したらそんなもんないよと言われた。
まぼろしで構わない、いい例です。
お互いうまれる時代まちがえたねって言われる系かな。
町の花ってね、マンホールによく書いてあるんだよ。
ぼくの誕生花はひとりしずかで野原で咲いているとうれしいです。
星の巡りとそこに咲く花のあることはとても素敵ですね。
だんだんとまた左手指がかたくなるのかな。
いやな思い出しかないギターが漂白された。
土日なおのことお忙しそうですね、お体ご自愛下さい。
あそぼうってぼくも言えるときがきたらいいなとおもいます。
どうしよう。胸のなかにしまった風船いつかふたりで割りましょう。
君の誕生花はなにですか?はやくかえってきてください。
youtube
3 notes
·
View notes
Text
230604
青組、速いです!赤組、頑張ってください!
マニュアル通りのやる気があるのかないのか分からない実況と聴き覚えのある、あの急かされる音楽で目を覚ます。
今日は近くの学校で運動会が行われているらしい。
そういえば 私も放送委員で同じような実況をしたっけ、と振り返る。小学生の頃、放送委員は運動会で担当の時間に自分の好きな曲を流して良いというルールがあり、私は一番ハマっていたアイドルの曲を流した。当時好きだった男の子に 「これ絶対○○(私)が流したと思った!でもちょっと(テイスト的に)違くない?」 と言われたことを思い出す。
放送委員という権力の下に 私は中学生になってから軽く暴走していた。朝にミセス、昼にマイファス(騒がしくない曲)、ユニゾン(騒がしくない曲)などを流していた。挙げ句の果てには、とある先生から 「君が担当の日は騒がしいね。」 などと皮肉を言われたのだが、やはり捻くれていた私は 黙って聴いてくれ、と反省などしていなかった。今になって振り返ると、甚だ迷惑な生徒だったと思う。
今日は朝から起きることができたからなのか、1人で出かけようという気分になった。
お気に入りのヒスのキャミを着る。
12時半が過ぎた頃、東京駅に着く。
高校3年の時の担任が骨董市で露天商として出店しているので、近況報告を兼ねて久しぶりに会いに行く。お土産を買って行こうとふらっとお店に入る。
「紫のピアスめっちゃ可愛いですね!」
レジをしてくださったお姉さんについ最近開けたナベルのピアスを褒められる。
私ファーストピアスこんなに可愛くなかったんですよ〜
私、これファーストピアスなんです、1週間前くらいに開けたばかりで
そうなんですか!いいな〜 可愛いです!
ありがとうございます〜
勢いで開けたピアスに母は苦言を呈していたが、褒められたことで肯定されたような気持ちになった。
完全に気分が良くなったところで恩師に会いに行く。
先生、お久しぶりです!
ん?誰だ?
前回も 誰だ?と言われたので思わず笑ってしまいながらマスクを取る。
〇〇です
お〜!!久しぶり!
就活が終わったことを報告する。
先生には、進路相談の際に 世間的に需要がある方を選ぶか、自分のやりたい方を選ぶか、と悩んでいることを話したことがあった。
「自分がやりたい方をやりなよ。」
「学校名よりも学部よりも大学生活において何か一つやり遂げることを経験しよう。」
���のアドバイスがあったおかげで、大学生活で一つ成果を残せたこと、自分が選択したやりたいことが実際に仕事で活かせること、何か道を選ぶ時に自分がやりたい方を選択できるようになったことへの感謝を述べた。
「大学で学んだことを就職して仕事で活かせる人なんてほとんどいないんだよ。俺だって、文学部は国語の教師になるしかないしな。だから、〇〇がやりたかったことが実際に仕事に活かせる所に就職が決まって良かったよ。いや〜今日は酒が美味く飲めそうだな〜。」
先生の最後の教え子になることができて光栄だったな、と思った。
電車に揺られ、14時半頃 高円寺に到着する。
今日は朝から何も口にしていなかったので、お気に入りの喫茶店に向かう。
アイスコーヒーとコーヒーゼリーを注文する。このお店はコーヒーゼリーのトッピングをアイスクリームか生クリームか選べるというちょっとした贅沢がある。
ゼリー好きなの?
はい、コーヒーゼリーが特に好きなんです。
マスターは、お店のコーヒーゼリーのこだわりや作り方などお話してくださった。そして、私の地元の話、就職後や残りの大学生活についての話を交わす。
「いっぱいバイトしてたくさん旅行に行きなね。」
学生生活もあっという間に終わりが見えていることに寂しさを覚えながら、残りの時間を有意義に使いたいと思った。
商店街に入り、以前行ったことのある古着屋さんに向かう。
インスタに投稿されていたハーレーのトップスが気になったためである。これは買わないといけない、と久しぶりに直感で感じたのだ。
店内に一歩足を踏み入れると古着屋さん独特の香りがする。素敵な古着屋さんは、あのお香の香りがする。
店員さんと話を交わす。就活が終わったご褒美に気になったトップスを見に来たこと、バイトを掛け持ちしようと考えていること、本当は古着屋さんや喫茶店で働きたかったこと。
「ウチ、最近 求人募集してて。」
求人募集って正社員さんだけかと思ってました
まあバイト場合によってはアルバイトも考えてて
え、そうなんですか!
オーナー上にいるので ちょっと呼んできますね
暫くするとオーナーの方がいらっしゃった。
どこから来たの?
私〇〇で、〇〇から〇〇分くらい下りです
下りなのか〜 場所どの辺りなの?俺の地元〇〇なんだけど
〇〇?!私も〇〇なんです、最寄りは〇〇なんですけど…
遠かったでしょ?俺も遠いのわかるから。
まさかの地元が同じという奇跡が起こり、最近で一番驚いた。
お二人にもヒスのキャミとナベルのピアスについて触れられる。有り難いことに他にも色々とお話することができた。
(君は)真面目でしょ?いい子だよね
やってみたかったら良いんじゃない?
お店を後にし、再び駅に向かう。予想外の展開にふわふわしながら歩く。やりたいことや夢は口にすべ��だとよく聞くが、本当にその通りかもしれない、とぼんやりした頭で考えていた。
動揺した心を落ち着かせるかのようにコンビニに入る。レジ待ちの列に並ぼうと、近くにいた男性2人組を避けようとしたところウエハースが1つ落ちてしまった。2人と目が合う。
あ、すみません
こちらこそすみません
あの、〇☆*#!〜〜
1人は酔っているのかシラフなのか判断に困るような状態で、もう1人が申し訳なさそうに苦笑いをしていた。
なんか お姉さん いい匂いするね
おい、気持ち悪いからやめとけって
いえいえ 良かったです(?)
謎の会話をして店を出ると先程の2人も同様に駅に向かっており、自然と会話をする。
え!お姉さんそれヒス?
そうですヒスです
俺もさあ、30年前はヒス好きで!着てたんだよ
え、本当ですか!
うん、あの〇〇〇〇のデザインのあったじゃん、知ってる?〇〇〇〇!
〇〇〇〇って言うなよ
ああ!知ってますよ
ほら!知ってるって!〇〇〇〇!
50代くらいの方に見えたが、若い頃はヒスをよく着ていたらしい。高円寺を感じる。
お姉さんやっぱりいい匂いするね
香水ですかね?
お前、、セクハラになるぞ
香水〜??
酔ってるのか酔ってないのかわからないその人は私に近づいて匂いの元を辿ろうとしていた。
普段ならば警戒心を持って離れていただろうが、その時は何故か この人面白いな〜、くらいにしか思わなかった。
ヒス似合ってるよ!素敵!
お姉さん ごめんなさいね〜〜
いえいえ!ありがとうございます
電車に乗り、今日一日を振り返ってみる。
高円寺、やはり面白い街だ。
今日は本当に出会いに恵まれた日だったな、と
感謝した。
3 notes
·
View notes
Text
if 画廊で
「右じゃねーの」 「………」 「俺は右だと思うけど」 「………」 「なんだよ、聞いてきたのはお前だろ」 「…うーん」
今回の個展も小規模なものなので、最近の作品をぜんぶ置くわけにはいかない。 ただでさえ多作な僕の作品の中から個展で並べるものを選ぶのはいつも冷泉か山雪だ。 冷泉は骨董の目利きができるし普段から随所のセンスがいい。 山雪は売れるものをさぐり当てる嗅覚に冴えている。 僕は二人の持つ抜群の感性にいつも頼りきっている。 僕がいいと思うものは、自分のものでも自分以外の作品でも大抵あまり評価されない。だから僕も僕のセンスは信用していない。 「左のがだめってんじゃないけど、置くなら右だろ」 二つの作品を並べて遠目に見ながら、冷泉と僕とで話しあう。 冷泉は右で譲らない。僕は 「…うーん、まあ、妥当なのかな…」 「お前は妙に攻めようとすんなよ滑るから。右。以上、終わり。」 「…もう決めたあの左から二つ目を退ければ並び的には左でバランスがとれていいんじゃない?」 「あのな……」 冷泉は一度言葉を切って長い前髪をかきあげながら僕のほうに向き直った。 「いやに拘るな。そんなに右を人の手に渡したくないならはじめから俺に見せんなよ」 …もっともな意見だな。選別が面倒だから部屋のすみに溜まっていたものをそのまま車に乗せたけど、この右のはよけておくべきだった。 青い地塗りに浮かぶざらついたマチエールを透明のメディウムで薄く覆ってある、珍しく静物画ではないもの。 「静物以外でもこれなら売れる」 「これは売れないと思うなぁ…」 「売れる。」 冷泉が断言するものは、売れる。 「僕はそんなに売れたいわけじゃ…」 「それなりに顧客がついてんだからどうせ何置いても売れる。それに自分で持っててもそのうち自分で処分するだろ、売ったほうがまだマシだ」 良い作品はたとえ作者であっても勝手に処分すべきでない、それは損失だと冷泉は言う。 言いたいことは分かるからよく僕は言い負かされる。 それでもこれは手元に置いておきたいような。 「…やっぱり両方やめて、違うものにしよう」 右か左の二択だから右になってしまうと言わんばかりの僕はまだ額装されていない二つのキャンバスを壁から取り上げてさっさと脇に抱えた。 冷泉は僕を見ながら呆れている。…少し驚いているかも。 「出来上がったものに関心はないんじゃなかったのか?」 「うん。……まぁ、例外もあるよ」 右のは、その少ない例外で、見ていると処分したくなるような、けど人手に渡ってしまうのも嫌だった。 「静物じゃないにしたって、お前のことだから抽象ってわけじゃないんだろ」 一見抽象だけど抽象ではない。僕が見えたそのままに描くことは冷泉もよく知ってる。 見えないように二つの作品のおもてを合わせて脇に抱えた僕に、冷泉はようやく納得いったような顔をした。 「……傷跡か」 「あたり。流石。」 モデルになった彼について特に訊かれたことも話したこともないけど、なんだか妙な噂だけ広まっているらしい。 それにしてもこの絵から彼を連想できるのは冷泉が僕をよく知ってるからだろう。 界隈ではどこからどうしてそうなったのか彼と僕が寝たことはもう周知になっていて、反論もできないから僕はただいつも通り口数少なめに居住まいを正している。 「あれは目立つから仕方ない」 「どこかで見た?」 「街中で。声をかけるのは控えた」 「目立つかな。そんなに派手な子じゃないんだけど」 「お前が描いたものを言ってみろよ」 「傷跡」 「それだろ」 僕は気にしたことがなかったけど、あの傷跡は目立つらしい。 ひび割れて捲れた古い木肌に似ている。 「お前のとこに出入りしてるってのも本当なんだな」 「うん。遊びに来てくれるんだ」 僕は室内でしか絵を描かないから、僕のキャンバスに描かれているなら僕の部屋に来たことになる。 「あの子と一緒にいて、楽しいばかりでもないんだけど…………」 「……………」 うまく続けられずに語尾が消えていった。 彼について多分あまり外聞のよくない噂ばかり耳にしているだろうに、冷泉は心底嬉しそうに微笑んだ。 誰の手にも譲らないことにしたキャンバスを抱えた僕の肩を、冷泉は優しく叩いて言った。 「ーーーよかったな」 そのまま階段を下りて冷泉は画廊の一階へ行った。 相変わらず不粋なことは極力しないというか、突っ込んだことはなにも言わなかったけど、僕はその一言が嬉しかった。
0 notes
Text
チャンスの夢。
私は男性で、骨董街のような芸術街のようなところに父の誕生日のプレゼントを選びにに来ている。外は青い海に白いビールとか最初は最高に気持ちがよい情景。
部屋の中と外が入り交じるが今は夜。
古めかしい鏡の作品がたくさんある部屋で急にスタッフにカウントダウンされ慌てて出る。後ろで防火扉のような扉が閉められる。スタッフは笑ってる。間に合わないで閉じ込められる人もたくさんいるし一緒に来てた人も閉じ込められてしまった。そうやって何度もカウントダウンされるたびに逃げ伸びなんとか安全な場所に出るが。
私は腕を怪我しているようだ。
気づくと知り合いとバーのマスターらしき人と一緒にいる。カウンターごしのマスターは陽気に話をしている。そのうちに肉の塊を2つカウンターの上に出して。
「あんまりそんなふうにしてるとまた腕食べたくなるだろ」とか言いはじめる。
私はかつて肩を折られてもぎ取られいる。
そうか、このマスターは友人で、なぜか私の腕を折ってたべたんだ。とじわじわ気づく。顔がかぎりなくチャンス大城に似ている。
友人は始終笑ってその話をしてくるし、肉の塊のひとつは私の肩肉の残りで、もうひとつは私の妹のだった。
「またやってしまうなあ」
そんなふうにいいながら腕をとろうとしてくる。知り合いがやんわり止めようとするがきかない。どんどんエスカレートしてくるのをかわそうとするがなかなかかわせない。
にやにやしながら、逃げられないように腕をしめてくるところで起きた。
おわり。
(肉に埋もれたような真っ黒い目玉だけが起きてからも目の前に焼き付いていていつまでも怖かった)
0 notes
Text
2022年2月の夢
2022年2月28日 月曜日 6:26 夢 忘れた。
- 2022年2月27日 日曜日 8:43 夢 何らかの運搬される乗り物のところに行くのだが、実際乗るには専用のジョイントがついた座席みたいなものを持参しなければならないらしい。すごい途中のところにいる。 何かをレンジにかける。 遠くからガーディアンに見つかった時のBGMが聞こえてきて、誰かがゲームをしていることがわかる。家電量販店のモニターがあるところみたいな雰囲気。実況者志望向けの抱き合わせの商品が法外な価格で売られているが、オンライン上では品切れで、驚く。大量の食材が置いてある。時間ばかりが経つ。かなり経ってから、仕方なしに何かおかずを作成することに協力しようという気分になり、着手する。明日お弁当の人がいるはずだから…。横に長いシステムキッチン×3くらいの広さ、二口コンロが3台くらいあり、人も多い。春雨を茹でて青いソースと和えた料理や、なぜか5パックほどもあったもやしを茹でてどうにかしようとしたものを同時並行で作る。黄色い鍋を五徳に置いたまま火をつけようとすると、そういうのに厳しい人、茶色い和服姿の同年代くらいの男性が火をつける際には鍋を置かない状態で火がつくのをしっかり見届けてからにしろと行動で示してくる。
- 2022年2月26日 土曜日 8:51 夢 オレンジ色の押し入れの内側があり、怖い。 水族館の写真。水を濾過するための長いユムシみたいな生き物が配線カバーのごとく壁を這っており不気味。でも私はこのエリアが一番好き。
- 2022年2月25日 金曜日 6:56 夢 青鏡という怪談がある。喫茶店の壁に角田光代の曽根崎心中の表紙みたいな絵が飾ってある。右目が赤く塗られており、これが青く見える人は憑かれている。 新しいスーツを購入している。黒に細いス��ライプ。すっかり忘れていた。 高い乗り物に乗っている。 どこかで甘いものを食べる。330円支払う。 ウインナコーヒーを飲む。
- 2022年2月21日 月曜日 13:07 夢 二度寝したら忘れた
- 2022年2月20日 日曜日 9:21 夢 足の毛穴がなぜかすごくよく見える。 女性の白っぽい体。 すごく混んでいる道。わざとらしいくらいにラーメンを食べる姿を見せながら歩いてくる力士や著名人たち。 韓国ラーメンの店。一店舗の面積に溢れ返るほどの辛いラーメンが直に作られており、食べている人がいる。辛い部分とそうでない部分があり、富めるものはそんなに辛くない部分、貧しいものは特に辛い部分を割り当てられ、途中でギブアップした者から追い出されていく。脚立に座って食べている。 秋田県からのレターパック。気仙沼みたいな文字列。同僚の人、本当は秋田出身だったんだ…と思う。
- 2022年2月19日 土曜日 7:15 夢 古式ゆかしい日本食店に丁稚として勤めている。三、四階建の日本家屋。薄暗くて梁とか黒光りする感じ。板前が怖い。外にはパステルカラーのVR空間が広がっている。いろいろあったが忘れた。
- 2022年2月18日 金曜日 5:51 夢 眠りが浅すぎてろくな夢を見なかった
- 2022年2月17日 木曜日 6:08 夢 せんべいの無人販売。先客がいる。しばらく待つとせんべい屋の息子が袋に入ったものを二つ���ど持ってくる。老母が煎餅を作っており、一日に14枚ほど。車で運ぶ。商売っけのなさ。 ハトの羽が抜けまくっている。 とんでもない男女が喧嘩している。 キャバ嬢みたいな子。黒い。明るい。知り合いとかぶってる。 変わった自販機があり、珍しく見る。
- 2022年2月16日 水曜日 6:04 夢 熊の皮。なんか見たが思い出せない。
- 2022年2月15日 火曜日 4:48 夢 実家の真横にすごいでかい鉄塔が立っている。地面をオレンジ色のレンガで舗装してある。 あんま思い出せないけどいい夢。
- 2022年2月14日 月曜日 6:49 夢 ベッドがたくさん並んでいる寄宿舎のような奥に長い部屋。一階ではない。薄暗くて紫の感じ。頭を壁際に向けて眠ると他の人の姿が目に入らない。同級生がシーツを替えている。 窓の外から隣のお宅の奥さんの姿が見える。自分より年下。子供と犬。まだ小さくて白っぽいハスキー犬。雨が降っている。旬を過ぎても生きるということ。 ダヴ90000のコントを見ようとしている。 暗い水の中を大きくて不気味な魚、その後ろを魚のような潜水艦が泳いでいる。何か名前がついていたが忘れた。一度だけ乗るなら15,000円、何度も乗るなら30,000円とのこと。かなり庶民的な街。霜降り明星が赤っぽくなっている。
- 2022年2月13日 日曜日 8:18 夢 バターフィンガーのことが頭から離れない。バルゥーフェングゥーのことが。 暗い橋の上を歩く。ものすごい人出。シルバニアファミリーのコマ送りの映像を撮影している中。左手にレインボーフェスのフロートみたいなものがあり、黒人ダンサーがひしめきあって踊っている。ちょっと懐かしめの洋楽。マルーン5みたいな。 何となく未来感のある筒状の居住地。なおくんの引っ越しの様子。荷物多いらしい。手伝っている。英語の家庭教師みたいなことをしていて15分で2万くらい取っているとのこと。かわいくない白猫。 飴などを売っている卸のような店におじいさんがちょくちょく入ってくる。
- 2022年2月12日 土曜日 7:37 夢 どこかの施設。関係者としての自分。郵便受けが3箇所あり、壁掛けの1箇所は撤去されている。開けると中はホコリや蜘蛛の巣があり、奥に郵便物、ぬりえセットの箱が見える。
- 2022年2月11日 金曜日 5:50 夢 三重の門扉のある洋館の内側にいる。 車で出発する。
- 2022年2月10日 木曜日 5:49 夢 知らない長屋のような平屋建てに引っ越している。 裏庭を見るとなぜか身に覚えのない犬がいる。黒い柴、柴、ダックスフンド、さらに子犬たくさん。咎められる空気。 タイのようなところ、観光客用にカートのようなものを貸し出している。TKと二人で乗り、進む。 射的のコルク弾が二発だけだった。
- 2022年2月9日 水曜日 5:08 夢 ビューさんのメチャ子のまんがの絵柄の夢。 骨董品や石を売っている寂れた施設。 薄い紫色の丸い貝の化石みたいなものを手に取る。 屋外で知らん相手と決死のプロレスみたいなことをする。 屈筋の弱さで押され、負ける。
- 2022年2月8日 火曜日 4:54 夢 妹と妹の彼氏。角部屋で、窓を2箇所開けてある。こちらに背を向けて妹の彼氏がいる。風がよく通る。夕飯の支度。とうもろこしのかき揚げやローストビーフのようなもの。母がいる雰囲気。妖怪。
- 2022年2月7日 月曜日 6:02 夢 室内にいる。結婚式が終わった後のような折詰の食品がある。鯛のようなもの。すぐに出発しなければならないらしい。いとこがおり、箱などをくれる。 なおくんといる。会場に、事前に申し込んだ人の荷物が届く手筈になっているが、その数が多すぎてストップが掛かる。 海外っぽい宿泊施設の3階。 温泉の露天のようなところ。 変わった野菜。扁平なレタスでテクスチャはスダチみたいなもの。キクラゲみたいなきのこ類。妙に色褪せたレトロなドリンク類。中に果物が浮いたボトル。浴槽が見えるが入っている人はいない。
- 2022年2月6日 日曜日 7:22 夢 水川かたまりと何らかの企画で同席する予定があるらしく嬉しがっている。 ツイストが入る遊具ともア��ラクションともつかない屋外の乗り物。DNAのらせんみたいにグルグル回るようになっているが、試みが新しすぎるのか乗ってる途中でよく詰まる。 屋外、誰かの家、古めの洋館というか北海道の開拓時代みたいな下見板張りの白い木造、トトロのサツキとメイの家みたいな、に、横から近づくと、でかいサメがいる。周りには落ち葉。 河童がおり、死にそうな目線と自分の目線が入れ替わる。何か伝えたいことがあるらしい。
- 2022年2月5日 土曜日 6:34 夢 Hさんと口論になり、その指示の出し方では結果が違ってくる、求める要件をまず述べてほしいと伝える。今回はスノースタンドの件だった。 赤黒黄のエリアがあり、他の国家らしい。 犬とか動物もその色。 天皇陛下みたいな人が車でずらずら通る。 紙を掲げて何らかの訴えをしている人たち。シームレスに誰かのゴミ屋敷になっている。
- 2022年2月4日 金曜日 6:09 夢 蜂の巣、バッタなどを大量に見る。食べるつもりでいたがやはりいっぱい見ると恐ろしい。鬼灯に頭から体突っ込んでいる蜂もいる 加藤さんがいる。加藤さんが加藤って書いてあるものを持っているの面白い気がする。 血の島裁判
- 2022年2月3日 木曜日 6:31 夢 白いペットボトルに赤の十字架が書いてあって薄ピンクの液体のスポーツドリンク。 松本人志が買い上げてやってるコンビニがある。フランチャイズの看板ではあるが完全に自分の采配でやってるらしい。店内は広く、L字型、床は暗めの板張り、入ってすぐに本の陳列棚が三つくらいあり、ラインナップに趣味が現れている。ビートメイクの本に目が止まる。 店内は人が多く、客層わりと若い。古着屋みたいだ。奥に行くと屈強な黒人の店員が多くなる。古い和だんすの引き出しに水パイプを収納している人がいる。強烈に大麻のにおいがする。 前々職の社長に似た人がいる。知り合いの社長に頼まれ、虎柄の布と赤い布を用意したらしい。
何かの写真が必要になり、撮る。 女性を引きで見て何枚か携帯のカメラで撮る。女性は知らん人で劇団員か何かしているらしい、写真のことで誰かに連絡をとっており、その影が地面に投影されている。
- 2022年2月2日 水曜日 6:33 夢 顔がざらざらしている。
1 note
·
View note
Text
さるかに編 第一話
「プルルル」
「おはよう、朝だよ」
だいぶ昔にやめた通信教育の目覚まし時計が、眠たいさかりのいたいけな少女に新しい学期がはじまって2日目の朝を無慈悲に告げる。最初は抗おうとするも、何度も繰り返されるその音をとめたくて、うすらまなこのままプラスチックの校舎をかたどった目覚まし時計から飛び出した赤いマスコットをぱちっと、屋根に押し込む。彼は暗い三角屋根のなかでこういった。
「たのしいいちにち!スタート!」
おいそこの赤い珍獣、わたしが反抗期の男子中学生じゃなくて命拾いしたな。君なんてプラスチックのおそまつな校舎もろとも壁に叩きつけられてバッキバキになっていただろうよ、ありがたく思いやがれ。なんて思いながら、洋服だんすのハンガーにかけられた制服一式をざっととりだす。無難な形をしたありがちな��レザーも、慣れればまあ悪くはないものだ。しかしわたしがこんなものを着るようになったのは、学力が足りなかったからじゃない。本当は瑞高の黒いセーラーを着るはずだったのに、まあ内申制度の闇ってやつだ。そもそもこんなん言ってる場合じゃない。アラームもよくよく考えれば長いこと鳴っていたわけで、まあぎりぎりな時刻をさしてる。引き出しをざっと開けて下着をあさる。今日は水色のお花が咲いてるやつにした。
制服に袖を通し、居間へ向かう。
「おはよー」
「おー」
父が返事をする。白いでかめのTシャツを着て、赤い柄のトランクスを履いた40代のガリガリおじさんは、朝シャワーで濡れた銀色の髪を鬱陶しそうに右に片手て流しながら、たまごかけご飯をかっこんでいる。灰色の目は、なんだかすこしおめでたいようにみえた。なんとなく様になって見えるのは、父がスウェーデン人と日本人のハーフで、色白で鼻筋がきれいなせいだからかもしれない。私はどうやら、そんな父に似たらしい。美少女かどうかはわからないが、まあよく似ている。父の横を通り過ぎ、横に長い作り付けのテレビ棚の端っこにたたずむ、ちっさな額縁のなかの母に手をあわせた。栗色の横はねした髪がかわいい。母は7年間、この姿のままだ。このさきもずっとそうだ。
「おはよー」
線香は焚かない。母も父もわたしも、線香は宿敵だからだ。法事で冷めかけたごはんをたべてるとき線香の匂いがぷおーんだなんてすると、口のなかで混ざってもうだめだ。ほんとうにえずいてしまう。
写真の前には灰皿とビックのライターが置いてある。父が吸ったハイライトの吸い殻がこんもりつもっては、いつの間にか消えている。えらいぞ父。
「昼飯代」 父はそう言うと、台所のカウンターに乗った千円札を指さした。
「あざっす」 反射的にぺこっとお辞儀をすると、私はそれを財布に入れる。
棚からどんぶりを取り出し、冷蔵庫から卵とめんつゆをだし、マッハでTKGを作った。
「いただきます!」
そう言ってTKGをかっこむ。立ち食いでも礼儀は忘れない。ああうまい。生食ができる国産の卵に感謝しながら、ダシの効いた溶き卵のコクと甘み、山形県産あきたこまちの喉ごしを堪能する。
「座って食えよぉ」
父があきれた声でぼそっと言う。
「ごっつあんです!」
秒速で歯磨きし、鍵とヘルメットを取り、表に停めてあるスーパーカブにまたがる。見よ、これが私の愛車だ。絵を描くノリでちょー大雑把に筆塗りしたからし色のボディーもまたご愛��である。そんな愛車との馴れ初めは去年の春。私が母のへそくりで二輪の免許合宿へ行き、見事センターで免許をもらって帰ってきた直後、行きつけの近所の蕎麦屋のジイさんがボケてしまい、店を畳んだ。こうなってくると出前用のカブは、もう用がない。いやしい私は、偶然お店の前にいたジイさんの長女にカブの話をふっかけた。娘さんは二輪免許を持ち合わせていなかったので90ccのカブには乗れないうえ、そもそもピカピカのボルボV60を乗り回されている方ゆえ、車は足りてるからだれにあげるかで迷っていたという。需要と供給が見事に一致した瞬間だった。とりあえず馴れ初めの話はおしまい。
くそぶかのジャンパーを羽織り、布で髪の毛を隠し、サングラスをかける。ふかめのジェットヘルメットを被れば、さすがに学校になんてばれるまい。キックでエンジンをかけ、ギアを入れたカブは住宅街から、だだっぴろい高架下の国道へと抜けていく。二段回右折のいらない原付二種の愛車は、心地良くうなりって���る。春ということもありこのうえなく快適極まりない。あっというまに学校近くへたどりつく。小汚いスーパーとパチ屋の間のせこい私道と駐車場がごっちゃになってるところに愛車を潜らせ、メットを外して愛車のハンドルにぶら下げ、となりの公園の便所に駆け込んだ。ささっと布をとり、ジャンパーを脱いでリュックにぶちこみ、おさげを結い直す。前髪をケープで仕上げたら、できあがり。
トイレから颯爽と登場したわたしは、何食わぬ顔をして学校まで400mの道のりをのんびりと歩いていた。おっと、グラサンをとるのをわすれていた、いけねいけね。
さて、愛馬としばしお別れしたあとは、さてさてお楽しみのチンパンジーたちと一緒の青春タイムの始まりだ。江戸川モンキーパーク正門に到着した。通称東京都立一之江高等学校。偏差値42と言われているが、おそらく名前かけなくても入れると思われる。
薬品臭くて無駄にだだっぴろい廊下をとおって、わたしは教室へ向かった。バカ学校として都の教育委員会からモロにみくびられているのだろうか、校舎のあちこちがぼろぼろである。ナショナルのスピーカーは、もはや骨董品である。まあ私は幸運だ。ここを卒業した駐在さんいわく、本校の教室にエアコンが導入されたのは都立高校の中でいちばん最後だったらしい。
そんなことはさておき。わたしの緻密な計算通り、「キーンコーンカーンコーン」の始まりとともに教室に入り、終わりとともに席に着いた。セーフだ。
「おい小田部」
おっとっと、この部屋を担当している飼育員こと可児龍児が、ドスの聞いた声で私を呼ぶ。なんだ難癖か?
「ち、こ、く」 今度はあざ笑うかのように言った。
「いや座りましたよね」
文明の利器まで使ったこのわたしが負けてたまるか。
「だからさあ、時間までに座れって言ってるだろ?チャイム始まるまえに座れ、携帯に時計ついてんだろ?」
渋々携帯を取り出して時計を見る。すると先生がこちらに近寄り、歌舞伎役者のような眼光をこちらに向け、卑しく笑った。その時だった
「ハイ!没収!!」
先生の細長い手に掴まれ、クレーンのカゴのように空高く登っていく赤いiPhone7をぼーっとみあげていた。
「電源消しとけって言ってるだろ?」
そんなことそ言い捨てたのち、真顔に戻る先生。しかしまあ、本当は携帯いじりたくて仕方ないソーシャルメディア中毒者のみんなが、人権を奪われる私を見ながら笑ってる光景はあまりにばかすぎておもしろい。ところでさっきからうつむいた先生の坊主頭から照り返した太陽が眩しすぎて仕方がない。目の色素がうすい私にとって、照り返しは宿敵である。思わず目を塞ぐ。
「放課後職員室に来るように」
真顔にもどった先生は、当たり前のようにズボンのポッケにわたしの携帯をねじ込む。
大変むかつくことにかわりはないが、今回は不幸中の幸いだ。iphone7の調子が悪く携帯回線が使えなくなってしまったため、前につかっていたiPhone5SにSIMカードを差し替えて、ちょうど二台持ちしていたところだった。そう、かったるくてつかえたもんじゃないけど、残機があるのだ。人権はかろうじて守られた。パスロックも解除できまい手前、先生からしたらただの文鎮に過ぎない。愛機よ、どうか無事でいてくれ。
「帰国子女さん、日本のルールは守ってね」
そういいながら、先生は私の髪の毛を軽く引っ張った。
唖然とした。とりえず前髪乱すなクソ野郎と言いそうになったが、怒ってるところはたぶんそこじゃない。そんなかわいいものじゃあないはずだ。怒りを通り越した諦めと落胆とやるせなさが、そこにはあった。後々思えば「そもそも帰国子女じゃねーよ」くらいのことはいえたはずなのに、反論する気力すらそのときは、どっかにいってしまった。
ああ面白いほどに、この猿山のチンパンジーはよく笑う。再生ボタンを押したかのようなタイミングで、わたしと先生のつまらないやりとりをばかみたいに笑うのだ。刑務所に慰問で芸能人が来た時の映像みたいな盛り上がりを見せている。ばかという生き物は、ある意味被害者だ。おろかさゆえに、どこにもいけない��いう宿命を背負っているから、笑いの沸点がばかみたいに低くなるんだとおもう。生存戦略ってやつか。私だって人のことはいえないさ。
「ててーててーてて ててててて」
だから私はXperiaと言わんばかりの着信音が流れている。先生は私の携帯の入ってる所とは反対のポッケから自分の携帯を取り出し、焦るような面持ちで電話に出た。ワン切りだったのか、すぐに耳から携帯を放し、赤い終話ボタンを押した。
待ち受けには先生と、先生の妻と思われる素敵な女性、先生にどことなく似た顔の小学校低学年くらいの女の子が一緒に写った写真があった。ご丁寧にスタジオアリスかなんかで撮られた家族写真のようだ。
そういえば2ヶ月前、親と箱根旅行へいったとき、強羅の公園で先生を目撃したことを思いだした。どうも見覚えのある白のいけすかないレクサスRXから、明らかに先生とわかる男性がこれまたいけすかないグラサンをかけて、さらには奥様らしき女性を連れて登場したのだった。鮮明に残ってる。それはもう馬鹿みたいに、獣のように人目も憚らずいちゃついていたから無理もない。奥様の顔も鮮明に覚えている。歳の差婚なのだろうか、どこかあどけなさの残る女性だった気がする。しかし、相当若かったな。わたしらから数えた方が歳近いんじゃないか?当時は単純にそう思っていた。 もう一度先生の手元をみた。先生は着信履歴をみていたが、その後一瞬だけホーム画面を見て、横のスイッチで画面を閉じた。家族写真の女性と、強羅の女性は、どう足掻いても、似ても似つかない別人だった。錯覚ではなかったらしい。
「おい、席に戻れ」
先生はわたしをみて、なにをぼーっとしてるのかといわんばかりの表情でこういった。わたしは我にかえったふりをしながら席に戻った。
どこにもいけないという宿命こそが、ばかという生き物の本質だとしたら、いまの先生は、たぶんばか以外のなにものでもないだろう。
わたしはこれから戦うことになる。 ああめんどくせえな。
つづく
0 notes
Text
【黒バス】love me tender/tell me killer
2013/10/27発行オフ本web再録
※殺し屋パロ
「はじめまして」
「……はじめまして」
「っへへ、やっぱ声も思ったとおり綺麗だわ。な、俺、タカオっての。お前、名前は?」
伝統の白壁作りの家々は、夜の闇にその白さをすっかり沈めてしまっている。時刻は零時を丁度回ったところ。街路樹が全て色を変えた季節のこと。
この国の秋はもう寒い。話しかけられた男の方は、きっちりと白いシャツのボタンを首筋まで止め、黒いネクタイを締め、黒いコートを風にはためかせている。コートを縁どる赤いラインがやけに目立った。話しかけた男はといえば対照的に、夜闇でも目立つ真夏のオレンジ色をしたつなぎを着ているのみだ。チャックを引き上げているとはいえ、その中身は薄いTシャツかタンクトップだろう。
しかし突然話しかけられたにも関わらず男は無表情を保ったままで、鮮やかな髪色と同じ、眼鏡の奥のエメラルドの瞳は瞬き一つしなかった。そしてまた対照的に、オレンジのつなぎを着た男は軽薄というタイトルを背負ったような顔で笑っている。不釣合いな二人は、真夜中の淵、高級住宅街の一つの屋根の上で会話をしていた。
「何故名乗らねばならん」
「え、それ聞いちゃう? だってそりゃ、好きな人の名前は知りたいっしょ」
「成程」
初対面である男に唐突な告白を受けても、緑色の男はやはり一つの動揺も見せなかった。その代わりに僅かに、それは誰も気がつかないほど僅かに、白い首を傾げた。白壁すら闇に沈む中で、その首筋の白さだけが際立っていた。
「ならば、死ね」
魔法のように男の手に現れたサイレンサー付きの拳銃から、嫌に現実的な、空気を吐き出す僅かな音。
雑多な人種が集い、少年が指先で数億の金を動かし、老人が路地裏で幼子を襲い、幼子がピストルを煌めかせるような腐った街で、世界を変える力など持たない二人の男が、この日、出会った。
【ターゲットは運命!?】
「ねえ真ちゃんー、愛の営みしようよー、それかアレ、限りなく純粋なセックス」
「お前が言う愛の営みの定義と限りなく純粋なセックスの定義を教えろ」
「やべえ真ちゃんの口からセックスって単語出てくるだけで興奮するわ」
高尾がそう告げ終わるか否かの瞬間に彼の目の前をナイフが通り抜けた。それは高尾が首を僅かに後ろに傾げたからこそ目の前を通り過ぎたのであって、もしもそのままパスタを茹でていたら今頃、寸胴鍋の湯は彼の血で真っ赤に染まっていただろう。壁に突き刺さったそれを抜き取りながら、彼は血の代わりに塩を入れる。
「お腹空いてんの?」
「朝から何も食べていない」
「ありゃー、それはそれは」
お仕事お疲れさん、と高尾は笑う。時刻は深夜一時、まっとうな人間、まっとうな仕事ならば既に眠って明日への英気を養っている時間帯である。
そしてその両方が当てはまらない人間は、こうやっておかしな時間帯に、優雅な夕食を食べようとしていた。落ち着いた深い木の色で統一されたリビングで、緑間はさして興味もない新聞を眺めている。N社の不正献金、農作物が近年稀に見る大豊作、オークション開催のお知らせ云々が雑多に並ぶ。
「しかし久々にやりがいがある」
「真ちゃんがそこまで言うなんてめずらし」
「ああ、俺の運命の相手だ」
緑間がそう告げた瞬間に、台所の方からザク、という壁がえぐれるような音がした。椅子に座る緑間は新聞から目を外すと、僅かに首を傾けてその方向を確認する。見慣れた黒髪と白い湯気。
「……ねえ真ちゃん、詳しく聞かせてよそれ」
「どうした高尾、腹が減っているのか」
「そうだね……俺は昼にシャーリィんとこのバーガー食ったかな……」
微笑みながら振り返る高尾の左手には先程緑間が投げたナイフが握られている。それなりに堅い建材の壁が綺麗にえぐれていることも確認して、彼は小さく溜息を��いた。
(台所は本当に壁が傷つきやすいな)
寝所やリビングはもう少し���シなのだが、と周囲を見渡せば、そうはいうもののあちこちに古いものから新しいものまで、大小様々な切り傷や銃創が残っている。床、壁、天井、家具、小物にタペストリー。無傷なものを探すほうが難しい。彼は一通り確認して、もう一度台所に視線をやって、さらにもう一度、リビングを確認する。
(この家は本当に壁が傷つきやすいな)
そう認識を改めると、緑間は満足げに頷いた。自分が正しく現状を認識したことに満足して。もしもここにまともな感性の人間がいたならば、壁が傷つきやすいのではなく、お前たちが壁を傷つけているのだと頭を抱えただろう。良い家だが、と緑間は思っている。その良い家を傷つけているのが誰かというのは、気にしない。
「はい、真ちゃん、どうぞ」
高尾は左手でナイフをいじったまま、緑間の前にクリームパスタをごとりと置く。ベーコン、玉ねぎ、にんにく、サーモン、それから強めの黒胡椒。
「そろそろ引越しを考えるか」
「え、どうしたの、別に良いけど」
そして悲しいことに、あるいは都合のいいことに、この部屋にはまともな感性の人間など一人としていないのであった。
引越しだ、引越しをしなくてはいけない。
*
緑間真太郎と高尾和成はフリーランスの殺し屋である。特殊な職業だねと八百屋の青年は冗談で流すかもしれないが、それは特殊であるというだけであって、この街ではありふれた職でもあった。なんなら、その八百屋の青年は、夜になったら配達先でナイフを燐かせているかもしれない。その程度である。その程度のありきたりさで、緑間と高尾はコンビで殺し屋をしていた。
しかし殺し屋がコンビを組むのは珍しいことではないが、コンビを組んだまま、というのはこの街でも非常に珍しいことだった。報酬の取り分や仕事のスタイル、そういったことで直ぐに仲違いをして、どちらかがゴミ溜めの上で頭から血を流すことになるのがオチだからである。
かといって、誰もがそんな下らないことで命を落としたくないと考えているのもまた事実で、コンビを組むのは一回か二回、そこで別れるのが一般的にスマートなやり方とされていた。
殺すも殺されるも一期一会と下品な男たちは笑う。
「ま、俺と真ちゃんは運命だから、そんなことにはなりませんけど」
笑いながら高尾は、真昼の路上を歩いている。彼にとって報酬はどうでもいいものであり、ただ緑間真太郎の隣にいることが彼の報酬そのものといえた。
別れるくらいなら死んだほうがマシ。いや真ちゃんが悲しむから死なないけど、あーでも真ちゃんかばって死ぬならまあギリギリ有りかな……いやいや高尾和成、人事を尽くせよそこは一緒に生き残るだろう? でも真ちゃんが万が一俺と別れたいと言ってきたらどうする? 緑間真太郎を殺して俺も死ぬか? いやいやいやいや、何がどうあれ、俺が、真ちゃんを殺すなんてありえない。ありえない!
微笑みを浮かべながら闊歩する高尾の脳内は地獄さながらに沸き立っている。けれど誰も彼を気に止めない。夕飯の買い物やのんびりとしたランチを楽しむ善良��市民たちに溶け込んで、柔らかい日差しを吸い込んでいる。世界に何億人といる、特徴のない好青年。その程度の存在として高尾は歩く。歩きながら考えている。
そう、そもそもそんなことになる筈がないのだ。だって、俺の運命の相手は緑間真太郎その人なんだから。
「運命の相手、ねえ……」
昨晩、正式には日付を跨いでいたので今日の夜だが、その夜、に、当の緑間真太郎が告げた台詞が高尾和成を苦しめている。俺の運命の相手。運命の相手。運命。いやいやいや、俺の目の前で真ちゃん、他の男の話とか無しっしょマジで。
意気消沈する高尾は、しかしそれで諦めるほどかわいらしい精神をしていない。彼がみすみす獲物を逃すことはないのである。逃すくらいなら奪って殺す。けれど彼に緑間真太郎を殺すことはできない。何故ならば愛しているからだ。ならば、彼の取るべき手段は一つだけだった。
「運命の相手の方殺すしかねーだろ」
いや別に殺さなくてもいい、相手が緑間真太郎を振ってくれるならそれでいい。いや、あの緑間真太郎を振る? それこそ万死に値するお前ごときが何真ちゃん振ってんだよそれはそれで死ねよもう。
自分で出した問いと答えに自分で怒りを爆発させるという器用なことをしながら、高尾和成は尾行していた。緑間真太郎を。
真ちゃん、今日も一日美しいね。
*
「ねえ真ちゃん、真ちゃん今日一日何してた……」
「仕事だが」
「うん、そうだね、そうだよね」
ビーフストロガノフを頬張りながら高尾は溜息をつく。その向かいでは黙々と緑間が口にスプーンを運んでいる。湯気で僅かに眼鏡がくもっているが本人は気にしていないらしい。
「ねえ真ちゃん、ちなみにどんなお仕事なの」
「個人の仕事には口を出さないのがルールだろう」
「それも知ってた……」
そう、フリーでコンビを組んでいるとはいえど、二人の得意とする分野はまるで違う。だからこそ互いに補い合えるわけだが、逆に言えば苦手な分野でない限りは、どちらか一人で事足りてしまうのだ。
そもそもコンビを組むまでに築き上げてきた地盤もお互い全く別のもの。必要以上の情報は公開しないことはお互いのためにも必然だった。
「あーあー、もー。高尾くんがこんなに悩んでんのに真ちゃんはお澄ましさんだもんなー」
「悩んでいるのか? おめでとう」
「ありがと」
お前に悩むだけの脳みそがあったことに乾杯、と言いながら緑間は赤ワインを傾ける。それに応えながら、高尾は左手に持っていた食事用のナイフを壁に投擲した。それはまるでバターを切る時のように白壁に刺さる。とすり、と軽い音。
「今度引越しをしよう、高尾」
「それこの前も言ってたね」
「ああ、俺が運命の相手を見つけたら、すぐにでも」
なに真ちゃん別居宣言なのいくらなんでも酷くない?! 泣きながらビーフシチューを掻き込む高尾に緑間は首を傾げていた。
高尾、食べやすいからと言ってライスを噛まないのはよくないぞ。
*
尾行が四日目にもなれば、いくら『人生楽しんだもん勝ち』を座右の銘に掲げる高尾といえど、纏う空気は重くなるというものだった。それもそのはず、この四日間緑間真太郎はといえば、近くの図書館にこもりきりなのだから。
「いや、でも、わかったこともある……」
窓際に座る緑間が見える、図書館向かいのカフェでジンジャエールをすすりながら高尾は溜息をつく。
まず、緑間真太郎が本を読みに行っているわけではないこと。毎回場所を変えてはいるけれど、常に入口が見える位置に陣取っていること。つまり、緑間は図書館に訪れるであろう誰かをずっと待っている。
それはわかった。しかしそれは、一日目の段階から薄々わかっていたことであった。ならば後は緑間が接触した相手を尾行し、暗がりにでも連れて行き、少し脅してどこか地球の裏側に行ってもらうか空の国に行ってもらえばいいと、彼はそう高をくくっていたのである。ところが、だ。
「なんで真ちゃん誰とも会わねーの……」
そう、緑間は誰とも接触をしていなかった。ただ黙々と本の頁をめくり、そして閉館時間までそこにいるのである。本に何かの暗号が隠されているのではと、その後忍び込んでみたが、まあ面白い程に何も無かった。
では本の種類か、と思ったが一体全体星占いの本で何を伝えるというのか。では帰り道か、そう思ってつけてみれば、そのまま家へと直帰したので夕飯の支度をしていなかった高尾は慌てふためいた。何せまだ夜の八時、普段からすれば早すぎるのである。
どうやら緑間は運命の相手探しとは別に、他の仕事をいくつか同時に請け負っているようだった。それが無い日は早く、あれば帰りにさっとどこかに寄って仕事をこなして帰っている。そして今の仕事は図書館で星占いの勉強だ。どうなってる、と高尾は頭を抱えることしかできない。
つまり朝家を出て、図書館に行き、帰る、今の緑間は基本的にはそれだけのことしかしていないのである。たまに何か軽い仕事をして帰る。何かに似ていると思ったら、職を追われたことを妻に隠して公園で鳩に餌をあげるサラリーマンだった。
そして今日も緑間真太郎は閉館時間まで本を読んでいる。もうその本を確認する気にもならなかった高尾は、緑間が立ち上がると同時に立ち上がった。
この図書館に何かあるのは間違いない。館内は飲食禁止というのを律儀に守る緑間真太郎は、毎晩腹を空かせて帰ってくるのだから。昼を食べに外に出ることも惜しんでいるのだろう。その間にターゲットが来てはたまらないから。そこまで緑間に想われている相手が憎くもあり、羨ましくもあり、そして今日も出会わなかったことに少しの安堵を覚えつつ、夕飯は何にしようと、高尾はもう考え始めている。
まずは胃袋をつかめって言うしな!
*
「ねえ真ちゃん、俺に何か隠し事してない?」
「数え切れないほどあるが」
フリットを黙々と頬張りながら緑間真太郎は首を傾げる。この姿を見るといつも餌付けしているような気持ちになって、高尾の心の独占欲やら征服欲やらが幾分か満足するのだが、今ばかりはその小首を傾げた姿が憎らしい。昼飯を抜いている緑間はよく食べる。とはいえど、もともと食が細い方なため、これでようやく高尾と同じくらいな���だが。
「いや仕事以外でさ、仕事以外」
「む」
少し遠回りに何かヒントでも出して貰えないだろうかとやけくそで告げた言葉だった。しかしその瞬間に緑間の眉が僅かに跳ね上がったのを、高尾は見逃しはしなかった。何かある。間違いない。
もしも心暗いところが無ければ、こんな質問は一蹴されて終わりなのに緑間はまだ頬張った白米を咀嚼しているのだから確定である。きっかり五十回噛んだのち、緑間はゆっくりと口を開いた。
「何故バレた」
「バレたっていうか、自分であんだけ色々言っておいてバレたも何も無いっつーか……」
「仕方がないだろう。住所やら証明印やら保証人だか何だかが必要だとぐちゃぐちゃ抜かしてくるから、カードごと叩きつけてきたのだよ」
「ごっめん待って真ちゃん俺は一体全体何の秘密を暴いちゃってるわけ?」
全く噛み合わない会話に高尾は額を押さえた。これはまずい、とカンカンカンカン警鐘が鳴る。響き渡っている。これは、恋や愛などのロマンチックなものではなく、もっともっと切実な話だ。
「? 俺のラッキーアイテムのことを言っているのではなかったのか」
「真ちゃん今度は何買ってきたの?!怪しい骨董買うのはもうやめなさいって言ったでしょ?!」
「怪しくは無いのだよ。曰くつきではあるが」
ちらりと視線をやった先には緑間が愛用する真っ黒ななめし革の鞄。フォークを置くのもそこそこに高尾が飛びついて中を確認すれば、ご大層なジュエルケースが無造作に突っ込まれていた。
「し、んちゃん、これ、何カラット……?」
彼が震える手で開いてみれば、そこには美術館で赤外線センサー付きガラスケースに収まっているような宝石がごろりと存在感を放っていた。青い光が安い蛍光灯の光を反射して奇しく光る。角度を変えれば色も虹色にさんざめいた。
「百七だったか。ポラリスの涙とかいう宝石で、手にした者は皆その宝石の美しさにやられて、目から血を流して死んでいくだとかなんだとか」
「それってただ単にこの宝石巡って争い起きまくってきましたってだけだろ! おい待てこれちょっとおい怖い聞くの怖い、いくら俺でも聞くの怖い怖すぎる怖すぎるけど聞くけどいくら」
「オークションで七億」
「俺たちの全財産じゃねえか!」
緑間真太郎は占いに傾倒している。そのことを高尾は出会って少ししてから知ったが、その理由は知らない。けれど事実として、緑間は好んで占いの情報を入手するし、そこに書かれていることは実行しようとする。物欲の無い緑間の、唯一の趣味だと高尾は思って普段はそれを流しているが、それにしても今回のは過去最高額も最高額、記録をゼロ二桁ほど抜かしてしまった。
手の平に収まる石が高尾をあざ笑うように輝く。
「それが身分を確認するだとかなんだとか面倒くさいことを言うし、まさか言うわけにもいかないし、仕方がないから口座のカードに暗証番号書いて叩きつけて来たのだよ」
「ああ、なるほど、そこに繋がるわけね?! 確かに俺たちの口座普通に偽名だし辿られても問題ないと思うけど、待ってまさか分散させてた口座全部」
「叩きつけてきた」
「もう普通に殺して奪えよ!」
愛は盲目とは言うが、盲目であっても腹は減るし、愛で空腹は満たせないのである。名の通った殺し屋として法外の報酬を得てきた二人にまさか明日の食事を気にしなければならない日が来るとは高尾はついぞ思っていなかった。
カードに暗証番号を全て書いて怒りながら叩きつけた緑間を思うと、本当に何故そんな手段しか取れなかったのかと高尾は純粋に疑問で仕方がない。方法は他にもっとあった筈である。いや、そもそも七億の宝石を買おうと思う時点でおかしいのだが。せめて盗め、ていうかもう殺して奪え、そう思う高尾の主張は、ろくでなしとしては非常に正しかった。
「馬鹿が。普通に殺すとはなんだ。殺しとは普通のことではない。そして普通、モノのやりとりには正当な対価が必要なのだよ」
「そうだね、でも俺たち殺し屋だからね?!」
しかしそれは同じろくでなしである筈の緑間には全く通用しないらしかった。台詞だけを取り出せば間違っているのは高尾だろうが、この状況を見れば正しいのは自分だと彼は自分を慰める。知らぬ間に目尻に浮かんだ涙に、それを宝石に落としてしまっては一大事だと高尾は慌てて輝くそれをしまった。
そして、どうやら一文無しになったことを悟った高尾は項垂れた。確かに二人の口座は共有で、さらに緑間は、今はもう抜けた組織の下にいた頃に膨大な金を蓄えている。割合で言えば緑間の取り分の方が余程多いだろう。
それでもそのうち一億くらいは俺の取り分だったと思うんだけどな、と高尾は涙目を隠しきれない。それは自分の分の報酬を取られたことではなく、明日からの食事の献立を考え直さねばならないことに対しての涙だったけれど。
あまりにも凹んでいる高尾の様子に、流石に罪悪感を覚えたのか緑間は僅かに視線を泳がせながら打ちひしがれる高尾の方に手をおいた。
「高尾、その、なんだ」
「真ちゃん……」
「明日には二百万稼げるから」
「そういう問題じゃねーよ! いやでもそういう問題か?! じゃあ明日も豪華な飯作るからな?!」
半泣きになりながら告げる高尾に緑間は頷きながらグラタンが良い、と答えた。
また適度に面倒くさいモン注文するよなお前は。
*
「で、真ちゃんそれいつ買ったの」
「一週間前」
一度落ち着こうと、二人はテーブルでコーヒーをすすっている。緑間の方は牛乳を入れすぎてもはや殆ど白い色をしているがそれで本人は満足らしい。
「あーー、一週間前じゃもう完全に差し押さえられてるよな……」
「だろうな」
「はーあ、真ちゃんの我侭にも困ったもんだわー」
机に頬をつけるようにして高尾は溜息をつく。左手でくるくると回していたナイフを机に突き立てればあっさりとめり込んだ。その様子を見て緑間は繰り返す。高尾、引越しをしよう、と。それにへいへいと頷きながら高尾はまたそのナイフを引き抜いて、寸分違わずに同じ場所に差し込む。
「あーあー、もー、真ちゃんのこんな我侭許してあげんの、俺だけだからな? 真ちゃんの運命の相手だってこんなの許してくれないよ?」
「お前は何を言っている。運命の相手に許すも許さないも無いのだよ」
「あー、はいはい、もうそんなの超越してるって?でもさ」
「いや、だから」
お前は何を言っているんだ? 本気で当惑したような表情の緑間に、どうやらこれは腰を据える必要があると高尾は顔をあげた。机に刺さったナイフは幾度も繰り返し繰り返し差し込んだことでついに貫通してしまっている。
取り敢えず、真ちゃん、コーヒーのおかわりいる?
*
「小学生?!」
「ああ」
「し、真ちゃんって、そんな趣味だった、の、いやお前年上好きって……でも俺今から小学生に……」
「違う、が、その少年しか手がかりが無いのだよ」
高尾の動揺を全て無視して緑間は説明を続けた。曰く、その少年が持っている物がほしい。曰く、姿格好や出会った時間帯から小学生であることは間違いない。曰く、出会ったのは運命だ。
「で、なんでそれが図書館につながるわけ?」
「この街で小学校に通うということはそれなりに裕福な家庭だろう。服も仕立ての良いものだったからな。そしてその年頃の子供の移動範囲は広くない。行ける施設も限られているだろう。治安が良い場所で、そんな小学生が行く場所といったら図書館しかない」
「いやいやいやいやいやいやいやいや」
自信満々に超理論を展開する緑間に、高尾は渾身の力で首を振った。この男は殺しに対してはとんでもない頭脳を発揮するし、普段からその利発さは留まることを知らない、才能の塊だと高尾は思っているが、たまに、とんでもなく、馬鹿だ。
「まあ小学生なのも移動範囲狭いのもいいとして、旅行者かもとか親に連れられてたかもとか色んなのも置いといて、なんで図書館なんだよ!」
「ほかに何がある」
「漫画あるとこでもいいし街中でもいいし公園とかでいいだろ! 図書館とか最も行かねえよ!」
あまりの言われように緑間も何か言い返そうと口を開いたが、「お前がいる間図書館に来た子供の数思い出せ!」という一言には反論ができなかったらしい。口を閉じて悔しそうに高尾を睨みつける。
いや、そりゃそうだろうと高尾は思う。そもそも図書館自体が上流階級の持ち物だ。緑間は何の気負いもなく入っていったが、高尾だってそうそう入りたい場所ではない。そこに、いくら身なりが整っているとしても子供が入っていく筈が無いだろう。
ふてくされた表情のまま、じゃあどうすればいいのだよと緑間は問う。
「その近辺の子供が行きそうな所しらみ潰しに探すしかねえだろ。路地裏とか屋上とか廃屋とか、公園とか、まあ、そういうの」
「面倒だな……」
「言いだしっぺお前!」
露骨に嫌そうな顔をした緑間に左手でナイフを投擲すれば緑間は瞬きもせずにその先を見送った。それは緑間の耳の真横を過ぎていったが、彼は微動だにもしない。ただ壁にナイフが刺さる音と、真新しい傷が一つ増えただけだった。
「てか何をそんなに探してるわけ?」
「俺もわからん」
「はあ?」
もう投げる���イフは無いんだけどなと思いながら高尾は笑顔で続きを促す。普通の人間ならばこの笑顔だけで凍りつかんばかりの恐怖を覚えるのだが、こと緑間にそれは通用しない。何も悪くないといった様子のまま、堂々と信じられない言葉を紡ぐ。
「わからん、が、あの子供に会えば自ずとわかるだろう。その少年が全てを握っているのだよ」
一体全体どこの組織の黒幕だ、といった内容だが、緑間の話しぶりからして恐らくただの中流のちょっと上くらい、育ちの良い所の坊ちゃんでしかないだろう。真に受けるにはあまりにも馬鹿らしい主張だが、緑間真太郎は嘘をつかない。会えばわかるのだろう。会えば。つまりどうしても会わなくてはいけないらしい。そして、一度決めた緑間真太郎を止める要素など高尾和成は持っていなかった。
「いーよ、協力するよ協力します」
「良いのか」
「いや、遠慮するポイントがいまいちよくわかんねーよ真ちゃん」
苦笑を浮かべながら、その表情にそぐわない満足気な声で、高尾はため息のように言葉を継いだ。
「俺はお前の目だからね」
その言葉を緑間は否定しない。否定しないということは肯定しているのと同じことだ。そのことは高尾を満足させるに十分である。
まあ、運命の相手が自分が考えていたものと違っただけえでも御の字とするべきだろう、そう高尾は考える。気持ちも浮上していく。つい先程七億円を失ったことなどすっかり頭の隅に追いやって、高尾はご機嫌に尋ねた。良いだろう、緑間真太郎が探すものならこの俺が探してやろう。俺の目から、逃れられるものなど、そういやしないのだから。
「で、真ちゃん、特徴は?」
サクッと見つけてこの問題を終わらせようとした高尾の、当然の質問は長い沈黙で返された。今まで一度も返答をためらわなかった緑間が、それこそ七億の時ですら堂々としていたあの緑間真太郎の目が泳いでいる。背中をつたう汗に気がついて、高尾の骨が僅かに震える。ここに来てまだこの愛しいお馬鹿さんは爆弾を落としてくれようというのか。おいまさか、おい、緑間。
「……………………ええとだな」
「特徴は?」
頑なに視線を合わせようとしない緑間の顎を掴んで無理矢理自分の方へと向けた高尾の瞳の奥は笑っていない。それでも視線を合わせようとしない緑間は、長い長い沈黙のあとに、聞こえなければいいというような小声で呟いた。
「………………小さかった」
「子供はみんな小さいし、だいたいの人間はお前より小せえよ! お前にデカいって言われるような小学生こっちがお断りだわ! てかお前それで探してたの?! あいかわらず人の顔覚えないのな?!」
「興味がないものを覚えても仕方がないだろう!」
「いや運命なんだろ?! 頑張れよ!」
「見ればわかる!」
「いやいやいや、俺が見てわかんなきゃ協力しようがないじゃん!」
ここぞとばかりに糾弾すれば言い返せないことが悔しいのか緑間の眉がどんどんひそめられていく。
鬱憤晴らしに顎を押さえていた手を離し、両手でエイヤと高尾が緑間の頬を挟めば男前も形無しの唇を突き出したような顔になって高尾は笑ってしまった。ここまでなすがままにされる緑間というのもレアである。どうやら今は何をしても良さそうだとその頬をいじる高尾の手は数秒後に跳ね除けられた。
流石にやりすぎたか、でも元はといえば真ちゃんが、そう言おうとした高尾の目に映るのは、僅かに微笑みを浮かべた緑間真太郎。
「そういえば高尾、お前、何故俺が図書館にこもっていたことを知っていた?」
先程投げて壁に刺さっていた筈のナイフがその手に握られている。
形勢逆転、ちょっと待ってよ真ちゃん。
*
「あ、緑のおじちゃんだ!」
「おじちゃんではない。おい、お前、この前のあの飲み物はどこで手に入れた」
夕方の公園、イチョウやカエデが舞い落ちる真っ赤な広場で、厳しい瞳をした緑間は無邪気そうな子供に話しかけている。高尾はといえばベンチに腰掛けてぐったりとしていた。
いくらなんでも瞳を酷使しすぎた。既にあの会話をした日から三日間が経過し、高尾はその広い視野を使って全力で子供を探していた。
ようやく見つけた少年は五歳ほどで、せめておおよその年齢くらいは指定が欲しかったと彼は目の周りをほぐしながら思う。
「この前の? 飲み物? ああ、おしるこのこと?」
「わからんがそれだ」
「あれはお母さんの手作りだよー」
遠くからその会話を聞きながら、いやわからないのにそれだとか断言しちゃって良いの真ちゃん、と高尾は心でツッコミを入れる。ナイフを投げる気力は残っていない。当の緑間はといえば、いたって真面目に、そうか、と頷くとコートの内ポケットから一つの袋と白い封筒を取り出してその少年に渡す。
「いいか小僧、あの味は素晴らしかった」
「そお? 甘すぎて僕そんなに好きじゃないなあ」
「あの良さがわからないとは……まあいい。今から俺が言う所にそのおしるこを持っていくのだよ。いいか、この紙と一緒に持っていけ。赤司征十郎に会わせろ、そう言うといい。手土産にはこれで十分だ」
しばらくやりとりを続けたあと、緑間が何を言ったのか高尾はもう聞き取れなかったが、どうやら子供は納得したらしい。明るい笑顔で駆けていった。その眩しい背中を見送る高尾に、緑間は、終わった、とそう一言声をかける。
「ねえ真ちゃん、あの子赤司ん所に送っちゃってよかったの?」
「何だ、何か問題でも」
「いや、普通、自分の命狙ってる奴のところに子供送らないでしょ」
緑間真太郎は友人であり元家族である赤司征十郎に指名手配されている。その原因でもある高尾は少しそのことを申し訳なく思っていなくもないのだが、当の本人だけは全く気にしていない。
「ふん、赤司は無駄な殺しはしないのだよ。俺に関わったというだけで殺していてはこの街が全滅だ」
逆に、関わったの定義が街全体に及び、その気になれば全滅させられるのだということを暗に示しているその言葉は恐怖しか呼び起こさないが、緑間は何故かそれを安全の担保にする。あいつは子供が好きだしな、という言葉には高尾の方が意外そうな顔をした。
「すでに行き詰まった大人と違って未来の可能性に満ちているから、らしいぞ」
「いやその資本主義やめようぜ」
高尾の言葉を無視して、緑間は家��を辿ろうとする。置いていかれそうになった高尾は慌てて立ち上がって隣に並んだ。真っ黒いコートと、オレンジ色のつなぎは夕日の色合いに似ている。そして高尾が必死についてくることを当然のように享受しながら、緑間は、まあともかく、と言葉を継ぐ。
「俺に関しては、ただちょっとばかし秘密を知りすぎているから取り敢えず殺しておけ、くらいのノリなのだよ」
「いや軽すぎ軽すぎ」
やはり変人の友人は変人だと、変人を愛する高尾は自分を他所にそう考えている。そして腹が鳴った瞬間に、そんなことも忘れてしまった。
「ま、全部終わったお祝いだし? 真ちゃん今日何食べたい?」
「できるだけ簡単なものでいい」
「ありゃ」
大げさに首をひねりながら、なんだろ、サンドイッチとかかな? と適当に言えば、ああそれが良いとこたえが返ってきた。
お祝いって言ってるのに、なんだか欲がないのね真ちゃん。
*
ガシャンと窓の割れる音がしたのと、二人がテーブルから飛びずさったのはほぼ同時だった。床板をはねあげて高尾はナイフを数本取り出し、緑間は棚を引き倒して奥にあるピストルを手に取る。
次の瞬間、ライフルとマシンガンの音が玄関先から飛んでくる。勿論、音だけではなく、銃弾も。入口からは死角になる場所で二人は身を小さくして様子を伺っていた。
「あーあー、食事中なんだけどな!」
「ふむ、やはり来たか」
「え、まさか真ちゃんだから簡単なので良いって」
「赤司のもとに人をやったからな。久々に真太郎を殺しに行ってもいいな、とか思われる可能性があるとは思っていたのだよ」
「だから軽すぎんだよお前の元家族!」
呆れた顔で高尾は手近にあった鏡を銃弾の嵐の中に投げ込む。投げた瞬間に全て粉々に砕けたが、その一瞬と散らばった破片で彼には十分だった。その動作を当たり前のように見ながら、緑間はやれやれとでも言いだしそうな顔で続ける。
「だから引越しをしようと言っただろう」
「いやいや、ええ、嘘だろ?! えっ、あれってそういうことなの?!」
運命の相手を見つけたら引越しをしよう。そんなことを確かに言っていたような気もするが、その説明は一言も無かった。もうちょっと説明があっても良いと思うんだけど、と、その言葉を口にはせずに高尾は鏡の反射で見えた人物像を緑間に告げる。男六人。全員黒髪で恐らくイタリア系。
「真ちゃん誰か知り合いいる?」
「いいや、知らん。外部から雇ったんだろう」
「そっか、じゃあ誰も殺せねえなあ」
鳴り止まない銃声の中で二人は呑気に会話を続ける。恐らく出口は全て塞がれている。銃声は段々と近づいてくる。どうやら絨毯爆撃ローラー作戦よろしくじわじわと追い詰めるつもりらしい。それでも二人に焦る様子は無い。
「真ちゃーん、貴重品は持ちましたかー」
「新しい銀行口座と印鑑持ったのだよ」
「俺との愛は?」
「お前が持ってろ」
台所に付けられたナイフの痕。あまりにも傷つきすぎて、それは、そう、きっと、大きな衝撃を与えれば崩れるだろう。爆発のような、大きな衝撃があれば、穴が空く。
良い家だったと緑間は笑う。笑いながら構えたのは、改���されたショットガンSH03-R。
「俺と真ちゃんの運命は切り離せないっての!」
轟音。
*
新居のあちこちに鼻歌をしつつ隠し扉や倉庫を作っていた高尾和成は、いつになく幸せそうな緑間真太郎の様子に首を傾げた。引越しの片付けを手伝うでもなく、ソファに座って何か手紙を読んでいる。この上機嫌は、先程届いた巨大なダンボール箱を開けてからである。あまりにも幸せそうな様子に、こっそりとその箱を覗いてみれば、そこにはぎっしりと同じ種類の缶が詰めこまれていた。
「新商品、デザート感覚で楽しめる魔法のスイーツ飲料『OSIRUKO』……?」
はっ、として会社を見てみればそれは赤司征十郎の経営する会社の傘下である食品会社の一つであり、オシルコという名前に高尾は聞き覚えがある。まさか、と思い振り返れば、緑間は同封された手紙を読み終わったところだった。
「し、真ちゃん、それ見せてもらえない?!」
「構わんぞ」
機嫌が最高潮に良いらしい緑間はあっさりと自分宛の手紙を高尾へと回した。そこに書いてある文面を読み終えて、彼は新居の床にうずくまる。
『親愛なる真太郎へ。
元気にしているようだね。少年から事情を聞いたよ。今年はアズキが豊作過ぎて廃棄していたから丁度良かった。お陰様で新商品が出来たので送る。お前が好きなら定期的に送ろう。それくらいの利益は出させてもらったのでね。刺激が足りないだろうと思って幾人かフリーの殺し屋を手配しておいたので一緒に楽しんでほしい。ではまた。これから寒さが厳しくなるが風邪などひかないように』
いやいやいや、殺そうとしてる相手に風邪の心配とか殺し屋サービスとかちょっと意味がわからないし、新商品? あのオシルコとかいう飲み物が? 緑間はそれを狙って赤司のところに少年を送ったのか? っていうかもう新居の場所バレてんじゃん?
数限りなく溢れてくる疑問とそれがもたらす頭痛に高尾は呻く。
高尾の視界の端で、緑間は幸せそうにオシルコの缶を開けている。よくよく見ればもう三缶目で、お前の運命の相手ってそういうことだったのと高尾は肩を落とさざるを得ない。そうだね、お前、コーヒー苦手だったもんね。
もういい、問題は全て投げ出してしまおう。やけくそになって高尾も缶のプルタブを開けた。勢いだけで喉に流し込む。噎せる。
どうも緑間の運命は、緑間に甘くできているらしい。
【昔の話Ⅰ】
「ひさしぶりー」
「そうだな、昨日ぶりだ」
暗に久しぶりではないと告げながら、黒いコートをまとった男の顔は目に見えて引きつった。初回に、死ね、と銃を顔面すれすれに撃ち込んでも瞬き一つしなかった、やけに自分を気に入っているらしい同業者のことはここ数日で危険人物として認定されている。この場から消えようにも、如何せん仕事前で、この場所は最も良いポイントだ。タカオと名乗る男は、恐ろしく目ざとくいつも彼を見つけた。
��ねえ、いい加減に名前教えてよ」
「断る」
「本当にほとんど毎日仕事してるよね? 疲れない? 休みたくならない? 手とか抜きたくなったりしない?」
「別に、そこにやるべきことがあるから人事を尽くしているだけだ」
お前には関係ないだろうと睨む緑髪の男には、出会った当初には伺えなかった諦めの色が僅かに浮かんでいる。どうせそう言っても、このタカオと名乗る男は気にしないのだろうと。
「うーん、やっぱ格好いいわ。好きだよ」
百発百中の殺し屋、誰にも媚びず決しておごり高ぶらない、緑色の死神。
「なんだそれは」
「え、知らないの? 巷じゃこっそり噂になってんだよ。緑色の美しい死神がいるってさ」
「下らない」
取り付く島もない返事にも、タカオは楽しそうに笑う。一体全体何がそんなに楽しいのかわからないまま、死神と呼ばれた男は苛立ちだけを募らせていく。早いところ、殺してしまった方が良い。殺してしまったほうが良い。けれど、今はまだ出来ない理由が彼にはあった。
【ターゲットは瞳!?】
「ねえ真ちゃん、いっぱい働こうね」
「なんだいきなり」
「お前が男らしく七億使った直後に引越し、装備も半分くらい置いてく羽目になって揃え直し、まあ金がねぇんだよ! 借金まみれだよ!」
「働いているぞ、俺は」
「俺もね! それでも全然足りないの!」
カレーを頬張りながら不満げな顔をする緑間に、高尾はこめかみを押さえる。緑間の金銭感覚がまともではないのは出会った当初からだが、今まではそれを支えるだけの収入と貯蓄があった。しかしいかな売れっ子殺し屋の二人とはいえど、七億の宝石は手に余る存在だった。なまじ緑間が派手に買っていったためにしばらくは闇に流すのも問題がある。いまいち状況を理解していない緑間に恨みがましい瞳を向けながら高尾は苦言を呈した。
「ご飯にも困るし、三食赤司からのおしるこは駄目だろ」
「それはそれで構わないが」
「栄養考えて! 俺は別に糖尿病の真ちゃんでも愛せるけどさ! でも糖尿病になって欲しいかって別の話じゃん!」
そもそも俺甘いものそんな好きじゃねえし、そう泣き言を言えども、緑間はお前の好みなど知ったことではないと取り付く島もない。新居は白い家具で揃えられているが、そこに切り傷が付くのも時間の問題と言えた。
「言っておくけど、このままだとラッキーアイテムも買えなくなるぞ」
「それは困る」
最終手段として持ち出してみれば、ようやく緑間は食いついた。カレーを丁寧に掬い取って口に入れる前に、仕方がない考えておくのだよ、とありがたいお言葉が高尾に降り注いだ。
なに真ちゃん、三大欲求よりラッキーアイテムですか。
*
「昔ペアを組んだ相手?」
「ああ」
数日後から緑間は頻繁に外に出るようになったが、その表情は日に日に厳しくなっているようだった。これは緑間には珍しいことである。彼は基本的に性格に難アリでも仕事に関しては天才だ。行き詰まるということは滅多にない。日を追えば追うほど狙いに迫り、予定日に目的を果たす。緑間のグラフは右肩上がり以外の形を取らない。
その男が、日を重ねるほどに重い空気を纏う。はて、何か難航しているのだろうかと高尾が首を傾げた頃、緑間の方から声がかかった。
「次の依頼はお前の協力がいる」
「おお?」
シチューを煮込む手を止めて高尾が緑間のもとへ向かえば、人に物を頼もうとしているとは思えないほど嫌そうな顔が高尾を出迎えた。緑間が何かを頼む際はおおよそ常にこのような感じなので高尾はもう気にしていない。むしろ愛する人から頼られて嬉しくない男がいるだろうかと、反比例するかのように高尾はご機嫌である。
「なになに珍しいね、いいよ手伝うけどどういう感じなの?」
「お前がいれば簡単な仕事なんだがな、俺だけでは少し厳しい」
「それこそ珍しいね。なんで?」
「俺のやり方を知っている相手がいる」
「んんん? どういうこと?」
そして緑間の口から告げられた言葉に、新しい家に記念すべき一つ目の傷がつけられたのであった。
「昔ペアを組んだ奴が相手だ」
ねえ、なんか前も言った気がすんだけど、だから他の男の話なんてしないでよ真ちゃん。
*
「組んだのはお前と会う前の一度きりだったし、顔を見て暫くしてようやく思い出したくらいの奴なんだが」
「それでも、真ちゃんが覚えてるなんて珍しいね」
「ああ」
なかなかに、印象的な奴だったからな、と他意なく言ったのであろう緑間の言葉に高尾は手に持っていたフォークを机に刺した。
緑間真太郎は興味の無いことは覚えない。関係の無い人物は覚えない。それはいっそ清々しいほどに全て忘れる。その緑間の意識に残っているというだけで高尾からすれば嫉妬に値した。けれどシチューに生クリームを垂らしている緑間は気にすることなく食事を続ける。
「それで? そいつがどうしたって?」
「今回の俺の標的に、そいつがボディガードとしてついている。そして、ここからが一番問題なんだが、どうやら俺に狙われていることを今回の標的は知っているらしい」
「情報が漏れてるってこと?」
「恐らく」
緑間が嫌そうな顔をしている理由がわかって高尾も溜息をついた。引き抜いたフォークで青いブロッコリーを突き刺す。さくりといく。
標的が緑間のことを知っていることが問題なのではない、情報が漏れていることの方が致命的なのだ。今バレているということは、これからもバレる可能性がある。単純な話だ。そしてそれは暗殺という点で致命的だった。その流出源を突き止めるのは、人を殺すよりもよほど面倒で手間がかかる。
「まあそちらを突き止めるのは後回しだ。時間がかかるしな」
「あいよ。ボディガード雇うってことはどうせお偉いさんでしょ」
「ネムジャカンパニーの社長だな」
「ああ、あの。なんだっけ、この前新聞で見たわ。ガウロ氏だっけ。結構長生きしてる会社じゃん。十年前くらいから勢い増してるとこか。まあ勢い良くなるのと一緒に悪い噂も増えたけど」
「どうせどこかで恨みを買ったんだろう。どうでもいい」
緑間がどうでもいいと言うならば、彼にとってそれは本当にどうでもいいことなのだ。どうやらこの話題は彼にとってあまり面白くないものらしいと高尾は悟った。自分から振ってきた仕事の話なのになあと彼は溜息をつく。ウイスキーを割りながら高尾はこの話題を終わらせるべく次へ進むことに決めた。
「で、次のチャンスっていつなわけ」
「明後日だ」
あまりにも急な話に高尾の喉から漏れたのはウイスキーと細かく砕きすぎた氷の欠片だ。噎せている高尾を、緑間は汚いと一蹴する。ごめんごめんと謝りながらも、何故自分が謝っているのか高尾は分かっていない。
ねえ真ちゃん、連絡はせめて一週間前って習わなかった?
*
「射程距離は一キロ、標的まで直線が開いてさえいれば決して外すことのない百発百中のスナイパー」
B級映画のような宣伝文句、それを現実に実行してしまう男がこの世の中にいるとは誰も思わないだろう。そう、緑間真太郎と、出会わなければ。
オーダーメイドのスーツに身を包み、新品の革靴を光らせ、髪の毛をきっちりセットした高尾は薄笑いを浮かべながら、現在八百mほど離れた屋上にいる男に思いを馳せる。まあ人外だよな、と彼は思う。
熟練した銃の狙撃はただでさえ厄介だ。それが一キロ先ともなれば視認することはまず不可能。周囲一キロを全て護衛することなど大統領クラスでなければ到底できやしない。いいや、今まで暗殺に倒れた大統領の中で、誰が数百メートル先からの銃弾に当たっただろうか。それは全て、至近距離からのものではなかったか。キロ単位なんて前代未聞。
そして一キロの距離を、弾丸は一秒で詰める。
それを避けられる人間がいるならば見てみたいと高尾は思う。
「失礼」
するすると宝飾にまみれた人ごみを避けて高尾は歩く。その動きは不審ではないが、もしも誰かがじいっと見つめていたらその滑らかさに感嘆したかもしれない。
けれど、どれだけ滑らかに動けども、人が歩く速度には限界がある。乗り物に乗って移動するにも限度がある。バイクに乗っても一キロ先に行くのに一分はかかるだろう。
そう一キロ先からの狙撃とは、そういうことだった。捕まえることが、出来ないのだ。
仮に一分でたどり着くとしても、その一分の間に緑間は装備を解体して車に乗り込むことができる。後は逃げればいいだけだ。それも、一キロ離れた狙撃元を明確に理解できていたら、というとんでもない前提をもとにした話、実際はそううまくはいかない。探す時間を含めて三分で済めば奇跡だろう。そしてそれは逃亡するには十分な時間である。
サイレンサーを付ければ音も消え、狙撃元はよりわかりにくくなる。
まだ高尾が緑間と直接出会う前、緑の死神と風の噂で流れては来たが、彼の緑色を捉えた時点で、その人物は相当の人間だったのであろう。普通は、その姿を見ることなく全て終わるのだから。
「招待状をこちらへ」
「お招きに預かり光栄です、ガウロ氏のお屋敷一度拝見したいと思っておりました」
人好きのする笑顔を浮かべながら高尾は招待状を差し出す。ポーターは無表情のまま招待状を受け取って裏へと消えていく。その間は警備員が高尾を見張っている。招待状は無論偽物だがバレるとは思っていない。ここでつまづいていては話にならないのだ。裏で招待状が綿密にチェックされている間、欠伸を噛み殺して、彼は愛する緑間真太郎を思う。この寒空の下、呼吸すら失ってただ���かにタイミングを待っている男のことを。
銃の射程距離は遠距離狙撃で三キロ以上のものもある。一キロという着弾距離自体は、別にないものではない。しかしそれが、百発百中というのが問題なのだ。問題。そう、緑間のそれは災害とも言うべき問題だ。一キロ先。天候や筋肉の微細な動き、銃の調子、全てがそれを左右する。一ミリのずれは、一キロ離れればメートル単位の誤差だ。それが百発百中というのだから、その技術がどれだけ繊細で神がかっているかわかるだろう。
「ようこそおいでくださいました、ミスタ」
暫くして出てきたポーターは招待状を高尾に返すと僅かに微笑んだ。うやうやしいお辞儀に見送られながら高尾は赤い絨毯を踏みしめる。
着飾った婦人と紳士の間を交わしながら、彼はホールへと向かう。この豪邸から少し離れた場所では子供たちがゴミ山で暖を取りながら埋もれていることなど信じられないような、きらびやかな世界。
しかしその華やかさとは裏腹に、全てのカーテンは分厚く閉ざされ、少し閉塞感を生み出していた。ご丁寧に固定され、風や客の手遊びで開いたりすることのないようになっている。
(成程、こりゃ確かにバレてるわ)
しかし緑間の正確さ、それは逆に言えば、つまり緑間の視界から外れさえすれば、狙われることは無いということである。
見えないものに向かって撃つことはできても、狙うことは出来ない。
これが緑間の正確さの弱点でもあった。他にも緑間には、自分の信念に基づいた致命的に大きな制限がある。故に、彼を相手にする際、他者を巻き込むような乱射や爆破に注意する必要は無い。スナイパーライフルは巨大だし、小型のピストルだって会場の入口で持ち物検査で引っかかって終わりだ。今回も勿論高尾は綿密なチェックを受けている。そもそも近距離で殺してしまっては、そこから逃げ出せるという緑間の特性が全く生かされない。
わざわざシェルターに閉じこもらなくとも、カーテンを締め切るだけで、緑間の視界からは外れる。単純だが効果的な手段だ。一生、緑間の目から逃れられるなら、緑間に殺されることはない。
けれど、金持ちが誰にも合わずにいられるはずもないのだ。
全くもって皮肉なことだと高尾は思う。金持ちになればなるほど恨まれやすくなり、標的になりやすくなる。そして、金持ちであればあるほど、社会的に上の立場にいればいるほど、彼らはそれをアピールしなければならない。そういった付き合いをしなくてはいけない。自分の権力を、財産を、力を、知らしめなければいけない。それが彼らの仕事の一つだ。そうしてまた、恨みを買っていく。その連鎖。
今回、高尾が潜り込んだのは、手に入れた宝石のお披露目パーティーとやらであった。その話を聞いた時はあまりのくだらなさに呆けてしまったものである。命を狙われていると知っているのに、しかもそれが緑間真太郎であると知っているのに、こんな下らないパーティーで命を危険に晒すというのか。
(ま、しかし赤司さまさまだわ)
それとも、潜り込むことなど出来ないという自信でもあるのだろうか。確かに緑間は近接の暗殺には向いていないし、コンビである高尾の存在を知らない人間は多いだろう。そのためにも、二人、極力別々に仕事をしているという側面もあるのだ。
まあ、それが運の尽きだと、何の感慨もなく彼は飲み込む。高尾和成を知らないことが、運命に選ばれなかったということなのだと。
(確かに赤司いなかったら厳しかったかもだし)
金持ちの親戚付き合い知り合い付き合いというのは広い。誰それの娘婿の弟の従兄弟の云々。関係は蜘蛛の巣のように広がり絡まっていく。そして結束を強くし、いらないものを切り捨てて肥えるものは益々肥えていく、それが金持ちの常套手段だ。顔も知らない相手を、利益になりそうだからと平気で招く。だからこそ招待カードには華美と工夫が凝らされるわけだが、それさえ偽造できてしまえばあとはこちらのものだった。
そして大抵の招待状は赤司の元に届いている。
それを緑間がどのようなやりとりの結果入手したのかは知らないが、流石に本物を使うことは禁止されていたが、本物があれば高尾にとってそれを偽造することはたやすい。緑間と違って近距離、接近しての暗殺がメインの高尾が長年の間に身につけた技術であった。
立食形式になっているらしい会場で、白い丸テーブルがランダムに、けれど一定の景観を損ねないように並んでいる。盛り付けられた花やレースは美しく、どうやらプランナーは一流のようだった。主席が来るであろう位置を確認した高尾は、それに背を向けるようにして適当なテーブルに陣取る。手持ち無沙汰にしている一人の婦人を見つけて笑いかける。そしてボーイから二つグラスを受け取って近づいていった。
さて、どうしましょうかね。
*
耳に当てた通信機から、数秒おいて悲鳴と怒号が聞こえたことを確認して緑間は伸びをした。数時間同じ姿勢で微動だにしなかった筋肉は固まっている。ストレッチをしながら、耳元の悲鳴をBGMに、仕事が成功したらしいことを思う。
てきぱきと荷物を片付けると彼は走ることもなく、平然と階段に向かっていく。下手に目立つことをする方が危ないと彼は知っている。どうせ、この場所を見つけるまでに五分はかかるのだから。焦る方が間抜けだと彼は思っていた。
さて、これからどうやって情報流出者を突き止めようかと次のことを考えていた彼の耳元で、唐突に音が途切れた。叫び声が消え、途端に夜の静寂が彼に襲いかかる。聞こえるのは彼自身の呼吸だけ。
通信が途切れた緑間は首を傾げた。無音。自分の機械を確認してみるが電源は変わらずに点いている。
脱出し、落ち合うまで通信機は入れっぱなしであるのが常である。何か非常事態があって電源を落としたとも考えられるが、そもそも通信機は見た目でバレるようなものではない。持ち物検査でも気がつかれないのだ。緑間から高尾に飛ばせない、高尾から緑間への音声の一方通行である代わりに、最大限に小型化され、洋服に仕込まれている。
数秒固まった緑間は、僅かに眉を潜めると屋上でコートを翻して走���出した。手すりに引っ掛けるようにしたロープを掴んで、減速することなく飛び降りる。ビルの下にはバイクがつけてある。
今高尾は潜入するために丸腰だ。小型通信機の持ち込みだけで精一杯。故障や何かの不慮の事故で電源が落ちただけならばいい。
けれどもしもそうでなかったなら、もしも見つかってしまったなら。もしも、緑間の仲間だと気がつかれたなら。
さて、どうしてやろうか。
*
「よくまあ気づいたよなあ。俺、目立つような行動一切してなかったはずなんだけど」
「お前がシンと一緒に歩いている所を見た」
「んあー、成程、そういうこと」
顔面から血を流して高尾は笑う。骨折まではしていないようだが、十分に痛めつけられているとわかる姿で、彼は一人の大男に引きずられていた。手足は拘束され、身動き一つ取れない状況で、屋敷の奥へと無理矢理連れられながら高尾は笑う。
「そうだよなあ、真ちゃんは目立つからなあ」
「よくあの男をそんな風に呼べるな」
「真ちゃん? 真ちゃんを真ちゃんって呼んでいいのは俺だけだし、真ちゃんって言葉じゃ表現できないくらいにかわいくてかわいくて仕方ないけど、でも別にそのかわいさを教えてやるつもりもないしなあ」
「いや、わかった、お前も相当にクレイジーな奴だ」
捉えられている筈の高尾は陽気に、そして引きずっている筈の男のほうが顔を引きつらせながら曲がりくねった廊下を歩く。侵入者を拒むように、複雑に作られた屋敷。
セレモニーの場に現れた男、今回のターゲットが額から血を溢れさせた時、高尾はその男に背を向けて談笑していた。目の前の婦人の悲鳴、さもそれで気がついたかのように後ろを振り返り、緑間の仕事が見事に成功したことを悟り、気を失いそうな婦人を介抱するフリをして外へ出ればそれで高尾の仕事は完了だったわけだが、どうやら本当に運の悪いことに、緑間とペアを組んでいた男は、高尾の顔も知っていたらしい。
いや、緑間が顔を見て思い出したと言っていた。そのことを高尾はこの期に及んで思い出す。緑間から見えたということは、この男からも見えたということだ。その時、高尾が側にいなかったと、誰が断言できるだろう。自分の迂闊さに彼は血の味しかしない口をあげて笑う。
「で、なんで殺さないわけ……って、わかりきってるか、そんなの」
「ああ」
「大分ボコってくれたけど」
「人の命を奪っているのだから、それくらいの報いはうけろ」
「そりゃ、その通りだわ」
高尾の左ポケットに入れていた通信機は衝撃で壊れている。小型はヤワでいけないねえと彼は改良を心に決めた。緑間に現状を伝える術はない。それでも、引きずられている自分の姿と、その男から伝わる振動に、高尾は笑っている。
ああ、もう、本当に、これだから!
*
「ようこそ。君がシンの相棒?」
「ありゃ、随分とちっせえなあ」
高尾が連れてこられた場所は屋敷の最奥、巨大な樫の木の扉を開いた応接室だった。扉を正面に、革張りの椅子に座る人物は、その椅子の重さに比べて、随分と軽そうな、男。
「ええ、ですがあと数年もしたら伸び始めますよ」
そう、男というよりは、少年という方が的確だった。まだ伸びきっていない手足に、滑らかな肌、声変わりをしたのか定かではない柔らかい声。
「あんたがこの屋敷の主人?」
「ええ」
「随分若いんだね」
「今年十六になります」
「そりゃ良いね」
「いやあ、良い事なんて何も無いですよ」
椅子に合わせ��机にも、少年の体は不釣り合いだ。それでも、そこに座るのが当然といった様子で彼は微笑んでいる。何かに似ている、と思った高尾は、一度だけ遭遇した緑間の元家族を思い出して溜息をついた。世の中には、たまにとんでもない子供が生まれるものだ。
「六歳の時に父さんや母さん兄さんを殺したまでは良かったんですけど、当時の僕は馬鹿でね、六歳なんて社会的になんの力も説得力もないということに気がついていなかったんです」。
「あんた、家族全員殺したのか」
「まあ、そういうことになりますけど、どうでもいいじゃないですか」
「そうかな」
「ええ」
僅かに目を細めた高尾に気がついているのか気がついていないのか、少年は話し続けている。その頬が僅かに上気していることに気がついて、高尾は僅かに哀れみを覚えた。
「殺してもらった彼は遠い遠い親戚なんですが、僕の力でここまで来れたというのに段々調子に乗ってきてね……まあ幸いにも、僕も自分の意思が認められる年齢になりましたから、ここらで死んでもらおうと思いまして」
これは、少年の自慢話なのだ。
「依頼主はぼくですよ」
種明かしをするように楽しそうに少年は笑うが、そんなことはこの部屋に入った瞬間から高尾にはわかっていたことであった。
「じゃ、なんで俺は捕まえられたわけ? あんたの希叶って良かったんじゃないの?」
「殺し屋を捕まえたほうが後継は楽でしょう」
そしてまた予想通りの答えに高尾は苦笑してしまう。
この少年が社会的にどういった扱いになっているのかはしらないが、ガウロを殺した実行犯を見つけ、ついでに誰か適当な人間をそのクライアントだったと糾弾し、自分がこの屋敷の正統な血統だと証明して跡を次ぐ。そんなシナリオを描いているのだろう。正直な話し、稚拙だ。稚拙で、単純である。しかし稚拙で単純なストーリーは人々の心に届きやすい。それは、わかりやすさに繋がるからだ。その点で、この少年は確かに正しかった。
「あなたたちのこと調べさせて頂きました。百%の達成率を誇る殺し屋。あの男が万全の警備をすることはわかりきっていましたしね、殺せないんじゃ仕方ない」
「別に俺たち以外にも適任は沢山いたと思うけど」
「調べさせてもらったと言ったでしょう。あなたがたは依頼された人物以外は殺さない。女子供老人若者、一般人もマフィアも。何故そんなポリシーを持っているのかは知りませんが、何より、敵に襲撃をされても殺さないというのは驚嘆に値します。だったら、僕が君たちを裏切っても、君たちは僕を殺せないでしょう?」
そう、少年の計画は単純ながら、単純ゆえに、正しかった。ただ、前提を圧倒的に間違えていただけであった。
「いや、君のこと頭良い少年かと思ったけど全部撤回するわ。君、ただの馬鹿だわ。それも、大馬鹿。ただのガキんちょ」
「なんですって」
「そんなちっこい体? あれ? 君百六十ある? ギリそんくらいだよね? まあそんな体でこんな計画して調子乗っちゃってんのはわかるけど、そんなでっけー椅子にふんぞり返って座っても大人にゃなれねえよ」
「負け惜しみですか」
「んん? 別にそう思ってもいいけど、真正面からお前に向き合ってる人間にそういうこと言うのはどうよ」
上気していた少年の頬は今怒りで赤く染まっている。それを見て、高尾はやはり哀れみしか覚えない。馬鹿だなあ、と、そう思うのみだ。そもそも十六歳という年齢に頼らなければ大人を従えられないという時点で器は知れていた。
赤司、お前と似てるとか言っちゃってごめん。少なくともお前は自分の年齢を言い訳になんて一度もしなかった。
「いやー、なんでこんな奴ん所で働いてるわけ?」
今までの全ての口上を無視して自分を連れてきた男に高尾は話しかけた。その様子に少年は気色ばんだが、話しかけられた男は、なんてことないようにその質問に答える。
「今度子供ができるんだ」
「なるほど」
満足げに笑って、高尾は少年に向き直った。その顔は笑ってはいたが、その瞳は猛禽類のように尖っている。少年は僅かに怯んだが、それはきっと、高尾に怯えるには少し遅すぎた。少年が、世界を知るには、遅すぎた。
口を開く最後の瞬間まで、高尾の表情は笑顔で象られていた。
「だってさ、真ちゃん」
「成程」
その瞬間、空気がかすれるような音が二発響いた。
いいや、殆どの人間には一発にしか聞こえなかっただろう。それほどまでにその音は連続しており、微笑む高尾の前で、少年は額から血をあふれさせている。そうしてそのまま、机にうつ伏せるように倒れた。その表情は高尾に怯えた瞬間のまま、自分が死んでいることにも気がついていない。
扉に空いた穴は一つ。正確な射撃は、一発目と全く同じ軌道で、一ミリもずれることなく二発目を撃ち込んだ。
障壁を壊す一発目はどうしても軌道がずれる。それをカバーするように、全く同じ軌道で撃ち込まれた二発目は正確に少年の額を貫いた。それは、先程ガウロを殺した時と全く同じ手段。
次の瞬間にドアノブが外側から高い金属音を立てて飛び散った。開く扉の向こうでは緑間が冷たい瞳で待っている。その瞳はたった今一人の少年を殺したとは思えないほど凪いでいた。
「俺の目から逃れられると思うな」
そう告げる緑間の言葉は、少年には届かない。
狙われた人間は緑間の視界から外れれば、死なないで済む。それは絶対の真理だ。緑間の目に、映らなければ。そう、風の噂で緑の死神を知っている人間はいれども、その死神にコンビがいることを知っている人間は少ない。
死神の瞳が、四つあることを、知っている人間は少ないのだ。
「久しぶりだな、ビル」
「廊下には十五人配置しといたんだけどなあ」
「百人用意しておけ」
十五人の警備がいたという廊下からは呻き声が聞こえる。死んではいないが、手足は使い物にならなくなっているのだろう。
うつ伏せて死んでいる少年に目もくれずに緑間は高尾のもとへと歩く。へらりと笑った頭を思い切り叩くと、拘束具をほどきにかかった。そのあまりの唯我独尊ぶりを、相変わらずだなとビルと呼ばれた男は笑う。
「あんたの相棒にちっとは手を出したが、そうじゃなきゃ俺が雇い主に疑われるんだ。骨まではやってねえ。勘弁してくれ」
ちらりと高尾から視線を上げると、緑間は暫く無言だったが、苦々しげに吐き捨てた。
「……まあ、お前には家族がいるしな」
その一言に、やはりまだあのルールは有効だったのかとビルは笑う。
緑間真太郎が自らに課した最も大きな制限、それは、家族がいる者は殺さない、そんな歪んだ正義である。その理由を知る者は少ない。緑間も正しいと思っているわけではなく、ただそれが彼のルールであるというだけだ。依頼を引き受けるか否かの基準も基本的には全てそれである。家族がいなければ良し、いれば断る。
彼が周囲の他の人物を殺さないのは、襲撃をされても決して殺さないのは、ただ、家族がいるかどうか咄嗟にはわからないから、その一点のみである。もしも天涯孤独の身の上ばかりをターゲットの周りに配置したならば、きっと緑間は無表情のままマシンガンを乱射していただろう。
「しっかしビルさん震えすぎだろマジで。俺笑い堪えんの必死だったわ」
「当たり前だ、緑の死神に依頼したって聞いた時はションベンちびるかと思ったぜ」
冗談を装っているが、実際にビルに触れてここまで連れてこられた高尾はその言葉が嘘でないことを知っている。彼はずっと怯えていた。元ペアを組んだ、緑の死神を、ずっと恐れていた。その振動は、引きずられている時から伝わっていた。その気持ちはわからなくもないと高尾は思う。間近で見ていたからこそ、その恐ろしさを知っている。
緑間の武器は銃全てだ。何もスナイパーライフルのみではない。ただ、安全面から遠距離を選択しただけ。近いのと遠いのだったら、逃げるとき遠い方がお得だろう、そんな単純な理論で彼は一キロ先からの狙撃を実現させた。
屋敷の奥、招待客がいなくなった場所で、緑間が遠慮する理由など一つもない。
「しかしまあビルさん、これから大丈夫なわけ? 依頼主死んじゃったし、報酬もないんじゃない?」
「別に警備団長ってわけじゃなし、そもそも殺し屋だ。こっち方面で評判が落ちたって気にすることじゃねえやな」
そうやって笑うビルには怯えた様子はもう見受けられず、なかなかにタフな男だと高尾は認識する。この世界で生き残っていくために必要な臆病さとタフさを、彼はしっかり兼ね備えているようだった。
「エリーは元気なようだな」
「お陰様で。今度見に来るかい」
「断固断る」
しかし目の前で高尾のわからない話を始める二人に、殴られても捕らわれても笑みを崩さなかった高尾はみるみるうちに不機嫌になっていった。
「ねえ真ちゃん!」
「なんだ」
「俺の前で前の男と話さないでよ!」
その瞬間に容赦なく振り下ろされた拳に、ビルは呆れたような溜息をついた。
緑の死神も、随分と俗物になったもんだ。
*
「え、真ちゃん、どうしたのこのお金」
「今回の報酬だ」
「いや、だって依頼主殺しちゃったじゃん?」
「俺のところに来た依頼は、カンパニーの社長を殺せ、という依頼だったからな」
「え?」
アタッシュケースを放り出した緑間は興味がないのか、くるくるとぬいぐるみの熊の手をいじっている。それは昨日までこの部屋に無かったはずのもので、どうやら緑間はまた散財をしたらしい。しかしそれを注意する余裕は今の高尾には無かった。
「何故名前の指定がないのかと思ったが、表と裏で二人いたのなら納得だ。全く、こんなことならもう少しふんだくればよかったのだよ」
「え、いや、だって依頼主ってその裏の少年の方で」
「ああ、そちらから、あの男、ガウロを殺せという依頼を受けて、ほかの奴からはカンパニーの社長を殺せという依頼がきた」
「同時に受けたの?!」
「同時期に来たのだから、両方受けて両方から金をもらうほうがお得だろう」
まあ今回は結局片方からしか受け取れなかったわけだが、零報酬よりはマシだったのだよと緑間は何でもないかのように言う。標的が同時期にかぶるというだけでも偶然の力は凄いが、じゃあお得だしという理由で両方同時に受けてしまう緑間の図太さも並大抵のものではない。
「嘘はついていないのだし」
と本人は言うがギリギリのところだろう。しかし。
「これで借金が返せるな」
と、そう言葉を継がれては高尾に返す言葉はないのであった。
真ちゃんって、本当に素直でかわいいおバカさんだよね。
【昔の話Ⅱ】
「いい加減に教えたらどうだ」
「何を?」
「お前の家族構成だ」
「えー、どうしよっかなー」
連日現れるタカオに、彼は苛立っていた。いらないことはべらべらと喋る癖に、肝心なことは一つも話そうとしない。
「早く教えろ、でなければお前を殺せない」
「情熱的だなあ」
へらへらと笑いながらも、タカオは彼に教えようとしない。銃口を突きつけても全く動揺する気配がない。家族構成を知らなければ殺せないと、口を滑らせるべきではなかったと彼は後悔する。けれど、最初の弾丸に全く怯えなかった時点で、この男に下手な脅しは無意味だと薄々気がついてしまったのだ。
「あ、じゃあさじゃあさ」
「なんだ、教える気になったか」
「名前! 教えてくれたら俺も教えるよ。どう?」
「却下だ」
一瞬もためらわずに切り捨てたことにタカオは落胆の色を隠さない。
「なんで? そんなに悪い条件じゃないと思うんだけど。俺はもう名前教えてるしさ、別に名前知られたら死ぬわけじゃないだろ? 日常生活、全部本名で暮らしてるわけじゃないだろうしさ」
「断る」
「なんで」
「名前は、家族だけが知っていればいいものだ」
「ええー」
一般とはかけ離れたその理論に、タカオは首を落とす。そうしてしばらく唸った後に、彼はさも名案を思いついたと言わんばかりにこう告げたのだった。
「じゃ、俺、お前の未来の家族になるわ!」
これは、いつかのどこか、昔の話である。
【ターゲットは君!?】
緑間真太郎が朝目覚めてみると高尾和成の姿がなく、朝食の準備もされていなかった。普段嫌というほどまとわりつき、朝になればベッドに潜り込んでいることもある煩い男は、忽然と姿を消した。
その日一日、彼は何も無いまま過ごした。そして高尾の作りおきのおしるこが無くなったことを確認して、缶のしるこを飲み、缶のしるこが残り八缶である、そのことを確認した。流石に夜になると腹が空いて仕方がなかったので、外に食べにでかけた。
そんなことを三日ほど繰り返したある日、彼は先日仕事で久々に再開した男にまた出会った。そういえば、と彼は思う。街で高尾と一緒にいるところを見られたのだから、似たような場所に住んでいる可能性は高かった。
*
「今日はタカオくん、一緒じゃないのか」
「消えた」
「え、大丈夫なのかよ、いつ」
「三日前の朝だ」
あまりにも常と変わらない緑間の様子にビルは戸惑っているようだった。以前の様子から、二人が互いのことを憎からず思っているのは自明の理のように思えた。それがどうだ、消えたというのに、片割れは平然とスパゲッティを口に運んでいる。
「お前、タカオくんのこと好き?」
「馬鹿か」
「あっそ、彼はのろけまくってくれたのにな」
「会ったのか」
「おう。つっても今日じゃねえよ。あれの四日後くらいかな。エリーって誰だって滅茶苦茶しつこく聞かれた。面白かったから言わなかったけどよ、お前、猫だって言ってなかったのか」
「そういえば言っていなかったな」
ビルの家族は猫だ。両親と死に別れたというビルは天涯孤独の身の上である。それを知った時、ではお前は殺してもいいな、と緑間は呟いたが、その時に彼は必死に主張したのだ。
確かに俺には親も恋人もいないが、俺にはエリーっつう大切な奴がいる。娘でもないし親でもないし恋人でもないが、俺の家族だ。
その主張を緑間は受け入れた。猫なんてあんな動物を家族と思うだなんて、お前は随分と変わっているなと、そのことは緑間の意識に強く残った。今度生まれるという子供も、そのエリーの子供だろう。
「そもそもお前、アイツと、タカオくんとどうやって出会ったんだよ」
猫を家族と呼んで憚らない男は、食事のつまみに思い出話を求める。
なあ、なんか、ロマンチックな出会いでもしたのか?
*
「何故昼間までついてくる……」
「いや、冷静に考えたんだよね」
「何をだ」
「なんで俺のこと信じてくれないかって。それで思ったんだけど、やっぱいきなり夜這いはまずかったよね。ちゃんとお日様の下、清く正しいデートをしてからのお付き合いが必要っつーか」
「死んでくれ」
仕事の時に毎回現れる男が、まっ昼間のカフェで現れた時、今度こそ彼は逃げようと思った。運ばれてきたばかりの前菜など知ったことではない。消えよう。立ち上がろうとする男に、タカオは勝手に向かいの席に座ると注文を済ませてしまう。そのタイミングでスープが運ばれてくれば、完全に彼は時期を逸してしまった。
「ねえ」
「なんだ」
「名前」
「断る」
サラダを食みながら緑髪の男はあっさりと切り捨てる。何度も尋ねればいずれ答えてもらえるとでも思っているのだろうか。何度聞いても答えはノーでしかないというのに、である。
けれどわざわざ昼間に出てくるだけあって、今度のタカオは少し方向性を変えたようだった。
「じゃあさ、あだ名教えてよ」
「は?」
「あだ名っつか、コードネームみたいなのあるだろ。仕事の都合で使う名前。本名じゃなくていいからさ」
「何故教えなくてはいけないんだ」
「だって俺これからもつきまとうけど、教えるつもりは無いんだろ? 俺に馴れ馴れしく『お前』とか呼ばれ続けたい?」
「…………」
「な、本名じゃなくていいから」
そしてきっと、彼が折れてしまったのも、ここが長閑な昼間のカフェだったからに違いないのだ。
「…………シン」
「え?」
「シン、だ。呼ぶなよ」
「わかった! じゃあシンちゃんね!」
「は?!」
渋々教えた仕事用の名前が、そら恐ろしい響きのものとして返ってきたことに彼は驚いた。それは、怯えに近いほどに驚いた。彼はそのように呼ばれたことなど無かった。それを発したタカオはといえば、遂に名前のはし切れを教えてもらえたことが嬉しいのか上機嫌でシンちゃんシンちゃんと繰り返す。
「即刻やめろ。今すぐにやめろ」
「ふふふーん、シンちゃんシンちゃん」
「やめろと言っているだろう、タカオ!」
激高した彼は街中だというのに普通に怒鳴ってしまった。視線が彼に集中する。しまった、と思うがすでに遅い。しかし、それに対してタカオが反省するでも怒るでもなく、酷く嬉しそうにしているもので、周囲の注意は案外すぐに逸れることとなった。
「今、俺のこと呼んでくれたね?!」
「はあ?」
「初めて俺のこと呼んでくれたじゃん! うわ、超嬉しい!」
どうやら自分がうっかり相手の名前を呼んだことにここまで喜ばれていると悟って、彼は遂に体から力を抜いた。真剣に対応している自分が酷く馬鹿らしく、滑稽に見える。
運ばれてきたメインディッシュを見て、彼はフォークをひっつかんだ。食べることに集中しよう。そう思ったのである。
そもそも何故こんな奴にまとわりつかれなくちゃいけないんだ。
*
「お前は何故俺にこだわる」
「シンちゃんのことが好きだから」
「ふざけるな」
そういえばその理由というものをしっかり聞いたことがなかったと、彼はことここに至ってようやく気がついた。いつもいつも、好きだ愛してる名前教えてと適当な言葉で誤魔化されて、本心など聞く前に疲弊しつくしていたのである。
タカオは左手でくるくるとパスタを巻きながら笑っている。誤魔化すつもりらしい。けれど彼に折れるつもりが無いのだと悟ると、タカオにしては珍しい、気まずそうな表情で語りだした。
「俺さ、実は前にシンちゃんにあったことあるんだ」
「なんだと?」
「いや、会ったっつーか、会ってないんだけど、なんつーかさ」
そこで僅かに首を傾げる動作を入れて、タカオは考え込んでいるようだった。それは、話す内容に悩んでいるというよりは、話している自分に疑問を抱いている、といったような様子である。
「俺の獲物横取りされたわけ」
「は」
「俺もさ、こう見えてもそれなりに仕事にゃプライド持ってたし、ちゃんと周囲に他に人がいないかとか全部気をつけてたのに、それでもお前に気がつかなかった。まさか一キロ先から狙撃してくるとは思ってなかったけどさ、そういう想定外の存在がいたっつーのが、なんか、悔しくてな」
「悔しいのか」
「悔しいさそりゃ」
怯えられ、恐れられ、疎まれることこそ始終だったが、悔しいと言われたことが初めてだった彼は戸惑った。以前一度だけ都合上仕方なくコンビを組んだ相手も、お前が怖いと、はっきりと彼に告げていた。そうはっきりと告げるだけ、そのコンビの相���はやりやすかったとも言えるが、それでも、だ。それでも、彼の周囲につきまとうのは怯え、あるいは、それを上回る怒りのみだった。
それ以外の感情を、彼に教えたのは、唯一。
「お前は、少し、赤司に似ているな」
「アカシ? 誰それ」
「…………俺の家族だ」
今度こそ完全に口をすべらせたことを悟って彼は舌打ちをした。その様子をタカオは不思議そうに眺めていたが、小さく「アカシ、ね」と呟くと、何事もなかったかのように続きを話し始める。
「ま、そんなわけで悔しくて悔しくてぜってーいつかお前超えてやると思って色々頑張ったり調べたりしてるうちになんかすっかりファンになっちゃって、好きになっちゃって、以上」
「全くわからないのだよ」
「恋ってそんなもんじゃねえの。じゃ、次シンちゃんの番な」
「は?」
「俺ばっかり話しても仕方ないじゃん。タカオくんから質問ターイム」
ふざけるな、俺は話さないぞ、そう言う前にタカオは笑みと共にたたみかけた。
「アカシって誰?」
ああ、やはり、昼間に会うべきではなかったのだ。彼の胸に襲い来るのは果てしない後悔である。何が何でも消えれば良かった。けれど日差しは柔らかく、人々が笑いさざめいているこの��やかな世界で、無駄な波乱を起こすことは、どうも彼にはためらわれたのだ。
「…………家族だと言っただろう」
「家族ねえ」
「ああ」
「家族かあ」
タカオは首を傾げている。シンちゃんは、家族を大切にするんだねえ、と一人で納得している。その様子が何故か不快で、これ以上話すまいと思っているにも関わらず彼の口からは言葉が飛び出した。
「家族を大切にしない奴はいないだろう」
「そうかな。家族でも酷いことするのなんてありふれた話じゃん」
「それは、家族ではないのだよ」
「ふーん?」
楽しそうにタカオは話を聞いている。けれど実際、楽しそうなのはその表情だけで、瞳の奥が全く笑っていないことに彼は気がついていた。家族は、誰にでも存在する、誰にでも存在するからこそ、誰もの傷に直結しているのだと、そう彼に教えたのも赤司だった。
「シンちゃんにとっての家族ってなにさ」
「家族は、家族だろう」
「血の繋がりってこと?」
「結婚した男女間に血のつながりはないだろう」
「そういうものじゃない。もっと精神的なものってこと?」
「そうだな、血が繋がっている必要は、無い」
「成程成程」
じゃあさ、とタカオは尋ねる。笑いながら尋ねる。けれど、その瞳の奥は確かに燃えている。彼にとって家族という存在が全ての基準になるように、タカオにとってもまた、その言葉は看過することのできない鍵の一つだったのだろう。
「もしも家族に殺されそうになったらどうすんの」
「家族は、殺さない」
「いや、そうじゃなくてさ」
「家族は、殺しあわないものだ。家族は、家族を殺さない」
そう、赤司が言っていたのだよ。そう告げた彼の表情を見て、タカオは先程までの炎はどこへやら、呆けたように彼を見つめていた。彼の、エメラルドの瞳を見つめていた。
「ごめん、ごめんシンちゃん、意地悪な質問した。ごめん。だから泣かないでよ」
タカオの言っている言葉の意味が彼にはわからない。泣いてなどいないのだよ。そう告げれば、でも泣きそうだよと笑われた。
「なあ、俺、わかった」
暫くの間、二人の間には沈黙が降りた。ウエイターが食後のコーヒーを持ってきたことを皮切りに、タカオはまた話し出す。俺、わかったよ。
「シンちゃんはさ、やっぱ、普通に幸せになるべきだ。素敵な幸せを手に入れるべきだ。こんなんじゃなくてさ。こんな殺し屋なんてやめちゃいなよ。シンちゃんなら他にいくらでもやりようがあるよ。この街ならやり直しなんていくらでもきく。そんでさ、幸せな家族作るべきだよ。『ただいま』って言ったら、『おかえり』って返ってきて、美味いメシとあったかい風呂があってさ、なんか適当にじゃれあいながらその日のこと話したりして寝るの。そういう、普通の幸せ。そういう家族をさ、手に入れるべきだって。」
微笑みながらタカオは畳み掛ける。シンちゃんはそれがいい。シンちゃんは、お日様の下が似合うよ。
「そしたら、俺は邪魔だけどさー」
笑いながら彼は告げる。暗殺者にふさわしくない、太陽のような笑顔で告げる。
シンちゃんがそれで幸せになるなら、俺は嬉しいなあ。
*
「真太郎」
「なんだ、赤司」
「次の依頼だ。ちょっといつもとは勝手が違う」
「どういうことだ」
「相手はお前と同じ殺し屋だ。どうも最近しつこく嗅ぎ回られて不愉快だからね」
「わかった」
「お前なら大丈夫だとは思うけど、一応相手もプロだから気をつけて。無理はするなよ。お前が怪我をするところはあまり見たくない」
「心配するな。俺なら問題無い」
「ああ、信じているよ」
「これが、資料か」
「ああ、そうだ。勿論相手に家族はいない。きっちり調べてあるから間違いない。遠慮なくいってくれ」
「…………」
「真太郎?」
「なんだ」
「僕はお前の家族だよ」
「……ああ、知っているのだよ」
「それなら良いんだ」
「赤司」
「なんだい?」
「…………いや、なんでもない」
「うん。それじゃあ、『行ってらっしゃい』」
*
「え、あれ、嘘、シンちゃんから会いに来てくれるとか、なにこれ夢かな?!」
真夜中の零時。彼の前でタカオは笑う。二人の距離は五メートル。走れば一秒かからないであろう距離。
けれど弾丸は、それよりも早い。
「なーんて、んな訳ないよなあ」
「っ、タカオ!」
銃声は一発、タカオが一瞬で左手に構えたナイフを弾き飛ばした。
それを成したのは常に彼が愛用しているスナイパーライフルではない。M28クレイジーホース、その愛機を彼は置いてきた。代わりに手にするのは近距離用リボルバー。
「はは、シンちゃん、手加減してくれたんだ」
直接撃ち抜かれたわけではないとはいえ、ナイフ越しに至近距離で当てられた左手は痺れて感覚も無いだろう。骨が砕けていてもおかしくない。
それでもタカオは笑っている。
「今、俺の頭撃ち抜けばそれで一発だったのに。それで全部終わったのに。なんでそういうことしちゃうかな、シンちゃんは」
「タカオ、お前は」
「俺、期待しちゃうじゃん」
その言葉が終わるか否かのうちにタカオは彼に向かって一直線に突っ込んできた。使えなくなった左手の代わりに、右手に別のナイフを持っている。
彼は咄嗟に、またそのナイフを狙った。迷いなく引かれた引き金は、そのナイフを弾き飛ばす。
「な、」
はずだったのだ。
けれど引き金と同じタイミングで、タカオはナイフを投げた。一直線に。真っ直ぐに。それは決して彼の弾道がブレないと信じているからこその賭けである。ナイフの中心を一ミリもずれずに狙った弾は、一ミリもずれることのないナイフに弾かれた。
次の瞬間、タカオの手には次のナイフが現れている。
「!」
次の瞬間には彼を押し倒すようにして、喉元にナイフをつきつけるタカオがいた。その額には、彼のリボルバーが突きつけられている。互いの命を互いが握っている状況で、タカオは笑っている。
「ダメだって、近距離戦じゃ。シンちゃんの武器はさ、それじゃないっしょ」
「お前、今の、ナイフ捌き」
「ああ、うん、気がついた?」
タカオは笑っている。悲しそうに笑っている。
「俺は右利きだよ、シンちゃん」
今まで、彼の記憶の中のタカオは常に左手を使っていた。物を食べるのにも、ナイフを構えるのにも、全て。
「お前に憧れて、左使ってただけ」
*
「お前、何故、赤司のことを調べ回ったんだ」
「……シンちゃんの家族が気になって」
「余計なお世話だ」
互いの急所に武器をつきつけて二人は会話している。今まで、こんなに近くに来たことがあっただろうかと、彼は場違いにも考えている。
出会ったのは、秋だった。木々の色が変わる頃。この国の秋は寒い。けれどどうだ、今はもう、日差しは柔らかくなった。いつの間にか冬すら超えて、季節はもう、春になろうとしている。
「赤司ってあのジェネラルコーポレーションの社長だろ。そんでもって、お前に殺しをさせてる張本人」
「俺が望んだことだ」
「おかしい、それは絶対に、おかしい」
「何が」
「だって、家族は殺しあわないんだろ」
かつて彼がタカオに告げた言葉が今返ってくる。彼の喉がひくりと震える。喉元に突きつけられたナイフは、その動きに合わせて僅かに深く刺さった。
「おかしいだろ。だって赤司は、お前を殺しの現場にやってんだろ。自分は安全な場所にいて、お前は死ぬかもしれない場所にやってる。それって間接的にお前のこと殺そうとしてるのと同じだろ」
「違う」
「違わない」
「違う」
「違わない!」
耳元で聞くタカオの怒鳴り声に彼は黙った。それは初めて聞く怒声だった。叫んだことを自ら恥じたのか、彼は顔を歪める。
「だが俺は殺し屋なのだよ。事実それ以外の道はない」
「そんなことない」
「ある」
「そんなことない」
「あるのだよ。お前は、俺のことを知らないだろう」
今度はタカオが黙る番だった。彼が言うことは正しかった。彼らはいくつかの季節を共に過ごしたかもしれないが、それが酷く偏った時間であることは自覚していた。否定することのできないタカオは、それでも必死に喉から声を搾り出す。
「……それでも、俺だったら、一緒に行くよ。行くなって言いたいけど、そこしか無いってんなら、その場所に行くよ。安全な場所で待ってたりなんかしない。お前が死にそうになってる場所に行って、一緒に死んでやれる」
*
どれだけの間、そのまま二人膠着していたのかはわからない。先に動いたのはタカオだった。首にかざしていたナイフをゆっくりと外して、放り投げる。彼の上からゆっくりと、どいていく。
「お前」
「はは、俺にシンちゃん殺せるわけないじゃん」
「タカオ、お前は」
「でも本当にさ、お前の方がずっと強いのにこんなことになっちゃうんだから、情けとかかけちゃダメだぜ。一発で決めろよ。できれば遠くから。そしたら多分、きっと、あんまりシンちゃん死なないだろうし」
対して、彼はゆっくりと立ち上がりながら、照準はずらさない。その銃口は、ぴたりとタカオの額を向いたままである。うっすらとタカオは笑っている。その瞳は燃えている。既に、覚悟を決めた瞳である。
「タカオ」
「なあに、シンちゃん」
「お前の家族構成を教えろ」
「……はい?」
今にも銃弾が額を撃ち抜くかと思っていたタカオは、想定外の質問に柄にもなく間抜けな顔をさらした。唖然、といった顔だった。段々と、その表情は苦笑に変わる。
「そんなの、もう赤司から情報回ってんだろ?」
「答えろ」
「いや、だからさ」
「答えろ!」
タカオにはわからない。何故彼が泣き出しそうな顔をしているのか。以前一度、泣かせかけてしまった時、その表情の美しさにタカオは一瞬見蕩れてしまったものだが、その時はタカオの言葉が原因だった。今はその理由がわからない。
いや、わかるのだ。ただ、それが真実だとタカオは信じられずにいる。
「赤司から、書類を受け取った」
「うん」
「だが、情報が一つ足りなかったのだよ」
「へ?」
「だから俺は、確かめる必要がある」
その声は震えている。眉を釣り上げ、睨みつけるようにして、彼は怒るように泣いている。その顔を見て、タカオは、自らの想像を確信に帰る。
「……おふくろは生まれた時にはいなかった。親父はアル中で、酔っ払ったところでマフィアに絡んであっさり殺されたよ。育ての親は俺のことが邪魔になった途端に殺そうとした。兄弟姉妹はいるのかもしれないけど俺は知らねえ。年齢はわかんねえけどまあ真ちゃんと大差ないくらいじゃねえかな。勿論誕生日もわからねえけどお前と相性が良いって信じてる。血液型はO型。これは前に輸血もらった時に聞いたから確実。そんでもって、」
「未来のお前の家族予定���
「……緑間真太郎だ」
「……へ?」
「俺の名前。色の緑に、時間の間、真実の真に、太郎は説明しなくてもわかるな」
「へ、あ、シンちゃん、いや、え、真ちゃん」
「家族の名前を知らないのは、おかしいだろう」
「……高尾和成です」
「高い低いの高いに、鳥の尾羽の尾、和を成す、で和成」
*
「何故お前に話さなくてはいけないんだ」
「へいへい、こりゃタカオくんも苦労するだろうな」
ビルの頼みをあっさり断って、緑間は珈琲を飲む。久々に飲むそれはミルクを大量に投入してもまだ苦く、彼は顔をしかめる羽目になった。
「それ、珈琲の味するのか?」
「する」
そういえば、高尾と初めて一緒に食事をした日、まだ互いの名前も知らなかった頃、同じことを聞かれたなと彼はふと思い出した。その時、緑間はなんと答えたのだろう。きっと、同じように答えたに違いなかった。
「なあ、シン、ずっと気になってたんだが」
「なんだ」
「お前さ、家族殺されたらどうするんだ?」
その問いも、やはり、あの日高尾が投げかけたものによく似ていた。家族に殺されかけたらどうする。
「一体全体どういう答えを求めているのかわからないんだが」
「求めてるとかじゃなくて、ただ気になるんだよ。お前の答えが」
「そうだな。もしもアイツが殺されても、別にいたぶったり懺悔させたり或いは……なんだ、まあ無駄なことをするつもりはない」
苦い珈琲を飲み干して緑間は答える。
「誰でも一発で殺してやる」
*
「いやさ、真ちゃんって家族持ち殺さないじゃん、けど俺って家族いねーわけ。天涯孤独の身の上だぜ? だからさ、全然真ちゃんは俺のこと殺しちゃって良いわけよ。だけど真ちゃん、俺が何しても俺のこと殺さないんだぜ? この前ベッドに押し倒したけど、ウザそうな目で『何してる』って言われただけで、それだけだぜ? いやいやいや俺も抑えましたよ、やっぱね、こういうのは順序踏んで優しくしたいからね。でもさ、これってすげーことだろ。真ちゃんは俺のこと殺さねーんだよ、家族もいない俺を殺さねーんだよ。やっぱ愛だよなこれって。だから俺も真ちゃんのことめいっぱい大切にしたいわけなんだけど、あー、でもいつか真ちゃんに家族って認められたらそん時はもうためらわずに行っちゃうかな。いっちゃうよ。もうなんつーか、狼になります。だって家族になったってことは、それってつまりオッケーってことだろ。いまはまだ家族予定だけどさ。うん? そうだよ。俺は、家族予定の候補者なんだよ」
*
一人取り残されたカフェで、いやはや、とビルは首を振る。おい、タカオくん、お前はどうやらとんでもない勘違いをしている。お前の執着は、どうやら、とんでもない勘違いをしている。
背中にびっしょりとかいた汗に気がつかないフリをしながら、彼はきつい酒をメニューから探す。
彼はわざと家族、と言ったのだ。一言も、高尾とは言わなかった。けれど緑間は自ら言ったのである。「アイツ」、と。それはそう、つまり、彼の中で、もう高尾は家族として認識されている。そうしてためらうことなく言うのだ。
「誰でも殺す」と。
こと緑間に限って、その言葉の重みをビルは知っている。誰でも。誰でも。恐ろしい言葉だ。家族の有無はそこに意味をなさない。いいや、究極的には、高尾の死に、関係が無くともいいのだ。誰でもとは、そういうことなのだ。老若男女、貧富も聖人悪人も何も関係なく、きっと彼は殺すだろう。例えばそれは、街一つくらいは。それくらいは軽くやりかねないと、正面からその時の緑間の瞳を見ていた彼はそう思うのだ。
なんで俺は、あいつに出会った時、いつもと変わらないなんて思っちまったんだろう。
*
「ただいま、真ちゃん」
「おかえり、高尾」
血まみれの高尾が入ってきた時、緑間真太郎はソファで興味の無い新聞をめくっていた。廊下にはぽたぽたと赤い染みがつき、折角引っ越したばかりの白い家具で統一された部屋を汚している。
「ごめんね真ちゃん、あったかいご飯食べよう」
「ああ」
その前に少し寝たらどうだと緑間は尋ねる。高尾は笑って、そうさせてもらおうかなと答える。実は結構眠くて死にそうなんだ、これが。
「死ぬなよ」
「死なないよ」
でも寝るわ。そう言ってバランスを崩した高尾を緑間は抱きとめた。さりげなく怪我を確認するが、いくつか深く切れている箇所は全て動脈を避けている。残りは返り血が主なようだった。
「真ちゃん」
「なんだ」
「今日も愛してるよ」
「そうか」
「真ちゃん」
「なんだ」
返事が返ってこないことに気がついた緑間は、腕の中で眠りに落ちている高尾和成に気がついた。僅かに首を傾げると、そのまま血が付くのも構わずに寝具に寝かせる。手早く応急処置をする。
安定した寝息に微笑むと、その額に僅かに触れるか触れないかの口づけを落として、緑間は笑みを崩さないまま、愛用するライフルの確認をした。それはあの日使わなかった、M28クレイジーホース。
「行ってきます」
*
高尾が目覚めてみれば、血だらけだった洋服は清潔な物に変えられ、傷には適切な処置がされていた。ああ、少し血が足りないなと思いながら彼がリビングへ向かえば、彼の愛する家族がリビングでつまらなさそうにナイフをいじっている。
「あー、真ちゃん」
「起きたか」
「色々ありがと」
「フン、洗濯もしてやったのだよ」
「嘘?! 真ちゃん洗濯できたの?!」
「馬鹿にするな」
「いや待って真ちゃん、これちゃんと染み抜きしてないっしょ! うわ、めっちゃまだらになってる! やっべえ俺の血でシーツめっちゃまだら! やべえ!」
「うるさい。さっさと飯の支度をしろ」
「はいはいはい」
笑いながら高尾は支度を始める。こんな生活がいつまでも続くはずがないと彼らは知っている。
いつか報いを受けて惨たらしく死ぬだろう。惨めに、哀れに、けれど同情の欠片もなく、唾を吐かれ踏みにじられて死ぬだろう。
「そうだ、言い忘れてた」
けれど今ここにあるのは、確かに一つの幸福な。
「おかえり、真ちゃん」
「ただいま、高尾」
Love me tender
Tell me killer
死が二人を分つまで
0 notes
Text
さあ 11月のご予定に・・11/17(日)
小樽は 骨董の似合う街 そして
和装の似合う街
小樽〈和〉コレクション 開催します。
#和装街小樽実行委員会 #小樽 #otaru
#NPO法人小樽民家再生プロジェクト
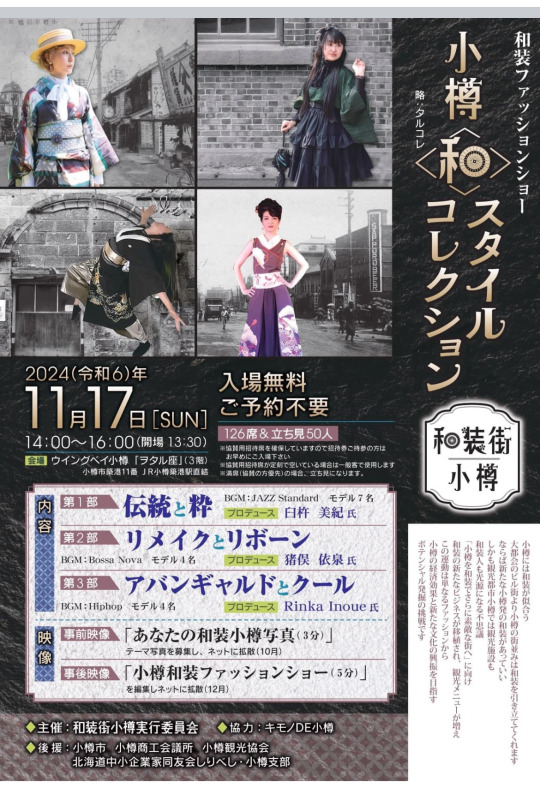

1 note
·
View note
Text
帰れない二人
ここに書かれた小説は、事実や日記をもとに書かれていますが、あくまでも小説ーすなわち、小説の定義であるところの「散文で書かれたフィクション」ーとはいかなるものなのかをどこまでも追求するために書かれたものといってしまっていいと思います。しかし、だからといって嘘を並べたてたわけでもありません。
この小説を四羽の鴨のヒナに捧ぐ
帰れない二人
私、もしくは彼、あるいはKには日記を書く習慣がある。この日記を読みかえしてみると、たいていの日が「朝、目が覚めると」という決り文句からはじまり、窓から差している光のことなどについて記され、それから並木道や横断歩道などを渡り歩いて最寄りの駅までゆく過程が仔細に記されることとなる。ある初夏の日の日記をここに引用してみる。
朝、目が覚めると、連日の雨模様からうって変わり、窓からの眩いひかりが部屋じゅうに充満している。小さな天窓からの光線は部屋のすみの物影にまでとどいて、そのひかりの帯のなかには塵が静寂をまもって浮かんでいるのがみえる。窓ががたんと音をたてる、今日は風がつよいらしい、と、部屋じゅうにふっと影が差したような、そのままじっとして様子をうかがっていると、こんどはふあっと部屋じゅうが明るくなる、どうやら上空を風に流れる雲が陽光にかかったらしい。
朝支度をして外へ出ると、くっきりした輪郭とその陰翳とをあわせもつ白い軍艦のような雲が青い空にいくつも流れている。風はひどく湿っていて、肌に纏いつくかのよう。ところが白い日差しの下にでるとそんな湿り気はたちまち吹き飛んでしまい、肌を刺すかのように注いでくる鮮烈な陽光の感触ばかりになる。白い軍艦雲の流れにともない、住宅街のせまい通りはその両側にたちならぶ家々の屋根ごと影に塗りつぶされては、またそぞろ明るくなってゆく。住宅街を折れ、近道の公園の大樹は風にわさんわさんと小刻みに揺れて、その緑の影はまるで水のような捉えどころのなさですでに乾ききった白い砂の上をしゅわしゅわ揺れている。
曲がりくねる並木道は連日の雨でいっそう鬱蒼として、瑞々しくはちきれんばかりに膨張した樹々の緑のほんのわずかな隙間から降ってくる木漏れ日のひかりと影とが歩くひとびとの背中や日除けの傘にストン、ストンとちょっと遅い流れ星のように落ちている。自転車が走れば、そのひかりは文字通りの流星になる。一方通行のこの通りにお尻の大きなトラックが迷いこんで来たらしい、その大きな荷台に樹々の枝がひっかかり、枝の揺れがどこか見憶えのあるような形の木漏れ日と影とを道に散乱させている。
この目が覚めてからのたったの数十分のくだりにたいして、それからの本来日記なるものに書かれるべきであろうその日に起こった出来事については、ずいぶんと省略してあっけなく記されるか、もしくは記されることすらない。たとえば、昼、カリーを食べる、とだけ記されているように。
私、もしくは彼、あるいはKはほかにはいくつか小説を書いたことがある。小説の書き始めとは、書き終わり以上に重要であろうことは、ある小説がどのように〆られたのかはろくに憶えていないのに、ある小説の冒頭についてはその文字の連なりを一字一句記憶してしまっていることからも明らかそうであるし、時代をこえて読まれ続けているいくつかの小説はそもそも���者の死により〆られることなく未完となっている。なるほど小説の始まりとは、まさしくそれ自体が丸ごとひとつの契機である、それがなければのっけから小説は存在することもできない。そこで私の書いたいくつかの小説の冒頭を読んでみると、そこにはどうやら規則性が見出せそうである。すなわち、そこでは唐突に小説が始まっている。何らかの意図や前提をもってこちら主導で語りが始められるというよりは、たとえば、日記とおなじように、朝、目が覚めるところから、なかばなし崩し的に語りが始まってしまうようなぐあいである。しかも、一般的にいう目覚めのよい意識のはっきりした朝であることはなく、とりわけ何か考えごとをするだけで頭の痛くなるような二日酔いの朝であるとか、意識のあいまいなときにかぎって始まっている。唐突に始まるばかりではなく、曖昧に始まってもいるのである。
これからあえて書いてみようとすることは、またしてもそのように、唐突に、曖昧に起こるのであった。
朝、夢うつつに、幾度か寝返りを打っているうちに目が覚めてしまった、もうすこし眠っていたかったのに。せっかくの休日なのだから早く起きて活動したい気持ちはある、それでも目の奥が鈍として重たければ、早起きしたところで仕方がない。それに今朝も日差しはおあずけらしい。七月のなかばをすぎても厚ぼったい灰雲の掃けない異例にながびく梅雨であった。昨年の夏は、観測史上初ということばを何度も耳にした。あまりにも暑い夏で、随所でいくたびも過去最高気温というやつを記録した。いまだかつて誰も体験したことのない暑さがいまここにあるなんて、そう考えるだけで興奮したものだった。あまりの暑さに死人もぽつぽつでたらしかった。それが今年の夏はいつまでも梅雨が明けず、かといって街を浸水させんばかりの大雨が三日三晩つづくのでもなく、傘のいらない程度の霧雨が降ったり止んだりをくりかえし、湿気の蔓延るばかりで、気がつけば観測史上初のながさの梅雨をその日も更新しつづけているありさまであった。梅雨入りまえの初夏こそはそこそこ暑い日もあったのに、ここ数日は夜になれば、ときには日中でも上着を羽織りたくなるほどの涼しい日々がつづいた。たいへん重度の夏好きとして、真冬の氷点下ちかくの日にも「寒い」とはいわず、あえて「涼しい」と不敵な笑みでいってのける者にしてみれば、それはそれは陰惨な涼しさであった。
あくまでももういちど眠りに就いて、つぎこそは目の奥の鈍重さを晴れやかに目覚めてやろうと気合をいれて目を瞑ると、こつこつ、こつこつこつと雨が窓硝子を打ちはじめる。困ったことにこの音はきらいではないので耳を澄ましているうちに昼になってしまった。ちょっとはうつらうつらしたかもしれない。雨はもうあがっている。
いまだ目の奥は重たいけれど、もう仕方がないのでシャワーを浴びることにする。風呂場はさすがにむっとしていて、裸になってみてはじめて、今日はここ数日よりいくらかは暑くなっていることに気がつく。水の蛇口をひねって、お湯を冷たくしていくと、シャワーの音が透きとおってよく耳にきこえるような気がする。
時枝はもうきっと公園についている頃だろう。髪はしぜんに乾くだろうから、硬球と左利き用のグラブの入ったナップサックを肩にかけて公園まで小走りで行く。相変わらずの鈍い天気、ちょっとは暑くなってきたものの、とうてい夏本番とは言いがたい空の下で、痺れを切らしたらしい一匹の蟬がとうとう鳴きはじめている。何かのまちがいで砂漠か深海か宇宙にでも産み落とされた赤子の産声のように、あまりにも孤独で、あまりにも無防備で、でもこの世界へ抵抗せんとする衝力だけはたしかに発しているような、そんな鳴声。道行く先に鳩の群れがわだかまっている、そのまま小走りで直進すると、いっせいに羽ばたいた。
「せみ、鳴きはじめたね」
あいさつ代わりに言うと、
「また産まれたの、カモの赤ちゃん」
そう言って時枝は池の中心あたりを指さす。
やがてカメが甲羅干しをしている大きめの岩の背後から、親ガモのあとについて、四匹のヒナが列になって泳いでいる。カモの一隊は、まるで池の周囲に集う観衆にじぶんたちの姿をお披露目するかのように、池じゅうをぐるりと行脚してみせる。大きい一匹と小さい四匹それぞれのあとには、ちょうど船の先端が水面をふたすじに切って波を起こすように波紋が尾をひいている。水面をみて、また雨がふってきたのかと思うと、それは池じゅう無数にいるアメンボたちの起こす小さな円い波紋で、ヒナたちが時折、赤ちゃんとは思えない素早い身のこなしで列をはなれるのは、どうやらアメンボを追いかけて食べている。
「はやいね」
「うん、はやい」
「産まれながらにして野生だね」
「うん、野生だ」
「癒やされるね」
「うん、癒やしだね。帰ってくるまでに全滅してるかどうか、賭けようか」
「賭けよう賭けよう、今日のカリー代」
「でも、じっさい、カラスに食べられる瞬間みたいかも、カモだけに」
「そんなこと言ってたら、また全滅しちゃうよ。とにかく急いで戻ってこようよ」
と言いつつ、時枝はたびたび立ち止まってはカメラのシャッターを切る。被写体に寄ってみたり、離れてみたり、背伸びしてみたり、屈んでみたり。こんどはいったい何を撮りだすのかと思うと、道端に停めてあるバイクに寄っていく、そしてバイクのミラーに向かってカシャ。そのミラーのなかを覗いてみると、近くの街路樹の枝の先と緑とが反射して映っている、かすかに風に揺れながら。
「あー。なんか先越された気分」
「だって、毎日あんな日記書かれて。同じものみてみたいって思うじゃない」
「読んでるんだ」
「このカメラ、白黒なんだよ。こっちはカラー用」
そう言って時枝は首からさげた骨董品のようなカメラに加えて、ウエストポーチからもうひとつ、ひとつめのよりははるかに近代的にみえる、それでもやっぱり時代を感じさせるフィルムカメラを取り出すと、
「いまのは白黒の目でみてたでしょ」
「いや、そうでもない」
「いや、白黒の目だ」
「だいたい、いつもみてるのは走ってる車とかバイクのバックミラーだよ。その走行に対してバックミラー��なかは逆行して流れていくようにみえる。その逆行の流れに樹の緑の揺れているのなんかが飛びこんでくるのが目に飛びこんでくるって感じ、緑の色も含めてね」
「いや、白黒の目だ。それは白黒の目なんだ」
「そうでもないって」
「ズバリ、白黒の目でしょう」
失笑で済ませるつもりが、堪えきれずにちょっと笑ってしまった。
「……きょう蒸し暑いね」
「うん、蒸し暑い」
ルナさんはヒジャブで被った浅黒い顔を厨房の奥からだして微笑んだ。ただ、微笑むだけ。目がくりっとしていて、上唇から覗いた歯がとても白い。こちらもお辞儀をして席につくと、水の入ったグラスを運んできてくれたその手でメニューの紙を案内してくれる。手の甲の色黒さにたいして、手のひらはまるでインク落としをつかったみたいに色素が抜けている。「ハラール対応」と書いてあるメニューは日替わりのカリーセットのただひとつだけなので、ただ頷くのみ。するとルナさんは、ただ微笑んで厨房へ戻っていく。
バングラディシュから来たルナさんの手料理を毎週末に必ず食べにいくようになってから一ヶ月ぐらいは経っただろうか。ルナさんのルナは月の意味だという。毎週かよっていたら顔を憶えてくれたらしく、いつも微笑むばかりでほとんど口をきかないルナさんが、自身の胸に手をあてて「ルナ。ツ、キ」と教えてくれた。時枝がどう思っているかは知らないが、ルナさんのカリーを食べにいくようになってから休日の過ごし方が上手になったと思う。せっかくの休日なのだから何かをしなくては、どこかへ行かなくては、と思わせられる足枷から自由になったとでも言うべきか。というより、もうルナさんのカリー自体がいちばんの目的なのだ。その目的さえ達してしまえば、重層的なスパイスの旨味で毛穴が剥き出しになりさえすれば、そう、無防備なまでの清涼感に包まれて、あとは野となれ山となれ。あるいはこれから海をみにいくにしても、なんら気負う必要はない、すっからかんの脳みそで海をみることができるのである。それぐらいルナさんの料理は美味しい、けっして食べて美味しかったと満足するだけではなく、味わいながらさらにもっと味わいたくなるような相乗的ななにか、それこそ海の揺らぎから目を離せなくなるようななにか、星空の瞬きから目を離せなくなるようななにかが。
「顔けわしいね」
「そんなことないよ」
「また、うんこ我慢してるのかと思って」
「今日はだいじょうぶ」
「じゃあ、なに考えてるの」
「いや、ルナさんの料理ってもの凄い引力だよね、月だけに」
「もうね、そうなの。大地の力を感じるっていうか、そりゃ火山は噴火するし、潮は満ち引きするワァ! 」
時枝は頭の上に両手で山をつくって、噴火するような身振りをすると、その手が天井からぶら下がっている唐草模様の間接照明にあたってぐらんぐらん揺れるのがテーブルの上のメニュー用紙にも影となって映じている。
「こらこらー。でも月ってじつは地球のまわりをまわってるんじゃないって知ってた」
「え」
「じつは地球も月のまわりをまわってるの、相互にまわり合いながら太陽のまわりをまわってる��てわけ。でも、その回転軸が地球の内部にあるから月だけがまわっているようにみえるというね」
「でも、このあいだね、咳風邪をこじらせて生理不順になってたときも、ルナさんのカレー食べた直後にきたんだよ」
「うんこが」
「うんこじゃない」
やがてルナさんが頭から足首までを被った装いで幽霊のように床を滑りながら、料理一式ののったお盆を地面と水平にして運んでくる。お盆の上のカリーの食器と、スープの食器のなかとで、ふたつはたがいに隔たっていながら、その水面はまるでひとつの地続きになっているみたいにまったくおそろいの揺れ方をしている。
ルナさんはいつものように口はきかず、メニュー用紙のお品書きと、それに対応する料理とを、色素の抜けた手のひらで交互に行ったり来たりさせて料理一式を案内してくれる。本日のメニューは、マトンカリー、キュウリとタリマンドのバングラサラダ、茄子のボルタ、オクラのバジ、鯖とトマトの酸っぱいスープ、そして粒のほそいシャダバット米の盛りに香菜とレモンが添えてある、これで千円ぴったり也。ひととおりの案内がすむと、ルナさんはいまいちどカリーを示して「キョウ、カライ」とだけ言った。
「ああ、ルナさんのカリーが食べたい」
食べ終えて、お代の千円をルナさんに手渡して、店をあとにしてすぐの時枝の口ぐせがいつもこうだった。
「もう食べ終えるまえから食べたいよ。食べながら食べたい」
「それ! まさにそれ! 食べながら食べたい。言い得て妙とはまさにこのことだね」
「いいえてみょう、どこでそんな言葉おぼえたの」
「もともと知ってるよ、ばかにしないでよ」
ふたりともどちらかといえば小食なほうなのに、このありさまである。ふだん辛いものを食べてもなんともないのに、ルナさんのカリーを食べたあとはじわりじわりと、それこそ地殻の内部でひそかに流動するマントルにのってプレートテクトニクスの運動が展開されるように、目にはみえない力が働いて、からだの内部のずっと底のほうから表面へ向けて順繰りに発汗作用のみなぎっているのを感じる。そればかりではなく、食後といえば眠くなるのが定番らしいが、それとは反対にあらゆる意味で目覚めたような気分になる。つまり、モノリスにさわった猿のようなものである。
駅前の高架沿いをあてどなく歩いていると、足もとに薄っすらと長方形の影が連なって流れてゆき、いちばんお尻となった四角い影をさかいに高架の影のみがあとにのこった。影がいってしまい、そうとわかったあとで、ガタンゴトン、ガタンゴトンと列車の遠ざかってゆく音がようやく耳に入ってきて、やがて、あとにのこされた高架の影もきえてしまった。わずかな微光さえとざしてしまう曇天を睨みつけながら、
「人類にも夜明けが来たというのに、まだ来てないのは夏だけだぞ」
ひとりごちると、
「そうだぞ、夏だけだぞ」
時枝が復唱する。
「ねえ、意味わかっていってる」
「なにが」
「まあいいや、説明がめんどくさい」
「なあに、なあに、教えて、教えて」
「それよりもなんだっけ、ええっと」
「なあに、なあに」
「そうそう、月と地球は相互にまわり合いながら太陽のまわりをまわってるわけじゃん。さらにね、その太陽系じたいも銀河をもの凄いスピードで移動してるんだよね。だから地球が太陽のまわりを一周するっていっても同じところに戻ってくるんじゃなくて、いちど通ったところはずっと永遠に置き去りで、ということは、この地球は宇宙の真っ暗闇をあてもなくずっと旅して……」
「ちがう、ちがう。それじゃなくて」
「なんか凄いよね。空恐ろしい気持ちになってくるよ」
「隠しごとはしないって言った」
「隠しごとなんかしてないって」
「言った、言った。隠しごとはしないって言った」
「そんなことないよ」
「ずるいんだ。ひとには洗いざらい話させておいて自分のことは隠すんだ」
「だから、そういう意味じゃなくて、なんにも隠してないって」
「ずるいんだ、卑怯者だ、藤木くんだ」
「そうじゃなくて、説明しはじめたら切りがないから。だって二00一年宇宙の旅みてないんでしょ」
「みたけどすぐに寝た」
「ほらあ」
「いいの、いいの、イチからちゃんと説明して。切りがなくてもいいから」
言い争いを一時中断、ふたりそろって点滅しはじめた青信号めがけて一目散に走り出す。横断歩道を半ばまで渡ったところで、もう大丈夫だろうと、歩幅を狭めると、そのまま走り抜けてゆく時枝の背中をグラブ入れのナップザックが左右にゆっさゆっさと揺れているのがみえた。時枝の背を見送ったその目で、いまいちど歩行者待ちの自動車の列を確認すると、列の途切れた車道のさらに先のほうで、前後にあるていどの距離のある二つの赤信号がパッと同時に青に切り変わった。遠近の法則なんてまるで無視して、ふたつのひかりはひとつの平面に隣合わせにあるみたいだった。プー、プー、先頭の車にクラクションを鳴らされてしまい慌てて歩道へ逃げ込むと、
「いま、なに見てたの」
先に歩道に渡っていた時枝が出し抜けに言う。
「え、信号だけど」
「なんで、どうして」
「そんなこと言われたって」
「また隠しごとだ」
「なんでって、とくに理由はないけども。また日記にでも書いておくからさ、読んでるんでしょ」
「そうやって、またじぶんだけの秘密みたいに日記に書いて」
「秘密じゃないよ。だって読んでるじゃん」
「ちがう、ちがう。そんなの秘密がここにありますよって、鼻先ににんじんぶら下げられてるようなものだよ。生殺しもいいところ。ほんとうの隠しごとよりずっとたちが悪い。ああ、なんて性格の悪さなんだ」
この信号を渡れば、すでにもとの公園の大樹の下、地域では特定保護の樹木として認定されているらしい。たしかに大きい。とても大きい。その影とも気づかない大きな影のなかでマーチングバンドの練習をしている三人の子どもたちがいる。トランペット、クラリネット、フルート、機敏な動きで楽器を上げ下げしたり、回したり、音楽を鳴らしながら踊っている。ほかにも大勢のひと、缶酎ハイを飲んでいたり、ウクレレをぽろぽろ弾いていたり、弁当をたべていたり、弁当の中身を覗き込んでいたり、たしかにあの弁当は美味しそうだなあ、ただベンチに座ってぼんやりしていたり、とにかく大勢のひとが微かに風に揺れうごくおなじ影のなかにいるのにマーチングバンドの練習をじっとみつめているのが時枝ただひとりだけだったのは少し意外に思えた。それでとくにわけもわからず、うん、うん、と頷いていると、時枝が子どもたちの機敏ではあるけれども勢い余って精度にはちょっと欠けるような動きをそっくりそのまま真似してみせる。
「上手いもんだね」
「子どもの頃ダンスやってたからね」
「そうなんだ。でも、ものまね何やっても上手いよね、感心しちゃった」
「そうお」
「うん、うん、役者になったほうがいいよ」
「ほんとお」
「向いてるよ。だって、あの子たちのちょっと下手くそな部分までそっくり真似できるんだもん。それは凄いことだよね、あの感じがいいよね、ちょっと感動しちゃった」
「嘘だ」
「え」
「またそうやってひとのことをバカにするんだ」
「え、ええー」
「そうなんだ、知ってるんだ。よくわかってるもん」
「ちがう、ちがうって。へたうまみたいのってあるじゃん。音程をあえてずらすとか、あえてリズムをずらすとかさ」
「下手くそって言いたいんだ」
「そんなのあの子どもたちに失礼だって。あれはあれで素晴らしいじゃん」
「ちがうもん。そんな気持ちでやってなんかない。ありのままにやっただけだし」
「じゃあいいじゃん。それが凄いって言ってるの」
「ほんとうにバカにしてないの」
「うん、素晴らしいよ」
「それなら、あの木のものまねして」
「え」
「あの木、好きでしょ、あのでかい木。あの木のものまねして、して」
「なんで」
「いいから。見たいから。あの木、好きでしょ。知ってるよ」
仕方がないので、樹のとにかく大きいところとか、一本のふとい幹が無数に枝分かれて伸びひろがっている様子なんかを足先から指先まで全身を隈なくつかって表現してみる。まず両足をくっつけて棒立ちになり、それから蟹股にひざを折り曲げていったん反動をつけてから、五本の指をひらひら動かして白鳥のポーズのように両手を伸びひろげる。
「どうですか」
「うーん、微妙。ほんとうに好きなの、あの木」
「なんか悔しいなあ。でもさあ、ひとは樹にはなれないんだから、いくらなんでも難しすぎない」
「そんなことないよ。へたうまとか何とかいってさあ、効果を狙ってやるからいけないんだよ。ありのままにやれば木にもなれるって。あとは何より、そのものを好きになることだね」
「それじゃあ、あの看板やってみせてよ。まえに写真にとってたけど」
青葉の繁みのなかにぽつんと立っている蜂に注意の黄色い立て看板を指さすと、時枝はすくっとそのものまねをしてみせる。なんだかその立ち姿がほんとうにそれっぽいので、おつぎは広場にある水色のすべり台を指さすと、これも難なくやってのける。ちいさな子どもがすべり台の坂道をすべり落ちそうになりながら懸命に四つん這いになってよじ登っていき、こんどは階段をすたすた駆け下りて、そのまま生垣の隙間を縫って向こう側にみえなくなった。やがて、子どものみえなくなった生垣の向こうから、ぽーんと、色鮮やかなブルーのゴムボールがあがった。
今回ばかりはカラスに食べられなかったとみえて、カモのヒナたちは四匹とも元気いっぱいに池じゅうを泳ぎまわったり、岩によじのぼったり、岩の上で甲羅干ししているカメを踏みつけたり、つついたり、カメが動いてびっくりしたりしている。
「よかったね」
「うん、ほんとうによかった」
前にこの池にヒナが孵ったときは、数時間後にもどってくると、もう親ガモだけ��なっていた。そのときは、ヒナのいるほうが特別な異常事態なのにもかかわらず、公園全体が素知らぬ顔をして、まるで遠い異国の旅先に来てしまったかのような寂しさを憶えたものだった。だからこそ、このよかったねにはほんとうに心がこもっている。
「元気だね」
「うん、ほんとうに素晴らしい」
このヒナたちのものまねしてよ、という言葉が喉まででかかったけれど、口をつぐんだ。時枝はさっそくヒナたちを写真におさめようと池の周りをぐるぐる、それは時枝だけにとどまらず、ほかにも大勢のひとびとがカモたちの行方を追っていた。
「ねえ! カモの赤ちゃん! カモの赤ちゃんだよ! 」
ママ友達と世間話をする母親の袖をひっぱって、無理にでも池まで連れていこうとする子どもがいる。はじめは面倒そうに子どもをあしらっていた母親も、いざ池まで来てカモの親子を目にすると、子ども以上のはしゃぎようで、こんどはママ友達を池までひっぱってくる。池の周囲は動物園さながらの盛り上がりで、生ぬるい風にまぎれてマーチングバンドの音がかすかにきこえてくる。
しばらくカモたちを観察していて気づいたことに、どうやら親ガモとその後にくっついてゆく子ガモたちは、だいたいおなじコースをくりかえし巡回しているらしい。池のなかを泳ぐだけではなく、毎回決まっておなじところから陸に上がり、その周辺をこれまた決まったルートで行脚してから池にもどってくる。池の縁にはちょっとした段差があり、親ガモはそれを難なく越えて上陸するものの、子ガモたちにしてみればそれはたいへんな絶壁とみえて、羽をひろげてジャンプしても四匹ちゅう三匹は陸まで届かず池にもどってきてしまう。親鳥はちょっといったところで全員の集合を待っている。というのは、子ガモは親とはぐれるときまってピイ、ピイと悲痛そうな鳴声を発するからで、親鳥はその声をちゃんときいて待っているらしい。ピイ、ピイと鳴きながら何度めかの挑戦のすえ四匹全員がようやく壁を越えると、ふたたびカモたちの行脚が再開される。池から陸にあがるときとは反対に、陸から池にもどるときは、親ガモのあとに続いて、一瞬のためらいはあるものの、四匹ともに豆鉄砲のごとくポンポンポンと水面に飛び込んでゆくさまは小気味よいものである。さらに観察していて気づいたのは、四匹のうち一匹だけ、額に白い斑点のある子ガモは生まれつき勘がいいのか、運動能力が高いのか、陸にあがるジャンプを一回できめていることがわかった。しょっちゅう列から離れてはアメンボを追いかけまわしているのもその子ガモらしい。
その額の白い斑点の子ガモを何となく「イダテン」と名付けることにして、
「イダテンすごいね。また一発できめたよ」
と言うと、時枝は、
「ちがうよ。あれはシロちゃん。シロちゃんすごいねー」
と言いながら、腰を屈めてシロちゃんのすぐあとを追ってゆく。時枝の両隣には年甲斐もなく壮年の男性と初老の女性がおなじように腰を屈めてシロちゃん、いや、イダテンのあとを追っている。その三人揃って突き出したお尻のおかしいこと、おかしいこと。いまこそ、時枝の首からぶら下げている写真機でカシャリと撮ってあげたいと思った。
親鳥は繁みを抜けたところの遊歩道で子ガモたちのやって来るのを待っている。やはり、そこにもすぐに人だかりが出来て、ちょっとした撮影会のようになっている。カモたちはとくにひとに怯える様子もなく、なんなら足をひろげた子どもの股をよちよちと潜ったりして観衆を沸かせている。傍若無人にも足もとを闊歩するカモたちにたいして、アーチをつくる子どものほうがおろおろと目を丸くして身動きがとれなくなってしまっている。
やがて、子ガモたちが親鳥の下に勢揃いしたちょうどその時、人だかりに闖入者あり。二匹のヨークシャーテリアが威勢よく吠えながら人だかりに割って入ってくる。
「リーちゃん! メロン! そっち行かない、行かないで! 」
耳に桃色のリボンをつけているほうがリーちゃんなのだろうか。左右それぞれの手で二匹のリードを握っているのはまだ小学生ぐらいの女の子、かかとで身体にストップをかけて仰け反りぎみになり、犬たちを必至になって押さえようとしている。犬たちはますます前のめりになり、我を忘れて野生に還ったかのように吠え散らかしている。
「こらメロン! リーちゃん! もうやめて! お願いだから」
飼い主の子どもに名前を呼ばれてもいっこうに反応する様子がなく吠えつづける。
人間にはまるで動じないカモたちも、さすがにこの狩猟犬たちの剣幕には驚いたとみえて、あたふたと方向転換、いつもの散歩コースを外れて池からどんどん離れてゆく。しかも、カモたちの歩いてゆく先にはもうすぐ公園の出口が。若干の胸騒ぎを憶えて、
「ちょっと、ちょっと、そろそろ止めたほうがいいよ」
最前線でカモの親子を追っている時枝に号令をかける。
「よしきた! 」
時枝は公園の出口付近に先まわりして、野球の内野手のような姿勢で構えている。
時枝選手、見事なまでのトンネル。
ボールは外野をてんてんと転がってゆく、かのごとく、カモの親子は公園の外の今日に限ってはいやに広々しく感じられる道路へ解き放たれた。
「今日のキャッチボール、ゴロの特守だな」
なおも最前線でカモの親子を追いかける時枝に追いつくと、
「ちがうもん、こんなはずじゃなかったもん。シロちゃーん、もどっておいで」
「エラーしたひとは誰だってそう言うよ。ほら、イダテン、もどってもどって」
いまいちど先まわりしてカモたちを反転させようとするも、親ガモを先頭にカモたちは直進をつづける。
「畜生、このバカどりが! 」
「ほら、言わんこっちゃない」
自転車をひきながらカモたちを追いかけてきたおばさんが、二輪のタイヤで行く手を塞ごうとするもこれも敵わない。おばさんはさらに、つばの広い麦わら帽子を左右にシッシと振って威嚇してもこれも通じない。
カモたちの公園から飛び出したのが車通りの少ない住宅街に面していたのは不幸中の幸いだったかもしれない。カモの一行とすれちがう徒歩や自転車の近隣の住民たちは誰しもその可愛らしい歩みをみてニコニコしながらすれちがってゆく。たまに自動車が通れば、自ずと誘導隊が結成され、カモたちを轢かないように配慮がなされる。幾人ものひとびとがカモの一行に一時合流しては、また各々の本来の目的のために散り散りになっていった。
カモの一隊は柵に囲われた更地の一区画に入ってゆく。見通しのきく更地のいちめんはその全体を緑がかったブルーシートに覆われて、その上には穴のひとつ空いた半分のサイズのコンクリートブロックが無数に点在して重しとしてある。穴の向きはふしぎとひとつに統一されていて、無数にあるすべての穴から一様にその向こう側を覗くことができる。点在する灰色の石群は、地上絵のような何かの模様にみえてきそうで、そうはならない。カモたちはコンクリートブロックを避けてそのあいだを縫うように更地を縦断している。ときどき、穴をくぐる子ガモもある。
「こいつは壮観な眺めだね」
「ほんと、まるで映画みたい」
「知らない景色でもないのに、カモが通るだけでこんなにもちがってみえるんだ。あっ、いま穴くぐったのはイダテンかな」
「ちがうよ、シロちゃんだよ」
「じゃあ、あいだをとってシロテンにしようよ」
「えー」
「だって、額に白い斑点でシロテンじゃん」
「ちぇ」
公園からカモを追いかけている古参のカモ追いびとは、麦わら帽子をかぶって自転車をひきずるおばさんとの三人だけになっていた。おばさんは手帖にカモたちの姿をスケッチしているらしく、自転車のスタンドを下ろして手帖とペンを手にしては、少し遅れること自転車を引いてまた追いついてくる。あっちへフラフラ、こっちにフラフラするカモたちの鈍行列車ぶりに、おばさんは上手いことリズムを合わせているかのようだった。
やがて、一行は閑静な住宅街の奥地にひっそりと大きな鳥居を構える社へ辿り着いた。境内は大樹の囲いに鬱蒼と覆われ、どこか密教めいていて、鳥居につづく参道はあまりにも薄暗い。ここからでは敷地の全体像はとても把握できないが、けっこうな広さをもっていそうなことぐらいはたやすく想像することができる。こんな辺鄙ところに遠いむかしの、このあたり一帯がひとくくりに武蔵野と呼ばれていた当時のままのような雑樹林があるなんて思いもよらなかった。吸い込まれてしまいそうなほど立派で巨大な鳥居がぽかんと口を開けていながら、どこかひとの侵入を拒むような不気味さがある。事実あたりにはひと影はいっさいない。
「もしかすると、カモはここに向かっていたのかな」
時枝は鳥居のなかを指差した。鬱蒼として薄暗い鳥居のなかを。
「ちょっとなかをみてきてもいいですか。池があるかもしれないので」
おばさんは快く留守番を承諾してくれた。
「どうする」
「うん」
「どっちの」
「いく」
鳥居をくぐると嘘のように空気がひんやりと一変した。それにもかかわらず、いつのまにか蝉時雨に包まれていた。あまりにも静かで、その流星群のように降りそそぐ音のどこまでも隙間なく充満して、それ以外には何もきこえなかった。公園の特定保護の大樹ほどもある樹がそこらに図太い根を張り巡らせて敷居の石垣を裂いたり盛り上がらせたりしている。いったい樹齢はどれぐらいになるのだろう。
手水舎のほうへ歩いてゆくと、木でできた古ぼけた看板が立っている。どうやら境内の地図らしい。ペンキがほとんど剥がれて、ささくれだった木肌が剥き出しになってはいるものの水色のペンキで描かれた楕円があるのはかろうじてわかる。敷地は想像以上に広い。ついでに柄杓で水を浴びると、木の音がカランとやたらに響いた。手水舎のさらに奥のほうに赤い頭巾を被せられた地蔵の群集がある。どの地蔵とも目が合う。じっと見られているように感じられた。
地図によると、池は本堂を越えたさらにその先にある。やぐら状に木材を組み合わせて底上げされた本堂は、さらに縦横に廊下を伸ばして、また別のお堂や蔵や厠と思わしき小屋に繋がっている。行く手を遮る廊下の床は頭よりもやや上にあり、どうやって向こう側へ行こうかと思案していると、廊下をくぐってゆけるよう石造りの階段が半地下へ伸びている場所がある。天井がずいぶん低く、頭をかがめて下りてゆくと、地下道は向こう側へ通ずる道のみならず、さらに左右にも伸びている。道の交わる地点で左右それぞれの道を覗くと、その道はさらに折れ曲がり、ちょうど誰かの後ろ足���歩き去ってゆくのが道角にチラリとみえた。
地下道を抜けると、様々な種の木々の群生する小道に出た。木々にまじって細長い石塔がぽつりぽつりと建っている。右手には依然としてお堂があり、微風が吹くと、瓦屋根のおうとつに木の葉がふれてシャリン、シャリンと音をたてる。お堂のなかからは、おそろしく低い声のお経がかすかにきこえてくる。小道を進んでゆくと、道の行止まりに、女神様の合掌している大きな石像の下に地蔵が大勢群がっている。と、ちょうどいま歩いて来たばかりの小道に覆い被さる木々の緑が向こうのほうでざわめいて、とっさに振り向くと、それがしだいに近づいて順々に木々をざわめかせてゆく。前髪が風になびいたかと思うと、しばらくして後方にある絵馬がカタカタと音をたてた。振り戻ると、地蔵の手に握られたいくつもの風車がいっせいにクルクルまわっている。まるで合掌する女神様が一陣の風を吹かせたかのようだった。
道は尽き、背丈より高い石造りの塀に辺りを囲われ、敷地はこれまでなのかと思うと、ひとひとりがようやくくぐれるほどの小さな門がある。時枝とひとりずつになって門をくぐると、驚いた。とたんに鬱蒼とした薄暗がりが解けて白い風景がひろがっていた。ひらけて広大な敷地に無数の墓石が並んでいる、縦横に、隙間なく、ぎっしりと、ただひとつだけ小ぶりの菩提樹がぽつんとやや斜めに生えているところを除いては。その菩提樹よりさらに先、墓石の途絶えるあたりに、それより先の視野を遮るように緑の群生がみられる。もし池があるとするなら、あのなかにちがいない。
ひゅるる、と、ひとすじの風が素肌をなめたかと思うと、あたりは急に静まり返り、透明な心地になった。すぐに音のない、音のないよりはるかに静謐な雨が降りはじめた。雨粒のひとつひとつは白い墓石に染み入り、瞬く間、自身の形づくった斑模様を塗りつぶしてゆく。やがて鈍い雷鳴が轟いて、不意にザアーッと来た。慌てて走り出す。斑模様は跡形もなく、墓石に跳ね返った雨粒が飛沫となって砕け散っている。一本だけの菩提樹とは平行線をたどりながら、背のほうへ後退りしてゆき、降りしきる雨の重圧に枝をしならせながら反発しようと揺れるさまは、まるで手を振ってさようならの挨拶をしているかのようだった。
驟雨はあっけなくあがった。対岸の雑樹林に着くと、葉脈をつたって葉先から零れる雨の滴が時折ボタボタッと落ちてくるばかりだった。服が湿って居心地が悪いので、ズボンの裾をたくし上げた。ギギ、ギギギ、と蝉が散発的に鳴いている。ここでもはやり、赤い頭巾を被せられた地蔵の群衆がじっとしてこちらの動向を窺っている。地蔵たちの視線を気にしながら歩いてゆくと、彼らは勢揃いして、いっせいに、コンパスの針を支点に円を描くように体をすすっと傾けた。やたら静かになったと思うと、いつのまにか蝉時雨が隙間なく空間を埋め尽くしていた。
と、地蔵の背後の木々の隙間に、深い藪に覆われた飛び石の小道がある。池があるとするなら、もうこのなか以外にはありえない。きっと池の畔に通ずる道なのだろう。藪は胸のあたりまで高さがあり、草を掻きわけながら、飛び石をひとつひとつつたって下りてゆく。あまり人通りがないのか、草のみならず、蜘蛛の巣も払い除けながらやっと下ってゆく。まもなく藪を抜けそうな、濃い緑の池の水面がみえてきたとき、ふいに胸騒ぎを憶えて足もとをみると、ながいながい蟻の行列が石のおうとつに通っていた。もう少しで蟻たちを踏み潰すところだった。その裾をたくし上げた剥き出しの脚をみて、ギョッとした、一瞬血の気がひいた。青白い素足に無数の黒い斑点が纏わりついて、ほとんど真っ黒になろうとしている。それらすべてが血を吸いに集まった蚊であった。
一目散に飛び石を駆け上がった。気味が悪かった。そのまま無我夢中で走り続けていると、いつのまにか住宅街を貫いてふたつに区分している環状道路沿いに出ていた。大型のトラックが地響きをたてて地面を揺らし、蝉時雨もきこえなかった。
無意識に走っているうちに、入って来た時とはちがう場所から出たらしかった。
「この場所わかる」
「うん、なんとなく」
「ああ! 」
「どしたの」
「グローブどこかに忘れてきた」
時枝はじぶんの両手がどちらともに塞がっていないを急に思い出してソワソワし始める。
「いやいや、あなたのはじぶんできちんと背負っていらっしゃる」
「おぼえてないの」
「うん、さっぱり」
「でも、急がないと。待たせてるんだし」
「それはそうだけど、せっかくもらったんだし。それに…… 」
大型のトラックが二台も三台もたて続けにすぐ真横を通過した。地響きが鳴り止むと、こんどは排気ガスが顔に煙たい。運転手が窓から放り捨てたのかなんなのか、新聞紙が一枚々々バラバラに分かれて散って、そのひと千切り、ひと千切りが風に低く舞いながら道路上を占拠している、まるで西部劇の舞台を転がる枯草のように。
「それに」
「すごく嬉しかったし」
「そうなんだ。嬉しかったんだ。ぜんぜん知らなかった。でも、なんか嘘くさい」
「嘘じゃないって」
「だって、そんなこと、日記には何にも書いてなかった。やっぱり嘘だ」
「そんなことないよ。だって、あれからしばらく、グローブの下に挟んであった置き手紙をひろげては、時枝さんってどんなひとだろうって、字づらから想像してたんだから。でも何度も言うようだけど、うまいこと渡ったもんだよね。奇跡だよね。手紙のおもてが《グローブなしで壁あてをしている左投げのきみへ》だったのには笑ったけどさ」
「そんなのたまたまグローブのない不憫なひとがいて、弟の使い古しがあったからだよ」
「それにしたって、ほかの誰かが持っていってたかもしれないよ。捨てられてたかもしれないし」
「そんなの、いっつも決まって同じ時間に壁あてしに来るんだもん。ちゃんとそうなるように計ったの」
「まあ、規則正しい生活には定評があるからね。でも、それだったら直接渡してくれてもよかったのに」
「そんなの、いきなりじゃ変なひとみたいじゃん」
「それもそうか」
社の外側をぐるっと大周りして、もとの地点にもどってくると、カモの姿も麦わら帽子のおばさんの姿もみられなかった。が、少し離れた道角に、おばさんの麦わら帽子が落ちているのを発見。風で飛んでいかないよう、麦わら帽子のなかにはバナナが重しとして置いてある。さらにその道角を曲がった先に、もうひとつバナナが置いてある。つぎの道角にもまたバナナが。そうしてバナナをひろっては麦わら帽子なかへ入れてゆくと、レンガ造りのマンションのまえに自転車が停めてある。そのマンション占有の駐車場におばさんとカモはいた。
「すっかり遅くなってしまって、すいませんでした」
バナナで一杯になった麦わら帽子を差し出すと、
「いえいえ、そんなことないですよ。これ、もしよかったら」
と、バナナを一本ずつ差しもどしてくれる。
「雨は大丈夫でしたか」
「いえ、こっちでは降っていないですけども」
そう言われてみると、水たまりはおろか、道路は湿ってすらもいない。よほど局所的な雨だったのか、それとも見てはならぬものみてしまったのか。
「それならよかったです。あ、これ頂きます」
バナナを剥くと、先っぽにひとつ黒い染みができていた。甘くて美味しい。
「見ての通り、この駐車場、袋小路になっていて。入口から出るということを知らないんですかねえ。さっきから出口を探そうとしてるみたいなんですけど、頑なに入口にはもどってくれなくて。これじゃあ帰ろうにも帰れない」
「鳥頭とは言ったものですけど、意外におぼえているんですかね」
「池はどうでしたか」
「あったにはあったんですけど、ここからだと公園にもどったほうがずっと早いと思います」
「そうでしたか」
親ガモは袋小路の金網フェンスにクチバシを突っ込んでみたり、噛み切ろうとしてみたり、道なき道をどうにか切り拓こうとしている。子ガモたちは手帖を片手にスケッチをとるバナナおばさんの足もとをチュンチュン歩きまわっている。
やがて、とうとう親ガモは出入口はひとつしかないことを、入って来たところに戻らなければならないことを悟ったのか、からだを反転させて、休日で車の出払った駐車場を歩きはじめた。子ガモたちも戯れをやめて、しっかりと親ガモのあとに続いてゆく。これでようやく、と思った。肩の荷が少し軽くなったような思いだった。ヒナがすぐにいなくなってしまうのはカラスの仕業だけではないだろうと考えはじめていた。数日前、近所の道端に干乾びた小鳥の亡骸があったのは、もしかすると鴨のヒナだったかもしれない。そういわれてみると、日に々々骨と皮だけになってゆく亡骸の足に水掻きのようなものが付いていた気がしなくもない。
カモたちは平たい水掻きの付いた足でペタペタと駐車場を歩いている。親と子で大きさはずいぶんちがっていても、歩き方のほうは、ま���そっくりである。と、親ガモにつづく子ガモの列から一羽の姿が唐突に消えた。マジックショーか何かのように、消えた。頭のほうでの理解が追いつかず、そのまま棒立ちになって立ち尽くしていると、さらに残りの三羽がごそっとおなじように消えた。時枝がバナナの皮を落っことして駆けていった。親鳥もすぐにこの事態に気がつき、あてもなく困惑した様子で周囲を窺っている。
何ということか、カモたちがそのとき歩いていたのは、地下に組み込まれた立体駐車場のてっぺんだった。ところどころに僅かな隙間があり、そこから子ガモたちは駐車場の地下へと落下したらしかった。
三人で手分けして、四つん這いになって、立体駐車場の隙間をのぞく。まもなく四羽の姿を目視。地下一階や地下二階の自動車の収まるスペースではない、いちばん底のコンクリートまで落ちている。地下に落下しても、四羽が仲良く一列になって、雨水を通すための浅い側溝をぺちぺち歩いているのがチラリと垣間みえた。なにしろ隙間が小さいので、子ガモたちの姿のみえたのはそれっきりで、耳を澄ますと辛うじてきこえてくる例のピイ、ピイの鳴声だけが子ガモたちの居所を伝えてくれた。
親鳥はガーガー鳴きながら、まるで何かの威嚇かアピールのように胸を張って翼をバサバサ開き閉じしている。突然、翼をひろげながら走り出し、もとの袋小路に戻ったかと思うと、また子ガモの落下した辺りまでやってきて、俯き加減にクチバシで周囲を突きながら右往左往としている。が、ふいに飛び立った。ずっと地べたを歩きまわるのを追っていたせいか、鴨が飛べるという事実をすっかり忘れていた。かりに子ガモが救出されても、親鳥がいなければどうしようもない。
慌ててマンションの管理室へ駆け込んだ。休日なので受付の小窓には内側からカーテンがかけられている。マンションの出入口で思案に暮れていると、空から親鳥のガーガー鳴く声がきこえた。どうやら諦めたのではなく、マンションの上空一帯を飛びまわって探しているらしい。こちらも負けてはいられない。ちょうどマンションに帰って来た住人と思わしき奥さんに勇気を出して声をかける。それでもやはり躊躇いがあったのか、いざ一歩目の踏み出しが遅れてしまい、後ろから追うかたちで、
「あのう、すみません」
まるで反応がないので、すぐ隣までまわりこんで、
「すみません」
すると奥さんはビクッとして、
「え、わたしですか」
はじめこそ、べっこう色の縁の付いた眼鏡の奥で不信そうな目をしていた奥さんは、カモの赤ちゃんという言葉をきいて態度を一変させた。奥さんも公園の池で子ガモをみていたのだった。
「うん、うん、それで今はどちらに」
「いました、いました、あれですよ。ああやって探しているんです」
奥さんを子ガモの落下地点まで案内する道すがら、また親鳥がガーガー鳴きながら上空を飛んでいった。
「たしかに、この下にいるんですよね」
「耳を澄ましてみてください。鳴いているのがきこえるので」
またしても親鳥がガーガー鳴きながら飛んでくる。それ��見送ってから、四人でそろって押し黙り、立体駐車場の上にしゃがみ込むと、やはり、ピイ、ピイ、と子ガモの悲痛な鳴声がきこえてくる。時枝は急に思い出したみたいにすくっと立ち上がり、さっき落としたバナナの皮を拾いにいった。
と、そこへマンションの裏口から駐車場に出てくるチェックの短パン姿の壮年の男性がある。時枝はバナナの皮を拾うのも忘れて、彼を立体駐車場の上まで引っぱってくる。
「ほう、ほう、そうでしたか。ちょうど車で出掛けるところだったんです。上げてみましょうか。この下ですから、私の車」
チェックのパンツからキーケースを取り出し、柱に埋め込まれた鍵穴に差し込んで、回した。気持ちは急いでいるのに装置の作動は緩慢きわまりなく、男性はそれを知っているのか、片手で鍵は回したまま、手持ち無沙汰になったもう片方の手を腰にまわして、さらに足を組んで、首を傾げ、変なポーズのような姿勢をとっている。ようやく、鈍くて荘厳な機械音とともに動作が開始されると、まるで寝息をたてる鯨の腹部のような鈍重さで、それまで足もとにあったてっぺんが盛り上がってゆき、全部で四列ある立体駐車場のうちのひとつがその本来の姿をあらわした。
「これで一段。あと下に三段つづいています。いちばん下まで上げてみますか」
「はい」
とはいっても、立体駐車場を底上げしたからといって、子ガモが上がってくるのではなく、無闇にてっぺんが高くなっているだけである。子ガモはさらに底のコンクリートまで落ちている。
「これって、半端なところでは止められないんですかね。階と階のちょうどあいだとか。そうすれば隙間をジグザグに縫って、いちばん底まで降りていかれるような気がするんですけど」
「いやあ、たぶん、そういうことができないように、しっかりと切りのよいところでしか止まれないようになってるんですよ」
「ですよね」
「私、そろそろ出なくてはならないので、すみません。駐車場の鍵はお預けしますので使ってください」
「✕○△号室の某といいます。鍵、有り難くお預かりします」
「私は✕○△号室の某です。代わりと言ってはあれですが、理事長を呼んでおくので」
「理事長さんとお付き合いあるんですか」
「じつは昨夜も遅くまでやってたんですよ」
クイッとお酒を飲む仕草をすると、
「彼、今日はずっと家にいると言っていたので、すぐに電話しておきます」
車が駐車場から出てゆき、まもなく裏口から理事長さんがやって来た。よれや色落ちのまったくないパリッとしたジーンズを穿いて、白んできた頭髪を色濃い焦げ茶色に染めてある。
「✕○△号室の某さんから連絡をもらいました✕○△号室の某です」
「✕○△号室の某といいます。理事長さん、わざわざありがとうございます、お休みのところ本当にすみません」
「いやいや理事長さんだなんて、某でけっこうですよ。それに順番がまわって来たので慣習にならって引き受けたまでです。そうはいっても当マンションきっての一大事ということですから、微力ながらお力添えできたらと思います」
と、そこへ駐車場の出入口からなかの様子を窺っていた親子がおっかなびっくり入ってくる。父親と息子、背丈はちょうど倍ぐらいちがっていて、ふたりとも小柄な丸顔で、風体も顔つきもとてもよく似ている。
「ど、どうかされたんですか」
「カモの赤ちゃんが立体駐車場の下に落ちてしまったんです」
「ええ! さっきまで僕たちも公園にいたんですよ。急に姿がみえなくなったと思ったら、こんなところまで来ていたんですね」
父親は息子の顔のちかくまで屈んで、
「カモの赤ちゃんが落ちちゃったんだって。ほら、さっきまで公園にいた」
息子の手には手作りのザリガニ釣り用の竿が握られている。
「四匹ともですか」
「そうなんです、四匹とも。この方たちが落ちたところをみたって。それからずっといてくれてるんです。でも、生きてはいるみたいで、たしかに鳴声がきこえるんです」
「昨日は六匹で、今日は四匹ときて、また猫かカラスにやられたものだと思っていたんですけど、とにかく生きていてよかったです」
父親はまた息子の顔のちかくまで屈んで、
「カモの赤ちゃん、生きてるんだって」
「ぼく、これで釣り上げてみる」
「うーん。これじゃあ、ちょっと長さが足りないよ」
時枝とバナナのおばさんが息子さんを落下地点へ案内してあげた。
「ここの住人さんですか」
父親に尋ねてみると、
「いやあ、まったくの通りすがりです。いったい何事だろうと思いまして。しかし、大変なことになりましたなあ」
「そうだったんですね。じぶんたちも住人ではないんですよ。公園から出ていったカモの行方を追っていたら、まさか、まさかの」
べっこう色の眼鏡の奥さんと、理事長さんは、腕を組んで真剣な面持ちで今後の打ち合わせをしている。
「やっぱりそうですよね。私もそう思います。うちの旦那が家に居ますから、番号を調べて持ってきてもらいましょう」
どうやら、とりあえずマンションの管理会社に相談することに決まったらしい。まもなく旦那さんがチラシの切れ端を持って下りてきて「✕○△号室の某です」と理事長さんに挨拶をした。旦那さんにくっついて、小学生ぐらいのふたりの兄妹も下りてきている。三人そろって部屋着に毛の生えたような恰好をしている。さらに一家と付き合いのあるらしいもうひと夫妻が「✕○△号室の某です」と挨拶をして合流した。
「あとのことは皆さん方にお任せしようかしらね」
バナナのおばさんは、ばつが悪そうに、そっと自転車をひいて駐車場が出ていった。
まずマンションの管理会社は、休日なので対応できる人員がいないこと、マンションの管理会社とはべつに立体駐車場の管理会社が存在していることを教えてくれた。べっこう色の眼鏡の奥さんが電話番号を復唱して、旦那さんが息子の背中を台代わりにしてメモをとる。妹のほうは長くなりそうと踏んだのか「着替えてくる」と言って部屋へ駆けていった。
ついで立体駐車場の管理会社は、休日で対応できる人員がいないのでマンションの管理会社に連絡したほうがいいのではないかということ、以前に怪我人がでているので許可なく立体駐車場のなかに入ってはいけないということ、どうしようもないのなら警察に相談してみるのがいいのではないかということを教えてくれた。
それならば、ということで、ついに一一〇番することになった。これまで流暢に電話口の対応を続けていたべっこう色の眼鏡の奥さんも、さすがに相手が警察官となると形式的にきかれることが多いのか、たどたどしく話を展開した。それから、じっさいに子ガモの落下を見たひとを出してほしいとの要請で、たしかに見ました、と証言した。
「たしかに駐車場の地下に落ちて、それを見たんですね」
と、電話口の警察官がくりかえすので、
「あまりにも一瞬のことで、子ガモが消えたかのようにみえましたけど、鳴声はきこえますし、地下の側溝を歩いているのもみました」
と、証言した。べっこう色の眼鏡の奥さんに電話を戻すと、さいごに住所、マンション名、それから「✕○△号室の某です」と通報者の氏名を名乗って、ながい電話が終了した。
妹が外行きの恰好で戻ってきて、父親の脇にぴったりくっついた。そして、ちょいちょいとTシャツの裾を引く。父親が身を屈めると、耳元に両手をそえて、こしょこしょと何かの内緒話をする。話を聞き終えると父親は、うんうんと頷いて、娘の頭を撫でた。
遅いですね、まだですかね、という会話を幾度かくりかえしても警察官が来ないので、近くの自動販売機まで冷たい水を買いにいった。喉��カラカラだった。時枝は三台ある自販機を四往復ぐらいして、得体の知れない邪悪な色の清涼飲料水のボタンを押した。ガッシャーンと缶が落ちてくると、ピロピロした電子音が鳴り、自販機のディスプレイにおなじデジタル数字が三つならんだ。ガッシャーン、得体の知れない邪悪な飲料がもうひとつ落ちてくる。
「あげる」
「えー、いらないよ、そんなの」
とは、反射で言ったものの、
「ちょっと毒見させて」
やっぱり時枝のをひとくち貰うことにする。落ちてきたばかりの冷たい缶の表面には薄っすらと水滴が張り巡らされている。
「マズ……」
時枝もひとくち口に含んで、
「なにこれ……」
「なんでこんな変なの選んだの。しかも、もうひとつ出てきちゃって」
「ごめん、ちょっと水もらっていい」
「いいよ、いいよ、飲みな。これはさすがにまずいって」
駐車場に戻ると、腰のひん曲がって杖をついている老人がひとり増えてはいても、警察官はまだ来ていない。
「ぼくものど渇いた」
そっくり親子の子どもがぼやくのをすかさず耳にして、
「これ、もしよければ。当たったんです」
「いやあ、いいんですか」
「でも、もの凄く不味いので、毒見したほうがいいかもしれないです」
ひとくちずつ飲んだきり、まったく中身の減っていない缶を手渡すと、子どもはちいさな両手で缶を受けとめた。そのまま両手で口まで持っていく。べえええ、いちど口に含んだものがそのまま口から流れでた。
「こらッ、みっともない! 」
「いいんです、いいんです、ほんとうに不味いんですから」
「お父さんもおひとついかがですか」
と、時枝が続いた。
「はあ、それではおひとつ」
息子が両手で缶を差し出すと、
「不味い! これはたしかに不味いですなあ」
そうこうしているうちに、ようやく若くて色白な警察官が、あからさまにタラタラ自転車を漕いでやって来た。その目に見えた態度とは裏腹に、警視庁とプリントされた紺色の制服はガチッとして、重そうで、形式的な威厳にあふれている。
まずは通報者の✕○△号室某さん婦人が招集され、電話口でも話したであろう形式的な質問の応答がはじまった。第一印象のとおり、この若い警察官は語尾がいちいち投げやりで、もともとがそうなのか、あるいは上官に嫌な役回りを演じさせられてそうなっているのか、はたまた別の理由によってそうなっているのかは分からなかった。
ついで、目撃者として、私、あるいは彼、あるいはKが招集された。電話口よりももっと仔細に、この子ガモたちを初めてみて、落下するのをみるまでの経緯をひとつびとつ詳しく質問されることとなった。✕○△号室某さん婦人の時と同様にメモを取りながらの質疑応答ととなった。社でのことは、わざわざ言うべきことではないと思い、あえて省いた。
「ではKさん、あなたは、鴨が公園から出て行くのをみすみす見逃したんですね」
「いえ、そうではありません。カモたちが公園から出ていってしまってはいけないと思って、どうにか止めようと努めました」
「しかし、Kさん、あなたは鴨が公園から出ていき、その後を追っていったとおっしゃった。ほんとうに公園から出て行くのがまずいのであれば、首根っこを掴んででも連れ戻すべきではなかったんじゃないですか」
「それができれば苦労はしないですし、こんなことにはなっていませんよ」
「なぜ、どうしてです」
「それは、それは、お巡りさんだって、あの場にじっさいにいれば、そうする他なかったと思いますけど」
「そんなことはないですね。私だったら、もし鴨をほんとうに公園の外に出したくないのなら、首根っこを掴まずとも虫捕り網か何かで捕獲して連れ戻そうとしますけどね」
「そんな、虫捕り網なんて、その場にはなかったわけですし」
「いえいえ、あなたは何か勘違いをしていらっしゃる、あくまでも例えの話です。Kさん、あなたは、鴨が公園から出て行ったのは犬が吠えたせいだとおっしゃった。しかし、飼い主だって、犬をどうにか止めようとしていたわけでしょう。事実、飼い主が犬を止めたお陰で、少なくとも鴨は喰い殺されずに済んだ。そのことについてはどうお考えですか」
「そんな、鴨と犬のはなしを一緒にされても」
「ほう、ひじょうに興味深い話だ。いや、私がこんなことを言うのは、鴨も犬もひとしく動物だと思うからです。何がどうちがうのか、是非ともお聞かせ願いたい」
「だって、鴨と犬ではどう考えても立場がちがうでしょう」
「ほう、立場とおっしゃる。立場とは、例えば、裁かれるものと、裁くものとのあいだに生じる差異のことですか。今回の場合で言うなれば、吠えられるものと、吠えるものとのあいだに生じる差異、ということになりますか」
「お巡りさん、いったい何を言っているんです。子どもは必死に犬のリードを握って、しかも二匹もですよ、力の限り止めようしていたんですよ」
「そう、そうなんです。私が聞きたいのはまさにそのことなんです。子どもですら犬を必死になって止めようとした。しかし、あなたの話からはどうもその必死さが感じられないんです。たとえ虫捕り網を持っていたとしても、子どもが犬にそうしたように、必死になって止めようとしたかどうかは疑わしい」
「それは、犬は、飼い犬ですから、周りに迷惑をかけないように」
「それなら鴨はいいと言うんですか。自分で言うのもなんですけど、警察が出動しているんですよ。私も暇ではないですし、取り締まらなければならないことが他にも山ほどある。いえ、すみません、ちょっと言い過ぎました。この対応も警察官としてのひとつの義務ですから。いまのは忘れてください」
「いえいえ、こちらこそ。きちんとした応答ができずに、申し訳ないです」
「しかし、あながち無関係でもない。いや、先ほどはほんとうに失礼しました。つい私情を挟んでしまって。ただ、飼い犬については迷惑をかけないようにときちんと思われるのに、カモさんたちについてはそこまで思われないのはどういうことかと思いまして。むしろ、カモさんが自動車に轢かれないように配慮までされていますよね。飼い犬であればそうなる前に止めているはずでしょう。まさか飼い犬のために自動車のほうに道をあけさせるなんてことはしないはずです。Kさん、あなたの場合は、いまひとつ対応が後手にまわっているといいますか。やはり、それよりももっと、轢かれるなりして大変なことになるのを未然に防ごうとする心理が働くのではないですか。なにせ飼い犬が轢き殺されてしまえば悲しいですし、そればかりではなく、やろうと思えば未然に止められたことを止められなければ罪悪感を抱くと思うんです」
「いやはや、お巡りさんの話には目から鱗が落ちる思いです。まず、この事態がお巡りさんの手を煩わせていることをもっと辛辣に考えてみるべきでした。そして何より、確かに必死さが足りていなかった。最悪の事態を未然に防ごうともしなかった。ただ、情けないことに、お巡りさんに言われるまでは気づかなかったことですが、あるひとつのことを尊重していたんです」
「ほう、それはいったい何ですか」
「鴨の自由です」
「鴨の、自由」
「そうです。そうなんです。きっと心のどこかで、カモたちに必要以上の干渉をすべきでないと思っていたんです。それでもやっぱり、最悪の事態は避けたいですから、あとを追いながら見守っていたんだと思います」
「なぜ、鴨に干渉すべきではないと」
「それは、このカモたちは野生の生きものだからですよ」
「ありがとうございました。これでようやく答えが出ました」
聴衆の注目が警察官に集まった。警察が来ていることで、さらに野次馬が増えていた。
「まず、第一に」
あたりは静まりかえり、誰かの唾を飲みこむ音がきこえた。
「某さんは、立体駐車場の管理会社から、許可なしになかへ侵入してはいけないと言われている。警察といえども、これを勝手に破るわけにいかないのは承知頂けますかな」
「それは、その通りです」
「ただ、事情が事情であれば、警視庁のほうで適切な令状を出し、正式な手続きをいくつか踏んだ上で侵入することは出来なくはないでしょう。それにしても、管理会社のほうは今日は対応できないと言っておられるようだし、何しろ手続きというものにはいつも大変な時間がかかる。明日になるか、明後日になるか、もしかすると一週間かかるかもしれません。その頃には鴨は衰弱して死んでいるでしょう」
誰しもが口をつぐんだ。
「そして、第二に、つい先ほどKさんは、この鴨が野生だとおっしゃった。野鳥というのは基本的に警察の管轄外にあたります」
色白の若い警察官は、管轄外の外のところにアクセントをつけて強調した。
「これが誰かの所有物であったり、つまりペットですね。あるいは誰かや誰かの所有物に著しい危害を加える可能性のある動物、たとえば熊とかイノシシですとか、そういった場合は警察の管轄内になります」
色白の若い警察官は、管轄内の内のところにもアクセントをつけて強調した。
「今回のケースはどう考えても警察の管轄外にあたります。当然ですが、管轄の外にでる行為は法律で違法と定められています。警察が違法行為をはたらくとどうなるかはご存じですね。いえ、警察に限った話でありませんでした。はい、そうです、クビです。私もさすがに鴨でクビにはなりたくないですから。わかっていただけますか」
誰も、何も言えなかった。色白の若い警察官は振り返り、聴衆はぞろぞろと重い足どりで彼のために道をあけた。と、
「じぶんのクビと、よっつの命と、どっちが大事なんだ」
そっくり親子の息子が口走った。子どもの声を止めようとしたり、諫めようとしたりする大人はここにはひとりもいなかった。ところがこんどは、さらに果敢なことに、足もとにあったバナナの皮を投げつけようする。これにはさすがに止めが入り、しかし、小さくてすばしっこい子どもは大人の手をすり抜けてゆく。ポーン。バナナの皮は見事に警官の後頭部に直撃。時枝がすかさず皮を拾いにゆく。
「すみません、ほんとうにすみません。バナナを食べたの、じぶんなんです。投げたのは子どもですけど。だからって、子どもに罪があるわけじゃないんです。バナナの皮を放っておいたじぶんが悪いんです。いつだってバナナはひとに危害を加えるでしょう、転んでしまったり。それを放置して未然に防ごうとしなかったのがいけないんです。お巡りさんも言ってたじゃないですか」
「いえいえ、慣れっこですから、こういうことは」
「これ、よかったらもらってください。まだ買ったばかりでよく冷えています」
時枝は当たったほうの未開封の缶を差し出した。
「いやいや、受け取れませんよ、そんな」
「いいんです、いいんです。こんなことで呼んでしまって、さらに失礼な態度まで」
「いや、��んとうにお気持ちだけでけっこうですから」
「いえ、ちがうんです、そうではなくて、こっちの気が済まないんです。あまりにも申し訳がなくって。これじゃあ喉に魚の骨が刺さったままでいるみたいで。ひとに親切でもするつもりで、ちょっとした人助けでもするつもりで、受け取ってもらえませんか。それとも、そういった行為も管轄外だと言うんですか」
「そこまで言うのなら受け取りましょう」
色白の若い警官は受け取った缶ジュースをかかげて、軽く聴衆にお辞儀をした。そっくり親子の父親が拍手をして、その拍手は事情を知らない聴衆全体にもひろがっていった。
警官は来たときと同様にタラタラ自転車を漕いで遠ざかってゆき、しばらくすると、プシュッとプルタブを引く音がきこえた。
「それにしても長い問答でしたね。お疲れ様でした。なにもあんなにまどろっこしくしなくても、野鳥は管轄外ですのひと言でよかったような気もしますけど」
べっこう色の眼鏡の奥さんが労ってくれた。
「いえ、ちがうんです。ただこのひとが偏屈なだけですよ。挙句の果てには、鴨の自由、とか何とか言ってみずから墓穴を掘っちゃって、ああ、恥ずかしい」
「そんなことないですよ、堂々として立派でした。それにあなたも。さっきの対応はほんとうに素晴らしかったですよ。事態はちっとも好転していないのに、どうしてかハッピーエンドみたいになってしまうなんて。子どもを庇っただけでなく、お巡りさんの立場まで、ねえ」
「ちがうんです、そんなに褒められたことじゃないんです。あの缶ジュース、じつはものすんごく不味くて、あの警官にちょっとでもダメージを与えてやりたくて、それで。厄介払いもできたし、ちょうどよかったんです」
「まあ! 」
べっこう色の眼鏡の奥さんは口に片手をあてて笑った。
ガヤガヤと人員が増え、時間がいたずらに経過したばかりで、為すすべもないまま事態はふりだしにもどってしまった。むしろ、後退したと言うべきかもしれない。時間だけが経ち、採るべき選択肢は減り、その代わりに禁止事項が増えたのだから。
杖をついた老人は、立体駐車場のてっぺんに立ち「ひらけー、ゴマ! 」とか「モーセよー、海を割りたまえ! 」とか言いながら足もとを杖でカツン、カツン叩いている。もはや神頼み、これでは世間話でもするほかなく、そっくり親子の父親に、
「息子さん、サウスポーなんですね。じつはじぶんもなんです。さっきの投げっぷりは凄かったなあ。それにコントロールも抜群で。きっと将来はいいピッチャーになりますよ」
「いやあ、お見苦しいところをおみせしてしまって、さらに庇ってまでいただいて」
と、そこへバナナおばさんが戻ってきた、自転車のカゴ一杯いっぱいにバナナを積んで。
「実はさっきも、知人のところへお裾分けしに行くさいちゅうだったんです。まだ家に段ボール箱で沢山あってとても食べ切れないので、ちょうど良いかと思いまして。でも、こんなに大勢になってしまって、これで足りるかしら」
バナナの皮事件の目撃者たちは、なるほど、こういうことだったのか、とクスクス笑い合っている。バナナのおばさんはクスクスと注がれる視線に、
「いったいどうしたのかしら」
と言いつつ、すぐに話を切り変えて、
「それで、あれからどうなりました」
と、まるで秘密の話でもするように声をひそめて言う。もしかするとバナナはあくまでも建前で、この場の当事者として鴨の行方を見守る正当な理由が欲しかったのかもしれない。さっきのバツの悪そうな去り方からして、そんなふうに思われてくるのだった。すると、そこへ理事長さんがバナナを片手にやって来て、
「差入れありがとうございます。脳の血糖値が下がっては、良い解決案も出ませんからな。マンションを代表してお礼申し上げます」
「いいんです、いいんです、ちょうど良かったものですから。こっちが助かってしまったぐらいなんです」
肩書ばかりで実際にはとくに何もしていない理事長さんも、ときには意外なところで役に立つと思った。その行動が功を奏したかどうかは別にして、いちばんの働き者として鴨救出部隊を引っぱっているべっこう色の眼鏡の奥さんも、
「戻られたんですね。実は方々に連絡して、警察にも来てもらったんですけど、まだダメなんです。なにか良い知恵があったら教えてくださいね」
と、バナナのおばさんを迎えている。
どんよりしたムードだったのが、バナナおばさんの再登場で、いい具合に仕切り直しとなった。大勢の大人子どもが揃いもそろってバナナをむしゃむしゃ頬張りながら、救出方法の議論をはじめたり、いまいちど立体駐車場のてっぺんにしゃがみ込んで子ガモのピイ、ピイの鳴声を聞き取ろうとする。落ちたばかりの頃より、確実に鳴声が小さくなっている。どうにかその鳴声を聞き取ろうと耳を澄ませていると、ブルブルと自動車のエンジン音が。サーフボードを積んだ白いアメ車が駐車場に入ってくる。白いキャップをしてサングラスをかけた比較的に若い女性が窓から肘を出して様子を窺っている。助手席には同じくサングラスをかけた男性がいる。女性はサングラスを外すと、
「みなさん、揃いもそろってバナナを持って、いったいどうされたんですか」
「カモの赤ちゃんが立体駐車場の下に落ちてしまったんです」
「え、カモの赤ちゃん。え、それでバナナはいったい」
「いえ、バナナはなんでもないんです。カモの赤ちゃんが隙間から地下に落ちてしまって」
「え、ちょっと状況がのみ込めないんですけど、車は停めていいんですよね」
「あ、はい。大丈夫ですよね」
べっこう色の眼鏡の奥さんが理事長さんに決断を振ると、そうするほか仕方がないといったふうに黙ったままゆっくりと頷いた。
白いキャップの女性は肘についで頭も窓から出して、車を反転させてから、バックで車を立体駐車場のてっぺんに駐車した。車の動きに合わせてバナナを持った大勢のひとが場所をあけるためにぞろぞろと連れ立って移動した。若い男女ふたりは大きな荷物を抱えて車からでてきて、いまいちど事情をきくと「それは大変ですね」と言って、大きな荷物を抱え直して部屋のほうへと運んでいった。
それはもちろんドライなひとだっているだろうと、大きな荷物とふたりの後ろ姿を見送ってから、しばらくすると、さっきのサングラスの男女が意外にも変身して、いや変装してもどって来た。男のほうは繋ぎの作業服に、頭にはタオルを巻いて、手には大きめのライトを持っている。女性のほうは上下ともに黒に白のラインの入ったジャージに、髪はすっきりとポニーテールにまとめてある。変装とはいっても、いったいどっちの姿がほんとうなのか分からないほどの変わりよう。
「どうもどうも。ちょっと地下までおりて様子をみて来ますよ。なんなら助けられるかもしれないし。虫捕り網とか持ってるひとはいないですか。生憎、うちにはなくて」
「それなんですけど、立体駐車場の管理会社から許可なしにひとが入ってはいけないと言われているんです」
「だいじょうぶですよ。このひと、電気工なんです。いつも高所とかで作業してるみたいなんで、ぜんぜん平気なんですって。ねえー」
「いや、たしかに高所で作業はしてるけど、地下の経験はそんなに。それに許可なしでは……」
「なあに言ってるの。その気があるからわざわざ着替えて来たんでしょ。とっととやっちゃいましょ」
「それもそうだな。ヨッシャ。じぶん、先に下おりてるんで、お子さんのいる家なんかで虫捕り網があったらよろしくッス」
そうして、あれよあれよという間に、いちど上まで引き上げられた立体駐車場の駐車スペースに乗って、キーの操作は上の人間に託し、繋ぎの作業服の兄ちゃんはきわめてゆっくりと周囲のひとびとに見守られながら下っていった。最後は首だけになり、気の利いた冗談のつもりなのか、親指を立てた握りこぶしを頭上に掲げながら、やがてそれもみえなくなった。
それにしても、男のほうはともかくとして、ジャージのお姉さんはわざわざ着替えてくる必要があったのか。よく見ると、お化粧まで小ざっぱりとしたものに変わっている。芸の細かさと、気合の入りようには唯々感心した。あるいは単に、そういう文化をもっているひとなのかもしれない。
一段、二段、と駐車場が地下に収まってゆき、そのたびごとに「はーい、もう一段下ろしてくださーい」と地下から声があがる。声は回を重ねるごとに小さくなる。とうとうてっぺんが足もとまでくると、さらに「もう一段」とずっと下のほうから反響した声がきこえてくる。もうこれ以上は下げられない旨を伝えると「了解でーす」と反響した声がかえってきた。そっくり親子の子どもが隙間から地下の様子を覗こうとする。
「何かみえた」
「ううん、なんにも」
「あげてくださーい」
地下から反響した声があがった。
「ねえねえ、このままここにいてみてもいい」
そっくり親子の父親がすかさず、
「駄目だよ、危ないから。はやくこっちに来なさい」
「それなら、いっしょに付いていましょうか。立たせないで座らせておけば大丈夫でしょう」
「いやあ、いいんですか」
「子どももそろそろ疲れてきたでしょうし、ちょうどよい息抜きになりますよ」
「いやあ、そうですか。それならお言葉に甘えて」
それならば、僕も、私も、と✕○△号室の某夫妻の兄妹も名乗りをあげる。べっこう色の眼鏡の奥さんも、いちど禁を破って吹っ切れてしまったのか、
「そしたら、あげてやってもらってもいいですか」
「ぜったい立たたないようにしっかり掴んでおきますから、安心してください」
ひとりで三人の子守は荷が重いので時枝に号令をかけると、
「よしきた! 」
そっくり親子の子どもを時枝が抱えることになった。こちらも兄妹を並んで座らせて、背後からふたりの肩に腕をまわす。ゆっくりと、ゆっくりと、尻もちをついている地面が盛り上がってゆく。親御さんたちは子どもが遊園地のアトラクションに乗って、やがて、みえなくなるのを見送るように手を振った。
「それじゃあ、アレだ。じぶんたちはアトラクションの座席に付いてる安全バーなんだな」
となりの時枝に声をかけると、
「ウィーン、ガッシャン」
と言いながら、安全バーに見立てた腕をそっくり親子の子どもの頭上から下ろし直した。
「安全バーのロックがきちんとかかっているか、確認してください」
そっくり親子の子どもが時枝の腕をガッシャン、ガッシャン揺らしてみる。
「だいじょうぶ! 」
「こっちもやっておく」
いちおう兄妹に尋ねると、
「いい」
と冷めた返事がかえってきた。
だんだんと見晴らしがよくなってきて、公園の大樹の緑の先がみえてきた。緑はすり鉢状の反対にひろがってゆく。よくみると、木の葉の一枚一枚は微風にきらきら��目にもとまらぬ速さで小刻みに揺れていて、その無数の集まりの緑の全容は鈍いスローモーションのように蠢き合っている。木の葉の一枚一枚と、緑の全容と、どちらかの速度に焦点を合わせると、もういっぽうの速度が目にみえなくなるのだった。
立体駐車場を下ろした時とはちがい、上げるときは一段一段止まらずノンストップでいくらしかった。一段が過ぎて、親御さんの姿がすっかり見えなくなると、時枝は子どもを抱えたまま後ろによこたわった。
「こっちもよこたわってみる」
「いいの」
「立っちゃだめとは言ったけど、寝ちゃだめとは言ってないからね」
ふたりの肩を抱えたままよこたわると、いきなり、空があった。それはそうにはちがいないが、あまりにも突拍子もなく眼前に空があるのに少し驚いた。まるで時間も距離も欠いているかのような見え方だった。
「空に浮かんでるみたい」
誰かが言った。
「うん」
また誰かが言った。まったくその通りに思っていたから、言ったのはじぶんだったかも知れなかった。誰ひとりとして互いに向かい合わず、一様に空と正対していると、案外誰の声なのかもわからないものだった。
「雲が流れてる」
誰かが言った。
「うん」
また誰かが言った。自然と口数が減っているようだった。それでも数少ない言葉はやっぱりじぶんの口からついて出たようでもあり、まるで周りの存在が消えて、ひとりでよこたわっているかのようだった。
そう、空一面の灰色の雲とはいっても、たしかに雲は流れている。あえてみようとする前から雲の流れにみいられていた。ふしぎな感じだった。みるよりも前に、みいられている。まるで、谷の向こうの山に「ヤッホー」と語りかけるより前から「ヤッホー」と言われているかのような、山先行のやまびこをきいているかのようなおかしさだった。
と、装置の作動音が鳴り止んだ。静かになると、ずっと遠い下のほうからひとの喋り声が微かにきこえる。何を喋っているのかはわからない。
鼻先をひとすじの風がとおっていった。ついで、どこかで小鳥の羽ばたく音がきこえた。自転車のリンリンいいながら走り去ってゆく音がきこえ、環状道路の自動車の走行音が途切れとぎれにきこえてきた。やがて、ガタンゴトン、ガタンゴトン、と、ずっとずっと遠くのほうから列車の連なって走ってゆく音がきこえた。航空機の大気を震わせる音がきこえた。音のきこえる範囲は透明なシャボン玉のようにどんどん膨らんでいるようだった。やがて、膨張の臨界点ともいうべき一点を突破したのか、ありとあらゆる音という音がきこえるよりも前にきこえられていた。山先行ならぬ、音先行の世界。数限りない音の鳴り、音のリズムがあって、とても静かだった。それぞれの独自のリズムで消えたり、あったりする地上の音と隣り合わせに、恒久的な雲の流れてゆく音もずっとここにあった。
いつのまにか立体駐車場は下っているらしかった。そうと分かったのは装置の作動音がふたたび鳴っているからで、じっさいには下っているのか、上っているのか、止まっているのかもわからなかった。空との距離は遠ざかっているようにも、縮んでいるようにも思われなかった。気が付いてみれば、親御さんたち囲われて、ふしぎそうな顔で見下ろされていた。
✕○△号室の某夫妻の妹は起き上がるなり父のところへ駆けて行った。ちょっとすると、父親と連れ立ってお礼に来た。父親が頭を撫でながら、
「どう、楽しかった」
「うん」
「そうかあ、よかったねえ」
「うん。でも、パパの肩車のほうがもっと楽しい」
父親は苦笑いを浮かべながら、もういちどお礼を言った。
「そういえば、お兄ちゃんは」
「知らなあい」
「さっき、虫捕り網をとりにいくって、部屋にもどって行きましたよ」
「ああ、そうでしたか。実はそれなんですけど」
繋ぎの作業服の兄ちゃん曰く、長い梯子か命綱のロープでもなければ底には下りていかれないとのことだった。ライトで照らしてみても子ガモの姿はみえず、ただ、たしかに小さく鳴声はきこえてくるとのことだった。向こうでジャージのお姉さんにどやされているのがきこえてくる。
「ねえ、ほんとうにだめだったの」
「もうさ、地下は真っ暗闇でなんにもみえないんだから。心細かったあ」
「なによ、男のくせに情けない」
「いやいや、ライトを当ててみたって、ぽっかり空いた空洞みたいに底がどこにあるのかもわからないんだから」
「そんなことってある。だってほら、この隙間から覗くと、うーん、たしかに薄暗いけど、まるっきり見えないこともないじゃない」
「外から覗くのと、中にいるのじゃあ、ぜんぜんちがうんだって」
ジャージのお姉さんの言うとおり、にわかには信じがたい話なので、じっさいに隙間を覗きにいってみると、子ガモが落ちたばかりの頃よりだいぶ暗くなっていた。ずっと曇り空の下にいるせいで気がつかなかったのか、もう、かなり太陽は傾いているらしかった。
そこへ車が入ってきた。理事長さんの飲み友達が用事を済ませて帰ってきたのだった。またしても立体駐車場が鈍い作動音とともに、ゆっくり、ゆっくりと上げられて、そして収納された。さらに二台、三台と相ついで車が駐車場に帰ってきた。そういう時刻らしかった。
気がつけば、はじめこそ車のすべて出払っていた駐車場のてっぺんは、残り一台ですべて埋まるところまできていた。ガー、ガー、ガー、と親鳥がひさしぶりに駐車場の上空を飛んでいった。そのつばさを広げた姿が、黒い影のシルエットとなって、連なって並んでいる自動車のフロントガラスに、ひとつだけの空車スペースはとばしてとびとびに映った。
「そういえばさあ、さっきのは凄かったよね。だって、いきなり空があるんだもん」
「でたあ! もうその手にはのらんぞ。オレはもう人参なんぞ食わん! 」
「え、なに、いきなりどうしたの。バナナじゃなくて」
「なにもきかない、なにもしらない」
「変なの」
「そんなことよりカモの赤ちゃんだよ。もうすぐ日も暮れちゃいそうだし」
そうなのだった。夜になれば子ガモの救出はますます困難になるのにちがいなかった。かといって、今さらあとに引くわけにもいかない。べっこう色の眼鏡の奥さんのにも、理事長さんにも、顔のしわのおうとつに昼間にはみられなかった陰翳が根差して、その表情からは若干の焦りがみてとれた。
「なんだっけ、いつかテレビでやってた。ほら、雨どいから壁と壁のあいだのわずかな隙間に落ちちゃった猫のはなし。なんかレスキュー隊員みたいなひとが来てなかったっけ」
「ちがうよ、あれは左官屋のおじさんが壁をコンコン叩いて、それで壁の構造をよんで、うまい具合に穴をあけて、みたいな話だったよ」
「なんか、ヘルメット被ったひと来てなかったっけ」
「ヘルメットを被ってたのは建築士のひとで、そう、その家が明治時代からある古民家だったから一級の建築士でも構造がよくわからなくて、そこで昔ながらの左官屋さんが大活躍ってわけ」
「くわしいね」
「いちおう、元テレビっ子だからね。そんなことよりも、いつも変なうんちくばかり言ってるのに、左官屋さんみたいな特殊技能のあるひとは知らないわけ」
「うーん。良い記録がでるように、風向きをよんでピストルを鳴らすスターターなら知ってるけど」
「ちがう、ちがう、そういうんじゃなくて」
べっこう色の眼鏡の奥さんが、眼鏡のレンズをブラウスの袖で拭きながら、
「何かちょっとでもヒントになりそうなことがあれば、遠慮なく言ってくださいね」
その顔には焦りばかりではなく、疲れの表情もみえてきていた。
と、そこへ、カン、カン、カンカン、と、まるで狐の嫁入りか、狸の葬列のように、赤い提灯をぶら下げた火の用心の行列が、たいへんゆっくりとした足取りで駐車場の入口をよこぎっていった、カン、カン、カンカン。みな、ぞろぞろと連れ立って行脚する人影に魅入っていた。そして、誰ともなく消防を呼んでみようという声があがり、そうしましょう、そうしましょう、と、やはり、べっこう色の眼鏡の奥さんが一一九番に電話をかけた。
じつに呆気のない、ふしぎな決定だった。昼間からああでもない、こうでもない、あれはしてはいけない、これはするべきではない、と、散々っぱら議論をかさねてきたのに、さらには色白の若い警察官に痛い目をみたのに、よりにもよって火事に特化した消防を頼ることにするなんて、ずいぶんといいかげんな話にちがいなかった。どうしてそんな決定がおのずと下されたのかといえば、とにかく時間が迫ってきていることと、たまたま火の用心の行列が通ったこと以外には理由は考えられなかった。それでも消防にいちるの望みを託すしかないのだった。
数分後、一台丸ごとの消防車が駐車場の入口に面した通りによこづけされた。いつまで経っても来ないうえに、自転車をたらたら漕いでやって来た警察とはえらいちがいだった。エンジン音が止まるまえからヘルメットを被った隊員二名が消防車から駆け出てきて、エンジン音が止んでから運転手の隊員がおくれて出てきた。壮年の隊長一名に、若い隊員二名の編成。若い隊員は丸顔で太っているのと、前歯の出ていて痩せているの。
隊長はちょっと話を聞くと、
「そうしたら、いちど駐車場を上げてもらってもいいですか」
そして、その間にも若い隊員たちにあれこれと指示を出して、消防車から色々と道具を持ってこさせている。ヘッドライト、伸縮式の梯子、輪になった太い縄、麻のズタ袋、等々。駐車場を上げるさなか、隊員に指示を出しながら、隊長はさらに駐車場の構造を観察したり、マンションの住民、とりわけ繋ぎの作業服の兄ちゃんから詳しい話をきいている。
「キーを右にまわすと上って、左にまわすと下がるんですね」
「そうです。ただし、半端なところでは止まれないようになっているので」
「わかりました。そしたらキーはいったんお借りします」
隊長は出っ歯の痩せのほうを呼んで、操作の説明を股伝えすると、彼にキーを託した。そして四列ある立体駐車場をすべて上げてしまうと、隊長はそのうちのひとつに道具一式をのせて下っていった。ちょっとすると、
「思ったより暗いなあ! たしか、繋ぎのお兄さんがライト持ってたでしょう。あれを貸してもらおう! ロープで下ろして! 」
すると、丸顔の太っちょが手持ちライトを借り受けて、おそらく消防士特有の結び方でロープに括りつけると、あらかじめ電源をつけてから、作動中にできる階と階との隙間からライトをスルスル下ろしていった。おそらく、くるくると回転しながら宙を下降しているらしいライトのひかりのすじが駐車場のわずかな隙間から灯台のひかりのように一定の間隔をおいてみてとれた。ただ突っ立って待っていることができず、��ながみな、随所に空いている隙間から地下の様子を窺っていた。ひかりのすじがすっかりみえなくなると、結び目のなくなった軽そうなロープだけがあがってきた。
隊長をのせた駐車場がいちばん上まで収納されると、梯子を設置するような音が、ガシャン、ガシャンとかなり遠巻きに響いてきた。
「とおうちゃああくう」
二重にも三重にも反響した声が地下の最地下からあがった。
「どおおうう、きこおええるうう」
「きこえるけど、かなり遠いです! 」
丸顔の太っちょが声を張りあげた。
「むせえんわああ」
太っちょが痩せの出っ歯のほうに目で合図して促すと、
「ドーゾー、ドーゾー、キコエマスカー」
無線機のマイクにカチカチと前歯があたっている。
「ドーゾー、ドーゾー、アーアー、アー」
痩せの出っ歯は太っちょのほうに首をふって合図をした。
「無線も遠いです! 」
「しかあたあなあいい、こええおうだあしてえいこおうう」
隊長の声は幾重にも反響して木霊するあまり、発せられた本人の肉声を遠く離れて、まるで発声者のいない風や空気のうたのようにきこえられた。意味のある言葉として、その声をきいているというよりは、たんに音楽として耳にはいってくるのにもかかわらず、あらかじめ込められたメッセージを知っているかのように意味がわかってしまうのはすこしふしぎに感じられた。
「あッ、ひかった」
「こっちでも」
「ひかった、ひかった」
子どもたちが反射のように口走るのは、地下を探索している隊長のライトのひかりらしい。こちらでもピカッとひかった。細長い閃光が壁を垂直に折れ曲がり、かなりの長物なのにいったいどうやってその身を隠したのか、瞬時に消えた。
「ああみい、あああたあよおねええ」
「はい! あります! 」
「ああとおう、ばあけえつうもお」
「すみません、どなたか、バケツをお借りできませんか」
「わたし、一階のすぐそこなので持ってきます」
料理中に気になって駐車場まで出てきたのか、エプロンを付けたままの肝っ玉かあさんといった風貌の奥さんが部屋へと駆けていった。
丸顔の太っちょは、少年から網を、肝っ玉かあさんからバケツを受け取ると、まずバケツをロープに括りつけ、器用にも余った先のほうで網を括りつけた。準備が整うと、痩せの出っ歯のほうに目で合図をする。そして、作動中にできる階と階との隙間からロープを垂らしていった。
「なあああわああ、そおのおまあまあでええ」
「もう一回お願いします! 」
「なあああわああ、そおのおまあまああ」
「え、すみません、どなたかわかった方、いらっしゃいますか」
「なわは、じゃないですか。ロープをそのまま垂らしておいてほしいのかと」
「あ、なるほど。でも、そのままにしておいたら挟まれちゃいますよね」
「たしかにこの太さでは」
「挟まれちゃいますよ! 」
「ああげえてええ、すうぐうにい、おおろおせえるうよおうにい、たあいいきいい」
「了解です! 」
いったん空のロープを引き上げて、駐車場が切りのよいところで静止すると、痩せの出っ歯はすぐにキーを反対方向にまわした。作動にはいちいち時間がかかるため、あらかじめ動かして隙間をつくっておいて、そのあいだに隊長から声がかかれば儲けものと判断したらしい。丸顔の太っちょも、しゃがみ込んで、いつでもロープを下ろせるように構えている。
一ターンめでは声がかからず、痩せの出っ歯がもういちど反対方向へキーをまわしてから少しすると、声がかかった。丸顔の太っちょがすかさずロープを垂らす。
「ああげええてええ」
引き上げられたバケツのなかには、一羽のからだをヒクヒク震わしている赤ちゃんガモが。ひどく汚れてぐっしょりと濡れている。
ついで、隊長が駐車場にのって地上にもどってきた。その手には口の縛られたズタ袋が抱えられている。
「中身を確認しますか」
誰しもが口をつぐんだ。
「いやあ、すっかり遅くなってしまって。弱っているだろうに、なかなか捕まらなくて。すばしっこい奴です。鳥のことは専門ではないので、あとのことは皆さんにお任せします。ただ、地下は油なんかの汚れがひどかったので、かるく洗ってあげたほうがいいと思います」
隊長はそう言い残すと、隊員二名をひきつれて消防車へ帰っていった。みな、口々にありがとうございました、ほんとうにありがとうございます、と言いながら、隊員たちを駐車場の外まで見送り、消防車が道角にみえなくなるまで見送った。
さて、バケツのなかでからだを震わせるこのヒナをどうするかが当面の問題になりかわわった。あまりにも無防備で、ちょっとした何かのまちがいひとつでどうにかなってしまいそうで、誰も迂闊には手を下せないように思われた。が、代わる代わるバケツを上から覗いて見守るだけの人だかりに、肝っ玉かあさんがドッコイショと割って入り、意図も簡単にヒナを鷲掴みにすると、エプロンで抱え込んだ。
「たしかにベタベタしてますね。どなたか、赤ん坊のいる家でベビーソープをお持ちの方、それからあ、植物由来の素肌にやさしい洗剤みたいのをお使いの方、いらっしゃったら貸してもらえませんか」
心当たりのあるひとびとがただちに散っていった。
「それから、あたしは、お湯と桶と清潔なタオルをもってくるので」
肝っ玉かあさんは、ヒナを抱えたエプロンを脱いで、たまたま隣り合わせていた時枝に託した。間近で、すぐ目と鼻の先で、ヒナの姿をみた。骨ばって黒々としたものが震えていた。弾力のあるゴムボールのように丸みを帯びたからだはどこへいってしまったのだろう。公園を周遊していた頃のカモの姿を思い出そうする。あ、そういえば。
「しばらく親鳥をみてないよね」
「うん」
「ちょっと公園までひとっ走りしてみてくる」
行こうとすると、ぼくも、わたしも、と子どもたちがこぞって先に走り出した。
住宅街よりよっぽど見晴らしのきく公園は、暮れかかりといっても、まだ空がずいぶん明るかった。ところどころ雲のきれつつある合間あいまから、ぽたぽたと淡い水色の空が垣間みえる。
「いたあ、いたよお」
先に池までたどり着いた子どもから声があがった。
「どこ、どこお」
池につくと、水面に反射して映っている樹々の幹を一羽の親鳥がすーっと揺らしていた。すーっとしたふたすじの波紋は、次第しだいに、ゆらゆらとおぼろげに池の全体へとひろがってほどけてゆく。そんな伝播のもようをひととおり見送ると、池の対岸に見憶えのあるものが項垂れてよこたわっている。グラブの入ったナップザックだった。
とりあえず親鳥は顕在ということがわかり、帰りは歩いた。そっくり親子の子どもがおんぶしてくれと言うので、ナップザックのほうは✕○△号室の兄妹に持ってもらった。兄は勝手に中身をあけ、グラブがじぶんの手に合わないとわかると、グラブのほうだけを妹に持たせて、球をポーン、ポーンと宙に投げながら歩いた。妹は向きが反対なのもおかまいなしに身に余るおおきなグラブを右手にはめて、兄に球を投げ入れてもらっていた。
駐車場にもどると、ちょうど肝っ玉かあさんがお湯を張った桶でヒナを洗いはじめるところだった。ひとまず親鳥はいました、と報告。それから時枝に、ついでにこれも、とぺったんこのナップザックをみせる。かえしてー、と中身を回収。
ちゃぽん、ちゃぽん、と、ヒナは肝っ玉かあさんの大きな手で撫でるように洗われた。黒い汚れがすこしずつ、すこしずつ、桶の水にとけていって、ヒナの琥珀色の羽毛がみえるようになってきた。その額には白い斑点が。イダテン、と心のなかでつぶやいた。シロちゃん、とつぶやく時枝の声はじっさいに口から漏れていた。
黒々として鬼っ子のような姿から、ヒナがカモのヒナらしい本来の姿をとりもどしつつあると、みなのあいだで安堵の気持ちがふくらんだのか、さて、このヒナをどうすべきか、という議論に移っていった。すぐに池の親鳥のもとへかえすべきか、それともしばらくこちらで面倒をみてヒナの回復を待つべきかの二択だった。もちろん、親鳥のもとへかえすのがいちばん望ましいとされたが、何しろヒナは衰弱しているので、そんなところをカラスに狙われでもしたらせっかくの救出が台無しになってしまう。が、回復を待っているあいだに、親鳥がどこかへ飛んでいってしまっても仕方がないにちがいなかった。
ヒナの回復を待つほうの派では、足早にもヒナに名前をつけましょう、つけましょう、と、イダテンでもシロちゃんでもない名前でヒナのことが呼ばれはじめていた。それでもまた、ヒナを名付けた同じひとが、やっぱりいますぐにでも親鳥のもとへかえしたほうがいいのでは、と意見をひっくり返すこともあった。
どちらの選択もけっして芳しくないことは誰の目にもあきらかだった。それでも、どちらかを選ばなければならない。ただでさえ、いちじるしく低い鴨の雛の生存率を知っているものであれば、自ずと答えは出そうなものだったが、それでも、いますぐ親鳥のもとへかえすべきだとする意見がだんだんと多数派となっていったのには、私たちはいったい何を信じてそうなったのだろう。ただ、かえすのであれば一刻の猶予も許されなかった。マンションの階段や廊下の電灯がぱちぱちといっせいに点った。
陽のあるうちに、かえすことに決まった。
マンションの駐車場から、とぼとぼと、ながい参列のようなひとの群れが公園へと伸びていった。列のひとびとの歩みはどこかためらいがちで、角をひとつ曲がるたびに、ちぎれちぎれになり、いくつかの小隊に分断されながら、列はさらに間延びしていった。
公園には、まだ明るさが残っていた。幾重にも折り重なって微風にゆれる樹々の向こうが銀色にかがやいていた。遠くのほうの空では灰雲がきれているらしかった。
肝っ玉のかあさんが、タオルで抱えていた額に白い斑点のある子ガモを池の縁のひらたい岩の上にかえした。からだを震わせる子ガモは、やがて、二本の足でしっかりと立ち、ピイ、ピイと鳴きはじめた。親鳥はたしかにその声を察知して、すこし離れたまた別の岩の上から子ガモの方向をじっと凝視している。子ガモはピイ、ピイとますます声を張り上げる。
こんなにも大勢のひとびとに囲われていては、おたがいに身動きがとれなかろうということで、一線をひいて、遠巻きに親子の動向を眺めることとなった。公園の人通りはもうだいぶ少なく、子ガモのピイ、ピイと鳴く声は離れていてもよく響いてきこえてきた。親鳥はその声に反応して、ガーガーと子を呼ぶように鳴いた。子どもたちが一線を破って近づいていこうとするのを、その都度、親御さんが止めていた。
そんなやりとりを数十分ほど繰り返しているうちに、やがて、公園のほうにも街灯が点った。カモの親子は向かい合ったまま依然として動こうとはせず、カン、カン、カンカン、と火の用心の打ちがきこえてきた、カン、カン、カンカン。その乾いた音の響きに導かれるようにマンションの住人たちは、あとは自然の摂理にお任せしましょう、と挨拶をして、来た時と同様にぞろぞろと連れ立って自宅へと帰っていった。
そっくり親子のふたりとバナナのおばさんともお別れの挨拶を交わして、それぞれに散り散りとなった。陽はとうに沈んでいても、ここの空でも灰雲はだいぶきれてきていて、青むらさきがかった濃紺色の空にはまだ明るさが微かに滲んでいた。さいごまで残ったじぶんたちも、夕食をたべに行くために、公園を立ち去ることにした。昼間はたったの一匹しか鳴いていなかった蝉が、夜のはじまる時間になってもいまだ、二、三匹にもなって鳴いていて、いま、この瞬間にも、夏のはじまりが来たように感じられた。
「日、落ちそうでおちないね」
「こんな変な時間に晴れてきたからねえ。それに、いまがいちばん日の長い季節なんだよ。これから夏本番にかけてどんどん短くなるんだよ」
「そっかー。中華たべたいなあ」
「だから、夏ってまぼろしみたいなのかも」
「うん。中華いこうよ」
冷房直下の席に案内されてしまい、夏がはじまったというのに肌寒いくらいだった。日曜の夜なので、お客は少なく、ほかの席に変えてもらうこともできそうだったが、いちにちじゅう緊張して立ちっぱなしでいたせいで、お尻と椅子がくっついてしまった。
塩味の野菜スープと、醤油味のワンタンスープを注文した。それから瓶ビールを一本にグラスをふたつ。家族でやっているお店で、いつもこんな調子なのか、それとも今宵はちょっと特別なのか、ちょっとした口喧嘩のような喋り声が厨房のなかからきこえていた。
テレビのニュースではどこかの都道府県の、甲子園予選の決勝がダイジェストされている。試合は一対0の均衡を保ったまま終盤までもつれこむ白熱の投手戦で、一回から相手打線を0に抑えている水色のユニフォームの左投手は、とてもエースの体格とは思えない小柄な痩せっぽちだった。もちろん球速もそんなにでていない。それでも振りあげた右足を肩にまでぶつける大胆なフォームでほいほいストライクをとっていく。クロスステップから放られる角度のある真っ直ぐで右打者の内角をえぐってから、アウトローに逃げながら落ちるチェンジアップで空振りをとるのが得意のパターンらしい。打者はこのチェンジアップにくるくる踊っている。
「あの左ピッチャー凄いねえ。小柄なのに、からだをいっぱいいっぱいに使って。このままだと完封して甲子園だよ。あッ、完封だって、甲子園だって」
時枝もテレビの画面をじっと凝視して、わかった、わかったから、とでもいうように手で待ての合図をした。そして、おもむろに電話をかけはじめる。
「もしもーし、うん、おめでとう。うん、うん、いや、みてない、いまニュースで、勝ったのに号泣してるじゃん、え、いまちょうど映ってるよ、そう、そう、お父さんとお母さんは、そっかー、よかったねえ、うん、うん、そっちの民放で生中継したの録画してあるんでしょ、うん、うん、ちゃんと持って帰らせてね、うん、いや、こっちにもみたがってるひとがいるから、ちがうちがう、そんなんじゃないよ、え、いやあ、ただ同じ左利きだからシンパシー感じてるんじゃない、もう、まったく、そうだよ、ああ、行きたいけど、平日だとなあ、うん、行けたらいくよ、そうだよ、勝ち進んだら行けるじゃん、うん、うん、あ、勝ち投手のインタビュー受けてるじゃん、はい、はい、そいじゃあね」
え、え、と目をぱちくりさせていると、時枝は、
「おとうと」
と、ひと言。
「時枝って、名字だったの」
「そっち」
「いや、どっちも」
「幼稚園ぐらいの頃かなあ、家族で甲子園みてたら、とつぜん宣言しだしてね。あの水色のユニフォーム着て甲子園に出るんだーって。わざわざ越県入学までしてさあ。今日その夢が叶った」
「じゃあ、下の名前なんていうの」
「ええ、言ってなかったっけ」
「言ってないよ。だって知らないもん」
「そうだっけ。このグローブは弟のだったんだよ」
「それは光栄だけど。うん、ほんとうに光栄。さっきのみて一瞬でファンになった」
「だと思った。球速はでないけど、コントロールとか、球持ちとか、それ以外の能力に長けてるピッチャー好きでしょ。知ってるよ」
「なんで知ってるの」
「なんとなく。試合の録画、持って帰ってきてくれるって。こんど観ようね」
「ていうか、下の名前は。なんで教えてくれなかったの」
「だって、聞かれたことないし」
「それにしたって、まちがえて呼んでたら正すでしょ、ふつう」
「まちがえてないよ。子どもの頃から時枝ちゃん、時枝ちゃんって、ダーを抜かして呼ばれてたんだから」
「なんかいいね。名前がふたつあるみたいで」
「いいでしょう」
「で、ほんとうの下の名前は」
「内緒。なんか、いまさら名乗るのも恥ずかしいし。時枝時枝でいいじゃん」
「隠しごとだ。それこそ隠しごとだ」
「隠しごとじゃないよ。だって、勝手に付けられたんだし。じぶんで付けた名前ならまだしも。そんなことよりも、そっちのほうがいつも隠しごとだよ。隠すどころか、どんどん新しい秘密までつくってさ。しかもさ、油断してるとこうやって立場が逆転してるんだもん。秘密だらけなのはそっちなのに。ああ、なんて性格の悪さなんだ」
「そのセリフ好きだね。本日二回目だよ」
「ちがうよ。喜びそうなことを言ってあげてるだけ。性格悪いって言われるの、好きでしょ。知ってるよ」
「それにしても、ほんとうの名前を隠すのはどうかと思うな」
「隠してないよ。だって名前は隠すよりまえからあるもん」
「それはへりくつだって」
「へりくつじゃない。へりくつじゃないよ。ほんとうの名前、ほんとうの名前って、むしろ隠されてるのはこっちだ。ほんとうの名前で呼んでよ。ほんとうの名前で呼ばれたい。知ってるでしょ、ほんとうの名前。知ってるよ」
「わかった、わかったから、もう聞かないから。さっきまで喧嘩してた厨房のなかのひとがクスクス笑いながら耳すましてるよ。でも、それはそれとして、当たったら正解ぐらいは言ってよね。知ってる、知ってる、わかってる、でも正解を知りたくなるのも人情じゃない」
声をひそめて言うと、
「うん、わかった。とっておきなの待ってる」
「当たったら、カリー代、驕りね」
「それはずるい、賭けになってないもん」
お店の奥さんが、ニコニコしながら、醤油味のワンタンスープと、塩味の野菜スープとをひとつずつ両手で抱えて運んできた。湯気を吹く丼ぶり並々のスープの表面には、微量の油がきらきらひかって浮かんでいる。
あつあつのスープをひとくち口にふくむと、緊張の糸がさらにほどけるようだった。お尻に汗疹ができているのが感じられた。グラスのなかでビールの泡粒が雪の降るみたいにしんしん昇っていた。テレビの音に紛れて、厨房で中華鍋の擦れる音や、冷房の風の音がきこえていた。数少ないお客のひとりが席をたち、レジのガチャーンと鳴る音についで、出入口のドアの鈴がちりん、ちりんと鳴った。厨房から流水の音がきこえて、壁に貼ってあるメニュー短冊の端がエアコンの送風にかすかに揺れていた。
お店を出ると、足はおのずと公園へ向かっていた。大通りには街灯の光のならびが一直線にふたつ連なり、信号機の赤や青やオレンジのひかりがまばらに点在していた。目のまえをひゅんひゅん走り抜ける自動車のヘッドライトのひかりは十字を切ったり、扇形に放射したりしながら目をすり抜けていった。
池の水面には、いくつかの円いひかりが浮かんでいた。月がでているかもしれないと思い、夜空を探してみた。見当たらなかった。ひかりはすべて街灯の反射だった。そのひかりのひとつの辺境にヒナの姿はあった。夕暮れにかえしたときの岩とはちがう、池の中ほどの岩の上。親鳥の岩にすこしだけ近づいている。が、そこでまたしても立ち往生しているらしかった。
おたがいに鳴き合う頻度はぐっと少なくなっていた。親鳥はまるで、ここま��来られなければ子とは認めないとでもいうように、ただじっと岩の上に伏していた。子のほうは、水面への一歩を踏み出そう、踏み出そう、とはしながら、いざ、なかなか最後の決心がつかない。その様子は、まさに決心のつきかねる惑いそのものだった。天真爛漫に、いつ何時も鋭敏な本能とともにあって、自らのとるべき行動をすでに知って動いているかのように勝手に思っていた動物像からは、まったく考えられない仕草だった。行くべきか、行かないべきか、額に白い斑点のついた子ガモは懸命に考えているのにちがいなかった。たとえ、どちらの選択もけっして正しくはないとしても。
ついに、一歩を踏み出した。からだがふしぎと沈んでゆく。まるで、何かに追われている夢のなかでのように、足掻いても、どう足掻いてみても、からだ沈んで、まえへは進まなかった。仕方なく、すぐ近くの岩に退避しようとするものの、その岩の斜面があまりの急勾配で、駆け上ろうにもあたまからひっくり返ってしまう。
水面に浮かんでいる街灯のひかりが大きくたゆたった。
それでも駆け上ろうとする。そうしなければ池の底に沈んでしまうから。駆け上ろうとするたびに、あたまからひっくり返った。
何度めかの挑戦で、駆け上り切らないまでも、岩の斜面の水際にへばりつくことを学んだ。少なくとも、これで、水面をジタバタしながら沈むのを待つことだけは避けられた。
と、そこへ、細長いライトのひかりを四方八方に散乱させながら肝っ玉のかあさんがやって来た。ここです、ここでーす、と両手を振って合図する。
「ずっといられたんですか」
「いえ、いちど食事をして、さっき戻ってきたんです」
「それで、どこにいます。さっきの岩にはいなかったんですけど」
そこです、あそこです、と上半身を乗り出して指さすと、四方八方に散っていた細長いライトの光線がヒナめがけて一直線に照射された。
「ここまでは自力で来れたんですね」
状況を説明すると、
「だろうと思ったんです。それが心配で、ずっと家で悩んでいたんです。ほら、クチバシで羽をついばんでいるでしょう。ああして羽毛に空気を入れようと��てるんですよ。羽毛に隙間がなくてふかふかしていないと沈んでしまうんです。もしかして、洗いが足りなかったんじゃないかと思って、それで」
「詳しいんですね」
「むかし、専門学校で習ったんです。でも、ほんとうに良かった、あなたたちがいてくれて。あたし、目が利かなくて、夜なんかはとくに。ほら、これでもぼやけるんです」
はずして見せてくれた眼鏡は見事なまでの牛乳瓶の厚底だった。ライトのひかりに羽虫が集まってきていた。足もとでは光沢のある黒いアブラムシが這って動くのがみえた。
「いえいえ、こちらこそ、ほんとうに良かったです。みえるだけで何も知らないし、何もできなかったんですから」
相談の結果、肝っ玉のかあさんが一晩だけヒナを連れ帰り、もういちど入念に洗い、乾かして、餌とあたたかい場所を用意することに決まった。
岩を飛んでつたって、足場の悪いなか、岩の斜面にへばりついているヒナを片手で鷲掴みにするしかなかった。そのとき、生まれてはじめて、鴨という生きものをこの手で触った。空気のように重みがなかった。
「餌だけが心配なんですよね。うちにあるものをはたして食べてくれるかどうか」
「昼間はアメンボを追っかけまわして食べてましたけどね」
「そしたら、最悪、捕まえに来ます」
と、肝っ玉かあさんは冗談めかして言った。そして、おやすみなさい、と、よろしくおねがいしますの挨拶を交わした。
「キャッチボールできなかったね」
「うん。暗いけど、ちょっとやってく」
「うん」
「さっきのみて、投げたくてうずうずしてたんだ」
「だろうと思った。知ってるよ」
光加減のちょうどよい街灯の近くに移動しようとすると、そっくり親子の父親が自転車の荷台に息子を乗せてやって来た。カゴにはバケツが入っている。
状況をひと通り説明してあげると、父親は、
「あの太ったおばさんが連れて帰ったんだって」
と、息子の顔のちかくまで屈んで教えてあげた。
「ちょうど、いまさっき別れたところなんです。自転車で行けば追いつくと思いますよ。餌の心配をしてたんで、そのバケツでアメンボを掬ってあげれば、助けになるかもしれません」
「はあ、そうですか。とりあえず行ってみます」
そっくり親子の父親は、カモの赤ちゃんがひとりになっていたらどうしよう、と息子にせがまれて公園にもどって来たらしかった。父親は息子の両脇を抱えると、ひと息に持ち上げて荷台に乗っけた。遠ざかってゆく自転車の荷台から、息子が半身でふり返って、手をふってくれた。ちいさく、顔のよこで手をふり返した。
「今日はあれかな、キャッチボールをさせてもらえない日なのかな」
「ハハ、そうにちがいない」
「痛快な投げならあったけどねえ」
「彼、きっと良いピッチャーになるよ」
街灯の近くとはいっても、暗くてみえにくいので、近距離からの下手投げでまずは目を慣らしてゆく。
「ちょっと、もう少しふわっと投げて」
「はいよッと」
「あッつ、これじゃあ、ふわっとしすぎて、ボールが街灯のひかりに消えちゃうよ」
「まったく、注文が多いなッと」
少しずつ、少しずつ、距離を伸ばしてゆく。そのたびに、お腹から声を張って、
「弟さん、からだ柔らかいよねッと」
「子どもの頃、いっしょにダンスもやってたからねッと」
「道理で、ホイッ」
時枝はキャッチしたボールをそのままにして、いったん流れを止めると、
「セイッ」
と、片足をまっすぐ百八十度に、ピタッとあたまの上まであげてみせた。
「すごいじゃん! 」
「うーん、ちょっとかたくなったかな。弟はあの調子じゃあ、いまでも楽勝だと思うよッと」
「ピッチャーって踊ってるみたいだよねッと」
「ええッと、どういうこと」
「あいよッと、踊ってるみたいじゃない」
「だからッと、どういうこと」
目が慣れ、距離もひろがってきたので、そろそろ上から投げることにした。
「ほら、いっくよー、時枝が乗り移った! 」
時枝弟のフォームを真似して、足をおおきく振りあげる。
「ちょっと、ちょっと、あぶないって! 」
「だいじょうぶ! チェンジアップだから! 」
「そういう問題じゃなーい! 」
力を込めたわりには、鷲掴みにしたボールがうまい具合に抜けて、スポッと時枝のグローブにおさまった。おおきく振りあげてから着地した足を軸に、からだがクルッと回転して、片足立ちでバランスをとるのに精一杯だった。
「ほら、投げ終えた直後のピッチャーって、バレエか何かのダンサーみたいじゃない」
「もう! びっくりさせないでよ! 」
意外にも、互いに遠ざかってからのほうがスムーズに投げ合うことができた。球の速さよりも、よりスピンをかけることを意識して、相手の胸にシュッとまっすぐ球のとどくように心がける。変に気をつかって山なりのボールを投げようとすると、とどかなかったり、行き過ぎてしまったり、あるいは街灯のひかりに吸い込まれて球が消えてしまうのだった。よりよい球を投げようとすると、いつしか口数は減って、球の行き来ばかりになった。シュッと投げたと思ったら、もうスパッと受けていた。まるで、投げることと投げられることとが相互に一体となって、向かい合ってキャッチボールをしているというよりは、ふたりそろって前だけを向いて投げているかのようだった。集中して、よりよい球を投げようとすればするほど、こんどは投げられるよりもまえに球が胸のなかにあった。
カン、カン、カンカン、ラスト十球と定めて、帰路につくことにした、カン、カン、カンカン。
ふかい濃紺の夜空にはきれぎれに雲が流れていた。雲の流れていないところでは星がまばらに瞬いていた。
「なんだか、今日は、ずいぶん遠くまで来たって感じがする」
「うん」
「きっと、帰ったら、旅行で何日も家をあけたときみたいに、部屋が素知らぬ顔をしてるんだろうなあ」
「うん、そっかあ、今日は誰もいないんだっけ」
「今日はそっちで寝てもいい」
「うん、いいよ。歓迎いたします」
寝るにはまだ早い時間だったので、部屋の灯りをすべておとして、映画を一本みた。
暗くなった画面にエンドロールが流れると、その白い文字列の連なりが本棚の背表紙のならびに反射してゆらゆらとひかりをなぞっていた。
時枝のために中二階のロフトに布団をひいてあげた。ぎしぎし言う梯子をくだって、ベッドによこたわると、
「わーお、知らない天井だ」
と、時枝の声だけがきこえてくる。
「いいでしょ、天井が高くて」
「ここからだと天井は低いよ、すぐこそだよ」
「そうだった、そうだった」
「あの天窓って開くの」
「開くけど、うえは暑いよ。いまはエアコンつけてるし」
「いいよお、開けて」
エアコンを切って、ちょうどベッドのところにぶら下がっているチェーンをガラガラまわした。チェーンにつるしてあるマダラエイやメンダコのキーホルダーがのぼってゆき、縦向きに隙間を閉ざしていたルーバー窓が天井と平行になって開かれた。せっかくなので、下の窓も開け放って風を通すことにする。
「ああ。気持ちがいい」
時枝のいまにも寝入りそうなふにゃふにゃした声だけがきこえてくる。生ぬるい夜の外気がエアコンのひんやりした空気を追いやって、部屋のなかに風の龍脈のかようのがほのかに感じられた。マダラエイもメンダコも、ながいながいチェーンごと、かすかに揺れている。
いまはまだよくても、さすがにうえは蒸し暑くなるだろうと思い、冷凍庫からアイス枕を持ってきてあげた。おーい、と呼びかけると、柵のあいだから腕だけが下りてきた。ヨッコラセと背伸びをして、アイス枕を手渡した。
いまいちどベッドによこたわり「映画、途中で寝かけてたでしょ」と天井めがけて声を発してみると、
「うんうん」
と、ふにゃふにゃした声だけがきこえた。
以下、この日以降の日記で、カモについて記された箇所を抜粋する。
七月二十二日。時枝が撮っていた、カモたちが元気だった頃の写真や動画をみる。
七月二十四日。親鳥もどこかへいってしまった、池は鯉が水面を揺らすばかり。
七月二十七日。スーパーにて二〇四号室の多田さんと鉢合わせる。たがいに秘密を共有する者同士のように目で挨拶を交わす。
八月八日。公園で小川さんと息子さんがキャッチボールをしているところに鉢合わせ、カモはすっかり姿をみせないですね、などと世間話をする。
九月十五日。ひと夏のあいだ、まるで姿を現わさなかったカモが五羽もやって来ている。五羽とも泳がずに池の縁にだらんと身をよこたえている。
九月十六日。カモたちは暢気そうに泳いでいる。
九月二十一日。鴨が一、二、三、四……、一羽ずつ数えてゆくと、なんと十三羽もいる。こんなにいるのは知っている限り初めてのことである。
九月二十二日。今日は鴨が七羽、亀が二匹。
九月二十三日。一匹だけアブラ蝉の鳴くのをきく、ツクツクホーシは真夏の蝉たちのように壮絶な死にもの狂いの鳴声を発している。今日も鴨が七羽、突風が吹いて周囲の樹々から枝や木の実が映画でみる銃弾のように斜めに降り注いで水面の水が飛沫をあげて飛び散る。
九月二十八日。近所の小学校では運動会��開催、グラウンドの周囲を色とりどりのシートを敷いた親御さんたち観衆が取り囲い、ふだんはガランとしている校庭が今日はずいぶんと狭く小さく感じられる。公園の池にはなんと鴨が十八羽も、亀は二匹。ちょうど一週間前にはまだ池の頭上に覆い被さっていた樹の緑はすっかりと落葉して、茶色い枝分かれの骨組みが寒々と浮彫になっている。そういえば、校庭には、小川さん親子や、水上さんのところの兄妹もいるんだろうか。
九月二十九日。鴨十三羽、亀二匹。
十月十九日。鴨たくさん。
十一月二日。鴨大勢。
十一月二十一。鴨たちは朝から素潜りに大忙し、水面にあがってくる鴨のからだには水玉が付着している。やはり、鴨の羽毛というのは水を弾くようにできているらしい。
十一月二十三。ここしばらく大勢の鴨で賑わって公園の池には、今日は三羽しかいない。三羽とも岩の上で雨に降られてじっとしているか、顔を翼のなかに突っ込んで眠ろうとしている。
十二月十四日。陽気。公園の池には鴨大勢。とても寒い日は縮こまってじっとしているのに、今日は元気に泳ぎまわっている。
十二月十五日。鴨大勢。
十二月二十七日。池にはヒッチコックの『鳥』ぐらい鴨がいてびっくりする。
十二月二十八。公園には鴨大勢。いつもは水に浸かっているか、岩の上にしゃがんでいるかなのが、今日は岩の上に立っているのが多くてオレンジ色の足が池の緑にカラフルに映えている。
十二月三十一日。鴨たちは全員が岩や池べりにあがって眠っている、誰もいない池の水面には風のさざめき。大樹木の下では轟音が唸っている、枝同士がガチガチとぶつかり合い、時々落ちてくる枝もある、まるで時化の海のような凄まじさ。
元旦の手記。初夏のカモの一件いらい、カモのことをよくみるようになった。それ以前にしてもよくみていたのにはちがいないが、みかたが変わった。もう以前のようにはみられないと思う。それが良いことなのか悪いことなのかはまだわからない。あれからひと夏、カモは公園にまるで姿をあらわさなかった。秋口になって二、三羽もどってきたかと思うと、その翌週には両手をつかって数えあげなければならないほどに増えていた。この数年間で、こんなに大勢のカモがいたことはないから、天気でいうならば異常気象のようなものだと思う。ちょうど、あの日のことを小説として書いてみようと思い立った矢先だった。
もともと町へ行くときは公園をとおる週間があった。公園をとおるといっても、池を大周りする道と、小周りする道とがある。根っからのせっかちで、にもかかわらず寝坊で時間を費やしがちな者にしてみれば、池を大周りしている時間はなく、小周りのほうがいつものコースだった。それがカモがもどってきてからは、カモをみるために大周りになった。いつしか大周りの習慣が根づいてしまうと、ふしぎとそのことに関しては時間がもったいないとは感じないようになった。
はじめの頃はカモの数を一羽一羽かぞえていた。とはいっても、カモたちは池の水面をゆらゆら泳いでいるから、とちゅうでどのカモを数えたのかわからなくなってしまい、三回かぞえてみても、三回とも数がちがうこともしばしばだった。それでもう数えるのはやめにした。
台風の日はスリリングだった。カモは風雨を避けてどこかへ行ってしまうにちがいないからだ。いるはずのものがいなくなっていたり、あるはずものがなくなっていたりすると、たいていは動揺する。事実、台風一過の池の水面には折れた樹の枝が大量に浮かんではいても、カモの姿はみられなかった。それでも二、三日すると、また大勢のカモが池の水面に暢気そうに浮かんでいた。
年末は二十七日の午後から休みになった。例年だと、このタイミングで緊張がとけてしまうのか、よく熱をだす。ただ、ことしは歯痛事件でお釣りがくるぐらい痛いめをみたせいか平気だった。で、あれよあれよと生活のリズムが崩れた。
三十日、町まで夕食をたべにでかけたのは夜の十一時ちかくだった。池の暗がりをのぞいてみると、黒い塊の斑点がまばらに浮かんでいる。ほとんどのカモが眠っているらしいなか、一羽だけ泳いでいるカモが水面に落ちている街灯のひかりをゆらしている。それがふしぎなことに0時過ぎにもどってくると、カモは一羽もいなくなっていた。
三十一日、大晦日。この日も十一時ちかくに夕食へでかける。暴風注意報がでているぐらい吹きだから、カモはいないかもしれないと思っていると、カモたちはこの夜も暗い塊の斑点となって浮かんでいる。さすがの吹きの大晦日で歩いているひとはまったくおらず、街灯のひかりに照らされた木の影の、まばらに残った枯葉の影が大きく風に揺れていて、まるでセットで撮られたフィルム・ノワールのような不気味さだった。そしてこの夜も、0時過ぎにもどってくると、カモは一羽もいなくなっていた。
一日、元旦。この日は十一時ぐらいには食事がすんだので、ここはひとつ、いったい何がおこっているのか、公園で待機してやろうと思った。ものすごく寒いだろうから、貰ったっきり一年ちかく放置していたウイスキーをあたためてもっていくことにした。やっぱりカモたちは黒い塊の斑点となって浮かんでいた。公園にはひとっ子ひとりいなかった。目が暗がりに慣れてくると、カモたちの姿がみえるようになった。どのカモも翼にあたまを突っ込んで眠っている。岩の上にいるのは、あたまだけではなく、片足も翼にしまってしまい、器用なことに片足立ちで眠っている。ウイスキーはすぐに冷たくなった。それでもないよりはましに思えた。0時ちかくになり、一羽のカモがビクッと翼からあたまを出した。それにつづいて周囲のカモたちも次々にあたまを出していく。そして、いっせいに羽ばたいた。一羽だけ飛びおくれて、まだ池を泳いでいるカモが水面に落ちる街灯のひかりをすーっとゆらして、羽ばたいていった。
一月五日。公園には鴨大勢。すれちがうひと、すれちがうひとが、うーさぶい、とか言いながら過ぎ去ってゆく。
一月八日。時枝から国際便で年賀はがきが届く。この国ではベースボールはマイナーなスポーツだからキャッチボールの相手がいないとか、でも、鴨はどこの池にもたくさんいるとか書いてある。鴨の行方を追ったあの夏が懐かしいです。また、いつか、キャッチボールのできる日が来るといいですね、と結ばれている。
一月十三日。鴨大勢。
一月十八日。雪が降るとうれしい。池の大勢の鴨たちは、こんなに寒くても元気いっぱいに泳いだり素潜りしたり、心なしかいつもより元気なようにみえる。
一月十九日。鴨大勢、この頃よくみる胸の赤い鴨が今日もいる。
二月十六日。雨。公園の鴨は半数以下まで減っている。
二月二十三日。鴨大勢、亀がぼけーっとアホ面を晒して水面から首を突き出している、長閑だなあ。
三月四日。キャッチボールをしている小川さん親子をみかける。
三月二十一日。桜がよく咲いて、公園は花見客で賑わっている。年に一度の池の水抜きで、鴨はどこかへ避難したらしい。
四月十三日。鴨二羽、つがいのようで並んで泳いでいる。
五月一日。鴨三羽。つがいの鴨に、もう一羽がちょっかいをだしている。それをみて微笑んでいると、隣で同じく鴨をみているひとと目が合う。あれ……、と三秒ほど間を置いて、あああっとなる。なんと、太っちょの肝っ玉かあさんである。憶えていてくれて光栄です。
五月二十四日。十羽のヒナが孵る。池の周囲はお祭り騒ぎ。池べりから鴨たちをみるひとだかりを押しのけて、甲羅から首を突き出す亀のように柵から身を乗り出す。すごい、鴨のヒナだ、元気いっぱい、しかも十羽も。時間が押していたけれど、池の周りを四周ぐらいする。夕方、用事を済ませて公園にもどってくると、鴨のヒナは十羽とも健在。ただ、周囲のひとたちの様子がちょっとおかしくて、よかったあ、ほんとうによかったあ、などと口々に言い合っている。どうやら、散歩の途中に一羽のヒナがはぐれてしまい、紆余屈折あって、どうにか親鳥や兄妹たちと再会することができたらしいのだ。私の知らないところで、私とは関係のないところで、いったいどんな冒険が繰り広げられていたんだろうか。それは私にはとても及び知らないことであるし、せいぜい又聞きすることぐらいしかできないけれど、今日という日にそんな冒険があったということを心から祝福したい気持ちでいっぱいだった。
0 notes
Text
新しい骨董 公開インタビュー(大阪・千鳥文化にて)
ちょうど関西に台風が直撃し、誰もが部屋にこもっていたため街中が閑散としていた2017年10月23日に、新しい骨董の展示が行われていた大阪・千鳥文化にてひっそりとトークイベントが開催されました。新しい骨董のこれまでについて改めてメンバーで振り返りかえったディープなトークショーの模様をボリュームたっぷりで公開します。
日時:2017年10月23日 場所:千鳥文化(大阪・北加賀屋)
出演:山下陽光(途中でやめる)、下道基行(アーティスト)、影山裕樹(編集者)、聞き手・文:竹内厚

新しい骨董が生まれたきっかけ
山下:これ、知ってます? 会場にもまわすのでひとつずつ食べてみてください。グミってもうあまり買わないじゃないですか。だけど、知らない間にこの20年でこんな進化してるのかってひっくり返ったんですよ。
―UHA味覚糖の新感覚グミ「cororo」、こんなのあるんですね。
下道:ほんと、果汁感がはんぱない。
山下:そうなんですよ。これで味覚糖が寿司ネタつくりはじめたらどうなんだってブログを書いてたら、もうね、海老焼売の味がする菓子とかつくってるんですよ。
下道:UHA味覚糖はヤバい、大阪の会社だよね。
山下:ですね。この20年でいろんなことが放ったらかしにされて、これくらい進化してたり、もしくは後退してたりもするんですよ。その典型じゃねぇかなって。
影山:お待たせしました。
―影山さんがトイレから戻ったのではじめましょう。新しい骨董って何なのか。まずは、職業も活動拠点もばらばらな3人がどうやって出会ったのかを教えてください。
影山:最初は、2013年に青森の十和田市現代美術館で「超訳 びじゅつの学校」という展覧会の企画に僕が関わっていて、そこに山下さん、下道さん、小説家の戌井昭人さんをお呼びしました。作品を展示するだけじゃなくて、会期中にいろんな部活動をつくって活動するという、観客参加型の企画で、山下さんは被服部、下道さんは写真部をやってもらったのかな。
下道:観察部です。
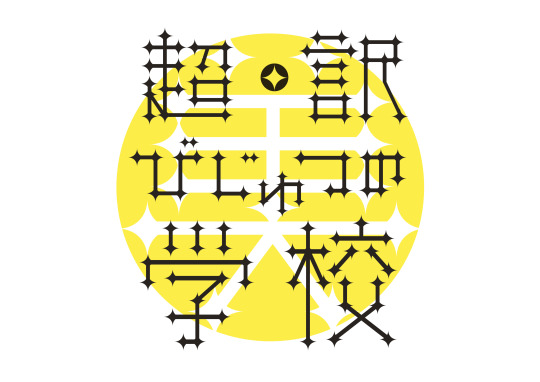
(「超訳 びじゅつの学校」十和田市現代美術館、2013)
影山:そうそう、「下を向いて歩こう」っていうのをテーマにして。そのときに、夜は十和田のスナックを飲み歩いて、その様子も次の日のトークで発表するみたいなこともやってたんです。
下道:当時は、藤浩志さんが十和田市現代美術館の副館長で、影山さんは企画協力という形で関わっていて、僕らを呼んでくれたと。
山下:そうでしたね。
影山:藤さんの家に泊めてもらったりしながら、1週間くらい飲み歩いたりして、そのときに「なにか一緒にやれたらいいね」って話が出たんだと思う。路上観察学会だったりとか、それぞれに共通して興味を持っていることもあったから。
―3人の頭の中には、路上観察学会という共通のキーワードがひとつあったんですね。
下道:いや、どこからその話になったんだろう。
山下:なかった。たぶん影山さんは思ってたかもしれないけど、オレ達は会ったばかりだし。
下道:僕は、何だろうこの人はって感じで、山下さんにビビってたからね(笑)。でも、共通する接点はあるよって、影山さんから少しずつ聞いていて。覚えてるのは、泊めてもらった藤さんの家がものすごく寒くて、スナック行っては帰ってきての繰り返しだったことくらい。
―影山さんが編集者らしく、ふたりを近づけていったのかな。
山下:いや、そのときはそれで終わりますよね。またやろうぜって感じでもなく。
下道:どうやって始まったんだろうね。「超訳 びじゅつの学校」と「新しい骨董」のつながりが明らかなことがひとつあって、ウェブの体裁がほぼ同じ。デザイナーさんも一緒だから。そのつながりはあるんだけど、どうやって「新しい骨董」が立ち上がったんだろう。
影山:具体的にこの3人でなにかやろうかって話は、「超訳 びじゅつの学校」の後、1年くらいしてから、僕が山下さんが住んでた長崎の家に遊びに行ったんですよ。そこで、下道くんとスカイプつないで話してみようかってなって。
下道:そうだそうだ。でも、そのときにはもう「新しい骨董」って名前は存在してた気がする。
山下:オレが覚えてるのは、スカイプ会議をやったときに、こっちはイオンにいて、レジ脇の床が擦れまくってるところ、これって新しいトマソンじゃねぇのみたいなことを言った記憶があるから。路上観察学会みたいなことをやろうって話は、もう出てたんだと思う。
下道:言ってたわ、それ。お互いの興味をすり合わせるようなことをしてたんだね。それに対して、僕は浜辺で拾ったウルトラマンセブンの消しゴムみたいなのを見せて、「僕的にはこういうことかな?」って言ってみたんだと思う。

―路上観察学会が見出したトマソン、イオンの擦れた床、拾ったウルトラマン消しゴム…と、気になるのはこれだよねという具体的なものを見せあって、だんだん3人が近づいていく。それにしても「新しい骨董」という名前はどこから?
影山:3人で活動するときの名前をどうするかっていうので、新しい路上観察とか、そんな名前をいろいろ挙げてたんだけど、山下さんがどこかで「いやいや、新しい骨董でしょ」って言いきったんですよ。
下道:うん、陽光くんのやってる「途中でやめる」と同じで、グループ名ぽくはないんだけど、すごくばっちりの名前だなと思った。
影山:その頃に山下さんが言ってたのは、雲仙普賢岳のことで。3人でFacebookでアイデアを出しあってたら、山下さんが雲仙普賢岳の話を書いてきて、それは「新しい骨董」のウェブの最初の記事(→リンク)にもなりました。
―その記事を読んでもらうのが早いと思いますけど、簡単にいえばどんな話なんでしょう。
山下:そうですね。雲仙普賢岳の噴火が1991年にあって、土石流で1階が埋まった家が永久保存されてるんだけど、かなり新しく見えるんですよ。しかも、それが完全なレプリカで。埋まった家を掘り起こして、それを移動させて、また埋めて、保存してる。なんだろうこの感覚って。
下道:原爆ドームに似てるんだけど、そのめっちゃ新しいバージョンというか。
―歴史を扱うような手つきだけど、そのもの自体は全然古びてないと。
山下:なおかつ、お土産として土石流を売ってるんですよ、500円で。
―埋まった家はモニュメントになって、土石流はお土産に。
山下:アトム書房と同じなんですよ。

影山:山下さんは、広島の原爆ドームのそばにできたアトム書房って本屋さんの写真をインターネットで見つけて、これはなんだって調べる活動をずっとやっていて、そのときに山下さんが言ってたのは、インターネットが今のストリートみたいなものなんだと。骨董、路上観察っていうと実際にある物がベースになるように思うけど、インターネット上にあるそういうものを探していくのが「新しい骨董」なのかなって、この頃からちょっと思いはじめてました。
下道:僕自身は、そういうことはあまり考えてなくて、僕自身はガチで路上を歩くタイプだから、陽光くんのそういう考えかたって結構、衝撃的なことで。だから、僕の場合は、「新しい骨董」によって自分の活動がハイブリッド化すればそれでいいかなっていうことは思ってた。
―下道さんとしては、山下さんの目線に似たものは感じるけども、フィールドややり方が違ってそれが新鮮だった。
下道:そう。その頃、自分で考えてたのは震災後の東北の風景なんだけど、瓦礫が片付けられたところに残された建物、その廃墟のような建物に案内看板が立ち始めてたんです。もう数年前に何もなくなった更地にも、「以前、この場所にはこれがありました」という仮設の看板が立ってるんですよ。 僕はこれまで作品を通して、過去が現在の自分にどうつながっているかを調べながら表現したいと思ってたんだけど、震災が起こった直後から自分がすごく未来志向になっていて、たとえば100年後にこの震災は人々からどう捉えられるかって頭に変わりはじめた。それって、陽光くんが「新しい骨董」のはじめの記事で提示したことに非常に似てるなって思っていて。
山下:僕は今年40ですけど、25歳になったくらいの頃から、子ども時代に流行った遊びが付加価値をつけて、また復活しはじめるんです。それも「ドラゴンクエスト」みたいな、みんなが知ってるものじゃなくて、「これ、ちょっと見落としてたな」みたいなものが1周まわって、価値をつけて出てくる。「熱血硬派くにおくん」とかね。
下道:そうそう。だけど、それってまだ近過去の話で、��光くんは最初に書いた記事で、もっと先の話まで書いてるから。ここですよ。
”これからさきは少し前を未来にするのではなくて、近未来を過去として予想してみる事にチャレンジしてみる。現在はまったくわからないけれど、2018年に検索されそうな言語を書いて、海にボトルレターを投げるように、書いた文章を投げまくって未来から検索して辿り着いてもらう事を予想しまくる。この文章こそが新しい骨董なんです。”
って、つまり、未来から先回りして過去を考えようと。これはぶっ飛ばしてるなって思った。
―それって、たとえばどんなことをイメージしてますか。
山下:mixiとか。
下道:もっと近いところでいえば、Facebookが「3年前のあなたはこんなことをやってました」って告知してくるのとか、まさに最先端の近過去で。ただ、それではそこまで面白くない。近過去のことを扱うひとはそれなりにいるからね。だから、陽光くんは近過去ではまだ足りないんじゃないかって最初から書いていて、「新しい骨董」は近未来のことを過去として想像してみるチャレンジなんだって。そこまで振り切りたいよね。
裏輪呑み、ウェブショップの誕生
―新しい骨董という名前や考えかたが少しずつ共有されていった過程が想像されますけど、3人以外が新しい骨董を知った、具体的な活動って何が最初ですか。
影山:それは「さいたまトリエンナーレ」ですね。
下道:その前って何もやってない?
山下:ネットで売りはじめてたんじゃない。
下道:いや、それ始まったのはトリエンナーレの下見1日目だから。
―ということは、まだ具体的な活動がはじまってない「新しい骨董」にトリエンナーレから声がかかったということ?
下道:まず僕に声がかかって、最初このトリエンナーレの主軸は、アーティストの新しい作品をドデンと置くのではなくて、さいたまに暮らす人たちとの恊働や新しい場づくりだったし、テーマが「未来の発見!」だったから、僕じゃなくて新しい骨董として受けたほうが面白いんじゃないかって提案したんです。そうだね、トリエンナーレまでは、新しい骨董のウェブ上でそれぞれが気になったことをアップして、意見を交換するだけの活動だったかな。
影山:まあ、みんな住んでる場所がばらばらだから。
山下:なんも覚えてない。どうだったかな。
下道:陽光くんは自分でもブログを持っていて、新しい骨董だけじゃなくて、いろんな興味がひとつになった状態でどんどん自分のブログに書いてたから。僕はそれを見ながら、この文章ってすごく「新しい骨董」の話なんだけどなぁって思って見てました。
―いろんなアイデアや意見がごちゃ混ぜになった山下さんのブログの中に、新しい骨董として発信したい内容も含まれていたんですね。
下道:そう、僕的には。影山さんがそういうことを新しい骨董のブログにあげてよってお願いするんだけど、書き直すわけにもいかないし。だから、新しい骨董感のある陽光くんの文章を僕が引っ張ってきて、まとめサイトみたいにまとめてみたり、そんなこともやってました。
山下:あー、やってたね。
影山:それで、「さいたまトリエンナーレ」に新しい骨董で参加しようって話が出てきて、ちょうどいい機会だし、集まって合宿もできるからって、3人で埼玉で合流して、またいろいろ動きはじめたんですね。
下道:3人で集まって話す機会ができたのは、結構大きかった。埼玉で集まったときに、拾ったものを売ってみようって話も出て、これは瞬発力で形にするべきだと思ったから、その日にすぐ新しい骨董のウェブショップを立ち上げた。
山下:そうだ、浦和のベローチェでね。
影山:そのときには、もう山下さんは新しい骨董に興味をなくしかけてたんですよ(笑)。買うを遊ぶとか、そういう話をずっとしていて。山下さんがつくる洋服も、原価を高くしていかに儲けを少なくするか、いかに安く売らなきゃいけないかってことを話し続けてた。
山下:いちばん安いコーヒー屋で。
下道:そこで新しい骨董のウェブショップを立ち上げて、陽光くんがポケットに入れてた鉄クズみたいなのと下道が道で拾った潰れた紙切れをアップしたら、一瞬で売れたんです。
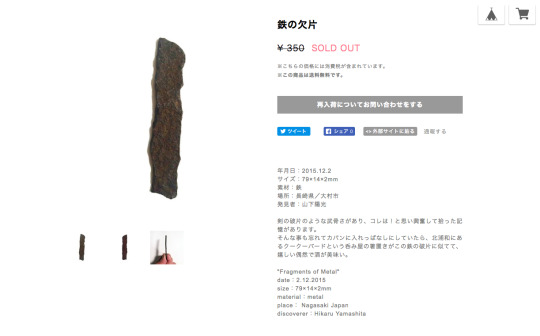
影山:それが次のブレイクスルーでしたね。
下道:新しい骨董のウェブショップを立ち上げるときに、陽光くんがずっと言ってたのは、「値段を3000円にしても10000円にしても変わらない。絶対に100円でいいから」って。いくらにしても買うやつは買うし、買わないやつは買わないからって。
―山下さんとしては、売り買いの行為こそが面白いってことですか。
山下:なんだろうね。写真集を本屋では買わないんだけど、夜中のAmazonだと買っちゃうみたいなことがあって。明日は仕事がむかつくなってときに、だまして売られるみたいな感じがあるから。その夜中にポチッとしてしまうのが、3000円じゃなくて300円だったらめちゃくちゃかわいいじゃないですか。しかも、下道氏は本気の梱包をするからね。
―新しい骨董ウェブショップで何かを買うと本気の梱包で商品が送られてくる。スタートした新しい骨董のウェブショップでそれからどんなものを販売してきましたか。
山下:下道氏がうちに遊びに来たときに、うちの娘がまだ当時2歳くらいで、納豆のパックを開けたら下のほうがビリビリって破れたんだけど、それを下道氏が狂気の眼で見てた。「それ、ちょっと金継ぎしたいんだけど」って。
影山:その納豆パックを金接ぎしたのも、ウェブショップにあげるとすぐに売れました。
下道:僕の中に「新しい骨董」チャンネルみたいなものが生まれてきて、気になるものを見つけた瞬間に、これ売りたい!って感じにはなってきたんです。
―ファウンドオブジェクト的な見つけたものだけじゃなく、手を加えたものも販売しているんですね。
下道:拾っただけのものはだいたい100円から200円で売って、手を加えたものはもう少し価値をつけてます。納豆パックの金継ぎも漆を乾かしたりするのに2~3日かかっているのにそれを2500円で売ったら、さすがに妻が怒ってました。
―何やってんだと。
下道:そう。他にも、ある朝妻が食パンを焦がしちゃったのを、捨てないでさらにじっくり焼いて炭化させて真っ黒にして、それも「焼きすぎたパン」として売りました。水分も何もかも全部飛ばしたら、カビることもないし、何百年と保つから。妻の朝の失敗を永遠に凍結して、未来に残す気持ちです。
―いい加減に怒られますよ。
山下:面白いのが、それ、2枚セットなんですよ。1枚焦げたからじゃあもう1枚って、レプリカとして完璧に炭化したパンを下道氏がつくって。

―そういったエピソードも購入者には伝えますか。
影山:買った人にはエピソードをプリントアウトしたものも送られてきます。
―ウェブショップには、一見、ゴミにも見えるものが並んでいますけど、ひとつひとつ物の来歴から、サイズや素材、発見日も記されて、だんだん美術作品のようにも見えてきます。
下道:僕的な密かな楽しみはそうかも。自分としては、現代アートでできないことが新しい骨董だったらやれると思って、続けてきたところもあるので。自分自身ではいつもは恥ずかしいからやらない”アート的”な行為を少し素直になってみる感覚もあるかも。
―現代アートだとできないことって?
下道:いや、僕自身がただできないこと。例えば、沖縄で路上で車にひかれてぺちゃんこになったコカコーラの空き缶を拾ってすぐに販売サイトにアップして売ってみたり。あと、拾った落ち葉も送料込みで350円で売ってるんですけど、これ、ドイツのカッセルで拾ったヨーゼフ・ボイスが植えた木の落ち葉なんですよ。でも、象徴的なアイコンとか有名作家の引用とか、そういうのの組み合わせでやっていくとなんか「現代アートっぽく」なってしまうなぁと。
山下:1万円ぽいってことですよね。
下道:そうそう!作家としては悩みながらそういうのとはなるべく距離を取っていた…。だけど新しい骨董でこれを100円で売るのなら面白いかなって。だから、なんか今まで実はやってみたかったことを、新しい骨董で遊ばせてもらってるなって思います。
―影山さんが売ったものってないんです��。
影山:ありますよ、ひとつ。たぶん自転車から壊れて落ちたカギ。ただ拾っただけなんだけど。
―影山さんが新しい骨董に期待してるのは何でしょう。
下道:どうなんすか、何を期待してるんですか。
影山:新しい骨董のウェブショップに関しては、わりと下道カラーが全面的に出ていて。
下道:そうね、僕メインでガーデニングみたいに日々耕しています。
影山:あとは、山下さんが言う、あり得ないくらいの値段が安いっていうのも反映されてるんです。だけど、山下さんってその値段の話もそうだけど、すぐに捨てちゃうんですよ。
山下:秒速で飽きるんですよ。与沢翼なので。
―話をちょっと戻すと、さいたまトリエンナーレの準備段階で、新しい骨董のウェブショップが立ち上がったと。
影山:裏輪呑みもそこで生まれたものだよね。みんなで京都へ行こうって話もそうだし。
―では、次は裏輪飲みのことを教えてください。
山下:ダイソーで売ってる��力マグネットラックみたいなのがあって、それを上下ひっくり返して街の自販機とかにつけたら、そこがカウンターになって街のどこでも飲めるんですよ。
―街のあらゆる場所が立ち飲み屋に。
山下:そしたら、街の見え方が全部変わってきて、そこに磁石があるか否かで見るんですね。ここならいけるとか。スクランブル交差点で飲んでても、自然に街に溶けこむ。そのカモフラージュ感がハンパねぇなって。

(裏輪呑みを紹介した記事はこちら→リンク)
―どこからそんなことを思いついたんでしょう。
影山:みんなでダイソーに行って、これがあれば街で飲めるじゃんみたいな話になったんだよね。
山下:もとはと言えば、オレが東京に遊びに来たときに、影山氏と御徒町で飲む機会があって、金持ってるヤツが酒買って、刺し身買おうってなったんだけど、影山氏はまさかの100円ショップで椅子を買ってきたんですよ。
影山:お風呂用の椅子でした。山下さんは、高円寺で「場所っプ」て店をやってたときから、路上で飲んだりよくしてたから、好きかなと思って。
山下:地べたリアンだったからね。だけど、その椅子があることで、地べたで飲んでてもオレらはもう店に来てるぞ、みたいな意識になったんですよ。で、帰りにその椅子をもらってコインシャワーに行ったら、あ、椅子があるから座れるわ。東京の答え、これで出たなと。
―どこでも座れる椅子が東京の答え。
山下:東京にいるとどこかに座るだけでいくらかお金を払わなきゃいけないのに、100円の椅子があるだけでどこでも座れるなって。ただ、路上に座ってるとヤカラな感じもあって、タチが悪い。それが、裏輪呑みだとただ人が立ってる感じしかしないんです。
影山:ダイソーで見つけた後で、試しに何時間か裏輪呑みをやってみたら、駅前の交番前でも全然怒られなかった。これってすごいんじゃないか、さいたまトリエンナーレの作品もこれでいいんじゃないって話になったんですよね。夜も泊まってた旅館でこれ(強力マグネットラック)見ながら飲んでね。
下道:そうだった、すごい発明だなって。
山下:シャッター商店街に対する答えだからね、これ。もう店を開けなくてもいい。

影山:裏輪呑みは全国に広がって、マネをする人が増えたのが大きかったですね。今年も山口のシャッター商店街で裏輪呑みをやった人がいて、それは商店街の人にもちゃんと交渉してました。
下道:この前、沖縄でもやってたよ。ダイソーに集合して。
影山:だけど、裏輪呑みは新しい骨董とは関係ないんです。
―副産物みたいなものでしかない。
影山:わりとバズったりはしたんですけどね。
―みんなで京都に行ったという話はどんなことでしょう。
下道:裏輪呑みをみんなでやったら面白いのではと、さいたまトリエンナーレに出品の企画として提案したんだけど、アルコールだったり路上で勝手にやる事がなかなか難しくて。
影山:そのときに『京都おもしろウォッチング』(路上観察学会・編/新潮社/1988年刊)という本を見て、ちょうど30年前に路上観察学会のメンバーが京都へ行って、面白いところを見つけるみたいなことをやってたんですよ。じゃあ僕らも京都の同じ場所へ行って、同じものを見つけようって京都旅行をしました。行為のコスプレって言いながら。
山下:その本に掲載されてる場所をひたすら探して、赤瀬川原平たちがどの道を歩いたかってことを特定しまくったんですよ。それはすごく面白かった。
影山:本の表紙に写ってる、人の顔が描かれた角石をいきなり下道くんが見つけちゃうんです。ただ、その角石も30年経ってるから、隣りの家にズレてたりして。そのときのことは、京都新聞でも記事になりました。
―角石(かどいし)、敷地の隅に置かれた石ですね。このときの京都旅行は、新しい骨董としてどこかに発表してるますか。
山下:ブログにオレが書くって言って、まだ書いてないんですよ。
下道:でも、いつこの本(「京都おもしろウォッチング」)を入手して、京都に行くことになったんだろうね。
山下:…あまり酒飲まないほうがいいね。
ボトルキープ、月刊 新しい骨董の発行
山下:いやー疲れましたね。クソつまんねぇグループの立ち上げ話を聞かされて。
―いやいや。
山下:早く終わんねぇかなと思って。今の話をしたいんですよ。去年の話とか、もう無理だから。
―さいたまトリエンナーレがどうなったかは聞かせてくださいよ。
下道:もういっこ、あちこちの店で「新しい骨董」の名前でボトルキープするってのも始めたんだけど、陽光くん、もう飽きてるよね。
―誰でも「新しい骨董」の名前でボトルをキープができて、そのボトルは誰でも「新しい骨董のボトルください」と出して飲んでいいというやつですね。ボトルキープをする意味については、新しい骨董のブログ参照(→コチラ)ということにしましょうか。だけど、トリエンナーレでアルコールはダメだったんですね。
下道:ボトルキープだとある程度特定のお店たちのみとの繋がりになってしまうのもダメだったのかと思います。ただ、浦和って大熊猫氏を筆頭にすごく呑兵衛が多くて、イカれた名店もあったりして、この時期にいろんな人が入れてくれたボトルキープはいまだに多くが呑み継がれていますし、100本到達記念で浦和の「ねぎ」にメンバーも集まってみんなで飲みました。
―では、それ以来ですか。
下道:そうだと思いますよ。
影山:いやいや、今年の新年会で1回会ったじゃない。単なる飲み会だったけど。
―そこでこれからの新しい骨董をどうしていくかという話も出た。
山下:いや、出てない…出たっけ?
下道:そのときに僕としてやりたいって話したのは、月刊 新しい骨董で。
―月刊 新しい骨董というのは、2017年1月にいちど発刊されているメルマガですね。

影山:下道くんが新しい骨董のウェブショップをリードしてきて、そこにあげた物はどんどんソールドアウトになって、で、裏輪呑みは全国的に広がってきた。それはいいんだけど、やっぱりもうちょっとインターネット的なことをやりたいねということで、新しい骨董のウェブマガジンを立ち上げましょうって話になったと思います。
山下:そうだね。それで、オレらが月刊 新しい骨董に原稿を書いて、その文字数が3000文字だから、それに対して3000文字書いてきたらそのメルマガを読めますよってことにしたんです。文字数の等価交換。これは大変なことになりましたね。読んだこともない文章が3000文字送られてくるんですよ。
下道:500文字しか送ってこなかったら、500文字だけ送って、のこりのテキストは塗りつぶして送るってコンセプトで。ここで生まれた副産物もいっぱいあるし、ほんとに文字数の等価交換というのは非常に面白い。だから、そこをもうちょっとやってみようよって、ぼくは新年会で言ったんですよ。
―副産物ってたとえばどういうことですか。
下道:わけわからない日記みたいなものが、僕ら3人だけに送られてくるんだけど、3000文字って言われても、何を書けばいいかわからないから、実はこんなことで悩んでるんですとか、うちの近所にサーファーがいて…とか。でも、それを読むのは3人だけ。
山下:でも、面白いですよね。
影山:うん、面白い。
下道:文字の等価交換ってすぱっと決まったコンセプトで、すごくいい。でも、その副産物的な部分の面白さは、陽光くんが最近出版した『バイトやめる学校』(山下陽光・著/タバブックス/2017年7月刊)では、本だけではなく読者が直接感想や悩みを送ってきていたりしたそれに応えているのに続いているのかな。
―山下さんとしては、文字の等価交換のアイデアはもういいやって感じですか。
山下:いや、面白いですよ。ただ、もう、オレは「これ面白いでしょ」みたいなことはもういいかなと思っていて。みんなにもっと余裕があれば、その面白いことで笑いたいけど、いまの世の中の状況で、「オレがいまから面白いことを言います」ってやっても、「いや、明日早いんで」って感じになっちゃうでしょ。
―笑えない状況だと。
山下:そうなんですよ。表現みたいなことを仕事にしてると、「オレはあいつと違って」みたいに、ちょっと蹴落とさなきゃいけない部分とか、ほんとは儲かってないのに儲かってるふりをしないといけないとか、それが結構ヤダなと思っていて。だからといって、真面目に勤めあげて、まったく面白くない仕事で20万とかもらって、空いた時間に好きなことをやるんじゃなくて、そうじゃない、もうちょっと違う状況をつくれるんじゃないのって思うんですよ。
影山:そうだね。
山下:ここから先は、ちょっとうさん臭くなるのでアイツ酔っ払ってんなと思ってもらっていいんだけど、なんかね、「楽勝っす、儲かってしょうがないんすよ」って言ってたら、ほんとに儲かってきちゃうことって多いんですよ。「世の中クソですよ」って言ってたら、ほんとに嫌になってきちゃうんだけど。だから、社長の自伝とか自己啓発本に書いてある「人の悪口は言うな」とか、あれ、わりと本当で。で、オレも結構せめぎ合いなんですよ。周りに裸の女が50人くらいいるけど、そこには一切触れず、性欲ゼロパーですって言��ながら、歩いてるみたいな感じ。どうやっても儲かるって話がめちゃめちゃ転がってるから。
影山:なのに眼をつぶって歩いてるんだ。
山下:そう。もう話すら聞きませんって感じで。それが超大変なのに楽しくて。昨日も京都のイベントがひとつ中止になったから、「途中でやめる」の服を売る機会がなくなって、それで今月の家賃が払えないんですよ。ヤベェぞと。だから、いそいで服を送り返してもらって、すぐに通販にアップして、売れたお金を銀行の口座からおろして家賃を払うってやらないと、もう、うちは破産するんです。
影山:そんな感じなんですね。そこ気になってました。
山下:だけど、それは100%売れるんです。あるものは絶対に売れるから。それがプラス50万になろうが、プラス1億だろうが、あんまり関係ないなって。このお金、誰が喜んでるんだろうって話でいえば、うち、最近、畑をはじめたんだけど、向かいに住んでる管理人のおばさんが「植木屋が刈っていった落ち葉がいっぱいあるんだけど、いる?」って落ち葉をくれるんですよ。向こうは落ち葉を捨てるための市指定のゴミ袋代が浮くし、こっちは腐葉土にして使えなくもないからって、これ、どっちがありがとうって言うべきなのか。ようは、払ってもいいし払わなくてもいいし、どっちでもいいっていうのが最高の世の中で。オレはそういうことをやりたいなと。
影山:僕もローカルをテーマに地方でいろんなことをやってるんですけど、地方って泥臭いことがいっぱいあるわけですよ。地方でのクリエイティブの仕事、特にデザインや編集ってお金が見えないから、その対価が現物支給だってこともリアルにある。それを見える化していくのも面白いかもしれない。
下道:そうだね。そこ、実は結構あるのに、見えてないもんね。ただちょっと思うのは、陽光くんの場合、全力で自分の生活を見える形で自分で賭けて生きるってことに100%で挑戦している人間で、僕はアーティストと言う生き方だと、やはり美術館は街や国が運営をしているし、だから絶対に自分だけで100%自立して生きていけないジレンマがある。だから、新しい骨董の活動っていうのは、僕的には、今まで疑問に思っていた別の自活して生きる方向の実験場って考えている。100%でそういう生き方を憧れる人は多いけど、本当に陽光くんみたいに100%で行なえる事ってなかなか難しい。
影山:高円寺でやってた頃の山下さんは、考えてる面白いことと自分の生活がもう少し切り離されてましたよね。
下道:しかも、もっと表現ということを考えてたような気がする。
山下:おうおう、考えてたね。
下道:だけど、いまは表現みたいなものは全部なし、みたいになっていて。わかるんだけど、そこを表現としてどう出せるかっていうのは、どう考えてるの?僕はやはり表現者として生きたいと考えているけど。
山下:思ってはいたんですよ。震災の後くらいまでは。でも、また原発がドカンといったら、そんなこと言ってる場合じゃないでしょうってなったら、オレがこれを信じてますってことが無意味なんだなって。だから、どうやって生きていけばいいかって超根源的になるしかなくて。いま、オレができているこの暮らしって、わりと誰でもできるんじゃないですか。みんなやってくださいよって言ってるつもりだけど、「なんかオレとは違うっす」みたいな距離ばかり見つけられて。いや、そうじゃないんだよってもんもんとしてる。

影山:山下さんは、アクティビスト的になってきてるんですよね。僕も本当はもっとカルチャーの仕事で食っていきたいんですよ。だけど、それだけでは難しくなってきたときに、その外側に食い扶持ができてきて、じゃあ、生活をどうクリエイティブにしていくかというところにシフトせざるを得ないところもある。で、アーティストもそうなりつつあって、作品をつくってるだけじゃなくて、生き方まで考える時代になってきた。カルチャーと生活の境界が曖昧になってきたとして、そこをどう楽しむか、実験するかというのを新しい骨董がやればいいんじゃないかなって気はするけどね。
山下:いや、オレは別にそんな食えなくてもいいっすけどね。
下道:でもね、陽光くんがどれだけ振り切った生活を見せても、みんなが同じようなセンスを持って100%で生きていくのは難しいんじゃないかな。
―売り買いを楽しむとか、骨董と名付けた意味をもういちど考えてみるのもありな気がします。
下道:ものすごく安く売るとか、文字の等価交換とか、新しい骨董がやってるのは価値の遊びだとは思います。ただ、何もないところからガンと打ち破って、少し前へ進むってのが価値のひとつめなんだけど、それって難しいし、結構周りには見えない。前衛の人たちってそのタイプだと思うけど、それが1周2周とまわった後に、アイツは価値をつくったんじゃないのって掘り起こされて、世間が気づくことがあると。陽光くんはそのゼロからイチみたいなことをしきりに言ってる気がして、だけど、僕にもそれは見えたり見えなかったりで、やっぱりあれいいよなって後で気づくこともある。僕の場合は、その陽光くんの投げ捨てていった物を「新しい骨董」のフレームで集めて延長させる感覚はあるな。
山下:しかしこれ、完全に飲み屋の話でしょ。イベント終わってからやるやつ。
影山:今日はこういうことを話し合うために集まったからいいんだけど、あとは二次会で話の続きをやるとか。
下道:ですね。
了
2 notes
·
View notes
Text
土曜日 ふるい街なめりかわ
美味しい海鮮丼のお店があった

ご飯の量が少なく、丁度良い。

ケーキ屋さん、ここはケーキを選んだらお皿に盛り付けてくれる。苦めの珈琲と実によく合う
古い街なめりかわ

古道具屋とれじ
欲しかったテーブルと椅子は既になく、アンティークは一期一会と実感する。とても良いものばかりで、先週も鞄をかった。鞄は設計会社で使用されていたものらしく、様々な書類を持ち運べそうだった。

とても感じのいい店主さんが声をかけてくださる。先週訪れた際、会計は電子マネーにも対応していると��い驚いた。古きと新しきが交差するお店だ。

旧8号線沿いのとらじを後に、滑川の旧市街、なかなめりかわ方面へ。滑川市役所最寄りの富山地方鉄道の中滑川駅脇の踏切を渡り、海辺の街「橋場」へ。

岸壁の間から青い海が顔をのぞかせていたので、好奇心から近づいた。細い道に入り、岸壁へ向かうと、そこには「古本いるふ」の駐車場があった。店舗からはかなり離れているし、これまで市有地の駐車場に停めてきたので、この駐車場は新鮮な発見だった。
古本いるふ

古本いるふさんで本を選び、車に戻ると、すでに陽は対岸に沈んでいた。
本は映画監督・実相寺昭雄の『星の林に月の舟』と澁澤龍彦の『高岳親王航海記』(文庫)を買った。どちらも読みたかった本だ。

富山湾は湾なので、太陽は海ではなく、海の彼方に見える対岸に沈む。みるところによっては滋賀県の琵琶湖のような景観に似ていると言えなくともない。海を挟んだ先に立山連峰が見える光景は不思議な風景だという人もいるらしい。我々には普通ではあるが。

山は西陽を浴びて、茜色に染まっていた
えもーしょなるな風景だった。
古いものの集積ということであれば、県内でこの中滑川に勝るものはないだろう。県内有数のあんてぃーくな都市、なめりかわと言ってよい
最近の休日といえば、
古道具屋「とらじ」で古道具を見て、買って、
「古本いるふ」で古書を読む。
そして、骨董「スヰヘイ」に立ち寄って、(現在休業中)
ハンモックカフェ「amaca」でランチ。
再び「古本いるふ」で本を選び、気に入ったら買って、旧宮崎酒造のカフェ「ぼんぼこさ」で本を読む。
失われた京都の百万遍や一乗寺、出町あたりで過ごした休日がなめりかわにはある。
あとは映画館と古着屋だろうか。出町座やほとり座のようなミニシアター系の映画が見られるスペースができると、なめりかわは古い街として完璧だろうね。採算って取れるのかわからないけど...無邪気に楽しむお客さんとして、そこは気にしないように、しかしなるべく本を買っていきたいと思う。明日からもこのような雰囲気が残り続けるように。
0 notes
Text
夜の残像/レオいず+凛月
※泉がモブ女と結婚済、(名前がついてる)娘もいます 凛月と泉の娘と、レオと泉のお話 「きーらきーら、ひーかる、おーそらのほーしーよ」 膝の上に乗った女の子が、澄んだ声で歌う。やはりその歌い方はどこか彼女の父親に似ていた。 かすみ、と名付けられたこの子は四歳になり、幼稚園にも通い始めた。柔らかく艶やかな黒い髪、それと同じ色をした瞳、高い鼻。容姿は母親そっくりだ。 この子がいるからこそ、余計に揉めているのだろう、と思いながら、鍵盤を優しく叩く。 この子の父親であり、凛月の高校時代からの戦友である瀬名泉は、三年前に結婚した妻に別れを切り出した。 妻は、養育費が、慰謝料が、と静かに反論していた。 原因がどこにあるのか、凛月は知っている。 妻は浮気をしている。その現場を見たことがある。若い男と腕を絡ませて、ホテル街へ消えていく背中をたびたび目撃した。 そして、また、泉も。 「……くまくん、」 「なぁに?」 丸くて大きな黒い瞳が凛月を見つめる。 「いつになったらおうちにかえれる?」 「うーん、おやつの時間になったら、かな」 泉の仕事がない日は、必ず離婚の話し合いに時間が潰される。その場合、大抵休業中の凛月がかすみを迎えに行き、凛月の家で時間を潰す。 ふぅん、とつまらなさそうに返事をして、首だけを動かして凛月を見上げる。 「ねぇ、くまくん、ピアノひいて」 「いいよ」 かすみが一番気に入っている曲を弾いてやる。滑らかで優しい旋律。優しい子守唄。 あぁ、この曲を書いているとき、彼はどんな気持ちだったのだろう。 この曲の楽譜を渡されたとき、彼はどんな気持ちだったのだろう。 ふわぁ、ふ、とかすみが腕の中で大きく欠伸をして、長い睫毛を伏せる。 馬鹿なふたり、と心の中で哀れむ。 ただ、口にはしない。 きっとふたりは、この子を置いて、凛月たちを置いて、どこかへ消えるのだろう。 すぅ、と寝息が聞こえてくる。その長い髪を撫でる。 初めてこの子に会ったとき、泉自身が言った。 ――――この子に、俺の血は一滴も流れてない。 そう、静かに告げた。 凛月は少し驚いてから、あぁ、でもそうか、と納得した。この女の子の容姿に、泉の面影はひとかけらさえなかったから。 凛月がかすみの手を握ると、泉はこう続けた。 ――――でも、面倒見てやってよ。身勝手なのは解ってるけど、くまくん、あんたに預けたい。 凛月はなにも言わなかった。ただ、この赤ん坊を見放してはいけないと思った。そうしなければ、自分と同じ道を辿ってしまうと、心のどこかで感じたから。 泉は、子どもを作った覚えはなかった。ただ彼女は、あなたとの子、と言い張った。凛月は面倒な女だねぇ、とコーヒーを啜りながら言ったが、泉は何も言わず、凛月に倣ってコーヒーを一口飲んだ。 泉の一番が彼女ではないのと同じように、きっと彼女の一番も泉ではない。ならなぜ結婚したのだろう、と考えたが、すぐに思考はぐるぐると混ざり合い、欠伸となって出た。 「……俺も眠くなっちゃったなぁ」 子ども特有の柔らかさと温かさを腕に抱いて、ピアノの蓋に頭を凭れ、凛月も瞼を閉じる。 耳に残った子守唄のメロデ��に身体を預け、そうして眠りに落ちていく。 「……くまくん、くまくん、」 肩を揺さぶられて、ゆっくりと身体を起こす。無理のある体勢で寝ていたからか、首と背中がぎしぎしと痛んだ。 「……セッちゃん、話終わったの?」 腕の中のかすみはまだすやすやと眠っている。その髪に鼻を埋めながら凛月を起こした泉を見上げる。玄関のドアは開けっ放しにしておいた、彼らのために。 うん、と擦れた声で泉は頷いた。 「……俺ら、離婚することにしたから」 甘い匂いがする。小さい子がいつも甘いお菓子みたいな匂いをまとっているのはなぜだろう。この香りも、もう離れていってしまうのか、なんて思った。 「この子はどうするの」 「……あっちが引き取る。本当の父親と、三人で暮らすって」 「やだ、」 子どもみたいな駄々が漏れた。ぎゅ、と腕に力を籠めると、唸りながらかすみが目を覚ます。 「んん~、くまくん……? なんでぎゅ~してるの」 「かすみ、」 「くまくん、おめめからみずでてるよ」 それから、かすみが顔を上げた。 「あ、パパぁ」 「かすみ」 「くまくん、ないてるのよ」 「……うん」 「よしよし、くまくん。いいこ、いいこ」 小さな掌が凛月の後ろ髪を撫でる。 「……くまくん、」 泉は、かすみの背中に回されたままの凛月の手を握った。少し湿っていて温かい手だった。 「ごめんね、ありがとう。くまくんにはずいぶん助けられちゃった」 「はは、セッちゃんがお礼言うなんてめずらしい、明日は雨だねぇ」 「バカ」 泉の手が離れていくと同時に、かすみも凛月の頭を撫でるのをやめた。 「……くまくん、げんきでた?」 「うん、出たよ。ありがとう、かすみ」 そう微笑むと、かすみは得意げに笑った。その表情や仕草は、やはりどこか泉に似ている。 「……かすみ、帰ろっか」 「うん。ママはおうちにいるの?」 「いるよ」 泉に抱きあげられて、それから凛月の方を振り向いた。凛月は立ち上がり、かすみの柔らかい頬を撫でた。 「かすみ、またね」 「ばいばい」 そして彼女は凛月の頬にキスをした。いつもの、別れの挨拶だ。 「……また電話する」 泉はそう言った。うん、と凛月は頷いて、かすみに手を振り返した。 がちゃん、と玄関のドアが閉まる音がした。 きっと、もうあの子に会うことはない。 大人のわがままに振り回されて、嘘を吐かれて、その事実を知ったら、きっとあの子は傷つく。そんなときに、傍にいてあげられる立場だったらよかったのに、凛月にそれはできない。 すとん、ともう一度椅子に座る。 どうか、神様、あの子は、俺とおんなじになんかしないで。 そう祈りながら、誰に聴かせるでもない子守唄を奏でた。 ◇ 部屋の隅に置かれた骨董品の黒電話が鳴ったのは、その日の、雨が降る深夜二時だった。 もしもし、と出ると、 「もしも~し」 という明るい声が返ってきた。彼もまた夜に強い。 「なぁに、『王さま』。こんな時間に」 そう言ったと同時に、窓にこつん、と何かが当たった。窓を開けて下を見る。 ダウンを着て、右手にスマートフォンを持った赤毛の男が、鼻を赤くして白い息を吐いた。その足元には小石が落ちている。 「……リッツ、ちょっと話そう」 夜闇の中で、彼の緑色の瞳が光った。どこか獣じみたその光が、凛月は好きだった。 「玄関の鍵、開いてるよ」 そう静かに笑いながら答えると、電話は切れ、彼は庭から姿を消した。そして、玄関のドアが開く、重たい音がした。 凛月が一階へ降りると、彼は広い玄関で濡れたスニーカーを脱いでいた。 「寒い」 「夕飯の残りのコーンポタージュあるけど。飲む?」 「うん」 リビングのソファーに座ったレオは、傍にあったブランケットを被って丸まった。まるで小さな子どもだ。そんな彼に、温めたコーンポタージ��を注いだマグカップを差し出す。ありがと、と彼は笑った。 ソファーの横に置かれた、小さなランプの鈍い橙色の光がレオの横顔を照らした。近くで見ると、前にはなかった皺が薄く刻まれているのが分かった。それでも三十路には見えない。 一口飲んだレオは、ふぅ、と息を吐いた。 「……まさか、戻ってくるとは思ってなかった」 ぽつり、とそう言えば、彼は困ったように笑った。そうすると顔に皺が寄って、やっと年相応に見えた。 「ほんと、なんで戻ってきたんだろうな」 レオは高校卒業後の十三年間、ほとんど海外で仕事をしていた。学院を出てからレオと再会したのは、これを含めてたった二度だ。手紙やメールが送られてきたこと、電話がかかってきたことを数えるのにも、両の手の指で足りる。 そんな彼が、三か月前に日本に戻ってきた。 庭のイチョウの木が黄色く色づいた、麗らかな秋の日の午後。かすみを膝に載せてピアノを弾いていた。四年前の結婚式に泉から手渡された楽譜を譜面台に立てて。 そのときだった。 「やっぱりリッツはピアノが上手いなぁ」 明るい声にハッとして顔を上げた。 広い庭に、スーツケースを片手に持ったレオが立っていた。何年ぶりかの再会に凛月は驚かなかった。庭とそこに立つレオの姿がひとつの絵画のようで、なんの違和感もなかったから。 「ふふ、だからこの子もピアノが上手になるよ」 目をまんまるくしてレオを見つめるかすみの髪に唇を寄せる。かすみは擽ったそうにして、レオはその子を見つめて優しく笑った。妹を持つ、優しい兄の目だ、と思った。 「その子の笑い方、ちょっとリッツに似てる」 「俺の子じゃないよ」 「知ってる。セナの子だろ」 「会ったの?」 と、訊いたと同時に、 「……レオ?」 という泉の声が聞こえた。レオは凛月とかすみの方を見て肩を竦めながらいたずらっぽく笑う。 「今な」 そうして、昔の恋人たちも再会を果たした。それから二か月後のことだ。泉とその妻の雰囲気は一層悪くなり始めたのは。 レオはコーンポタージュを飲み干して、空になったマグカップをローテーブルの上にそっと置いた。 「なんで来たの」 「ん~、リッツのところに行かないと、って思ったんだよ」 相変わらず、と笑えばレオも笑った。そして、急に視界がぼやける。 「……『王さま』」 「なに」 「あの子は、かすみは、……どうなるの」 レオは、何も言わなかった。柱時計の振子が揺れる音だけが静かに響く。 「……ごめん、リッツ」 そして彼は立ち上がり凛月の傍に来て、自然に抱き締めた。 セッちゃんも、『王さま』も、わがままだ。 そして自分自身も、わがままだ。 あぁ、俺も人間みたいだ、と思った。わがままで、貪欲で、浅はかで、寂しがりな。涙まで出てきてしまう。 うぅ、ぐ、と詰まった声と嗚咽が漏れる。 これから、膝の上に感じる重みも、鍵盤を叩く小さな手を見つめることも、甘い香りを嗅ぐことも、別れ際のキスをすることも、なくなる。 彼女の未来に、幼い頃の自分を重ねていた。 大人のわがままに振り回されて、嘘を吐かれて、その事実を知ったら、きっとあの子は傷つく。幼かった凛月が、そうであったように。 レオは凛月の涙を拭った。繊細さのかけらもないその拭い方は昔から変わっていなくて安心した。 「……『王さま』、もう、帰りなよ。夜は危ないよ」 「うん、そうだなぁ」 下手くそな作り笑いを残して、彼は庭から外へ出た。 ダウンの背中が夜闇に溶けていくのを、凛月は二階の窓から見つめていた。レオは一度振り返った。街灯の下で、彼のエメラルドグリーンが光り、手を振って、また前を向いて歩き出した。 どうか、神さま。意地悪するのは俺だけにして。みんなには優しくしてよ。 夜に消えた残像を見つめながら、懇願するように、彼が作ったあの子守唄を口ずさむ。 ◇ 201608 https://touch.pixiv.net/novel/show.php?id=7112101
1 note
·
View note
Text
やっときたインド #01
インドにはいつか行ってみたかった。今回FabLabのアジア地区のイベントがムンバイとコーチンで開催されることになって、これはいい機会!ということでおやすみをもらって行ってきました。高校の頃に「河童が覗いたインド」を何十回も読んでからいつか行ってみたいと思っていたけど、なかなか踏ん切りが付かず。やっと行けることに。インドで気になったものを紹介していく全2回の1回め。

ムンバイの朝。見かけたトラックが派手だなあと思ったらだいたいどのトラックも派手だった。

大学のカフェテリア。左奥のキャッシャーで注文して支払い、もらったレシートを右のサービスと書いてるところのおじさんに渡して商品をもらう。チャイ10ルピー。他の物は何があるかわからないので頼めなかった。このシステムは結構あちこちで見かけた。道端のドライブインとか。

教室のエアコン。寒い。設定温度15度とかにしてるでしょ?それに4連装。

どこでも犬が寝ている。あまり起きてる犬を見なかった。大抵寝ている。

わぁ〜!本当に牛が道端にいるよ!

最寄り駅のChembur駅では猫が駅員だった。「無賃乗車はダメだにゃ」記念撮影を日本台湾チーム

長距離列車のターミナルの一つ、Lokmanya Tilak駅のチケット売り場。右側に「予約」とか書いてあるがそっちに行くと予約を代わりに取るおじさん達の餌食に成る。自分はちょっと彼らに余分に取られた。でもまあいいや。

日本、台湾、ベトナム連合で行った初日の晩御飯。HOTEL SUNNYで集合ということでUberで向かったんだけどHOTELとは思えないこじんまりとしたお店だったので、本当にここで良いのか不安になった。こっちでは食堂もHOTELなのかもしれない。16人くらいいたので入れるか不安に成ったけど、店の奥にエアコン&ファミリールームと言うのが幾つかあって余裕で入れた。見た目よりずっと中は広かった。味は美味しかったけど、予期しない甘さのものもあったり。焼き魚が生だった疑惑があって一人お腹を壊したみたい。

Chembur駅近くの夜店。23時くらいまで。賑やかで良い。何か買ってみたかったけどこの時は2000ルピーとかしか持ってなくて無理だった。両替所は行く前に報道で見たよりは新札切り替えの行列が減っていた。ATMも使えたけど2000ルピーしかないとかはあった。

夜の街を牛車が来たので興奮して写真撮ったけどなんかブレた・・・。このツノすごいわ。

朝早く、他の店がまだ閉まっている中店を開けていた鶏肉屋さん。生きている鶏と、肉になっている鶏。

インド名物のめちゃ混みの電車。しかし日本で鍛えられた我々には大したことはなかった。問題はドアが閉まらないのでドア付近に乗ると落ちる可能性があることだ。

日本、台湾、ベトナム、フィリピン連合で電車に乗って夜にムンバイの中央駅、昔はビクトリア駅と言った場所へ。乗ってきた電車と記念撮影。

列車を待つ人でごった返す駅。インドの女性の服って綺麗だよなと。

ライトアップされるムンバイ中央駅。格好良かった。

中央駅付近にあった、ちょっとだけ高級なレストラン。最後清算が終わった後でチップを要求されたので、仕方なく払った。先に言ってよw

渋滞では隙間が少しでもあるとバイクやリキシャ、下手すると車が突っ込んでくるのでここでは運転できないわ〜。

ジュースとアイスクリームの屋台。ジュースはガラスのコップで出してくれるけど、洗うのは足元の緑と白のバケツに漬けるだけ。

ムンバイの空港の脇は巨大なスラム街。夜は電気が点いていたりするのでどうやって電気を引いてるのか気になるところ。

コーチン空港近辺は森が多かった。ムンバイでは森は見なかったように思う。

コーチンの食堂の店先で。こうやって見せられると食べたくなる。

ので、食べる。「おいおい外人だぞ!」みんなジロジロ見てくる。こちらに興味津々という感じ。美味しかった。彼らはチャイとパン一個とかをかじってすぐ出て行くがどんどん入れ替わる。人気の店なのかな?

八百屋さん、美味しそうだった。

魚屋さん、チャイニーズ・フィッシュネットがこの辺りでは盛んらしいのでそういうので取れたのかな?

インドでうまくいってるといえば、スズキ。現地ではMULTI・SUZUKIという名前で合弁している。大学の頃にタダでもらって乗っていたアルトの拡大版がまだまだこちらでは現役。懐かしい。

コーチンでは禁止されたココナッツのお酒TODDYをリキシャを雇って飲みに行った。ちょっと炭酸。飲みやすい。ちょっと発泡の日本酒みたいな感じ。赤い柄の濾し器で漉しながらコップに注いで飲むらしいが、テーブルに直に置いてあるので漉した方が汚くなる気がするのです。フィリピンにも同様のTUBAというのがあるらしい。

店の奥で作っているらしく見せてくれた。左下の青い大きなバケツにココナッツの汁を入れて1日置いたら瓶に入れて出来上がり。えっ?!1日だけ?詳しいことが不明。浜松の竹さんが飲みに行きたがってたけど15kmとか離れていて躊躇していたので、「今行けば15kmだけど帰国したら何千kmですよ。」とそそのかして同行。自分が行きたかっただけw

可愛い色の3輪車。自家用なのかな?

道端のお店。Uncle JOHNが目を引くが、上の看板を見ると、インドはジオン軍の勢力下であることがわかった。

門扉に溶接で名前を付けている家をコーチンには何軒か見かけた。結構格好いい。日本のようになんでも既製品だとこう言うのは贅沢ですよね。

フォート・コーチンのホワイト・ジュー地区の骨董屋さん。日本から買い付けに来るそうな。ホーローのカップくらいなら記念に買ってもいいかなと思ったけどバカバカしい値段だったので辞退。その値段だったらすげーいいの買えるよ。日本で。

バイク・ドクター。救急車の代わりにお医者さんがバイクで駆けつけるようなサービスもあるらしい。

ロイヤル・エンフィールド。クソ格好いい。最近のバイクに混ざって結構いっぱいいて、わざわざこれを選ぶインド人が結構いるのが嬉しい。

ポスト。昔の日本のにちょっと似てる。

やっぱ乗らないとね♫ メーターで走ってくれたらラッキー。値段交渉になるとしんどい。

中古の建具屋さん。こう言うところで仕入れられると雰囲気ある窓とかドアを家に付けれるのかなあ。運賃がひどいことになるかな?

コーチンの街中にあちこち、DYFIって書いてあってなんなのかな?と思ったら共産主義の大会が今度このあたりであるんだとか。でそのイベントの名前らしい。なので赤い星もついてる。
続く。
2 notes
·
View notes
Text
サニーサマーレイン
☂8月23日
「ゲームセット!ウォンバイ青春学園、越前リョーマ」 歓声が、遠い残響のように聞こえた。 真っ二つに割れたボールが足元でひっくり返っている。それを茫然と眺めているうち、勝つことしか考えられず熱を持っていた頭が、少しずつ冷えていった。全身から力が抜けて、その場に立ち尽くす。はー、と勝手に息が洩れた。 「ねえ」 対岸から呼ばれる。越前くんが手を差し伸べていた。 重い足を動かして、ネット際に歩み寄った。 こうして対戦相手とまともに握手ができるのはいつぶりだろう。五感を失い這いつくばった姿を見下ろすのがお決まりだった。今までのろくに顔も覚えていない選手たちを思い出しながら、手を伸ばす。 手のひらを強く握られ、俺も同じぐらいの力で返した。越前くんは目の縁を尖らせる。試合は終わっても、瞳の中には火が点っていた。ぎらぎらした目で俺を見据えて、それから、笑顔を弾けさせた。 俺より少し小さなボウヤの手は、俺と同じぐらい節くれだっていた。それだけ多く、ラケットを振って、ボールを打ったということだ。血が噴き出しそうなほどの努力を、まだ成長途上の体で重ねてきた。そういうことだ。 今さらながら、とんだ化け物を相手にしていたことに気がつく。もっとも、試合中の彼は化け物というより、天使とか神様の申し子とか形容した方がしっくりくるのだけれど。今だって、俺に向ける笑顔はひたすらに温かくて、やさしい。 握っていた手を離した。彼いわく「楽しいところ」へ俺をいざなおうとする手を、今はまだ取ることができない。 越前くんは、しょうがないな、という顔で俺を見て、仲間のもとへ駆けて行った。待ってる。そう、その背中に言われているような気がした。 立海のベンチへ戻ると、対岸のお祭り騒ぎとは打って変わって、ひどく沈んでいた。みんな俯いて、悲痛な面持ちをたたえている。嗚咽を隠しもせずに泣いている部員もいた。 誰も俺を見ようとはしな��った。ただひとり、真田を除いて。その真田も、瞳がゆらゆらと揺れている。 しばらくして、迷子のような足取りで真田は俺に近づいてきた。おずおずと差し出された手に、ラケットを託す。 「準優勝だ、幸村」 真田がそう言って俺を見つめた。 「……負けたんだね」 頭では分かっている筈なのに、負けた、という言葉がただの音としか捉えられなかった。三文字は俺の心の中をうわすべりして、霧散した。 代わりに、真田の眉間に深い皺が寄る。負けという言葉を使わなかったのは、真田なりの気遣いだったんだと気づいた。もしかしたら、真田自身だって聞きたくなかったのかもしれない。 それでも、真田は深く頷いた。 わあ、といっそう大きく青学が湧く。越前くんが胴上げされていた。青空めがけて、高く、たかく。 あれは、去年までの俺たちの姿だ。優勝だ、と真田が俺に告げる姿が頭をよぎる。普段の落ち着いた様子からは想像できないほど浮かれた真田の声。そして、俺も。頬が熱くなるのを感じながら、笑顔で待つ仲間に飛びつくのだった。 これ以上、何を言ってどうしたらいいのか、分からなくなった。 「両校、整列してください」 審判の号令で、動けなくなっていた体を半ば無理やりに動かすことができた。相手に情けない顔を見せてたまるものかと、負けず嫌いの部員たちは唇を引き結び、厳しい顔をした。 青学と礼をし合って、それから、ふと客席を見る。父さん、母さん、お祖母ちゃん、妹。やはり、悲しそうな顔をさせてしまった。 感傷にひたる間もなく、すぐに表彰式が始まる。 式の間、テニスコートはおごそかに静まりかえる。聞こえるのは、選手を称える拍手ばかり。割れるようなそれに包まれながら、誰もがひと夏の軌跡を振り返り、噛み締める。 「準優勝、立海大附属」 前へ出ようとすると、背後から遮られた。 「俺が行く。いいな」 問いかけではなくて、決まったことを確認する口調だった。俺が答えもしないうちに、真田は壇上へと歩み出す。 その眼前に、盾が差し出される。にぶい銀色をした盾が。真田にとっては、突きつけられた、と言ってもいいぐらいかもしれない。 しかし真田は表情ひとつ変えず、それを受け取った。両手に抱えて、いつも以上に背中を真っすぐに伸ばして、頭を垂れた。 「優勝、青春学園」 続いて、手塚と大石が壇上に上がる。まだ高い太陽に照らされて、手塚の持つトロフィーも、大石が掲げる優勝旗も、さんさんと輝く。 俺の手の中は空っぽだった。真田は、盾をじっと見ていた。振り返ると、赤也が、泣きそうになりながら表彰台を見上げていた。 赤也をはじめ、レギュラーとして戦うのは初めての部員も多かった。初めての夏を、胸を張って終わることは叶わなかった。 ぜんぶ、俺のせいだ。 「真田、やってくれ」 だから、ミーティングを始める前に、そう告げた。 周りにいた部員たちが、血相を変える。でも、真田はもともとそのつもりだったのだろう。ためらいも滲ませず、こくりと頷いた。 「遠慮はせんぞ」 「掟に遠慮も何もあるものか」 打ちやすいように、真田の正面に立った。真田は手首を握り、調子と覚悟とを整える。 俺と真田に気づく部員が増えるにつれて、ざわめきも大きくなった。 「静かにせんか!」 真田の一喝で、ほぼ全員が俺たちに視線を注いだ。却ってよかったと思う。証人が多い方が、けじめをつけるにはふさわしい。 「歯を食いしばれ」 真田が手のひらを振りかぶる。焼きつけておくために瞼を見開いた。 病室で俺を打った姿が重なる。絶望の淵から俺をすくい上げた、その手、その熱さ。 今さらになって、走馬灯みたいに記憶がよみがえってくる。本当はおそろしくて仕方がなかった手術。俺がいれば、と悔やんだ関東大会の敗北。死に物狂いでリハビリをして、やっと踏みしめた緑の芝生。 長い、本当に長い夏だ。 打たれる瞬間、どうしても反射で目を閉じてしまう。 頬に触れたのは、熱い風だった。たったそれだけ、だった。 目を開ければ、あともう少しで俺に届きそうだった真田の手が、ぱたりと落ちる。 「……できん」 「……どうして」 「理由がない」 聞いたことがないぐらい、声が震えていた。黙って、続きを促す。 「お前は負けた。だがお前の戦いに、驕りも油断も、微塵も感じられなかった」 真田の呼吸が徐々に乱れていく。 「むしろ……っ」 とうとう、言葉はただの吐息に変わった。真田はそれでもどうにか言葉を継ごうとして、面持ちをぐしゃりと歪ませた。涙がひとつ零れる。 「……っ、すまないっ」 真田は片手で瞼を覆って、俯いた。それでも抑えきれない涙が、頬にいくつもの線を描いていく。 ふくぶちょう、と赤也がつぶやく。真田よりもっと大粒の涙が、そのまなじりからぼろぼろと落ちる。咄嗟に赤也をかたわらで支えたブン太も、ともすれば一緒に崩れてしまいそうだ���た。 水面に石が投げられたみたいに、波は広がった。気がつけば、仁王までもが、目の端を赤くし鼻をすすっている。 俺の敗北がどれだけ大きいものだったか、ようやく実感した。真田に打たれて終わりにしようとした、自分の浅はかさも。 「すまなかった」 自然と深く腰が折れる。 やめてください、そんなことしなくていい、と何人かが叫んだけれど、しばらく頭が上げられなかった。 部員たちの嗚咽が、もの悲しく降ってくる。こんなにも苦い思いを味わわせてしまったことに、ただただ詫びることしかできない。 「幸村、もういい」 真田に体ごと引き上げられて、抱き締められた。痛みを感じるほど、きつく。 体を震わせて咽喉を引き攣らせて、真田は泣く。覆うものが何もなくなったせいで、たちまちにジャージの肩が濡れた。幼い頃ですら、ここまで泣く真田を見たことがない。 俺は、泣けなかった。 ああ、と思わず嘆息した。いたたまれない。 俺の中で何かが欠けている。申し訳ない、それしかなかった。こうして目の前で真田が、みんなが、俺のために泣いてくれてもなお、一緒に泣くことができない。他人事みたいに茫然としている。 取り巻く空気が湿度を増す中で、目が乾く、とすら思った。
☂8月24日
全国大会の翌日は焼肉屋で打ち上げ、というのが立海のはるか昔から続く伝統だ。 レギュラーたちは、ものすごい勢いで肉に食らいつく。瞼さえ腫れていなければ、昨日あんなに泣いていたのが嘘みたいだった。 ウーロン茶とジュースで乾杯をして、誰もが雰囲気に酔っていた。負けたのに、などと野暮なことは言わない。 目の前では、ちょうどブン太と赤也のカルビ争奪戦に終止符が打たれたところだった。赤也は、覚えとけよ、と空の取り皿を抱えて涙目で言い残し、蓮二に席替えをお願いしに行った。 俺はといえば、ジャッカルばかりが焼かされているのがかわいそうで、それを手伝っていた。 「幸村くんさあ、なんで真田と仲いいの」 真田が別のテーブルにいるのをいいことに、ブン太がなかなかに突っ込んだ質問をしてきた。 「あ、別に変な意味じゃなくて。言っとくけど俺あいつのこと嫌いじゃねーよ。苦手だけど」 「おい」 あまりにもブン太が正直なのを、ジャッカルが咎める。俺は、あけすけだけどわりと愛のこもった言い方だと受け取った。 「幸村くんと真田、好きなもんとか何ひとつ被ってなさそうじゃん」 「実際、被ってないね。一緒に遊ぶと時々困る」 印象派の美術展に行ったとき、終始真田は首を傾げていた。反対に、骨董の壺だらけのお店に連れて行かれたときは、俺の目にはどれも同じに映って、盛り上がる店主と真田の横であくびを噛み殺していた。 「好きなものがはっきりしない頃からの幼馴染だから……かな」 「だったら趣味は似るような気もするけどな」 「俺とジャッカルもやってたゲームとか同じだぜい」 たしかに、目の前のダブルス以上に俺と真田の付き合いは長い。ただ不思議と、俺のガーデニングも真田の剣道も、一緒にやろうと誘い合ったことはなかった。 俺と真田が一緒にすることって、と思い浮かべてみたら、答えはあっという間に出た。 「テニスはふたりとも好きだと思う」 遊んだ日の締めくくりには、お互いの退屈を晴らすため、テニスコートへ赴くことも多い。 そう言うと、何故かきょとんとした顔をされた。 「……好きなんだ」 「好きじゃなかったら部長なんかやらないだろ。もともと俺は部長向きのたちじゃないよ」 全体を俯瞰して見ることはできても、最後には自分が興味のあるところばかりに目が行ってしまうし、集中したい。もっとひどい話をすると、入院というブランクはあれど、未だに全部員の名前を覚えていない。覚える必要がないとも思っている。 大好きなテニスで三連覇をすることしか考えていないような人間が、部長に選ばれた。理由はいたって単純だ。実力主義のこの学校で、いちばん強いのが俺だったというだけ。 部長になってからは、ひたすら好き勝手にやらせてもらった。実力で周りを黙らせてきたけれど、さすがに運動部らしいしがらみを無視する訳にもいかなかったそれ以前とは違って。 誰に対しても分け隔てなく厳しくできる真田や優しくできる蓮二が隣にいなかったら、この部はどうなっていただろう、ということをよく考える。 「真田の方が部長に向いてると思う」 ジャッカルもブン太も勢いよく首を���に振った。まあ、短気ですぐに手が出るところは玉に瑕だろうか。 「なんで真田じゃだめなんだい」 「怖い」 ジャッカルのシンプルな即答に、思わず笑った。 「ブン太は?」 ううん、とブン太は唸る。 「……ひとりでなんでもしようとするから」 急に声音が真剣になった。ああ、とジャッカルもいささか引き締まった顔をして、頷く。 「時々一緒のチームでいる意味が分かんなくなるんだよ。勝ちたいって気持ちとかは一緒だと思うんだけど、もうちょっと、こう……」 「頼ってほしいよな」 「それ!」 ジャッカルがしみじみと言うのを聞いて、昨日、真田の試合が終わった後、断られてもアイシングを持って追いかけていった姿を思い出した。 「手塚に勝った後、あいつひとりで泣いてた」 「へえ、そうだったのか」 次の試合が始まるのも見届けずにどこかへ行ってしまったのに、そんな訳があったとは。手塚は、真田にとって俺の次に倒すべき相手だった。長年の雪辱が晴れて、感極まったのも無理はない。 「嬉しいのは俺たちも同じだし、一緒に喜びたかったよな」 「そうだね」 相槌を打った途端、ブン太が俺を見て目を三角にする。少したじろいだ。 「なに」 「幸村くんもそういうとこ、あるぜ。俺基本的にお前のこと好きだから、もっと頼ってくれたらもっと好きになるかも」 冗談めかしてウィンクされる。 「あ、もう焼けてる」 すぐに興味を移したブン太は、ロースを俺の小皿に放った。すっかり食べ物のことを忘れていた。 「まあ、明日からすぐに俺たちにも任せろとまでは言わないけどさ。せめて真田とぐらい分け合ってみたら」 「……うん」 やけに暗い声が出た。 「わり、なんか説教っぽい。引退だし許して」 それにすぐ気づいたブン太は、もう一度ウィンクして、ぺろりと舌を出す。 入院中、誰よりもみっともない姿を真田には見せた。時には縋ったこともある。いや、縋ってしまった。そう思っているあたり、ジャッカルとブン太に言われたことは的を射ている。俺も真田も、本当の弱みは誰にも見せたくないんだ。 「んだよジャッカル、にやにやして」 ブン太の声で、引き戻される。 「好きなものは被ってなくても、似てるんだな。幸村と真田」 「……俺がどうかしたのか」 「げ」 いつの間にか、真田がブン太とジャッカルの間、赤也が座っていたところに立っていた。 向こうのテーブルを見ると、蓮二がひらひらと手を振る。その隣、安息の地で、赤也がブン太に取られた分を取り返そうと、がつがつと肉と米をかき込んでいた。たぶん、さっきまで真田が座っていた席だ。甘やかされてるなあ、赤也。 むっとした顔の真田に、とりあえず座るよう促す。 「俺も真田もテニスが好きだよねって話をしてた」 助かった、という視線が目の前のダブルスから寄越された。別に悪口を話していた訳でもないし、堂々としていればいいのに。 「うむ」 真田が肯定したのかただ単に相槌を打ったのか、よく分からなかった。少なくとも、機嫌が直ったから、悪い気はしなかったはずだ。
☂8月25日
家族に手間も心配もかけたくなくて、ひとりで行ける、と言ったものの、案の定入口で足が竦む。病院独特の消毒の匂いとけぶった白色。かつてここに閉じ込められていた記憶を無理やりに引きずり出されて、苛まれる。 主治医からは、絶対に今日来てくださいね、と念を押されていた。二学期から大手を振って学校に通うためには、今日中に検査を受けなければならないらしい。 通院を減らして全国大会に集中したい、というのは本音でしかなかったけれど、検査から目を背けるための口実でもあった。 これは、健康というお墨付きをもらうためだけのものだ。一昨日まであんなに激しいスポーツをしていたくせに、何を怖がることがあるんだ。自分に言い聞かせても、怖いものは怖いのだった。 どうにか一歩踏み出そうとしたそのとき、狙ったかのようなタイミングで電話が鳴った。ディスプレイには真田の名前。 長くかかる用件のような気がしたものの、つい通話ボタンを押す。真田の声を聞けば、きっと少しは楽になれる。逃げ場にしようとしていることは悟られないようにしなければならないけれど。 「部の引き継ぎの件で相談があるのだが」 やっぱり、長めの用件だった。真田が何もなくて連絡を寄越すことはほとんどない。 「ごめん、これから検査なんだ。今、病院に着いたところ」 「む、すまん。あとでかけ直す」 もう切るのか。少しがっかりしたことは、おくびにも出さない。 「夕方には終わるから、俺からかけるよ」 じゃあね、と言うと、真田が言葉を継ごうとする気配がした。 「ご家族はそこにいらっしゃるのか?」 「ううん、用事があるみたいだったから付き添いは断った」 「ではお前ひとりか」 「そう」 ごそごそと何かをしている音が続いた。 「すぐに向かう」 びっくりして、すぐに返事ができなかった。 病院に足を踏み入れる憂鬱も、検査を受けることをどうしようもなく恐れているのも、きっと真田には見透かされている。普段はにぶいくせに、どうして分かってしまうんだろう。 「……予約の時間に間に合わなくなるよ」 側にいて、不安をやわらげてほしい。わがままが口から零れそうになるのを抑えて、言った。 せめて真田とぐらい分け合ってみたら。昨日のブン太の台詞が頭をよぎった。やっぱり、すぐには無理だ。どうもこの幼馴染の前では、負けず嫌いの俺が色濃く出てしまう。 電話の向こうで小さく唸る声がする。しばらく、真田は考えているようだった。 「大丈夫だから」 真田だけに言うつもりが、俺自身にも言い聞かせている。 「……待っている」 やけにやさしい声。 「ありがとう」 今度はなんのためらいもなく、言葉が口から零れた。 「は、早く部のことを話し合わなければならんからな」 照れたのか、取ってつけたことを返してくる。下手くそだなあ。 あらためて真っ白な建物と対峙する。俺を暗い気分にさせるだけだった白に、ほのかな明かりが差して見えた。消毒くささも、さっきよりずいぶんとましなような気がした。 「もう、大丈夫」 電話を切って、つぶやく。 ほんの少し軽くなった足取りで、病院の自動ドアをくぐった。
部屋を次から次へと移動して、腕や足を動かしたりよく分からない機械で何かを計測されたりしているうちに、検査はすべて済んだ。意外と早かった、と体感として思う。入院中にも何度か受けたものばかりで、説明されなくてもするべきことが分かるぐらいには慣れていたのが大きいかもしれない。 残るは、主治医の問診だった。これですべてが決まる。気が尖っていくのをなだめながら、先生の向かいの丸椅子に腰かけた。 「これから普通に学校に通っていいですよ」 「部活……テニスをしても?」 「それはもうしちゃっただろう」 カルテから顔を上げて、先生は困ったように笑った。君の回復力には本当に驚かされる、と付け加えて。 「全国大会、どうだった?」 「準優勝です」 「ええ!すごいね。おめでとう」 驚いてくれたので、俺も愛想笑いを返した。俺たちにとって優勝が当たり前だったことを知らない人にとっては、こんなものなんだ。 「きちんと結果が出るのは、五日後。異常がなければ電話でいいかな」 「はい、お願いします」 ほら、何も怖がることなんてなかった。胸を撫で下ろし、そっと息を吐く。
病院の最寄駅で両親に結果を知らせたあと、真田にも電話をした。 「待たせたね」 「いや」 一拍置いて、どうだった、と訊かれる。 「ちゃんとした結果はまだだけど、普通に学校に行って生活していいって」 「そうか。では、テニスもできるのか」 さっきの俺と同じ質問がすぐに投げられる。真田も怖いのか、語尾がわずかに震えていた。 「テニスも問題ないみたいだ。試合にももう出ちゃっただろって先生にはちょっと呆れられたよ」 「そうか」 さっきと同じ相槌でも、声が違っていた。安堵したのが明らかだった。 「心配させてすまないね」 「気にするな」 さて、と言って、また声音が変わる。今度は副部長の声。 「蓮二に聞いたのだが、次の代は仕事の割り振りを見直したいそうだ」 「了解。蓮二のことだから、もうプランまでできてるんだろ」 俺も部長らしく返してみる。 「ああ、お前が検査を受けている間にその確認を取っていた。今よりずっと効率的にできると言っていたぞ」 「三人で会って話そうか。俺はいつでもいいから」 「俺も午後なら構わん。蓮二の予定次第で調整しよう」 それから一言ふた言を交わして、電話を切った。 部長の仕事、入院でほとんどできなかったけど、まとめておかなきゃな。あれこれと思考しているうちに、電車がホームに入���てくる。 乗車して初めて、ずいぶん長い間ホームに立っていたことに気づく。つい最近まで駅ですら怖いと思っていたのに。 こうやって、ひとつひとつ、平気になっていく。
☂8月28日
宿題と部の仕事の合間に、庭をいじったり絵を描いたりクラシックを聴いたり詩集を読みふけったりと好きなものにまみれていたら、あっという間に二日間が過ぎた。いくら好きといっても延々と続けていられるものでもなくて、最後の方はブラームスさえも俺の退屈を満たしてはくれなかった。 ただ、テニスだけはしなかった。決勝の日からずっと、ラケットもボールもバッグの中で眠っている。 少しの空き時間があればテニスをしていた俺にとっては有り得ないことで、家族も、口には出さずとも不思議そうな顔をしていた。 そういえば、テニスをしないとなると全然真田に会わない。三日空くというのも有り得ないことだ。 久しぶり。目の前の真田に、頭の中で言ってみた。 真田は眉間に皺を寄せて、蓮二が作ってきた資料とにらめっこをしている。超優秀な参謀の立てたプランに欠点なんてないに決まっているのに、ばか真面目にひとつずつ検分しないと気が済まないんだ。ちなみに俺は十分以上前に読み終えた。 「精市、何か飲むか」 「じゃあ、アイスティ��。ありがとう」 蓮二は俺の分のコップも持って、ドリンクバーへと向かった。 「そのプラン、もっと改善した方がいいところとかあった?」 進捗確認も兼ねて、真田に話しかけた。 「今のところないな。さすが蓮二だ」 「そう。……真田、最近どうしてる」 「もっぱら道場にいる」 顔を上げないまま、真田が答える。 「飽きない?」 「……お祖父様には絶対に言えんが、さすがに飽きてきたな」 真田にとっては後ろめたいことなんだろう。誰に聞かれる心配もないのに声を潜めるのがおかしかった。 「だよね。いきなり夏休みって言われても何したらいいか分からないよな」 テーブルに残った水滴を指先ですくって、アコーディオンみたいに縮まったストローの包み紙に垂らす。包み紙はゆっくりと間抜けに伸びていった。こんな風に緩慢に、俺の夏休みは終わっていくのだろうか。 いつの間にか俺の手なぐさみを見ていた真田に、行儀が悪い、とたしなめられた。 「いっそ旅行にでも行くか」 真田が資料を置いて、切り出す。唐突すぎて、言われたことを理解するのに少し時間がかかった。 「いつ」 「明日から二泊三日でどうだ。母の田舎にあてがある。旅行といっても何もないから、観光はできんが」 「また急だな」 と言っても、特に予定がある訳でもない。宿題もあと数ページ。今日中に終わらせられる。 「でも、行けるな」 「何の話だ?」 ちょうどいいところに戻ってきた蓮二を誘ってみるも、すぐに首を横に振られてしまった。 「せっかくだが、家庭教師をしなければならない」 「なに、赤也かっ」 真田が吼えそうになったので、どうどうとなだめた。唯一の二年生として俺たちについてきてくれた赤也は、特に宿題どころじゃなかっただろう。間違っても勉強の得意な子ではないけれど、多少目を瞑ってあげなければ。 それに、旅行をするにあたって、もっと大変なことがある。 「俺と真田のふたり?」 「ああ」 「ふたりきり?」 「それがどうかしたのか」 何を今さら、という態度を真田は崩さない。がっかりした。こう、照れたりとかなんかあるだろう。 「恋人ができたらそんな態度じゃだめだよ」 「たわけたことを」 ふん、と真田が鼻を鳴らす。だからそうじゃなくて。 「おい、いつまで俺はお前たちのやり取りを聞いていればいいんだ?胸やけがしてきたぞ」 甘いな、と冷ややかに言う蓮二の声で我に返った。一体真田に何を期待してるんだ、俺は。 蓮二が持ってきてくれた紅茶を口にして、頭を冷やした。 「それで、来るのか来ないのか」 「たぶん行けるよ」 真田が資料に没頭している間に、家族の了解を取りつけるべく、メールを打った。数分後、あっさりと明日からの真田との旅行が決まった。
☂8月29日
電車を乗り継いで四時間と少しで、その町に着いた。車だと早いのだが、とさすがの真田も疲れた顔で言い訳をした。 俺たちの宿は、ときょろきょろしている間に、真田はどんどん前へ進んでいった。慌ててその隣に並んでついていく。 住宅街を抜けて、さらに奥へ。駅に降りたときから田畑が多く見られるのどかな場所だったのが、もっと緑が豊かになってきた。 ようやく、真田は立ち止まった。 「……これ登るんだよな」 「一時間ほどの辛抱だ。徒歩ならこちらが近道だぞ」 荷物は軽めに、と言われた理由が一瞬で分かった。うっそうと茂る木々の間に、とてもよく言えばハイキングコース、見たままで言えばけもの道が、山奥へと続いている。 旅行というかもはや合宿だ。今年は参加できなかったから、ちょうどいいかもしれないということにしておこう。 そんなことをのんきに考えられていたのは初めだけで、しばらくすると家を出るときにもらったお小遣いに頼りたくなった。山の中で暑さはやわらいでいるといえど暑いものは暑いし、しかもこの悪路。検索してみようと携帯電話を見て、仰天した。まさか、今どき電波が通じなかった。もともと必要なとき以外は使わないから、構わない。けれど。 「本当にふたりきりじゃないか」 思わずつぶやく。 「何か言ったか」 「なかなかすごいところに来たなって、それだけ」 「あまりに田舎で驚いたか」 からからと真田は笑う。そうじゃないけど、まあいいや。なんて、やっぱり俺は何を思ってるんだろう。 喋る余裕もなくもくもくと歩いているうち、整備された大きな道に合流した。あと十五分だ、と真田。 道中、二泊分の物資を調達するために、個人の商店に立ち寄った。色あせた看板と外壁。店内の電気が点いていなかったら、見落としてしまいそうだった。 おそるおそる入店すると、失礼ながらお店の見た目に反して、商品はきれいに並べられ、埃のひとつも落ちていなかった。 「すみません」 真田が声をかけると、しばらくして、奥からお婆さんが出てきた。歳はうちの祖母と同じぐらいだろうか。化粧っけがなくて人がよさそうで、いかにも田舎のお婆さん、という見た目だった。 お婆さんはレジ越しに真田を見て、ぱちぱちとまばたきをする。 「あなた、真田さんのところの。大きくなって」 「お久しぶりです」 今度は俺を見る。 「あなたはお友達?」 「はい、幸村と言います」 「……真田と幸村」 含み笑いをされた。 「げんちゃんから何回か聞いたことがある。テニススクールのお友達でしょう」 「今は同じ部活ですよ」 げんちゃん、と呼ばれた真田は、俺に聞かれたのが嫌だったのか、少しぶっきらぼうな口調になった。 お婆さんは、自分たちで食事を作るならあれがいいとか今の季節はこれが美味しいとか、一緒に店内を回って教えてくれた。さらに親切に、真田にお菓子を握らせたり、お友達にも、と言って俺にもくれたり。 籠の中が充実してきたので、買い忘れはないだろうか、ともう一度売り場を見回す。あるものに気づいた。 「これやろうよ」 花火を手にして、真田の前に持っていく。 「ふたりだけでするのか?」 「まだ今年はやってないんだ」 「ご近所の迷惑にならないだろうか」 眉間に皺を寄せて、真田は渋る素振りを見せた。 「いいだろ、げんちゃん」 不意打ちだったらしく、言葉に詰まる。作戦成功だ。 「幸村、後で話がある」 「もう季節も終わりだから安くするよ、げんちゃん」 お婆さんに勢いを削がれたらしい真田は、こくりと頷く。つい笑ってしまうと、俺と違って狙った訳ではないお婆さんは、不思議そうな顔をした。 会計を済ませると、お婆さんはお店の外まで出て見送ってくれた。 「げんちゃん」 ぽつりと言ってみただけで、真田がすごい勢いで振り返る。 「間違っても学校で言うなよ」 「いいじゃないか、かわいくて」 目の端が吊り上がってきたので、からかうのはそのぐらいにしておいた。
真田のお母さんのお祖父さんとお祖母さん、つまり曾祖父母が住んでいたというその家は、今では別荘のように使われているらしい。 床に荷物を置く前に、手で埃を払う。 「さすがに二年来ないと、埃は積もるな」 「掃除すればいいよ……あ、これ」 立ち上がろうと顔を上げると、本棚にずらりと並んだ小説や図鑑が目に入った。 「整理をしなければならないとは話しているがな」 真田の言う通り、別荘と言うわりには家の端々に生活の匂いが残っている。 「俺はこういう方が好みだけど」 一冊を手に取って、ぱらぱらと捲る。日焼けした歴史書。真田の歴史好きはもう片方のお祖父さん譲りだと思っていたけれど、実はここにルーツがあるのかもしれない。紙の上に、達筆な文字が書きつけられていた。誰のものかは分からないけれど、これも、さすが真田と血がつながっているだけあって、字がどことなく似ている。 「おい、始めるぞ」 俺が本を眺めているうちに、真田は掃除機を持ってきていた。 「えー、ちょっと休憩」 「駄目だ」 休むにしてもこう汚くては、と背中を叩かれた。仕方なく重い腰を上げる。 掃除機をかけて水拭きをすると、なかなかに良い時間になった。学校の当番や母さんの手伝いをすることはあっても、普段からこんなに大規模にしている訳ではないから、やけに時間がかかった。 ぴかぴかになった床に座って、足を投げ出す。もうどれぐらい動き続けているだろう。やっぱり、休んでおけばよかった。 「お腹すいたな。なんか作る?」 「ああ」 真田の頬にも空腹だと書いてある。ただし頷きはするものの、乗り気ではなさそうだ。 「真田って料理できた?」 「少しだけ」 俺も、たまにお弁当の具の一部を作るくらいだ。掃除の二の舞になる予感がした。 商店で買った野菜や調味料をかき分けて、奥にしまっておいたカップ麺を取り出す。 「我ながら名案だと思うけど、どうかな?」 ポットにはもうお湯が沸いている。そう付け加えると、真田はさっきよりも深く頷いた。 カップにお湯を注ぐ俺の一挙一動を逃すまいとでもいうかのような視線。そのままでは味気ないので卵を割り入れると、おお、と感嘆された。たったこれだけで。今日は自炊をやめて正解だった。 「食べたことなかった?」 「うむ」 真田は、いかにも見よう見まねという素振りでお湯を注いでみせた。嫌な予感が深まる。結局、卵は俺が割った。 真田はじっと時計の秒針を見つめていた。適当でいいよ、と教えたのだけれど。 蓋を剥がす。湯気と一緒に、鶏と醤油の匂いが立ちのぼってくる。割り箸を折るより先に、耐えかねた腹の虫が、大きい音で鳴いた。真田が俺を横目で見て、ふっと笑う。はずかしい。 「いただきます」 三分きっかりを測り終えた真田は、俺に倣って蓋を剥がした。おそるおそる箸先をスープにつけて、麺を一本引き出す。 「毒見じゃないんだから、普通に食べたら。ジャッカルのお父さんのラーメンほど美味しくはないけどね」 「うむ」 今度はきちんと束で取って、口へ運ぶ。眉尻がぴくりと動いた。 「これは意外と」 言い終わる前に、言葉は麺をすする音に変わった。真田も俺に負けず劣らず空腹だったんだろう、はふ、とスープの熱さを冷ましつつかき込んでいく。 「真田とふたりだけで食事なんていつぶりだろう」 「思い出せん」 ジャンクフードを一緒につつくことに至っては、初めてだ。お堅い真田は、部活の後の買い食いすら良しとしない。 「たまにこういうジャンクなものが食べたくなるよね……って分からないか」 「うむ。そもそも縁がない」 そう考えると、俺と真田はあんまり中学生らしい付き合いをしていないのかもしれない。 「テニスばかりしているからな」 真田は言ってから、しまった、という顔をした。別にかまわないのに。 真田のばつの悪さを蹴り飛ばしてやるつもりで、言った。 「じゃあ明日から一緒にしようよ、テニス以外のこと」
☂8月30日
隣でごそごそと動く音がして、目が覚めた。薄っすら瞼を開けると、カーテンの隙間からやわらかい陽の光が差し込んでいた。 運動部の体力をもってしても昨日は疲れたらしく、布団に入ってすぐに眠って、それきり目が覚めることはなかった。 「起こしたか」 真田の声がした方に視線を移せば、すでにトレーニングウェアに着替えていた。ベッドサイドの時計は八時。どのみち起きなければいけない時間だ。首を横に振る。 「走ってきたのか」 「ああ」 上体を起こして伸びをする。朝は決して得意ではないけれど、今朝はしゃっきりと目覚めることができた。 「俺も走ろうかな」 「付き合おう。道も分からんだろう」 「うそ、ダラダラしたいよ」 わざと、もう一度シーツにくるまった。 「たっ……」 たるんどる、と言いかけてやめる。下手くそめ。 「嘘だよ、ダラダラはしない。朝ごはん食べたらさ、散歩がしたいな」
朝ごはん食べたらさ、と簡単に言ってのけたものの、まずこれが大変だった。トーストと目玉焼きとサラダというシンプルな献立に、俺も真田もやたら苦戦して、包丁の特訓をしよう、と誓い合った。片付けも、言わずもがな。 昼食は、とあまり考えたくなくなっていたことを相談したら、どうやら外にうってつけの場所があるらしい。朝食で残った食材でサンドイッチを作ったり、その他もろもろの出発の準備をして、と忙しくしていたら、目的地に着いたときには十一時を回っていた。 八月も終わりになると、空気は熱くても、川の水温は十分に冷たい。 真田は持って来た胡瓜とトマトをざるに入れて、川の水に浸した。その絵だけで、いかにも夏休みといった風情だった。さっきまでの慌ただしさが、嘘みたいに流れていく。 滑るなよ、と子どもみたいな注意を受けながら、飛び石の上に立つ。落ちていた木の棒を片手に持っていたせいで少しふらついて、岸にいた真田がすぐ隣の飛び石までやって来た。 「あのボウヤ」 「誰だ」 「越前リョーマ」 その名前を出しただけで、空気が変わる。真田はなんでもない風を装って、相槌を打った。 「軽井沢で修業してて記憶喪失になったんだって?こういうところだったのかな」 しゃがみ込んで、水の中から小石を拾いあげる。 「修行って何してたんだろうね」 テニスの要領で、木の棒を振って小石を打った。小石は二十メートルぐらい真っすぐに飛んで落ちて、勢いよく水を跳ねあげた。試合だったらサービスエースを獲れていただろう。 「ラケットを持ってきてもよかったな」 木の棒で素振りをする。ラケットよりずっと軽くて、手からすり抜けていきそうだ。 「テニスではないことをするのではなかったのか」 「そうでした」 どうしてもすぐにテニスへと道が逸れてしまう。いや、もしかしたらテニスこそが俺たちの正しい道で、それ以外のことをしようとする今が脱線しているのかもしれない。 これ以上真田を困らせるのもかわいそうな気がした。棒を水の中に放ると、真田の面持ちに安堵が滲む。 「気遣ってるだろ。俺からテニスの話を遠ざけようとか、のんびりさせてあげようとか」 首を横に振ろうとするのを、遮った。 「いいよ、もう分かってる」 「お前には敵わん」 真田は苦々しげにつぶやいて、あっさり白旗をあげた。気を遣うのも隠し事をするのも、真田は大の苦手だ。とっくに限界だったんだろう。 俺にしてみれば、俺がほぼ無意識にテニスを避けていることを敏感に感じ取った真田にこそ「敵わん」のだけれど。 今度は俺が素直になる番だ。そう思った。 「実はね、まだ負けたっていう実感がないんだ」 真田は黙って、続きを促した。 「いや、実感はあるのかな。君たちに申し訳ないって気持ちは今だってずっとあるよ。でも、何もかも腑に落ちた訳じゃない」 うろうろと言葉がさまよう。ずっと抱えていた気持ちを吐き出すうちに、心細さばかりが嵩を増していく。 みんなと一緒に泣きたかった。泣けなかった。何がみんなに、真田に、涙を流させているのか分からなかった。 だから、あの日以来テニスには触っていない。逃げているだけだと、自分でも痛いほどに分かっている。ずっとこのままではいられないことも。 どうしたらいい、と真田に縋りたいとすら思った。なけなしの自尊心が、それを咽喉で押しとどめた。 俺がすべてを吐き出し終えるまでずっと、真田は俺を見つめていた。 「冷たく聞こえたら悪いのだが」 前置きをして、咳払いをひとつ。 「俺の知ったことではない。答えを俺に求められても、それはお前が導くものだ、幸村」 視線以上に言葉は真っすぐで正しくて、鋭利だった。伸ばしかけた手を払いのけられる。俺はたったひとり、谷底へと突き落とされたにも等しかった。 「そのとおりだね」 俯いて足元を見て、そう頷くのがやっとだった。飛び石の岩肌とその間を流れるせせらぎとが見えることに、ほんの少しだけ安心する。 「いつか答えが出たら、そのときは一緒に抱えてやる。それぐらいはできるぞ」 はじかれたように顔を上げる。真田と目が合う。目線はほとんど同じ高さなのに、はるか上を見上げる心地だった。 突き落とされても、這いあがれるのなら。そう言って、そう信じて、真田は俺に手を差し出す。 青学のボウヤ、立海の仲間、真田。ほんの少しあたりを見回すだけで、こんなにもたくさんの人が、俺ならできる筈だと、盲目的と思えるほどに信じてくれている。過度な期待だと言い換えてもよかった。彼らもそれをよく分かっていて、尚言うのだった。 まったく、ひと月前まで体を動かすこともままならなかった人間に、なんて無茶をさせるんだ。――絶対に答えを出してみせる。 はは、と勝手に笑みが零れた。それは武者震いにも似ていた。 「……そういえば」 「どうした」 「ん、いや、もう冷えたかな、野菜」 「お前は……」 呆れて絶句されてしまった。だって、これ以上何も言う必要はないだろう。 もう少しだけ、上で待っててよ。真田の立つ飛び石に乗って、その肩を軽く叩いた。伝わったのやらそうでないのやら。岸へ引き返す俺に、真田は黙ってついて来た。 引き揚げた胡瓜を齧ると、まだ生ぬるかった。体感ではひどく時間が経った気がするのに、現実にはせいぜい十分ほどの出来事でしかなかったらしい。 「どれ」 真田は俺の手首を握って、ずいと顔を近づけてきた。後ずさる間もなく、胡瓜の天辺はその口の中へ。 「もうしばらく待たねばならんな」 「真田、きみ」 俺が食べた後から、そんな風にためらいもなく。と言いかけたけれど、お互い幼馴染相手にはよくやることだった。たとえばスポーツドリンクの回し飲みなんて、もう何百回もしている。 「わ、悪かった」 ところが、さっきまで平然とした顔をしていた真田までもが、急に赤面して謝ってきた。 「いや、いいけど!いきなりだから、ちょっとびっくりした……」 そう、たぶん、いつもとは違うシチュエーションに驚いてしまっただけだ。急にどきどきし始めた心臓に、真田の赤い顔に、無理やり理由をつける。 一度齧ったものを戻すのもな、とぬるい胡瓜を手に持ったまま、形のいい真田の歯形を見つめていた。
「夏休みが終わるよ」 西の空ではたった今、夕焼けの最後のひとかけらが夜に呑まれたばかり。 真田と妙にぎくしゃくしてしまった昼間の出来事を振り払うのに、半日を要した。ずいぶん時間がかかったものだ。 「まだ一日と少し残っているだろう」 バケツを床に置くと、ぱしゃんと水が撥ねた。 「そういう気分ってこと」 花火というものは、どうしたって感傷を呼ぶ。 お婆さんのお店で買った、打ち上げ花火が五つ。ふたりしかいないのにあまり多くても、とこの数になった。夏休みのフィナーレを飾るべく、それらを点々と並べていく。 俺の背後でマッチを手にした真田が、ぽつりとつぶやいた。 「どうやって点火するのだ」 すごい勢いで振り返ってしまった。これはもしや、カップ麺に引き続き。 「やったことない?」 「……その通りだ」 家族とやるときは男手として駆り出されるものだろう、と思ったけれど、そういえば真田は次男、しかもお兄さんとは歳が離れている。 「この線に火を点ければいいんだな」 「いいよ、俺がやるよ。あっちで見てて」 ここで怪我をされてはたまったものじゃない。うう、と不服そうに唸りはしても、真田は素直に従った。急に真田が弟のように思えてきた。 まずはひとつ。火を点けて、真田のいるところまで走った。ひゅう、という音で空気を裂いて光の玉が宙へ飛んで行った。 「きれいだね」 そう言って隣を見ると、なぜだか浮かない顔。 「俺もやる」 腕を組んで唇をへの字に曲げて、こうなったらもう真田は譲らないだろう。次の花火は駄々っ子につきっきりで点火を見守った。 「なんだ、簡単ではないか」 たくさんの光が空を彩っては、消える。真田が次から次へと火を点けるので、たった五つの花火はすぐにあとひとつになってしまった。 花火より、得意げな真田の横顔を見ている時間の方が長かったかもしれない。もう少し多く買えばよかった。そうすれば、かわいい真田をもっと見ていられたのに。――一体誰がかわいいって? 「……なんだ���もう、決定的だ」 「幸村、最後だぞ」 ああうん、と心ここにあらずな返事をしてしまった。真田は気にすることなく、マッチを擦る。最後なだけに、あからさまに張り切っているのがかわいい。 空でうつくしく舞う光たちがついに目に入らなくなり、申し訳ない気分だった。
布団に入ってしばらくして、なあ、と真田が声をかけてきた。いつもは直滑降で眠りに落ちるのに、どうやら寝つけないらしい。しかも、珍しく弱気な声音だった。 「退屈しなかったか」 「なんのこと」 真田の言っている意味が分からなかった。 「旅行と言って連れ出したのに、何もないところで驚いただろう」 最初にそう言っていたじゃないか。ますます分からない。首を傾げてしまった。 「それに、俺はお前に頼ってばかりで……のわっ」 真田のすぐ横に転がって、うつぶせに倒れた。そのまま布団の端を持ち上げて、侵入する。 「おい、入ってくるんじゃない!」 「昔はよくこうやって寝てたじゃないか」 「何年前の話をしているんだ」 しばらく真田と攻防を続け、最後には無理やりに体すべてを布団の中におさめる。こういうときに真田が俺に勝てないのは分かっていた。本人が気づいているのかは知らないけれど、そういうルールと言ってもいい。真田は俺に甘い。 案の定、はああ、と長いため息をついて、諦めたようだった。 「楽しい」 退屈だなんて、とんでもない。そんなつまらない心配を口にするな。 「次に同じこと言ったら、怒るよ」 まったくの本心だった。 真田のため息が、安堵から来るものに変わる。 「真田のこと、ずいぶんたくさん分かったし。十年も一緒にいて、今さらだけど」 たとえば、ほら、こういうこととか。 真田の髪に指をくぐらせた。触れた瞬間だけ真田は体を強ばらせたけれど、嫌がられはしなかった。 見た目どおり硬い感触だった。針金みたいで、少しちくちくとする。真田らしいな、と思って、口元がゆるんだ。 つい五秒前には知らなかったこと。記憶がひとつ、積み上げられていく。 「俺も、ほとんどお前を知らなかったのだな」 真田の指先が俺の髪に触れる。まさかやり返されるとは予想していなくて、今度は俺が緊張する番だった。できるだけ悟られないように、体の力を抜く。 ごつごつと硬い手のひらもぎこちないやり方も、決して心地いいものではないのに、まったく嫌だと思わなかった。 どちらかといえば、商店で適当に買ったシャンプーを使っているせいで、髪の毛がごわごわしているのが気になる。女の子じゃあるまいし、と思うけれど、触れられるのは初めてだから。真田の中に、俺の髪がこういうものなんだという印象がついてしまったら、なんだか嫌だ。 昼間にどきどきしたみたいに、段々と鼓動が速くなる。決定的だ、とふたたび胸中でつぶやいた。昼のあれは決して驚いた訳じゃないことに、もうとっくに気づいている。 いつからだったのかな。ここへ来たときには確かにもう、心の中にあった。決勝の直後に抱き締めてくれたとき、病室に足しげく通って不器用に励ましてくれたとき、同じ学校へ行こうと誓い合ったとき。同じ布団で眠るのが当たり前だった頃から、もしかしたら、ずっと。 真田の中にもそれはあるだろうか。俺はうぬぼれてもいいのだろうか。教えてほしい。 「もっと知りたいよ、真田のこと」 ひとつひとつ、丁寧に知りたい。 瞼を閉じて、そっとつぶやいた。 真田が聞いていたのか、それとももう眠ってしまったのかは、分からない。いつの間にか、髪を撫でる手は動きを止めている。さっきまでより温かくなった体温に、ただ安らいだ。 「俺もだ」 まどろみの中で、ひどくやさしい真田の声を聞いた気がした。
☂8月31日
翌朝も、真田は俺より先に起きていた。 「起こしたか」 首を横に振って、既視感のあるやり取りをした。真田の様子はまるで昨日と変わらなくて、夜の出来事が夢だったように思える。 「もう帰る日か、早いね」 寝ているベッドが初日とは違うものだということが、かろうじて証拠になるだろうか。ぼんやりしたまま掛布団の端をめくると、ふわりと真田の匂いがした。ひと息に記憶がよみがえり、襲ってくる。振り払おうとして、布団をすべて跳ねのけた。 「そのことだが」 真田は俺の挙動不審を気にしなかった。命拾いした。 「帰りにひとつだけ寄りたいところがある」 「いいよ。どこ?」 「挨拶をしておきたい人がいてな」
荷物をまとめておいたお陰で、出発にそう時間はかからなかった。けもの道を、来たときとは違うルートで下って行く。着いたのは墓地だった。 かつてあの家に住んでいた人たち、真田の曾お祖父さんや曾お祖母さん、もっと昔のご先祖様たちが眠っているらしい。 「なるほど、挨拶をしておきたい人ね」 「すまん、俺のわがままに付き合わせて」 お墓はきれいに手入れされていて、ほとんど掃除は必要なく、花立ての中身を新しい花と水に取り替えるだけでよかった 「曾お祖父さんたちに会ったことはある?」 「生まれたばかりの頃にな。だから、あまり記憶はないのだが」。 真田は線香の火を手であおいで消し、皿の上に寝かせた。 「今日は幸村を連れてきました」 言いながら墓石に水をかけて、その前にしゃがんだ。 「俺の……親友の」 親友、という言葉を使うのに、どこかためらいがあった。真田は、変わりつつある俺との関係をうまく言い表せないみたいだった。 「真田くんにはいつもお世話になってます」 俺も一緒で、あいまいに誤魔化した。 真田は手を合わせて、目を伏せた。俺もその横にしゃがんで、真田に倣った。 ちらりと横目で窺うと、真田は難しい顔をしていた。ご先祖様にたくさん報告したいことがあるみたいだった。 俺は何をどう言えばいいんだろう。弦一郎くんと俺の行く末を、どうか温かく見守ってくだされば嬉しいです?大事な子孫はお前にやれん、って祟られたらどうしよう。いや祟るなんて、ご先祖様に失礼だな。 悩んでいるうちに突然、携帯電話が鳴った。母さんからの着信だった。知らない間に電波が復活していたようだ。 真田が片目だけ開けて、俺を見る。 「……ごめん、こんなところで」 「いいから、出ろ」 促されて、通話ボタンを押す。ハイのハの字も言わないうちに、精市あなたどこにいるのいつ帰るの真田くんは一緒なの、と矢継ぎ早に質問をぶつけられた。 母さんはおかんむりだった。連絡がつかなくなったことというより、そのせいで検査の結果を伝えられなかったことに。そういえば、異常がなければ電話で、と先生と話した覚えがある。 珍しく音量が大きくなった母さんの声は外に洩れまくっているらしく、知らないうちにご先祖様への話を終えていた真田に苦笑いされる。 どうにか母さんをなだめて、電話を切った。 「解決したのか」 「うん、帰ったらあらためて雷が落ちるだろうね」 「ならば、早く帰らんとな」 「……帰りたくない」 また来ます、と律儀に挨拶をして、真田は桶と柄杓を手に立ち上がった。俺がわざとのろのろしているうちに、踵を返して行ってしまう。強引だ。 「この前の検査、ちゃんと結果が出たそうだよ」 真田が借りたものを元の場所に戻すのを待って、言った。歩みを進めながら。 「どうだった」 「寛解って言うんだって」 字面がうまく浮かばなかったのか、カンカイ、とおうむ返しされる。 「ほとんど完全に治ったっていう意味」 真田は吐息を零した。すぐに言葉が浮かばないようで、咽喉を詰まらせる。結果は分かりきっていたけれど、やはり心配させていたようだ。 「……よかったな」 「うん、よかったよ」 でも。 真田に比べると俺の声は冷ややかで、自分でも驚いた。安堵はあっても、いざ結果が出ると手ばなしでは喜べなかった。 検査の数値は、決勝戦から二日後の俺の体を表している。たった二日間であの病気がどうにかなるとは思えない。 つまり、決勝戦のあの日、俺は病に倒れる前と同じコンディションで、テニスコートに立った。 「いつもどおりに戦って、俺は負けたんだね」 真田の瞳が揺れる。痛みに耐えるように、切れ長の目が鋭くなって、眉間には皺が寄った。 「そうだ」 それでも、真田は確かな声で肯定した。 決勝の日の情景が、鮮烈に蘇った。誰も俺を見ようとはしない中、真っ先に俺を見つめ頷いた真田と、今目の前にいる真田とが、重なる。 ――負けた。その三文字が、急に胸の中いっぱいに広がった。 その場に縛りつけられたかのように足が動かなくなる。追いかけなければ、と思うのに、俺と真田の歩幅は開いていく。 「……幸村?」 怪訝そうに、真田が振り向いた。 「ごめん、なんか、いきなり」 奥歯がかちりと鳴る。震えだす肩を、自分で抱いた。 いつか答えが出たら、そのときは一緒に抱えてやる。昨日真田が言った「そのとき」は想像していたよりずっと早く訪れて、答えはいたって単純だった。 「……悔しいなあ」 悔しい。ただそれだけ。 言葉にした瞬間、こめかみがぎゅっと熱く、痛くなる。 勝ちたかった。欲しかった、みんなに、真田にあげたかった。誰もが俺たちの勝利を祝福する拍手喝采。トロフィーの金色の美しさ。風を受けて翻る優勝旗の重み。そこに刻まれた「優勝」のふた文字が、どんなに誇らしいか。 すでに知っているからこそ、それらすべてを俺の手で葬ってしまったことが、悔しくて仕方がない。そのためだけに生きて、テニスをしてきたと言っても過言ではなかった。いっそ死んでしまいたいぐらいだ。 は、と息が洩れたのが引き金だった。まなじりを涙が伝う。それが地面に落ちるより先に、新しい滴が流れる。すぐに頬も顎もしとどに濡れた。 とうとう歯の根が合わなくなった。浅い呼吸が勝手に繰り返されて、息の仕方が分からなくなる。苦しくて唇を結ぶこともできなくて、嗚咽が勝手に溢れ出す。こんな子どもみたいな泣き声が到底自分のものだと思えなくて、驚いた。子どもの頃だってこんな風に泣いたことはなかったかもしれない。 真田どころか誰の目にふれるか分からない場所で醜態を晒す恥ずかしさで、頬が灼けた。それでも、悔しさの方がずっと大きくて、抑えきれなかった。 「幸村」 真田はほんの少し猫背になって、俺の両肩を手のひらで包んだ。指が筋肉に食い込んで、少しだけ痛い。 ぼやけた視界の中で、真田の真っ黒な瞳だけがはっきりと映った。ふたつの���は俺をとらえて離さない。あまり泣き顔を見せたくないのに。 両手で顔を隠そうとしたとき、真田の顔が近づいてくるのが分かった。 「なっ、なに……」 近すぎる、と思ったときにはもう、距離はゼロになっていた。震えてろくに言葉も作れない俺の唇に、真田の唇が被さる。 涙が、もしかしたら鼻水まで口に入ってしまうかもしれないだとか、真田の唇も俺と同じくらい震えていて、とてつもなく緊張しているんだな、とか。とりとめもないことが次々に頭をよぎっては消える。 生まれて初めてのキスを奪われたのに、怒りも嫌悪もそこにはなかった。 ひたすらに、安堵していた。 俺はずっとひとりで戦っていたんじゃない。みんなが言葉で態度で示してくれていたことが、今やっと腑に落ちる。 ふっと息を逃がして、真田は退いた。唇が重なっていた時間は、きっと三秒にも満たなかった。 「すまん、こうしたら治まるかと思った」 言い訳ではなくて、本気でそう思っただろうことが伝わってくる声音だった。真田は時々とんでもないことをする。 しかも治まるどころか、逆効果だ。悔しさに安心が加わったせいで、体中の水分が出てしまうんじゃないかと心配になるぐらい、涙の量が増えた。 「……さなだあ」 真田、さなだ、とばかみたいに名前を呼んだ。真田は、ああ、とそのひとつひとつに律儀に応えてくれた。俺が一緒にいる。そう言外に含ませて。 しかしそれだけではどうにも心細くて、今度は俺から顔を近づけた。真田の唇を啄む。うまくいかない俺の呼吸が正しい真田のそれに同期されるぐらい、深く。 肩にあった真田の手が、遠慮がちに背中に回る。俺も腕を伸ばすと、抱き締められた。 乾いてささくれた唇が、その奥の正反対にやわらかい粘膜が、俺よりも高い体温が、背中に食い込む腕の力が、真田が俺の側にいて、俺を決してひとりにしないことを教えてくれる。 耳鳴りの向こう側で、蝉の鳴き声が聞こえた。もうすぐやって来る命が燃え尽きる瞬間に憔悴したかのように、けたたましく鳴き続ける。 「……っ、は」 お互いに息継ぎの仕方を知らないせいで、そう長い間唇を塞いではいられなかった。離れがたい、とためらいながら、距離を置く。 口づけの間も流れ続けた俺の涙は、真田の頬までも濡らしていた。点々と残る滴が、まるで俺と一緒に泣いたみたいだった。 真田は俺のよるべだ。今までも、これからも。 思わず、真田に触れる指をぎゅっと丸める。確かな感触と温度がそこにある。 「痛いぞ、幸村」 真田がほほ笑むのが分かった。仕返しのつもりなのか、さっきよりも強い力で抱かれた。 どちらからともなくまた唇を合わせると、一瞬だけ蝉の声が止んだ。 夏が終わる。長い、本当に長い夏、だった。
☀9月1日
「どうしたんスか」 ステージの下にやって来た幸村部長を見て、訊かずにはいられなかった。 瞼をぱんぱんに腫らし、女子たちが騒ぐ整った顔立ちも形無しだった。マジひっでえ顔。 たぶん、昨日泣いたんだというのは察しがつく。俺もつい一週間ぐらい前の決勝の次の日、同じような顔になったから。 「やっぱり分かるかい?」 「分かりすぎてやばいっスけど……どうしたんスか」 分かっていながらも、衝撃的すぎて二回も同じことを訊いてしまった。そもそもどんな理由でこんなになるまで泣いたのかっていう好奇心もあって。 「……秘密」 ふふ、と笑う部長。いつもみたいに様にならないと思ったら、照れているみたいで、頬がほのかに赤くなっている。あ、悪い理由じゃないんだ。少し安心した。 「大会終わってから、なんかしました?」 「すごい田舎に行って、夏休みらしく過ごしたよ」 「へえ、いいっスね。俺宿題やばくて休みどころじゃなかったっス」 「それは終わったのだろうな」 いきなり真田副部長が割って入ってきて、びくっとしてしまった。 「蓮二に相当頼ったと聞いたが」 「あー、そりゃもうお陰様で!すげえ助かりました……へへ……」 ぎろりと睨みつけられるのを、笑って受け流した。頼りはしたけど答えは絶対に教えてもらえなくて、泣きながら、これはたとえじゃなくて五回ぐらいマジ泣きしたけど、まあそんなかんじでどうにか片付けた。 というエピソードを話してもよかったけどやぶへびになりそうで、会話を打ち切る。表彰、とっとと呼ばれねーかな。 文武両道を良しとする学校なだけあって、夏休み明けは表彰の数がとんでもないことになる。女テニが賞状渡されてるから、次ぐらいだろうか。 女テニの成績は、全国には進出したものの、決して華々しくはなかった。それでもレギュラーの面々は目に涙を浮かべていた。嬉しいのか悔しいのか、たぶん両方だ。 俺はどういう顔をしてあそこに立てばいいんだろう。 「男子硬式テニス部」 答えを出す暇もなく呼ばれた。部長を先頭にしてシングルス組、その後ダブルス組、という隊列で壇上に進んだ。 「団体戦、準優勝」 そう告げられるなり、空気が急にざわめき立つ。優勝できなかったことを今知った奴らだ。それどころか、結果をとうに知っていた校長も、俺たちに残念そうな顔を向けてきやがった。どいつもこいつもうるせえんだよ。なんにも分かんねえくせに。 「言わせておけばいい」 俺がイラついてるのをいち早く察しただろう柳先輩に、小声で諭された。 「……あざっす」 先輩の言うとおり、誰がなんと言おうと、俺たちが精一杯やった結果には変わりなかった。誇らしい結果。せめて、と思って、胸を張ろうとして、失敗した。 幸村部長が、ひとりいちばん前へと躍り出たからだ。迷いのない足取りだった。 かたわらの真田副部長は、微動だにしなかった。てっきり今回も副部長が受け取るものだと思っていたから、マジでびびった。誰も口にしなかったけれど、俺たちの間には、優勝旗以外は部長に触らせたくないという気持ちが確かにあった。 「準優勝、おめでとう」 二本の腕をぴんと伸ばして、幸村部長は校長から盾を受け取った。盾に大きく書かれた準優勝の文字をじっと見て、それから、この世界でいちばん大切なものみたいに、銀色の盾を抱えた。 部長はゆっくりと振り返る。壇上から、真っすぐに全校生徒を見据えた。 「ありがとうございました」 校庭中に響く声だった。ひどく震えた声、だった。 瞳に張った涙の膜を揺らして、唇をぎゅっと引き結んで、緊張した肩を震わせて。こんなに悔しそうな幸村部長を、俺は見たことがなかった。涙を零さないのは、きっと部のトップとしての最後の意地だった。 真田副部長は眩しそうに目を眇め、部長を見つめていた。見守っていた。 たちまちに目の奥が熱くなる。 みんなが見てる中で泣きたくなかったのに、結局俺は、柳先輩にあやすみたいに背中をさすられるぐらいぼろぼろになった。勘弁してくれ、クラスの奴らになんて言われるか、ああクソ治まる訳がねえよ、だって、幸村部長が俺たちと一緒に泣けてよかった。 もうどこにも、幸村部長がひとりで戦う必要なんてなくて、よかった。
(2014/11/30)
0 notes