#寒くて猫背ウサギだけどうさき
Explore tagged Tumblr posts
Text
クスノキの木が芳しい
クスノキの木が芳しい
——あろ
二十九歳の足取りは地面いっぱいの落ち葉を踏んでいます。乾いた音とともに、記憶のクラクションを鳴らしています。瞳が潤んで、リュックサックをそっと下ろしたような淡々とした微笑は十年前に成長したと考えられています。青の渋い歳月の中で、思春期の美しさは歳月の洗浄を経て、その時のように執着することはできません。大人になってからは考えが多くなく、抱き合った記憶だけがあって、純粋にお互いに話ができなくて、簡単に心の声を語り合います。数年後、私は自分がまだ誰かを愛していると思います。記憶が軽くなり、涙が桜のように頬に落ち、また3月に微笑が咲きます。
「何をお願いしましたか?」私の十七歳の誕生日に、楊容疑者は私の前に顔を寄せて、優しく紳士的に聞きました。
私は簡単に彼に私の願いを伝えました。「愛を持ちたいです。簡単に生活し、一緒に奮闘し、幸せな生活を送りたいです。一緒に仕事をしながら景勝を見物したいです。」
彼は答えを聞いてにっこり笑った。彼は笑った時に国を傾けて城を傾き、このように頭に刻みつけた。
アブと過ごした八年間は、彼を楊真っ白雲の存在と見なしていました。彼は四月に出発する時、私はどこにいても、どこにもいません。
落さん、愛している人もあなたを愛していると確信しています。離れないで捨てないですか?布さんはいつもぼんやりとベッドのそばやソファーのそばに座っています。8月の週末、いたずらをして私に聞いてみてください。雨が舞い散って、花びらを打っています。深い思索を持っています。
「私たちは一緒にいられないと思います。顔がやつれています。クズだらけです。結果のない話が多くて古いです。」彼に一言返しました。
「いい芸術の答えです。ひげを剃る時はとても魅力的です。痩せたあなたがとても好きです。かっこいいです。あなたは私があなたを愛しないと思っています。桜が舞うのはあなたの季節です。いない日はお大事に!」彼はこの話を言い終わって、指で前髪をしごいて、手提げかばんを持って、足早に出発して、私はぼんやりと彼の立ち去る後ろ姿を見ていて、彼が遥か遠い空の果てで消えてなくなるまで。
今年は2020年になりました。長江のほとりでは、澄んだ水がとても親切に感じられます。靴を脱いで、服のポケットに靴下を入れて、足を水の中に入れてみます。氷があります。春の川の水はヒマラヤ山脈の温度を持っています。遠いところの存在を感じます。遠くの誰かの親しみを感じているようです。あの人は大丈夫ですか?」私は内心で自分に聞いていますが、答えのない疑問がおかしいと思います。
立ち上がって、前に向かって、江水は足首を漫然と過ぎて、澄みきって透明な水しぶきを蹴って、孤独と夕日の相互の呼応は私に更に時間の中で遥か遠い人を思い出させます。携帯を取り出��て、自分の水しぶきのために記念写真を撮ります。子供の頃はスマートフォンがなく、多くの可能性を失っていました。一枚の写真で十分です。また元の場所に戻ってビデオを見てみます。同感の映像はどれも自制多情の代入です。彼は超能力で多くの人を踊らせたり、歌を歌ったりすることができません。私の携帯の画面に現れて対話します。よく考えてみると、話をしたり、ダンスを踊ったり、歌ったりする歌は私とあまり関係がありません。人を懐かしみます。彼は道の次の角に現れると思います。
引き続き前へ歩いて、語彙の熟知している場所を忘れに来て、地面いっぱいの落葉、私の白色のレジャーシューズはそっと入って、香樟の木の芬芳芳芳馥郁、マスクをつけていて依然としてかすかな香りをかぐことができて、風が吹いて私の前髪を吹いて、木の葉はざくざくと音を立てて、昔の事の雲と煙は軽やかに舞っています。
目じりは少し湿っぽくて、私は静かにクスノキを囲んでぐるぐる回って、そっと離れて、子供の時友達と一緒に下校する道を歩いて、たくさんの人の様子が目の前に浮かんで、かすかに笑って、あれは思春期に帰って、鹿がむやみに胸をときめかす年ごろです。
15歳の時、私は一人に会いました。彼の髪は日光の下で私の好きな茶色が現れています。濃い眉毛は故郷の山脈の曲線のようです。目は前方を見ています。彼の足取りはとても開けていて、私は彼のかっこいいことを凝視しています。神様は電柱にぶつかって、本は地面に落ちています。彼は声を聞いて、私に向けて、本を拾うのを眺めています。彼の両手が私の視線の中に現れて、感電のように彼を見ました。彼は私のために本を拾ってくれましたが、表情もなく、忘れ物を渡してくれました。
日照りが長く続いていますが、八月はアブのプールで水浴びが好きです。
アブさんは水泳が好きで、彼は言いました。「水の中を全く泳いでいて、外の音が聞こえません。水の流れ以外に、自分は自由自在な魚のように感じられます。いつも子供のころのようにのんびりしていたいです。」
布は水面をボーリングし、濡れた髪をしごいて乾かし、両手で顔を拭き取り、彼は向こうの池の壁にもたれかかっています。そばの飲み物を持って行きます。彼は額を覆って笑って言いました。「プールの中を行ったり来たりするのはおかしいです。」
「いつか水泳を教えてくれる人に会いたいです。たくさんのところに行きます。澄んだ水の中で泳いでいます。」私はアブの前に行ってジュースを一杯注いであげました。
布はジュースを持って、ストローをくわえて、彼のところを見て、私を見て、ジュースを吸って水面を見ていてぼんやりしています。彼は言います。
私は微笑んでジュースを置いて、「どこに行きますか?」
彼は首を振りながら、「遠いところにいる」と言った。
「えっ!」私は口から出任せに答えた。
「聞かないとまた会いますか?」彼は水面をスライドしている。
「ずいぶん前にも同じ質問をしましたが、今は幼稚だと思います。なぜですか?私に電話してください。」
両手で水面をたたき、水しぶきを上げて言いました。「プールがないと、夏は暑くてたまりません。」
以前のように、毎日水道の水が冷たいです。
アブはぽかんとしていました。私の目の前の光が彼に気づきました。「あなたはまだあの汚い部屋に帰りますか?」
水の中に手を置いて、コップの半分を水に浸して、太陽の光が点々と輝いています。大学に合格すれば、すべてがよくなる。いい仕事があります。ここを離れて私のほしい人生を追いかけます。お金があったら故郷に帰ります。その部屋はきれいに掃除します。
「あなたの話を見ていると、あなたは迷いの中にいます。」アブは突然にハハと笑い、彼は言った。
私は行くところがありません。
アブさんは私の話を中断してプールにコップを投げました。両手を私の頬に置いて、目つきをしっかりと教えてくれました。「自分の夢を追いかけて、華灯の初めのところで待っています。」
私はすばやくしゃがんで、水を全身に浸らせて、また水の中から立ち上がって、水しぶきが四方にあふれます。揺れている水滴が布の上にはねています。私も髪を拭いて、顔の水を消します。
アブは避けて、笑いながら言いました。「恋をしました。」
驚きのあまり、目を開けて、「いつ結婚しますか?」
彼の微笑みは恋の蜜壺に浸り、目つきには愛の甘さがあふれていた。首をひねりながら、口を尖らせて言いました。「彼女はきっといい娘です。」
「これからはあなたを愛する人が必ずいます。春秋冬夏!」
「最近出会った人の顔がとても綺麗で、着飾っていて、彼とすれ違いました。とても魅力的です。」私は思い出にうっとりしています。
「彼と同じ品位を持ちたいです。頑張ってください。あと五、六年であなたもかっこよくて魅力的です。」布さんはこぶしを握って応援してくれました。
これからの週末に射撃場でターゲットの練習をします。半年ほど訓練して、また出会った人に会って、彼の練習をぼんやり見ていました。
彼は防音イヤホンを外して、私を見ていて、隣に行って飲み物を一杯飲んでください。彼は言います。「四、五ヶ月です。いつも私を見ています。おかしいと思わないですか?」
ジュースを吸いながら、首をかしげて、「楊凱雲さん、好きです。」
「えっ!」彼は後ろにもたれていて、語気が長く引いています。彼は興味深く私を見ています。
名前は何ですか?彼はまばたきをしただけです。
私は楊真っ白な雲の目を見ていて、両足をベンチに曲げて、両手で膝を抱えて言いました。
彼の目はさっとまばたきして、微笑みは凝結して、続いてため息をついて、整然としている歯を現します:“昇原は阿落といいます!”
楊真っ白な雲が口を覆っています。彼は素早く振り返って聞きました。「彼女がいますよね。私のことが好きですか?」
私はジュースを飲みました。彼の目を迎えて、自分の悲しみを装って、「私のことが好きな人がいない」と言いました。
彼は首を振って、「夏休みはどこに行きたいですか?」
最近悲しいです。遠くに行ってリラックスしたいです。私は頭を下げてジュースコップを見ています。
ヤンさんは立ち上がって、顔を上げて彼を見上げました。「数日間出張します。私と一緒に旅行しませんか?」
私はうれしくてたまらなく椅子から飛び降りて、「はい」と言いました。
一週間後に、私は飛行機に乗りました。彼は私の右手に座っています。
飛行機がゆっくりと飛び立つのを見ていて、窓の外の翼が都市を走っています。飛行機が都市の電線と密接に接触するのを心配して、飛行機が早く雲に届くように祈ります。
楊容疑者は私の心配を察知して、「パイロットの運転能力を疑っていますか?」
すぐ口を開けて言いました。「いいえ、ありません。私は今までこんな飛行機に乗ったことがありません。ちょっと特別だと思います。」
「えっ!」ポプラ雲は目のカバーを下に置いて、位置に横になって、とても速くて、呼吸が均一になります。
彼が寝た後、私は窓の外の景色を見ていて、だんだんつまらなくなりました。運転室に行きました。
運転室の中のパイロットはハンサムでかっこいいです。痩せた体は私よりずっと高いようです。私はそばに座って、前の星空を見ています。
黒い幕のような空には無数の星がきらめいています。銀河のリボンが見えます。こんな素晴らしい景色は見たことがありません。遠くの空をぼんやり見ています。私は空の美しさに驚嘆しています。「わあ!」
大人になったら何が一番したいですか?
彼の横顔を見て、長い間考えてみました。「生活を良くしたい、望みがない、好きな人と一緒にお金を稼いで、人生の意味を体験したいです。」
好きな人はあなたが好きですか?彼は聞きます。
私はため息をついて言いました。「まだ会っていません。いつか私を愛している人に会って、魅力の都に行きましょう。」
目的地に着いたら、たくさん行ってみてください。
ちょっと長い間、私は運転席を離れて、��オルを二つ持って楊真っ白雲のそばに帰りました。夜は少し涼しくて、彼のために覆いました。自分で豆乳を一杯飲みました。口を綺麗に塗りました。タオルで彼の左手を覆いました。
放送で目を覚まして、窓の外の空はまだ夜です。私は操縦室に行きます。飛行機がゆっくりと路面に降りるのを見ています。
前に二人がいます。彼らは雑談しています。私はパイロットと一緒に飛行機から降りました。彼は私よりずっと背が高くて、話をしています。
私はパイロットに「一緒に買い物しませんか?」
パイロットは携帯を取り出して言いました。「明日の午後は出勤します。ゆっくり休んでください。」
携帯を取り出して彼と連絡先を交換しました。楊さんは地図とホテルの情報を教えてくれました。飛行機の前の人と車で離れました。
遠くに手を招いて、車に乗せられて離れました。ホテルに行って、部屋に入ると、素敵な内装に驚きました。
私は部屋の静かな体験が好きです。壁の絵は面白いです。ソファーに座って、天井を見ています。「いつか多くのお金を稼いで、毎日このような環境の中で、とても穏やかで、私を愛する人がいます。一緒に生命の繁栄を楽しみましょう。」
バスルームに行ってシャワーを浴びて、パジャマを着替えて、ベッドの上に飛んで、すぐに寝ます。
私は目を覚まして風呂に入り、服を着て、テレビ番組を見ていました。しばらくしたら、面白くない��思い、外に出て散歩するつもりです。帽子をかぶって、マスクをして、バッグの中に唐辛子の水を入れて、シャツ、ジーンズ、白い運動靴を鏡の前で左右に見ています。とてもきれいで、ドアから出たと思います。
大都会では故郷のようにあいさつもせず、デパートの近くを歩いて街を歩いています。いろいろな色の人が来ていて、驚きました。彼らのファッションは全部違っています。ジュースを売っているところに行くと、財布の中には楊真っ白雲から何百円もくれました。マスクを外してジュースを飲んでいたら、私のほしい生活だと思いました。
多くの人が振り返って私を見ています。帽子をかぶるのが忙しいです。持っている小さい鏡を取り出して、おしぼりで頬とおでこを拭いて、リップクリームを取り出して唇を潤します。私は地図を頼りに公園に行きます。そこには多くの人が芝生に座って遊んでいます。私も芝生に座って、みんなのジョギングと遊びを見ています。私は地面に横になって、ひと言を思い付きます:あなたと国際で大都、公園の日光を体験して、緑の木の葉と風はそっと揺れ動いて、光線はまだらで、あなたは私の側にいます。
広場のスクリーンに広告が流れています。人波で沸き返る大通りを散歩しています。孤独な感じで、しばらく付き合っていた人を思い出します。寂しいです。
夕方になってから、ホテルに戻って、楊容疑者は髪が濡れてソファーに座ってテレビを見ています。彼は「食べましたか?」
彼の顔を見て、「ハンバーガーを食べたばかりです。口の中にまだ味があります。」
早く洗面してください。
私は急いで服を脱いで、一日の汗を洗い、洗い終わった。パジャマを着て、楊騷雲のそばに来た。
彼は言いました。「これから使ったパジャマとタオルはホテルに取り替えてもらいます。きれいにしてください。」
私は急いでうなずいて言いました。「初めてあなたを見た時、あなたはとても遠いと感じました。あなたは今私の隣に座っています。夢のようです。」
彼は振り向いて私を見て、言いました。「今はまだ小さいです。あなたのだらしなさに耐えたいです。ずっとあなたのそばにいて、あなたが似合うかどうか見たいです。他の人に離れないようにしてください。あなたがどれだけ自分を愛しているかを見てください。」
私は目をぱちぱちさせながら言いました。「あなたが言ったことは考えられませんでした。自分を愛することを教えてください。」
髪の毛が濡れています。母が髪の毛を乾かさないと脳卒中になりやすいと言っていますが、乾かないですか?彼の意見を聞いています。
彼は口もとを上に曲げてカーブを作って言いました。「あなたと私の関係はあまり良くないです。髪の毛を乾かしてください。」
浴室に行ってドライヤーを出して、彼の髪をふいてあげます。
ドライヤーを使うのは初めてですか?彼は優しく尋ねた。
髪の毛を洗ったら、乾かします。よく吹きませんでした。髪の毛が乱れてしまうのではないかと心配しています。
「髪を吹いてくれてとても楽しかったです。久しぶりにこんな感じを体験しました。」
「どんな感じですか?」
彼は軽く頭を振って,笑って答えない。彼のために髪を乾かしました。ドライヤーを元の位置に返します。
「今日は街をぶらつきに行きました。小さい頃は世界の街だと思っていました。市内が広いので、とても新鮮です。いろんな人種の人たちがいます。彼らの顔は私たちと違って、服も違っています。これからはここに住むことができると思います。」ソファーに座って、彼の右手を引っ張って話します。
あなたはお金をたくさん稼ぎます。帰り道が見つからないので心配です」一面の雲がゆるみ、けだるいように横たわっています。
これは私がもらった最高の卒業プレゼントです。
「三日間だけ滞在します。今回の旅行があなたの心の傷を癒してくれますように、楽しみにしています。」
「なぜ自分が悲しいのか分かりません。何かを食べて胸が痛くなり、涙がこぼれました。友情が招いたと勘違いしました。」
彼はしっかりと私の手を握って、私に言いました。「あなたは恋人が一人しかいません。恋人が一人しかいません。二人は長年あなたが持っていない友情です。あなたは大切にしました。あなたが愛したことがあります。どんなに多くの抵抗があっても仕方がないです。未来の道は孤独ですが、出会いを学びたいです。」
あなたは私の友達ですか?眉をひそめて聞く。
「眉をしかめると、眉の角に筋肉ができて悪魔のような顔になります。子供を騙したくないです。友達ではないです。いつか離れます。最近頭が混乱しています。自分で自分の面倒を見てほしいです。」
ずっとあなたを愛しています。ずっとあなたのことが好きです。初めて会ったところにいます。離れません。彼の手をしっかりつかんで、心臓の近くに置きます。
あなたは私の顔に惹かれますか?それとも私の服に惹かれますか?
全部ありますそれに、あなたの身長が羨ましいです。残念ながら、隣の人からもらった毒で、背が伸びることができなくなりました。身長が六、五メートルというのは一生耐えられないです。これからはおしゃれを習って、自分を綺麗にします。
今のあなたも醜くないです。
最近眠れなくなりました。未来はずっと眠れないかどうか分かりません。
「お供します。ベッドに入って、お話をします。」ヤングクラウドが私の王女をベッドに抱いて、彼の右側に横になって彼の話を聞いています。
この本を書いた時、哲理が分かりました。
「昔は子猫とウサギがいました。彼らは仲の良い友達です。子猫はいつも川で釣りをしています。ウサギはいつも土の中で大根を掘っています。彼らは仲がよくて、いつも一緒に食事をします。ウサギは魚を食べません。猫は大根を食べないので、魚がなくなったり、大根がなくなったら一緒に他のところに行きます。「ある日、彼らは新しい場所に行きました。黒うさぎと黒猫を見ました。彼らは離れたことがなく、快適な大きな家に住んでいます。幸せな生活を送っています。うさぎちゃんとねこちゃんは美しい生活に一瞬で魅了されました。毎日のクロウサギは大根を掘るだけではなく、まめに大根を植えています。黒猫は池を手入れしています。このように彼らの食べ物は後を絶たず、ウサギや猫のようにあちこち移動しなくてもいいです。食べ物を探したり、道を移動したりする時間を多く使わなくてもいいです。家や垣根の園を作る時間がもっと多くなりました。家具もいろいろあります。
楊さんは私を見て、続けて言いました。ウサギちゃんと猫ちゃんは喜んで彼らを受け入れました。数年後、彼らは城を建てて、もっと多くの仲間ができました。彼らはこの上なく楽しく過ごしました。」
話が終わったら寝ます。
「あなたの前では子供のように感じられます。あなたがストーリーを話してくれてとても嬉しいです。この席ですぐ寝ます。今晩一緒にいてもいいですか?」
「うん」彼は肯定しています。私はすぐに甘い夢の中に入りました。
毎日散歩に出かけて、車に乗って窓の外の都市の風景を見ています。夜、私は楊蚯雲と夜景を見て、美しい都市を見ました。「自分の青春時代にマスクをしていました。いつか私の美しい顔がきれいにならなくて、もったいないと思う時があります。」
ヤンさんは私のこの感嘆を聞いて、思わず大笑いしました。「いつかあなたはブスになるかもしれません。」
「それは大変ですね。でも怖くないです。十分なお金を稼いだら、自分の顔を綺麗にしてくれるはずです。
マスクを外してもいいです。肌がそんなに白いです。誰もおかしいと思わないし、私がいます。何が怖いですか?
彼の話を聞いて、私も自分が安全だと思って、マスクを外して、通行人はいつも振り向いて私を見ています。あの時代はまだ「振り返る率」というネットスラングがなかったので、彼がそばにいると安心しました。
その日の夜、私たちはステーキを食べに行きました。もっと遠いところを回って、ホテルに帰りました。彼に聞きました。
楊さんは雲さんに頭をなでて言いました。「もう仕事を完成しました。もし新鮮さがあれば、何日間一緒にいられますか?」
「一日二十四時間は私のそばにいるという意味ですか?」
楊さんは雲をかぶってうなずいた。私は彼の懐に飛び込んで、「お兄さんがいて、とてもかわいがります。」
楊容疑者は私を懐に抱いて、「いつ自分の部屋に戻りますか?」
何ですかちょっと迷っています。
あなたの家は狭いですが、そこはあなたの部屋です。いつも実家に頼ってはいけません。
私は経済的に自立していません。両親のところに住んでいません。どのように服を着て食事をしますか?学校の授業料までです。自分で稼いだと思いますか?あなたは私があなたを探すことができると思います。このよく知らない国際大都市の中で、見知らぬ人はあなたと仲がいいと思います。私は年下です。あなたに頼ることができます。出張のついでに、私を連れて世間を見に来てください。」
あなたの話を聞いてとても嬉しいです。私もあなたに内緒にしないで、ここ数日で一緒に過ごします。楊容疑者の表情は少しぎこちないです。
あなたの仕事は分かります。相変わらず愛しています。またお会いしましょうか?」
分かりません。
「それはすべての縁です。長く付き合っていますが、おいくつですか?」
あなたが知っていると思いました。
私は頭を振って言いました。「分かりません。」
今年は二十三歳です。
「いい歳ですね。あなたの年齢で幸せになりますように。」
重慶に帰ったら、何をするつもりですか?一面の雲が私を抱いて聞きます。
「私の仕事を続けています。給料はそんなに高くないですが、まだ若いです。公務員になりたいと思っていましたが、この様子では、全員が私が最低で、基礎も壊してほしいと願っています。不可能です。私は本を読んで良い大学を試験して、良い仕事を探し当てて、私の小さい家を装飾して、自分で大きい部屋を買って、店をオープンして、企業をします。安定収入がよくて、あちこち歩き回っています。まだ世界を見たことがありません。見に行きたいです。余生を享楽しながら、シンプルに楽しく過ごします」
楊容疑者は慎重に私を見て、「あなたが欲しいのは鐘が鳴る生活です。」
「間違いない!」
もしある日あなたが本当にできたら、私を引っ張ることができますか?
私は30代のうちに���標を達成して、毎年200万円の���益を上げて、できるだけ毎年の利益を上げていきたいです。千万円がある時に来てくれれば、歓迎します。その時のこのお金は私たちの生活費に十分です。でも、私が本当にできるようにしないと、一緒に貧しい生活を送ります。
落さん、どうしてあなたが私をあなたに要求しましたが、あなたは私に要求しませんでしたか?
私はそっと言いました。「今のあなたは何を手伝ってくれますか?あなたの羽根が豊かな時に、もし私が思い付いた目標を達成するならば、あなたは私を助けてくれます。資金を起動して儲けるのは簡単ではないです。短期的に上昇することは難しいです。
もし私が助けられなかったら?楊容疑者は慎重に質問した。
「それはいいです。私もあなたの大切な人ではありません。何か予定がありますか?」
あなたの優しさに感謝します。あなたに出会ったのは私の幸運です。あなたの秘密は守ります。絶対に言いません。」
ありがとうございます実は秘密でもないです。もう慣れました。」
私は簡単なつもりです。綺麗な奥さんを探して、このまま過ごしました。
いい計画ですね。もう適当な人がいますか?
まだ追っています
成功を求めてほしいです。
「将来的に企業を成功させたいです。これからも故郷に帰りますか?」
彼らはまだそこにいます。私はいつも帰ります。老いても重慶に残ります。江津の冬は寒いです。南岸に住むかもしれません。
「お金があったら、暖房器具をつけて、お手伝いさんが世話してくれます。まだそこにいますか?」
「もちろん、毎日がシンプルでいいです。でも、大都市の生活を見ています。故郷のあっさりした人生に慣れるかどうかは分かりません。
「だから、未来は不安です。帰って、そこで暮らしたり、家族のお供をしたりするべきです。あなたが去ったら、帰りにくいと思います。」
「わかりました。あなたの言っていることも正しいです。私のような若僧は子供の時からどこまでも家です。卒業後、広州に行きます。お金を稼いで、だんだん発展します。いつか私の会社は深センの甲級オフィスビルにいます。そこで仕事をします。
私たちはもう二日間滞在しましたが、この二日間は一面真っ白な雲があって、私と一緒に幸せです。もっと遠くの観光スポットを回ってみましたが、写真を撮っていませんでした。
「ある日あなたは作文に成功しました。私たちが歩いたところと楽しみを文字にしました。」
若い私はまだ写真の記念の意味が分かりません。もし写真を撮ったら、今出しても懐かしいと思います。
帰りの飛行機で豆乳を一杯持ってきました。ありがとうございます。リュックサックからキャンデーを二つ取り出して、彼に一つを渡しました。
彼はキャンデーを持ったことがあります。私は自分のキャンデーの包装を引き裂いて口に入れます。「一人で好きになるのはとてもいい感じです。」彼は荷物を開けました。中にアルミの金属箱があります。渡してくれました。「プレゼントは何もありません。7歳の時に銃器の使い方がとてもよかったです。この中にはシミュレーションの銃があります。記念として残してください。」
彼のプレゼントを受け取って箱を開けたら、中は小さくて精巧な米国のカートM 9111の模型で、私は模型銃のベルトを解いて、銃身を触ります。「これは全部の金属ですか?」
「金属製品は長く保存されます。」
プレゼントをくれてありがとうございます。小さい年齢の私は分かりません。私は銃を置いて、アルミの金属箱を隣のテーブルに置いた。私は続けて言います。「初めてお会いしました。その感じは本当に素晴らしいです。」
楊さんは雲にぼーっとしていて、話をしていません。
飛行機が到着した後、もう夜明けです。楊蝓雲さんからのプレゼントを他の人に渡しました。「家に帰ってこれを持ってくるのは不便です。後でください。」私は楊鳔雲に乗り継ぎをして、飛行機の明かりが次第に上がるのを見ていて、だんだん消えていきます。
私はため息をついて、渝中区に行き、ケーキを買って部屋に入りました。
私はろうそくを取り出して、全部で16本をケーキの上に挿して、ろうそくに火をつけて、願い事をして、また一気に息を吸って、ろうそくを吹き消して、私は自分に言います。「今年は16歳です。誕生日おめでとうございます。」
鏡の前に行って、「これからは苦労しても、そんなに強いお酒を飲むな」と自分に言いました。
私は酒棚のワインを取り出して、自分のために小さなコップを注いだが、酒気をかいでいて、急に吐き気がして、グラスの酒をこぼしてしまった。
「しまった、胃の調子が悪くなりました。体を養生したいです。残念ですが、このバラフェです。」私は木の栓をしっかりと瓶の口を塞ぎました。「これからも飲んでほしいです。バカです。これは半年分の給料です。」
ケーキを分けて、自分で一つ食べました。食べきれないだけでお腹がいっぱいになりました。
横になって3時間以上休んで、車で江津の周辺に行きます。ヘリコプターが私を待っています。ロープを締めて屋上に降ります。
下に下りて、ドアを開けて、ベッドに横になって引き続きぐうぐう寝て、私は疲れきっています。夜、両親が家に帰っても分かりません。勝手に何かを食べました。
夜中に目が覚めて、ロッカーの中の小霊通を充電しました。誰も連絡してくれませんでした。
ベッドのそばに座っています。この都市はとても悲しいようで、突然眠れません。そこでテレビをつけて、音楽番組のランキング音楽を聞いて、だんだん心が落ち着きました。
その日の朝早くお母さんのところに行って、毎日何十斤の唐辛子をお客さんにつぶしてあげます。私はちょうど休みになりました。そこで手伝います。毎回鉄板を上げて唐辛子をつぶしている時、井山兄さんと天蕊を懐かしみます。
私は100元を使って、車屋で自転車を買いました。午後は用事がない時に広場で練習します。
母は顔をしかめながら、「安いから、壊れやすい」と笑った。
「まずは覚えておきます。壊れたら捨てます。どうせ高くないです。」彼女を慰めながら言った。
初日はなかなか上手になれませんでした。どうしてもバランスが取れなくて、翌日はおじさんのおばさんの助けで自転車を覚えました。四五メートルまで乗れるようになりました。
自転車を覚えた後、私は川のそばで自転車に乗るのが好きです。風が襟を吹いています。私は新しい出会いを迎えています。これらの美しい記憶はここで一段落しました。
私は川のそばに立って夕日を見ています。綺麗な落日に対して、「あなたと抱き合って、あなたがくれた最高のプレゼントです。」
まぶしいと、二十九歳で、大きな木を通って、心より静かに過ごします。
終了:2020年5月18日月曜日
0 notes
Text
【小説】The day I say good-bye(4/4) 【再録】
(3/4)はこちらから→(https://kurihara-yumeko.tumblr.com/post/648720756262502400/)
今思えば、ひーちゃんが僕のついた嘘の数々を、本気で信じていたとは思えない。
何度も何度も嘘を重ねた僕を、見抜いていたに違いない。
「きゃああああああああああああーっ!」
絶叫、された。
耳がぶっ飛ぶかと思った。
長い髪はくるくると幾重にもカーブしていた。レースと玩具の宝石であしらわれたカチューシャがまるでティアラのように僕の頭の上に鎮座している。桃色の膨らんだスカートの下には白いフリルが四段。半袖から剥き出しの腕が少し寒い。スカートの中もすーすーしてなんだか落ち着かない。初めて穿いた黒いタイツの感触も気持ちが悪い。よく見れば靴にまでリボンが付いている。
鏡に映った僕は、どう見てもただの女の子だった。
「やっだー、やだやだやだやだ、どうしよー。――くんめっちゃ女装似合うね!」
クラス委員長の長篠めいこさん(彼女がそういう名前であることはついさっき知った)は、女装させられた僕を明らかに尋常じゃない目で見つめている。彼女が僕にウィッグを被らせ、お手製のメイド服を着せた本人だというのに、僕の女装姿に瞳を爛々と輝かせている。
「準備の時に一度も来てくれないから、衣装合わせができなくてどうなるかと思っていたけど、サイズぴったりだね、良かった。――くんは華奢だし細いし顔小さいしむさくるしくないし、女装したところでノープロブレムだと思っていたけれど、これは予想以上だったよっ」
準備の際に僕が一度も教室を訪れなかったのは、連日、保健室で帆高の課題を手伝わされていたからだ。だけれどそれは口実で、本当はクラスの準備に参加したくなかったというのが本音。こんなふざけた企画、携わりたくもない。
僕が何を考えているかを知る由もない長篠さんは、両手を胸の前で合わせ、真ん丸な眼鏡のレンズ越しに僕を見つめている。レーザー光線のような視線だ。見つめられ続けていると焼け焦げてしまいそうになる。助けを求めて周囲をすばやく見渡したが、クラスメイトのほぼ全員がコスチュームに着替え終わっている僕の教室には、むさくるしい男のメイドか、ただのスーツといっても過言ではない燕尾服を着た女の執事しか見当たらない。
「すね毛を剃ってもらう時間はなかったので、急遽、脚を隠すために黒タイツを用意したのも正解だったね。このほっそい脚がさらに際立つというか。うんうん、いい感じだねっ!」
長篠さん自身、黒いスーツを身に纏っている。彼女こそが、今年の文化祭でのうちのクラスの出し物、「男女逆転メイド・執事喫茶」の発案者であり、責任者だ。こんなふざけた企画をよくも通してくれたな、と怨念を込めてにらみつけてみたけれど、彼女は僕の表情に気付いていないのかにこにこと笑顔だ。
「ねぇねぇ、――くん、せっかくだし、お化粧もしちゃう? ネイルもする? 髪の毛もっと巻いてあげようか? あたし、――くんだったらもっと可愛くなれるんじゃないかなって思うんだけど」
僕の全身を舐め回すように見つめる長篠さんはもはや正気とは思えない。だんだんこ���人が恐ろしくなってきた。
「めいこ、その辺にしておきな」
僕が何も言わないでいると、思わぬ方向から声がかかった。
振り向くと僕の後ろには、長身の女子が立っていた。男子に負けないほど背の高い彼女は、教室の中でもよく目立つ。クラスメイトの顔と名前をろくに記憶していない僕でも、彼女の姿は覚えていた。それは背が高いという理由だけではなく、言葉では上手く説明できない、長短がはっきりしている複雑で奇抜な彼女の髪型のせいでもある。
背が決して高いとは言えない僕よりも十五センチほど長身の彼女は、紫色を基調としたスーツを身に纏っている。すらっとしていて恰好いい。
「――くん、嫌がってるだろう」
「えー、あたしがせっかく可愛くしてあげようとしてるのにー」
「だったら向こうの野球部の連中を可愛くしてやってくれ。あんなの、気味悪がられて客を逃がすだけだよ」
「えー」
「えー、とか言わない。ほらさっさと行きな。クラス委員長」
彼女に言われたので仕方なく、という表情で長篠さんが僕の側から離れた。と、思い出したかのように振り向いて僕に言う。
「あ、そうだ、――くん、その腕時計、外してねっ。メイド服には合わないからっ」
この腕時計の下には、傷跡がある。
誰にも見せたことがない、傷が。
それを晒す訳にはいかなかった。僕がそれを無視して長篠さんに背を向けようとした時、側にいた長身の彼女が僕に向かって口を開いた。
「これを使うといいよ」
そう言って彼女が差し出したのは、布製のリストバンドだった。僕のメイド服の素材と同じ、ピンク色の布で作られ、白いレースと赤いリボンがあしらわれている。
「気を悪くしないでくれ。めいこは悪気がある訳じゃないんだけど……」
僕の頭の中は真っ白になっていた。突然手渡されたリストバンドに反応ができない。どうして彼女は、僕の手首の傷を隠すための物を用意してくれているんだ? 視界の隅では長篠さんがこちらに背を向けて去って行く。周りにいる珍妙な恰好のクラスメイトたちも、誰もこちらに注意を向けている様子はない。
「一体、どういう……」
そう言う僕はきっと間抜けな顔をしていたんだろう、彼女はどこか困ったような表情で頭を掻いた。
「なんて言えばいいのかな、その、きみはその傷を負った日のことを、覚えてる?」
この傷を負った日。
雨の日の屋上。あーちゃんが死んだ場所。灰色の空。緑色のフェンス。あと一歩踏み出せばあーちゃんと同じところに行ける。その一歩の距離。僕はこの傷を負って、その場所に立ち尽くしていた。
同じところに傷を負った、ミナモと初めて出会った日だ。
「その日、きみ、保健室に来たでしょ」
そうだ。僕はその後、保健室へ向かった。ミナモは保健室を抜け出して屋上へ来ていた。そのミナモを探しに来た教師に僕とミナモは発見され、ふたり揃って保健室で傷の手当を受けた。
「その時私は、保健室で熱を測っていたんだ」
あの時に保健室に他に誰かいたかなんて覚えていない。僕はただ精いっぱいだった。死のうとして死ねなかった。それだけで精いっぱいだったのだ。
長身の彼女はそう言って、ほんの少しだけ笑った。それは馬鹿にしている訳でもなく、面白がっている訳でもなく、微笑みかけてくれていた。
「だから、きみの手首に傷があることは知ってる。深い傷だったから、痕も残ってるんだろうと思って、用意しておいたんだ」
私は裁縫があまり得意ではないから、めいこの作ったものに比べるとあまり良い出来ではないけどね。彼女はそう付け足すように言う。
「使うか使わないかは、きみの自由だけど。そのまま腕時計していてもいいと思うしね。めいこは少し、完璧主義すぎるよ。こんな中学生の女装やら男装やらに、完璧さなんて求めてる人なんかいないのにね」
僕はいつも、自分のことばかりだ。今だって、僕の傷のことを考慮してくれている人間がいるなんて、思わなかった。
それじゃあ、とこちらに背を向けて去って行こうとする彼女の後ろ姿を、僕は呼び止める。
「うん?」
彼女は不思議そうな顔をして振り向いた。
「きみの、名前は?」
僕がそう尋ねると、彼女はまた笑った。
「峠茶屋桜子」
僕は生まれて初めて、クラスメイトの顔と名前を全員覚えておかなかった自分を恥じた。
峠茶屋さんが作ってくれたリストバンドは、せっかくなので使わせてもらうことにした。
それを両手首に装着して保健室へ向かってみると、そこには河野ミナモと河野帆高の姿が既にあった。
「おー、やっと来たか……って、え、ええええええええええええ!?」
椅子に腰掛け、行儀の悪いことに両足をテーブルに乗せていた帆高は、僕の来訪を視認して片手を挙げかけたところで絶叫しながら椅子から落下した。頭と床がぶつかり合う鈍い音が響く。ベッドのカーテンの隙間から様子を窺うようにこちらを見ていたミナモは、僕の姿を見てから興味なさそうに目線を逸らす。相変わらず無愛想なやつだ。
「な、何、お前のその恰好……」
床に転がったまま帆高が言う。
「何って……メイド服だけど」
帆高には、僕のクラスが男女逆転メイド・執事喫茶を文化祭の出し物でやると言っておいたはずだ。僕のメイド服姿が見物だなんだと馬鹿にされたような記憶もある。
「めっちゃ似合ってるじゃん、お前!」
「……」
不本意だけれど否定できない僕がいる。
「びびる! まじでびびる! お前って実は女の子だった訳!?」
「そんな訳ないだろ」
「ちょっと、スカートの中身、見せ……」
床に座ったまま僕のメイド服に手を伸ばす帆高の頭に鉄拳をひとつお見舞いした。
そんな帆高も頭に耳、顔に鼻、尻に���尾を付けており、どうやら狼男に変装しているようだ。テーブルの上には両手両足に嵌めるのであろう、爪の生えた肉球付きの手袋が置いてある。これぐらいのコスプレだったらどれだけ心穏やかでいられるだろうか。僕は女装するのは人生これで最後にしようと固く誓った。
「そんな恰好で恥ずかしくないの? 親とか友達とか、今日の文化祭に来ない訳?」
「さぁ……来ないと思うけど」
僕の両親は今日も朝から仕事に行った。そもそも、今日が文化祭だという事実も知っているとは思えない。
別の中学校に通っている小学校の頃の友人たちとはもう連絡も取り合っていないし、顔も合わせていないので、来るのか来ないのかは知らない。僕以外の誰かと親交があれば来るのかもしれないが、僕には関係のない話だ。
そう、そのはずだった。だが僕の予想は覆されることになる。
午前十時に文化祭は開始された。クラス委員長である長篠めいこさんが僕に命じた役割は、クラスの出し物である男女逆転メイド・執事喫茶の宣伝をすることだった。段ボール製のプラカードを掲げて校舎内を循環し、客を呼び込もうという魂胆だ。
結局、ミナモとは一言も言葉を交わさずに出て来てしまった、と思う。うちの学校の文化祭は一般公開もしている。今日の校内にはいつも以上に人が溢れている。保健室登校のミナモにとっては、つらい一日になるかもしれない。
お化け屋敷を出し物にしているクラスばかりが並んでいる、我が校の文化祭名物「お化け屋敷ロード」をすれ違う人々に異様な目で見られていることをひしひしと感じながら、プラカードを掲げ、チラシを配りながら歩いていくと、途中で厄介な人物に遭遇した。
「おー、少年じゃん」
日褄先生だ。
目の周りを黒く塗った化粧や黒尽くめのその服装はいつも通りだったが、しばらく会わなかった間に、曇り空より白かった頭髪は、あろうことか緑色になっていた。これでスクールカウンセラーの仕事が務まるのだろうか。あまりにも奇抜すぎる。だが咄嗟のことすぎて、驚きのあまり声が出ない。
「ふーん、めいこのやつ、裁縫上手いんじゃん。よくできてる」
先生は僕の着用しているメイド服のスカートをめくろうとするので、僕はすばやく身をかわして後退した。「変態か!」と叫びたかったが、やはり声にならない。
助けを求めて周囲に視線を巡らせて、僕は人混みからずば抜けて背の高い男性がこちらに近付いてくるのがわかった。
前回、図書館の前で出会った時はオールバックであったその髪は、今日はまとめられていない。モスグリーンのワイシャツは第一ボタンが開いていて、おまけにネクタイもしていない。ズボンは腰の位置で派手なベルトで留められている。銀縁眼鏡ではなく、色の薄いサングラスをかけていた。シャツの袖をまくれば恐らくそこには、葵の御紋の刺青があるはずだ。左手の中指に日褄先生とお揃いの指輪をしている彼は、日褄先生の婚約者だ。
「葵さん……」
僕が名前を呼ぶと、彼は僕のことを睨みつけた。しばらくして、やっと僕のことが誰なのかわかったらしい。少し驚いたように片眉を上げて、口を半分開いたところで、
「…………」
だが、葵さんは何も言わなかった。
僕の脇を通り抜けて、日褄先生のところに歩いて行った。すれ違いざまに、葵さんが何か妙なものを小脇に抱えているなぁと思って振り返ってみると、それは大きなピンク色のウサギのぬいぐるみだった。
「お、葵、お帰りー」
日褄先生がそう声をかけると、葵さんは無言のままぬいぐるみを差し出した。
「なにこのうさちゃん、どうしたの?」
先生はそれを受け取り、ウサギの頭に顎を置きながらそう訊くと、葵さんは黙って歩いてきた方向を指差した。
「ああ、お化け屋敷の景品?」
葵さんはそれには答えなかった。そもそも僕は、彼が口を利いたところを見たことがない。それだけ寡黙な人なのだ。彼は再び僕を見ると、それから日褄先生へ目線を送った。ウサギの耳で遊ぶのに夢中になっていた先生はそれに気付いているのかいないのか、
「男女逆転メイド・執事喫茶、やってるんだって」
と僕の服装の理由を説明した。だが葵さんは眉間の皺を深めただけだった。そしてそのまま、彼は歩き出してしまう。日褄先生はぬいぐるみの耳をぱたぱた手で動かしていて、それを追おうともしない。
「……いいんですか? 葵さん、行っちゃいましたけど……」
「あいつ、文化祭ってものを見たことがないんだよ。ろくに学校行ってなかったから。だから連れて来てみたんだけど、なんだか予想以上にはしゃいじゃってさー」
葵さんの態度のどこがはしゃいでいるように見えるのか、僕にはわからないが、先生にはわかるのかもしれない。
「あ、そうだ、忘れるところだった、少年のこと、探しててさ」
「何か用ですか?」
「はい、チーズ」
突然、眩しい光が瞬いた。一体いつ、どこから取り出したのか、先生の手にはインスタントカメラが握られていた。写真を撮られてしまったようだ。メイド服を着て、付け毛を付けている、僕の、女装している写真が……。
「な、ななななななな……」
何をしているんですか! と声を荒げるつもりが、何も言えなかった。日褄先生は颯爽と踵を返し、「あっはっはっはっはー!」と笑いながら階段を駆け下りて行った。その勢いに、追いかける気も起きない。
僕はがっくりと肩を落とし、それでもプラカードを掲げながら校内の循環を再開することにした。僕の予想に反して、賑やかな文化祭になりそうな予感がした。
お化け屋敷ロードの一番端は、河野帆高のクラスだったが、廊下に帆高の姿はなかった。あいつはお化け役だから、教室の中にいるのだろう。
あれから、帆高はあーちゃんが僕に残したノートについ��一言も口にしていない。僕の方から語ることを待っているのだろうか。協力してもらったのだから、いずれきちんと話をするべきなんじゃないかと考えてはいるけれど、今はまだ上手く、僕も言葉にできる自信がない。
廊下の端の階段を降りると、そこは射的ゲームをやっているクラスの前だった。何やら歓声が上がっているので中の様子を窺うと、葵さんが次々と景品を落としているところだった。大人の本気ってこわい。
中央階段の前の教室では、自主製作映画の上映が行われているようだった。「戦え!パイナップルマン」というタイトルの、なんとも言えないシュールな映画ポスターが廊下には貼られている。地球侵略にやってきたタコ星人ヲクトパスから地球を救うために、八百屋の片隅で売れ残っていた廃棄寸前のパイナップルが立ち上がる……ポスターに記されていた映画のあらすじをそこまで読んでやめた。
ちょうど映画の上映が終わったところらしい、教室からはわらわらと人が出てくる。僕は歩き出そうとして、そこに見知った顔を見つけてしまった。
色素の薄い髪。切れ長の瞳と、ひょろりとした体躯。物静かな印象を与える彼は、
「あっくん……」
「うー兄じゃないですか」
妙に大人びた声音。口元の端だけを僅かに上げた、作り笑いに限りなく似た笑顔。
鈴木篤人くんは、僕よりひとつ年下の、あーちゃんの弟だ。
「一瞬、誰だかわかりませんでしたよ。まるで女の子だ」
「……来てたんだ、うちの文化祭」
私立の中学校に通うあっくんが、うちの中学の文化祭に来たという話は聞いたことがない。それもそのはずだ。この学校で、彼の兄は飛び降り自殺したのだから。
「たまたま今日は部活がなかったので。ちょっと遊びに来ただけですよ」
柔和な笑みを浮かべてそう言う。だけれどその笑みは、どこか嘘っぽく見えてしまう。
「うー兄は、どうして女装を?」
「えっと、男女逆転メイド・執事喫茶っていうの、クラスでやってて……」
僕は掲げていたプラカードを指してそう説明すると、ふうん、とあっくんは頷いた。
「それじゃあ、最後にうー兄のクラスを見てから帰ろうかな」
「あ、もう帰るの?」
「本当は、もう少しゆっくり見て行くつもりだったんですが……」
彼はどこか困ったような表情をして、頭を掻いた。
「どうも、そういう訳にはいかないんです」
「何か、急用?」
「まぁ、そんなもんですかね。会いたくない人が――」
あっくんはそう言った時、その双眸を僅かに細めたのだった。
「――会いたくない人が、ここに来ているみたいなので」
「そう……なんだ」
「だからすみません、今日はそろそろ失礼します」
「ああ、うん」
「うー兄、頑張って下さい」
「ありがとう」
浅くもなく深くもない角度で頭を下げてから、あっくんは人混みの中に消えるように歩き出して行った。
友人も知人も少ない僕は、誰にも会わないだろうと思っていたけれど、やっぱり文化祭となるとそうは言っていられないみたいだ。こうもいろんな人に自分の女装姿を見られると、恥ずかしくて死にたくなる。穴があったら入りたいとはまさにこのことなんじゃないだろうか。
教室で来客の応対をしたりお菓子やお茶の用意をすることに比べたらずっと楽だが、こうやって校舎を循環しているのもなかなかに飽きてきた。保健室でずる休みでもしようか。あそこには恐らく、ミナモもいるはずだから。
そうやって僕も歩き出し、保健室へ続く廊下を歩いていると、僕は突然、頭をかち割われたような衝撃に襲われた。そう、それは突然だった。彼女は唐突に、僕の前に現れたのだ。
嘘だろ。
目が、耳が、口が、心臓が、身体が、脳が、精神が、凍りつく。
耳鳴り、頭痛、動悸、震え。
揺らぐ。視界も、思考も。
僕はやっと気付いた。あっくんが言う、「会いたくない人」の意味を。
あっくんは彼女がここに来ていることを知っていた。だから会いたくなかったのだ。
でもそんなはずはない。世界が僕を置いて行ったように、きみもそこに置いて行かれたはずだ。僕のついた不器用な嘘のせいで、あの春の日に閉じ込められたはずだ。きみの時間は、止まったはずだ。
言ったじゃないか、待つって。ずっと待つんだって。
もう二度と帰って来ない人を。
僕らの最愛の、あーちゃんを。
「あれー、うーくんだー」
へらへらと、彼女は笑った。
「なにその恰好、女の子みたいだよ」
楽しそうに、愉快そうに、面白そうに。
あーちゃんが生きていた頃は、一度だってそんな風に笑わなかったくせに。
色白の肌。華奢で小柄な体躯。相手を拒絶するかのように吊り上がった猫目。伸びた髪。身に着けている服は、制服ではなかった。
でもそうだ。
僕はわかっていたはずだ。日褄先生は僕に告げた。ひーちゃんが、学校に来るようになると。いつかこんな日が来ると。彼女が、世界に追いつく日がやって来ると。
僕だけが、置いて行かれる日が来ることを。
「久しぶりだね、うーくん」
「……久しぶり、ひーちゃん」
僕は、ちっとも笑えなかった。あーちゃんが生きていた頃は、ちゃんと笑えていたのに。
市野谷比比子はそんな僕を見て、満面の笑みをその顔に浮かべた。
「……だんじょぎゃくてん、めいど……しつじきっさ…………?」
たどたどしい口調で、ひーちゃんは僕が持っていたプラカードの文字を読み上げる。
「えっとー、男女が逆だから、うーくんが女の子の恰好で、女の子が男の子の恰好をしてるんだね」
そう言いながら、ひーちゃんはプラスチック製のフォークで福神漬けをぶすぶすと刺すと、はい、と僕に向かって差し出してくる。
「これ嫌い、うーくんにあげる」
「どうも」
僕はいつから彼女の嫌いな物処理係になったのだろう、と思いながら渡されたフォークを受け取り、素直に福神漬けを咀嚼する。
「でもうーくん、女装似合うね」
「それ、あんまり嬉しくないから」
僕とひーちゃんは向き合って座っていた。ひーちゃんに会ったのは、僕が彼女の家を訪ねた夏休み以来だ。彼女はあれから特に変わっていないように見える。着ている服は今日も黒一色だ。彼女は、最愛の弟、ろーくんが死んだあの日から、ずっと黒い服を着ている。
僕らがいるのは新校舎二階の一年二組の教室だ。PTAの皆さまが営んでいるカレー屋である。この文化祭で調理が認められているのは、大人か、調理部の連中だけだ。午後になり、生徒も父兄も体育館で行われている軽音部やら合唱部やらのコンサートを観に行ってしまっているので、校舎に残る人は少ない。店じまいしかけているカレー屋コーナーで、僕たちは遅めの昼食を摂っていた。僕は未だに、メイド服を着たままだ。
ひーちゃんとカレーライスを食べている。なんだか不思議な感覚だ。ひーちゃんがこの学校にいるということ自体が、不思議なのかもしれない。彼女は入学してからただの一度も、この学校の門をくぐったことがなかったのだ。
どうしてひーちゃんは、ここにいるんだろう。ひーちゃんにとって、ここは、もう終わってしまった場所のはずなのに。ここだけじゃない。世界じゅうが、彼女の世界ではなくなってしまったはずなのに。あーちゃんのいない世界なんて、無に等しいはずなのに。なのにひーちゃんは、僕の目の前にいて、美味しそうにカレーを食べている。
ときどき、僕の方を見て、話す。笑う。おかしい。だってひーちゃんの両目は、いつもどこか遠くを見ていたはずなのに。ここじゃないどこかを夢見ていたのに。
いつかこうなることは、わかっていた。永遠なんて存在しない。不変なんてありえない。世界が僕を置いて行ったように、いずれはひーちゃんも動き出す。僕はずっとそうわかっていたはずだ。僕が今までについた嘘を全部否定して、ひーちゃんが再び、この世界で生きようとする日が来ることを。
思い知らされる。
あの日から僕がひーちゃんにつき続けた嘘は、あーちゃんは本当は生きていて、今はどこか遠くにいるだけだと言ったあの嘘は、何ひとつ価値なんてなかったということを。僕という存在がひーちゃんにとって、何ひとつ価値がなかったということを。わかっていたはずだ。ひーちゃんにとっては僕ではなくて、あーちゃんが必要なんだということを。あーちゃんとひーちゃんと僕で、三角形だったなんて大嘘だ。僕は最初から、そんな立ち位置に立てていなかった。全てはそう思いたかった僕のエゴだ。三角形であってほしいと願っていただけだ。
そうだ。
本当はずっと、僕はあーちゃんが妬ましかったのだ。
「カレー食べ終わったら、どうする? 少し、校内を見て行く?」
僕がそう尋ねると、ひーちゃんは首を左右に振った。
「今日は先生たちには内緒で来ちゃったから、面倒なことになる前に帰るよ」
「あ、そうなんだ……」
「来年は『僕』も、そっち側で参加できるかなぁ」
「そっち側?」
「文化祭、やれるかなぁっていうこと」
ひーちゃんは、楽しそうな笑顔だ。
楽しそうな未来を、思い描いている表情。
「……そのうち、学校に来るようになるんだって?」
「なんだー、あいつ、ばらしちゃったの? せっかく驚かせようと思ったのに」
あいつ、とは日褄先生のことだろう。ひーちゃんは日褄先生のことを語る時、いつも少し不機嫌になる。
「……大丈夫なの?」
「うん? 何が?」
僕の問いに、ひーちゃんはきょとんとした表情をした。僕はなんでもない、と言って、カレーを食べ続ける。
ねぇ、ひーちゃん。
ひーちゃんは、あーちゃんがいなくても、もう大丈夫なの?
訊けなかった言葉は、ジャガイモと一緒に飲み込んだ。
「ねぇ、うーくん、」
ひーちゃんは僕のことを呼んだ。
うーくん。
それは、あーちゃんとひーちゃんだけが呼ぶ、僕のあだ名。
黒い瞳が僕を見上げている。
彼女の唇から、いとも簡単に嘘のような言葉が零れ落ちた。
「あーちゃんは、もういないんだよ」
「…………え?」
僕は耳を疑って、訊き返した。
「今、ひーちゃん、なんて……」
「だから早く、帰ってきてくれるといいね、あーちゃん」
そう言ってひーちゃんは、にっこり笑った。まるで何事もなかったみたいに。
あーちゃんの死なんて、あーちゃんの存在なんて、最初から何もなかったみたいに。
僕はそんなひーちゃんが怖くて、何も言わずにカレーを食べた。
「あーちゃん」こと鈴木直正が死んだ後、「ひーちゃん」こと市野谷比比子は生きる気力を失くしていた。だから「うーくん」こと僕、――――は、ひーちゃんにひとつ嘘をついた。
あーちゃんは生きている。今はどこか遠くにいるけれど、必ず彼は帰ってくる、と。
カレーを食べ終えたひーちゃんは、帰ると言うので僕は彼女を昇降口まで見送ることにした。
二人で廊下を歩いていると、ふと、ひーちゃんの目線は窓の外へと向けられる。目線の先を追えば、そこには旧校舎の屋上が見える。そう、あーちゃんが飛び降りた、屋上が見える。
「ねぇ、どうしてあーちゃんは、空を飛んだの?」
ひーちゃんは虚ろな瞳で窓から空を見上げてそう言った。
「なん���あーちゃんはいなくなったの? ずっと待ってたのに、どうして帰って来ないの? ずっと待ってるって約束したのに、どうして? 違うね、約束したんじゃない、『僕』が勝手に決めたんだ。あーちゃんがいなくなってから、そう決めた。あーちゃんが帰って来るのを、ずっと待つって。待っていたら、必ず帰って来てくれるって。あーちゃんは昔からそうだったもんね。『僕』がひとりで泣いていたら、必ずどこからかやって来て、『僕』のこと慰めてくれた。だから今度も待つって決めた。だってあーちゃんが、帰って来ない訳ないもん。『僕』のことひとりぼっちにするはずないもん。そんなの、許せないよ」
僕には答える術がない。
幼稚な嘘はもう使えない。手持ちのカードは全て使い切られた。
ひーちゃんは、もうずっと前から気付いていたはずだ。あーちゃんはもう、この世界にいないなんだって。僕のついた嘘が、とても稚拙で下らないものだったんだって。
「嘘つきだよ、皆、嘘つきだよ。ろーくんも、あーちゃんも、嘘つき。嘘つき嘘つき嘘つき。うーくんだって、嘘つき」
ひーちゃんの言葉が、僕の心を突き刺していく。
でも僕は逃げられない。だってこれは、僕が招いた結果なのだから。
「皆大嫌い」
ひーちゃんが正面から僕に向かい合った。それがまるで決別の印であるとでも言うかのように。
ちきちきちきちきちきちきちきちき。
耳慣れた音が聞こえる。
僕の左手首の内側、その傷を作った原因の音がする。
ひーちゃんの右手はポケットの中。物騒なものを持ち歩いているんだな、ひーちゃん。
「嘘つき」
ひーちゃんの瞳。ひーちゃんの唇。ひーちゃんの眉間に刻まれた皺。
僕は思い出す。小学校の裏にあった畑。夏休みの水やり当番。あの時話しかけてきた担任にひーちゃんが向けた、殺意に満ちたあの顔。今目の前にいる彼女の表情は、その時によく似ている。
「うーくんの嘘つき」
殺意。
「帰って来るって言ったくせに」
殺意。
「あーちゃんは、帰って来るって言ったくせに!」
嘘つきなのは、どっちだよ。
「ひーちゃんだって、気付いていたくせに」
僕の嘘に気付いていたくせに。
あーちゃんは死んだってわかっていたくせに。
僕の嘘を信じたようなふりをして、部屋に引きこもって、それなのにこうやって、学校へ来ようとしているくせに。世界に馴染もうとしているくせに。あーちゃんが死んだ世界がもう終わってしまった代物だとわかっているのに、それでも生きようとしているくせに。
ひーちゃんは、もう僕の言葉にたじろいだりしなかった。
「あんたなんか、死んじゃえ」
彼女はポケットからカッターナイフを取り出すと、それを、
鈍い衝撃が身体じゅうに走った。
右肩と頭に痛みが走って、無意識に呻いた。僕は昇降口の床に叩きつけられていた。思い切り横から突き飛ばされたのだ。揺れる視界のまま僕は上半身を起こし、そして事態はもう間に合わないのだと知る。
僕はよかった。
怪我を負ってもよかった。刺されてもよかった。切りつけられてもよかった。殺されたって構わない。
だってそれが、僕がひーちゃんにできる最後の救いだと、本気で思っていたからだ。
僕はひーちゃんに嘘をついた。あーちゃんは生きていると嘘をついた。ついてはいけない嘘だった。その嘘を、彼女がどれくらい本気で信じていたのか、もしくはどれくらい本気で信じたふりを演じていてくれていたのかはわからない。でも僕は、彼女を傷つけた。だからその報いを受けたってよかった。どうなってもよかったんだ。だってもう、どうなったところで、あーちゃんは生き返ったりしないのだから。
だけど、きみはだめだ。
どうして僕を救おうとする。どうして、僕に構おうとする。放っておいてくれとあれだけ示したのに、どうして。僕はきみをあんなに傷つけたのに。どうしてきみはここにいるんだ。どうして僕を、かばったんだ。
ひーちゃんの握るカッターナイフの切っ先が、ためらうことなく彼女を切り裂いた。
ピンク色の髪留めが、宙に放られるその軌跡を僕の目は追っていた。
「佐渡さん!」
僕の叫びが、まるで僕のものじゃないみたいに響く。周りには不気味なくらい誰もいない。
市野谷比比子に切りつけられた佐渡梓は、床に倒れ込んでいく。それがスローモーションのように僕の目にはまざまざと映る。飛び散る赤い飛沫が床に舞う。
僕は起き上がり走った。ひーちゃんの虚ろな目。再度振り上げられた右手。それが再び佐渡梓を傷つける前に、僕は両手を広げ彼女をかばった。
「 」
一瞬の空白。ひーちゃんの唇が僅かに動いたのを僕は見た。その小さな声が僕の耳に届くよりも速く、刃は僕の右肩に突き刺さる。
痛み。
背後で佐渡梓の悲鳴。けれどひーちゃんは止まらない。僕の肩に突き刺さったカッターを抜くと彼女はそれをまた振り上げて、
そうだよな。
痛かったよな。
あーちゃんは、ひーちゃんの全部だったのに。
あーちゃんが生きているなんて嘘ついて、ごめん。
そして振り下ろされた。
だん、と。
地面が割れるような音がした。
一瞬、地震が起こったのかと思った。
不意に目の前が真っ暗になり、何かが宙を舞った。少し離れたところで、からんと金属のものが床に落ちたような高い音が聞こえる。
僕とひーちゃんの間に割り込んできたのは、黒衣の人物だった。ひーちゃんと同じ、全身真っ黒で整えられた服装。ただしその頭髪だけが、毒々しいまでの緑色に揺れている。
「…………日褄先生」
僕がやっとの思いで絞り出すようにそれだけ言うと、彼女は僕に背中を向けてひーちゃんと向き合ったまま、
「せんせーって呼ぶなっつってんだろ」
といつも通りの返事をした。
「ひとりで学校に来れたなんて、たいしたもんじゃねぇか」
日褄先生はひーちゃんに向けてそう言ったが、彼女は相変わらず無表情だった。
がらんどうの瞳。がらんどうの表情。がらんどうの心。がらんどうのひーちゃんは、いつもは嫌がる大嫌いな日褄先生を目の前にしても微動だにしない。
「なんで人を傷つけるようなことをしたんだよ」
先生の声は、いつになく静かだった。僕は先生が今どんな表情をしているのかはわからないけれど、それは淡々とした声音だ。
「もう誰かを失いたくないはずだろ」
廊下の向こうから誰かがやって来る。背の高いその男性は、葵さんだった。彼はひーちゃんの少し後ろに落ちているカッターナイフを無言で拾い上げている。それはさっきまで、ひーちゃんの手の中にあったはずのものだ。どうしてそんなところに落ちているのだろう。
少し前の記憶を巻き戻してみて、僕はようやく、日褄先生が僕とひーちゃんの間に割り込んだ時、それを鮮やかに蹴り上げてひーちゃんの手から吹っ飛ばしたことに気が付いた。日褄先生、一体何者なんだ。
葵さんはカッターナイフの刃を仕舞うと、それをズボンのポケットの中へと仕舞い、それからひーちゃんに後ろから歩み寄ると、その両肩を掴んで、もう彼女が暴れることができないようにした。そうされてもひーちゃんは、もう何も言葉を発さず、表情も変えなかった。先程見せたあの強い殺意も、今は嘘みたいに消えている。
それから日褄先生は僕を振り返り、その表情が僕の思っていた以上に怒りに満ちたものであることを僕の目が視認したその瞬間、頬に鉄拳が飛んできた。
ごっ、という音が自分の顔から聞こえた。骨でも折れたんじゃないかと思った。今まで受けたどんな痛みより、それが一番痛かった。
「てめーは何ぼんやり突っ立ってんだよ」
日褄先生は僕のメイド服の胸倉を乱暴に掴むと怒鳴るように言った。
「お前は何をしてんだよ、市野谷に殺されたがってんじゃねーよ。やべぇと思ったらさっさと逃げろ、なんでそれぐらいのこともできねーんだよ」
先生は僕をまっすぐに見ていた。それは恐ろしいくらい、まっすぐな瞳だった。
「なんでどいつもこいつも、自分の命が大事にできねーんだよ。お前わかってんのかよ、お前が死んだら市野谷はどうなる? 自分の弟を目の前で亡くして、大事な直正が自殺して、それでお前が市野谷に殺されたら、こいつはどうなるんだよ」
「……ひーちゃんには、僕じゃ駄目なんですよ。あーちゃんじゃないと、駄目なんです」
僕がやっとの思いでそれだけ言うと、今度は平手が反対の頬に飛んできた。
熱い。痛いというよりも、熱い。
「直正が死んでも世界は変わらなかった。世界にとっちゃ人ひとりの死なんてたいしたことねぇ、だから自分なんて世界にとってちっぽけで取るに足らない、お前はそう思ってるのかもしれないが、でもな、それでもお前が世界の一部であることには変わりないんだよ」
怒鳴る、怒鳴る、怒鳴る。
先生は僕のことを怒鳴った。
こんな風に叱られるのは初めてだ。
こんな風に、叱ってくれる人は初めてだった。
「なんでお前は市野谷に、直正は生きてるって嘘をついた? 市野谷がわかりきっているはずの嘘をどうしてつき続けた? それはなんのためだよ? どうして最後まで、市野谷がちゃんと笑えるようになるまで、側で支えてやろうって思わないんだよ」
そうだ。
そうだった。日褄先生は最初からそうだった。
優しくて、恐ろしいくらい乱暴なのだ。
「市野谷に殺されてもいい、自分なんて死んでもいいなんて思ってるんじゃねぇよ。『お前だから駄目』なんじゃねぇよ、『直正の代わりをしようとしているお前だから』駄目なんだろ?」
日褄先生は最後に怒鳴った。
「もういい加減、鈴木直正の代わりになろうとするのはやめろよ。お前は―――だろ」
お前は、潤崎颯だろ。
やっと。
やっと僕は、自分の名前が、聞き取れた。
あーちゃんが死んで、ひーちゃんに嘘をついた。
それ以来僕はずっと、自分の名前を認めることができなかった。
自分の名前を口にするのも、耳にするのも嫌だった。
僕は代わりになりたかったから。あーちゃんの代わりになりたかったから。
あーちゃんが死んだら、ひーちゃんは僕を見てくれると、そう思っていたから。
でも駄目だった。僕じゃ駄目だった。ひーちゃんはあーちゃんが死んでも、あーちゃんのことばかり見ていた。僕はあーちゃんになれなかった。だから僕なんかいらなかった。死んだってよかった。どうだってよかったんだ。
嘘まみれでずたずたで、もうどうしようもないけれど、それでもそれが、「僕」だった。
あーちゃんになれなくても、ひーちゃんを上手に救えなくても、それでも僕は、それでもそれが、潤崎颯、僕だった。
日褄先生の手が、僕の服から離れていく。床に倒れている佐渡梓は、どこか呆然と僕たちを見つめている。ひーちゃんの表情はうつろなままで、彼女の肩を後ろから掴んでいる葵さんは、まるでひーちゃんのことを支えているように見えた。
先生はひーちゃんの元へ行き、葵さんはひーちゃんからゆっくりと手を離す。そうして、先生はひーちゃんのことを抱き締めた。先生は何も言わなかった。ひーちゃんも、何も言わなかった。葵さんは無言で昇降口から出て行って、しばらくしてから帰ってきた。その時も、先生はひーちゃんを抱き締めたままで、僕はそこに突っ立っていたままだった。
やがて日褄先生はひーちゃんの肩を抱くようにして、昇降口の方へと歩き出す。葵さんは昇降口前まで車を回していたようだ。いつか見た、黒い車が停まっていた。
待って下さい、と僕は言った。
日褄先生は立ち止まった。ひーちゃんも、立ち止まる。
僕はひーちゃんに駆け寄った。
ひーちゃんは無表情だった。
僕は、ひーちゃんに謝るつもりだった。だけど言葉は出て来なかった。喉元まで込み上げた言葉は声にならず、口から嗚咽となって溢れた。僕の目からは涙がいくつも零れて、そしてその時、ひーちゃんが小さく、ごめんね、とつぶやくように言った。僕は声にならない声をいくつもあげながら、ただただ、泣いた。
ひーちゃんの空っぽな瞳からも、一粒の滴が転がり落ちて、あーちゃんの死から一年以上経ってやっと、僕とひーちゃんは一緒に泣くことができたのだった。
ひーちゃんに刺された傷は、軽傷で済んだ。
けれど僕は、二週間ほど学校を休んだ。
「災難でしたね」
あっくん、あーちゃんの弟である鈴木篤人くんは、僕の部屋を見舞いに訪れて、そう言った。
「聞きましたよ、文化祭で、ひー姉に切りつけられたんでしょう?」
あーちゃんそっくりの表情で、あっくんはそう言った。
「とうとうばれたんですか、うー兄のついていた嘘は」
「……最初から、ばれていたようなものだよ」
あーちゃんとよく似ている彼は、その日、制服姿だった。部活の帰りなのだろう、大きなエナメルバッグを肩から提げていて、手にはコンビニの袋を握っている。
「それで良かったんですよ。うー兄にとっても、ひー姉にとっても」
あっくんは僕の部屋、椅子に腰かけている。その両足をぷらぷらと揺らしていた。
「兄貴のことなんか、もう忘れていいんです。あんなやつのことなんて」
あっくんの両目が、すっと細められる。端正な顔立ちが、僅かに歪む。
思い出すのは、あーちゃんの葬式の時のこと。
式の最中、あっくんは外へ斎場の外へ出て行った。外のベンチにひとりで座っていた。どこかいらいらした様子で、追いかけて行った僕のことを見た。
「あいつ、不器用なんだ」
あっくんは不満そうな声音でそう言った。あいつとは誰だろうかと一瞬思ったけれど、すぐにそれが死んだあーちゃんのことだと思い至った。
「自殺の原因も、昔のいじめなんだって。ココロノキズがいけないんだって。せーしんかのセンセー、そう言ってた。あいつもイショに、そう書いてた」
あーちゃんが死んだ時、あっくんは小学五年生だった。今のような話し方ではなかった。彼はごく普通の男の子だった。あっくんが変わったのは、あっくんがあーちゃんのように振る舞い始めたのは、あーちゃんが死んでからだ。
「あいつ、全然悪くないのに、傷つくから駄目なんだ。だから弱くて、いじめられるんだ。おれはあいつより強くなるよ。あいつの分まで生きる。人のこといじめたりとか、絶対にしない」
あっくんは、一度も僕と目を合わさずにそう言った。僕はあーちゃんの弱さと、あっくんの強さを思った。不機嫌そうに、「あーちゃんの分まで生きる」と言った、彼の強さを思った。あっくんのような強さがあればいいのに、と思った。ひーちゃんにも、強く生きてほしかった。僕も、そう生きるべきだった。
あーちゃんが死んだ後、あーちゃんの家族はいつも騒がしそうだった。たくさんの人が入れ替わり立ち替わりやって来ては帰って行った。ときどき見かけるあっくんは、いつも機嫌が悪そうだった。あっくんはいつも怒っていた。あっくんただひとりが、あーちゃんの死を、怒っていた。
「――あんなやつのことを覚えているのは、僕だけで十分です」
あっくんはそう言って、どうしようもなさそうに、笑った。
あっくんも、僕と同じだった。
あーちゃんの代わりになろうとしていた。
ただそれは、ひーちゃんのためではなく、彼の両親のためだった。
あーちゃんが死んだ中学校には通わせられないという両親の期待に応える���めに、あっくんは猛勉強をして私立の中学に合格した。
けれど悲しいことに両親は、それを心から喜びはしなかった。今のあっくんを見ていると、死んだあーちゃんを思い出すからだ。
あっくんはあーちゃんの分まで生きようとして、そしてそれが、不可能であると知った。自分は自分としてしか、生きていけないのだ。
「僕は忘れないよ、あーちゃんのこと」
僕がそうぽつりと言うと、あっくんの顔はこちらへと向いた。あっくんのかけている眼鏡のレンズが蛍光灯の光を反射して、彼の表情を隠している。そうしていると、本当に、そこにあーちゃんがいるみたいだった。
「……僕は忘れない。あーちゃんのことを、ずっと」
自分に言い聞かせるように、僕はそう続けて言った。
「僕も、あーちゃんの分まで生きるよ」
あーちゃんが欠けた、この世界で。
「…………」
あっくんは黙ったまま、少し顔の向きを変えた。レンズは光を反射しなくなり、眼鏡の下の彼の顔が見えた。それは、あーちゃんに似ているようで、だけど確かに、あっくんの表情だった。
「そうですか」
それだけつぶやくように言うと、彼は少しだけ笑った。
「兄貴もきっと、その方が喜ぶでしょう」
あっくんはそう言って、持っていたコンビニの袋に入っていたプリンを「見舞いの品です」と言って僕の机の上に置くと、帰って行った。
その後ろ姿はもう、あーちゃんのようには見えなかった。
その二日後、僕は部屋でひとり寝ていると玄関のチャイムが鳴ったので出てみると、そこには河野帆高が立っていた。
「よー、潤崎くん。元気?」
「……なんで、僕の家を知ってるの?」
「とりあえずお邪魔しまーす」
「…………なんで?」
呆然としている僕の横を、帆高はすり抜けるようにして靴を脱いで上がって行く。こいつが僕の家の住所を知っているはずがない。訊かれたところで担任が教えるとも思えない。となると、住所を教えたのは、やはり、日褄先生だろうか。僕は溜め息をついた。どうしてあのカウンセラーは、生徒の個人情報を守る気がないのだろう。困ったものだ。
勝手に僕の部屋のベッドに寝転んでくつろいでいる帆高に缶ジュースを持って行くと、やつは笑いながら、
「なんか、美少女に切りつけられたり、美女に殴られたりしたんだって?」
と言った。
「間違っているような、いないような…………」
「すげー修羅場だなー」
けらけらと軽薄に、帆高が笑う。あっくんが見舞いに訪れた時と同様に、帆高も制服姿だった。学校帰りに寄ってくれたのだろう。ごくごくと喉を鳴らしてジュースを飲んでいる。
「はい、これ」
帆高は鞄の中から、紙の束を取り出して僕に差し出した。受け取って確認するまでもなかった。それは、僕が休んでいる間に学級で配布されたのであろう、プリントや手紙だった。ただ、それを他クラスに所属している帆高から受け取るというのが、いささか奇妙な気はしたけれど。
「どうも……」
「授業のノートは、学校へ行くようになってから本人にもらって。俺のノートをコピーしてもいいんだけど、やっぱクラス違うと微妙に授業の進度とか感じも違うだろうし」
「…………本人?」
僕が首をかしげると、帆高は、ああ、と思い出したように言った。
「これ、ミナモからの預かり物なんだよ。自分で届けに行けばって言ったんだけど、やっぱりそれは恥ずかしかったのかねー」
ミナモが、僕のプリントを届けることを帆高に依頼した……?
一体、どういうことだろう。だってミナモは、一日じゅう保健室にいて、教室内のことには関与していないはずだ。なんだか、嫌な予感がした。
「帆高、まさか、なんだけど…………」
「そのまさかだよ、潤崎くん」
帆高は飄々とした顔で言った。
「ミナモは、文化祭の振り替え休日が明けてからのこの二週間、ちゃんと教室に登校して、休んでるあんたの代わりに授業のノートを取ってる」
「…………は?」
「でもさー、ミナモ、ノート取る・取らない以前に、黒板に書いてある文字の内容を理解できてるのかねー? まぁノート取らないよりはマシだと思うけどさー」
「ちょ、ちょっと待って……」
ミナモが、教室で授業を受けている?
僕の代わりに、ノートを取っている?
一体、何があったんだ……?
僕は呆然とした。
「ほんと、潤崎くんはミナモに愛されてるよねー」
「…………」
ミナモが聞いたらそうしそうな気がしたから、代わりに僕が帆高の頭に鉄拳を制裁した。それでも帆高はにやにやと笑いながら、言った。
「だからさ、怪我してんのも知ってるし、学校休みたくなる気持ちもわからなくはないけど、なるべく早く、学校出て来てくれねーかな」
表情と不釣り合いに、その声音は真剣だったので、僕は面食らう。ミナモのことを気遣っていることが窺える声だった。入学して以来、一度も足を向けたことのない教室で、授業に出てノートを取っているのだから、無理をしていないはずがない。いきなりそんなことをするなんて、ミナモも無茶をするものだ。いや、無茶をさせているのは、僕なのだろうか。
あ、そうだ、と帆高は何かを思い出したかのようにつぶやき、鞄の中から丸められた画用紙を取り出した。
「……それは?」
「ミナモから、預かってきた。お見舞いの品」
ミナモから、お見舞いの品?
首を傾げかけた僕は、画用紙を広げ、そこに描かれたものを見て、納得した。
河野ミナモと、僕。
死にたがり屋と死に損ない。
自らの死を願って雨の降る屋上へ向かい、そこで出会った僕と彼女は、ずるずると、死んでいくように生き延びたのだ。
「……これから、授業に出るつもり、なのかな」
「ん? ああ、ミナモのことか? どうだろうなぁ」
僕は思い出していた。文化祭の朝、リストバンドをくれた、峠茶屋桜子さんのこと。僕とミナモが出会った日に、保健室で僕たちに偶然出会ったことを彼女は覚えていてくれていた。彼女のような人もクラスにはいる。僕だってミナモだって、クラスの人たちと全く関わり合いがない訳ではないのだ。僕たちもまだ、世界と繋がっている。
「河野も、変わろうとしてるのかな……」
死んだ方がいい人間だっている。
初めて出会ったあの日、河野ミナモはそう言った。
僕もそう思っていた。死んだ方がいい人間だっている。僕だって、きっとそうだと。
だけど僕たちは生きている。
ミナモが贈ってくれた絵は、やっぱり、あの屋上から見た景色だった。夏休みの宿題を頼んだ時に描いてもらった絵の構図とほとんど同じだった。屋上は無人で、僕の姿もミナモの姿もそこには描かれていない。だけど空は、澄んだ青色で塗られていた。
僕は帆高に、なるべく早く学校へ行くよ、と約束して、それから、どうかミナモの変化が明るい未来へ繋がるように祈った。
河野帆高が言っていた通り、僕が学校を休んでいた約二週間の間、ミナモは朝教室に登校してきて、授業を受け、ノートを取ってくれていた。けれど、僕が学校へ行くようになると、保健室登校に逆戻りだった。
昼休みの保健室で、僕はミナモからルーズリーフの束を受け取った。筆圧の薄い字がびっしりと書いてある。
僕は彼女が贈ってくれた絵のことを思い出した。かつてあーちゃんが飛び降りて、死のうとしていた僕と、死にたがりのミナモが出会ったあの屋上。そこから見た景色を、ミナモはのびのびとした筆使いで描いていた。綺麗な青い色の絵具を使って。
授業ノートの字は、その絵とは正反対な、神経質そうに尖っているものだった。中学入学以来、一度も登校していなかった教室に足を運び、授業を受けたのだ。ルーズリーフのところどころは皺寄っている。緊張したのだろう。
「せっかく来るようになったのに、もう教室に行かなくていいの?」
「……潤崎くんが来るなら、もう行かない」
ミナモは長い前髪の下から睨みつけるように僕を一瞥して、そう言った。
それもそうだ。ミナモは人間がこわいのだ。彼女にとっては、教室の中で他人の視線に晒されるだけでも恐ろしかったに違いないのに。
ルーズリーフを何枚かめくり、ノートの文字をよく見れば、ときどき震えていた。恐怖を抑えようとしていたのか、ルーズリーフの余白には小さな絵が描いてあることもあった。
「ありがとう、河野」
「別に」
ミナモは保健室のベッドの上、膝に乗せたスケッチブックを開き、目線をそこへと向けていた。
「行くところがあるんじゃないの?」
もう僕に興味がなくなってしまったかのような声で彼女はそう言って、ただ鉛筆を動かすだけの音が保健室には響き始めた。
僕はもう一度ミナモに礼を言ってから、保健室を後にした。
ずっと謝らなくてはいけないと思っている人がいた。
彼女はなんだか気まずそうに僕の前でうつむいている。
昼休みの廊下の片隅。僕と彼女の他には誰もいない。呼び出したのは僕の方だった。文化祭でのあの事件から、初めて登校した僕は、その日のうちに彼女の教室へ行き、彼女のクラスメイトに呼び出してもらった。
「あの…………」
「なに?」
「その、怪我の、具合は……?」
「僕はたいしたことないよ。もう治ったし。きみは?」
「私も、その、大丈夫です」
「そう……」
よかった、と言おうとした言葉を、僕は言わずに飲み込んだ。これでよいはずがない。彼女は無関係だったのだ。彼女は、僕やひーちゃん、あーちゃんたちとは、なんの関係もなかったはずなのに。
「ごめん、巻き込んでしまって」
「いえ、そんな……勝手に先輩のことをかばったのは、私ですから……」
文化祭の日。僕がひーちゃんに襲われた時、たまたま廊下を通りかかった彼女、佐渡梓は僕のことをかばい、そして傷を負った。
怪我は幸いにも、僕と同様に軽傷で済んだようだが、でもそれだけで済む話ではない。彼女は今、カウンセリングに通い、「心の傷」を癒している。それもそうだ。同じ中学校に在籍している先輩女子生徒に、カッターナイフで切りつけられたのだから。
「きみが傷を負う、必要はなかったのに……」
どうして僕のことを、かばったりしたのだろう。
僕は佐渡梓の好意を、いつも踏みつけてきた。ひどい言葉もたくさんぶつけた。渡された手紙は読まずに捨てたし、彼女にとって、僕の態度は冷徹そのものだったはずだ。なのにどうして、彼女は僕を助けようとしたのだろう。
「……潤崎先輩に、一体何があって、あんなことになったのか、私にはわかりません」
佐渡梓はそう言った。
「思えば、私、先輩のこと何も知らないんだなって、思ったんです。何が好きなのか、とか、どんな経験をしてきたのか、とか……。先輩のクラスに、不登校の人が二人いるってことは知っていました。ひとりは河野先輩で、潤崎先輩と親しいみたいだってことも。でも、もうひとりの、市野谷先輩のことは知らなくて……潤崎先輩と、幼馴染みだってことも……」
���とひーちゃんのことを知っているのは、同じ小学校からこの中学に進学してきた連中くらいだ。と言っても、僕もひーちゃんも小学校時代の同級生とそこまで交流がある訳じゃなかったから、そこまでは知られていないのではないだろうか。僕とひーちゃん、そして、あーちゃんのことも知っているという人間は、この学校にどれくらいいるのだろう。
さらに言えば、僕とひーちゃんとあーちゃん、そして、ひーちゃんの最愛の弟ろーくんの事故のことまで知っている人間は、果たしているのだろうか。日褄先生くらいじゃないだろうか。
僕たちは、あの事故から始まった。
ひーちゃんはろーくんを目の前で失い、そして僕とあーちゃんに出会った。ひーちゃんは心にぽっかり空いた穴を、まるであーちゃんで埋めるようにして、あーちゃんを世界の全てだとでも言うようにして、生きるようになった。そんなあーちゃんは、ある日屋上から飛んで、この世界からいなくなってしまった。そうして役立たずの僕と、再び空っぽになったひーちゃんだけが残された。
そうして僕は嘘をつき、ひーちゃんは僕を裏切った。
僕を切りつけた刃の痛みは、きっとひーちゃんが今まで苦しんできた痛みだ。
あーちゃんがもういないという事実を、きっとひーちゃんは知っていた。ひーちゃんは僕の嘘に騙されたふりをした。そうすればあーちゃんの死から逃れられるとでも思っていたのかもしれない。壊れたふりをしているうちに、ひーちゃんは本当に壊れていった。僕はどうしても、彼女を正しく導くことができなかった。嘘をつき続けることもできなかった。だからひーちゃんは、騙されることをやめたのだ。自分を騙すことを、やめた。
僕はそのことを、佐渡梓に話そうとは思わなかった。彼女が理解してくれる訳がないと決めつけていた訳ではないが、わかってもらわなくてもいいと思っていた。でも僕が彼女を巻き込んでしまったことは、もはや変えようのない事実だった。
「今回のことの原因は、僕にあるんだ。詳しくは言えないけれど。だから、ひーちゃん……市野谷さんのことを責めないであげてほしい。本当は、いちばん苦しいのは市野谷さんなんだ」
僕の言葉に、佐渡梓は決して納得したような表情をしなかった。それでも僕は、黙っていた。しばらくして、彼女は口を開いた。
「私は、市野谷先輩のことを責めようとか、訴えようとか、そんな風には思いません。どうしてこんなことになったのか、理由を知りたいとは思うけれど、潤崎先輩に無理に語ってもらおうとも思いません……でも、」
彼女はそこまで言うと、うつむいていた顔を上げ、僕のことを見た。
ただ真正面から、僕を見据えていた。
「私は、潤崎先輩も、苦しかったんじゃないかって思うんです。もしかしたら、今だって、先輩は苦しいんじゃないか、って……」
僕は。
佐渡梓にそう言われて、笑って誤魔化そうとして、泣いた。
僕は苦しかったんだろうか。
僕は今も、苦しんでいるのだろうか。
ひーちゃんは、あの文化祭での事件の後、日褄先生に連れられて精神科へ行ったまま、学校には来ていない。家にも帰っていない。面会謝絶の状態で、会いに行くこともできないのだという。
僕はどうかひーちゃんが、苦しんでいないことを願った。
もう彼女は、十分はくらい苦しんできたと思ったから。
ひーちゃんから電話がかかってきたのは、三月十三日のことだった。
僕の中学校生活は何事もなかったかのように再開された。
二週間の欠席を経て登校を始めた当初は、変なうわさと奇妙な視線が僕に向けられていたけれど、もともとクラスメイトと関わり合いのなかった僕からしてみれば、どうってことはなかった。
文化祭で僕が着用したメイド服を作ってくれたクラス委員の長篠めいこさんと、リストバンドをくれた峠茶屋桜子さんとは、教室の中でときどき言葉を交わすようになった。それが一番大きな変化かもしれない。
ミナモの席もひーちゃんの席も空席のままで、それもいつも通りだ。
ミナモのはとこである帆高の方はというと、やつの方も相変わらずで、宿題の提出率は最悪みたいだ。しょっちゅう廊下で先生たちと鬼ごっこをしている。昼休みの保健室で僕とミナモがくつろいでいると、ときどき顔を出しにくる。いつもへらへら笑っていて、楽しそうだ。なんだかんだ、僕はこいつに心を開いているんだろうと思う。
佐渡梓とは、あれからあまり会わなくなってしまった。彼女は一年後輩で、校舎の中ではもともと出会わない。委員会や部活動での共通点もない。彼女が僕のことを好きになったこと自体が、ある意味奇跡のようなものだ。僕をかばって怪我をした彼女には、感謝しなくてはいけないし謝罪しなくてはいけないと思ってはいるけれど、どうしたらいいのかわからない。最近になって少しだけ、彼女に言ったたくさんの言葉を後悔するようになった。
日褄先生は、そう、日褄先生は、あれからスクールカウンセラーの仕事を辞めてしまった。婚約者の葵さんと結婚することになったらしい。僕の頬を殴ってまで叱咤してくれた彼女は、あっさりと僕の前からいなくなってしまった。そんなこと、許されるのだろうか。僕はまだ先生に、なんのお礼もしていないのに。
僕のところには携帯電話の電話番号が記されたはがきが一枚届いて、僕は一度だけそこに電話をかけた。彼女はいつもと変わらない明るい声で、とんでもないことを平気でしゃべっていた。ひーちゃんのことも、僕のことも、彼女はたった一言、「もう大丈夫だよ」とだけ言った。
そうこうしているうちに年が明け、冬休みが終わり、そうして三学期も終わった。
三月十三日、電話が鳴った。
あーちゃんが死んだ日だった。
二年前のこの日、あーちゃんは死んだのだ。
「あーちゃんに会いたい」
電話越しだけれども、久しぶりに聞くひーちゃんの声は、やけに乾いて聞こえた。
あーちゃんにはもう会えないんだよ、そう言おうとした僕の声を遮って、彼女は言う。
「知ってる」
乾燥しきったような、淡々とした声。鼓膜の奥にこびりついて取れない、そんな声。
「あーちゃん、死んだんでしょ。二年前の今日に」
思えば。
それが僕がひーちゃんの口から初めて聞いた、あーちゃんの死だった。
「『僕』ね、ごめんね、ずっとずっと知ってた、ずっとわかってた。あーちゃんは、もういないって。だけど、ずっと認めたくなくて。そんなのずるいじゃん。そんなの、卑怯で、許せなくて、許したくなくて、ずっと信じたくなくて、ごめん、でも……」
うん、とだけ僕は答えた。
きっとそれは、僕のせいだ。
ひーちゃんを許した、僕のせいだ。
あーちゃんの死から、ずっと目を背け続けたひーちゃんを許した、僕のせいだ。
ひーちゃんにそうさせた、僕のせい。
僕の罪。
一度でもいい、僕が、あーちゃんの死を見ないようにするひーちゃんに、無理矢理にでも現実を打ち明けていたら、ひーちゃんはきっと、こんなに苦しまなくてよかったのだろう。ひーちゃんの強さを信じてあげられなかった、僕のせい。
あーちゃんが死んで、自分も死のうとしていたひーちゃんを、支えてあげられるだけの力が僕にはなかった。ひーちゃんと一緒に生きるだけの強さが僕にはなかった。だから僕は黙っていた。ひーちゃんがこれ以上壊れてしまわぬように。ひーちゃんがもっと、壊れてしまうように。
僕とひーちゃんは、二年前の今日に置き去りになった。
僕の弱さがひーちゃんの心を殺した。壊した。狂わせた。痛めつけた。苦しめた。
「でも……もう、『僕』、あーちゃんの声、何度も何度も何度も、何度考えても、もう、思い出せないんだよ……」
電話越しの声に、初めて感情というものを感じた。ひーちゃんの今にも泣き出しそうな声に、僕は心が潰れていくのを感じた。
「お願い、うーくん。『僕』を、あーちゃんのお墓に、連れてって」
本当は、二年前にこうするべきだった。
「……わかった」
僕はただ、そう言った。
僕は弱いままだったから。
彼女の言葉に、ただ頷いた。
『僕が死んだことで、きっとひーちゃんは傷ついただろうね』
そう書いてあったのは、あーちゃんが僕に残したもうひとつの遺書だ。
『僕は裏切ってしまったから。あの子との約束を、破ってしまったから』
あーちゃんとひーちゃんの間に交わされていたその約束がなんなのか、僕にはわからないけれど、ひーちゃんにはきっと、それがわかっているのだろう。
ひーちゃんがあーちゃんのことを語る度、僕はひーちゃんがどこかへ行ってしまうような気がした。
だってあんまりにも嬉しそうに、「あーちゃん、あーちゃん」って言うから。ひーちゃんの大好きなあーちゃんは、もういないのに。
ひーちゃんの両目はいつも誰かを探していて、隣にいる僕なんか見てくれないから。
ひーちゃんはバス停で待っていた。交わす言葉はなかった。すぐにバスは来て、僕たちは一番後ろの席に並んで座った。バスに乗客の姿は少なく、窓の外は雨が降っている。ひーちゃんは無表情のまま、僕の隣でただ黙って、濡れた靴の先を見つめていた。
ひーちゃんにとって、世界とはなんだろう。
ひーちゃんには昨日も今日も明日もない。
楽しいことがあっても、悲しいことがあっても、彼女は笑っていた。
あーちゃんが死んだ時、あーちゃんはひーちゃんの心を道連れにした。僕はずっと心の奥底であーちゃんのことを恨んでいた。どうして死んだんだって。ひーちゃんに心を返してくれって。僕らに世界を、返してって。
二十分もバスに揺られていると、「船頭町三丁目」のバス停に着いた。
ひーちゃんを促してバスを降りる。
雨は霧雨になっていた。持っていた傘を差すかどうか、一瞬悩んでから、やめた。
こっちだよ、とひーちゃんに声をかけて歩き始める。ひーちゃんは黙ってついてくる。
樫岸川の大きな橋の上を歩き始める。柳の並木道、古本屋のある四つ角、細い足場の悪い道、長い坂、苔の生えた石段、郵便ポストの角を左。
僕はもう何度、この道を通ったのだろう。でもきっと、ひーちゃんは初めてだ。
生け垣のある家の前を左。寺の大きな屋根が、突然目の前に現れる。
僕は、あそこだよ、と言う。ひーちゃんは少し目線を上の方に動かして、うん、と小さな声で言う。その瞳も、口元も、吐息も、横顔も、手も、足も。ひーちゃんは小さく震えていた。僕はそれに気付かないふりをして、歩き続ける。ひーちゃんもちゃんとついてくる。
ひーちゃんはきっと、ずっとずっと気付いていたのだろう。本当のことを。あーちゃんがこの世にいないことを。あーちゃんが自ら命を絶ったことも。誰もあーちゃんの苦しみに、寂しさに、気付いてあげられなかったことを。ひーちゃんでさえも。
ひーちゃんは、あーちゃんが死んでからよく笑うようになった。今までは、能面のように無表情な少女だったのに。ひーちゃんは笑っていたのだ。あーちゃんがもういない世界を。そんな世界でのうのうと生きていく自分を。ばればれの嘘をつく、僕を。
あーちゃんの墓前に立ったひーちゃんの横顔は、どこにも焦点があっていないかのように、瞳が虚ろで、だが泣いてはいなかった。そっと手を伸ばし、あーちゃんの墓石に恐る恐る触れると、霧雨に濡れて冷たくなっているその石を何度も何度も指先で撫でていた。
墓前には真っ白な百合と、やきそばパンが供えてあった。あーちゃんの両親が毎年お供えしているものだ。
線香のにおいに混じって、妙に甘ったるい、���コナッツに似たにおいがするのを僕は感じた。それが一体なんのにおいなのか、僕にはわかった。日褄先生がここに来て、煙草を吸ったのだ。彼女がいつも吸っていた、あの黒い煙草。そのにおいだった。ついさっきまで、ここに彼女も来ていたのだろうか。
「つめたい……」
ひーちゃんがぽつりと、指先の感触の感想を述べる。そりゃ石だもんな、と僕は思ったが、言葉にはしなかった。
「あーちゃんは、本当に死んでいるんだね」
墓石に触れたことで、あーちゃんの死を実感したかのように、ひーちゃんは手を引っ込めて、恐れているように一歩後ろへと下がった。
「あーちゃんは、どうして死んだの?」
「……ひとりぼっちみたいな、感覚になるんだって」
あーちゃんが僕に宛てて書いた、彼のもうひとつの遺書の内容を思い出す。
「ひとりぼっち? どうして? ……私がいたのに」
ひーちゃんはもう、自分のことを「僕」とは呼ばなかった。
「私じゃだめだった?」
「……そんなことはないと思う」
「じゃあ、どうして……」
ひーちゃんはそう言いかけて、口をつぐんだ。ゆっくりと首を横に振って、ひーちゃんは、そうか、とだけつぶやいた。
「もう考えてもしょうがないことなんだ……。あーちゃんは、もういない。私が今さら何かを思ったって、あーちゃんは帰ってこないんだ……」
ひーちゃんはまっすぐに僕を見上げて、続けるように言った。
「これが、死ぬってことなんだね」
彼女の表情は凍りついているように見えた。
「そうか……ずっと忘れていた、ろーくんも死んだんだ……」
ひーちゃんの最愛の弟、ろーくんこと市野谷品太くんは、僕たちが小学二年生の時に交通事故で亡くなった。ひーちゃんの目の前で、ろーくんの細くて小さい身体は、巨大なダンプに軽々と轢き飛ばされた。
ひーちゃんは当時、過剰なくらいろーくんを溺愛していて、そうして彼を失って以来、他人との間に頑丈な壁を築くようになった。そんな彼女の前に現れたのが、僕であり、そして、あーちゃんだった。
「すっかり忘れてた。ろーくん……そうか、ずっと、あーちゃんが……」
まるで独り言のように、ひーちゃんは言葉をぽつぽつと口にする。瞳が落ち着きなく動いている。
「そうか、そうなんだ、あーちゃんが……あーちゃんが…………」
ひーちゃんの両手が、ひーちゃんの両耳を覆う。
息を殺したような声で、彼女は言った。
「あーちゃんは、ずっと、ろーくんの代わりを……」
それからひーちゃんは、僕を見上げた。
「うーくんも、そうだったの?」
「え?」
「うーくんも、代わりになろうとしてくれていたの?」
ひーちゃんにとって、ろーくんの代わりがあーちゃんであったように。
あーちゃんが、ろーくんの代用品になろうとしていたように。
あっくんが、あーちゃんの分まで生きようとしていたように。
僕は。
僕は、あーちゃんの代わりに、なろうとしていた。
あーちゃんの代わりに、なりたかった。
けれどそれは叶わなかった。
ひーちゃんが求めていたものは、僕ではなく、代用品ではなく、正真正銘、ほんものの、あーちゃんただひとりだったから。
僕は稚拙な嘘を重ねて、ひーちゃんを現実から背けさせることしかできなかった。
ひーちゃんの手を引いて歩くことも、ひーちゃんが泣いている間待つことも、あーちゃんにはできても、僕にはできなかった。
あーちゃんという存在がいなくなって、ひーちゃんの隣に空いた空白に僕が座ることは許されなかった。代用品であることすら、認められなかった。ひーちゃんは、代用品を必要としなかった。
ひーちゃんの世界には、僕は存在していなかった。
初めから、ずっと。
ずっとずっとずっと。
ずーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと、僕はここにいたのに。
僕はずっと寂しかった。
ひーちゃんの世界に僕がいないということが。
だからあーちゃんを、心の奥底では恨んでいた。妬ましく思っていた。
全部、あーちゃんが死んだせいにした。僕が嘘をついたのも、ひーちゃんが壊れたのも、あーちゃんが悪いと思うことにした。いっそのこと、死んだのが僕の方であれば、誰もこんな思いをしなかったのにと、自分が生きていることを呪った。
自分の命を呪った。
自分の存在を呪った。
あーちゃんのいない世界を、あーちゃんが死んだ世界を、あーちゃんが欠けたまま、それでもぐるぐると廻り続けるこの不条理で不可思議で不甲斐ない世界を、全部、ひーちゃんもあーちゃんもあっくんもろーくんも全部全部全部全部、まるっときちっとぐるっと全部、呪った。
「ごめんね、うーくん」
ひーちゃんの細い腕が、僕の服の袖を掴んでいた。握りしめているその小さな手を、僕は見下ろす。
「うーくんは、ずっと私の側にいてくれていたのにね。気付かなくて、ごめんね。うーくんは、ずっとあーちゃんの代わりをしてくれていたんだね……」
ひーちゃんはそう言って、ぽろぽろと涙を零した。綺麗な涙だった。綺麗だと、僕は思った。
僕は、ひーちゃんの手を握った。
ひーちゃんは何も言わなかった。僕も、何も言わなかった。
結局、僕らは。
誰も、誰かの代わりになんてなれなかった。あーちゃんもろーくんになることはできず、あっくんもあーちゃんになることはできず、僕も、あーちゃんにはなれなかった。あーちゃんがいなくなった後も、世界は変わらず、人々は生き続け、笑い続けたというのに。僕の身長も、ひーちゃんの髪の毛も伸びていったというのに。日褄先生やミナモや帆高や佐渡梓に、出会うことができたというのに。それでも僕らは、誰の代わりにもなれなかった。
ただ、それだけ。
それだけの、当たり前の事実が僕らには常にまとわりついてきて、その事実を否定し続けることだけが、僕らの唯一の絆だった。
僕はひーちゃんに、謝罪の言葉を口にした。いくつもいくつも、「ごめん」と謝った。今までついてきた嘘の数を同じだけ、そう言葉にした。
ひーちゃんは僕を抱き締めて、「もういいよ」と言った。もう苦しむのはいいよ、と言った。
帰り道のバスの中で、四月からちゃんと中学校に通うと、ひーちゃんが口にした。
「受験、あるし……。今から学校へ行って、間に合うかはわからないけれど……」
四月から、僕たちは中学三年生で高校受験が控えている。教室の中は、迫りくる受験という現実に少しずつ息苦しくなってきているような気がしていた。
僕は、「大丈夫」なんて言わなかった。口にすることはいくらでもできる。その方が、もしかしたらひーちゃんの心を慰めることができるかもしれない。でももう僕は、ひーちゃんに嘘をつきたくなかった。だから代わりに、「一緒に頑張ろう」と言った。
「頭のいいやつが僕の友達にいるから、一緒に勉強を教えてもらおう」
僕がそう言うと、ひーちゃんは小さく頷いた。
きっと帆高なら、ひーちゃんとも仲良くしてくれるだろう。ミナモはどうかな。時間はかかるかもしれないけれど、打ち解けてくれるような気がする。ひーちゃんはクラスに馴染めるだろうか。でも、峠茶屋さんが僕のことを気にかけてくれたように、きっと誰かが気にかけてくれるはずだ。他人なんてくそくらえだって、ずっと思っていたけれど、案外そうでもないみたいだ。僕はそのことを、あーちゃんを失ってから気付いた。
僕は必要とされたかっただけなのかもしれない。
ひーちゃんに必要とされたかったのかもしれないし、もしかしたら誰か他人だってよかったのかもしれない。誰か他人に、求めてほしかったのかもしれない。そうしたら僕が生きる理由も、見つけられるような気がして。ただそれだけだ。それは、あーちゃんも、ひーちゃんも同じだった。だから僕ら���不器用に、お互いを傷つけ合う方法しか知らなかった。自分を必要としてほしかったから。
いつだったか、日褄先生に尋ねたことがあったっけ。
「嘘って、何回つけばホントになるんですか」って。先生は、「嘘は何回ついたって、嘘だろ」と答えたんだった。僕のついた嘘はいくら重ねても嘘でしかなかった。あーちゃんは、帰って来なかった。やっぱり今日は雨で、墓石は冷たく濡れていた。
けれど僕たちは、やっと、現実を生きていくことができる。
「もう大丈夫だよ」
日褄先生が僕に言ったその声が、耳元で蘇った。
もう大丈夫だ。
僕は生きていく。
あーちゃんがいないこの世界で、今度こそ、ひーちゃんの手を引いて。
ふたりで初めて手を繋いで帰った日。
僕らはやっと、あーちゃんにサヨナラができた。
あーちゃん。
世界は透明なんかじゃない。
君も透明なんかじゃない。
僕は覚えている。あーちゃんのことも、一緒に見た景色も、過ごした日々のことも。
今でも鮮明に、その色を思い出すことができる。
たとえ記憶が薄れる日がきたって、また何度でも思い出せばいい。
だからサヨナラは、言わないんだ。
了
0 notes
Text










2020-12-19 (土) 💁🗼🆚🔋🖊💡✨
👑 No. 104 ⟴ チャンネル
(n‘∀‘)η< 偶然の一致❕😨😘😚
❤︎⃜…// 大レースを狙えるサラブレッド 🐴🐎𓂃𓂂🍃
⿴⿻⿸ 馬さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 サラブレッド🐴🐎
⿴⿻⿸ 牛さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 後嗣(こうし)🐮🐃🐂🐄
⿴⿻⿸ 数えながら寝る羊さん(¥ ¥)一頭・用意 🐑💤💭 (_ *˘ω˘)_Zzz…💴
❣️:.︎。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ :.。❣️
( •̀ᴗ•́ )/:伝える言葉が残される ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:問わず語りの心が切ないね ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あわれんでも答えもしない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あなたにつたえるすべもない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:涙がこぼれないように ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:古い愛の歌を とぎれず唄ってた ...♪*゚
ˣx✖ˣ♡✖ˣx♡xˣ✖xˣ♡ˣx✖ˣx♡xˣ✖♡ˣ✖xˣ
撮影日:2020-12-17 (木)
初雪・粉雪が降り始めた深夜の時間帯 🌃
初雪・粉雪の降った朝時間帯 😴🐓☀
(*•̆ ·̭ •̆*)むぅ 〖報告日〗:2020-12-16 (水)
今年の冬になって一番の寒さを自覚しながら、日中の9時~12時まで電信柱の配線工事があり電気が止まっていました。
家で動いている時間は、かなりの忍耐勝負になります。
丸一日、最低限の範囲内から生活して、無駄な動きをしないで全ての問題を解決することが出来たらいいのになぁと夢みたいな話を思ってみたり、このまま人間界から離れて熊の冬眠と同じ行動をしていたいくらい現実逃避に身を置いて、一年の締めくくりを寒々と歌詞の記憶から遠のいて、途中退場のリセットボタンを押したい心境にかられています。~🐻❄️🐻❄️🐻❄️~
(*•̆ ·̭ •̆*)むぅ 撮影日:2020-12-15 (火)
外では、スマホを持つ手が痛く感じてイヤになる寒さの到来を実感しました。❄:;((>﹏<๑));:❄
⋆დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆
❥·・ 昼間・夜時間・雨降り逢瀬の立証 🎵🎵
撮影日:2020-12-16 (水)
❤︎⃜…// ラスト冬の黄色い菊 \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ (➖):黄色いマイクを置く 🎵🎵
撮影日:2020-12-12 (土)
調理日:2020-12-14 (月)
購入・白い部分が紫色の変わりネギ(葱)
あまりの寒さに、早速ですが、すき焼きの😋Σd(゚д゚,,★)💓美味しい旬の食材を堪能しました。
撮影日:2020-12-11 (金)
⋆͛♡̷♡̷⋆ 牛さん代用の庭木
_((Ф(.. )カキカキ 白い花アベリア咲き終わり日
撮影日:2020-12-12 (土)
\❤︎/ 猫柳の傘 ☂️☂☔
//♡︎ᵎᵎᵎ♡(ؔᵒ̶̷ᵕؔᵒ̷̶)ℓσνє♡
撮影日:2020-12-13 (日)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱが風に吹かれ動いて片耳になったウサギさん初登場‼🐰
撮影日:2020-12-14 (月)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱの残っていた片耳が風に吹かれ両方が消えて、ウサギさん初登場‼🐰
_(=×=_∪)⌒)ο ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ ♡。 ∩∩
撮影日:2020-12-13 (日)
𓂃𓃺𓈒𓏸 ポコンポコン穴掘りもぐらさん登場4度目❕
撮影日:2020-12-06 (日)
❥ ... 最近もぐらの通った後 ♪♩♬
❤︎⃜…// 上手に倒さずソーラーライトを棒から外す技 (゜〇゜)
撮影日:2020-12-10 (木)
\❤︎/ 庭木オオデマリ(大手毬)
❥·・ テレビ画面の背中を指す枝☝
撮影日:2020-12-09 (水)
ʚ♡⃛ɞ 芝生に延びる影 🌳🍃
\ Hello ♡/ 左側:オオデマリ(大手毬)♡‴ 亀さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 右側:名前の分からない庭木 ♡‴ 鶴さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-16 (水)
❤︎⃜…// 霜が降りて冷えきったお庭
撮影日:2020-12-16 (水)
⋆͛♡̷♡̷⋆ ネクタイ 👔代用・鉢植え
❥·・ 入り込んだ枯れ葉 ͛.*🍃𓂃 𓈒𓏸🍂
𐀪𐁑 集まった人たち ୧( ⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)୨
❥·・ ラスト枯れ葉1枚の庭木
撮影日:2020-12-13 (日)
❤︎⃜…// ブルーベリー果樹
⋆͛♡̷♡̷⋆ 2種類 植樹 ~♩♩
❥ ... (➖):冬ラスト・消えた赤い葉っぱ ( ' '♬)
⋆͛♡⋆͛ 左側:裸の蓄音機 \ ♩ /
⋆͛♡⋆͛ 右側:裸のレコードプレーヤー \ ♪♪ /
\ Hello ♡/ お庭に残されるたんぽぽ ♬.*゚
撮影日:2020-12-16 (水)
⋆͛♡⋆͛ ひとり玄関エントランスに腰掛けて見ていました。
伝説のスター 師弟物語
遠藤実✖️森昌子
人生を変えた師匠の教え
歌は人生の友
第4回日本歌謡大賞より
第14回日本レコード大賞・新人賞
第3回日本歌謡大賞・放送音楽新人賞
❥ ... 冬に1つだけ雑草の傘をさしているたんぽぽ花 ♬*.+゜
❥ ... 桟橋になった茎 ♪♩♬
\ Hello ♡/ 先頭たんぽぽ代用の太陽☀︎*.。・野ざらし駐車スペース ♬*.+゜
\ Hello ♡/ 引っこ抜けない省スペースたんぽぽ *♬೨̣
\ Hello ♡/ 物置(灯油缶の保管・枝切り・刈り込みばさみ・芝生刈りはさみ)の前のしぶとい芝生たんぽぽ ♪♩♬
\ Hello ♡/ お魚釣りの出来ない枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ ハンカチ落とし終わり・山盛り枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-09 (水)
\ Hello ♡/ 捨てゴミの処理・小5袋 💴 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ (➖):秋の黄色い菊カット・捨てゴミ処理 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\❤︎/ 裏道に生け垣の船1つ・右側&左側の合体
撮影日:2020-12-17 (木)
\❤︎/ 太陽 ☀️.° 🌞😊🌞🔆🔅
撮影日:2020-12-10 (木)
___ ✍🏻 残念なことに都合により充電切れで、夕方になってから撮影出来ませんでした。
撮影日:2020-12-11 (金)
撮影日:2020-12-13 (日)
🌹💫⭐︎ 明るさ💡を - + 調整して撮影・赤く見える夕やけ空 ️️️⛅️
撮影日:2020-12-15 (火)
❤︎⃜…// ️️️冬の空・⛅️夕暮れ・日暮れ・鉄塔&夜空🔛星空 ♪̊̈��̆̈♪̊̈♪̆̈♪̊̈
撮影日:2020-12-07 (月)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:19
撮影日:2020-12-08 (火)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:21
撮影日:2020-12-09 (水)
☆*°月のない空 おやすみ(ृ ु⁎ᴗᵨᴗ⁎)ु.💤🌙
撮影時刻 🔜 04:25
〽 浅間山 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-05 (土)
撮影日:2020-12-07 (月)
撮影日:2020-12-08 (火)
撮影日:2020-12-12 (土)
〽〽〽 (➖):遠くに見える北アルプス〽〽〽
撮影日:2020-12-11 (金)
〽 黒斑山・山並み 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-12 (土)
撮影日:2020-12-13 (日)
___ ✍🏻 市内撮影・本町~ミズヒキ(ミズヒキ)亀と鶴 𓆉𓇼𓆉𓇼
撮影日:2020-12-08 (火)
❥❥» チカラシバ(力芝)・南側の片方カット ♪ૢ
ੈ✩ 沢山の指揮者・ストップ・指揮棒 ♪ૢ
❤︎⃜…// 冬に向かって残したラスト北側の指揮棒
撮影日:2020-12-12 (土)
❥ ... (➖):北に棲むやさしい鳥さん 𓎤𓅮 ⸒⸒ ⸜🕊⸝ 🕊 𓈒 𓂂𓏸🕊💭
ʚ♡⃛ɞ 仏壇と向かい合う指揮者へ \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ 東西南北の方角に向き合う指揮者へ \ ♪♪ /
♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪
《花言葉》
信念・気の強い・尊敬
❤︎⃜…// 裏庭コムラサキ生け垣
⋆͛♡̷♡̷⋆ 着物の代用 ~♩♩
👘 万祝(まいわい)👘
撮影日:2020-12-12 (土)
ੈ✩ ツルニチニチソウ(蔓日々草 )⋆͛♡̷♡̷⋆
❥ ... 太鼓&滝の代用・ツル性植物 ♪ૢ
💡ソーラーライト🔛スポットライト
和名: 蔓日々草(ツルニチニチソウ)
別名: 蔓桔梗(ツルギキョウ)、ビンカ
ヨーロッパでは、常緑で冬も枯れないことから不死のシンボルとして、またツルニチニチソウを身に付けると繁栄と幸福をもたらしてくれる、という古くからの言い伝えがあります。そのため別名も 「大地のよろこび」 、 「魔女のすみれ」 などと呼ばれるそうです。イタリアでは亡くなった子供をこのツルニチニチソウで飾ることから 「死の花」 とも呼ぶそうです。
φ(σ_σ)思い出をかき集めれば、山のように本物のお金だけしか動かない枯れ葉の幻想お庭
....φ(⊂︶■︶⊃)φ.... ....φ(⊂︶■︶⊃)φ....
\ Hello ♡/ 老老介護(ろうろうかいご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 老老看護(ろうろうかんご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
♬♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬
〖芸能ニュース👏ニッカンスポーツ・コム〗
[2007年8月2日 8時14分 紙面から]
最期の仕事は、今月22日発売の渚ようこのアルバム 「ノヴェラ ダモーレ」 に 「KABUKU」 「どうせ天国へ行ったって」 の2曲の詞を書き下ろした。「どうせ-」 では、死後のことを 「どうせ天国なんて 誰もいないから イヤよ」 とつづっている。当時、歌手の岩崎宏美(48)が車いすに乗った恩師に 「どこか痛いところはあるんですか」 とたずねると 「痛くないところがないんだよ」 と、寂しそうにつぶやいたという。常々 「自分には見えっぱりな部分や、強がるところがある」 と話し、教え子の和田アキ子(57)が見舞いを申し出ても 「元気な姿しか見せたくない」 と断っていた阿久さんも、最近は体調不良を訴えることも多かったという。
阿久さんが作詞家を志す原点は結核を発病した14歳のころ。医者から 「激情を抱くと、胸が破れて死ぬ」 と宣告され 「文書を書くか絵を描くかしかなさそうだ」 と心に決めたという。
⁎⋆*❇☆:⁎⋆*☆†_(σ_σ)β))☆⁎⋆*:☆🕯𓈒 𓏸✴⁎⋆*
by 松田聖子『PEARL-WHITE EVE』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 赤いキャンドルが燃えつきるまで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 抱きしめて 折れるほど ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 誰も愛さない そう決めたのに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) もう誓いを破ってる ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 真珠の雪をリングにして指に飾って ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今夜私はあなたのものよ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 素顔のままで 粉雪の夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 暖炉の炎が消えそうだから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) あたためて身体ごと ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 不幸な恋なら前にしたけど もう一度信じたい ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 氷の張った池の上を歩くようだわ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 勇気を出して あなたの胸に ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 飛びこみたいの 粉雪の夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 心を見えない糸で結んで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 永遠にそばにいて ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) かたく閉ざした貝のように 生きて来たけど ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 両手広げて粉雪の夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 目覚める頃はプラチナの朝 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 汚れひとつない世界 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 真珠の雪をリン���にして指に飾って ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ピンクのパジャマ リボンほどいて ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) それが私の贈りものなの ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 壁のスキーの雪が溶けて 滑り落ちてく ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今夜私はあなたのものよ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 生まれたままで 粉雪の夜 ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
by 中森明菜『帰省~Never Forget~』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 深い眠りの中 今は遠いあなた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 古い愛の歌を とぎれず唄ってた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 絶望の淵でも 眠れぬ夜でも ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) その先の明日を信じ会えたはずなのに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 雪を 雪を見たかった ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 真っ白な雪を 知らない二人 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 疲れを知らない 時間は駆け足 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 春と夏を過ぎて その先はない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 輝いてたはずの 自由に迷うとき ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 都会の空の下 鳥は居場所をなくしてた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 叶わぬ夢 他の誰かじゃなく ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今は背中 まだ見せないで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 唄い続けてる限り 同じ道を歩いたあなたへ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) このかすれた声消えるまで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) Ah 夢を愛を唄うの 祈りたい 届けたい人いる限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せめて今を恥じないで 負けないで生きている だから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 同じ夢すごした日々を忘れない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今夜も眠れず 街に冷たい月 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 語り合った夢も ぬくもりもない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) うつろう昨日は果てしない明日へ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 抱きしめた体も凍えてゆくばかり ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 折れた翼 もとに戻せるなら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 二人の夢も また変わるのに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 追いかけて行くから いつも微笑んでいたあなたを ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) この曇った空 晴れるまで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) Ah 遠く一人唄うの 雪が降る 誰もいないこの街で ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 過去じゃなく明日じゃなく ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今を唄い続ける限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) その瞳 歩いた道を忘れない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) Ah 夢を愛を唄うの 祈りたい 届けたい人いる限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せめて今を恥じないで 負けないで生きている だから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 同じ夢過ごした日々をわすれない ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
by 山口百恵『白い約束』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 白く透き通る 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 音もしなやかに 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 人の汚れた心を埋めてゆくように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 綺麗なまま 生きることは ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 無理なのかしら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 私達も 愛し合うと ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) いつかは汚れてしまうのかしら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 白く透き通る 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 息をするように 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 人の涙や悲しみ 知っているように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 冷たい眼で 見られるのは ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) いつまでかしら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 私達は どんな時も ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 信じていること 約束するわ ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
_φ( 'ㅁ' * ) あなたへ差し出す涙で書いた手紙 ✉ 📄
(¥♡¥) 💸 ((¥▁¥)) 💸 \(¥Д¥)/金ーー!
◆ お金は大事だけど、すべてじゃないよ!٩(•౪• ٩)
(ღ˘⌣˘ღ)iloveyou ここへ逢いに来てくれてありがとう (Ü)۶♡٩(Ü)
☆*ɢᵒᵒᵈ ɴⁱᵍʰᵗ *☪︎。.🐏💭⋆。˚ᎶᎾᎾⅅ ℕᏐᎶℍᎢ⋆。˚✩🌟
#公開日記
#無料代行サービス #処理係
#お庭 #日本 #Japan
#2020年#12-19#12-18#12-17#令和#令和二年#歌詞#歌詞本#中森明菜#帰省~Never Forget~#山口百恵#白い約束#公開日記#無料代行サービス#処理係#チャンネル#104#初雪#粉雪#朝時間#庭木#ラスト#冬の菊#マイクを置く#アベリア#牛さん#イチゴ鉢植え#松田聖子#PEARL-WHITE EVE
0 notes
Text
07072343
容姿もいいし仕事も出来る、一流企業に勤めていて、気遣いもできて優しい。そんな完璧な彼に、たった一つだけ、どうしても腑に落ちない趣味があった。
それは、ぬいぐるみと一緒に日々を過ごす、という趣味。むしろもう、性癖にも近かった。いい歳をして、あまりメジャーではないが可愛らしい女児向けのキャラクターの人形を猫可愛がりする姿は、お世辞にも可愛らしいとは言えず、気味が悪い部類だった。
付き合ってから彼の家に初めて行った時、写真も置物も何もない、モノトーンに支配されたシックな部屋の中、黒で統一されたベッドに置かれた一つのぬいぐるみが、嫌に浮いていて奇妙に見えた。可愛らしいはずのそのぬいぐるみがただただ不気味だった。彼は何も気にせずぬいぐるみに近付き、「ただいま。」と声を掛け、頭をそっと撫でた。気味が悪い。異物、だとすら思えた私は、思わず指を差して彼に問いただした。その時のことは、忘れることができない。
「ねぇ、あれ何?」
「アレって呼ぶのはやめてもらえないかな。紹介するね。彼女は僕の大切な人。リリーだよ。」
彼がまるで赤ちゃんのように抱きしめたそのぬいぐるみは、薄汚れたウサギのぬいぐるみ。大体50センチくらいで、2頭身、口が無く、真っ黒に塗り潰されたような目が特徴的なキャラクター。所々手垢だろうか、浅黒くなったその綿の塊を、まるでベッドで私に触れる時のような、否、それ以上に慈しみを込めた手つきで撫で、そしてまたベッドへと置いた彼は、どこかうっとりとした顔でぬいぐるみを見つめ、私へ向き直った。
「彼女には触らないでね。」
「...分かった。」
「彼女、僕以外に触れられることを酷く嫌がるんだ。君の為だから。」
「分かった、お風呂借りるね。���
「どうぞ、ごゆっくり。」
入浴を済ませ部屋に戻っても、ぬいぐるみは変わらず枕元へと鎮座していた。底のない目が不気味で、暖まった体が寒気で身震いした。
「ねえ、もう眠るんでしょ?それ、退かさないの?」
「彼女は僕と眠るから、あのままでいいんだ。一人じゃないと眠れないなら、僕と彼女はソファーで眠るよ?」
「...ううん、いい。私、貴方と一緒に寝たいから。」
彼に抱かれて眠りに落ちる瞬間まで、彼の、反対の手に抱かれたぬいぐるみの目が、頭から離れなかった。穴を開けたような虚無がこちらを見て、引き摺り込もうと手を拱いているような気がした。鼻をつく百合の匂い。私は彼の胸に顔を埋め、記憶が消えないかと目をきつく瞑って眠りについた。
翌朝目が覚めリビングに行った私の目の前で、ダイニングテーブルに座らされたそのぬいぐるみを見た時の私の気持ちが、分かるだろうか。いや、きっとその光景を見ない限り、分からないだろう。喉の奥から叫びそうになる、得体の知れない気持ち悪さ。
「ねぇ、そのぬいぐるみ、なんなの?」
「大切な人、って言ったでしょ?そのままだよ。僕の、大切な人。」
本当に完璧だった。料理も出来て、綺麗好きで、何もかも完璧なのに、そのぬいぐるみと過ごす日々だけがどうしようもなく彼にとっての欠損だった。けど、一つの欠陥くらいあってこその人間だ、彼がそこまで言い張るなら仕方がない、と私は自分に言い聞かせ、彼を夫にし、私は彼の妻となり、共に暮らし始めた。
「おはよう、リリー。」
私より先に起きる彼が、必ずぬいぐるみに挨拶し、そのまま抱きかかえて寝室を出ていくことも、気にならない。
「触らないで。」
シーツを変える時、ベッドを動かす時、手を伸ばしただけで怒ってぬいぐるみを抱きしめ私から遠ざけることも、気にならない。
「誕生日おめでとう。」
ぬいぐるみにあるはずのない誕生日を祝い、私に買ってくるのと同じようなケーキを買って、手紙を書いて、幸せそうに1日を過ごすことも、気にならない。
「お義母さん、初めまして。」
彼の母、そして私の母の墓参りに、ぬいぐるみを連れてきて、挨拶をさせることも、気に、
ならないわけがないでしょ。なるよ。気になるよ!頭おかしいんじゃないの!?たかが布と綿の塊を人間扱いして、話しかけて抱きしめて、一緒にいるとこっちが頭おかしくなりそうになる。常軌を逸してる。呪い?ぬいぐるみに呪われてるの?理解が出来ない。とにかく気味が悪い。きっと、彼はあのぬいぐるみと離れた方がいい。根拠はないけど、そう思う。
彼が出勤したある日、彼に内緒で私は有給を取った。仕事に行くフリの身支度をしながら彼を見送り、そして、静かになった部屋の中でぬいぐるみと向き合う。
「本当、気味の悪い、ぬいぐるみ。」
そして初めてそのぬいぐるみに触れた。指先が触った瞬間、ぞわり、背中に悪寒が走る。そして、よく見るとそのぬいぐるみがどこか歪な、滑らかな綿ではない形状をしている事に気づく。何が奇妙なのか分からないままぬいぐるみを引き寄せ持ち上げる。重い。と、ぬいぐるみの腹あたりから、何かが飛び出しているのが見えた。
「何これ、毛...?」
飛び出ていたのは、茶色で猫っ毛の私よりもしっかりとした、黒々とした人毛。引っ張ればしゅるり、しゅるりとぬいぐるみから抜け出てくる。長い髪の毛だ。私でも、もちろん彼でもない。不倫相手から貰ったぬいぐるみだとしたら笑い草じゃない、と、詰まっていた髪を引き抜くように力を入れ引っ張る。
ブチ、ゴソッ
引き摺られてぬいぐるみから突き出した髪の束に思わず吐き気を催して、ぬいぐるみを床へ投げ出した。トサ、と決して軽くない音がする。ヒュッと息が詰まる感覚がして、ただ、そのままにしておくわけにもいかない、と、傍の文具入れに立ててあったハサミを手に取り、ぬいぐるみの足に先端を差し込み、少しずつ、布を切る、と、
「......何、これ...」
溢れ出たのは大量の髪の毛。長髪の、人一人分はあるだろう量がだらりと溢れて指に纏わりついてくる。慌ててハサミを投げ出しぬいぐるみを足で蹴って離れ、ゴム手袋とゴミ袋を探し出しぬいぐるみをそこへ突っ込んだ。胃が気持ち悪い。今にも朝食を吐きそうだ。半透明の袋越しに、ぬいぐるみの目がまだこちらを向いている。壊さなければ、と、頭のどこかから声が聞こえた気がして、落としてしまったハサミを拾い上げ、なるべくぬいぐるみを見ないようにして、手、足、耳、首を引き裂いた。袋の中は淡い色と、そして圧倒的な黒の塊のモザイクになった。
紙の袋、そして黒い袋に3重で包んだそれを、共同のゴミ捨て場に投げて、急いで家に帰る。何処かから追いかけてくるような、見ているような、そんな心地がして挙動不審になる自分を必死で落ち着かせた。
...気付いたら、ソファーで眠ってしまっていたんだろう。部屋の中はもう薄暗くなっていた。かたり、小さな音がして、慌てて玄関まで向かえば、仕事を終えて帰宅した彼の姿があった。
「おかえりなさい。」
「ただいま。今日は君が先だったんだね。」
「えぇ。体調が悪くて、早退させてもらったの。ごめんなさい、寝てしまってて、夕飯の支度が...」
「構わないよ。久しぶりだし、二人で何か食べに行こうか。」
ネクタイを解きながら部屋に入った彼は着替えを終えた後、私の座るソファーに腰掛け、ただいまを言ったテンションのまま、ぬいぐるみのことを尋ねた。
「彼女をどこへやった?」
「...実は、掃除中に汚してしまって、」
「風呂に入れたの?」
「.........捨て、たの。」
「......そっか。もう、歳だったからね。」
激昂される、殴られるかもしれない、と身構えていた私を他所に、彼は案外平気そうな顔で、どこか諦めたような顔で、ぽつり呟いた。もしかしたら彼も、あのぬいぐるみの処理に困っていたのかもしれない。ならば私はむしろ、良いことをしたのではないか。
「仕方ないね。仕方ない、仕方ない、仕方ない。」
「...貴方?」
「仕方ないよなぁ、これも。」
目を細めて笑う彼が手を振り上げ、目の前が真っ白に光った瞬間、何も分からなくなった。
「う......」
「おはよう。」
目覚めたらベッドの上、胴体と太腿をベルトでベッドに固定され、身動きの取れない状態で彼が私を見下ろしていた。力の限り暴れようとしてもびくともしない。目の焦点が段々と合っていき、私は叫んだ。
「おはよう、って、リリーも言ってるよ。」
彼の腕の中に、捨てたはずのぬいぐるみがいた。ぬいぐるみの、成れの果て、と呼ぶ方が正しいだろう。ボロボロの布切れを黒い目立つ糸でザクザクと縫い合わせて、おおよそ元の形とは違う姿にして、中身だけ戻した得体の知れない生き物の塊。所々からはみ出ているチクチクとした黒い物が何なのか、考えたくない。
「なんで、それを...」
「外に出ていたから、連れ帰ったんだ。」
「貴方、おかしいわよ、中身見たの!?髪の毛よ!?」
「これは!!!!母さんの、形見なんだ。」
「...はい?」
彼がぬいぐるみに頬擦りして、はみ出た髪を撫でる。先端に口付けて、何度も口付けを落として、そしてむしゃり、母親らしき髪の毛を口に含んだ。
「母さんが、亡くなる前に、形見として残してくれた。リリーは、母さんなんだ。僕にとって唯一の、大切な、かけがえのない人。」
「......そんな、だとしても、髪の毛を詰めるなんて、どうかしてる!」
「どうかしてたよ。だから家に、身体拘束用の道具があるんじゃないか。」
途端に、私の身体の自由を奪うあれそれもまるで髪の毛のように纏わりついてくる感覚がして、無駄なのをわかっていてももがきたくなる。嫌だ、離して。
「反省してくれたら、許してあげる。僕は酷く傷付いたんだ。人の物を勝手に捨てるってことが、どういうことなのか、よく考えた方がいいよ。」
髪をもごもごと咀嚼したまま彼は私の腕に何かを刺し、そして、部屋を後にした。防音のマンションだと彼が話していたことを、他人事のように思い出した。
監禁されてから次第に、彼がくると幸福感に満たされ、暫くすると焦燥感、不快感、不安、で体をジッとさせていられなくなった。
身体が痒い。身体中が痒い。何かが這い回るような、むずむず、ぞわぞわ、肌が痒くてたまらない。手だけは自由にしてもらえてる分、露出している腕、胸、脇腹、首を掻き毟った。
痛みよりも、掻く気持ち良さが勝った。気持ちいい、気持ちいい。
ふと見た自分の手、爪の間に、真っ白い何かがびっしり詰まっていた。ヒィッ、と小さく叫んで、爪でその詰まりを摘んで取る。とってもとっても爪の間からそれが溢れてくるようで、終わらない。普段と何かが違う、感覚がおかしい、と己の腕を見下ろせば、腕の掻き傷、ミミズ腫れになった箇所に所々、白いものが溢れていた。
「......?」
なに、これ。つまんで、引っ張る。つまんで、引っ張る。つまんで、引っ張る。つまんで、引っ張る。つまんで、引っ張る。つまんで、引っ張る。あれ、この動き、どこかで見たような、気が、する。
「わかった!!!わたし、わかった!!ねえ!!!わかったぁの!!!」
少しして部屋の扉が開く。現れた彼は口元に笑みを浮かべ、そして私のそばへ座った。どうしたの、と、口が動いて、私の腕を触る。
「これ!みて!しろいの、わたなの、わたしがおにんぎょうになったの!」
「そう、君が人形に?」
「そう!だから!わたしなったの!!!」
「そうだね......うん。」
彼がうれしそうに笑って、ああ、また幸せにしてもらえる、って思うと、かおがしあわせなかおになってしまうきがする。しあわせ。はやくほしい。はやく。
「やっぱり、違う。」
「リリーじゃない。」
「作った偽物は、本物には程遠かった。」
「手、足、耳、首、だったか。」
「彼女になったなら、彼女と同じ結末を辿るべきだね。」
0 notes
Text
ひとみに映る影 第三話「安徳森の怪人屋敷」
☆プロトタイプ版☆ こちらは無料公開のプロトタイプ版となります。 段落とか誤字とか色々とグッチャグチャなのでご了承下さい。 書籍版では戦闘シーンとかゴアシーンとかマシマシで挿絵も書いたから買ってえええぇぇ!!! →→→☆ここから買おう☆←←← (あらすじ) 私は紅一美。影を操る不思議な力を持った、ちょっと霊感の強いファッションモデルだ。 ある事件で殺された人の霊を探していたら……犯人と私の過去が繋がっていた!? 暗躍する謎の怪異、明らかになっていく真実、失われた記憶。 このままでは地獄の怨霊達が世界に放たれてしまう! 命を弄ぶ邪道を倒���ため、いま憤怒の炎が覚醒する!
(※全部内容は一緒です。) pixiv版
◆◆◆
1989年十月、フロリダ州の小さな農村で営業していた時の事だ。 あの村で唯一と言っても過言ではない近代的施設、タイタンマート。 グロサリーを買いこむ巨人の看板でお馴染みのその大型ショッピングセンター前で、俺はポップコーン屋台付き三輪バギーを駐車した。 エプロンを巻き、屋台の顔ポップ・ガイのスイッチを入れ、同じツラのマスクを被り、 「エー、エー、アーアー。ポップコーン、ポップコーンダヨ」 …スピーカーから間の抜けたボイスチェンジャー声が出ることを確認したら、俺の今日の仕事が始まる。
積載電源でトウモロコシを爆ぜていると、いつもならその音や匂いに誘われて買い物客が集まってくる。 だがその日は駐車場の車が少なく、やけに閑散としていた。 ひょっとして午後から臨時閉店か?俺は背後のマート出入口に張り紙でも貼っていないか、様子を見に行った。 一歩、二歩、三歩。屋台から目を離したのは、たった三歩の間だけだった。
ガコッ!ガコガコガシャン!突然背後から乱暴な金属音がして俺は振り返った。 そこには、一体どこから湧いて出たのか、五~六人の村人が俺の屋台バギーを取り囲んでいた。 奴らはポップ・ガイの顎を強引にこじ開けた。 ガラスケース内のポップコーンが紙箱受けになだれ込む。それを男も女も、思い思いにポリ袋やキャップ帽などを使って奪い合う。
「あぁー!!?何しやがるクソッタレ!!!」 俺はマスクを脱ぎ捨て、クソ村人共を押しのけようとした。その時。 サクッ。…背後で地面にスコップを突き立てたような音がした。 振り返るとそこには、タイタンマートのエプロンを着た店員と…空中に浮く、木の棒? いや、違う。それは…俺の背中に刺さった、鉈か鎌か何かの柄だ。 俺は自分の置かれた状況が理解出来なかった。背中を刺されたという事実以外は。 ただ、脳が痛覚を遮断していたのか、痛みはなかった。異物感と恐怖心だけがあった。 目の前では相棒が、俺のポップ・ガイが、農村の狂った土人共にぶちのめされている。 奴らはガラスケースを割り、焼けた調理器に手を突っ込んでガラスの破片とポップコーンを頬張り、爆裂前のトウモロコシ粒まで奪い合いながら、「オヤツクレ」「オカシ」「カシヲクレ」などとわけのわからない事を叫んでいやがる。
そのうち俺を刺しやがったあのクソ店員が、俺のジーンズからバギーのキーを引ったくり、屋台を奪って急発進させた。 ゾンビめいた土人共がそれにしがみつく。何人かは既に血まみれだ。 すると駐車場の方からライフルを抱えたクソが増えた。 ターン、ターン、ターン。タイヤを撃たれたバギーが横転する。ノーブラで部屋着みてぇなブタババアが射殺される。俺の足に流れ弾が当たる…痛ぇな、畜生!
ともかく逃げないとヤバい。こいつらきっとハッパでもキメてやがるんだ。 それにしても、俺の脳のポンコツめ。背中の痛みはないのに、なんで足はこんなに痛いんだクソッタレ! 「コヒュッ…コヒュッ…」息ができない。傷口が熱い。体が寒い。全身の血が偏ってきていやがる。 もはや立ち上がれない俺は匍匐前進でマートの死角まで這って逃げた。 そこには大量のイタチと、中心に中坊ぐらいのニヤついたガキが立っていた。 そいつは口元が左右非対称に歪んでいて、ギンギンに目の充血した、見るからに性根の腐っていそうな奴だった。 作業ツナギの中にエド・ゲインみてえな悪趣味なツギハギのTシャツを着て、右手にニッパーを、左手にカラフルな砂か何かの入った汚ねえビニール袋を持っていた。
「おっさん、魚みてえだな」…あ? 「背中にヒレ生えてるぜ。それに口パクパクさせながら地面をクネクネ這いずり回ってさ。 ここは山ばっかだから見た事ねえが、沖に打ち上げられたイルカってこんな感じなのかな」 何言ってやがる…このガキもキチガイかよ。それにイルカ��哺乳類だ。どうでもいいがな。
「気に入ったぜ。おっさん、俺が解剖してやるよ」…は?? 「心配するな。川でナマズを捌いた事がある。おいお前ら、オヤツタイムだぜ!」
おいジーザス、いい加減にしろ!あのクソガキは俺にキチガイじみた虹色の砂をブチまけてきやがった! 鼻にツンとくるクソ甘ったるい匂い。そうか、こいつはパフェによくかかっているカラースプレーだ。しかもよく見ると、細けえキャンディやチョコレートやクッキーまで混じっていやがる。 ファック!このガキ、俺をデコレーションケーキか何かと勘違いしてんじゃねえのか!?
「あんたのポップコーン、いつも親が買ってたぜ。油っこくて美味かった。 だからあんたの魂は俺達の仲間に入れてやるよ…」 なんでなんでなんで。なんで俺の生皮がいかれたガキのニッパーで引き裂かれてやがる。なんで俺の身体が汚ねえイタチ共に食い荒らされてやがる! カラースプレーが目に入った。痛え。だからなんで背中以外は痛えんだってえの。 俺が何をしたっていうんだジーザス。みんなの人気者のポップ・ガイがなんの罪を犯したっていうんだ。
やだよ。こんな所で死にたくねぇよ。 こんなシケた田舎のタイタンマートなんかで…おいクソ巨人、お前の事だ!クソタイタンマートのクソ時代遅れなクソ看板野郎!なに見てやがる! 「Get everything you want(何でも揃う)」じゃねえよとっととこのクソガキを踏み殺せ!! こんなに苦しんで死ななきゃならねぇならせめてハッパでもキメときゃ良かった!死にたくねぇよ!ア!ア!ア!アー!
そうだ。こんな物はただの夢だ。クソッタレ悪夢だ。もうハッパキメてたっけ? まあいい。こんな時は首筋をつねるんだ。俺は首筋をつねれば大概のバッドトリップからは目覚める事ができるんだ。 そう、こんな風に―
◆◆◆
「あいててててて痛え!!!」 ジャックさんは首筋をつねる動作をした瞬間、オリベちゃんのサイコキネシスを受けて悶絶した。
磐梯熱海温泉の民宿に集った私達一同は、二台繋げたローテーブルを囲い、タルパの半魚人ジャック・ラーセンさんが殺害された経緯を聴取していた。 「そんなに細かく話すな!イジワル!!」 涙目のイナちゃんが、私のモヘアニットのチュニックを固く握りしめたまま怒鳴った。 彼の話に「ライフルを持ったクソ」が出てきたあたりから、彼女はずっと私にしがみついてチワワのように震え続けている。 おかげで買ってまだSNSにも投稿していないチュニックが、ヨレヨレに伸びきってしまっていた。
<あんたあのね、女子高生の前でクソとかハッパとか、言葉を選びなさいよ!> ローテーブルの対面で、オリベちゃんがジャックさんを叱責する。 「まあまあ。そんで死んだ後はどうなったん…なるべく綺麗な言葉で説明してくれよ」 一方譲司さんは既に、ポメラニアンのポメラー子ちゃんのブラッシングを終え、何故か次はオリベちゃんのブラッシングをさせられている。
「まあ、その後はだな。要するに、お前達のお友達人形にされてたってわけさ」 ジャックさん、オリベちゃん、譲司さん。三人のNICキッズルーム出身者の過去が繋がった。 イナちゃんがこれから行くキッズルームは、バリ島院以外にも世界各支部に存在する。 アジア支部のバリ島院、EU支部のマルセイユ院…オリベちゃんと譲司さんが子供時代を過ごした中東支部キッズルームは、テルアビブ院だった。 (アラブ人ハーフの譲司さんは、十歳まで中東で暮らしていたんだ。)
その当時テルアビブ院には、魂を持つ不思議な人形と、それを操って動かす黒子の少年がいた。 少年は人形と同じ顔のマスクを被っていて、少年自身の意思を持っていなかった。 でもある日突然、少年は人形を捨て、冷酷な本性を剥き出しにしてNIC職員や子供達を惨殺して回ったという。 つまり、少年…生き物の魂を奪って怪物を作る殺人鬼、サミュエル・ミラーは、人形のジャックさんという仮面を被ってNICに近づき、油断した脳力者の魂を収穫したんだ。
「その辺の話は、俺よりお前ら自身の方が嫌でも覚えてるだろ。 あいつがわざわざ変装用の魂をこしらえたのは、オリベ…お前みたいに人の心を覗ける奴が、NICにはわんさかいるからだろうな。 俺は自分が自分の黒子に殺された事なんざ忘れちまってたし、 用済みになった後も奴の脳内に格納されて、長い眠りについていたようだ。 友達や先生方の死に面を拝まずに済んだ事だけは、あのクソサイコ野郎に感謝だな」 ジャックさんがニヒルに笑う。殺人鬼の隠れ蓑にされていたとはいえ、彼とオリベちゃん達の間の友情は本物だったんだろう。 仮面役に彼が選ばれたのは、生前の彼が子供達に愛されるポップコーン売りだったからだと私は推測した。
サミュエルは殺人に、怪物タルパを取り憑かせたイタチを使うらしい。 人間のお菓子や人肉を食べるように調教されたイタチは人間を襲い、イタチに噛まれた人間は怪物タルパに取り憑かれる。 取り憑かれた人間は別の人間を襲う。その人間も怪物に心を支配され、別の人間を襲う。 そうしてゾンビパニック映画のように、怪物に操られた人間がねずみ算式に増えていく。 サミュエルはこのようにして、自ら手を下さ��に集団殺し合いパニックを引き起こすんだ。 1990年。二十年前のNIC中東支部を襲った惨劇も、この方式で引き起こされた。 幼い頃のオリベちゃんはその時、怪物タルパとイタチを一掃するために無茶なサイコキネシスを放った後遺症で構音障害になった。そして…
「なあジャック」譲司さんが口を開く。 「アッシュ兄ちゃんって、覚えとるか? 弱虫でチビやった俺を、一番気にかけてくれとった」 「ん、ああ。勿論覚えてるさ。 ファティマンドラの種をペンダントにしていた、サイコメトリーの脳力児。あいつがどうかしたのか」 ジャックさんがファティマンドラという単語を口にした瞬間、譲司さんは無意識に頭に手を当て、 「ハァー、…フーッ」肺の空気を入れ替えるダウザー特有の呼吸をした。そして、 「…アッシュ兄ちゃんは。俺の目の前で、サミュエルに殺された。 その時…兄ちゃんの魂は胸の種に宿って、ファティマンドラになったんや」胸元に手を当てて言った。 「なんてこった…!」 ジャックさんは目元を強ばらせる。
話を理解できなかったイナちゃんが、私のチュニックをクイクイと引っ張った。 「ええとね…ファティマンドラっていうのは、簡単に言えば動物の霊魂を宿して心を持つ事ができる霊草の事なの。 譲司さんの幼馴染のアッシュさんは、殺された時、その種を持っていたおかげで怪物に魂を取られずに済んだけど、代わりに植物の精霊になっちゃったんだ」 「そなんだ…。ヘラガモ先生、今も幼馴染さんいるですか?」 「ああ。種はもう花を咲かせてなくなっとるけど、兄ちゃんは俺と完全に溶け合って、二人合わさった。 せやから、アッシュ兄ちゃんは今俺の中におる」 「すまねえ…あいつの事を思い出せなくて、お前らみたいなガキ共を巻き込んじまって。本当にすまねえ」 ジャックさんがオリベちゃんと譲司さん、そして譲司さんと一つになったというアッシュさんをまっすぐに見つめる。 一方、当のオリベちゃん達は、ジャックさんが謝罪する謂れはないとでも言いたげに、彼に優しい微笑みを向けていた。
「ヒトミちゃん」 しんみりとしたムードの中、イナちゃんが芝居がかった仕草で私のチュニックを掴んだ。 「ごめんなさい、チュニック、伸ばしちゃたヨ。 お詫びにあげたい物あります。お着替え行こ」 「え?」 「ポメラーコちゃんにも!」 「わぅ?」 私はポメちゃんを抱えたイナちゃんに誘導され、別室に移動した。
◆◆◆
「へえ、韓国娘。あんた粋なことするじゃないの」 高天井の二階大部屋。剥き出しの梁の上では人間体のリナが、うつ伏せで頬杖をついたまま私達を見下ろしていた。 その時イナちゃんが着ていたのが水色のパフスリーブワンピースだった事も相まって、まるで不思議の国のアリスとチェシャ猫みたいな構図だ。 二階に上がったのは私とイナちゃん、ポメラー子ちゃんにリナ。階下に残ったのは中東キッズルーム出身の三人のみ。 そういう事か。 「『後は若い人達に任せましょう』。私が好きな日本のことわざだモン」 胸を張ってイナちゃんが得意気に言う。それ、ことわざだったっけ…?
イナちゃんは中身を詰めすぎて膨らんだスーツケースの天板を押さえながら、布を噛んだファスナーを力任せに引いて開けた。 ミチミチの服と服の間から、哀れにも角がひしゃげたユニコーン型化粧ポーチを引き抜くと、何かを探すように中身を床に取り出していく。 「ボタニカル・ボタニカル」のオールインワン下地、「リトルマインド」のリップと化粧筆一式、「安徳森(アンダーソン)」の特大アイシャドウパレット… うーん、錚々たるラインナップ!中華系プチプラブランドの安徳森以外、どのコスメも道具も、高校生のお小遣いでは手を出し難い高級品だ。 蝶よ花よと育てられた、いい家のお嬢様なのかもしれない。
「あったヨ!」 ユニコーンポーチの底からイナちゃんが引き抜いたのは、二重丸の形をした金色のペンダント。 「ここをこうしてネ…ペンダントと、チャームなるの」 二重丸の中心をイナちゃんが押し上げると、チリチリとくぐもった金属音を立てて内側の円形が外れた。それは留め具付きの丸い鈴だった。 『링』 『종』 中央が空洞化してリング型になったペンダントと鈴の双方に、それぞれ異なる小さなハングル文字が一文字ずつ刻印されている。 それを持ったイナちゃんの両手も、珍しく左右で手相が全然違う模様なのが印象的だった。 左は生命線からアルファベットのE字状に三本線が伸びていて、右は中央に大きな十文字。手相には詳しくないから占いはできないけど。
イナちゃんはE字手相の左手でペンダントを私の首にかけ、右手の鈴はポメちゃんの首輪に括りつけた。 金属のずっしりとした重量感。これも高価な物なんだろうと察せる。 「イナちゃん、これ貰っちゃっていいの?まさか金じゃないよね?」私は恐る恐る聞いた。 「『キム』じゃないヨ。それは、『링(リン)』と読みます。リングだからネ。 キーホルダーは『종(チョン)』、ベルを意味ですヨ」 「い、いやいや、ハングルの読み方を聞いたんじゃなくて」チャリンチャリンチャリン!「ワンワンっ!」 私のツッコミは鈴の音を気に入って飛び跳ねるポメちゃんに遮られた。 「ウフッ、ジョークジョーク。わかてますヨ、ただのメッキだヨ」 「な…なんだ、良かった。それでもありがとうね」
貰ったペンダントを改めて見ていると、伸びたチュニックが一層貧相に見えてきた。 この後私達はお蕎麦屋さんに夕食を予約している。さすがにモデルとして、こんな格好で外を出歩くわけにはいかない。 折角貰ったいいペンダントに合わせて、私は手持ちで一番フォーマルな服に着替える事にした。 切り絵風赤黒グラデーションカラーのオフショルワンピースだ。
「アハ!まるで不思議の国のアリスとトランプの女王だわ」 梁から降りたイナが、私とイナちゃんが並んだ様子を比喩する。 「そういうリナはさっきまで樹上のチェシャ猫だったじゃない」 「じゃあその真っ白いワンコが時計ウサギね」 私達は冗談を重ね合ってくすくす笑う。こんな会話も久しぶりだな。 そこにイナちゃんも加わる。 「ヒトミちゃん、ジョオ様はアイシャドウもっと濃いヨ」 さっき床に散らかしたコスメの中から、チップと安徳森のアイシャドウパレットを持って、イナちゃんはいたずらに笑った。 安徳森、アンダーソンか…。そういえば…
「私…磐梯熱海で、アンダーソンって名前のファティマンドラの精霊と会ったことがあるな」 私はたった今思い出した事を独り言のように呟いていた。 イナちゃんの目が好奇心に光る。 「さっき話しした霊草の魂ですか?ここにいるですか!」 「うーん、もう3年前の事だけどね…」
それは私が上京する直前のこと。 ヒーローショーの悪役という、一年間の長期スパンの仕事を受ける事になった私は、地元猪苗代を発つ前にここ磐梯熱海温泉に立ち寄った。 和尚様と萩姫様にご挨拶をするためだ。 するとその日は、駅を出るとそこらじゅうに紫色の花が咲いていた。 私は合流した萩姫様に伺い、それがファティマンドラの花だと教わった。 そしてケヤキの森で、それらの親花である魂を持つファティマンドラ、アンダーソン氏を紹介して頂いた。 アンダーソン氏は腐りかけの人脳から発芽したせいで、ほとんど盲目で、生前の記憶もかなり欠落していた。 ただ一つ、自分の名前がアンダーソンだという事だけ辛うじて覚えていたという。
とはいえ、元警察官の友達から聞いた話では、ファティマンドラは麻薬の原料にもなり日本では栽培を許可されていないらしい。 ファティマンドラには類似種の『マンドラゴラ・オータムナリス』というよく似た花があるから、駅に咲いていたものに関しては、オータムナリスだったのかもしれない。
「改めて今熱海町に来たら、もう駅前の花はなくなってるし、さっきケヤキの森を通った時もアンダーソンさんはいなかったの。 もう枯れちゃったかな…魂はどこかにいるかも」 「だといいネ。私も見てみたいです。 そのお花さんに因みな物あれば、私スリスリマスリして呼び出せるですけど」 「え、すごいね!イナちゃん降霊術もできるんだ…」
スタタタタ!…私達が話している途中から、誰かがものすごい勢いで階段を駆け上がる音がした。 二階部屋の襖がターン!と豪快に開き、現れたのはオリベちゃん。 <そのファティマンドラよ!今すぐ案内して頂戴!!> 「オモナっ!」驚いたイナちゃんが顔の前で手を合わす。
「え!?ど、どういう事ですか?」 <サミュエルは最後に逃亡する直前、ジャパニーズマフィアの薬物ブローカーだったの。そして麻薬の原料としてファティマンドラの種子を入手していた。 だからそれを発芽させるために、ブローカー仲間の女子大生を殺害して、その人の肉や脳を肥料に与えていたというのよ> 「ああ…女子大生バラバラ殺人の事ですね。指名手配のポスターで有名な」 物騒な話題にイナちゃんは顔を引きつらせる。またストレスで悪霊を呼び寄せないように、すかさずリナは彼女の体を抱き寄せて頭を撫でた。
イナちゃんは知らないだろうけど、実はサミュエルの通名、水家曽良という名は日本では有名だ。 彼は広域指定暴力団の薬物ブローカーで、ブローカー仲間だった女子大生を殺害した罪で指名手配されている。 だから駅や交番のポスターには、彼の名前と似顔絵がよく貼ってあるんだ。
<その女子大生から生まれたと思しきファティマンドラがね…なんと、眠っていたジャックを呼び覚まして助けた張本人らしいのよ!> 「そうなんですか!」 オリベちゃんに続き、そろそろとジャックさんと譲司さんも二階に上がってきた。 ただ譲司さんは、興奮気味のオリベちゃんとは裏腹に煮え切らない顔をしている。 「いや、せやけどなオリベ。殺された女子大生は『トクモリ・アン』って名前やろ。 ジャックが言っとったファティマンドラは『アンダーソン』って名乗っとったらしいし…『アン』しか合っとらんやん」 トクモリアン?ああ、はい。 私とイナちゃんとリナは三人同時に察して、ニヤリと顔を見合わせた。
「ダウザーさん、その被害者の名前の漢字、当ててあげようか」挑発的にリナが譲司さんに微笑む。 リナが目配せすると、イナちゃんはあのアイシャドウパレットを譲司さんの前に持っていった。 「あん、とくもり…安徳森!何で?」 「そです。でもちがうヨ!中国語それ『アンダーソン』て読みます」 「なるほど!」 「そういう事だったのか」 <え…ど、どういう事ですって?> 譲司さんとジャックさんが納得した一方、ユダヤ人のオリベちゃんだけは頭にはてなマークを浮かべた。 私はパレットの漢字を指さしながら、非アジア人の彼女に中国語と日本語の漢字の読み方を解説した。
<じゃあ、中国語でそれはアンダーソンになって、日本語ではアン・トクモリになるの!面白いカラクリだわ。> 「ファティマンドラ化した徳森安は生前の記憶を殆ど失っている。 その文字列が印象に残っていても、自分の名前じゃなくて有名な化粧品ブランドの読み方をしちまったのかもな。 あれでも女子大生だったし」ジャックさんが補足する。
<となるとやっぱり、殺された女子大生で間違いないようね。 ジャックを蘇らせてくれたお礼と、サミュエルに関しての情報も聞きたいわ。 どうにかして彼女と会えないかしら?> 「ケヤキの森にいないなら…怪人屋敷に行けば何かわかるかもしれねえな。 まだあいつが成仏していなければ、だが」 ジャックさんが親指に当たるヒレをクイクイと動かす。その方角は石筵を指していた。 「怪人屋敷って、石筵の有名な心霊スポットですよね?山にある廃工場の。 実際はこの辺りで生まれたタルパとか式神達の溜まり場で、それを見た人間が『人間とも動物とも違う幽霊がいっぱいいる!』と思って怪人屋敷って呼び始めた…」 「何よ、じゃあ私も人間にとっては怪人だっていうの?失礼しちゃうわ!」 リナがイナちゃんを撫でながらプリプリと怒る。 「怪人屋敷なら俺が場所を案内できる。かつてのサミュエルの潜伏地点だ」 「そうか。よし、夕食までまだ時間がある。車で行ってみよう」
◆◆◆
日が沈みかけていた。 私達を乗せたミニバンは西日に横面を照らされながら、石筵の霊山へ北上する。 運転してくれたのは、譲司さんに半身取り憑いたジャックさんだ。 生前は移動販売をしていただけあって、私達の中で一番運転が上手い。同乗していて、坂道やカーブでも全くGを感じない。 譲司さんも彼のハンドルテクに、時折感嘆のため息を漏らしていた。 故人の意識にハンドルを任せたのはギリギリ無免許運転かもしれないけど、警察にそれを咎められる人はいないだろう。
廃工場の怪人屋敷か。私が観音寺に住んでいた頃は、そんな噂があるとは知らなかった。 でも行ったことは何度もある。 あそこには沢山の式神、精霊、タルパ、妖怪がいた。みんな幼い私と遊んでくれたいい人達だ。 人に害をなす魂がいなかったのは、すぐ近くに和尚様が住んでいらしたから、だったのかも。 私はリナと共に影絵を交えながら、そんな思い出話をイナちゃんやオリベちゃんに語った。
「ジャックさんは、会ったことありますか?和尚様。 怪人屋敷のすぐそばの観音寺です」 私はバックミラー越しにジャックさんを見ながら話題を振った。 「残念だが、俺があの屋敷にいた時は、サミュエル本体に色々あって夢うつつだったんだ。 ファティマンドラの幻覚と現実の狭間をずっと彷徨ってた感じだ。 けど、少なくともその世界には神も仏もいなかったぜ」 「そうなんですか…。後でちょっと寄らせて下さい。紹介したいです」 「ああ、俺も知り合っておきたい。本場チベット仕込みのタルパ使いなんだろ、その坊さん。 だったらあのクソに作られた俺みてえな怪物も、いざという時に救って下さるかもしれねえよな」 「そんなこと言わないで下さい、ジャックさんいい人ヨ」 イナちゃんが身を乗り出して反論した。 ジャックさんは目線をフロントガラスに向けたまま、小さく口角を上げた。
カッチ、カッチ、カッチ。リズミカルなウィンカー音を鳴らしながら、ミニバンは車道から舗装されていない砂利道に入る。 安達太良山の麓にそびえ立つ石筵霊山の、殆ど窓のない無機質な廃工場が見えてきた。 多彩な霊魂が行き交い、一部の界隈では魔都と呼ばれるこの郡山市でも、ここは一際邪悪な心霊スポットとして有名な場所だ。 そんな噂が蔓延しだしたのはいつ頃の事だっただろうか。 少なくとも私の知っている廃工場は、そこまで物々しい場所じゃなかったのに…。 ジャックさんが工場脇の搬入口にミニバンを駐車している間、私は和尚様の近況を案じた。
その不安感が現実になったかのように、ミニバンを開けた瞬間何かを察知して顔を引きつらせたのは、意外にも譲司さんではなくオリベちゃんだった。 <あの二階、何かある。何だかわからないけどとんでもない物があるわ!> テレパシーやサイコキネシスを操る彼女だけが、その有り余るシックスセンスで異変を察知したんだ。 オリベちゃんが指さした工場の二階には窓があるけど、中は暗くて見えない。 私やリナ、イナちゃん、ジャックさんには遠すぎて霊感が届かないし…、 「すまん、オリベ。あの窓はめ殺しで開かんやつやから、俺にはわからん」 空気や気圧でダウジングする譲司さんには尚更読み難い状況だ。
「それより、あっちに…」 譲司さんが言いかけた事を同時に反応したのは、ポメラー子ちゃんだった。 ポメちゃんは鈴を鳴らしながら譲司さんの脇をすり抜け、バイク駐輪場らしきスペースに駆けていき、 「わうわお!」こっちやで!とでも言っているような鳴き声で私達を誘導した。 そこにあった物は…
◆◆◆
「うぷッ」 条件反射的に私の胸がえずく。直後に頭痛を催すような強烈な悪臭を感じた。 隣でオリベちゃんが咄嗟に鼻をつまみ、リナはイナちゃんの目を隠す。 既に察していた譲司さんは冷静に口にミニタオルを当てていた。
そこにあったのは、腐敗した汚泥をなみなみと湛えた青い掃除用バケツ。 ハエがたかる焦茶色の液体の中には、枯葉に覆われて辛うじて形を保った、チンゲン菜のような植物の残骸が見える。 花瓶に雨水が入って腐ったお墓の仏花を想起させるそれは…明らかに、ファティマンドラの残骸だった。
「アンダーソン」ジャックさんが歩み寄る。 「もう、いないのか?あいつを待ちくたびれて、くたばっちまったんだな」 ジャックさんは汚泥にヒレをかざしたり、大胆にも顔を突っ込んだりしながら故人の霊魂を探した。 でも、かつて女子大生の脳肉だった花と汚泥が、彼の問いかけに脳波を返す事はなかった。
するうちリナの腕をほどいてイナちゃんが割って入る。 また彼女の精神がショックを受けて、悪霊を呼び出さないかと心配になったけど、 驚く事に彼女は腐った花に触れ、「スリスリマスリ…スリスリマスリ…」と追悼の祈りを捧げた。
「い…イナちゃん、大丈夫なの?」私達は訝しみながら彼女の顔色を覗きこむ。 しかしイナちゃんは涼しい顔で振り返った。 「安徳森さん、ジャックさんのオンジン。だたら私のオンジンヨ。 この人天国に行ってますように、そこにいつかジャックさんも行けますように。 スリスリマスリ、私お祈りするますね」 イナちゃんが微笑む。その瞬間、悪臭と死に満ちた廃工場の空気が澄み渡った気がした。 譲司さんは前に出て、ファティマンドラをイナちゃんの手からそっと取り、目を閉じる。
「オモナ…ヘラガモ先生?」 「サイコメトリーっていってな。触れた物の残留思念、つまり思い出をちょっとだけ見ることが出来るんや。 死んだ兄ちゃんがくれた脳力なんよ…」目を閉じたまま譲司さんが答えた。 そのまま数秒集中し、彼は見えたヴィジョンをオリベちゃんに送信する。 それをオリベちゃんがテレパシーで全員に拡散した。
ザザッ…ザリザリ…。チューニングが合わないテレビのように、ノイズ音と青黒い横縞模様の砂嵐が視覚と聴覚を覆う。 やがて縞模様��複雑に光彩を帯びて、青単色のモノトーン映像らしきものを映し出し、ノイズ音の隙間からも人の肉声が聞こえてきた。
ザザザ「…ん宿のミ…ム、元店ち…すね。署までご同こ」ザザザザッ「…い人屋敷へか…んな化け物を連れ」ザザ…「…っている事が支離滅れ…」「…っと、幻覚を見」ザザザザッ…
「あかん。腐敗が進みすぎて殆ど見えん」譲司さんの額は既に汗ばんでいる。 それでも彼は…プロ根性で、ファティマンドラを握る手を更に汚泥の中へ押しこんだ! 更に、汚泥が掻き回されてあまつさえ悪臭の漂う中、「ハァー、フゥーッ…ウッ…ハァー、フゥーッ…」顔にグッショリと脂汗を湛えてえずきながら、ダウジングの深呼吸を繰り返す!
彼の涙ぐましすぎる努力と、サイコメトリー・ダウジングの相乗効果によって、残留思念は古いVHSぐらい明瞭になった。 「新宿のミラクルガンジ…」ザザッ「…元店長の水家曽良さんですね。署までご同行願えますか」ザザザッ。 未だ時折ノイズで潰れているが、話の内容から女性警察官らしき声だとわかる。でも映像に声の主は映っていない。 ファティマンドラの低い目線視点でわかりづらいが、映像で確認できる人物はサミュエル・ミラーらしき男性だけだ。
「あ?はは、なんだ…」ザザザッ「一体何の冗談…」ザザッ「さあ、怪人屋敷へ帰るぞ…」ザザッ。 オリベちゃんの口角が露骨に下がった。これは水家曽良、つまり殺人鬼サミュエル・ミラーの声だろう。 「言っている事が支離滅裂で…」ザザザッ「…え。彼はきっと幻…」ザザッ。 サミュエルとは違う男性と、女性の声。彼を連行しようとしている『見えない警察官』は、複数人いるようだ。
「幻覚?何を今更。…あれも、これも!ははは!ぜんぶ幻覚じゃねえか!!!」ザバババババ!! 錯乱したサミュエルが周囲の物を手当り次第投げる。 ファティマンドラの安徳森氏は哀れにも戸棚に叩きつけられ、血と脳肉が飛び散った。 その瞬間から、またノイズが酷くなっていく。 「はいはい。後でじっくり聞い…」ザザッ「暴れな…」ザザッ「…せ!どうせお前らも俺の妄そ」ザリザリ!ザバーバーバー!! 残留思念はここで途絶えた。
「アー!」色々と限界に達した譲司さんが千鳥足で、駐輪場脇の水道に走る。 譲司さんは汚い手で触れないように肘で器用に蛇口を回すと水が出た。 全員が安堵のため息を漏らす。幸い廃工場の水道は止まっていなかったみたいだ。山の湧き水を汲んでいるタイプなんだろう。 同じく安徳森氏に触ったイナちゃんも、譲司さんと紙石鹸をシェアしながら一緒に手を洗った。
◆◆◆
グロッキーの譲司さんを車に乗せるわけにもいかず、私達は扉が開けっ放しの廃工場、通称怪人屋敷のエントランスロビーで休憩する事にした。 「あんた根性あるのね。見直したわ!」リナが譲司さんの周りをくるくる飛び回る。 対して満身創痍の譲司さんはソファに横たわり、「やめてぇ…」とヒヨコのような弱々しい声で喚いた。 <無茶した割に手がかりにならなかったわね。サミュエルはまだ指名手配犯だから、あれは警察じゃない。 でも正体はわからないままよ>手厳しいオリベちゃん。 「無茶言わんでくれぇ…あんなん読めへんもんもうやあわあ…」最後の方は言葉にすらなっていない譲司さん。 結局、あの偽警察官は何者だったのか…もし残留思念の通りなら、生きた人間じゃない可能性もある。 それでも、イナちゃんにお祈りされ、譲司さんにあそこまで記憶を読み直してもらった安徳森氏は、浮かばれるだろうと願いたいものだ。
カァーン!…カァーン!…電気の通っていないはずの廃工場で、突然電子音質の鐘の音が鳴った。 リナとイナちゃんがビクッと身構える。…いや、リナ、あんた怪人側の人じゃん。 「俺や」音源は譲司さんのスマホだった。 彼は以前証券会社の社長だったから、これは株式市場の鐘の音なのかもしれない。 譲司さんがスマホを出そうとスウェットパンツのポケットをまさぐる。指が見えた。穴が開いているのを着続けているみたいだ。
「もしもし?」譲司さんはスマホを耳に当てた。着信は電話だった。 (もしもし。すまない、テレビ通話にしてくれないか?) 女性の声だ。静かな廃工場だから、スピーカー越しに相手の声が聞き取れる。 電話をかけておいて名乗りもしない相手を訝しみながら、譲司さんは通話をカメラモードに切り替えた。すると…
「あ…あなたは、まさか!」 驚嘆の声を上げた譲司さんに、私達全員が近寄る。 皆でスマホの画面を覗かせてもらうと、テレビ通話のカメラは私達の顔ではなく、誰もいないロビー奥の方向を映している。 でも画面の中では、明らかに人工霊魂とわかる、翼の生えた真っ赤なヤギが浮遊していた。
0 notes
Text
スノーベリーのクロスタータとミルク
旅の連れが出来て、食べる物が変わった。
何か高価なものを買う訳ではないのだが、樽の底に捨てられた古い野菜を食べることはなくなった。最初に出したリンゴとキャベツとヤギ足肉のシチューの正体が「樽から出てきたリンゴとキャベツ、山賊の隠れ家から奪い取ってきたヤギ足肉を盗品のエールで煮込んで」だったと知ったらさすがのルマーリンも顔を青くするだろう。私の食生活は他者にはあまりお勧めできない。とかく常に襲ってくる飢餓感を満たすためには、人肉だろうと木の皮だろうとベニテングタケであろうと食べ続けていないといけないのだ。野菜の出自をどうこう言っている場合ではない。
さて、最初はルマーリン、この召喚師の癖に剣と弓しか喚べないアルトマーの青年(三百は生きている私から見れば彼は十分青年だ)とは別々に食事をしようと思っていた。ところが向こうは違ったらしい。初めて会った次の日、しなびた上に一度凍り付いて解凍されたウリをかじっている時に不意にルマーリンが聞いてきたのである。金色の明るい瞳を興味深げに輝かせて。猫髭めいた戦化粧を本物の猫のごとくひくひくさせて。
「デザートから先に食べるのも悪くないですが、今日の昼御飯は何ですか? 私、ずっと考えていたんですけれど。昨日のシチューはヤギの足肉ではなくウサギの肉を使うのも良かったと思うんですよ。ああ、でも朝パンを刻んだものを鍋に入れて粥にしたのは悪くなかったですね。パサパサしなくて済みますから」
それから私のウリをちらりと見て、
「あ、そのウリはやめておきます」
と言った。
「自分の分はないのか」
「ハニーナッツのおやつじゃおなかは膨れないと思いますよ。もう一つしかありませんし」
「……山の中でどうやって生きていくつもりだったんだ」
「ウィンドヘルムに戻ろうかと思っていたんです」
それじゃあ何かあった時に餓死するだろうと思って呆れ、それから私は「この男、見ず知らずの旅人に夕飯をたかったのか」と思ってさらに呆れた。多分本人はたかった気はしていないだろうからさらにさらに呆れた。そして料理を作ると言い出したのは私であったわけで何とも言えない顔になった。
「というわけで何かありません? さっきのウリや最初に見た栄養剤とは……こう……違う何か」
少し考える。私の背嚢の中の食物は大体が奪ったものかくすねた物で品質は度外視だった。腐りかけているものもあるはずだ。
「ないな」
「そうですか」
「このウリのような物なら沢山あるが」
「遠慮しておきます。あまり、その、私からは美味しそうには見えないので」
私の「物を美味しいと感じる機能」は無くなって久しい。甘味苦み等は感じられるが、それが美味しさと一致しないのである。ただ、ああ、味だなと通り過ぎていくだけだ。擦り切れて消えてしまったのだろう。生きていくうえで無くても困らない。一部の宿屋の主や食事をふるまってくれる輩には怪しまれるが、その時は「甘みと酸味の比率が合わさっている」やらそのようなことを言っておけばアルトマーの奇癖だと思われるのか特に深くは扱われない。少なくともここ二百年はそうだった。元々アルトマーは親類のボズマーにこそ負けるが奇矯な所があると他種に思われることが多い種族であった。オブリビオン動乱直後のシロディールにも変人のアルトマーは多々いた。有名なところではニルンルート研究で有名なシンデリオン師も実際に会った「先生」の談によると「面白いエルフ」であったらしい。なお現在は諧謔に富んだアルトマーは生真面目なサルモールに駆逐されて久しい。支配の下では、誰も心からは笑えない。そして、一度飛び去ったかろやかな笑いは、かつての形では二度と戻ってこない。私に残されたのは残酷な笑いのみだ。最も笑いも味覚と同じように無くても困らないのだが。おそらくは。
ともかく、ルマーリンは昼食をご所望らしい。
「もう少し行けばウィンターホールドだ。昼飯とおやつを同時に取ればいい」
ルマーリンは自分のローブをちらと見た。そして魔術師の集まるウィンターホールド大学と自分の偽大学ローブの関係性について何か言おうとした。
「行くぞ」
遮って先へ行く。ルマーリンは何も言わず付いてきた。
海岸線に沿ってウィンターホールドへ。道中オオカミや氷の生霊に襲われ、時折保存食の為にホーカーを襲いながら進む。空腹だというのに(空腹だからか?)ルマーリンの冗談は止まらず、私はそれを聞き流しながら歩いていく。
やがてウィンターホールドにたどり着く。空は昼だというのに暗く、雪は止むことを知らない。かつては威容を誇ったらしい街も今は見る影なく寂れ、廃墟より少しマシ、というありさまである。店と言えば宿屋と雑貨屋が一軒ずつある程度。
「選択の余地が無いので気楽ですね。入ってもいいですか? このままだとエルフの氷像が二つ出来上がります……アルトマーの平均より数インチ背が高いのと、一インチ低いのと」
皮肉なんだか本気なんだかと思ったものの、確かに打ち付ける雪と吹き付ける風は体温を確実に奪っていく。ちなみに私は背が高い。娘時代はそのことを気にしていたものだ。曰く、ドレスが似合わない、口づけする相手より背が高いのはロマンティックではない、と。傭兵、山賊時代はこの背の高さが役に立った。相手を威圧するのに十分だったのと、歩幅が大きいので歩く速度、走る速度が増すためだ。
物思いにふけっている数拍の間に、先に入りますよ、という顔をしてルマーリンは宿へと入っていった。私も後に続く。中に入ると典型的なノルド様式の宿で、内気の温かさがこれまでの旅の疲れを強制的にほぐしていく。子供達が遊んでいたが、セリフから察するに「悪いエルフを退治する」という内容だったせいかいきなり入ってきたアルトマー二匹を見て顔を見合わせ、別の遊びをはじめた。大学関係者だろうか、他にもアルトマーの男が一人居て研究の余波ですごい臭いがしたことでああだこうだ言われていたが、やがて部屋に戻っていった。
宿の主人とその妻がルマーリンの本物とは見分けのつかぬ偽大学ローブを見て少し複雑な表情を浮かべたが、いらっしゃい、とどこにでもある宿屋の対応をした。どうやらここでは大学関係者は微妙な位置にあるらしい。
適当に座り、喉を潤すものと胃に溜まるものを、と注文する。その横でルマーリンはせっせと注文をしていた。
「ラベンダーのパイとホーカーのシチュー、それとパンに鶏肉のパイ、温めて蜂蜜とバターを落としたミルク。あ、パイは一切れずつ」
そんなに食べられるのかと心配しかけ、別に腹痛に困る羽目になっても宿屋に転がしておけばいいと割り切る。私の目的は呪文書の購入であってこの若いアルトマーの世話をすることではないのだ。
店の主人は頭を振り、
「ラベンダーのパイと鶏肉のパイは扱ってないね。ホーカーのシチューに使う分でラベンダーは精いっぱい、鶏は卵をとる分で精いっぱいだ……見ればわかるだろう、ここは物資がいつでも足りないんだ」
確かにラベンダーは比較的温かいホワイトランではよく見たが、雪深いこの辺りには生えそうもない。
「なら、何か肉っぽい物と甘いものでいいですよ」
「ホーカーのパイとスノーベリーのクロスタータならあるが」
「ああ、いいですね。それでお願いします」
満足げな猫の顔をして、ようやくルマーリンは椅子に座った。
待つことしばらく。予想外だったのは「ホーカーのシチューとパンにホーカーのパイ、温めて蜂蜜とバターを落としたミルク、それとスノーベリーのクロスタータ」が二人分来たことだった。どうやら宿屋の主人の頭で注文は都合よく解釈されたらしい。幸い私は量も取る方であったので問題はなかった。財布に余裕もある。連れのアルトマーの財布事情は知らないがさすがに「払ってください」というほど面の皮が厚いとは思わない。多分。
「ミルク飲みは馬鹿にされますけどね、こうやって温めたのにパイの皮を浸すと楽しいんですよ。知ってました?」
ルマーリンはパイを解体しては皮をミルクに浸して食べるというマナーとは真逆の行為に耽っていた。私はああ、と空返事をしてホーカーのシチューにパンを浸してたべる。ラベンダー臭が少し、肉の臭みは少なく、塩分は適量。温度も適温。これが私の認識できる味覚の限界であり、美味しいに結びつくことはない。
ホーカーのパイを解体し終わったルマーリンはせっせとスノーベリーのクロスタータに手を付ける。パイとは似ているがクロスタータはクッキー生地のタルトと言った方が近く、パイと同じ気持ちで手を付けたルマーリンの目の前で見事に崩壊した。
ルマーリンがどうしましょうね、これ、といいたげな顔でこちらを見た。
「それこそミルクで流し込め。胃に入れば同じだろう」
「なるほど、至言です」
クロスタータの残骸を掻き込んで、彼はミルクを口に含んだ。
その後、黙々と私は食べ続け、ルマーリンはホーカーについての冗談三つ、スノーベリーについての冗談を五つほど飛ばしながらせっせと食べ続けていた。
「はあ、食べました! ホラアナグマに襲われそうでももう動きたくありませんね」
見事に平らげられた皿の前でフォークとナイフを並べたり横にしたりしながら満足げにつぶやくルマーリン。今やサマーセットでは見かけられないであろう心からの笑みを浮かべたアルトマーがそこにいた。それを見て私は思わず下を向いた。
同胞にこの笑みがある未来を与えられなかった――結局は守れなかった。
敗北に逃走、そして「緑炎の夜」の大虐殺。捨て去ったはずの感傷と後悔が、悪夢を思い出すかの如くふと浮かび上がる。
「どうしたんです難しい顔をして。別に動かなくてもいいんですよ」
「いや、なんでも。動けないならここにいろ。私は大学に行く。宿賃は折半だ。互いに気がないなら、別に同じ寝台でも構いやしないだろう」
しばし彼は目をぱちくりさせ。
「ベッドの大きさにもよりますね」
そう言って相場の半分の宿賃を取り出して払った。宿の主人は複雑な顔になった。アルトマー二人からふんだくれると思っていたのだろうか。残り半分を私が払い、満腹のルマーリンを残して大学への道を急いだ。
呪文書を買い(この年になって入学する羽目になったのは予想外だったが)、晩飯にまたホーカー尽くしを食べる。私は背嚢の中の凍った野菜でよかったのだが一人宿屋で別行動をして怪しまれるのは勘弁だったのでルマーリンに付き合う。そして特にロマンチックなこともない一夜を過ごして朝を迎える。寝台は狭くなかったが、さすがにアルトマー二人が並んで寝るとなると予想以上にきつかった。
「次からは別々に寝よう」
「ええ。背中のあたりがぱりぱりになりました」
そういえば道連れのいる旅はどれ位ぶりだろうか? ぼんやりとそんなことを考え、朝食を選ぶ。
「クロスタータ、まだありますか? あとヤギのチーズ」
「はいよ。焼きたてとは言わないが、まだあるな」
ルマーリンはスノーベリーのクロスタータがずいぶんお気に召したらしい。もしくは新しいメニューを開拓するのが面倒だったのかもしれない。
「同じのを」
私は頼む。昼晩朝とまともな食事をとったことになる。我ながら珍しい。
「ああ、そうだ。少し食材を分けてもらえないか。これからドーンスターとモーサルを通ってソリチュードに行く。この連れが良く食べるみたいだから、「まともな食材」が必要なんだ」
店の主人に話しかけると商売のチャンスと思った彼は交換に嬉々として応じてくれた。ルマーリンは何か言いたげにこち��を向いたが、残念ながら口にクロスタータを頬張っていた。
背嚢の傷んで凍った食物類はこっそり宿の裏に捨てていくことにした。
昼は最後のクロスタータとニンニクで臭みをとって焼いたホーカー肉。
夜は牛乳抜きクラムチャウダーとパン。(これは不評だった)
朝はその残りに刻んだ野菜を突っ込んだもの(ルマーリンはまずまずの顔をした)
こんな具合でドーンスターに着き、また食材を買って進む。モーサルを経由し、また様々な食材を買い込む。朝食にはマッドクラブのスープを食べ、昼には塩漬けの鮭を焼いた。
「いろいろ作れるんですね。どこで覚えたんですか」
意外だとばかりに、ルマーリンは聞く。
「娘時分に一通りの家事と錬金術を叩き込まされてね。あとは魔法と隠密も」
「変わった家の方針ですね」
「教わった人間が冒険者上がりだった」
エルフイヤーリーフを振った鮭を切り分けながら、「先生」の胡散臭い顔を思い出す。よくもまあ、こんな昔のことを覚えていたものだ。ルマーリンは切り分けた側から鮭を平らげていく。
「……味は、おかしくないか?」
「まずまずですよ、まずまず」
私はしかめっ面になった。何故この男が「まずまず」と言うたびに不満げな気持ちが沸き上がるかがいまいち分からなかった。美味しさのわからぬ奴が作った料理などまずまずで当たり前だろうに。
「地図が正しければ、日が沈むまでにはソリチュードに着くだろう」
「私、ソリチュードは門までの坂がきつすぎると思うんですけどどうです?」
「行ったことがないから分からん」
「そうですか。あ、でもスパイス入りワインはいいですね。温めて飲むと寒気が吹き飛んで踊りたくなります」
「そうか」
私も鮭を口に含んだ。塩気と鮭特有の油の味がし、エルフイヤーリーフの香りが口にあふれた。
それだけだった。
*
これの続き。TES5の心が乾いた味覚不全アルトマー、ジンジェレル&Interesting NPCsのユーモアにあふれたアルトマー、ルマーリンの二次……ですが多大に想像で書いてます。ルマーリンがミルク嫌いだったらどうしよう。
0 notes
Text










2020-12-18 (金) 💁🗼🆚🔋🖊💡✨
👑 No. 103 ⟴ チャンネル
(n‘∀‘)η< 偶然の一致❕😨😘😚
❤︎⃜…// 大レースを狙えるサラブレッド 🐴🐎𓂃𓂂🍃
⿴⿻⿸ 馬さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 サラブレッド🐴🐎
⿴⿻⿸ 牛さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 後嗣(こうし)🐮🐃🐂🐄
⿴⿻⿸ 数えながら寝る羊さん(¥ ¥)一頭・用意 🐑💤💭 (_ *˘ω˘)_Zzz…💴
❣️:.︎。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ :.。❣️
( •̀ᴗ•́ )/:伝える言葉が残される ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:問わず語りの心が切ないね ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あわれんでも答えもしない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あなたにつたえるすべもない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:涙がこぼれないように ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:古い愛の歌を とぎれず唄ってた ...♪*゚
ˣx✖ˣ♡✖ˣx♡xˣ✖xˣ♡ˣx✖ˣx♡xˣ✖♡ˣ✖xˣ
撮影日:2020-12-17 (木)
初雪・粉雪が降り始めた深夜の時間帯 🌃
初雪・粉雪の降った後の朝時間帯 😴🐓☀
(*•̆ ·̭ •̆*)むぅ 〖報告日〗:2020-12-16 (水)
今年の冬になって一番の寒さを自覚しながら、日中の9時~12時まで電信柱の配線工事があり電気が止まっていました。
家で動いている時間は、かなりの忍耐勝負になります。
丸一日、最低限の範囲内から生活して、無駄な動きをしないで全ての問題を解決することが出来たらいいのになぁと夢みたいな話を思ってみたり、このまま人間界から離れて熊の冬眠と同じ行動をしていたいくらい現実逃避に身を置いて、一年の締めくくりを寒々と歌詞の記憶から遠のいて、途中退場のリセットボタンを押したい心境にかられています。~🐻❄️🐻❄️🐻❄️~
(*•̆ ·̭ •̆*)むぅ 撮影日:2020-12-15 (火)
外では、スマホを持つ手が痛く感じてイヤになる寒さの到来を実感しました。❄:;((>﹏<๑));:❄
⋆დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆
❥·・ 昼間・夜時間・雨降り逢瀬の立証 🎵🎵
撮影日:2020-12-16 (水)
❤︎⃜…// ラスト冬の黄色い菊 \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ (➖):黄色いマイクを置く 🎵🎵
撮影日:2020-12-12 (土)
調理日:2020-12-14 (月)
購入・白い部分が紫色の変わりネギ(葱)
あまりの寒さに、早速ですが、すき焼きの😋Σd(゚д゚,,★)💓美味しい旬の食材を堪能しました。
撮影日:2020-12-11 (金)
⋆͛♡̷♡̷⋆ 牛さん代用の庭木
_((Ф(.. )カキカキ 白い花アベリア咲き終わり日
撮影日:2020-12-12 (土)
\❤︎/ 猫柳の傘 ☂️☂☔
//♡︎ᵎᵎᵎ♡(ؔᵒ̶̷ᵕؔᵒ̷̶)ℓσνє♡
撮影日:2020-12-13 (日)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱが風に吹かれ動いて片耳になったウサギさん初登場‼🐰
撮影日:2020-12-14 (月)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱの残っていた片耳が風に吹かれ両方が消えて、ウサギさん初登場‼🐰
_(=×=_∪)⌒)ο ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ ♡。 ∩∩
撮影日:2020-12-13 (日)
𓂃𓃺𓈒𓏸 ポコンポコン穴掘りもぐらさん登場4度目❕
撮影日:2020-12-06 (日)
❥ ... 最近もぐらの通った後 ♪♩♬
❤︎⃜…// 上手に倒さずソーラーライトを棒から外す技 (゜〇゜)
撮影日:2020-12-10 (木)
\❤︎/ 庭木オオデマリ(大手毬)
❥·・ テレビ画面の背中を指す枝☝
撮影日:2020-12-09 (水)
ʚ♡⃛ɞ 芝生に延びる影 🌳🍃
\ Hello ♡/ 左側:オオデマリ(大手毬)♡‴ 亀さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 右側:名前の分からない庭木 ♡‴ 鶴さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-16 (水)
❤︎⃜…// 霜が降りて冷えきったお庭
撮影日:2020-12-16 (水)
⋆͛♡̷♡̷⋆ ネクタイ 👔代用・鉢植え
❥·・ 入り込んだ枯れ葉 ͛.*🍃𓂃 𓈒𓏸🍂
𐀪𐁑 集まった人たち ୧( ⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)୨
❥·・ ラスト枯れ葉1枚の庭木
撮影日:2020-12-13 (日)
❤︎⃜…// ブルーベリー果樹
⋆͛♡̷♡̷⋆ 2種類 植樹 ~♩♩
❥ ... (➖):冬ラスト・消えた赤い葉っぱ ( ' '♬)
⋆͛♡⋆͛ 左側:裸の蓄音機 \ ♩ /
⋆͛♡⋆͛ 右側:裸のレコードプレーヤー \ ♪♪ /
\ Hello ♡/ お庭に残されるたんぽぽ ♬.*゚
撮影日:2020-12-16 (水)
⋆͛♡⋆͛ ひとり玄関エントランスに腰掛けて見ていました。
伝説のスター 師弟物語
遠藤実✖️森昌子
人生を変えた師匠の教え
歌は人生の友
第4回日本歌謡大賞より
第14回日本レコード大賞・新人賞
第3回日本歌謡大賞・放送音楽新人賞
❥ ... 冬に1つだけ雑草の傘をさしているたんぽぽ花 ♬*.+゜
❥ ... 桟橋になった茎 ♪♩♬
\ Hello ♡/ 先頭たんぽぽ代用の太陽☀︎*.。・野ざらし駐車スペース ♬*.+゜
\ Hello ♡/ 引っこ抜けない省スペースたんぽぽ *♬೨̣
\ Hello ♡/ 物置(灯油缶の保管・枝切り・刈り込みばさみ・芝生刈りはさみ)の前のしぶとい芝生たんぽぽ ♪♩♬
\ Hello ♡/ お魚釣りの出来ない枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ ハンカチ落とし終わり・山盛り枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-09 (水)
\ Hello ♡/ 捨てゴミの処理・小5袋 💴 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ (➖):秋の黄色い菊カット・捨てゴミ処理 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\❤︎/ 裏道に生け垣の船1つ・右側&左側の合体
撮影日:2020-12-16 (水)
\❤︎/ 太陽 ☀️.° 🌞😊🌞🔆🔅
撮影日:2020-12-10 (木)
___ ✍🏻 残念なことに都合により充電切れで、夕方になってから撮影出来ませんでした。
撮影日:2020-12-11 (金)
撮影日:2020-12-13 (日)
🌹💫⭐︎ 明るさ💡を - + 調整して撮影・赤く見える夕やけ空 ️️️⛅️
撮影日:2020-12-15 (火)
❤︎⃜…// ️️️⛅️夕暮れ・日暮れ・鉄塔&夜空🔛星空 ♪̊̈♪̆̈♪̊̈♪̆̈♪̊̈
撮影日:2020-12-07 (月)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:19
撮影日:2020-12-08 (火)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:21
撮影日:2020-12-09 (水)
☆*°月のない空 おやすみ(ृ ु⁎ᴗᵨᴗ⁎)ु.💤🌙
撮影時刻 🔜 04:25
撮影日:2020-12-17 (木)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
〽 浅間山 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-05 (土)
撮影日:2020-12-07 (月)
撮影日:2020-12-08 (火)
撮影日:2020-12-12 (土)
撮影日:2020-12-17 (木)
〽〽〽 (➖):遠くに見える北アルプス〽〽〽
撮影日:2020-12-11 (金)
〽 黒斑山・山並み 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-12 (土)
撮影日:2020-12-13 (日)
___ ✍🏻 市内撮影・本町~ミズヒキ(ミズヒキ)亀と鶴 𓆉𓇼𓆉𓇼
撮影日:2020-12-08 (火)
❥❥» チカラシバ(力芝)・南側の片方カット ♪ૢ
ੈ✩ 沢山の指揮者・ストップ・指揮棒 ♪ૢ
❤︎⃜…// 冬に向かって残したラスト北側の指揮棒
撮影日:2020-12-12 (土)
❥ ... (➖):北に棲むやさしい鳥さん 𓎤𓅮 ⸒⸒ ⸜🕊⸝ 🕊 𓈒 𓂂𓏸🕊💭
ʚ♡⃛ɞ 仏壇と向かい合う指揮者へ \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ 東西南北の方角に向き合う指揮者へ \ ♪♪ /
♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪
《花言葉》
信念・気の強い・尊敬
❤︎⃜…// 裏庭コムラサキ生け垣
⋆͛♡̷♡̷⋆ 着物の代用 ~♩♩
👘 万祝(まいわい)👘
撮影日:2020-12-12 (土)
ੈ✩ ツルニチニチソウ(蔓日々草 )⋆͛♡̷♡̷⋆
❥ ... 太鼓&滝の代用・ツル性植物 ♪ૢ
💡ソーラーライト🔛スポットライト
和名: 蔓日々草(ツルニチニチソウ)
別名: 蔓桔梗(ツルギキョウ)、ビンカ
ヨーロッパでは、常緑で冬も枯れないことから不死のシンボルとして、またツルニチニチソウを身に付けると繁栄と幸福をもたらしてくれる、という古くからの言い伝えがあります。そのため別名も 「大地のよろこび」 、 「魔女のすみれ」 などと呼ばれるそうです。イタリアでは亡くなった子供をこのツルニチニチソウで飾ることから 「死の花」 とも呼ぶそうです。
φ(σ_σ)思い出をかき集めれば、山のように本物のお金だけしか動かない枯れ葉の幻想お庭
....φ(⊂︶■︶⊃)φ.... ....φ(⊂︶■︶⊃)φ....
\ Hello ♡/ 老老介護(ろうろうかいご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 老老看護(ろうろうかんご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
♬♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬
〖芸能ニュース👏ニッカンスポーツ・コム〗
[2007年8月2日 8時14分 紙面から]
最期の仕事は、今月22日発売の渚ようこのアルバム 「ノヴェラ ダモーレ」 に 「KABUKU」 「どうせ天国へ行ったって」 の2曲の詞を書き下ろした。「どうせ-」 では、死後のことを 「どうせ天国なんて 誰もいないから イヤよ」 とつづっている。当時、歌手の岩崎宏美(48)が車いすに乗った恩師に 「どこか痛いところはあるんですか」 とたずねると 「痛くないところがないんだよ」 と、寂しそうにつぶやいたという。常々 「自分には見えっぱりな部分や、強がるところがある」 と話し、教え子の和田アキ子(57)が見舞いを申し出ても 「元気な姿しか見せたくない」 と断っていた阿久さんも、最近は体調不良を訴えることも多かったという。
阿久さんが作詞家を志す原点は結核を発病した14歳のころ。医者から 「激情を抱くと、胸が破れて死ぬ」 と宣告され 「文書を書くか絵を描くかしかなさそうだ」 と心に決めたという。
⁎⋆*❇☆:⁎⋆*☆†_(σ_σ)β))☆⁎⋆*:☆🕯𓈒 𓏸✴⁎⋆*
by 松田聖子『PEARL-WHITE EVE』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 赤いキャンドルが燃えつきるまで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 抱きしめて 折れるほど ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 誰も愛さない そう決めたのに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) もう誓いを破ってる ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 真珠の雪をリングにして指に飾って ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今夜私はあなたのものよ ��♪"
(ღ•ㅂ•๐) 素顔のままで 粉雪の夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 暖炉の炎が消えそうだから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) あたためて身体ごと ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 不幸な恋なら前にしたけど もう一度信じたい ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 氷の張った池の上を歩くようだわ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 勇気を出して あなたの胸に ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 飛びこみたいの 粉雪の夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 心を見えない糸で結んで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 両手広げて粉雪の夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 目覚める頃はプラチナの朝 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 汚れひとつない世界 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 真珠の雪をリングにして指に飾って ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ピンクのパジャマ リボンほどいて ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) それが私の贈りものなの ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 壁のスキーの雪が溶けて 滑り落ちてく ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今夜私はあなたのものよ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 生まれたままで 粉雪の夜 ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
by 中森明菜『帰省 ~Never Forget~』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 深い眠りの中 今は遠いあなた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 古い愛の歌を とぎれず唄ってた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 絶望の淵でも 眠れぬ夜でも ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) その先の明日を信じ会えたはずなのに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 雪を 雪を見たかった ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 真っ白な雪を 知らない二人 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 疲れを知らない 時間は駆け足 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 春と夏を過ぎて その先はない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 輝いてたはずの 自由に迷うとき ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 都会の空の下 鳥は居場所をなくしてた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 叶わぬ夢 他の誰かじゃなく ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今は背中 まだ見せないで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 唄い続けてる限り 同じ道を歩いたあなたへ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) このかすれた声消えるまで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) Ah 夢を愛を唄うの 祈りたい 届けたい人いる限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せめて今を恥じないで 負けないで生きている だから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 同じ夢すごした日々を忘れない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今夜も眠れず 街に冷たい月 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 語り合った夢も ぬくもりもない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) うつろう昨日は果てしない明日へ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 抱きしめた体も凍えてゆくばかり ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 折れた翼 もとに戻せるなら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 二人の夢も また変わるのに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 追いかけて行くから いつも微笑んでいたあなたを ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) この曇った空 晴れるまで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) Ah 遠く一人唄うの 雪が降る 誰もいないこの街で ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 過去じゃなく明日じゃなく ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今を唄い続ける限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) その瞳 歩いた道を忘れない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) Ah 夢を愛を唄うの 祈りたい 届けたい人いる限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せめて今を恥じないで 負けないで生きている だから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 同じ夢過ごした日々をわすれない ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
by 山口百恵『白い約束』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 白く透き通る 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 音もしなやかに 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 人の汚れた心を埋めてゆくように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 綺麗なまま 生きることは ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 無理なのかしら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 私達も 愛し合うと ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) いつかは汚れてしまうのかしら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 白く透き通る 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 息をするように 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 人の涙や悲しみ 知っているように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 冷たい眼で 見られるのは ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) いつまでかしら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 私達は どんな時も ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 信じていること 約束するわ ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
_φ( 'ㅁ' * ) あなたへ差し出す涙で書いた手紙 ✉ 📄
(¥♡¥) 💸 ((¥▁¥)) 💸 \(¥Д¥)/金ーー!
◆ お金は大事だけど、すべてじゃないよ!٩(•౪• ٩)
(ღ˘⌣˘ღ)iloveyou ここへ逢いに来てくれてありがとう (Ü)۶♡٩(Ü)
☆*ɢᵒᵒᵈ ɴⁱᵍʰᵗ *☪︎。.🐏💭⋆。˚ᎶᎾᎾⅅ ℕᏐᎶℍᎢ⋆。˚✩🌟
#公開日記
#無料代行サービス #処理係
#お庭 #日本 #Japan
#2020年#12-18#12-17#令和#令和二年#歌詞#歌詞本#中森明菜#帰省~Never Forget~#山口百恵#白い約束#公開日記#無料代行サービス#処理係#チャンネル#103#初雪#朝時間#浅間山#山並み#アスファルト#太陽#道#松田聖子#PEARL-WHITE EVE
0 notes
Text










2020-12-18 (金) 💁👏🗼🆚🔋🖊💡✨
👑 No. 102 ⟴ チャンネル
(n‘∀‘)η< 偶然の一致❕😨😘😚
❤︎⃜…// 大レースを狙えるサラブレッド 🐴🐎𓂃𓂂🍃
⿴⿻⿸ 馬さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 サラブレッド🐴🐎
⿴⿻⿸ 牛さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 後嗣(こうし)🐮🐃🐂🐄
⿴⿻⿸ 数えながら寝る羊さん(¥ ¥)一頭・用意 🐑💤💭 (_ *˘ω˘)_Zzz…💴
❣️:.︎。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ :.。❣️
( •̀ᴗ•́ )/:伝える言葉が残される ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:問わず語りの心が切ないね ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あわれんでも答えもしない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あなたにつたえるすべもない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:涙がこぼれないように ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:古い愛の歌を とぎれず唄ってた ...♪*゚
ˣx✖ˣ♡✖ˣx♡xˣ✖xˣ♡ˣx✖ˣx♡xˣ✖♡ˣ✖xˣ
撮影日:2020-12-17 (木)
初雪・粉雪が降り始めた深夜の時間帯 🌃
初雪・粉雪の降った後の朝時間帯 😴🐓☀
(*•̆ ·̭ •̆*)むぅ 〖報告日〗:2020-12-16 (水)
今年の冬になって一番の寒さを自覚しながら、日中の9時~12時まで電信柱の配線工事があり電気が止まっていました。
家で動いている時間は、かなりの忍耐勝負になります。
丸一日、最低限の範囲内から生活して、無駄な動きをしないで全ての問題を解決することが出来たらいいのになぁと夢みたいな話を思ってみたり、このまま人間界から離れて熊の冬眠と同じ行動をしていたいくらい現実逃避に身を置いて、一年の締めくくりを寒々と歌詞の記憶から遠のいて、途中退場のリセットボタンを押したい心境にかられています。~🐻❄️🐻❄️🐻❄️~
(*•̆ ·̭ •̆*)むぅ 撮影日:2020-12-15 (火)
外では、スマホを持つ手が痛く感じてイヤになる寒さの到来を実感しました。❄:;((>﹏<๑));:❄
⋆დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆დଓ ���დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆დଓ ⋆დଓ⋆
❥·・ 昼間・夜時間・雨降り逢瀬の立証 🎵🎵
撮影日:2020-12-16 (水)
❤︎⃜…// ラスト冬の黄色い菊 \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ (➖):黄色いマイクを置く 🎵🎵
撮影日:2020-12-12 (土)
調理日:2020-12-14 (月)
購入・白い部分が紫色の変わりネギ(葱)
あまりの寒さに、早速ですが、すき焼きの😋Σd(゚д゚,,★)💓美味しい旬の食材を堪能しました。
撮影日:2020-12-11 (金)
⋆͛♡̷♡̷⋆ 牛さん代用の庭木
_((Ф(.. )カキカキ 白い花アベリア咲き終わり日
撮影日:2020-12-12 (土)
\❤︎/ 猫柳の傘 ☂️☂☔
//♡︎ᵎᵎᵎ♡(ؔᵒ̶̷ᵕؔᵒ̷̶)ℓσνє♡
撮影日:2020-12-13 (日)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱが風に吹かれ動いて片耳になったウサギさん初登場‼🐰
撮影日:2020-12-14 (月)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱの残っていた片耳が風に吹かれ両方が消えて、ウサギさん初登場‼🐰
_(=×=_∪)⌒)ο ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ ♡。 ∩∩
撮影日:2020-12-13 (日)
𓂃𓃺𓈒𓏸 ポコンポコン穴掘りもぐらさん登場4度目❕
撮影日:2020-12-06 (日)
❥ ... 最近もぐらの通った後 ♪♩♬
❤︎⃜…// 上手に倒さずソーラーライトを棒から外す技 (゜〇゜)
撮影日:2020-12-10 (木)
\❤︎/ 庭木オオデマリ(大手毬)
❥·・ テレビ画面の背中を指す枝☝
撮影日:2020-12-09 (水)
ʚ♡⃛ɞ 芝生に延びる影 🌳🍃
\ Hello ♡/ 左側:オオデマリ(大手毬)♡‴ 亀さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 右側:名前の分からない庭木 ♡‴ 鶴さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-16 (水)
❤︎⃜…// 霜が降りて冷えきったお庭
撮影日:2020-12-16 (水)
⋆͛♡̷♡̷⋆ ネクタイ 👔代用・鉢植え
❥·・ 入り込んだ枯れ葉 ͛.*🍃𓂃 𓈒𓏸🍂
𐀪𐁑 集まった人たち ୧( ⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)୨
❥·・ ラスト枯れ葉1枚の庭木
撮影日:2020-12-13 (日)
❤︎⃜…// ブルーベリー果樹
⋆͛♡̷♡̷⋆ 2種類 植樹 ~♩♩
❥ ... (➖):冬ラスト・消えた赤い葉っぱ ( ' '♬)
⋆͛♡⋆͛ 左側:裸の蓄音機 \ ♩ /
⋆͛♡⋆͛ 右側:裸のレコードプレーヤー \ ♪♪ /
\ Hello ♡/ お庭に残されるたんぽぽ ♬.*゚
撮影日:2020-12-16 (水)
⋆͛♡⋆͛ ひとり玄関エントランスに腰掛けて見ていました。
伝説のスター 師弟物語
遠藤実✖️森昌子
人生を変えた師匠の教え
歌は人生の友
第4回日本歌謡大賞より
第14回日本レコード大賞・新人賞
第3回日本歌謡大賞・放送音楽新人賞
❥ ... 冬に1つだけ雑草の傘をさしているたんぽぽ花 ♬*.+゜
❥ ... 桟橋になった茎 ♪♩♬
\ Hello ♡/ 先頭たんぽぽ代用の太陽☀︎*.。・野ざらし駐車スペース ♬*.+゜
\ Hello ♡/ 引っこ抜けない省スペースたんぽぽ *♬೨̣
\ Hello ♡/ 物置(灯油缶の保管・枝切り・刈り込みばさみ・芝生刈りはさみ)の前のしぶとい芝生たんぽぽ ♪♩♬
\ Hello ♡/ お魚釣りの出来ない枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ ハンカチ落とし終わり・山盛り枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-09 (水)
\ Hello ♡/ 捨てゴミの処理・小5袋 💴 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ (➖):秋の黄色い菊カット・捨てゴミ処理 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\❤︎/ 裏道に生け垣の船1つ・右側&左側の合体
撮影日:2020-12-17 (木)
\❤︎/ 太陽 ☀️.° 🌞😊🌞🔆🔅
撮影日:2020-12-10 (木)
___ ✍🏻 残念なことに都合により充電切れで、夕方になってから撮影出来ませんでした。
撮影日:2020-12-11 (金)
撮影日:2020-12-13 (日)
🌹💫⭐︎ 明るさ💡を - + 調整して撮影・赤く見える夕やけ空 ️️️⛅️
撮影日:2020-12-15 (火)
❤︎⃜…// ️️️⛅️夕暮れ・日暮れ・鉄塔&夜空🔛星空 ♪̊̈♪̆̈♪̊̈♪̆̈♪̊̈
撮影日:2020-12-07 (月)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:19
撮影日:2020-12-08 (火)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:21
撮影日:2020-12-09 (水)
☆*°月のない空 おやすみ(ृ ु⁎ᴗᵨᴗ⁎)ु.💤🌙
撮影日:2020-12-17 (木)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 04:25
〽 浅間山 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-05 (土)
撮影日:2020-12-07 (月)
撮影日:2020-12-08 (火)
撮影日:2020-12-12 (土)
〽〽〽 (➖):遠くに見える北アルプス〽〽〽
撮影日:2020-12-11 (金)
〽 黒斑山・山並み 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-12 (土)
撮影日:2020-12-13 (日)
___ ✍🏻 市内撮影・本町~ミズヒキ(ミズヒキ)亀と鶴 𓆉𓇼𓆉𓇼
撮影日:2020-12-08 (火)
❥❥» チカラシバ(力芝)・南側の片方カット ♪ૢ
ੈ✩ 沢山の指揮者・ストップ・指揮棒 ♪ૢ
❤︎⃜…// 冬に向かって残したラスト北側の指揮棒
撮影日:2020-12-12 (土)
❥ ... (➖):北に棲むやさしい鳥さん 𓎤𓅮 ⸒⸒ ⸜🕊⸝ 🕊 𓈒 𓂂𓏸🕊💭
ʚ♡⃛ɞ 仏壇と向かい合う指揮者へ \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ 東西南北の方角に向き合う指揮者へ \ ♪♪ /
♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪
《花言葉》
信念・気の強い・尊敬
❤︎⃜…// 裏庭コムラサキ生け垣
⋆͛♡̷♡̷⋆ 着物の代用 ~♩♩
👘 万祝(まいわい)👘
撮影日:2020-12-12 (土)
ੈ✩ ツルニチニチソウ(蔓日々草 )⋆͛♡̷♡̷⋆
❥ ... 太鼓&滝の代用・ツル性植物 ♪ૢ
💡ソーラーライト🔛スポットライト
和名: 蔓日々草(ツルニチニチソウ)
別名: 蔓桔梗(ツルギキョウ)、ビンカ
ヨーロッパでは、常緑で冬も枯れないことから不死のシンボルとして、またツルニチニチソウを身に付けると繁栄と幸福をもたらしてくれる、という古くからの言い伝えがあります。そのため別名も 「大地のよろこび」 、 「魔女のすみれ」 などと呼ばれるそうです。イタリアでは亡くなった子供をこのツルニチニチソウで飾ることから 「死の花」 とも呼ぶそうです。
φ(σ_σ)思い出をかき集めれば、山のように本物のお金だけしか動かない枯れ葉の幻想お庭
....φ(⊂︶■︶⊃)φ.... ....φ(⊂︶■︶⊃)φ....
\ Hello ♡/ 老老介護(ろうろうかいご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 老老看護(ろうろうかんご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
♬♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬
〖芸能ニュース👏ニッカンスポーツ・コム〗
[2007年8月2日 8時14分 紙面から]
最期の仕事は、今月22日発売の渚ようこのアルバム 「ノヴェラ ダモーレ」 に 「KABUKU」 「どうせ天国へ行ったって」 の2曲の詞を書き下ろした。「どうせ-」 では、死後のことを 「どうせ天国なんて 誰もいないから イヤよ」 とつづっている。当時、歌手の岩崎宏美(48)が車いすに乗った恩師に 「どこか痛いところはあるんですか」 とたずねると 「痛くないところがないんだよ」 と、寂しそうにつぶやいたという。常々 「自分には見えっぱりな部分や、強がるところがある」 と話し、教え子の和田アキ子(57)が見舞いを申し出ても 「元気な姿しか見せたくない」 と断っていた阿久さんも、最近は体調不良を訴えることも多かったという。
阿久さんが作詞家を志す原点は結核を発病した14歳のころ。医者から 「激情を抱くと、胸が破れて死ぬ」 と宣告され 「文書を書くか絵を描くかしかなさそうだ」 と心に決めたという。
⁎⋆*❇☆:⁎⋆*☆†_(σ_σ)β))☆⁎⋆*:☆🕯𓈒 𓏸✴⁎⋆*
by 松田聖子『PEARL-WHITE EVE』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 赤いキャンドルが燃えつきるまで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 抱きしめて 折れるほど ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 誰も愛さない そう決めたのに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) もう誓いを破ってる ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 真珠の雪をリングにして指に飾って ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今夜私はあなたのものよ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 素顔のままで 粉雪の夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 暖炉の炎が消えそうだから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) あたためて身体ごと ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 不幸な恋なら前にしたけど もう一度信じたい ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 氷の張った池の上を歩くようだわ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 勇気を出して あなたの胸に ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 飛びこみたいの 粉雪の夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 心を見えない糸で結んで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 永遠にそばにいて ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) かたく閉ざした貝のように 生きて来たけど ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 両手広げて粉雪の夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 目覚める頃はプラチナの朝 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 汚れひとつない世界 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 真珠の雪をリングにして指に飾って ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ピンクのパジャマ リボンほどいて ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) それが私の贈りものなの ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 壁のスキーの雪が溶けて 滑り落ちてく ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今夜私はあなたのものよ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 生まれたままで 粉雪の夜 ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
by 中森明菜『帰省~Never Forget~』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 深い眠りの中 今は遠いあなた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 古い愛の歌を とぎれず唄ってた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 絶望の淵でも 眠れぬ夜でも ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) その先の明日を信じ会えたはずなのに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 雪を 雪を見たかった ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 真っ白な雪を 知らない二人 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 疲れを知らない 時間は駆け足 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 春と夏を過ぎて その先はない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 輝いてたはずの 自由に迷うとき ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 都会の空の下 鳥は居場所をなくしてた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 叶わぬ夢 他の誰かじゃなく ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今は背中 まだ見せないで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 唄い続けてる限り 同じ道を歩いたあなたへ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) このかすれた声消えるまで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) Ah 夢を愛を唄うの 祈りたい 届けたい人いる限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せめて今を恥じないで 負けないで生きている だから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 同じ夢すごした日々を忘れない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今夜も眠れず 街に冷たい月 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 語り合った夢も ぬくもりもない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) うつろう昨日は果てしない明日へ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 抱きしめた体も凍えてゆくばかり ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 折れた翼 もとに戻せるなら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 二人の夢も また変わるのに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 追いかけて行くから いつも微笑んでいたあなたを ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) この曇った空 晴れるまで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) Ah 遠く一人唄うの 雪が降る 誰もいないこの街で ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 過去じゃなく明日じゃなく ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 今を唄い続ける限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) その瞳 歩いた道を忘れない ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) Ah 夢を愛を唄うの 祈りたい 届けたい人いる限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せめて今を恥じないで 負けないで生きている だから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 同じ夢過ごした日々をわすれない ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
by 山口百恵『白い約束』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 白く透き通る 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 音もしなやかに 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 人の汚れた心を埋めてゆくように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 綺麗なまま 生きることは ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 無理なのかしら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 私達も 愛し合うと ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) いつかは汚れてしまうのかしら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 白く透き通る 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 息をするように 雪が降る ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 人の涙や悲しみ 知っているように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 冷たい眼で 見られるのは ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) いつまでかしら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ねえ 私達は どんな時も ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 信じていること 約束するわ ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
_φ( 'ㅁ' * ) あなたへ差し出す涙で書いた手紙 ✉ 📄
(¥♡¥) 💸 ((¥▁¥)) 💸 \(¥Д¥)/金ーー!
◆ お金は大事だけど、すべてじゃないよ!٩(•౪• ٩)
(ღ˘⌣˘ღ)iloveyou ここへ逢いに来てくれてありがとう (Ü)۶♡٩(Ü)
☆*ɢᵒᵒᵈ ɴⁱᵍʰᵗ *☪︎。.🐏💭⋆。˚ᎶᎾᎾⅅ ℕᏐᎶℍᎢ⋆。˚✩🌟
#公開日記
#無料代行サービス #処理係 #お庭 #日本 #Japan
#2020年#12-18#12-17#令和#令和二年#歌詞#歌詞本#中森明菜#帰省~Never Forget~#山口百恵#白い約束#公開日記#無料代行サービス#処理係#チャンネル#102#初雪#夜時間#朝時間#粉雪#松田聖子#PEARL-WHITE EVE
0 notes
Text







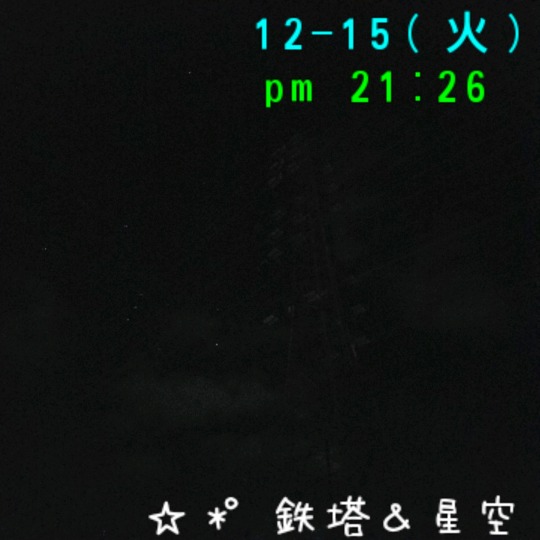


2020-12-16 (水) 💁🗼🆚🔋🖊💡✨
👑 No. 97 ⟴ チャンネル
(n‘∀‘)η< 偶然の一致❕😨😘😚
❤︎⃜…// 大レースを狙えるサラブレッド 🐴🐎𓂃𓂂🍃
⿴⿻⿸ 馬さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 サラブレッド🐴🐎
⿴⿻⿸ 牛さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 後嗣(こうし)🐮🐃🐂🐄
⿴⿻⿸ 数えながら寝る羊さん(¥ ¥)一頭・用意 🐑💤💭 (_ *˘ω˘)_Zzz…💴
❣️:.︎。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ :.。❣️
( •̀ᴗ•́ )/:伝える言葉が残される ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:問わず語りの心が切ないね ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あわれんでも答えもしない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あなたにつたえるすべもない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:一人ぽっちの夜 ...♪*゚
ˣx✖ˣ♡✖ˣx♡xˣ✖xˣ♡ˣx✖ˣx♡xˣ✖♡ˣ✖xˣ
撮影日:2020-12-15 (火)
外では、スマホを持つ手が痛く感じてイヤになる寒さの到来を実感しました。❄:;((>﹏<๑));:❄
❥·・ 昼間・夜時間・雨降り逢瀬の立証 🎵🎵
撮影日:2020-12-14 (月)
❤︎⃜…// ラスト冬の黄色い菊 \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ (➖):黄色いマイクを置く 🎵🎵
撮影日:2020-12-12 (土)
調理日:2020-12-14 (月)
購入・白い部分が紫色の変わりネギ(葱)
あまりの寒さに、早速ですが、すき焼きの😋Σd(゚д゚,,★)💓美味しい旬の食材を堪能しました。
撮影日:2020-12-11 (金)
⋆͛♡̷♡̷⋆ 牛さん代用の庭木
_((Ф(.. )カキカキ 白い花アベリア咲き終わり日
撮影日:2020-12-12 (土)
\❤︎/ 猫柳の傘 ☂️☂☔
//♡︎ᵎᵎᵎ♡(ؔᵒ̶̷ᵕؔᵒ̷̶)ℓσνє♡
撮影日:2020-12-13 (日)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱが風に吹かれ動いて、片耳になったウサギさん初登場‼🐰
撮影日:2020-12-14 (月)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱの残っていた片耳が風に吹かれて両方が消えて、ウサギさん初登場‼🐰
(๑´×`๑) ᕱ⑅ᕱ♥
(・ x ・) (/* °×° *\) ᙏ̤̫͚♡♥︎
𓂃𓃺𓈒𓏸 ᙏ̤̫͚ᙏ̤̫͚ ( ´•̥ × •̥` ) (*'×'*)
/) /) ⌒( ó × ò)⌒ /) /)
ᕱ⑅ᕱ゛(U。・×・。U) ( ó × ò)
ᕱ⑅ᕱ" ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ 🐇💗
🐰🍓💕🐰💭 /) /) (|(| ꪔ̤̱ꪔ̤̱ꪔ̤̱
∩__∩ /) /) (´º×º) 𓃹ಇ ̯ꪔ̤̮*.˚
_(・×・_∪⌒)ο _(˘×˘_∪⌒)ο
_(=×=_∪)⌒)ο ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ ♡。 ∩∩
撮影日:2020-12-13 (日)
𓂃𓃺𓈒𓏸 ポコンポコン穴掘りもぐらさん登場4度目❕
撮影日:2020-12-06 (日)
❥ ... 最近もぐらの通った後 ♪♩♬
❤︎⃜…// 上手に倒さずソーラーライトを棒から外す技 (゜〇゜)
撮影日:2020-12-10 (木)
\❤︎/ 庭木オオデマリ(大手毬)
❥·・ テレビ画面の背中を指す枝☝
撮影日:2020-12-09 (水)
ʚ♡⃛ɞ 芝生に延びる影 🌳🍃
\ Hello ♡/ 左側:オオデマリ(大手毬)♡‴ 亀さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 右側:名前の分からない庭木 ♡‴ 鶴さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-15 (火)
❤︎⃜…// 霜が降りて冷えきったお庭
撮影日:2020-12-15 (火)
⋆͛♡̷♡̷⋆ ネクタイ 👔代用・鉢植え
❥·・ 入り込んだ枯れ葉 ͛.*🍃𓂃 𓈒𓏸🍂
𐀪𐁑 集まった人たち ୧( ⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)୨
❥·・ ラスト枯れ葉1枚の庭木
撮影日:2020-12-13 (日)
❤︎⃜…// ブルーベリー果樹
⋆͛♡̷♡̷⋆ 2種類 植樹 ~♩♩
❥ ... (➖):冬ラスト・消えた赤い葉っぱ ( ' '♬)
⋆͛♡⋆͛ 左側:裸の蓄音機 \ ♩ /
⋆͛♡⋆͛ 右側:裸のレコードプレーヤー \ ♪♪ /
\ Hello ♡/ お庭に残されるたん���ぽ ♬.*゚
撮影日:2020-12-14 (月)
⋆͛♡⋆͛ ひとり玄関エントランスに腰掛けて見ていました。
伝説のスター 師弟物語
遠藤実✖️森昌子
人生を変えた師匠の教え
歌は人生の友
第4回日本歌謡大賞より
第14回日本レコード大賞・新人賞
第3回日本歌謡大賞・放送音楽新人賞
❥ ... 冬に1つだけ雑草の傘をさしているたんぽぽ花 ♬*.+゜
❥ ... 桟橋になった茎 ♪♩♬
\ Hello ♡/ 先頭たんぽぽ代用の太陽☀︎*.。・野ざらし駐車スペース ♬*.+゜
\ Hello ♡/ 引っこ抜けない省スペースたんぽぽ *♬೨̣
\ Hello ♡/ 物置(灯油缶の保管・枝切り・刈り込みばさみ・芝生刈りはさみ)の前のしぶとい芝生たんぽぽ ♪♩♬
\ Hello ♡/ お魚釣りの出来ない枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ ハンカチ落とし終わり・山盛り枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-09 (水)
\ Hello ♡/ 捨てゴミの処理・小5袋 💴 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ (➖):秋の黄色い菊カット・捨てゴミ処理 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\❤︎/ 裏道に生け垣の船1つ・右側&左側の合体
撮影日:2020-12-09 (水)
\❤︎/ 太陽 ☀️.° 🌞😊🌞🔆🔅
撮影日:2020-12-10 (木)
___ ✍🏻 残念なことに都合により充電切れで、夕方になってから撮影出来ませんでした。
撮影日:2020-12-11 (金)
撮影日:2020-12-13 (日)
🌹💫⭐︎ 明るさ💡を - + 調整して撮影・赤く見える夕やけ空 ️️️⛅️
撮影日:2020-12-15 (火)
❤︎⃜…// ️️️⛅️冬の空・夕暮れ・日暮れ・鉄塔&夜空🔛星空 ♪̊̈♪̆̈♪̊̈♪̆̈♪̊̈
撮影日:2020-12-07 (月)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:19
撮影日:2020-12-08 (火)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:21
撮影日:2020-12-09 (水)
☆*°月のない空 おやすみ(ृ ु⁎ᴗᵨᴗ⁎)ु.💤🌙
撮影時刻 🔜 04:25
〽 浅間山 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-05 (土)
撮影日:2020-12-07 (月)
撮影日:2020-12-08 (火)
撮影日:2020-12-12 (土)
〽〽〽 (➖):遠くに見える北アルプス〽〽〽
撮影日:2020-12-11 (金)
〽 黒斑山・山並み 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-12 (土)
撮影日:2020-12-13 (日)
___ ✍🏻 市内撮影・本町~ミズヒキ(ミズヒキ)亀と鶴 𓆉𓇼𓆉𓇼
撮影日:2020-12-08 (火)
❥❥» チカラシバ(力芝)・南側の片方カット ♪ૢ
ੈ✩ 沢山の指揮者・ストップ・指揮棒 ♪ૢ
❤︎⃜…// 冬に向かって残したラスト北側の指揮棒
撮影日:2020-12-12 (土)
❥ ... (➖):北に棲むやさしい鳥さん 𓎤𓅮 ⸒⸒ ⸜🕊⸝ 🕊 𓈒 𓂂𓏸🕊💭
ʚ♡⃛ɞ 仏壇と向かい合う指揮者へ \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ 東西南北の方角に向き合う指揮者へ \ ♪♪ /
♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪
《花言葉》
信念・気の強い・尊敬
❤︎⃜…// 裏庭コムラサキ生け垣
⋆͛♡̷♡̷⋆ 着物の代用 ~♩♩
👘 万祝(まいわい)👘
撮影日:2020-12-12 (土)
ੈ✩ ツルニチニチソウ(蔓日々草 )⋆͛♡̷♡̷⋆
❥ ... 太鼓&滝の代用・ツル性植物 ♪ૢ
💡ソーラーライト🔛スポットライト
和名: 蔓日々草(ツルニチニチソウ)
別名: 蔓桔梗(ツルギキョウ)、ビンカ
ヨーロッパでは、常緑で冬も枯れないことから不死のシンボルとして、またツルニチニチソウを身に付けると繁栄と幸福をもたらしてくれる、という古くからの言い伝えがあります。そのため別名も 「大地のよろこび」 、 「魔女のすみれ」 などと呼ばれるそうです。イタリアでは亡くなった子供をこのツルニチニチソウで飾ることから 「死の花」 とも呼ぶそうです。
φ(σ_σ)思い出をかき集めれば、山のように本物のお金だけしか動かない枯れ葉の幻想お庭
....φ(⊂︶■︶⊃)φ.... ....φ(⊂︶■︶⊃)φ....
\ Hello ♡/ 老老介護(ろうろうかいご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 老老看護(ろうろうかんご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
♬♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬
〖芸能ニュース👏ニッカンスポーツ・コム〗
[2007年8月2日 8時14分 紙面から]
最期の仕事は、今月22日発売の渚ようこのアルバム 「ノヴェラ ダモーレ」 に 「KABUKU」 「どうせ天国へ行ったって」 の2曲の詞を書き下ろした。「どうせ-」 では、死後のことを 「どうせ天国なんて 誰もいないから イヤよ」 とつづっている。当時、歌手の岩崎宏美(48)が車いすに乗った恩師に 「どこか痛いところはあるんですか」 とたずねると 「痛くないところがないんだよ」 と、寂しそうにつぶやいたという。常々 「自分には見えっぱりな部分や、強がるところがある」 と話し、教え子の和田アキ子(57)が見舞いを申し出ても 「元気な姿しか見せたくない」 と断っていた阿久さんも、最近は体調不良を訴えることも多かったという。
阿久さんが作詞家を志す原点は結核を発病した14歳のころ。医者から 「激情を抱くと、胸が破れて死ぬ」 と宣告され 「文書を書くか絵を描くかしかなさそうだ」 と心に決めたという。
⁎⋆*❇☆:⁎⋆*☆†_(σ_σ)β))☆⁎⋆*:☆🕯𓈒 𓏸✴⁎⋆*
by 寺尾聰『ルビーの指環』♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) くもり硝子の向うは風の街 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 問わず語りの心が切ないね ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 枯葉ひとつの 重さもない命 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 貴女を失ってから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 背中を丸めながら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 指のリング抜き取ったね ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 俺に返すつもりならば ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 捨ててくれ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) そうね 誕生石ならルビーな��� ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) そんな言葉が頭に渦巻くよ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) あれは八月 目映い陽の中で ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 誓った愛の幻 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 孤独が好きな俺さ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 気にしないで行っていいよ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 気が変わらぬうちに早く ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 消えてくれ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) くもり硝子の向うは風の街 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) さめた紅茶が残ったテーブルで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 襟を合わせて日暮れの人波に ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 紛れる貴女を見てた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) そして二年の月日が流れ去り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 街でベージュのコートを見かけると ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 指にルビーのリングを探すのさ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 貴女を失ってから ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
by 森昌子『せんせい』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 淡い初恋 消えた日は ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 雨がしとしと 降っていた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 傘にかくれて 桟橋で ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ひとり見つめて 泣いていた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) おさない私が 胸こがし ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 慕いつづけた ひとの名は ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せんせい せんせい それはせんせい ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 声を限りに 叫んでも ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 遠くはなれる 連絡船 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 白い灯台 絵のように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 雨にうたれて 浮んでた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 誰にも言えない 悲しみに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 胸をいためた ひとの名は ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せんせい せんせい それはせんせい ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 恋する心の しあわせを ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) そっと教えた ひとの名は ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せんせい せんせい それはせんせい ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
_φ( 'ㅁ' * ) あなたへ差し出す涙で書いた手紙 ✉ 📄
(¥♡¥) 💸 ((¥▁¥)) 💸 \(¥Д¥)/金ーー!
◆ お金は大事だけど、すべてじゃないよ!٩(•౪• ٩)
(ღ˘⌣˘ღ)iloveyou ここへ逢いに来てくれてありがとう (Ü)۶♡٩(Ü)
☆*ɢᵒᵒᵈ ɴⁱᵍʰᵗ *☪︎。.🐏💭⋆。˚ᎶᎾᎾⅅ ℕᏐᎶℍᎢ⋆。˚✩🌟
#公開日記
#無料代行サービス
#処理係
#2020年#12-16#12-15#令和#令和二年#歌詞#歌詞本#寺尾聰#ルビーの指環#森昌子#せんせい#公開日記#無料代行サービス#処理係#チャンネル#97#最後の一葉#代用#ネクタイ#鉢植え#入った枯れ葉#たんぽぽ#桟橋の茎#夜時間#夜空#星空#お庭#日本#Japan
0 notes
Text










2020-12-15 (火) 💁🗼🆚🔋🖊💡✨
👑 No. 96 ⟴ チャンネル
(n‘∀‘)η< 偶然の一致❕😨😘😚
❤︎⃜…// 大レースを狙えるサラブレッド 🐴🐎𓂃𓂂🍃
⿴⿻⿸ 馬さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 サラブレッド🐴🐎
⿴⿻⿸ 牛さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 後嗣(こうし)🐮🐃🐂🐄
⿴⿻⿸ 数えながら寝る羊さん(¥ ¥)一頭・用意 🐑💤💭 (_ *˘ω˘)_Zzz…💴
❣️:.︎。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ :.。❣️
( •̀ᴗ•́ )/:伝える言葉が残される ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:問わず語りの心が切ないね ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あわれんでも答えもしない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あなたにつたえるすべもない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:一人ぽっちの夜 ...♪*゚
ˣx✖ˣ♡✖ˣx♡xˣ✖xˣ♡ˣx✖ˣx♡xˣ✖♡ˣ✖xˣ
撮影日:2020-12-15 (火)
外では、スマホを持つ手が痛く感じてイヤになる寒さの到来を実感しました。❄:;((>﹏<๑));:❄
❥·・ 昼間・夜時間・雨降り逢瀬の立証 🎵🎵
撮影日:2020-12-14 (月)
❤︎⃜…// ラスト冬の黄色い菊 \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ (➖):黄色いマイクを置く 🎵🎵
撮影日:2020-12-12 (土)
調理日:2020-12-14 (月)
購入・白い部分が紫色の変わりネギ(葱)
あまりの寒さに、早速ですが、すき焼きの😋Σd(゚д゚,,★)💓美味しい旬の食材を堪能しました。
撮影日:2020-12-11 (金)
⋆͛♡̷♡̷⋆ 牛さん代用の庭木
_((Ф(.. )カキカキ 白い花アベリア咲き終わり日
撮影日:2020-12-12 (土)
\❤︎/ 猫柳の傘 ☂️☂☔
//♡︎ᵎᵎᵎ♡(ؔᵒ̶̷ᵕؔᵒ̷̶)ℓσνє♡
撮影日:2020-12-13 (日)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱが風に吹かれ動いて、片耳になったウサギさん初登場‼🐰
撮影日:2020-12-14 (月)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱの残っていた片耳が風に吹かれて両方が消えて、ウサギさん初登場‼🐰
(๑´×`๑) ᕱ⑅ᕱ♥
(・ x ・) (/* °×° *\) ᙏ̤̫͚♡♥︎
𓂃𓃺𓈒𓏸 ᙏ̤̫͚ᙏ̤̫͚ ( ´•̥ × •̥` ) (*'×'*)
/) /) ⌒( ó × ò)⌒ /) /)
ᕱ⑅ᕱ゛(U。・×・。U) ( ó × ò)
ᕱ⑅ᕱ" ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ 🐇💗
🐰🍓💕🐰💭 /) /) (|(| ꪔ̤̱ꪔ̤̱ꪔ̤̱
∩__∩ /) /) (´º×º) 𓃹ಇ ̯ꪔ̤̮*.˚
_(・×・_∪⌒)ο _(˘×˘_∪⌒)ο
_(=×=_∪)⌒)ο ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ ♡。 ∩∩
撮影日:2020-12-13 (日)
𓂃𓃺𓈒𓏸 ポコンポコン穴掘りもぐらさん登場4度目❕
撮影日:2020-12-06 (日)
❥ ... 最近もぐらの通った後 ♪♩♬
❤︎⃜…// 上手に倒さずソーラーライトを棒から外す技 (゜〇゜)
撮影日:2020-12-10 (木)
\❤︎/ 庭木オオデマリ(大手毬)
❥·・ テレビ画面の背中を指す枝☝
撮影日:2020-12-09 (水)
ʚ♡⃛ɞ 芝生に延びる影 🌳🍃
\ Hello ♡/ 左側:オオデマリ(大手毬)♡‴ 亀さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 右側:名前の分からない庭木 ♡‴ 鶴さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-15 (火)
❤︎⃜…// 霜が降りて冷えきったお庭
撮影日:2020-12-15 (火)
⋆͛♡̷♡̷⋆ ネクタイ 👔代用・鉢植え
❥·・ 入り込んだ枯れ葉 ͛.*🍃𓂃 𓈒𓏸🍂
𐀪𐁑 集まった人たち ୧( ⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)୨
❥·・ ラスト枯れ葉1枚の庭木
撮影日:2020-12-13 (日)
❤︎⃜…// ブルーベリー果樹
⋆͛♡̷♡̷⋆ 2種類 植樹 ~♩♩
❥ ... (➖):冬ラスト・消えた赤い葉っぱ ( ' '♬)
⋆͛♡⋆͛ 左側:裸の蓄音機 \ ♩ /
⋆͛♡⋆͛ 右側:裸のレコードプレーヤー \ ♪♪ /
\ Hello ♡/ お庭に残されるたんぽぽ ♬.*゚
撮影日:2020-12-15 (火)
⋆͛♡⋆͛ ひとり玄関エントランスに腰掛けて見ていました。
伝説のスター 師弟物語
遠藤実✖️森昌子
人生を変えた師匠の教え
歌は人生の友
第4回日本歌謡大賞より
第14回日本レコード大賞・新人賞
第3回日本歌謡大賞・放送音楽新人賞
❥ ... 冬に1つだけ雑草の傘をさしているたんぽぽ花 ♬*.+゜
❥ ... 桟橋になった茎 ♪♩♬
\ Hello ♡/ 先頭たんぽぽ代用の太陽☀︎*.。・野ざらし駐車スペース ♬*.+゜
\ Hello ♡/ 引っこ抜けない省スペースたんぽぽ *♬೨̣
\ Hello ♡/ 物置(灯油缶の保管・枝切り・刈り込みばさみ・芝生刈りはさみ)の前のしぶとい芝生たんぽぽ ♪♩♬
\ Hello ♡/ お魚釣りの出来ない枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ ハンカチ落とし終わり・山盛り枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-09 (水)
\ Hello ♡/ 捨てゴミの処理・小5袋 💴 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ (➖):秋の黄色い菊カット・捨てゴミ処理 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\❤︎/ 裏道に生け垣の船1つ・右側&左側の合体
撮影日:2020-12-15 (火)
\❤︎/ 太陽 ☀️.° 🌞😊🌞🔆🔅
撮影日:2020-12-10 (木)
___ ✍🏻 残念なことに都合により充電切れで、夕方になってから撮影出来ませんでした。
撮影日:2020-12-11 (金)
撮影日:2020-12-13 (日)
🌹💫⭐︎ 明るさ💡を - + 調整して撮影・赤く見える夕やけ空 ️️️⛅️
撮影日:2020-12-15 (火)
❤︎⃜…// ️️️⛅️冬の空・夕暮れ・日暮れ・鉄塔&夜空🔛星空 ♪̊̈♪̆̈♪̊̈♪̆̈♪̊̈
撮影日:2020-12-07 (月)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:19
撮影日:2020-12-08 (火)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:21
撮影日:2020-12-09 (水)
☆*°月のない空 おやすみ(ृ ु⁎ᴗᵨᴗ⁎)ु.💤🌙
撮影時刻 🔜 04:25
〽 浅間山 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-05 (土)
撮影日:2020-12-07 (月)
撮影日:2020-12-08 (火)
撮影日:2020-12-12 (土)
〽〽〽 (➖):遠くに見える北アルプス〽〽〽
撮影日:2020-12-11 (金)
〽 黒斑山・山並み 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-12 (土)
撮影日:2020-12-13 (日)
___ ✍🏻 市内撮影・本町~ミズヒキ(ミズヒキ)亀と鶴 𓆉𓇼𓆉𓇼
撮影日:2020-12-08 (火)
❥❥» チカラシバ(力芝)・南側の片方カット ♪ૢ
ੈ✩ 沢山の指揮者・ストップ・指揮棒 ♪ૢ
❤︎⃜…// 冬に向かって残したラスト北側の指揮棒
撮影日:2020-12-12 (土)
❥ ... (➖):北に棲むやさしい鳥さん 𓎤𓅮 ⸒⸒ ⸜🕊⸝ 🕊 𓈒 𓂂𓏸🕊💭
ʚ♡⃛ɞ 仏壇と向かい合う指揮者へ \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ 東西南北の方角に向き合う指揮者へ \ ♪♪ /
♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪
《花言葉》
信念・気の強い・尊敬
❤︎⃜…// 裏庭コムラサキ生け垣
⋆͛♡̷♡̷⋆ 着物の代用 ~♩♩
👘 万祝(まいわい)👘
撮影日:2020-12-12 (土)
ੈ✩ ツルニチニチソウ(蔓日々草 )⋆͛♡̷♡̷⋆
❥ ... 太鼓&滝の代用・ツル性植物 ♪ૢ
💡ソーラーライト🔛スポットライト
和名: 蔓日々草(ツルニチニチソウ)
別名: 蔓桔梗(ツルギキョウ)、ビンカ
ヨーロッパでは、常緑で冬も枯れないことから不死のシンボルとして、またツルニチニチソウを身に付けると繁栄と幸福をもたらしてくれる、という古くからの言い伝えがあります。そのため別名も ���大地のよろこび」 、 「魔女のすみれ」 などと呼ばれるそうです。イタリアでは亡くなった子供をこのツルニチニチソウで飾ることから 「死の花」 とも呼ぶそうです。
φ(σ_σ)思い出をかき集めれば、山のように本物のお金だけしか動かない枯れ葉の幻想お庭
....φ(⊂︶■︶⊃)φ.... ....φ(⊂︶■︶⊃)φ....
\ Hello ♡/ 老老介護(ろうろうかいご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 老老看護(ろうろうかんご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
♬♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬
〖芸能ニュース👏ニッカンスポーツ・コム〗
[2007年8月2日 8時14分 紙面から]
最期の仕事は、今月22日発売の渚ようこのアルバム 「ノヴェラ ダモーレ」 に 「KABUKU」 「どうせ天国へ行ったって」 の2曲の詞を書き下ろした。「どうせ-」 では、死後のことを 「どうせ天国なんて 誰もいないから イヤよ」 とつづっている。当時、歌手の岩崎宏美(48)が車いすに乗った恩師に 「どこか痛いところはあるんですか」 とたずねると 「痛くないところがないんだよ」 と、寂しそうにつぶやいたという。常々 「自分には見えっぱりな部分や、強がるところがある」 と話し、教え子の和田アキ子(57)が見舞いを申し出ても 「元気な姿しか見せたくない」 と断っていた阿久さんも、最近は体調不良を訴えることも多かったという。
阿久さんが作詞家を志す原点は結核を発病した14歳のころ。医者から 「激情を抱くと、胸が破れて死ぬ」 と宣告され 「文書を書くか絵を描くかしかなさそうだ」 と心に決めたという。
⁎⋆*❇☆:⁎⋆*☆†_(σ_σ)β))☆⁎⋆*:☆🕯𓈒 𓏸✴⁎⋆*
by 錦野旦『空に太陽がある 限り』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 愛してる とても ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 愛してる 本当に ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 愛してる いつまでも ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 空に太陽がある限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 君と僕は 君と僕は ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 二人で一人 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 愛してる 愛してる ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 空に太陽がある限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 愛してる 心 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 愛してる 瞳 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 愛してる いつまでも ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 空に太陽がある限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 君と僕も 君と僕も ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 生命の限り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 愛してる 愛してる ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 空に太陽がある限り ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
_φ( 'ㅁ' * ) あなたへ差し出す涙で書いた手紙 ✉ 📄
(¥♡¥) 💸 ((¥▁¥)) 💸 \(¥Д¥)/金ーー!
◆ お金は大事だけど、すべてじゃないよ!٩(•౪• ٩)
(ღ˘⌣˘ღ)iloveyou ここへ逢いに来てくれてありがとう (Ü)۶♡٩(Ü)
☆*ɢᵒᵒᵈ ɴⁱᵍʰᵗ *☪︎。.🐏💭⋆。˚ᎶᎾᎾⅅ ℕᏐᎶℍᎢ⋆。˚✩🌟
#公開日記
#無料代行サービス
#処理係
#2020年#12-15#令和#令和二年#歌詞#歌詞本#錦野旦#空に太陽がある 限り#公開日記#無料代行サービス#処理係#チャンネル#96#冬の空#太陽#晴れ間#曇り空#浅間山#山並み#お庭#道#日本#Japan
0 notes
Text










2020-12-15 (火) 💁🗼🆚🔋🖊💡✨
👑 No. 94 ⟴ チャンネル
(n‘∀‘)η< 偶然の一致❕😨😘😚
❤︎⃜…// 大レースを狙えるサラブレッド 🐴🐎𓂃𓂂🍃
⿴⿻⿸ 馬さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 サラブレッド🐴🐎
⿴⿻⿸ 牛さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 後嗣(こうし)🐮🐃🐂🐄
⿴⿻⿸ 数えながら寝る羊さん(¥ ¥)一頭・用意 🐑💤💭 (_ *˘ω˘)_Zzz…💴
❣️:.︎。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ :.。❣️
( •̀ᴗ•́ )/:伝える言葉が残される ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:問わず語りの心が切ないね ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あわれんでも答えもしない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あなたにつたえるすべもない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:一人ぽっちの夜 ...♪*゚
ˣx✖ˣ♡✖ˣx♡xˣ✖xˣ♡ˣx✖ˣx♡xˣ✖♡ˣ✖xˣ
❥·・ 昼間・夜時間・雨降り逢瀬の立証 🎵🎵
撮影日:2020-12-14 (月)
❤︎⃜…// ラスト冬の黄色い菊 \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ (➖):黄色いマイクを置く 🎵🎵
撮影日:2020-12-12 (土)
調理日:2020-12-14 (月)
購入・白い部分が紫色の変わりネギ(葱)
あまりの寒さに、早速ですが、すき焼きの😋Σd(゚д゚,,★)💓美味しい旬の食材を堪能しました。
撮影日:2020-12-11 (金)
⋆͛♡̷♡̷⋆ 牛さん代用の庭木
_((Ф(.. )カキカキ 白い花アベリア咲き終わり日
撮影日:2020-12-14 (月)
\❤︎/ 猫柳の傘 ☂️☂☔
//♡︎ᵎᵎᵎ♡(ؔᵒ̶̷ᵕؔᵒ̷̶)ℓσνє♡
撮影日:2020-12-13 (日)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱが風に吹かれ動いて、片耳になったウサギさん初登場‼🐰
撮影日:2020-12-14 (月)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱの残っていた片耳が風に吹かれて飛ばされ両方が消えて、ウサギさん初登場‼🐰
(๑´×`๑) ᕱ⑅ᕱ♥
(・ x ・) (/* °×° *\) ᙏ̤̫͚♡♥︎
𓂃𓃺𓈒𓏸 ᙏ̤̫͚ᙏ̤̫͚ ( ´•̥ × •̥` ) (*'×'*)
/) /) ⌒( ó × ò)⌒ /) /)
ᕱ⑅ᕱ゛(U。・×・。U) ( ó × ò)
ᕱ⑅ᕱ" ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ 🐇💗
🐰🍓💕🐰💭 /) /) (|(| ꪔ̤̱ꪔ̤̱ꪔ̤̱
∩__∩ /) /) (´º×º) 𓃹ಇ ̯ꪔ̤̮*.˚
_(・×・_∪⌒)ο _(˘×˘_∪⌒)ο
_(=×=_∪)⌒)ο ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ ♡。 ∩∩
撮影日:2020-12-13 (日)
𓂃𓃺𓈒𓏸 ポコンポコン穴掘りもぐらさん登場4度目❕
撮影日:2020-12-06 (日)
❥ ... 最近もぐらの通った後 ♪♩♬
❤︎⃜…// 上手に倒さずソーラーライトを棒から外す技 (゜〇゜)
撮影日:2020-12-10 (木)
\❤︎/ 庭木オオデマリ(大手毬)
❥·・ テレビ画面の背中を指す枝☝
撮影日:2020-12-09 (水)
ʚ♡⃛ɞ 芝生に延びる影 🌳🍃
\ Hello ♡/ 左側:オオデマリ(大手毬)♡‴ 亀さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 右側:名前の分からない庭木 ♡‴ 鶴さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-07 (月)
❤︎⃜…// 霜が降りて冷えきったお庭
撮影日:2020-12-14 (月)
⋆͛♡̷♡̷⋆ ネクタイ 👔代用・鉢植え
❥·・ 入り込んだ枯れ葉 ͛.*🍃𓂃 𓈒𓏸🍂
𐀪𐁑 集まった人たち ୧( ⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)୨
❥·・ ラスト枯れ葉1枚の庭木
❤︎⃜…// ブルーベリー果樹
⋆͛♡̷♡̷⋆ 2種類 植樹 ~♩♩
撮影日:2020-12-13 (日)
❥ ... (➖):冬ラスト・消えた赤い葉っぱ ( ' '♬)
⋆͛♡⋆͛ 左側:裸の蓄音機 \ ♩ /
⋆͛♡⋆͛ 右側:裸のレコードプレーヤー \ ♪♪ /
\ Hello ♡/ お庭に残されるたんぽぽ ♬.*゚
撮影日:2020-12-14 (月)
⋆͛♡⋆͛ ひとり玄関エントランスに腰掛けて見ていました。
伝説のスター 師弟物語
遠藤実✖️森昌子
人生を変えた師匠の教え
歌は人生の友
第4回日本歌謡大賞より
第14回日本レコード大賞・新人賞
第3回日本歌謡大賞・放送音楽新人賞
❥ ... 冬に1つだけ雑草の傘をさしているたんぽぽ花 ♬*.+゜
❥ ... 桟橋になった茎 ♪♩♬
\ Hello ♡/ 先頭たんぽぽ代用の太陽☀︎*.。・野ざらし駐車スペース ♬*.+゜
\ Hello ♡/ 引っこ抜けない省スペースたんぽぽ *♬೨̣
\ Hello ♡/ 物置(灯油缶の保管・枝切り・刈り込みばさみ・芝生刈りはさみ)の前のしぶとい芝生たんぽぽ ♪♩♬
\ Hello ♡/ お魚釣りの出来ない枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ ハンカチ落とし終わり・山盛り枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-09 (水)
\ Hello ♡/ 捨てゴミの処理・小5袋 💴 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ (➖):秋の黄色い菊カット・捨てゴミ処理 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\❤︎/ 裏道に生け垣の船1つ・右側&左側の合体
撮影日:2020-12-09 (水)
\❤︎/ 太陽 ☀️.° 🌞😊🌞🔆🔅
撮影日:2020-12-10 (木)
___ ✍🏻 残念なことに都合により充電切れで、夕方になってから撮影出来ませんでした。
撮影日:2020-12-11 (金)
撮影日:2020-12-13 (日)
🌹💫⭐︎ 明るさ💡を - + 調整して撮影・赤く見える夕やけ空 ️️️⛅️
❤︎⃜…// ️️️⛅️夕暮れ・日暮れ・鉄塔&夜空🔛星空 ♪̊̈♪̆̈♪̊̈♪̆̈♪̊̈
撮影日:2020-12-07 (月)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:19
撮影日:2020-12-08 (火)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:21
撮影日:2020-12-09 (水)
☆*°月のない空 おやすみ(ृ ु⁎ᴗᵨᴗ⁎)ु.💤🌙
撮影時刻 🔜 04:25
〽 浅間山 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-05 (土)
撮影日:2020-12-07 (月)
撮影日:2020-12-08 (火)
撮影日:2020-12-12 (土)
〽〽〽 (➖):遠くに見える北アルプス〽〽〽
撮影日:2020-12-11 (金)
〽 黒斑山・山並み 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-12 (土)
撮影日:2020-12-13 (日)
___ ✍🏻 市内撮影・本町~ミズヒキ(ミズヒキ)亀と鶴 𓆉𓇼𓆉𓇼
撮影日:2020-12-08 (火)
❥❥» チカラシバ(力芝)・南側の片方カット ♪ૢ
ੈ✩ 沢山の指揮者・ストップ・指揮棒 ♪ૢ
❤︎⃜…// 冬に向かって残したラスト北側の指揮棒
撮影日:2020-12-12 (土)
❥ ... (➖):北に棲むやさしい鳥さん 𓎤𓅮 ⸒⸒ ⸜🕊⸝ 🕊 𓈒 𓂂𓏸🕊💭
ʚ♡⃛ɞ 仏壇と向かい合う指揮者へ \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ 東西南北の方角に向き合う指揮者へ \ ♪♪ /
♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪
《花言葉》
信念・気の強い・尊敬
❤︎⃜…// 裏庭コムラサキ生け垣
⋆͛♡̷♡̷⋆ 着物の代用 ~♩♩
👘 万祝(まいわい)👘
撮影日:2020-12-12 (土)
ੈ✩ ツルニチニチソウ(蔓日々草 )⋆͛♡̷♡̷⋆
❥ ... 太鼓&滝の代用・ツル性植物 ♪ૢ
💡ソーラーライト🔛スポットライト
和名: 蔓日々草(���ルニチニチソウ)
別名: 蔓桔梗(ツルギキョウ)、ビンカ
ヨーロッパでは、常緑で冬も枯れないことから不死のシンボルとして、またツルニチニチソウを身に付けると繁栄と幸福をもたらしてくれる、という古くからの言い伝えがあります。そのため別名も 「大地のよろこび」 、 「魔女のすみれ」 などと呼ばれるそうです。イタリアでは亡くなった子供をこのツルニチニチソウで飾ることから 「死の花」 とも呼ぶそうです。
φ(σ_σ)思い出をかき集めれば、山のように本物のお金だけしか動かない枯れ葉の幻想お庭
....φ(⊂︶■︶⊃)φ.... ....φ(⊂︶■︶⊃)φ....
\ Hello ♡/ 老老介護(ろうろうかいご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 老老看護(ろうろうかんご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
♬♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬
〖芸能ニュース👏ニッカンスポーツ・コム〗
[2007年8月2日 8時14分 紙面から]
最期の仕事は、今月22日発売の渚ようこのアルバム 「ノヴェラ ダモーレ」 に 「KABUKU」 「どうせ天国へ行ったって」 の2曲の詞を書き下ろした。「どうせ-」 では、死後のことを 「どうせ天国なんて 誰もいないから イヤよ」 とつづっている。当時、歌手の岩崎宏美(48)が車いすに乗った恩師に 「どこか痛いところはあるんですか」 とたずねると 「痛くないところがないんだよ」 と、寂しそうにつぶやいたという。常々 「自分には見えっぱりな部分や、強がるところがある」 と話し、教え子の和田アキ子(57)が見舞いを申し出ても 「元気な姿しか見せたくない」 と断っていた阿久さんも、最近は体調不良を訴えることも多かったという。
阿久さんが作詞家を志す原点は結核を発病した14歳のころ。医者から 「激情を抱くと、胸が破れて死ぬ」 と宣告され 「文書を書くか絵を描くかしかなさそうだ」 と心に決めたという。
⁎⋆*❇☆:⁎⋆*☆†_(σ_σ)β))☆⁎⋆*:☆🕯𓈒 𓏸✴⁎⋆*
by 寺尾聰『ルビーの指環』♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) くもり硝子の向うは風の街 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 問わず語りの心が切ないね ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 枯葉ひとつの 重さもない命 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 貴女を失ってから ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 背中を丸めながら ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 指のリング抜き取ったね ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 俺に返すつもりならば ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 捨ててくれ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) そうね 誕生石ならルビーなの ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) そんな言葉が頭に渦巻くよ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) あれは八月 目映い陽の中で ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 誓った愛の幻 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 孤独が好きな俺さ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 気にしないで行っていいよ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 気が変わらぬうちに早く ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 消えてくれ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) くもり硝子の向うは風の街 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) さめた紅茶が残ったテーブルで ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 襟を合わせて日暮れの人波に ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 紛れる貴女を見てた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) そして二年の月日が流れ去り ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 街でベージュのコートを見かけると ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 指にルビーのリングを探すのさ ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 貴女を失ってから ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
by 森昌子『せんせい』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 淡い初恋 消えた日は ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 雨がしとしと 降っていた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 傘にかくれて 桟橋で ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) ひとり見つめて 泣いていた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) おさない私が 胸こがし ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 慕いつづけた ひとの名は ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せんせい せんせい それはせんせい ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 声を限りに 叫んでも ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 遠くはなれる 連絡船 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 白い灯台 絵のように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 雨にうたれて 浮んでた ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 誰にも言えない 悲しみに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 胸をいためた ひとの名は ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せんせい せんせい それはせんせい ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 恋する心の しあわせを ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) そっと教えた ひとの名は ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) せんせい せんせい それはせんせい ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
_φ( 'ㅁ' * ) あなたへ差し出す涙で書いた手紙 ✉ 📄
(¥♡¥) 💸 ((¥▁¥)) 💸 \(¥Д¥)/金ーー!
◆ お金は大事だけど、すべてじゃないよ!٩(•౪• ٩)
(ღ˘⌣˘ღ)iloveyou ここへ逢いに来てくれてありがとう (Ü)۶♡٩(Ü)
☆*ɢᵒᵒᵈ ɴⁱᵍʰᵗ *☪︎。.🐏💭⋆。˚ᎶᎾᎾⅅ ℕᏐᎶℍᎢ⋆。˚✩🌟
#公開日記
#無料代行サービス
#処理係
#たんぽぽ #雑草の傘 #茎の桟橋
#お庭 #日本 #Japan
#2020年#12-15#12-14#12-13#令和#令和二年#歌詞#歌詞本#寺尾聰#ルビーの指環#森昌子#せんせい#公開日記#無料代行サービス#処理係#チャンネル#94#最後の一葉#代用#ネクタイ#枯れ葉#鉢植え#集まった人たち#ウサギさん#落ち葉#雑草#耳#イチゴ鉢植え#穴掘り#もぐら
0 notes
Text










2020-12-15 (火) 💁🗼🆚🔋🖊💡✨
👑 No. 93 ⟴ チャンネル 1
(n‘∀‘)η< 偶然の一致❕😨😘😚
❤︎⃜…// 大レースを狙えるサラブレッド 🐴🐎𓂃𓂂🍃
⿴⿻⿸ 馬さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 サラブレッド🐴🐎
⿴⿻⿸ 牛さん !(¥..¥)! 一頭・用意 💴 後嗣(こうし)🐮🐃🐂🐄
⿴⿻⿸ 数えながら寝る羊さん(¥ ¥)一頭・用意 🐑💤💭 (_ *˘ω˘)_Zzz…💴
❣️:.︎。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ *:..。oƒ :.。❣️
( •̀ᴗ•́ )/:伝える言葉が残される ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:問わず語りの心が切ないね ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あわれんでも答えもしない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:あなたにつたえるすべもない ...♪*゚
( •̀ᴗ•́ )/:一人ぽっちの夜 ...♪*゚
ˣx✖ˣ♡✖ˣx♡xˣ✖xˣ♡ˣx✖ˣx♡xˣ✖♡ˣ✖xˣ
撮影日:2020-12-12 (土)
調理日:2020-12-14 (月)
購入・白い部分が紫色の変わりネギ(葱)
あまりの寒さに、早速ですが、すき焼きの😋Σd(゚д゚,,★)💓美味しい旬の食材を堪能しました。
撮影日:2020-12-11 (金)
⋆͛♡̷♡̷⋆ 牛さん代用の庭木
_((Ф(.. )カキカキ 白い花アベリア咲き終わり日
撮影日:2020-12-14 (月)
\❤︎/ 猫柳の傘 ☂️☂☔
//♡︎ᵎᵎᵎ♡(ؔᵒ̶̷ᵕؔᵒ̷̶)ℓσνє♡
撮影日:2020-12-13 (日)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱが風に吹かれ動いて、片耳になったウサギさん初登場‼🐰
撮影日:2020-12-14 (月)
⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝⸜❤︎⸝ 偶然左側の鉢植えイチゴに入った葉っぱの残っていた片耳が風に吹かれて飛ばされ両方が消えて、ウサギさん初登場‼🐰
(๑´×`๑) ᕱ⑅ᕱ♥
(・ x ・) (/* °×° *\) ᙏ̤̫͚♡♥︎
𓂃𓃺𓈒𓏸 ᙏ̤̫͚ᙏ̤̫͚ ( ´•̥ × •̥` ) (*'×'*)
/) /) ⌒( ó × ò)⌒ /) /)
ᕱ⑅ᕱ゛(U。・×・。U) ( ó × ò)
ᕱ⑅ᕱ" ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ 🐇💗
🐰🍓💕🐰💭 /) /) (|(| ꪔ̤̱ꪔ̤̱ꪔ̤̱
∩__∩ /) /) (´º×º) 𓃹ಇ ̯ꪔ̤̮*.˚
_(・×・_∪⌒)ο _(˘×˘_∪⌒)ο
_(=×=_∪)⌒)ο ˙˚ ᕱ⑅ᕱ ɞ˚˙ ♡。 ∩∩
撮影日:2020-12-13 (日)
𓂃𓃺𓈒𓏸 ポコンポコン穴掘りもぐらさん登場4度目❕
撮影日:2020-12-06 (日)
❥ ... 最近もぐらの通った後 ♪♩♬
❤︎⃜…// 上手に倒さずソーラーライトを棒から外す技 (゜〇゜)
撮影日:2020-12-10 (木)
\❤︎/ 庭木オオデマリ(大手毬)
❥·・ テレビ画面の背中を指す枝☝
撮影日:2020-12-09 (水)
ʚ♡⃛ɞ 芝生に延びる影 🌳🍃
\ Hello ♡/ 左側:オオデマリ(大手毬)♡‴ 亀さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 右側:名前の分からない庭木 ♡‴ 鶴さん ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-07 (月)
❤︎⃜…// 霜が降りて冷えきったお庭
撮影日:2020-12-10 (木)
⋆͛♡̷♡̷⋆ ネクタイ 👔代用・鉢植え
❥·・ 入り込んだ枯れ葉 ͛.*🍃𓂃 𓈒𓏸🍂
𐀪𐁑 集まった人たち ୧( ⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)୨
❥·・ ラスト枯れ葉1枚の庭木
❤︎⃜…// ブルーベリー果樹
⋆͛♡̷♡̷⋆ 2種類 植樹 ~♩♩
撮影日:2020-12-13 (日)
❥ ... (➖):冬ラスト・消えた赤い葉っぱ ( ' '♬)
⋆͛♡⋆͛ 左側:裸の蓄音機 \ ♩ /
⋆͛♡⋆͛ 右側:裸のレコードプレーヤー \ ♪♪ /
❤︎⃜…// 冬ラスト黄色い菊の花 \ ♪♪ /
❥·・ 昼間・夜時間・雨降り逢瀬の立証 🎵🎵
\ Hello ♡/ お庭に残されるたんぽぽ ♬.*゚
撮影日:2020-12-09 (水)
⋆͛♡⋆͛ ひとり玄関エントランスに腰掛けて見ていました。
伝説のスター 師弟物語
遠藤実✖️森昌子
人生を変えた師匠の教え
歌は人生の友
第4回日本歌謡大賞より
第14回日本レコード大賞・新人賞
第3回日本歌謡大賞・放送音楽新人賞
❥ ... 冬に1つだけ雑草の傘をさしているたんぽぽ花 ♬*.+゜
❥ ... 桟橋になった茎 ♪♩♬
\ Hello ♡/ 先頭たんぽぽ代用の太陽☀︎*.。・野ざらし駐車スペース ♬*.+゜
\ Hello ♡/ 引っこ抜けない省スペースたんぽぽ *♬೨̣
\ Hello ♡/ 物置(灯油缶の保管・枝切り・刈り込みばさみ・芝生刈りはさみ)の前のしぶとい芝生たんぽぽ ♪♩♬
\ Hello ♡/ お魚釣りの出来ない枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ ハンカチ落とし終わり・山盛り枯れ葉のお金(捨てゴミ) ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
撮影日:2020-12-09 (水)
\ Hello ♡/ 捨てゴミの処理・小5袋 💴 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ (➖):秋の黄色い菊カット・捨てゴミ処理 ✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\❤︎/ 裏道に生け垣の船1つ・右側&左側の合体
撮影日:2020-12-09 (水)
\❤︎/ 太陽 ☀️.° 🌞😊🌞🔆🔅
撮影日:2020-12-10 (木)
___ ✍🏻 残念なことに都合により充電切れで、夕方になってから撮影出来ませんでした。
撮影日:2020-12-11 (金)
撮影日:2020-12-13 (日)
🌹💫⭐︎ 明るさ💡を - + 調整して撮影・赤く見える夕やけ空 ️️️⛅️
❤︎⃜…// ️️️⛅️夕暮れ・日暮れ・鉄塔&夜空🔛星空 ♪̊̈♪̆̈♪̊̈♪̆̈♪̊̈
撮影日:2020-12-07 (月)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:19
撮影日:2020-12-08 (火)
☆*° 月夜 🌙.*·̩͙🌛*゜☪·̩͙☪︎⋆。˚✩🌜
撮影時刻 🔜 01:21
撮影日:2020-12-09 (水)
☆*°月のない空 おやすみ(ृ ु⁎ᴗᵨᴗ⁎)ु.💤🌙
撮影時刻 🔜 04:25
〽 浅間山 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-05 (土)
撮影日:2020-12-07 (月)
撮影日:2020-12-08 (火)
撮影日:2020-12-12 (土)
〽〽〽 (➖):遠くに見える北アルプス〽〽〽
撮影日:2020-12-11 (金)
〽 黒斑山・山並み 🗻 /'''\ ⛰️
撮影日:2020-12-12 (土)
撮影日:2020-12-13 (日)
___ ✍🏻 市内撮影・本町~ミズヒキ(ミズヒキ)亀と鶴 𓆉𓇼𓆉𓇼
撮影日:2020-12-08 (火)
❥❥» チカラシバ(力芝)・南側の片方カット ♪ૢ
ੈ✩ 沢山の指揮者・ストップ・指揮棒 ♪ૢ
❤︎⃜…// 冬に向かって残したラスト北側の指揮棒
撮影日:2020-12-12 (土)
❥ ... (➖):北に棲むやさしい鳥さん 𓎤𓅮 ⸒⸒ ⸜🕊⸝ 🕊 𓈒 𓂂𓏸🕊💭
ʚ♡⃛ɞ 仏壇と向かい合う指揮者へ \ ♪♪ /
⋆͛♡̷♡̷⋆ 東西南北の方角に向き合う指揮者へ \ ♪♪ /
♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪♬ ʅ( ՞ω՞)ʃ¯♪
《花言葉》
信念・気の強い・尊敬
❤︎⃜…// 裏庭コムラサキ生け垣
⋆͛♡̷♡̷⋆ 着物の代用 ~♩♩
👘 万祝(まいわい)👘
撮影日:2020-12-12 (土)
ੈ✩ ツルニチニチソウ(蔓日々草 )⋆͛♡̷♡̷⋆
❥ ... 太鼓&滝の代用・ツル性植物 ♪ૢ
💡ソーラーライト🔛スポットライト
和名: 蔓日々草(ツルニチニチソウ)
別名: 蔓桔梗(ツルギキョウ)、ビンカ
ヨーロッパでは、常緑で冬も枯れないことから不死のシンボルとして、またツルニチニチソウを身に付けると繁栄と幸福をもたらしてくれる、という古くからの言い伝えがあります。そのため別名も 「大地のよろこび」 、 「魔女のすみれ」 などと呼ばれるそうです。イタリアでは亡くなった子供をこのツルニチニチソウで飾ることから 「死の花」 とも呼ぶそうです。
φ(σ_σ)思い出をかき集めれば、山のように本物のお金だけしか動かない枯れ葉の幻想お庭
....φ(⊂︶■︶⊃)φ.... ....φ(⊂︶■︶⊃)φ....
\ Hello ♡/ 老老介護(ろうろうかいご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
\ Hello ♡/ 老老看護(ろうろうかんご)✧ᴴᴱᴸᴸᴼ✧
♬♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ♫:;;;: ♫ ♬
〖芸能ニュース👏ニッカンスポーツ・コム〗
[2007年8月2日 8時14分 紙面から]
最期の仕事は、今月22日発売の渚ようこのアルバム 「ノヴェラ ダモーレ」 に 「KABUKU」 「どうせ天国へ行ったって」 の2曲の詞を書き下ろした。「どうせ-」 では、死後のことを 「どうせ天国なんて 誰もいないから イヤよ」 とつづっている。当時、歌手の岩崎宏美(48)が車いすに乗った恩師に 「どこか痛いところはあるんですか」 とたずねると 「痛くないところがないんだよ」 と、寂しそうにつぶやいたという。常々 「自分には見えっぱりな部分や、強がるところがある」 と話し、教え子の和田アキ子(57)が見舞いを申し出ても 「元気な姿しか見せたくない」 と断っていた阿久さんも、最近は体調不良を訴えることも多かったという。
阿久さんが作詞家を志す原点は結核を発病した14歳のころ。医者から 「激情を抱くと、胸が破れて死ぬ」 と宣告され 「文書を書くか絵を描くかしかなさそうだ」 と心に決めたという。
⁎⋆*❇☆:⁎⋆*☆†_(σ_σ)β))☆⁎⋆*:☆🕯𓈒 𓏸✴⁎⋆*
by 坂本九『上を向いて歩こう』 ♪̊̈♪̆̈
(ღ•ㅂ•๐) 【歌詞】
(ღ•ㅂ•๐) 上を向いて歩う ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 涙がこぼれないように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 思い出す 春の日 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 一人ぽっちの夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 上を向いて歩こう ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) にじんだ星をかぞえて ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 思い出す 夏の日 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 一人ぽっちの夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 幸せは 雲の上に ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 幸せは 空の上に ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 上を向いて歩こう ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 涙がこぼれないように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 泣きながら 歩く ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 一人ぽっちの夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) (口笛…) ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 思い出す 秋の日 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 一人ぽっちの夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 悲しみは星のかげに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 悲しみは月のかげに ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 上を向いて歩こう ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 涙がこぼれないように ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 泣きながら 歩く ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 一人ぽっちの夜 ♪♪"
(ღ•ㅂ•๐) 一人ぽっちの夜 ♪♪"
🐴🐎♩*。♫.°♪*。♬꙳♩*。♫♩*。♫.°🐎🐴
_φ( 'ㅁ' * ) あなたへ差し出す涙で書いた手紙 ✉ 📄
(¥♡¥) 💸 ((¥▁¥)) 💸 \(¥Д¥)/金ーー!
◆ お金は大事だけど、すべてじゃないよ!٩(•౪• ٩)
(ღ˘⌣˘ღ)iloveyou ここへ逢いに来てくれてありがとう (Ü)۶♡٩(Ü)
☆*ɢᵒᵒᵈ ɴⁱᵍʰᵗ *☪︎。.🐏💭⋆。˚ᎶᎾᎾⅅ ℕᏐᎶℍᎢ⋆。˚✩🌟
#公開日記
#無料代行サービス
#処理係
0 notes