#合理的にあり得ない ~探偵・上水流涼子の解明
Explore tagged Tumblr posts
Text
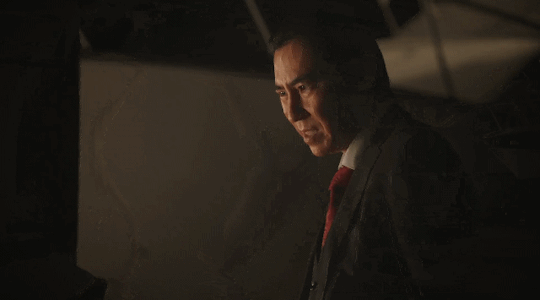



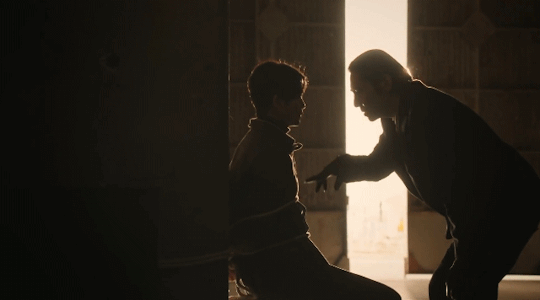
Goritekini Arienai: Tantei Kamizuru Ryoko no Kaimei Ep 01
#Goritekini Arienai: Tantei Kamizuru Ryoko no Kaimei#合理的にあり得ない ~探偵・上水流涼子の解明#asian whump#whump#jdrama whump#japanese whump#tied to chair#threatened#whump manhandled#Ep 01#matsushita kouhei
111 notes
·
View notes
Text
【gooニュース】「合理的にあり得ない〜探偵・上水流涼子の解明〜」天海祐希と共に気持ちよくゴール出来た(碓井広義)
23/08/04 04:08
gooニュースでこちらの紹介がありましたので、備忘録的にブログに残しました。
「合理的にあり得ない〜探偵・上水流涼子の解明〜」天海祐希と共に気持ちよくゴール出来た(碓井広義)
【碓井広義テレビ見るべきものは!!】先週いっぱいで4月クールのドラマはすべて店じまいとなった。天海祐希主演「合理的にあり得ない〜探偵・上水流涼子の解明〜」(関西テ...
「合理的にあり得ない〜探偵・上水流涼子の解明〜」天海祐希と共に気持ちよくゴール出来た(碓井広義)
以前、単行本を読んだことがあり、懐かしく思いました。
当時の感想文は、例えば、こちら。
推理小説(探偵小説)「合理的にあり得ない 上水流涼子」より、最終5編目「心理的にあり得ない」の読書感想文 - Wozéqui - soleil ブログ
正月休みに読み始めた読書の感想文の第5弾(今回、最終回)をブログ投稿したく思います。推理小説(探偵小説)「合理的にあり得ない上水流...
goo blog
https://blog.goo.ne.jp/wozequi/e/63c9551e492f3741b151457372ea4985
以上、このブログにお付き合いくださり、ありがとうございました。
#news:合理的にあり得ない〜探偵・上水流涼子の解明〜
#天海祐希と共に気持ちよくゴール出来た
#news:エンタメ
#ニュース
#探偵
#上水流
#上水流涼子
#情報モラル
#みんなの日記
#日記
カテゴリー:情報・モラル
最新の画像

【情報・モラル】最近届いたメールに「IPアドレス」云々があること⇔2年弱前との比較
2023年8月2日 
【日記】「平和と公正」について
2023年8月1日 
【日記】「平和と公正」について
2023年8月1日 
【教育界】今日(2023.7.22.土曜)中日新聞さんの朝刊で、池田町の教育長について取り上げられていました。
2023年7月22日
もっと見る
【情報・モラル】最近届いたメールに「IPアドレス」云々があること⇔2年弱前との比較
一覧
0 notes
Text
iFontMaker - Supported Glyphs
Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£���¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨ���リルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲��兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌��飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍���丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker
#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language
8 notes
·
View notes
Text
涼風に鳴る幽かの怪―参
その日は、昼過ぎから少しばかり俄雨が降った。 未だすっきりとはしないが辺りに立ち込めた雲は夕方になるにつれて徐々に通り過ぎていったようにも感じる。 西洋作りの街灯は雨のせいで夜と昼の区別がつかなかったのか途惑うように点滅している。通りの向こうから覗いた夕日は沈まぬままに此方を覗いていた。 「夏の雨は大袈裟だからね」 雨傘をくるりと回して、振り仰いだ緋桐はたまを手招いた。もう雨は随分前に止んでしまったというのに、彼は傘をさしたままだ。 こうして、彼と調査と称した散歩に出る様になってから三日経つ。一度、家に戻って旦那様に言わないとと進言したたまに必要ないと言ってのけた緋桐は悪巧みをするような子供の顔をして調査契約を行った日の夜に雨を理由に逗留を促した。 「ねえ、そろそろ帰らないと」 「帰らなくていいよ」 ぴしゃりと言ってのけた彼は金の瞳を光らせた。 自分が家に帰らないままでは旦那様が心配するという言葉には緋桐は正治にたまを預かった旨を届けて欲しいと伝えておいたという。幾度繰り返しても帰ってもいいという話にならないあたり、やはり詐欺師だったのではないか――そう考えるのも無理ない話だ。 「あの……捜査って具体的には何をするの?」 幽霊退治の依頼をしに来たはずなのに、彼と散歩を行うだけの毎日。あまりに理解不能な行動に流石に痺れも切れてくるころだ。 「本当に狐に化かされたみたい……」 ぼやいたたまは���たまりをぴしゃりと踏みしめる。揺れた水面はあまりの衝撃だったのかたまの顔を映してはいなかった。 「明日になったら本格的に始めようか。 今日はもう遅いし――それに、雨雲もまだ残っているからね」 表情は暗い――晴れ間が出ているというのにぽたぽたと雨が降る。それを、狐の嫁入りと呼ぶのだと誰かが言っていた。 朝になれば、見慣れぬ天井がそこにはある。客間に用意されていた布団はふかふかとしており、実家や病院の固い煎餅布団との違いに驚かされた。 一先ず階下に下がればぼさぼさとした髪を結わえる事無く机に突っ伏している緋桐が存在する。どうやら、早朝から起きて何かしらの作業を行っていたらしい。 「緋桐さん?」 「んー……うん、おはよう。たまちゃん」 僅かに頭をあげて、ひらりと手を振った彼へと近づけば、ひとまず風呂に入った後なのだろう。その心地よさでうたた寝をしていたことが分かった。濡れたままの髪を布で拭き上げ、櫛で鮮やかな髪を梳く。適当に近場においてあるリボンで結わえれば美少年の完成だ。 「ありがとう」 小さく返されたそれに頷けば、玄関から正治がいつも通りの強面で訪れる。だらしがないと緋桐に小言を漏らしながら朝食を用意するのが彼の日課のようだ。 「毎日、こうして緋桐さんのお世話をしているの? 大変ね」 「まあ、それなりに世話にはなっているからな」 ふい、と顔を逸らした正治にたまは照れてるのね、と小さく笑う。生真面目な彼のことだこの状況居なってからは毎日の緋桐の世話も一つの仕事だと認識しているのだろう。 ソファに座っていれば日本茶がやってくることをたまは知っている。どうしたことか、この生活にすっかりなじんでいる時分がいることに彼女は不思議と嫌悪感はなかった。 「食事をしたら今日は幽霊退治の調査に出かけようか」 食事が終われば、彼は英国紳士のように着飾った。ブーツと袴と言った普通の女学生という格好のたまとはあまりに不思議な組み合わせにも思えた。 街に出れば、たまは「ハイカラね」と何度も繰り返している。最も、ここから数年経てば、緋桐の服装もそうそう違和感を感じるものでもなくなっているだろう――最もここから数年経てば男性は山高帽子にセーラーパンツに細身のステッキを手に街を闊歩し女性はアッパッパ等を纏ってショートカットで赤いルージュを引きながらモダン・ボーイ、モダン・ガールという時代が到来するのだ。 「……そういえばさ、たまちゃんはスカートって履かないの? 興味あるなら1着位買ってあげるけどさ」 「スカートは、その……はしたなくないかしら? 世間様ではパーマも流行っているけれど私は、ちょっとね」 曖昧な返事を返した自分が居心地悪くて、たまは肩を竦めたまま石畳を見下ろした。流行のファッションに関しての話題は苦手だ。たまは世間の流行に触れる事が無かったからとぼやき、石ころを蹴り飛ばした。 「――……ああ、じゃあ、髪飾りとかはどうかな?」 「髪飾り?」 突拍子もなく、告げられた言葉にたまは首を傾げる。その言葉に首を傾いだのは正治も同じようだった。髪飾りを贈られる間柄でなければ、彼と自分は依頼者と探偵だ。報酬の関係から調査を共に行っているだけだ。 「たまちゃんは可愛いからね。それに、幽霊退治を一緒に行うんだよ? 妖怪のオレや『特殊』な正治なら兎も角さ、何の耐性もない君が一緒だと危険な目に合うかもしれない」 裏路地の片隅に存在する店を指さして緋桐は「ね?」と小さく首を傾いだ。彼の言は尤もだ。妖狐のクオーターであるという緋桐と、特殊――特殊な? 「特殊な、って……?」 不安げに正治を見つめるたまは彼が『妖怪』の類なのだろうかとゆっくりと息を飲む。 そうだとしたならば問題だ。狐の手の内に転がり込んでしまったことの証明になってしまう。 「あれ、言ってなかったっけ? 正治は簡単に言えば『視える』人だよ」 「視え……?」 視力がいい、と言う訳ではないのかもしれない。 帝都の街の中、行き交う人々はそんな会話に何も目を止めやしない。緋桐の言葉に、何の返答も返さぬまま正治は口を閉ざしていた。 「幽霊とか。正治は小さい頃から妖怪とか、そういうの得意でしょ」 「……普通に視えているからな。区別は、つかないが」 ぼそり、と小さく呟いた正治はその血筋の事を言いたくなかったとでもいう様に顰め面を見せる。 曰く、彼には幼い頃から幽霊や妖怪と言った幽世(かくりよ)の存在が見えるのだというのだ。日本には古来から陰陽師が存在し、幽世の存在が現世(うつしよ)へ影響を及ぼす事を防いでいた。その正統なる血筋――の分家だと緋桐は正治の紹介を改めて行った。 「オレみたいな紛い物よりさ、正治の方がよっぽどキチンとしてるってことだよ。 妖狐(オレ)を見たから、たまちゃんはすんなり信じるだろうけどね、こういうのって偽りだなんだって良く言われるそうだよ」 だから、言わないんじゃないかなと緋桐は傍らで渋い顔をした正治を見上げる。 小さい頃は、普通に視えていたから何もない所に話しかける事があり、家族以外の周囲の人間からは気味悪がられていたこともあるそうだ。 区別がつかないという事は、しっかりとその存在が見えているという事だ。陰陽師としての技能を詰め込んだわけではない以上、彼が出来るのは見る事だけだそうだが。 「じゃあ、緋桐さんよりよっぽど幽霊退治なら信頼してもいいってこと?」 「オレは幽霊とそうじゃないものの区別はついてるんだけどな? あと、結構強いよ」 ふん、と胸を張った彼に正治は「だが、普段は弱い」と付け足した。 拗ねた様に地団駄を踏んだ子供のような仕草にたまは彼を信頼していいものか、悩ましいと泣き出しそうな空をぼんやりと見上げた。 「……いいの、かしら」 雲の切れ間から太陽が見える。日傘を差した女性たちの間を擦り抜けて、帝都の街を行く馬車に気を付けながらたま子は慣れた様子で進む緋桐を追いかける。 「たまちゃん、ここだよ」 帝都の路地の裏、人目を避ける様に存在していた雑貨類を取り扱う商店は西洋街の真ん中にあるはずなのに茫と赤い提灯を垂らしている。妙に違和感を感じる様相だ。我が物顔で入店する緋桐に手招かれるままにたま子が足を踏み入れれば、商店の奥から「いらっしゃい」と軽い声が返ってきた。 「あれま、紛い物のおにいさんが女連れかいな。 あの陰陽師の血のおにいさんはどうしたの? もう死んだ?」 「まさか! 正治は中々死なないよ」 軽口を交わした二人の様子に、たまは馴染みの店なのかと小さく首を傾ぐ。 「へえへえ、かわいい女の子じゃないかい、美味しそうな……」 射干玉を思わす髪を簪で一つに纏めた美しい女は、書物の遊女のようだとたまは思う。 その彼女が、近寄ってくるまではその感想だけでよかった。 たまの許へと近寄ってきた彼女が動くとずるりと何かを擦る音がする。 「え、」 そこにあったのは蛇。女の胴によりしたには蛇の尾が存在していたのだ。怯え竦んで肩を震わせたたまに、店主は「あらま」と小さく笑う。 「お嬢ちゃん、妖怪の世界は馴染みないのかい?」 「え、ええ……」 こうして妖怪が様々な場所に居るのだと思わなかった。そう呟けば蛇女は楽し気に笑った。この店は妖怪達が利用する場所であるそうだ――普通の人間が訪れることはそうそうないのだと店主は続ける。 「そんで、そんなお嬢ちゃんを連れて何の用だい?」 「髪飾りが欲しくってね。訳アリだよ」 これがいいな、と彼が手に取ったのは椿の髪飾り。緋桐曰く、それはお守りなのだそうだが……妖怪の店で買ったものにそのような効果があるのかは疑問だ。 本物かどうかを聞こうにも正治は隣にいない。 そういえば正治は店内にいないのだな、と振り仰いだ時には買い物も終了していたのか店舗から退出するようにと緋桐に促されたのだが。 「��ら、たまちゃん」 鮮やかな紅色の椿に少しばかりの装飾が愛らしい。お洒落をしたいのは女性としての素直な欲求だ。こうして、男性にプレゼントされると思えばたまの頬も自然に赤らんだ。 この際、お守りかどうかなど気にならない程に可愛らしい髪飾りだ。……妖怪の店で購入したものでなければ、だ。 「……緋桐さんって、意外にシュミいいのね」 実年齢を知った後ではあるが、同年代にしか見えない彼についつい軽口をたたいてしまうのはたまの中に芽生えた気恥ずかしさからか。 そんな言葉にも楽し気に笑った緋桐は「ハイカラかな?」と冗句を交えてたまを見遣った。 「ハイカラか。ハイカラといえば、エス……えすかれーたー……? とやらがあったな。俺はあれをよく知らないが狐塚は見に行ったと言っていたな」 「まあ文化ですから」 茶化して告げた緋桐に『妖怪の店』から出て来た二人に何気ない日常会話を続ける正治。先程の蛇女の衝撃から抜け出せないたまは椿の髪飾りを握りしめたまま視線をあちらこちらへとうろつかせた。 「ええと……これ、は、」 「あ、つけておいてね」 気恥ずかしい、それに、妖怪の店で購入したものだ。 一寸した戸惑いを感じるのは人間として当たり前じゃないか。 そう言う事も出来ないままに髪に据え置かれた椿。困り顔のたまに似合うとしどろもどろになりながら返した正治にたまは曖昧に頷いた。 (……思ってもないことが言える人じゃないんでしょうけれど) それでも、妖怪の商店に彼がいなかったことは少しばかり裏切り者、と罵ったっていいんじゃないだろうか――そんな気持ちになったのだって仕方がない。 「はいはい、じゃあ調査に向かおうか。 とりあえずは猫探しからだね。正治、たまちゃん」 「ねこォ?」 にゃん、と鳴いて見せた狐。 幽霊退治と何か関係があるのかと問い質したくなる気持ちをぐ、と答えてたまは頬を膨らました。 今までの事で頬を膨らませることくらい許して欲しい。 「いや……役人からの依頼で先に熟しておいて欲しいんだ」と頬を掻いた彼に、顔に似合わず苦労性なのねと失礼なことを考えながらたまは何とか気持ちを鎮めた。 「そんな目で見ないでよ」 じとりと見つめるたまに緋桐は何食わぬ顔で笑う。目での抗議は失敗だ。それ所か何か言っても彼は適当に受け流してしまうことだろう。「にゃん」ともう一度鳴いた彼に何かを言う気もなくなってたまは小さく息を吐いた。 「……で、どんな猫ちゃんなんですか?」 「ぶさいく、だそうだ」 「もう一度」 「ぶさいく、だそうだ」 「それで、判ると思うたか!」 たまは吼えた。冷静な顔をして得てる情報はこれだけだと告げる正治に我慢ならなかったのだ――様々な思いを混ぜ込んで吼えた彼女を行き交う人々は振り仰ぐ。大和撫子、これでは只のはしたない女性になってしまう。 「ほら、たまちゃんどうどう。 一先ず情報は僕から話すから、こっちへおいで」 ぶさいく猫だなんて帝都にはたんまり存在しているのに��憤慨するたまを宥めながら緋桐は銀座へ向かおうと馬車を呼ぶ。頬を膨らませるたまは正治を横目で見据えながら唇を尖らせた。 「帝都にぶさいくさんなんて山ほどいるんだもの……。美人猫さんだってたんまりと存在しているもの……。そんなの情報にならないわ」 自分の依頼をそっちのけでぶさいくな猫を探せなんて堪らない。たまを馬車へと乗せて、気まずいと視線を外へやったままの正治に笑いをこらえて緋桐はたまと向き直った。 「馬車の中だからちゃんと話しをしようね」 馬の蹄の音と馬車の車輪が回る音がする。拗ねたたまに緋桐は「正治」と傍らの友人へと呼びかける。 「尻尾が二本あって、言葉を喋るぶさいくな猫ってちゃんと言わなきゃ分からないだろう?」 「そっちの方が分かる訳なかろ!」 またしてもたまは吼えた。さも当然のように妖怪を探す依頼だった時、人間はどんな顔をするべきなのだろうか? そもそもだ、そもそも妖怪は当たり前のこととして、現世に『存在してはいけない』ものだ。緋桐がその身に流れる血に妖怪というものを孕んでいようとも、蛇の店主が店を営んでいようとも、だ。普通の人間の前には妖怪は存在してはいけないのだ。 それを言い出してはキリもない。たま自身も幽霊退治を依頼したのだから。 「……それで、なんで妖怪の猫ちゃん何ですか?」 「……いや、何分訳ありな猫でな」 もごもごと幾度も口の中で繰り返す正治はどう説明したものかと珍しく緋桐へ視線を送っている。 足を組み窓の外へを視線を投げる彼は正治の視線に気づかぬ儘、茫としている。金の瞳は何処か胡乱だ。 「……あの?」 いつもの調子なら楽し気に笑って小粋な冗談を交えるであろう彼は小さく舌打ちをひとつ。子供のかんばせには似合わぬ大人びた態度にたまはびくりと肩を揺らした。 「ああ、今日も正しい意味で晴れてはいないからな」 彼の態度に何かを悟った様に正治は視線を落とす。先程、簪を付けた際に緋桐がたまに持たせた小さな鞄にはびいどろを思わせる粒が入っていた。 「狐塚」 慣れた手付きでいくつか掴んだ正治が緋桐へとそれを差し出す。たまには一体それが何であるかは分からない――『健康体』であったたまには、薬であることなど、判らない筈なのだ。 「……正治、たまちゃんの前で薬は出さないで」 「お薬……?」 やっぱり、と呟いたことにも彼女は気付かない。 正治の掌からすぐにそれを奪って緋桐は何食わぬ顔で笑みを溢した。 「依頼の話をするのだったね。彼女は化け猫ちゃんなんだけどさ、まあ、ブサイクって言われるのは猫の姿だけでさ……その実、千里眼持ちだとか美女に化けるだとか言われているんだ」 新聞に載っちゃう恥ずかしいお話だと笑う緋桐に普段通りだと安心したたまは僅かに首傾ぐ。今までしおらしい態度だっただけに、突然の豹変に聊かついていけない。 「わ、」 どう反応するのが正しいのだろうか。恥ずかしいと顔を隠し、ちらりとこちらを伺った狐。その態度に普段の自分なら飛び出して思わず���りつけているだろう――さあ、どうするべきか。 答えは、ひとつだった。 「わぁ~、ききたいなぁ~」 「たまちゃん、無理しなくていいよ。ごめんね」 にたりと笑った緋桐にたまの惑いはバレていた。 一々演技掛った口調で話すという事には数日間の間に良く理解してたが、真面目でない相手の反応には惑ってしまう。 『真面目な人間が周囲に多かった』からか――それとも。 「狐塚、冗談は止してそろそろ説明してやれ」 「お前が出来ないからって押し付けておいてそれかい?」 何処か拗ねたように言う緋桐は「美人に化ける化け猫ちゃんって言葉がぴったりだよ」とその言葉をつづけた。 「化け猫……」 「そう、さっきの蛇やオレと一緒。妖怪はどんなところにも存在するんだ。中々に美人に化けるもんだからね。お役人さんが一目惚れ。ううん、事件だ」 面白おかしく言ってのける緋桐。時代も時代だ。たまは世相に疎いためにあまりその辺りは理解していないが、成金が増え、中流層には民主主義が台頭したこのご時世だ。スキャンダルともとられるネタは大正デモクラシーだなんだかんだと騒がしい時代にあまりにも似つかわしくない。化け猫に惚れた役人だと周囲に流れてしまえば、政府が『妖怪』の存在を見つめたとゴシップにされてしまう。 「つまりは、化け猫に惚れた役人はどうしても彼女を探したい。だが、相手は妖だ。下手にそれが出回れば、妖の存在が世間を騒がせ、統治に響くかもしれない――だからこそ、狐に頼んだ、と」 「娯楽でやってる探偵業だってね、お客さんがいなきゃつまらないでしょ。正治が『持って』来てくれた仕事だし?」 ちらりと視線をやる緋桐に「借りを返した」とだけ告げる正治。本当に腐れ縁なのかしらんとたまは朝食の準備まで担当する正治と緋桐の関係性を計り知れないと首を傾いだ。 外見からは分からないが中身だけを見れば年下の男を虐める兄貴分という図式が出来上がっている。そう思えば、このような貸し借り勘定がまかり通る関係も男同士の友情らしくてよいのだろう。 つまり、正治はパシりなのか、とたまは一人で結論に至るが――「今、よからぬことを考えただろう」 勘が鋭い青年将校だ。 ぎろりと睨みつけるその視線にたまは肩を竦め、慌てて馬車の外へと視線を送った。 往来は賑わい、走り抜けるバスから立ち上った砂埃が何処か擽ったい。たまは到着だと告げる緋桐に手を引かれ馬車をゆっくりと降りた。 見慣れぬ街は人々でごった返し、愛らしく着飾った女性たちが西洋の傘を開いて語り合う。フルーツパーラーに視線を奪われたたまの手をくいくいと何度も引いて緋桐は困った様に首を傾いだ。 「そんなに行きたい?」 「……いえ、その、そんなことは――」 行ったことないのだから興味がないわけではない。 今度はたまが口の中でもごもごと言う番だった。 曇天��昏く見えた街中を困った様に笑った緋桐に手を引かれ進んでゆく。フルーツパーラーは今度ね、と何となく付け加えられた言葉にたまは小さく頷いた。 「それで、どこへ?」 「……さあ? どこだろうね」 帽子をかぶり大衆向けの新聞を手に政治がどうだと議論を酌み交わす紳士や学生の間を擦り抜ければ、気づけば路地の中。往来の賑わいとは違った雰囲気を感じさせた。たまはその異様な空気に慣れないと背後をゆったりと歩く正治へと視線を向けた。 目線はやや下向きに。議論を酌み交わす青年たちとは目を合わせぬように息を殺した青年将校にとって、彼らは異教徒と呼ぶにふさわしいのかもしれなかった。 どうしたものかと視線をうろつかせるたまはぴたりと緋桐が止まった事に気づく。慌てて一歩下がった彼女の前には古びた活動写真感。木造建築なのであろうか、傾いだ看板が風にばたりばたりと音たてて揺れている。 周囲に転がった酒瓶をブーツの爪先でつん、と触ってたまはぱちくりと瞬いた。 「ここ――」 古びているからか、何処かいかがわしい場所に見える。清廉潔白な少女としては頬を赤らめずにはいられないとたまは目線を下げた。 幻灯機が置かれたこの場所は表通りの人気の場所……なのだが、古びた活動写真館となれば状況が違う。裏にヒッソリと隠れたその場所では女学生にはとても口にできないものの上映が行われているに違いなかった。 それが、たまの妄想上のものだとしても、緋桐は見逃さない。 「どうしたの? 厭らしい事でも考えた?」 「え!?」 「……やだなぁ、図星? オレ、『君』みたいなのに興味はないよ」 「失礼ね!?」 含みのある言い方をされ、カチンとくるたまに緋桐はさも当然でしょうという顔をした。 一方で、その言葉に引っ掛かりを感じた正治が首を傾げたが、緋桐は正治の様子を見て見ぬ振りをしてずんずんと活動写真館の中へと足を進めた。 「ちょ、ちょっと、緋桐さん? 話は終わってないっ!」 慌てて走り緋桐の許へと飛び込む。ぐん、とたまに腕を引かれれば、小さな緋桐の躰は簡単に傾ぐ。 頬を赤らめ、眉を寄せて抗議がましい顔をしたたまは「あのねえ」と緋桐に向き直る。 「確かに私、ちょっと体が弱くって内気ですけ……ん? 私、明るく元気な事がとりえで、ええと……」 「それ、誰の話?」 唇を尖らせ話して居たたまの足がぴたりと止まる。 緋桐の言葉に何故だか竦んでしまった。彼の煌めく金の瞳が濁って見える――まるで、血の色のような……その感覚にたまの背には何か嫌な気配が流れた。 ぞ、とした感覚を振り払う様に「やだなあ」と小さく笑う。 「たまちゃん?」 彼の声は、彼の瞳は全てを見透かすようだから――誰の話、それは、 明るく元気な事が取り柄で女学校は途中で行かなくなった……。 大好きな友達がいて、風鈴が……。 ちりん―― 「たま?」 訝しげに覗きこむ正治の顔が真っ正面にある。小さく首を振り、なんでもないのと囁いたたまの事を緋桐はじっと見つめていた。 胸の中を擽られる感覚がする。まるで見透かされているかのような瞳が――気持ち悪くて。 「緋桐さん……その目、止めて下さい。怖いんですけど」 「ああ、ごめん。つい」 見ちゃった、と初めて会った時と同じような人懐っこい子供のような笑みを浮かべる緋桐にたまは居心地の悪さを感じる。彼のその笑顔は嘘が塗り固められたものだと、何となくだが知ってしまったからだろうか。 「狐塚」と嗜める様に呼んだ正治は緋桐の代わりにすまないと小さく頭を下げる。 「あ、あの……正治さんのせいじゃないのよ」 髪飾りをくれて少しは見直したのに。ああやってすぐにからかうのだから――ひょっとして贈り物をしたはいいけれど、似合っていないとでも言いたいのかしら! (全く、失礼な人っ!) 頬を膨らませた少女はずんずんと活動写真館の中を進んでいく。 先ほどまでの恥じらいも何もかも忘れてしまったように彼女は苛立ったように場を踏み荒らす。緋桐なんて置いていくという様に進むたまに「たーまーちゃーん」と彼の声が聞こえた。 「転ぶよー」と続いた言葉の通り、ずる、とたまの足は縺れた。 「痛いっ! もうっ!!」 「がっ」 転んだ姿勢から勢いよく起き上った……ものの……今――? 緋桐の笑い声が聞え、慌てて振り返るたまの目の前では勢いよく後ろに倒れ込んでいる正治。もしかして、とたまの血の気が引いていく。転んだからと手を貸してくれようとしていたのに気付かずに勢いよく起き上がったせいで彼の顎へと攻撃を喰らわせてしまったのだろう。 そういえば、後頭部が痛い……。 「え、えっ!? 正治さん、大丈夫ですか!?」 「あ、ああ……石頭だな……」 褒められてるのかしらん、と微妙な気持ちになりながらたまは苦笑いを浮かべる事しか出来なかった。 けらけらと笑う緋桐は怒ることも泣くこともできず曖昧な表情を見せる正治が面白いという様に両の手を叩き始める。 「も、もう、緋桐さんの笑い上戸!」 正治に手を差し伸べたまま、たまは頬を膨らませる。 「ご、ごめんね……面白いなあ……――とか言ってたら、おでましかな?」 涙を滲ませた金の瞳を揺らす緋桐はゆっくりと顔をあげる。暗がりの奥へと視線を向けた彼につられてたまと正治もそちらへ視線をむけた。 何かが、歩いてくる音がする。草履がぺたぺた地面を擦る音でなければブーツや靴底がぶつかる音でもない。それでも闇の中に目を凝らせば何か白いものが此方へ向かってくる事だけはわかる。 「……何……?」 身構えるたまの腕を掴み、庇う様に前へと出る正治。二人に走る緊張は緋桐の許にくる依頼が大概『オカシナモノ』だという共通認識があるからだろうか。 白い存在はどうやら思ったよりも小さい。人間ではなく、犬よりも小さな――動物だろうか。 奥から歩いてくる存在へと警戒心を露わにする正治の前をゆっくりと進む緋桐は肩を竦めて小さく笑った。 「うるさいのぉ」 聞こえた声は、老婆を思わせる。 「やあ、君は相変わらずだね? 元気��ったかな?」 そこに居たのは、ずんぐりむっくりとした、白い猫だった。
0 notes
Text
黎明、即ち再開の空の下で/10/2011
どこをどうして迷い込んだのか、今となっては思い出せない。
百合子は広すぎる洋館のしんと静まった暗い廊下を一人で歩いていた。 女中も召使いも誰もおらず、先ほどまで一緒だった兄さえもいなくなっていた。
普段からお転婆がすぎると母から怒られてはいたが、今日ばかりは深く反省した。 廊下は広く長く、一歩一歩進むごとに暗闇が深くなっているような気がする。 じんと鼻先が痛み、涙が溢れそうになるのを百合子は堪えた。
しばらく行くと暗い廊下にぽつりぽつりと灯りがつきはじめた。 百合子はほっとしたが、それらの灯りはより深く暗いところへ行くための目印だったのだ。 そうと走らない百合子はその灯りを頼りに、階段を降りる。
下階の方からは、ごうんごうんと音が聞こえてくるので誰かいるのかもしれないと思った。 階段を踏み出せば不思議な匂いがした。それは苦いような青臭さだった。 しばらく行くと古い扉があらわれ、音も匂いもその中からしているようだった。 その取っ手に手を伸ばし、引いてみるがぎしりと金属音がするだけで開かない。
百合子は何度か押したり引いたりしてみたりしたが、どうやら鍵がかかっているらしくびくともしなかった。
「誰かいないの?」
声をかけてみても同じで、がっくりと諦めて更に続く階段を降り始める。 階段は行き止まりにまた扉があって、百合子はそれを押して開けてみた。
瞬間、あふれる光りに百合子は思わず目を瞑った。 さわさわと何かが風に揺れる音がして、甘い香りが鼻孔をくすぐる。 ゆっくりと目を開き、何度かぱちぱちと瞬きをしてようやくそこが花いっぱいの温室だと分かる。
「まあ……」
先ほどまでの寂しさを忘れ百合子はその花々に見蕩れた。 白や朱に黄色、薄紫に紅といった様々な色の花が百合子の背丈ほど伸びているのだ。 花壇はきっちりと区切られ、脇には水路がちょろちょろと流れている。 そして更に上を見上げると、ガラス張りの天井に魚が泳いでおり、その透明な天井から差し込む陽の光はとても明るかった。 まるで夢のなかのようだと思う。
「きれいね」
百合子はそう言って花に触ろう手を伸ばした。
「ダメですよ」
急に声をかけられて振り返った。 そこには下働きらしい少年がおり、厳しい顔つきをして百合子を見ていた。
「あの……あ、わ、私、迷ってしまって……」
とっさに口をついて出たのはそんな言い訳だった。 花を盗もうとしたのだと思われたのではないかと不安になる。
「それに……花をとろうとしたのではないわ。みたかっただけなの」 「花が――お好きなんですか?」 「ええ、好きよ」
少年の顔つきが幾分か柔らかくなった気がして、ほっとしながら百合子はそう答えた。
「ここの花はダメですけど、庭園にはもっといろいろな花があります。 それなら、良いですよ」 「本当?」 「はい」
少年はそういうとすたすたと部屋を出る。 百合子もそれに遅れまいと追いかける、二人が部屋を出るとがちゃんと音を立てて扉がしまり暗い廊下に戻る。 暗い階段を少年の後をついて歩きながらそれでもどこからかあの花の匂いがした。 そして、それが少年から香っていることに百合子は気がついた。
がたん、と自動車が揺れる。 うとうととうたた寝をしていた百合子は窓硝子に額を打ち付けた。
「っ……」
不意の痛みに思わずぶつけた額を押さえて苦悶の声をあげる。 じんじんと痛む額をおさえつつ、何か夢を見ていたような気がしたのだが、どんな内容だったか思い出せなくなってしまっていた。 掬い上げては指の隙間からこぼれ落ちる砂のように、夢の記憶が遠ざかる。
「あともう少しで到着しますよ」
運転手が百合子に声をかけて返事をするときには、すっかりと夢の内容は思い出せなくなっていた。 深い緑が続く車道。 百合子は、神奈川県の山奥に建つある洋館に招待されていた。 事の起こりは数週間前、百合子のもとに不思議な手紙が送られてきたことから始まった。
/-/-/-/-/-/
名探偵、野宮百合子嬢に告ぐ。 貴方が真の名探偵であるというのならこの家に伝わる財宝を探し当てよ。
「随分と挑発的な手紙だな」
斯波の服装はすでに病院の用意したものではなく、自前のいつもの洋装だった。 まだ退院は早いのか、それでも会社への指示だけは出すようになっていた。 前日にあのようなことがあったばかりだというのに、百合子はその手紙をもって斯波の病室を尋ねている。 考え始めたらだめなのだ、深く考えてしまうと今でも顔から火が出るほど恥ずかしいし手も震える。 心臓の鼓動は鳴りっぱなしになるし、まともに斯波の顔を見られなくなる。
「そうなの、それでねこの差出人がまた奇妙なの」 「蔵元澤三郎っていうと、数年前に死んでるじゃないか。 たしか心の臓が弱っての病死だったか――それにしても面白い偶然だな」 「偶然?」
きょとんとした百合子に斯波は知らなかったのかとばかりに驚きながら言った。
「真島芳樹は蔵元邸の庭師だったんだぞ」 「蔵元邸の?――藤田は蔵田家の庭師だったと言っていたわ」
百合子はそれを聞いてわずかに戸惑う。 確かに藤田に確認した時はそう言っていたはずだ。 藤田は真島よりも長く野宮家に仕えていたから、情報は確かなはずだった。 その情報を知ってから一度だけ蔵田家を訪れたがすでに邸は売買され、違う住人が住んでいた。 手伝いのものや女中などもすっかり人が変わっていたためそれ以上足跡をたどることはできなかったのだ。 その事を斯波に伝えると、なるほどなと頷きながら説明し始めた。
「蔵元は、元々蔵田家の番頭をやっていたんだ。 江戸時代末期、蔵田は水田開発だ��塩田開発だので土地持ちになって、更に質商や金融業も営んでの豪商となった。 そして、当時多くの豪商が私札を発行することになる――ところがだ、私札を発行した家は大名に賃金を支払不能にされたりして没落の道をたどった。 ただ、蔵元は私札発行には目もくれず東京近隣の土地を買い上げた。 だから、あの頃の蔵田家といっても実質は借金まみれの没落家だったはずだろう。 蔵元は恩返しのつもりかいくつか蔵田の借金を負っていたはずだから……東京にある蔵田の邸はほとんど蔵元の所有と思っていいだろう」
そこまで喋って斯波は百合子の視線に気がついた。 じとりと湿り気の帯びた瞳が、不審そうに斯波を見つめている。
「何だお姫さん」 「どうしてそんなに詳しいの?」
百合子が不審がってそう問うと、斯波はにやりと口の端を釣り上げて答える。
「敵情視察は基本ですからね、真島とやらのことを聞いてからは人をやって調べさせた」 「探偵の助手が別の探偵を雇って?」 「別の探偵じゃない俺の部下だ。――それでこの挑戦受けるのか?」 「……まだ、受けないわ。だってまだ斯波さんも本調子じゃないし、 仮に今受けると言ったらあなた無理やりにでもついてくるでしょ?」
白いシャツの下にはぎゅうぎゅうときつくさらしが巻いている。 毎日包帯を取り替えて抜糸もされていない傷口を日に何度も消毒する。 夏も終わりようやく涼しくなってきたものの、斬りつけられた傷口が化膿しなかったのは運が良かったのだろう。
「傷はもう塞がってるが……」 「いいえ、そんな状態でついてこられたら逆に足手まといですからね。 あなたの性格はよおく知っているもの、斯波さんの傷が癒えるまでは保留にするわ。 それに、いまだに記者が家の周りをうろついていて……何を書かれるか分からないものね」 「ああ、それは英断だな」
斯波は手紙を折りたたんで百合子に手渡す。 秋の涼しい風が開いた窓から入り、白いカーテンをはためかせる。 百合子が見舞いにと持ってきた花がそよそよと揺れた。
(そういえば斯波さんのために花を選ぶ日がくるとは思わなかったわ)
百合子は自分の髪が長かった頃のことを思い出していた。 自分も斯波もあの頃から随分と変わってしまったような気がする。 そう思ってちらりと斯波を盗み見ると、斯波も百合子を見ていたようで一瞬目があう。 百合子はどきりと心臓が跳ね、ゆっくりと顔が紅潮していくのがわかった。 そんな百合子に対して斯波はどこか気の抜けたような顔をして笑った。
「ところで、今日は林檎を食わしてくれないのか?」
重湯が物足りないと文句を言っていた時に、差し入れにと市場で買った林檎をもってきたのだが、 刃物の扱いが苦手な百合子は随分と苦労して皮を剥いたのだ。 ごつごつと見た目も悪く、買った店が悪かったのかすかすかと海綿のような林檎だった。
「私がやるよりも、斯波さんがやった方がお上手だったじゃない」
見かねた斯波が一つ試してみたらするすると器用に林檎の皮を剥いていくのだ。 まるで職人技のようだと百合子は感動したが、何をやらせても器用にこなす斯波を少しだけ憎らしく思った。
「なんだなんだ、連れない人だな。俺はお姫さんが切ってくれた林檎を食いたいんだ」 「もう、そんなに言うのならやりますけど」
そう言って机に置かれた籠を取る。そこには水果千疋屋と書かれていた。
/-/-/-/-/-/
(結局、斯波さんを騙して一人で来てしまったけれど……まさか後から追っては来ないわよね)
斯波にはしばらく親戚の家で大人しくしているつもりだから、当分見舞いに行けないかもしれないと伝えておいたのだ。
東京から神奈川まで自動車でだと半日もあればつくが、そこから山奥の別荘へと向かう道は悪路が続いていた。 こんな山奥に邸を建てるなどと酔狂なことだと百合子は考えながらぼんやりと車窓を見つめる。 そして、木々の間から見え始めた塔を見て絶句する。 とても山奥に建っているとは思えないほどの、別荘と呼ぶには些か大きすぎる建物が見えてきた。
「あの、あれが……」 「蔵元邸です――まあ地元の人間は蔵元城と呼んでいますけどね」 「そう、城……」
聳え立つ塔をもち、外堀をめぐらせ跳ね橋をかけている様は城と形容するのが一番ふさわしいだろう。
「何でも英吉利の有名な建築家を呼んで作らせたっていうほど先代が英吉利贔屓��しくてね。先の災害にも耐えたそうですよ」 「先代っていうと、数年前に亡くなった?」 「そうそう、港の辺りの土地を持っていたらしいし、土地開発と貿易なんかで儲けたらしいけどね。 この辺りじゃどこぞの議員さんやら華族さまよりも有名だよ。ところでお嬢さんはどういった用事なんだい?」 「雑誌の取材です、こう見えて編集者なので」
運転手は何も知らされていないのか、呑気に問いかける。 百合子もとっさに答えたが、どうにも”探偵”です、とは言えなかった。
「へえ、東京からわざわざねえ。へえ、雑誌の記者さんか」
ミラー越しに検分されるように見られているのを感じる。 百合子は気にもしないと言う風に軽く髪の毛を触った。 薄紫のモダンな洋装に手首までの白い手袋、流行りの帽子を被ってタイを結んでいる。 どこからどうみても東京のモダン・ガールであり、職業婦人である。 そしてミラーの視線に今気がついたという風に、にっこりと笑って見せてから問いかけた。
「蔵元家は地元の皆さんにも慕われていたみたいですね」 「そうだねえ、俺の曾祖父さんがよく言っていたけどほら天保の飢饉には金何両だかを献じたって。 先代で一時期ちょっと雲行きが怪しくなった時があったらしいが、やはり商才だろうね。 すぐに立ち直って――まあ、その矢先に先代さんはお亡くなりになったんだけどね」 「そうなんですか、えっとじゃあ今は――」 「跡取り息子の宗太さまって方が継いだらしいけど、どうだろうね。 北海道あたりの――何と言ったかな室蘭だったかな……とにかくそのあたりに製銅所が出来るという話があってそれの投資に躍起になっていたと聞くよ」 「そうなんですか」
興味深そうに相槌を打ったのが気になったのか、運転手の顔が曇る。
「あ、今の雑誌に書くつもりかい?まずいなあ……」 「いいえ、大丈夫ですよ」
運転手は困ったように頬を掻くと、それきり黙ってしまった。 もう少し話を聞きたかったが、仕方が無いと諦める。 百合子も自分で下調べをしてはみたものの、さすがに限界があった。 今はもう新聞社に立ち入ることもできないし、斯波を頼りにすることもできない。 けれど、今まで詳細のつかめなかった真島の過去に何か触れられるのなら、と思うと居ても立ってもいられなくなったのだ。 斯波はきっと怒るだろうな、と百合子は思った。 何も告げずに一人で行動することに、眉根をよせて作るしかめっ面を思い出す。 くす、とわずかに笑みが溢れるのを居住まいを正す事でどうにか誤魔化した。
/-/-/-/-/-/
病室の扉が開く。 現れたのは山崎だった。 しゃくしゃくと瑞々しい林檎を頬張りながら、斯波は山崎を一瞥して確信したように頷いた。
「山崎、行ったか」 「ええ、社長の仰るとおりでした」 「やはりな――。よし、ではこの中から一番目を引く見出しを選べ」
斯波は寝台にあぐらをかき、敷物の上にに筆文字で書いた半紙を並べた。
一、怪奇!死人からの挑戦状、野宮百合子最後の事件! ニ、T氏の埋蔵金を探せ!美人探偵百合子の事件帖! 三、華族探偵野宮百合子と呪われた洋館の謎! 四、名探偵野宮百合子、危機一髪!~呪われし財宝と最後の事件~
それに全て目を通して、しばし考えこむ。 そして、どこか誇らしげにしている斯波に率直に聞いた。
「社長、これは一体……」 「もちろん、各新聞社に送るタレコミだ」 「なぜ、新聞社にこれを送る必要が?」 「山崎、良い質問だな。真島芳樹にお姫さんを見つけさせるためだ」
自慢気に言う斯波の顔を今度は心配そうに山崎は見つめた。 その視線に気がついたのか、ばつの悪そうな顔をする。 眉根をよせてしかめっ面を作ると、少し気分を害した様な声を出した。
「何だその目は、ん?」 「いえ、三日三晩の高熱の後遺症かと……」 「馬鹿者。いいか、真島とやらはお姫さんに見つからないように逃げてるんだぞ。 それを見つけようと探すのははっきり言って無理だ」 「左様で……」
山崎はほっと胸を撫で下ろす、どうやら頭が茹だってしまったわけではないらしい。 それを見て斯波も調子がついたのか、自らの作戦の構想を語りだした。
「だからだな、今の華族探偵ムーブメントにのるであろうこの記事を真島が目にするとだな。 真島がこれは一大事とお姫さんの様子を窺いに現れるかもしれん。 何しろこの蔵元家はかなりきな臭い。政治家に心酔しおかしな投資に大金を突っ込み傾きかけたはずが、貿易で急に盛り返したりとまあ何とも動きが怪しい」 「それはまあ社長の仰りたいことは分かりましたが……いいのですか? お二人が出会ってしまったら、恋心が再燃して愛の逃避行に走る可能性も……」
その言葉に斯波はぴくりと眉尻をあげた。 そして少しだけ考えこむように沈黙するが――。
「まあ、もちろんその可能性も考えなかったわけではない。 しかしお姫さんは俺に”嫁になってもいい”と言ったんだ。 どうだ、これはかなり俺を好いている、いや俺のことを着実に愛し始めていると言っても過言ではないぞ? (あまりの可愛さに理性がぶち切れてつい手を出しそうになってしまったがな、はは) こうなると――禍根は、この真島だけなんだからな。 まあ、俺もこんな記事を打ちつつも真島がお姫さんの前に現れる確率など五分……いや、いいところ二分くらいなものだろうと考えている。 探しても見つからない、炙り出しても現れない、そうなってようやくあの頑固者――いやいや意思の固いお姫さんも諦めるというものだ。なあ」 「仰るとおりで」 「さあ、ぐずぐずしていられないぞ。 記事の方にもそれとなく蔵元家の存在を匂わしつつ真島に伝言を入れ込まねば。 いいか、場所や個人名が特定されてしまって記者が嗅ぎつけたら元も子もないからな、塩梅だぞ塩梅。 よおし、まずは熱い茶だ。茶を入れろ!」 「はい」
山崎はそう命ぜられて一旦病室を出る。 中ではああでもないこうでもないと原稿を推敲する斯波の声が聞こえる。 側仕えの女中に熱い茶を入れるように言うと、深くため息をついた。
(百合子さんが関わられると急に人がお変わりになる……)
斯波の作戦が成功しようが失敗しようが、山崎の心労が晴れることは無さそうだった。
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
衰退する蔵田家の一方で、蔵元家が急成長した理由にとある共同経営組織の存在があった。 これは元は清と英吉利の貿易を代行している会社で、貿易の中継地点として日本での拠点になる会社の経営を蔵元に願い出たのだった。 日本での活動をより円滑にするために財界や政界にも顔が広い蔵元に支援を受けていた会社が、いずれ蔵元を内側から食い荒らすほどの巨大な組織であった事は蔵元の当主であった先代しか知らない。 毎年毎年生み出される莫大な利益が何から生まれているのか、それを知ったときにはもはや後戻りはできないほどの闇の深みへと沈んでいたのだ。 人の欲を食って膨らみ続ける金――権力や富をもう欲しいとは思えなかった。 だから、共同経営者の使いから火急の要件を聞いた時、何十年ぶりかに心の休まる思いがした。
それは、組織が蔵元から手を引くというものだった。 蔵元名義の会社や工場、港は全て閉鎖か転売するという内容だった。 手元に残るのはほんの少しの資産とわずかな土地くらいなものだろう。 いつ、政府や役人にあの恐ろしい罪が暴かれるかと不安に思う日々に比べれば多少の不便など目を瞑ることが出来た。
こうなると、悩みの種は一人息子のことだった。 そんな内情を知らない息子は、会社の権利書や土地の証明書などを引っ張り出しては調べ上げている。 何をどう勘違いしたのか資産を隠し持っていると考えているようだ。 ふ、と例の共同経営者について全て洗いざらいを話して、説得してみようかと考えてみるもすんでで思いとどまる。 それが共同経営者の男との盟約だったのと、何よりこの邸の秘密を知った息子は恐れるよりも喜び勇んで利用するだろう。 だから、やはりこの邸は男の言う通り、朽ちるに任せるのが一番いいのだ。
ずぎり、と心臓が痛む。 もうずっと、体調が思わしくない。 ふるえる手で水差しを探すが、ぶるぶると震えて焦点が定まらない。 手の甲が硝子に触れ、勢い余って机から水差しが落ちる。 絨毯に水差しが転がる重い音がして、水を散らしながら転がる。 ぜいぜい、と額に脂汗を浮かせて床に倒れ込んだ。
その音を聞きつけた秘書が扉を開けて駆け込む。 ぼんやりとした意識の向こう側で必死に名前を呼ぶの分かる。
「この邸だけは……」
震える舌は最後の言葉をどうにか紡ぎ出し、糸が切れたようにそのまま力が抜ける。
/-/-/-/-/-/-/-/-/
城には二つの種類がある。 一つは敵の侵攻を防ぐ要塞としての城、ぐるりと囲む城壁や堀にかかる跳ね橋は城塞としてのそれである。 そしてもう一つはマナーハウスと呼ばれ、貴族たちの別荘としての建物で広く美しい庭をもつものだった。 蔵元の城はその二つを兼ね揃えていた。
威圧感のある城壁に、跳ね橋をみてよくも政府などに目を付けられなかったものだなと思ったが、一歩跳ね橋より中に入ってみるとそこは美しい庭が広がりその中央に噴水が輝いていた。 開けた道が一本噴水まで続く、そしてその奥に欧州の絵本の挿絵をそのままそっくり建築したようなマナーハウスが建つ。 道なりに両脇には動物を象った木の葉が刈りこまれており、造形は躍動する馬だとか跳ねる兎だとかで、午後の日差しも相俟って庭は不思議な雰囲気が漂う。 マナーハウスは薄いクリーム色をした建物で、外壁を緑の蔦がからみつくように覆っている。 背後には森が続いているようで城壁が見えないほど広い。 自動車が止まり、運転手にドアを開けられて外に出ると城壁によって外界と遮断され、まるで本当に別の国に迷い込んだようだった。
「お待ちしておりました、名探偵殿」
百合子にそう声をかけたのは30代半ばほどの男だった。 焦げ茶色の洋装に撫で付けた髪に口髭、微笑んでいるが目の奥は百合子を検分するように光る。
「素敵な招待��をありがとうございます、ご依頼はどのような?」
男は苦笑して答える。
「招待状の通りです、私の父は数年前に病気で亡くなったのですがその際遺産を屋敷に隠したと遺言を残したんです、遊び心の多い人でしたので。 最近、貴方のご活躍を耳にしましてね、是非我が邸の謎も解いてもらおうと思ったんですよ」 「それにしても、亡くなったお父上のお名前を使うなんて……」 「これは賭けだったんですよ、なあ?」
男は後ろに控えている秘書に笑って同意を求める。 50代前半ほどの老紳士風の秘書は無表情のままかしこまって礼をした。
「ここではそれほどでないが、東京では今や貴方の名前を知らない者はいない。 そんな有名な探偵殿に普通に依頼を出しても選り好みをして受けてはもらえないだろう?」
得意そうに弁舌を振るう当主。 百合子が依頼を受けたのは全く別の理由だし、嫌味な言い方にかちんとくるも微笑んで同意してみせた。
「旦那様、野宮様もお疲れのことでしょう」 「ああ、そうだな。兎に角、貴方の手腕が発揮されるのを楽しみにしているよ。 依頼の説明や身の回りの世話は秘書の日野に任せてある」 「まずは宿泊のお部屋にご案内を」 「ええ、では失礼いたします」
自動車に積んだ荷物を持ち秘書の男が邸を案内する。 残された当主は内懐から煙草を取り出し火をつけ、興味深そうに百合子の後ろ姿を目で追った。 ふうと煙を吐き出して、吸殻を捨てる。ぎゅっぎゅと革靴の底で踏みつぶしながら今度こそはどうだろうと思案に暮れる。
(本当に遺産なんてあるのか?)
父親が病死して土地という土地、遺品という遺品を総ざらいしてみたもののそれらしい遺産は何もなかった。 傍から見ればあれほど土地持ちだ資産家だと思っていた邸は空蝉のごとく何も残っていない。 財界を唸らせるほどの金と権力が父親の死によって、全て見せかけだったと気付かされる。
(いや、そんなはずはない――)
では、あれほどの金はどこから出ていたのか。 やはり何か隠してあるに違いない、否、そうでなければならない。 当主を継いだ宗太は焦りを感じていた。 北海道の投資に失敗して以来、それの損失を補填しようと様々な事に手を出した。 どこそこの土地に線路が走るだの、土地開発案があるだのと仲間内からの情報を信じて買ってみれば全て嘘の情報であったり値を吊り上げられていたりし、急かされて金を渡せば仲買人が金を持ったまま失踪したり��た。 先日もまた戦争があるからと儲け話を持ちかけられ、唯一残っていた不動産やら証券を整理して逐次注ぎ込むも利益は全く上がらなかった。 どれもこれも最初だけは上手く運用出来て潤沢な配当があった、それが日が経つに連れ雲行きが怪しくなりそして損失を補うために次に次にと財産を注ぎ込むことになるのだった。
そして勝手に土地を抵当に入れているの��、当時当主だった父親の知るところになったのが運の尽きだったように思う。 当主とはいってもどうしてかすでに半分隠居したような暮らしをしていた父親に、金の無心をせまるも無下に断られる。 これから戦争で世界が動く、日本だって動かざるをえない状況になる、そうすれば人も金も物も動き絶好の機となると何度説得しても応じなかった。 宗太は慌てた。他の仲間達は我先にと儲け話に乗っているのに、自分だけはただ借財が増えるばかりだ。 蔵元の財産と呼べるものはこの邸以外にはもうほとんど残っていなかった。 土地も山も、田畑も、不動産も、貿易会社工場も――全て名義だけが蔵元で実質は色々なところに切り売りされていた。
もはや宗太が頼れることは死に際の父親が繰り返した、この邸だけは人に売るな――。というその言葉だけだった。これが遺言らしい遺言ともとれる。 英吉利の建築家が設計したという城を、これまで何人も探偵を雇って調べさせてはみたが何もでない。 本当に父親の遺産は全て幻だったのだろうか。 もう二年半も人をやっては調べさせている、しかし何もでない。 潮時を感じていた、この邸を売るなという遺言はあれどこのあたり一帯、背後の山も森も湖まで含めての残された唯一の土地。 売ればいったいいくらになるだろうと考えていた。
「申し訳ございません」 「いいんです慣れてますから」
秘書が百合子に頭を下げる。 先ほどの当主の無礼な言動を思ってのことだろうが、こういった事は初めてではない。 形式通りに邸を一巡案内される。 広すぎる廊下、広間、書斎、渡り廊下を経て玄関からテラスに出た。
「あの噴水は裏手の湖から直接水を引いています。 日中はあのように陽の光を受けて虹色になるように設計されています」
説明を受けて噴水を覗き込むとたしかに清らかな水が流れ、鮮やかな色をした魚が放されていた。 中央から吹き出す飛沫が美しい虹を作る。
「使用人の方にお話を伺っても?」 「それは構いませんが先代の頃にだいぶ人を減らしまして今残っているのは本当に少数です」 「その、先代様が資産を整理されて寄付をされた――というのは何か理由があったんですか? それに、人員の整理をするなんてまるで全てから手を引くような印象を受けたんですが」 「それは――私にも分かりかねます」 「そうですか……」 「ではお食事をこちらの部屋まで運ばせて、その後に使用人をお呼びしましょうか」 「ええ。――いえ、皆さんお仕事で忙しいでしょうから調査も兼ねて私が伺います。 なのでお話だけ通しておいてください」
斯波の情報が正しければ、真島はここで庭師をしていたのだ。 使用人たちに聞けば何か分かるかもしれない、ふと秘書の日野に真島のことを聞こうと顔を上げるが僅かなためらいの後に言葉を飲み込んだ。 そんな百合子の様子に気がつかず、秘書が部屋から去ってからほっと一息つく。 何だか一挙手一投足を監視されているようで居心地が悪い。
(あの秘書は食えないやつだ、お姫さん気をつけたほうがいいぞ)
今ここに居ないはずの助手がそう言うのが目に浮かぶ。 そう、当主などよりもよっぽど切れ者であるあの秘書こそ一番気をつけたほうがいい人間だろうということを百合子も薄々感づいていた。 先代の秘書と言うのなら財政には一番詳しかったはずである。 帳面などの管理や資産運用も先代に代わって取り仕切っているはずの秘書が、なぜ先代が資産の全てを寄付したのかという問いに「教えられない」「答えられない」ではなく、「分からない」と答えるはずがない。 食事を終えて紅茶を飲むと、調査も兼ねて邸の散策に出かけた。
(皆、言うことは先代様は素晴らしい方だったということばかりなのよね)
判を押したような答えに不思議に思いながらも、庭師の老人を訪ねて番小屋へ向かった。 ざくっざくっ、と土を掘り返す音が聞こえそちらへ向かう。 邸の使用人は洋装で統一されているのか、庭師の老人も汚れたシャツを来ていた。 年齢は勿論、格好も違うのに、百合子はなぜか少しだけどきりとした。 土を耕すその姿がどことなく真島と重なって見えたからだ。
「あの――」
振り返った老人は白髪で日に焼けた顔にはたくさんの皺がきざまれていた。 真島とは似ても似つかない姿形だった。 呼びかけた声に額の汗を手ぬぐいで拭きながら腰を上げ、老人は百合子を見て微笑んだ。
「ああ、噂の探偵さんか――ご苦労様で」 「お仕事中に申し訳ないですが、いくつかお聞きして良いですか?」 「ええ、勿論。まあ、私が知っていることと言ったらこの庭のことぐらいなものですけどね」 「以前勤めていた真島芳樹という男を知っている?」
蔵元の遺産関連の質問にこの邸の使用人はまるで回答を用意しているかのように、百合子の質問に答えた。 遺産があるとすればそれは全て寄付された、先代様は偉い方だ。――と。 思い切って別の質問に切り替えようと思ったのはそのためだった。 そこから会話を切り崩そうと考えて、あえて真島のことを話題にした。
「は?ええ、――たしかに、真島という男がいました。 けれど、なぜそれを?」 「私の邸の庭師だったの」
するりと百合子は答えた。
「とすると、貴方……もしかして野宮子爵の……?」 「そう、もう爵位は返上してしまったけど……」 「そうかい、それは懐かしいねえ。あの小さな姫様が」
老人の返答に驚くのは百合子だった。
「お前、私を知っているの?」 「ええ、一度だけお会いしましたよ。姫様はたぶん覚えていないでしょうが……」 「私、この邸に来たことがあるの?」
それは老人に向けた言葉だったが、同時に自分にも問いかけていた。 老人はいつだったかなと想い出すように空を見上げた。
「そう思い出しました、昔は先代様がハウスパーティーをよく開いていたんです。 その時に――確か皆様でいらっしゃいました。若様が十になるかどうかで姫様はまだ五つかそこらだったと」 「そうなの?全然――思い出せない」
どうにか思い出してみようとするも何も思い出せなかった。 もどかしさばかりが胸につのる。
「あの子は私もびっくりするほど植物を咲かせるのが上手でね、今も元気にしてるのかい?」 「……爵位を返上して邸を手放した時に真島とも別れ��した。 そう、ではやはり彼はここで庭師をしていたのね」 「ああ元々は先代様の共同経営者の下働きをしていたらしいんだが、彼がそうだな十二、三のころかな一時期ここの庭師の手伝いとして雇われるようになってね。 すごく腕が良かったから私もこれでようやく弟子が出来たと喜んでいたんだが――すぐにまた別の仕事につかされたらしくてね。 まあ、頭の良い子だったから庭師にはもったいないと思ったんだろうね」 「では、ずっとここで働いていたわけではないの?」 「そうさね、それから十年も経ったかなあという頃にまた戻ってきてね。 その頃にはしっかりとした青年になっちまってて見違えたよ、それで庭師の仕事も相変わらず見事でどこで修行を積んできたんだと笑ったよ」 「じゃあ、その頃に私の父にその庭師の腕を気に入られて?」 「そうそう、蔵田の邸に移ってすぐね」
真島はその空白の十年の内に復讐に必要な全てを用意したのだ。 そしてそれはこの実体の見えない蔵元家の内情に深く関わることのようにも思えた。
その日の夕方、当主は最後まで姿を現さなかった。 百合子としてもこれ以上嫌味な言葉を言われる心配がなくなり少しだけ安堵した。 夕食も部屋で取る。 食前酒のアルコールがきいたのだろうか、百合子は強い眠気に襲われた。
(何か思い出せればいいんだけど――)
百合子はうとうととしながら、記憶の底を覗き見る。 そもそも五つか六つの頃の記憶などあってもちらほらとしたものばかりだった。
(真島が下働きをしていたという会社は何をしていたのかしら――)
先代の書斎にある名簿などを調べればまた違う糸口が見つかるかもしれない。 そう思いながら百合子は眠りについた。
/-/-/-/-/-/
夢の中で百合子は五つだった。 猫がぐるぐると百合子を取り囲み、その三日月のような瞳が不気味に笑う。 すると、次は黒い影が伸びて馬の影絵が現れる。 ウサギがぴょんぴょんと飛び跳ねて百合子の背を叩く。
Gone to get a rabbit skin, To wrap his baby bunting in♪
外国の言葉など何一つ知らないのに百合子にはそれが恐ろしい呪いの歌のように聞こえて耳を塞いだ。 じっとうずくまり、海底に沈んだ石ころのようにぎゅうとからだを縮こませて。 ふわりと、花の匂いが漂ってそれにつられて目を開けると、動物たちは消えていた。
どこをどうして迷い込んだのか、今となっては思い出せない。 百合子は広すぎる洋館のしんと静まった暗い廊下を一人で歩いていた。
Purple, yellow, red, and green♪
百合子は色とりどりの花を摘みながら歌う。 誰かに教えてもらった詩を口ずさみながら。
/-/-/-/-/-/
悪夢にうなされるようにして百合子は目覚めた。 ぐっしょりと寝汗をかき、身体が硬直して動かせない。 まだ身体は夢を見ている状態なのだ――。指を動かそうともぴくりとも動かず、息も浅く緩く繰り返す。 ただ、頭だけは冴え渡っていてとっさに身体が動かない事がもどかしい。 視界もまだぼんやりとしており、真っ暗な天井に差すわずかな月の光がちらちらと見えるだけだ。
働き過ぎて疲れた夜に同じようなことを体験した。 百合子は半ばあきらめて、先ほどの夢を思い出していた。 あれが夢の出来事なのか、それとも何かしら昔の記憶が混ざっているのか判断がつかなかった。 ただ夢の中で流れていたあの奇妙な歌には覚えがあった。
特有の残酷な詩が百合子は苦手だった。 あの詩を教えてくれたのは兄だっただろうか――。 それも思い出そうとするが、教えてくれた相手は顔に靄がかかっている。 それに、あの兄が外国の動揺を歌って聞かせてくれただろうか、と。
氷が溶けるようにゆっくりと百合子の身体もほぐれ、 凝り固まっていた体の節々がぐぐぐと引きつるように伸びた。
ぎしりと寝台の音をたてて起き上がり、カーテンの隙間から夜の庭園を望む。 月光を受けた噴水の水がきらきらと光っていた。
翌朝、先代の書斎に入り従業員名簿などを調べてみたが、そこに真島の名前はなかった。 共同経営者だったという男やその会社について調べてみても同じだった。
「この共同経営者という男に、遺産を全て騙し取られたと考えるのが妥当だと思いますが――」 「ではなぜ父は、この邸だけは手放すなという遺言を残したんだ?」 「それは――例えばこの邸が凄く気に入っていたとか……」
百合子の答えに現当主は嘲笑した。
「遺産は必ずある――。依頼を受けたからにはきちんと調査ぐらいはしてもらいたい」 「この邸に、動く壁だとか回る本棚だとかそういった仕掛けがあるとは思えないんですが」 「ふん、ならば遺産ではなく、父がこの邸に執着した理由を探ってもらいたいな」 「執着――」 「そう、父のこの邸に対する思いはそれこそ異常だった」 「それは例えば――どんな風にですか?」 「とにかく、人の手に渡らせるなだの朽ちるに任せろだの。 死に際はそんなことばかり言っていたな」 「それで、あなたは先代様が何か遺産を隠していると?」 「他に何がある?」
どうやら、現当主はその逆のことは考えもつかないようだった。 百合子には先代の執着はまるでこの邸を恐れているかのように感じた。 現当主の後ろに控えている秘書に目を向けて問う。
「どちらにしろ、この共同経営者とやらが何者かが気になりますわ」 「それは――私共も気になって何度も調査をしていたのですが、 先代様はその会社のことについては蔵元家の者は一切関わらせず社員の多くは共同経営者側の人間だったようです」 「その代表の方のお名前と会社名を教えていただいても?」
百合子はその名前を書き取り、使用人に案内され電話を借りた。 交換手に取次ぎ、斯波の入院している病院にかける。
「ああ、お姫さん。どうだ、親戚の家はゆっくりできてるか?」 「え、ええ。まあね、も、もちろんよ。 それよりも、ちょっと調べて欲しいことがあるんだけど――」
百合子は斯波に現状を悟られないように、詳細を説明した。
「その会社と代表なら知ってるぞ。――なるほどな、そういう事か」 「どういうこと?」 「その会社も代表もそっくり蔵元と同じような状況なんだよ」 「どこかの会社に買収されていた――ってこと?」 「そうだ。いくつもの会社を経由して元締めの組織を隠しているんだ。 よほど表に出たら危険な組織なんだろうな……」 「それでも、たどっていけばいずれは分かるのでしょう?」 「それは分かるが――ここまで���心深いんだちょっとやそっとじゃ尻尾を掴ませないだろうな。 まあ、調べてはみるが……」 「ええ、ありがとう」 「いいのか、真島はその中枢にいるんだ。 調べたら知りたくない事実を知らなくてはいけないかもしれない」 「……いいわ。毒を食らわば皿までねぶれ、よ!」 「お姫さん……」
勇ましすぎる百合子の言葉にうなだれるような斯波の声が聞こえた。
/-/-/-/-/-/
その日は午後からまた庭師の老人を訪ねて、階下に降りた。 虹を作る噴水の横を通り、動物の形に刈り込んだ植樹の通りをまっすぐに歩く。 その時に百合子は違和感を覚える。 しかし、それが何なのか分からないまま庭師の番小屋へ向かった。 小屋の周りには食用の小さな菜園があり、脇には大きな井戸がある。 菜園を見てそこに茄子や南瓜と言った野菜が植えられていて百合子は真島を思い出さずにはいられなかった。 番小屋の扉を叩いてみても反応がなく、どうやら庭師はどこかへ出かけているようだった。
少しだけ散歩をしようと花々の咲き誇る庭園を歩く。 その時、ふとある香りが漂った。 それは昔の記憶を呼び起こす鮮烈な香り――。
「真島?」
振り返り、背後を見る。 ひらひらと蝶蝶が舞い、午後の日差しに咲く花があるだけだった。 太陽の香り、花の香り――何とも形容しがたいあのあたたかく甘い香りに脳が揺さぶられる思いがした。
ふ、と記憶の一部分が蘇る。
目の前を歩く少年の姿。 百合子は暗い階段を少年の後をついて歩きながらそれでもどこからかあの花の匂いがした。 そして、それが少年から香っていることに気がついた。
「これは、記憶なのかしら――それとも私が勝手に作り上げた幻想?」
それでも確かに、あの少年は真島なのではないかと思えた。 庭を一周する。次第に日が傾き、木々の黒い影がぬるりと伸びる。 それ以上の収穫らしい収穫はなく、また遊歩道を通って邸へ向かう。
足元に、動物の影が落ちて一瞬ぎくりとする。 それは猫の形をしており、尻尾がくるりと巻き、あくびをするように身体を伸ばしている。
百合子はどうしてかゆっくりと、動物の影を作る植樹に近づく。 葉は刈りこまれて、綺麗に整えられている、誰かが毎日世話をしている証拠だった。 横には馬が、そしてその向かいにはウサギの植樹が並ぶ。
確かに子供の頃、この植樹を追ってどこかに迷い込んだはず……。
百合子は遊歩道を引き返して番小屋に向かっていた。
/-/-/-/-/-/-/
「もしもし。 そちらにお邪魔している野宮百合子嬢の助手の斯波というものだ。 彼女に話があるんだが」 「申し訳ございませんが、そのような方はおりません」 「何を馬鹿なことを言って――」 「お掛け間違いでしょう、それでは失礼致します」
日野は電話を切ると現当主の居る書斎へ向かった。 扉を叩く暇もなく、部屋へ入る。
「どうやら、あの女探偵が遺産の隠し部屋を見つけたようです」 「本当か?」 「はい、どうやら庭園の一角に入り口があったようで――」 「庭?……庭とは盲点だったな。ようし、行くぞ」 「はい」
喜び勇んで部屋を出る現当主の後に日野も続いた。
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
リンゴみたいにまあるくて、コップのように深くって、 王様の馬が集まっても持ち上げられないものってなあんだ?
庭園の一角にある東屋で人々が集い午後の茶会を開いている。 ハウスパーティと銘打たれた茶会に百合子はうんざりとしていた。 茶会に参加している他の子供達はやれ流行り着物だの新しいドレスだのと自慢ばかりしているし、 同じ年頃の男の子はどうしてか百合子に意地の悪い言動ばかりかませてくるしと、 百合子は兄と一緒に茶会を抜けだして庭園を散策する方が楽しかった。
着せられた新しい洋服が腹に苦しくて一刻も早く脱ぎ捨てたいと思う。 少し年上の女の子には「あまり似合ってないわね」とからかうように笑われたのも屈辱だった。 思い出しただけでも恥ずかしさに顔が赤らむ。 そして今もまた妙に作り上げた猫なで声で兄の名を呼んでいるのがそうだ。 馴れ馴れしく瑞人さんなどと呼び、大胆にもにっこりと微笑んで向こうに何々の花がありますのよとしなを作ってみせていた。 兄も悠然と微笑みそうですかなどと答えて、百合子にお前も一緒に行こうという。 おじゃま虫の百合子を例の少女はじとりと嫌な目で見た。
百合子はとっさに、私はもう少しこの花を見てます、ともごもごと答えてその場から逃げる。 兄の呼ぶ声が聞こえたが今更戻るのも癪だった。 当て所なく庭園を彷徨っていると、美しい蝶が一匹ひらりと目の前を舞う。 色は黒く、わずかに深い瑠璃色が模様で入っている美しい蝶だ。 それが風に乗ってふわりと飛ぶと、甘い花の香りがした。 花の蜜の香りに誘われるように、百合子もその蝶を追う。 どうぶつのかたちの植木を撫でて、遊歩道を外れる。
背の高い草木が生い茂る道を横切ると、一瞬、蝶を見失う。 どこへ行ったのかときょろきょろと視線を泳がせていると、がさりと草を踏む音がした。 百合子は人がいるとは思わず、ぎょっとしてそのまま固まる。どうしてか、息を殺してそっと見を屈めた。
百合子のいる場所の少し先に一人の少年が居た。 向こうは百合子に気が付かず、がさがさと背の高い草をかき分けてまたどこかへ消えてしまった。
蝶が消えた瞬間に、入れ替わるように少年が現れたので百合子は彼が蝶の化身のようにも思えた。 なにより、ちらと見えた少年の顔に表情はなかったがその横顔ははっと息を呑むほど美しかった。 そしてやはり、花の蜜のような甘い香りがあたりを漂う。
(一体何の花かしら……)
こんなにも芳しい香りを放つ花を百合子は知らなかった。 気がつけば先ほど少年が歩いていた道をたどるように百合子も歩いている。 そして開けた場所に出たと思えば、そこには大きな井戸があった。
(リンゴみたいにまあるくて、コップのように深くって、 王様の馬が集まっても持ち上げられないものってなあんだ?)
周りに先ほどの少年の気配はない。 井戸に近づくと先ほどの甘い香りとは打って変わって、苦いような青臭い匂いが一瞬ぷんと立ち上る。 百合子は後退って、再びきょろきょろと周囲を見渡した。 ふわふわと蝶が井戸の周りを舞う。
「この中?」
聞いてみても答えはないと分かっていても百合子は蝶に問いかけてみた。 すると蝶は、そうだ、と言う風に百合子の肩に止まる。 井戸の蓋をとってみる、想像以上に重くて百合子は新しい洋服の袖が汚れてしまったがすでに足元は泥や草花の種で汚れているので気にしない��とにした。 ささくれだった木の蓋の枠に気をつけながら、ずりずりとずらして半分井戸の入り口が開く。
「誰かいないの?」
暗闇を覗き込んで呼ぶ。 足元の石ころを拾って井戸に投げ入れるとすぐにからんころんと音がして、中に水がないこととそれほど深くないことがわかった。 そして奥のほうから苦い胸のただれるような匂いに混じって、ふわと甘い香りがした。 その香りで百合子は先程の少年がこの中に入っていったと確信する。 井戸の縁を見れば底に続く梯子がかかっていた。お転婆の百合子ですらも、一瞬は躊躇せざるを得ない闇と深み。
「深いと言ってもコップくらいだわ」
自分に言い聞かせるように言うと、汚れた袖をまくりあげて井戸の縁に足をかけた。
/-/-/-/-/-/-/-/-/
とっぷりと日が暮れて、ぱつぱつと遊歩道脇の街灯が明かりを灯す。 邸を振り返ってみれば、あの僅かばかりの住人が住む部屋の窓からも明かりが漏れている。 迷路のようになった庭園を早足で駆け抜けて、番小屋を目指す。 庭園の奥深くへと入ってしまうと、そこにはもう街灯の明かりは届かなかった。 雲の切れ間に挿し込む月の光だけを頼りに、百合子は進んだ。 あの日のような甘い香りも、青臭い苦い香りもしなかった。 ただ、夜露に濡れる草花の匂いだけ。
開けた場所には井戸が、そして今は番小屋が建っている。 百合子の背丈ほどもあると思った背の高い草は今はもう胸元ほどであの日のようには青々とはしていない。
井戸の蓋を軽々と持ち上げて中を覗く。 そこにひっそりと沈む闇と深みはあの時と同じだった――いや、むしろ以前よりももっと濃く底のない無限の穴に見えた。 ごくりと唾を飲み込み、あの日のように袖をまくって井戸の縁に手をかけた。
底まで降りて見上げると小さな丸い入口が見えた。 目を凝らしてみても真っ暗で、百合子は手探りで壁に触れてその凹凸からどうにか入り口を見つけた。 ようやく暗闇にもなれると薄っすらと周囲が見え始めた。 井戸の底から扉を開けて一旦中に入ってしまえば、そこは狭いしんとした廊下だった。 横にいくつか部屋の扉があるが、施錠されていて開かなかった。 ざらざらとした壁を手で伝いながら、かつこつと石畳の廊下を歩く。
一歩、一歩と歩みすすめるたびに霞となっていた記憶が実体を持ち始める。
長い廊下を一人で歩き、いつしか行き止まりまで来ていた。 そこから下は階段になっている――古くなった燭台は埃が被っている。 真っ暗なまま、階段を一段、また一段と降りる。
しばらくいくと古い扉が現れる。 取っ手に手を伸ばし、ぐいと押す。ぎしぎしと音がして緩く扉が動く。 もう一押し、百合子は力を込めてその扉を押すと、がりがりと擦れる音をさせながら扉は開いた。
中は広い工場のような作りになっており、銅色に鈍く光る天井まで届くほど巨大な太い筒が三本伸びている。 そしてそれに配管のようなものが無数に繋がり、壁や天井を這いまわる。 今はしんと静まったそこが、過去にはごうんごうんと音を立て青臭い匂いを発しながら阿片を製造していた部屋だということは百合子にも分かった。 暗闇に浮かぶ物言わぬ機材たちを見てぞくりと震える。 日本の政府は日本への阿片の密輸、密売を徹底的に取り締まる動きを見せている。 それなのに、東京にも近いこの土地にこのような製造工場があり、それこそ十数年前は確実に稼働していたのだ。
ぼんやりとした記憶の中で、あの夢の中の光景を思い出す。 あの時の少年は真島だったのだともう確信を持っていた。 庭師の老人の言葉が頭の中で反芻する。 百合子はその先に待ち構える漠然とした不安を振り払うように強く目を瞑って頭を振った。 その時、背後の扉が音を立てて開いた。 現れたのは蔵元の当主とその秘書、どうやら百合子の後を追ってきたらしい。
「なんだここは?」 「……おそらく、阿片の製造工場だと思います」 「あ、阿片?!」
思いがけぬ百合子の言葉に当主は素っ頓狂な声をあげた。 色々な情報が錯綜しているのか、そのまま呆然と立ち尽くす。 本当に一切知らされていなかったのだ。
日野と当主はひと通り部屋の中を歩き、今は動かぬその機械を見上げる。
「先代の遺言通りこれはこのまま――朽ちるに任せた方が」
百合子の言葉にはっと顔をあげて、青ざめた顔で頷く。
「そう、そうだな――」
当主言い終わるのよりも早く、日野が当主の後頭部を殴りつけた。 その手には黒光りする拳銃が握られており、無表情のままそれを百合子につきつける。 当主は呻き声を二、三あげてがくりと膝をつき、そのまま床に倒れこんだ。 痛みに悶える当主に日野がちらと目をやった隙に、百合子は床を蹴って配管の裏に回った。 威嚇するように一発、地面に向けて撃つ。 薄暗の闇にチカリと銃弾が床に撃ち込まれて爆ぜる花火が浮かぶ。
(ほ、本物――)
ひやりと冷や汗が首筋を伝う。 買ったばかりの皮のブーツ、ここに来るまでに泥や埃で汚れてしまったが踵が石畳のくぼみに足を取られ苦労した。 百合子はそれを脱ぎ、���管ごしに日野に投げつけた。 当たりはしないし、当たっても傷にもならないだろうが、日野は音のする方へ拳銃を向けてまた一発銃弾を放つ。 鈍い音にそれが配管に当たってしまったのだと日野も気がついたのだろう、舌打ちをする。 百合子は裸足のまま扉にむかい走る、足の裏がごつごつとしざらざらとした石の感覚に痛むが、弾を込める隙にどうにかその部屋から脱出出来た。 扉を乱暴に閉め、その背後から日野の怒鳴るような声があがる。 百合子は咄嗟に階段をかけ降りた。
螺旋状の階段に息の上がった百合子の吐息が反響する。 がつがつと追いかけてくる日野の足音が次第に迫っているのが聞こえた。 心臓は追い立てられる恐怖にどくどくと痛むほど打つ、壁を伝う手のひらも足も擦り傷だらけになりじくじくと痛んだ。
日野は恐らく、同じ事をしようと思っているのだろう。 当主を傀儡にして、もう一度阿片を製造し密売しようと。 そのためには表に出すための当主はまだ必要だ、ただ真実を知る百合子を始末すれば――と。
百合子はついに最後の扉にたどり着いた。 取っ手を回す余裕もなく身体をぶつけるようにして、扉を開ける。 転が��込むように部屋に入ると、そこは月の光が差し込む庭園だった。 今までの暗い部屋とは違いくっきりと薄闇に光が差し込んでいる、地下なのになぜと上をあおぎみると上はガラス張りになっていた。
「噴水?」
天井を色とりどりの魚が泳ぐ。 ぼうぼうと伸び放題の草花はもうここに何年も人の出入りがないことを教える。 整然としていた花の区画は曖昧になり、それでもちょろちょろと清水がどこから湧き出し床を濡らす。 管理する庭師を失った庭園でも花々は生命力たくましく生き続けていたのだ。 その花の蜜は人々の心を壊す毒だというのに、ただ生きるために繁殖し、床に壁に伝う様は神々しくもあった。
「さて……」
背後で日野の声がした。 百合子がゆっくりと振り向くと、ぐいと腕を掴まれた。 日野はただ拳銃を背中に突きつけて百合子の反応を見る。 陳腐な悪者にありがちな交換条件などは一切口にせず、このままここで百合子を殺してしまうつもりなのだと思った。
「私がここに居ることは助手が知っているわ、それに私の死体なんかがあがってみなさい。 どの新聞社だってほうっては置かないわよ」 「確かに、今この時期に死体があがれば――そうでしょう。 人の存在を確実に消すのは行方不明にしてしまうこと」
淡々と告げる言葉に百合子は震え上がる、殺されてたまるものかと百合子はぎりと奥歯を噛み締めるも固く掴まれた腕はびくともしない。 頭の中が恐怖でいっぱいになり、止めどなく溢れる思考を整理するまもなく、がちゃりと音がして撃鉄があがる。
その時ゆらりと目の前が揺れて、百合子は幻を見た。
「誰だ――」
二人の前に現れた人物を見て、日野がまっさきに声をあげた。 ぐいと背中を押す力が増すも、わずかに震え動揺しているのが分かる。
「お前が助手か? 一歩でも動いて見ろ、この女を撃つぞ」
そう言うと百合子の額に拳銃を突きつけた。
「取引のつもりか知りませんが、俺は助手なんかじゃありませんよ。 まあその女ともどもここで始末するつもりだから、手間が省けてちょうどいい」 「な、では、お前は――」
思わぬ第三者に日野の声が上ずった。 蔵元の者でもなく、探偵の助手ではない――そうなると必然的に残るのはこの阿片組織の人間だった。 日野ははあはあと息が上がり、現状を脱却する術を探す。
「わ、ま、まて! 私は蔵元の秘書で……」 「待つと思うのか?」
嘲笑するように言う。 日野は怒りにぶるぶると震え百合子を盾にしたまま、男に拳銃を向け直した。
その時、どんと大きな揺れが起こった。 足元から救われるような大きな揺れにふらつき、百合子は屈み込んだ。 瞬間に、だんと音がして日野の身体が弾け飛ぶ。 まるで揺れが起こることを知っていたのかのように男は冷静だった。 わずか数秒ほどで揺れは収まったが、建物の揺れは続いていた。
「な、地割れ……?」 「いいえ、仕掛けた爆薬が爆発したんです」
百合子の腕をそっと掴み起こす。
「私も殺すの?真島……」
百合子は真島の顔を見て問いかけた。
「いいえ、ああ言わないと貴方が危ないと思ったんです。 ――ここも危ないですよ」
この衝撃に天井の硝子も鉄骨も耐えられない事は一目瞭然で、しかも上にある噴水は裏手の湖から水を引いているのならばこの地下は全て水没してしまうだろう。 百合子は真島に言われるがまま手を引かれ、上へ上へと階段を登る。 階下で轟音が響く。 あの美しい庭園が水の底にたゆたい、魚たちが自由に泳ぎ回るさまを百合子は見たような気がした。
お前は、なぜここにいるの。 お前は、阿片組織の人間だったの。 お前は、今、どうしているの――。
百合子は聞きたい気持ちが溢れ、胸が詰まってしまった。 ただもくもくと階段を駆け上がる、時折ずずんと建物自体が沈みぱらぱらと砂が降ってきた。 ぜいぜいと息を繰り返し、苦しさで胸が痛む。 もう考える暇もなく、ひたすらに真島に手を引かれて階段を登っている。 聞きたいことをひとつひとつ足場に落としながら。
「そろそろ出ます」 「え?」
そう言うと、びゅうと風がふいた。はたはたと裾がはためき、夜風が肌に染みる。 苦しさに痛む胸を抑えつつあたりを見回すと、そこは城の一角にある塔だった。いつの間にか城を見下ろすほど高いところまで登っていたのだ。 ごうと瓦斯の燃える匂いがして、そちらをみると巨大な風船があった。 それは気球だろうということは知識としてだけ知っていた。 真島は網かごに乗り込み機材の調整をし、初めて見る気球に驚いている百合子に声をかける。
「乗ってください」 「こ、これに?」
じりじりと炎の調節をする真島。炎に照らされた横顔は何の表情もない、いや、むしろ――。
「真島、怒ってるの?」 「……久しぶりに再会して聞くのがそれですか。 ええ、まあ。怒ってます。いいですか、置いて行きますよ」 「ま、待って」
慌てて網かごに足をかけてのぼる。 すでに裸足だったし、裾はどろどろに汚れていたし、と思っても顔から火が出るほど恥ずかしい。 真島は百合子が乗ったのを確認すると、塔と気球をつなぎとめる太い縄をためらうことなく拳銃で撃ちぬいた。
真っ暗な闇空を、ゆっくりと気球が舞い上がる。 眼下には蔵元の邸が広がる。 爆発により地下が埋まり、そこに噴水の水が流れ込んだらしく大騒ぎになっていた。 暗闇にゆらゆらと松明の火のようなものが見えた。
「あ、当主が……」 「気絶していたので運び出しました。 あの辺りは前の災害で地盤が緩み始めていたので時間の問題だったんですが。 聡い割に傍迷惑な探偵が余計な事をしてくれたおかげでこの様です」 「な、私はただ単に依頼を――。 だって、私は……! わ、私……どうしても……お前に会いたかった」
別れを一方的に告げられて、ぽっかりと心に穴が空いてしまった。
「会って、それでどうするんですか?」 「私は、――莫迦みたいだけどお前を幸せにしたいと思ってた。 何も知らない子供だったから――そんな残酷なことを考えられたのね」
幸せであるということは絶対だと思っていた。 けれど、様々な事件にめぐり合う度に幸せとは何かと考えざるを得なかった。 実の妹を殺した姉、復讐に取り付かれた鬼、出生を呪う男――。 妬みや恨みと言った物を何一つ知らず、ぬくぬくと暮らし���きた百合子にとってそういった感情を理解するのは難しかった。
幸せの形は違うのだ。 ましてや真島は百合子を――野宮一家を心底憎んでおり、その人間から幸せにしたいなどと言われるなど屈辱以外のなにものでもあるまい。
「それでも私はお前が幸せでありますようにと願わずにはいられない」
真島が大好きだったから。 その言葉は決して口にできないし、言うつもりもない。 だから、百合子にはそう願うしか出来なかった。 人間とは不思議な力があって、何でも出来るような気がした。 強く願えば、そしてそれに怠らぬ努力をすれば、きっと何か奇跡のような事が起こせると信じていた。
「姫さま……」 「な、泣いてないわよ。これは――」
百合子は我慢しきれずに瞳に涙を浮かべていた。 対等な人間として話をしたかった。だから、決して泣くまいと思っていたのに。 自分の弱さに歯がゆさを感じてわざと乱暴に目元を拭う。
「――俺はね、絶対に幸せにはなれないんだと思っていました」
真島がぽつりと漏らす。 その顔には微笑みが浮かんでいて百合子は驚いた。 山の端が白み始め、夜明けが近づく。 新しい陽の光が山々に差し込み、闇空を照らす。
「俺は愚か者です。幸せとは去った後に光を放つのだと――ずっと後になって気がつきました。 姫さまと過ごした日々を失って初めてあの日々こそが幸せだったのだと知った。 俺も――あの日からずっと祈っています、姫さまが幸せであるようにと」 「――っ、わ、私は、――わたしは、幸せよ。……幸せ、だわ」
こらえ切れなくなり嗚咽をあげて泣く。 おそらく、これでもう本当に二度とは会えないだろうと言う気がしていた。 あの日、一方的に別れを告げた真島に百合子は答えられなかった。 真島のさようなら、と言う言葉に同じように返してしまったら別れを認めなくてはならないから。 これはきっとさようならと真島に言うための道のりだったのだ。 拒否し続けてきた別れを、今こそ受け止めるための長い道のり。 今の百合子ならこの別れに耐えられる、だからせめて少しでも笑って――。
「真島、さようなら」
/-/-/-/-/-/-/-/-/
「お姫さああん!」
自動車の窓から身を乗り出して斯波は叫んだ。 上空を漂う気球に百合子がいると信じて疑わない。
「や、や、山崎!もっと速度をあげろ!」 「しゃ、しゃちょう無理です!道も悪いですし何しろ向こうは空を飛んでいるわけで……」 「ええい、何を情けのない声を出してる!代われ莫迦者!! お姫さん今行くぞ!!!」
山崎を押しのけて運転席に座るも、ぐんとアクセルを踏み込んだ途端にハンドルが言うことを聞かなくなりきゅるきゅるとタイヤが空回りする。
「社長!気球が下降しています!」 「何?!ようし、あの方向は牧場だな、掴まれ!」
がたがたがたと揺れながら自動車は道を外れて牧場を爆走する。 途中に放牧された牛と正面衝突しそうになるが、ぐぐっとハンドルを切りぎりぎりの所でかわした。 しかし、何か石のようなものに乗りあげてバスンと嫌な音がして速度が急激に落ちる。
「社長!パンクしました!」 「くっ、仕方ない。山崎、そこの拳銃をよこせ!」 「どうするおつもりか聞いても?」 「最悪、あの気球を――撃ち落とす!」 「……」 「……冗談だ。相手はあの阿片王だぞ? 備えあって憂いはない」
そんなやり取りをしているうちに、気球が再び上昇する。
「ほら見ろ!いいから、拳銃を貸せと言っているんだ!」 「社長、向こうから人が歩いてきてますが……」 「何?!」
斯波が目を細めて牧場の丘陵を見据えると確かに人がこちらに向かって歩いてきてる。 遠目でもそれが百合子だと分かるやいなや、自動車に急ブレーキをかけた。
「お姫さん!無事か?!」 「斯波さん!どうしてここが?!」
斯波は百合子に駆け寄り躊躇なく抱きしめた。 顔を確かめるように少しだけ上体を離して、両手で頬を包み込み額の泥を拭う。 そして、今は小さい粒になった気球を見上げた。
「あの気球は真島か?」 「ええ」 「貴方は裸足じゃないか……!」 「これは、靴を日野という秘書に投げつけて……」 「ふ、服に血が……」 「これも――たぶん、日野という秘書の……」 「遺産探しだと思っていたのに、どんな危険な目にあったんだ!」 「話すと長くなるのだけど……」 「いや、良い!今はまだ聞きたくない、俺の心臓がもたんからな。 しかし、どうして真島と一緒に行かなかったんだ?」 「それも話すと長くなるのだけど……」 「いやいやいや。分かってるぞお姫さん」
斯波の表情がすっと引き締まり、真剣味を帯びる。 思わず百合子はどきりとしてその瞳を見つめた。
「社長~~~お忘れ物ですよ」 「山崎……なっ、それは持ってくるなと言っただろうが!!」
山崎が後から追いかけて持ってきたものは紙の束だった。 百合子はそれに見覚えがあった――原稿用紙だ。
「あの、これは?」
ミミズがのたうつような文字がいっぱいに書いてある。 紙であれども束になるほど多いので、腕にずっしりと重い。
「はあ、あの社長の所に編集長という方が来まして……」 「勝手に辞表を出すとは何事か、と怒っていたぞ。俺に辞表を押し返された。 ――それで、タイプライターで文字を打つならどこぞの自宅でもできようと……これを」 「そうだわ、私には借財返済という大きな目標があったわ……」
これからどうしようなどと途方に暮れる暇もない。 夜が明けて、日の出の眩しさに目を細める。 疲れきって身体は思いし、あちこちの擦り傷も痛む。 それでも心は晴れやかだった、束になった原稿を抱えて朝日に向かってぐっと拳を握る。
「私の夜明けはこれからよ!」 「お、お姫さん……」
斯波はその場にがくりと膝をついた。
数年も経てば、あの騒ぎもすっかりと忘れ去られていた。 ようやくタイピストから編集へと復帰して、探偵の依頼もまた少しづつではあるが受け始めていた。 大きな事件は少なく、失せ物探しや人探し素行調査と言った事件ばかりではあったが、それなりにこなしていた。
そして今日もまた鏡子婦人に呼び出されてホテルの一室に向かっている所だ。 他にも用事がある、それはようやく鏡子婦人の借財を返済するめどがついたことだった。 婦人はきっちりと貸し、そして百合子はそれをきっちりと返しきった。 その関係が、信頼で結ばれている証だった。 いつもはホテルのラウンジなのに、今日に限ってホテルに一室をとるということは恐らく借財の話などもあるのだろうと、百合子は感じながら案内された部屋を叩く。 すると、中から聞こえた声は鏡子婦人のものではなかった。
「あら、斯波さん早いのね」
扉を開けてみるとやはりソファに腰掛けていたのは斯波だった。 相変わらず派手な洋装を見事に着こなしている。 それにしても助手の斯波も呼び寄せているということは、なかなか難しい依頼なのだろうかと考えていると斯波がごほんと咳き込んだ。
「ああ、今日の依頼人は俺なんだ」 「……斯波さんが?」
ふと、最初の事件を思い出す。斯波が依頼を出すことなどあの事件以来初めてのことだ。
「どんな事件なの?」 「いや、事件じゃない。ちょっと人を探していましてね」
促されるまま百合子はソファに腰掛けた。 斯波の微笑んでいる目元に、僅かに不安を感じる。 入れたばかりの珈琲に口も付けず、少しだけ斯波は目を瞑った。 よほど難しい事件なのだと百合子は思い、居住まいを正して背を伸ばした。
「その人に、この手巾を返したいんだ」
胸元のポケットから取り出したのは一枚の真っ白な手巾だった。 とても大切な物を扱うように、そっと机に置く。
「手巾?」
それを手に取った瞬間に、百合子の時は止まった。 真っ白な手巾、それに見覚えがあった。 頭の芯の方から記憶が洪水のように溢れ、光のように周囲を照らす。 息が上がり、言葉が詰まる。
「これ、――私の、だわ」
そう、その手巾は百合子のものだった。 仏蘭西の特注品であまりにも白くて美しくて、一度も使ったことがなかった。 それと同時に、もう一つの記憶が呼び覚まされる。
「あ――」
その曖昧な記憶が逃げてしまわないように、目の前の斯波を見つめる。 確かに、昔、この手巾を一人の少年にあげたのだ。 その少年は泥にまみれて汚れていたことはかすかに記憶にあるが、顔には靄がかかり思い出せない。 浅く呼吸を繰り返す。
「あなた、なの?」
斯波がゆっくりと頷くと、百合子は初めてあった夜の斯波を思い出す。 妙に自分に執着する男――ただ単にそういう印象しかなかった。 斯波に気を許せるようになってきたのも、探偵業を初める前後ぐらいからでそれまではむしろ不審に思っていた。 百合子はどうして、と聞けなかった。きっと斯波はそういう男なのだから。
「ずっと貴方を愛していた」
その言葉は重く、百合子は不安になる。 自分はそれ程までに強く想われて良い人間なのだろうかと。 その気持ちを察知したのか、斯波は更に言う。
「貴方を知れば知る程にその思いは強くなった。 俺はもう貴方なしの人生など考えられない」 「私――もう歳だし、沢山子供生めないかもしれないわよ」 「ああ、俺は貴方がいればそれで十分だ」 「それに――たぶん、仕事も辞められないわ」 「分かってる」 「あの時からずっと私のことを想っていてくれたのね」 「そうだ」 「どうしてもっと早くに言わないの!!! 私だけが何も知らなくて、これじゃあただの莫迦みたいじゃない!!!」
混乱する百合子を斯波が優しく抱きしめて耳元で謝る。
「すまない――すまない」 「謝ってほしいんじゃないわ!いいえ、謝ったって許してやらないから!」 「そうか……」
きっと百合子は斯波を見上げて睨む。
「もっともっと強く抱いて、沢山愛してると言ってくれなきゃ許さないわ。 それも、ずっとずっとよ。貴方か私かのどちらかが老いて死ぬまでずっとよ」 「ああ、百合子さん愛してる」
百合子の言われる通りに強く抱きしめて搾り出すようにそう言うと、わなわなと震えている百合子の唇に���を押しあてて吸い上げた。
「ああ、貴方の唇はなんて甘いんだ――」 「も、もう嘘ばっかり」 「嘘なものか、もう一度確かめさせてくれ」
恥ずかしさに俯いた百合子の顎を持ち上げて更に深く口付ける。 息をつく暇もないほどの激しい口付けに百合子は腰が抜けてソファに崩れ落ちる。
「あ、あの斯波さ――私もう……」 「部屋をとって正解だったな」 「だ、だ、だめよ。あああ、貴方まさかそのつもりで?」 「なぜ駄目なんだ」 「私たちまだ結婚していないのに。 それなのに――こんなこんな昼間から……ふ、ふ、不埒だわ」 「結婚していて夜ならいいんだな?」 「そ、それは、ふ、夫婦の営みとして――」 「分かった、では今日は貴方の口を吸うだけで我慢しよう」
ソファに横たわる百合子に覆いかぶさって、再び口を吸う。 オーデコロンの香りがふわりと降り注ぎ、葉巻の苦い香りが鼻を突く。 心地の良い重みに、服を隔てた皮膚がじんわりと熱を帯びた。 どんどんと息が上がり、口付けだけで快感に震える身体に怖気付いた。
「は、は恥ずかしくて……心臓が壊れてしまうわ」 「あまり可愛いことを言ってくれるなよ――」
どくどくと脈打つ百合子の心臓の音を確かめるように胸に触れる。 首筋まで真っ赤になった百合子が可愛くてそこを吸うと、ふわりと甘い香りが立ち上る。 それを吸ってしまってはもう斯波には我慢など出来なくなっていた。
洋装のタイを緩めてシャツの襟元を開ける。 がしがしと頭をかき、おもむろに立ち上がって部屋のカーテンを閉めた。
「百合子さん」 「は、はいっ」
百合子が上ずった声で返事をする。
「――俺の妻になってくれるか」 「はい……」 「よし」 「だ、だめ――私、下着が……」 「下着?」 「あ、ああ、洗いふるしたやつで――」 「大丈夫だ、暗いからしっかりとは見えん。 ――他には?」 「え?」 「もう、心配事はないか」
色々と言いたいことはあるはずなのに、その場の雰囲気に押されてか、多少の興味もあってか、この血が沸くほどの緊張の心地よさのためか――。 百合子は何も無いとばかりに首を振った。 二人ともおかしな熱病に浮かされているのだ、正気であってはこんな事は決して出来ない。 百合子は自分にそう言い聞かせた。
/-/-/-/-/-/
「あらあら、うふふ……」
鏡子は扉の前で意味ありげに微笑を浮かべた。 どんな塩梅かと心配して見にきたものの、大きなお世話だったようだ。
「差し詰め、野宮百合子の事件帖、終幕といったところね」
ちょいちょいと癖のように項の髪を持ち上げると、足取り軽やかに廊下を後にした。
0 notes
Text
花で酒を作る話。
TRPG「トワイライトガンスモーク」の自PCの話。NNちゃんはTwitterのフォロワーさんのPC。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ヘマと言えばヘマだ。だけど、まあ、これくらいならよくあることと言えばその程度だろう、と吹き飛ばされそっくり中身の抜け落ちた腹の中とそれほど形の残っていない左腕、歩いているというより繋がっているというだけで無理やり支えに使われているような左足を見て思う。
ーーーーーーーーー
「酒だ。酒を探して欲しい」
どうにも、依存性の高い悪質な酒が出回っているらしい。その出処を調べてほしいという依頼が、ニルギリの営む探偵事務所に舞い込んできた。依頼人はあまりこのあたりには顔を出すことがないタイプの人種らしく、ここまでに至る道中の愚痴を会話の端々に滲ませていた。
幾度かの災難にあった事務所も無事もとの様相を取り戻し機嫌よく、はるばるやってきたお客人のために菓子とともに紅茶を振る舞う。今日はいつも不機嫌そうな顔をしている助手の姿がないが、いつものことといえばこれもまたそうだ。
依頼内容から察するに、お偉いさんのご子息ご令嬢あたりがどこかのパーティで紛れ込んだその代物を再び手に入れたい、とそういう事情だろう。
「よければこちらで現物を調達いたしましょうか?このあたりで直接取引をしようとなると不慣れな場合大変でしょう」
「…あまり上乗せするなよ」
訝しげに眉を寄せたが、金は大元から出てくるのだし、子供の娯楽程度に自分の身を危険に晒すほど彼は仕事熱心なわけではなかったのだろう。依頼は酒の入手とその販売元からの買い占め、もしくは継続購入の契約ということになった。
調査料としての前金と失敗した場合使わなかった分は返却する旨を告げ、成功した折の報酬などを書類にまとめ連絡先を交換し、依頼主に関する秘匿が多かったが(これもよくあることだ)聞き出せる限りの捜索物に関する情報を聞き出す。
自分は直接口にしたわけではないが、ときっちりとした仕立てのよいスーツにを身に着けた神経質そうな男は、どこか清涼感のあるひどく甘ったるいにおいが特徴的だったと続けた。
ーーーーーーー
とは言え、この怪我が直接依頼に関係があるかというとそこまで深い話ではなく、捜査の基本は聞き込みだとばかりに多少治安の悪い酒屋を梯子していたら、同じくこの酒にえらくご執心な方々の諍いに巻き込まれただけ、という顛末ではある。これで終わりとする気は、もちろん毛頭ないけれど。
そろそろ、夜の帳が再び幕を開けようとする時刻に近い。
依頼が来るまでその存在を耳にしたことはなかったが、下層では随分出回っている酒のようだ。依存性が高いというのも聞いた以上のもので、関連するいざこざがちらほらと起き始めているのだという。
泥やらで薄汚れ、何に使われていたのかわからない機材や、砕けた瓶、空き缶が転がるごみ溜のような路地の壁をさらに赤茶色く汚しながら進む。
一度死んだ身。何の因果がゾンビのごとく動き回っているこの身体が、このくらいでどうこうなるとも思えないが、疲れるものは疲れるし動けないものは動けない。今度来る時は助手に護衛に来てもらうことにしよう、と力の抜けた足を休ませるようにずるりとその場に崩れるようにしゃがみこんだ。
ふと、閉じかけた横目が、褪せた路地裏には場違いに目の冴えるような白を見た。
ーーーーーーーーーーーーー
あの調子の良い探偵が姿を見せなくなって、数日。
あまり出入りすることのない酒屋で一悶着を起こしたようだ、と風のうわさを聞いて周辺の探索をはじめてしばらく。いよいよどこぞで野垂れ死んだか、とも淡く期待をしてはみるもののそれほど簡単にこの��を去ってくれるのならば今までの苦労などは要らない。
せめて少しでも弱っていれば最後のひと撃ちを、とすっかり金属に改められたその手に込めた銃弾をNNは確認する。
「遅かったじゃないか。また迷子?」
ふいに、うしろから声がかかる。
多少なりとも弱っているかと思えば、調子の変わらない軽い口調に嫌気が差して銃口をつきけるようにして振り向けば、話しぶりほど万全とは言えない様相。
「もう少し傷んでいるかと思えば、早く来すぎたようですね」
引きずり気味の左足と右腕は応急処置とも言えない程度に撒かれた包帯の塊で、いつも来ている無駄に身の丈丁度のスーツの上衣の代わりにいささか大きい白いシャツ。
「いやあちょっと、ヘマやっちゃったよー。やっぱり君がいてくれないと駄目だねえ」
などと真面目に思っているのかいないのか軽口を叩いたかと思えば、ああ、そうだ見てみて!と無意味に高いテンションで着ているシャツの裾をめくりあげる。
色鮮やかな、黄色や青や白。
それから細かい明度彩度の違う朱。
花だ。
普通ならそんなところにあろうはずもない、花。
薄汚れた泥のような暗い赤一色に塗りつぶされるのを未だ逃れ、摘み取られたばかりの艶やかさをその腹の中で咲き誇っている。
なにをどうしてそんなことに、と聞こうという気も起きないその前に、
「助けてくれた子供がくれたんだ」
と自慢げに声を弾ませている。
何がそんなに楽しいのか。
眼の前にいる探偵は、好物が荒らされたときくらいにしかその表情を曇らせない。
ーーーーーーーーーーーーーー
少女だ。
一輪の、白い百合のような花を持った少女がたっている。
色の落ちた髪と、多少煤けたワンピースの上に真っ白いエプロンが、場の彩度を上げていた。
「けが、してるの?」
おそるおそるかかる声。
大丈夫だからと、返答しようにも思いの外身体のダメージは大きいようで、掠れた言葉はそちらまでは届かなかった様子。
探るように少しづつ近づいてきた彼女は、側にしゃがみ込み悲しそうな目で
「おなかのなかがなくて、かわいそう」
そっと、触れようと手を伸ばす。
汚れるからという制しも効かず、持っていた花をそっと空いた腹に押し込める。
それから、なにか良いことを思いついたというように明るく顔を上げ
「まってて!」
と、そのまま駆け出していった少女はどこからか抱えるその顔も見えない程、両手いっぱいに色とりどりの花を持って帰ってきた。
「きれいでしょう!おとうさん、おはなやさんなんだ」
ばらばらと、手にしていた花を壁に背を預けてしゃがんでいたニルギリの周囲に落とし、ばっと側にしゃがみ込むとどれがいいかと選んでは、空っぽの腹の中に押し入れていく。清々しさも感じる混じり合った花の匂いが腹にたまる。
「ちょ、っとまって。おはなやさん?商品じゃないの」
「うん!おはなやさん!だから、いっぱいあるからだいじょうぶだよ?」
にこやかな答えに、それじゃあやっぱり売り物じゃないかと苦笑する。
この様子じゃ勝手に持ち出しているのだろう。店の方も大変だろうと止めようと口を開くも、あまりに懸命にそのちいさい手で花を一つづつ詰めているものだから。
僅かに取り残された臓器と、どろりと赤黒い肉壁を晒すばかりの空洞となった腹の中に、季節感など無視した鮮やかな花が次々と咲いていく。無理に差し込まれる尖った茎の先端が、内側の柔らかな肉をざくりとえぐっていく感覚に思わずそっと息を吐く。
満足気に花を手に取る様子を、微笑ましげにみつめ親御さんには悪いけど後で花代をまとめて届けるとしようと目を閉じた。
ーーーーーーーーーーーーーーー
腹に花を詰めて帰ったかと思えば、捜し物はただの酒。
取り出した花は、わざわざ花瓶をだしてきて事務所に飾るという神経。どういう構造なのかは知らないが、数日すると欠けていた身体もすっかり元のように再生していた。
受けた依頼を遂行するためにもと護衛を頼まれ、無頼の者を吹き飛ばす程度のことならあわよくば巻き添えにできないかという目論見とともに、適当に同行することとした。
売られていたらしい、という僅かな情報を頼りに来る日も星の数ほどある寂れた酒屋、屋台を飲み歩く。売られた酒は店に個人が持ち込んだ物で、もとより数のあるものではないということはわかってきた。たいていの店の主がそもそものその酒の依存に浸っている状態で、必要以上の情報は教えてくれはしない。一度来た店にまた来るとも限らないらしい。
やって来るのは荒野の商人かというほどにぐるりと布で顔を隠した、おそらく男、だそうだ。
これからどうするというのか。探偵を見やればそこに姿はなく。
屋台のような移動式の花屋の少女に声をかけ、なにやら店主に気前よく金を渡そうとしては遠慮されを繰り返し、最終的に金を押し付けた代わりに花の束を受け取っていた。
「なにやってんですか」
「お礼だよお礼。助けてもらった恩は返さなくっちゃ」
大きく手を振る少女と頭を下げる店主に、笑顔で手を振り返している。
状況が少し変わったのは、その数日後のこと。
と言っても事件に関してではなく、探偵の状況が、だが。
はじめはなにやら腹の調子がおかしい、というようなことを言っていた。
寝ていると、かさりと何かがこすれるような音がして目が覚める。その音がどうやら腹の中から聞こえてくるようだとのたまっていた。
「どうせまた変なものでも食べたんでしょう」
「んー。あれ、そういや最近何も食べてない」
言ったかと思えば、ばたりとその場に倒れた。
健康で文化的な最低限度の生活からも見放されているような環境とは言え、医者、らしきことを生業としている者もいる。NNの師匠もそうではあるが、この探偵を関わらせるのも申し訳ないと近場のどちらかと言うとなにやら研究の片手間に人を看ているらしい愛想のない医者のもとに放りこんだ。ついに年貢の納め時かとも思ったけれど、こんなわけの分からないまま先立たれるのもそれはそれで腹が立つ。
医療に関係があるとも思えない機材が乱立し、元の部屋の広さはうかがい知れなくなっている室内。
気だるげな目線に金ならそいつが払うでしょう、と寝台の上でただ寝ているようにしか見えない探偵を示せば、億劫そうに触診をはじめる。腹の調子が悪いと言っていたと告げれば、その手は腹部に伸びる。
ぐちゃり、とおよそ人の腹を押してでる音ではない耳障りな水音。
「おなかの中、腐ってしまってると思いますよ」
ため息混じりの診断結果。
動く死体なんてそんなものかと思っていた。
ーーーーーーーーーーーーー
さくりと刃が入れば、血玉が腹部の曲面に沿って流れていく。
やたらと広いベットの上にひかれた真新しいシーツが、赤く染まる。
割られた腹から漏れ出すのは、予想した強い鉄と酸いた匂いの代わりにむせ返るような甘い、香り。
どろりと粘性の強い煮詰めたかのような血液がゆっくりとこぼれ落ちていくのと同時にとろけたような腐肉と、どこか清涼感の残る香りが室内に満ちる。
「開けてみないとわかりませんが、すっかり取り替えてしまったほうがいいでしょう。一度死んだ身体ならそれで問題無いと思いますが」
ようやっと目が覚めた探偵が医者から、腹の中が腐っているようだと診断結果を告げられ、一も二もなくじゃあ頼むよ!と安く請け負ってから数分。
麻酔もなく自分の身体が裂かれていくのを、何が面白いのか興味深げに眺めている。
嫌な予感しかしないと早々に場を離れようと思ったが、どうにもタイミングを失ってしまい、見るともなしにそんな状況の中にいる。
裂かれた腹の隙間から溢れ出た臓腑が、みずみずしく艶めく。
夥しい血液と共に引き出された臓腑には、うす茶色い紐状のものが絡みついている。
植物の根、のようにみえる。およそ人間の内部にはあろうはずのないものだ。
「根、ですね」
「根、か~」
淡々とした医者の声と能天気な探偵の声。
やはりそうなのかという納得、とそんな反応でいいのかという疑問。
引っかかりがあるのか、医者が腸を引く手に力を込めて手繰り寄せればがさり、がさりと音を立てしっかりと奥深くまで張った根が塊となって姿を見せる。
根だけではない。十字に開けた腹の内側一面に、細長い葉が体液に湿ってへばりついている。端から引っ掛ければ剥がれるものもあるが、体内と同化してしまったものもあり周囲の肉壁ごとを抉らなければ全ては掻き出せないそうだ。
植物の張り付かれた部分は腐敗が早いらしく、清々しい植物の香と甘ったるい醸造された肉の匂いが混じり合う。
引き出されていく腸とかき出される肉と葉の山のなかに、白い物が見え始める。
一枚一枚、花弁の大きい百合のような白い花。
そっともぎ取られた花びらが体液を弾き、血溜まりが滴っている。
腸壁のいたるところに褪せて枯れた花が、びったりと濡れて張り付いている。
甘さの中に清々しさの残る花の香りが溢れる。
「ああ、あの花か」
とばらまかれた自分の腸を手遊びに、なにとはなしに作業を見ていた探偵が目を留めつぶ���く。
熟れた果肉のように赤く光る表面に立てられた爪が、抵抗もなくその腑を割き、部屋を満たす甘い香りが一層強くなり、軽いめまいを覚える。
「この花は元々生き物の死骸に根付く種類なのですが、花粉の酵母にはこういう効果もあったのですね」
医者は花を一つ一つ採取するように丁寧にもぎ取りながら、独り言のようにぽつりぽつりと解説している。
マスクで口元を覆っているからなのか、この嫌に甘い匂いにあてられている様子はない。
その言葉に何かに気づいたように、ぐちゃぐちゃと何が楽しいのか自分の腸を潰して遊んでい���どろどろに汚れた指をそのまま口に運ぶ。
「なるほど」
と、勝手に何かを納得した顔で頷いているのを、それ以上観るに耐えずに目をそむけるようにして部屋を後にした。
ーーーーーーーーーーーーーー
「ニルギリ探偵事務所です。ご依頼の品を入手することができましたのでご連絡いたしました。
申し訳ないのですが、販売元の連絡先はお教えすることはできないのですが、こちらを通しての販売は受け付けていただけるそうです。ええ」
ですので、成功報酬は三分の二で構いません、と続ければ例の神経質そうな依頼人が訝しげに眉を寄せているのだろうと想像して、白い花の刺さった酒瓶を撫でながら笑みをもらす。
0 notes
Text
手術幻情(98枚)
杏 土呂夢(あん どろむ) 夜明け前の湖周道路をぶっ飛ばすのは、人影はもとより、車影もなくて、気ままで、爽快である。 このあたりまで来ると、道は湖岸に沿って、ゆるく蛇行して進んで行くのだが、湖の所々に突き出ている丘陵に差し掛かると、雑木林の中を急なS字のカーブの連続を登って、峠の頂上に着くこととなる。 見透の全然効かない急坂を右に切り、左に切って、すぐにまた右に切ろうとした峠の頂上付近で、路肩に立っている凸面鏡に、対向車の車影が見えたと思った刹那、道路の左側の茂みの中から、狐か鼬(いたち)かが、地面にへばりつくようにして、這うように、男の車の左前に飛び込んで来た。男は咄嗟に、それを避けようと、ハンドルを右に切ったのだが、車はセンターラインを割ってしまい、峠の頂の急カーブを曲がって、いま、姿を現したばかりの対向車に、急ブレーキを踏み込んだものの、スピードを出し過ぎていたためか、男の車はスリップし、右のライトのあたりを、派手にぶつけてしまった。ポーンという、衝突の凄まじい音と共に、ライトのガラスが砕け散った。 大き目の、半透明の、黒色のサングラスをかけた背の高い女が、現われ、男の運転席を覗き込む。「どうしますか?} 男は、女が事故処理の仕方について、訊いているのだろうと思う。 「電話は?」女が訊く。男は、女が、警察か保険会社への、電話連絡のことを言っているのだろうと思う。 男は、ギアをバックに入れ、緩くアクセルを踏んでみる。女の車に喰らい付いた男の車は、感じ悪くスリップをし続けるだけで、離れようとしない。 大き目の、半透明の、黒色のサングラスをかけた背の高い女が、現われ、男の運転席を覗き込む。「どうしますか?」 男は、女が事故処理の仕方について、訊いているのだろうと思う。 「電話は?」女が訊く。男は、女が、警察か保険会社への、電話連絡のことを言っているのだろうと思う。 男は、ギアをバックに入れ、緩くアクセルを踏んでみる。女の車に喰らい付いた男の車は、感じ悪くスリップをし続けるだけで、離れようとしない。 「連絡は?」女が訊く。 「じゃ、免許証…」と女が言う。 男は、免許証を、女に渡す。名前か何かでもをメモるのだろうと思っていると、女は男の免許証を見もしないで、肩に引っ掛けていた、黒い、細い、長い革紐のついた小っちゃなレザーのバッグの中に、そのまま仕舞い込んでしまった。変わったことをする女(ひと)だな、と男は思った。しかし、男は、ひと言もしゃべろうとしなかった。 何回目かに、男が、思いっきし強くアクセルを踏み込むと、ひと揺れした後、やっと、二台の車は離れた。 男は工具の鉄棒で、女の車のフロント右の車輪のあたりを二、三度、力任せに捏ね上げた。走行は充分可能だろう。車はドイツ車で、ダークグリーンのロードスターだった。 女は、小さく一つうなずくと、「急いでいるので」と言って、急発進し、タイヤを軋らせ、去って行ってしまった。 峠を下り始めると、男は、ぶつけたあたりのフロント右に、かすかな異常を感じた。そこで、車を止め、女の車にしたと同じように、鉄棒をかまして、二、三度乱暴に捏ね上げた。そして、この時初めて、男の頭に、想いが一つよぎった。美女だ…揺るぎない…正真正銘の…なんという、…。男は、この時まで、狐か鼬(いたち)かの飛び出しと、回避、衝突のショックで脳味噌が凍て付いてしまい、きっと、失語症みたいになっていたに違いない。 「坊ちゃん、あなた免許証がどのようなものか、分っているんでしょうね」〈センセイ〉が、電話で、言っている。「信じられないようなヘマですよ。…ヘタすると、あなた、一巻の終わりにすらなりかねない…相手の…つまり、手合い次第では…。どこか、ヤバイところへでも持って行かれてごらんなさい。…どうするつもりなんですかねェ、今後?…」 男も、内心不安がないでもない。時間が経つにしたがって、むしろその念は増大して来ているみたいだ。しかし、男は言っている。「あの女(ひと)は、そんな女(ひと)じゃない。…あなたは悪く解釈し過ぎている…」 「解釈も何もありませんよ…わたしは一般的のことを、客観的に、ただ、亡き父君の顧問弁護士としてですな、言っているまでですから…当然じゃありませんか…なら、訊きますが、相手の名前は?相手の電話番号は?…尋ねていますか?…あなたも相手の免許証を預かりましたか?…それごらんなさい…全然、何もしていない…ただ一方的に、されるがまま、なされるがまま、つまり、奪われるがまま、といった体(てい)…どうです、図星でしょう…腑抜け同然じゃありませんか、極めて失礼な言い方を敢てさしていただければですよ…」 「ま、結果的には、そのようにみられても、仕方ない節(ふし)が…。しかし、本当は、それとは、ちょっと違う。まあ、全然違う。しかし、他人(ひと)に言っても仕方ない。理解されないだろう。うまく、口にはできないような、デリケイトな問題がね。つまり、手っ取り早く言えば、感情、みたいなもの。物事には、法律以上があり、法律的があり、法律以下がある。あの女(ひと)のことは、超法律、超日常、超打算、つまり、特別、不合理、不公平、即ち、一切、全て、なのだ。おれは、信頼している。また、目下、そうせざるを得ない。そうしないと、すべてが倒壊する可能性が出てくる。とはいえ、何か法律的の問題でもが起これば、仕方ない、あなたにお願いせざるを得ないでしょう。だが、万が一にも、そのようなことは起こらないし、…あの方はそんな方じゃないからだ。それに、もし、そのようなことが起これば、あなたの勘の方が、わたしの勘より、優(まさ)っていたというようなことになりかねない…そんなことはあ��得ないし、また、あってはならない…それに、金など…慰謝料か…もし求められるのなら、即座に、いくらでも払ってしまったらいい。躊躇わず、払ってください。おれは、我慢するよ。任せるから、よろしく…」 「そんな、気違いじみた、無茶苦茶な、ほんとに、もし父君(ちちぎみ)がいらしたら、もし、父君がご存命なら、あなたなんぞ、鐚一文…お金お金といっても、父君のご遺産なんですからね、父君の残された。…わたしは、あなたの父君に管理を頼まれ、そのお約束を誓った者として、法律家としてですな…ですから、坊ちゃん、健全なる、…ご遺産だけで、その配当と金利だけで、何もしなくても、ただ健全に、配当金とお利息だけで、人並みのリッチな生活が…。もし、元金さえ目減りさせなければ、ですよ、ずっとずっと、保障できるのですから。…ほんの少しでも、元金に手を付けちゃいけません。そんなことをすれば、立ちどころに、生活に困り、仕事につかなければならないような羽目に、働かなければ生きていけないような状態に…」 「仕事か、おれは仕事なんぞ望んでおらん。仕事は人間よりもコンピューター、つまり、ロボットか、ロボットに、より、向いている、ふさわしい…」 「そんな、もう…わたしはそんなことを言ってるのじゃありません…わたしは、坊ちゃん…」 「あなた?あなたですか?」電話に女の声がしている。T道路のB大橋近くの喫茶店にいるから来ないかと女は言っている。「五分で来られるでしょうね?」 「それは、無理でしょう…」 「なら、もう居ないかもしれないわよ…」 「いくらなんでも、それは無理でしょう」 「ぶっ飛ばしなさい、ぶっ飛ばしなさい、もし、あたしに逢いたいのなら」 『これは、困ったことだ』と男は思う。しかし、男は、諦めようなどとは毛頭思っていないみたいだ。 アクセルを踏み込む度に、タイヤがスリップして軋む。男は、アクセルペダルと、そのペダルを支えている細くて丸い鉄棒との溶接部分でもがヘシ折れはしないかと危ぶまれてくる程度にまで、アクセルを、極度に、乱暴に、踏み込む。そして、そのあげくは、急ブレーキー、そしてまた、急加速…男は運転席にあって、まるで、馬の曲乗りをでもしているみたいな体(てい)だ。 喫茶店に着くと、ボーイに名前を訊かれる。「そう」と男が言うと、三階の専用の個室に案内された。男の期待は裏切られ、女は独りではなく、いま一人の男と一緒にいた。「それでは…」とか「それでは、また、お電話を…」とか、いま一人の男が言っている。部屋には、黒い革張りの長椅子や肘掛け椅子とテーブルや数多くの観葉植物が置かれている。鉢に立っている名札には、大鉢で、パキラ、アラレヤ、ドラセナ・コンシンナ、それに、中鉢では、クロトン、カラテア、ストロマンテとなっている。壁には数枚額が掛かっている。ヒンドゥー教の石窟寺院やそこにある神像の写真みたいだ。『トリムールティー像 エレファンタ石窟寺院奧殿本尊』『パールバティー女神 エレファンタ石窟寺院奧殿前室浮彫』『宝輪 コナラクのスールヤ祠堂前殿基部の浮彫』『カンダリヤー・マハーデーヴァ寺院』… 「免許証を手掛かりに…」と女は言っている。そしてしばらくの間、小さく柔らかく声を立てて笑っている。なぜそう女が、にこにこ、にこやいでいるのか、男には理解できない。しかし、上機嫌の女を、輝くばかりの美女を、ほかに誰も居ない部屋の中で見つめることができるということは、激しい苦しみであると同時に、この上もない心地よさでもあった。 「…社の者に、あなたのことを、ちょっと、調べさせました」女は、また、小さく笑った。「変わっていますのねえ…珍しい方ですわねえ…」女が部下の者に調査させた、男に関するメモの一節は、大略、以下のごとくだったらしい。 「独身…無職…《一体、男は、時間をどう過ごしているのか。退屈じゃないのか。まるで仕事無しで…どんな金持ちでも、四六時中、働く。きっと働かないことに極度の不安を感じるからなのだろう。働かないことに不安を感じない者など一人もいない。働かない者は尋常ではなく、異常であり…そうではないのか…》…資産**億、主として有価証券、それに山林《すべて土地成金の一人息子として相続したもの》…教育は一応一流《一応、というのは、実のところは、分らない。大学をただ卒業したと言っても、ある種の面においては、特に、品性の点においては、極めて劣等、かつ異常なものが皆無ではない》…目下のところ、艶聞、醜聞、一切なし。かつてのことは不明。《これは調査機関の探偵たちのいうことだから百パーセントは信用できない。ヒドイ場合には、直接、当の本人からコメントをもらってデタラメを作文する探偵がいるくらいだからだ》」女の部下が、女にした報告は、大略、以上の様なものだったらしい。 ここで女の顔から微笑みが消え、女は言った。「免許証もっと大切にしなければ…わたしのクルマのこと、もういいから。…忙しいので、それでは、これで、ね」 女は、免許証を男に返した。白くきらめく長い女の指が…爪のマニキュアの銀色が… エンドレスに流れ続けるCDからは、『悲惨な戦争』が聞こえている。女性の声が、「No,my love. No.」と歌っている。CDを切ると、自動的にラジオに変わり、株式市況で「イタガラ、****円、**円安…」と言った具合で、「総じて売り一色、小甘い程度ではない」らしい。いま、岸辺はハーバーらしく、遠目にはクルーザー級のヨットやモーターボートが湾内をびっしり埋め尽くしているのが眺められ、こちらへと登ってくる陸(おか)の上にも、台車の上に乗せられた流線型の船体が、次から次から、現れてきては、後へと流れ去る。リゾート地帯特有の傾向で、往き交うクルマは外車の比率が異常に高い。 「あなた大変な女にぶっかっていますよ」〈センセイ〉が電話で言っている。「もうこれは非常なことです」一体、何のことだか男には、さっぱり、分らない。「あの女のこと調べてみましたが、かなり手強い、と言うか、もうほとんど完全に強力な…パワフルな…トップレディって言うのか、なんて言うのか、医者のくせに医者にならず、つまり大学は医者の大学、医学部か、医学部を、それも、外科、外科…信じられない…出ておきながら、医者にならず、…不自由ならしい、医者は自由業だけれど、不自由ならしい。つまり、時間を縛られ、また、病人相手にあまりにも責任が重過ぎる、と女は考えているらしい。つまり、裏を返せば、かなりズボラな性格の女と言える…もちろん、よく言えば、自由な女、だ。…社会性のない、自己中心的な…そこで何か、経営、つまり商売、輸入会社か、絵画関係の、美術…しかも、その一方で、趣味で、どこかの大学で講師をやり、インド美術…なかでも、特に、ヒンズー教寺院の石窟レリーフか…何かに特に興味があるらしい。要するに、それを大学では講じているらしい。しかも一番いけないのが、大変な、異常なまでの、美女ときている。Face & Body において、極度に…もう一目見ただけで、ただでは捨てて置けない衝動に、どうかしなければいけないという運命みたいなものの暗示に…何がどうなろうとも、もう知らない、つまり命懸けででも…気狂い…この女のために人生を狂わされた男は大学生時代から、何百人と束になって、数知れないらしい…勿論、狂う方が勝手に独りで狂っているだけなのだから、一切の責任は男達にあり、極めて迷惑なのは女の方に決まっているのだろうけれど…彼女は人目の多いところには近寄らないらしい。それは恐ろしい電気メスのような我を忘れた男達の視線に次から次と連続的に身をさいなまれているようなものだからであるらしい。アイクチのような視線が、おびただしく、刹那刹那、すれ違いざま、路上で犯しにくるのだ。美女の憂鬱どころの騒ぎじゃない。美女の悲劇だ。からだが目立ち、自然と挑発的な上に、顔がまた非常に悩ましいまでに艶やかな…ということは、心もまた、あるいは、大変な、好色女で…」 「もう結構、センセイ、わかりました。しかし、調査と言っても、それらは、ブリキみたいに平板な、誤った伝聞記事…調査会社社員の、一定時間内における一定の、つまりノルマのために、あえて作られた単調無能なブリキ作文にしかすぎない。ホラだ、ズボラなダボラだ。それにひきかえ、おれはすでに彼女と衝突しており、…事故か…衝突を通じて、彼女がどんな脳味噌コンピューターをしているのか、つまり血液コンピューターだな…感じ取っているはずだし…大切なのは、目の色、だ…彼女の目の色の意味…しかしそんなことは、いくら考えたとて分るものではない…われわれは何も理解できない。訳もなく感じ、ただ漂うだけだ…それに、もうすべては落着した。事故は無かったのだ。女神は去られたのだ。一切は、束の間の、幻影か、まぼろしか…ただ、心には、おびただしい、飢渇だけが…心臓の締め付けられるような痛みだけが…悲しみの念、だけが…どうにもならない、莫大な悲嘆が…」 「坊ちゃん、そのようなことは、そのような生々しいことは、心の奥に押し込めて、蓋をして…押さえつけられまして、抑圧に抑圧を重ね��決して口外など…それにしても、もしそれが事実なら…儲かると言うか、損せずに済むと言うか…慰謝料、修理費の点、よかった、よかった…何もかも、失われること無く、無傷でよかった。無事円満解決。これほどよいことが…」 暗闇に、ヘッドライトの光芒の中に、白く、雪が吹きつける。CDは『沈黙の音』『花はどこへ行ったの』『風に吹かれて』と続き『トルコ風ブルーロンド』『テイク・ファイブ』タンゴで『夜のタンゴ』『オレ・グァパ』ときて、ガーシュインで『ラプソディ・イン・ブルー』『パリのアメリカ人』…時は、エンドレスにCDから流れる音楽によって刻まれているみたいだ。時刻は、すでに、完全に真夜中を過ぎ、おそらく、丑の刻、丑三つ時頃、だろう。 湖周道路には、この辺りまで来れば、すでに人家は無く、一切の建物も無く、車影も無く、いま、闇と雪と孤独だけが…雪はフロントグラスに、暗闇の奥から、次から次から、盲滅法に、永遠の狂気みたいに、ぶち当たって来る。左手は、闇の奥に、湖面だろう。右手は、同じく、闇の奥で、葦の生い茂る、湿地、沼、荒れ地…ときに河口、ときに水門…湖周道路は、いま、丑の刻、人気(ひとけ)も無く、光も無く、無際限の闇と、無際限の孤独と…スピーカーはガンガンと耳をつんざくばかりの音を繰り返し…フロントグラスには、群れなし狂う雪片が…車は闇に突き刺さり… 路面は、いま、ヘッドライトに照らされて、艶やかに黒い。それは、いくらぶっ飛ばしても終わりが来ない。夜の、闇の中の、黒く濡れた、アスファルトの、直線の、起伏もない…車の左右では、事物が、猛烈なスピードで、きっと、飛び去っていっているのだろう。それは、左手は、湖面であり、右手は、荒地、葦原、沼地…だろう。 車に、遠心力が…カーブだ…左側にふくれようとする…厭な気分だ。ライトに照らし出された前景は、物凄いスピードで左に流れて行く。一体何が見えているのか定かでない。きっと、藪、雑木林、下生えの茂み、といった類(たぐい)なのだろう。道は昇っている。カーブは連続的なS字だ。湖面に、またも、岬でもが突出しているのだろうか。きっと、地形は、そんな具合なのだろう。やがて路は下りに、平地の直線となり、またも、沼、荒地、葦原(よしはら、あしはら?悪し原?)と続くのだろうか、どうなのか… 仕方なく、脇道に入り、男は車を止める。ドアを開くと、冷気が薄着の身にしみる。雪は、後から後から舞い落ちてくる。雪片は、ここでは大きく見え、牡丹雪だろう、雪はすぐに溶け、髪の毛を濡らす。巨大な、無限と連結した闇の中、ただ、ヘッドライトの光の筒の中だけに、へら雪が後から後から舞い落ちる。 男は、やがて、いま立っている前方は湖面だろう、という朧な予見みたいなものを心にもって、無謀に、前へ、暗闇の中へと進んで行く。すると、背筋がぞっとする。どうやら、一つならず、二つならず、古びた墓石が…よく見ると、なんと、墓石だらけである。ここはもしかすれば、すでに捨てられてしまった、昔の墓場みたいなところなのか…よりによって、また。…信じられないことだ。男は、今度は、反対側を…まさか、と願いつつ、恐る恐る闇の中を覗いてみる。しかし、やはりこちらも…しかも、こちら側は、湖面側よりも、もっとおびただしい数の、ほとんど闇の奥へと、いま、無限につながっているようにさえ見える古い古い墓石が…完全な、古い墓場のど真ん中に、男は…いま、丑の刻、舞い散る雪の中で… 「墓場へ、墓場の中へ…墓場で、だ…よくよく、だ」男は思う。「真夜中過ぎに、だ。暗闇の、見捨てられた、古い古い墓石の群れの中で、だ。雪は、後から後から舞い落ちてきて、だ。…おれは一体どういう運をしているのだろう。偶然迷い込んだとはいえ、どうもこの種のものが付き纏う」男の頭に、この時、車で!、だ、すぐにも脱出!という思いがよぎる。しかし、まさにその刹那、遠くに、一条の光が…光の揺れが…その光は、見る見る、こちらに近づいて来て…車のようだ。車のヘッドライトみたいだ。これはいけない。ただ事ではあるまい。時刻が時刻だけに、何か犯罪じみた。どうにもならない不自由に巻き込まれ…犯罪は、うるさいぞ。何しろ強制的だからな。自由の真反対だ。時間を、完全に、奪われてしまう。…男は、一瞬、墓場の墓石の群れの中へ逃げ込み、隠れようかと思う。しかし、車を、そこに残したままでは、かえって不自然だ。遅すぎる。すでに捕らえられている。厭な思いで、男は両のこめかみの辺りに、ヒヤーと痺れみたいなものが走るのを感じる。男は、いまでは、近づく車のヘッドライトを真っ正面から身に浴び、まばゆい光にさらされ、棒立ちしている。諦めて、すっかり観念したのだろうか、どうなのか… ヘッドライトが消され、車は止まり、エンジンが切られる。男の車のフォグライトの淡い光の中に、舞い散る濃い雪の群れの奥に、人影が、コツコツとリズミカルな足音が、…両の肩に黒い毛皮のコートを引っ掛けた、凛々しくて高貴な、素敵なあの女の姿が… 「どうしたんです?」 「どうもしないわよ」女はほほ笑んでいる。 「人気(ひとけ)もなくて、寂しくて、まるで、荒涼とした、地の果てみたいな、ここで…」 「嫌いなの?」 「いや、嫌いでも好きでもないけれど、ちょっと怖かった…濡れるといけないから…雪…車に…」 「あたしは時々ぶっ飛ばすわよ。真夜中、頭が冴えた時…」 湖面が見てみたい、と言って、女は先になって湖側の墓場の方へ、歩み始めようとしていた。しかし、すぐに立ち止まると、男の手を、ぎゅっと、握りしめてしまった。 「親しくなりたいの」女は言った。 男には、信じられないことだった。男は一瞬とまどった。しかも躊躇いは許されないようにも思われた。男の脳味噌コンピューターは一瞬のうちに気違いみたいにフル回転した。多くの、数知れない演算が刹那のうちに行われた。女が、おおよそ、どんな罠に、二人して掛かろうとしているのか、見当がつかないでもなかったが、突然、選択を迫られると、幾分、恐ろしいことのように思えた。新しい口づけをする度に、どうしても、いままでの自分では居られなくなるだろうし、否応無く未知の世界に歩み入らねばならない不安や苦悩や、時には、恐怖すらが待ち受けているだろうし…新しい口づけには、恐怖が…それでも男は女に口づけせざるを得ないだろう…それは、とろけるような、不自然な味の全然しない、違和感の無い完全に許し切った、柔らかい、ふっくらとしてふくよかな、夢の中でのように軽やかな、べっとりとして甘美な、一度その味を覚えてしまったら二度と後戻りすることができないような、天国で居るみたいな…その口づけは、まさに成熟し切ろうとしている女の自然から湧き出る、一切のためらいの無い…それはきっと、いま丑三つ時、闇へととろけ去る数知れない墓石の群れの中…しかし一方冷徹なものでもあった。女の毛皮のコートのお陰で、男は女を、何か抱きしめにくく、抱きしめ切れず、抱きしめても抱きしめても、その分、毛皮が反発し、長くて腰の強い毛皮の毛がつっぱっているみたいで、まるで女の体には、いつまでたっても到達できないみたいな…しかし、女の顔は、火照っていて熱く、吐く息も熱く、それは闇の奥から、いま舞い落ちてくる白い雪を溶かし、男の顔に心地よい熱を…女の脚から力が抜けていくのか、その分、いま男の腕に重みが増して来たみたいで… 雪は容赦なく舞い狂い、女の頬を打ち、髪の毛を濡らす。夜の闇は深く、時は停止してしまったみたいに、まるで時は…そして、時は… しかし、やはりそれでも時は過ぎ、西の空の雲は切れ、星々は輝き…プレアデス星団が、ヒアデス星団が…牡牛、オリオン…ヴェテルギウス、シリウス、プロキオン…懐かしい冬の空の星々が…しかし、瞬く間に、またも、いったん蹴散らされた雲は逆巻き群がり連なり、厚く厚くとろけ合い、闇が、分厚い闇が、またしても雪片が… 「写真等データ見せてもらったんだけれど、あなたには、悪いところがありますよ」車のシートに寝そべったままの女が言っている。「手術なさい。…できれば、一つくらいは、あたしが直接してあげてもいいのだけれど…可能なのか、どうなのか…」 「悪い…?」 「まず、肺。それから、肝臓。それにきっと、性交後に痒みを感じると言っていた、陰嚢」 「インノウ?」 「陰嚢。…詳しく診てみなければ、定かな判断はできないけれど、きっと、切ってしまった方がいいでし��う。何もかも悪いところは、切り捨ててしまった方が…完治するためには。肉体がすっかり改善されるためには。心配しなくても、すぐに新しいものが生えてきます」 男は、もしかすれば心に悪いところがあるかもしれないとは思っていたけれど、からだにまで悪いところがあろうなどとは思ってもみなかった。朝であれ夜であれ夜中であれ、眠ろうが眠るまいが、疲労はひとつも感じられず、自分は不死身であるとさえ、内心、思っていた。しかし、彼女がとても好きだし、彼女を尊敬しているし、彼女の言うことに、できれば、訳もなく逆らいたくはなかった。彼女の長い、ひんやりとして冷たそうな、美しい指が、自分の内臓を良い方に、良い方にと、すばらしい敏捷さでもって、改善していってくれるのだと思うと、思ってみただけでも、極めて有意義、というよりは、むしろ甘美かつ魅惑的、最高、だとさえ思われた。しかし反面、また、冷静に考えるなら、それだけ切って切って切りまくるのだから、それは相当な手術になるだろう、信じられないような、手術に。…だから、万が一にしろ、運悪く、もしかすれば命を落とすようなこともあり得るのではないか。…しかし、そのようなことに仮なっても、すべてのことを一切合財考え合わせれば、やはり、ひとの命というものは、定かならぬものなのだから、仕方ない、仕方あるまい…とも思われた。 「おなかが減ったみたい」ほほ笑みながら女が言う。「夜明けが近いのかしら」 「そうですねえ」と男は言う。「でも、ここには何もないですよ」 「それなら何もない方がよい…気分いいのに、あなたはどうしてそんなに、おとなしいの。…助けてあげるから、安心なさいね…まだまだ手遅れではないんだから…」 女は、いま、やや横寝になって、腋のラインからはみ出ているたわわな乳房のすっきりとした弧の線が目立つ。いくら口づけしても飽き足りない。可愛い乳首が勃起する。 車の中は暖かく、暑いくらいで、女の薫りが、かすかにしている。それは、表面、あっさりとして爽やかな香りなのだが、裏に、奥の方に、濃密な、濃厚な、しかし嫌味は全然感じられない、どうにもならないような、悩ましい、蕩けるような魔力のある、不思議な、…きっとフランス製かイタリア製か(あるいは、オマーン製かもしれない)の香水に彼女の強烈な体臭が、微妙にミックスされて出来た独特な香りなのだろうか、どうなのか。 男は、女の汗の匂いが、特に好きだ。それを嗅ぐと、果てしない魅惑を感じ、頭がクラクラして、すぐにキスしたくなる。 闇がかすかに白み、東方に光が…東の空が茜色に…。前方には、広々と、青く湖面が広がり、その彼方上方に、真っ白に雪化粧しているH山系の、信じられないような、見上げるほどの間近な姿が…まだ昇りきらない、わずかに赤味を帯び始めたばかりの太陽のこの日の最初の光に、神々しいまでに輝く峰々…無数の山襞は、刻々昇り刻々その射す光の角度を変えて行く陽の光を浴びて、微妙に異なった輝きを反映する無数の面に…山襞は一つ一つ襞毎に、白、銀色、灰色、オレンジ、ピンク…と色付き輝き…それらは、また刻々と色を移し変え… 女は、いま、まどろんでいる。男はその女の顔を、まじまじと、見つめる。そして、その美しさに、あらためて感動し、納得し、満足する。長い、細いうなじのライン。いくらキスしても飽き足りないような、か弱そうな可愛いうなじ。顔は細面。鼻は高く、鼻筋は、すっきりと、通っているが、小鼻がなく、頂上から二つの穴へのラインが可愛く緩やかな幾分丸味を帯びているので、威圧感は全然ない。いまは閉じられているが、両の目、もし見開かれれば、一目見ただけでも容易に忘れがたい深い印象を残す黒目の輝き。まぶたの下のラインは、ほぼ、真横だが、目尻の最後のところでわずかに上方に切れ上がっている。上のラインは大きく孤を描き、もし目蓋が開かれれば、そこに黒くて大きい輝く不思議な魅惑をたたえた愛らしい力強く高貴な両眼が見られることとなるだろう。口は小さく、上唇は細く一直線で冷たく理知的であるが、下唇は幅広くふくよかで、真ん中のところが、やや、平べっちゃく、少しへこんだ様な感じさえ与える。もし口づけすれば、そこは耐え難い快楽へと誘う吸盤のような感触となるだろう。そして下唇のラインは上反りなので、いかにも肉感的で挑発的であると同時に親しみやすい感を与える。下唇は、まるで、無数の果てしない、心地よい悦楽を約束しているみたいだ。長い髪は、いま、アップで、女神のように、気位高く、つむじのあたりで小さな低い塔のように、やや無造作に、束ねられている。そのヘアスタイルは、また、うなじのラインの可愛らしさと透き通るような肌の初々しさと横顔の愛らしさを際立たせているみたいだ。男は、女の化粧なしの素肌なのが好きだったし、装身具皆無なのも好きだった。 『女。自分には身に余るような高貴な女…』男は、独り、思い続ける。 「まるで、ドラキュラに愛されたみたい」女は、いま、車のバニティ・ミラーで、首筋の辺りを調べながらほほ笑んでいる。そしてスカーフを固く固く巻きつけて、首筋のそれらの傷跡を隠してしまう。 「忙しいから、あたし、今度いつ会えるかわからない」女は言っている。「でもその時は、また連絡してあげるからね、あたしの方から」 男は非常に悲しく思う。男はもうこのまま、永遠にずっと女と離れずに一緒に居たく思う。男は、いま、急に女を見失ってしまったような気分になり、苦しみの念に満たされる。ひとつの山を征服し、印に山頂に旗を掲げたつもりだったのだが、霧が晴れてよく眺めてみると、なんと、その頂は山全体の頂ではなく、より高い峰が霧の奥の遥か彼方に、意気高く、高貴に聳え立っているではないか。男は、屈辱をすら感じざるを得ない。しかし女は、スパッと、まるで平気なみたいに、去って行こうとしている。男の車のドアを、後ろ手にバタンと力強く閉めると、自分の車の方へと去っていく。その姿は、凛々しく美しい。エンジンを掛けると、左手でハンドルを握り、右手を上げて別れの合図をし、ほほ笑む。こんな悲しい時に、よくも平然と美しい微笑を浮かべていられるものだ、と男は思う。女は左いっぱいにカーブを切りながら、大胆に、滅茶苦茶に、一気にアクセルを踏み込んだみたいだ。それも、ここ、湖岸の砂地で…。だから、車は激しくスリップして、そこに残っている男の車に、一面もろに砂塵を撥ね掛けて… 今日は、土曜日なのか、それとも日曜日なのか、湖周道路には、遠方からの〈遊び車〉が氾濫し、またもT道路は渋滞している。CDは、いま、エーロン・コープランドで『エル・サロン・メヒコ』だ…しかし、もしCDを切れば、自然とラジオに切り替わり…そしてまたも、それは株式市況で…《売り一色、陰の極》とでも来ているのか、どうなのか…もっとも、もし、今日が、本当に、土日なら、勿論、相場は休みとなり、市況のアナウンスもあるはずがないのであって…真ん前を行く車は見慣れない。イタリア車くらいなのかもしれない。横に美しいラインで膨れ、上にもかなり盛り上りのある、見事な尻、をしている。多分、ヨーロッパの車なのだろう… 女からの連絡で、公的なものではないが、なにか人間ドックみたいな所へ入るように言われた。各種の検査をしたり、何より、禁酒、禁煙し、体力をつけるためらしい。部屋は、個室で、三階の南向きの広々とした清潔で、調度類は簡潔な部屋だった。白衣を着ているわけではないが、明るいカラーの制服を着た娘達が、入れ代わり立ち代わり、部屋へ出入(ではい)りしていた。各種のデーターを揃えているのだろう。中には、素手で男の胸にさわり、撫で回し…男が我慢していると見て取ると、クスクス笑う娘がいた。「検査のためなのだから我慢して」と娘は言っている。それから指で胸の肉を摘んで引っ張り上げ、男が「痛い痛い」と言うと「脂肪の層を測っているところなの」と言って笑っている。変わったことをするもんだ、と男は思う。食事はやたらと肉料理が出てきた。缶入りタバコも葉巻もワインも、全部禁止された。これはもう、男にとっては、拷問みたいなものだった。しかし、女(いや、女神)への愛のためには、これくらいの苦しみには耐えなければ…とも思えた。約一週間、タバコが欲しくなるたびに、隠し持っていたジンを一口喇叭飲みした。冷えてもいないし、カクテルも作れなかったが、この際、贅沢は言っておれなかった。こうして、タバコは、必死の意志力の下、止まったのだが、その分、アルコールの量がやけに増えた。しかし、禁酒より、むずかしいだろうと思っていたタバコが止まったことはうれしかった。 〈センセイ〉からの電話は、惨憺たるものだった。男を頭から馬鹿にし、ほとんど気違い扱いしていた。 「あなた、どこが悪いのです。どこも悪くないじゃありませんか。…だるい?…放蕩が過ぎてるんじゃないですか、放蕩が。…放蕩皆無?…なら、それは気持ちのせいでしょう。持ち株の…株価の暴落とか、なにか…なにっ!金にも一切興味ない?…無頓着?…もし本当にそうだとしたら、それこそが、まさに、病気なんですよ。カネを寝ても覚めても、とことん追求する、そうしないからこそ、病魔にも…あなたは常々、わたしがカネのことを考え過ぎるといって軽蔑なさっていますがね、考えないあなたの方こそ精神に、どこか異常があるのです。ですから、坊ちゃん、必要なのは、あなたの場合、外科手術ではなくて、精神科…きっと、どこか脳味噌の電気反応にでも異常が…」 「そりゃ違う、まったく。肺に癒着があるんですよ…肺と肋膜?…胸膜?まさか、腹膜じゃないだろう、全然、そのあたりは、詳しくは分らないがね…癒着が…それを、アノヒトが…」男は、女の事は〈センセイ〉には、もう内緒にしていた。「あのひと?」「いや、その診てもらった、掛かりつけのお医者が…」「ますますもって、坊ちゃん、あなたはおかしいんじゃありませんか。…何か夢、悪夢にでも…しかし、癒着なんぞというものは、誰にでもという訳ではありませんが、そんなもの…何が手術です、放って置けば、どおってことないじゃないですか…なにか、誰かの、術中に…陥って…悪徳医の、切り切り魔にでも…なにかそんな…」「そりゃ違う、とんでもない。疑られては困る。いっさい、わたしを信じるよう。…ただ、費用の支払いの方は、この際万端、ひっくるめて、すっかり頼んでおくからね、すっぱり手落ちのないようにね…」 女から、連絡があった。そして外出が許された。迎えの車が来るらしい。 車は、旧い型のデボネアだった。「骨董もんだね」と運転していた男に言ってやると、その男は苦笑していた。しかし、口など利かなかったらよかった。運転手の男は、やがて女の陰口を利き、男はつい我慢できなくなり、拳骨でストレートを一発、運転手の頬骨目掛けて食らわした。「本当に事実を知っているのか」と問い詰めると、いや、ひとから聞いた噂だ、と言っていた。「噂だけで、ひとを傷つけるようなことを、そうそう簡単に口にしていいのか」と怒鳴り付けてやると、いいえ、とその男は言っていた。その後は、案外素直な喋り方をするので、男は、かっ、とした自分を後悔した。男は途中で車を降りてしまった。しかし、降りると同時に、しまったことをした、と思われた。第一、行き先が分らない。第二に、誰とであれ、トラブルなど起こしてしまって、きっと作用は反作用を呼び、結局は、巡り巡って、彼女に不利な力となってはね返って来るのでは…いま、男の心には、いやな想いが、後から後から噴出して来た。…「本当のところは、嫉妬したんだろうな…」と男は思う。しかし、実際、仕方ないことだった。他の女たちと比べて、彼女はあらゆる点で、はるかに魅惑的なのだから…男は女に連絡をとってみた。女は留守で、次から次へ、回された。「**番へ損にして掛けてみてください」こればかりである。…しかし、到頭、女の声に巡り会えた。運転手のことを謝ってみると、すでに「知っている」と言っていた。 ラブホテルは、なおも続き、終わりが来ないみたいだ。それは〈メルヘン〉、〈ドリーム〉、〈2番館〉…〈ベルローゼ〉、〈セント・ジェームズ〉、〈OZ〉…〈サン・クリスタル〉、〈トレンピア〉、〈セルベーヌ〉と連なり、〈エンセラー〉、〈ミシガン〉、〈アルテミス〉そして〈シルビア・ルーム〉…といった具合である。要するに、切りがない。一画は、市街地からはかけ離れた、湖と内湖に挟まれているような感じのところだった。 女の車は、とある建物の中庭へと入って行った。そこには、手入れの行き届いた欅の並木があった。車は噴水べりに止められた。その円形の池には、錦鯉が泳いでいた。それらは、三毛(さんけ)、金兜、銀兜、秋水、紅白…中には、ドイツ鯉も混じっているようで… 「錦鯉、好き?」女が、言っている。 「いや、好きでも、嫌いでも…」と男が言う。 女が幾分身を前傾にして池を覗き込むものだから、ただでさえドギツイからだの凹凸(おうとつ)のラインが、より挑発的に魅惑的に男を刺激する。男は、恐る恐る、女の腰のくびれに手を置く。男は燃えるような恋の想いで、いま、心がとても不安定だ。その点、女がゆったりと���ほ笑んでいてくれているのは非常にうれしい。しかし、その女の心も、いつ急変するか知れたものじゃないと思うと、安心など、いつになってもできるものではない、と男には思えた。男は女の腰に置いた手を、もう一歩進めてスカートの中へ、いま、池の中の鯉を見るために、半ば縦に開かれている女の太ももと太もものあわい、つまり、陽毛、陽唇、陽核のあたりへ…やりたい…あるいは、やるべきかどうか、つまり、そうすることが、女への敬意、ないしは、女への愛に違反しないのか、どうなのか、思い迷っていた。しかし、もしそうすると、女のいまあるほほ笑みが、消え去らないまでも、幾分薄れたり歪められたり、…いや、それは、やはり完全に消え去ってしまうだろう。そして、それは苦しみの表情に、たとえ表面だけにしろ…しかも、表面以外に一体何が分るというのだろう。分かるということと、推測できるということとは別のことである。つまり、表面は、…表面もまた…。 女は、「いらっしゃい」と言って、男を建物の中へ誘った。 ブザーが鈍く鳴った。小っちゃな電子レンジのドアみたいなところを開くと、注文したCD四、五枚とワインとオードブルが届いていた。ここには、束縛がなかった。自在空間だった。コンピューターは怖くない。怖いのは人間だ。特に人間の目なのだ。 二十四時間くらいならもつでしょう、と言って、女は笑っている。モーゼル・ワインとニンニク入り豚の腸詰(少なくとも、オーストラリアかドイツ産の、中国、朝鮮のものも、うまかったように思うが…)さえあれば、いくらでも…と男は思う。 「もうこれで、最後になるかも」と男は思う。「手術がうまくいけば、永遠に、永遠みたいに幾度も、このひとと逢えるかもしれないけれど…うまく行かなかった日には、今日が、これが、いまが最後となる…」 CDからは、『ジーラ・ジーラ』が聞こえている。演奏は、もしかすれば、ホセ・バッソ楽団かもしれない。女は男に、すっかり裸になるよう言っている。湖岸の自転車道で、毎日、雨さえ降らなければ自転車を楽しみ鍛えた男の体は、全身太い筋肉で起伏に富んでいる。男は、ダブルベッドに、仰向けに横たわった。 女はまず、男の首筋に指先を当て、リンパ球でもを調べているみたいだった。「どうです?」男が訊いてみた。ううん、と女医さんは言っている。しかしそれ以上は何も言わない。そして、ほんの少し、軽く、両の耳たぶを親指と人差し指で摘んでひと撫でし、(彼女の指先の感触は、とても心地よい。頭の芯が、すううっ、として来て、男は心地よく感じる。彼女の指に触れられていると、自然と、なにか、心が和んでくる、そういった感じのものだった)…それから、乾いて、いま、かさかさになっている、緊張した男の唇を潤すみたいに、そっとキスをし、今度は、男の胸を調べにかかった。肋骨と肋骨の間へ指先を立てて押していくのである。まるで、最良の指圧でもをされているみたいな感じだ。 「確かに、癒着があります。右肺下葉です。それに、穴の開いているところ、つまり空洞ですね、空洞があります。しかもこの空洞の影は、断層、ならともかく、普通のレントゲン写真には出ないでしょう。いや、写るのは写るのですが、少なからぬ医者が、もしかすれば、まあ十中八九見落とすかもしれません。それに鎖骨の真下になっているから、この間の平面写真では鎖骨の影に重なって、見辛くなっていたのです。早晩、断層写真を撮ることでしょう。…右、上葉、ですね。…検査の結果では、まだ開放性ではないみたいだけれど…」 男は、全身の皮膚が非常に敏感にできているので、愛する女(ひと)の接近と触診で、もうすでに我慢できないくらいになっていた。…男は、腕を伸ばし、リモコンでライトを消した。CDのボリュウムも、リモコンで下げた。タンゴは『ガウチョの嘆き』が終わって、いま、『オー・ドンナ・クララ』になっている。ボリュームは極度に絞られ、もう殆ど聞き取ることが出来ないくらいにまで絞られ、そして早晩、それは完全に消え去るだろう。そして、タンゴが薄れ消え去っていくのに連れて、女の吐息が、喘ぎが…ああ、と泣き叫ぶ悲しい悲しい女の叫び声が…「これは、本当に悦楽なのだろうか…ひとはこれを悦楽と呼ぶのだけれど…あまりにも、ぎりぎりの女の叫び声を耳にしていると、何が何だか…一体、これは…」 「こんなこと急に仕出かして」と女医さんが、穏やかに、微笑みながら言っている。「まだまだ診察は、すっかりすっかり終わっていないんだから…」 女の、ゆったりとした、安らいだ表情を目にして、男は、はじめて、自分も仕合せな気分になる。いま女は、男の腕に身を任せ、男の脇に寝ている。 「ほら、ここもいけませんね」女医さんは言っている。男の脇っ腹のあたりに女医さんの関心は移っているようだ。手のひらの先半分くらいを使って、非常に柔らかく、また優美に、男の右肺下葉の、いま少し下の付近を、押したり緩めたりしているのだが、時々、ふざけて、ちょっと摘んでみたり、爪先を、わざと、たててみたりもして楽しんでいる。 「これはアルコールが原因です。ずい分と飲むでしょう。…最初のうちは、ま、いいのです。しかし、あなたの場合は、その段階をとっくに通り過ぎてしまっているのです。アルコール性だけのものなら、アルコールを断ち切れば、それだけで、もうよくなるのです、やがては。しかし、あなたの場合は、その段階を通り過ぎてしまっていて、どうしても切り捨てざるを得ないところ、つまり、すでに肝臓としての機能を果たしていない、血行の悪い単なる脂肪塊が…固く固くなった単なる繊維質の部分が…かも知れませんね…」 「ぼくは、非常に元気なんですが…元気そのものなんですが」と男は言う。「それでもやはり、いけないんでしょうか」 「それはいいことです。元気なのは、いいことです。それは、かけがえのない素質です。それだけでも、もう十分とさえ言えるくらいです。…しかし、このままでは、早晩死ぬでしょう。ですから、試みです。一つの、…」 男は、いまだに、ぴんと来なかった。自分が長生きする、ということに関しては、ほとんど興味がなかった。野生の動物のように、生きるだけ生きて、それでも、なおかつ死ななければならないのなら、そのまま、死ぬ。それだけのことである、と男は思っている。また、元気なのだから、病気など無いと同然、と判断すべきか、病気があると言われているのだから、いくら元気でも、医者の言うことに従うべきなのか、結局、男の場合、女への愛に帰するように思われる。愛していれば、命など惜しくない。信じ、任せる。ましてや科学的真偽という風な簡潔な次元での悶着など…気風(きっぷ)、というものである、一切、お任せしたい。勿論、これは、やせ我慢、ないしは、愚かな独断主義、とも考えられる…、のか、どうなのか。男は、いま、自分が躊躇っていることを知っていた。しかし、やがて今まで同様、一直線に前進を始めるだろうとも思っていた。それにしても、一旦疑り始めると、愛は、地獄である。 「まあ、まあ、どうしたの?」と女が言っている。「いけませんよ、なんという���動悸です。わたしにはあなたの考えていることが、手に取るように分りますよ。しかし、わたしもまた、あなたと同じ…そっくり同じ恋人で…恋をしている人間に、ほんの少し先でも、何かその恋について理解することができるでしょうか。あなたは、あたしの本当に大切なひとではなかったんですか…」…分った分った、と男は思う。ごめんごめん、気が弱ってしまっている。これは本当に病気なのかもしれない。第一、もし彼女が平穏で、かつ苦にならないような女だったら、そしてわたしを本当に愛してしまったりしていたら、後にどんな魅力が残っているというのだろう。きっと、退屈してしまうこととなるだろう。魅力などあるはずがないのである。だから、もしそうであるとするなら、常にまた、疑念というものは、付き物であって…。結局、すべては自在である。楽しむ自由があり、苦しむ自由がある。お前は、いま、彼女が欲しいのかどうか。もし欲しいのなら、それはそれでもう充分なのだ。お前も彼女のために命でも何でも、一切合財、くれてやればよいのである。それ以外に、恋などしようがない。もともと、何か不都合な極度の矛盾でもがなければ、恋など起こり得ようがないのだから。…美が…そして悦楽が…である。…あなたは美しい、あなたには気位がある、気高さがある、いい頭をしている、心地よい肉質の唇をしている、潤沢で繊細なくせに極度に引き攣る膣壁をしている。何よりも、悩ましく死にたくなるほど苦しめてくれて有難う。 女は、ワインを口移しに男の口に注ぎ込んだ。からだが火照っているせいか、それは特別に冷やっこく感じられ、とてもおいしかった。女は、片脚を男の片脚に引っ掛け、半ば開かれた股を男の脇っ腹に、ちょうど肝臓の真下辺りに擦りつけ、こぼれる様に、朧に蕩ける様に、消そうにも消しようがないほほ笑みを浮かぶにまかせて… 「腸にも少し…つまり、スリップが…しかしこのような異常はむしろ捨てて置いた方が得策でしょう。あるいは、精管の異常を改善する際に、どのみち下腹を開けなければならないので、その際にでも…だから、手術のプランとしては、まず、陰嚢、そして肺、と行きましょう。陰嚢に関して言えば、…」いま、彼女は、極めて巧みに、陰嚢の触診を始めていた。それは不思議な感触で、きつくもなく緩くもなく、しかも丹念なもので、内部構造に無知なものでは到底行い得ない体の指捌きだった。「陰嚢に関しては、やはり、いま直ちに症状が出ているわけではないのだけれど、つまり精管外に漏れた精子が、比較的微細な量で即座に吸収されているので何の症状も無いみたいだけれど、やがてこのバランスが崩れると、特に激しいクライマックス、クライマックスが激しければ激しいほど、その性交による横溢が激しくなる。すると、かゆみ、痛み程度の症状には留まらず、やがては、瘤(りゅう)、つまり精子の瘤、精瘤となるのです」 「セイリュウ?」 「そうです、陰嚢精瘤、です。陰嚢が、精管から溢れ出た精子で、段々段々いくらでも、ますます大っきく、いくらでも大っきく膨れ…」 男は笑ってしまった。狸の焼き物のことを想ったからである。 「笑い事なんかじゃ全然ないですよ」彼女はなおも平然としている。だから男はド狸のことを言ってみると、とうとう、やっと、女医さんも我慢できずに笑い出した。「後々、どんな苦しみが来るかも知らないで、よく馬鹿な冗談言っておられるわね」 「それにしても、そもそも、何でそんな馬鹿な事態に陥るのでしょう?原因…?」 「滅多にないでしょうね?非常に珍しいケースです。外国の稀な症例では、なにか男性が無理矢理複数の女性によって強姦?、連続的に、輪姦?って言うんでしょうか、された、繰り返し…その際に…そんな例があります。戦時のことですがね」 「男が?…される?…無理矢理?…そんなことが肉体的に可能なんでしょうか?…厭なら勃起しないでしょうに?」 「ペニスの付け根を縛りあげ、静脈の血流を遮断するのです。そうすると動脈からは、なおも、血液が流れ込もうとするのに、静脈からは流出しにくくなり、勃起に似た状態になるのだそうです。すっかりすっかり信じ切るわけにも、行かないのだけれど…」 「そうですねえ…」 「戦時の、苛酷な状態下でのことだったのでしょう…それと、もう一つの例は、あまりパートナーにやさしくし過ぎてもいけないようです。パートナーにあまりにもせがまれ過ぎて、幾度も幾度も、幾分無理して射精を続けたような場合です。瞬間的に、精子が尽き果て、精管内に真空状態でもが生じるのかもしれませんね。その際に、精管の破損が…」 「分らんですね…一体に、そんなに意識的な性交なんて…」 「全然、気にしなくっていいのです。結局は、相対的な強度の問題だと思われます。クライマックスの射精の激しさから生じる力とその際の精管の肉質の強度、その二つの相対関係でしょうね、結局は」 男は、完全には、納得出来なかった。そして憂鬱な気分に満たされた。 しかし、こうしている間にも、時は流れ、過ぎ去って行き…またも、闇が、虚空が、悲しみが、悦楽と言う名の死のような気違いじみた虚無が…女はかすかな声で何かを言い続け、また可愛い声で何かを唱え続け、心は高まって高まって遂には肉から逸脱してしまい、朝焼けの空を羽ばたく水鳥のように飛翔し、また海鷲のように急降下し、一瞬身を翻し、急上昇し、あがき、喘ぎ、悲しさのあまり泣き、叫び…神経系統、このシステムが、その痺れ、幻影が…それらは、ひとに思い知らせるだろう…存在のこの不可解と無のあの気違いじみた莫大を。 このようにして、男と女は、闇の中で、タンゴの曲とワインとまどろみの生活を、まるで無限の時の間みたいに、続く限り、無頓着に(実際には、およそ百時間くらいのことだったのだろうけれど…それとも、そうではなかったのだろうか)…そして、到頭、「さあ」と女が、もうすでに十辺も繰り返した、おそらくは、すでに二十四時間も前から空しく発せられているであろう掛け声を…(男はこの点、底なしである。時のこのような事態がまるで価値だと信じているみたいで…それとも、ただ泥沼に…ただただ燃え尽きて落ちるしかない隕石みたいに…なのだろうか、どうなのか) 女は、今度こそ自分に打ち勝ったみたいだ。男は、いま、まどろんでいるところだった。置手紙の最後は、「…あなたの可愛い女より」となっていた。もっとも、可愛い女、の四文字には、傍点が付されてはいたのだけれど。 手術室で、最初に一番に気をひかれたことは、まばゆさである。真上の天井全体が、まるで、蜂の巣のように見える正六角形のライトの集まりからできているみたいだ。 ベッドの足元のところに、両眼以外を、すっぽり、白布(緑色ではない)で覆った医者(あれこれ指示を出しているところからすれば、そう思われる)が一人いる。その脇に、もう一人の男がいる。医者の言いなりになっているところからすると、見習い、インターンの男、つまり、病院実習の医学生なのだろうか、どうなのか。(医者は、彼女ではない。彼女はどうしたのだろう。彼女が恋しい。彼女が、専門外だから、専門医に依頼してくれたのかも知れない。あるいは、全然そうではないのかもしれない。物事には、道理と言うものがあるのだから、やたら疑り、悪い方に悪い方に疑り、邪推、あるいは、悲観の誤謬、か、…疑るだけが能ではない。…しかし、それにしても、彼女は、一体…) 男の頭部すぐのところには、女看護士が一人いる。(入室前に、男の陰毛をすべて剃り落とした女看護士と同じなのか、違うのか。顔全体、今は、すっぽりマスクをしてしまっているので、分らない。おそらく専門違いで、別人なのだろう。それにしても、あの陰毛すべてのカミソリでの剃り落としは大変な作業だった。人気(ひとけ)の全然ない、静かな広い部屋で、産婦人科用の開脚ベッドに開脚して寝かされた。剃っている間中、柔らかい指で、陰茎中心に、そこら中触られまくり続けるのだから堪ったものではない。しかも、あまりにその女看護士が若く(見習いのまだ看護学校の生徒だったのかもしれない)しかも、清純な感じの綺麗な娘だったので、その間ずっと最初から最後まで、男の陰茎は、馬鹿みたいに、きつく勃起したままだった。男は、見つめられ触られ続けるままなので、なんとも具合が悪く恥ずかしく、どうにもならず、死ぬ思いがした。あれだけ女と過ごした直後なのだから、すっかり空になってしまっていて、音無しくしてくれていてもよさそうな筈だったのに、と男は思う。不意を突かれると、人間の道徳とか倫理とか意志とか精神などというものも、どこかへ吹っ飛んでしまっているのだろうか、一切何の役にもたっていない。それにしても、病院側も、もっと刺激の少ない、老看護士をでも、そのような仕事には配置しておいてくれれば、男も、長時間、その間中、赤恥をかき続ける被害に遭わずに済んでいたのかも知れない…) 男の頭部のところの看護士は、いま、男の額に触ったり、手に触ったりしている。そこには、汗でもが、すでに、にじんできているのだろうか。 「横寝してーッ」医者が言っている。低音で、慣れた落ち着いた口調で、いやに語尾を長く引っ張っている。何か、ひとを催眠にでも掛けようとしているみたいな感じである。男は、ボオッ、としていて、医者の言葉に反応しない。そこで、枕元の看護士が手伝って、男の身を横寝にする。すると、陰茎の先っちょ、つまり、亀頭か、…亀頭が手術台の固いざらざらしたシーツに触れるのが感じられる。 「海老のように背を曲げてーッ」医者が声を張り上げている。海老のように背を曲げて、と口調は全然違うけれど、女看護士が医者と同じ文言(もんごん)を繰り返し、男の首や頭や手に触って、仕向ける。医者の手が男の足首のところを握っている。インターンの男は大きな針のようなものを掴んでいるみたいだ。六、七センチはあるように見えたが、実際には四、五センチ、もしかすれば、三、四センチだったのかもしれない。握りのところは、注射針みたいに太くなっているみたいだ。 「もっと、腰のところを突き出してーッ」医者が、相変わらずの口調で、言っている。 インターンの男が、男の腰のあたりの背骨に針を突き刺す。医者が男の足首のところを押さえつけ、女看護士が男の肩と手首のところを押さえつけている。その圧迫する力が、いま、一段と強くなる。男の脚は、くの字に、折れるだけ鋭角に、きつく折り曲げられている。ここまでくると、男はもう、自分がもはや人間ではなくなり、なにか本当の海老にでもなっていくような錯覚に襲われる。海老だ、伊勢海老、車海老…伊勢志摩、鳥羽に、大王崎…ギリギリと背骨が痛む。何回繰り返しても、背骨に針は突き刺さらないみたいだ。インターンの男は、きっと、腰椎麻酔の壷をはずしたままで、むやみと男の背骨を、幾度も幾度も、突き刺しているに違いない。針を、腰椎と腰椎の間へ(そこは軟骨ででもできているのだろうか、…それとも、単なる隙間が?)針を、そこへ、…しかし、全然、うまくはいっていないのだろう。男は、大変な痛みを感じる。しかし、じっと、我慢している。騒いだとて、誰も、どうにもなるまい。医者は、それにしても、インターンの男の不手際に、幾分、苛立ってきているように見受けられる。男の額には、脂汗でもがにじみ出ているのだろうか。看護士が、ガーゼでぬぐう。男の背骨に、いま突き刺されているのは、単なるせいぜい四、五センチの針なのだろうが、男には、実際には、太い何かネジ釘でもがねじ込まれているように、とても痛く感じられる。それでも男は、全身の力と気力を振り絞って、我慢を続ける。すると、脂汗が、額に…そこで看護士がガーゼで、またも汗を…勿論、インターンの男が拙く針を男の背骨に壷を外して突き刺すその瞬間には、看護士もガーゼで男の汗を拭ったりしている余裕はなく…つまり、看護士も医者も、男の手首と足首のところを精一杯押さえつけて、男の体を海老型に固定して置くのがやっとである。 医者は「力を抜いてーッ」と言っている。そこで、それに従って男が力を抜くと、今度はすぐに「腰のところを、もっと、突き出してーッ」とおいでる。しかし、これは矛盾しているように思われる。突き出せば筋肉に力が入るし、力を抜けば、筋肉は緩み、腰は自然にへこむだろう。まあ普通なら、実際には、そうこうしている内に、うまく行くのが常ということなのだろうけれど…異常にも、二十回前後も、突き刺されたのではなかろうか、そして、遂に、針の先が、腰椎の中を行く神経にでも触れたのだろうか(それとも男は医者の暗示にでも掛かり、すっかり催眠状態にでも…あるいは、疲労困憊の末の泣き寝入り状態にでも…)男に、痺れ、酔い、眠気みたいなものが…そして、やがてはうわ言でもが…心は肉体を離れ、天翔(あまが)け…もはや、苦痛も苦悩も遠く去り、まるで天国にいるみたいに、かってそうであり、やがてそうなるであろう、まるで虚空を漂う粒子みたいに、無みたいに、つまりは、死みたいに… 「感じるか?」ピンセットに挟んだ、アルコールをたっぷり滲みこませた脱脂綿で、男の下腹部を無造作にこすりながら、医者が男に訊いている。しかし、男はいま、すでに眠り込んでしまったような状態になっていて、何の反応もない。 「感じるか?」医者は、今度は、金属(メスの握りの部分の角?)で男の下腹を左右に引っかきながら、訊いている。しかし、医者は、大声でそう言いながらも、小声では、すでにインターンの男に、「行けるぞ。…ぼつぼつ行けるぞ」などと、囁いているのか、どうなのか。…いずれにせよ、やがて、すぐに、男の下腹(正確には、鼠蹊部(そけいぶ)?)は、メスで、引き裂かれることとなるだろう。そして、陰嚢が捲(めく)られ、白膜、精細管、睾丸、副睾丸、精管…それから、鼠蹊輪、直腸管…と調べ、いじくられて行くこととなるだろう。…しかし、そのうち、もともと不十分だった腰椎麻酔も切れてきて(見習いの男が、何かと処置に、時間を余分に取り過ぎたのだろうか、どうか)男は夢見心地の雲上から地上に落下し、痛みや、悩みや、苦しみが、またも始まる。「ヤブ…ボンクラ…我利我利…能なし…馬鹿医者…拷問、まるで生体実験じゃないか」と男は思う。「痛い痛い」と男は心の中で叫ぶ。しかし、声には出さず我慢する。そして、我慢した分、目つきが悪くなり、脂汗が滲み、身がよじれる。きっと、声に出して弱音を吐くことは、男の自尊心が許さないのだろう。いわゆる、やせ我慢みたいなものか、どうなのか。(彼女がしてくれているのなら、痛い痛い、と言って甘えてみたくもなるのだろうが…)痛い痛い。またまた脂汗。そして、看護士のガーゼ、である。下腹を切開して、めくったり、めくり返したり、また元に戻したり、切る、つまむ、削る、針を刺す…要するに、むやみといじくり返しているのである。しかも麻酔は切れてしまっているのであるから(医者は、この事を、信じていない。つまり、インターンの男の突っ込んだ針は、最初からうまく、つまり、充分には、効果をあらわしておらず、通常の時間よりは大幅にはやく、腰椎麻酔は切れてしまっている…医者は、この事実を理解していない。また、一番いけないことは、理解しようとする態度を持っていない。硬直している。たとえば、鈍感な大臣。これは、そう珍しくなく、あり得るだろう。しかし、副大臣、ないしは、お取り巻きの官僚がしっかりしておれば、それはそれで、もつかも知れない。別段、大過なく過ぎ行くかもしれない。しかし鈍感な手術医(この際は、泌尿器外科医?)、これはもう困ったものだ。人の腹を引っかいておきながら、どこが悪いのかも、どう治せばよいのかも予想していない。まったくの、泥縄、である。…しかし、こうも考えられる。男の症例が非常に珍しいもので、前例皆無で、いかなる医者にとっても、開(あ)けてみなければ分らない…過度な、または異常な、類(たぐい)稀な悦楽への耽溺が、新たな病の誕生の土壌となるのかも知れない。しかし、それにしても、実際これは、生体実験、ないしは、すっかり切腹を体験しているようなものだ、と男は思う。いくら二人掛りで押さえつけようとしても、筋肉が痛みで反射的に自動的に暴れ回るものだから、今ではどうにもならない。意志などとは関係ない。意志が有効なのは、ある種の系が平穏無事の際でのことであろう。ここまでくると、収拾がつかない。肉の反乱、である。… やっと、医者は、諦めにかかったのだろうか。それとも、「無理です」と、男の苦悶を見るに見かねた看護士が一言もらしでもしたのだろうか。(しかし、看護士が医者に口出しなどしようものなら、それこそいっぺんに…なのだろうか、どうなのか)看護士には全ての事実が(麻酔が、まず、充分にはかかっていなかった、ということ。いまでは、麻酔は切れてしまっていること)が分っているのかも知れない。どのあたりで、この男の腰椎麻酔が切れかけていたのかも。(看護士の方が、男の頭部に近い分、医者より情報量は豊富なのかも)…あるいは、医者も、本当の事態を、勿論、知ってはいるのかもしれない。しかし、もしそうであるのなら、にもかかわらず、捨てておくその理由は?…そんなことは、分らない。邪推、というものかも知れない。 いま、もう一人の医者が現れる。これは麻酔医かもしれない。マスクを持っている。ここまできて、やっと、全身麻酔をやるというのだろうか。男の手術前の希望通り、初手から全身麻酔にしておいてくれればよかったのに、と男は思う。もし、疑れば、インターンの男に、残酷すぎて最近では患者には全然人気のない腰椎麻酔を練習させる場を与えるためにのみ…つまり、男は、インターンの男の修練の実験材料として…と考えられなくもない。もしそうなら、大学の付属病院でもないくせに…もちろん、大学の付属病院であろうが、なかろうが、生体実験の道具になど、誰一人賛成などするものか…、男の頭に、怒りがキイーッ、とくる。練習実習なら、インターン同士が交互に患者になり合って、医者のアドバイスを受けながら、納得のいくまで繰り返し練習すればよいのである。(実際には、腰椎麻酔にも、長所は多々あるのだろうから…)それにしても、今度は、全身麻酔だ。またもや、そして、今度こそより完璧に、離脱、飛翔、暗黒、無限、つまり、死の予行演習が始まるのだろうか、どうなのか。 ガラガラ、と音がしているのが聞こえる。ベッドが勢いよく動いているのだろう。手術は終わり、手術室から廊下へ…なのだろうか。一切が輝き、歓喜に満ち満ちている。全身が、心地よい。「ああ、いい。…気持ちいい」と男は思う。しかしすぐに、これは夢かもしれない。あまりにも、苦痛が皆無であり過ぎる。〈天国チック〉であり過ぎる。霊魂がうわずっている。フワフワしている。浮き、飛び、酔い、痺れ、…麻酔の麻薬の仕業かも。(それにしても、彼女は、一体…下界が恋しい…湖、湖周道路…リゾートは、今日も、〈遊び車〉で渋滞し…それにしても、おれは本当に治るのだろうか…二度とあの悦楽の味を味わえなくなったのではなかろうか…使い物になるのだろうか…そもそも睾丸はあるのだろうか…) 「睾丸は、あるのか」と言うべきところを、「キンXX」はあるのか、と言ってしまったものだから、(男は麻酔でまだ幾分頭が弱くなっていたのだろう)、看護士たちは、大笑いだった。麻酔呆けのした人間など正面からは相手にしていない。「大丈夫ですよ。安心安心ですよ」まるで子供扱いである。自分の手で直接触ってみれば分るかもしれないのだが、股全体に大きくて分厚い傷への当て物がされているのであろう、全く接近不可能である。しかも、まだまだ、付近の神経は痺れてしまっているので、結局何も分らない。 女が現れる。麻酔後のまだ酔いの心地よさの幾分残る男の脳味噌には、彼女の美が、より一段と、艶に、鮮明に、身に沁みる。目、鼻、唇、髪、項、首…全部好きだ。全部に、いくらでも、キスしたい。 「痛がり屋さん、それにしても、よく頑張ったわね。先生も感心していたわよ」彼女が、ほほ笑みながら、言っている。麻酔呆けした男を、幾分からかっているのかもしれない。あんな鈍感なボンクラ医者に感心されても、何もうれしくない、と男は思う。むしろ今でも、思い出すと腹が立つ。自棄(やけ)のヤンパチで、顎に一発、パンチでも喰らわしてやりたいくらいだ。(勿論、このような感情を持つということは、そのこと自体���すでに自らの精神の劣等を意味しているに違いないのだろうけれど…なぜなら、素人に、専門医の配慮などは理解できる筈はないのである。邪推である。ましてや、恨むにいたっては…まともな患者、標準の人間、正しい心の持ち主、とはどうしても言えないだろう…) 「結局は、厳密には」と彼女は言っている。「悪いところがどこだか、傷口が分らなかったみたい…」 何という事だ、と男は思う。あれだけ時間を掛け、あれだけ苦痛に耐え、ひとを切腹同然の目に遭わせて置きながら…。しかし同時に、そんなことがあっても不思議はないのかも、とも思う。医者自身の資質のせいも大いにあろうけれど、手術のみならず、概して人間の試みることといえば、当て外れが多いものなのだ…と男は思う。 いま、何がしてほしい、と彼女が訊くものだから、仕方なく、恐る恐る、あれがしたい、と本当のことを言ってみると、彼女は、最初ほほ笑んでいたのだが、急に顔を真っ赤にした。 病室には、医者も看護師も居た訳ではないのに。男は一瞬困惑した。プリンがほしい、とか、りんごを下ろしてほしい、とか言っておけば、無難だったのかもしれない。実際、手術にともなった微熱が出ていたのである。こういう時には、冷やっこいものを言うのがよかったのかもしれない。それにまだまだ、頭には麻酔が残っているのか、ボオーッとしている。 そんな馬鹿なこと、と言って、彼女はプンプンしている。 まあ、勿論、その通りなのだが、それでも、そうしたく思ったのだから…彼女の顔、特に、目とか鼻とか唇をみていると、すぐにしたくなるのだから、困ったものだ。…自由、放埓、滅損…自由、放埓、破損…自由は放埓に変じ、放埓は破滅へと至る…男は考える。しかし、自己破滅だけなら、何も自分からは望みはしないが、誰にでも起こりうる一つの確率的事象にしか過ぎないのではないのか、前もって恐れる必要もない。一方、女には、この男の愚かしい激しさは、この分では、きっと、最後には自らの命に損傷を加える程度にまで至るのではなかろうか、と思われる。 男の、つまり病人の、余りにも執拗な願望のため、拒否し続けることの健康への不利益の方が、かえって、より大きいのではないかと判断し始めた女は、それでもためらいながら、服を着けたまま、ベッドの中へ、男の脇へ入っていった。男の、この愚かしさの原因は、まだ残っている麻酔のせいだろうと、女には思えた。「ほら入ったわよ。いい女でしょう」女は、冗談を言っている。男は、望みが叶い、にこにこと笑い、笑いが一向に止まらないといった風だ。勿論、少しでも賢い平均以上の男なら、平均どころか大多数の男なら、もしかすればこの男以外の全ての男性が、こんな時に、こんな事を望む、しかも衷心よりそれを喜ぶ、そんな馬鹿なことは、望みようもないし、考えようもないし、いわんや実行に至っては、あまりに法外な、愚の骨頂、痴の極、痴れ床虜情、と考えるだろう。当然である。それが、尋常、穏当、賢明、無事、というものである。ところが、この男と来た日には、事ここに到っても、まだ普段の悪癖から抜け切れないのである。隣接、近接、交接…要は、美の深奥への接触である。勿論、目下は、それは不可能だろうけれど…それでも、男は、ねえ、ねえ、と、ねだっている。ねえ、はやく…女の柔らかい肉体が自分の脇に横たわっていてくれてこそ、初めて男は心の安らぎを覚える。心のうちのどこかに潜む、不安や苦悩や、苦痛はすっかり消え去り、空は青く青く澄み渡り…「麻薬の後に、また麻薬」男は女の頬に、眼に、鼻の穴に、首筋に、そこら中に…恭(うやうや)しいキスをしながら、そう思う。しかし、この麻薬には、実(じつ)がある。まるで麻薬ではない麻薬みたいだ。 「また何か、変なこと考えているでしょう。…わたしにはすぐ分る」小声に、まどろむ様に、耳元で、女が囁いている。 「なにも」男は、うそぶいている。 女は、手の平を男の額にあてがい、強く押して、男の上体をのけ反らす。そして、目の奧底を覗き込む。まるでその一瞬で、男に、すっかりすっかり身を任せるか任せないかを決めにかかっているみたいに。 男の腕が女のからだに巻きつく。それは蔦のようでもあり、小動物のようでもある。女は、顔を、男の胸に埋めている。その唇は、ときに男の首筋に口づけし、ときに熱い息を吐きかけ、やがては、狂おしく、その肉を噛み締めるようなこととなるのだろうか、どうなのか。…女は、あえぎ、苦しさに身もだえし、小さく悲しく泣き声を漏らし、最後には、やはり男の肩の肉を噛みしだくこととなるのだろうか、どうなのか。男の肩には、突き刺さった女の歯の痕が赤黒い色をして残り、そして、ずっと後になっても、もし、バスにでも浸かれば、そこには湯がしみて、ピリピリと、きっと、痛みを感じることとなるのだろうか、どうなのか。 …女は、ときに髪を振り乱し、首筋をのけ反らし、背骨は弓なりに反り返り、膣の肉はリング状に、万力みたいに、圧倒的に、恐ろしいまでの力で…締めつけてしまうのだろうか、どうなのか。底揺れする大地。奥の奥、果ての果てから、おびただしい洪水が押し寄せてくるまで、どうしようもないこの悲しみみたいな絶無の時が… 女は、いま、男の指を握りしめ、狂おしく口づけする。「美しい指、あたしの指…信じられないくらい、鋭いものなのね…」 女は去り、男には、苦悩の時が始まる。それは、女の自由からもたらされるものに違いない。しかし男は、愚直にも、すべての女は自由でなければいけないと思っている。結局は、自分の苦しさから、彼女と別れなければならないようなこととなるのだろうか。女の自由は、男の不自由であり、もし男が自由の方に近づこうとすれば、きっと今ある女の自由を束縛することとなるだろう。これは望めないだろうし、望みたくもない。彼女のいまある自由は、そのままにしておいてあげたい。(もしかすれば男は、少年時代に、自由を奪われた完全に悲惨な女を目の当たりにして育ってきたのかも知れない。そしてその結果として、一つの決意、固定観念みたいなもの、つまり、女を不自由にするようなことだけは自分は一生絶対にしてはいけない、ということが自然に心に決まってしまっていたのかも知れない)しかし、それにしても、自分も自由でありたい。しかし今や、それはどうも不可能なように思えてくる。不自由は嫌いだ、束縛も嫌いだ、と男は思う。未来は、百パーセント自由に取って置かなけばならない。もしそうでなければ、借金をしょい込むようなものだ。未来を食い潰してはいけない。それにまた、彼女の自由も、ほんの少しでも傷つけてはいけない。なぜなら、彼女は自分よりも、ずっと、優れた人間なのだから。だから、論理的には、もはや、どうにもならない。どん詰りみたいなものだ。ばら色の、無心の、朝焼けみたいな時は、すでに終わって過ぎ去ってしまったのだろうか。純なる時も、もはや終わってしまったのだろうか。愛の時も恋の時も、すべての好ましい時は、知らぬ間に、過ぎ去ってしまったというのだろうか。しかし、それにしても、耐えられない。苦しい。この苦しみが彼女との関係に必要な要件だとは分っていても、やはり苦しく、苦しみからは逃れたくなる…どうもここはむずかしい。実際、時によって、気がいろいろに変わっていけない。それは事態が正確に理解できていないからか、あるいは、自分の心がはっきりしていないからなのか、おそらくは、その両方なのだろう。事実というものも、個別の意識と無関係には存在し得ないのだから、可変的、ないしは、正確には、無限に深化し得るものとして捉えられなければならないのだろう。だとすると、それは、男には、どうしても不確定なもののように思えてくる。だから実際の決断に当たっては、事実と言えども、それは確固とした容易なものではなく、実に厄介な悩ましい事柄に映ってくる。弱い人間は苦しみ、そして苦しみからは、なりふり構わず、ただ逃れようとする。そもそもは、口づけなのだ。あの時、墓場で、あの口づけをせずに、我慢してさえおれば、こんな苦悩は味わわずにすんだだろうに。しかしその口づけも、今思い返してみても、どうにも仕方なかった事のようにも思える。今でも、やはり、あのような事態になったら、自分という男は、同じようなことをしていたのだろう。それは、最初の最初の事故のとき、彼女を一目見て好きになってしまったのだから、もうどうにもならない。考えてみれば、もう最初の最初からどうにもならなく、がんじがらめになっていたのである。因果の理法、つまり、因果関係の稠(ちゅう)密性、即ち、無限の因果関係の網目としての、つまりは、宿命、である。うまく、逃れる。うまく、逃れる。今となっては、これ以外に道はない。『逃れる』これが、自分のためだ。『うまく』これが、彼女のためだ。やみくもに、逃れる、ではいけない。うまく、だ。さて… 看護士が勢いよく入って来た。医者も、後に続いて入って来た。回診みたいだ。やっと、男の苦しみの時も、しばし中断されるみたいだ。 「どうです?」医者は言っている。手術をした医者とはまた違う医者みたいだ。若く、痩せて背が高く、誠実そうな感じだ。外科一般を受け持っている医者との事だ。看護士は、男の毛布を威勢よくひっぺがし、トランクスも当て物も、慣れた手付きで、何の躊躇いもなく、取っ払ってしまう。男の股ぐらは、見てる間に、丸出しだ。医者は手際よくちょっと睾丸に触れてみたり、左下腹の傷口の糸を調べてみたり、その接触は、素早く軽やかだ。 「一週間以内に退院でしょう」医者は言っている。 「大丈夫でしょうか?」 「大丈夫です」 「化膿などは?」 「大丈夫」医者は、いま看護士が準備している、ど太いリンゲルを指す。化膿止めの薬剤でもが、たっぷり入っているとでも言っているのだろう。 一週間。要するに、一週間、だ。 車のCDから、いま、『ジーラ・ジーラ』が聞こえている。…バンドはコンチネンタルだろう。行き交う車は、赤、黄、緑…ドイツ、フランス、イタリア…ヨーロッパの車が目立って多い。…時はタンゴ・リズムが刻む。このような時こそ、本来の時、つまり、我が時、真の時だと男は思う。 しかし、もし音楽を止めれば、即、自動的にカー・ラジオに切り替わり、それはまたも懲りずに、株式市況をやっているのか、どうなのか。陰の極か、それとも、陽の極か…悲観の誤謬か、楽観の誤謬か、そこのところは知らないけれど、他愛ないというか、微笑ましいというか、浮きつ沈みつ、この不確実性の上に、この純然たる大博打の上に(もし望めば、やり方にさえよれば、賭博以外の何者でもない事象にだってしてしまうことが十分可能だろう)この軟弱な動態の上に、まさにこの世は乗っかろうとしているのだろうか、どうなのか。現にある、この世の、純にして聖なる一切のものも、それのみでは、絶対的には、もはや存在しえない、とでもいうのだろうか。(現実は、人々が考えていた計画性(観念)を越えていた。計画性を遥かに超えたものとしてこの世は常に現れる。世は、望ましく、豊饒なのかも知れない)信じられないような軽薄さと共にしか、あるいは、それと抗(あらが)いながらしか、純正が存在し得ない。善きも悪しきも、その存在を主張する。すべてが在り、すべてが抗う。自由は永遠になく、にもかかわらず、ないしは、それゆえに、希求され続けられ… 〈センセイ〉からの連絡である。「やあやあ」と、ちょっと、普段とは違った感じの話しぶりだ。「株、駄目ですよ…目減り、目減り…半減しています、半減以下?厳密には…。…山林も、馬鹿落ち…含みは、吹っ飛んでしまいそう。…もう、坊ちゃん、大変、大変…。…公定歩合さえ、下げてくれれば、すぐにもまた上昇が…。…ポートフォリオ理論などというものも、下降期にあっては、何の役にも、屁の突っ張りにも…ニューヨークでならいざ知らず…下がる日にゃ全部が全部、一様に下がる。打つ手など何もない。何でもかんでも下がりまくる。自棄自棄(やけやけ)に下���る。頭に来るといった程度じゃすまない。勿論、頭にも来るが…。動悸、胃炎、便秘下痢、痔痛…ドタマのみならず、心臓、胃、腸…もうすっかりすっかり全身だ。全身打撲。まるで、大木の…椋(むく)の木のてっぺんから落下して直接地面に叩きつけられた様な…殿様蛙がアスファルト道路に力いっぱい叩きつけられたみたいに…ところで、話が、おっとっとっとう…しかし、坊ちゃん、これは本当はチャンスなんです。売り買いさえ、あなたが許してくれればですよ。下がり切る前に売っ払ってしまい、下がり切ってから買い戻しゃいいんです。大儲けです。ところが、あなたは売買を許してくれない。禁止している。滅茶苦茶ですよ、これは。インカムゲインなど、定額預金とは違いますよ、株式は。キャピタルゲインこそが、目下の東京市場の…実際、無茶苦茶です。信じられない。売り買い禁止。何ですこれは?まったく馬鹿げた事です、これは。…」 「株は、おやじのものだ。おれが買ったものではない」 「それは、言い逃れです…相続してしまえば、その瞬間、あなたの責任です」 「今は、忙しい。何と言っても…」 「その内その内で何年経っているのです」 「生活費は?大丈夫?」 「それは、まあ、いくら下がったといえども当たり前のことでして。おそらく、二、三百年がところは、きっと…配当と含み益とでですな…まあ、ほとんど永遠分くらいの生活費がですな、無茶使いさえしなければの話ですよ…つまり遊蕩無比…マカオ、モナコ、ラスベガス、バーデンバーデン、ここいらで派手にやりまくれば、一夜の夢で、全部が全部吹っ飛ばそうと思えば吹っ飛ばすことだって出来ないことはないでしょう…永遠にですな…」 「まあ、管理の方は、いろいろ手続き等、手間も大変だろうけれど、今後とも、よろしく、お願い、ね」 「お任せお任せ…任せといてくださいまし。…ときに、坊ちゃん、傷口の方は?その後、いかがです?」 「痛い、痛い、まだ痛む。手術医が変なことしやがって…ヤブだ、何か肉より硬いものを、プラスチックか何かだろうな、勿論、硬質の物ではないだろうが、合成もん?軟質の、埋め込んだみたいな感じだ。漏れ口が分らなかったものだから、ヤマ勘で、その辺り一体の精管をカバーするためにだ。だからそれが周囲の肉に突っ張って…」 「痛む?」 「痛い痛い、痛くって…うまく肉になじまないようなことになって水でも溜まると、またまた切開だろうな、これは。まだ固まっていない、ぶよぶよの肉を、だ。また切開…ヤブだ。ボンクラ。真のヤブ。真っ暗闇だ。もっとも、こちらも悪いのは悪いらしい。つまり、この種の傷は名医といえどもなかなか分らない場合が多いらしい。ヤブならずとも…どこから精子が漏れているのか、発見できない場合が珍しくないみたいだ。これは別の医者の意見だがね。それにしても、どんなところでも、事実あんなところでも、使い過ぎ、肉の使い過ぎ、無理、酷使、こいつは怖い…肉は弱く、極度に弱く…されど、肉以外には、人生、何も無いと来ているんだからな。分らない。生きているということは、まったくの無明みたいにも、思えてくるが…」 「またまた、弱気を…急速に。…急変するんだから。しっかりしなきゃ、坊ちゃん、腐る程あるんだから、少し海外旅行にでも。憂さ晴らし。今のままでは、もったいない。猫に小判だ。実際、今日日(び)、大多数の者が、遊蕩三昧、やってるんだから…」 「まあ、それは、しかし、平凡、かつ、安易、…と違うか…カネで出来る事と言えば、すべて、ありきたり、単純かつ陳腐、本当は退屈なのと違うか。旅行会社、航空会社、ホテル、の仕組まれたカラクリの餌になっているだけと違うか。窮屈と余裕。悦楽は余裕にこそあるのであって…そうではないか?自他共の余裕。余裕のあるもの同志。相手あっての悦楽なんだから」 「またまた、格好付けちゃって。格好付けた小難しいことおっしゃって。坊ちゃんのこと思って言ってあげているのに…」 「ああ、ごめんごめん。キン玉のせいかな。イン(陰)でゴタゴタ起こされて…インの反乱だな。車に乗っただけでも痛むんだから、やりきれない。まるで何かに復讐されてるみたいな感じだ。早く万端すっきりとしてくれなくては、困る困る」 「どう?…痛みは?」女が訊く。暗闇の中で、男の肩の辺りに擦りつけていた女の顔が、少し、いま、蠢いたみたいだ。男は、仰向けに寝て、真っすぐに身を伸ばしている。 「ほとんど、痛まなくなった。段々良くなっている。痛みというより、いまは、違和感が少し、といった程度」 「よかった」 「うん」 「今度は、胸」 「うん」 「あまり乗り気でないみたい」 「うん」 男の、胸の上に乗っていた女の手も離れて行き、すっかり、男と女の身は離れてしまう。 「全然、乗り気でないみたい」 「うん」 「しっかりなさいよ」 「うん」 「ねえ…」 「苦しい」 「何?」 「全部が、苦しい」 「苦しくっても、切るべきものは、切らなきゃ」 「ううん」 「厭になったの?」 「…そんな…。苦しい。苦しい。要するに、苦しい。…ただ、苦しい」 「弱いのよ」 「そうかも知れん…」 「わたしから見れば、信じられないくらい。強いところは、またヤケに強すぎるくせに…」 「そうかも知れん…」しばし沈黙。静寂の時が流れた。それから男が言った。「ねえ、…」 女は何も言わなかった。男は、しまった、と思った。どうして別れることなど出来るだろう。嘘をついているのだ。もう何も無くなってしまうだろう。彼女こそが、この世なのだ、と男は、いま、思う。彼女の有する一切の価値のこと、彼女の美と愛らしさのことを考えれば、彼女と別れるなどということは、嘘である。虚弱。能無し。卑劣。卑怯。…まあまあそう堅苦しく考えないで…恋をしてるんだろう。恋などというものは、もっといい加減に、軽やかに、まるで風の中の羽根のように…できることなら、もっともっと軽妙に、恋というものの本質に似っかわしく…しかし、俺には出来ない。俺は、まるで、男と女のことを、なにか行(ぎょう)か修行か苦行か…まるで人間関係の研究題目、分析対象…実際、堪ったものでないだろうな、パートナーは…。これは野暮というものかも知れないぞ、相手の身にもなってみろ、愚物、うすのろ、脳足りん… 「物凄いテレパシー…」 「至近距離だものね」 「我慢できないの?」 「理屈では、分っているつもり。しかし何か余分な、はみ出たところ、仮、分ってもどうにもならない脳味噌内の暗闇…そのことを思うと非常に苦しくて…。勿論、あなたのせいではない。少なくとも、あなたにどうこう出来る問題ではないでしょう。どうにもならない事。あるいは、結局は、ぼくの頭、考え方…。もう二度と、あなたのような美しいひと、魅惑的なひと、強力なひと、愛らしいひと、可愛い人…一生あなたのようなひととは、二度と会えない…きっとそうだろうと思う。でも、いま、それでも、愚かにも、薄情にも…」 「わたしは、一瞬のうちに、見つけたの。そしていままた、一瞬のうちに、見失おうとしてるんだわ。わざわざ、墓場まで、跡をつけたというのに…」 「それで、墓場で、出会えたの?」 「そう」 「ね」と女は言う。「あなたに、いい女(ひと)できてもいいから、ときどき、あたしたち、一生、会いましょう…」 「うん」と男は言う。しかし、内心、それはできないだろう、と男は思う。 男が、この年上の女と別れるにあたっては、この会話から、なお九年という膨大な刻々の快と苦の稜線でのさ迷い、が必要だったのだろう。そしてその別れの結果はといえば、女は、単に一人の男を失ったというに過ぎないのだが、男は、一生心がひん曲がる程の、ほとんど全快不能ともいうべき程の深手を…。もっとも、男の鼠蹊部の手術の方の傷跡は、きっと、今ではすっかりすっかり黒々とした陰毛に覆われて、見た目には、手で直接触れてでも見ない限りは、跡形も無く快癒しているのだろうけれど。 それとも全然そうではなくて、別れ話など一切無く、男は女のすすめに忠実に従い、��の手術も受け入れることとなったのだろう。しかし、手術後、その日の夜半、不意の水道事故により、使用中の医療機器(右肺上葉切除並びに下葉癒着剥離手術後の出血を体外に吸出するもの(ベルヌーイの定理でもを利用しているのだろう))が停止するという極めて稀な突発事故に見舞われ(また、加うるに、このような際には、水道水使用機器から、直ちに電気使用機器に交換する定めになっているのだが、当直の看護士も予想だにしなかった事故だったので、真夜中過ぎから夜明け頃までの機器停止の事実に気付かなかったというミスも重なり)不運にも、男は、予想外に短かかった生涯を、閉じることとなってしまった。 死の間際の男の想いに関しては、定かなことは一切何も分っていない。手術室へ入って、手術台の上に横たえられ(男は、裸で、空色のタオル地のブリーフだけを身に着けて、触れるとヒヤッ、と感じられるステンレス張りの平板そのものといった風の、手術台に横たわった)次いで、麻酔医がマスクで男の鼻と口をすっぽり覆い、男に深呼吸を促す。麻酔医が数を数える。ヒトーつ、フターつ、ミッ、くらいまでは男の意識も確かだったのだが、しかし、その後はもはや何も…またもや、無、死のような無、完璧な無、が…。おびただしい、メスによる肉の切断と出血の数時間(癒着剥離に手間取り予定を2時間以上もオーバーしたらしい)その間にも、想いなどというものは、男には何も無い。皆無。手術が終わってリカバリ(リカバリー・ルーム)へ移されてからも、何も無い。無であり、死同然である。多量の血痰も、口許までは無意識に押し出される。まだ自律的に肉ないしは神経系統は作用しているのであろう。しかしそれ以上は、すべて看護士の努力によらなければならない。男の意思とか努力とかは全く関与していないのだ。機能しているのは、たかだか、無意識の、自律反射的なものだけなのだ。しかし、こんな不十分な意識の状態にある男にも、この世の最後の最後、この一瞬、つまり、真際、今はの際(きわ)、ともなれば、脳に、信じられないような、異常に急激な変化が起こり、ほんの束の間とはいえ、意識が、閃光のごとく、明々(あかあか)と甦り、照り、映え、映え反(か)える。男は、ここに到って、女への想いを馳せるのだろうか、どうなのか。もはや、苦しみも、悩みも…悪の想いはすべて過ぎ去ってしまい、今では、ほほ笑みだけが、愛の想いだけが、完璧な充足が… さよなら、愛しいひと、ぼくの女友達…片割れであり、相棒であり、深い時を、ときに珍奇な時を、共に分かち合った懐かしいひと…ご機嫌よう、好敵手、美しく高貴な、ぼくの大切な大切な大切な…男の想いは、なおも、明々と燃え上がり、その輝きの、照り返しのうちに、こうして、いま、生きて在ること自体への驚異と感動の念が、すべての存在物への共生感が、共に存在するものとしての、砂利道でダンプカーに轢かれて行く、そこに転がっている、石ころ達への友情が、すぐに、男もそうなるであろう、宇宙を漂う一つ一つの塵への、粒子への、永遠に共に存在していることへの充足と無としての完全な安泰の念が、男の身の内に込み上げて来たのだろうか、どうなのか。…このような意識の状態で、つまり、光輝のうちに、男は最後の息を引き取れたのだろうか、どうなのか…
(連絡先:[email protected])
0 notes
Text
涼風に鳴る幽かの怪―壱
リン―― 鈴の音が聞こえる。何処からだろう……。鈴なんて、この部屋には無かった筈なのに。見慣れぬ嫁入り道具に、着古した袴が何処か懐かしさを感じさせた。 「――ま、ちゃん……」 ……何て? 「た――ちゃん……」 どこかで。 「たま、ちゃん……」 「――え?」 私を、呼んだのは、誰。 薄らと開いた視界の向こうには見慣れぬ明るい朝の景色が広がっている。滲み一つない天井に、ふかふかとした布団が自分の身体を護る母体の様に感じて違和が胸を過ぎる。 いや、違う。これは何時もと変わりない『朝』の筈なのだ。 使い古した枕に頭を埋め、畳みの目を眺め数える。嗅ぎ慣れた香りが心を落ち着かせる。妙に懐かしさを感じる夢が、頭の中を渦巻いていた。 ……何の夢だったのだろうか。あれは、何処かで体験した事のあるような――何処かで聞いた事がある声だったのだろうか。 たまちゃんと、そう呼んでいた名前には覚えがある。 覚えが――ある……? 小さな欠伸を漏らしながら小鳥の囀りを茫と聞き続ける。 水を掛けられたかのような感覚ですくりと起きあがった『たま子』は「懐かしいわ」とぽつりと呟いた。 長い髪を結わえながら、布団の上から立ち上がった彼女は纏わり付いた寝間着をさっと脱ぐ。何時までもこの格好では義母が頭ごなしに叱る事を彼女はよく理解していたからだ。 「もう朝ですね、起きてらっしゃる?」 はぁい、と間延びする声を返して彼女は朝餉の用意の為に板張りの廊下を走る。義母の事など、どうでも良いがたま子にとっては腹を空かせた愛おしい旦那様の方が一大事なのだから。 年若くして良縁に恵まれ嫁いだ彼女は頬をぺちんと叩く。やる気を漲らせる様に淑女にはあるまじき「よしっ」と発した声は若草香る女学校の頃に教師達に叱られた仕草だが、嫁いだ後も抜ける事が無い。 「たま子さん!」 叱るような声に慌てて走る『たま子』は小さな息を付いた。 毎日は代わり映えしない。 数年前にはお上の神人なる方が死去し、『明治』から『大正』に改められた年号が何処かくすぐったい。年号が変わると言うのは重大な動乱だ。その波に乗じてか世間では様々な革命や騒動が起こっている。それでも安寧なる生活が送れるのは女学校で習った内閣制度や政治制度を制定した英雄達のお陰であろうか。もしも、英雄たちがいなければたま子だって今の旦那様とは出会えていなかった――かもしれないのだから。 浪漫を語るのは女学生ならばお手のもの。それこそ殿方に見初められる経験をしたならば、それに拍車がかかるのも仕方がないというものだ。 「ふふん」 鼻を鳴らし誰へとでもなく勝ち誇ったたま子は朝餉の用意を中途半端に済ませた義母へ何と声を掛けようかと考えながらゆっくりと廊下を進む。 ちりん―― 『また』だ、と。感じたのは夢の中でも聞いた音だったから。 懐かしい夢だ。旦那様に見初められ、女学校を去る際に、親友に手渡した風鈴。そして、その会話。 嫁入り後に幾度か交わした手紙も何時しか途絶えてしまった。人の記憶が箪笥に例えられるならその奥深く��仕舞いこんでいた思い出とでも言えば随分とを感じられる。 「八重ちゃん……」 鈴の音は、その名前は、懐かしい音色を孕んでいる。 訝しげな表情を浮かべながら洗い場へと降りて行くたま子の背に彼女の『旦那様』は「いかがなすった」と可笑しそうに笑ってみせた。 珍しく朝寝坊をした嫁が訝しげな表情をしているのだから、気にも止めるというものだ。からからと笑う旦那君にたま子はむっと唇を尖らせて「あのねえ」と振り仰いだ。 「鈴の音が聞こえるのですわ」 「鈴? 風鈴などないけれどね」 首を傾げる彼へとたま子は小さく頷く。 また可笑しな事を言って気を引いたと笑う旦那君にたま子は拗ねた様な顔をして背を向ける。 たま子は勝気で明るい娘だ。成金の娘や財閥の令嬢と違い、脊髄反射で動き考える少女だったのだから、旦那君が可笑しなことを言うのは気を引く為だと笑うのだって致し方が無い。 「酷い御方ですこと」 「母さんが居るからと、そう肩肘を張らないでおくれよ、たま。そんな気難しい顔をして、鈴の音が聞こえただなんて……夢の続きを見ている様な顔をしているよ」 肩を竦め、御名答ですことと小さく返す彼女に旦那君はからからと更に笑った。年の数は幾分か離れている。だからこそ、幼さを感じさせるたま子の仕草を旦那君は気に入っていたし、旦那君は童話を語る嫁が己との対話の為に作り話をしていると考えたのだろう。 「夢で見たのです。嘘ではないですよ」 「嘘でないと」 はて、と首を傾げる彼へと記憶をなぞる様にたま子は語る。 嫁入り前に親友とした会話がありありと思い出される。 あの時、彼女に手渡したのは――鈴だったのではないだろうか。己の後ろに何時も隠れていた可愛い小さな『八重ちゃん』。病がちで女学校を休んでいた彼女の健康を祈って手渡した風鈴の音に似ている気がする。そう言えば、彼女は―― 「……悪い夢ですこと」 ふるりと首を振ったたま子に青年は「そうかね」と椅子へどかりと腰掛けて興味深そうに呟いた。 たま子の思い出は何処までも美しいものだった。 『たまちゃん』 結った髪が風に揺れている。秘密の場所と咳込む彼女の手を引いて、二人きりの場所へと走って行った。 『ねえ、たまちゃん』 記憶を辿って、たま子は静かに眸を伏せる。 風鈴。そんな季節になったのだろうか――夏の気配を存分に孕んだ空を見上げてたま子は小さな溜め息を付く。 風鈴……。軒先に風鈴を飾る家は少なくない。この家には飾って居ないはずなのに、どうしてこうも近く聞こえるのだろうか……――。 ちりん―― (風鈴ね、きっと――……) ふる、と首を振る。違和感が首を擡げたまま存在している事に『脊髄反射』で動く彼女はどうしても抑えられぬ衝動を我慢する様にうずうずと身体を動かした。 あの時、彼女と話した内容はよくよく覚えている。 白い肌に、良く映える臙脂色の召し物は結婚式には伺えないからとわざわざ誂えたものを着てきたのだと言っていた。 秘密の場所で、向かい合って二人きり。臙脂色に包まれた彼女は何処までも高尚な存在に見えて――眩しかった。 『結婚するのよ』 ゆっくりと、その言葉を彼女へと告げた。 知っていますと頷く友人は切なげに笑って手にした花束を差し出してきた。両の掌に抱えきれない大輪は百合の花――令嬢が選んだ一番に愛おしい華なのだという。 『たまちゃん……』 呼び声に、小さな咳と瞬きが今も鼓膜や網膜に張り付いている。頬に張り付いた髪に、涙の意味が分からなくてたま子は小さく首を振った。一緒に居られないと手を伸ばし、抱きしめた華奢な身体は微かに震えていた事を覚えている。 『たまちゃん、幸せになってね』 『ええ。わたし、幸せになる為に結婚するのよ』 きっと、彼女は幸せになれない―― 心のどこかで知っていたのかもしれない。老い先短い彼女と共に在る己に優越感を感じていたのかもしれないし、その短い生で誰かを思いやる彼女の高尚さにお得意の浪漫を感じていたのかもしれない。 『わたし――……たまちゃんみたいになりたかった』 八重ちゃん、と唇の端から漏れだした声に旦那様は首を傾げる。そうだ、八重子ちゃん。彼女は今、どうしているだろうか。 ゆっくりと炊事場から歩きだし、玄関先へと歩を向ける。 電報を実家に飛ばせば彼女の事は解るだろうか。 八重ちゃん。八重ちゃん――かわいい、私の親友。 ちりん―――― 「そうだわ、風鈴……わたし、お渡ししたの」 「たま子?」 背に走った寒気にたま子は大げさな程に身震いを一つ。気付いてはいけない事に気付いたと顔を覆った。血の気が引いて行く感覚に、ふらつく足が縺れて畳みへとへたり込む。 「大丈夫かい?」 「風鈴、風鈴だわ! きっと、そうよ。そう違いないわ」 玄関先へ向かう足は震えて立てやしない。彼女の言葉に首を傾げた旦那君は「幽霊でも出たのかい」と冗句のように投げかけた。丑三つ時ですらない、ましてや早朝のこんな時間に幽霊などと余りに可笑しな話ではないか。 「冗談はお止しになって」と小さく笑ったたま子の胸に感じた妙な違和は『八重ちゃん』のその後を嫌な程に連想させた。旦那様は冗句の心算で発したのかもしれない。 死を想起させた病に罹った親友が生きているという証左もない――『風鈴』『幽霊』 もしかして……。 「ふふ、幽霊かしら? 風鈴のお化けなんて風流ね。貴方が怖がらせるからつい足が縺れてしまったわ」 「ああ、きみはそんなに怖がりだったかな? 虫だって平気で殺せてしまうだろうに」 小さく笑った旦那様にほっと胸を撫で降ろしてたま子は午後の予定を考えた。確かめよう。彼女の事を。 ちりん、と聞こえたその音色の意味を。彼女は、今―― 蝉の鳴き声が煩わしい。暦を数えて春を終えて、夏へと変化する頃に、怪談話はいくつも増えてくる。居間からは幽霊の話を交わす男女の楽し気な声が聞こえてきた。 買い出しに言ってくると告げた言葉に返事はなかったが、彼女は気にするそぶりもなく玄関へと足を向ける。 残暑だというのに求愛を口にする蝉たちのせいで耳から暑さが倍増されていく。開け放った玄関の向こう側は青々と茂った葉が妙に鬱蒼として見えた。 「お化けなんて家に居て堪るものですか」 拗ねた様に呟く彼女は玄関先の下駄に目もくれず洋物のブーツへと足を通す。履き潰すと決めていたのに、まだ使えるのだから英国からの流通品は中々に勝手が良い。慣れない紐を縛って、小さく頷く彼女は結わえた髪を確かめてから「よしっ」と気合を込めた。 「直らないものね」 先生から言われても、と付け加えたのは口癖の様になった『よし』の気合の入れ方。 幽霊が居るから陰陽師を呼びましょうと絵巻物で読んだ嘘に頼るのも、性質の悪い除霊師に頼むのも莫迦らしい。 そもそも、彼らに依頼するのは大金を叩いて自己満足を満たすだけではないだろうか。解っているのだ。記憶の中にあるその姿が、『幽霊』の正体だと――その正体を知っていて、知らない振りをしているのだから。 だから、彼女は『風鈴の幽霊』とそれを呼んだ。 ちりん―― 聞こえるその音に「いやね」ともごもごと口の中で呟いた彼女の視線はぴたりと柱へと向けられる。空き家になった軒に張り付けられた古びた紙切れは幼い子供の悪戯にも見えた。 「西洋インクだわ……」 何処かの商家の坊ちゃんの落書きであろうか。 滲んだ文字が読み取り辛いが、愛らしさも感じる文字の一つ一つを読み取ることが出来る気がする。じつと目を凝らした彼女はその文字を口にしながらゆっくりと読み上げた。 『ゴイライ オウケシマス ネコサガシ カラ ユウレイタイジ マデ』 なんともまあ、胡散臭い広告だ。 訝しげな表情で広告から目を離さない彼女の背後で女学生たちがくすくすとささめきあって笑っている。 「探偵様の広告はまだ張ってありますのね」 「本当。御依頼あるのかしらん」 巷では話題になるのだろうか。暇潰しや話題に作りには丁度良いのかもしれない――こんな西洋の高価なモノを使用した悪戯などそうそうお目に書かれない。 しかし『探偵様』。高価な紙にこの様に書いて帝都に張り巡らせるだけの財力があるならば、相当に頼りがいがあるのではないだろうか。もしくは、成金の道楽か。 女学生の噂の的となる位に胡散臭いのならば昼下がりの暇潰し程度でも良い。『お暇な探偵様』ならば困り顔で少女が尋ねれば相談位には乗ってくれるだろう。もしも凄腕であれど、仕事に困っていれば格安で引き受けてくれる可能性だってある……。 何より、探偵が幽霊退治をすると明言しているのだ。 霊能力者でもないくせに、ともごもごと呟きながら彼女は広告を剥ぎ取り描かれた住所と地図を辿り往く。 和洋の入り交じった街の中は、見慣れぬ物も沢山あった。 日本も随分と侵食されたものだと父達は口々に言っていたなと薄く記憶に残っている。馬車が走り、汽車が往く。三越にぞろりと集まる人波に目もくれず――否、誰の目にも止まらず、彼女は人気のない西洋の住宅の並ぶ丁番を目指した。 急ぎ足なブーツの踵を行き交う人の群れに取られてごろん、と大きく転ぶ。鼻先を擦り、肘に出来た傷口に痛いと不平を述べる彼女へと差し伸ばされる手は無い。知らん顔で歩く紳士に「酷い方」と彼女は悪態をつきながら立ち上がる彼女に帝都の風は冷たい。 よく、帝都は様変わりしたと言う人が居る。西洋の人間は和の心を持たず、素知らぬ女が転んだ所で助けることもないのだろう。これが、『帝都が様変わりした���『冷たい』とでも言うことなのだろうか。 文句を漏らしながらもゆっくりと立ち上がり、身震いを一つしながら足を向けたのは煉瓦に覆われた西洋街。帝都の街並みなんかより、もっと豪奢なその群れは、異国の情景の様だと彼女は息を飲んだ。 「……違う国の様だわ」 余りに見慣れぬ『帝都』 田舎町とは違い、明治期に完成した日本鉄道の巨大な駅。皇居の正面に出来上がった東京駅はとても美しい建築美だ。西洋の煉瓦作りの住居と比べ、祖国はまだまだ土と木で出来た『おんぼろ』ばかり。戯洋風建築だとか女学校では言っていた気がする――が、そんなこと忘れてしまった。 「凄い、おうちだわ……」 詳しい事までは知らないし、学問など軒並み役に立たないが、これはまるで西洋の強国へと紛れこんでしまったみたいではなかろうか。一度、紳士が講師としてやって来た時に、「英国の建築は実に素晴らしい」と褒め称えていた気がする。 素晴らしいの言葉に尽きるが、純和風の国で育った彼女にとって、この場所は居心地が悪い。 煉瓦の『西洋街』をそろりそろりと抜ける彼女は広告の地図を幾度も見直した。帝都の外れの空き家の軒先へと広告を張り付ける『なんとも奇天烈愉快な胡散臭い探偵』のイメージと掛け離れた豪華絢爛な街並みは庶民にとっては政府のお役人たちでなければそうそう足を踏み入れない場所でしかない。 「こういうの、横濱や長崎にあると聞いた事があるわ……」 ぶつぶつと呟きながら、彼女はゆっくりと地図から手を離す。そうだ、きっとこの洋館の群れを抜けた先に郊外の寂れたお屋敷がある筈だ。そうして、そこで探偵がボロを纏って待って――待っては、いない。 「……嗚呼」 思わず一歩、後ずさった。 これでは『道楽探偵』だろう。格段の安さで受けて貰うなんて夢のまた夢。成金か財閥の坊ちゃまや嬢が道楽の為に、適当に張った広告だったのだろう。 『脊髄反射で動くのはやめなさい』とはよく言ったものだ。 まさしくその通り――ここで幽霊退治など……。 「……貴殿、何を突っ立っている」 「は、はひっ」 眩暈を起こし、ぐらぐらと揺れた彼女の肩を『がしり』と掴んだ大きな掌は、少女を混乱させるに容易かった。 まるでの様に首を動かして振りむいた彼女を見下ろした青年は「何をしていると聞いた」と無愛想な表情で苛立ちと露わにしている。 齢にして三十が近いだろうか。ぴしりと襟を締めた陸軍の軍服は見慣れぬもので。日ノ本で神人へと誓いを立てた軍人様の問い掛けに少女は首をふるふると幾度も振った。 怯え、答える事の出来ぬ様子の少女にどうしたものかと青年将校は頬を掻く。短くしっかりとっと尾の得られた黒髪から彼の誠実さを伺えるが――そう言ってはいられない。西洋街に出入りすると言う事は、ここは何処かの『要人』の家なのだろう。そして、彼はそれを護る守衛とでも言った所か。 「……あ、あの……」 ぽつり、と零した言葉に耳を傾ける様に青年は「ふん」と小さく呟く。 「わ、私……広告を、見て、えっと」 「広告? ああ……狐塚の奴、広告を張ったのか」 『狐塚』 聞き慣れない言葉に首を傾げた少女へと青年将校はどうしたものとかと首を捻る。先程まで感じさせていた威圧感は何処か遠くへ飛んで行ってしまったかのように――幼い子供が悪戯を失敗したかのような表情を見せている。 「あ、あの」 ぽそりと呟く様に声をかけた彼女へと青年将校は鋭い眼光で射ぬく様に視線を動かして「なんだ」と口の中で言った。 正しく言えば『もごもご』と呟いた――のだろう。 軍人にしては可笑しな素振りだと茫と考える。そもそも、彼女は女学生の様な幼い風貌をしているのだ。そんな彼女に遠慮の一つをして見せる等、軍人としてあるまじき態度ではなかろうか。 (軍人さんというのは、案外お優しいものね……) 彼の顔をまじまじと見つめれば、鋭い眼光は煩わしいと言わんばかりにぎょろぎょろと動いている。 「なんだ、と聞いた」 「ん、ええと、い、依頼が――あの、依頼がしたくって……」 依頼、と。 その響きを幾度も繰り返す青年将校に少女は怯えきった表情で「だ、だめですか」と小さく呟く。 胸中では広告を出しておいてと憤って居ても、相手は武具を持った軍人だ。余りに勝手なことは出来ない。 「名前は」 「え、た、たま」 「では、たま。どんな依頼に来たんだ」 青年将校の態度は一貫して冷たい物だ。『たま』は要人護衛の任に就いた彼が曲者であるかを判断すべく質問しているのだと勝手な認識をしていた。 そう認識してしまう程の豪邸なのだ。財閥や成金、華族の住居だと言われても納得してしまうし、それこそ政府の要人の別宅だと言われても頷ける。 ああ、来なければ良かったと彼女の胸の中を駆け巡る後悔の念など知らずに青年将校は依頼の内容を教えろと苛立った様子でたまを見下ろしているではないか。 「う、あの、幽霊が……幽霊退治をしてくださると聞いて、お、お願いに来たの、です」 風鈴の幽霊――到底信じては貰えない事だろう。 幽霊を退治すると広告に書いてあるから来たと付け加えて視線をあちらこちらへと揺れ動かしたたまは青年将校の困り顔に肩を竦める。 「幽霊退治……ね。ああ、喜びそうな話だが――止めておいた方がいい。ここの主は、」 関わらない方がいい、と。 青年将校が告げた声に子供の明るい声音が被さった。 「お客さんなのかい?」 先程まで閉じられていた屋敷の扉が僅かに開いている。声の主は部屋の奥へと引っ込んでしまったのだろうか。その姿や影は無い。 頭を抱えた青年将校は「たま」と立ち竦んだ少女を手招いて扉へと手を掛けた。彼の困り顔は本当に情けなさを感じさせるものだ。まるで子供に手を焼いている様な――そんな、青年将校らしからぬ表情をして。 「どうやら狐塚はお前に興味を持った様だ。……どうなっても知らんがな」 狐塚と言うのは先程の声の主のことなのだろうか。 声からして年の頃はまだ若い。それこそ学生だと言われても納得してしまいそうな、柔らかな童の声。大層な悪戯っ子なのか、それとも手もつけられない財閥の坊ちゃまなのか――どちらにせよ、たまにとって『不運』であることには違いないと青年将校は念を押す様に付け加える。 「あ、え、」 「入れ。元より、招かれなくとも入るつもりだったろう」 「あ――……はい。あの、お、お名前は」 「ああ、俺は八月朔日 正治。 それでこの屋敷の主人は狐塚――狐塚 緋桐。 これは経験則から物を言うのだが、最初に忠告しておく。 あいつに関わると碌な事が無いからな。……まあ、もう遅いんだろうが」
0 notes