#J.W. Schmidt.
Explore tagged Tumblr posts
Link
0 notes
Video
youtube
MODERAT - MORE D4TA - FAST LAND (OFFICIAL VIDEO)
© 2022 Monkeytown Records Director: Ben Miethke DoP: Maximillian Pittner Editor: Michael Welcker Production: Le Berg Co-Production: Phantasm Music Video Commission: Matthias Klein c/o Magick Exec. Produer (Le Berg): Yannick Fauth Exec. Producer (Phantasm): Olivier Muller & Maeva Tenneroni Head of Production: Vera Mayskaya Producer: Samara Daioub Production Assistant: Meret Balmer Production Assistant: Lille Hansen Casting Direction: Ilaaf Khalfalla & Lea Gugler / First Encounters 1st AD: Yana Viktorova 1st AC: Florian Bellack 2nd AC: Carolin Obitz 3rd AC: Clemens Szelies Steadicam: Yoshua Berkowitz Drone Operator: Maximilian Raschke DIT & VTR: Aljoscha Samain Gaffer: Thorsten Kosellek Best Boy: Tim Bornhöft Electrician: Philipp Lange Electrician: Luca Stoll Light Assistant: Taha Schulze Bord Operator: Lukas Hippe Key Grip: Börge Wiesenthal Grip: Stephan Gallinat Crane Operator: Christoph Sobisch Truck Driver: C. Ayguen Driver/Runner: C. Pintor Runner: M. Sehmrau Visual Effects Supervisor: Samara Daioub, Felix Geen Styling: Natalia Wierzbicka Styling Assistant: Pauline Reitzig Hair & Make-Up Artist: Christian Fitzenwanker Set Design: Stefanie Grau Set Design Assistant: Arabella Romen Head of Post Production: Samara Daioub Post Production (Phantasm): Maxime Dabel Co-Editor: Martin Malnoë Data Artist: Harald Schaack / grotesk.group Assistant Data Artist: Denis Sokolowski / grotesk.group Color Grading: Nicke Cantarelli Title Design: Johannes Geier Compositing & Retouching: Felix Geen Retouching: Anthony Lestremau Neuroimaging: Lucius Fekonja Main Cast: Skjold Rambow, Mitja Over, Sofia Lordanskaya, Linus Gross, Phil Stahlhut, Toni Heinig, Marie Birger, Hans Heyduck, Michael Reinhold, Alex Schmidt, Erik Schwede, Oumou Aidara, Emma-Belinda Müürsepp, Linh Truong, Magali Greif, Lam Funke, Hans Heyduck, Sarah Al-Azab, Lukas, Justin Bornschein, Ali, Leo Bunte, Lilian Anderson, Nokia, Alex Batonon, Naomi Eyele, Luise von Cossart, Marek Gouders, Luka Ahrens, Libert Supporting Cast: C. A. Barrero, F. Ahmad, Min Kha Le, J. Joosten, Ha my le thi, S. Klockenbusch, H. C. Francisco, A. L. Wolfe, L. Kreißl, S. Schäfer, Yi-Wei Tien, Y. Shin, Lara-Marie, M. Hoang Nguyen, H. Stork, S. Pomplun, A. Sprenger, L. Killing, Z. Mawududzi Ablavi, A. Wencelides, N. Brummer, M. Bonakdar, A.Kuyatsemi, A. Kogge, G. Söder, J. Beck, D. Tran, M. I. F. Garcia, L. Rütters, X. Lan, F. Bashir Abdulkadir, K. Mehrabizadeh, Honarmand, A. Gronas, Q. Kasenbacher, B. Tamenut, R. Yapar, K. Baholzer, N. Susyak, Helina, Brenda, Rephe, Tarek, Skylar, Luna, Till, Yi-li, J. Zhang Zooming into the black hole jet in M87: NASA, ESA and G. Bacon (STScl); constellation Region of Galaxy M87 credit: A.Fujii; Galaxy M87 credit: R. Gendler; Hubble View of M87 Jet credit: NASA, ESA, E.Meyer, W.Sparks, J.W. Sparks, J. Biretta, J. Anderson, S.T. Sohn, and R. van der Marel (STScI), C. Norman (Johns Hopkins University), and M. Nakamura (Academia Sinica), and G. Bacon (STScI) The ISS 30 minutes before the Crew Dragon...who didn't show up, Paris, May 27 2020: Astrophotogrpahy/ Digital imaging (CCD) by Thierry Legault - astrophoto.fr/ [email protected] The completed SDSS-IV extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: 1000 multi-tracer mock catalogues with redshift evolution and systematics for galaxies and quasars of the final data release: Cheng Zhao, Chia-Hsun Chuang, Julian Bautista, Arnaud de Mattia, Anand Raichoor, Ashley J. Ross, Jiamin Hou, Richard Neveux, Charling Tao, Etienne Burtin, Kyle S. Dawson, Sylvain de la Torre, Héctor Gil-Marín, Jean-Paul Kneib, Will J. Percival, Graziano Rossi, Amélie Tamone, Jeremy L. Tinker, Gong-Bo Zhao, Shadab Alam, Eva-Maria Mueller, LASTRO_EPFL, https://youtu.be/Ld5kE1k8-Ls, and licence (CC-BY) Differentiation-of-Apical-and-Basal-Dendrites-in-Pyramidal-Cells-and-Granule-Cells-in-Dissociated-pone.0118482.s003.ogv: Wu Y, Fujishima K, Kengaku M (2015). "Differentiation of Apical and Basal Dendrites in Pyramidal Cells and Granule Cells in Dissociated Hippocampal Cultures". PLOS ONE. DOI:10.1371/journal.pone.0118482. PMID 25705877. PMC: 4338060. AutoNeuron technology in Neurolucida 360: Automatic 3D Neuron Reconstruction and Quantitative Analysis - Neurolucida 360 software, MBF Bioscience 185 Allen Brook Lane, Suite 101, Williston, VT 05495 USA Automatic 3D Neuron Reconstruction and Quantitative Analysis - Neurolucida 360 software, MBF Bioscience 185 Allen Brook Lane, Suite 101, Williston, VT 05495 USA: Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Brain Mechanism for Behavior Unit (Gordon Arbuthnott), 1919-1 Tancha, Onna-son, Kunigami-gun, Okinawa, Japan 904-0495, https://www.oist.jp/video/imaging-rev..., licence (CC-BY)
2 notes
·
View notes
Photo

CSS Alabama (1862-1864). 1961 painting by Rear Admiral J.W. Schmidt, USN, depicting Alabama in chase of a merchant ship. Source available in comments. via ImaginaryWarships
6 notes
·
View notes
Text
Uruguay contra Sudáfrica (1906)

Combinado uruguayo. De pie: Guillermo McFarlane (árbitro), Carlos Urioste, Cayetano Saporiti y Juan Bertone. En la fila de en medio: Luis Carbone, Francisco Branda, Pedro Zuazú y Leonardo Crossley (linier). Sentados: Carlos Cuadra, Gonzalo Rincón, Juan Peña, Alejandro Cordero y Cándido Betancourt. Se han añadido nuevos datos, completado vacíos informativos y subsanado errores en la subsección Uruguay contra Sudáfrica (1906) de Curiosidades celestes.
Recordemos que tras muchos retrasos los sudafricanos se presentaron en Montevideo en la calurosa tarde del miércoles 18 de julio en el Gran Parque Central. A pesar del elevado precio de la entradas una concurrencia estimada en 5.000 espectadores se hizo presente para presenciar el match frente a un combinado de nuestra League formado por seis jugadores del Club Nacional de Football, cuatro del Montevideo Wanderers y uno del C.U.R.C.C. El encuentro fue arbitrado por el Sr. Guillermo MacFarlane y como era de prever los sudafricanos golearon seis a uno al entusiasta equipo local. Tras ello volvieron a Argentina para disputar un partido más y se despidieron del continente en San Pablo, donde le endosaron un 6-0 a la selección brasileña.
Recordemos que hoy soplan velas dos clubes uruguayos.

Sudáfrica. Fotografía del team que enfrentó a Montevideo XI.

Sudáfrica. Otra foto del equipo sudafricano. De pie: W.G. Brown, F. Findlay, A.W. McIntyre, G. Hartigan, W.F. Schmidt y H.J. Henman; sentados: A.W. King, R.F. Thorne, J.H. Robison, H.N. Heeley, T. Chalmers, W.T. Mason y R. Taylor; en el suelo: E.H. Johnson y J.W. Binckes.
#Amateurismo#Uruguay#Época Amateur#1906#Sudáfrica#Nacional de Montevideo#Club Nacional de Football#Wanderers#CURCC#Argentina#Brasil#Quilmes
0 notes
Photo

An oil on canvas painting by Rear Admiral J.W. Schmidt showing the US Navy 74 gun ship of the line U.S.S. Delaware.
0 notes
Note
Identity asks: 1, 15, and 19?
1. if someone wanted to really understand you, what would they read, watch, and listen to?
I LOVE this question.
So.
Read: roman love poetry and greek drama (to understand my educational background), a LOT of Robert Frost, Harry Potter, LotR, (my own writing? does that count?), Faust (an absolutely *genius* drama by J.W. Goethe, this is something I think a lot of Germans would identify with when it comes to literature in general. Also his poetry, and F. Schiller’s poetry. Seriously, try it). Les Miserables…
I’m gonna stop. This list could go on and on and on…
Listen: Rachmaninov (first and foremost). Beethoven. Queen. Sinatra. Billie Holiday. I see fire by Ed Sheeran. La mamma morta from Andrea Chénier by Umberto Giordano. Joseph Schmidt (a german lyric tenor who was best known in the 30s/ 40s), Glen Miller, Nessun dorma from Turandot by Puccini. (This is all so random??)
Watch: Oi. Don’t think there’s any specific movie or tv series or anything of the like that would tell you very much about me? I feel like music and poetry (and prose, to a certain extent) would give more
15. five most influential books over your lifetime.
See above for the sake of the length of this post.
19. which Harry Potter house would you be in? or are you a muggle?
I’m in Hufflepuff :)
Thank you for the ask @5ftgarden. It took me a while since my cat spilled soda all over my old keyboard a few days ago and I had to order a new one :/
3 notes
·
View notes
Photo
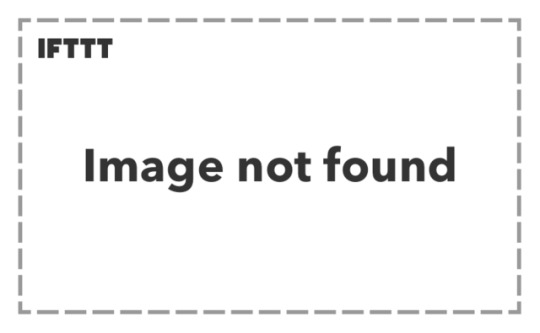
ソフトウェア工学 「第 1 章 ソフトウェアとは」のまとめ https://ift.tt/2Jr0D0P
これは
1. 現代社会を動かすソフトウェア — 1. 社会のインフラとソフトウェア — 2.ソフトウェアの語源
2. ソフトウェアの特徴 — 1. ソフトとソフトウェア — 2. あらゆる分野が対象 — 3. ハードウェアのソフト化
3. ソフトウェアの種類 — 1. 情報システムと組み込みシステム — 2. 汎用性品と注文製品 — 3. システム・ソフトウェアとアプリケーション — 4. オープンソース・ソフトウェア — 5. サービス思考とクラウド・コンピューティング
4. 誰がどう作るか — 1. 情報産業 — 2. ソフトウェア技術者 — 3. ソフトウェアの生産体制 — 4. 人間的側面
以上
これは
放送大学大学院文化科学研究科の「ソフトウェア工学」という授業で使われる「ソフトウェア工学」という教材書籍を自分なりにまとめたものです.
放送大学 授業科目案内 ソフトウェア工学(’13)
第 1 章では, ソフトウェアってそもそもなんなのか, ソフトウェアの歴史や, 様々なソフトウェアの特徴について, 幾つかの例をあげつつ説明されていて, SaaS やクラウド・コンピューティングなどについても書かれていました.
尚, 本まとめについては, 以下の Github リポジトリで管理しており, 加筆修正はリポジトリのみ行います.
software_engineering - 放送大学大学院文化科学研究科 / ソフトウェア工学 inokappa/software_engineering - GitHub
github.com
1. 現代社会を動かすソフトウェア
1. 社会のインフラとソフトウェア
現代社会のインフラストラクチャー
道路, 鉄道, 上下水道, 電力網, 通信網等
これらのインフラを構成するシステムはソフトウェアが支えている
インフラを利用する産業
金融, 流通, 通信・放送, 製造業等多岐にわたる
これらの産業の根幹に情報システム, 制御システムが動いており, その中心で動いているのがソフトウェア
身の回りのソフトウェア
自動車 (数十から百個の半導体チップ)
携帯電話
エアコンや冷蔵庫
2. ソフトウェアの語源
ハードウェアという言葉
古くから利用されている
ナイフ等の金物や兵器
ソフトウェアがコンピュータを動かすものとして最初に使われた用例
米国数学月報 1958/1 プリンストン大学統計学専門教授の J.W. Tukey
コンピュータの計算回路や記憶素子等をハードウェアと呼び, それを操作する抽象的な指令列をソフトウェアと呼ぶことにしたっぽい
コンピューターとは無関係なソフトウェア
1850 年
「チャールズ・ディケンズ・ウィークリー」という雑誌の短編小説の一節
腐るもの全てを「ソフトウェア」として表現されている
ニューヨーク・タイムズ
1961 年に登場している
日本の新聞
1969 年 4 月 12 日の朝日新聞
ソフトウェア (利用技術)
利用技術 = コンピューターを利用する技術
2. ソフトウェアの特徴
1. ソフトとソフトウェア
ソフトウェアよりも「ソフト」という言葉が幅をきかせている
映像「ソフト」
音楽「ソフト」
ソフトウェアは目に見えない為, 人間はその存在を意識しない
物理的な制約が無い
「腐る」こともなく, 錆びることも摩耗することも無い
「腐る」ことはあるような気がする
物理的な制約が無い
本質的に自由であるが, 巨大化し複雑化する
抽象的なものである
ムーアの法則
インテルの創業者 Gordon Moore が 1965 年に提言
半導体の集���度の上昇について, 向こう 10 年は集積度が毎年 2 倍に増大し, その後, 1 年半で 2 倍に達する
ソフトウェアが大きくなろうが, 重くなろうが, ハードウェアの進歩がそれを吸収してしまう
ソフトウェア開発上の制約は, それを設計し開発, 保守する人間の能力の限界…
2. あらゆる分野が対象
ソフトウェアはあらゆる産業で使われ, あらゆる製品の中で組み込まれている
業界間の交流は無く, 一般性のあるソフトウェア工学技術という視点をあまり意識せずに, 作られてきた傾向がある
銀行のオンラインシステム, 自動車のエンジン制御ソフトウェア, ゲームソフト, ソフトウェアとしては見かけは変わらない
3. ハードウェアのソフト化
従来ハードウェアとして作られていたものが, ソフトウェアで実現されるようになってきている
電話 (ダイヤルからプッシュ), テレビのチャンネル (レバーからリモコンボタン)
機械的な部分がデジタル信号による制御に切り替わっている
ファームウェア
ハードウェアを制御する為に機器に組み込まれたソフトウェア
ROM に書き込まれていて簡単に書き換えることが出来ない
最近は, フラッシュメモリを使うことにより, 出荷後の変更も可能
3. ソフトウェアの種類
1. 情報システムと組み込みシステム
情報システム
企業, 政府機関, サービス機関が外部に情報サービスを提供システム
内部の情報管理, 意思決定支援に用いる
データ処理, 事務処理, ビジネス・アプリケーション
エンタープライズシステム
最近では Web を用いたアプリケーションとして作られている
組み込みシステム
自動車, 家電製品, 計測制御機器等に搭載されている
その他のシステム
鉄鋼プラント, 原子力プラント, 重化学工業プラント等を動かす制御システム
ゲームソフトウェア
2. 汎用性品と注文製品
パッケージ・ソフトウェア (シュリンクラップ)
パッケージの箱を包装する樹脂のラップ
「ラップを破ることで使用許諾の条項を承認したと見なす」という売り方
COTS (Commercial Off The Shelf)
古くなってきている
オンライン販売
主流となってきている
SaaS
製品としてのソフトウェアを購入することなしに, そのサービスのみをインターネットを介して利用する
クラウド・コンピューティング
注文製品
使用する企業・組織から外部の業者に発注され生産される
日本のソフトウェア産業の売上に占める比率は, 受託開発によるものがパッケージ販売に比べて圧倒的に高い (85%)
パッケージ・ソフトウェアの多くが海外製品
オペレーティング・システム
オフィスソフト
ERP (ドイツの SAP が大きなシェア)
CAD
3. システム・ソフトウェアとアプリケーション
ソフトウェアの分類としては, システム・ソフトウェアとアプリケーション・ソフトウェアという分け方もある
システム・ソフトウェア = オペレーティング・システム (OS) とほぼ同じで, コンピュータを動かす為の基本となる汎用ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェア = 個別の適応分野に応じて作られている (数は圧倒的に多い)
ミドルウェア = OS とアプリケーションの中間に位置しており, アプリケーションが OS の機能を使うのを媒介する
データベース管理システム
トランザクション監視システム
メッセージ通信基盤
OS とミドルウェアを合わせてシステム・ソフトウェアと呼ぶことが多い
4. オープンソース・ソフトウェア
ソースプログラムを一般に公開しているもの
Linus Torvalds によって開発が始められた OS の Linux
Apache や Eclipse, Firebird 等
オープンソースはソフトウェアの形態というよりも, ソフトウェアを開発するプロジェクトのスタイルを指している
不特定の個人が自由に参加出来る
使うだけのユーザー, バグ報告をするユーザー, プログラムの修正, 追加を行う人々
オープンソース・ソフトウェアの最大の長所
多数の目によってプログラムを監視し, 欠陥を修正していくというプロセスを取ることによる信頼性の向上
5. サービス思考とクラウド・コンピューティング
ソフトウェアをパッケージとして販売するより, サービスとして提供するという方向への変化進行している
サービス指向アーキテクチャ (SOA: Service Oriented Architecture)
サービス提供 (ビジネスプロセスを構成するサービス単位をネットワーク上に公開する)
ホテル予約
レンタカーのサービスシステム
サービス連携 (提供されたサービス単位を相互に連携させてビジネスシステムを構築するもの)
Web サービスとして旅行手配システムを作る場合, 航空券予約, ホテル, レンタカー等の既存サービスを組み合わせる
サービスとしてのソフトウェア (SaaS: Software as a Service)
ソフトウェアの機能のうち, ユーザーが必要とするものだけをインターネットを介してサービスとして提供するビジネス形態
Salesforce.com
利用側から見ると自社固有のシステムを保有したように見えるようにする
システムを動かす為の計算機資源をユーザーが保有する必要がない
クラウド・コンピューティング
2006 年 8 月, Google CEO の Eric Schmidt がサンノゼで提言したとされている
雲 (インターネット) の向こうにあるコンピュータを利用する
ユーザーは自分でコンピュータやソフトウェアを保有せず, 利用に応じて料金を払う
SaaS とクラウドの違い
単にソフトウェアだけが提供されているものではない
インフラプラットフォームを提供している
グーグルやアマゾンのような大企業による寡占化されてきている
4. 誰がどう作るか
1. 情報産業
日本のソフトウェア産業の年間売上高は約 20 兆円 !!! (ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業約 18,000 事業者)
ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業以外の業者でも多様な組織でソフトウェアが作られている
2. ソフトウェア技術者
プログラマ (設計仕様を与えられてコードを書く作業に従事する人)
分析や設計をする技術者 (ソフトウェア技術者) と区別する傾向がある
ソフトウェア技術者の総数は, 2009 年時点で 128 万人という推計がある
ソフトウェア技術者に要求される知識と能力
アメリカでは SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) というソフトウェア工学の知識体系が作られている
日本では J07 が 2008 年 3 月に公表されている
経産省が行う国家試験
基本情報技術者, 応用情報技術者, システムアーキテクト等の 12 区分
IT スキル標準 (IT Skill Standard: ITSS)
3. ソフトウェアの生産体制
ハッカーと呼ばれる天才的なプログラマが一人, または少人数のグループで開発
Unix
WWW (World Wide Web)
google
Emacs
表計算ソフト
Visicalc
Dan Bricklin と Bob Frankston が 1979 年に作った
Excel に踏襲されている
ソフトウェア工場
ウォータフォール
要求仕様, 設計仕様, テストケース等の文書形式を定型化して開発される
ソフトウェア技術者が一つ, 一つのソフトウェアを開発するプロセスは, 工業製品の設計作業に相当する
4. 人間的側面
ソフトウェア開発上の制約 = 人間の能力
ソフトウェア開発の自動化はある程度進んできている
とは言え, 属人化する面が大きく, 知識集約的且つ労働集約的
労働集約的 = 「労働集約型とは、生産要素に占める資本の割合が低く、人間の労働力に頼る割合が大きい産業のこと」(こちらより引用)
ソフトウェア開発に関する重要な要素
ソフトウェアを使うのは人間
要求を人から抽出して要求仕様にまとめることが最初に行うべきこと
人と人の間の利害が対立することもあるので, それらの調整や社会的な観点からの判断
ヒューマン・インターフェースの設計
汎用製品の開発でも, 利用者の使いやすさは重要な要素
ヒューマン・インターフェースの設計は製品の優劣に大きな影響を与える
人間の認知的な側面への考慮がソフトウェア開発に占める比重が高い
以上
まとめでした.
人間的側面, やっぱり最後は人なんだなあと今の時点では思っております…
元記事はこちら
「ソフトウェア工学 「第 1 章 ソフトウェアとは」のまとめ」
April 25, 2018 at 04:00PM
0 notes