#美辞麗句と現実の戦乱混���
Explore tagged Tumblr posts
Text
社会主義の敗北、サヨクがバカにされる、ハリスの敗北、 ざっくり共通点 いいこと言っててもなんか料簡が狭いなー(その理想、実現手段が足りてない感じ、今、実際は無理っぽいなー)、だから
#パーツ不足#不十分#自分でもわかるでしょ#現実全部をちゃんと勘定に入れないと#実現しないことを語って結局ウソっぽくなってる#身近なところで実現しよう#自分が幸せになって見せて#実現あるのみ。議論はその次#言葉だけ#美辞麗句と現実の戦乱混乱#抑えが効かない#現実#抑圧がどういうかたちで必要なのか現実的にとらえないと#抑圧・権威主義、を無視してると、現実の権威主義に負けてしまう#手段不十分#発想貧困#足りない#頭が足りない#バカ#データ不足#パーツ#データ
9 notes
·
View notes
Text
我が国の未来を見通す(81)
『強靭な国家』を造る(18)
「強靭な国家」を目指して何をすべきか(その8)
宗像久男(元陸将)
───────────────────────
□はじめに
2週遅れになってしまいましたが、8月15日、7
8回目の「終戦記念日」に感じたことをまとめてお
きたいと思います。
式典において、天皇陛下は「戦没者に対する慰霊、
人々のたゆまぬ努力によって平和と繁栄が築かれて
いること、さらには過去の反省と再び戦争を繰り返
さないこと」などのお言葉を述べられました。
岸田首相は天皇陛下と同趣旨の式辞の最後に「積極
的平和主義の旗の下で、国際社会と手を携え、世界
が直面する様々な課題の解決に全力で取り組む」
「今を生きる世代、これからの世代のために国の未
来を切り開いていく」旨の言葉を付け加えました。
細田衆院議長は「日本国憲法の精神を体して恒久平
和の実現に全力を尽くす」、尾辻参院議長は自分の
体験談を述べられた後に「犠牲となられた方々のこ
とを忘れない」「戦争を絶対に起こしてはならない」
と結びました。
8月のこの時期になると、日本人として戦没者に対
する鎮魂は当然としても、「平和」(「戦争」���起
こさない)という言葉がそこはかとなく“一人歩
き”をして、多くの国民をして、“こうして念仏の
ように「平和」を口にしておれば、「平和」が向こ
うからやってくる”という錯覚に陥らせている(思
考停止というべきか)と考えるのは、うがった見方
なのでしょうか。
15日当日、各政党の談話も発表されました。談話
の全文は読んでいませんが、新聞紙上に発表された
その要旨だけでも考えさせられるものがあります。
紙面の都合上、紹介する価値があると考える政党談
話のみをさらに要約します。読者の皆様は、ぜひそ
れぞれの番号の談話がどの政党の談話かを想像して
お読みください。ウクライナ戦争などの厳しい安全
保障環境に対する認識はほぼ共通していますが、当
然ながら、その後に続く主張は各政党によって違い
ます。
唯一の被爆国として、「核兵器のない世界」の実現
に向けて現実的・実践的な取り組みを進めていく。
必要な防衛力を整備しつつ、国際協調と対話外交、
多国間協調を深め日本周辺の平和を守り、地域の緊
張を緩和させる努力をする。
他国に侵略を思いとどまらせる抑止力の確保、我が
国の主権と国民を守り抜くために積極防衛力を抜本
的に強化、整備する。
核兵器による威嚇など現実の脅威にさらされている。
「核の先制不使用」の議論を、今こそ日本が主導す
べきである。
食料やエネルギーの自給体制の強化を含めて「自分
の国は自分で守る」という現実的な安保政策を進め
ていく。
二度と戦争に巻き込まれないために、国のまもりに
対する国民の意識を高め、抑止力の構築が現実的な
手段との認識が必要である。
これらから、どの談話が与党で、その与党の安全保
障・防衛政策に反対の立場を主張する野党の談話が
どれなのか、混乱し、考え込み、そして安堵し、ま
た呆れもしました。
安堵したのは、「日頃、色々反対しているが、案外
分かっているではないか」と感じた野党に対してで
あり、呆れたのは、「相変わらず、足元を見ないで
とぼけたことを言っている。それが本心なのか」と
思ってしまう与党に対してでした。
各談話の正解は、(1)自民党、(2)立憲民主党、(3)日
本維新の会、(4)公明党、(5)国民民主党、(6)参政党
��す。
総括すれば、(特に与党に対してですが)「国会議
員であることをもっと自覚して、我が国内外に起き
ている様々な事象をよく勉強して、危機意識を持っ
て国の舵取りをしていただきたい」の一言です。
(6)の参政党の冒頭には「恒久的な平和は美辞麗句を
並べるだけでは実現しない」とありましたが、その
ようなことを国民に最も声高に訴え、理解を促す必
要がある与党が「保守」の看板を下ろし、「リベラ
ル」のような主張をすることは、我が国にとって決
して幸福なことではないと思います。百田尚樹氏が
「結党宣言」し、保守の論客諸氏がこぞって現政権
を批判する訳もこのあたりにあるのでしょうし、最
近の世論調査からすると、国民の多くも見抜いてい
るのでしょう。読者の皆様はどう考えるでしょうか。
▼我が国の「防衛力」の“急所”─同盟
気を取り直して本題です。本メルマガでもすでに紹
介しましたが、私は、愚書『日本国防史』((※)に
おいて、「我が国の歴史から学ぶ4つの知恵」をま
とめ、その筆頭に「孤立しないこと」を上げ、人も
国家も仲間を選び、失わないことの大切さを強調し
ました。
(※)『世界の動きとつなげて学ぶ日本国防史』
https://amzn.to/44xI30c
その内容を要約すれば、「日米同盟」の強化・対等
化、「日米豪印戦略対話(QUAD)」や「自由で
開かれたインド太平洋戦略(FOIP)」などを対
中国包囲網として同盟化まで引き上げることなどに
加え、本メルマガにおいても、貿易や食料・肥料な
ど経済的な“中国依存”から速やかに脱却すること
なども提唱してきました。
今回、改めて、我が国の「防衛力」の“急所”とし
ての「同盟」について考えてみたいと思います。た
だし、この「同盟」にからむ様々な論点を子細に紹
介しますと、本メルマガ数回分に及び、本来の「国
力」分析の視点から外れてしまう可能性もあります
ので、私の問題意識を簡潔に紹介することに留めま
す。
島田洋一氏は、自書『腹黒い世界の常識』(※)の
第1章冒頭に「同盟とは何か」と題して、「同盟は
一瞬にして敵対関係に変わる。共に戦う限りにおい
てアメリ���は日本の同盟国だが、日本が中国に降伏
した途端、敵の戦略拠点として使われないよう、ア
メリカは日本を攻撃対象にしてくる。『血を流して
守る』以外に、『破壊して去る』という選択肢もあ
る。それが国際常識である」と述べています。
(※)
これまで、様々な戦争の歴史を勉強して、島田氏の
指摘のようなことがたびたび繰り返されてきたとい
う事実を知っている私でさえ、この文章を読んだト
タン、ハッとして背筋が凍りました。
我が国には、軽々に「中国が攻めてきたら、白旗を
あげればよい」と口に出す人がいますが、そのこと
は即、アメリカを敵にまわすことであり、最悪の場
合、アメリカの攻撃によって陸海空自衛隊の基地や
装備が攻撃され、国土が再び“焦土と化す”ことま
でを考えなければならないのです。
島田氏も実例として取り上げていますが、第2次世
界大戦において、フランスがドイツに降伏し、パリ
無血入城を許した時、イギリスはフランス海軍が
(海上兵力が弱点だった)ドイツ海軍に組み込まれ
ることを防ぐため、フランス海軍の艦艇を空爆で破
壊し、1000名を超える兵士も犠牲になりました。
このような経験を乗り超えてイギリスとフランスは
この後も同盟国として共に戦ったのですが、ある事
象や事件をきっかけにして「昨日の友は今日の敵」
になったことなども歴史上枚挙にいとまがありませ
ん。
さて、細部の経緯は省略しますが、1952年4月、
「サンフランシスコ講和条約」と同時に発効された
「日米安全保障条約」は、戦後の占領に続き、アメ
リカ軍による保護協定的性格が強いものでした。ア
メリカは、日本の再軍備を抑え込むと同時に、日本
列島というアジア大陸東側の戦略的拠点を敵対勢力
の手に渡さないことが目的だったために、NATO
のように「相互性」を持たない「片務性」で妥協し
たのでした。
1960年、激しい安保闘争の中で、より共同防衛
に近い条約に改正されましたが、憲法上の制約もあ
って、引き続き日本本土に米軍を駐留することを容
認しつつ、「片務性」もそのまま残存された形の
「軍事同盟」が継続されました。
この結果、日本政府は、我が国の安全保障の多くを
アメリカに担ってもらい、「軽武装・重経済」とい
われる経済発展のみを政策の最優先課題とすること
ができて、実際に高度経済成長にもつながりました。
そして、1983年、中曽根元首相のアメリカ訪問
時の「共同宣言」をきっかけに、「日米同盟」とい
う言葉が市民権を得ました。「日米同盟」は、“
「日米安全保障条約」を根幹とする日本とアメリカ
の間の包括的な協力関係”と定義され、安全保障・
防衛面だけでなく、政治、経済、社会など幅広い分
野において機能することを指しています。
以来、我が国は、ほぼあらゆる政策を「日米同盟」
を基軸にして立案し、実行してきました。一時、民
主党政権時には米中を絡めた「二等辺三角形」論も
ありましたが、そのような考えは長くは持ちません
でした。よって、歴代の首相をはじめ政治家、官僚、
有識者、それに私たち自衛隊関係者にあっても、
「日米同盟がなくなる」とか「日米同盟なき我が国
の繁栄」などについて、一瞬たりと頭をかすめたこ
とはないでしょう。
特に、防衛分野においては、戦争経験のない自衛隊
は米軍の豊富な実戦経験から学ぶことが多々ありま
したし、個人的な経験でも、在日米軍の高官たちと
親しく付き合って、お互いの信頼や友情を深めまし
た。
一方、高度成長の結果、一時は世界第2位、現在で
も世界第3位のGDPを誇りならも、防衛予算は
「GDPの約1%」にとどまり、「日米安全保障条
約」は、憲法上の制約を盾に「片務性」についても
今日まで手付かずのまま放置されています。
「同盟」を維持させるためにはそれ相応の努力が必
要なことは言うまでもありません。長年、日本の約
15倍、GDPの約3.5%に相当する巨額の軍事
予算を投入しているアメリカが、その大元が戦後の
対日方針にあるとはいえ、この状態に不公平感を持
つのは当然なのです。
2019年、トランプ前大統領が「日本が攻撃され
れば、我々は第3次世界大戦を戦うことになり、あ
らゆる犠牲を払って日本を守るが、アメリカが攻撃
されても日本は我々を助ける必要がない。彼らはソ
ニー製のテレビでそれを見ていられる」と「片務性」
を痛烈に批判し、話題になりました。
「この批判が何を意味するか」について、当時、ほ
とんどの日本人に理解していなかったと今なお想像
しています。実際、アメリカにおいては、憲法上、
条約の批准は上院の3分の2の賛成を必要とすると
の高いハードルがありますが、条約の破棄は大統領
の判断で行なうことができます。トランプ大統領の
発言はけっして脅しでもなんでもなく、大統領一人
の判断でいつでも条約を破棄することはできるので
す。
現在、「日米同盟」はアメリカの「国益」にも合致
しているし、これから先もそう願いたいですが、国
際社会を取り巻く“様々な情勢”が変われば、未来
永劫に「日米同盟」が継続される保証はありません。
大統領の判断一つで「昨日の友は今日の敵」になる
可能性��潜めていることを常に頭に置く必要がある
と私は思います。だからこそ、「自主防衛」を筆頭
にした「自助努力」が必要なのですが、それについ
ては後述しましょう。
▼我が国の「防衛力」の“急所”─同盟(続き)
今後変わるかも知れない、国際社会を取り巻く“様
々な情勢”についても触れておきましょう。前回紹
介しました伊藤貫氏によれば、冷戦終了後、アメリ
カは、人類史上一度も実現されたことがなかった
「世界一極体制」を創ろうとの野心と自信をもって
様々な外交を展開しました。その特徴は、アメリカ
を例外的に優れた国とする「アメリカン・エクセプ
ショナリズム」をもって、国際政治にアメリカの政
治制度や経済システムを採用させようとし、それに
抵抗する国々は、裁き、処罰し、時には破壊しまし
た。実際に、冷戦終結直後の1989年の「パナマ
侵攻」以降、アメリカが関与した世界の紛争は17
紛争を数えます(『習近平が狙う「米一極から多極
化へ」』遠藤誉著より)。
アメリカのこの「新外交理論」は一世を風靡し、日
本人の中にも「熱心な信者」を輩出しましたが、2
0世紀になった頃から、中東地域、ロシア、中国、
北朝鮮などが反旗を翻すなど様々な厄災が表面化し
て、ほころびを露呈し始めてきました。なかでも、
中国、インド、ロシアなどの台頭は、「一極体制」
を形なきものにして、「多極化」に拍車がかかりま
した。
そのような状況から、オバマ元大統領の「アメリカ
は世界の警察官ではない」やトランプ前大統領の
「アメリカン・ファースト」の発言などにつながり、
このたびの「ウクライナ戦争」をもって、「世界一
極体制」はその原型を留めることなく、世界は「多
極化時代」、というか「分裂の時代」に再突入した
と考える必要があるでしょう。現に、スウェーデン
にある「民主主義多様性研究所」によれば、今や世
界人口の72%に相当する57億人が「専制主義的
(権威主義的)な傾向の強い国」に住んでいるとの
ことで、これらの国々はアメリカが提唱する政治制
度や経済システムに与することをかたくなに拒否し
ているのです。
基軸通貨である「米ドル」についても、近年はユー
ロや人民元に押され、外貨準備高の約60%はドル
建て資産といわれながらも、国際決済においては4
2%に留まっているなど脱ドル化が進み、将来はそ
の地位が危ぶまれる“様々な現象”が発生するとの
予測もあります。
さて話を本題に戻しましょう。このように、将来
“混とんとした国際情勢”になることを予想せざる
を得ないなかにあっても、なおかつ「日米同盟」は
盤石で、その延長で“アメリカの「核の傘」は有効
と断定できるのか否か”を議論する時が来たのでは
ないかと考えるのです。
これまでのようなアメリカであれば、水戸黄門の
「葵の紋所」のように、それを見せるだけでひれ伏
す国はあったとしても、これから将来はその“効き
目”があるのか、逆に、アメリカが「葵の紋所」を
“出し惜しみ”するような情勢は来ないのか、など、
それらの想定を「もしかして」の範疇として捉え、
最も大事な「我が国の抑止力は大丈夫なのか」につ
いて、しっかり議論すべきなのです。
前回、中国や北朝鮮などは、自国の犠牲回避を最優
先しない可能性があることに触れましたが、差し伸
べてもらった「傘」にも問題があるとすれば、過剰
な依存を止め、逆に相対的な力関係を補い、より盤
石な抑止力を構築する上でも、(それぞれ微妙に違
う)イギリスやフランス、そしてドイツの抑止戦略
などを研究しつつ、我が国独自の「自主防衛」につ
いても検討する時期に来ていると考えます。
かつてのアメリカは、「日本の核武装は力づくでも
阻止する」との勢力が大半を占めていたものから、
キッシンジャー、ウォルツ、ホフマンなどのリアリ
スト戦略家たちのように我が国の「自主防衛」を容
認する勢力が増えつつあるのは、それが日本の「国
益」に留まらず、アメリカの「国益」にもつながる
との認識を持っているからなのです。
まさに、“時代は変わりつつ”あります。冷静沈着
に「あらゆる戦争を抑止するために、我が国の防衛
をどうするか」についてタブーを廃して、真剣に考
える時期に来ています。
令和6年度防衛予算の概算要求は過去最高の7.7
兆円だそうで、これによって通常戦力が増強され、
陸海空領域に加えて「宇宙」「サイバー」「電磁波」
に至る「領域横断」を強化する方向に舵を切ってい
るのでしょうが、これだけでは、あらゆる「戦争」
の発生を未然防止するのは困難と考えます。不確定
で、かつ厳しさを増す情勢を目前にして、ここで思
考を断ち切ることは、冒頭に述べた、念仏のように
「平和」を願うことと“大同小異である”ことを悟
る必要があるでしょう。
▼我が国の「防衛力」の“急所”─「足かせ」にな
っているもの
最後に、「防衛力」の“急所”として「足かせ」に
なっているものついて触れておきましょう。
先般のNATO会議において、東京事務所の開設に
ついては、フランスの反対もあって実現しませんで
した。NATO加盟国は、1949年に署名された
「北���西洋条約」の条約第5条において「一方の加
盟国が武力攻撃を受けた場合、他方の加盟国も共同
して自衛すること」と定めておりますが、これは
“一方への攻撃は全員への攻撃とする”「集団的自
衛権」の原則そのものの適用です。
「日米安全保障条約」は戦後の特殊事情によって
「片務性」が容認されましたが、NATOへの加盟、
あるいはNATOの東アジアへの拡大を企図すれば、
もはや「片務性」は容認されないでしょう。
第1次世界大戦時、「日英同盟」下にあった日本に
対して、イギリスから日本の参戦について再三の要
求がありましたが、日本は「国防の本質を完備しな
い外征はなじまない」と「参戦地域の限定」に執着
し、海軍の特務艦隊の派遣を除き、陸軍の派遣は拒
否しました。そのことが、のちの「日英同盟」破棄
につながったという“前歴”があります。
もし、東アジア地域で何かあった場合、NATOの
支援を得ることを期待するなら、もし欧州で何かあ
った場合に、自衛隊を派遣することを“拒否できな
い”ような「枠組み」を求められるでしょう。その
ためには、現在、憲法上、「権利はあるが、行使で
きない」としている「集団的自衛権」を行使できる
ように解釈を見直すか、憲法そのものを見直すか、
他に方法がありません。
そのよう制約は、冒頭に述べたQUADやFOIP
を実質的同盟のレベルまで引き上げる場合、あるい
は8月18日に合意された「日米韓安保協力」をさ
らに盤石なものにする場合でも同様でしょう。
いよいよ戦後80年近く、かたくなに守り続けてき
た憲法、さらにはあの手この手を使い、屁理屈をつ
けつつ、潜り抜けてきた憲法解釈や現憲法のもとの
防衛政策が限界に来ているということでもあり、
“見切りをつける”時が来たということではないで
しょうか。
その決断こそが、我が国の「国力」を維持し、憲法
でいう「国際社会において名誉ある地位を占める」
ための唯一の道なのです。皮肉と言えば皮肉ですが、
それが現在の我が国の置かれた立場であり、これま
での“ツケ”の集大成こそが将来に向けた生存の道
であろうと私は考えます。
軍事力(防衛力)についてはひとまずこのぐらいに
しておきましょう。次回は、本メルマでもすでに取
り上げた「食料・天然資源」を「国力」の要素との
観点から再度取り上げ、その後、「政治力」につい
て素人の立場ながら「何が問題なのか」について迫
ってみます。
(つづく)
(むなかた・ひさお)
2 notes
·
View notes
Text
【その他】
これから本当の意味での「戦後昭和体制」(※)が終わる令和の日本。無意識と化すほど自然化されていた社会的価値観の大幅な変化に対応しなければならなくなる(価値観を作り変えなければならなくなる)。今日に至るまで続く戦後昭和体制は政治的に言うなら前回民主党が政権奪取した時に終わらせるべきだったが、残念ながらそれは失敗に終わった。初めての政権担当に民主党自体が舞い上がってしまったのもあるし、構想が膨らみ過ぎて頭でっかちになっていたのもあ���たと思う。端的に実務経験の不馴れさが露骨なまでに露呈したと言わざるをえなかった。政権を再奪取した自民党がゼロ金利政策でマネーを市場に大量に流通させた上で、社会全体の機運を上昇させるべく高度成長期の再来を夢想してオリンピックと万博を誘致したことに現れているように景気刺激のカンフル剤を打ってはみたものの経済成長に資するような実効性を上げることはできなかったと言っていい。結果から見れば内政において自民党(安倍政権)がやったことは大局に立って構造の変革を志向することなく社会的象徴事のイベントを掲げてなんとか誤魔化しながら戦後昭和体制のベースをそのまま平成の終わりまで間延びさせて延命させただけであるが、その間に日本社会の傷は今日に至ってより深くなってしまった。意気込みや心の持ちようで好転するようなものではないにもかかわらず、自民党が政権を担いさえすればまだまだ日本は大丈夫だとの安倍一強体制がばら撒いた美辞麗句が醸成した空気に多くの有権者が乗っかり(小泉-竹中体制の時と同じ翼賛体制)国全体を包摂してしまった。何より大きかったのは小泉ー安倍政権の間に日本で全面開花していった新自由主義のイデオロギー(ロバート・ノージックーミルトン・フリードマンーアメリカ共和党)の一般社会への浸透と蔓延化が日本国内に幅厚く存在していた中産階級を破壊したことだった。しかし、いずれにせよこれからの日本は自らの意思による主体的な変革ではなかったにせよ(日本という国にそんなものはないのかもしれない)、社会的変動による大きなうねりに引きずられる形で新たな社会的価値観に刷新されていくはずだ。今までとは違う価値観の変化に対応する新しい社会に移行させるためにはしばらくのあいだは混乱を伴う厳しい時期が続くが、その後の再起と展望のためにそれは必要であり、その避けられない(避けるべきではない)混乱は新しい価値観に基づく新しい社会のためには必要な混乱と言える。それができなければこの国は底が抜けたように堕ちるところまで堕ちていく。真の変化に混乱は切り離せない。途中でやめたり、戻ったりしないことが大事。後向きにならずに受け止めて対応することができるかどうか。もう日本はギリギリのところまで来ているのではないかと思う。絶望に近い少しの希望を何とか保ちつつ前向きになるしかない。
※ 何か特定の領域における限定した話ではなく、現在も社会全域に及んでいる昭和の残党とでも呼びたい定式化されている考え方やそれに付随して表れ出るような派生現象のほとんどすべて。
0 notes
Text
永遠の初恋びと
「世界選手権ではどのような演技をしたいですか?」 「そうですね……、全日本選手権でも四大陸選手権でも、成績はよかったのですが、自分の中では納得していない部分が多くて、もっとこうできたんじゃないかとか、あそこはああしたほうがよかったんじゃないかとか、いろいろ考えることがあって、課題ができたので、今回の試合はシーズンの集大成ですし、そういうことのないように、ショートもフリーもノーミス��、どちらかだけがいいというのではなく、両方そろえて、いい演技にしたいと思っています」 「記録の点ではいかがでしょう? 四大陸選手権でも、勝生選手ご自身の持つフリーの歴代最高得点には及びませんでしたが」 「それは、い���演技ができればあとからついてくるものだと思っています」 「師弟関係を結んでから初めて、ご自身のコーチであるヴィクトル・ニキフォロフ選手と対戦しますね。どんな気持ちでのぞまれますか?」 「コーチが誇れるよう、彼の名に恥じない戦いをしたいと思います」 「勝てそうですか?」 「どちらがどちらにですか? 負ける要素は見当たりません」 「……どちらがどちらにですか?」 勇利はにっこり笑って答えた。 「どちらもです」 リンクに立ち、フェンスを挟んで立った勇利の手を、ヴィクトルが情熱的に握りしめた。勇利は静かに握り返し、彼の目をまっすぐに見てほほえんだ。これから勇利のショートプログラムが始まる。 「ヴィクトルはぼくにどんな演技をしてもらいたい?」 「勇利が勇利であってくれればそれでいいよ」 「そう? すこしはヴィクトルの希望も取り入れようかなと思ったんだけどね」 「そうか。じゃあ……」 ヴィクトルは勇利の耳元にくちびるを近づけ、低くてつやっぽい声ではっきりと言った。 「バンケットで初めて俺を誘惑したときみたいに、手をつけられないほどどきどきさせて欲しい……」 「ぼく、おぼえてないんだけど」 「記憶になくても勇利ならできるさ」 「どきどきしすぎて自分の演技に差し支えが出ても知らないよ」 勇利が笑うと、彼の名が呼ばれ、歓声が上がった。 「勇利のラストエロスだね……」 ヴィクトルがつぶやく。勇利はにっこりし、「最後の誘惑だ」と同意した。 「ヴィクトル、わかってる?」 「何が?」 「演技はもう始まってるんだ」 「え?」 勇利は両手を差し伸べると、ヴィクトルの頬を包みこみ、顔を近づけてまぶたを閉じた。ヴィクトルが瞳をみひらいて息を止め、ものすごい悲鳴と歓声がリンクを圧するほどにみたした。 勇利はさっと身をひるがえすと、衣装をなびかせてリンクの中央まで行き、静かな気持ちで目を伏せた。ヴィクトルはいまどんな顔をしているだろう? 驚いている? 余裕ぶって笑っている? あきれて苦笑している? 見られないのが残念だ。勇利はくちびるにそっとふれた……。 情熱的なしらべに乗って、幾度も幾度もさらったステップシークエンスを披露する。最初これをヴィクトルがすべっているのを見たとき、勇利は、「こんなのぼくすべれるの?」と困惑した。でもいまは、もう自分のものになっている。ヴィクトルが初めてくれたプログラム。「みんなが思うことの反対をしなきゃ」と新しい勇利を引き出してくれた。こんなプログラム、いままでのコーチは誰もやれと言わなかったし、勇利も挑戦しようなんていう発想はまるでなかった。けれどヴィクトルは、勇利に似合う、勇利ならできるときめて道を示してくれたのだ���これをすべるのは今日で最後。 いちばんよい成績を出せたのはロシア大会だった。あの時点で「エロス」は完成していたといえる。しかし、それだけでは勝てないと踏んだ勇利は、高得点を狙って、ジャンプを構成し直した。ジャンプを変更するというのは簡単なことではない。ジャンプ自体の難度も上がるが、プログラム全体の調和というものも変わる。踏み切りが変化するというだけで、それまでつくり上げた流れは失われる。それを再びなめらかになじませなければならないのだ。 グランプリファイナルでは、跳びたいという気持ちが強すぎて手をついた。全日本選手権では一瞬方向を見失い、転倒してしまった。四大陸選手権では回転しすぎ、マイナスがつくような着氷になった。フリースケーティングのおりも別のミスを犯している。今度こそ──そろそろきちんと跳べてもよいころだ。ヴィクトルの言う「いつまで予行演習やってるつもりだい?」である。いい加減跳べるようにならなければ。 ターンをし、方向を変えたら、ヴィクトルの姿がちらと視界に入った。一瞬のことだがすぐにわかる。ヴィクトルはそこにいるだけで華やかだ。きっといまも、勇利から目を離さず、熱心に見てくれていることだろう。そう──ぼくを見ていて。ぼく、すっごく美味しいカツ丼になるんで。──一年前に言った自分の言葉を思い出す。ヴィクトルは美味しいと思ってくれているだろうか? いま……。勇利の子どもっぽい言い分に笑いもせず、「カツ丼大好きだよ」と答えてくれたヴィクトルだった。あのとき、あのひとことがどれほどうれしかったかしれない。 勇利はあの瞬間の気持ちを思い出した。ヴィクトル、ぼくを食べてよ。思えば、初めてきちんと踊った「エロス」は本当につたなく、幼かった。ヴィクトル、ぼく、成長したでしょう? あのころより色っぽくなった? ファイナルのときのこと、ヴィクトルは「おまえは俺を捨てようとした」と言ったね。そんなつもりはなかったんだよ。ぼくは次の男へ行くことなんてできなかったし、貴方もそれをゆるさなかった。男から男へと渡り歩く美女よりも、たったひとりの男に愛され続ける美女こそが究極のエロスじゃない? ──ヴィクトル、ぼくのこと、手放せなくなったでしょう? 割れるような歓声に我に返り、勇利はゆっくりと瞬いた。息が切れ、頬が上気していた。あれ、終わっちゃった? ほっぺたに手を当て、首をかしげる。状況がよくわからなかった。とても身体が熱く、ほてりきっている。勇利は戸惑いながら挨拶を済ませ、おむすびのぬいぐるみを抱きしめてヴィクトルのもとへ戻った。 どんな演技をしたのか自分でよくわからない。でも、とてもみちたりていた。ヴィクトルの視線を常に感じていた。彼の愛情深い、情熱的な視線を。 「ヴィクトル」 ヴィクトルが両手をひろげて待っている。勇利を抱きしめようと。 「ヴィクトル、ぼく、綺麗だった?」 ヴィクトルが目をみひらいた。彼は勇利を力いっぱい抱擁し、「勇利、おまえは最高にうつくしい」と甘ったるい声で褒めた。彼は���ぐにうやうやしくナショナルジャージを着せかけ、勇利のことをキスアンドクライへ導いた。勇利は彼に手を引かれるまま座り、紅潮した頬をヴィクトルに向けた。 「ねえ、四回転フリップ成功した?」 「え?」 「記憶がないんだ。飛んじゃってて……もしかして失敗したのかな?」 ヴィクトルはぽかんとし、それから勇利を引き寄せてつむりを撫でた。 「綺麗だったよ。GOEプラス3だ」 「ヴィクトルがきめちゃうの?」 「もしプラス3になっていなかったら、あとでジャッジに抗議を申し入れる」 得点が出た。勇利はあぜんとした。ヴィクトルは黙って勇利を抱きしめた。そしてまるで演技前のお返しだとでもいうように、熱っぽくくちびるを重ねた。勇利は押されて、後ろに倒れこみそうになった。 「ちょっと!」 「勇利」 「ちょっと──見えない。得点が見えないよ! いまの見間違い? 眼鏡持ってきて!」 「間違ってないよ」 勇利は改めて点数を確認し、両手を頬に当ててヴィクトルをみつめた。 勝生勇利は、ショートプログラムにおいても歴代最高得点を更新したのだ。 「お疲れ様でした」 「ありがとうございました」 「まずはいまの率直な気持ちをお聞かせください」 「あの……、まだ整理できてなくて。混乱しているというのが本当のところです。すみません」 「歴代最高得点を更新されましたね」 「そうですね。えっと……、うれしいです」 「ノーミスでした」 「はい。それはずっと目指してやってきたことだったので、今回きちんと達成することができて、本当によかったと思います」 「ロシア大会で完成したかに見えたショートプログラムですが、構成を変更し、グランプリファイナルでは調子がよくありませんでしたね」 「調子というか、あれはただ単純なミスというか……。基礎点の高いジャンプを跳んでも、成功させて加点をもらえなければああなりますし、つまり諸刃の剣で、もとの構成のまま完璧な仕上がりを目指したほうが、安全にいい点を取れるかもしれないですが、それでは勝てないし、それはぼくの中ではちがうという気がしたので、もっと上を目指して、目指した結果が今日につながって、挑戦し続けてよかったと思います」 「コーチにはなんと言われましたか?」 「あの、褒めていただきました」 「どんな言葉をかけられましたか?」 「えーっと、そう、いい子だねって……そういう感じです」 「そわそわしていらっしゃいますね」 「あ、すみません。すぐコーチの演技なので……すみません。あの……」 「どうぞご覧になってください。どうもありがとうございました。フリーも期待しています」 「ありがとうございました」 勇利はリンクサイドまで急いで走った。 「恥をかいた」 勇利はぷりぷり怒っていた。そばにいるヴィクトルは笑って、「そんなことはないさ」となぐさめた。 「いまごろみんな笑ってるよ。歴代最高更新して浮かれてたやつは誰だっけって。たいしたこともないのににこにこインタビューに応じて、まったくみっともなかったってね」 「そんなことはない」 ヴィクトルはベッドに座って拗ねている勇利の隣に腰掛け、そっと手を握った。 「勇利が為し遂げたことはすばらしいことだ。誰も文句は言えないさ。俺にだってね」 「自分より上手いやつはいないみたいな顔をして、えらそうに受け答えしてた、どこにでもいる間抜けなスケーターなのに?」 「そんな顔はしてなかったよ」 ヴィクトルは笑いをかみ殺しながらかぶりを振った。 「きみはいつだって真摯だ。まじめで、努力家で、ふるまいは気品高い」 「ヴィクトルがぼくの記録を抜いたりするからいけないんだよ!」 勇利はヴィクトルをにらみつけた。 「生徒に恥をかかせて、申し訳ないと思わないの?」 ヴィクトルはとうとうこらえきれなくなったのか、声を上げて笑い出し、勇利を抱き寄せてまなじりに接吻した。 「ああ、恥ずかしい」 勇利は左手で頬を押さえた。 「自分の更新した最高得点をほんの数分で越されることほど恥ずかしいものはないね。今後はもし記録を塗り替えることがあっても、どうせすぐ抜かれるんだって肝に銘じて、えらそうな態度は取らないでおくよ。もっとも、そんな機会がこのさきあるかどうか知らないけどね」 「恥ずかしくない。勇利の記録は立派だ。それに、これからいくらだって機会はあるさ。きみふうに言えばいま『浮かれてえらそう』にしている俺だって、いずれきみにまた追い抜かれる」 「ああ、もう、どうしてこんなことになっちゃったんだろ? ヴィクトル・ニキフォロフに勝つことは不可能なの?」 勇利は悩ましくつぶやいた。ヴィクトルが噴き出しそうになっている。 「コンマ以下の差じゃないか」 「当たり前だよ!」 勇利は声を荒らげた。 「あの演技で、十点も二十点も差をつけられたらやってられないよ!」 「その通りだね」 「まったくもう……、ほんと、最高の出来だったんだよ……おぼえてないけど。でも、VTRを見たらかなりのものだったよ。どこのトップスケーターかと思ったよ」 「日本のトップスケーターだよ」 ヴィクトルが勇利に頬を寄せた。 「『エロス』で出すことのできる上限の得点に迫ったんだよ! なのに、なのに……ヴィクトル・ニキフォロフとかいう皇帝が……」 「まったく悪いやつだね」 「すっごく上手にヴィクトルを誘えたと思ったのに……」 「うん。最高だったよ。だから俺も興奮しちゃって……」 「もう、ちょっと、べたべたしないでよ!」 勇利は、さっきから話しながら勇利の髪や頬にくちづけしたり、背中を撫でたり、手の甲を指先でなぞったり、とにかく愛情表現をふんだんにしていたヴィクトルをつきのけた。 「ぼく、いますごく機嫌が悪いの! あんまり話しかけないで!」 「俺はいますごく機嫌がいい。勇利をずっと抱きしめていたい気分だ」 「ああ、腹が立つ……」 「勇利がどんなに俺に腹を立てて俺を嫌いになったとしても、俺は勇利を愛してるよ」 「勘違いしないで。ヴィクトルのことは大好き。ぼくが腹を立ててるのは自分自身に対してだよ。ああ、ねえヴィクトル、あの着氷よくなかったのかな……ジャンプも、入るとき、明確じゃなかった? どうして3をつけない採点員がいたんだろう。サルコウはいつまでもぼくを悩ませるね。コンビネーションにしたせいかな。どう思う? ううん、もうショートのことを考えるのはよそう。フリーに気持ちを切り替えなきゃ」 「その通りだ。さすがは俺の勇利」 「ヴィクトル、ぼくはフリーで皇帝を逆転するからね」 「その意気だ」 「ばかにしてるでしょ? なんだい、余裕ぶっ��ゃって……」 勇利は頬をふくらませて拗ねた。 「ちがうよ。勝ちに行こうとしてる勇利がとてもうつくしくて、感激してるんだよ」 「そうやって実力を見せつけていい気になってればいいよ。でもねヴィクトル……」 勇利はまだべったりとくっついているヴィクトルを無理やりに引きはがすと、彼の前に立ち、腰に片手を当てて、もう一方の手ではひとさし指を振りたて、厳しく言い放った。 「ヴィクトル・ニキフォロフなら相手にとって不足はないよ。覚悟してて。絶対勝ってみせるからね。ヴィクトルが世界王者と呼ばれる時代ももう終わりなんだから!」 き、緊張してきた……。演技前、勇利は胸に手を当て、深呼吸をくり返していた。ショートプログラムでは二位だったので、一位のヴィクトルを逆転することしか考えていなかったけれど、勇利はいま、��リースケーティングの世界記録保持者なのだ。あいつは歴代最高得点を持っている実力者だ、倒さなければ、という圧倒的な威圧をあちこちで感じた。自分は追いかける立場だと信じて疑っていなかったのに、本当はそうでもないのだということを思い出させられたのだ。それがたいへんな重圧だった。 みんな、落ち着こうよ。もっとすごい人が目の前にいるじゃない。ヴィクトル・ニキフォロフを追いかけるほうがずっと意欲の向上につながらない? ぼくなんかたいしたことないんだから、意識したってしょうがないよ。ねえ……。 追われるのが苦手な勇利は、すっかりかたくなってしまった。 「おいブタ! おどおどしてんじゃねえ! 邪魔だ!」 「あっ、す、すみません……」 廊下でぼんやりしていたら、ユーリに押しのけられてしまった。勇利はすみのほうへ行ってちいさくなった。 「勇利、大丈夫?」 ヴィクトルが優しく言って勇利の手を握る。 「そんなにおびえなくていいよ。勇利よりうつくしい者は会場にいない」 「ヴィクトルがいるじゃない……」 ヴィクトルは笑って勇利を抱きしめた。 「そうだ、俺がいるな。まわりなんか見ないで。俺だけを見て」 「う、うん……」 勇利はこくこくとうなずき、ちいさくぶるっとふるえた。ヴィクトルが苦笑を浮かべる。 「まったく、上がったり落ちたり、忙しい子だな」 「え?」 「なんでもなーいよ。かわいいな」 勇利はそわそわと落ち着かない気持ちで自分の番を待ち続け、ほかの選手が高得点を次々と出していくのを見ていた。ああ、ぼくは無理だ。みんなノーミス。パーソナルベストがどんどん出てる。きっとぼくだけ最低記録を出すんだ。声をかけるのも悪いようなとんでもない得点。ああ、ああ、どうしよう。そんなことになったらヴィクトルが。ヴィクトルが……きっとかなしむし、まわりにも好奇の目で見られて……だめだ、だめだそんなのは……。 「勇利」 ヴィクトルが勇利の頬にふれた。氷の上に立った勇利は、青い顔をしてヴィクトルを見返した。 「ひどい顔色だね……」 ヴィクトルが優しく頬を撫でた。 「そんなに不安なのかい?」 「そ、そ、そんなことないよ」 「あきらかに調子が悪そうだ」 ヴィクトルがくすっと笑った。 「でも……、おかしいな」 彼は首をかしげ、不思議そうに眉を寄せた。 「勝生勇利は、俺に勝つとか覚悟してろとか、もうヴィクトル・ニキフォロフが世界王者と呼ばれることはないとか、そんなことを言ってたはずなんだけどな……」 勇利ははっとして顔を上げた。 「俺の聞き間違いだったかな?」 ヴィクトルは口元に指を当て、にやっとする。 「勇利なら確かにそうできるだろうと思ったんだけど……無理なんだ」 勇利のくちびるがかすかにふるえた。 「そうか。そんなに緊張して、おびえてちゃできないよね。残念だな。期待してたのに」 「ぼ、ぼくは……ぼくは……」 「勇利が俺と本気で対戦してくれると思って期待してたのになあ……」 ヴィクトルは微笑を口元に漂わせ、いたずらっぽく勇利を見た。 「できないなら……、やめとく?」 勇利の頬がかっと熱くなった。なにそれ。なにそれなにそれなにそれ。ばかにして! 勇利は叫ぶように言った。 「やる!」 「オーケィ」 ヴィクトルがにっこりし、勇利の手をぎゅっとつかんだ。 「それでこそ俺の勇利だ。さあ、きみの愛を見せて。おまえの愛でヴィクトル・ニキフォロフを倒してみせて」 勇利の紹介がなされ、勇利は氷を蹴ってリンクの中央へ向かった。身体じゅうが熱く、力がみなぎっていた。愛。そうだ。このプログラムは、勝生勇利の愛のプログラムなのだ。ヴィクトルとふたりでつくった。ああしよう、こっちがいい、もっとこうしたい、ねえ、ヴィクトル、聞いて。何度も何度も話しあい、考え、積み重ねてつくり上げた。 誰も追いつけるはずがない。勇利の織りなす愛には──誰も。 氷の上にいるのは、いま、ぼくだけなんだ……。 演技が始まったとき、一瞬、ヴィクトルがほほえんだ気がした。遠くからの判断なので本当かどうかはわからない。でも、きっとそうだ。ヴィクトルはいま笑っている。 そういえば、初めて長谷津に来たときもヴィクトルは笑っていたな、と勇利は思い出した。不躾に浴場へ入っていった勇利に顔をしかめもせず、開口一番、「俺はおまえのコーチになる!」と言い放った。あれは勇利が懇願した返事だったらしいが、それにしたって、あのヴィクトル・ニキフォロフが、「コーチになって」と言われて了承するなんて前代未聞だ。彼には自分のスケートがあり、計画があり、将来があった。それなのにそれらをすべて置いて、勇利のところへ来てくれたのだ。 そう思えば、勇利のくちびるにも自然と笑みがにじんだ。この一年、いろいろなことがあった。ヴィクトルがロシアへ帰ってしまうのではないかと心配したり、大好きなあこがれのひとなのになかなかなじめず、失礼なこともした。もう一度跳んで、ジャンプを見せて、といくたびもねだってこき使った。ヴィクトルはいつも笑っていた。とても優しかった。 スケートだけに集中せず、ふたりで遊ぶこともおぼえた。プールへ行ったり、海へ行ったり。お祭りも楽しんだし、たわいない散歩もした。ヴィクトルはひとりでいなくなることも多かったが、帰ってくると必ず、体験したことを洗いざらい勇利に話し、勇利の言葉にも耳を傾け、それぞれ別々に過ごした時間を共有しようとした。そしてそのうち、ひとりきりで出かけることはなくなり、いつだって勇利を誘うようになった。 ヴィクトルは勇利の世界を変えてくれた。彼といることで、よくものごとが見えるようになった。自分の環境も、向けられている愛情も。ああ、こんな中に自分はいたのかと気づくことができた。 ヴィクトルはコーチとしては上質とはいえず、勇利も精神がしっかりしていないので、お互い手探りだった。彼の前で泣いたり、めちゃくちゃなことを言ったりしてあきれさせ���こともある。でも、いつだってふたりは相手のことを考えていた。だから、ヴィクトルがそばにいない試合はひどくさびしく、苦しかった。このひととずっと一緒にいたいと思い、しかしそれはいけないことなのだとつらい思いをした。 終わりにしようと言ったとき、まさかヴィクトルが泣くとは思わなかった。あれは何の涙だったのだろう。ヴィクトルは「怒ってるんだよ」と言ったけれど、人は怒ると泣くものなのだろうか。変なひとだ。ヴィクトルってわからない。でも──そんな突拍子もない、いつだって理解できないヴィクトルのことを、勇利は深く愛している。 一年前の世界選手権の日、勇利は長谷津のリンクで、ヴィクトルのプログラムをすべっていた。そして一年を経たいま、世界の舞台で、ヴィクトルと一緒につくり上げたプログラムをおどっている。 長くスケートをしてきた。でも、ヴィクトルと過ごしたこの一年ほど濃密で愛の深かった時期はない。ヴィクトルを愛し、ヴィクトルに愛されたこの時間が、勇利はいとおしくて仕方なかった。ふたりで織りなし、かたちにしたのが、「YURI ON ICE」なのだ。 このプログラムも、今日で最後……。 ぼくはもうすぐ、ヴィクトルのいるロシアへ行く。彼と新しい時代を経験する。でも、関係を始めたこの一年、いろいろとぶつかりあい、探りあい、初めての愛に戸惑いながら過ごしたこの時は、もう二度と訪れないのだ。 ヴィクトル……。 最後のジャンプ。四回転フリップだ。四大陸選手権、ショートプログラムでまわりすぎてしまったため、フリースケーティングでは抑えめに跳んだ。すると今度はアンダーローテーションを取られた。グランプリファイナル以来、クリーンに降りていない。どうしてもこのジャンプが綺麗に入らなかった。昨日だって、ヴィクトルは褒めてくれたけれど、すべての採点員が「3」をつけたわけではない。ほんのわずか、足りなかったのだ。でもそれは──今日のためだったのかもしれない。 勇利は視線を据えた。いままででいちばんうつくしい四回転フリップを跳びたい。GOEプラス3がついたグランプリファイナルのフリースケーティングよりもいいジャンプが。ヴィクトルが教えてくれた──ヴィクトルの四回転フリップが跳びたい! 着氷の瞬間、ヴィクトルが両手を上げたのが見えた。ヴィクトル、あんなにはしゃいじゃって。自分のときには平然としてるのにね。ヴィクトル……。 ねえヴィクトル……、ぼくのジャンプ、どうだった? よくお説教する貴方だけど、すてきだったよって言ってくれるかな? 貴方が跳ぶみたいに、ぼくはこのフリップを跳べたかな? ねえ、ヴィクトル……。 ぼくは……。 ぼくは、金メダルを獲るよ。 貴方と……。 「フロムジャパン。ユーリ・カツキ」 「YURI ON ICE」の繊細で純真なしらべが流れ出す。ほの暗く青いリンクに踏み出した勇利は、ゆっくりと滑走し、観客に向かって挨拶した。お辞儀をするたび歓声がわき上がる。勇利は頭を上げると、表彰台に向かってすべってゆき、赤いじゅうたんの上にそっと乗った。 「勇利」 ヴィクトルが手をひろげて勇利を招く。勇利は一瞬くちびるを噛みしめたあと、何かを振り切るようにヴィクトルに近づいて、両腕で彼にぎゅっと抱きついた。 「おめでとう、勇利。とても立派ですてきだったよ。俺は鼻が高い」 勇利の視界がじわっとにじんだ。勇利は急いでヴィクトルから離れ、彼の隣の台に静かに立った。続いてクリストフが呼び出され、ヴィクトルと勇利にそれぞれ抱擁した。じゅんぐりにメダルが授与されてゆく。そのあいだ、勇利はほとんど上の空だった。花束と記念品を持ち、撮影のときになっても、まだ彼はぼんやりしていた。 「勇利、笑って」 「…………」 「メダルを見せて……にっこり笑うんだ。誇りを持っていいんだよ」 「…………」 「勇利」 カメラのフラッシュが、ヴィクトルのかかげたメダルを純粋な金色に輝かせた。勇利の手元では、銀色のメダルが光った。その瞬間、勇利の目から堰を切ったようにどっと涙があふれた。 「うあぁ……」 勇利は天を仰ぎ、大声を上げて泣き始めた。 「ああ、あぁ、ああ、あぁあああぁ……」 ヴィクトルが目をまるくし、クリストフが仰天したように勇利を見た。 「ごめん、ヴィクトルごめん、金メダル獲れなかった。金メダル獲れなかったよぉお……」 勇利はぼろぼろと涙をこぼしながら、手放しで泣き続けた。 「ああん、ああぁん、あぁああぁあ……ああ、うっ、ああ、うぅ……」 「勇利」 激しくフラッシュが焚かれ、観客たちが「勇利くーん」「勇利くん、泣かないで」と口々に言った。しかし勇利の耳には入らなかった。 「うぁ、ああん、うっ、うっ、あぁああ、えっ、う、うぁああ……」 しゃくり上げ、激しく肩をふるわせながら、勇利は顔をぐしゃぐしゃにして泣きじゃくった。ヴィクトルは笑い出し、いとおしそうに、力いっぱい勇利を抱きしめた。 「勇利、泣かなくていい。本当にすばらしかった。俺を本気にさせたのは勇利なんだから」 「うあ、あぁ……」 「そんなに悔しかった? かわいいな。本当に一生懸命だったんだね。勇利ががんばり屋さんなのは知ってたし、そういうところがかわいいと思ってたけど、こんなふうに号泣するとは考えてなかった。いい子だから泣くんじゃない」 「ううっ、う、ごめんなさいヴィクトル、金メダル、金メダルかけてあげようと思ったのに」 「いいんだ」 「貴方じゃない! コーチのヴィクトルにあげたかったんだよ! うあぁ……」 クリストフが可笑しそうに笑い出した。ヴィクトルもくすくす笑い続けている。 「うう、うんっ、う、ひっく、あ、うう……」 「勇利……本当にかわいいね」 「ううーっ……」 涙をぬぐいもせず泣き続ける勇利を見て、ヴィクトルとクリストフがこっそり目を見交わした。ヴィクトルはぐいと勇利を抱き寄せ、クリストフもヴィクトルにそっと寄った。 「いい写真になりそうだね」 クリストフがからかった。 「こんなにすてきな記念撮影、いままで経験したことないよ」 勇利は激しく嗚咽を漏らしながら、笑顔のヴィクトルの隣で写真に写った。 そのあとの記者会見でも、勇利はずっと泣き通しだった。大きな声を上げて泣きわめくことはないものの、涙は止まらず、ずっとうつむいて肩をふるわせていた。 「勝生選手。ショート、フリーともに歴代最高得点を出しながら、直後にニキフォロフ選手に更新されてしまったわけですが、その悔しさがいまの涙につながるのでしょうか」 記者が発言すると、勇利の目から大粒の涙がこぼれた。ヴィクトルが「そういう意地悪な質問は勘弁して欲しいなあ」とにっこりした。それからは彼が質問を受け、クリストフにも話題が及んで会見は進んだ。勇利はタオルで一生懸命目元をぬぐっていた。ヴィクトルは終始勇利に寄り添い、ときおり「大丈夫かい?」「気分は悪くない?」と優しく尋ね、腫れたまなじりにそっと接吻した。 「勝生選手、いまのお気持ちをお願いします」 会見も終わるころ、最後に勇利に声がかけられた。勇利はおもてを上げ、赤くなった頬と鼻、まぶたをさらした。 「ぼ、ぼくは……」 声がふるえた。ヴィクトルがぎゅっと机の下で手を握る。 「悔しくて……、もっといい演技ができ���ばよかったと……ヴィクトル���ーチに申し訳ないです……」 「勇利の演技は最高だったよ」 ヴィクトルがあとを引き受けて言った。 「とくにあのフリーはすごかった。演技のあと、みんな言葉を失っていたもの。もちろん俺もね」 「でも……」 勇利は嗚咽を漏らした。 「負けた……」 悔しい、ともう一度つぶやくと、ヴィクトルは笑み崩れてたまらなくかわいいというように勇利を抱きしめ、「俺の生徒は負けず嫌いでね」と片目を閉じた。 「とても純粋なんだ。かわいいだろ? なんてまじりけのない素直な子なんだって記事に書いておいて」 最後にクリストフが、ヴィクトルを冷やかすように見てひとこと言った。 「やーい、ヴィクトルが泣かしたー」 ホテルに戻っても勇利はずっとうつむいていた。涙は止まったけれど、完全にというわけではなく、何かの拍子に思い出して、ぽろりと何度でもこぼれた。 「勇利、本当に悔しかったんだね」 一緒に入浴したヴィクトルは、浴槽の中で背後から勇利を抱きしめ、泣き腫らしたまぶたに優しくくちづけながら、甘ったるい声で言った。 「俺も金メダルを獲ったと思ったよ。勇利の演技を見たとき、これは勝てるって。あの演技で優勝できないほうがおかしい。ショートもほんのちょっとの差だったしね。普通は越えられない。誰も」 「…………」 「でも……しょうがないね。今回はそれを上まわったやつがいたということさ」 勇利は厚ぼったいまぶたを伏せ、胸元にあるヴィクトルの手をそっと握った。 「ヴィクトル……ごめん……」 「謝る必要はない」 「一緒に獲ろうねって言ったのに……。ぼくはいつも、肝心なところで失敗するんだ……」 「失敗なんてしていない。勇利にいけないところは、ひとつもなかったよ」 「ヴィクトルがすばらしいコーチだって、ぼくは証明したかったんだ……」 「勇利……、知らないの?」 ヴィクトルは笑ってささやいた。 「試合が終わった瞬間から、俺もエージェントもヤコフも、電話鳴りっぱなし。ヴィクトル・ニキフォロフにコーチしてもらいたいんだってさ」 勇利はくすんと鼻を鳴らし、そっとヴィクトルを振り返った。ヴィクトルが優しく笑う。 「本当だよ」 「…………」 「早い者勝ちだとでも思ってるんだね。そうじゃないと断られるって。みんなばかだよ。遅いとか早いとか関係ない。俺の生徒は、生涯たったひとりだけなのに……」 勇利の目から清純な涙があふれ出し、糸を引くようにすっと頬にすべり落ちた。それはおとがいのさきからしたたって、湯の中にぽとんと落ちてとけていった。ヴィクトルは勇利の身体をぐるっとまわして向かいあった。彼の青い瞳がきらきらと輝いている。 「勇利、生徒としても競技者としても、俺を興奮させ、本気にさせるのはおまえだけだよ」 勇利は濡れたまつげでゆっくりと瞬いた。 「勇利……、俺も、きみは世界一の選手だって、証明したかった。みんなに教えたかったんだ」 ヴィクトルはそっと額を合わせ、勇利の頬を撫でてつぶやいた。 「ごめんね……勝たせてあげられなくて」 勇利のくちびるがふるえた。 「ヴィクトル・ニキフォロフは手ごわいね。でもいつか必ず倒そう。ふたりで」 「う……」 「だからもう泣かないで。俺だって悔しいよ。あとすこしだったのにね」 勇利はヴィクトルに抱きついた。ヴィクトルの力強い腕が背中にまわる。勇利は彼に頬をすり寄せ、「ヴィクトル、いままででいちばん強かった……」とつぶやいた。 「うん……そうだね」 ヴィクトルは目を閉じてうなずいた。 「勇利がいたからだよ」 その夜は、ヴィクトルに抱きしめられ、彼のあたたかい胸で思う存分泣いた。翌朝目ざめた勇利は、気分がすっきりし、すがすがしく、晴れやかで、気持ちが穏やかになっていることに気がついた。ヴィクトルはまだ眠っていた。ゆうべカーテンを引き忘れたせいで、彼のおもてに白いひかりが差して、うつくしい顔立ちをきわだたせていた。勇利はヴィクトルに寄り添ったまま、彼の頬に手を当て、指をおとがいへとそっとすべらせた。まくらべの金と銀のメダルがきらっと光った。 「……このひとは勝ったんだ」 勇利はつぶやいた。 「ヴィクトルは金メダルを獲ったんだ」 その瞬間、胸に誇らしい気持ちがわき上がってきた。ヴィクトル・ニキフォロフは誰にも負けない。いつまでも伝説の男なのだ。 「ヴィクトル、起きて。ヴィクトル起きて」 勇利はゆさゆさとヴィクトルを揺さぶって彼を起こした。 「んー……勇利、おはよう……」 ヴィクトルが眠そうに瞬き、まぶたをほそめる。 「おはようヴィクトル! 起きて。聞いて」 「なに……?」 「ぼくのヴィクトルが昨日、金メダルを獲ったんだよ!」 ヴィクトルはぼんやりと勇利を見た。彼はもぞもぞと寝返りを打ち、勇利をぎゅーと胸に抱きしめて、「そうだったね」とうなずいた。 「さすがはヴィクトルだよ。ヴィクトルが金メダルを獲るのなんて当たり前なんだけどね。でもね、勝生勇利は、ショートでもフリーでも歴代最高得点を出したし、フリーが終わった瞬間は、誰がどう見ても彼が金メダルだったんだよ」 「ああ、そうだった。観客は総立ちだったね」 「キスクラでの盛り上がり見た? 勝生勇利が、勝生勇利の持つ記録を更新したんだ」 「すばらしかったね」 「本当だよ。そのあとのインタビューでも、会心の演技でしたね、って記者に言われたんだよ」 「そうか」 「でも、でも……」 勇利はふくみ笑いを漏らし、ヴィクトルの胸に頬をすり寄せた。 「そんな選手にだって、ヴィクトルは勝っちゃうんだ!」 「ああ……」 「やっぱりヴィクトルはすごい。ヴィクトルに敵うやつなんてどこにもいないよ。ヴィクトルよりすごいスケーターはいないの」 「ふ……」 ヴィクトルがほのかに笑い、勇利の髪をそっと撫でた。勇利は彼の腕をまくらにし、頬を紅潮させ、夢中で話し続ける。 「ヴィクトルは、もうね、勝生勇利がどんな得点だって問題じゃない、みたいな感じで、更新された記録をまたさっと更新しちゃったんだよ」 「そうか」 「コーチをしながらだよ! 勝生勇利みたいに、リビングレジェンドにコーチしてもらって、甘えて頼りきってたわけじゃないんだ。ヴィクトルはコーチをしながら自分のこともしてたんだ。すごいよね。最高。本当にかっこいい。ぼくのあこがれ。こんなひとどこにもいない。すてきな選手……」 「ああ」 「ヴィクトルが勝って本当にうれしい。信じてたけど。ヴィクトルが負けるわけないってわかってたけど……、でもやっぱりうれしいよ。ぼくにとってヴィクトルは、いつだって世界一の男なんだ」 「知ってる」 「何があっても負けないんだよ。きっと引退までそうだね。金メダルを保管するの大変そうだよね。たくさんあるから」 「ロシアに来たら、どんなふうに保管してるか見せてあげるよ」 「ああ、ヴィクトルかっこよか……」 勇利はうっとりと目をほそめた。 「最高……大好き……本当に愛してる……」 「うん……」 「彼が世界王者じゃないなんて、そんなこと、とうてい考えられないよ」 「きみの理想の男でいられて本当によかったよ。今回はあぶなかった」 ヴィクトルはくすくす笑った。勇利が口をとがらせる。 「なに言ってるの? ヴィクトルがあぶないなんてことないよ……じつは余裕だったんでしょ?」 「おやおや」 「ヴィクトル……」 勇利はヴィクトルの端正なおもてを夢見るようにみつめた。 「金メダル、本当におめでとう……」 「ありがとう」 「貴方のこと、尊敬しています」 「ああ」 「貴方ほ��強い男はいないよ……」 「そう?」 「あの……ぼく……ぼく……」 勇利はもじもじして口元に手を当てた。ヴィクトルは赤くなった勇利をしばらくおもしろそうに眺めていたが、やがて勇利の身体を転がしてあおのかせ、のしかかる姿勢になると、「本当にわからない子だなあ」と楽しげに言った。 「でもそういうところがかわいいよ」 「あのぉ……」 「うん」 ヴィクトルはにっこりした。 「強い男に支配されたくなった?」 「えっとぉ……」 勇利は慌てて目をそらした。泣き腫らしたまぶたはまだ痛々しく、ほんのりと桃色だった。ヴィクトルはそこにうやうやしく接吻し、「また泣かせちゃうかも」とくすくす笑った。勇利はおもてを上げ、急いで言った。 「いいよ、そんなの!」 「いいのかい?」 「いいよ……だって、ヴィクトルだもの……」 勇利はヴィクトルを見、視線をそらし、もう一度おずおずと目を合わせた。ヴィクトルが噴き出し、「かわいいね」とささやく。 「ヴィクトル……」 勇利は、ヴィクトルのてのひらを腰のあたりに感じながらまぶたを閉ざした。 「よかったぁ……」 「何がだい?」 「ヴィクトルが世界王者で」 勇利は口元をほころばせた。 「ヴィクトルがすべての最高得点の記録保持者で」 「…………」 「ヴィクトル、ぼくやユリオに一度抜かれちゃったんだもん……あんなのはいけないよ……」 勇利はぱっと目をひらいた。彼はきらきら輝く黒い瞳でヴィクトルをじっと見る。 「もう、誰にも追い越されちゃだめだよ」 勇利はけなげな口ぶりで、熱心に、約束を求めるように言った。彼の白い頬はさくら色に染まり、くちびるはヴィクトルが特別気をつけているためつややかで、ヴィクトルの頬に伸びる指は、生涯をかけて愛するひとにふれるように誘惑的だった。 「誰にも負けないでね……」 勇利の大切そうなねがいを、ヴィクトルは目をほそめて聞いていた。彼は勇利の身体からバスローブを払い落とした。 「こんなお祝いをもらえるなら、毎回絶対金メダルを獲るよ」 「世界選手権、銀メダルおめでとうございます」 「ありがとうございます」 「どちらもパーソナルベストを出されて、演技も集大成といった感じで、すばらしかったのですが、試合後の写真が泣き顔しかないという……」 「すみません。いま見るとめちゃくちゃ恥ずかしいです。それもすごい泣き方で……止まらなかったんです、あのときは。自然に出てきてしまって」 「あれは悔し涙だったのでしょうか」 「そうですね……それと、申し訳なかったというか。一度もヴィクトルに金メダルをかけてあげられてないので……。あんなすごいコーチがいるのに不甲斐ないです」 「あのとき、ヴィクトル選手は……いえ、ヴィクトルコーチとお呼びしたほうがよろしいのでしょうか。ヴィクトルコーチは何かおっしゃってましたか?」 「一生懸命ぼくを慰めてくれました。大変そうでした」 「でも、表彰式ではずっと笑ってましたね」 「子どもみたいにぼくが泣いてたので……」 「口が『かわいいかわいい』と動いているように見えましたが」 「そうだったかな……ヴィクトルに訊いてみてください。あ、やっぱり訊かないでください」 「今シーズンを終えて、いまどのようなお気持ちですか」 「そうですね……、いろんなことがありましたけど……、価値観も、スケートも、感情も、すべてヴィクトルに変えてもらった感じです。濃密な時間を過ごせたと思います。そして、ヴィクトル・ニキフォロフはやっぱり強かったです。ヴィクトルと一緒にスケートができてしあわせです」 「勝生選手、あなたにとってヴィクトル・ニキフォロフコーチとはどんな存在でしょう?」 「……生涯離れずにそばにいてもらいたい、愛の力でつながった、ぼくにとってたったひとりのひとですね」 「では、ヴィクトル・ニキフォロフ選手は?」 「そうですね……」 勇利はしばらく考え、やがてすがすがしく白い歯を見せた。 「あこがれ、片想いし、追いかけ続ける、永遠の初恋のひとです」
3 notes
·
View notes
Text
iFontMaker - Supported Glyphs
Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加���貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼��跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker
#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language
7 notes
·
View notes
Text
『地図と拳』小川哲
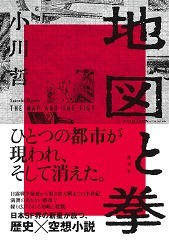
一八九九年の夏、南下を続ける帝政ロシア軍の狙いと開戦の可能性を調査せよ、という参謀本部の命を受け、高木少尉は松花江を船でハルビンに向かっていた。茶商人に化けて船に乗ったはいいが、貨物船の船室は荷物で塞がれ、乗客で溢れた甲板では何もかもが腐った。腐った物は船から松花江に捨てるのが元時代からの習慣だった。一人の男が死体を投げ捨て、「こいつは燃えない土だ」と呟いた。高木は「どういうことだ?」と尋ねた。
男は「土には三種類ある。一番偉いのが『作物が育つ土』で、二番目が『燃える土』。どうにも使い道のないのが『燃えない土』だ。『燃える土』は作物を腐らせるが、凍えたときに暖をとれる。だが、『燃えない土』はどんな用途にも使えない。死体も同じことだ」と言った。通訳の細川が男の出身地を問うと「奉天の東にある李家鎮(リージャジェン)」と答えた。土が燃えるのは石炭が混じっているからだ。これは使える、と細川は思った。
李家鎮は何もない寒村だったが、その地に居を構える李大綱という男が、冬は暖かく夏は涼しく、アカシアの並木がある美しい土地だ、という噂を流した。相次ぐ戦乱で家を失くし、職を奪われた人々��桃源郷の夢を追い、はるばる来てみると、夏は暑く冬は寒く、アカシアなどどこにもない。怒る人々に、李大綱は、誰がそんな嘘を流したと憤って見せ、住む気があるなら、空いている家に住めばいい、土地ならある、と応じた。帰る家のない人々は李大綱から金を借りて家を修繕し、それぞれ仕事をはじめ、李家鎮は体裁を整えていった。
満州東北部にある架空の村を舞台にした歴史小説である。史実を押さえながらも、正史には登場することのない人物を何人も創り出し、日本が中国、ロシア、そして米英との戦争に非可逆的に引きずり込まれていく時代を描いている。人によって読み方は色々だろうが、こういう読みはどうだろうか。当時の日本は、戦争に駆り立てられていたように見えるが、果たしてそうか? 日本の戦争遂行能力を正確に把握していた者は一人もいなかったのか。もしいたとしたら、その結果はどうなっていただろうか、というものだ。
大陸のはずれで清朝の支配の及び難い満州という土地は、ロシアと戦うことになった場合、日本にとって是非とも押さえておきたい土地であった。また、日露戦争で多くの戦死者を出した手前、放棄もできない。リットン調査団が何と言おうが、むざむざ利権を諦めることは不可能だ。そこで、満州族が自ら支配する独立国という建前を作り、五族協和、王道楽土の美辞麗句で飾り立てた。満州国建国は列強を意識した苦肉の策だった。
「五族協和」がどこまで本気だったかは知る由もない。ただ、歴史年表を追うだけで、その当時の日本の軍国主義化にはすさまじいものがあることがわかる。満州国建国に携わった人々の胸にどれほど美しい夢があったのかは知らないが、軍部の力によってそれはどんどんねじまげられていく。その有様を一つのモデルとして描いて見せるのが、李家鎮という街の興亡である。
魯迅の言葉に「思うに希望とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ(『故郷』)」というものがある。「地上に道がない」というのは、冒頭のエピソードでも分かるように、当時の中国では水運が中心だったからだ。
もともとはただの平原であったものを、一人の説話人がかたった話が人々の頭に理想郷を作り上げた。絵空事を信じてやってきた者は無理にでも芝居を続けるよりほかはない。そうして幾人もの人の思いを寄せ集めて出来上がったのが李家鎮。後の仙桃城(シェンタオチェン)である。ロシアにとっては不凍港、旅順に至る要衝、日本にとっては戦争を続けるための石炭という資源の宝庫。仙桃城は、人々の欲望��よって築き上げられた架空の都邑だ。
細川は彼の目的にかなう人材を各方面からスカウトしてくる。彼の言い分が通るのは、 参謀本部が後ろで動いているからだろう。満鉄からの依頼で、存在が不確かな「青龍島」の存否を明らかにする仕事についていた須野も細川にスカウトされた一人。須野は細川の紹介で満州で戦死した高木大尉の妻と結婚し、明男という子を授かる。高木の遺児である正男と共に、この親子は日本の勝利の可能性を探ろうと悪戦苦闘する細川の手駒となって働く。
表題の「地図」とは国家を、「拳」は戦争を意味する。この物語は現実には存在しない「青龍島」が、なぜ地図に書き込まれることになったかという謎を追うミステリ風の副主題を持っている。「画家の妻の島」の挿話をはじめとする、地図に関する蘊蓄も愉しい。細川の徹底したリアリズムに対し、須野のロマンティシズムがともすれば暗くなりがちな話に救いを与えている。幼少時より数字にばかり固執する明男が、母の心配をよそに順調に成長し、建築家になるという教養小説的側面も併せ持つ。
登場人物の大半が男性であり、恋愛もなければ房事もない、近頃めずらしいさばさばした小説だ。戦争に材をとりながらも、威張り散らす軍人は脇に追いやられ、主流は知的かつ怜悧な人物で占められているのが読んでいて気持ちがいい。しかし、議論を重ね、言葉を尽くして、日本に戦争遂行能力がないことを解き明かしても、戦争は阻止できない。「問答無用」は日本の病理なのか、と暗澹とした思いに襲われる。それどころか、よくよく見れば、この国は以前より愚昧さを増しているようにさえ見える。せめて、虚構の中だけでも論理的整合性を味わいたい、そんな人にお勧めする。
0 notes
Photo


AVAILABLE TO STREAM/DOWNLOAD ON NOV 23th CHECK IT OUT "Spotify"

"Apple Music"

"Amazon Music"

youtube
RECORDING MEMBER 野口英律 (Hidenori Noguchi) LeftsideDrums,Keybords,Synth,Bells,Tabla etc 石原雄治 (Yuji Ishihara) RightsideDrums, Bells アライカズヒロ (Kazuhiro Arai) Nylon Gt, Mandolin 安西哲哉 (BxAxNxZxAxI) ElectricGuitar Tsubatics ElectricBass 安藤裕子 (Yuko Ando) SopranoSaxophone 遠藤里美 (Satomi Endo) AltoSaxophone 桑原渉 (Wataru Kuwabara) Trumpet 松井修司 (Sshuji Matsui) Metallophone エリヲ (Eriwo) Percussion 武田理沙 (Risa Takeda) Keybords DJ MEMAI Turntable 千代 (Chiyo) Lyric 永田健太郎 (Kentaro Nagata) Mix & Master release event 2019 / 01 / 14 @新代田FEVER MUSQIS (ORCHESTRA SET) PANICSMILE 二宮友和+MUSQIS open 17:30 / start 18:00 adv2500 / door3000 yen + DrinkOrder
COMMENT “イマジネーションのブイヨン、そしてコーダのまろみ。 エスノすぎずラップすぎずカオスすぎずポップすぎず、 オモシロ具材が沢山入ってるけど、 キチンと破綻しないポトフ。“
赤倉滋(LOOLOWNINGEN&THE FAR EAST IDIOTS)
“人間は何処から来て 人間は何者なのか。 日々模索する日々。 MUSQISという音楽があると言う事は 自分にとって共にこの時代を 共に戦う仲間が居るという事。 そんな強くて、繊細な音が 本作には詰まっています。 更に先へ行こう。“
クロダセイイチ(Genius P.J's)
"舞台はチベットの山岳。 礼装した人々が供物を載せた家畜を引き練り歩く。 人はどこから来て、どこへ行くのか、それは誰のための祈りなのか。 人類のルーツを探る一大スペクタクルここに誕生。 そんな映画みたいな作品です。かっちょいい。"
長谷部 (大塚MEETS店長/DOSTRIKE)
"1945年の敗戦以降、 アメリカによる徹底的な文化侵略に曝され続ける子供達。 舶来のロックミュージックを浴びるように聴いて育った植民地第三世代は、 己れの遺伝子と模倣子の共鳴する音楽の起源を探求する中で 現在進行形の民族音楽を発明するに至った。 普遍性と個別性が同居する矛盾、 調和と混沌の狭間に生じる時空の裂け目をじっと覗き込んでみよう。 家の裏庭で幻の超古代兵器を発掘してしまったみたいな戦慄と興奮があなたの知的好奇心を刺激するに違いない。"
原田卓馬 (WINDOWZ)
"また来る冬を越えて僕らは何を覚えているのだろう。 ツギハギの社会、情報過多、積み重ねた忘却、幼少期、脳内で反復する言葉、季節の匂い。ノイズ。 そんな記憶を呼び覚まされる楽曲。"
100take(Light Source Definitions)
"人間という言葉はヒトとヒトの間に形成されるものなので、 プログラムでもあると僕は思ってます。 美辞麗句を超えたあるべき人間の姿について詠う事と空を眺める事を同じくらい忘れそうになってました。 この音楽が今鳴らされることに頼もしさを感じます。"
tani (ギタリストのような何か/インプロヴァイザー/ Tabletop Guitars/drop the delay)
"配信リリースおめでとうございます! MUSQISというバンドは、というより野口さんという人は多分、 宇宙から来たいや、宇宙に適応しちゃいそうな人なんだと思います。 交信はもう始まってますね、多分。 適応した後に、なんか適応しちゃったとか笑ながら言うんだと思います。 宇宙とノリで適応しちゃいそうな人が作る音楽興味ありますよね? サイケデッリクでオリエンタルなMUSQIS式宇宙適応術講座です、激必聴。"
藤村JAPAN (SEMENTOS / 新宿NINE SPICES 店長)
たとえば金曜日、午後9時50分。 しばしの休息を前にした、仕事帰りの労働者であふれるセブンイレブン。 ヨレヨレのスーツを着たサラリーマン風の男が、レジ前に立っている。 30代半ばくらいだろう。 耳には、Appleの白い純正イヤフォン。 大量のカップ麺と、大量のヨーグルトと、大量の発泡酒。 週末のプライベートタイムを、 ただれた飲食に費やすのだろう。 会計を終えた店員が尋ねる。 「お箸とスプーンお付けしましょうか?」 スーツの男は下をうつむいたまま、無言だ。 ふたたび、店員がさらに尋ねる。 「お箸とスプーンお付けしましょうか?」 スーツの男は無言だ。 やや声を張り、店員がさらに尋ねる。 「お箸とスプーンお付けしましょうか?」 スーツの男は無言だ。 吐き捨てるように店員が尋ねる。 「お箸とスプーンお付けしましょうか?」 スーツの男はそれでも、無言だ。 男の背後には、会計待ちの列ができている。 殺気。 舌打ちとため息。 「お箸とスプーンお付けしましょうか?」 スーツの男は無言だ。 よく見ると、男は右手の人差し指を一定のBPMで動かしている。 心なしか、頭も左右に揺れているようだ。 とてもゆっくりと。 男はグイッと、Appleの白い純正イヤフォンを力強く、耳に挿しなおす。 もしかすると、男の唯一の意思表示なのかも知れない。 「俺は今、音楽を聴いている。このツインドラムが醸し出すDOPENESS。 このリリックが浸食するWILDERNESS。それを遮る権利は誰にもない」 あるいは、そんな脳内宣言を繰り出しているのかも知れない。 男が聴いている音楽が、 たとえば、MUSQISだとすれば。
山下哲史(ターンテーブル奏者/即興演奏者)
"JTNCに呼応するかのようなMUSQIS最新型Experimental Music!!! "
高澤 瑛 (lang / Bridge Guitars店主)
"万物を楽器と捉えることができる自然なイマジネーション。 確かに光っているものであればどんな��見えにくい光でも、 その光の魅力を感じることができる審美眼。 そして、時を経ても尚、正解のない問題を明日も新鮮な気持ちで解きあかそうとする精神。 そこに住む人々の独特な呼吸音から始まり、民族音楽は生まれたと聞く。 MUSQISの呼吸を、しっかりと感じとれる。 それはセンセーショナルでありながら、何かの否定から生まれたものではなく。 全てを包み込むような温かさを持ちながら自然の中で力強く生きていく文化が生んだ呼吸。 わいは美しいものを心で自然に美しいと感じられる尊さを感じたんや。 ほんまやで。 "
Taka-shit JPN aka 安藤 (ライブハウス北浦和KYARA店長)
"リリースおめでとうございます。 野口くんはまず人柄がとても良いのですが、 彼の音楽を聴いたりパフォーマンスを見たりすると、 この人なんなんだろうな、とわからなくて面白いです。 天然の部分とコントロールされた緻密さがすごいなと思います。 この曲も、スピリチュアルで抑制された雰囲気の中、聴くたびにいろんな音といろんな意図が発見できる曲です。"
キシノジュンヤ ( HOPI / the mornings )
"直線的イメージと、 360°包囲される感覚 出発と、エンディング どこだか分からない異国感と、 どこで感じたか分からない懐かしさ 伝達系統の中で ネットワークが意志を持って 自由に拡張と収束を繰り返す そんな行ったり来たりをしているうちに いつの間にか曲が終わってました! リリースおめでとう!!。"
まいこ (つしまみれ)
"ライブとは別物のテクスチャとバランス感覚。 でもブレない。 極端さはないが、穏やかに近づいて、穏やかに喉元まで登ってくる。"
タナカユウキ (extremeOBSN/suthpire/ZENANDS GOTS/whales)
"優れたミュージシャンたちの集まりがMUSQISだと思っていたが この音源を聴いて認識を改めた。 強烈な芸術家集団である。 油絵のように色を織りなし一個の明らかなイメージとなり、 音楽的知性とは違うところにある感性に迫ってくる。"
二宮友和(PANICSMILE、uIIIn)
"東京を離れて5年ぐらい経つと住んでいた時にぼんやり感じていたものが輪郭を持ってくるのか、 摩訶不思議な街だったんですよね、強烈で。 海外の映画に出てくる東京、 とかあと80年代の東京のニューウェーヴ/オルタナロックから感じた強烈なアジア感、みたいなキラキラ感、猥雑な感じ。 スパイスカレーが大好きな人が沢山周りにいたなあとか。 それを再認識しております。 こうして福岡でMUSQISの曲聴いてい��更に明確になったというか、 とてもリアリティがあって、 正に今の「気分」の曲でした。 言葉も音も凄く面白いです。"
吉田肇(PANICSMILE)
"ノスタルジーと先進。洗練と混沌。美と醜悪。 幻想的でいつつひどく現実的。 相反するものが同居する音世界"
イワモトミサト (HELLO STRANGER)
"歴史や匂いや風景や色や建物とか、 たくさんのレイヤーが統合される寸前のギリギリを保ってそこに存在している感じ。 液体よりは個体。 ラストは都会の雑踏、 巨大なスクランブル交差点の中で長い夢から覚めた感覚。"
おのてらえみ (The Taupe)
"楽曲も音もとても好きです。 緻密でミニマル、でも人間味がありワイルドで力強く、 作戦を遂行する姿は、幻影旅団みたいだなと思いました。"
小倉直也 (MASS OF THE FERMENTING DREGS , baduerykah , SYMBOL)
"この楽曲に持ったイメージは砂漠を旅するジプシー。 MUSQISというグループはリーダーの野口氏を核として流動的に活動しているのでその辺もまたジプシー感を僕は感じています。 ただここに出てくる砂漠とはいわゆる東京砂漠。 混沌と秩序、 狂気と正気、 理性と感覚、 不安と平静、 とそんなものが同居しているようなまさに東京という砂漠を僕自身も旅している気分になりました。 リリースおめでとう!"
久恒 亮(AxSxMxUx / Transkam / studio Zot)
"部屋で一人で聴くの危険! ディープな精神世界から戻れなくなっちゃう!"
御代田悟 (K-MIX SHIZUOKA HITS ON PARADE パーソナリティ)
"哲学的な響きだ。 聴き終えて、もう一度聴く。 冒頭の砂利を踏むような音が人間が前に進む思考する音に聴こえる。 哲学的な響きだ。 緻密に構築された音が幻惑的で民族感があり、 個人差あるだろうが、これはリゼルグ酸かなんかで俺の脳内で流れていて 現実には存在しない音楽なんじゃないか? と心配になるほどサイケデリックに鳴る。 一度聴けば、ロジカルな音像に、 もう一度聴けば、ラジカルで哲学的で、 さらに一度聴けば、全て引っ括めて脳へのドープだ。 うだうだ言いましたが、とにかく素晴らしいの一言です。 作ってくれて有難うございます!!"
榮勇太 (ゆれる)
"やばいです! 音楽で地球とか作ろうとしてるんじゃないかって思いました。 (MUSQISが地球作ろうとしている前提で話しますが)あなたは音楽で地球作ろうと思ったことありますか? 俺は残念ながら思ったことがありません。。。(これから作って見ます!) 大地の鼓動や地平線のはるか向こうや生命の脈々��受け継がれし何やかんや、 そして最新のテクノロジーまでを感じたい方はぜひご一聴を。"
松本一輝 (Temple of Kahn , ravenknee , phai)
"十数年前、はじめてDCPRGを聴いたとき 「どんな生活をして、何を食べ、どんな体験をすれば、こんな音楽に辿りつくのか?!なんだこの(よい意味で)キチガイな音楽は?!」 ってなったことが記憶に蘇ってきた。 たとえば、それがMUSQISだったとしても、そのときの僕は同じ印象を持っただろうな。"
タニタカヤ ( LLRR, ex.otori )
"宇宙と無。 異国と日本。 古代と現在。 BGMと精神的音楽。 相反する要素がたっぷり詰まってて、しかも全てハマってる。 面白い。 MUSQISは10年後もMUSQISのままでいてほしいし、きっとそうであってくれると思う。"
森大地(Temple of Kahn / kilk records)
"踏みしめる足音、 旅の途中、 脳内で繰り返すギターメロディ、 雪月風花、 四分半の己との対峙、葛藤、 ただ、つま先は前を向いてる"
キドウラコウイチ (World Wide Size/kiyasu orchestra/HAIGAN)
"東京銀河音楽です。"
MORIKON (pocketlife / PAPRIKAN / Delicate Zoons )
"目標物が何も無く、薄暗い一面雪の中を真っ直ぐ、ただただ歩いている映像。 対して、遊牧民が周りを浮遊、回転しながら祝祭を行なっている様にも思え、混乱。 エネルギーの向かう方向、かつて内に向かって凝縮されるように感じていた。 CuriousSystemでは強烈に外へ。 矢印は様々な曲がり方、でもあくまで個。 音楽としての次元が上がったから?以前よりハッキリと感じる。 霧散されているわけでは無く、複数の線が世界地図を手前から奥に塗り潰す様。 混乱。 高円寺の喫茶店、お婆さんが隣の席のBボーイ、ガールカップルに声をかけオリジナルマッサージを施術中。 お婆のテンションはエスカレート、 Bボーイ彼氏の背中をハデにバシバシ、シバきはじめた。 喫茶店中が注目しているが、お婆は御構い無しにバシバシシバく。 あ、Bボーイがキレた。霧散。 昨日一昨日、酔いに任せ夢遊し何度も聴いていた。 高円寺、博多駅、呟きながら歩いた。 左右に振られたドラム、野口君のツイートを思い出しながら数えながら歩く。 MUSQISのブレイクから戻ってくるスピードが速いとこがたまらなく好き。 いまは福岡、今はどこか?いつか? ヴィジョンや言葉で表現できないこと、面白いけど、今回のムスキスはなんだか掴めそう? 掴んでいる?かも。"
じった(マクマナマン / KELP / snarekillsnation)
"8+6の変拍子が身体に落とし込まれて、 言葉が何かを訴えていく果てに破綻して広がる宇宙感覚は太い幹のようだ。 荒寥として無国籍エスニックな皿は既に僕らの背骨を貫通している。 そこに言葉が刻み込まれて解放される。 深く深く。 野口の長い髪の匂い。"
佐々木すーじん (scscs)
"僭越ながら、こうして楽曲にコメントをさせていただくのは初めての経験でして、とても嬉しく思います。 「Curious System」を聴きまして、 スピリチュアルとか虚無的といったイメージや手触りがまずあったのですが、 何度も聴いていくうちに不思議なあたたかみのようなものを感じるようになりました。 "わたしたち"や"かつてのわたしたち"がためらってしまったであろう藪を掻き分けていった先に広がる茫洋たる思索の荒野、 その果てに集った人間たちの祝賀か呪詛かそのどちらもか。 次なる荒野を目指すかのように盛大かつ粛々と奏でられる音に、 脳細胞と筋肉とぜい肉と骨が等価値で躍動させられながら "音楽のはじまり"に思いを馳せました。"
kawauchi banri (てあしくちびる)
"ラップの声に癒されます。中東な音もいい感じ"
宝生久弥 (Scaperec)
MUSQIS MAIN PAGE HERE
1 note
·
View note
Text
王様の自滅 自国を滅ぼす方法など
⦅操縦七術[韓非]から続く⦆

〖国を滅ぼす王様の特徴〗 01_王様が宮殿や庭園の建築にうつつをぬかし、車や衣服珍品集めなどの道楽に凝って、国民から絞りあげては浪費する。 殷 ( いん ) の 紂 ( ちゅう ) 王が象牙の箸をつくらせた。 箕子 ( きし ) (紂王の叔父。狂ったふりをして身を守った)は恐怖を覚えた。 彼はこう思ったのだ。 象牙の箸となれば、汁のうつわも素焼きの土器ではすまなくなる。 きっと 犀 ( さい ) の 角 ( つの ) か玉でできた豪華なうつわを使うだろう。 玉のうつわに象牙の箸ということになれば、豆や豆の葉という質素な料理ではすまなくなる。 きっと 旄牛 ( からうし ) ・象・ 豹 ( ひょう ) の胎児などの美味珍味��ならざるをえない。 こうした美味珍味を食べるとなれば、着るもの住む家も普段着や 茅 ( かや ) 葺きではすまなくなる。 きっと 錦 ( にしき ) を重ね、広大な屋敷をつくるだろう。 こうして釣り合いを求めていけば、いつしか天下の富を根こそぎつぎ込んでも、まだ不足する。 ほんの小さな兆候候をも見逃さず、始まりを見て結末を察知するのが聖人だ。 箕子が象牙の箸を見て恐怖を覚えたのは、その段階で、天下全体ものを使っても不足する結果を見抜いたからだ。 殷 ( いん ) の 紂 ( ちゅう ) 王は、部屋の窓を閉ざして明かりを灯し、百二十日を一夜として「酒池肉林」の宴を続けたために、日がわからなくなってしまった。 「さて今日は何日だったかな」と、お側の者にたずねたが、誰一人としてわからない。 そこで、 箕子 ( きし ) のもとに使いを出して、たずねさせた。 箕子は家臣にこう言った。 「天下の 主 ( あるじ ) となりながら、国中誰も日がわからないという。 これでは天下は保てまい。国中誰もが知らないことを、わたし一人が知っていたとなれば、わが身があぶない」。 そして、自分も酔ってわからない、と使者に答えたという。 桓公が管仲に尋ねた。「富には限界があるのだろうか」。 「水の限界は水のなくなるところ、富の限界は人がそれに満足したところです。ところが、人間は満足することができず、富をむさぼって、ついには身を滅ぼしてしまいます。これが富の限界でしょうか」。 紹績昧 ( しょうせきまい ) は酒に酔って寝てしまい、皮の上着をなくした。 宋 ( そう ) 王が不思議に思って、彼に聞いた。 「酒に酔ったくらいで皮の上着までなくすものか」。 「 夏 ( か ) の 桀 ( けつ ) 王は酒で天下をなくしました。それゆえ 康誥 ( こうこう ) (書経の一篇)には『酒を 彛 ( い ) するなかれ』とあるのです。酒を彛するとは、酒を常にするという意味です。酒を常飲すれば、天子は天下を失い、庶民も自分の命を失うのです」。 昔、 弥子瑕 ( びしか ) という美少年が、 衛 ( えい ) の 霊 ( れい ) 公の寵愛を受けていた。 衛の法律では、許しなく王様の車に乗った者は、足切りの刑に処せられる。 ところが、弥子瑕は夜中に母が急病だという知らせを受け、君命といつわって王様の車を使った。 それを聞いた霊公は、罪を問うどころかほめるのだった。 「親孝行なことではないか。母を思うあまり、自分が足を切られるのさえ忘れるとは」。 また、ある日、霊公のお供をして果樹園に散歩に行ったとき、弥子瑕が桃を食べたところ、あまりにおいしいので、半分残して霊公に薦めた。 霊公は、「王様思いではないか。自分が食べるのを忘れてまで、わしに食べさせてくれるとは」。 だが、やがて弥子瑕の容色が衰えて、霊公の寵愛がうすれてきた。 すると、霊公は、弥子瑕が前にしたことに腹を立てて、「こいつは、嘘までついてわしの車を使ったことがある。またいつぞやは、わしに食いかけの桃を食わせおった」。 02_吉だ凶だと日柄を気にし、 鬼神 ( きしん ) をありがたがり、占いの結果を真に受けて、何かといえば、 祭祀 ( さいし ) をやりたがる。亀の甲に穴を開けて火であぶったり、 筮竹 ( ぜいちく ) を数えて占った結果に従って戦をした 燕 ( えん ) や 趙 ( ちょう ) は、負けることが多かった。 03_限りない欲張りで、利益とみれば見さかいなく飛びつく。 宋 ( そう ) の国に 監止子 ( かんしし ) という金持ちの商人がいた。 あるとき、他の商人と時価百金の 粗玉 ( あらたま ) を 競 ( せ ) りあったことがある。 監止子はまちがったふりをして粗玉を落とし、傷をつけた。 百金の弁償をして引き取り、きれいに傷を磨き落として売ったところ、千金あまりの大金を得た。 一般に、何かを行って失敗しても、何もやらなかったよりもましな場合がある。 監止子のように、タイミングよく責任を引き受けた場合がそれだ。 04_法に基づかず、無原則に刑罰を加える。空理空論に耳を傾け、現実に役立つかどうかを考えない。外見を飾り立てて、実用を無視する。 05_独善的で協調性がなく、 諫言 ( かんげん ) されればむきになる。国家全体のことを考えずに軽率に動き、しかも自信満々だ。 食客のなかに、不老長寿法を教えるという者がいたので、 燕 ( えん ) 王は家来のひとりに習わせたが、その家来がまだ習い終えないうちに、食客は死んでしまった。燕王は怒って家来を殺した。食客が自分を騙したのに気づかず、習い方が遅いといって死刑にしたのだ。道理に合わないことを信じて罪のない家来を殺すとは、また浅はかなことであった。 誰でも一番大切なのは自分の体のはずだ。その自分が死を免れないでいて、他人の燕王を不老長寿にすることなどできるはずがない。 06_王様がずぼらで、およそ反省ということをせず、どんなに国が乱れていても自信満々で、自国の経済力を考えずに、隣の敵国を組みしやすしとする。 07_国が弱小であるのに、尊大にふるまい、強国を警戒しない。国境を接している大国をバカにして、礼をもって対しようとしない。 昔、晋の公子 重耳 ( ちょうじ ) が亡命し、曹に立ち寄った。 曹の王様は服をはだけさせて重耳を見せ物にした。 そのとき 釐負羈 ( きふき ) と 叔瞻 ( しゅくせん ) が曹の王様に付き添っていた。 叔瞻は曹の王様に申した。私、晋の公子を観ましたところ、ただ者ではございません。王様はこれに無礼をなさいました。彼がもし時を得て国に帰り、挙兵すれば、恐らく曹の害となりましょう。王様はこれを殺してしまうのがよいでしょう、と。 しかし曹の王様は聴き入れなかった。 釐負羈は帰って浮かぬ顔をしている。 妻が問うた。あなたは外から帰ってきて浮かぬ顔をしておられるのは何故ですか、と。 釐負羈は言った。私はこう聞いている。良いことには 与 ( あずか ) らず、悪いことには連なる、と。今日我が君は晋の公子を招き、無礼をはたらいた。私はそのとき付き添っていたので浮かぬ顔をしているのだ、と。 妻は言った。私が晋の公子を観るに、大国の主のようです。その左右の従者は大国の宰相のようです。それが今、窮乏して曹に立ち寄り、曹はこれに無礼をはたらきました。これがもし国に帰ることになりますと、必ずや無礼を 誅 ( ちゅう ) しましょう。曹はその手始めとなりましょう。あなたはどうぞ今のうちに 誼 ( よしみ ) を通じておきなさいませ、と。 釐負羈は言った。よろしい、と。 黄金を壺に盛り、食べ物で蓋し、玉壁をその上にのせ、夜、使者を公子に遣いさせた。 公子重耳は使者に会い、再拝の礼で食べ物を受け取り、玉壁は辞退した。 公子は曹から楚に入り、楚から秦に入った。 秦に入って三年、秦の 穆公 ( ぼくこう ) は群臣を集め 謀 ( はかりごと ) をして言った。昔、晋の献公と私が仲良く交流していたことは諸侯のうちで知らぬ者はいない。献公は不幸にも群臣から離れて亡くなり、十年が経つ。その 世嗣 ( よつ ) ぎは出来が良くない。私は心配だ。このままでは晋の 宗廟 ( そうびょう ) は清く保たれず、 社稷 ( しゃしょく ) の供物が絶えはせぬかと。このような状態にもかかわらず晋の足元を固めてやらないのは、献公との交流してきた道に反する。私は重耳を助けて晋に入れようと思うが、どうであろうか、と。 群臣は皆言った。よろしゅうございます、と。 穆公はそこで挙兵した。 革鎧の戦車五百乗、騎兵二千、歩兵五万、重耳を助けて晋へ入れ、立てて晋君にした。 重耳は即位して三年後、挙兵して曹を 伐 ( う ) ちに向かった。 そこで重耳は使者を送って曹の君主に告げさせた。叔瞻を城壁から懸け下ろして出せ、私が殺して処刑してやる、と。 また使者を送って釐負羈に告げさせた。我が軍勢が城に迫っている。私はあなたが礼に 背 ( そむ ) かなかったことを知っている。あなたの住まいに目印をたてておかれよ。私は命令して軍勢がそこを攻めぬようにさせよう、と。 曹の人々はこれを聞き、親戚をかき集めて釐負羈の住まいへ逃げ込む者が七百余家にも及んだ。 08_王様が臆病で信念が貫けない。すなわち予測するだけで決断ができず、やらなければと思うだけで手が下せない。 呉 ( ご ) 王の 闔廬 ( こうりょ ) が、 楚 ( そ ) の都の 郢 ( えい ) を攻め、三戦三勝した。 呉王は 伍子胥 ( ごししょ ) に意見を求めた。 「このぐらいで引き揚げてよいだろう」。 「いけません。人を 溺死 ( できし ) させようとするとき、一飲みさせたところで、止めたのでは、溺死するわけがありません。手をゆるめず押さえつけ、このさい、徹底的に沈めてしまうべきです」。 09_都合が悪ければ理屈をつけて法をまげ、何かにつけ公事に私情をはさむ。その結果は 朝令暮改 ( ちょうれいぼかい ) 、次から次へと新しい法令が発せられる。 斉 ( せい ) �� 魯 ( ろ ) を破ったとき、魯の宝である 讒 ( ざん ) という 鼎 ( かなえ ) を要求した。 魯はニセ物を持って行かせたが、見破られてしまった。 「ニセ物ではないか」。 「いや本物です」。 「それでは貴国の 楽正子春 ( がくせいししゅん ) ( 曾子 ( そうし ) の弟子)を連れて来てもらいたい。彼なら信用できる」。 魯王は楽正子春にうまくごまかしてくれるように頼んだ。 楽正子春は魯王に尋ねた。 「なぜ本物を持って行かせなかったのです」。 「本物は惜しいからさ」。 「わたしも自分の信用を惜しみます」。 10_もともと地の利に恵まれないうえに、城郭も欠陥だらけ、物資の蓄えはなく、生産力も低い。すなわち長期戦に耐える力がないのに、軽挙妄動して戦いをしかける。 11_視野が狭くてせっかちで、 些細 ( ささい ) なことで簡単に行動を起こし、すぐにカッとなって前後の見境がつかなくなる。 12_怒りっぽいうえに戦好きで、本務たる農政に力をいれず、何かといえば武力を発動する。 大臣を侮辱してプライドを傷つける。庶民に厳しい刑罰を加えて、過酷な使役に駆り立てる。これを当然のこととして繰り返せば、謀反を 企 ( たくら ) むものが、必ず現れる。 13_王様が大利を目前にして傍観するばかり、また禍いを予測していながら対策を立てようとしない。そして防衛ということにまったく無知でありながら、「仁義」によって自己の行為を飾り立てようとする。 14_雄弁だが「法」という筋が通っていない。聡明ではあるが、肝腎の「術」を心得ていない。能力そのものはあるのだが、「法」によって事を運ぼうとしない。 〖本心を隠す〗 王様が心の 裡 ( うち ) を見透かされると、 家来 《 けらい 》 たちに付け込まれる。 楚 ( そ ) の霊王が細い腰の美人を好むと、 楚 ( そ ) の都には絶食して痩せようとする者があとをたたなかった。 臥薪嘗胆 ( がしんしょうたん ) の故事で有名な越王 勾践 ( こうせん ) は、勇者を好んだ。越の決死隊は、呉の陣の前で一斉に自分の首を 刎 ( は ) ねた。呉軍の兵卒は、あっけにとられ、その隙に奇襲攻撃をかけられて総崩れとなった。 斉 ( せい ) の桓公は好色で嫉妬深かった。 豎刁 ( じゅちょう ) は、自ら去勢手術を受けて、後宮の 宦官 ( かんがん ) になり、信頼を得て大臣に任命された後、謀反を起こして桓公を部屋に閉じ込め飢え死にさせた。 桓公は食い道楽でもあった。料理人の 易牙 ( えきが ) は、自分の長男を蒸し焼きにして差し出した。易牙も、豎刁の謀反に参加した。 燕 ( えん ) の 子噲 ( しかい ) は人格者を好むと思われていた。大臣の 子之 ( しし ) は、国を譲られても受けないと公言して信頼を得、政治を任されて実権を奪った。伝説時代に、 堯 ( ぎょう ) という天子がいて、 許由 ( きょゆう ) という隠者に天下をゆずろうとしたが、許由は受けず、耳が穢れたといって耳を洗ったという。子噲は子之が辞退するのを確かめておいて、堯のまねをしたのに、子之の方が上手だった。 王様が好悪を見せなければ、家来は素を表わし、王様はだまされない。 堂谿 ( どうけい ) 公が、 韓 ( かん ) の 昭 ( しょう ) 侯に尋ねた。 「 価 ( あたい ) 千金の 玉杯 ( ぎょくはい ) があったとする。もし底がなかったとしたら、これに水を入れることができるでしょうか」。 「だめだ」。 「では素焼きの器があるとする。これには底があって漏らないとしたら、酒をつぐことができるでしょうか」。 「できる」。 そこで堂谿公は言うのだった。 「素焼きの器はとるにたらぬ粗末なものですが、漏りさえしなければ酒をつぐこともできます。価千金の玉杯はまことに貴重なものですが、底がなくて漏るとしたら、水さえ入れることができません。まして、これに飲み物を入れる者があるでしょうか。家来の言葉を他人に漏らす王様は、ちょうど底の抜けた玉杯のようなものです。いくら王様に知恵があっても術をつくすことができないのは、人に漏らしてしまうためです」。 それからというもの昭侯は、大きな計画を考えているときには、必ずひとりで寝た。 寝言を聞かれて、他人に計画が漏れることをおそれたのだ。 斉国の正室が亡くなったとき、大臣の 薛 ( せつ ) は、 威 ( い ) 王の意中の人を新しい正室に 推薦 ( すいせん ) しようと考えた。薛は、玉の耳飾り九組に特に美しい耳飾りを一つ加え十組にして王に献上した。翌日、薛は、特に美しい耳飾りをしている側室を確認して王に推薦した。 〖信ずる者は 騙 ( だま ) される〗 王様が妻を信じたら、腹黒い家来は王様の妻を利用して私欲をとげようとする。 優施 ( ゆうし ) という役者は、 晋 ( しん ) の 献 ( けん ) 公の愛妾 麗姫 ( りき ) に取り入り、世継ぎの 申生 ( しんせい ) を殺して、麗姫の子 奚斉 ( けいせい ) を擁立した。 王様が我が子を盲信すると、腹黒い家来は王様の子を利用して私欲をとげようとする。 趙の武霊王(在位 前325年~299年)は 胡服騎射 ( こふくきしゃ ) (騎馬民族の戦法)をいち早くとりいれ、趙を軍事的に発展させたが、寵愛した恵后のために後継問題の処理を誤った。太子に決まっていた長子 章 ( しょう ) を廃嫡して、恵后の子 何 ( か ) (恵文王)に王位を譲り、自分は 主父 ( しゅほ ) と称して院政をしいたが、恵后の死後、廃嫡した長子 章 ( しょう ) の処遇に迷い内乱を起こさせてしまった。主父も、 沙丘 ( さきゅう ) の別宮で三箇月包囲されて餓死した。そのときの包囲軍の指揮官は 李兌 ( りたい ) だった。 妻子でさえ裏切ることがあるのに、他人である家来を信じたら、 悲惨 ( ひさん ) な結果が待っているかもしれないことを知らなければならない。 王様の世継ぎが立てられたら、妻は、我が子の即位を待ち望むもの。 男は五十になっても色好みはやまないのに、女性は三十になれば容色は衰える。 衰えた容色で色好みの夫に仕えれば、疎まれ 貶 ( さげす ) まれるようになり、「これでは我が子は、あとを継げないのではないか」と、妻は疑う。我が子が王様の座につけば、何でも命令できるし、嫌なことも禁止できる。男女の楽しみは、夫の死後も以前にも増して楽しめる。大国を思いのままに動かしても、誰からも文句は出ない。 毒を盛ったり、闇打ちをしたりのお家騒動が尽きないのも、こういうところに原因がある。 桃佐春秋 ( とうさしゅんじゅう ) には、「まともな死に方をする王様は半数に満たない」と書かれている。 魏 ( ぎ ) 王が 楚 ( そ ) 王にひとりの美女を贈った。 楚 ( そ ) 王はこの美女がすっかり気に入った。 楚 ( そ ) 王の側室 鄭袖 ( ていしゅう ) は王がこの美女を可愛がるのを見て、王が可愛がる以上に自分も可愛がり、衣裳でも何でも彼女の欲しがるままに与えていた。 王はそれを見て言った。 「 鄭袖 《 ていしゅう 》 はわたしがあの女を可愛がるのを知って、わたし以上に可愛がってやっている。まるで親孝行な子が親をおもい、忠臣が王に仕えるようではないか」。 …「王様は自分が嫉妬していないと信じている。これでよし」と思った 鄭袖 《 ていしゅう 》 は美女に「王様は女性が手で口を覆う仕草が好きだから、王様に近づくときは手で口を覆うようにしなさい」と教えた。美女はその話を信じ、始めて王様とのお目見えする際にさっそくその仕草を実行する。事情を知らない王様がその理由を周囲に尋ねると、鄭袖が「あの女は王様の匂いを嫌って手で鼻を覆っているのです。」とウソを付いた。王様は、激怒し、美女の鼻を削ぐよう命じた。 〖人材活用〗 楚 ( そ ) が 陳 ( ちん ) を攻めたとき、 呉 ( ご ) は陳を助けた。 楚 ( そ ) ・ 呉 ( ご ) 両軍は三十里をおいて 対峙 ( たいじ ) した。 ある夜、十日も降り続いた雨がやみ、星が見えた。 楚 ( そ ) の 左史 ( さし ) の 倚相 ( いしょう ) は将軍の 子期 ( しき ) に言った。 「十日の雨のあいだに、呉軍は準備をととのえたはずです。きっと攻めてくるにちがいありません。備えた方がよろしいでしょう」。 そこで、 楚 ( そ ) 軍は、陣形をととのえたが、はたして、準備が終わるか終わらないうちに、呉軍がやって来た。 しかし、 楚 ( そ ) 軍に備えがあるのを見ると、戦わずして引き返した。 左史は言った。 「呉軍は往復で六十里歩かなければなりません。帰れば疲れて将軍は休む、兵士は食事をするはずです。一方わが方は三十里ですみます。すぐ攻め��ば勝てましょう」。 楚 ( そ ) 軍は呉軍を追いかけ、これを破った。 孟嘗君率いる斉・魏・韓の連合軍が���谷関に攻めてきたとき、秦の昭襄王は大臣に「三国の兵が秦に深く攻め込んでいる。河東郡の数県を与えて和睦しようと思うが、どうか」と尋ねた。 大臣は、「河東郡の数県を与えるのは、大きな損失です。王子様とご相談なさってはいかがでしょうか?」と答えた。 王様から相談された王子は、「和睦してもしなくても、後悔は避けられません。…和睦したら、『三国はもともと引き上げようとしていたのに、むざむざ三城もただでやってしまった』と、後悔するでしょう。…和睦しなかったら、 韓 《 かん 》 に集結した三国軍に大損害を与えられ、『しまった、三城をやらなかったばかりに、こんなことになってしまった』と、後悔するでしょう。」と答えた。 昭襄王は、「後悔するのなら、三つの城を失って後悔する方が、国が危険な状態になって後悔するより余程マシだ。」と考え、和睦を決めた。 管仲 ( かんちゅう ) と 鮑叔 ( ほうしゅく ) が相談をした。 「このご乱行では 斉 ( せい ) の 御代 ( みよ ) も変わるにちがいない。斉の公子のなかで、将来性のあるのは 糾 ( きゅう ) さまか、 小白 ( しょうはく ) さまだ。この二人にわれわれは一人ずつ仕え、先に出世した者が他を引き立てることにしよう」。 こうして管仲は糾に、鮑叔は小白に仕えた。 はたして斉は混乱状態におちいり、王様が殺された。 そしてまず小白が亡命先から帰国して王様の座についた。 管仲は糾とともに 魯 ( ろ ) に逃れていたが、魯の人につかまって小白に引き渡されたが、鮑叔の口添えによって宰相になることができた。 〖王様への意見の出しかた〗 [説得]は、相手の心を正確に見ぬき、自分の意見をそこに合わせることが必要。知識や弁舌だけでは不十分。 名声の高さを求める相手に、利を得る術を説けば、下劣で卑しい奴と思われ、遠ざけられる。利を求める相手に、名声の高まる術を説けば、気配りできず現実に疎い者と思われる。 名声を大切にしているように見せかけながら、内心では利を求めている相手に、名声の高まる術を説けば、得心した様子を見せられながら、実際には疎んじられるだろう。逆に利を得る術を説けば、得心させても、用いられることはない。 01_王様が自分の利益を満たそうとしているときには、国法を述べてそれを強制する。それでも欲望を捨て切れないときは、欲望に理屈をつけてやる。実行に移せない道義には、とやかく言わないでおく。 02_理想が高すぎて非現実的なときは、理想の欠点をあげ、実行しない。それは難しいでしょうなどと、ケチをつけてはならない。 03_知識・見識に自信もってる相手には、同類の別の事例を挙げて下地を準備しておき、相手が自ら選ぶように仕向けて、そしらぬ顔をする。 04_他国と友好関係を保つように説得するには、立派な名目を上げてやり、それとなく自分の利益にもなることを示す。 05_国の害になることを分からせるには、道義に反しているとはっきり言い、自分の損にもなると分からせる。 06_直接相手を誉めるよりは、相手と同じ事をしているものをほめ、他の事で王様の計画と同じものがあれば、そのことを議論で取り上げた方が効果がある。 07_王様と同じ失敗をした者は、たいした過失ではないと言って弁護しておく。相手がよい計画だと思っているのに、悪いところをあげつらって追いつめてはいけない。 08_長い月日を経て、王様の信任も厚くなり、立ち入った策を奏上しても疑われず、王様と言い争っても罰せられなくなったならば、堂々と利害を判断して述べ、自分の意見を実現化して事の是非をずばりと述べることを身上とする。こうして王様と対等の関係を保てるようになれば、これこそが献策の最上のものとなる。 〖 和氏 《 かし 》 の 璧 ( へき ) 〗 昔、 楚 ( そ ) の国に 和氏 ( かし ) という男がいた。 あるとき、彼は 楚 ( そ ) 山の山中で 粗玉 ( あらたま ) を見つけ、これを 厲 ( れい ) 王に献上した。 厲王は宝石師に鑑定させた。 「これは、ただの石でございます」。と宝石師は言った。 厲王は和氏をペテン師として足切りの刑を命じ、左足を切らせた。 厲王が死に、 武 ( ぶ ) 王が即位した。 すると、和氏はまた同じ粗玉を献上した。 武王は宝石師に鑑定させた。 「石でございます」。と宝石師が言った。 武王は和氏をペテン師として足切りの刑を命じ、右足を切らせた。 武王が死に、 文 ( ぶん ) 王が即位した。 今度は和氏は粗玉を抱き、 楚 ( そ ) 山のふもとで泣き続けるのだった。 三日三晩がたった。 涙は枯れはてて、眼に流れるものは血であった。 文王はそのことを聞くと、和氏のもとに人をやってわけを尋ねさせた。 「世の中に足切りの刑にあった者も多いが、どうしておまえは、そんなに悲しげに泣くのか」。 「わたくしは足を切られたことが悲しいのではありません。宝石が石ころだと言われ、正直者がペテン師だと言われた。それがわたくしは悲しいのです」。 文王は、宝石師にその粗玉を磨かせてみた。 はたしてそれは宝石であった。 その宝石は、彼の名をとって、「 和氏 ( かし ) の 璧 ( へき ) 」と呼ばれた。 宝石というものは、王様が喉から手が出るほど欲しがるものだ。 そして 和氏 ( かし ) が献上した 粗玉 ( あらたま ) が、もし宝石でなかったとしても、王様が何の損をするわけでもない。 それにもかかわらず、和氏は両足を切られてから、はじめてその粗玉が宝石であると認められたのだ。 王様が欲しがる宝石でさえ認められるのは、これほど困難なのだ。 ところが[法・術]となると、王様は「和氏の 璧 ( へき ) 」のようにこれを欲しがってはいない。 王様たちは、それほど熱心に家来や国民のかげの悪事を抑えようとはしていないのだ。 [法・術]を主張する者が、王様に殺されずにいるのは、彼がまだ[法・術]という粗玉を献上していないからにすぎない。 王様が「術」を使ったとしたら、大臣が政治を専断することも、側近が王様の威を借りることもなくなるだろう。 「法」が国に行きわたれば、流民の 類 ( たぐい ) は姿を消し、すべての国民は農耕に追いやられ、事あるときには戦場で生命の危険をおかすことになるだろう。 つまり[法・術]は、家来と国民にとっては、 禍 ( わざわい ) となるものだ。 したがって、王様が、大臣の反対と国民の非難を押しきって、[法・術]に耳を傾けようとするのでなければ、たとえ命を進言したとしても、[法・術]が王様に取り上げられる見込みはない。 〖使いこなせない者とは〗 もし人が衣服を着ることもなく、食事をとることもないのに、餓え凍えることがなく、また死もこわくないとすれば全て満ち足りており、お上に仕える気はとんとならないであろう。すると、王様によって支配されることを嫌う気持ちになる。そのような人物は、臣下として使いこなすことはできない。 〖小さな信用を重ねる〗 呉起 ( ごき ) は外出先で知人に出会い、食事に招いた。 知人は承知して、「のちほど伺うから、それまでお待ちいただきたい」。 「では、あなたがおいでになるまで、お待ちいたしましょう」、呉起はそう答えた。 その知人は日暮れになっても来なかった。呉起は食べずに待った。 そして、翌朝、知人を呼びにやり、彼が来てから食事した。 越王 勾践 ( こうせん ) が呉王 夫差 ( ふさ ) を攻め、 降伏 ( こうふく ) させた。 呉王夫差が謝罪して 赦 ( ゆる ) しを願った。 越の大臣たちは、越王勾践に、「天命が[越]を与えようとしたとき[呉]が受け取らなかったから、今、天命は[呉]を[越]に与えようとしているのです。天意に 背 ( そむ ) いてはなりません。」と言った。 呉の大臣は、越の大臣に手紙を送った。「すばしっこい兎が狩りつくされてしまうと、猟犬は煮て食べられる。敵国が滅びると、軍師は殺される。呉を赦して残せば、貴方はまだまだ仕事ができる。」 越の大臣は、これを読んで大きくため息をつきながら、「呉が滅べば私は用無しになるのか…」とつぶやいた。
0 notes
Text
【小説】フラミンゴガール
ミンゴスの右脚は太腿の途中から金属製で、そのメタリックなピンク色の輝きは、無機質な冷たさを宿しながらも生肉のようにグロテスクだった。
彼女は生まれつき片脚がないんだとか、子供の頃に交通事故で失くしたのだとか、ハンバーガーショップでバイト中にチキンナゲット製造機に巻き込まれたのだとか、酒を飲んでは暴力を振るう父親が、ある晩ついに肉切り包丁を振り上げたからなのだとか、その右脚についてはさまざまな噂や憶測があったけれど、真実を知る者は誰もいなかった。
ただひとつ確かなことは、この街に巣くう誰もが、彼女に初めて出会った時、彼女はすでに彼女であった――ミンゴスは最初から金属の右脚をまとって、我々の前に現れたということだ。
生身である左脚が描く曲線とはまるで違う、ただの棒きれのようなその右脚は、しかし決して貧相には見えず、夜明け前の路地裏を闊歩する足取りは力強かった。
脚の代わりでありながら、脚に擬態することをまったく放棄しているその義足は、白昼の大通りでは悪目立ちしてばかりいた。すれ違う人々は避けるように大きく迂回をするか、性質が悪い連中はわざとぶつかって来るかであったが、ミンゴスがそれにひるんだところを、少なくとも俺は見たことがない。
彼女は往来でどんな目に遭おうが、いつだって澄ました表情をしていた。道の反対側から小石を投げてきた小学生には、にっこりと笑って涼しげに手を振っていた。
彼女は強かった。義足同様に、心までも半分は金属でできているんじゃないかと、誰かが笑った。
夏でも冬でも甚平を着ている坊主崩れのフジマサは、ミンゴスはその芯の強さゆえに、神様がバランスをとる目的で脚を一本取り上げたのだ、というのが自論だった。
「ただ、神様というのはどうも手ぬるいことをなさる。どうせしてしまうのならば、両脚とももいでしまえばよかったものを」
そう言いながら赤提灯の下、チェ・レッドを吸うフジマサの隣で、ミンゴスはケラケラと笑い声を零しながら、「なにそれ、チョーウケる」と言って、片膝を立てたまま、すっかりぬるくなったビールをあおった。
彼女は座る時、生身である左脚の片膝を立てるのが癖だった。まるで抱かれているように、彼女の両腕の中に収まっている左脚を見ていると、奇抜な義足の右脚よりも、彼女にとって大切なのはその左脚のような気がした。それも当然のことなのかもしれなかった。
彼女も、彼女を取り巻いていた我々も、彼女が片脚しかないということを気にしていなかった。最初こそは誰しもが驚くものの、時が経てばそれは、サビの舌の先端がふたつに裂けていることや、ヤクザ上がりのキクスイの左手の指が足りていないこと、リリコの前歯がシンナーに溶けて半分もないこと、レンゲが真夏であっても長袖を着ていることなんかと同じように、ありふれた日常として受け入れられ、受け流されていくのだった。
「確かにさぁ、よく考えたら、ミンゴスってショーガイシャな訳じゃん?」
トリカワが、今日も焼き鳥の皮ばかりを注文したのを頬張ってそう言った。発音はほとんど「超外車」に近かった。
「ショーガイシャ?」
訊き返したミンゴスの発音は、限りなく「SHOW会社」だ。
「あたし障害者なの?」
「身体障害者とか、あるじゃん。電車で優先席座れるやつ」
「あー」
「えー、ミンゴスは障害者じゃないよ。だって、いっつも電車でおばあちゃんに席譲るじゃん」
キュウリの漬物を咥えたまま、リリコが言った。
「確かに」
「ミンゴスはババアには必ず席譲るよな、ジジイはシカトするのに」
「あたし、おばあちゃんっ子だったからさー」
「年寄りを男女差別すんのやめろよ」
「愚か者ども、少しはご老人を敬いなさいよ」
フジマサが呆れたように口を挟んで、大きな欠伸をひとつした。
「おばあちゃん、元気にしてんのかなー」
まるで独り言のように、ミンゴスはそう小さくつぶやいて、つられたように欠伸をする。
思えばそれが、彼女が家族について口にしたのを耳にした、最初で最後だった。
俺たちは、誰もろくに自分の家族について語ろうとしなかった。自分自身についてでさえ、訊かれなければ口にすることもなく、訊かれたところで、曖昧に笑って誤魔化してばかりいた。
それでも毎日のように顔を突き合わせ、特に理由もなく集まって酒を飲み、共に飯を食い、意味のない会話を繰り返した。
俺たちは何者でもなかった。何かを共に成し遂げる仲間でもなく、徒党を組んでいたというにはあまりにも希薄な関係で、友人同士だと言うにはただ他人行儀だった。
振り返ってみれば、俺がミンゴスや周りの連中と共に過ごした期間はほんの短い間に過ぎず、だから彼女のこと誰かに尋ねられる度、どう口にすればいいのかいつも悩んで、彼女との些細な思い出ばかりを想起してしまう。
ミンゴスは砂糖で水増ししたような甘くて怪しい錠剤を、イチゴ柄のタブレットケースに入れて持ち歩いていた。
彼女に初めて出会った夜のことは、今でも忘れられない。
俺は掃き溜めのようなこの街の、一日じゅう光が射さない裏路地で、吐瀉物まみれになって倒れていた。一体いつからうつ伏せになっているのか、重たい頭はひどく痛んで、思い出すのも困難だった。何度か、通りすがりの酔っ払いが俺の身体に躓いて転んだ。そのうちのひとりが悪態をつき、唾をかけ、脇腹を蹴り上げてきたので、もう何も嘔吐できるものなどないのに、胃がひっくり返りそうになった。
路地裏には俺のえづいている声だけが響き、それさえもやっと収まって静寂が戻った時、数人の楽しげな話し声が近付いて来るのに気が付いた。
今思えば、あの時先頭を切ってはしゃぎながら駆けて来たのはリリコで、その妙なハイテンションは間違いなく、なんらかの化学作用が及ぼした結果に違いなかった。
「こらこら、走ると転ぶぞ」
と、忠告するフジマサも足元がおぼつかない様子で、普段は一言も発しないレンゲでさえも、右に左にふらふらと身体を揺らしながら、何かぶつぶつとつぶやいていた。サビはにやにやと笑いながら、ラムネ菓子を噛み砕いているかのような音を口から立てて歩いていて、その後ろを、煙管を咥えて行くのがトリカワだった。そんな連中をまるで保護者のように見守りながら行くのがキクスイであったが、彼はどういう訳か額からたらたらと鮮血を流している有り様だった。
奇妙な連中は路地裏に転がる俺のことなど気にも留めず、よろけたフジマサが俺の左手を踏みつけたがまるで気付いた様子もなく、ただ、トリカワが煙管の灰を俺の頭の上めがけて振るい落としたことだけが、作為的に感じられた。
さっきの酔っ払いに蹴り飛ばされてすっかり戦意喪失していた俺は、文句を言う気もなければ連中を睨み返してやる気力もなく、ただ道に横たわっていた。このまま小石にでもなれればいいのに、とさえ思った。
「ねーえ、そこで何してんの?」
そんな俺に声をかけたのが、最後尾を歩いていたミンゴスだった。すぐ側にしゃがみ込んできて、その長い髪が俺の頬にまで垂れてくすぐったかった。
ネコ科の動物を思わせるような大きな吊り目が俺を見ていた。俺も彼女を見ていた。彼女は美しかった。今まで嗅いだことのない、不可思議な香水のにおいがした。その香りは、どこの店の女たちとも違った。俺は突然のことに圧倒された。
彼女は何も答えない俺に小首を傾げ、それからおもむろにコートのポケットに手を突っ込むと、そこから何かを取り出した。
「これ舐める? チョー美味しいよ」
彼女の爪は長方形でピンク色に塗られており、そこに金色の薔薇の飾りがいくつもくっついていた。小さな花が無数に咲いた指先が摘まんでいたのはタブレットケースで、それはコンビニで売られている清涼菓子のパッケージだった。彼女はイチゴ柄のケースから自分の手のひらに錠剤を三つほど転がすと、その手を俺の口元へと差し出した。
「おいミンゴス、そんな陰気臭いやつにやるのか?」
先を歩いていたサビが振り返って、怪訝そうな声でそう言った。
「それ、結構高いんだぜ」
「いーじゃん別に。あたしの分をどうしようと勝手じゃん」
彼女が振り向きもせずにそう言うと、サビは肩をすくめて踵を返した。連中はふらふらと歩き続け、どん��ん遠ざかって行くが、彼女がそれを気にしている様子はなかった。
「ほら、舐めなよ」
差し出された彼女の手のひらに、俺は舌を突き出した。舌先ですくめとり、錠剤を口に含む。それは清涼菓子ではなかった。これはなんだ。
「ウケる、動物みたいじゃん」
からになった手を引っ込めながら、彼女は檻の中の猛獣に餌をあげた子供みたいに笑っていた。
口の中の錠剤は、溶けるとぬるい甘みがある。粉っぽい味は子供の頃に飲まされた薬を思わせ、しかし隠し切れないその苦味には覚えがあった。ああ、やはりそうか。落胆と安堵が入り混じったような感情が胃袋を絞め上げ、吐き出すか悩んで、しかし飲み込む。
「ほんとに食べてんだけど」
と、彼女はケラケラ笑った。その笑い声に、冗談だったのか、口にふくまないという選択肢が最良だったのだと思い知らされる。
それでも、目の前で楽しそうに笑っている彼女を見ていると、そんなことはどうでもよくなってくる。こんな風に誰かが喜んでいる様子を見るのは、いつ以来だろうか。笑われてもいい、蔑まれても構わない。それは確かに俺の存在証明で、みじめさばかりが増長される、しがない自己愛でしかなかった。
からかわれたのだと気付いた時には彼女は立ち上がっていて、俺を路地裏に残したまま、小さく手を振った。
「あたしミンゴス。またどっかで会お。バイバーイ」
そう言って歩き始めた彼女の、だんだん小さく、霞んでいく後ろ姿を見つめて、俺はようやく、彼女の右脚が金属製であることに気が付いたのだった。
人体の一部の代用としては不自然なまでに直線的で、機械的なシルエットをしたその奇妙な脚に興味が湧いたが、泥のように重たい俺の四肢は起き上がることを頑なに拒み、声を発する勇気の欠片も砕けきった後であった。飲み込んだ錠剤がその効用をみるみる発揮してきて、俺はその夜、虹色をした海に飲み込まれ、波の槍で身体を何度も何度も貫かれる幻覚にうなされながら眠りに落ちた。
その後、ミンゴスと名乗った彼女がこの街では有名人なのだと知るまでに、そんなに時間はかからなかった。
「片脚が義足の、全身ピンク色した娘だろ。あいつなら、よく高架下で飲んでるよ」
そう教えてくれたのは、ジャバラだった。ピアス屋を営んでいる彼は、身体のあちこちにピアスをあけていて、顔さえもピアスの見本市みたいだ。薄暗い路地裏では彼のスキンヘッドの白さはぼんやりと浮かび上がり、そこに彫り込まれた大蛇の刺青が俺を睨んでいた。
「高架下?」
「あそこ、焼き鳥屋の屋台が来るんだよ。簡単なつまみと、酒も出してる」
「へぇ、知らなかった」
そんな場所で商売をして儲かるんだろうか。そんなこと思いながら、ポケットを探る。ひしゃげた箱から煙草が一本出てくる。最後の一本だった。
「それにしても……お前、ひどい顔だな、その痣」
煙草に火を点けていると、ジャバラは俺の顔をしみじみと見て言った。
「……ジャバラさんみたいに顔にピアスあけてたら、大怪我になってたかもね」
「間違いないぞ」
彼はおかしそうに笑っている。
顔の痣は触れるとまだ鈍く痛む。最悪だ。子供の頃から暴力には慣れっこだったが、痛みに強くなることはなかった。無抵抗のまま、相手の感情が萎えるのを待つ方が早いだとか、倒れる時の上手な受け身の取り方だとか、暴力を受けることばかりが得意になった。痛い思いをしないで済むなら、それが最良に決まっている。しかしどうも、そうはいかない。
「もう、ヤクの売人からは足を洗ったんじゃないのか?」
「……その仕事はもう辞めた」
「なのに、まだそんなツラ晒してんのか。堅気への道のりは険しいな」
掠れて聞き取りづらいジャバラの声は、からかっているような口調だった。思わず俺も、自嘲気味に笑う。
学んだのは、手を汚すのをやめたところで、手についた汚れまで綺麗さっぱりなくなる訳ではない、ということだった。踏み込んでしまったら二度と戻れない底なし沼に、片脚を突っ込んでしまった、そんな気分だ。今ならまだ引き返せると踏んだが、それでも失った代償は大きく、今でもこうしてその制裁を受けている現状を鑑みれば、見通しが甘かったと言う他ない。
「手足があるだけ、まだマシかな……」
俺がそう言うと、ジャバラはただ黙って肩をすくめただけだった。それが少なからず同意を表していることを知っていた。
五体満足でいられるだけ、まだマシだ。特に、薄汚れた灰色で塗り潰された、部屋の隅に沈殿した埃みたいなこの街では。人間をゴミ屑のようにしか思えない、ゴミ屑みたいな人間ばかりのこの街では、ゴミ屑みたいに人が死ぬ。なんの力も後ろ盾も、寄る辺さえないままにこの街で生活を始めて、こうしてなんとか煙を吸ったり吐いたりできているうちは、まだ上出来の部類だ。
「せいぜい、生き延びられるように頑張るんだな」
半笑いのような声でそう言い残して、ジャバラは大通りへと出て行った。その後ろ姿を見送りながら、身体じゅうにニコチンが浸透していくのを脳味噌で感じる。
俺はミンゴスのことを考えていた。
右脚が義足の、ピンク色した天使みたいな彼女は、何者だったのだろう。これまでどんな人生を送り、その片脚をどんな経緯で失くしたのだろう。一体、その脚でなんの代償を支払ったのか。
もう一度、彼女に会ってみたい。吸い終えた煙草の火を靴底に擦りつけている時には、そう考えていた。それは彼女の片脚が義足であることとは関係なく、ただあの夜に、道端の石ころ同然の存在として路地裏に転がっているしかなかったあの夜に、わざわざ声をかけてくれた彼女をまた一目見たかった、それだけの理由だった。
教えてもらった高架下へ向かうと、そこには焼き鳥屋の移動式屋台が赤提灯をぶら下げていて、そして本当に、そこで彼女は飲んでいた。周りには数人が同じように腰を降ろして酒を飲んでいて、それはあの夜に彼女と同じように闊歩していたあの奇妙な連中だった。
最初に俺に気付いたのは、あの時、煙管の灰をわざと振り落としてきたトリカワで、彼はモヒカンヘアーが乱れるのも気にもせず、頭を掻きながら露骨に嫌そうな顔をした。
「あんた、あの時の…………」
トリカワはそう言って、決まり悪そうに焼き鳥の皮を頬張ったが、他の連中はきょとんとした表情をするだけだった。他は誰も、俺のことなど覚えていなかった。それどころか、あの夜、路地裏に人間が倒れていたことさえ、気付いていないのだった。それもそのはずで、あの晩は皆揃って錠剤の化学作用にすっかりやられてしまっていて、どこを通ってどうやってねぐらまで帰ったのかさえ定かではないのだと、あの夜俺の手を踏んづけたフジマサが飄々としてそう言った。
ミンゴスも、俺のことなど覚えていなかった。
「なにそれ、チョーウケる」
と、笑いながら俺の話を聞いていた。
「そうだ、思い出した。あんた、ヤクをそいつにあげてたんだよ」
サビにそう指摘されても、ミンゴスは大きな瞳をさらに真ん丸にするだけだった。
「え、マジ?」
「マジマジ。野良猫に餌やってるみたいに、ヤクあげてたよ」
「ミンゴス、猫好きだもんねー」
どこか的外れな調子でそう言ったリリコは、またしても妙なハイテンションで、すでに酔っているのか、何か回っているとしか思えない目付きをしている。
「ってか、ふたりともよく覚えてるよね」
「トリカワは、ほら、あんまヤクやんないじゃん。ビビリだから」
「チキンだからね」
「おい、チキンって言うな」
「サビは、ほら、やりすぎて、あんま効かない的な」
「この中でいちばんのジャンキーだもんね」
「ジャンキーっつうか、ジャンク?」
「サビだけに?」
「お、上手い」
終始無言のレンゲが軽い拍手をした。
「え、どういうこと?」
「それで、お前、」
大きな音を立てて、キクスイがビールのジョッキをテーブルに置いた。ジョッキを持っていた左手は、薬指と小指が欠損していた。
「ここに何しに来た?」
その声には敵意が含まれていた。その一言で、他の連中も一瞬で目の色を変える。巣穴に自ら飛び込んできた獲物を見るような目で、射抜かれるように見つめられる。
トリカワはさりげなく焼き鳥の串を持ち変え、サビはカップ酒を置いて右手を空ける。フジマサは、そこに拳銃でも隠しているのか、片手を甚平の懐へと忍ばせている。ミンゴスはその脚ゆえか、誰よりも早く椅子から腰を半分浮かし、反対に、レンゲはテーブルに頬杖を突いて半身を低くする。ただリリコだけは能天気に、半分溶けてなくなった前歯を見せて、豪快に笑う。
「ねぇ皆、違うよ、この子はミンゴスに会いに来たんだよ」
再びきょとんとした顔をして、ミンゴスが訊き返す。
「あたしに?」
「そうだよ」
大きく頷いてから、リリコは俺に向き直り、どこか焦点の定まらない虚ろな瞳で、しかし幸福そうににっこりと笑って、
「ね? そうなんだよね? ミンゴスに、会いたかったんでしょ」
と、言った。
「あー、またあのヤクが欲しいってこと? でもあたし、今持ち合わせがないんだよね」
「もー、ミンゴスの馬鹿!」
突然、リリコがミンゴスを平手打ちにした。その威力で、ミンゴスは座っていた椅子ごと倒れる。金属製の義足が派手な音を立て、トリカワが慌てて立ち上がって椅子から落ちた彼女を抱えて起こした。
「そーゆーことじゃなくて!」
そう言うリリコは悪びれた様子もなく、まるでミンゴスが倒れたことなど気付いてもいないようだったが、ミンゴスも何もなかったかのようにけろりとして椅子に座り直した。
「この子はミンゴスラブなんだよ。ラブ。愛���よ、愛」
「あー、そーゆー」
「そうそう、そーゆー」
一同はそれで納得したのか、警戒態勢を解いた。キクスイだけは用心深く、「……本当に、そうなのか?」と尋ねてきたが、ここで「違う」と答えるほど、俺も間抜けではない。また会いたいと思ってここまで来たのも真実だ。俺が小さく頷いてみせると、サビが再びカップ酒を手に取り、
「じゃー、そーゆーことで、こいつのミンゴスへのラブに、」
「ラブに」
「愛に」
「乾杯!」
がちゃんと連中の手元にあったジョッキやらグラスやらがぶつかって、
「おいおい愚か者ども、当の本人が何も飲んでないだろうよ」
フジマサがやれやれと首を横に振りながら、空いていたお猪口にすっかりぬるくなっていた熱燗を注いで俺に差し出し、
「歓迎しよう、見知らぬ愚か者よ。貴殿に、神のご加護があらんことを」
「おめーは仏にすがれ、この坊主崩れが」
トリカワがそう毒づきながら、焼き鳥の皮をひと串、俺に手渡して、
「マジでウケるね」
ミンゴスが笑って、そうして俺は、彼らの末席に加わったのだ。
ミンゴスはピンク色のウェーブがかった髪を腰まで伸ばしていて、そして背中一面に、同じ色をした翼の刺青が彫られていた。
本当に羽毛が生えているんじゃないかと思うほど精緻に彫り込まれたその刺青に、俺は幾度となく手を伸ばし、そして指先が撫でた皮膚が吸いつくように滑らかであることに、いつも少なからず驚かされた。
腰の辺りが性感帯なのか、俺がそうする度に彼女は息を詰めたような声を出して身体を震わせ、それが俺のちっぽけな嗜虐心を刺激するには充分だった。彼女が快楽の海で溺れるように喘ぐ姿はただただ扇情的で、そしていつも、彼女を抱いた後、子供のような寝顔で眠るその横顔を見ては後悔した。
安いだけが取り柄のホテルの狭い一室で、シャワーを浴びる前に外されたミンゴスの右脚は、脱ぎ捨てられたブーツのように絨毯の上に転がっていた。義足を身に着けていない時のミンゴスは、人目を気にも留めず街を闊歩している姿とは違って、弱々しく薄汚い、惨めな女のように見えた。
太腿の途中から失われている彼女の右脚は、傷跡も目立たず、奇妙な丸みを帯びていて、手のひらで撫で回している時になんとも不可思議な感情になった。義足姿は見慣れていて、改めて気に留めることもないのだが、義足をしていないありのままのその右脚は、直視していいものか悩み、しかし、いつの間にか目で追ってしまう。
ベッドの上に膝立ちしようにも、できずにぷらんと浮いているしかないその右脚は、ただ非力で無様に見えた。ミンゴスが義足を外したところは、彼女を抱いた男しか見ることができないというのが当時囁かれていた噂であったが、俺は初めて彼女を抱いた夜、何かが粉々に砕け散ったような、「なんだ、こんなもんか」という喪失感だけを得た。
ミンゴスは誰とでも寝る女だった。フジマサも、キクスイも、サビもトリカワも、連中は皆、一度は彼女を抱いたことがあり、それは彼らの口から言わせるならば、一度どころか、もう飽き飽きするほど抱いていて、だから近頃はご無沙汰なのだそうだった。
彼らが彼女の義足を外した姿を見て、一体どんな感情を抱いたのかが気になった。その奇妙な脚を見て、背中の翼の刺青を見て、ピアスのあいた乳首を見て、彼らは欲情したのだろうか。強くしたたかに生きているように見えた彼女が、こんなにもひ弱そうなただの女に成り下がった姿を見て、落胆しなかったのだろうか。しかし、連中の間では、ミンゴスを抱いた話や、お互いの性癖については口にしないというのが暗黙の了解なのだった。
「あんたは、アレに惚れてんのかい」
いつだったか、偶然ふたりきりになった時、フジマサがチェ・レッドに火を点けながら、俺にそう尋ねてきたことがあった。
「アレは、空っぽな女だ。あんた、あいつの義足を覗いたかい。ぽっかり穴が空いてたろう。あれと同じだ。つまらん、下種の女だよ」
フジマサは煙をふかしながら、吐き捨てるようにそう言った。俺はその時、彼に何も言い返さなかった。まったくもって、この坊主崩れの言うことが真であるように思えた。
ミンゴスは決して無口ではなかったが、自分から口を開くことはあまりなく、他の連中と同様に、自身のことを語ることはなかった。話題が面白かろうが面白くなかろうが、相槌はたいてい「チョーウケる」でしかなく、話し上手でも聞き上手でもなかった。
風俗店で働いている日があるというリリコとは違って、ミンゴスが何をして生計を立てているのかはよくわからず、そのくせ、身に着けているものや持ちものはブランドもののまっピンクなものばかりだった。連中はときおり、ヤクの転売めいた仕事に片脚を突っ込んで日銭を稼いでいたが、そういった時もミンゴスは別段やる気も見せず、それでも生活に困らないのは、貢いでくれる男が数人いるからだろう、という噂だけがあった。
もともと田舎の大金持ちの娘なんだとか、事故で片脚を失って以来毎月、多額の慰謝料をもらい続けているんだとか、彼女にはそんな具合で嘘か真実かわからない噂ばかりで、そもそもその片脚を失くした理由さえ、本当のところは誰も知らない。訊いたところではぐらかされるか、訊く度に答えが変わっていて、連中も今さら改まって尋ねることはなく、彼女もまた、自分から真実を語ろうとは決してしない。
しかし、自身の過去について触れようとしないのは彼女に限った話ではなく、それは坊主崩れのフジマサも、ヤクザ上りのキクスイも、自殺未遂を繰り返し続けているレンゲも、義務教育すら受けていたのか怪しいリリコも、皆同じようなもので、つまりは彼らが、己の過去を詮索されない環境を求めて流れ着いたのが、この面子という具合だった。
連中はいつだって互いに妙な距離を取り、必要以上に相手に踏み込まない。見えないがそこに明確な線が引かれているのを誰しもが理解し、その線に触れることを極端に避けた。一見、頭のネジが外れているんだとしか思えないリリコでさえも、いつも器用にその線を見極めていた。だから彼らは妙に冷めていて、親切ではあるが薄情でもあった。
「昨日、キクスイが死んだそうだ」
赤提灯の下、そうフジマサが告げた時、トリカワはいつものように焼き鳥の皮を頬張ったまま、「へぇ」と返事をしただけだった。
「ドブに遺体が捨てられてるのが見つかったそうだよ。額に、銃痕がひとつ」
「ヤクの転売なんかしてるから、元の組から目ぇ付けられたのか?」
サビが半笑いでそう言って、レンゲは昨日も睡眠薬を飲み過ぎたのか、テーブルに突っ伏したまま顔を上げようともしない。
「いいひとだったのにねー」
ケラケラと笑い出しそうな妙なテンションのままでリリコがそう言って、ミンゴスはいつものように、椅子に立てた片膝を抱くような姿勢のまま、
「チョーウケるね」
と、言った。
俺はいつだったか、路地裏で制裁を食らった日のことを思い出していた。初めてミンゴスと出会った日。あの日、俺が命までをも奪われずに済んだのは、奇跡だったのかもしれない。この街では、そんな風に人が死ぬのが普通なのだ。あんなに用心深かったキクスイでさえも、抗えずに死んでしまう。
キクスイが死んでから、連中の日々は変化していった。それを顔に出すことはなく、飄々とした表情を取り繕っていたが、まるで見えない何かに追われているかのように彼らは怯え、逃げ惑った。
最初にこの街を出て行ったのはサビだった。彼は転売したヤクの金が手元に来たところで、一夜のうちに姿をくらました。行方がわからなくなって二週間くらい経った頃、キクスイが捨てられていたドブに、舌先がふたつに裂けたベロだけが捨てられていたという話をフジマサが教えてくれた。しかしそれがサビの舌なのか、サビの命がどうなったのかは、誰もわからなかった。
次に出て行ったのはトリカワだった。彼は付き合っていた女が妊娠したのを機に、故郷に帰って家業を継いで漁師になるのだと告げて去って行った。きっとサビがここにいたならば、「お前の船の網に、お前の死体が引っ掛かるんじゃねぇの?」くらいは言っただろうが、とうとう最後まで、��ジマサがそんな情報を俺たちに伝えることはなかった。
その後、レンゲが姿を見せなくなり、彼女の人生における数十回目の自殺に成功したのか、はたまたそれ以外の理由で姿をくらましたのかはわからないが、俺は今でも、その後の彼女に一度も会っていない。
そして、その次はミンゴスだった。彼女は唐突に、俺の前から姿を消した。
「なんかぁ、田舎に戻って、おばあちゃんの介護するんだって」
リリコがつまらなそうに唇を尖らせてそう言った。
「ミンゴスの故郷って、どこなの?」
「んー、秋田」
「秋田。へぇ、そうなんだ」
「そ、秋田。これはマジだよ。ミンゴスが教えてくれたんだもん」
得意げにそう言うリリコは、まるで幼稚園児のようだった。
フジマサは、誰にも何も告げずに煙のように姿を消した。
リリコは最後までこの街に残ったが、ある日、手癖の悪い風俗の客に殴られて死んだ。
「お前、鍵屋で働く気ない? 知り合いが、店番がひとり欲しいんだってさ」
俺は変わらず、この灰色の街でゴミの残滓のような生活を送っていたが、ジャバラにそう声をかけられ、錠前屋でアルバイトをするようになった。店の奥の物置きになっていたひと部屋も貸してもらい、久しぶりに壁と屋根と布団がある住み家を得た。
錠前屋の主人はひどく無口な無骨な男で、あまり熱心には仕事を教えてはくれなかったが、客もほとんど来ない店番中に点けっぱなしの小型テレビを眺めていることを、俺に許した。
ただ単調な日々を繰り返し、そうして一年が過ぎた頃、埃っぽいテレビ画面に「秋田県で殺人 介護に疲れた孫の犯行か」という字幕が出た時、俺の目は何故かそちらに釘付けになった。
田舎の街で、ひとりの老婆が殴られて死んだ。足腰が悪く、認知症も患っていた老婆は、孫娘の介護を受けながら生活していたが、その孫に殺された。孫娘は自ら通報し、駆けつけた警察に逮捕された。彼女は容疑を認めており、「祖母の介護に疲れたので殺した」のだという旨の供述をしているのだという。
なんてことのない、ただのニュースだった。明日には忘れてしまいそうな、この世界の日常の、ありふれたひとコマだ。しかし俺は、それでも画面から目を逸らすことができない。
テレビ画面に、犯人である孫娘が警察の車両に乗り込もうとする映像が流れた。長い髪は黒く、表情は硬い。化粧っ気のない、地味な顔。うつむきがちのまま車に乗り込む彼女はロングスカートを穿いていて、どんなに画面を食い入るように見つめても、その脚がどんな脚かなんてわかりはしない。そこにあるのは、人間の、生身の二本の脚なのか、それとも。
彼女の名前と年齢も画面には表示されていたが、それは当然、俺の知りもしない人間のプロフィールに過ぎなかった。
彼女に限らない。俺は連中の本名を、本当の年齢を、誰ひとりとして知らない。連絡先も、住所も、今までの職業も、家族構成も、出身地も、肝心なことは何ひとつ。
考えてもしょうがない事柄だった。調べればいずれわかるのかもしれないが、調べる気にもならなかった。もしも本当にそうだったとして、だからなんだ。
だから、その事件の犯人はミンゴスだったのかもしれないし、まったくなんの関係もない、赤の他人なのかもしれない。
その答えを、俺は今も知らない。
ミンゴスの右脚は太腿の途中から金属製で、そのメタリックなピンク色の輝きは、無機質な冷たさを宿しながらも生肉のようにグロテスクだった。
「そう言えば、サビってなんでサビってあだ名になったんだっけ」
「ほら、あれじゃん、頭が錆びついてるから……」
「誰が錆びついてるじゃボケ。そう言うトリカワは、皮ばっか食ってるからだろ」
「焼き鳥は皮が一番美味ぇんだよ」
「一番美味しいのは、ぼんじりだよね?」
「えー、あたしはせせりが好き」
「鶏の話はいいわ、愚か者ども」
「サビはあれだよ、前にカラオケでさ、どの歌でもサビになるとマイク奪って乱入してきたじゃん、それで」
「なにそれ、チョーウケる。そんなことあったっけ?」
「あったよ、ミンゴスは酔っ払いすぎて覚えてないだけでしょ」
「え、俺って、それでサビになったの?」
「本人も覚えてないのかよ」
「リリコがリリコなのはぁ、芸能人のリリコに似てるからだよ」
「似てない、似てない」
「ミンゴスは?」
「え?」
「ミンゴスはなんでミンゴスなの?」
「そう言えば、そうだな。お前は初対面の時から、自分でそう名乗っていたもんな」
「あたしは、フラミンゴだから」
「フラミンゴ?」
「そう。ピンクだし、片脚じゃん。ね?」
「あー、フラミンゴで、ミンゴス?」
「ミンゴはともかく、スはどっからきたんだよ」
「あれじゃん? バルサミコ酢的な」
「フラミンゴ酢?」
「えー、なにそれ、まずそー」
「それやばいね、チョーウケる」
赤提灯が揺れる下で、彼女は笑っていた。
ピンク色の髪を腰まで伸ばし、背中にピンク色の翼の刺青を彫り、これでもかというくらい全身をピンクで包んで、金属製の片脚で、街角で、裏路地で、高架下で、彼女は笑っていた。
それが、俺の知る彼女のすべてだ。
俺はここ一年ほど、彼女の話を耳にしていない。
色褪せ、埃を被っては、そうやって少しずつ忘れ去られていくのだろう。
この灰色の街ではあまりにも鮮やかだった、あのフラミンゴ娘は。
了
0 notes
Text
世相に関する覚書
ものぐさでいい加減な私は人をまとめたり動かしたりするのが極端に苦手な性分で、今でも人と仕事をするのが苦痛で仕方なく、例えば、ある作品の評論を書いてくれと依頼があっても、依頼主の意向を無視したものを書き上げてしまい、折角の仕事の話を頓挫させてしまったことが幾度となくある。
「井原西鶴はスタンダールやバルザックと同じリアリズム文学の創始者であり、当時、大阪はパリに匹敵する文化都市だった、だからこそ、大阪維新の会のような文化破壊をあたかも道徳のように行う政党は決して許してはならない」と書いて、失笑されること数回。十三の風俗嬢とその馴染み客の恋愛を書けば、織田作の模倣に過ぎないと馬鹿にされ、踏んだり蹴ったりの私。それでも井原西鶴や織田作、宇野浩二、武田麟太郎、葛西善蔵、林芙美子を見習い、軽佻浮薄にケラケラ笑いながら私は生きている。
こんな愚図な私はどうにもならん、いくら賞レースに参加したとて、風俗壊乱の下卑た作品しか書けないので、富と名声までは程遠い。いつまで月給取りをしなくてはならないのだと不甲斐ない自身を罵りながら日常を過ごす。
そんな私だから、音楽なんてとうの昔に辞めて正解であった。もともと不器用なんだから音楽なんてそれはとても私の技量にかなうものではなかったのだ。
退屈で無為な学生時代、セカンドスクールだがなんだかに通い詰めたりして「お前は挫折したことないから、そこへ行ってる俺の真剣さなんて分かりっこない」などと威張り散らし、自身の優越を誇示するのに必死な連中との付き合いに疲れ果て、私はそんな窮屈な人間関係から逃れるために読んだスタンダールの「赤と黒」とバルザックの「ゴリオ爺さん」などの古典文学にこそ、私の居場所があった様なものだった。人間の矛盾に満ちた本質など変わりはしないし、それを責めても何も生まれないのだと思うと、多少、卑屈な思いも鎮まるものである。どうにかしてこのクソ退屈で屈辱に満ちた時間と場面をやり過ごすことしか他はなかったのだ。
そもそも世渡り下手でなにかと不器用な私であったし、といってそれほど学術的に優秀でもない。それに取り柄なんてない。皆の様に明確に目指すものなんてあるわけもない。
私には捉え難いものを追うことしかできず、厄介なことに迷うことでしか多くの物事が分からないのだ。取り返しのつかない失敗と破綻の上に、私の思考が成り立つという厄介さ。
頭のいい方々は羨ましいものだ。路頭に迷い、誰からも必要とされない孤独感や他人との協調が上手いがために疎外感を知らずに、ただ、目の前にある課題をこなすだけで満足そうなのだから。
私の場合はそうはいかない。満足なんてどこにもなく、何かを知れば知るほど、何かをやればやるほど、現実が差し迫って来て、理想は遠く離れていく様に見える。それ故に、常に何かに迫られるような切迫感があって、何処にも落ち着きそうがない。自嘲的にいえば、私はいつまでも年相応の生き方に馴染めず、ただ、当て所なく迷うのだ。放蕩無頼とはよくいったもので、私もそれに近いものがある。
ただ、こんな私でもこれまでの時代は西成の薄暗い商店街の路地裏にいる八卦見にでも見てもらえばよかった。
モーパッサンの「女の一生」の最後、召使いが仕えていた婦人に言うようなことを彼なら答えると分かってる、この言葉を第三者から聞ければ、満足だった。
「結局、未来なんて期待していたほど良くもなく、といって失望していたほどのものでもない」
ところがこんな楽観が成立していた時代が徐々にこの日本から消えつつある。しかもその消失速度はここところ否応無しに増すばかりで、いくら愚図で鈍間な私でも分かる。
実際、私はこのことについて直感的に分かっていたといっていいか。白状するが、大学のキャンパスだろうが、風俗店の受付だろうが、ジャンキーやヤリ目のパリピー野郎ばかりが屯するクラブだろうが、今の職場であろうが、どんなに目を背けても直視せざるを得ない危機が迫っていることだけは分かっていた。
だからといって自身を逞しくしたり資格の勉強をしようとまで思わなんだ。何故って、それは余りにも私には不自然なことだった。所詮、資格なんて役に立たないし、専門性を持てば結局自身の無謬性を過信することとなり大きく判断を見誤るからだ。
例えば、精神科医が大量の薬を出し、多くの薬害を生み出すことは、自身の無謬性を一瞬たりとも疑���たことがない所以ではないか?
かつて私は自身の特殊性ー頭の構造がおかしいのか、頭が時折人との会話や目下の作業についてこれず、注意散漫になって、思考が筋から大きく違う方向へ逸れてしまうーのために、若干精神を病んでしまい、頭に喝を入れるアンフェタミンと精神状態を穏やかにするセロトニンの混合薬欲しさに医者に行ったことがある。そこで医者にこんなことを聞かれた。
「このまま消えたいとかそういった希死念慮はありませんか?」
別に死にたくもないのにどうしてこんなことを聴かれねばならないのかと不貞腐れた私は、
「別にないです。私が欲しいのはただ穏やかさと覚醒だけですがね」
すると、医者はこの答えに不満ありげに、
「おかしいですね?本来なら自殺願望がこういった抑うつ症状の場合にはみられるのですがね…本当はどうです?実際はあるでしょう?」
こう聞く医師の目にどこか見当違いの既視感があるように私には思えてた、抑鬱ならばこの答えではなくては困るといったような、そんな雰囲気を醸し出されており、私は些か困惑した。
まるで鬱に憔悴した人は皆自殺願望でもあるかのように患者に決めつけるところなぞ、なんという傲慢さだろうか。
後々分かったことであるが、私はうつ病でもなければ統合失調症でもなかった。何たる誤診だったろう。こういった行き違いばかりの診察で出された薬に手もつけなかった。私の精神状態が脳の問題であれば、脳波でも見れば良いものを、なんたって本人との面談だけで、あれだけ易々と薬が出せたのだろうか、それが不思議でならなかったのだ。
恐らく医者はその説明を拒むだろう。自身の無謬性に一つでもケチが付けば、彼の自尊心は忽ち崩れ、そして、これまでの経歴を自ら疑わずにはいられなくなる。となると、皮肉なことに、彼こそが向精神薬のお世話になる羽目になるのだ。
ーこうした精神運動が権威と集団に結びつき、少数からの真っ当な非難を論拠なしに厳しい口調や態度で退け続け、悲惨な結末をもたらす自身の行為を改めずに続けること、これをセンメルヴェイス反射という。日本社会に起きている多くの弊害はこうした心理現象に由来するとも言える。他にも合成の誤謬、認知的共同体などが挙げられる。ー
こんな例はいくつもある。
幸か不幸か、私の身内の多くは精神障害者であり、精神科医の被害者である。その多くは医師の言いつけ通りに処方された薬を飲み続け、文字通り、ヴォガネットの作品に出てくる登場人物のように頭がどっかーんとぶっ飛んだ。
通院すればするほど、会話が支離滅裂なものとり、動作がどんどん鈍くなっていく。
その結果、ある者は還暦を前にしてすでに手足の関節の膠着が見られ、自身で排泄と食事すらできなくなるほど衰弱し、その上、会話も成立しない。そして尿道にはチューブが繋がれ、病床に臥したきりになっている。
誰も指摘しないが、これは薬害ではないかと私は思う。
こんなことが頻発しているのであれば、日本の精神医療は最低といっても過言ではない。
地獄への道は善意で彩られているとはよく言ったもので、このほかにも政府や官僚、エリートたちが社会保障の充実のための増税だと、将来世代にツケを残さないためだとかなんとか、美辞麗句ばかり並びたてている。だが、結局、消費税を上げるたびに、日本人は総じて貧乏になり、その供給能力(即ちそれは国家の経済力を指す)は著しく毀損された。
介護医療、土木建設などの生活の根幹をなす業界の現場は、「無駄を減らせ」「民間の知恵を入れろ」との美辞麗句に彩られた合言葉から始まった目的のない緊縮財政と構造改革の煽りで、その運営手段は民営化されたために、作業効率はかえって悪くなり、報酬は減り続けた結果、廃業にまで追い込まれるところが相次ぎ、人手不足で相当悲惨なことになっている。
鈍感ではあったが、世の中が見る見る悪くなると察した私は、将来に向けて努力する同級生を見ても焦りもしなかった。そもそも私が無気力な状態であったことは言うまでもないが、ただ、その焦りは結局、何らかのビジネスに利用されるということを感じたからでもある。
実質賃金が漸次的に減少し、全体のパイが縮小していくデフレ経済下で勝てるのは持てる者だけで、多くは頑張れば頑張るほど燃え尽きるのだ。浮かばれない自身をSNSにでも投稿して憂さを晴らす姿はなんとも惨めったらしくて遣る瀬無い。そしてこの無為とも思われる努力の過程で積もり積もった妬みは政治家や官僚、メディア、詐欺師などに巧みに利用されて、自身の立場を知らず知らず危うくしてしまう。
公務員を叩いて何が良くなった?
何一つ良くなっていない、災害があれば、都市機能は一瞬で麻痺し、復旧には多くの時間と労力を要するだけで、日常生活に以前よりも支障を来すだけの結果にしかならず、何の足しにもなっていなかった。
リーマンショックの時、何か重大な機構の歯車が外れて未来への軌道が逸れた気がした。これまで是としてきたことがすべてまやかしだったというようなことが仄めかされたといっていい。世間の空気が少しだけ冷たくなり、より一層協調を求め、画一化されていくことを人々に強要していた。
「負け組にならないために、空気を読まねばならない。」
その空気とはなんであったか、今でも私には分からない。ただならぬものが何か一定の思考を強いるようなものであったのは確かだった。
後にトクヴィルの「アメリカの民主主義」という書物に出会い、朧げに見えてきたのは、「多数派の専制」がこの日本で行われつつあることであった。
階級や中間共同体が撤廃されて、人々が一様に平等となったとき、慣習や伝統を見失い、模範とすべき対象がないと多く嘆かれる。その時、頼るべきものを見失った人々はメディアが喧伝するイデオロギーや合言葉を、それが正しいかどうかなど関係なく、一斉に飛びついて信じてしまう。そして少数派の非難や意見はことごとく無視され、多数派がその社会を支配する。この多数派の専制が更に進めば、思考の自由すら人々は手放し、多数派の思考に隷属していく。
つまり、全体主義と民主主義は表裏一体。
私が物心ついた時からすでに社会はこの「多数派の専制」のメカニズムを順当に辿っていたのではないか。
阪神淡路大震災以後の日本文明は、何かと言えば、「無駄を省け」「これからは金融の時代だ」「規制緩和して市場を活性化すれば、より経済は活発になる」といった根拠なき意見が散見される次第、しかも何処にも確証もなければ論証もない。これらの試みが失敗したところで誰も責任を取らないどころか、「改革を十分に徹底していなかったから良くなかった、だからより抜本的に行う必要がある」という意見が支配的で、もう手の施しようがない。
つまりこの日本では健全な民主主義が機能していないのだ。
東日本大地震になると、この民主主義の機能不全は輪をかけて酷くなり、福島原発の爆発を見て、人々は恐れ��ののき、科学的根拠もなく、メディアの扇動だけで直ぐにでも脱原発と声高に多数派は叫ぶ有様。
正直にいって私も当初煽られてしまった。追い追い情報を精査すると、この事故はやむを得なかった。何しろ、想定外の事が起きたのだから。だったら、この想定外を上回る危機にも耐え得る原発を作れば良いではないか。しかしそんな議論は無かった。あったのは原発廃止、それだけ。
しかも脱原発に煽られて、人々は一斉に原発を叩き、根拠なき恐怖心は再エネビジネスに利用されたのだった。
結果、電気代に再エネ促進費用を上乗せされて支払う羽目になり、そのままその金は外資規制もなく再エネ事業者に横流し。しかもビジネス目的で山の斜面に多く作られたソーラーパネルのせいで、豪雨が見舞えば、土砂崩れは頻発する有様。
敗戦のショック同様に、このショックは人々の思考を停止に至らしめ、その隙間を邪なビジネスマンや工作勢力に利用されたのだった。
これをショックドクトリンという。
大惨事が起きるたびにこの国ではビジネスチャンスとなるわけだ。
過去の大戦の原因の一つが、石油をめぐるアメリカに対する我が国の過度な依存であったと分かれば、自ずと、結論は、エネルギーを自前で賄える可能性を有した原発を日本は国を挙げて維持すべきといった意見に傾く。この事故をあくまで日本の宿命と受け止めるべきではなかろうか。自立するために、多少の犠牲を払わなければならない日本の運命的境遇を理解できれば、何でもかんでも反原発と騒ぐのは話があまりにも飛躍しているのではないか。
しかし、こんな私の意見なんて多数派には届くはずもない。多くの人たちは、東電の管轄下にあったものが事故を起こしたのだから、その責任を国が東電に押し付けて当たり前と考え、異論すら聞き入れなかった。
想定外の事が起きているところへ、責任問題として、この事故を扱うこの国のエリート層の知性の劣化にはこの私でも舌を巻くものだった。これは誰の責任でもなく、その負担は政府をはじめとする国家全体が負うべき種類のものだろう。
しかし、政府はその負担を東電に押し付けた。メディアは、また放射能の被害を被った福島の農家に東電職員が土下座する写真を新聞の一面に載せたのだった。
どこまで煽られないと人々は気づかないのか。
その年行われたロックフェスは、従来通り、大量の電力を消費する大規模なものであったのに、ステージに立つ連中は悉く脱原発のイデオロギーに染まり、ある政治集団に至ってはジョンレノンに憧れてるのか、そこで夜中、大音量で音楽をかけながら、環境保護を標榜する集会を開いていた。60年代後半のウッドストックにいたヒッピーの幻想に頭がヤラレだのだろう、原発の利権構造が悪など偉そうな事を言う一方、大量の電力がなければ成り立たない生活をしている自身の矛盾には目を背け、偉そうに騒ぎ立てる姿は、自己欺瞞そのもので、実におめでたい姿だった。この光景をみて、こんな軽薄な連中とつるむのが気恥ずかしくなったものだ。私もそれだけ歳をとったのかわからぬが、彼らに言い知れぬ違和感を覚え、これ以降、私は音楽をやっている連中に関心を寄せなくなったのは事実だ。
一体、奴らの政治的主張のどこに耳を傾ける必要があろうか?実際、彼らの歌詞を仔細に読めば、その内容の空虚さ、幼稚さ、軽薄さが目につくだけで私は、彼らの音楽の不協和音も相まって、一層不快になってしまう。まさにこの自己欺瞞は滅びの兆候といってもいいのだろう。
こんな自己欺瞞ばかりの音楽の世界から遠ざかりたい一心で文学へと関心を移したわけだけど、これと同じことが文学でも起きていると分かった時の落胆は相当深刻なものだった。なんたって文学者の多くは音楽のそれと違って政治力まであるのだ。
私はそれでもこのクソみたいに高慢で自己欺瞞している連中の間で軽佻浮薄な振る舞いをして、世間の失笑と顰蹙を買うことだろう。
0 notes
Text
遅い奴
遅い。 遅すぎですね。今何日ですか。9日ですよ。秋公園の終演は?4日。切腹。 綺麗な臓物が出てくる自信がないので腹を切るのは止めておきますが、それにしても各方面の方々申し訳ございませんでした。
こんな書き方をしているので自己紹介はいらないと思うのですが、Airmanです。 誰お前?へぇ、B脚本「メタフィクション:ザ・ゲーム」の脚演です。 あー………………って顔してる。今絶対あー………………って顔してますよね。そうです。もうネタバレも怖くないのでぶっちゃけますが、暗殺者の首を折ったりエルフをバットでリンチしたりするシーンで子供さんを泣かしたのは私です。その節は本当に申し訳ございません。 なんでそんな事になったのかは後々お話しするとして、いや変ですよね。後でご紹介する石英さんも言及なさっておられたのですが、何故人は役者紹介の最初に自分の名前を書かないのでしょうか?いやでも分かる。その気持ちは分かる。その方がクイズみがあって面白いって考えるんですよね。実際そういう面白さはあるんですが、「そこで面白さを取るか、役者紹介において必須の『誰が誰を紹介している』という前提を先に伝えて情報の伝達性を良くするか」というのは尽きない議論ですね?いや尽きるかも。割とすぐ尽きちゃうかも。 ようやく温まりました。 何がしたいかというと、役者紹介です。 諸々の都合で敬称略です。
・ニッキ役/でぃあ(31期) イカレた世界のイカレた主人公を演じてくださいました………………え?。読み合わせの前段階で既に役を作ってくる?え、何イリハケ表?はー、神。 いや、そんな気はまぁうすうすしていたというか、やぁまさか本当に役を作ってきて下さるとは思いませんでしたが「ヤケに嵌まってるなぁ」という気はしたというか、凄い。役者魂。楽ステ最後のアドリブにも対応して下さるあたり、いやもうこの方は役者として域に達している気がします。怠惰ゲージがMAXになると自分で自分を傷つけて死ぬタイプの演出だったので、そうした心労を大分軽減して下さった神ですあなたは。そして場当たりの時は酷使して、というか変更点を噴出させて本っっっっっっ当に申し訳ございませんでした。なます斬りされてもおかしくなかった。というかされたかった。だってこの人��演じるニッキ本当に狂っててカッコいいんですよ。全編ふざけた勢いだけで押し通してしまいそうな役ですが、この方は締める所ちゃんと締めて下さる。そして作中でも〆るべき敵をちゃんと〆て下さる。でぃあさんに主人公お任せして本当に本当に楽しかったです。秋公演まではそんなにお話しする機会もなくて、正直ニッキというキャラクターをそこまで気に入って下さって嬉しかった。「自分以外にニッキは演じさせない」。その覚悟を、この一か月間通してしかと目に焼き付けました。
怨霊の手が肩を撫でる。気色が悪い。 しかし中身を聞くと妙に笑える。
負け犬が。
そんなんだから死ぬんだっつのバーカ。 恨み言吐いてる余裕があったら首でも締めて来いや。 テメェで持ってきたルールさも当然みたいな顔で宣いやがって。 だったら!………………殺してみろ。
そう思ったのが、疑いなく口に出ていた。
・レミ役/児玉桃香(29期) ペチカさん!御紹介致します、私の師です(無許可)。シザーズの時に演出としての基礎知識を叩き込んで下さった恩人です。あれ一般化してマニュアルにして後世の演出に読まれるべき。まず役者に脚本を読ませ、該当部分を一人で演じさせてみる。その上で、違和感のある部分があれば/役者さんが違和感を覚えていそうな部分があれば演出が質問を受けに行き、適宜イメージを調整する。「頑張って考えた演技の方向性を全否定してくる演出にはなってほしくない」という言葉から、演技というものがどれだけ役者さんの内的イメージによって生まれ、変わってくるかに気付けました。そうですね。生地に型を押し付けてもその型通りにはならないんですね。だから生地の元の形にある程度あった型を選んで、自分からそこに入ってもらう事が大事なんですね。オムニの最初は重大な勘違いをしていた私ですが、今回はそうでなかったのであれば有難いです………………! 余談ですが、私はPCの音声データを普段イヤホンで聞きます。諸事情でペチカさんにはキャラクターのセリフを読んで頂いた音声を送って頂いたのですが………………いや、もう二度としません。アレはマズい。意味合いが変わってくる。違う、そう言う個人的な目的で送ってもらったんじゃないのに、その、あの、ペチカさんの演技が上手過ぎるからぁ………………!!(涙) 完全に予想外でした。具体的にはバイノー………………何でもないです。特定の方へ後でファイルをお送りします。そして私の方からは完全に削除します。それがいい。あれは世の中から消すべきではないけど、私が持つべきものではない。本当にそう。 告解が終わり、私の黒歴史がまた一つ増えました。死んで詫びたいレベルです。ごめんなさい。
あーあ、死んじゃった。 日用品で喉掻っ切られちゃって、死んじゃった。 これが呪い? あっけなーい。
ねぇ、どんな気持ち? 格下だと思って気楽に襲い掛かって、結局お仲間さんと一緒に殺されちゃって。 分かるよ。辛いよね。怖いよね。屈辱だよね。 こんなにいろいろ予想外だと、一周回って笑えてきちゃうよね。 子犬みたいな目で縋ってきちゃって。 嘘ついたら目ぇ輝かせちゃって。 裏切ったら傷付いて激昂しちゃって………………ねぇ、バカなの? 殺しに来た奴助ける訳ないよ。当たり前じゃん。 そんで、殺したらそうやって血ぃぴゅーぴゅー噴いちゃって。 あー、もぅ。
かーわい。
・マギー役/ちゃわんちゃうか?(31期) 芸名を訳すと「違わないのではないか?」となるのではないでしょうか?御本人の知った事でしょうか?これ所謂クソリプという奴ではないでしょうか?でもエアーマン、お前の存在その物がクソだからある意味当然ではないでしょうか?それもクソリプではないでしょうか?どうでもいいのではないでしょうか? えっと、新入生の方です。疑わないで下さい。マギー役、この人以外には務まらなかったと思います。だってFF7レベルの大剣持たされるんですもん。完全に演出の悪乗りでした。途中から刃の部分持っておられたので、あーマギーの肉体は刃の概念を理解してないんだな、つまりマギーの中でコレは鈍器のカテゴリなんだなぁと解釈してました。いや、でもマギーは強い。貞子レベルの怪物を素手で殺る。 ただの脳筋キャラにしたくなくて色々詰め込みましたし、役者さんの今までの御経験なども彷彿とさせながら「バカっぽく見えていろいろ考えてるキャラ」を目指してみたら演出の中で見事にブレまくり。最終的に丸投げしてしまったのですが、楽しんで頂けた様で何よりです(クズ)。 今思うと素のマギーは四千頭身の後藤さんみたいな雰囲気かも知れませんね。更に訳わかんねぇ。 本公演ではめちゃくちゃ暴れて下さいましたが、いつか素でカッコいいこの方を見てみたいというのはあります。実力不足でした。次回はちゃんとキャラクターを練ってきます。
呪い、ってくらいだから何かあんだろうよ。 ぼんやりと、ただそう思った。 根拠なんてねえけど。 だから、寝ずの番って奴をやってやった。 実際、俺はいなくてもいい。トークならあいつらの方が上手い。
何が来ても相討ち覚悟で殺す。 最初に死ぬなら、俺が一番良い。 何の感動もなくそう思って、色んなモンが転がった床に寝た。
出た。
出たよ。
マジで出たよ。
いやいやいやンだコイツ。忍者。忍者か。そこは幽霊とかそんな感じの奴寄越せや。 なんだ「呆気ない、ものよな」って。呆気ねえのはお前だよ。多分。 刀を避けたら目ぇ丸くしてやがった。 顔に一発。鳩尾にキック。めっちゃ吹っ飛んで机とか巻き込んで壁にドーン。どうでもいいけど真夜中なのにすっげえ音した。御近所さん迷惑だな。つかアイツら起きんじゃねえか。 そんで呻いて咳き込んで逃げようとしやがるから背中に乗って首をゴキッと。いっちょ上がり。
いや弱っ。 呆気ねえもんだな。
・いろり役/久保伊織(29期) 正式名称がめちゃくちゃ長いバンコクの様な方です。これは私の予想ですが、ここから約10年で何度か二刀流スキルを獲得したりヒノカミ神楽を学校教育に取り入れたり��ラックを異世界転生させたり未曽有の星6鯖を手に入れたりしてなんやかんやで宇宙を何回か救ってその度に二つ名が増え、最終的には「18カ月ごとに名前の長さが倍になるイケメン」という称号を手になさいます。実を言うと予想ではなく真実です。 役の名前と御本人の芸名が似ている事で同じ29期の先輩方からいじられたり演出から呼び間違え………………てません。ホントです。そんな事してません。一回位素で間違えたとかそんな事は絶対にないです。空飛ぶスパゲッティモンスターに誓って本当です。様々な人物を惹きつける魅力をお持ちの方で、もうちゃうかのイケメンといえば物理的にも精神的にもこの方に他ならない、と言った感じです。しかしアレですね。去年(2018)の新歓公演を見た直後の私に本公演の写真を見せたらマジでお前何したんとかなじられそうですね。その位今回は今までの役との差分が凄かったのではないでしょうか。ヒールとして妖しい魅力を存分に………………ヒール?あれ?主人公サイドですよね?でも陽な感じの狂気を称えた技術顧問、という中々ない、それまでのイメージとは大分違う役を最高の笑顔で演じ切って、最高に弾けて下さいました。 本当に何をなさってもそのイケボで彩って下さる、そしてノリもいいし、あと殺陣。キャスパ中の殺陣とかvs剣客とか全部この方が担当なさってます。凄いですよね。「PCを腕に巻き付けて戦ってほしい」「短剣は二種類用意してほしい」みたいな無茶振りにも応えて下さって………………いや神です。この稽古場にはなんて神が多いんだろう。 いつかこの方を主人公にしたなろう小説を書きたいです。本当にお世話になりました。
これをこうして………………っと。 おニッキ、丁度良かった。割ったゲームのコピーガード突破したぜ……… 「なぁいろり。お前秘蔵のエロ画像とか持ってる?」 ………………いや急かよ。何だよ。持ってたとして何に使うんだよ。 「企画に………………」 ほう貴様さてはネタ切れか。 「うっせー!あーネタ切れだよ何か文句あんのかよ!」 別に?まそんな気はしてたけどな。 で、どんな企画? 「い、『いろりのエロ画像だいこうかーい』、いぇーい………………」 ハッ。 「鼻で笑うんじゃねーよお前こっちは昨日夜通しで考えたんだかんな!」 何が夜通しだ何が。 お前ら三人「企画会議ぃ」とか言って結局夜中じゅう酒飲んで暴れて近所のアパマンショップに放火してただけじゃねぇか。つーかその様子撮っときゃ良かったろ。 「いや、流石にスポンサ��敵に回すのはマズい………………」 逆にそこでよく理性が働いたな。もうええわ。 で、どうすんの。俺そういうの持ってねえけど。 「は?」 いや、逆に俺がそういうのに興味あると思う?割れるゲームも弄れるコードも溢れてる世の中で何で他人の裸見て興奮すんのかマジで理解できねえ。 「あーそういやお前そういう奴だったわ………………うわ最悪」 何が最悪だよ。無いなら作ればいいじゃん。 「え、どゆ事?」 要はその辺から適当に落としてくりゃいいんだろ。『プライベートな写真を公開されて俺がひたすら困ってる』って絵が撮れればいいなら別に俺が普段使ってる奴じゃなくてもいい、それっぽくヤバい性癖の画像漁って来るわ。 「や、でも本物じゃねえとリアクションが………………」 言っとくけど俺結構演技上手いからな。死にゲー実況とか何度気ぃ使って死んでると思う? 「え、あれ演技?マジか初耳」 あぁあとな、ただ公開するんじゃ面白くないだろ。他のYoutuberみたく「お前ら三人と俺でミニゲームやって、俺が勝ったら公開阻止」��たいなルールにすれば尺も稼げる。お、そうだ。ただ公開するんじゃなくて「ネット上に公開された暗号を解けばエロ画像にありつける」みたいな形にして最終的に「釣りでした」ってやれば……………… 「いろり」 何だよ。 「………………お前、最強の友達だな」 ヘヘッ………………そういうの。『悪友』って、言うんだぜ。
『泣きながら抱き合って何してんのかな、あの二人』 『そういう事だ、ほっといてやろうぜ』 『………………いや、ちょっと何言ってんのか分かんない』 『何で分かんねえんだよ。つか俺がツッコミかよ』 『もうええわ!』 『いや雑か。こっちサイド雑すぎだろ色んな意味で』 ・織戸役/武田聖矢(29期) 見透かされている。何を?どこまで? 物凄く頭が回る方、というイメージでした。「この場にいる方の中で、私の発言の意図をこの方だけが理解している」というシーンが何度かありました。かなり分かり辛く、さりとて特に面白くない事を言う事が多い私ですが、それでもぽにょさんには全て見透かされている。その上で何かのリアクションを返してくださる程優しい方です。演出としてぽにょさんにお世話になるのは二度目ですが、思えばシザーズの頃から言葉足らずな私の意図を汲んで下さり、最適な知恵を………………オムニの場当たりでは御迷惑をお掛けしました。ちょっとした事で自信を喪失しがちな私に優しく声を掛けて下さり、気付けば近くにいらした時に心の中で何となく癒しを求めてしまう自分がいました。物語の最後の最後に真理っぽい事を言って去っていく織戸。キャスト選考の際に何故かぽにょさんの姿が被ったのですが、いやでもカッコいいんですぽにょさん。スタッフワークではめちゃくちゃかっこいいのに、基本的に舞台上では何か叫ぶ系の可愛い役ばっかり。もっと教え説くようなカッコいい役回りの、あるじゃーん!という訳で、大分すんなり決まりました。ちゃうかで普通の人をやるぽにょさんが見られて満足ですが、もっと見たかったです。 「あれ、もういいの?」 「はい。………………もう、大丈夫です」 じゃあ、気を付けて。 大人としては無責任かもしれない一言を残して、職務に戻る。 随分しっかりした感じの子だった。 本当は誰かとはぐれてなんていなかったのかも知れない。 となると、こんな街の中を一人で………………親はどうしているのだろう。 首を振り、妙な邪推も振り払う。 この区画で育児放棄なんて珍しくもない。 あの子の境遇は自分の仕事と関係ない。 それこそ、あの子が死体にでもならない限りは。 もしくは……………… そこまで考えて、下らないと切り捨てた。 そう言えば、警察の役目を教えてくれた人。 別に、「何が悪か」までは教えてくれなかった。 それから十数年。 考えてみれば、別に大した話じゃなかったのかも知れない。 「正義」や「悪」は、道具だ。 守るべきものが「正義」。倒すべきものが「悪」。 互いにそう決めつけあってるだけで、本当にあるのは単に殴ったら殴り返されるだけ、自己責任の野蛮な世界。 「なんでマイナスの平方根があるんですか」みたいな質問みたいなもの。便利だからそこにあるだけで、それ自体に意味なんてない。 下らないけど、それで社会は回ってる。 別に壊す理由も、逆らう理由もない。 それでも、あえて「正義」を見出すなら。 廊下を歩き、仕事をする。 その事に疑いはない。 突然爆発が起こって壁が吹き飛ぶ事も、ない。 深く考えないで、前に進める環境。 当たり前が当たり前のままであり続ける。 それも、一つの正義。 それを守る事が、自分達の正義。 そう思うと、今の自分は間違っていないように思えた。 急に、暖かさを感じる。 体のどこかに熱がこもったかの様な感覚があって、それでようやく迷いが消えて……………… 焦げ臭い匂いで、それが違和感に変わった。 暖かい、じゃない。熱い。 いつのまにかポケットに入れたタバコが、スーツを内側から焦がしていた。 それに気付いて、絶叫した。 ・芒役/大林弘樹(29期) サイゴンさん。すごく優しい方です。そしてすごくエ【自主規制】アンケートを拝見しました所、御自分でなさったのであろう芒としてのメイクは「大学生とは思えない」等と評判を博していました。思えばオムニバス公演で役者メイクについて教えて下さったのもこの方だった、そんな気がします。まぶたの縁のギリギリに鉛筆を突っ込むという(役者としての通例とは言え)なかなかの恐怖体験ですが、サイゴンさんに指導していただいている最中はそんな不安もありませんでした。 本公演では主にいろり役のイッヒさんと過激なスキンシップを………………詳細は述べませんが、中々に印象的な光景でした。あとすれ違う時には【検閲済】とある事情でアドリブが多くなりがちな刑事サイドでしたが、それを自然な演技で軌道修正して下さるという点ですごく頼りになる存在でした。芒という「場を取り仕切る」役に最も馴染み、その持ち味を最大限に生かして下さったと思います。そのお陰で周りの役者さんもアドリブをぶち込み易かったのではないでしょうか。いえ私は怒りません。ただし一部のアドリブについて周囲の役者さんがどう思うかは別問題です。「悪い事は自己責任」。 文字通り予測不能、キャラと同じく胃の痛い環境の中で進行を務めて下さってありがとうございます。 「織戸の野郎、どこほっつき歩いてやがる」 「絶叫しながら廊下走ってましたよ。服に火が付いたとかで」 「何やってんだアイツ………………」 現状報告を終えた部下を見送り、溜め息を吐く芒。 学歴を鼻に掛けて露骨に見下してくる同僚は何故か辞表を提出した。 加えて最近自らを悩ませていた肩の荷がようやく降りた、そんな感覚。 芒の記憶は数週間分不自然に抜け落ちていた。 だが、その上でなおも本能が「終わった事だ」と訴える。 そんなものか。 声に応じ、その傷が癒える事を許し始める。 当たり前の様に信じていた法則が破壊される。 予測しようもない事態が次から次へと襲い来る。 白昼夢の様な経験。 省みるでもなく、懐かしむでもなく。 ただ人として、芒はそれらを「呑み込んだ」。 後には何も残らない。 それで良い。 根拠の無い確信は、何故だかある種の安心感を伴っていた。 「遅ぇんだよ。何時間かけてんだ」 険のある声色に思考が遮られる。 同じ部署の人間が作業机に部下を呆れた顔で叱り付けていた。 「おぅ、どうした」 「芒さん。聞いて下さいよ、コイツ中々作業を進めないんです」 ふぅむと唸り、当の人物を見遣る芒。 俯き、混乱した様な表情。目は泳ぎ、脂汗を流している。 屈む事で視線を合わせ、その奥の感情を見据えようと試みる。 「どうした? ………………訳があるなら話してみろ」 「いえ、その………………」 「何だ?」 怪訝な表情が威圧となって相手を怯えさせる。 その事に気付き、芒は慌てて柔和そうな態度を取り繕う。 数秒後、件の人物は意を決して話し始めた。 「字が、読めないんです」 「読めない。前からか?」 「突然です。朝起きたら、急にそうなってて………………文字が全部ミミズみたいな記号に見えて、日本語のはずなのに全く意味が」 「下らない事言ってんじゃねえ。仮にも警察官が、そんな出まかせで仕事サボれるとでも思ったか?芒さん、コイツ人事に掛け合って更迭しましょう」 「………………いや、待て」 芒は悩んでいた。 『刑事として培われた長年の勘』なるものも、この場合は上手く働かない。 見え透いた嘘、と断じるには絶望した様な表情が真に迫りすぎている。 しかし、発言の内容が内容故においそれと信じる事も出来ない。 仕事柄、作業量の多さや精神的な負担に耐えかねて心を壊す同僚の存在は少なくない。芒自身、そうした人物を幾度と無く目にしてきた。 今回もその類の事かと結論付けた所で、 軽い眩暈が芒を襲う。 知るはずもない人物の、聞くはずもない言葉が脳裏に過る。 『呪いの渦中にいない以上、その呪いについてとやかく邪推すべきでない。 大きなお世話という物です』 『御自分の考え、常識。そうした物を一義的であると思わぬ方がいい』 気付けば体勢を崩していた。 叱っていた人間はおろか、先刻まで怯えていた人物にすら心配そうな視線を向けられている。 仕切り直す様に芒は姿勢を整え、指示を下す。 「今日はもう上がれ。んで病院行って来い」 「良いんですか?」 「おう。場所は分かるか………………というか、行けるか?」 「はい、何とか。ありがとうございます!」 「ちょっと、芒さん!?」 「この作業代わってやれ。大した量じゃねえだろ。 今の仕事があったらそっちは持ってやる」 「しかし、現状の案件は………………」 「気にすんな。なんだ、今流行ってんだろ。マルチタスクがどうたら」 少なくとも、すべき事はある。 それを続けていれば、自らの勢いが衰える事はない。 漠然とした、にもかかわらず確かなる信念を持って。 芒も、また再び歩み始めた。 件の人物が実際にとある病気を発症していたと分かるのは、先の話。 ・大下役/渡部快平 ワカさん。今年「美」に目覚めたんだな、と思いました。 思えば今年度の新歓、まさか脚選でご自分の脚本をお書きになるとは思いませんでした。それからオムニで一度脚本を通し、その美しい世界観は言うまでもなく好評を博しておられました。その後は言うまでもなく劇団内にも固定ファンをされ、舞台監督としても多くの団員から信頼を集めている凄い方です。 社会派な作品を書きたいと仰っていたのが私個人の記憶に新しいですが、それと関係があるのかないのか今回の大下という役ではめちゃくちゃ輝いて下さいました。「低学歴」を見下すあの表情。何て楽しそう。いや、ありがとうございます。「普段の様子を知っているから逆に面白い」という声が何となく理解できました。やー、面白かった。 癖も強く、中々演じたがられなさそうな大下という役の魅力をここまで引き出して下さったのはひとえにワカさんの教養というか、想像力というか、そういう部分があったからだと思います。「脚本を書く上で人間性の闇と向き合い続けたら病んだ」という逸話をお持ちなくらいなので、それだけ人間の負の側面という物を見据えて来られたのだと思います。だからあの闇の塊みたいな大下もあの仕上がりに。すごい。でも、人間の闇ってそこ止まりじゃないんですよ。RPG「ダークソウル」シリーズとかプレイした後になるにぃさんの動画とか見てみて下さい。ちなみに私は未プレイです。 未明とは言え、人の往来は少なくない。 市街地の中心地、一際大きな交差点。 行き交う各々の事情に思いを馳せるでもなく、その怪人物は佇んでいた。 薄汚れた赤いトレンチコート。 風呂に入っているのかも怪しいボサボサの髪。 中華風の丸いサングラス。 長老の様に伸びた無精髭。 所々生地がほつれ、破れた焦げ茶色のベスト。 ダボついた深緑のズボン。 全体的に浮浪者じみた風体は、少なからず衆目を集める。 その中に二つ、明らかな警戒を孕んだ視線。 ある種の殺意めいた物を背中に感じながら、怪人は動き出す。 信号は既に青。 それをちらと確認し、尾行者二名もあくまで自然な風を装って歩を進めた。 区画の発展は目覚ましいが、完全ではない。 主な通りを少し外れれば程なく「裏路地」に入る。 解体されずに放置された廃墟群。 複雑に絡み合った利権や都合が整理を許さない文字通りの暗部。 如何ともし難く、さりとて誰にとっても有用でない無法地帯。 というよりは、無の地帯。 誰もいない、敢えて足を踏み入れない、ビルに挟まれた虚無の歩道群。 尾行者は並みでない苦労を強いられていた。 第一に、通路の複雑な構造。 不規則に別れ、出鱈目に繋がったそれらの中では一歩先を行く人物の位置すら把握が困難になる。 第二に、尾行対象の挙動。 おちょくっている。 尾行者の片割れは直感した。 一つの通路へ頭を向けたと思いきや、そちらには行かない。 足を踏み入れた、次の瞬間バックステップで急に元の分岐点へ戻る。 恐る恐る様子を伺う相棒が息を呑む様子が聞こえた。 以降、対象の挙動は激しさを増す。 時折何の脈絡もなく振り返る。 明らかに不必要な動きが増える。 ゴミを拾って見せる。 何かを思い出し、腹を抱えて笑う。 立ち止まってロボットダンスを披露したかと思えば急に歩き出す。 相棒の困惑した視線を受け取る。尾行者は頷く。 意を決して身を乗り出したその瞬間、怪人は軽やかなターン。 慌てて遮蔽物に飛び込むも時既に遅し。体が急な制動に対応しきれずバランスを崩す。強かに尾てい骨を打った。 起き上がるや否や、怪人が逃走を始める。 追う相棒が怪人へ怒号を飛ばし、慌ててそれに着いて行く。 以降、仁義なき追走劇が10分程度。 息切れも激しく、明らかに許容量を超えた運動を行ったと分かる。 満身創痍の二人に目もくれず、余裕綽々と言った怪人がせせら笑う様に背中を���けて立ち止まる。 埒が明かないとばかりに尾行者は懐へ手を入れる。 「動くな」 台詞の内容、金属部品が擦れ合う音。 取り出した物を察したのか、怪人の様子が変わる。 言わずもがな、拳銃。 漸く話の通じそうな雰囲気を感じ取り、尾行者が要件を口にする。 「警察だ。署まで同行しろ」 「ちょ、流石に拳銃はマズいですよ。一応任意同行なのに」 「うるせえ。散々面倒掛けてくれやがって、この………………」 「………………何故、私が?」 くぐもった声。 対称的に毅然とした声で返す警察の片割れ。 「礼楽町付近で起きた連続不審死。 ここ最近、現��周辺にお前みたいな奴の姿が複数回目撃されてる」 「どう考えても関係者だな、テメェ。何を知ってる」 観念したかのように怪人が振り向く。 瞬間、その眉尻が上がる。 「………………織戸君に、芒さん?」 「は?」 「え、えー。うわー、意外だなぁ。もう会う事ないとばかり思ってたけど、まさかこんな感じで再会するなんて。ねぇ、二人とも元気でやってます?大事件とかない?その辺どうなんです、ねぇ」 「お、ち、近寄んな!これ拳銃!見えねえのか!?」 「安全装置外し忘れてますよ。それじゃ撃てない」 「あ、本当だ。何してんですか」 「うわ、クッソ………………つうかそじゃねえ、そうじゃねえ!」 親し気な様子で近付いて来た不審者に調子を崩され、一瞬和気藹々とした雰囲気に呑まれかける芒。 幸いにして持ち直し、根本的な問いを放つ。 「テメ誰だ!少なくとも俺の身内に浮浪者はいねえぞ!」 「浮浪者?あー、そっか。イメチェンしたんだった」 「イメチェン………………?」 「参ったな。あ、サングラス外せば分かる?」 訝しむ織戸を他所に、怪人物は一方的に自らの素性を明かそうとする。 隠されていた目元が明らかになった事でその顔立ちの全貌が見える。 髪や髭に邪魔されて輪郭が見えづらいものの、その人を食った様な独特な表情、整った各部の配置はその人物を特定するに十分だった。 今世紀最大の驚愕を込め、芒が情けなく叫ぶ。 「お………………………………大下ァ!?」 「え、そんな驚きますか。僕が僕で」 「変わったな………………というか変わりすぎでしょ! もう原型留めてないもん!」 「そこまで言う?やー、意外だなぁ。 自分じゃそんなに変わってないつもりだったんだけど」 「いやいやいや………………あ、違う!大下テメェ! 現場近くで、そのクッソ怪しい風体で何してやがった!」 呆れも込めた激しい追及に、あっけらかんとして答える大下。 数か月前とは打って変わり、その様子には一切のしがらみを感じさせなかった。 「何って、捜査ですよ。聞き込みというか、情報収集?」 「捜査って、警察は辞めたはずじゃ………………」 「こっちの話。要は、そういう仕事があるんです。金さえあれば、普通の警察が太刀打ちできない事件の全貌を明らかにできるって約束の仕事」 「はぁ?」 只管困惑する二人を前にして、大下はマイペースに言葉を紡ぐ。 「という訳で、昔の同僚とはいえ今は部外者。 本件に介入させる訳には行きません、お引き取り願えますか」 「こっちの台詞だ!おい、今のお前が何に手ぇ染めてるかはどうでもいい。 ただな、お前の言動は明らかに捜査妨害………………」 「あーその辺の問題じゃないんですよ。こっちにも同じ事情があるって言うか………………面倒臭いな。おい!」 「はいはーい!」 大下が呼びかけ、返事を返したのは路地裏の上方。 道を挟むビルの屋上、その縁に座る小柄な人影。 妙な既視感が奇妙な風切り音に遮られる。 矢。 妖しく白い輝きを放つそれが、織戸と芒の足元に突き刺さる。 驚く間も与えず、矢は一際眩い光を放つ。 強烈な眠気によって二人が倒れるのに、そう時間は要しなかった。 効果の程を確認すべく、寝顔をまじまじと眺める大下。 その様子を見た人影が、猫じみた身のこなしで飛び降りる。 高さと質量からは想像も出来ない程に軽やかな着地音を聞き、思わず感嘆の声が漏れる。 「俺も中々かと思ったけどさ、やっぱお前は大分違うな。 2,3日でもう人間辞めやがって」 「人でなしみたいな性格した人に言われたくないなぁ。 でぇ、大下さーん。今日の分のお小遣いは?」 後ろで手を組み、上目遣いで期待を込める大下の協力者。 そのわざとらしさに若干白い目を向けながら、大下は苦々しく確認する。 「隠しカメラとか仕込んでねえだろうな」 「まっさかぁ。ケーヤクイハンだし?」 「白々しい………………」 「あ、でも報酬次第だかんね。 動画にした方が儲かるなら無許可でそっちに切り替えるし、その辺宜しく」 「………………4人分か?」 「当然でしょ。4人揃ってこぉそぉのブランドなんだし」 「なぁにがブランドだ。どぉせこないだの放火もお前らだろ。 炎上系の癖に気取りやがって、偉そうに。地獄に落ちろ」 「そんな連中頼ってメシ食ってんだし、お互い様でしょー?」 「ハッ。そうだな………………」 自嘲気味の笑いを漏らし、清々しさを湛えた顔で向き直る。 煽った相手も心底楽しそうな笑みを浮かべていた。 厚みを持った封筒を手渡すや否や、協力者は当然の様にひったくる。 苦笑いを浮かべながら、険の無い口調で嫌味を放った。 「じゃ、午後もよろしく。犯罪集団」 「どーも、似非捜査官さん」 別れの言葉もそこそこに、互いに別の方向へ歩み出す二人。 相変わらず白目を向いて横たわる織戸と芒。 それぞれの姿を、上り始めた朝日の反射光が照らしていた。 ・三珠役/遠藤由己(29期) ハイ。説明不要でカッコよくて面白くて優しい我らが座長です。そして本公演での舞台監督です。そのゴリラとバナナと演劇に対する情熱で皆から愛される凄い方。え、完璧。欠点と言ったら作ったラーメンの生地をサークルの冷蔵庫の中で腐らせる事くらいしか思いつきません(実話。なお物体Xはちゃんと処分されました)。面白い人ってたまに人をダシにして笑いを取る、いわゆる陽なイメージがあるんですけど、この方には一切それがない。絶対に他人を責めないし、本気で人を蔑んでる所とかみたことがないし、ミスをしてもちゃんと注意して許して下さるし、もう、ちゃうかにとって太陽みたいな方だったと思います。リミッター掛けずに暴れて他人様に迷惑を掛ける事が多くて、後会話が苦手でよく人を避けがちな私にも沢山話しかけて下さったり、もう天使みたいな人です。本公演も滅茶苦茶なスケジューリングの所為で予定押しまくって、御自分が泣きたいくらいの状況においても優しい言葉で気に掛けて下さって、もう色々限界に近い様な状況でも絶対に激昂したりせず笑顔を保ち続けて下さった、それらの事へ申し訳ないの気持ちと伝えきれない程の感謝の気持ちが渦巻いております。本当に御迷惑をお掛けしました。そして、本公演本当にお疲れさまでした。 ………………はっ!「役者」紹介なのに役者としてのエンドゥーさんをご紹介出来ませんでした。カッコいいのはそうなんですけど、実際面白い、というかアドリブを多めに入れて下さる方です。 とはいえ今回はその余裕がない脚本でした。いえアドリブが悪かった訳ではなく、そうした「遊べる」部分がないような脚本だったのが良くなかったかな、と思ってます。 なので、その無念を晴らすべく脚本の方を書き換えてみます! IFストーリー、「もし三珠がアドリブしやすい環境だったら」。 「所有者は実行ファイルをJadでデコポンした、と言ってましたが」 「デコポ………………デコンパイルの事っすか?」 「そうそう、そのデコピン」 「デコンパイルっす。ちょっと遠くなってる」 「ほう、そのデコッパチってのは大変なんですかい」 「いや惜しい。今までのに比べたら惜しいレベル」 「レコンキスタが何ですって?」 「あ大分離れた。イベリア半島の再征服活動は全く関係ないっす大下さん」 「デコレーションケーキですかな?」 「矢盛さんデコしか合ってない。というかあなたもそっち側なんすか」 「えーっと、………………ヒロポン」 「いや原型失ってるっす。何すかヒロポンって。 思い付かないからってデコポンから雑に派生すんのやめて下さい」 「ちゃんぽん」 「クーポン」 「ピンポン」 「じゃんけんぽん」 「NEXCOニシニッポン」 「ポンで畳みかけないで下さい。 そもそも『デコンパイル』にポンつかねーから!」 「えっと、何の話でしたっけ………………」 「忘れてんじゃねーよ!」 結論:話が進まない。 おあとがいけないようで。 本式のIFは後で書きます。予告しよう。長いよ。 ・矢盛役/石英(29期) 入団当初、まだ人間性を獲得しておらず暴れまくっていた頃の私は(今思うと大分失礼な発言ですが)ある方に似ている、と言われた事がありました。無論見境がない分私の方がヤバかったらしいですが………………お察しの通り、その方が■■さんです。一目見たとき「あ、キャラ被ってる」と思ってしまいました。眼鏡、あと敬語キャラ。後者が特に大きかった。しかし聞いて下さい、色んな意味で暴走する私と違って■■さんは落ち着いた凄い人なんです、言わば私の上位互換。ああでも■■さんを私ごときの上位互換だとか言ったらそれはそれで無礼度がマッハ有頂天、どうしよう、みたいな事になったのでとりあえず私はフードとマスクとサングラスを着用しました(全くの無関係)。 この方の普段の振る舞いを見るとまず「人間科学ってすげぇ」という感想が溢れてきます。人間に精通している。どう言えば伝わり、どうすれば動き、何をやっても大丈夫なのか把握しておられる気がします。そして私の取り扱い説明書を持っておられる貴重な方です。通訳さんとして大分お世話になりましたし、この公演中「この方にしか理解できないだろうなぁ」みたいな事も大分お話させていただいた事があります。あと照明の「チーフ補」を務めて頂きました。もう、諸々神の様なお方です。私にとっては最高神。 お世話になった事を箇条書きしていったらそれだけで脚本が一個できるレベルで御迷惑をお掛けしました。役者として?めっちゃくちゃ上手い方です。脚本の理解に掛ける執念と言え、プラス私の脳内を推察できる方なのでもうそれはシンクロです。不明点などどんどん質問して下さって、本当に有難うございました。長台詞ばっかりでごめんなさい、でもカッコよく決めて欲しかった、啓蒙の高いカッコよさを存分に示してほしかったのです!よって後悔はありません、お疲れ様でした!なんて鬼畜な私ぃ! 「それで、話というのは何ですか。久保田君」 昼下がり。 どこにでもある喫茶店。 二人の客が会話を始める。 「………………お願いがあるんです」 「ほう、お願い」 「ええ。自分が、死んだ後の事を」 尋ねた方の人物が片眉をひそめ、もう片方を吊り上げる。 薄布で出来た黒のローブ、頭には二本の蝋燭。 奇態な格好が衆目を集める事は、何故かなかった。 相対する紙袋を被った人物、久保田についてもそれは同様だった。 「死ぬとはまた縁起でもない。一体何に首を突っ込んだんです?」 「………………他愛もない、呪いの類です。 ネット上に転がってて、まだ誰も傷付けた事がない様な」 「それを、消そうとしたのですな?」 「そうです。でも………………」 「上手く行かなかった。なるほどなるほど」 オカルトじみた服装の人物、矢盛。 最も酷薄な、かつ当たり前の言葉を選び、相手に向けて躊躇なく吐き出す。 「まぁ、自業自得でしょうな。 どんな理由があったかは知りませんが、その辺に転がる呪いに手を触れるなどあってはならない事。無論君ならば良く分かっていたはずです。 その上で、なぜその様な真似を?」 「………………子供」 「はい?」 「子供が作った呪いなんです、それは」 矢盛の脳内を様々な推測が去来する。 亜事象………………呪いを含む、超常現象。 それらを構築する知識を子供が得るのも、あり得ない話ではない。 しかしながら。 「一体なぜ?」 爆弾を作る知識を偶然手に入れた子供、そのどれだけが実際に爆弾を作ろうとするだろうか。倫理的な問題は省くにせよ、手間は掛かる。一歩間違えれば自らの身に危険が降りかかる。「面白そうだから」という目的だけで殺人兵器を完成させる物は、まずいない。 誰かに殺意でも抱いたのだろうか。それでは「誰も傷付けていないまま、呪いがネットに流れている」状況と矛盾する。誰を狙って? 久保田の答えは、そうした矢盛の疑問を更に深める事となった。 「芸術………………多分、そんな感じだと思います」 「どういう意味です?」 「その子は、その呪いを一つの作品として完成させたんです。 誰かを殺すことも、その一部として」 要領を得ない答えが返る。 様々な疑問を飲み込み、矢盛は最低限の解釈で応じた。 「………………ただの子供では、ないと」 「ええ」 「しかし、それならますます意味が分からない。 君、なぜそんな人物を敵に回したのですか?自分の命すら危険に晒して」 沈黙。 紙袋の上から、その表情は窺い知れない。 「………………守りたかったんです」 「誰を。何から?」 「その��をです。このままだといずれあの子は、あの呪いは、誰かを傷付ける。それだけじゃ済まない、いずれあの子自身も復讐に遭って殺される。 誰かを殴れば���り返されて死んでしまう、それをあの子は!」 「お、落ち着いて。あ、どうもすいませんね店員さん。 ほら。一旦食べて落ち着きましょう」 「あ、すいません………………」 立ち上がっていた久保田が気を取り直し、椅子に座る。 紙袋の所為で悪くなった視界は、プレートを持ったまま困惑する店員の存在を捉えていなかった。 矢盛の注文はパンケーキ。久保田はフレンチトースト。 すぐさまナイフを入れ、舌鼓を打ちながら互いに考えを整理する。 もきゅもきゅ。 全てを胃袋に収める頃には、矢盛はある程度その理解を纏めていた。 紙ナプキンで口元を拭い、再び話を切り出す。 「つまり、アレですな。 亜事象世界のシンプルで残酷な掟からその子を庇護したかったと。 その子、ひいてはその呪いに関わるにあたって、どうしても君自身が狙われる必要があったと」 「ええ。道を踏み外したとはいえ、あの子にはそれだけの才能がある。 若い芽が摘まれるなんて、俺には耐えられない」 「正義感の強い君らしいですな。 誰かを殺めようとする子供すらそこまで気に掛けるなど。 しかし、才能というのは呪いを作る事だけですかな?」 「どういう事です?」 「いや何。先程から話を聞いてみると、何か君自身その呪いに感銘を受けた節が感じられると思いまして」 「………………一つ、見ていただけますか。 呪いに関わる画像なので、あまり」 「その程度気にしていたら亜事象家などやっていられませんよ。是非」 促され、久保田はポケットから一枚の紙を取り出す。 画像がプリントされたそれを見て、矢盛はただ美しいと感じた。 中世のそれを思わせる、ファンタジー的な街並み。 山肌の質感。自然な光。現実には存在しえない、だが「何処かにあってもおかしくない」とすら感じさせる趣ある建築。細部に至るまで生々しく描写された人、生物、その他全て。 最新のCG技術ですら再現出来ない程の光景、一枚の紙に映し出されたそれですら矢盛の心を掴むには十分だった。 「ほう、なるほど……………亜事象で生成した光景、ですか。 ここまで見事な物は見た事がありません。しかし、呪いと何の関係が?」 「呪いのゲームのスクリーンショットです。 この世界の中で悪行を犯したプレイヤーは裁きを受ける」 「何と。要はグラフィックがめちゃくちゃ綺麗な呪い版UNDERT〇LEと。 はー、確かにこれは危険ですな。良い評判に騙されてその辺の一般人が手を出してしまうかもしれない」 「でしょう? こんなに美しい物が作り出せる子なのに、勿体ない」 「ちなみに『子供』というのは、何故?」 「追われてる時に何回か姿を見ました。 やってる事と言い体格と言い、少なくとも大人じゃない気がして」 「ほーん………………」 納得しかけた所で、本題から逸れた事を思い出す矢盛。 そも、久保田から自分に託された願いとは何であったか。 AM6:00。 日が昇り、矢盛は「吸血鬼」の亡骸が崩れ去るのを確認する。 亜事象の研究家として適宜警察等の公共機関に協力し、必要に応じて自ら手を下してほしい。 丸投げともとれる雑な願いに対し、事実矢盛はやり遂げるに至った。 身勝手に命を賭け、死んでいった久保田。 その行いに、何らかの意味があったのか。 確かめる術もないまま、弔いを胸に矢盛は佇む。 もう、あの姿のままで相まみえる事はない。 路地裏の静寂が、惜別の情を静かに包んでいた。 昼下がりの喫茶店。 甘味を味わい尽くし、席を立とうとする二人。 今生の別れを前に、矢盛が希望的観測を口にする。 「時に、久保田君。 怨霊を、信じますか」 「………………信じます」 「そうですか………………」 根拠もなければ、証拠もない。 ただ、「そうであれば良い」だけの噂。 「この世界は、産み落とした物を無碍にはしないそうです。 例え姿形が変わろうとも、今ある物は残り続ける」 矢盛が久保田から視線を外す。 「いずれ、また会いましょう。 互いが互いに出来る事をやり尽くした、その後で」 その声は、心なしか震えていた。 応える久保田も、また死の恐怖を掻き消すように声を張る。 「ええ。負けません。 必ず、この世に想いを遺します」 それが、矢盛の聞いた久保田の最後の一言となった。 ・玉池役/堀文乃 らめるさん。お世話になるのはシザーズ以来ですね。 いや、プロです。上手い。それっぽく投げたイメージの解像度を物凄く引き上げて下さる神です。それだけに学生役にとどめるのが申し訳なかった。前座コントで見た様な虚無感の演技然り、もっと幅広い顔があるはずなのにそれを見る事が出来ないっ………………!!!!あ、ああ悪役!次は悪役をお願いします!!!フリーが濃すぎた影響か、今回の役は割と常識的に見えたかもしれませんがホントにすごいんです。楽しみ方とか喜び方とか満面の笑みがもう輝くような感じだし、「草」の言い方とか「あミスった」とかすごい自然だし、推しに遭えた感情で限界に達するムーブとか安易に共感できて、もう玉池やってもらってよかったなぁと。配役に関する個人的な妄想をもう少し広げると、そうですね………………次はめっちゃクールな役も見てみたいし、自然に微笑みながらサラッととんでもない事を語るようなにこやかサイコパスも見てみたいし、逆に怒涛のツッコミをお任せしまくるのもいっかなぁ、あーでも笑顔が見れない、何をお願いしても笑顔��演じ切ってくれそうな感じがあるからこそその笑顔がもっと輝いてほしい、はぁよすぎでしんど。でも一番しんどいのは勝手に色々言われてるご本人かもしれませんね。この辺で止めにしときます。 ・多賀役/岡山桃子 この方の優しさをフルコースで体験しました。いや音響。音響。舞台上の役者の動きに合わせて音が鳴ったりするんですが、今回はその回数が3桁を超えたそうです。やーすごいですね。誰のせいなんでしょう。下手人は大集会室の床に土下座の要領で頭を叩きつけまくって脳漿をぶちまければいいのに。すいません私ですごめんなさい。でも全然キレないんですこの方。慈悲の化身か。本当にしんどい思いをさせて申し訳ございませんでした。 役者としてですが、可愛らしい役をする事が多い方だと思ってます。それだけに今回はただ可愛いというよりも大人しい感じの役だったというか、そこまであざとさに向いてなかったというか、むしろカッコいい部分もあったかもしれない?スタッフワークとかで人間性的なカッコ良さを発揮する人が舞台上でそうなれないのに耐えられなかったんだよ!!!!!(謎の告白)何でしょうね。そう考えると今回はまだ役にイケメンさが足りなかったかも知れないです。でもいつかどちゃくそイケメンな役を演じさせてみたい。そして全国のみこた………………みこさんランドの住民の村を焼きたい。見てみたくないですか?私は見たい。 久保田inにその片鱗はあった気がする。目覚めよその魂………………!! ・中西役/lulu ラブノートからの………………ペチカさんの所でコレ書くんだったー!!先に言っておくと、luluさん/児玉桃香さん/中戸太一さん/サミュエル・ツヤンさんの4名とは2018オムニB脚本「LOVE NOTE」メインキャストからの仲です!なのでこの5人はこの脚本に揃ってました!懐かしー! え、役者として?この御方を誰だと思ってるんですか。luluさんですよ。初登場からその圧倒的なカリスマ性で固定ファンを大量に獲得、今やその影響力は政財界の域を超えを揺るがさんとしているluluさんですよ?真実はさておき、私も稽古場で「ルルさんに逆らうんですか?」という脅し文句を使った事があります。怒られました。いやでもカッコいい。キャスパも凄い。一回ぐらい主役やってほしい。というか最近「殺されるならこの人かな」みたいな感情が芽生えてきています。気持ち悪いですね。今作ではツッコミ役の学生としてこれ以上ないほどリアルで引き締まるような演技を披露して下さいました。 本公演では演出補佐も務めて下さいました。そう考えると演技面ここどう思いますか、みたいな感じでもっと御意見を求めれば良かったのかな、と思うシーンが山の様にあります。いやでも十分ですね。キャスパしかり、学生サイドの監修しかり、「一つのシーンが演出の手を経ずにほぼほぼ完成する」という夢の様な事例を作って下さってありがとうございました!luluさん最高! マッカブランカによる前代未聞の生放送企画から3週間後。 一切の情報を残さず、件の4人は消息を絶った。 遺されたのは、一瞬の安寧。 あるいは……………… 「玉池ぇ、いい加減立ち直んなよ。 別にマッカが死んだって決まった訳じゃ………………」 「アァアァアァアァァァ………………」 「しょうがないよ。あれからすっかり落ち込んじゃって。 夜も眠れず食事も喉を通らない、唯一体が受け入れるスタバの新作メリーストロベリーケーキフラペチーノで辛うじて生きながらえてるんだって」 「弱ってるにしちゃ主食がハイカロリーだな」 あるいは、死んだ目の玉池。 生気を感じない瞳の下には幾重にも隈ができ、顔色は青白さを通り越して純白、あらゆる問いかけに対して「マッカしゅき」としか返さぬ有様。 ゾンビ。 端的に表現���れば、それそのものとしか言い様がなかった。 「どうすんのコイツ。てか何でこんななってんの?」 「何日か前からおかしかったっちゃおかしかったんだよね。 最初こそ『大丈夫。マッカは生きてる』って怖いくらいの笑顔で言ってたんだけど、段々『マッカニウムが足りない』とか『まばゆい推しの記憶があたしを生かし、同時に苦しめるんだ』とかうわ言いい出すようになって」 「しまいに教室のど真ん中でカッター持って『我ガ臓器ヲ捧ゲマッカヲヨビダス』とか叫びやがった、と」 「止めてなかったらホントに切腹してたかもね………………」 多賀が玉池の様子をみやる。 焦点の合わぬ視線が虚空を見据え、時に痙攣しては弛緩していた。 その様に呆れ、中西が眉間を指で抑える。 「勘弁してよ………………このままじゃウチらまで変人扱いじゃん。 玉池、どうしてもマッカじゃないとダメなn」 「いい訳ないでしょぉおぉぉぉおおおお!!?!?!?!?!?!?」 「うわっ………………」 「二度とあたしに向けてその言葉を放つな、それはあたしにとっての禁句だ、いいか。故郷に替えが利かない様に」 「おかえり玉池」 「ただいま多賀。一生の推しはずっと代えられない。他人がどうだか知らないけど、あたしにとっての推しYoutuberは今後一生、何があっても絶対、どんな不幸や災難があたしを襲おうとも、間違いなく、確実に、マ、ッ、カ、ブ、ラ、ン、カ、だ分かったかぁ!!!!!」 「離せ」 「あいだだだだだだギブギブギブ!!!」 激昂しながら中西に掴み掛かり、結果手酷い反撃を受ける玉池。 野に咲く花を見るかの様な面持ちで眺める多賀。 最早、日常であった。 関節技を解かれるや否や、玉池が喚く。 「あー中西余計な事すんなよぉ、何も言わなきゃあたしは今も虚ろで空虚な夢の中を一人さみしく泳いでいられたのにぃ」 「『虚ろ』と『空虚』は同じだよ」 「るっさい。あー、やだなぁ。これから何十年もマッカのいない世界を生きてかなきゃいけないのかぁ。退屈だなぁ、いっそ死んでやろうかなぁ。しかし死ぬと言っても色々方法はある。転落、焼死、窒息死………………」 「お前は何がなんでも過去公演ネタをやらないと気が済まんのかい」 「え、じゃあ何?信じてればいつかあたしの目の前にドラゴンに乗ったマッカブランカの4人が来てくれるとでも?」 「いや知るかよ。勝手に信じてれば」 「ハクジョーな事いうなよー友達だろー?」 「とち狂った挙句クラスみんなの前で割腹自殺しようとするような奴を友達とは呼びたくない」 「ひどい………………え待って何の話」 「記憶すらねーのかよ最悪だな」 「二人とも」 縋りつく玉池、邪険にする中西。 二人が、多賀の声によってようやく異変に気付く。 周囲を見れば、クラスメートも同様に騒いでいる。 薄暗い。 教室のみならず、学校全体を覆う影。 窓から見えるは硬く、煌びやかに輝く固い鱗の群。 古典的RPGじみたドラゴン。 何かを振り落とさんと、必死に暴れ翔んでいた。 そして、その背中には。 「視聴者のみなさーん、おっひさー! 待たせたお詫びに今回は特大スペシャル!何とみんなの目の前でドラゴンの解体実況をやっちゃいまーす!いぇーい!」 多賀や中西にとっても見覚えのある、クロスボウを抱えた小柄な人物。 背後にはいつもの3人。 謎の空撮ドローンに向かって手を振りながら声を張る、その様は。 玉池が、弾けた。 枯れかけた草木が生命の輝きを取り戻すかの如く、弾けた。 肌は瑞々しさを取り戻し、四肢には宿るは火事場の馬鹿力。 特に邪魔だった訳でもない中西の足を掴んで持ち上げ、後ろに放り投げる。 宙を舞う中西。 飛距離は5m。 壁に激突。 駆け寄る多賀。 唖然とするクラスメ���ト。 それら全てを完全に意識から外しながら、玉池は。 力の限り。 喉が割れんばかりの大声で、叫んだ。 「マッカじゃああぁあぁあぁあぁあぁあぁあぁあぁぁあぁああぁあぁあぁあぁああぁぁぁああああっぁあぁあぁあぁあぁあぁあぁっぁあぁああぁあぁぁああああああぁあぁぁあぁあぁぁあぁぁぁぁあぁぁぁあぁぁぁぁぁぁぁぁぁああぁあぁあぁあああぁぁああぁああぁああぁあああああああああぁああぁあぁんっっっっっっっっっ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」 教室のガラスが、一斉に吹き飛ぶ。 クラスの大半が耳を抑え、うち幾人かは失神する。 数百人分のそれに匹敵する声量の応援を受け、レミがそちらに手を振る。 玉池の視力、今や5.0。 無論その仕草を捉え、その精神が天へと召されゆく。 推し、即ち神。 自らの声が神に届けられる。 この世の何物にも耐え難い自己肯定の証左、狂おしい程の悦楽に呑まれながら玉池は有頂天であった。 ふと、側頭部に違和感を覚える。 足。 どす黒い殺意を纏った中西の飛び回し蹴りが、玉池の頭蓋に横から深く食い込み、破壊する。 必死に止めようとした多賀は、既に振り払われていた。 ああ、何だ。 たった、それだけの事か。 意識が、徐々に霞となって消える。 机や椅子を薙ぎ倒し、玉池の体が床へと零れ落ちる。 暖かい布団に包まれ、微睡みに墜ちるかの様に。 怒り冷めやらぬ中西の幾度とない踏み付けを食らっても、なお。 玉池は、笑顔であった。 ………………駄目だ。耐えられない。 一つのキャラにつき一つの物語を書かないなんて、そんな馬鹿な。 待てよ、僕の仕事は………………こんな風に、想像する事。 文字によって、頭の中の世界を描く事じゃなかったか? そうだ。 何を忘れていたんだろう。 これはあくまでも本編後のアフター/IFストーリー。 役者紹介は、その口実に過ぎない。 ハ………………ハハハ。そうだ。それこそが、僕の! 「ちょっと待って」 ………………誰だ? 「お世話になった人、迷惑をかけた人。 その人たち全てに感謝と謝罪の念を述べ、過去を供養する事。 その大切さを、君は忘れている」 何を、言って………………ぐっ!? ぐ、ぐあ………………あが、ぐあぁあぁああぁああぁああ!!! できません……………… 私の仕事は、公式二次創作を、書く事だから………………!!! 「違うって。 君の仕事は、役者紹介だよ」 -transmission complete- ぐ、ぎゃぁあぁああぁああぁああぁあ!!!!!!! あ、あ……………… 『メタフィクション:ザ ゲーム』に、接続。 マジですいません。 流石に十勇士ぐらいはまとめます。
0 notes
Text
SAKI the HERO 2
割れそうなほど力強い管楽器に、ピアノの軽やかなステップ。大音量で流れるカレントリップの音楽を頭上に感じながら、ハリはじっくりとインクの中に潜んでいた。アロワナモールのナワバリバトル。現在の戦況は味方三落ち、相手一落ち。相手側の陣営の様子を観察する。スプラシューターコラボが中央の高台にいて、髪が光っている。もしハリが姿を現したら、ジェットパックを発動するだろう。カーボンローラーは相手の陣営の下の方を塗っている。スクリュースロッシャーネオが落ちていて、左手の高台にスプラスコープだ。二つ結びのガール。ハリのよく見知ったイカである。 サキたちの旧友であるオトハは、二つにくくった細切りの髪を揺らし、ハリのいるナワバリバトルにしばしば乱入してきた。仲間は引き連れていない。大抵、ひとりで混ざってくる。それは彼女がハリに対し「つきまとう」宣言をしてからずっと続いていた。だからもう、そこそこ長い期間の付き合いとなる。 あの一件以来、一種の「野良友だち」のようになってしまったふたりは、お互いの立ち回りを嫌というほど知ることになった。つまりキルを取るには、見せたことのない手を使わなければならない。あの手この手で下しあい、やったことのない挑戦的な道を通ることもあった。ハリはイカニンジャをつけて壁や細いヘリにセンプクし突然飛び出してみたり、イカ速で揃えて異常な速度で仕掛けてみたりした。オトハはスペシャル増量を積んでハイパープレッサーを連発したり、復活ペナルティアップでハリの動きを鈍くしようとしたりした。彼女たちの戦いには、偶然居合わせた多くのイカたちが巻き込まれた。 ハリは、オトハのことが嫌いではなかった。最初こそ彼女の執着性や乱暴な言葉遣いに恐怖したものの、今は何ともなくへっちゃらであった。むしろ、楽しみなところもあった。オトハは強いのだ。ほかのイカたちよりも、ずっと。彼女とやり合うようになってから、ガチマッチのウデマエがSにあがった。オトハはたくさんの実戦をハリに経験させてくれたのである。 アロワナモールで予定されていた全試合が終了した。今日のオトハとの一対一は、二十勝十八敗でややハリに分があった。仲間への挨拶をそこそこに、ハリはアロワナモールを後にしようとする。そのときだった。耳元をインクが鋭い音を立てて通り過ぎ、ハリの目の前にある壁に当たり、弾ける。振り返ると、オトハがスコープ越しにハリを見ていた。 「エリア、S帯に行ったんだ?」 「……うん」 オトハの確認にハリは肯く。オトハとこうして会話をすることも、最近増えてきたように思う。大体は、あちらが話し掛けてくるのをハリが受け止めているだけだが。 「じゃ、野良でマッチングするかもね」 「オトハも、Sなんだね」 「目障りだわ、アンタみたいなスロッシャーなんて」 「どうして?」 「嫌なことを思い出すから」 えらく個人的な理由だった。ハリは髪を揺らしながら首を傾けて「わたしは、チャージャーが好きだよ」と言った。嘘でもないし、機嫌を伺ってのことでもなかった。本当に、ハリはそう思ったのだ。一方オトハは、鼻を鳴らして目を逸らした。 ハリは、彼女の行動のことを実に不思議に思っていた。彼女は自分に付きまとってくるが、本当にそれだけであった。しかしサキはそれを心配していて、バトルに行くときは呼んでくれ、とそこそこ煩く呼びかけていた。ハリは、呼ばなかった。オトハはルールブックで禁止されているような行為はしてこないということを、よく知っているからだった。 そして、これはまったくの勘であるが……彼女の態度や言動で、ハリはなんとなく彼女の気持ちを察しつつあった。その昔、サキはスロッシャーを使っていた。スロッシャーを見ると、彼女は嫌なことを思い出すという。彼らはかつて、喜びも苛立ちも共にした仲間、だったはずである。 オトハの苛立ちの原因は、自分ではなくサキにあるのではないか。そしてオトハはそれを、ハリに気付いて欲しいと思っているのではないだろうか。初めこそノックアウトを取れなかったからただ再戦を申し込みにきただけだったとは思う。しかし勇んで行ってみると、そこには彼女にとって最悪なことに、あらゆる元凶のサキがいたのだ。それで、後には退けなくなった……自惚れかもしれないが、そう感じたのである。 そう思ったハリは、思い切って訊いてみることにした。 「オトハは多分、バケツが嫌いなわけじゃないんだよね」 「はあ?」 「サキがバケツを使っていたから……わたしの戦略が、サキに似ていたから」 自分のプレイスタイルがサキに似ているなんて、烏滸がましいかとは思ったが、しかしハリは自信を持ってそう伝えた。ハリの立ち回りは、サキから教わったのだ。最初こそうまくできなかったし、独り立ちしてからは自分で考えて動いてはいるけれど、自分の立ち回りの根っこにあるのは、サキなのである。それはどうやっても裏返ることのない事実だった。 「過去に何があったかは知らないんだけど、何となく、サキとのわだかまりを感じていて」 「……だから、なに?」 ずきん、とハリの心が痛んだ���その通りだ。だからなんだ、という話である。ハリは俯いて、「ごめんね。今のは、忘れてね」と言ってオトハに背を向けた。サキやマツリやオトハたちに何があったか、なんて、自分が首を突っ込めることでもないのに。自分の愚かしさが、悔しくなった。 「わたしが邪魔なんでしょ? 付きまとわれて、正直迷惑してるんでしょ」 オトハが吠える。ハリは背中を向けたまま「ううん、それはないよ」と答えた。歩みは止めなかった。
・
ひょんなことから世界を救うことになったサキの始まりの一日は、いきなり家を引き払うことから始まった。トーマの真剣な眼差しについ天性の世話焼き心が折れたサキは、「オレにできることなら、手伝うよ」という返事をしたのだが、それが大体夜が明けてすぐだった。それからトーマは魚を焼いてくれ、ふたりは朝の七時ごろに朝食をとっていたのだが、食べている間にインターホンが鳴った。サキは箸で持っていた魚の身を慌てて口に放り込み、だれかの来訪に応じようとする。 しかし、トーマの行動のほうが一足先んじていた。「早いなー」と言いながらトーマは立ち上がり、ドアを開けに行く。トーマの客、なのか。乗り遅れたサキは咄嗟にそう判断したものの、とはいえここは自分の家で放っておくわけにもいかないし、と思い箸を置き魚を飲み込み首を伸ばして廊下を覗き込んだ。すると屈強なクリオネたちが三体入り込んできたものだから、サキは首を引っ込めて絶句するしかなかった。 「ごめんなサキ、今から荷物運ぶな。机以外からやるようにするよ、ゆっくり食べてていいから」 「は、え……は?」 「あ、言ってなかったっけ。引っ越すんだ。ここは危ねーからな!」 トーマは何事もなかったかのように座り直し、箸を持った。そうして普通にご飯を食べ始め、世間話でも語るようにどうして引っ越しをしなければならないか説明した。タコたちは、すでに地上に出てきているものもある。その一部がスパイとなって、地下を脅かそうとするイカの寝込みを襲うことがあるらしい。実はついこの間、四号と呼ばれるイカが襲われてしまった。四号は、今回の戦いにおいて唯一のヒーローだった。 「だから、新しいヒーローを探しにきたわけ。サキはさしづめ、ヒーロー四号代理ってとこだな」 「ヒーロー四号代理」 「悪く思うなよ。五号にはできないんだ。ちょっと色々事情があるんだよなー。ところでサキ、あの棚は運んで大丈夫か?」 トーマの指差す方を見る。まだ新しい木の色が美しい棚の前には、三体のクリオネのうち一体がじっと佇んでいた。 「あー、家具は置いていってくれ。備え付けだから……中身はオレが出す」 「わりいな」
引っ越しというものは業者を使えばこれほどまでに早く終わるものなのかということを、サキは独り立ちしてから初めて知った。サキがご飯を食べている間に、全てのあらゆるものがこの部屋から運び出されていった。見ていて清々しいほどだった。ついこの間掃除をしたばかりということもあって、クリオネが来てからこの部屋ががらんどうになるまでものの十分位だった。 サキが学校を卒業して実家を後にしたとき、というのはもう随分前のことになるが、そのときは業者は呼ばなかった。大きな鞄にフクや食糧をたくさん詰め、引っさげたバケツに描いた絵とアイドルのポスターを突き刺し、それこそ家出のような風貌で自分の人生を自分の足だけで歩き始めたのである。最初はサーモンランというやや危険な日雇いの仕事で食い繋ぎ、安くて狭くて綺麗でないホテルに滞在していたが、これではいけないと思って職探しをした。それで出会った職と家が、ここエスカベースだった。 「トーマ、シガニーに挨拶してくるよ。もうここに住まないなら当然、仕事も辞めなきゃいけないし……」 正直なところ気が重かった。サキはわりと適当な性格ではあるが、仕事を辞めるだとか退去するだとか、そういうものに対してはきちんとしていたかったから、彼に合わせる顔がないと思った。しかしトーマは「ああ、いいっていいって」と言いながら食器を台所に運んで水に浸した。そうして戻ってくると、こう言った。 「もう話はつけてあるんだ。一週間前だったかな。ブキチと談判しに行ったんだけど……あ、ブキチはオレたちの仲間だから、ブキの新調とか調整とかで色々世話になると思う……まあ、話のわかるカニで良かったよ」サキは、本当かよ、と思った。しかし、朝から色んな信じがたいことが目まぐるしく起きているのをいい加減認めざるを得なく、もはやサキはトーマを信じて飲み込むしかなかった。「あ、でも、言付けを頼まれたな。訊く?」 「もちろんだよ、なんて?」 「出世するまで顔出す��。店を出すならバッテラにしろ。……ってさ」 シガニーらしい言葉足らずな花向けに、サキは堪らずため息をついた。でも、平静なら抱いていたような苛立ちはやってこなかった。シガニーは、未熟な自分を信じ面倒を見てくれた唯一のオトナだった。普段の生活を送る上でそういうことは忘れて生きるようにしていたが、本当はいつだって感謝の気持ちを抱いていた。せめて、旅立つときには伝えたかったが……。 「巻き込んで、わりいな」 すっかり綺麗になった部屋に、トーマの声がクリアに響いた。 「でも、四号がやられたって訊いたとき……サキしか居ないって思ったんだ。ほら、大体のイカは適当だろ?」 「オレだって、結構適当だよ」 「でも、お前は投げ出さない。それくらい、判るよ」 トーマはまっすぐにそう言い、照れもせず笑った。イカらしい……図々しさと、朗らかさがあった。そんな風に言われたら、なおさら断れないものである。 彼らは拳を一回だけ付き合わせ、まっさらな部屋を後にした。もう、ここには二度と戻って来ないだろう。
0 notes
Text
【記事】フィギュアスケートマガジン 山口真一氏
<リンク>
2018年12月 僕が羽生結弦に教わったこと
=略=
今季のグランプリ・ファイナルは、昨シーズンに続いて、本来なら男子の主役というべき選手が出場しない。いうまでもない。羽生結弦だ。
僕はフィギュアの雑誌では「羽生ストーカー」とか「文字テロ」と言われていて、なぜかというと記者仲間からそう揶揄されていたのが、どこかのタイミングでネットに乗って(自分で書いたんだっけか?)読者の方までそう呼んでくれるようになった。「テロとかストーカーとか、軽々しく扱う言葉じゃない」なんて声もいただいたが、読者の方が楽しんでくれるならそれも仕事のうち、なんて思っていた。
「ストーカー」という言葉で思い出すことがある。2年前、2016年のグランプリ・ファイナル。フランスのマルセイユという、南部の港町で行われた大会だ。ちょうどフランスで「テロ」が多発していた時期で、機関銃を抱えた兵隊が並ぶパリの駅から列車でマルセイユに着いたときは、さすがにほっとしたし、少し落ち着いてから「あれ、なんか暑くね?」と感じたのを覚えている。
実際、暑かった。街のあちこちにソテツが植えられ、ウインタースポーツにふさわしくないムード。12月なのに昼間は半袖で十分だった。出場選手が少ないので1日あたりの試合時間は短く、空き時間はレジデンス風のホテルに戻って原稿を書いたり、写真選びをしていたが、洗濯物を増やしたくないので、部屋ではもっぱらTシャツとパンツ一丁だった。外に食事に行く時間がとれず、食事は3食ともレンジでチン。ある日はサンドイッチ、ラザニア、パスタ。翌日はパスタ、サンドイッチ、ラザニアという感じで、ホテル近くのスーパーで買った冷凍食品を温め、日本から持参した割りばしで食べるという、しゃれた1週間を過ごした。
マルセイユでの取材は、いま思い出してもほろ苦い。というか、胸が締め付けられる思いがする。ご存知の方も多いと思うが、フィギュアスケートはショートプログラムとフリースケーティング、2種目の合計得点で順位が決まる。羽生はショートプログラムでトップに立ち、1日おいたフリーに出場。そのときに、ちょっとした出来事があった。
担当していたフィギュアスケート雑誌の看板は、羽生の大会密着記事だった。朝の会場入りから練習、練習後にいったんホテルに戻るまで見届け、再びの会場入りから6分間練習、演技、記者会見から会場を後にするまで、そこで起きたことを分単位で記録するのだ。「皇族記事並みですね」と記者仲間から苦笑されていたが、とにかく羽生の一挙手一投足、一飲み一転び一脱ぎに至るまで細かく文字に書きとどめ、会見で発した言葉も忠実に再現するのが、僕に与えられたミッションだった。
その日は確か、女子のフリーが行われている時間に、羽生がウォーミングアップをしていた記憶がある。選手は演技の前に6選手が一斉に「6分間練習」をするのだが、氷に上がる前には、ホッケーと同様に陸上でウォームアップをする。マルセイユの会場は記者控え室の裏にウォームアップルームがあり、選手の様子を見ようと思えば見られるのだが、暗黙の了解として、記者は覗き込むことはない。選手の集中を殺いでしまうからだ。
女子のシングルに日本人選手が出ていたから、記者はみんなリンクサイドで取材をしていた。控え室に残っていたのは僕だけ。羽生が発するウォームアップの音に耳を澄ませながら、「いま、縄跳びをしているんだ」「大股でステップしているのかな」と想像し、ノートに記録していた。と、その瞬間だった。
ウォームアップルームから、白いマスクをした羽生がキャリーバッグを引きながら姿を見せた。前述したように、記者室には僕1人。羽生は律儀な性格だから、体ごとこちらに向けて深々と、「行ってまいります」というように細い体を折り曲げて頭を下げ、階下のリンクに降りるエレベーターに乗り込んでいった。
そう書くと大したことないように思えるが、このとき、僕は固まっていた。体が縮こまっていた。なんてことをしてしまったんだと頭の中がグラングランしていた。実際、体は縮んでいたと思う。普段は身長183センチなのだが、この時は165センチくらいだったと記憶している。「羽生に気を使わせてしまった」「大切な勝負の前に集中を乱してしまった」と、しばらく動悸が収まらなかった。
なぜ咄嗟に観葉植物のフリができなかったのか。「はにゅうくん、どうしてぼくにおじぎをするの。ぼくはサボテンだよ。にんげんじゃないの。植物なの」と腹話術のようにモゴモゴとしゃべればよかったではないか。このマルセイユに来ることができたのも羽生のおかげなのに、その羽生に、こともあろうに大切な演技の前に余計な気を使わせてしまうとは。ストーカーの風上にも置けないとはこのことだ。そもそも、ストーカーがストーキング相手に見つかった挙句、深々とお辞儀をされるなんて聞いたことがない。ストーカーとして最低だ。いや、ストーカー自体が最低なことだから、最低なストーカーというのはむしろ超最高なのか…などと混乱しながら、スタンドの記者エリアに座った。動揺が顔に出ていたのだろう。「山口さん、どうしたんですか」とスポーツ紙の女性記者に聞かれたのを覚えている。
今だから冗談めかして言えるが、本当にその時は気が気でなかった。自分はプロとして失格だと思った。大切な勝負を前にしたアスリートに、些細なことであっても気を使わせてしまってい��はずがない。羽生はこのマルセイユに、戦いに来ているのだ。それを一介の記者が、1万分の1であっても集中を殺ぐなんてことはあってはならない。
その年のグランプリ・ファイナルは、羽生にとって史上初の4連覇がかかっていた。ショート1位の羽生は、フリーでも4回転ジャンプを決め、快調な滑り出し。「よし、ちゃんと集中できてるじゃないか。世界よ見たか、これが羽生結弦だ」と叫びたかった。
が、演技の後半になって歯車が狂いだす。ジャンプで失敗が続いたのだ。「ああ、俺が集中を乱してしまったせいだ」と落ち込んだが、結局、ショートの点数が生きて総合優勝、羽生は4連覇を達成した。ショートとフリー、2つで争うのがフィギュアスケート。羽生自身、満足はしていないけれども納得はしているように見えた。フリーでも1位だったら「世界よ、見たか。これが羽生結弦だ」と表紙に載せようと思ったが、それはまた、いつかのために取っておこう。1人でハラハラしたり、ほっとしたりした1日の取材を終え、同宿だった折山淑美記者と歩くマルセイユの夜道を、この先もずっと忘れないと思う。
フィギュアスケートは華麗なイメージがある一方で、孤独で残酷な一面を持つ競技だ。たとえば羽生は、その2016-2017シーズンはショートプログラムで『レッツゴー・クレイジー』というロック調の曲で演技したのだが、一番最初の4回転ジャンプで失敗すると、場内が「ああ~」というため息に包まれる。それでも羽生とすれば、落ち込んでもいられない。なにしろ演技は始まったばかりだからだ。場内にはアップテンポの曲が流れ、それとは対照的な重い空気の中で、ダウンしがちな自分のメンタルと向き合いながら滑り続ける羽生の姿を何度か見てきた。
今、ふと羽生のそんな姿を思い出すのは、僕自身が今、重い気持ちで1日をスタートさせることが少なくないから。アイスホッケーの学生選抜を結成し、1~2月に東京で集客試合を行う。今、そのために格闘しているのだが、うまい具合に進まないことも多く、そのたびに落ち込んでいる。
そんなとき、僕は羽生結弦を思い出す。彼は冒頭のジャンプで失敗してしまった後、どんな気持ちで滑っていたんだろう。本当は泣きたいのに、無理やり笑顔を浮かべながら、必死こい…必死に戦っていたのだろうか。それとも、何があっても冷静に喜怒哀楽をコントロールしていたのか。僕はこれから羽生結弦のように、何があっても強い心を持って戦うことができるのだろうか、と。
今年の冬、前回に続いてグランプリ・ファイナルに羽生の姿はない。今、彼は痛めた足を抱え、自分との戦いを続けているだろう。アイスホッケーを仕事にしたことに後悔はない。でも、今の気持ちを、苦しみと向き合っている今の気持ちを羽生に直接、聞いてみたい。そんなことを考えながら僕は、今年のグランプリ・ファイナルをテレビで見るんだと思う。
アイススポーツジャパン代表 山口真一
<フィギュアスケートマガジン>
コラムページリンク
0 notes
Text
Yours forever
勇利は幼いころ、ヴィクトルと会ったことがある。遠くから見かけたというようなかるいものではなく、きちんと対面し、言葉を交わし、ほほえみあって親しくふるまったのだ。ヴィクトルはその逢瀬を「デート」だと表現した。そのころ勇利はデートというなりゆきの特別性なんてまるでわかっていなかったのだけれど、ヴィクトルのその物言いと優しいまなざしには苦しいほどのときめかしさをおぼえ、それから数日はよくねむれなかった。いまでも、そのおりのことをベッドに入ってから思い出せば目が冴えてしまう。勇利にとってあれは、いつまでも色褪せることのない、あざやかですてきな記憶なのだ。 ヴィクトル自身は、もうおぼえていないだろうけれど……。 そのとき勇利はジュニアの選手だった。ヴィクトルはシニアで戦っていたが、まだ髪が長いころだ。あのうつくしい髪をなびかせて氷上で舞うヴィクトルに、勇利はどれほどあこがれたか知れない。ヴィクトルの映像を見てはまねをしてすべり、ヴィクトルならこう、ヴィクトルはもっとジャンプが高い、と彼みたいになりたくて一生懸命だった。あこがれるあまり髪も伸ばしていたし、ようやく結わえられるようになったそれを後ろでちょこんとまとめてすべっていると、ヴィクトルと同じだ、と思えてうれしかった。まだそれほどの長さではないため、激しく踊ればみだれてきて、いくすじも落ちかかってしまうのが悩みの種だったけれど、でも切ってしまおうとは思わなかった。 ヴィクトルの試合をこの目で見たい、といつもねがっていた。画面の中ではなく、すぐそこにいる彼を感じたい。きっとヴィクトルはテレビで見るよりずっと速度があって、もっと迫力のある演技をするのだろう。どうしても彼の演技を同じ空間で見たい、と勇利は、苦しいほどに切望していた。 毎日ねがいをかけたから、神様が聞き入れてくれたのか、勇利は思ったより早くその機会に恵まれた。関係者として観戦してよいとスケート連盟から許可されたのである。グランプリシリーズだったのか、世界選手権だったのか、よくおぼえていない。ヴィクトルに会える、ということがあまりにうれしく、こまかなことは記憶から抜け落ちているのである。 演技のあとは、もちろん花を投げ入れるつもりだった。それから、できれば手紙も渡したい。しかし、花束にまぎれこませることは考えなかった。ヴィクトルに絶対に読んでもらいたいけれど、ヴィクトル以外には読まれたくない。ヴィクトルが贈られる花の数は尋常ではない。そんな中から勇利の手紙をまちがいなく彼が抜き取ってくれるなんて、そんなことがあるはずがないと、勇利は断定していたのである。しかし、手紙は書いた。もしかしたら、廊下で偶然会えるかもしれないではないか。そのときになって、何も持っていないと悔やんでも遅い。できることはしておかなければ。 だが勇利は、そこまでの幸運が起こるはずがないということもまたわかっていた。ヴィクトルの演技を間近で見られるだけでもすばらしいことなのだ。そんな偶然まで神様が気遣ってくれるはずがない。けれど、想像するのは自由だ。勇利は幾度も、勇利が差し出した手紙をヴィクトルが受け取り、「どうもありがとう。とてもうれしいよ」と礼を述べてくれるのを思い浮かべ、しあわせを味わった。 東京の会場まで行き、関係者席で勇利はヴィクトルの演技を見た。付き添いは誰もいなかった。許可証は首からさげているし、いつも自分が試合に出るときみたいにふるまえばよいのだとわかっていたので、不安はいっさいなかった。そんなことより、ヴィクトルを見られる、ということで勇利は興奮していた。ヴィクトルの演技はすばらしく、優美で、華麗で、勇利はすっかり感激してしまった。いままで、きっと生で見られたらこんなふうなんだろうな、と思案をめぐらせたどんな演技より、彼は麗しかった。見ていて泣いてしまったので、まわりの人たちに「大丈夫?」と心配されたほどだった。 ショートプログラムが終わると、あまりに胸が苦しくて何も喉を通らず、勇利はホテルに帰って早々に寝てしまった。夢でヴィクトルと会った。勇利は目を輝かせて言うのだ。 「今日のショート、すっごくすっごくすてきでした!」 「そう? どうもありがとう」 ヴィクトルはにっこり笑ってうなずく。 「見てくれたんだね。うれしいな。勇利のためにすべったんだよ」 「ほ、本当?」 「本当……」 ヴィクトルは優しい瞳をして勇利の髪にふれ、 「黒くて綺麗な髪だね。俺みたいに伸ばすの?」 とささやいた。勇利がまっかになって答えられずにいると、ヴィクトルは身をかがめて、勇利のくちびるに──。 「わっ」 勇利はぱっと目を開けた。カーテンの隙間からきらきら��ひかりが差しこんでいる。もう朝か、と身体を起こしたが、胸がどきどきしていて頬が熱かった。 ぼ、ぼく、ヴィクトルとちゅーしそうだった……。 頬に手を当ててうつむく。どうして? そんなふうに一度も考えたことないのに。キスって恋人同士がするものだ。ぼく、ヴィクトルと恋人になりたいのかな。──ヴィクトルと恋人? 「むりむりむりむり!」 なれるとかなれないとかいうことより、そんな次第になったら心臓がいくつあっても足りない。絶対にできない。 「……まあ、心配しなくてもそんなことは起こらないけど」 勇利は息をついた。でも、恋人にはなれなくても、まだフリーの演技がある。そのことを考えると、胸が痛くなるくらいどきどきした。 一日おいて、フリースケーティング当日、勇利は朝から緊張しきっていた。自分の試合より緊張してるかも、と思った。ヴィクトルのフリーを見られる。あのフリー。シーズン当初からみつめてきたプログラムを思い浮かべる。あれが目の前で起こるなんてうそみたいだ。夢のよう……。これは夢じゃありませんように、と勇利はいくたびも吐息をついた。ずっと顔はまっかで、気持ちが高揚していた。 フリースケーティングでのヴィクトルの演技のあと、勇利は席から動けなかった。感動して泣いたし、泣きすぎて頭が痛いし、朝から興奮していて気持ちが疲れていたし、遠出をしてきたことで身体にも疲労があったし、ほとんど何も食べずにいたので、とにかく力が出なかったのだ。ずいぶんと時間が経って、人がだいぶいなくなってから、勇利はよろよろと立ち上がった。帰らなくちゃ、と廊下を歩いていった。でも気持ち悪い。吐き気かな。ちがう気がする。貧血かも。視界が暗い。ここ、もっと明るかったはずだけど。なんだかもやがかかったみたいで……。 「あぶない!」 突然後ろから腕が伸びてきて支えられ、勇利はびくっとして身体をかたくした。 「大丈夫? ふらふらしてると転んじゃうよ」 ものすごくいい匂いがした。すこしだけ汗の匂いが混じっている。選手かな、迷惑かけちゃった、と振り返った勇利は、きらきらと輝く銀髪と、おそろしいほどに整った面立ちを見て息をのんだ。──ヴィクトル。 「どこの子? ジュニアの選手かな?」 ヴィクトルは勇利の着ているナショナルジャージを見てほほえんだ。 「ああ、ジャパン。地元の選手だね」 「…………」 「後ろから見てたら、なんだか足元がおぼつかないみたいだったけど、平気? もしかして具合が悪い?」 「…………」 「誰か一緒に来た人はいないのかい?」 「…………」 「ねえきみ、聞いてる? 英語わかんないのかな……」 ヴィクトルが困ったように髪を後ろへ払った。英語はちゃんとわかっていた。いつかヴィクトルと話したい、と思うようになってから、一生懸命勉強したのだ。ヴィクトルは意識してか、ゆっくりと発音してくれるので、聞き取りやすく、言っていることはすべてわかった。にもかかわらず、勇利は返事ができなかった。口をひらいたら涙がこぼれてしまいそうだったのである。ヴィクトル。ヴィクトルだ。本物のヴィクトル・ニキフォロフ……。 「困ったなあ……」 ヴィクトルがつぶやいた。勇利ははっと我に返り、背負っていたかばんを急いで下ろした。ヴィクトルが目をまるくする。 「あっ、あの、あのあのあのあの、ヴィクトルっ……」 中から、一生懸命書いた手紙を取り出した。ヴィクトルの瞳みたい、と思って選んだすてきな色の封筒だ。 「ぼ、ぼく、ぼくファンですっ……」 勇利は深くつむりを下げ、両手で捧げ持つようにして手紙を差し出した。 「大好きです! 大好き……!」 「…………」 ヴィクトルは何も言わなかった。勇利はぎゅっとまぶたを閉じていた。早く何か言ってよ、と思い、もしかして頭のおかしい子と思われたのかな、と不安になった。どうしよう、変なやつがいるって警備員呼ばれたら……。 「……ありがとう」 すっと手から封筒が抜き取られた。勇利はぱっとおもてを上げる。ヴィクトルは片目を閉じ、くちびるに指を当ててにっこりした。 「日本にこんなにかわいいファンがいたなんて、感激だね。うれしいよ」 「あ……」 「いつか大会で会えるといいね」 かあ、と勇利の顔がまっかになった。勇利はぺこんとお辞儀をすると、「さ、さよなら!」と叫んでいきなり駆け出した。ヴィクトルのもとから逃げ出したのである。ものすごく失礼なことしちゃった、と気づいて落ちこむのは、ホテルの自室に戻ってからだった。 「ああ……ヴィクトル、おかしなやつだと思っただろうなあ……ヴィクトルはファンには優しいからそんなこと口には出さないけど、内心では不審者扱いしてたかもしれない……」 勇利はその夜、疲れからすぐ眠ってしまったが、うれしいのにかなしくて、浮かれているのに落ちこんでいて、奇妙なこころもちだった。目ざめると目元が引きつっていたので、寝ているあいだに泣いたのだろう。 しかし、そんな失敗はあったけれど、勇利にとってはやはり夢のようなひとときだった。ヴィクトルのあの優美な演技を見ることができ、当人にも会えたのである。ほほえみかけてさえもらえた。勇利は長谷津へ帰ってから、そのときのことを思い出してはひとりで赤くなり、ヴィクトル、大好き、大好き、と思って上機嫌で過ごした。ときおり、礼を失してしまった、と��うことがこころに強く浮かび上がってき、そのときはしょんぼりした。浮かれたりしゅんとしたり忙しかった。 それが届いたのは、勇利がまた「ヴィクトルに向かってあんなことして……」と沈みこんでいるときだった。 リンクへは、学校から直接かよっている。だから勇利が帰宅するのは夜遅くなってからだ。部屋へ入り、おなかすいたな、とかばんを下ろしたとき、机の上に封筒が置いてあるのに気がついた。 「なんだこれ……」 手紙をもらうことなんてまずない。ファンレターは届くことがあるけれど、それは自宅へは来ず、スケート連盟からまとめて受け取るのである。いったい誰からだろう? 取り上げると、エアメールだった。海外のスケート友達かな、でもそんなに親しい人いないしな、そもそも住所知ってるスケーターなんていないし……。 差出人の名を見た瞬間、勇利は目をみひらき、全身から力が抜けた気がした。実際、彼はその場にへたりこんだ。力が入らず、立っていられなかったのだ。信じられない。差出人の名前はこうだった。Victor NIKIFOROV。 勇利の頭は混乱した。なんで? なんで? なんでヴィクトルが? どうしてぼくのうち知ってるの? 手紙を持つ手がふるえた。一生懸命思い起こす。そうだ。ヴィクトルは知っている。書いたではないか。手紙に。べつに返事を期待してのことではない。ただ、どこの誰ともわからない相手から手紙なんてもらったら気持ち悪いのではないかと、そう考えてのことだった。まさか返事をくれるなんて。なんで? どうして? 勇利は封を切ることができなかった。三日ほど、何かのまちがいではないか、と思ってそのままにしていた。しかし四日目に、もしかしたら消えてしまうんじゃないか、夢かもしれないから、目がさめる前に読まなくちゃもったいないんじゃないか、と気がついて、やっぱりふるえる手でようやく開封した。中身は丁寧な文字で書かれた、礼儀正しい返信だった。手紙をありがとう、うれしく読みました、すてきな言葉ばかりでした、という短い文句だったけれど、お愛想で書いたのではなく、まじめに、こころをこめて綴っていることがよくわかる文章だった。それから、きみのことを教えて、ということが最後に付け加えてあった。勇利は仰天した。これって、ぼくがまたヴィクトルに手紙を書いていいってことなの? ちゃんとヴィクトルの所在が記してある。スケートクラブの住所のようだが、それでも勇利は感激した。 これで書かなかったら失礼だよね? でも本当に書いてもいいのかな。社交辞令だったのにまた手紙を送ってきた、っていやがられたらどうしよう。ストーカー扱いされちゃったら? ──でもヴィクトルはそんなこと思うひとじゃない。優しいもの……。だけどだけど、ヴィクトルにはファンがたくさんいるんだ。その中でぼくだけ特別扱いしてくれるはずないから、やっぱりこれは送ったりしたらずうずうしいのかもしれない。 勇利は悩みに悩み、結局、返事を書いた。いろいろ考えながら書いたので、二週間もかかってしまった。そしてまた、出すまでに二週間かかった。本当に送ってもよいのか、と苦しんだ。最終的には、迷惑ならヴィクトルは無視するだろうから大丈夫、と自分に言い聞かせて実行した。そのあとしばらくは落ち着かなかったけれど、だんだんと、あれはヴィクトルの気まぐれだったのかもしれない、と思えて気持ちが静まってきた。雑誌などで見るヴィクトルは奔放な性質のようである。たまたま何かのはずみで勇利のことを思い出して、なんとなく手紙を送ってみたのだろう。そうにきまっている。 勇利はヴィクトルからの手紙をおまもりとしてずっと持ち歩いた。試合のときも、それがあると元気になれる気がした。しかしだからといって緊張しないわけではなく、失敗したときは、ふとんの中で手紙と愛犬のヴィクトルを抱きしめて泣いた。そんな日々をくり返していると──、また、エアメールが届いた。 さすがにこのほどは、ヴィクトルからかもしれない、という期待を持って確かめた。まさにその通りだった。すぐに読んだ。文面は、楽しい手紙をありがとう、きみのことを知られてうれしい、ということと、俺のことも話すね、とヴィクトルについて書かれたものだった。勇利は、これは本当に現実なのだろうかとしばし悩んだ。ぼく、ヴィクトルと文通してる。ほんとに? 最初はおずおずと、やがてはすこしは落ち着いて、勇利はヴィクトルと手紙のやりとりをした。どうしてこんなことをしてくれるのかはよくわからなかった。ファンサービスの一環だろうと想像したけれど、ヴィクトルには何千何万というファンがいるのである。その全員と文通するわけにはいかない。勇利とだけこんなことをしてくれる理由は思い当たらない。しかし、そのことを彼は口に出さなかった。尋ねて、そのせいで「そろそろやめよう」と言われたらかなしい。ときおり、これはヴィクトルではなく、彼以外の誰かがいたずらで勇利の相手をしているのではないかと思うこともあったが、手紙で言ってくることと、インタビューに答える彼の言葉とは確かに重なっており、勇利にはどうしても別人に思えないのだった。 まことにしあわせな日々だった。ヴィクトルからの手紙は、返事を出したすぐあとに来ることもあったし、二ヶ月も間が空くこともあった。しかし、いつでも彼は陽気な文句で勇利を元気づけ、楽しませる。勇利は郵便受けをのぞくのが楽しみだった。中にエアメールを発見すると、たちまち異様なほど動悸がし、胸が躍る。彼は急いで二階へ駆け上がって、大急ぎで封を切るのだ。最初は正座をして、精神を落ち着かせて、とやっていたのだけれど、すぐにそんなとりつくろいはできなくなってしまった。勇利はヴィクトルからの手紙を受け取り、それに返事を書くたび、彼への愛情がどんどん深くなるのを感じた。 けれど──、そのうち勇利は、違和感をおぼえるようになった。いや、もともとそんな気はしていたのだけれど、ヴィクトルと文通できることがうれしく、そのことばかりに気持ちが向いていたので、なかなかみとめられなかったのだ。だが、それはだんだんと色濃く、不安な疑いとなって勇利のこころに影を落とした。勇利の心配はこういうことだ。つまり──。 ヴィクトルは、勇利のことを女の子だと思っているのではないか? 普通では考えられないことだった。ヴィクトルは勇利と直接会っているのである。けれど、彼はロシア人だ。日本人を見慣れているわけではない。海外の人から見ると、東洋人はひどく幼く思えるというし、勇利くらいの年頃の者なら、男女の区別がつかないかもしれない、という気がした。それに勇利は、ずっと髪を伸ばしているのだ。後ろ髪を結わえている子がいたら、普通、人は女の子だと思うだろう。何よりも、「勇利」という名前。英語表記すると「Yuri」だ。もしかしたらヴィクトルは「ユリ」と読んでいるかもしれない。ロシア人の彼が、日本の名前で男女の区別がつくかどうかは難しいところだが、そんなことは調べればすぐにわかる。 ヴィクトルは手紙によく、「髪はどのくらい伸びた?」とか「勇利は華奢だから」とか「試合会場で人に声をかけられても、簡単についていっちゃいけないよ」とか、そういうことを書いてくる。男子を相手にそんな話をするだろうか? それに──、ヴィクトルがこうして勇利と文通しているという事実。最初から変だと思ってはいたのだ。ヴィクトルはあのとき、勇利を女の子だと思い、好きになってしまったのではないだろうか。あのヴィクトル・ニキフォロフが、とは思うけれど、そんなことを言えば、あのヴィクトル・ニキフォロフが名もないスケーターである勇利と文通しているという事実がすでにおかしいのである。たいしたことのない男子と仲よくしたがっていると考えるよりは、女子として好きになってしまったのだと受け止めるほうがまだしも実際的ではないだろうか。人の好みはわからない。勇利はごく普通の容貌をしているが、ロシア人の彼から見れば何か珍しいものがあったのかもしれない。 「ど、どうしよう」 勇利は悩んだ。ぼく女の子じゃないです、と伝えるべきか。でも、そんな話題になっていないのに、いきなりそういう話をするのも妙だ。それに、もしそう告白して、「あ、そうなんだ。がっかりだな。じゃあもう文通はやめよう」と言われたらどうする? 女の子じゃないなら興味はないと言われたら? 「あ……」 ヴィクトルと手紙の交換ができなくなる。そう思っただけで勇利の目にはいっぱいに涙が溜まり、あっという間に頬にこぼれ落ちた。いやだ。ヴィクトルと離れてしまうなんていやだ。かなしい。そんなこと、耐えられない……。 勇利は結局、ぼくは男子です、と言えないままヴィクトルとの交流を続けた。常に罪悪感がつきまとい、苦しかった。でも、うそはついていない。勇利は一度も「ぼく女の子です」なんて言ってはいない。 「ぼくはヴィクトルを騙してるわけじゃないんだ。騙してないんだ……」 それでも勇利はせつなかった。 夏は合宿の時期だ。勇利も去年は国内の合宿に参加した。シニアの選手に混じって練習したのだ。それはひどく刺激的で、すばらしい時間だった。今年もそういう合宿に行きたいものだと思案していたら、スケート連盟から国外の合宿練習に参加しないかという通知が来た。その内容を見て勇利は仰天した。行き先はロシアだ。ヴィクトルのいるクラブだったのだ。 勇利はひどく迷った。ヴィクトルに会いたい。しかし、会えば男子だということが露見してしまう。だが、この機会を逃すのはたいへんもったいない。甚だしく有名なクラブなのだ。練習に参加できる機会なんてもうないかもしれない。どれほどそれが自分の力になることか。あきらめてしまうのは惜しい。 結局勇利は、その提案を承諾した。そもそも、ヴィクトルは世界の頂点にいる選手なのだ。ジュニアの選手が参加するような練習に来るはずがない。会えるわけがないのである。それなら、ヴィクトルのことは頭から無理にでも追い出して、ただ稽古に没頭するのがいい。 そのあとも一度手紙のやりとりをしたけれど、ロシアに行くことを、勇利はヴィクトルにはひと��とも漏らさなかった。合宿に行くということだけは書き送ったが、そんなことは誰にでもある話なので真実がヴィクトルに伝わるわけがない。 勇利はロシアへ、練習と、ヴィクトルがいる場所だという感激のためにおもむくことにした。 チムピオーンスポーツクラブの練習は、それはそれは厳しかった。まず、バレエのレッスンが過酷だ。勇利は最初、ついていけないのではないかと動揺した。ミナコのもとでしごかれた時間を思い出し、どうにかこうにか乗り切りはしたけれど、ひどく疲れてしまった。こんなことで明日からやっていけるのだろうかと泣きたくなった。しかし、二日、三日と経つうちに、環境に慣れ、緊張もほぐれ、ずいぶんと自然にふるまえるようになった。落ち着けばできるんだ、と思うとゆとりが生じ、コーチに実りのある助言をしてもらえた。するとだんだん楽しくなる。勇利は夢中で練習をした。 氷の上に立つと、まわりにいるすべての選手が自分より上手に思える。とくにロシアの選手はすばらしい。まず、もう見ただけでいかにもすべれそうだし、観察していると実際よい動きをしているし、容貌もたいへん大人びているのだ。この人はシニア選手なのでは、と思った相手と口を利いたとき、おずおずと年齢を尋ねてみたら、勇利よりみっつも年下だった。勇利は落ちこんだ。相手の男子にも、「ノービスの子にしては上手だね?」と言われたのでますますしょんぼりした。 「あと、君は女子じゃないの?」 「ぼく男だよ……」 「そう。かわいい顔だし、髪が長いから……」 「これはヴィクトルにあこがれてるから、まねして……」 「ああ、そういう子多いよね。わかる」 「あの……、ヴィクトルに会ったことある?」 「ないよ。もちろん遠くから見かけたことはあるけど」 「そっか」 やっぱりここで練習していてもヴィクトルには会えないんだな。ほっとしたような、がっかりしたような、奇妙なこころもちだった。それにしても、やはり勇利は女の子に見えてしまうらしい。衝撃だ。髪、切っちゃおうかな。でもせっかく肩まで伸びたのに。だけど、ヴィクトルみたいに綺麗じゃないからな……。 合宿の日々はあっという間に過ぎた。最終日には、ヴィクトル・ニキフォロフの演技を見せてもらえることになり、幼いスケーターたちは歓声を上げた。勇利も顔を輝かせて手を叩いた。 ヴィクトルは、昨季のフリースケーティングを演じてくれた。髪を結わず、そのままさらっと下ろしてすべった。勇利はけっして前には行かず、みんなの後ろのほうでちいさくなっていたが、近いとか遠いとかは関係がなかった。彼は両手を握り合わせ、瞳を星のように輝かせて、うっとりしながらヴィクトルをみつめていた。恍惚の時間だった。とろりととろけた彼の表情は、ここにいる誰よりもヴィクトルに恋をしているようだった。目の表面は陶酔にうるおい、くちびるはわずかにひらいてほほえみのかたちになって、視線は常にヴィクトルに釘付けだった。 もう、死んでもいい……。 そう思えるほど勇利は感激した。 演技が終わると泣き出し��しまい、彼は、勇利を女子とまちがえたあのロシアの選手にからかわれた。 明日は日本へ帰る日だ。勇利はその夜、一生懸命に荷造りをしていた。どうにかトランクに必要なものを詰めこんでしまうと、もう大丈夫だろうかと部屋の中をひとわたり調べた。忘れ物はないようだ。 勇利が泊まっていたのは、クラブ所有の寮だった。本当はふたり部屋なのだけれど、参加者の数が奇数だったのでひとりあまり、勇利は悠々と部屋を使うことができた。これは幸運だった。彼は人との付き合いが苦手なのである。もしふたり部屋だったら、もっと憂鬱な毎日になっていたかもしれない。 時計を見た。そろそろ夕食の時刻だ。食堂へ行こうかな、と思ったとき、ノックの音がした。勇利は困惑した。ほかの選手が食事に誘いに来たのかと思ったのだ。いやではないのだけれど、気を遣うので困るなあ、とためらった。しかし、ごそごそと動きまわっていたので、部屋にいることはわかっているだろう。無視するわけにもいかない。 「はい……」 勇利は扉を開けた。そして息をのんだ。目の前ににこにこしながら立っているのは、ヴィクトル・ニキフォロフだったのだ。 「ハイ」 彼は笑顔で手を上げた。 「久しぶりだね、かわいこちゃん。どうしてここへ来るって教えてくれなかったの? 知ってたら、最初の日から連れ出して、いろいろ案内してあげたのに」 「あ、あ、あ、あの、あの……」 「さあおいで。明日帰るんだね。さびしいな。今夜は忘れられない夜にしてあげる」 「あのっ……」 口も利けない勇利を、ヴィクトルは部屋から連れ出した。 「ヴィ、ヴィクトル……!」 「ほらこっち。ごはんに連れてってあげる。外へなんか出てないんだろう? デートしよう」 手を引かれながら、勇利は、果たしてこれは現実だろうかと思い惑った。ヴィクトルがぼくと手をつないでる。こんな異国の地で! すべてが非現実的で、夢のようだ。 「ヴィクトル……」 つぶやいたのはささやかな声だった。しかしヴィクトルは聞こえたかのように振り返り、いたずらっぽく勇利に笑いかけた。きらめく髪。深く澄んだすばらしく青い瞳。勇利の手をつかむしなやかで長い指。本物のヴィクトル・ニキフォロフだ。 「何が食べたい?」 ヴィクトルが気軽に尋ねた。 「ぼ、ぼく、なんでも……」 実際、胸がいっぱいで、何も喉を通りそうになかった。ヴィクトルは微笑して勇利の手を握り直し、表通りへ出たところで足をゆるめた。夏という季節でも、夜ともなれば寒さを感じることも多い。ロシアの夏は白夜のため明るいが、気温は日本のように高めというわけにはいかない。おまけにこの日はひどく曇っており、いまにも雨が降り出しそうという天候だった。 「寒い?」 ぶるっとふるえた勇利を見て、ヴィクトルが心配した。 「そのままぐいぐい引いてきちゃったからな……、これを着て」 ヴィクトルが、彼しか着こなせないような上品な上着を脱いで勇利に着せかけた。勇利はびっくりして、「い、いいです!」と拒絶した。 「でも、寒いんだろ?」 「大丈夫です」 「風邪をひかせるわけにはいかないよ」 「そんなの、ぼくだってヴィクトルに風邪をひかせるわけにはいきません。ぼくよりずっと貴重なひとなのに……」 ヴィクトルは目をまるくし、にっこり笑うと、身をかがめて勇利の耳元にささやきかけた。 「いいから、着て……」 勇利は断固として拒否するつもりでいたのに、そのひみつめかした声音と吐息で、もうわけがわから��くなった。 「は、はい……」 彼は打って変わって従順にヴィクトルの言うことを聞き、服に腕を通した。すてきな匂いがした。胸がどきどきと高鳴り、頬が熱くなる。ヴィクトルだ、といまさらながらに思った。 すると周囲から、同じようにヴィクトルだ、ヴィクトルだ、という声が聞こえた。ロシア語だったけれどわかる。ヴィーチャ、という声も聞こえた。勇利はうつむいた。ヴィクトルは、サインが欲しいと言ってきた女の子たちに笑顔で応じ、話しかけられるのにも優しく答えた。彼女らは、勇利のほうをちらと見て、何なのこの子、というような目をした。勇利は泣きたくなった。彼女たちがこわいというより、ヴィクトルのそばにいるのがこわい。この女の子たちの気持ちは理解できる。自分だって、よくわからない子どもがヴィクトルにぴったりくっついていたら、いったいどういう子だろう、と思うはずだ。自分なんかが一緒にいてよい相手ではないのだ。 「あ、この子?」 しかしヴィクトルは明るい様子で笑い、勇利のことを抱き寄せた。 「俺のすごく大事な子なんだ。日本人なんだよ。かわいいでしょ? ジュニアの世界大会に出てくる子だから、注目しててね」 「ヴィ、ヴィクトル!」 ヴィクトルはそれを英語で言ったので、勇利は仰天しておもてを上げた。女の子たちは、聞き取れなかったのかきょとんとしている。するとヴィクトルはロシア語で言い直した。勇利はまっかになった。あきらかに、勇利に聞かせるために言ったのだ。勇利がせつない思いをしているのに気がついて……。 「俺、目立つね」 ヴィクトルはファンたちが去るとほほえんだ。 「そういうの、嫌いじゃないんだけど、いまは困るな……」 「あの、ぼく、もう……」 「外で食べるのはよそう」 ヴィクトルはもっともらしくうなずいた。 「持ち帰ってきみの部屋で食べようよ。ほらおいで」 ヴィクトルは時間がもったいないと言い、近くの店にさっさと入ると、夕食にできそうなものを次々と買いこんだ。 「特別に美味しいものを食べさせてあげたいけど、今日はゆとりがない。それはまた今度ね」 「…………」 「まったく、もっと早くに言ってくれればいいのに。俺は今日きみがいることに気づいたんだぞ。どういうことなんだ?」 ヴィクトルはぶつぶつ言っている。あんなにすみのほうにいたのに、こんなに冴えない容貌なのに、ヴィクトルは勇利に気がついたというのだろうか。だって、たった一回会ったきりだ。 やっぱり「好きな女の子」のことだからわかったのかな……。勇利はずきりと胸が痛んだ。どうしよう。いまきっとヴィクトルは、ぼくのこと女の子だと思ってるんだ……。 うつむいて、無造作に結った髪にそっとふれる。前髪が眼鏡にかかった。ぼくこんなにみっともない。もうちょっと綺麗にしておけばよかった……。 「どうしたの?」 ヴィクトルが不思議そうに尋ねる。 「そんなにうつむかないで。かわいい顔なんだから、俺に見せて」 「あ……」 ヴィクトルの指がおとがいをすくい上げた。勇利は首をもたげ、ヴィクトルと目が合った瞬間、頬をまっかにした。 「うん、かわいい」 ヴィクトルが目をほそめる。 「美味しそうだね」 「ど、どれがですか?」 ちゃんと話をしようと、ヴィクトルの買ったものに視線を向ける。ヴィクトルはくすくす笑うばかりだった。 外へ出ると、雨が降っていた。ヴィクトルは店に戻り、何か声をかけて傘を借りた。 「店主と知り合いなんだ。さ、こっちおいで」 傘からはみ出さぬよう、勇利を抱き寄せて入れてくれる。勇利は同じほうの手と足が一緒に前に出そうだった。 「風が強くなってきたね。寒いかな?」 「いえ、平気です。上着貸してくれたから……」 「きみはジャージなんだね。普通の服持ってないの?」 「あんまり持ってきてません……練習しに来たんだし……」 「それはそうだけどね。部屋着もジャージっていうのは感心しないなあ。でもジャパンナショナルのジャージは変なデザインじゃなくてよかったよ」 「そ、そうですね」 勇利はよくわからなかったけれど、とにかくうんうんとうなずいてあいづちを打った。ヴィクトルがくすっと笑う。 「いまのきみって、なんでも俺の言う通りって感じだね。ノーと言えるようにならなきゃだめだぞ」 「え?」 「日本人はそうだからなあ。でも、好意は感じてるよ。きみは俺のことが好きだよね?」 「え? え?」 勇利は首まで赤くなった。 「ね?」 瞳をのぞきこまれ、片目を閉じられてはどうしようもない。勇利は夢見ごこちでこっくりとうなずいた。 「そうだろう」 ヴィクトルが満足げに目をほそめる。勇利の足元がふらつく。 「おっとあぶない」 ヴィクトルは勇利をより強く抱き寄せた。 「早く帰ろう」 「はい……」 「早くふたりきりになろう」 勇利はうつむいた。本当のことを言わなくちゃ。ぼくは男の子なんだって……。 しかし何も言えないまま勇利は寮まで導かれ、ヴィクトルはまるで自分の部屋にでも案内するかのように勇利の私室へ入りこんだ。ちいさなテーブルでささやかな夕食をとる。勇利は胸の苦しさとうっとりした気持ちとで感情が定まらず、混乱していた。 「このピロシキ、美味しいよ。俺がいつも食べてるやつ」 「はい……」 「あとはボルシチと、サラダと、チキンと、パイと……食べられないものはある? いまさら訊いても遅いね」 「はい……」 勇利は何も食べられないと思ったが、ヴィクトルが美味しそうに食事をしているのを見ると、それに釣られ、どうにか口を動かすことができた。ヴィクトルがぼくのために選んでくれたんだ、と思えば、味もちゃんとわかるようになった。 「ね、なんで言ってくれなかったんだい?」 ヴィクトルがおおげさに眉を寄せて勇利をとがめる。 「前の手紙のときには、もうこの合宿のことはきまってたんだろう?」 「あの……、ヴィクトルに会えるかわからなかったし……」 「言ってくれたら会えるようにしたよ」 「それならなおさら言えないし……」 「なぜ?」 「なぜって……」 勇利は困った。 「すべりながら、なんだか見たことある子がいるなあって思ったんだ。まさかってあとで急いで名簿を確認した。きみの名前があった。思わずそばにいたヤコフを締め上げちゃったよ」 「な、なんで」 「なんでって?」 「なんでそんな、ぼくのこと……」 「そんなの、会いたかったからにきまってるだろう?」 ヴィクトルは、何を言っているんだこの子は、というように勇利を眺め、口元についたドレッシングを舐め取った。 「きみは俺に会いたくなかったの?」 「そんなことは、ないですけど……」 でもぼく女の子じゃないし……。勇利は泣きたくなった。 「ねえ、ところで」 ヴィクトルがふいに声をひそめ、勇利の目をのぞきこむ。勇利はどぎまぎした。 「あの、やたらときみに話しかけてたロシアの男子」 「え?」 「友達になったのかい? 彼のことが好きなの?」 「え、ええっと」 勇利は、誰のことについて言われているのかよくわからなかった。ただ、ヴィクトルの指摘していることはちがう、という気持ちだけはあったので、大きくぶんぶんとかぶりを振り、否定した。 「ぼくが好きなのは、ヴィクトルです……」 ヴィクトルは目をまるくした。それから彼はにっこり笑い、「そうだよね」と大きくうなずいた。 食事を終えると、ふたりは並んでベッドに座った。ヴィクトルが陽気にいろいろな話をしてくれたけれど、勇利は緊張と不安と申し訳なさで上手く返事ができず、終始上の空だった。 「どうしたの?」 「なんでもないです……」 「さっきからこのやりとり、五回はくり返してるけど。もしかして、俺といるの、つまらない?」 「そんなことない!」 むきになって言い張ったら、ヴィクトルがくすっと笑い、勇利の頬にかるくキスした。勇利はそこを思わず押さえ、まっかになってヴィクトルをみつめた。 「きみって本当にかわいいね」 ヴィクトルが歌うように言った。 「初めて会ったときから、そうやって何かを秘めた目で俺を見るんだ。どうしてそんな忘れられない目をするの?」 彼の言っていることが、勇利にはよくわからなかった。ただ、頬に手を添えてぼんやりしていた。 「言ってくれればよかったのに。そうしたら俺、きみと一緒にすべれたのにな」 ヴィクトルはふいに勇利を抱きしめ、甘やかな吐息を漏らしてうっとりとささやいた。 「でも、帰る前にすこしでも会えたのは幸運だ。気がつけてよかった。知ってた? みんなの前でした演技、あれはきみに見せるためだったんだよ。ほかの子たちには悪いけど」 勇利の頭はぼうっとなり、なんだか上手くものが考えられなかった。ヴィクトルの匂いがする。髪が頬に当たってくすぐったい。 「この気持ちは何なんだろうな……よくわからないけど……」 ヴィクトルが溜息をついてつぶやいた。 「大人になったらわかるんだろうか……」 「……ヴィクトルは、もう大人じゃないの?」 「俺はまだ子どもだよ」 ヴィクトルがかすかに笑った。 「まだまだ子ども……、自分の考えていることも理解できない、どうしようもない幼子だ」 こんなにすてきなのに、と勇利は思った。ヴィクトルが子どもだなんて、そんなこと、あるはずがない……。 「……教えてくれる?」 ヴィクトルは勇利の瞳をじっとのぞきこみ、その奥にある感情をすくい上げようとでもするかのように熱心にみつめた。 「……何を……?」 勇利は熱に浮かされたように答えた。 「俺のいまのこの……」 「……?」 「…………」 ヴィクトルは苦笑を浮かべた。彼は勇利のとろんとなったまぶたにかるくキスすると、後ろへ手をやり、結わえていた髪をするっとほどいた。やわらかく勇利の髪が落ちて、それにヴィク��ルの指がからんだ。 「……髪、伸びたね」 「……はい」 「かわいいな……」 勇利は胸が痛くなった。言わなくちゃ。言わなくちゃ、女の子じゃないって。ヴィクトルが好きって思う気持ちはまちがいなんだって……、言わなくちゃ。 「ああ、なんだかいい気持ちになってきた」 ヴィクトルがはにかんだように笑って首を傾けた。 「きみといるからかな……すごくどきどきしてるよ。これはいったいどうしたことだろうね」 勇利はうつむいた。こんなふうに幸福そうにしているヴィクトルに、その幸福を打ち破ることを告げるなんて、勇利にはとうていできないことだった。 「ね、今日はここで一緒に寝よう」 ヴィクトルが指を一本立て、うれしそうに提案した。 「いいだろ?」 「え、えと……」 「いいんだよ。ほら、そっちへつめて」 「え、もう……?」 「まだ起きてたい?」 ヴィクトルがくすっと笑った。 「起きてて、俺と何したいの……?」 「な、何って……」 勇利はよくわからない気恥ずかしさがこみ上げ、まっかになった。 「きみはいまいくつだっけ? どうも日本人は子どもっぽくて。でも、そうだな、十代なかばならできないこともないけど……」 「な、何が?」 「でも……、ちょっと早いかもね」 ヴィクトルが片目を閉じた。 「きみも、……俺もね」 彼はうつくしい横顔を見せ、憂いを帯びた表情でつぶやいた。 「この気持ちの正体がわかるまでは、まだ……」 「?……」 彼は落ちかかる髪をゆっくりとすくい上げ、耳にかけた。たったそれだけのしぐさなのに、勇利はものすごくどきどきして見ていられなくなってしまった。これが色っぽいということなのだな、と初めてよく理解した。 「そういうのは、大人になってからしようね」 ヴィクトルがぱっと振り返り、すこしだけはにかんで明るく言った。勇利はわからないながらも、ヴィクトルの言うことはなんでもその通りにしたかったので、「はい」と素直に答えた。 ふたりしてベッドに横になり、するとヴィクトルにぎゅっと抱きしめられた。勇利は身体をかたくし、こんなんじゃねむれないよ……と緊張しきった。 「……あったかいね、きみは」 「そ、そうかな……」 ��うん。ものすごく安心するぬくもりだ。それに俺が抱きしめるとぴったりだよ。ちょうどいい。きみも具合いいだろ?」 「は、はい……」 「パズルみたいに……」 それきりヴィクトルは黙りこんだ。寝たのかな、と思い、勇利は、ぼくはひと晩じゅうきっと寝られない、と断じた。けれど、ヴィクトルの深い呼吸に合わせて息をしていると、だんだんと気持ちがほぐれ、目つきはとろけ、やすらいだこころもちになってきた。 あ、寝そう……。 勇利はほとんど夢うつつになった。──と。 「…………」 名前を呼ばれた気がした。 勇利は返事をしたつもりだったが、「んん……」という声にしかならなかった。ヴィクトルが、もぞ、と動く。あ、離れちゃう、と思った瞬間、彼は真上から覆いかぶさってきた。 「ン……」 くちびるをふさがれた。え、なにこれ、やわらかい……と勇利はうっとりした。優しく甘噛みされて、抱きしめられて、撫でられて……。 抱き返したい。 そう思ったのに、もう勇利には意識がなかった。 翌朝、勇利が目ざめたとき、ヴィクトルはまだすやすやとねむっていた。出発の時刻が迫っている。勇利は急いで起き上がり、身支度を整え、それから短い時間で手紙をしたためた。夕食と、一緒にいてくれたことへの礼、それからうれしかったということ、大ファンで大好きだということ、そして。 黙っていてごめんなさい。ぼく、女の子じゃないんです。男です。 もう手紙は書きません。でもいつか、貴方と同じ氷の上に立ちたいです。そのために、ぼく、がんばります。そのことだけ考えて、スケートします。 本当にごめんなさい。大好きです。大大大好きです。さようなら。 Yours forever. Yuri KATSUKI * * * ロシアに来て、一ヶ月が過ぎていた。勇利の感想は、なんて寒い国なのだろうというひとことに尽きた。試合で幾度か来たし、幼いころにはここで合宿だって──もっとも、あれは夏だったが──経験した。しかしそんな記憶はいっこうに役に立たず、春だというのに寒いことに勇利は溜息をついていた。 だが、近頃では、「寒い」と言うのを彼は控えている。なぜなら──。 「オハヨー勇利。今日も寒い?」 こうしてヴィクトルが抱きついてきて、「寒いならあたためてあげる」「俺といれば寒くないよ」「人肌がいちばんぬくもるって知ってた?」と隙あらば勇利に何かしようとするのである。勇利だって、ヴィクトルが純粋な思いから体温を分け与えようとしてくれているなら素直に受け取るけれど、彼の頭の中は感心しないことばかりなので辟易している。ぼくなんかの何がいいんだろうと、ずっと悩んでいた。 勇利だって、ヴィクトルが嫌いなわけではない。むしろ好きだ。大好きだ。セックスだって、彼が望むなら、いくらでも応じたいのである。けれど、やはり心配もある。そんなことをしたら自分たちの今後の関係が変わってしまうのではないかとか、ヴィクトルが飽きたらもとに戻れるのだろうかとか、そもそもヴィクトルはどうしてそんなことをしたがるのかとか、とにかく憂鬱だ。結局、いろいろなことを考えなければならない、そしてふたりの将来に影が落ちるくらいなら、しないほうがよいのではないかというところに落ち着くのである。 「俺は勇利としたいよ?」 どういうつもりなのかとか、本気で言っているのかとか、とがめるように尋ねれば、ヴィクトルはそんなふうに答える。うそではないと思う。しかし、その様子があまりにもあっけらかんとしているので、このひとあんまり���く考えてないな、と思うのである。ヴィクトルは自分の感覚に従って好きに生きている男だから、勇利のほうで気をつけなければならない。その瞬間その瞬間の思いにすべて身をまかせていたら、あとで苦しいものが跳ね返ってくることになる。ヴィクトルはそういう生き方が似合うし、彼なら失敗はないだろうけれど、これはヴィクトルだけの問題ではない。ふたりですることなんだからな、と思うと、いつものように、「ヴィクトルの好きにしたら」とは言えないのである。 「寒くない。もう慣れたよ」 背中にぐっとのしかかってくるヴィクトルを押しのけて、勇利は朝食の支度をした。 「だいたい、家の中は適温に保たれてるじゃないか。おおげさなこと言ってないで座って。今日はリンクに行くんでしょ?」 まだ急いで練習を始める時期ではない。なまらないように身体を動かしながら、曲を選んだり、どういう振付がよいかと話しあったりしているところだ。メディアからの仕事なども入るが、ふたりはいま、比較的自由の身だった。 「そのつもりだったんだけど、起きたらやる気がなくなってた」 「あのね……」 勇利はヴィクトルをにらみつけた。ヴィクトルはにこにこして、「家でゆっくりしようよ」と提案する。 「ゆっくりなんかしない。家にいるならやることがあるでしょ」 「なになに?」 「掃除とか、整理とか、洗濯とか」 「うーん……」 掃除と洗濯は日々の仕事だけれど、整理は別だ。ヴィクトルは勇利を迎えるにあたり、とくに家の中を模様替えしたりはしなかった。勇利が来てから、ふたりで使いやすい家にするために、いろいろ手を加えたのだ。それはあらかた済んだが、済んだからこそ、勇利はヴィクトルの私室が気になっていた。散らかっているということはないのだけれど、余計な書類をいつまでも置いているのである。ヴィクトルには完璧でいてもらいたい勇利は、「これ、ぼく整理していい?」と了解をとりつけようとした。ヴィクトルはそういうことに積極的ではなかったが、いやがってもいないようで、「時間があるのならね」と気のない返事だった。家にいるのならその仕事を進めたい。 「べつにヴィクトルはしなくていいんだよ。ぼくがひとりでやるから」 「勇利が働いたら、俺はつまらないじゃないか」 ヴィクトルはおおげさにかなしそうな顔をし、「俺と掃除と、どっちが大事なのっ!?」と芝居がかって言った。 「ヴィクトルは買い物してきて。足りないものがたくさんあるでしょ。洗剤とか、トイレットペーパーとか、ティッシュとか」 「そうだね、ティッシュはふたりでたくさん使うもんね」 「ぼくヴィクトルがそういうこと言うの好きじゃない」 「そういうことってなに? 何を想像したのかな、勇利は」 「お昼ごはんいらないんだね」 「悪かった。愛してるよ勇利」 「さっさと行く!」 「はあい」 食事を済ませたヴィクトルは、「勇利と一緒に買い物行きたかったな……」としょんぼりしながら着替えた。勇利はほほえみ、玄関口まで彼を送ると、抱き寄せられるままになり、キスされたらかるく返して「いってらっしゃい」とささやいた。 「おみやげ買ってきてあげる」 「そっちに気を取られて買うべきものを忘れないでよ」 勇利はヴィクトルを送り出すと、ソファで寝ているマッカチンのつむりを撫で、ヴィクトルの私室へ行って仕事を始めた。 「よし、やるぞ」 人の部屋を勝手にいじるなんて、という気がしないでもなかったけれど、ヴィクトルが勇利に「してはいけない」と禁じたことなどひとつもない。何をさわられても、何を見られても構わないといった具合である。ヴィクトルには私生活のひみつというものがないのだろうか、と勇利は首をかしげた。 黒光りするほど格調高いデスクに向かい、ひきだしを開ける。いっぱいに紙がつまっている。いらない書類だ、ということはわかっているのだけれど、つい逐一調べてしまう。雑誌の刷り出しやヴィクトルに関連する商品についての資料、ためしに撮ったポラロイドなどである。見ていると、これは捨てるのはもったいないのでは、という気がしてくる。いらないならこれ、ぼくにくれないかな……。 それでも、本当に必要のない書類も混じっているので、勇利はひとつひとつ確かめて選り分け、捨てるものと捨てないものに分類していった。なんだか楽しくなってくる。ヴィクトルは帰ってこない。静かな部屋で、ずいぶんとはかどった。 「ん……なんだこれ……」 いちばん深いひきだしの底に、綺麗な箱がしまってあった。茶色い木目調の、映画に出てくる宝箱みたいなちいさなものである。鍵がかかっていそうだな、と思いながら手をかけたら、簡単にひらいたのでびっくりした。なんとなく、見てもいいのかな、とひるんでしまう。なんだかヴィクトルの大切な思い出という感じがするではないか。だって、ほかのものは、乱雑ではないけれど無造作にひきだしに押しこんであったのだ。それなのに、これは……。 勇利はためらった。見てはいけないと言うのをヴィクトルが忘れたのかもしれない、と思った。けれど、見られたくないものがあるのに、注意するのを失念するだろうか? そういった大事なひみつは、まず最初に思い浮かべるものではないだろうか。 勇利は考えこみ、結局、すこしだけ調べてみることにした。いかにもヴィクトルの極秘の情報という感じだったなら、見なかったことにすればよい。 おずおずと中をのぞきこんだ。手紙がいくつか入っている。私的なものだろうか? ためらいつつも封筒をひらいた。宛名書きは下手くそな英語文字だったが、中を見たかったのでよく確かめなかった。昔の恋人の写真なんかが出てきたらどうしよう、とどきどきした。もちろんぼくには腹を立てる権利なんかないんだけど。腹が立つっていうより、むしろ、こんな美人と付き合ってたのか……って感慨深くなっちゃいそうかも。それにしても、なんだかこの封筒、見覚えがあるような……。 勇利は便せんを取り出してゆっくりと読みくだしてみた。ずいぶんと畏まった、まるで教科書から書き写してきたみたいな表現の英文である。ぼくも昔こんなだったな、と可笑しくなった。もっとくだけた表現でいいのに、と海外の友人に言われたことがある。 手紙の文字は稚拙だ。けれど、一生懸命、丁寧に書いたということだけは伝わってきた。ヴィクトルのファンのようだ。きっと幼い子だろう。彼は昔、子どものファンと交流していたのだろうか? 勇利は、ヴィクトルへの熱情を一生懸命に語っている文面をほほえましく感じ、これがヴィクトルの極秘の情報? と笑ってしまった。この子はいまごろどうしているのだろう。スケーターだということは読み取れるけれど、いまも続けているだろうか? 名前は……。 「え」 勇利は目をみひらいた。署名に信じられないものを見た。まさか。え? どうして? 「ユウリ・カツキ……?」 一瞬のうちに呼吸がみだれた。ぼく? ぼくの手紙? ぼくが送ったやつなの? ヴィクトルは大事に取っておいてくれたの? もちろん勇利は、昔、ヴィクトルと文通をしていた時代があったことをおぼえていた。おぼえていたけれど、何を書いたかまではおぼえていなかった。記憶はうすれ、あれは夢だったのでは、と思うようになっていた。ヴィクトルの手紙はいまでも大切に持っているけれど、みっともないすべりしかできなかった時期に、つらくなって机の奥に片づけて��まった。ぼくはヴィクトルに一生近づくことさえできない、と泣いてばかりいたころだった。 ヴィクトルがこれを持っている。なぜ? おぼえてたの? それとも、しまったまま忘れてただけ? そうだよね。そうにきまってる。こんなの宝物みたいに取り扱うわけないし。ヴィクトルってすぐになんでも忘れるし。ぼくのことだって……。 「──勇利」 突然後ろから抱きしめられ、勇利は息をのんだ。ヴィクトルが勇利の持っている便せんを指ではじき、くすっと笑って「何してるの」ととがめる。 「な、なにって……、あ、あの、おかえり……」 「ただいま、俺のかわいこちゃん」 ヴィクトルが勇利の頬にキスした。 「おみやげはケーキだよ。でも食べたらそのぶん消費させるからね。さきに消費してから食べるのでもいいけど。ところでもう一度訊くけど、何をしてたの?」 「あ、あ、えっと……」 「…………」 ヴィクトルが手紙をつまみ上げ、机の上に丁寧に置く。彼は勇利の座っている椅子をくるりとまわし、自分のほうを向かせた。 「俺のひみつを知ったからには……」 ヴィクトルが腰をかがめて上品に笑う。 「ただで済ませるわけにはいかないなあ……」 「あっ、あっ、あの、あの、ごめ、ごめん……なさ……」 「口封じかな?」 ヴィクトルが、彼のくちびるで勇利のくちびるをふさいだ。勇利は目をみひらいた。 「……勇利はすぐに俺とのことを忘れる」 ヴィクトルが可笑しそうにささやく。 「バンケットのことも、このことも忘れてしまったんだろう……」 「忘れてない!」 勇利はむきになって言い返した。 「バンケットのほうは……ちょっと、あれだけど、手紙は……」 「そう?」 ヴィクトルが前髪をかき上げ、余裕ぶって勇利を見下ろす。 「おぼえてるのかい?」 「お、おぼえてるよ……ヴィクトルと試合会場で会って……それで手紙を渡して……」 「そう、そこからやりとりしたんだったね。それから」 「ぼくがロシアの合宿に参加して……そして……」 「一緒に寝た。そのこともおぼえてる?」 「……うん」 「じゃあ、そのときに俺が言ったこともおぼえてるんだね。オーケィ。だったら問題ないな」 ヴィクトルはいきなり勇利を横抱きにしてさらい、大股で彼の私室から出ていった。勇利はわけがわからず、「なに、なに、えっ、なになに」と騒ぐ。ヴィクトルはそんな彼を気にかけることもなく、寝室へ踏みこみ、大きなベッドに勇利を下ろした。 「おぼえているなら話は早い。だったらどうして俺をずっと拒んでいたんだ? じらしてたの?」 「な、何を言って……」 「大人になってから、しようね」 ヴィクトルはベッドに片膝をつきながら上がり、にっこりと笑った。 「そう言っただろう?」 勇利が口をあんぐりとひらく。 「勇利、俺はね……」 ヴィクトルが、みずからのシャツのボタンをひとつひとつはずしてゆく。そのしぐさがすべてかっこうよくて、勇利はぼうっと見蕩れていた。 「もう、自分の気持ちはわかっているよ」 彼はシャツを投げやると、勇利の両側に腕をつかえておとがいを上げた。 「俺は子どもじゃない」 ヴィクトルのくちびるが勇利の首筋にふれ、手がシャツの下へ入りこむ。 「きみも子どもじゃない」 すこし力をこめられただけで、わずかに浮いていた背中が敷布にくっつき、もう起き上がれなくなってしまう。これはいったいどうしたことだろう。 「勇利……」 ヴィクトルがつやめかしい吐息に混ぜて勇利を呼んだ。これはとても逆らえない魔法だ……。 「俺のひみつをあばいたんだから、ただでは済まさない。もうめろめろにして、俺から離れられなくするしかないな……」 勇利はまぶたを閉ざした。もうなんでもいい、と思った。好きにして……。 ヴィクトルが勇利の衣服をみだし、はしたないかっこうにさせてゆく。勇利は、彼と素肌がふれあったとき、ぞくぞくっとして身震いした。 「髪、切っちゃったんだね……」 ヴィクトルが勇利の髪にキスした。 「俺もそうだから、おあいこか」 勇利はそこではっとした。髪──髪? 「ヴィ──ヴィクトル!」 ぱっと目を開け、ヴィクトルをみつめる。湖と星と宝石を閉じこめたような、はかりしれない深い瞳が、優しく勇利をまっすぐ見ていた。 「なに……?」 「ぼく……、女の子じゃないよ!?」 ヴィクトルはきょとんとし、ぱちりと瞬き、それから陽気な声を上げて笑い出した。 「──そんなこと、最初から知ってたさ!」 彼は勇利の脚を押しやった。 「ね? 大人だっただろう?」 あたたかい上掛けの内側で、ヴィクトルがいたずらっぽくささやいた。 「ぼくは?」 「大人じゃなかったら、ただじゃ済まさないなんて言わないさ……」 勇利はヴィクトルの腕の中でもぞもぞと身じろいだ。全身がけだるい。しかし、こころよい疲労が身体のすみずみにみちている。 「気持ちよかった?」 「なんだか……」 勇利はぼんやりと答えた。 「最高の演技をして、満足してるときみたい……」 ヴィクトルは楽しそうに笑った。 「すてきな感想だね」 「ヴィクトルは?」 「俺は、そうだな……」 ヴィクトルはいたずらっこのように目をほそめた。 「あのときこうしていたら、きっともっとわけがわからなくなっただろうから、十年待ってよかったかな、っていう気持ちだね」 「ヴィクトルは子どもっぽいから……」 「きみは大人っぽいの?」 「ぼくはあのときしててもよかった」 ふたりは黙ってみつめあい、それから同時に噴き出した。 「勇利、ケーキふたつ食べてもいいよ」 「えっち」 「それから……」 「なに」 「これからは、もう断るのなんてだめだからね」 「そんなわがままは聞き入れられない」 「なぜ? もう大人なんだろう? 俺よりもさ」 「大人は、自分の意見をはっきり言うものです」 勇利はとりすまして断言した。 「あのときしてたら……、もう、断るなんて思いもよらなかったけど……」 「日本へ帰っちゃったくせに。俺があのあと、どれだけしょんぼりしたかも知らないで……」 「あのときしてたら、離れたくない、ロシアにずっといる、ってヴィクトルに泣いてしがみついてたよ」 「抱いておけばよかった」 ヴィクトルがきまじめに言うので、勇利は彼がいとおしくてくすくす笑った。ヴィクトルもすぐに笑い、勇利の頬にくちびるを寄せる。 「でもわかってるよ。きみはもう断らないさ」 「ずいぶんな自信だね。どうして?」 「だってきみ、永遠に俺のものだって自分で言ったじゃないか」 勇利はヴィクトルが何を言っているのかわからず、とっさにやり返そうとした。しかし、声を出す前に理解してしまった。頬があっという間にまっかになる。ヴィクトルが、もがく勇利をあざやかな手並みで抱きしめ、ちいさく笑ってから、色っぽい、不届きなほど甘美な声で宣言した。 「Yours……、forever.」
4 notes
·
View notes
Text
VIXX白昼夢・日本公演
7/15、VIXX(以下びくす)ジャパンツアー「白昼夢」の東京、昼・夜公演に行ってまいりました。
あと、具体的な実際のステージ構成やセトリは他のどなたかが書くだろうからと思って、 私は自分が萌えたことと考えたことを書いてます(要は「いつも通り自分のメモなのでセトリとか知りたい場合は他の方の記事をお勧めします」)
それと、公演直後にTwitterで「VIXXを働かせすぎだ」って件について書いたんですが、 その件については末尾で触れてるので以下の本文中では特に書いてないです。 (末尾には、あのあとFC問い合わせに送信した「昼夜二部構成&日本活動スケジュールをあんまり過密にしないでくれ」って内容の文章を掲載) (載せるかためらったものの、好きな相手がしんどい状況に置かれてることに対して運営に連絡取るのは全然おかしいことじゃないし、 もし今後同じような辛さを感じた人がここにたどり着いたときなにかの参考になるかもなと思って。 もしあなたが、これから相手がしんどくないように動きたいなと思ってる人だったら、私の文章が何か力になれば幸い たとえファンの大半が気にしてないことでも、自分が気になったことを「こうしてくれ」って運営に伝えるのは傲慢なことじゃないし卑屈になりすぎる必要もないなと思う)
——————————————————————
【〜ここが萌えたよ白昼夢 昼の部編〜】
日本オリジナル公演ではないため、衣装も韓国で使っていたものと同じだったことにまず興奮した。 音楽番組やTwitterで見て憧れたあの衣装でみんなが踊ってる!ということに大興奮。 初っ端のまっしろい衣装、あれ、あれがね、びくすの王子様力を爆発させていて大好きなの…!
パフォーマンスに関しては、身長が揃っていて体格も同様なのに、踊り方が全員違って! 動画で見ているよりも明らかにそれぞれの特徴がよく見えた。ファンカムの方が特徴わかりやすいかと思ってたけど、 みんなで並んでいるところを全体で見たほうが癖がよく見えると学んだ。 やはりエンちゃんは端正で一番お手本っぽいし、ラビは上半身を下げがちで、レオとケンちゃんは手を使ったポイントダンスが得意なのね〜 あとは、ファンタジーやエラーの冒頭、ブラックアウトで長いあんよを見せびらかすところなど、 全員揃って踊るところを見ると迫力があるね!ここでスタイルの良さと揃った体格が生きているなと思った。 歌に関してはケンちゃんが…強すぎるんだよな…彼が声を発した瞬間から空気が変わって ああ、舞台を経験したスキルすっごいなかっこいいな…!と震えた…!
☆
MCについて。まず、エンちゃん・ひょっくん・ケンちゃんの三人が舞台に残り話し始める。止まっていると光沢のある赤い衣装がよく見えた。 MCは総じてエンちゃんの教師ぶりが際立つ(「みなさん声が小さいですね」・「わかりますか?」などなど)。 エンちゃんは最も日本語ができるが故に他のメンバーに通訳したり単語を教えたりしてあげてた。 ひょっくんが日本語を頑張っていることをなにかにつけてアピールし、 ひょっくんが話したあと「日本語上手ですねえ」といいつつ他のメンバーの顔を覗き込むエンちゃん。聖母。 (あと、このあとのMCでレオやラビが「バカですね」って言い合ってるのに「それはいけない言葉ですよ」って注意したり、 ケンちゃんがふざけてラビにパンチしてるのに対して「叩いちゃダメですよ、ラビさんは弱いですから」って言ったり、 やっぱり総じて面倒見が良かった。 ちなみにエンちゃんに注意されたやりとりのあとのラビは「触らないでください」ってケンちゃんに言ってて (お!?お前が言うの��!?)と思った!!)
エンちゃん・ひょっくん・ケンちゃんが退場後、ラビ・レオ・ホンビンの三人が入れ替わりに登場してMC。 すれ違いざまにラビがケンちゃんを触りまくって背中触って、袖に退場するまでお見送り。 (ここで同行の友達(非ドルオタ)が「ラビはなんでわざわざあんなことを…?」と混乱し始める) ラビが間違えてしまった時、ホンビンが下向いて「なんで僕が恥ずかしいんだろう…」って韓国語でつぶやいていて 顔の真っ赤さとラビに対する兄弟感みたいなものに超萌えた。 ホンビンはやはり笑った顔がいいな…
☆
総じてラビがケンちゃんに超触ってた。MC中、ポッケに手を突っ込んでた。 挙げ句の果てには一度、首触って、ケンちゃんが心底鬱陶しそうに振り払っててあまりのことに悶えた。 あのふたりはほんっっとに日頃からああなんだろうな!?!?!?
☆
映像も全て韓国公演と同じ内容を使ってたようで、二重人格ホンビン・ひょっくんの手のペイントとワイングラスを掲げる端正な美しさ(エンちゃんと…エンちゃんとあの手の目がひょっくんに…!)などなど見所が大きい!花に埋もれるエンちゃん!縛りあげられるラビの表情! ソウルコンの映像の白竜が素晴らしくて、演出もパフォーマンス内容も桁違いなのだと実感して憧れがつのる。ラビのソロステージ映像がかっこよすぎ!
☆
以下余談。
この回はアイドルに興味ないお友達と行った。ら、開演前、体調が心配で痛み止めを持参したと言われて笑う。
お友達「興奮しすぎて頭痛とかしちゃわないかと思って…」 私「ふふ(微笑ましいな)」 お友達「のぶちゃんが…」 私「ああ…(納得)それはありがとう」
☆
開演前、この同行の友人に「ラビはケンちゃんが大好きなんだよ」「ケンちゃんにベタベタ触ってるの」などなど説明したものの全く信じてもらえなかった。 しかし、終演後の彼女が「ラビって本当にケン好きだったんだね、のぶちゃんの妄想かと思ってたけど実際にベタベタしてた」と発言。快哉を叫ぶ。そうなんだよラビがケンちゃんを大好きなのは実話なの…
☆
おまけ。非ドルオタの友人からヒアリングしたメンバーのイメージ
エン 「見た目は中粋な子どもみたいな印象だったけど、すごくお兄さんでしっかりしていた。空気読むし進行するし、一人だけ涼しい顔で踊っていてかっこいい! 第一印象ではラビの方がしっかりしててエンがマイペースだと思ってたけど実際は逆だったね」
レオ 「控えめで綺麗、特に笑い方」
ケン 「外見と性格のギャップに驚いた。ちょっと変わってる?歌がものすごく上手い!」
ラビ 「一番好き!男っぽくてかっこいいルックス!!でも彼もギャップに驚いた。兄貴分かと思ったらMCとかかなりマイペースだね。 引っ張って進行して行くのかと思ったら問題児タイプ?で、弟ぶんのケンちゃんが大好きなんだろうなって思って…(ここで私がラビの方がケンより下だと伝える)…?え?ラビの方が年下なの?(私「そう、あれはお兄ちゃん大好きってことなの)そうなの!?そしたらケンしっかりしろって思うわ!!えーーーーーラビとケンは年齢差がイメージと違ってそれを知ると全部印象変わる!」
ホンビン 「普通に男前」
——————————————————————
【〜ここが萌えたよ白昼夢 夜の部編〜】
☆
友人「あのラビのジャケットの着方、かっこいいと思ってやってるんだろうね」 私「ああ、初っ端の白いジャケットのところからしてたね、まあ実際かっこいいので」 友人「かっこいい…」
☆
ケンちゃんがエリック役の曲を一節歌いあげた際、 昼の部と照明演出が変わってた(ピンスポットになってた)ことに気づく。 この照明変更で歌う姿が際立っていたな〜 昼の部と夜の部の間で話し合って反省点を改善したんだろうな、と思うと より良いステージのためにあんな短い間で変更してくれたことが嬉しかった。
☆
ひょっくんのお誕生日をみんなで祝福したあと、ひょっくんがカバー曲を歌ってくれたのも嬉しくて!! レオやケンちゃんといったボーカルラインはよくやってるけど、 ひょっくんがああ言う場所で自分の気持ちを伝える手段として「歌」を選んでくれたことが珍しい気がしてなおさら嬉しかった。昼公演の時はなかったし ああやってひょっくんの歌を聴く機会が増えたらいいなー!!
☆
二回目のMC(三人組の組み合わせは昼公演と同じ)。 ラビ、ふざけて「さっさと出て行け」とばかりにエンちゃんたちをしっしって追い払う。 レオがマタハリの一節を歌ってくれ(この歌唱が素晴らしく、私は今公演で一番記憶に残っている)、 そのあとホンビンとラビがふざけて泣き出すふりをしていて、 揃っておにいちゃんをからかってる同い歳コンビが愛おしい。 あんなに圧倒的な歌唱を見せたお兄ちゃんに、「わあ!すごいですね!」とか返すのではなく ふざけてみせる余裕があって、ああ彼らはレオの実力を何度も目にしてよく知ってて、 その上でふざける信頼を築いてるんだな、と日常を感じてそこも萌えた。
☆
レオ「(客席に向かって)マタハリ見ましたか」 (客席、ほとんど手が上がらない) レオ「ああ…(非常に残念そう)」 ホンビン「マタハリ見たいです」 レオ「メンバーのみなさんは忙しいですから…」 ホンビン「招待してください」 レオ「招待したら必ず来てくださいね」 ホンビンに念押ししてるレオ、萌えた…
☆
今やってるドラマの仕事でキスシーンがあることをラビに振られて 耳が真っ赤になるホンビン。うう…(萌え) このころから同行の友人(参戦前はエンちゃんが気になると言っていた)がホンビンに転がり落ち始める。 友人「ホンビンの前髪が〜〜❤」
☆
ケンちゃんの笑い方「へへえ」 あざとい かわいい
☆
(ラビが数回コメントやラップを間違えてしまってて、このMCのときも一語ごとに他のメンバーや通訳さんに直してもらっていたため) エンちゃん「いま日本語勉強してるんですか?今はコンサート中ですよ?」 ラビ「毎日勉強です」 (あまりにうまい返しに客席が沸く) ラビ「매일(めいる。毎日)매일(毎日)勉強…(ここで若干のドヤ顔)」
☆
アンコール非常に長くて雰囲気良くて最高。
上から降ってきたキラキラの紙吹雪?を拾ってレオにかけて笑って走り回るひょっくん、という絵面が美しく幸福だった…ひょっくん、エアギターして見せたりぴょんぴょん飛んだり、その度に整った脚や屈託のない笑顔が見えて、ああ普通の青年だー!と実感したよ!! 舞台の高いところにたってエッヘン!ポーズを決めるエンちゃんに向かって「初めてエンさんが一番背が高いですね^^」って言い放ったひょっくんも愛おしかったなあ!
ケンちゃんとエンちゃんが一緒にぎゅーーー!って強く抱きしめあった後、カメラに向かって笑ってるのが自慢しているようだった。
(これは私は確認してなくて、同行の友人から聞いて萌えたんだけど)手をつないで横一列でお辞儀するところ、一番右端のラビがお辞儀したまま袖に行こうとして、それに伴ってラビの隣のホンビンも袖に行こうとしたんだけど、中央のエンちゃんが(まだダメ!)って感じで止めたら、ホンビンが��尻でエンちゃんをドン!ってしていたらしい いいな!!ホンビンはここ以外でもおしりでどんってしてる瞬間があってかわいいんだ〜 ホンビン、テンション上がると笑って水かけたり飛び跳ねたりするタイプなんだろうなって昔から思っていたけど、実際にその瞬間を見られて改めて好きだと思った。
それからラビとエンちゃんの顔が近くてヒッ…!!!っとなっていたら、レオが近づいてきて二人の顔をまとめてタオルでくっつけててトドメを刺された。
最後の最後、ずっと客席に手を振ってるホンビンの腕をぐっとつかんで袖に連れていくレオの彼氏っぽさに死にそうだった。 なんか…夜の部のレオとホンビンは距離が近かった気がするんだけど気のせいかな?昼の部と夜の部の間に何かあったのかな?ホンビンがレオにお菓子をわけてあげたとか?
☆
まあ大体こんな感じでした。以下今回のコンサートから感じたこと。
私は通路沿いでレオとケンちゃんが隣を通り、ひょっくんとエンちゃんに至ってはハイタッチしてしまった。今でもすごく不思議だ、Twitterで、インスタで見るたび、「この人が隣に居たんだよなあ」と思って…今回は昼も夜も素晴らしい席だった… (ちなみになぜレオとケンちゃんとは接触してないのかというと、別に塩対応だったとかでなく、レオに対してはあまりのことに体が動かず、ケンちゃんには見とれていたから)(お友達も「レオは神々しくて恐れ多くて触れない」って言っててあの謎の王族オーラを実感した)
レオ、私の隣を通った直後に体をひるがえして振り向いたから、背中だけじゃなくて全身の様子や動いた仕草が全部見えて、 その様子が優雅で美しくてなによりも楽しそうに歌っていて、こんなに魅力的な人がいるんだなと思った。今でも思っている。 あまりに整った手首がまずパッと目に入って、そこからマイクをたどって視線を喉に移すと、塑像の芯棒みたいにしっかりしている首が見えて、 あの声や言葉や舞踊が生身の肉体から生まれていること・それがここにあることにぶわっと歓喜の念を感じた。 レオが生きてて、美しいパフォーマンスや魅力的な考え方や立ち居振る舞いをする人で、 それが全部触れられる肉体に根付いてるんだなって思い知らされた。
私は防弾少年団のラップモンスター(ナムジュン)ガチ恋勢を自称していて、 実際彼と付き合いたいですとか、人にトレカを見せるときには「あ、彼氏です」って言ったりしているんだが、 まあ当然ながら冗談である。私は現実世界���彼のために恋人として特別な行為は何もできない(人並みにCDは買ってコンサートに行ってグッズや特典集める程度)。 これはあくまでキャーキャー言ってるのが楽しい思考遊戯みたいなもので、 「ワー彼氏!特別!」といいつつも実際の行為として特別なことはしない。やりようがないしね
でも、レオは、これからいろんな現実世界での行動を私に起こさせるかもな、と思った。 例えばCDを買うこと、例えばイベントに行くこと、韓国に行くこと、語学を学ぶこと、ミュージカルに行ってみること、 そうやって現実世界や生活に干渉することを、レオをきっかけにこれからたくさん行ってしまいそうだな、と思った。 今回のコンサートがなかったら、ミュージカル行きたくなってソウルコンにこんな強く惹かれることなんてなかっただろうし。 彼が地続きの世界で生きてる生身の人間なんだな、と思って、会いに行けるし会いに行かなきゃと実感したから これからいろんなことしちゃいそうなんだよ…
レオには徴兵が迫っている。 会いに行くなら今しかない、って頭ではわかっていても、実際に生きている人間として目の前にしたら、 「この人は生きている人間で、徴兵されて、これからいくら会いたいとしても残された時間は多くないんだな」って実感してしまった。 もっと早く出会っていればさらに長く一緒に活動期間を過ごせたかもな〜とは思うけど、 このタイミングで好きになってしまったことを後悔してはいなくて、 たぶん今じゃなかったらこんなに残りの時間を意識してできることを一個ずつ考えていなかっただろうから いまこの白昼夢に参加できてよかった。 魅力がわかって、そのうえで残された時間が多くないことを実感できてよかった。 できることもやりたいこともいっぱいあるなー!目下はソウルコンと、彼のミュージカルを観に渡韓!
コンサートの恐ろしいところは、それまで当たり前だった日常の流れを、分岐点みたいにどこか別のところへ連れていってしまうところだなー。 コンサートの前と後とでは、大小に渡ってやりたいことが何倍にもなっている(わたし、いつもはちゃんと丁寧に料理することとか全然やる気が起きないし、カレーの材料炒めることなんてしないで全部つっこむんだけど、この手がエンちゃんとハイタッチしたのかと思うと今はすごくちゃんと料理して食事を食べたいwこの手の細胞をできる限り上質な形で長生きさせたいw)! たのしいんだよなー!
——————————————————————
そしてここから、今回のコンサートにおけるメンバーの消耗ぶりについての話。
結局、今回目にしたことから、「VIXXがあまりに過密労働だな」と思ったために今回FC問い合わせをした(詳細はこちら http://twilog.org/doanob1/date-170715/allasc をご覧ください)。 なんかなーアイドルの過重労働に関して、「本来異様に忙しいものだ」「そういう仕事してお金もらってる」「だれにでもできるんことじゃない」ことだから、仕方ない、 っていう意見もあるし実際一理あるなと感じるんだけど、 「仕方ない」っていう言葉自体、本当は諦めたくないときに使ってる表現だと思うので 私はあの子達が明らかにしんどい状況を諦めたくないんだよ… 働かせすぎてやめる、忙しすぎて怪我する、っていう事態はこれまでこの業界で山ほど繰り返されてきてる、 びくすがどんな形で終わるかはわからないし、考えたくもない部分でもあるとはいえ、 いつか否応なく徴兵も終わりもやってくる。 だったら、彼らが疲れ切って怪我するようなかたちで終わってほしくない。
さっき、私はレオに「彼は私に現実での行動させる人間だな」と思った…って書いたけど、 その一環がこの問い合わせでもある…
以下、問い合わせで送信した内容。
いつか、アイドルと私たちが「全然疲れてません」「大丈夫です」っていう明らかな社交辞令じゃなくて、 「めちゃめちゃくちゃしんどくてすごくすごく疲れたけど、最高に楽しかったです、また会いましょう」って言い合える関係になれたらいいなあ。
——————————————————————
【VIXX日本活動における、昼夜二部構成の中止要望】
ご担当者様
いつもVIXXの活動を届けてくださり、ありがとうございます。 桃源境でのカムバックも素晴らしかったです。
また、今年に入ってリニューアルしたHPの構成ですが、 韓国での活動も掲載されたり企画形態が変わったりと、 求めている情報が得られるかたちに変わり 非常に感謝しております。 日本にいながらにして「彼らがいまどう活動しているのか」を知るうえでは SNSの果たす役割が最も大きいとはいえ、 公式HPで事前に予定をまとめてくださっていることは渡韓の目安にもなりますし なによりも公式情報の安心感が大きいです。 ありがとうございます。
さて、先日、東京での昼夜公演に参加いたしました。 最高のステージでした。 私はレオが好きで、彼に最も期待していましたが、 実物のパフォーマンスは想像以上に覇気がありました。 また、マタハリの一節も、帰ってから何度も思い出しています。 ミュージカルへ行ってみたいと言う気持ちも膨らみ 予想外の収穫を多く得ました。
しかし、(レオに限らず)彼らがあまりに疲れ切っていることが辛かったです。 曲が終わった瞬間床に座り込み、水を飲むこともできない姿に、衝撃を受けました。 私は猛烈なアイドルファンというわけではありませんが、幅広く様々なグループの現場に行くよう心がけてはいます。 そのうえで、彼らの消耗ぶりは違和感を覚えるレベルでした。
ここで強くお伝えしたいのは、決して彼らに「疲労を見せるな」「プロ意識がない」「発言に気をつけろ」と思っているわけではありません。 (仮に隠したところで、何度も映像や現場を見ているファンはパフォーマンスや表情を見れば疲労はすぐにわかります) あまりに彼らのスケジュール、労働状況が過酷なのではないか、と思ったため、 日本での活動の過密さを改善していただきたいのです。 具体的には、今後の活動での昼夜に渡る二部構成を変更することを要望いたします。
「あと一分だけ休ませてください」と言う言葉を聞いたとき、そんな奴隷のような言葉を言うほど働いているのかと思いました。 「大丈夫です、まだ若いから大丈夫です」「いつまでもそばで歌います」と言われたとき、これからもずっと応援していきたいと思っていた気持ちは、(ずっといるなんて不可能だ)という悲しさに変わりました。 これから若さからは離れていくなかで、「若いから大丈夫だ」と言う言葉は不安の裏返しであり、これからも同じ形で働き続けることは不可能だということです。
私がお金を払うからこそ彼らがこんなに働きづめなのか、と、帰ってからずっと考えています。 そういう仕事だとか「誰にでもできることじゃないから」ということは一理ありますし、 特に日本活動では過密なスケジュールではないとこなせないのかもしれません。 しかし、せめて昼夜二部構成は今後改善できないでしょうか。 忙しい中でも踊るプロだと彼らを褒めることは簡単ですが、 あの姿を見てその言葉を言うことは私にはできません。 正直、過重労働を賛美するようだからです。
もしかすると、今回私が出した要望に関するようなことは、 韓国の彼らの所属事務所の意向であって、 日本の事務所にこうしてお問い合わせしても 改善しないのかもしれないとは思っています。 私は韓国語が使いこなせないために こうして日本語でお伝えしておりますが、 いかに感謝しているか、そして彼ら��助けたいと思っているか、 日本のスタッフの方にお伝えすることで 今後VIXXが受ける負担を少しでも減らしたいです。
長々と失礼いたしました。 いつも彼らに会うことを支えてくださって、ありがとうございます。 これからも彼らに会うことを楽しみにしています。
0 notes