#三脚持って行かなかったのでノイズはご勘��。
Explore tagged Tumblr posts
Text


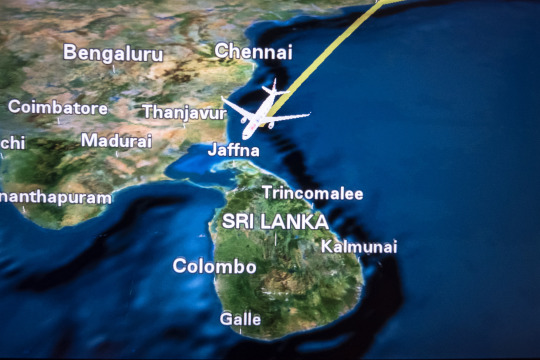








お久しぶりです。
少し旅してきました。
スパイスヲタ & 3輪乗りとして
前から行きたかったスリランカへ。
アイルランドから5年ぶりの空を超えた飲み歩き。
今回はどんな旅になるのか…
っと、Sub blogの方で予告しておきながら
長らく放置してました スミマセンwww
直通便がないスリランカへの往路は
何かと噂の上海プードントランスファー。
思ったよりイージーでしたが、
上海で並ぶのが移動時間よりも疲れたw
合計13時間の移動でした。
夜に到着し鉄格子に守られた酒屋で
早速ビールとアラックを購入して宿へ。
飲みながら鋭気を養った初日の夜。
スリランカ編スタートです。
→→→→→
Sub blog : こぱるこっきんぐ
https://copal-xxx.tumblr.com/
128 notes
·
View notes
Text
NIGHTCALL(柴君)
▽
その日の君下はすこぶる機嫌が悪かった。
元々の鋭い目付きと無愛想な性格が相まって、だいぶ人相が良くない自覚はある。それ故に君下はクラスで浮いている存在だった。親しい友人もいなければ、用がない限り誰も彼に近づこうとしない。通常運転で既にこれだから、今日のように君下が青筋を何本も立てて座っていると、あからさまに教室の空気が何キロも重くなった。
ーー事の発端は前日の練習後に遡る。
すっかり日の落ちきった午後8時過ぎ。
その日鍵当番だった君下は倉庫に備品を片付け終えて、鍵を返しに体育教官室へと向かった。ノックをして「失礼します」と声をかけると、白く烟った教官室の奥から「君下、ちょっと」と顧問である中澤の声がした。グラウンドの脇にある小さなプレハブで、ほとんど体育教師たちの喫煙所と化しているそこは、普段ならば生徒が立ち入ることは許されていない。君下は初めて足を踏み入れる場所に少しドキドキしながら、「ッス」と小さく返して扉を閉めた。
「おう。どうだ、新しいポジションは」
ぎい、と椅子が鳴り、パーテーションの向こうに背伸びをした中澤の頭が見えた。いつ見てもとっ散らかった黒髪にいくらか白いものが混じり、疲労が���み出ているようだった。
「まあ、ぼちぼちです」
「そうか」
二人の間でゆらゆらと紫煙が燻っている。中澤は咥え煙草のまま、無言で何か言いたげな目を向けていた。そうして暫くの沈黙が続くと、ようやく君下は腹の底で蟠っていた疑問を口にした。
「でもなんで、俺がフォワードなんすか」
数時間前、中澤は部活前の君下を呼び止めて、ポジション変更を告げていた。入学して以来ずっとトップ下を守ってきた君下に、センターフォワードに入れと言ったのだ。
このチームでプレイして半年は過ぎたが、君下には中澤の考えがいまいち分からないままだった。そもそも君下を聖蹟に引っ張ってきたのは他でもない中澤であったが、たかが中学生にエースナンバーをくれてやると約束したこともまた、腑に落ちないことだった。とはいえ当時の君下は、自分の力を過信していたきらいがあった。それに加え貰えるものはありがたく貰う主義なので(俗に言う貧乏性というやつだ)、返すつもりもなかったのだが。
「お前ならできると思ったからだ」
「はぁ」
「まあまだ初日だ。明日も同じ形でいくから、焦らずやってみろ」
中澤は深くヤニを吸うと、ゆっくりとした動きで目を伏せて灰を落とす。それからもう一度まっすぐ君下と向き合った。
「それと大柴のことなんだが」
その名前を耳にして、君下の顔がぴく、と引き攣った。なんとなく、こちらが話の本題なのだろうと思った。中澤もそれに気づいたようで、言葉を区切ると片眉を僅かに上げた。
「なんだ、なにか聞いていたか?」
「いや、なにも」
「そうか」
「で、何なんすか」
「一週間ほど休むそうだ」
「……は?」
君下はぽかんと口を開けながら、なるほど合点がいった。
君下がいきなりフォワードにコンバートされたのは、正規のフォワードである大柴が何かしらの理由でポジションを外れたから。大柴がいない理由などそんなことはどうでもいいが、問題はなぜパサーである君下がそこに入るのかということだ。
選手層の厚いこの学校にはフォワードをやるものはいくらでもいる。それに君下がトップ下を離れるのならば、ふたたび開いたその穴には一体誰が入るというのだろう。
君下の賢い頭脳は一瞬にしていくつもの疑問が浮かべたが、そのどれもが意味のないことのように思えた。中澤の光のない瞳がじっとこちらを伺っている。監督には何か考えがあるのかもしれなかった。
「……ポジション交代はその一週間だけっすよね」
「いや、それはわからん」
「おいおい、俺は嫌ですよフォワードなんて」
よりによって、あいつの代わりだなんて。
���う言い返すのも憚られた。そのぐらい、君下は大柴喜一という男が気に食わなかった。
蘇る中学都選抜時代の記憶。同じチームにいながら味方同士で競い合うようにボールを奪っていたあの頃。たしかに君下は、最初からパサーをしていたわけではない。むしろ今の大柴のように、自分で積極的にゴールを狙うようなプレイスタイルだった。頭も切れて自分で点を取れる。それ故に中学選抜でついたあだ名は「悪童」であり、おそらく中澤もそれを知っているのだろう。そうでなければこの指示には疑問点があまりに多い。
いつのまにか握った拳に汗をかいていた。君下が目の前の男を睨むように立っていると、煙草の火を消した手でぽん、と肩を叩かれる。力強いが、それでいてやさしい手つきだった。
「君下。賢いのは随分だが、そうあまり深く考えるな。俺はこのチームのありとあらゆる可能性を試したいだけだ」
「……」
「やるだけやってみろ。ただ、チームが今のままでは勝てる試合も勝てん。そのぐらい、ピッチに立っているお前なら分かってるだろ」
「ッ……クソが」
君下は昨日のことを思い出して、小さく舌打ちを零した。
結局何も言い返すことができなかった。中澤の突拍子も無い提案はともあれ、言っていることはあながち間違いではなかったからだ。
七月、夏のインターハイは予選決勝で敗退した。
一年生である君下にとって高校最初の大舞台だった。敗因はオフェンス陣が思うように点が取れなかったことと、チームの司令塔である君下との連携がほとんど機能しなかったことだった。
苦汁を舐めることは二度としたくなかった。あんな無様に敗けるのは御免だった。中学時代の大敗を教訓にしてきたつもりだったが、その結果がこれだった。
勝てない。
だから君下は的を絞るために、チームの頭脳であり心臓であるパサーに徹することにした。たとえ自分の得点を捨ててでも。
だがそれでも勝てなかったら、あの努力の日々には一体何の意味があるのだろう。
「おーい君下、寝てんの?」
唐突に声がして、背後から肩を叩かれ君下はハッとした。そこでようやく自分がぼんやりとしていたことに気がついた。
「うぉ、何だよ」
「何だよじゃねーよ、さっきから何回も呼んでるんだけど」
「悪い……」
君下に声をかけたのは鈴木だった。同じサッカー部の一年で、レギュラーではないがそこそこ上手い経験者。地味だが人好きする性格で、部内でも浮き気味の君下に気軽に声をかけてくるような男だった。
「どうした、寝れてないのか? すごい顔してるぞ」
「うるせぇこれは元からだ」
「それは否定しないけど、今日は特にひどいぜ。乾燥した日のグラウンドみたいな顔色してる」
「��前わりと失礼だな……」
あまりにもじっと見つめられるので、君下はなんだか気恥ずかしくなってきた。目を逸らして、「何でもねぇよ」と小さく呟くと、鈴木は紙パックの牛乳を啜りながら「ならいいけどさ」と、さして興味もなさそうに教室の入り口を見ている。
「君下がいつもに増してすげー顔してるから、みんな怖がってるぜ」
そう言われて、君下はようやく周りを見た。昼休みである今、自分の周りの席はおろか、君下の席からきっちり教室半分は人が居なかった。ドアの周辺に佇んでいる、不安げにこちらを見つめるクラスメイトの集団に気づいたところで、再び鈴木に視線を戻す。君下と鈴木を見つめるたくさんの目は、まるで檻の中にいる猛獣でも見ているかのような視線だった。
見た目で勘違いされやすいが、君下はいわゆる不良などではなかった。根はクソがつくほどの真面目であり、寧ろ学業における成績は優秀で、入学以来ずっと学年一位をキープしている。それに加えて強豪サッカー部の特待生で奨学金を貰っている身であるから(君下の家は貧乏な父子家庭だった)、素行不良などどうしたってできるわけがなかった。
ただ大柴と居ると、腹の奥底から湧き上がる得体の知れない感情に左右されやすくなる。あのふざけた態度と面を見ているだけで、どうにも我慢が効かなくなってしまうのだ。
顔を合わせればどちらかがーーどちらかと言えば大柴からの方が多いがーー喧嘩を吹っかけて、その場で睨み合いや口論になる。悪ければ互いに手がでることもあるが、大抵の場合がその場に居合わせた誰かの仲裁で未遂に終わった。そう言うことがしばしば起こり、いつのまにか二人は犬猿の仲として学校中に認知されるようになったのだ。
▽
「あの赤アタマ、とうとうクビになったのか?」
「さぁ、知らね。ともかく1つ席が空いて良かったよな」
「ほんとそれ。ただでさえレギュラーなんて狭き門なのによ、一年が二人も居座っちゃあな」
「最初から先輩に席を譲れってんだよ」
「言えてる」
「つーか君下もだよ、なんであいつがフォワードなんだよ」
「あーあれ監督の指示だとよ。臼井が聞いたって」
「マジ? なんでよ」
「知らん」
「ついにケツでも開いたか?」
「ギャハハあり得る」
「おい! きったねぇなー、飛ばすなよ」
「だってよぉ、夏負けたの、明らかにあいつのせいだったろ?」
「な、流石の悪童もブルっちまったんじゃね?」
「あーあったな悪童とかいう大層なあだ名」
「ハッ、どこでもいいから使ってくれってか、一年坊が。調子に乗りがって」
大柴がいない部活はいつも通りだった。
入学早々レギュラー入りを果たした君下や大柴が、控えの上級生に陰口を叩かれているということはなんとなく想像がついた。今までだって何度も似たような経験をして、その度に結果で黙らせてきた君下だったが、こんなあからさまな陰口を偶然聞いてしまって、素直に気分がいいとは言えなかった。
大柴の不在についてミーティングで中澤は何も言わなかったし、それについてわざわざ聞き返す者もいなかった。君下が大柴の居たポジションにコンバートされた今、大柴はドロップアウトと考えるのが妥当だった。
君下は当然のようにフォワードの練習に混ぜられ、久しぶりにも感じるシュート練習に身を入れた。トップ下でもそれなりに蹴る機会には恵まれるが、聖蹟高校の得点数の8割以上は、伝統である三本の矢からなるフォワードの功績だった。総シュート数で考えても、圧倒的に場数が違��。
加えてフォワードは敵ディフェンダーとのぶつかり合いになることが多い。前線でボールを保持するための身体の強さは勿論のこと、それを振り切るだけの脚力と、飛んできたボールに合わせられるジャンプ力や背の高さも必要になる。
君下はそのどれもを持っていない。背や筋肉量といった先天的なフィジカル面も足りなければ、瞬発力だって左サイドの水樹に比べれば今ひとつだった。だから何も持たない君下が前線で勝負するためには、シュートの精度を上げる以外に道はない。
慣れない雰囲気での練習を終え、君下は日課にしている勉強もそこそこに眠り込んでしまった。一日中気が立っていたこともあり、無意識のうちに疲労が溜まっていたらしい。夢も見ないほどぐっすりと眠り、目が覚めたのは翌朝5時だった。
「……寝すぎたな」
ベッドの上で背伸びをして、ブランケットに包まったままカーテンの外を見る。秋の朝は遅い。空は夜を色濃く残したまま、まだ星がいくつか輝いていた。こんな時間に目が覚めたのはあの夏の試合ぶりだった。
だが起きるのには僅かに早い時間だった。自主参加の朝練には顔を出すつもりだが、それでもあと30分は眠れるだろう。君下はゆるく瞼を閉じて、再び睡魔がやってくることを祈った。
そうして暫くうとうととしていると、ブルッ、と枕元のスマホが振動した。震え続けるスマホに苛立ち、チッと短く舌打ちをしてもぞもぞと手繰り寄せる。
「あ?」
あれからまだ十分も経っていなかった。当然アラームも鳴っていない。ホーム画面に残っていたのは、メッセージアプリからの通知で「バカ喜一:不在着信」の文字。
「電話……あいつが?」
中学都選抜の付き合いで止むを得ず連絡先を交換した記憶はあるが、実際に番号を使ったことなど今まで一度もなかったはずだった。メッセージアプリって電話帳が勝手に登録されるのか? 寝ぼけた頭でそんなことを考えていると、手の中のスマホがもう一度震えだす。また「バカ喜一」からの着信だった。本当に本人なのか怪しいところだが、君下は出るかどうか迷った末、緑の通話マークに触れた。
「……おう」
『お、繋がった。そっち何時だ?』
「はあ?」
『だから、何時だって聞いてんだろ』
電話の相手はちゃんと大柴だった。だが言われた言葉の意図がよく分からない。もしかしてかけ間違いなのか? 偉そうな口調はいつも通りなのに、随分と久しぶりに声を聞いたような気がした。
「朝5時過ぎだが」
『ア? んな早く起きてるとか、ジジイかよ』
「んだとテメェ」
親切に教えてやった挙句に罵られ、カッと頭に血が上った君下は通話を切った。強制終了。二度とかけてくるんじゃねぇと思いながら、ブロックしようと思ったがどうにもやり方がわからなかった。覚えていたらあとで鈴木に聞こうと思った。
へんな電話のせいですっかり目が覚めてしまった。少し早いが支度をして、まだ空が暗いうちに家を出た。その後電話がかかってくることもなければ、人の疎らな電車に揺られてぼんやりとしていると、あれだけ嫌っていた大柴から着信があったことなどすっかりと忘れてしまった。いつのまにか日が昇っている。たくさん寝たからか、昨日よりは少しマシな気分だった。
「お、昨日より元気そうだな」
そう言われて君下が振り返ると、いつのまにか鈴木が後ろの席に座っていた。鈴木はいつものように牛乳パックのストローを噛みながら、片手であんぱんの袋を破っている。この男はたしか君下の隣のクラスだったはずだが、まるで最初から自分の席だと言わんばかりの態度で他人の席に腰掛け、口の端からパンくずをぼろぼろと零していた。
「食い方が汚ねぇ……」
「いやこれパッサパサなんだって。見ろよ、半分食ったのにまだあんこが出てこない」
「やめろ、食いかけを人に向けるな」
「絶対あんこ入ってないよな? チクショウ売店のおばちゃんに文句言ってくるわ」
ドッコイセ、ととても高校生に似合わない掛け声とともに、鈴木はのそりと立ち上がると大きく背伸びをした。くああ、と大きく口をあけて欠伸をする鈴木に向かい、「お前こそちゃんと寝てんのか?」と問いかけると、背伸びのせいではみ出したシャツをスラックスに押し込みながら「いやーホラゲ実況見てたら寝れなくなってさ」とケシの実のついた口でぼそぼそ呟いている。
「あ、」
唐突に声を上げた君下は、そういえばこの男に聞きたいことがあったはずだった。律儀にも椅子を元に戻した鈴木が「ん? なに?」と首を傾げていたが、やっぱり思い出すことができずに「いや、忘れたわ」とだけ返した。鈴木はしばらく不思議そうな顔をしていた。
「君下ってわりとおしゃべりだよな」
「別に、普通だろ」
「なんか色んな噂が立ってるからさ��てっきりヤバいやつかと思ってたけど。口が悪いしちょっと変だけど、思ったより親しみやすいっていうか」
「変って、どこが」
「そのインナーの信じられないほどのダサさとか」
「ハァ? 目ぇついてんのか格好良いだろうが」
「あとそのネックレス、田舎のチンピラみたい」
「お、お洒落だろ……」
「全然。てか普通に怖いからやめたほうがいいよ」
そんな感じでああだこうだと一通り文句をつけて、鈴木は去っていった。不思議な男だった。それでも嫌な気がしないのは、陰口を言う上級生たちとは違い、この男に一切の悪気が感じられないからだろうか。
▽
枕元で長い振動がして、君下は無意識のうちにスマホを手に取ったらしい。枕に顔を埋めたままそれを耳元へ当てると、ガザガザとしたノイズに混じり、男の低い声がする。
『おい、起きてるか』
「んーー……ぁんだよ、」
喋りながら、寝起きの君下は自分が誰と話しているのかわからなかった。頭が重い。昨夜は遅くまで予習をしたから、あまり寝たような気がしなかった。そんな君下の都合など知らない男は、『なんだよ、毎朝5時に起きてるんじゃないのか』と不貞腐れている。
『寝ぼけてんのか?』
「………………っるせーんだよタワケが」
ムニャムニャと呟いて、諦めたように薄っすらと目を開ける。ぼやけた視界が捉えたスマホの通話画面には「バカ喜一」の文字があった。ちょうど朝5時を過ぎたところで、昨日も似たような時間に電話があったことを思い出した。
「テメェ……ふざけんのも大概にしろよ。こんな朝っぱらに電話してきやがって」
『るせぇな、俺だって暇じゃないんだよ』
「つーかお前、今どこに居んだ」
『イギリス』
「ハア? テメェのほうこそ寝ぼけてんのか?」
『昨日言っただろうが』
「聞いてねぇ。 つか、イギリスがどこか知ってんのかよ」
『当然だろ、馬鹿にするな』
「馬鹿だろうが」
『ブッ殺す』
そこでブチッと通話が切れた。大柴が切ったようだ。
「いや……何なんだよ」
君下はスマホを放り投げると目を瞑り、ごろりと仰向けになった。両腕を額の上に乗せて、はぁーっと長い溜息をついた。
……イギリスだと?
学校も練習も来ないやつが、なんで突然そんなところに居やがるんだ。テメェが練習に��ないせいで、俺はやりたくもないフォワードをさせられているというのに。
ブーッと再びバイブレーションが鳴った。また大柴からの着信だった。自分から切っておいて掛けてくるとは、奴は余程暇なのだろう。電話に出るか迷った君下は起き上がり、のろのろと部屋を出て小用を足しに行った。戻ってくるとまだスマホが健気に鳴っているので、仕方なく濡れた手で通話ボタンに触れる。
『遅い』
「うるせぇ俺はテメーと違って暇じゃねぇんだ」
『せっかく俺様が起こしてやったってのに』
「早すぎだ馬鹿が。そっちは……夜8時ってとこか」
『ああ、結構寒いぞ』
君下は通話開始5秒で電話に出たことを後悔した。どうやら大柴はモー��ングコールのつもりで電話を掛けてきたらしい。余計なお世話だ。
だが本当にイギリスにいるのだな、と君下は思った。そもそも日本にいるのならば、大柴がこんな時間に起きているはずがない。
「つーか、なんで急にイギリスに?」
『従姉妹の結婚式だ。俺も練習があるし、最初は行く予定じゃなかったんだが無理矢理母さんが……まあ、いろいろあんだよ。家庭の事情ってやつだ』
「ハッ、金持ちも大変だな」
『そういうお前は、練習はどうだ?』
「あぁ……」
君下は黙ってしまった。あれだけ練習に不真面目だった大柴が、部活のことを気にかけているのが心底意外だった。だからこの男に本当のことを言うべきなのか、少しの間迷ってしまった。
俺が今、お前のポジションをやっていること。俺のいたポジションには、大して上手くもない三年が入っていること。そのせいでなかなか連携が取れずに水樹が苦労していること。皆はお前がもう戻って来ないと思っているということ。
……というか、お前は本当に戻ってくるんだよな?
そんならしくもない疑問までもが浮かんできたところで、電話の向こうから『喜一、そろそろ出掛けるわよ』と彼の姉らしき声が聞こえてきた。
『悪い、もう行くわ。今から夕食なんだ』
「あ、ああ……そうか」
『じゃあな、俺の分までしっかり練習したまえ』
「うるせぇタワケが。お前こそサボってんだから筋トレぐらいしとけよ」
『余計なお世話だバーカ』
ブツリ、そこで今度こそ通話は終わった。
最後、咄嗟に口うるさいことを言ってしまった君下に対し、大柴は本気で怒っている様子ではなかった。どちらかというと仲の良い友人に対して使うような、気安い軽口のような「バーカ」だった。聞きなれない声になんだか胸のあたりがむず痒く、自分のベッドの上だというのに居心地が悪かった。
いつのまにか、普段起床する時間になっていた。アラームのスヌーズ機能を切った君下は、もうすっかりと目が覚めている。
▽
翌朝も大柴から電話が掛かってきた。やはり朝5時ちょうどだった。
『起きてるか?』
「ン゛……んだよ喜一……」
『おい起きろよ、俺は夕食前しか時間が取れねぇんだ』
聞き飽きているはずの大柴の声はどことなく落ち着いていて、寝起きの耳にやさしい、低い声だった。君下は練習の疲労が溜まっているせいか身体が怠く、目を閉じたままごろりと寝返りを打って仰向けになる。
『お前が疲れてるなんて珍しいじゃねぇか』
「別に、いつも通りだろうが」
『あっそ』
「それで結婚式とやらは終わったのか?」
『いや、明後日だよ』
「そうかよ……」
一言二言と適当に話しているうちにだんだんと頭が回ってくる。冷静になった君下は、なぜ俺はこいつとどうでもいい話をしているのだろう、と訳がわからなくなった。思い返してみれば大柴と、こんな友人同士の世間話のような会話をしたことがなかった。
昨日だってそうだった。部活の様子を聞いてきた大柴があまりにも意外だったので、君下はつい本当のことを言い止まってしまった。つまり君下は大柴に気を遣ったのだ。この犬猿の仲である男に、悪童と呼ばれた男が、だ。信じ難いことである。
『そういや今日筋トレしたぞ』
「テメェどうせ腹筋10回とか、そんなしょうもねぇこと言うんだろ」
『なぜ分かった?!』
「バカじゃねーの」
『う……で、でも走ったぞ! ホテルの横にバカでかい公園があって、デカイ犬もいっぱい走ってた』
「へーへー」
『んだよ舐めやがって……フン、まあいい。俺様は今からレストランへ行くからな』
今日はロブスターだ! と電話口で叫ばれ、思わず顔を顰めているとそこで電話は切れていた。ロブスターは羨ましいが、一体あいつは何がしたいんだ。
その日は土曜日で、午後の練習では他校との練習試合が組まれていた。相手は東京でベスト8に残る常連校であり、選手層も厚く、攻守ともにバランスのいいチームだ。そこへ君下が初めてフォワードとして、ボールキックをすることになったのだった。
「君下、お前は無理に取りに行かなくてもいい。が、来たボールは必ず拾え。自分で狙えるなら狙って、無理ならいつも通り水樹か、右サイドの橋本に流せ。俺はお前にフォワードに入れと言ったが、お前のやることは普段と少しも変わりないよ」
試合前に中澤の言葉を聞いた君下は、あぁなるほど、と思った。まだ一年の君下にエースナンバーを与え、トップ下としての才能を見出したのは中澤であり、敗戦が続いた今でもその可能性を見捨てられたわけではないことを理解した。
要するに司令塔のポジションが一列上がっただけだ。とは言えそこはチームの最前線であり、全体の指揮を執るには偏りすぎている。後列を動かすためにはどうしたって中盤、とくにトップ下を経由しなくてはいけない。その為の「大してうまくもない三年生」だった。つまり君下が全てパスで動かせばいい。
結果は、数字だけで見れば引き分けで思うようにはいかなかったが、君下にはたしかに手応えがあった。課題も見えた。後半で蹴ったフリーキックがうまく入ったとき、求めていた何かが満たされる感覚があった。本来ストライカーならば持っているはずの獰猛さを、この練習試合を通して君下はまざまざと思い出したのだった。
「おつかれ〜」
首元をひやりとしたものが触れ、君下は思わず「ヒッ!」と悲鳴を上げた。ゾゾゾ、と鳥肌を立たせながら振り向くと、冷えたスポーツドリンクを片手に鈴木が立っていた。その後ろに佐藤という、いつも鈴木と組んでいる男もいる。
「テメェは……いつもいつも俺の背後に立つんじゃねぇ」
「こわ、どっかの殺し屋みたいだな」
君下が「ほい」と手渡されたドリンクを受け取ると、二人は君下の隣に座り込んだ。試合に出ていない二人は何をするわけでもなく、ただ君下が靴紐を解いているさまをじっと見ているだけなので、どうにも居心地の悪い君下は「んだよお前ら」と渋い声を出す。
「君下、なんか今日は吹っ切れたみたいな顔してる」
「そうか?」
「うん、ちょっと嬉しそうだよ。な、佐藤」
「うーん���ごめん。俺には全然わかんないんだけど」
いきなり話を振られた佐藤は、眉を下げて困ったように笑っている。君下はあまりよく佐藤のことを知らないが、こいつは苦労人タイプだろうなと思った。
「でもお前、あれはまさか狙って打ったのか?」
「あのフリーキックな。相手チームもびっくりしてたよな」
「まあ、あんなのはマグレだ。毎回入るようなもんじゃねぇ」
半分は謙遜だったが、それを百発百中にするための練習をしてきたつもりだった。今日入ったのはそのうちの何割かに過ぎないのだろうが、キックの精度は経験の数に比例すると君下は思っている。しばらくどん底を歩いてきた分、この1点は希望を持つには十分な1点だった。
「ていうかさ、大柴って辞めてないよな」
何気ない佐藤の一言に、君下は飲んでいたスポーツドリンクを吹き出しそうになった。寸でのところで飲み込むと、気管に入ったのか「ゴホッ!!」と大きく咳き込む。鼻の奥がつんとする。
「うわッ大丈夫か?」
「……な、何でもねぇ」
「あー佐藤、こいつの前で大柴の話はナシだろ」
「え、そうなの?」
君下は口元を拭いながら、キッ、と隣の鈴木を睨んだ。当の鈴木は涼しい顔で、しかしぺろりと舌を出している。なんだか嫌な予感がしていた。
「喧嘩の相手がいなくなってさ、ほんとは寂しいんだよこいつ」
「おい、何バカなこと言ってやがる」
「そうなのか?」
「あ、水樹先輩」
「なっ……?! アンタも信じてんじゃねぇ!」
鈴木の両頬をつねる君下の後ろに、いつのまにか二年生である水樹と臼井が立っていた。「いひゃい、いひゃい」と抵抗する鈴木の声に、通りかかった他の先輩らも「え、なになに?」「何してんの?」と次々と群がってくる。
君下は咄嗟に鈴木の顔から手を離し、「あ、いや、何でもないっす」と、わざとらしい笑顔を貼り付けて肩を組んでみせた。これ以上鈴木が何も言わないように、肩を組むふりをして首を締めようという魂胆だったが、水樹の隣に立っていた臼井が唐突に「それにしても、今日のお前はすごく良かったよ、君下」と褒め出したので、それがあまりに意外だった君下は「あ、あざす……」と答えることしかできなかった。
「確かにあのキックは痺れたわ」
「わかる、最近めっちゃ蹴ってたしな」
「ポジション変わって大変だったろ? ほんとお前はよくやってるよ」
結果は引き分けで褒められたものではない。だがそれでもきちんと評価してくれる者もいる。その事実にほんの少しだけ泣きそうになっていると、首を大きく傾けた水樹に「今日の君下は、なんか大柴みたいだった」と言われて、君下はその日で一番キレ散らかしたのだった。
▽
電話が鳴っている。
君下はスマホを手に取り、「着信:バカ喜一」の文字をぼうっと眺めた。
大柴がいなくなって既に5日が経っていた。
「おう」
『あ? なんだ、起きてやがる』
「毎日テメェに起こされるのも癪だからな」
自分で言いながら思わずふ、��小さく笑うと、聞こえていたらしい大柴が『なんだよ、気持ち悪いな』と笑っていた。
未だに電話で話していることが幻のように感じるのは、大柴の声が記憶の中よりも柔らかいからだろうか。あの嫌味ったらしい顔も見えないせいなのか、不思議と君下が本気で苛つくことはなかった。
『さっきまで隣の公園で子供たちとサッカーしてたんだ。俺様の圧勝だったけど、でもさすがはヨーロッパって感じだったな。俺らが子供のときより上手いかも』
「へぇ、折角だから負けてくれば良かったのに」
『負けねーよ。俺を誰だと思ってる』
「大人げねぇな」
『それで急に土砂降りになって、慌てて戻ってきたところだ』
「そりゃあ、災難だったな」
『うわ、道が冠水してやがる。酷いなこれ』
大柴の声が遠くなったので、恐らく窓を見に行ったのだろう。そういえば電話に出たときからザーザーと雨のような音がしてた。
「明日なんだろ、結婚式。あ、待てよ、日曜なら今日か?」
『明日で合ってる』
「せいぜい楽しんで来いよ」
『ん。式が終われば明後日にはもう飛行機だ』
あ、帰ってくるのか、と、君下は当たり前のことを思った。中澤にも言われていたので分かってはいたが、なんだか実感がまるでなかった。
大柴は戻ってくる。そうしたら君下はもうフォワードじゃなくなる、かもしれない。元に戻ることは喜ばしいことのはずだった。
だが君下は、昨日の練習試合で何かを掴みかけた気がした。出来ることが増えるということは、単純に考えて良い事のはずなのに、大柴の居ないチームがうまくまわりはじめてなんだか寂しく思ったことを、鈴木に言われた君下は気づいてしまったのだ。
同時に君下はずっと苛立っていたのだ。
大柴がいなくなり、それを受け入れはじめたチームと君下自身に。
当然のように中澤が君下をフォワードに置き換えたことに。
君下に黙って、勝手にイギリスなんかに行ってしまった大柴に。
「ハハッ」
思わず君下は笑った。自分でも気味が悪かった。それでも笑わずにいられなかった。お前がいなくて寂しいと言ったら、この男はどんな顔をするだろうか。そう考えて、今だけは電話越しで顔が見えないことが惜しかった。
「さっさと帰って来ねぇと、寂しくて泣いちまうだろうが」
『……へ? な、なに言って……おま、』
予想通りの反応を見せた大柴がおかしくて、笑い死にそうだった。君下は暫く笑いを堪えていたが、どうしても漏れてしまう吐息を聞いて、本当に泣いているのだと勘違いした大柴が「いや、仕方ねぇだろ……」と慰めのような言葉を吐くので、もう限界だった。笑いすぎて本当に涙が出てくる。
「冗談だバーカ。だがぼーっとしてると、俺がテメーの背番号貰っちまうからな」
『あ゛?! なんでそうなるんだよ!』
「ああ、言い忘れてたが、俺いまお前のポジションしてんだわ」
『ハア?! 聞いてねぇぞ!』
「まあ言ってないからな。お、練習の時間だ。せいぜい旅行を楽しめよ」
『おい待てっ!』
ブツリ。通話を切って、ついでに電源���落とした。
君下はもう寂しくなどなかった。
君下の電話に怒り狂った大柴が帰ってくるのが楽しみだった。
( NIGHTCALL / おしまい )
0 notes
Text
慟哭は復讐の声 1.奴が帰ってきた
2017年3月に行われたサタスペのキャンペーン・青空爆発ドッグスの最終話を小説風に脚色したものです。
いつの間にか久し振りに飲もうぜなどと言い合える連中になってしまった。それに二つ返事で喜べる仲になってしまったのだ。誰がなんと言おうとも、自分たちが実のところどう思っていようとも。
「みっちゃんとリーダーはまだ来てないみたいですねえ」 ダイキリを片手に呟いたのは崔恭一だった。紫の瞳は壁に掛かっていた時計を確認したがさっき見たときと変わらず二時十七分で止まっているらしく、当てにならないと顔をしかめては酒を煽った。よく見たらガラスが割れているし中に蜘蛛の巣が入り込んでいる。 「まあリーダーが時間にルーズなのは今に始まったことじゃないですしね」 酒を勧めてくる悪い大人にNOが言える優等生DB・マヤンはカラシニコフを玩具のようにして遊んでいる。チョコレートの盛り合わせは地下の籠った熱で溶け始めているところ。室内でのマナーと言って着こんでいた帽子とコートとジャケットも脱いでいた崔も少し暑そうだ。 「一松も適当なところあるしな」 黒くないビールをぐっと傾けて一気に飲み干したのはヴィンセント・ジョーンズ。空いた腹にアルコールは良くないと頼んだつまみに手を付けないまま三杯目だった。口に白いヒゲがついたのを褐色肌の少年が揶揄い、黙って手の甲で拭う大男を横目で見ながら、自分は次にどんなものを飲もうかと崔は考える。昔から所以だの謂れだのを考えるのが好きで、特に拘ってるのがジンクスだ。ちなみにダイキリについた意味合いとは、希望らしい。 例え亜侠などと言うボンクラであったとしても酒を飲むなら日が落ちてから、全員が揃ってからと思っていたのにリーダーであるパット・ユーディーともう一人の一松三子が現れる気配が無いので痺れを切らして諸々を注文したのが三十分前になる。お決まりになってしまったこの個室はそれはもう店の奥の奥で、料理の映えなど気にもかけない白熱灯が光るばかりで外が今どんな様子なのかは把握できない。相変わらず狭い部屋はあと二人を収容出来るのかも疑わしいくらいだがパットはまだ成長しきっていない少年だし一松は枝みたいに細いから結局は大丈夫なのだろう。 「なんだっけ? パソコンのCPUのクロックアップ? あれに凝ってるって言ってたっけ。僕わかんないです」 銃を傍らに置いたマヤンがもうぬるくなってしまったオレンジジュースを少しだけ飲んだ。 「まあ……一松のほうは最近恋人も出来たしな」 「最近? もう半年も前の話ですよ。若いんだからその感覚は治しましょうよ」 「いやいや忙しかったからさ、時間が経つのが早かっただろ」 最年長に老いを指摘されてヴィンセントが焦る。言い分はまぁ、わからなくもないが。 「この半年の間になにがありましたっけ?」 因幡の白兎が頼んできた件は何ヶ月前でしたっけという少年の問いに、三人は六ヶ月を思い浮かべ始めた。ワニとサメが合体した化物を海上に浮かぶ船から相手するのはシビアなものだった、舵を取ったマヤンは免許を取れる腕前に変わり果て、依頼人のウサギに騙されたとわかるとこういうときはパイにするんだよと一松が喜々として包丁を研いでいたこととか。さるかに合戦は親の敵討ちをとカニが頼んできたが実際にはサルはむしろ良い奴で、カニ率いる詐欺師集団が豪邸を奪い取る算段だったらしい。甲羅が嘘みたいに硬くて銃弾を物ともしないので崔が無理だと泣き喚き、結局ヴィンセントが手足をもいで物理で解決させた。あと一回だけ珍しく人間がやってきて某盟約で秘密裏に開発されているウィーゼルの詳細を調べてくれとのことがあったが、実際に生み出されていたのは洗脳された殺人イタチであった。結局動物じゃねえかとパットが叫んでいたが同情禁じ得ないぇ 「どうでもいいですけど本当に動物関係多いですね、ウチは」 ようやくグラスを空にして、店員を呼ぶのに立ち上がりながら崔は呟いた。 「なんか呪いなんじゃないですか」 マヤンが言った。割と呪い染みた運命だと。錬金術師が言うと洒落にならんなとヴィンセントは追加のジョッキを頼んでいた。
それから十数分、パットと一松は未だ来て居らず、幸運にも趣味の近い者同士であったため途切れなかった会話に割り込んでマヤンの携帯が鳴った。数年前にヒットした映画の荘厳な主題歌はチープなアレンジに変えられ、すぐに通話ボタンを押される。聞こえたのは荒い息遣いで、その向こうから意味を成さない騒音が重なっていた。正確には動物の鳴き声がほとんどだった。苦しそうな呼吸が三回、それから相手は声を発する。 「すまぬ、マヤン」 この声を知っている。マヤンの脳裏にはエンペラーペンギンの顔が浮かんでいた。もう若干懐かしいくらいのあのペンギンである、一時は長電話した仲ではあるがその後についてはお互いなんの音沙汰も無く過ごしていた。 「どうしたんですか、なにがあったんですか?」 彼に何故こんなにも余裕がないのか心当たりがない。それはもう当然のように喉から出てきた。マヤンの不安を滲ませた声に崔とヴィンセントも動きを止める。 「奴が帰ってきた」 エンペラーの声に油断は許されていなかった。奴について尋ねる前に動物園の惨劇は彼を吞み込まんとしていた。多くを語れないと判断した彼が慎重に付け加える。 「私もここまでのようだ……奴らには気をつけろ」 「ど、どうしたんですか! なにがあったんですか、返事をしてください! エンペラー!」 続いて、爆発音。マヤンの耳が壊れる前に電話はぶつ切りされ、状況から取り残された故の空しい呼び掛けが残り、その余韻もいよいよ無くなると温情とばかりにラジオにノイズが走った。ブレイク三歩手前のバンドミュージックを流していた店内放送は公共の電波に切り替わり、たった今の速報を流す。 『臨時ニュースです、天王寺動物園が爆破されました。被害のほうはまだわかっておりません。近隣の住人はすぐさま避難をお願いします』 なんと他人事な声なのか。繰り返しを聞き流しながら、齢十三は呆然としたままなんとか携帯を落とさないように必死だった。 「一体なにが……」 「なにか……爆発があったとかなんとかって言ってますねぇ」 崔はいつの間にか上着を着ていた。エンペラーどうこうって、ひょっとしてあの? と腕を横に曲げて手のひらをぱたぱた動かしているが、それはペンギンのつもりなのだろうか。 「天王寺動物園は今や彼のキングダムです、そこが爆発されたということは」 言葉はどうしても続かなかった。予測出来た会話ほど無駄な時間があるだろうか。一瞬で誰もが無口になり、焦燥感が追い立てるように神経を焼く。この町で最も静かな場所に違いなかったが、やがて扉のノックが三人を、少なくともこちら側へ呼び戻した。しかしそれが安心できる切っ掛けだとは思えない。 「雲行きが怪しいですねぇ」 眉を顰める崔がちらりと長年の友人を見た。嗚呼、了解、言われなくてもとヴィンセントが扉に近寄る。何者だ、尋ねる前にガチャガチャと言った複数の銃の準備に気付いた。途端に吹き飛ばされたドアノブがマスターキーによるものだと言う認識は後で良い、それよりもまず。 「物陰に隠れろ!」 戦闘力に特化した男の剛腕が、物量が乗った木製のテーブルを倒した。入口を塞ぐように天板を向けたがしかし、食器が割れるよりも先に手榴弾が投げ込まれるのを目撃する。キン、と光が飛ぶような音が耳をつんざいた。 「ヴィンス!」 真っ先に反応出来たのはマヤンだったが余りにも唐突過ぎて体が追い付かない、足は床の凹凸に引っかかって大きくバランスを崩した。勢いのままヴィンセントを倒し、大男は幼い身を庇うために受け身を取らずに少年を抱えて壁際に転がる。後ろにいた崔は奇しくも巻き込まれ潰されたが、全員が部屋の隅でギリギリ爆風を��けたと言うことになった。 まだ晴れない土煙を薙ぐ如く重い一撃が振り下ろされたのも、ヴィンセントが咄嗟に起き上がってバットを握れたのも、片膝に体重を掛けて力任せにスイングしたのも、まるで瞬間的で、脅威は男の横に逸れてぐざんと床を抉った。ちょうど腰の抜けた崔の足元で、動きを止めてようやくごつい斧であることがわかった。ぱらぱらと破片が落ちる音。 「もう勘弁してくださいよ!」 崔が悲鳴を上げながら襲撃者を確認しようと上を向けば、開幕とでも言うように視界は良くなり、そこに蜜のような髪をふわりとなびかせた少女がいた。よくある組み合わせだと思う奴は現実を見たほうが良い、マヤンよりもずっと小さい女性が体格を遥かに凌ぐ斧を使ってこちらを真っ二つにしようとしてきたのだから。彼女は幼い顔立ちで丸く大きな目をしていたが、そこに光は見えず黒い鏡のような球に男を映すばかりだった。そしてまた同じように少女を凝視していた三人の傍へカツン、カツン、誰かがこちらへ近寄ってくる。 「モミジさんモミジさん、早まり過ぎですよ」 名前を聞いた瞬間に、全身が赤の匂いを思い出した。それが秋の葉の色なのか、血の溜まりだったか、判別を拒む程度に遠慮願いたい相手である。しかも非常に信じられないことにだが、やってきた男の声は知っているものだった。キングと呼ばれた男のものだ。 「その女はもしかして……あの……俺らが島で殺した奴か」 ヴィンセントは珍しくしかめっ面で、であるにも関わらずモミジと名称のある少女は静かにこちらを見つめるばかり。 「モミジさんは最近転生したばかりで言葉は喋れないようなんですよ、ご了承ください」 部屋に立ち込めていた砂埃はもうすっかり無くなっている。それでも聞き慣れない言葉を耳から入れた脳は困惑していた。一体何処のファンタジー時空からやってきた方々なのか、そう本気で思えたらどれだけ平静で居られたことだろう、まあ恐らく同時に死んでいるだろうけれど。 改めて確認すると、大斧を持ち必要最低限のプロテクターを身に着けた少女と、ペストマスクで顔の見えない軍服の男がいた。男のほうはやけに嵩張る外套と艶やかな素材で出来た傘を持っている。属性過多。その二人の後ろからもう一人が顔を出した。まだ増えるのかよ。 「やぁやぁやぁ! 皆さん、お久し振り……へけっ!」 うわ。 「いやー、この格好だと『へけっ』まで言わないとたぶんわかってもらえないからなー」 そう困ったように笑う白衣の青年は流石元マスコットの肩書を持っていただけあると言うか、だとしても素性を知っている分腹の立つ顔ではあるのだが、小動物的な愛らしさはあったかと思う。イメージカラーのオレンジが鮮やかだ。 「状況はわかってきたかな?」 「ジャパニーズノベルに帰れ!」 今まで黙っていただけだった���ヤンが耐え切れず声を上げた。それでも歯牙にもかけないと彼らは笑っている、いや一人は無表情だしもう一人はマスクを被っているから読み取れないが。 「地獄の閻魔様に復讐がしたいと言ったら、帰してくれたんでね? このチャンスをものにしに来ただけですよ」 東洋の冥界というのは、サボタージュが問題にならないのかな。動物から人間に生まれ変わる確率と言うのはかなり低い、それを少なくとも三回通しているのだからちょっと仏様を信じられなくなる。 「今日はただ遊びに来ただけです。当初の目的は達成していますので」 そのうちまた顔を合わせることになるでしょう、キングは言った。 「今この場で即行二度と顔も見たくないんだけど」 間髪入れずにマヤンは返す。素直で良いことだ、苦い顔の少年にやはり男はさも愉快と息を漏らす。 「人の姿なら殺れるんじゃないんですか、ヴィンス。やっちゃってください!」 「そういう問題じゃないだろ」 「だってあの巨大なクマがその可愛い女の子なんでしょ? なんとかなるんじゃないんですか!」 「さっきの斧結構ギリギリだったぞ?」 「またまた御冗談を」 「恭一さん、ただの女の子が、斧を振り回したりなんか、しない」 ならば試しにと崔はヴィンセントを壁にしながらモスバーグの銃口を少女に向けた。この距離なら当たらないこともあるまい、引き金を引くまでの時間は一秒も無かったがそれを見越していたかのようにキングが前に躍り出て持っていた傘を広げた。随分広い面積のそれはどんな細工を施しているのか全ての散弾を受け止める。崔が短い悲鳴を上げたとき、ヴィンセントは飛び出した。防衛線なら破壊すべき、と、しかし傘の先端に穴が空いているのを見たとき、そして瞬時に火花が散ったとき、なんとか銃弾を受け止めたバットは手から撃ち落とされていた。 「手が早いのはそちらも一緒でしたか」 その声はもう悦を隠すのを止めたようだ。けらけらと明らかにこちらを下に見る態度にヴィンセントがいよいよ声を低く唸らせる。 「……舐められたままでいられるかよ」 「いえいえいえ? しかし、本気になって貰えるのは嬉しいですね」 「命狙われて本気にならない奴がどこにいるんだこの野郎」 「本気を出してもらわなきゃ困りますよ、こちらも狩りのつもりで来ていますので」 「獣が人の姿を持ってから調子に乗りやがって」 その言葉にふん、と鼻を鳴らしたのは公太郎だった。細めた目にわざとらしく上がった口角、彼は耳に残る声で言い放つ。 「調子に乗っているのは皆さん人間のほうじゃないか」 ぎっとヴィンセントが睨み返せばやーいやーいと手をぴろぴろさせてくるので、駄目だこれは低レベルだとマヤンがスーツの裾を引っ張って静止させた。 「あなた方の命は私たちが頂きます。それまで余生をお楽しみください」 キングの右手が高く掲げられると、小気味好く高い音が響く。空気を弾くようなその合図は、遥か彼方からなにかを呼び寄せていた。それがなにか���と言うのは唐突に地層が軋み地下に位置するこのロクでもない酒場が崩壊しそうな揺れと激しい噴射音で、ただ大きなものであることしかわからない。そんな疑問も個室の天井の一角がごりっと盛り上がり穴が空くことで解決する。ちょっと訂正しよう、ロクでもない酒場が崩壊した。 冗談かなにかのように、ペンギンを象った巨大ロボがそこにいた。そうして差し込んだ手のひらにひょいひょいと元動物たちが乗り込み、用は済んだとこちらに振り返りもせずに帰っていく。そういえばロボットと戦ったこともあったな、あれは差し詰め百万ペンギン力と言ったところだろうか、パットが喜んだらどうしよう。ぽっかり空いた大きな穴から飛び去るロボットは憎し��を差し引いても恰好良かった。超絶技巧には付き物な盛大な効果音が聞こえなくなると、今度は結構な雨の音が聞こえる。季節外れにもほどがある夕立だ。 「夢じゃないですよね……」と崔恭一。 「ほっぺでも引っ張りましょうか?」とDB・マヤン。 「死にかけたのは現実だぞ」とヴィンセント・ジョーンズ。 「とりあえずリーダーとみっちゃんにも連絡を取らないと」 「……と言うか、二人の身のほうがよっぽど危ないんじゃないですか?」 「一人だしな」 「特に一松さんが一番危ない気がするんですけど」 「……アリエルがいるだろ?」 「なにはともあれ仲間がピンチなんだから急ぎましょうよ」 「おう、そうだな」 電話番号を探しながら三人は思う。どうか、どうか無事で居てくれと。
◇
ベンチマークの結果はなかなかに良いものだったし、今月中はランキング十位圏内は安定だろう。別に誰かと競争したいわけでもないが、記録は残しておきたかった。楽しすぎて時が止まったかのような感覚だったのだ。無論あくまで感覚の話で現実は足早に動き続け、結局約束の時間の五分後に家を出た。遅刻は確定しているとわかっているが出来るだけ急ごうと思う。半年前から愛用しているマルチボードに乗っかって人の合間を縫いながら最高速度だ。 しかし、JAIL HOUSEまであと十数分というところで。つまりは天王寺動物園を横切ろうというところで、その公共施設から大きな爆発音が聞こえ、パットは足を止めた。今日はなにかのパーティーだっただろうか、だとしたら随分オーバーすぎる花火だけど、領地を区別するための柵の向こうに煌々と燃え上がる火の海を見てしまえばそれは厄介ごとの類であるという認識に変わる。それにあの場所にはかつて依頼で知り合ったエンペラーがいるはずだった。荷物の中からごそごそと取り出すのはペンギン帽子だ。使えるかもしれない、いや使いたいわけじゃないけど、絶対に使いたいとかじゃないけど、念のため。誰に言うでもない言い訳が心に渦巻いているとその出会いは突然に訪れた。 「パーット!」 可憐ではつらつとした透き通る声だった。それは聞いた者の脳に春を呼んで蝶が飛ぶように目の前をチカチカさせた。体温は先走りすぎて夏の暑さだったし、比喩的に空まで跳ねた心臓はびくびくと脈打っていた。そういう体の症状を無視するかのように頭の上からサアと血の気が引いているような気がしている。目の前が真っ暗になりかけた。ここで意識を失ったらどうなってしまうのだろう、考えたくない。それでもパットはぎこちなく後ろを向いた。 見た目は全然知らない女性だった。天使を思わせる純白の髪に鮮やかな青いリボンのカチューシャ。目は大きくてあくまで美しく長い睫毛を持っている、虹彩は深い緑で、白い肌に際立っている。ブラウスは透けたフリルが軽やかで上品なリボンが装飾としてついていてまるでお嬢様のようだ。全然知らなかったが、重なる部分がどうしてもあのネズミを思い出してしまう女性だった。ロマンスの神様、この人でしょうか? 「誰だお前は?!」 これでどうかまったく違う名前だったら良かったのに、彼女はにこにこしながら、えー覚えてないのー、などとからかってくる。可愛い。違う。埒が明かないと思ったのでじりじりと後退りをしたが、柔らかな指がそっと腕を這うだけで鉛を飲み込んだように足が重たくなる。逃げないで。呟いたか、そうではなかったかは定かではないがパットの体は本当に動かなくなってしまった。 「パット、どこにいくのよ?」 全然怖くないちょっと怒った声でパットに詰め寄る。甘い良い香りがした。違う、違う今本当にそういうことはいらない。 「な、何故貴様が生きている?!」 あの時確かに死ぬような目に合わせたはずだった。ていうか一回死んだよな? 赤い糸って地獄まで続くものなのか、マジか、知らなかったなぁ。今すぐ縁を切りたいと思った。そんな心情を露ほども知らずにパットに愛玩的な視線を送る乙女は、やっぱり可愛いわーなどと非常にマイペースである。そこに前ほどの策略は感じられないが、それでも怖いものは怖いのである。年下の男の子に合わせて少し屈み、どうしたのと覗き込む愛らしい顔を見て、気が付いたら周囲が思わず振り向くほどの悲鳴を上げていた。パットの叫び声はそれはもう天を穿つほどで、曇り空からは破裂したように雨が落ちてくる。思春期の仁義無き戦いだった。 思考停止は悪手だ、アドバンテージをどうにか上手く使いたい。本当は金輪際アプローチをしてこないで頂きたいが果たしてこの百戦錬磨を言いくるめられるかと言われると残念ながら自信が無い。昔から女と付き合って上手く別れられた試しが無いんだよな。嗚呼、ここにチームの皆がいてくれたら形振り構わず助けを求めているところだ、最悪こういうのが得意な恭ちゃんだけでもいいから居て欲しかった、自分が遅刻したのが悪いんだけど。仕方ないからせめて時間を稼ごう、そうせめて皆に会いに行って対処を考える時間を、そしてチームを揃える時間を。ここまで1.4秒。 「……二十四時間」 ���戦態勢と言うべき状況に女はくすくすと笑うだけだった。潰したい、こいつを潰したい。 「二十四時間、俺になにもするな。関わるな」 「本当にいけずなんだから……そういうところも好きよ」 彼女はぱちんと器用にウインクをしてから、目線を外して考え込んだ。濡れてしまった細い髪が肌に張り付いている。暗い所にいたら幽霊と勘違いしてしまいそうだった。いや、幽霊かもしれないけれど。 「まぁでも、また会うことになると思うわ」 そう告げると、彼女は後ろを向いて花びらのような手をひらりと振りながらようやく離れて行った。凍っていた体が自由になると、パットは反射とばかりにチーフスペシャルを取り出して乱射したがやはり、まるで当たることはない。やっぱり幽霊なのではないか。スカートの裾が揺れて疎らで灰色の人ごみの中に消えていく。雨は落ち続けて、落ち続けて、道はどす黒くなっていた。 少年は大きく息を吐き出したが、動悸が収まる気配は無いようだ。いっそ心臓を取り換えることが出来たら良かったのに、彼女の笑顔が刻まれた脳みそだけ切り取れれば良かったのに。呪いのような愛だ。
いつまでも濡れているわけにはいかなかったので軒下に潜り込めば、忍ばせていた携帯が鳴った。待ってた。相手を特に確認せず、パットは電話を取る。 「大変だ! 奴が! 蘇った!」 「嗚呼、そっちもか……」 疲れたような声をしていたのはヴィンセントだ。そのすぐ傍でマヤンと崔が生きてた良かったなどと喜んでいるのもわかる。死んでたほうがマシだったかもとは言い辛い。 「こっちもな、ちょっと色々変なことがあったんだよ。蘇ってきたような……人間型のペンギンに、人間型のネズミに、人間型のクマが」 「落ち着いてください、今までの仇敵が何故か知らないけど人になって戻ってきたんです」 擬人化って夢があるけど、これは悪夢です。マヤンが訴えるように言った。 「なるほど、擬人化が得意なフレンズが蘇ったと言うことだな、すごーい!」 「やばーい!」 お子様方は半ば自棄になっている、と大人二人は思う。島に行ったときからなんだか二人が狂いだしている衒いがあるが大丈夫だろうか、崔とヴィンセントは無言で相談していた。リーダーは元から狂ってた気がしないでもないが。 「ま、まさかとは思うがその敵の中にあのクソマスコットはいなかっただろうな?」 「……正直なところ、全員蘇ってても不思議じゃないんじゃないか?」 「���ってください、全てが蘇ったって言うんなら、一松さんが危ない!」 「アリエルがいるから大丈夫って言っただろ」 「お約束かと思って」 大変だったと言う割に電話の向こうは楽しそうだった。それにしても、一松がいないのか。でも問題ないだろう、アリエルがなんとかすると俺でも思う。むしろ敵と相打ちになってあわよくば死ね。たまに肉盾として蘇ってくれ。 「アリエルがボコボコにされてたら嫌でしょ? 急ぎましょうよ」 「お、おう、じゃあ車出してくれ車」 はーいと良い子の返事をしたマヤンがフェードアウトしていき、鍵ちゃんと持った? 大丈夫? と崔が再三確認していて、ヴィンセントはそれじゃあ沙京で一松を探そうと言って通話を切った。 「もう、やなんだけどあいつら相手にすんの」
◇
いつも持ってるジッポー��忘れたのだ。特別に思い入れがあるわけではないけれど、なんとなく身近にあったものだから無いと落ち着かなかった。無視も出来る軽い理由で後戻りの面倒臭い帰路を辿ったのは何故だろう、胸騒ぎがしたからだろうか、ちょっと遅れたくらいでは気に留める人はいないと思っていたのもあって、一松は自宅と言うにも憚られる居住地へ引き返していた。空は一雨来そうな面持ちで冷たい水を吐き出さんとばかりに鈍い色を広げている。ずっと外にいるわけにもいかないと空気を確かめながらふと、焦げた臭いが鼻を突いた。沙京で火を使った形跡なんて悪い予感しかしないし、余計なものは見たくないと避けて通っているにも関わらずその不穏は徐々に近づいてくるのが気に掛かる。そう、悪い予感がする、自分の身に降りかかる予感だ。 果たしてそれは的中する。狭い路地裏は炎を抱え込んでやけに明るく燃えており、一松が寝床にしていた鉄製の檻が熱の揺らめきの隙間から僅かに見えた。ぬいぐるみを詰めていたのだからさぞかし火が回ったことだろう、気まぐれに集めていたものだったけれどこうも儚い別れになるとは。頭のほんの隅っこで考えながら、炎の前に立つ男とその足元に倒れ込んだ恋人のアリエルを素早く確認した。ここを離れたほんの十数分でなにが起こったのか見当も付かない。 「君は誰だ?」 ある程度の距離を詰めて、捻らずに声を掛けた。彼が振り向くとタイミング良く装置を起動したかのように突然強く雨が降り始めた。痛みにも似た寒さは周囲を凍らせて緊迫を育てる。 「お前に復讐しに来たんだ」 そう語る彼の姿は、まあ彼と言うからには性別は男で、大体同い年くらいに見える。中国系なのかもしれない辮髪と虎の刺繍の入ったスカジャンより、唯々こちらを睨みつけてひび割れたように歪む表情だけが夢に出てくるレベルで印象的だった。正直こういうのは得意じゃない。ここ最近アリエルに致命傷の与え方を教わりはしたがまだ頻発出来るほどじゃないし、そのアリエルは地に伏せている。そういえば地に伏せている、大丈夫だろうか? 「悪いけど覚えてないね、恨まれるようなことはたくさんしてきたし」 かと言ってこの手の輩を上手く切り抜けるための手札は無かった、そりゃ勘弁してほしい、家が燃えてるのを確かめてまだ一時間も経ってない。放火犯であろう男は、呆れたような表情も滲ませながら言葉を返した。 「そうだろうな、お前は極悪人だ。心当たりなんて腐るほどあるんだろう?」 小さく頷いてやれば反比例する如く溜め息を吐かれる。その息は怒りのままに震えていて、獣の唸り声のように不明瞭に呟く。なんだかおかしいなと思ったけれど、感情がそれしか感じられないのがどうにも人間味に欠けているようだ。 「俺の母親はお前との決闘で負った傷のせいで亡くなった。���親もだ、あの日お前が天王寺動物園に来なければ……!」 「嗚呼、そう言われれば見たことがある気がするけど、それだけ?」 彼の目が怨嗟で濁った。黒目がちのその瞳が人間のそれではないと言うことに気が付くと納得も出来る、何故ならば不本意にも害獣専門になりつつある亜狭チームが自分の所属する青空爆発ドッグスだからだ。それもあの夏の日を思い出す滲むような暑さと殺意を向けられれば結成当日を思い出さないのも無理な話だろう。良い日だった。だけど親が後から死んだ責任を取れと言われても困る、昨今親を殺される話も親に殺される話もよく聞く。大体私がなにをしたと言うんだ、ほとんどなにもしてない。猫に気に入られる性分と言うのも考え物のようだ。 「畜生共の恨みねぇ」 こいつはトラだと一松は理解した。 「畜生と言うのは、ちょっと違うな」 見ているこっちが引き攣りそうな顔面をしながら彼は言った。どういう意味か、尋ねようとしたところで落方に巨悪の影が見えた。激しい雨が遮るこの距離で見えるのだから大したものだ、ちょうどミナミのほうにロボットが降り立っているのがわかった。それがペンギンなどとふざけた外見でなかったらなんか面白いことが起きてるなと勘違いしそうなくらいに非日常だ。馬鹿みたいに豪勢な地響きに揺られながら、もしかしたらあそこはJAIL HOUSEかもしれないと感じた。 「そうそう天王寺動物園は爆破したよ」 「へぇ、派手なことしたね」 「俺は興味なかったけどな、あそこにはキングの敵がいるし」 ペンギンと来たから絡んでるかと思ったけど嗚呼やっぱり。あとハムスターがいるな。最悪で熊も追加だ。振り返っては改めてトンデモな事件に巻き込まれていたと眩暈がしそうだ。 「まぁ今日は挨拶だけにしておけとキングが言っているからな、この辺にしといてやろう」 「猶予が貰えるならこちらとしてはありがたいけど」 「猶予じゃない、これは狩りだ。獲物をじわじわと追い詰めて本気で怯えたところを仕留めたい」 「じゃあ今度は本気になれることを頼むよ」 「……そうだな、今度は本気にさせてやる」 彼は刺すような視線を残しながら、かつてそうだったのだろう虎の如き身のこなしで建物の高いところまでジャンプするとそのままビルの陰へ隠れていった。雨音がようやく耳に入り込む沈黙が出来て、自分がずぶ濡れなことにも気が付く。見慣れた路地裏は天上から落ちる雨で炎が消えていて黒く焦げているばかり。もう判別の出来ない綿の塊と随分壊れかけていた檻の破片がちんまりと置き去りになっていた。明らかな、二度と使えないのだという無言の訴えだ。 「アリエル」 思い出したように、というかあのトラを前にして油断できなかった分、放置してしまっていた恋人の名を呼ぶ。どうしてここにいるのかはわからないが、やはり青年の手によって致命傷を負ったのだと思う。品の良いブラウスに血の色が大きく染み込んでいる。皮膚は色を失くして氷のようだったし、体の力は全て抜けていて、か細く呻いたきり眉一つ動かさなくなって十数秒。死んでほしくないなと思った。実の所、これは彼女の気の迷いでそのうち自分に飽きて離れていくか殺されるかされてるだろうと予想していたけれど、半年の間に随分絆されていたらしい。滴る赤い髪を撫でながらゆっくり、柔らかい体を楽なようにしてやってから横に抱く。気を失ってるのだから支えてくれる手は伸びない、それでも彼女を運ばなければならなかった、なにせここに治療できる設備がない。あってもちょうど燃えて朽ちたところだ。最近の若い女の子は軽い、これくらい大した労力じゃないさ。
◇
JAIL HOUSの中はやはり騒然としていて、ただでさえ人がゴミのように集まっているのに混乱する者は混乱して、固まる者は固ま���ていて、とにかく脱出までに時間がかかった。地下から這いずり出ても先程までロボットが現れていた現場である、この雨でこの野次馬の多さは呆れかえるほどだ。小さな体を駆使して群衆をすり抜けシトロエンに乗り込むと、マヤンは少々オーバー気味にエンジンを吹かし周囲を散らした。見計らって、ヴィンセントと崔が後頭部座席に座る。それからは轢いても構わないようなスピードで町を駆け抜けた。 ヴィンセントは携帯を持ったまま珍しく煙草に火を付けず、というか付ける暇も無いのだろうが、リーダーと違ってまるで出る気配のない一松に対して焦っている。崔は肘を膝に乗せて前屈みになって眉を顰めているが、その内車酔いでも起こすのではないだろうか。マヤンは面倒な事故を起こさないように視界を確保しようとしているが、ワイパーで何度上下しても力強い濁流にはまるで敵いやしない。ミナミの人通りはこの時間帯にしては多いようにも思えるし、酷い雨のせいか少ないようにも思える、ただ車で出掛けようと言う人は多かったのだろうとなかなか進まない大通りに苛立ちながら、場違いなバラードが流れるカースピーカーと単調な呼び出し音だけが狭い車内に響いていた。 そんな道から横に逸れて十分、目を凝らせばようやく沙京の橋まで一直線。思い切りアクセルを踏もうとしたところで見つけたかった女性を見つけ、マヤンは驚いたように声を上げた。急なドリフトは成人男性をも揺らし、耳障りな音を立てながら通りを遮るようにシトロエンが横になる。確認するように崔も助手席にしがみ付きながら身を乗り出し、みっちゃんだ、と呟いた。 突撃せんとばかりの車の目の前に、彼女はそこに現れた。真っ赤な髪も濃い色のパーカーも濡れて色を暗くしていて、長い時間外にいたのだということがわかる。肌を伝っていく雨のせいで泣いているようにも見えたけれどこちらが想像していたよりもずっと落ち着いた顔をしていた、いや一松はこんな奴だったかもしれない。ヴィンセントが鳴らすコール音にワンテンポ遅れて標準から変えていない着信音が鬱陶しく響いていた。携帯が取れなかったのは両手が塞がっていたからだと一松の腕の中でぐったりとお姫様抱っこされている血塗れアリエルを見て思う。春の嵐は花の��を断つ勢いでざくざくと轟いていた。 「一松さん!」 窓を開けてマヤンが叫んだ。すぐに発進出来るように握られたハンドルに伝うのが雨なのか汗なのか、正直よくわからない不快感だった。 「どうしたんだ一体」 ちょうど沙京側に座っていたヴィンセントが車から飛び降りると、ようやく一松は視線を合わせる。ぐっしょりと水を吸った背中を押すように歩くのを促し、ドアの前まで近付いてから彼女は運転手に聞こえるようにはっきりと声を出した。 「細かい話は後にしてくれ、病院に行きたい」 ドアが開くと、大きな体を屈ませたヴィンセントは中に座っていた崔に詰めるように言ってから自分は助手席へ移動した。崔は言われた通りに端に身を寄せながら、濡れた二人分の体が座った車の中が冷えていくのを感じていた。少しの間外へ出ただけのヴィンセントの肩も雨に打たれて重たそうだ。本当に随分な雨天である。一松がそっとアリエルの体を抱き寄せたのは、寒いせいだろうか、心細いからだろうか、誰にもよくわからなかった。 「飛ばしますよ? 乃木クリニックでいいですね?」 「嗚呼、構わない」 大きい病院なら他にもいくつかあるが、自分たちのような半端物を見てくれる医者と言われれば非常に限られている、どころか一ヶ所しかなかろう。シトロエンは来た道を引き返して宣言通りの猛スピードでミナミを走り始めた。
一方でパットは、既に沙京に着いていて至る所へ奔走していた。しかし大した当てもなく人を探すというのは難しいもので、全く一松を見かけることが出来ずにいる。そもそもどこに住んでるのかも知らなかったしどこに行く人なのかも知らない。いや、前にいろんなところほっつき歩いてるとか言ってたな。なにも参考にならないじゃないか。本当に居ねぇ、何処だ何処にいるんだ。向かい来る大量の雨粒に打たれながらマルチボードを走らせていると実に偶然にも知っている気配のするシトロエンと並走し始めた。流水の隙間から見えたマヤンの金色の目が鈍い光を映したのを確認し、パットは声を張り上げる。 「一松はどこにいるか知らないかっ?!」 マヤンが一瞬呆けた顔をした。それから車の前方についているいくつかのボタンのうちの一つをぽちぽちと押すと。 「ここにいるけど」 右側の後ろ座席の窓から至って普通に一松が出てきた。 「えっ」 「もう後ろに乗ってるぜ」 「えっ?!」 ヴィンセントの対応はあくまでフランクで、逆に軽すぎてすっと力が抜けてしまって体重の掛からなくなったマルチボードが減速していった。驚いた拍子で飛び出た声がそのまま長い溜息と共に情けなく洩れていく。シトロエンは何事も無かったかのように走っていき、ついには濃い雨の壁に遮られて姿を消してしまった。どうせ定員オーバーで乗せてはもらえなかっただろうしかしこの仕打ちはなんだ。人間、努力の甲斐がどこにも求められないとなると遣る瀬無さが煮えてくるものである。パットは愚痴を零さないように努めて携帯を取り出した。運転しているのはマヤンだし行先も知っていることだろう。彼がすぐに出てくれたのは救いだった。 「どこに向かってる?」 「今は乃木クリニックに急行中です、特に指示が無ければリーダーもそちらにどうぞー?」 「あ、はーい……」 すぐに切られてしまうのは罪だろうか罰だろうか。頬を伝うのはただの雨だ、そうであってほしい、肯定してくれる人が誰もいない、辛い。必死に探したのに。辛い。濡れて肌にべったりと引っ付いた服がなお重く圧し掛か���てくる。不幸に温度があったらきっとこんな感じなんだろう。あまり切らないでいた厚みのある髪が顔に張り付いてくる頃に、パットはもう一度歩き出す気になれた。マルチボードを起動させてのろのろと上に立つと、全てを振り切るかのような最高速度で指定された場所へと飛んで行った。 かくして、乃木クリニックには五分で着いた。入口にはクローズの札が下げられていて、明かりの消されている待合室は先生も看護婦もいるとは思えなかった。まぁ、亜侠が来るべきはこちらではない、そう思って裏口に回ったもののしっかりと鍵が掛かっていて入り込めそうも無い。おや、これはあれをする機会ではないか、パットはマルチボードの高度を徐々に上げていき、ついに二階の窓へ到達すると顔を交差させた腕で庇いながら「ダイナミックお邪魔します!」と叫んでガラスを打ち破った。派手な音が清潔感のある廊下を抜けていく。ここにも誰かがいる気配はないが、しかし階段の下から蛍光灯の光が漏れているのが見えた。みんなは一階にいるようだ。パットは一歩一歩に水溜まりを作りながらそちらへ向かった。
◇
乃木太郎丸と言えば年下の美形の男の子が好きと言うのが有名な話で、詰まる所ドッグスにはあまり優しくない印象があったのだが、今日に限っては顔を見るなり神妙な面持ちで小言の一つ無く中へ入れてもらえた。前に話をしたときだってここまでスムーズじゃなかったのに、とマヤンは思いながら誰よりも先にアリエルを抱えて車を降りた一松に声を掛ける。 「一松さん、なにはともあれ急いで」 「……言われなくても」 彼女の恋人は本当に助かるのか不安になるほどに動かず、怪我をしたところから血が滲んで全身を真っ赤にしていた。一松は腕が汚れていることも厭わずに先生の横を通り抜けていった。扉の横にはヴィンセントが愛用のバッドを構えながら周囲を警戒していて、あとの二人が入ってから外を睨みつつ中へ入る。それを確認してから先生も度が過ぎるほどに辺りを確認し、音がしないように扉を閉めた。 「随分物々しいですね」 「そりゃあ急患ですし?」 崔とマヤンが一言交わすと、先生は呆れたように溜め息を吐いた。顰めた眉こそいつもの面倒くさい彼だったが、視線には憐れみの情が見える。どういう意味だろうとヴィンセントは首を傾げた。 「君たちがここに来るとは……っ!」 「なんだ来ちゃいけないのか」 低く尋ねたのは一松だった。そこにあったストレッチャーの上にアリエルを乗せながら、細い目を彼に向けている。 「君たち状況を分かってないのか」 「なんか不味かったんです?」 マヤンが尋ねると、先生は黒い長方形を押し付けてアリエルを手術室へ運んで行った。それはリモコンだった、おそらくは部屋の隅に置いてあるテレビのものだ。電源の赤いボタンを押すと昔からやってるニュース番組の速報が流れていた。アナウンサーがぼそぼそとなにかを喋ってから、パッと画面によく知っている顔が映る。それは紛うこと無く自分たちだった。トランク二個分の懸賞金でキングが探しているということまで教えてくれた。 「あーそういうことか……気に入らねぇなあのペンギンは」 非常に不機嫌な声でヴィンセントが吐き出す。手術の準備をするために一旦戻ってきた先生が口を挟んだ。 「それに付け加えてあのロボットだろ? 大阪中大騒ぎさ」 「まぁ沙京からでも見えたしね」 一松はあの光景を思い出しながらテレビを眺めている。 「君たちは今世界の敵になってるんだよ」 世界の敵。細々と動物と戯れてきた自分たちが、よもやその肩書を手に入れることになるとは思いも寄らなかった。崔が眉間の皴を深くした。 「こうも大々的にやりますか。キングが懸賞金を掛けたなら厄介ごとが舞い込んでくるでしょう、さてどう動きますかね」 「……車に乗ってる奴らの顔なんてそんなに見ないだろうが、今後は気を付けて行かないとな」 マンハントとして自分たちを狙う亜侠どもが襲ってくることがあるだろう。それらを対処しながらキング率いる動物園を倒しに行かなくてはならない。身の隠れ方と、対峙するであるロボットの情報、彼ら個人の詳細も必要だろうか? マヤンは一松のほうを見た。一松もマヤンを見て、まぁ頑張るよと呟く。 「それに仲間の大事な奴も傷付けられたわけだしな」 ヴィンセントはぴったりと閉められた手術室の扉を見つめながら言った。どこからかつまみ出してきたバスタオルを頭にかぶって体を拭く一松は冷静に見えるが、心中穏やかなわけがない。押した背中が震えていたことは、触ったヴィンセントだけが知っている。ふと崔が見上げた時計が夜の九時だった。そろそろ寝ないと明日の朝がきついだろうか、窓の外はそれなりに暗く、結構な時間が経っているようだ。騒ぐわけにもいかない状況の中で彼がキョロキョロと外を観察している。 「そろそろリーダー来るんじゃないですか?」 ガシャン、と聞こえたのはそれが言い終わるか終わらないかというタイミングだった。叫びこそしなかったものの崔の肩は跳ねたし、その拍子で落としたモスバーグを即座に構えるのを見てマヤンも無言でカラシニコフを用意した。一松もそっとベレッタを取り出し、ヴィンスは迫りくる足音を仕留めようと扉の横でバッドを振り下ろさんとしている。それはぴちゃぴちゃと水滴を滴らせ、雨の匂いとともにゆっくりとこちらを探しているようだった。廊下の一つ一つの部屋を確認しているのか、開けては閉める扉の音がする。いよいよこの部屋の前、と言うところでヴィンセントがバッドを振り下ろした。 「ふぅ、えらい目にあっ」 扉を開けたパットが即座に息を呑んだのは自分に向けられる三つの銃口と硬度を感じるほどに近付けられたバッドのせいである。 「た」 「おっ……と」 危ない危ないと呟くのは、まさに致命傷を与えようとしていたヴィンセントだった。リーダー殺害未遂二度目だ。慎重にバッドを横に逸らしこっそり心臓を痛くしている。 「なんだ、リーダーじゃないか」 務めて冷静に言ったつもりだったが、ぎぎぎと緊迫したまま固く視線をこちらに向ける少年の顔は真っ青で気の毒だ。息が出来ているかも怪しい。ぼたぼたと床を濡らす雨の味はおそらくしょっぱいと思う。他の三人があれ? と銃を下ろしても、しばらくパットは動けないでいた。 「トランク二個って割高じゃねぇか?」 先生はぼそっとそんな評価を下し、清潔のための衣類に着替え終えた。やれやれと言った面持ちで体を石のようにしたパットを見つめる。崔は、いやごめんねと苦笑いをしてモスバーグをコートに隠し、一松はばつが悪そうに視線を逸らした。マヤンは言い訳も謝罪も言うタイミングを逃したような気がして、気を取り直して先生に振り向く。 「そういえば乃木センセイ、素朴な疑問があるんですけどいいですか?」 「おう、なんだ?」 褐色肌のショタが猫を被っている姿がお気に召したのか、先生は急ぐ足を止めて対応した。疑問が至ってシンプルで、巨大ペンギンロボットの被害はどの程度かと言う話だ。それは、JAIL HOUSが一軒潰れただけだと言った。続けて崔が盟約の動きはと聞いた。被害があったのがミナミであることと、狙いはあくまでも青空爆発ドッグスであるということで、今のところ動いてはいないらしい。中立地帯を上手く利用されたって感じですねぇ、マヤンが一通りを聞いてぼやく。 「しかも被害がジェイルハウス一軒ってことならこれはたぶん警告みたいなもんだろうな」 ヴィンセントがようやく煙草に火をつけ始めた。マールボロの丸味を帯びた苦い香りが彼の周りを漂う。 「復讐銘打っておきながら完全にどたま冷静じゃないですか、一番嫌なタイプだ」 マヤンが露骨に嫌な顔をしてまだ手に持っていたカラシニコフで遊び始める。そのままパットに顔を向けて、リーダーはどうする? と聞いてきた。要するに作戦会議の時間だった。まずは移動しやすいように人の目を欺く手段を見つけるべきだろうか? あるいは敵を知るべきか? 一松の壊れたアジトもどうにかしなければならないのか。当面の問題は尽きず、五人はやがて疲労によって落ちるように眠っていった。
◇
「ま、それが人間の狩りと言う奴だろう」 冷たい空気が漂うのは、ここが日の当たらない場所で、金属に囲まれているからだろうか。尤もそれを気にする者はこの場には居らず、四人の人物が離れたところから会話していた。仲間ではあるが仲は良くない距離である。一人の青年が長く垂れた髪を逆立てるように唸る。 「でも、それをやる必要があるか?」 「大切な人を奪われる辛さは君がよくわかってるんじゃないかな?」 白衣を着込んだ男が確認するように言った。ねぇ、君もそう思うだろ、と人形のような佇まいをした少女にも尋ねるが、彼女は一切の反応はしなかった。ただ、これは呑み込んでおけと言うように青年をじっと見つめる。 「お前の恨みだけを晴らすわけにもいかないんでな。それに、これからもっとたくさんを巻き込むだろう」 ペストマスクの下で男が笑う。彼���にとって青空爆発ドッグスとは念入りに殺さなければならないと同時に最初の踏み台であった。これからオオサカを地獄にするようなヴィジョンが彼らにはあるのだ、たかだか人質を躊躇っている場合じゃない。 「上手くやってくれたまえよ、どうせあいつらは行動を起こすだろう。こちらも妨害しなければな」 「……俺はあいつらだけ狙うからな」 青年は素早く身を翻すと、瞬く間に外へ消えてしまった。残った三人の内ペストマスクと白衣が嘲りながら顔を見合わせる。 「しょうがないなあいつは」 「今更人間を庇ったってしょうがないのにね。まだ動物園が恋しいのかな?」 「パパとママが死んで寂しいだけだからな。私とは違うさ」 「ひっどいこと言うね、キング」
0 notes