Text
白騎士の冒険異聞 異国の魔女とまみえたる話 四
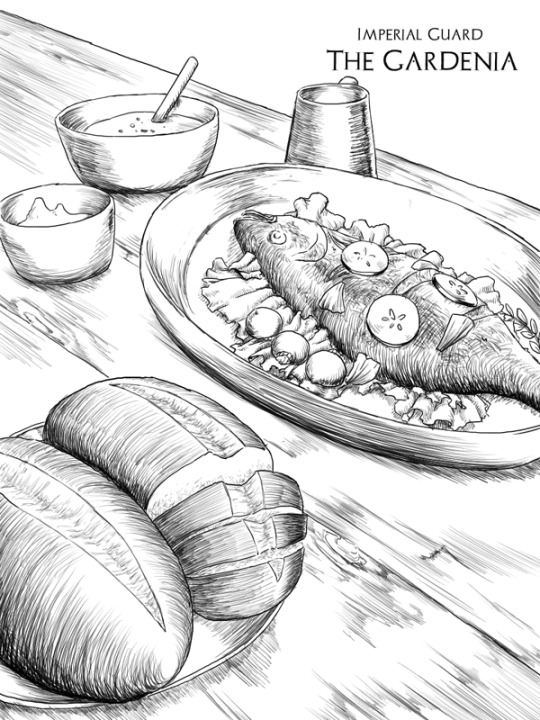
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ゲストキャラクター原案: みみづく 氏
続く
0 notes
Text
白騎士の冒険異聞 異国の魔女とまみえたる話 三

1

2

3
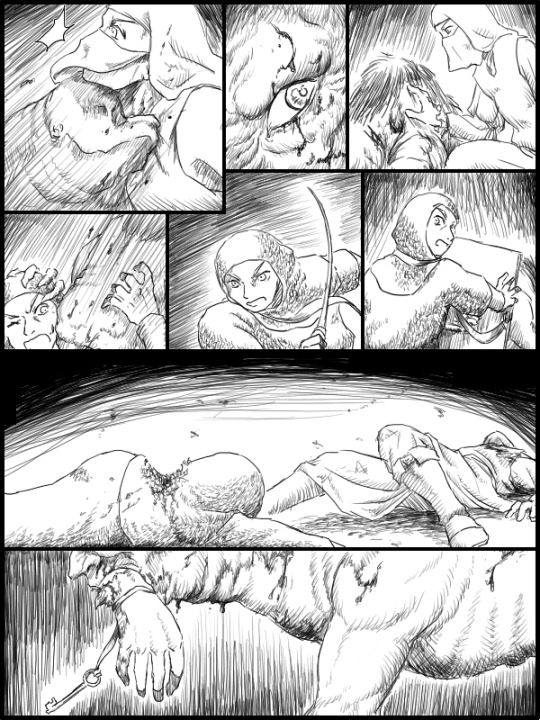
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ゲストキャラクター原案: みみづく 氏
続く
0 notes
Text
白騎士の冒険異聞 異国の魔女とまみえたる話 二

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ゲストキャラクター原案:みみづく 氏
続く
0 notes
Text
白騎士の冒険異聞 異国の魔女とまみえたる話 始

1

2

3

4
*

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
*

15

16

17

18

19

20
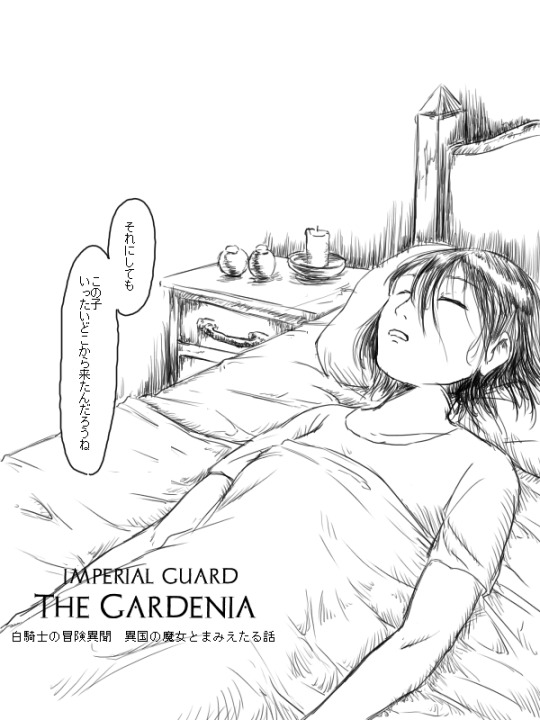
21
ゲストキャラクター原案: みみづく 氏
続く
0 notes
Text
The Lore 目次
◆白騎士の冒険
■本編 ・貧農の子が騎士に叙されたる話 序 ・騎士が故郷に帰りたる話 新米騎士道 ・領内を荒らす盗賊を討伐せしめたる話 遺跡の盗賊団 上 遺跡の盗賊団 下 ・領内の森に侵入したる巨人を退治せしめた話 森の巨人 上 森の巨人 下 ・死者の国の秘宝を奪取したる話 魔宮の秘宝 始 魔宮の秘宝 二 魔宮の秘宝 三 魔宮の秘宝 四 魔宮の秘宝 五 魔宮の秘宝 終 ・騎士が捕虜になった話 夢幻の闘技場 始 夢幻の闘技場 二 夢幻の闘技場 三 ■外伝漫画 ・異国の魔女とまみえたる話 ゲストキャラクター原案:みみづく さん くちなしの歌 始 くちなしの歌 二 くちなしの歌 三 くちなしの歌 四
0 notes
Text
白騎士の冒険 夢幻の闘技場 三
ヴェルカンは誤解していたことだったが、闘士はそう毎日試合に駆り出されるわけではない。劇場はその名の通り演劇や大道芸の見世物の用途で用いられることが大半であり、一日に行われる剣闘試合は一度か、多くても三度。全く行われない日もある。 また人間同士の戦いだけでなく、人間と猛獣、あるいは猛獣同士の戦いが組まれることもある。ヴェルカンたち新入りが初日に行った連戦は、減った闘士を補充する際に適正検査を兼ねて行われる特別なものであったらしい。
だが、試合のたびに誰か、もしくは何かが死ぬのは変わらない、と雄牛の血で汚れた腕を洗い流しながら思う。 鋭い角を振りかざし、地響きを引き連れて迫ってくる、人とはまるで勝手の異なる巨体は、それだけで身を竦ませるに足るものだった。とっさに槍の石突を地面に立てかけて全力で踏ん張らなければ、貫かれていたのは自分の方だったろう。 この地に来てから幾らかの日が過ぎていた。が、ヴェルカンたち新米闘士が駆り出されることは思いのほか多い。興行師は有名で観客の受けも良い古参の闘士を極力温存したがり、危険な試合、地味な試合には新米を優先して送り出す。時には他の闘士団の強豪闘士に倒させるために新人をあてがうこともある。 そういうわけであるから、同時期に入った者もすでに幾人かが姿を消した中、いまだに健在である己はやはり運が良いのだろうか、とも思う。
だがそれよりも、当初の吐き気を催すような嫌悪感が次第に薄れつつあるのをヴェルカンは感じていた。 この慣れとも適応とも呼べる事態を喜ぶべきなのか、恥じるべきなのか。 己のために他者を弑することが日常となった時、己はどうなってしまうのか。
そして思うのは故郷のこと。���主がいなくなり、封土はどうなったのか。衛兵隊長やみんなは大騒ぎしているのではないだろうか。 いつか家に帰るその日まで、運が続けばよいと思う。 しかし、いつ? 幾日?幾月?もしくは幾年?いつか終わるその日まで、何人の命と引き換えに?
剣奴として買われてから幾度となく重ねた思案は、決まってそこで停止する。 そこから先に踏み出してはいけないという予感があった。 だから、考えない。代わりに明日をどう生き延びるか、興行師の目を盗んで逃げだすには、と夢想じみた思索にただ逃げ込む。 今日も、明日も。その先も。おそらくはここでの暮らしが終わる、その日まで。
*
客席の地下、闘士控え室に隣接する訓練場で案山子相手に稽古に励んでいたヴェルカンは、その闘士が入って来たとき、目を丸くした。
「戦う格好ではないな」
腹や肩を大きく露出した防具が、着用者の性別を如実に語る。おまけにまだ若い女ではないか――思わず無遠慮な視線を向けたヴェルカンを険のある目で見上げながら、艶やかな黒髪を後ろで束ねた女闘士はずかずかと近づいてきた。
「あなた新入りでしょ。甘く見てると怖いわよ」
脅す女の肌は抜けるように白い。整った顔立ちと合わせて、よくできた人形のようだった。
「北方民族か」
遥か北の地に絹のごとき肌を持つ民がいると聞く。書物で得た知識を頼りに訊いてみれば「当たり」と思いのほか嬉しそうな返事。
「そちらは白の帝国の人間に見えるわね」
正体を明かしてはならないという命題が脳裏を埋め、咄嗟の返答を鈍らせる。寸の間の沈黙をどう捉えたか「図星ね」と女がいたずらっぽいにやにや笑いを浮かべた。
「外国人は別に珍しくもないからね。むしろこの国の奴のほうが珍しいくらい」
名声や金銭目当てで自ら戦奴になるのは少数派で、囚人や外から奴隷として売られてきた者が大半であるという。
「あなたも売られた口でしょう。でも腕は立つんだって評判よ」 「あなたも、ということは、そちらもそうなのか?」
女は答えずにヴェルカンの前を通り過ぎ、壁際に設えられた武器の棚に手を伸ばした。取り出したのは先端に巻き付けた布を槍の穂に見立てた棒。さほど高くない女の背を超える長大なものだったが、手の中でくるりと半回転させ、そのまま小脇に抱えるように構える姿は思いのほか様になっている。 だしぬけに飛んできた棒の穂先がヴェルカンの右手の木剣を打ち、くぐもった音を立てた。
「出番までは間があるの。一本どうかしら?」
どこか見下ろすような挑戦的な目つきに、思わず眉が動いた。無言で棚に歩み寄り、手に取ったのは女と同じく穂の代わりに布を巻いた棒。ただしこちらは幾分短く、ちょうど帝国の兵士が使う片手槍に近い感触だ。 訓練場の中央、模擬戦用に砂が敷かれた一画に場所を移したふたりは向かい合った。片やヴェルカンは左手の盾を突き出し、右手の棒を高く掲げ、対する女闘士は両手で支えた棒を低く落とし、やや地面に向けた穂先を揺らめかせる。
「面白い型ね」 「そちらこそ」
短いやり取りの終わりは斜めにすくい上げる棒の穂先。ほぼ反射的に盾で払いのけざま、お返しと放った突きを、女闘士は半歩退きながら傾けた棒で受け流した。 素早く引こうとした棒はしかし、円を描くように動く穂先に絡め取られた。そのまま巻きつくように延びてくる突きは枝を這う毒蛇を思わせた。 咄嗟に棒を手放し、入れ違いに突きだした盾で受け止めた毒牙は思ったよりも軽い。 武器を捨てたヴェルカンに向かって次々と飛んでくる突きは変幻自在、右から薙ぐように迫る攻撃に向かって盾をかざせば隙間の空いた足元を狙われ、慌てて盾を向けた時には既に引かれていた穂先が肩めがけて飛んでくる。 いずれも挑発するような連撃は誘いだ、とヴェルカンは分析した。おそらくどこかで力を込めた本命の一撃が飛んでくるはず。それを躱し、隙をついて優勢に持ち込む。 右から飛んできた攻撃を最小限の力で受け流す。盾の表面を撫でた穂先が弧を描いて女の右肩の後ろに流れた。 細い肩の筋肉がわずかに動くのが見て取れ、来る、と直感する。 毒蛇のごとくよじらせた華奢な体全体に満たされた力の奔流が、肩から腕へと流れ込むのが目に見えるようだった。 顔を狙って空を切る穂先を盾で受けるのではなく、身を退いてぎりぎりの間合いで躱した、はずだった。 目の前を流れていくはずの穂先が、突如するりと伸びてきた。 驚く間もなく顔面に衝撃が走り、視界に火花が散る。目元に溢れた熱が鼻の奥を伝い落ちる感触に慌てて手をやると、掌全体がべったりと赤く濡れた。
「あら男前」
目を細める北方人の右手、力なくぶら下げた棒が先ほどより長く握られていることに気付く。命中の直前に握る手の力を抜き、遠心力を利して棒の間合いを長く押し出したのだ。まさに一瞬の早業だった。
「女だからって手加減してるから怪我するのよ。新入りさん」
図星を刺された羞恥と小馬鹿にするような眼差しがないまぜとなり、生臭い息苦しさも手伝って頭に血が上った。伝い落ちる鼻血を舐め拭き、足元に転がる棒を拾って立ち上がるや否や、ヴェルカンは攻勢に転じた。 顔を狙って右手から薙ぐように放った突きを、女は上半身を大きく左に倒してやすやすと躱した。だがそれは形ばかりの一撃、素早く引いたそれと入れ違いに、女の頭を迎え撃つ形で盾の縁を繰り出す。 女の目が初めて驚きに見開かれた。それでも歪んだ姿勢のまま棒をかざして受け止め、その反動で体勢を立て直してみせる。 くるりと身を翻しざま一歩退き、再び踏み出す爪先が、砂に円弧の軌跡を描いた。だが叩き込まれる棒の先、そしてヴェルカンを見据える切れ長の目にはこれまでにない力が込められている。 再び退いた女が棒を大上段に掲げた。対するヴェルカンは突き出した盾の後ろに丸めた背を隠す。向かい合って構えたまま、互いに回り込むように足を滑らせる。 膠着したかに思えた状況は突然動いた。ヴェルカンが盾の上辺からわずかに顔を覗かせた瞬間を見逃さず、棒が振り下ろされた。 だが次の瞬間、もたげられた盾に女の棒が弾かれた。そのまま帽子を被るがごとく盾を掲げたヴェルカンは大きく足を開いて砂を蹴った。 ちょうど女の足元に跪くような形になったヴェルカンは、煌びやかな前垂から覗く白く長い脚を間近に、被ったままの盾の下から女の顔目がけて棒を突き上げた。 相手の息遣いが激しく乱れた。手応えを感じる間もなく細い足が空を掻き、砂場の外に降り立つ。
顔を背け、口元を押さえる女の目は驚きのあまりこぼれ落ちそうなほど。しきりに口元や鼻に手をやり、怪我がないことを確かめる仕草がどこか新鮮で、思わず笑みが浮かぶ。 次に振り向いた女の顔に浮かんでいたのは敵意と闘志。どうやら本気で怒らせてしまったらしいと気づき、盾を持ち上げ、再び身構える。 ところが、女は不意に踵を返した。背を向けたまま、手をひらりと振って見せる。
「もうすぐ試合なの」
つい今しがたまでの燃え盛る闘志はどこへやら、後でね、と言い残した声音は朗らかそのもの。棒を掲げた間抜けな姿のまま、ヴェルカンはその背中が扉の向こうに消えるのを見送ることしかできなかった。
*
北方人の闘士が再び姿を見せたのは日没間近、���食の刻限。厨房から麦粥の椀を受け取り、後続の邪魔にならぬよう足を運んだ控え室は、予想どおり誰もいない。静かに食事を楽しめそうだと長椅子の端に腰かけた時だった。 無人の控室に、戸を開く音は意外と大きく響いた。 目を向けた先で、ヴェルカンと同じく椀を抱えた女闘士が手を振っていた。
「座っても?」
訊くや、答えも待たずに隣に腰を下ろす。
「あなた結構強いのね。見直した」 「そちらこそ」
今夕食を共にしているということは、あの後の試合で勝利したということ。言外に褒めると女はくすぐったそうに笑った。
「素人には見えないわね。戦士か何かだったの?」
気をよくしたか、続けざまに尋ねてくる。どう答えたものか考えあぐねていると、女はふと黙り込んだ。
「私もあなたと同じ。��こには売られてきたの」
突然変わった話題が、昼間ヴェルカンが放った質問に対する答えだと気づくのにいささかの間を要した。
「お察しの通り、あたしは北の方の村にいたんだけどね。人買いに襲われて連れ去られたってわけ」
彼女と数人の友人は故郷を遠く離れたこの地の闘士団に売り飛ばされた。 右も左も分からぬ少女たちは、いきなり闘技場に立たされることになった。触ったこともない武器は細腕に重くのしかかり、剥き出しの肩や腰がやけに寒かった。
「女子供に戦わせるのか!?」
闘技試合といえば腕自慢、少なくとも大の男が互いに優劣を競い合うものと決めてかかっていたヴェルカンは思わず唸った。
「世の中には可愛い女の子が血だるまになって苦しむ姿を見るのが好きな変態がごまんといるのよ」
自らを可愛い女の子と言ってのけたことをからかえる空気ではない。 相槌すら忘れたヴェルカンの事など意にも介さず、女は続ける。
闘技場には飢えた肉食獣が放たれていた。
「虎って知ってる?」 「聞いたことがある。縞模様のある金色の猫だろう」 「……まあ、あながち間違いでもないかな」
牛よりも大きく、猫がネズミを狩るように人間を食い殺す怪獣だと聞き、ヴェルカンは慄然とした。
真っ先に虎の餌食になったのは女闘士の親友だった。
「確かにおっぱいもお尻も大きくてよくモテたけど、獣の目にも美味しそうだったのね……でも頭を砕かれちゃ美人も形無しだわ」
熱に浮かされたように話す口調こそ軽いものだったが、その目はどこでもない一点を凝視し、動かない。ヴェルカンもまた、その硬く凍てついた横顔から目が離せなかった。
「まん丸な目ン玉がこう、ぽろっと飛び出しちゃっててさ。残った下の顎に舌がくっついてるのよ」
暴力を知らずに育ったいたいけな娘たちにはあまりに���惨な光景だった。ある者は脇目も振らずに逃げ惑い、またある者は腰を抜かして声にならぬ悲鳴を漏らし。残虐な見世物に観客は嫌悪と興奮の声を上げた。
「で、そこで助けてくれたのが先生――先輩の闘士なんだけどね」
突如、馬に跨った闘士が現れ、食事に夢中になっていた虎に槍を投げつけた。虎は怒り狂い、暴れまわったが、闘士はその周りをぐるぐる回りながら次々に槍を投じ、ついに獣は沈黙、場内は熱狂にどよめいた。
「でもね、槍を何本も突き刺されて、真っ赤な血を流して苦しむ虎を見て思ったの。こいつも、あたし達と同じなんだなって」
おそらくは訳も分からず捕らえられ、故郷から遠く離れた地で見世物の種として殺された哀れな怪獣。友人の仇のはずなのに目が離せないでいる彼女のもとに悠然と歩み寄ると、煌びやかな鎧を身に着けた闘士は静かに手を差し伸べた。 乙女の危機に駆けつける正義の戦士。そんな筋書きの試合だったことを知ったのはずっと後のことだ。
その先輩闘士は生き残った少女たちに武器の扱い方、戦うすべを教えた。少女たちは自然と彼を先生と呼び、敬うようになっていった。 しかし闘士は死ぬのも仕事のうち。少女たちの未来は決して明るいものではなかった。
「いちばん運のいい子は余所に買われて抜け出した。次に運の良かった子は怪我で使い物にならなくなって放り出された。いちばん運の無かった子は死んじゃった」
そして、同様の運命は“先生”にも。
「なんでだろうな、あんなに強かったのに、牛に踏み潰されちゃうなんて」
体調は万全、装備もよく手入れされていたはずだった。当時最強と謳われた闘士の、あまりにあっけない最期。 しばしば闘士は兵士に似ている、と言われることもある。兵士は勝つために戦い、闘士は相手を倒すために戦う。 一見同じに見えて、そのふたつには大きな隔たりがある。闘士には逃げることも、戦い以外の道を選ぶことも許されない。一旦闘技場の砂を踏み、相手と向かい合えば、外に出るにはふたつにひとつ。相手を殺すか、もしくは相手に殺されるか。新米も古兵も変わらぬ宿命。
「いつの間にか残ってるのはあたしひとり。これは運がいいのかな。それとも悪いのかな」
誰に向けて放った問いかけだったのか。ひとり考え込む女の姿にどこか親近感を覚える。目を向けた横顔、形の良い鼻筋に小窓から差し込む残照が赤い線となって浮かび、思わず見とれる。
と、女がだしぬけに振り返った。真っ黒な目に真っ向から覗きこまれ、訳もなくどぎまぎする。
「はい、あたしの話はこれでおしまい。次はあなたの番」
なんともあっけらかんとした口調に、いささか興を削がれた思いで眉をひそめる。 だがほぼ一方的とはいえ、ここまで話させたのだ。だんまりを決め込むのも品がないだろう。 しかし、どこまで話していいものやら。ヴェルカンは腕組みして唸った。己を捕えさせる方便だったのだとしたら、いまさら身分を隠しても仕方ないかもしれない。 が、宝石泥棒の罪で捕まった奴隷が本当は皇帝に仕える騎士だなどと、誰が信じる?
「……君の読み通り、私は白の帝国から来た。さる領地で兵士をしていた」
嘘ではない。騎士に叙される前は西の湿地領の衛兵隊に属していたのだ。 衛兵として長年勤めた功績が認められ、休暇を許可されたこと。そうして物見遊山に訪れたこの町でひょんなことから無実の罪を着せられ、捕縛されたこと。
事実を微妙に捻じ曲げ、脚色して話しながら、ふと、女もまた作り話をしていたのではないかという疑念が浮かぶ。 しかし、やはり嘘をつくのはあまり心地の良いものではない。露見に対する恐れや、相手を裏切ることへの罪悪感がないまぜとなり、胸がざわつくような心地がする。 内心の動揺を押し隠して話すヴェルカンを、女は興味津々のていで見つめていたが、捕縛された後にそのまま奴隷市場行きとなったくだりで気の毒そうにため息をついた。
「役人のやつら、囚人を売りとばした上前で小遣い稼ぎしてるのよ。ついてないね」
そのため、本来なら釈放されるような微罪、あるいはまったくの無実であっても強引に罪状をでっち上げ、奴隷市場送りにされることすらあるのだという。 それもこれも、闘技場を中心にした巨大な需要があるためだ。
「この町のすべてが劇場を中心に回ってる」
毎日、国内外から多くの人間が劇場を訪れる。そうして注ぎ込まれた金貨は水が低いところへ流れ落ちるがごとく溢れ出し、町全体を潤す。 だが同時に、おびただしい量の血も流れている、と女闘士は語る。
「町を流れる金貨はどれも、あたしたち闘士の血にまみれているの」
訓練場は静かだった。いつしか窓から差し込んでいた夕日の最後の一筋も消え失せ、代わりにどこかで灯されたかがり火の光がわずかに差し込む薄暗がりの中、女の白い肌だけがうっすらと浮かび上がるようだった。 目を落とした先、冷めた麦粥の面が揺れた。匙を差し込んで口に運んでみれば、熱を失った粘りが味気なく舌に絡みついた。
*
とりとめのない話をしながら食事を終えた頃には、すっかり日が落ちていた。訓練場を出たふたりは、そこで興行師に出くわした。
「こんな時間に何をしている」
ヴェルカンを険のある目で見上げる興行師の手には鍵束。夜間の施錠のために来たのだろう。 素直に従うのが癪で沈黙を返事にすると、舌打ちがひとつ飛んでくる。
「奴隷、明日は試合だぞ。とっとと寝て備えろ」
言い捨て、踵を返して去っていく興行師の背中に向かって、それまで黙っていた女闘士が舌を出した。
「すっかり嫌われ���るわね」
初日の口喧嘩がいまだに響いているのかと思ったが、どうやらそれだけではないらしい。
「白騎士ヴェルカンの事をこき下ろしたりするからよ」
思わず眉をひそめると、女は鼻を鳴らした。 聞けば、興行師は白の帝国のヴェルカンなる騎士を題材にした詩を収集しており、彼の話となると目の色が変わるのだという。
「いい歳して物語読みなんて、笑っちゃうよね」 「ヴェルカンの詩だと?」
自分がそのヴェルカンだなどとは言い出せず、何ともむず痒い心地に耐えながら問うてみる。
「そ。『巨人殺し』の異名をとる若き騎士。その強さと知略でもって未踏の秘境を難なく乗り越え、その勇気は世にも恐ろしい怪物すら屠り、その美貌でもって数多の美女と浮名を流し……どうかしたの?気分でも悪いの」
己が詩歌に語られているらしいことは噂で聞いてはいたが、どうもかなりの脚色が加えられているようだ。 それにしても、己の風聞を赤の他人として聞くというのは、なんとも妙な気分だ。
「ほんと、すごい人間もいたものね」 「どうせ子供だましのでたらめなんだろう」 「これで意外と面白いんだよ。うちの団にも持ってる人がいたから、貸してもらいなさいな」
ふと、帝都の宴で会った黒岩領の令嬢を思い出す。彼女が憧れたという騎士ヴェルカンは、果たして宴に参加していたヴェルカンと同一だったのか。
どちらにせよ、このままではヴェルカンの詩も打ち止めだな。
そんなことを自嘲的に思い浮かべた直後、まったく別の考えにとらわれる。 己がこの町に閉じ込められていようと、さらには名もなき闘士として死んでいたとしても、お構いなしにヴェルカンの詩だけが新たに紡がれていくとしたら?
それはとても恐ろしく、また同時にどこか寂しいことのようにヴェルカンは感じた。
*
今日の闘技試合は出来試合になる。
そんな噂を小耳に挟んだのは、翌朝の厨房でのことだった。
「なんでも相手方が大物を繰り出して来るらしい。それに先んじてうちの団長にいくらか包んだって話だ」
椀を受け取った時、そんな声に思わず振り向けば、古参の闘士たちが額を突き合わせてひそひそとやっているところだった。
「で、今日死ぬ気の毒な新入りは誰なんだ?」 「さてな。ひょっとしたらお前かもしれんぞお」
冗談に肩を震わせる闘士たちとは対照に、ヴェルカンは腹の底が冷えていくのを感じた。昨夜の団長こと興行師の言葉を思い出したからだ。
つまり、今日死ぬことになっているのは私か。
出来試合というからには相手を勝たせるためにヴェルカンに対してなんらかの妨害が加えられることも考えられる。何も試合中ばかりではない。試合前に事故に遭う、何者かに襲われて怪我をする、食事に毒を盛られる―― そこまで考えたところで、ふと手元の椀に目を落とす。
「後がつかえてるんだ、さっさと行きな」
確かめる間もなく促され、慌ててその場を後にする。むろん、朝食は後でこっ��り捨てるつもりだ。
問題の試合は午後一番に行われることになった。一食抜いたところでどうということはないが、不慮の“事故”を避けるため、無人の宿舎の寝台で何もせずにじっとしているのはさすがに少しばかり堪えた。 雑用係に手渡された防具の裏地や剣の柄に毒針でも仕込まれてはいまいかと確かめ、そこでようやく妨害工作など杞憂だったかと胸をなでおろす。
が、だからといって安心はできない。試合前は安全でも、試合中に何が起こらぬとも限らない。何より相手は出来試合を望まれるほどの古参闘士、その人気は腕前に裏打ちされたものだろう。 となれば小手先の通用しない相手とみるべきだ。
「さあさ、皆さまお待ちかね!闘技試合の時間にございます!!」
陽光を照り返して焼けた砂、そびえる客席、取り巻く観客と歓声。もはやすっかりおなじみの光景の中、すっかりおなじみとなった司会の口上を、馬上のヴェルカンはひとり、砂地の真ん中で聞いていた。対戦相手の姿はなく、控室に通じる大扉も閉ざされたまま。
「本日命を賭けて戦うはこの男!日は浅くともその堅実な戦いぶりで着実に勝利を重ねる、『白刃団』期待の新人!」
わっ、と強くなる歓声に両手を挙げて応える。だがいつもよりもいささか弱い。彼らの本当の目当てはこの後に来るからだ。
「対するは、かつては貴族でありながら五年前に闘技場の砂を踏んで以来、常勝無敗を誇る生ける���説!『赤羽組合』が誇る『血塗れ卿』!」
同時、ラッパと鼓の音、そして割れんばかりの歓声を引き連れて大扉がゆっくりと持ち上げられた。 色とりどりの布で飾られた馬の背に跨って悠然と進み出たのは、斧を提げ、盾に投槍を挟んだ壮年の闘士。流麗な浮き彫りを施された青銅の板金鎧は黄金色の光を放ち、兜に挿した色とりどりの羽根飾りが映える。
これでは道化だな。ヴェルカンは兜の下で自嘲の笑みを浮かべた。かろうじて胴を覆う鎖帷子も、古びた無地の円盾も、豪奢を具現化したような相手と並べばいかにもお粗末。跨る馬もどこか毛並みの悪い痩せ馬だ。 それもそのはず、ヴェルカンは無様に負けるためにこの場に引き出されたのだ。これ以上の道化ぶりがあろうか。
だが、無論むざむざ殺されてやるつもりはない。
決意は口にはしない。ただ視線に乗せ、相手に叩きつける。
やがて司会が開戦を告げ、血塗れ卿の馬がゆっくりと進みだした。合わせてヴェルカンも馬の腹を蹴る。相手が右手に向かって進めば、ヴェルカンは内壁沿いを反対��向に走る。最初は緩やかだった馬脚が次第に速まり、互いに追いかけるように円を描く軌道は次第に狭く。ついに真っ向から向き合った彼我の距離が急速に縮まる。 血塗れ卿が投槍に手をかけた。素早く丸めた背中のすぐ上を槍が唸りを上げて飛び越していく。体勢を整える前に相手がさらにもう一本を手に取るのが見え、盾を目一杯突き出す。 激しい衝撃を伴って盾を貫通した穂先が把手を握る親指のすぐそばに飛び出し、木屑を浴びせた。長い槍が突き刺さったままの盾がにわかに重みを増し、引きずられる前に投げ捨てる。その間に血塗れ卿は斧を抜き放ち、振りかぶっていた。
すれ違いざまに斧と剣がぶつかり合った金属音と火花は瞬く間に背後に流れ去った。咄嗟に力を抜いても腕ごともぎ取られそうな衝撃が肩を苛む。 思わず顔をしかめながらも馬首を巡らせて、血塗れ卿と再び相対しようとした時だった。 手綱を引いて制動をかけた瞬間、体が前のめりにつんのめった。正確には足腰を支える鞍が突然跳ね上がったのだ。 何が起きたのか理解できず、暴れる馬をどうにか御しながら見下ろせば、馬具の留め紐が何本かちぎれ、馬の動きに合わせてはためいている。 体を支えきれなくなる前に身を投げ出す。飛び降りるというよりは半ば転げ落ちる形で背中を地面に打ちつけ、柔らかい砂地ではあっても一瞬、息が詰まった。 垂れ下がったままの馬具を引きずって駆けていく馬を見やりながら立ち上がろうとしたところで、杖代わりにしようとした剣が根元から無残に折れていることを知る。 たかがいちど打ち合っただけで……不格好な切断面を呆然と見つめることしばし、ようやくこれこそが妨害工作だと気付く。おそらくは馬具も同様、すぐに壊れるよう細工が施されていたのだろう。血塗れ卿の勝利を確実なものとするために。 舌打ちひとつ、問題の血塗れ卿に目を向ける。悠々と馬首を巡らせ、歓声に応えるように斧を振り上げる。そのまま馬の腹を蹴り、ヴェルカン目がけてまっすぐに突進してくる。 馬に乗った人間があれほど大きく見えるなど、初めて知った。横っ飛びに身を躱し、頭を覆って倒れ込んだ直後、目と鼻の先を巨大な蹄が踏みしだいていく。 勢いをつけるため、相手がいったん離れていく隙にあたりを見回し、使えるものがないか探す。
乗り捨てた馬は?遠すぎる。血塗れ卿が最初に投げた槍は?同様。 あとは己が投げ捨てた盾。だが刺さった槍の柄が邪魔で防具としては役に立たない。ならば……
迷っている暇はない。即座に飛び起き、走り出す。背後で蹄の音が少しずつ速く、そして近づいてくる。 人間の脚で馬と張り合うなど、どだい無理な話だ。だが一瞬でも長く、一歩でも遠くを目指し、必死で足を動かす。 さほど長くないはずの距離が限りなく遠く感じた。一歩ごとに近づいてくる馬蹄の音に合わせて斧の刃が食い込む���視が何度も脳裏をかすめ、背中にちりちりと痛みにも似た感覚が走る。
投槍に飛びつきざま、体を丸めて転がった勢いで身を起こし、相手と向かい合う。既にすぐそばまで迫っていた馬と血塗れ卿は逆光となり、さながら黒々とそびえ立つ塔のよう。砂埃を蹴立てる地響きが足元から伝わり、早鐘を打つ鼓動をかき乱す。手は汗で濡れ、槍が落ちぬよう握り直す。 振り上げられた斧が陽光にぎらりと輝く。筋を浮かべた馬の筋肉が捩れ、躍動するのが異様にゆっくりと見て取れる。 少し傾いた太陽が馬の鼻面に隠され、その輪郭が明々と浮かび上がった瞬間、ヴェルカンは槍を力の限り振り抜いた。
突然目の前に現れた盾の縁に横っ面を強打された馬が驚いて嘶き、後脚で立ち上がって激しくもがいた。その拍子に血塗れ卿が体勢を崩し、大きくのけ反る。 この機を逃すヴェルカンではない。間髪入れずに槍を再び振り上げる。 穴の開いた円盾と斧が同時に落ち、続く一撃を胸に受けた血塗れ卿の尻が鞍から離れた。 直後上がったどよめきは驚愕。
伝説の血塗れ卿が背中を地につけた。それも相手はどこの馬の骨ともつかぬ新米闘士。
戸惑いと驚きがないまぜになったざわめきだけが不思議と耳につく中、ヴェルカンは素早く拾った斧を振り上げた。 打ち下ろした斧の刃は、血塗れ卿が咄嗟にもたげた盾の面に深々と突き刺さった。引き抜こうとするより早く盾もろとも激しく揺さぶられ、奪い取られる。 お返しとばかりに倒れたままの血塗れ卿を盾の上から何度も蹴りつけ、五度目で盾をもぎ取ることに成功する。だが喜ぶ間もなく、今度は血塗れ卿の蹴りに足を絡め取られ、たまらず倒れ込んでしまう。 入れ違いに起き上がった血塗れ卿がヴェルカンに馬乗りになった。青銅の手甲に覆われた拳が鎖帷子越しの腹に食い込み、声すら上げられないほどの衝撃と激痛が走る。 さらに追い打ちをかけてこようとする拳を痛みをこらえつつ押しのけ、開いた右手で相手の兜を掴んで上半身を跳ね上げ、頭突きを食らわせる。
兜同士が金属の悲鳴を上げ、残響が頭蓋を揺さぶった。相手も同様だったらしく、頭を押さえて唸りがらヴェルカンから離れようとする。そこを逃さず、掴んだままの兜を力任せに引き抜き、現れた髭面に向かって思い切り叩きつける。 立ち上がろうとすると殴られた腹にひきつったような痛みが走った。前かがみになり、腹を庇いながら肩で息をするヴェルカンの前で、血塗れ卿がゆっくりと身を起こした。
「いい顔になったな」
顔の上半分を青筋で、豊かな髭に覆われた下半分を血で飾った血塗れ卿はヴェルカンの挑発に凄まじい形相を浮かべた。
「……殺す」
折れた歯とおびただしい血に混じって、そんな言葉が吐き出される。冷徹な闘士の顔が剥がれ落ち、怒りと殺意が剥き出しになった瞬間だった。 血塗れ卿は四足獣のごとく飛びかかってきた。押し倒されながら、その顔面に爪を立てる。 そこからはお互いにがむしゃらだった。互いに殴り、蹴りつけ、上になり下になり、髪を���み髭を引っ張り。もはや試合などと呼べるようなものではなく、さながら子供の喧嘩のごとき戦いを、観覧席を埋め尽くす観客たちが声援も忘れて見つめる。 そしてとうとう、ヴェルカンの体重を乗せた肘打ちを横っ面に受けた血塗れ卿が仰向けに倒れ込んだきり、動かなくなった。顔を歪め、激しく肩を上下させるだけとなった相手を見下ろしているうちに、麻痺していた痛覚が次第に戻ってきて全身を苛む。だが、まだ膝はつかない。それが許されるのは己の勝利が確たるものとなってから――
客席から上がるは賞賛の歓声ではなく、困惑のざわめき。司会すら言葉を忘れ、ただ嫌なざわめきだけが増幅されていく。 ふと、古い記憶が蘇った。騎士に叙される前、帝都で行われた闘技試合に参加した時のことだ。己が優勝を手にした時、多くの貴族が異を唱えた。
曰く、奴隷上がりの下男に優勝はふさわしくないという。
あの時は帝都や闘技試合の威容にすっかり飲まれて分からなかったが、今、当時の光景が蘇るにつれ、ふつふつとわき上がってくるものがあるのをヴェルカンは感じていた。 血塗れ卿のもとに歩み寄ったヴェルカンは、感情の赴くままに青銅の胸当てに足をかけ、踏みにじった。血塗れ卿が苦しげに呻き、美しい浮彫がみるみる砂で薄汚れていく。 なるほど、確かに血塗れ卿は歴戦の闘士であり、また自分はこの男を勝利させるために砂場に上がったかもしれない。だが数多の妨害をくぐりぬけてなお己は勝った。実力にせよ運にせよ、この男より強く、より勝利に足る存在だったのだ。だがなぜ誰も認めようとしない?新入りの自分には分不相応だとでもいうのか? 血塗れ卿を足蹴にしたまま、誇示するように客席を見上げ、睨みつける。
こちらの勝利を認められないというならそれでいい。代わりに相手を徹底的に無様に、惨めったらしく敗北させてやるまでだ。
その意志が伝わったわけでもないだろうが、司会がようやくヴェルカンの勝利を告げた。だが称える口上にいつものきれの良さはなく、それに合わせて上がる喝采にもどこか勢いがない。 これ以上この場にいても余計気分がささくれるだけだ。もはや相手にとどめを刺すのも馬鹿馬鹿しく、最後に軽く頭を蹴りつけてその場を後にする。 ふと振り返り、頭を抱えて呻く血塗れ卿の姿に僅かに溜飲を下げ、直後、そんな己にどうしようもない嫌悪感を覚えた。
*
控室では興行師が待っていた。勝ってしまったことで叱責されるようならどうやり返してやろうかと考えていたヴェルカンだったが、出迎えたのは満面の笑みだった。
「やったな新人。あの貴族崩れをやっつけるとは、見直したぞ」
予想外の言葉に鼻白むヴェルカンに構わず、興行師は雑用係を呼びつけた。てきぱきと鎧が外され、手拭いが渡される。 そこらじゅうに痣や擦り傷をこさえた体が露わになると、興行師は顔をしかめた。
「こいつは派手にやられたな。どれ、見せてみろ」
近くの椅子にヴェルカンを座らせ、傷痕に膏薬を塗り、包帯���巻いていく。手慣れた手つきを意外な思いで見つめていると、盃が手渡された。満たされていた黄色い半透明の液体を飲み下すと、むせ返るような強烈な甘味が喉を焼き、その熱が全身に広がって暖めていくような感覚があった。
「みんな驚きのあまり声も出ないって感じだったな。だが明日になりゃ、町はお前の話でもちきりのはずさ」
淀みなく動く手をぼんやりと眺めていたヴェルカンだったが、ついに意を決して顔を上げた。
「私を死なせるつもりだったのか」
問うや、興行師の手がふと止まり、ほどなく再び膏薬を塗り広げ始める。
「どこでそれを……いや、やっぱりいい」
折よく処置が終わったとみえ、薬入れを懐にしまうと、腰に手を当ててため息ひとつ。
「まあ、そうだな。確かに武器と馬具に細工をした。歴戦の血塗れ卿の相手に新入りのお前をあてがった」 「なぜ」 「赤羽から勝たせて欲しいと要請があったからな。金も受け取ったし」 「なぜ私だったんだ?」 「別にお前でなくてはならん訳もない。新米や弱いやつなら誰でも選ばれる可能性があり、今回はたまたまお前だったってだけだ」
あっけらかんとした口調とは裏腹に、興行師の表情がみるみる変化していくことに気づく。ご機嫌の皮の下で苛立ちが蠢き、次第に露わになっていく。
「勘違いするなよ。確かに俺は相手が勝ちやすいように仕組んだが、お前が勝つこと自体まで禁じた訳じゃねえ。現にこうやってお前が戻って来ても、小言ひとつ言わなかっただろうが」
お前の無駄口のせいでそうもいかなくなったがな、と嫌味たっぷりに付け加えてから、興行師はぐいと顔を近づけてきた。
「確かにお前のことは気に入らんが、何も死んでほしいと思ってる訳じゃねえ。奴隷ってな安い買い物じゃないんでな」
意外といえば意外な言葉に思わず口をつぐむと、相手はさらにたたみかけてきた。
「不当な扱いが嫌ならもっと敵を殺し、名を上げろ。最初に言った通り、砂場の上では何をしようがお前たちの自由だ。 貴族だろうが罪人だろうが関係ない。強い者、長く生き残った者が実力に見合った扱いを受ける平等な世界、それがこの闘技場だ」
ひと息に言い切ると、反論の暇も与えずに立ち上がった。
無人となった控室でひとり取り残されたヴェルカンは、ややあってため息をついた。 力が欲しい。最後にそう思ったのはいつのことだったろうか。 そして今再び思��。腕力が、富が、名声が欲しいと。 この地で生き延びるために。いつか帰る日のために。
そしてはたと気づく。己ひとりのために力を願ったのは初めてだと。
立ち上がろうとした瞬間、治まりかけていた痛みがぶり返し、顔をしかめて腰を下ろす。 もう少し休んでから……宿舎に帰って寝るとしよう。
0 notes
Text
白騎士の冒険 夢幻の闘技場 二
冗談ではない、と思わず声が漏れた。一度、先帝たちから教わった偽の身元を伝えてもみた。が、証となるものを持っていないとしてあっけなく突っぱねられた。よしんば賠償を代行してくれる者が存在したとしても、連絡もつかないのにどうやって引き受けに現れるというのか。 だが役人はヴェルカンの抗議など聞こえないとでもいう風に顔を背け、それが合図とばかりに刑吏たちはヴェルカンの両腕を掴み、引きずっていった。
続いて訪れたのは、さほど遠くはない、が、うらぶれた刑場よりもずっと賑やかな場所だった。巨大な天幕があちこちに並べられ、渦巻く人々の声は混ざり合って濁流にも似た重低音と化し、あたりを満たす。 役人たちは入場門を素通りし、張り巡らされた簡素な柵に沿って歩き始めた。引きずられながらぼんやりと眺めた人ごみ、その間から時折、檻のようなものが見え隠れすることにふと気づく。その中身は――
「商品の追加だ」
素通りした入場門のちょうど反対側に設けられたもうひとつの入り口、というよりは柵の隙間から滑り込んだ役人たちは、そんなことを言いながらヴェルカンを巨大な檻に放り込んだ。尻を蹴飛ばされてつんのめった先にいた女が慌てて跳びのき、その拍子に痩せた老人に背中からぶつかり、二人まとめて転ぶ。 子供の背丈ほどの高さの檻の中には、既に大勢の人間が詰め込まれていた。あるいは不安げに見開かれた目で辺りを見回し、あるいはあらゆるものを敵意もむき出しに睨みつけ、またあるいは身の回りの全てから目を背けるように抱えた膝に顔を埋め。服装も年齢も人種もばらばらな彼らに共通するのは、手首にはめ込まれた錠前つきの鉄の腕輪。そしてまた、檻に入れられる直前、ヴェルカンも同様のものを取り付けられていた。
先客たちの邪魔にならぬよう、柵に背を預けて息をついたのもつかの間、突然、背後から伸びた腕に顎を掴まれ、強引に振り向かされる。
「ほう、こいつは生きが良さそうだなあ」
そう笑いながら柵越しにヴェルカンの顔を覗き込むのは腰に棍棒を下げた男。 力任せに振り払うも、それす��も笑い声で受け止められる。ふと、幼い日のことを思い出す。手に繋がれた縄に引きずられ、目の前の巨大な背中についていくしかなかったあの日。金貨の袋と引き換えに故郷を連れ出され、まったく見知らぬ他人に身を預けねばならなかった不安がふとこみ上げる。
説明されるまでもなく、この場所が奴隷市場であることは分かった。『水龍の国が身柄を預かる』その意味を知り、舌打ちひとつ。 檻の外からはヴェルカンたちを興味深そうに見る客たちの群れ。そして彼らの間からは他の檻や高台に繋がれた奴隷たちが見え隠れ。 これで名実ともに奴隷騎士というわけだ。帝都で出会った騎士の顔を思い出し、自嘲と苦味がないまぜになった歪みが唇に浮かぶ。
一度は騎士にまで登りつめた奴隷が、またしても奴隷に逆戻りしたわけか――
かぶりをふってくだらない考えを振り払っていると、がたがたと音を立て、檻の戸が開かれた。短剣で囚人たちを遠ざけながら入ってきた奴隷商人が手を伸ばしたのは、先ほど転んだ娘。
「来な。新しいご主人様がお待ちかねだ」
咄嗟に逃れようとして逃げ切れず、後ろ髪を掴まれた娘が驚きと泣き声がないまぜになった悲鳴を上げる。 娘の姿が、幼いころに目の前で引きずられていった姉に重なり、気が付いた時には奴隷商人に体当たりしていた。腰を屈めていたせいであっけなく体勢を崩した奴隷商人の手を掴んで捻り上げ、女を解放する。 純粋な義憤というよりは、これまで散々な扱いを受けた鬱憤が当たり所を見つけて一気に噴出した感じだった。思わずうずくまった奴隷商人に背後から馬乗りになり、さらに頭を掴んで床に擦りつける。 が、つかの間の抵抗は腕に走った鈍痛に頓挫した。騒ぎを聞きつけてやってきた別の男に殴られたのだと知ったのは、咄嗟に手を離し、檻の隅まで退避した後。
「この野郎、今度やったらその腕切り落としてやる!」
地面にうずくまり、必死で空気を吸い込む男を助け起こしながら怒鳴るのは、こちらは握りしめた棍棒の他に腰に鞭を巻きつけた奴隷商人。 結局、娘はさらに現れた別の奴隷商人に連れ出され、ヴェルカンはもう一発殴られる羽目になった。 脇腹をさすりながら人ごみに紛れて消えていく娘の後姿を見やり、舌打ちしていると、同じ檻に入れられていた男のひとりがのそのそと這い寄ってきた。
「いきなり襲いかかるなんて、あんたもやるねえ」
欠けた歯を見せながら愉快そうに笑う。あの女に惚れたか、なんでぶち込まれた、元は何をやってたと遠慮なく問うてくる。 生返事でやり過ごしていると、さして気にした様子もなく、檻の戸に目を向ける。 彼が言うには、今の娘は貴族の出であるという。 思わず驚きの目を向けると、男はまたしても笑った。今度は無知な若造への苦笑だ。
「おいおい、そう驚くことじゃなかろうよ。ふとした拍子に落ちぶれる奴なんざ身分を問わずいるさ」
災害か、戦禍か、はたまたわきまえない贅沢か。望むと望まざるに関わらず、入ってくる分を出ていく分が上回れば身を持ち崩すのは貴賤に関わらぬ道理。
「かわいそうに、借金のかたに家財産根こそぎ持ってかれて、愛娘は売られ者。親兄弟とも泣き別れさ」
可哀想とは言いながら男はさもおかしそうに腹を抱えて笑う。
「とはいえ女の子なのは幸運だったな。貴族の娘なんざ珍味だから、娼館にでも放り込めばたちまち満員御礼だろうて」
胸が悪くなる話にため息ひとつを返事にし、さっさと話題を変えることにした。 問えば、男は以前の身分をこそ話したがらなかったが、自分は望んでここにいる、あの貴族娘とは違うと強硬に言い張った。
聞けば、こういうことだ。
「買われりゃ少なくともおまんまと寝床にゃ困らんからな。うまく立ち回りゃ立身や恩赦も夢じゃねえ」
奴隷は決して安い買い物ではない。買う側も自ずから慎重になり、手に入れた奴隷を大切に扱う。完全な所有物であり、徹底的に自由がないことを除けば安定した身分だ、というのが男の弁だ。
「東の帝国にゃ、騎士に叙された奴隷もいるって話だぜ」
それはまさか……と問おうとして思いとどまる。
「そこまで成り上がれるのはよほど運の良い奴だろう。たいていの奴隷はそうはいくまい」
言いながら、己は運が良いのだろうかと内心で自問する。思えば、吹けば飛ぶような貧農の子が皇帝の目に留まり、騎士にまで叙されるなど、あまりに出来すぎではないか。さらに、そもそものきっかけは皇帝時代の先帝が――
わざとらしいため息が、ヴェルカンの意識を檻の中に引き戻した。
「あんたも夢がないねえ」 「そちらが楽天的すぎるだけだと思うぞ」
言い合っていると、またしても奴隷商人が背を屈めて入ってきた。見れば、先ほど殴り倒した男で、ヴェルカンを見下ろす目は苦い。
「喜べ。お前を買いたいという奴が現れたぞ」
おとなしくついていくのが癪で、ことさらに、ほう、と笑みを浮かべて見せる。
「そいつもお前みたいに痛めつけてやろうか?」 「そういう減らず口を叩くような命知らずが欲しいんだと。舌を失いたくなけりゃとっとと来い」
一度は檻から引き出されたヴェルカンだったが、それも束の間、今度はずっと狭い檻に放り込まれることになった。 檻は痩せたロバが曳く馬車に載せられた。縄を握るのは白い服に浅黒い肌が際立つ小柄な男。商人らしく、荷車には包みや箱が満載で、荒い息で喉を鳴らすロバは今にも崩れ落ちそ���だ。
「でかくて強そうな奴を、と注文を受けてたんだ。ぴったりのが見つかって良かったよ」
振り返り、相好を崩す男の風貌は帝国では珍しい類のものだが、ヴェルカンはよく似た者たちを知っている。
「山の民が、こんな場所で商売をするのか」
かつて出会った、深山の奥深くで弓を手に疾駆する生き様とはかけ離れた姿に、つい声が漏れた。そこだけ同胞の面影を��す、独特の刺繍を凝らした鉢巻の下から振り向いた大きな黒い目が束の間見つめてくる。
「山の子にも色々いるのさ。里人の中にもあんたみたいに売り物になる奴がいるようにな」
奴隷として売られていく我が身を揶揄されたことに気づき、思わず口をつぐむ。 反論の言葉は渦巻く思案を巡らせる間に細かく砕かれ、喉から滑り出る時には苦いため息になっていた。
「濡れ衣なんだ。私は無実だ」 「そりゃお気の毒に」
あっけらかんとした声音には同情のかけらもない。聞こえないように放った舌打ちで我慢し、ヴェルカンは声を潜めた。
「私を解放してくれたら、私を売るのと同じ値を出そう。いや、二倍……三倍払ってもいい」
この言葉に、山の民の商人はつと足を止めた。 水龍の国の物価は詳しくないが、奴隷の値はどこもそう変わらぬはず。そう当たりをつけ、領地の財政状況と頭の中で天秤にかけてみる。三倍以上出すことになれば普段は甘い衛兵隊長もさすがに眉をひそめるだろうか。 必死に思案を巡らせるヴェルカンを黙って見つめていた商人だったが、ややあって目を逸らすと、再びロバの綱を引き始めた。
「長くこんな仕事をやってると、そいつの言ってることが本気なのか、その場しのぎの言い逃れでしかないのか、結構わかるようになるんだよ」
いくぶんの間を置いて出てきた次の言葉は、ロバのひいひいと軋むような息に半ば紛れてしまっていた。
「あんたは嘘はついてないんだろう。金もあるだろうし、その金を約束通り支払うくらいは義理堅そうだ」 「それでは」
一瞬の沈黙ののち、商人は唐突に話題を変えた。
「あんた、商売でいちばん大切なことはなんだと思う?」 「より大金を稼ぐことじゃないのか」
この回答がお気に召した様子で、山の民の口が三日月の形に跳ね上がった。
「それもそうなんだけどね。そのために肝心なことがあるんだよ」
首をひねり、考え込むヴェルカンの姿をひとしきり堪能したのち、商人は勿体ぶった口調で「信用だよ」と告げた。
「商いといったって、ほとんど使い走りみたいなものさ。だが俺だって、最初から奴隷みたいな高級品を任されてたわけじゃない」
通常の商店とは異なり、客や他の商人から注文を受けてから品物を調達してくるのが男の生業。元手もなく、駆け出しの頃は安い雑穀やガラクタ同然の古物を端金で運ぶ日々だったが、そのなかでも守っていたことがあった。
「麦の一粒、端切れ一枚に至るまで、寸分違わず送り届けた。一度の間違いも誤魔化しもしたことがない」
同業には商品の数を誤魔化したり、安価な粗悪品を混ぜることで上前をはねて小銭を稼いでいた者もあったが、そういった悪事はえてして思いもよらないきっかけで露見して、そういったことをしていた者はえてして落ちぶれた。 そんななか、毎回正確に注文通りの品物を持ってくる商人は少しずつ顧客の信用を勝ち取り、次第により多くの客がより貴重な商品を任せるようになっていった。例え���宝飾品、例えば魔法の品、そして例えば奴隷――
「こいつに任せれば安心だ、こいつなら損はしない――商売するのも人間だからな。最後にモノを言うのは結局のところ、相手に対する感情なのさ」
しみじみと述べたのち、再び芝居がかった仕草でヴェルカンを振り返る。浅黒い肌に白い歯が映えた。
「そんな積み重ねがあって、今あんたと話しているって次第さ」 「信用、ね……」 「もしあんたを逃せば、俺は何年もかけて積み上げてきた顧客の信用と、この先何年も請けるはずだった仕事と稼ぎを一気に失うんだ。その分もあんたに払えるかい」
何も言い返せず、ヴェルカンは唸ったが、相手はそもそも返事を期待していたわけではないようだった。「逃がしてはやれないが、助言ならできる」とさらに話題を変えた。
「ひとつ、誰でもいいから信用を勝ち取ること。もうひとつは、信用してくれた相手を決して裏切らないことだ」
それは奴隷にも当てはまるのだろうか。問おうとして、そもそも無意味な質問であることに気付く。
「……忠告、痛み入る」 「ま、せいぜいがんばんな。応援してるよ」
やがて馬車は魚の旗が彩る城門を抜け、町へと滑り込んだ。街並みを眺める気にもなれず、檻の硬い床に寝そべって見上げた空を切り取るは噂に聞く石の壁。死者の国を思い出すが、精緻な彫刻は複雑な陰影をヴェルカンの顔に投げかける。がつがつと無遠慮に背を打つ感触は石の道を進んでいるからだろうか。
「さあ着いたぞ。ここがあんたの新しい家だ」
そんな言葉とともに檻の鍵が開けられた。痛む尻をさする間もなく伸びてきた二本の腕に捕まり、引き出される。 目の前にそびえるのは、それはそれは巨大な建物。見上げる分には全貌は定かではないが、緩やかな弧を描く壁面は帝都の闘技場を彷彿とさせる。 同時に衛兵隊長から聞かされた、本物の殺し合いを供するという劇場の話を思い出してしまい、口の中が苦くなる。 思わず振り返ったが、金貨の袋を弄びながら去っていく山の民の商人はヴェルカンの姿を見ようともしなかった。
*
半ば予想通り、建物は闘技場であり、ヴェルカンは闘士として売られてきたのだと知れるまで、そう時間はかからなかった。 薄暗く黴臭い控室はそこそこ広い部屋ではあったが、ヴェルカンを始め所在なく見回す大勢の男たちで立錐の余地もない。 身じろぎや咳払いばかりが響く時間が過ぎ、やがて新たにひとりの人間が現れた。 派手なマントで身を飾った彼は興行師を名乗り、男たちを裸に剥くと一列に並べた。
「お前、強そうだな」
最初に声をかけたのはいちばん端に立っていた男。中背ながら古傷に覆われた肉体は筋骨隆々、髭もじゃの顔も厳めしい。
「傭兵をやってた。二十人は殺した」
そう言って浮かべた表情は、笑うというよりは牙を剥き出した獣の様相だったが、興行師は「志願組か」軽く鼻を鳴らしただけだった。
「安心しろ。二一人目に殺されるように試合を組んで、そ��業深い人生に幕を引いてやる……お前は?」
続いて隣に立っていた男。傭兵以上に逞しい体つきと、妙に生白い肌がちぐはぐだ。
「あの、鉱夫をやってました」 「殺しの経験は?」 「いえ、ありませんです」
いかにも朴訥そのもの、自分がなぜここにいるのか分からないといった風情の大男を上から下までひとしきり眺めた後、興行師は手を伸ばしてその肩を叩いた。
「鉱石と人間の頭はどちらが硬いか、試してみるんだな……次!」
闘士たちに順番に声をかけていく興行師は、やがてヴェルカンの前に立つと、その引き締まった体をじろじろと観察し、最後に灰青色の目を見上げた。
「何ができる?」 「歩く死体の軍勢と渡り合った」
軽い気持ちで口走り、直後、かつてまみえた地下王国の民たちを侮辱しているような心地になり後悔する。 だが興行師には気付かれなかったらしい。あからさまに顔をしかめ「死体だぁ!?」と頓狂な声を上げた。
「いい加減な事ぬかしてんじゃねえ。白騎士ヴェルカンでも気取ってんのか」
今度はヴェルカンが驚く番だった。
「なに、白騎士だと」 「知らんのか。東国の騎士を歌った詩だ。巨人退治やら秘宝探索やら、いくつもの大冒険を果たした英傑さ」
自身が詩になっているなど、寝耳に水だった。絶句している騎士本人など気にもとめず、興行師は詩の一説を暗唱し始めた。
「高らかに名乗る騎士、怪物の雄叫びをものともせず槍を振るう。白い鋼の矛先は巨人の喉を貫きて、穢れの血を……」 「やめろ!あんな奴の話など、聞きたくもない!」
古傷を岩塩で抉られるような心地に思わず声を荒げたヴェルカンに、興行師は初めて驚いたような顔をした。
「なんだ、知ってるのか」 「知ってるとも。剣を振り回して暴れるしか能のないろくでなしさ」
唇を歪めてみせれば、目を三角に吊り上げた興行師はヴェルカンの胸を何度も指で突いた。
「咎人だか捕虜だかしらんがな、しょっぱい売られ者の剣奴風情が、知ったような口をきくんじゃねえ!」
罵詈雑言の限りを尽くした後、他の闘士たちの視線に気づいたらしい興行師の熱が瞬く間に引いた。
「俺様相手にここまで吹かしたクソ度胸は買ってやる。覚えてろ。次だ!」
*
全員に声をかけ終えると、興行師は闘士の間を行ったり来たりしながら声を張り上げた。
「ここがどういう場所かは知っているだろう。名高い水龍の王国の劇場だ」
あるいはお前たちの中にも以前客席から砂場を見下ろしたことがある奴がいるかもしれない。が、今度はお前たちが観客どもに見下ろされながら派手に殺し合いをする番だ。
一息に言い切り、反応を伺うように見回す。大げさな仕草で振り返った拍子にマントが大きくはためく。
「何の因果でこんな場所にやってきたのか、興味はない。俺を恨もうが憎もうが大いに結構。斬り合いが嫌というならそれも構わん。対戦相手の手柄になってもらうだけだ」
男たちは沈黙を保った��ま、それでも興行師の一挙手一投足を見逃さぬよう目で追いかける。
「ただし、勝てば金は手に入るし、奴隷として惨めったらしく這いつくばるはずだったお前たちが大勢の人間から畏怖されることになる。 ……どうしたいかは自分で決めろ。舞台の上だけがお前たちの自由だ」
以上、の言葉で締め、もう一度居並ぶ男たちを見渡す。やはり誰ひとり何ひとつ口にすることはなく、互いにちらちらと視線を交わすばかり。 やがて興行師が退室してしまうと、どこからともなくため息が聞こえた。
「俺たち、とんでもないところに来ちまったな」
誰の放った言葉か、詮索するのは無駄だろう。ヴェルカンも同じことを考えていたところであったし、他の者たちもおそらく同様だろうから。
*
翌日、鍵付きの狭苦しい宿舎で眠れぬ夜を明かしたばかりのヴェルカンは、早速試合に組み込まれた。やはり興行師の不興を買ったのがいけなかったか、などと考えている間に、雑用係の手で合わない防具が着せられ、古びた戦槌が手渡される。
「もっと大きめの鎧はないのか。それに剣か槍の方が得手なんだが」 「試合が終わったら選ばせてやるよ」
軽口に同程度の軽口で返され、やや憮然としていたところに、呼び出しの鐘の音が響いた。 今更じたばたしても始まらぬ。せいぜい全力を尽くすまで。 一度深呼吸をすると、ヴェルカンは控え室を飛び出した。
闘技場は帝都のそれと同じく、中心に穴の空いた円柱形をしている。中央の穴はいうまでもなく闘士が命がけで戦う舞台、円柱の上部は観客席だ。そして選手の控え室は観客席の真下、“穴”とは短い通路を隔てられただけの場所にある。そのため、控え室から一歩外に出ただけで群集のざわめきが耳に届いた。
おぞましい殺し合いの見せ物を心待ちにする声だ。
重い戦槌を手に階段を登ると、待っていたように鎖を巻き上げる音が響き、巨大な落とし戸が一気に開いた。
刹那、凄まじい光と音が押し寄せて体中を満たし、ヴェルカンは息を飲んで立ち尽くした。 やがて体に感覚が戻ってくると、ヴェルカンはぎらつく陽光が降り注ぐ闘技場に立っていた。様々な理由で地面が汚れても容易に交換が可能なよう砂利が敷き詰められた広場、その一段上のぐるりを取り巻く盆地型の観客席は今、老若男女様々な人間に埋め尽くされている。そのすべてから上がる歓声がぶつかり混ざり合って増幅され、場内に音の洪水と異様な熱気を生み出していた。
「さあさ、皆���まお待ちかね!本日も血沸き肉躍る闘技試合の時間がやってまいりました!」
高らかな司会の声に合わせて再び歓声が上がる。 砂場の反対側に立つは対戦相手。昨日、薄暗い控室で元傭兵を名乗った男は古傷だらけの筋肉を防具に包み、鋭い刃を植えた手甲を掲げて歓声に応えている。
「何やってる。お前も愛想のひとつも振りまくんだよ」
目を白黒させて突っ立っているばかりのヴェルカンに業を煮やしたか、壁に並んだ小窓から興行師の��咤が飛ぶ。 慌てて拳を突き上げると、観客席のどよめきは一層激しさを増した。
「今回、命を賭して闘うはこのふたり!この地の砂を初めて踏んだ新兵なれど、いずれ劣らぬ百戦錬磨の古強者!」
傭兵の方はすでに準備万端といったおもむき。歓声に合わせて拳を振り回し、雄叫びを上げる。
「いいぞ、あの生白いのをやっちまえ!」 「お前に賭けてるんだ、負けるなよ!」
そんな野次が飛び交い、人々の歓声や足踏みが音の濁流と化して全身を揺さぶる。感覚が麻痺しかかった頭蓋は、ともすれば今から殺し合いを始めるのだということさえ失念しそうになる。 それは傭兵も一緒なのか、あるいは元々荒事を好むタチなのか。面甲の下で白い歯を覗かせて吼える大きな口からは判然としない。
「さあ戦士たちよ武器を取れ!存分に引き裂き、切り刻み、叩き潰すのだ!」
司会の宣言に合わせてラッパが吹き鳴らされた瞬間、場の興奮は最高潮に達した。 いち早く動いたのは傭兵だった。赤銅のごとき筋肉を躍動させて距離を詰め、咄嗟に身構えたヴェルカンの目の前で身を沈める。
ほんの一瞬、相手の姿が視界から消えた。
刹那、顎から胸にかけてちりちりとした疼きを感じ、それが何かを判じる前に一歩身を引いた時には鼻先が触れる位置に手甲が突き上げられていた。 目の前の刃に映る灰青色の瞳に腹の底がすっと冷たくなり、己の息遣いがひどくゆっくりと感じられる中、男の腕に蠢く血管の一本一本までがはっきりと見て取れた。 お返しと振り抜いた戦鎚を傭兵はやすやすと躱し、今度は飛び上がって体重を乗せた一撃を繰り出してくる。 斧のごとく振り下ろされた鉄拳をかざした戦鎚の柄で受け、寸の間、がら空きになった胸当てを力任せに蹴り飛ばす。 間髪入れずによろめいた傭兵の脳天を狙って戦鎚を振り下ろす。が、相手はくるりと身を翻し、虚しく砂を散らした柄頭から走った衝撃に腕が揺さぶられる。 小さく舌打ちが漏れた。慣れない戦鎚は扱いに難しく、ともすれば自分が振り回されそうになる始末。隙あらば懐へと潜り込もうとする身軽な相手を払いのけるのに精一杯で、反撃すらままならぬ。
と、再び振り上げようとした戦槌の柄頭を傭兵の足が踏み押さえた。反射的に引き抜こうと腕に力を入れると同時、頑丈な脚が再び目にも留まらぬ早業で打ち下ろされた。弾けるような音を立て、戦槌の重みが突然消えた。 自らの力に引きずられて二、三歩後ずさり、そこで柄頭が折り取られたことを知る。舌打ちする間もなく飛んできた右の拳を棒きれと化した戦槌の柄で払いのけ、続けざまに突きこまれた左の拳を身をよじって避けようとして避けきれず、輝く刃がヴェルカンの胸当ての表面を削ぎ、右腕の肌を裂いて血滴を散らした。 ひやりと涼しい風が触れたような感触が一瞬遅れて痺れにも似た熱に取って代わり、瞬く間に観衆の熱気に変わる。 だがヴェルカンも負けてはいなかった。棒きれとはいえ無造作に折り取られた柄の先端は鋭く尖り、重さも手頃。傭兵から後ずさって距離を取りながらそのことを見て取り、素早く持ち直す。
休む暇を与えず追撃してきた傭兵の右手を跳ね上げた柄で打ち払い、そのままの勢いで相手の胸を狙って突きを繰り出す。 思いがけない反撃に傭兵が怯んだ。咄嗟に片足を引いて直撃を躱したものの、その目は驚きに見開かれている。だが次の瞬間、驚きは怒りに急速に変じ、筋を浮かべた足が己が間合いに踏み込まんと砂を散らした。陽光を照り返し、手甲が炎と燃え盛る。 飛んできた左の手甲を、ヴェルカンは身をよじってかいくぐり、そのまま右腕と脇腹で挟み込み、締め上げた。 傭兵の顔に明らかな動揺が走った。慌てて右拳を繰り出してきたが、ヴェルカンはそれを左手で掴んで食い止めると、抱き合ったような恰好のまま膝蹴りを相手のむき出しの腹に叩き込んだ。 小さく折り曲がった体を跳ね上げて傭兵が上げた苦悶の声は沸き起こった歓声にかき消された。束の間力を失い、沈み込んだ相手の体に引きずられないよう咄嗟に手を離し、一歩退く。だが敵もさるもの、よろめきながらも踏みとどまり、ヴェルカンから距離を取ろうとする胆力は歴戦の戦士のなせる業か。 が、この好機を逃す手はない。ヴェルカンは柄を握りなおすと力任せに振り下ろした。鋭くささくれた先端が筋肉の束のごとき太腿に深々と食い込み、血と悲鳴を迸らせた。 よたよたとおぼつかない足取りで後ずさろうとして果たせず、ついに傭兵が砂埃を立てて崩れ落ちる。その眼にもはや闘志はなく、ただ生への希求が見て取れるばかり。幸い出血はそれほど酷くはない。適切な処置を施せば助かるはずと見込み、手を差し伸べようとした時だった。
初めは観衆の単なる歓声と思えた。だがそれは次第に規則性をもってまとまり始め、やがてひとつの音を結んだ。
殺せ!殺せ!殺せ!
今や観客のすべてがひとつの生き物と化し、繰り返し叫ばれる言葉はさながら鼓動。止むことなく発せられる律動は愕然と立ち尽くすヴェルカンの全身を揺さぶった。
「何をぼさっとしてる。さっさとやれよ」
またしても小窓から興行師の顔が覗く。
「しかし……」
無抵抗の相手の息の根を止めるなど、と反駁しようとした矢先、興行師の目が吊り上がった。
「文句があるならお前が奴の代わりに死ぬか?ならせいぜい派手にやれよ。お客が喜ぶようにな」
思わず言葉に詰まると同時、奴隷という己の身の上を思い出す。「客をあまり待たせるなよ」と有無を言わさず興行師は引っ込み、ヴェルカンはただひとり取り残された。 歩み寄ったヴェルカンを、傭兵は荒い息の下、血走った目で見上げた。目を合わせないようにしながら手甲をもぎ取る。もはや力が残っていないのか、僅かに抵抗したのを最後に力を失った手が砂埃を立て、それも風に消える。
恨むなよ――――
無意味と知りつつ内心で語りかけながら、両手で支えた手甲の刃を下に向けて掲げる。一瞬で終わらせるべく狙うは喉。邪魔されぬよう傭兵の手を踏み押さえ、激しく上下する喉仏以外の一切を視界から追いやる。観衆の声にことさらに意識を振り向け、思考を塗りつぶ���ていくのを待ち、そして――
一瞬、高みへと跳ね上がった歓声が束の間に萎み、僅かの沈黙を経て拍手に代わった。
「試合終了!見事な闘いを披露した二人の闘士に、惜しみない賞賛を!」
司会の宣言が高らかに響き渡り、またも湧き上がった歓声が闘技場を満たしていく。その声に応える気力はもはや失せ、半ば押されるようにしてふらつく足を進める。 再び開かれた落とし戸をくぐる直前、血に塗れた手甲を握ったままなのに気づいた。投げ捨てた拍子に、手にまとわりついた血の粘りが強く感じられ、思わず手を擦る。粘りはますますひどくなり、腕全体に広がるようだった。
*
「おめでとう、新闘士の諸君」
窓から星明りが差し込む刻限。宿舎の一角で、興行師は笑みを浮かべた。 彼の周りには温かい料理が燭台に照らされて艶やかな輝きを放ち、そのさらに周りにはヴェルカンたち新入りの奴隷たちが炎に浮かび上がる。その人数は昨日のちょうど半分。元傭兵を始め、昨日まではいたはずの幾人かの顔が見当たらない。彼らの末路を想像するのはおよそ詮無きことであろう。
「今日ここをもって、お前たちは我が闘士団の正式な闘士となった。今後は活躍次第で富も名声も思いのまま、恩赦をくれてやることだってありえる」
この国には複数の闘士団が存在し、今後はそれらが擁する闘士たちと試合を繰り広げることになる。そのほか日々の仕事はどうだ、報酬はこうだ、と細々とした説明のあと、再び笑って料理を示す。
「面倒な話はこれくらいにしておいて、とりあえず今夜は祝いだ。遠慮せず食え」
初めは遠慮がちに顔を見合わせていた新闘士たちも、ひとりが意を決して串焼き肉に口をつけると我も我もと手を伸ばし始めた。 ここで待っていたように入ってきた一団があった。老若男女、様々な顔ぶれの彼らはいずれも先達の闘士たちということで、新入りを歓迎するべく押しかけたのだ。 自己紹介と祝いの言葉を重ね、固かった新入りたちの表情も次第に和らぎはじめる。ヴェルカンも闘士たちに囲まれ、笑いと冗談に囲まれているうちに、少しだけ気分が軽くなるのを感じた。 よくよく見てみれば、目の前に並ぶ豚の丸焼きや魚の煮凝り料理、香辛料を溶いた葡萄酒も、居城の質素な厨房ではついぞ目にしたことのないものばかり。祝いとはいえ奴隷にこれだけのものを食べさせるとは、よほど特別な行事なのか、この国の豊かさを示すものか。 摘んだ豚肉の脂は見た目通りの濃厚さと豊潤さで口中に広がり、思わず唸る。
「よく味わっとけよ。同類の命と引き換えに食うごちそうだからな」
おそらく軽い冗談のつもりだったのだろう。誰が放ったか、呟くような声はあっという間にかき消え、他の誰ひとり気にも留めない。が、昼に浴び続けた歓声が抜けたヴェルカンの胸の中にその声はたやすく滑り込み、根を張って肥え育つようだった。 手に付いた脂のぬめりは傭兵の血を彷彿とさせた。頬張った豚肉を反射的に���き出したくなった衝動をこらえ、どうにか飲み下すと、今度は胃の底からせり上がるような嘔気が襲いかかってくる。 何度も唾を飲み込み、どうにか皆の目の前で吐く失態は犯さずに済んだが、もはやこれ以上宴を楽しむ気になれず、さりげなく身を引く。と、やはり闘士たちの輪の外にぽつねんと座っている者を見つけ、そちらに近づいてみることにした。
膝を抱え、大きな体を縮めるようにしている男が鉱夫上がりの奴隷だったことを思い出すまでに多少の思案を要した。 視線に気づき、男が頭をもたげた。もとより色白の頬はいまや血の気を失い、遠く燭台の炎のせいで土気色にも見えた。
「あんなに血が出るなんて思わなかったんだ。痛い痛いって転げまわってて、それで……」
怯えた目をヴェルカンに向け、そこまで言ったところでおもむろに立ち上がった鉱夫は、窓辺に駆け寄るや激しく嘔吐し始めた。その背をさすってやると、手のひら越しに震えが伝わってきた。 おそらくこれが正常な反応なのだろう、と暢気にどんちゃん騒ぎに興じる闘士たちを尻目に思う。
ふと、昼に倒した傭兵を思い出す。 彼は数十もの敵を屠ってきたことを誇りにしていた。自ら闘士として志願したことから、もとより残虐な男だったやも知れぬ。 とはいえ、それはいつも己がしていることではないか。遮るようにさらに別の声が聞こえた。騎士として、民のためと称して数多の敵を――それぞれに人生も、守るべきものもあったであろう人間たちの命を奪ってきた。 傭兵と、彼を殺したヴェルカンとの間に何の違いがある?己の行いに何の義があったといえようか。 違う、とさらに別の声がした。それはあくまで強いられたことであり、やむを得ず―― 結論の出ない自問は、最後に傭兵にとどめを刺した血だらけの己の姿と、その瞬間に沸き起こった人々の大喝采を鮮明に蘇らせ、五感を揺さぶった。
あの場で私がしたのは何だっだのだろう。この国がしていることは何なのだろう。
行き場を失った思惟は身の内を暴れ狂い、やがて喉元をせり上がってくる感覚があった。 大慌てで窓から首を突き出し、口中にまで達していた思惟の塊を一気に吐き出す。臓腑が締め上げられるような不快感と鼻を刺す酸臭が交互に押し寄せ、宴で口にしたことごとくを絞り出す。 ふと、背中に硬いぬくもりが触れた。それが鉱夫の手だと気づいた瞬間、不思議と体が楽になる。それはあるいは苦楽を共にする仲間の存在があると知れたからだろうか。 まったく、とすっかり空になった腹の中から掠れた声が滲み出た。
「とんでもないところに来てしまったものだ」
口にしてから、どこかで聞いたような言葉だと思った。が、どこで誰が口にしたのかはついぞ思い出せなかった。
0 notes
Text
白騎士の冒険 夢幻の闘技場 始
騎士が捕虜になった話
まともな城壁もないヴェルカンの城館だが、棟に囲まれた中庭はある。初めは土が剥き出し、中央を飾る鎧騎士の石像も蔓草に覆われてひどい有様だったが、厨房番の老婆の献身的な手入れの甲斐あって、小さな庭園は種々の薬草と野菜が生い茂る畑となっていた。 この日もこの日で、ヴェルカンが中庭に出ると、厨房番が土いじりをしていた。
「これは城主様。日向ぼっこですか」 「毎日、精が出るな」 「ええ、好きですからね」
泥だらけの手を前掛けで拭いながら機嫌よく笑う。
「城主様が持って帰ってくださった土のおかげで、どれもこれも、ほんによく育って……」
料理するのが楽しみです、という声を笑いながら受け、向かう先は庭の隅、小さな土饅頭。かつての友達が眠る墓は、死者の国から持ち帰った生命の石粉を使わずとも常に花が咲き乱れ、芳しい香りであたりを満たす。 日にいちどはここを訪れるのがヴェルカンの日課になっていた。ただ土饅頭の前に立ち、わずかな時をぼんやりと過ごすだけの時間ではあったが、ヴェルカンはこの時間を何よりも大切にしていた。
私は、強くなれただろうか。
通り抜ける風が立てる微かな葉擦れの音を聞きながら胸の内で語りかける。 幾多の困難を経て、財も名声も手に入れつつある。だが、まだだ。子供のころに離してしまった手はいまだ時の霧の向こう。 いつものように、花畑の下に眠る友は何も答えない。それでもいい。今はまだ。
*
自室の扉の前で待っていたのは書簡を手にした衛兵隊長だった。帝都から使者が訪ねて来たのだという。
「帝都から祝宴の招待状が届いております。再来月、闘技試合が催されるとか」 「闘技試合?」 「今回の賞品は皇帝家お抱えの鍛冶師が拵えた飾り盾だそうで」 「今回の、というと、過去にもあったのか」
聞きとがめると、衛兵隊長の太い眉がわずかに下がった。曰く、闘技試合や宴席への招待状は以前からも何度か届いていたのだという。
「これまでは盗賊騒ぎやら秘宝探索やらで忙しゅうございましたからな。卿には申し訳ないですが、私の独断でお断りさせていただいておったのですが」
このところ平穏であるのだし、せっかくだから参加してみてはどうかという。
「卿は働きづめでしたからな。たまには羽を伸ばすのもようございます」
衛兵隊長の言葉に、ヴェルカンは顎に手をやって唸った。
*
建国以来二度の遷都を経て現在の場所に収まったという帝都は、大陸を中央で十字に区切って見た場合、南東の地域の中央やや南に鎮座している。周囲にはべらせたいくつもの街、無数の村からは物資を満載した馬車の列がひっきりなしに往来し、遠目には道自体がうねっているようにも見える。いつ訪ねてもそれは変わらない。それはおそらくこれからも。そうであればよいと思う。
赤い鎧を着た闘士が倒れ伏す音は沸き起こった大歓声にかき消された。緑の鎧を着た闘士が上げた勝ち鬨がそこに混ざる。
「いやはや、やはり試合というものは血が騒ぎますな」
葡萄酒の盃を片手に笑うのは衛兵隊長。頬がやや赤く上気しているのは酔いによるものか、闘技場を包み込む熱気にあてられたものか。 闘技場は城門のほど近くに建設された巨大な建物で、基本的な構造は中心をくりぬいた円筒といった趣だ。ずっと昔、騎士として叙される前にいちど、参加者として入れてもらった内部は迷路のように複雑かつ堅牢で、案内役がいなければ迷ってしまいそうなほどだった。万が一の際には避難所もしくは要塞として機能するため、地下には単なる娯楽施設らしからぬ量の食料や武具の類が備蓄されているのだとその時に聞かされ、また闘技場と帝宮とをつなぐ秘密の地下通路があるという噂を聞かされたのはしばらく後の事だった。 とはいえ、闘技場がそのような目的で使用されたことは都が築か���てから現在に至るまで一度もなく、日々客席を埋め尽くす観客の肴として供されているのが備蓄食料の現状であるという。
「卿も参加してみればよろしいのに。見ているだけでよろしいので?」 「私が出たら結果を予想する楽しみがなくなるだろう?」
ずいぶん大きく出ましたな、と衛兵隊長は目元の皺をいっそう深くする。
「それでなくとも戦い続きだったからな。たまには休むのもいいだろう」
確かに、という言葉を耳に、改めて闘技場を見下ろす。 戦えば誰かが傷つき、倒れる。にも拘らず、なぜひとはこうも剣の打ち合いに心惹かれるのか。
「試合なら誰も死にませんからな。剣技の妙や闘士の強さを存分に楽しむことができるからでは��いですか」
いかにも武辺者らしい衛兵隊長の言葉は、新たな試合の開始を告げる合図と、再び沸き起こった歓声にかき消された。
*
闘技試合の後、帝宮では宴が催された。優勝した闘士を祝い、ねぎらうため……というのは名目で、要はどんちゃん騒ぎのついでに貴族同士の親睦を深める機会だというのは衛兵隊長の弁だ。 そういうわけであるから、宴席にはヴェルカンのみならず、帝国内の多くの貴族諸侯が招かれていた。 帝宮内の一角、そこだけで城がひとつ建てられそうな大広間は、いまや貴族や騎士とその従者でごった返し、その合間を縫って無数の給仕が駆け回り、片隅のわずかな隙間に食い込んだ楽団や詩人が楽器をかき鳴らす騒乱の坩堝と化していた。
「来る場所を間違えたらしい」
両脇に衛兵が列成す大扉をくぐった直後、目の前の光景に圧倒され、しばし立ち尽くしたヴェルカンがどうにか絞り出した言葉だった。 宴の出席者たちは老いも若きも、男も女もみな盛大にめかし込み、彼らが織り成す色彩の奔流は眺めているだけで目がちらつくほど。無論ヴェルカンもマントと目玉模様をあしらった首飾りで精一杯にめかし込んできたつもりだったが、フリルとレースが宝石を着て歩いているような貴族たちの宴席ではいかにも場違いに思えた。
「おお、あなたはもしや、西の湿地のヴェルカン卿ではございませぬか」
上ずった声の方向に目を向ければ、まん丸に肥えた体を真っ赤なひだ付きマントでさらに膨らませた男。卓と客たちの間を転がるようにして近づいてきた男の髭面に見覚えがなく、ヴェルカンは会釈しながらも曖昧に唸った。
「黒岩の領主閣下とお見受けします。ご機嫌麗しゅう」
とっさに首飾りの紋章を見て取った衛兵隊長が助け舟を出してくれた。やはり初めて会う相手だ。
「いかにも私がヴェルカンです。お初にお目にかかります」
改めて頭を下げれば、黒岩の領主は機嫌よく笑った。
「さすがは今を時めくヴェルカン卿、まだお若いのに人間ができておられる」
飾るのが苦手で最低限の挨拶をしただけなのだが、こうも褒めちぎられるとこそばゆい。
「時めくなど。私など一介の騎士に過ぎぬ身。恐縮です」 「いや、いや。あなた様の血湧き肉躍る冒険の数々は帝国中の男の憧れといえましょう」
まさか、と思わず衛兵隊長と顔を見合わせる。担がれているのかとも思ったが、こうして見知らぬ貴族にも顔が知れ渡っているのだ。有名になっているのはあながち嘘でもないらしい。 ひたすら領民の幸福と皇帝への報恩ばかりを考えて職務に邁進していたつもりのヴェルカンとしてはまったくの寝耳に水だった。
「ところで、これは私の娘でして」
それまで領主の背後に隠れていた小柄な少女が歩み出てぺこりと会釈。美人というよりは愛らしさが勝っており、父親譲りのまん丸顔に埋め込まれた、これまたまん丸な青い目がヴェルカンを見上げてくる。
「女子ながらに英雄譚や騎士物語に憧れておりまして。明けても暮れてもあなた様の話ばかり。今日もかのヴェルカン卿が来ると聞いて、どうしても自分も同席したいと言って聞きませなんだ」
この言葉に、令嬢がさも恥ずかしそうに父親の肩をひっぱたく。愛娘をいとおしげに振り返ってから、父親はにわかに顔を曇らせた。
「とはいえなにぶん世間知らずな娘のこと、こんな人の多い場所で、どんな悪い虫がつくやも知れません。そこで無礼を承知でお願いしたいのだが、あなたがそばについてやって下されば、おかしな気を起こす輩もおりますまい、と、思うのですが……」
ちらちらと窺う視線に、どうにもおかしな運びになってきた、と眉を歪めたヴェルカンだったが、立て板に水を流すがごとき早口に阻まれて口を挟めない。 思わず横目で見やると、すべて承知したという顔の衛兵隊長が、あえてヴェルカンの方だけを見て口を開いた。
「お取込みのところ恐れ入りますが、西の湿地領主との約束もございます。そろそろお急ぎになった方がよろしいかと」
本当は約束などありはしないのだが、これ幸いと口裏を合わせ、別れの挨拶もそこそこに、さも急いでいる風を装って呼び止められるのを防ぐ。
とにかくその場を離れ、追いすがるような視線が行き交う人ごみに遮られたところでようやく息をつく。念を入れてさらに距離を取ろうとした瞬間、目の前に長い脚が突き出された。 咄嗟に立ち止まったため蹴飛ばさずには済んだものの、停まれなかった衛兵隊長の体当たりを背に受け、つんのめってしまう。周囲の視線が一斉に集まり、すぐに離れていく中、ひとりの視線だけが残った。
「これはこれは、ヴェルカン卿ではございませぬか」
どこか絡みつく色を漂わせた声音の主は、やはり貴族と思しき男。衛兵隊長を見習って目を向けた首元に光る首飾りの意匠は帝国の目玉模様。同じ物はヴェルカンの襟にもぶら下がっている。 騎士――それも自分と同じ皇帝直属親衛騎士だ。
「このところ景気がおよろしいようですな。陛下の覚えも上々、さぞ気味の良いことでしょう」
無遠慮な上目遣い、取り囲むような足運び、まとわりつくような口調。本能的に相手に背を見せまいと向きを変えるヴェルカンの顔面に、敵意が細針となって突く。
「おっしゃる意味が図りかねます」
ヴェルカンも負けじと戦意を視線に乗せ、相手にぶつけた。わずかに目を細めた相手の声から上辺だけの礼節が消えた。
「奴隷騎士が。貴様のような賎民と我々が同列だと思うだけで虫唾が走る」
奴隷騎士――久々に耳にした侮蔑に一瞬で血が上った。思わず拳に力を込めたのを目ざとく見取り、距離を取った身のこなしは曲がりなりにも戦士のそれ。
「おお、怖い怖い。所詮は卑しい奴隷上がり、手は早いと見える」
皇帝のお膝元で殴り合いでも始めればどうなるか。言外に滲ませ、ほくそ��む。
「まったく、皇帝陛下もなにゆえ貴様のような賎民風情を重んじられるのであろうな。酔狂が過ぎる」
と、それまで黙ってなりゆきを見守っていた衛兵隊長が一歩進み出た。
「それより先は口になさらぬ方が御身のためと存じまする」 「従者の分際で意見する気か」 「それ以上おっしゃるならば陛下に対する批判としてあなたを告発せねばなりませぬゆえ」
わずかに挑発の色を含んだ声に相手の眉がぎゅっと持ち上がった。
「脅すとは面白い。きさまの顔は憶えておくぞ」
抑えた舌打ちとともにマントを翻し、足取りも荒々しく離れていく背中が人の波に紛れたのを確認し、ようやく肩の力を抜いた衛兵隊長に、二度も助けてくれた礼を述べる。
「礼には及びません。卿も災難ですな」
味方も増えるが敵も多くなる。名を上げ、力を得るとはこういうことかとため息つきたい気持ちになる。 いくぶんささくれた思いで円卓によりかかり、蜂蜜酒が喉を焼くに任せていると、今度は背後から肩を叩いた者があった。
「久しいの、ヴェルカン卿……どうした、怖い顔をして」 「あ、西の湿地の……お久しゅうございます」
かつての主君の姿に、慌てて踵を揃える。
「そなたが珍しく参加していると聞いての。捜しておったのだ」
そう言って目を向けた先、近づいてくる男の姿に、ヴェルカンは声を上げそうになった。
「堅苦しい挨拶はよしてくれよ。今日は西の閣下の甥なんだから」
反射的に膝をつきそうになったヴェルカンに先んじて、かつての皇帝はやんわりと笑みを浮かべた。
「まったく、閣下も酔狂が過ぎますぞ。ここには何人の貴族が顔を並べているとお思いなのか」 「なればこそ、ここで盃を傾ける僕が、まさか先の皇帝だと思い至る者もおるまいよ」
ねえ叔父上、とわざとらしく呼びかけられ、西の領主は珍しく苦虫を噛みつぶしたような顔をする。こうしてみていると本当の家族のようで、ふたりともなんだかんだで楽しんでいるのではないかとヴェルカンは思う。 そんな彼らが、自分にどういった用があるというのか。尋ねようとすると、先帝は無言で入口の大扉を指し示した。
大扉を閉め、前庭の池のそばまでやってくると、宴の騒音はほとんど聞こえなくなり、代わりにかがり火の薪が爆ぜる音や庭園に住む虫たちの声が耳に届くようになってくる。 少し離れた場所で立哨にあたる警備兵のマントが夜風にはためくのを眺めながら、西の領主は簡素な小箱を取り出した。
「これをある人物に届けてもらいたい」
開かれた小箱を覗き込んだ衛兵隊長は目を丸くした。
「じつに見事な首飾りですな」
色とりどりの宝石を管にして黄金の鎖で繋ぎ合わせた首飾り、その中心を飾るのは鶉の卵ほどの透き通った宝石。松明の赤い灯を浴びているにも関わらず、紫がかった冷たい煌めきを放つさまは、地下王国の生命の石もかくやという美しさ。
「これひとつでちょっとした屋敷が買えるほどだ」
そんな値打ちものを渡すほどの相手とは何者か。西の領主が言うには、黒の王国との国境沿いにある小国の商人であるという。
「��竜の住処という名の国だ。ご存知かな」 「硝子の都ですか。若い頃に一度行ったきりですが、素晴らしい場所です」
懐かしそうに笑みを浮かべたのは衛兵隊長。街中に張り巡らされた清潔な水路が陽光を照り返す有様は、さながら町全体が硝子細工と化したかのごとき美しさであるという。豊かな水源を擁する立地がなせる業で、水竜の名を冠するゆえんだ。
「その硝子の都で、わが国の商人による市場を開拓したい」
そのためには現地で力を持つ商人の許諾と協力が不可欠で、宝石はいわば心づけというわけだ。 しかし、つまるところ既存の市場を押しのけるような真似をするのだ。はたして余人が黙っているかどうか。
「それに、私の記憶が確かならば、彼の国は現在、黒の王国の属領であったはずでは?」
衛兵隊長の指摘に、先帝も難しい顔で頷く。
「そこでヴェルカン卿、君の出番というわけだ」
なるべく隠密に、最低限の手間で件の商人に宝石を届ける。その役目はヴェルカンこそ適任だと判断された。
「君はたったひとりで生ける死者が闊歩する地に潜入し、見事秘宝を手にして帰還した実績がある。道中、多少の揉め事があっても独力で解決し、確実に任務を果たしてくれると見越しての人選だ」 「揉め事と申しましたか」
耳ざとく聞きつけ、衛兵隊長の眉が微かに持ち上がった。
「そういったことが起こる可能性も否定できない、というだけだよ。なに、荷物を届けるだけだ。本当に何か起こるとでも?」
慌てたように言い繕われても答えられる問いでもなし。衛兵隊長と顔を見合わせていると、今度は西の領主が口を開く。
「実は、此度の件にそなたを推挙されたのは、ほかでもない皇帝陛下その方なのだ」
この言葉には、さすがの衛兵隊長も絶句した。「陛下が!?」と呟くように吐きだしたきり、何か言いたげに口をもぐもぐするばかり。
「左様。近頃のそなたの活躍にはかのお方もいたく注目しておいででな」
機嫌よく目を細める西の領主に咄嗟に返事をしかねていると、今度は再び先帝が口を開く。
「ところで、かの国は奴隷貿易が盛んでね」
ぴくり、とヴ���ルカンの眉が微かに動いた。それを見た先帝の唇が少しだけ持ち上がって見えたのは気のせいだろうか。
「多くの奴隷商人や人買いが出入りしている。あるいは君の姉君に至る手がかりも見つかるかもしれないよ」
今でも時折夢に見る。こちらを振り返りながら遠ざかっていく背中。ずっと昔に離してしまった温かい手――
「どうだろう、引き受けてくれるか」
その時、何と言って了承したのか、ヴェルカンにはついぞ思い出せなかった。
*
「またなんともきな臭い仕事とは思いませぬか」
帝都からの帰路。よく晴れた草原を馬の背で揺られながら、衛兵隊長はそんなことを言い出した。 任務にあたっては身元を明かすようなものは持たず、また余人にも話さぬよう、きつく命じられていた。旅の間、ヴェルカンは『西の湿地領内に居を構える皇帝直属騎士』ではなくなるのだ。それはすなわち、何が起こっても���国に応援を求められないことを示していた。
「水龍の国は黒の王国の属領なのだろう?無用な混乱を防ぐ、妥当な判断だと思うが」 「だからこそですよ。なぜ白の騎士たるあなたをわざわざ送り出すのか」
純白の甲冑に身を包み、皇帝に連なることを示す目玉模様の紋章を戴く直属騎士は、まさに帝国騎士の花形。それをあえて正体を隠してまで宿敵たる黒の王国の勢力圏に派遣する理由。
「だから、私を評価してくれているのだろう?」
自分で言うのは何ともむず痒く気恥ずかしいが、衛兵隊長が虚空を睨んで唸るのはそれが理由ではないらしい。「それだけでしょうか……」と歯切れも悪く逡巡する。
「ただの届け物だろう?何を難しく考える必要がある」
どちらにせよ、引き受けた以上今更手のひらを返すわけにはいかず、そも、皇帝の勅命とあれば拒むこともあり得ない。とすればあとはどう任務をこなすかに集中したほうがよい、というのがヴェルカンが騎士という身分の中で築き上げてきた思想だった。
「それはそうと、水龍の国に行ったことがあると言ったな。何があるんだ?」 「まさか、物見遊山としゃれ込むおつもりで?」
楽天的な主君にため息をつきながらも、衛兵隊長は顎に手をやって唸った。 美しい水路、行き交う小舟、水で傷まぬよう石で築かれた家々と見どころは多い水龍の国であるが、その中でも他に類を見ないないものがあるという。
「劇場でしょうな、やはり」 「劇場なら西の湿地にもあるだろう」 「いえいえ、劇場というのは便宜上の呼び名で、実態は闘技場です。それも本物の殺し合いを見世物とする」
本物の?思わず問い返せば、本物の。との言葉が首肯とともに返ってくる。防具で身を固めた闘士が木剣や棒きれで突き合い、危うくなれば降参を叫べば済む甘いものではない。真剣や凶器が相手の肉体を容赦なく破壊するために振るわれ、合戦さながらの血みどろの戦いが繰り広げられる――――金を払った見物客が押しかける、純然たる娯楽の一環として。 なんとも血なまぐさい娯楽もあったものだと内心呆れつつ、真っ先に気になったことを尋ねてみる。
「試合のたびに死なせていてはあっという間に闘士がいなくなってしまうだろうに」 「奴隷貿易が盛んな理由はそこですな。ほかにも囚人なんぞを投入して補填しているとか」
そこまで言って、主君の眉に深い皺が寄っていることに気付いた衛兵隊長は肩を竦めて見せた。
「ま、日によっては普通の芝居を上演することもありますからな。好き好んで生臭物を見ることもありますまいて」 「私はそちらにしておこう」 「そんなことよりも、なるべくお早めにお戻りいただいたほうがよろしいかと」
*
西の領主が派遣してくれた代官の到着を待って出立したヴェルカンは初めに西へと馬を進め、『街』で糧食を補充した後は黒の王国との国境沿いに宿を転々としつつ南下する進路を取った。 衛兵隊長の心配とは裏腹に、旅路はいたって平和なものだった。天気は良好、馬脚��軽やか、このままならば予定どおりに到着できそうだ。
事件が起こったのは、水龍の国まであと数刻という頃合いだった。日はとうに落ち、かすかな星明かりを頼りに進む道中、前方に見えた赤い灯は、近づくにつれて篝火に姿を変え、そばに立つ武装した男たちを照らし出す。 追い剥ぎの類かと寸の間ひやりとしたものの、よくよく見れば体の長い黄色い魚が描かれた青い旗が掲げられ、男たちが水龍の国の人間であることを物語る。 検問だろうか。迂回することも考えたが、距離から考えて向こうもヴェルカンの姿を捉えているはず。とすれば下手に避けようとすれば却ってよからぬ疑いを招く恐れがある。 そも、何をやましく思うことがあろうかと、堂々と胸を張って馬を進め、制止の声にも素直に足を止める。
「どこへ行くつもりか」 「水龍王国まで、荷物を届けるよう仰せつかっている」
命じられるままに馬を降り、兵士が体を改めるのに任せる。鞄から食料や薬を取り出していく兵士を眺めていると、別の兵士がふと口を開いた。
「半月ほど前、市内の商店で盗みがあってな。それ自体はまあ珍しいことじゃねえ」
何気ない口調だったが、なぜか背筋にちりちりと緊張が走るのをヴェルカンは感じた。
「ところが今回は犯人の姿を見てた奴がいてな。おまけににここ何日かのうちにそいつがこの道を通ると通報があったんだよ」 「それで網を張っているわけか」 「そう、そのとおり――」
言い終わらぬうちに、兵士が素早く剣を抜き放ち、ヴェルカンに向けた。
「おい、何の――」
思わず詰め寄ろうとした胸元に左右から槍の穂先が突きつけられ、強引に足を止める。
「貴様を逮捕するよう命令が出てるんだよ」
そんな言葉とともに取り出された人相書きは、細部の差異はあれヴェルカンの特徴をよく捉えたもの。さらに盗品として示された図には、間違いなく先帝から預かった首飾りが描かれている。 人違いだと叫ぶより早く、ヴェルカンの荷物を漁っていた男から「ありました!」と声が上がる。その手には例の首飾り。その瞬間、ヴェルカンを拘束していた兵士の唇がにんまりと持ち上がった。
「おい、勝手に触るな!」 「あれをどうするつもりだったんだ?」 「だから言ったろう。国内の商人に届けねばならんのだ。店の名前は『日の目堂』といった」
あまり余人に知られたくはなかったが、止むを得ず届け先の名を告げる。ところが、次の瞬間、兵士たちの間から爆笑の渦が沸き起こった。未だに状況が飲み込めず、目を色黒させているヴェルカンに、兵士は笑いすぎて涙の浮かんだ目を向けた。
「言い訳が下手だな。いくら何でも盗んだ店の名前を出すなんてな」
よっぽど慌ててたのか?という皮肉交じりの言葉に言い返すことすらできなかった。頭の中が真っ白になり、何も考えられない。
「おまえを日の目堂窃盗の犯人として逮捕する」
あれよあれよという間に後手に縄を打たれ、覆面を被されたヴェルカンの耳に、兵士たちの雑談が飛び込んできた。
「それにして���、ブツを引っさげたままこの辺りをうろついてるなんざ、おかしくないか?事件からはもう日も経ってるし」 「知るか。俺たちはあいつを捕らえるよう命じられただけだ。あとは上で審議してくれるだろうよ。たっぷりとな」
*
咄嗟に腹筋に力を込めても、食い込んだ鉄拳がもたらす衝撃は胃腸を揺さぶり、無理な姿勢で捩じ上げられた肩を容赦なく苛んだ。 せり上がる嘔気に歯を食いしばって耐えるヴェルカンの髪を掴んで引き上げ、拷問官が威圧的な視線をぶつける。
「いい加減認めたらどうなんだ。証拠は上がってるんだぞ」
連れ込まれたのは四方を石の壁で囲まれた部屋。冷たく湿った土の匂いから地下室だろうと見当をつけるが、それ以外のことはわからない。
「……何度も言ってるだろう。私ではない。濡れ衣だ」
次の瞬間、後頭部を拘束具に叩きつけられ、目の前に星が散った。呻くヴェルカンの頭を離し、拷問官が近くの作業台に歩み寄った。
「その強情がいつまで持つかねえ」
取り上げたのは革の鞭。無数に枝分かれした先端には鋭い鉤針。
「こいつで皮膚が剥がれるまでぶちのめしてやろうか。それとも爪先から寸刻みに釘を打ち込んでいくってのも悪くないな。いっそあそこを切り落とすのも一興かもしれん ……なに、死にはしないよ。最後まで生かしておいてやるから安心しな」
太い針や鋭い刃物や、何に使うのか考えたくもないようなものが作業台には所狭しと並べられている。それらをひとつひとつ見せつけながら、拷問官はにやにや笑いを浮かべた。拷問具が放つ鉄の輝きはそれだけで心肝を寒からしめるものだったが、恐怖だけは見せまいと精一杯睨みつける。
「さて、改めて自己紹介といこうや。おまえは何者だ?」
ここで帝国の名と白騎士の身分を明かせば、あるいは違った結末が得られたかもしれない。しかし、今回の旅において、ヴェルカンは己の正体を隠すよう厳命されている。一応、西の領主からは道中名乗る名前、そして偽の来歴を教わっていたが、このような場でそれを話したところで、後で調べられて騙りだと知られれば事態は余計に悪くなる。 思案に暮れているとまた腹に一発貰った。胃がねじれるような苦痛に悶えながら、棘つき鞭ではなかったことに少しだけ安堵する。
「そのくらいにしておけ。どうせ有罪は確定なんだ。傷物にでもしたら大変だ」
口を挟んだのは近くに腰かけて眺めていた別の拷問官。手を止めたのも一瞬、そうだな、と呟いてあっさりと離れていくのを、意外な思いで見つめる。が、不思議と事態が好転したという気分にはなれなかった。
半ば突き飛ばされて足がもつれたが、後ろ手に縛られたままでは受け身も叶わず無様に倒れ込んでしまう。不快に湿った土床の冷たさを頬に感じながら、体を折って拷問の苦痛が引くのを待つ。
「馬鹿なやつ。身元くらい明かせば故郷に手紙のひとつも書かせてやったものを」
独房の木戸が閉じられる音とともに笑い声が背を打ったが、ヴェルカンは聞いていなかった。脳裏に浮かぶのはこことはあらゆる意味でかけ離れた帝都の宴の様子。並んで立つかつての主君たちの、なんの含みも匂わせない無邪気な笑顔。
なぜこうなった。
検問はヴェルカンが通る道と時間を完璧に把握していた。例の贈り物が盗品であったことも併せ、先帝なり西の領主なりが己を捕らえさせる算段をつけ、誘き出したとしか思えぬ。そこまで考えて、今度は、ではなぜか、という疑問がヴェルカンの頭を満たす。
何らかの不興でも買ったか――
そこまで考えて、ぞくりと背筋が粟立つのを感じる。彼らは正体を明かすなときつく言った。その言葉に従い、皇帝から賜った剣も紋章つきの首飾りも持っていない今、ヴェルカンの身分を証明するものはない。まんまとしてやられたと臍を噛む思いと同時に、やはり腑に落ちないのは動機の点。領主にも先帝にも不始末を起こした覚えはなく、むしろよく買ってくれているものと思っていた。
ふと、宴席で喧嘩になりかけた騎士を思い出す。彼と同じく、知らぬところで貴族にでも敵を作っていたのだろうか。名を上げた今ではありえぬ事でもなく、とすれば西の領主たちもまたヴェルカンとの繋ぎ役として利用されただけということもある。 彷徨う思考は、やがて不安げに下がった衛兵隊長の太い眉に行き着いた。先帝は水龍の国にしばらく滞在してはどうかとしきりと勧めてきた。もし勾留されていたとしても、国元が主人の不在を物見遊山と決め込んでいれば気付くのには時間がかかり、その間にヴェルカンは誰にも悟られることなく葬られるという寸法だ。 次第に湧き上がってきたのは静かな怒り。感情の赴くままに身を起こせば未だ癒えぬ激痛がぶり返したが、怒りはそれすらも糧にしてなお一層膨れ上がる。 座り込み、明かりひとつない暗闇に幻視するは顔のない本当の敵。
必ず生きて帰ってやる。
0 notes
Text
白騎士の冒険 魔宮の秘宝 終
『これが、こたびのその方らの働きに対する褒賞である』
ひとしきり感謝の言葉を並べたのち、死者の王が示したのは荷車いっぱいに積み込まれた生命の石。目を丸くし、荷車と王の顔を交互に見やると、黒騎士は頭を掻いた。
「石は封印するのではなかったのか」
つい先ほどまで、口を酸っぱくして石を手に入れると豪語していただけに、そんな言葉を吐く姿はいささか滑稽にも見えた。が、ヴェルカンにしても同じことを考えていたので口にはしないでおく。 王は『確かにそう言った』と頷いたのち、だが、��言葉を重ねた。
『その方らへの報酬として約した以上、王として違えるわけにはいくまい。それに』
珍しく考え込むようなそぶりを見せる。
『そなたたちはあの力がどのようなものか、知っている。その知識を生かし、我々よりは力を正しく使いこなせると思うのだ』 「ずいぶん買ってくれるじゃないか。いいのかそれで。噂を聞きつけて再び多くの人間が押しかけるかもしれんぞ」 『たとえそうだとしても、知恵は残っている』 「あくまで人間の賢さを信じるか。前はそれでしくじったのではないか」
思わず口走った様子の黒騎士の言葉に、死者の王は肩を震わせた。
『痛いことを言う。だが、たとえ再び誤ったとしても、それはそなたらの問題。我らのあずかり知るところに非ず』 「それはそれは……」
つられて黒騎士も力なく笑うが、あるいはそれは、この地下世界で数え切れぬほどの齢を重ねてきた王がたどり着いた諦観であったのかもしれない。
「巨人がいなくなった今、あなた方は、これからどうなさるおつもりです?」
話題を変えれば、死者の王は腕を組む。
『これまでと変わりはしない。この国を、山の心臓の鉱脈を守っていくのみ』
そういう不死者は、しばしの沈黙の後、それから、と付け加える。
『あの巨人はまだいなくなったわけではない。たとえ一欠片の石と化そうとも、最後に残った意識の断片までもが時に溶け去るまでは、見届けねばなるまいて』
それがかつての王たるものの務め、と言い添えた言葉に嘘はないのだろう。
『さらば、命ある若人たちよ。勝ち取りし力を正しく導かんことを』
*
嫌がる黒馬に荷車を繋いだ一行は、山の民の長が見出していた抜け道を伝って地上を目指すことにした。
「てっきり逃げ出したのかと思っておりましたが、違ったようで」 「それも考えはしたのですが」
魔法使いの言葉に、初めて会った頃より幾分伸びた顎髭を撫でながら頭上を覆う岩壁を見上げる。 死者たちの“声”を聞き分け、巧みに姿を隠した族長は、岩巨人の襲撃で破壊された城壁を乗り越え、とうとう城外に脱出を果たした。そのまま家に帰ることも考えたが、さりとて囚われたであろう同道者の安否も気になる。
「そこで“声”を使って、死者たちに呼ばわってみたのです」
己の声を頼りに追ってくる兵士から逃げ回りながら、族長は死者たちに向かって敵意がないことを訴え続けた。そんな中、主人を捜して迷い込んだのだろう黒馬に出会ったという。 やがて、ついに死者の側から、捕虜ではなく客人として迎え入れる旨の声が届き、族長は再び街へ向かったのだが…… 黙って聞いていた黒騎士が、呆れたように声を上げた。
「丸ごと信じてのこのこと舞い戻ったのか。そのまま捕らえられていたかもしれんのだぞ」 「脱獄を手引きした負い目もありましたゆえ。ですから贈り物を用意し、誠意を示すことにしたのです」 「贈り物?」
聞き返せば、族長が視線を向けた先、真っ黒な鬣の下から、赤く血走った目が睨み返す。直後、三角に尖った青灰色の目も。
「貴様、人の馬を手土産にしたのか!?」
本気で怒る声に、族長はひいと叫んで身を強張らせた。魔法使いが笑いながらとりなす。
「まあ、何もなかったのだから良しとしましょう。そちらも愛馬と再会できたわけですし」 「まったく、死者たちが話の分かる相手で助かったな」
かくして王に謁見し、皆の無事を確かめた族長だったが、やはりひとり逃げ出した手前、今更おめおめと顔を出すのも気がひける。結局、一行とは離れ、主に街の外を探索していたのだ。その間に書き記したという地図は現在、荷車を伴った一行が地上を目指す道しるべとなっている。
「あんたも色々やってたんだな」 「それなりに」 「まあ、巨人を倒せたのはあんたが奴の目を逸らしてくれたおかげみたいなもんだからな。感謝はしてるよ」
鼻を鳴らしながら放たれたぶっきらぼうな礼に、顎鬚は太い眉を下げて力ない笑みを浮かべるのだった。
*
顎鬚の地図を頼りに進むにつれ、洞窟は次第に細く、険しくなっていった。地面の起伏に車輪が取られることも一再ではなく、そのたびに男四人、荷車に取りついて押したり引いたりでようやく前に出る道のりは大変には違いないが、それでも休みなく歩き続けられたのは覆いの下から微かな燐光を投げかける魔法の石の効力か、はたまた洞窟そのものの力か。 やがて上り坂に差し掛かった頃に届き始めた風は湿った木々と土が混ざった森の匂い。力の限り荷車を押し合いへし合い、最後に道を塞いで垂れ下がる蔓草を切り払えば、目を射るは久しく浴びていなかった日の光。 しばしの間、全員が目を押さえ、そのあまりの眩しさに慣れるのを待つ。 一行が立っていたのは、森の中の、そこだけ木々が途切れた丘の下。ちょうど頭の真上に位置した太陽から燦々と降り注ぐ光は、生命の石とは似て非なる熱で肩を暖めてくれた。
「……長い夢を見ていた気分だな」
洞窟とは異なる、湿った空気を胸いっぱいに吸い込みながら黒騎士が呟く。死者の王国にはずいぶん長いこと滞在していたような気もするが、いざ思い返してみれば、あの竪穴をくぐったのはつい先ほどのような心地さえしてくる。ほんの束の間、午睡の夢とすら思えてくる。ただ、土埃で濁った装束と、荷車が放つ燐光が、一連の奇妙な探索行が夢ではなかったことを物語る。
「ところで、石の事ですがな。どうでしょう、皆で公平に分け合うというのは」
だしぬけに魔法使いがそんなことを言い出した。思わず黒騎士を見やれば、同じくこちらを振り向いたらしい青灰色の目と視線がぶつかる。 そうだ、こいつが残っていた。すぐ隣に位置する、巨大な敵国の手先。今倒しておかねば、後々どのような障りがあるか知れない。だが―― 黒騎士がふと目を逸らしたため、その時何を考えていたのかは定かではない。
「そうだな。それがいい」
いずれにせよ、争わずに済んだことに安堵している自分に気付く。魔法使いや顎鬚を巻き込まずに済んだからかもしれない。もう戦いに倦み疲れていたからかもしれない。もしくは曲がりなりにも共に盾を並べて戦った縁だからか―― もし衛兵隊長がいたら叱られるところだ。己の甘さに思わず自嘲の笑みがこぼれる。 ヴェルカンの笑顔をどう取ったか、衛兵隊長と瓜二つの魔法使いは満足げに頷いた。
*
結局、森を抜けて道が見える場所まで案内してくれた顎鬚こと山の民の族長だったが、最後まで石を受け取ろうとはしなかった。
「おそらく私たちではもてあますばかりでしょう。お気持ちだけで結構です」 「しかし、これがあれば病を癒したり、火や風を起こすこともできるのだぞ」 「これまで我々は石なしで十分豊かに生きてきたのです。これ以上何を求めましょう」
それ以上強く勧めることもできないでいる三人を尻目に「家族が心配しているでしょうから、これで」と森の中へと消えていく小柄を、ヴェルカンは無言で見送った。
魔法使いが念話を用いて迎えを呼んだことを打ち明けたのは、森を抜けて間もなくだった。街に向かって草原を数刻も歩けば鉢合うはずだという。 相変わらず便利なものだと感心していると、魔法使いはわずかに得意げな表情を浮かべて見せた。
「こういった技の数々を発展させ、ひいては魔力の素質のない者でも使いこなせるよう研究するのが我々の使命です」 「すると、いつ���我々でも魔法を使えるようになると?」 「生命の石を研究することがその一助となるのではと思うとります」
やがて地を走る道に差し掛かった一行は足を止めた。魔法協会からの馬車を出迎えるべく先行する魔法使いの背中が草むらに隠れると、黒騎士が荷車に背を預けて座り込む。それを見下ろしながら、ヴェルカンは口を開いた。
「やい黒いの。今回の一件、本国にはどう説明するつもりだ」
じろりとヴェルカンを睨み返したのも一瞬、唇の端を意味ありげに持ち上げる。
「そうだな。大王陛下に挙兵を上申してみるか。死者たちとて王国全軍を投入すればあるいは」
貴様……と思わず槍を掴んだヴェルカンの様相に、黒騎士が「冗談だよ」と慌てて手を振った。
「今回見つけたこれで全部、とでも言っておくさ。交渉も通じない不死身の軍団が守る場所だ、万の兵士でも落とせんだろう」
それに、と、にわかに表情を引き締める。
「あれを御する力は、今の人間にはない」 「今の人間には、か」
今ではないいつか、祖国がその力の重みに耐えうるまでに大きくなった、その時までは。
「安らかに眠れ、地の底に、か……」 「その時、か。本当に来るのだろうか ……来るべきなのだろうか」
さてな。そう肩をすくめた黒騎士は立ち上がり、荷車の幌に手をかけた。日の光の下で見る山の心臓の光は、地下で見た時よりずっとおぼろげで弱々しい。 その中から赤子ほどの石をひとつ持ち上げ、そばの地面に置く。続いてふたつ目、三つ目と石を取り出す姿をきょとんとして見守るヴェルカンを、眉根に皺を寄せた黒騎士が振り返った。
「なにしてる、お前も手伝え」
慌てて立ち上がり、並んで石を運び出す作業に入る。荷車の石が減っていくにつれ、地面に積み上げられた山は大きくなり、そのてっぺんがいちど崩れた頃、黒騎士がやめの合図を出した。いわく、荷車に残った石が王国の取り分、取り出した石が帝国と協会の取り分だという。 この言葉に、今度はヴェルカンが口元を歪めた。
「我々の取り分が少なすぎる。これくらいが妥当だ」 「おい、勝手に持ち出すな!」 「地下で巨人に真っ先に挑んだのは私だぞ」 「その貴様が叩き潰されそうになってたのを助けてやったのは俺だろうが」
言い合い奪い合いしているうちに、やがて互いがどうにか妥協できる按配に分け合うことができた。 首を振り振り、しゃがみこんで足元に散らばる光る石を検分していると、すぐ背後でごろりと重たげな音を立て、荷車の車輪がゆっくりと地を噛みはじめた。
もう行くつもりかと振り返り問えば、馬の尻を叩いて歩かせながらのんびりと見返してくる。
「これ以上王国人と帝国人が一緒にいるのはまずいだろう。他人にでも見られたら面倒だ」
お前の顔も見飽きたしな。と取ってつけたような一言に足元の土を蹴飛ばして応じ、慌てて身を避ける姿に溜飲を下げる。 舌打ちひとつ、敵意の籠った視線を叩きつけたのも一瞬、黒騎士はすっかり見慣れた笑みを浮かべた。
「あばよ白いの。次会うときまでは生きてろよ」 「いつどこで会うにせよ、次は敵同士だ。せいぜい首を洗っておくことだ」 「前言撤回だ。おまえなんか二度と顔も見たくねえ」
言い合いながら離れていく荷車が見えなくなると、途端に静けさがあたりを満たすようだった。それまで意識に上らなかった葉擦れの音が耳に付きはじめ、なぜだかよく分からないうちに大きく息をついていた。
やがて新たに聞こえ始めた車輪の音に目を向ければ、魔法使いが馬車を伴ってやって来るところだった。黒騎士が先に帰ったと知るとわずかに意外そうな表情を見せたものの、さほど驚いた様子もない。
「まあ、妥当な判断でしょうな」
それだけ言ってマントの裾を地面に広げながら生命の石を拾うのを手伝い、荷台に山ができていくのを眺める。
「思えば、ずいぶん寂しくなってしまいましたなあ」
積み込みを終え、腰を押さえて伸びをした魔法使いがぽつりと呟いた。「まったくです」と素直に飛び出したことに自分で驚く。
魔法を操る者と異国の騎士、さらには未知の狩人。足並み揃えて乗り込みたるは生ける死者たちが統べる失われし地下王国。
「されど共に歩みたる戦士たちも今はなく、野にはただ風が吹くのみ……」
馬車の尻に腰掛け、少しずつ遠くなっていく禿山を視界に収めていると、御者席のすぐ後ろの魔法使いが首をひねって口の端を持ち上げた。そんな表情は衛兵隊長そっくりであることに今更ながら気付く。
「なかなかお上手ではないですか。歌のひとつも作ってみてはいかがです?」
まさか聞こえていたとはつゆ知らず、気まずい思いを後ろ首を掻いてごまかす。そんなヴェルカンの胸中を知ってか知らずか、魔法使いはふっと息を吐く。
「ま、我々ならずとも他の誰かが此度の冒険を歌にするやもしれませぬなあ」
魔法使いもヴェルカンも、そしておそらくは黒騎士も、今回の一件を報告せねばなるまい。そうして他者の知るところとなった話はさらに人伝てに語り伝えられ、やがて詩歌として広く親しまれる物語となる。 それはあるいは誇るべきことなのかもしれない。しかし、と魔法使いは言葉を繋ぐ。
「私としては、今回見聞きした諸々に関してはあまり市井に流布されるべきではないと考えておりまするが」
命を贖う石を御する力は、今の人間にはない。今はまだ。
そんな声が聞こえた気がして、魔法使いをまじまじと見やる。何か?と目だけで問うてきたのを、視線を逸らしてやり過ごす。
「……私も同感です」
*
街に到着したヴェルカンは、翌朝早くに出立することになった。 魔法協会の客室を手配するという申し出を断り、泊まった安宿。食事はかなりきつい味付けで鮮度をごまかした肉料理と麦粥だったが、久方ぶりの食事の一口ごとにもたらす充足感は手を休めることすら忘れさせ、蜂蜜酒を片手に瞬く間に平らげてしまった。そして久しく忘れていた睡眠を貪り、夜明けと共に目を覚ました時には、生まれ変わったような心地さえした。表門への道中、朝焼けに染まる家々を眺め、冷たく湿った空気を吸うことがこれほど心地よいことだとは知らなかった。
森で放してしまった馬に代わり、新たな荷馬を用意してくれたのは魔法使いだった。
「あなた様がおらずんば果たし得なんだ探索行なれば。手間賃にもなりませぬが、遠慮なくお受け取りください」 「こちらこそ、貴殿には世話になり通しでありました。感謝を」
右手に手綱を、左手に荷馬の引き綱を握り、馬の腹を蹴る。
「兄によろしく。もしくは弟に」
そんな挨拶を交わしてから幾ばくか、ふと振り返った街はすでに朝霧に青く霞み、広がる丘に半ば隠れてしまっていた。見渡しても道を行くは己ばかりで人影すらない。にわかに寂しさが押し寄せたが、ヴェルカンはその思いを素直に受け入れることにした。 ひとつ所に寄り集まり、道を共にした者たちは再び別れて各々の道を往き、不思議の冒険は終わりを告げた。だが旅はまだ終わっていない。
帰ろう、祖国に。
*
ヴェルカンが帝都の外れの屋敷を再び訪ねた時には、時折吹く冷たい風が冬の気配を運んでくるようになっていた。実際はそれほどでもないのだが、前回からずいぶん長い時間が経ったように思う。 数か月ぶりに再会した先帝は、差し出された生命の石に感嘆の声を上げた。
「美しいな。やはり君に頼んで正解だった」 「お役に立てて光栄です」
膝の上に抱えた石を映して青く光る目がヴェルカンを捉えた。
「その目で様々なものを見てきたのだろう。どうだろう、聞かせてはくれないか」
国境線に並ぶ城塞の残骸、数多の人でごった返す街のにぎわい、どこまでも深く暗い森のありさま。もとより口の回るほうではなく、またすべてを思い出せるわけでもない。すべてを憶えているようでいて、その実いざ語ろうとするそばから抜け落ちていくような感覚はひどくもどかしい。 それでも、先帝は語られる旅の情景に目を輝かせて聞き入っていた。その表情はどこか無邪気な子供のようで、かつて皇帝の冠を戴いていたことすら忘れてしまいそうになる。
「本当に色々なものを見てきたのだな。実にうらやましいよ」
途中、話しすぎてもつれた舌をほぐそうと葡萄酒を流し込んでいたとき、先帝がしみじみと述べた。皇帝という身分に縛られ、一線を退いた今も病弱な肉体に縛られているひとりの男。ことさらに無邪気を感じさせる口調の中にそんなものを垣間見た気がして、ヴェルカンは束の間言葉に詰まった。 救いを求める目を向けた先で控えていた木製の侍女――魔法人形は微動だにせず、背景の一部と化しているばかり。
「閣下もまだお若い。それに石もございます」
しばし考えたのち、どうにか絞り出す。少し意外そうな面持ちでヴェルカンを見つめたのち、先帝はただ、そうだなあ、と笑みを浮かべるのだった。
やがて話は地下の王国での一件に差し掛かった。黒騎士や魔法使いとの話し合いもあり、ここで見聞きしたすべてを話すのは躊躇われたが、同時にこの屋敷に隠棲している先帝には一切を話して聞かせたいとも思うのだ。
歩く死者と聞き、さしもの先帝も目を見開いた。力を求めて派遣された調査隊が築いた地下王国の興亡の顛末、命さえ贖う力がもたらした光と、その下で色濃く延び広がった影。忘れ去られた王国を死してなお守り続ける王と兵士たち。異形と化してなお石を求め続ける岩の巨人――
自身がその重みを感じているかのように、先帝は大きく息をついた。その視線は手元の輝きに向けられている。
「思ったよりも危ういものに手を出していたみたいだな」
しかしその手は変わらず石に乗せられたまま。なぜならそれが今の彼の命綱だから。どれほどの可能性と危険を秘めたものかさえ定かではなく、たとえその力のほんの一部を利用しているだけであっても、もはや手放すことなどできはしない。
「こんな得体の知れないものに縋らねばならない僕を、弱いと思うかね」
突然の自虐的な口調に驚く。滅相もない、と反射的に返しつつ、思わず見つめた細面は相変わらずの無邪気な微笑を浮かべたまま。それを真っ向から見返し、死者の王の言葉を思い出す。
「得体が知れずとも、今は先人たちが残した知恵がございます」
それは力の使い方を誤った者たちが祖国と引き換えに得、幾星霜を経て旅人に授けた智の力。後世に語り継がれ、世代を隔てて延び育つ大樹の芽は今、散らばった旅人たちによって方々にもたらされつつある。 今ではない、それでも、いつか必ず。それがどれほど恐ろしいものであったとしても、何度失敗したとしても。得たものを正しく用いることができる日が来るのではないか。 死してなお後世のために力を守り続ける死者たちの姿に、時が満ちるまで秘密を隠そうと誓い合った異国の旅人たちの姿に、そう思えるのは、あるいは楽観が過ぎるだろうか。
「いつかは人がこの力を完全に御することができる日が来ると?」 「そう信じております」
頷いたヴェルカンを、先帝は黙って見つめた。目を逸らせば自身の言葉がすべて偽りになってしまうような気がして、ヴェルカンもまたかつての皇帝を真っ向から見据えた。 先に視線を外したのは先帝のほうだった。
「強いな、きみは」
呟くように流れ出た言葉にどう応えたものか。先帝の胸中ともども判断に迷い、ヴェルカンは、ところで、と話題を変えた。
「道中、黒の王国の間者に襲われました」
口にした途端、先帝の細面から表情が消えた。 最後に残った謎。何ゆえ黒騎士は山の心臓を、さらにはヴェルカンたちがそれを探していることを知りえたのか。紆余曲折あって共闘し、最終的に宝を分け合う羽目になったことは伏せておいたが……
「あるいは、間諜が��るのやも知れませぬ。今一度身辺を改められた方が……」 「その心配はいらない」
思いがけず強い語調に思わず口をつぐんだヴェルカンの前で、先帝はゆったりと立ち上がった。どこか覆い���ぶさるように見下ろしてくる姿は意外と背が高いことを知る。
「むろん、調査はさせる。君は何も気にする必要はない」 「しかし、宮中に内通者がいるとなれば一大事」 「忠告は心に留め置こう。ところですっかり話し込んでしまったな。少し疲れてしまったよ」
一転、肘掛椅子にすとんと腰を下ろせばいつもの先帝が戻ってくる。その姿に浮かんでくるのはどこか煙に巻かれた思い。とはいえ一介の騎士に過ぎぬ身なればそれ以上の追及は不可能であり、なにより宮中に疎い自分がどうこうできる問題ではないことに気付き、ヴェルカンは内心で歯噛みするほかなかった。
今夜は泊っていくといい。そんな言葉に目を向ければ、先ほどの話などなかったかのように酒杯を差し出してくる無邪気な笑顔が目に飛び込んできた。
*
いささか釈然としない思いを抱えて帰郷したヴェルカンだったが、そこでさらなる事件に巻き込まれる羽目になった。
「卿。旅先で面白いご友人ができたようですな」
城館の玄関で武器を預かった衛兵隊長の笑み混じりの言葉に眉をひそめていると、突如、忙しない足音と荒い息遣いが猛烈な勢いで近づいてきた。 そちらに目を向けた時には、目の前を真っ黒な何かに視界をふさがれ、次の瞬間には地面に押し倒されていた。 咄嗟に突き出した手を難なく押しのけ、迫ってきた巨大な口が牙をぬめらせながら激しく開閉し、蠕く舌がヴェルカンの顔を撫で回し、臭い唾液を振りかける。 思わず驚愕の悲鳴を上げたヴェルカンの耳に届いたのは、衛兵隊長の抑えた笑い声。状況がまるで理解できず、ただただ目を白黒させていると、唐突に黒いものが体の上から離れた。衛兵隊長の手を借り、やっとの思いで起き上がったヴェルカンが目にしたのは、
「い、犬?」
口にした途端、背筋を冷たいものが伝い落ちたのは、過去に猟犬に襲われた恐ろしい記憶を呼び覚まされたからか。それでなくとも、後脚で立ち上がれば衛兵隊長すら見下ろしそうな毛むくじゃらの巨体が、互いの鼻息もかかる位置に鎮座している光景は、それだけで心肝を寒からしめるに十分ではあった。筋肉の塊のような引き締まった身体とは裏腹に、老人のように皮膚が幾重にも垂れ下がった皺だらけの顔立ちはある種の穏やかさも感じられたが、それも一本一本が指ほどの太さがある牙が居並ぶ口吻を目にするまでのこと。 聞けば、黒の王国で品種改良された猟犬であり、賢さと忠実さを併せ持った堂々たる体躯は、国内外を問わず高い人気を誇るのだという。
「街の魔法協会に務める兄のもとに、黒の王国のさる騎士から贈られてきたのです。帝国の共通の知人に差し上げるように、とね」 「兄というと、まさか」 「弟かもしれません。双子でしてね、両親ですら見分けがつかない」
それだけですべて合点がいった。あいつめ……とため息ひとつ、ヴェルカンは衛兵隊長に向き直った。
「件の王国騎士に返礼をしたいのだが」 「帝国騎士がおおっぴらに王国に贈り物をするのはいただけませんな」 「わかっている。届け先は街の魔法協会だ」 「私の兄は駅馬車ではありませんぞ」 「もちろんそちらにも謝礼は弾むさ。それと、山の民たちにも何かしら届けたいな」 「……まったく、本当に面白いご友人がたくさんいらっしゃるようで」
衛兵隊長のため息に呼応するように、犬がひと声吠えた。
*
さる年の秋、白の騎士ヴェルカンは皇帝家の密命を受け、秘宝探索の旅に出たが、この秘宝が具体的に何であったかは伝えられていない。しかしこの次の年以降、長らく耕作に向かない不毛の地として知られていた彼の封土は数年にわたる奇跡的な豊作に恵まれ、後年、西の湿地を襲った飢饉に際しても豊富な食料を供出、犠牲者を最小限に留めることができたとの記録が残っている。そのため、秘宝とは新式の農法だったとする説もある。
0 notes
Text
白騎士の冒険 魔宮の秘宝 五
死者の国がまだ生者の国だった頃。生命の石の力で栄えゆくうち、周囲の国々の目は次第に変化していった。羨望はいつしか疑惑に、驚嘆はやがて危機感に――
『我らが未知の力を独占しているのが妬ましく、また恐ろしかったのだろうな』
周囲の国々から送られる使者たちは、あるいは莫大な貢物を、またあるいは恫喝めいた文言を携え、そして一様に山の心臓の秘密を公のものとするよう迫るのだった。その裏側では大勢の間諜が送り込まれ、地下の王が放った間諜と壮絶な暗闘を繰り広げていた。 王国は石にまつわる諸々をひた隠しにする一方、さらに研究を進め、次々と新しい利用法を編み出していった。太陽のごとき灯の下、石の力を浴びてたくましく豊かに育つ実りを糧にする民はますます健やかに、石の力で動く機械が作り出す富で国はますます富み栄えた。灯の届かぬ議会の裏側からは腐敗が流れ込み、路地では混乱が渦巻いた。闇から逃れるように町がその光を強めるほど、陰はそれだけますます濃く強く。 王が山の心臓を“不吉なもの”として封じることを決意したのは、国と民を守るための苦肉の策であったのか、はたまた終わりなき戦いに倦み疲れたからか。表情のない眼窩が語ることはない。
『いくら腕ばかりが強くとも、重いものを担ぎ続ければ足腰を痛める。強い足腰を持たなんだ我ら、いや、そもそもヒトが御するには過ぎた力であったのだ』 「諸国の力関係が変わってしまうほどの力か。手にすれば世界すら握れるほどの」 「だがそれだけに、ひとたび手にすれば世界中が敵に回ることにもなりかねない」
そして実際、この国はそうなりかけた。だから、すべてなかったことにしてしまおうとしたのだ。だがすでに手遅れであったことに気付くのは間もなく。
『以前、いちど尋ねたが、今、改めて問おう。その方らが欲するはそうしたもの。手に入れて何とする』
ヴェルカンたちはすぐには答えることができなかった。
*
「王はああ言っていたが、どう思う」 「正直なところ、あれほどまでの代物とは思ってもみませなんだ」
太い眉を下げ、魔法使いは唸る。険しい山の奥底で幾代もの時をかけて凝った莫大な力は、人の意志によっていかようにもその姿を変える。望めば光となって街中を照らし、また望めば火となって人々を暖め、そして望めば命を購うことさえも。
そんな力は手に余る。
今は姿が見えない山の民の長はそう言って笑っていた。無くて困らぬものなら捨て置く。ひょっとするとそれが正しいあり方なのかもしれない。 だが、と黒騎士は鼻を鳴らす。
「宝がここにあるとわかった以上、俺は諦めるつもりはないぜ」 「たとえ決して必要ではないものでもか」 「あれば不可能が可能になる。だからお前も、魔法使いさんもここにいるんだろうが」
現在よりも、さらなる繁栄を。明日をより豊かに生きるために。
「俺としても、帝国に先んじさせるつもりはないぜ」
その言葉に思わず向き直る。すっかり忘れていたが、目の前の男は帝国の敵なのだ。巨人との戦いに決着がついたら、こちらもどうにかせねばならない。 そして気づく。たとえその正体がなんであれ、力は必要なのだ。隣にいる黒い国よりももっと大きく、より先に行くために。相手のあぎとに飲まれぬよう。十年先の安寧よりも、明日を生き延びるために。
「結論は出たみたいだな」
ため息交じりの声に、そうですな、と魔法使いが唱和する。その顔には一片の笑みもなく、黒騎士もまた唇を曲げて唸るばかりだった。
*
力は我らにとっては大気も同じだ、と死者の王は語る。その暑さ寒さ、濃さ、匂い。大気に常に触れ、その感触に慣れきってしまっているがゆえに人はそれを見ることも聞くこともかなわない。 死者たちにとっては力の源たる生命の石こそがそれなのだという。魂を滅びた肉体に繋ぎ止め、自我を維持せしめるほど深く深く結びついた力は、それゆえに五感の埒外にある。凝った力が鉱物の形を成していることは知識として理解していても、どの岩がそれなのか見分けるのは難しい。
『だがその方らは違う』
力を異質なものとして捉え、識ること。それは外部からやって来た生者たるヴェルカンたちにこそ可能な業だという。
「魔法使い殿は?魔力に対してさぞ鋭い感覚をお持ちのはずだが」 「前にも少し話しましたが、敏感すぎて逆に上手くいかんのです」
他の者には熾火ほどの魔力でも、魔法使いにとっては松明のごとく鮮明に映る。まして生命の石ほどの魔力の塊ともなれば、それはさながら太陽、不用意に正対すれば苦痛すら伴うだろう。
「つまり程よく鈍い俺たちだからこそ、巨人の体内に埋め込まれた心臓の詳しい在り処を感知できると?」
この言葉に、王は我が意を得たりとばかりに頷く。 ところが、黒騎士はまだ腑に落ちない様子で顎を撫でた。
「前にここに来たやつがいたろう。奴もあの化け物と渡り合って石を手に入れたのか?」 『いや。奴め、巨人の姿をひと目見るや雲を霞と逃げ出しよったわ。とんだすくたれ者よ』
おまけに巨人襲来の混乱に乗じて王宮に忍び込み、地下深くに厳重に保管されていた生命の石のかけらを盗み出して、だ。 先帝のところにあった石はそうしてもたらされたものだったのだ。 これで冒険家の手記から手がかりを探る目論見はついえた。残る情報源はただひとつ。
「そろそろ話してくれてもいいだろう。あの岩の巨人は何なんだ」
これまでにない強い語気に、王はにわかに鼻白んだ様子だった。
「昨日今日現れた敵じゃない、何も掴んでいないというのは不自然だぜ」
黙り込んで見上げる王に詰め寄り、黒騎士が睨みつける。
「なあ、俺たちゃあんたらのために身体張ろうってんだぞ。なのに必要な情報ひとつ満足に寄越せないってのか?」
挑発的ですらある物言いを諌めると、黒騎士は首を振る。
「隠し事の多い連中だけどな。岩巨人を仕留めるのに俺たちの力が必要だってのは確からしいな」
真実を隠してまで協力を仰ぐのはそれだけの理由があるのだという。
「お前もせいぜい今のうちに吹っかけとけ。こいつらのことだ、振れば振るだけ出てくるだろうよ」
『確かにその通りだな』
きいん、と耳鳴りがするほど強い声だった。一方でうなだれるように頭を落とした姿にはこれまでにない疲れが見て取れるのだった。
『望むすべてを話してやろう。 ……それが役に立つかは定かではないがな』
地下の王国が生命の石を封印すると決めた時、国民たちは強く反発したという。
『言葉を尽くし、説得したが、ついぞ分かってはもらえなんだ。ひとたび便利に慣れると、失うことを極端なまでに恐れる。もともと石などなくとも十分に暮らしてきていたものを、なんとも浅ましいことだ』 「そりゃあ同じ人間の手で、それも身勝手な都合で失われるとなればな」
黒騎士の皮肉を、王は聞こえないふりで跳ね返した。 王城に詰めかけた民たちを迎え撃ったのは、王に絶対の忠誠を誓う選りすぐりの精鋭たち。彼らには生命の石を砕き煎じた水薬が与えられた。
『秘薬を服した彼らはまさに無敵だった。殴られようが石を投げられようが微塵も揺るがず、民たちは城には一歩たりとも近づけなかった』
だが攻めてきたのは民だけではなかった。
『内乱の動きありと知れたのであろうな。いつの間にやら包囲されておった』
流血を恐れ、王城に立て篭もっていた兵士たちには城門を打ち崩し、町になだれ込む隣国の軍隊を止める手立てなどありはしなかった。
『山の心臓はあらゆる力を引き寄せ、解き放つ。人の欲さえも糧にして』
力を狙い、破壊と略奪の限りを尽くす隣国の軍兵は城からうって出た兵士たちと激突し、王国はさらなる災禍と破壊に見舞われた。 七日七晩続いた戦いが集結した時、王の兵士たちが――王の兵士たちだけが、生きて立っていた。
『自分たち以外のすべてが物言わぬ骸と化し、折り重なる光景は忘れようもない。ましてそれが己の無知が引き起こしたとすれば――』
よく知りもせぬ物体を使い、栄えようと思わなければ。そもそも石を掘り出すことなどなければ、こんなことにはならなかったのに。 だが全ては後知恵に過ぎず、起こったことを取り消すことは生命の石にも叶わなかった。そして何より、石を狙う国は隣国だけでは無かったことを、王はほどなく思い知らされることになった。
王に率いられた軍隊、富と名声を求める冒険家、火事場泥棒を狙うならず者。数多の国、山ほどの人間が、不老不死の秘密を求めて押し寄せた。まるで大地に溢れる力が凝り、石と成すがごとく―― 王国の兵士は戦い続けた。もう二度と悲劇を繰り返さぬよう。石から精製した秘薬を飲み続けて。
『決して倒れぬ我が兵を見て、敵は一層激しく攻め寄せてきた』 「……その力が自分たちのものになると信じて、か」 もはやどれほどの間戦い続けたものか、誰にも分からなくなっていた。死体は王国から離れた坑道に埋められたが、すぐに溢れかえったために第二第三の穴が用意された。 やがて山の心臓を狙うものはもういないと確信すると、王は死者たちを弔った後、すべてを消し去ることを決めた。王国と地上をつなぐ道をすべて埋め塞ぎ、町を閉鎖した。そして残るは石に関する情報を握る自分たち。
ところが、だ。
『誰ひとり死ねんのだ』
剣で突き刺しあっても死なず、錘を抱いて水に身を投げても苦しいばかり、油をかぶって火を放てども焼けた肉の下から新たな皮が浮き出てくる始末。 石の力を大量に飲み続けた兵士はもとより、石を手元に置き、長らく間近でその力を浴びていた王もまた同様だった。
『喉を裂かれ、肺腑に血が流れ込む苦しみは知っておるか。辛いものだぞあれは』 「知りたいとも思わないな」 「不死の力を求めた奴らはみんな滅び、力を捨て去ろうとしたあんたらがそうなっちまったわけか」
皮肉交じりに放たれたため息を、王は俯けた額に受けた。
どうにか死のうと四苦八苦するうちに肉は削げ血は乾き、骨ばかりのおぞましい姿となってもなお生き続ける。
『山の巫女の言った障りとはこれだったかと思ったよ。山の奥深くに眠り続けるべき力を人の世界に引きずり出した、これは罰なのかとね』
大地の奥底に伏し、絶望に暮れ幾星霜、果つることなき悔恨と苦悩。日の出も星の運行も知ることなく、訪う者もない、一切の変化なく行き過ぎる平坦な日々。 やがて時の感覚さえもあやふやになるころ、王たちはようやく各々の心に整理をつけ、平静を取り戻すことができた。一種諦めに近い心境ではあったが、再び過ちを犯す者が現れぬよう、生ける死者として王国を守り続けるという王の意志には全員が賛成した。
『そなたらが岩の巨人と呼ぶあれが現れたのは、そんな頃であったか』
城壁にも及ぶ身の丈を誇る怪物の出現はまったくの突然だった。剣や弓矢も効かず、圧倒的な腕力の前に、さしもの兵士たちも跳ね飛ばされた。
「奴と組み合う中、我らは山の心臓を求める“声”をはっきりと聞いた」
石が欲しい。不死の力が欲しい。 かつて同じことを叫ぶ者たちが刃の下に沈んだのはどれほどの昔であったか。それでも、その声は掠れてぼやけていた記憶を呼び覚ますのに十分な衝撃をもたらした。
『どうにか追い払うことができたが、もしやと思い後で兵に後を追わせてみた』
岩の巨人が帰って行った穴倉は、いつしか忌み嫌われるようになり、訪ねるものもなくなっていた場所。数え切れぬ死が眠っていたはずの穴倉。
「つまり何か。巨人は、あんたらの国民と、近隣諸国の兵士だってのか」
暗い洞穴の奥底に積み重なった数多の思いは、そのさらに奥に眠っていた力によって繋ぎ止められ、失った血肉を冷たく硬い石に置き換え、ついに蘇ったのだ。
『すでに肉体を失い、数多の人格が溶け合っている。元の自我はほとんど残っていないだろう。奴に残されているのは山の心臓に対する飢餓感めいた欲求ばかりだ』 「そう、あんたらは思いたいんだな」
そうだ、と王は言葉短く、しかしゆっくりと背を伸ばして告げた。
『そしてあやつを仕留めるには、どうしてもそなたらの助けが必要なのだ』
*
少なくとも相手の正体ははっきりした。さらにはこの国の起源も。 もっとも王の言葉通り、さほど役に立つ情報でもなかったわけだが。
次に岩巨人が現れれば門楼に昇り、槍撃ち弓を操作して巨人を狙撃するのがヴェルカンたちの役目となった。巨人を倒すには心臓部である生命の石に強烈な一撃を加える必要があり、それがどこに埋め込まれているか、感知できるのは生者だけだから、というのが死者たちの言。なおその間、骸骨兵士たちは門から打って出て時間稼ぎに当たるという。
「ならば我々も戦場に立ち、間近で奴を観察したほうがよいのでは」 『諸君は此度の作戦の要なれば。無理は禁物であるぞ』
作戦と呼べるかも怪しい策だが、他に手立てらしいものもなし。 大量の金属部品で構成された複雑怪奇な見た目とは裏腹に、槍撃ち弓の操作は驚くほど容易だった。大きさに似合わず照準を定める把手は驚くほど軽く、発射後の矢弾の再装填と弓弦の巻き上げまでも起重機によって自動で行われる。おかげでごくわずかな人員で操作が可能なのだ。その仕組みは多くを理解すること叶わぬ代物だったが、機械を操作するために弁を開閉すると蛇の威嚇にも似た音を立てて湯気が噴き出すことに黒騎士は気づいた。
「この管を伝って熱風が届き、からくりを動かしているのだな」 「風の力で?ではその風はどうやって起こしているのだろうか」 「さてな。それこそ山の心臓の魔法じゃないか?」
そこまで言ってため息ひとつ。
「これほどの力を持っていながら、なあ」
一方、魔法使いもまた別の準備に駆り出されていた。 工房の作業台には腕ほどの大きさの生命の石。いずれも一方を尖らせた杭の形に成形されたそれらのひとつに手を当て、魔法使いはじっと瞑目していた。そのままどれほどの時間が過ぎたか、ようやく息をついて顔を上げた魔法使いは、そこで初めて工房の入り口で固まるヴェルカンに気づいた。 邪魔しては悪い気がして身動きできずにいたことを打ち明ければ、笑いを含んだ感謝の言葉��返ってきた。何をしていたか改めて問うてみれば、石が持つ魔力が思い通りに働くよう、術を施していたのだという。
「一種の魔法人形ですな。もっとも私ひとりの技なれば、そう複雑なものはできませぬが」 「して、いかな術を?」 「力をすべて外へ向け、急激に放出するよう仕向けましてございます」
魔法使いは、杭を槍の穂の代わりにし、槍撃ち弓に装填してほしいという。
「もし術がうまく働けば、標的に命中した石は熱と光を伴う暴風を巻き起こし、周囲一帯を吹き飛ばすはずです」
例えるなら稲妻が落ちるようなもの、直撃を受ければさしもの岩巨人もただでは済むまい、と胸を叩く姿に、にわかに不安に駆られ、さりげなく後ずさり。ところが魔法使いには気付かれてしまった。
「そうたやすく爆ぜはしませんよ――おそらくはね」
そうは言われたが、ヴェルカンには杭を槍撃ち弓まで運搬する度胸はなかった。
「敵さんはいつ現れるんだ?」 『さほど間を空けずに来る時もあれば、かなりの期間、動かなかったこともある』
今や王の言葉は魔法使いの“通訳”がなくともかなりはっきりと聞き取れるまでになっていた。いくら封印されていても、ここは生命の石の直上、力の影響はすでに自分たちにも及んでいるのか、このまま力を浴び続ければどうなってしまうのか。じわりと染み入るような不安を感じているヴェルカンに対し、黒騎士は少なくとも表面上は冷静な振る舞いを見せている。
「つまり完全にでたらめってわけだ。あいにくあんたらと違って俺たちの時間は無限じゃない。いつまでもは待てないぜ」
ここで、ひとつ提案がある、と言葉を継いだのは魔法使い。
「餌を使って奴をおびき出すのです。この国に眠るすべての石を持ち出せば、力に惹かれて出てこずにはおりますまい」 『寝た子を起こせと申すか。いかな障りがあるやら』
漏れ出る力を浴びて、巨人が一層力を増すこともあり得るという。
「相手は強力です。たとえどのような手を使っても、こちらも全力でことに当たらねば」
生者三人、言葉を揃えれば、さしもの王も頭を抱えた。
結局、臣下たちと協議をすると言う死者の王の頼みもあり、ヴェルカンたちは宮殿をあとにした。
「まんまと追い出されちまったな」
とはいえ、ヴェルカンたちの考えも所詮は浅知恵に過ぎない。それがどれほど有効で、かつどれほど危険な手立てかは、長年この地のすべてを見てきた者たちのみの知るところ。 いつでも変わらぬ無人の街路を並んで歩きながら、ところで、とヴェルカンは頭の片隅で考えていたことを口にした。
「岩巨人は、もとはここの市民だったのだろう」
平和と繁栄を享受していたはずが、あずかり知らぬところで繰り広げられた国同士の争いに巻き込まれ、すべてを奪われた者たち。何の因果か、異形の姿で蘇った彼らを、ヴェルカンたちは再び倒そうとしている。 黒騎士も唇をゆがめ、唸った。
「憐れな話だ」
だが、とその語気を強いものに変える。 事情はどうあれ、彼らは遥かな昔に国もろとも滅んだ。 そして自分たちが戦うのは、生ある者のため。今栄えようとしている祖国のため。
「俺は手を引くつもりはないぜ。山の心臓は必ず手に入れる。それが巨人の討伐と引き換えでもな」 「そういうものだろうか」 「お前は違うのかよ」
いや、違わない。内心で首を振る。ヴェルカンを信頼し、帰りを待っている人がいる。その者のためにも、山の心臓を持ち返らねばならない。いかなる障害であっても乗り越えねばならない。 黒騎士の強い語調は、あるいは己と同じ迷いの裏返しだったのかもしれない。そんな考えも浮かんだが、ヴェルカンはこの話題を切り上げることにした。
そうしているうちに宿舎にたどり着いた。また待つしかないのか……と石合戦の盤を取り出した矢先だった。ふと魔法使いが顔をもたげた。
「王の声です。至急、戦の準備をせよと」
動きを止めたのも束の間、この時を今か今かと待ち構えていた身体はすぐさま反応した。素早く鎧を身につけ、武具を携えて飛び出した街路には、同じく命令を受け取ったらしい骸骨兵士たちが兜の緒を締めながら駆けていく。 門前にはすでに多数の兵士が集結していた。以前大きく破壊された城壁は一目見ただけではそれとわからぬほどきちんと修理され、その上には弓を携えた一隊がずらりと居並ぶ。門脇右手の塔がヴェルカンたちの持ち場だった。螺旋階段を駆け上がり、槍が装填されていることを手早く確かめ、そして――
「……奴はどこだ?」
城壁の向こうに広がる薄明の世界、ひたすらなだらかな地下洞窟のどこを見ても、うごめく岩山の影はない。何を思って招集などかけたのか――外に向けて一糸乱れぬ隊列を組む死者たちを見やり、続いて己と同じく所在なさげに辺りを見回す生者を見やり。そのままの流れで王城に目を向けようとした時だった。 初めは風と思えた。しかし風というにはあまりに重々しく、耳鳴りを伴って肌を否応なく粟立ててのしかかるようなそれは、例えるなら岸に打ち寄せる波に近いかもしれない。踏ん張っていないと押し流されてしまいそうな“風”に塔の床は鳴動し、槍撃ち弓が軋みを上げた。 そして風に一息遅れ、王城の壁から天に向けて伸びた光は月光にも似た青。されど急速に拡がり、瞬く間に街全体を覆い尽くして目を灼くは陽光の激しさ。並ぶ煙突は煙を噴き上げ、石と金属の獣と化して唸る。 山の心臓が目覚めたのだと即座に理解できたのは、少しずつ力に身体が馴染んでいたからか。
幾世を経て蘇った王国は、それだけで目を奪い、また同時に肌を粟立たせるなにかだった。
「大勢の人間がこぞって押し寄せるわけだ」
そして、城壁の外で変化が起こったのは間もなく後のこと。 視界の端で舞った砂埃を、目を皿のごとく見開いていたヴェルカンは見逃さなかった。
「出たぞ!!」
ほぼ反射的に叫び、槍撃ち弓の把手を回す。
一歩ごとに巻き上がる粉塵に半身を隠されながらも、巌の身から放たれる重圧感は遥か遠くで槍撃ち弓の狙いをつけるヴェルカンたちにものしかかる。口の中が乾いていく感覚を無視しながら見下ろせば、門前に居並ぶ骸骨兵士たちは固く寄り集まり、盾と長槍を前面にした横列を形作ったところ。不死身の軍勢が織りなす青銅の壁はしかし、迫り来る大岩の連なりの前ではあまりに小さく、頼りなく見える。
突然、すぐ近くで叩きつけるような轟音が発した。隣の塔から槍が放たれたのだ。わずかな仰角で放たれた槍は緩やかな弧を描いて飛び、岩巨人の右脚を捉え――いくばくかの破片を散らして跳ね返された。続いて端の塔から撃ち出された槍は巨人の肩を掠めて彼方へ飛び去り、三の槍は胸と腹の隙間に食い込み、そのまま噛み合う岩の鎧に砕かれた。 今や平原に面したすべての塔から槍が吐き出され、間断なく降り注いでいたが、そのいずれも巨人の歩みを妨げるには至らない。把手を掴んだまま思わず歯噛みしたヴェルカンの肩を黒騎士が掴んだ。ヴェルカンたちが操る槍撃ち弓につがえてあるのは魔法使い特製の炸裂槍。ひとりの力でどうにか準備できたのは全部で三本。確実に弱点を捉え、誤ることなく必殺の一矢を叩き込まねばならぬ。そしてその弱点を見極めるのは、他でもない生者の使命。少なくとも王はそう語った。
「見えるか?」
黙って首を振る。どれだけ目をこらしても、岩は岩。その厚い殻の下のどこに魔力の核が埋め込まれているのか、見当もつかない。 ついに兵士たちの列に巨人が到達した。盾の壁を物ともせず押しひしげ、繰り出された槍の青銅もどこ吹く風。立ちはだかる不死の軍勢を文字通り蹴散らす歩みは微塵も淀むことなく城門に迫り寄る。
どこだ、どこを狙えばいい?
迎え撃つ骸骨たちも負けてはいない。いくら吹き飛ばされようと即座に立ち上がり、自身の何倍もの岩山に取りつく。すべては生者たちが矢を放つ、その瞬間のために。 さしもの巨人もうるさく感じたのか、腕を振り回し、身を捩じらせ、まとわりつく骸骨を振り落とす。そのさなか、岩巨人がその巨大な足を持ち上げ、回り込んだ兵士を踏みつぶさんと全身をゆっくりと翻した。 その右の肩の付け根、腕を持ち上げた拍子に生じた甲殻の隙間、そこに見紛う事なき青い光の筋を認め、ヴェルカンは目を見開いた。
「背中か!」
黒騎士とふたり、同時に上げた声は地響きに半ばかき消され、舞い上がる砂煙の中、兵士の腕が飛んでいくのが遠く見えた。把手を回し、装填された槍の穂先を向けるも、すでに巨人は城門に向き直っている。
「奴の背中をこちらに向けさせてくれ!」
魔法使いは答えない。兵士たちの指揮を執る死者の王に意志を伝えるので精いっぱいだからだ。だがその声は届いたとみえ、兵士たちは驚くほど素早く反応した。巨人の横から背後へと回り込み、激しく攻め立てる。 しかしその時には、巨人はもはや足元で蠢く小さな物たちなど気にも留めなくなっていた。すぐ目の前の壁を乗り越えれば、長らく恋い焦がれた宝が手に入る。その渇きを満たすため、さらなる一歩を踏み出す。
と、門から飛び出したものがあった。巨大な黒い影が黒騎士の愛馬と気づくと同時、その背中に小さなものが巻きついているのが見て取れた。
「族長殿!?」
巨馬の背に跨る――というより、嫌がって暴れる背中に必死でしがみついている小柄は、さらに小脇に大ぶりな袋を抱えていた。そこから漏れ出る青い光をみとめ、黒騎士が身を乗り出した。 鬣を掴む山の民の手に従っているのかいないのか、巨馬は太い首を振り巡らしながら兵士の列を飛び越え、巨人の腕の下を潜り抜け、なお疾駆する。 目の前に餌を差し出され、さしもの巨人も反応した。瓦礫をまき���らして身を屈め、平原を遠ざかる馬を追ってその広い背中をよじる。その瞬間、再び裂けた甲殻から山の心臓がその光芒を覗かせた。 この機を逃すまいと、ヴェルカンはあらん限りの勢いで把手を回した。じれったいほどゆっくりと持ちあがった槍の穂先が巨人の背中を捉え、その核と呼応するかのごとく束の間輝く。いちど深く沈みこんだ巨人の背中が再び持ちあがり、照準の内に戻った。
「今だ!」
ヴェルカンの合図に、黒騎士が弦受けの棒を引き抜いた。瞬間、解き放たれた弦は限界まで引き絞られた弓が元に戻ろうとする力のままに台座を奔り、番えた槍が木屑を散らして猛然と飛び出した。たわんだ弦が台座を激しく打ち、巨大な槍の反動に銅管は軋んだ。 途端、時の流れがにわかに遅くなったようだった。微かな白煙を引き連れて宙を駆け、巨人の背中に吸い込まれる槍の軌跡が不思議なほどゆっくりと鮮明に見て取れ、そして―― 稲妻が目の前に落ちたがごとき閃光が視界を白に染め、轟音は破城鎚と化してヴェルカンを打った。立てかけられた槍に背中から叩きつけられた痛みと眩む目の痛みが同時に襲いかかり、続いてちらつく光の粒を残して視界が黒一色に塗りこめられていった。
気を失っていたのか、それともあまりの衝撃に束の間絶えた五感に惑わされただけだったのか。視界の端でうつ伏せに倒れていた魔法使いがのろのろと身を起こすのを見とめつつ、ヴェルカンは槍打ち弓の台座を支えに上体を引き上げた。先ほどの残響がいまだに兜の中に響いており、気持ちが悪い。 胸壁にもたれてどうにか立ち上がった黒騎士と並んで見下ろした先に巨人の影はなく、代わりに平原に向かって扇状に散らばった大小さまざまな岩の塊と、その合間には兵士たちの破片が見て取れた。無事だった兵士たちはそれらの隙間を駆け巡りながら、同族だったものを選り分け、復元するのに大忙し。
終わったのか……?
にわかに信じられず、目を向けた先で、魔法使いは首を振った。 指し示されるままに再び見下ろせば、巨人の残骸が微かに蠢いていた。あるいは身もだえするように揺らぎ、より小さな破片は転がり、そのそれぞれがひとつところを目指して寄り集まっていく。 黒騎士と顔を見合わせたのも一瞬、万一に備えて隅に固めてあった槍と盾を手に取る。もはや痛みなど気にならなかった。
門から飛び出した時には魔法使いの伝令が届いていたのだろう、骸骨兵士たちはいち早く巨人の破片を拾い集め、取り押さえてくれていた。しかしその中央では、取りこぼした大小の破片が不格好に積み重なり、四肢と胴体を形成したところだった。その姿はかつての山のごとき巨躯とは比べるべくもないが、それにしても身の丈にしてヴェルカンが見上げるほど。胸を形成するは山の心臓。今や燐光が急流に落ちる陽光もかくやと目まぐるしく揺らめき、その眩さは魔法使いでなくとも目が痛むほど。誰にやられたのか知っているのか、それともこの地にあっては珍しい生者の気配を嗅ぎつけたか、まっすぐに向かってくる。 盾を突き出し、視界を埋める岩の塊が刻々と大きさを増すのを見据えながら怒鳴る。
「私が先に仕掛ける!いいな!」
背後で黒騎士が頷く気配があった。地を蹴って跳び出した拍子に岩巨人が右腕を振り上げたのが目に入り、咄嗟に盾を掲げて身を沈める。それでも降り注ぐ岩に盾は砕け、外周に張り巡らした補強の鉄輪が弾けた。なお殺ぎきれない衝撃が肩から背中に抜け、地面に膝をついてしまう。激しくぶれた視界の中、巨人の腕が再び持ち上がるのが見て取れた。 と、その右手を黒と赤が駆け抜けていく。ヴェルカンの兜を掠めて戦槌が振りぬかれた拍子に、微かな鋼鉄の唸りが耳を刺す。その先端が巨人の右脇を打ち、石くれの一片を弾き飛ばすとともにその身を大きくよろめかせる。 その隙に立ち上がったヴェルカンだったが、瞬間左手に走った痛みに思わず顔をしかめて舌打ち。真っ二つに裂けた盾を捨て、右手だけで振り上げた槍を巨人の胸に叩きつける。 と、数人の骸骨兵士が駆け寄り、巨人に組みついた。鉱物の四肢に白骨の腕が何本も絡みつき、動きを封じる。手足を引き伸ばされ、露出した心臓の光は、今は無数の泡沫が弾けるような瞬きに変じていた。 ひょっとすると光の揺らぎは、声なき巨人の感情なのかもしれない。ふとそんなことを思いつく。
ならばおまえは何を思う?
姿かたちも名前も、個すらも失いながら蘇った亡者たち。その心は今や山の心臓にのみ向けられているというが、果たして本当だろうか。 だが、どちらにせよ知ることは叶わぬだろうし、知ったところでどうしようもない。ならば知りたいとも思わぬ。
巨人の胸郭に手を伸ばし、心臓に腕を絡める。と、横合いからさらに二本の腕が差し出され、黒い手甲を青く染めた。 首をひねり、すぐ間近に黒い面甲を確かめると同時、目出し穴の向こうから青灰色の目が見返してくる。 目配せひとつ、巨人の膝に足をかけ、渾身の力で引っ張れば、黒騎士も呼応して��を込める気配があった。さらに群がる死者たちも。 岩と岩とが擦れ合う耳障りな音が絶え間なく響き渡り、ますます激しく渦巻く燐光は顔を背けてもなお、兜の目庇を貫いて目を灼く。
いま感じているのは怒りか、それとも恐れ?あるいは――
これまでとは異なる、湿ったような音が耳を打ち、だしぬけに手にかかる負荷が消えた。 心臓を抱えたまま、後ろ向きにひっくり返ってしまったヴェルカンの、急速に下へと流れていく視界の中、核を失った身体が石くれの群れとなってほどけ、崩れ落ちていく。 その様子を最後まで見届けた直後、どっと疲れが噴き出し、寝そべったまま息をついて天を見上げる。 洞窟の高い高い天井が見せるは、黄昏の空にも似た薄暗がり。されどそはまことの空にあらず。まがい物の星空は、その下にある者どもを、変わらぬ光で照らし出していた。
0 notes
Text
白騎士の冒険 魔宮の秘宝 四
「彼がこの地の王です。『その方らが我らと切り結びし暴れ馬か。近う寄れ』とおっしゃっております」 「暴れ馬、ねえ……」
魔法使いは生者と死者の橋渡しというわけだ。 黒騎士と揃って跪き、名乗ると、王はころころと笑った。
『そなたらは面白いな。我々を前に物怖じもせず、まるで王にでもするように挨拶を述べおる』 「あなた様は、この地の長であらせられるのでは?」 『いかにも。余がこの国を統べる王なるぞ。血も涙もない、骨ばかりの王ぞ』
重臣たちが音を立てて肩を震わせる中、はあ……と生返事ひとつ、思わず騎士ふたり、顔を見合わせる。 肉のない顔は例のごとく表情に乏しく、魔法使いの通訳も飾り気のないものだったが、その実ずいぶん冗談が好きな性分なようだ。おまけに自分たちの姿が生者にどんな印象を与えるか、よくよく理解している。 だが多少変わり者だろうと、話が通じるのは確からしい。
『してその方ら、生あるものの身でありながら何のゆえあってこの地に足を踏み入れた』
問われ、ふと返答に詰まる。ここに来るまでに、実に様々な目にあった。森の中で黒の王国の騎士と刃を交え、山の民を案内人に仕立て。地下に隠された王国、歩き回る死者たち。そして岩の巨人。 だがそれでいて、それらがすべてついさっき起こったばかりのような心地さえする。それはこの地に溢れる“力”のなせる業か。 ヴェルカンたちは再び目を見合わせ、本題に入ることにした。
*
冗談好きな死者の王だが、真面目な話と笑い話の区別はつく人物だった。生命の石の話を切り出した時、王は微かに姿勢を正した。
『以前にも山の心臓を探していると言ってきた者がいたな。よく覚えておる』 「いつのことでしょう?」 『さて……つい昨日であったか、百年からの昔であったか……』
指で額を押さえて唸る姿に冗談めいたものはなく、真剣にわからないようだった。時間の感覚が希薄なのはヴェルカンたちも同様だが、死者たちはさらに深刻らしい。もっとも、老いや飢えの心配がないとなれば、ことさらに時間を気にする必要もないのかもしれない。
だしぬけに、外の世界ではどれほど時間が経ったのだろうと思い至る。首尾よく石を手に入れても、外に出たときは国そのものが移り変わるほどの時間が流れていたのでは話にならない。
『ひとつ問う。その方ら、山の心臓を手に入れて何とする』
これまでにない真剣な声音に、思わず返答に詰まる。この国の“力”は意志そのものを媒介となって伝えるという。あるいは気づいていないだけで、自分たちの胸の内も周囲に聞かれているのだろうか。
『なに。はるかな昔、山の心臓を求め、故に滅び去った国があるのでな』
物騒な話もあったものだった。そも、話を聞くに山の心臓こと生命の石はその名の通り、生き物に活力を与えるもの。それがどのように害をもたらすのか。 ところが死者の王はこれには答えず、話を戻した。
『事情はどうあれ、欲しいというならくれてやれんこともない』 「まことですか!?」
そこまで言って、王は身を乗り出したふたりを制するように手を掲げた。 生命の石は相応の労働の報酬として明け渡すというのだ。
『我が国はあるものに脅かされておる。不死たる我が軍兵にあってなお勝てぬ相手よ』 「岩の巨人……」
思わず口走ると、死者の王が表情は乏しいままに驚くのがはっきりと感じられた。
『知っておったか』 脱獄した���に見たと知り、ますます驚いた様子の王に、岩巨人について改めて尋ねてみる。
『あれがいつ頃生じたものなのか、それは定かではない。だが気づいたときには我が国へ攻めてくるようになっていた』 「して、あれは何者なのです?土くれが意思を持って動き回るなど、聞いたこともない」
そこまで言って、今話しているのがこれまた想像だにしなかった生ける死者であることを思い出す。この地にあっては慣れ親しんだ世界のありようは捨て去った方がよいのかもしれない。
『あれなるは我らと同じ生ならざりしもの。刃も火も、彼奴に手傷を負わせることは敵わぬ』
不死身の彼らでも勝てない相手に、生身の人間がただのふたりで何ができるのだろうか。 王は顎に手をやり、値踏みでもするかのように黒騎士たちを交互に見やった。
『あやつこそが、その方らが求めるものへの鍵だと言ったら?』
事情をいち早く飲み込んだのは黒騎士の方だった。つまり……と目を細める。
「奴と山の心臓に関わりがあると?」 『関わりなどではない。あれこそがそなたらの求める宝――生命の石そのものよ。もし欲するなら、彼奴を降し、奪い取るのみ』
*
「そりゃあな。ただでくれるなんてそんな美味い話があるはずがないよな」
窓から城塞を眺めながら黒騎士がぼやく。一行には先まで詰め込まれていた牢獄ではなく、城塞にほど近い宿舎の一室があてがわれた。例によって久しく利用されていなかったらしい室内は殺風景で調度の類もない。これでも他の部屋よりは整っているという話だが……
「生命の石てのは、あんな化け物だったのか」 「そんなはずはない。黒いの、お前は今回の件について、どこまで把握してる?」 「俺の任務はあくまでお前らが探してるものを突き止め、先んじて奪うことだ。それが何かまでは聞いてない」 「魔法使い殿は」 「正直、私も驚いております。手記にはあのような怪物のことなど、一言も記されてはおりませなんだからな」 「見落としたんじゃないのか」
黒騎士は半ば茶化すが、おそらく嘘ではないのだろう。だがそれならば、冒険家はなぜ岩巨人のことを記さなかったのか。あるいは、岩巨人と生命の石は全くの無関係なのかもしれない、と思い至る。死者の王が、ヴェルカンたちの助力を取りつけるために嘘をついていることは考えられる。もっとも、それを証明する手立てはない。
最初は魔法使い、今は死者の王。改めて他者の言葉を鵜呑みにし、右往左往するしかない現状にため息が漏れる。普段は騎士だ領主だと威張っていながら、ひとたび異界にあっては何も知らず、己の身の振り方さえも他者に委ねるしかない未熟者なのだとまざまざと思い知らされる。 ふと、今なお消息不明の山の民の長を思い出す。発見の報がないということは隠れおおせているのだろうか。ヴェルカンたちと同様、この地には不案内のはずだが、その善し悪しは別にしても自らなすべきことを見出し、即座に行動に移す身の軽さは、今となっては少しだけ眩しく映る。
私も指を咥えて見ていることはないな。
おもむろに立ち上がったヴェルカンを、魔法使いが驚いた様子で見上げる。
「どちらへ?」 「少し出てきます。とにかく今は情報が欲しい」
剣を腰帯に留めていると、背後から、待て、と声がかかった。
「俺も行こう」
そう言いながらマントを羽織る長身を意外な思いで見つめれば、ぐんにゃりと歪んだ眉毛の下から青灰色の目が睨みつけてくる。
「ただ待ってるだけなのも性に合わん。それに帝国に抜け駆けされるのも面白くない」
お前と同道するのは業腹だがな、と付け足された一言を舌打ちで跳ね返しながらも、黒騎士も自分と同じ考えだったことを知り、胸中はいささか複雑���った。 まあいい、と気を取り直し、扉に手をかける。今はとりあえず見えている道を歩き出せばいい。そうすれば次に足を踏み出すべき場所も見えてくるはずだ。
*
一番初めに、ふたりは岩巨人が襲撃した城門に足を運んだ。道中は荷物を担いだ骸骨兵士たちが列をなし、町はいつにない賑わいを見せていた。すでに触れが行き届いているのか、生者が列に加わっても死者たちはもはや見向きもしない。 城壁に沿って組まれた囲いと足場の規模から、損害は相当なものとみえた。城壁の下では運び込まれる袋の中身を空けては水と混ぜて桶に汲み取り、城壁の上からは起重機で吊り上げた桶の中身が囲いの中に流し込まれる。隙間なく木板を敷き詰めた囲いが型の役目を果たし、灰色の泥状になった溶液が漏れ出ることはない。袋は次から次へと運ばれ、汲み上げられては囲いの中に注がれていく。
「連中、泥で壁を築いていたのか」
とはいえ巨大な城壁はもとより、城門や塔といった構造物をも支えうる素材、単なる泥ではあるまい。手で触れてみれば、泥が乾いたものと思しき壁面は石と変わらぬ感触と堅さを伝えてくる。 にわかに興味を駆られ、続いて足を踏み入れたのは、城門の脇にそびえる角塔。螺旋階段を昇った先、塔の頂上には石の台座がしつらえられ、木と金具を組み合わせた器具が固定されていた。 湾曲した木の腕の両端を太い縄でつないだそれは、一見すると弓にも見えた。ただし、弓というには弦にあたる縄ですら人の腕ほどの太さがある巨大なものであり、そばに束ねて積み上げられた矢はさながら丸太。先の戦いで岩巨人に打ち込まれた、槍と見えたものはこれであろう。 弓も矢も、人の腕力では到底動かせる代物ではないが、台座を中心に複雑に絡み合う青銅の管や無数の歯車を見るに、何らかのからくりによって駆動するらしい。
「あの禿山は国からもちょくちょく眺めてたもんだが、その真下にこんなものが埋まってるなんて、当時は考えもしなかったな」
黒騎士の言葉にもヴェルカンは唸るばかり。 魔法か、もっと別の何かか。この地下世界には、まだまだ秘密がありそうだった。そしておそらく、ヴェルカンたちにはその多くを理解することもかなわぬのだろう。
*
囚人から客人に処遇改善されるに伴い、ヴェルカンたちは町ばかりか王城の出入りも許可されていた。寛容を通り越して不用心ではと若干呆れないでもないが、これもまた不死ゆえの余裕なのかもしれない。 しかしながらその一方、できることもさほど多くないと悟るのにそう時はかからなかった。食料を要しない国民性ゆえか料理屋や酒屋は見当たらず、外部との交易も希薄か存在しないらしく市や特産品の類も皆無。劇場や遊技場はあれど役者はいない。そもそも町を出歩く人影が極めて少なく、時折巡回中の兵士と出会うのがせいぜいとくれば、どこへ行ってものっぺりと代わり映えせず、常時薄暗い景色など早々に飽きる。 やがて魔法使いは王城の図書館に入り浸るようになり、ヴェルカンと黒騎士も観光は諦め、さりとて他にすることも思いつかず、結局渋々ながら行動を共にすることが多くなった。
そしてほどなく知ったのは、黒騎士が“石合戦”を知らないということ。とはいえヴェルカンも西の湿地領で仕えていたころに幾度か遊んだきりなのだが。 盤に無数の点を等間隔に穿ち、そこに歩兵部隊や弓兵部隊に見立てた石を並べていく。石は一回につき縦横斜めの隣り合った点に移動することができ、対手と交互に自軍の石を動かしていくことで部隊の配置を整えつつ、同じように対手が操る敵軍と戦っていく……という具合の遊戯であり、かつて将軍や士官が指揮能力を鍛えるために行っていた机上戦がその始まりだという。 はじめは面倒臭そうに、そのうち身を乗り出して説明を聞いていた黒騎士は、実際にヴェルカンと幾手か交えるうちにすっかりその魅力に取りつかれてしまったようだった。他に娯楽も話し相手もいない状況がなせる業ではあったのかもしれないが、折を見ては勝負を持ちかけてくる黒騎士のおかげで退屈することがなくなったのは事実だ。
「お前も騎士なんだろう。どこの家の出なんだ」
この時も盤を睨みながら、黒騎士がそんな事を聞いてきた。折しも黒騎士軍の槍兵とヴェルカン軍の槍兵がぶつかり合い、膠着状態に陥っている時だった。付近の歩兵部隊を向かわせて挟撃しようとしたヴェルカンは、そうすれば黒騎士が配した弓兵隊の射程に入ってしまう事に気づき、慌てて手を止めた。唸ったのは次の手と黒騎士の質問の両方を考えあぐねたためだ。 いくら白の騎士として任務に携わる身とて、貧農の子という出自は変えようがない。そして厄介な事に、いくばくかの勲功と名声を得た今なお、いやむしろ今だからこそ、それを知られるのは恥ずべきことと考えるようになった己がいる事にヴェルカンは気づいた。持てるものが多くなればなるほど、その一部でも欠けることが偏執的なまでに恐ろしい。それはあるいは、得る喜び、持てる喜びを知ってしまったがゆえか。
「両親は平民だった。家と呼べるほど大層なものはない」
そしてまた、恥をかくことを恐れつつも誤魔化しや嘘は良しとしないのがヴェルカンという騎士だった。不器用だと家臣らが口をそろえるのも無理はない、と内心で自嘲する。 黒騎士はといえば、へえ、と感嘆したような声を上げた。
「平民が騎士になれるのか」
もたげた顔には純粋な驚き以外は見て取れなかった。すこしだけ安堵したヴェルカンは問い返してみることにした。
「王国は違うのか」 「こっちじゃ騎士は��侯貴族の子息と相場が決まってる。騎士叙任は人の上に立つものとしての一種の通過儀礼みたいなもんだ」
今度はヴェルカンが感嘆の声を上げる番だった。
「じゃあお前もどこかの王子なのか」 「三男坊だから継承権にはちと遠いがな」
それでも、目の前の男は生まれながらの貴族なのだ。毎日栄養満点の食事に舌鼓を打ち、十分な勉学と鍛錬で幼い頃から才能を伸ばす機会に恵まれていたのだろう。ちょうどヴェルカンが明日をも知れぬ日々をどうにか生き延びていた、まさにその頃に。 どろりとした感情が湧き上がってくるのを感じつつ、具体的にどこの王子なのか重ねて尋ねようとすると、黒騎士は笑って首を振った。
「ここは社交場じゃないんだぜ。そうやすやすと教えられるもんか」
敵に身元を明かすのはわざわざ急所を晒すようなものだという。���ちらも訊いてきたくせに、と言い返すより早く、その点、と言葉を継ぐ。
「お前はそういう心配とは無縁なわけだ。もしとっ捕まって強請られても、皇帝陛下さまが直々に馬鹿でかい財布から身代金を出してくれるんだろうし」
皮肉ではなく純粋にそう思っているらしい声に、思わず、なるほど、と舌を巻く。
持たざるものには持たざるものなりの強みがあるのだ。
少し軽くなった気持ちで動かした弓兵の石は、直後、間髪入れずに飛んできた騎兵にあっさり蹂躙された。
*
さて、一行はなにもただ暇を持て余しているばかりではなかった。死者の王は時折ヴェルカンたちを呼び出しては話をしたがった。話題にするのはもっぱら地上の事で、方々の様々な出来事を尋ねては興味深そうに頷くのだ。呼び出されるのはヴェルカンひとりのときもあれば黒騎士と揃っての時もあった。当然、魔法使いは通訳として同行する。 話すうち、死者の国は驚いたことに白の帝国が建国される前からこの地にあること、さらに驚くことには、この国がもともとは生者の国だったということが分かった。
『生者がおらねば死者は生じ得ぬだろうに。なにをうろたえることがあろうや』
確かにその通りではあるのだが。
「なにゆえ今のようなお姿に?」 『今の姿とは、血肉を失ってなお動き回る異形ということかな』
返す言葉を失った生者ふたりの前で、死者の王は足を組み替えた。
『われわれとて元は生きた人間だったのだ。この地に眠る力を求めてやってきた――ちょうど今のそなたらのようにな』
*
始まりは幾代の昔か。さる力ある魔法使いがこの山に膨大な魔力の源を嗅ぎ取り、調査隊が編成された。調査隊はほどなく地下洞窟を発見し、そこを拠点と定め、四方に採掘を開始した。 しかしながら、掘れども掘れども件の力の源は見いだせず、時間ばかりが過ぎていった。やがて発掘現場から銀の鉱脈が見つかると、基地には人が集まり物が集まり、本来の目的を忘れつつあった調査隊の数を入植してきた鉱夫や商人が上回った頃を境に次第に鉱山町として栄えていくようになる。 町にあふれ返る人々を束ねるべく、かつての調査隊の指導者が長に選ばれたのは当然のなりゆきだっただろう。 やがて近隣の村や集落の協力を得、本国からの援助を必要としなくなると、町はいつしかひとつの国として独立し、世襲制で任命されていた町長はそのまま王となった。
『私の祖父だ』
ようやく事態が動き始めたのは、三代目の王――現在の死者の王――が即位してまもなく。世代を経て相当の深さにまで掘り進められていた坑道からそれは見出された。 金とも銀とも異なる、自ら燐光を放つ鉱石の発見に、鉱夫たちは大騒ぎとなった。ほどなく、鉱石は膨大な魔力を内包していることが判明し、また時を同じくして、遥か昔の文献を浚った王は、王国がかつての調査隊の根拠地後に築かれていたこと、そして鉱石こそが調査隊が捜していたものだということを知ったのだった。
『まさか余が父祖の悲願を果たそうとは、思いもよらなんだ』
もっとも、それまではその悲願すら忘れ去られていたのだが、と死者の王は自嘲気味に笑う。
その後、王国中から学者や魔法使いが集められ、鉱石の調査にあたることになった。ほどなく鉱石から魔力を取り出し、利用する技術が実用化されると、鉱石は王国中の様々な場所に用いられるようになっていった。
『燃料や機械動力のみならず、砕いて畑に撒けば作物の生長を助け、煎じて病人に飲ませればたちどころに癒してしまう。まさに万能の物質であったよ』
国内は当代きっての魔法技術であふれ返り、国外からは莫大な金銀財宝を携えた商人が殺到し、王国は瞬く間に栄華を極めるまでになった。 だが富であれ魔法であれ、巨大な力は良くも悪くも人の目を引き付ける。
最初は隣国だった。同盟を結ぶ代わりに鉱石や技術の提供を求めてきたのだ。 しかしながら、地下の王はこの申し出を黙殺した。
『初めは警戒心からであった。友好関係にあるとはいえ、他国が力を持つのが恐ろしかったのだ』
同様の申し出は他の国や勢力からもあったが、地下の王はそれらをすべて蹴り、またそれまで行っていた魔法製品の輸出もやめてしまった。
『ちょうど鉱石を発見したころ、山の民の巫女が訪ねてきたことがあったのを思い出してな』
巫女は鉱石を“山の心臓”と呼び、扱いにはくれぐれも注意するよう警告した。
あれなるは山に凝った力の源、外に持ち出さばいかな障りがあるやもしれませぬ――
当時は蛮族の戯言と相手にもしなかったが、年月を経るほどに王の中でその言葉が少しずつ重みを増していくようだった。 あるいはそれは予感だったのかもしれない。外部へ持ち出すことはなくなったが、領内ではますます鉱石の利用が盛んになり、いつしか鉱石なしでは生活が成り立たなくなるまでになっていた。 異常が表れ始めたのは、鉱石が最初に発見されて十年も過ぎたころだった。
『国内で病人や死人が出なくなった』
いつ倒れてもおかしくない老人がいつまでも元気に働いている。落盤で大怪我を負った鉱夫が、わずかな時間で立ち上がれるまでに回復する。王も当時すでに老境にさしかかりつつある頃だったが、若々しい姿のままだと話題になった。 これらの変化は、最初は喜ばしいこととして受け止められた。山の心臓がもたらした不老長寿の実現。生ある者の枷から解き放たれたと誰もが浮かれた。
『その行き着いた果てがこれよ』
そう締めくくり、王ははだけた胸骨をざらりと撫でた。
*
「王はああ言っていたが、どう思う?」
玉座の間から引き上げるや、黒騎士がそんなことを尋ねてきた。
「確かに肉が失せて骨だけの姿になるのはいささか困るが、それで永遠の命が手に入るなら安い���のではないかな」 「同感だ」
果てることなき命、永劫の時間。誰もが求め、それでいてどれほどの金銀財宝でも贖うことかなわぬ、そういうたぐいのものだったはずだが。
「山の心臓が手に入れば、俺たちにも機会があるわけだ」
どこか不敵な笑みを浮かべ、顎を撫でる黒騎士は、ぐいと身を乗り出してきた。
「もし不死身になれたら何をする?」
そうだな、とヴェルカンは唸った。不死の肉体、手に入るのは永遠と可能性だ。
「不死の体になれたら、何でもできるな」
どれほど危険なことでも、どれほど時間を要する事柄であっても成しうることができる。 黒騎士はどこかわが意を得たとばかりに頷く。実のところ、あまりに話が大きすぎて実感が湧かずに出た回答だったとは言えそうもなかった。
「それにしても、この国にはなにゆえ民がおらぬのでしょうな」
ふと、魔法使いがそんなことを言い出した。確かに、とヴェルカンたちも改めて首をひねる。一度は鉱山町として栄えたのだ。もっと大勢の住民が暮らしていてもおかしくはないはずだ。 そしてまた、王国がかつて誇ったという魔法技術を偲ばせるものがひとつも見当たらないのはどうしたわけか。どこを向いても飾り気のない無人の建物が並ぶばかり、殺風景なことこの上ない。 あるいは、すべては王の出任せだったのだろうか。
「だいたいおかしいじゃねえか。いくら昔の話とはいえ、こんな場所に王国があると、なぜ誰にも知られていないんだ。なぜ王たちは外部との交わりを絶った?」
いったん出始めれば、疑問は後から後から湧いてくる。
「いっちょう王を問い詰めてみるか」 「生命の石は彼が握ってる。下手な出方でヘソを曲げさせたくない」
魔法使いが太い眉を指で掻いた。
「王は、生命の石をさほど快く思っとらんように見えましたな」
彼の言葉を借りれば、生命の石があったばかりに滅んだ国があるという。さらにその口ぶり、滅んだのは他でもないこの国であると言わんばかり。住民の姿が見えないのと何か関係があるのだろうか。
「……岩巨人か」
岩の巨人はすなわち生命の石そのもの。
「採掘によって、眠っていた怪物が目覚めたとでもいうのか」 「あり得ますな」 「そしてこの国は奴によって滅びた……」
一応、筋は通る。というより、一切が想像の埒外にある以上、そうとでもせねば納得できないというほうが正しい。
「俺たち、そんな相手に戦いを挑むってのか」
無理難題を押しつけて諦めさせようとしているかとも思わないでもないが、それなら客としてもてなす理由がない。
「何かあるはずなんだ。俺たちがあの怪物に勝てる理由が」
そしてそれを知りうるはただひとり。真っ白な頬骨と、その上の真っ黒な眼窩を思い浮かべ、ヴェルカンは腕組みした。
*
生命の石を得るには岩巨人を倒さねばならぬというが、問題の巨人が姿を見せぬとあってはどうしようもない。次はいつ現れるのか、どこに住んでいるのか、そしてどれほどの強さなのか��まるで知らぬ敵を今か今かと待ち続ける苦痛は、緊張感とはいささか性質が異なる。 奪われたと思っていた武具は、死者たちによって丁重に保管され、ありがたいことに手入れまでされていた。 目の前にかざした剣の刃先は、工房の灯を飲み込んで冷たく照り返す。帝国が誇る白の鋼で覆われた厚みのある刀身は、鉄の兜をも叩き割る切れ味と、そうしても刃こぼれひとつ起こさぬ強靭さを併せ持つ。しかしながら生ける死者を完全に滅ぼせる力はないし、岩巨人の巨体を斬るにはやはり心もとない。死者たちの秘術か、ヴェルカンの灰青色の瞳が映るまでに磨き上げられた甲冑も、文字通り巌の拳を受け止めて無事で済むかどうか。
「何かいい作戦はあるのか?」
そう言うのは、自分も武具の手入れをしていた黒騎士。そちらは?と反問すればあっさり首を横に振る。まるで悪びれもしないのはヴェルカンにも妙案がない事を知っているためだ。 いちど本国に帰還報告し、応援を要請すべきか。そんな考えを披露すれば、相手は腕組みして鼻を鳴らした。
「白黒両軍が顔を突き合わせるのか。そりゃさぞ楽しいことになるだろうよ」
なにより、元が存在するかも定かではない魔法の宝という雲を掴むような話なのだ。いくら騎士の要請であれ、おいそれと軍が動くとは思えない。 第一、岩巨人は不思議な業を数多有する死者の軍兵たちですら苦戦する相手、生身の人間が束になったところで敵うかどうか。 考えあぐねたふたりの話題は、そのうち依然行方不明の山の民の族長へと移っていった。ヴェルカンも黒騎士も、時間が余っているのをいい事にしばしば捜してはいるのだが、手がかりのひとつも得られないでいる。いちど魔法使いに念話を使って呼びかけてもらったのだが、それでも返事はなかった。 もとより今回の探索行には何の関わりもない人間、さっさと地上の家へと帰ってしまったのかもしれなかったが、一言の断りもないのも妙な話だ。
「まあ、所詮蛮族だしなあ」
そう言いつつも少しだけ寂しさを覗かせた声音に密かに共感を覚えたヴェルカンだったが、暇潰しの石合戦の誘いは断った。
街の外を探検したいという黒騎士と別れ、王城に向かったヴェルカンの予想通り、魔法使いは図書館で書物の山に埋もれて唸っていた。その目の前の作業台には親指ほどの鉱物がいくつか。
「生命の石、ここらでは山の心臓と呼ばれとるものですな」
調査用にと、厳重に保管されていた標本を貸し出してくれたのだという。つまみ上げると、それ自体が意思を持っているかのごとく揺らめいた光がヴェルカンの指を青く染めた。
「驚いたものです。金属や無機物に魔力を満たす業は古くからございますが、この石はほとんど魔力そのものが凝固しているのですな」
四方から寄り集まり、凝った剥き出しの力は、今度は周囲に魔力を放出し、様々な影響を及ぼす。そうした力を一箇所に収束し、制御を可能にしたものがこの国の動力機関なのだという。
「もっとも、それらのほとんどは解体され、今ではわずかに残された設計図が当時の断片を物語るばかりですがな」
残念至極、と魔法使いは眉を下げるが、一方のヴェルカンの関心事は、もっと短絡的で即物的なところにある。 岩の巨人の話と知り、いささか興をそがれた様子の魔法使いだったが、それでもいくつか資料を見つけてくれていた。
「この国の他の機械がそうであったように、例の巨人も山の心臓が核になっておるようです」
体内に内蔵された山の心臓が岩の頭蓋の内に意思と思考を維持せしめ、手足を自在に動かす動力源となっているのだ。
「そんなことが可能なのか」 「そもそも魔法とは意思でもって無形の魔力に指向性を持たせる技ですゆえ。十分な力量があれば無生物に思考力を持たせることも不可能ではありませぬ」
その言葉で思い出すのは先帝の館で目にした木製の侍女。館に安置された生命の石の力でものを考え、さながら人そのものの振る舞いを見せるものどもを、若き先帝は何と呼んでいたか……
「魔法人形などはその最たるものでしょうな。そして遺骸が生命の石の力でもって人格を持ち、生ける者のごとく振る舞っているという点においては、この国の者たちもみな一種の魔法人形と言えるやもしれませぬ」 「生者の頃の人格が、石の力で死後もそのまま残っていると?」 「その可能性は考えられます」 「不老不死の実現はその身を生きた人形と化すことだった……」
わが身が人ならざる者に変じたことに気付いたとき、王は何を思ったか。
「では岩巨人は?ただの力の塊に自然と意識が芽生えたというのか」
そんな疑問がふと浮かんだが、魔法使いは、その点に関する資料は見つからなかったと首をひねるばかり。
「あるいは精霊かも知れませぬな。山の心臓に取りついた邪鬼悪霊の類が悪さをしているということも」
いずれ、推測の域を出ませぬが。そう締めくくり、書棚を見上げた視線につられ、ヴェルカンも首をもたげてみたものの、書物の山は答えてくれそうになかった。
*
「なんだ、まさか迎えに来たのか」
門のそば、埃をかぶっていた厩舎にいた黒騎士がそんな軽口を叩いたが、ヴェルカンはすぐには返事ができなかった。黒騎士の大柄の背後、さらにそびえる巨体に目を奪われていたからだ。 平原を彷徨っていたのを偶然発見したのだという。
「かわいそうに、餌も食わずにずっと俺のことを探してたんだな」
そうは言うものの、遥かな頭上から繰り出される臭い鼻息の前では、ささやかな同情など吹き散らされてしまう。
「ここでは餌も必要ないだろう」
おそらくはヴェルカンたちが通ってきた以外にもいくつもの抜け道があるのだろう。いつになく嬉しそうな様子で巨馬の鬣に手櫛を入れていた黒騎士が、ふと振り返った。
「これで俺は帰りの足が手に入ったが……帝国人殿はどうなさるおつもりかな?」
にやにや笑いと芝居がかった仕草とともに放たれた質問を理解した瞬間、危うく声を上げそうになった。 もし首尾よく岩巨人を倒し、生命の石を手に入れたとしても、今のヴェルカンには運ぶ手立てがないのだ。 馬の背で揺られる黒騎士の隣で、石を背負って汗みずくになっている己の姿を想像し、ヴェルカンは青くなった。
巨人はいまだ現れない。
0 notes
Text
白騎士の冒険:魔宮の秘宝 二
「おい、黒いの」
今もまた、数歩後ろを手綱を引いてついてくる黒い小札鎧はそっぽを向いたまま、返事もしない。
「黒いの!聞いてるのか」
声を荒げてようやく返ってきたのは、さも忌々しげな舌打ちひとつ。
「俺は騎士だぞ。『黒いの』じゃない」 「なら貴様も私のことを『白いの』と呼ぶのはよせ。私だって騎士だ」 「はいはい仰せのままに……それで何の用だ白いの」
ふたりの間に挟まれ、ずっと不毛なやり取りに晒されている魔法使いは心底うんざりしたようにかぶりを振った。
「黒の王国の狙いは何だ。なぜ宝を狙う?」
故意か無意識か、生命の石という呼び方を避けたヴェルカンに、黒騎士は鼻を鳴らしてみせた。
「訊いてどうする。事情いかんによっては譲ってくれるのか?」 「馬鹿が。訊いただけだ」 「なら無駄な質問だな」
ここでとうとう魔法使いが声を荒げた。
「お二方とも、子供みたいな口喧嘩しかできないなら少し黙っていただけませんかな!」
一部の隙もない正論ではあったが、険のある口調にいい加減荒んでいたヴェルカンの胸中はさらにささくれ立った。
「魔法使い殿がさっさと宝物を見つけてくだされば、こんな喧嘩もせずに済むのですがね」
魔法使いの眉が音をたてそうな勢いで吊り上ったが、何も言わずに手記に視線を落としたのは年季のなせる業だろうか。その仕草は失言に気付いた身に却って堪えた。 すまない、と謝る声を魔法使いは沈黙で受けた。 事態は思わしくない。難航する探索、黒の騎士との不和が全員の心に影を落とし、そこに暗く重い森の空気が拍車をかける。 有無を言わさず追い返しておけばよかったか――相変わらず鎧で身を固め、面甲で表情を隠した黒騎士を振り返り、思わずため息をついたヴェルカンの態度をどう思ったか、向こうもまた聞こえよがしに鼻を鳴らしてみせたのだった。
「このままでは埒が開きませんな」
翌日、そう言って魔法使いは大きく進路を変えた。木に登り、あたりを見回したヴェルカンからの情報を頼りに、森の真ん中に鎮座する禿山を目指す。これまでとは異なり、明確な目的を感じさせる淀みない歩調にどこへ向かっているのか、と尋ねれば「山です」と実に簡潔かつとりとめのない答えが返ってきた。
「山?山に宝があるのか?」 「そうではありません。見つけてもらうのを待っているのです」
言っている意味がよく分からず、思わず黒騎士を見る。やはり相手も答えを持ち合わせてはいなかったようで、首を振って肩を竦めた。
魔法使いの言葉を理解できたのは、山を目指し始めて早くも次の日だった。 機嫌がいいのか、杖で下草を払いながら鼻歌混じりに歩く魔法使いの背中を眺めていると、数歩後ろを巨馬を牽い��いた黒騎士がさりげなく隣に並び、脇腹を肘でつついた。
「気付いているか」
耳打ちに黙って頷き返す。森中に漂う陰鬱な空気に、これまでとは明らかに異なる新たな気配が加わっている。ちょうど魔法使いが山を目指し始めて間もなく、後をつけてきている者がある。 だがそれがどこから発せられているのか、何者によるものなのかが掴めず、剣に手をかける。
「一、いや二……?」
黒騎士の呟きが聞こえたかのように、魔法使いがふと足を止めた。
「気付いているぞ。私の呼びかけに応じて来たのなら姿を見せよ」
驚いて立ち止まったヴェルカンの右手で、抑えた笑い声が枝葉に反響して消えた。咄嗟に振り向いた黒騎士の背後で木の枝が折れる音が弾けた。 落ち葉を踏む音を引き連れ、巨木の陰から二人の男が歩み出た。それぞれ手にした弓に矢をつがえ、いつでも放てるように引き絞っている。片方は一行の右手、他方は背後に陣取り、互いを射てしまわないようにしている。 およそ見たことのない類の人間だった。黒い髪がかかる浅黒い顔は年齢を感じさせず、小柄な体格と合わせて子供にも見える。纏った長衣は冴えない褐色で、木漏れ日の下では景色に溶け込んでまるで目立たない。 魔法使いが両手を広げ、武器がないことを示した。
「敵意はない。頼みたい仕儀があって来た」
人里を嫌い、文明を嫌い、山や森にひっそりと住まう者たちがいるという。山の精霊を奉じ、畑を耕す代わりに木の実や茸を摘み、牛馬を育てる代わりに山の獣を狩って暮らす彼らは、広く原始的な蛮族と知られていた。とはいえ、ヴェルカンが実際に目にするのは初めてだ。 蛮族の片方、顎髭を伸ばした男が口を開いた。
「ここは里人が来るような場所ではない。何の用向きか?」 「魔法使いと護衛の戦士、てところか。おかしなことを企んでるんじゃないだろうな」
背後に立つ男が敵意を孕んだ声を放つ。こちらは正真正銘の子供らしい。が、脅すような弓の軋みは本物だ。咄嗟に黒騎士と並んで盾を突き出し、壁を作る。黒馬が前脚を高々と撥ね上げ、激しく嘶いた。 魔法使いと顎髭の男が同時に制止の声を発した。続いて声を発したのは顎髭のほう。
「我々を呼んでいたのはあなたらしいな」 「呼んでいた?」
思わず問い返した黒騎士に、魔法使いはちらと目を向けて頷いた。
「念話……魔力に声を乗せ、道々放っていたのです」
相手を定めぬゆえ、受け取ってもらえるかは不安でしたが、と再び顎髭に視線を戻す。
「森に人がいるのは数日前から気付いていた。“声”を放っていたのも。何を言っているかまでは読み取れなかったが……」
魔法に疎いヴェルカンについていける話ではなく、魔法使いたちにしても第三者相手に一から十まで説明する必要を感じなかったらしい。 顎髭が分厚いケープに包まれた肩の力を抜く気配があった。
「里の者、まして魔法使いが我々と接触を持とうとすることはほとんどない。まして頼みごとなど」 「俺たちを蛮族と散々馬鹿にしたお前たちが、なにを企む?」
いまだ警戒しているらしい少年の声は尖ったまま。魔法使いはあくまで顎髭に目を向けたまま、噛んで含めるように穏やかな声で語る。
「このあたりに強い魔力の源があるように思える。何かご存知ではないか」
簡潔な問いに顎髭の目がすっと細まる。少年も思わずといった具合で押し黙った。ややあって再び魔法使いに顔を向けた時には目つきが変わっていた。
「ずっと以前にも同じようなことを言って訪ねてきた者がいた」
この言葉に、魔法使いがわずかに表情を変えた。 よくよく話を聞いてみれば、さかのぼること幾年か、少年――顎髭の息子が乳飲み子だった頃のこと。禿山の中腹にある彼らの村を訪れたその男は、珍奇な話や品々を求めて旅をしていると語り、山の者たちにもそういった事どもを知らぬか尋ねて回った。
森の外からの客は珍しい。はじめは警戒し、遠巻きにしていた村民たちも次第に打ち解け、めいめいが我こそはと思うものを男のところに持ち込んだ。 ある者が山に住む鹿の化け物の話をすれば、別の誰かが古くから伝わる精霊の物語を話して聞かせる。女たちは刺繍の入った服を見せびらかし、子供たちは拾い集めた珍しい木の実や鉱石を差し出す。そのお返しに、男は森の外の世界について話した。 一部を除いて森からは滅多に出ないが、決して頑迷ではない山の民にとって、男の話はいつまで聞いていても飽きない未知の物語。みな時間を見つけては村に逗留している男の庵を訪ねるようになった。
「どうやら例の冒険家らしいな」
やがて男の鞄が品物や記録で一杯になる頃、村の長老は男に『山の心臓』について聞かせた。
遥か連なる山々その真下、厚い岩の骨に守られた地の底に横たわる“力”。天地の精気が混じり合い凝り固まったそれが放つ力の大なること甚だしく、物事のことわりすら歪めるほど。 山の心臓すなわち生命の石のことであろうか。分からぬなりにあたりをつけたヴェルカンは口を挟んだ。
「ことわりを歪める、とは?」 「古老も詳しくは知らぬようだった。幾代の昔より語り伝わる話ゆえ」
動くはずのものを止め、動かざるものさえも動かす力。
その謎めいた言葉に何を見たか、間もなく男は意気揚々と出発し、二度と姿を見せることはなかったという。
「彼があなたらの言う冒険家とやらか、私たちにはわからぬが……」 「山の心臓まで案内してもらえないだろうか」
何の含みもない言いように、魔法使いは隠しだてする必要を感じなかったらしい。
正直に伝えれば、相手もしごくあっさりと頷いた。
「案内だけでよければ」
※
「例の冒険家が山の心臓を取って行っちまったんだろう。もう残っていないんじゃないのか?」
山の民ふたりを加え、幾分賑やかになったおかげだろうか。黒騎士の口から軽口まじりの言葉が転がり出るようになっていた。 魔法使いは宙を見上げて顎を掻いた。
「ひょっとするとそうなのかも知れません。しかし根源を失ったあとの残滓というにはあまりに鮮明な魔力を感じるのですよ」 「だが正確な位置も分からんくらい微弱なものなんだろう?」 「逆です。魔力が強すぎて却って出所が見えんのですな」
眩しい光を見ようとすれば目が眩み、光源は分からなくなってしまうのと同じことだという。魔法使いとしてはもっとも平易な喩えを挙げたつもりなのだろうが、黒騎士はいつになく頼りない調子で「そんなもんかねえ」と唸ったきり。ヴェルカンも早々に理解を諦めていた。
「要は石がまだ残ってるということだな?」
そう結論付けるが、魔法使いは曖昧な笑みを浮かべつつも結局何も言わなかった。
山の民のふたりは実に淀みない足取りで一行を先導した。もつれ合う木々も積み重なる岩礫もなんのその、舗装道路を行くかのごとき軽快さにヴェルカン達がついていけるはずもなく、何度も彼らを呼び止めて休みを乞う羽目になった。 さらに憎たらしいことに、そうして足を止めるたびに顎髭の息子はあからさまに鼻を鳴らしたり小ばかにしたように口元を歪めて見せるのだった。
「あんな蛮族に道案内をまかせて本当に大丈夫なのかよ」
荒い息の下で黒騎士がぼやく。山の民に道を選ぶ心遣いはない。激しく上下する肩当てはこれまで以上の悪路を踏破する間に樹液と埃に塗り固められ、もはや見る影もない。それはヴェルカンも同様だ。
「蛮族、ですか」
魔法使いが髪についた小枝を払い落とすのを、黒騎士は首を傾げて見やった。
「違うのか。字も持たず、畑の耕しかた、家の建て方ひとつ知らん奴らだろう。布きれを張っただけの屋根の下で寝ているとか」 「ですが幼子ですら星の運行から季節を知り、風の匂いから明日の天気を読むすべを知っている。それほどの人間が帝国や王国にはどれほどおりましょうや」 「それだけじゃないぞ。俺なんかこないだこんな大きな猪をしとめたんだぜ」
聞き耳を立てていたらしい少年が両手を広げながら口を挟んだ。それを面倒くさそうにあしらいながら「何が言いたい?」と黒騎士。
「山と森のことで彼らの右に出るものはいないということです」
やり取りを黙って聞いていた顎鬚がここで笑い声を上げた。聞けば、山の民の出というだけで野蛮人のそしりを受けていた身には新鮮な評価だという。
「ことにあなたは魔法協会の人間。我々の目には少々珍しく映ります」 「そういうものでしょうか……」
太い眉毛を下げ、いささか所在無さげに頭を掻く魔法使いの姿に、顎鬚はまたしても笑い声を上げたのだった。
大騒ぎしていると道は短くなるものらしい。ここです、の言葉に目を向ければ、地面にぱっくりと口を開いた裂け目。大きさは人間が数人束になっても楽に通り抜けられそうなほどだが、
「これは知らなきゃ分からんぜ」
黒騎士の言葉ももっともで、目印らしい目印もなく、下草に大部分が隠された洞穴は、一見しただけでは地面の陰としか見えない。むしろ穴と気づかずに踏み抜き、落ちてしまいそうだ。 と、周囲を調べていた魔法使いが太い縄を拾い上げた。一端はすぐそばに刺さった杭に、そしてもう一方は洞穴にまっすぐ伸びている。風雨に洗われ、ほつれているところからかなり古いものと分かる。ほぼ間違いなく件の冒険家が伝って降りて行った跡なのだろう。
「この下はどうなっているんだ?」
火のついた松明を落としてみたが、途中で道が捩れてしまっていて奥までは見通せない。空気はあるようなのだが…… なんとなく尋ねてはみたものの、山の民の親子は顔を見合わせるばかり。彼らも知らないらしい���知り、黒騎士が面甲の下でため息をついた。
「行ってみるしかないのか」 「そのために来たんだろうが。行くぞ」
言いざま、さりげなく後ろに回ってふくらはぎを軽く蹴る。ぎょっとして振り返ったところを、何食わぬ顔で洞穴を指す。憶えてろよ……とでも言いたげな敵意に溢れた一瞥を目出し穴越しによこしたのもつかの間、黒騎士は素直に先に立ち、杭に新しい縄を結び始めた。
「なあ、父さん」
黒騎士の丸まった背中を見下ろしながら、少年が口を開いた。
「おれもこの人たちについてっていい?」
思わず見つめた少年の顔は、あながち冗談を言っている風でもない。とはいえ、楽しい物見遊山というわけではないのだ。確認してみたものの、少年は「それくらいわかってるよ」と眉根にしわを寄せるばかり。意思を曲げるつもりはないようだった。
「なあ、いいだろ。足手まといにはならないからさあ」
半分はヴェルカンたち、もう半分は父に向けて甘えた声を出すが、この小憎らしい少年からこの声が飛び出るのは違和感があった。そしてこの場合、決定権はひとりの大人にある。 首をひねった先で、顎鬚は実に情けない表情を浮かべていた。
*
「本当に何も知らないのか。あんたらにとっては庭みたいなもんじゃないのか」
先導する黒騎士が振り返った拍子に、兜の角飾りが岩肌を擦って埃を散らした。 その視線の先、しんがりをついてくるは顎鬚。彼が言うには、洞穴の存在は山に住むもののほとんどが知っているが、せいぜい子供が入口を探検してみる程度、奥まで探検してみたことはないという。 へえ、と不思議そうな声が岩肌にぶつかってかすかに反響した。宗教的な理由からかとも思ったが、冒険者が探索するのを許したことからそうではなさそうだ。ただ単に放置していただけなのだろう。
「すぐ足元に山の心臓だか何だかが眠ってるってのに、見向きもしないなんてな」
半分呆れた声に、顎鬚は、そういうものでしょうか、と首を傾げた。
「これまで山の心臓などなくともやってこれましたからね。今更掘り返す必要もありますまい」
この言葉に、今度は黒騎士が首を傾げる。
「とんでもないお宝か、もしくはとんでもない危険物かもしれんのだぞ」 「どちらにせよ私たちの手に余ります。そのようなものを探すのは無駄に思えます」 「山の民ってのはみんなそうなのか?」
先頭としんがりのやり取りを黙って聞いていたヴェルカンだったが、ついにこらえ切れなくなって割り込んだ。
「ところで、あなたは族長なんだろう。ついて来たりしてよかったのか」
騎士たちに同行したいと駄々をこねる少年を、土産話を持ち帰るという約束で何とか帰したものの、蓋を開けてみれば当の顎鬚自身は村を統べる長だということが分かったのだ。
「もし何かあっても責任は取れんぞ」 「それよりも万一のことが起こって、あんたの村の連中にあらぬ疑いを持たれるのはごめんだぜ」
それぞれが抱く危惧を率直に述べるも、顎鬚は動じない。
「あの子はああ見えて聡い。私の言葉を皆に正しく伝えてくれましょう」 「そうは言ってもな……」
とにかく無茶だけはせんでくれ。そう言い含めれば、じつにあっけらかんと頷く。
「本当に大丈夫なのでしょうか?」
こっそりと耳打ちしたが、魔法使いはしかし、諦めたように眉を下げて首を振るばかりだった。
*
捻じ曲がった洞窟は次第に広く、なだらかになりつつあった。 さらに顕著な変化が足元から及び始めたことに最初に気付いたのは、先頭を行く黒騎士。
「階段だ」
驚きを露わにした声に一行揃って首を伸ばせば、風化し、崩れて降り積もった土砂に半ば埋まりながらも、明らかに人の手になる段差が松明の灯によって陰の連なりを形作る。 再び進みだした黒騎士の足取りは幾分速くなっていた。そして後に続くヴェルカンたちもまた。どこまでも続く階段を下へ下へ。ほとんど駆け足になり、それでもなお果てぬ階段を降りて降りて、右へ折れ左へ曲がり、足を踏み外しかけてつんのめった勢いすらも利してさらに降りる。 最後はもつれ合い、転げるようにしてたどり着いた先には古びた扉。 逸る心を抑えて息を殺し、耳を押し当ててみるも、扉の向こうからは何の気配も伝わってこない。無言で振り向けば、魔法使いと顎鬚が揃って頷く。 この先に魔力の源があるのだ。
黒騎士が盾を掲げて身を守りつつ、戦鎚で扉を軽く押すと、開いた隙間から光が差し込んできた。
「何が見える?」 「道が見える」 「道だと?」 「きれいな石畳だ……誰もいないがな」
舗装道路など、よほどの大都市の周囲でなければ拝めない。それがこんな人里離れた地下深くに存在するとは。 俄然興味をそそられたヴェルカンは黒騎士の背中をつついた。
扉を開け、その先へと歩を進めた一行は思わず絶句した。 狭い洞窟は扉一枚を隔てて一気に広がっていた。いや、広がるなどという生易しいものではなく、まさに別世界といって差し支えない。振り返ればどこまでも続く絶壁、振り仰げば天井ははるかな高み、散らばる星にも似たきらめきはそこに開いた穴や裂け目で、広大な地下洞窟を薄明の世界に変えていた。埃ひとつない澄み切った空気の中を、はるかな深みにまで届いた光の下、確かに黒騎士が言った通り、道が伸びている。そしてその先には――
初めは天井が崩れてできた岩山と見えた。されど自然の岩礫とするにはあまりに整然たるありさまは明らかに人の手になるもの。目を凝らせばそれが積み重なった家々の集まりであることに気付く。
「地下の町、か……」 「まさか長年住み慣れた地の、すぐ足の下にこんな世界が広がっていたとは……」
魔法使いに追随した顎髭の絶句が、彼の驚きを雄弁に物語っていた。
「こんな場所、どこの文献でも載ってないぜ」
黒騎士も興奮を隠さない様子で眺めやる。
「そして手記が正しければ、ここは死者の国ということになりますな」
ぽつりと呟いたのは魔法使い。一瞬のうちに沈黙した黒騎士が、寸の間をおいて問いかける。
「その死者の国ってのは何なんだ?」 「なにぶん手記全体が謎めいた言い回しで記されておりますゆえ」 「文字通りに解釈すれば滅んだ国ということになるのだろうか」
頭をひねりながら足を運ぶうちに、次第に街の様子が明らかになってきた。道沿いに並ぶ家々はレンガ造りの簡素な作りながら、いずれも二階建て三階建ての大規模なもの、洞窟の中で雨を防ぐ必要がないからか、屋根は平たく、一見すれば整然と巨大な箱が並んでいるようでもある。手前に位置する城壁は高さこそ家々に劣るものの、やはり滑らかな表面は作りの良さを感じさせる。 だがヴェルカンには気付いたことがあった。
「人の気配が全くしないな」 「それだけじゃない、よく見てみろ」
黒騎士が指したのは城壁の前に広がるだだっ広い荒野。 しばし思案を経てヴェルカンは思わず目をぱちくりさせた。 通常、数百からの民が暮らす町の周囲には、彼らの食事を産出するために畑や牧場が広がっているのが常。またそうでなくとも、必要な物資を貯蔵、供給するための施設や市場が立てるざわめきがまるで聞こえてこない。長い時間で失われたのか、もしくは最初からなかったのか……
先帝の館で感じたのと同じ、まがい物じみた匂いを感じたヴェルカンは鼻を鳴らした。
「まあ、見えない場所にあるだけかもしれんしな。町の向こう側にあるのかもしれん」
誰に言い聞かせるでもなくつぶやいてみる。
*
道路を辿って城門にたどり着くまでには幾分時間を要した。
「信じられるか。これで地面の下なんだぞ。あんたの家もこの上にあるんじゃないか」
黒騎士が冗談交じりに肘で突けば、いまだ圧倒されているらしい顎鬚は相変わらず口をぽかんとあけたまま生返事。 敵ながら意外と気さくな奴なんだろうか――こんな場所だからだろうか、ヴェルカンはふとそんなことを感じた。
ところが、そんなささやかな感慨は城門の下にあったものを見た途端、吹っ飛んでしまった。 危険はないとわかってはいても、こういう時にこういうものを遠巻きにしてしまうのは人の性なのだろうか。 古びた兜の下に覗くは遙か昔に血肉削げ落ち、年月に洗われた白いしゃれこうべ。よく磨かれた甲冑に身を包んだまま壁にもたれかかり、俯いている姿は戦いで死んだというよりは居眠りでもしているように見える。
「人身御供か……?」
遙かな太古、国の統治者や王は、自らの亡骸とともに莫大な財宝、そして数多の召使いや兵士を生きたまま葬ったという。死を現世における消滅であり、同時に異界における転生であるとする考えが、死後も権勢を保とうとするいにしえの権力者にそのような行為をさせ、またそうすることが当たり前の世界だったのだ。
「まさか町ごと葬ったのか…… 」
呟いたヴェルカンが青銅の肩当てに手を置いたその次の瞬間、兵士の骸骨が大きく傾いだ。 まずい!と咄嗟に支えようと突き出した手は空を掻いた。びくりと跳ねた骸骨が自ら体勢を立て直したからだ。 呆気に取られて見つめる目の前で、骸骨はわずかに傾いた姿勢のまま、空っぽの眼窩で二度三度とあたりを見回し、最後に目と鼻の先にあるヴェルカンに顔を向けたまま固まってしまった。
突然叩き起こされて驚いているようにも見えるな――
人骨の、どこか滑稽な仕草にそんな感慨が浮かんだのもつかの間、かたりと音を立てて髑髏の口が開いた。 次の瞬間、骸骨が絶叫したようにヴェルカンたちには感じられた。喉も舌もない口からは何の音も発せず、一切の静寂なれど、確かに吠えた。 黒騎士とふたり、飛び退いて槍を拾い上げた先で、骸骨の兵士が一歩進み出た。その手には青銅の片刃剣。驚くほど手入れの行き届いた刀身が黄金色の光を放つ。 逃げるか、戦うか。束の間浮かんだ思案は、四対一という状況にあっさり片付き、ヴェルカンは黒騎士に目配せすると、自身はゆっくりと骸骨の右手に回り込んだ。 骸骨が壁に背を預けるように立っているのは挟撃を防ぐため、楕円盾を掲げているのは黒騎士の背後から狙いを定める顎鬚の矢を防ぐためだろう。 初めに仕掛けたのは黒騎士だった。ときの声も高らかに戦槌を振り下ろす。切っ先が銅板張りの盾に食い込んだ瞬間、ヴェルカンが左手から強襲した。 右から迫る黒騎士に盾を向けた隙に、がら空きになった左半身を突く。ことのほかうまく運んだ即興の作戦は、槍の穂先が敵の脇腹に届いた時、初めて躓いた。 人間の上半身を模したような意匠の胸当ての隙間を狙って放った槍越しに届いたのは肉を切り裂く濡れた感触ではなく、なんともうつろな感触。よく考えてみれば相手の甲冑の下にはあばらと背骨があるばかり、腹を突いたところで手応えがないのも無理はない。 そればかりか、敵はむしろ槍を己が腹に深く食い込ませる形で距離を詰めてきた。青銅剣の刃先がとっさにのけ反った兜の目庇をかすめ、鋼の擦れ合う音がヴェルカンの心臓を震わせた。
「死なないぞこいつ!」 「最初から死んでるんだから当たり前だろ!」 「そもそも死人は動かん!」
言い合う間にも骸骨は狂ったように打ちかかってくる。自らが傷つくことをまるで恐れていない戦いぶりに、さしものヴェルカンたちも押され気味。死体が動き、襲いかかってくるという異常事態にようやく頭が追いついてきたというのもある。これまで戦ってきた数多の誰とも異なる相手だった。 大慌てで槍を引き抜こうとしたヴェルカンだったが、骸骨は刺さったままの槍の柄を握りしめ、逆に引き寄せようとする。 と、黒騎士が再び戦鎚を振りかぶった。ヴェルカンにかかりきりでがら空きになっていた兜をすくい上げる一撃が直撃し、頭部もろとも高々と打ち上げる。石畳に落ちた兜がけたたましい音を響かせると同時、首から上を失った骸骨が力なく崩れ落ちた。 今更のように噴き出した汗を拭う隣で、黒騎士が今は形を失った骸骨を戦鎚で軽く突く。
「首を落とすのは正解だったな」
少なくとも倒せることはわかった。これは大きな前進と言えた。とりわけ――
振り返った先、開かれた門の向こうから、次から次へと骸骨兵士が湧き出してくる。それらは門を塞ぐように一列に並ぶと、一斉に盾を突きだし、即席の壁をなした。さらに隊列の両端を構成する骸骨たちが鎧をがちゃつかせながら歩み出し、隊列全体がひとつの生き物のごとくヴェルカンたちを包み込もうとする。
「勝てると思うか?」
足を踏みしめ、大盾に身を押しつけて構える黒騎士を横目に、誰にともなく呟く。骸骨たちはどれもまるで同じ顔、白く洗われた顔面に一切の表情はなく、一言の声すら上げることはない。その異形はしかしながら、どれもがかつては命ある人であったはずなのだ。 皮一枚失うだけでこうも変ずるものなのか。そんな己の想念に思わず身震いが走る。
ふと盗み見た黒騎士はあくまで冷静だった。もしくは鎧と血肉の下に巧妙に動揺を隠しているのか。 その姿を見ているうちに、己も平静を取り戻したヴェルカンは、槍を投げ捨てると腰の剣を抜き放った。混戦になれば長い槍はかえって邪魔になる。
「降伏が通じる相手に見えるか?」 「……だな」
その一言を皮切りにふたりは戦端を開いた。咄嗟に右端に狙いを定めたヴェルカンの左に立つ黒騎士が大盾を掲げ、他からの攻撃を一手に引き受ける。その間に目標の骸骨に体ごとぶつかるようにして動きを封じつつ隊列から押し出し、体勢を整える暇を与えずに横っ面に肘打ち。板金同士が散らす火花を顔に浴びつつ、大きく傾いだ兜に盾の縁を叩きつける。下顎を失った敵がもんどりうって倒れたときには、黒騎士も正面の骸骨の右手を打ち落としていた。
「もたもたすんな!まだいるんだぞ!」
わかってるよ!と怒鳴り返しざま、黒騎士の背後に滑り込み、新手の斬撃を受け止める。狭まりつつある包囲網、攻撃はますます苛烈になっている。身を低くした姿勢のまま足払いを繰り出し、転んだところに剣を突き立て、腰骨を切り離す。敵が動かなくなるのを確認する間もなく、身をよじって飛んできた突きを躱す。 額に流れてきた汗を拭うことも叶わず、目を瞬く。その合間にも背後から繰り出された青銅剣を斜に構えた盾で受け流し、手首もろとも切り落とす。 それにしても、とすぐそばで骸骨兵士相手に切り結ぶ黒騎士を視界に入れる。いかにも重そうな戦鎚と、身の丈ほどある大盾を振り回し、並み居る敵をねじ伏せていく姿に舌を巻く。が、そんな感慨はその向こうで繰り広げられる光景を目にした途端、吹っ飛んでしまった。 頭を失い、動かなくなった骸骨に、隊列から離れた他の一体が歩み寄った。ほど近くに落ちていた兜に包まれたままの頭蓋骨を拾い上げると、倒れた兵士の首元に置き直す。 と、倒れたはずの骸骨がかたかたと震えたかと思うと、頭を押さえて起き上がった。具合を確かめるように首をひねると、次の瞬間には剣を振り上げて向かってくる。 よく見ればあちこちで同様の光景が繰り広げられていた。手を失ったものは手を、足を失ったものは足を正しい位置に戻せば、たちどころに元通りになってしまうのだ。
「嘘だろ……!」
黒騎士が苦悶の声を上げた。敵は頭数だけなら十人と少し、だが実質的な戦力は底がないということだ。それをわずかふたりでしのぐのはいくらなんでも無理がある。それこそ魔法の所業でもなければ……
「あんたらも何とかしろ!」
不思議と静かな魔法使いたちを振り返ったヴェルカンは絶句した。 棒立ちのまま沈黙する魔法使い、その喉元には黄金色の刃。細身の体に巻きつき、締め付けるは白骨の指。口を塞がれながらも、生ある者の目は驚愕と恐怖、そして多少の申し訳なさを伝えてくる。顎鬚はといえばいち早く逃げたのか姿はない。 呆気に取られ、束の間戦いを忘れて武器を下げたヴェルカンたちを中心に瞬く間に包囲が築かれる。青銅の切っ先が喉に胸に脚に擬されるが、いずれも攻撃してくる様子はない。 黒騎士とふたり、恐る恐る顔を見合わせる。
「……降伏が通じる相手だと思うか?」 「……わからん」
言いながらも黒騎士はさっさと戦鎚と盾を投げ捨て、両手を広げて見せた。ヴェルカンも盾を地に置き、剣を捨て――ようとしたのも束の間、腰に鞘に収めると、留め紐をきつく結んで黒騎士と同じように手を上げた。 直後、待っていたように背後から目隠しを打たれ、腰の剣をむしり取られる感触があった。全身に骨の手が絡み付き、動きを封じる。
少なくとも降伏は通じるらしい――
半ばもみくちゃにされ、引きずられ、やけくそのようにそんなことを考えていたヴェルカンだった。
0 notes
Text
白騎士の冒険 魔宮の秘宝 始
「何、先帝閣下が?」
はるばる帝都からの使者がヴェルカンの城を訪ねたのは、風が実りも間近の青々しい香を運んでくる頃。
「はい、是非とも『巨人突き』の力を借りたい件がある、と」
その渾名を耳にした瞬間、ヴェルカンの眉根に微かに皺が寄ったことに使者は気付かなかったらしい。 先帝閣下からです、と差し出された手紙には目玉模様の封印。まごうことなき皇家からの書状と知った途端、手紙はにわかに重みを増し、ヴェルカンにのしかかるようだった。
使者を客室に通し、老使用人たちがもてなしている間、ヴェルカンと衛兵隊長は執務室で書簡を前に唸っていた。難解かつ迂遠な表現で飾られた文面はヴェルカンには多くは理解できなかったが、つまるところ現皇帝の父祖たる先帝が何らかの問題の解決をヴェルカンに要請したいと考えており、詳細を伝える為にもいちど居城を訪ねてほしい、というような具合だった。
「白の騎士という立場からすれば、ようやくそれらしい任務を賜る機会が巡ってきたわけですな」
そう言うのは衛兵隊長。白の騎士は皇帝直属の戦士であり、その縁者からの要請とあらば命に代えても達するのが務めではある。
「先帝というと、陛下の父君であらせられるのか」 「母君やもしれませぬ」 「というと?」 「陛下は皇帝位にあられる間は他の何者でもないからです」
男でもなく女でもなく、若人でもなく老人でもなく、親でもなく子でもない。ただ皇帝とのみ呼ばれる絶対権力は、血筋にその位を継がせた時、初めて人に戻れるのだという。
「現陛下のご即位は、確か三年ほど前でしたかな」 「最近の事なのにえらく曖昧だな」 「何せ報せがないので。風の噂であらましを知るのがせいぜいです」 「黒の王国では、大王に選出された君主は大々的な祝賀会を催すと聞くが」
ヴェルカンが隣国の名を挙げると、衛兵隊長は頷いた。
「それに婚儀や誕生日もね」
権力者が自らを誇示するのはどの国も行っていることで、そうすることよって尊敬と権威を維持しているのだ。そしてまた、行き過ぎた示威行為が災いして身を滅ぼした権力者も歴史上数多い。
「そう考えると陛下は随分慎ましいお方なのだな」 「むしろ何もかもを隠そうとしているようにすら思えます」
白の帝国という巨大国家の、正真正銘純粋なる心臓。そこに名や顔といった、生身の人間を示す要素の入り込む余地はないのかもしれない。 以前��謁した、一部の隙もないほどに全身を飾り立てた小柄を思い出したヴェルカンは、その重みを想像して唸った。
*
先帝の住まいは帝都からいくぶん東に外れた丘の上にてんと建つ、じつに慎ましい屋敷だった。 一応、元は皇帝だったのだからもう少し豪奢な暮らしぶりでもよさそうに思えるが、上品でこそあれ質素な作りの館には衛兵の姿もない。聞くところによればこの館が先帝の住まいだと知る者もほとんどいないという。 案内の使者は先に帰ってしまい、仕方なくヴェルカンはひとり鉄格子の門を叩いた。 屋敷の者が現れて用向きを尋ね、門を開けてくれるまでにどれほどの時間がかかるのか。そんなことを考え始めるより早く、門が軋みながら内側に開き始め、びっくりする。 さては門扉の陰に人でも忍ばせていたのかと回り込んで見たものの、それらしい気配はなく、また門柱にも特別な仕掛けはなさそうだ。 ひとしきり首をひねったヴェルカンは、この問題を一時棚上げし、先帝のもとに急ぐことにした。
門から本館までは四季折々の草花が植えられた庭園になっていた。見慣れた野菜や薬草に混ざって、書物でしか見たことがない海を越えた異国の花や、厳しい冬の寒さでしか育たない薬草が植えられ、どんな仕掛けなのかそのどれもがよく育ち、たわわに実を結んでいる。 さぞ腕の良い庭師がいるのだろうが、それらしい姿は見当たらず、ヴェルカンはまたも首を捻った。 と、ごろごろと音を立て、滑るように近づいてきたものがあった。思わず身をよけたヴェルカンのすぐそばで停まったそれは、何の変哲もない、彫刻が施された石造りのアーチ。ただし、ひとりでに走るアーチなど聞いたこともなかったが。 ヴェルカンが見ている前で、アーチのてっぺんから彫刻の一部と見えた石の腕が伸びると、その指先から水が噴き出し、緑の葉を濡らしていく。見回してみてもアーチを操作する人影は見当たらない。
「ひとりでに水やりを行う装置か……」
故郷では聞いたこともない機械に思わず唸る。流石は帝都のお膝元といったところか。
重く厚い玄関扉もヴェルカンが叩くより早く内側に開いた。やはり動かしている人の姿はない。 帝国の多くの城がそうであるように、、玄関の向こうはそのまま大広間になっていた。石の上から真っ白な漆喰で塗り固めた壁はよく清められ、上品な壁掛けも絨毯も新品同然、磨き上げられた燭台はまさに顔が映るほど。隠居の身とはいえ、ヴェルカンからすれば十分すぎるほど絢爛豪華な住まいぶりに思わずため息が漏れる。
しかし、この人気のなさはなんだろう。どの調度も綺麗というよりは人の手が触れた形跡自体がほとんど見られず、空気にも大勢の人間が暮らす城に特有の匂いが感じられない。 かつてある貴族に見せてもらった人形の家を思い出す。豆粒ほどの大きさながらも本物さながらに作られた家具も壮麗な装飾の数々も、いずれもただそこにあるだけ。誰にも使われることなく、それらしさを演出するためだけの無用の長物。寒々しいまがい物――――
「ヴェルカン様ですね。お待ち申し上げておりました」
いつからいたのか、二階へと続く階段の中ほどに侍女らしき婦人が立ち、見下ろしていた。 不躾に見回していたことも見られていたのかと頬が熱くなる。
「これは失敬――」
頭を掻くヴェルカンの前に、女性は足音ひとつ立てず、滑るような滑らかさでに階段を下りてくると、優雅な仕草で腰を折った。
「皇帝直属精鋭騎士、ヴェルカン様ですね」 「主君の求めに応じ、馳せ参じました。ヴェルカン卿であります……」
同じく下げた頭を上げると、侍女の整った顔が鼻先が触れそうな位置にあり、思わずのけぞる。 その肌質のなんと硬いこと。それもそのはず、侍女の肌は白く塗られてこそいるものの、まごうことなき木でできていた。何か話すたびに頬に裂け目が走り、紅をさした唇が開く様子は奇怪そのもの。 ――彼女、いやこれは人間なのか?
「主人がお待ちです。剣をこちらへ」
唖然としている客人の様子など気にも留めず、節々に甲冑の継ぎ目を思わせる筋の入った手が伸びてきて促す。 得体の知れない場所で得体の知れない相手に武器を預けるのは不安だったが、ここは皇帝家の館だと己に言い聞かせ、強引に納得する。 触れた手はやはり木の硬さと冷たさを伝え、身構えていても何とも言えない違和感に駆られた。
*
かつての皇帝というからには老人を想像していたヴェルカンだったが、通された私室で出会った先帝はまだかなり若い、壮年といっても差し支えのない痩身の男だった。
「噂はかねがね聞いている。いちど会ってみたいと思っていた」
跪き、床に視線を落とすヴェルカンに歩み寄ると、顔を上げるように促す。
「堅苦しいのは無しだ。君と僕の仲だろう」
思いがけない言葉に思わず顔を上げる。 大帝国の頂点にあり、ましてこんな怪しげな館に住んでいるとは思えないほど人懐っこく、溌剌とした若さすら感じられる顔立ちは、言われてみればなるほど確かに見覚えがあるような気がする。しかしどこであったか…… 悩むヴェルカンを見下ろし、若き先帝はいたずらっぽい笑みを浮かべた。
「僕の犬の事は忘れてしまったか?」
その言葉、声、言い方。一瞬の後、降り積もった記憶の深みからある場面が急速に浮かび上がってきた。 まだ西の湿地領主の下で小間使いとして仕えていた時代。領主の狩りに同行した貴族の中に、ヴェルカンに猟犬をけしかけた男がいた。 記憶にある顔と目の前の顔が重なった瞬間、脳裏を稲妻が奔った。
「驚いたか」
驚愕と混乱にかき乱された頭はろくな言葉を紡ぎ出せず、むなしく口をぱくぱくさせるヴェルカンを、かつて彼を殺しかけた青年貴族は心底楽しそうに見つめた。
「い、犬の件は、まことに申し訳ありませんでした……!」
真っ先に思い付いたことを口にする。再び頭を下げた騎士の肩を先帝は叩いた。
「あの時は一歩間違えれば君が死んでいた。こちらこそ、本当にすまなかった」
そう言うや、先帝は深々と頭を下げた。主君に謝罪されたとあってはヴェルカンも頭を上げられず、かくしてふたりして頭を下げ合うという間抜けな光景が繰り広げられた。もっとも、それを見ていたのは木でできた不気味な侍女だけだったが。
「僕は別にあの男の縁者というわけではない」
あの男、というのは西の湿地領主の事だ。曰く、病弱故に早逝した先々代皇帝の後を継ぎ、当時すでに皇帝の身であった彼は、領主の親族を偽り、お忍びで貴族の狩猟に参加していたのだという。
「演技とはいえ、皇帝たる僕を本気で怒鳴りつけたのだから奴も相当な役者だよ」 「なにゆえ、自分に犬を?」
新しく事実を知るごとに新しく疑問が湧いてくる。不躾に質問をぶつける非礼にも気付かない騎士に、先帝はちょっとバツが悪そうに頭を掻いた。
「つい羽目を外してしまった。本当に愚かだったよ」
心底申し訳なさそうな声。しかしヴェルカンは内心で首をひねった。ついさっき出会ったばかりではあるが、目の前の男は気まぐれで人を殺しかけるような人物に見えなかった。 しかしながら自身の眼識に絶対の自信があるわけでなし、ひとまずは納得する他なかった。
本題に入る前に、先帝は侍女に葡萄酒を持たせた。盃に酒を注ぐ楚々とした仕草は木彫りの人形とは思えないほど滑らかだ。 先帝は侍女の整った顔を見上げた。
「君を呼んだのは助けてほしいからだ。僕と、彼女たちの命を」
このような場には何とも物騒な言葉に、盃に口をつけた手が一瞬止まった。
「命を、でありますか?」
葡萄酒は程よい酸味と甘み、芳醇な香りを備え、ヴェルカンの舌にも高級な品だとわかる。それを先帝がこともなげに飲み干せば、待っていましたとばかりに侍女がお代わりを注ぐ。
「僕は先代の病弱の血を引いてしまったらしくてね。だからこの年で皇帝の座を次代に譲って、こんな場所で隠棲しているというわけさ」
親や子ではなく、先代、次代という無味乾燥な呼び方は人ならぬ皇帝であった頃の名残であろうか。 本来いつ死んでもおかしくない体であった先帝が健康を得られたのには秘密がある。
「学者どもは生命の石と呼んでいた」
長らく本来の用途では使われていないらしい鎧櫃から取り出されたのは、ひと抱えはあろうかという青黒く透き通った石。先帝の手の中で、それは微かに淡い光を放っていた。 遡ること十年前、病床で苦しんでいた先帝――当時の皇帝のもとに、ひとりの冒険家の手によってその石は持ち込まれた。 手元に置いておけば体に活力がみなぎってくる。そんな冒険者の言うとおりにしてみたところ、身を起こすのがやっとだった皇帝はひと月と経たぬ間に寝所を飛び出して馬を駆り、お忍びで貴族の狩猟に同行できるまでになった。 とはいえ皇帝としての激務に耐えられるほどではなく、世継ぎが充分に成長するのを見計らって皇帝は一線を退き、先帝となって隠棲したが、その後も生命の石のおかげで体調はすこぶる良いという。
「なんでも一種の魔力が込められているのだとか」
石から滲み出る力は生き物の体に活力を与え、それは館の周りの草木を年中枯れることなく茂らせるほど。
「そしてまた、彼女たちの命の源でもある」
そう示すのは隣に控えた木でできた侍女。ぺこりと頭を下げる仕草は人間そのものなのだが、それが却って違和感と不気味さを醸し出す。
「魔法人形を見るのは初めてかな。学者どもが僕のお守に作ったものだ」
込められた高度な魔法によって作動する、生きた人形たち。この館に先帝以外の人間はおらず、門扉の開閉から庭園の世話、身���回りの世話といった一切の雑事は大小さまざまな人形たちが行っているという。 食事も休む必要もなく、命令に忠実に働き続ける完璧な使用人たちだということだが、ヴェルカンはなぜか好きになれなかった。 そんな内心を見抜いたのか、先帝は苦笑顔。
「気持ち悪い、信用ならないと思う者も多いようだな。長く付き合っていると実に良いやつらなのだが」
だが最近、石の輝きが薄れてきているようなのだ、と先帝は語った。込められた魔力が時とともに滲み出るうちに尽きかけているのだという。魔力が完全に枯渇すれば、先帝はおそらくたちまち体調を損ない、動力を館に安置された生命の石に頼っている魔法人形たちも遠からず機能停止するだろう、ということだった。
ヴェルカンの任務はわずかな手がかりを残してすでに他界している冒険家に代わって、新たな生命の石か、それに代わる何かを手に入れることだ。 ひとしきりの説明を終えたのち、先帝は、君だけが頼りだ、と頭を下げた。 長く険しい道のりになるだろう。行く先に何が待ち受けているかもわからない秘宝探求の旅路。 だが、皇帝とその縁者に仕え、その使命を全うするのが白の騎士の務め。ヴェルカンは躊躇うことなく膝をついた。
「主君の望みとあらば、この命に代えましても」 「君ならそう言ってくれると思っていた。助力は惜しまない」
しかしヴェルカンは改めて先帝の置かれている状況に思いを馳せた。帝国中の畏敬を集めていた皇帝の時代から一転、歴史から忘れられ、うすら寒い館で人形たちに囲まれてたったひとり。
「寂しくはないのですか」
自然と疑問が口をついていた。先帝は一瞬呆気に取られたように目を見開いたが、すぐにやんわりとほほ笑んだ。
「僕も人形たちも、本来ないはずの命を永らえている点では同じ。そう思えば何ということはない」
そういう考え方もあるのかもしれない。しかし、
「やはり寂しいですよ、それは」
思わず口にしたが、先帝は聞こえなかったように、それから、と付け加えた。
「黒の王国の者には気をつけるんだ」
突然飛び出た隣国の名に戸惑う。これまでとは打って変わって先帝は厳しい表情を浮かべた。
「噂ではあるのだが、かの国の者も魔法の石を探していると聞く。是が非でも先を越されてはならん。必要とあらばどんな手も惜しむな」
その瞬間は権力の頂点にあった威厳で締めくくった細面に、ヴェルカンはただ頷くことしかできなかった。
*
先帝はヴェルカンにまずは“街”に向かうように命じた。そこで協力者が待っているというのだ。 その言葉に従い、領地で旅支度を整えたヴェルカンは宿を転々としながら西の方角を目指して馬を進めた。
かつて何度も覇権を争い、しのぎを削った白の帝国と黒の王国。両国が競って建造しては打ち壊された見張り塔や砦の残骸が列成す国境線に沿って北上すること二日ばかり。やがて丘の向こうに尖塔が小さく見え始め、程なく円形の城壁に囲まれた都市国家に姿を変えた。 城壁沿いに張り巡らされた濠を迂回して北の正門をくぐれば、そこは活気溢れる商業地区。各地のあらゆる品を商う店が所狭しと敷き詰められ、わずかな隙間を買い物客と商人と衛兵、さらに冷やかしにならず者とあらゆる人種が埋め尽くす。それらが発する喧噪は領地ののどかな田園風景に慣れきった身には少々厳しく、ヴェルカンは人波に揉まれるようにしてどうにか近くの酒場に滑り込んだ。
手近な席にへたり込むと、息をつく暇も与えずに亭主が注文を尋ねてくる。ややうんざりしながら葡萄酒を求め、ようやくひと息つくことができた。そう思った矢先、円卓の向かいに腰を下ろした者があった。 席をお間違えでは、と言おうとするより早く、相手が頭巾を取った。
「白の帝国のヴェルカン殿ですな」
その声、その顔立ちに、ヴェルカンは目を丸くした。
「え、衛兵隊長!?」
思わず頓狂な声を上げてしまったヴェルカンを眺め、家臣にそっくりな男は軽く笑った。
「あなたの事は兄から常々聞いております」 「兄だと」 「ひょっとすると弟かもしれませぬ……双子でして。両親ですら見分けがつかない」
重ねて問おうとする機先を制するように衛兵隊長似の男が説明してくれた。 言われてみれば短く刈り込んだ鈍色の髪を後ろに撫でつけている衛兵隊長に対し、男は鈍色の髪を長く伸ばし、襟元で束ねている。また着ているものも衛兵隊長の趣味とは異なる豪奢なマント。しかし逆に言えば、異なるのはそれくらいのもので、ヴェルカンはいささか混乱した。 男は街の南にある魔法協会の支部に勤めていると言った。魔法には疎いヴェルカンもその名は聞いたことがあった。世界中の魔法使いの互助会のようなもので、白の帝国領内にも無数の拠点を有する一大機関だ。魔法の品絡みの任務ということで先帝が協力を仰いだのだろう。
「協会も生命の石には多大な関心を寄せておりましてな。まして帝国の大貴族からの依頼とあれば熱も入ります」
例のごとく身分を偽った先帝から莫大な報酬と命の石に関する権限、そして『巨人突き』のヴェルカンの派遣が約束され、かくして魔法協会は調査に乗り出すことになったというわけだった。
やがて料理が運ばれてきた。白の帝国では見たことのない色鮮やかな豆は、遠い異国の地からはるばる運ばれてきたものであるという。
「大陸のちょうど中央に位置するこの街には様々な地の品が流れ込み、流通の中心となっておるわけです」
自身は魚料理に舌鼓を打ちながら、魔法使いは、便利な街です、と語った。その顔をしばらく眺めていたヴェルカンは口火を切った。 そもそも生命の石とは何か。 単刀直入に問えば、魔法使いは少々バツが悪そうに頭を掻いた。
「実は、多くは分かっておらんのです」
膨大な魔力を封じた鉱石であることは間違いない。器物に魔力を封入し、必要に応じて取り出す技術ははるか昔から存在するものの、何人もの優秀な魔法使いが全魔力をつぎ込んでも敵わないほどの膨大な魔力を収める業はいかなるものか。 長々と説明しようとする魔法使いを遮って、ヴェルカンは腕組みをした。
「どこに行けば手に入るんだ?」 「なんともさっぱりした尋ねようですな」
特に気を悪くした様子もなく、魔法使いは鞄から一冊の古びた書物を取り出した。聞けば、かの冒険家の手記であるという。
「手に入れるのはずいぶん骨でした」
めくれば、精緻な挿絵と解説で埋め尽くされた紙面が次々に展開する。 この手記に残された手がかりから、魔法協会は件の石が街の北にある馬蹄型の山脈、その麓に広がる森に隠されているのではないか、と読んでいる。
「冒険家によれば、そこには歴史に残されていない国があるとか ――なんでも、死者が闊歩する呪われた王国であるそうな」 「死者の王国……」
しかし魔法協会が過去に派遣した調査隊はそれらしい痕跡を発見できなかった。 手記にあった不吉な文句は何らかの謎かけであろうか。
「あの山には強い魔力の痕跡が存在します。何かがあるのは間違いありません。おそらく厳重に隠されておるのでしょう」 「魔法使いたちが見つけられなかったものを、私が見つけられるのでしょうか」
いつしか料理はすっかり冷めていたが、まるで気にならなかった。
「まあ、一切の手がかりがないわけでもなし。やるだけやってみましょう」
眉を下げた表情も衛兵隊長にそっくりだ。なんの脈絡もなくヴェルカンは思った。
*
街は帝国領ではないが、帝国の経済網は深く食い込んでいる。帝国民向けの銀行から引き出した路銀で野宿の準備を整えたヴェルカンと魔法使いはさっそく出立した。
舗装道路はいくらもせぬ内に途切れたが、件の山はまだ遠い。蹄が土を噛むごとに馬の背に下げた盾と鎧が虚ろな音を立てる。 道中、青く霞んだ岩山を視界に収めながら、ヴェルカンは黒の王国について尋ねてみた。 が、魔法使いは首を振るばかり。曰く、魔法協会が石の事を外部に漏らしたことはないという。
「とはいえ、冒険家が黒の王国にも売り込んでいたことは充分考えられます」 「しかし、彼が亡くなって久しい。なぜ今なんだ?まるで――」
先帝が探し始めるのを待っていたかのようだ。言いかけて慌てて口を噤む。幸い魔法使いは気付かなかったらしく、難しい顔で唸る。
「こたびの探索、一筋縄ではいきそうもありませんな」 「それは最初から分かっていたことでありましょう」
まあ、それもそうですね。そう言って眉を下げた魔法使いは、目の前の山を指して話題を変えた。
「あの禿山。はるか昔に人間と神々の大戦があったといわれのある山でしてな」 「お山の戦ですか」
思わず即答すれば、魔法使いは目を丸くした。ご存知でしたか、と感嘆も露わに重ねてくるのを生返事で躱す。山に住んでいたという巨人の記憶はまだ新しい。
「なんでも、あの山には数多の神々や精霊、魔物が住みついていたそうです」
戦の後、その数を大きく減じながらも、現在でも数多の怪異が現れる地であるという。
「あるいは、そういった魔性や不思議のものを引き寄せる場所なのやもしれませぬなあ」 「そういう場所があるのですか」 「逆に不思議を生み出す場所やも。そのような“力”の集まる地はこの世界の多くの場所に存在します」
街に東西通津浦々の物品と人々が集まるように、力が集まるところがある。 そうして寄り集まった力の結晶が生命の石ではないか、と魔法使いは推測している。 そのような場所にふたりだけで乗り込んで大丈夫なのか。さすがに多少の不安を覚えたが、弱腰と受け取られては面白くないので黙っておいた。
*
他の多くの森がそうであるように、山の麓に広がる森もまた地面に線でも引いたかのごとくある一点から唐突に始まっていた。ただひとつ、他の森と異なる点はその木々の密度。みっしりと生い茂り、互いに枝葉を絡ませるはいずれ劣らぬ齢重ねた大樹。頭上に十重二十重と覆いかぶさる葉は厚く、まだ日の高い刻限であるにもかかわらず暗い影を森中に落とす。 道らしい道もなく、足元���這い回る根と重く濃い空気が馬の脚を絡め、鈍らせた。早々に馬に乗るのを諦め、放したふたりは荷物を背負い、ため息をついた。
「口が減って良かったではないですか」
魔法使いの冗談はヴェルカンの耳にも強がりと聞こえた。馬は動物の勘で帰り道を見つけだす。こんな深い森の中で当てもなく歩き回り、もし首尾よく命の石を見つけだしたところで帰りはどうするのか。不安ばかりが募るが、これも先帝の命と気を引き締める。 皇帝には奴隷だった己を騎士に取り立ててもらった恩がある。その親族が望みとあらば何が何でも成し遂げるつもりだった。 と、己に言い聞かせてみたところで、やはりではどうするのかという不安はある。ヴェルカンはまたしてもため息をついたのだった。
木々が夕日を遮る森の日暮れは早い。ヴェルカンたちはわずかな空き地を見つけると腰を下ろし、慣れない悪路で酷使した足を休めることにした。 魔法使いは僅かな残照を頼りに、拾った木切れと、別の木切れを擦り合わせる方法で火をつけた。
「魔法で火を点けることはできないのですか?」
意外な光景に思わず問うと、魔法使いは苦笑を浮かべた。
「できなくはないですよ。ただ、こちらのほうが楽なんですな」
魔法の行使には多大な集中力と魔力を要する���より手軽な方法があるならそちらを用いたほうが手際がよい。 そういうものか……と失望を隠せない声を上げてしまったヴェルカンに、魔法使いの苦笑が深くなる。
「魔法の研究もまだまだ途上でありますれば」
なればこそ生命の石の秘密を解明し、さらなる発展の一助とする魔法協会。先帝の健康を望む白の帝国。そして目的はわからないが生命の石を狙う黒の王国。さまざまな思いが絡み合い、さながら魔力を引き寄せるがごとくヴェルカン達をこの地に引き寄せたわけだ。
堅焼きパンを水で流し込んだが、疲れているせいか却って食欲が出ない。食料が節約できて好都合だと良い方向に考えることにする。
「こうも豊かな森なら、片っ端から伐り倒していけば立派な城がいくつもできそうですなあ」
しかし実際は木こり小屋のひとつも見当たらないのは、この森の暗く重い空気を恐れてか。見上げた枝葉の間から何かがこちらを窺っている気がする。焚き火の灯の届かない暗がりからいくつもの目が覗いている気がする。 魔法使いから聞いた話のせいか、あらぬ妄想ばかりが膨らむ。 なかば強がりで横になってみたが、眠気はなかなか訪れなかった。
*
次の日、ヴェルカン達はまだ暗いうちから探索を開始した。とはいえ、森の外は既に日も高い刻限だったかもしれない。いずれ、外界から隔絶されたような森の中では知るすべはなく、また知る必要もなかった。 どこまで行っても同じような景色、同じような匂い。森を歩くすべを知らぬヴェルカンの代わりに頼れるのは手記とにらめっこをしながら先を歩く魔法使いの足取りばかり。それにしても時折足を止めたりだしぬけに方角を変えたり、いささか危なっかしい。 ふと、ヴェルカンは遥か昔、痩せて小柄な貧農の子だった時のことを思い出した。両親の手で売り飛ばされ、人買いと共に旅をした幾日か。どこに行くのか、己がどうなるのかすら知るすべもなく、ただ諾々と目の前の巨大な背中について行くほかなかった日々。むろん、魔法使いには人買いのような悪意は当然ないが、それでもあまりよく知らない相手に自身の道行きも委ねる所在なさを久々に思いだし、思わず木漏れ日差し込む頭上を仰ぐヴェルカンだった。
変化が訪れたのは実りのない探索行が三日を数えた頃。相手に気取られるより先にそれを見出したのは僥倖というほかなかった。 ごつ、ごつ、と音を立てて木の根を噛むは並のひと回りは幅広い蹄、その上に揺れるは並のふた回りは太い骨ばった脚。鼻息は洞穴を抜ける風の唸りにも似て、そのたびに筋肉の塊のごとき真っ黒な胴が大きく伸縮する。太く長い首を揺り動かし、赤く血走った小さな目で辺りを睥睨するさまはむしろ獲物を求める肉食獣を思わせた。 まるで見たことのない馬だった。そもそも馬なのかすら疑わしい。 そのぎらつく視線から逃れるように近くの岩陰に身を伏せながら思わず唸る。黒馬は野生のものではなかった。その証拠に蹄には蹄鉄が履かされ、太い胴を頑丈そうな馬具が覆う。そして背を覆う黒い布に赤い花の紋章を見とめた瞬間、ヴェルカンの喉がひゅっと音を立てた。
「黒の王国……」
幸い、馬は繋がれており、近くに馬主の姿も見当たらない。だが、先帝の話は本当だった。この森に黒の王国の手が及んでいる。 ようやく自分の出番が回ってきたらしい。そんな考えに身震いが走る。
よからぬことをお考えではございますまいな。 そんな呟きが背後で放たれたが、聞こえないふりをした。
その後、ふたりは黒馬から幾分離れた場所に明かりもつけずに隠れ潜んだ。倒木に他の木が根を張り巡らし、その上を苔と菌類が複雑な凹凸を刻むその真下、寸先も見えぬ陰の中に身を伏せ、じっと待つこと幾刻か。やがて木立の向こうに小さな明かりが見え、程なく近づいてきたそれは松明を手にした人影に姿を変えた。松明の光を受けてなお黒々と輝く小札鎧の上にマントを羽織った大柄は歩み寄った巨馬にも見劣らない。 息を詰めて見守る前で、小札鎧は馬のそばで火を起こすと、ヴェルカンに横顔を向ける形で腰を下ろした。
「私は黒の王国の妨害はいかな手を使っても排除するよう命を受けている」
禍々しい意匠を施された黒い兜を尻目に小声で囁きかける。
「まさか殺すおつもりですか?」 「他に方法を知っていればよいのですが」
そう言い置き、槍を握りしめた右手を、魔法使いはやんわりと抑えた。
「お待ちを。魔法協会はどんな勢力に対しても絶対中立を旨としております」
つまり立場上、彼はヴェルカンを手助けするわけにはいかないのだ。 無論だ、と返し、純白の板金鎧を脱ぎ捨て、鎖帷子一枚になる。白の帝国の騎士が隣国の人間を手にかけたとあれば大問題になる。円盾の紋章もマントで隠したヴェルカンは、小札鎧の背後の倒木によじ登った。 兜のつるりとした後頭部を見下ろし、首元の防具の継ぎ目に狙いを定め――ふと動きを止める。
思えば、甲冑を着たまま過ごすことに慣れている様子からかなりの手練れと見受けられるが、それにしても上の誰かから命じられ、送り込まれたに過ぎないのだろう。ヴェルカンからすれば何の恨みもない相手、いきなり仕掛けるのは躊躇いを覚えた。 戦い、倒すことでしか物事を解決できない不器用さに、今さらのようにため息が漏れそうになるが、これも主君の恩に報いるため、と己に言い聞かせる。
恨むなよ――――
そう胸中に語りかけつつ、槍を振り上げ、跳躍する。長身のヴェルカンの体重を乗せた槍の穂が鎧の隙間を貫く――寸前、目の前が黒と赤で塗りこめられた。 それが目にもとまらぬ早業で撥ね上げられた方盾だと気付いたのは、弾かれた穂先が硬い音を立てた直後。体勢を崩して転げ落ちそうになるのをどうにか立て直した目の前で、黒い戦士も戸板のごとく巨大な黒い盾から落ち葉を払い落して立ち上がったところだった。
「馬鹿め、貴様の動きなどお見通しだ」
兜の下からくぐもった声がこぼれた。つまりまんまと誘い込まれたわけだ。 ヴェルカンは何も答えず、覆面代わりのマントを巻き直し、盾を突き出しつつ槍を構えた。相手は戦槌を抜き、こちらも応戦の構え。その背後で黒馬が威嚇じみた嘶きを上げる。 俄然騒がしくなった夜の森、新たに加わるは戦槌を頭上で振り回す音。角のある魔物を思わせる兜が巨大な盾の後ろで焚き火を照り返し、赤黒く輝く。
「わざわざ背中を狙う臆病者はどいつだ?ただの物盗りではあるまい」
煽るような問いかけに沈黙で答えつつ、内心で舌打ちする。奇襲が失敗した以上、正体を明かさぬよう装備を捨てたヴェルカンはかなり不利といえた。幅広い盾と堅固な小札鎧を破って刃を届かせてくれるほど甘い相手とも思えない。 厚い面甲で隠された顔がはっきりと笑みを形作る気配があった。
「さては怖気づいたか。白の帝国の犬め」
どうにか声を上げずに済んだものの、それでも一瞬息が乱れた。黒の戦士が今度こそ声を上げて笑う。
「言ったろう、お見通しだと。ここまでの道案内ご苦労だった」 「後を尾けられたか……」
歯噛みの返事代わりに飛んできたのは戦槌の鋭い切先。柄頭が食い込んだ盾は軋み、なお打ち消しきれない重い衝撃が腕から肩に抜けた。足を踏ん張って耐え、お返しとばかりに槍を振るう。長さと遠心力を利して方盾を滅多打ちにすると、黒い戦士がたまらず身を縮める。だが直後、盾もろともぶつかってきたのをすんでのところで後ろに飛んで躱す。
「それまで!」
闘技場の審判を思い出させる凛とした声に、黒の戦士ともども思わず手を止める。揃って見上げれば、倒木の上に立つ魔法使いの姿が松明に浮かび上がる。
「これ以上の争いは不要。双方、剣をお引きください」
理由は?武器を下げ、傾げた首だけで黒い戦士が問う。
「あなたの目的は我々と同じはず。ならばここは力を合わせたほうが良い結果が得られるのではないですか?」 「お宝を手に入れた後は?」 「私は協会のために相応の取り分さえいただければ後は知りません。勝手に奪い合えばよろしい」
分かりやすい奴だな、と戦士が肩を震わせたが、その笑いは皮肉を含んでいた。
「今こいつを片づけて、後憂を絶っておくのはどうだ?」
無造作にヴェルカンを指す。自分のほうが強い、と信じて疑わない声音だ。そんな黒い戦士を魔法使いは余裕綽々といった調子で腕組み、横目��見下ろす。
「宝に至る有力な手がかりは得られていないのでしょう?」
だからこそヴェルカンたちを尾行し、その動きを把握していたのだという。 鋭い指摘に黒い戦士が一瞬詰まる。
「我々と行動を共にしたほうがあなたのためにもなるのでは?」 「帝国人を殺したうえでお前を脅し、宝まで案内させてやってもいいんだぞ」 「今回私はあくまで帝国の依頼で動いておりますすえ。事情はどうあれ寝返ったとでも思われては色々まずいんですな」
王国と事を構えるつもりはないが、進んで協力するつもりもない。それが魔法協会の立場だった。
「俺たちが料理して、食うのは協会というわけだな」
食えない連中だな。吐き捨てるような言葉を、魔法使いは懐から取り出した手記で跳ね返した。
「それとも、ここにある手がかりを独力で読み解き、宝に辿りつける自信があるなら、どうぞ私を倒して奪ってごらんなさい」 「魔法使いどの、危険です」
思わず声を上げてしまったヴェルカンだったが、当の魔法使いはあくまで黒い戦士に向き合い、挑むような視線を浴びせる。 危なすぎる賭けに絶対の自信を見たのか、とうとう黒い戦士がため息ひとつ、肩を竦めた。
「……いいだろう。あんたの言うとおりにしよう」
この言葉に安堵したように息をついたのは、彼なりに緊張していたからだろうか。倒木を降りた魔法使いは、ヴェルカンが問い質すより早く「荷物を取ってきます」と言い残して場を離れようとした。
「まさか私を庇ってくれたのですか」
すれ違いざま、囁きかける。魔法使いは一瞬足を止めたものの、すぐに意味ありげな笑みを残してヴェルカンの肩を掠めて去っていった。 何やら取り残されたような心地で黒い戦士と向かい合う。お互い、どう声をかけたものか分からない、といった具合で立ち尽くしていたのも束の間、
「命拾いしたな。だが次はこうはいかんぞ。せいぜい背中には気をつけることだ」
敵意も剥き出しに言われてはさすがにむっとした。
「今の言葉、そっくりそのまま返してやる」
言いざま背を向け、苛立ちを地面にぶつけるようにしながらその場を後にする。何はともあれ、寝首をかかれぬよう鎧を身に着けることが先決だった。
0 notes

