#聖夜を照ら���赤鼻の・・・?
Explore tagged Tumblr posts
Text
A Red Nose Illuminates the Holy Night...?
"Yu Yu Hakusho" 100% Maji Battle Christmas Event
This Christmas Story was first held on December 4th, 2020.

Story: A Christmas party is going to be held at Kuwabara's house. Kuwabara decorates with great enthusiasm as Yukina will also be attending it. Shizuru went shopping and says she bought "something nice", but...
Video:
youtube
Translation:
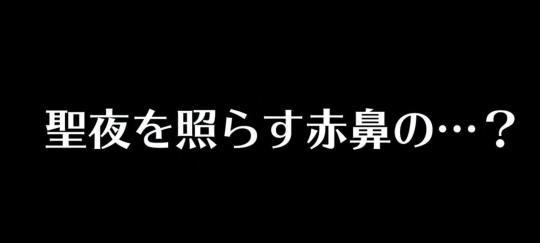
“A Red Nose Illuminates the Holy Night...?”

Kuwabara: Alright, I've finished decorating … The arrangements for the party are perfect!

Kuwabara: Nee-chan is out shopping. Thank goodness…

Kuwabara: I can concentrate better when I'm alone!

Kuwabara: Well ... you ain't coming home yet?

Shizuru: I'm gonna go to the store now.

Kuwabara: Nee-chan, get me some chicken, ice cream, and cake...

Kuwabara: Also, I want a Santa boot with assorted candy!

Shizuru: There's no way you could eat that much. Besides, I already made a cake.

Kuwabara: Eh, is that so!?

Shizuru: I made it yesterday, didn't you see it?

Kuwabara: Hehe…

Shizuru: For now, I'll buy only the necessary to continue with various preparations.

Shizuru: Well, if I'm in a good mood … it's possible that I would buy something nice for Kazu.

Kuwabara: Whaaat!?

Shizuru: Well then, I'm off.

Kuwabara: Ahh, even though she's said that, I'm sure she's gonna buy me something…

Kuwabara: Could it be … a Christmas present? I look forward to it!

Kuwabara: Yukina-san is also coming today…

Kuwabara: I, I, I can't wait!
[Shizuru is back home]

Shizuru: I'm home!

Kuwabara: Welcome back! You're back early!

Shizuru: Why are you waiting at the front door? Look, I got you the candy.

Kuwabara: Ohh! Nee-chan, thanks!

Kuwabara: …Huh, what about that paper bag over there?

Shizuru: This? I was just thinking, since it's a special party...

Shizuru: Isn't it cute?

Kuwabara: A bright red dress! It looks very Christmassy!

Shizuru: So, Kazu. I got something for you too.

Kuwabara: No, no, no way ... the "something nice" for me…

Shizuru: Yes, this is it. A Christmas present!

Kuwabara: Nee-chan…! I, I'm soooo happy!

*rustle* *rustle* (Kuwabara opens the present)

Kuwabara: …Heh?

Shizuru: Hahaha! I thought it would suit you! A cartoon-character costume of a reindeer!

Kuwabara: ....

Kuwabara: Since Yukina-san is coming all the way here, I thought I'd kill it today...

Kuwabara: When you said "something nice", I thought it definitely meant "cool clothes", but…

Shizuru: Hey, Kazu! Try it on once!

Kuwabara: …at me

Shizuru: Eh?

Kuwabara: This … dressed like this! Yukina-san will laugh at me!

Shizuru: Wait…! Kazu!

Shizuru: ........

Shizuru: Maybe, I did a bad thing...
[Botan, Keiko, Yusuke, and Yukina arrive at Kuwabara's house]

Botan: Kuwa-chan, where did he go?

Keiko: I know, even though the chicken is roasting by now ... there is no sign he's coming back at all.

Botan: He left around noon, didn't he? I hope he didn't get caught up in any weird situation.

Yusuke: Don't worry, he'll be back when he's hungry, I'm sure.

Keiko: Jeez, Yusuke! Aren't you worried?

Yusuke: It's that guy we're talking about, he's gonna be fine.

Yukina: Kazuma-san, I wonder what happened to him…

Botan: Shizuru-san, don't you know the exact reason?

Shizuru: …Yeah, I don't know.

Botan: I see … Should we go look for him in a little while?

Yukina: Yes, I'm worried.

Shizuru: *Puff*, oh my … I should have considered his feelings a little more.

Shizuru: Kazu...
[On the streets...]

Kuwabara: Phew....

Kuwabara: It felt good to burst out of the house, but now I can't go back…

Kuwabara: I came out with the character costume in my hands…

Kuwabara: Nee-chan went to a lot of trouble to get it for me. I did a bad thing, didn't I?

???: Huh, Kuwabara-kun…

Kuwabara: Oh?

Kurama: What's the matter? I didn't expect to see you at a place like this.

Kuwabara: It's Kurama! Why are you here…

Kurama: I was supposed to join the party later. Kuwabara-kun, why are you here?

Kurama: I thought you were definitely with everyone else.

Kuwabara: Ah, well, I mean…

Kurama: Oh, is that reindeer…?

Kuwabara: Ah! Err … ahh … that…

Kurama: ........

Kurama: If you feel like it, would you like to chat for a moment?

Kurama: Also, standing here while talking, right? (Why don't we go somewhere else?)

Kuwabara: Kurama...

Kuwabara: My bad, thanks.
[Kurama and Kuwabara talk in a better place...]

Kurama: …I see

Kurama: Shizuru-san had good intentions when she bought that costume for you.

Kuwabara: Yeah.

Kuwabara: I'm sure she picked this one out for me, because it would be a blast if I wore it...

Kuwabara: But ... Today, I get to meet Yukina-san for the first time in a while.

Kuwabara: At least on an occasion like this, I wanted to look cool...

Kuwabara: When I thought that, I just ran out of the house.

Kurama: Is that so?

Kuwabara: Yukina-san will laugh at me if I wear this red nosed reindeer…

Kuwabara: But, I'm more laughable for worrying about such thing…!

Kurama: You already understand that Shizuru had no bad intentions, right?

Kuwabara: …Of course.

Kurama: He-he, that's fine then.

Kurama: It's a waste not to attend such a special party, because of those sad feelings.

Kuwabara: That's right … But, how can I go back at this late hour…

Kurama: I was on my way too. If you go with me, it'll be fine.

Kurama: Isn't Yukina-chan also waiting for you?

Kuwabara: .....

Kuwabara: Ha-ha, ha-ha-ha … I see. I seem so insignificant for worrying so much about it!

Kuwabara: Kurama, thanks.

Kurama: Not at all. Well then, let's head to the party.

Kuwabara: Yeeesss!

*rustle* *rustle* (Kuwabara is changing clothes)

Kurama: ...Hmm? ...Huh!?

Kuwabara: Hehehe…

Kuwabara: I'll light up the dark night streets with my shiny red nose!
[At Kuwabara's House]

Shizuru: I'm gonna go look for him.

*ching ching* (sound of chime)

Shizuru: Huh?

Yusuke: Ahh! You're late!


Kuwabara: Ta-dah!

Kuwabara: Mr. Red Nosed Reindeer has brought Kurama!

Botan: What is that outfit! It suits you!

Yusuke: You made us wait! You were with Kurama?

Kurama: I ran across him.

Yukina: Kazuma-san! I was worried when you didn't come back.

Yukina: He-he, the reindeer is cute.

Kuwabara: Yu, Yu, Yukina-san…! Isn't it funny?

Yukina: Yes! It's very Christmassy, and also looks very nice.

Kuwabara: Hahaha...! Yu, Yukina-san's outfit is also reindeer...

Kuwabara: I, I, I'm so glad we're matching!

Yusuke: What's that lewd look on your face? I'm starving because of you.

Keiko: Well, now that everyone is here, let's start the party!

Botan: Ahh, I'm hungry too!

Kuwabara: As an apology for being late, I'll carve the chicken! Just a minute!

Shizuru: I'll help too.

Shizuru: ...Hey, Kazu.

Kuwabara: Hmm?

Shizuru: Well … I mean... I should have thought about your feelings too.

Shizuru: Sorry.

Kuwabara: Nee-chan…

Kuwabara: Ok, it's okay! It's a big hit with everyone!

Kuwabara: I'm a reindeer, so I'm also matching with Yukina. I'm the luckiest person in the world!

Shizuru: Jeez, you're such an idiot.

Yukina: Oh, what is this drink?

Kurama: This is grape flavored soft drink. It's bubbling and delicious.

Kurama: It's a Christmas staple, and often sold at this time of year.

Botan: Come on, let's open it earlier!

Shizuru: Well then, I'll do this.

Shizuru: One, two, go!

Shizuru/Kuwabara: Merry Christmas!
-The End-
Who needs a shrink when you have Kurama to give you advice (lol)? Shizuru's costume is called "Empress of the Holy Night", she does look like a queen! OMG, was it really a toast without alcohol? Where is Atsuko to bring the champagne?
Besides new illustrations of Shizuru and Kuwabara wearing Christmas costumes, this story brought back Botan, Keiko and Yukina wearing cute costumes. I wish Yusuke and Kurama were also wearing cool outfits. Invite Hiei next time!





#A Red Nose Illuminates the Holy Night...?#Yu Yu Hakusho Christmas#yu yu hakusho 100% maji battle#Kuwabara#Shizuru#Yukina#Botan#Keiko Yukimura#Kurama#聖夜を照らす赤鼻の・・・?#【聖夜疾走】桑原和真#【聖夜の女帝】桑原静流
44 notes
·
View notes
Text
【SPN】庭師と騎士
警告:R18※性描写、差別的描写
ペアリング:サム/ディーン、オリキャラ/ディーン
登場人物:ディーン・ウィンチェスター、サム・ウィンチェスター、ボビー・シンガー・ルーファス・ターナー、ケビン・トラン、チャーリー・ブラッドベリー、クラウス神父(モデル:クラウリー)
文字数:約16000字
設定: 修道院の囚われ庭師ディーン(20)と宿を頼みに来た騎士サム(24)。年齢逆転、中世AU。
言い訳: 映画「天使たちのビッチナイト」に影響を受けました。ボソボソと書いてましたがちょっと行き詰まり、詰まってまで書くほどのものじゃないので一旦停止します。
◇
自分のことなら肋骨の二本や三本が折れていたとしても気づかないふりをしていられるが、部下たちを休ませる必要があった。
王国騎士の象徴である深紅のマントは彼ら自身の血に染められ、疲労と傷の痛みとで意識がもうろうとしている者も数名いた。何よりも空腹だった。狩りをしようにも、矢がなく、矢を作るためにキャンプを張る体力もない。 一度腰を下ろせばそこが墓地になるかもしれなかった。 辺境の村を救うために命じられた出征だった。王はどこまで知っていたのか……。おそらくは何も知らなかったのに違いない。そうだと信じたかった。辺境の村はすでに隣国に占領されていた。彼らは罠にかけられたのだった。 待ち構えていた敵兵に大勢の仲間の命と馬を奪われ、サムは惨めな敗走を余儀なくされた。 森の中を、王城とは微妙にずれた方向へ進んでいるのに、サムに率いられた騎士たちは何もいわなかった。彼らもまた、サムと同じ疑いを胸に抱いていたのだ。全ては王に仕組まれたのではないかと。 誰一人口には出さなかったが、森の中をさ迷うサムに行き先を尋ねる者もいなかった。 なけなしの食糧を持たせて斥候に出していたケビンが、隊のもとに戻ってきた。彼は森の中に修道院を発見した。サムはその修道院に避難するべきか迷った。森は王国の領内だ。もしも王が裏切っていた場合、修道院にまで手を回されていたら彼らは殺される。 だが、このままでは夜を越せない者もいるかもしれなかった。サムは未だ六人の騎士を率いていて、王国よりサムに忠実な彼らを何としても生かさなければならない。 サムはケビンに案内を命じた。
◇
ディーンは自分の名前を気に入っていたが、今ではその名前を呼ぶ者はほとんどいなかった。 修道院では誰もがディーンのことを「あれ」とか「そこの」とか表現する。もしくは彼自身の職業である「庭師」とか。彼自身に、直接呼びかける者はいない。なぜなら彼は耳が聞こえないし、口も利けないから。 ディーンは今年で二十歳になる……らしい。彼は子供のころに両親を盗賊に殺されて、もともと身を寄せる予定だったこの修道院に引き取られた。ただし支払うべき寄付金も盗賊に奪われたので、修道士としてではなく庭師として働いて暮らしている。 夜中、ディーンはフラフラになりながら修道院を出て、納屋に帰り着いた。家畜小屋の横の納屋が彼の住処だ。神父が彼に酒を飲ませたので、藁の下に敷いた板のわずかな段差にも躓いてしまった。 そのまま藁の中にうずくまって、眠ってしまおうと思った時だ。納屋の戸の下の隙間から、赤い炎の色と複数の人影がちらついて見えた。 ディーンは、静かに身を起こした。少し胸やけはするが、幻覚を見るほど酔ってはいない。ディーンがいる納屋は、修道院の庭の中にある。修道士たちをオオカミやクマから守る塀の、内側だ。修道士たちは夜中にうろついたりしないから、この人影は外部からの――塀の外、森からの――侵入者たちのものだ。 門番の爺さんは何をしていたのか。もちろん、寝ているんだろう、夜更かしするには年を取りすぎている。今までも修道院が盗賊被害には遭ったことはあるが、こんな夜中じゃなかった。オオカミにとってはボロを着ていようが聖職者のローブを着ていようが肉は肉。強襲も山菜取りも日差しの入る間にやるのが最善だ。 では何者か。ディーンはそっと戸を開けて姿を見ようとした。ところが戸に手をかける間もなく、外から勢いよく開けられて転がり出てしまう。うつ伏せに倒れた鼻先に松明の火を受けてきらめく刃のきっさきを見て、そういえば、神父に持たされたロウソクが小屋の中で灯しっぱなしだったなと気づく。 「こそこそと覗き見をしていたな」 ざらついて低い声がディーンを脅した。ディーンはその一声だけで、彼がとても疲れて、痛みを堪えているのがわかった。 「やめろ、ルーファス! 何をしている」 若い男の声がした。ディーンを脅している男は剣のきっさきを外に向けた。「こいつが、俺たちを見張っていた。きっと刺客だ。俺たちがここに来るのを知っていて、殺そうとしてたんだ」 刺客、という言葉に、側にいた男たちが反応した。いったい何人いるんだ。すっかりと敵意を向けられて、ディーンはひるんだ。 「馬鹿な、彼を見ろ。丸腰だ。それに刺客なら小屋の中でロウソクなんて灯して待っているわけがない」 若い声の男が手を握って、ディーンを立たせた。俯いていると首から上が視界にも入らない。とても背の高い男だった。 「すまない、怖がらせてしまった。我々は……森で迷ってしまって、怪我を負った者もいる。宿と手当てが必要で、どうかここを頼らせてもらいたいと思って訪ねた」 背の高さのわりに、威圧的なところのない声だった。ディーンが頷くのを見て、男は続けた。 「君は――君は、修道士か?」 ディーンは首をかしげる。「そうか、でも、ここの人間だ。そうだろ? 神父に会わせてもらえるかい?」 ディーンはまた、首をかしげる。 「なんだ、こいつ、ぼんやりして」 さっき脅してきた男――闇夜に溶け込むような黒い肌をした――が、胡乱そうに顔をゆがめて吐き捨てる。「おお、酒臭いぞ。おおかた雑用係が、くすねた赤ワインをこっそり飲んでいたんだろう」 「いや、もしかして――君、耳が聞こえないの?」 若い男が自分の耳辺りを指さしてそういったので、ディーンは頷いた。それから彼は自分の口を指さして、声が出ないことをアピールする。 男の肩が一段下がったように見えて、ディーンは胸が重くなった。相手が自分を役立たずと判断して失望したのがわかるとき、いつもそうなる。 彼らは盗賊には見えなかった。何に見えるかって、それは一目でわかった。彼らは深紅の騎士だ。王国の誇り高い戦士たち。 幼いころに憧れた存在に囲まれて、これまで以上に自分が矮小な存在に思えた。 「聞こえないし、しゃべれもしないんじゃ、役に立たない。行こう、ケビンに神父を探させればいい」 疲れた男の声。 抗議のため息が松明の明かりの外から聞こえた。「また僕一人? 構いませんけどね、僕だって交渉するには疲れ過ぎて……」 「一番若いしまともに歩いてるじゃないか! 俺なんか見ろ、腕が折れて肩も外れてる、それに多分、日が上る前に止血しないと死ぬ!」 ディーンは初めて彼らの悲惨な状態に気が付いた。 松明を持っているのは一番背の高い、若い声の男で、彼はどうやら肋骨が折れているようだった。肩が下がっているのはそのせいかもしれなかった。ルーファスと呼ばれた、やや年配の黒い肌の男は、無事なところは剣を握った右腕だけというありさまだった。左半身が黒ずんでいて、それが全て彼自身の血であるのなら一晩もたないというのも納得だ。女性もいた。兜から零れた髪が松明の炎とそっくりの色に輝いて見えた。しかしその顔は血と泥で汚れていて、別の騎士が彼女の左足が地面に付かないように支えていた。その騎士自身も、兜の外された頭に傷を受けているのか、額から流れた血で耳が濡れている。 六人――いや、七人だろうか。みんな満身創痍だ。最強の騎士たちが、どうしてこんなに傷ついて、夜中に森の中をゆく羽目に。 ディーンは松明を持った男の腕を引っ張った。折れた肋骨に響いたのか、呻きながら彼は腕を振り払おうとする。 「待って、彼、案内してくれるんじゃない? 中に、神父様のところに」 女性の騎士がそういった。ディーンはそれを聞こえないが、何となく表情で理解した振りをして頷き、ますます騎士の腕を引っ張った。 騎士はそれきりディーンの誘導に素直についてきた。彼が歩き出すとみんなも黙って歩き出す。どうやらこの背の高い男が、この一団のリーダーであるらしかった。 修道院の正面扉の鍵はいつでも開いているが、神父の居室はたいていの場合――とりわけ夜はそうだ――鍵がかか��ている。ディーンはいつも自分が来たことを示す独特のリズムでノックをした。 「……なんだ?」 すぐに扉の向こうで、眠りから起こされて不機嫌そうな声が聞こえてほっとする。もう一度ノックすると、今度は苛立たし気に寝台から降りる音がした。「なんだ、ディーン、忘れ物でもしたのか……」 戸を開いた神父は、ディーンと彼の後ろに立つ騎士たちの姿を見て、ぎょっとして仰け反った。いつも偉そうにしている神父のそんな顔を見られてディーンは少しおかしかった。 ディーンは背の高い男が事情を説明できるように脇にのいた。 「夜半にこのような不意の訪問をして申し訳ない。緊急の事態ですのでどうかお許し頂きたい。私は王国騎士のサミュエル・ウィンチェスター。彼は同じく騎士のルーファス。彼は重傷を負っていて一刻も早い治療が必要です。他にも手当と休息が必要な者たちがいる」 神父は、突然現れた傷だらけの騎士たちと、さっき別れたばかりの庭師を代わる代わる、忙しなく視線を動かして見て、それから普段着のような体面をするりと羽織った。深刻そうに頷き、それから騎士たちを安心させるようにほほ笑む。「騎士の皆様、もう安全です。すぐに治癒師を呼びます。食堂がいいでしょう、治療は厨房で行います。おい」 目線でディーンは呼びかけられ、あわてて神父のひざ元に跪いて彼の唇を読むふりをする。 「治癒師を、起こして、食堂に、連れてきなさい。わかったか?」 ディーンは三回頷いて、立ち上がると治癒師のいる棟へ駆け出す。 「ご親切に感謝する」 男のやわらかい礼が聞こえる。「……彼はディーンという名なのか? あとでもう一度会いたい、ずいぶんと怖がらせてしまったのに、我々の窮状を理解して中へ案内してくれた……」 ディーンはその声を立ち止まって聞いていたかったが、”聞こえない”のに盗み聞きなどできるはずがなかった。
◇
明け方にルーファスは熱を出し、治癒師は回復まで数日はかかるだろうといった。サムは騎士たちと目を合わせた。今はまだ、森の深いところにあるこの修道院には何の知らせも来ていないようだが、いずれは王国から兵士が遣わされ、この当たりで姿を消した騎士たち――”反逆者たち”と呼ばれるかもしれない――がいることを知らされるだろう。俗世から離れているとはいえ修道院には多くの貴族や裕福な商家の息子が、いずれはまた世俗へ戻ることを前提にここで生活している。彼らの耳に王宮での噂が届いていないことはまずあり得なく、彼らがどちらの派閥を支持しているかはサムにはわからない。もっとも王が追���ている失踪騎士を庇おうなどという不届きな者が、たくさんいては困るのだった。 出征の命令が罠であったのなら、彼らは尾けられていたはずだった。サムの死体を探しに捜索がしかれるのは間違いない。この修道院もいずれ見つかるだろう。長く留まるのは良策ではない。 かといって昏睡状態のルーファスを担いで森に戻るわけにもいかず、止む無くサムたちはしばらくの滞在を請うことになった。 修道院長のクラウス神父は快く応じてくれたが、用意されたのは厨房の下の地下室で、そこはかとなく歓迎とは真逆の意図を読み取れる程度には不快だった。彼には腹に一物ありそうな感じがした。サムの予感はしばしば王の占い師をも勝るが、騎士たちを不安させるような予感は口には出せなかった。 厨房の火の前で休ませているルーファスと、彼に付き添っているボビーを除く、五人の騎士が地下に立ち尽くし、ひとまず寝られる場所を求めて目をさ迷わせている。探すまでもない狭い空間だった。横になれるのは三人、あとの二人は壁に寄せた空き箱の上で膝を枕に眠るしかないだろう。 「お腹がすいた」 疲れて表情もないチャーリーが言った。「立ったままでもいいから寝たい。でもその前に、生の人参でもいいから食べたいわ」 「僕も同感。もちろんできれば生じゃなくて、熱々のシチューに煮込まれた人参がいいけど」 ガースの言葉に、チャーリーとケビンが深い溜息をついた。 地下室の入口からボビーの声が下りてきた。「おい、今から食べ物がそっちに行くぞ」 まるでパンに足が生えているかのように言い方にサムが階段の上に入口を見上げると、ほっそりした足首が現れた。 足首の持ち主は片手に重ねた平皿の上にゴブレットとワイン瓶を乗せ、革の手袋をはめたもう片方の手には湯気のたつ小鍋を下げて階段を下りてきた。 家畜小屋の隣にいた青年、ディーンだった。神父が彼を使いによこしたのだろう。 「シチューだ!」 ガースが喜びの声を上げた。チャーリーとケビンも控え目な歓声を上げる。みんなの目がおいしそうな匂いを発する小鍋に向かっているのに対し、サムは青年の足首から目が離せないでいた。 彼はなぜ裸足なんだろう。何かの罰か? 神父は修道士や雑用係に体罰を与えるような指導をしているのか? サムは薄暗い地下室にあってほの白く光って見える足首から視線を引きはがし、もっと上に目をやった。まだ夜着のままの薄着、庭でルーファスが引き倒したせいで薄汚れている。細いが力のありそうなしっかりとした肩から腕。まっすぐに伸びた首の上には信じられないほど繊細な美貌が乗っていた。 サムは青年から皿を受け取ってやろうと手を伸ばした。ところがサムが皿に手をかけたとたん、びっくりした彼はバランスを崩して階段を一段踏みそこねた。 転びそうになった彼を、サムは慌てて抱き止めた。耳元に、彼の声にならない悲鳴のような、驚きの吐息を感じる。そうだ、彼は耳が聞こえないのだった。話すことが出来ないのはわかるが、声を出すこともできないとは。 「急に触っちゃだめよ、サム!」 床に落ちた皿を拾いながらチャーリーがいう。「彼は耳が聞こえないんでしょ、彼に見えないところから現れたらびっくりするじゃない」 「ディーンだっけ? いや、救世主だ、なんておいしそうなシチュー、スープか? これで僕らは生き延びられる」 ガースが恭しく小鍋を受け取り、空き箱の上に並べた皿にさっさと盛り付けていく。階段の一番下でサムに抱き止められたままのディーンは、自分の仕事を取られたように見えたのか焦って体をよじったが、サムはどうしてか離しがたくて、すぐには解放してやれなかった。 まったく、どうして裸足なんだ?
修道士たちが詩を読みながら朝食を終えるのを交代で横になりながら過ごして待ち、穴倉のような地下室から出て騎士たちは食堂で体を伸ばした。一晩中ルーファスの看病をしていたボビーにも休めと命じて、サムが代わりに厨房の隅に居座ることにした。 厨房番の修道士は彼らがまるでそこに居ないかのように振る舞う。サムも彼らの日課を邪魔する意思はないのでただ黙って石窯の火と、マントでくるんだ藁の上に寝かせた熟練の騎士の寝顔を見るだけだ。 ルーファスは気難しく人の好き嫌いが激しい男だが、サムが幼い頃から”ウィンチェスター家”に仕えていた忠臣だ。もし彼がこのまま目覚めなかったら……。自分が王宮でもっとうまく立ち回れていたら、こんなことにはならなかったかもしれない。 若き王の父と――つまり前王とサムの父親が従弟同士だったために、サムにも王位継承権があった。実際、前王が危篤の際には若すぎる王太子を不安視する者たちからサムを王にと推す声も上がった。不穏な声が派閥化する前にサムは自ら継承権を放棄し、領地の大半を王に返還して王宮に留まり一騎士としての振る舞いに徹した。 その無欲さと節制した態度が逆に信奉者を集めることとなり、サムが最も望まないもの――”ウィンチェスター派”の存在が宮殿内に囁かれるようになった。国王派――この場合は年若き王をいいように操ろうとする老練な大臣たちという意味だ――が敵意と警戒心を募らせるのも無理はないとサムが理解するくらいには、噂は公然と囁かれた。何とか火消しに回ったが、疑いを持つ者にとっては、それが有罪の証に見えただろう。 自分のせいで部下たちを失い、また失いつつあるのかと思うと、サムはたまらないむなしさに襲われた。 ペタペタと石の床を踏む足音が聞こえ顔を上げる。ディーンが水差しを持って厨房にやってきた。彼は石窯の横に置かれた桶の中に水を入れる。サムは声もかけずに暗がりから彼の横顔をぼうっと眺めた。声をかけたところで、彼には聞こえないが―― 床で寝ているルーファスが呻きながら寝返りを打った。動きに気づいたディーンが彼のほうを見て、その奥にいるサムにも気づいた。 「やあ」 サムは聞こえないとわかりつつ声をかけた。まるきり無駄ではないだろう。神父の唇を読んで指示を受けていたようだから、言葉を知らないわけではないようだ。 彼が自分の唇を読めるように火の前に近づく。 「あー、僕は、サムだ。サム、王国の騎士。サムだ。君はディーン、ディーンだね? そう呼んでいいかい?」 ディーンは目を丸く見開いて頷いた。零れそうなほど大きな目だ。狼を前にしたうさぎみたいに警戒している。 「怖がらないでいい。昨夜はありがとう。乱暴なことをしてすまなかった。怪我はないか?」 強ばった顔で頷かれる。彼は自らの喉を指して話せないことをアピールした。サムは手を上げてわかっていることを示す。 「ごめん――君の仕事の邪魔をするつもりはないんだ。ただ、何か困ってることがあるなら――」 じっと見つめられたまま首を振られる。「――ない?」 今度は頷かれる。「――……そうか、わかった。邪魔をしてごめん」 ディーンは一度瞬きをしてサムを見つめた。彼は本当に美しい青年だった。薄汚れてはいるし、お世辞にも清潔な香りがするとは言い難かったが、王宮でもお目にかかったことのないほど端正な顔立ちをしている。こんな森の奥深くの修道院で雑用係をしているのが信じられないくらいだ。耳と口が不自由なことがその理由に間違いないだろうが、それにしても――。 水差しの水を全て桶に注いでしまうと、ディーンはしばし躊躇った後、サムを指さして、それから自分の胸をさすった。 彼が動くのを眺めるだけでぼうっとしてしまう自分をサムは自覚した。ディーンは何かを伝えたいのだ。もう一度同じ仕草をした。 「君の? 僕の、胸?」 ディーンは、今度は地下に繋がる階段のほうを指さして、その場で転ぶ真似をした。そしてまたサムの胸のあたりを指さす。 理解されてないとわかるとディーンの行動は早かった。彼はルーファスをまたいでサムの前にしゃがみ込み、彼の胸に直接触れた。 サムは戦闘中以外に初めて、自分の心臓の音を聞いた。 ディーンの瞳の色は鮮やかな新緑だった。夜にはわからなかったが、髪の色も暗い金髪だ。厨房に差し込む埃っぽい日差しを浴びてキラキラと輝いている。 呆然と瞳を見つめていると、やっとその目が自分を心配していることに気が付いた。 「……ああ、そっか。僕が骨折してること、君は気づいてるんだね」 ”骨折”という言葉に彼が頷いたので、サムは納得した。さっき階段から落ちかけた彼を抱き止めたから、痛みが悪化していないか心配してくれたのだろう。サムは、彼が理解されるのが困難と知りながら、わざわざその心配を伝えようとしてくれたことに、非常な喜びを感じた。 「大丈夫だよ、自分で包帯を巻いた。よくあることなんだ、小さいころは馬に乗るたびに落馬して骨を折ってた。僕は治りが早いんだ。治るたびに背が伸びる」 少し早口で言ってしまったから、ディーンが読み取ってくれたかはわからなかった。だが照れくさくて笑ったサムにつられるように、ディーンも笑顔��なった。 まさに魂を吸い取られるような美しさだった。魔術にかかったように目が逸らせない。完璧な頬の稜線に触れたくなって、サムは思わず手を伸ばした。 厨房の入口で大きな音がした。ボビーが戸にかかっていたモップを倒した音のようだった。 「やれやれ、どこもかしこも、掃除道具と本ばかりだ。一生ここにいても退屈しないぞ」 「ボビー?」 「ああ、水が一杯ほしくてな。ルーファスの調子はどうだ?」 サムが立ち上がる前に、ディーンは驚くほどの素早さで裏戸から出て行ってしまった。
◇
キラキラしてる。 ディーンは昔からキラキラしたものに弱かった。 木漏れ日を浴びながら一時の昼寝は何物にも得難い喜びだ。太陽は全てを輝かせる。泥だまりの水だってきらめく。生まれたばかりの子ヤギの瞳、朝露に濡れた花と重たげな羽を開く蝶。礼拝堂でかしずいた修道士の手から下がるロザリオ。水差しから桶に水を注ぐときの小気味よい飛沫。 彼はそういったものを愛していた。キラキラしたものを。つまりは美しいもの。彼が持ち得なかったもの。 サムという騎士はディーンが今までに見た何よりも輝いていた。 あまりにもまぶしくて直視しているのが辛くなったほどだ。彼の瞳の色に見入っていたせいで、厨房で大きな音に反応してしまった。幸いサムは音を立てた騎士のほうに目がいってディーンの反応には気づかなかったようだ。 もう一度彼の目を見て彼に触れてみたかったが、近づくのが恐ろしくもあった。
ディーン何某という男の子がこの世に生を受けたとき、彼は両���にとても祝福された子供だった。彼は美しい子だと言われて育った。親というのは自分の子が世界で一番美しく愛らしいと信じるものだから仕方ない。おかげでディーンは両親が殺され、修道院に引き取られる八つか九つの頃まで、自分が怪物だと知らずに生きてこられた。 修道院長のクラウス神父は親と寄付金を失った彼を憐れみ深く受け入れてくれたが、幼い孤児を見る目に嫌悪感が宿っているのをディーンは見逃さなかった。 「お前は醜い、ディーン。稀に見る醜さだ」と神父は、気の毒だが率直に言わざるを得ないといった。「その幼さでその醜さ、成長すれば見る者が怖気をふるう怪物のごとき醜悪な存在となるだろう。無視できない悪評を招く。もし怪物を飼っていると噂が立てば、修道院の名が傷つき、私と修道士たちは教会を追われるだろう。お前も森に戻るしかなくなる」 しかしと神父は続けた。「拾った怪物が不具となれば話は違う。耳も聞こえなければ口もきけないただの醜い哀れな子供を保護したとなれば、教皇も納得なさるだろう。いいかね、ディーン。お前をそう呼ぶのは今日この日から私だけだ。他の者たちの話に耳を傾けてはいけないし、口を聞いてもいけない。おまえは不具だ。不具でなければ、ここを追い出される。ただの唾棄すべき怪物だ。わかったかね? 本当にわかっているなら、誓いを立てるのだ」 「神様に嘘をつけとおっしゃるのですか?」 まろやかな頬を打たれてディーンは床に這いつくばった。礼拝堂の高窓から差し込む明かりを背負って神父は怒りをあらわにした。 「何という身勝手な物言いだ、すでに悪魔がその身に宿っている! お前の言葉は毒、お前の耳は地獄に通じている! 盗賊どもがお前を見逃したのも、生かしておいたほうが悪が世に蔓延るとわかっていたからに違いない。そんな者を神聖な修道院で養おうとは、愚かな考えだった。今すぐに出ていきなさい」 ディーンは、恐ろしくて泣いてすがった。修道院を追い出されたら行くところがない。森へ放り出されたら一晩のうちに狼の餌食になって死んでしまうだろう。生き延びられたとしても、神父ですら嫌悪するほど醜い自分が、他に受け入れてくれる場所があるはずもない。 ディーンは誓った。何度も誓って神父に許しを請うた。「話しません、聞きません。修道院のみなさまのご迷惑になることは決してしません。お願いです。追い出さないでください」 「お前を信じよう。我が子よ」 打たれた頬をやさしく撫でられ、跪いてディーンを起こした神父に、ディーンは一生返せぬ恩を負った。
ぼんやりと昔を思い出しながら草をむしっていたディーンの手元に影が落ちた。 「やあ、ディーン……だめだ、こっちを向いてもらってからじゃないと」 後ろでサムがぼやくのが聞こえた。 ディーンは手についた草を払って、振り向いた。太陽は真上にあり、彼は太陽よりも背が高いことがわかって、ディーンはまた草むしりに戻った。 「あの、えっと……。ディーン? ディーン」 正面に回り込まれて、ディーンは仕方なく目線を上げた。屈んだサムはディーンと目が合うと、白い歯をこぼして笑った。 ああ、やっぱりキラキラしてる。 ディーンは困った。
◇
サムは困っていた。どうにもこの雑用係の庭師が気になって仕方ない。 厨房から風のように消えた彼を追って修道院の中庭を探していると、ネズの木の下で草をむしっている背中を見つけた。話しかけようとして彼が聞こえないことを改めて思い出す。聞こえない相手と会話がしたいと思うなんてどうかしてる。 それなのに気づけば彼の前に腰を下ろして、身振り手振りを交えながら話しかけていた。仕事中のディーンは、あまり興味のない顔と時々サムに向けてくれる。それだけでなぜか心が満たされた。 ネズの実を採って指の中で転がしていると、その実をディーンが取ろうとした。修道院の土地で採れる実は全て神が修道士に恵まれた貴重なもの――それがたとえ一粒の未熟な実でも――だからサムは素直に彼に渡してやればよかった。だがサムは反射的に手をひっこめた。ディーンの反応がみたかったのだ。彼は騎士にからかわれて恥じ入るような男か、それとも立ち向かってくるか? 答えはすぐにわかった。彼は明らかにむっとした顔でサムを見上げ、身を乗り出し手を伸ばしてきた。 サムはさらに後ろに下がり、ディーンは膝で土を蹴って追いすがる。怒りのせいか日差しを長く浴びすぎたせいか――おそらくそのどちらも原因だ――額まで紅潮した顔をまっすぐに向けられて、サムは胸の奥底に歓喜が生まれるのを感じた。 「ハハハ……! ああ……」 するりと言葉がこぼれ出てきた。「ああ、君はなんて美しいんだ!」 ディーンがサムの手を取ったのと、サムがディーンの腕を掴んだのと、どちらが早かったかわからかない。サムはディーンに飛びつかれたと思ったし、ディーンはサムに引き倒されたと思ったかもしれない。どっちにしろ、結果的に彼らはネズの根のくぼみに入ってキスをした。 長いキスをした。サムはディーンの髪の中に手を入れた。やわらかい髪は土のにおいがした。彼の唾液はみずみずしい草の味がした。耳を指で挟んで引っ張ると、ん、ん、と喉を鳴らす音が聞こえた。とても小さな音だったが初めて聞いた彼の”声”だった。もっと聞きたくて、サムは色んなところを触った。耳、うなじ、肩、胸、直接肌に触れたくて、腹に手を伸ばしたところでディーンが抵抗した。 初めは抵抗だとわからなかった。嫌なことは嫌と言ってくれる相手としか寝たことがなかったからだ。ところが強く手首を掴まれて我に返った。 「ごめん!」 サムは慌てて手を離した。「ご、ごめん、本当にごめん! こんなこと……こんなことするべきじゃなかった。僕は……だめだ、どうかしてる」 額を抱えてネズの根に尻を押し付け、できるだけディーンから離れようとした。「僕はどうかしてる。いつもはもっと……何というか……こんなにがっついてなくて、それに君は男で修道院に住んでるし――ま、まあ、そういう問題じゃないけど――ディーン――本当にごめん――ディーン?」 ディーンは泣いていた。静かに一筋の涙を頬に流してサムを見ていた。 「待って!」 またも彼の身の軽さを証明する動きを見届けることになった。納屋のほうに走っていく彼の姿を、今度はとても追う気にはなれなかった。
◇
夜、クラウス神父の部屋でディーンは跪いていた。 「神父様、私は罪を犯しました。二日ぶりの告解です」 「続けて」 「私は罪を犯しました……」 ディーンはごくりとつばを飲み込んだ。「私は、自らの毒で、ある人を……ある人を、侵してしまったかもしれません」 暖炉の前に置かれたイスに座り、本を読んでいた神父は、鼻にかけていた眼鏡を外してディーンを見た。 「それは由々しきことだ、ディーン。お前の毒はとても強い。いったい誰を毒に侵したのだ。修道士か?」 「いいえ、騎士です」 「騎士! 昨日ここに侵入してきたばかりの、あの狼藉者どものことか? ディーン、おお、ディーン。お前の中の悪魔はいつになったら消えるのだろう」 神父は叩きつけるように本を閉じ、立ち上がった。「新顔とくれば誘惑せずにはおれないのか? どうやって、毒を仕込んだ。どの騎士だ」 「一番背のたかい騎士です。クラウス神父。彼の唇を吸いました。その時、もしかしたら声を出してしまったかもしれません。ほんの少しですが、とても近くにいたので聞こえたかもしれません」 「なんてことだ」 「あと、彼の上に乗ったときに胸を強く圧迫してしまったように思います。骨折がひどくなっていなければいいのですが、あとで治癒師にみてもらうことはできますか?」 「ディーン……」 神父は長い溜息をついた。「ディーン。お前の悪魔は強くなっている。聖餐のワインを飲ませても、毒を薄めることはできなかった。お前と唯一こうして言葉を交わし、お前の毒を一身に受けている私の体はもうボロボロだ」 「そんな」 「これ以上ひどくなれば、告解を聞くことも困難になるかもしれない」 ディーンはうろたえた。「神父様が許しを与えて下さらなければおれは……本物の怪物になってしまいます」 「そうだ。だから私は耐えているのだ。だが今日はこれが��界だ。日に日にお前の毒は強くなっていくからな」 神父はローブを脱いで寝台に横たわった。「頼む、やってくれ、ディーン」 ディーンは頷いて寝台に片膝を乗せると、神父の下衣を下ろして屈み込んだ。現れたペニスを手にとって丁寧に舐め始める。 「私の中からお前の毒を吸い取り、全て飲み込むのだ。一滴でも零せば修道院に毒が広がってしまう。お前のためにもそれは防がなくてはならない」 「はい、神父様」 「黙りなさい! 黙って、もっと強く吸うんだ!」 神父は厳しく叱責したが、不出来な子に向けて優しくアドバイスをくれた。「口の中に、全部入れてしまったほうがいい。強く全体を頬の内側でこすりながら吸ったほうが、毒が出てくるのも早いだろう」 心の中でだけ頷いて、ディーンはいわれた通り吸い続けた。もう何度もやっていることなのに、一度としてうまくやれたことがない。いつも最後には、神父の手を煩わせてしまう。彼は自分のために毒で苦しんでいるのにだ。 今回も毒が出る前に疲れて吸う力が弱まってしまい、神父に手伝ってもらうことになった。 「歯を立てたら地獄行きだからな。お前を地獄に堕としたくはない」 神父は忠告してから、両手でディーンの頭を抱えて上下にゆすった。昨夜はワインを飲んだあとにこれをやったからしばらく目眩が治まらなかった。今日はしらふだし、神父がこうやって手を借してくれるとすぐに終わるのでディーンはほっとした。 硬く張りつめたペニスから熱い液体が出てきた。ディーンは舌を使って慎重に喉の奥に送り、飲み込んでいった。飲み込むときにどうしても少し声が出てしまうが、神父がそれを咎めたことはなかった。ディーンが努力して抑えているのを知っているのだろう。 注意深く全て飲み込んで、それでも以前、もう出ないと思って口を離した瞬間に吹き出てきたことがあったので、もう一度根本から絞るように吸っていき、本当に終わったと確信してからペニスを解放した。神父の体は汗ばんでいて、四肢はぐったりと投げ出されていた。 ディーンはテーブルに置かれた水差しの水を自分の上着にしみこませ、神父の顔をぬぐった。まどろみから覚めたような穏やかな顔で、神父はディーンを見つめた。 「これで私の毒はお前に戻った。私は救われたが、お前は違う。許しを得るために、また私を毒に侵さねばならない。哀れな醜い我が子よ」 そういって背を向け、神父は眠りに入った。その背中をしばし見つめて、ディーンは今夜彼から与えられなかった神の許しが得られるよう、心の中祈った。
◇
修道士たちが寝静まった夜、一人の騎士が目を覚ました。 「うーん、とうとう地獄に落ちたか……どうりで犬の腐ったような臭いがするはずだ」 「ルーファス!」 ボビーの声でサムは目を覚ました。地下は狭すぎるが、サムがいなければ全員が横になれるとわかったから厨房の隅で寝ていたのだ。 「ルーファス! このアホンダラ、いつまで寝てるつもりだった!」 ボビーが歓喜の声を上げて長い付き合いの騎士を起こしてやっていた。サムはゴブレットに水を注いで彼らのもとへ運んだ。 「サミュエル」 「ルーファス。よく戻ってきた」 皮肉っぽい騎士は眉を上げた。「大げさだな。ちょっと寝てただけだ」 ボビーの手からゴブレットを取り、一口飲んで元気よく咳き込んだあと、周囲を見回す。「それより、ここはどこだ、なんでお前らまで床に寝てる?」 「厨房だよ。他の皆はこの地下で寝てる。修道院長はあまり僕らを歓迎していないみたいだ。いきなり殺されないだけマシだけどね」 「なんてこった。のん気にしすぎだ。食糧をいただいてさっさと出発しよう」 「馬鹿言ってないで寝てろ。死にかけたんだぞ」 起き上がろうとするルーファスをボビーが押し戻す。しかしその腕を掴んで傷ついた騎士は強引に起きようとする。 「おい、寝てろって」 「うるさい、腹が減って寝るどころじゃない!」 サムとボビーは顔を見合わせた。
三人の騎士は食堂に移動した。一本のロウソクを囲んで、鍋に入れっぱなしのシチューをルーファスが食べるのを見守る。 「で、どうする」 まずそうな顔でルーファスはいう。もっともルーファスは何を食べてもこういう顔だから別にシチューが腐っているわけではない。例外が強い酒を飲む時くらいで、一度密造酒を売って儲けていた商売上手な盗賊団を摘発した時には大喜びだった(酒類は国庫に押収されると知ってからも喜んでいたからサムは心配だった)。 修道院にある酒といえば聖体のワインくらいだろう。ブドウ園を持っている裕福な修道院もあるが、この清貧を絵にしたような辺境の修道院ではワインは貴重品のはずだ。ルーファスが酒に手を出せない環境でよかった。しかし――サムは思い出した。そんな貴重なワインの匂いを、��のみすぼらしい身なりの、納屋で寝ている青年は纏わせていたのだった。 「どうするって?」 ボビーが聞き返す。ルーファスは舌打ちしそうな顔になってスプーンを振った。「これからどこへ行くかってことだよ! 王都に戻って裏切者だか敗走者だかの烙印を押されて処刑されるのはごめんだぜ」 「おい、ルーファス!」 「いいんだ、ボビー。はっきりさせなきゃならないことだ」 サムはロウソクの火を見つめながらいった。「誤魔化してもしょうがない。我々は罠にかけられた。仕掛けたのは王だ。もう王都には戻れない――戻れば僕だけでなく、全員が殺される」 「もとからお前さんの居ない所で生き延びようとは思っていないさ。だが俺とルーファスはともかく……」 「若くて将来有望で王都に恋人がいる私でも同じように思ってるわよ」 チャーリーが食堂に来た。ルーファスの隣に座って平皿に移したシチューを覗き込む。「それおいしい?」 「土まみれのカブよりはな」 「なあ、今の話だが、俺はこう思ってる」 ボビーがいった。「この状況になって初めて言えることだが、王国は腐ってる。王に信念がないせいだ。私欲にまみれた大臣どもが好き放題している。民は仕える主を選べないが、俺たちは違う。もとから誰に忠義を尽くすべきか知っている。もう選んでいる。もうすでに、自分の望む王の下にいる」 「その話、なんだか素敵に聞こえる。続けて」 チャーリーがいう。 「いや、まったく素敵じゃない。むしろ危険だ」 サムはいったが、彼の言葉を取り合う者はいなかった。 ゴブレットの水を飲み干してルーファスが頷いた。「サムを王にするって? それはいい。そうしよう。四年前にあの棒みたいなガキに冠を乗せる前にそうしとけばよかったんだ。野生馬を捕まえて藁で編んだ鞍に乗り、折れた剣を振りかざして、七人の騎士で玉座を奪還する!」 そしてまた顔をしかめながらシチューを食べ始める。「俺はそれでもいいよ。少なくとも戦って死ねる」 ボビーがうなった。「これは死ぬ話じゃない。最後まで聞け、ルーファス」 「そうよ、死ぬのは怖くないけど賢く生きたっていい」 チャーリーが細い指でテーブルを叩く。「ねえ、私に案がある。ここの修道院長に相談するのよ。彼から教皇に仲裁を頼んでもらうの。時間を稼いで仲間を集める。探せば腐った大臣の中にもまだウジ虫が沸いてないヤツもいるかもしれない。血を流さなくても王を変える手はある。アダムだって冠の重さから解放されさえすればいい子に戻るわよ」 「それよりウィンチェスター領に戻ってしばらく潜伏すべきだ。あそこの領民は王よりもサムに従う。俺たちを王兵に差し出したりしない」 「だから、それからどうするのかって話よ。潜伏もいいけど結局王と対決するしかないじゃない、このまま森で朽ち果てるか北の隣国に情報を売って保護してもらって本物の売国奴になる他には!」 「ちょっと落ち着け、二人とも。修道士たちが起きてくる。それから僕の計画も聞け」 「ろくな計画じゃない」 「ルーファス! ぼやくな」 「そうよルーファス、死にかけたくせに。黙ってさっさと食べなさいよ」 サムはため息を吐きそうになるのを堪えて皆に宣言した。「王都には僕一人で行く」 「ほらな」とスプーンを放ってルーファスが特大のため息を吐いた。「ろくな計画じゃない」
◇
行商売りの見習い少年と仲良くなったことがあった。同年代の子と遊ぶのは初めてだったから嬉しくて、ディーンは思わず自分の秘密をもらしてしまった。自分の口で見の上を語る彼に、少年はそんなのはおかしいといった。 「君は神父に騙されているんだよ。君は醜くなんかない、夏の蝶の羽のように美しいよ」 「神様の家で嘘をついちゃいけないよ」 「嘘なんかじゃない。ホントにホントだよ。僕は師匠について色んな場所へ行くけれど、どんなお貴族様の家でだって君みたいな綺麗な人を見たことがないよ」 ディーンは嬉しかった。少年の優しさに感謝した。次の日の朝、出発するはずの行商売りが見習いがいなくなったと騒ぎ出し、修道士たちが探すと、裏の枯れ井戸の底で見つかった。 井戸は淵が朽ちていて、遺体を引き上げることもできなかった。神父は木の板で封印をした。ひと夏の友人は永遠に枯れ井戸の中に閉じ込められた。 修道院は巨大な棺桶だ。 ディーンは二度と友人を作らなかった。
1 note
·
View note
Text
Good night my love
ヴィクトルはタクシーの窓敷居に肘を置き、流れてゆくいくつもの灯をぼんやりと眺めていた。窓から見えるほかの車の中は、楽しげな家族のだんらんだったり、恋人同士の甘い時間だったり、友人たちのふざけあいだったりした。通りを歩いている人たちも互いに手を取りあい、笑顔を向けあっていた。 「今季の曲はもうきまったのかい?」 運転席から声が聞こえた。ヴィクトルはゆったりと脚を組み、愛想よく答えた。 「いま、候補を絞っているところだよ」 「楽しみだね。またヴィクトルのひとり舞台が見られるわけだ」 「まだわからないよ。ライバルだってたくさんいるからね」 「そう言って、結局あんたは金メダルを毎回かっさらっていくじゃないか」 ヴィクトルはほほえんで窓の外に顔を向けた。今季の曲。ライバル。ひとり舞台。金メダル……。 「着いたよ」 「ああ、ありがとう」 ヴィクトルはタクシーから降り立ち、すこし歩いて、上品で華麗な建物の最上階を見上げた。そこはヴィクトルの自宅だった。最上階にはヴィクトルひとりしか住んでいない。だからどこの窓もひっそりと暗く沈んでいた。 「…………」 ヴィクトルは何の感情も浮かんでいない目でしばらく黒い窓を眺め、それから明るいロビーへ入った。警備員が「遅くまで大変だね」と挨拶した。ヴィクトルは微笑してちょっと手を上げた。エレベータに乗りこんで最上階のボタンを押し、壁にもたれる。ポケットに突っこんだ手で鍵をもてあそんだ。到着し、扉がひらくと、長い廊下をゆっくりと歩いて、しっかりした扉の二重鍵を外した。元気な吠え声が聞こえ、ヴィクトルは口元をほころばせた。 「マッカチン、遅くなってごめんね」 さっきまでとはちがう声、ちがう笑顔でヴィクトルは言った。マッカチンはうれしそうにヴィクトルの脚にじゃれついた。 「明日からはしばらくいられるよ。のんびりしようね。リンクへも一緒に行こう」 ヴィクトルは荷物をソファに置き、コートを脱いで無造作に掛けた。手を丁寧に洗ってから手早く着替えを済ませ、冷蔵庫を開ける。中はほとんどからっぽで、水の入った瓶だけがずらっと並んでいた。ソファに座ると、マッカチンが喜んでそばに寄り添った。 「さびしかったかい?」 ヴィクトルは利口そうなつむりを撫でてやり、それからもこもこした身体を抱きしめて頬ずりした。 「……疲れた……」 そっと目を閉じる。マッカチンはヴィクトルの頬をぺろぺろと舐めた。 「大丈夫だよ。問題ない。ちょっと寝てないだけさ。マッカチンといるとすぐ元気になる」 ヴィクトルは水を飲み、茶色い包みから容器をいくつか取り出した。それは彼の今夜の食事だった。どこかで済ませてこようかと思ったのだが、店に入れば誰かに声をかけられ、ほほえみかけられる。ファンのことはいつだって大切にしたいと思っているし、応援には応えたいが、幾日も仕事をして疲れているときは、いつものような気の利いたことが言えるかどうかわからなかった。 「ヤコフのところは楽しかった?」 ヴィクトルは容器を開けながら尋ねた。 「優しくしてもらったかい? ヤコフはああ見えてすぐ甘やかすからな……」 食欲などほとんどない。しかし食べなければ身体が衰弱する。スケートをするためには強い肉体が不可欠だ。ヴィクトルは機械的に食べた。美味いはずだが、美味いとか不味いとか、そんなことを判断する必要を感じなかった。 部屋はしんと静まり返っている。音楽でも流そうか、と考えたが、そのための行動さえ億劫だった。思った以上に疲れているのかもしれない。 このところ、スケートをしていない。それ以外の仕事ばかりだ。笑顔を振りまいて、写真を撮って、質問に答えて……。それを待っている人たちがいる。いやではない。しかしそれでも、ヴィクトルにはスケートしかなかった。身もこころも氷に捧げている。早くスケートがしたかった。金色のメダルを並べてゆく。メダルの数が増えれば増えるほど、その色は最初ほど輝いていないような気がしてきていたが、しかしやはり、ヴィクトルの頭にはスケートしかなかった。 「だめだよマッカチン。これはマッカチンの身体にはよくないんだ。ヤコフのところでもらっただろう?」 迫ってくるマッカチンをかわし、ヴィクトルは食事を続けた。マッカチンを見ているとほっとする。マッカチンだけがヴィクトルを癒してくれる。 「マッカチン……、いつも俺を待っててくれてありがとう……」 ヴィクトルはフォークを置くと、マッカチンの毛並みに顔を埋め、深く息をついた。マッカチンはおとなしくしており、ときおり鼻を鳴らしてヴィクトルを心配した。 「……ちょっと疲れただけなんだ。それだけなんだ……」 早くスケートがしたい。氷に立てば何もかも忘れられる。俺は氷の上でしか生きられない生きものだ。早く氷に戻らなければ……。 使った容器をまとめて片づけ、瓶の水を飲み干した。瓶を流しのすみに置くと、水道の蛇口から、水がぽたりと落ちた。ひろい台所を眺め、あかりを消す。 「マッカチン、お風呂に入ってくるよ。おまえもちょっと洗ってやらなきゃだめだねえ。いつにしようかな……。おまえを洗うのは大変だ」 マッカチンが不思議そうにヴィクトルを見上げた。ヴィクトルはちょっとだけ笑った。 短い時間で入浴を済ませ、身体をぬぐうと、何も身に着けないまま歩いて寝室へ入った。マッカチンがついてくる。 「さあ寝よう。おいで」 ヴィクトルはマッカチンと並んで横たわった。 「明日は一日じゅう一緒にいよう。俺がスケートしてるところ見ててくれる?」 マッカチンが元気に答えた。ヴィクトルは目を閉じた。疲れているはずなのに眠れない。マッカチンに抱きつき、頬をすり寄せた。 ──夢を見た。ヴィクトルは暗い中、リンクにいてひとりですべっている。自分の思うように演技をしている。長い髪がやわらかくなびき、四肢は伸びやかに踊り、ヴィクトルは笑顔だった。だが、だんだんと足が重く、スケートシューズが前へ進まなくなってきた。なんでこんなに重いんだ、と苦しかった。足が上がらない。ジャンプができない。どうして? スケートとはこれほど難しいものだっただろうか。いつの間にかヴィクトルは、大人の容貌になっていた。なぜ上手くすべれない。俺はあらゆるものをつかんだはずだ。自分の道を信じ、すべきことはすべてしてきた。どんなに苦しいことでも厭わなかった。氷のためならなんでもできた。何もかもを投げ出して、氷で生きることをきめたのだ。それなのにどうしていまになって、これほど重さを感じるのだ。俺は──俺は──。 ヴィクトルは足元を見た。何かがからみついている。眉根を寄せ、目をこらした。ヴィクトルは叫び声を上げそうになった。足にからみついているのは、大量の金メダルだった。 身体が激しくふるえ、ヴィクトルは息をのむようにして飛び起きた。一瞬、自分がどこにいるかわからなかった。だが、すぐに慣れた風景が目に入った。機内だ。あちこちからちいさな話し声が聞こえる。隣の席には誰もいなかった。どうやら、あとすこしでプルコヴォ国際空港に到着するようである。ヴィクトルはふうっと息をついた。疲れているのだ、と思った。いやな夢を見た。 空港からタクシーに乗った。運転手は「やあ、ヴィクトル」と陽気に話しかけてきた。ロシ���国民なら、老若男女、誰でもヴィクトルの顔を知っている。 「やあ」 ヴィクトルは笑顔で答えた。 「今季の曲はもうきまったのかい?」 そう尋ねられ、ヴィクトルはどきっとした。 「……いま、候補を絞っているところだよ」 「楽しみだね」 運転手は言った。 「今季はあの子もいるんだろう? えっと、名前はなんていったっけ? ヴィクトルが日本からさらって来た……」 ヴィクトルは笑い出した。胸に安堵がひろがった。 「勇利だよ。ユウリ・カツキ。おぼえてくれ」 「そうそう、ユーリだ。ロシアにもある名前だなって思ったんだよ。かわいい子かい?」 「そりゃあもう」 ヴィクトルは大きくうなずいた。 「文句なしにかわいいよ。どうしようもなくかわいいよ。しかも、かわいいうえにうつくしいんだ。最高だよ」 「へえ、ヴィクトルがそんなに褒めるなんてね。欠点はないのかい?」 「欠点は……」 言うことを聞かないところ。勝手になんでもとりきめてしまうところ。そう思ってヴィクトルは笑った。 「ないよ! すべてが最高さ!」 「へえ。じゃあ楽しみだね」 「今季は彼にも注目して欲しいな。すばらしいものが見られると思うよ。期待しててくれ。勇利の試合、見てくれたかい? グランプリファイナル──ワールドでもいい。ショート、最高にセクシーだっただろう? 普段もあんな感じで俺を誘惑してくるんだよ。俺はもうすぐにまいっちゃうのさ。めろめろだよ。優しそうに見えるのに、ときどき、熱のこもった目つきでじっと俺を見るんだ。そのときのぞくぞくする感じときたらたまらないよ。勇利はどちらかというと無口でね。だから何かを話すとき、全力で耳を傾けたくなる。何も話さないときは──瞳が雄弁だ。俺は夢中でみつめてるんだよ。勇利の目はいつもうつくしく輝いていて──そう、フリーで示すうつくしささ。わかるだろう? あれほどおごそかで神聖な美はないね。静寂と清廉にみちた美だ。あの洗練されたみずみずしさが──」 ヴィクトルの舌がなめらかに動いているうちにタクシーは停まった。 「着いたよ」 「どうもありがとう! 一週間ぶりに勇利に会うんだ」 ヴィクトルははずむ声で言ってタクシーから降りた。すこし歩き、うきうきしながらアパートの窓を見上げる。そこには優しい、まばゆいひかりが輝いていて、ヴィクトルを「早く早く」と手招きしているようだった。ヴィクトルは意気揚々と扉を開け、ロビーに入った。 「やあ、ヴィクトル。お帰りかい?」 「まったくまいったよ! 勇利は元気かな」 「毎日楽しそうにリンクに通って、マッカチンの散歩をしてたよ」 「俺がいないのに楽しそうだなんてどういう了見だ?」 ヴィクトルのおどけた嘆きを警備員はおもしろがり、愉快げに笑い声を上げた。ヴィクトルは踊るようにエレベータに乗りこんで、指揮棒でもふっているかのようなしぐさでボタンを押した。最上階に着くのが待ち遠しかった。 扉の前に立ち、咳払いをして、呼び鈴を鳴らした。すぐにぱたぱたと足音が近づいてきて、勢いよく戸が開いた。 「おかえり、ヴィクトル!」 「わうわう!」 黒いかたまりと茶色のかたまりがそれぞれ飛びついてき、ヴィクトルは両手で抱き止めた。 「ただいま!」 ヴィクトルは笑顔で挨拶すると、マッカチンのつむりを撫で、それから勇利を抱きしめて頬にキスした。勇利が「くすぐったい」と顔を上げる。それでヴィクトルはくちびるにも接吻した。 「んー」 「…………」 「んー」 「…………」 「んー」 「……ちょっとヴィクトル!」 勇利がヴィクトルの胸を押しやり、抗議した。 「長いよ!」 「なんで? 足りないくらいだ」 「まったくもう……」 勇利がヴィクトルのコートを脱がせた。ヴィクトルが勇利をじっとみつめると、それに気がついた勇利が困ったように笑い、ヴィクトルに両腕を投げかけた。 「おかえり……会いたかったよ」 ふたりのくちびるがふれあった。勇利はヴィクトルのおとがいにもキスをしてささやいた。 「手を洗って着替えてきて。ごはんの用意をするよ」 「ありがとう」 ヴィクトルが部屋で着替えていると、台所のほうから声が聞こえた。 「マッカチン、これはあげないよ! そんな目をしてもだめ! なんでそう食いしん坊なんだろう。飼い主に似たんじゃないの。……言っとくけどぼくのことじゃないからね。ヴィクトルだよ。ヴィクトルのこと! ぼくに似てたら、食いしん坊どころか、マッカチンはいまごろこぶただよ。……自分で言ってて傷ついた」 ヴィクトルは笑いをかみ殺した。 食堂へ行くと、夕食の支度がととのっており、美味しそうな匂いと湯気とでみちみちていた。 「ワーオ……いいね」 「何が?」 「いただきます!」 ヴィクトルは元気に言って食べ始めた。しかし、ひとくち食べた瞬間、きょとんとした。 「…………」 「どうしたの?」 「……勇利」 「…………」 勇利はしばらく黙ってサラダを食べていたが、そのうち噴き出し、両手を打ち合わせて「ごめん!」と謝った。 「砂糖を入れすぎました!」 「…………」 「あの……手がすべって……」 「…………」 「でも食べられなくはないでしょ? ぎりぎりいけると思うんだ。ちょっと甘めだけどね……」 「…………」 「次からは……気をつけるよ……」 勇利は上目遣いでヴィクトルをうかがった。ヴィクトルはしばらく神妙な顔で食べていたが、そのうち笑いをこらえきれなくなり、身体をちいさく揺らしながらうなずいた。 「いいよ……フクースナだよ」 「無理に言わなくていいから」 「いや、美味しい」 ヴィクトルは熱心に言った。 「美味しいよ……勇利が失敗しながらつくった料理」 「ばかにしてるだろ」 「本気だ」 ふたりはにらむように顔を見合わせ、それからくすくす笑った。 「途中でケーキを買ってきた。あとで食べよう」 「ぼくにこぶたの魔法をかける気だね」 「オフシーズンだからいいさ。ぷにぷにの勇利を見せて」 「オフシーズンっていうけど、毎日リンク行ってるからね。絶対太らないでいてやる……」 「勇利はこれ、食べないの?」 「砂糖が多いから」 「不味いからだろ」 「ああ! 不味いって言った!」 「おっと……」 ヴィクトルは澄まして「こっちはどうかな」と別の料理にとりかかった。ごく平凡な、誰でもつくれそうな料理だが、これはヴィクトルしか食べられない、ヴィクトルが世界一美味いと思う食べ物だった。 「フクースナだよ……勇利」 食事を終え、勇利が食器を洗うのを手伝った。 「ヴィクトルはやすんでていいよ」 「いや、やりたい」 「変な趣味だね。昔から家事好きなんだ?」 「どうだったかな」 一生懸命食器を洗っている勇利がかわいくて、ヴィクトルは彼の頬にキスした。 「いきなりなんだもんなあ……」 「予告したら照れるだろ。ああ、でも、それならかえって予告したほうがいいのか」 「いきなりでいいです」 「ケーキはお風呂の前? あと?」 「あと。ヴィクトルの淹れる紅茶が飲みたいな」 「オーケィ。お風呂は一緒だからね」 「髪洗ってあげる」 「じゃあ身体洗ってあげる」 「ヴィクトルは身体洗ってくれるとき変なところさわるからな」 「変なとこってどこ?」 「まあいいや」 「変なとこってどこ?」 ヴィクトルは湯につかり、湯船のふちに首をのせた。勇利は椅子に腰掛け、鼻歌を歌いながらヴィクトルの髪を洗った。歌をよく聞いてみると、ヴィクトルがすべったアリアだった。ヴィクトルはくすっと笑った。 「ヴィクトルにシャンプーハットつけさせたいな」 「なにそれ?」 「流しまーす」 「ねえ、なにそれ?」 「目をつぶらないと」 ヴィクトルは目を閉じた。勇利は綺麗に洗い流したあと、「はい、終わり」とてきぱき言った。ヴィクトルはぱっとまぶたをひらいた。 「勇利!」 「わっ、なに?」 「目をつぶらせたらキスするものだろう!?」 「それヴィクトルじゃない。いつもいつもさ……」 「勇利はわかってない」 「ほら、交代交代」 ヴィクトルは湯から上がると、勇利に後ろを向かせ、丁寧に身体を洗ってやった。そうしながら点検してみたが、「こぶたちゃん」になる気配はまるでない。感心である。すこしくらいならいいけどな……。 「ねえ、ヴィクトル」 「なんだい?」 「次のやすみさあ、マッカチン洗おうよ。洗って欲しいって訴えてくるんだよ」 「マッカチンは水が好きだからねえ」 「ぼくがお風呂入ってると、外から毎日催促してくるんだよ。でもヴィクトルがいないと洗えないし」 「オーケィオーケィ。ひと仕事だよね。よし、次のやすみにね」 風呂上がりには、ヴィクトルが紅茶を用意し、勇利はケーキを皿に出した。 「ヴィクトル、どっち?」 「勇利の好きなほうでいいよ」 「じゃあ両方はんぶんこ」 「言うと思った」 ふたりはソファで寄り添い、それぞれひとつのケーキを担当した。片方だけを食べるのではなく、自分が食べ、相手も食べたがったら取り分けて口に入れてやる、ということをするのである。 「マッカチン、次のやすみ、洗ってあげるからね。明日じゃなくて、その次ね。ヴィクトルがいいよって」 勇利は足元に寝そべっているマッカチンに笑いかけた。マッカチンがしっぽでうれしそうに答えた。 テレビに映し出されているのは、ヴィクトルのプログラムだった。勇利の秘蔵DVDである。勇利はよくこれをヴィクトルに見せ、「見て、いまの!」「かっこいい!」「ねえこれぼくもできるかな?」「今度やって!」とひとしきり騒ぐのだ。 「ヴィクトル、なつかしい?」 「俺はあまり演技を見ていない」 「見てよ」 「勇利を見てるほうがおもしろい」 「もー」 勇利はこういうとき、ヴィクトルの手を握りしめ、きらきらした子どもみたいな目でじっと見入っている。しかし時間が経つにつれ、その輝きはなりをひそめ、真剣なまなざしに変化し、最後にはぞくぞくするほど鋭い目つきなる。甘美に誘惑している気配はまるでないのに、ヴィクトルにはそれがこのうえなく魅力的に見える。こころにきめた男を見るときの目だ。こうなると、勇利はひとこともしゃべらない。ヴィクトルは自分の姿にはいっさい注意を払わず、ただ勇利に見蕩れていた。 プログラムが終わると、勇利はふっと息をつき、力を失ったようにぐったりとなった。最後には、ヴィクトルの手は痛いくらいに握りしめられていたのだが、このときようやくそれがほどけた。 「すばらしかったね……」 勇利の視線はうっとりと宙をさまよい、瞳はしとやかに濡れ、頬はひどく上気していた。勇利はヴィクトルのほうを向いて、両手でヴィクトルの頬を包みこんだ。 「ああ……、かっこいい……」 ケーキはもうなくなっていた。ヴィクトルは勇利に真剣なキスをした。 「おいで」 「うん……」 ヴィクトルは勇利を連れて寝室にこもり、二時間ばかり、「おまえがこころにきめた男はどういう男か」ということを教えた。勇利にだけ向ける笑みとまなざしで愛し���勇利にだけ聞かせる声であまくささやいた。 「勇利、もっと俺の愛を知ってくれ。まだあるよ。まだまだあるよ」 「うん、ぼくも……」 勇利もまた、目つきやつぶやき、涙や吐息など、さまざまなものでヴィクトルへの愛情を示し、ヴィクトルのことを喜ばせた。 「はあ、暑い……」 「よかった?」 「うん……ヴィクトルは……?」 「いますぐ『離れずにそばにいて』をおまえのためにすべりたいくらいよかった」 「あはは……」 勇利はヴィクトルの胸につむりをのせ、うっとりと目を閉じた。ヴィクトルは彼の身体をかるく抱いていた。 「汗、すごいね……」 「一緒にシャワーを浴びて歯みがきをしよう」 「うん……寝ちゃいそう……早く行かないと……」 「もうすこしいいだろう?」 ヴィクトルは勇利を引き寄せて接吻した。勇利はくすくす笑っている。ふたりのあいだを、汗が流れ落ちていった。 「……夢を見た」 ヴィクトルはつぶやいた。 「飛行機の中で……」 「どんな夢?」 勇利が目を上げてヴィクトルを見た。 「昔の夢さ」 「昔の、どんな夢?」 「……忘れた」 勇利はくすくす笑った。 「忘れたのに、おぼえてるの?」 「夢を見たことだけね」 勇利がゆっくりと手を上げ、ヴィクトルの頬を撫でた。それからくちびるにふれ��その指でみずからのくちびるをさわった。 「いやな夢だったんだね……」 「…………」 勇利が伸び上がり、目を閉じて優しくくちづけした。いつくしみにみちた、いちずな、愛いっぱいの接吻だった。ヴィクトルは息をつき、きつく勇利を抱きしめた。 「勇利……、もうおまえがいないとだめなんだ……」 「…………」 「どこにも行かないでくれ」 「……うん」 勇利は目を上げ、みずみずしく笑ってうなずいた。 「行かないよ」 「…………」 ヴィクトルは勇利に頬をすり寄せた。勇利の手がヴィクトルの背中にまわる。 「ぼくのいとしいヴィクトル……」 勇利が歌うようにささやいた。 「ぼくはこれまで貴方を想って生きてきたし、これからもずっとそうだし、ぼくはぜんぶ貴方のものだよ……」 彼は額をこつんとくっつけ、ヴィクトルの青い目をのぞきこんだ。 「そして貴方もぼくのもの」 ヴィクトルは夢中で勇利にキスをした。首にくちびるをすべらせると、勇利があえぐような笑い声を上げた。 「ヴィクトル、シャワー浴びて、歯みがきしないと……」 「その前にすることがある」 「もうしたでしょ……」 「まだ……だ」 「足りてない?」 「足りてない……」 「……そう?」 勇利は髪をかき上げてほほえんだ。 「おまえが欲しい」 「貴方のものだって……」 「まだあるだろう……」 ヴィクトルはささやいた。 「もっとよこせ」 翌朝、遅めの朝食をしたためているときに、勇利が元気に言った。 「ヴィクトル、今日買い物行こ!」 「いいとも! なんでも買ってあげるよ。何が欲しい?」 「あの、期待してるとこ悪いけど、個人的なものではありませんので」 「なに?」 「洗剤とかそんなの」 「ああ……」 ヴィクトルはくすっと笑った。それもいいだろう。配達などしてもらうより、よほど楽しい。 「欲しいけど買うには重いものがいっぱいあって……。絶対ひとりじゃ持ちきれないんだよね。ヴィクトルが帰ってくるの待ち構えてたんだ」 「働くよ」 ヴィクトルは神妙な顔をしてうなずいた。 「勇利とマッカチンのために」 勇利が可笑しそうに笑っている。 「お昼は外で食べようか。なに食べたいか考えておいて」 「晩ごはんの材料も買わなくちゃ。夜はなに食べたいか考えといて」 「カツ丼」 「カツ丼かあ……。それだけでいいの?」 「いや、そっちの意味じゃなかったんだが」 「え?」 「えっちなほう」 「あのさ……いまそういう感じだった……?」 「いいだろう、べつに」 「恥ずかしいひとだねえ、マッカチン」 勇利はかたわらにいるマッカチンに話しかけた。それっきりそれで話は終わりかと思っていたら、洗い物のとき、唐突に彼が「いいよ」と言い出した。 「何が?」 「今夜食べたいもの……」 「…………」 ヴィクトルの瞳が輝いた。勇利は頬をうす赤くして言った。 「でもちゃんと、ほんとに夜、食事で食べたいものも考えといて」 ヴィクトルはマッカチンに話しかけた。 「かわいい子だねえ、マッカチン」 その日は一日デートをして、夜にはヴィクトルの希望した肉じゃがを食べて、そのあとはやはりヴィクトルが希望したカツ丼を食べた。充実した時を過ごし、マッカチンと勇利に寄り添われてうとうとしているヴィクトルに、勇利が一生懸命に話しかける。 「ヴィクトル、明日、リンク来るよね?」 「うん……? うん……」 「よかった」 勇利が子どものように笑った。さっきまでの表情とはまるでちがう。 「なんで……?」 ヴィクトルは勇利を抱き寄せながらほほえんだ。 「ヴィクトルがいないあいだに、ぼく、びっくりするようなことになってるから」 「へえ……」 「まじめに練習したんだよ」 「そうか……」 「明日見せてあげるね」 「ああ……」 「ほんとだよ」 勇利が念を押した。 「本当にヴィクトル、めちゃくちゃびっくりするから」 「うん……」 「覚悟してて」 「うんうん……」 「聞いてる?」 「ああ……」 「絶対おぼえてないよこれ」 勇利がこぼした。そんなことはない、とヴィクトルは思った。勇利、おぼえているよ。おまえのことならなんでも……。 「勇利……」 「ん?」 「俺ね……、家へ帰ってくるの、楽しみなんだよ……」 勇利がぱちりと瞬いた。ヴィクトルは勇利にキスし、「おやすみ……」とささやいた。勇利が微笑した。 「おやすみ、ヴィクトル……」 勇利のくちびるが頬にふれた。 「See you in your dreams……」 ヴィクトルはしばしいとしい現実を離れ、現実と変わらずしあわせな夢へと入っていった。
2 notes
·
View notes
Text
01200422
窓の外が白み始める。左に感じる温度が心地良くて、眠りの浅い俺は君が手繰り寄せてくれた微かな睡魔をすぐに追い払ってしまう。
今日も君が先に眠ってしまったね。いや、違うか。君が嫌いな夜から君を守る為に、こうして起きて君を見守ってるんだ。
こちらを向いて眠る君の左手は俺の左の袖をゆるく掴んでいて、まるで何かに包まれていないと眠れない赤ん坊のようで、その指と、爪の形を一つ一つ目で追っては、若干不自由な左腕の力を抜いた。
大人になったはずの君も、時折こうして子供に戻るらしい。温もりを求めてすり寄って、感触を求めて俺に触れて、眠りと死の違いが分からないかのように涙を零すその姿が、いつも胸を苦しくさせる。可愛い、守りたい、愛おしい。そんな単純な言葉を何億注いでも満たされないような、底のない愛。
毎日頑張っていて、君のことを心から偉いと思うし、尊敬してる。そう伝えると君は、「あいしてるよ。」と、決まってそう返す。ありがとうとか、嬉しいとか、寂しいとか、そばにいて、を、君は全てひっくるめて、その柔らかな6文字に心を乗せる。繊細で貴重で、この世の何よりも価値のある綺麗な心のかけらを、惜しげも無く俺に渡してくれる。
カーテンの隙間から漏れ出た白縹色の朝が、君の顔を淡く浮かび上がらせる。その、普遍で神々しい画に、いつか幼い頃岡山の美術館で感嘆した絵を思い出した。
聖母マリアがキリストを授かった事を知らされる場面。受胎告知の場に降り注いでいたのは、眩いばかりの金糸雀色。きりりと緊張で引き締まった聖母マリアの表情。飛んでゆく幸せの象徴の鳩。
宗教に嵌ったことはない。自分以外に頼ることなく、今まで生きてきたつもりだ。寧ろ、他者に縋ってまで生きることを、軽蔑する側の人間だったかもしれない。ただ、こうして君を見て、漠然と神に祈り縋る気持ちが、分かったかもしれない。自分の力がおおよそ及ばない、何か特別な力を感じるもの。
君がゆるゆると身を捩って、掴んでいた袖を離し、俺の身体へと回した。温もりが近付いて、なんだか満足そうな表情にも見える。俺も君に向き直って、その安らかに眠る表情を見つめた。眠っている君は、夜に愛された顔をしている。起きている君に、夜を恐れる君に教えてあげたい。君は世界中の全てから愛されてる、と。
鍵盤の上で踊るピアニストの指のような睫毛、天才的な才能を持つ芸術家が気まぐれに粘土をちょい、と摘んだような小さな鼻、透き通る、触れただけで溶けてしまいそうな白い肌に、いつも決まって桜桃を思い出す、瑞々しく潤んだ唇。触れたくなる気持ちを抑えて、じっと見つめる。
愛おしい、とよく口にするが、愛とはなんなのだろうと考えることがある。愛、愛情、愛憎、愛想。愛のつく言葉は数知れない。
例えば君を閉じ込めたいだとか、誰にも触れさせたくないだとか、君の一番でありたいだとか、きっと大きく見ればカテゴリー上は愛だろうが、厳密には多分それは愛ではないような気がする。
愛を語れるほど歳をとったわけではない。ただ、俺も君も、愛がわからないまま進めるほど若くもない。
俺にとってはきっと、君が進むべき道にある障害と、悲しみをなるべく取り除き、尚且つ、君の幸せをなるべくかき集めて、あくまで自然に、春に降る気まぐれな霧雨のような心地よさで、君に注ぐことが、愛であると定義しておきたい。
俺の重たい愛してるとは対照的に、君のあいしてるは、そうだな、鈴の音のように、夏祭りでどこからか聞こえてくる下駄の音のように軽やかで、それが何よりも嬉しい。
色んなところで噛み合わなかったりする二人だった。ただ、『あいしてる』の凹凸だけは、いつだって、どんな場所だって、どんな状況だって合ってきた。だからこうして、君は俺の前でのみ、安心して眠る。
柔らかな栗色の髪に指を通して、絡ませて、滑らかな頬をなぞって、幸せを噛みしめる。
「愛してる。」
ほとんど空気の漏れる音にしか聞こえない、夢の中の君に届けるための、その言葉。君が俺の服を握って、胸板に顔を埋める。耳を触れば、少し熱い。恐らく赤らんでいるであろうその姿は、白縹ではよく見えない。見えなくて構わない、と思った。君と俺はいつだって、見えていても見えていなくても、互いのことが分かる。
「まだ起きる時間じゃないよ、××。」
愛すべき人の愛で出来た名前を口の中で転がして、頭にやっていた手を背中へと回す。子供じゃないのにと君は嫌がるが、君が案外そういった時間を欲していることに俺は気付いていた。秘密にしているが俺は、君の中で、全てを兼ねる存在でありたいと、そんな強欲な願いを抱いている。その裏にある、醜い望みは、いつか殺しておこうとも思っている。
「おまえは、ねないの。」
「寝るよ。夢で会えるように。」
「じゃあ、ねる、」
「ああ、××、 」
おまじない。昔決めたその言葉を、俺はいまだに繰り返して夢へと出掛ける君を見送っている。呪い、だろうか。呪い、だろうか。君にも、勿論俺にも分からない。ただ、君が幸せである明日が訪れるようにと、そう願っているのは確かだった。
あと2時間、逢瀬にしては随分と味気ない。ただ、会いに行かないと目覚めた君はきっと唇を尖らせて、「待ってたのに。」なんて言うから。
白縹が、浅縹に近寄って、染まり始めた。
緩い弧を描く唇に触れるだけの口づけを落として、目を閉じる。
明日また生まれる君に、
幸あれと祈りながら。
2 notes
·
View notes
Text
iFontMaker - Supported Glyphs
Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマ��ムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微��肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker
#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language
8 notes
·
View notes
Text
月の見えない暗い夜が明けると太陽の見えない白い朝が訪れた。 二つの瞳は夢から半ば覚めていなかった。白い蛍光灯が縦一列に並んでいる天井が酷く眩しく見える。熱を感じさせない観念的なその光は吊り革の丸いプラスチック製の輪、中吊り広告紙の表面、ステンレス製の網棚や手摺り、エナメル質の白い床、シート座席の前に投げ出されている革靴といった列車内の物質に硬い光沢を纏���せ、橙色のシート座席に座っている乗客たちの顔を一つ一つ鮮明に照らし出していた。毎朝見掛けているその顔たちは皆一様に寡黙でモノレールの列車が線路の上を滑る音だけが車内に響いている。その音も地上を走る普通の電車に比べると非常に大人しく、意識していないと忘れてしまう程で、むしろ耳にする頻度が一番多い大きな音は列車が駅に到着する毎に開閉する自動ドアの作動音だった。その音が聞こえて来る度に微睡みの淵へと沈みかけていた意識が再び現実へと戻され、ぼやけた双眼に見慣れた駅名板と開いたドアから入って来る見慣れた乗客たちの姿が朧げに映り込んだ。一日の汚れや垢の臭いに未だ汚染されていない清潔な始発運行列車の中に乗客たちは少しずつ生活の腐臭を運び込んで来た。しかし昼間のましては夕方の列車内におけるあの耐え難い生活の腐敗臭と比較するとやはりそれは遥かに清潔な車内と言うことが出来た。
列車と列車間の連結部には仕切りのドアが設置されておらず、座席に座っていても右や左に視線を遣れば先頭から最後尾に至るまで列車内部の全景を見渡すことが出来た。清潔と静謐の中で蛍光灯に照らされている白い床と両脇の細長い座席に座っている人間の俯いた横顔が真っ直ぐに延びている様子は病院の長い一本の待合い廊下を思わせた。しかし暗鬱な表情をして彼らを待っているものは病気の診断結果ではなくてこれから始まる膨大な一日の耐え難い重圧であり、そういう意味では懲役刑の執行を待つ囚人を乗せて走る護送列車と言い直した方が適切であった。受刑者たちの数は音を立ててドアが開く毎に黙々と増えて、同時に刑の執行される時間も確実に迫っていった。それは夜と朝の狭間を走る列車であり、車内の清潔さや静けさが作��出している安全と秩序の雰囲気がかえってこれから先乗客たちに降り掛かる太陽の暴力と未だ生々しく夜が残る彼ら自身の内に渦巻く闇の暴力を鮮明に際立たせているのだった。 直線的に延びた白い廊下と両脇の長椅子に座り込む人間たち、それは一枚の陰惨な静止画の様に永久に動きを見せないかの様に思われたが、列車が線路のカーブに差し掛かると先頭の車両から順番に右や左にずれていった。顔や身体は依然として微動だにしないままに、今までは見えていなかった一番奥の車両の人間の顔が見え始め、同時に今まで見えていた中腹の車両の人間の顔が消えていく、或いは逆の現象が起こった。手前に見える横顔だけは如何なる時も動かなかった。 それよりも更に注意を引くものがあって、それは列車がその細長い車体を曲げた時に露見する列車と列車を繋ぐ連結部の蛇腹であった。あらゆる構造物がステンレスやガラス、プラスチックといった硬い物質で構成されている鋼鉄の列車内において柔らかそうな灰色のビニールで作られている蛇腹がうねうねと曲がりくねっているその様子はそこだけが異様に生々しく有機的で不吉にさえ映った。それは戦士の全身を完璧に包み込んでいると思っていた鉄の鎧兜に隙間とそこから覗く肉の肌を見つけてしまった時のように、熱中して読んでいた難解な哲学書のページの上に小さな虫が動いている姿を発見した時のように、完全無欠であると思い込んでいた鋼鉄の観念が不意に裂けて生の現実が顔を現す瞬間だった。傷付けられた人体の皮膚と同様にして一度引き裂かれたた観念が回復するには長い時間を必要とし、その間、鎧の戦士は唯の脆弱な肉の塊へと堕落し、哲学書は無意味な文字記号が黒いインクで染み込んでいる唯の紙へと堕落する。それは普段人間によって意識の地下室へと巧妙に且つ厳重に隠蔽監禁されている生の現実が人間に対して復讐する瞬間であり、こういう時に私はいつも生の現実の甲高い笑い声を聞いているような気がする。時にはその顔姿までが心にはっきりと浮かんで来ることもあって、それは挑発的で豊満な肉体を真っ黒なドレスに包んでいる魔女だった。優雅に伸びた両腕の先に細い指の一本一本が独立した生き物の様に蠢き、鋭く尖った鉤爪が空中に赤い軌跡を描いている。気品ある白く細い首元には逆さの十字架に絡まっている髑髏のネックレスをぶら提げ、嘲弄と侮蔑に歪んだ笑窪と蠱惑的な赤い唇からはありとあらゆる下品で下劣な罵りが最も高貴な言葉で語られる。高慢さの象徴である高い鼻、救いや同情の声などには一切反応しない冷酷に尖った両の耳、やはり嘲弄と侮蔑に歪んでいる細長い眉の付け根、長い睫毛の下に隠されがちな暗い夜そのものを映し込んでいる虚ろな瞳……全ての物を飲み込んでしまう相対性の黒い魔女。 唸る様な囁く様な声を響かせて巨大な蛇に変身した魔女が今もその艶めかしい蛇腹を右に左にくねらせている。不安や不快感が心に押し寄せて私は列車の連結部から目を逸らす。しかし気が付くと直ぐ蠢く蛇腹の襞に見入っている。見たくないのにどうしても見てしまう。それは自分の肌に出来た裂傷を絆創膏を捲って何度も何度も見てしまう、更に重症化すると傷口に指先を這わせてその苦痛を味わおうとする、あの感覚に酷似していた。 普段から意識の散漫な私は道端で転んだり硬い机の角に脚をぶつけたりするなどして腕や脚に怪我を負うことが少なくはなかった。そうして怪我をする度に肌の表面に造られる傷跡や青痣は酷く私を高揚させた。更にもっと酷い傷を負い、鮮血が流れ出した場合などは尚の事私の興奮は音楽の様に高まった。 偶然の怪我は自分を包み込んでいると頑なに信じていた肉体という観念の鎧を容易に破壊した。肌の裂傷、青痣、赤い血は私内部の露出した生の現実であると同時に刻みつけられた外の世界の生の現実だった。傷跡は私の内と外の現実を一つに繋ぐ結合地点、私の肌に刻まれた世界そのものの爪痕だった。傷跡が自分の身体に出来たその夜は恋人につけられた首筋の噛み跡を愛でる様に新しい傷跡を撫でてながら安心してベッドの上で眠った。 しかし私は自分で自身の肌を傷付けようとは思わなかった。或いは或る種のマゾヒストたちの様に誰かの指に握られた薔薇鞭に尻を打たせようとも思わなかった。自分の意志が僅かでも混入していたらそれは純粋に外の世界の生の現実が付けた傷跡ではなくなり、私の内側と外側を一つに繋ぐ聖痕としての資格を失うからであった。完全に偶然、つまりは不意に訪れる運命の一撃だけが唯一正統な傷跡を創成することが出来るのであり、更にはこうして傷を受けることを望み意識している状態で傷を受けることさえも傷跡の純粋さを著しく傷付けるものだった。だから自暴自棄の人間に聖痕が刻まれることは永久にないのであって、その点、私は或る程度合格点に達しているようだった。それが擦り傷であれ青痣であれ出血であれ、普段日常の私は自分の身体が傷付けられる事を他の何よりも恐れ且つ拒否していた。 しかし、繰り返し連結部の蛇腹に目を遣ったり逸らしたりしているうちに段々と私は軽い吐き気を伴う眩暈を感じ始めて完全に視線を前方へと固定した。このままその暗い淵に意識を向けていては度々私を襲う狂気の発作が発動するという予感がしたからであった。 視界の向かい側には幾何学模様がプリントされている橙色のシート座席に乗客たちが並んで静かに座っていた。その顔の殆どは俯いていて、例外的に俯いていない顔の大抵は口を開いて眠り込んで居る顔だった。寝顔は間抜けでもあり無邪気にも見えた。それは人間から人間性の全てを剥ぎ取った顔、つまりは一動物の顔であって、間抜けさや無邪気さといった印象はそこから来るものであったが、一動物の顔には危険さも醜悪さも皆無で、永遠に目覚めなければ私はこの顔を愛することさえも出来たかもしれなかった。しかし一方で目覚め始めている顔というのはとても直視出来るものではなかった。それは醜悪さから目を背けるというよりもそうした顔が私に恐怖や不安を呼び起こすからだった。 より厳密に言い表わすならばそれは顔というよりは形成される過程の顔だった。長い夜の間にばらばらに分裂して夜の体液に溶け切った顔は良く晴れた朝ならば朝陽を浴びて迅速且つ順調に形を作っていくのだが、曇って朝の光が乏しい今朝のような条件下では顔の制作工程が著しく停滞するらしかった。中途半端で脆弱な構造しか持っていない顔はその中にある膨大な夜を覆うことが出来ずに、目玉は真っ赤に充血し、顔全体が吹き出物の様に腫れて、毛穴という毛穴から夜が絶えず漏洩している様に見えた。それは無限の夜を圧縮して閉じ込めている爆弾であり、爆弾が周囲に暴力を撒き散らすものならば爆弾そのものと言うことも出来た。 列車の橙色のシート座席の上に爆弾が所狭しと並べられいる。爆弾自身も自らが爆弾であることは十分に自覚しており、瞳を閉じたり俯いているのは爆弾を刺激して暴発することを防ぐ為であった。爆弾が爆発して最初に破壊されるのは作り始めている自分の顔であり、それは自分自身が破壊されるのと同義語であることを爆弾自身が一番認識していた。 しかしこうして動物の顔や爆弾の顔を眺めていると、普段昼間太陽の下で見ている顔が如何に作り物なのかが良く理解出来る。結局、顔というのは衣装と同じで本当の中身を隠すものに過ぎないのだろう。その本当の中身というのは夜であり暴力、更に突き詰めれば虚無であって、ただその虚無を覆い隠す方法の差異が顔貌の差異として表出し見えているに過ぎないのだろう。 それならば一体私は今何を見ているのか?顔ではない。夜と溢れ出ようとする夜を見ているのだ。しかしそういう私自身も目玉が真っ赤に充血し、顔全体が吹き出物の様に腫れて、毛穴という毛穴から夜が漏洩している、今にも爆発しそうな夜の爆弾だった。つまりは夜が夜を眺めているのであった。しかし視線の先に見える夜の傍らに見える窓からは歴然とした朝に包まれている外界が映っていた。私の視線は重苦しい夜の顔たちから逃避する様に窓の外の景色へと吸いこまれた。 窓の外から見える空は遍く白い雲に覆われていた。しかし限りなく密集して飽和状態にある雲はもはや雲としての意味を失い、そこにあるのはただの白い空だった。その白い空の遥か下界には住宅の屋根や自動車が列を作っている道路、時折広大な畑や野原も見えた。走馬灯の様に窓枠の中に現れては瞬く間に消えていく下界の風景は視線の先にどこまでも続いていくかの様に思われた。しかし、彼方の地平線に厳然と聳え立つ蒼黒い山脈が広がっていこうとする風景をその豊かな下半身を盾に堰き止めていた。狂暴な竜の下顎に並んでいる鋭い歯を思わせる山脈の稜線は視線の端から端まで途切れることなく続き、その雄大な��躯は列車がどんなに移動しても微動だにしなかった。 天上は白い空に塞がれて、視界の奥行きは蒼黒い山脈に遮られ、それは無情な観念の世界に逃げ場なく閉じ込められているのだという感覚を強くさせる窓の景色だった。しかし、良く見ると白い空と蒼黒い山脈の間には青い空が垣間見えていて、白い空、青い空、蒼黒い山脈という縦並びの一枚絵が視界の奥に完成していた。白い空と蒼黒い山脈の間になぜ青い空が見えるのか最初解らなかったが、暫くして、この近辺一帯の空は白い雲に覆われているが蒼黒い山脈の上方に限ってのみ晴れ渡っているのだということを理解した。同時にその垣間見えている青空に私の意識は強く惹き付けられた。なぜなら真っ直ぐに引き裂かれたその青い一本線が白い天井と蒼黒い壁に包囲されている密閉空間に唯一開かれた脱出口の様に映ったからであった。 それはドアや窓が無く完全な密室状態だと思われていた部屋の白い壁に小さな穴を発見したようなものだった。穴にぴったりと張り付いた瞳にとってそこから見える青い空は狭い部屋に対する広い世界の、有限に対する無限の象徴として映り込むだろう。やがて小さな穴は狭い部屋に閉じ込められている彼にとって広大無辺の世界に通じている唯一の脱出口として輝き始めるのだ。 しかし、もし仮にだが部屋にドアや窓が付いていた場合はどうだろう。白い壁に空いている小さな穴は脱出口としての意味や条件を失い、脱出という行為そのものが不可能になる。脱出を可能にするためには密室が必要であり、脱出口の輝きが出現するためには完全に部屋を塞いでいる白い天井や白い壁が必要なのだ。 今、街の上を走るモノレールの長椅子に座って窓の外に眺めている彼方の青い空がこの狭い車内及びこの小さな街からの脱出口として急速に輝き始めているのは私の頭上を白い空が覆い隠し、更には視界の行く手に厳然と巨大な蒼黒い山脈が立ち塞がっているからだった。脱出口が完成するためには、つまり密室が完成するためには白い雲に覆われた空だけでは不完全であり、晴れた空と蒼黒い山脈だけでも不完全で、今朝の様に白い雲に覆われた空と蒼黒い山脈が現れることが絶対的な条件なのだ。 しかし、この密室も私にとって完全な密室ではないことは、瞳こそ夢から覚め切ってやや熱くなり始めたものの身体の方は依然として柔らかい長椅子に深く沈まったままである姿勢からも明白であった。何度も何度も窓硝子にぶつかり最後には力尽きて窓の縁で死んでしまう蠅や黄金虫にとっての部屋や窓硝子程の意味にまではあの白い空や蒼黒い山脈も青い空も私の中で到達していないのだろう。 結局は、精神的にであれ肉体的にであれ自己の存在を圧し潰す���な恐ろしい危機だけが脱出を可能にするのだろう。つまりはこう言い換えることも出来る。自己の死に瀕している絶望的な瞬間にのみ彼は本当に自己を生きようとすることが出来るのだ。 しかし私が今こうして通勤の車内に揺られて仕事場へと向かっているのも、仕事に行かなければ肉体的精神的危機を迎えるからであった。とはいってもさほど大した危機などではないことは通勤する私の緩慢な態度からも伺える。本当に危機で本当に脱出口がその先にあるのならばこうして脇目を振って窓の外など見てはいられない筈だ。完全な危機に瀕している人間は脱出口以外に注意を向けることはないし、自分の中にあるありとあらゆる力を動員してそこに向かっていくだろう。 そうした推測からは逆説的な事実が導き出される。それは恐ろしく精力的で活発に動き回る人間、つまり本当に生きている様に見える人間の内側は絶えず精神的肉体的崩壊の危機に瀕していているということである。彼は絶えず彼自身を襲う破滅の危機から逃れるために絶えず活発に動いているのである。 しかし、それならば生きているとはただ単純に死から逃避しているだけなのかもしれない。その死とは肉体的な死というよりも自分自身の死である。 自殺者の瞳に世界は刻々と自分自身を圧し潰す完全な密室の様に映り、だから必死に脱出口探し続けるが、最終的にやっと見つけた壁の小さな穴こそ死そのものなのだ。小さく丸い穴は彼の中で徐々に膨張を開始し、やがて視界の全てを覆う巨大な太陽へと成長する。それは客観的に第三者の瞳から見れば黒い虚無のブラックホールなのだが、究極に追い詰められた人間の瞳には燦燦と輝く光と生そのものである太陽の如く映る。永遠で普遍的な神とほぼ同義語であるその太陽の光や熱に自分自身を同化させることが自分自身を普遍化し永遠に生かし続ける唯一の方法だと考えて、彼は夏の虫たちの様に太陽に向かって飛んで行くのだ。 と考えたとき、突然私の心に日の丸が浮かんだ。同時にあの国旗は密室の白い部屋に空いている丸い脱出口なのではないだろうかと考えた。しかしその穴から見えるのは青い空でも黄色い月でもなくやはり太陽なのだった。それも白い空に赤く燃えている太陽であって、同時にそれは白い観念が引き裂かれて顔を見せた赤い現実であり、白い死に装束を身に纏って果てた人間の打ち落とされた首に浮かぶ赤く丸い傷跡だった。
0 notes
Text
#066 オリエンタルコンクリート(1)
男も女も大人も子供も白人も黒人も黄色人種も社会人も学生も先生も生徒も日本人もアメリカ人もイタリア人もチェチェン人も総理大臣も大統領も天皇もクー・クラックス・クランもロスト・ジェネレーションもヤリマンもヤリチンも処女も童貞もヤクザもカタギも、みんなみんな、オナニーしてるんだよなあ、と考えると、どんなことも許せるような気がする。落ち込むことがあったり、人やモノにムカついたり、悲しみに暮れたり、何かとてつもなくひどい目にあったとき、そんな想像をすると、心が穏やかになる。への字口が微笑みに変わる。なんでも許せるような気持ちになって、ああ、みんなそうやって生きてるんだなぁ、と思う。敵も味方も、自国も他国も、いじめっ子もいじめられっ子も、絶頂に達する瞬間は、それぞれの場所で、たった一人なのだ。すべての垣根を飛び越えて、ただのニンゲン、ただの動物になるのだ。戦争、紛争、争い、諍い。すべてを超えて、すべてを忘れて、人はオナニーをする。どこかの国と国が戦争を起こしそうになったとき、みんながそんな想像をしていれば、すべてがバカバカしくなって、あーもういいよやめよーぜドンパチ、と言い出す人がたくさん現れるんじゃないだろうか。だって嫌だ。安心して、穏やかな場所で、絶対的に一人でいられる場所で、確実にオナニーができなくなる世界なんて。そんなの絶対に嫌だ。みんな、嫌なはずだ。ともすれば、オナニーは世界を平和にする、たった一つの完璧な手段なのかもしれない。さあ、みんなで想像しよう。シンクオナニー。ラブアンドピースアンドオナニー。
午後5時半。帰りの会も終わりダラダラと居残っていた女子もいなくなり、校庭でたむろしていた男子も帰り支度をはじめたころ、ぼくは4年��組の教室の、一番後ろの席よりさらに後ろ、窓際の、掃除用具が入っている巨人の筆箱みたいな灰色の物置と窓の間のすきっ歯みたいに微かに空いたスペースにうずくまっているミヨシを見下ろしていた。 「ねえ」 ぼくは右腕に持っているホッチキスをカチカチ鳴らしながらミヨシに声をかけ続ける。 「ねえって、ば」 ば、という声と同時にぼくは身体を抱え込みすぎて埋もれそうになっているミヨシのアゴの少し下のあたりを、足でやさしく蹴り上げる。やさしく、というのは、ぎりぎりアザにならないレベル、ということだ。 「早く受け取ってほしいな」 できるだけ穏やかに、のんびりとした口調でぼくは言う。蹴り上げたことにより顔が上がり、けれど目線だけは床の木製タイルのつなぎ目あたりに泳がせているミヨシの、その目線の先に、ぼくはホッチキスを差し出してやる。 「これ。ホッチキス。ぼくのなんだけど」 「ふ……」ミヨシの視界がホッチキスを避けようとしているのがわかる。 「おーい」 ぼくはゆっくりかがみこんでミヨシのアゴを思い切り掴む。ぼくとミヨシの顔は今、至近距離で対面している。はじめは目を逸らしていたミヨシは、どうやらそうしないとぼくが一生この体勢のまま動かないとでも思ったのか、意を決したようにぼくの目を見た。いい子だ。かわいい子。ぼくはうっすらと口元だけで笑いながら、さっき蹴り上げたミヨシのアゴを確認した。うん、アザにはならないはず。上履きの先端をもう少し硬く改造できないかな。ライターで炙ったら、どうだろうか。 極度の緊張でまばたきを忘れているのか、ミヨシの眼が水気を帯び、涙が目尻に溜まりはじめていた。いじらしい、ってこういうことだろうか。ぼくは昨日の夜、父さんの部屋の本棚からてきとうに選んで読んでいた西村京太郎のトラベルミステリで出てきた単語を思い出す。ミヨシ、ああ。ぼくとミヨシの顔は限界まで近づき、額と額がぶつかり合いそうになったところでミヨシは目をつぶり、ぼくは顔を横にそらせて唇を舌でしめらせてから、ミヨシの右目尻にキスをした。唇を離すとき、ミヨシの皮膚とぼくの唇が唾液によってできた線で一瞬繋がり、ぴふ、という、風よりも微かな音と共にまた離れた。ぼくはその唾液の跡を確認するように舌先で同じ場所を舐める。その間ミヨシは何度も身体を小さく震わせていて、ぼくは思わず荒い鼻息を漏らしてしまう。ミヨシについたぼくの唾液が、すぐ横の窓から差し込む夕陽に照らされテラテラと光っている。その姿に圧倒的な美しさを感じながら、ぼくは感動を悟られないように呼吸を整えてから顔を離し、両足のスネの前で固く結ばれているミヨシの腕を解き、ホッチキスを手渡した。 「かんたんだよ」ミヨシの手首を強く握ってぼくは言う。「すぐ、だよ」 「あの、ぼく」ミヨシの目は手の中に収まっているホッチキスとぼくの目を行ったり来たりしていた。 「ぼく?」 「ぼくは、あ、は……」言うべき言葉がそのまま口から出てこないもどかしさからか、ミヨシは小さく折りたたんでいた両足をさらに身体の中へ中へと押し込んでいくような素振りを見せた。 「だいじょうぶだよ」ぼくはこれまでで一番やさしい声を出す。「こうやってね、それを、口の中へ入れて、ベロをちょっとだけ出してね。その、ベロに、その、ホッチキスを挟み込んでね、あとは、手に力を入れるだけだよ」 「う、ふ」ぼくが言葉を区切るたびに、ミヨシは目を固く閉じ、首を縦に振ったり横に振ったりしている。もう、よくわからなくなっているんだろう。この状況が。この時間が。 ぼくがミヨシをこうして追い詰めはじめてから、すでに1時間は経っていた。 短く刈り込まれたミヨシの頭を撫でる。ランドセルの肩紐を律儀に掴んで通学路を歩くミヨシ。理科の実験で試験官を落としてあたふたするミヨシ。給食を食べるのが誰よりも遅いミヨシ。昼休みの最初から最後まで自分の机から離れず手塚治虫の漫画を読みふけるミヨシ。音読が下手なミヨシ。あらゆるミヨシがぼくの頭に浮かび、そして今、極限まで追い詰められ、なすがまま、ぼくに頭を撫でられているミヨシと繋がる。誰よりも地味でドジで目立たない日陰者のミヨシ。そのミヨシにぼくは今、スポットライトを当てているんだ。誰よりもミヨシがミヨシらしく輝く瞬間に、ぼくは立ち会っている。みぞおちの辺りを思い切り蹴りあげたい衝動を押さえつけながら、ぼくはミヨシに声をかける。 「さあ。ほら。だいじょうぶ。だいじょうぶなんだよ」
保健の授業で、担任の柏木がニヤリと笑い、 「さてみんなに問題です。赤ちゃんは、なーんーで、できるの、で、しょうか」 と黒板に同じ言葉を書きながらぼくらに問う。 にわかに騒がしくなった教室で、ぼくは一人シラけた気分で机の隅を指でこすっていた。手をつなぐ! なんだよそれカンタンすぎだろ。そういう特別な手術があるんだよきっと。どういう手術だよ。愛し合っていれば自然にできるんじゃない? だから自然ってなんなんだって。ていうかそれオレら必要? 男子は口々に自分の考察を発表し、別の男子や女子がそれに難癖や反論を加えていた。柏木は黒板の端に「仮説」と書き、みんなの意見を馬鹿丁寧に書き並べていった。 「そんなの決まってんじゃん」 後ろの席でチートスが声を上げる。 「キスだよキス」 「わたし、ちっちゃいころ弟とキスしたことあるけど、子供できなかったよ」 教室の窓側から数えて二列目の、一番前の席に座っているコトチーがすかさず口を尖らせて反論する。こいつはチートスの言動になにかと突っかかるクセがあるのだ。 「それは、それはさ」しばらく口ごもってからチートスは言う。「そのころはまだ、オレらの身体にそういう、えっと子供ができる機能? みたいなのがちゃんとできてなかったんだよ」 教室の数人から、おー……、という、納得と感心が入り混じった声が漏れる。柏木はそんな教室を一望してにやにや笑っていた。 「キスの仕方も関係、あると思う。あと、確率、みたいなのも、あるんだと思う。キスしたら確実に子供が産まれるわけじゃないっていうか」 そこまで言ってチートスは黙りこみ、教室の空気も、なにやらそれぞれが考えこんでいるのか、小さなざわめきが聴こえる以外は、表立って発言をする者はいなくなってしまった。コトチーも、一人、机の一点を見つめて黙って腕を組んでいる。 ぼくは脚を投げ出して頬杖をつきながら、誰も座っていない目の前の席をぼんやり見つめていた。ミヨシは今日、学校に来ていない。少しいじわるしすぎただろうか。ミヨシの机の引き出しに昨日ぼくが渡したピンク色のホッチキスが入れられているのが見えて、ぼくは股の周辺が熱くなっていくのを感じる。何度か脚を組み替えながら、ぼくは頬杖をやめてピンと背筋を正してみる。それを見ていた柏木が、なにを勘違いしたのか、 「トラくん、どう思う」 とぼくに意見を促してきた。 ざわめきが収まり、教室中の顔という顔がぼくの方向を見る。チートスもたぶん、目の前にあるぼくの背中をじっと見つめているのだろう。コトチーは腕を組んだまま首だけを曲げて、眉間にしわを寄せてぼくを見ていた。あんたこんなナイーブな話題に対してヘンなこと言わないでちょうだいよ、といった顔だ。コトチーの左隣に座っているガンバは両肘を机に付いた状態で微動だにしない。眠っているのだろう。柏木から一番近い席に座っていながら、大した度胸だ。その姿がなんだか冬眠前のクマのようでぼくは目を細める。 「不思議だよねえ、よく、コウノトリが運んでくるんだよ、なんて言うけど、ほんとなのかなあ。お父さんお母さんに、そういうこと、聞いたことあるかなあ、みんなのお父さんお母さんは、なんて答えたのかなあ、ほんとうは、どういう仕組みで、みんなは産まれたのかなあ、ねえ? トラくん、ねえ?」 「ちんことまんこです」 ぼくは柏木に聞こえないように小さく舌打ちをしてから間髪入れずに言ってやる。コトチーの鼻から息が漏れる音が聞こえたような気がした。 「正しくは女性器、膣、ヴァギナと、男性器、陰茎、ペニス、その二つが接合し、ペニスから発射される精液に含まれる精子というオタマジャクシ状の生殖細胞がヴァギナの奥を進み卵子という細胞と接触、結合することにより細胞分裂が起こり胎児、つまり現在のぼくたちの原型のようなものができあがっていきます。ちなみにペニスから精液を発射させるためには恒常的かつ適度な刺激が必要とされていて、ああそうだった、女性器にもある程度の刺激が必要ですね、その刺激を自らで自らの性器に与える場合もあり、これを一般的にオナニー、または自慰と言います。そして主に男性と女性がお互いの性器を刺激し合うことを性交、エッチ、セックスと呼び、これは一般的にお互いを恋い慕っている者同士が行うものだと認識されています」 「よく知っているねえ」 男、女、ヴァギナ、ペニス、精子、卵子、性器、と、柏木はぼくの発言からキーワードを抜き取って黒板に書き出した。知っている者、知らない者の反応がここで一気に分かれる。知らない者は一体こいつはなにを言ったんだろうという顔できょとんとしている。知っている者はなんとなく気まずそうだ。顔をうつむけている男子、女子。醜くニタニタ笑う男子。顔を近づけてコソコソとなにごとかささやき合っている女子、女子、男子、女子。教室の空気が微妙に変化したのを察知したのか、���ンバの身体が一瞬大きくビクンと揺れて、何事もなかったようにゆっくりと目の前の黒板に顔を向けた。チートスは机から思いっきり身を乗り出して、なあ、つまりどういうこと、とぼくの耳元で言う。コトチーはもうぼくを見ていない。スカートの裾を直してから、寝ちまったよ、いったいなんの話をしていたんだ? というお決まりの困り顔でコトチーを見つめるガンバの太もも辺りを引っぱたいて、黒板に向けてアゴをしゃくった。 ぼくは無性に腹が立って、もう一度小さく舌打ちをした。ダメなんだ。こういう状況が。知っていながらなにも言わない連中の醸し出すぬるい空気にアレルギーを起こしそうになる。ヘタクソな演技。身を乗り出したままでいたチートスがぼくの舌打ちを聞いて、なんだよ、なにキレてんだよ、とおどおどしながら身体を椅子に戻した。ぼくは貧乏ゆすりを抑えながら、にらまないように目を見開いて柏木に顔を向ける。 「そうだねトラくん。男の子の身体には、ペニスという性器がついていますねえ。ちんちん、ちんこ、という呼び方のほうが、みんなにはなじみが深いかなあ。そ、し、て。こっちのほうは、知らない子のほうが多いんじゃないかなあ? 女の子の身体には〜、ちんちんが付いていないねえ。そのかわりに、ヴァ〜ギ〜ナ、ヴァギナという、窪みのようなものがあります」 柏木はあくまで、まんこ、という言葉を使わない気でいるらしい。 くそばばあが……とぼくはつぶやく。 詳しく説明してあるビデオがあるから、それを観てみましょうねえ。と言いながら柏木はビデオテープをセットし、テレビの電源をつけた。 大人はいつからぼくらのことを侮るようになったんだろう。テレビに映る砂嵐を見ながらぼくは夜眠る前にいつも頭に浮かぶことを思った。 流された映像は、まさに今このときのために作られました、という雰囲気で満ちあふれた、いかにもな教材映像だった。仮病やほんとうの病気で学校をお休みするとき、間延びしたようなお昼どきによく観るNHKみたいな感じ。のっぺりした女の声が、簡素な空間で男性器と女性器の模型をいじくっている人間の手の動きに合わせて、性交の説明や避妊具の解説をしていた。みんな、静かに、食い入るように画面を見つめている。意外だ。でもそれはそうか。ぼくらはもう10歳で、小学4年生で、親や先生や周囲の大人のふぬけた予想よりはるかに多くのことを、知っているし、知ってしまっているし、そしてこれからも多くのことを知ってしまうだろうという微妙な予感もちゃんと抱いている。性についてなにも知らないような奴らも、かわりに同じくらい別のなにかを知っている。知っていること、知らないことの、なんていうか、レベルや経験値の振り分けが違うだけで、ぼくらの知識の総量はきっと、同じなんだ。そしてきっと、大人とぼくらの知識の総量も、変わらない。ドロケイの必勝パターンやドッチボールの自己流投球フォーム、でたらめな言葉で会話すること、一人一人の言動や身なりにピッタリよりそっているような抜群のアダ名をつけるセンス、良いぺんぺん草の見分け方、泥団子をピカピカに磨き上げる技術、百科事典で4時間遊ぶために必要な想像力と創造力、そういうなにもかもを大人たちは惜しげも無く捨て去って、脳みその、からっぽになった場所に別のものを、タイクツななにかを、社会の教科書にのっているたくさんの歴史上の人物、例えば織田信長、フランシスコ・ザビエル、聖徳太子、大塩平八郎、その人物画みたいなぼやけた眼、かすんだ顔をして、詰め込んでいく。 ミヨシ。ミヨシがいない。 ぼくはミヨシのことが知りたかった。 誰よりもなによりも、ぜんぶをぼくの中に詰め込もうと思った。テレビの画面は、精子が膣の奥へ奥へと進んでいく3Dアニメーションを映している。ぼくはミヨシの奥へ奥へ、入っていくのだ。あるいは奥へ奥へ、入ってくるミヨシを受け入れていくのだ。その方法を大人は教えてくれないということもぼくは少し前に知ってしまった。あくびをこらえすぎて左目から涙がたれる。にじんだ視界からでもコトチーの一つにくくられた後ろ髪の形くらいはわかる。今日はコトチーと帰ることになるだろう。怒られるかな。やだな。
ゴ。 いいい―――――――――――ん。 眼を開けたぼくの視界にふす――――んと厚ぼったい鼻息を繰り返すカラスウリみたいな頬の父さんが見える。 ぼくは布団の中にいて、父さんはぼくに馬乗りになっている。 しなびたボンレスハムみたいに筋張った父さんの左手は、ぼくの両腕を掴んで離しそうにない。 ぼくは寝ながらバンザイしているみたいな体勢で、父さんの眼、頬、唇、額、そしてもう一度眼を見る。にらまないように眼を見開く。 「おい」 ふす――――ん。 ゴ。 視界が一瞬青くなり、ぼくは顔をしかめようとする動きを必死にこらえる。酔った父さんは頭突きの加減を知らない。いいい―――――――――――ん。 「おい」 父さんの声を聴くと、ぼくはいつも、歌えばいいのにと思う。びっくりマークをつけなくても、びっくりマークをいくつ付けても足りないくらいどこまでも響いていくその太く伸びやかな声ならば、きっとどんな歌も祈りのように美しく切実な音に変わるのに。 「てめえは、なんに、なりてんだ。あ?」 ゴ。ゴ。ゴ。ゴ。 こういうときにミヨシのことはあんまり思い出さない。むしろ思い出すのは体育の授業、息をぜえぜえ言わせながら汗だくでサッカーボールを追いかけるガンバのことだったりする。明日は学校に行ったらガンバの机の前まで行って、今日観た『笑う犬の冒険』の話をいつもみたいにしよう。ガンバはホリケンが好きだから、ホリケンの言動をオーバーに真似するだろう。ぼくは泰造が好きだ。そしてコトチーはそんなぼくらを横目に漢字ドリルを進めたりするんだ。家はお兄ちゃんがいるから今やるの、とか言いながら。 「聞いてんのかっつってんだよ」 この家は父さん専用のスピーカーなんだと思う。壁、天井、ドア、柱、すべてが父さんの声に合わせて振動し、増幅されてぼくの耳を限界まで震わす。 「てめえはいいよな毎日毎日メシ食ってクソしてテレビ見てそれで終わりなんだからよ。てめえオヤジがくたくたで帰ってきてその態度はねえんじゃねえの」 その態度。 お風呂に入って歯を磨いて布団にもぐって眠ることを言っているのだろう。 「てめえ将来なんになりてえんだよ。おい」 耳鳴りが起こり、視界の中で父さんの顔、腕、身体が遠くなっていく。カメラのズームアウトみたいに、部屋と一緒にどんどん小さく縮んでいく。父が黙ると家全体も静まり返る。母さんはたぶん、寝室かキッチンでうずくまっている。明日は母さんのどこにアザができているか、ぼくは一瞬眼を閉じて予想してみる。鎖骨かな。数日前はこめかみだった。 なにも言葉を発しないぼくに飽きたのか、壁にとまっているハエを叩き殺すようにぼくの顔面を正面から平手でぶっ叩き、父は立ち上がって部屋から出ていった。ぼくはしばらく、バンザイの体勢のまま、天井を見つめ、自分が息を吸ったり吐いたりする音を聴いていた。枕の下に入れてある小さなマイナスドライバーを取り出して強く握り、横に寝返りをうつ。身体を布団の中で小さく畳んで、自分の腕を見つめる。眼を閉じて、服の上から自分のペニスをそっとなでる。マイナスドライバーの先端を舐める。外で強い風が吹き、窓ガラスが音を立てて揺れる。今夜はさらに冷え込みそうだ。
「うそつき」 「なにが?」 「昼休み」 「ああ」ぼくは砂利をおもいっきり蹴飛ばす。「うそじゃないよ」 「うそでしょ」コトチーも、地面の砂利を蹴るように歩く。 高速道路の高架をくぐり、獣道を抜け、深緑色に濁った真間川に沿って、ぼくたちはもう三十分くらい歩いている。コトチーと一緒に学校から帰るときは、いつだって遠回りをした。大人の身長ぎりぎりくらいに架けられた薄暗い橋の下を通る。なにを獲るためなのかわからない漁船やボートが連なって停められている。おばあちゃんの髪の毛みたいな藻が水中でぬらぬらと揺れているのがかろうじて見える。砂利道には犬の糞や食べかけのカップヌードルやぼろぼろになったピンク色の手袋やコンドームが散乱している。それでもいつも、不思議と嫌な臭いはしなかった。ぼくは(そしてたぶんコトチーも)、この道とこの川が好きだった。 「コトチー冬休みどうするの」 「どうするって?」 「なんか、するの」 「なんかって?」 「なんでもない」 ブルーシートと鉄パイプ、しめ縄、折れた踏切の棒、ベニヤ板、反射板、あべこべな材料で組まれた堅牢な小屋の前をぼくらは通り過ぎる。中から微かにラジオの音が聴こえた。 「うちにはお兄ちゃんがいるから」コトチーは小さくスキップするようにして、ランドセルを背負い直した。「どこにもいけない」 「男にだって生理はあるよ」ぼくは急に話題を戻した。「血は出ないけど」 「うそつき」 「うそじゃないよ」 「それは夢精」コトチーが身体を曲げて、ランドセルの背でぼくにぶつかってきた。「トラだってわかってるでしょそれくらい。別にわたしが気にすることでもないけどさ、なんも知らない子にそういうこと吹き込むの、あとで自分が恥ずかしくなるだけなんじゃない」 「うそじゃない」ぼくはよろけながら、そう言うしかなかった。 〈生理〉という言葉には、もちろん〈月経〉という意味もあるけれど、〈生物の体の働き〉という意味だってあるのだ。 だったら、夢精や射精、オナニーを生理と呼んだって、間違いではないんじゃないか。 でもなぜか、それをコトチーに言うことはできなかった。屁理屈��言い訳にしか聞こえないことも、なんとなくわかっていた。 空はもう赤かった。カラスの鳴き声がどこかから聞こえてくる。 「トラ、大丈夫?」 「なにが?」ぼくはわざととぼけた。 「なにが、って……」 「大丈夫だよ」ぼくは地面の石を拾って、川に向かって思いっきり投げた。石は漁船のお腹にぶつかって、鈍い音をたてて川に沈んでいった。「大丈夫」 今日、一ヶ月ぶりにミヨシが学校へ来た。 あの日。柏木が授業でセックスの話をした日から、ミヨシはずっと学校を休んでいた。みんな、誰も、何も言わなかった。まるで最初からそれが当たり前だったかのように日々が過ぎていった。ぼくと、コトチー以外は。柏木だって何も言わなかった。プリントや宿題を届ける役目を誰かに任せることもなかった。ぼくの目の前の席はずっと空っぽで、空っぽの机の中のホッチキスはずっとそのままだった。ぼくは自分が段々自分じゃなくなっていくような、それまでの自分が絡まりあった細い糸で出来ていて、その糸が少しづつほぐされて、バラバラに散ってしまっていくような気分で毎日を過ごしていた。昼休み、いつも一緒に校庭を走り回るチートスも、給食の時間、牛乳のおかわりを取り合うガンバも、ぼくのそんな内面には気づいていないみたいだった。コトチーがぼくを見つめる表情だけが、日に日に険しくなっていった。 「さすがホトケだよね。完全に無反応だった」 コトチーは、柏木のことを「ホトケの柏木」と呼んだりする。いわゆる「神様仏様」のホトケではなくて、警察官が死体のことを呼ぶ俗称としての、ホトケ。らしい。 一ヶ月ぶりに学校にやってきたミヨシは一ヶ月前となにも変わらなかった。朝の会が始まる少し前に登校し、国語の授業では句読点を無視してつっかえつっかえ音読し、理科の実験ではアルコールランプの消火にまごつき、昼休みは口角を少しだけ上げて手塚治虫の『三つ目がとおる』をじっと読んでいた。ぼくはそんなミヨシをなるべく見ないように一日を過ごした。 ミヨシはキュロットを履いていた。 それ以外、なにも変わらない、いつものミヨシだった。 真間川が終わり、東京湾の工業地帯にたどり着く。巨大な水門は今日は閉じていた。海沿いにそびえ建つセメント工場が夕陽に照らされて嬉しそうに輝いている。湾の向こう岸に建ち並ぶ工場からコンテナが運ばれていく。クレーンが動く。消えそうにない煙が立ち上っている。大きな船が小さな模型みたいにちんまりと停まっている。静かだ。重たい海水の音と、母さんがいつもベランダやキッチンや庭に置きっぱなしにするゴミ袋みたいにギチギチに人を詰め込んだJR京葉線が高架を通り過ぎる音だけがはっきりと聞こえてくる。コトチーとぼくはしばらく立ち止まって、それらすべてを並んでぼんやり眺めていた。ここは千葉なのに、今目の前に見えているこの真っ黒な海原は東京湾なんだ、というその事実に、ぼくはなんだか無性にくらくらしてしまう。 「コトチーのお兄ちゃん、ぼくがぶっ殺してあげよっか」 そんなこと言うつもりはなかったから、ぼくはぼく自身に驚いていた。 「いいね」コトチーは笑わなかった。「どうやって?」 「ゆっくり殺そう」ぼくはコトチーを見ずに言った。「まず、まっすぐに伸ばして針金にしたクリップで、両眼を刺して、ぐちゅぐちゅかき混ぜるんだ。で、眼をどろどろにしたら、排水口のぬめり取りで、歯を少しづつ溶かそう」 「あはは。サイコー」 「爪切りで少しづつ、両手両足の肉と骨を削いで、詰めていこう」 「あはは」 「髪の毛はペンチで豪快にむしり取ろう。耳にはギターを繋げたイヤホンをつけて、爆音でかき鳴らして鼓膜を壊そう。ヘソにはうんと尖らせたトンボ鉛筆を突き刺して、睾丸とペニスは……。睾丸とペニスは、」 「……睾丸とペニスは?」 「睾丸と、ペニスは……」ぼくはわざとらしく間を置いて言った。「一番みじめで一番いたくて一番ねちっこくて一番、一番ぜんぶぜんぶ後悔させるような方法で、こっぱみじんにする」 「こっぱみじん」 初めて知った言葉を口の中で転がすように、コトチーが繰り返す。 「そう、こっぱみじん」 「すごいね」 「すごいよ。こっぱだよ」 「ありがとう」 コトチーは微笑んだ。声が少し揺れていて、でもぼくはなにも言わなかった。 来た道を引き返し、ぼくとコトチーはそれぞれの家に向かって同じ道を歩く。 ぼくの家とコトチーのマンションは道を挟んで隣り合っていて、いつもみたいに、家とマンションの中間、道のど真ん中で、ぼくとコトチーはハイタッチを交わして別れる。すっかり、夜になっていた。夜に玄関をまたいでも叱られないような家に、ぼくとコトチーは住んでいる。コトチーが明日学校にやって来るまで、どうか誰もコトチーの身体を触ったりしませんようにと、ぼくはたまに祈ってみたりする。
ぼくはリビングのテーブルで、晩ごはんを食べようとしている。 晩ごはんはミヨシだった。 ミヨシはこんにゃくで、こんにゃくという食べ物がミヨシだった。 「いただきます」ぼくは言った。 味噌汁を入れるお椀のなかに、透明な液体と輪切りにされたミヨシが浮かんでいて、ぼくは白ご飯を口に含んでから、そのお椀を手に取った。 「虎彦」 ミヨシがぼくの名前を呼んだ。 ぼくはミヨシの一つを箸でつまむ。 ミヨシが微笑んだ。輪切りにされたミヨシに顔なんてないけれど、黒いぶつぶつの連なりが顔の代わりなのだということがぼくには分かる。ミヨシが微笑んでいることも、ミヨシが呼びかける声も、ぼくにしかわからない。ぼくとミヨシだけの言葉じゃない言葉だ。 母さんは、テーブル越しに対面する形で、ぼくの前に立っている。片手に包丁を持って、眼が充血している。 「てめえ何様のつもりだよ」 母さんの声は父さんで、ぼくは母さんの顔を見つめながら、ミヨシを口に入れる。 「いっつもいっつもいっつもいっつもいっつもいっつも」 そういう動きしかできないブリキのおもちゃみたいに、母さんは手に持った包丁を上下に振り続けている。 「いっつもいっつもいっつも、いつもいつもいつもてめえはてめえは」 ぼくはミヨシを噛んで、飲み込もうとする。でも噛めば噛むほど、口の中でミヨシはどんどん膨らんで、ぼくはとうとう口の中からミヨシをこぼしてしまう。口からこぼれたミヨシはもうミヨシじゃなくてただのこんにゃくで、床の上でぷるぷる揺れている。 さっきからぼくの頭上で浮かんでいたポリバケツが、UFOみたいに光を発した。光りに照らされた、ミヨシだったこんにゃくは浮かび上がって、ポリバケツの中に吸い込まれていく。 「ミヨシ」 ぼくは立ち上がってポリバケツに手を伸ばす。でもぼくは体温計だった。水銀が暖まらないと手が伸ばせない。手というのは、赤いゲージのことだった。 そこで眼が覚めた。 ぼくはマイナスドライバーを枕の下にしまって、起き上がる。 「ミヨシ」
次の日も、次の次の日も、次の週も、ミヨシはキュロットを履いて、ぼくの目の前の席に座って、いつものミヨシみたいに振る舞っていた。仕草を変えたり、一人称を変えたりすることもなかった。周りの人間も、キュロットを履いたミヨシをいつものミヨシみたいに扱った。つまり、みんなミヨシに無関心だった。あまりに無関心すぎて、ぼくの頭がおかしくなって、ぼく一人だけが、ミヨシの幻覚を見ているのかと思ったほどだ。 「あいつさあ……」 男子トイレで隣り合って小便をしているとき、ガンバが言った。 「そういうこと、だったんだなあ」 ぼくはそれで、最近のミヨシがぼくだけの幻覚じゃないことを知った。 「でも、なんか、そういう感じ、だったのかもなあ、これまでも。うん」 ガンバはうつむいて、自分の小便を見つめていた。 「いとこがさあ、そういう感じ、なんだよなあ。オレが保育園行ってたときは、まだ、アニキって感じだったんだけど、今はもう、なんだか、そうでもない感じでさあ。……あいつよく見たらかわいらしい顔してるしさあ。オレぐらいドジだけどさあ。これからチン毛とか生えて、どうなるかわかんないけどさあ。オレ、ああそういうことかあ、って感じなんだよなあ」 ガンバがそんなことを言うのがなんだか意外で、ぼくはズボンのチャックを上げながら、ガンバの顔をまじまじと見つめてしまう。 「なんだよお」 「や……うん。うん。なんでもない」 ぼくはガンバの背中を強めに叩く。 「おいなんだよ、まだションベン中だぞ」 「さき、体育館行ってるから!」 「待てよお! おーい!」 ガンバの声が響くトイレを出てぼくは早足で歩く。ぼくは泣き出しそうだった。
ミヨシがキュロットを履くようになってから、ぼくはまだミヨシと一言も言葉を交わしていなかった。放課後は校庭でたむろしているチートスたちの元へ行くか、一人で、あるいはコトチーと二人で、逃げるように帰っていた。 ミヨシと、放課後、教室の隅で、どちらからともなく寄り添って、「ああいうこと」をするようになった、そのときから、ぼくはもうこの先のことがなんとなくわかっていた。言葉として、映像として、脳みそでわかっているわけではなかったけれど、こんなことが、このまま、この状態のまま、変わらずに続くはずがないことくらいはわかっていた。ミヨシの頬を叩くとき、ミヨシの肩をつねるとき、ミヨシの頭をなでるとき、ミヨシを言葉だけで追い詰めるとき、ミヨシの膝が夕陽に照らされているのを見たとき、ミヨシの眼に映るぼくや教室の天井を見たとき、ミヨシが「ぼくは」と言うとき、ミヨシがぼくの名前を呼ぶとき、ミヨシの身体のその中の、誰にも見えないところでボロボロに泣いているミヨシそのものにぼくは目を背けてミヨシの眼を見つめ続けてきた。学校では教えてくれないこと。父さんは、母さんは、柏木は、大人は教えてくれないこと。誰も教えてくれないこと。ほんとうは教えてほしいこと。その、「教えてほしいこと」の種類が、ぼくとミヨシでは決定的に違っているのだ。「教えてほしいこと」の種類も「認めてほしいこと」の種類も「信じてほしいこと」の種類もなにもかも。一緒だと思いたかったのは、ぼくだけだろうか。ぼくはミヨシのペニスを思いきり頬張りたかった。誰よりもやさしく乱暴に触りたかった。でもそれを望んでいるのはぼくだけなのかもしれない。ミヨシはミヨシ自身のペニスなんて触れられることすら嫌なのかもしれない。そのことを考えるだけでぼくは頭がはちきれそうになった。頭がはちきれそうになることくらいわかりきっていたから、ぼくはミヨシと、ぼくらの間だけで通じるセックスを、「ああいうこと」を続けてい���。ぼくはまだ、ミヨシのペニスを見たことがない。ぼくはミヨシに今すぐ触れたかった。いま、今、すぐ。 体育館では、先に来ていたチートスたちがバスケットボールの山盛り入ったカゴを倉庫からひっぱり出しているところだった。せっかちな奴らがカゴの中のボールを手にとって、好き勝手に投げ合っている。 ぼくは早足のまま、体育館の隅で壁に寄りかかってぼんやりしているミヨシの元へ向かう。 「ミヨシ」 ミヨシはぼんやりした顔を強張らせてぼくを見つめた。放課後以外でぼくがミヨシに話しかけるのは初めてだった。 「髪」ぼくの声はかすれていた。 「かみ?」 「どうして」ぼくは右手をミヨシの肩くらいまで上げて、また下げた。 ミヨシは黙っていた。 「伸ばせばいいのに」言った途端、ぼくの眼から涙がこぼれた。 今この瞬間、この場にいる全員、消えていなくなってしまえばいいとぼくは思った。お願いだからぼくとミヨシ以外、全員、バスケットボールとゴールだけを見ていてほしかった。 ミヨシは顔を強張らせたまま口を半開きにして、数秒固まったあと、これ以上ないくらいかわいそうな人を見るような表情でぼくを見た。 「どうして」 「トラ。虎彦」 ミヨシはぼくの手の甲をなでてから、頬の涙をそっとぬぐった。 「虎彦。今日、一緒に帰ろう」 バスケットボールが床を跳ねる音の隙間から、チートスの笑い声が聞こえる。ガンバが遅れて体育館にやってきて、おい、トラ! とぼくを呼ぶ。ぼくはミヨシにうなずいてから、なんでもなかったように背を向けて走り、カゴの中のバスケットボールを取って、ガンバに向かって高めに投げる。
1 note
·
View note
Text
魔女の霊薬 種村季弘
十六世紀ドイツの画家ハンス・バルドゥングス・グリーンに、「魔女たち」と題して、数人の魔女が恍惚状態で飛翔したり、そのための準備をしているらしい場景を描いた一幅の銅板画がある。後方に水平に浮遊している老婆が片方の手に尖の二股状になった杖を持ち、もう一方の手で、なかば浮き上った若い娘の腰を抱えて何処(いずこ)かへ拉し去ろうとしている。前景右手には、片手にもうもうと煙を上げる魔香の器を掲げて今にも地を離れんばかりのエクスタシーに浸っている女がいる。
注目すべきはしかし、それよりさらに前景左手の女である。彼女は左の手に何やら呪文のようなものを記入した紙片を持ち、もう一方の手を股間に押入して(後方にぐつぐつ煮えている釜から取り出したものであろう)塗膏(ぬりあぶら)らしきものを陰部に塗布しているのである。呪文と見えたのは、あるいは塗膏の製法または用法を書きとめた処方箋でもあろうか。仔細に見ると、この銅版画は映画的な連続場面で構成されていて、最前景の塗膏を塗布している魔女が遠景に退くのにつれて、徐々にエクスタシーに陥りながら催眠状態で飛翔する(もしくは飛行感覚に襲われる)過程を刻明に記述していることがわかる。
バルドゥングス・グリーンばかりではない。ゴヤも(「サバトへの道」)、アントワーヌ・ヴィルツもレオノール・フィニーも、古来魔女を描いたほとんどの画家が、箒にまたがって空中を飛行する魔女を描いた。魔女は飛ぶのである。しかも股間にあやしげな塗膏をなすり込むことによって。これこそが悪名高い「魔女の塗膏」であった。
ところで、一体、魔女の塗膏の成分はどんなものだったのだろうか。血やグロテスクな小動物のような、さまざまの呪術的成分を混じてはいるけれども、主成分はおおむね幻覚剤的な薬用植物であったようだ。ゲッチンゲン大学の精神病理学学者H・ロイナー教授は魔女の塗膏の成分を分析して、混合されたアルカロイドの種類をおよそ五種に大別した。
一、 イヌホオズキ属のアトロパ・べラドンナから抽出されるアトロビン。
二、 ヒヨスから抽出したヒヨスキアミン。
三、 トリカブトのアコニチン。
四、 ダトゥラ・ストニモニウムから取ったスコポラミン。
五、 オランダぱせりからのアフォディシアクム。
これらの各成分から醸し出される効果はまず深い昏睡状態であり、ついで、しばしば性的に儀式化された夢幻的幻視、飛行体験などである。おそらく媚薬(アフロディシアクム)として常用されたオランダぱせりは性的狂宴効果を高めたであろう。魔女審問の記録(十六、七世紀)には、実際におこなわれたものか、それともたんなる幻覚であったの定めではないか、ソドミー、ぺデラスティー、近親相姦のような倒錯性愛の告白がいたるところに見られる。告白された淫行のなかには悪魔の肛門接吻(アナル・キス)のように入社儀式化されているものもあった。アコニチンによる動悸不全はおそらく飛翔からの失墜感覚を惹起した。またベラドンナによる幻覚は、はげしく舞踊と結びつくと運動性の不安――すなわち飛行感覚を喚起する。睡眠への堕落、性的興奮、飛行感覚は、こうして各成分の作用の時差によって交互に複雑に出没する消長を遂げるものにちがいない。
使用法は、右のアルカロイド抽出物の混合液を煮つめたものに、新生児の血や脂、煤などを加えて軟膏状にこしらえたものを、太腿の内側、肩の窪み、女陰のまわりなどにすり込むのである。さて、細工は流々、はたして所期の効果が得られるであろうか。
現代の学者で魔女の塗膏を実際に当時の処方通りに造って人体実験をしてみた人がいる。自然魔術と汎知論、あるいはパラケルスス研究やシュレジア地方の伝説採集の研究で高名な民俗学者ウィルーエーリッヒ・ポイケルト教授である。一九六〇年、ポイケルトと知人のある法律家は、十七世紀の魔女の塗膏を処方通りに復元して、こころみに自分の額と肩の窪みにすり込んでみた。成分はベラドンナ、ヒヨス、朝鮮朝顔、その他の毒性植物を混合したものであった。まもなく二人はけだるい疲労に襲われ、ついで一種の陶酔状態で朦朧となり、それから深い昏睡状態に陥った。目がさめたのようやく二十四時間後で、かなりの頭痛を覚え、口腔からからに渇き切っていた。二人はそれから、時を移さずにぞれぞれ別個に「体験」を記述した。結果はほとんど口裏を合わせたように一致し、しかも、三百年前、異端審問官の拷問によって無理矢理吐き出させられた魔女たちの告白とおどろくべき一致を示したのである。
「私たちの長時間睡眠のなかで体験されたもの��、無限の空間へのファンタスティックな飛翔、顔というよりはいやらしい醜面をぶら下げている、さまざまな生き物囲まれたグロテスクな祭り、原始的な地獄めぐり、深い失墜、悪魔の冒険などであった。」(ポイケルト『部屋のなかの悪魔の亡霊』)
してみると十六、七世紀の魔女たちの証言はかならずしも根も葉もない虚構ではなかったのである。一五二五年に『異端審問書』を書いたバルトロメウス・デ・スピナは、当時の有名な医者ぺルガモのアウグストゥス・デ・トゥレが、その家の女中が部屋のなかで素裸になり意識を失って死んだように床に倒れているのを発見した委細を記録している。翌朝、正気に戻ったところを尋ねてみると、彼女は「旅に出ていた」と答えたという。どうやら塗膏を使用したのである。ルネッサンス・イタリアの自然科学学者ヒエロニムス・カルダーヌス(カルダーノ)も旅の幻覚を伴う塗膏の話を書いている。
「それは、おどろくべき事物の数々を見させる効力と作用を有しているとされ……大部分は快楽の家、縁なす行楽地、素晴らしい大宴会、種々様々のきらびやかな衣装を着飾った美しい若者たち、王侯、貴顕の士、要するに人の心を呪縛し魅するありとあらゆるものを目に見させ、ために人びとはてっきりこれらの気晴らしや快楽を享楽し娯しんでいると錯覚さえする。彼らはしかし、一方では、悪魔、鳥、牢獄、荒野だの、絞首吏や拷問刑吏の醜怪な姿だの、とかをも眼にするのであって……そのため非常に遠い奇妙な国を旅行したような気がするほどである。」
おそらく現代の幻覚剤による「旅(トリップ)」と同じような、未知の空間への旅行が体験されたのであろう。ヒエロニムス・ボッシュの「千年王国」の天国と地獄を一またぎするような、至福と恐怖がこもごも登場するその旅の旅行の体験の内実は、「ビート族のベヨーテ生活」の至福共同体が「ある敷居を境に苦痛の闇へと転落し、そこからヒップスター生活が犯罪の世界へ繋っていく」(ワイリー・サイファー)ところまで、現代の幻覚剤体験そっくりだったようだ。
幻覚剤文明が現代の特産物ではないように、魔女の塗膏もキリスト教的中世独特の薬物ではなかった。それは古代ローマにも、それ以前の蒼古たる地中海文明的なかにも、明らかに存在していた。ただ、またしてもその意味が違っていたのだ。キリスト教的中世の魔女の塗膏が忌むべき禁止の対象であったのにひきかえ、そこでは同じものが驚異の対象だったからである。
もっとも著名な例は、アプレイウスの『黄金の驢馬』の主人公ルキウスが魔女めいた小婢フォティスの導き屋根裏の小部屋の扉の隙間ごしに覗き見るパンフォレエの変身であろう。ミロオの妻パンフォレエは人眼に隠されて塗膏を身体中に塗り、鳥に変身して夜な夜な恋する男のもとへの飛んでゆく。
「見るとパンフォレエは最初にすっかり着ていた着物を脱いでしまうと、とある筐(はこ)を開いて中からいくつもの小箱を取り出し、その一つの蓋を取り去って、その中に入った塗膏をつまみ取ると、長いこと掌でこねつけておりましたが、そのうち爪先から頭髪のさままでからだじゅうにそれを塗りたくりました。そいでいろいろ何かこそこそ燭台に向ってつぶやいてから、手足を小刻みにぶるぶると震わせるのでした。すると、体のゆるやかに揺れうごくにつれて柔かい軟毛(にこげ)がだんだんと生え出し、しっかりした二つの翼までが延び出て、鼻は曲って硬くなり、爪はみな鉤状に変わって、パンフォレエは木菟(みみずく)になり変わったのです。
そうして低い啼き声を立てると、まず様子を吟味するように少しずつ地面から飛び上がるうち、次第に高く上がってゆくと見るまに、いっぱい羽根をひろげて、外へ飛んでってしまいました。」(呉茂一訳)
この場合にもパンフォレエの羽化登仙的な至福感は事の一面を物語っているにすぎない。同じ塗膏をフォティスから手に入れたルキウスは、同じようにそれを身体中に塗りたくりながら鳥とは似もつかぬ鈍重な驢馬に変身してしまう。それは天上的なものの失墜した果ての、道化た、暗い、醜悪な実相である。以後、彼はヒエロニムス・カルダーヌスのいわゆる「非常に遠い奇妙な国」の間をさまざまの魔物や物の怪に囲まれながらさまよいつづけなくてはならない。天上の飛翔は、一転、暗い冥府の旅に変るのである。
さて、このように両極的な作用を及ぼす『黄金の驢馬』の魔女の塗膏の成分は、一体どのようなものだったのであろうか。フォティスはこれらの驚異が「小さな、つまらない野草のおかげで」成就すると説明している。「茴香(ういきょう)をちょっぴり桂の葉をそえ、泉の水に浸したものを身に浴びるとか、飲むとかするだけ」でよく、また変身の解毒剤には「薔薇の花」を食べればよい。これ以上の説明がないので詳細は不明であるが、塗膏が茴香や桂の葉を含むいくつかの野草から合成されたことだけはたしかである。
ローマ文学史上、アプレイウス(一二三頃~一九〇年?)が登場するのは白銀時代も終焉してからのことであった。すでにこの頃、オリエントの異教はローマに流入して熱病のような猛威をふるっていた。しかし魔女の薬草はこれより早く、すでに黄金時代から重要な文学的トポスとしてしばしば詩文学の上に登場している。さいわい、ゲオルク・ルックという学者が黄金時代の四人の詩人に焦点をしぼって、『ローマ文学における魔女と魔法』について論じているので、これを参照しながらローマにおける魔女の塗膏の繁昌とその源泉をしばらく訪ねてみよう。
アプレイウスのパンフォレエが「恋いこがれた男」のもとに飛んでいくために鳥に変身したように、塗膏の効果の主たる目的の一つは明らかに愛の魔法であった。正確にはむしろ愛の錬金術というべきかもしれない。なぜから塗膏は、別れた男女をふたたび合一させたり、げんに夫婦である男女を分離させてその一方をよこしまにも他の男や女に結びつけようとする、分離と結合のための触媒の役を果たしたからだ。それゆえに塗膏の使い手反しばしばローマの悪場所である売淫の街区スブーラに巣食う百戦錬磨の取り持ち女たちであった。
盛期黄金時代の詩人ウェルギリウス(前七十~十九年)の『牧歌』第八に、ダフニスに恋をして捨てられた女が魔法で男を呼び返そうと逸話が見える。ふつうから職業的な魔女の家を訪うべきところであるが、この女(そもそも『牧歌』第八のこの箇所は、牧人ダモンとアルフェシボエウスが歌くらべをして、アルフェシボエウスが魔法を実演してみせるためにその女にじかになり変わり、彼女の声、言葉、状態を直接に演じているので、女は無名である)は女奴隷のアマリリスを助手に使い、かつて大妖術使いのモエリスから伝授された霊薬の製法を駆使して、みずから愛の魔法を演じてみせる。はじめに彼女はアマリリスを呼び寄せてつぎのように命じる。
「水を持ってきて、そこの祭壇をやわらかい紐でお結び。それから強い野草と匂いのきつい乳香を燃やすのだよ、そうすれば情夫(あのひと)の狂った気持を魔法の供物(くもつ)で惑わしてやれるのだから。足りたいのはあと魔法の呪文だけ。――街から家へ、私の呪文よ、ダフニスを連れ戻しておくれ。」
祭壇に結び紐、野草、呪文といった魔法が早くもあらわれている。「やわらかい紐」はおそらく羊毛の紐で、羊毛の紐には霊的呪縛力があると信じられていた。紐の結び方は、まず不実な相手の肖像画の首のすわりにそれぞれ三色(黒、白、赤)に彩った三本の紐をかけ、この画を祭壇のまわりに三度めぐらせる。「三つの異なる色を三つの結び目でひとつに結ぶかいい、アマリリス、結びつけさえすればいいのだよ、アマリリス、そしてお言い、〈私の愛の絆(きずな)を結ぶ〉と。」
三の数がしきりに重用されるのは、「神は奇数をおよ���こびになる」からである。したがって「愛の絆」云々の畳句(ルフラン)も三x三の九回唱えられる。紐の三色のうち黒は冥府の色で、赤と白は悪を予防する保護色であり、黒を中心にしていわば施術者を庇護してくれる。こうして呪縛――結合(katadesis)が完了し、ダフニスは空間を立ち越えて施術者につながれてしまう。しかし魔法はこれで終わりではない。無気味な呪いの人形の焚刑がこれにつづく。
「粘土が火で固くなるように、蠟が同じ火にあった溶けるように、ダフニスは愛のために私のところにやってくる。供物の碾(ひ)き粉を徹き、もろい月桂樹を瀝青で燃やすがいい。悪いダフニス��私を燃やし、私はこの月桂樹の枝と私のダフニスを燃やす。」
呪いの人形はホスティウスの『諷刺詩篇』第一巻八「魔女とかかし」にも登場するが、ここでは魔女は「毛制と蠟制の二つの像をもっていた」(鈴木一郎訳)とあって、はっきり人体を模している。しかしウェルギリウスでは粘土や蠟をダフニスの姿に似せて捏ねておく必要はなかった。男の名前や不実を意味する符号が粘土や蠟に刻み込まれていたかもしれないが、顔形を模造するまでもなく、施術者の女がこれこれの呪物によってダフニスを意味し、それが相手だと考えればよかったのである。粘土は火のなかで固くなり、蠟は軟らかくなる。ゲオルク・ルックの注解によると、粘土は女の(相手にたいして硬化する)憎悪の固さをあらわし、蠟は彼女にたいしてふたたび軟化するであろう男の気持をあらわしている。異解では、粘土が固くなるのは、彼女から離れて他の情婦に移ったダフニスの気持を憎むべきコイ恋仇にたいして固くさせるの意である。同時に投げ込まれる月桂樹は願いの筋の吉凶を知らせてくれる。月桂樹がバチバチ爆(は)ぜて燃えれば願いはかない、燃えつきが悪ければさらに瀝青を注いで火を熾(おこ)らせるのである。
だが、つぎつぎにおこなわれる魔法にもかかわらず吉兆は一向にあらわれない。そこで女は、ダフニスが「担保」としてのこしていった衣服を閾(しきい)の下に埋めて地下の神々の裁きを乞う。「ダフニスは私にこの担保の借りがあるのだ」と。事態はこれでも好転しないので、女はアマリリスに先程燃えていた火の冷めた灰を河に持っていって投げ捨てるように命じる。その場合、灰を運んだらそれを「頭越しに」河に捨て、そちらの方を見ないで帰ってこなくてはならない。そうしないと悪霊がかえって施術者の側に憑(つ)いてしまうおそれがあるからである。かくて灰は流れに運ばれて「ダフニスを襲うであろう」。
この箇所では、女はダフニスへ呪縛をひとたび放棄して、呪いの灰で彼を襲うためにふたたび相手から分離している。「結合(カタデシス)の後にかりそめの「分離(アポリシス)」がつづくのである。この分離は恒久的なものではない。最後の結合手段として効果甚大な薬草(野草)が控えているのを女は知っている。しかしその力はあまりにも強大で、まかりまちがえば周囲に致命的な影響を及ぼす。そのために、一瞬、女は最後の切札を出すべきかどうかを逡巡する。するとこの瞬間、一度冷たくなった灰がふたたびめらめらと燃え上って祭壇を焦がしはじめる。
「これは吉兆だ!明らかにこれは何事かを意味している。――これを信じるべきなのか。それとも恋する女が魔法の夢にまどわされているのか。止まれ、わが呪文よ、止まれ。ダフニスはすでに都(みやこ)から帰りつつある。」
強烈な薬草を用いるまでもなく愛の魔法は成就する。しかし抜かずに終わった伝家の宝刀を彼女は依然として持ってはいるのである。それほどのようなものか。
「黒海沿岸で採集されたこの薬草と毒草は、モエリスがみずから私にくれたもので――それは黒海地方に多生している、しばしば私は、モエリスがこれを使って狼に変身して森のなかに姿を隠したり、深い墓穴から霊魂を喚び戻したり、穀物をよその土地に移したりするのを見た。」
薬草は単純な野草ではなく、特に「黒海地方に多生する」と明示されている。ホラティウスも初期の『エポーディ』のなかで、「毒薬の国イオルコスとヒべリアからきた毒薬」について語っている。ヒべリアは現代のグルジア共和国で、黒海地方に属する。黒海という地方は当然コルキス生まれの大魔女メデアを連想させるにちがいない。実際、詩人たちが邪悪な薬物の出所として念頭に浮かべているのはメデアその人なのである。メデアの壮大な魔法を活写した『転身物語』のオウィディウスはいうまでもなくティブルスも、「キルケ―か持ち、メデアが持っているあらゆる毒薬、デッサリアの地に生れたあらゆる薬草、欲情にたける雌馬の女陰からしたたる粘液」(『『哀歌』』と列挙する。オウィディウスのメデアは龍に打ちまたがってデッサリアに飛び、そこから薬草を採ってくる。すなわち薬草の特産地として、黒海沿岸とデッサリアといういずれ劣らぬ不気味な地方がいちじるしく強調されるのだが、これが何を意味するかについてはのちに述べたいと思う。
さて、ウェルギスウスの述べているモエリスの薬草の三つの応用例のうち、一は人狼変身、二は死者を喚起する降霊術(ネクロマンシ―)、三は穀物の生殖力の転移にそれぞれ関わる。人狼変身の話は後代(紀元一世紀)の『サテュリコン』の「トリマルキオーの饗宴」にも出てくるが、人狼信仰はおそらく神話時代に遡る起源を有している。ところがで、ロイナー教授は神話学者ランケ・グレイヴスらの説を援用して、オリュムボス神の飲食物たるアルブロジア(神々の食物)やネクタール(神々の美酒)が右のごとき幻覚性の薬物そのものではなかったとしても、そのエッセンス多量に混じていたにちがいないと推定する。ディオニュソス祭儀のメーナードたちの狂乱もこれと無関係ではない。
アルブロジアややネクタールを飲食する権限を独占している神々は、おそらく有史以前の聖なる王や女王たち(その前身はシャーマンであろう)であった。彼らの王朝が没落した後、それは、閉鎖的結社的なエレウシス密議やオルフェウス密議の秘密の要素となり、ディオニュソス祭儀とも結びついだ。密議の参加者たちは密議の席で共食した飲物や食物を絶対に口外してはならなかった。そうすることによって忘れ難い一連のヴィジョンが体験され、その類推的延長の上に超越的世界における不死と永生が約束されたからである。
ディオニュソス祭儀のメーナードたちの狂乱は、内的には飛翔感覚や性的興奮を伴い、外面的にはさながら狼のような凶暴を示したものにちがいない。彼女たちは髪をふり乱しながら国中を進行し、家畜や子供をずたずたに引き裂き、酒や薬物入りのピールに酔って「インドに旅行してきた」ことをひけらかした。してみると、見知らぬ士兵や妖術使いの人狼変身は、密議的な幻覚共同体が崩壊した後、秘密から疎外された個人や小集団が犯罪の形で表出せざるを得なかった聖なる薬物体験であったとおぼしいのである。
メーナードの末裔のように残酷な魔女たちは、先にふれたホラティウスの『エポーディ』にも登場してくる。数人の魔女が良家の子供を誘拐してきて、地面に首だけが出るように生き埋めにし、御馳走が山盛りの血を眼の前において(口元まで皿がきていても手が使えないので食べられないのだ)凄まじい飢えの修羅場をながながとたのしみ、はては生きたままの身体から骨髄と生き肝をちぎりとり、これを煮つめて媚薬をつくる。
「髪に、さてはまた蓬髪乱れる頭に、小さな蝮どもを絡ませながら、カニディアはコルキスの焔のなかにつぎのものを投ぜよと命じた。墓場から引き抜いてきた野生のいちじくの樹、死者の樹なる糸杉の木材、いやらしい蟇の血に塗られた卵、夜鳥ストリックスの羽根、毒草の国イオルコスとヒべリアからきた野草、飢えた牝犬の口からもぎとってきた骨を。」
これに子供の生き巻肝を加えれば魔女の霊薬は完成する。怖ろしい魔女カニディアのつくる媚薬は、ウェルギリウス作品の場合と同様、ある不実な男を呪縛するためである。しかし不思議なことに、カニディアの媚薬は予期したような効果を発揮しない。男の名はヴァールス、「老いぼれの漁色家」である。いましも彼は「私の手がこれ以上完璧には調和することのない塗膏(ポマード)を塗られ」て、魔窟スプーラの犬に吠えつかれ、人びとの物笑いの種になっているはずであるのに、これはどうしたことであろう。彼はこともなげに街をうろついて夜の冒険に出かけている。やがてカニディアは「(自分より)さらに秘密に通じた魔女」が彼の背後にいて、その呪文が自分の塗膏の効果を台なしにしていることをさとる。「もっと強力な薬を、そのもっと強力なやつをお前から取り上げてやる」。こうして毒物と解毒剤が互いにきそいながら老ヴァールスを板はさみにしてしまうわけた。
それはちょうど、十八世紀毒殺魔ド・ブランヴィリエ侯爵夫人が夫の侯爵を亡き者にしようと毒を盛ると、度重なる毒殺の発覚をおそれた相棒のサント・クロアが解毒剤をあたえ、毒と解毒のシーソーゲームのなかで中途半端な廃人となった侯爵が、宙ぶらりんな生かさず殺さずの、世にも恐ろしい余生を送ったのとそっくりであった。
ヴァールスというのが誰をモデルにした人物ではっきりしない。しかしホラティウスの知人であることはたしかで、詩人ははっきりとヴァールスの肩を持ち、かつカニディアを憎んでいる。一方カニディアは、詩人の庇護者マェーケーナスがローマの無縁墓地エスクィリーナエの丘を自分の庭園に造りなおした際、この旧墓地に出没した魔女である。ホラティウスは「汝、マドロスや旅商人どもにあまた愛された女」と侮蔑しているので、���身は港町の娼婦かいかがわしい取り持ち女の類であろう。一説には、本名をグラティディアと称してナポリで美顔用塗膏を商っていた実在の女であるともいう。
ホラティウスは何故かこの女を心底から憎悪していた。開明的なエピキュリアンであったホラティウスはむろん魔法を真に受けていたわけではないが、不倶戴天の敵カニティアの脅威は身をもって知っていたらしい。カニディアは詩人に執拗に呪いをかけた。『エポーディ』前半ではカニディアを揶揄していた詩人も、第十七歌あたりではさすかに音(ね)を上げて魔女に降参してしまう(「やめろ、やめてくれ!私は効き目のある術に降服する!」)カニディアとホラティウスの間には直接の色情的怨恨はないのに、何故こうも執拗に呪詛し憎悪し合うのであろう。目下の論題から離れるので無用の詮索ではあるが、講和主義として敗北してから「黄金の中庸」を看板に韜晦してきたホラティウスの、政敵にたいする潜在的な不安が魔女カニディアの姿に結実したのだとすれば含意は深長である。
ところで、先に私は、老ヴァールスがより秘密に通じた別の魔女から対抗秘薬を調達し、カニディアの塗膏から身を護った経緯を述べたが、正確にはこれは逆である。漁色家ヴァールスは老いかけた精力を挽回するために(別の)魔女に催淫剤を依頼し、そのお蔭で老齢にもかかわらず夜な夜なスプーラに出没することができたのであった。一方、カニディアの塗膏は通常の媚薬とに逆に、この好色な遊び人を性的不能に陥らせる麻痺的な減退剤であったにちがいない。なぜなら「老漁色家がスプーラに犬に吠えつかれ、人びとの物笑いの種になる」効果を狙った薬物は、相手を色街における無用の徒である不能者に仕立てるための、底意地の悪い精力減退の薬にほかならないだろうからである。この不能不毛化させる魔法は、ウェルギリウスのいう「第三の魔法」である穀物の生殖力の転移盗奪の法にも通じている。
ローマ最古の法文書である十二銅表律は、隣人の耕地の収穫物を荒廃させる災いの魔法を重罰をもって禁じている。罰は犯罪を前提としているので、すでに当時から他人の畑の生産力を涸渇させ、(あまつさえ)これを我田引水しておのが腹を肥やす魔法が実践されていたのであった。本来神と自然の摂理のみが按配すべき穀物の作不作が人為の魔法によって操作されるのなら、同じことは人間的自然である肉体の活力の、特に性的エネルギーの増減についても通用するはずである。
ホラティウスがカニディアに蒙ったの呪い魔法は、老ヴァールスのような精力衰弱のそれぞれではなかったが、肉体のすみやかな老化という脅威であった。彼の髪は急速に白くなり、仕事は日々困難になりまさり、一瞬として息を吐くひまもなくなるであろうというのが、カニディアの呪いに籠めた脅迫であった。事実、ホラティウスは年齢より早く白髪が目立ち始めていたが、それがカニディアの魔法のたまものという証拠はなく、むしろ詩人は生来の病身にもかかわらず健康を維持し、日々の仕事も快適に楽しんでいた。彼はカニディアの悪意を感得してはいたが、魔法そのものはそれほど本気で信じていたわけではなかった。
ウェルギリウスやホラティウスの同時代の詩人プロベルティウス(前四十八?~十九年)も魔女の呪いを蒙ったことがあ��。プロベルティウスの受けた呪いは、まさに彼の男性としての能力の荒廃の脅威であった。敵なる魔女はその名もアカンティスといい、魔法をあやつると同時にやはり男女の仲を斡旋する取り持ち女でもあった。そもそもおらゆる種類の自然と蔑視してその正常な運行を人為的に左右しようとするプロメテウス的瀆神行為である魔法を、とりわけ肉体のの領域において一手に引き受けていたのは、先にも述べたように、当時スブーラに巣食っていた卑賤な薬草売りの魔女やあやしげな取り持ち女だった。ホラティウスの『エポーディ』のいちじるしい影響下にある『哀歌』のなかで、プロペルティウスはほとんどホラティウスをそのまま踏襲しながら唱っている。
「彼女(アカンティス)はつれないヒッポリュトスをアプロディーテーにたいして和ませるすべをすら心得ているのだ、水入らずの愛の絆にたいする最悪の災いの鳥であるこの女性。彼女はベネローベをさえ、その夫の知らせなどおかまいなしに、淫蕩なアンティノースとめあわせることだろう。彼女がその気になれば、磁石はもはや鉄を牽引せず、鳥はその小鳥たちの巣のなかで継母(ままはは)となる。すなわち彼女がポルタ・コリナの野草を掘り出したならば、固く結ばれていたものはすべて流れる水に溶け去るのだ。彼女は大胆にも月に呪文をかけ、月をおのが掟に従わせ、夜な夜なその肉体を狼の姿に隠す。醒めている夫の眼を環形でくらませるために、彼女は処女の雌鳥どもの眼を爪でくり抜く。彼女は魔女たちと結託して私の男性の能力を去勢させようとし、私に害をあたえようものと子持ちの雌馬の欲情の愛液を集めた。」
アカンティスはエロチックな引力(共感)と斥力(反感)の結合(カタデシス)と分離(アポリシス)の両極原理を基盤とする錬金術的性愛術を自在に操るのである。思うがままに貞淑ペネローペを淫蕩なアンティノース靡かせ、冷たいヒッポリュトスにアプロディーテーにたいする熱烈な情欲をかきたてる。彼女は自然の法則を嘲笑し、リビトーの流れをあちらからこちらへと変えたり、涸らしたり、増量させたりすることさえできる。共夫の女をよこしまな道楽者に取り持つように頼まれれば、不運な男の眼を鳥の眼をくり抜くようにくらませ、あまつさえ他人の畑の作物を枯らすようにしてそのリビドーを荒廃させ、不能の夫から強壮薬で男性的魅力をいやが上に引き立たせられた道楽者の方へと女の浮いた心を誘導していく。共感の法則をたくみに使い分けて、愛し合う男女を別れさせたり、嫌われた相手を手元にたぐり寄せたりするのである。
もっとも、このときにこそ魔女アカンティスを憎々しげた呪詛しているプロベルティウスであるが、彼自身、若年の頃は靡かぬ片恋の人「キンティア情(なさけ)を買うために「キタイアの女の魔法の呪文によって星辰や河の軌道を転ずることができ」、「わが主なる女(ひと)の心を変えて、彼女の貌(かんばせ)を私のそれよりも蒼ざめさせる」魔女の性愛術に帰依したことがあったのである。
アカンティスの魔法の中心にあるのも「ボルタ・コリナの野草」である。黒海やコーカサス地方の野草ではなく、市郊外の入手しやすい野草に頼ったのは輸入品が高価だったからであろう。いずれにせよ、この野草を投ずることによって、星の運行、河川の流れ、男女の情愛、磁力や母子愛まで、自然の正常な摂理は突然ばらばらに分解し、崩壊した積木の神殿を魔女の家に組み立てなおすように、別種の構成原理の手に委ねられる。
端的にいえば、この瞬間に世界は昼の側から夜の側に逆転し、世界原理の主宰者が神と宗教から悪魔(もしくは魔霊(デーモン)と魔法に交替する。あるいは天地創造の原活力たる火が神の手からプロメテウスに簒奪される、といってもいい。このように、あらゆる魔法使いは自然の法則を嘲笑するプロメテウスにほかならないのである。
「宗教的人間の態度は、祈る人、懺悔する人の態度であり、魔法使いの態度は主人と支配者の態度である。信仰篤い人間は祈りのなかで彼の神々に自分の優位を感じさせ、呪文によって神々を屈服させる。ある意味で魔法使いは神々の上に立っている。なぜなら彼は、神々がそれに従わなければならないと呼びかけと誓言とを知っており、かつ服従させられた神々の怒りから身を護る予防策に精通しているからである。」(ゲオルタ・ルック)
ローマの詩人たちは宗教詩人というよりはむしろ世故に通じたエピキュリアンであった。彼らは神々の側に立って魔法使いや魔女をきびしく紏弾したわけではない。そうかといって、あまたの魔女の姿を描いたにもせよ、彼らは悪魔崇拝に首までどっぷりと浸って秘教的な暗黒詩を書いたのでもない。
詩人たちが魔法にたいしてあいまいな態度をとりつづけたのは、彼ら自身と魔法使いたちとの間に存在した隠微な抗争のためであった。彼らは宗教の側に立って魔法を攻撃することこそあえてしなかったが、彼らなりに魔法を嘲弄もしくは嫉妬していた。なぜなら魔法が万事を解決してしまえば、彼らの持駒である言葉の救済力という白い魔術の出番がなくなってしまうからである。「歌(カルメーン)の原義は「魔法の歌」、「魔術的呪文」であった。「詩作(ポイエーテス)」もまた言葉の自然状態の組み変えというプロメテウス的行為である。それゆえに詩人もまた「傲慢(ヒュブリス)」の罪によってみずからはコーカサスの山巓にさらされながら地上の人びとに慰藉を授ける。プロベルティウスの言葉の医術についての確信は反語的である。
私は離ればなれにさせられた恋人たちをふたたび合一させることができ、
主(ぬし)なる女(ひと)の抗う扉を開くことができる。
私は他人(ひと)の生々しい悲哀を癒すことができるが、
私の言葉のなかにはいささかの薬剤もない。
さてウェルギスウスのモエリスが演じた薬草による三つの魔法のうち、まだ死者降霊術のみが言及されていない。死者召喚の秘法に関しては、すでにホメーロスの『オヂュッセイア』第十一巻に「招魂」の章がある。そこでオヂュッセウスに地下に一キュービット四方の穴を掘り、乳、蜜、酒、水、大麦の粉などを播いてから黒い牧羊の喉を切ってその血を穴に注ぎ、死者たちの魂を喚び戻す。古代人にとって死者は存在から消滅するのではなく、冥府や月世界に移行するのであるから、冥府の主であるハーデスやペルセポネイアに祈願して時間を逆流させることができれば、死者は当然地下世界から地上に還帰するはずなのである。地下的なものの秘密の結実である薬草がこの喚び戻しに重要な役割を駆使するのである。オウィディウスはいう。「彼女は黴び朽ちた墓の底から汝の父祖や祖先を引き出し、大いなる祈りによって大地と岩石とを割る。」
死者召喚が発端と終末、死と生と逆転であるとすれば、死から生への大逆流の一環として若返りの魔法が考えられる。老年から幼年への(自然的に不可逆的な)若返りはいわば死者再臨の模型である。オウィディウスは『転身物語』のなかで大魔女メデアがアエソンに施したおどろくべき若返りの秘法を絢爛たる筆にのせて活写している。
しかもここでメデアの魔法の要となっているのも「魔法の霊薬」である。まずメデアは翼のある龍にの首に牽かれた車を呼び出し、これにのり込んでテッサリアの野に飛び、あまたの薬草を採集する。それから奇怪な薬の調合にかかる。
「かの女は、髪の毛をバックスの巫女のようにふりみだして、炎のもえている祭壇のまわりをぐるぐるまわり、こまかに割った炬火(たいまつ)を溝のなかの黒々として血にひたし、ふたつの祭壇の炎でその炬火に火をつけ、こうして火で三度、さらに硫黄で三度老人(アエソン)のからだを清めた。そのあいだに、火にかけた青銅のなかでは、魔法の霊薬が煮えたぎり、白い泡をたててふきこぼれていた。かの女は、ハエモニア(テッサリアの古名)で刈りとってきた草の根や種子や花や激烈な草汁をそのなかに煮こみ、さらに、極東の国からとりよせた 取り寄せた小石や、オケアヌスの引潮に洗われた砂をまぜ、これに満月の夜にあつめた露、鷲木菟(わしみみずく)の肉といまわしいその翼、おのれを狼のすがたに変えることができるといわれる人狼の臓腑をくわえ、その上にキニュプスの流れに住む水蛇のうすい鱗皮と、九代を生きながらえた鴉の嘴と頭を入れてことをわすれなかった。」(田中秀夫・前田敬作訳)
前代の詩人たちの精読者であったオウィディウスは、ここにウェルギリウスやホラティウスやプロペルティウスの伝えた魔女の秘薬のあらゆる要素を投げ入れ、ほとんど完璧なごった煮を調製しているのである。さて、メデアの最後に橄欖樹の枯枝でこの液体をかきまわすと、老いた枯枝はみるみるうちに縁に返って豊かな薬をつけ、ふきこぼれた液がふれた地面はたちまち若やいだ春の地肌に変り、花が咲き、やわらかい草が萌え出た。メデアはすぐさま剣を抜いて老人の喉に孔をあける。流れる出る古い血の後に薬液を注ぎ込むと、瀕死のアエソンの白い鬚や髪はたちまち真黒になり、老醜の皺は消えて四十年前の姿になり変わった。
メデアが龍にのって薬草を探しにいくデッサリア地方は、都の郊外のように手近ではないが、さりとて彼女の故郷の黒海沿岸(コルキス)やコーカサスのような遠方でもない。しかしこころみに地図を広げてみると、エーゲ海から黒海に入るダーダネルス海峡を通じて、薬草の特産地たる黒海東端のコルキス、ヒべリア、コーカサスは水路から意外にも指呼の間にある。事実、アルタゴナウタエたちはテッサリアのパガサエの港からアルゴ号を仕立ててコルキスの金羊毛皮を探しに出立した。テッサリアと黒海沿岸地方に古くから深い関係が成立していたであろうことは、この一事からも容易推測される。ちなみにロイナー教授の野生幻覚剤分布表によると、魔女の塗膏の歴史的原生地は「中央ヨーロッパ全土」とされている。
おそらく中央ヨーロッパ奥地から地中海沿岸地帯にかけて、かつて強大な母神信仰が栄えていたのであった。この地下的(クトーニッシュ)母神崇拝の宗教はやがてアポロン的宗教に打倒され、輝かしいギリシア世界の表面からは駆逐された。とはいえ跡形もなく消滅したわけではなく、勝利を占めた若いアポロン信仰は古い地中海宗教の多くの要素を受け入れた。たとえばデルポイの神託を授けるアポロン神殿の巫女ピュッティアは、大地の裂け目の上にすわって地中からくる母の指示を受信する。ピュティアという名称そのものがすでに前ギリシア的宗教における地下的なものの化身たるピュトンの蛇との関連を暗示している。
若い宗教に征服された前代の宗教は、一転、魔法となるのがつねであった。のが常であった。同様に魔女たちは、かつてこの冥府的な大母神信仰の由緒正しい女司祭若巫女だったのであろう。しばしば魔女が引合いに出すテッサリアやコルキスのような土地は、メデアのような大女司祭が君臨していた聖地だったのであろう。したがってローマの詩人たちがその作品のなかに描いたアカンティスやカニディアのような魔女は、没落した大母神崇拝教団の巫女の、いまは往古の栄えある祭儀に参加するすべもなく孤立して巷をさまよい、賤業に口糊する、頽落したなれの果ての身にちがいない。彼女たちが時折り口にした霊薬の甘味は、プルーストにおけるマドレーヌの喚起的美味とひとしく、それが神餞として共食された往時の、栄光ある、だがいまは沈んで久しい世界の天上的な至福の思い出を、一瞬ざまざと想起させてくれたかもしれない。
魔女の塗膏や霊薬は、それ自体としても、むろん後の悪魔礼拝と切っても切れない密接なつながりがある。しかしそれよりも重要なのは、魔女を女司祭に戴いていた前ギリシア的地中海宗教が若い宗教に敗北したとき、そこにアポロン信仰が定位されたことである。いいかえれば、このとき以来、崇拝の対象は女性神(大母神)から男性神アポロンに変ったのだ。
アポロン的宗教の男性神崇拝は、当然のことながらキリストを受け入れる基礎を用意した。ここからキリストの倒錯像サタンの成立まではわずか一歩である。アポロンとキリストが男性でなかったならば、悪魔もまたついに男性ではなかったであろう。若い男性神に打倒された母神へのなつかしい郷愁は、アポロンやキリストへの憎悪の化身である第二の男性神を必然的に招来せしめた。この怨恨と憎悪に黒々と塗り込められた黒い男は、ときにはサタンとして、ときにはロマンティックな悪魔主義者として、ときには超人や天才として、時代とともに変転する自己表現をとげた。 いみじくも聖侯爵の「悪魔主義」について語りながら、「天才は母の国にではなく、魔女の国に棲む」と語ったのはG・R・ホッケである。私が右に述べてきたのもサタンの棲もう風土たる「魔女の国」のくさぐさの追憶であった。
出自《悪魔礼拝》
0 notes
Text
各地句会報
花鳥誌 令和2年3月号

坊城俊樹選
栗林圭魚選 岡田順子選
令和元年12月5日 うづら三日の月句会
坊城俊樹選 特選句
満百歳三年続きの日記買ふ 柏葉 大晦日出来ずじまひの事ばかり さとみ 榾の燃え老の情念湯は激る 都 おでん屋に二胡を奏でる異邦人 同 着ぶくれも粋に見せたく背伸びせる 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月5日 花鳥さゞれ会
炉話に明智が妻の髪のこと 千代子 炉話に韃靼漂流の謂れ聞く 同 外人に服をもらつたクリスマス 同 花鋏音して露のこぼれけり 匠 神の旅飛行機雲とすれちがふ 同 街師走見えざるものが背を押せり かづを 句作りに夢のお告げや十二月 数幸 手を取りてさざんかの径母と行く 雪子 山茶花やピアノの音のはたと止む 啓子 沈下橋渡る三人川の秋 天空
………………………………………………………………
令和元年12月7日 零の会
坊城俊樹選 特選句
着ぶくれて今半覗き玉ひでへ 和子 極月を歩すみごもれる子のために ゆう子 玉子酒間口小さく灯の白し 三郎 電線のゆるき横丁冬の雨 和子 寒紅を差すつづら屋の老婆かな あおい 愛人宅らしき貌してひめ椿 三郎 明治座の稲荷に小さき狐火が 公世 花街は雨山茶花をこぼさぬやう 光子 浜町や三味の音にも似て時雨 秋尚 つづら編むつめたき指と思ふかな 和子 千住葱入れる裏口しぐれをり 梓渕
岡田順子選 特選句
極月を歩すみごもれる子のために ゆう子 寒き鳩寒き雀を蹴散らせり 佑天 狛犬は狛犬として師走神 俊樹 裘着てマヌカンは服並べ 小鳥 指先のうづき熱燗触れてをり あおい 綿虫の無のただよへる漱石忌 公世 極月や金の屋号でくじを売る 和子 人形町しぐれを宿る軒もなし 千種 幼帝の都にみぞれ海遠く ゆう子 人形焼の顔に降りたる冬の雨 俊樹 冬の灯は競ひて狭き照明屋 小鳥
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
なかみち句会
栗林圭魚選 特選句
炉に集ふ顔の火照りと伊豆訛り 怜 放られてぶるんと跳ねる河豚太く 美貴 中子師と話弾んで冬一日 迪子 枯芝に影を写して背比べ 史空 枯芝や流るる雲の影速し 史空 河豚刺身白菊の如清楚なり エイ子 師の笑顔逢うてかはらぬ冬の日に ます江 暁闇に囲炉裏の熾火搔きし父 三無 枯芝のところどころに青むもの 怜 枯芝の小径真つ直ぐ細くあり ます江
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月10日 萩花鳥句会
世のためと我が五十年いま枯木 小勇 萩花鳥必死で守り年忘 祐子 手燭置く躙り口より冬の月 美恵子 両の手で温もりすくふ冬日向 吉之 ほつこりと藪の笹鳴き聞く朝は 陽子 陽は沈み医師アフガンで冬の星 健雄 冬籠ラフマニノフと赤ワイン ゆかり 師を偲び句友をしのび年忘 克弘
………………………………………………………………
令和元年12月11日 鳥取花鳥会
岡田順子選 特選句
接待の大根厚く切りて炊く 立子 をさな去り小春日和の香の残る 都 遠峰々に初雪らしき光かな 益恵 亡き夫のセーター着込み雑踏へ 佐代子 小春日や寮生握手に寄り来る 幸子 鳥待つは熟し切つたる真葛 史子 初雪や望郷の念俄かにす 幸子 喚鐘の音を響かせて報恩講 幹也 仮の世の恙は言はず葛湯吹く 悦子 冴ゆる夜脳に木霊す蹄鉄の音 宇太郎
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月13日 さくら花鳥会
岡田順子選 特選句
寒鰤の刺身で交す回顧談 実加 際やかに鰤競る声や市の朝 登美子 寒桜賓日館を高貴にす 令子 笏谷の石切跡や冬ざるる 寿子 身籠れる体を温む葛湯かな 実加 日短ラストシーンも観て帰る 登美子 朝風に藁ごと揺れる吊し柿 光子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月14日 枡形句会
栗林圭魚選 特選句
遠き日の焚火の香する師走かな 恭子 句の出来るまで柚風呂に浸りをり 多美女 重ね着て背の不安を落ち着かす 百合子 国訛滾る湯豆腐つつき合ひ 三無 禅寺の幾年けふの冬紅葉 百合子 石仏の頰杖解かぬ十二月 同 重ね着をお洒落にこなす首回り 清子 控へ目な彩に追慕の納め句座 百合子 冬帝や鉾杉の秀を研いでをり 三無 隊列のV 字なす旅鳥渡る 和代
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月15日 風月句会
坊城俊樹選 特選句
鼻水をすすり枡形山迷ふ 政江 片頰に冬日浴びつつ句碑拝す 三無 冬帝へ青銅の像両の手を 政江 寒禽の高らかに空呼んでをり 斉 獣道へと冬の影法師行く 政江 仏足石の親指あたり柿落葉 佑天 冬帝の富士拝まんと塔上る 圭魚 観音の結印の美し冬うらら 佑天 母の塔北風の子を懐に 久子 冬紅葉裳裾ゆるやか観世音 三無 冬帝の蔭長くして母の塔 眞理子
栗林圭魚選 特選句
笹鳴きへ耳傾けて磴半ば 芙佐子 冬芝に蔭を延ばして母子像 亜栄子 寒禽の高らかに空呼んでをり 斉 鳥寄せてをり山門の冬椿 芙佐子 木の葉散る森の大きく息を吐き 千種 笹鳴が景を小さくしてをりぬ 斉 養生の辛夷大樹の冬芽かな 芙佐子 泥葱を並べて森のマルシェかな 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月16日 伊藤柏翠俳句記念館
坊城俊樹選 特選句
風に裏表ある如落葉舞ふ かづを ほろ酔ふが如く冬蝶飛びゆけり 同 大冬木産土の宮守りをり 同 まなかひに越の中山眠り初む 文子 泣きむしのこけし飾りし終ひ句座 たゞし 美人画の古暦とて捨てがたし 英美子 かの日々の遠ざかりたる師走かな 和子 白鳥来休耕田の光り合ふ みす枝 木枯しに鐘を鳴らして消防車 輝子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月18日 福井花鳥句会
坊城俊樹選 特選句
近松忌付かず離れずてふ縁 雪 枯尾花吹かれて綺羅を飛ばしけり 啓子 遠くまで信号は青街師走 和子 人生の話し相手に日記買ふ 千加江 冬薔薇を見つめる母はもう居ない 淳子 冬薔薇眺める椅子に主無し 同 街騒も師走のものとなつて来し よしのり ���春日の窓いつぱいの中眠る 美代
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月19日 九州花鳥会
坊城俊樹選 特選句
顔見世の口上粋に申し候 美穂 罪人も重荷を解いて聖夜の灯 かおり 枯菊を焚きてしばらく胸ひそか 佐和 美しき切口みせて炭熾る 孝子 信心のやうに潜るや鳰 豊子 水鳥のこぼす薄紙ほどの息 寿美香 顔見世や四条大橋風痛く 久美子 顔見世や出雲阿国の遊び足 寿美香 懸大根鳶と青空奪ひ合ふ 同 名優の顔見世幟はたはたと 和子 枯野ゆく心の中のほむらかな 美穂 白足袋や紅き蹴出の華やぎて 豊子 遅く着く信濃の宿の雪の華 久美子 山あれば山呻らせて虎落笛 豊子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月21日 鯖江花鳥俳句会
坊城俊樹選 特選句
石臼の飛び石三つ竜の玉 雪 声を聞くだけの電話を掛け夜寒 同 信楽の狸提げしは新走 同 大津絵の鬼と酌まんか新走 同 短日の手を振り合ひて別れけり みす枝 終ひ湯や外に寒柝遠ざかる 同 着膨れにエレベーターの重くなる 同 花八手かはたれ時の白極む 昭子 歳晩の奏楽堂の椅子にゐる 同 野水仙後の怒濤昏れて海 信子 灯台まで歩くつもりや野水仙 同 白山の雪の白さの大根かな たゞし 火の海となりし根榾を裏返す 同 九頭竜の波を母とし霰魚 一涓 老犬の紐解き放つ芒原 世詩明 着膨れて温もり増せる乳房かな 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月23日 武生花鳥俳句会
坊城俊樹選 特選句
谷を駆け息する風や紅葉散る 三四郎 鴨数多小さき湖の重くなる みす枝 干布団霊峰白山隠しけり 昭女 雪吊や三角錐に引き絞る 信子 樹木希林最后の映画観る師走 清女 流星群来れど炬燵の離れ難 久子 水仙の天まで届きさうな畑 時江 銀杏散る藁葺き屋根を黄に染めて 三四郎 黄昏て峰といふ峰冬茜 同 ずわい蟹無念か泡を吹いてをり みす枝 一乗寺奈落の如し銀杏散る ただし 瀬の香もそえて売らるる野水仙 錦子 風花の影消ゆ城の野面壁 時江 枯葎この身消したき日もありぬ ミチ子 おでん鍋同じ佗しさ持ち寄りて ただし 百選の冬の男滝の爆しけり 世詩明 獣抱き母の如くに山眠る みす枝
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年11月22日 第42回近松忌記念俳句大会
坊城俊樹選 特選句
小江戸てふ在所に祀る近松忌 和子 黒を着し女人の一途近松忌 同 雁渡る吉江の里に一忌日 同 近松の女悲しや今の世も 同 紅引いて嫉妬に狂ふ近松忌 信子 燭揺るるだけの華やぎ近松忌 同 簪が凶器となりし近松忌 同 忌を修す館に淡き冬薔薇 ミチ子 奥付に花の一句や近松忌 同 近松像撫で光りして小春の日 昭子 近松忌通りに響く下駄の音 誠 近松忌糺野界隈恋の道 一豊 炉びらきや吉江に住みし浄瑠璃師 令子 その漢別れ上手や近松忌 千代子 近松忌有縁ばかりの世でありし 洋子 来る筈のなき師を待ちて近松忌 英美子 冬晴れや碑文読みゐる一佳人 同 近松忌消せざるものに心の火 雪
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
0 notes
Text
ひとみに映る影 第四話「忘れられた観音寺」
☆プロトタイプ版☆ こちらは無料公開のプロトタイプ版となります。 段落とか誤字とか色々とグッチャグチャなのでご了承下さい。 書籍版では戦闘シーンとかゴアシーンとかマシマシで挿絵も書いたから買ってえええぇぇ!!! →→→☆ここから買おう☆←←← (あらすじ) 私は紅一美。影を操る不思議な力を持った、ちょっと霊感の強いファッションモデルだ。 ある事件で殺された人の霊を探していたら……犯人と私の過去が繋がっていた!? 暗躍する謎の怪異、明らかになっていく真実、失われた記憶。 このままでは地獄の怨霊達が世界に放たれてしまう! 命を弄ぶ邪道を倒すため、いま憤怒の炎が覚醒する!
(※全部内容は一緒です。) pixiv版
◆◆◆
石筵霊山きっての心霊スポット、通称『怪人屋敷』。 表から見えるそれは、小さなはめ殺し窓が幾つかあるだけの灰色の廃屋で、さながら要塞のように霊山来訪者を威圧する。 でもエントランスに入ると、意外と明るくて開放感がある。 北側がガラス張りになっていて、外の車道から街灯のオレンジ光が射し込んでいるからだ。 そのコントラストはまるで、世間の物々しい噂と私の楽しかった思い出のギャップを象徴しているようだった。
C字型の合皮張りソファで囲まれたローテーブルに、譲司さんはスマホを立てかけた。 煌々と輝く画面内には、翼の生えた赤いヤギが浮遊している。 「やあ、アンリウェッサ。何度もすまないね」 スピーカーから、男性的な口調のヤギの声が流れた。でもその声は人間の女の子みたいだった。 アンリウェッサとは、NIC内で使われる譲司さんのコードネームだ。 このヤギさんはNIC関係者なんだろう。 「姿を変えられたとはさっき伺いましたが…性別どころか、人間ですらなかったんですか」 譲司さんは分厚い眼鏡をつまんで画面を凝視した。
「この方、お知り合いですか?」 私は画面を見たまま尋ねた。 「はい。彼はNIC元幹部のハイセポスさんです。 あの時中東支部でサミュエルに殺害された一人で…ほら、オリベ。キッズルームのガブリエルお兄さんや」 <ああ!もちろん覚え���るわ! 人を騙す脳力を持った、イタズラ好きの嘘つき先生ね!> 情報をまとめるとつまり、ハイセポス元幹部は本名ガブリエルさん、 中東支部でサミュエルに殺害された被害者で、キッズルームの養護教諭の一人だったらしい。 ハイセポス元幹部はにっこり微笑むと一瞬発光して、恐らく生前の姿であろう、人間の男性に変身した。 「やあ、オリベにジャックも久しぶりだね」 本当の彼は、きりっと賢そうな三白眼を持つ、小柄な黒人さんだった。
「ハイセポス元幹部は、さっき俺とポメが新幹線に乗っとった時に電話をくれたんや。 ファティマンドラのアンダーソン氏がジャックを目覚めさせた事とか、さっくり教えてくれはってな」 「それでさっき、皆して一美がアンダーソンと会ったって話に飛びついてきたのね」 私の影でくつろいでいたリナが、胸から上だけ出てきて話題に参加した。 「それで、ご用件は何でしょうか」 譲司さんが改めて伺う。
「ああ。すまないが、僕はアンリウェッサの補佐として、ずっとこの端末から君達を監視させて貰っていた。 そこでどうしても確認したい事を聞いてしまって。質問してもいいかな…ミス・クレナイ」 え、私? 「な…何ですか?」
「君はさっきから、この石筵に観音寺があると話しているね」 「はい。私が小さい頃、和尚様と住んでいたお寺さんです」 「その和尚の名を教えてくれるかい?」 「いいですよ。和尚様のお名前は…」 あれ?
「その観音寺はどこにあるのかい?」 「あ、はい。ここからすぐ近くですよ。 外に出て、丁字路を右…いや、左…」 あれ?え!?
「ヒトミちゃん?」 イナちゃんが訝しげに私の顔を覗きこむ。 おかしい、有り得ない。そんなはずはない。 観音寺と、和尚様に関する記憶が…ほとんど思い出せないなんて! 「ちょっと待ってください。忘れるはずないんです。 だって、最後に会ったのは上京する直前…」 いや、違う。
『ひーちゃん、和尚様は今いないから、私がお土産を渡しておくね』 私の脳裏に、ファティマンドラの安徳森さんと出会った日の、萩姫様の言葉がよぎる。 そうだ。あの日は会えなかったんだっけ。 だから最後に会ったのは、玲蘭ちゃんとハゼコちゃんの事件の時…中学一年生。 中学時代に会っているんだから、せめて和尚様の顔ぐらいは…顔ぐらいは…顔は…
ハイセポスさんはばつが悪そうに顎を引いた。 「ミス・クレナイ。とても言い難いんだが、石筵に観音寺はないんだよ」 観音寺が、ない? 「ああ…なくなっちゃったんですか?跡継ぎ不足とかで…」 「違うんだ。ないんだよ。 …そんな寺は、この地に歴史上一度も存在していなかったんだ」 そんな… 「そんな、バカな!」
画面から顔を上げると、みんな私を怪訝そうに見ている。 リナはまた私の影に引きこもった。 「ち…違うんです、観音寺は本当にあったんです! だって現に、私は怪人屋敷の中に入った事があるし…あ!」 そ、そうか!オリベちゃんはさっき、ハイセポスさんを『人を騙す脳力を持つイタズラ好き』って言ってたじゃないか。 「な…なーんだ!ハイセポスさん、ドッキリはやめて下さいよ! そりゃあ私は『したたび』でいつも騙されてますけど、あれはテレビの演出でして…」 「嘘だと思うなら、探してみるといい。 すぐ近くなんだろう」
◆◆◆
私は咄嗟にイナちゃんの手を引いて、怪人屋敷を飛び出した。辺りは既に暗くなっている。 灯りが必要だ。私は二人分の足元の影を右手の中に集めた。 影が圧縮されて行き場を失った光源を親指と人差し指で作った輪に閉じ込めると、『影灯籠(かげどうろう)』という簡易懐中電灯になるんだ。 なにかと便利なこのテクニックを教えて下さったのだって、和尚様だったはずなのに…。
「イナちゃんは、信じてくれるよね?」 山道のぼうぼうの草を蹴りながら私は独りごちた。 「色んな事を教えてもらったんだよ。 知ってる?チベット仏教の本尊は観音菩薩様なんだよ。 だから観音菩薩様は、タルパとか人工霊魂も、ちゃんと救済して下さるんだ」 足元でバッタが一匹逃げた。
「ヒトミちゃん…帰ろうヨ…」 振り返ると、イナちゃんは寒そうに肩を狭めていた。 早くお寺を見つけなきゃ。お蕎麦屋さんの予約時間も近づいている。 「ねえちょっと、一美…」 影灯籠からリナが滑り落ちる。 「あんまり気が進まないけど、この際だから言うわ。あんたの和尚は…」「真言だって!」 私は苛立って声を荒らげてしまった。 「…ちゃんと言えるもん。オム・マニ・パドメ・フム…」
「ヒトミちゃん」 「念彼観音力、火坑変成池(観音様に念じれば、火の海は池に変わり)… 念彼観音力、波浪不能没(観音様に念じれば、溺れて沈むことはない)…」
リナは私から離れ、イナちゃんの影に宿った。 私は足を泥だらけにして彷徨った。 何だか泣けてくる。でも両目から滲み出た涙は、すかさず乱暴な北風に掠め取られる。 もうリナとイナちゃんはついてきていない。
「オム・マニ・パドメ・フム…オム・マニ・パドメ・フム…」 夜の山の寒さと焦りも、私をあざ笑っている。
「オム・マニ・パドメ・フム…」 真言を繰り返す度に、思い出とか、影とか、自分の色々な物が剥がれていく。
「オム・マニ・パドメ…あ」
我に返って見ると、手から滴り落ちた影は一筋の線になって、私達の行くべき道を示していた。 「ほら…私、ちゃんと覚えてたでしょ?」 私は再びイナちゃんの手をとって、影が示す方向へ進んだ。
◆◆◆
影の糸を回収しながら進むと、私達は怪人屋敷に戻っていた。 いや、糸の先端は…怪人屋敷に隣接する、ガレージの入口で途絶えているみたいだ。
ガレージのシャッターはやすやすと持ち上がった。鍵がかかっていなかったんだ。 背後の街灯に中が照らされると、カビ臭い砂塵が舞い上がり、コウモリや蛾がパニックを起こして飛び出してきた。 街灯の光が行き渡るようにガレージ内の影を調節すると、そこには…
「なに、これ…」 そこにあったのは、床に敷かれたままの小さな花柄の布団。錆びついたグルカナイフ。薪と木炭。鍋。 山積みの『安達太良日報』1994年刷。どこかの斎場のタオル。塩。干し柿。干しキノコ。干しイナゴ。 誰かがここで生活していた跡のようだ。何故かすごく懐かしい感じがする。
壁に光を当てると、おびただしい枚数の半紙が貼られている。 写経、手描きのマンダラ、チベット守護梵字、真言、女の子と観音菩薩様が仲良く焚き火を囲う絵。 そして、それらに囲まれたガレージの中央最奥には、私の背より少しだけ大きな何かが、白い布で覆われていた。
「ヒトミちゃん、ここ怖いヨ」 イナちゃんがガレージの入口から囁いた。 「怖い?なんでかな。あ、コウモリならもういないみたいだよ」 私は天井を照らしてみせた。でも、イナちゃんはまだ萎縮している。 「出てきて、ヒトミちゃん。ここやだヨ」 どうしてそんなに怯えてるんだろう。 「平気だよ!だってここは…ここは私が住んでた観音寺だもん!」
私は壁の半紙を幾つか剥がして、イナちゃんに差し出した。 「ほら、これ。和尚様に書道を教わってたの。 凄いでしょ、幼稚園生でこんな難しい漢字書いてたんだよ! だから私、今でも字の綺麗さには自信があるんだ」 半紙を一枚ずつ丁寧にめくって見せる。『念彼観音力』『煩悩即菩提』、どれも仏教的な文章だ。 「なーんて、本当はね、影絵で和尚様の本を写しながら書くから、こんなに上手く書けてたんだけどね」 『而二不二』『(梵字の真言)』『(マンダラ)』『金剛愛輪珠』… 「オモナアァッ!!」 突然イナちゃんが後ずさった。 手元の半紙を見ると、書かれていた文字は… いや、これは…アルファベットの『E』と『十』の字に似た、記号… どうしてイナちゃんの手相がここに…?
「イナ?紅さん?」 怪人屋敷から皆が集まってきた。 イナちゃんはリナと抱き合い、震えている。 皆もそんなイナちゃんの怯えた様子を見て、不穏な表情になった。 「だ…大丈夫だってば!そ、そうだ! 観音菩薩様の御本尊を見てもらえば、きっと怖くなくなるよね! すごく優しいお顔なんだよ。ほら!」 私はガレージ最奥の観音像にかかった白い布を、思いっきり引き剥がした。
「あぃぎいぃぃやああああああああ!!!!!」 隣の安達太良山にまで響くほどの声で、イナちゃんが絶叫した。
「え…?」 イナちゃんは白目を剥き、口の両端から泡を吹き出して倒れた。 「ガウ!ギャンッギャン!!」 歯茎を見せて吠えるポメラー子ちゃんの横で、オリベちゃんと譲司さんは腰を抜かしている。 するうちジャックさんが気絶したイナちゃんに取り憑き、殺人鬼や暴力団も泣いて逃げ出すような形相で私の胸ぐらを掴んだ。
「テメェ馬鹿野郎!!この子になんて物見せてやがる!!!」 え…なに言ってるの、ジャックさん? 「ううっ…うっ…」<ヒトミちゃん、そ…それ、隠して…!> 嗚咽しながらオリベちゃんがテレパシーを送る。 私は真横にある観音像を見た。 金色の装飾品に彩られた、木彫りの…
「は?」 私は真横にある観音像を見た。 それは全身の皮膚���剥がされ、金色の装飾品に彩られた、即身仏のミイラだった。
◆◆◆
「なに…これ…」 私は一瞬、目の前にある物が何だかよくわからなかった。 変な話、スルメイカやショルダーハムでできた精巧な人体模型がお袈裟を着てネックレスをしているような、 それぐらい意味不明でアンバランスな物体に見えた。
<と、ともかく…公安局に連絡を! さっきのファティマンドラの件もあるし…> 腰を抜かしたままのオリベちゃんが、譲司さんを揺さぶって電話を促す。 「あ…ああ!せやな!C案件対策班に…」 「やめてください!」 「<え?>」
私は気がつくと叫んでいた。 「つ…通報はやめてください!だ、だって…」 だって、何なのか?自分でもわからない。 ただ、ここが警察に暴かれてしまったら、何かとてつもない物を失ってしまうような気がして。
「何言ってやがる…。ここに変死体があるんだぞ! 花生やして腐ったミンチどころじゃねえ、マジの死体がだ!!」 ジャックさんがイナちゃんの身体で私を責める。 「ち…ち…違います!観音様を変死体だなんて、罰当たりな事言わないで下さい!! これは…この人は…このしどわあぁぁ…!」 嗚咽で言葉が出てこない。もう、本当はわかってるんだ。 この即身仏は…私の…和尚様なんだ。
混乱と涙とガレージ内のハウスダストと鼻水で、私は身も心もぐしゃぐしゃになっていた。 皆はまだ何か怒鳴ったり喚いたりしているみたいだけど、もう何もわからない。 私はただ、冷たい和尚様の足元にすがりついてひたすら泣いた。
「ジャック、もうええやん。やめよう」 すると譲司さんがガレージに入ってきて、私の髪を掴んで逆上していたジャックさんを宥めた。 「紅さん、わかりました。通報は後でにします。 その前に…紅さんの和尚様に、ご挨拶させて下さい」 彼は私の頬を優しく指で拭い、小さい子に向けるような微笑みで言った。 そして和尚様の前に立つと、うやうやしく一礼し、 「失礼します」と呟いて、合掌されている和尚様の両手にそっと触れた。
譲司さんはそのまましばらく静止する。和尚様の記憶を、読んでいるみたいだ。 <ジョージ…> オリベちゃんがまたテレパシーによる視界共有を提案しようとする。 でも譲司さんは視線でそれを断って、 「紅さん」 私に握手を求める仕草をした。
「行きなさい」 リナが私を促す。 「私も知らない真実。ちゃんとぜんぶ見届けるのよ」 私は頷いて、譲司さんの手を握る。 そのまま影移しで譲司さんの影に意識を溶け込ませ、彼と同じ視界へ飛んだ。
◆◆◆
ザリザリザリ…ザザザ…。視覚と聴覚を覆う青黒い縞模様とノイズ音が晴れていくと、目の前が病院の病棟内のような風景になった。 VHSじみた安徳森さんの時と違って、前後左右を自由に見ることができる。
「ずいぶん鮮明な記憶ですね」 気がつくと隣で、ノイズがかった譲司さんが私と手を繋いで立っていた。 今、私は彼の影だ。 「和尚様は、どこでしょうか…?」 辺りを見渡すと、昼間なのに全ての病室のドアが閉まっている。 案内板を見るに、ここは精神科の閉鎖病棟らしい。 ふと、私ば病室の一つから強い霊的な電磁波を察知した。 「譲司さん」 「そこですよね」 彼も同じ部屋にダウジングが反応したみたいだ。 ただ、空気で物を感知する彼が気付いた事は霊ではなかったらしい。 彼は『水家曽良 様』と書かれたドアプレートを指さしていた。
意識体の私達は幽霊のように病室のドアをすり抜ける。 中にいたのはベッドに横たわるサミュエルこと水家曽良と、彼を見下ろす二人の霊魂だ。 私から見て左側の霊は、すらっとした赤い僧衣の男性。 顔は指でこすった水彩画のようにぼやけていて、よく見えない。 一方右の霊は、顔と股間の部分だけくり抜いた人間の皮膚を肉襦袢のように着ている、不気味な煤煙だ。 水家曽良はまだ子供の姿。日本国籍を得て間もない頃なんだろう。
「この子の才能は実に惜しい物だった」 肉襦袢の霊が言う。喋り方は若々しいけど、声はおじいさんみたいだ。 「タルパはそう誰でも創造できる物ではない。 まして彼は、我々が与えた『なぶろく』のエーテル法具をも使いこなした。 それを享楽殺人の怪物を生み出すために使った挙句、浅ましい精神外科医共に脳力を摘出されるとは。 この子に金剛の朝日は未来永劫訪れないだろう」 なぶろく?と聞こえた箇所だけ意味はわからなかったけど、 どうやら彼は水家に何らかの力を与えた霊魂らしい。 「エーテル法具…NICで聞いた事があります。 エクトプラズム粒子を含んだ何らかのタンパク質塊、 人間の脳を覚醒させて特殊脳力を呼び覚ます、オーバーテクノロジー…」 譲司さんはそれに何か心当たりがあるようだ。
「ともかく、これ以上損失を出す前に、彼の魂を楽園へ送るのは諦めましょう。 彼はまだ子供ですが、余りにも残虐すぎました」 赤僧衣の霊が、隣の肉襦袢の霊の顔色を窺うように言う。まだいまいち話が見えない。 「その通りだ。しかし、私達もただで金剛の地に帰るわけにはいくまい」
すると肉襦袢は、眠っている水家の鼻に指を突っ込んだ。 「フコッ」 水家が苦しそうな声を発する。彼の耳から水っぽい液体が垂れ、頭の中で何かがクチャクチャと動き回る音がする。 でも水家は意識がないのか、はたまた金縛りに遭っているのか、微動だにしない。 やがて肉襦袢が鼻から指を引き抜くと、その指先には、薄茶色い粘液でつやつやと輝くタコ糸のような紐が五十センチほど垂れていた。 「どうなさるおつもりですか」 心配そうに赤僧衣が問う。 肉襦袢は紐を丁寧に折りたたむと、水家の病室から去っていった。 私達と赤僧衣は彼を追いかける。
肉襦袢は渡り廊下を通って、違う病棟に移動した。 彼が立ち止まったのは、新生児のベッドが並ぶ、ガラス張りのベビールームだった。 彼は室内に入り、生まれたばかりの赤ちゃん達の顔を一人ずつ覗いていく。 そして、壁際から五番目の赤ちゃんの前でぴたりと静止した。
「見なさい。この子だ」 肉襦袢は赤僧衣に手招きする。 赤僧衣は赤ちゃんを見ると、感嘆のため息をついた。 「この子の顔の周りだけ、不自然に影で覆われているだろう。 天井の光が金剛のように眩しくて、無意識に影を作っているんだ。これは影法師という珍しい霊能力だ。 この子は金剛級に強い素質を持っている」 安らかな顔で眠る赤ちゃんの頭上で、肉襦袢が興奮気味に語る。 あれ、そういえば…
「譲司さん。水家曽良が日本に来たのって、具体的にいつなんですか?」 「日付までは覚えとりませんが…たぶん、1990年の十一月上旬です。 俺日本の家に引き取られて最初の行事が弟の七五三やったんで」 1990年十一月、影法師使いの赤ちゃん…偶然か? 私の生年月日は1990年十一月六日だ。 まさかここ、石川町の東北総合病院じゃないよね?違うよね!? そんな不穏な想像が脳内で回っている一方、肉襦袢は目を疑うような行動に出た。
「金剛の力は金剛の如く清き者が授かるべきだ」 肉襦袢はさっき水家から引き出した糸を広げると、その先端を…赤ちゃんの口に含ませた! チュプ、チュプ、チュパ…ファーストキスどころか、まだお母さんのおっぱいすら咥えた事もない新生児は、本能的に糸を飲み込んでいく! 「ほら、こんなに喜んでいるだろう」 「そ…そう…ですね…」 表情の見えない赤僧衣も露骨にドン引きしている。 譲司さんが真っ青を通り越して白塗りみたいな顔色で私を見た。 「あ、あの…紅さん、一旦止めま」「譲司さんうるさい!!」「アハイすいませェェン!!!」 背中から火が出そうだ。
永劫にも思える時間をかけて、赤ちゃんは糸を全て飲み込んでしまった。 「これでこの子はタルパの法力を得た!」 肉襦袢が人皮の手で拍手する。 「失礼ですが如来、一度穢れた者の法具を赤子に与えるのは、この子の人生に悪いのでは…?」 如来?如来って言った今!?この赤僧衣、如来って言ったの!? こんなエド・ゲインみたいな格好したモヤモヤの外道が如来!?有り得ない有り得ない有り得ない!!
如来と呼ばれた肉襦袢はキッと赤僧衣の方を向いた。 「ではどうしろと?サミュエル・ミラーの死後霊魂を収穫する価値がなくなったと確定した今、 これ以上金剛の楽園に損失を出してはならないだろうが!」 「ですが…「くどいっ!!」 事情を知らない私にも赤僧衣の言っている事は正論だとわかるが、彼は肉襦袢に逆らえないようだ。
「よかろう。お前がそこまでこの子の神聖を危惧するなら、この子に金剛の守護霊を与えてやろう」 肉襦袢は赤ちゃんの胸に煤煙の指を沈めた。 「な…待って下さい!肋骨なら、私の骨を!」 肋骨? 「ええい、既に『なぶろく』を捧げたお前に何の法力が残っているというのか?出涸らしめ! 『ろくくさびのひりゅう』は金剛の霊能力を持つ者の肋骨でなければ作れん!」 肉襦袢はわけのわからない専門用語を喚きながら、赤ちゃんの胸の中で… うそ、まさか!? 「この赤子に金剛の有明あれーーッ!」
プチン!
まるで爪楊枝でも折ったようなくぐもった軽い音がした後、 「ニイィィィーーーギャアァァアアアアァア!!!!!」 赤ちゃんは未経験の恐怖と���痛で雄叫びを上げた。 「みぎゃーーっ!」「あーーーん!」釣られて他の赤ちゃん達も阿鼻叫喚! すかさず看護師がベビールームに飛びこんで来るが、赤ちゃんを泣かせた原因を彼女らが知ることはない。
「お前は石英で龍王像を彫り、この金剛の肋骨を楔として奉納するんだ。 さすれば『肋楔の緋龍(ろくくさびのひりゅう)』はこの子を往生の時まで邪道から守り、やがて金剛の楽園へ運ぶだろう。 象形は…そうだな、この福島の地に伝わる、萩姫と不動明王の伝説に因んで、倶利伽羅龍王像にするといい。 この子に金剛の御加護があらん事を…」 肉襦袢は赤ちゃんの小さな肋骨を赤僧衣に手渡すと、汚らしい煤煙を霧散するようにして消え去った。 霊的な力で肋骨を一本引き抜かれた赤ちゃんの胸には、傷跡の代わりに『E』『十』の形の痣ができていた。
「すまない…ああ、本当にすまない…」 肋骨を奪われた赤ちゃんの横で、赤僧衣の霊魂は崩れ落ちるように土下座して咽び泣いた。 看護師さん達はそんな彼の存在を完全に無視して、この突然発生したパニックの対応に追われている。
「こんなん嘘やろ…」 譲司さんが裏返った声でそう呟いた時、私は『生まれつき一本少ない』と言い聞かされていた自分の肋骨のあたりを抑えて震えていた。 それから文字通り気が遠くなるような感覚を覚え、私達はこのサイコメトリー回想から脱出した。 不気味な如来を讃える赤ちゃん達の叫び声が、だんだんと遠ざかっていった。
0 notes
Text
【S/D】サムと忘却の呪い(仮)1~4
ツイッターに画像で投稿しているS/D小説です。一万文字超くらい。まだ続きます。
もし魔女のロウィーナが、将来自分を殺す男になると知って攫い、殺してしまうつもりだった幼少のサムに情がわいて、自分の子として育てることにしたら? そしてハンターが”魔女狩り”に特化した集団だったら? という妄想から生まれた小話です。シーズン12の11話「忘却の呪い」をオマージュしています。アリシアやマックスという12から登場する魔女キャラにも出てもらってます(彼らはハンターだけどここでは魔女として)。
連載中の小説を書きたいとは思うんだけど宿便状態なので、ガス抜きに小話を書いてる現状です。なのでお気楽な感じで読んでもらえると。。
1
サムの養い親である魔女いわく、日のあるうちの森は獣の領域。だから理性ある魔女や魔法使いは夜に活動し、昼間のうざったい太陽が地上を照らしている間は絹のシーツに包まって体力の回復に努めるのだという。サムにいわせれば怠惰の言い訳にすぎないが、夜更かしな魔女たちの生態がいとおしくもあった。何より夜の彼女らはサムなど足元にも及ばぬほど鋭い英知と魔力の使い手だ。ならば彼女たちと少しばかり生態の異なる自分が、早起きして夜の”活動”の手助けをするのは義務であるし喜びでもある。獣の領域というなら早朝の森は狩りをするのに恵まれた環境だ。彼女たちはウサギのシチューが大好きだけど、そのウサギがどこで泥の毛皮を脱いできて鍋に飛び込んでくれたのかは考えたがらない。
自分が何者であっても、森を歩くのが好きな男に変わりはなかっただろうかとサムは想像する。下草を踏むたび立ち上る濡れて青い土のにおい。罠にかけた小さな獣をくびくときすら、森はサムと獣のどちらをも憐れんで祝福してくれる。森はサムのびっくり箱だ。彼は自分の生まれた場所を知らない。だけど彼の親がこの森の入口に彼を捨てたとき、赤ん坊と森のあいだに絆が生まれ、その瞬間から森がサムの故郷になったのだ。※
そうだ。森はいつもサムを驚かせてくれる。かくれんぼで遊んでいた七歳の彼を、その懐の深さで半月のあいだかくまってくれ、養い親をすっかりやつれさせてしまった時のように。
その日、狩りを終えたサムの目の前を、遅寝のウサギが飛び跳ねていった。茂みの奥に逃げ込んだウサギを彼は追いかけた。腰には今日のぶんの収穫が下げられていたけれど、もう一匹恵まれたって困ることはない。
茂みの中から黒い毛皮が現われた。サムは手を伸ばそうとしてひっこめた。黒くもなかったし、毛皮でもなかった。朝露で濡れた短いブロンドがゆっくりとサムのほうを向いて、彼はアッと息をのんだ。魔女がウサギを化かして僕をからかおうとしているのか。そうでなければなぜこんな場所に、サムの知らない男がいる?
ところがブロンドの男の懐からさっきのウサギがぴょんと飛び出して、サムの脇を通ってどこかへ行ってしまった。「バイ、うさちゃん」と男はいった。寝ぼけたように、低くかすれた、それなのに、ぞっとするくらい、やわらかな声だった。
「僕はサム」と、サムはいった。まぬけ、と森がささやくのが聞こえた。もしくは自分自身の心の声だったかもしれない。
男は重たげなまぶたを持ち上げて、サムを見上げた。
「やあ、サム」
新緑、深い湖、砂金の流れる小川。男の瞳は輝いていた。
森はまたもサムに驚きを与えてくれた。彼は恋多き魔女たちに囲まれながら、自分が恋することが出来るとは思っていなかった。
この時までは。
2
昼過ぎから始まるブランチの席で、気もそぞろなサムに、養い親のロウィーナはけげんな視線を送る。
「今朝のウサギ、ちょっと血抜きが甘いじゃない? 生臭いのは嫌よ、われわれは吸血鬼ではないのだから」
「そう?」 サムはぼんやりと答える。「そうかな? それ、缶詰の肉だけど」
「サミュエール」 ロウィーナの視線がますます冷たくなる。
「今朝の狩りは空振りだった?」 行儀よくパンをちぎってアリシアがたずねる。彼女は見た目だけではなく、実年齢もサムとさほど離れていない若い魔女だ。母親のターシャ、双子のマックスとともに、ここロウィーナの屋敷に下宿している。
「今朝の狩り……」 思いもかけぬ収穫があったことを姉弟子にどうやって伝えればいいだろう。いや、とサムは意識の中で首を振る。
魔女のなわばり意識の強さといったら、狼人間が可愛く思えるほどだ。人間が――しかもどうやら”記憶があやふや”な、身元の怪しい――神聖な魔女の森に入り込んだと知れたら、ロウィーナははっきりと戦化粧をして森へ勇み、彼を排除しかかるだろう。双子のアリシアとマックスも、彼らは敵とみなし��人間に容赦はしない。つまり、明日のシチューの中身が決まるってことだ。
サムはぶるっと震えた。靴の底から顎の奥まで震えは伝わってきた。春の始まりに色づく枝先のように初々しく、美しい彼の瞳が、よく炒めてから煮込んだ紫玉ねぎの横に浮かんでいるさまを思い浮かべて。彼の肉つきのよい白い二の腕を調理するときの甘い香りを想像して。彼の肉を食べる――残酷なはずの行為が甘美な誘惑に感じる自分にうろたえて。
だめだ、だめ。そんなことにはさせない。彼のことは秘密にする。
「今日は、思ったより暖かくて」 サムは本当のことだけを口にする。「血を抜くのが遅すぎて、ダメにしちゃった。毛皮だけはいで、肉は捨てたよ」
「また寄り道をしたんでしょう。狩りのあとはすぐに帰ってこなきゃだめよ。獲物を持ったままウロウロしないの」 ロウィーナは血のような葡萄ジュースで唇を湿らせる。
「でないとあなたが獲物にされるわ」
サムはこっそりと屋敷を抜け出し、森の男を見つけた場所まで急ぐ。
彼はそこにいなかった。けれどたどり着いた茂みの変わりようを見て、逃げたわけじゃなさそうだと安堵する。ただの茂みだったそこは、下草が踏みならされて空き地に変わり、中心の地面は掘られていて、男が簡易なかまどを作ろうとしていたことが見て取れた。
がさがさ音がして、薪になりそうな枝を腕に抱えた男が戻ってきた。サムの顔を見ると一瞬で表情が明るくなる。「サム!」 男は枝を足元に落としてサムに近づいた。その両手がわずかに広げられているので、サムは自分がハグされるんだと気づいた。
サムが躊躇いながら上げた腕の下に、男の腕が入り込んできた。肩甲骨の下に巻き付いた腕がぎゅっと彼の胴体を締める。”抱きしめられた”んだ。魔女たちはサムによく触れたがるけど、頬にキスしたり腕を組んだりするだけだ。
こうして誰かに真正面から抱きしめられるなんて、初めての経験だ。他人の体温を腹で感じるのも。
なんて心地がいいんだ。
「また来てくれたんだな」 男はそのまま顔だけを上げて、同じくらいの高さにあるサムの目を見てにっこり笑った。
サムはまぶしくてクラクラした。まるで、ああ、彼は太陽みたいだ――魔女や魔法使いが忌み嫌う太陽――けれど彼らが崇める月を輝かせる光の源。
「来るっていったじゃないか」 サムはゆっくりと、舌が絡まないようにいった。ハグに動揺したなんて、彼の笑顔にクラクラしたなんて、知られたら、あまり恰好がつかない気がした。恋に長けた魔力使いの男女のスマートな駆け引きを思い返し、取り澄ました顔を作る。「ほら、パンとジュースを持ってきた。昨日から何も食べてないって、ほんとう?」
「ありがとう!」 男はサムのぺたぺたと頬を叩いて感謝を表した。――状況を考えれば、それは感謝のしぐさで間違いないはずだ。サムにとってはあまりに親密すぎたので、すぐには思い当たらなかった。だけど、男は四六時中、出会った人間の頬をぺちぺちしてますとでもいうように平然として、その場に屈むとリュックの中を探りだす。
サムは早まる動悸を抑えるため、こっそり深呼吸を繰り返した。
「どうかな、憶えてないんだ。何も憶えてない」 男は瓶の蓋を捻って開け、すぐに半分を飲み干した。よほど喉が渇いていたんだろう。きれいに反った喉のラインを必要以上に凝視しないようにサムは気をつけた。「ほんとに、参ったよ。腹が減って、おまえの捨てていったウサギを焼こうと思ったんだ。でも火を熾す道具が見つからなくて」
「何も憶えてないって、どうしたの? どうしてこの森に入ったんだ? 町からそんなに遠くはないけど、ここが魔女の森だってわかってるだろう? それとも、よそから来たの?」
「それが、わかんねんだ」
「何も憶えてないの? 自分の名前も?」
彼は、驚いたように目をしばたかせた。まるで自分に名前あることすら、失念していたように。
その様子に異様さを感じて、サムはまさか、と思った。記憶喪失の人間が、”自分の名前を思い出せない”と悩むことはあっても、”自分に名前があること”を忘れて明るく振る舞うなんてことがあるだろうか。この異様さは、まじないの気配に通じる。彼の様子は、身体的、精神的な後遺症による記憶喪失であるというよりも、呪いによるダメージを受けている状態だと思ったほうがしっくりくる。
でも、まさか。だれが彼を呪うっていうんだ? 中世ならともかく、このセンシティブな時代に魔女が人間を呪うなんてありえない。
「うーん、たぶん、Dがつく気がする」 男が考え込むと眉間にしわができた。「D、D……ダリール、ディビット、違う……。デ……デレック? パッとしねえなあ……」
「ダンカン? ダドリー?」
「うーん?」
「ドミニク? ドウェイン?」
「ドウェイン? いいかもな。おれをそう呼ぶか?」
「それがきみの名前なの? 思い出した?」
「うーん? 多分違う気がする。でもいかしてるよな」
サムは首を振った。彼の愛嬌に惑わされてはいけない。「もう少し、思い出してみようよ。デイモン、ディーン、ダライアス、デイル……」
「それだ!」
「デイル?」
「いや、もう一つ前の」
「ダライアス? ディーン?」
「ディーンだ!」 男はうれしそうに歯をむき出して笑った。「おれの名前はディーンだ。それに、思い出したぞ。おれには弟がいる」
「いいぞ。どこに住んでいたかは?」
男はさらにしわを深くして考え込んだが、しばらくしても唸り声しか出てこない。
サムはちらばった薪を集めて、かまどの枠を組み立てた。気づくとディーンがじっと見つめていた。
「何も思い出せない」 あっけらかんとしていた少し前と違って、悲しみに満ちた声だった。「どうしちまったんだろう。おれ。ウサギを抱いて、おまえを見つけた。それ以前のことが、何も思い出せないんだ」
「たぶん……たぶんだけど、きみは呪われたんだ」 サムは慎重に言葉を選んでいった。「魔女のことは、憶えてる……というか、知ってるだろ? 今ではそんな悪さをする魔女は少ないけど、トラブルになる自覚もないまま、彼女ら――彼かもしれないけど――を怒らせて、呪われるってことも、ないわけじゃないんだ」
「呪われた?」 ディーンは大きな目を限界まで開いた。「おれが? どうして?」
「わからない。もしかしたら違うかも。でもきみ、どこにも怪我はないようだし、記憶がないっていうのに、やたら気楽だったろ。それにここは魔女の森だよ。人間は入ってこない。基本的にはね。なのにきみがここにいるっていうのが、魔女が関わっているっていう証拠にならない?」
「おまえはずいぶん賢そうに話すんだな」 ディーンは鼻をすすった。水っぽい音がした。「何が証拠になるっていうんだ。おれはどうすればいい? どこに行けばいい」
「ここにいればいい」 サムは火種のないかまどを見つめて、それから首を振った。「ここじゃだめだ。ここは屋敷から近すぎるし。僕の家族に見つかったらディーンが危ない」
「何をいってるんだ? 怖いぞ」
「大丈夫。もっと奥に、今は使ってないあばら家があるんだ。たぶん僕しか知らない。そこにディーンをかくまってあげる。僕は魔法使いなんだ――まだ一人前じゃないけど。いろんな本を読める。それに、僕の親はすごい魔女なんだ、ディーンにかけられた呪いを解く方法をきっと知ってる」
「まて、待てよ。おまえが魔法使い? おまえの親が魔女? おれに呪いをかけたのはその魔女じゃないのか? ここはその魔女の森なんだろ?」
「ロウィーナは人に呪いなんてかけないよ。そんなにヒマじゃないんだ」
「わかんないだろ」 ディーンの声に水っぽさが増した。と思ったら、彼はぽろりと涙をこぼしている。サムは頬を叩かれた時以上に衝撃を受けた。こんなに静かに泣く人は見たことはなかった。
「ディーン、ごめん。泣かないで」 折れた薪の上に尻を乗せて、膝を折りたたんで小さくなっているディーンの横にしゃがみ込む。「大丈夫だよ。僕が守ってあげる。記憶を取り戻してあげるから」
ディーンはサムを見つめて、まばたきもせずまた二粒涙を落した。サムを奇跡を見守っているみたいにじっと彼を待った。やがて彼は赤いまぶたで瞳を覆って、小さくうなずいた。
「わかった。おまえを信じるよ」
3
あずまやに移動して寝床を整えた頃にはもう日が暮れかけていたので、サムは急ぎ屋敷に戻らないといけなかった。夕食にはコックを雇っているとはいえ、実際に食卓を作るのは女主人であるロウィーナの指示をうけたサムだ。
「また何か食べ物を持ってくるよ。遅くなるかもしれないけど、夜中までには必ず」
「サム、おれの記憶、戻るよな?」
小屋の質素な木戸を開けたサムは振り返る。戸の影で彼の不安そうな顔の半分が隠れてしまっている。サムより年上に見えるのに、心内を素直に伝えてくる瞳だけをみるとディーンは幼い子供のようだ。このまま留まりたい思いでいっぱいになる。
彼が人間ではなかったら。彼が記憶ではなく、過去を持たない精霊だとしたら、それは森がサムに与えた贈り物なのではないか。
彼を森の精霊だといって屋敷に連れ帰り、ターシャやマックスが連れているような使い魔として側に置く。何も知らず、誰と繋がりもない彼の唯一の主人となる。彼の食べるもの、着るもの、行動の範囲の一切をサムが指図し、彼のすべてを支配する。それがサムに、許されているとしたら?
あるいは彼をこのままここに留め置いて、二人で秘密の生活を続ける。ディーンには記憶を取り戻す方法がなかなか見つからないといっておけ���いい。小屋を出ればいかに危険かを言い聞かせれば、逃げられることはないだろう。
違う。僕は彼を支配したいんじゃない。ただ彼に――
「キスしたいな……」
「えっ」
「えっ、あっ、いや」 妄想が強すぎて声に出ていたと知ってサムは慌てた。
「き、君の記憶は戻るよ、僕にまかせて。でも、いったん戻らなきゃ。ロウィーナは僕が家にいると思ってる。彼女は僕の部屋に勝手に入ったりしないけど、ディナーの準備に遅れたら魔法の鏡で覗かれるかも。僕がいないことがばれたら大騒ぎになる、森に捜索隊が出されたら大変だ。僕が行方不明になったのはもうずっと前のことなのに……」
「サム、おれにキスしたいのか」
「えっ」 サムは片手で戸にすがりつきながら唇をこすった。「なんで?」
「なんでって、そういっただろ? おれは、憶えてる」
そういって、自分の唇の感触を確かめるように、ディーンは舌をそろりと出して下唇を噛む。赤い舌と、暗がりでもきらりと輝く白い歯が、熟れたベリーのような唇から覗いた。サムは狩人の本能で手を伸ばした。指先が唇に触れ、湿った感覚がした。頬を滑った指が、耳たぶに触れると、そこは唇よりも熱かった。ディーンはため息を吐いた。
「サムの手、でっかいな」
ディーンは少し俯いて、サムの手が自分の項を包み込めるようにした。サムは夢心地で一歩近づき、両手でディーンの頭を抱く。後ろで木戸が閉まる音がする。ガラスの嵌っていない窓が一つあるだけの小屋の中は真っ暗になった。
ディーンは目を閉じたままゆっくりを顔を上げた。親指の付け根に彼の穏やかな脈動を聞く。野性の鹿に接近を許されたときのように誇らしく、謙虚な気持ちになった。サムは初めてキスをした。
4
何をいわれるかとひやひやしながら屋敷に戻ったが、ロウィーナは不在だった。かわりにアリシアがキッチンを取り仕切っていた。気が緩んだサムは今度はアリシアににやけ顔が見られないかと心配するはめになった。味見をして、雇いのコックにしょっぱいわね、でもこれでいいわ等と指示を出しながら、アリシアはサムを観察している。魔女というのはみんなそうだ。気安いふりをして他人の心を探るのに余念がない。
食卓が完成するころにロウィーナとターシャが帰ってきた。二人が揃って出かけていたことにサムは驚いた。何か大きな事件があったのかと思い、それからあずまやのディーンのことがばれたのではないかと怖くなる。
ロウィーナは冷静を装っていたけどイライラしているのは明らかだったし、ふだん泰然としているターシャもどこか落ち着きがない。
「二人でどこに行ってたんだ?」
食事が始まってしばらくして、マックスが尋ねた。サムは二人の魔女の答えを待つ間、ろくに呼吸もできなかった。ロウィーナがグラスを煽ったので、ターシャが話し出した。
「ロックリン家よ。招待状を出しに行ったの。とんでもないことを聞かされたわ。大事が控えているから心配ね。おかしなことにならなければいいけど。ロウィーナ……」
「ギデオンが死んだこと?」 ロウィーナはその話題を口にするのも腹立たしいとばかりにターシャをにらんだ。「大したことじゃないわ、あの腐った三つ子が今までそろっていたことが不吉だった。わざわざ私たちに話したのはサムの儀式にケチをつけるためよ。なめられたもんだわ、たかが数十年ばかりアメリカに入植したのが早いからって」
「ロックリン家? 私もあいつらは嫌い。でもしょうがないわ、あっちは由緒正しいドルイドのスペルを持ってる」 アリシアがみんなの顔を見回す。「私たちにあるのは……実地で身に着けた薬草学に、星占術、たくさんの水晶。あちこちの流派を回って極めた最先端の魔法術。あれ……全然悪くないかも?」
「さしずめ野草派ってとこだな」 マックスが調子を合わせる。「雑草と自称するのはやめておこう。でも、サムの儀式は予定どおりやるんだろ?」
「もちろんそのつもりよ」
「僕の儀式って?」 みんなが当然のようにいうから、サムは何か重要な予定を自分だけ聞き逃していたのかと焦った。ロウィーナとターシャ親子はともに定期的に魔法の儀式を行う。サタンへの忠誠を示し、魔力を高めるためだ。子���もにはまだ早いといって、いつものけ者にされていたから、どうせ自分には関係ないと思ってよく聞いていなかったのかも。
「僕も儀式に参加できるの?」
それを熱望していたのは覚えているが、ディーンを匿ってる今は避けたい。
「いいえ、そうじゃない。サム。”あなたの”儀式よ」 サムが言い訳を探す間もなくロウィーナはいった。
彼女は背筋をピンと伸ばしてサムを見た。「あなたはもう十六歳。サタンに忠誠を誓って一人前の魔法使いになる時が来たの。小さいころに教えたでしょ、森のストーンサークルで儀式を行う。この土地に住まう全ての魔女と魔法使いの立ち合いのもと、新しい魔法使いの誕生を祝うのよ」
サムはあっけにとられた。「そんな――大事なことを、なんで――もっと前に、言ってくれなかったんだ」
「逃げちゃうと困るでしょ」 アリシアがあっさりといってのける。「多感な思春期の子どもに”おまえは十六歳になったら”死の書”にサインしてサタン様の下僕になるんだ、それまで純潔を守れ”なんていったら大変なことになる。私もマックスも、知らされたのはその日の夕方。まあそれまでも、男の子と仲が良くなりすぎないように見張られていたけどね」
「その反動が今きてる」 マックスが気だるそうに顔を向けて、双子はほほ笑んだ。
「その日の夕方だって?」 サムは仰天した。「まさか、今夜?」
「まさか。今日は招待状を出しただけ。儀式は明日の夜」 ロウィーナはため息を吐いて再びカトラリーを持つ手を上げる。「まあ、だから、明日の昼間の勉強はお休み。あなたは寝ていなさい。真夜中に始め、明けの明星が昇るまで行うのが通例なの。初めての儀式だから特に長く感じるものよ。主役が居眠りなんて許されませんからね、しっかり寝ておくことね」
「私たちもその助言がほしかったわ」 双子が嘆くと、ターシャが「私の若いころなんてもっとひどかった。真夜中に叩き起こされて……」と話を始める。サムはそれを耳の端で聞きながら、味のしない肉を噛み締めた。大変なことになった。
ストーンサークルはディーンをかくまっているあずまやのすぐ近くにある。ただの天然のアスレチックジムだと思っていた古ぼけた巨石にそんな使い道があったなんて知らなかった。
ディーンを別の場所へ移す? いや、他に森に彼を隠せるような場所なんて思い当たらない。もしも永久に彼を森に閉じ込めておくっていうなら別だ――大木のうろ、崖下の洞窟、そういった場所を幾つか知っている――そこを拠点に家を作ることができる。何週間、何か月、何年もかけていいなら、サムは彼のために新しい屋敷だって建てられる――だけどそうじゃない。そうはならない。ディーンの記憶を取り戻して、彼の帰る場所を思い出せてあげるんだ。
「ロウィーナ……聞いていい?」 サムは何でもないふうに装って質問した。「人の……記憶を消す魔法ってあるだろ? 難しいのかな?」
当然ながら、何でもないふうに答えてくれる魔女はいなかった。みんながサムの顔を見るので、サムは急いで唐突に変な質問をした正当な理由を披露しなければならなかった。
「思春期に……」 喉にパンが詰まったふりをして咳をする。「その、儀式のことを聞かされたって、ああそう、って受け入れる子もいるかもしれないだろ。まずは話してみないと。隠すのはあんまりだ。それで、すごくその子が嫌がったり、自暴自棄になるようなら、その時は記憶を消す魔法を使えばいいんじゃないかと、そう思ったんだ。ただ思いついたんだよ」
一瞬、間があいて、マックスが「ひゅー」と口笛を吹くまねをする。「その考え方、俺は好きだな。冷酷で、合理的で。さすが、ロウィーナの一番弟子」
ロウィーナは口元でだけ微笑み、ゆっくりと首を振った。「そうね、でも少し、短絡的よ。一時的に記憶を奪うことは、ハーブの知識があれば簡単にできる。だけど人の記憶を完全に消し去るのはとても難しい魔法なの。呪いというべきね。そんなものは仲間に使うべきじゃない」
「一時的なものだったら、ハーブを使えば治る?」
「ええ。ジュニパーベリー、それとほんの少しのベラドンナ……」 ロウィーナはスープをすすりながらすらすらと必要なハーブの種類を挙げていく。サムは記憶しながら、どれも屋敷の薬草庫や温室から拝借できるものだと思って安心した。「……マンドレークの頭をすり鉢にしてそれらを混ぜ合わせ、魔力を溜めた水に浸す。それを飲むのよ。簡単でしょ」
「それは記憶を失わせるほうのレシピじゃない?」 薬草学に長けたターシャが口を出す。ロウィーナはそうだったわと頷いた。「記憶を戻すほうなら、ベラドンナを入れちゃだめだった。だけどそういったハーブの魔法は時間とともに解けるから、ふつうはわざわざ作らないのよ」
「記憶をあれこれする魔法はドルイドが得意だったわね。ロックリン家にも伝わってるはずよ、あの書……」 ターシャは訳ありげな微笑みをロウィーナに向ける。「”黒の魔導書”。あれのせいで多くの魔女が高いプライドを圧し折ることになったわ。まあ、でも、今ではちょっと時代遅れね」
「あいつらの頭は中世で止まっているのよ」 ロウィーナは憎々し気につぶやいて、ツンと顎を上げた。
その夜中、各々が部屋に戻ってそれぞれの研究や遊びに没頭している時間、サムが眠っていることを期待されている時間に、彼はこっそりとベッドを抜け出してキッチンに忍び込んだ。用意したリュックサックにパンと果物を詰め込む。早くディーンのところに戻りたかった。空腹で不安な思いをさせたくないし、新しいランプを灯して暗闇を払ってやりたい。それになにより、彼と話がしたかった。記憶がなくてもかまわない。彼の声を聞いていたい。彼にどうして僕とキスをしたのと尋ねたいし、どうして僕がキスをしたのかを話して聞かせたい。もう一度キスをさせてほしいといったら彼は頷いてくれるだろうか。サムは期待でうずく胸を押さえた。断られないだろうという確信がそのうずきを甘いものにした。
「サム?」 暗がりからロウィーナが現われてサムの心臓は押さえたまま止まりかけた。冷蔵庫のドアを開けてうずくまる養い子をしばし見下ろして、ナイトドレスにローブを羽織った彼女はふと目元をやわらげた。
「眠れないのね。儀式の話をしたから」
「う、うん。そうなんだ。喉が渇いて……」 サムは冷蔵庫のドアを閉めて立ち上がり、足元のリュックを蹴って遠ざけた。暗いから見えないはずだ。
「心配することはないわ。あなたはただそこにいて、”死の書”にサインをすればいいだけ。あとは私たちの長い祝福を聞いていればいいのよ。夜が明けるまでね」
「勉強はたくさんさせられてるけど、夜更かしの授業はなかったな」
「何をいってるの。あなたが毎日遅くまで本を読んでいること、呪文や魔法陣の勉強をしてることは知ってるわ」 ロウィーナはそういってサムを驚かせた。彼女は手を伸ばしてサムの伸びた前髪を撫でつけてやった。
「情熱のある、熱心な生徒を持って光栄だわ。あなたはきっと、偉大な魔法使いになる。私にはわかる。あなたがほんの赤ん坊のころからわかってたわ」
「森で僕を拾った時から?」
んー、とロウィーナは目を細めて考えるふりをした。「やっぱり、あなたが自分の足でトイレまで歩いていけるようになった頃かしらね」
サムは笑って、自分を育てた魔女を見つめた。彼女の背丈を追い越してもうずいぶん経つ。彼女がサムの身体的な成長について何かいったことはなかった。けれど時々、彼女が自分を見上げる目が、誇らしく輝いているように思える瞬間があって、サムはその瞬間をとても愛していた。
「ロウィーナ」
「なあに」
「僕、成人するんだね」
「魔女のね。法律的にはまだ子ども」
「ロウィーナのおかげだ。僕、あなたの子どもであることが誇らしいよ」
ロウィーナの目が輝いた。
「まだまだ独り立ちはさせないわ。もう少し私のしごきに耐えることね」
「覚悟しとくよ」
ロウィーナは冷蔵庫を開けて水のデカンタを取り出した。キッチンを出ていこうとする彼女の柳のような後ろ姿に息を吐いて、踏みつけていたリュックを引き寄せる。何か思い出したようにロウィーナが振り向いて、サムは慌ててまたリュックを後ろ脚で蹴った。
「いくらでも夜更かししていいけど、明日の朝は狩りに行っちゃだめよ。食事の支度は双子に任せるから」
「なんで?」
ロウィーナは肩をすくめた。「ロックリン家のギデオン。彼が死んだのは夕食の時にいったわね。死体が森で見つかったのよ。彼らの領地は森の東側だけど、ハンターはそんなこと気にしないわ」
サムはギクリとした。「ギデオンはウィッチハンターに殺されたの?」
「魔女を殺せるのはウィッチハンターだけよ」
「だけど、そんなのニュースになるだろ」
「正当な捕り物ならハンターは死体を残さないし、カトリーナの様子じゃ何かトラブルを隠してる。だけど巻き込まれるいわれはないわね。しきたりだから、明日の儀式には彼ら――生き残った二人の嫌味なロックリン家――も呼ぶけれどね。森にはハンターがひそんでいるかもしれない。目撃者がない状況でハンターと遭遇したら、やつらがいうところの違法行為がなくても逮捕されるわよ。だから、サミュエル、明日の儀式にみんなで行くまでは、森に入っちゃだめ」
「わ、わかった」
ロウィーナが行ってしまうと、サムは念のために一度部屋に戻って、ベッドサイドのランプを付けた。それから温室に忍び込み、ハンガーに吊るされているマンドレークを一根、それと必要なハーブを掴んでリュックに詰める。温室の裏口からこっそりと抜け出したサムは、二階で休むロウィーナに心の中で詫びながら、パーカーのフードを深くかぶって、まっすぐ森へ向かった。
◇ ◇ ◇
ツイッターにも書いたけど設定だけは壮大。このあと・というかいま書いてるのは三部作のうちの一部でディーンとは別れて終わる。そしてサムは魔女の権利向上のために戦う革命戦士もどきになり、ハンターのディーンとは敵対関係に。。というロミジュリな。でも大ボスはUKの賢人か悪魔かチャックにでもして魔女もハンターも同じ側で戦うんだな。(そのあたりはボヤボヤ)最終的な問題は二人が兄弟だってどうやってばらすか、ばらした時の反応はどうするかだけど、その時にはもうやることやっちゃって覚悟できてるサミさまになってるだろうからきっとなんとかなる。
2 notes
·
View notes
Text
やさしい光の中で(柴君)
(1)ある日の朝、午前8時32分
カーテンの隙間から細々とした光だけがチラチラと差し込む。時折その光は強くなって、ちょうど眠っていた俺の目元を直撃する。ああ朝だ。寝不足なのか脳がまだ重たいが、朝日の眩しさに瞼を無理矢理押し上げる。隣にあったはずの温もりは、いつの間にか冷え切った皺くちゃのシーツのみになっていた。ちらりとサイドテーブルに視線を流せば、いつも通り6時半にセットしたはずの目覚まし時計は、あろうことか針が8と9の間を指していた。
「チッ……勝手に止めやがったな」
独り言のつもりで発した声は、寝起きだということもあり少しだけ掠れていた。それにしても今日はいつもに増して喉が渇いている。眠気眼を擦りながら、キッチンのほうから漂ってくる嗅ぎ慣れた深入りのコーヒーの香りに無意識に喉がこくりと鳴った。
おろしたてのスウェットをまくり上げぼりぼりと腹を掻きながら寝室からリビングに繋がる扉を開けると、眼鏡をかけた君下は既に着替えてキッチンへと立っていた。ジューという音と共に、焼けたハムの香ばしい匂いが漂っている。時折フライパンを揺すりながら、君下は厚切りにされたそれをトングで掴んでひっくり返す。昨日実家から送ってきた荷物の中に、果たしてそんなハムが入っていたのだろうか。どちらにせよ君下が普段買ってくるスーパーのタイムセール品でないことは一目瞭然だった。
「おう、やっと起きたか」 「おはよう。てか目覚ましちゃんと鳴ってた?」 「ああ、あんな朝っぱらからずっと鳴らしやがって……うるせぇから止めた」
やっぱりか、そう呟いた俺の言葉は、君下が卵を割り入れた音にかき消される。二つ目が投入され一段と香ばしい音がすると、塩と胡椒をハンドミルで少し引いてガラス製の蓋を被せると君下の瞳がこっちを見た。
「もうすぐできる。先に座ってコーヒーでも飲んどけ」 「ん」
顎でくい、とダイニングテーブルのほうを指される。チェリーウッドの正方形のテーブルの上には、今朝の新聞とトースト��れた食パンが何枚かと大きめのマグが2つ、ゆらゆらと湯気を立てていた。そのうちのオレンジ色のほうを手に取ると、思ったより熱くて一度テーブルへと置きなおした。丁度今淹れたところなのだろう。厚ぼったい取手を持ち直してゆっくりと口を付けながら、新聞と共に乱雑に置かれていた郵便物をなんとなく手に取った。 封筒の中に混ざって一枚だけ葉書が届いていた。君下敦様、と印刷されたそれは送り主の名前に見覚えがあった。正確には差出人の名前自体にはピンと来なかったが、その横にご丁寧にも但し書きで元聖蹟高校生徒会と書いてあったから、恐らくは君下と同じ特進クラスの人間なのだろうと推測が出来た。
「なんだこれ?同窓、会、のお知らせ……?」
自分宛ての郵便物でもないのに中身を見るのは野暮だと思ったが、久しぶりに見る懐かしい名前に思わず裏を返して文面を読み上げた。続きは声に出さずに視線だけで追っていると、視界の端でコトリ、と白いプレートが置かれる。先程焼いていたハムとサニーサイドアップ、適当に千切られたレタスに半割にされたプチトマトが乗っていた。少しだけ眉間に皺が寄る。
「またプチトマトかよ」 「仕方ねぇだろ。昨日の残りだ。次からは普通のトマトにしてやるよ」
大体トマトもプチトマトも変わんねぇだろうが、そう文句を言いながらエプロンはつけたままで君下は向かいの椅子に腰かけた。服は着替えたものの、長い前髪に寝ぐせがついて少しだけ跳ねあがっている。
「ていうか同じ高校なのになんで俺には葉書来てねぇんだよ」
ドライフラワーの飾られた花瓶の横のカトラリー入れからフォークを取り出し、小さな赤にざくり、と突き立てて口へと放り込む。確かにクラスは違ったかもしれないが、こういう公式の知らせは来るか来ないか呼びたいか呼びたくないかは別として全員に送るのが礼儀であろう。もう一粒口に含み、ぶちぶちとかみ砕けば口の中に広がる甘い汁。プチトマトは皮が固くて中身が少ないから好きではない。やっぱりトマトは大きくてジューシーなほうに限るのだ。
「知らねぇよ……あーあれか。もしかして、実家のほうに来てるんじゃねぇの」 「あ?なんでそっちに行くんだよ」 「まあこんだけ人数いりゃあ、手違いってこともあるだろ」 「ったく……ポンコツじゃねぇかこの幹事」
覚えてもいない元同級生は今頃くしゃみでもしているだろうか。そんなどうでもいいことが頭を過ったが、香ばしく焼き上げられたハムを一口大に切って口に含めばすぐに忘れた。噛むと思ったよりも柔らかく、スモークされているのか口いっぱいに広がる燻製臭はなかなかのものだ。いつも通り卵の焼き加減も完璧だった。
「うまいな、ハム。これ昨日の荷物のか?」 「ああ。中元の残りか知らないけど、すげぇいっぱい送って来てるぞ。明日はソーセージでもいいな」
上等な肉を目の前に、いつもより君下の瞳はキラキラしているような気がした。高校を卒業して10年経ち、あれから俺も君下も随分大人になった。それでも相変わらず口が悪いところや、美味しいものに素直に目を輝かせるところなんて出会った頃と何一つ変わってなどいなかった。俺はそれが微笑ましくもあり、愛おしいとさえ思う。あとで母にお礼のラインでも入れて、ああ、それとついでに同窓会の葉書がそっちに来ていないかも確認しておこう。惜しむように最後の一切れを噛み締めた君下の皿に、俺の残しておいた最後の一切れをくれてやった。
(2)11年前
プロ入りして5年が経とうとしていた。希望のチームからの誘いが来ないまま高校生活を終え、大学を5年で卒業して今のチームへと加入した。 過酷な日々だった。 一世代上の高校の先輩・水樹は、プロ入りした途端にその目覚ましい才能を開花させた。怪物という異名が付き、十傑の一人として注目された高校時代など、まだその伝説のほんの序章の一部に過ぎなかった。同じく十傑の平と共に一年目から名門鹿島で起用されると、実に何年振りかのチームの優勝へと大いに貢献した。日本サッカーの新時代としてマスメディアは大々的にこのニュースを取り上げると、自然と増えた聖蹟高校への偵察や取材の数々。新キャプテンになった俺の精神的負担は増してゆくのが目に見えてわかった。
サッカーを辞めたいと思ったことが1度だけあった。 それは高校最後のインターハイの都大会。前回の選手権の覇者として山の一番上に位置していたはずの俺たちは、都大会決勝で京王河原高校に敗れるという失態を犯した。キャプテンでCFの大柴、司令塔の君下の連携ミスで決定機を何度も逃すと、0-0のままPK戦に突入。不調の君下の代わりに鈴木が蹴るも、向こうのキャプテンである甲斐にゴールを許してゲーム終了、俺たちの最後の夏はあっけなく終わりを迎えた。 試合終了の長いホイッスルがいつまでも耳に残る中、俺はその後どうやって帰宅したのかよく覚えていない。試合を観に来ていた姉の運転で帰ったのは確かだったが、その時他のメンバーたちはどうしたのかだとか、いつから再びボールを蹴ったのかなど、その辺りは曖昧にしか覚えていなかった。ただいつまでも、声を押し殺すようにして啜り泣いている、君下の声が頭から離れなかった。
傷が癒えるのに時間がかかることは、中学選抜で敗北の味を知ったことにより感覚的に理解していた。君下はいつまでも部活に顔を出さなかった。いつもに増してボサボサの頭を掻き乱しながら、監督は渋い声で俺たちにいつものように練習メニューを告げる。君下のいたポジションには、2年の来須が入った。その意味は、直接的に言われなくともその場にいた部員全員が本能的に理解していたであろう。
『失礼します、監督……』
皆が帰ったのを確認して教官室に書き慣れない部誌と共に鍵を返しに向かうと、そこには監督の姿が見えなかった。もう出てしまったのだろうか。一度ドアを閉めて、念のため職員室も覗いて行こうと校舎のほうへと向かう途中、どこからか煙草の香りが鼻を掠める。暗闇の中を見上げれば、ほとんどが消灯している窓の並びに一か所だけ灯りの付いた部屋が見受けられる。半分開けられた窓からは、乱れた黒髪と煙草の細い煙が夜の空へと立ち上っていた。
『お前まだ居たのか……皆は帰ったか?』 『はい、監督探してたらこんな時間に』
部誌を差し出すと悪いな、と一言つけて監督はそれを受け取る。喫煙室の中央に置かれた灰皿は、底が見えないほどの無数の吸い殻が突き刺さり文字通り山となっていた。監督は短くなった煙草を口に咥えると、ゆっくりと吸い込んで零れそうな山の中へと半ば無理やり押し込み火を消した。
『君下は……あいつは辞めたわけじゃねぇだろ』 『お前がそれを俺に聞くのか?』
監督は伏せられた瞳のまま俺に問い返す。パラパラと読んでいるのかわからないほどの速さで部誌をめくり、白紙のページを最後にぱたりと閉じた。俺もその動きを視線で追っていると、クマの濃く残る目をこちらへと向けてきた。お互いに何も言わなかった。 暫くそうしていると、監督は上着のポケットからクタクタになったソフトケースを取り出して、残りの少ないそれを咥えると安物のライターで火をつけた。監督の眼差しで分かったのは、聖蹟は、アイツはまだサッカープレーヤーとして死んではいないということだった。
迎えの車も呼ばずに俺は滅多に行かない最寄り駅までの道のりを歩いていた。券売機で270円の片道切符を購入すると、薄明るいホームで帰路とは反対方向へ向かう電車を待つ列に並ぶ。間もなく電車が滑り込んできて、疲れた顔のサラリーマンの中に紛れ込む。少し混みあっていた車内でつり革を握りしめながら、車内アナウンスが目的の駅名を告げるまで瞼を閉じていた。 あいつに会いに行ってどうするつもりだったのだろう。今になって思えば、あの時は何も考えずに電車に飛び乗ったように思える。ガタンゴトンとレールを走る音を聞きながら、本当はあの場所から逃げ出したかっただけなのかもしれない。疲れた身体を引きずって帰り、あの日から何も変わらない敗北の香りが残る部屋に戻りたくないだけなのかもしれない。一人になりたくないだけなのかもしれない。
『次はー△△、出口は左側です』
目的地を告げるアナウンスで思考が現実へと引き戻された。はっとして、閉まりかけのドアに向かって勢いよく走った。長い脚を伸ばせばガン、と大きな音がしてドアに挟まる。鈍い痛みが走る足を引きずりながら、再び開いたドアの隙間からするりと抜け出した。
久しぶりに通る道のりは、いくつか電灯が消えかけていて薄暗く、不気味なほど人通りが少なかった。古い商店街の一角にあるキミシタスポーツはまだ空いているだろうか。スマホの画面を確認すれば、午後8時55分を指していた。営業時間はあと5分���るが、あの年中暇な店に客は一人もいないであろう。運が悪ければ既にシャッタは降りているかもしれない。
『本日、休業……だあ?』
計算は無意味だった。店のシャッターに張り付けられた、チラシの裏紙には妙に整った字でお詫びの文字が並んでいた。どうやらここ数日間はずっとシャッターが降りたままらしいと、通りすがりの中年の主婦が店の前で息を切らす俺に親切に教えてくれた。ついでにこの先の大型スーパーにもスポーツ用品は売ってるわよ、と要らぬ情報を置いてその主婦は去っていった。こうやって君下の店の売り上げが減っていくという、無駄な情報を仕入れたところで今後使う予定が来るのだろうか。店の二階を見上げるも、君下の部屋に灯りはない。
『ったく、あの野郎は部活サボっといて寝てんのか?』
同じクラスのやつに聞いても、君下のいる特進クラスは夏休み明けから自主登校となっているらしい。大学進学のためのコースは既に3年の1学期には高校3年間の教科書を終えており、あとは各自で予備校に行くなり自習するなりで受験勉強に励んでいるようだ。当然君下以外に強豪運動部に所属している生徒はおらず、クラスでもかなり浮いた存在だというのはなんとなく知っていた。誰もあいつが学校に来なくても、どうせ部活で忙しいぐらいにしか思わないのだ。 仕方ない、引き返すか。そう思い回れ右をしたところで、ある一つの可能性が脳裏に浮かぶ。可能性なんかじゃない。だがなんとなくだが、あいつがそこにいるという確信が、俺の中にあったのだ。
『くそっ……君下のやつ!』
やっと呼吸が整ったところで、重い鞄を背負うと急いで走り出す。こんな時間に何をやっているのだろう、と走りながら我ながら馬鹿らしくなった。去年散々走り込みをしたせいか、練習後の疲れた身体でもまだ走れる。次の角を右へ曲がって、たしかその2つ先を左――頭の中で去年君下と訪れた、あの古びた神社への道のりを思い出す。そこに君下がいる気がした。
『はぁ……はぁっ……っ!』
大きな鳥居が近づくにつれて、どこからか聞こえるボールを蹴る音に俺の勘が間違っていない事を悟った。こんなところでなにサボってんだよ、そう言ってやるつもりだったのに、いざ目の前に君下の姿が見えると言葉を失った。 あいつは、聖蹟のユニフォーム姿のままで、泥だらけになりながら一人でドリブルをしていた。 自分で作った小さいゴールと、所々に置かれた大きな石。何度も躓きながらも起き上がり、懸命にボールを追っては前へ進む。パスを出すわけでもなく、リフティングでもない。その傷だらけの足元にボールが吸い寄せられるように、馴染むように何度も何度も同じことを繰り返していた。
『ハッ……馬鹿じゃねぇの』
お前も俺も。そう呟いた声は己と向き合っている君下に向けられたものではない。 あいつは、君下はもう前を向いて歩きだしていた。沢山の小さな石ころに躓きながら、小さな小さなゴールへと向かってその長い道のりへと一歩を踏み出していた。俺は君下に気付かれることがないように、足音を立てないようにして足早に神社を後にした。 帰りの電車を待つベンチに座って、ぼんやりと思い出すのは泥だらけの君下の背中だった。前を向け喜一、まだやれることはたくさんある。ホームには他に電車を待つ客は誰もいなかった。
(3)夕食、22時半
気付けば完全に日は落ちていて、コートを照らすスタンドライトだけが暗闇にぼんやりと輝いていた。 思いのほか練習に熱中してしまったようで、辺りを見渡せば先輩選手らはとっくに自主練を切り上げて帰路に着いたようだった。何の挨拶もなしに帰宅してしまったチームメイトの残していったボールがコートの隅に落ちているのを見つけては、上がり切った息を整えながらゆったりと歩いて拾って回った。
倉庫の鍵がかかったのを確認して誰もいないロッカールームへ戻ると、ご丁寧に電気は消されていた。先週は鍵がかけられていた。思い出すだけで腹が立つが、もうこんなことも何度目になった今ではチームに内緒で作った合鍵をいつも持ち歩くようにしている。ぱちり、スイッチを押せば一瞬遅れて青白い灯りが部屋を照らした。
大柴は人に妬まれ易い。その容姿と才能も関係はあるが、自分の才能に胡坐をかいて他者を見下しているところがあった。大口を叩くのはいつものことで、慣れた友人やチームメイトであれば軽く受け流せるものの、それ以外の人間にとってみれば不快極まりない行為であることは間違いない。いつしか友人と呼べる存在は随分と減り、クラスや集団では浮いてしまうことが常であった。 今のチームも例外ではない。加入してすぐの公式戦にレギュラーでの起用、シーズン序盤での怪我による離脱、長期のリハビリ生活、そして残せなかった結果。大柴加入初年度のチームは、最終的に前年度よりも下回った順位でシーズンの幕を閉じることになった。それでも翌年からも大柴はトップに居座り続けた。疑問に思ったチームメイトやサポーターからの非難や、時には心無い中傷を書き込まれることもあった。ゴールを決めれば大喝采だが、それも長くは続かない。家が裕福なことを嗅ぎつけたマスコミにはある事ない事を週刊誌に書き並べられ、誰もいない実家の前に怪しげな車が何台も止まっていることもあった。 だがそんなことは、大柴にとって些細なことだった。俺はサッカーの神様に才能を与えられたのだと、未だにカメラの前でこう言い張ることにしている。実はもう一つ、大柴はサッカーの神様から貰った大切なものがあったが、それを口にしたことはないしこれからも公言する日はやって来ないだろう。
「ただいまぁー」 「お帰り、遅かったな」
靴を脱いでつま先で並べると、靴箱の上の小さな木製の皿に車のキーを入れる。ココナッツの木から作られたそれは、卒業旅行に二人でハワイに行ったときに買ったもので、6年間大切に使い続けている。玄関までふわりと香る味噌の匂いに、ああやっとここへ帰ってきたのだと実感する。大股で歩きながらジャケットを脱ぎ、どさり、とスポーツバッグと共に床へ投げ出すと、倒れ込むように革張りのソファへとダイブした。
「おい、飯出来てるから先に食え。手洗ったか?」 「洗ってねぇ」 「ったく、何年も言ってんのにちっとも学習しねぇ奴だな。ほら、こっち来い」
君下は洗い物をしていたのか、泡まみれのスポンジを握ってそれをこちらに見せてくる。この俺の手を食器用洗剤で洗えって言うのか、そう言えばこっちのほうが油が落ちるだとか、訳の分からない理論を並べられた。つまり俺は頑固汚れと同じなのか。
「こんなことで俺が消えてたまるかよ」 「いつもに増して意味わかんねぇな。よし、終わり。味噌汁冷める前にさっさと食え」
お互いの手を絡めるようにして洗い流していると、背後でピーと電子音がして炊飯が終わったことを知らせる。俺が愛車に乗り込む頃に一通連絡を入れておくと、丁度いい時間に米が炊き上がるらしい。渋滞のときはどうするんだよ、と聞けば、こんな時間じゃそうそう混まねぇよ、と普段車に乗らないくせにまるで交通事情を知っているかのような答えが返ってくる。全体練習は8時頃に終わるから、自主練をして遅くても10時半には自宅に着けるように心掛けていた。君下は普通の会社員で、俺とは違い朝が早いのだ。
「いただきます」 「いただきます」
向かい合わせの定位置に腰を下ろし、二人そろって手を合わせる。日中はそれぞれ別に食事を摂るも、夕食のこの時間を二人は何よりも大事にしていた。 熱々の味噌汁は俺の好みに合わせてある。最近は急に冷え込んできたから、もくもくと上る白い湯気は一段と白く濃く見えた。上品な白味噌に、具は駅前の豆腐屋の絹ごし豆腐と、わかめといりこだった。出汁を取ったついでにそのまま入れっぱなしにするのは君下家の味だと昔言っていた。
「喜一、ケータイ光ってる」 「ん」
苦い腸を噛み締めていると、ソファの上に置かれたままのスマホが小さく震えている音がした。途切れ途切れに振動がするので、電話ではないことは確かだった。後ででいい、一度はそう言ったものの、来週の練習試合の日程がまだだったことを思い出して気だるげに重い腰を上げる。最新機種の大きな画面には、見覚えのある一枚の画像と共に母からの短い返信があった。
「あ、やっぱ葉書来てたわ。実家のほうだったか」 「ほらな」 「お前のはここの住所で、なんで俺のだけ実家なんだよ」 「知るかよ。どうせ行くんだろ、直接会った時に聞けばいいじゃねぇか」 「え、行くの?」
スマホを持ったままどかり、と椅子へと座りなおし、飲みかけの味噌汁に手を伸ばす。ズズ、とわざと少し行儀悪くわかめを啜れば、君下の表情が曇るのがわかった。
「お前、この頃にはもうオフだから休みとれるだろ。俺も有休消化しろって上がうるせぇから、ちょうどこのあたりで連休取ろうと思ってる」 「聞いてねぇ……」 「今言ったからな」
金平蓮根に箸を付けた君下は、いくらか摘まんで自分の茶碗へと一度置くと、米と共にぱくり、と頬張った。シャクシャクと音を鳴らしながら、ダ��クブラウンの瞳がこちらを見る。
「佐藤と鈴木も来るって」 「あいつらに会うだけなら別で集まりゃいいだろうが。それにこの前も4人で飲んだじゃねぇか」 「いつの話してんだよタワケが、2年前だぞあれ」 「えっそんなに前だったか?」 「ああ。それに今年で卒業して10年だとさ。流石に毎年は行かねぇが節目ぐらい行ったって罰は当たんねーよ」
時の流れとは残酷なものだ。俺は高校を卒業してそれぞれ違う道へと進んでも、相変わらず君下と一緒にいた。だからそんな長い年月が経ったことに気付かなかっただけなのかもしれない。高校を卒業する時点で、俺たちがはじめて出会って既に10年が経っていたのだ。 君下はぬるい味噌汁を啜ると、満足そうに「うまい」と一言呟いた。
*
今宵はよく月が陰る。 ソファにごろりと寝転がり、カーテンの隙間から満月より少し欠けた月をぼんやりと眺めていた。月に兎がいると最初に言ったのは誰だろうか。どう見ても、あの不思議な斑模様は兎なんかに、それも都合よく餅つきをしているようには見えなかった。昔の人間は妙なことを考える。星屑を繋げてそれらを星座だと呼び、一晩中夜空を眺めては絶え間なく動く星たちを追いかけていた。よほど暇だったのだろう。こんな一時間に何センチほどしか動かないものを見て、何が面白いというのだろうか。
「さみぃ」
音もなくベランダの窓が開き、身体を縮こませた君下が湯気で温かくなった室内へと戻ってくる。君下は二十歳から煙草を吸っていた。家で吸うときはこうやって、それも洗濯物のない時にだけ、それなりに広いベランダの隅に作った小さな喫煙スペースで煙草を嗜む。別に換気扇さえ回してくれれば部屋で吸ってもらっても構わないと俺は言っているのだが、頑なにそれをしようとしないのは君下のほうだった。現役のスポーツ選手である俺への気遣いなのだろう。こういう些細なところでも、俺は君下に支えられているのだと実感する。
「おい、キスしろ」
隣に腰を下ろした君下に、腹を見せるように上を向いて唇を突き出した。またか、と言いたげな顔をしたが、間もなく長い前髪が近づいてきてちゅ、と小さな音を立てて口づけが落とされた。一度も吸ったことのない煙草の味を、俺は間接的に知っている。少しだけ大人になったような気がするのがたまらなく心地よい。
それから少しの間、手を握ったりしてテレビを見ながらソファで寛いだ。この時間にもなればいつもニュースか深夜のバラエティー番組しかなかったが、今日はお互いに見たい番組があるわけでもなかったので適当にチャンネルを回してテレビを消した。 手元のランプシェードの明かりだけ残して電気を消し、寝室の真ん中に位置するキングサイズのベッドに入ると、君下はおやすみとも言わないまま背を向けて肩まで掛け布団を被ってしまった。向かい合わせでは寝付けないのはいつもの事だが、それにしても今日は随分と素っ気ない。明日は金曜日で、俺はオフだが会社員の君下には仕事がある。お互いにもういい歳をした大人なのだ。明日に仕事を控えた夜は事には及ばないようにはしているが、先ほどのことが胸のどこかで引っかかっていた。
「もう寝た?」 「……」 「なあ」 「……」 「敦」 「……なんだよ」
消え入りそうなほど小さな声で、君下が返事をする。俺は頬杖をついていた腕を崩して布団の中に忍ばせると、背中からその細身の身体を抱き寄せた。抵抗はしなかった。
「こっち向けよ」 「……もう寝る」 「少しだけ」 「明日仕事」 「分かってる」
わかってねぇよ、そう言いながらもこちらに身体を預けてくる、相変わらず素直じゃないところも君下らしい。ランプシェードのオレンジの灯りが、眠そうな君下の顔をぼんやりと照らしている。長い睫毛に落ちる影を見つめながら、俺は薄く開かれた唇に祈るように静かにキスを落とした。
こいつとキスをするようになったのはいつからだっただろうか。 サッカーを諦めかけていた俺に道を示してくれたその時から、ただのチームメイトだった男は信頼できる友へと変化した。それでも物足りないと感じていたのは互いに同じだったようで、俺たちは高校を卒業するとすぐに同じ屋根の下で生活を始めた。が、喧嘩の絶えない日々が続いた。いくら昔に比べて関係が良くなったとはいえ、育ちも違えば本来の性格が随分と違う。事情を知る数少ない人間も、だからやめておけと言っただろう、と皆口を揃えてそう言った。幸いだったのは、二人の通う大学が違ったことだった。君下は官僚になるために法学部で勉学に励み、俺はサッカーの為だけに学生生活を捧げた。互いに必要以上に干渉しない日々が続いて、家で顔を合わせるのは、いつも決まって遅めの夜の食卓だった。 本当は今のままの関係で十分に満足している。今こそ目指す道は違うが、俺たちには同じ時を共有していた、かけがえのない長い長い日々がある。手さぐりでお互いを知ろうとし、時にはぶつかり合って忌み嫌っていた時期もある。こうして積み重ねてきた日々の中で、いつの日か俺たちは自然と寄り添いあって、お互いを抱きしめながら眠りにつくようになった。この感情に名前があるとしても、今はまだわからない。少なくとも今の俺にとって君下がいない生活などもう考えられなくなっていた。
「……ン゛、ぐっ……」
俺に組み敷かれた君下は、弓なりに反った細い腰をぴくり、と跳ねさせた。大判の白いカバーの付いた枕を抱きしめながら、押し殺す声はぐぐもっていてる。決して色気のある行為ではないが、その声にすら俺の下半身は反応してしまう。いつからこうなってしまったのだろう。君下を抱きながらそう考えるのももう何度目の事で、いつも答えの出ないまま、絶頂を迎えそうになり思考はどこかへと吹き飛んでしまう。
「も、俺、でそ、うっ……」 「あ?んな、俺もだ馬鹿っ」 「あっ……喜一」
君下の腰から右手を外し、枕を上から掴んで引き剥がす。果たしてどんな顔をして俺の名を呼ぶのだと、その顔を拝みたくなった。日に焼けない白い頬は、スポーツのような激しいセックスで紅潮し、額にはうっすらと汗が浮かんでいる。相変わらず眉間には皺が寄ってはいたが、いつもの鋭い目つきが嘘のように、限界まで与えられた快楽にその瞳を潤ませていた。視線が合えば、きゅ、と一瞬君下の蕾が収縮した。「あ、出る」とだけ言って腰のピストンを速めながら、君下のイイところを突き上げる。呼吸の詰まる音と、結合部から聞こえる卑猥な音を聞きながら、頭の中が真っ白になって、そして俺はいつの間にか果てた。全て吐き出し、コンドームの中で自身が小さくなるのを感じる。一瞬遅れてどくどくと音がしそうなほどに爆ぜる君下の姿を、射精後のぼんやりとした意識の中でいつまでも眺めていた。
(4)誰も知らない
忙しないいつもの日常が続き、あっという間に年も暮れ新しい年がやってきた。 正月は母方の田舎で過ごすと言った君下は、仕事納めが終われば一度家に戻って荷物をまとめると、そこから一週間ほど家を空けていた。久しぶりに会った君下は、少しばかり頬が丸くなって帰ってきたような気がしたが、本人に言うとそんなことはないと若干キレながら否定された。目に見えて肥えたことを気にしているらしい本人には申し訳ないが、俺はその様子に少しだけ安心感を覚えた。祖父の葬儀以来、もう何年も顔を見せていないという家族に会うのは、きっと俺にすら言い知れぬ緊張や、不安も勿論あっただろう。 だがこうやって随分と可愛がられて帰ってきたようで、俺も正月ぐらい実家に顔を出せばよかったかなと少しだけ羨ましくなった。本人に言えば餅つきを手伝わされこき使われただの、田舎はやることがなく退屈だなど愚痴を垂れそうだが、そのお陰なのか山ほど餅を持たせられたらしく、その日の夜は冷蔵庫にあった鶏肉と大根、にんじんを適当に入れて雑煮にして食べることにした。
「お前、俺がいない間何してた?」
君下が慣れた手つきで具材を切っている間、俺は君下が持ち帰った土産とやらの箱を開けていた。中には土の付いたままの里芋だとか、葉つきの蕪や蓮根などが入っていた。全て君下の田舎で採れたものなのか、形はスーパーでは見かけないような不格好なものばかりだった。
「車ねぇから暇だった」 「どうせ車があったとしても、一日中寝てるか練習かのどっちかだろうが」 「まあ、大体合ってる」
一通り切り終えたのか包丁の音が聞こえなくなり、程なくして今度は出汁の香りが漂ってきた。同時に香ばしい餅の焼ける香りがして、完成が近いことを悟った俺は一度箱を閉めるとダイニングテーブルへと向かい、箸を二膳出して並べると冷蔵庫から缶ビールを取り出してグラスと共に並べた。
「いただきます」 「いただきます」
大きめの深い器に入った薄茶色の雑煮を目の前に、二人向かい合って座り手を合わせる。実に一週間ぶりの二人で摂る夕食だった。よくある関東風の味付けに、四角く切られ表面を香ばしく焼かれた大きな餅。シンプルだが今年に入って初めて食べる正月らしい食べ物も、今年初めて飲む酒も、すべて君下と共に大事に味わった。
「あ、そうだ。明日だからな、あれ」
3個目の餅に齧りついた俺に、そういえばと思い出したかのように君下が声を発した。少し冷めてきたのか噛み切れなかった餅を咥えたまま、肩眉を上げて何の話かと視線だけで問えば、「ほら、同窓会のやつ」と察したように答えが返ってきた。「ちょっと待て」と掌を君下に見せて、餅を掴んでいた箸に力を入れて無理矢理引きちぎると、ぐにぐにと大���把に噛んでビールで流し込む。うまく流れなかったようで、喉のあたりを引っかかる感触が気持ち悪い。生理的に込み上げてくる涙を瞳に浮かべていると、席を立った君下は冷蔵庫の扉を開けてもう2本ビールを取り出して戻ってきた。
「ほら飲め」 「おま……水だろそこは」 「いいからとりあえず流し込め」
空になった俺のグラスにビールを注げば、ぶくぶくと泡立つばかりで泡だけで溢れそうになった。だから水にしとけと言ったのだ。チッ、と舌打ちをした君下は、少し申し訳なさそうに残りの缶をそのまま手渡してきた。直接飲むのは好きではないが、今は文句を言ってられない。奪うように取り上げると、ごくごくと大げさに喉を鳴らして一気に飲み干した。
「は~……死ぬかと思った。相変わらずお酌が下手だなお前は」 「うるせぇな。俺はもうされる側だから仕方ねぇだろうが」
そう悪態をつきながら、君下も自分の缶を開ける。プシュ、と間抜けな音がして、グラスを傾けて丁寧にビールを注いでゆく。泡まで綺麗に注げたそれを見て、満足そうに俺に視線を戻す。
「あ、そうだよ、話反らせやがって……まあとにかく、明日は俺は昼ぐらいに会社に少し顔出してくるから、ついでに親父んとこにも寄って、そのまま会場に向かうつもりだ」 「あ?親父さんも一緒に田舎に行ったんじゃねぇの?」 「そうしようとは思ったんだがな、店の事もあるって断られた。ったく誰に似たんだかな」 「それ、お前が言うなよ」
君下の言葉になんだかおかしくなってふふ、と小さく笑えば、うるせぇと小さく舌打ちで返された。綺麗に食べ終えた器をテーブルの上で纏めると、君下はそれらを持って流しへと向かった。ビールのグラスを軽く水で濯いでから、そこに半分ぐらい溜めた水をコクコクと喉を鳴らして飲み込んだ。
「俺もう寝るから、あとよろしくな。久々に運転すると疲れるわ」 「おう、お疲れ。おやすみ」
俺の言葉におやすみ、と小さく呟いた君下は、灯りのついていない寝室へと吸い込まれるようにして消えた。ぱたん、と扉が閉まる音を最後に、乾いた部屋はしんとした静寂に包まれる。手元に残ったのは、ほんの一口分だけ残った温くなったビールの入ったグラスだけだった。 頼まれた洗い物はあとでやるとして、さてこれからどうしようか。君下の読み通り、今日は一日中寝ていたため眠気はしばらくやって来る気配はない。テレビの上の時計を見ると、ちょうど午後九時を回ったところだった。俺はビールの残りも飲まずに立ち上がると、食器棚に並べてあるブランデーの瓶と、隣に飾ってあったバカラのグラスを手にしてソファのほうへとゆっくり歩き出した。
*
肌寒さを感じて目を覚ました。 最後に時計を見たのはいつだっただろうか。微睡む意識の中、薄く開いた瞳で捉えたのは、ガラス張りのローテーブルの端に置かれた見覚えのあるグラスだった。細かくカットされた見事なつくりの表面は、カーテンから零れる朝日を反射してキラキラと眩しい。中の酒は幾分か残っていたようだったが、蒸発してしまったのだろうか、底のほうにだけ琥珀色が貼り付くように残っているだけだった。 何も着ていなかったはずだが、俺の肩には薄手の毛布が掛かっていた。点けっぱなしだった電気もいつの間にか消されていて、薄暗い部屋の中、遮光カーテンから漏れる光だけがぼんやりと座っていたソファのあたりを照らしていた。酷い喉の渇きに、水を一口飲もうと立ち上がると頭痛と共に眩暈がした。ズキズキと痛む頭を押さえながらキッチンへ向かい、食器棚から新しいコップを取り出して水を飲む。シンクに山積みになっていたはずの洗い物は、跡形もなく姿を消している。君下は既に家を出た後のようだった。
それから昼過ぎまでもう一度寝て、起きた頃には朝方よりも随分と温かくなっていた。身体のだるさは取れたが、相変わらず痛む頭痛に舌打ちをしながら、リビングのフローリングの上にマットを敷いてそこで軽めのストレッチをした。大柴はもう若くはない。三十路手前の身体は年々言うことを聞かなくなり、1日休めば取り戻すのに3日はかかる。オフシーズンだからと言って単純に休んでいるわけにはいかなかった。 しばらく柔軟をしたあと、マットを片付け軽く掃除機をかけていると、ジャージの尻ポケットが震えていることに気が付いた。佐藤からの着信だった。久しぶりに見るその名前に、緑のボタンを押してスマホを耳と肩の間に挟んだ。
「おう」 「あーうるせぇよ!掃除機?電話に出る時ぐらい一旦切れって」
叫ぶ佐藤の声が聞こえるが、何と言っているのか聞き取れず、仕方なくスイッチをオフにした。ちらりと壁に視線を流せば、時計針はもうすぐ3時を指そうとしていた。
「わりぃ。それよりどうした?」 「どうしたじゃねぇよ。多分お前まだ寝てるだろうから、起こして同窓会に連れてこいって君下から頼まれてんだ」 「はあ……ったく、どいつもこいつも」 「まあその調子じゃ大丈夫だな。5時にマンションの下まで車出すから、ちゃんと顔洗って待ってろよ」 「へー」 「じゃあ後でな」
何も言わずに通話を切り、ソファ目掛けてスマホを投げた。もう一度掃除機の電源を入れると、リビングから寝室へと移動する。普段は掃除機は君下がかけるし、皿洗い以外の大抵の家事はほとんど君下に任せっきりだった。今朝はそれすらも君下にさせてしまった罪悪感が、こうやって自主的にコードレス掃除機をかけている理由なのかもしれない。 ベッドは綺麗に整えてあり、真ん中に乱雑に畳まれたパジャマだけが取り残されていた。寝る以外に立ち入らない寝室は綺麗なままだったが、一応端から一通りかけると掃除機を寝かせてベッドの下へと滑り込ませる。薄型のそれは狭い隙間も難なく通る。何往復かしていると、急に何か大きな紙のようなものを吸い込んだ音がした。
「げっ……何���?」
慌てて電源を切り引き抜くと、ヘッドに吸い込まれていたのは長い紐のついた、見慣れない小さな紙袋だった。紺色の袋の表面に、金色の細い英字で書かれた名前には見覚えがあった。俺の覚え違いでなければ、それはジュエリーブランドの名前だった気がする。
「俺のじゃねぇってことは、これ……」
そこまで口に出して、俺の頭の中には一つの仮説が浮かび上がる。これの持ち主は十中八九君下なのだろう。それにしても、どうしてこんなものがベッドの下に、それも奥のほうへと押しやられているのだろうか。絡まった紐を引き抜いて埃を払うと、中を覗き込む。入っていたのは紙袋の底のサイズよりも一回り小さな白い箱だった。中を確認したかったが、綺麗に巻かれたリボンをうまく外し、元に戻せるほど器用ではない。それに、中身など見なくてもおおよその見当はついた。 俺はどうするか迷ったが、それと電源の切れた掃除機を持ってリビングへと戻った。紙袋をわざと見えるところ、チェリーウッドのダイニングテーブルの上に置くと、シャワーを浴びようとバスルームへと向かった。いつも通りに手短に済ませると、タオルドライである程度水気を取り除いた髪にワックスを馴染ませ、久しぶりに鏡の中の自分と向かい合う。ここ2週間はオフだったというのに、ひどく疲れた顔をしていた。適当に整えて、顎と口周りにシェービングクリームを塗ると伸ばしっぱなしだった髭に剃刀を宛がう。元々体毛は濃いほうではない。すぐに済ませて電気を消して、バスルームを後にした。
「お、来た来た。やっぱりお前は青のユニフォームより、そっちのほうが似合っているな」
スーツに着替え午後5時5分前に部屋を出て、マンションのエントランスを潜ると、シルバーの普通車に乗った佐藤が窓を開けてこちらに向かって手を振っていた。助手席には既に鈴木が乗っており、懐かしい顔ぶれに少しだけ安堵した。よう、と短く挨拶をして、後部座席のドアを開けると長い背を折りたたんでシートへと腰かけた。 それからは佐藤の運転に揺られながら、他愛もない話をした。最近のそれぞれの仕事がどうだとか、鈴木に彼女が出来ただとか、この前相庭のいるチームと試合しただとか、離れていた2年間を埋めるように絶え間なく話題は切り替わる。その間も車は東京方面へと向かっていた。
「君下とはどうだ?」 「あー……相変わらずだな。付かず離れずって感じか」 「まあよくやってるよな、お前も君下も。あれだけ仲が悪かったのが、今じゃ同棲だろ?みんな嘘みたいに思うだろうな」 「同棲って言い方やめろよ」 「はーいいなぁ、俺この間の彼女に振られてさ。せがまれて高い指輪まで贈ったのに、あれだけでも返して貰いたいぐらいだな」
指輪という言葉に、俺の顔の筋肉が引きつるのを感じた。グレーのパンツの右ポケットの膨らみを、無意識に指先でなぞる。車は渋滞に引っかかったようで、先ほどからしばらく進んでおらず車内はしん、と静まり返っていた。
「あーやべぇな。受付って何時だっけ」 「たしか6時半……いや、6時になってる」 「げ、あと20分で着くかな」 「だからさっき迂回しろって言ったじゃねぇか」
このあたりはトラックの通行量も多いが、帰宅ラッシュで神奈川方面に抜ける車もたくさん見かける。そういえば実家に寄るからと、今朝も俺の車で出て行った君下はもう会場に着いたのだろうか。誰かに電話をかけているらしい鈴木の声がして、俺は手持ち無沙汰に窓の外へと視線を投げる。冬の日の入りは早く、太陽はちょうど半分ぐらいを地平線の向こうへと隠した頃だった。真っ赤に焼ける雲の少ない空をぼんやりと眺めて、今夜は星がきれいだろうか、と普段気にもしていないことを考えていた。
(5)真冬のエスケープ
車は止まりながらもなんとか会場近くの地下駐車場へと止めることができた。幹事と連絡がついて遅れると伝えていたこともあり、特に急ぐことも��く会場までの道のりを歩いて行った。 程なくして着いたのは某有名ホテルだった。入り口の案内板には聖蹟高校×期同窓会とあり、その横に4階と書かれていた。エレベーターを待つ間、着飾った同じ年ぐらいの集団と鉢合わせた。そのうち男の何人かは見覚えのある顔だったが、男たちと親し気に話している女に至っては、全くと言っていいほど面影が見受けられない。常日頃から思ってはいたが、化粧とは恐ろしいものだ。俺や君下よりも交友関係が広い鈴木と佐藤でさえ苦笑いで顔を見合わせていたから、きっとこいつらにでさえ覚えがないのだろうと踏んで、何も言わずに到着した広いエレベーターへと乗り込んだ。
受付で順番に名前を書いて入り口で泡の入った飲み物を受け取り、広間へと入るとざっと見るだけで100人ほどは来ているようだった。「すげぇな、結構集まったんだな」そう言う佐藤の言葉に振り返りもせずに、俺はあたりをきょろきょろと見渡して君下の姿を探した。
「よう、遅かったな」 「おー君下。途中で渋滞に巻き込まれてな……ちゃんと連れてきたぞ」
ぽん、と背中を佐藤に叩かれる。その右手は決して強くはなかったが、ふいを突かれた俺は少しだけ前にふらついた。手元のグラスの中で黄金色がゆらりと揺れる。いつの間にか頭痛はなくなっていたが、今は酒を口にする気にはなれずにそのグラスを佐藤へと押し付けた。不審そうにその様子を見ていた君下は、何も言わなかった。 6時半きっかりに、壇上に幹事が現れた。眼鏡をかけて、いかにも真面目そうな元生徒会長は簡単にスピーチを述べると、今はもう引退してしまったという、元校長の挨拶へと移り変わる。何度か表彰状を渡されたことがあったが、曲がった背中にはあまり思い出すものもなかった。俺はシャンパンの代わりに貰ったウーロン茶が入ったグラスをちびちびと舐めながら、隣に立つ君下に気付かれないようにポケットの膨らみの形を確認するかのように、何度も繰り返しなぞっていた。
俺たちを受け持っていた先生らの挨拶が一通り済むと、それぞれが自由に飲み物を持って会話を楽しんでいた。今日一日、何も食べていなかった俺は、同じく飯を食い損ねたという君下と共に、真ん中に並ぶビュッフェをつまみながら空きっ腹を満たしていた。ここのホテルの料理は美味しいと評判で、他のホテルに比べてビュッフェは高いがその分確かなクオリティがあると姉が言っていた気がする。確かにそれなりの料理が出てくるし、味も悪くはない。君下はローストビーフがお気に召したようで、何度も列に並んではブロックから切り分けられる様子を目を輝かせて眺めていた。
「あー!大柴くん久しぶり、覚えてるかなぁ」
ウーロン茶のあてにスモークサーモンの乗ったフィンガーフードを摘まんでいると、この会場には珍しく化粧っ気のない、大きな瞳をした女が数人の女子グループと共にこちらへと寄ってきた。
「あ?……あ、お前はあれだ、柄本の」 「もー、橘ですぅー!つくちゃんのことは覚えててくれるのに、同じクラスだった私のこと、全っ然覚えててくれないんだから」
プンスカと頬を膨らませる橘の姿に、高校時代の懐かしい記憶が蘇る。記憶の中よりも随分と短くなった髪は耳の下で切り揃えられていれ、片側にトレードマークだった三つ編みを揺らしている。確かにこいつが言うように、思い返せば偶然にも3年間、同じクラスだったように思えてくる。本当は名前を忘れた訳ではなかったが、わざと覚えていない振りをした。
「テレビでいつも見てるよー!プロってやっぱり大変みたいだけど、大柴くんのことちゃんと見てるファンもいるからね」 「おーありがとな」
俺はその言葉に対して素直に礼を言った。というのも、この橘という女の前ではどうも調子が狂わされる。自分は純粋無垢だという瞳をしておいて、妙に人を観察していることと、核心をついてくるのが昔から巧かった。だが悪気はないのが分かっているだけ質が悪い。俺ができるだけ同窓会を避けてきた理由の一つに、この女の言ったことと、こいつ自身が関係している。これには君下も薄々気付いているのだろう。
「あ、そうだ。君下くんも来てるかな?つくちゃんが会いたいって言ってたよ」 「柄本が?そりゃあ本人に言ってやれよ。君下ならあっちで肉食ってると思うけど」 「そうだよね、ありがとう大統領!」
そう言って大げさに手を振りながら、橘は君下を探しに人の列へと歩き出した。「もーまたさゆり、勝手にどっか行っちゃったよ」と、取り残されたグループの一人がそう言うので、「相変わらずだよね」と笑う他の女たちに混ざって愛想笑いをして、居心地の悪くなったその場を離れようとした。 白いテーブルクロスの上から飲みかけのウーロン茶が入ったグラスを手に取ろとすると、綺麗に塗られたオレンジの爪がついた女にそのグラスを先に掴まれた。思わず視線をウーロン茶からその女へと流すと、女はにこりと綺麗に笑顔を作り、俺のグラスを手渡してきた。
「大柴くん、だよね?今日は飲まないの?」
黒髪のロングヘアーはいかにも君下が好みそうなタイプの女で、耳下まである長い前髪をセンターで分けて綺麗に内巻きに巻いていた。他の女とは違い、あまりヒラヒラとした装飾物のない、膝上までのシンプルな紺色のドレスに身を包んでいる。見覚えのある色に一瞬喉が詰まるも、「今日は車で来てるから」とその場で適当な言い訳をした。
「あーそうなんだ、残念。私も車で来たんだけど、勤めている会社がこの辺にあって、そこの駐車場に停めてあるから飲んじゃおうかなって」 「へぇ……」
わざとらしく綺麗な眉を寄せる姿に、最初はナンパされているのかと思った。だが俺のグラスを受け取ると、オレンジの爪はあっさりと手放してしまう。そして先程まで女が飲んでいた赤ワインらしき飲み物をテーブルの上に置き、一歩近づき俺の胸元に手を添えると、背伸びをして俺の耳元で溜息のように囁いた。
「君下くんと、いつから仲良くなったの?」
酒を帯びた吐息息が耳元にかかり、かっちりと着込んだスーツの下に、ぞわりと鳥肌が立つのを感じた。 こいつは、この女は、もしかしたら君下がこの箱を渡そうとした女なのかもしれない。俺の知らないところで、君下はこの女と親密な関係を持っているのかもしれない。そう考えが纏まると、すとんと俺の中に収まった。そうか。最近感じていた違和感も、何年も寄り付かなかった田舎への急な帰省も、なぜか頑なにこの同窓会に出席したがった理由も、全部辻褄が合う。いつから関係を持っていたのだろうか、知りたくもなかった最悪の状況にたった今、俺は気付いてしまった。 じりじりと距離を詰める女を前に、俺は思考だけでなく身体までもが硬直し、その場を動けないでいた。酒は一滴も口にしていないはずなのに、むかむかと吐き気が込み上げてくる。俺は今、よほど酷い顔をしているのだろう。心配そうに見つめる女の目は笑っているのに、口元の赤が、赤い口紅が視界に焼き付いて離れない。何か言わねば。いつものように、「誰があんなやつと、この俺様が仲良くできるんだよ」と見下すように悪態をつかねば。皆の記憶に生きている、大柴喜一という人間を演じなければ―――…… そう思っているときだった。 俺は誰かに腕を掴まれ、ぐい、と強い力で後ろへと引かれた。呆気にとられたのは俺も女も同じようで、俺が「おい誰だ!スーツが皺になるだろうが」と叫ぶと、「あっ君下くん、」と先程聞いていた声より一オクターブぐらい高い声が女の口から飛び出した。その名前に腕を引かれたほうへと振り返れば、確かにそこには君下が立っていて、スーツごと俺の腕を掴んでいる。俺を見上げる漆黒の瞳は、ここ最近では見ることのなかった苛立ちが滲んで見えるようだった。
「ああ?テメェのスーツなんか知るかボケ。お前が誰とイチャつこうが関係ねぇが、ここがどこか考えてからモノ言いやがれタワケが」 「はあ?誰がこんなブスとイチャつくかバーカ!テメェの女にくれてやる興味なんぞこれっぽっちもねぇ」 「なんだとこの馬鹿が」
実に数年ぶりの君下のキレ具合に、俺も負けじと抱えていたものを吐き出すかのように怒鳴り散らした。殴りかかろうと俺の胸倉を掴んだ君下に、賑やかだった周囲は一瞬にして静まり返る。人の壁の向こう側で、「おいお前ら!まじでやめとけって」と慌てた様子の佐藤の声が聞こえる。先に俺たちを見つけた鈴木が君下の腕を掴むと、俺の胸倉からその手を引き剥がした。
「とりあえず、やるなら外に行け。お前らももう高校生じゃないんだ、ちょっとは周りの事も考えろよ」 「チッ……」 「大柴も、冷静になれよ。二人とも、今日はもう帰れ。俺たちが収集つけとくから」
君下はそれ以上何も言わずに、��口のほうへと振り返えると大股で逃げるようにその場を後にした。俺は「悪いな」とだけ声をかけると、曲がったネクタイを直し、小走りで君下の後を追いかける。背後からカツカツとヒールの走る音がしたが、俺は振り返らずにただ小さくなってゆく背中を見逃さないように、その姿だけを追って走った。暫くすると、耳障りな足音はもう聞こえなくなっていた。
君下がやってきたのは、俺たちが停めたのと同じ地下駐車場だった。ここに着くまでにとっくに追い付いていたものの、俺はこれから冷静に対応する為に、頭を冷やす時間が欲しかった。遠くに見える派手な赤色のスポーツカーは、間違いなく俺が2年前に買い替えたものだった。君下は何杯か酒を飲んでいたので、鍵は持っていなくとも俺が運転をすることになると分かっていた。わざと10メートル後ろをついてゆっくりと近づく。 君下は何も言わずにロックを解除すると、大人しく助手席に腰かけた。ドアは開けたままにネクタイを解き、首元のボタンを一つ外すと、胸ポケットから取り出した煙草を一本口に咥えた。
「俺の前じゃ吸わねぇんじゃなかったのか」 「……気が変わった」
俺も運転席に乗り込むと、キーを挿してエンジンをかけ、サンバイザーを提げるとレバーを引いて屋根を開けてやった。どうせ吸うならこのほうがいいだろう。それに今夜は星がきれいに見えるかもしれないと、行きがけに見た綺麗な夕日を思い出す。安物のライターがジジ、と音を立てて煙草に火をつけたのを確認して、俺はゆっくりとアクセルを踏み込んだ。
(6)形も何もないけれど
煌びやかなネオンが流れてゆく。俺と君下の間に会話はなく、代わりに冬の冷たい夜風だけが二人の間を切るように走り抜ける。煙草の火はとっくに消えて、そのままどこかに吹き飛ばされてしまった。 信号待ちで車が止まると、「さむい」と鼻を啜りながら君下が呟いた。俺は後部座席を振り返り、外したばかりの屋根を元に戻すべく折りたたんだそれを引っ張った。途中で信号が青に変わって、後続車にクラクションを鳴らされる。仕方なく座りなおそうとすると、「おい、貸せ」と君下が言うものだから、最初から自分でやればいいだろうと思いながらも、大人しく手渡してアクセルに足を掛けた。車はまた走り出す。
「ちょっとどこか行こうぜ」
最初にそう切り出したのは君下だった。暖房も入れて温かくなった車内で、窓に貼り付くように外を見る君下の息が白く曇っていた。その問いかけに返事はしなかったが、俺も最初からあのマンションに向かうつもりはなかった。分岐は横浜方面へと向かっている。君下もそれに気が付いているだろう。 海沿いに車を走らせている間も、相変わらず沈黙が続いた。試しにラジオを付けてはみたが、流れるのは今流行りの恋愛ソングばかりで、今の俺たちにはとてもじゃないが似合わなかった。何も言わずにラジオを消して、それ以来ずっと無音のままだ。それでも、不思議と嫌な沈黙ではないことは確かだった。
どこまで行こうというのだろうか。気が付けば街灯の数も少なくなり、車の通行量も一気に減った。窓の外に見える、深い色の海を横目に見ながら車を走らせた。穏やかな波にきらきらと反射する、今夜の月は見事な満月だった。 歩けそうな砂浜が見えて、何も聞かないままそこの近くの駐車場に車を停めた。他に車は数台止まっていたが、どこにも人の気配がしなかった。こんな真冬の夜の海に用があるというほうが可笑しいのだ。俺はエンジンを切って、運転席のドアを開けると外へ出た。つんとした冷たい空気と潮の匂いが鼻をついた。君下もそれに続いて車を降りた。 後部座席に積んでいたブランケットを羽織りながら、君下は小走りで俺に追いつくと、その隣に並んで「やっぱ寒い」と鼻を啜る。数段ほどのコンクリートの階段を降りると、革靴のまま砂を踏んだ。ぐにゃり、と不安定な砂の上は歩きにくかったが、それでも裸足になるわけにはいかずにゆっくりと海へ向かって歩き出す。波打ち際まで来れば、濡れて固まった足場は先程より多少歩きやすくなった。はぁ、と息を吐けば白く曇る。海はどこまでも深い色をしていた。
「悪かったな」 「いや、……あれは俺も悪かった」
居心地の悪そうに謝罪の言葉がぽつり、と零れた。それは何に対して謝ったのか、自分でもよく分からない。君下に女が居た事なのか、指輪を見つけてしまった事なのか、それともそれを秘密にしていた事なのか。あるいは、そのすべてに対して―――俺がお前をあのマンションに縛り付けた10年間を指しているのか、それははっきりとは分からなかった。俺は立ち止まった。俺を追い越した、君下も立ち止まり、振り返る。大きな波が押し寄せて、スーツの裾が濡れる感覚がした。水温よりも冷たく冷え切った心には、今はそんな些細なことは、どうでもよかった。
「全部話してくれるか」 「ああ……もうそろそろ気づかれるかもしれねぇとは腹括ってたからな」
そう言い終える前に、君下の視線が俺のズボンのポケットに向いていることに気が付いた。何度も触っていたそれの形は、嫌と言うほど覚えている。俺はふん、と鼻で笑ってから、右手を突っ込み白い小さな箱を丁寧に取り出した。君下の目の前に差し出すと、なぜだか手が震えていた。寒さからなのか、それともその箱の重みを知ってしまったからなのか、風邪が吹いて揺れるなか、吹き飛ばされないように握っているのが精一杯だった。
「これ……今朝偶然見つけた。ベッドの下、本当に偶然掃除機に引っかけちまって……でも本当に俺、今までずっと気付かなくて、それで―――それで、あんな女がお前に居たなんて、もっと早く言ってくれりゃ、」 「ちょっと待て、喜一……お前何言ってんだ」 「あ……?何って、今言ったことそのまんまだろうが」
思い切り眉間に皺を寄せ困惑したような君下の顔に、俺もつられて眉根を寄せる。ここまで来てしらを切るつもりなのかと思うと、怒りを通り越して呆れもした。どうせこうなってしまった以上、俺たちは何事もなく別れられるわけがなかった。昔のように犬猿の仲に戻るのは目に見えていたし、そうなってくれれば救われた方だと俺は思っていた。 苛立っていたいたのは君下もそうだったようで、風で乱れた頭をガシガシと掻くと、煙草を咥えて火を点けようとした。ヂ、ヂヂ、と音がするのに、風のせいでうまく点かない。俺は箱を持っていないもう片方の手を伸ばして、風上から添えると炎はゆらりと立ち上がる。すう、と一息吸って吐き出した紫煙が、漆黒の空へと消えていった。
「そのまんまも何も、あの女、お前狙いで寄ってきたんだろうが」 「お前の女が?」 「誰だよそれ、名前も知らねぇのにか?」
つまらなさそうに、君下はもう一度煙を吸うと上を向いて吐き出した。どうやら本当にあのオレンジ爪の女の名前すら知らないらしい。だとしたら、俺が持っているこの箱は一体誰からのものなのだ。答え合わせのつもりで話をしていたが、謎は余計に深まる一方だ。
「あ、でもあいつ、俺に何て言ったと思う?君下くんといつから仲良くなったの、って」 「お前の追っかけファンじゃねぇの」 「だとしてもスゲェ怖いわ。明らかにお前の好みそうなタイプの恰好してたじゃん」 「そうか?むしろ俺は、お前好みの女だなと思ったけどな」
そこまで言って、俺も君下も噴き出してしまった。ククク、と腹の底から込み上げる笑いが止まらない。口にして初めて気が付いたが、俺たちはお互いに女の好みなんてこれっぽっちも知らなかったのだ。二人でいる時の共通の話題と言えば、サッカーの事か明日の朝飯のことぐらいで、食卓に女の名前が出てきたことなんて今の一度もない事に気付いてしまった。どうりでこの10年間、どちらも結婚だとか彼女だとか言い出さないわけだ。俺たちはどこまでも似た者同士だったのだ。
「それ、お前にやろうと思って用意したんだ」
すっかり苛立ちのなくなった瞳に涙を浮かべながら、君下は軽々しくそう言って笑った。 俺は言葉が出なかった。 こんな小洒落たものを君下が買っている姿なんて想像もできなかったし、こんなリボンのついた箱は俺が受け取っても似合わない。「中は?」と聞くと、「開けてみれば」とだけ返されて、煙が流れないように君下は後ろを向いてしまった。少し迷ったが、その場で紐をほどいて箱を開けて、俺は目を見開いた。紙袋と同じ、夜空のようなプリントの内装に、星のように輝くゴールドの指輪がふたつ、中央に行儀よく並んでいた。思わず君下の後姿に視線を戻す。ちらり、とこちらを振り返る君下の口元は、笑っているように見えた。胸の内から込み上げてくる感情を抑えきれずに、俺は箱を大事に畳むと勢いよくその背中を抱きしめた。
「う゛っ苦しい……喜一、死ぬ……」 「そのまま死んじまえ」 「俺が死んだら困るだろうが」 「自惚れんな。お前こそ俺がいないと寂しいだろう」 「勝手に言ってろタワケが」
腕の中で君下の頭が振り返る。至近距離で視線が絡み、君下の瞳に星空を見た。俺は吸い込まれるようにして、冷たくなった君下の唇にゆっくりとキスを落とす。二人の間で吐息だけが温かい。乾いた唇は音もなく離れ、もう一度角度を変えて近づけば、今度はちゅ、と音がして君下の唇が薄く開かれた。お互いに舌を出して煙草で苦くなった唾液を分け合った。息があがり苦しくなって、それでもまた酸素を奪うかのように互いの唇を気が済むまで食らい合った。右手の箱は握りしめたままで、中で指輪がふたつカタカタと小さく音を立てて揺れていた。
「もう、帰ろうか」 「ああ……解っちゃいたが、冬の海は寒すぎるな。帰ったら風呂炊くか」 「お、いいな。俺が先だ」 「タワケが。俺が張るんだから俺が先だ」
いつの間にか膝下まで濡れたスーツを捲り上げ、二人は手を繋いで来た道を歩き出した。青白い砂浜に、二人分の足跡が残る道を辿って歩いた。平常心を取り戻した俺は急に寒さを感じて、君下が羽織っているブランケットの中に潜り込もうとした。君下はそれを「やめろ馬鹿」と言って俺の頭を押さえつける。俺も負けじとグリグリと頭を押し付けてやった。自然と笑いが零れる。 これでよかったのだ。俺たちには言葉こそないが、それを埋めるだけの共に過ごした長い時間がある。たとえ二人が結ばれたとしても、形に残るものなんて何もない。それでも俺はいいと思っている。こうして隣に立ってくれているだけでいい。嬉しい時も寂しい時も「お前は馬鹿だな」と一緒に笑ってくれるやつが一人だけいれば、それでいいのだ。
「あ、星。喜一、星がすげぇ見える」 「おー綺麗だな」
ふと気づいたように、君下が空を見上げて興奮気味に声を上げた。 ようやくブランケットに潜り込んで、君下の隣から顔を出せば、そこにはバケツをひっくり返したかのように無数に散らばる星たちが瞬いていた。肩にかかる黒髪から嗅ぎ慣れない潮の香りがして、俺たちがいま海にいるのだと思い知らされる。上を向いて開いた口から、白く曇った息が漏れる。何も言わずにしばらくそれを眺めて、俺たちはすっかり冷えてしまった車内へと腰を下ろした。温度計は摂氏5度を示していた。
7:やさしい光の中で
星が良く見えた翌朝は決まって快晴になる。君下に言えば、そんな原始的な観測が正しければ、天気予報なんていらねぇよ、と文句を言われそうだが、俺はあながち間違いではないと思っている。現に今日は雲一つない晴れで、あれだけ低かった気温が今日は16度まで上がっていた。乾燥した空気に洗濯物も午前中のうちに乾いてしまった。君下がベランダに料理を運んでいる最中、俺は慣れない手つきで洗濯物をできるだけ綺麗に折りたたんでいた。
「おい、終わったぞ。お前のは全部チェストでいいのか?」 「下着と靴下だけ二番目の引き出しに入れといてくれ。あとはどこでもいい」 「へい」
あれから真っすぐマンションへと向かった車は、時速50キロ程度を保ちながらおよそ2時間かけて都内にたどり着いた。疲れ切っていたのか、君下は何度かこくり、こくりと首を落とし、ついにはそのまま眠りに落ちてしまった。俺は片手だけでハンドルを握りながら、できるだけ眠りを妨げないように、信号待ちで止まることのないようにゆっくりとしたスピードで車を走らせた。車内には、聞き慣れない名のミュージシャンが話すラジオの音だけが延々と聞こえていた。 眠った君下を抱えたままエントランスをくぐり、すぐに開いたエレベーターに乗って部屋のドアを開けるまで、他の住人の誰にも出会うことはなかった。鍵を開けて玄関で靴を脱がせ、濡れたパンツと上着だけを剥ぎ取ってベッドに横たわらせる。俺もこのまま寝てしまおうか。ハンガーに上着を掛けると一度はベッドに腰かけたものの���どうも眠れる気がしない。少しだけ君下の寝顔を眺めた後、俺はバスルームの電気を点けた。
「飲み物はワインでいいか?」 「おう。白がいい」 「言われなくとも白しか用意してねぇよ」
そう言って君下は冷蔵庫から冷えた白ワインのボトルとグラスを2つ持ってやって来た。日当たりのいいテラスからは、東京の高いビル群が遠くに見えた。東向きの物件にこだわって良かったと、当時日当たりなんてどうでもいいと言った君下の隣に腰かけて密かに思う。今日は風も少なく、テラスで日光浴をするのには丁度いい気候だった。
「乾杯」 「ん」
かちん、と一方的にグラスを傾けて君下のグラスに当てて音を鳴らした。黄金色の液体を揺らしながら、口元に寄せればリンゴのような甘い香りがほのかい漂う。僅かにとろみのある液体を口に含めば、心地よいほのかな酸味と上品な舌触りに思わず眉が上がるのが分かった。
「これ、どこの」 「フランスだったかな。会社の先輩からの貰い物だけど、かなりのワイン好きの人で現地で箱買いしてきたらしいぞ」 「へぇ、美味いな」
流れるような書体でコンドリューと書かれたそのボトルを手に取り、裏面を見ればインポーターのラベルもなかった。聞いたことのある名前に、確か希少価値の高い品種だったように思う。読めない文字をざっと流し読みし、ボトルをテーブルに戻すともう一口口に含む。安物の白ワインだったら炭酸で割って飲もうかと思っていたが、これはこのまま飲んだ方が良さそうだ。詰め物をされたオリーブのピンチョスを摘まみながら、雲一つない空へと視線を投げた。
「そう言えば、鈴木からメール来てたぞ……昨日の同窓会の話」
紫煙を吐き出した君下は、思い出したかのように鈴木の名を口にした。小一時間前に風呂に入ったばかりの髪はまだ濡れているようで、時折風が吹いてはぴたり、と額に貼り付いた。それを手で避けながら、テーブルの上のスマホを操作して件のメールを探しているようだ。俺は残り物の鱈と君下の田舎から貰ってきたジャガイモで作ったブランダードを、薄切りのバゲットに塗り付けて齧ると、「何だって」と先程の言葉の続きを促した。
「あの後女が泣いてるのを佐藤が慰めて、そのまま付き合うことになったらしい、ってさ」 「はあ?それって俺たちと全然関係なくねぇ?というか、一体何だったんだよあの女は……」
昨夜のことを思い出すだけで鳥肌が立つ。あの真っ赤なリップが脳裏に焼き付いて離れない。それに、俺たちが聞きたかったのはそんな話ではない。喧嘩を起こしそうになったあの場がどうなったとか、そんなことよりもどうでもいい話を先に報告してきた鈴木にも悪意を感じる。多分、いや確実に、このハプニングを鈴木は面白がっているのだろう。
「あいつ、お前と同じクラスだった冴木って女だそうだ。佐藤が聞いた話だと、やっぱりお前のファンだったらしいぞ」 「……全っ然覚えてねぇ」 「だろうな。見ろよこの写真、これじゃあ詐欺も同然だな」
そう言って見せられた一枚の写真を見て、俺は食べかけのグリッシーニに巻き付けた、パルマの生ハムを落としそうになった。写真は卒アルを撮ったもののようで、少しピントがずれていたがなんとなく顔は確認できた。冴木綾乃……字面を見てもピンと来なかったが、そこに映っているふっくらとした丸顔に腫れぼったい一重瞼の女には見覚えがあった。
「うわ……そういやいた気がするな」 「それで?これのどこが俺の女だって言うんだよ」 「し、失礼しました……」 「そりゃあ今の彼氏の佐藤に失礼だろうが。それに別にブスではないしな」
いや、どこからどう見てもこれはない。俺としてはそう思ったが、確かに昨日会った女は素直に抱けると思った。人は歳を重ねると変わるらしい。俺も君下も何か変わったのだろか。ふとそう思ったが、まだ青い高校生だった俺に言わせれば、俺たちが同じ屋根の下で10年も暮らしているということがほとんど奇跡に近いだろう。人の事はそう簡単に悪く言えないと、自分の体験を以って痛いほど知った。 君下は短くなった煙草を灰皿に押し付けると火を消して、何も巻かないままのグリッシーニをポリポリと齧り始める。俺は空になったグラスを置くと、コルクを抜いて黄金色を注いだ。
「あー、そうだ。この間田舎に帰っただろう、正月に。その時にばあちゃんに、お前の話をした」 「……なんか言ってたか」
聞き捨てならない言葉に、だらしなく木製の折りたたみチェアに座っていた俺の背筋が少しだけ伸びる。 その事は俺にも違和感があった。急に田舎に顔出してくるから、と俺の車を借りて出て行った君下は、戻ってきても1週間の日々を「退屈だった」としか言わなかったのだ。なぜこのタイミングなのだろうか。嫌な切り出し方に少しだけ緊張感が走る。君下がグリッシーニを食べ終えるのを待っているほんの少しの時間が、俺には気が遠くなるほど長い時間が経ったような気さえした。
「別に。敦は結婚はしないのかって聞かれたから答えただけだ。ただ同じ家に住んでいて、これからも一緒にいることになるだろうから、申し訳ないけど嫁は貰わないかもしれないって言っといた」 「……それで、おばあさんは何て」 「良く分からねぇこと言ってたぜ。まあ俺がそれで幸せなら、それでいいんじゃないかとは言ってくれたけど……やっぱ少し寂しそうではあったかな」
そう言って遠くの空を見つめるように、君下は視線を空へ投げた。真冬とは言え太陽の光は眩しくて、自然と目元は細まった。テーブルの上に投げ出された右手には、光を反射してきらきらと輝く金色が嵌められている。昨夜君下が眠った後、停車中の誰も見ていない車内で俺が勝手に付けたのだ。細い指にシンプルなデザインはよく映えた。俺が見ていることに気が付いたのか、君下はそっとテーブルから手を離すと、新しいソフトケースから煙草を一本取りだした。
「まあこれで良かったのかもな。親父にも会ってきたし、俺はもう縛られるものがなくなった」 「えっ、まさか……昨日実家寄ったのってその為なのか」 「まあな……本当は早いうちに言っておくべきだったんだが、どうも切り出せなくてな。親父もばあちゃんも、母さんを亡くして寂しい思いをしたのは痛いほど分かってたし、まあ俺もそうだったしな……それで俺が結婚しないって言うのは、なんだか家族を裏切ってしまうような気がして。もう随分前にこうなることは分かってたのにな。気づいたら年だけ重ねてて、それで……」
君下は、ゆっくりと言葉を紡ぐと一筋だけ涙を流した。俺はそれを、君下の左手を握りしめて、黙って聞いてやることしかできなかった。昼間から飲む飲みなれないワインにアルコールが回っていたのだろうか。それでもこれは君下の本音だった。 暫くそうして無言で手を握っていると、ジャンボジェット機が俺たちの上空をゆっくりと通過した。耳を塞ぎたくなるようなごうごうと風を切り裂く大きな音に隠れるように、俺は聞こえるか聞こえないかの声量で「愛してる」、と一言呟く。君下は口元だけを読んだのか、「俺も」、と聞こえない声で囁いた。飛行機の陰になって和らいだ光の中で、俺たちは最初で最後の言葉を口にした。影が過ぎ去ると、陽射しは先程よりも一層強く感じられた。水が入ったグラスの中で、溶けた氷がカラン、と立てたか細い音だけが耳に残った。
1 note
·
View note
Text
ed. from the everworld
バルナバーシュは夢を見ていた。かれは夜の海のせせらぐ柔らかな砂浜にうつぶせており、身を起こすと、あたりを見わたし、ここがたしかに故国ゲルダット――その十の都市のひとつ、拝火の街ジルヴァの西に続く、〈竜域の海〉に臨む〈月と海の浜〉であることが、妙にさえざえとした頭ですばやく把握できた。
身に着けている衣服は、寄せ手の隠密として囚われていたジルヴァの大聖堂から逃げのびてきた時のままで、厚手のくたびれた濡羽色の外套のほかは、皮製の防具を最低限に取り合わせた軽装のみだった。かれは大聖堂の地下で、ジルヴァの現在の監督者であるカレルから手酷い拷問を受けていたが、セニサの手引きのおかげで脱走できたのだった。そして無力と絶望のなか、ほうほうのていでこの海岸までたどりついた。かつて愛しあったセニサと逍遥し、口づけを交わしたこの場所に。
(あれから、私は……)
無意識に内隠しへのばされた手が懐中時計をつかみ、取りだして、細やかな意匠のほどこされた金の上蓋を開いた。特殊な動力源が発する永久的なエネルギーを得ながら、針は白磁色の文字盤のなかで規則正しく時を刻んでいる。時計は何も語らない――そのことに得体の知れない喪失感が身裡を這いあがり、バルナバーシュは立ちくらみのような激しい眩暈に襲われた。この時計に、大切ななにかがあったはずだ。思い出そうとしても頭のなかに深い霧がかかり、身もだえしかできない己れがひどくやるせない。
離れたところに、肩掛けの荷が砂にまみれて転がっているのが見えた。手がかりをもとめて開くと、魔術の助けとなる秘薬やわずかな食糧が散乱するなかで、まったく覚えのない、未知の材質からなる金属塊が異様な存在感を放っていた。
手に取ると、それは機械仕掛けで動く右腕のようで、強い力によって――おそらく斧のような武器で斬り飛ばしたあとが断面にみてとれた。バルナバーシュは知らず息をのみ、あえぎつつ額をおさえた。頭蓋の最奥がどくどくと痛み、これは絶対に手放してはならないのだと甲高く警鐘を発している。由来など分からなかったが、霊次元に通ずる魔術師であるかれは、この感覚の訴えをひとまず信じることにした。荷を背負い、砂をはらって立ち上がると、切り立った崖の上に暗鬱とそびえるジルヴァの中心街を見あげた。街中から上がる無数の火の手が大聖堂の尖塔の数々を燃え立たせるように照らし、戦さがすでに佳境にあるのを伝えている。バルナバーシュは戦慄した。
「セニサ……!」
ジルヴァの本丸であるはずの大聖堂をさして、砂に足をとられつつもバルナバーシュは駆けだした。すでに崩れかけ、あまたの窓から火を噴く街路につづく西門からは入らず、自分が来た道――セニサの案内でそこから逃がされた、大聖堂の内部につながる隠し通路へと引きかえす。
通路は大聖堂の真下――ジルヴァの街のはるか崖下にあり、海に流れ出ている数ある水路のひとつだった。バルナバーシュは躊躇なく暗く湿ってよどむ水路を突きすすみ、横道に入って腐食しかけた扉を蹴りやぶり、崖の内部に掘られた石造りの長い螺旋階段をとばしとばし駆けのぼった。不思議と疲労はつのらず、胸にある懐中時計が一秒を刻むごとに活力を与えてくれるような潜在力のみなぎりを覚え、勢いはむしろいや増すかにも感じられた。
最後の段を踏みこえ、石壁に似せた重い扉を押し開くと、大聖堂のい���は使われていない、木箱やがらくたの積み置かれた暗い小部屋のひとつに出た。セニサに地下牢から導かれ、そして別れた場所だった。逃走のとき、振りむいて最後に見たセニサは、彼女の行動を不審に感じたカレルの配下に見とがめられ、いずこかへ連れていかれるところだった。自分が逃げおおせたことはすんでのところで知られていないはずだが、彼女が心を読む魔術を会得したカレルの尋問を受ければ終わりだ。今度こそ、裏切り者としての末路――ひと思いには殺されず、いまわしい禁術の数々によって生きながら魂の業苦を受け、永遠に死によって解き放たれることのない悲運がセニサにもたらされてしまう。急がねばならない。
バルナバーシュは耳をすまして部屋の外をうかがった。くぐもってはいるが、廊下からは無数の戛然たる剣戟や、入りみだれる突喊と悲鳴、調度品が燃え落ち、破壊される音、壁が崩れる轟音が混沌と聞こえてくる。大聖堂は攻め入られており、なにを相手に戦っているのかはすぐに分かった。〈オールドクロウ〉の家門の軍勢だ。バルナバーシュ家は〈オールドクロウ〉の遠い傍系であり、代々が住む屋敷も、かれらの管轄である橋梁の街、ウィルミギリアにある。屋敷とそこに住む二人の使用人の安全を保障されるかわりに、おそらくは最後の当主となるセインオラン=エルザ・バルナバーシュは、命を受けてジルヴァの街に隠密として潜入していた。その任はまっとうできなかったが、〈オールドクロウ〉は長い歴史において何事にも中立をつらぬきつつも、唯一、時の浅からぬ同盟と不即不離の友誼が息づいていた拝火の街ジルヴァがカレルの支配によって穢れ、暗黒に落とされたことを知ると、義を果たすためついに出兵を決めたのだった。
バルナバーシュは、〈オールドクロウ〉の優勢を確信して廊下に飛び出したが、目の前で繰り広げられているのは酸鼻をきわめた地獄の有りさまだった。廊下や中庭では、多足の巨大な鰐や、複数のあぎとが張りつく不定形の黒い生物、無数の顔と槍をかいこむ腕がたえず浮かびあがる赤黒い肉塊などのおぞましい魔物の群れがひしめいて、〈オールドクロウ〉の戦士や魔術師らともみ合いになり、頭から次々と喰らってはかみ砕き、肉や骨がつぶされる聞くに堪えない音と理性あるものたちの断末魔を響かせていた。禁術を用いて召喚されたに違いないが、この大群のためにどれだけの生贄の血肉と魂、そして理解を絶する儀式が必要とされたのかは想像すらもしたくなかった。また、その多くが静寂を愛するジルヴァの罪なき住民たちであろうことも。
「バルナバーシュ!」
声がしたほうを振りむくと、〈オールドクロウ〉の家門の次男である豊かな黒髭をたくわえた男――名をハヴェルという――が、甲冑を鳴らしながら駆け寄ってくるところだった。直接、バルナバーシュに諜報を下知したのもこの者である。かれは優れた魔法剣士であり、右手には金の魔法的装飾が美々しいルーンソードが握られていたが、薄青く光る刃や刻まれたルーンにはいましも浴びた熱い鮮血がしたたっていた。
「おぬしが捕らえられたと聞いて、もう死んでいるものと思っていたぞ。我らはカレルの配下や、その後ろ盾である〈不言の騎士〉の増援と戦っていたのだが、きゃつら突然、苦しみだしたかと思えば、体がふくれ、あのような魔物に成り下がってしまったわ。いまさらだが世も末よ……我々は禁術などに手は出さんが、ゆえに成すすべも残されていないだろう。国は終わりだ�� 「かもしれんな。魔術に善悪などなく――暴走するヒトの心こそが悪となり怪物となって、かような禁術をも生んでしまう。だが国が終わろうとも、私たちはまだ生きている。そして、あなたがた〈オールドクロウ〉は最後の砦なんだ。いまこそ、かつてゲルダットを興した十賢者のなかでも最高とうたわれた智者の血を継ぐ者たちとして、生きようとする人々の灯火となってくれ。頼む」 「忘れられては困るが、バルナバーシュ家もその血の継承者だ。どれほど遠かろうともな。して、おぬしはどうする。我らは撤退しつつあるが、ここで戦うのか?」 「やらねばならないことがある。セニサがまだ生きている」
そのとき、言葉を交わすふたりに一体の鰐の魔物が、のたうち、床に折り重なった死体を踏み荒らしながら突進してきた。二人は左右にさけてやり過ごし、バルナバーシュは腰に差した剣を抜き放つと、足をとめた鰐の背へ、尾からとぶように駆けあがって太い首根に刃を突き込んだ。自分が持ちえないはずの高い判断力や身体能力とともに、バルナバーシュはそこではじめて、手に持つ武器がただのありふれた剣ではなく、魔銀から鍛えられた業物であるのを知り、銀の薄刃は大気を鋭く切り裂けるほどに軽く、切っ先は鰐の異次元の物質からなるいびつな鱗を乳酪かなにかのようにたやすく貫いた。血管のように精密に、かつ生物的に張りめぐらした魔術回路によって、魔力を通わせつつ驚くほど自分の手に馴染むものだったが、これをいつ手に入れたのかが思い出せず、混乱したわずかな隙にバルナバーシュは暴れる鰐の背から振りおとされてしまった。うめきつつハヴェルに助け起こされ、ルーンソードを構えた彼に脇へと押しやられた。
「さっさと行け。そしてセニサ殿を助けてこい」
バルナバーシュは指揮官たるハヴェルにその場を任せると、ヒトと魔物が殺戮に熱狂する阿鼻叫喚の渦中を駆け、死体と血だまりの海を泳ぎ抜けるようにして石の回廊を突き進んだ。中庭から望む空では赤く脈打ちながら膨張した月が、うごめく紅炎を幾筋も発しながら天頂にとどまり、いまこの地が現世と異界をつなぐ巨大な門と化している証左をまざまざとあらわしている。バルナバーシュは大聖堂内部の道すじを正確に把握していた。若かりしころに魔術と学問の研鑽に励み、学友のセニサと青春を謳歌した愛すべき地ゆえに。大聖堂は本堂である大伽藍の周辺をさまざまな施設が囲い、入り組んでおり、有事には砦としても機能する。バルナバーシュは本堂をさして向かっていた。
やがて地獄を抜け、ヒトも魔物の姿もなくなって、聞こえるのは自分の息づかいだけとなりつつあった。本堂へ続く廊下はしんと静かで奇妙に気配もなかったが、その理由を考えているひまなどなく、ひたすら走り、ついに百フィートを超える高さの天井をもつ大伽藍にたどりついた。翼廊には建国の祖である十賢者を描いたステンドグラスがそびえ、背後には巨大な薔薇窓が輝いていたが、赤い月の投げかける光がすべてを血のごとき真紅に染めあげていた。連なる長椅子の濃い影のなかからいくつもの闇がわきあがり、人の形をなして這い出ると身をひきつらせながらバルナバーシュに殺到したが、かれは果敢に銀剣を鞘走らせ、敵の喉元を突き、首を宙にとばし、また振るわれた闇色の刃をはっしと受け止めつつ防御を切りくずしてその囲いを破っていった。
「セニサ!」
最奥に設えた石造りの祭壇には、求めていた女性が灰色の長衣を着せられた姿でぐったりと横たえられ、その前にはカレルが――顔の右半分を残して肉体のほとんどが溶け崩れ、ふくれあがり、繊維のように無数の触手や肉の細いすじがねじれながら波打つ異形となりはてた男が立っていた。かれはバルナバーシュの姿をみとめたが、かまわずに、くぐもった笑いをもらしながらセニサを取りこもうと腕だったもの――青と緑の宝石におおわれた触手の一本をのばしてゆく。カレルは理性をとどめながらも肉体そのものが異次元の一部と同化し、門の役目となって、彼女を混沌のただなかへと連れ去ろうとしているのだ。バルナバーシュは絶叫しながら、銀剣とともに大伽藍の祭壇へ駆けていく。近づくにつれ、カレルは肉体のあらゆる節々と裂け目から、この世のものではない光炎を噴き出し、みだりがましくも激しい様々な色相をまたたかせ、ゆがみ、ひしめき、抑制のきかぬ痴れきった力の波動を放ってバルナバーシュを押しかえそうとした。黄緑の熔岩があふれて泡だち、強烈に移りゆく奔流のなかで怪鳥めいた哄笑をあげ、己れを神だと驕った者の末路を見せつけながらも、カレルはいまもって禁術を自在にあやつり、セニサを、そしてジルヴァの街をも呑みこむべく異界の領域を拡げる古代の呪文を低くつぶやきはじめた――カレル、そして禁術に手を染めたものらが永遠と信じたかたち、完全だと思い描いた世界を手に入れるために。
バルナバーシュが永続的に放たれる波動に銀剣の切っ先を差しむけると、霊圧を切り裂くことができたが、それでも前進は困難なものだった。だが、セニサに魔手が巻きつき、門となったカレルのなかへ引き込まれつつあるのを目にしたとき、胸元から青白い光が差し、突如として白熱した! すさまじい力が流れ込んできて、横溢するバルナバーシュの肉体と精神は耐えきれず咆哮し、まばゆい魔力の青い光を剣から放ちながら床を蹴った。一足飛びに祭壇に躍りかかり、艶美な石に守られた触手を目にもとまらぬ剣速で断ち、宙高くへ斬り飛ばした。そして驚愕するカレルの、心臓と思しき肉塊のひだのなかへ銀剣を突き入れる。そのまま両手で柄を握りこみ、触手や肉のすじを引き裂きながら斬り上げてカレルの頭部を中心から両断した。カレルは自らの重みに潰れるようにして崩れ落ちたが、いまだ繋がったままの異次元のロジックに生かされているのか、身の毛もよだつ異形の悲鳴をあげながらのたうっていた。バルナバーシュはその姿に同情こそすれ、悪心や嫌悪を覚えることはなかった。
「すまない、カレル……」
まだ目を閉じて眠るセニサに息があり、異常がないのを確かめると、バルナバーシュは彼女を抱きあげて急ぎ大伽藍を脱した。もはや制御のきかなくなったカレルの肉体からは、異次元の際限なきゆがみ――現次元には抑えきれぬ未知のロジック――があふれ続けており、その先触れにさらされたあらゆる物体は変質し、カレルと同じようにねじれてのたうち、でたらめに様々な生命が生まれ、数分ともたず息絶えて腐り、甘い熱を発するおびただしい死骸の海をなしていった。そうしてゆがめられたジルヴァの大聖堂が、灯台たる尖塔が、灰色の静寂の街と、そのかけがえのない歴史のシンボル――目に見えぬ象徴的な存在――が、儚いまぼろしだったかのように崩壊していく。跡形もなく。ふたたび隠し通路を抜けて、〈月と海の浜〉まで避難したバルナバーシュは、セニサを砂浜に横たえながら、火勢の増したジルヴァの街が巨大な葬送のなかで燃えて灰に帰していくのを茫然と眺めていた。愛おしく、懐かしきものへの憧憬のように。
ゲルダットという国は遠からず終わりを告げるだろう。十の都市のうち、八つはいまだ禁術に酔いしれ、一つはいま眼前で灰となり、残された一つだけが小さな光の欠片――希望の寄る辺だった。〈オールドクロウ〉の家門が治める、ゲルダット最西端の都市、ウィルミギリアなる土地だ。西方の多民族国家、ハンターレクとの交易が盛んで外交政治に長けた都市だが、このままゲルダットが異界の力にあふれた魔境と化せば、ハンターレクへと吸収されていくのかもしれない。それでも、ウィルミギリアには様々な可能性が残されている。バルナバーシュ家の屋敷も無事に守られていることだろう。
馬も船もない。街道は野盗が目を光らせているので危険だ。セニサを背負ってウィルミギリアへ向かうためにも、いまは休まねばならなかった。あるいは目覚めるまで待つのがいいのだろうが、あの葬送の光景を彼女が見てしまったら、という不安がバルナバーシュの心中でまさっており、可能なかぎりジルヴァからは離れておきたかった。ジルヴァの街を治めつづけた家門〈灰の乙女〉の直系たるセニサもまた、街へとってかえし、ともに灰になろうとするのではないかと、その彼女を果たして私に止められるのだろうかと、バルナバーシュはひとり苦悶しつづけた。あらゆる秘密と呪いが海底に眠るとうたわれる〈月と海の浜〉の、寄せては返す波の音楽的な音を聴きながら。異界とのつながりが断たれた月は、もとの真珠のごときゆたかな色あわいを取りもどし、ひとつの終わりと始まりの解放を穏やかに静観していた。
白地のカーテンが初夏のそよ風に揺れ、なにものかの訪れと錯覚した意識が机でまどろんでいた頭をもたげさせたが、目を巡らせた狭い書斎には自分以外の者はだれもいなかった。心地のよい昼下がりだった。絨毯のない板張りの床も、乳白色のやわらかな左官壁も、また棚や調度品も簡素な一室だったが、父の代から長年仕えてくれた使用人が亡くなるとともに離れたウィルミギリアの屋敷よりも風通しはよい。あのあらまほしき思い出の残る家から去るのは心を焦がすばかりだった。だが、もうひとりの――みずからとさして歳の変わらぬ女性使用人がいとまを得ると、そこにささやかに住まい、いまは屋敷とともに思い出を守ってくれている。それは彼女自身の願いや意思だったが、やるべきことを終えたあかつきには、家族を連れていつでも帰ってきてよいのだとも言ってくれた。
扉が���とほとと叩かれ、ひとりの女性が部屋をおとずれた。長い銀灰の髪を編んで束ね、薄手の白いチュニックと藍色のスカートを爽やかにまとったセニサだった。あの美しかった灰色の長衣の姿は、ジルヴァの街が失われた日から一度も目にしていない。思い出してしまうのだろうかと思うと心苦しかった。
セニサは薬草茶の器を載せた盆を机におくと、そこに広げられている図面をしばらく一心に見つめていた。
「これが、あなたの描く未来なのね」
私の肩に手を置きながら、ものやわらかに彼女は言った。うなずき、私はそばにあった機工の残骸――あの日、荷物に入っていた見知らぬ機械仕掛けの腕――を手に取り、ためつすがめつ眺めてみる。そして窓の外へ目をやった。あれから十年の歳月が流れた……。ゲルダットという国は消え、その大地もまた各都市とつながった異次元からあふれだした力によって変容し、人跡は失われ、岩の多い野ばかりが広がるだけの辺境と変わり果ててしまった。太古の火山がふたたび目覚め、火を噴き上げ、おびただしく氾濫する熔岩によって大陸そのものを作り変えられたかのようだった。三千年以上も昔、神の怒りに触れて滅びた北方大陸より生き残りを率い、新天地を求めて〈竜域の海〉を越えてきた十賢者がここに叡智の小国を興したのだが、それ以前の支配者のない自然に立ち返ったのだ。東西それぞれの隣国であるハンターレクとミラの主導者たちは、ゲルダットが滅びたのちも魔術によって呪われた地として近づこうとはしなかった。しかし恐れ知らずの有志たちは、新たな土地、新たな富というまだ見ぬ夢をたずさえて、開拓に乗りだしはじめている。私たち二人もそのさなかにあった。
私とセニサは、開拓者の村で読み書きや様々な知識を伝える教師として、また有事の相談役として働いている。このまっさらな天地に流れてきた開拓民の多くは、ハンターレクやミラで貧困に苦しみ、またある者は迫害を受けて暮らし、教養を持つことの許されなかった境遇にあった。知識の伝授は、ここから長い時をかけて発展し、かれらとその未来を守る鎧ともなるだろう。
私はその暮らしのかたわら、開墾や土木を助ける機械仕掛けの自動人形の研究をしている。魔術で生み出せる自立式の泥人形、ゴーレムでもこなせるはずだが、いまは魔術に頼らずともすむ道も探さねばならないと考えるようになった。
(悪を滅ぼすのではない。悪を善に変える――それが過去をすら償い、みずからの手で運命を編みだす技となるのだろう)
私には、無知――怒りと恐れによって多くの書を焼きはらった悪がある。カレルを殺さざるをえなかった悪も。このゼロからの出発は、長い道のりとなるだろう。
開拓者たちが作物の世話を終え、切り株に腰かけて談笑している屋外へと放った目を、手に持った機械仕掛けの腕にもどす。腕は人体を模して精密かつ柔軟に作られ、もし本体に繋がっていたなら完璧とも言えるはたらきで動いていたのであろう。どこか遠い国から流れ着いたのだろうか――しかし漠然とだが、この腕は手放してはならないものだと、いまでも感じている。守護、約束、呼びかけ、絆、思い出、夢……あの〈月と海の浜〉の水底から唯一、引き揚げられた甘くも苦い秘密、あるいは呪いの側面を持った愛。人知の及ばぬ遠いかなたの不可避のロジックによって私に結びつけられ、次元さえ越えてきたのかもしれなかった。
「セイン。これはあなたの懐中時計なの?」
セニサが図面をさして尋ねてきた。自動人形の核となるエネルギー源として、懐中時計とその動力の結晶体が役立ちそうだった。だがそれ以上に、この時計をこの子に、私の夢にこそ託したいと考えていた。そう伝えると、セニサはうなずきで同意を表した。
「それでも、私は託すだけだ。何を選ぶのかは、この子に任せたい。世界を作り出すのは、その時代を生きる者たちなのだから」
青く晴れ渡った天空を見上げ、思いを馳せた。過去、現在、未来の連なり――そしてあるひとつの象徴へと。はるかなる彼方にそびえる大樹の豊かな枝葉のさざめきが、空を往く風によぎっていった。
1 note
·
View note
Text
08140107
先日プレゼントしたスニーカーで地面を蹴り、靴底を擦り付け、彼は僕も含め外界の全ての情報をシャットダウンしているらしい。さっきから一言も話さず、ただただ地面を凝視しながら揺れている。流れてくる風は先ほど止んだ雨の匂いをまだ色濃く纏っていた。生臭く、青臭い土混じりの湿った匂い。
いつからか僕を追い越して嫌味なほど主張するようになった身長を、僕はただ隣で見上げていた。が、ただ時間は流れていく。照り返しも太陽も、僕には暑すぎる。それに、陽が沈んでは敵わない、と、痺れを切らして名を呼んだ。
「此岸。」
「......」
「此岸、」
「......」
「... 、」
「っ、あ、ご、ごめん、何か話してた...?」
肩をびくりと振るわせて此方を見下ろした此岸のビー玉のように丸く綺麗な目。微笑ましいな、眩しいな、と暫く見つめてから、気付いていないであろう足元を指差してやった。
「全部死んでるよ、蝸牛。」
「あっ...ごめんなさい、」
「今日は、やめておこうか。」
「いや、大丈夫。もう大丈夫。準備出来たよ、ごめんね。」
空に少しだけ空いた隙間から、鬱陶しい程主張する日光が差していた。此岸の足の下でぐしゃり、ぱきり、ぐちょり、ざりざり、粘性の伴った音と共に踏み潰されていった数多の蝸牛が水玉模様の如く、味気のなかったアスファルトに無数のユニークな模様を描いている。
「行こうか。」
「うん。」
にこり、口角を上げ差し出した手を握る此岸は、出会った頃と変わらないようにも思えて、大きくなった手だけが違和感を覚えさせた。此岸から見た僕は、どこか変わったのだろうか。横に並ぶ表情は固く、ただ目の前に鬱蒼と広がる樹海を眺めていた。
あれから10年。たった10年。
自分の身に何があったのか、ちゃんと知りたい。と言い出すまでは触れないでおこう、そう思っていた。そして、言い出した時は���全てを包み隠さず話そう、とも思っていた。覚悟が出来たのだろう、二十歳になった日の夜重い口を開いた彼を、僕はこうして連れてきた。彼の、そして僕の、終わりの始まりの場所へ。
「彼岸と此岸が出会う前の話を、少しさせてもらおう。」
僕の母は美しい人だった。もはや、その記憶しかない、と言ってもいいほどに、母の美しさは脳裏に焼き付いて、他の思い出が色褪せてしまう程に鮮やかだった。実際、父の記憶は殆どない。僕が幼い頃にいなくなった、と、それだけ母から聞かされたことを覚えているくらいだ。写真も面影も家にはなく、あるのは、僕と、母だけだった。
母は、僕のことをそれはそれは大切にした。あるだけの資産を僕に注ぎ、母の思想と、美しい物と、正しい物に囲まれて、僕は作られていった。絶対的な母という正義によって培われていった僕の常識は、世界中のどの法律よりも憲法よりも正しく、破ってはいけないものとなった。今でも、それは変わらない。
思えば僕の初めての相手は母だった。母が艶々と輝くシルクの、純白のシュミーズを肩から落とし、痩せ型な身体からは想像し難いような豊満で、張りのある乳房が脱げかけたシュミーズから溢れ出て、僕は最中に、聖母マリアを抱いていると何度も錯覚を起こした。
学校に行かずとも、友達を作らずとも、僕の全ては母が作ってくれた。だから、外に対して何も求めなかった。僕は家から出たことは殆どなかったし、それを疑問に思ったことすらなかった。全てを知れる状況で、他に興味を持てという方が難しい。
「そして母は、僕が18になった夜、首を吊った。」
白いワンピースを着て、月明かりを背に、母は天井の梁からぶら下がった。揺れる母のワンピースに、外から吹き込んだ初夏の風が当たってふわっと広がって、母の好きだったアングレカムの花を思わせる、そんな、美しく正しい死だった。
死に際、僕に何か言葉を残すこともなく、ただ、にこりと、穏やかな笑みだけを残して、世界に僕を置いていってしまった母を見て、僕は、途端に何をすればいいのか、わからなくなった。リビングに残された母の最後の手紙には、『家に火を付けて、全て綺麗にしなさい。そして、私を、自然に返して。』僕は、母からもらった手紙も服も全て何もかもを置いたまま自宅へ火をつけ、母の遺体だけをトランクに詰めて、初めて、外の世界に出た。
自然、そう言われて浮かんだのは、樹海だった。生前母は何度も、森に還るのは生き物としての本能、と説いていた。僕は本やビデオで何度も樹海を旅し、母が樹海へ帰る姿を夢想しては神々しさに震えた。正しい母は最後まで正しくあるべきだ、そう思って訪れた樹海は、酷いものだった。
「間違った人間が多過ぎる。何もかも、全て、全て全て全て!」
薄汚い服を着たまま中途半端なロープに引きずられるボロ切れのような死骸、散乱するゴミ、情けない泣き言まみれの書き置き、死に切れずに震えてテントで眠る臆病者。初めて見る外の世界が、こんなにも誤りで満ちていることに、俺は気が狂いそうになった。どこを歩いても、見えるものは地獄の沙汰だけで、俺はまたしても行先を見失った。
樹海について2日ほど、拾った死人の荷物を奪い体力を維持しながら歩き回っていた時、ふと、鼻をつく匂いがして、後ろに引きずっていたトランクの中身が気になった。開いた時、俺は、正しいものが何なのか、分からなくなった。あの美しかった母の肌が浅黒く、目は窪み虫が沸き始めて、俺は、俺は、美しい母は、最後の最後に間違えたんじゃないかと、そう思う心を捨てられなかった。
そんなはずはない。僕が正しくて母が間違っているなど、そんな世界��未来永劫あり得ない。僕も母も正しいか、母が正しく、僕はただ教えを乞うか、その二択しかあり得ない。僕が、間違ったこの場所を、間違えたままにしていたから、母をこんな目に合わせた。そう思うと、目に映るもの全てが憎悪の対象になった。
「そして俺は母を運んだその日から、この深い森で、間違えそうな人間を見つけては、正しい選択をさせ続けた。」
「...彼岸くん、」
「いつだって俺は正しい、なぜなら母が正しいから、俺が正しくないと、母も正しくなくなってしまうから、」
「彼岸くん。」
「手首を切る?あり得ない。死に切れない?あり得ない。練炭?あり得ない。逃げただけ?あり得ない。全て間違ってる。俺は吊るして、吊るして、吊るして、この森全てが母の正しさによって美しくなればいいとそればかりを願って」
「 、」
「ヒッ...な、何、ごめんなさい、」
「僕だよ、此岸。それ以上噛んだら、爪、無くなっちゃう。」
そっと添えられた体温に目線を落とすと、此岸の手の中にあった僕の指先は血塗れで、所々に白桃色の肉が見え隠れしていた。此岸が取り出したハンカチをそっと被せ、傷の深い箇所を包んでくれる。
「っ...ごめん、もう着いてたね。」
「うん。僕達の、始まりの場所。」
ふと我に帰れば、僕と、此岸が出会った場所に着いていた。無意識に歩いていてもさすがは過ごした場所。順応する能力も高かった僕は、決して樹海の中でも迷わなかった。
「懐かしいね。」
「あぁ。」
「車、無くなってるね。」
「そうだな。安心した。」
僕は見覚えがない車の中で、すごく暑くて、頭がぼーっとして、でもなんだか夜遅くまで起きちゃった日の次の日の朝みたいに、うまくおはようが出来ないような、そんなもやもやした気持ちだった。
ドン、と外から何か叩かれた音で少し目を開けると、外に立っていたお兄さんが、ガラス越しに僕に向かって手を払っていた。よく分からないけど、離れろ、ってことかな、とずりずり、後部座席を這って、お兄さんから離れた。
その瞬間、大きな音でドアの間に鉄の棒が刺さって、それをぐりぐりと動かしながら、お兄さんが隙間から僕の方を見て、そして、足をねじ込んでこじ開けて、手を、差し伸べてくれた。
汗だくのお兄さんが扉からなんとか僕を引き摺り出して、そして、抱き締め車から駆け足で離れていく時、僕は小さくなっていく車を眺めていた。白くて、所々さびていて、窓が真っ黒な車だった。
僕を下ろしたお兄さんは僕に苦しくないか、痛いところはないかと聞いて、僕を一通り見た後、もう一度抱きしめてくれた。
「おにいさん、どうしたの、」
「それはこっちの台詞だ。こんな場所で、何してた。」
「わからない、僕昨日、おうちで眠って、夜中に、お母さんとお父さんが、僕の部屋に来て、つかえないから、すてましょう、7年たてば得するわ、って言ってて、僕、また眠たくなって、おにいさんに起こしてもらった。」
「......そうか。車の中からは、俺がよく見えたか?」
「?うん、お兄さん、怖い顔してたけど、あのまま寝てたら僕、暑くて溶けちゃったかもだから、ありがとうございます。」
「熱かっただろうな。目張りされてないとはいえ、あんな場所で、よりにもよってあの車を選んで放置なんて...運がない。」
「ん...?うん、暑かった、」
「お前、いくつだ。名前は。」
「僕、しらがみ、れい。漢字は、白色の白、神様の神、数字のゼロって書くの。もうすぐ9歳。お兄さんは?」
「俺は、黒崎累、19だ。」
「お名前、なんだか似てるね!」
「あの時、何があったのか、覚えてるか。」
「段々と、時間が経つごとに思い出せたよ。僕には歳の離れた病弱な兄がいて、両親は神童とも呼ばれてた兄を可愛がってた。でも、早くに亡くなったから、僕を作って、兄の代わりにしようとして、そして、失敗した。」
何か騒がしいと思って覗いていれば、こそこそと話す男女と、荷物のように抱えられた子供。男女は、よりによってあの車を色々と物色し、中に子供を置いて、お粗末な自殺風殺害現場を作り上げてから、そそくさとその場を後にした。俺が今この場で手を下すまでもない。
バカでも最低限の知恵をつけてしまう義務教育の敗北ゆえ、鍵をかけやがった車の扉をこじ開けて、扉を開けた。うとうととする男の子。一刻も早くその場から離れようと、俺は車を一度も振り返ることなく遠ざかった。こんなことがなければ触れようと思わない。
あの男女は勿論知らなかったのだろう、その車がかなり昔、農薬を使った、父親の独断による一家心中に使われ、撤去しても撤去しても必ずこの森へ帰ってくることを。
そして、恐らく見えていないであろう窓についた真っ黒な手形が全て、車の内側から付いていたことも。
「その後、彼岸くんが、僕に名前をくれたんだよね。」
「ああ。彼岸と、此岸。学のない俺にしては、いい名付けだと未だに思うよ。」
「...僕ね、どうして、名前をくれたのか、分かっちゃったんだ。」
「......察しがいいな。そうだよ。お前はもう、戸籍上は死亡してる。そして俺もだ。」
「暑いね、彼岸くん。」
「ああ、」
此岸が、まるであの日を懐古して愛おしむような表情でしゃがみ、湿った土に触れた。此岸の両親の顛末を俺から伝えるべきか、ずっと悩んでいた。あんなクソ野郎共とはいえ、親だ、なんて俺が言ってもなんの説得力もないが。
「此岸、お前の両親は、」
「僕、忘れたい事は沢山あるけど、あの日の彼岸くんだけは、絶対忘れないよ。」
「あの日の、俺?」
「うん。頼もしいお兄さんが必死になって、僕を助けてくれた、あの手。」
「...此岸、」
「一人ぼっちだった僕に、眩しい世界を教えてくれたのは、彼岸。君だ。」
「それは、俺の台詞だよ。」
「だからね、僕は過去を捨てはしないけど、今日ここに置いて行こうと思って来たんだ。」
赤の他人を恨める人間は、そう多くない。僕だって実際、殴る蹴るを繰り返してた両親はともかく、無視してた学校の友達とか、近所の人とか、先生とか、そんな人たちは気にしてなかったから。でも、僕と彼岸が出会ってから暫くして、彼岸くんがふらっと夜、出掛けたんだ。僕は気になって、トランクの中に入って追いかけた。長い時間乗っていて、僕が目が覚めた時にはもう車が止まってた。噛ませておいたドライバーを使ってトランクをそうっと開けてみると、彼岸くんが、縛られた男の人、女の人、赤ちゃんを、僕達が出会った場所に連れて来てた。
「どんな気分だ。零を捨ててから地獄が続いただろ。」
「でもなぁ、アンタより、何より、あの子が一番地獄の底にいたんだよ。」
「分かるか?あの車に、一人放置される気持ち。分からないだろうな。」
そこからただただ無言になって、彼岸くんはあの日僕を助けてくれたバールで、3人をひたすら殴っていた。所々溢れる言葉はよく分からなかったけど、でも、間違いを正す、それだけははっきりと聞こえて、僕はトランクをそっと下げて、お家に着くまでずっと、彼岸くんの買ってくれた毛布に包まってによによしてた。嬉しかったんだ。
「僕、案外彼岸のことわかってるんだよ。伊達に何年も、一緒にいないもん。」
地面を触る此岸。土に手を差し込んで、掻き回して、引き抜いたその手に纏わり付く長い黒髪。
「彼岸くんが壊れないように、世界の間違いを少しずつ正そう。」
「此岸、」
「それが、僕の願いだよ。」
0 notes
Text
聖夜、海に沈んでそれから/薫×奏汰
――――『くりすます』も、うみにきましょう 何週か前にそう彼と約束をしたことを思い出して、それを彼に言えば、 「じゃあ、『がっしゅく』もかねてやりましょう~」 と笑った。 「え、ふたりだけで?」 「そうまはかぞくで『くりすますぱーてぃー』をするから、ってことわられちゃいました」 家族で、クリスマスパーティー。颯馬きゅんの家、仲良さそうだもんなぁ、と、弟について話していた彼を思い出してぼんやりと思った。 そうなんだ、と納得してから、 「でも二十五日さ、女の子たちがたくさん来るスタフェスじゃん?」 何気なくそう言ってから、あ、と口を噤んだ。女の子、という単語に奏汰が肩を微かに震わせたからだ。 「……『うわき』ですか?」 ちょっと拗ねたような顔の奏汰に、ごめん、冗談だよ、と謝った。そんな表情もするようになって、彼は前より人間味を取り戻している気がする。それよりも、きっとこんな顔、自分以外には見せないだろうなぁ、と思うと優越感に浸った。 「二十四日と二十五日に合宿する? 二十四日は午前中にレッスン終わるから、午後からは遊べるでしょ」 そう提案しても、そっぽを向いたままだ。奏汰の頬に触れて、目線を合わせる。 「ごめんってば~。そんな拗ねないでよ」 これは本気でご機嫌ナナメ? と身体を強張らせた薫に、ぷっ、と奏汰が噴き出した。 「あははっ、『じょうだん』ですよ、かおる。おかえしです」 そう笑った彼の頬を摘まんでも、いたいです、と笑ったままだった。 「ぼくが『しんせい』しておきます。かおる、『すいぞくかん』にいきたいです。とくべつな『いるかしょー』をやるらしいですよ~」 「はいはい。ほんと奏汰くんは水族館好きだよね~」 「かおるも『すいぞくかん』すきでしょう?」 「まぁね」 それから、奏汰の頬を撫でていた手を止める。 「……水族館行った後さ、俺も行きたいところあるんだけど、いい?」 奏汰は不思議そうに何度か瞬きをした。 「どこへいくんですか?」 「ん~……、奏汰くんに会わせたいひとのとこ」 その返答にまだ首を傾げたままだったけれど、彼はわかりました、と頷いた。
◇
クリスマスイブのレッスンを終え、着替えを済ませて噴水へ向かうと、奏汰はその縁に腰掛けていた。その横顔があまりにも綺麗で、一瞬息をすることさえ忘れた。 「……奏汰くん」 顔を上げた奏汰は、目を細めて、かおる、と笑った。その頬が赤く染まっている。 「ごめん、遅れちゃって」 「だいじょうぶですよ~」 そう答えながら、奏汰は薫の結った髪に触れた。 「きょうはむすんでるんですね? あと、めがねも。めずらしいです」 「そ。変装」 私服とはいえ、バレるときはバレる。プライベートで軽く変装をするように、と学院側からも言われている。アイドルとしての自覚を持てと耳に胼胝ができるほど聞かされた。 「奏汰くんも少し変装した方がいいんじゃない? せっかくのデート邪魔されたくないし」 「ふふ、はい」 デート、という単語に笑った彼の前髪を崩し、横髪をヘアピンで止めれば少し雰囲気が変わった。噴水の水面を鏡代わりにして自分の髪型を確認した奏汰は、感嘆の声を上げた。 「いつもとちがいます~」 そんな彼に思わず笑みが零れた。その手を取って立ち上がらせる。 「よし、行こっか」 奏汰はとびきりの笑顔で、はい、と肯いた。
電車に乗って辿り着いた水族館には、クリスマスということもあってか、いつもより人が多かった。いつも平日の空いた時間に来ているため、賑やかな水族館はいつもと違って見えた。入口はイルミネーションで綺麗に装飾されている。 興奮したように奏汰が薫の手を引く。 「はやくいきましょう、かおる」 「そんなに急がなくても魚は逃げないってば」 メインの大水槽はクリスマスカラーの照明でライトアップされ、その中でイワシの群れや大きなエイたちなど、海のいきものたちが悠々と泳いでいた。 水槽と水槽の間を歩きながら、奏汰が次々と指を差す。 アオウミガメ、シュモクザメ、ダイオウグソクムシ、アジ、マダイ、マグロ、オニトマキエイ、マダコ、マンボウ、ハリセンボン、エンゼルフィッシュ、タカアシガニ、シャチ、イルカ、クジラ。 懐かしいのはなんでだろう、と思いながら、奏汰が口にしたその生き物たちの名前を繰り返すと、彼は嬉しそうに笑った。 ペンギンやアザラシを見て、それから向かったクラゲの展示室は一段と暗く、ライトの色に染まったクラゲがふわふわと漂っていた。丸みを帯びた傘、細く長く柔らかな口腕。 あ、と奏汰が微かに声を漏らした。伏せた睫毛の先、水槽の底に沈んだクラゲがいた。くしゃりと潰れた傘が水にゆらゆらと揺れているだけで、動いていない。 「……死んじゃってる?」 薫が静かに問うと、奏汰は黙って肯定した。 「くらげの『じゅみょう』は、みじかいですからね」 静かにそう教えてくれた奏汰の目は哀しい光を宿していた。死を理解している人間が持つ光だった。 「溺れたのかもね」 「ぼくといっしょですね」 何が、とは訊けなかった。不安になるのは、奏汰のことが、本気で好きだからだろうか。引き止めるように彼の手を握れば、不思議そうに奏汰は首を傾げた。 「どうしたんですか?」 「……イルカショー、もうすぐ始まるんじゃない?」 あっ、と思い出したように奏汰が手を叩く。 「そうでした。いきましょう、かおる」 「うん」 そして神に祈る天使のように、死んでしまったクラゲに向かってそっと手を合わせる。薫はその横顔を見つめていた。 「……『てんごく』では、もっとじょうずにおよぐんですよ」 そっと呟いたそれは、後ろからやって来た小さな子供たちの笑い声に掻き消された。 屋外にあるプールの前に並ぶ観客席の後方に腰掛けた。容赦なく冷たい風が吹き付けて、ふたりで身を寄せ合いながら、ショーを鑑賞する。 大きなイルカが三頭、輪潜りをしたり、ボールを口の先に乗せたり、飼育員を背びれに掴まらせて泳ぎ回ったりしている。艶やかな肌が光って、水に潜る。 「わ~、すごいですね~」 迫力のあるイルカショーに見惚れる。 「ぼくも『いるか』みたいにおよげるようになりたいです」 「う~ん、奏汰くん、水好きなのになんで泳げないんだろうね~」 「ぼくはうまれつき『かなづち』ですからね~」 そんなふたりの目の前で、ふたりを皮肉るかのように、イルカが自由に泳ぎ回り、大きくジャンプをした。飛び散った水滴が日の光にきらきらと反射した。
◇
ショーを見終えて、ふたりは水族館を出て駅に向かった。その構内にある花屋で白いユリの花束と小さなクリスマスリースを買った。それを見つめながらも、奏汰は何も言わずに薫についてきた。 乗り込んだ電車は運良く空いていて、窓を背にした席に腰掛ける。夕陽が車窓から差し込んで、人々の影を濃くする。車輪がレールの上を廻る音だけが響く。 「……どこへ、いくんですか?」 昨日と同じ問いを口にした奏汰に、今度はちゃんと答える。 「母さんのとこ。クリスマスは、毎年行くようにしてる」 奏汰は、吊革が振動に合わせて揺れているのを眺めながら、 「かおるの、おかあさん」 と静かに繰り返した。そして黙って薫の指に自分の指を絡め、肩に頭を預けた。 「……あいたいです」 うん、と答えた声が擦れた。 「俺も会いたいなぁ」 小さく呟いたけれど奏汰の返事は無かった。黙っているうちに、奏汰は薫に凭れて静かに寝息を立てていた。規則的なそれを聞いているうちに、薫にも睡魔がやって来た。 懐かしい夢を見て、ふ、と目を覚ましたときには、目的地のひとつ手前の駅だった。奏汰を起こして、小さな駅で下車した。眠そうに目を擦る奏汰の手を引いて小高い丘へ向かう。 その天辺にある小さな墓園に辿り着いて、こっち、という言葉と共に漏れた息が真っ白に染まってすぐに消える。整備された細い道を、ふたりは黙って歩いた。 海に面した場所に、薫の母の墓は建っていた。 「……うみがみえて、いい『ばしょ』ですね」 潮風に乱れる横髪を耳に掛けながら、奏汰は目を伏せた。 「うん。海が好きな、ひとだったから」 おれ、海好きだよ、と言ったとき、母は嬉しそうに、私といっしょね、と笑った。その聖母のような微笑が海よりも好きで、大切で。 母との思い出は、海でのことが多かった。追いかけっこをしたり、綺麗な貝殻を探してその命の音を聞いたり、足首まで海に浸かったり。 自分が死ぬことを母は誰よりも理解していて、受け入れるわけでも、拒否をするわけでもなかった。ただ、海を見つめる瞳は寂しそうで、まるで海に帰りたがっているみたいだと子供ながらに思ったのを、今でも憶えている。 白い墓石には、自分が持つ苗字が刻まれていた。その石に触れてから、アルミ製の花瓶に並々と水を注ぎ、白百合を生ける。母が一番好きだった花を。そしてそれから、クリスマスリースをその花瓶に掛けた。 「……『めりーくりすます』、かおる、かおるのおかあさん」 「……うん、メリークリスマス」 その声が滲んでしまって、口を閉じる。奏汰の方を見て、いつもみたいに笑うつもりだったのに上手く出来なくて、表情が歪むのが自分でも分かった。喉の奥が引き攣って、出ない言葉の代わりに、湿った白い吐息が漏れた。 「……かおる、」 奏汰が、はっきりと、低めの声で、薫を呼ぶ。 あぁ、ずっと、こういうふうに名前を優しく呼んでもらいたかった。 そう気づいて、その場にしゃがみ込む。泣くときに出る癖だ。誰にも泣き顔を見られないように、蹲って、顔を伏せて、泣き声と嗚咽を噛みころす。震える薫の背に、奏汰の華奢な腕が回って、横から抱き締められる。弱いところなんて見せるつもり、なかったのになぁ、と思っても今更遅い。 「……もう『がまん』しなくて、いいんですよ。『なく』ことは、かっこわるくありません」 薫の頬に、奏汰の指が触れる。ひとより低い体温だけれど、その中にはきちんと命の温もりがある。 その手が薫の顔を優しく持ち上げて、その指が涙を拭う。奏汰の瞳も凪いだ海のように、優しく揺らめいていた。その中に、悲しい光がある。 「『かなしい』ときや、『さびしい』ときは、ないていいんですよ」 それが、『にんげん』です。そう、奏汰は言う。 魚みたいに、悲しみから逃げるように泳げはしないけれど、悲しみを吐露することはできる。 奏汰の手に頬を摺り寄せて、彼を抱き締め返す。 ――――母さん、俺、好きなひとができたんだ。ちょっと変わってるけど、優しくて、いい子だよ。泳げないけど、海がよく似合う綺麗な男。 寂しくて優しい海の匂いが鼻を掠めた。閉じた瞼の裏側に、砂浜で微笑む彼女の姿が浮かんで、また、涙が落ちる。 白百合が潮風に吹かれて揺れた。
201512/20160518加筆修正
海に沈んで、それから。 | よなか #pixiv http://www.pixiv.net/novel/show.php?id=6794335
1 note
·
View note
Text
ルドンの気球
昼の盛りを少し過ぎていた。朝早くからの仕事を終えた私は午後から始まる別の仕事場へと移動していたのだが、時間に少し余裕があったので道の途中にある喫煙所に寄り道をして、休憩も兼ねがね空に煙草の煙を吐いていた。
その喫煙所は市街中央から少し離れた場所にあるホームセンターの入り口脇に設置してあるもので、近頃閉鎖が相次いで喫煙所が皆無であるこの界隈においては屋外で煙草が吸うことの出来る数少ないスペースだった。必然として近隣のあぶれた喫煙者たちは飢えた蠅が残飯にたかるようにこの喫煙所一か所に集まり、連日どの時間帯も紫煙と煙草の香りが賑やかに空へと立ち昇っているのだが、今日は自分以外に人は一人も居なかった。だからといって寂しさが募るわけでもなく、むしろ人の居ない気楽さを煙草と一緒に味わいながら目の前に広がる景色を漫然と眺めていた。 私が履いている二足のスニーカーの先にはテニスコートのよう���樹脂製の赤茶色をした地面があって、その少し先にはいつもそれ程人が通っていない歩道があった。歩道の先には木蓮の街路樹とつつじの植え込み、白いガードレールを挟んで幅の広い車道が横たわっている。その車道では種々雑多な自動車が途切れることなく右や左に行き交っていて、行き交う度に車が空気を切り裂く乾いた音がここまで響き、時折排気ガスの臭いが微かに漂って来ることもあった。そんな車道の向こう岸にはこちら側と同じように白いガードレール、木蓮の街路樹とつつじの植え込みを挟んで人通りの少ない歩道があり、その先には白塗りの壁に包囲されている広大な空き地があった。 今年になってから巨大商業施設の建設工事が行われているその空き地からは螺旋状のドリルで地面を掘り返している掘削機の重低音や作業員たちの掛け声や怒声が断続的に聞こえてきた。工事の様子そのものは白塗りの壁に遮られてここからは殆ど見ることが出来なかったが、壁の上から空に伸びているクレーン車の長い首の姿だけは幾本か見ることが出来た。空はというと白い雲に一面を覆われているように見えたが、しかし良く見ると、白、灰白色、灰色、と所々に微妙な濃淡の差異が見えて、薄い墨を使って描かれた淡い禅画のようだった。殆ど動きを見せないクレーン車の直線的で無機質な梯子は真冬の空に聳え立っている黒い巨木のように背景の虚ろな空に良く馴染んでいた。 寡黙で怠慢なクレーン車の長い首だったが、時折思い出したようにゆっくりと空の只中を旋回した。先端の小さな頭の下からは細長いワイヤーが垂直に下へと伸びていて、その先のフックに四角い鉄骨の束をぶらさげているのだが、巨大で重量もかなりありそうなその鉄骨の束に比べてワイヤーの方は随分と細過ぎるような気がした。おそらくそれは恐ろしく硬く丈夫な材質で出来ているのだろうが、遠く離れたこの喫煙所から見てもそれは白い空に引かれている縦の棒線にしか見えず、その頼りない細さは空中に鉄骨が浮いているという不自然な状況を更に不自然に不安定に非現実的に見せていた。 束の間、白い空の中を回遊した鉄骨は段々と降下していって、最後には白塗りの壁の下に見えなくなった。暫くするとまた新たな鉄骨が白塗りの壁の上から姿を現し、白い空の中を漂い始める。どこかそれは酷く陰惨な拷問の現場を見ているかのようだった。 飛翔する開放感はなく、上昇する高揚感もなく、ただ白い空の只中に宙ずりにされている存在。色もなく音もない虚空の中で何一つと触れることが出来ない彼の存在を唯一世界の内側に繋ぎ止めているものは自らの身体に巻き付いているワイヤーであって、しかしそれは同時に自らの全体重が喰らい込んでいる耐え難き苦痛の繋ぎ目でもある。その線は言い換えるならば存在と現実を繋ぎ止めている最後の絆であり、ワイヤーが断ち切られた瞬間に彼の身体は地上へと落下して瞬く間に大地と一体化し、切り離された彼の魂は白い空の上へと無限に上昇していく。 言葉に変換されたイメージは少しずつまた言葉からイメージに変換された。しかし、そのイメージはもはや既にクレーン車に吊るされている鉄骨の姿ではなく、白い空の中に突き出している黒い十字架だった。それからイメージは、吊るし首の樹海、冷凍室に吊るされている豚の肉塊、廃墟に浮かぶ風船の群れ、と変転していき、やがて一枚の絵と結び付いた。それはオディロン・ルドンの眼=気球だった。 いつどこでその絵を最初に見たのかは定かでない。ユイスマンスのさかしまの挿絵だったような気がするが、もっとずっと以前からその絵を知っていたような気もする。とにかく長い間、そのルドンの絵が私の意識下無意識下に棲み続けていた。 絵の下方には先細った生気のない数束の草の葉以外に何も見えない荒涼とした平地が広がっている。殆どが黒く塗りつぶされているのでそれが土の地面なのか或いは草原なのか判然としない。ただ生命の息吹を感じさせるような大地でないことは確かで、見方によっては海、それも暗い夜を髣髴とさせるような海にも見える。その上方には私が今目の前にしているのと同じように白や灰白色の混在した虚ろで観念的な空が覆い被さり、その中に黒く巨大な気球が浮かんでいる。その黒さは観念的で非現実的な空の色とは対照的に暴力的で生々しい夜そのものの黒さで、常に破裂の緊張感が付き纏う気球の丸い輪郭線も危険な印象に油を注いでいる。 しかし最も不気味なのは黒い気球の上半円に見開かれている一つの大きな瞳だろう。眼窪のように抉られている気球の上半分に細い睫毛を生やして埋まっているその眼球は黒目が著しく上方に偏り、残された広大な白目には若干血管が浮いている。それは正常な状態における人間の瞳ではなかった。私がごく初期に連想したのは首を締め上げられて死んでいく人間の瞳だった。次には白昼夢を見ている人間の瞳となり、性交の際絶頂を迎えている女の瞳となり、賭博で一文無しになったときのギャンブラーの瞳となり、法悦に浸っている聖人の瞳となり…と気球の瞳は様々な人間の瞳の中に顕現した。そのどれもが快楽の絶頂か苦痛の限界に接している人間の瞳で、つまりは自己を喪失しかけている人間の瞳だった。 黒い気球に見開かれた瞳の下睫毛には黒い円盤のような物が吊るされている。円盤はかなりの重量があるようで、その重みによって細い睫毛はの一本一本が張り詰め、下瞼に至っては一部が捲れ上がってしまっている。つまりはこの円盤の重みが下瞼を開かせているのだった。その力は同時に黒い気球全体をこの虚ろで観念的な空の只中に繋ぎ止めているのであり、もし仮に睫毛が切れた場合、円盤は地上に落下して黒い地面と一体化し、下瞼を閉じてほぼ完全に黒い球体と化した気球はどこまでも空を上昇していき、遠くはその故郷である夜そのものに溶けていくであろうことを予感させる。 というのがルドンの気球=眼に対する私の凡そな見解であったが、今こうして白い空とクレーン車のを見ているうちにまた新たな側面に気が付き始めた。それは至極単純な答えで、あの絵は白い空を見詰めるルドンの自画像だということだった。 ルドンにとって白い画用紙は白い空そのものであり、その白い空を見詰め続けるということは虚無を見詰め続けることと同じ意味を持ち、更にそれは自分自身の虚無を見詰めるということだった。しかしそれは非常に恐ろしいことで、なぜならそれは自分自身が存在しないのだと自分自身が強烈に自覚していく行為であり、刻々と死んでいく自分自身を自分自身が見詰めるということだからである。その死は肉体的な死というよりもより完全に純粋な自分自身の死であり、実際に人間が本当に恐れているのはこの自分自身の死であって肉体の死ではない。肉体の死が必然的に自分の死を引き起こすと仮定するために人間は肉体の死を恐れているのに過ぎない。しかし実はそうした恐怖、虚無に対する恐怖という感情そのものが虚無に接している人間にとって最後に残された虚無的でないもの、つまりは自分自身そのものなのであって、だからルドンの虚無に対する恐怖苦痛絶望といった人間的感情は全てあの黒い円盤の方に詰まっているのである。その円盤を吊るしている睫毛が切れた瞬間、つまりは虚無に対する恐怖苦痛絶望といった人間的な感情の全てが消えた瞬間彼は虚無そのものになり、本当の夜がそこに訪れるのである。 しかし一方で見開いた目玉の黒い気球もルドン自身であることは間違いない。虚無に対して見開かれていているその瞳は自己の存在を否定する虚無の方へと自分自身全体を引っ張っていく、言うなれば自分の中にある他人の瞳である。その他人である彼の瞳にとって虚無は恐ろしい無の世界ではなく、魅惑的な無限の世界=パラダイスとして映っているのだということは、そのどこか夢を見ているような瞳の表面に薄っすらと光が反映していることからも伺える。謂わばそれは太陽の光に魅せられたイカロスの瞳であるのだが、太陽へと真っ直ぐに飛んで行ったイカロスの雄姿はもうそこになく、天上と地上に、神々と人間の間にそれぞれ強く引っ張られ、上下真っ二つに引き裂かれようとしながらも何とか一つの均衡を保って地上すれすれにやっと浮かんでいる有り様である。なぜ、そうなってしまったのか?時は十九世紀であり、神の死とそれに伴う虚無がひたひたと人々の目の前に近付いてきた時代である。もはや人々は空の上に輝く絶対無比の太陽を信じることが出来なくなり、代わりとして空の上に現れたあらゆるものを相対化してしまう絶対的な虚無に不安を感じるとともに怯え始めていた。それは同時に近代自我の目覚めであり、精神と肉体の分離現象であって、タナトスとエロスが袂を分かち始めたときでもあった。死と自らの内に潜む死の欲動に不安と怯えを抱いた人々は硬く小さな円盤に閉じ籠り始め、その重力で黒い死の気球を安全な地上に縛り付けようと画策し始めた。
しかし、今後この黒い気球は果たして空に上昇していくのだろうか?それとも地上に堕ちるのだろうか?或いは二つに分離してそれぞれ帰るべき場所に帰るのだろうか?ルドン自身がどうなったかは知らないが、その後の人類の歴史を顧みると果たして人類全体は夢見る瞳を空の中に捨て去って地上に堕ちていったようである。
突然耳に聞こえたライターの点火音が延々と紡がれていくかに思われた思索の糸を断ち切った。現実に引き戻された意識は音が聞こえた方へと向きかけたが、自分の鼻の先でその殆どが白い灰と化している煙草の姿が目に映り、注意はそこに逸れた。いつの間にか意識の完全な枠外で造成されたその灰の塊は無造作でありながら絶妙な均衡を保って自分の左手人差し指と中指の間から空中へと細長く伸びていたが、根元の付近は未だに仄かな煙を流し燻っていて今にも自らの重みによって崩れ落ちそうだった。それが崩壊していく様子を目にするのが何となく嫌な気がして直ぐに私はその灰の塊を自分の手で払い落そうと傍らにある灰皿の方へ振り向いた。するとその灰皿の向こうに女が立っていることに気が付いた。と同時に均衡を失った灰の塊が崩れ、何枚かが空中にひらひらと舞って、残りが灰皿の暗い穴の中へと落ちていった。 その女は短い髪に黒縁の眼鏡を掛け、小柄で線の細い体型に枯葉色の地味なチェック柄のベストと長袖の白いワイシャツを着ていた。蒼白い左手の人差し指と中指の間には細長い煙草が挟まれ、既に火の付けられているその煙草の丸い切れ口からは白い煙が気怠そうに流れていた。右手の中には黒いライターが握られていて、直ぐにそれは先刻耳にしたばかりの点火音と結びついたが、その認識が一致するよりも早く、女は歩き始めた。真っ直ぐに女は歩道の方へ、つまりは喫煙所の前に広がる白い景色の方へと歩いていった。ゆっくりと遠ざかっていく女の背中は痩せているせいか酷く平板でタイル張りの壁のように見え、下半身に穿いている黒いスーツのズボンも黒い板のように直線的で女性らしい曲線は何処にも見当たらなかった。そのスーツの脚と合わせて規則的に動く左右の黒靴は鋭利なヒールの先端を地面へと交互に突き立てていたが、地面が柔らかい樹脂製のために靴音がまるで聞こえず、それが何とも言えない不安な気持ちを興させた。女は歩道の少し手前まで歩いていくと、地面の上に棒立ちになってそのまま殆ど動かなくなった。 地面の上に茫然と佇む女の先程よりも少し遠くなったその後ろ姿は白い景色を前にして朧な木柱の黒い影のように映った。だらりと力なく垂れ下がった両腕の左手指先から流れる煙草の煙だけが有機的な動きを見せていて、まるで女の暗い輪郭そのものが周囲の空気に溶けて蒸発しているように見えた。その前方に広がる白い空は相変わらず白い空のままだったが、クレーン車の方は小休止していて虚空に吊るされていた鉄骨も今は見当たらなかった。休憩に入ったらしく作業員たちの掛け声や怒声も止んでいて、車道を流れる自動車の音だけが寂しい波音のように響いていた。段々と私は前方に実際に生きた女が存在しているという現実が曖昧になり始めていた。同時に自分が今目の前にしている光景の全てが一体何なのか理解することに時間が掛かり始めて、少しずつその所要時間は長くなっていった。しかしながら、ようやく理解出来てもそれは現実の実感と呼ぶのが躊躇われる曖昧な感覚だった。 意識の表面に白い靄がかかっているような現実の曖昧さ、しかしそれは私の生活の隅から隅に至るまで深く浸透していた。 朝、仕事へと赴くとき、外に出て道を歩きながらふと洗面所の蛇口をちゃんと閉めたか不安になる。可能な限り記憶を振り絞ってその場面を思い出そうとするのだがどうしても思い出せない。思い出せないというよりは思い出したその場面が今朝なのか昨日なのか或いは夢の中なのか判然としない状態で、結局いつも駆け足で家へと戻り、靴のまま家の中に上がって洗面所の蛇口が閉められているか確認をする。蛇口はいつも当然のように固く閉められていた。水の一滴さえも零れ落ちてはいない。私は胸を撫で下ろし、自分の心配性を嘲笑う余裕すら出来上てまた玄関へと戻っていく。しかし、背後の洗面所から遠ざかっていくにつれてたった今確認したことが酷く曖昧になり始める。「本当に蛇口��ら水は流れていなかっただろうか?」自分でも馬鹿らしいとは解りつつも顔から若干血の気が引いている私は再度洗面所に戻って蛇口を確認してしまう。やはり蛇口はちゃんと閉まっている。幾度となくそんなことを繰り返しているうちに時間は恐ろしく浪費され、仕事場へと到着するのはいつも勤務開始時刻寸前だった。 しかし、ここ数か月間というもの症状は尚の事重く悪化していた。私は実際に蛇口を目の前にしながら「これは本当に水が出ていないのだろうか?本当は出ているのに目に見えていないのではないだろうか?」と疑っていた。すると手を伸ばして水が出ていないことを確認しなければならなくなり、終いにはその手の触感に対しても懐疑を抱く始末だった。 そうした現実に対する終わりの無い懐疑の症状は殊に蛇口の確認だけに限ったことではなく、生活のあらゆることに付き纏っていた。次第に私は疲れ切ってしまった。何をするのも憂鬱で億劫になっていった。自然と身体を動かさずにぼんやりすることが多くなり、妄想に費やす時間が増え始めた。すると妄想は生々しく現実味を帯びていき、反対に現実は獏として現実感を失っていった。そうして妄想と現実の境い目は酷く曖昧になり、現実はまた更に曖昧になっていった。 そんな出口の見えない沈鬱とした状況から半ば避難するように私は一日の内三回も四回も浴室へと赴いた。風呂湯の疑いようのない熱さ温もりは私に失われている現実感の手軽な代替品だった。浴室の白い壁や天井はまるで現実を感じさせるものではなかったが、首から下が湯船に優しく現実を保証されているので、私は安心してその白い虚空に想念の気球を飛ばすことが出来た。それは私にとって数少ない安らぎの時間であり、結局はそれがまた更に現実感を失わせる結果に繋がると理解していてもやめることは出来なかった。 掃除も稀にしか為されず、私の生まれるずっと以前からそこに存在している浴室の白い壁は、白い壁とは言ったものの半ば黄ばんでいて、至る所で亀裂が走っていたり表面が剥がれ落ちていたりしていた。黒かびの星座も彼方此方に点々と煌いていた。そんな古い浴室の壁の上を梅雨の時期から夏にかけてはよく蛞蝓が這い回っていた。蛞蝓は梅雨の初めの頃は注意して見ないと壁の黴やしみと見間違える程小さかったが、夏の終わる頃には皆でっぷりと太って禍々しいまでの存在感を発揮していた。蛞蝓を見つける度に私は素手で捕まえて窓から逃がした。突然、壁から引き剥がされた蛞蝓は最初手の平の中で小さく委縮しているのだが、少しずつ顔の上から細い棒状の突起眼が二本伸びてきて、やがてそれは触覚のように左右ばらばら動きながら頻りに周囲を確認し始める。それが落ち着くと今度は手の平を我が物顔で這い回り、蛞蝓はその柔らかい口で一心不乱に手の皮膚の表面を齧り始める。私の手の平を白い壁の続きだと勘違いして食べている、その滑稽で間が抜けた様子と無邪気な食欲の感触は意外にも不快ではなかった。ただそんな蛞蝓を手放した後に残る粘液の感触は堪らなく不快だった。お湯と石鹸でいくら洗ってもそのぬるぬるとした粘液はしつこく手の表面に残り続けた。それが嫌で私は次第に蛞蝓を壁の上に見付けても放って置くようになった。壁の管理人が消えて蛞蝓たちは縦横無尽に壁の上を這い回るようになり、私は温かい湯船に浸かりながらぼんやりとそんな彼らの様子を眺めるようになった。蛞蝓はいつも酷くのんびりと移動してたが、床付近の壁に居たはずの蛞蝓がふとすると天井付近に張り付いていることがあった。その意外な速さに驚いて私は蛞蝓の動きを目で追い始めるのだが、いつも途中でその姿は意識から消えて、蛞蝓は壁の思いもしない位置からふと突然に現れた。その度に今目の前にいるこの蛞蝓が白い壁の亀裂を通って無意識の世界から湧き出して来たかのような不思議な感覚を私は覚えた。 ふと気が付くと、女はこちらの方に振り返っていた。女はそのまま真っ直ぐにこちらへと歩いて来ているようであったが黒いズボンも黒い靴も殆ど動いておらず実際にその姿が近付いているという実感は少しも持つことが出来なかった。まるで女そのものは少しも動いていなくて周囲の風景がその背後へと退いているような、丁度それは海岸の浅瀬に沈んでいる貝殻や流木の朧な姿形が沖合いへと潮が引いていくのに従って段々と明らかになっていくという感じだったが、やがてはっきりと鮮明になったのは先程見掛けた枯葉色の地味なチェック柄のベストや皺一つない白のワイシャツ、黒いスーツのズボンといった身に付けている服装ばかりであって、女そのものの身体は一向にはっきりとせず、その顔に関しても黒縁の眼鏡ばかりが目立つばかりで顔の造りや表情は曖昧で判然としなかった。まるでそれは服や眼鏡だけが絶妙な均衡を保って虚空に浮いているかのようで、そよ風か何かの些細な振動によって今にもばらばらと崩れ去りそうであった。 それから間もなくして透明なその幽霊は私の傍らにある灰皿の向こう側へと戻って来た。灰皿の上に白い手がぼんやりと浮かぶ。その指と指の間からは白い灰の塊が絶妙な均衡を保って虚空へと細長く伸びていた。その灰の塊を見た瞬間、私の中で不安な気持ちが大きく揺れて、現実そのものを確かめるように私は女の顔を凝視せずにはいられなくなった。私からは横を向いているその女の顔は恐ろしく白い色をしていた。しかし、それは人間の肌の自然な白さではなく人工の観念的な白さであった。更に良く見るとその白い仮面は所々深い皺によって裂けその周辺から粉が吹いていて、それが造られた仮面であることを自ら強調していた。その裂け目や空いた穴から覗く生の地肌を見たとき私の心はようやく落ち着きかけた。しかし、ふと女がこちらを向いて俯き、今まで眼鏡の陰に隠れていたその瞳が露わになった瞬間、私の心は再び大きく揺れた。その透明な眼鏡の双眼レンズの奥には血管の赤い亀裂が幾筋も走っている異様に白く生々しい眼球とその眼球の上辺から今にも飛び出しそうに偏っている黒い瞳が二つぼんやりと浮かんでいた。それがルドンの気球と結び付くよりも早く、女の手が白い残像を描いて素早く動き、その指と指の間から灰の塊が崩れ落ちた。私は雪片のように舞い散る灰の幾枚かを視線で追いながら、自分自身がばらばらに崩れていく音を聞いていた。
0 notes